ワルラウネ
添加标签
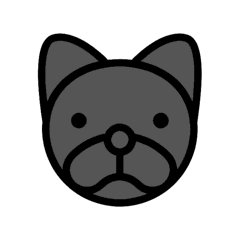
Se
sevendayofgun
ワルラウネ
僕は、ふらふらとその森に入っていった。
今がいつか、ここがどこかも分からない。
ただ、その香りに誘われるままに――
……とても甘く芳しい匂い。
……そして、どこかいやらしい匂い。
頭がぼんやりする。
物事がはっきり考えられない。
そして気がついた時には、森のかなり奥深くまで来てしまったようだ。
「どこだ、ここ……」
僕は夢うつつのように呟いた。
匂いは、森のさらに奥の方からだ。
「こんな広い森、危ないよな。早く戻らないと……」
森の奥へ、さらに奥へ……
「さあ、こんなとこウロついてないでさっさと帰ろう……」
そう言いながらも、僕はこの匂いの元を探してふらふらと進んでいった。
「ふふ……いらっしゃい、ボウヤ」
いつの間にか、目の前にはハダカの美しい女性がいた。
森の中に立つ、綺麗な女性――その髪は緑色で、下半身は毒々しいピンク色の花びらに覆われている。
一目見て、人間ではないと分かる女性――それを前にしても、なぜだか僕は心が乱れなかった。
それどころか、彼女のものになってしまいたいとしか思えないのだ――
「私はアルラウネ。人の精を糧にする花の淫魔よ……」
彼女は、さらりと美しい髪をかき上げる。
ふわっ……と、甘い匂いがさらに濃くなった。
まるで、周囲がピンク色に見えるほどに。
「あ、あう……」
「ボウヤの精も吸い尽くしてあげる。気持ちい~い、お花のベッドの中でね……」
アルラウネが、足元に軽く息を吐き掛ける。
すると魔法のように、彼女の足元へとみるみる花畑が広がっていた。
うち一房の花がむくむくと膨らみ、人間サイズの大きさとなり――巨大なバラの花が現われる。
そのピンク色の花びらはつぼみのようにすぼまり、まるで寝袋のようになっているみたいだ。
人間の身体全体を、すっぽりと包んでしまえるような大きさである。
「そのお花の中に入りなさい、ボウヤ。とっても素敵な気持ちになれるわよ……」
「は、はい……」
僕はアルラウネに促されるまま、花のベッドへと歩み寄った。
花びらはまるで、幾重にも重なった肉厚の布団のよう。その中には、ヌルヌルの蜜が満ちているらしい。
「あ、あぅぅ……」
服を脱いで全裸になり、その花の中に足を入れ、ゆっくりと中に身体をねじ込み……
僕は夢うつつの気分のまま、言われるがままに花びらのベッドに身を委ねてしまった。
……じゅるじゅるじゅる。
「あぅ……」
僕は首まで花に埋まってしまい、柔らかく温かい花びらが全身を包み込んでくる。
やはり中はヌルヌルで、驚くほど気持ちがいい。
その中は温もりと安らぎに満ち、蜜でねっとりとネバついた甘い空間。
女性の子宮内は、こんな心地なのだろうか――思わず、そんな事を考えてしまった。
こうして恍惚に浸る僕に投げ掛けられたのは、アルラウネの酷薄な言葉だったのである。
「あははっ……なんてお馬鹿なボウヤ。自分からその中に入ってしまうなんて」
アルラウネの顔は、いつしか淫靡で嗜虐的なものに変っていた。
獲物を捕えた捕食者そのものの、優越感と征服感に満ちた冷笑。
「その妖花は、包んでしまった男の精気を搾り取るためのもの。
ボウヤも、命尽きるまで精を吸い尽くされてしまうのよ……うふふ」
「え……? あ、あぁぁぁぁぁ……!」
くにゅくにゅくにゅ……!
ぐっちゅぐっちゅぐっちゅ……!
ぬちゅ、ぬちゅぬちゅ……ぬちゅり……
まるで巨大な口に咀嚼されるように、僕の身体を包み込んでいる花びらが蠢き始めた。
花という大きな器官に全身を咥え込まれ、舐めしゃぶられているかのようだ――
「ふぁぁ……気持ちいい……」
全身に与えられる粘着質の快感に、股間がみるみる熱くなっていく。
すると大きくなったペニスにも、ぬめった花びらがまとわりついてきた。
ぬちゅぬちゅと音を立て、とろけそうな快感が股間を責め嫐ってきたのだ。
「あ、あぁぁぁぁぁぁぁ……!」
「気持ちいいでしょう? そのまま情けな~くおもらしして、精液を吸ってもらいなさい……」
「あ、あぅぅぅ……こんな……す、すごい……」
ぐちゅ、ぐちゅぐちゅぐちゅる……
ぬちゅぬちゅぬちゅ……ぬちゃぁ……
「あうっ……!」
まるで溶かされているかのような、ねっとりと粘り着く肉の感触。
膣肉のような花びらにペニスを包み込まれ、うねるような刺激にさらされ――僕はひとたまりもなく精を放ってしまった。
全くこらえる余裕もなく、簡単に射精させられてしまったのである。
「あはははは! もう出しちゃった! そんなに気持ちよかったのぉ?」
「あぅ……きもちいいぃぃ……」
ドクドクと溢れ出した精液が、花びらの表面に吸い取られていくのが分かる。
そればかりではなく――僕の全身をずっぽりと包み込んでいる花びらまでが、ちゅうちゅうと何かを吸い取り始めたようだ。
まるで巨大なヒルに全身を包み込まれ、じわりじわりと体液を吸い取られているような――そんな感覚。
その生理的嫌悪感とは裏腹に、驚くほどの快感と安らぎを伴っていた。
「ふぁぁ……き、きもちいいよぉ……」
しかし全身からじわじわと吸い取られているのは、体液などではない。
もっと大切な何か。まるで、生命そのもののような――
それがじっくりと妖花に啜り出されているというのに、とろけそうなほど心地よい。
ちゅぅっ……ちゅるるるるるる……
ぐちゅっ、じゅるり……。じゅるるるるるる……ぬちゅ。
「はぅ……これ、なに……? なにされてるの……?」
「ふふ……精気が吸い出されているのが分かるでしょう。
それは、ボウヤの命の素。それを吸い出されているのに気持ちよくなっちゃうなんて……いけないボウヤね」
アルラウネは目を細め、くすくすと笑う。
「あ、あうぅぅぅぅ……」
本来なら、怖がらなければいけないはずなのに。
逃げ出さなければいけないはずなのに――僕は陶酔に浸り、この花に身を委ねきっていた。
そんな僕にご褒美をくれるかのように、妖花は身体の隅々までぬるぬるの花びらで愛撫してくれるのだ――
じわりじわりと、「精気」という生命エネルギーを搾り取りながら。
それが尽きてしまった時、僕という存在は――
「あ、あぅぅぅぅぅ……」
それでも、抗う気持ちが全く起きない――それどころか、身体から力がどんどん抜けていく。
ペニスには花びらが幾重にも絡み付き、じゅるじゅると咀嚼されているかのようだ。
揉みたてられるような、舐め回されるような刺激は、人智を超えた人外の快楽。
それに抗うこともできず、僕は連続で射精させられる。
「ふふっ……私、かわいらしいオチンチンが大好きなの。
ボウヤのオチンチンもたっぷりいたぶってあげるから、精液を漏らし尽くしなさい」
「ふぁ、あぁぁぁぁぁぁ……」
執拗に股間へと与えられるじゅるじゅるの刺激に、どくっ、どくっと精液は漏れ続ける。
男性器に浴びせられる強制快楽で、精液を吸い出されていくかのようだ。
「あぅぅぅ……」
そして全身をくるんでいる花びらもじゅるじゅると蠕動し、僕の身体から精気を吸い出していく。
どんどん力が抜け、意識が薄れていくのに――それなのに、とっても幸せな気分だ。
逃げ出さないといけないのに、このままだと死んでしまうのに――
ぬちゅり、ぬちゅぬちゅぬちゅ……
じゅるり、ぐちゅ……じゅるるるるるるり………
「ああぁぁ、きもちいいよぉ……」
「ふふ……最高の快感の中で果ててしまいなさい。そのままボウヤは逝ってしまうの」
アルラウネの嗜虐的な視線にさらされながら、花のベッドで精を搾られ続ける――
にゅるにゅると蠢く花びらに覆い包まれ、その快感に僕は溺れるのみだった。
とろけそうな刺激に精液が漏れ続け、甘い陶酔が脳内を支配していく――
もう、何も考えられなくなってしまう――
じゅるじゅるじゅる……ぬちゅっ……
ぐにゅぐにゅ、ぐちゅぐちゅぐちゅ………
「みじめねぇ、ボウヤ。肉欲に溺れ、淫魔の餌食にされるなんて……」
くすくすと笑うアルラウネの言葉も、天使の甘い囁きに聞こえる。
精液は絶えずドクドクと漏れ続け、じっくりと生命力が吸い出されているかのようだ。
意識には甘いモヤが広がり、身体には完全に力が入らなくなってしまった。
もはや、自分の意志では指一本も動かせないほどに――
ぐっちゅ、ぐっちゅ……ぐちゅぐちゅ……
ねちゅねちゅ、にゅるる……
「ボウヤの精気を啜り尽くした後……残った肉体も、溶かして食べてあげるわ。
嬉しいでしょう……ボウヤの精も肉も、全て私のエサにしてもらえるのよ」
「あぁぁ……」
この快感の中で、生命エネルギーを吸い尽くされる――それは、とても幸せなことのように思える。
全身を花びらでしゃぶられ、じっくりと精気を吸われ、味わってもらい……そして、果ててしまうのだ。
美しいアルラウネの糧にしてもらえる……これ以上の喜びがこの世にあるのだろうか。
じゅるり、じゅるじゅる……じゅるるるっ。
ぐちゅぐちゅ、ぐちゅ……ぐちゅっ、にゅるるるるっ。
「そのまま……あま~い、あま~い夢の中で果てなさい。
ボウヤの精気は、この私が最後の一滴まで味わってあげるから……」
全身を包む卑猥な音と、溶かされるように薄甘い快感。
甘いモヤの中に、僕の意識が段々と消えていく。
びゅるびゅると精液が漏れ、じっくりと吸い出される。
生命の素が身体の外に流れ出し、じわじわ啜り尽くされていく――
じゅくっ……ぐちゅぐちゅっ。
にゅるるるるり……じゅるっ……じゅるるるるっ……
にゅぐにゅぐ、じゅるるるるり……
ぐちゅっ……じゅるるるるっ……ぬちゅぬちゅ……ぐちゅっ……
ぬちゅっ、じゅるじゅるじゅる……ぬちゅっ……
じゅるり、じゅるるる……ぐちゅっ、ぐちゅぐちゅ……
ぐちゅ、じゅるるっ……
そして僕は――精を啜る花びらのベッドの中で身体を弛緩させ、精気を搾り尽くされてしまった。
幸せな陶酔感に浸りながら、アルラウネの糧となって果ててしまったのである。
安らぎに満ちた、妖花のベッドに横たわりながら――
「ふふ……美味しかったわ、ボウヤ」
今がいつか、ここがどこかも分からない。
ただ、その香りに誘われるままに――
……とても甘く芳しい匂い。
……そして、どこかいやらしい匂い。
頭がぼんやりする。
物事がはっきり考えられない。
そして気がついた時には、森のかなり奥深くまで来てしまったようだ。
「どこだ、ここ……」
僕は夢うつつのように呟いた。
匂いは、森のさらに奥の方からだ。
「こんな広い森、危ないよな。早く戻らないと……」
森の奥へ、さらに奥へ……
「さあ、こんなとこウロついてないでさっさと帰ろう……」
そう言いながらも、僕はこの匂いの元を探してふらふらと進んでいった。
「ふふ……いらっしゃい、ボウヤ」
いつの間にか、目の前にはハダカの美しい女性がいた。
森の中に立つ、綺麗な女性――その髪は緑色で、下半身は毒々しいピンク色の花びらに覆われている。
一目見て、人間ではないと分かる女性――それを前にしても、なぜだか僕は心が乱れなかった。
それどころか、彼女のものになってしまいたいとしか思えないのだ――
「私はアルラウネ。人の精を糧にする花の淫魔よ……」
彼女は、さらりと美しい髪をかき上げる。
ふわっ……と、甘い匂いがさらに濃くなった。
まるで、周囲がピンク色に見えるほどに。
「あ、あう……」
「ボウヤの精も吸い尽くしてあげる。気持ちい~い、お花のベッドの中でね……」
アルラウネが、足元に軽く息を吐き掛ける。
すると魔法のように、彼女の足元へとみるみる花畑が広がっていた。
うち一房の花がむくむくと膨らみ、人間サイズの大きさとなり――巨大なバラの花が現われる。
そのピンク色の花びらはつぼみのようにすぼまり、まるで寝袋のようになっているみたいだ。
人間の身体全体を、すっぽりと包んでしまえるような大きさである。
「そのお花の中に入りなさい、ボウヤ。とっても素敵な気持ちになれるわよ……」
「は、はい……」
僕はアルラウネに促されるまま、花のベッドへと歩み寄った。
花びらはまるで、幾重にも重なった肉厚の布団のよう。その中には、ヌルヌルの蜜が満ちているらしい。
「あ、あぅぅ……」
服を脱いで全裸になり、その花の中に足を入れ、ゆっくりと中に身体をねじ込み……
僕は夢うつつの気分のまま、言われるがままに花びらのベッドに身を委ねてしまった。
……じゅるじゅるじゅる。
「あぅ……」
僕は首まで花に埋まってしまい、柔らかく温かい花びらが全身を包み込んでくる。
やはり中はヌルヌルで、驚くほど気持ちがいい。
その中は温もりと安らぎに満ち、蜜でねっとりとネバついた甘い空間。
女性の子宮内は、こんな心地なのだろうか――思わず、そんな事を考えてしまった。
こうして恍惚に浸る僕に投げ掛けられたのは、アルラウネの酷薄な言葉だったのである。
「あははっ……なんてお馬鹿なボウヤ。自分からその中に入ってしまうなんて」
アルラウネの顔は、いつしか淫靡で嗜虐的なものに変っていた。
獲物を捕えた捕食者そのものの、優越感と征服感に満ちた冷笑。
「その妖花は、包んでしまった男の精気を搾り取るためのもの。
ボウヤも、命尽きるまで精を吸い尽くされてしまうのよ……うふふ」
「え……? あ、あぁぁぁぁぁ……!」
くにゅくにゅくにゅ……!
ぐっちゅぐっちゅぐっちゅ……!
ぬちゅ、ぬちゅぬちゅ……ぬちゅり……
まるで巨大な口に咀嚼されるように、僕の身体を包み込んでいる花びらが蠢き始めた。
花という大きな器官に全身を咥え込まれ、舐めしゃぶられているかのようだ――
「ふぁぁ……気持ちいい……」
全身に与えられる粘着質の快感に、股間がみるみる熱くなっていく。
すると大きくなったペニスにも、ぬめった花びらがまとわりついてきた。
ぬちゅぬちゅと音を立て、とろけそうな快感が股間を責め嫐ってきたのだ。
「あ、あぁぁぁぁぁぁぁ……!」
「気持ちいいでしょう? そのまま情けな~くおもらしして、精液を吸ってもらいなさい……」
「あ、あぅぅぅ……こんな……す、すごい……」
ぐちゅ、ぐちゅぐちゅぐちゅる……
ぬちゅぬちゅぬちゅ……ぬちゃぁ……
「あうっ……!」
まるで溶かされているかのような、ねっとりと粘り着く肉の感触。
膣肉のような花びらにペニスを包み込まれ、うねるような刺激にさらされ――僕はひとたまりもなく精を放ってしまった。
全くこらえる余裕もなく、簡単に射精させられてしまったのである。
「あはははは! もう出しちゃった! そんなに気持ちよかったのぉ?」
「あぅ……きもちいいぃぃ……」
ドクドクと溢れ出した精液が、花びらの表面に吸い取られていくのが分かる。
そればかりではなく――僕の全身をずっぽりと包み込んでいる花びらまでが、ちゅうちゅうと何かを吸い取り始めたようだ。
まるで巨大なヒルに全身を包み込まれ、じわりじわりと体液を吸い取られているような――そんな感覚。
その生理的嫌悪感とは裏腹に、驚くほどの快感と安らぎを伴っていた。
「ふぁぁ……き、きもちいいよぉ……」
しかし全身からじわじわと吸い取られているのは、体液などではない。
もっと大切な何か。まるで、生命そのもののような――
それがじっくりと妖花に啜り出されているというのに、とろけそうなほど心地よい。
ちゅぅっ……ちゅるるるるるる……
ぐちゅっ、じゅるり……。じゅるるるるるる……ぬちゅ。
「はぅ……これ、なに……? なにされてるの……?」
「ふふ……精気が吸い出されているのが分かるでしょう。
それは、ボウヤの命の素。それを吸い出されているのに気持ちよくなっちゃうなんて……いけないボウヤね」
アルラウネは目を細め、くすくすと笑う。
「あ、あうぅぅぅぅ……」
本来なら、怖がらなければいけないはずなのに。
逃げ出さなければいけないはずなのに――僕は陶酔に浸り、この花に身を委ねきっていた。
そんな僕にご褒美をくれるかのように、妖花は身体の隅々までぬるぬるの花びらで愛撫してくれるのだ――
じわりじわりと、「精気」という生命エネルギーを搾り取りながら。
それが尽きてしまった時、僕という存在は――
「あ、あぅぅぅぅぅ……」
それでも、抗う気持ちが全く起きない――それどころか、身体から力がどんどん抜けていく。
ペニスには花びらが幾重にも絡み付き、じゅるじゅると咀嚼されているかのようだ。
揉みたてられるような、舐め回されるような刺激は、人智を超えた人外の快楽。
それに抗うこともできず、僕は連続で射精させられる。
「ふふっ……私、かわいらしいオチンチンが大好きなの。
ボウヤのオチンチンもたっぷりいたぶってあげるから、精液を漏らし尽くしなさい」
「ふぁ、あぁぁぁぁぁぁ……」
執拗に股間へと与えられるじゅるじゅるの刺激に、どくっ、どくっと精液は漏れ続ける。
男性器に浴びせられる強制快楽で、精液を吸い出されていくかのようだ。
「あぅぅぅ……」
そして全身をくるんでいる花びらもじゅるじゅると蠕動し、僕の身体から精気を吸い出していく。
どんどん力が抜け、意識が薄れていくのに――それなのに、とっても幸せな気分だ。
逃げ出さないといけないのに、このままだと死んでしまうのに――
ぬちゅり、ぬちゅぬちゅぬちゅ……
じゅるり、ぐちゅ……じゅるるるるるるり………
「ああぁぁ、きもちいいよぉ……」
「ふふ……最高の快感の中で果ててしまいなさい。そのままボウヤは逝ってしまうの」
アルラウネの嗜虐的な視線にさらされながら、花のベッドで精を搾られ続ける――
にゅるにゅると蠢く花びらに覆い包まれ、その快感に僕は溺れるのみだった。
とろけそうな刺激に精液が漏れ続け、甘い陶酔が脳内を支配していく――
もう、何も考えられなくなってしまう――
じゅるじゅるじゅる……ぬちゅっ……
ぐにゅぐにゅ、ぐちゅぐちゅぐちゅ………
「みじめねぇ、ボウヤ。肉欲に溺れ、淫魔の餌食にされるなんて……」
くすくすと笑うアルラウネの言葉も、天使の甘い囁きに聞こえる。
精液は絶えずドクドクと漏れ続け、じっくりと生命力が吸い出されているかのようだ。
意識には甘いモヤが広がり、身体には完全に力が入らなくなってしまった。
もはや、自分の意志では指一本も動かせないほどに――
ぐっちゅ、ぐっちゅ……ぐちゅぐちゅ……
ねちゅねちゅ、にゅるる……
「ボウヤの精気を啜り尽くした後……残った肉体も、溶かして食べてあげるわ。
嬉しいでしょう……ボウヤの精も肉も、全て私のエサにしてもらえるのよ」
「あぁぁ……」
この快感の中で、生命エネルギーを吸い尽くされる――それは、とても幸せなことのように思える。
全身を花びらでしゃぶられ、じっくりと精気を吸われ、味わってもらい……そして、果ててしまうのだ。
美しいアルラウネの糧にしてもらえる……これ以上の喜びがこの世にあるのだろうか。
じゅるり、じゅるじゅる……じゅるるるっ。
ぐちゅぐちゅ、ぐちゅ……ぐちゅっ、にゅるるるるっ。
「そのまま……あま~い、あま~い夢の中で果てなさい。
ボウヤの精気は、この私が最後の一滴まで味わってあげるから……」
全身を包む卑猥な音と、溶かされるように薄甘い快感。
甘いモヤの中に、僕の意識が段々と消えていく。
びゅるびゅると精液が漏れ、じっくりと吸い出される。
生命の素が身体の外に流れ出し、じわじわ啜り尽くされていく――
じゅくっ……ぐちゅぐちゅっ。
にゅるるるるり……じゅるっ……じゅるるるるっ……
にゅぐにゅぐ、じゅるるるるり……
ぐちゅっ……じゅるるるるっ……ぬちゅぬちゅ……ぐちゅっ……
ぬちゅっ、じゅるじゅるじゅる……ぬちゅっ……
じゅるり、じゅるるる……ぐちゅっ、ぐちゅぐちゅ……
ぐちゅ、じゅるるっ……
そして僕は――精を啜る花びらのベッドの中で身体を弛緩させ、精気を搾り尽くされてしまった。
幸せな陶酔感に浸りながら、アルラウネの糧となって果ててしまったのである。
安らぎに満ちた、妖花のベッドに横たわりながら――
「ふふ……美味しかったわ、ボウヤ」
