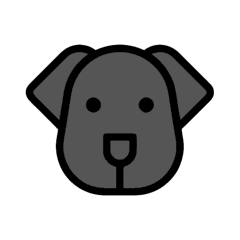魅惑の皇后 第五章
添加标签
王国執務室。
王国最高レベルの政策決定機関にして、国家の命運を握る場所である。
華やかな王宮のイメージに反し、ここはとてつもなく質素なつくりをしていた。
窓際をそむけるように、重厚な執務机が不愛想に鎮座する。
室内の壁側は書籍棚が立ち並び、埋め尽くされた書類が天井まで届く。
床を覆う絨毯は当初あった鮮やかさを失い、鈍い紅色が部屋に暖かさを添える。
それ以外、部屋には余計な物は一切置かれていない。
政務をほとんど顧みることが無かった先王時代では、この部屋は長きにわたって埃をかぶっていた。
それが今のあるじを迎えてからは、一転して毎日のようにインクの香りが満ち溢れる。
その少年は今、机の前に座っていた。
昼過ぎの陽光が窓越しに、彼の美しい金髪に降り注ぐ。
女の子と見間違われるほど秀麗な顔立ち。
それは国民に絶大な人気を誇る、先代王妃とよく似ていた。
羽ペンを握る手肌は、透き通るように白い。
机の横長さと比較すると、細身の体つきはより一層華奢に見える。
顔の造形にまだ幼さが残るものの、その一挙一動から君主の風格が溢れ出る。
少年の名はシャロス、王国の次期継承者である。
まだ若いながらも、その明哲さはすでに地方都市の巷まで噂となっていた。
特に執務室に運ばれる大量の書類を、毎日淡々と処理していく様は、廷臣の間で語り草になるほどだ。
そんな執務机の一角に、今日も国内各地から上奏文が寄せられていた。
シャロスの身長よりも高く積まれただろう書類の山。
いつもなら、朝見の後にすぐ処理できる量である。
しかし今日は一向に減る気配が無かった。
部屋にはいつもと違い、一つ余分な存在が混ざっているからだ。
公文書の山の横に、一人の侍女が腰を掛けていた。
国の最高権力者を目の前にして、少女は遠慮のかけらも無く両腕を背後に突き立て、気楽そうにシャロスのことを見つめていた。
クリっとした瞳が印象の、活発そうな女の子。
床から浮いた両脚は、リズムに乗って小さく揺れる。
短めのスカートからはみ出る太ももは、黒のガーターベルトに包まれ、女性的な色香を醸し出す。
侍女服に覆われた体つきは、年相応の健康的なものに思える。
だが実際の裸体は遥かに魅力的であることを、シャロスは十分すぎるほど知っていた。
彼女はシャロスをじっと見つめる。
シャロスは書類をじっと見つめる。
少女の太ももがシャロスの視界にかすれる度に、彼の集中力も一緒に揺らしていく。
やがて同じ行間を三度目に読み間違えた時、シャロスはとうとう我慢できなくなった。
「おい、マナ。なぜまだここにいる」
「ん、なぜって?」
まるで心外と言わんばかりに、マナと呼ばれた少女は訝しそうだった。
「私は王子様にお食事を持って参りましたのよ」
「頼んだ覚えはない。さっさと帰れ」
「リテイア様からは、王子様が食べるところまで見届けろ、って仰せつかったのに」
シャロスはあくまでも不機嫌な表情を崩さず、マナを冷たく見つめた。
溌剌としたメイドの少女。
わがままな悪戯をしてきたかと思えば、次の瞬間は飼い猫のように甘えてくる。
シャロスに対しても、彼女はまるで恐れず、不遜な態度で接し続ける。
普段まわりの唯々諾々に慣れたシャロスにとって、そんな彼女は刺激に満ちた異性であった。
マナはそばにある食器トレイに手を伸ばすと、カップを口元に近づき、蜂蜜のスープを一口すすってみせた。
「あ~あ、せっかくアツアツのうちに運んできたのに。毎日いそしむ王子様のため、皇后様が自ら調理されたものですよ? こんな幸せを味わえるのは、国中を探してもシャロス王子しかいないわ」
皇后のものだからこそ、口にしないのだ。
白々しい気持ちを抑えて、シャロスは更に口調を強めた。
「そんな気遣いはご無用だと皇后陛下に伝えてくれ。私は執務室にいる時、食べ物を一切口にしない習慣だ」
「困ります。それでは私が怒られてしまいます」
まったく困ってない表情でそう言いながら、マナは焼きリンゴの細切りにフォークを突き刺した。
それを口に運ぶと、うーんと満悦そうに鼻を鳴らす。
「おいしい! リテイア様の料理はやはり最高だわ。これが毎日食べられるなら、マナも王子様の身辺で働きたいな」
「そんなことしていいのか? 皇后陛下が知ったら、お怒りになるぞ」
「毒見ですよ、ど・く・み。シャロス様のことですから、どうせ『これに皇后陛下が何か毒を入れているに違いない~』とか思ってるでしょ」
図星だった。
シャロスはマナの得意顔から背け、トレイに乗せられた焼きリンゴと蜂蜜スープの皿を見つめた。
人生の中で、食べる行為を楽しんだ記憶は一度も無い。
食事に困る身分ではなかったし、何より日々身を置かれた権力闘争の中、それを楽しむ心情など持ち合わせていなかった。
しかし、先日皇后リテイアが用意した物を口にしてから、食事に対する感覚が一変した。
その絶妙な味付けは一度味わえば、病みつきになるほどの美味だった。
シャロスは毒物に疎いが、命を奪うほどの毒でないことくらいは知っていた。
それどころか、皇后の食事を口にすると、全身に力がみなぎって、何もかも忘れてしまうような気持ち良さがわいてくる。
毒の知識なら近衛隊長のレイラが詳しそうだが、シャロスには彼女に相談できない事情がある。
ここ最近皇后との間に発生した関係は、レイラに全て内密にしているからだ。
日が経つにつれ、秘密がどんどん増えていき、気が付けば打ち明けようにもできなくなってしまった。
机の上を座るマナの姿は、まるで無防備だった。
スカートから伸び出る太ももを見ると、ついその奥にある黒艶の下着を想像してしまう。
彼女の息遣いをこんなにも近く感じるのは、倉庫で肌を合わせたあの時以来だ。
こうして近くにいるだけで、彼女の体から漂う甘い香りを思い出してしまう。
今すぐマナを抱きしめたい。
彼女の胸に顔を埋めて、彼女の唇にキスしたい。
そして、体内の溜まりに溜まった劣情をぶつけたい。
それなのに、当のマナはあれ以来、シャロスを意識する素振りをまったく見せないのだ。
まるで自分だけが一方的に気を掛けているようで、なんとも面白くない。
その気持ちが表に出ないよう気を付けながら、シャロスは一度深呼吸して自分を落ち着かせる。
「じゃあ、どうしたらここを出てくれる」
「そうね。王子様がこれをちゃんと召し上がってくれたら、私も皇后陛下にご報告に行けるわ」
そう言って、マナはフォークでもう一切れ突き刺し、それを差し出した。
こんがりと狐色に焼かれた果物。
精製したバターと砂糖に浸された甘ったるい香りが、シャロスに向かって漂ってくる。
見た目から想像できるまろやかな味に、口の中が唾液でいっぱいになる。
「ね、おいしそうでしょう? 残していたら、もったいないですよ」
「分かった分かった。それを食べたら、退いてくれるだろうね」
「やった。では王子様、口をあけて『あーん』して下さい」
マナが嬉しそうに言いながら、手本を示すように口を開けてみせた。
(くっ、今まで無視してきた仕返しか)
拒否しても、このまま引き下がる感じでは無かった。
シャロスは顔を少し赤らめ、やがて口をぎこちなく広げた。
伸びてきたフォークの先に、噛みつこうとしたその瞬間。
マナは不意に腕を引っ込め、リンゴのかけらを自らの口の中に放り込んだ。
シャロスは茫然とした。
悠々とかみこなすマナの姿を見て、ようやく自分がからかわれたことに気付く。
「お前、なにを……!」
怒りのセリフを言おうとしたその時。
マナは突然シャロスの顔を掴み、口と口を重ね合わせた。
一瞬にして、シャロスの思考が停止した。
ついさっきまでマナが咀嚼していたものが口腔を通り、自分の喉へと流し込まれる。
小さく噛み砕かれた果物、香ばしい果汁、そこに混ざり合うマナの唾液。
それらを目の前の美少女が口に含んでいたと思うと、言いようの無い妖しい感情が脳を痺れさせる。
全てのものを口移した後、マナは唾液の銀糸を伸ばしながら離れた。
そしてそのまま、シャロスの耳元で小声で囁く。
「はい、そのまま口を閉じて、モグモグさせましょうね。ちゃんと味わうように、慌てず飲み込むのよ」
まるであやされたよう赤ん坊のような、気持ち良い心地だった。
シャロスはぼんやりとしたまま、言われた通り口内の果実を続けて噛み砕いた。
甘さの中に含まれるマナの唾液。
それを意識しただけで、いやらしい気持ちが胸中に広がる。
ねっとりとした果汁が喉を通る時、まるで体の隅々までにマナの味が滲み込んだようだ。
「はい、いい子いい子。とてもよくできましたわ」
マナに頭を優しく撫でられると、シャロスは気持ち良さとともに、どうしようもない被虐的な気持ちが芽生えた。
子供扱いされているのに、なぜかシャロスはマナを振り払うことができなかった。
「そんないい子の王子様に、特別ご褒美をあげるわ」
マナはシャロスの正面に腰を移動させ、小悪魔な笑みを浮かべる。
その笑顔だ。
双子の妹が決して見せない、妖艶かつ悪意に満ちた笑み。
彼女がそれを浮かべた時、決まって悪さを披露してくれる。
だがその悪戯っぽい笑顔で見つめられていると、シャロスはなぜかゾクゾクしてしまう。
「今度は、私の下の口で食べさせてあげるね」
マナは両目を細めて、両手をスカートの下に伸ばした。
シャロスの心臓の鼓動が一気に早まる。
彼女は慣れた手つきで下着を脱がし、見せびらかすように両脚から布切れを通す。
女性の最も魅惑的な部位がシャロスの目の前に晒される。
それを目のあたりにした途端、シャロスの脳内に快楽の記憶が強烈に蘇る。
その表情の変化をあざわらうように、マナは蜂蜜を盛った容器を持ち上げた。
そしてシャロスが凝視している前で服の裾をたくし上げ、上から蜜液を垂らした。
美しい琥珀色の液体が、つーと少女の下腹部に零れ落ち、閉じ合わせた太ももの間に、黄金色の水溜まりを作る。
ごくり、と喉を鳴らすシャロス。
息がどんどん荒くなっていく。
半透明の液体を透けて見える秘所は、その淫らさを一段と強調する。
「ねぇ、王子様」
少女は声のトーンを落として、誘惑するように生暖かい息を吐く。
その心地よさ、シャロスはまるで催眠されたような快感を覚える。
「私のここ、舐めてみたくないですか? 舌を出して、ぺろっと」
マナは舌を舐めずり、挑発的な視線をシャロスに送った。
ドクン、ドクン。
シャロスの心の鼓動が早まる。
トロリとした黄金の粘液。
そこに舌を這わせたい衝動が、彼の常人よりも強いはずの精神を蝕む。
だが王族たる者が下人の股間に頭をうずめるなど、想像するだけでも屈辱極まりない行為だ。
ましてや、敵の一派である人間に屈するなど。
「ねえ王子様、なにを迷ってるの。きっと、すごーく甘い味がしますわよ」
少女のささやき声が敵愾心を薄める。
なんとかそれに支配されないようこらえるシャロス。
しかし、マナの言葉が心の防壁を一枚ずつ剥がし、その奥にある欲望をさらけ出す。
「お願い、王子様。抵抗はしちゃだめよ? 身分とかプライドとか、そんなくだらないことは全部忘れちゃいましょう。今の王子様が思い出していいのは、あの日私と王子様がエッチしたことだけ」
ねめつけるような目つきがシャロスを絡める。
彼女のねっとりとした吐息に触れただけで、シャロスはビクッと背筋を震わせる。
いつの間にか、マナの言葉は命令となっていた。
だがその命令に抵抗するだけの意思を力、シャロスは持っていなかった。
「でも、私はこの国の王子で……」
「言ったでしょ? 今だけ、そのことを忘れなさいって。今のあなたは、女の裸を見ただけで発情してしまう、最低なオスなの。私に夢中で、好きで好きでたまらない、下賤な男の子なの」
「うっ……」
「さあ、素直になって。今のシャロス様は、何よりも私のあそこを舐めたい。そうでしょ?」
マナが下半身を前に突き出すと、一段と濃い芳香がシャロスの鼻腔をくすぐる。
その香りに誘われるがまま、シャロスは虚ろな目つきでマナの秘部に近付く。
そしてついに、神秘な水溜まりに舌先を入れてしまった。
とろけるような甘い液体が喉元を通り、全身の温度が急上昇する。
その甘汁がまるで少女の秘所から溢れているかのようだ。
ぴちゃ、ぴちゃと水音を立たせるシャロス。
そんな一心不乱に舐める姿を見て、マナは得意げに笑った。
「ふふっ、ペロペロしちゃって。かわいい子犬みたい」
マナはそう言いながら、シャロスの頭を撫で始めた。
その行為に、彼の体が小さく震える。
「ねぇ、王子様。どんな味なのか、私にも教えてくれる?」
「甘くて、いい香り……マナの匂いと同じ……」
少しためらったが、結局ボソリと語るシャロス。
言葉を口にしてから、彼は後悔と恥ずかしさのために顔を俯けた。
その仕草を見たマナは、ますますおかしそうに笑う。
「まあ、本当にかわいいんだから」
頭を撫でる手つきの優しさに、シャロスはまるます頬を紅潮させる。
心拍数がどんどん上昇して、何も考えられなくなる。
液体をすすっていればいるほど、全身がのぼせたように熱くなり、気力が抜けてしまう。
頭の中はマナのことでいっぱいになる。
その液体の中に何が入っているかなど、もはや気にすることも無くなった。
蜜の液をすべて飲み干した後、そこには粘液にまみれた秘所が外気に触れた。
「まあ、命令に忠実な子犬だこと。ご褒美に、マナの大事なところ、もっとちゃんと見せてあげるよ」
マナはスカートの裾を掴み上げたまま、机の上で両足を広げた。
シャロスの目の前に、オスの性欲を最も滾らせる景色が完璧に現れる。
日差しを照り返す黄金色の光沢。
その蜜の液体は重力に引きつられて、少女の割れ目に集まり、一滴、また一滴と床へと垂れ落ちる。
少女という外見から、とても想像できないような淫靡な行為だった。
心臓をぐっとわし掴まれたように、シャロスは一瞬たりとも目が離せなかった。
花の蜜に誘惑された虫のごとく、彼はマナの股間に顔を近づける。
そして粘液に最も濡れた溝に、舌を這わせた。
そんな彼の姿を、マナは勝ち誇ったように見下ろす。
「それにしても無様ですね、シャロス様は。以前私のことを淫売だって罵りましたよね? それが今、こんなおいしそうに私のあそこを舐めるなんて。シャロス様には、プライドという物が無いのですか?」
「うぅ……」
シャロスはただ恥辱に震えるしかなかった。
皇后によって幾度もなく誇りを打ち砕かれて、自分でも気付かないうちに、被虐的な性癖が植え付けられていた。
それに加えて、マナ自身非常に魅力的な女の子だった。
明朗快活の中に潜む、危険な淫らさ。
その淫らさは、王族の気高さと相反するものである。
そして、オスの欲望を最も焚きつけるものでもあった。
この娼婦のような女に、自分が跪いて舌で奉仕している。
この放蕩な女に、自分が恋に似た感情を抱いている。
意識すればするほど、被虐的な気持ちが血に混ざり、下半身の一物に集まっていく。
そんなシャロスの異変に、悪魔のような娘は見逃すはずが無かった。
「あら、王子様。あそこをこんなに硬くさせちゃって、どうしたのかしら」
ふと、マナの右足のつま先がシャロスの股間に触れた。
シャロスが思わずうめき声を漏らすと、マナは意地悪そうに笑う。
「私のを舐めて、大きくなっちゃったの? ふふっ、恥ずかしいと思わないの?」
「それは……」
「でも心配しないで、シャロス様。男というのは、もともとそういう生き物なの。こうやって女の子にあそこを踏まれたら、誰しも喜んじゃう下等生物なのよ。王子様も男の子なんだから、例外じゃないわ」
「くっ……」
「ふふっ、このまま服の上から射精させてあげようかしら? きっと気持ちいいわよ。そしたら、メイド達の間でしっかりと噂を流してあげるわ。王子様は女の人にあそこを踏まれて、情けなく射精するのが大好きな人だって」
「そんな……! お願い、それだけは……っ」
シャロスが逃げるようにして、椅子へ寄りかかろうとした。
その時だった。
執務室の扉が、ゆっくりと三回ノックされた。
「近衛騎士隊長レイラ、ただいま戻りました」
優雅で落ち着いた女性の声が扉越しに響く。
だが今のシャロスにとって、その声は青天の霹靂に等しかった。
「レ、レイラ、ちょっと待っ……!」
慌てて顔を上げて、言葉を紡ごうとするシャロス。
だが続きの言葉を遮るように、マナがシャロスに口付けをする。
口移しの時とは違う、淫靡なディープキス。
シャロスの全身に快感と焦燥感が走る。
扉の外から声が続く。
「シャロス様、失礼いたします」
「むっ……!」
扉がゆっくりと開けられ、一人の女騎士が隙の無い足取りで入室する。
そして机の向こう側に座るシャロスを確認して、女騎士は安堵の表情を浮かべた。
「シャロス様、何かありました?」
「いいえ。予定より早く王都に戻ったね、レイラ」
「はっ。隠密調査は滞りなく終えることができました」
レイラと呼ばれた女騎士は、恭しく一礼をした。
身につけた軽鎧から、長旅を経た風の匂いが漂う。
急いで帰還したせいか、その美しい風貌にやや疲れが滲み出る。
だがシャロスの顔を見た途端、彼女の顔に明るい色が戻る。
女騎士レイラ。
王宮を護衛する精鋭部隊である近衛隊隊長にして、大陸でも有数の剣士である。
そしてシャロスの有力な腹心であり、母親の記憶が無い彼にとって、唯一心が許せる女性である。
「して、首尾はどうか」
シャロスはコホンと咳払いして、淡々とした表情で言った。
だがその裏で、心は天地がひっくり返るほど慌てていた。
レイラが頭を伏せている間、シャロスはチラッと机の下を見た。
そこに身を隠れるマナがてへッと舌を出して、シャロスに対しあっかんべを作った。
板に遮られているため、机の下の空間は反対側から見えない構造となっている。
レイラが入室するまで咄嗟の間に、シャロスがマナをそこへ押し込めたのだ。
そんなことも知らずに、レイラは報告を始める。
「ご明察の通りです。辺境地のウェルヘン伯が反乱を企てている件ですが、根も葉も無い嘘です。伯は善政を敷き、領民への増税をよしとせず、巡察使達が求めた賄賂を拒んできました。それ、今回の事件の起因になったようです」
「世襲貴族の蛆虫どもめ。今の地位に足りず、まだ毟り取ろうというのか」
いつまでも巡察院に居座る貴族達の顔を思い出し、シャロスは苦虫を噛み潰したような表情を浮かべる。
君主の代わりに民達の声を聴く役人と言えば聞こえはいいが、その実態は特権を駆使して地方官や民から搾取し、私腹を肥やしている悪人どもである。
国王直属の役職で、本来ならばシャロスが真っ先に掌握する勢力だった。
だが王宮の権力争いが続く中、巡察院を改革する余裕など無いに等しい。
「しかし、不審な点もあります。巡察使が最初に申し立てたのは、ウェルヘン伯の悪政でした。それがいつの間にか、無断に私兵をかき集め、反乱を準備しているという噂になっている」
「皇后派の工作だ」
シャロスが迷いもなく断言する。
「近頃、皇后一派は軍部にも勢力を伸ばそうとしている。王国軍は代々王家に忠誠を誓っている伝統があるため、付け入る隙はなかなか無いだろう。だがもし反乱のような事態が起きれば、軍備拡大の口実ができる」
「今の軍部が影響を及ぼさないところで新しい役職を作り、そこに勢力をねじり入れる……!」
「その通り。今はまだ噂レベルだが、いずれ王都でも広がり、議会で提起されるだろう。そこで私が王国軍の出動を拒絶すれば、それこそ皇后派の思いの壺だ」
「ウェルヘン伯は領民の間で深く支持されています。万が一不測な事態になれば、多くの領民が伯爵のために立ち上がるだろう」
「それでは本当の反乱になってしまう。レイラ、命令だ」
「はっ」
「巡察使が収賄した証拠を集め、身柄を拘束せよ。手段は任せる、多少強引な方法を使っても構わない」
「かしこまりました」
「公文班に勅令の起草を伝えよ。王の名のもと、讒言を晴らし、民心を安定させる。枢密院は通さず、ただちに王令として出せ」
「ははっ」
「ウェルヘン伯には褒美を与えよ。領主の役目をまっとうし、国境の地をよく守り続けた。そして領民を守るために高官の圧力にも負けず、王都にその実態をよく知らせたと。巡察使を拘束した暁に、手柄は全て彼のものとする」
レイラの目つきが鋭くなる。
そんな名目で褒美を取らせたら、巡察院の貴族達はウェルヘン伯のことを目の敵にするだろう。
それは今後ウェルヘン伯が王子派に接近し、頼り続けなくてはならないことを意味する。
「お前の隊の者なら、うまくやってくれるだろう」
「無論でございます。では、私はこれにて……」
レイラは一礼してから、シャロスに背を向けて退出した。
彼女にとって、シャロスは完璧な君主像である。
信念は固く、だが驕れることは無く。
民のことを思い、だが軟弱になることは無く。
権力の残酷さをよく知り、だが腐敗に染まること無く。
まだ少年でありながら、彼は歴代王者の中で最高の素質を見せている。
彼女にとって、シャロス以外の人物が王になるなど、考えられないことであった。
レイラの後ろ姿を見て、シャロスはほっと息をついた。
武術の達人だけあって、レイラの感覚は常人の域を超えている。
マナが大人しくしてくれたこともあって、この場はなんとかやり過ごせた。
(そういえばマナのやつ、さっきから何をしている)
シャロスは不思議になって、机の下をちらっと見た。
すると、あまりもの驚く光景に椅子から飛び上がりそうになった。
マナは一言も発さずに、なんとシャロスから下半身に着けていた服を剥き取ろうとしていた。
慌てて両手を伸ばして阻止するシャロス。
その些細な物音が、すでに出口まで歩んだレイラを振り返らせる。
「殿下、いかがなさいました?」
「あっ、いや……」
彼が怯んでいる隙に、マナが力をいっぱい込めて、シャロスの両手からズボンを引き下ろした。
太ももの肌が外気に触れる。
シャロスは出来る限り平然の顔を作り、椅子のせもたれに背中を付ける。
だがその背中には、速くも冷え汗にまみれた。
「こたびの調査、よくぞやった。君も、君の部下達も」
「もったいないお言葉です。殿下の微力になれれば……」
(ううんっ!)
シャロスの眉がビクンと跳ねた。
とある刺激のせいで、レイラの言葉を最後まで聞きとれなかった。
机の下に目をやると、丁度マナが下着をずらし、男性の象徴を取り出す瞬間を目撃する。
マナは彼の怒りに怖気づくところか、むしろ挑発するようにウィンクをしてみせ、手にした一物に息を吹きかける。
生暖かい風圧が裏筋に当たる。
たったそれだけの刺激で、一物がむくむくと膨らみ、やがて完全に勃起した。
さきほどまでマナから受けた快楽が蘇る。
体の火照りも、脳を包む夢心地も、全て元通りに復元されてしまった。
思いもよらない事実がシャロスに襲い掛かる。
自分は今、下半身を露出させている。
それも机を隔てて、レイラがいる目の前で。
全身の神経が緊迫する。
ゾクゾクするような倒錯的な快感。
抵抗できないことをいいことに、マナは舌をシャロスの一物に這わせ、巧みに唾を絡み合わせる。
シャロスを見つめるレイラの目つきは、徐々に疑念を抱き始める。
どんなことがあっても、レイラだけにはバレたくなかった。
「せっかくの週末だ。隊員達と一緒に、休暇を取ったら……どうだ」
シャロスは語尾のうわずりをなんとか気力で抑えた。
股間の一物に、何か生ぬるいものが覆いかぶさる。
チラッと見る。
ちょうどマナは亀頭から舌を離し、自分に向かってニコッとしたのが見えた。
そして彼女はそのまま、唇を一物の根元まで含ませる。
(んぐ……っ!)
思わず俯いて、ゆがめそうになる顔をレイラから隠す。
マナの柔らかい唇と舌が、竿全体を包み込む感覚が分かる。
耐え切れないほどの快感が背筋を伝って昇り、喉から声が出ようとしている。
机の下でマナが一物を吐き出し、悪戯っぽく微笑んだ。
だが今のシャロスには、彼女を責める余裕さえなかった。
背中に冷や汗が滝のように流れるのを感じる。
――レイラが気付きはじめている。
顔を伏せても、レイラの視線が段々と鋭くなっていくのを感じる。
天下に誇る王国軍において、とりわけ個人戦に特化した王宮近衛隊。
そしてシャロスに直属し、時には正規軍では実行できないような命令を執り行う精鋭集団。
その集団の隊長を、レイラが務めているのだ。
「シャロス様、どうかなされましたか」
レイラはいつもと変わらない、落ち着いた口調だった。
彼女は一度机の上に置かれた食事のトレイを見て、また何事も無かったように視線をシャロスに戻す。
だがシャロスには分かる。
レイラの意識は、すでに部屋の不自然さに集中しつつある。
執務室にいる時、シャロスは食べ物を口にしない。
その習慣は、もちろんレイラもよく知っている。
あと二十秒もしないうちに、彼女はこの部屋に第三者が来たことを推察するだろう。
その十秒後に、机の死角に誰かが隠れているじゃないかと勘づく。
五秒後に、シャロスはその人物によって脅迫されているではないかと疑い始める。
その直後に、彼女はきっと行動を起こす。
脅迫者に気付かれることなく、そして交渉の余地を一切与えずに、目の前にある数十キロもの机を蹴り上げて、不意を突かれた敵を掴み上げて生け捕りにするだろう。
長い間一緒にいるからこそ、シャロスはレイラの行動力をよく知っていた。
そして恐ろしいことに、彼女には一連の行動を完遂するだけの能力が備わっている。
レイラを止めるには、最初の二十秒内の時点でその考えを中止させなければならない。
だがどうすればいいのか、まったく思いつかないのだ。
レイラとは信頼し合うことがあっても、騙すことは今まで一度もなかった。
緊迫した状況にも関わらず、マナは自重するどころか口で深く咥えながら、頭の上下運動をますます加速させる。
快感と緊張が壮絶にねじり、シャロスの神経をピンと張らせる。
「そう言えばレイラ、ここしばらく剣技の稽古をまったくしていなかった」
「むっ」
絶体絶命の状況を切り抜けるために、シャロスは言葉を口走る。
今にも歩み出そうなレイラだったが、その言葉を聞いた途端、不機嫌そうに立ち止まる。
「殿下。お言葉ですが、武芸の稽古は登山と一緒です。一日でも道中を休んだら、次も、そのまた次も休もうと思ってしまいます。その遅れを取り戻すため、大変な思いをしなければなりません」
「ああ、だから今すぐお前と一緒に練習したい」
「えっ?」
「でもお前が帰還したばかりで、疲れているというのなら仕方は無いが……」
「いいえ、とんでもありません! すぐに準備にかかります。訓練場でお待ちしております!」
さきほどまでの態度はどこへやら、レイラはまるで誕生日プレゼントを手渡しされた子供のように両目を輝かせて、いそいそと部屋から出た。
自分と一緒に武芸の稽古をする。
それがレイラがどんな不機嫌な時でも、彼女の機嫌を直す魔法の呪文だった。
彼の予想通り、レイラの顔つきは美しい花のように綻びる。
足音が遠ざかっていくのをしっかり聞いてから、今度こそシャロスは緊張の糸が切れてぐったりとした。
「きゃはは。王子様ってば、演技がお上手なんですね」
「貴様……!」
「きゃっ」
シャロスは机の下から現れたマナを、いきなり机に向かって押し倒した。
「誰のせいで、こんな目にあってると思ってるんだ!」
「あはん、殿下が怒った」
「ふざけるな! どこまでも人を馬鹿にして!」
「いやん、王子様……」
シャロスがマナのメイド服を乱暴に脱がすと、少女は小さく悲鳴を上げた。
はだけた上着から、汗ばんだ肌色が見え隠れる。
黒いブラジャーの縁に薔薇模様が散らばり、胸部の勾配を悩ましく描き出す。
シャロスはマナの両腕を抑えつけながら、荒々しく呼吸を繰り返した。
マナの体が、以前にも増して煽情的に思えた。
可愛らしい頬は赤く染まり、小さく開いた唇から、胸の起伏に合わせて吐息が漏れ出る。
時折シャロスを振りほどこうとするも、両腕をがっしり掴まえられたため身動きがまったく取れない。
その小動物のようなささやかな抵抗がまた、男の獣欲を掻き立てる。
シャロスの灼熱のまなざしに耐えられないのか、マナは顔を横に向けた。
その無防備な態度に、シャロスの全身の欲望が爆発しそうになる。
マナの白いうなじに口付けしたい。
彼女が着ている服をバラバラに切り裂き、その濡れそぼった秘所を乱暴に犯したい。
口に無理やり一物をねじり込んで口淫させたい。
生意気な表情を快楽と苦悶に染めてあげたい。
だが黒い欲望が溢れ出る前に、シャロスはとある笑顔を思い出す。
部屋を出た時に見せた、レイラの屈託の無い笑顔。
自分が苦しいと思った時に、何度も助けられてきた顔。
「あれれ?」
マナは両目を大きく見開き、不思議そうな声をあげた。
シャロスは黙ったまま立ち上がり、服を着始めたのだ。
「この前みたいに、気持ちいいことをして下さらないですか?」
「人を見くびるのも、いい加減にしろ!」
「まあ。ここまで来て、止めちゃうんですか?」
「これだけは覚えておけ。男だからといって、誰もがお前の思い通りになると思ったら、大間違いだよ!」
シャロスは袖口を整えると、机に横たわるマナに目も触れず部屋を出た。
「ふふっ、面白かったですわ。ますます堕としたくなってきたじゃない」
残されたマナはおかしそうに呟いた。
彼女は息があがったように立ち上がり、机に腰を寄せた。
乱れた服装の下で、汗に濡れた肌はなおも紅潮し続ける。
マナは机の上に残された蜂蜜スープの容器を手に取った。
容器の底に、黄金色の残液が綺麗にきらめく。
「さすがリテイア様の媚液。少ししか飲んでいないのに、私でもこんなに効き目が現れるなんて」
カップを握る手は小さく震えた。
息詰まるような心臓の鼓動、欲求への渇望と焦燥感。
常人なら耐えられず発情する状況を、マナはまるで楽しんでいた。
「まったく驚かされるわ。邪魔が入ったとはいえ、王子様はあそこまで意志が固いとは。これも全て、あのレイラとかいう女のせいかしら」
シャロス王子とは同じように、マナもまたレイラがこんなにも速く秘密任務から戻ることを知らなかった。
カップの中に残された蜜液を指ですうと、マナは舌先で色っぽく舐めとる。
「でも、その一番大切にしてきた女を、これから王子様は自ら裏切るんですから」
体を燃やし尽くすような渇望に身を焦がされながら、マナは執務室の窓際から、シャロスの去り姿を見つめ続けた。
王国最高レベルの政策決定機関にして、国家の命運を握る場所である。
華やかな王宮のイメージに反し、ここはとてつもなく質素なつくりをしていた。
窓際をそむけるように、重厚な執務机が不愛想に鎮座する。
室内の壁側は書籍棚が立ち並び、埋め尽くされた書類が天井まで届く。
床を覆う絨毯は当初あった鮮やかさを失い、鈍い紅色が部屋に暖かさを添える。
それ以外、部屋には余計な物は一切置かれていない。
政務をほとんど顧みることが無かった先王時代では、この部屋は長きにわたって埃をかぶっていた。
それが今のあるじを迎えてからは、一転して毎日のようにインクの香りが満ち溢れる。
その少年は今、机の前に座っていた。
昼過ぎの陽光が窓越しに、彼の美しい金髪に降り注ぐ。
女の子と見間違われるほど秀麗な顔立ち。
それは国民に絶大な人気を誇る、先代王妃とよく似ていた。
羽ペンを握る手肌は、透き通るように白い。
机の横長さと比較すると、細身の体つきはより一層華奢に見える。
顔の造形にまだ幼さが残るものの、その一挙一動から君主の風格が溢れ出る。
少年の名はシャロス、王国の次期継承者である。
まだ若いながらも、その明哲さはすでに地方都市の巷まで噂となっていた。
特に執務室に運ばれる大量の書類を、毎日淡々と処理していく様は、廷臣の間で語り草になるほどだ。
そんな執務机の一角に、今日も国内各地から上奏文が寄せられていた。
シャロスの身長よりも高く積まれただろう書類の山。
いつもなら、朝見の後にすぐ処理できる量である。
しかし今日は一向に減る気配が無かった。
部屋にはいつもと違い、一つ余分な存在が混ざっているからだ。
公文書の山の横に、一人の侍女が腰を掛けていた。
国の最高権力者を目の前にして、少女は遠慮のかけらも無く両腕を背後に突き立て、気楽そうにシャロスのことを見つめていた。
クリっとした瞳が印象の、活発そうな女の子。
床から浮いた両脚は、リズムに乗って小さく揺れる。
短めのスカートからはみ出る太ももは、黒のガーターベルトに包まれ、女性的な色香を醸し出す。
侍女服に覆われた体つきは、年相応の健康的なものに思える。
だが実際の裸体は遥かに魅力的であることを、シャロスは十分すぎるほど知っていた。
彼女はシャロスをじっと見つめる。
シャロスは書類をじっと見つめる。
少女の太ももがシャロスの視界にかすれる度に、彼の集中力も一緒に揺らしていく。
やがて同じ行間を三度目に読み間違えた時、シャロスはとうとう我慢できなくなった。
「おい、マナ。なぜまだここにいる」
「ん、なぜって?」
まるで心外と言わんばかりに、マナと呼ばれた少女は訝しそうだった。
「私は王子様にお食事を持って参りましたのよ」
「頼んだ覚えはない。さっさと帰れ」
「リテイア様からは、王子様が食べるところまで見届けろ、って仰せつかったのに」
シャロスはあくまでも不機嫌な表情を崩さず、マナを冷たく見つめた。
溌剌としたメイドの少女。
わがままな悪戯をしてきたかと思えば、次の瞬間は飼い猫のように甘えてくる。
シャロスに対しても、彼女はまるで恐れず、不遜な態度で接し続ける。
普段まわりの唯々諾々に慣れたシャロスにとって、そんな彼女は刺激に満ちた異性であった。
マナはそばにある食器トレイに手を伸ばすと、カップを口元に近づき、蜂蜜のスープを一口すすってみせた。
「あ~あ、せっかくアツアツのうちに運んできたのに。毎日いそしむ王子様のため、皇后様が自ら調理されたものですよ? こんな幸せを味わえるのは、国中を探してもシャロス王子しかいないわ」
皇后のものだからこそ、口にしないのだ。
白々しい気持ちを抑えて、シャロスは更に口調を強めた。
「そんな気遣いはご無用だと皇后陛下に伝えてくれ。私は執務室にいる時、食べ物を一切口にしない習慣だ」
「困ります。それでは私が怒られてしまいます」
まったく困ってない表情でそう言いながら、マナは焼きリンゴの細切りにフォークを突き刺した。
それを口に運ぶと、うーんと満悦そうに鼻を鳴らす。
「おいしい! リテイア様の料理はやはり最高だわ。これが毎日食べられるなら、マナも王子様の身辺で働きたいな」
「そんなことしていいのか? 皇后陛下が知ったら、お怒りになるぞ」
「毒見ですよ、ど・く・み。シャロス様のことですから、どうせ『これに皇后陛下が何か毒を入れているに違いない~』とか思ってるでしょ」
図星だった。
シャロスはマナの得意顔から背け、トレイに乗せられた焼きリンゴと蜂蜜スープの皿を見つめた。
人生の中で、食べる行為を楽しんだ記憶は一度も無い。
食事に困る身分ではなかったし、何より日々身を置かれた権力闘争の中、それを楽しむ心情など持ち合わせていなかった。
しかし、先日皇后リテイアが用意した物を口にしてから、食事に対する感覚が一変した。
その絶妙な味付けは一度味わえば、病みつきになるほどの美味だった。
シャロスは毒物に疎いが、命を奪うほどの毒でないことくらいは知っていた。
それどころか、皇后の食事を口にすると、全身に力がみなぎって、何もかも忘れてしまうような気持ち良さがわいてくる。
毒の知識なら近衛隊長のレイラが詳しそうだが、シャロスには彼女に相談できない事情がある。
ここ最近皇后との間に発生した関係は、レイラに全て内密にしているからだ。
日が経つにつれ、秘密がどんどん増えていき、気が付けば打ち明けようにもできなくなってしまった。
机の上を座るマナの姿は、まるで無防備だった。
スカートから伸び出る太ももを見ると、ついその奥にある黒艶の下着を想像してしまう。
彼女の息遣いをこんなにも近く感じるのは、倉庫で肌を合わせたあの時以来だ。
こうして近くにいるだけで、彼女の体から漂う甘い香りを思い出してしまう。
今すぐマナを抱きしめたい。
彼女の胸に顔を埋めて、彼女の唇にキスしたい。
そして、体内の溜まりに溜まった劣情をぶつけたい。
それなのに、当のマナはあれ以来、シャロスを意識する素振りをまったく見せないのだ。
まるで自分だけが一方的に気を掛けているようで、なんとも面白くない。
その気持ちが表に出ないよう気を付けながら、シャロスは一度深呼吸して自分を落ち着かせる。
「じゃあ、どうしたらここを出てくれる」
「そうね。王子様がこれをちゃんと召し上がってくれたら、私も皇后陛下にご報告に行けるわ」
そう言って、マナはフォークでもう一切れ突き刺し、それを差し出した。
こんがりと狐色に焼かれた果物。
精製したバターと砂糖に浸された甘ったるい香りが、シャロスに向かって漂ってくる。
見た目から想像できるまろやかな味に、口の中が唾液でいっぱいになる。
「ね、おいしそうでしょう? 残していたら、もったいないですよ」
「分かった分かった。それを食べたら、退いてくれるだろうね」
「やった。では王子様、口をあけて『あーん』して下さい」
マナが嬉しそうに言いながら、手本を示すように口を開けてみせた。
(くっ、今まで無視してきた仕返しか)
拒否しても、このまま引き下がる感じでは無かった。
シャロスは顔を少し赤らめ、やがて口をぎこちなく広げた。
伸びてきたフォークの先に、噛みつこうとしたその瞬間。
マナは不意に腕を引っ込め、リンゴのかけらを自らの口の中に放り込んだ。
シャロスは茫然とした。
悠々とかみこなすマナの姿を見て、ようやく自分がからかわれたことに気付く。
「お前、なにを……!」
怒りのセリフを言おうとしたその時。
マナは突然シャロスの顔を掴み、口と口を重ね合わせた。
一瞬にして、シャロスの思考が停止した。
ついさっきまでマナが咀嚼していたものが口腔を通り、自分の喉へと流し込まれる。
小さく噛み砕かれた果物、香ばしい果汁、そこに混ざり合うマナの唾液。
それらを目の前の美少女が口に含んでいたと思うと、言いようの無い妖しい感情が脳を痺れさせる。
全てのものを口移した後、マナは唾液の銀糸を伸ばしながら離れた。
そしてそのまま、シャロスの耳元で小声で囁く。
「はい、そのまま口を閉じて、モグモグさせましょうね。ちゃんと味わうように、慌てず飲み込むのよ」
まるであやされたよう赤ん坊のような、気持ち良い心地だった。
シャロスはぼんやりとしたまま、言われた通り口内の果実を続けて噛み砕いた。
甘さの中に含まれるマナの唾液。
それを意識しただけで、いやらしい気持ちが胸中に広がる。
ねっとりとした果汁が喉を通る時、まるで体の隅々までにマナの味が滲み込んだようだ。
「はい、いい子いい子。とてもよくできましたわ」
マナに頭を優しく撫でられると、シャロスは気持ち良さとともに、どうしようもない被虐的な気持ちが芽生えた。
子供扱いされているのに、なぜかシャロスはマナを振り払うことができなかった。
「そんないい子の王子様に、特別ご褒美をあげるわ」
マナはシャロスの正面に腰を移動させ、小悪魔な笑みを浮かべる。
その笑顔だ。
双子の妹が決して見せない、妖艶かつ悪意に満ちた笑み。
彼女がそれを浮かべた時、決まって悪さを披露してくれる。
だがその悪戯っぽい笑顔で見つめられていると、シャロスはなぜかゾクゾクしてしまう。
「今度は、私の下の口で食べさせてあげるね」
マナは両目を細めて、両手をスカートの下に伸ばした。
シャロスの心臓の鼓動が一気に早まる。
彼女は慣れた手つきで下着を脱がし、見せびらかすように両脚から布切れを通す。
女性の最も魅惑的な部位がシャロスの目の前に晒される。
それを目のあたりにした途端、シャロスの脳内に快楽の記憶が強烈に蘇る。
その表情の変化をあざわらうように、マナは蜂蜜を盛った容器を持ち上げた。
そしてシャロスが凝視している前で服の裾をたくし上げ、上から蜜液を垂らした。
美しい琥珀色の液体が、つーと少女の下腹部に零れ落ち、閉じ合わせた太ももの間に、黄金色の水溜まりを作る。
ごくり、と喉を鳴らすシャロス。
息がどんどん荒くなっていく。
半透明の液体を透けて見える秘所は、その淫らさを一段と強調する。
「ねぇ、王子様」
少女は声のトーンを落として、誘惑するように生暖かい息を吐く。
その心地よさ、シャロスはまるで催眠されたような快感を覚える。
「私のここ、舐めてみたくないですか? 舌を出して、ぺろっと」
マナは舌を舐めずり、挑発的な視線をシャロスに送った。
ドクン、ドクン。
シャロスの心の鼓動が早まる。
トロリとした黄金の粘液。
そこに舌を這わせたい衝動が、彼の常人よりも強いはずの精神を蝕む。
だが王族たる者が下人の股間に頭をうずめるなど、想像するだけでも屈辱極まりない行為だ。
ましてや、敵の一派である人間に屈するなど。
「ねえ王子様、なにを迷ってるの。きっと、すごーく甘い味がしますわよ」
少女のささやき声が敵愾心を薄める。
なんとかそれに支配されないようこらえるシャロス。
しかし、マナの言葉が心の防壁を一枚ずつ剥がし、その奥にある欲望をさらけ出す。
「お願い、王子様。抵抗はしちゃだめよ? 身分とかプライドとか、そんなくだらないことは全部忘れちゃいましょう。今の王子様が思い出していいのは、あの日私と王子様がエッチしたことだけ」
ねめつけるような目つきがシャロスを絡める。
彼女のねっとりとした吐息に触れただけで、シャロスはビクッと背筋を震わせる。
いつの間にか、マナの言葉は命令となっていた。
だがその命令に抵抗するだけの意思を力、シャロスは持っていなかった。
「でも、私はこの国の王子で……」
「言ったでしょ? 今だけ、そのことを忘れなさいって。今のあなたは、女の裸を見ただけで発情してしまう、最低なオスなの。私に夢中で、好きで好きでたまらない、下賤な男の子なの」
「うっ……」
「さあ、素直になって。今のシャロス様は、何よりも私のあそこを舐めたい。そうでしょ?」
マナが下半身を前に突き出すと、一段と濃い芳香がシャロスの鼻腔をくすぐる。
その香りに誘われるがまま、シャロスは虚ろな目つきでマナの秘部に近付く。
そしてついに、神秘な水溜まりに舌先を入れてしまった。
とろけるような甘い液体が喉元を通り、全身の温度が急上昇する。
その甘汁がまるで少女の秘所から溢れているかのようだ。
ぴちゃ、ぴちゃと水音を立たせるシャロス。
そんな一心不乱に舐める姿を見て、マナは得意げに笑った。
「ふふっ、ペロペロしちゃって。かわいい子犬みたい」
マナはそう言いながら、シャロスの頭を撫で始めた。
その行為に、彼の体が小さく震える。
「ねぇ、王子様。どんな味なのか、私にも教えてくれる?」
「甘くて、いい香り……マナの匂いと同じ……」
少しためらったが、結局ボソリと語るシャロス。
言葉を口にしてから、彼は後悔と恥ずかしさのために顔を俯けた。
その仕草を見たマナは、ますますおかしそうに笑う。
「まあ、本当にかわいいんだから」
頭を撫でる手つきの優しさに、シャロスはまるます頬を紅潮させる。
心拍数がどんどん上昇して、何も考えられなくなる。
液体をすすっていればいるほど、全身がのぼせたように熱くなり、気力が抜けてしまう。
頭の中はマナのことでいっぱいになる。
その液体の中に何が入っているかなど、もはや気にすることも無くなった。
蜜の液をすべて飲み干した後、そこには粘液にまみれた秘所が外気に触れた。
「まあ、命令に忠実な子犬だこと。ご褒美に、マナの大事なところ、もっとちゃんと見せてあげるよ」
マナはスカートの裾を掴み上げたまま、机の上で両足を広げた。
シャロスの目の前に、オスの性欲を最も滾らせる景色が完璧に現れる。
日差しを照り返す黄金色の光沢。
その蜜の液体は重力に引きつられて、少女の割れ目に集まり、一滴、また一滴と床へと垂れ落ちる。
少女という外見から、とても想像できないような淫靡な行為だった。
心臓をぐっとわし掴まれたように、シャロスは一瞬たりとも目が離せなかった。
花の蜜に誘惑された虫のごとく、彼はマナの股間に顔を近づける。
そして粘液に最も濡れた溝に、舌を這わせた。
そんな彼の姿を、マナは勝ち誇ったように見下ろす。
「それにしても無様ですね、シャロス様は。以前私のことを淫売だって罵りましたよね? それが今、こんなおいしそうに私のあそこを舐めるなんて。シャロス様には、プライドという物が無いのですか?」
「うぅ……」
シャロスはただ恥辱に震えるしかなかった。
皇后によって幾度もなく誇りを打ち砕かれて、自分でも気付かないうちに、被虐的な性癖が植え付けられていた。
それに加えて、マナ自身非常に魅力的な女の子だった。
明朗快活の中に潜む、危険な淫らさ。
その淫らさは、王族の気高さと相反するものである。
そして、オスの欲望を最も焚きつけるものでもあった。
この娼婦のような女に、自分が跪いて舌で奉仕している。
この放蕩な女に、自分が恋に似た感情を抱いている。
意識すればするほど、被虐的な気持ちが血に混ざり、下半身の一物に集まっていく。
そんなシャロスの異変に、悪魔のような娘は見逃すはずが無かった。
「あら、王子様。あそこをこんなに硬くさせちゃって、どうしたのかしら」
ふと、マナの右足のつま先がシャロスの股間に触れた。
シャロスが思わずうめき声を漏らすと、マナは意地悪そうに笑う。
「私のを舐めて、大きくなっちゃったの? ふふっ、恥ずかしいと思わないの?」
「それは……」
「でも心配しないで、シャロス様。男というのは、もともとそういう生き物なの。こうやって女の子にあそこを踏まれたら、誰しも喜んじゃう下等生物なのよ。王子様も男の子なんだから、例外じゃないわ」
「くっ……」
「ふふっ、このまま服の上から射精させてあげようかしら? きっと気持ちいいわよ。そしたら、メイド達の間でしっかりと噂を流してあげるわ。王子様は女の人にあそこを踏まれて、情けなく射精するのが大好きな人だって」
「そんな……! お願い、それだけは……っ」
シャロスが逃げるようにして、椅子へ寄りかかろうとした。
その時だった。
執務室の扉が、ゆっくりと三回ノックされた。
「近衛騎士隊長レイラ、ただいま戻りました」
優雅で落ち着いた女性の声が扉越しに響く。
だが今のシャロスにとって、その声は青天の霹靂に等しかった。
「レ、レイラ、ちょっと待っ……!」
慌てて顔を上げて、言葉を紡ごうとするシャロス。
だが続きの言葉を遮るように、マナがシャロスに口付けをする。
口移しの時とは違う、淫靡なディープキス。
シャロスの全身に快感と焦燥感が走る。
扉の外から声が続く。
「シャロス様、失礼いたします」
「むっ……!」
扉がゆっくりと開けられ、一人の女騎士が隙の無い足取りで入室する。
そして机の向こう側に座るシャロスを確認して、女騎士は安堵の表情を浮かべた。
「シャロス様、何かありました?」
「いいえ。予定より早く王都に戻ったね、レイラ」
「はっ。隠密調査は滞りなく終えることができました」
レイラと呼ばれた女騎士は、恭しく一礼をした。
身につけた軽鎧から、長旅を経た風の匂いが漂う。
急いで帰還したせいか、その美しい風貌にやや疲れが滲み出る。
だがシャロスの顔を見た途端、彼女の顔に明るい色が戻る。
女騎士レイラ。
王宮を護衛する精鋭部隊である近衛隊隊長にして、大陸でも有数の剣士である。
そしてシャロスの有力な腹心であり、母親の記憶が無い彼にとって、唯一心が許せる女性である。
「して、首尾はどうか」
シャロスはコホンと咳払いして、淡々とした表情で言った。
だがその裏で、心は天地がひっくり返るほど慌てていた。
レイラが頭を伏せている間、シャロスはチラッと机の下を見た。
そこに身を隠れるマナがてへッと舌を出して、シャロスに対しあっかんべを作った。
板に遮られているため、机の下の空間は反対側から見えない構造となっている。
レイラが入室するまで咄嗟の間に、シャロスがマナをそこへ押し込めたのだ。
そんなことも知らずに、レイラは報告を始める。
「ご明察の通りです。辺境地のウェルヘン伯が反乱を企てている件ですが、根も葉も無い嘘です。伯は善政を敷き、領民への増税をよしとせず、巡察使達が求めた賄賂を拒んできました。それ、今回の事件の起因になったようです」
「世襲貴族の蛆虫どもめ。今の地位に足りず、まだ毟り取ろうというのか」
いつまでも巡察院に居座る貴族達の顔を思い出し、シャロスは苦虫を噛み潰したような表情を浮かべる。
君主の代わりに民達の声を聴く役人と言えば聞こえはいいが、その実態は特権を駆使して地方官や民から搾取し、私腹を肥やしている悪人どもである。
国王直属の役職で、本来ならばシャロスが真っ先に掌握する勢力だった。
だが王宮の権力争いが続く中、巡察院を改革する余裕など無いに等しい。
「しかし、不審な点もあります。巡察使が最初に申し立てたのは、ウェルヘン伯の悪政でした。それがいつの間にか、無断に私兵をかき集め、反乱を準備しているという噂になっている」
「皇后派の工作だ」
シャロスが迷いもなく断言する。
「近頃、皇后一派は軍部にも勢力を伸ばそうとしている。王国軍は代々王家に忠誠を誓っている伝統があるため、付け入る隙はなかなか無いだろう。だがもし反乱のような事態が起きれば、軍備拡大の口実ができる」
「今の軍部が影響を及ぼさないところで新しい役職を作り、そこに勢力をねじり入れる……!」
「その通り。今はまだ噂レベルだが、いずれ王都でも広がり、議会で提起されるだろう。そこで私が王国軍の出動を拒絶すれば、それこそ皇后派の思いの壺だ」
「ウェルヘン伯は領民の間で深く支持されています。万が一不測な事態になれば、多くの領民が伯爵のために立ち上がるだろう」
「それでは本当の反乱になってしまう。レイラ、命令だ」
「はっ」
「巡察使が収賄した証拠を集め、身柄を拘束せよ。手段は任せる、多少強引な方法を使っても構わない」
「かしこまりました」
「公文班に勅令の起草を伝えよ。王の名のもと、讒言を晴らし、民心を安定させる。枢密院は通さず、ただちに王令として出せ」
「ははっ」
「ウェルヘン伯には褒美を与えよ。領主の役目をまっとうし、国境の地をよく守り続けた。そして領民を守るために高官の圧力にも負けず、王都にその実態をよく知らせたと。巡察使を拘束した暁に、手柄は全て彼のものとする」
レイラの目つきが鋭くなる。
そんな名目で褒美を取らせたら、巡察院の貴族達はウェルヘン伯のことを目の敵にするだろう。
それは今後ウェルヘン伯が王子派に接近し、頼り続けなくてはならないことを意味する。
「お前の隊の者なら、うまくやってくれるだろう」
「無論でございます。では、私はこれにて……」
レイラは一礼してから、シャロスに背を向けて退出した。
彼女にとって、シャロスは完璧な君主像である。
信念は固く、だが驕れることは無く。
民のことを思い、だが軟弱になることは無く。
権力の残酷さをよく知り、だが腐敗に染まること無く。
まだ少年でありながら、彼は歴代王者の中で最高の素質を見せている。
彼女にとって、シャロス以外の人物が王になるなど、考えられないことであった。
レイラの後ろ姿を見て、シャロスはほっと息をついた。
武術の達人だけあって、レイラの感覚は常人の域を超えている。
マナが大人しくしてくれたこともあって、この場はなんとかやり過ごせた。
(そういえばマナのやつ、さっきから何をしている)
シャロスは不思議になって、机の下をちらっと見た。
すると、あまりもの驚く光景に椅子から飛び上がりそうになった。
マナは一言も発さずに、なんとシャロスから下半身に着けていた服を剥き取ろうとしていた。
慌てて両手を伸ばして阻止するシャロス。
その些細な物音が、すでに出口まで歩んだレイラを振り返らせる。
「殿下、いかがなさいました?」
「あっ、いや……」
彼が怯んでいる隙に、マナが力をいっぱい込めて、シャロスの両手からズボンを引き下ろした。
太ももの肌が外気に触れる。
シャロスは出来る限り平然の顔を作り、椅子のせもたれに背中を付ける。
だがその背中には、速くも冷え汗にまみれた。
「こたびの調査、よくぞやった。君も、君の部下達も」
「もったいないお言葉です。殿下の微力になれれば……」
(ううんっ!)
シャロスの眉がビクンと跳ねた。
とある刺激のせいで、レイラの言葉を最後まで聞きとれなかった。
机の下に目をやると、丁度マナが下着をずらし、男性の象徴を取り出す瞬間を目撃する。
マナは彼の怒りに怖気づくところか、むしろ挑発するようにウィンクをしてみせ、手にした一物に息を吹きかける。
生暖かい風圧が裏筋に当たる。
たったそれだけの刺激で、一物がむくむくと膨らみ、やがて完全に勃起した。
さきほどまでマナから受けた快楽が蘇る。
体の火照りも、脳を包む夢心地も、全て元通りに復元されてしまった。
思いもよらない事実がシャロスに襲い掛かる。
自分は今、下半身を露出させている。
それも机を隔てて、レイラがいる目の前で。
全身の神経が緊迫する。
ゾクゾクするような倒錯的な快感。
抵抗できないことをいいことに、マナは舌をシャロスの一物に這わせ、巧みに唾を絡み合わせる。
シャロスを見つめるレイラの目つきは、徐々に疑念を抱き始める。
どんなことがあっても、レイラだけにはバレたくなかった。
「せっかくの週末だ。隊員達と一緒に、休暇を取ったら……どうだ」
シャロスは語尾のうわずりをなんとか気力で抑えた。
股間の一物に、何か生ぬるいものが覆いかぶさる。
チラッと見る。
ちょうどマナは亀頭から舌を離し、自分に向かってニコッとしたのが見えた。
そして彼女はそのまま、唇を一物の根元まで含ませる。
(んぐ……っ!)
思わず俯いて、ゆがめそうになる顔をレイラから隠す。
マナの柔らかい唇と舌が、竿全体を包み込む感覚が分かる。
耐え切れないほどの快感が背筋を伝って昇り、喉から声が出ようとしている。
机の下でマナが一物を吐き出し、悪戯っぽく微笑んだ。
だが今のシャロスには、彼女を責める余裕さえなかった。
背中に冷や汗が滝のように流れるのを感じる。
――レイラが気付きはじめている。
顔を伏せても、レイラの視線が段々と鋭くなっていくのを感じる。
天下に誇る王国軍において、とりわけ個人戦に特化した王宮近衛隊。
そしてシャロスに直属し、時には正規軍では実行できないような命令を執り行う精鋭集団。
その集団の隊長を、レイラが務めているのだ。
「シャロス様、どうかなされましたか」
レイラはいつもと変わらない、落ち着いた口調だった。
彼女は一度机の上に置かれた食事のトレイを見て、また何事も無かったように視線をシャロスに戻す。
だがシャロスには分かる。
レイラの意識は、すでに部屋の不自然さに集中しつつある。
執務室にいる時、シャロスは食べ物を口にしない。
その習慣は、もちろんレイラもよく知っている。
あと二十秒もしないうちに、彼女はこの部屋に第三者が来たことを推察するだろう。
その十秒後に、机の死角に誰かが隠れているじゃないかと勘づく。
五秒後に、シャロスはその人物によって脅迫されているではないかと疑い始める。
その直後に、彼女はきっと行動を起こす。
脅迫者に気付かれることなく、そして交渉の余地を一切与えずに、目の前にある数十キロもの机を蹴り上げて、不意を突かれた敵を掴み上げて生け捕りにするだろう。
長い間一緒にいるからこそ、シャロスはレイラの行動力をよく知っていた。
そして恐ろしいことに、彼女には一連の行動を完遂するだけの能力が備わっている。
レイラを止めるには、最初の二十秒内の時点でその考えを中止させなければならない。
だがどうすればいいのか、まったく思いつかないのだ。
レイラとは信頼し合うことがあっても、騙すことは今まで一度もなかった。
緊迫した状況にも関わらず、マナは自重するどころか口で深く咥えながら、頭の上下運動をますます加速させる。
快感と緊張が壮絶にねじり、シャロスの神経をピンと張らせる。
「そう言えばレイラ、ここしばらく剣技の稽古をまったくしていなかった」
「むっ」
絶体絶命の状況を切り抜けるために、シャロスは言葉を口走る。
今にも歩み出そうなレイラだったが、その言葉を聞いた途端、不機嫌そうに立ち止まる。
「殿下。お言葉ですが、武芸の稽古は登山と一緒です。一日でも道中を休んだら、次も、そのまた次も休もうと思ってしまいます。その遅れを取り戻すため、大変な思いをしなければなりません」
「ああ、だから今すぐお前と一緒に練習したい」
「えっ?」
「でもお前が帰還したばかりで、疲れているというのなら仕方は無いが……」
「いいえ、とんでもありません! すぐに準備にかかります。訓練場でお待ちしております!」
さきほどまでの態度はどこへやら、レイラはまるで誕生日プレゼントを手渡しされた子供のように両目を輝かせて、いそいそと部屋から出た。
自分と一緒に武芸の稽古をする。
それがレイラがどんな不機嫌な時でも、彼女の機嫌を直す魔法の呪文だった。
彼の予想通り、レイラの顔つきは美しい花のように綻びる。
足音が遠ざかっていくのをしっかり聞いてから、今度こそシャロスは緊張の糸が切れてぐったりとした。
「きゃはは。王子様ってば、演技がお上手なんですね」
「貴様……!」
「きゃっ」
シャロスは机の下から現れたマナを、いきなり机に向かって押し倒した。
「誰のせいで、こんな目にあってると思ってるんだ!」
「あはん、殿下が怒った」
「ふざけるな! どこまでも人を馬鹿にして!」
「いやん、王子様……」
シャロスがマナのメイド服を乱暴に脱がすと、少女は小さく悲鳴を上げた。
はだけた上着から、汗ばんだ肌色が見え隠れる。
黒いブラジャーの縁に薔薇模様が散らばり、胸部の勾配を悩ましく描き出す。
シャロスはマナの両腕を抑えつけながら、荒々しく呼吸を繰り返した。
マナの体が、以前にも増して煽情的に思えた。
可愛らしい頬は赤く染まり、小さく開いた唇から、胸の起伏に合わせて吐息が漏れ出る。
時折シャロスを振りほどこうとするも、両腕をがっしり掴まえられたため身動きがまったく取れない。
その小動物のようなささやかな抵抗がまた、男の獣欲を掻き立てる。
シャロスの灼熱のまなざしに耐えられないのか、マナは顔を横に向けた。
その無防備な態度に、シャロスの全身の欲望が爆発しそうになる。
マナの白いうなじに口付けしたい。
彼女が着ている服をバラバラに切り裂き、その濡れそぼった秘所を乱暴に犯したい。
口に無理やり一物をねじり込んで口淫させたい。
生意気な表情を快楽と苦悶に染めてあげたい。
だが黒い欲望が溢れ出る前に、シャロスはとある笑顔を思い出す。
部屋を出た時に見せた、レイラの屈託の無い笑顔。
自分が苦しいと思った時に、何度も助けられてきた顔。
「あれれ?」
マナは両目を大きく見開き、不思議そうな声をあげた。
シャロスは黙ったまま立ち上がり、服を着始めたのだ。
「この前みたいに、気持ちいいことをして下さらないですか?」
「人を見くびるのも、いい加減にしろ!」
「まあ。ここまで来て、止めちゃうんですか?」
「これだけは覚えておけ。男だからといって、誰もがお前の思い通りになると思ったら、大間違いだよ!」
シャロスは袖口を整えると、机に横たわるマナに目も触れず部屋を出た。
「ふふっ、面白かったですわ。ますます堕としたくなってきたじゃない」
残されたマナはおかしそうに呟いた。
彼女は息があがったように立ち上がり、机に腰を寄せた。
乱れた服装の下で、汗に濡れた肌はなおも紅潮し続ける。
マナは机の上に残された蜂蜜スープの容器を手に取った。
容器の底に、黄金色の残液が綺麗にきらめく。
「さすがリテイア様の媚液。少ししか飲んでいないのに、私でもこんなに効き目が現れるなんて」
カップを握る手は小さく震えた。
息詰まるような心臓の鼓動、欲求への渇望と焦燥感。
常人なら耐えられず発情する状況を、マナはまるで楽しんでいた。
「まったく驚かされるわ。邪魔が入ったとはいえ、王子様はあそこまで意志が固いとは。これも全て、あのレイラとかいう女のせいかしら」
シャロス王子とは同じように、マナもまたレイラがこんなにも速く秘密任務から戻ることを知らなかった。
カップの中に残された蜜液を指ですうと、マナは舌先で色っぽく舐めとる。
「でも、その一番大切にしてきた女を、これから王子様は自ら裏切るんですから」
体を燃やし尽くすような渇望に身を焦がされながら、マナは執務室の窓際から、シャロスの去り姿を見つめ続けた。

Z3
z334565893
Re: 魅惑の皇后 第五章
求大佬翻译
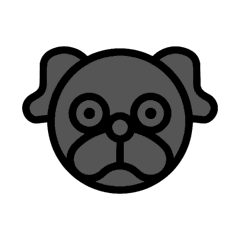
13
1357924680
Re: 魅惑の皇后 第五章
求翻译
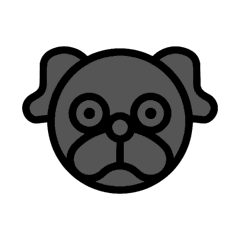
13
1357924680
Re: 魅惑の皇后 第五章
求翻译,各位大神拜托了

Sh
shuangyue520
Re: 魅惑の皇后 第五章
好吧,第五章出了,求大神翻译了
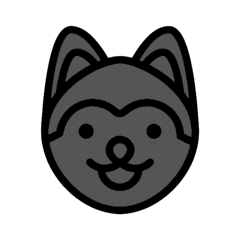
Da
dahaorensxt123
Re: 魅惑の皇后 第五章
先来个机翻也可以啊
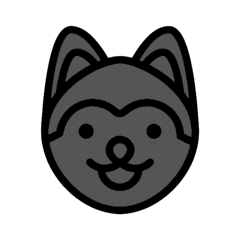
Da
dahaorensxt123
Re: 魅惑の皇后 第五章
先来个机翻