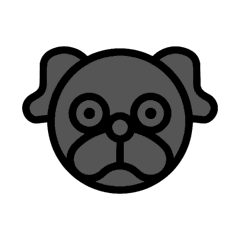【自译小说No.6】魅惑的皇后
添加标签

Ws
wssbgundam
Re: 【自译小说No.6】魅惑的皇后
好赞顶!强烈期待后续~LZ加油!

Ma
magicstaff
Re: 【自译小说No.6】魅惑的皇后
加油翻译吧
第二話
朝。
太陽の光がカーテンに遮られ、布の縁から輝きが優しく漏れる。
シャロスはゆっくりと目を覚ました。
「うっ……」
あんまりいい目覚めではなかった。
体のあちこちにけだるい疲労感が残る。
「あれは……夢だったんだろうか……」
シャロスは曖昧になった記憶を思い起こした。
「確か昨日の夜はレイラが来て、その後皇后が……それからは……」
そこまで思い出すと、シャロスの顔から火が噴くほど真っ赤になった。
皇后にあそこをいじられ、生まれて初めてイカされた。
そのうえ、皇后をお母さんと呼んでしまった屈辱。
(くっ……私はなんてことをしてしまったんだ。あんな淫乱女をお母さんと呼ぶなんて、母上への冒涜だ!
)
シャロスの心は後悔の念が満ち溢れる。
リテイア皇后といえば、噂では不貞を続けるふしだらな女性である。
シャロスにとって、彼女は貞淑な母上とは大違いで、下賎で淫猥で、いやしい女である。
(昨日のことだって、あの女の色仕掛けに間違いない……くそっ、それが分かってるというのに!)
そうと思ったものの、シャロスは嫌悪以外に、何か不思議な感情を抱いていた。
リテイアを淫乱女と思えば思うほど、少年の心がドキドキし、息が苦しくなった。
目を瞑れば、リテイアが黒の下着だけ身に着け、しなやかな肢体を妖艶にひねらせる光景が、
いきいきと浮かび上がる。
彼女が男を誘惑する時の表情を想像すると、シャロスの全身の血流が速まり、股間のペニスが硬くなった。
シャロスはリテイアにされた行為を思い返すと、やがて自然と股間の一物を握り、こすりはじめた。
「あっ……!」
くぐもった声を抑えながら、シャロスは自慰に耽った。
彼の股間の先はすでにぬるぬると濡れ、竿は赤く醜く怒張していた。
「くっ……あ、うっ!」
あの女がもしこんなみっともない自分を見たら、きっと冷たい視線を向けてあざ笑うだろう。
その悔しい気持ちは、逆にシャロスの欲望を煽った。
彼はリテイアの手つきを思い出しながら、自分のペニスをしごき続いた。
(はぁっ……また、あの感触が……ああ、出る!)
一物がドクン、ドクンと大きく脈打つと、シャロスは盛大に射精した。
白く濁った熱液がシーツに散らばり、全身から力が抜けた。
「はぁ、はぁ……」
シャロスの体中に汗が噴き出た。
頭がぼうっとしていて、考えがまったく定まらない。
しかし、彼が余韻に浸っている最中、不意に寝室の扉が開けられた。
「おはようございます、シャロス様」
「ひゃっ!?」
シャロスは思わず露出した下半身を奥側へ隠し、突如現われた少女を見つめた。
彼女は黒のメイド服を着ていた。
眉目は秀麗で、悩ましい首筋は綺麗だった。
服の下から胸が程よく膨らみ、女性的な部分がシャロスを挑発する。
半袖のスリーブから真っ白い二の腕が露出する。
手首にはカフスがつけており、彼女の腕をより可愛らしく見せる。
白いエプロンは黒服の上から前側を覆い、清潔感を感じさせる。
いわゆるフレンチメイド服だろうか、彼女のスカートの裾は膝よりも上で、裾下からは白いフリルが隠れ見
える。
光沢の帯びた黒ストッキングは彼女のほっそりとした両足を覆い、優雅であると同時に妖しい魅力を放って
いた。
つややかな髪にフリルのカチューシャがつけられている。
そして、後ろへ垂れ下がるポニーテールにシャロスは見覚えがあった。
「お前は皇后様の……?なぜここに……」
「はい。リテイア様の言いつけで、本日より王子様の身の回りの世話をさせて頂く、エナと申します」
「ほかの人はどうした?」
「王子様はお取り込み中なので、退避させました」
エナはそう言って、見透かしたような目でシャロスに一瞥した。
シャロスは思わず焦った。
「お前をここにいれた覚えは無い、皇后のところへ……」
「王子様、いけませんわ。まだ病み上がりなのに、あそこを裸のままにしては」
突然、エナはベッドに近づき、シャロスの下半身を覆う布を拾い上げた。
「あら、こんないっぱい出たのですね」
空気がひんやりとしてシャロスの股間を襲う。
下半身の醜態は、全て相手に見せてしまった。
シャロスはまるで毒牙を抜かれたかのように、どうしたらいいか分からない表情になった。
しかし、エナは大したリアクションもせず、
あらかじめ準備した暖かいてぬぐいを取り出し、手際よくシャロスの股間を拭う。
すぐさま、彼のあそこはほかほかした感触が包む。
シャロスの心は驚愕と疑念に満ちた。
彼は顔を赤らめながらも、とろけそうな気持ちを押さえ込み、
「お前は、一体いつから部屋の外にいた?」
「しばらく前からです」
エナは表情一つ変えず、淡々と答えた。
だがその一言に、シャロスのプライドが傷ついた。
(それじゃ、物音が全部聞かれてしまったのか……)
しかし、彼はすぐに動揺を治め、つとめて普段の気迫を取り戻す。
「もうよい。さがれ」
「分かりました。しかし、お風呂の用意ができましたので、先にそちらで身を清めさせて下さい」
言われてみれば、シャロスは自分は汗だくになっていることを思い出す。
彼は一瞬戸惑ったが、やがてエナの意見を受け入れた。
「ふん、ずいぶん用意周到じゃないか」
シャロスがエナに王子専用の広い浴室に導かれた。
エナは「失礼します」と言って、シャロスの貴族の服を脱がせる。
その瑞々しい指先を感じ、シャロスはまたもや落ち着きを失う。
エナが彼のズボンを脱がしたとき、上から見下ろすと、ちょうど彼女の無防備の谷間が覗ける。
シャロスは顔を赤らめ、慌てて他の方向へむいた。
王族だから、これぐらい奉仕されるのは慣れたはずだが、
昨日リテイアによって射精させられてから、シャロスは無性に異性が気になった。
気付いたら、シャロスの股間部が再び疼いた。
「もういい、後は私自身がやる」
「はい」
エナはやや驚く顔をみせるが、シャロスの命令には逆らわなかった。
彼女が去ったあと、シャロスは下着を脱いで裸になった。
案の定、彼のまだ幼さが残る一物は、硬くなっていた。
シャロスは浴室に入り、真っ先に冷水をすくい、それを頭の上からかぶった。
骨を突き刺すような冷感が皮膚から伝わる。
普通の人間にとって厳しい冷たさだが、
毎日冷水浴を続け精神を鍛えた王子にとって、これぐらいは平気だ。
彼は五度ほど水をかぶった後、お湯に浸かった。
冷え切った体を、今度は熱い温度があたためる。
こうしているうちに、シャロスはいつもの感覚を取り戻した。
(あの召使いは皇后の人間だ。もしかしたら皇后と同じように、
私を誘惑してくるかもしれない。気をつけなければ……!)
湿った蒸気が立ち上がり、浴室全体は霧に覆われたかのようだった。
そんな中で、突如入り口の方から物音がした。
「誰だ!」
「エナです。王子様の御体を洗わせていただきます」
「なっ……!」
シャロスの集中力が途切れた。
もやもやした向こうから、髪を短く巻いたエナの姿が近づく。
メイド服は脱がされ、その代わりに薄地の白い素衣を着ていた。
質素で丈の短い衣だが、服の下にある少女の胴体のラインをはっきりと描いた。
可憐な肢体は、あらぬ妄想を起こすほど魅力的だった。
彼女の艶姿を確認すると、シャロスは顔を真っ赤にさせた。
「ここに入っていいと、誰が言った!」
「申し訳ありません。私がリテイア様に仕えた時、いつも御体を洗わせて頂いたもので……」
「私にそんなのいらん」
「はい……しかし、お言葉ですが、王子様はいずれこの国の王になるもの。
こんな些細なことまでご自分の手を煩わせては、きりがありませんわ。
リテイア様が私を王子様の側に置いたのは、まさにこういう事を奉仕させて頂くためかと存じます」
エナの視線は、まっすぐシャロスの両目を捉える。
シャロスは彼女の妖しい躯体を見つめ、ついに折れてしまった。
「……ふん、好きにしろ」
「ありがたき御幸せ。では、こちらへどうぞ」
と、エナはシャロスを浴室の大鏡の前に座らせた。
鏡の中で、エナは服を着ているのに、自分が裸である。
そう思うと、シャロスはなぜか恥ずかしい気分になった。
エナは無表情のままなので、彼はその心境を推測できなかった。
(なんだか、すっごく馬鹿にされたみたい……
こっちがこんなに恥ずかしがってるのに、むこうが全然気にしていないなんて……)
エナはシャロスの背後にひざまずき、水がめやシャンプを用意した。
「しばし目をつむって下さい」
シャロスは言われたとおりに目を閉じる。
頭上から、暖かいお湯がゆっくりと垂れる。
エナは彼の高貴なブロンドを優しくほどき、撫で下ろす。
彼女の指に頭を撫でられると、脳の裏から甘い痺れがじんわりと広がる。
シャロスは思わず考え事を止め、彼女の指使いに委ねた。
サラサラとした金色の長髪は、エナによって水を含まされ、地面のタイルに届く。
そして、エナは何かひんやりとした溶液を頭上に垂らした。
彼女は十本の指を使い、その溶液を巧みに髪にしみこませる。
たちまち泡が広がる音が聞こえ、そしてかぐわしい香りがシャロスの鼻に浸透する。
(ああ、この匂い……リテイアの匂いと、すごく似ている……)
シャロスの緊張がゆるみ、心がリラックス状態になった。
エナの指は、時は放射線状に頭を撫で、時は爪を立たせてやや強くひっかき、
シャロスの髪の毛を泡の中で洗浄する。
目を閉じたまま彼女の手加減を感じると、シャロスはまるで雲の中に浮いているようで気持ちよかった。
エナは後ろ髪に手をそっと添え、それを掻き分けるように優しく指を滑らす。
広い浴室の中は水が滴る音と、髪の毛がザワザワ触れる音しか聞こえない。
洗うことに集中しているのか、エナは黙ったまましゃべらない。
生温い空気や、はてしない静けさが心地よい。
全て終わった後、エナはもう一度頭からお湯をかぶる。
エナはシャロスの閉じた目を優しく拭う。
「もう目を開いても、よろしいですわ」
「はっ……」
シャロスはやっと我に帰り、鏡を見つめる。
この鏡は特殊な薄膜を施されており、湯気の水滴は弾かれる構造となっている。
王族の育ちらしく、シャロスの肌はエナに負けないほど雪白く、キメが細かい。
常にストレスを抱いているためなのか、彼の成長が遅く体は小柄で、後ろのエナと同じぐらい背丈であった
。
彼はエナに気付かれないように、彼女のほうを見た。
さきほどの水をかぶったせいか、エナの薄地の白服は濡れてしまい、べったりと肌に貼りつく。
そのため、彼女の女らしいラインは今まで以上にくっきりと現われ、柔らかそうな乳房がうっすらと映る。
シャロスは口の中が乾いていくのを感じた。
その時、エナは石鹸をシャロスの背中に滑らせていた。
どうやら、自分の服が透けて見えるのが気付いていないようだ。
シャロスはなんとなく股間のところを手で覆い、罰悪そうな表情を浮かべた。
もともと秀麗で凛々しい顔立ちは、今でははにかむ少女のように赤くなっていた。
彼はいけないと知りつつも、ついついエナの肢体を見続けた。
今まで召使いに奉仕されることは何度もあったが、シャロスはこれほど興奮したことが無かった。
昨日のリテイアの下着姿を見てから、シャロスはどうしても女性が持つ神秘さに惹かれた。
「王子様、いかがなさいました」
「は、はうっ?い、いいえ……ちょっと考え事してて……」
「まあ。私はてっきり湯加減が至らないかと」
「ううん、大丈夫だよ。エナの手つき、すごく気持ちよくて……」
そう言った後、自分のペニスをしごいたリテイアの手つきを思い出し、慌てて頭を伏せた。
「お褒め頂き、大変光栄です。私、実は按摩を少し心得ています。どうかそちらもご堪能してください」
エナの細い指はシャロスの肩にかかると、ぬるぬるした泡を掻き分けるかのように、彼の肩のツボを押した
。
「あっ!」
シャロスは思わず声を漏らした。
あまりにも気持ちいい快感が、彼の神経を瞬時に通過する。
エナの親指は肩の下側に突き、やや痛みを感じるぐらいの力加減で押し続ける。
その位置は肩から、徐々に背筋のほうへ移り、そしてまた背中の外側へ移る。
味わったことも無い痛快さがシャロスを襲う。
エナにさわられた筋肉は、まるで彼女に支配されたかのように、シャロスの言うことを聞かなくなり、力が
抜けていく。
エナの手は彼の背筋を続けて押さえ、腰際まで強く撫でられる。
やがて、背中に力が入らなくなったシャロスは、後ろのエナの体へ倒れ掛かった。
「あっ……」
なんとか起こそうとしても、体は彼の言うことを聞かない。
「大丈夫です、そのまま私に寄りかかってください」
エナの言葉を聞くとシャロスはなぜかほっとした。
だが次の瞬間、彼は背中に二つの柔らかい肉感が当たっていることに気付いた。
(これは……エナの胸……!?)
シャロスの心臓の勢いは一気に増加した。
鏡を見ると、彼の体は完全にエナの体とくっついていた。
しかし、エナはまったく気にする気配を見せなかった。
女性特有の柔らかい感触が、背中から広がっていく。
シャロスはその感触に陶酔し、何も考えられなくなった。
エナはそんなことをまったく知らない素振りで、背後からシャロスの左腕に両手を移した。
彼女の十本指は、まるで触手のようにシャロスの細腕に絡み、妖しく蠢いた。
右の腕も同様に、指の先までエナにほぐされると、シャロスはついに恍惚の表情を浮かべた。
エナが体を動かすたびに、胸の先端の柔らかい感触がコツコツと当たり、
シャロスの欲望を掻き立てる。
彼女の指先は徐々に中央へ滑り、シャロスの胸に触れた。
(あっ……そこは……!)
わざとやっているのか、それとも無意識なのか。
エナの指先はシャロスの乳首のまわりをくすぐるように、円を描いていた。
気持ちいい波紋が体中へ広がるが、もどかしい気が充満した。
「体を横にしますね」
突然、エナはシャロスを床に倒す。
(えっ?)
シャロスは慌てて股間に両手を置き、いきり立ったペニスを強引に押し倒す。
頭の下は、折り畳んだタオルが当てられる。
エナはシャロスの裸体の上にまたがり、彼の足の方に頭を向けた。
そして、彼の足のふくらはぎを按摩した。
どうやら股間が膨らんでいることは、ばれていないようだ。
シャロスは思わずほっと息を吐いた。
しかし、彼はすぐに目の前の光景に固まった。
エナの体勢はちょうどシャロスと逆向きになっていた。
彼女は足をシャロスの体の両側に分けてひざまずき、一心不乱に彼の足のマッサージを続ける。
そのため、今の彼女の両足、無防備に開かれていた。
濡れた裾は彼女の魅惑な美尻にぴったりとくっつく。
その下に、女の大事な部分が見え隠れする。
それに気付いた瞬間、シャロスの股間は爆発しそうになった。
エナの動きと共に裾が上下する。
女体の最も神秘な茂みが、シャロスの視界にチラつく。
彼は懸命に首の角度を変え、そのむこうにある光景を目に収めようとした。
(ああっ……もう少しなのに……!)
エナはまるでシャロスを焦らすように、お尻を少しずつ揺らす。
彼女が動くたびに、シャロスも角度を変えなければならないため、とにかく首を動かし続けた。
柔らかそうなお尻と水平に、彼女の美乳が服を突き下げ、ピンク色の先端がうっすらと見える。
シャロスはゴクリと唾を呑み、欲情したサルのように、エナの動きを追った。
その時だった。
シャロスの足裏から、突然激しい痛みが広がった。
「うああーっ!」
シャロスは思わず大きな悲鳴を上げる。
「あっ、すみません。足裏のツボで痛がるということは、体に何らかの不具合があるということです。
王子様はきっと普段で勤労なさっているから、疲れが溜まったでしょう。
しばらく痛いかと思いますが、どうか我慢してください」
エナが言い終わると、激痛が連続してシャロスの足裏から襲う。
「ああっ、ううっ……ああああぁぁ!」
痛感の中には快いものも混ざっている気がしたが、シャロスはそれを感じる余裕が無かった。
彼は痛みの間を徘徊しながら、ただ情けない悲鳴を出すしかなかった。
五分もすると、彼の額に大粒の汗が滴り、目の焦点が合わなくなった。
「はい、おしまいです。少し力を入れすぎたでしょうか?
でも、こうして続けていれば、王子様もいずれ痛みではなく、快感しか感じられないようになりますわ」
エナの無表情の顔に、ほのかな笑みが含まれていた。
しかし、彼女の意味深長な言葉は、シャロスの心に届かなかった。
「はぁ、はぁ……」
「おや、王子様のあそこ、すごく腫れているようですが」
「はあぁっ!?」
痛みのせいで、シャロスはあそこを隠すことをすっかり忘れてしまった。
彼は慌てて覆おうとするが、それよりも速くエナの頭が覆い被さる。
「大変申し訳ありません。王子様がこんなに溜まっているのを、
気付かなかったなんて。私にぜひご奉仕させてください」
シャロスが拒否する間もなく、エナは可愛らしい舌を吐き出し、シャロスのペニスの先端をチョン、と舐め
た。
「うっ……!」
あそこから走る衝撃は、シャロスの全ての言葉を封じ込めた。
エナは指でシャロスの剥けたばかりのペニスを摘み、赤ピンク色の亀頭を口に含んだ。
ねっとりとした異空間が、シャロスのペニスを覆う。
「ああっ!うぐっ……はぁっ」
シャロスは思わずリテイアにされたことを思い出した。
あの時味わった新鮮な感触は、エナによって再現される
エナは口をすぼめたり、吸い付いたりする動作がシャロスの目に入る。
生暖かい舌は蛭のように蠢き、彼女の唾液をいやらしく絡ませ、ぬるぬると滑らせる。
その熟練とした動きは、経験が少ないシャロスを追い詰めるのに余裕だった。
シャロスが彼女の下のほうを見ると、襟の開きに沿って、胸元の谷間が覗ける。
まるでシャロスを誘惑するかのように、服越しの乳房が激しく揺れる。
こんな時でも、エナの顔はただ動く機械のように、行為を淡々と続ける。
まるで彼女が扱っているのは男ではなく、もっとどうでもいい物体のようだ。
シャロスはその涼しげな目元を見ると、彼女にとって自分はなんともない存在のように感じ、
とても惨めな気分になった。
しかし、それでもシャロスはエナから目を離すことができず、彼女の女性の象徴に興奮した。
「あっ、だ……め、はぁああ!」
やがて、欲望が一つの塊に凝縮され、徐々にシャロスの下腹部へと集まった。
また、イカされてしまう。
自分の意思とは無関係に、ほかの人にイカされてしまう。
プライドの高いシャロスにとって、それは許しがたい事である。
しかし、今の彼は、エナ押しのける力さえ残っていなかった。
彼はただ弱々しくうめき声を上げた。
「はむっ……んはぁ、王子様、どうか我慢なさらないで下さい。
私の口の中でザーメンを存分に出してください」
「うっ……だ、だめ……い、いやっ!」
シャロスは顔を歪め、絶頂にのぼりつめる一瞬を味わおうとした。
だが、エナはそこでペニスの根元をギュッと押さえ、頭が離れた。
彼女の唇とペニスとの間、唾液の糸が一筋伸びる。
「えっ……?」
シャロスは突然の停止に混乱した。
彼の体内の苦悶は後一歩のところで、発散できなくなった。
エナの方を見ると、彼女はおもむろに立ち上がり、シャロスをゆっくりと立ち上がらせた。
「大変残念ですが……王子様がイヤだというのであれば、仕方ありません」
「えっ?」
シャロスは焦った。
どうやら、彼が先ほど口走った「いや」という言葉を、エナが実行したらしい。
しかし、だからといって「続けろ」という言葉も、言えるはずが無かった。
そんな事を言ったら、まるで自分が快感に溺れたようで、エナに軽く見られるじゃないかという恐怖があっ
た。
王子としての威厳がシャロスを苦しめる。
ペニスはビクビクとわなないたまま。
大きく腫れあがった一物は、刺激を追い求めるように、醜く蠢く。
その様子を見て、エナは挑発的な口調で尋ねる。
「王子様、本当によろしいでしょうか?」
「……うっ、うん、だ、大丈夫だ」
言った後、シャロスは激しく後悔した。
浴室を出た後、シャロスは軽い朝食を取り、そのまま執政殿へ赴いた。
その間も欲望の熱は冷めなかった。
シャロスはあそこを触りたい気持ちでいっぱいだったが、
エナがずっと側にいたため、それさえ叶わなかった。
朝から執政殿で群臣と国政を討議することは、この国のしきたりであり、
そのため明け方の自由時間は非常に少ない。
確かに過去には幾人もの愚君が登場し、国政を放り投げた国王もいた。
しかし、将来に向けて抱負を持つシャロスは、決してそのよう真似はしなかった。
皇后と宰相の発言権が強いとはいえ、群臣の中には王子に忠誠を誓う臣下もいる。
何かがあると、執政殿の朝会でしばしば険しい答弁が続く。
シャロスの役割は、皇后派の発言を食い止め、彼らの言うことへすんなりと傾けさせない事にある。
名目上とはいえ、シャロスは次期国王。
彼は唯一皇后と対等になれる身分である。
「殿下、ご機嫌麗しゅうございます」
「ああ。皆のもの、おもてを上げてよいぞ」
シャロスは王座に居座った。
その気品高い外見、まだ十六歳とはいえ王者の威風が漂っていた。
しかし、今日のシャロスはいつものように、瀟洒に振舞うことが出来なかった。
高貴な貴族服の下で、下賎な欲情が出口を見つけることが出来ず、彼の体内で暴れる。
シャロスはそれを顔に出さないように努めた。
執政殿に群臣が集まり、官位に従って近くから遠くへ立ち並んでいた。
シャロスの王座は高く設置されているため、彼を見つめるのに、必ず見上げなくてはならない。
もちろん、理由も無く王子に眼を飛ばす人間は誰一人いない。
それを知っていても、シャロスは自分のいきり立つ股間がばれてしまわないか、と心配していた。
「殿下、ご機嫌麗しゅうこと」
突然、誘うような甘い声が響いた。
シャロスが声の方を見ると、王座より五段ほど下がったところに、皇后リテイアの姿が現われた。
王子がいる位置と床の間に十段差があり、それはリテイアは群臣よりも高い地位を持つこと表す。
今日のリテイアは、濃紺のドレスを着ていた。
切り開いた胸元に、趣向が凝ったリボンを結ばれ、その中心は赤い宝石がはめてある。
肉感のある乳房はドレスに持ち上げられ、魅惑な輝きを放つ。
胴体はヘソまで締まり、女らしいくびれが現われる。
紺色スカートの中央は白い三段フリルが挟み込まれ、その鮮やかさに発見した者は驚く。
スカートの柄は高級感のある刺繍が二枚構造に施され、彼女の下半身を装飾する。
その煌びやかな出で立ちは人目を奪う一方、
一体どれほどのお金を費やしたかと想像したくなるほど豪華さがあった。
しかし、その服飾は彼女の魅力を最大限に引き立てたことに、誰も疑うことが出来ない。
外に露出したうなじや胸肌は、男の欲情をそそるのに充分だった。
艶麗な笑顔と人を見下ろすようなな目付きは、他人をひざまずかせるような魔力がある。
いつもなら、シャロスは嫌悪感溢れる気分になるはずだった。
しかし、今日のシャロスは彼女を見た途端、言いがたい甘い気持ちが心に充満した。
股間の一物は今でも無かったほど苦しむ。
昨夜見た彼女の肢体が、まるで悪魔のように浮かび上がる。
魅惑的な微笑み。
自分をあざ笑うかのような目線。
いやらしくひねる太もも、黒い下着に包まれた神秘の区域。
このまま彼女の淫乱な体に抱きつき、成熟した乳房をしゃぶりたい衝動が、シャロスを激しく襲う。
彼女の濡れた唇と重ね、舌を中に入れて絡められる。
彼女にいやらしい手に股間の一物を握られ、色っぽい言葉をかけられながら射精させられる。
リテイアの艶美な姿を見れば見るほど、シャロスの中に妄想が大きく膨らんだ。
(そんな……!くっ、彼女に一回イカされたぐらいで、こんなになるなんて……)
シャロスは渾身の意志をかき集め、やっとの思いでリテイアの体から目を離した。
しかし、数秒もたたないうち息苦しくなり、あまりにも切なく胸が詰まってしまう。
シャロスは再び首をひねると、ちょうどリテイアもこちらに笑顔を向けてきた。
その笑顔に触れた途端、まるで年上の綺麗なお姉さんに恋をしてしまった男のように、
シャロスは照れくさそうに顔を赤らめた。
(シャロス、しっかりしろ!あの女は、男なら誰でも喜ぶ、娼婦のような女だぞ!
しかもあいつはお前の敵だ!いつまで惑わされてるのか)
彼は額に汗をかき、自分を叱責した。
だが、彼女を見れば見るほど、リテイアの豊艶な体が彼の脳に焼きつく。
「皇后陛下、お言葉ですが……殿下より遅く到着するのは、いかがなことかと」
と、一人の臣下が前に出て、厳しい口調でリテイアを咎めた。
その男は灰色の眉と髭を伸ばし、満面の正気で凛としていた。
その名はスデラス伯爵、王国軍を率いる五将軍のうちの一人で、中央軍を統制している。
武人らしい面影からも分かるように、根っからの熱血漢である。
「あらスデラス伯、今日もお元気で。わらわは少し身内の用事ができたため、仕方なく遅れましたわ」
「たとえ皇后陛下というお方でも、殿下を待たせるのは大いなる侮辱行為であり、罰を受けなければならな
い」
「ふふふ、スデラス伯ったら、大袈裟ね。それでしたら、侮辱かどうか、
殿下ご本人に聞いてみましょう。ねぇ、殿下、どう思われます?」
そう言うと、リテイアはくすりと微笑み、シャロスの視線を絡めるように見つめた。
彼女の嬌艶な仕草を見ると、シャロスの背筋がぞくりとした。
「ねぇ、殿下、わらわは今回、本当に仕方なかったのですの。
心の中でちゃんと反省するから、見逃してくれない?」
リテイアの優しい語り口は、シャロスの心をくすぐった。
「う、うん……皇后様も多忙の身。今回は特別に許そう」
「ふふふ、聞いたかしら、スデラス伯?殿下も許してくれるって。これでまだ意見あるわけ?」
「……いいえ。殿下がそうおっしゃるのなら」
スデラス伯爵は一歩下がった。
「さて、今日の朝会を始めよう」
そう言った後、リテイアはシャロスに向かってこっそりとウィンクを投げた。
それを見て嬉しくなったことに、シャロス自身はまだ気付かなかった。
いつもなら精力的に臣下の報告に耳を傾けるシャロスであったが、
今日に限って一刻も速く終わってほしいと思った。
彼はもともとエナによって欲情が引き起こされ、
それがリテイアと対面した後、更に油に火が注ぐ状態となった。
おもてでは臣下の言葉を聞くふりをするが、裏では股間をしごきたい願望で頭一杯だった。
「……と思われます。ところで、トーディザード卿にお伺いしたいことがありますが」
「何でしょうか、オイバルト殿」
突然、場の空気が険しいものへと変わった。
シャロスもそれに察し、発言者のオイバルトを見た。
三十代の活力的な男で、物事をはっきりと言う人間である。
その権威を恐れない性格が災いし、同僚から推挙されることはなかなか無い。
そして今も、彼は自分より位が遥かに高いトーディザード宰相に、意見を述べようとしている。
「トーディザード卿、失礼を承知しておうかがうが、王都の近郊で王家の名を騙り、
農民から土地を取り上げる事件をご存知ですが?」
トーディザードはふんと鼻を鳴らし、
「オイバルト殿は随分お暇のようですな。そんな風の影のような事に、いちいち労力を費やしておられるの
か」
「しかし、もしそれが本当であるとしたら、王に反逆を企てると同様の重罪でございます」
オイバルトは一歩も引かなかった。
「オイバルト殿、それはあなたの管轄範囲ではないはず。
土地関係のことなら、そちらの専務機関がわしに報告してくるだろう」
「その専務機関が機能していないとしたら、いかがでしょうか」
まさに一触即発の場面だった。
その時、リテイアの心地よい声が割り込む。
「オイバルト殿もトーディザード卿も、少し落ち着きなされ。ここでずっと争っても、
結論は出てこないでしょう。今日の殿下は、気分がまだ優れないようですし……ねぇ、殿下?」
リテイアは意味ありげに、シャロスの股間を一瞥してから、ニコッと笑った。
「あ、ああ……」
シャロスは顔を真っ赤に染めた。
「しかし、私には確かなる証拠が……」
「オイバルト殿、いいかげんにしなさい。わらわは殿下を休ませようと言ったのよ。
国を案じるのなら、まず殿下の身を案じなさい」
オイバルトはしばらく黙った後、
「はっ。度が過ぎたことを、お詫び申し上げます」
とシャロス王子が何も異論を返さないことに驚きつつ、引き下がった。
「今日の朝会は、ここでおしまいにしましょう」
リテイアはそう宣言した。
群臣の中には、シャロスの様子におかしいと感じた者もいた。
しかし、彼らはリテイアの言ったとおり、それを王子はまだ病み上がりであると解釈した。
シャロスは一足速く執政殿から出た。
彼は自分の失態を反省しながら、一刻も早く誰も居ない場所へ行きたかった。
(くっ……なんてことを!あの女の姿に、自分を見失うとは)
リテイアが見えなくなってから、シャロスはやっと我に帰り、そして自分の不甲斐無さを悔やむ。
メイド服のエナはすかさず彼の側へ駆けつき、
「王子様。リテイア様より伝言です。昼食を共に進めたいため、ぜひ後宮へお越し頂きたいとのことです」
一瞬、シャロスの頭にリテイアの妖艶な笑顔が横切る。
彼は慌てて頭からその念頭を追い出し、
「ふん、彼女に伝えとけ。私は体が不調であるゆえ、参られないと……」
「あら、せっかく殿下のためにいろいろ用意したのに」
突如、美しい女声がシャロスの言葉を遮る。
そして次の瞬間、シャロスはその人物から放たれた香りに反応し、彼女へ振り向いた。
濃紺のドレスを着たリテイア皇后と、エナと同じ顔立ちのマナがそこにいた。
マナはエナと同じメイド服を着て、悪戯っぽい笑顔を浮かべていた。
「皇后様……」
「ねぇ、殿下。今日どうしてもお越し頂かないの?」
リテイアはやや悲しげな表情を作る。
彼女の熱っぽい視線に見られると、シャロスの胸は破裂しそうになった。
彼は罰悪そうに相手から視線を逸らし、
「し、しかし……」
「わらわは殿下の体を思い、回復を速める滋養品を選りすぐりましたの。
……ふふふ、殿下の体も、きっとそれに喜ぶわよ」
リテイアの言葉は、シャロスの妄想をかきたてる。
彼女についていったら、何が起こるかわからない。
しかし、むしろ何かが起きると思うと、シャロスの胸に妖しい期待が躍り出る。
理性と欲望は互いに争い、彼の心を苦しめる。
「ふふふ、迷っているようですわね。とりあえずわらわに付いて来ましょう。
途中で意見が変わったら、わらわも止めませんわ」
「う、うん……」
シャロスは迷った表情のまま頷いた。
彼女について行ったら、きっともう意見が変わることは無いと分かっていたが、彼にはどうすることもでき
なかった。
しばらく歩いていると、后妃や女召使いたちが住んでいる区域に足を踏み入れた。
ここは王族を除けば、女性のみが入れる禁区である。
その理由もあって、宮殿全体を守る近衛隊は女性のみ構成される。
近衛隊隊長のレイラは太子派であるため、リテイアの勢力下にある後宮は普段から近衛隊と距離を取ってい
る。
そのため、後宮の情勢は不透明である。
シャロスはまわりの建物を見て、ふと小さい頃を思い出した。
あの頃、ここのあるじは彼の母上であった。
彼の幼年はここで母上と共に過ごし、そしてレイラと知り合ったのもここの庭だった。
「殿下……殿下ったら!」
「はっ!」
シャロスの目の前に、リテイアのやや不機嫌な顔があった。
「どうしたでしょうか、皇后様……」
「殿下ったら、さっきからずっと上の空。わらわという人が側にいながら、何をお考えでしょうか」
リテイアはまるで恋人に向かって拗ねる様な口調で言った。
恋愛経験がまったく無いシャロスは、すぐに飲み込まれてしまった。
「い、いいえ……」
「殿下、いいかしら?殿下は今、わらわに招かれています。だから、わらわ以外の女性を、考えてはなりま
せぬ」
「は、はい……」
シャロスは左右をチラッと見た。
エナは相変わらず無表情だが、マナはニヤリと微笑んだ。
その意味ありげな笑顔に、シャロスの顔は赤くなる。
道で出会った人は、みんな女性であった。
当然といえば当然だが、自分だけ男という環境に、シャロスは焦りを感じた。
しばらくすると、彼らは一番豪華な屋敷にたどり着いた。
正門から十数人のメイドが立ち並び、リテイアやシャロスをみかけると、みな恭しく頭を下げた。
彼女達もまた、マナやエナと同じ服飾をし、彼女達二人に負けないぐらいの美貌の持ち主だった。
シャロスが連れて来られたのは、趣きのある小さめな部屋であった。
部屋の中央に円卓があり、その上には綺麗なテーブルクロスが敷いてあった。
「わらわは殿下の近くに座りたいから、このセッティングを許してください」
リテイアの言葉通り、テーブルの向かい側に置かれた二つの椅子の間は近かった。
彼女とシャロスが席に着くと、マナはワインとグラスを持ってきた。
エナは料理の準備を進めに行ったのか、どこかへ消えた。
「ふふふ、わらわと殿下との、お近づきの印よ」
と、リテイアは注がれた赤ワインを口元に持っていった
シャロスもおもむろにそれを口元に持っていくが、眉をしかめた。
記憶の曖昧なところ、どこかいやな感じがした。
「あら、まさか殿下はわらわが毒を入れたと疑っているかしら」
「いいえ、そんなことを、私が思うはずはありません」
「では、なぜ殿下は嫌がるようなそぶりを見せるのです?ふふう、わらわが先に飲んで、潔白を証明いたし
ます」
リテイアはグラスの縁につややかな唇を乗せ、グラスを傾けた。
ワインは彼女の口へなまめかしく流れ込む。
その量が半分ほど減った時点で、リテイアは唇を離れた。
グラスの縁に、赤いルージュの跡がくっきりと残った。
「いかがですか、殿下?」
「皇后様が私を害するなど、最初から思っておりません。皇后様も、ご冗談を……」
シャロスはやや引きつった笑顔を浮かべて、自分のグラスを持ち上げた。
しかし、その手をリテイアが遮り、
「いいえ、冗談ではありませんわ。殿下はきっと、そのグラスが細工されているじゃないかと、
疑っていることでしょう。殿下には、私のグラスを飲んでいただきます」
リテイアはそう言うと、自分が飲んだグラスを、シャロスの口元へ近づける。
彼女の言動にシャロスは困惑した。
それを見たリテイアは、悪戯っぽい表情を浮かべる。
「ふふふ……さあ、殿下。口を開けてごらん」
魔力を帯びた音色に、シャロスのあらがう意思が薄くなる。
リテイアはルージュの跡が残った側を、シャロスに向けた。
(はぁ、そ、それは……!)
そこにリテイアが口付けをしたと思うと、シャロスの股間が反応した。
「さあ、殿下。遠慮しないで下さい」
ついに、シャロスの唇はルージュの跡と重なる。
甘いぬくもりと、ワインの芳ばしい味が口の中に広がる。
シャロスはまるで、リテイアの唾液を味わっているような居心地になった。
やっと全て飲み干すと、アルコールが彼の身をめぐり、血流を速めた。
リテイアは突然身を乗り出し、シャロスの耳元でささやく。
「これで殿下はわらわと間接キスを交わしちゃったね」
「あっ!」
シャロスは思わずビクンと跳ねた。
横からマナがくすくす笑っているのを見て、彼は自分の失態に気付き、更に顔を真っ赤に染める。
「ふふふ……殿下って本当に面白いお方ね。さあ、マナ。あなたは下がって頂戴」
「はい、リテイア様」
マナは一礼すると、扉を閉じて退出した。
二人っきりになると、部屋中に微妙な空気が流れる。
「皇后様、私は……」
突然、リテイアはシャロスの唇に柔らかい指を立て、
「だめよ、シャロス。二人っきりになったとき、わらわのことを『お母さん』と呼ぶの、約束したじゃない
?」
彼女の優しい語りは、昨日と同じ妖艶な悪魔になった
シャロスの胸がドキドキに鳴り続き、息が浅くなった。
「うふふ……そんな緊張しないで。それとも、硬くなったあそこのせいかしら……?」
「ああぁっ!」
シャロスは悲鳴を上げた。
テーブルの下から、リテイアの足先が彼の股間に当たった。
「いやらしい子ね。さっきからずっと硬くなってるのを、わらわが知らないとでも思って?」
リテイアは小さな子を咎めるように語り口だった。
その言葉は、まるで鋭い刃物のように、シャロスの心の防壁を切り裂いた。
「ああ……ご、ごめん……お母さん!」
「ふふふ……こんなビンビンになっちゃって!そんなにしてほしかったら、自分から腰を動かしてみたら?
」
「はぁ、はあん……」
シャロスは切ない息を吐き、言われたとおりにリテイアの足にあそこを懸命にこすりつける。
「ふふふ、そうよ。そうやってどんどんスケベになっていきなさい……」
「お母さん、お願い……また、昨日のように、イカせて……」
「だめよ!言ったでしょ、あそこがイライラしたとき、ちゃんと自分で処理しなさいって!」
リテイアのつま先は布を通して、シャロスの一物を摘み、激しく動かせる。
シャロスの余裕が消えた顔には、どうしようもない屈辱と、妖しい悦楽が入り混じる。
「あ、朝起きたとき、一回やったの……ちゃんと、お母さんのことを思いながら……」
「あーら、なんて淫乱な子かしら!朝一度抜いたのに、またこんな硬くさせるなんて!」
「ご、ごめんなさい!で、でも……エナが、エナがあそこを舐めて……そ、それが途中で終わって……」
「あら、エナがそんなことを。……だれか!」
リテイアが高らかに呼び出すと、すぐに駆け付く足音が起きた。
「はい」
「マナ。エナをここに連れてきなさい」
「はい」
しばらくすると、顔が瓜二つの少女が部屋に入り、頭を伏せる。
リテイアはポニーテールの少女に向かい、
「エナ、殿下から聞いた話だと、あなたは朝ご奉仕をしましたね」
「はい」
「しかし、行為は最後まで行き届いていないそうね」
「はい」
「なぜそんな中途半端なことをなさるのかしら。わらわがあなたに、
殿下の煩悩を解かせる為に置いたのよ。
それなのに、行為を怠るなんて……いったいどういうつもり?」
「申し訳ありません。しかし、王子様自身がそれを嫌がっておられまして……」
「殿下が……?その言葉に嘘はないのか?」
「はい」
エナは淡々とその時のいきさつを述べ続けた。
マナはかたわらで時々盗み笑いをこぼし、
それとは対照にシャロスは地面に穴があれば入りたいほど恥ずかしかった。
「ふふふ……はははは!」
「こ、皇后様!笑わないで下さい!」
「ふふっ、これは失礼したわ。その時の様子、大体分かったわ。エナ」
「はい」
「あなたは勘違いをしてるのよ」
「勘違い……ですか?」
エナの瞳に、不思議そうな輝きがした。
「あの時王子様は確かにイヤだとおっしゃったが、それは口先だけなのよ」
「では、その時の言葉は偽りだったということですか?」
エナの生真面目な態度に、リテイアは失笑した。
「そうでもないわ。体の方はしてほしいのに、理性の方がそれを恐れている。
殿下はその時、自分の感情を勘違いしているのよ。覚えなさい、殿方はみんな射精が大好きなの。
一度勃起したら、ちゃんと最後までやりなさい」
「はい、心得ました」
「ふふふふ……殿下、私の言った通りでしょ?彼女はとても素直な子なのよ。
今回は殿下も悪いのよ。エナはあなたの召使いだから、彼女にちゃんと命令しないと」
「は、はい……」
シャロスは叱られた子供のように、口答えが出来なくなった。
「それにしても、殿下のあそこ……すっごく大きくなってるわ。朝から今まで、ずっと我慢していらっしゃ
ったのね」
「はぁ、うっ……うう!」
リテイアの足がまた上下にしごく。
その微妙な刺激に、シャロスは喘ぎ声を漏らした。
「ねぇ、殿下。このままでは、いつまでもうじうじしているつもりなの?」
「う、うう……」
「殿下も、速く抜きたいでしょ?」
「は、はい……抜きたいです!」
シャロスは思わず淫語を繰り返した。
彼のペニスは幾度と挑発され、もはや一触即発の状態だった。
「ふふふ……じゃあ、今度こそエナに役目を果たしてもらおうかしら」
「えっ?」
リテイアの足はシャロスの股間から離れた。
「あ、ああっ」
「さあ、殿下。今度はちゃんとエナに指示するのよ」
「し、指示って……」
「殿下のおちんちんに、ご奉仕させることに決まってるじゃない!」
「そ、そんな……!」
その浅ましい発言は、シャロスのプライドに邪魔されて言えなかった。
彼は今日初めて自慰したが、なんとなくそれはいけない事だと感じた。
女にあそこを触られるなんて、もってのほかだ。
「殿下、その姿のままじゃ、とても苦しいでしょ?それに、大臣だって貴族だって、
みんなやってることなのよ。ただ、おもてでは誰も言わないだけよ。
殿下も将来立派な王様になるんだから、今からちゃんと慣れておかないと、ね?」
「うっ……」
リテイアの言葉に、シャロスは動揺した。
欲情に混乱した頭は、その真偽を判断する力が無かった。
「さあ、言ってみなさい。『エナ、そのいやらしい口を使って、
私のおちんちんをしゃぶり、汚いチンポ汁を出させてください』って」
(くっ)
とても屈辱的な言葉であった。
しかし、そんなことよりも、股間から広がる苦悶のほうがもっと苦しかった。
シャロスは口を開き、泣きそうな声で呟いた。
「エ、エナ……その、いやらしい口を使って、わ、私のおちんちんをしゃ、
しゃぶり……汚いチンポ汁を出させてください!」
「はい、かしこまりました」
エナはシャロスのズボンや下着をおろし、慣れた手つきで彼の腫れたペニスを露出させた。
淫猥なオスの匂いが部屋中に広がる。
シャロスはとても惨めな気持ちになった。
側ではリテイアのみならず、メイドのマナまで、彼の下半身を見てくすくす笑っていた。
エナの息が掛かると、ペニスは更に大きく膨らみ、表面に浮かぶ血管がドクン、ドクンと蠢く。
ペニスの先端はぬるぬると湿っていた。
エナは愛おしそうに根元の部分に手を添え、彼の先端から口を覆い被さる。
「あああぁっ!」
とてつもなく敏感になった部分から、雷を撃たれた様な快感が走る。
エナが頭を前後に動かすたびに、彼女のすぼめた口が竿をこすり、舌が亀頭をなだめる。
「はあぁあぁ!も、もう我慢できない、ああ、あああぁあああ!」
シャロスは狂い出すような声で呻いた。
彼はエナの頭を掴むと、シャロスは腰を突き上げた。
「うぅんん――!」
エナはくぐもった悲鳴を上げた。
しかし、シャロスはそれにかまわず腰を振った。
散々溜まった濁汁は、凄まじい勢いでエナの喉へ直射する。
大量の粘液にエナはやや眉をしかめたが、ゴクン、ゴクンと飲み干した。
やがて、シャロスの一物は何もかも吐き出し、小さく萎縮してエナの口からはずれた。
彼は思わず尻を床につかせた。
「あーあ、もうイッたなんて……いくら焦らされたからと言って、速すぎるわ」
「ご、ごめんなさい……でも、どうしても……」
「殿下、早漏れの男性は、女性に好かれないわよ。これからはちゃんと長持ちするよう、気をつけなさい」
「はい……」
「それと、これから自分でイクのが難しいとき、ちゃんとエナに手伝ってもらいなさい。
そのために、彼女がいるんだからね」
「は、はい、皇后様……」
シャロスはそう言って、ついに気を失った。
王子が確実に堕落していく様子を見て、リテイアは会心の笑みを作った。
第三話
最近、シャロスはイライラするようになった。
皇后邸の出来事から数日の間、シャロスは毎日欠かさず自慰をしていた。
彼が行為をする時、いつもリテイアの妖艶な肢体を思い浮かべていた。
黒いブラジャーに包まれた、豊満な乳房。
絹の薄地を通り抜けて、見えそうで見えない乳首。
悩ましい腹や、背中のライン。
そレースの刺繍を施されたショーツ。
刺繍の合間に、女性の淫靡な茂みが浮かんでくる。
そして、その体の持ち主が、魂を吸い込むような深い瞳で、
シャロスの行為を見下ろしながら、薄笑いを浮かべ……
そこまで想像すると、シャロスは例外なく果ててしまう。
残されるのは激しい疲れと、自分に対する虚しい気持ちだった。
欲望に負けて自慰に耽ってしまい、そしてリテイアを思いながらオナニーしてしまうことは、
彼にとって屈辱的なことであった。
召使いとして彼の側にいるエナも、厄介な存在だ。
最近、シャロスは自主的に彼女と距離を置くようにしていた。
エナは確かに一流のメイドだ。
彼女が用意してくれ服飾はその日の気候に相応しく、シャロスに快適な一日を過ごさせてくれる。
彼女が調理してくれ食事はシャロスの食欲を満たし、今まで食べ慣れた宮殿料理に無い味を作ってくれる。
喉が乾いたと思った時に、紅茶を持ってくる。
疲れたと思った時に、肩を程よい力で揉んでくれる。
シャロスが口に出さずとも、彼女は彼の心情を的確に読み取ってくれる。
彼女の奉仕は、実に用意周到で気持ち良いものだ。
そして、その存在感も、徐々に大きな物へと変化しつつある。
シャロスは彼女の可愛らしい姿を見るたびに、頭を悩ませた。
エナの背後に、皇后の陰謀が隠れていることは明白だった。
しかしその一方で、彼はエナをはっきりと拒絶することができない。
エナの艶やかな柔肌と、少年の性欲をくすぐる身のこなし。
それに、彼のどんな命令にも従ってくれる絶対的な従順さ。
皇后リテイアとは違い、彼女はまた違うタイプの魅力があった。
今日もシャロスはぼんやりと、腹心であるレイラから報告を受けていた。
彼はほとんど聞き流しながら、数日前に見たエナの半裸を思い返した。
「……それと、殿下……あのエナという者ですが、彼女は明らかに皇后側の人間です。
そのような者を殿下のお側で置いていかれるのは、いかがなものかと」
「ああ……」
「…………殿下!」
突然、レイラは口調を強めた。
彼女の意志がこもった口調に驚き、シャロスは目を丸くして我に帰る。
「お言葉ですが、殿下は最近、心が廃れているように思われます」
「えっ?」
「何よりも、殿下は以前のような気迫がございません。
殿下は万民を救う立場の者、どうかご自分を戒め、その示しをつけてください」
レイラの表情は厳しかった。
彼女にそれほど叱責されるのは、子供の時以来のことであった。
シャロスは生来高貴な立場にいた者だが、彼は他人の忠告を素直に受け入れる人間である。
だから、シャロスはすぐさま自分の失態に気付いた。
「……すまない、レイラ。お前の言うとおり、私は最近どうかしている。お前のおかげで、目が覚めたよ」
「分を超えた言葉で申し訳ありません。どうか、お許しを」
「いいえ、それでいいのだ。お前はいつも私の鏡のように、私の過ちを諌めてくれる。これからも、私を支
えてくれ」
「勿体無いお言葉です」
レイラは頭を深々と下げた。
彼女にとって、シャロスの言葉はいかなる時でも至上のものであった。
シャロスは目を輝かせ、表情を明るくさせた。
それに伴って、彼は聡明な頭脳を素早く回転させた。
「こうしてはいられん、レイラ!」
「はっ」
「税務管理局のイルバフ長官に伝えろ。王国陸送隊の貿易収支を徹底的に調査させろ」
「はっ。しかし、それは……?」
「陸送隊指揮官のザーロンが提出した出納帳に目を通したが、前年と数字が合わない箇所がいくつもある。
ザーロンのやつ、私をひよっこだと思って油断しているだろう。あやつは、皇后派に賄賂を贈って今の地位
に登り詰めた者だ。
ふん、皇后の傘に入っていれば問題無いと思って安心しているだろうが、そうはさせない」
「はい。……ふふっ、あの『狐目のイルバフ』にかかれば、すぐに尻尾が掴まれることでしょう」
レイラは思わず笑いをこぼした。
税務局主席を努めるイルバフ氏は、その老獪さで王宮内外に知られる棘だらけな人間で、
干からびたパンから水滴を絞りだせると評価される人物である。
彼にザーロンを搾り取らせるには、これ以上ないほど適任している。
「証拠のつかみ次第、それをオイバルト卿に伝え、ザーロンを弾劾させよ」
「はっ」
「それと……先日に行った皇家艦隊再建の進展はどうなったか」
「相変わらず宰相のトーディザード卿が所々横槍を入れているため、資金の調達が停滞しているようです」
レイラは難色を浮かべた。
シャロスの国は周辺諸国の宗主国になって、長い間戦争が起きなかった。
そのため王国軍の戦力は下がり、とりわけ存在価値の低い海軍隊は完全に廃れた。
しかし、シャロスの代になってから、海賊や他国の秘密私掠船が横行し、
海上運輸が思うように進まない状態になっている。
そこで、皇家海軍隊の復建を打ち出すのは急務だったのだ。
「やはりか」
シャロスの視線が鋭く険しいものとなった。
彼は立ち上がり、窓の方へ歩んだ。
秀麗な顔立ちは光に照らされ、色の深い瞳に知恵の輝きが宿りはじめる。
レイラはそんなシャロスの姿を見るのが大好きだ。
彼の凛々しい後姿は、決して他者の追随を許さない。
早熟した英断は、どんなことも解決してくれるような安心感がある。
――王子様はいずれ英邁な国王となり、歴史に名を残すほどの名君となるだろう。
レイラは、そんな尊敬の意を心に抱き、憧れがこもった視線でシャロスを見続ける。
ふと、シャロスは対策を思い浮かんだかのように振り返り、
「テクド商会に使者を遣わせろ。彼らに資金投資を協商させよう」
「……テクド家は財界でも屈指の商人連合。あそこは中立しているとはいえ、我々に協力してくれるだろう
か」
「一年前、テクド傘下の商人グループが冤罪をかけられた時、私が手配を取り消したことがある。
テクド家のライト子爵は恩義を重んじる男だ。やつなら、我々に協力してくれるだろう。
艦隊が建設できた暁に、海上貿易を彼らに率先させよう。そうすれば、喜んでついてくれるだろう」
「なるほど。テクド家は長年、皇后派に味方するハエリオン家とライバル関係にある。
これで我らの味方に引き入れれば、一石二鳥ですね」
「ああ。それと、王族の出費もできるだけ節約させよう。
今年の南テドン地方は干ばつだと聞くが、減税を命じよう」
「民もさぞ、喜ぶことでしょう」
「我々上部の人間が浪費しているんじゃ、格差が広がってしまうばかりだ」
「殿下、なんとお優しい心を」
「これぐらいは当然の事だ。レイラ、私はまだまだ足りない部分が多いが、
できるだけ多くの人を幸せにしたいと思っている。今後とも、あなた達の良き働きを期待する」
「有難い御言葉でございます。……では、私はこれにて」
レイラは一礼をすると、部屋から退出した。
その後も、シャロスは憮然と眉をしかめて考え事をした。
毎年、王室の出費は高額なものとなっている。
その一番の原因を、シャロスはよく知っている。
皇后リテイアの浪費なのだ。
後宮に関する支出項目には不透明なものが多く、額面も非常にでかい。
彼女の権力や地位もあって、シャロスの配下が表立って詰問することは難しい。
(この問題、やはり私自身が決着をつけなければ……)
シャロスはため息をつくと、部屋から出た。
「王子様、どちらへ……」
シャロスはそばを見ると、そこには恭しく待っていたエナの姿があった。
(ふん、私を監視するつもりか)
「剣技場だ。私がどこへ行こうと、お前の意見を聞く必要があるのか」
「いいえ、滅相もありません」
シャロスはわざと冷たい口で答えると、エナはうつむいた。
そうでもしないと、エナの妖しい魅力に惹かれそうで恐いのだ。
シャロスはまつりごとはもちろん、剣術、馬術、弓術などの武術も一通りできる。
そして、彼は日課のように毎日何らかの運動を行ってきた。
最近特にあらぬ感情に惑わされたこともあって、シャロスはそれを運動で発散しようとした。
シャロスは早足で皇居を出て、苛立った気持ちで御道を歩いた。
エナはそれ以上のことを尋ねず、ただ黙ったまま彼の後を付いた。
ちょうどその時、向かい側からやってきた一両の馬車は、彼の横に止まった。
壮麗な金色紋章が施されたキャリッジは、持ち主の豪華にこだわる風格を物語った。
馬車の窓から、柔らかい女の声が伝わる。
「あら、やはり殿下でしたね」
皇后リテイアの美しい笑顔が覗き出て、シャロスに向けられる。
彼女の妖艶な目元を見ると、シャロスの心は大きく動揺した。
「リテイア皇后……!これは、奇遇ですね」
「ええ、そうですわね。付き人がほとんどいなかったものですから、最初は殿下だと気付きませんでしたわ
」
「私は、堅苦しいのが嫌いですからな」
「殿下らしいお考えですわ。わらわは、丁度ライフォン夫人のところから帰ってきたところです」
ライフォン夫人の名前を聞いて、シャロスは眉をしかめた。
貴族の中では、身分や皇后の威光を頼って、奢侈な生活を送る者が大勢いる。
そんな浪費者達に、シャロスは快いと思うはずが無い。
彼の心情を読み取ったのか、リテイアの宝石のような瞳が輝く。
「あら、今日の殿下は随分とご機嫌斜めですね」
「ふん……そんなことは無い」
シャロスはリテイアから目を逸らした。
彼女の美麗な顔立ちを見ると、あの淫らな記憶を思い浮かびそうで恐かった。
「ところで、殿下はこれからわらわと一緒に来て頂きませんか?もちろん、エナも一緒に」
「えっ?」
リテイアの突然の誘いに、シャロスは無意識のうちに顔を真っ赤に染めた。
(リテイアのところに行けば、またあんなことを……でも……)
シャロスは戸惑った表情を浮かべた。
心の中で理性の警鐘が鳴り響いた。
その一方で、リテイアの誘いに従いたい欲望が膨らみ上がってくる。
彼女の挑発的な瞳は、まるでねっとりとした網のように、シャロスの心と体を絡め取っていく。
そんな目で見られると、ひそかにシャロスの股間が硬くなりはじめた。
御者台からマナが降り、馬車の扉を開けて恭しく頭を下げた。
「王子様、せっかく皇后様からのお誘いです。どうか、彼女の厚情をお受けください」
「う、うん……」
シャロスはついに甘い感情に打ち勝つことができず、複雑な気持ちで馬車に乗り込んだ。
エナは馬車の扉を丁寧に閉めると、マナとともに前方の御者台へのぼった。
「どーっ!」
外でマナの元気一杯の掛け声が叫ばれると、馬車はゆっくりと動き出した。
シャロスは馬車に揺られながら、隣に座るリテイアの体を感じた。
彼は一生懸命自分の気を逸らそうとしたが、忘れようとすればするほど彼女を意識してしようがなかった。
今日のリテイアは羽飾りの帽子をかぶり、人の目を惹く真紅のシルクドレスを着ていた。
絹のすべらかな材質は光沢を反射し、首より下げた銀のネックレスははだけた谷間にぶら下がる。
大きな胸元は、ギリギリなところまで露出し、その豊満さをたっぷりと見せ付ける。
目の外縁から入る彼女の乳房は、馬車の動きと同調して揺れ、シャロスの欲望をかきたてる。
馬車が道を曲がる時、シャロスはうっかりリテイアと体を密着してしまい、その肌の柔らかさにどぎまぎし
てしまった。
その時リテイアの体から発される香りは、シャロスの眠っていた感情を呼び起こした。
(……はっ、この匂いは……)
シャロスは思わず、生まれて初めて女性にイカされた夜のことを思い出した。
あの夜も、リテイアの体からこの香りが漂っていた。
この淫靡な香りはあのいやらしい行為とともに、
シャロスの脳の深い場所に烙印をつけ、彼女の虜にしょうとしていた。
「殿下ったら、またぼうっとしちゃって。わらわと一緒にいるのは、そんなに退屈なのでしょうか」
リテイアは意地悪そうな笑みを浮かべながら、甘ったるい声で言った。
意識が薄れたシャロスは、自然と「いいえ、そんなこと無いよ」と答えそうになった。
しかし、彼が口を開こうとした時、ふとリテイアは自分にそのセリフを言わせるのが目的であると感じ取る
。
(しっかりせねば……!皇后のやつ、また色仕掛けようとしたな。だが、今回こそ……!)
シャロスは自分に言い聞かせるようにして、努めて正気を保とうとした。
「……いいえ、私はただ考え事をしまして」
「おや、わらわの見当違いでしたか。して、一体どんなお考え事を?」
「ついさきほどまで帳簿と睨めっこしていたが、今年の王宮予算のやりくりは大変厳しくて。
これでは、王子である私が、先に餓死してしまうじゃないかと、不安で不安で仕方がありません」
「ふふ……殿下の冗談はまことに面白いですわ。王子様が餓死なんてしたら、この国では誰も飽食できませ
んわ」
「ははは、確かにそうかもしれません。しかし私は、王室が少しでも浪費を抑えなければならないと考えて
いる。
皇后様にも、ぜひ自分の振る舞いを見直し、私に協力してほしいかと存じます」
シャロスの口調は一転して、鋭いものへとなった。
「あら、わらわが無駄使いをしているとおっしゃるのですか」
リテイアは目を細め、声を低く抑えた。
だが、シャロスは一歩も引かなかった。
「……かねてから、私は皇后様の出費に疑問を持っております」
彼は目線を伏せながらも、言葉を緩めなかった。
ここで押し進まないと、また皇后が言い逃れてしまいそうだからだ。
「そんなことを言われるとは、心外ですわ。
……そうですね、せっかくですから、殿下にはあそこを見てもらいましょう」
「あそこ、とは?」
「ふふふ、とてもいい場所ですわ。……この暑い季節を過ごすのに、ぴったりの施設ですわ。
これを見ていただけたら、殿下もきっと考えが変わることでしょう」
シャロスはまだ質問しようとしたが、途中で口を閉じてしまった。
なぜならこの時、リテイアは孔雀の羽毛で編まれた扇子を取り出し、自分の体をあおぎ出したのだ。
彼女はさきほど何か激しい運動をしたのか、体から汗の匂いや、
それ以外に何かいやらしい感情を催す匂いが染み出る。
それが彼女の香水と混ざり合い、扇子のそよ風に乗って伝わってくる。
その匂いを嗅いだだけで、シャロスの頭はぼうっとなり、股間の一物に血が集まった。
リテイアの女性特有の体臭は、シャロスがまだ知らない官能的なものであった。
彼は自分自身でも気付いていないうちに、リテイアによって性への欲求を開発されていた。
思春期にある純潔だったはずの幼き心は、淫猥なものに興味を抱き始め、徐々に黒い欲望によって染まられ
ていた。
シャロスは自分の中で膨張する未知なる興奮に、うすうす背徳間を抱いていた。
しかし、まだ色事を接して日が浅い彼には、その感情はどうすればいいのか分からなかった。
目線が泳いでいる間、突然リテイアの滑やかな腋が目に入った。
白く透き通った腋は、その露出した胸や背中と同調して、美しいラインを描いていた。
彼女が扇子を軽くあおぐ度に、綺麗な柔肌が見え隠れしてシャロスの視界をくすぐる。
「殿下、わらわの体になにかありますか?」
「えっ?い、いいえ……」
シャロスは顔を真っ赤にして、慌ててうつむいた。
彼の恥じらう仕草に、リテイアはかすかにほくそ笑む。
彼女はさりげなくシャロスの股間に腕を伸ばした。
「殿下の様子は、何かおかしいですわ」
突然、リテイアの人差し指に力を入れ、シャロスのすでに勃起した股間の先端を軽くつついた。
「あぁっ!」
「あーれー、どうしたのかしらね?殿下のあそこ、ビンビンに立っていらっしゃるわ」
リテイアは悪魔のように口元を吊り上げる。
シャロスが取り乱している間、リテイアは掌を彼の股間の上を乗った。
手の重さに反応して、彼の心も一物もビクンと躍った。
その妖しい感触に、シャロスは皇女を非難することさえ忘れ、口をどもりながら身じろぎした。
「ひょっとして……殿下は最近、溜まっていらっしゃるんですか?」
「な、なにを仰いますか、皇后様」
「うふふ……でも、殿下のあそこのほうが、正直みたいですわ?」
「あぁっ!」
リテイアが少しりきむと、シャロスは腰を一瞬震わせた。
シャロスは口をパクパクさせて、どう答えるべきか分からず狼狽した。
普段なら一寸と乱れる論理を繰り広げる弁舌も、今では跡形も無かった。
勃起を見破られた恥ずかしさだけでなく、彼女に下半身をいいように操作されたことに、シャロスはいらだ
ちを感じた。
「あれれ、本当に溜まっていらっしゃったんですか。殿下の欲求を解消させるために、
エナをわざわざ置いたというのに。殿下、彼女に抜いてもらいませんでしたか?」
「い、いいえ……」
「はぁ、これじゃあメイドとして失格ですわ。あとで、彼女に厳しいお仕置きをしなくては」
「いいえ、違います!これは、エナのせいじゃありません」
「そうですか。では、どうして殿下の御体が、こんなに苦しい思いをしているのかしら。
……まさか、殿下は自分で慰めていたりして」
「えっ?そ、それは……」
いきなり図星を突かれて、シャロスの顔は青ざめた。
彼がはっきりと否定しない様子を見て、リテイアは驚愕の表情を作った。
「あら、本当にそうなされたのですか」
「う……」
「殿下は国主たる者です、ご自由に振る舞いって結構ですが……
ご自身の手で自分を慰めるなんて、大変お恥ずかしい事ですわよ」
リテイアはあざ笑うかのような、軽蔑するかのような口調で言った。
シャロスはそれを感じ取ると、自分のことがとてつもなく惨めに感じ、恥ずかしい気持ちで胸いっぱいだ。
いま目の前に穴があれば入りたい気持ちになった。
リテイアの言葉は鋭利な刃物となって、普段からの威厳の防壁をズタズタに切り裂く。
そこで剥き出されたのは、年上の美女に弄ばれるウブな少年の姿だった。
「まあ、それだけ殿下が大人に近づいた証拠ですから、わらわは嬉しく思いますよ。
でも、せっかくエナをお側にはべらせておりますから、彼女を使ってあげてください」
「そ、そんなんじゃ……」
「どうか遠慮なさらずに。エナもきっと、そうされることを期待していますから」
「……」
シャロスは母親になだめられた子供のように、顔をうつむいた。
会話してから早々、シャロスにはリテイアを言い返す余裕が無くなってきた。
幸いなことに、そこで馬車が止まった。
マナが外から扉を開けると、シャロスはまるで逃げるように降りる。
彼のあたふたとは対照的に、リテイアはマナの手を借りて、優雅に足を地面に置く。
外の新鮮な空気に触れてから、シャロスの頭はようやくはっきりしてきた。
(くっ……またこの女狐のペースにはまってしまった……このままでは、またあいつらのいいなりになって
しまう……)
シャロスは心の中で嘆きながら、周囲を見渡した。
リテイアに気を取られたため、途中の道のりをほとんど覚えていなかった。
目の前に王宮にも負けない絢爛な屋敷があり、入り口から高級石材をふんだんに使われ、壮麗に積まれてい
る。
正門の真正面に大きな噴水があり、その真ん中に黒曜石の彫像がそびえる。
あたりは半径数百メートルにも渡って、手入れをされた緑の低木が広大に囲み、目を一新させる麗しい光景
を作り出す。
白石で舗装された道は、設計の意図を凝らして低木群とともに円周を描く。
「ここは……?」
「わらわの別荘でございます」
「別荘?」
「ええ。娯楽用に建築されたものですわ。いかがかしら?国中の職人を集めて、作られた場所です」
「……この壮観の裏にどれだけの民が虐げられたかと思うと、心が痛んで甚だしい」
シャロスは心を鉄にして、リテイアへの嫌悪感を思い立たせる。
「民というのは、王室である我々に仕える者。わらわ達を満足させられることこそ、至高の幸福ではないか
しら」
「ふん……」
シャロスは鼻を鳴らし、明らかに不満を示した。
それに対し、リテイアは相変わらずの微笑で、
「どうやら、殿下は気が召されないようですわね。ならば中の様子を、直に見せてあげますわ」
言い終わると、マナが「さあこちらへ」とシャロスをいざなった。
シャロスは仕方なく、渋々と彼女の後についた。
屋敷の中では、外の景観に負けないぐらい豪華なつくりとなっていた。
扉から真紅の絨毯が敷かれ、靴越しに高級そうな踏み心地を感じる。
道中随所に珊瑚の木、東洋の白磁、翡翠や瑪瑙といった貴重な装飾が置かれ、
今まで見た事も聞いた事も無いような品々が、廊下を通り過ぎるたびに出てくる。
シャロスはそれらに目を奪われながら、心の中で疑念を募った。
王子である彼よりも、まるで皇后リテイアの方が金持ちであるようだ。
彼の思考を断たせるように、リテイアは心を撫でる様な柔和な声で話しかけた。
「ところで、殿下は最近お疲れのようですわね」
「どうしてですか?」
「わらわの気のせいなら申し訳ありません。でも、最近の殿下はどうもうわの空が多い様子ですわ。
御体には、もっと気を使うべきですわ」
リテイアの含みのある言葉に、シャロスは顔を赤らめる。
彼は何かを言い返す前に、リテイアは言葉を続けた。
「ここにお越しいただいたのは、殿下の疲れを取るためですわ」
「それは、どういうことだ?」
「殿下は、サウナという言葉を聞いたことあるかしら?」
「サウナ?それは一体……」
「異国より伝わる健康法ですわ。蒸気を発生させ発汗させる事で、
体をほぐす機能があるですわ。ぜひ、殿下にも試して頂きたくて」
「ふん、私にはそんな暇など無い。まだやることが山ほど残っているため、帰らせて……」
「殿下、たまにはごゆっくりなさっても、いいじゃありませんか」
リテイアは湿気を帯びたピンク色の唇を軽く弾ませ、シャロスの腕にしがみついた。
「国も仕事も何もかも忘れ、わらわと二人で、気持ちいいことをしましょう。……ねぇっ?」
リテイアの潤いだ瞳に見られると、シャロスはまるで心が霧に覆われたかのように、意志が朦朧としてきた
。
腕に彼女の豊かな乳房が密着し、男の本能を呼び覚ます。
彼女の言葉には危ない香りが含んでいた。
だがそれは男にとって、また刺激的な事柄であった。
まだ成年していないシャロスでも、その先の事をなんとなく想像できる。
「さあ、一緒に行きましょう」
リテイアはくすりと笑うと、シャロスの手を引っ張って歩き出した。
その女性らしい柔らかい感触に、シャロスの心に甘い感情が広がり、彼女の後に従った。
程なくすると、シャロスは一つの個室に連れ込まれる。
そこにはすでに六人の女召使いが控えていた。
彼女達は左右に三人ずつ分かれ跪き、頭を深く伏せていた。
「「お帰りなさいませ、リテイア様」」
彼女達は頭を下げたまま、語頭から語尾までぴったり一致するように言葉を発した
「今日は、大事なお客様がお見えになるから、丁寧になさい」
「「はい、リテイア様」」
メイド達が異口同音に返事すると、スカートの裾を掴み優雅な姿勢で立ち上がった。
その動作もまた見事に揃っていて、まるで長い間訓練されてきたようだ。
三人の召使いはリテイアに、残りの三人はシャロスの周りに立ち、マナとエナはその場から退いた。
彼女達は顔をうつむき目を伏せていたが、どれもスレンダーな体系をし、上質な美少女であることがうかが
える。
シャロスが怪訝していると、一人の召使いが彼の上着のボタンをほどき、もう一人は背後から脱がせる。
残りの一人は、彼女達から服を受け取ると、丁寧にハンガーにかけた。
三人とも目線を伏せたままで、シャロスと面を合わせなかった。
しかしその動作は非常に慣れたもので、お互い隙間がまったく無い。
そのため、シャロスは抵抗する時間もなく、またたく間に半裸となってしまった。
「ちょっと、これはどういうことだ!」
「殿下、これはこれから行う事のための準備ですわ」
「しかし……」
いいかけた言葉を飲み込み、シャロスは息を止めた。
すでに裸となったリテイアの姿は、彼の心を射止めた。
真っ先に、眩しいほど白くてたおやかな乳房が目に入った。
その色白さは、まるで漆のようにシャロスの脳内を真っ白に染めあげる。
リテイアは恥じらいの表情を微塵とも表さず、メイド達が奉仕する中、
その美しい裸体をシャロスに存分に見せつけた。
彼女のへそのラインに沿って、シャロスは視線を下へ滑らした。
しなやかな腰つきや、肉感のある臀部。
そして正面の股間には、女性の性徴でもある、神秘なる茂みがあった。
シャロスはこれで生まれて初めて女性の陰部を目にした。
何もかも不思議な光景で、リテイアが持つ独特の妖艶さによってそれらがより一層蠱惑的に表現され、
シャロスの男性的な欲情を催した。
リテイアはシャロスの視線を捕らえ、余裕っぽい表情でニコッと微笑みかけた。
その時、シャロスは初めて自分の失態に気付き、思わず顔を熟したトマトのようにして顔を伏せた。
――裸になっているのは相手だというのに、なぜか自分のほうがずっと恥ずかしい。
その屈辱的な状況はさらにシャロスを焦らせ、平常心を失わせる。
ふと、シャロスは自分がメイド達によって椅子に座らされたことに気付く。
そして次の瞬間、メイド達は貴族服の下半身部を正確にもぎ取る。
「あ、そ、それは……」
賢明な少年王を演じてきたシャロスは、すぐにあたふたするばかりの男の子に成り下がった。
メイド達は素早く彼のズボンを、さらに下着まで除去すると、シャロスのいきりたった一物が空気に触れた
。
まだあどけなさが残っている陰茎だが、シャロスの意志とは関係なく醜く腫れ上がり、
彼の身体が求めていることを暴露した。
周囲のメイド達は彼の一物を見て、心なしかあざ笑うかのような目付きになるような気がした。
シャロスの心拍数は一気に上がり、反射的に股間部を手で遮った。
そのぎこちない仕草を見て、リテイアは再びくすりと笑った。
「殿下、王族たるものには、恥ずかしい部分は何も無いはずですわ。
どうかその高貴な体を隠さず、堂々としていてください」
「あ、うん……」
リテイアの優しい口調に諭され、シャロスはややためらった後、ついに両手を離した。
次の瞬間、大勢の女性の中で性器を晒しだすみじめな感情が、彼の心を襲った。
「さあ、わらわについていらっしゃい」
「あっ……」
シャロスは心細い気持ちになり、できる限りリテイアの裸を見ないようにしながら後についた。
股間で硬くなった一物が、歩行すると同時に左右へ揺れ動く。
彼はまわりのメイド達が、含み笑いをしているじゃないかと疑心暗鬼に陥った。
しかし、彼女たちの顔を直視して確認する勇気は、どこにもなかった。
自分がまったく知らない環境、全裸となって歩行する。
今の彼は、目の前のリテイアにすがりたい気持ちで一杯だった。
次の一室までたどり着くと、そこは暖かい湯気が立ちこめていた。
青いタイルで敷かれた床や壁は、光に反射して輝く。
メイド達はそこに備えてあった水がめから湯を汲み取り、シャロスやリテイアの体にやさしくかける。
シャロスの綺麗な金色のロングヘアはメイドに解かれ、水で濡らされる。
暖かい水流に体中の筋肉が一気にほぐされ、なんともいえない気持ちよさにシャロスは心を穏やかにした。
しかし横目でリテイアの裸体がちらちら見えてしまうと、シャロスの緩めたばかりの神経はまたすぐに緊張
した。
逞しい陰茎だけ、いつまでも暖かい水流に逆らって怒張していた。
「殿下、そんなに固くならないで。これからは殿下に享受してもらうものですから、
殿下が疲れては、意味がありませんわよ」
「う、うん……」
湯気がかったリテイアの体は、見え隠れする分より魅力的なものとなった。
彼女の豊満の乳房に気をとらわれたため、シャロスは言い返す言葉を思い浮かべることができず、
ただぼうっとしていた。
ある程度体を流されると、メイド達は白い粉末を盛った壷を取り出した。
彼女達はその粉末をしゃくると、それをシャロスの体にしみこませるように塗る。
「これは……?」
「塩でございます」
「塩?なぜそれを?」
「体の悪い脂肪だけを溶かし出し、皮膚呼吸を正常化させ、美容する効果があるのです。
ちなみに、この塩は大変貴重な自然塩ですの。南海の海水を引き込み、
五年間をかけ濃縮した結晶を収穫した最高級のもので、他所ではまず手に入らないでしょう」
皇女が説明している間、他のメイド達は絶えずシャロスの体を撫で回す。
塩が体に付着する気持ちよさに、シャロスは反感を抱くことさえ忘れた。
メイド達の手つきは彼の胸板に触れ、敏感になった乳首をなぜる。
両腕を上げられると、彼のつるつるの腋に粉末が添えられる。
太ももを塗られ、最後は足裏まで揉まれる。
思わず目をつむりたくなるような気持ち良さだが、このままではリテイアの思うつぼに嵌るような気がする
と、
くすぐったい気持ちになった。
彼はリテイアのほうを盗み見すると、全身に流れる血液がさらに加速し出した。
リテイアのグラマーな肢体はメイド達の手によって撫でられ、弾力に富んだ様がより一層強調された。
とりわけ二つのたわわな乳房は背後から揉まれ、白い粉末がその表面に吸い付く。
そのいやらしい感触を想像すると、シャロスの股間の一物はますます硬くなり、情けなく自己主張をし続け
た。
全てを塗り終わった後、メイド達は二人に薄いデシン質の肌着を着させた。
塩まみれになった体の上から、シルクのすべすべした服が密着して、なんとも歯痒い感覚であった。
シャロスの困惑した表情を見ると、リテイアはニッコリと微笑み、
「殿下、これからはいっぱい汗をかくために、この装束を着させていただいたですわ。
……それとも、裸のままの方が、良かったかしら?」
「そ、そんなことはないよ!」
「うふふ……今のは、ほんのした冗談ですから、気になさらないで下さい」
「くっ……」
リテイアはからかうような笑みのままで、奥の部屋へと進んだ。
シャロスは悔しいながらも、薄い肌着に包まれた彼女の体を追うしかなかった。
さきほど目に焼きついたリテイアの裸が布一枚越しにすぐ目の前にあると思うと、
シャロスはどうしても落ち着けなかった。
衣に隠された彼女の肉体は、裸の時とはまた一味違った魅力を醸し出していた。
うっすらと浮かぶ臀部や胸の輪郭は、シャロスの性欲を常時くすぐる。
最奥の部屋に導かれると、メイド達は扉を開き、恭しくひざまずく。
その部屋はこれまでに無い濃い霧に包まれ、蒸し暑かった。
シャロスはリテイアに従って入ると、背後の扉を閉められた。
途端に、全身がまるで温かい蒸篭に入れられたように、暑苦しくなってきた。
「わらわは熱いのが苦手なものですから、低温サウナにしております。この程度なら、
少々激しい運動をしても、体に危害を加える心配は無いですわ。殿下もすぐ慣れると思いますが、いかがで
すか?」
「私は、大丈夫だ」
シャロスは不安な気持ちで周囲を眺めた。
先ほどまでとは違い、部屋全体は木材で作られ、ヒノキの独特の香りが蒸気と共に部屋中を充満する。
中央の堀には熱く焼けた石が置いてあり、その側に水を盛った桶や杓子があった。
どうやら、その石に水をかけることによって、蒸気を発生させる仕組みになっているようだ。
さらに堀から少し離れたところで、ござが敷き詰められた二つの寝台が用意されてあった。
寝台の上には柔らかそうなビロードが敷かれ、見た者にその上を寝転がったらどんなに気持ち良いかを連想
させる。
入り口のすぐ側で、いつの間に素衣に着替えたマナとエナが侍っていた。
シャロスやリテイアが現れると、彼女達はまったく同じタイミングでお辞儀をした。
その華奢な体つきは甘い果実のように、シャロスの視界に別の刺激を加える。
エナはロングヘアをなびかせ、相変わらず無表情のままで、シャロスを寝台の方へみちびく。
髪がうなじにかかるマナはリテイアに奉仕しながらも、
時々シャロスに向かって悪戯っぽい笑みを浮かべ、彼を赤面させる。
台の上にうつ伏せにさせられると、シャロスは服下から伝わるビロードの感触に心酔した。
蒸気で湿った敷き布は生暖かく、彼の生まれつき滑々な肌を静かに受け止める。
マナとエナは、何やら植物の枝葉を束ねたもの取り出した。
シャロスの疑問に満ちた表情を察すると、リテイアは柔和な声で語りだした。
「これは高原でしかとれない、シラカンバの木からとったものです。
体にはたくことによって、発汗作用をよくさせ、血行を促進する効果があるらしいわ」
「……そうなのか。皇后様は、よくいろいろとご存知ですね」
「ふふっ、殿下は療養に関してまったく気をつかわないからですわ」
シャロスは悶々としたが、それ以上皮肉を言わなかった。
今までの見聞きしてきた限り、ここでの全てのものは、かなり贅沢に作られたものだと推測できる。
エナが振り下ろしたシラカンバの葉は、やさしくシャロスの背中を叩く。
葉自体それほど痛くない上、エナはほど良く加減しているため、心地よい刺激がシャロスの脳髄を襲う。
枝葉が背中から腕、太ももへと叩くうちに、シャロスはたちまち昏々として、まぶたをおろした。
体が鉛のように重く鈍くなり、少しも動きたくなくなった。
しばらくすると、体中から汗が噴き出て、服との間の隙間を滴るようになった。
全身を撒かれた塩はその汗に流され、シャロスの体を洗浄する。
小さな粒に体を磨かれる感じはくすぐったいが、確かに気持ち良い感触でもあった。
葉枝のリズミカルな叩きとあいまって、汗水は肌着を湿らせる。
シャロスはついに目を閉じた。
今まで仕事に勤しんできた心は、気持ち良さに流れて緩んできた。
ふと、全ての悩み事を忘れられたらどんなに楽だろうか、とシャロスは思った。
彼は小さい頃から立派な王様になることだけを考え、今までの人生を過ごしてきた。
その間、彼は趣味といえる趣味は無く、享楽を追求したことも無かった。
王宮で権利闘争を繰り返す日々に、彼は一度も心の防壁をはずすことが無い。
それだけに、今日のように心から何かを興じることは、彼にとって新鮮な経験であった。
「失礼します」
エナは小声で言うと、シャロスの体を優しく仰向けにさせた。
彼女の行き届いた気遣いは、シャロスの心を満足してくる。
宮殿生活という異常な環境下で、シャロスは平常の少年とは異なる思春期を過ごしてきた。
男女の営みを知識として知っていたが、実際の誰かを愛意を抱く体験は無かった。
そのため、目の前にいるエナの小綺麗な顔立ちは、彼に恋意を催す魅力的なものであった。
彼女が自分に尽くしている姿を見ると、脳内では今まで感じたことも無い甘い幸福感が充満する。
そう思うと、シャロスの下半身は突然せつなくなった。
数日前エナが自分に施した淫らな行為を思い返すと、いやしい煩悩が再び胸を焦がした。
股間の一物も今までの鎮まりをはねかえし、肌着の下から段々と突きあがってきた。
(あっ、だめ……!)
シャロスは歯を食いしばって、懸命に欲望を抑えようとした。
しかし、心の中を抑えれば抑えるほど、性への意識が昂ぶってしまう。
さきほど目に焼き付けたリテイアの裸姿が鮮明と浮び、シャロスの抵抗を弱める。
「殿下、いかがなさいました?温度が熱すぎたかしら?」
シャロスは声の方に振り向くと、リテイアは足を組みながら嫣然と微笑みかけてくれた。
マナは彼女の足元でしゃがみ、足の爪を丹念に磨いていた。
「い、いいえ……」
シャロスは曖昧な返事をしながら、リテイアの体を見つめ、ごくりと唾を飲んだ。
蒸気や汗がしみ込んだ薄着は、半透明な膜となって彼女の体にぴったり貼り付く。
そのため、体のラインはおろか、その下にある肉体まで見えてしまう。
服の吸いつき具合によって見える面積が違ってくるが、
その不規則な見せ方はかえってエロティックなものだった。
彼女が両足を重ねて組んで座っているため、裾の下から真っ白な太ももがそのまま露出している。
胸部の布は大きく押し上げられ、覆い隠しきれない谷間がシャロスの脳内を占領する。
先端の突起はそのまま服を突き、うっすらと乳輪が見える。
いけないことだと知っていても、シャロスは淫らな欲望を抑え切れず、いつまでも彼女の体をながめた。
自分の体の表面の粉末はほとんど汗に溶け、ねっとりとして液となって肉体を摩擦する。
シャロスは高ぶる心を静めるため、意を決して首を曲げようとしたが、
その直前リテイアの秋波のような瞳に見つめられると、まるで意識を吸い取られたように動けなくなった。
その魂を抜かれたような様子を見て、リテイアは妖艶な笑みを作る。
シャロスは彼女の一挙一動に反応して、心拍数が急激に変化した。
そうしているうちに、彼の頭の中は、リテイアの事以外なにも考えられなくなった。
「マナ、エナ、もう下がってよいぞ」
「はい」
「はい」
二人はまったく同じ角度で会釈すると、部屋の扉から出て行った。
生温い蒸気のこもった部屋は、微妙な雰囲気に変化した。
聡明なシャロスには、これは相手のたくらみであることにうすうす気付いていた。
しかし知ったところで、彼にはもはやリテイアの魅力を跳ね返すほどの自制力を持っていなかった。
「どうしたの、シャロス」
「……!」
リテイアの慈しむ声で名前を呼ばれると、彼女と過ごした淫らな記憶が無理やり引っ張り出された。
それはシャロスにとって、快楽のトラウマでもあった。
「ねぇシャロス、もう誰もいなくなったわ。わらわのとなりに来ないの?」
「っ……」
リテイアの甘い誘いは、シャロスの脳内に激しい闘争を起こした。
敵の立場にある彼女の命令を従うのは、とてつもなく屈辱的なことである。
その一方で、リテイアのみずみずしい肉体は悪魔のような香りを放ち、シャロスの心を鷲掴みにする。
リテイアは足を組んだまま、誘惑の微笑を向けた。
その耐え難い魅力に、シャロスはついに心が折れ、リテイアの寝台へ歩き出した。
「ふふふ、そうよ。わらわの言うことを聞いていればいいわ……」
リテイアはシャロスの体を自分の方へ招き寄せた。
朦朧となった意識で彼女のとなりに座ると、
服越しに柔らかい乳房がシャロスの体と接触し、彼の神経を鈍らせた。
また彼女に負けてしまった悔しい気持ちと、女の肉体を感じる良い気持ちが混ざり合って、シャロスの精神
をせめる。
「皇后様……」
「はい、もう一回。二人きりの時、わらわのことをどう呼ぶべきかしら?」
「……お、お母さん……」
シャロスは悔しい気持ちでいながら、その言葉を吐き出してしまった。
一度崩れた心の防壁は、もはやふせぐことはできない。
「うん、これでもう完璧に覚えたわね。ふふ、良い子にはご褒美をあげなくちゃ」
リテイアはそう言うと、シャロスを抱きしめた。
「あっ?!」
突如な出来事に、シャロスは抵抗することさえ忘れ、リテイアの胸の中に顔を埋めた。
最初は脱出しようと考えもしたが、やがてリテイアの胸に染み付いた官能的な匂いに魅了されていった。
女性に抱きしめられる安心感や欲情が入り混じって、シャロスを少しずつ溶解していく。
リテイアは彼の耳側に唇をそっと当てて、小声で囁いた。
「シャロス、今からわらわだけ考えて。それ以外の事、みーんな忘れなさい。
……うふふっ、あそこがビンビンになってるわね。
さっきから私の体をじろじろ見てて。そんなに良かったのかしら?」
「そ、それは……」
シャロスは悪いことをした子供のように、口をどもらせた。
リテイアは彼の肉棒の先端に人差し指を当て、服越しに滑らせる。
「っああ!」
「あら、もう我慢できないぐらい敏感になってるじゃない。
本当、いやらしい子だね。皇后であるわらわに欲情するなんて……」
「うっ……」
「でも、心配しないで。シャロスは男の子だから、女の体を見て欲情するのは、当たり前なことなのよ。
これからも、わらわの体を見ただけで、すぐにあそこを勃起させられるようにしなさい。いいわね?」
リテイアは目を細め、シャロスの亀頭の裏筋をクリッと押し捻った。
「あぁん!」
シャロスは甲高い声をあげ、無防備になった脳はリテイアの言葉を刷り込まれる。
「ふふふ……シャロスは、本当に女の子みたいだわ。
綺麗な顔に、輝かしいブロンド。それに、肌がこんなにすべすべしているなんて」
「あっ……」
リテイアはシャロスの服の中に手を入れると、彼の汗に濡れていた体を触れた。
肋骨に沿って下腹部を掠め、そして細長い指で鎖骨や首筋に撫でる。
それはそれで気持ちいいが、同時に自分がペットのように扱われたような気がして、悔しい気もした。
やがて、シャロスは麻酔を注入されたかのように、リテイアの体に寄り添って動けなくなった。
まわりは生暖かい水蒸気が充満し、まるで雲の中に漂うような気分になる。
気持ち良さの頂点に辿りつこうとした時、リテイアは突然両手を収めた。
「はぁ、もし王子は本当に女の子だったら、
わらわがもっといろんな事をしてあげられたのに。少し残念ですわ」
「あ、ああっ……」
シャロスは物足りない気持ちを抑えきれず、小声を漏らしてしまった。
残されたムラムラ感に、シャロスは歯痒さを感じずにいられなかった。
彼は潤いだ目でリテイアを見上げると、彼女はくすりと微笑んだ。
「良かったわ。わらわは最近、てっきりシャロスに嫌われたと思ったわ」
「どうして……?」
「だって、最近はまたわらわをいやがる顔を向けてきたじゃない。
この前二人きりで会ったときあんな仲良かったのに……わらわは、とても悲しかったわ」
「そ、そんなことは……」
「あ・る・よ。ついさっきだって、わらわから逃げようとしたじゃない」
リテイアのやや拗ねた態度に、シャロスは完全に翻弄されてしまった。
彼には一国の行方を英断する力があっても、女性の甘い言葉を対する免疫力が無かった。
相手が自分を誘惑していると分かっていても、彼は無意識のうちにリテイアの機嫌を取り直すように心が動
いた。
「い、いいえ、あの時はただ疲れただけで……」
「ふふっ、本当かしらね。もしそうであるのなら、そうね……ここでわらわに口付けをしなさい。
そうすれば、その言い訳を信じてあげてもいいわよ」
「えっ?」
シャロスは心をドクンと躍らせ、リテイアの口を覗いた。
やや開いた唇は湿気を帯びて潤い、悩ましい息を吐いていた。
「どうしたの。それともやはり、わらわを誤魔化しているのかしら」
リテイアは挑発的な目でシャロスを見つめた。
それはまるで獲物を見下ろすような、雌豹の睨みであった。
「いいえ、私はそんなつもりはありません」
「じゃあ、してくださるのね」
そう言うと、リテイアは静かに目を閉じた。
彼女の無防備な構えに、シャロスの理性が飛び弾けた。
シャロスは震え気味になりながら、リテイアの肩をつかみ、彼女の魅惑な唇に口を重ねた。
次の瞬間、口の表面に甘い感触が広がる。
彼がしばらく浸っていると、やがてリテイアの方から唇を押し開け、シャロスの口中に舌を忍び込ませる。
彼女はまるで水蛇のように軽快に動き、シャロスの舌を絡めとる。
そして彼の口中で舌を吸い付き、思う存分に蹂躙する。
彼女の熟練したテクニックに、シャロスはただ相手の思うがままにされるしかなかった。
全身の血流が早まり、股間の一物はビンビンにいきりたつ。
ようやくリテイアが離れた頃、シャロスは虚ろな目で荒れる呼吸を繰り返した。
口の中では、女性の甘いエキスが残る。
彼が恍惚な表情を浮かべたのを見て、リテイアは笑みを浮かべた。
「わらわとのキス、そんなに気持ちよかったかしら?」
「う、うん……」
「ふふふ、素直で良い子だわ。……はぁ、少し熱くてなってきたわね」
リテイアは額の汗を拭き取ると、自分の肌着に手をかけ、首下の部分を左右へ緩めた。
彼女の白い両肩は露出し、胸の谷間もほとんどあらわとなった。
乳首の部分だけギリギリ見えないが、それがまた男の視線を絶妙に惹きつける。
真珠のような水玉は彼女のうなじから乳房の上部に垂れ落ち、そして谷間の中央を経て滑り落ちる。
そのいやらしい様子に、シャロスは喉奥から唸り声を上げた。
目線が自分の胸に釘付けとなった事を気付くと、リテイアは悪魔のような笑みを浮かべる。
「ねぇ、シャロス王子……私の胸、舐めてみる?」
「ええ?!」
唐突な発言に、シャロスは一瞬戸惑った。
しかしその言葉の淫靡な響きを汲み取ると、彼の心の奥底から限りない欲望が盛り上がる。
「ふふふ……見ているだけじゃ、物足りないでしょ?」
シャロスの口内はカラカラに渇いた。
リテイアの乳房は室内の光に反射して、魅惑な輝きを照らす。
プライドの高い彼にとって、相手の言いなりになるのは屈辱的なことである。
しかし、今はそんなプライドよりも、劣情の方が確実に上回っていた。
「ほら、シャロス。遠慮なんてしないで。自分の欲望のままに……していいんだよ」
リテイアの悪魔の囁きは、シャロスの葛藤を徐々に溶解していく。
彼は心臓をドキドキさせながら、やがて皇后の胸に口を近づき、舌を出して乳房の上に這わせた。
充分に濡れていた乳房の表面は塩分を含み、味わいのあるものだった。
シャロスは自然と舌を谷間に滑らせ、そして乳首に吸い付いた。
「はぅっ……あぁん!」
リテイアは頬をやや赤く染め、くぐもった喘ぎ声を漏らした。
その仕草は、シャロスの欲念に油を注いだ。
彼はリテイアを寝台の上に押し倒し、血走った目でリテイアを見下ろす。
自分の股下で、リテイアは弱々しく横たわる。
彼女の濡れた髪は四方へ拡散し、乱れた息をしていた。
ピンク色の唇が呼吸するたびに、豊満な胸はリズミカルに上下し、シャロスの獣欲をそそる。
肌着の前方の開いた部分から白い肌が見え隠れし、男なら誰でも理性を失わせる魔の魅力を放つ。
シャロスの股間の一物はビクン、ビクンと脈打つ。
リテイアの半開きの目は拒んでいるようにも、誘うっているようにも見える。
その火照った顔を見つめると、シャロスは我慢できるはずがなかった。
彼はリテイアのうなじに唇をそえ、懸命に舐めまわす。
両手は彼女の柔らかい乳房を掴み、本能が赴くままに揉んだ。
「はぁん、ああっ……!」
リテイアは放蕩な呻き声を上げ、シャロスの劣情を確実に煽る。
彼はリテイアの腋や、おへそに舌先を立てて、ぴちゃぴちゃと音を立てて吸い付く。
そしておへそより下へ進むとき、その邪魔な腰帯をほどいた。
次の瞬間、シャロスの目の前に女性の下半身が晒された。
つややかな茂みと未知なる場所に、シャロスは思わずくい込むように見入った。
自分の股間は今まで無いぐらいにギンギンと疼いた。
「王子様、それ以上は……我々は最後の一線だけは、越えてはならない身分だわ」
「……!」
リテイアの言葉はシャロスの脳天に直撃した。
彼のどす黒い欲情にまみれた心に、かすかな倫理感がよみがえる。
(そうだ、彼女は名目上でも、父上の妻である。それに、父上が亡くなられたばかりというのに……)
心の中では分かっていても、目線はついついリテイアの淫裂に移る。
滾っていた欲望の中で、残りわずかな理性はギリギリのラインでさまよい、シャロスの劣情を抑えた。
彼が必死に自制する様子を見て、リテイアは心の中で嘲笑した。
「残念ですわ。わらわは普通の女だったら、王子様に尽くせたのに……
シャロス王子も年頃の男の子だもん、女の体がほしくてたまらないよね。
ふふふ、今日だけ、特別に気持ちいいことをしてあげますわ」
リテイアは潤いだ瞳でシャロスを見つめ、彼の両手を握った。
そして腰を浮かせて、陰唇の割れ目を彼の一物の上に乗せた。
「中には入れられないけど、これで気持ちよくさせてあげるわ」
そう言いながら、彼女は腰を前後に揺らして、淫裂でシャロスの肉棒をしごいた。
「あああぁっ!」
ビンビンになった肉棒の上に、リテイアの濡れきった秘所が滑る。
いやらしい愛液がふんだんに塗りたくられ、シャロスの触感を刺激する。
皇后と股間を擦り合わせるこの行為は、淫猥で背徳な快楽をもたらした。
それは、シャロスの最後の理性を摘み取ったことにほかならなかった。
リテイアの腰の動きとともに、彼の瞳から理性の光が消えていく。
「ねぇ、シャロス、気持ちいい?……ひゃっ!」
突然、シャロスはリテイアの腰を掴んだ。
それから、彼女の淫らな割れ目に、本能のように自分の一物を入れた。
「はあぁん……うっ、あぁん!」
リテイアは悩ましい喘ぎ声を吐いた。
シャロスは獣のように瞳孔を広がせ、原始的な欲望に駆られるまま動いた。
淫らな襞の合間に、硬くなった肉棒が突き込んでいく。
先端の先走り汁とリテイアの淫液が混ざり合って、彼と彼女の間を濡れ合せる。
初めて味わう女性の中に、シャロスは雄叫びを上げた。
窄めた小さな穴の入り口を、彼の最も敏感部分である亀頭が押し広げる。
カリが陰唇を捻りこむと、肉棒がずぶずぶと彼女の中へ入っていく。
途端、相手に包み込まれた感触が股間から拡散する。
肉棒を覆う蜜壷は、まるで何十本ものミミズが織り交ぜたように蠢く。
淫液が溢れる穴の中で、肉棒と膣の襞はよく擦れ合い、シャロスの一物を絶えずしごいた。
そこは一度飲み込んだら、全て搾り取るまで離さないような、淫魔のような膣であった。
「はぁう……ああぁん!」
リテイアがシャロスを掴む手に力が入ると、彼女のあそこも追随して、ねっとりと彼の根元から締め付けた
。
「ぐっ……がぁああ!」
シャロスは呻き声をあげながらも、懸命に腰を抽送しつづけた。
初めて感じる異性の中は、天にも昇るような絶妙な境地であった。
「はぁん、ぐっ……ああん、ああんっ!」
リテイアは喘ぎ声をあげて、淫らな表情を浮かべてシャロスを見上げた。
胸がぷるんと揺れるたびに、純潔な水玉が弾き飛ぶ。
もやもやした視界の中、彼女のしなやかな肢体はシャロスをさらに興奮させる。
シャロスはただリテイアの姿に見惚れたまま、自制が効かなくなった腰を突きまくった。
リテイアの中では、膣の筋道が数段に分かれて、
シャロスが腰を上下すると共に、肉棒への刺激に強弱をつける。
無数のひだひだは時には彼に密着し、時には彼から離れ、緩急を分けて空間をすぼめる。
その微妙な力加減に、シャロスの欲望は徐々に拡大されていく。
初めて性行為を行うシャロスには、もちろんそれを耐えられるはずが無かった。
「はぁ、気持ちいい……体が止まらないよ!」
「あぁん、はぁんっ!ああ……王子様、だめ……そんな力いっぱい突かれた、おかしくなっちゃう……!」
リテイアが快楽をこらえるような表情は、シャロスを阻止するどころか、
彼をますます欲望の虜へ変化させた。
妖艶な皇后を好きのように蹂躙できる征服感や、自分の股下で淫らに乱れる光景は、
どんな媚薬よりもシャロスを興奮させた。
数分もしないうちに、シャロスの体に溜まっていた熱いたぎりが股間の根元に集まっていく。
「はあっ、もうだめ……出る……精液が出るぅ――!」
「はぁん……ああぁぁぁ!」
シャロスは体を前屈みにし、食いしばった口からよだれが零れ落ちた。
最後は肉棒全体を強く締め付けられると、熱い白液がリテイアの中でほとばしった。
その瞬間、シャロスは天にも昇ったような気持ちになった。
頭の中から何も消え、ただ欲望を放射する快感だけ彼をとらえる。
それは今まで手でしごかれたよりも、はるかに気持ちいい体験であった。
シャロスは足の爪先まで力を込め、精液を全て吐き出すまで腰を突き上げた。
そしてしばらく痙攣した後、脱力した体をリテイアの横に倒させた。
おびただしい量の白液とともに、醜い肉棒が吐き出された。
彼女の淫裂はビクビクと震え、シャロスの精液を溢れさせた。
「はぁ……はぁ……」
シャロスは虚ろな目で天井を見つめ、絶頂を迎えた後の余韻に浸った。
心頭はようやく明るみを取り戻し、さきほどの快楽に溺れる自分を思い返しながら、段々と自己嫌悪に陥っ
た。
「はぁ……シャロス、わらわの中にだしてはいけないと、あれほど言ったのに」
「……ご、ごめんなさい……」
「このことが外に噂されたら、どうなると思う?母と子が交えたことは、国中に大きく噂されてしまうのよ
。
そうなったら、王室の威信もガタ落ちになってしまうわ」
「全て私が、悪かったです……」
シャロスの心は悔恨の念に満ちた。
欲望が全て消え去った今、自分がどれだけの愚行をしてきたか、嫌というほど分かってしまう。
疲れきった体だけに、その衝撃は重かった。
「でも、安心しなさい」
リテイアはシャロスを胸でそっと抱きしめ、
「今日のこと、わらわが全部内緒にしてあげるわ」
「お母さん……?」
「いいかしら?これはシャロスとわらわの二人だけの秘密。誰にも教えてはなりませぬ。
あなたにとってどんなに身近な人でも、どんなに信頼できる人でも。できるわね、シャロス?」
「は、はい!」
「ふふふ、いい子だわ……もしそれを守れた、今度はまた、気持ちいいことをしてあげてもいいわよ」
「お、お母さん……」
リテイアの柔らかい胸の中で、シャロスの重いまぶたは徐々に垂れ下がった。
心身とも疲労に満ちた彼は、リテイアから得られる安心感を無条件に受け入れ、そして安らかな眠りに陥っ
た。
「うふふ、今はゆっくり休んでね……これからはいずれ、わらわに服従する人形になってもらうから」
自分のふところの中で軽い寝息を立てる美少年を見て、リテイアは悪魔のような笑みを浮かべた。
それから一日後。
シャロスは今日も領内各地からの報告書に目を通していたが、
いつもとは違い、意識はなかなか集中しなかった。
「……ああぁぁぁ!」
彼は報告書を机の上に叩きつけた。
インクスタンドがその機にゆれ倒れ、机の上を黒い液体で汚す。
今日ほど不機嫌な日はなかった。
その原因を、シャロス自身もよく分かっていた。
目を閉じればリテイアの魅惑な微笑みが浮かび、耳をすませば淫らな声が聞こえるような気がする。
朝目覚めたとき、彼はたまらずオナニーをして自分を静めようとした。
しかし、一度リテイアの味を覚えてしまった体は、満足にイクことがなかなかできなくなってしまった。
女性の性器に挿入する幻想は、絶えず彼の思考を煩わせた。
「殿下、いかがなされましたか」
物音を聞きつけたレイラが現れた。
「何もない、大丈夫だ」
「しかし、さきほどは……」
「何もないと言った!出て行け……っ!」
「……はっ……」
これほど怒鳴られた経験は今まで無かったため、レイラは少し戸惑った。
彼女は伏せた顔を少しあげると、ふとシャロスの異様なめつきに気付いた。
その視線は、まるで自分が身に着けている制服を見貫くかのようの鋭かった。
そして、何か危険な感情がこもっているようにも感じた。
レイラはなぜかは分からないが、顔を赤らめてしまった。
「あ、あの……王子様?」
「うっ、ああ。すまない、レイラ。ちょっと疲れただけだから、心配はいらない。
お前に向かって大声をあげて、すまない」
「とんでもありません。殿下、どうか御体に気をつけてください。
もしよろしかったら、私が御医を呼びましょうか」
「いいえ、いいのだ。少し休めばいいことだ。お前はもう下がってよいぞ……今は一人にしてくれ」
「はっ」
レイラはそれ以上の進言をせず、シャロスの命令に従って部屋から出た。
彼女と入れ替わるように、メイド服を着たエナが現れた。
「王子様、一息休まれてはいかがでしょうか」
エナは香ばしい紅茶をシャロスの側に置くと、机上にこぼれたインクを片付けた。
「あ、ああ……」
シャロスはエナの白いうなじを見ながら、レイラの肢体を思い返した。
(くっ……私はいったい何を考えているんだ!)
レイラは長年シャロスに仕えていたが、シャロスにとってレイラは姉にも似たような人物で、
一度も愛欲を思い浮かべたことが無かった。
だがリテイアと性交して女性の体を知った今では、
シャロスはレイラの体が気になって気になって仕方が無かった。
彼女の軽鎧の下に、魅力的な乳房やいやらしい性器が隠されていることを思うと、
どす黒い邪念がシャロスの心を充満する。
そして今も、目の前にいるメイドの美少女を欲望に満ちた目で眺めていた。
エナは無表情ながら、どんな命令にも逆らわないほど従順さを持っていた。
もしここで自分が強制すれば彼女ならきっと自ら体を晒し出すだろう。
その可憐な裸姿を想像すると、シャロスの股間は疼いた。
「王子様、僭越ながら申し上げますが、私には王子様が欲求不満に陥っているように見えますわ」
「ふん、そんなことあるか!」
シャロスは無理やり自分の顔を冷やせた。
しかし、その動きは数日前と比べると、随分と余裕の無いものになった。
「でも、王子様の御体の方は、そうでないようですが」
「くっ……」
「どうか、私に慰めさせてください」
「……ふん、好きにしろ!」
シャロスは溜まらず強がりのセリフを吐き捨てるが、
エナはまったく意に介せず、淡々と彼のズボンを脱がせた。
案の定大きく勃起した一物の先端から、先走り汁が溢れていた。
「では、失礼させていただきます」
エナは可愛らしい口をあけると、その怒張した一物を含んだ。
生暖かい口腔の感触は、すぐにシャロスの硬い心を溶かした。
彼は苦悶に満ちた表情を浮かべ、腰を浮かせた。
エナの慣れた舌の動きは、シャロスのウィークポイントを的確に暴き、
彼の意志を脆弱なものへと変貌させる。
リテイアとセックスした体験がさらに拍車をかけて、彼を絶頂へと導く。
シャロスは一際大きい呻き声上げると、エナの口の中でドロドロの精液をこぼした。
エナが淡々と自分の精液を飲み干した光景を見て、シャロスの頭の中に獣のような感情が蘇る。
彼は唇をかみしめた後、ぼそっとと呟いた。
「……エナ」
「はい」
「服を脱げ」
「えっ……」
エナが無表情のまま頬を少し赤らめた。
「……分かりました」
しかし、エナはシャロスの命令に抵抗しなかった。
彼女はおもむろに立ち上がり、襟のボタンをはずし、メイド服を脱ぎ去った。
ほっそりとした肩口や胴体は、素肌のままであらわとなった。
シャロスは両目を光らせて、彼女の手つきを追った。
エナの顔色は徐々に赤く染まったが、しかし手の動きが止まることはなかった。
彼女はスカーカを脱ぎ、さらにブラジャーをはずした。
流れるようなロングヘアが彼女の背後になびく。
そしてついに、彼女は白のショーツを膝まで下ろし、それを足に通した。
頭につけたフリル付きカチューシャと、黒のニーソックスのみを残し、
彼女の少女らしい裸は全てシャロスの前に晒された。
シャロスは瞳に欲望の火をともらせ、彼女の体を嘗め回すように眺めた。
その突き刺さるような視線を感じると、エナの顔はますます赤くなり、目を泳がせた。
普段の彼女が絶対に見せないたじろぎは、シャロスの嗜虐心を大きく煽った。
彼は乱暴にエナの細腕をつかむと、奥の寝室へ向かった。
「あっ!」
ベッドに身を投げられると、エナは小さな悲鳴を上げた。
彼女は可憐な小動物のように瞳を潤わせ、両足をうちまたに曲げて、さりげなく太ももの付け根を隠した。
メイドの黒ニーソックスに包まれた彼女の太ももは、シャロスの心を焼き焦がす。
彼は外に聞こえないように寝室の扉を閉め、エナの上にまたがった。
それから彼女の形の良い胸に舌を這わせ、もう片方の乳房を手でまさぐった。
「ああっ!」
エナはくぐもったような小さな声を上げ、耐え切れないようで体を蠢かせた。
その可愛らしい仕草を見ると、シャロスはたまらず大きく膨張したチンポを握り、
それをエナの中に挿入した。
「ああっ、あああぁぁぁぁ!」
エナはひときわ大きい悲鳴を上げた。
彼女の蜜壷は、リテイアのものより窮屈であった。
しかし欲情に満ちたシャロスは、それを考慮する余裕などなかった。
彼は硬くなった一物でエナの中を少しずつえぐると、やがて何かを突き抜けたように感じた。
次の瞬間、エナの秘所との結合部から、処女の血が溢れ出た。
それと同時に、彼女の両目から清らかな涙が溢れ出た。
「エナ……?これは……」
シャロスは思わず動きを止めた。
しかし、エナはすぐさま彼の体にしがみつき、乱れるように話した。
「はぁん、王子様……お願い、止めないで下さい……このままエナを、もっと痛めつけてください!」
彼女がシャロスに密着した勢いで、シャロスの一物はさらに深いところまで貫いた。
「ぐっ……ああぁっ!」
すぼまった襞がより強く擦り合うと、シャロスの戸惑いは欲情によって上書きされた。
エナの恥じらう顔に涙の粒が滑り落ちる。
その痛みをこらえる表情は、シャロスの陵辱心をかきたてる。
彼女のいつもとのギャップは、これ以上無い可愛いものであった。
シャロスは渾身の力で腰を振りおろし、鉄のように硬くなった一物を激しく上下に運動させた。
「あぁっ、うっ……ぐぅぅ!」
エナはベッドのシーツを強く掴み、可愛らしい顔立ちに苦悶の表情が満ちた。
肉棒が彼女の入り口から一番奥まで貫くたびに、エナは口を大きく開き、
我慢しているような喘ぎ声を小刻みに吐き出す。
そして激しい痛みをやり過ごすためのように、足の裏でベッドの上を何度もさする。
シャロスは荒々しい息になって、腰の動きを徐々に早めた。
今の彼には、もはや途中で止めることなどできなくなった。
それを察したのか、エナは潤いだ瞳でシャロスを見上げ、
「……シャ、シャロス様……どうか、エナの中に……熱いザーメンを一杯注いでください!」
彼女の熱っぽい口調は、シャロスの頭中のトリガーをはずした。
今まで溜まってきた欲情は一気に肉棒に流れ込み、彼のあそこをビクビク躍動させた。
「エナ……!」
「シャロスさまっ!」
エナはシャロスが出す直前に、腰を迎合させた。
そのはずみに、シャロスの亀頭は柔らかい子宮膜衝突した。
「うわああぁぁぁ――!」
シャロスの一物がドクドク震えると、熱くたぎった精液が彼女の中に注がれた。
「はぁああっ……」
エナは全身をわななかせ、体をえびの様に反らせた。
秘所の結合部から、精液と血が混ざり合ったピンク色の体液が溢れ出た。
欲望が萎縮していくと同時に、シャロスの体から力が抜け出た。
朦朧となった意識のまま、エナのそばに横たわり、彼女の胸の起伏を眺めながら息を整えた。
熱が冷えていくと、悔恨の念が徐々に心情を曇らせた。
(また、こんなことをしてしまった……)
ついさっきまでいきり立っていた自分の性器は、みっともなく垂れ下がっていた。
事後の余韻を味わいながらも、シャロスはこの淫蕩な行いに対し複雑な思いを抱いた。
(これが、セックスの快感なのか。今までこの行為を憎んできたというのに……)
隣のエナはおもむろにベッドから立ち上がり、乱れた髪を整えた。
その顔から熱が引き、いつもの無表情になった。
彼女は秘所の狼藉をハンカチでぬぐと、一言も発さずにメイド服を着付けた。
そして、部屋外からお湯とタオルを持ち込み、シャロスの体をふきとる。
暖かいタオルの感触が、シャロスの陰茎を包み込む。
彼は顔を真っ赤にさせ、小声でつぶやいた。
「エナ、その……ごめん、私が強引に……」
「いいえ、王子様は何も悪くなんかありません。私の体はもう王子様のものですから、
どうか好きにお使いになってください。……あの、大変……気持ち良い痛みでした」
エナは最後だけ視線をそらし、ほのかに顔を赤らめた。
彼女の従順な仕草を見ると、シャロスの欲望は一段と強くなった。
ついさっき得られた快感を思い返すと、彼の一物はまたもや膨張し始めた。
その時ふと、心の中でリテイアの魅惑な笑顔が思い浮かんできた。
(皇后だって言っていた……私達身分の高い人を満足させられることが、彼らの至高の幸福だって
……エナもそれでいいというのなら、私は何も負い目を感じる事は無いだろう……)
シャロスは発情した獣のように、目をギラギラ輝かせた。
その瞳には、早くもエナの艶かしい体しか映っていなかった。
□
王子の寝室から遠く離れたところ、暗い部屋の中で居座るリテイアの姿がいた。
彼女は豪奢な貴人服を着て、手に持っているグラスに唇をそっとつけ、中にあるワインを口に注いだ。
顔をグラスから離れると、そこに彼女の艶かしい口紅の跡が残った。
その近くで、銀のトレイを持ったマナの姿がいた。
彼女はリテイアの機嫌を取るかのように、笑みを浮かべていた。
「これで王子様は、リテイア様のいいなりになったのも同然ですわね」
「ふふふ……これでシャロス王子は、女を見ただけで興奮するケダモノとなった。
セックスの快楽を知った彼には、もはや逃れることは無いでしょう」
「普通の男でも、一度リテイア様と交われば虜になっちゃうですもの。まして、王子みたいな童貞を捧げた
人なんて」
「そうだね。彼にとってわらわとのセックスは、これから一生、記憶の深いところまで刻まれたことでしょ
う。
そして彼がセックスを重ねていけばいくほど、女色に溺れていくわ」
「あんな賢そうな王子が、エロエロのスケベ男になっちゃうと思うと、いろいろ楽しみですわ」
「ええ。いずれ国や民なんか、どうでもよくなるような王様に成長させるわ。
それまでには、エナにがんばってもらわなくちゃ」
リテイアがそこまで話すと、マナは頬をやや不満げに膨らませた。
「リテイア様、エナばっかり奉仕させてずるいですわ。マナも、王子様の側にいたいです!」
「あらあら、せっかちな子ね。……ふふふ、いいわよ。そろそろ王子をもっと堕落してもらう頃だもの。
マナ、今度はあなたの力で、王子を楽しませてね」
「やったー!ありがとうございます、リテイア様!マナ、体を張ってがんばっちゃいます!」
マナは子供のような明るい笑顔を作った。
その無邪気な素振りを眺めながら、リテイアは妖艶な笑みを浮かべた。
リテイアはグラスに注がれたワインを眺めると、近いうちにシャロスが彼女にひざまずく光景が見えてきた
。
第四話
一本の蝋燭が灯り、薄暗い部屋を少しだけ明るくさせる。
壁に映る二つの影法師は、激しく絡め合っていた。
部屋の中で、若い二人の男女の粗い息遣いや喘ぎ声が途切れ途切れになって、
韻事を進める情緒をもたらしてくれる。
灯りの前で、二つの熱っぽい肉体がこすれ合う。
お互いのぬめった性器から、いやらしい水音が聞こえる。
やがて、男女の声は徐々に高まり、動きも一段と速くなった。
くぐもった呻き声が起きると、部屋の中は再び静寂に戻り、
ただ事後の乱れた呼吸音が残るのみとなった。
シャロスはベッドに横たわり、息を大きく吸ったり吐いたりしながら、
ぼんやりと側にいる裸の少女を見つめた。
彼女の白い頬はいまだに火照りが残り、潤んだ瞳の奥で官能を誘う情熱が籠る。
メイドのカチューシャが無い今、美しいロングヘアはさらさらと両肩や美乳にかかっていた。
その柔らかそう皮膚の表面を綺麗な汗のしずくが付着し、
彼女の胸呼吸に合わせて乳から下へ滑り出る。
少女は無表情のまま身を起こし、まだ余韻に浸しているシャロスに寄り添った。
可愛らしい唇が、彼の口に重ねられた。
シャロスの意識は甘ったるい感触にかすみ、自然と相手のぬめりとした舌を口内に受け入れた。
ぴちゃ、ぴちゃという淫靡な音がしばらく続く。
少女が顔をあげると、二人の口の間に銀色の糸が引かれた。
その雰囲気を惜しむように、少女はゆっくりとシャロスのうなじに口をつけ、
彼の喉笛あたりをピンク色の唇でキスしながら愛撫した。
その気持ちよさに、シャロスは思わずまぶたを閉じて呻き声を上げた。
少女は彼の鎖骨に接吻し、胸にある乳首を軽くかじって、そのまま優しくしゃぶる。
魂を削られたような感触に、シャロスは快楽の嘆声を唸った。
艶かしい舌はすべすべしたお腹を舐め過ごし、やがて射精したばかりの一物の先端に吸い付いた。
シャロスのベニスは、彼の精液や彼女の愛液にまみれていた。
少女は顔に降りかかる髪を手で耳の後ろにかきわけ、
シャロスの一物のまわりをじっくりと舐め取り、そして中に残る残滓をすすった。
彼女の念入りな動きが、シャロスの疲れ果てた体を徐々にほぐしていく。
(エナ……)
心の中で相手の名前を呟きながら、疲れ果てたシャロスは昏睡状態に陥った。
エナの処女を貫いてから、速くも十日間が過ぎた。
その間、シャロスはほぼ毎日、彼女と性行為をしてきた。
彼がその気を少し持っただけで、エナはすぐに彼の内心を見通してくれる。
そして彼女の気遣いの良さや従順さもまた、シャロスの欲望を助長してきたのだ。
今のシャロスにとって、彼女はもはや無くてはならない存在となった。
しかし、シャロス自身はこの状況は良くないと知っていた。
結婚相手以外の女性と不純関係を持つことは、倫理の上では不当なことである。
権力者にとって、これぐらいの色事は大したことじゃないかもしれない。
だが立派な王様を志すシャロスにしてみれば、それは彼の信念とぶつかる問題であった。
しかし、だからといって、シャロスは今更エナを手放すことはできなくなった。
血の気が多く、思春期である彼にとって、
一度味わった女の瑞々しい肉体を、そう簡単に頭から消せない。
朝、シャロスはゆっくりと目を覚ますと、側から心地よい声が聞こえてきた。
「王子様、おはようございます」
エナは普段通りのメイド装束で、恭しく寝台の横で侍っていた。
彼女の白玉のような綺麗な顔立ちには、昨晩の乱れた痕跡が一切なく、無表情のままになった。
シャロスはその表情を見る度に、プライドが酷く傷つけられ感じになる。
まるでそれが、「あくまでリテイア様の命令でセックスしているだけ」と物語っているようだった。
彼女の奉仕は全てにおいて、今までどんな侍女よりも優れている。
しかし、その完璧に近いところが、かえってシャロスに歯痒い思いをもたらす。
□
「レイラ隊長、夜の巡回、お疲れ様です」
「ありがとう、ファロア。今日の警備担当は、あなたの班だったわね。
今日も一日、護衛の任務を怠らずがんばってね」
「はい!」
ファロアと呼ばれた先頭の女剣士はきりっと一礼をすると、軽装備をした女性隊員達を率いて、その場から
去った。
彼女達の姿が見えなくなると、レイラは小さくため息をついた。
朝の太陽は空をのぼり、朝風が心地よく宮殿全域を吹き巡る。
しかし、彼女はそれを感じる気持ちが少しも無かった。
最近の巡回で、シャロス王子からは彼の寝室に近づかないよう、きつく命令された。
小さい時から王子の身近に仕えていた身として、どこか寂しく感じる命令であった。
それでも、レイラはシャロスの命令に従った。
(殿下はもうすぐ成人する御身。それに、世間でも言うじゃない。ちょうど今が自立心が強くなる年頃だっ
て)
レイラはそうやって解釈をした。
しかし、女特有の鋭い勘からして、理由はそれだけじゃないのでは、という疑念は確かにあった。
彼女はうすうすといくつか心に残るような形跡を感じたが、それを無理やり心中に押さえ込んだ。
「どうしたんですか、レイラ隊長」
兵舎の食堂まで来ると、一人の小柄な女剣士がレイラに近寄った。
レイラは彼女から水を盛ったコップを受け取り、感謝の言葉を告げる。
「ありがとう、ナリア。昨晩の巡回で夜風を受け過ぎたか、ちょっと頭が痛くてね。
ところで、あそこの集団は何をやっているのか、私に教えてくれないかしら」
レイラは喉を潤わせながら、むこうにあるテーブルで何やら喧騒する一団を見つめた。
十数人もの女性隊員が、一つのテーブルを囲んでいた。
そのテーブルの両側に二人の若い隊員が座り、お互い片方の肘をテーブルにつき、手を握り合っていた。
どうやら、腕相撲を始めようとしている模様だ。
小柄な隊員はニコッと微笑み、
「サネットとフェリッサですよ。どっちのほうが腕力あるか!という話になって、それで腕相撲で勝負しよ
うと……」
「はぁ、相変わらず元気だね」
レイラは苦笑を浮かべた。
女性隊員とはいえ、ここにいるのはみんな情緒が明るい若き兵士達。
娯楽とは無縁な彼女達にとって、こういった勝負事が特に盛り上がるのだ。
「レイラ隊長は、どっちが勝つと思いますか?」
「サネット」
「ええ?どうしてですか?うちの隊の中では、フェリッサが一番剛腕というのは
みんな認めていることじゃないですか」
「なんなら、賭けてみる?もしサネットが勝ったら、今日午後のナリアちゃんの訓練相手、私がやるわ」
「えー、そんな……」
レイラは普段から上官のような威張った態度を取らず、常に隊員のことを考慮する優しい隊長である。
そのうえ剣の腕は確かで容貌も凛々しく、みんなが憧れる人気高い隊長である。
だがその代わりに、訓練時のレイラほど恐ろしいものはない。
彼女に直接指導してもらうことはもちろん有益ではあるが、
自分がヘトヘトになるまでやらされることを考慮すると、小柄の隊員は少しためらった。
ナリアはサネットとフェリッサを見比べながら、意を決して口を開いた。
「分かりました。では、もしフェリッサが勝ったとしたら……」
「ショートケーキをおごってあげるわ」
「本当ですか?」
ナリアは嬉しそうに丸い頬っぺたを抱え、随分前におごってもらった甘い味を想像した。
しかし、彼女はすぐにハッとなり、
「隊長は、どうしてサネットが勝つと思うのですか?
普通に考えたら、フェリッサに決まってるんじゃないですか」
「だからだよ。サネットは負けを承知して意地に走る人じゃないわ。
みんなが認めていることをあえて挑もうというのなら、何か秘策があるに違いないわ」
レイラはコップの中身を飲みほし、
「今回もきっと、サネットからいろいろ挑発して、フェリッサをうまく口車に乗せたであろう」
ナリアは大きな瞳をパチパチさせた。
「驚きましたよ。隊長はまるでさっきからここにいるみたいです。全部、隊長の言ったとおりですわ」
彼女が言っている途中、テーブルの方で勝負が開始したのか、二人の隊員が腕に力を込めはじめた。
数秒もしないうち、赤いハチマキで髪の毛をまとめた少女が優勢に立った。
彼女は相手の腕を反対側へぐいぐいと押してきた。
周囲の隊員達はあるいは応援を、あるいは野次を飛ばして、その場を盛り上げた。
ハチマキの女性は不敵な笑みを浮かべ、言葉を発した。
「ほらどうしたの、サネットさんよ。大口を叩いたわりに、大したことないじゃない」
「ふっ、笑止だわ。これぐらいで勝ってる気分になるなんて……まだまだお子様だね」
ブロンドの少女は腕をガタガタ震わせながらも、気丈な表情を見せていた。
「ふん、強がりやがって。いいわ、一気にかたを付けてやる!」
ハチマキの少女が強気を見せると、腕でいきなり押しかかった。
それを機に、周囲の声援が高潮を迎えた。
「ところで、フェリッサ。ちょっと、尋ねたいことがあるんだけどさ」
「なんだ?」
「あなたは今度、中央軍部の殿方に、ラブレターを出すんだって?」
「ぶはっ!」
フェリッサが大きく動揺している隙に、サネットは彼女の腕を反対側のテーブルにひっくり返した。
「はい、私の勝ちね。約束通り、今度の射的場に行くとき、おごって貰うんだから」
「てーめ、なんて汚い手を使いやがる!っていうか、誰がラブレターを出すんだよ!」
涼しい顔をするサネットに向かって、フェリッサは納得いかない様子で拳を握り締めた。
「私が聞いた話によると、なんでも最近軍部のほうで活躍している青年将校の……
ホーラフさんだっけ?に、手紙を出すだって」
サネットの一言に、周囲の女性隊員たちがざわめいた。
「えー?ホーラフ?」
「あのホーラフだって!」
「だれだれ?その人は」
「知らないの?最近軍部でもっとも注目を集めている三人の若い将校の一人だよ。
なんでも、シャロス王子様から騎士の勲章をもらったんだって」
「そうそう。武勇に長けるホーラフ、知略に長けるエンルード。そして文武両道のドスラット」
「すごーい!シャロス様からじかに認めてもらえるなんて」
「へー、そのホーラフという人に、フェリッサが……」
まわりの反応を見回し、フェリッサは狼狽した。
「ちょ、ちょっと、違うって!あたしはただ、あのホーラフとかいうやつが腕が立つと聞いて、
挑戦状みたいのを出したいなーと思って……っていうか、
あたしの好きなタイプは、どっちかというとエンルードだぞ」
「なるほど、近衛隊一の駻馬と呼ばれるフェリッサは、そういう男がタイプだったのか」
「た、隊長!」
側へ歩み出たレイラに気付き、フェリッサやほかの隊員たちは驚いた。
「ち、違うんです!わ、私はただ……」
「うふふ、いいのよ。宮殿近衛隊だからといって、恋愛を禁止している訳じゃないんだから。
でも、そのホーラフに出す挑戦状というのは、やめたほうがいいわね」
レイラは後輩を諭すような優しい口調で言った。
「はい、すみません……私、そのホーラフという奴がすごく強いて聞いたから、つい熱くなって……」
「まあ、負けず嫌いなのはいいことだ。お互い切磋琢磨して、競い合って。
でも、私が挑戦状を出さないほうがいいと言ったのは、今のフェリッサの実力では、ホーラフ殿に勝つのが
難しいからよ」
「それは、本当ですか?」
フェリッサは大の負けず嫌いであるが、彼女はレイラのことを誰よりも信頼していた。
レイラの否定的な意見を聞くと、フェリッサはがっくりと肩を落とした。
「三ヶ月前、私は用務があってスデラス将軍のもとへ行った時。
偶然そのホーラフ殿とドスラット殿が訓練場で対戦しているのを見たわ」
レイラが静かに語り出すと、隊員達はみんな彼女の言葉に耳を傾けた。
「それで、どっちが勝ったんですか?」
ナリアは横から尋ねると、レイラは首を振った。
「その時は、引き分けだった。彼らはいずれも素晴らしい才能を持った剣士だ。でも、私の観察からすれば
、
ホーラフのほうが一枚上ってところかしら。彼の剣術のセンスは、特に輝いている物がある。
数年経てば、おそらくホーラフは我が国において、誉れの高い剣士となるだろう」
「でも、うちの近衛隊だって負けませんよね?あいつとファロアなら、どっちが上ですか?」
「ホーラフが勝つでしょう」
「えー、そんな……」
隊員の中で、剣術が最も優れるファロアまで負けると聞いて、フェリッサ達は悔しい気持ちをあらわにした
。
女性のみに組成された隊員達は、自然と男勝りの性格を身に付けていたのだ。
「でも、あえてあげるとしたら……そうね、サネットが一番勝つ可能性を持ってるじゃないかしら」
「私ですか?」
サネットはびっくりした表情で自分を指差した。
「ええ。臨機応変に富むサネットなら、もしかしたら運が傾けて、勝てるかもしれないわ」
「やった!ほらほらフェリッサ聞いた?これでもうはっきりしたでしょう。剣の腕前なら、あなたより私の
方が上だわ」
サネットが嬉しそうに飛び上がり、フェリッサの膨れる頬を突いた。
「いいえ、剣の腕前ではありません」
「えっ、どういうことですか?」
「サネットが今みたいな妙策を成功させたら、何かが間違って勝てるかもしれない、ということだ」
「そんな……レイラ隊長、ひどいですよ」
サネットが困った表情になると、フェリッサをはじめほかの隊員達は笑い出した。
レイラのおもしろい語り口は、いつも彼女達を笑顔にしてくれる。
「知ったか、サネット。レイラ隊長はあえて言わなかったけど、
お前が実力で勝てるようにもっと真面目に練習しろ、という教示だぞ」
「フェリッサに言われたくないわ。それに、勝てるのなら、どんな手段を使ったっていいじゃん」
「なまいきな!」
「フェリッサこそ!」
二人が言い争いを始めると、レイラはまたかという苦笑を浮かべた。
サネットは腕を組み、クールな表情を作った。
「ふん、フェリッサはこれだから。まぁ、いつまでも子供のままで、幸せだからいいけど」
「ちょっと、どういう意味なのよ!」
「別に。……ただ仲間として親友として、このままフェリッサが自分を磨かないと、
将来は苦労するんじゃないかなと心配してさ」
「なんだと?」
「いつまでもガキみたいでいると、いい男が好きになってくれないわよ」
「余計なお世話よ。あたしだって、色気を出そうと思えば、できるんだからね!」
「はっはぁーん。その小さな胸を張ったところで、何の説得力も無いんだけどね」
「ううぅー!」
かなり痛いところを突かれたのか、フェリッサは言葉がつまり、頬を膨らませた。
宮殿近衛隊は女性のみで成り立つため、異性と交際するチャンスはなかなかできない。
そのため結婚年齢になると、今までの功労を認められ、
王室が主導して良家の男性と結んで、退役するのが暗黙の慣例となっている。
それは王室近衛隊の特権に近いものである。
とはいえ、全てうまく行く保証は無いので、いつまでもお転婆娘のままでは、お見合い相手すら見つから可
能性も出てしまう。
「それを言うなら、サネットだって……!」
「ふふっ、それはどうかしら」
サネットは得意げに胸をはった。
「私なら、いつも殿方に惚れられるよう、いろいろ気を使っていますもの。
スタイル良し、顔良し、性格もよし。こんないい女は、なかなかいないですわ」
サネットは深窓の令嬢を真似て、手の甲を口元に当てエレガントを装った。
まわりの隊員達はその仕草に笑いながらも、それを認めるしかなかった。
性格良しは別としても、サネットはなかなか見当たらない上質な美女である。
「そんなこと言っちゃって!うちの隊で一番の美人というなら、レイラ隊長でしょう」
「えっ?」
まさか自分が話題になると思わなく、レイラは戸惑った。
「うっ……そ、それは!……確かに……」
「そうですよ、私達の中で一番速く結婚するとしたら、レイラ隊長ですわ」
ナリアが一言に、サネットを含めて隊員達は一斉に頷いた。
「ちょっと、結婚だなんて……私、まだ全然考えたこと無いわ」
「レイラ隊長は、一体どうやってそのようなプロポーションを保っているんですか?」
「私は、そういうのは今まで気にしてないわ」
レイラは照れくさそうに頬をかきながら答えた。
彼女のさりげない一言に、尋ねたサネットはショックを受けてしまう。
「そ、そんな……」
サネットは羨ましそうにレイラの体を見渡した。
「レイラ隊長みたいなお方は、将来きっと素敵な出会いが待ってるのに違いありませんわ」
ナリアは瞳をキラキラさせながら言った。
「ははっ、そんな大層な……」
「そうだね、やっぱりシャロス王子様のような、素敵な男性じゃないと釣り合わないもん」
「こらっ、ナリア!殿下になんという侮辱を」
「いやでも、私もナリアの気持ち分かるわ。
殿下みたいな凛々しくて、立派なお方でないと、レイラ隊長はもったいないですもの」
「うんうん。でも、シャロス様以外で、あれほど素敵な男性はいるかしら」
「もう、あなた達には、付き合え切れないわ。
ほら、昼飯の時間が終わったら、あなた達をきつく訓練してあげるから、覚悟しなさいよ」
「「はーい」」
隊員達は明るく返事し、残りの時間をくつろいだ。
レイラはやれやれといった表情を作るが、心底ではひそかに嬉しい気分が溢れ出た。
だがそれは一体なぜなのかは、レイラには理解できなかった。
□
賢王の再来とも予言されるシャロスは、天成の治世家であった。
利害や問題点を一瞬で判断し、前例に無い手法を大胆に駆使する。
先王の急逝により招いた国はしばらく混乱が続いたが、それも彼の統治によって徐々に落ち着いたのだ。
しかし最近、エナと肉体的関係を持ち始めてから、シャロスは以前ほどの鋭い判断力が発揮できなくなった
。
今日の昼前も、シャロスは今までに無かった焦燥感に責め続けられるのであった。
山のように積もる報告書の側、彼は悶々と座り続ける。
目線はただ報告書の上を走り、内容を短絡的に見通すだけだった。
股の下で一物が衰えることなく張り続け、彼の思考回路を邪魔する。
シャロスは精神を収集するが、淫らな思いは消えるどころか、体中に広まっていく。
エナとの天国をさまようような体験は、いつしか茨のように彼の華奢な心身を巻きつく。
その淫靡な光景を理性が拒んでも、悪魔のような欲望の声が耳元で響く。
ペニスが絶えずドクン、ドクンと脈打ち、シャロスをせめ立てる。
「くっ……」
シャロスはたまらず立ち上がり、外へと出かけた。
宮殿を囲んでいる大きな庭園は、建国以来の長き歴史を渡り、多くの園丁の手によって営んできた。
かなりの広さがあるため、シャロスは目的も無いまま歩いていたら、いつの間にか普段行くことの無い区域
に出た。
「あっ、王子様!」
突然起きた黄色い声に、シャロスは背後を振り返えった。
すると、エナと瓜二つの顔立ちを持つ少女が視界に飛び込んできた。
「やっぱり、王子様だったんですね!」
元気一杯で、屈託の無い笑顔。
エナの双子の姉妹、マナというメイドであった。
「マナ!どうしてここに?」
「遠くから王子様のお姿をお見えになったので、
こっそり後をつけました。それに、ちょうど私もこちらに用がありまして」
「ここは一体?」
「あれ、王子様は知らないで来たのですか?どうりでおかしいと思いましたわ。
王子様のような高貴なお方が、私達のような下人が働く場所に来てくださるなんて」
ふと、マナはずる賢い小猫のよう表情を浮かべ、いきなりシャロスの腕にしがみついた。
シャロスはその不意打ちに避けることができず、マナに抱きつかれてしまった。
服越しに感じる胸の柔らかい感触に、彼の顔はさっと赤めた。
エナとは何度か行為をしてきたが、基本的に彼は女性に対する免疫力が無いのだ。
その初々しいぶりを見て、マナはひそかにほくそ笑んだ。
「マナ……な、何をしている!」
「うふふ。こうしていると、王子様と恋人同士になったような気分になれるの……
ねぇ、王子様は、私のことお嫌いですか?」
マナはシャロスの腕を自分の胸に擦りながら、潤んだ両目で彼を見上げた。
そのまるで小動物のような可愛らしい表情に、シャロスの心が大きく揺らいだ。
普段それと同じ顔つきの冷淡さを見慣れていたせいか、余計に色っぽく感じてしまう。
「こんなところで誰かに見られたら、大変なことになるぞ」
「ふふふ……じゃあ、嫌いじゃないのね」
マナはシャロスの股間に手を伸ばし、その上を軽く撫でた。
たったそれだけの行為で、シャロスの体がビクンと動いた。
彼が顔を真っ赤に染めるのを見ながら、マナはけらけらと笑った。
「王子様のあそこ、ビンビンじゃない。こんなお昼からお盛りになるなんて……エッチなことで、頭いっぱ
いなのね」
「そ、それは……」
マナに痛いところを突かれたシャロスは、思わず顔を俯いた。
「私はこれから用事があるので、ある場所に行かなければなりません。
王子様も、私と一緒に行きませんか?そこなら、誰にも見られませんわ」
マナは挑発的な笑みで、シャロスを見上げた。
その言葉の裏にある淫らな意味が、シャロスの心をくすぐった。
聡明だったはずの意識も朦朧となり、思わず頷いてしまった。
マナはもう一度かわいらしい笑みを浮かべて、彼に体をくっつけたまま歩き出した。
シャロスは自分の優柔不断を責めながらも、腕を引かれるまま進むしかなかった。
しばらくすると、二人は庭園のはずれに位置する古ぼけた楼閣へやって来た。
「ここは、いわゆる倉庫ってところですわ。まあ、王子様には、目にするどころか、聞いたことも無いでし
ょうね」
マナはシャロスの疑問の表情を察すると、解説を加えた。
中へ進むと、そこはシャロスが住む御殿よりずっと簡素なつくりであった。
飾り気のない廊下を通り過ぎながら、所々いろんな備え付けの品物が積まれているのが見える。
両側にいくつもの部屋があるが、中には万年使う機会が無いのか、蜘蛛の巣や塵で汚れた扉もあった。
高級生活に慣れ親しんだシャロスにとって、それはそれで新鮮な光景だった。
横から五つ目の部屋の前へ来ると、マナはその扉をあけ、シャロスを中へ連れ込んだ。
奥のほうには数多くの木箱が積まれ、窓の光を遮っていた。
そこでマナは扉をしめると、薄暗い空間に、ただ二人の男女が残されるのみとなった。
神秘な静寂に包まれる空気の中で、シャロスはわけもわからず心を高鳴らせた。
しばらく目が慣れると、彼は部屋中の様子を観察した。
いくつかのテーブルや椅子が、無造作に並べられている。
横には羊毛で編まれた高級絨毯が、柔らかそうに何枚も重ねられていた。
マナは鼻歌をうたいながら、悠然とした表情で一つの椅子に座った。
しかしシャロスはどうすればいいのかさえ分からず、ただ立ち尽くすしかなかった。
その困惑した立場を解消するために、彼は腹の中で言葉を捜し続けた。
「……ここは、どこなの?」
「宮殿に置かれている物って、いつか壊れるんじゃないですか。そのために、ここで備品を蓄えているんで
すよ」
マナは軽い口調で答えながら、熱そうにメイド服の襟ボタンをはずした。
シャロスは瞬時に顔を赤らめ、彼女から目線をはずした。
そのはにかむ仕草を見て、マナは微笑んだ。
「でも、ここでの取り出し作業は、そんなに頻繁ではないのです。
むしろほかの目的のために、良く使われているのかしら」
「ほかの……目的?」
「はい。逢引き、なんですよ」
「あいびき?」
聞いたことも無いワードに、シャロスは首をかしげる。
その様子を見たマナは、おかしそうに笑い出した。
自分がバカにされたようで、シャロスは憮然とした。
マナはそんな彼の心情を察したのか、すぐに謝った。
「ごめんなさい、今のは私が悪かったですわ」
「ふん、別に……」
シャロスはそう言って顔をそむけるが、突如マナが彼を壁際に押さえ付けた。
「何をするつもりだ」
「もう、そんなに怒らないで、王子様。マナは、王子様に良くしたくて、ここにつれてきたのです。
お詫びと言ってはなんですが、これからは王子様はマナと、逢引きをしてみませんか」
マナは顔に柔和な表情を掲げ、軽やかな声で囁いた。
その女らしい仕草を受けて、シャロスの怒気は一気に和らいだ。
彼女はその華奢な体を軽くシャロスに押し付け、彼の両手首を掴んだ。
不思議な事にシャロスは彼女の無礼を咎める念頭は、なぜか思い立たなかった。
それどころか、体が密着することによって、彼女を可愛いと思う気持ちが段々と大きくなった。
時には悪戯っぽく、時には皮肉っぽく、時には優しく変化する彼女の態度は、まるで掴み所が無かった。
しかし、その変わりやすい性格がまた彼女の魅力であった。
そんな憎めない彼女をいつの間にか好きになった事に、シャロスは気付かなかった。
彼はつとめて不機嫌そうな顔を装った。
「お前はエナと顔はまるっきり同じなのに、中身が全然違うんだな」
「ふふふ、それは当然ですもの。私とエナは物覚えを始めたときから、別々の環境に分けられ、
リテイア様やフシーさんに厳しくしつけを受けました」
「フシーさん?」
「はい、彼女は私達のメイド長で、私達にとってリテイア様の次に偉い人なの。
もっとも、リテイア様に仕えるメイドは、みんな彼女のしつけを受けるけど」
「そうなのか?」
「はい。あの女だけは、私も苦手なのよ。王子様も注意してね。王子様のようなかわいい男の子が彼女の手
に堕ちたら、
どんなふうに調教されることや……あっ、それもそれで見たいですわね」
シャロスはマナの言葉を半信半疑に聞きながら、彼女はその人物が好きじゃないということを理解した。
「皇后は、一体なにを狙っている?」
「なんのことでしょうか?」
「とぼけるな。エナやお前を私に近づかせたのは、何か目的があるだろう」
「そんなの、言いがかりですわ。私はただ、王子様に気持ちよくなってもらいたくて」
「なにを……むぐっ!?」
マナは彼の抵抗しようとする両手を抑え、その口の上に潤んだ唇を重ね合わせた。
シャロスの瞳はぼんやりととろけ始めた。
少女の柔らかい唇は積極的に彼にしゃぶり付き、なめらかな舌を進入させて絡ませる。
それと同時に、彼女はシャロスの股間に膝をあてがった。
「むむっ!」
今まで悶々としてた場所が、それを機に燃え上がった。
マナは彼の首に手を絡ませながら、太ももを使ってゆっくりと両足を開かせる。
たちまちシャロスの体から抵抗しようとする意思が消え、マナに身をゆだねてしまった。
しばらく経った後、マナはようやくシャロスから顔を離した。
シャロスは全身を火照らせ、ぼんやりとした表情でマナを見つめる。
マナは両手で彼の頬を抱き上げ、
「うふふ……王子様って、本当にかわいいわよね。まるで、女の子みたいだわ」
悪巧みの笑みを浮かべると、シャロスの股間を当てる膝に力を入れた。
「ああっ……!」
シャロスは思わず内股になった。
服の上から、マナはちょうどいい力加減で彼のあそこを挑発し、欲望を増大させた。
自分でもあそこが爆発しそうなぐらいに、血液が集中していくのが分かる。
気持ち良さのせいで足に力が入らなくなり、マナに押されるままズルズルと壁を滑って床に倒される。
マナはそのまま上を這い、柔らかい乳房の部分をシャロスの胸にくっつけ、彼の耳元で色っぽく囁いた。
「ねぇ、王子様。聞こえるでしょう?私の心臓が、ドクン、ドクンと鳴ってるの。
王子様とこんな近くにいられるなんて、私すごく緊張してるの」
シャロスは耳元や股間から来る妖しい快感を耐えながら、懸命に理性を取り戻そうとした。
「で、でも……王宮内で、こんなふしだらなことをするなんて……」
「それなら、みんなやってるわよ。言ったでしょ、ここは宮殿の下人達がこっそり会う場所なの。
宮殿内ではいろいろ厳しい規則あるが、ここなら人の目を盗んで、いろいろやらしい事ができるの」
「ど、どうしてお前がそんなことを知ってるの?」
マナは答えないままニコッと微笑み、シャロスの白いうなじに舌を這わせ、優しく舐めた。
湿った舌の滑らかさが一瞬のうちに通り過ぎ、シャロスの思考回路をショートさせた。
その恍惚になりかけた様子を見て、マナは会心の笑みを作った。
彼女はシャロスが見る前で、人差し指と中指をぴったりくっつけて、棒の形を作った。
そして挑発的な目線を送りながら、唾液をふんだんに含んだ口で指をくわえる。
シャロスは目の前の光景を見せ付けられて、胸が大きく揺らいだ。
マナは口をすぼめながら、白くて長い指を舐め続けた。
その先端を舌先でぺろりとくすぐり、その横を角度変えながら濡らし、そして根元まで口内に含ませる。
そしてしばらく唾を溜め込み、それを指の上につーっと垂らして、シャロスの瞳を見つめながら舌で唾液を
舐め取る。
まるで自分のあそこが舐められているようで、シャロスは太ももをうじうじさせた。
彼女の柔らかい胸の鼓動を感じながら、シャロス自身の心も跳ね上がった。
相手の瞳の中に含まれた艶笑のようなものに、シャロスは屈辱のような感情を覚える。
それはまるで、見とれてしまった自分をあざ笑う物のようだった。
万人の上に立つ者として、これほど不甲斐無く思うことは無かった。
マナから目が離せない自分が悔しい。
一人の侍女にいいように扱われるのがもどかしい。
しかし、その悔しさやもどかしさの裏側に、かすかながら快感に近い感情があった。
「ねぇ、王子様は気持ちよくなりたいでしょ?」
「そ、それは……」
「そうだったらそうで、ちゃんと『うん』とか『はい』とか言うのですよ。
それとも、やめちゃってもいいかしら、王子様?」
「う、うん!」
「うふふ、いい子ね。じゃあ、これから私の言うことを良く聞いて。口をあーんっとあけてごらん」
マナは悪戯っぽい笑みを浮かべて言った。
自分とはそう違わない歳なのに、子供扱いされてしまったことが悲しかった。
しかし、それでもマナの言うことに逆らえず、シャロスは口を開いた。
「じゃあ、私のつばが一杯染みこんだ指を味わいなさい」
マナは透明な唾液で濡れた二本の指をシャロスの口内に入れ、彼に口を閉じさせた。
「ううむん!」
「ほら、舌をもっと使って、満遍なく舐めなさい。さっき私がどういう風に舐めたかを、思い出しながら」
マナに言われると、シャロスは仕方なく彼女の指に舌を絡ませた。
ぬるぬるした他人の甘い味が、口内に広がる。
それが目の前にいる悪魔のような美少女の物だと思うと、悔しくも股間の一物が意気地なしにも反応した。
そのささやかな変化を、マナは当然見逃すわけが無かった。
「ふふふ、私の指を舐めながらあそこをギンギンにさせるなんて……
王子様って、ひょっとして変態さんなのかしら?」
マナはほくそ笑みながら、シャロスの口内で指をかき回した。
彼女の指に付着した唾液は舌に擦り付けられ、シャロスの口の中で香ばしい味が広がった。
シャロスは背徳感に責められながらも、犬になった気持ちで彼女の指をしゃぶり続けた。
しばらくすると、マナは指を抜き取り、シャロスの体から離れた。
シャロスは息を荒くしながら見上げると、マナの挑発的な微笑みと、彼女のスカートの中身が見えた。
太ももまで覆うスカートの中に、黒の下着の姿があった。
その黒い下着を、マナはゆったりとした動作で脱いだ。
シャロスは思わず瞳孔を大きく開かせた。
スカートの裾で見え隠れする中、女性の最も神秘な場所が生まれたままの姿を晒す。
形良く整えたアンダーヘアの下に、淫らな割れ目がそこにあった。
シャロスがもっと見たいと思った矢先に、マナは指でショーツをくるくるしながらその場から離れる。
彼女は小悪魔のような愛しい笑みを浮かべ、椅子に座って足を組んだ。
スカートの裾は重ねられた太ももの上でとどまり、彼女のアソコの様子が完全に見えなくなった。
その誘惑的な光景は、シャロスの欲情を大きく焦らした。
彼はその場から立ち上がり、自分の両手をどこに置けばいいのかさえ分からないほど慌てた。
「マ、マナ……」
「王子様は、マナのあそこを、もっと見たい?」
「う、うん……」
「ふふふ、嬉しいわ。でも、私だけアソコが裸で、王子様が服を着ているなんて……
ちょっとずるいと思いませんか?」
「えっ?でも、どうすれば……」
「王子様にも、下の服をぜーんぶ脱いでもらおうか」
シャロスはうろたえた。
自分の部屋でもお風呂場でもない場所で裸になることは、もちろん抵抗がある。
「どうしたの、王子様。ひょっとして恥ずかしいのかしら?大丈夫ですよ。
前にも、王子様は私に裸を見られていたではないですか」
マナの悠然とした態度を見て、シャロスは意を決してズボンを脱ぎ始めた。
躊躇はしたものの、結局下着まで全て脱いだ。
すると、熱くたぎったペニスが天井を向かっていきり立つ。
「やっぱり王子様はあそこを勃起させていましたのね」
マナがシャロスのあそこを見てくすくす笑うと、シャロスは恥ずかしさで胸いっぱいになる。
上半身だけ服を着て、下半身が全裸に。
そして、メイドである少女に見られ、笑われる。
そんな状況に反し、一物が萎えるところが、ますます硬くなっていた。
「じゃあシャロス様、こっちに来て、私の前でしゃがんでごらん」
マナが手招きすると、シャロスは仕方なく彼女の前にやってき、膝を床に突いた。
少女は椅子の上にのぼると、両足を外側に開き、秘所が良く見えるように開かせた。
「ふふふ、どう?これが女のオマンコよ」
マナは腰を柔らかくしなやかせると、シャロスの顔面の前に、彼女の性器が晒しだされた。
今まで何度も性経験してきたが、こんな間近で女性の性器を見るのは初めてだった。
桃色の淫唇は、シャロスのまだ幼さが残る心に淫らな方向へ刺激する。
「ねぇ、私のアソコにもっと顔を近づかせて。それから、大きく息を吸ってごらん。
そう、そうやってスーハーするの。どう、アソコの匂いは?すごくエッチで、いやらしいでしょ」
「う、うん……」
シャロスは茫然とした表情で、こくりと頷いた。
彼は言われるがままに、マナのアソコの前で息を繰り返した。
「うふふ……そうよ。そうやって、私の匂いが、王子様の脳の奥まで染み渡るように。
その匂いを、よく覚えていなさい。これからはこの匂いを嗅いだだけで、あなたは私の言うことをなんでも
聞きたくなるように」
まるで魔法にかかったように、シャロスは目を虚ろにした。
彼の恍惚な表情を見下ろし、マナは会心の笑みをあらわにする。
突然、扉が「ドン、ドン、ドン」と叩かれる音がした。
「……!」
シャロスは咄嗟に我に返り、その場で固まった。
「あ~あ、邪魔が入っちゃったね。王子様、何者かが来たようですわ」
「ど、どうすればいいの?こ、こんなところで見られたら……」
シャロスは顔色を青ざめた。
悪いことをしてしまった彼には、罪悪感のため逃げることしか考えられなかった。
しかしこの部屋は入り口の扉以外、封鎖された窓しかない。
「王子様、あそこの木箱の裏側に隠れてください。後ろは空きペースがありますので、そこでじっとしてい
てください」
「わ、分かった!」
「それと、これもお持ちになって」
マナはシャロスに黒い下着を手渡した。
「な、なぜこれを?」
「あははっ、途中でしたくなったら、それで私の匂いを思い出してね」
扉がもう一度ドンドンドン、と叩かれる。
マナは相変わらず緊張感の無い笑顔を作るが、今のシャロスにはそれを反論する余裕が無かった。
シャロスはショーツを握り、急いで木箱の後ろに駆け込んだ。
そこでしゃがんでから、シャロスはまだ下半身が裸であることに気付いた。
焦燥の表情で頭を出すシャロスに対し、マナは悪巧みの笑みを浮かべて、シャロスの服を反対方向の角へ投
げ込んだ。
(あいつ、わざとやって……!)
シャロスは胸の中で怒りを焼くが、どうすることもできなかった。
マナはスカートを少し整えると、ゆっくりと扉のほうへ近づいた。
そして彼女の次の行動は、シャロスの予想を越えるものとなった。
彼女は、扉の外の人間と同じようなテンポで、扉を三回叩き返したのだ。
かすれるような軋み音とともに、扉がゆっくりと開かれる。
シャロスは自分の心臓が口から飛び出すじゃないかというぐらい緊張した。
彼はただ、マナがうまく外の人間を言いくるめることを祈るほかなかった。
だがマナの行動から、シャロスは何かが変であることに気づいてしまう。
木造の床が軋み、一つの足音が近づいてくる。
シャロスは木箱を背にして座り、背中に冷え汗を流した。
「遅かったじゃない。私、ずっと待ってたんだからね」
マナの駄々をこねる口調は、シャロスを大きく驚かせた。
しかし、もう一つの声に、彼はさらにきょとんとなる。
「……すまない。スデラス将軍の軍議が終わったら、すぐここに向かったつもりだった」
(軍議……?)
聞き覚えのある声と、気になる単語。
危険な状況ではあるが、シャロスの好奇心が大きく膨らんだ。
彼は木箱の隙間に顔を近づけ、部屋の中央を見つめた。
椅子に座るマナの側で、鎧を装備した騎士が立ち尽くしていた。
やや動揺気味の様子ではあったが、女性の目を惹くようなかっこいい顔立ち。
その容貌を記憶の中で探り当てたとき、シャロスは思わず声をあげそうになる。
目の前にいる男こそ、最近期待を集める青年将校、スデラス将軍の麾下であるドスラットその人である。
――中央軍部で突出した才能を持つ三人の若者。
武勇に優れるホーラフ。
知略に優れるエンルード。
そして、武勇や知略の両方に長けるドスラット。
彼ら三人は、老将スデラスにも認められた人材である。
つい先日、騎士の勲章を受けたばかりで、今後の軍界を担う若武将として注目を浴びている。
そのドスラットが、一体どうしてここにいるというのか。
「例の物を、持ってきたかしらね」
「……ああ……」
マナの問いかけに、ドスラットはそっけなく答えた。
二人の間に流れる奇妙な空気に、シャロスは疑問を抱いた。
接する期間はまだ短いものの、シャロスはドスラットという人間を良く知っているつもりだ。
謙虚だが決断力があって、冷静だが決して怯まない。
そして歳が若いわりには、大局を見据える力が備わっている。
彼と軍事の問答をしている時、その核心に迫る見方が特に印象的だった。
そんな前途有望な若者が、一体何故侍女と接触するのか。
「どうしたの?あなたはそれを私に渡したくて、ここに来たじゃないの?」
マナの余裕綽々の態度とは対照的に、ドスラットはパッとしない面立ちであった。
彼は黙ったままふところから一つの書類を持ち出し、それをマナに手渡した。
マナは素早く書類に一通り目を通して、満足した表情でスカートポケットに入れた。
「うん、よくやったわ。さすが騎士さま、この中央軍部の作戦指針書の副本をとるのに、大変だったでしょ
」
マナはただニッコリとしただけだが、聞いていたシャロスは驚愕の表情になる。
帝国五大軍は、五つの軍部によって統制され、その上国王が統轄するシステムとなっている。
軍事行動の実態、予算、今後の展望など数々の機密データを含む作戦指針書は、
この国の命運を握ると言っても過言ではない。
そして、今期の中央軍の作戦指針書は、まだシャロスの手元に届けられていないのだ。
中央軍統帥のスデラス将軍の側近であるドスラットなら、その書類をいち早く拝めることができるだろう。
しかしまさかをこんな形で、一介の侍女の手に渡っているとは、シャロスは夢にも思わなかった。
「俺は、本当に許されるんだろうか。こんなことがもしばれたら……」
「何いまさら焦ってるの。もうずっと前から、やってきたことじゃない。
今のあなたに残されてる道は、これからもうまくばれない様にやり続けることなのよ」
「お前は……まだ俺を利用し続けるというのか!」
「大丈夫よ。うまくやってくれたあかつきに、上の人間だってきっとあなたを認めてくれるわ」
マナはくすりと笑って、固まるドスラットに抱きついた。
彼女が言う「上の人間」はリテイア皇后を暗示していること、シャロスはすぐに感じとった。
マナはドスラットの唇に軽くキスしてから、ぐるりと体をまわして離れた。
「ねぇ、今はそんな物騒な事を気にするより、私といいことをしましょ?
ふふふ、あなたの悩みを、全部忘れさせてあげるから」
少女はその歳にそぐわない妖艶な笑みを浮かべ、ゆっくりとスカートの裾を持ち上げた。
ドスラットはまさか彼女は下に何も着ていないと思わず、ビックリした表情になった。
彼がマナの体に触れようと手を伸ばすと、マナはくすっと笑って裾をおろし、妖精のように軽やかにかわし
た。
遠くから見ているシャロスでも、心がうずうずしてたまらなかった。
可愛らしいな顔立ちと放蕩な仕草。
メイド服の下にあるのは、青春の息が溢れる肢体。
そして、ひらひらと漂うスカートと、そこから見える陰部。
どんな生真面目な男性にとっても、食指を動かさずにいられない光景だろう。
マナは煽情的な笑い声をこぼし、誘うように体を躍らせた。
ドスラットはすっかりその虜になったのか、魅入られたような目付きで彼女を捕まえる。
「ははっ、騎士さまったら。いいわ、マナが気持ちよくさせてあげる」
そう言って、マナはドスラットの首に腕をまわし、口付けをした。
彼女のふしだらな行動にむっとしながらも、
シャロスはそのなまめかしい舌の動きを無意識のうちに想像してしまった。
マナの体はだんだんと柔らかくなり、遠くから見てもその顔が火照り出したのが分かる。
その色っぽいさまに、シャロスの股間の一物がそびえ始めた。
(くっ……そんな、体が勝手に……)
シャロスは思わず硬くなったペニスに指を添え、ゆっくりと弄りだす。
二人のほうから、いやらしいキスの音が断続的に聞こえてくる。
ようやく顔を離れたときに、マナは乱れた髪を整えて、頬を赤らめた。
「ねぇ、騎士さま。マナのことをよく見て」
マナはゆっくりメイド服に手を掛け、上着から脱ぎ始めた。
彼女の大胆な行動に、シャロスもドスラットも視線が釘付けとなる。
布が肌をかすめる音がしばらく続いた後、マナは今まで身につけていた物を全て脱ぎ捨て、
それから裸のままかたわらの織物の上に横たわった。
シャロスは今までずっと、淫らな女性はみんな不潔だと考えてきた。
しかし、目の前のマナの裸姿は、そんな彼の思いを覆した。
皓月のような白い肢体と、女性特有の柔らかい曲線。
それが横たわっている優美かつ官能的な光景は、絵画のように美しかった。
たおやかな乳房と、しなやかな腹部や臀部。
綺麗に整えた陰毛は、淫猥な光沢を跳ね返してくる。
マナはさりげなく腕があげ、背中をさすった。
彼女の滑らかな腋肌は優美に表現され、背中やお尻、太ももと並んで美しいラインを描く。
マナはけだるそうに両目を細め、含みのある笑顔を青年騎士に向けた。
騎士の緊張な面立ちとは対照に、彼女の表情は余裕に満ちていた。
その誘惑を含んだ余裕さは、男の欲望を更に煽る。
「ねぇ、どうしたの?私と気持ちいいことをしたくないの?」
マナは潤んだ唇を開き、耳元で響くような心地よい声で言った。
その柔和な声を聞いただけで、シャロスの心が大きく動揺した。
甘くて恋しい感情がぼんやりと脳の中を広がり、彼女の言うことなら何でも従いたい気分になってしまう。
マナの間近に立つドスラットはその影響をより多く受けたか、何も言えずに彼女に近づく。
彼は震えた両手でマナに触れようとすると、マナはくすりと笑い出した。
「そんな暑苦しい鎧を着たまま、私とするというの?おバカさん」
「あっ、うっ、すまない……」
ドスラットは言われて初めて気付いたか、そそくさに鎧をはずし始めた。
しかし、あまりにも慌てているせいか、金具をはずすのに何度も失敗した。
彼のぎこちない手つきを見て、マナは更に笑い出した。
「うふふ、騎士さまなのに、まるで新兵みたいじゃない。
いいのよ、落ち着いて。ここには私達以外に誰もいないんだから」
ドスラットは顔を真っ赤にさせて、何か反論することもできず、
ただ無言のまま身に着けているものを全て脱ぎ捨てた。
普段なら雄々しく戦場に立つ彼が、今ではまるで無力の子供のようにマナに使役されていた。
「騎士さま、はやく来て。マナのいやらしい体を、味わってください」
マナが猫なで声で誘うと、ドスラットはマナに覆い被さった。
彼は欲望が満ちた獣のように、白い乳房にすいつく。
「あはぁん。もう、慌て者なんだから」
マナは淫らに微笑むと、妖艶な水蛇のように体をドスラットに巻きつかせた。
彼らの淫靡な行為を見て、シャロスは溜まらず自分の一物をしごきだした。
耳から聞こえてくる淫蕩な喘ぎ声に、彼の喉がからからになった。
シャロスは一時もマナの裸から目を離さず、彼女の恍惚な表情を追いながら欲望を滾らせた。
柔らかい織物の上で二人の男女は激しく蠢き、やがて股を重ね合わせた。
(くっ、足りない……こんなんじゃ、足りないよ!)
シャロスは自分の渇きを感じていた。
マナの艶かしい裸を抱きたい。
彼女のあそこに、熱い精液を注ぎたい。
ドスラットの動きに合わせ、腰を悩ましく動かすマナの姿に、シャロスはこれ以上無い欲情を覚えた。
そして時々、マナはドスラットの背中を越して、シャロスがいる方向に淫らな笑みを送ってくる。
相手が自分を挑発しているのを分かっている。
しかし、シャロスは歯痒い思いを抑えることができなかった。
ふと、彼の目線はさきほどマナから預けられた黒い下着に触れてしまう。
その途端、マナの誘惑するような言葉が耳元でよみがえる。
(途中でしたくなったら、それで私の匂いを思い出してね)
シャロスはその黒い布切れを見て、ごくりと息を飲んだ。
刺繍を施されたシルクは、触り心地がとても良かった。
薄めの布地は、それを履いた者のあそこを軽く隠していることを想像すると、心が大きく興奮した。
やってはいけない行為と分かっていた。
一国の王となる者が、そんなはしたない事をするなんて、彼のプライドが許さない。
しかし、今のシャロスにとって、マナへの欲望は何よりも魅力的なものであった。
彼はゆっくりとシルクのショーツを持ち、彼女の陰部に当たる部分を鼻に近づかせ、大きく息を吸った。
うっすらと甘酸っぱい匂いが、脳に染み渡っていく。
(はぁ……これが……マナの匂い)
シャロスは左手でショーツを持ったまま、右手でペニスをより強くしごいた。
そして、彼は熱い目線をまぐわう二人の男女に注いだ。
「はぁっ、うくっ……はああぁ!」
「はぁ、はぁ……」
「あははっ、いいわ、騎士さま!もっと、マナを突いて!私のいやらしいオマンコに、もっと欲情して!」
「うっ……そ、そんな、締まる……だめだ、もう、出るぞ!」
「あははは、それはだーめ!」
マナは笑いながら、ドスラットのたくましい胸板に両手をつき、動きを止めた。
彼女の体中に汗玉がきらめき輝き、濡れていた背中や乳房が美しく映された。
「くっ……も、もう我慢できない……」
「うふふ……じゃあ騎士さま、イク前に聞かせて。騎士さまは、私のこと好き?」
「あっ、ううっ……す、好きだ!」
「私のことを、この世の誰よりも愛していると誓える?」
「ちっ、誓う!俺は、お前のことを……この世で一番愛してる!」
「じゃあ、これからも私の言うことを全部聞いてくれるよね?
どんな難しい注文でも、私のために、忠実にやってくれるよね?」
「はぁ、うぐっ……誓うよ!これからも、お前のためなら、俺はなんだってやる!
だから、速く……速くイカせてくれー!」
彼の言葉を聞くと、マナは満足の笑みを浮かべた。
「うふふ、よく言ってくれたわ。ご褒美に、盛大にイカせてあげるわ!
これからもずっと、ただ私の奴隷となって生きなさい!」
マナは自分の体を上にして、ドスラットの上で腰を波のように強くうねらせた。
「ああ、ああぁぁぁ!」
ドスラットの口から、快楽に満ちた悲鳴が出てきた。
「そうよ!そうやって、私のオマンコを感じなさい!
もう二度と忘れられないように、私のオマンコの味を覚えさせてあげる!」
マナはあどけなさが残る顔を邪悪な笑みで染め、ドスラットの上で激しく動いた。
その快感を想像しながら、シャロスは股間の物を高速にしごく。
鼻の中を充満するマナの匂いが、シャロスの理性を暗闇へと葬る。
マナと性交している錯覚を覚えると、彼のあそこがビクビクと跳ね出した。
「ああぁっ、もう……だめだ!で、出てしまうっ!」
「はぁん、いいわよ……私の中に出して。あなたの汚らしいザーメンを、いっぱい出してちょうだい!」
マナは口元を吊り上げ、腰をギュッとひねった。
その衝撃に、ドスラットは乾いた悲鳴を出した。
それに合わせて、シャロスのあそこからもドピュッと白い精液が吐き出された。
「ああっ、うぐっ……ううっ!」
ドスラットは歯を食いしばって、腰を懸命に突き上げた。
「あはぁん、いいわよ……私の中で出すために、そんなにがんばっちゃって。
ああぁん、出てくる……中で精液がいっぱい出てくる!」
マナは熱っぽい表情で、快感のために体をしなやかせた。
彼女は両足を痙攣させながらも、最後の一滴までを搾り出すように、腰をゆっくりと上下に動かし続けけた
。
その妖しい快楽に、ドスラットはただ体を震わせながら、床に身を置いたまま耐え続けるしかなかった。
□
「じゃあ、先に出るぞ」
「ええ。軍部に戻っても、見破られないように、気をつけてね」
マナは揶揄めいた口調で、ドスラットの腰や両足を見つめた。
「……分かってるよ」
ドスラットはたまらないといった様子で、あたりをうかがいながら部屋から離れた。
その気配が遠のいていくのを感じながら、シャロスは自分の下半身を呆然と見つめた。
他人の行為を見ながら、自慰に耽る自分が情けなかった。
「王子様、もう出てきてもいいわよ」
マナは木箱を支えながら、突然シャロスの側に現れた。
「マ、マナ!」
「どうだったかしら?その様子だと、王子様も充分に楽しまれたようですね」
マナはシャロスの左手に握るショーツと股間の狼藉を見ながら、あざ笑うかのように彼を見下ろした。
「こ、これは……」
「あははは、隠さなくてもいいのよ。でも、嬉しいですわ。
王子様が、私がセックスしているところ見ながらオナニーしてくださるなんて」
マナはシャロスの腕を引っ張り、彼を部屋の中央に導いた。
「マナ、お前は他の男と密会するつもりだったのに、わざと私をここに誘ったな!」
「そんなつもりはありませんわ。でも良かったじゃないですか?スリルがありまして」
「あのな――!」
シャロスは必死に彼女を嫌悪する感情を呼び起そうとした。
目の前の女には憎めない可愛らしさがあって、それがシャロスの理性を邪魔する。
「くっ……お前は、いや、お前達は一体何をたくらんでいる?軍部の機密情報を手に入れて、どうしようと
いうのだ」
「さあ。私みたいな下っ端には、分かりませんわ」
「とぼけても無駄だ。この後、私がドスラットの奴に問いただせば、全部暴露できるからな」
「別に、いいですわ」
「なに?」
「だって、そんなことを聞いたら、王子様が私としたことも、全部ばれるじゃない」
「くっ……」
「ふふふ、どうせこのままでも、あの男にはもう未来が無いから。立派な軍人さんだったらしいけど、
彼はもう私にメロメロになったんだから。これからも骨を抜かれたまま、私の言いなりになるでしょう」
「なんということを……」
「ねぇ、そんなことより……王子様は、私のアソコに入れてみたくないですか?」
マナは淫らな笑みを浮かべて、裸姿のまま椅子に座った。
彼女の美しい裸体の下で、白い精液にまみれた淫裂がシャロスの視界を奪う。
溢れ出すねばねばした液体が、マナの太ももをつたって、ゆっくりと地面に垂れ滴る。
そのあまりにも淫猥な光景に、シャロスはごくりと喉をうならせた。
精液を中に出されたばかりの陰唇は、ビクビクと蠢いて彼を誘う。
彼の果てたばかりの一物は、たちまちもとの硬さを取り戻した。
「王子様ったら、かわいい顔をしているくせに。あそこがずいぶん元気じゃないですか」
マナはふざけるように、赤く腫れた一物の亀頭を指で弾いた。
女の手に触れられた性器は、すぐにビクンと反応を見せた。
「うふふ……シャロス様のあそこは、もう我慢できないとおっしゃっていますわね」
「くっ……!」
シャロスは突然マナの裸に抱きつき、彼女の体を覆った。
彼は上からマナの無抵抗な裸体を見ながら、心の中で理性と欲望が激しく戦う。
しかし、マナは彼の努力を残酷にも取り壊した。
彼女は自らシャロスに抱きつき、彼の耳元で悪魔のように甘く囁いた。
「王子様、速く私の中に来て……さあ、マナのいやらしいオマンコをぐちゅぐちゅさせて。
そうすれば、私は王子様にいっぱい、女の体に溺れる快感を教えてあげられるから。
もうエッチな事しか考えられないような、淫蕩に耽る男になれるように」
マナの悪戯っぽい笑顔を作り、彼の劣情を煽った。
その色っぽい顔を見て、シャロスはマナの両足を大きく広げ、彼女の膣に一物を突き刺した。
「ああぁん!いいっ……いいわ!」
マナはシャロスの頭を胸で抱きしめた。
彼女の膣中にはヌルヌルしていて、一物のすべりをよくした。
「いかがですか、王子様?あはぁん……ついさきほど、ほかの男に精液を出されたオマンコに、
オチンチンを突っ込む感じは……でも、みっともないですよね。王子様のような高い身分のお方がメイドに
、
しかも他の男性と交わったばかりの女性に、一生懸命腰を振るなんて。恥ずかしくないんですか?
今のお姿が大臣や側近達に見られたら、どうなるのかしら」
マナは熱い息を吐きながら、少女特有の無邪気な口調でシャロスに話し掛け続けた。
彼女の言葉は一字一句、鋭利なナイフのようにシャロスの心をえぐる。
「うっ、くっ……お、お願い……そんな事、言わないで!」
シャロスは苦痛と快楽が混ざり合った複雑な表情を浮かべた。
マナの言うとおり、他人と交わったばかりの女性と性交する自分が悔しい。
しかし、それでも彼は腰の振りをやめるわけにはいかなかった。
「うふふ……はしたないわね。王子様のような聡明なお方が、私のような淫らな侍女に惚れ込むなんて」
「ああっ!」
一物が膣によって締められた感じに、シャロスは悲鳴を上げた。
「あはは、今の王子様は、とてもいい顔をなさっていますわ。ほかの平俗な男と同じように、
私のことが好きで好きでたまらない情けない表情。でも、私はそんな王子様、大好きですわ」
マナを体をひねらし始めると、シャロスから主導権を奪った。
「ああっ、んふっ……ああぁぁ!」
再び射精感が込み上げてきたため、シャロスは苦しそうに呻いた。
だが彼がまさに出そうとした瞬間、マナはすかさず指で彼の根元を握り締めた。
「っ……えっ?」
マナはそのままシャロスから離れ、まるで何事もなかったかのように服を着始めた。
「そ、そんな……どうして?」
「ふふふ……私の中で射精できるとでも思ったの?あははは、王子様ったら、バッカみたい!
残念だったね。私はね、取引き相手にしか中に射精させないの。王子様といっても、私の中ではほかの男と
同じなの。
そもそも王子様が中に入れられたのも、サービスみたいなものだし」
マナはカフスのボタンを止めながら、可愛らしく舌を吐き出し、あっかんべをつくった。
シャロスは股間にあつまるマグマを抑えながら、これ以上無いせつなさを覚えた。
後一歩のところで寸止めさせられたペニス。
ミミズのような血管が表面を走り、血行とあわせてビクビク跳ね続けた。
完全に服を着終わると、マナはシャロスの顎をしゃくって、うーんと声をうならせた。
「はぁーん、なんてかわいい顔かしら。まるで主人に乞う仔犬みたいだわ、うふふ……
でも、残念だね。これは決まり事だから」
マナは怒張った亀頭を爪先で弱くひっかくと、シャロスは苦痛の満ちた声で喘いだ。
「お、お願い、マナ……私を、私をイカせて!」
「ふふっ、そんなにイキたいなら、自分ですればいいじゃない?……私のパンツを使って!」
マナはシャロスから黒いショーツを奪い、それをシャロスの膨らんだ股間にあてがった。
「ああっ!」
シルクのすべすべした感触が敏感な亀頭にあたり、快楽のさざなみを起こす。
「ほら、王子様。私のオマンコをオカズにして、あそこをシコシコしてください」
マナはスカートの裾を口に咥えさせ、精液にまみれるあそこを指で広げた。
その瞬間、シャロスによってかき回された白液が下へ垂れ下がった。
マナの淫らな仕草は、そのままシャロスの脳内まで黒く染めあげる。
シャロスは食い込むようにマナのあそこを見つめながら、黒ショーツ越しにペニスを握った。
「うふふ……そうそう、ちょうど私のオマンコの筋に当たる部分が、王子様のオチンチンと重なるように。
私の中に入れてるところを想像しながら、シコシコしちゃって!」
「くっ……んふっ」
シャロスはマナの言葉に従い、シルクのショーツを通して、夢中になって自分の股間をしごき続けた。
絶頂へたどり着く快感が、瞬時に体中をよぎる。
「どう、王子様?私のアソコの染みに、オチンチンを一生懸命擦りつける感じは。
あははは、顔をよく見えるように、私に向けなさい。
あなたがイク時の情けない表情を、私が見てあげるから!」
「うっ……ああぁっ!」
マナが繰り出す言葉は、シャロスの屈辱心をかき回した。
その悔しい気持ち自体、彼に堕落する快感を与えた。
マナに見られながら果ててしまう光景を想像すると、シャロスは倒錯とした感情を覚えた。
股間の一物は沸騰した熱湯のように滾り、痺れる心地よさが全身を支配し始める。
マナはたまらないという表情になり、シャロスをもっと誘惑するように秘所を弄った。
「はぁん……私はね、強い男や、かっこいい男が誘惑に負けて、私の虜になるところを見るのが大好きなの
。
あのドスラットという男もそうなのよ。はじめの時はかっこよく私を拒んできたけど、今となっては、
私の命令ならなんでも聞くヘタレな男になったのよ。男達が私に屈してしまうとこを見ると、
私のアソコが濡れてくるの……ほら見て、王子様。今でも、私のアソコがいやらしい汁を垂らしてるのよ」
マナは心の琴線を震わせるような声で、シャロスを挑発し続けた。
その悪魔のようなセリフに、シャロスは背徳的な快楽を感じずにいられなかった。
「うっ、ううっ、マナ……イ、イクッ!」
「そう。じゃあ、腰をいっぱい浮かせて、一生懸命振りなさい!そして、全部吐き出すのよ」
「ああっ……ああああぁぁ!」
シャロスは両足をガタガタとわななかせ、黒ショーツの中に白い精液を大量に噴出した。
「ああっ……がああぁぁ!」
シャロスは思わず床に尻を付けた。
彼の視線は散乱と宙に向け、体中が疲労と快楽が満ち溢れた。
マナはシャロスに近づいてくすっと笑い、
「はい、よくできましたわ。じゃあ、パンツを返してもらうね。これは私のお気に入りだから、簡単にあげ
られないの。
……あ~あ、こんなによごしちゃって」
マナは精液でしわくちゃになった下着を広げ、それに足を通した。
「はぁん、あそこが精液と触れちゃって、ぬるぬるして気持ち悪いわ。これも間接セックスと言えるのかし
ら?うふふ……」
マナは濡れたショーツを履いたまま、服を全体的に整えた。
彼女はまだ起きられないシャロスの側にしゃがみ、彼の唇に指を当てた。
「もしこれから、王子様が私と本番をしたくなったら、私がほしいような物を用意することだね。
うーん、そうだね……たとえば、この国の一番美しい宝石とか。確かあれは、王子様が持ってるんだよね?
シネラリアとか言う、王室代々に伝わるすごいやつ」
「はぁ、はぁ……なぜ、それを知って……?」
「リテイア様から聞いたことがありますの。なんでも、かつてはこの宝石を目当てに、
隣国と戦争になっただとか。私、ぜひその宝石を見てみたいの」
「そ、そんなこと、できるか」
「あら、それは残念だわ。見せてくれれば、私は王子様にもっと気持ちいいことしてあげられたのに」
マナはいかにも遺憾な面立ちで立ち上がり、部屋から出ようとした。
「ま、待って!」
「じゃあね、王子様。もし考えが変わったら、いつでも私のところに来てね。私、待ってるから」
マナは最後にウィンクを投げると、陽気な笑顔で部屋の外へ出た。
「くっ……」
シャロスは悔しそうに、しかしどこか未練がましく、彼女が去った跡を見つめ続けた。
□
(王子様は、一体どこにおられる……)
昼過ぎてもシャロスの姿を見当たらなかったため、レイラはついに我慢できず探しに出かけた。
シャロスからはかまうなとは言われたが、彼の身に何か危険が降りかかっているかもしれないと思うと、
いても立ってもいられなかった。
歩いている途中、レイラは今朝の隊員達との会話を思い返し、なぜか胸がドキドキした。
(そういえば、シャロス様もそろそろ異性に興味を持ち始めるお年頃だわ……
シャロス様も政事ばかりに没頭せず、そろそろ嫡室の選別をして頂かないと……)
戴冠式の時、シャロスの凛々しい姿の側に美しい妃の姿がいれば、国民の歓喜はより一層高まることでしょ
う。
しかし、それ以降自分が彼の側にいなくてもいいと思うと、レイラは心が急にちくっとした痛みを感じた。
彼女は思わずびっくりして、自分の胸を抑えて。
(今一瞬、刺が刺さったような感じが……なぜだろう?)
あんまり慣れない感情に、レイラは頭をぶるぶる振るわせた。
(はぁ、いつまでもこんなくだらない事を思ってるんだ。
今は、殿下を探すのが先決ではないか。速く、殿下を探さなきゃ)
レイラ踵を返そうとしたとき、耳元に残るような声が彼女を呼び止めた。
「あら、レイラさんではありませんか」
「……皇后様!」
レイラはその姿を確認すると、すぐにひざまずいた。
彼女を呼び止めたのは、皇后のテイアであった。
今日の彼女は、ゆったりとした翡翠色のドレスを着ていて、その後ろに一人のメイドを従えていた。
レイラは同じ女性でありながら、リテイアの美しさを賛美せずにいられなかった。
ドレスの縁はきらめく瑪瑙に飾られ、すべすべの肌とあいまって、彼女の魅力をふんだんに引き出していた
。
卑俗過ぎず地味過ぎない服飾は、彼女の妖艶な肢体と自然的な一体感を紡ぐ。
それに加えて、弾力に富む綺麗な肌は、まだ二十過ぎたばかりの自分と比べても全然遜色が無かった。
リテイアの素性を知る者は、ほとんどと言っていいほど誰もいない。
レイラがまだ小さかった頃、リテイアは後妻として先代国王の妃に迎えられた。
その時、彼女のきめ細かい肌や美しい容貌が、多くの人を魅了してきた。
年老いた国王の隣に並ぶ妖艶な美女は、レイラの記憶に深い印象を残してきた。
だが今から見直しても、リテイアの容姿は当時とさほど変わらなかった。
乙女のようなみずみずしい体と、どんな男をも虜にしてしまう艶かしさ。
その二つの要素が、彼女の身の上で見事に融合していた。
リテイアは実は魔女ではないかという噂も流れているが、
そのような童話世界に出てくる話しをレイラは当然信じなかった。
ただし、時々彼女から感じるぞっとするような魅力に、レイラは背筋に寒気を感じていたのだ。
「くるしゅうない。護衛の任務、いつもご苦労ですわ。レイラ隊長がいたおかげで、我々はいつも安心でき
るわ」
「お褒め頂き、ありがとうございます」
「それにしても、この場にいるのは何用かしら」
「はっ。少し前に、殿下が一人になりたいとおっしゃられました。
それでしばらく経ってもお姿がお見えになられなかったので。私が殿下を探しております」
「ふふふ。まあ、良いではないか。
隊長さんの忠誠心は素晴らしいですが、たまには殿下を自由にさせることも大事ですわ」
「しかし」
「それに、これはわらわからのつたない助言ですが、隊長さんも、
これからはもっと自分のために気を使ってもよろしいかと」
「それは、一体どういうことですか?」
レイラは不思議そうにリテイアを見つめた。
リテイアの瞳は、どこか人を深く溶け込ませるような輝きがあった。
「殿下の身を心配するのも大事です。しかし、隊長さんは、もっと積極的に自分の幸せを掴まなくちゃ。
女が花を咲かせる時期は、一生に一度しかないのですから」
「はあ……」
レイラは要領をつかめないまま、答えた。
「では、護衛の任務がんばってください。わらわはここで失礼させてもらうわ」
リテイアはそう言ってその場から立ち去った。
彼女の背後にいたメガネをかけたメイドは、レイラに軽く会釈してから皇后に追随した。
(彼女はいったい、私に何を言いたかったのかしら……)
レイラは納得しないまま、しばらく考え込んだ。
庭園道を少し歩いたところ、リテイアはゆっくりと尋ねる。
「フシー、あの子を見て、どう思うかしら」
「……リテイア様がおっしゃったとおり、すばらしい逸材です。
正しく磨くことができれば、今よりずっと輝くことができるでしょう」
フシーと呼ばれたメイドは恭しく述べた。
そのメガネの後ろには、リテイアとよく似た妖しく光る瞳があった。
「あなたの目にそう映るのなら、間違いないでしょう。いつかは、彼女に手伝ってもらえれば良いですね」
「……その通りでございます」
フシーは淡々と、しかし堅実な口調で答えた。
「これからが、楽しみですわ」
リテイアは心底から愉しんでいるように、遠くにある宮殿を見つめた。
陽炎に包まれた壮麗な宮殿は、幻に包まれた優美さがあった。
话说这就是剩下的全部内容,哪位好心人来翻译下造福广大人民群众啊……
朝。
太陽の光がカーテンに遮られ、布の縁から輝きが優しく漏れる。
シャロスはゆっくりと目を覚ました。
「うっ……」
あんまりいい目覚めではなかった。
体のあちこちにけだるい疲労感が残る。
「あれは……夢だったんだろうか……」
シャロスは曖昧になった記憶を思い起こした。
「確か昨日の夜はレイラが来て、その後皇后が……それからは……」
そこまで思い出すと、シャロスの顔から火が噴くほど真っ赤になった。
皇后にあそこをいじられ、生まれて初めてイカされた。
そのうえ、皇后をお母さんと呼んでしまった屈辱。
(くっ……私はなんてことをしてしまったんだ。あんな淫乱女をお母さんと呼ぶなんて、母上への冒涜だ!
)
シャロスの心は後悔の念が満ち溢れる。
リテイア皇后といえば、噂では不貞を続けるふしだらな女性である。
シャロスにとって、彼女は貞淑な母上とは大違いで、下賎で淫猥で、いやしい女である。
(昨日のことだって、あの女の色仕掛けに間違いない……くそっ、それが分かってるというのに!)
そうと思ったものの、シャロスは嫌悪以外に、何か不思議な感情を抱いていた。
リテイアを淫乱女と思えば思うほど、少年の心がドキドキし、息が苦しくなった。
目を瞑れば、リテイアが黒の下着だけ身に着け、しなやかな肢体を妖艶にひねらせる光景が、
いきいきと浮かび上がる。
彼女が男を誘惑する時の表情を想像すると、シャロスの全身の血流が速まり、股間のペニスが硬くなった。
シャロスはリテイアにされた行為を思い返すと、やがて自然と股間の一物を握り、こすりはじめた。
「あっ……!」
くぐもった声を抑えながら、シャロスは自慰に耽った。
彼の股間の先はすでにぬるぬると濡れ、竿は赤く醜く怒張していた。
「くっ……あ、うっ!」
あの女がもしこんなみっともない自分を見たら、きっと冷たい視線を向けてあざ笑うだろう。
その悔しい気持ちは、逆にシャロスの欲望を煽った。
彼はリテイアの手つきを思い出しながら、自分のペニスをしごき続いた。
(はぁっ……また、あの感触が……ああ、出る!)
一物がドクン、ドクンと大きく脈打つと、シャロスは盛大に射精した。
白く濁った熱液がシーツに散らばり、全身から力が抜けた。
「はぁ、はぁ……」
シャロスの体中に汗が噴き出た。
頭がぼうっとしていて、考えがまったく定まらない。
しかし、彼が余韻に浸っている最中、不意に寝室の扉が開けられた。
「おはようございます、シャロス様」
「ひゃっ!?」
シャロスは思わず露出した下半身を奥側へ隠し、突如現われた少女を見つめた。
彼女は黒のメイド服を着ていた。
眉目は秀麗で、悩ましい首筋は綺麗だった。
服の下から胸が程よく膨らみ、女性的な部分がシャロスを挑発する。
半袖のスリーブから真っ白い二の腕が露出する。
手首にはカフスがつけており、彼女の腕をより可愛らしく見せる。
白いエプロンは黒服の上から前側を覆い、清潔感を感じさせる。
いわゆるフレンチメイド服だろうか、彼女のスカートの裾は膝よりも上で、裾下からは白いフリルが隠れ見
える。
光沢の帯びた黒ストッキングは彼女のほっそりとした両足を覆い、優雅であると同時に妖しい魅力を放って
いた。
つややかな髪にフリルのカチューシャがつけられている。
そして、後ろへ垂れ下がるポニーテールにシャロスは見覚えがあった。
「お前は皇后様の……?なぜここに……」
「はい。リテイア様の言いつけで、本日より王子様の身の回りの世話をさせて頂く、エナと申します」
「ほかの人はどうした?」
「王子様はお取り込み中なので、退避させました」
エナはそう言って、見透かしたような目でシャロスに一瞥した。
シャロスは思わず焦った。
「お前をここにいれた覚えは無い、皇后のところへ……」
「王子様、いけませんわ。まだ病み上がりなのに、あそこを裸のままにしては」
突然、エナはベッドに近づき、シャロスの下半身を覆う布を拾い上げた。
「あら、こんないっぱい出たのですね」
空気がひんやりとしてシャロスの股間を襲う。
下半身の醜態は、全て相手に見せてしまった。
シャロスはまるで毒牙を抜かれたかのように、どうしたらいいか分からない表情になった。
しかし、エナは大したリアクションもせず、
あらかじめ準備した暖かいてぬぐいを取り出し、手際よくシャロスの股間を拭う。
すぐさま、彼のあそこはほかほかした感触が包む。
シャロスの心は驚愕と疑念に満ちた。
彼は顔を赤らめながらも、とろけそうな気持ちを押さえ込み、
「お前は、一体いつから部屋の外にいた?」
「しばらく前からです」
エナは表情一つ変えず、淡々と答えた。
だがその一言に、シャロスのプライドが傷ついた。
(それじゃ、物音が全部聞かれてしまったのか……)
しかし、彼はすぐに動揺を治め、つとめて普段の気迫を取り戻す。
「もうよい。さがれ」
「分かりました。しかし、お風呂の用意ができましたので、先にそちらで身を清めさせて下さい」
言われてみれば、シャロスは自分は汗だくになっていることを思い出す。
彼は一瞬戸惑ったが、やがてエナの意見を受け入れた。
「ふん、ずいぶん用意周到じゃないか」
シャロスがエナに王子専用の広い浴室に導かれた。
エナは「失礼します」と言って、シャロスの貴族の服を脱がせる。
その瑞々しい指先を感じ、シャロスはまたもや落ち着きを失う。
エナが彼のズボンを脱がしたとき、上から見下ろすと、ちょうど彼女の無防備の谷間が覗ける。
シャロスは顔を赤らめ、慌てて他の方向へむいた。
王族だから、これぐらい奉仕されるのは慣れたはずだが、
昨日リテイアによって射精させられてから、シャロスは無性に異性が気になった。
気付いたら、シャロスの股間部が再び疼いた。
「もういい、後は私自身がやる」
「はい」
エナはやや驚く顔をみせるが、シャロスの命令には逆らわなかった。
彼女が去ったあと、シャロスは下着を脱いで裸になった。
案の定、彼のまだ幼さが残る一物は、硬くなっていた。
シャロスは浴室に入り、真っ先に冷水をすくい、それを頭の上からかぶった。
骨を突き刺すような冷感が皮膚から伝わる。
普通の人間にとって厳しい冷たさだが、
毎日冷水浴を続け精神を鍛えた王子にとって、これぐらいは平気だ。
彼は五度ほど水をかぶった後、お湯に浸かった。
冷え切った体を、今度は熱い温度があたためる。
こうしているうちに、シャロスはいつもの感覚を取り戻した。
(あの召使いは皇后の人間だ。もしかしたら皇后と同じように、
私を誘惑してくるかもしれない。気をつけなければ……!)
湿った蒸気が立ち上がり、浴室全体は霧に覆われたかのようだった。
そんな中で、突如入り口の方から物音がした。
「誰だ!」
「エナです。王子様の御体を洗わせていただきます」
「なっ……!」
シャロスの集中力が途切れた。
もやもやした向こうから、髪を短く巻いたエナの姿が近づく。
メイド服は脱がされ、その代わりに薄地の白い素衣を着ていた。
質素で丈の短い衣だが、服の下にある少女の胴体のラインをはっきりと描いた。
可憐な肢体は、あらぬ妄想を起こすほど魅力的だった。
彼女の艶姿を確認すると、シャロスは顔を真っ赤にさせた。
「ここに入っていいと、誰が言った!」
「申し訳ありません。私がリテイア様に仕えた時、いつも御体を洗わせて頂いたもので……」
「私にそんなのいらん」
「はい……しかし、お言葉ですが、王子様はいずれこの国の王になるもの。
こんな些細なことまでご自分の手を煩わせては、きりがありませんわ。
リテイア様が私を王子様の側に置いたのは、まさにこういう事を奉仕させて頂くためかと存じます」
エナの視線は、まっすぐシャロスの両目を捉える。
シャロスは彼女の妖しい躯体を見つめ、ついに折れてしまった。
「……ふん、好きにしろ」
「ありがたき御幸せ。では、こちらへどうぞ」
と、エナはシャロスを浴室の大鏡の前に座らせた。
鏡の中で、エナは服を着ているのに、自分が裸である。
そう思うと、シャロスはなぜか恥ずかしい気分になった。
エナは無表情のままなので、彼はその心境を推測できなかった。
(なんだか、すっごく馬鹿にされたみたい……
こっちがこんなに恥ずかしがってるのに、むこうが全然気にしていないなんて……)
エナはシャロスの背後にひざまずき、水がめやシャンプを用意した。
「しばし目をつむって下さい」
シャロスは言われたとおりに目を閉じる。
頭上から、暖かいお湯がゆっくりと垂れる。
エナは彼の高貴なブロンドを優しくほどき、撫で下ろす。
彼女の指に頭を撫でられると、脳の裏から甘い痺れがじんわりと広がる。
シャロスは思わず考え事を止め、彼女の指使いに委ねた。
サラサラとした金色の長髪は、エナによって水を含まされ、地面のタイルに届く。
そして、エナは何かひんやりとした溶液を頭上に垂らした。
彼女は十本の指を使い、その溶液を巧みに髪にしみこませる。
たちまち泡が広がる音が聞こえ、そしてかぐわしい香りがシャロスの鼻に浸透する。
(ああ、この匂い……リテイアの匂いと、すごく似ている……)
シャロスの緊張がゆるみ、心がリラックス状態になった。
エナの指は、時は放射線状に頭を撫で、時は爪を立たせてやや強くひっかき、
シャロスの髪の毛を泡の中で洗浄する。
目を閉じたまま彼女の手加減を感じると、シャロスはまるで雲の中に浮いているようで気持ちよかった。
エナは後ろ髪に手をそっと添え、それを掻き分けるように優しく指を滑らす。
広い浴室の中は水が滴る音と、髪の毛がザワザワ触れる音しか聞こえない。
洗うことに集中しているのか、エナは黙ったまましゃべらない。
生温い空気や、はてしない静けさが心地よい。
全て終わった後、エナはもう一度頭からお湯をかぶる。
エナはシャロスの閉じた目を優しく拭う。
「もう目を開いても、よろしいですわ」
「はっ……」
シャロスはやっと我に帰り、鏡を見つめる。
この鏡は特殊な薄膜を施されており、湯気の水滴は弾かれる構造となっている。
王族の育ちらしく、シャロスの肌はエナに負けないほど雪白く、キメが細かい。
常にストレスを抱いているためなのか、彼の成長が遅く体は小柄で、後ろのエナと同じぐらい背丈であった
。
彼はエナに気付かれないように、彼女のほうを見た。
さきほどの水をかぶったせいか、エナの薄地の白服は濡れてしまい、べったりと肌に貼りつく。
そのため、彼女の女らしいラインは今まで以上にくっきりと現われ、柔らかそうな乳房がうっすらと映る。
シャロスは口の中が乾いていくのを感じた。
その時、エナは石鹸をシャロスの背中に滑らせていた。
どうやら、自分の服が透けて見えるのが気付いていないようだ。
シャロスはなんとなく股間のところを手で覆い、罰悪そうな表情を浮かべた。
もともと秀麗で凛々しい顔立ちは、今でははにかむ少女のように赤くなっていた。
彼はいけないと知りつつも、ついついエナの肢体を見続けた。
今まで召使いに奉仕されることは何度もあったが、シャロスはこれほど興奮したことが無かった。
昨日のリテイアの下着姿を見てから、シャロスはどうしても女性が持つ神秘さに惹かれた。
「王子様、いかがなさいました」
「は、はうっ?い、いいえ……ちょっと考え事してて……」
「まあ。私はてっきり湯加減が至らないかと」
「ううん、大丈夫だよ。エナの手つき、すごく気持ちよくて……」
そう言った後、自分のペニスをしごいたリテイアの手つきを思い出し、慌てて頭を伏せた。
「お褒め頂き、大変光栄です。私、実は按摩を少し心得ています。どうかそちらもご堪能してください」
エナの細い指はシャロスの肩にかかると、ぬるぬるした泡を掻き分けるかのように、彼の肩のツボを押した
。
「あっ!」
シャロスは思わず声を漏らした。
あまりにも気持ちいい快感が、彼の神経を瞬時に通過する。
エナの親指は肩の下側に突き、やや痛みを感じるぐらいの力加減で押し続ける。
その位置は肩から、徐々に背筋のほうへ移り、そしてまた背中の外側へ移る。
味わったことも無い痛快さがシャロスを襲う。
エナにさわられた筋肉は、まるで彼女に支配されたかのように、シャロスの言うことを聞かなくなり、力が
抜けていく。
エナの手は彼の背筋を続けて押さえ、腰際まで強く撫でられる。
やがて、背中に力が入らなくなったシャロスは、後ろのエナの体へ倒れ掛かった。
「あっ……」
なんとか起こそうとしても、体は彼の言うことを聞かない。
「大丈夫です、そのまま私に寄りかかってください」
エナの言葉を聞くとシャロスはなぜかほっとした。
だが次の瞬間、彼は背中に二つの柔らかい肉感が当たっていることに気付いた。
(これは……エナの胸……!?)
シャロスの心臓の勢いは一気に増加した。
鏡を見ると、彼の体は完全にエナの体とくっついていた。
しかし、エナはまったく気にする気配を見せなかった。
女性特有の柔らかい感触が、背中から広がっていく。
シャロスはその感触に陶酔し、何も考えられなくなった。
エナはそんなことをまったく知らない素振りで、背後からシャロスの左腕に両手を移した。
彼女の十本指は、まるで触手のようにシャロスの細腕に絡み、妖しく蠢いた。
右の腕も同様に、指の先までエナにほぐされると、シャロスはついに恍惚の表情を浮かべた。
エナが体を動かすたびに、胸の先端の柔らかい感触がコツコツと当たり、
シャロスの欲望を掻き立てる。
彼女の指先は徐々に中央へ滑り、シャロスの胸に触れた。
(あっ……そこは……!)
わざとやっているのか、それとも無意識なのか。
エナの指先はシャロスの乳首のまわりをくすぐるように、円を描いていた。
気持ちいい波紋が体中へ広がるが、もどかしい気が充満した。
「体を横にしますね」
突然、エナはシャロスを床に倒す。
(えっ?)
シャロスは慌てて股間に両手を置き、いきり立ったペニスを強引に押し倒す。
頭の下は、折り畳んだタオルが当てられる。
エナはシャロスの裸体の上にまたがり、彼の足の方に頭を向けた。
そして、彼の足のふくらはぎを按摩した。
どうやら股間が膨らんでいることは、ばれていないようだ。
シャロスは思わずほっと息を吐いた。
しかし、彼はすぐに目の前の光景に固まった。
エナの体勢はちょうどシャロスと逆向きになっていた。
彼女は足をシャロスの体の両側に分けてひざまずき、一心不乱に彼の足のマッサージを続ける。
そのため、今の彼女の両足、無防備に開かれていた。
濡れた裾は彼女の魅惑な美尻にぴったりとくっつく。
その下に、女の大事な部分が見え隠れする。
それに気付いた瞬間、シャロスの股間は爆発しそうになった。
エナの動きと共に裾が上下する。
女体の最も神秘な茂みが、シャロスの視界にチラつく。
彼は懸命に首の角度を変え、そのむこうにある光景を目に収めようとした。
(ああっ……もう少しなのに……!)
エナはまるでシャロスを焦らすように、お尻を少しずつ揺らす。
彼女が動くたびに、シャロスも角度を変えなければならないため、とにかく首を動かし続けた。
柔らかそうなお尻と水平に、彼女の美乳が服を突き下げ、ピンク色の先端がうっすらと見える。
シャロスはゴクリと唾を呑み、欲情したサルのように、エナの動きを追った。
その時だった。
シャロスの足裏から、突然激しい痛みが広がった。
「うああーっ!」
シャロスは思わず大きな悲鳴を上げる。
「あっ、すみません。足裏のツボで痛がるということは、体に何らかの不具合があるということです。
王子様はきっと普段で勤労なさっているから、疲れが溜まったでしょう。
しばらく痛いかと思いますが、どうか我慢してください」
エナが言い終わると、激痛が連続してシャロスの足裏から襲う。
「ああっ、ううっ……ああああぁぁ!」
痛感の中には快いものも混ざっている気がしたが、シャロスはそれを感じる余裕が無かった。
彼は痛みの間を徘徊しながら、ただ情けない悲鳴を出すしかなかった。
五分もすると、彼の額に大粒の汗が滴り、目の焦点が合わなくなった。
「はい、おしまいです。少し力を入れすぎたでしょうか?
でも、こうして続けていれば、王子様もいずれ痛みではなく、快感しか感じられないようになりますわ」
エナの無表情の顔に、ほのかな笑みが含まれていた。
しかし、彼女の意味深長な言葉は、シャロスの心に届かなかった。
「はぁ、はぁ……」
「おや、王子様のあそこ、すごく腫れているようですが」
「はあぁっ!?」
痛みのせいで、シャロスはあそこを隠すことをすっかり忘れてしまった。
彼は慌てて覆おうとするが、それよりも速くエナの頭が覆い被さる。
「大変申し訳ありません。王子様がこんなに溜まっているのを、
気付かなかったなんて。私にぜひご奉仕させてください」
シャロスが拒否する間もなく、エナは可愛らしい舌を吐き出し、シャロスのペニスの先端をチョン、と舐め
た。
「うっ……!」
あそこから走る衝撃は、シャロスの全ての言葉を封じ込めた。
エナは指でシャロスの剥けたばかりのペニスを摘み、赤ピンク色の亀頭を口に含んだ。
ねっとりとした異空間が、シャロスのペニスを覆う。
「ああっ!うぐっ……はぁっ」
シャロスは思わずリテイアにされたことを思い出した。
あの時味わった新鮮な感触は、エナによって再現される
エナは口をすぼめたり、吸い付いたりする動作がシャロスの目に入る。
生暖かい舌は蛭のように蠢き、彼女の唾液をいやらしく絡ませ、ぬるぬると滑らせる。
その熟練とした動きは、経験が少ないシャロスを追い詰めるのに余裕だった。
シャロスが彼女の下のほうを見ると、襟の開きに沿って、胸元の谷間が覗ける。
まるでシャロスを誘惑するかのように、服越しの乳房が激しく揺れる。
こんな時でも、エナの顔はただ動く機械のように、行為を淡々と続ける。
まるで彼女が扱っているのは男ではなく、もっとどうでもいい物体のようだ。
シャロスはその涼しげな目元を見ると、彼女にとって自分はなんともない存在のように感じ、
とても惨めな気分になった。
しかし、それでもシャロスはエナから目を離すことができず、彼女の女性の象徴に興奮した。
「あっ、だ……め、はぁああ!」
やがて、欲望が一つの塊に凝縮され、徐々にシャロスの下腹部へと集まった。
また、イカされてしまう。
自分の意思とは無関係に、ほかの人にイカされてしまう。
プライドの高いシャロスにとって、それは許しがたい事である。
しかし、今の彼は、エナ押しのける力さえ残っていなかった。
彼はただ弱々しくうめき声を上げた。
「はむっ……んはぁ、王子様、どうか我慢なさらないで下さい。
私の口の中でザーメンを存分に出してください」
「うっ……だ、だめ……い、いやっ!」
シャロスは顔を歪め、絶頂にのぼりつめる一瞬を味わおうとした。
だが、エナはそこでペニスの根元をギュッと押さえ、頭が離れた。
彼女の唇とペニスとの間、唾液の糸が一筋伸びる。
「えっ……?」
シャロスは突然の停止に混乱した。
彼の体内の苦悶は後一歩のところで、発散できなくなった。
エナの方を見ると、彼女はおもむろに立ち上がり、シャロスをゆっくりと立ち上がらせた。
「大変残念ですが……王子様がイヤだというのであれば、仕方ありません」
「えっ?」
シャロスは焦った。
どうやら、彼が先ほど口走った「いや」という言葉を、エナが実行したらしい。
しかし、だからといって「続けろ」という言葉も、言えるはずが無かった。
そんな事を言ったら、まるで自分が快感に溺れたようで、エナに軽く見られるじゃないかという恐怖があっ
た。
王子としての威厳がシャロスを苦しめる。
ペニスはビクビクとわなないたまま。
大きく腫れあがった一物は、刺激を追い求めるように、醜く蠢く。
その様子を見て、エナは挑発的な口調で尋ねる。
「王子様、本当によろしいでしょうか?」
「……うっ、うん、だ、大丈夫だ」
言った後、シャロスは激しく後悔した。
浴室を出た後、シャロスは軽い朝食を取り、そのまま執政殿へ赴いた。
その間も欲望の熱は冷めなかった。
シャロスはあそこを触りたい気持ちでいっぱいだったが、
エナがずっと側にいたため、それさえ叶わなかった。
朝から執政殿で群臣と国政を討議することは、この国のしきたりであり、
そのため明け方の自由時間は非常に少ない。
確かに過去には幾人もの愚君が登場し、国政を放り投げた国王もいた。
しかし、将来に向けて抱負を持つシャロスは、決してそのよう真似はしなかった。
皇后と宰相の発言権が強いとはいえ、群臣の中には王子に忠誠を誓う臣下もいる。
何かがあると、執政殿の朝会でしばしば険しい答弁が続く。
シャロスの役割は、皇后派の発言を食い止め、彼らの言うことへすんなりと傾けさせない事にある。
名目上とはいえ、シャロスは次期国王。
彼は唯一皇后と対等になれる身分である。
「殿下、ご機嫌麗しゅうございます」
「ああ。皆のもの、おもてを上げてよいぞ」
シャロスは王座に居座った。
その気品高い外見、まだ十六歳とはいえ王者の威風が漂っていた。
しかし、今日のシャロスはいつものように、瀟洒に振舞うことが出来なかった。
高貴な貴族服の下で、下賎な欲情が出口を見つけることが出来ず、彼の体内で暴れる。
シャロスはそれを顔に出さないように努めた。
執政殿に群臣が集まり、官位に従って近くから遠くへ立ち並んでいた。
シャロスの王座は高く設置されているため、彼を見つめるのに、必ず見上げなくてはならない。
もちろん、理由も無く王子に眼を飛ばす人間は誰一人いない。
それを知っていても、シャロスは自分のいきり立つ股間がばれてしまわないか、と心配していた。
「殿下、ご機嫌麗しゅうこと」
突然、誘うような甘い声が響いた。
シャロスが声の方を見ると、王座より五段ほど下がったところに、皇后リテイアの姿が現われた。
王子がいる位置と床の間に十段差があり、それはリテイアは群臣よりも高い地位を持つこと表す。
今日のリテイアは、濃紺のドレスを着ていた。
切り開いた胸元に、趣向が凝ったリボンを結ばれ、その中心は赤い宝石がはめてある。
肉感のある乳房はドレスに持ち上げられ、魅惑な輝きを放つ。
胴体はヘソまで締まり、女らしいくびれが現われる。
紺色スカートの中央は白い三段フリルが挟み込まれ、その鮮やかさに発見した者は驚く。
スカートの柄は高級感のある刺繍が二枚構造に施され、彼女の下半身を装飾する。
その煌びやかな出で立ちは人目を奪う一方、
一体どれほどのお金を費やしたかと想像したくなるほど豪華さがあった。
しかし、その服飾は彼女の魅力を最大限に引き立てたことに、誰も疑うことが出来ない。
外に露出したうなじや胸肌は、男の欲情をそそるのに充分だった。
艶麗な笑顔と人を見下ろすようなな目付きは、他人をひざまずかせるような魔力がある。
いつもなら、シャロスは嫌悪感溢れる気分になるはずだった。
しかし、今日のシャロスは彼女を見た途端、言いがたい甘い気持ちが心に充満した。
股間の一物は今でも無かったほど苦しむ。
昨夜見た彼女の肢体が、まるで悪魔のように浮かび上がる。
魅惑的な微笑み。
自分をあざ笑うかのような目線。
いやらしくひねる太もも、黒い下着に包まれた神秘の区域。
このまま彼女の淫乱な体に抱きつき、成熟した乳房をしゃぶりたい衝動が、シャロスを激しく襲う。
彼女の濡れた唇と重ね、舌を中に入れて絡められる。
彼女にいやらしい手に股間の一物を握られ、色っぽい言葉をかけられながら射精させられる。
リテイアの艶美な姿を見れば見るほど、シャロスの中に妄想が大きく膨らんだ。
(そんな……!くっ、彼女に一回イカされたぐらいで、こんなになるなんて……)
シャロスは渾身の意志をかき集め、やっとの思いでリテイアの体から目を離した。
しかし、数秒もたたないうち息苦しくなり、あまりにも切なく胸が詰まってしまう。
シャロスは再び首をひねると、ちょうどリテイアもこちらに笑顔を向けてきた。
その笑顔に触れた途端、まるで年上の綺麗なお姉さんに恋をしてしまった男のように、
シャロスは照れくさそうに顔を赤らめた。
(シャロス、しっかりしろ!あの女は、男なら誰でも喜ぶ、娼婦のような女だぞ!
しかもあいつはお前の敵だ!いつまで惑わされてるのか)
彼は額に汗をかき、自分を叱責した。
だが、彼女を見れば見るほど、リテイアの豊艶な体が彼の脳に焼きつく。
「皇后陛下、お言葉ですが……殿下より遅く到着するのは、いかがなことかと」
と、一人の臣下が前に出て、厳しい口調でリテイアを咎めた。
その男は灰色の眉と髭を伸ばし、満面の正気で凛としていた。
その名はスデラス伯爵、王国軍を率いる五将軍のうちの一人で、中央軍を統制している。
武人らしい面影からも分かるように、根っからの熱血漢である。
「あらスデラス伯、今日もお元気で。わらわは少し身内の用事ができたため、仕方なく遅れましたわ」
「たとえ皇后陛下というお方でも、殿下を待たせるのは大いなる侮辱行為であり、罰を受けなければならな
い」
「ふふふ、スデラス伯ったら、大袈裟ね。それでしたら、侮辱かどうか、
殿下ご本人に聞いてみましょう。ねぇ、殿下、どう思われます?」
そう言うと、リテイアはくすりと微笑み、シャロスの視線を絡めるように見つめた。
彼女の嬌艶な仕草を見ると、シャロスの背筋がぞくりとした。
「ねぇ、殿下、わらわは今回、本当に仕方なかったのですの。
心の中でちゃんと反省するから、見逃してくれない?」
リテイアの優しい語り口は、シャロスの心をくすぐった。
「う、うん……皇后様も多忙の身。今回は特別に許そう」
「ふふふ、聞いたかしら、スデラス伯?殿下も許してくれるって。これでまだ意見あるわけ?」
「……いいえ。殿下がそうおっしゃるのなら」
スデラス伯爵は一歩下がった。
「さて、今日の朝会を始めよう」
そう言った後、リテイアはシャロスに向かってこっそりとウィンクを投げた。
それを見て嬉しくなったことに、シャロス自身はまだ気付かなかった。
いつもなら精力的に臣下の報告に耳を傾けるシャロスであったが、
今日に限って一刻も速く終わってほしいと思った。
彼はもともとエナによって欲情が引き起こされ、
それがリテイアと対面した後、更に油に火が注ぐ状態となった。
おもてでは臣下の言葉を聞くふりをするが、裏では股間をしごきたい願望で頭一杯だった。
「……と思われます。ところで、トーディザード卿にお伺いしたいことがありますが」
「何でしょうか、オイバルト殿」
突然、場の空気が険しいものへと変わった。
シャロスもそれに察し、発言者のオイバルトを見た。
三十代の活力的な男で、物事をはっきりと言う人間である。
その権威を恐れない性格が災いし、同僚から推挙されることはなかなか無い。
そして今も、彼は自分より位が遥かに高いトーディザード宰相に、意見を述べようとしている。
「トーディザード卿、失礼を承知しておうかがうが、王都の近郊で王家の名を騙り、
農民から土地を取り上げる事件をご存知ですが?」
トーディザードはふんと鼻を鳴らし、
「オイバルト殿は随分お暇のようですな。そんな風の影のような事に、いちいち労力を費やしておられるの
か」
「しかし、もしそれが本当であるとしたら、王に反逆を企てると同様の重罪でございます」
オイバルトは一歩も引かなかった。
「オイバルト殿、それはあなたの管轄範囲ではないはず。
土地関係のことなら、そちらの専務機関がわしに報告してくるだろう」
「その専務機関が機能していないとしたら、いかがでしょうか」
まさに一触即発の場面だった。
その時、リテイアの心地よい声が割り込む。
「オイバルト殿もトーディザード卿も、少し落ち着きなされ。ここでずっと争っても、
結論は出てこないでしょう。今日の殿下は、気分がまだ優れないようですし……ねぇ、殿下?」
リテイアは意味ありげに、シャロスの股間を一瞥してから、ニコッと笑った。
「あ、ああ……」
シャロスは顔を真っ赤に染めた。
「しかし、私には確かなる証拠が……」
「オイバルト殿、いいかげんにしなさい。わらわは殿下を休ませようと言ったのよ。
国を案じるのなら、まず殿下の身を案じなさい」
オイバルトはしばらく黙った後、
「はっ。度が過ぎたことを、お詫び申し上げます」
とシャロス王子が何も異論を返さないことに驚きつつ、引き下がった。
「今日の朝会は、ここでおしまいにしましょう」
リテイアはそう宣言した。
群臣の中には、シャロスの様子におかしいと感じた者もいた。
しかし、彼らはリテイアの言ったとおり、それを王子はまだ病み上がりであると解釈した。
シャロスは一足速く執政殿から出た。
彼は自分の失態を反省しながら、一刻も早く誰も居ない場所へ行きたかった。
(くっ……なんてことを!あの女の姿に、自分を見失うとは)
リテイアが見えなくなってから、シャロスはやっと我に帰り、そして自分の不甲斐無さを悔やむ。
メイド服のエナはすかさず彼の側へ駆けつき、
「王子様。リテイア様より伝言です。昼食を共に進めたいため、ぜひ後宮へお越し頂きたいとのことです」
一瞬、シャロスの頭にリテイアの妖艶な笑顔が横切る。
彼は慌てて頭からその念頭を追い出し、
「ふん、彼女に伝えとけ。私は体が不調であるゆえ、参られないと……」
「あら、せっかく殿下のためにいろいろ用意したのに」
突如、美しい女声がシャロスの言葉を遮る。
そして次の瞬間、シャロスはその人物から放たれた香りに反応し、彼女へ振り向いた。
濃紺のドレスを着たリテイア皇后と、エナと同じ顔立ちのマナがそこにいた。
マナはエナと同じメイド服を着て、悪戯っぽい笑顔を浮かべていた。
「皇后様……」
「ねぇ、殿下。今日どうしてもお越し頂かないの?」
リテイアはやや悲しげな表情を作る。
彼女の熱っぽい視線に見られると、シャロスの胸は破裂しそうになった。
彼は罰悪そうに相手から視線を逸らし、
「し、しかし……」
「わらわは殿下の体を思い、回復を速める滋養品を選りすぐりましたの。
……ふふふ、殿下の体も、きっとそれに喜ぶわよ」
リテイアの言葉は、シャロスの妄想をかきたてる。
彼女についていったら、何が起こるかわからない。
しかし、むしろ何かが起きると思うと、シャロスの胸に妖しい期待が躍り出る。
理性と欲望は互いに争い、彼の心を苦しめる。
「ふふふ、迷っているようですわね。とりあえずわらわに付いて来ましょう。
途中で意見が変わったら、わらわも止めませんわ」
「う、うん……」
シャロスは迷った表情のまま頷いた。
彼女について行ったら、きっともう意見が変わることは無いと分かっていたが、彼にはどうすることもでき
なかった。
しばらく歩いていると、后妃や女召使いたちが住んでいる区域に足を踏み入れた。
ここは王族を除けば、女性のみが入れる禁区である。
その理由もあって、宮殿全体を守る近衛隊は女性のみ構成される。
近衛隊隊長のレイラは太子派であるため、リテイアの勢力下にある後宮は普段から近衛隊と距離を取ってい
る。
そのため、後宮の情勢は不透明である。
シャロスはまわりの建物を見て、ふと小さい頃を思い出した。
あの頃、ここのあるじは彼の母上であった。
彼の幼年はここで母上と共に過ごし、そしてレイラと知り合ったのもここの庭だった。
「殿下……殿下ったら!」
「はっ!」
シャロスの目の前に、リテイアのやや不機嫌な顔があった。
「どうしたでしょうか、皇后様……」
「殿下ったら、さっきからずっと上の空。わらわという人が側にいながら、何をお考えでしょうか」
リテイアはまるで恋人に向かって拗ねる様な口調で言った。
恋愛経験がまったく無いシャロスは、すぐに飲み込まれてしまった。
「い、いいえ……」
「殿下、いいかしら?殿下は今、わらわに招かれています。だから、わらわ以外の女性を、考えてはなりま
せぬ」
「は、はい……」
シャロスは左右をチラッと見た。
エナは相変わらず無表情だが、マナはニヤリと微笑んだ。
その意味ありげな笑顔に、シャロスの顔は赤くなる。
道で出会った人は、みんな女性であった。
当然といえば当然だが、自分だけ男という環境に、シャロスは焦りを感じた。
しばらくすると、彼らは一番豪華な屋敷にたどり着いた。
正門から十数人のメイドが立ち並び、リテイアやシャロスをみかけると、みな恭しく頭を下げた。
彼女達もまた、マナやエナと同じ服飾をし、彼女達二人に負けないぐらいの美貌の持ち主だった。
シャロスが連れて来られたのは、趣きのある小さめな部屋であった。
部屋の中央に円卓があり、その上には綺麗なテーブルクロスが敷いてあった。
「わらわは殿下の近くに座りたいから、このセッティングを許してください」
リテイアの言葉通り、テーブルの向かい側に置かれた二つの椅子の間は近かった。
彼女とシャロスが席に着くと、マナはワインとグラスを持ってきた。
エナは料理の準備を進めに行ったのか、どこかへ消えた。
「ふふふ、わらわと殿下との、お近づきの印よ」
と、リテイアは注がれた赤ワインを口元に持っていった
シャロスもおもむろにそれを口元に持っていくが、眉をしかめた。
記憶の曖昧なところ、どこかいやな感じがした。
「あら、まさか殿下はわらわが毒を入れたと疑っているかしら」
「いいえ、そんなことを、私が思うはずはありません」
「では、なぜ殿下は嫌がるようなそぶりを見せるのです?ふふう、わらわが先に飲んで、潔白を証明いたし
ます」
リテイアはグラスの縁につややかな唇を乗せ、グラスを傾けた。
ワインは彼女の口へなまめかしく流れ込む。
その量が半分ほど減った時点で、リテイアは唇を離れた。
グラスの縁に、赤いルージュの跡がくっきりと残った。
「いかがですか、殿下?」
「皇后様が私を害するなど、最初から思っておりません。皇后様も、ご冗談を……」
シャロスはやや引きつった笑顔を浮かべて、自分のグラスを持ち上げた。
しかし、その手をリテイアが遮り、
「いいえ、冗談ではありませんわ。殿下はきっと、そのグラスが細工されているじゃないかと、
疑っていることでしょう。殿下には、私のグラスを飲んでいただきます」
リテイアはそう言うと、自分が飲んだグラスを、シャロスの口元へ近づける。
彼女の言動にシャロスは困惑した。
それを見たリテイアは、悪戯っぽい表情を浮かべる。
「ふふふ……さあ、殿下。口を開けてごらん」
魔力を帯びた音色に、シャロスのあらがう意思が薄くなる。
リテイアはルージュの跡が残った側を、シャロスに向けた。
(はぁ、そ、それは……!)
そこにリテイアが口付けをしたと思うと、シャロスの股間が反応した。
「さあ、殿下。遠慮しないで下さい」
ついに、シャロスの唇はルージュの跡と重なる。
甘いぬくもりと、ワインの芳ばしい味が口の中に広がる。
シャロスはまるで、リテイアの唾液を味わっているような居心地になった。
やっと全て飲み干すと、アルコールが彼の身をめぐり、血流を速めた。
リテイアは突然身を乗り出し、シャロスの耳元でささやく。
「これで殿下はわらわと間接キスを交わしちゃったね」
「あっ!」
シャロスは思わずビクンと跳ねた。
横からマナがくすくす笑っているのを見て、彼は自分の失態に気付き、更に顔を真っ赤に染める。
「ふふふ……殿下って本当に面白いお方ね。さあ、マナ。あなたは下がって頂戴」
「はい、リテイア様」
マナは一礼すると、扉を閉じて退出した。
二人っきりになると、部屋中に微妙な空気が流れる。
「皇后様、私は……」
突然、リテイアはシャロスの唇に柔らかい指を立て、
「だめよ、シャロス。二人っきりになったとき、わらわのことを『お母さん』と呼ぶの、約束したじゃない
?」
彼女の優しい語りは、昨日と同じ妖艶な悪魔になった
シャロスの胸がドキドキに鳴り続き、息が浅くなった。
「うふふ……そんな緊張しないで。それとも、硬くなったあそこのせいかしら……?」
「ああぁっ!」
シャロスは悲鳴を上げた。
テーブルの下から、リテイアの足先が彼の股間に当たった。
「いやらしい子ね。さっきからずっと硬くなってるのを、わらわが知らないとでも思って?」
リテイアは小さな子を咎めるように語り口だった。
その言葉は、まるで鋭い刃物のように、シャロスの心の防壁を切り裂いた。
「ああ……ご、ごめん……お母さん!」
「ふふふ……こんなビンビンになっちゃって!そんなにしてほしかったら、自分から腰を動かしてみたら?
」
「はぁ、はあん……」
シャロスは切ない息を吐き、言われたとおりにリテイアの足にあそこを懸命にこすりつける。
「ふふふ、そうよ。そうやってどんどんスケベになっていきなさい……」
「お母さん、お願い……また、昨日のように、イカせて……」
「だめよ!言ったでしょ、あそこがイライラしたとき、ちゃんと自分で処理しなさいって!」
リテイアのつま先は布を通して、シャロスの一物を摘み、激しく動かせる。
シャロスの余裕が消えた顔には、どうしようもない屈辱と、妖しい悦楽が入り混じる。
「あ、朝起きたとき、一回やったの……ちゃんと、お母さんのことを思いながら……」
「あーら、なんて淫乱な子かしら!朝一度抜いたのに、またこんな硬くさせるなんて!」
「ご、ごめんなさい!で、でも……エナが、エナがあそこを舐めて……そ、それが途中で終わって……」
「あら、エナがそんなことを。……だれか!」
リテイアが高らかに呼び出すと、すぐに駆け付く足音が起きた。
「はい」
「マナ。エナをここに連れてきなさい」
「はい」
しばらくすると、顔が瓜二つの少女が部屋に入り、頭を伏せる。
リテイアはポニーテールの少女に向かい、
「エナ、殿下から聞いた話だと、あなたは朝ご奉仕をしましたね」
「はい」
「しかし、行為は最後まで行き届いていないそうね」
「はい」
「なぜそんな中途半端なことをなさるのかしら。わらわがあなたに、
殿下の煩悩を解かせる為に置いたのよ。
それなのに、行為を怠るなんて……いったいどういうつもり?」
「申し訳ありません。しかし、王子様自身がそれを嫌がっておられまして……」
「殿下が……?その言葉に嘘はないのか?」
「はい」
エナは淡々とその時のいきさつを述べ続けた。
マナはかたわらで時々盗み笑いをこぼし、
それとは対照にシャロスは地面に穴があれば入りたいほど恥ずかしかった。
「ふふふ……はははは!」
「こ、皇后様!笑わないで下さい!」
「ふふっ、これは失礼したわ。その時の様子、大体分かったわ。エナ」
「はい」
「あなたは勘違いをしてるのよ」
「勘違い……ですか?」
エナの瞳に、不思議そうな輝きがした。
「あの時王子様は確かにイヤだとおっしゃったが、それは口先だけなのよ」
「では、その時の言葉は偽りだったということですか?」
エナの生真面目な態度に、リテイアは失笑した。
「そうでもないわ。体の方はしてほしいのに、理性の方がそれを恐れている。
殿下はその時、自分の感情を勘違いしているのよ。覚えなさい、殿方はみんな射精が大好きなの。
一度勃起したら、ちゃんと最後までやりなさい」
「はい、心得ました」
「ふふふふ……殿下、私の言った通りでしょ?彼女はとても素直な子なのよ。
今回は殿下も悪いのよ。エナはあなたの召使いだから、彼女にちゃんと命令しないと」
「は、はい……」
シャロスは叱られた子供のように、口答えが出来なくなった。
「それにしても、殿下のあそこ……すっごく大きくなってるわ。朝から今まで、ずっと我慢していらっしゃ
ったのね」
「はぁ、うっ……うう!」
リテイアの足がまた上下にしごく。
その微妙な刺激に、シャロスは喘ぎ声を漏らした。
「ねぇ、殿下。このままでは、いつまでもうじうじしているつもりなの?」
「う、うう……」
「殿下も、速く抜きたいでしょ?」
「は、はい……抜きたいです!」
シャロスは思わず淫語を繰り返した。
彼のペニスは幾度と挑発され、もはや一触即発の状態だった。
「ふふふ……じゃあ、今度こそエナに役目を果たしてもらおうかしら」
「えっ?」
リテイアの足はシャロスの股間から離れた。
「あ、ああっ」
「さあ、殿下。今度はちゃんとエナに指示するのよ」
「し、指示って……」
「殿下のおちんちんに、ご奉仕させることに決まってるじゃない!」
「そ、そんな……!」
その浅ましい発言は、シャロスのプライドに邪魔されて言えなかった。
彼は今日初めて自慰したが、なんとなくそれはいけない事だと感じた。
女にあそこを触られるなんて、もってのほかだ。
「殿下、その姿のままじゃ、とても苦しいでしょ?それに、大臣だって貴族だって、
みんなやってることなのよ。ただ、おもてでは誰も言わないだけよ。
殿下も将来立派な王様になるんだから、今からちゃんと慣れておかないと、ね?」
「うっ……」
リテイアの言葉に、シャロスは動揺した。
欲情に混乱した頭は、その真偽を判断する力が無かった。
「さあ、言ってみなさい。『エナ、そのいやらしい口を使って、
私のおちんちんをしゃぶり、汚いチンポ汁を出させてください』って」
(くっ)
とても屈辱的な言葉であった。
しかし、そんなことよりも、股間から広がる苦悶のほうがもっと苦しかった。
シャロスは口を開き、泣きそうな声で呟いた。
「エ、エナ……その、いやらしい口を使って、わ、私のおちんちんをしゃ、
しゃぶり……汚いチンポ汁を出させてください!」
「はい、かしこまりました」
エナはシャロスのズボンや下着をおろし、慣れた手つきで彼の腫れたペニスを露出させた。
淫猥なオスの匂いが部屋中に広がる。
シャロスはとても惨めな気持ちになった。
側ではリテイアのみならず、メイドのマナまで、彼の下半身を見てくすくす笑っていた。
エナの息が掛かると、ペニスは更に大きく膨らみ、表面に浮かぶ血管がドクン、ドクンと蠢く。
ペニスの先端はぬるぬると湿っていた。
エナは愛おしそうに根元の部分に手を添え、彼の先端から口を覆い被さる。
「あああぁっ!」
とてつもなく敏感になった部分から、雷を撃たれた様な快感が走る。
エナが頭を前後に動かすたびに、彼女のすぼめた口が竿をこすり、舌が亀頭をなだめる。
「はあぁあぁ!も、もう我慢できない、ああ、あああぁあああ!」
シャロスは狂い出すような声で呻いた。
彼はエナの頭を掴むと、シャロスは腰を突き上げた。
「うぅんん――!」
エナはくぐもった悲鳴を上げた。
しかし、シャロスはそれにかまわず腰を振った。
散々溜まった濁汁は、凄まじい勢いでエナの喉へ直射する。
大量の粘液にエナはやや眉をしかめたが、ゴクン、ゴクンと飲み干した。
やがて、シャロスの一物は何もかも吐き出し、小さく萎縮してエナの口からはずれた。
彼は思わず尻を床につかせた。
「あーあ、もうイッたなんて……いくら焦らされたからと言って、速すぎるわ」
「ご、ごめんなさい……でも、どうしても……」
「殿下、早漏れの男性は、女性に好かれないわよ。これからはちゃんと長持ちするよう、気をつけなさい」
「はい……」
「それと、これから自分でイクのが難しいとき、ちゃんとエナに手伝ってもらいなさい。
そのために、彼女がいるんだからね」
「は、はい、皇后様……」
シャロスはそう言って、ついに気を失った。
王子が確実に堕落していく様子を見て、リテイアは会心の笑みを作った。
第三話
最近、シャロスはイライラするようになった。
皇后邸の出来事から数日の間、シャロスは毎日欠かさず自慰をしていた。
彼が行為をする時、いつもリテイアの妖艶な肢体を思い浮かべていた。
黒いブラジャーに包まれた、豊満な乳房。
絹の薄地を通り抜けて、見えそうで見えない乳首。
悩ましい腹や、背中のライン。
そレースの刺繍を施されたショーツ。
刺繍の合間に、女性の淫靡な茂みが浮かんでくる。
そして、その体の持ち主が、魂を吸い込むような深い瞳で、
シャロスの行為を見下ろしながら、薄笑いを浮かべ……
そこまで想像すると、シャロスは例外なく果ててしまう。
残されるのは激しい疲れと、自分に対する虚しい気持ちだった。
欲望に負けて自慰に耽ってしまい、そしてリテイアを思いながらオナニーしてしまうことは、
彼にとって屈辱的なことであった。
召使いとして彼の側にいるエナも、厄介な存在だ。
最近、シャロスは自主的に彼女と距離を置くようにしていた。
エナは確かに一流のメイドだ。
彼女が用意してくれ服飾はその日の気候に相応しく、シャロスに快適な一日を過ごさせてくれる。
彼女が調理してくれ食事はシャロスの食欲を満たし、今まで食べ慣れた宮殿料理に無い味を作ってくれる。
喉が乾いたと思った時に、紅茶を持ってくる。
疲れたと思った時に、肩を程よい力で揉んでくれる。
シャロスが口に出さずとも、彼女は彼の心情を的確に読み取ってくれる。
彼女の奉仕は、実に用意周到で気持ち良いものだ。
そして、その存在感も、徐々に大きな物へと変化しつつある。
シャロスは彼女の可愛らしい姿を見るたびに、頭を悩ませた。
エナの背後に、皇后の陰謀が隠れていることは明白だった。
しかしその一方で、彼はエナをはっきりと拒絶することができない。
エナの艶やかな柔肌と、少年の性欲をくすぐる身のこなし。
それに、彼のどんな命令にも従ってくれる絶対的な従順さ。
皇后リテイアとは違い、彼女はまた違うタイプの魅力があった。
今日もシャロスはぼんやりと、腹心であるレイラから報告を受けていた。
彼はほとんど聞き流しながら、数日前に見たエナの半裸を思い返した。
「……それと、殿下……あのエナという者ですが、彼女は明らかに皇后側の人間です。
そのような者を殿下のお側で置いていかれるのは、いかがなものかと」
「ああ……」
「…………殿下!」
突然、レイラは口調を強めた。
彼女の意志がこもった口調に驚き、シャロスは目を丸くして我に帰る。
「お言葉ですが、殿下は最近、心が廃れているように思われます」
「えっ?」
「何よりも、殿下は以前のような気迫がございません。
殿下は万民を救う立場の者、どうかご自分を戒め、その示しをつけてください」
レイラの表情は厳しかった。
彼女にそれほど叱責されるのは、子供の時以来のことであった。
シャロスは生来高貴な立場にいた者だが、彼は他人の忠告を素直に受け入れる人間である。
だから、シャロスはすぐさま自分の失態に気付いた。
「……すまない、レイラ。お前の言うとおり、私は最近どうかしている。お前のおかげで、目が覚めたよ」
「分を超えた言葉で申し訳ありません。どうか、お許しを」
「いいえ、それでいいのだ。お前はいつも私の鏡のように、私の過ちを諌めてくれる。これからも、私を支
えてくれ」
「勿体無いお言葉です」
レイラは頭を深々と下げた。
彼女にとって、シャロスの言葉はいかなる時でも至上のものであった。
シャロスは目を輝かせ、表情を明るくさせた。
それに伴って、彼は聡明な頭脳を素早く回転させた。
「こうしてはいられん、レイラ!」
「はっ」
「税務管理局のイルバフ長官に伝えろ。王国陸送隊の貿易収支を徹底的に調査させろ」
「はっ。しかし、それは……?」
「陸送隊指揮官のザーロンが提出した出納帳に目を通したが、前年と数字が合わない箇所がいくつもある。
ザーロンのやつ、私をひよっこだと思って油断しているだろう。あやつは、皇后派に賄賂を贈って今の地位
に登り詰めた者だ。
ふん、皇后の傘に入っていれば問題無いと思って安心しているだろうが、そうはさせない」
「はい。……ふふっ、あの『狐目のイルバフ』にかかれば、すぐに尻尾が掴まれることでしょう」
レイラは思わず笑いをこぼした。
税務局主席を努めるイルバフ氏は、その老獪さで王宮内外に知られる棘だらけな人間で、
干からびたパンから水滴を絞りだせると評価される人物である。
彼にザーロンを搾り取らせるには、これ以上ないほど適任している。
「証拠のつかみ次第、それをオイバルト卿に伝え、ザーロンを弾劾させよ」
「はっ」
「それと……先日に行った皇家艦隊再建の進展はどうなったか」
「相変わらず宰相のトーディザード卿が所々横槍を入れているため、資金の調達が停滞しているようです」
レイラは難色を浮かべた。
シャロスの国は周辺諸国の宗主国になって、長い間戦争が起きなかった。
そのため王国軍の戦力は下がり、とりわけ存在価値の低い海軍隊は完全に廃れた。
しかし、シャロスの代になってから、海賊や他国の秘密私掠船が横行し、
海上運輸が思うように進まない状態になっている。
そこで、皇家海軍隊の復建を打ち出すのは急務だったのだ。
「やはりか」
シャロスの視線が鋭く険しいものとなった。
彼は立ち上がり、窓の方へ歩んだ。
秀麗な顔立ちは光に照らされ、色の深い瞳に知恵の輝きが宿りはじめる。
レイラはそんなシャロスの姿を見るのが大好きだ。
彼の凛々しい後姿は、決して他者の追随を許さない。
早熟した英断は、どんなことも解決してくれるような安心感がある。
――王子様はいずれ英邁な国王となり、歴史に名を残すほどの名君となるだろう。
レイラは、そんな尊敬の意を心に抱き、憧れがこもった視線でシャロスを見続ける。
ふと、シャロスは対策を思い浮かんだかのように振り返り、
「テクド商会に使者を遣わせろ。彼らに資金投資を協商させよう」
「……テクド家は財界でも屈指の商人連合。あそこは中立しているとはいえ、我々に協力してくれるだろう
か」
「一年前、テクド傘下の商人グループが冤罪をかけられた時、私が手配を取り消したことがある。
テクド家のライト子爵は恩義を重んじる男だ。やつなら、我々に協力してくれるだろう。
艦隊が建設できた暁に、海上貿易を彼らに率先させよう。そうすれば、喜んでついてくれるだろう」
「なるほど。テクド家は長年、皇后派に味方するハエリオン家とライバル関係にある。
これで我らの味方に引き入れれば、一石二鳥ですね」
「ああ。それと、王族の出費もできるだけ節約させよう。
今年の南テドン地方は干ばつだと聞くが、減税を命じよう」
「民もさぞ、喜ぶことでしょう」
「我々上部の人間が浪費しているんじゃ、格差が広がってしまうばかりだ」
「殿下、なんとお優しい心を」
「これぐらいは当然の事だ。レイラ、私はまだまだ足りない部分が多いが、
できるだけ多くの人を幸せにしたいと思っている。今後とも、あなた達の良き働きを期待する」
「有難い御言葉でございます。……では、私はこれにて」
レイラは一礼をすると、部屋から退出した。
その後も、シャロスは憮然と眉をしかめて考え事をした。
毎年、王室の出費は高額なものとなっている。
その一番の原因を、シャロスはよく知っている。
皇后リテイアの浪費なのだ。
後宮に関する支出項目には不透明なものが多く、額面も非常にでかい。
彼女の権力や地位もあって、シャロスの配下が表立って詰問することは難しい。
(この問題、やはり私自身が決着をつけなければ……)
シャロスはため息をつくと、部屋から出た。
「王子様、どちらへ……」
シャロスはそばを見ると、そこには恭しく待っていたエナの姿があった。
(ふん、私を監視するつもりか)
「剣技場だ。私がどこへ行こうと、お前の意見を聞く必要があるのか」
「いいえ、滅相もありません」
シャロスはわざと冷たい口で答えると、エナはうつむいた。
そうでもしないと、エナの妖しい魅力に惹かれそうで恐いのだ。
シャロスはまつりごとはもちろん、剣術、馬術、弓術などの武術も一通りできる。
そして、彼は日課のように毎日何らかの運動を行ってきた。
最近特にあらぬ感情に惑わされたこともあって、シャロスはそれを運動で発散しようとした。
シャロスは早足で皇居を出て、苛立った気持ちで御道を歩いた。
エナはそれ以上のことを尋ねず、ただ黙ったまま彼の後を付いた。
ちょうどその時、向かい側からやってきた一両の馬車は、彼の横に止まった。
壮麗な金色紋章が施されたキャリッジは、持ち主の豪華にこだわる風格を物語った。
馬車の窓から、柔らかい女の声が伝わる。
「あら、やはり殿下でしたね」
皇后リテイアの美しい笑顔が覗き出て、シャロスに向けられる。
彼女の妖艶な目元を見ると、シャロスの心は大きく動揺した。
「リテイア皇后……!これは、奇遇ですね」
「ええ、そうですわね。付き人がほとんどいなかったものですから、最初は殿下だと気付きませんでしたわ
」
「私は、堅苦しいのが嫌いですからな」
「殿下らしいお考えですわ。わらわは、丁度ライフォン夫人のところから帰ってきたところです」
ライフォン夫人の名前を聞いて、シャロスは眉をしかめた。
貴族の中では、身分や皇后の威光を頼って、奢侈な生活を送る者が大勢いる。
そんな浪費者達に、シャロスは快いと思うはずが無い。
彼の心情を読み取ったのか、リテイアの宝石のような瞳が輝く。
「あら、今日の殿下は随分とご機嫌斜めですね」
「ふん……そんなことは無い」
シャロスはリテイアから目を逸らした。
彼女の美麗な顔立ちを見ると、あの淫らな記憶を思い浮かびそうで恐かった。
「ところで、殿下はこれからわらわと一緒に来て頂きませんか?もちろん、エナも一緒に」
「えっ?」
リテイアの突然の誘いに、シャロスは無意識のうちに顔を真っ赤に染めた。
(リテイアのところに行けば、またあんなことを……でも……)
シャロスは戸惑った表情を浮かべた。
心の中で理性の警鐘が鳴り響いた。
その一方で、リテイアの誘いに従いたい欲望が膨らみ上がってくる。
彼女の挑発的な瞳は、まるでねっとりとした網のように、シャロスの心と体を絡め取っていく。
そんな目で見られると、ひそかにシャロスの股間が硬くなりはじめた。
御者台からマナが降り、馬車の扉を開けて恭しく頭を下げた。
「王子様、せっかく皇后様からのお誘いです。どうか、彼女の厚情をお受けください」
「う、うん……」
シャロスはついに甘い感情に打ち勝つことができず、複雑な気持ちで馬車に乗り込んだ。
エナは馬車の扉を丁寧に閉めると、マナとともに前方の御者台へのぼった。
「どーっ!」
外でマナの元気一杯の掛け声が叫ばれると、馬車はゆっくりと動き出した。
シャロスは馬車に揺られながら、隣に座るリテイアの体を感じた。
彼は一生懸命自分の気を逸らそうとしたが、忘れようとすればするほど彼女を意識してしようがなかった。
今日のリテイアは羽飾りの帽子をかぶり、人の目を惹く真紅のシルクドレスを着ていた。
絹のすべらかな材質は光沢を反射し、首より下げた銀のネックレスははだけた谷間にぶら下がる。
大きな胸元は、ギリギリなところまで露出し、その豊満さをたっぷりと見せ付ける。
目の外縁から入る彼女の乳房は、馬車の動きと同調して揺れ、シャロスの欲望をかきたてる。
馬車が道を曲がる時、シャロスはうっかりリテイアと体を密着してしまい、その肌の柔らかさにどぎまぎし
てしまった。
その時リテイアの体から発される香りは、シャロスの眠っていた感情を呼び起こした。
(……はっ、この匂いは……)
シャロスは思わず、生まれて初めて女性にイカされた夜のことを思い出した。
あの夜も、リテイアの体からこの香りが漂っていた。
この淫靡な香りはあのいやらしい行為とともに、
シャロスの脳の深い場所に烙印をつけ、彼女の虜にしょうとしていた。
「殿下ったら、またぼうっとしちゃって。わらわと一緒にいるのは、そんなに退屈なのでしょうか」
リテイアは意地悪そうな笑みを浮かべながら、甘ったるい声で言った。
意識が薄れたシャロスは、自然と「いいえ、そんなこと無いよ」と答えそうになった。
しかし、彼が口を開こうとした時、ふとリテイアは自分にそのセリフを言わせるのが目的であると感じ取る
。
(しっかりせねば……!皇后のやつ、また色仕掛けようとしたな。だが、今回こそ……!)
シャロスは自分に言い聞かせるようにして、努めて正気を保とうとした。
「……いいえ、私はただ考え事をしまして」
「おや、わらわの見当違いでしたか。して、一体どんなお考え事を?」
「ついさきほどまで帳簿と睨めっこしていたが、今年の王宮予算のやりくりは大変厳しくて。
これでは、王子である私が、先に餓死してしまうじゃないかと、不安で不安で仕方がありません」
「ふふ……殿下の冗談はまことに面白いですわ。王子様が餓死なんてしたら、この国では誰も飽食できませ
んわ」
「ははは、確かにそうかもしれません。しかし私は、王室が少しでも浪費を抑えなければならないと考えて
いる。
皇后様にも、ぜひ自分の振る舞いを見直し、私に協力してほしいかと存じます」
シャロスの口調は一転して、鋭いものへとなった。
「あら、わらわが無駄使いをしているとおっしゃるのですか」
リテイアは目を細め、声を低く抑えた。
だが、シャロスは一歩も引かなかった。
「……かねてから、私は皇后様の出費に疑問を持っております」
彼は目線を伏せながらも、言葉を緩めなかった。
ここで押し進まないと、また皇后が言い逃れてしまいそうだからだ。
「そんなことを言われるとは、心外ですわ。
……そうですね、せっかくですから、殿下にはあそこを見てもらいましょう」
「あそこ、とは?」
「ふふふ、とてもいい場所ですわ。……この暑い季節を過ごすのに、ぴったりの施設ですわ。
これを見ていただけたら、殿下もきっと考えが変わることでしょう」
シャロスはまだ質問しようとしたが、途中で口を閉じてしまった。
なぜならこの時、リテイアは孔雀の羽毛で編まれた扇子を取り出し、自分の体をあおぎ出したのだ。
彼女はさきほど何か激しい運動をしたのか、体から汗の匂いや、
それ以外に何かいやらしい感情を催す匂いが染み出る。
それが彼女の香水と混ざり合い、扇子のそよ風に乗って伝わってくる。
その匂いを嗅いだだけで、シャロスの頭はぼうっとなり、股間の一物に血が集まった。
リテイアの女性特有の体臭は、シャロスがまだ知らない官能的なものであった。
彼は自分自身でも気付いていないうちに、リテイアによって性への欲求を開発されていた。
思春期にある純潔だったはずの幼き心は、淫猥なものに興味を抱き始め、徐々に黒い欲望によって染まられ
ていた。
シャロスは自分の中で膨張する未知なる興奮に、うすうす背徳間を抱いていた。
しかし、まだ色事を接して日が浅い彼には、その感情はどうすればいいのか分からなかった。
目線が泳いでいる間、突然リテイアの滑やかな腋が目に入った。
白く透き通った腋は、その露出した胸や背中と同調して、美しいラインを描いていた。
彼女が扇子を軽くあおぐ度に、綺麗な柔肌が見え隠れしてシャロスの視界をくすぐる。
「殿下、わらわの体になにかありますか?」
「えっ?い、いいえ……」
シャロスは顔を真っ赤にして、慌ててうつむいた。
彼の恥じらう仕草に、リテイアはかすかにほくそ笑む。
彼女はさりげなくシャロスの股間に腕を伸ばした。
「殿下の様子は、何かおかしいですわ」
突然、リテイアの人差し指に力を入れ、シャロスのすでに勃起した股間の先端を軽くつついた。
「あぁっ!」
「あーれー、どうしたのかしらね?殿下のあそこ、ビンビンに立っていらっしゃるわ」
リテイアは悪魔のように口元を吊り上げる。
シャロスが取り乱している間、リテイアは掌を彼の股間の上を乗った。
手の重さに反応して、彼の心も一物もビクンと躍った。
その妖しい感触に、シャロスは皇女を非難することさえ忘れ、口をどもりながら身じろぎした。
「ひょっとして……殿下は最近、溜まっていらっしゃるんですか?」
「な、なにを仰いますか、皇后様」
「うふふ……でも、殿下のあそこのほうが、正直みたいですわ?」
「あぁっ!」
リテイアが少しりきむと、シャロスは腰を一瞬震わせた。
シャロスは口をパクパクさせて、どう答えるべきか分からず狼狽した。
普段なら一寸と乱れる論理を繰り広げる弁舌も、今では跡形も無かった。
勃起を見破られた恥ずかしさだけでなく、彼女に下半身をいいように操作されたことに、シャロスはいらだ
ちを感じた。
「あれれ、本当に溜まっていらっしゃったんですか。殿下の欲求を解消させるために、
エナをわざわざ置いたというのに。殿下、彼女に抜いてもらいませんでしたか?」
「い、いいえ……」
「はぁ、これじゃあメイドとして失格ですわ。あとで、彼女に厳しいお仕置きをしなくては」
「いいえ、違います!これは、エナのせいじゃありません」
「そうですか。では、どうして殿下の御体が、こんなに苦しい思いをしているのかしら。
……まさか、殿下は自分で慰めていたりして」
「えっ?そ、それは……」
いきなり図星を突かれて、シャロスの顔は青ざめた。
彼がはっきりと否定しない様子を見て、リテイアは驚愕の表情を作った。
「あら、本当にそうなされたのですか」
「う……」
「殿下は国主たる者です、ご自由に振る舞いって結構ですが……
ご自身の手で自分を慰めるなんて、大変お恥ずかしい事ですわよ」
リテイアはあざ笑うかのような、軽蔑するかのような口調で言った。
シャロスはそれを感じ取ると、自分のことがとてつもなく惨めに感じ、恥ずかしい気持ちで胸いっぱいだ。
いま目の前に穴があれば入りたい気持ちになった。
リテイアの言葉は鋭利な刃物となって、普段からの威厳の防壁をズタズタに切り裂く。
そこで剥き出されたのは、年上の美女に弄ばれるウブな少年の姿だった。
「まあ、それだけ殿下が大人に近づいた証拠ですから、わらわは嬉しく思いますよ。
でも、せっかくエナをお側にはべらせておりますから、彼女を使ってあげてください」
「そ、そんなんじゃ……」
「どうか遠慮なさらずに。エナもきっと、そうされることを期待していますから」
「……」
シャロスは母親になだめられた子供のように、顔をうつむいた。
会話してから早々、シャロスにはリテイアを言い返す余裕が無くなってきた。
幸いなことに、そこで馬車が止まった。
マナが外から扉を開けると、シャロスはまるで逃げるように降りる。
彼のあたふたとは対照的に、リテイアはマナの手を借りて、優雅に足を地面に置く。
外の新鮮な空気に触れてから、シャロスの頭はようやくはっきりしてきた。
(くっ……またこの女狐のペースにはまってしまった……このままでは、またあいつらのいいなりになって
しまう……)
シャロスは心の中で嘆きながら、周囲を見渡した。
リテイアに気を取られたため、途中の道のりをほとんど覚えていなかった。
目の前に王宮にも負けない絢爛な屋敷があり、入り口から高級石材をふんだんに使われ、壮麗に積まれてい
る。
正門の真正面に大きな噴水があり、その真ん中に黒曜石の彫像がそびえる。
あたりは半径数百メートルにも渡って、手入れをされた緑の低木が広大に囲み、目を一新させる麗しい光景
を作り出す。
白石で舗装された道は、設計の意図を凝らして低木群とともに円周を描く。
「ここは……?」
「わらわの別荘でございます」
「別荘?」
「ええ。娯楽用に建築されたものですわ。いかがかしら?国中の職人を集めて、作られた場所です」
「……この壮観の裏にどれだけの民が虐げられたかと思うと、心が痛んで甚だしい」
シャロスは心を鉄にして、リテイアへの嫌悪感を思い立たせる。
「民というのは、王室である我々に仕える者。わらわ達を満足させられることこそ、至高の幸福ではないか
しら」
「ふん……」
シャロスは鼻を鳴らし、明らかに不満を示した。
それに対し、リテイアは相変わらずの微笑で、
「どうやら、殿下は気が召されないようですわね。ならば中の様子を、直に見せてあげますわ」
言い終わると、マナが「さあこちらへ」とシャロスをいざなった。
シャロスは仕方なく、渋々と彼女の後についた。
屋敷の中では、外の景観に負けないぐらい豪華なつくりとなっていた。
扉から真紅の絨毯が敷かれ、靴越しに高級そうな踏み心地を感じる。
道中随所に珊瑚の木、東洋の白磁、翡翠や瑪瑙といった貴重な装飾が置かれ、
今まで見た事も聞いた事も無いような品々が、廊下を通り過ぎるたびに出てくる。
シャロスはそれらに目を奪われながら、心の中で疑念を募った。
王子である彼よりも、まるで皇后リテイアの方が金持ちであるようだ。
彼の思考を断たせるように、リテイアは心を撫でる様な柔和な声で話しかけた。
「ところで、殿下は最近お疲れのようですわね」
「どうしてですか?」
「わらわの気のせいなら申し訳ありません。でも、最近の殿下はどうもうわの空が多い様子ですわ。
御体には、もっと気を使うべきですわ」
リテイアの含みのある言葉に、シャロスは顔を赤らめる。
彼は何かを言い返す前に、リテイアは言葉を続けた。
「ここにお越しいただいたのは、殿下の疲れを取るためですわ」
「それは、どういうことだ?」
「殿下は、サウナという言葉を聞いたことあるかしら?」
「サウナ?それは一体……」
「異国より伝わる健康法ですわ。蒸気を発生させ発汗させる事で、
体をほぐす機能があるですわ。ぜひ、殿下にも試して頂きたくて」
「ふん、私にはそんな暇など無い。まだやることが山ほど残っているため、帰らせて……」
「殿下、たまにはごゆっくりなさっても、いいじゃありませんか」
リテイアは湿気を帯びたピンク色の唇を軽く弾ませ、シャロスの腕にしがみついた。
「国も仕事も何もかも忘れ、わらわと二人で、気持ちいいことをしましょう。……ねぇっ?」
リテイアの潤いだ瞳に見られると、シャロスはまるで心が霧に覆われたかのように、意志が朦朧としてきた
。
腕に彼女の豊かな乳房が密着し、男の本能を呼び覚ます。
彼女の言葉には危ない香りが含んでいた。
だがそれは男にとって、また刺激的な事柄であった。
まだ成年していないシャロスでも、その先の事をなんとなく想像できる。
「さあ、一緒に行きましょう」
リテイアはくすりと笑うと、シャロスの手を引っ張って歩き出した。
その女性らしい柔らかい感触に、シャロスの心に甘い感情が広がり、彼女の後に従った。
程なくすると、シャロスは一つの個室に連れ込まれる。
そこにはすでに六人の女召使いが控えていた。
彼女達は左右に三人ずつ分かれ跪き、頭を深く伏せていた。
「「お帰りなさいませ、リテイア様」」
彼女達は頭を下げたまま、語頭から語尾までぴったり一致するように言葉を発した
「今日は、大事なお客様がお見えになるから、丁寧になさい」
「「はい、リテイア様」」
メイド達が異口同音に返事すると、スカートの裾を掴み優雅な姿勢で立ち上がった。
その動作もまた見事に揃っていて、まるで長い間訓練されてきたようだ。
三人の召使いはリテイアに、残りの三人はシャロスの周りに立ち、マナとエナはその場から退いた。
彼女達は顔をうつむき目を伏せていたが、どれもスレンダーな体系をし、上質な美少女であることがうかが
える。
シャロスが怪訝していると、一人の召使いが彼の上着のボタンをほどき、もう一人は背後から脱がせる。
残りの一人は、彼女達から服を受け取ると、丁寧にハンガーにかけた。
三人とも目線を伏せたままで、シャロスと面を合わせなかった。
しかしその動作は非常に慣れたもので、お互い隙間がまったく無い。
そのため、シャロスは抵抗する時間もなく、またたく間に半裸となってしまった。
「ちょっと、これはどういうことだ!」
「殿下、これはこれから行う事のための準備ですわ」
「しかし……」
いいかけた言葉を飲み込み、シャロスは息を止めた。
すでに裸となったリテイアの姿は、彼の心を射止めた。
真っ先に、眩しいほど白くてたおやかな乳房が目に入った。
その色白さは、まるで漆のようにシャロスの脳内を真っ白に染めあげる。
リテイアは恥じらいの表情を微塵とも表さず、メイド達が奉仕する中、
その美しい裸体をシャロスに存分に見せつけた。
彼女のへそのラインに沿って、シャロスは視線を下へ滑らした。
しなやかな腰つきや、肉感のある臀部。
そして正面の股間には、女性の性徴でもある、神秘なる茂みがあった。
シャロスはこれで生まれて初めて女性の陰部を目にした。
何もかも不思議な光景で、リテイアが持つ独特の妖艶さによってそれらがより一層蠱惑的に表現され、
シャロスの男性的な欲情を催した。
リテイアはシャロスの視線を捕らえ、余裕っぽい表情でニコッと微笑みかけた。
その時、シャロスは初めて自分の失態に気付き、思わず顔を熟したトマトのようにして顔を伏せた。
――裸になっているのは相手だというのに、なぜか自分のほうがずっと恥ずかしい。
その屈辱的な状況はさらにシャロスを焦らせ、平常心を失わせる。
ふと、シャロスは自分がメイド達によって椅子に座らされたことに気付く。
そして次の瞬間、メイド達は貴族服の下半身部を正確にもぎ取る。
「あ、そ、それは……」
賢明な少年王を演じてきたシャロスは、すぐにあたふたするばかりの男の子に成り下がった。
メイド達は素早く彼のズボンを、さらに下着まで除去すると、シャロスのいきりたった一物が空気に触れた
。
まだあどけなさが残っている陰茎だが、シャロスの意志とは関係なく醜く腫れ上がり、
彼の身体が求めていることを暴露した。
周囲のメイド達は彼の一物を見て、心なしかあざ笑うかのような目付きになるような気がした。
シャロスの心拍数は一気に上がり、反射的に股間部を手で遮った。
そのぎこちない仕草を見て、リテイアは再びくすりと笑った。
「殿下、王族たるものには、恥ずかしい部分は何も無いはずですわ。
どうかその高貴な体を隠さず、堂々としていてください」
「あ、うん……」
リテイアの優しい口調に諭され、シャロスはややためらった後、ついに両手を離した。
次の瞬間、大勢の女性の中で性器を晒しだすみじめな感情が、彼の心を襲った。
「さあ、わらわについていらっしゃい」
「あっ……」
シャロスは心細い気持ちになり、できる限りリテイアの裸を見ないようにしながら後についた。
股間で硬くなった一物が、歩行すると同時に左右へ揺れ動く。
彼はまわりのメイド達が、含み笑いをしているじゃないかと疑心暗鬼に陥った。
しかし、彼女たちの顔を直視して確認する勇気は、どこにもなかった。
自分がまったく知らない環境、全裸となって歩行する。
今の彼は、目の前のリテイアにすがりたい気持ちで一杯だった。
次の一室までたどり着くと、そこは暖かい湯気が立ちこめていた。
青いタイルで敷かれた床や壁は、光に反射して輝く。
メイド達はそこに備えてあった水がめから湯を汲み取り、シャロスやリテイアの体にやさしくかける。
シャロスの綺麗な金色のロングヘアはメイドに解かれ、水で濡らされる。
暖かい水流に体中の筋肉が一気にほぐされ、なんともいえない気持ちよさにシャロスは心を穏やかにした。
しかし横目でリテイアの裸体がちらちら見えてしまうと、シャロスの緩めたばかりの神経はまたすぐに緊張
した。
逞しい陰茎だけ、いつまでも暖かい水流に逆らって怒張していた。
「殿下、そんなに固くならないで。これからは殿下に享受してもらうものですから、
殿下が疲れては、意味がありませんわよ」
「う、うん……」
湯気がかったリテイアの体は、見え隠れする分より魅力的なものとなった。
彼女の豊満の乳房に気をとらわれたため、シャロスは言い返す言葉を思い浮かべることができず、
ただぼうっとしていた。
ある程度体を流されると、メイド達は白い粉末を盛った壷を取り出した。
彼女達はその粉末をしゃくると、それをシャロスの体にしみこませるように塗る。
「これは……?」
「塩でございます」
「塩?なぜそれを?」
「体の悪い脂肪だけを溶かし出し、皮膚呼吸を正常化させ、美容する効果があるのです。
ちなみに、この塩は大変貴重な自然塩ですの。南海の海水を引き込み、
五年間をかけ濃縮した結晶を収穫した最高級のもので、他所ではまず手に入らないでしょう」
皇女が説明している間、他のメイド達は絶えずシャロスの体を撫で回す。
塩が体に付着する気持ちよさに、シャロスは反感を抱くことさえ忘れた。
メイド達の手つきは彼の胸板に触れ、敏感になった乳首をなぜる。
両腕を上げられると、彼のつるつるの腋に粉末が添えられる。
太ももを塗られ、最後は足裏まで揉まれる。
思わず目をつむりたくなるような気持ち良さだが、このままではリテイアの思うつぼに嵌るような気がする
と、
くすぐったい気持ちになった。
彼はリテイアのほうを盗み見すると、全身に流れる血液がさらに加速し出した。
リテイアのグラマーな肢体はメイド達の手によって撫でられ、弾力に富んだ様がより一層強調された。
とりわけ二つのたわわな乳房は背後から揉まれ、白い粉末がその表面に吸い付く。
そのいやらしい感触を想像すると、シャロスの股間の一物はますます硬くなり、情けなく自己主張をし続け
た。
全てを塗り終わった後、メイド達は二人に薄いデシン質の肌着を着させた。
塩まみれになった体の上から、シルクのすべすべした服が密着して、なんとも歯痒い感覚であった。
シャロスの困惑した表情を見ると、リテイアはニッコリと微笑み、
「殿下、これからはいっぱい汗をかくために、この装束を着させていただいたですわ。
……それとも、裸のままの方が、良かったかしら?」
「そ、そんなことはないよ!」
「うふふ……今のは、ほんのした冗談ですから、気になさらないで下さい」
「くっ……」
リテイアはからかうような笑みのままで、奥の部屋へと進んだ。
シャロスは悔しいながらも、薄い肌着に包まれた彼女の体を追うしかなかった。
さきほど目に焼きついたリテイアの裸が布一枚越しにすぐ目の前にあると思うと、
シャロスはどうしても落ち着けなかった。
衣に隠された彼女の肉体は、裸の時とはまた一味違った魅力を醸し出していた。
うっすらと浮かぶ臀部や胸の輪郭は、シャロスの性欲を常時くすぐる。
最奥の部屋に導かれると、メイド達は扉を開き、恭しくひざまずく。
その部屋はこれまでに無い濃い霧に包まれ、蒸し暑かった。
シャロスはリテイアに従って入ると、背後の扉を閉められた。
途端に、全身がまるで温かい蒸篭に入れられたように、暑苦しくなってきた。
「わらわは熱いのが苦手なものですから、低温サウナにしております。この程度なら、
少々激しい運動をしても、体に危害を加える心配は無いですわ。殿下もすぐ慣れると思いますが、いかがで
すか?」
「私は、大丈夫だ」
シャロスは不安な気持ちで周囲を眺めた。
先ほどまでとは違い、部屋全体は木材で作られ、ヒノキの独特の香りが蒸気と共に部屋中を充満する。
中央の堀には熱く焼けた石が置いてあり、その側に水を盛った桶や杓子があった。
どうやら、その石に水をかけることによって、蒸気を発生させる仕組みになっているようだ。
さらに堀から少し離れたところで、ござが敷き詰められた二つの寝台が用意されてあった。
寝台の上には柔らかそうなビロードが敷かれ、見た者にその上を寝転がったらどんなに気持ち良いかを連想
させる。
入り口のすぐ側で、いつの間に素衣に着替えたマナとエナが侍っていた。
シャロスやリテイアが現れると、彼女達はまったく同じタイミングでお辞儀をした。
その華奢な体つきは甘い果実のように、シャロスの視界に別の刺激を加える。
エナはロングヘアをなびかせ、相変わらず無表情のままで、シャロスを寝台の方へみちびく。
髪がうなじにかかるマナはリテイアに奉仕しながらも、
時々シャロスに向かって悪戯っぽい笑みを浮かべ、彼を赤面させる。
台の上にうつ伏せにさせられると、シャロスは服下から伝わるビロードの感触に心酔した。
蒸気で湿った敷き布は生暖かく、彼の生まれつき滑々な肌を静かに受け止める。
マナとエナは、何やら植物の枝葉を束ねたもの取り出した。
シャロスの疑問に満ちた表情を察すると、リテイアは柔和な声で語りだした。
「これは高原でしかとれない、シラカンバの木からとったものです。
体にはたくことによって、発汗作用をよくさせ、血行を促進する効果があるらしいわ」
「……そうなのか。皇后様は、よくいろいろとご存知ですね」
「ふふっ、殿下は療養に関してまったく気をつかわないからですわ」
シャロスは悶々としたが、それ以上皮肉を言わなかった。
今までの見聞きしてきた限り、ここでの全てのものは、かなり贅沢に作られたものだと推測できる。
エナが振り下ろしたシラカンバの葉は、やさしくシャロスの背中を叩く。
葉自体それほど痛くない上、エナはほど良く加減しているため、心地よい刺激がシャロスの脳髄を襲う。
枝葉が背中から腕、太ももへと叩くうちに、シャロスはたちまち昏々として、まぶたをおろした。
体が鉛のように重く鈍くなり、少しも動きたくなくなった。
しばらくすると、体中から汗が噴き出て、服との間の隙間を滴るようになった。
全身を撒かれた塩はその汗に流され、シャロスの体を洗浄する。
小さな粒に体を磨かれる感じはくすぐったいが、確かに気持ち良い感触でもあった。
葉枝のリズミカルな叩きとあいまって、汗水は肌着を湿らせる。
シャロスはついに目を閉じた。
今まで仕事に勤しんできた心は、気持ち良さに流れて緩んできた。
ふと、全ての悩み事を忘れられたらどんなに楽だろうか、とシャロスは思った。
彼は小さい頃から立派な王様になることだけを考え、今までの人生を過ごしてきた。
その間、彼は趣味といえる趣味は無く、享楽を追求したことも無かった。
王宮で権利闘争を繰り返す日々に、彼は一度も心の防壁をはずすことが無い。
それだけに、今日のように心から何かを興じることは、彼にとって新鮮な経験であった。
「失礼します」
エナは小声で言うと、シャロスの体を優しく仰向けにさせた。
彼女の行き届いた気遣いは、シャロスの心を満足してくる。
宮殿生活という異常な環境下で、シャロスは平常の少年とは異なる思春期を過ごしてきた。
男女の営みを知識として知っていたが、実際の誰かを愛意を抱く体験は無かった。
そのため、目の前にいるエナの小綺麗な顔立ちは、彼に恋意を催す魅力的なものであった。
彼女が自分に尽くしている姿を見ると、脳内では今まで感じたことも無い甘い幸福感が充満する。
そう思うと、シャロスの下半身は突然せつなくなった。
数日前エナが自分に施した淫らな行為を思い返すと、いやしい煩悩が再び胸を焦がした。
股間の一物も今までの鎮まりをはねかえし、肌着の下から段々と突きあがってきた。
(あっ、だめ……!)
シャロスは歯を食いしばって、懸命に欲望を抑えようとした。
しかし、心の中を抑えれば抑えるほど、性への意識が昂ぶってしまう。
さきほど目に焼き付けたリテイアの裸姿が鮮明と浮び、シャロスの抵抗を弱める。
「殿下、いかがなさいました?温度が熱すぎたかしら?」
シャロスは声の方に振り向くと、リテイアは足を組みながら嫣然と微笑みかけてくれた。
マナは彼女の足元でしゃがみ、足の爪を丹念に磨いていた。
「い、いいえ……」
シャロスは曖昧な返事をしながら、リテイアの体を見つめ、ごくりと唾を飲んだ。
蒸気や汗がしみ込んだ薄着は、半透明な膜となって彼女の体にぴったり貼り付く。
そのため、体のラインはおろか、その下にある肉体まで見えてしまう。
服の吸いつき具合によって見える面積が違ってくるが、
その不規則な見せ方はかえってエロティックなものだった。
彼女が両足を重ねて組んで座っているため、裾の下から真っ白な太ももがそのまま露出している。
胸部の布は大きく押し上げられ、覆い隠しきれない谷間がシャロスの脳内を占領する。
先端の突起はそのまま服を突き、うっすらと乳輪が見える。
いけないことだと知っていても、シャロスは淫らな欲望を抑え切れず、いつまでも彼女の体をながめた。
自分の体の表面の粉末はほとんど汗に溶け、ねっとりとして液となって肉体を摩擦する。
シャロスは高ぶる心を静めるため、意を決して首を曲げようとしたが、
その直前リテイアの秋波のような瞳に見つめられると、まるで意識を吸い取られたように動けなくなった。
その魂を抜かれたような様子を見て、リテイアは妖艶な笑みを作る。
シャロスは彼女の一挙一動に反応して、心拍数が急激に変化した。
そうしているうちに、彼の頭の中は、リテイアの事以外なにも考えられなくなった。
「マナ、エナ、もう下がってよいぞ」
「はい」
「はい」
二人はまったく同じ角度で会釈すると、部屋の扉から出て行った。
生温い蒸気のこもった部屋は、微妙な雰囲気に変化した。
聡明なシャロスには、これは相手のたくらみであることにうすうす気付いていた。
しかし知ったところで、彼にはもはやリテイアの魅力を跳ね返すほどの自制力を持っていなかった。
「どうしたの、シャロス」
「……!」
リテイアの慈しむ声で名前を呼ばれると、彼女と過ごした淫らな記憶が無理やり引っ張り出された。
それはシャロスにとって、快楽のトラウマでもあった。
「ねぇシャロス、もう誰もいなくなったわ。わらわのとなりに来ないの?」
「っ……」
リテイアの甘い誘いは、シャロスの脳内に激しい闘争を起こした。
敵の立場にある彼女の命令を従うのは、とてつもなく屈辱的なことである。
その一方で、リテイアのみずみずしい肉体は悪魔のような香りを放ち、シャロスの心を鷲掴みにする。
リテイアは足を組んだまま、誘惑の微笑を向けた。
その耐え難い魅力に、シャロスはついに心が折れ、リテイアの寝台へ歩き出した。
「ふふふ、そうよ。わらわの言うことを聞いていればいいわ……」
リテイアはシャロスの体を自分の方へ招き寄せた。
朦朧となった意識で彼女のとなりに座ると、
服越しに柔らかい乳房がシャロスの体と接触し、彼の神経を鈍らせた。
また彼女に負けてしまった悔しい気持ちと、女の肉体を感じる良い気持ちが混ざり合って、シャロスの精神
をせめる。
「皇后様……」
「はい、もう一回。二人きりの時、わらわのことをどう呼ぶべきかしら?」
「……お、お母さん……」
シャロスは悔しい気持ちでいながら、その言葉を吐き出してしまった。
一度崩れた心の防壁は、もはやふせぐことはできない。
「うん、これでもう完璧に覚えたわね。ふふ、良い子にはご褒美をあげなくちゃ」
リテイアはそう言うと、シャロスを抱きしめた。
「あっ?!」
突如な出来事に、シャロスは抵抗することさえ忘れ、リテイアの胸の中に顔を埋めた。
最初は脱出しようと考えもしたが、やがてリテイアの胸に染み付いた官能的な匂いに魅了されていった。
女性に抱きしめられる安心感や欲情が入り混じって、シャロスを少しずつ溶解していく。
リテイアは彼の耳側に唇をそっと当てて、小声で囁いた。
「シャロス、今からわらわだけ考えて。それ以外の事、みーんな忘れなさい。
……うふふっ、あそこがビンビンになってるわね。
さっきから私の体をじろじろ見てて。そんなに良かったのかしら?」
「そ、それは……」
シャロスは悪いことをした子供のように、口をどもらせた。
リテイアは彼の肉棒の先端に人差し指を当て、服越しに滑らせる。
「っああ!」
「あら、もう我慢できないぐらい敏感になってるじゃない。
本当、いやらしい子だね。皇后であるわらわに欲情するなんて……」
「うっ……」
「でも、心配しないで。シャロスは男の子だから、女の体を見て欲情するのは、当たり前なことなのよ。
これからも、わらわの体を見ただけで、すぐにあそこを勃起させられるようにしなさい。いいわね?」
リテイアは目を細め、シャロスの亀頭の裏筋をクリッと押し捻った。
「あぁん!」
シャロスは甲高い声をあげ、無防備になった脳はリテイアの言葉を刷り込まれる。
「ふふふ……シャロスは、本当に女の子みたいだわ。
綺麗な顔に、輝かしいブロンド。それに、肌がこんなにすべすべしているなんて」
「あっ……」
リテイアはシャロスの服の中に手を入れると、彼の汗に濡れていた体を触れた。
肋骨に沿って下腹部を掠め、そして細長い指で鎖骨や首筋に撫でる。
それはそれで気持ちいいが、同時に自分がペットのように扱われたような気がして、悔しい気もした。
やがて、シャロスは麻酔を注入されたかのように、リテイアの体に寄り添って動けなくなった。
まわりは生暖かい水蒸気が充満し、まるで雲の中に漂うような気分になる。
気持ち良さの頂点に辿りつこうとした時、リテイアは突然両手を収めた。
「はぁ、もし王子は本当に女の子だったら、
わらわがもっといろんな事をしてあげられたのに。少し残念ですわ」
「あ、ああっ……」
シャロスは物足りない気持ちを抑えきれず、小声を漏らしてしまった。
残されたムラムラ感に、シャロスは歯痒さを感じずにいられなかった。
彼は潤いだ目でリテイアを見上げると、彼女はくすりと微笑んだ。
「良かったわ。わらわは最近、てっきりシャロスに嫌われたと思ったわ」
「どうして……?」
「だって、最近はまたわらわをいやがる顔を向けてきたじゃない。
この前二人きりで会ったときあんな仲良かったのに……わらわは、とても悲しかったわ」
「そ、そんなことは……」
「あ・る・よ。ついさっきだって、わらわから逃げようとしたじゃない」
リテイアのやや拗ねた態度に、シャロスは完全に翻弄されてしまった。
彼には一国の行方を英断する力があっても、女性の甘い言葉を対する免疫力が無かった。
相手が自分を誘惑していると分かっていても、彼は無意識のうちにリテイアの機嫌を取り直すように心が動
いた。
「い、いいえ、あの時はただ疲れただけで……」
「ふふっ、本当かしらね。もしそうであるのなら、そうね……ここでわらわに口付けをしなさい。
そうすれば、その言い訳を信じてあげてもいいわよ」
「えっ?」
シャロスは心をドクンと躍らせ、リテイアの口を覗いた。
やや開いた唇は湿気を帯びて潤い、悩ましい息を吐いていた。
「どうしたの。それともやはり、わらわを誤魔化しているのかしら」
リテイアは挑発的な目でシャロスを見つめた。
それはまるで獲物を見下ろすような、雌豹の睨みであった。
「いいえ、私はそんなつもりはありません」
「じゃあ、してくださるのね」
そう言うと、リテイアは静かに目を閉じた。
彼女の無防備な構えに、シャロスの理性が飛び弾けた。
シャロスは震え気味になりながら、リテイアの肩をつかみ、彼女の魅惑な唇に口を重ねた。
次の瞬間、口の表面に甘い感触が広がる。
彼がしばらく浸っていると、やがてリテイアの方から唇を押し開け、シャロスの口中に舌を忍び込ませる。
彼女はまるで水蛇のように軽快に動き、シャロスの舌を絡めとる。
そして彼の口中で舌を吸い付き、思う存分に蹂躙する。
彼女の熟練したテクニックに、シャロスはただ相手の思うがままにされるしかなかった。
全身の血流が早まり、股間の一物はビンビンにいきりたつ。
ようやくリテイアが離れた頃、シャロスは虚ろな目で荒れる呼吸を繰り返した。
口の中では、女性の甘いエキスが残る。
彼が恍惚な表情を浮かべたのを見て、リテイアは笑みを浮かべた。
「わらわとのキス、そんなに気持ちよかったかしら?」
「う、うん……」
「ふふふ、素直で良い子だわ。……はぁ、少し熱くてなってきたわね」
リテイアは額の汗を拭き取ると、自分の肌着に手をかけ、首下の部分を左右へ緩めた。
彼女の白い両肩は露出し、胸の谷間もほとんどあらわとなった。
乳首の部分だけギリギリ見えないが、それがまた男の視線を絶妙に惹きつける。
真珠のような水玉は彼女のうなじから乳房の上部に垂れ落ち、そして谷間の中央を経て滑り落ちる。
そのいやらしい様子に、シャロスは喉奥から唸り声を上げた。
目線が自分の胸に釘付けとなった事を気付くと、リテイアは悪魔のような笑みを浮かべる。
「ねぇ、シャロス王子……私の胸、舐めてみる?」
「ええ?!」
唐突な発言に、シャロスは一瞬戸惑った。
しかしその言葉の淫靡な響きを汲み取ると、彼の心の奥底から限りない欲望が盛り上がる。
「ふふふ……見ているだけじゃ、物足りないでしょ?」
シャロスの口内はカラカラに渇いた。
リテイアの乳房は室内の光に反射して、魅惑な輝きを照らす。
プライドの高い彼にとって、相手の言いなりになるのは屈辱的なことである。
しかし、今はそんなプライドよりも、劣情の方が確実に上回っていた。
「ほら、シャロス。遠慮なんてしないで。自分の欲望のままに……していいんだよ」
リテイアの悪魔の囁きは、シャロスの葛藤を徐々に溶解していく。
彼は心臓をドキドキさせながら、やがて皇后の胸に口を近づき、舌を出して乳房の上に這わせた。
充分に濡れていた乳房の表面は塩分を含み、味わいのあるものだった。
シャロスは自然と舌を谷間に滑らせ、そして乳首に吸い付いた。
「はぅっ……あぁん!」
リテイアは頬をやや赤く染め、くぐもった喘ぎ声を漏らした。
その仕草は、シャロスの欲念に油を注いだ。
彼はリテイアを寝台の上に押し倒し、血走った目でリテイアを見下ろす。
自分の股下で、リテイアは弱々しく横たわる。
彼女の濡れた髪は四方へ拡散し、乱れた息をしていた。
ピンク色の唇が呼吸するたびに、豊満な胸はリズミカルに上下し、シャロスの獣欲をそそる。
肌着の前方の開いた部分から白い肌が見え隠れし、男なら誰でも理性を失わせる魔の魅力を放つ。
シャロスの股間の一物はビクン、ビクンと脈打つ。
リテイアの半開きの目は拒んでいるようにも、誘うっているようにも見える。
その火照った顔を見つめると、シャロスは我慢できるはずがなかった。
彼はリテイアのうなじに唇をそえ、懸命に舐めまわす。
両手は彼女の柔らかい乳房を掴み、本能が赴くままに揉んだ。
「はぁん、ああっ……!」
リテイアは放蕩な呻き声を上げ、シャロスの劣情を確実に煽る。
彼はリテイアの腋や、おへそに舌先を立てて、ぴちゃぴちゃと音を立てて吸い付く。
そしておへそより下へ進むとき、その邪魔な腰帯をほどいた。
次の瞬間、シャロスの目の前に女性の下半身が晒された。
つややかな茂みと未知なる場所に、シャロスは思わずくい込むように見入った。
自分の股間は今まで無いぐらいにギンギンと疼いた。
「王子様、それ以上は……我々は最後の一線だけは、越えてはならない身分だわ」
「……!」
リテイアの言葉はシャロスの脳天に直撃した。
彼のどす黒い欲情にまみれた心に、かすかな倫理感がよみがえる。
(そうだ、彼女は名目上でも、父上の妻である。それに、父上が亡くなられたばかりというのに……)
心の中では分かっていても、目線はついついリテイアの淫裂に移る。
滾っていた欲望の中で、残りわずかな理性はギリギリのラインでさまよい、シャロスの劣情を抑えた。
彼が必死に自制する様子を見て、リテイアは心の中で嘲笑した。
「残念ですわ。わらわは普通の女だったら、王子様に尽くせたのに……
シャロス王子も年頃の男の子だもん、女の体がほしくてたまらないよね。
ふふふ、今日だけ、特別に気持ちいいことをしてあげますわ」
リテイアは潤いだ瞳でシャロスを見つめ、彼の両手を握った。
そして腰を浮かせて、陰唇の割れ目を彼の一物の上に乗せた。
「中には入れられないけど、これで気持ちよくさせてあげるわ」
そう言いながら、彼女は腰を前後に揺らして、淫裂でシャロスの肉棒をしごいた。
「あああぁっ!」
ビンビンになった肉棒の上に、リテイアの濡れきった秘所が滑る。
いやらしい愛液がふんだんに塗りたくられ、シャロスの触感を刺激する。
皇后と股間を擦り合わせるこの行為は、淫猥で背徳な快楽をもたらした。
それは、シャロスの最後の理性を摘み取ったことにほかならなかった。
リテイアの腰の動きとともに、彼の瞳から理性の光が消えていく。
「ねぇ、シャロス、気持ちいい?……ひゃっ!」
突然、シャロスはリテイアの腰を掴んだ。
それから、彼女の淫らな割れ目に、本能のように自分の一物を入れた。
「はあぁん……うっ、あぁん!」
リテイアは悩ましい喘ぎ声を吐いた。
シャロスは獣のように瞳孔を広がせ、原始的な欲望に駆られるまま動いた。
淫らな襞の合間に、硬くなった肉棒が突き込んでいく。
先端の先走り汁とリテイアの淫液が混ざり合って、彼と彼女の間を濡れ合せる。
初めて味わう女性の中に、シャロスは雄叫びを上げた。
窄めた小さな穴の入り口を、彼の最も敏感部分である亀頭が押し広げる。
カリが陰唇を捻りこむと、肉棒がずぶずぶと彼女の中へ入っていく。
途端、相手に包み込まれた感触が股間から拡散する。
肉棒を覆う蜜壷は、まるで何十本ものミミズが織り交ぜたように蠢く。
淫液が溢れる穴の中で、肉棒と膣の襞はよく擦れ合い、シャロスの一物を絶えずしごいた。
そこは一度飲み込んだら、全て搾り取るまで離さないような、淫魔のような膣であった。
「はぁう……ああぁん!」
リテイアがシャロスを掴む手に力が入ると、彼女のあそこも追随して、ねっとりと彼の根元から締め付けた
。
「ぐっ……がぁああ!」
シャロスは呻き声をあげながらも、懸命に腰を抽送しつづけた。
初めて感じる異性の中は、天にも昇るような絶妙な境地であった。
「はぁん、ぐっ……ああん、ああんっ!」
リテイアは喘ぎ声をあげて、淫らな表情を浮かべてシャロスを見上げた。
胸がぷるんと揺れるたびに、純潔な水玉が弾き飛ぶ。
もやもやした視界の中、彼女のしなやかな肢体はシャロスをさらに興奮させる。
シャロスはただリテイアの姿に見惚れたまま、自制が効かなくなった腰を突きまくった。
リテイアの中では、膣の筋道が数段に分かれて、
シャロスが腰を上下すると共に、肉棒への刺激に強弱をつける。
無数のひだひだは時には彼に密着し、時には彼から離れ、緩急を分けて空間をすぼめる。
その微妙な力加減に、シャロスの欲望は徐々に拡大されていく。
初めて性行為を行うシャロスには、もちろんそれを耐えられるはずが無かった。
「はぁ、気持ちいい……体が止まらないよ!」
「あぁん、はぁんっ!ああ……王子様、だめ……そんな力いっぱい突かれた、おかしくなっちゃう……!」
リテイアが快楽をこらえるような表情は、シャロスを阻止するどころか、
彼をますます欲望の虜へ変化させた。
妖艶な皇后を好きのように蹂躙できる征服感や、自分の股下で淫らに乱れる光景は、
どんな媚薬よりもシャロスを興奮させた。
数分もしないうちに、シャロスの体に溜まっていた熱いたぎりが股間の根元に集まっていく。
「はあっ、もうだめ……出る……精液が出るぅ――!」
「はぁん……ああぁぁぁ!」
シャロスは体を前屈みにし、食いしばった口からよだれが零れ落ちた。
最後は肉棒全体を強く締め付けられると、熱い白液がリテイアの中でほとばしった。
その瞬間、シャロスは天にも昇ったような気持ちになった。
頭の中から何も消え、ただ欲望を放射する快感だけ彼をとらえる。
それは今まで手でしごかれたよりも、はるかに気持ちいい体験であった。
シャロスは足の爪先まで力を込め、精液を全て吐き出すまで腰を突き上げた。
そしてしばらく痙攣した後、脱力した体をリテイアの横に倒させた。
おびただしい量の白液とともに、醜い肉棒が吐き出された。
彼女の淫裂はビクビクと震え、シャロスの精液を溢れさせた。
「はぁ……はぁ……」
シャロスは虚ろな目で天井を見つめ、絶頂を迎えた後の余韻に浸った。
心頭はようやく明るみを取り戻し、さきほどの快楽に溺れる自分を思い返しながら、段々と自己嫌悪に陥っ
た。
「はぁ……シャロス、わらわの中にだしてはいけないと、あれほど言ったのに」
「……ご、ごめんなさい……」
「このことが外に噂されたら、どうなると思う?母と子が交えたことは、国中に大きく噂されてしまうのよ
。
そうなったら、王室の威信もガタ落ちになってしまうわ」
「全て私が、悪かったです……」
シャロスの心は悔恨の念に満ちた。
欲望が全て消え去った今、自分がどれだけの愚行をしてきたか、嫌というほど分かってしまう。
疲れきった体だけに、その衝撃は重かった。
「でも、安心しなさい」
リテイアはシャロスを胸でそっと抱きしめ、
「今日のこと、わらわが全部内緒にしてあげるわ」
「お母さん……?」
「いいかしら?これはシャロスとわらわの二人だけの秘密。誰にも教えてはなりませぬ。
あなたにとってどんなに身近な人でも、どんなに信頼できる人でも。できるわね、シャロス?」
「は、はい!」
「ふふふ、いい子だわ……もしそれを守れた、今度はまた、気持ちいいことをしてあげてもいいわよ」
「お、お母さん……」
リテイアの柔らかい胸の中で、シャロスの重いまぶたは徐々に垂れ下がった。
心身とも疲労に満ちた彼は、リテイアから得られる安心感を無条件に受け入れ、そして安らかな眠りに陥っ
た。
「うふふ、今はゆっくり休んでね……これからはいずれ、わらわに服従する人形になってもらうから」
自分のふところの中で軽い寝息を立てる美少年を見て、リテイアは悪魔のような笑みを浮かべた。
それから一日後。
シャロスは今日も領内各地からの報告書に目を通していたが、
いつもとは違い、意識はなかなか集中しなかった。
「……ああぁぁぁ!」
彼は報告書を机の上に叩きつけた。
インクスタンドがその機にゆれ倒れ、机の上を黒い液体で汚す。
今日ほど不機嫌な日はなかった。
その原因を、シャロス自身もよく分かっていた。
目を閉じればリテイアの魅惑な微笑みが浮かび、耳をすませば淫らな声が聞こえるような気がする。
朝目覚めたとき、彼はたまらずオナニーをして自分を静めようとした。
しかし、一度リテイアの味を覚えてしまった体は、満足にイクことがなかなかできなくなってしまった。
女性の性器に挿入する幻想は、絶えず彼の思考を煩わせた。
「殿下、いかがなされましたか」
物音を聞きつけたレイラが現れた。
「何もない、大丈夫だ」
「しかし、さきほどは……」
「何もないと言った!出て行け……っ!」
「……はっ……」
これほど怒鳴られた経験は今まで無かったため、レイラは少し戸惑った。
彼女は伏せた顔を少しあげると、ふとシャロスの異様なめつきに気付いた。
その視線は、まるで自分が身に着けている制服を見貫くかのようの鋭かった。
そして、何か危険な感情がこもっているようにも感じた。
レイラはなぜかは分からないが、顔を赤らめてしまった。
「あ、あの……王子様?」
「うっ、ああ。すまない、レイラ。ちょっと疲れただけだから、心配はいらない。
お前に向かって大声をあげて、すまない」
「とんでもありません。殿下、どうか御体に気をつけてください。
もしよろしかったら、私が御医を呼びましょうか」
「いいえ、いいのだ。少し休めばいいことだ。お前はもう下がってよいぞ……今は一人にしてくれ」
「はっ」
レイラはそれ以上の進言をせず、シャロスの命令に従って部屋から出た。
彼女と入れ替わるように、メイド服を着たエナが現れた。
「王子様、一息休まれてはいかがでしょうか」
エナは香ばしい紅茶をシャロスの側に置くと、机上にこぼれたインクを片付けた。
「あ、ああ……」
シャロスはエナの白いうなじを見ながら、レイラの肢体を思い返した。
(くっ……私はいったい何を考えているんだ!)
レイラは長年シャロスに仕えていたが、シャロスにとってレイラは姉にも似たような人物で、
一度も愛欲を思い浮かべたことが無かった。
だがリテイアと性交して女性の体を知った今では、
シャロスはレイラの体が気になって気になって仕方が無かった。
彼女の軽鎧の下に、魅力的な乳房やいやらしい性器が隠されていることを思うと、
どす黒い邪念がシャロスの心を充満する。
そして今も、目の前にいるメイドの美少女を欲望に満ちた目で眺めていた。
エナは無表情ながら、どんな命令にも逆らわないほど従順さを持っていた。
もしここで自分が強制すれば彼女ならきっと自ら体を晒し出すだろう。
その可憐な裸姿を想像すると、シャロスの股間は疼いた。
「王子様、僭越ながら申し上げますが、私には王子様が欲求不満に陥っているように見えますわ」
「ふん、そんなことあるか!」
シャロスは無理やり自分の顔を冷やせた。
しかし、その動きは数日前と比べると、随分と余裕の無いものになった。
「でも、王子様の御体の方は、そうでないようですが」
「くっ……」
「どうか、私に慰めさせてください」
「……ふん、好きにしろ!」
シャロスは溜まらず強がりのセリフを吐き捨てるが、
エナはまったく意に介せず、淡々と彼のズボンを脱がせた。
案の定大きく勃起した一物の先端から、先走り汁が溢れていた。
「では、失礼させていただきます」
エナは可愛らしい口をあけると、その怒張した一物を含んだ。
生暖かい口腔の感触は、すぐにシャロスの硬い心を溶かした。
彼は苦悶に満ちた表情を浮かべ、腰を浮かせた。
エナの慣れた舌の動きは、シャロスのウィークポイントを的確に暴き、
彼の意志を脆弱なものへと変貌させる。
リテイアとセックスした体験がさらに拍車をかけて、彼を絶頂へと導く。
シャロスは一際大きい呻き声上げると、エナの口の中でドロドロの精液をこぼした。
エナが淡々と自分の精液を飲み干した光景を見て、シャロスの頭の中に獣のような感情が蘇る。
彼は唇をかみしめた後、ぼそっとと呟いた。
「……エナ」
「はい」
「服を脱げ」
「えっ……」
エナが無表情のまま頬を少し赤らめた。
「……分かりました」
しかし、エナはシャロスの命令に抵抗しなかった。
彼女はおもむろに立ち上がり、襟のボタンをはずし、メイド服を脱ぎ去った。
ほっそりとした肩口や胴体は、素肌のままであらわとなった。
シャロスは両目を光らせて、彼女の手つきを追った。
エナの顔色は徐々に赤く染まったが、しかし手の動きが止まることはなかった。
彼女はスカーカを脱ぎ、さらにブラジャーをはずした。
流れるようなロングヘアが彼女の背後になびく。
そしてついに、彼女は白のショーツを膝まで下ろし、それを足に通した。
頭につけたフリル付きカチューシャと、黒のニーソックスのみを残し、
彼女の少女らしい裸は全てシャロスの前に晒された。
シャロスは瞳に欲望の火をともらせ、彼女の体を嘗め回すように眺めた。
その突き刺さるような視線を感じると、エナの顔はますます赤くなり、目を泳がせた。
普段の彼女が絶対に見せないたじろぎは、シャロスの嗜虐心を大きく煽った。
彼は乱暴にエナの細腕をつかむと、奥の寝室へ向かった。
「あっ!」
ベッドに身を投げられると、エナは小さな悲鳴を上げた。
彼女は可憐な小動物のように瞳を潤わせ、両足をうちまたに曲げて、さりげなく太ももの付け根を隠した。
メイドの黒ニーソックスに包まれた彼女の太ももは、シャロスの心を焼き焦がす。
彼は外に聞こえないように寝室の扉を閉め、エナの上にまたがった。
それから彼女の形の良い胸に舌を這わせ、もう片方の乳房を手でまさぐった。
「ああっ!」
エナはくぐもったような小さな声を上げ、耐え切れないようで体を蠢かせた。
その可愛らしい仕草を見ると、シャロスはたまらず大きく膨張したチンポを握り、
それをエナの中に挿入した。
「ああっ、あああぁぁぁぁ!」
エナはひときわ大きい悲鳴を上げた。
彼女の蜜壷は、リテイアのものより窮屈であった。
しかし欲情に満ちたシャロスは、それを考慮する余裕などなかった。
彼は硬くなった一物でエナの中を少しずつえぐると、やがて何かを突き抜けたように感じた。
次の瞬間、エナの秘所との結合部から、処女の血が溢れ出た。
それと同時に、彼女の両目から清らかな涙が溢れ出た。
「エナ……?これは……」
シャロスは思わず動きを止めた。
しかし、エナはすぐさま彼の体にしがみつき、乱れるように話した。
「はぁん、王子様……お願い、止めないで下さい……このままエナを、もっと痛めつけてください!」
彼女がシャロスに密着した勢いで、シャロスの一物はさらに深いところまで貫いた。
「ぐっ……ああぁっ!」
すぼまった襞がより強く擦り合うと、シャロスの戸惑いは欲情によって上書きされた。
エナの恥じらう顔に涙の粒が滑り落ちる。
その痛みをこらえる表情は、シャロスの陵辱心をかきたてる。
彼女のいつもとのギャップは、これ以上無い可愛いものであった。
シャロスは渾身の力で腰を振りおろし、鉄のように硬くなった一物を激しく上下に運動させた。
「あぁっ、うっ……ぐぅぅ!」
エナはベッドのシーツを強く掴み、可愛らしい顔立ちに苦悶の表情が満ちた。
肉棒が彼女の入り口から一番奥まで貫くたびに、エナは口を大きく開き、
我慢しているような喘ぎ声を小刻みに吐き出す。
そして激しい痛みをやり過ごすためのように、足の裏でベッドの上を何度もさする。
シャロスは荒々しい息になって、腰の動きを徐々に早めた。
今の彼には、もはや途中で止めることなどできなくなった。
それを察したのか、エナは潤いだ瞳でシャロスを見上げ、
「……シャ、シャロス様……どうか、エナの中に……熱いザーメンを一杯注いでください!」
彼女の熱っぽい口調は、シャロスの頭中のトリガーをはずした。
今まで溜まってきた欲情は一気に肉棒に流れ込み、彼のあそこをビクビク躍動させた。
「エナ……!」
「シャロスさまっ!」
エナはシャロスが出す直前に、腰を迎合させた。
そのはずみに、シャロスの亀頭は柔らかい子宮膜衝突した。
「うわああぁぁぁ――!」
シャロスの一物がドクドク震えると、熱くたぎった精液が彼女の中に注がれた。
「はぁああっ……」
エナは全身をわななかせ、体をえびの様に反らせた。
秘所の結合部から、精液と血が混ざり合ったピンク色の体液が溢れ出た。
欲望が萎縮していくと同時に、シャロスの体から力が抜け出た。
朦朧となった意識のまま、エナのそばに横たわり、彼女の胸の起伏を眺めながら息を整えた。
熱が冷えていくと、悔恨の念が徐々に心情を曇らせた。
(また、こんなことをしてしまった……)
ついさっきまでいきり立っていた自分の性器は、みっともなく垂れ下がっていた。
事後の余韻を味わいながらも、シャロスはこの淫蕩な行いに対し複雑な思いを抱いた。
(これが、セックスの快感なのか。今までこの行為を憎んできたというのに……)
隣のエナはおもむろにベッドから立ち上がり、乱れた髪を整えた。
その顔から熱が引き、いつもの無表情になった。
彼女は秘所の狼藉をハンカチでぬぐと、一言も発さずにメイド服を着付けた。
そして、部屋外からお湯とタオルを持ち込み、シャロスの体をふきとる。
暖かいタオルの感触が、シャロスの陰茎を包み込む。
彼は顔を真っ赤にさせ、小声でつぶやいた。
「エナ、その……ごめん、私が強引に……」
「いいえ、王子様は何も悪くなんかありません。私の体はもう王子様のものですから、
どうか好きにお使いになってください。……あの、大変……気持ち良い痛みでした」
エナは最後だけ視線をそらし、ほのかに顔を赤らめた。
彼女の従順な仕草を見ると、シャロスの欲望は一段と強くなった。
ついさっき得られた快感を思い返すと、彼の一物はまたもや膨張し始めた。
その時ふと、心の中でリテイアの魅惑な笑顔が思い浮かんできた。
(皇后だって言っていた……私達身分の高い人を満足させられることが、彼らの至高の幸福だって
……エナもそれでいいというのなら、私は何も負い目を感じる事は無いだろう……)
シャロスは発情した獣のように、目をギラギラ輝かせた。
その瞳には、早くもエナの艶かしい体しか映っていなかった。
□
王子の寝室から遠く離れたところ、暗い部屋の中で居座るリテイアの姿がいた。
彼女は豪奢な貴人服を着て、手に持っているグラスに唇をそっとつけ、中にあるワインを口に注いだ。
顔をグラスから離れると、そこに彼女の艶かしい口紅の跡が残った。
その近くで、銀のトレイを持ったマナの姿がいた。
彼女はリテイアの機嫌を取るかのように、笑みを浮かべていた。
「これで王子様は、リテイア様のいいなりになったのも同然ですわね」
「ふふふ……これでシャロス王子は、女を見ただけで興奮するケダモノとなった。
セックスの快楽を知った彼には、もはや逃れることは無いでしょう」
「普通の男でも、一度リテイア様と交われば虜になっちゃうですもの。まして、王子みたいな童貞を捧げた
人なんて」
「そうだね。彼にとってわらわとのセックスは、これから一生、記憶の深いところまで刻まれたことでしょ
う。
そして彼がセックスを重ねていけばいくほど、女色に溺れていくわ」
「あんな賢そうな王子が、エロエロのスケベ男になっちゃうと思うと、いろいろ楽しみですわ」
「ええ。いずれ国や民なんか、どうでもよくなるような王様に成長させるわ。
それまでには、エナにがんばってもらわなくちゃ」
リテイアがそこまで話すと、マナは頬をやや不満げに膨らませた。
「リテイア様、エナばっかり奉仕させてずるいですわ。マナも、王子様の側にいたいです!」
「あらあら、せっかちな子ね。……ふふふ、いいわよ。そろそろ王子をもっと堕落してもらう頃だもの。
マナ、今度はあなたの力で、王子を楽しませてね」
「やったー!ありがとうございます、リテイア様!マナ、体を張ってがんばっちゃいます!」
マナは子供のような明るい笑顔を作った。
その無邪気な素振りを眺めながら、リテイアは妖艶な笑みを浮かべた。
リテイアはグラスに注がれたワインを眺めると、近いうちにシャロスが彼女にひざまずく光景が見えてきた
。
第四話
一本の蝋燭が灯り、薄暗い部屋を少しだけ明るくさせる。
壁に映る二つの影法師は、激しく絡め合っていた。
部屋の中で、若い二人の男女の粗い息遣いや喘ぎ声が途切れ途切れになって、
韻事を進める情緒をもたらしてくれる。
灯りの前で、二つの熱っぽい肉体がこすれ合う。
お互いのぬめった性器から、いやらしい水音が聞こえる。
やがて、男女の声は徐々に高まり、動きも一段と速くなった。
くぐもった呻き声が起きると、部屋の中は再び静寂に戻り、
ただ事後の乱れた呼吸音が残るのみとなった。
シャロスはベッドに横たわり、息を大きく吸ったり吐いたりしながら、
ぼんやりと側にいる裸の少女を見つめた。
彼女の白い頬はいまだに火照りが残り、潤んだ瞳の奥で官能を誘う情熱が籠る。
メイドのカチューシャが無い今、美しいロングヘアはさらさらと両肩や美乳にかかっていた。
その柔らかそう皮膚の表面を綺麗な汗のしずくが付着し、
彼女の胸呼吸に合わせて乳から下へ滑り出る。
少女は無表情のまま身を起こし、まだ余韻に浸しているシャロスに寄り添った。
可愛らしい唇が、彼の口に重ねられた。
シャロスの意識は甘ったるい感触にかすみ、自然と相手のぬめりとした舌を口内に受け入れた。
ぴちゃ、ぴちゃという淫靡な音がしばらく続く。
少女が顔をあげると、二人の口の間に銀色の糸が引かれた。
その雰囲気を惜しむように、少女はゆっくりとシャロスのうなじに口をつけ、
彼の喉笛あたりをピンク色の唇でキスしながら愛撫した。
その気持ちよさに、シャロスは思わずまぶたを閉じて呻き声を上げた。
少女は彼の鎖骨に接吻し、胸にある乳首を軽くかじって、そのまま優しくしゃぶる。
魂を削られたような感触に、シャロスは快楽の嘆声を唸った。
艶かしい舌はすべすべしたお腹を舐め過ごし、やがて射精したばかりの一物の先端に吸い付いた。
シャロスのベニスは、彼の精液や彼女の愛液にまみれていた。
少女は顔に降りかかる髪を手で耳の後ろにかきわけ、
シャロスの一物のまわりをじっくりと舐め取り、そして中に残る残滓をすすった。
彼女の念入りな動きが、シャロスの疲れ果てた体を徐々にほぐしていく。
(エナ……)
心の中で相手の名前を呟きながら、疲れ果てたシャロスは昏睡状態に陥った。
エナの処女を貫いてから、速くも十日間が過ぎた。
その間、シャロスはほぼ毎日、彼女と性行為をしてきた。
彼がその気を少し持っただけで、エナはすぐに彼の内心を見通してくれる。
そして彼女の気遣いの良さや従順さもまた、シャロスの欲望を助長してきたのだ。
今のシャロスにとって、彼女はもはや無くてはならない存在となった。
しかし、シャロス自身はこの状況は良くないと知っていた。
結婚相手以外の女性と不純関係を持つことは、倫理の上では不当なことである。
権力者にとって、これぐらいの色事は大したことじゃないかもしれない。
だが立派な王様を志すシャロスにしてみれば、それは彼の信念とぶつかる問題であった。
しかし、だからといって、シャロスは今更エナを手放すことはできなくなった。
血の気が多く、思春期である彼にとって、
一度味わった女の瑞々しい肉体を、そう簡単に頭から消せない。
朝、シャロスはゆっくりと目を覚ますと、側から心地よい声が聞こえてきた。
「王子様、おはようございます」
エナは普段通りのメイド装束で、恭しく寝台の横で侍っていた。
彼女の白玉のような綺麗な顔立ちには、昨晩の乱れた痕跡が一切なく、無表情のままになった。
シャロスはその表情を見る度に、プライドが酷く傷つけられ感じになる。
まるでそれが、「あくまでリテイア様の命令でセックスしているだけ」と物語っているようだった。
彼女の奉仕は全てにおいて、今までどんな侍女よりも優れている。
しかし、その完璧に近いところが、かえってシャロスに歯痒い思いをもたらす。
□
「レイラ隊長、夜の巡回、お疲れ様です」
「ありがとう、ファロア。今日の警備担当は、あなたの班だったわね。
今日も一日、護衛の任務を怠らずがんばってね」
「はい!」
ファロアと呼ばれた先頭の女剣士はきりっと一礼をすると、軽装備をした女性隊員達を率いて、その場から
去った。
彼女達の姿が見えなくなると、レイラは小さくため息をついた。
朝の太陽は空をのぼり、朝風が心地よく宮殿全域を吹き巡る。
しかし、彼女はそれを感じる気持ちが少しも無かった。
最近の巡回で、シャロス王子からは彼の寝室に近づかないよう、きつく命令された。
小さい時から王子の身近に仕えていた身として、どこか寂しく感じる命令であった。
それでも、レイラはシャロスの命令に従った。
(殿下はもうすぐ成人する御身。それに、世間でも言うじゃない。ちょうど今が自立心が強くなる年頃だっ
て)
レイラはそうやって解釈をした。
しかし、女特有の鋭い勘からして、理由はそれだけじゃないのでは、という疑念は確かにあった。
彼女はうすうすといくつか心に残るような形跡を感じたが、それを無理やり心中に押さえ込んだ。
「どうしたんですか、レイラ隊長」
兵舎の食堂まで来ると、一人の小柄な女剣士がレイラに近寄った。
レイラは彼女から水を盛ったコップを受け取り、感謝の言葉を告げる。
「ありがとう、ナリア。昨晩の巡回で夜風を受け過ぎたか、ちょっと頭が痛くてね。
ところで、あそこの集団は何をやっているのか、私に教えてくれないかしら」
レイラは喉を潤わせながら、むこうにあるテーブルで何やら喧騒する一団を見つめた。
十数人もの女性隊員が、一つのテーブルを囲んでいた。
そのテーブルの両側に二人の若い隊員が座り、お互い片方の肘をテーブルにつき、手を握り合っていた。
どうやら、腕相撲を始めようとしている模様だ。
小柄な隊員はニコッと微笑み、
「サネットとフェリッサですよ。どっちのほうが腕力あるか!という話になって、それで腕相撲で勝負しよ
うと……」
「はぁ、相変わらず元気だね」
レイラは苦笑を浮かべた。
女性隊員とはいえ、ここにいるのはみんな情緒が明るい若き兵士達。
娯楽とは無縁な彼女達にとって、こういった勝負事が特に盛り上がるのだ。
「レイラ隊長は、どっちが勝つと思いますか?」
「サネット」
「ええ?どうしてですか?うちの隊の中では、フェリッサが一番剛腕というのは
みんな認めていることじゃないですか」
「なんなら、賭けてみる?もしサネットが勝ったら、今日午後のナリアちゃんの訓練相手、私がやるわ」
「えー、そんな……」
レイラは普段から上官のような威張った態度を取らず、常に隊員のことを考慮する優しい隊長である。
そのうえ剣の腕は確かで容貌も凛々しく、みんなが憧れる人気高い隊長である。
だがその代わりに、訓練時のレイラほど恐ろしいものはない。
彼女に直接指導してもらうことはもちろん有益ではあるが、
自分がヘトヘトになるまでやらされることを考慮すると、小柄の隊員は少しためらった。
ナリアはサネットとフェリッサを見比べながら、意を決して口を開いた。
「分かりました。では、もしフェリッサが勝ったとしたら……」
「ショートケーキをおごってあげるわ」
「本当ですか?」
ナリアは嬉しそうに丸い頬っぺたを抱え、随分前におごってもらった甘い味を想像した。
しかし、彼女はすぐにハッとなり、
「隊長は、どうしてサネットが勝つと思うのですか?
普通に考えたら、フェリッサに決まってるんじゃないですか」
「だからだよ。サネットは負けを承知して意地に走る人じゃないわ。
みんなが認めていることをあえて挑もうというのなら、何か秘策があるに違いないわ」
レイラはコップの中身を飲みほし、
「今回もきっと、サネットからいろいろ挑発して、フェリッサをうまく口車に乗せたであろう」
ナリアは大きな瞳をパチパチさせた。
「驚きましたよ。隊長はまるでさっきからここにいるみたいです。全部、隊長の言ったとおりですわ」
彼女が言っている途中、テーブルの方で勝負が開始したのか、二人の隊員が腕に力を込めはじめた。
数秒もしないうち、赤いハチマキで髪の毛をまとめた少女が優勢に立った。
彼女は相手の腕を反対側へぐいぐいと押してきた。
周囲の隊員達はあるいは応援を、あるいは野次を飛ばして、その場を盛り上げた。
ハチマキの女性は不敵な笑みを浮かべ、言葉を発した。
「ほらどうしたの、サネットさんよ。大口を叩いたわりに、大したことないじゃない」
「ふっ、笑止だわ。これぐらいで勝ってる気分になるなんて……まだまだお子様だね」
ブロンドの少女は腕をガタガタ震わせながらも、気丈な表情を見せていた。
「ふん、強がりやがって。いいわ、一気にかたを付けてやる!」
ハチマキの少女が強気を見せると、腕でいきなり押しかかった。
それを機に、周囲の声援が高潮を迎えた。
「ところで、フェリッサ。ちょっと、尋ねたいことがあるんだけどさ」
「なんだ?」
「あなたは今度、中央軍部の殿方に、ラブレターを出すんだって?」
「ぶはっ!」
フェリッサが大きく動揺している隙に、サネットは彼女の腕を反対側のテーブルにひっくり返した。
「はい、私の勝ちね。約束通り、今度の射的場に行くとき、おごって貰うんだから」
「てーめ、なんて汚い手を使いやがる!っていうか、誰がラブレターを出すんだよ!」
涼しい顔をするサネットに向かって、フェリッサは納得いかない様子で拳を握り締めた。
「私が聞いた話によると、なんでも最近軍部のほうで活躍している青年将校の……
ホーラフさんだっけ?に、手紙を出すだって」
サネットの一言に、周囲の女性隊員たちがざわめいた。
「えー?ホーラフ?」
「あのホーラフだって!」
「だれだれ?その人は」
「知らないの?最近軍部でもっとも注目を集めている三人の若い将校の一人だよ。
なんでも、シャロス王子様から騎士の勲章をもらったんだって」
「そうそう。武勇に長けるホーラフ、知略に長けるエンルード。そして文武両道のドスラット」
「すごーい!シャロス様からじかに認めてもらえるなんて」
「へー、そのホーラフという人に、フェリッサが……」
まわりの反応を見回し、フェリッサは狼狽した。
「ちょ、ちょっと、違うって!あたしはただ、あのホーラフとかいうやつが腕が立つと聞いて、
挑戦状みたいのを出したいなーと思って……っていうか、
あたしの好きなタイプは、どっちかというとエンルードだぞ」
「なるほど、近衛隊一の駻馬と呼ばれるフェリッサは、そういう男がタイプだったのか」
「た、隊長!」
側へ歩み出たレイラに気付き、フェリッサやほかの隊員たちは驚いた。
「ち、違うんです!わ、私はただ……」
「うふふ、いいのよ。宮殿近衛隊だからといって、恋愛を禁止している訳じゃないんだから。
でも、そのホーラフに出す挑戦状というのは、やめたほうがいいわね」
レイラは後輩を諭すような優しい口調で言った。
「はい、すみません……私、そのホーラフという奴がすごく強いて聞いたから、つい熱くなって……」
「まあ、負けず嫌いなのはいいことだ。お互い切磋琢磨して、競い合って。
でも、私が挑戦状を出さないほうがいいと言ったのは、今のフェリッサの実力では、ホーラフ殿に勝つのが
難しいからよ」
「それは、本当ですか?」
フェリッサは大の負けず嫌いであるが、彼女はレイラのことを誰よりも信頼していた。
レイラの否定的な意見を聞くと、フェリッサはがっくりと肩を落とした。
「三ヶ月前、私は用務があってスデラス将軍のもとへ行った時。
偶然そのホーラフ殿とドスラット殿が訓練場で対戦しているのを見たわ」
レイラが静かに語り出すと、隊員達はみんな彼女の言葉に耳を傾けた。
「それで、どっちが勝ったんですか?」
ナリアは横から尋ねると、レイラは首を振った。
「その時は、引き分けだった。彼らはいずれも素晴らしい才能を持った剣士だ。でも、私の観察からすれば
、
ホーラフのほうが一枚上ってところかしら。彼の剣術のセンスは、特に輝いている物がある。
数年経てば、おそらくホーラフは我が国において、誉れの高い剣士となるだろう」
「でも、うちの近衛隊だって負けませんよね?あいつとファロアなら、どっちが上ですか?」
「ホーラフが勝つでしょう」
「えー、そんな……」
隊員の中で、剣術が最も優れるファロアまで負けると聞いて、フェリッサ達は悔しい気持ちをあらわにした
。
女性のみに組成された隊員達は、自然と男勝りの性格を身に付けていたのだ。
「でも、あえてあげるとしたら……そうね、サネットが一番勝つ可能性を持ってるじゃないかしら」
「私ですか?」
サネットはびっくりした表情で自分を指差した。
「ええ。臨機応変に富むサネットなら、もしかしたら運が傾けて、勝てるかもしれないわ」
「やった!ほらほらフェリッサ聞いた?これでもうはっきりしたでしょう。剣の腕前なら、あなたより私の
方が上だわ」
サネットが嬉しそうに飛び上がり、フェリッサの膨れる頬を突いた。
「いいえ、剣の腕前ではありません」
「えっ、どういうことですか?」
「サネットが今みたいな妙策を成功させたら、何かが間違って勝てるかもしれない、ということだ」
「そんな……レイラ隊長、ひどいですよ」
サネットが困った表情になると、フェリッサをはじめほかの隊員達は笑い出した。
レイラのおもしろい語り口は、いつも彼女達を笑顔にしてくれる。
「知ったか、サネット。レイラ隊長はあえて言わなかったけど、
お前が実力で勝てるようにもっと真面目に練習しろ、という教示だぞ」
「フェリッサに言われたくないわ。それに、勝てるのなら、どんな手段を使ったっていいじゃん」
「なまいきな!」
「フェリッサこそ!」
二人が言い争いを始めると、レイラはまたかという苦笑を浮かべた。
サネットは腕を組み、クールな表情を作った。
「ふん、フェリッサはこれだから。まぁ、いつまでも子供のままで、幸せだからいいけど」
「ちょっと、どういう意味なのよ!」
「別に。……ただ仲間として親友として、このままフェリッサが自分を磨かないと、
将来は苦労するんじゃないかなと心配してさ」
「なんだと?」
「いつまでもガキみたいでいると、いい男が好きになってくれないわよ」
「余計なお世話よ。あたしだって、色気を出そうと思えば、できるんだからね!」
「はっはぁーん。その小さな胸を張ったところで、何の説得力も無いんだけどね」
「ううぅー!」
かなり痛いところを突かれたのか、フェリッサは言葉がつまり、頬を膨らませた。
宮殿近衛隊は女性のみで成り立つため、異性と交際するチャンスはなかなかできない。
そのため結婚年齢になると、今までの功労を認められ、
王室が主導して良家の男性と結んで、退役するのが暗黙の慣例となっている。
それは王室近衛隊の特権に近いものである。
とはいえ、全てうまく行く保証は無いので、いつまでもお転婆娘のままでは、お見合い相手すら見つから可
能性も出てしまう。
「それを言うなら、サネットだって……!」
「ふふっ、それはどうかしら」
サネットは得意げに胸をはった。
「私なら、いつも殿方に惚れられるよう、いろいろ気を使っていますもの。
スタイル良し、顔良し、性格もよし。こんないい女は、なかなかいないですわ」
サネットは深窓の令嬢を真似て、手の甲を口元に当てエレガントを装った。
まわりの隊員達はその仕草に笑いながらも、それを認めるしかなかった。
性格良しは別としても、サネットはなかなか見当たらない上質な美女である。
「そんなこと言っちゃって!うちの隊で一番の美人というなら、レイラ隊長でしょう」
「えっ?」
まさか自分が話題になると思わなく、レイラは戸惑った。
「うっ……そ、それは!……確かに……」
「そうですよ、私達の中で一番速く結婚するとしたら、レイラ隊長ですわ」
ナリアが一言に、サネットを含めて隊員達は一斉に頷いた。
「ちょっと、結婚だなんて……私、まだ全然考えたこと無いわ」
「レイラ隊長は、一体どうやってそのようなプロポーションを保っているんですか?」
「私は、そういうのは今まで気にしてないわ」
レイラは照れくさそうに頬をかきながら答えた。
彼女のさりげない一言に、尋ねたサネットはショックを受けてしまう。
「そ、そんな……」
サネットは羨ましそうにレイラの体を見渡した。
「レイラ隊長みたいなお方は、将来きっと素敵な出会いが待ってるのに違いありませんわ」
ナリアは瞳をキラキラさせながら言った。
「ははっ、そんな大層な……」
「そうだね、やっぱりシャロス王子様のような、素敵な男性じゃないと釣り合わないもん」
「こらっ、ナリア!殿下になんという侮辱を」
「いやでも、私もナリアの気持ち分かるわ。
殿下みたいな凛々しくて、立派なお方でないと、レイラ隊長はもったいないですもの」
「うんうん。でも、シャロス様以外で、あれほど素敵な男性はいるかしら」
「もう、あなた達には、付き合え切れないわ。
ほら、昼飯の時間が終わったら、あなた達をきつく訓練してあげるから、覚悟しなさいよ」
「「はーい」」
隊員達は明るく返事し、残りの時間をくつろいだ。
レイラはやれやれといった表情を作るが、心底ではひそかに嬉しい気分が溢れ出た。
だがそれは一体なぜなのかは、レイラには理解できなかった。
□
賢王の再来とも予言されるシャロスは、天成の治世家であった。
利害や問題点を一瞬で判断し、前例に無い手法を大胆に駆使する。
先王の急逝により招いた国はしばらく混乱が続いたが、それも彼の統治によって徐々に落ち着いたのだ。
しかし最近、エナと肉体的関係を持ち始めてから、シャロスは以前ほどの鋭い判断力が発揮できなくなった
。
今日の昼前も、シャロスは今までに無かった焦燥感に責め続けられるのであった。
山のように積もる報告書の側、彼は悶々と座り続ける。
目線はただ報告書の上を走り、内容を短絡的に見通すだけだった。
股の下で一物が衰えることなく張り続け、彼の思考回路を邪魔する。
シャロスは精神を収集するが、淫らな思いは消えるどころか、体中に広まっていく。
エナとの天国をさまようような体験は、いつしか茨のように彼の華奢な心身を巻きつく。
その淫靡な光景を理性が拒んでも、悪魔のような欲望の声が耳元で響く。
ペニスが絶えずドクン、ドクンと脈打ち、シャロスをせめ立てる。
「くっ……」
シャロスはたまらず立ち上がり、外へと出かけた。
宮殿を囲んでいる大きな庭園は、建国以来の長き歴史を渡り、多くの園丁の手によって営んできた。
かなりの広さがあるため、シャロスは目的も無いまま歩いていたら、いつの間にか普段行くことの無い区域
に出た。
「あっ、王子様!」
突然起きた黄色い声に、シャロスは背後を振り返えった。
すると、エナと瓜二つの顔立ちを持つ少女が視界に飛び込んできた。
「やっぱり、王子様だったんですね!」
元気一杯で、屈託の無い笑顔。
エナの双子の姉妹、マナというメイドであった。
「マナ!どうしてここに?」
「遠くから王子様のお姿をお見えになったので、
こっそり後をつけました。それに、ちょうど私もこちらに用がありまして」
「ここは一体?」
「あれ、王子様は知らないで来たのですか?どうりでおかしいと思いましたわ。
王子様のような高貴なお方が、私達のような下人が働く場所に来てくださるなんて」
ふと、マナはずる賢い小猫のよう表情を浮かべ、いきなりシャロスの腕にしがみついた。
シャロスはその不意打ちに避けることができず、マナに抱きつかれてしまった。
服越しに感じる胸の柔らかい感触に、彼の顔はさっと赤めた。
エナとは何度か行為をしてきたが、基本的に彼は女性に対する免疫力が無いのだ。
その初々しいぶりを見て、マナはひそかにほくそ笑んだ。
「マナ……な、何をしている!」
「うふふ。こうしていると、王子様と恋人同士になったような気分になれるの……
ねぇ、王子様は、私のことお嫌いですか?」
マナはシャロスの腕を自分の胸に擦りながら、潤んだ両目で彼を見上げた。
そのまるで小動物のような可愛らしい表情に、シャロスの心が大きく揺らいだ。
普段それと同じ顔つきの冷淡さを見慣れていたせいか、余計に色っぽく感じてしまう。
「こんなところで誰かに見られたら、大変なことになるぞ」
「ふふふ……じゃあ、嫌いじゃないのね」
マナはシャロスの股間に手を伸ばし、その上を軽く撫でた。
たったそれだけの行為で、シャロスの体がビクンと動いた。
彼が顔を真っ赤に染めるのを見ながら、マナはけらけらと笑った。
「王子様のあそこ、ビンビンじゃない。こんなお昼からお盛りになるなんて……エッチなことで、頭いっぱ
いなのね」
「そ、それは……」
マナに痛いところを突かれたシャロスは、思わず顔を俯いた。
「私はこれから用事があるので、ある場所に行かなければなりません。
王子様も、私と一緒に行きませんか?そこなら、誰にも見られませんわ」
マナは挑発的な笑みで、シャロスを見上げた。
その言葉の裏にある淫らな意味が、シャロスの心をくすぐった。
聡明だったはずの意識も朦朧となり、思わず頷いてしまった。
マナはもう一度かわいらしい笑みを浮かべて、彼に体をくっつけたまま歩き出した。
シャロスは自分の優柔不断を責めながらも、腕を引かれるまま進むしかなかった。
しばらくすると、二人は庭園のはずれに位置する古ぼけた楼閣へやって来た。
「ここは、いわゆる倉庫ってところですわ。まあ、王子様には、目にするどころか、聞いたことも無いでし
ょうね」
マナはシャロスの疑問の表情を察すると、解説を加えた。
中へ進むと、そこはシャロスが住む御殿よりずっと簡素なつくりであった。
飾り気のない廊下を通り過ぎながら、所々いろんな備え付けの品物が積まれているのが見える。
両側にいくつもの部屋があるが、中には万年使う機会が無いのか、蜘蛛の巣や塵で汚れた扉もあった。
高級生活に慣れ親しんだシャロスにとって、それはそれで新鮮な光景だった。
横から五つ目の部屋の前へ来ると、マナはその扉をあけ、シャロスを中へ連れ込んだ。
奥のほうには数多くの木箱が積まれ、窓の光を遮っていた。
そこでマナは扉をしめると、薄暗い空間に、ただ二人の男女が残されるのみとなった。
神秘な静寂に包まれる空気の中で、シャロスはわけもわからず心を高鳴らせた。
しばらく目が慣れると、彼は部屋中の様子を観察した。
いくつかのテーブルや椅子が、無造作に並べられている。
横には羊毛で編まれた高級絨毯が、柔らかそうに何枚も重ねられていた。
マナは鼻歌をうたいながら、悠然とした表情で一つの椅子に座った。
しかしシャロスはどうすればいいのかさえ分からず、ただ立ち尽くすしかなかった。
その困惑した立場を解消するために、彼は腹の中で言葉を捜し続けた。
「……ここは、どこなの?」
「宮殿に置かれている物って、いつか壊れるんじゃないですか。そのために、ここで備品を蓄えているんで
すよ」
マナは軽い口調で答えながら、熱そうにメイド服の襟ボタンをはずした。
シャロスは瞬時に顔を赤らめ、彼女から目線をはずした。
そのはにかむ仕草を見て、マナは微笑んだ。
「でも、ここでの取り出し作業は、そんなに頻繁ではないのです。
むしろほかの目的のために、良く使われているのかしら」
「ほかの……目的?」
「はい。逢引き、なんですよ」
「あいびき?」
聞いたことも無いワードに、シャロスは首をかしげる。
その様子を見たマナは、おかしそうに笑い出した。
自分がバカにされたようで、シャロスは憮然とした。
マナはそんな彼の心情を察したのか、すぐに謝った。
「ごめんなさい、今のは私が悪かったですわ」
「ふん、別に……」
シャロスはそう言って顔をそむけるが、突如マナが彼を壁際に押さえ付けた。
「何をするつもりだ」
「もう、そんなに怒らないで、王子様。マナは、王子様に良くしたくて、ここにつれてきたのです。
お詫びと言ってはなんですが、これからは王子様はマナと、逢引きをしてみませんか」
マナは顔に柔和な表情を掲げ、軽やかな声で囁いた。
その女らしい仕草を受けて、シャロスの怒気は一気に和らいだ。
彼女はその華奢な体を軽くシャロスに押し付け、彼の両手首を掴んだ。
不思議な事にシャロスは彼女の無礼を咎める念頭は、なぜか思い立たなかった。
それどころか、体が密着することによって、彼女を可愛いと思う気持ちが段々と大きくなった。
時には悪戯っぽく、時には皮肉っぽく、時には優しく変化する彼女の態度は、まるで掴み所が無かった。
しかし、その変わりやすい性格がまた彼女の魅力であった。
そんな憎めない彼女をいつの間にか好きになった事に、シャロスは気付かなかった。
彼はつとめて不機嫌そうな顔を装った。
「お前はエナと顔はまるっきり同じなのに、中身が全然違うんだな」
「ふふふ、それは当然ですもの。私とエナは物覚えを始めたときから、別々の環境に分けられ、
リテイア様やフシーさんに厳しくしつけを受けました」
「フシーさん?」
「はい、彼女は私達のメイド長で、私達にとってリテイア様の次に偉い人なの。
もっとも、リテイア様に仕えるメイドは、みんな彼女のしつけを受けるけど」
「そうなのか?」
「はい。あの女だけは、私も苦手なのよ。王子様も注意してね。王子様のようなかわいい男の子が彼女の手
に堕ちたら、
どんなふうに調教されることや……あっ、それもそれで見たいですわね」
シャロスはマナの言葉を半信半疑に聞きながら、彼女はその人物が好きじゃないということを理解した。
「皇后は、一体なにを狙っている?」
「なんのことでしょうか?」
「とぼけるな。エナやお前を私に近づかせたのは、何か目的があるだろう」
「そんなの、言いがかりですわ。私はただ、王子様に気持ちよくなってもらいたくて」
「なにを……むぐっ!?」
マナは彼の抵抗しようとする両手を抑え、その口の上に潤んだ唇を重ね合わせた。
シャロスの瞳はぼんやりととろけ始めた。
少女の柔らかい唇は積極的に彼にしゃぶり付き、なめらかな舌を進入させて絡ませる。
それと同時に、彼女はシャロスの股間に膝をあてがった。
「むむっ!」
今まで悶々としてた場所が、それを機に燃え上がった。
マナは彼の首に手を絡ませながら、太ももを使ってゆっくりと両足を開かせる。
たちまちシャロスの体から抵抗しようとする意思が消え、マナに身をゆだねてしまった。
しばらく経った後、マナはようやくシャロスから顔を離した。
シャロスは全身を火照らせ、ぼんやりとした表情でマナを見つめる。
マナは両手で彼の頬を抱き上げ、
「うふふ……王子様って、本当にかわいいわよね。まるで、女の子みたいだわ」
悪巧みの笑みを浮かべると、シャロスの股間を当てる膝に力を入れた。
「ああっ……!」
シャロスは思わず内股になった。
服の上から、マナはちょうどいい力加減で彼のあそこを挑発し、欲望を増大させた。
自分でもあそこが爆発しそうなぐらいに、血液が集中していくのが分かる。
気持ち良さのせいで足に力が入らなくなり、マナに押されるままズルズルと壁を滑って床に倒される。
マナはそのまま上を這い、柔らかい乳房の部分をシャロスの胸にくっつけ、彼の耳元で色っぽく囁いた。
「ねぇ、王子様。聞こえるでしょう?私の心臓が、ドクン、ドクンと鳴ってるの。
王子様とこんな近くにいられるなんて、私すごく緊張してるの」
シャロスは耳元や股間から来る妖しい快感を耐えながら、懸命に理性を取り戻そうとした。
「で、でも……王宮内で、こんなふしだらなことをするなんて……」
「それなら、みんなやってるわよ。言ったでしょ、ここは宮殿の下人達がこっそり会う場所なの。
宮殿内ではいろいろ厳しい規則あるが、ここなら人の目を盗んで、いろいろやらしい事ができるの」
「ど、どうしてお前がそんなことを知ってるの?」
マナは答えないままニコッと微笑み、シャロスの白いうなじに舌を這わせ、優しく舐めた。
湿った舌の滑らかさが一瞬のうちに通り過ぎ、シャロスの思考回路をショートさせた。
その恍惚になりかけた様子を見て、マナは会心の笑みを作った。
彼女はシャロスが見る前で、人差し指と中指をぴったりくっつけて、棒の形を作った。
そして挑発的な目線を送りながら、唾液をふんだんに含んだ口で指をくわえる。
シャロスは目の前の光景を見せ付けられて、胸が大きく揺らいだ。
マナは口をすぼめながら、白くて長い指を舐め続けた。
その先端を舌先でぺろりとくすぐり、その横を角度変えながら濡らし、そして根元まで口内に含ませる。
そしてしばらく唾を溜め込み、それを指の上につーっと垂らして、シャロスの瞳を見つめながら舌で唾液を
舐め取る。
まるで自分のあそこが舐められているようで、シャロスは太ももをうじうじさせた。
彼女の柔らかい胸の鼓動を感じながら、シャロス自身の心も跳ね上がった。
相手の瞳の中に含まれた艶笑のようなものに、シャロスは屈辱のような感情を覚える。
それはまるで、見とれてしまった自分をあざ笑う物のようだった。
万人の上に立つ者として、これほど不甲斐無く思うことは無かった。
マナから目が離せない自分が悔しい。
一人の侍女にいいように扱われるのがもどかしい。
しかし、その悔しさやもどかしさの裏側に、かすかながら快感に近い感情があった。
「ねぇ、王子様は気持ちよくなりたいでしょ?」
「そ、それは……」
「そうだったらそうで、ちゃんと『うん』とか『はい』とか言うのですよ。
それとも、やめちゃってもいいかしら、王子様?」
「う、うん!」
「うふふ、いい子ね。じゃあ、これから私の言うことを良く聞いて。口をあーんっとあけてごらん」
マナは悪戯っぽい笑みを浮かべて言った。
自分とはそう違わない歳なのに、子供扱いされてしまったことが悲しかった。
しかし、それでもマナの言うことに逆らえず、シャロスは口を開いた。
「じゃあ、私のつばが一杯染みこんだ指を味わいなさい」
マナは透明な唾液で濡れた二本の指をシャロスの口内に入れ、彼に口を閉じさせた。
「ううむん!」
「ほら、舌をもっと使って、満遍なく舐めなさい。さっき私がどういう風に舐めたかを、思い出しながら」
マナに言われると、シャロスは仕方なく彼女の指に舌を絡ませた。
ぬるぬるした他人の甘い味が、口内に広がる。
それが目の前にいる悪魔のような美少女の物だと思うと、悔しくも股間の一物が意気地なしにも反応した。
そのささやかな変化を、マナは当然見逃すわけが無かった。
「ふふふ、私の指を舐めながらあそこをギンギンにさせるなんて……
王子様って、ひょっとして変態さんなのかしら?」
マナはほくそ笑みながら、シャロスの口内で指をかき回した。
彼女の指に付着した唾液は舌に擦り付けられ、シャロスの口の中で香ばしい味が広がった。
シャロスは背徳感に責められながらも、犬になった気持ちで彼女の指をしゃぶり続けた。
しばらくすると、マナは指を抜き取り、シャロスの体から離れた。
シャロスは息を荒くしながら見上げると、マナの挑発的な微笑みと、彼女のスカートの中身が見えた。
太ももまで覆うスカートの中に、黒の下着の姿があった。
その黒い下着を、マナはゆったりとした動作で脱いだ。
シャロスは思わず瞳孔を大きく開かせた。
スカートの裾で見え隠れする中、女性の最も神秘な場所が生まれたままの姿を晒す。
形良く整えたアンダーヘアの下に、淫らな割れ目がそこにあった。
シャロスがもっと見たいと思った矢先に、マナは指でショーツをくるくるしながらその場から離れる。
彼女は小悪魔のような愛しい笑みを浮かべ、椅子に座って足を組んだ。
スカートの裾は重ねられた太ももの上でとどまり、彼女のアソコの様子が完全に見えなくなった。
その誘惑的な光景は、シャロスの欲情を大きく焦らした。
彼はその場から立ち上がり、自分の両手をどこに置けばいいのかさえ分からないほど慌てた。
「マ、マナ……」
「王子様は、マナのあそこを、もっと見たい?」
「う、うん……」
「ふふふ、嬉しいわ。でも、私だけアソコが裸で、王子様が服を着ているなんて……
ちょっとずるいと思いませんか?」
「えっ?でも、どうすれば……」
「王子様にも、下の服をぜーんぶ脱いでもらおうか」
シャロスはうろたえた。
自分の部屋でもお風呂場でもない場所で裸になることは、もちろん抵抗がある。
「どうしたの、王子様。ひょっとして恥ずかしいのかしら?大丈夫ですよ。
前にも、王子様は私に裸を見られていたではないですか」
マナの悠然とした態度を見て、シャロスは意を決してズボンを脱ぎ始めた。
躊躇はしたものの、結局下着まで全て脱いだ。
すると、熱くたぎったペニスが天井を向かっていきり立つ。
「やっぱり王子様はあそこを勃起させていましたのね」
マナがシャロスのあそこを見てくすくす笑うと、シャロスは恥ずかしさで胸いっぱいになる。
上半身だけ服を着て、下半身が全裸に。
そして、メイドである少女に見られ、笑われる。
そんな状況に反し、一物が萎えるところが、ますます硬くなっていた。
「じゃあシャロス様、こっちに来て、私の前でしゃがんでごらん」
マナが手招きすると、シャロスは仕方なく彼女の前にやってき、膝を床に突いた。
少女は椅子の上にのぼると、両足を外側に開き、秘所が良く見えるように開かせた。
「ふふふ、どう?これが女のオマンコよ」
マナは腰を柔らかくしなやかせると、シャロスの顔面の前に、彼女の性器が晒しだされた。
今まで何度も性経験してきたが、こんな間近で女性の性器を見るのは初めてだった。
桃色の淫唇は、シャロスのまだ幼さが残る心に淫らな方向へ刺激する。
「ねぇ、私のアソコにもっと顔を近づかせて。それから、大きく息を吸ってごらん。
そう、そうやってスーハーするの。どう、アソコの匂いは?すごくエッチで、いやらしいでしょ」
「う、うん……」
シャロスは茫然とした表情で、こくりと頷いた。
彼は言われるがままに、マナのアソコの前で息を繰り返した。
「うふふ……そうよ。そうやって、私の匂いが、王子様の脳の奥まで染み渡るように。
その匂いを、よく覚えていなさい。これからはこの匂いを嗅いだだけで、あなたは私の言うことをなんでも
聞きたくなるように」
まるで魔法にかかったように、シャロスは目を虚ろにした。
彼の恍惚な表情を見下ろし、マナは会心の笑みをあらわにする。
突然、扉が「ドン、ドン、ドン」と叩かれる音がした。
「……!」
シャロスは咄嗟に我に返り、その場で固まった。
「あ~あ、邪魔が入っちゃったね。王子様、何者かが来たようですわ」
「ど、どうすればいいの?こ、こんなところで見られたら……」
シャロスは顔色を青ざめた。
悪いことをしてしまった彼には、罪悪感のため逃げることしか考えられなかった。
しかしこの部屋は入り口の扉以外、封鎖された窓しかない。
「王子様、あそこの木箱の裏側に隠れてください。後ろは空きペースがありますので、そこでじっとしてい
てください」
「わ、分かった!」
「それと、これもお持ちになって」
マナはシャロスに黒い下着を手渡した。
「な、なぜこれを?」
「あははっ、途中でしたくなったら、それで私の匂いを思い出してね」
扉がもう一度ドンドンドン、と叩かれる。
マナは相変わらず緊張感の無い笑顔を作るが、今のシャロスにはそれを反論する余裕が無かった。
シャロスはショーツを握り、急いで木箱の後ろに駆け込んだ。
そこでしゃがんでから、シャロスはまだ下半身が裸であることに気付いた。
焦燥の表情で頭を出すシャロスに対し、マナは悪巧みの笑みを浮かべて、シャロスの服を反対方向の角へ投
げ込んだ。
(あいつ、わざとやって……!)
シャロスは胸の中で怒りを焼くが、どうすることもできなかった。
マナはスカートを少し整えると、ゆっくりと扉のほうへ近づいた。
そして彼女の次の行動は、シャロスの予想を越えるものとなった。
彼女は、扉の外の人間と同じようなテンポで、扉を三回叩き返したのだ。
かすれるような軋み音とともに、扉がゆっくりと開かれる。
シャロスは自分の心臓が口から飛び出すじゃないかというぐらい緊張した。
彼はただ、マナがうまく外の人間を言いくるめることを祈るほかなかった。
だがマナの行動から、シャロスは何かが変であることに気づいてしまう。
木造の床が軋み、一つの足音が近づいてくる。
シャロスは木箱を背にして座り、背中に冷え汗を流した。
「遅かったじゃない。私、ずっと待ってたんだからね」
マナの駄々をこねる口調は、シャロスを大きく驚かせた。
しかし、もう一つの声に、彼はさらにきょとんとなる。
「……すまない。スデラス将軍の軍議が終わったら、すぐここに向かったつもりだった」
(軍議……?)
聞き覚えのある声と、気になる単語。
危険な状況ではあるが、シャロスの好奇心が大きく膨らんだ。
彼は木箱の隙間に顔を近づけ、部屋の中央を見つめた。
椅子に座るマナの側で、鎧を装備した騎士が立ち尽くしていた。
やや動揺気味の様子ではあったが、女性の目を惹くようなかっこいい顔立ち。
その容貌を記憶の中で探り当てたとき、シャロスは思わず声をあげそうになる。
目の前にいる男こそ、最近期待を集める青年将校、スデラス将軍の麾下であるドスラットその人である。
――中央軍部で突出した才能を持つ三人の若者。
武勇に優れるホーラフ。
知略に優れるエンルード。
そして、武勇や知略の両方に長けるドスラット。
彼ら三人は、老将スデラスにも認められた人材である。
つい先日、騎士の勲章を受けたばかりで、今後の軍界を担う若武将として注目を浴びている。
そのドスラットが、一体どうしてここにいるというのか。
「例の物を、持ってきたかしらね」
「……ああ……」
マナの問いかけに、ドスラットはそっけなく答えた。
二人の間に流れる奇妙な空気に、シャロスは疑問を抱いた。
接する期間はまだ短いものの、シャロスはドスラットという人間を良く知っているつもりだ。
謙虚だが決断力があって、冷静だが決して怯まない。
そして歳が若いわりには、大局を見据える力が備わっている。
彼と軍事の問答をしている時、その核心に迫る見方が特に印象的だった。
そんな前途有望な若者が、一体何故侍女と接触するのか。
「どうしたの?あなたはそれを私に渡したくて、ここに来たじゃないの?」
マナの余裕綽々の態度とは対照的に、ドスラットはパッとしない面立ちであった。
彼は黙ったままふところから一つの書類を持ち出し、それをマナに手渡した。
マナは素早く書類に一通り目を通して、満足した表情でスカートポケットに入れた。
「うん、よくやったわ。さすが騎士さま、この中央軍部の作戦指針書の副本をとるのに、大変だったでしょ
」
マナはただニッコリとしただけだが、聞いていたシャロスは驚愕の表情になる。
帝国五大軍は、五つの軍部によって統制され、その上国王が統轄するシステムとなっている。
軍事行動の実態、予算、今後の展望など数々の機密データを含む作戦指針書は、
この国の命運を握ると言っても過言ではない。
そして、今期の中央軍の作戦指針書は、まだシャロスの手元に届けられていないのだ。
中央軍統帥のスデラス将軍の側近であるドスラットなら、その書類をいち早く拝めることができるだろう。
しかしまさかをこんな形で、一介の侍女の手に渡っているとは、シャロスは夢にも思わなかった。
「俺は、本当に許されるんだろうか。こんなことがもしばれたら……」
「何いまさら焦ってるの。もうずっと前から、やってきたことじゃない。
今のあなたに残されてる道は、これからもうまくばれない様にやり続けることなのよ」
「お前は……まだ俺を利用し続けるというのか!」
「大丈夫よ。うまくやってくれたあかつきに、上の人間だってきっとあなたを認めてくれるわ」
マナはくすりと笑って、固まるドスラットに抱きついた。
彼女が言う「上の人間」はリテイア皇后を暗示していること、シャロスはすぐに感じとった。
マナはドスラットの唇に軽くキスしてから、ぐるりと体をまわして離れた。
「ねぇ、今はそんな物騒な事を気にするより、私といいことをしましょ?
ふふふ、あなたの悩みを、全部忘れさせてあげるから」
少女はその歳にそぐわない妖艶な笑みを浮かべ、ゆっくりとスカートの裾を持ち上げた。
ドスラットはまさか彼女は下に何も着ていないと思わず、ビックリした表情になった。
彼がマナの体に触れようと手を伸ばすと、マナはくすっと笑って裾をおろし、妖精のように軽やかにかわし
た。
遠くから見ているシャロスでも、心がうずうずしてたまらなかった。
可愛らしいな顔立ちと放蕩な仕草。
メイド服の下にあるのは、青春の息が溢れる肢体。
そして、ひらひらと漂うスカートと、そこから見える陰部。
どんな生真面目な男性にとっても、食指を動かさずにいられない光景だろう。
マナは煽情的な笑い声をこぼし、誘うように体を躍らせた。
ドスラットはすっかりその虜になったのか、魅入られたような目付きで彼女を捕まえる。
「ははっ、騎士さまったら。いいわ、マナが気持ちよくさせてあげる」
そう言って、マナはドスラットの首に腕をまわし、口付けをした。
彼女のふしだらな行動にむっとしながらも、
シャロスはそのなまめかしい舌の動きを無意識のうちに想像してしまった。
マナの体はだんだんと柔らかくなり、遠くから見てもその顔が火照り出したのが分かる。
その色っぽいさまに、シャロスの股間の一物がそびえ始めた。
(くっ……そんな、体が勝手に……)
シャロスは思わず硬くなったペニスに指を添え、ゆっくりと弄りだす。
二人のほうから、いやらしいキスの音が断続的に聞こえてくる。
ようやく顔を離れたときに、マナは乱れた髪を整えて、頬を赤らめた。
「ねぇ、騎士さま。マナのことをよく見て」
マナはゆっくりメイド服に手を掛け、上着から脱ぎ始めた。
彼女の大胆な行動に、シャロスもドスラットも視線が釘付けとなる。
布が肌をかすめる音がしばらく続いた後、マナは今まで身につけていた物を全て脱ぎ捨て、
それから裸のままかたわらの織物の上に横たわった。
シャロスは今までずっと、淫らな女性はみんな不潔だと考えてきた。
しかし、目の前のマナの裸姿は、そんな彼の思いを覆した。
皓月のような白い肢体と、女性特有の柔らかい曲線。
それが横たわっている優美かつ官能的な光景は、絵画のように美しかった。
たおやかな乳房と、しなやかな腹部や臀部。
綺麗に整えた陰毛は、淫猥な光沢を跳ね返してくる。
マナはさりげなく腕があげ、背中をさすった。
彼女の滑らかな腋肌は優美に表現され、背中やお尻、太ももと並んで美しいラインを描く。
マナはけだるそうに両目を細め、含みのある笑顔を青年騎士に向けた。
騎士の緊張な面立ちとは対照に、彼女の表情は余裕に満ちていた。
その誘惑を含んだ余裕さは、男の欲望を更に煽る。
「ねぇ、どうしたの?私と気持ちいいことをしたくないの?」
マナは潤んだ唇を開き、耳元で響くような心地よい声で言った。
その柔和な声を聞いただけで、シャロスの心が大きく動揺した。
甘くて恋しい感情がぼんやりと脳の中を広がり、彼女の言うことなら何でも従いたい気分になってしまう。
マナの間近に立つドスラットはその影響をより多く受けたか、何も言えずに彼女に近づく。
彼は震えた両手でマナに触れようとすると、マナはくすりと笑い出した。
「そんな暑苦しい鎧を着たまま、私とするというの?おバカさん」
「あっ、うっ、すまない……」
ドスラットは言われて初めて気付いたか、そそくさに鎧をはずし始めた。
しかし、あまりにも慌てているせいか、金具をはずすのに何度も失敗した。
彼のぎこちない手つきを見て、マナは更に笑い出した。
「うふふ、騎士さまなのに、まるで新兵みたいじゃない。
いいのよ、落ち着いて。ここには私達以外に誰もいないんだから」
ドスラットは顔を真っ赤にさせて、何か反論することもできず、
ただ無言のまま身に着けているものを全て脱ぎ捨てた。
普段なら雄々しく戦場に立つ彼が、今ではまるで無力の子供のようにマナに使役されていた。
「騎士さま、はやく来て。マナのいやらしい体を、味わってください」
マナが猫なで声で誘うと、ドスラットはマナに覆い被さった。
彼は欲望が満ちた獣のように、白い乳房にすいつく。
「あはぁん。もう、慌て者なんだから」
マナは淫らに微笑むと、妖艶な水蛇のように体をドスラットに巻きつかせた。
彼らの淫靡な行為を見て、シャロスは溜まらず自分の一物をしごきだした。
耳から聞こえてくる淫蕩な喘ぎ声に、彼の喉がからからになった。
シャロスは一時もマナの裸から目を離さず、彼女の恍惚な表情を追いながら欲望を滾らせた。
柔らかい織物の上で二人の男女は激しく蠢き、やがて股を重ね合わせた。
(くっ、足りない……こんなんじゃ、足りないよ!)
シャロスは自分の渇きを感じていた。
マナの艶かしい裸を抱きたい。
彼女のあそこに、熱い精液を注ぎたい。
ドスラットの動きに合わせ、腰を悩ましく動かすマナの姿に、シャロスはこれ以上無い欲情を覚えた。
そして時々、マナはドスラットの背中を越して、シャロスがいる方向に淫らな笑みを送ってくる。
相手が自分を挑発しているのを分かっている。
しかし、シャロスは歯痒い思いを抑えることができなかった。
ふと、彼の目線はさきほどマナから預けられた黒い下着に触れてしまう。
その途端、マナの誘惑するような言葉が耳元でよみがえる。
(途中でしたくなったら、それで私の匂いを思い出してね)
シャロスはその黒い布切れを見て、ごくりと息を飲んだ。
刺繍を施されたシルクは、触り心地がとても良かった。
薄めの布地は、それを履いた者のあそこを軽く隠していることを想像すると、心が大きく興奮した。
やってはいけない行為と分かっていた。
一国の王となる者が、そんなはしたない事をするなんて、彼のプライドが許さない。
しかし、今のシャロスにとって、マナへの欲望は何よりも魅力的なものであった。
彼はゆっくりとシルクのショーツを持ち、彼女の陰部に当たる部分を鼻に近づかせ、大きく息を吸った。
うっすらと甘酸っぱい匂いが、脳に染み渡っていく。
(はぁ……これが……マナの匂い)
シャロスは左手でショーツを持ったまま、右手でペニスをより強くしごいた。
そして、彼は熱い目線をまぐわう二人の男女に注いだ。
「はぁっ、うくっ……はああぁ!」
「はぁ、はぁ……」
「あははっ、いいわ、騎士さま!もっと、マナを突いて!私のいやらしいオマンコに、もっと欲情して!」
「うっ……そ、そんな、締まる……だめだ、もう、出るぞ!」
「あははは、それはだーめ!」
マナは笑いながら、ドスラットのたくましい胸板に両手をつき、動きを止めた。
彼女の体中に汗玉がきらめき輝き、濡れていた背中や乳房が美しく映された。
「くっ……も、もう我慢できない……」
「うふふ……じゃあ騎士さま、イク前に聞かせて。騎士さまは、私のこと好き?」
「あっ、ううっ……す、好きだ!」
「私のことを、この世の誰よりも愛していると誓える?」
「ちっ、誓う!俺は、お前のことを……この世で一番愛してる!」
「じゃあ、これからも私の言うことを全部聞いてくれるよね?
どんな難しい注文でも、私のために、忠実にやってくれるよね?」
「はぁ、うぐっ……誓うよ!これからも、お前のためなら、俺はなんだってやる!
だから、速く……速くイカせてくれー!」
彼の言葉を聞くと、マナは満足の笑みを浮かべた。
「うふふ、よく言ってくれたわ。ご褒美に、盛大にイカせてあげるわ!
これからもずっと、ただ私の奴隷となって生きなさい!」
マナは自分の体を上にして、ドスラットの上で腰を波のように強くうねらせた。
「ああ、ああぁぁぁ!」
ドスラットの口から、快楽に満ちた悲鳴が出てきた。
「そうよ!そうやって、私のオマンコを感じなさい!
もう二度と忘れられないように、私のオマンコの味を覚えさせてあげる!」
マナはあどけなさが残る顔を邪悪な笑みで染め、ドスラットの上で激しく動いた。
その快感を想像しながら、シャロスは股間の物を高速にしごく。
鼻の中を充満するマナの匂いが、シャロスの理性を暗闇へと葬る。
マナと性交している錯覚を覚えると、彼のあそこがビクビクと跳ね出した。
「ああぁっ、もう……だめだ!で、出てしまうっ!」
「はぁん、いいわよ……私の中に出して。あなたの汚らしいザーメンを、いっぱい出してちょうだい!」
マナは口元を吊り上げ、腰をギュッとひねった。
その衝撃に、ドスラットは乾いた悲鳴を出した。
それに合わせて、シャロスのあそこからもドピュッと白い精液が吐き出された。
「ああっ、うぐっ……ううっ!」
ドスラットは歯を食いしばって、腰を懸命に突き上げた。
「あはぁん、いいわよ……私の中で出すために、そんなにがんばっちゃって。
ああぁん、出てくる……中で精液がいっぱい出てくる!」
マナは熱っぽい表情で、快感のために体をしなやかせた。
彼女は両足を痙攣させながらも、最後の一滴までを搾り出すように、腰をゆっくりと上下に動かし続けけた
。
その妖しい快楽に、ドスラットはただ体を震わせながら、床に身を置いたまま耐え続けるしかなかった。
□
「じゃあ、先に出るぞ」
「ええ。軍部に戻っても、見破られないように、気をつけてね」
マナは揶揄めいた口調で、ドスラットの腰や両足を見つめた。
「……分かってるよ」
ドスラットはたまらないといった様子で、あたりをうかがいながら部屋から離れた。
その気配が遠のいていくのを感じながら、シャロスは自分の下半身を呆然と見つめた。
他人の行為を見ながら、自慰に耽る自分が情けなかった。
「王子様、もう出てきてもいいわよ」
マナは木箱を支えながら、突然シャロスの側に現れた。
「マ、マナ!」
「どうだったかしら?その様子だと、王子様も充分に楽しまれたようですね」
マナはシャロスの左手に握るショーツと股間の狼藉を見ながら、あざ笑うかのように彼を見下ろした。
「こ、これは……」
「あははは、隠さなくてもいいのよ。でも、嬉しいですわ。
王子様が、私がセックスしているところ見ながらオナニーしてくださるなんて」
マナはシャロスの腕を引っ張り、彼を部屋の中央に導いた。
「マナ、お前は他の男と密会するつもりだったのに、わざと私をここに誘ったな!」
「そんなつもりはありませんわ。でも良かったじゃないですか?スリルがありまして」
「あのな――!」
シャロスは必死に彼女を嫌悪する感情を呼び起そうとした。
目の前の女には憎めない可愛らしさがあって、それがシャロスの理性を邪魔する。
「くっ……お前は、いや、お前達は一体何をたくらんでいる?軍部の機密情報を手に入れて、どうしようと
いうのだ」
「さあ。私みたいな下っ端には、分かりませんわ」
「とぼけても無駄だ。この後、私がドスラットの奴に問いただせば、全部暴露できるからな」
「別に、いいですわ」
「なに?」
「だって、そんなことを聞いたら、王子様が私としたことも、全部ばれるじゃない」
「くっ……」
「ふふふ、どうせこのままでも、あの男にはもう未来が無いから。立派な軍人さんだったらしいけど、
彼はもう私にメロメロになったんだから。これからも骨を抜かれたまま、私の言いなりになるでしょう」
「なんということを……」
「ねぇ、そんなことより……王子様は、私のアソコに入れてみたくないですか?」
マナは淫らな笑みを浮かべて、裸姿のまま椅子に座った。
彼女の美しい裸体の下で、白い精液にまみれた淫裂がシャロスの視界を奪う。
溢れ出すねばねばした液体が、マナの太ももをつたって、ゆっくりと地面に垂れ滴る。
そのあまりにも淫猥な光景に、シャロスはごくりと喉をうならせた。
精液を中に出されたばかりの陰唇は、ビクビクと蠢いて彼を誘う。
彼の果てたばかりの一物は、たちまちもとの硬さを取り戻した。
「王子様ったら、かわいい顔をしているくせに。あそこがずいぶん元気じゃないですか」
マナはふざけるように、赤く腫れた一物の亀頭を指で弾いた。
女の手に触れられた性器は、すぐにビクンと反応を見せた。
「うふふ……シャロス様のあそこは、もう我慢できないとおっしゃっていますわね」
「くっ……!」
シャロスは突然マナの裸に抱きつき、彼女の体を覆った。
彼は上からマナの無抵抗な裸体を見ながら、心の中で理性と欲望が激しく戦う。
しかし、マナは彼の努力を残酷にも取り壊した。
彼女は自らシャロスに抱きつき、彼の耳元で悪魔のように甘く囁いた。
「王子様、速く私の中に来て……さあ、マナのいやらしいオマンコをぐちゅぐちゅさせて。
そうすれば、私は王子様にいっぱい、女の体に溺れる快感を教えてあげられるから。
もうエッチな事しか考えられないような、淫蕩に耽る男になれるように」
マナの悪戯っぽい笑顔を作り、彼の劣情を煽った。
その色っぽい顔を見て、シャロスはマナの両足を大きく広げ、彼女の膣に一物を突き刺した。
「ああぁん!いいっ……いいわ!」
マナはシャロスの頭を胸で抱きしめた。
彼女の膣中にはヌルヌルしていて、一物のすべりをよくした。
「いかがですか、王子様?あはぁん……ついさきほど、ほかの男に精液を出されたオマンコに、
オチンチンを突っ込む感じは……でも、みっともないですよね。王子様のような高い身分のお方がメイドに
、
しかも他の男性と交わったばかりの女性に、一生懸命腰を振るなんて。恥ずかしくないんですか?
今のお姿が大臣や側近達に見られたら、どうなるのかしら」
マナは熱い息を吐きながら、少女特有の無邪気な口調でシャロスに話し掛け続けた。
彼女の言葉は一字一句、鋭利なナイフのようにシャロスの心をえぐる。
「うっ、くっ……お、お願い……そんな事、言わないで!」
シャロスは苦痛と快楽が混ざり合った複雑な表情を浮かべた。
マナの言うとおり、他人と交わったばかりの女性と性交する自分が悔しい。
しかし、それでも彼は腰の振りをやめるわけにはいかなかった。
「うふふ……はしたないわね。王子様のような聡明なお方が、私のような淫らな侍女に惚れ込むなんて」
「ああっ!」
一物が膣によって締められた感じに、シャロスは悲鳴を上げた。
「あはは、今の王子様は、とてもいい顔をなさっていますわ。ほかの平俗な男と同じように、
私のことが好きで好きでたまらない情けない表情。でも、私はそんな王子様、大好きですわ」
マナを体をひねらし始めると、シャロスから主導権を奪った。
「ああっ、んふっ……ああぁぁ!」
再び射精感が込み上げてきたため、シャロスは苦しそうに呻いた。
だが彼がまさに出そうとした瞬間、マナはすかさず指で彼の根元を握り締めた。
「っ……えっ?」
マナはそのままシャロスから離れ、まるで何事もなかったかのように服を着始めた。
「そ、そんな……どうして?」
「ふふふ……私の中で射精できるとでも思ったの?あははは、王子様ったら、バッカみたい!
残念だったね。私はね、取引き相手にしか中に射精させないの。王子様といっても、私の中ではほかの男と
同じなの。
そもそも王子様が中に入れられたのも、サービスみたいなものだし」
マナはカフスのボタンを止めながら、可愛らしく舌を吐き出し、あっかんべをつくった。
シャロスは股間にあつまるマグマを抑えながら、これ以上無いせつなさを覚えた。
後一歩のところで寸止めさせられたペニス。
ミミズのような血管が表面を走り、血行とあわせてビクビク跳ね続けた。
完全に服を着終わると、マナはシャロスの顎をしゃくって、うーんと声をうならせた。
「はぁーん、なんてかわいい顔かしら。まるで主人に乞う仔犬みたいだわ、うふふ……
でも、残念だね。これは決まり事だから」
マナは怒張った亀頭を爪先で弱くひっかくと、シャロスは苦痛の満ちた声で喘いだ。
「お、お願い、マナ……私を、私をイカせて!」
「ふふっ、そんなにイキたいなら、自分ですればいいじゃない?……私のパンツを使って!」
マナはシャロスから黒いショーツを奪い、それをシャロスの膨らんだ股間にあてがった。
「ああっ!」
シルクのすべすべした感触が敏感な亀頭にあたり、快楽のさざなみを起こす。
「ほら、王子様。私のオマンコをオカズにして、あそこをシコシコしてください」
マナはスカートの裾を口に咥えさせ、精液にまみれるあそこを指で広げた。
その瞬間、シャロスによってかき回された白液が下へ垂れ下がった。
マナの淫らな仕草は、そのままシャロスの脳内まで黒く染めあげる。
シャロスは食い込むようにマナのあそこを見つめながら、黒ショーツ越しにペニスを握った。
「うふふ……そうそう、ちょうど私のオマンコの筋に当たる部分が、王子様のオチンチンと重なるように。
私の中に入れてるところを想像しながら、シコシコしちゃって!」
「くっ……んふっ」
シャロスはマナの言葉に従い、シルクのショーツを通して、夢中になって自分の股間をしごき続けた。
絶頂へたどり着く快感が、瞬時に体中をよぎる。
「どう、王子様?私のアソコの染みに、オチンチンを一生懸命擦りつける感じは。
あははは、顔をよく見えるように、私に向けなさい。
あなたがイク時の情けない表情を、私が見てあげるから!」
「うっ……ああぁっ!」
マナが繰り出す言葉は、シャロスの屈辱心をかき回した。
その悔しい気持ち自体、彼に堕落する快感を与えた。
マナに見られながら果ててしまう光景を想像すると、シャロスは倒錯とした感情を覚えた。
股間の一物は沸騰した熱湯のように滾り、痺れる心地よさが全身を支配し始める。
マナはたまらないという表情になり、シャロスをもっと誘惑するように秘所を弄った。
「はぁん……私はね、強い男や、かっこいい男が誘惑に負けて、私の虜になるところを見るのが大好きなの
。
あのドスラットという男もそうなのよ。はじめの時はかっこよく私を拒んできたけど、今となっては、
私の命令ならなんでも聞くヘタレな男になったのよ。男達が私に屈してしまうとこを見ると、
私のアソコが濡れてくるの……ほら見て、王子様。今でも、私のアソコがいやらしい汁を垂らしてるのよ」
マナは心の琴線を震わせるような声で、シャロスを挑発し続けた。
その悪魔のようなセリフに、シャロスは背徳的な快楽を感じずにいられなかった。
「うっ、ううっ、マナ……イ、イクッ!」
「そう。じゃあ、腰をいっぱい浮かせて、一生懸命振りなさい!そして、全部吐き出すのよ」
「ああっ……ああああぁぁ!」
シャロスは両足をガタガタとわななかせ、黒ショーツの中に白い精液を大量に噴出した。
「ああっ……がああぁぁ!」
シャロスは思わず床に尻を付けた。
彼の視線は散乱と宙に向け、体中が疲労と快楽が満ち溢れた。
マナはシャロスに近づいてくすっと笑い、
「はい、よくできましたわ。じゃあ、パンツを返してもらうね。これは私のお気に入りだから、簡単にあげ
られないの。
……あ~あ、こんなによごしちゃって」
マナは精液でしわくちゃになった下着を広げ、それに足を通した。
「はぁん、あそこが精液と触れちゃって、ぬるぬるして気持ち悪いわ。これも間接セックスと言えるのかし
ら?うふふ……」
マナは濡れたショーツを履いたまま、服を全体的に整えた。
彼女はまだ起きられないシャロスの側にしゃがみ、彼の唇に指を当てた。
「もしこれから、王子様が私と本番をしたくなったら、私がほしいような物を用意することだね。
うーん、そうだね……たとえば、この国の一番美しい宝石とか。確かあれは、王子様が持ってるんだよね?
シネラリアとか言う、王室代々に伝わるすごいやつ」
「はぁ、はぁ……なぜ、それを知って……?」
「リテイア様から聞いたことがありますの。なんでも、かつてはこの宝石を目当てに、
隣国と戦争になっただとか。私、ぜひその宝石を見てみたいの」
「そ、そんなこと、できるか」
「あら、それは残念だわ。見せてくれれば、私は王子様にもっと気持ちいいことしてあげられたのに」
マナはいかにも遺憾な面立ちで立ち上がり、部屋から出ようとした。
「ま、待って!」
「じゃあね、王子様。もし考えが変わったら、いつでも私のところに来てね。私、待ってるから」
マナは最後にウィンクを投げると、陽気な笑顔で部屋の外へ出た。
「くっ……」
シャロスは悔しそうに、しかしどこか未練がましく、彼女が去った跡を見つめ続けた。
□
(王子様は、一体どこにおられる……)
昼過ぎてもシャロスの姿を見当たらなかったため、レイラはついに我慢できず探しに出かけた。
シャロスからはかまうなとは言われたが、彼の身に何か危険が降りかかっているかもしれないと思うと、
いても立ってもいられなかった。
歩いている途中、レイラは今朝の隊員達との会話を思い返し、なぜか胸がドキドキした。
(そういえば、シャロス様もそろそろ異性に興味を持ち始めるお年頃だわ……
シャロス様も政事ばかりに没頭せず、そろそろ嫡室の選別をして頂かないと……)
戴冠式の時、シャロスの凛々しい姿の側に美しい妃の姿がいれば、国民の歓喜はより一層高まることでしょ
う。
しかし、それ以降自分が彼の側にいなくてもいいと思うと、レイラは心が急にちくっとした痛みを感じた。
彼女は思わずびっくりして、自分の胸を抑えて。
(今一瞬、刺が刺さったような感じが……なぜだろう?)
あんまり慣れない感情に、レイラは頭をぶるぶる振るわせた。
(はぁ、いつまでもこんなくだらない事を思ってるんだ。
今は、殿下を探すのが先決ではないか。速く、殿下を探さなきゃ)
レイラ踵を返そうとしたとき、耳元に残るような声が彼女を呼び止めた。
「あら、レイラさんではありませんか」
「……皇后様!」
レイラはその姿を確認すると、すぐにひざまずいた。
彼女を呼び止めたのは、皇后のテイアであった。
今日の彼女は、ゆったりとした翡翠色のドレスを着ていて、その後ろに一人のメイドを従えていた。
レイラは同じ女性でありながら、リテイアの美しさを賛美せずにいられなかった。
ドレスの縁はきらめく瑪瑙に飾られ、すべすべの肌とあいまって、彼女の魅力をふんだんに引き出していた
。
卑俗過ぎず地味過ぎない服飾は、彼女の妖艶な肢体と自然的な一体感を紡ぐ。
それに加えて、弾力に富む綺麗な肌は、まだ二十過ぎたばかりの自分と比べても全然遜色が無かった。
リテイアの素性を知る者は、ほとんどと言っていいほど誰もいない。
レイラがまだ小さかった頃、リテイアは後妻として先代国王の妃に迎えられた。
その時、彼女のきめ細かい肌や美しい容貌が、多くの人を魅了してきた。
年老いた国王の隣に並ぶ妖艶な美女は、レイラの記憶に深い印象を残してきた。
だが今から見直しても、リテイアの容姿は当時とさほど変わらなかった。
乙女のようなみずみずしい体と、どんな男をも虜にしてしまう艶かしさ。
その二つの要素が、彼女の身の上で見事に融合していた。
リテイアは実は魔女ではないかという噂も流れているが、
そのような童話世界に出てくる話しをレイラは当然信じなかった。
ただし、時々彼女から感じるぞっとするような魅力に、レイラは背筋に寒気を感じていたのだ。
「くるしゅうない。護衛の任務、いつもご苦労ですわ。レイラ隊長がいたおかげで、我々はいつも安心でき
るわ」
「お褒め頂き、ありがとうございます」
「それにしても、この場にいるのは何用かしら」
「はっ。少し前に、殿下が一人になりたいとおっしゃられました。
それでしばらく経ってもお姿がお見えになられなかったので。私が殿下を探しております」
「ふふふ。まあ、良いではないか。
隊長さんの忠誠心は素晴らしいですが、たまには殿下を自由にさせることも大事ですわ」
「しかし」
「それに、これはわらわからのつたない助言ですが、隊長さんも、
これからはもっと自分のために気を使ってもよろしいかと」
「それは、一体どういうことですか?」
レイラは不思議そうにリテイアを見つめた。
リテイアの瞳は、どこか人を深く溶け込ませるような輝きがあった。
「殿下の身を心配するのも大事です。しかし、隊長さんは、もっと積極的に自分の幸せを掴まなくちゃ。
女が花を咲かせる時期は、一生に一度しかないのですから」
「はあ……」
レイラは要領をつかめないまま、答えた。
「では、護衛の任務がんばってください。わらわはここで失礼させてもらうわ」
リテイアはそう言ってその場から立ち去った。
彼女の背後にいたメガネをかけたメイドは、レイラに軽く会釈してから皇后に追随した。
(彼女はいったい、私に何を言いたかったのかしら……)
レイラは納得しないまま、しばらく考え込んだ。
庭園道を少し歩いたところ、リテイアはゆっくりと尋ねる。
「フシー、あの子を見て、どう思うかしら」
「……リテイア様がおっしゃったとおり、すばらしい逸材です。
正しく磨くことができれば、今よりずっと輝くことができるでしょう」
フシーと呼ばれたメイドは恭しく述べた。
そのメガネの後ろには、リテイアとよく似た妖しく光る瞳があった。
「あなたの目にそう映るのなら、間違いないでしょう。いつかは、彼女に手伝ってもらえれば良いですね」
「……その通りでございます」
フシーは淡々と、しかし堅実な口調で答えた。
「これからが、楽しみですわ」
リテイアは心底から愉しんでいるように、遠くにある宮殿を見つめた。
陽炎に包まれた壮麗な宮殿は、幻に包まれた優美さがあった。
话说这就是剩下的全部内容,哪位好心人来翻译下造福广大人民群众啊……

Ma
max2963116
Re: 【自译小说No.6】魅惑的皇后
顶啊

Ma
max2963116
Re: 【自译小说No.6】魅惑的皇后
顶