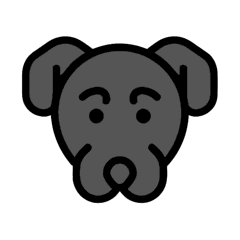【转载·日语原文】レイコとシンジ リベンジ·復讐するは我にあり·罪と罰·らせん
添加标签
说明
- 首先必须强调,本文的作者为SPIT ME。本楼转载未经作者授权。
- 关于本小说的介绍,详见论坛帖子《『レイコとシンジ』-美少女S的诞生-》(http://www.mazochina.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=42106)的序言部分。
- 转载内容源于2016年我在ミストレスカフェ(https://www.mistress-cafe.net/reiko_and_shinji,现服务器已停)复制下来的存稿,存在部分字符编码错误。
- 目前没有翻译全文的打算,总共150万字以上的工作量足以令任何译者惶恐。
1
玲子たちの鞭道場は毎週末、三週間連荘で開催された。玲子たちは我流で技を磨き、試行錯誤もあったのに対し、富美代と朝子は玲子たちの経験を活かし、効率よく鞭の極意を吸収していった。その三週間で富美代たちはのべ1000発は鞭を振るったであろうか。とりも直さず慎治たちは1000発以上の鞭を浴びたことになる。鞭道場が終了し、礼子たちが鞭道免許皆伝を言い渡した時、富美代も朝子も鞭を自在に使いこなせるようになっていた。手首のコントロール一つで強く、弱く。打ち据えたり手足に絡めて引きずり倒したり。間合いを調整して先端部分のみをヒットさせたり身体に絡みつくように打ち据えたり。信次たちの苦痛を自由自在にコントロールできるようになっていた。
さて、礼子たちはもともと同じ乗馬クラブ、郊外の丘陵地帯に位置する由緒あるクラブのメンバーだった。五月頃、富美代と朝子も二人に誘われてこのクラブの会員になっていた。このクラブのメンバー資格審査は厳しいものの、先代からの会員である礼子たちの紹介であれば審査はフリーパスだ。しかも富美代と朝子も家柄はかなりよく、経済的にも十分余裕があり、二人の上品な雰囲気はクラブに問題なく溶け込めそうだった。礼子たちが誘うと、富美代も朝子も大乗り気だった。そして双方の両親共、娘が礼子たちと同じ乗馬クラブに入りたい、と切り出すと二つ返事でOKだった。流石に富美代も朝子も、週末だけの練習なので礼子たちみたいに障害競技までこなすプロ級の腕前、とは行かないものの普通に馬を乗りこなし、意のままに走らせる程度は全く問題なくこなせるレベルに達していた。そして天気予報が軒並み週末の秋晴れを予想したある日、玲子が今度の週末、四人そろってクラブに行こう、と切り出した。「クラブ?」確かにこのところ週末は慎治たちを苛めるのに忙しく、クラブにも少し足が遠のいていた。「いいよ、確かに久しく行ってないし。楽しそうね・・・だけど、なんで急に?玲子、何か企んでるんじゃない?」朝子の疑問は当然のことだった。「うん!実は先週の日曜ね、私クラブでちょっと遠乗りしてきたんだ。そこで結構逝けてる場所見つけたのよ!こりゃ、みんなで来るしかないなって思って。幸い明日はお天気もいいみたいでしょ?みんなで行こうよ!」土下座している信次の頭を踏みながらクスリと朝子が笑った。「逝けてる、て玲子、それ勿論、信次たちと遊ぶのに逝けてる、て意味でしょ?なに見つけたのよ、教えてよ?」「フフ、信次たちと遊ぶ場所だ、ていうのは確かなんだけどね。ま、どういうとこかは着いてからのお楽しみにしようよ。実はね、もう良治先生たちに車を出してもらうのも頼んどいたんだ!」信次たちの予定など一切お構いなしに玲子たちはさっさと予定をセットしてしまった。
そして翌日、処刑場に引きずられる羊のように悲しげな顔をして信次たちは集合場所に現れた。「やあ信次君、遅かったじゃないか!君がラストだよ!」相変わらず妙に爽やかな声と笑顔で亮司が声をかけてきた。傍らには自分と同じく、この上なく悲しげな顔をした慎治がいた。「全く、二人ともなに暗い顔してるんだい?礼子ちゃんたちだけでなくて今日は可愛い子が四人も一緒に遊んでくれる、ていうんだよ?もっとうきうきした顔しなくちゃ、だめじゃないか!」良治の声に礼子も大きくうなづいた。「そうよ慎治、全く二人とも暗いんだから!お天気もいいし、明るくパーッといきましょ!」な、なにが明るくパーッとだ・・・声にならない慎治たちの声を無視するかのように二台のランクルは走り出した。良治たちと礼子たち、六人が楽しくはしゃいでいるのに対し、慎治たち二人だけが泣きそうな顔で震えていた。やがて高速を降り、丘陵地帯へと入っていったランクルは目指すクラブのフロントに滑り込んでいった。「さあ着いたわよ!さっさと降りて!」玲子の声に弾かれ、車から降りた信次は気圧されたように辺りを見回した。無理もない、そこは高級な乗馬クラブ、ある種の社交クラブ的な雰囲気を漂わせていた。信次たちとは一生縁のないような上品な、そしてどこか威厳のある人間ばかりが歩いていた。そういった人たちと玲子たちは親しげに挨拶を交わしていた。自分たちの知らない上流社会。そこに自然に溶け込んでいる玲子たち。そして朝子たちでさえ、既にその社会に暖かく迎え入れられていた。だが、卑屈さを全身から発散し、おどおどしている信次たちに構う人は誰もいなかった。なに、あれ・・・場違いなぼうやたちね・・・バイトにでも来たのかしら・・・言葉こそないが、まさに白眼視、信次たちだけが疎外されていた。
おどおどしている信次たちに構わず、一通り挨拶を済ませた玲子たちはさっさとチェックインの手続きをした。「ほら信次、あんたのロッカーのキーよ。ぐずぐすしないでさっさと着替えてくる!」ポーン、とキーを二つ放り投げると玲子たちは女性用ロッカールームに入っていった。えっ・・・見ると良治たちが男性用のロッカールームに入っていくのが見えた。あ、あっちか・・・着替え終えた信次たちが外に出て暫くすると、玲子たちが出てきた。四人ともお揃いのファッションだ。ハッ・・・慎治は思わず息を呑んだ。白いシャツの上にクラブのロゴが入った、鮮やかな赤いジャケット。下半身は白の乗馬パンツにピカピカに磨き上げられ、黒光りする乗馬ブーツを履いている。そして手には信次たちが見慣れたもの・・・長い乗馬鞭をしならせていた。その姿はまさに、慎治が中学生の時憧れていた高嶺の花、クラス中に出回った写真をひそかに購入して何度も何度も溜息交じりで見つめ続けた、憧れの天城礼子の姿そのものだった。いや、こうして間近に見る礼子の姿は写真撮影時から1年の成長を反映し、更に美しさを増していた。礼子の美貌、長身、高級そうなウェア、どれを取っても慎治たちが永久に持ち得ないものだ。そもそも慎治たちではこのクラブにビジターで入ることすらままならない。乗馬服など、一生着る機会すらないだろう。着古した、薄汚れたスウェット上下とスニーカー姿の慎治にとって、間近で見る礼子の乗馬服姿は単に美しい、と言う言葉では言い表せない。それはあらゆる面で恵まれた礼子と何もない慎治との身分差を凝縮していた。美しい・・・だが同時に礼子の乗馬服姿は威厳と高慢に満ちていた。そして今日、慎治の目の前にいるのは礼子だけではない。玲子に富美代、朝子の三人もいた。礼子に負けず劣らず長身の玲子、そして小柄な富美代と朝子。三人とも細身で脚がスラリと長く、見事なスタイルだ。だが礼子も含め、四人を際立たせているのはスタイル、ルックスだけではない。乗馬服を着こなしていることだった。どんなスポーツでも同じだが、全く同じウェアを着ても上級者と初心者では一目瞭然に差が分かる。高級なウェアになればなるほど、初心者が着るといかにも不自然、服に着られている、と言った印象を与えてしまう。礼子たち四人はいずれも、乗馬服を見事に着こなしていた。高級かつ閉鎖的なクラブの雰囲気に溶け込み、乗馬服を見事に着こなした四人。クラブの中でも一際目立ち、礼子たちの周りだけ華やかな雰囲気が漂っていた。
慎治の視線が釘付けになっているのを礼子は満足げに眺めていた。恐怖に震えながらもぼうっと自分を見つめている慎治の呆け顔に大きく頷きながら礼子が口を開いた。「慎治、どう、私の乗馬服姿、生で見るのは初めてでしょ?遠慮しないで見ていいわよ。慎治も中学の時、私の乗馬服姿の写真、買ってたらしいじゃん?あの写真も確か今日のと同じ、白のパンツに赤いジャケットのコンビだったわね。フフ、如何かしら、憧れの私の乗馬服姿は?お気に召した?」「か、買ってたって・・・そ、そんな、し、知ってたの!?」「当たり前でしょ!そういうことはね、いくら隠していたって本人には結構確実に伝わるものよ。全くもうこの写真小僧たちは!て結構、本気で怒ってたのよ。一度本気でとっちめてやろうか、て思ってた位。フフ、あのとき我慢してあげた貸し、返して貰うわよ。慎治、今日は覚悟しておくのね。私の乗馬服姿の拝観料、高いわよ!ましてや玲子に富美代に朝子、聖華の美女軍団四人がそろって極めてきてあげたんだからね、これは高くつくわよー・・・慎治に払えるかしらね。」確かに礼子の乗馬姿は惚れ惚れするほど格好よかった。だが、いくら格好よくても、苛められる、それも息も絶え絶えになるほど鞭で打たれる、というのでは憧れなど、最早持ちようがなかった。憧れより恐怖の方が遥かに大きい。乗馬服姿で極めた四人は立っているだけで強烈な威厳がある。そして礼子たちが気合の入った服装をすることが何を意味するか。この前のブーツ責めで十二分に思い知らされていた。礼子たちは部活で道着に着替えると気合が入ってくるのと同じように、服装によって気合の入り方が違ってくるタイプだった。礼子たちが特別な服装に着替える、それは礼子たちの心のブレーキを解除するスイッチ、残忍性をフルに解放するスイッチが入ることを意味する。こ、怖い・・・何も言われなくとも礼子たちの意気込みがヒシヒシと伝わってくる。信次も全く同じ事を感じていた。玲子の手にしている乗馬鞭が今にも襲いかかってくる恐怖に、信次はその鞭から目が離せなかった。信次が早くも顔面蒼白で怯えているのを見て朝子がクスクス笑った。「やーねー信次ったら!玲子の鞭をそんなに見つめちゃって!そんなに早く鞭が欲しいの?」「あ、本当だ!でもね信次、この鞭はお馬さん用なの。信次を叩いた鞭で触っちゃったりしたらお馬さんが可哀想でしょ?信次の鞭はここに入っているからね。あとでゆっくりご馳走してあげる!」パンッと玲子がバッグを叩いた。そこへ従業員が四頭の馬を連れてきた。「お待たせしました。いつもの四頭です。今日は遠乗りでしたね。お気をつけて、ごゆっくりどうぞ。」従業員は礼子たち四人に馬を引き渡すと、慎治たちのことは存在しない人間かのように全く無視しながら礼子たちにだけ丁重に挨拶し、去って行った。え・・・遠乗り・・・そうか、どこかへ場所を移すのか・・・でも馬は四頭しかないよ・・・礼子、富美代、玲子、朝子・・・女の子が四人と信次とぼく・・・六人いる・・・僕たちは礼子さんたちと二人乗りかな・・・ぼんやりと考えている慎治を見て礼子は微かに嘲笑った。「さあ行こう!案内は今日の主催者の玲子ね!慎治たち、しっかりついてくるのよ!ゆっくりにはしてあげるけど、遅れたらどうなるかわかっているわね!」
「え、そ、そんな・・ついてこいって、ど、どうすればいいの?」「そ、そうだよ、まさか、僕たちにも馬に乗れっていうの?ぼ、僕たち、馬になんか乗れないよ・・・」慎治たちの間の抜けた返事に礼子たち四人はドッと笑い出した。「うーん、慎治、ギャグとしては今の、なかなか優秀よ。でもね、慎治たちは馬になんか乗れる身分じゃないでしょ?慎治たちは当然、走ってついてくるのよ!」そ、そんな!い、いくらなんでも酷い!だが否やを言う間はなかった。礼子たち四人は慎治たちの抗議を一切無視し、各々の愛馬に颯爽と跨った。「さあ、行くよ!」礼子の声を合図に四人は一斉に馬を歩かせ始めた。ま、待って、馬になんて追いつけない・・・慎治たちの心配は当然だった。馬が本気で走り出せば、人間がどうやったって追いつくことはできない。例えオリンピック選手だって無理だ。それ位のことは礼子たちには十分に分っていた。だから礼子たちは馬を早足程度のスピードに抑えて走らせた。そのスピードならなんとか、慎治たちもついてこれる。だが、慎治たちにとっては「必死で走ればなんとかついていける」というレベルで、余裕を持っていられるようなスピードではない。慎治たちはあっという間に悲鳴を上げ始めた。「ひっ・・・ま、待って・・・お、願い・・・も、もっとゆっくり・・・し、死んじゃう・・・」慎治の悲痛な哀願が礼子たちを楽しませた。「ほら慎治、遅れない! しっかり走んないと、後で鞭が増えるよ!」礼子の脅しは効果てきめんだった。馬に鞭を入れる、と言うが、慎治たちには鞭を入れる必要すらなかった。鞭、という言葉で脅すだけで十二分な効果があった。走った。慎治たちはひたすら走り続けた。どれ位走っただろうか。玲子が目的地を教えてくれないのが余計辛かった。いつまで走り続けるのか、あとどれ位なのか、一切分からない。もう着くのか、まだ半分も来てないのかも分からない。肉体的に辛いのは勿論だが、このいつまで続くか分からないマラソンは精神的に非常に堪えた。30分以上は走っただろうか。慎治たちが全身を汗にまみらせ、息も絶え絶えになってきたころ、漸く待ち望んだ声が聞こえた。「さあみんな、着いたわよ!ここ。ここを入るのよ!」玲子が立ち止まったところには一枚の木の立看板があった。「平成国際秀優大学グラウンド」そしてその路地の入り口にはチェーンが張ってあった。平成国際秀優大学。仰々しい名前だが,余り聞いたことのない校名だった。「なに玲子、ここなの?知らない校名だけど、ここ、どっかの大学のグラウンドでしょ?で、どこが気に入ったの?」馬を止めて礼子が尋ねた。「うん。この学校、平成元年だから丁度バブルの真っ盛りにできた私立大学なんだけどね、ま、要するに経営失敗したのよ。で去年、あえなく潰れちゃったってわけ。でも今更こんな田舎のグラウンドなんて買うとこあるわけないじゃん?と言うわけでこの物件、あえなく野ざらしの空き地に成り果てた、ていうわけ。」ポンッと礼子が手を打った。「そっか!潰れた、ていうことはこのグラウンド、誰も使わないんだ。じゃ、フルタイムで私たちの使い放題ね!」「そう。大体校名聞けばこの大学の経営陣、馬鹿者揃いだったってことが良く分かるでしょ?平成、国際、て来ただけで三流大学の条件満たしてる上に秀優だもんね、いくらバブルだって言ったって、こんだけ馬鹿大学宣言してるとこ、殆どないわよ。だからお金の計算も出来なかったみたいでね、このグラウンドも思いっきりバブルのりで作っちゃって、まあ新設大学のくせして、中はやたらと広くて立派なのよ。だから信次たちがいくら悲鳴上げたって誰にも聞かれる心配はないわ。おまけに学校が潰れたのが去年だからさ、まだあんまり荒れてないのよね。そこがまたグッドなのよ。」道端に倒れこみ、喘ぎながら束の間の休息を貪っていた慎治たちもようやく悟った。やっと苦行が終わったのではなく、今から漸く、本物の苦行が始まることを。
2
チェーンの横をすり抜けて一行は中へ入っていった。グラウンドは道路より50メートルほど奥にあり、木の影に隠れて道路からは全く見えない。確かにこれなら玲子の言うとおり、ちょっとやそっと悲鳴を上げても誰にも聞こえそうになかった。グラウンドは本当に広々としていた。400メートルのフルトラック、そしてトラックの中はサッカー用のピッチになっていた。ピッチは芝に覆われていた。手入れするものがいなくなり、かなり雑草が増えているとは言え、まだまだいいコンディションを保っていた。そしてこのグラウンドでどういう目にあうか、信次たちにも薄々わかってきた。「さあ、準備をしようか!信次、二人ともさっさと服を脱ぎなさい!」玲子の声が凛と響いた。そして四人の美少女は馬から一旦降り、吊るしておいたバッグから各々、愛用の鞭を取り出した。礼子たちは黒い鞭、そして富美代たちは茶色い鞭。いずれも信次たちの血と涙と悲鳴をたっぷりと吸った鞭だった。ゆっくりと四人はストレッチをし、体をほぐした後、再びひらりと身を翻し、騎乗した。「さあ、始めようか!信次、ここは広いからね、思いっきり逃げ回っていいよ!壁もないし、逃げ回る場所はたっぷりとあるからね。鞭で叩かれるのが嫌だったら、精々必死で逃げ回ることね!」「そ、そんな、だって玲子さんたちは馬に乗ってるじゃないか!ヒッ!」信次の必死の抗議は玲子の鞭にあっさりかき消されてしまった。「ほら信次、一番手は私よ!さっさと逃げないと、鞭でタコ殴りだよ!」ヒ、ヒーッ・・・悲鳴を上げながら信次は殆ど反射的に逃げだした。信次がグラウンドの半ば位まで行った時、玲子がニヤリと凄絶な笑みを浮かべながら軽く唇を舐めた。
「さあ、行くよ、ハッ!」玲子は掛け声と共に愛馬をスタートさせた。パカッバカッ、玲子が駆る馬のひずめの音が迫ってくる。信次がいくら必死で逃げたって馬のスピードに比べれば悲しい位のろい。あっという間に玲子に追いつかれてしまった。「ほら、このドン亀!そんなグズは、こうしてやる!」ビュォッと凶暴な音を立てて玲子の鞭が振り下ろされた。バッシーンッッッと派手な音を立て、信次の背中に凄まじい鞭が炸裂した。「ギ、ギエッ!」獣のような声を立てて信次はエビのようにのけぞった。ただでさえ長身の玲子が馬上から振り下ろす鞭だ。重力を味方にし、思いっきり振り切った鞭は凄まじい威力だった。痛い、なんて言葉では生ぬるい。打たれた瞬間、息が詰まるような、背中を打たれた筈なのに内蔵を通り、腹まで衝撃が突き抜けるような凄まじい一撃だった。「ほらほらほら!それそれそれ!」玲子は立て続けに鞭を振り下ろした。「ビッ、ギァッギャッ・・ベッ、ギェッッッッ!!!」玲子の鞭が炸裂する度に信次は断末魔のような悲鳴を上げ続けた。両手は縛られていない。だから少しでも鞭をよけようと両腕で頭を抱え込み、体を丸めるようにしていたが、玲子の強烈な鞭の前にはそんなガード、全くの無意味だった。これほど強烈な鞭なら、何も背中や尻にこだわる必要はない。腕だろうが足だろうが、どこでもいい。皮膚があり、神経が走っているところならどこにでも十分な苦痛を与えられる。と、いうことは信次の全身どこを鞭打っても構わない、ということだ。間断なく降り注ぐ玲子の鞭が信次の体のどこかを捕える度に、信次は絶叫を上げながら打たれた箇所を反射的に引っ込めるように体を反らしたり、逆に折り曲げたり、足を上げたり、腕を下ろしたり、と殆ど統一的な意志の感じられない反射運動を続けた。それは傍から見ていると珍妙なダンスだった。「アハハッ、なに信次のあの格好!玲子、もっと踊らせてよ!」朝子が大笑いしながら声をかけた。
「OK!ほら信次、ギャラリーが見てるわよ、LET’S DANCE!」玲子は笑いながら鞭を振るい続けた。ピシッ・・・パアン・・・ビシッ・・・パシーンッ・・・玲子の鞭音が響き続けた。「ギャッ・・や、やべ・・・ミ゛エ゛ッ!!!い、いだいーっっ!だ、だずげでーっっっ!!!」信次の動きと悲鳴が徐々に小さくなっていく。「ブギャッ・・・」フラフラになった信次は足をもつれさせ、芝に倒れこんだ。止めを刺そうかしら。馬を止め、大きく振りかぶった腕を玲子はゆっくりと下ろした。いけないいけない。私まだ、一番手なんだよね。いきなり信次を潰しちゃったら、朝子が遊べなくて怒っちゃうわ。「ほら信次、もう終わりにしてあげるから、立ちなさい。」玲子が声をかけても信次は倒れこんだまま、動けずにいた。背中も腕も足も、全身が痛みと灼熱感に包まれていた。全く、効いたふりしちゃって、あんたがこの程度で本当に終わっちゃうわけないでしょ!役者やなー・・・「信次、立ちなさい!それとも、鞭で叩き起こしてほしい!?」ひっ、そ、それだけは・・・全身をまだ包む激痛にうめきながら信次は必死で立ち上がり、のろのろと玲子の後ろについてスタート地点に戻っていった。「信次、いい色になって帰って来たじゃない!ほら、慎治も見てごらんよ。この蚯蚓腫れ、どんどん盛り上がってきているよ?」礼子はフラフラになって帰ってきた信次の傷を鑑賞しながら、傍らに慎治をはべらせた。言うまでも無い。礼子の大好きな精神的拷問だった。生来短気な玲子は先責めが好きなのに対し、礼子は大体において後責めを好んだ。玲子の鞭に、蹴りに、拳によって信次が全身ボロボロにされるのを見せ付け、その傷をたっぷりと見せ付け、慎治が怯える様を見るのが大好きだった。フフ、怯えてる、怯えてる・・・たっぷりと怖がってね。恐怖が最高潮に達したところで・・・その恐怖、現実にしてあげる!慎治の顔が恐怖に歪み、間もなく自分を襲う苦痛を想像し、絶対に許してもらえないことに絶望しながら、それでも藁をも掴む思いで泣きそうな顔になって哀願するのを見るのが礼子は何より好きだった。慎治、あなたを虐待し、地獄に突き落とす当の私に向かって哀願するその目、大好きよ。必死の努力が徒労になる人間の目って素敵。ずっとずっと、その目をさせたいわ。そして必死の哀願を冷たく踏み躙り、刑の執行を宣告する時の慎治の表情は礼子にとって最上のご馳走だった。絶望、恐怖、そして微かに入る怒りや覚悟の色がまた、何とも言えずいい味を出すスパイスのようだった。止められない・・・こうやって慎治の精神も肉体も嬲り尽くすのって、最高・・・慎治の表情を楽しみながら、礼子は至福の時を噛みしめていた。私、どっちなのかな。慎治のこの表情を楽しむために、鞭を振るって痛めつけているのかな。それとも鞭を楽しむためのオードブルとして慎治の怯えを楽しんでいるのかな・・・まあ、どっちでもいいや。卵が先か鶏が先か、みたいなものね。私、オムレツもフライドチキンも両方とも好きよ。そう、慎治を泣かせるのも大好きだけど、鞭も勿論、大好きなんだから!!!
「さあ,行こうか!」礼子は身を翻すと愛馬に騎乗した。「さあ慎治、どうすればいいかは分かるわね?」慎治の耳元で鞭をヒュンッと鳴らした。「慎治、折角の広いグラウンドよ。自由に逃げていいわ。信次の背中、見たでしょ?追いつかれたら慎治の背中もああなっちゃうわよ?フフ、精々一生懸命逃げることね。いい、もう一度言ってあげる。追いつかれたら・・・痛いわよ?」そ、そんな!!!馬から逃げられるわけない・・・ヒッ!慎治の背中を襲った鞭がゲームの開始を告げた。に、逃げなくちゃ・・・無駄と分かっていても、その場から逃げずにはいられなかった。慎治が50メートルほど逃げた辺りで礼子は声をかけた。「慎治、そろそろいいかな?行くよ!ハッ!」馬に一鞭くれると礼子は慎治を追って馬を走らせた。ドドッ、ドドッ・・・馬の走る音が背後から迫る。や、やだ、追いつかれたくない!!!だが礼子の駆る馬はあっという間に慎治に追いつき、鞭の射程圏内に入った。「ほら遅い!そんなんじゃ背中、すぐ真っ赤になっちゃうよ!」ヒュンッという風を切る音とともに鞭が慎治の背中を襲った。ビシッ・・・「ひ、びあっっっっ」い、痛い・・・いつもの鞭より痛い。馬に乗って高いところから振り下ろす鞭、おまけに走りながらだから馬のスピードまで加わっている。慎治は反射的に体をエビのようにそっくり返らせ、よろける足を絡ませながら必死で逃げようとした。
礼子は慎治が逃げるのを敢えて止めなかった。いいわよ。そう、逃げなさい。私の鞭の痛さが身にしみたでしょ?叩かれたくなかったら逃げなさい!必死で走りなさい!そして慎治が数メートル逃げたところで再び馬を走らせ、鞭を浴びせた。「ひ、いたい!!!」「ふう。礼子ってほんと、悪魔ね。あれじゃ慎治、蛇の生殺しじゃない。一思いに打ちのめしてやればいいのに。」流石の玲子が慎治に些か同情したかのように呟いた。その通りだった。なまじ連続して鞭打たれないため、慎治の苦痛は延々と続いた。礼子の鞭は痛すぎる、強制されないで、自分の意志でその鞭を受け続けることなど不可能だった。一発鞭打たれるたびに慎治は悲鳴をあげながら逃げまどった。体育館と違って壁がない、広い、遮るものが何もないグラウンドだ。ある意味ではどこまででも逃げられる。だが礼子は馬に跨っている。慎治より遥かに素早く動き、鞭で追い立て、自由に慎治の動きをコントロールできる。慎治に逃げる術などなかった。逃げられること、それが却って慎治の苦痛を倍加させていた。背中を襲う鞭の苦痛。逃げても逃げても背後に迫る馬のひづめの音の恐怖。そして休みなく走り続けさせられ、心臓も肺も限界に達していく。脚の筋肉も痙攣しかかっていく。そして見えない背後からいつ襲うかも分からぬ鞭の恐怖と、騎乗の美少女に、自分のクラスメートに追い回される屈辱。心身を内から外から、何重にも苛ぶる礼子の責めだった。気絶しようにも鞭と鞭の合間に僅かながらインターバルがある。連打ではない分、なかなか気絶できない上に、一鞭一鞭フレッシュな痛みをじっくりと味あわされていた。ひ、いっそ一思いに殺して・・・慎治は大粒の涙をこぼし、恥も外聞もなく泣き喚きながら走り回った。そして慎治のその無様な格好は馬上から鞭を振るう礼子にとって、最高の悦楽だった。どれだけ走らされたことだろう。慎治はついに精魂尽き果てて地面にのめりこむように倒れこんだ。「あらあら慎ちゃん、もうダウン?早く起きないと痛い痛いよ?」ピシッ・・・礼子は倒れたままの慎治に一鞭くれた。うぐっ・・・うめき声と共に慎治の背中が動いたが、立ち上がれない。本当に逝っちゃったのかしら?ピシーッ!パシーッンッ!スナップを思いっきり効かせ、礼子は強烈な鞭を立て続けに浴びせた。ひっ・・・びえっ・・・慎治はうめき声を上げたがもう動けなかった。全精力を使い果たし、最早動く気力も礼子の鞭を多少たりともガードしようと手を動かす力さえ残っていなかった。フフ、慎治、どうやら本当に逝ったみたいね。結構楽しかったよ。また遊ぼうね。「ま、こんなもんかしら?みんなおいでよ、私の番はお終いよ!」未だ立ち上がれない慎治の傍らに礼子は皆を呼び寄せた。「わあ、礼子すっごーい!随分いっぱい叩いたんだ。慎治、背中もう真っ赤っ赤じゃん!」富美代が感心したような声をあげた。「本当ねー。玲子と違って連打しなかったけど、結構一杯叩いてたんだね。うーん、信次、ちょっと背中出して!」朝子は二人の背中をじっくりと見比べてみた。「そうね。やっぱり滅多打ちにした分、身体の前の方は玲子の鞭の勝ちだけど、背中については後ろからの追い鞭に徹した分、礼子の勝ちね!」「やーねー二人とも、別にこれ、勝ち負け競ってるわけじゃないじゃん!」玲子の呆れたような声に四人は一斉に大笑いした。だが楽しいのは四人の美少女だけだ。信次たちにとってはちっとも楽しくない。いや、二人にも分かっていた。未だ鞭は終わりでないことを。朝子と富美代も鞭を楽しまなくては収まりがつかないことを。「さあ信次、礼子の鞭の間に少しは休めたでしょ?次は私の番よ!早く順番こないかなって、もううずうずしてたんだから!」朝子が飛び乗るように馬に跨った。「あー、朝子いいなあ。私、またまちぼうけじゃん。」富美代が心底羨ましそうな声をあげた。「お預け、富美ちゃん!まあいいでしょ、富美ちゃん大トリなんだから。ビシッと締めてね、じゃ、お先!」朝子が信次を追いかけまわす間、富美代はずっと自分の鞭プランを考えていた。どうやって追いかけまわそうかな。走らせるのもいいし、タコ殴りもいいし・・・幼馴染を苛める、一緒に遊び、おやつも食べた仲の慎治を地獄に突き落とすことに富美代はなんの躊躇もなかった。いや、躊躇、と言う言葉すら不自然、富美代は既に慎治のことなど、何も考えてなかった。頭の中にあるのは只一つ、どうやって楽しもうか、それだけだった。
3
朝子と富美代が鞭を終えた時、慎治たち二人は最早息も絶え絶えだった。全身に無数に鞭を浴び、体中真っ赤、蚯蚓腫れと青痣に彩られていた。体力も気力も限界に達していた。「も、もう・・・ゆるして・・・」倒れこんだまま慎治はうめいた。余りに多くの鞭を受け、背中の感覚、痛覚すら薄れつつあった。パカッ、パカッ・・・馬の軽い足音がした。しかも一人ではなく四人全員の音のようだった。ま、また、今度は全員・・・死んじゃう・・・だが足音は慎治から遠ざかっていった。遠くで礼子たちの明るい声が聞こえた。なんだろう。だが首を動かす気力もなかった。5分ほど経っただろうか、「慎治、慎治ったら、早くおいでよ!」礼子の声に必死の思いで起き上がると、礼子たちはスタート地点にシートを広げ、ランチの用意をしていた。「ほら慎治、いつまでも寝てないで早くおいでよ、お昼にしよう!」富美代が手招きしていた。のろのろと慎治が歩いていくと、驚いたことに慎治たちの席もちゃんとあった。慎治は礼子と富美代の間に。そして信次は玲子と朝子の間に。サンドイッチ、鶏の唐揚げ、ウインナー、サラダ・・・色とりどりの典型的なピクニックランチが並んでいた。「どう慎治、みんなで分担して作ったんだからね。結構おいしそうでしょ?感謝してよ。私たちの手作りお弁当を食べられるなんて、クラスの男の子たちが聞いたら泣いて羨ましがるわよ?」ランチは確かにおいしかった。どうせ残飯を投げ与えられるか、またブーツで踏み潰されたものを犬食いさせられるのか・・・と思っていたが、そうではなかった。玲子たち四人はそんな素振りは一切見せず、むしろ甲斐甲斐しく慎治たちの皿に色々と取ってやり、飲み物を与え、食後のデザートまでくれた。フルーツとチョコケーキ。疲れ果てた身体に糖分は何よりのご馳走だった。良かった・・・どうやら四人とも、満足してくれたみたいだな・・・そうだよな、あれだけ鞭を振るったんだ。もう十分だよな。ランチが終わったら、きっと帰れる・・・喉元過ぎればなんとやら、信次たちの読みは相変わらず甘すぎた。夏休みの別荘を思い出すべきだった。玲子たちが食事と睡眠だけは十分にくれたことを。大事な玩具を責め潰さないために、メンテナンスには抜かりないことを。
破局はすぐにやってきた。食休みも終えランチセットを片付けると礼子が慎治に向き直った。「どう、慎治。午前中の私たちの鞭、痛かった?」「は、はい・・・とても痛かったです。ほ、ほんと、死にそうなくらい痛かったです・・・」「そう。そりゃそうよねー。みんな結構本気で叩いてたものね。でも慎治、お弁当も十分食べたし、結構ゆっくり休んだから大分体力回復したんじゃない?」「そうよね、礼子。ほら見てごらんよ、信次なんか、さっきは死にそうな蒼い顔してたのに、今じゃすっかり顔色も良くなってるわよ。」礼子たちのこのセリフが何を意味するか、慎治たちにももうわかっていた。「ま、まさか、そんな・・!」ニコッと礼子は天使のような優しい笑顔で答えた。「そうよ、午後の部、開始よ。」や、やだーっ!!!慎治たちの悲鳴を全く無視しながら礼子は続けた。「あ、みんな、午後の部開始の前にトイレ行っとく?私、さっきから我慢してたんだ。玲子がね、あっちに簡易トイレ作っといてくれたんだって。」礼子が指差した先にあるものはグラウンドの隅にある用具倉庫、それも鍵をかけられており、入ることはできなそうだった。そして建物らしきものは、他には何もなかった。と、トイレって・・・なにもないじゃない・・・どこでするの?ま、まさか・・・そのとおり、慎治たちが引き立てられた先は倉庫の横だった。凍りつく信次に玲子がごく自然な口調で宣告した。「野外トイレは信次たちの口に決まってるでしょ?でもね、私も礼子も信次たちに飲ませるのはいいけど、互いの見てるとこでパンツおろす気にはならないわよね。朝子たちもそうでしょ?だからね、両側に一つずつトイレ作ったんだ。それならお互いに見られないでできるからね。」そ、そんな・・・先週、富美代と朝子のおしっこを飲まされた記憶がリアルに蘇った。ま、また飲まされる・・・礼子たちだけではなく、富美代と朝子のおしっこも飲まされる、共同便所への転落。だが礼子たちにとって慎治たちの葛藤など、知ったことではない。二人はそのまま野外トイレに引き立てられ、寝転がされた。まず礼子たち、そして富美代と朝子、立て続けにたっぷりとおしっこを飲まされ、口中一杯に塩気とアンモニアの香りが生臭く漂う。だが便器になるだけでは済まされない。午後の部、新たな鞭が慎治たちに忍び寄っていた。
「さあ、じゃあそろそろ始めようか。」玲子の声に信次たちは現実に連れ戻された。始める・・・痣だらけの全身に痛みがリアルに甦った。い、一体何を・・・信次は必死で無い知恵を絞って考えてみた。今まで玲子たちはこういうイベント的な苛めの時、どんな事をしたっけ?何かパターンがあったはず・・・そう、バリエーション、だ。同じ鞭でも責めのパターンを変え、より多くの恐怖と苦痛を与えようとする。それが玲子たちの苛めのパターンだ。だったら、どう苛める気だ?馬、新しい責め・・・想像がつかなかった。分からない分、恐怖だけが一人歩きしていった。信次が必死で考えているのに気づいた礼子が声をかけた。「信次、何考え込んでるの?もしかして、どう苛められるのかなあ、て考えてた?そうだよね。いつもは信次が先責めでやられてるからね。だけどまあ、今は安心していいよ。」ビクッと慎治が震えた。礼子の読み通り、慎治はとりあえず何も考えずに現実逃避しようとしていた。どうせ信次が責められるところをたっぷり見せ付けられる。嫌というほど怖がらせられるんだ。だったら、せめて今は何も考えたくない・・・慎治の心は空白状態、責められる心の準備が出来ていなかった。「えっっっ、ぼ、僕からなの?!」「そうよ慎治、先攻玲子、後攻私がルールだなんて、誰が決めたの?たまには私か先攻の時もあるのよ。」礼子は楽しそうに笑っていた。バカね慎治、すっかり油断してたでしょ?何もいつもいつも拷問見物させるだけが能じゃないのよ。油断させといての先責め、て言うのも結構、堪える精神的拷問でしょ?
突然の恐怖に震える慎治を見下ろしていた礼子がすっと馬から降りてきた。え・・・慎治が直感的に予想していたのは二人懸かりでの鞭打ちだった。きっと礼子と富美代の二人に追い回され、鞭打たれるに違いない。だが礼子の想像力は慎治の遥か上にあった。下馬した礼子が用意したのは長いロープだった。訝しげに玲子が尋ねた。「ねえ礼子、何する気?縛るの?礼子が私と違って、抵抗できなくしてから鞭打つのが大好きなのは知ってるけどさ、なんか、折角こんな広いとこに来たのに勿体無くない?」「フフ、大丈夫、大丈夫。私がそんなぬるいこと、するわけないでしょ?まあ、ゆっくり見ててよ。慎治、両手を出して!」礼子は慎治に両手を出させると、手首のところで厳重に縛りあげた。だが、他の所はまったく自由のままだ。10メートル以上ある長いロープは慎治の両手を何重にも縛っても尚、相当な長さを残していた。「れ、礼子さん・・・な、何を、何をするんです・・・か・!?」恐怖に怯え、泣きべそをかきながら慎治は必死で尋ねた。聞きたくはない。どんな酷い目に合わされるのか、知りたくもない。だが、聞かずにはいられなかった。
「フフ、慎治、怖い?でも安心していいわよ。私、鞭を使うつもりはないから。それだけは約束してあげる。」え・・・鞭、じゃない・・?ほっとした慎治の背筋にぞくっと寒気が走った。な、何を安心しているんだ俺は。鞭じゃないからって、礼子さんはきっと、鞭よりもっと酷いことを企んでいるに違いない!なんだなんだ・・・鞭じゃない・・・ロープ・・・縛る・・・しかも両手のみ・・ま、まさか!!!「そうよ、慎治、どうやら感づいたみたいね。」礼子は残忍な笑みを浮かべつつ、慎治の両手を縛ったロープのもう片端を馬の鞍の後ろに結んだ。「そうよ。前にも言ったわね。私、子供の頃西部劇が大好きで、特に悪漢が町の人をリンチしたり拷問するシーンが大好きだった、て。慎治も西部劇で見たことあるでしょ、悪漢がこうやって縛った人たちのことを馬で引き摺り回してボロボロにするのって。」ガチガチ・・・慎治の歯が恐怖の余り勝手に震えだしていた。「や、、、やめて・・・お、願い・・・」消え入りそうな声で慎治は哀願した。震える慎治の頬を優しく撫で、天使のような微笑を浮かべながら礼子は宣告した。「慎治、今からあなたのこと、たっぷりと引き摺り回してあげるわね。」現実認識を失い、声も出せずに立ちすくんでいる慎治の頬に軽くキスすると礼子は身を翻し、愛馬に跨った。「行くわよ、ハッ!」礼子はゆっくりと馬を歩かせはじめた。緩んでいたロープはすぐにピンと張り、引きずられた慎治が歩き始めた。「そうそう慎治、必死でついてくることね。転んだら終りよ。」礼子は徐々にスピードを上げていった。慎治は必死で走り出す。だが馬と人間のスピードは違いすぎる。「ひっ、、、ま、待って!も、もっとゆっくり・・・スピード、落として!!!」後ろを振り返り、慎治が恐怖に顔を歪ませながら絶叫するのを見た礼子は、楽しげに笑いながら更にスピードを上げた。慎治は徐々に悲鳴すら出せなくなっていく。鈍足の慎治にとってはもう,フルスピードに近い。そして人間がフルスピードを出し続けられるのはオリンピック選手クラスでも10秒が限界だ。慎治はあっという間に限界に達してしまった。礼子は振り返り、慎治が限界に来ていることを見極めた。いいわ慎治、いたぶるのはこの程度にしてあげる。さあ、本番逝くわよ!礼子は右手を高く上げ、ピシリと乗馬鞭で愛馬の尻を打つと同時にブーツの拍車で腹を蹴った。GO!礼子の愛馬は騎乗の美少女の意図を的確に理解し、それまでの早足から一気に駆け出した。あっと言う間もない。慎治はそれでも必死で若干の距離を走ったが馬のスピードに追いつけるわけがない。千切れそうな腕の痛みと共に慎治の上半身が前方に引き倒されていき、足が絡まりはじめた。限界より速く走られると、いくら足を前に動かそうとしても、最早単に抵抗になるだけだった。「ひっ!」悲鳴をあげながら遂に、慎治はつんのめるように膝を地面についた。立ち上がる暇などない。膝を支点にして倒れこみながらも慎治の腕は前方に引き伸ばされ、そのまま膝が、腹が、胸が地面を滑り出した。慎治の目の前を芝生とあちこちに伸びる雑草が高速で通り過ぎていく。ロープに縛られた手首から肩にかけて全体重がかかり、引っこ抜かれるような激痛が走った。「ビアーっっっっや、やべでーーー!!!」断末魔のような悲鳴をあげつつ慎治は引き摺られていった。礼子は馬を疾走させながら振り返った。自分が駆る馬に引き摺られ、慎治が悲鳴を上げていた。自分の愛馬で人間を引き摺り回している!長い間、夢にまで見た光景だった。最高!私、これをやるために乗馬を習ったのかもね。「ほらほら慎治、まだまだ引き摺り回してやるからね!」ピッチの端に来た礼子は、そのまま馬を返すと反対側に走らせた。
4
一旦、ロープは緩んだもののあっという間に反対向きにピンと張り詰め、再び慎治を引き摺り回す。しかも今度は回転したタイミングのせいか、慎治は仰向けにひっくり返り、背中を下にして引きずられていった。「ぎあ——!」慎治の悲鳴が轟いた。今度は秋晴れの澄んだ青空が慎治の視界を流れていく。だが慎治にそんな青空を眺めている余裕などない。肩に、さっきとは異なる角度からの痛みが襲い掛かった。礼子はわざとグラウンド内の、芝生に覆われたサッカー用のピッチからは出なかった。硬い土のグラウンドを引き摺り回せば慎治により多くの苦痛を与えられるのは分かっていたが、そうするつもりはなかった。なにしろ鞭を楽しむために、慎治は一糸まとわぬ裸にひん剥いてあるのだ。そのまま土の上を引き摺り回したりしたら、あっという間に全身の皮膚が擦り剥けてしまう。別に慎治が因幡の白兎になろうがどうなろうが礼子の知ったことではないが、流石にずる剥けになってしまっては、今日のパーティーはお開きになってしまう。そんな勿体無いことをするつもりは毛頭なかった。だから礼子はあえて、慎治を引き摺り回すのは柔らかい芝生と雑草で保護されたピッチ内だけに留めていた。だが慎治の苦痛は十二分に酷いものだった。腕が痛いだけではない。いくら柔らかい芝生の上とは言っても、高速で引き摺り回されては全身、地面との摩擦で焼けるように痛い。そして整備されていないピッチは決して平面ではない。スパイクの跡、草の根・・・細かい起伏がたくさんあり、それらのギャップに跳ねられて慎治の全身は微妙にバウンドしながら引き摺られていった。苛め、といった領域を遥かに通り越した礼子の責めだった。「もう駄目!!!誰か、誰か助けてーーっ!!お願いーーっっっ!!!」スタート地点まで引き戻され、礼子が再びUターンしようとした時、慎治は玲子たちに向かって必死で絶叫した。玲子たちの誰かが止めてくれることを期待して。誰かは分からない。だが三人もいるのだ。誰か一人くらいは流石に見かねて止めてくれるだろうと期待して。だが、慎治は未だ甘かった。玲子たちにとって、慎治の苦痛など単なる遊び道具でしかないのだから。一対一の時だったら多少は情けも期待できたかもしれない。だが四人集まった時の礼子たちの集団心理は慎治が期待したのとは正反対の方向に働いていた。残虐性は四倍、いや四乗に、そして同情心は四分の一、いや四乗根に。
慎治の悲鳴に真っ先に反応したのは富美代、幼馴染、ということでせめて富美ちゃんは助けてくれるんじゃないか、と慎治が最も期待していた当の富美代その人であった。「礼子楽しそう!私もジョインする!」再び引き摺られていく慎治を追いかけるように、富美代は自分の馬に鞭を入れ走り出した。走りながら乗馬鞭を一本鞭に持ち替え、その鞭をヒュンヒュン振り回しながら慎治に並走する富美代を見て、礼子は富美代が何をするつもりか直ぐに理解した。「OK,OK,富美ちゃん、やっちゃってくださーいっ!」おどけたような礼子の声を合図に富美代は引き摺られていく慎治の背中に思いっきり鞭を振り下ろした。「ぎあ——!」慎治が獣のような悲鳴を上げた。「アハハハハッ!最高!ほら慎治、もっともっと泣いちゃえーっ、ほらほらほらほら!!!!」富美代は慎治の悲鳴に興奮し、一層激しく、凄まじいピッチで間断なく鞭を振り下ろした。ドドッ、ドドッと二頭の馬が走る重い音、ズザーッという慎治の肉体が引き摺られる音、そしてヒュンヒュン唸る富美代の鞭の風切り音とビシッ、バシッと振り下ろされる鞭が慎治の裸体を打ち据える音。そして礼子と富美代のキャハハッという心の底からこみ上げる、抑えようのない楽しさを満喫している笑い声とビア゛<bと全身を間断なく苛む激痛に声にすらならない慎治の絶叫。天国と地獄の音がコントラストを描いてグラウンド中に響いていた。
そして玲子と朝子も興奮のピークに達していた。「朝子、私たちも行こう!」ヒッ、目の前で繰り広げられる狂宴を呆然と眺めていた信次の全身に電流が走った。に、逃げなくちゃ!!!信次は恐怖に足を絡ませながら必死で逃げようとした。だが、「ぐえっ・・」三歩と逃げないうちに信次は背後から首に絡まりついた黒い蛇に締め上げられ、苦しげな悲鳴を上げた。「どこ逃げる気よ信次!逃げられるとでも思っているの!」玲子の鞭が素早く信次の首に絡まりつき、締め上げていた。「そうよ信次、余計な手間かけさせないでよ!この馬鹿!」駆け寄った朝子の右拳、ついで右膝が信次の鳩尾にめり込んだ。「ぐぼっ・・」思わずうずくまる信次の背中を蹴り倒すと朝子は素早く背中に馬乗りになり、両手を縛り上げた。「玲子!」朝子が放り投げたロープの反対端をキャッチすると、玲子は自分の馬の鞍に結びつけた。「ほら信次、手間かけさせた罰よ!」朝子が信次の腹を数回、立て続けに蹴りつけた。固いブーツの爪先が腹にめり込む。さらに朝子は全体重をかけながら信次の顔を踏みつけた。朝子のブーツの底に踏み躙られる信次の頭は、そのまま地面にめり込んで行きそうだった。痛い。だが、信次としてはこの程度の痛みにうめいているほうが遥かに幸せだった。「朝子、遊んでないで早くおいでよ、置いてくよ!」「あん、待ってよ玲子ったら!」玲子の興奮しきって上ずった声に朝子はハッと我に返り、お遊びを止め自分の愛馬に駆け寄って行った。朝子が馬に跨り、鞭を握ったのを確認すると玲子は大声を上げた。「朝子、準備OK?よし、じゃあ信次、覚悟はいいわね、行くわよ!ハッ!」「いやーっ!やべでーっ!!!」胃袋を破裂させるかのような朝子のトーキックに呻いていた信次は、未だ立ち上がることすらできない。だが悠長に痛みが治まるのを待っている余裕など、玲子たちは与えてくれなかった。信次は地べたに這いつくばったまま悲鳴を上げながらロープに引き摺られはじめた。「い、いだだだ゛!!」か、肩が抜ける・・・玲子が鞭と拍車を使い、馬のスピードを上げていく。「ぎ、ギヴァーーーーーっっっ!!!」全身の関節がバラバラになりそうな苦痛と引き摺り回される恐怖に狂ったように絶叫しながら、嫌々をするように左右に首を激しく振る信次の視界にもう一頭の馬が見えた。朝子の馬だった。朝子は馬のスピードを巧みに調節し、引き摺りまわされる信次とピッタリ並走しながら右手に握った鞭をヒュンヒュンと水車のように振り回していた。「ほら信次、頭上にご注意!」ビュォッ、朝子が振り下ろした鞭が信次の背中めがけて襲い掛かった。パシッ・・・手加減抜きの鞭が信次の背中に更なる苦痛を加える。バシ、パシ、ピシ・・・朝子は完全に頭に血が上ってしまったかのように、間断なく鞭の雨を降らせた。仰向け、うつぶせ関係ない。地面を引きずられる痛みと鞭の痛みと、上下から同時に襲ってくる激痛は片時の休みもない。しかも両手を縛られて引き摺られているのだ。体のどこをガードすることもできない。ただひたすら苦痛を味わうこと。信次にできることはそれだけだった。そして鞭の痛さに体をよじったり膝や肘を立てたりすると、それが抵抗となって体がバウンドし、信次を更に苦しめる。そしてバウンドしながら引き摺りまわされる信次の姿は、玲子と朝子から見ると珍妙なダンスを踊っているようだった。「ビアーーッッッッ!!!」信次は叫び続けた。獣のような声だ、何で自分がこんな声を出せるのか理解できなかった。本能的な、断末魔の叫びなのかも知れない。だが叫び続けることが唯一、自分を確認させてくれることだった。叫び続けないと気が狂ってしまいそうだった。
何周引き摺り回されただろうか。礼子たちの馬は漸く止まった。ハアハア・・・やっ、やっと終わった・・・慎治たちは芝生に顔を埋めたまま喘いでいた。鞍からロープを外し、二人が降りてきた。「どーお慎治、楽しい?私、最高よ、夢がかなって最高にハッピーよ。」礼子はブーツの爪先で慎治の頬を小突きながら笑った。返事をする気力もない慎治に礼子は更に続けた。「慎治、まさかもう、引き回しの刑が終わったなんて思ってないでしょうね?これからプレイヤー交代なんだからね。」こ、交代・・・まさか・・・真っ白になっていた信次の頭にも急速に意識が戻ってきた。こうたいこうたい・・・まさか!!「ブギャッ!」立ち上がろうとした信次の頭を玲子が踏みつけた。「玲子―、早く早く!私も引き摺りたいーっ!」「ハイハイ、もう朝子ったら駄々っ子ちゃんなんだから、ほら、早く結びなさい!」玲子の鞍から外したロープを、今度は朝子が自分の愛馬の鞍につないでいた。「ヤ、ヤダーッ!」信次は必死で起き上がろうとしたが、玲子のブーツにグイッと力が込められ、踏み潰されたまま地面に顔をめり込まされてしまった。「ああ信次、今いいとこなんだからさ、ちょっとの間大人しくしてなさい。すぐ遊んであげるから。」朝子と富美代がロープをつなぎ終えると同時に玲子たちは信次たちを靴底から解放してやった。頭を踏み潰される苦痛から解放され、一瞬信次たちはほっとした。だが、すぐに拷問が再開された。「さあ行くよ!」今度は富美代と朝子が引摺役、礼子たちが鞭打役だった。「ギアーッ!!!た、助けてーっっっ!」「ま、ママーッ、ママーッッッ!!!痛い、痛いよーーっっっ!」慎治たちは絶叫しながら引き摺られていった。鞭を振るいながら礼子は慎治の苦悶をじっくりと鑑賞していた。さっき引き摺り回した時は慎治の様子をずっと見ていられた訳ではない。チラチラと頻繁に後ろを見ながら、苦痛に喚きつつ必死で自分に哀願する慎治の顔を楽しんではいたが、こうやって横から見ているほどじっくりと楽しめた訳ではない。だが、富美代に引き摺られながらだと、慎治の苦悶の様子が特等席で、ライブで鑑賞できる。いいわ。引き摺るのもいいけど、こうやって横から鑑賞するのもまた楽しいわね。鑑賞、と言っても鞭を振る手は片時も止まらないのだが。
楽しんでいるのは玲子も同じだった。芝生の上を引き摺られていく信次の体に自分の鞭が当たるたび、ビクッ、ビクッと反射的に信次の体が震える。その痙攣が新たな抵抗を生み、信次の体を微妙にジャンプさせて引き摺られていく苦痛を倍加させる。朝子と私、息あってるじゃん!信次の苦痛を更に引き出すべく、玲子は腕も千切れよとばかりに鞭を大きく振るった。スナップも思いっきり効かせた。せ、背中が裂ける・・・信次は上下から同時に加えられる激痛に喚き続けた。上から下から、いや腕、肩も加えて前後から、まるで両面グリルに入れられた焼き魚のように、信次の全身は苦痛の炎でじっくりと炙られていた。バーベキュー、苦痛のバーベキューだ。生きながらにして炎に炙られる生き地獄。ピッチを何周も何周も引き摺り回され、漸く解放された時、信次たちは二人とも全身ボロボロ、胸も腹も背中も尻も、全身を真っ赤に腫れ上がらせ、蚯蚓腫れを蜘蛛の巣のようにまとい、そして血を滲ませていた。立つことはおろか、ピクリと動く気力すらなかった。「み、水・・・」慎治は虫の息で喘いでいた。全身を、体の表も裏も苦痛だけが支配していた。焼けつくような痛み、擦り傷、打ち身、手首も肩も脱臼しかかっていた。そして手首にはくっきりとロープの跡が刻まれていた。だが一番辛いのは喉の渇きだった。絶叫し続けた喉は血が出ているのかと思うほど痛く、何より隈なく痛めつけられた全身が水分を欲していた。水分に対する欲求、生物の本能とも言える欲求だった。だが、慎治たちに与えられる水分は当然の如く、礼子たちの排泄物、人間にとって最悪の屈辱に満ちた汚水だけだ。「み、水・・・」信次もうめいた。「二人とも水が飲みたいの?いいわ、飲ませてあげる。じゃ、どこに行けば飲ませてもらえるか、分かるわね?」礼子が相変わらず優しげな笑顔を浮かべながら答えた。どこに行けば・・・そうか、おしっこか・・・慎治たちはのろのろと這うように用具倉庫横の簡易便所に歩き始めた。最早おしっこを飲まされることに抗議する気力すらなかった。いや、二人とも内心の葛藤はただ一つ、おしっこを飲むことに対する葛藤ではなく、おしっこを飲める、兎に角水分を補給できる、と喜んでいる自分のあさましさ、卑しさに対する葛藤だけだった。信次がブロックの間に横たわると間もなく、玲子がやってきた。「フフ、信次、水を飲ませてあげる、て言っただけでちゃんとトイレに行くなんて、結構躾が行き届いてきたみたいね。いいわ、信次の口、段々便器が板についてきたわよ。」ゆっくり、じっくりと排泄を楽しむ玲子の尻の下で信次も束の間の幸せに浸っていた。待ちに待った水分が体にしみていく。何より、こうやっておしっこを飲まされている間は鞭で打たれる心配だけはない・・・玲子が立ち去ると入れ替わりに朝子が入ってきた。「ジャーン、信次、今日二回目のトイレットタイムね。」朝子もなんの躊躇も無くブロックに上り、乗馬ズボンとパンティを下ろすと信次の顔面にしゃがみ込んだ。「全く、信次ったら水を飲む、て聞いただけで黙ってトイレに直行だもんね。呆れちゃったわよ。あ、でもそうか。信次は女の子のおしっこ飲んでも恥ずかしげも無く生きていられる変態ちゃんだもんね。信次にとってはここが水飲み場なんだ。私たち人間にとってはトイレなんだけどね、私たちが汚いものを排泄する出口が信次にとっては入口なわけね。」
悔しい、汚らわしい、おぞましい・・・発狂しそうな屈辱を味わいながら慎治たちは四人の美少女のおしっこを飲み続けた。何度飲まされても決して慣れるものではない。まさに人格否定。SMプレイの乗りで「女王様のご聖水をお飲み!」とでもやられれば、まだ遊び、冗談、と割り切って自分を誤魔化すこともできる。だが礼子たちは、あくまで単純におしっこを排泄しているだけなのだ。その排泄物を無理やり飲まされている。余りにも当然に飲まされている。こんな苛めに馴れるわけがない。しかし、慎治たちはおしっこを拒絶するには余りに打ちのめされていた。全身ボロボロ、とにかく水分が欲しい。そしてもう一つ、寒かった。もう秋、いくら快晴といっても日差しは強くない。素っ裸でいると、鞭で追い回されている間はまだしも、立ち止まって暫くすると寒くて震えが止まらないほどだった。寒さと鞭で追い回される惨めさと消耗し尽くしたプアな体力と・・・慎治たちは濡れネズミのようにブルブルと震えていた。そして寒さに震える体に・・・礼子たちのおしっこは暖かく、優しかった。美少女の体温と同じ温度まで温められた水。それが人間にとって最も汚い他人の排泄物であっても尚、その汚水に慎治たちの凍えた体が中から温められていることは確かな事実だった。それはあたかも命の水であるかのように、二人の体に浸みこんでいった。礼子のおしっこが口に注がれた時、慎治は不覚にもああ、おいしい・・・と陶然としかけていた。寒さに震えながら漸く家に辿り着いて飲む熱いミルクティーのようだった。礼子が放尿を終え立ち去った後、良かった、未だ富美ちゃんのおしっこも飲めるな、早く富美ちゃんこないかな、という考えが慎治の頭を掠めた。な、なんで俺はほっとしているんだ!も、もっと飲みたいだなんて、お、俺はおしっこを、おしっこを飲まされているんだぞ!!!だがいくら必死で否定しても、慎治の心の中のもっとおしっこを飲みたい、という欲求は消しようがなかった。そして、それは信次も同様だった。たっぷりと放尿を終えた玲子が立ち去ると信次もまた、思わずああ、もっと・・・と言いたくなっていた。そして朝子が現れた時、思わず嬉しい、とさえ感じてしまったほどだった。
玲子たちの鞭道場は毎週末、三週間連荘で開催された。玲子たちは我流で技を磨き、試行錯誤もあったのに対し、富美代と朝子は玲子たちの経験を活かし、効率よく鞭の極意を吸収していった。その三週間で富美代たちはのべ1000発は鞭を振るったであろうか。とりも直さず慎治たちは1000発以上の鞭を浴びたことになる。鞭道場が終了し、礼子たちが鞭道免許皆伝を言い渡した時、富美代も朝子も鞭を自在に使いこなせるようになっていた。手首のコントロール一つで強く、弱く。打ち据えたり手足に絡めて引きずり倒したり。間合いを調整して先端部分のみをヒットさせたり身体に絡みつくように打ち据えたり。信次たちの苦痛を自由自在にコントロールできるようになっていた。
さて、礼子たちはもともと同じ乗馬クラブ、郊外の丘陵地帯に位置する由緒あるクラブのメンバーだった。五月頃、富美代と朝子も二人に誘われてこのクラブの会員になっていた。このクラブのメンバー資格審査は厳しいものの、先代からの会員である礼子たちの紹介であれば審査はフリーパスだ。しかも富美代と朝子も家柄はかなりよく、経済的にも十分余裕があり、二人の上品な雰囲気はクラブに問題なく溶け込めそうだった。礼子たちが誘うと、富美代も朝子も大乗り気だった。そして双方の両親共、娘が礼子たちと同じ乗馬クラブに入りたい、と切り出すと二つ返事でOKだった。流石に富美代も朝子も、週末だけの練習なので礼子たちみたいに障害競技までこなすプロ級の腕前、とは行かないものの普通に馬を乗りこなし、意のままに走らせる程度は全く問題なくこなせるレベルに達していた。そして天気予報が軒並み週末の秋晴れを予想したある日、玲子が今度の週末、四人そろってクラブに行こう、と切り出した。「クラブ?」確かにこのところ週末は慎治たちを苛めるのに忙しく、クラブにも少し足が遠のいていた。「いいよ、確かに久しく行ってないし。楽しそうね・・・だけど、なんで急に?玲子、何か企んでるんじゃない?」朝子の疑問は当然のことだった。「うん!実は先週の日曜ね、私クラブでちょっと遠乗りしてきたんだ。そこで結構逝けてる場所見つけたのよ!こりゃ、みんなで来るしかないなって思って。幸い明日はお天気もいいみたいでしょ?みんなで行こうよ!」土下座している信次の頭を踏みながらクスリと朝子が笑った。「逝けてる、て玲子、それ勿論、信次たちと遊ぶのに逝けてる、て意味でしょ?なに見つけたのよ、教えてよ?」「フフ、信次たちと遊ぶ場所だ、ていうのは確かなんだけどね。ま、どういうとこかは着いてからのお楽しみにしようよ。実はね、もう良治先生たちに車を出してもらうのも頼んどいたんだ!」信次たちの予定など一切お構いなしに玲子たちはさっさと予定をセットしてしまった。
そして翌日、処刑場に引きずられる羊のように悲しげな顔をして信次たちは集合場所に現れた。「やあ信次君、遅かったじゃないか!君がラストだよ!」相変わらず妙に爽やかな声と笑顔で亮司が声をかけてきた。傍らには自分と同じく、この上なく悲しげな顔をした慎治がいた。「全く、二人ともなに暗い顔してるんだい?礼子ちゃんたちだけでなくて今日は可愛い子が四人も一緒に遊んでくれる、ていうんだよ?もっとうきうきした顔しなくちゃ、だめじゃないか!」良治の声に礼子も大きくうなづいた。「そうよ慎治、全く二人とも暗いんだから!お天気もいいし、明るくパーッといきましょ!」な、なにが明るくパーッとだ・・・声にならない慎治たちの声を無視するかのように二台のランクルは走り出した。良治たちと礼子たち、六人が楽しくはしゃいでいるのに対し、慎治たち二人だけが泣きそうな顔で震えていた。やがて高速を降り、丘陵地帯へと入っていったランクルは目指すクラブのフロントに滑り込んでいった。「さあ着いたわよ!さっさと降りて!」玲子の声に弾かれ、車から降りた信次は気圧されたように辺りを見回した。無理もない、そこは高級な乗馬クラブ、ある種の社交クラブ的な雰囲気を漂わせていた。信次たちとは一生縁のないような上品な、そしてどこか威厳のある人間ばかりが歩いていた。そういった人たちと玲子たちは親しげに挨拶を交わしていた。自分たちの知らない上流社会。そこに自然に溶け込んでいる玲子たち。そして朝子たちでさえ、既にその社会に暖かく迎え入れられていた。だが、卑屈さを全身から発散し、おどおどしている信次たちに構う人は誰もいなかった。なに、あれ・・・場違いなぼうやたちね・・・バイトにでも来たのかしら・・・言葉こそないが、まさに白眼視、信次たちだけが疎外されていた。
おどおどしている信次たちに構わず、一通り挨拶を済ませた玲子たちはさっさとチェックインの手続きをした。「ほら信次、あんたのロッカーのキーよ。ぐずぐすしないでさっさと着替えてくる!」ポーン、とキーを二つ放り投げると玲子たちは女性用ロッカールームに入っていった。えっ・・・見ると良治たちが男性用のロッカールームに入っていくのが見えた。あ、あっちか・・・着替え終えた信次たちが外に出て暫くすると、玲子たちが出てきた。四人ともお揃いのファッションだ。ハッ・・・慎治は思わず息を呑んだ。白いシャツの上にクラブのロゴが入った、鮮やかな赤いジャケット。下半身は白の乗馬パンツにピカピカに磨き上げられ、黒光りする乗馬ブーツを履いている。そして手には信次たちが見慣れたもの・・・長い乗馬鞭をしならせていた。その姿はまさに、慎治が中学生の時憧れていた高嶺の花、クラス中に出回った写真をひそかに購入して何度も何度も溜息交じりで見つめ続けた、憧れの天城礼子の姿そのものだった。いや、こうして間近に見る礼子の姿は写真撮影時から1年の成長を反映し、更に美しさを増していた。礼子の美貌、長身、高級そうなウェア、どれを取っても慎治たちが永久に持ち得ないものだ。そもそも慎治たちではこのクラブにビジターで入ることすらままならない。乗馬服など、一生着る機会すらないだろう。着古した、薄汚れたスウェット上下とスニーカー姿の慎治にとって、間近で見る礼子の乗馬服姿は単に美しい、と言う言葉では言い表せない。それはあらゆる面で恵まれた礼子と何もない慎治との身分差を凝縮していた。美しい・・・だが同時に礼子の乗馬服姿は威厳と高慢に満ちていた。そして今日、慎治の目の前にいるのは礼子だけではない。玲子に富美代、朝子の三人もいた。礼子に負けず劣らず長身の玲子、そして小柄な富美代と朝子。三人とも細身で脚がスラリと長く、見事なスタイルだ。だが礼子も含め、四人を際立たせているのはスタイル、ルックスだけではない。乗馬服を着こなしていることだった。どんなスポーツでも同じだが、全く同じウェアを着ても上級者と初心者では一目瞭然に差が分かる。高級なウェアになればなるほど、初心者が着るといかにも不自然、服に着られている、と言った印象を与えてしまう。礼子たち四人はいずれも、乗馬服を見事に着こなしていた。高級かつ閉鎖的なクラブの雰囲気に溶け込み、乗馬服を見事に着こなした四人。クラブの中でも一際目立ち、礼子たちの周りだけ華やかな雰囲気が漂っていた。
慎治の視線が釘付けになっているのを礼子は満足げに眺めていた。恐怖に震えながらもぼうっと自分を見つめている慎治の呆け顔に大きく頷きながら礼子が口を開いた。「慎治、どう、私の乗馬服姿、生で見るのは初めてでしょ?遠慮しないで見ていいわよ。慎治も中学の時、私の乗馬服姿の写真、買ってたらしいじゃん?あの写真も確か今日のと同じ、白のパンツに赤いジャケットのコンビだったわね。フフ、如何かしら、憧れの私の乗馬服姿は?お気に召した?」「か、買ってたって・・・そ、そんな、し、知ってたの!?」「当たり前でしょ!そういうことはね、いくら隠していたって本人には結構確実に伝わるものよ。全くもうこの写真小僧たちは!て結構、本気で怒ってたのよ。一度本気でとっちめてやろうか、て思ってた位。フフ、あのとき我慢してあげた貸し、返して貰うわよ。慎治、今日は覚悟しておくのね。私の乗馬服姿の拝観料、高いわよ!ましてや玲子に富美代に朝子、聖華の美女軍団四人がそろって極めてきてあげたんだからね、これは高くつくわよー・・・慎治に払えるかしらね。」確かに礼子の乗馬姿は惚れ惚れするほど格好よかった。だが、いくら格好よくても、苛められる、それも息も絶え絶えになるほど鞭で打たれる、というのでは憧れなど、最早持ちようがなかった。憧れより恐怖の方が遥かに大きい。乗馬服姿で極めた四人は立っているだけで強烈な威厳がある。そして礼子たちが気合の入った服装をすることが何を意味するか。この前のブーツ責めで十二分に思い知らされていた。礼子たちは部活で道着に着替えると気合が入ってくるのと同じように、服装によって気合の入り方が違ってくるタイプだった。礼子たちが特別な服装に着替える、それは礼子たちの心のブレーキを解除するスイッチ、残忍性をフルに解放するスイッチが入ることを意味する。こ、怖い・・・何も言われなくとも礼子たちの意気込みがヒシヒシと伝わってくる。信次も全く同じ事を感じていた。玲子の手にしている乗馬鞭が今にも襲いかかってくる恐怖に、信次はその鞭から目が離せなかった。信次が早くも顔面蒼白で怯えているのを見て朝子がクスクス笑った。「やーねー信次ったら!玲子の鞭をそんなに見つめちゃって!そんなに早く鞭が欲しいの?」「あ、本当だ!でもね信次、この鞭はお馬さん用なの。信次を叩いた鞭で触っちゃったりしたらお馬さんが可哀想でしょ?信次の鞭はここに入っているからね。あとでゆっくりご馳走してあげる!」パンッと玲子がバッグを叩いた。そこへ従業員が四頭の馬を連れてきた。「お待たせしました。いつもの四頭です。今日は遠乗りでしたね。お気をつけて、ごゆっくりどうぞ。」従業員は礼子たち四人に馬を引き渡すと、慎治たちのことは存在しない人間かのように全く無視しながら礼子たちにだけ丁重に挨拶し、去って行った。え・・・遠乗り・・・そうか、どこかへ場所を移すのか・・・でも馬は四頭しかないよ・・・礼子、富美代、玲子、朝子・・・女の子が四人と信次とぼく・・・六人いる・・・僕たちは礼子さんたちと二人乗りかな・・・ぼんやりと考えている慎治を見て礼子は微かに嘲笑った。「さあ行こう!案内は今日の主催者の玲子ね!慎治たち、しっかりついてくるのよ!ゆっくりにはしてあげるけど、遅れたらどうなるかわかっているわね!」
「え、そ、そんな・・ついてこいって、ど、どうすればいいの?」「そ、そうだよ、まさか、僕たちにも馬に乗れっていうの?ぼ、僕たち、馬になんか乗れないよ・・・」慎治たちの間の抜けた返事に礼子たち四人はドッと笑い出した。「うーん、慎治、ギャグとしては今の、なかなか優秀よ。でもね、慎治たちは馬になんか乗れる身分じゃないでしょ?慎治たちは当然、走ってついてくるのよ!」そ、そんな!い、いくらなんでも酷い!だが否やを言う間はなかった。礼子たち四人は慎治たちの抗議を一切無視し、各々の愛馬に颯爽と跨った。「さあ、行くよ!」礼子の声を合図に四人は一斉に馬を歩かせ始めた。ま、待って、馬になんて追いつけない・・・慎治たちの心配は当然だった。馬が本気で走り出せば、人間がどうやったって追いつくことはできない。例えオリンピック選手だって無理だ。それ位のことは礼子たちには十分に分っていた。だから礼子たちは馬を早足程度のスピードに抑えて走らせた。そのスピードならなんとか、慎治たちもついてこれる。だが、慎治たちにとっては「必死で走ればなんとかついていける」というレベルで、余裕を持っていられるようなスピードではない。慎治たちはあっという間に悲鳴を上げ始めた。「ひっ・・・ま、待って・・・お、願い・・・も、もっとゆっくり・・・し、死んじゃう・・・」慎治の悲痛な哀願が礼子たちを楽しませた。「ほら慎治、遅れない! しっかり走んないと、後で鞭が増えるよ!」礼子の脅しは効果てきめんだった。馬に鞭を入れる、と言うが、慎治たちには鞭を入れる必要すらなかった。鞭、という言葉で脅すだけで十二分な効果があった。走った。慎治たちはひたすら走り続けた。どれ位走っただろうか。玲子が目的地を教えてくれないのが余計辛かった。いつまで走り続けるのか、あとどれ位なのか、一切分からない。もう着くのか、まだ半分も来てないのかも分からない。肉体的に辛いのは勿論だが、このいつまで続くか分からないマラソンは精神的に非常に堪えた。30分以上は走っただろうか。慎治たちが全身を汗にまみらせ、息も絶え絶えになってきたころ、漸く待ち望んだ声が聞こえた。「さあみんな、着いたわよ!ここ。ここを入るのよ!」玲子が立ち止まったところには一枚の木の立看板があった。「平成国際秀優大学グラウンド」そしてその路地の入り口にはチェーンが張ってあった。平成国際秀優大学。仰々しい名前だが,余り聞いたことのない校名だった。「なに玲子、ここなの?知らない校名だけど、ここ、どっかの大学のグラウンドでしょ?で、どこが気に入ったの?」馬を止めて礼子が尋ねた。「うん。この学校、平成元年だから丁度バブルの真っ盛りにできた私立大学なんだけどね、ま、要するに経営失敗したのよ。で去年、あえなく潰れちゃったってわけ。でも今更こんな田舎のグラウンドなんて買うとこあるわけないじゃん?と言うわけでこの物件、あえなく野ざらしの空き地に成り果てた、ていうわけ。」ポンッと礼子が手を打った。「そっか!潰れた、ていうことはこのグラウンド、誰も使わないんだ。じゃ、フルタイムで私たちの使い放題ね!」「そう。大体校名聞けばこの大学の経営陣、馬鹿者揃いだったってことが良く分かるでしょ?平成、国際、て来ただけで三流大学の条件満たしてる上に秀優だもんね、いくらバブルだって言ったって、こんだけ馬鹿大学宣言してるとこ、殆どないわよ。だからお金の計算も出来なかったみたいでね、このグラウンドも思いっきりバブルのりで作っちゃって、まあ新設大学のくせして、中はやたらと広くて立派なのよ。だから信次たちがいくら悲鳴上げたって誰にも聞かれる心配はないわ。おまけに学校が潰れたのが去年だからさ、まだあんまり荒れてないのよね。そこがまたグッドなのよ。」道端に倒れこみ、喘ぎながら束の間の休息を貪っていた慎治たちもようやく悟った。やっと苦行が終わったのではなく、今から漸く、本物の苦行が始まることを。
2
チェーンの横をすり抜けて一行は中へ入っていった。グラウンドは道路より50メートルほど奥にあり、木の影に隠れて道路からは全く見えない。確かにこれなら玲子の言うとおり、ちょっとやそっと悲鳴を上げても誰にも聞こえそうになかった。グラウンドは本当に広々としていた。400メートルのフルトラック、そしてトラックの中はサッカー用のピッチになっていた。ピッチは芝に覆われていた。手入れするものがいなくなり、かなり雑草が増えているとは言え、まだまだいいコンディションを保っていた。そしてこのグラウンドでどういう目にあうか、信次たちにも薄々わかってきた。「さあ、準備をしようか!信次、二人ともさっさと服を脱ぎなさい!」玲子の声が凛と響いた。そして四人の美少女は馬から一旦降り、吊るしておいたバッグから各々、愛用の鞭を取り出した。礼子たちは黒い鞭、そして富美代たちは茶色い鞭。いずれも信次たちの血と涙と悲鳴をたっぷりと吸った鞭だった。ゆっくりと四人はストレッチをし、体をほぐした後、再びひらりと身を翻し、騎乗した。「さあ、始めようか!信次、ここは広いからね、思いっきり逃げ回っていいよ!壁もないし、逃げ回る場所はたっぷりとあるからね。鞭で叩かれるのが嫌だったら、精々必死で逃げ回ることね!」「そ、そんな、だって玲子さんたちは馬に乗ってるじゃないか!ヒッ!」信次の必死の抗議は玲子の鞭にあっさりかき消されてしまった。「ほら信次、一番手は私よ!さっさと逃げないと、鞭でタコ殴りだよ!」ヒ、ヒーッ・・・悲鳴を上げながら信次は殆ど反射的に逃げだした。信次がグラウンドの半ば位まで行った時、玲子がニヤリと凄絶な笑みを浮かべながら軽く唇を舐めた。
「さあ、行くよ、ハッ!」玲子は掛け声と共に愛馬をスタートさせた。パカッバカッ、玲子が駆る馬のひずめの音が迫ってくる。信次がいくら必死で逃げたって馬のスピードに比べれば悲しい位のろい。あっという間に玲子に追いつかれてしまった。「ほら、このドン亀!そんなグズは、こうしてやる!」ビュォッと凶暴な音を立てて玲子の鞭が振り下ろされた。バッシーンッッッと派手な音を立て、信次の背中に凄まじい鞭が炸裂した。「ギ、ギエッ!」獣のような声を立てて信次はエビのようにのけぞった。ただでさえ長身の玲子が馬上から振り下ろす鞭だ。重力を味方にし、思いっきり振り切った鞭は凄まじい威力だった。痛い、なんて言葉では生ぬるい。打たれた瞬間、息が詰まるような、背中を打たれた筈なのに内蔵を通り、腹まで衝撃が突き抜けるような凄まじい一撃だった。「ほらほらほら!それそれそれ!」玲子は立て続けに鞭を振り下ろした。「ビッ、ギァッギャッ・・ベッ、ギェッッッッ!!!」玲子の鞭が炸裂する度に信次は断末魔のような悲鳴を上げ続けた。両手は縛られていない。だから少しでも鞭をよけようと両腕で頭を抱え込み、体を丸めるようにしていたが、玲子の強烈な鞭の前にはそんなガード、全くの無意味だった。これほど強烈な鞭なら、何も背中や尻にこだわる必要はない。腕だろうが足だろうが、どこでもいい。皮膚があり、神経が走っているところならどこにでも十分な苦痛を与えられる。と、いうことは信次の全身どこを鞭打っても構わない、ということだ。間断なく降り注ぐ玲子の鞭が信次の体のどこかを捕える度に、信次は絶叫を上げながら打たれた箇所を反射的に引っ込めるように体を反らしたり、逆に折り曲げたり、足を上げたり、腕を下ろしたり、と殆ど統一的な意志の感じられない反射運動を続けた。それは傍から見ていると珍妙なダンスだった。「アハハッ、なに信次のあの格好!玲子、もっと踊らせてよ!」朝子が大笑いしながら声をかけた。
「OK!ほら信次、ギャラリーが見てるわよ、LET’S DANCE!」玲子は笑いながら鞭を振るい続けた。ピシッ・・・パアン・・・ビシッ・・・パシーンッ・・・玲子の鞭音が響き続けた。「ギャッ・・や、やべ・・・ミ゛エ゛ッ!!!い、いだいーっっ!だ、だずげでーっっっ!!!」信次の動きと悲鳴が徐々に小さくなっていく。「ブギャッ・・・」フラフラになった信次は足をもつれさせ、芝に倒れこんだ。止めを刺そうかしら。馬を止め、大きく振りかぶった腕を玲子はゆっくりと下ろした。いけないいけない。私まだ、一番手なんだよね。いきなり信次を潰しちゃったら、朝子が遊べなくて怒っちゃうわ。「ほら信次、もう終わりにしてあげるから、立ちなさい。」玲子が声をかけても信次は倒れこんだまま、動けずにいた。背中も腕も足も、全身が痛みと灼熱感に包まれていた。全く、効いたふりしちゃって、あんたがこの程度で本当に終わっちゃうわけないでしょ!役者やなー・・・「信次、立ちなさい!それとも、鞭で叩き起こしてほしい!?」ひっ、そ、それだけは・・・全身をまだ包む激痛にうめきながら信次は必死で立ち上がり、のろのろと玲子の後ろについてスタート地点に戻っていった。「信次、いい色になって帰って来たじゃない!ほら、慎治も見てごらんよ。この蚯蚓腫れ、どんどん盛り上がってきているよ?」礼子はフラフラになって帰ってきた信次の傷を鑑賞しながら、傍らに慎治をはべらせた。言うまでも無い。礼子の大好きな精神的拷問だった。生来短気な玲子は先責めが好きなのに対し、礼子は大体において後責めを好んだ。玲子の鞭に、蹴りに、拳によって信次が全身ボロボロにされるのを見せ付け、その傷をたっぷりと見せ付け、慎治が怯える様を見るのが大好きだった。フフ、怯えてる、怯えてる・・・たっぷりと怖がってね。恐怖が最高潮に達したところで・・・その恐怖、現実にしてあげる!慎治の顔が恐怖に歪み、間もなく自分を襲う苦痛を想像し、絶対に許してもらえないことに絶望しながら、それでも藁をも掴む思いで泣きそうな顔になって哀願するのを見るのが礼子は何より好きだった。慎治、あなたを虐待し、地獄に突き落とす当の私に向かって哀願するその目、大好きよ。必死の努力が徒労になる人間の目って素敵。ずっとずっと、その目をさせたいわ。そして必死の哀願を冷たく踏み躙り、刑の執行を宣告する時の慎治の表情は礼子にとって最上のご馳走だった。絶望、恐怖、そして微かに入る怒りや覚悟の色がまた、何とも言えずいい味を出すスパイスのようだった。止められない・・・こうやって慎治の精神も肉体も嬲り尽くすのって、最高・・・慎治の表情を楽しみながら、礼子は至福の時を噛みしめていた。私、どっちなのかな。慎治のこの表情を楽しむために、鞭を振るって痛めつけているのかな。それとも鞭を楽しむためのオードブルとして慎治の怯えを楽しんでいるのかな・・・まあ、どっちでもいいや。卵が先か鶏が先か、みたいなものね。私、オムレツもフライドチキンも両方とも好きよ。そう、慎治を泣かせるのも大好きだけど、鞭も勿論、大好きなんだから!!!
「さあ,行こうか!」礼子は身を翻すと愛馬に騎乗した。「さあ慎治、どうすればいいかは分かるわね?」慎治の耳元で鞭をヒュンッと鳴らした。「慎治、折角の広いグラウンドよ。自由に逃げていいわ。信次の背中、見たでしょ?追いつかれたら慎治の背中もああなっちゃうわよ?フフ、精々一生懸命逃げることね。いい、もう一度言ってあげる。追いつかれたら・・・痛いわよ?」そ、そんな!!!馬から逃げられるわけない・・・ヒッ!慎治の背中を襲った鞭がゲームの開始を告げた。に、逃げなくちゃ・・・無駄と分かっていても、その場から逃げずにはいられなかった。慎治が50メートルほど逃げた辺りで礼子は声をかけた。「慎治、そろそろいいかな?行くよ!ハッ!」馬に一鞭くれると礼子は慎治を追って馬を走らせた。ドドッ、ドドッ・・・馬の走る音が背後から迫る。や、やだ、追いつかれたくない!!!だが礼子の駆る馬はあっという間に慎治に追いつき、鞭の射程圏内に入った。「ほら遅い!そんなんじゃ背中、すぐ真っ赤になっちゃうよ!」ヒュンッという風を切る音とともに鞭が慎治の背中を襲った。ビシッ・・・「ひ、びあっっっっ」い、痛い・・・いつもの鞭より痛い。馬に乗って高いところから振り下ろす鞭、おまけに走りながらだから馬のスピードまで加わっている。慎治は反射的に体をエビのようにそっくり返らせ、よろける足を絡ませながら必死で逃げようとした。
礼子は慎治が逃げるのを敢えて止めなかった。いいわよ。そう、逃げなさい。私の鞭の痛さが身にしみたでしょ?叩かれたくなかったら逃げなさい!必死で走りなさい!そして慎治が数メートル逃げたところで再び馬を走らせ、鞭を浴びせた。「ひ、いたい!!!」「ふう。礼子ってほんと、悪魔ね。あれじゃ慎治、蛇の生殺しじゃない。一思いに打ちのめしてやればいいのに。」流石の玲子が慎治に些か同情したかのように呟いた。その通りだった。なまじ連続して鞭打たれないため、慎治の苦痛は延々と続いた。礼子の鞭は痛すぎる、強制されないで、自分の意志でその鞭を受け続けることなど不可能だった。一発鞭打たれるたびに慎治は悲鳴をあげながら逃げまどった。体育館と違って壁がない、広い、遮るものが何もないグラウンドだ。ある意味ではどこまででも逃げられる。だが礼子は馬に跨っている。慎治より遥かに素早く動き、鞭で追い立て、自由に慎治の動きをコントロールできる。慎治に逃げる術などなかった。逃げられること、それが却って慎治の苦痛を倍加させていた。背中を襲う鞭の苦痛。逃げても逃げても背後に迫る馬のひづめの音の恐怖。そして休みなく走り続けさせられ、心臓も肺も限界に達していく。脚の筋肉も痙攣しかかっていく。そして見えない背後からいつ襲うかも分からぬ鞭の恐怖と、騎乗の美少女に、自分のクラスメートに追い回される屈辱。心身を内から外から、何重にも苛ぶる礼子の責めだった。気絶しようにも鞭と鞭の合間に僅かながらインターバルがある。連打ではない分、なかなか気絶できない上に、一鞭一鞭フレッシュな痛みをじっくりと味あわされていた。ひ、いっそ一思いに殺して・・・慎治は大粒の涙をこぼし、恥も外聞もなく泣き喚きながら走り回った。そして慎治のその無様な格好は馬上から鞭を振るう礼子にとって、最高の悦楽だった。どれだけ走らされたことだろう。慎治はついに精魂尽き果てて地面にのめりこむように倒れこんだ。「あらあら慎ちゃん、もうダウン?早く起きないと痛い痛いよ?」ピシッ・・・礼子は倒れたままの慎治に一鞭くれた。うぐっ・・・うめき声と共に慎治の背中が動いたが、立ち上がれない。本当に逝っちゃったのかしら?ピシーッ!パシーッンッ!スナップを思いっきり効かせ、礼子は強烈な鞭を立て続けに浴びせた。ひっ・・・びえっ・・・慎治はうめき声を上げたがもう動けなかった。全精力を使い果たし、最早動く気力も礼子の鞭を多少たりともガードしようと手を動かす力さえ残っていなかった。フフ、慎治、どうやら本当に逝ったみたいね。結構楽しかったよ。また遊ぼうね。「ま、こんなもんかしら?みんなおいでよ、私の番はお終いよ!」未だ立ち上がれない慎治の傍らに礼子は皆を呼び寄せた。「わあ、礼子すっごーい!随分いっぱい叩いたんだ。慎治、背中もう真っ赤っ赤じゃん!」富美代が感心したような声をあげた。「本当ねー。玲子と違って連打しなかったけど、結構一杯叩いてたんだね。うーん、信次、ちょっと背中出して!」朝子は二人の背中をじっくりと見比べてみた。「そうね。やっぱり滅多打ちにした分、身体の前の方は玲子の鞭の勝ちだけど、背中については後ろからの追い鞭に徹した分、礼子の勝ちね!」「やーねー二人とも、別にこれ、勝ち負け競ってるわけじゃないじゃん!」玲子の呆れたような声に四人は一斉に大笑いした。だが楽しいのは四人の美少女だけだ。信次たちにとってはちっとも楽しくない。いや、二人にも分かっていた。未だ鞭は終わりでないことを。朝子と富美代も鞭を楽しまなくては収まりがつかないことを。「さあ信次、礼子の鞭の間に少しは休めたでしょ?次は私の番よ!早く順番こないかなって、もううずうずしてたんだから!」朝子が飛び乗るように馬に跨った。「あー、朝子いいなあ。私、またまちぼうけじゃん。」富美代が心底羨ましそうな声をあげた。「お預け、富美ちゃん!まあいいでしょ、富美ちゃん大トリなんだから。ビシッと締めてね、じゃ、お先!」朝子が信次を追いかけまわす間、富美代はずっと自分の鞭プランを考えていた。どうやって追いかけまわそうかな。走らせるのもいいし、タコ殴りもいいし・・・幼馴染を苛める、一緒に遊び、おやつも食べた仲の慎治を地獄に突き落とすことに富美代はなんの躊躇もなかった。いや、躊躇、と言う言葉すら不自然、富美代は既に慎治のことなど、何も考えてなかった。頭の中にあるのは只一つ、どうやって楽しもうか、それだけだった。
3
朝子と富美代が鞭を終えた時、慎治たち二人は最早息も絶え絶えだった。全身に無数に鞭を浴び、体中真っ赤、蚯蚓腫れと青痣に彩られていた。体力も気力も限界に達していた。「も、もう・・・ゆるして・・・」倒れこんだまま慎治はうめいた。余りに多くの鞭を受け、背中の感覚、痛覚すら薄れつつあった。パカッ、パカッ・・・馬の軽い足音がした。しかも一人ではなく四人全員の音のようだった。ま、また、今度は全員・・・死んじゃう・・・だが足音は慎治から遠ざかっていった。遠くで礼子たちの明るい声が聞こえた。なんだろう。だが首を動かす気力もなかった。5分ほど経っただろうか、「慎治、慎治ったら、早くおいでよ!」礼子の声に必死の思いで起き上がると、礼子たちはスタート地点にシートを広げ、ランチの用意をしていた。「ほら慎治、いつまでも寝てないで早くおいでよ、お昼にしよう!」富美代が手招きしていた。のろのろと慎治が歩いていくと、驚いたことに慎治たちの席もちゃんとあった。慎治は礼子と富美代の間に。そして信次は玲子と朝子の間に。サンドイッチ、鶏の唐揚げ、ウインナー、サラダ・・・色とりどりの典型的なピクニックランチが並んでいた。「どう慎治、みんなで分担して作ったんだからね。結構おいしそうでしょ?感謝してよ。私たちの手作りお弁当を食べられるなんて、クラスの男の子たちが聞いたら泣いて羨ましがるわよ?」ランチは確かにおいしかった。どうせ残飯を投げ与えられるか、またブーツで踏み潰されたものを犬食いさせられるのか・・・と思っていたが、そうではなかった。玲子たち四人はそんな素振りは一切見せず、むしろ甲斐甲斐しく慎治たちの皿に色々と取ってやり、飲み物を与え、食後のデザートまでくれた。フルーツとチョコケーキ。疲れ果てた身体に糖分は何よりのご馳走だった。良かった・・・どうやら四人とも、満足してくれたみたいだな・・・そうだよな、あれだけ鞭を振るったんだ。もう十分だよな。ランチが終わったら、きっと帰れる・・・喉元過ぎればなんとやら、信次たちの読みは相変わらず甘すぎた。夏休みの別荘を思い出すべきだった。玲子たちが食事と睡眠だけは十分にくれたことを。大事な玩具を責め潰さないために、メンテナンスには抜かりないことを。
破局はすぐにやってきた。食休みも終えランチセットを片付けると礼子が慎治に向き直った。「どう、慎治。午前中の私たちの鞭、痛かった?」「は、はい・・・とても痛かったです。ほ、ほんと、死にそうなくらい痛かったです・・・」「そう。そりゃそうよねー。みんな結構本気で叩いてたものね。でも慎治、お弁当も十分食べたし、結構ゆっくり休んだから大分体力回復したんじゃない?」「そうよね、礼子。ほら見てごらんよ、信次なんか、さっきは死にそうな蒼い顔してたのに、今じゃすっかり顔色も良くなってるわよ。」礼子たちのこのセリフが何を意味するか、慎治たちにももうわかっていた。「ま、まさか、そんな・・!」ニコッと礼子は天使のような優しい笑顔で答えた。「そうよ、午後の部、開始よ。」や、やだーっ!!!慎治たちの悲鳴を全く無視しながら礼子は続けた。「あ、みんな、午後の部開始の前にトイレ行っとく?私、さっきから我慢してたんだ。玲子がね、あっちに簡易トイレ作っといてくれたんだって。」礼子が指差した先にあるものはグラウンドの隅にある用具倉庫、それも鍵をかけられており、入ることはできなそうだった。そして建物らしきものは、他には何もなかった。と、トイレって・・・なにもないじゃない・・・どこでするの?ま、まさか・・・そのとおり、慎治たちが引き立てられた先は倉庫の横だった。凍りつく信次に玲子がごく自然な口調で宣告した。「野外トイレは信次たちの口に決まってるでしょ?でもね、私も礼子も信次たちに飲ませるのはいいけど、互いの見てるとこでパンツおろす気にはならないわよね。朝子たちもそうでしょ?だからね、両側に一つずつトイレ作ったんだ。それならお互いに見られないでできるからね。」そ、そんな・・・先週、富美代と朝子のおしっこを飲まされた記憶がリアルに蘇った。ま、また飲まされる・・・礼子たちだけではなく、富美代と朝子のおしっこも飲まされる、共同便所への転落。だが礼子たちにとって慎治たちの葛藤など、知ったことではない。二人はそのまま野外トイレに引き立てられ、寝転がされた。まず礼子たち、そして富美代と朝子、立て続けにたっぷりとおしっこを飲まされ、口中一杯に塩気とアンモニアの香りが生臭く漂う。だが便器になるだけでは済まされない。午後の部、新たな鞭が慎治たちに忍び寄っていた。
「さあ、じゃあそろそろ始めようか。」玲子の声に信次たちは現実に連れ戻された。始める・・・痣だらけの全身に痛みがリアルに甦った。い、一体何を・・・信次は必死で無い知恵を絞って考えてみた。今まで玲子たちはこういうイベント的な苛めの時、どんな事をしたっけ?何かパターンがあったはず・・・そう、バリエーション、だ。同じ鞭でも責めのパターンを変え、より多くの恐怖と苦痛を与えようとする。それが玲子たちの苛めのパターンだ。だったら、どう苛める気だ?馬、新しい責め・・・想像がつかなかった。分からない分、恐怖だけが一人歩きしていった。信次が必死で考えているのに気づいた礼子が声をかけた。「信次、何考え込んでるの?もしかして、どう苛められるのかなあ、て考えてた?そうだよね。いつもは信次が先責めでやられてるからね。だけどまあ、今は安心していいよ。」ビクッと慎治が震えた。礼子の読み通り、慎治はとりあえず何も考えずに現実逃避しようとしていた。どうせ信次が責められるところをたっぷり見せ付けられる。嫌というほど怖がらせられるんだ。だったら、せめて今は何も考えたくない・・・慎治の心は空白状態、責められる心の準備が出来ていなかった。「えっっっ、ぼ、僕からなの?!」「そうよ慎治、先攻玲子、後攻私がルールだなんて、誰が決めたの?たまには私か先攻の時もあるのよ。」礼子は楽しそうに笑っていた。バカね慎治、すっかり油断してたでしょ?何もいつもいつも拷問見物させるだけが能じゃないのよ。油断させといての先責め、て言うのも結構、堪える精神的拷問でしょ?
突然の恐怖に震える慎治を見下ろしていた礼子がすっと馬から降りてきた。え・・・慎治が直感的に予想していたのは二人懸かりでの鞭打ちだった。きっと礼子と富美代の二人に追い回され、鞭打たれるに違いない。だが礼子の想像力は慎治の遥か上にあった。下馬した礼子が用意したのは長いロープだった。訝しげに玲子が尋ねた。「ねえ礼子、何する気?縛るの?礼子が私と違って、抵抗できなくしてから鞭打つのが大好きなのは知ってるけどさ、なんか、折角こんな広いとこに来たのに勿体無くない?」「フフ、大丈夫、大丈夫。私がそんなぬるいこと、するわけないでしょ?まあ、ゆっくり見ててよ。慎治、両手を出して!」礼子は慎治に両手を出させると、手首のところで厳重に縛りあげた。だが、他の所はまったく自由のままだ。10メートル以上ある長いロープは慎治の両手を何重にも縛っても尚、相当な長さを残していた。「れ、礼子さん・・・な、何を、何をするんです・・・か・!?」恐怖に怯え、泣きべそをかきながら慎治は必死で尋ねた。聞きたくはない。どんな酷い目に合わされるのか、知りたくもない。だが、聞かずにはいられなかった。
「フフ、慎治、怖い?でも安心していいわよ。私、鞭を使うつもりはないから。それだけは約束してあげる。」え・・・鞭、じゃない・・?ほっとした慎治の背筋にぞくっと寒気が走った。な、何を安心しているんだ俺は。鞭じゃないからって、礼子さんはきっと、鞭よりもっと酷いことを企んでいるに違いない!なんだなんだ・・・鞭じゃない・・・ロープ・・・縛る・・・しかも両手のみ・・ま、まさか!!!「そうよ、慎治、どうやら感づいたみたいね。」礼子は残忍な笑みを浮かべつつ、慎治の両手を縛ったロープのもう片端を馬の鞍の後ろに結んだ。「そうよ。前にも言ったわね。私、子供の頃西部劇が大好きで、特に悪漢が町の人をリンチしたり拷問するシーンが大好きだった、て。慎治も西部劇で見たことあるでしょ、悪漢がこうやって縛った人たちのことを馬で引き摺り回してボロボロにするのって。」ガチガチ・・・慎治の歯が恐怖の余り勝手に震えだしていた。「や、、、やめて・・・お、願い・・・」消え入りそうな声で慎治は哀願した。震える慎治の頬を優しく撫で、天使のような微笑を浮かべながら礼子は宣告した。「慎治、今からあなたのこと、たっぷりと引き摺り回してあげるわね。」現実認識を失い、声も出せずに立ちすくんでいる慎治の頬に軽くキスすると礼子は身を翻し、愛馬に跨った。「行くわよ、ハッ!」礼子はゆっくりと馬を歩かせはじめた。緩んでいたロープはすぐにピンと張り、引きずられた慎治が歩き始めた。「そうそう慎治、必死でついてくることね。転んだら終りよ。」礼子は徐々にスピードを上げていった。慎治は必死で走り出す。だが馬と人間のスピードは違いすぎる。「ひっ、、、ま、待って!も、もっとゆっくり・・・スピード、落として!!!」後ろを振り返り、慎治が恐怖に顔を歪ませながら絶叫するのを見た礼子は、楽しげに笑いながら更にスピードを上げた。慎治は徐々に悲鳴すら出せなくなっていく。鈍足の慎治にとってはもう,フルスピードに近い。そして人間がフルスピードを出し続けられるのはオリンピック選手クラスでも10秒が限界だ。慎治はあっという間に限界に達してしまった。礼子は振り返り、慎治が限界に来ていることを見極めた。いいわ慎治、いたぶるのはこの程度にしてあげる。さあ、本番逝くわよ!礼子は右手を高く上げ、ピシリと乗馬鞭で愛馬の尻を打つと同時にブーツの拍車で腹を蹴った。GO!礼子の愛馬は騎乗の美少女の意図を的確に理解し、それまでの早足から一気に駆け出した。あっと言う間もない。慎治はそれでも必死で若干の距離を走ったが馬のスピードに追いつけるわけがない。千切れそうな腕の痛みと共に慎治の上半身が前方に引き倒されていき、足が絡まりはじめた。限界より速く走られると、いくら足を前に動かそうとしても、最早単に抵抗になるだけだった。「ひっ!」悲鳴をあげながら遂に、慎治はつんのめるように膝を地面についた。立ち上がる暇などない。膝を支点にして倒れこみながらも慎治の腕は前方に引き伸ばされ、そのまま膝が、腹が、胸が地面を滑り出した。慎治の目の前を芝生とあちこちに伸びる雑草が高速で通り過ぎていく。ロープに縛られた手首から肩にかけて全体重がかかり、引っこ抜かれるような激痛が走った。「ビアーっっっっや、やべでーーー!!!」断末魔のような悲鳴をあげつつ慎治は引き摺られていった。礼子は馬を疾走させながら振り返った。自分が駆る馬に引き摺られ、慎治が悲鳴を上げていた。自分の愛馬で人間を引き摺り回している!長い間、夢にまで見た光景だった。最高!私、これをやるために乗馬を習ったのかもね。「ほらほら慎治、まだまだ引き摺り回してやるからね!」ピッチの端に来た礼子は、そのまま馬を返すと反対側に走らせた。
4
一旦、ロープは緩んだもののあっという間に反対向きにピンと張り詰め、再び慎治を引き摺り回す。しかも今度は回転したタイミングのせいか、慎治は仰向けにひっくり返り、背中を下にして引きずられていった。「ぎあ——!」慎治の悲鳴が轟いた。今度は秋晴れの澄んだ青空が慎治の視界を流れていく。だが慎治にそんな青空を眺めている余裕などない。肩に、さっきとは異なる角度からの痛みが襲い掛かった。礼子はわざとグラウンド内の、芝生に覆われたサッカー用のピッチからは出なかった。硬い土のグラウンドを引き摺り回せば慎治により多くの苦痛を与えられるのは分かっていたが、そうするつもりはなかった。なにしろ鞭を楽しむために、慎治は一糸まとわぬ裸にひん剥いてあるのだ。そのまま土の上を引き摺り回したりしたら、あっという間に全身の皮膚が擦り剥けてしまう。別に慎治が因幡の白兎になろうがどうなろうが礼子の知ったことではないが、流石にずる剥けになってしまっては、今日のパーティーはお開きになってしまう。そんな勿体無いことをするつもりは毛頭なかった。だから礼子はあえて、慎治を引き摺り回すのは柔らかい芝生と雑草で保護されたピッチ内だけに留めていた。だが慎治の苦痛は十二分に酷いものだった。腕が痛いだけではない。いくら柔らかい芝生の上とは言っても、高速で引き摺り回されては全身、地面との摩擦で焼けるように痛い。そして整備されていないピッチは決して平面ではない。スパイクの跡、草の根・・・細かい起伏がたくさんあり、それらのギャップに跳ねられて慎治の全身は微妙にバウンドしながら引き摺られていった。苛め、といった領域を遥かに通り越した礼子の責めだった。「もう駄目!!!誰か、誰か助けてーーっ!!お願いーーっっっ!!!」スタート地点まで引き戻され、礼子が再びUターンしようとした時、慎治は玲子たちに向かって必死で絶叫した。玲子たちの誰かが止めてくれることを期待して。誰かは分からない。だが三人もいるのだ。誰か一人くらいは流石に見かねて止めてくれるだろうと期待して。だが、慎治は未だ甘かった。玲子たちにとって、慎治の苦痛など単なる遊び道具でしかないのだから。一対一の時だったら多少は情けも期待できたかもしれない。だが四人集まった時の礼子たちの集団心理は慎治が期待したのとは正反対の方向に働いていた。残虐性は四倍、いや四乗に、そして同情心は四分の一、いや四乗根に。
慎治の悲鳴に真っ先に反応したのは富美代、幼馴染、ということでせめて富美ちゃんは助けてくれるんじゃないか、と慎治が最も期待していた当の富美代その人であった。「礼子楽しそう!私もジョインする!」再び引き摺られていく慎治を追いかけるように、富美代は自分の馬に鞭を入れ走り出した。走りながら乗馬鞭を一本鞭に持ち替え、その鞭をヒュンヒュン振り回しながら慎治に並走する富美代を見て、礼子は富美代が何をするつもりか直ぐに理解した。「OK,OK,富美ちゃん、やっちゃってくださーいっ!」おどけたような礼子の声を合図に富美代は引き摺られていく慎治の背中に思いっきり鞭を振り下ろした。「ぎあ——!」慎治が獣のような悲鳴を上げた。「アハハハハッ!最高!ほら慎治、もっともっと泣いちゃえーっ、ほらほらほらほら!!!!」富美代は慎治の悲鳴に興奮し、一層激しく、凄まじいピッチで間断なく鞭を振り下ろした。ドドッ、ドドッと二頭の馬が走る重い音、ズザーッという慎治の肉体が引き摺られる音、そしてヒュンヒュン唸る富美代の鞭の風切り音とビシッ、バシッと振り下ろされる鞭が慎治の裸体を打ち据える音。そして礼子と富美代のキャハハッという心の底からこみ上げる、抑えようのない楽しさを満喫している笑い声とビア゛<bと全身を間断なく苛む激痛に声にすらならない慎治の絶叫。天国と地獄の音がコントラストを描いてグラウンド中に響いていた。
そして玲子と朝子も興奮のピークに達していた。「朝子、私たちも行こう!」ヒッ、目の前で繰り広げられる狂宴を呆然と眺めていた信次の全身に電流が走った。に、逃げなくちゃ!!!信次は恐怖に足を絡ませながら必死で逃げようとした。だが、「ぐえっ・・」三歩と逃げないうちに信次は背後から首に絡まりついた黒い蛇に締め上げられ、苦しげな悲鳴を上げた。「どこ逃げる気よ信次!逃げられるとでも思っているの!」玲子の鞭が素早く信次の首に絡まりつき、締め上げていた。「そうよ信次、余計な手間かけさせないでよ!この馬鹿!」駆け寄った朝子の右拳、ついで右膝が信次の鳩尾にめり込んだ。「ぐぼっ・・」思わずうずくまる信次の背中を蹴り倒すと朝子は素早く背中に馬乗りになり、両手を縛り上げた。「玲子!」朝子が放り投げたロープの反対端をキャッチすると、玲子は自分の馬の鞍に結びつけた。「ほら信次、手間かけさせた罰よ!」朝子が信次の腹を数回、立て続けに蹴りつけた。固いブーツの爪先が腹にめり込む。さらに朝子は全体重をかけながら信次の顔を踏みつけた。朝子のブーツの底に踏み躙られる信次の頭は、そのまま地面にめり込んで行きそうだった。痛い。だが、信次としてはこの程度の痛みにうめいているほうが遥かに幸せだった。「朝子、遊んでないで早くおいでよ、置いてくよ!」「あん、待ってよ玲子ったら!」玲子の興奮しきって上ずった声に朝子はハッと我に返り、お遊びを止め自分の愛馬に駆け寄って行った。朝子が馬に跨り、鞭を握ったのを確認すると玲子は大声を上げた。「朝子、準備OK?よし、じゃあ信次、覚悟はいいわね、行くわよ!ハッ!」「いやーっ!やべでーっ!!!」胃袋を破裂させるかのような朝子のトーキックに呻いていた信次は、未だ立ち上がることすらできない。だが悠長に痛みが治まるのを待っている余裕など、玲子たちは与えてくれなかった。信次は地べたに這いつくばったまま悲鳴を上げながらロープに引き摺られはじめた。「い、いだだだ゛!!」か、肩が抜ける・・・玲子が鞭と拍車を使い、馬のスピードを上げていく。「ぎ、ギヴァーーーーーっっっ!!!」全身の関節がバラバラになりそうな苦痛と引き摺り回される恐怖に狂ったように絶叫しながら、嫌々をするように左右に首を激しく振る信次の視界にもう一頭の馬が見えた。朝子の馬だった。朝子は馬のスピードを巧みに調節し、引き摺りまわされる信次とピッタリ並走しながら右手に握った鞭をヒュンヒュンと水車のように振り回していた。「ほら信次、頭上にご注意!」ビュォッ、朝子が振り下ろした鞭が信次の背中めがけて襲い掛かった。パシッ・・・手加減抜きの鞭が信次の背中に更なる苦痛を加える。バシ、パシ、ピシ・・・朝子は完全に頭に血が上ってしまったかのように、間断なく鞭の雨を降らせた。仰向け、うつぶせ関係ない。地面を引きずられる痛みと鞭の痛みと、上下から同時に襲ってくる激痛は片時の休みもない。しかも両手を縛られて引き摺られているのだ。体のどこをガードすることもできない。ただひたすら苦痛を味わうこと。信次にできることはそれだけだった。そして鞭の痛さに体をよじったり膝や肘を立てたりすると、それが抵抗となって体がバウンドし、信次を更に苦しめる。そしてバウンドしながら引き摺りまわされる信次の姿は、玲子と朝子から見ると珍妙なダンスを踊っているようだった。「ビアーーッッッッ!!!」信次は叫び続けた。獣のような声だ、何で自分がこんな声を出せるのか理解できなかった。本能的な、断末魔の叫びなのかも知れない。だが叫び続けることが唯一、自分を確認させてくれることだった。叫び続けないと気が狂ってしまいそうだった。
何周引き摺り回されただろうか。礼子たちの馬は漸く止まった。ハアハア・・・やっ、やっと終わった・・・慎治たちは芝生に顔を埋めたまま喘いでいた。鞍からロープを外し、二人が降りてきた。「どーお慎治、楽しい?私、最高よ、夢がかなって最高にハッピーよ。」礼子はブーツの爪先で慎治の頬を小突きながら笑った。返事をする気力もない慎治に礼子は更に続けた。「慎治、まさかもう、引き回しの刑が終わったなんて思ってないでしょうね?これからプレイヤー交代なんだからね。」こ、交代・・・まさか・・・真っ白になっていた信次の頭にも急速に意識が戻ってきた。こうたいこうたい・・・まさか!!「ブギャッ!」立ち上がろうとした信次の頭を玲子が踏みつけた。「玲子―、早く早く!私も引き摺りたいーっ!」「ハイハイ、もう朝子ったら駄々っ子ちゃんなんだから、ほら、早く結びなさい!」玲子の鞍から外したロープを、今度は朝子が自分の愛馬の鞍につないでいた。「ヤ、ヤダーッ!」信次は必死で起き上がろうとしたが、玲子のブーツにグイッと力が込められ、踏み潰されたまま地面に顔をめり込まされてしまった。「ああ信次、今いいとこなんだからさ、ちょっとの間大人しくしてなさい。すぐ遊んであげるから。」朝子と富美代がロープをつなぎ終えると同時に玲子たちは信次たちを靴底から解放してやった。頭を踏み潰される苦痛から解放され、一瞬信次たちはほっとした。だが、すぐに拷問が再開された。「さあ行くよ!」今度は富美代と朝子が引摺役、礼子たちが鞭打役だった。「ギアーッ!!!た、助けてーっっっ!」「ま、ママーッ、ママーッッッ!!!痛い、痛いよーーっっっ!」慎治たちは絶叫しながら引き摺られていった。鞭を振るいながら礼子は慎治の苦悶をじっくりと鑑賞していた。さっき引き摺り回した時は慎治の様子をずっと見ていられた訳ではない。チラチラと頻繁に後ろを見ながら、苦痛に喚きつつ必死で自分に哀願する慎治の顔を楽しんではいたが、こうやって横から見ているほどじっくりと楽しめた訳ではない。だが、富美代に引き摺られながらだと、慎治の苦悶の様子が特等席で、ライブで鑑賞できる。いいわ。引き摺るのもいいけど、こうやって横から鑑賞するのもまた楽しいわね。鑑賞、と言っても鞭を振る手は片時も止まらないのだが。
楽しんでいるのは玲子も同じだった。芝生の上を引き摺られていく信次の体に自分の鞭が当たるたび、ビクッ、ビクッと反射的に信次の体が震える。その痙攣が新たな抵抗を生み、信次の体を微妙にジャンプさせて引き摺られていく苦痛を倍加させる。朝子と私、息あってるじゃん!信次の苦痛を更に引き出すべく、玲子は腕も千切れよとばかりに鞭を大きく振るった。スナップも思いっきり効かせた。せ、背中が裂ける・・・信次は上下から同時に加えられる激痛に喚き続けた。上から下から、いや腕、肩も加えて前後から、まるで両面グリルに入れられた焼き魚のように、信次の全身は苦痛の炎でじっくりと炙られていた。バーベキュー、苦痛のバーベキューだ。生きながらにして炎に炙られる生き地獄。ピッチを何周も何周も引き摺り回され、漸く解放された時、信次たちは二人とも全身ボロボロ、胸も腹も背中も尻も、全身を真っ赤に腫れ上がらせ、蚯蚓腫れを蜘蛛の巣のようにまとい、そして血を滲ませていた。立つことはおろか、ピクリと動く気力すらなかった。「み、水・・・」慎治は虫の息で喘いでいた。全身を、体の表も裏も苦痛だけが支配していた。焼けつくような痛み、擦り傷、打ち身、手首も肩も脱臼しかかっていた。そして手首にはくっきりとロープの跡が刻まれていた。だが一番辛いのは喉の渇きだった。絶叫し続けた喉は血が出ているのかと思うほど痛く、何より隈なく痛めつけられた全身が水分を欲していた。水分に対する欲求、生物の本能とも言える欲求だった。だが、慎治たちに与えられる水分は当然の如く、礼子たちの排泄物、人間にとって最悪の屈辱に満ちた汚水だけだ。「み、水・・・」信次もうめいた。「二人とも水が飲みたいの?いいわ、飲ませてあげる。じゃ、どこに行けば飲ませてもらえるか、分かるわね?」礼子が相変わらず優しげな笑顔を浮かべながら答えた。どこに行けば・・・そうか、おしっこか・・・慎治たちはのろのろと這うように用具倉庫横の簡易便所に歩き始めた。最早おしっこを飲まされることに抗議する気力すらなかった。いや、二人とも内心の葛藤はただ一つ、おしっこを飲むことに対する葛藤ではなく、おしっこを飲める、兎に角水分を補給できる、と喜んでいる自分のあさましさ、卑しさに対する葛藤だけだった。信次がブロックの間に横たわると間もなく、玲子がやってきた。「フフ、信次、水を飲ませてあげる、て言っただけでちゃんとトイレに行くなんて、結構躾が行き届いてきたみたいね。いいわ、信次の口、段々便器が板についてきたわよ。」ゆっくり、じっくりと排泄を楽しむ玲子の尻の下で信次も束の間の幸せに浸っていた。待ちに待った水分が体にしみていく。何より、こうやっておしっこを飲まされている間は鞭で打たれる心配だけはない・・・玲子が立ち去ると入れ替わりに朝子が入ってきた。「ジャーン、信次、今日二回目のトイレットタイムね。」朝子もなんの躊躇も無くブロックに上り、乗馬ズボンとパンティを下ろすと信次の顔面にしゃがみ込んだ。「全く、信次ったら水を飲む、て聞いただけで黙ってトイレに直行だもんね。呆れちゃったわよ。あ、でもそうか。信次は女の子のおしっこ飲んでも恥ずかしげも無く生きていられる変態ちゃんだもんね。信次にとってはここが水飲み場なんだ。私たち人間にとってはトイレなんだけどね、私たちが汚いものを排泄する出口が信次にとっては入口なわけね。」
悔しい、汚らわしい、おぞましい・・・発狂しそうな屈辱を味わいながら慎治たちは四人の美少女のおしっこを飲み続けた。何度飲まされても決して慣れるものではない。まさに人格否定。SMプレイの乗りで「女王様のご聖水をお飲み!」とでもやられれば、まだ遊び、冗談、と割り切って自分を誤魔化すこともできる。だが礼子たちは、あくまで単純におしっこを排泄しているだけなのだ。その排泄物を無理やり飲まされている。余りにも当然に飲まされている。こんな苛めに馴れるわけがない。しかし、慎治たちはおしっこを拒絶するには余りに打ちのめされていた。全身ボロボロ、とにかく水分が欲しい。そしてもう一つ、寒かった。もう秋、いくら快晴といっても日差しは強くない。素っ裸でいると、鞭で追い回されている間はまだしも、立ち止まって暫くすると寒くて震えが止まらないほどだった。寒さと鞭で追い回される惨めさと消耗し尽くしたプアな体力と・・・慎治たちは濡れネズミのようにブルブルと震えていた。そして寒さに震える体に・・・礼子たちのおしっこは暖かく、優しかった。美少女の体温と同じ温度まで温められた水。それが人間にとって最も汚い他人の排泄物であっても尚、その汚水に慎治たちの凍えた体が中から温められていることは確かな事実だった。それはあたかも命の水であるかのように、二人の体に浸みこんでいった。礼子のおしっこが口に注がれた時、慎治は不覚にもああ、おいしい・・・と陶然としかけていた。寒さに震えながら漸く家に辿り着いて飲む熱いミルクティーのようだった。礼子が放尿を終え立ち去った後、良かった、未だ富美ちゃんのおしっこも飲めるな、早く富美ちゃんこないかな、という考えが慎治の頭を掠めた。な、なんで俺はほっとしているんだ!も、もっと飲みたいだなんて、お、俺はおしっこを、おしっこを飲まされているんだぞ!!!だがいくら必死で否定しても、慎治の心の中のもっとおしっこを飲みたい、という欲求は消しようがなかった。そして、それは信次も同様だった。たっぷりと放尿を終えた玲子が立ち去ると信次もまた、思わずああ、もっと・・・と言いたくなっていた。そして朝子が現れた時、思わず嬉しい、とさえ感じてしまったほどだった。
1
富美代と朝子のおしっこも飲み終えた慎治たちは、這うようにしてグラウンドに戻ってきた。漸く全身の激痛も治まりつつあったが、もう体力の限界に来ていることは間違いなかった。のろのろと礼子たちの所に戻ってきた慎治たちは半ば倒れこむように座り込んだ。もう流石に終わりだろう・・・全身ボロボロ、今日何発の鞭を受けたか、数え切れないほどだ。もうないよな・・・「信次、ちょっとそこに寝てみてくれない?ああ、うつ伏せのほうがいいわ。」玲子に促され、信次はその場にうつ伏せに横たわった。「うわ凄い・・・縞々模様って言ってあげたいけど、格子模様みたいね。」信次の背中の傷をブーツの爪先で突っつきながら玲子は満足気に頷いた。「慎治、あんたも寝てみてくれない?こっちで信次と並んで寝てよ。鞭跡の品評会やるからさ。」慎治は玲子の言うとおり、信次と並んでマグロのように横たわった。四人の美少女はブーツの爪先や踵で信次たちを弄びながら鑑賞会を開いていた。長い鞭を玲子はリング状に丸めて肩にかけ、礼子はベルトの様に腰に巻いていた。朝子はショールよろしく首に引っ掛け、富美代は二の腕に蛇のように巻きつけていた。自分たちを徹底的に苛めつけた少女たちに踏まれながら、傷跡を鑑賞される。信次たちの凄惨な苦痛の跡を、四人の美少女は絵でも楽しむかのように、信次たちに一片の同情すら見せずに鑑賞していた。この悪魔・・・心の中で信次は毒づいていた。だが、言葉にできる訳がない。自分を責め嬲る美少女たちは鞭を、散々泣き叫ばせられた拷問具を持っているのだ。逆らえるはずがない。「どう礼子?パッと見、二人とも鞭の跡はほぼ互角、てところね。結構いい染まり方じゃない?」「そうね・・・鞭跡もいいけど、やっぱり引き摺り回しってグーね。きれいに全身、赤くなってるわね。」信次の頭を爪先で軽く踏みながら朝子も頷いた。「本当ねー、ここまでやれれば大満足って感じよね、でもやっぱり、鞭って最高ね!」「本当!それにここ最高じゃん、また来ようよ!」富美代も満足しきった様子だった。
礼子たちは憐憫、同情心のかけらも感じていなかった。普段は優しいのに。武道をやっていても、否、やっているからこそ他人に理由もなく暴力を振るうことは絶対にないのに、慎治たちに鞭を振るう時、礼子たちは誰も、慎治たちが痛くて可哀想、とは全く思わなかった。当然と言えば当然だ。鞭、慎治たちを打ち据えている本物の一本鞭は通常、殆どの人間が一生見ることも触れることもないものだ。だからその鞭がどれ位痛いかなど、想像することすら難しい。鞭跡の蚯蚓腫れにしても、自分が知らない痛みだ。だから手加減がない。どれ位痛いか、すら想像できないのだから、相手を傷つけることに対する恐怖、内心の無意識に近いブレーキが働かない。いくら慎治たちが絶叫してもその苦痛は実感としては伝わらず、単に自分の鞭で慎治たちを泣き喚かせている、という快感、満足感に置き換えられてしまう。ぼろぼろになった慎治たちを見ても他人事としてしか感じられず、全く大騒ぎしちゃって、位にしか感じられない。これもまた、鞭の魔力の一つかもしれない。鞭、この効率よく他人に苦痛を与えられる道具は単に慎治たちに肉体的な苦痛を与えるだけではなく、鞭を握る礼子たちの精神までも改造していた。
か、勝手な事ばかり言って・・・礼子たちの足元に横たわり、ブーツで鞭跡を小突き回されながら慎治は悔しさを必死で堪えていた。ち、畜生・・・人の事をこんなになるまで痛めつけるなんて、この悪魔!鬼!・・・こんな地獄のようなとこ、もう二度と来てたまるもんか!だけど、今は何も言っちゃいけない・・・もうすぐ、もうすぐ終わる・・・辛かった今日も終わる。礼子さんも富美ちゃんも、流石にもう満足しているようだからな・・・もう終わる・・・
慎治の期待は当然だった。礼子たちは四人とも、もう終わる気だった。ああ、今日は楽しかった・・・場の空気が急速に弛緩していった。「ふう、ま、今日はこんなもんかしらね。そろそろ帰ろうか?」今日の主催者、玲子の口から信次たちが待ちに待った言葉が紡ぎだされた。「そうね、ああ楽しかった。また来ようね。」朝子と富美代ももう終わる気になっていた。そして礼子も今の今まで、すっかり終わる気になっていた。だが、玲子の声を聴いた瞬間、礼子の心の中に囁くものがあった。チャンス!と。
入学当初こそ対立したものの、礼子と玲子は苛めという共通の趣味を通じて親友になっていた。別に慎治たちを苛める時だけではない。クラブに行ったり、買い物を楽しんだり、この乗馬クラブにしても、苛め抜きで健康的に楽しむだけでもよく一緒に来ていた。だが、いくら仲がいいと言っても、お互いの心の奥底には相手に負けたくない、というライバル意識もある。ルックス、スタイル、知性、家柄・・・全てに恵まれているだけに、二人のプライドもまた、強烈なものだった。玲子にだけは負けたくない・・・礼子に勝つのって最高・・・陽気に、オープンに張り合うから陰湿な所がなく、競い合うことが仲を悪くすることはないが、互いに勝とうとする意識は常にある。そのライバル意識が最もストレートに表れるのが、慎治たちを苛める時だった。ストリートの連中が腕力を競うのと同じように、礼子たちは慎治たちに対して、どちらがより残酷になれるか、どちらがより多くの苦痛を与えられるか、どちらがより多く慎治たちを泣き叫ばせられるか、を競うところがあった。
そして今、玲子が信次をもう許してやろう、と言っている。その瞬間、礼子にピンと来るものがあった。玲子は許してやる、て言ってる・・・良かったね信次、ご主人様のお許しが貰えて。だけどね信次、私は玲子ほど優しくないよ。私の慎治共々、もう一鞍苛めてあげる!ついてない、そう、信次たちにとって、ついてない、としか言えない展開だった。もう終わろう、と言ったのが富美代か朝子だったら、礼子も間違いなく終わりにしていたはずだ。玲子が、玲子さえ何も言わなければ・・・最後の、文字通り最後の一瞬で信次たちの運命は更に深く暗転していった。
「ねえ玲子、もう終わるのはいいんだけどさ、私、まだ一つ忘れてる気がするんだ。」「忘れてる?何を?そりゃまあ、色々遊び方はあると思うんだけどさ、今日のところはやり尽くしてない?」いいわ玲子、玲子でも未だ気づいてないのね。「うん、忘れてる、ていうのはね、人数なのよ。」「人数?」「そう、午前中は一対一でみんな遊んだでしょ?で、今の引き摺りは基本的に二対一よね。」「そっか!」富美代がポンッと手を叩いた。「礼子、もしかして、四対一で遊ぼうって考えての?」
「ビンゴ!富美ちゃん冴えてるー!」朝子も悪戯っぽい笑いを漏らした。「フフ、礼子ってアクマー!四対一だって?それって、要するにタコ殴り、てことじゃん?ねえ信次、どうする?これから四人掛りでのタコ殴りだって。大丈夫?あんたたち、下手したら本当に死んじゃうかもね!」やられた!玲子の胸中を礼子に出し抜かれた悔しさが占拠した。四対一かあ・・・あーん、私ってオバカ!このパターンを忘れてるなんて。一瞬、意地になって反対しようか、とも思った。だがすぐに玲子は気を取り直した。ま、今のは礼子にやられたってことでいいとするか!だって・・・タコ殴り、楽しそうジャン!「全く礼子ったら・・・ホント、あんたって鬼畜よねー。しょうがないなあ、信次、私はね、本当は可哀想だから信次のこと、もう許してあげたいなって思うんだけど、礼子がああ言うんじゃ仕方ないわ。信次、あなたも辛いと思うけど、もうちょっと、がんばってね。」「ひっど―い、玲子ったら人を悪者にしちゃって!あたしのこと鬼畜、とか言ってるくせして鞭を握り直してるの、一体誰よ!?」「あ、ばれた?ま、四対一のタコ記念日っていうことで全てOK!」「何が全てOKよ、全く、調子がいいんだから、もお!」そ、そんな馬鹿な!!!慎治たちは思わず絶叫してしまった。「や、やめてーっっっ!!!」「も、もうおねがい!!!し、死んじゃうよーっっっ!!!かえろ、ね、帰ろうよーーー!!!」「うるさいわね、信次、あんた死ぬ死ぬって気軽に言い過ぎよ。」照れ隠しのように玲子はブーツに強くウェイトをかけ、信次の顔を地面にめり込ませた。「全く、ロシア鞭の拷問じゃあるまいし、こんなんで死ねるもんなら死んでごらん!ほら、死んでごらんよ!」玲子は全体重をかけ、グリグリと信次の顔を踏み躙った。そ、そんな・・・信次が泣き喚こうと息を吸い込んだ瞬間、玲子は信次の胸倉を掴んで引き摺り起こした。
「さあみんな、パーティー再開よ!馬に乗って!」「OK!」礼子たち三人は再び愛馬に跨ると肩から、腰から、首から、腕から愛用の鞭を外し、身構えた。「で、玲子、どう行く?なんか楽しみ!信次を鞭打つのって、久し振りよね!」礼子が楽しそうに笑いながら鞭を振り回した。「そうね・・・じゃ富美ちゃんは斜め右、朝子は斜め左で20メートル位間隔取って。で、礼子は私の対面。やっぱ20メートル、ううん、もう少し奥に行って。」四人は一辺20メートル程度の正方形に並んだ。
「さあ行こうか!」玲子は四人で形作った正方形の内側に信次を入らせ、自分の右前方、鞭を最も振るいやすい位置に立たせた。更に両足を50センチ程度のロープで縛り、よちよち歩きしか出来ないようにし、更に両手も後ろ手にしっかり縛り上げ、余計な抵抗が一切できないようにした。「信次、もう分かるわね。これから信次には私たちのリングの中をたっぷりと歩いて貰うわ。安心して。もう疲れてるでしょう?さっきみたく走らなくていいからね。ゆっくり歩くだけでいいわ。私が一緒にスタートして、まずは朝子のところまでエスコートしてあげる。次は朝子に礼子のところまで送って貰いなさい。で、礼子は富美ちゃんへ、富美ちゃんは私へと信次をエスコートしてあげる。嬉しいでしょ?聖華の誇る、私たち美女四人にまとめてエスコートしてもらえるなんて、もうこの幸せ者!」「そ、そんな!!!み、みんなで鞭だなんて・・・や、やだーーーっっっ!!!ひ、ひどいよ、死んじゃう、死んじゃうよーっっ!」信次の絶叫に玲子たちはどっと笑い転げた。「やーねー信次ったらほんと、大袈裟なんだから。じゃ、いいこと教えてあげる。玲子の鞭がそんなに怖かったらね、早く私のとこまで逃げておいで!」「ああ、朝子ったらいい子ぶりっ子しちゃって!自分だって思いっきり引っ叩こうとしてるくせして!」「あ、バレた?うん、私ね、早く信次のこと引っ叩きたくて、もううずうずしちゃってるんだ!」幸せ者、確かに玲子たち四人は美少女で有名だ。近隣の高校でも有名な存在であり、ラブレターを貰ったり合コンに誘われるなど数え切れないほどだ。その四人全員が何の取柄もない信次と一緒に全身全霊込めて遊んでくれる。天国のようなシチュエーションだ。但し、四人が鞭を持っていなければ、の話だ。既にぼろぼろになるまで鞭打たれ、全身傷だらけだ。その傷口を更に鞭打たれる。い、いったいおれ、どうなっちゃうんだ・・・考えたくもない、死ぬほど痛そうだな・・・現実感すら失われつつあった。
だが心配はいらない。玲子はそんなに信次を待たせる気はなかった。怯えてるわね信次、ま、当然だろうけどね。でも安心していいよ。私、礼子みたく精神的に拷問する気はないから。直ぐに苛めてあげる!「さあ信次、幸せたっぷり噛み締めてね!レディ・・・GO!」ヒョオッ・・・パシッ・・・今日は一体何回この音を聞かされただろうか。ヒァッ!!!信次は悲鳴をあげながら歩き出した。玲子たちのゲームが始まってしまえば、信次に何かを考える余裕などない。只ひたすら責苦に耐えながら泣き喚き、時間が過ぎるのを待つだけだ。それでも信次は反射的に玲子の鞭から逃れようと走り出した。両足を縛られているのも忘れて。「うがっ!」つんのめり、バランスを崩した信次は2,3歩で前のめりに転んでしまった。「アハッ!信次、もう転んじゃって!そっか、やっぱり信次ったら私とずっと遊んでいたいのよねー。うん、分かる分かる。私と信次はいつも一緒に仲良しこよしだもんねー。私の鞭が大好きなんでしょ、じゃ、もっともっといーっぱいあげるね。ほら!」
ピシッ、パシッ・・・玲子は心底楽しそうに高笑いしながらも鞭を振るう手を片時も休めない。ひーっっ!!い、痛い!!!一日中散々打ち据えられ、引き摺り回された信次の背中は傷だらけだ。どこを打たれても傷口を抉られる、痛い、と言うより不快感を伴った苦痛に襲われる。しかも、引摺刑の最後の頃には余りの苦痛に痛覚が半ばマヒし、信次にせめてもの安らぎを与えていた。だが、僅かな時間とはいえ休息を与えられていたため、全身の感覚が蘇っていた。もちろん、痛覚も。一旦忘れかけていた痛覚がまた復活しただけで耐えがたいのに、更に傷口を抉られる痛みをプラスされるのだ。堪ったものではない。い、いたいいたいいたい!!!にげなくちゃにげなくちゃ!!!
2
信次の頭の中全てを、玲子の鞭から逃げることだけが占領した。だが両足を縛られ、ゆっくりとしか歩けない信次にとって、20メートルは長い長い道のりだった。玲子は信次の斜め後ろで、追い立てるでもなくゆったりと馬を進め、存分に鞭打ちを楽しんだ。ハヒッ・・・ひ、ひっ・・・「ハイ信次、第二ポイントとうちゃーくっ!私はここでおしまいよ!」パシーンッ・・・一際高い鞭音をたて、信次を激痛に仰け反らせながら玲子は別れを告げた。ハアッハヒッ・・・や、やっと着いた・・・ギアッ!パシーンッ・・・「もう信次、遅いじゃない。待ちくたびれちゃったわよ。いくら玲子が好きだからってさ、そんな露骨にツーショット見せつけられたら妬いちゃうよ!」目の前には朝子が待ち構えていた。「い、イヤーッッッ!!!」そう、これで責め苦が終わったわけではない。いや、未だ始まったばかりなのだ。絶望に叫ぶ信次を朝子は無慈悲に打ち据えた。「ほら信次、私とも遊んでよ、さ、行こう!」ピシッパシッ・・・朝子が十字に鞭を振り回し、立て続けに信次を打ち据える。ヒ、ヒイッッッ!!!信次は泣きながら歩き始めた。その背中を朝子は容赦なく打ち据える。追い立てられた信次は鞭打たれる度に背中を仰け反らせながら歩き続けた。礼子の下へ。
「はーい礼子、お待たせ!後はよろしくお願いしまーす!」「はーい、確かに信次一匹受け取りましたー!」朝子と礼子は笑いながら前後から同時に鞭を振るった。ピシーッパシーンッ・・・キアーーーッッッ!!!二発同時の強烈な鞭打ちに信次は金切り声をあげた。「信ちゃん、いらっしゃーい。私、最近慎治とばっかり遊んでたからなんか楽しみよ。どう、久しぶりの私の鞭、信次にも新鮮な味かな?」礼子は笑いながら信次に鞭を振るった。背中のあちこちに的を散らし、かつ全ての鞭が傷跡を捕らえるように巧みにコントロールして。「ひ、い、い゛だい゛゛゛っっっ!」礼子の巧みな鞭さばきに信次は断末魔のような悲鳴をあげた。「アハハッ、信次、そんなに私の鞭、痛い?良かった!たっぷり楽しんでね、私も楽しいよ!」信次により多くの苦痛を味合わせようと波のように強弱をつけ、礼子は鞭を巧みにコントロールした。信次の悲鳴を、全身の痙攣を微妙な力加減一つで自由自在にコントロールしている。うーん、楽しいな。たまには信次で遊ぶのも悪くないや。礼子に弄ばれながら、漸く信次は最終チェックポイントにたどり着いた。「はい富美ちゃんお待たせ!」「はーい、お待たせされました!もう信次、遅いよ!あんまり信次がのそのそ歩いてるもんでさ、私首を長くして待ちすぎてキリンになっちゃったよ。ちゃんと責任とってよね!」せ、責任ヒ、ヒーンッ!富美代は早速鞭を振るい始め、信次の背中に更に鞭を当てた。信次の背中はもう一面傷だらけだ。傷がない、赤くないところなどもうどこにもない。傷だらけの、痛覚が剥き出しになっているかのような背中を見ても富美代は何の憐憫も感じなかった。きれい・・・もっと赤くしてあげる・・・「信次、どう私の鞭のお味は?私、信次のこと殆ど引っ叩いてあげてないよね?どう、結構痛いでしょ?たっぷり堪能してね!」玲子と同じく、子供の頃から苛めっ子で通ってきた富美代だ。信次がどれだけ泣き叫んでも全く容赦しない。ひたすら苛めを楽しみ続けた。声を限りに泣き叫ぶ信次の悲鳴は富美代を興奮させるスパイスに過ぎない。信次、私の鞭、もっともっと味合わせてあげる。手加減抜きの鞭を縦に横に背中に脇腹に、左から右から・・・縦横無尽に振るい続け、思う存分信次を打ちのめした。そして信次は漸く、ゴール地点にたどり着いた。玲子の足元へ。全身が粟立ち、体中が激痛に痙攣していた。お、おわった・・・やっと・・・も、もうだめ・・・信次がその場に倒れこみそうになった瞬間、下から掬い上げるような鞭が信次の胸を打った。「ぐ、グボエ゛ッ!!」思わず咳き込む信次に玲子は馬上から冷たく言い放った。「信次、なにか勘違いしてない?私、たった一周でお終い、だなんて言った覚えないんですけど?勝手に休まないでくれる、みんな白けちゃうじゃん、ほら二周目、さっさとスタートよ!」そ、そんなーっっっ!!!やっと、やっと辿り着いた安住の地は蜃気楼のように儚く掻き消され、漸く逃げてきたと思った地獄の入り口がそこにあった。ひ、ひどい!!!苦痛と絶望に信次は気が狂いそうになった。だが玲子の鞭の威力、そして何より玲子に対する恐怖が信次の体を突き動かした。信次は更に一周半歩き続け、鞭を浴び続け、そして倒れた。倒れたポイントは丁度礼子のすぐ手前だった。「あん信次、もう駄目?またお芝居してるんじゃない?」「そうよ信次、ほら立って。こっちのむーちはあーまいぞっと!」朝子と礼子の二人は更に数発鞭を加え、それでも信次が動かないのを見ると馬から下りて信次を引っくり返し、軽く頬を打ってみた。「はいはい信ちゃん、生きてますかー?」礼子の呼びかけにも信次は全く反応しなかった。「ふう。どうやら完全に気絶したみたいね。OK,玲子、どうやら信次、完全にあぼーんね!」倒れたままの信次を放り出し、礼子たちは慎治に近づいてきた。そう、慎治の番が来たのだ。
慎治は震えが止まらなかった。目の前で信次が極限まで痛めつけられ、ぼろきれのように横たわっていた。そして馬に跨り、鞭を持った四人の美少女は倒れたままの信次に何の手当てもせず、遊び終わったおもちゃのように放り出してゆっくりと慎治の方にやって来た。四人を代表するかのように礼子が馬を下り、慎治に向かい合った。自分より背の高い女の子。裸で恐怖に打ち震える自分を見下ろす、ブーツを履き鞭を持った支配者。何も言う必要はない。赤い乗馬服を身に纏った憧れの美少女は、慎治を責め苛む残酷な女神として目の前に君臨していた。怯える慎治を見下ろしながら礼子は優しい微笑を浮かべると手にした鞭を二つ折りにし、すっと慎治の首にかけた。ピクッと恐怖に慎治の全身が震えた。散々自分を痛めつけてきた鞭。冷たい触感と革の香りが慎治の恐怖に直結する。そして何か違和感のある感触も感じた。どこかヌルッとした、水気のある感触。恐々下を見ると、礼子の鞭が触れたところに赤い物が付着していた。なんだろう・・・一瞬後にゾクッと悪寒が走った。それは信次の血だった。血・・・自分の体も朝から無数に打たれ、全身のあちこちが蚯蚓、というより太い蛇が皮膚の下でのたくっているかのように内出血して腫れ上がっていた。その蚯蚓腫れが遂に余りの鞭に耐え切れず、破裂したに違いない。そういえば、信次の体の周りで何か赤い霧を見たような気がしたけど、あれは錯覚じゃなかったんだ。あれは・・・信次の血飛沫だったんだ!!!血飛沫・・・皮膚が裂け、内出血して皮膚下に溜まった血が吹き出たんだ・・・怖い、というしかなかった。今まで散々鞭打たれたが、血が多少滴ることはあっても血飛沫が上がるほど鞭打たれた記憶はなかった。だけど・・・だけど!!!「さあ慎治、待たせたわね。アン、何震えて恐がってるのよ。心配しないで、これで正真正銘オーラスよ。今日のパーティーはこれでお開きなんだから、しっかり盛り上げてね!期待してるわよ。」礼子は声も出せずに震えている慎治の頭を優しく抱き締め、髪を撫でると頬にキスした。ふわっと礼子の甘い体臭が慎治の鼻腔をくすぐる。天城礼子に抱き締められ、キスされる。普通の男だったら天国に上る気分だろう。だが、慎治にとっては礼子の抱擁は死神の抱擁、礼子のキスは死刑執行の宣告書だった。
「さ、みんな待ってるわよ。行こう。」礼子は犬の首輪を引くように、慎治を首にかけた鞭で引きずって玲子たちの足元に連れて行き、そのまま地べたに正座させた。「礼子、仕上げはどうやる?今日の大トリ、面白い企画を期待してるわよ!」期待満々にはしゃいだ玲子の声に苦笑しながら礼子も自分の愛馬に跨った。「ったく玲子ったら!そんなにはしゃいでほら、慎治がすっかり怯えちゃってるじゃない!私の慎ちゃんのこと、苛めないで頂戴!」楽しげに笑いながら戯れる礼子たちの声は慎治にとって遥か天上、馬に跨った礼子たちの顔が位置する2メートル以上の上空の高みで繰り広げられる、残酷な女神たちの戯れだった。そして気まぐれな女神たちはほんの一時の戯れのために、地上の虫けらに死ぬほどの苦痛と恐怖を与える。「そうね・・・ねえ、子供の頃、かーもめかもめ、てやらなかった?」「かーもめかもめ?あの後ろの正面だーれだ?ってやつ?うん、やったけど・・・あ!そうか、わかった!」玲子がポンッと手を叩いた。「あ、あたしもあたしも!」「うんうん、いいじゃん、やろうやろう!」流石に鞭の楽しみを共有する仲、富美代と朝子も瞬時に礼子の企みを理解した。
「え、な、なに、、、ぼ、ぼくをどうするつもりなの!?!?」一人わけがわからず怯えている慎治の質問を無視して礼子が合図をかけた。「さ、みんな離れて離れて!」礼子の声と共に四人は互いの馬をゆっくりと二、三歩歩かせ、正方形を形作った。但し、今度の正方形は先ほど信次を苛めた時の正方形よりずいぶん小さい。一辺5メートルちょっとの正方形、そう、四人とも、自分の鞭の射程距離に慎治を丁度収める間合いだった。礼子たちは慎治を中心にゆっくりと円を描いて回り始めた。「フフ、慎治、怖い?どうされるか心配?なんかこれって私の好きな西部劇、インディアンの幌馬車襲撃シーンみたいね。」礼子の声が熱を帯び始めた。「あ、そのシーンなら私も知ってる!こうやって幌馬車を取り囲んで回りながら、死角をついて攻撃してくんだよね!」玲子にもすっかり手順はわかっていた。「そう、嬲り殺しよ!ハイヤーッ!」慎治の視線は本能的に礼子を追っていた。自分を最も酷く虐待する拷問者。残虐な飼主を。礼子の掛け声と鞭を振り上げる動作に慎治はビクッと反応し、本能的に両手を前に出し、頭を抱え込むようにしてガードらしき姿勢を取った。散々礼子に鞭打たれた慎治の反能としては無理もない。だが慎治は忘れていた。鞭は四本あることを。「ぎあっ!」慎治は背中に手を回して飛び上がった。慎治の予期せざる方向から鞭は飛んできた。背後から鞭を振り下ろしたのは玲子だった。「ひっ・・ひいっ!」悲鳴を上げながら慎治は玲子の方に向き直ろうとする。だが体を四分の一も回転させない内に富美代の鞭が慎治の尻を打った。「アウッ!」思わず両手で打たれた尻を押さえてしまい、前面ががら空きになった。「ほらほら慎治、ちゃんとガードしないでいいの?」ヒュンッ・・・パシーッと派手な音を立てて朝子の鞭が正面から、慎治の肩から背中にかけて絡みついた。「ピア゛―!!」激痛に肩を押さえて慎治が蹲りそうになり、曝け出された背中に遂に本命、礼子の鞭がキスした。パシーッッ・・・「イアーッッ!!!」一際高い鞭音と慎治の悲鳴が轟いた。
3
四人でグルグル回転しながらの鞭、堪ったものではない。慎治がどう動いても、どうガードしようとしても必ず無防備の箇所がある。全く見えない場所がある。そこに礼子たちの鞭が襲い掛かる。誰が鞭を振るうか、どこを狙うか。僅かなアイコンタクトだけで十分だった。だが慎治には全く予想がつかない。予期せぬ方向から予期せぬタイミングで襲い掛かる鞭。慎治は恐怖のあまりパニック状態だった。どこを鞭打たれるのか、いつ鞭打たれるのか、誰に鞭打たれるのか、全く予想ができない。精神的な苦痛だけではない、心の準備ができない分、余計に鞭が痛く感じる。礼子たち四人は慎治を囲み、長年のキャリアを積み熟成された室内管弦楽カルテットのように、息のあった鞭打ちを思う存分、繰り広げた。熟練した職人技のように礼子たちの鞭は慎治の苦痛を極限まで絞りだしていく。カルテットというのは正しくないかもしれない。四人の輪の中心で、鞭と戯れるように慎治は踊っていた。見えない所から襲い掛かる鞭が体を打ち据える度に、全身をビクッと震わせ、悲鳴をあげながら体をよじる。礼子たちの鞭に慎治は全身で反応していた。その様は傍から見ているとカルテットではなくクインテット、慎治を中心にした五重奏団のようだった。
ヒッ・・・に、逃げなくちゃ・・こ、このままじゃ殺される!!!慎治は必死で礼子たちの囲みから逃れようと、一番怖い礼子に背を向けて走り出した。「グヴォッ!」礼子が逃すわけがない。背後から首に巻きついた礼子の鞭に締め上げられ、慎治は海老のように仰け反りながらうめいた。「あら慎治、そんなに私の鞭が欲しかったの?早く言ってよ、私と慎治の仲じゃない、いいわ、いっぱい鞭、あげる!」正面から八の字を描くように玲子の鞭が慎治の胸、脇腹を打ち据えた。「ヒギャァーッッ!!!」慎治は玲子の鞭と礼子の締め技の二段攻撃に血の出るような悲鳴をあげた。「あっそのペア攻撃、面白そう!朝子、私たちもやろう!」「OK!ほら慎治、これはどう?」礼子の鞭から漸く開放され、苦しげに咳き込む慎治の腕から肩にかけて、左から富美代、右から朝子の鞭が同時に絡みついた。「ハイヤーッ!」富美代と朝子は慎治に鞭を絡めたまま、愛馬を一歩外側に歩かせる。「アイ゛ダ゛゛゛!」慎治は両腕が引っこ抜かれるような痛みに悲鳴をあげながら十字架に架けられたように両手を広げる。だが、これは前段階、苦痛の本番はこれからだった。「ほーら慎治、つーかまえたっと!礼子、やっちゃえやっちゃぇーっ!」「OK!玲子、行くよ!」富美代の掛け声を合図に礼子たち二人は両手を引っ張られ、身動きできない慎治に前後から猛烈な鞭を浴びせた。パシーンッ、ピシッ、パシッ、パウッ、ビシーッ・・・「ほら慎治、踊れ踊れーっ!」「そらそら!これでもかこれでもか!」「ピギッ・・・アヒーッッッッや、やべでゆるじでーーっっっ!!!」「バーカ、許すわけないじゃん!?」「もっとよもっともっと!ほらほら慎治、泣け、喚け、もがき苦しめーっっっ!」四人の美少女は慎治の断末魔のような悲鳴にすっかり興奮してしまった。二本の鞭の同時攻撃。今まで礼子たちに散々鞭打たれてきたとは言え、基本的には一対一だ。二本の鞭で同時に打たれたことなどない。しかも流石に共に鞭を振るってきた仲、礼子たち二人の鞭の呼吸はピッタリ合っていた。絶妙の間合い、寸分違わぬタイミングで打ち込まれる二本の鞭。絡んだり、邪魔しあうことなく慎治の体を同時に打ち据え、一本の時の数倍の苦痛を慎治に味合わせる。
富美代と朝子が鞭を緩め、慎治を解放するとすかさず今度は礼子と玲子の鞭が慎治の首に前後両方から絡みつき、締め付ける。「ぐ、ぐヴえべべべ!!!」悲鳴を上げながら慎治は必死で首に絡みついた二本の鞭を掴み、何とか少しでも呼吸をしようとする。礼子たちは締め落とす気はないから、窒息する程きつくは締め上げないが、それでも慎治が鞭を必死で掴めねば耐え切れないほどの強さで鞭を引き、慎治の全ての抵抗を封じた。そして倒れることもできずにうめく慎治の全身を左右から富美代と朝子が鞭打つ。「キャハハハッ!!!ほら慎治、踊れ踊れ踊れーっ!!!」「アーハッハッハッ!!!最高、もっと泣け泣け泣けーっっっ!!!」すっかり頭に血が上った富美代と朝子は全く手加減なしで、滅茶苦茶なピッチで慎治の全身に鞭を往復ビンタの様に浴びせ続けた。背中や尻だけではない。胸、腹、脇腹、太腿、腿の裏、・・・慎治の全身を隈なく鞭打ち、蚯蚓腫れと青あざを刻み込んでいく。慎治の体に傷が増えるのを見ることが、富美代と朝子にとって全身を支配する最高の快感と直結していた。そしてぼろほろになった慎治の全身、何度も鞭があたった箇所は既に内出血の圧力が高まり、皮膚が破れる寸前だった。「OK!そろそろフィニッシュ行こうか!」礼子の声に、富美代と朝子が一旦、鞭を休めて呼吸を整えた。そして礼子たち二人が慎治を鞭から解放すると、慎治は倒れる気力すらなくフラフラと立ち尽くしたまますすり泣いていた。「アヒッ・・・ヒック・・う、ウェッッッ・・・い、いたい・・・」顔中を涙と涎でグチャグチャにしながら慎治は喘いでいた。視線は定まらず、指先一本動かす気力すらない。最高よ慎治、さあフィニッシュ、楽しませて頂戴!頭上でグルグルと鞭を振り回しながら礼子が気合を入れた。「みんないい!フィニッシュ行くよ?さあ慎治、覚悟はいいわね。止めは・・・二倍二倍で・・・四倍鞭よ!せーの、ハッ!」ビシバシピシバウッ・・・「ギアーッッッ!!!」左肩越しに前から礼子、右肩越に後ろから玲子、背中から右脇腹に朝子、腹から左脇腹に富美代、四人の鞭が同時に慎治の体に襲い掛かった。痛い、という感覚を既に超えていた。慎治は上半身が千切れたような感覚に襲われた。皮膚の表面だけに止まるような生易しい痛さではない。筋肉、脂肪を貫通し、内蔵にまで響くような鞭の衝撃に慎治の視界がチカチカと瞬き始めた。体の奥底、はらわたから重苦しい、酸っぱいような血生臭いような塊がこみ上げてくる。余りの激痛に慎治は思わず死すら願った。「死ぬ、死んじゃう・・・いや、こ、殺して、こ、こんな痛いの、も、もういやーっ!!!いっそ一思いに殺してーっ!!!」
4
「アハハハッ!慎治、何バカ言ってんのよ!死ねるもんなら死んでごらんよ!ほらほらほら!死ね死ね死ねーっ!!!」礼子は慎治の悲痛な叫びに一層興奮し、更に力を込めて鞭を浴びせかけた。鞭の真の残酷さはそこにこそあった。慎治に気の狂わんばかりの激痛を与えながらも、礼子たちの鞭は決して致命傷にはならない。ロシア鞭クヌートのように皮膚を引き裂き、肉を弾けさせるような鞭でも使わない限り、いくら厳しい鞭でもそう簡単に人間の体は死ねないようにできているのだ。そしてこれだけ激しい苦痛を間断なく、しかも全身のあらゆる箇所に分散して与え続けられては気絶することさえ難しい。だから慎治はひたすら激痛に全身を犯され続けるしかなかった。「ギア゛ッ・・・ギャーッ・・・ビエ゛<bッッ!!!」四人が前後左右から同時に加える鞭に慎治は悲鳴を上げ続けた。体を吹き飛ばされるような、全身がばらばらに引き裂かれるような痛み。礼子たちの長い鞭は慎治の体に絡みつき、打撃の苦痛を加えた後に、そのまま体の中に食い込むように絡みつき、締め付けるような苦痛を体の内部へと送り込む。「グウィーッッ、グ、グルジイ・・・」慎治は礼子たちの鞭が巨人の手に変り、自分の体を握りつぶそうとしているような錯覚さえ感じた。余りの痛さに呼吸することさえ困難な苦痛だ。四倍鞭どころではない、十倍、二十倍の激痛だ。しかもその激痛の鞭は四方から間断なく飛んでくる。あまりに数が多すぎていつ、誰の鞭に打たれているのかさえ、もうわからない。よけるも何もない。ただ鞭打たれるだけ。倒れることすらできない。な、なぜ・・・なぜこんな目にあわされているんだ???ぼ、ぼくがなにをした???すべての疑問さえ無意味だ。慎治が立たされている空間は礼子たち四人の鞭で満たされていた。苦痛と絶望のみが存在する世界、月並みな言い方だが地獄、と呼ぶしかない空間だった。そしてその地獄を現出させているのは、醜い地獄の鬼とは対照的な美しい四人の少女だった。醜い、といえば裸にされて鞭打たれ、涙と涎に顔中グチャグチャにして泣き喚いている慎治の方がよほど醜かった。さすれば、鬼はむしろ慎治、そして礼子たちは地獄の鬼どもさえ罰することのできる女神、ワルキューレといった方が似つかわしかった。
慎治は無限とも思える時間、苦痛のみを味わい続けた。だが漸く、凍りついた時間も動き出そうとしていた。四人掛かりの鞭、その余りの威力に慎治の肉体が限界に達し、全身に刻まれた内出血の跡の何箇所かが皮膚の張力の限界をついに超えて裂け、血を吹き出した。「やったやったーっ!血よ、血が出たわーっ!みんな、集中攻撃よ!止めを刺すわよ!」礼子の号令に合わせ四人全員が鞭の打ち方を変えた。全員の鞭が慎治の傷に集中する。更に礼子たちは絡めた鞭を素早く手元に引き戻す引き鞭の責めを加え、慎治の皮膚を引き裂きにかかった。ビッ・・・ピシュッ・・・バシュッ・・・パシューンッ・・・巨人、いや魔神の手と化したような礼子たちの鞭は今までの打撃と締め付けに加え、爪で慎治の体を引き裂く責めを追加する。慎治たちを何千回も打ち据えてきた礼子たちの鞭テクニックは最初の頃とは比べ物にならない位、上達している。単に打ち据えて打撃の痛みのみを与える、絡むように打ち据えて打撃と締め付けの二重の苦痛を与える、そして絡ませた後に素早く鞭を手元に引き戻し、打撃、締め付けに加えて返しの鞭で皮膚を切り裂く三重苦を味合わせる。自由自在に鞭を操り、慎治の苦痛のレベルを思うがままにコントロールできる。
単純に鞭打たれるだけの苦痛なら痛い、とは言っても慎治たちにもなんとか耐えられる。だが礼子たちが磨き上げた鞭の技術、様々な残酷なテクニックを駆使してくるともう駄目だ。慎治たちの痛みに対する耐久力レベルは最初と比べ、多少は向上しているとは言っても大した進歩はない。余程強烈な信念でもない限り人間が耐えられる苦痛には限界がある。それに対して礼子たちの技術の進歩には限界がないのだ。だから今では、礼子たちはいともた易く慎治たちの限界を超える苦痛を与えられるようになっていた。慎治たちが耐えられるのは単に、礼子たちが鞭打ちをゆっくり楽しむために苦痛のレベルを下げてやっている時だけだ。礼子たちが手加減し、弄んでいる間は延々と苦痛が続く。そして礼子たちが本気を出したら・・・破局が待つのみだ。
礼子たちだって最初の頃はただ単純に鞭を振るい、打ち据えるだけしかできなかった。だが体育会的な生真面目さ、とでも言ったらいいのだろうか、礼子たちは慎治たちを鞭打ちながら熱心に技術を向上させていった。その成果だった。礼子たちは鞭に本気でのめり込んでいた。慎治たちを鞭打つ時だけではない。自宅にサンドバッグまで用意し、色々トレーニングを積んでいた。巧みに鞭を相手に絡める感覚、間合いの掴み方はそのトレーニングの賜物だ。今、慎治が味合わされている引き鞭も礼子たちが何度も何度も練習を積んで身につけた貴重な技術だ。スナップを効かせながら打ち込んで、鞭が相手に食い込む感触を覚えた時はあっ、分かった、と一つ自分のレベルが上がった実感に喜んだものだ。そして相手の体に食い込ませた鞭を素早く手元に引き戻す、打ち込んだ次の瞬間に鞭を引き戻し、相手の体の上に鞭を走らせるテクニックは何度も何度もサンドバッグ相手に練習し、漸くモノにした財産だ。サンドバッグに食い込んだ鞭がビシュッと表面を走っていく感触を始めてゲットした時にも、よし、この感覚ね、と何とも言えない達成感があったものだ。礼子たちだけではない。いくら礼子たちにコツを懇切丁寧にコーチされたとは言っても、富美代と朝子だって簡単に、単に慎治たちを1000発程度鞭打っただけで免許皆伝となったわけではない。二人もやはり、毎日のように自分の部屋でサンドバッグ相手に熱心に鞭を練習し続けて教わったテクニックを自分のモノにしたのだ。空手や合気道、少林寺拳法の練習用に買ったサンドバッグだったが、鞭の練習用にも最適だった。鞭を振るう時だけではない、全ての格闘技の基本となる様々な筋力トレーニング、ストレッチングを礼子たち四人は毎日欠かしたことがない。
努力に勝る天才なしとよく言うが、天才が努力したら凡人がどんなに努力しても絶対に追いつけない。丁度タイガーウッズがそうであるように。礼子たち二人は紛れもない天才、その天才がこれだけ練習したのだ、鞭が上達しないわけがない。富美代と朝子にしても、礼子たち程ではないにしても相当程度の才能がある。熱心なトレーニングと礼子たちの的確なコーチングがその才能を如何なく開花させていた。鞭打つ側の四人がこれだけ練習していたのに対し、慎治たちは何をしたのだろうか。何もしなかった。ひたすら礼子たちのご機嫌を損ねないようにビクビクし、鞭打たれる時には情けなく泣き喚いて許しを乞うだけだ。何もしていない。体を鍛えたわけでもないし少しでも痛みを和らげる方策を考えたわけでもない。あれだけ痛めつけられたのだ、痛みに慣れ、多少は痛みに対する免疫ができたとは言っても所詮、受身に過ぎない。頭も体も、何も使っていないのだ。これではどうしようもない。努力した天才と何もしない凡人。只でさえ鞭打つ側の礼子たちは鞭打たれる側の慎治たちより絶対的に有利なのに加え才能の差も歴然。その上更に努力まで礼子たちが遥かに上ではどうしようもない。
5
礼子たちが最初に鞭を振るった時、慎治たちは余りの痛さに絶叫したが未だ、多少は耐えることができた。その意味では鞭打つ礼子たちと鞭打たれる慎治たちの能力は一応、対等に近い水準にあった、と言える。だが、その後の積み重ねが大きな差を作っていた。今では礼子たちの苦痛を与える能力は、慎治たちの苦痛に耐える能力を遥かに上回り、しかもその差はどんどん拡大していた。丁度戦争中のアメリカと日本の力関係みたいなものだろうか。開戦直後は五分に戦えた両軍が次第に実力差がつき、最後には質量全ての面においてアメリカと日本に圧倒的な差がついてしまい、どう足掻いても太刀打ちできなくなってしまったのと同じようなものだ。
慎治たちにしてみれば、もともと一方的に鞭で打たれる身、上達も何も端から圧倒的に不利、勝てるわけがない、と言いたいだろう。だが、この差は単に鞭だけの話ではない。勉強、武道、あるいはファッションセンスから音楽に至るまで、どんなことについても同じだった。勉強を例に取れば確かに最初の内、礼子たちは慎治たちが勉強するのを禁じ落ちこぼれになるように仕向けた。だが最近では勉強に対する妨害は何もしていない。何故か、答えは簡単、一度落ちこぼれてしまった慎治たちが追いつくための努力を放棄し、「礼子さんたちに勉強を禁止されてるからどうしようもない」「毎日毎日こんなに苛められてちゃ、勉強なんか手につくわけないよ」という言い訳に安住し、勝手に加速度的に成績を悪化させているからだ。部活にしてもそうで、確かに慎治たちは雑用係兼サンドバッグでこき使われ、何も教えてもらえない身分だが陰で練習、せめて筋力トレーニングだけでもして女の子にさえ劣る体力をアップしよう、という努力を何もしていない。音楽にしても礼子たちは実に色々なジャンルを聞き、J-ポップからロック系、ジャズからクラシックに至るまで色々と聞いて楽しんでいるのに対し慎治たちは精々、テレビで流れる安っぽい商業ポップを聞くだけだ。本に至っては小説、エッセイ以下色々と読んでいる礼子たちに対し、慎治たちはマンガ以外を読むことは殆どない。要は積極的に自分を高めようとしている礼子たちに対し、慎治たちは単に流されるがままに、苦痛も娯楽も全て受身で生きていた。これでは一日一日差がついていくのも当然だ。礼子たちの時間が濃密で一日一日充実しているのに対し、慎治たちの一日はなんとも希薄、無為な日々だった。富美代や朝子も礼子たち程ではないにしても、充実した濃密な日々を送っている。身近な親友がこれだけ色々とアクティブに生き、豊富な話題を、刺激を与えてくれるのだ、富美代や朝子も当然のように自分を高めることに熱心になっていた。誰に強制されたわけでもない。単に楽しいから、自分が成長していく実感が楽しいから、そしてその成長が周りの人間にも認められる嬉しさがあるから濃密な日々を過ごせるのだ。この楽しさは三流の商業高校や底辺校の生徒、ましてやそんなレベルの高校すら中退してしまうような連中には一生縁のない楽しさだろう。そして慎治たちはそれ以下、自分が楽しいと思うことは何か、すら分からず、ひたすら怯えて暮らしている。三流高校中退の連中でさえ、せめてその昆虫並みの頭で気持ち良い、楽しいと感じることを追求すること位には熱心だ。本能的、といったレベルにすぎないが楽しいことを追求する、例えどんなに安っぽい無価値な楽しみでも、自分から積極的に快楽を求める程度の意思はある。だが慎治たちにはそれすらない。あるのは只受身、待ちの姿勢だけ。傍から見ていると、自分の意志を持たないのなら生きていても仕方ないだろう、としか思えない、意思を持たない植物同然の日々を送っていた。まさに自己否定の人生。生産性など何もない。
慎治たちにも、礼子たちが自分よりどんどん高いところに昇りつづけているのは十二分に分かっていた。別に苛められる時だけではない。礼子たちが機嫌いい時に普通に話しかけられても、礼子たちがほんの基礎知識と思っていることすら知らないから全く話が通じず、バカにされ笑われることなど日常茶飯事だ。授業などで一緒の班になった時など、礼子たちの合理的、論理的な思考回路や頭の回転の速さは正直、自分と違う人種としか思えない。何をやってもどうやっても勝てないどころか次元が違うところにいる人種、それが礼子たちだった。だから慎治たちは礼子たちが何もしない時でも、声をかけられるだけで、いや視線を投げられるだけでコンプレックスに苛まされていた。慎治たちがこれだけ酷い目に合わされても僅かな逆ギレ、反抗すらてできないのはそうやって礼子たちに精神的に屈服しているから、という要因が大きい。礼子たちにとって、慎治たちを苛めて遊ぶのは自分の時間のほんの一部、無数にある楽しみの一つに過ぎない。だが慎治たちにとっては礼子たちに苛められることが全てなのだ。礼子たちの苛め以外の部分での成長、そこで人間としての価値にどんどん差がついていた。ましてやその礼子たちが権威と力の象徴である鞭を握ったりしたら、慎治たちの精神は地虫より卑屈になってしまう。強制されるわけでもなんでもなく、勝手に同級生の女の子に敬語を使ってしまう始末だ。身分、まさしく生まれつきではなく、生まれてからの生き方によって礼子たちと慎治たちの間には厳然たる身分の上下が出来上がっていた。
そしてあらゆる面で慎治より優れる四人の美少女は、無数に持つ特筆すべき能力の内の一つを、他人に苦痛を与える能力を今、一切の手加減抜きでフルに解放していた。スナップを思いっきり効かせて鞭を慎治の体に絡ませ、手応えを感じた次の瞬間手首をこねる様に返し、鞭を猛スピードで慎治の皮膚上に這わせながら手元に引き戻す。打撃、締め付け、切り裂き、一鞭で三度痛い残酷な鞭を四人の美少女は四方から間断なく打ち込み続けた。慎治は先ほど、信次の体から血飛沫が飛んだのに恐怖した。だが信次はまだまだ運が良かった。引き鞭までは味合わされずに済んだのだ。慎治はそうは逝かない。礼子たちが本当に全力を出したらどうなるか、慎治はたっぷりと味合わされることになった。「ひ、ヒエーッッ!!!い、いだいーっっっ!や、ヤベ、、ビッ!イャ!イヤイヤイヤーッ!!!ユルジデーッッッ!!!」血の出るような慎治の悲鳴に比例するかのように、皮膚のあちこちが裂けていく。全身のここそこで血が吹き出る。加速度的に傷の数は増えていく。その傷を礼子たちは無慈悲に狙って鞭打ち続けた。ナイフで切り裂かれるような、いや生皮を剥ぎ取られる激痛を慎治の全身に刻み込みながら、礼子たちの鞭は的確に慎治の傷口に叩き込まれる。そして鞭に叩き出された内出血が慎治の傷口から霧のように吹き出した。出血の量は大したことはない。だが、一鞭毎に生皮を剥がれ、傷口を鞭打たれる激痛は慎治の限界を遥かに超えていた。慎治は腕をだらんと下げ、体を庇う余裕すらなく呆けたように立ちすくみ、絶叫しながら鞭を受けていた。四人がかりの鞭を何発受けただろうか。漸く失神という慈悲の女神が慎治に微笑んだとき、慎治の全身は見るも無残な鞭跡に埋め尽くされていた。
富美代と朝子のおしっこも飲み終えた慎治たちは、這うようにしてグラウンドに戻ってきた。漸く全身の激痛も治まりつつあったが、もう体力の限界に来ていることは間違いなかった。のろのろと礼子たちの所に戻ってきた慎治たちは半ば倒れこむように座り込んだ。もう流石に終わりだろう・・・全身ボロボロ、今日何発の鞭を受けたか、数え切れないほどだ。もうないよな・・・「信次、ちょっとそこに寝てみてくれない?ああ、うつ伏せのほうがいいわ。」玲子に促され、信次はその場にうつ伏せに横たわった。「うわ凄い・・・縞々模様って言ってあげたいけど、格子模様みたいね。」信次の背中の傷をブーツの爪先で突っつきながら玲子は満足気に頷いた。「慎治、あんたも寝てみてくれない?こっちで信次と並んで寝てよ。鞭跡の品評会やるからさ。」慎治は玲子の言うとおり、信次と並んでマグロのように横たわった。四人の美少女はブーツの爪先や踵で信次たちを弄びながら鑑賞会を開いていた。長い鞭を玲子はリング状に丸めて肩にかけ、礼子はベルトの様に腰に巻いていた。朝子はショールよろしく首に引っ掛け、富美代は二の腕に蛇のように巻きつけていた。自分たちを徹底的に苛めつけた少女たちに踏まれながら、傷跡を鑑賞される。信次たちの凄惨な苦痛の跡を、四人の美少女は絵でも楽しむかのように、信次たちに一片の同情すら見せずに鑑賞していた。この悪魔・・・心の中で信次は毒づいていた。だが、言葉にできる訳がない。自分を責め嬲る美少女たちは鞭を、散々泣き叫ばせられた拷問具を持っているのだ。逆らえるはずがない。「どう礼子?パッと見、二人とも鞭の跡はほぼ互角、てところね。結構いい染まり方じゃない?」「そうね・・・鞭跡もいいけど、やっぱり引き摺り回しってグーね。きれいに全身、赤くなってるわね。」信次の頭を爪先で軽く踏みながら朝子も頷いた。「本当ねー、ここまでやれれば大満足って感じよね、でもやっぱり、鞭って最高ね!」「本当!それにここ最高じゃん、また来ようよ!」富美代も満足しきった様子だった。
礼子たちは憐憫、同情心のかけらも感じていなかった。普段は優しいのに。武道をやっていても、否、やっているからこそ他人に理由もなく暴力を振るうことは絶対にないのに、慎治たちに鞭を振るう時、礼子たちは誰も、慎治たちが痛くて可哀想、とは全く思わなかった。当然と言えば当然だ。鞭、慎治たちを打ち据えている本物の一本鞭は通常、殆どの人間が一生見ることも触れることもないものだ。だからその鞭がどれ位痛いかなど、想像することすら難しい。鞭跡の蚯蚓腫れにしても、自分が知らない痛みだ。だから手加減がない。どれ位痛いか、すら想像できないのだから、相手を傷つけることに対する恐怖、内心の無意識に近いブレーキが働かない。いくら慎治たちが絶叫してもその苦痛は実感としては伝わらず、単に自分の鞭で慎治たちを泣き喚かせている、という快感、満足感に置き換えられてしまう。ぼろぼろになった慎治たちを見ても他人事としてしか感じられず、全く大騒ぎしちゃって、位にしか感じられない。これもまた、鞭の魔力の一つかもしれない。鞭、この効率よく他人に苦痛を与えられる道具は単に慎治たちに肉体的な苦痛を与えるだけではなく、鞭を握る礼子たちの精神までも改造していた。
か、勝手な事ばかり言って・・・礼子たちの足元に横たわり、ブーツで鞭跡を小突き回されながら慎治は悔しさを必死で堪えていた。ち、畜生・・・人の事をこんなになるまで痛めつけるなんて、この悪魔!鬼!・・・こんな地獄のようなとこ、もう二度と来てたまるもんか!だけど、今は何も言っちゃいけない・・・もうすぐ、もうすぐ終わる・・・辛かった今日も終わる。礼子さんも富美ちゃんも、流石にもう満足しているようだからな・・・もう終わる・・・
慎治の期待は当然だった。礼子たちは四人とも、もう終わる気だった。ああ、今日は楽しかった・・・場の空気が急速に弛緩していった。「ふう、ま、今日はこんなもんかしらね。そろそろ帰ろうか?」今日の主催者、玲子の口から信次たちが待ちに待った言葉が紡ぎだされた。「そうね、ああ楽しかった。また来ようね。」朝子と富美代ももう終わる気になっていた。そして礼子も今の今まで、すっかり終わる気になっていた。だが、玲子の声を聴いた瞬間、礼子の心の中に囁くものがあった。チャンス!と。
入学当初こそ対立したものの、礼子と玲子は苛めという共通の趣味を通じて親友になっていた。別に慎治たちを苛める時だけではない。クラブに行ったり、買い物を楽しんだり、この乗馬クラブにしても、苛め抜きで健康的に楽しむだけでもよく一緒に来ていた。だが、いくら仲がいいと言っても、お互いの心の奥底には相手に負けたくない、というライバル意識もある。ルックス、スタイル、知性、家柄・・・全てに恵まれているだけに、二人のプライドもまた、強烈なものだった。玲子にだけは負けたくない・・・礼子に勝つのって最高・・・陽気に、オープンに張り合うから陰湿な所がなく、競い合うことが仲を悪くすることはないが、互いに勝とうとする意識は常にある。そのライバル意識が最もストレートに表れるのが、慎治たちを苛める時だった。ストリートの連中が腕力を競うのと同じように、礼子たちは慎治たちに対して、どちらがより残酷になれるか、どちらがより多くの苦痛を与えられるか、どちらがより多く慎治たちを泣き叫ばせられるか、を競うところがあった。
そして今、玲子が信次をもう許してやろう、と言っている。その瞬間、礼子にピンと来るものがあった。玲子は許してやる、て言ってる・・・良かったね信次、ご主人様のお許しが貰えて。だけどね信次、私は玲子ほど優しくないよ。私の慎治共々、もう一鞍苛めてあげる!ついてない、そう、信次たちにとって、ついてない、としか言えない展開だった。もう終わろう、と言ったのが富美代か朝子だったら、礼子も間違いなく終わりにしていたはずだ。玲子が、玲子さえ何も言わなければ・・・最後の、文字通り最後の一瞬で信次たちの運命は更に深く暗転していった。
「ねえ玲子、もう終わるのはいいんだけどさ、私、まだ一つ忘れてる気がするんだ。」「忘れてる?何を?そりゃまあ、色々遊び方はあると思うんだけどさ、今日のところはやり尽くしてない?」いいわ玲子、玲子でも未だ気づいてないのね。「うん、忘れてる、ていうのはね、人数なのよ。」「人数?」「そう、午前中は一対一でみんな遊んだでしょ?で、今の引き摺りは基本的に二対一よね。」「そっか!」富美代がポンッと手を叩いた。「礼子、もしかして、四対一で遊ぼうって考えての?」
「ビンゴ!富美ちゃん冴えてるー!」朝子も悪戯っぽい笑いを漏らした。「フフ、礼子ってアクマー!四対一だって?それって、要するにタコ殴り、てことじゃん?ねえ信次、どうする?これから四人掛りでのタコ殴りだって。大丈夫?あんたたち、下手したら本当に死んじゃうかもね!」やられた!玲子の胸中を礼子に出し抜かれた悔しさが占拠した。四対一かあ・・・あーん、私ってオバカ!このパターンを忘れてるなんて。一瞬、意地になって反対しようか、とも思った。だがすぐに玲子は気を取り直した。ま、今のは礼子にやられたってことでいいとするか!だって・・・タコ殴り、楽しそうジャン!「全く礼子ったら・・・ホント、あんたって鬼畜よねー。しょうがないなあ、信次、私はね、本当は可哀想だから信次のこと、もう許してあげたいなって思うんだけど、礼子がああ言うんじゃ仕方ないわ。信次、あなたも辛いと思うけど、もうちょっと、がんばってね。」「ひっど―い、玲子ったら人を悪者にしちゃって!あたしのこと鬼畜、とか言ってるくせして鞭を握り直してるの、一体誰よ!?」「あ、ばれた?ま、四対一のタコ記念日っていうことで全てOK!」「何が全てOKよ、全く、調子がいいんだから、もお!」そ、そんな馬鹿な!!!慎治たちは思わず絶叫してしまった。「や、やめてーっっっ!!!」「も、もうおねがい!!!し、死んじゃうよーっっっ!!!かえろ、ね、帰ろうよーーー!!!」「うるさいわね、信次、あんた死ぬ死ぬって気軽に言い過ぎよ。」照れ隠しのように玲子はブーツに強くウェイトをかけ、信次の顔を地面にめり込ませた。「全く、ロシア鞭の拷問じゃあるまいし、こんなんで死ねるもんなら死んでごらん!ほら、死んでごらんよ!」玲子は全体重をかけ、グリグリと信次の顔を踏み躙った。そ、そんな・・・信次が泣き喚こうと息を吸い込んだ瞬間、玲子は信次の胸倉を掴んで引き摺り起こした。
「さあみんな、パーティー再開よ!馬に乗って!」「OK!」礼子たち三人は再び愛馬に跨ると肩から、腰から、首から、腕から愛用の鞭を外し、身構えた。「で、玲子、どう行く?なんか楽しみ!信次を鞭打つのって、久し振りよね!」礼子が楽しそうに笑いながら鞭を振り回した。「そうね・・・じゃ富美ちゃんは斜め右、朝子は斜め左で20メートル位間隔取って。で、礼子は私の対面。やっぱ20メートル、ううん、もう少し奥に行って。」四人は一辺20メートル程度の正方形に並んだ。
「さあ行こうか!」玲子は四人で形作った正方形の内側に信次を入らせ、自分の右前方、鞭を最も振るいやすい位置に立たせた。更に両足を50センチ程度のロープで縛り、よちよち歩きしか出来ないようにし、更に両手も後ろ手にしっかり縛り上げ、余計な抵抗が一切できないようにした。「信次、もう分かるわね。これから信次には私たちのリングの中をたっぷりと歩いて貰うわ。安心して。もう疲れてるでしょう?さっきみたく走らなくていいからね。ゆっくり歩くだけでいいわ。私が一緒にスタートして、まずは朝子のところまでエスコートしてあげる。次は朝子に礼子のところまで送って貰いなさい。で、礼子は富美ちゃんへ、富美ちゃんは私へと信次をエスコートしてあげる。嬉しいでしょ?聖華の誇る、私たち美女四人にまとめてエスコートしてもらえるなんて、もうこの幸せ者!」「そ、そんな!!!み、みんなで鞭だなんて・・・や、やだーーーっっっ!!!ひ、ひどいよ、死んじゃう、死んじゃうよーっっ!」信次の絶叫に玲子たちはどっと笑い転げた。「やーねー信次ったらほんと、大袈裟なんだから。じゃ、いいこと教えてあげる。玲子の鞭がそんなに怖かったらね、早く私のとこまで逃げておいで!」「ああ、朝子ったらいい子ぶりっ子しちゃって!自分だって思いっきり引っ叩こうとしてるくせして!」「あ、バレた?うん、私ね、早く信次のこと引っ叩きたくて、もううずうずしちゃってるんだ!」幸せ者、確かに玲子たち四人は美少女で有名だ。近隣の高校でも有名な存在であり、ラブレターを貰ったり合コンに誘われるなど数え切れないほどだ。その四人全員が何の取柄もない信次と一緒に全身全霊込めて遊んでくれる。天国のようなシチュエーションだ。但し、四人が鞭を持っていなければ、の話だ。既にぼろぼろになるまで鞭打たれ、全身傷だらけだ。その傷口を更に鞭打たれる。い、いったいおれ、どうなっちゃうんだ・・・考えたくもない、死ぬほど痛そうだな・・・現実感すら失われつつあった。
だが心配はいらない。玲子はそんなに信次を待たせる気はなかった。怯えてるわね信次、ま、当然だろうけどね。でも安心していいよ。私、礼子みたく精神的に拷問する気はないから。直ぐに苛めてあげる!「さあ信次、幸せたっぷり噛み締めてね!レディ・・・GO!」ヒョオッ・・・パシッ・・・今日は一体何回この音を聞かされただろうか。ヒァッ!!!信次は悲鳴をあげながら歩き出した。玲子たちのゲームが始まってしまえば、信次に何かを考える余裕などない。只ひたすら責苦に耐えながら泣き喚き、時間が過ぎるのを待つだけだ。それでも信次は反射的に玲子の鞭から逃れようと走り出した。両足を縛られているのも忘れて。「うがっ!」つんのめり、バランスを崩した信次は2,3歩で前のめりに転んでしまった。「アハッ!信次、もう転んじゃって!そっか、やっぱり信次ったら私とずっと遊んでいたいのよねー。うん、分かる分かる。私と信次はいつも一緒に仲良しこよしだもんねー。私の鞭が大好きなんでしょ、じゃ、もっともっといーっぱいあげるね。ほら!」
ピシッ、パシッ・・・玲子は心底楽しそうに高笑いしながらも鞭を振るう手を片時も休めない。ひーっっ!!い、痛い!!!一日中散々打ち据えられ、引き摺り回された信次の背中は傷だらけだ。どこを打たれても傷口を抉られる、痛い、と言うより不快感を伴った苦痛に襲われる。しかも、引摺刑の最後の頃には余りの苦痛に痛覚が半ばマヒし、信次にせめてもの安らぎを与えていた。だが、僅かな時間とはいえ休息を与えられていたため、全身の感覚が蘇っていた。もちろん、痛覚も。一旦忘れかけていた痛覚がまた復活しただけで耐えがたいのに、更に傷口を抉られる痛みをプラスされるのだ。堪ったものではない。い、いたいいたいいたい!!!にげなくちゃにげなくちゃ!!!
2
信次の頭の中全てを、玲子の鞭から逃げることだけが占領した。だが両足を縛られ、ゆっくりとしか歩けない信次にとって、20メートルは長い長い道のりだった。玲子は信次の斜め後ろで、追い立てるでもなくゆったりと馬を進め、存分に鞭打ちを楽しんだ。ハヒッ・・・ひ、ひっ・・・「ハイ信次、第二ポイントとうちゃーくっ!私はここでおしまいよ!」パシーンッ・・・一際高い鞭音をたて、信次を激痛に仰け反らせながら玲子は別れを告げた。ハアッハヒッ・・・や、やっと着いた・・・ギアッ!パシーンッ・・・「もう信次、遅いじゃない。待ちくたびれちゃったわよ。いくら玲子が好きだからってさ、そんな露骨にツーショット見せつけられたら妬いちゃうよ!」目の前には朝子が待ち構えていた。「い、イヤーッッッ!!!」そう、これで責め苦が終わったわけではない。いや、未だ始まったばかりなのだ。絶望に叫ぶ信次を朝子は無慈悲に打ち据えた。「ほら信次、私とも遊んでよ、さ、行こう!」ピシッパシッ・・・朝子が十字に鞭を振り回し、立て続けに信次を打ち据える。ヒ、ヒイッッッ!!!信次は泣きながら歩き始めた。その背中を朝子は容赦なく打ち据える。追い立てられた信次は鞭打たれる度に背中を仰け反らせながら歩き続けた。礼子の下へ。
「はーい礼子、お待たせ!後はよろしくお願いしまーす!」「はーい、確かに信次一匹受け取りましたー!」朝子と礼子は笑いながら前後から同時に鞭を振るった。ピシーッパシーンッ・・・キアーーーッッッ!!!二発同時の強烈な鞭打ちに信次は金切り声をあげた。「信ちゃん、いらっしゃーい。私、最近慎治とばっかり遊んでたからなんか楽しみよ。どう、久しぶりの私の鞭、信次にも新鮮な味かな?」礼子は笑いながら信次に鞭を振るった。背中のあちこちに的を散らし、かつ全ての鞭が傷跡を捕らえるように巧みにコントロールして。「ひ、い、い゛だい゛゛゛っっっ!」礼子の巧みな鞭さばきに信次は断末魔のような悲鳴をあげた。「アハハッ、信次、そんなに私の鞭、痛い?良かった!たっぷり楽しんでね、私も楽しいよ!」信次により多くの苦痛を味合わせようと波のように強弱をつけ、礼子は鞭を巧みにコントロールした。信次の悲鳴を、全身の痙攣を微妙な力加減一つで自由自在にコントロールしている。うーん、楽しいな。たまには信次で遊ぶのも悪くないや。礼子に弄ばれながら、漸く信次は最終チェックポイントにたどり着いた。「はい富美ちゃんお待たせ!」「はーい、お待たせされました!もう信次、遅いよ!あんまり信次がのそのそ歩いてるもんでさ、私首を長くして待ちすぎてキリンになっちゃったよ。ちゃんと責任とってよね!」せ、責任ヒ、ヒーンッ!富美代は早速鞭を振るい始め、信次の背中に更に鞭を当てた。信次の背中はもう一面傷だらけだ。傷がない、赤くないところなどもうどこにもない。傷だらけの、痛覚が剥き出しになっているかのような背中を見ても富美代は何の憐憫も感じなかった。きれい・・・もっと赤くしてあげる・・・「信次、どう私の鞭のお味は?私、信次のこと殆ど引っ叩いてあげてないよね?どう、結構痛いでしょ?たっぷり堪能してね!」玲子と同じく、子供の頃から苛めっ子で通ってきた富美代だ。信次がどれだけ泣き叫んでも全く容赦しない。ひたすら苛めを楽しみ続けた。声を限りに泣き叫ぶ信次の悲鳴は富美代を興奮させるスパイスに過ぎない。信次、私の鞭、もっともっと味合わせてあげる。手加減抜きの鞭を縦に横に背中に脇腹に、左から右から・・・縦横無尽に振るい続け、思う存分信次を打ちのめした。そして信次は漸く、ゴール地点にたどり着いた。玲子の足元へ。全身が粟立ち、体中が激痛に痙攣していた。お、おわった・・・やっと・・・も、もうだめ・・・信次がその場に倒れこみそうになった瞬間、下から掬い上げるような鞭が信次の胸を打った。「ぐ、グボエ゛ッ!!」思わず咳き込む信次に玲子は馬上から冷たく言い放った。「信次、なにか勘違いしてない?私、たった一周でお終い、だなんて言った覚えないんですけど?勝手に休まないでくれる、みんな白けちゃうじゃん、ほら二周目、さっさとスタートよ!」そ、そんなーっっっ!!!やっと、やっと辿り着いた安住の地は蜃気楼のように儚く掻き消され、漸く逃げてきたと思った地獄の入り口がそこにあった。ひ、ひどい!!!苦痛と絶望に信次は気が狂いそうになった。だが玲子の鞭の威力、そして何より玲子に対する恐怖が信次の体を突き動かした。信次は更に一周半歩き続け、鞭を浴び続け、そして倒れた。倒れたポイントは丁度礼子のすぐ手前だった。「あん信次、もう駄目?またお芝居してるんじゃない?」「そうよ信次、ほら立って。こっちのむーちはあーまいぞっと!」朝子と礼子の二人は更に数発鞭を加え、それでも信次が動かないのを見ると馬から下りて信次を引っくり返し、軽く頬を打ってみた。「はいはい信ちゃん、生きてますかー?」礼子の呼びかけにも信次は全く反応しなかった。「ふう。どうやら完全に気絶したみたいね。OK,玲子、どうやら信次、完全にあぼーんね!」倒れたままの信次を放り出し、礼子たちは慎治に近づいてきた。そう、慎治の番が来たのだ。
慎治は震えが止まらなかった。目の前で信次が極限まで痛めつけられ、ぼろきれのように横たわっていた。そして馬に跨り、鞭を持った四人の美少女は倒れたままの信次に何の手当てもせず、遊び終わったおもちゃのように放り出してゆっくりと慎治の方にやって来た。四人を代表するかのように礼子が馬を下り、慎治に向かい合った。自分より背の高い女の子。裸で恐怖に打ち震える自分を見下ろす、ブーツを履き鞭を持った支配者。何も言う必要はない。赤い乗馬服を身に纏った憧れの美少女は、慎治を責め苛む残酷な女神として目の前に君臨していた。怯える慎治を見下ろしながら礼子は優しい微笑を浮かべると手にした鞭を二つ折りにし、すっと慎治の首にかけた。ピクッと恐怖に慎治の全身が震えた。散々自分を痛めつけてきた鞭。冷たい触感と革の香りが慎治の恐怖に直結する。そして何か違和感のある感触も感じた。どこかヌルッとした、水気のある感触。恐々下を見ると、礼子の鞭が触れたところに赤い物が付着していた。なんだろう・・・一瞬後にゾクッと悪寒が走った。それは信次の血だった。血・・・自分の体も朝から無数に打たれ、全身のあちこちが蚯蚓、というより太い蛇が皮膚の下でのたくっているかのように内出血して腫れ上がっていた。その蚯蚓腫れが遂に余りの鞭に耐え切れず、破裂したに違いない。そういえば、信次の体の周りで何か赤い霧を見たような気がしたけど、あれは錯覚じゃなかったんだ。あれは・・・信次の血飛沫だったんだ!!!血飛沫・・・皮膚が裂け、内出血して皮膚下に溜まった血が吹き出たんだ・・・怖い、というしかなかった。今まで散々鞭打たれたが、血が多少滴ることはあっても血飛沫が上がるほど鞭打たれた記憶はなかった。だけど・・・だけど!!!「さあ慎治、待たせたわね。アン、何震えて恐がってるのよ。心配しないで、これで正真正銘オーラスよ。今日のパーティーはこれでお開きなんだから、しっかり盛り上げてね!期待してるわよ。」礼子は声も出せずに震えている慎治の頭を優しく抱き締め、髪を撫でると頬にキスした。ふわっと礼子の甘い体臭が慎治の鼻腔をくすぐる。天城礼子に抱き締められ、キスされる。普通の男だったら天国に上る気分だろう。だが、慎治にとっては礼子の抱擁は死神の抱擁、礼子のキスは死刑執行の宣告書だった。
「さ、みんな待ってるわよ。行こう。」礼子は犬の首輪を引くように、慎治を首にかけた鞭で引きずって玲子たちの足元に連れて行き、そのまま地べたに正座させた。「礼子、仕上げはどうやる?今日の大トリ、面白い企画を期待してるわよ!」期待満々にはしゃいだ玲子の声に苦笑しながら礼子も自分の愛馬に跨った。「ったく玲子ったら!そんなにはしゃいでほら、慎治がすっかり怯えちゃってるじゃない!私の慎ちゃんのこと、苛めないで頂戴!」楽しげに笑いながら戯れる礼子たちの声は慎治にとって遥か天上、馬に跨った礼子たちの顔が位置する2メートル以上の上空の高みで繰り広げられる、残酷な女神たちの戯れだった。そして気まぐれな女神たちはほんの一時の戯れのために、地上の虫けらに死ぬほどの苦痛と恐怖を与える。「そうね・・・ねえ、子供の頃、かーもめかもめ、てやらなかった?」「かーもめかもめ?あの後ろの正面だーれだ?ってやつ?うん、やったけど・・・あ!そうか、わかった!」玲子がポンッと手を叩いた。「あ、あたしもあたしも!」「うんうん、いいじゃん、やろうやろう!」流石に鞭の楽しみを共有する仲、富美代と朝子も瞬時に礼子の企みを理解した。
「え、な、なに、、、ぼ、ぼくをどうするつもりなの!?!?」一人わけがわからず怯えている慎治の質問を無視して礼子が合図をかけた。「さ、みんな離れて離れて!」礼子の声と共に四人は互いの馬をゆっくりと二、三歩歩かせ、正方形を形作った。但し、今度の正方形は先ほど信次を苛めた時の正方形よりずいぶん小さい。一辺5メートルちょっとの正方形、そう、四人とも、自分の鞭の射程距離に慎治を丁度収める間合いだった。礼子たちは慎治を中心にゆっくりと円を描いて回り始めた。「フフ、慎治、怖い?どうされるか心配?なんかこれって私の好きな西部劇、インディアンの幌馬車襲撃シーンみたいね。」礼子の声が熱を帯び始めた。「あ、そのシーンなら私も知ってる!こうやって幌馬車を取り囲んで回りながら、死角をついて攻撃してくんだよね!」玲子にもすっかり手順はわかっていた。「そう、嬲り殺しよ!ハイヤーッ!」慎治の視線は本能的に礼子を追っていた。自分を最も酷く虐待する拷問者。残虐な飼主を。礼子の掛け声と鞭を振り上げる動作に慎治はビクッと反応し、本能的に両手を前に出し、頭を抱え込むようにしてガードらしき姿勢を取った。散々礼子に鞭打たれた慎治の反能としては無理もない。だが慎治は忘れていた。鞭は四本あることを。「ぎあっ!」慎治は背中に手を回して飛び上がった。慎治の予期せざる方向から鞭は飛んできた。背後から鞭を振り下ろしたのは玲子だった。「ひっ・・ひいっ!」悲鳴を上げながら慎治は玲子の方に向き直ろうとする。だが体を四分の一も回転させない内に富美代の鞭が慎治の尻を打った。「アウッ!」思わず両手で打たれた尻を押さえてしまい、前面ががら空きになった。「ほらほら慎治、ちゃんとガードしないでいいの?」ヒュンッ・・・パシーッと派手な音を立てて朝子の鞭が正面から、慎治の肩から背中にかけて絡みついた。「ピア゛―!!」激痛に肩を押さえて慎治が蹲りそうになり、曝け出された背中に遂に本命、礼子の鞭がキスした。パシーッッ・・・「イアーッッ!!!」一際高い鞭音と慎治の悲鳴が轟いた。
3
四人でグルグル回転しながらの鞭、堪ったものではない。慎治がどう動いても、どうガードしようとしても必ず無防備の箇所がある。全く見えない場所がある。そこに礼子たちの鞭が襲い掛かる。誰が鞭を振るうか、どこを狙うか。僅かなアイコンタクトだけで十分だった。だが慎治には全く予想がつかない。予期せぬ方向から予期せぬタイミングで襲い掛かる鞭。慎治は恐怖のあまりパニック状態だった。どこを鞭打たれるのか、いつ鞭打たれるのか、誰に鞭打たれるのか、全く予想ができない。精神的な苦痛だけではない、心の準備ができない分、余計に鞭が痛く感じる。礼子たち四人は慎治を囲み、長年のキャリアを積み熟成された室内管弦楽カルテットのように、息のあった鞭打ちを思う存分、繰り広げた。熟練した職人技のように礼子たちの鞭は慎治の苦痛を極限まで絞りだしていく。カルテットというのは正しくないかもしれない。四人の輪の中心で、鞭と戯れるように慎治は踊っていた。見えない所から襲い掛かる鞭が体を打ち据える度に、全身をビクッと震わせ、悲鳴をあげながら体をよじる。礼子たちの鞭に慎治は全身で反応していた。その様は傍から見ているとカルテットではなくクインテット、慎治を中心にした五重奏団のようだった。
ヒッ・・・に、逃げなくちゃ・・こ、このままじゃ殺される!!!慎治は必死で礼子たちの囲みから逃れようと、一番怖い礼子に背を向けて走り出した。「グヴォッ!」礼子が逃すわけがない。背後から首に巻きついた礼子の鞭に締め上げられ、慎治は海老のように仰け反りながらうめいた。「あら慎治、そんなに私の鞭が欲しかったの?早く言ってよ、私と慎治の仲じゃない、いいわ、いっぱい鞭、あげる!」正面から八の字を描くように玲子の鞭が慎治の胸、脇腹を打ち据えた。「ヒギャァーッッ!!!」慎治は玲子の鞭と礼子の締め技の二段攻撃に血の出るような悲鳴をあげた。「あっそのペア攻撃、面白そう!朝子、私たちもやろう!」「OK!ほら慎治、これはどう?」礼子の鞭から漸く開放され、苦しげに咳き込む慎治の腕から肩にかけて、左から富美代、右から朝子の鞭が同時に絡みついた。「ハイヤーッ!」富美代と朝子は慎治に鞭を絡めたまま、愛馬を一歩外側に歩かせる。「アイ゛ダ゛゛゛!」慎治は両腕が引っこ抜かれるような痛みに悲鳴をあげながら十字架に架けられたように両手を広げる。だが、これは前段階、苦痛の本番はこれからだった。「ほーら慎治、つーかまえたっと!礼子、やっちゃえやっちゃぇーっ!」「OK!玲子、行くよ!」富美代の掛け声を合図に礼子たち二人は両手を引っ張られ、身動きできない慎治に前後から猛烈な鞭を浴びせた。パシーンッ、ピシッ、パシッ、パウッ、ビシーッ・・・「ほら慎治、踊れ踊れーっ!」「そらそら!これでもかこれでもか!」「ピギッ・・・アヒーッッッッや、やべでゆるじでーーっっっ!!!」「バーカ、許すわけないじゃん!?」「もっとよもっともっと!ほらほら慎治、泣け、喚け、もがき苦しめーっっっ!」四人の美少女は慎治の断末魔のような悲鳴にすっかり興奮してしまった。二本の鞭の同時攻撃。今まで礼子たちに散々鞭打たれてきたとは言え、基本的には一対一だ。二本の鞭で同時に打たれたことなどない。しかも流石に共に鞭を振るってきた仲、礼子たち二人の鞭の呼吸はピッタリ合っていた。絶妙の間合い、寸分違わぬタイミングで打ち込まれる二本の鞭。絡んだり、邪魔しあうことなく慎治の体を同時に打ち据え、一本の時の数倍の苦痛を慎治に味合わせる。
富美代と朝子が鞭を緩め、慎治を解放するとすかさず今度は礼子と玲子の鞭が慎治の首に前後両方から絡みつき、締め付ける。「ぐ、ぐヴえべべべ!!!」悲鳴を上げながら慎治は必死で首に絡みついた二本の鞭を掴み、何とか少しでも呼吸をしようとする。礼子たちは締め落とす気はないから、窒息する程きつくは締め上げないが、それでも慎治が鞭を必死で掴めねば耐え切れないほどの強さで鞭を引き、慎治の全ての抵抗を封じた。そして倒れることもできずにうめく慎治の全身を左右から富美代と朝子が鞭打つ。「キャハハハッ!!!ほら慎治、踊れ踊れ踊れーっ!!!」「アーハッハッハッ!!!最高、もっと泣け泣け泣けーっっっ!!!」すっかり頭に血が上った富美代と朝子は全く手加減なしで、滅茶苦茶なピッチで慎治の全身に鞭を往復ビンタの様に浴びせ続けた。背中や尻だけではない。胸、腹、脇腹、太腿、腿の裏、・・・慎治の全身を隈なく鞭打ち、蚯蚓腫れと青あざを刻み込んでいく。慎治の体に傷が増えるのを見ることが、富美代と朝子にとって全身を支配する最高の快感と直結していた。そしてぼろほろになった慎治の全身、何度も鞭があたった箇所は既に内出血の圧力が高まり、皮膚が破れる寸前だった。「OK!そろそろフィニッシュ行こうか!」礼子の声に、富美代と朝子が一旦、鞭を休めて呼吸を整えた。そして礼子たち二人が慎治を鞭から解放すると、慎治は倒れる気力すらなくフラフラと立ち尽くしたまますすり泣いていた。「アヒッ・・・ヒック・・う、ウェッッッ・・・い、いたい・・・」顔中を涙と涎でグチャグチャにしながら慎治は喘いでいた。視線は定まらず、指先一本動かす気力すらない。最高よ慎治、さあフィニッシュ、楽しませて頂戴!頭上でグルグルと鞭を振り回しながら礼子が気合を入れた。「みんないい!フィニッシュ行くよ?さあ慎治、覚悟はいいわね。止めは・・・二倍二倍で・・・四倍鞭よ!せーの、ハッ!」ビシバシピシバウッ・・・「ギアーッッッ!!!」左肩越しに前から礼子、右肩越に後ろから玲子、背中から右脇腹に朝子、腹から左脇腹に富美代、四人の鞭が同時に慎治の体に襲い掛かった。痛い、という感覚を既に超えていた。慎治は上半身が千切れたような感覚に襲われた。皮膚の表面だけに止まるような生易しい痛さではない。筋肉、脂肪を貫通し、内蔵にまで響くような鞭の衝撃に慎治の視界がチカチカと瞬き始めた。体の奥底、はらわたから重苦しい、酸っぱいような血生臭いような塊がこみ上げてくる。余りの激痛に慎治は思わず死すら願った。「死ぬ、死んじゃう・・・いや、こ、殺して、こ、こんな痛いの、も、もういやーっ!!!いっそ一思いに殺してーっ!!!」
4
「アハハハッ!慎治、何バカ言ってんのよ!死ねるもんなら死んでごらんよ!ほらほらほら!死ね死ね死ねーっ!!!」礼子は慎治の悲痛な叫びに一層興奮し、更に力を込めて鞭を浴びせかけた。鞭の真の残酷さはそこにこそあった。慎治に気の狂わんばかりの激痛を与えながらも、礼子たちの鞭は決して致命傷にはならない。ロシア鞭クヌートのように皮膚を引き裂き、肉を弾けさせるような鞭でも使わない限り、いくら厳しい鞭でもそう簡単に人間の体は死ねないようにできているのだ。そしてこれだけ激しい苦痛を間断なく、しかも全身のあらゆる箇所に分散して与え続けられては気絶することさえ難しい。だから慎治はひたすら激痛に全身を犯され続けるしかなかった。「ギア゛ッ・・・ギャーッ・・・ビエ゛<bッッ!!!」四人が前後左右から同時に加える鞭に慎治は悲鳴を上げ続けた。体を吹き飛ばされるような、全身がばらばらに引き裂かれるような痛み。礼子たちの長い鞭は慎治の体に絡みつき、打撃の苦痛を加えた後に、そのまま体の中に食い込むように絡みつき、締め付けるような苦痛を体の内部へと送り込む。「グウィーッッ、グ、グルジイ・・・」慎治は礼子たちの鞭が巨人の手に変り、自分の体を握りつぶそうとしているような錯覚さえ感じた。余りの痛さに呼吸することさえ困難な苦痛だ。四倍鞭どころではない、十倍、二十倍の激痛だ。しかもその激痛の鞭は四方から間断なく飛んでくる。あまりに数が多すぎていつ、誰の鞭に打たれているのかさえ、もうわからない。よけるも何もない。ただ鞭打たれるだけ。倒れることすらできない。な、なぜ・・・なぜこんな目にあわされているんだ???ぼ、ぼくがなにをした???すべての疑問さえ無意味だ。慎治が立たされている空間は礼子たち四人の鞭で満たされていた。苦痛と絶望のみが存在する世界、月並みな言い方だが地獄、と呼ぶしかない空間だった。そしてその地獄を現出させているのは、醜い地獄の鬼とは対照的な美しい四人の少女だった。醜い、といえば裸にされて鞭打たれ、涙と涎に顔中グチャグチャにして泣き喚いている慎治の方がよほど醜かった。さすれば、鬼はむしろ慎治、そして礼子たちは地獄の鬼どもさえ罰することのできる女神、ワルキューレといった方が似つかわしかった。
慎治は無限とも思える時間、苦痛のみを味わい続けた。だが漸く、凍りついた時間も動き出そうとしていた。四人掛かりの鞭、その余りの威力に慎治の肉体が限界に達し、全身に刻まれた内出血の跡の何箇所かが皮膚の張力の限界をついに超えて裂け、血を吹き出した。「やったやったーっ!血よ、血が出たわーっ!みんな、集中攻撃よ!止めを刺すわよ!」礼子の号令に合わせ四人全員が鞭の打ち方を変えた。全員の鞭が慎治の傷に集中する。更に礼子たちは絡めた鞭を素早く手元に引き戻す引き鞭の責めを加え、慎治の皮膚を引き裂きにかかった。ビッ・・・ピシュッ・・・バシュッ・・・パシューンッ・・・巨人、いや魔神の手と化したような礼子たちの鞭は今までの打撃と締め付けに加え、爪で慎治の体を引き裂く責めを追加する。慎治たちを何千回も打ち据えてきた礼子たちの鞭テクニックは最初の頃とは比べ物にならない位、上達している。単に打ち据えて打撃の痛みのみを与える、絡むように打ち据えて打撃と締め付けの二重の苦痛を与える、そして絡ませた後に素早く鞭を手元に引き戻し、打撃、締め付けに加えて返しの鞭で皮膚を切り裂く三重苦を味合わせる。自由自在に鞭を操り、慎治の苦痛のレベルを思うがままにコントロールできる。
単純に鞭打たれるだけの苦痛なら痛い、とは言っても慎治たちにもなんとか耐えられる。だが礼子たちが磨き上げた鞭の技術、様々な残酷なテクニックを駆使してくるともう駄目だ。慎治たちの痛みに対する耐久力レベルは最初と比べ、多少は向上しているとは言っても大した進歩はない。余程強烈な信念でもない限り人間が耐えられる苦痛には限界がある。それに対して礼子たちの技術の進歩には限界がないのだ。だから今では、礼子たちはいともた易く慎治たちの限界を超える苦痛を与えられるようになっていた。慎治たちが耐えられるのは単に、礼子たちが鞭打ちをゆっくり楽しむために苦痛のレベルを下げてやっている時だけだ。礼子たちが手加減し、弄んでいる間は延々と苦痛が続く。そして礼子たちが本気を出したら・・・破局が待つのみだ。
礼子たちだって最初の頃はただ単純に鞭を振るい、打ち据えるだけしかできなかった。だが体育会的な生真面目さ、とでも言ったらいいのだろうか、礼子たちは慎治たちを鞭打ちながら熱心に技術を向上させていった。その成果だった。礼子たちは鞭に本気でのめり込んでいた。慎治たちを鞭打つ時だけではない。自宅にサンドバッグまで用意し、色々トレーニングを積んでいた。巧みに鞭を相手に絡める感覚、間合いの掴み方はそのトレーニングの賜物だ。今、慎治が味合わされている引き鞭も礼子たちが何度も何度も練習を積んで身につけた貴重な技術だ。スナップを効かせながら打ち込んで、鞭が相手に食い込む感触を覚えた時はあっ、分かった、と一つ自分のレベルが上がった実感に喜んだものだ。そして相手の体に食い込ませた鞭を素早く手元に引き戻す、打ち込んだ次の瞬間に鞭を引き戻し、相手の体の上に鞭を走らせるテクニックは何度も何度もサンドバッグ相手に練習し、漸くモノにした財産だ。サンドバッグに食い込んだ鞭がビシュッと表面を走っていく感触を始めてゲットした時にも、よし、この感覚ね、と何とも言えない達成感があったものだ。礼子たちだけではない。いくら礼子たちにコツを懇切丁寧にコーチされたとは言っても、富美代と朝子だって簡単に、単に慎治たちを1000発程度鞭打っただけで免許皆伝となったわけではない。二人もやはり、毎日のように自分の部屋でサンドバッグ相手に熱心に鞭を練習し続けて教わったテクニックを自分のモノにしたのだ。空手や合気道、少林寺拳法の練習用に買ったサンドバッグだったが、鞭の練習用にも最適だった。鞭を振るう時だけではない、全ての格闘技の基本となる様々な筋力トレーニング、ストレッチングを礼子たち四人は毎日欠かしたことがない。
努力に勝る天才なしとよく言うが、天才が努力したら凡人がどんなに努力しても絶対に追いつけない。丁度タイガーウッズがそうであるように。礼子たち二人は紛れもない天才、その天才がこれだけ練習したのだ、鞭が上達しないわけがない。富美代と朝子にしても、礼子たち程ではないにしても相当程度の才能がある。熱心なトレーニングと礼子たちの的確なコーチングがその才能を如何なく開花させていた。鞭打つ側の四人がこれだけ練習していたのに対し、慎治たちは何をしたのだろうか。何もしなかった。ひたすら礼子たちのご機嫌を損ねないようにビクビクし、鞭打たれる時には情けなく泣き喚いて許しを乞うだけだ。何もしていない。体を鍛えたわけでもないし少しでも痛みを和らげる方策を考えたわけでもない。あれだけ痛めつけられたのだ、痛みに慣れ、多少は痛みに対する免疫ができたとは言っても所詮、受身に過ぎない。頭も体も、何も使っていないのだ。これではどうしようもない。努力した天才と何もしない凡人。只でさえ鞭打つ側の礼子たちは鞭打たれる側の慎治たちより絶対的に有利なのに加え才能の差も歴然。その上更に努力まで礼子たちが遥かに上ではどうしようもない。
5
礼子たちが最初に鞭を振るった時、慎治たちは余りの痛さに絶叫したが未だ、多少は耐えることができた。その意味では鞭打つ礼子たちと鞭打たれる慎治たちの能力は一応、対等に近い水準にあった、と言える。だが、その後の積み重ねが大きな差を作っていた。今では礼子たちの苦痛を与える能力は、慎治たちの苦痛に耐える能力を遥かに上回り、しかもその差はどんどん拡大していた。丁度戦争中のアメリカと日本の力関係みたいなものだろうか。開戦直後は五分に戦えた両軍が次第に実力差がつき、最後には質量全ての面においてアメリカと日本に圧倒的な差がついてしまい、どう足掻いても太刀打ちできなくなってしまったのと同じようなものだ。
慎治たちにしてみれば、もともと一方的に鞭で打たれる身、上達も何も端から圧倒的に不利、勝てるわけがない、と言いたいだろう。だが、この差は単に鞭だけの話ではない。勉強、武道、あるいはファッションセンスから音楽に至るまで、どんなことについても同じだった。勉強を例に取れば確かに最初の内、礼子たちは慎治たちが勉強するのを禁じ落ちこぼれになるように仕向けた。だが最近では勉強に対する妨害は何もしていない。何故か、答えは簡単、一度落ちこぼれてしまった慎治たちが追いつくための努力を放棄し、「礼子さんたちに勉強を禁止されてるからどうしようもない」「毎日毎日こんなに苛められてちゃ、勉強なんか手につくわけないよ」という言い訳に安住し、勝手に加速度的に成績を悪化させているからだ。部活にしてもそうで、確かに慎治たちは雑用係兼サンドバッグでこき使われ、何も教えてもらえない身分だが陰で練習、せめて筋力トレーニングだけでもして女の子にさえ劣る体力をアップしよう、という努力を何もしていない。音楽にしても礼子たちは実に色々なジャンルを聞き、J-ポップからロック系、ジャズからクラシックに至るまで色々と聞いて楽しんでいるのに対し慎治たちは精々、テレビで流れる安っぽい商業ポップを聞くだけだ。本に至っては小説、エッセイ以下色々と読んでいる礼子たちに対し、慎治たちはマンガ以外を読むことは殆どない。要は積極的に自分を高めようとしている礼子たちに対し、慎治たちは単に流されるがままに、苦痛も娯楽も全て受身で生きていた。これでは一日一日差がついていくのも当然だ。礼子たちの時間が濃密で一日一日充実しているのに対し、慎治たちの一日はなんとも希薄、無為な日々だった。富美代や朝子も礼子たち程ではないにしても、充実した濃密な日々を送っている。身近な親友がこれだけ色々とアクティブに生き、豊富な話題を、刺激を与えてくれるのだ、富美代や朝子も当然のように自分を高めることに熱心になっていた。誰に強制されたわけでもない。単に楽しいから、自分が成長していく実感が楽しいから、そしてその成長が周りの人間にも認められる嬉しさがあるから濃密な日々を過ごせるのだ。この楽しさは三流の商業高校や底辺校の生徒、ましてやそんなレベルの高校すら中退してしまうような連中には一生縁のない楽しさだろう。そして慎治たちはそれ以下、自分が楽しいと思うことは何か、すら分からず、ひたすら怯えて暮らしている。三流高校中退の連中でさえ、せめてその昆虫並みの頭で気持ち良い、楽しいと感じることを追求すること位には熱心だ。本能的、といったレベルにすぎないが楽しいことを追求する、例えどんなに安っぽい無価値な楽しみでも、自分から積極的に快楽を求める程度の意思はある。だが慎治たちにはそれすらない。あるのは只受身、待ちの姿勢だけ。傍から見ていると、自分の意志を持たないのなら生きていても仕方ないだろう、としか思えない、意思を持たない植物同然の日々を送っていた。まさに自己否定の人生。生産性など何もない。
慎治たちにも、礼子たちが自分よりどんどん高いところに昇りつづけているのは十二分に分かっていた。別に苛められる時だけではない。礼子たちが機嫌いい時に普通に話しかけられても、礼子たちがほんの基礎知識と思っていることすら知らないから全く話が通じず、バカにされ笑われることなど日常茶飯事だ。授業などで一緒の班になった時など、礼子たちの合理的、論理的な思考回路や頭の回転の速さは正直、自分と違う人種としか思えない。何をやってもどうやっても勝てないどころか次元が違うところにいる人種、それが礼子たちだった。だから慎治たちは礼子たちが何もしない時でも、声をかけられるだけで、いや視線を投げられるだけでコンプレックスに苛まされていた。慎治たちがこれだけ酷い目に合わされても僅かな逆ギレ、反抗すらてできないのはそうやって礼子たちに精神的に屈服しているから、という要因が大きい。礼子たちにとって、慎治たちを苛めて遊ぶのは自分の時間のほんの一部、無数にある楽しみの一つに過ぎない。だが慎治たちにとっては礼子たちに苛められることが全てなのだ。礼子たちの苛め以外の部分での成長、そこで人間としての価値にどんどん差がついていた。ましてやその礼子たちが権威と力の象徴である鞭を握ったりしたら、慎治たちの精神は地虫より卑屈になってしまう。強制されるわけでもなんでもなく、勝手に同級生の女の子に敬語を使ってしまう始末だ。身分、まさしく生まれつきではなく、生まれてからの生き方によって礼子たちと慎治たちの間には厳然たる身分の上下が出来上がっていた。
そしてあらゆる面で慎治より優れる四人の美少女は、無数に持つ特筆すべき能力の内の一つを、他人に苦痛を与える能力を今、一切の手加減抜きでフルに解放していた。スナップを思いっきり効かせて鞭を慎治の体に絡ませ、手応えを感じた次の瞬間手首をこねる様に返し、鞭を猛スピードで慎治の皮膚上に這わせながら手元に引き戻す。打撃、締め付け、切り裂き、一鞭で三度痛い残酷な鞭を四人の美少女は四方から間断なく打ち込み続けた。慎治は先ほど、信次の体から血飛沫が飛んだのに恐怖した。だが信次はまだまだ運が良かった。引き鞭までは味合わされずに済んだのだ。慎治はそうは逝かない。礼子たちが本当に全力を出したらどうなるか、慎治はたっぷりと味合わされることになった。「ひ、ヒエーッッ!!!い、いだいーっっっ!や、ヤベ、、ビッ!イャ!イヤイヤイヤーッ!!!ユルジデーッッッ!!!」血の出るような慎治の悲鳴に比例するかのように、皮膚のあちこちが裂けていく。全身のここそこで血が吹き出る。加速度的に傷の数は増えていく。その傷を礼子たちは無慈悲に狙って鞭打ち続けた。ナイフで切り裂かれるような、いや生皮を剥ぎ取られる激痛を慎治の全身に刻み込みながら、礼子たちの鞭は的確に慎治の傷口に叩き込まれる。そして鞭に叩き出された内出血が慎治の傷口から霧のように吹き出した。出血の量は大したことはない。だが、一鞭毎に生皮を剥がれ、傷口を鞭打たれる激痛は慎治の限界を遥かに超えていた。慎治は腕をだらんと下げ、体を庇う余裕すらなく呆けたように立ちすくみ、絶叫しながら鞭を受けていた。四人がかりの鞭を何発受けただろうか。漸く失神という慈悲の女神が慎治に微笑んだとき、慎治の全身は見るも無残な鞭跡に埋め尽くされていた。
1
「ふう・・・やっと逝ったわね。」愛馬から下り、礼子はブーツの爪先で地面に倒れたままの慎治の頭を軽く小突いたが、完全に失神している慎治からは全く反応がなかった。信次は呆然としながらも内心ほっとしていた。ひ、ひどい・・・玲子さんたち、可愛い顔してよくあんなに、あんなに冷酷になれるもんだな・・・なんで、なんであんなに気軽に人のことを鞭打てるんだ、あ、あんなに思いっきり鞭で叩くなんて・・・でも良かった。俺も散々鞭で叩かれて痛かったけど、あいつほどじゃなかったもんな・・・慎治、大丈夫かな?まさか死んじゃいないよな・・・未だ背中の鞭跡はピリピリとした痛みを放っていたが、信次はとりとめもない雑念に浸っていた。とにかく終わった。四人掛かりでの鞭乱打、流石にみんな満足そうな表情をしている。時間も遅いし、今度こそ、今度こそ本当に終わりだよな・・・玲子たちも同感だった。日も翳ってきたし、丘陵地帯の秋は冷え込みが急速だ。ああ、今日は楽しかった。さ、そろそろ帰ろうか。弛緩した空気が漂っていた。ホスト役の玲子が口を開きかけた時、ボトボトッと変な音がした。「あん、もうこの子ったら!」ふと見ると朝子の馬が馬糞をボトボトと落としていた。「アハハ、朝子の馬も帰り支度なんじゃない?おなかの中軽くしてさ?」「もう玲子ったら!お下劣!」笑いながら朝子の脳裏に電流が走った。うん。もう今日は鞭は十分だけど、帰る間も信次のこと、ちょっと苛めてやりたいな。追い鞭で走らせようかな?でもなあ、今日はもう痛いこと一杯したから、なんか他のことがいいな・・・信次が精神的に屈辱に悶え苦しむようなこと。でもおしっこはもうたっぷり飲ませちゃったし・・・その時だった。朝子の愛馬が馬糞を落としたのは。こ・れ・ね!!!クスクスッと小悪魔のような微笑を、あどけなさを感じさせる整った小さな顔に浮かべながら朝子は玲子の袖を引いた。「何よ朝子、どうしたの?トイレだったら信次連れてさっさと行っといでよ。」「ううん、トイレじゃないの。ねえ玲子、私、いいこと思いついちゃった。クラブまで帰る間もさ、信次が泣き続けそうな遊び。」「何それ?鞭で追い立てるの?朝子もほんと、鞭が好きねえ。ま、勝手に楽しんでよ。私は流石に疲れたからパスしとくわ。」「ううん、鞭だったらさ、私だってもう十分堪能したわよ。じゃなくってさ、蝶々してやろうよ。」「蝶々?昆虫の?じゃなさそうね。もしかしてあの、四人でやる蝶々のこと?あれを信次にやろうっていうの?・・・あ!わかった!この悪魔!」玲子は漸く朝子の企みを理解した。「何、蝶々って、なんのこと?」礼子が不思議そうに聞いてきた。「ほら、相手うつ伏せにさせてさ、四人で両手両足一本ずつ持って、で、ちょーちょ、ちょーちょ、ってみんなで歌いながら上下に空中遊泳させてやるのって、やったことない?空手部で結構はやってて時々やるんだけど。」と朝子が答えた。「ああ、あれね。あれだったら私もやったことあるけど。ていうかさ、私なんかウェイト軽いから、どっちかというと蝶々はやられる方だけどね。朝子も多分、やられる方が多いんじゃない?でもあれ、結構気持ち良くない?なんで今信次を蝶々するの?」富美代もまだ理解できないでいた。「うん。私も普段は確かにやられる方が多いんだけどね。でもね、蝶々、着陸地点があそこだったらどう?」朝子が指差した先は、愛馬の後ろの地面だった。
「あ!そういうこと!」「うわ・・・朝子、あんたって・・・鬼、ほんと、鬼畜ねえ!」礼子と富美代が同時に声をあげた。「ひっどーい、富美ちゃんったら、こんな大人しい私のこと捕まえて鬼畜だなんて!でも、楽しそうでしょ?やりたくない?」「もちろん!」礼子も富美代も俄然、興が乗ってきた。「じゃ、決まりね。信次、そこにうつ伏せになって!」玲子の命令に信次は思わず凍りついた。「え・・・ま、また、またですかあー!?、もっと苛める気なの!?も、もうやめて・・・おねがい・・・」「信次、何ビビッてるのよ。そんなに私たちの鞭怖い?安心していいわよ。もう鞭はおしまいだから。」え、もう鞭はない?信次は拍子抜けした気分だった。鞭だけは、とにかく鞭だけはいや。もうこれ以上鞭打たれるのだけは絶対に嫌だった。逆に言えば、鞭でなければ多少のことなら耐えられるような気がした。おしっこ飲まされるくらいなら、我慢できる・・・「ほ、本当に鞭はないんですか???」おどおどと怯えた、猜疑心に満ちた目で尋ねる信次に玲子はにやりと微笑んだ。「本当よ。約束するわ。もう鞭はなし。ほら、私の鞭、しまってあげる。」玲子は自分の鞭を丸めると愛馬の鞍に引っ掛けた。「さあ信次、安心した?じゃ、さっさとうつ伏せになりなさい!」何をされるんだろう?恐怖に震えながらうつ伏せになった信次の周りを四人が取り囲んだ。右手に朝子、左手に玲子、右足に礼子、左足に富美代。な、何をする気なんだろう?踏み付け?唾?それとも四人同時におしっこを引っ掛ける気?「信次、そんなに心配しないでいいわよ。痛いことじゃないから。」朝子が笑いながら信次の手首をつかんだ。「みんなで蝶々してあげるだけだから。信次だって蝶々くらい、みたことあるでしょ?あんなの全然怖くないでしょ?」蝶々?確かに見たことはある。あれ位なら全然、痛くないよな・・・だけどなぜ???戸惑いながらも確かに余り痛くはなさそうだと思った信次は、とりあえずなすがままにされていた。「いい、みんなOK?じゃ行くよ!せーの、ちょーちょ、ちょーちょ・・・」朝子の声に合わせて四人の美少女は信次の体を上下させた。体をビヨーン、ビヨーン、と上下に彷徨わされながら信次は少し安心していた。ふう・・・女の子にこうやって弄ばれるのは恥ずかしい、と言えば恥ずかしいけど、この位ならまあいいや・・・だが信次が気づかないうちに、信次の体は危険な位置に連れてこられていた。さっきまで朝子の愛馬がいた方へ。「・・・に止まれ・・・いい、せーの、そーれ!」朝子が歌を止めると同時に信次の体は前方に向かってひときわ高く振り上げられ、同時に空中でパッと全員の手が離された。
「あ、あわわ!」突然のことに信次は空中で両手両足をばたつかせたが、姿勢を変えられるわけがない。お、落ちる・・ふと下を見ると、茶色っぽい小山が腹の下辺りにあった。え、何あれ?ま、まさか・・・馬糞!!!ドシャッ!!!あっという間もなく信次はうつ伏せのまま朝子の愛馬が排泄した馬糞の上に落ちていった。生暖かい塊を自分の腹が潰す感触が走った。押し潰され、広がった馬糞が腹から胸に広がる。「い、いやーっっっっ!!!」悲鳴をあげて信次は反射的に飛び起きようとした。だが起きられなかった。「キャハハッ!やったやったーっ!」大喜びしながら朝子が高々とジャンプし、信次の背中のど真ん中に飛び乗っていた。グエッ!背中を思いっきり朝子の乗馬ブーツに踏み付けられ、信次はあえなく潰されてしまった。「ほーらほらほら!もっと馬糞まみれにしてやるーっ!」朝子は高笑いしながら何度も何度も信次の背中でジャンプした。朝子のブーツが信次の背中に食い込む度に、信次の体がより深く馬糞に食い込んでいくかのようだった。「ふうーっ!蝶々作戦大成功!」漸く信次の背中から朝子が降りた。「ひ、ひどい・・・あ、あんまりだーっっっ!!!」泣きながら起き上がった信次の胸から腹にかけて、広範囲に馬糞が付着していた。いや、付着していた、というのは生ぬるい。擦り込まれていた、と言った方が正確だった。「こ、こんな・・・き、きたない・・・あんまりだ・・・・」信次は泣きじゃくり続けた。「み、みず・・・水道はどこ・・・あ、洗わなきゃ・・・落としてくる・・・」「ばーか信次、何寝言言ってんのよ!このグラウンド、潰れた大学のグラウンドよ?水道なんかとっくに止められてるわよ!」玲子の嘲声に信次は文字通り凍り付いてしまった。「す、水道が止まってる???じゃ、ど、どうやってこれ落とすの???」「そんなの私たちの知ったことじゃないわよ。ま、クラブまで戻れば水道もあるわよ。いいじゃん別に。どうせこんな山道、人なんか殆ど通らないわ。馬糞まみれで帰るのも信次らしくていいじゃない?」ひ、ひどい!!!ぽかんと口を開ける信次に更に追い討ちをかけるように富美代が声をかけた。「そうよ信次、ちょっとこっち向いてごらんよ!」慌てて振り返ると富美代は信次の脱ぎ捨てた服を持って、つい先ほどまで信次が転がされていた馬糞の横にいた。え、ま、まさか!!!「いや、や、やめてーーっ!」信次の悲鳴を聞いた富美代の頬に氷のような冷たい微笑が浮かんだ。次の瞬間、何の躊躇もなく富美代はその服を馬糞の上に落とした。「あ、ああ・・・ひ、酷い・・・」「酷い?バカ言わないでよ。酷いって言うんなら、せめてこれ位やってから言ってほしいわね。ええ?これ位わね!」富美代は怒ったような口調でを詰りながら、馬糞の上に落とした信次の服を踏み躙った。信次の服の上を踏んでいるから、富美代のブーツが汚れる心配はない。だが、踏み躙られている信次の服は持ち主同様、あっという間に馬糞まみれになってしまった。
「やるー!富美ちゃん最高!」駆け寄った朝子とハイタッチを交わしながら富美代は玲子に向かって言った。「玲子、ちょっとよけてて。外れたらばっちいからね!」ばっちい、玲子にはその意味は直ぐに分かった。「ちよっと待ってよ富美ちゃん、タンマ!私がどいてからにしてよ!」玲子は信次を放り出して大慌てで逃げだした。後には未だ分からない、鈍い信次だけが取り残された。玲子が安全圏に避難したのを確かめると富美代はブーツの爪先に信次の汚れた服を引っ掛けた。「ほら信次、取りに来るの面倒でしょ?私が取ってあげる。ちゃんと取るのよ!」言うや否やすっと伸びた細い脚を蹴り上げた。ああ、僕の服・・・思わず手を伸ばした信次の視界に入った服の下側は茶色い馬糞にまみれていた。ああ、、、思わず信次の手が止まってしまった。最悪の選択だった。手で払い落とせばいいものを、白痴のように呆けて動きを凍りつかせてしまったおかげで、服の汚れた部分がまともに信次の顔を直撃した。「うわっ!!!グエッヴベッベッベッ!!!」「あははっ!信次バッカじゃないの!何顔で受けてんのよ!」「あ、でも結構お似合いじゃない?信次ってなんか、馬糞まみれが似合ってない?」「あ、言えてる言えてる!これが本当の、くそったれ、てやつ?」「やっだーっ、礼子ったら。お嬢様がくそったれ、だなんて、お下品ですことよ!」余りの屈辱に声を上げて泣きながら、必死で全身にこびり付いた馬糞を少しでも落とそうと悪戦苦闘している信次を眺めながら、四人の美少女は全身をよじって大笑いし続けた。「ひっひーっ、ああおかしい!もう笑い死にしちゃいそう!信次、あんたのその顔、結構破壊力あるよ!さ、帰ろう帰ろう、丁度慎治もお目目覚ましたみたいだし!」玲子が指差した先で、慎治が漸く意識を取り戻していた。
未だ全身に鞭の痛みがピリピリと火傷のように走っている。気持ち悪いのも収まっていない。だが、意識朦朧としながらも慎治は今の虐待の一部始終を見ていた。ひ、酷い・・・酷すぎる・・・に、人間を馬糞まみれにするなんて・・・だが一方で慎治は微かな満足感も感じていた。ああ良かった。あんな目に会ったのが僕じゃなくて。あんな、あんな汚い目に会わされる位なら、鞭で半殺しにされた方がまだマシだったよね。「そうね、帰ろう!あ、でも私、その前にトイレ行っとく。慎治、おいで!」礼子の命令に慎治はいそいそとついて行った。おしっこを飲まされるのは分かりきっていた。堪らなく嫌だ。だが死ぬほど鞭打たれ、おまけに信次が馬糞まみれの刑を加えられるのを見た直後だ。帰れるならもう、なんだっていい。おしっこ位、いくらでも飲んでやるさ・・・四人分飲めばいいんだろ、簡単なことさ・・・慎治をトイレに残して礼子が戻ってきた。「あ、じゃ次、私いい?」玲子が次にトイレに向かい、後には富美代と朝子が順番待ちで残っていた。「ふうーっ・・・富美ちゃん、今日はほんと、楽しかったね。」朝子の声に富美代も大きく頷いた。「ほんとねー。でも最後の仕上げさ、朝子も冴えてるよねー。よく、あれだけ手軽にできて、しかも信次が一番嫌がりそうな苛め、考え付いたもんよねー。大したアドリブだわ。」「えへへ。お褒めに預かって恐縮です!」のんびりとした会話のなかで、富美代の中にも何か引っ掛かるものがあった。帰り道ねえ・・・あいつはもういいけど、慎治の方だけ楽させてやることもないんじゃない?かと言って、馬糞責めをもう一回やるのもかったるいし・・・何かないかなあ・・・おしっこ飲ませて終わり、ていうのも今一、締まんないなあ・・・うん!?「ねえ朝子、慎治なんだけどさ、私たち二人であいつも帰り道、泣き続ける目に合わせてやらない?」「え、なに?富美ちゃんなんか考え付いたの?いいけど、何かお手軽苛めあるの?もうおしっこして帰る時間だよ?」「うん。そのおしっこだけでOKよ。実はね・・・」富美代が耳打ちしたプランを聞くにつれ、朝子の顔にまた、小悪魔の微笑が浮かんできた。「OK!それGOODよ、やろう!玲子たちはもうおしっこ済んじゃっただろうけど、私たちのおしっこだけで十分、効くよ!」「何々、富美ちゃんたちなんか企んでるみたいね。何やるの?私にも教えてよ。」トイレから戻ってきた礼子が富美代たちの悪戯計画に気づいたようだった。「あ、わかった?流石礼子、勘がいいわね。ま、楽しみに見ててよ。お手軽苛めだけど、その割りにたっぷりと慎治のこと、泣かせてやるからさ!」あらあらまあ、富美ちゃんたちって、本当に苛めっ子ね、しょうがないんだから。自分のことを棚に上げて礼子が苦笑している所に、玲子も戻ってきた。「お待たせー。ああすっきりした。次どっち?富美ちゃん?朝子?」「うん、私。じゃ朝子、行ってくるね!」興奮した面持ちでトイレに向かう富美代を見て玲子が些か怪訝な表情をした。「富美ちゃんどうしたの?なんか妙に楽しそう。まさか、もうひと苛め行く気なの?」「みたいね。全く好きなんだから。どうやら朝子も一枚噛んでるようよ。」「あ、そう言えば朝子もにやついてる!もう、どうする気か・・・楽しみね!」
2
トイレでは地面に横たわったまま、慎治が次の客を待っていた。礼子たちと慎治はもう何十回もおしっこを飲み飲まされしてきた仲だ。もうお互い慣れたもの、慎治は二人のおしっこの殆どをこぼさずきれいに飲み干していた。地面にこぼれた跡もほんの少ししかない。・・・ああ、次は富美ちゃんか。慎治は見上げながら殆ど無表情のまま大きく口を開けた。どうぞ、どうせ富美ちゃんも一杯おしっこするんでしょ。いいよ、飲むから。後二人、富美ちゃんと朝子のおしっこ飲めば帰れるんだから、早く飲ませてよ・・・慎治の表情の90%以上は諦めだったが、その中に少しだけだが安堵と解放感が漂っていた。甘いわね、慎治。もう一苛めあるのよ。
「もう慎治、そんなに堂々と口開けないでよ。ま、この私のおしっこだもんね、飲みたいのはわかるけどさ、ちょっとは恥じらいとかテレとか見せて欲しいものよね。」富美代はコツコツとブーツの爪先で慎治の頭を小突いた。「慎治、でね、折角便器に成りきってるとこ悪いんだけどさ、私、今そのポーズ気分じゃないんだ。さっさと起きてそこに正座してくれる?」正座?え、な、何をする気なの?まさか立ったままでおしっこ飲ませる気?不思議に思いながらもとにかく慎治はその場に正座した。「あん、そこじゃないの、もっと下がって、そのブロックの真ん中あたりに座って!」「え、ブロックの真ん中?ふ、富美ちゃん一体、何する気なの?」「いいから、何するかなんてすぐにわかるわよ!ほら、別にいいでしょ、私鞭持ってないんだから、痛い目にあう心配はないわよ!・・・最も、慎治がグズグズして私をいらつかせるなら、鞭取ってこようかな?」鞭!慎治は電流に弾かれたように動き、足置き台代わりに置かれたブロックの間に正座した。慎治が正座すると、富美代は乗馬ズボンのボタンを外し、ゆっくりとズボンを下ろした。但し、今度はそのままズボンを脱ぎ、更にパンティも脱ぎ捨ててしまった。上半身は赤いジャケットのままで下半身は裸体にブーツ。妙に艶めかしい姿だった。だが、慎治にとって艶めかしい、等と富美代の肢体を愛でる心の余裕があるわけない。怯える慎治を見下ろしながら富美代はゆっくりとブロックに上った。地べたに正座した慎治の顔より上に富美代の股間が位置する。「さあ慎治、もうわかったでしょ?今からシャワーを浴びせてあげる。私のおしっこ、慎治の頭から顔、体、全身にたっぷりと引っ掛けてあげる。どう?うれしい?」お、おしっこを頭から浴びせる!?そ、それじゃ信次と同じようなもんじゃないか!「そ、そんな!!!お、おしっこのシャワーだなんて、や、やめて!!!」慎治は思わず立ち上がろうとしたが、富美代は慎治の耳を引っつかみ、無理やり正座させた。「うるさいわね!慎治、あんたにははいっ、ていう返事以外、教えてないはずなんだけどな。それとも何、未だ私の教育が足りないのかな?大人しく座っていないなら・・・鞭持ってくるよ!」鞭、その一言は絶大な効果だった。
観念してその場に正座し、俯く慎治の顎を富美代はグイッとこじ上げた。「慎治、下向いてちゃ駄目でしょ!顔に引っ掛けられないじゃない!ちゃんと上向いて、私におしっこ引っ掛けられるのをしっかり見てなさい!」残酷な命令だった。目を伏せることすら許されない。顔で、自分の顔で富美代のおしっこを、他人の汚い排泄物を受けされられるのだ。あ、あんまりだ・・・慎治の頬を悔し涙が伝っていった。「フフ、慎治、悔しい?顔も体も、全身私のおしっこまみれにされるのってそんなに悔しい?いい気味ね。たっぷりと引っ掛けてあげるからね。」富美代は威嚇するかのように腰をぐるりと回した。体内で尿意が急速に高まってくる。「さあ、慎治、行くよ!いい、逃げたり顔をそむけたりしたら、死ぬほど鞭で叩いた上で、クラブまで引き摺ってってやるからね!」言い終わると同時に富美代は股間の緊張を緩めた。限界近くまで高まっていた水圧が解放される。ちょろろ・・・と流れ出した水流はあっという間に太さを増し、いくつかの支流に分かれながら慎治の顔を直撃した「ワッ!う、ウブブァッ!!!」慎治の顔面で跳ねた水流はそのまま慎治の胸へ、腹へと流れていく。更に富美代がホースで水を撒くかのように腰を前後左右に動かすと、それにつれて排泄されるおしっこも生き物のように動き、散らばりながら慎治の顔の各所、そして髪の毛までも濡らしていく。上から見下ろす富美代は、自分のおしっこが慎治の全身に降り注がれるのをたっぷりと楽しんでいた。飲ませるのともまた違う感覚だ。他人におしっこを飲ませる、というのがどこか特殊な、ある種遊びに近い要素を孕んでいるのに対し、今やっている、おしっこを他人に引っ掛けるという行為は遊び、というよりはるかに強く、侮辱の要素を含んでいるように感じる。自分のおしっこが慎治の顔で弾け、髪を、胸を、背中を、全身を伝っていく。そう、この感じ、慎治に初めて唾を吐き掛けてやった時と似ているな。うん、確かに唾って、相手に対する徹底した侮蔑の表現でしょ、じゃ、おしっこを引っ掛けることって、その上級バージョン、慎治の人間性に対する冒涜ってとこかしらね。いや、人間性に対する冒涜だけではない。唾を吐き掛ける時は、必ずしも相手を無抵抗の状態にしておく必要はない。だがおしっこを引っ掛けるには相手を無抵抗な、全く動けない状態にしておかなくてはならない。それを、縛りもせずに命令ひとつで逃がさずに、思う存分おしっこを引っ掛けられる。支配、いや暴虐、と言った方がいい振る舞いだ。慎治、私に吐き掛けられた人生最初の唾、一生忘れられない嫌な記憶になってるんでしょ?じゃあ今日、もっと酷い記憶を植え付けてあげる。女の子におしっこを引っ掛けられた記憶を。一生消えないトラウマを刻み込んであげる!慎治の全身を流れる自分のおしっこが、そのまま慎治の精神を溶かし、崩壊させていくのが直感できる。富美代の頭の中では硫酸か何かを浴びせ、慎治の身体をどろどろに溶かしていく拷問をしている自分の姿があった。慎治の肉体を溶かしているのは幻想だが、精神を溶かしているのは紛れも無い現実だ。幼馴染の私、一緒に遊んだ仲、ずっと一緒の学校の同級生だけど、唾を吐き掛け、慎治に人生最初のトラウマを刻み込んだ私。その私におしっこ引っ掛けられてるのよ。慎治、このトラウマ、一生絶対に消えないわよ!
「アハハハハッ!!!慎治、どう、私のおしっこ、あったかくていい気持ちなんじゃない!?」富美代は高笑いしながら放尿を続けた。慎治の精神をズタズタに踏み躙る快感が、富美代の性器から背骨を突き抜け脳天まで駆け上がる。自分の性器から排泄されているものがおしっこではなく、慎治の精神を破壊するトラウマそのもののようにすら感じる。全身で人格破壊の快感を味わいながら富美代は全身の力を解放していた。ああ楽しい、このおしっこ、人生最高のおしっこだわ・・・同じ人格破壊でも唾は一発一発細切れなのに対し、おしっこを引っ掛けるのは連続した責めだ。シャブをやりながらのセックスが連続した絶頂感を与えるのと同じように、おしっこを慎治の顔に引っ掛けるのは富美代に連続したね無限の間とも思えるほど持続する絶頂感を与えてくれた。至福の時を噛み締めながら富美代はたっぷりと、我ながら驚く程の量のおしっこを慎治に浴びせ掛けた。漸く富美代が放尿を終えた時、慎治の全身は頭のてっぺんから足の先まで、富美代のおしっこでビショビショにされていた。「ああすっきりした。あ、慎治、未だ立たないでいいよ。次は朝子が来るから、そのままで待ってなさい。」自分の排泄したおしっこにまみれながら、余りの悔しさにすすり泣き続ける慎治に構わず富美代はさっさとズボンを履き、トイレから出て行った。
「あ、富美ちゃん帰ってきた!どう、上手くいった?」「もちろん!慎治ったら、馬鹿みたいにメソメソ泣いてるよ。朝子、早いとこ仕上げしてやってよ。」「OK!任せといて!」朝子は慎治の服を掴むとトイレに入っていった。「ああ、本当だ。慎治ったら本当に意気地なしね!おしっこ引っ掛けられた位でそんなに泣いちゃって、慎治、あんた本当に男の子なの?」朝子は笑いながら慎治の目の前に服を放り出した。「あ、ありが・・・いだだ!」服を掴もうとした慎治の手を朝子はブーツで踏みつけた。「バーカ、甘ったれるんじゃないの!私が慎治のこと心配して服持ってきてあげた、とでも思ったの?」にやにや笑いながら朝子もズボンのボタンを外し、パンティごと一気にずり下ろし、慎治の服の上にしゃがみこんだ。「あ、ああ・・・そ、そんな・・・」「あ、やっと分かったみたいね。じゃ、そこでしっかり見てるのよ。私が慎治の服、おしっこまみれにしてあげるところをね!」いい終わると同時に朝子は放尿を開始した。放尿しながら腰を回転させ、慎治の服に隈なくおしっこを行き渡らせる。あ、ああ・・・慎治は自分の服が朝子のおしっこでびしょびしょになるのを呆然と見ていた。ひ、ひどい・・・自分の全身は富美代のおしっこまみれ、そして服は朝子のおしっこまみれ。水道もないここで、どうやってきれいにすればいいの!?慎治の絶望の表情を楽しみながら、朝子は存分に放尿を楽しんだ。ふう、さっぱりした・・・立ち上がり、ズボンを履きなおした朝子は慎治に言った。「さ、慎治、行こう。もうみんなお待ちかねよ。慎治もま、今日はよく頑張った、てことで、この位で許してあげる。その服持って、さっさとおいで!」朝子はそう言い残すとさっさとトイレから出て行った。「あ、朝子、お帰り。慎治は?」礼子が早速尋ねた。「うん、すぐ来ると思うよ。あ、ほら来た!」「あ、慎治お帰り・・・あーあ、なにその格好!全く、服持ってるんならちゃんと着てくりゃいいじゃない!あら、玲子、慎治、なんか垂れてない?」「・・・本当だ。あ、慎治、よく見るとあんた、ビショビショじゃない!あーあ、体だけじゃなくて服もビショビショじゃん。あ、そうか・・・分かった!富美ちゃんと朝子、あんたたち、慎治に飲ませたんじゃなくて、思いっきりおしっこ引っ掛けたんでしょ!」「そうなの!」富美代と朝子は声を合わせて答えた。「ねえ、ばっちい思いしながら帰るのが信次だけじゃ不公平でしょ?だから慎治のこともおしっこまみれにしてあげた、てわけ。」礼子たちは呆れたように肩をすくめた。「全く、富美ちゃんも朝子も苛めっ子なんだからもう!ねえ玲子!?」「本当よねえ。仕上げのこの苛め、私と礼子とじゃ、ちょっと考え付かないよねえ。」「あん、もう!礼子たちひっどーい!なんか私たちのこと悪者にしちゃてるーっ!自分たちだって楽しんでるくせに!」「まあね。でもまあそれはそうとして、そろそろ本当に帰ろうか。いい加減寒くなってきたよね。」
確かに日はもう完全に沈み、冷気が急速に忍び寄っていた。四人の美少女はさっさと荷物をまとめると各々の愛馬に跨った。ああ、やっと帰れる。慎治たちもほっとしていた。同時に耐え難い寒さを感じた。ブルッ・・・素っ裸でいられる気温ではなかった。服を着なくちゃ・・・と、見た自分たちの服。それは余りに悲惨な状況だった。慎治の服はおしっこでビショビショ、信次の服は馬糞まみれ。信次の全身あちこちにはまだ馬糞がこびりつき、慎治は髪や体のあちこちから富美代のおしっこを滴らせている。ど、どうすりゃいいんだ・・・恨みがましそうに、かつどこか救いを求めるかのように慎治たちは馬上の礼子たちを見上げた。だが勿論、救いの手など差し伸べられるわけがない。「信次、二人とも道は分かっているね。遅いと先帰っちゃうからね!道草食わないでさっさと帰ってくるのよ!じゃ、みんな行こう!ハッ!」玲子の声を合図に四人は一斉に馬を走らせ、グラウンドから去っていった。取り残された慎治たちは暫く呆然としていた。寒い・・・日はとうに翳り、急速に迫る冷気は慎治たちの体温を容赦なく奪う。服を、早く服を着なくちゃ、で、でも・・・「ど、どうする・・・」「どうするって・・・き、着るの?こ、これを???」慎治たちは自分の手にある、汚れきった服を力なく見つめた。朝子のおしっこ、馬糞にまみれた二人の服は見るだけで吐き気を催すほど汚い。だがクラブまではどう考えても5キロはある。一時間はかかる道のりだ。それだけの距離を全裸で歩ききることは不可能だ、凍死すらありうる。命にも関わりかねない無謀さだし、第一いくら人通りは殆ど無い、と言っても無人島にいるわけではない。たまには人も通るし車も通る。その道のりを全裸で歩いていくのはきちがい沙汰だった。
3
先に動いたのは慎治だった。全身に引っ掛けられた富美代のおしっこは、最初こそ富美代の体温と同じ温もりを持ち、慎治をむしろ温めてくれる温水だったがとっくに冷め切っていた。冷め切った富美代のおしっこは、今では慎治の体の表面から容赦なく気化熱を奪い、排泄した当の富美代が去った後も尚、慎治のことを今度は寒さで苛め続けていた。ブルッと慎治の全身が悪寒に震えた。カタカタカタカタ・・・気がつくと奥歯が寒さに鳴っていた。ふ、拭かなくちゃ・・・せめて体を、富美ちゃんのおしっこを拭かなきゃ、風邪ひいちゃう・・・だが体を拭くタオルなど、どこにもない。拭くもの、なにかないかな・・・あるものは唯一つ、自分が持っている服だけ、朝子のおしっこでびしょびしょになっている服だけだった。こ、こんな、こんなもので・・・ふ、拭くの・・・だが他に選択肢は無い。寒さに震えながら慎治は手に持った服をギュッと絞った。ボタボタ・・・服から大量の朝子のおしっこが絞り出され、地面に垂れていく。絞り出されたおしっこの一部は慎治の手を伝って垂れていく。ち、ちくしょう・・・な、なんで・・・お、おしっこを・・・他人のおしっこを絞らなくちゃいけないんだ・・・ち、ちくしょう・・・慎治は悔し涙を洩らしながら絞り続けた。
漸く絞り終えた服で自分の顔を、髪を、体を拭く。冷たく湿った服で拭いていると、まるで朝子のおしっこを自分自身の手で顔に、髪に、体にすり込んでいるようだった。いや、それだけではない。排泄されてから時間がたった二人のおしっこはアンモニア臭い臭気を増しつつあった。自分の全身から立ち上る富美代のおしっこの臭いは徐々に強くなる臭いだからまだ余り感じずに済んでいたが、服にたっぷりと浸み込んだ朝子のおしっこの臭いはそうはいかない。真っ先に顔を拭こうと服を顔に近付けた時、ツンと悪臭が鼻をついた。すぐに分かるおしっこの臭い。自分のものと余り変わらない臭い。自分が他人のおしっこまみれの服で顔を拭こうとしている、と否応なしに実感させる臭いだ。余りの嫌悪感に吐き気すら感じる。なんとかにおいを感じないようにと息を止めながら顔を、体を拭くがおしっこの臭いは鼻、というより直接脳に浸み込んでくるようだ。いくら息を止めても、必死で考えまい、としても富美代と朝子のおしっこの臭いは慎治の嗅覚から決して立ち去らなかった。そしてふと気づくと、折角絞った服に今度は富美代のおしっこがしみ込み、また濡れてきていた。もう一回服を絞る。チョロチョロと富美代のおしっこ、いやおそらくは富美代と朝子のおしっこがミックスされた液体が搾り出される。絞り終えた服でもう一度全身を拭く。富美ちゃんと朝子のおしっこを全身にすり込んでいる・・・漸く全身を拭き終えた慎治の手がワナワナと震える。次に何をしなくてはいけないか、一つしかない。服を着ること。朝子と富美代のおしっこがたっぷりとしみ込んだ服を着ること。そしてクラブまでの道のり、一時間はかかる道のりを二人のおしっこまみれの服を身に纏いながら歩き続けねばならないのだ。ほ、本当に・・・こ、これを・・・き、着るのか???慎治は二人のおしっこが浸み込み、重く湿った服を見続けた。だが寒さは刻一刻と増している。もう限界だった。グッと吐き気を堪えながら一気に服に頭を、腕を通す。冷たく冷え切った服の冷たさにゾクッとくる。だ、だめ、か、考えちゃ・・・い、一気に着なくちゃ!!!必死の形相でブリーフとズボンを履き、スニーカーを履く。ビチャッ・・・スニーカーの中に溜まっていた朝子のおしっこが内底のクッションからしみ出る。ぐ、グエエッッッ!!!限界だった。慎治はその場に突っ伏し、激しく嘔吐した。
一方、信次も状況は似たようなものだった。全身が濡れてはいない分、慎治よりいくらか寒さはマシ、とは言っても単なる比較の問題だ。裸でいられる時間は限られている。横で慎治が全身を拭きだしたのにつられるように、信次も作業を開始しようとした。でもどうやって?おしっこではない、信次は全身馬糞まみれだ。服も馬糞まみれだし、そして仮にその服で体を拭いたところでどの道、着ていける服はそれだけなのだ。何の解決にもならない。信次は呆然と自分の手を見た。どう考えても方法は一つしかない。手で、自分の素手で全身と服にこびりついた馬糞を可能な限りこそぎ落とすしかない。う、嘘だろ・・・ば、馬糞を・・・て、手で?いじるの???信次は余りのことに全身を怒りでワナワナと震わせていた。だが信次をこの地獄に突き落とした朝子たちは既に帰ってしまっている、抗議の声をあげる相手すらいないのだ。信次がここでいくら絶叫しても、朝子たちの耳に届きすらしない。そして寒さは刻一刻とつのっていく。ち、ちくしょぅ・・・信次は弱々しく呪いの言葉を呟きながらのろのろと手を動かし、まず胸にこびりついた馬糞に触れた。未だ乾いていない馬糞の冷たく、ねっとりとした感触が堪らなく気持ち悪い。粘土、というには柔らかすぎる、やや固めに練った泥、といった感触だ。必死でこそぎ落とし、指についた馬糞をグラウンドの芝になすりつけるように拭く。胸、腹、腰・・・信次は必死で作業を続けた。だが水もなしで拭こうとしても限界がある。やがて体中、まだまだ十二分に汚いのに殆ど取れなくなってしまった。いくらこそぎ落とそうとしても、もう馬糞は落ちない、却って自分で自分自身の体に擦り込んでいるようなものだった。ち、ちくしょう・・・も、もう駄目なのかよ・・・信次は体を諦め、服に取り掛かった。だがこっちはもっと酷い。富美代に踏み躙られ、信次の服には馬糞がたっぷりと擦り込まれた状態だ。手できれいになどできるわけがない。精々、大きな塊を落とすのが関の山だ。必死で作業を続けたが、直ぐにどうしようもなくなってしまった。信次は血走った目で手に持った服を凝視した。く、くそ・・・こ、これを・・・着ろっていうのかよ!!!あ、あんまりだ・・・あ、朝子は、朝子も富美代もこうなっちゃうのを知ってて、知っててやったんだ!あ、あんまりだーっ!!!ぜ、ぜったい、絶対着るもんか!!!だが信次の誰にも気付いてさえもらえない情けない決意など、寒さの前では全くの無力、あっという間に覆されてしまう。ヒュゥッ・・・風、そよ風程度だが風が吹き、一層寒さがつのる。横では慎治が体を拭き終え、のろのろと富美代と朝子のおしっこまみれの服を着始めている。ブルッ・・・だ、だめ、もう我慢できない・・・寒さに歯をガチガチ鳴らしながら信次は一気に、馬糞まみれの服に頭を、腕を通していった。草食動物である馬の糞は人間のに比べ、遥かに臭いは少ない。しかも人間の感覚で嗅覚は最も鈍感かつマヒしやすい感覚だ。実際、全身を馬糞まみれにされた当初暫くは悪臭に苛まされていたものの、少しは鼻が慣れたのか、悪臭は苦痛というレベルではなくなっていた。しかし服を着て、新しい馬糞がプラスされるともう駄目だった。擦り込まれ、広げられた分、悪臭は体からの臭いより服からのものの方が却ってきついかもしれない。ガ、オヴェーーッッッ!!!信次も耐え得る限界を超えてしまった。吐いても吐いても吐き気はおさまらない。いや自分のゲロの臭いと馬糞の臭いがミックスし、更に横で吐いている慎治のゲロの臭いも加わり、破壊的なレベルに達した悪臭が更なる吐き気を呼ぶ。だ、だめ、こ、ここにいたら・・・信次は必死で立ち上がり、ふらつき、ゲロをそこここに撒き散らしながら歩いていった。
やがて胃液すら吐き尽くした二人はよろよろと立ち上がった。「か、帰ろう・・・」「あ、ああ、か、帰ろう・・・」二人はとぼとぼとグラウンドを出て人気のない道を歩き始めた。道に出たところで慎治は後ろを振り返った。このグラウンドにだけは二度と、絶対にこないぞ・・・だが内心分かっていた。礼子たちがこのグラウンドでの遊び、大いに気に入ったに違いないことを。そして慎治たちがどんなに嫌がろうが泣き喚こうが、これから先、何度も何度もここに連れてこられ、今日同様、死ぬほど鞭打たれ、引き摺り回され、何度も何度もおしっこを飲まされることを。そのことが容易に想像できるだけに、慎治たち二人の絶望は深かった。だが、今は泣いている時ではない。二人は重い足を引き摺り、歩き続けた。途中、どこかで公園でもあれば体を洗おう・・・二人はそう思っていたが、そもそも人気のない田舎で公園などある筈がない。歩いても歩いても体を洗える水道はない。願いも空しく歩き続けた二人にやっと救いの神が現れた。乗馬クラブの案内の看板が道端に立っていた。「ああ、あと少しだね・・・」「うん・・・早く、とにかく早く体を洗いたいよ・・・」微かな希望に二人は歩みを速めた。そしてやっと現れた乗馬クラブ入口の看板。こ、ここを曲がればクラブハウスまでもうすぐだ!やっと、やっと体を洗える!だが喜び勇んで角を曲がった二人が見たものは、路肩に停車している見慣れた二台のランクルと、その周りで楽しそうに談笑している6人の男女だった。「やあ、慎治君たち、遅かったじゃないか!お嬢さんたち、お待ちかねだよ!」良治の夕暮れ時には相応しくないほど明るい声が響いた。「そうだよ全く!みんな待ちくたびれてブーブー言ってたよ。駄目だなあ、女の子を待たせちゃあ!」負けず劣らず爽やかに大声を出す亮司の後ろから玲子たち四人が近づいてきた。全員、既に着替えていた。シャワーを浴びて汗を流し、ゆっくりと寛いでいかにもさっぱりとした礼子たちと、全身ボロボロで疲れきった、生気を失った慎治たち。しかも慎治たちは糞尿と汗にまみれ、凄まじい悪臭を放っているのだ。う、羨ましい・・・ぼ、ぼくたちも早く体を洗いたい・・・
「遅かったわね信次・・・ウッワーッ!クッサーイッ!」玲子の大声に笑いながら礼子も近づいてきたが、慎治たちの傍までくると大袈裟にのけぞった。「ワッ!本当だ。二人とも全く、臭いったらありゃしない!なんなのよあんたたち、その臭いは!まるでホームレスみたいじゃない、ちょっと近づかないでよ、私まで臭くなっちゃいそう!」富美代と朝子も近づいてくるなり、キャァッと声をあげて飛びのいた。「うわっ、、、なにこの臭さ!慎治、あんた全身、おしっこ臭いじゃない!こんな臭い撒き散らしながら歩いてきたわけ?」慎治の目から押さえきれない悔し涙が溢れた。「そ、そんな・・・お、おしっこ、おしっこひ、ひっかけたのは・・・ふ、富美ちゃんじゃないか!そ、それを、じ、じ、自分で、自分で引っ掛けておいて、く、臭いだなんて・・・あ、あんまりだ、あーんまりだーっっっ!!!」「うるさいわね慎治、確かに私、おしっこ引っ掛けたわよ。だけどそのままで歩いて来い、だなんて言っちゃいないわよ?どこかで洗ってくればいいでしょ!水道探すなり、何もなかったらそれこそ川で洗ったっていいじゃない!おしっこまみれで帰ってきたのは慎治の勝手でしょ、全く!平気でおしっこまみれでいられる変態のくせして私を逆恨みするだなんて、慎治、あんた本当に根性腐ってるわね!ペッ!」渾身の軽蔑を込めて吐き出された富美代の唾が慎治の鼻先を直撃した。「ハッハッハッ!慎治君、君の負けだな、その格好じゃ何言ったって説得力ないよ!第一、女の子に唾引っ掛けられるなんて、男の一生の恥だな!」良治は楽しそうに笑いながら頷いている。朝子も大きく頷いた。「本当よねー。信次、私も信次には心底驚かされるわ。まっさか、お馬ちゃんのうんちまみれのままで帰ってくるとわねー。いくらあんたでも、流石にどっかで体、洗ってくるとは思ったんだけどねー。うん、凄い、あんたは偉い!感動した!ペッ!」信次の額から朝子の唾がゆっくりと頬を伝っていく。「うーん、ま、信次君、馬糞まみれで歩き回った挙句に女の子に唾引っ掛けられてたんじゃ、君、人間廃業だよ。折角こんなに可愛い女の子たちが付き合ってくれてるんだからさ、お兄さんはもう少し、自分を大事にすることをお勧めするよ!」な、何が自分を大事にだ!亮司の過剰なほど爽やかな、偽善に満ち溢れた言葉が信次の踏み躙られたプライドを更に痛めつける。だが、未だ、未だ終わってはいなかった。
4
ポンッと礼子が慎治たちの目の前に二つの財布を放り投げた。え、なにこれ・・・僕たちの財布だ。なんでここで財布を渡されるの???訝る二人を見て礼子が冷たく微笑んだ。「慎治、いい?このクラブはね、高級な、上品なクラブなの。はっきり言ってね、おしっこや馬糞にまみれた汚いホームレスに入られちゃ、困るのよ。だからね、あんたたちも私たちと一緒にチェックアウトしといたわ。荷物も全部出して、もう亮司先生たちのランクルのトランクに入れといたからね。」「そ、そんな・・・じゃ、じゃあ・・・シャワーも浴びられないじゃないですか!」「ひ、ひどい!じゃ、せ、せめて・・・せめて荷物だけは返して!す、水道だけ借りて着替えるから、せ、せめて荷物だけは・・・」哀願する信次たちを満足げに見下ろしながら、玲子が後を引き取った。「そう。礼子の言うとおり、汚い格好でこのクラブの回りをうろつかれちゃ迷惑なのよ。あんたたちはどう見ても常識っていうものが全くない恥知らずみたいだからさ、放っといたらこんなとこで裸になったり、汚い体洗い始めたりしてクラブのみんなに大顰蹙買いそうだわ。だからね、そんなバカな真似できないようにあんたたちの荷物、私たちが預かっといてあげる。この道まっすぐ行けばJRの駅だから、そこの待合室に置いとくわよ。ま、無くなるといけないから一応、貴重品だけは返してあげる。」「分かったわね、二人とも。そんな汚い格好でクラブに入ったりしたら、後で酷い目に会わせるからね!最も、」礼子は慎治たちに言い渡しながらクスクスと笑い出した。「このクラブ、セキュリティはしっかりしてるからね。ちゃんとゲートのところではフルタイムでガードマンが入場者をチェックしているわ。あんたたちみたいな汚いの、絶対に入れてくれないけどね。嘘だと思うなら、試してみてもいいわよ。」あ、ああ・・・そ、そんな・・・慎治たちはへなへなとその場に座り込んでしまった。や、やっと、やっと体を洗えると思ったのに。やっと着替えられる、と思ったのに。また、また歩け、て言うの?こ、ここから駅までってどれ位あったっけ・・・ぞくっ・・・二人の背筋に悪寒が走った。どう考えても10キロはある・・・ば、倍・・・グラウンドからここまでの倍以上じゃない!!!「お、お願い・・・」思わず慎治は両手を胸の前で組み、祈りのポーズになって哀願した。「お、願い・・・じゃ、じゃせめて、せめて・・・駅まで僕たちも乗せて行って・・・おねが・・・」信次も必死で哀願した。「そ、そう、そうだよ!!!せめて駅まで、と、トランクでもどこでもいいから、おねがい、おねがいしま・・・」だが慎治たちの哀願は亮司の声に掻き消されてしまった。「おいおいバカ言っちゃいけないよ慎治君!僕たちの愛車だよ、いくらなんでもそんな汚いままで乗せられるないだろう!?なあ良治?」「ああ、全くだ!それにね、二人とも行きは一緒に乗せて来てあげたろう?で、一日中玲子君たち美女を独占してたっぷり楽しめたんだ。せめて帰り位、僕たちにも美女独占のサービスタイムにしてくれてもいいんじゃないかい?言われなくても気を利かせて、ここで失礼します、位のこと言えなくちゃ駄目だよ、全く気が利かないなあ。」
必死で喚き続ける慎治たちを無視し、一行はさっさと二組に分かれてランクルに乗り込みむと未だ立てないでいる慎治たちをその場に放り出したまま、さっさと走り去ってしまった。あ、ああ・・・行ってしまった・・・二人は無言のまま、暫く呆けたように涙を流しながらすすり泣いていた。泣き続けている二人の横を、クラブから出て行く何台もの高級車が過ぎていった。立てなかった。立ち上がる気力はもうどこにもなかった。だが、いつまでも座り込んでいることすらできなかった。「おい、ここで何をしているんだ!?」野太い声が頭上から降ってきた。見ると大柄な、がっしりとしたゴリラのような体格のガードマンが慎治たちを見下ろしていた。礼子たちか、あるいは慎治たちの横を通り過ぎていった誰かがクラブに連絡したのだろう。「ここは私有地だぞ。さっさと出て行くんだ。大体、そんな汚い格好でこの周りをうろうろするんじゃない!ここのお客様の迷惑だろう、さっさとどこかに行け!」「は、はい・・・い、行きます、行きますから、お願い、水道だけ貸してくださ・・・」慎治は最後まで言うことすらできなかった。「何をバカ言ってるんだ!おまえらみたいな汚い、臭いガキを入れるわけないだろう!さっさと失せろ!ぶん殴られたいのか!」そのガードマンは腰に差した警棒を引き抜き、慎治たちを無慈悲に追い立てた。「おら、さっさと失せろ!また来るからな、その時に未だこの辺うろついてたら、足腰立たなくなるまでぶん殴るぞ!」
融通、慈悲など全くない、脳まで筋肉で出来ているようなガードマンに追い払われ、慎治たちは暗い夜道を駅に向かってとぼとぼと歩き出した。疲労、苦痛、絶望・・・ありとあらゆる負の感情が二人を支配する。10キロ・・・二時間はかかる。既に真っ暗になり、気温は急速に下がっている。身に浸み入る夜の冷気に震えながら、慎治たちはとぼとぼと歩き続けた。単調な田舎道。ポツン、ポツンと立つ街燈の回り以外は真っ暗な道。歩く人などいない、時折自動車が猛スピードで走り過ぎるだけだ。寂しい夜道を二人は延々と歩き続けた。既に疲れた、という感覚からなくなりつつある。ただただ足を動かすだけ。多分、一度止まったらもう歩けない。そして歩けなくなっても、慎治たちを心配してくれる人はどこにもいないのだ。止まったら・・・マジで死ぬかもしれない・・・死に対する恐怖のみが二人の足を動かしていた。延々と歩き続ける内に、漸く何もなかった道端にポツン、ポツンと民家が建ち並び始めた。ああ、漸く駅に近づいてきたんだな・・・少し、ほんの少しだけ元気を、余裕を取り戻した途端、忘れていた感覚が蘇ってきた。嗅覚が。二人の体にこびりついた汚物はもう、すっかり乾いていた。だが富美代たちのおしっこも馬糞も時間が経つにつれ、乾いてきたはいいものの臭いはむしろきつくなっていた。く、臭い・・・急に自分の発散する悪臭を感じた。自分が悪臭にまみれ、場末の公衆便所なみの悪臭を発散していることがわかる。そして全身から立ち上る臭いが、体に付着した汚れから出ているのではなく、自分自身の体から出ている、そう、自らの体臭のような気さえしてきた。悪臭に頭がクラクラしてきた。「ふ、富美ちゃん・・・あ、朝子さん・・・ひ、酷いよ・・・」ぼそっと慎治が呟いた。富美代に引っ掛けられたおしっこはとっくに乾いている。かなりが全身に浸みこんでしまっているだろう、もう体を洗っても拭いても、落とせないに違いない。そして服に引っ掛けられた朝子のおしっこも慎治の体温で既に乾燥している。二人分のおしっこがミックスされた僕の体臭。この臭い、もう抜けないんじゃないだろうか・・・「ひっ・・・ひっく・・・う、ウエッッッ・・・」傍らからすすり泣きが聞こえた。見ると信次が肩を震わせて泣いていた。「し、慎治なんか、ま、まだ・・・まだいいよ・・・お、おれなんか・・・ば、馬糞だぜ???う、うんこまみれだよ・・・」信次も涙を流していた。二人はメソメソ泣きながら歩き続けた。やがて着いた駅はローカル線の小さな無人駅だった。誰もいない、蛍光灯が寒々と冷たい光を発する待合室を見ると、二人のバッグが置いてあった。良かった・・・無くなってなかった・・・小さな喜びを噛み締めつつ二人はバッグをひしと抱きしめた。ああ、良かった・・・これでやっと、今度こそ体を洗える・・・水道はどこ?だがホームに水道はなかった。やっと見つけた水道はただ一つ、今時男女共用になっている小さな便所の手洗い用だけだった。無人駅だけに、ろくに掃除もされていない小汚い便所だ。べ、便所・・・また便所・・・だが他に選択肢はない。二人はのろのろと服を脱ぎ、体を洗い始めた。冷たい水を何度も何度も体にかける。バッグから引っ張り出したタオルで何度も何度も全身を拭く。だが所詮、冷水で拭いただけだ、完全にきれいにはならない。30分近く洗い続け、とうとう諦めた二人はのろのろと服を着始めた。
「駅の便所で体を洗って着替えか・・・俺たち、ホームレスみたいだな・・・」ぼそっと信次が呟いた。「ホームレス・・・はは、確かにね。でもホームレスの方が未だマシかもね・・・」「そうだよな・・・ホームレスは鞭で叩かれたりしないよな・・・」「それに、おしっこ引っ掛けられたりもしないよね・・・」はは、はははは・・・・二人は力なく笑い続けた。「慎治の背中、見事な蚯蚓腫れだらけだぜ・・・」「そういう信次の背中なんか、もうどす黒くなってるよ・・・お互い、酷くやられたもんだね・・・」「ああ、今までは玲子さんたちだけだったのが、朝子や富美代もいたんだもんな・・・」「倍、本当に倍、鞭で叩かれたよな・・・富美ちゃん・・・幼馴染なのに・・・」「朝子、苛めた、苛めたって・・・ちょっとからかっただけなのに・・・100、100万倍返しだなんてよ・・・」「あれじゃ礼子さんたちと変わらないじゃないか・・・」「う、ううん・・・玲子さんたちより、しつこい位かもしれないよな・・・」もう止まらなかった。一瞬、二人の視線が合った。「ち、ちくしょう・・・」「ひ、ひどいよ、ひどすぎるよ・・・」「鞭だなんて・・・」「ブーツだなんて・・・」「唾だなんて・・・」「おしっこだなんて・・・」「お、おれたちだって・・・」「に、にんげん、にんげんなんだ・・・」「そ、それを・・・」「あ、あんまりだ・・・」「こ、このままじゃ殺されちゃう・・・」「じ、自殺してやろうか・・・」自分の言葉に驚いたように慎治が悔し涙と涎でグチャグチャの顔をあげた。「で、でも・・・な、なんで、なんでぼくたちが、ぼくたちが自殺しなくちゃいけないんだ・・・」信次もグチャグチャの顔をあげた。「そ、そうだ、そうだよ・・・し、死ぬのは、死ななくちゃいけないのはおれたちじゃない・・・あいつらだ・・・」「天城礼子と」「霧島玲子と」「神崎富美代と」「萩朝子だ!!!」「あ、あいつらを」「あいつらをこ、殺してやる」「や、やっつけてやる、仕返ししてやる!」「ひ、酷い目に、俺たちよりも酷い目に会わせてやる!」「お、思い知らせてやる!ぼ、ぼくをバカにするとどうなるか!」二人は自分たちの言葉に酔ってきたかのように叫び続けた。熱に浮かされたように。そうやって憎悪を募らせることだけが唯一、生への執着と希望を掻き立てるものだった。例えその希望が、パンドラの箱に唯一入っていた希望と同じく、自分たちをより深い地獄へと導くものだとしても。見詰め合う二人の口から同時に言葉が迸り出た。「ふ、、ふ、復讐してやる・・・」「り、り、リベンジ、リベンジだーーーっっっっ!!!」
「ふう・・・やっと逝ったわね。」愛馬から下り、礼子はブーツの爪先で地面に倒れたままの慎治の頭を軽く小突いたが、完全に失神している慎治からは全く反応がなかった。信次は呆然としながらも内心ほっとしていた。ひ、ひどい・・・玲子さんたち、可愛い顔してよくあんなに、あんなに冷酷になれるもんだな・・・なんで、なんであんなに気軽に人のことを鞭打てるんだ、あ、あんなに思いっきり鞭で叩くなんて・・・でも良かった。俺も散々鞭で叩かれて痛かったけど、あいつほどじゃなかったもんな・・・慎治、大丈夫かな?まさか死んじゃいないよな・・・未だ背中の鞭跡はピリピリとした痛みを放っていたが、信次はとりとめもない雑念に浸っていた。とにかく終わった。四人掛かりでの鞭乱打、流石にみんな満足そうな表情をしている。時間も遅いし、今度こそ、今度こそ本当に終わりだよな・・・玲子たちも同感だった。日も翳ってきたし、丘陵地帯の秋は冷え込みが急速だ。ああ、今日は楽しかった。さ、そろそろ帰ろうか。弛緩した空気が漂っていた。ホスト役の玲子が口を開きかけた時、ボトボトッと変な音がした。「あん、もうこの子ったら!」ふと見ると朝子の馬が馬糞をボトボトと落としていた。「アハハ、朝子の馬も帰り支度なんじゃない?おなかの中軽くしてさ?」「もう玲子ったら!お下劣!」笑いながら朝子の脳裏に電流が走った。うん。もう今日は鞭は十分だけど、帰る間も信次のこと、ちょっと苛めてやりたいな。追い鞭で走らせようかな?でもなあ、今日はもう痛いこと一杯したから、なんか他のことがいいな・・・信次が精神的に屈辱に悶え苦しむようなこと。でもおしっこはもうたっぷり飲ませちゃったし・・・その時だった。朝子の愛馬が馬糞を落としたのは。こ・れ・ね!!!クスクスッと小悪魔のような微笑を、あどけなさを感じさせる整った小さな顔に浮かべながら朝子は玲子の袖を引いた。「何よ朝子、どうしたの?トイレだったら信次連れてさっさと行っといでよ。」「ううん、トイレじゃないの。ねえ玲子、私、いいこと思いついちゃった。クラブまで帰る間もさ、信次が泣き続けそうな遊び。」「何それ?鞭で追い立てるの?朝子もほんと、鞭が好きねえ。ま、勝手に楽しんでよ。私は流石に疲れたからパスしとくわ。」「ううん、鞭だったらさ、私だってもう十分堪能したわよ。じゃなくってさ、蝶々してやろうよ。」「蝶々?昆虫の?じゃなさそうね。もしかしてあの、四人でやる蝶々のこと?あれを信次にやろうっていうの?・・・あ!わかった!この悪魔!」玲子は漸く朝子の企みを理解した。「何、蝶々って、なんのこと?」礼子が不思議そうに聞いてきた。「ほら、相手うつ伏せにさせてさ、四人で両手両足一本ずつ持って、で、ちょーちょ、ちょーちょ、ってみんなで歌いながら上下に空中遊泳させてやるのって、やったことない?空手部で結構はやってて時々やるんだけど。」と朝子が答えた。「ああ、あれね。あれだったら私もやったことあるけど。ていうかさ、私なんかウェイト軽いから、どっちかというと蝶々はやられる方だけどね。朝子も多分、やられる方が多いんじゃない?でもあれ、結構気持ち良くない?なんで今信次を蝶々するの?」富美代もまだ理解できないでいた。「うん。私も普段は確かにやられる方が多いんだけどね。でもね、蝶々、着陸地点があそこだったらどう?」朝子が指差した先は、愛馬の後ろの地面だった。
「あ!そういうこと!」「うわ・・・朝子、あんたって・・・鬼、ほんと、鬼畜ねえ!」礼子と富美代が同時に声をあげた。「ひっどーい、富美ちゃんったら、こんな大人しい私のこと捕まえて鬼畜だなんて!でも、楽しそうでしょ?やりたくない?」「もちろん!」礼子も富美代も俄然、興が乗ってきた。「じゃ、決まりね。信次、そこにうつ伏せになって!」玲子の命令に信次は思わず凍りついた。「え・・・ま、また、またですかあー!?、もっと苛める気なの!?も、もうやめて・・・おねがい・・・」「信次、何ビビッてるのよ。そんなに私たちの鞭怖い?安心していいわよ。もう鞭はおしまいだから。」え、もう鞭はない?信次は拍子抜けした気分だった。鞭だけは、とにかく鞭だけはいや。もうこれ以上鞭打たれるのだけは絶対に嫌だった。逆に言えば、鞭でなければ多少のことなら耐えられるような気がした。おしっこ飲まされるくらいなら、我慢できる・・・「ほ、本当に鞭はないんですか???」おどおどと怯えた、猜疑心に満ちた目で尋ねる信次に玲子はにやりと微笑んだ。「本当よ。約束するわ。もう鞭はなし。ほら、私の鞭、しまってあげる。」玲子は自分の鞭を丸めると愛馬の鞍に引っ掛けた。「さあ信次、安心した?じゃ、さっさとうつ伏せになりなさい!」何をされるんだろう?恐怖に震えながらうつ伏せになった信次の周りを四人が取り囲んだ。右手に朝子、左手に玲子、右足に礼子、左足に富美代。な、何をする気なんだろう?踏み付け?唾?それとも四人同時におしっこを引っ掛ける気?「信次、そんなに心配しないでいいわよ。痛いことじゃないから。」朝子が笑いながら信次の手首をつかんだ。「みんなで蝶々してあげるだけだから。信次だって蝶々くらい、みたことあるでしょ?あんなの全然怖くないでしょ?」蝶々?確かに見たことはある。あれ位なら全然、痛くないよな・・・だけどなぜ???戸惑いながらも確かに余り痛くはなさそうだと思った信次は、とりあえずなすがままにされていた。「いい、みんなOK?じゃ行くよ!せーの、ちょーちょ、ちょーちょ・・・」朝子の声に合わせて四人の美少女は信次の体を上下させた。体をビヨーン、ビヨーン、と上下に彷徨わされながら信次は少し安心していた。ふう・・・女の子にこうやって弄ばれるのは恥ずかしい、と言えば恥ずかしいけど、この位ならまあいいや・・・だが信次が気づかないうちに、信次の体は危険な位置に連れてこられていた。さっきまで朝子の愛馬がいた方へ。「・・・に止まれ・・・いい、せーの、そーれ!」朝子が歌を止めると同時に信次の体は前方に向かってひときわ高く振り上げられ、同時に空中でパッと全員の手が離された。
「あ、あわわ!」突然のことに信次は空中で両手両足をばたつかせたが、姿勢を変えられるわけがない。お、落ちる・・ふと下を見ると、茶色っぽい小山が腹の下辺りにあった。え、何あれ?ま、まさか・・・馬糞!!!ドシャッ!!!あっという間もなく信次はうつ伏せのまま朝子の愛馬が排泄した馬糞の上に落ちていった。生暖かい塊を自分の腹が潰す感触が走った。押し潰され、広がった馬糞が腹から胸に広がる。「い、いやーっっっっ!!!」悲鳴をあげて信次は反射的に飛び起きようとした。だが起きられなかった。「キャハハッ!やったやったーっ!」大喜びしながら朝子が高々とジャンプし、信次の背中のど真ん中に飛び乗っていた。グエッ!背中を思いっきり朝子の乗馬ブーツに踏み付けられ、信次はあえなく潰されてしまった。「ほーらほらほら!もっと馬糞まみれにしてやるーっ!」朝子は高笑いしながら何度も何度も信次の背中でジャンプした。朝子のブーツが信次の背中に食い込む度に、信次の体がより深く馬糞に食い込んでいくかのようだった。「ふうーっ!蝶々作戦大成功!」漸く信次の背中から朝子が降りた。「ひ、ひどい・・・あ、あんまりだーっっっ!!!」泣きながら起き上がった信次の胸から腹にかけて、広範囲に馬糞が付着していた。いや、付着していた、というのは生ぬるい。擦り込まれていた、と言った方が正確だった。「こ、こんな・・・き、きたない・・・あんまりだ・・・・」信次は泣きじゃくり続けた。「み、みず・・・水道はどこ・・・あ、洗わなきゃ・・・落としてくる・・・」「ばーか信次、何寝言言ってんのよ!このグラウンド、潰れた大学のグラウンドよ?水道なんかとっくに止められてるわよ!」玲子の嘲声に信次は文字通り凍り付いてしまった。「す、水道が止まってる???じゃ、ど、どうやってこれ落とすの???」「そんなの私たちの知ったことじゃないわよ。ま、クラブまで戻れば水道もあるわよ。いいじゃん別に。どうせこんな山道、人なんか殆ど通らないわ。馬糞まみれで帰るのも信次らしくていいじゃない?」ひ、ひどい!!!ぽかんと口を開ける信次に更に追い討ちをかけるように富美代が声をかけた。「そうよ信次、ちょっとこっち向いてごらんよ!」慌てて振り返ると富美代は信次の脱ぎ捨てた服を持って、つい先ほどまで信次が転がされていた馬糞の横にいた。え、ま、まさか!!!「いや、や、やめてーーっ!」信次の悲鳴を聞いた富美代の頬に氷のような冷たい微笑が浮かんだ。次の瞬間、何の躊躇もなく富美代はその服を馬糞の上に落とした。「あ、ああ・・・ひ、酷い・・・」「酷い?バカ言わないでよ。酷いって言うんなら、せめてこれ位やってから言ってほしいわね。ええ?これ位わね!」富美代は怒ったような口調でを詰りながら、馬糞の上に落とした信次の服を踏み躙った。信次の服の上を踏んでいるから、富美代のブーツが汚れる心配はない。だが、踏み躙られている信次の服は持ち主同様、あっという間に馬糞まみれになってしまった。
「やるー!富美ちゃん最高!」駆け寄った朝子とハイタッチを交わしながら富美代は玲子に向かって言った。「玲子、ちょっとよけてて。外れたらばっちいからね!」ばっちい、玲子にはその意味は直ぐに分かった。「ちよっと待ってよ富美ちゃん、タンマ!私がどいてからにしてよ!」玲子は信次を放り出して大慌てで逃げだした。後には未だ分からない、鈍い信次だけが取り残された。玲子が安全圏に避難したのを確かめると富美代はブーツの爪先に信次の汚れた服を引っ掛けた。「ほら信次、取りに来るの面倒でしょ?私が取ってあげる。ちゃんと取るのよ!」言うや否やすっと伸びた細い脚を蹴り上げた。ああ、僕の服・・・思わず手を伸ばした信次の視界に入った服の下側は茶色い馬糞にまみれていた。ああ、、、思わず信次の手が止まってしまった。最悪の選択だった。手で払い落とせばいいものを、白痴のように呆けて動きを凍りつかせてしまったおかげで、服の汚れた部分がまともに信次の顔を直撃した。「うわっ!!!グエッヴベッベッベッ!!!」「あははっ!信次バッカじゃないの!何顔で受けてんのよ!」「あ、でも結構お似合いじゃない?信次ってなんか、馬糞まみれが似合ってない?」「あ、言えてる言えてる!これが本当の、くそったれ、てやつ?」「やっだーっ、礼子ったら。お嬢様がくそったれ、だなんて、お下品ですことよ!」余りの屈辱に声を上げて泣きながら、必死で全身にこびり付いた馬糞を少しでも落とそうと悪戦苦闘している信次を眺めながら、四人の美少女は全身をよじって大笑いし続けた。「ひっひーっ、ああおかしい!もう笑い死にしちゃいそう!信次、あんたのその顔、結構破壊力あるよ!さ、帰ろう帰ろう、丁度慎治もお目目覚ましたみたいだし!」玲子が指差した先で、慎治が漸く意識を取り戻していた。
未だ全身に鞭の痛みがピリピリと火傷のように走っている。気持ち悪いのも収まっていない。だが、意識朦朧としながらも慎治は今の虐待の一部始終を見ていた。ひ、酷い・・・酷すぎる・・・に、人間を馬糞まみれにするなんて・・・だが一方で慎治は微かな満足感も感じていた。ああ良かった。あんな目に会ったのが僕じゃなくて。あんな、あんな汚い目に会わされる位なら、鞭で半殺しにされた方がまだマシだったよね。「そうね、帰ろう!あ、でも私、その前にトイレ行っとく。慎治、おいで!」礼子の命令に慎治はいそいそとついて行った。おしっこを飲まされるのは分かりきっていた。堪らなく嫌だ。だが死ぬほど鞭打たれ、おまけに信次が馬糞まみれの刑を加えられるのを見た直後だ。帰れるならもう、なんだっていい。おしっこ位、いくらでも飲んでやるさ・・・四人分飲めばいいんだろ、簡単なことさ・・・慎治をトイレに残して礼子が戻ってきた。「あ、じゃ次、私いい?」玲子が次にトイレに向かい、後には富美代と朝子が順番待ちで残っていた。「ふうーっ・・・富美ちゃん、今日はほんと、楽しかったね。」朝子の声に富美代も大きく頷いた。「ほんとねー。でも最後の仕上げさ、朝子も冴えてるよねー。よく、あれだけ手軽にできて、しかも信次が一番嫌がりそうな苛め、考え付いたもんよねー。大したアドリブだわ。」「えへへ。お褒めに預かって恐縮です!」のんびりとした会話のなかで、富美代の中にも何か引っ掛かるものがあった。帰り道ねえ・・・あいつはもういいけど、慎治の方だけ楽させてやることもないんじゃない?かと言って、馬糞責めをもう一回やるのもかったるいし・・・何かないかなあ・・・おしっこ飲ませて終わり、ていうのも今一、締まんないなあ・・・うん!?「ねえ朝子、慎治なんだけどさ、私たち二人であいつも帰り道、泣き続ける目に合わせてやらない?」「え、なに?富美ちゃんなんか考え付いたの?いいけど、何かお手軽苛めあるの?もうおしっこして帰る時間だよ?」「うん。そのおしっこだけでOKよ。実はね・・・」富美代が耳打ちしたプランを聞くにつれ、朝子の顔にまた、小悪魔の微笑が浮かんできた。「OK!それGOODよ、やろう!玲子たちはもうおしっこ済んじゃっただろうけど、私たちのおしっこだけで十分、効くよ!」「何々、富美ちゃんたちなんか企んでるみたいね。何やるの?私にも教えてよ。」トイレから戻ってきた礼子が富美代たちの悪戯計画に気づいたようだった。「あ、わかった?流石礼子、勘がいいわね。ま、楽しみに見ててよ。お手軽苛めだけど、その割りにたっぷりと慎治のこと、泣かせてやるからさ!」あらあらまあ、富美ちゃんたちって、本当に苛めっ子ね、しょうがないんだから。自分のことを棚に上げて礼子が苦笑している所に、玲子も戻ってきた。「お待たせー。ああすっきりした。次どっち?富美ちゃん?朝子?」「うん、私。じゃ朝子、行ってくるね!」興奮した面持ちでトイレに向かう富美代を見て玲子が些か怪訝な表情をした。「富美ちゃんどうしたの?なんか妙に楽しそう。まさか、もうひと苛め行く気なの?」「みたいね。全く好きなんだから。どうやら朝子も一枚噛んでるようよ。」「あ、そう言えば朝子もにやついてる!もう、どうする気か・・・楽しみね!」
2
トイレでは地面に横たわったまま、慎治が次の客を待っていた。礼子たちと慎治はもう何十回もおしっこを飲み飲まされしてきた仲だ。もうお互い慣れたもの、慎治は二人のおしっこの殆どをこぼさずきれいに飲み干していた。地面にこぼれた跡もほんの少ししかない。・・・ああ、次は富美ちゃんか。慎治は見上げながら殆ど無表情のまま大きく口を開けた。どうぞ、どうせ富美ちゃんも一杯おしっこするんでしょ。いいよ、飲むから。後二人、富美ちゃんと朝子のおしっこ飲めば帰れるんだから、早く飲ませてよ・・・慎治の表情の90%以上は諦めだったが、その中に少しだけだが安堵と解放感が漂っていた。甘いわね、慎治。もう一苛めあるのよ。
「もう慎治、そんなに堂々と口開けないでよ。ま、この私のおしっこだもんね、飲みたいのはわかるけどさ、ちょっとは恥じらいとかテレとか見せて欲しいものよね。」富美代はコツコツとブーツの爪先で慎治の頭を小突いた。「慎治、でね、折角便器に成りきってるとこ悪いんだけどさ、私、今そのポーズ気分じゃないんだ。さっさと起きてそこに正座してくれる?」正座?え、な、何をする気なの?まさか立ったままでおしっこ飲ませる気?不思議に思いながらもとにかく慎治はその場に正座した。「あん、そこじゃないの、もっと下がって、そのブロックの真ん中あたりに座って!」「え、ブロックの真ん中?ふ、富美ちゃん一体、何する気なの?」「いいから、何するかなんてすぐにわかるわよ!ほら、別にいいでしょ、私鞭持ってないんだから、痛い目にあう心配はないわよ!・・・最も、慎治がグズグズして私をいらつかせるなら、鞭取ってこようかな?」鞭!慎治は電流に弾かれたように動き、足置き台代わりに置かれたブロックの間に正座した。慎治が正座すると、富美代は乗馬ズボンのボタンを外し、ゆっくりとズボンを下ろした。但し、今度はそのままズボンを脱ぎ、更にパンティも脱ぎ捨ててしまった。上半身は赤いジャケットのままで下半身は裸体にブーツ。妙に艶めかしい姿だった。だが、慎治にとって艶めかしい、等と富美代の肢体を愛でる心の余裕があるわけない。怯える慎治を見下ろしながら富美代はゆっくりとブロックに上った。地べたに正座した慎治の顔より上に富美代の股間が位置する。「さあ慎治、もうわかったでしょ?今からシャワーを浴びせてあげる。私のおしっこ、慎治の頭から顔、体、全身にたっぷりと引っ掛けてあげる。どう?うれしい?」お、おしっこを頭から浴びせる!?そ、それじゃ信次と同じようなもんじゃないか!「そ、そんな!!!お、おしっこのシャワーだなんて、や、やめて!!!」慎治は思わず立ち上がろうとしたが、富美代は慎治の耳を引っつかみ、無理やり正座させた。「うるさいわね!慎治、あんたにははいっ、ていう返事以外、教えてないはずなんだけどな。それとも何、未だ私の教育が足りないのかな?大人しく座っていないなら・・・鞭持ってくるよ!」鞭、その一言は絶大な効果だった。
観念してその場に正座し、俯く慎治の顎を富美代はグイッとこじ上げた。「慎治、下向いてちゃ駄目でしょ!顔に引っ掛けられないじゃない!ちゃんと上向いて、私におしっこ引っ掛けられるのをしっかり見てなさい!」残酷な命令だった。目を伏せることすら許されない。顔で、自分の顔で富美代のおしっこを、他人の汚い排泄物を受けされられるのだ。あ、あんまりだ・・・慎治の頬を悔し涙が伝っていった。「フフ、慎治、悔しい?顔も体も、全身私のおしっこまみれにされるのってそんなに悔しい?いい気味ね。たっぷりと引っ掛けてあげるからね。」富美代は威嚇するかのように腰をぐるりと回した。体内で尿意が急速に高まってくる。「さあ、慎治、行くよ!いい、逃げたり顔をそむけたりしたら、死ぬほど鞭で叩いた上で、クラブまで引き摺ってってやるからね!」言い終わると同時に富美代は股間の緊張を緩めた。限界近くまで高まっていた水圧が解放される。ちょろろ・・・と流れ出した水流はあっという間に太さを増し、いくつかの支流に分かれながら慎治の顔を直撃した「ワッ!う、ウブブァッ!!!」慎治の顔面で跳ねた水流はそのまま慎治の胸へ、腹へと流れていく。更に富美代がホースで水を撒くかのように腰を前後左右に動かすと、それにつれて排泄されるおしっこも生き物のように動き、散らばりながら慎治の顔の各所、そして髪の毛までも濡らしていく。上から見下ろす富美代は、自分のおしっこが慎治の全身に降り注がれるのをたっぷりと楽しんでいた。飲ませるのともまた違う感覚だ。他人におしっこを飲ませる、というのがどこか特殊な、ある種遊びに近い要素を孕んでいるのに対し、今やっている、おしっこを他人に引っ掛けるという行為は遊び、というよりはるかに強く、侮辱の要素を含んでいるように感じる。自分のおしっこが慎治の顔で弾け、髪を、胸を、背中を、全身を伝っていく。そう、この感じ、慎治に初めて唾を吐き掛けてやった時と似ているな。うん、確かに唾って、相手に対する徹底した侮蔑の表現でしょ、じゃ、おしっこを引っ掛けることって、その上級バージョン、慎治の人間性に対する冒涜ってとこかしらね。いや、人間性に対する冒涜だけではない。唾を吐き掛ける時は、必ずしも相手を無抵抗の状態にしておく必要はない。だがおしっこを引っ掛けるには相手を無抵抗な、全く動けない状態にしておかなくてはならない。それを、縛りもせずに命令ひとつで逃がさずに、思う存分おしっこを引っ掛けられる。支配、いや暴虐、と言った方がいい振る舞いだ。慎治、私に吐き掛けられた人生最初の唾、一生忘れられない嫌な記憶になってるんでしょ?じゃあ今日、もっと酷い記憶を植え付けてあげる。女の子におしっこを引っ掛けられた記憶を。一生消えないトラウマを刻み込んであげる!慎治の全身を流れる自分のおしっこが、そのまま慎治の精神を溶かし、崩壊させていくのが直感できる。富美代の頭の中では硫酸か何かを浴びせ、慎治の身体をどろどろに溶かしていく拷問をしている自分の姿があった。慎治の肉体を溶かしているのは幻想だが、精神を溶かしているのは紛れも無い現実だ。幼馴染の私、一緒に遊んだ仲、ずっと一緒の学校の同級生だけど、唾を吐き掛け、慎治に人生最初のトラウマを刻み込んだ私。その私におしっこ引っ掛けられてるのよ。慎治、このトラウマ、一生絶対に消えないわよ!
「アハハハハッ!!!慎治、どう、私のおしっこ、あったかくていい気持ちなんじゃない!?」富美代は高笑いしながら放尿を続けた。慎治の精神をズタズタに踏み躙る快感が、富美代の性器から背骨を突き抜け脳天まで駆け上がる。自分の性器から排泄されているものがおしっこではなく、慎治の精神を破壊するトラウマそのもののようにすら感じる。全身で人格破壊の快感を味わいながら富美代は全身の力を解放していた。ああ楽しい、このおしっこ、人生最高のおしっこだわ・・・同じ人格破壊でも唾は一発一発細切れなのに対し、おしっこを引っ掛けるのは連続した責めだ。シャブをやりながらのセックスが連続した絶頂感を与えるのと同じように、おしっこを慎治の顔に引っ掛けるのは富美代に連続したね無限の間とも思えるほど持続する絶頂感を与えてくれた。至福の時を噛み締めながら富美代はたっぷりと、我ながら驚く程の量のおしっこを慎治に浴びせ掛けた。漸く富美代が放尿を終えた時、慎治の全身は頭のてっぺんから足の先まで、富美代のおしっこでビショビショにされていた。「ああすっきりした。あ、慎治、未だ立たないでいいよ。次は朝子が来るから、そのままで待ってなさい。」自分の排泄したおしっこにまみれながら、余りの悔しさにすすり泣き続ける慎治に構わず富美代はさっさとズボンを履き、トイレから出て行った。
「あ、富美ちゃん帰ってきた!どう、上手くいった?」「もちろん!慎治ったら、馬鹿みたいにメソメソ泣いてるよ。朝子、早いとこ仕上げしてやってよ。」「OK!任せといて!」朝子は慎治の服を掴むとトイレに入っていった。「ああ、本当だ。慎治ったら本当に意気地なしね!おしっこ引っ掛けられた位でそんなに泣いちゃって、慎治、あんた本当に男の子なの?」朝子は笑いながら慎治の目の前に服を放り出した。「あ、ありが・・・いだだ!」服を掴もうとした慎治の手を朝子はブーツで踏みつけた。「バーカ、甘ったれるんじゃないの!私が慎治のこと心配して服持ってきてあげた、とでも思ったの?」にやにや笑いながら朝子もズボンのボタンを外し、パンティごと一気にずり下ろし、慎治の服の上にしゃがみこんだ。「あ、ああ・・・そ、そんな・・・」「あ、やっと分かったみたいね。じゃ、そこでしっかり見てるのよ。私が慎治の服、おしっこまみれにしてあげるところをね!」いい終わると同時に朝子は放尿を開始した。放尿しながら腰を回転させ、慎治の服に隈なくおしっこを行き渡らせる。あ、ああ・・・慎治は自分の服が朝子のおしっこでびしょびしょになるのを呆然と見ていた。ひ、ひどい・・・自分の全身は富美代のおしっこまみれ、そして服は朝子のおしっこまみれ。水道もないここで、どうやってきれいにすればいいの!?慎治の絶望の表情を楽しみながら、朝子は存分に放尿を楽しんだ。ふう、さっぱりした・・・立ち上がり、ズボンを履きなおした朝子は慎治に言った。「さ、慎治、行こう。もうみんなお待ちかねよ。慎治もま、今日はよく頑張った、てことで、この位で許してあげる。その服持って、さっさとおいで!」朝子はそう言い残すとさっさとトイレから出て行った。「あ、朝子、お帰り。慎治は?」礼子が早速尋ねた。「うん、すぐ来ると思うよ。あ、ほら来た!」「あ、慎治お帰り・・・あーあ、なにその格好!全く、服持ってるんならちゃんと着てくりゃいいじゃない!あら、玲子、慎治、なんか垂れてない?」「・・・本当だ。あ、慎治、よく見るとあんた、ビショビショじゃない!あーあ、体だけじゃなくて服もビショビショじゃん。あ、そうか・・・分かった!富美ちゃんと朝子、あんたたち、慎治に飲ませたんじゃなくて、思いっきりおしっこ引っ掛けたんでしょ!」「そうなの!」富美代と朝子は声を合わせて答えた。「ねえ、ばっちい思いしながら帰るのが信次だけじゃ不公平でしょ?だから慎治のこともおしっこまみれにしてあげた、てわけ。」礼子たちは呆れたように肩をすくめた。「全く、富美ちゃんも朝子も苛めっ子なんだからもう!ねえ玲子!?」「本当よねえ。仕上げのこの苛め、私と礼子とじゃ、ちょっと考え付かないよねえ。」「あん、もう!礼子たちひっどーい!なんか私たちのこと悪者にしちゃてるーっ!自分たちだって楽しんでるくせに!」「まあね。でもまあそれはそうとして、そろそろ本当に帰ろうか。いい加減寒くなってきたよね。」
確かに日はもう完全に沈み、冷気が急速に忍び寄っていた。四人の美少女はさっさと荷物をまとめると各々の愛馬に跨った。ああ、やっと帰れる。慎治たちもほっとしていた。同時に耐え難い寒さを感じた。ブルッ・・・素っ裸でいられる気温ではなかった。服を着なくちゃ・・・と、見た自分たちの服。それは余りに悲惨な状況だった。慎治の服はおしっこでビショビショ、信次の服は馬糞まみれ。信次の全身あちこちにはまだ馬糞がこびりつき、慎治は髪や体のあちこちから富美代のおしっこを滴らせている。ど、どうすりゃいいんだ・・・恨みがましそうに、かつどこか救いを求めるかのように慎治たちは馬上の礼子たちを見上げた。だが勿論、救いの手など差し伸べられるわけがない。「信次、二人とも道は分かっているね。遅いと先帰っちゃうからね!道草食わないでさっさと帰ってくるのよ!じゃ、みんな行こう!ハッ!」玲子の声を合図に四人は一斉に馬を走らせ、グラウンドから去っていった。取り残された慎治たちは暫く呆然としていた。寒い・・・日はとうに翳り、急速に迫る冷気は慎治たちの体温を容赦なく奪う。服を、早く服を着なくちゃ、で、でも・・・「ど、どうする・・・」「どうするって・・・き、着るの?こ、これを???」慎治たちは自分の手にある、汚れきった服を力なく見つめた。朝子のおしっこ、馬糞にまみれた二人の服は見るだけで吐き気を催すほど汚い。だがクラブまではどう考えても5キロはある。一時間はかかる道のりだ。それだけの距離を全裸で歩ききることは不可能だ、凍死すらありうる。命にも関わりかねない無謀さだし、第一いくら人通りは殆ど無い、と言っても無人島にいるわけではない。たまには人も通るし車も通る。その道のりを全裸で歩いていくのはきちがい沙汰だった。
3
先に動いたのは慎治だった。全身に引っ掛けられた富美代のおしっこは、最初こそ富美代の体温と同じ温もりを持ち、慎治をむしろ温めてくれる温水だったがとっくに冷め切っていた。冷め切った富美代のおしっこは、今では慎治の体の表面から容赦なく気化熱を奪い、排泄した当の富美代が去った後も尚、慎治のことを今度は寒さで苛め続けていた。ブルッと慎治の全身が悪寒に震えた。カタカタカタカタ・・・気がつくと奥歯が寒さに鳴っていた。ふ、拭かなくちゃ・・・せめて体を、富美ちゃんのおしっこを拭かなきゃ、風邪ひいちゃう・・・だが体を拭くタオルなど、どこにもない。拭くもの、なにかないかな・・・あるものは唯一つ、自分が持っている服だけ、朝子のおしっこでびしょびしょになっている服だけだった。こ、こんな、こんなもので・・・ふ、拭くの・・・だが他に選択肢は無い。寒さに震えながら慎治は手に持った服をギュッと絞った。ボタボタ・・・服から大量の朝子のおしっこが絞り出され、地面に垂れていく。絞り出されたおしっこの一部は慎治の手を伝って垂れていく。ち、ちくしょう・・・な、なんで・・・お、おしっこを・・・他人のおしっこを絞らなくちゃいけないんだ・・・ち、ちくしょう・・・慎治は悔し涙を洩らしながら絞り続けた。
漸く絞り終えた服で自分の顔を、髪を、体を拭く。冷たく湿った服で拭いていると、まるで朝子のおしっこを自分自身の手で顔に、髪に、体にすり込んでいるようだった。いや、それだけではない。排泄されてから時間がたった二人のおしっこはアンモニア臭い臭気を増しつつあった。自分の全身から立ち上る富美代のおしっこの臭いは徐々に強くなる臭いだからまだ余り感じずに済んでいたが、服にたっぷりと浸み込んだ朝子のおしっこの臭いはそうはいかない。真っ先に顔を拭こうと服を顔に近付けた時、ツンと悪臭が鼻をついた。すぐに分かるおしっこの臭い。自分のものと余り変わらない臭い。自分が他人のおしっこまみれの服で顔を拭こうとしている、と否応なしに実感させる臭いだ。余りの嫌悪感に吐き気すら感じる。なんとかにおいを感じないようにと息を止めながら顔を、体を拭くがおしっこの臭いは鼻、というより直接脳に浸み込んでくるようだ。いくら息を止めても、必死で考えまい、としても富美代と朝子のおしっこの臭いは慎治の嗅覚から決して立ち去らなかった。そしてふと気づくと、折角絞った服に今度は富美代のおしっこがしみ込み、また濡れてきていた。もう一回服を絞る。チョロチョロと富美代のおしっこ、いやおそらくは富美代と朝子のおしっこがミックスされた液体が搾り出される。絞り終えた服でもう一度全身を拭く。富美ちゃんと朝子のおしっこを全身にすり込んでいる・・・漸く全身を拭き終えた慎治の手がワナワナと震える。次に何をしなくてはいけないか、一つしかない。服を着ること。朝子と富美代のおしっこがたっぷりとしみ込んだ服を着ること。そしてクラブまでの道のり、一時間はかかる道のりを二人のおしっこまみれの服を身に纏いながら歩き続けねばならないのだ。ほ、本当に・・・こ、これを・・・き、着るのか???慎治は二人のおしっこが浸み込み、重く湿った服を見続けた。だが寒さは刻一刻と増している。もう限界だった。グッと吐き気を堪えながら一気に服に頭を、腕を通す。冷たく冷え切った服の冷たさにゾクッとくる。だ、だめ、か、考えちゃ・・・い、一気に着なくちゃ!!!必死の形相でブリーフとズボンを履き、スニーカーを履く。ビチャッ・・・スニーカーの中に溜まっていた朝子のおしっこが内底のクッションからしみ出る。ぐ、グエエッッッ!!!限界だった。慎治はその場に突っ伏し、激しく嘔吐した。
一方、信次も状況は似たようなものだった。全身が濡れてはいない分、慎治よりいくらか寒さはマシ、とは言っても単なる比較の問題だ。裸でいられる時間は限られている。横で慎治が全身を拭きだしたのにつられるように、信次も作業を開始しようとした。でもどうやって?おしっこではない、信次は全身馬糞まみれだ。服も馬糞まみれだし、そして仮にその服で体を拭いたところでどの道、着ていける服はそれだけなのだ。何の解決にもならない。信次は呆然と自分の手を見た。どう考えても方法は一つしかない。手で、自分の素手で全身と服にこびりついた馬糞を可能な限りこそぎ落とすしかない。う、嘘だろ・・・ば、馬糞を・・・て、手で?いじるの???信次は余りのことに全身を怒りでワナワナと震わせていた。だが信次をこの地獄に突き落とした朝子たちは既に帰ってしまっている、抗議の声をあげる相手すらいないのだ。信次がここでいくら絶叫しても、朝子たちの耳に届きすらしない。そして寒さは刻一刻とつのっていく。ち、ちくしょぅ・・・信次は弱々しく呪いの言葉を呟きながらのろのろと手を動かし、まず胸にこびりついた馬糞に触れた。未だ乾いていない馬糞の冷たく、ねっとりとした感触が堪らなく気持ち悪い。粘土、というには柔らかすぎる、やや固めに練った泥、といった感触だ。必死でこそぎ落とし、指についた馬糞をグラウンドの芝になすりつけるように拭く。胸、腹、腰・・・信次は必死で作業を続けた。だが水もなしで拭こうとしても限界がある。やがて体中、まだまだ十二分に汚いのに殆ど取れなくなってしまった。いくらこそぎ落とそうとしても、もう馬糞は落ちない、却って自分で自分自身の体に擦り込んでいるようなものだった。ち、ちくしょう・・・も、もう駄目なのかよ・・・信次は体を諦め、服に取り掛かった。だがこっちはもっと酷い。富美代に踏み躙られ、信次の服には馬糞がたっぷりと擦り込まれた状態だ。手できれいになどできるわけがない。精々、大きな塊を落とすのが関の山だ。必死で作業を続けたが、直ぐにどうしようもなくなってしまった。信次は血走った目で手に持った服を凝視した。く、くそ・・・こ、これを・・・着ろっていうのかよ!!!あ、あんまりだ・・・あ、朝子は、朝子も富美代もこうなっちゃうのを知ってて、知っててやったんだ!あ、あんまりだーっ!!!ぜ、ぜったい、絶対着るもんか!!!だが信次の誰にも気付いてさえもらえない情けない決意など、寒さの前では全くの無力、あっという間に覆されてしまう。ヒュゥッ・・・風、そよ風程度だが風が吹き、一層寒さがつのる。横では慎治が体を拭き終え、のろのろと富美代と朝子のおしっこまみれの服を着始めている。ブルッ・・・だ、だめ、もう我慢できない・・・寒さに歯をガチガチ鳴らしながら信次は一気に、馬糞まみれの服に頭を、腕を通していった。草食動物である馬の糞は人間のに比べ、遥かに臭いは少ない。しかも人間の感覚で嗅覚は最も鈍感かつマヒしやすい感覚だ。実際、全身を馬糞まみれにされた当初暫くは悪臭に苛まされていたものの、少しは鼻が慣れたのか、悪臭は苦痛というレベルではなくなっていた。しかし服を着て、新しい馬糞がプラスされるともう駄目だった。擦り込まれ、広げられた分、悪臭は体からの臭いより服からのものの方が却ってきついかもしれない。ガ、オヴェーーッッッ!!!信次も耐え得る限界を超えてしまった。吐いても吐いても吐き気はおさまらない。いや自分のゲロの臭いと馬糞の臭いがミックスし、更に横で吐いている慎治のゲロの臭いも加わり、破壊的なレベルに達した悪臭が更なる吐き気を呼ぶ。だ、だめ、こ、ここにいたら・・・信次は必死で立ち上がり、ふらつき、ゲロをそこここに撒き散らしながら歩いていった。
やがて胃液すら吐き尽くした二人はよろよろと立ち上がった。「か、帰ろう・・・」「あ、ああ、か、帰ろう・・・」二人はとぼとぼとグラウンドを出て人気のない道を歩き始めた。道に出たところで慎治は後ろを振り返った。このグラウンドにだけは二度と、絶対にこないぞ・・・だが内心分かっていた。礼子たちがこのグラウンドでの遊び、大いに気に入ったに違いないことを。そして慎治たちがどんなに嫌がろうが泣き喚こうが、これから先、何度も何度もここに連れてこられ、今日同様、死ぬほど鞭打たれ、引き摺り回され、何度も何度もおしっこを飲まされることを。そのことが容易に想像できるだけに、慎治たち二人の絶望は深かった。だが、今は泣いている時ではない。二人は重い足を引き摺り、歩き続けた。途中、どこかで公園でもあれば体を洗おう・・・二人はそう思っていたが、そもそも人気のない田舎で公園などある筈がない。歩いても歩いても体を洗える水道はない。願いも空しく歩き続けた二人にやっと救いの神が現れた。乗馬クラブの案内の看板が道端に立っていた。「ああ、あと少しだね・・・」「うん・・・早く、とにかく早く体を洗いたいよ・・・」微かな希望に二人は歩みを速めた。そしてやっと現れた乗馬クラブ入口の看板。こ、ここを曲がればクラブハウスまでもうすぐだ!やっと、やっと体を洗える!だが喜び勇んで角を曲がった二人が見たものは、路肩に停車している見慣れた二台のランクルと、その周りで楽しそうに談笑している6人の男女だった。「やあ、慎治君たち、遅かったじゃないか!お嬢さんたち、お待ちかねだよ!」良治の夕暮れ時には相応しくないほど明るい声が響いた。「そうだよ全く!みんな待ちくたびれてブーブー言ってたよ。駄目だなあ、女の子を待たせちゃあ!」負けず劣らず爽やかに大声を出す亮司の後ろから玲子たち四人が近づいてきた。全員、既に着替えていた。シャワーを浴びて汗を流し、ゆっくりと寛いでいかにもさっぱりとした礼子たちと、全身ボロボロで疲れきった、生気を失った慎治たち。しかも慎治たちは糞尿と汗にまみれ、凄まじい悪臭を放っているのだ。う、羨ましい・・・ぼ、ぼくたちも早く体を洗いたい・・・
「遅かったわね信次・・・ウッワーッ!クッサーイッ!」玲子の大声に笑いながら礼子も近づいてきたが、慎治たちの傍までくると大袈裟にのけぞった。「ワッ!本当だ。二人とも全く、臭いったらありゃしない!なんなのよあんたたち、その臭いは!まるでホームレスみたいじゃない、ちょっと近づかないでよ、私まで臭くなっちゃいそう!」富美代と朝子も近づいてくるなり、キャァッと声をあげて飛びのいた。「うわっ、、、なにこの臭さ!慎治、あんた全身、おしっこ臭いじゃない!こんな臭い撒き散らしながら歩いてきたわけ?」慎治の目から押さえきれない悔し涙が溢れた。「そ、そんな・・・お、おしっこ、おしっこひ、ひっかけたのは・・・ふ、富美ちゃんじゃないか!そ、それを、じ、じ、自分で、自分で引っ掛けておいて、く、臭いだなんて・・・あ、あんまりだ、あーんまりだーっっっ!!!」「うるさいわね慎治、確かに私、おしっこ引っ掛けたわよ。だけどそのままで歩いて来い、だなんて言っちゃいないわよ?どこかで洗ってくればいいでしょ!水道探すなり、何もなかったらそれこそ川で洗ったっていいじゃない!おしっこまみれで帰ってきたのは慎治の勝手でしょ、全く!平気でおしっこまみれでいられる変態のくせして私を逆恨みするだなんて、慎治、あんた本当に根性腐ってるわね!ペッ!」渾身の軽蔑を込めて吐き出された富美代の唾が慎治の鼻先を直撃した。「ハッハッハッ!慎治君、君の負けだな、その格好じゃ何言ったって説得力ないよ!第一、女の子に唾引っ掛けられるなんて、男の一生の恥だな!」良治は楽しそうに笑いながら頷いている。朝子も大きく頷いた。「本当よねー。信次、私も信次には心底驚かされるわ。まっさか、お馬ちゃんのうんちまみれのままで帰ってくるとわねー。いくらあんたでも、流石にどっかで体、洗ってくるとは思ったんだけどねー。うん、凄い、あんたは偉い!感動した!ペッ!」信次の額から朝子の唾がゆっくりと頬を伝っていく。「うーん、ま、信次君、馬糞まみれで歩き回った挙句に女の子に唾引っ掛けられてたんじゃ、君、人間廃業だよ。折角こんなに可愛い女の子たちが付き合ってくれてるんだからさ、お兄さんはもう少し、自分を大事にすることをお勧めするよ!」な、何が自分を大事にだ!亮司の過剰なほど爽やかな、偽善に満ち溢れた言葉が信次の踏み躙られたプライドを更に痛めつける。だが、未だ、未だ終わってはいなかった。
4
ポンッと礼子が慎治たちの目の前に二つの財布を放り投げた。え、なにこれ・・・僕たちの財布だ。なんでここで財布を渡されるの???訝る二人を見て礼子が冷たく微笑んだ。「慎治、いい?このクラブはね、高級な、上品なクラブなの。はっきり言ってね、おしっこや馬糞にまみれた汚いホームレスに入られちゃ、困るのよ。だからね、あんたたちも私たちと一緒にチェックアウトしといたわ。荷物も全部出して、もう亮司先生たちのランクルのトランクに入れといたからね。」「そ、そんな・・・じゃ、じゃあ・・・シャワーも浴びられないじゃないですか!」「ひ、ひどい!じゃ、せ、せめて・・・せめて荷物だけは返して!す、水道だけ借りて着替えるから、せ、せめて荷物だけは・・・」哀願する信次たちを満足げに見下ろしながら、玲子が後を引き取った。「そう。礼子の言うとおり、汚い格好でこのクラブの回りをうろつかれちゃ迷惑なのよ。あんたたちはどう見ても常識っていうものが全くない恥知らずみたいだからさ、放っといたらこんなとこで裸になったり、汚い体洗い始めたりしてクラブのみんなに大顰蹙買いそうだわ。だからね、そんなバカな真似できないようにあんたたちの荷物、私たちが預かっといてあげる。この道まっすぐ行けばJRの駅だから、そこの待合室に置いとくわよ。ま、無くなるといけないから一応、貴重品だけは返してあげる。」「分かったわね、二人とも。そんな汚い格好でクラブに入ったりしたら、後で酷い目に会わせるからね!最も、」礼子は慎治たちに言い渡しながらクスクスと笑い出した。「このクラブ、セキュリティはしっかりしてるからね。ちゃんとゲートのところではフルタイムでガードマンが入場者をチェックしているわ。あんたたちみたいな汚いの、絶対に入れてくれないけどね。嘘だと思うなら、試してみてもいいわよ。」あ、ああ・・・そ、そんな・・・慎治たちはへなへなとその場に座り込んでしまった。や、やっと、やっと体を洗えると思ったのに。やっと着替えられる、と思ったのに。また、また歩け、て言うの?こ、ここから駅までってどれ位あったっけ・・・ぞくっ・・・二人の背筋に悪寒が走った。どう考えても10キロはある・・・ば、倍・・・グラウンドからここまでの倍以上じゃない!!!「お、お願い・・・」思わず慎治は両手を胸の前で組み、祈りのポーズになって哀願した。「お、願い・・・じゃ、じゃせめて、せめて・・・駅まで僕たちも乗せて行って・・・おねが・・・」信次も必死で哀願した。「そ、そう、そうだよ!!!せめて駅まで、と、トランクでもどこでもいいから、おねがい、おねがいしま・・・」だが慎治たちの哀願は亮司の声に掻き消されてしまった。「おいおいバカ言っちゃいけないよ慎治君!僕たちの愛車だよ、いくらなんでもそんな汚いままで乗せられるないだろう!?なあ良治?」「ああ、全くだ!それにね、二人とも行きは一緒に乗せて来てあげたろう?で、一日中玲子君たち美女を独占してたっぷり楽しめたんだ。せめて帰り位、僕たちにも美女独占のサービスタイムにしてくれてもいいんじゃないかい?言われなくても気を利かせて、ここで失礼します、位のこと言えなくちゃ駄目だよ、全く気が利かないなあ。」
必死で喚き続ける慎治たちを無視し、一行はさっさと二組に分かれてランクルに乗り込みむと未だ立てないでいる慎治たちをその場に放り出したまま、さっさと走り去ってしまった。あ、ああ・・・行ってしまった・・・二人は無言のまま、暫く呆けたように涙を流しながらすすり泣いていた。泣き続けている二人の横を、クラブから出て行く何台もの高級車が過ぎていった。立てなかった。立ち上がる気力はもうどこにもなかった。だが、いつまでも座り込んでいることすらできなかった。「おい、ここで何をしているんだ!?」野太い声が頭上から降ってきた。見ると大柄な、がっしりとしたゴリラのような体格のガードマンが慎治たちを見下ろしていた。礼子たちか、あるいは慎治たちの横を通り過ぎていった誰かがクラブに連絡したのだろう。「ここは私有地だぞ。さっさと出て行くんだ。大体、そんな汚い格好でこの周りをうろうろするんじゃない!ここのお客様の迷惑だろう、さっさとどこかに行け!」「は、はい・・・い、行きます、行きますから、お願い、水道だけ貸してくださ・・・」慎治は最後まで言うことすらできなかった。「何をバカ言ってるんだ!おまえらみたいな汚い、臭いガキを入れるわけないだろう!さっさと失せろ!ぶん殴られたいのか!」そのガードマンは腰に差した警棒を引き抜き、慎治たちを無慈悲に追い立てた。「おら、さっさと失せろ!また来るからな、その時に未だこの辺うろついてたら、足腰立たなくなるまでぶん殴るぞ!」
融通、慈悲など全くない、脳まで筋肉で出来ているようなガードマンに追い払われ、慎治たちは暗い夜道を駅に向かってとぼとぼと歩き出した。疲労、苦痛、絶望・・・ありとあらゆる負の感情が二人を支配する。10キロ・・・二時間はかかる。既に真っ暗になり、気温は急速に下がっている。身に浸み入る夜の冷気に震えながら、慎治たちはとぼとぼと歩き続けた。単調な田舎道。ポツン、ポツンと立つ街燈の回り以外は真っ暗な道。歩く人などいない、時折自動車が猛スピードで走り過ぎるだけだ。寂しい夜道を二人は延々と歩き続けた。既に疲れた、という感覚からなくなりつつある。ただただ足を動かすだけ。多分、一度止まったらもう歩けない。そして歩けなくなっても、慎治たちを心配してくれる人はどこにもいないのだ。止まったら・・・マジで死ぬかもしれない・・・死に対する恐怖のみが二人の足を動かしていた。延々と歩き続ける内に、漸く何もなかった道端にポツン、ポツンと民家が建ち並び始めた。ああ、漸く駅に近づいてきたんだな・・・少し、ほんの少しだけ元気を、余裕を取り戻した途端、忘れていた感覚が蘇ってきた。嗅覚が。二人の体にこびりついた汚物はもう、すっかり乾いていた。だが富美代たちのおしっこも馬糞も時間が経つにつれ、乾いてきたはいいものの臭いはむしろきつくなっていた。く、臭い・・・急に自分の発散する悪臭を感じた。自分が悪臭にまみれ、場末の公衆便所なみの悪臭を発散していることがわかる。そして全身から立ち上る臭いが、体に付着した汚れから出ているのではなく、自分自身の体から出ている、そう、自らの体臭のような気さえしてきた。悪臭に頭がクラクラしてきた。「ふ、富美ちゃん・・・あ、朝子さん・・・ひ、酷いよ・・・」ぼそっと慎治が呟いた。富美代に引っ掛けられたおしっこはとっくに乾いている。かなりが全身に浸みこんでしまっているだろう、もう体を洗っても拭いても、落とせないに違いない。そして服に引っ掛けられた朝子のおしっこも慎治の体温で既に乾燥している。二人分のおしっこがミックスされた僕の体臭。この臭い、もう抜けないんじゃないだろうか・・・「ひっ・・・ひっく・・・う、ウエッッッ・・・」傍らからすすり泣きが聞こえた。見ると信次が肩を震わせて泣いていた。「し、慎治なんか、ま、まだ・・・まだいいよ・・・お、おれなんか・・・ば、馬糞だぜ???う、うんこまみれだよ・・・」信次も涙を流していた。二人はメソメソ泣きながら歩き続けた。やがて着いた駅はローカル線の小さな無人駅だった。誰もいない、蛍光灯が寒々と冷たい光を発する待合室を見ると、二人のバッグが置いてあった。良かった・・・無くなってなかった・・・小さな喜びを噛み締めつつ二人はバッグをひしと抱きしめた。ああ、良かった・・・これでやっと、今度こそ体を洗える・・・水道はどこ?だがホームに水道はなかった。やっと見つけた水道はただ一つ、今時男女共用になっている小さな便所の手洗い用だけだった。無人駅だけに、ろくに掃除もされていない小汚い便所だ。べ、便所・・・また便所・・・だが他に選択肢はない。二人はのろのろと服を脱ぎ、体を洗い始めた。冷たい水を何度も何度も体にかける。バッグから引っ張り出したタオルで何度も何度も全身を拭く。だが所詮、冷水で拭いただけだ、完全にきれいにはならない。30分近く洗い続け、とうとう諦めた二人はのろのろと服を着始めた。
「駅の便所で体を洗って着替えか・・・俺たち、ホームレスみたいだな・・・」ぼそっと信次が呟いた。「ホームレス・・・はは、確かにね。でもホームレスの方が未だマシかもね・・・」「そうだよな・・・ホームレスは鞭で叩かれたりしないよな・・・」「それに、おしっこ引っ掛けられたりもしないよね・・・」はは、はははは・・・・二人は力なく笑い続けた。「慎治の背中、見事な蚯蚓腫れだらけだぜ・・・」「そういう信次の背中なんか、もうどす黒くなってるよ・・・お互い、酷くやられたもんだね・・・」「ああ、今までは玲子さんたちだけだったのが、朝子や富美代もいたんだもんな・・・」「倍、本当に倍、鞭で叩かれたよな・・・富美ちゃん・・・幼馴染なのに・・・」「朝子、苛めた、苛めたって・・・ちょっとからかっただけなのに・・・100、100万倍返しだなんてよ・・・」「あれじゃ礼子さんたちと変わらないじゃないか・・・」「う、ううん・・・玲子さんたちより、しつこい位かもしれないよな・・・」もう止まらなかった。一瞬、二人の視線が合った。「ち、ちくしょう・・・」「ひ、ひどいよ、ひどすぎるよ・・・」「鞭だなんて・・・」「ブーツだなんて・・・」「唾だなんて・・・」「おしっこだなんて・・・」「お、おれたちだって・・・」「に、にんげん、にんげんなんだ・・・」「そ、それを・・・」「あ、あんまりだ・・・」「こ、このままじゃ殺されちゃう・・・」「じ、自殺してやろうか・・・」自分の言葉に驚いたように慎治が悔し涙と涎でグチャグチャの顔をあげた。「で、でも・・・な、なんで、なんでぼくたちが、ぼくたちが自殺しなくちゃいけないんだ・・・」信次もグチャグチャの顔をあげた。「そ、そうだ、そうだよ・・・し、死ぬのは、死ななくちゃいけないのはおれたちじゃない・・・あいつらだ・・・」「天城礼子と」「霧島玲子と」「神崎富美代と」「萩朝子だ!!!」「あ、あいつらを」「あいつらをこ、殺してやる」「や、やっつけてやる、仕返ししてやる!」「ひ、酷い目に、俺たちよりも酷い目に会わせてやる!」「お、思い知らせてやる!ぼ、ぼくをバカにするとどうなるか!」二人は自分たちの言葉に酔ってきたかのように叫び続けた。熱に浮かされたように。そうやって憎悪を募らせることだけが唯一、生への執着と希望を掻き立てるものだった。例えその希望が、パンドラの箱に唯一入っていた希望と同じく、自分たちをより深い地獄へと導くものだとしても。見詰め合う二人の口から同時に言葉が迸り出た。「ふ、、ふ、復讐してやる・・・」「り、り、リベンジ、リベンジだーーーっっっっ!!!」
1
初めてだった。翌朝目覚めた時、背中、尻、脇腹、慎治たちの全身に礼子たちの鞭の痛みが残っていた。それだけならいつものことだ。だが恨み、富美代と朝子におしっこを引っ掛けられ、馬糞まみれにされた恨みは消えていなかった。いや、一晩置いて尚一層、恨みはつのっていたかもしれない。肉体的な痛みは時間と共に急速に薄れていく。だが精神的な痛みは時間と共に却って増していく。慎治たちはその痛みに駆り立てられるように、復讐の幻想を語り合い、精神の傷口を舐めあっていた。二人は本気だった。本気で,真面目に仕返ししようと必死で知恵を絞って、来る日も来る日も復習計画を練っていた。
それが間違いだった。考えれば考えるほど、礼子たちと自分たちの実力差に思いが至ってしまう。いや、礼子たちどころではない。仮に二人掛かりで行ったとしても、慎治たちの腕力では富美代や朝子にも軽くあしらわれてしまうだろう。そのことは嫌と言うほど思い知らされている。だから慎治たちの企みはとんでもない方向に進んでいってしまった。そう、誰か人を,礼子たちより強い人に頼んで、礼子たちをやっつけてもらう、という考えに。とんでもない考え違いだった。確かに礼子たちは慎治たちより遥かに強い。だが、それがどうしたと言うのだろうか。礼子たちといえども、24時間いつも気を張っているわけではない。慎治たちが本当に自分を捨て,復讐を最優先とするならば、手段などいくらでもある。例えば後ろからナイフで刺すとか闇討ちをかけるとか家に火をつけるとか、極端に言えばヤクザからピストルを買い,撃つという手だってある。いくら礼子たちが強い,と言っても,それは真っ向から向かい合った時の話だ。慎治たちが、自分が犯罪者になったって構わない,という覚悟さえできれば、手段はいくらでもある。突き詰めれば人を殺す,ということはナイフを10センチ前に突き出す,ピストルの引き金を数センチ引く,と言った,僅か数センチの動きを躊躇い無くできるかどうか、に過ぎない。慎治たちはその数センチの覚悟がなかった。本当にもう礼子たちに苛められるのが嫌だ,この地獄から抜け出るためなら,どんなことでもする、自分が犯罪者になるのなんて、全然構わない。礼子たちを殺すか,自分たちが死ぬか,どちらか二つに一つだ。ここまで考え覚悟を固めていれば、おのずと腹も固まり,本当に復讐できたかも知れない。だが慎治たちはそうではなかった。何が何でも復讐してやる,という硬い決意を持てないままに、言葉だけで復讐,という重い覚悟を孕んだ言葉を弄んでいた。逆に言えば,そうやっていつまでたっても覚悟が固まらず,無意味なプチ反抗だけを繰り返してきたからこそ、礼子たちにここまでいいように苛められて来た訳だが。ともあれ、慎治たちはおよそ最悪の選択,自分たちの運命を賭けた復讐を赤の他人に依頼しよう、という致命的なミスをおかしてしまった。赤の他人,慎治たちと違い,礼子たちに別に恨みがあるわけでも何でもないから、失敗しても別にどうということはない人間に復讐を依頼する、というのが何を意味するか。そして、その所詮他人事の依頼が失敗した場合に、礼子たちがどういう行動に出るか,慎治たちは考えを巡らすことができなかった。むしろ、「礼子さんたちよりもっと強い人に頼めばいいんだ!」と何か,自分たちがぶつかっている分厚い壁をブレイクする天啓を得たかのような幻想に酔い,甘い期待に打ち震えてしまっていた。だが復讐を依頼できる相手はなかなか見つらなかった。強く,しかも礼子たちを,女の子を平気でグチャグチャにできる男。もともとワルでもなんでもない慎治たちにそんな知り合いがいるわけない。だが八方手を尽くして探している内に,一本の糸が繋がってしまった。そして慎治たちの運命も、大きく変わろうとしていた。
「なあ慎治、あいつらのこと、先輩に頼んでやっちゃおうぜ・・・」またか、慎治は何の気なしに応じた。先輩、信次が中学の頃、パシリに使われた先輩とやらに頼んで礼子たちをやっつけて貰おう、て話だよな。全く、そんなこと、出来るわけ無いくせに・・・何十回目かの答えだった。「やっちゃうって、誰に?そんな中学の時の先輩に頼む位なら、ヤクザでも雇った方がまだマシじゃない?」いつもだったら、ここでおしまいの話だ。だが今日は違っていた。信次は目をギラつかせながら、身を乗り出してきた。「違うんだよ、慎治、俺の直接の先輩じゃないんだけどさ、紹介してくれる、ていうんだよ。」紹介ね、ふーん、誰を?どうせ、どうでもいい、その辺にたむろってるチンピラだろ?「いや慎治、それが驚けよ、SNOW CRACKだぜ?あそこの坊野さん、あの人と話が繋がる、て言うんだよ!」慎治もこれには些か驚いた。SNOW CRACK、一見テニスサークルかと思うような軟派な名前の彼らは,通称白ギャンとも呼ばれ地元で一目置かれる、いや最悪,札付きのワルだった。専門は名前のとおりドラッグの密売だが、幹部を含め末端に至るまで全員理性が欠片すらない、イカれたメンバー揃いのギャングだった。男は殴る,女はレイプする,金が欲しけりゃ強盗でもなんでもする、狂犬同然の連中だった。いずれあと数年したら全員、ヤクザ、廃人、黒枠の写真に収まっている,のどれかだ、と奄ウれるだけあり手のつけ様が無い、本職のヤクザでさえ関わりあいになるのを嫌がる連中だった。勿論、マジ坊の慎治は名前だけは知っているが、会ったこともない、遠い存在だ。その連中に信次はあたりをつけられる、と言うのだ。「信次、それ、本当か?スノー、て、あのチームだろ?幾らなんでも、あそこに頼めるわけないだろ?僕たちなんか,会っただけで金、せびられるのがオチじゃないの?」「いや、これが本当なんだよ。中学の時の先輩の友達の従兄弟がさ、あそこのプレジの坊野さんなんだよ。でさ、頼めば、カネ次第では坊野さん、力貸してくれそうだっていうんだよ。上手いことにさその人、サブ、ていうより坊野さんとタメの検見川さんって人ともツーカーだっていうんだぜ、どうだい、これ、凄え話じゃないか?」
2
けみがわ・・・けみがわ、検見川・・・慎治の頭の中で引っ掛かるものがあった、検見川、随分珍しい苗字だな・・・「信次、ひょっとしてその検見川さん、て人、僕と中学一緒じゃない?でさ、ホストっぽい、矢鱈と逝けてるルックスの人じゃない?」「あ、そう言えば・・・確かに検見川さん、慎治と同じ中学だよ。うん、確かにあの人、滅茶苦茶鬼畜な癖して,顔は矢鱈と逝けてるけどさ、それがどうかしたのか?」「その検見川さん、僕たちより2年上、丁度僕たちが新入生の頃の最上級生だよね・・・検見川、そんな珍しい苗字の人、あの人しかいないよ、きっと!」「な、なになに慎治、検見川さん、知ってるのか?」「うん・・・いや、僕は殆ど話したことないんだけどさ、富美ちゃんが超お熱だったんだよ。検見川さん、ちょっと危ない感じもする人じゃん?だからさ、富美ちゃん、最後まで告れないまま検見川さんが卒業しちゃってさ、それっきりになっちゃったんだ。だけど、富美ちゃんが超お熱だったのはみんな知ってる、有名な話だよ。」運命の歯車がコトリと不吉な音を立てた。「・・・慎治、プレジの坊野さんだけじゃなくてサブの検見川さんとも話つながりそうじゃん・・・これ、これって・・・俺たちにも、俺たちにもやっと、やっとツキが回ってきたかもしれないぜ!」
早速セットに入った慎治たちに朗報がもたらされたのは、2週間後だった。指定されたファミレスで慎治が会ったのは確かに、中学の時にいた検見川先輩だった。「オウヨ?おまえ、なんか見覚えあるな。もしかして、おまえ、中学の時,俺と被ってなかったか?確か・・・富美代だっけ、あの小うるせーガキとつるんでなかったっけ?」「は、はい。富美ちゃんのこと、覚えていらっしゃいましたか?」「ああ。あいつ、小便臭いガキのくせしてうるさく付きまといやがってよ、結構ウザかったな。あいつ、真面目な子のくせして俺のこと、なんかいい人系と勘違いして付きまとってたろ?笑っちまうよな、こっちは全然その気ないのによ。ウゼーから一回姦っちまうか、と思ってたけどよ、あの頃は俺も人間、丸かったからな、いい人ごっこして遊んでる内に卒業しちまって、それっきりになったけどな。どうよ、あいつも元気してるか?」よかった。覚えていてくれた、しかも富美ちゃんのこと、好意も何も持ってない、じゃあ話は早い。慎治たちは手早く用件を説明した。話は簡単,言葉にすれば僅か1,2行だ。天城礼子,霧島玲子,神崎富美代,萩朝子、この四人を攫ってグチャグチャにレイプして欲しい。できたらレイプ写真も撮って欲しい。そんな写真をばら撒かれたら二度と表を歩けない,という位,恥ずかしい写真を撮って欲しい・・・「ふーん、慎治,何があったかは知らねーけどさ、よっぽど富美代たちのこと、むかついてるんだなー。大方,お前ら高望みしてこいつらに告って派手に振られた、てとこか?ま、別にいいけどよ。坊ちゃん,どうよ?」「おう・・・でもよ,この子たち、マジでいけてねーか?こりゃよ・・・こいつらの依頼抜きでもやっちまいてーよな。こういうお高く止まった女のよ、姦った時の泣き声ってシビレルからな。四人か、全員いい線逝ってるじゃねーか。じゃーよ、奈良村と須崎もこういうタイプ、結構好みだからな、連中も誘ってやろうぜ。・・・OK、おい、おまえ信次、て言ったな、普段はこんな値段じゃ動く気しねーけどな、こいつら上玉揃いだ、出血大サービスしてやるよ。一人十万,四人で四十万積みな。そしたらよ、おまえらの望み通り、グチャグチャに姦ってやるよ。今言った奈良村と須崎な、こいつら、うちのNO.3とNO.4だぜ?それに俺とケミ、うちのNO.1からNO.4揃い踏みの超豪華メンバーで姦ってやるぜ・・・望みどおり姦ってやるぜ。派手に、たっぷりとな。ケミちゃん、この内のこいつ、知り合いなんだろ?だったら、絵は描きやすくねーか?頼むぜ,こいつら上玉揃いじゃん?俺にも楽しませてくれよ!」「オウヨ!ま、その手の絵は俺の専門分野だからな、任せときな。富美代か、よく見ると中坊の時よりグッといい女になってるじゃねーか。中坊の時は食いそびれたけどな、今度は遠慮なく食わしてもらおうか!」
やった、やった、やったーっっっ!!!慎治たちは外に出てから、思わず抱き合って大喜びしてしまった。「や、やった、やったな慎治!」「うん!うん!聞いた?派手に、たっぷりと姦ってくれるんだって!あの人たちが派手に、て言うんだよ!?富美ちゃんも礼子さんたちも、もう終わった、て感じ?」「そうだそうだ!もう四人まとめて終わったよな!キケケケケ!あいつらの泣き顔が目に浮かぶようだぜ!」「イヒ、イヒヒヒヒ!あー、もう早く姦ってくれないかな!富美ちゃんたちが姦られた後、どんな顔して出てくるか、考えただけでも興奮しちゃぅよ!!!」慎治たちは復讐の快感、未だ実際には何も起きていないのに、もう復讐を果たしたかのように束の間、復讐の快感に浸っていた。
検見川は早速、富美代を誘うきっかけを探り始めた。余計な警戒心を持たれずに接触するいい方法を。「よし、慎治、おまえ、富美代たちとよく話すんだろ?そろそろ文化祭シーズンだからよ、連中もどっかの高校の文化祭、行く筈なんだよ。それ聞き出したらよ、俺に報告しな。そこで偶然の再会って奴を演出してやるからよ。」検見川の読み通りだった。人気ブランド校の聖華だ、文化祭シーズンになると各校からの誘いは激しい。そして聖華の中でも有数のハイレベルを誇る礼子たち四人は当然の如く人気抜群だ。慎治が横で聞き耳立てていると、毎週のようにあっちこっちの文化祭に出かけているようだった。慎治たちを毎週末鞭打つ、とは言っても人間の身体だ、土日両日とも鞭打っていたのでは流石に慎治たちの身体が持たない。だから礼子たちの基本的なパターンは土曜に慎治たちを苛め、日曜は自分たちだけでどこかに遊びに行く、というものだった。慎治が礼子たちの予定を逐一、検見川に報告していると、ある一校のところで検見川の目が光った。「うん?来週、二宮義塾か。いいな、ここ坊野の高校だ。ここにするか。」慎治にとっては意外な一言だった。二宮義塾、相当にハイレベルの高校だ。受験偏差値で言えば聖華より高い位、都内でも上位に属する高校だ。実は坊野に限らず、検見川、奈良村、須崎は皆、比較的レベルの高い高校に通っている。彼らは決して馬鹿ではない。彼らに言わせれば工業高校にでも通って族やギャングをやってる連中はサルなみの低脳、時代遅れのパフォーマンスしか出来ない連中だ。今時、気の利いたワルをやるには、少しは頭が必要だろ、と思っている。実際、彼らはレイプ、恐喝、暴行なんでもありの凶悪チームのくせして未だ警察につかまったことはなかった。勿論、警察に相当マークはされているのだが、周到な準備、口封じを徹底し、捕まるにしても精々下っ端、坊野たち四人は今まで全くの無傷だった。
そして日曜日、二宮義塾の文化祭に礼子と富美代が現れた。ブラブラ催し物を見ている二人に次々と誘いがかかる。遠くからでも強烈に目立つ二人だ、誘いは引っ切り無しにかかる。それを適当にあしらいながら回っている二人が漸く一息ついたタイミングを計り、検見川と坊野は行動に移った。「あれ、もしかして富美ちゃん、神崎、富美ちゃんじゃない?」え、誰かしら?知ってる人かな?ベンチに座ってコーヒーを飲んでいるところに後ろから声をかけられ、振り向いた富美代は思わず声を上げそうになった。「あ、け、検見川先輩じゃないですか!え、先輩、この高校なんですか?」そこに立っていたのは中学のとき憧れていた先輩、検見川だった。相変わらずの端正な顔に爽やかな微笑と驚いたような表情を浮べ、両手を広げていた。「いや、俺はここじゃないんだけどさ、友達がここだから遊びに来てたんだよ。あ、紹介するよ、坊野、て言うんだ。」「あ、よろしく、ケミの後輩?」内心のどす黒さを隠しながら、坊野も爽やかな微笑を浮べた。フン、今日は二人だけか。依頼のあったもう二人、霧島玲子と萩朝子は一緒じゃないな。まあいい、今日は仕込みだけにしとくか。食うのは後でゆっくりと楽しめばいいからな・・・それにしても、こいつら二人、マジ上玉だな。後で輪姦すのが楽しみだな。余計な警戒心をもたれないように近くのオープンカフェに二人を誘い、検見川は如何にも嬉しそうに切り出した。「いやー、でも驚いたなあ。こんなとこで富美ちゃんに会うなんてさ。でもほんと、可愛くなったね。今、どこに通ってるの?」「え、せ、聖華です。礼子も聖華のクラスメートなんですよ。」「あ、聖華なんだ。いいねえ。あそこ名門じゃん?」中学の時の憧れ、検見川先輩との思わぬ再会に富美代はすっかり舞い上っていた。高いプライドと十分な警戒心を持っている富美代は普段、ナンパなんぞについていくタイプではない。だが今日ばかりは警戒心がすっかり緩んでいた。横にいる礼子も半ば苦笑していた。あらあら顔真っ赤にしちゃって。クールが売りの富美ちゃんがこんなに顔に出るなんて、初めて見たわ。後で精々冷やかしてやろうっと!検見川たちはしたたかだった。今日、無理してどこかに誘えば余計な警戒心を持たせかねない。だから深追いして無理に誘ったりはせず、携帯ナンバーだけ聞き出すとさっさと話題を切り替え、次に繋ぎながら巧みにリリースに取り掛かった。
「ふう、本当はもっとゆっくりしてたいんだけどさ、俺たちも今日は自分のサークルにも顔出さなくちゃいけないんだ。悪いけど、お先に失礼な。また今度、どこかで会えるといいね。」え、折角再会したのにもう行っちゃうの!?富美代は思わず焦ってしまった。憧れの検見川先輩との予期せぬ再会に舞い上がったところにあっさり終わりを告げられ、すっかり動揺した富美代は普段からは考えられない行動に出てしまった。「え!も、もう行っちゃうんですか!もうちょっといいじゃないですか!せ、折角会えたんだし・・・」フン、バカが、引っ掛かりやがったな。耳まで赤くしている富美代を見ながら、冷酷さを内面に隠しながら検見川はあくまで爽やかそうに、かつ、いかにも残念そうに首を振った。「ああ、ほんと、ごめんな。俺もまさか今日、富美ちゃんと会えるとは思ってなかったからさ、この後、予定びっしり入れちゃったんだよ。ほんと、残念だなあ、もっとゆっくりしてたいんだけどね。なあ、坊野?」「ああ、俺も折角だし、もうちょっとお茶してたいんだけどな。でも、もうマジで行かないと、遅れちゃうぞ!?」え、ええ?本当に行っちゃうの?完全に動転した富美代は思わず、常日頃とは正反対の行動に出てしまった。自分から誘う、という行動に。「せ、先輩!じゃ、じゃあ今度、い、一回どこか、ゆっくり遊びに連れてってくださいよ!」ゲット!検見川が内心、ほくそえんでいるだろうと思い、坊野は笑いを押さえるのに必死だった。ったく、ケミは女引っ掛けるの、上手いよな。この手のお高く止まった女はこっちからいくら誘ったってなびかねーからな、こうやって一度リリースしといて、てめえの方から誘わせるのがコツなんだよな。絶妙の間合いと本日最高の笑顔で検見川は誘い返した。オッケー、一匹ゲット!ったく、この手はよく効くな。「あ、嬉しいな!富美ちゃんもまた、会いたい、て思ってくれたんだ!いや、俺もさ、絶対もう一度会いたいな、て思ったんだけどさ、富美ちゃん、あんまり可愛くなってたんで、ついつい誘いにくくてさ、後でメールでも送ろうか思ってたんだよ。じゃあさ、ほら俺たち、富美ちゃんたちから二個上だろ、丁度四輪の免許取ったとこなんだよ。でさ、坊野と俺、車買ったばかりだからさ、後二人、奈良村と須崎、ていう友達がいるんだけど、そいつらと毎週ドライブ行ってるんだ。どう、富美ちゃんと礼子ちゃんも今度、一緒に行かない?誰か後二人誘ってさ、四対四で行かないかい?」「え、本当ですか!わあ、嬉しい!検見川先輩とドライブできるなんて最高!うん、勿論行きます!ね。礼子、礼子も勿論OKよね?先輩たち四人だから、私たちも後二人、玲子と朝子を誘おうよ!」はいはい、富美ちゃん、もう完全その気ね。玲子と朝子も呼ぶですって?超豪華メンバーじゃない、なんか勝負入ってない?まあ、いいけど。中学の時の憧れの先輩だもんね、いいわよ、ドライブ位、付き合ってあげる。半ば呆れながらも礼子はニッコリと輝くような笑顔でフォローした。「うん、いいわよ。富美ちゃんの先輩とドライブだなんて、私も嬉しいな!私も喜んで行きます!」礼子の返事を聞いて坊野と検見川は内心、ニヤリとほくそ笑んだ。上手く引っ掛かったな。残りの二人、霧島玲子と萩朝子もこれで誘い出せたぜ。バーカ、俺たちにノコノコついて来るなんてよ、一生忘れられないドライブにしてやるぜ・・・余計な警戒を持たれないように、検見川はこの日はこのまま本当に、あっさりと富美代たちを帰した。その代わり、メールを二日おきに入れてメンテを怠らず、富美代の熱を保ちつづけた。一方、その夜富美代は早速、玲子と朝子に誘いの電話を入れていた。「ねえ玲子、お願い!私、先輩と上手く行きそうなんだからさ、協力してよ!」「朝子、絶対付き合って!今度、なんでも好きなの奢るからさ!」全く、富美ちゃんがちょっと笑ってあげれば、向こうから必死で追っかけてくるに決まってるじゃん。あんたの方から追っかけてどうするのよ。富美ちゃんも意外とお子様なんだから・・・礼子と同じく、半ば呆れながらも玲子と朝子もOKした。ま、富美ちゃんがこんだけ言うんだもん、しゃーないわね、ドライブ位、付き合ってあげるわよ。
3
だが、四人の中で唯一、玲子だけは何か妙に引っ掛かるものを感じていた。偶然の再会、ドライブ、今度は四人で行こうよ・・・何か変ね。何か出来すぎてるような気がするな。一つ一つは極めて自然よ。でも・・・まあ検見川さんは富美ちゃんにとって、ずっとお熱の先輩なんだからね、余裕かましてられるかも知れないけど、あの日は礼子も一緒にいたのよね・・・あの二人とお茶して、あんなにあっさり帰るなんて、普通ある?そりゃ、確かに人には好み、ていうものがあるからね、いくら礼子といっても、ああいう真面目でお高いタイプが苦手の男にとってはNOINTかも知れないわ。だけど、だったらわざわざ四対四で、人数増やしてドライブ行こうなんて誘うかしら?メアド交換したのよ、富美ちゃんだけどこかに誘えば十分じゃない?礼子に舞い上がってたならともかく、随分あっさり別れたんでしょ?それでドライブ?何か変ね・・・玲子の直感、礼子たちより少しワルの部分の多い玲子の直感は鋭かった。元々、中学の頃はクラスメートを自殺未遂に追い込むほどの冷酷な苛め常習犯だった玲子だ。今でこそ信次たちという格好のオモチャと、礼子たちといういい友達の両方を得てすっかり更生しているとはいえ、その頃の知り合いで高校ではヤンキー化している連中は何人もいる。早速ツテを辿って調べてみた。結果は・・・ビンゴだった。玲子からその名前を聞いた連中は異口同音にこう答えた。「二宮義塾の坊野、それに検見川だって?そいつら、SNOW CRACKのNO.1とNO.2だぜ?男は殴る、女は輪姦す、最低最悪の連中だよ。で、何?後の二人は奈良村と須崎?そいつらはNO.3とNO.4だぜ。おいおい、SNOW CRACKの幹部揃い踏みじゃん!え、あいつらが中学の時の後輩と健全なお付き合い?するわけないだろ!宅間守が小学校の先生やります、て言ってるようなもんだぜ!?あいつら、野獣以下の連中だぞ、大方、グチャグチャに輪姦してビデオでも撮って裏に流そう、ていう魂胆だろ?玲子、その子が玲子の友達だったら、絶対にやめさせた方がいいぞ。その子に一生取り返しのつかない傷を負わされること、100%保証付きだぜ。悪い事言わねえ、断れないんだったらマジで速攻、警察行ったほうがいいぜ?あいつらが相手だったら、警察だって絶対、何もないうちにだって手、貸してくれるぞ。」
「ふう、やっぱりね。ありがとう、よく分かった、恩に着るわ。」三人目の電話を切り、玲子は軽く溜息をついた。どう見ても罠だ。今なら簡単、誘いを断り逃げればいい。流石にこの段階なら大丈夫、向こうも勘付かれた、と気づいてもう近づいてこないだろう。確かに警察沙汰にする手もある。普通なら警察が未だ何も起きていない今の段階で動くわけないけど、相手はSNOW CRACK、警察も何とかしてくれるだろう。最悪、自分と礼子の両親の名前を出せば、多分助けてくれるわ。だけど・・・問題は富美ちゃんよね。こう盛り上がってる時に水掛けて、あの子止まるかしら。玲子は富美代に直接電話するのを止め、まずは礼子に相談することにした。「ふーん、確かに。言われてみると、やっぱり妙に不自然よね。文化祭で出くわすのはよくあるパターンだとしても、確かに出来すぎよね。ましてや、相手がそういう・・・SNOW CRACKだっけ?そういう極悪の連中だとしたら、尚更よね。ふう、玲子が調べてくれて助かったわ。ありがとう・・・だけど・・・問題はやっぱり、富美ちゃんよね。」流石に検見川たちに何の思い入れもない礼子は冷静だった。玲子の話を素直に受け止め、もう検見川たちのことは全く信用していない。「でしょ?で、どうなの実際?富美ちゃん今の話聞いて、すぐに目を覚まして引きそう?あの手の手合い、一番いいのは関わりあわない事よ。今の段階なら、適当な理由つけて断って、その後二度と合わなければまあ、向こうも諦めて別の獲物探しに行くと思うのよね。だけど富美ちゃん、すんなり引いてくれそう?」
礼子の脳裏に富美代の端正な顔が浮かんだ。富美ちゃん、顔立ちも態度も普段はクール系なのにな、時々、スイッチが入るとやたら熱くのめりこじゃうのよね。のめりこんじゃった富美ちゃんを止めるのって、結構骨だわ・・・「うーん、正直言って、厳しいわね。玲子もそう思ってるんでしょ?富美ちゃん、ああ見えて妙に一途だからさ、未だ何も起きてない今の段階で止める、て言うのは、結構難しいわね。」「やっぱね・・・私もそうじゃないかと思ったんだ。でね、最悪のパターン、て分かる?最悪のパターンはね、私や礼子たちは引いちゃったけど、富美ちゃんは私の言うこと信じられなくて、ズルズル連中の誘いに乗っちゃって一人でついてっちゃうこと。それは・・・お願い、私をレイプして、て、おねだりしに行くようなものよ。連中、人間じゃないわ。野獣同然だからね。そんな連中相手に一人で行くなんて、文字通り自殺行為よ。」「参ったわね、全く。どうしよう・・・玲子、こういう方面は玲子の方が詳しいわ。何かいい考えない?」「そうね・・・礼子、会ったのは二人、坊野と検見川、て言ってたわね。私が聞いた限りじゃ、あの二人がチームのNO.1とNO.2だそうなのよ。で、見た感じどうだった?連中がどの程度の強さなのか、礼子なら分かるんじゃない?」
礼子は二人の姿を思い浮かべてみた。身長は175センチ前後、礼子たちよりやや上だが、大して大柄なわけではない。決して貧弱な体格ではないが、肩幅、体の厚みもそれほどではない。「・・・そうね。確かに悪くない体格だけど、そう特別いいわけではないわ。少なくとも空手とか柔道とか、本格的に格闘技をやり込んだ、プロの格闘家系の体じゃないわね。あんまりじっくり観察したわけじゃないけど、格闘系に限らなくても、とにかく体を鍛えこんでる、ていう感じはしなかったわね。そんなに絶対的なパワーがあるタイプには見えなかったな。極悪チームなんでしょ?喧嘩はし慣れてるんだろうけど、多分、鍛えたのは路上の実戦で、ていうタイプ、腕力よりむしろナイフとか、すぐ武器に頼るタイプだと思うわ。」「そう。じゃ素直に見て、もしやりあったとしたら、どう、勝てそうな相手?」「うーん、まともに一対一、素手対素手でやり合えば、多分勝てると思うわ。だけど、多分ナイフかなんか持ってると思うわ。ナイフなんか出されたら、たとえ勝ててもこっちも無傷じゃ済まないかも知れないよ?」玲子はクスッと笑った。「そこは大丈夫。確かにナイフ対素手だったら、怪我するかも知れないわ。だけど、予め相手がそういう手合いだと分かっていれば、こっちも準備していけるわ。礼子も私も、武器は得意よね。素手で勝てる相手になら、武器を持ったら更にその差は広がるわ。こっちも準備して行けば大丈夫よ!」
礼子たちの見立ては正確だった。坊野たちは確かに極悪チームで有名だし、喧嘩は日常茶飯事だ。だが、彼等が極悪チームと言われる所以は喧嘩の強さそれ自体ではない。むしろ、そのやり口に負うところが大きい。彼等は一言で言って、汚い喧嘩専門だ。一対多数、素手対武器有、といった汚い手を専門としており、得意技は闇討ち、騙まし討ちである。坊野にしろ検見川にしろ、堂々とタイマン張ったことなど、殆どない。タイマンを申し込まれても受けずに逃げ回り、不意討ち、闇討ちで相手を潰すのが常套手段だった。玲子はそれを逆手に取ろうと考えていた。正面から行けば、今度の誘いに敢えて乗ってやれば、向こうは私たちのこと、女の子、と油断してくるはず。チームの他のメンバーを連れてくることはないんじゃないかしら。そうしたら四対四、実質、一対一の勝負に持ち込める。一対一の勝負であれば、なんとかなるんじゃないかしら。そして向こうが襲ってきたところを返り討ちにすれば、後は警察に引き渡せるわ。レイプ未遂、ということで連中をまとめて少年院送りにできる。たとえ勝っても、リターンマッチ代わりに付け狙われたんじゃ、勝ったことにならないものね。一気にカタをつけるには、どうしても連中を少年院送りにしなくちゃならないけど、向こうの誘いに乗ってやっての返り討ちなら、正当防衛と警察に引き渡す理由と、両方一気に条件クリアよ!いくら礼子たちが強い、と言っても流石に女の子の限界はある。肉体、パワーの壁は如何ともし難いものがある。礼子たちをもってしても本格的に鍛えこんだ、たとえば極真の有段者クラスと正面からぶつかっては勝ち目は薄い。そして礼子たちにとって、最もやりにくい相手は鍛え上げ、パワーに溢れたゴリラタイプだ。そういったパワーファイターであれば、極端な話、全く格闘技経験がなくても十二分に脅威だ。例えばラグビーのフォワードやアメラグのラインをやっている連中にフルパワーのタックルだけ、電車道のように往復されれば本当に対処に困ってしまう。だが、幸い坊野たちはそうではない。汚い手が得意、という相手には、こっちも準備さえしっかりしていけば、対応法はいくらでもあるわ。玲子の決断は明快だった。
「礼子、危険はあるけど仕方ないわ。忠告だけして、後は自己責任よ、て言って放っとく考えもあるけど、みすみす富美ちゃんをレイプさせるわけにはいかないわ。そうでしょ?だったら手は一つ、逃げられないなら前に出て、あいつらを叩き潰すしかないわ。向こうは油断してる。一気に向こうのトップ四人を潰して、少年院送りにしちゃえば私たちの勝ちよ。どう、やる?」「そうね。・・・富美ちゃんを見捨てるわけにはいかないわ。玲子、やろう!」礼子の美しい瞳の奥に、青白い炎が燃え上がった。そして礼子たちは朝子にも十分な説明をし、手を貸してくれるよう頼んだ。「うん、分かった。いいよ、富美ちゃんが危ないんじゃ仕方ないよね。私もやるよ!」朝子も腹をくくった。
慎治に待ちに待った連絡が来たのは金曜だった。「オウ、慎治か!?俺だ、検見川だ。例の件な、あさっての日曜にやるぜ!でな、俺たちは寛大だから、特別サービスをつけてやるよ。」「え、さ、サービスって、な、何ですか?」電話の向こうで検見川の笑い声が聞こえる。「オウ、おまえら、富美代たちに恨みがあるんだろ?だったらよ、やつらが輪姦されるとこ、ライブで見たくねーか?」「え、み、見せて貰えるんですか!?」「オウ、俺たちがいつも使ってるアジトに夕方連れ込むからよ、そこの二階からなら、たっぷりと特等席でショーを拝めるぜ。なんなら、俺たちの後でおまえらも姦らせてやろうか?」ひ、そ、そんな!僕たちが関わってるなんてバレタら、間違いなく礼子さんに殺される!「い、いえ、そ、それだけは・・・」「・・・あんだ?度胸のねー奴だな、ったく。ま、いいや、姦りたくねーんなら、好きにしな。で、どうするよ、ショーは見るか?」これには一も二もない。「お、お願いします!ぜ、ぜひ、ぜひお願いします!」慎治たちにとっても、眠れぬ夜のカウントダウンが開始された。そしてドライブの日がきた。集合場所に集まった四人、坊野、検見川、奈良村、須崎の四人は一見、別に普通の高校生と区別はつかない。茶髪でストリート系のファッションだが、実態の凶悪さを感じさせる出で立ちではない。そして三々五々礼子たちが現れた。礼子たちは警戒心を持たせぬよう、一見、普通に振舞っていたがどこか、緊張感を漂わせている。礼子はベージュのレザージャケットに焦茶色のスエードっぽいフェイクレザーパンツ、それに同じく茶色のショートブーツを合わせていた。玲子は黒いレザージャケットに細身のデザイナージーンズ、そして脚の細さを強調するかのように、ジーンズの上に黒いロングブーツを履いている。そして朝子は白いブラウスの上に明るい茶色のレザーベストと同系色のレザースカート、そして白いウエスタンブーツを履いてきた。三人三様、だが奇妙な共通点があった。三人ともブーツを履いているが、ハイヒールではなく、極めて動きやすそうなタイプであること、そしてベルト、がっちりした、如何にも硬そうなバックルのついた革ベルトを締めていることだった。
そして最後に今日の主役、富美代が現れた。「あーっ何、富美ちゃん、随分可愛く極めてきたわね!」礼子が呆れたような声をあげた。富美代は白いブラウスの上に赤いベスト、そして赤をベースにしたタータンチェックのスカート、そして一体どこで探したのか、真っ赤な膝下まであるロングブーツを履いていた。ワインカラーのような落ち着いた色ではない、トマト色、とでも言ったらいいだろうか、極めて明るいイタリアンレッドのブーツ、そしてそのヒールは7センチの高さは良いとして、極めて細いメタルピンヒールだった。鮮烈な赤にメタルの銀色が絶妙のアクセントになっている。「全く、一体どこで買ったの、そんなブーツ、初めて見たわ!」「えへへ、検見川先輩、赤が大好きだ、て言ってたからさ、思わず買っちゃったの!どう、似合う?」「・・・うん、確かに似合うけど・・・」確かにそのブーツは富美代にとてもよく似合っている、だが礼子の心配は別のところにあった。「でも凄いピンヒールね。それ、歩きにくくない?」大丈夫?今日は多分、大立ち回りが控えているのよ?「うん、それがね、このブーツ、意外と歩きやすいんだ。ヒールが上手く重心の位置にあるせいかしらね、ちょっと位なら走っても大丈夫なほどよ!」ふーん・・・まあ、それならいいんだけどね・・・礼子たちは些か不安げに視線を交わした。ドライブは比較的穏やかに進んだ。四人を乗せた二台のチェロキーはアクアラインを通って木更津に渡り、そこから湾岸を一周するようにしてお台場に向かって快適なドライブを続けた。そして日が傾きだしたころ、お約束のレインボーブリッジを渡っていた。ここまでならどうということはない普通のドライブ、礼子たちも些か拍子抜けするほどだった。だがブリッジを渡りながら、検見川が口を開いた。「今日は楽しかったね。富美ちゃんたちとこんなドライブできて、最高だったよ、また誘わせてよ?」富美代は白い頬を赤く上気させながら答えた。「もちろん!私も先輩とドライブできで最高です!ほんと、絶対、絶対また誘って下さいね!」OKOK,誘ってやるともさ、言われなくてもな。嫌だと言っても誘ってやるよ・・「じゃあさ、最後に俺たちのガレージ覗かせてあげるよ!この車、結構いじってあるだろ?これ全部、自分たちでやったんだぜ。でさ、マンションの駐車場は狭いんでガレージ借りたんだ。そこ、見せてあげるよ。俺たちの城だからさ、滅多に人、連れてかないんだぜ?富美ちゃんたちだけ、特別に招待するよ!」
憧れていた検見川先輩が、私を特別に招待してくれる!富美代は天にも昇る気持ちだった。「わー、嬉しい!見せて見せて、先輩のガレージ、連れてって下さい!ね、礼子、もち行くよね!」「・・・うん、喜んで!」はしゃぐ富美代と対照的に礼子はどこかヒリヒリと引き締まった表情になってきた。・・・ガレージね・・・無意識の内に、礼子は両手首をほぐし始めていた。精神の戦闘準備スイッチが入る。いよいよね。背筋を何匹もの虫が這いまわる。自分の目が吊り上っていくのを感じる。礼子にしては珍しく緊張したせいか、ブーツの中で足がじっとりと汗ばむのを感じる。怖い?不快?いや、むしろ心地良い緊張だった。いつ来るかいつ来るか、今日一日、来い、来るなとアンビバレンツな感情に引き裂かれて来た自分が一点に集束していく快感だった。ジリッ・・・ジリッ・・・礼子の脳裏にふとゴングのイメージが走る。もうすぐ鳴るのね、ゴングが。大丈夫、もう十分に心の準備はできてる。いいわよ、いつでも準備OKよ!レインボーブリッジを渡ったチェロキーは直ぐに首都高を降り、芝浦の工場街に向かって行く。そしてある工場の前に止まるとシャッターを開け、中に入っていった。中はガランと広い。既にオーナーは倒産した廃工場だった。二台のチェロキーを中に止め、坊野、検見川、須崎、奈良村の四人は先に車から下りた。そして出口に一番近かった須崎が素早く、厳重に入口をロックした。四人は無言のまま、二台のチェロキーを取り囲むように立っている。暫く、沈黙の時間が流れた。
中にいるのは却って不利ね。このままじゃ思うように戦えないわ。「富美ちゃん、下りるわよ。」礼子に促され富美代も車から下りた。見ると玲子も朝子も既に下りている。冷たい空気が流れる。ついさっきまでの和やかムードはもうどこにもない。礼子たちの表情がどんどん険しくなっていく。「な、なに、みんな、どうしたの、怖い表情して・・・せ、先輩、ここ、なんなんですか?ガレージ?でも、ここ、違いますよね?何かの冗談、そう、冗談なんでしょ?私たちを脅かそうとして、冗談なんでしょ!?」検見川は黙ってラークを取り出すと、火をつけた。「・・・ねえ、先輩!お願い、何とか言ってくださいよ!」検見川はゆっくり富美代の方を振り向き、ゆっくりと近づいてきた。二メートルくらいの距離まで検見川が近づいてきた。「先輩!」富美代の声が祈りにも似た悲鳴に変わって工場に響いた。「アツッ!」検見川は持っていたタバコを指で弾くかのようにして富美代に投げつけた。思わず振り払ったタバコから飛んだ火の粉が富美代の顔をかすめる。「な、なにするんですか!せ、先輩、ま、まさか!?」「うぜーんだよ、いいかげん黙れ、このクソガキ!」さっきまでとはうって変わった検見川の怒声が響いた。その顔にはもう微笑はなく、凶悪な冷笑が浮かんでいた。「バカかおまえ?この俺が本気でお前のこと、気に入ったとでも思ってんのか?タコ!誰がおめーみてーなションベンくせーガキなんか、相手にするかよ!」「そ、そんな・・・せ、先輩、だ、騙したのね!!!」「騙した?人聞きの悪いこと言うんじゃねーよ。お前が勝手にのぼせ上がっただけだろうが、バーカ。今日一日遊んでやっただけでもよ、一生感謝してもらわなくちゃあわねーぜ?なあおい?」ゲヘヘ・・・クックックッ・・・ギャハハハハ・・・下品な声で笑っていた坊野たちが大きく頷きながら近づいてくる。「・・・たくだぜ、俺たちSNOW CRACKを一日中引きずりまわしやがってよ、俺たちゃおめーらのパシリじゃねーっつーの!」「たけ≠コ?俺たちの日当はよ?」「先輩だってよ、いいぜいいぜ、俺たち先輩がたっぷりと人生って奴を指導してやりましょ、体でよ!」下卑た言葉を吐き続ける坊野たちに対し、玲子が妙に冷静に尋ねた。「指導ね。で、こんなところに連れ込んで、私たちをどうするつもりなの?」「決まってるじゃね-か!」坊野が中指を突き立て、お決まりのファックポーズを取った。「てめーら全員、たっぷりと輪姦してやるぜ!?グフフフフ、ここにはビデオも用意してあるからよ、てめーらがよがり狂うとこをたっぷりと撮ってよ、裏ビデオに流してやるぜ!四人分まとめて売りゃ、結構いい値になるだろうぜ?」「オウヨ!でよ、俺たちが十分楽しんだらチームの下の連中にくれてやるぜ。良かったな、てめーら今日から一生、男には不自由しねーぜ!!!」「イヒッ、イヒッ、イヒヒヒヒッッッ!!!」「ヒャハッ、ヒャハハッヒャハハハハハッッッ!!!」二階の小部屋の窓から作業場を見下ろしながら、慎治たちは必死に笑いを噛み殺していた。声を出しちゃいけない、大声出しちゃ、礼子さんたちに気付かれる。だから大声あげて笑い、踊り回って喜びに浸りたいのを必死で抑えていた。「・・・ヒ、ヒヒッ、やった、やった!富美ちゃん、泣いてるよ!ぼ、僕を、僕を苛めたバチが当たったんだ!」「ブヒャヒャヒャヒャーッ!玲子さんも朝子も、もうすぐレイプされちゃうんだ!ざまーみろ!散々人のこと、苛めやがって!他人のことを鞭で叩いたりおしっこ飲ませたりできる女なんて、いつかはこういう目に会うんだーっ!」「ざまー見ろ!礼子さん、いつまで取り澄ましていられるかなー?もうすぐ、礼子さんも、礼子さんもグッチャングッチャンに姦られるんだよーん!!!」顔中に下卑た笑いを浮かべつつ、慎治たちは復讐の喜びに打ち震えていた。
いつ以来だろう、こんなに心の底から笑っているのは。慎治たちは入学後、間もなく礼子たちに苛められ始めていた。毎日毎日、女の子に苛められ、辱められる。いつしか笑顔などというものは忘れてしまっていた。ああ、笑う、ていうのはこういう感覚だったんだ。俺たち、笑うのは鞭を許して、もう苛めないで、て卑屈にお追従笑いを浮かべる時だけだったもんな。笑うって、こんなに楽しいことだったんだ。信次の脳裏を玲子たちに苛められた辛い記憶が走馬灯の様に横切る。引っ叩かれ、蹴られ、唾を吐き掛けられ、靴を舐めさせられ、オカマを掘られ・・・鞭で打たれ、おしっこを飲まされ・・・辛い記憶が次々と甦る。だが不思議といい気分だった。そりゃ当然だよな、だって、俺たちをこんな目に合わせた玲子たちが、これからその報いを受けるんだもんな。ヒッヒッヒ!泣け!喚け!もがき苦しめ!俺たちが味わった苦痛の万分の一でも味わえ!俺たちのこの世界に決定的に足りなかったものは・・・俺たちが心底求めていたものは・・・只一つ、玲子たちの泣き顔だけ・・・ああ、癒される。心の傷が癒えていく・・・お前たちも一緒に地獄に堕ちろーっ!復讐の快感は信次に何とも言えない無上の解放感を与えていた。ああ、最高だ・・・万歳、万歳、復讐万歳!余りのことに富美代は呆然としていた。富美代の頭の中を検見川たちの声が飛び廻る。中学生の頃の検見川の思い出が飛び廻る。今日の楽しい一日が飛び廻る。現実認識を失った富美代の両目から涙がツッと溢れた。「キャハハハハッ!泣いてやんの、このガキ、駄目だぜ、泣いたって許してなんかやらないよーん!」検見川の下卑た声と殆ど同時に、パーンと乾いた音が響いた。礼子が富美代の頬を思い切り平手打ちした音だった。「分かった?富美ちゃん、目、覚めた?」頬を走る痛みにより現実に引き戻された富美代の肩を礼子が激しく揺さぶる。「これが富美ちゃんの憧れていた先輩の正体よ。SNOW CRACK,最悪チームのサブ、女の子を騙して輪姦すのが専門、ていう最低男、それが検見川の正体なのよ!」頬の痛みと礼子の凛とした声が、富美代の意識を現実に引き戻していく。そうよ富美ちゃん、私たちの方に帰って来て!富美代の瞳に意識が戻ってきたのを見て、玲子も続けた。「分かる、富美ちゃん?あいつらはね、富美ちゃんをダシにして、私たちをレイプするために汚い罠を仕掛けたのよ。それでもいいの、富美ちゃん?こんな目にあわされて、黙って泣いている富美ちゃんなの!?まさか、このまま大人しく輪姦されるなんて気、あるわけないよね!?そんな富美ちゃんじゃないよね!?!?!?」
4
無理矢理現実に引き戻された富美代の意識は乾いていた。悲しみ、後悔にすすり泣いて自我を虚空の彼方に失った富美代はもうどこにもいない。乾ききり、ぽっかりと空虚になった富美代の精神を、虚無の暗黒の空間を、唯一つの感情、怒りが満たしていく。玲子の言葉は富美代の精神に満ち満ちたどす黒い感情に、富美代自身形容し難い、強いて言えば只一つの言葉に集約される感情、そう、怒りに炎を灯した。炎は見る見る内に大きく、激しく燃え上がった。ワナワナ・・・下を向いた富美代の肩が小刻みに震え始めた。「・・・先輩・・・ゆる・・・さない・・・」富美代の悲しみは怒りとなり、怒気は闘気となって急速に膨れ上がっていく。日頃クールな、冷たいとも評される富美代の怒り、それは真っ赤を通り越して更に熱気を増し青白い炎となって燃えさかっていく。何、この闘気、殆どオーラじゃない!?こんな闘気、見たことないわ!礼子たちでさえたじろぐほどの勢いで、富美代は闘気を全身から発散させている。俯いていた富美代がゆっくりと顔をあげた。ゾクッ・・・思わず礼子の背筋に寒気が走った。涙を流しながら、美しい顔全てに怒りと憎悪と闘気を満ち溢れさせた富美代の美貌、それは人間の表情ではなかった。それは、そう、夜叉、と呼ぶしかないものだった。
それが検見川には気に入らなかった。なんだ、このガキ、もっと泣き喚きやがれよ、でないと犯りがいがねーだろーがよ?検見川は内心、富美代の余りに凄まじい怒りの表情に半ば気圧されていた。今まで連れ込んだ女たちはみんな、ただ泣いて許しを乞うだけだった。怒りの富美代とクールな礼子たち、予想外の反応に戸惑いながらも、まだ検見川は何も分かっていなかった。あんだ、盛りあがんねーな、ったくよ。まあいいか、どうせ輪姦してやりゃ、嫌でも泣き喚くんだからよ。だからガキは困るんだよ。「何怒ってんだ、コラ?ゆるさねーだと?あ?そりゃこっちのセリフだっつーの、たく、ガキの分際で手焼かすんじゃねーよ。オラ、大人しく服脱げっつんだよ?!それとも、引っぺがしたろーか?」無造作に検見川は手を伸ばしてきた。パシーン!「ハッ!」「グアッ!」富美代は下から検見川の手を跳ね上げると、返す刀で鳩尾に思いっきり当身を叩き込んだ。不意をつかれた検見川は息が詰まり、思わずうずくまるようにして後ずさった。「ヒャハハッ!おいケミ、ダッセーッ!んなチビにやられるなんてよ、焼きがまわったかー?手、貸したろか?」検見川の失態を坊野が指差して大笑いした。検見川の頭に血がのぼる。「るせーよ!?ちと遊んだだけだろーが!おい、富美代、てめー、んなことしてどうなるか、分かってんだろーな、コラ!後悔すんじゃねーぞ?」呼吸を整えると検見川は両腕を広げ、飛び掛るように富美代に掴み掛かっていった。検見川はまさか、富美代が合気道を中心に護身術を本格的に学び、十分な戦闘能力を備えているとは想像もつかなかった。単に不用意に出した手を撥ね退けられ、たまさか何かの弾みでボディーに一発食らった、程度にしか考えていなかった。だから再び富美代に掴み掛かろうとしながらも、未だ十分な気構えは出来ていなかった。検見川は愚かにも、未だ本気の喧嘩ではなく、単なるレイプのオードブルとしか考えていなかった。その油断は全身あちこちに巨大な隙を作っていた。
一方、富美代は不思議な気分だった。怒っている。今までの人生で最高に怒っている。怒りで気も狂いそうなほどだ。だが同時に不思議な位冷静な自分を感じていた。首から下は身の置き場もないほど熱く燃え上がっているのに、頭だけは妙に冷静だった。富美代は検見川が迫るのを見ても、怖くもなんともなかった。許せない・・・私を騙した・・・先輩、私だけじゃない、何人も何人もこうやって騙してレイプしてきたのね・・・最低・・・激しい憎悪と強烈な嫌悪感、軽蔑が富美代の全身を貫く。余りの嫌悪に口の中に自然と唾が涌き出るのを感じた。迫る検見川にどう対応する?ファーストアタックの後の攻撃を有利に進めるために、一番有利な手段は何?コンマ何秒もない、この一瞬の間に富美代の頭はコンピューターのように素早く働いた。うん、これがいい。この攻撃、先輩には予想もつかないはずよ。検見川の手は富美代の間近に迫っていた。「オラッ!」検見川は左手で富美代の髪の毛を掴み、引き摺り回しながら右手で富美代の顔面を殴るつもりだった。女の子の顔面を殴ることに躊躇を覚えるような検見川ではない。だが無造作に伸ばした左手を富美代に下から掴まれ、富美代を引き摺り回すどころか逆に腕を伸ばした自らの勢いそのままに前方に姿勢を崩され、引き摺られていく。「アオッ!」態勢を立て直す余裕もなく、蛇のように絡みついた富美代の手に手首の関節を極められ、更に外側に捻り上げられた。検見川の手首、肘、肩の関節に電流が走る。靭帯が悲鳴を上げる。「アウチッ!」検見川は余りの痛さに思わず悲鳴を上げてしまった。検見川の意識の全てが左手に行き、自由な右手も無意味に宙をさまようだけ、全身無防備状態だ。腕を引き摺られて反射的に腰を屈めた検見川の、戸惑ったような顔が富美代の方を見上げる。富美代はそのタイミングを逃がさなかった。「ペッ!ペッ!」桜色をした富美代の美しい唇が急速に盛り上がり、白い矢のように大きな唾の塊を二発吐き出した。ビチャッペチッ!「アウワッ!」宙を切り裂いた唾は狙い過たず、検見川の両目に見事に命中する。礼子たち四人の中でも富美代はこと、唾に関しては間違いなくNO.1のテクニックを誇っている。射程距離は優に2メートルを超え、更に狙った的にピンポイントで命中させる見事なコントロールと、唾を細かい水滴に分散させず、大きな塊のまま飛ばせる巧みなテクニックを併せ持っている。実戦の最中とは言え検見川との距離は今、1メートル程度に過ぎない。富美代にとっては唾を完璧にコントロールして吐き掛けるのに、何の造作もない間合いだ。左手の痛みに目を大きく見開いていた検見川は視界を完全に富美代の唾に塞がれてしまう。唾の大部分はゆっくりと両目から溢れ出し、頬を伝って流れていくが検見川の視界は泡の多い富美代の唾に白く曇り、霞のかかったような状態になる。屈辱を与え、挑発して頭に血を上らせると同時に視界を奪い、戦闘能力を半減させる。嫌らしい位に合理的な富美代の攻撃だった。唾をも武器として使う、流石に唾吐き名人の富美代らしい創造力に溢れた攻撃だった。精神と肉体と、富美代の唾攻撃は予想以上の、見事な効果を発揮した。
思わぬ、想像もしなかった方法での反撃に検見川は思いっきりたじろいでしまったが次の瞬間、激しい怒りに完全に飲み込まれてしまった。「て、てめえ・・・よ、よくもやりやがったなーっっっ!!!」唾を、女の子に唾を吐き掛けられた、ということに漸く気づいた検見川は凄まじい声で絶叫すると同時に手を捻られた痛みをも忘れ、動きを封じる富美代の腕を力任せに振り払おうとした。愚かな選択だ、唾を吐き掛ける、という富美代の挑発にまんまと乗り、検見川は完全に自分を見失っていた。ビチッ、という破滅的な音を肘が発したのにも気づかない。完全に極められた腕を力任せに振り払ったおかげで検見川の左肘の靭帯は完全に伸び、使い物にならなくなってしまった。ふん、馬鹿な先輩、自分で肘壊しちゃって。ま、いいわ。いずれにせよこの左腕、もう用済みね。富美代は冷静に判断して不要になった検見川の左手を解放し、一旦間合いを取る。左腕を代償としながらも、漸く自由を取り戻した検見川は思いっきり体を後ろに捻り、力任せに右ストレートを繰り出した。視界を塞ぐ唾を拭うのも忘れて大振りな、雑なこと極まりないパンチを。全力でのパンチだ、確かに威力はあるだろう。だがそれは当たれば、の話だ。大振りで簡単に起動が読める上に、唾が目に入り、視界が霞んでターゲットの富美代の姿がぼんやりとしか見えない状態では狙いもいい加減極まりない。富美代は余裕でそのパンチを見切っていた。相手に余裕を持たれる。実戦での必敗パターンだ。富美代は殴りかかる検見川の右手を左手で払いながら右手で肘を掴み、体を捻って勢いを受け流す。「アオッ・・・」唾越しにぼんやり見える富美代の姿が回転すると同時に、ターゲットを失った自らの必殺パンチに引きずられ、検見川はたたらを踏む。そして富美代は検見川を引き摺り回しながら完全に腕を極め、更にその腕を引き込み、自分の背中越しに物の見事に検見川の体を宙に舞わせた。検見川の、ぼんやりと唾に霞んだ視界が急速に回転し、天地が逆転する。教科書のような見事な投げが決まる。だが、そこからが教科書とは違った。道場では相手が怪我しないように、更に相手を回転させて背中から落とす。だが富美代は検見川の体が宙を舞っている、まさにその時に膝を折り、両手の動きを連動させて真下に引きずり落とした。「ガアッ!!」受身の取りようがない。検見川はまともに脳天から、まっさかさまにコンクリートの床に叩きつけられた。頭蓋骨や首はかろうじて折れなかった。だがまともに頭を強打し、意識が掠れる。完全に無防備状態となった検見川に富美代は冷静にとどめを刺した。腕を極めたまま、大の字になってピクピク痙攣している検見川の首、耳の下辺りに再び強烈な当身をめり込ませ、完全に失神させた。
富美代が検見川を打ちのめしているのとほぼタイミングを同じくして、朝子は須崎と対峙していた。須崎はSNOW CRACKではNO.4だが、身長は180センチを超え、四人の中では最も長身だった。一方、朝子は156センチしかない。身長差は30センチ近い。向き合いながら須崎は余裕綽綽だった。喧嘩の際、長身の須崎は基本的に相手を見下ろして戦うことが多い。朝子は自分より遥かに小さい上に、なんと言っても女だ。喧嘩にもなりはしない。ま、多少は抵抗するかもしれないけど、二、三発引っ叩けば大人しくなるわな。どうやって朝子を倒すか、なんて全く考えてすらいない。後のレイプのことだけを考えていた。今日は獲物が四人もいるんだからな。たっぷり楽しめるぜ・・・須崎は朝子が抵抗するとは、想像すらしていなかった。ましてや、自分が身長の低い相手を得意とするのと同様、朝子にとってはむしろ自分より長身の相手とのファイトの方が慣れていて手が合う、等とは想像もつかなかった。油断しきっていた須崎は、小首を傾げ、キョトンと大きな瞳で無表情に自分を見つめる朝子を、いつも自分がレイプしてきた女の子と同じくショックに動転して半失神状態なんだろう、と気軽に考えていた。玲子はチラリと自分の横にいる朝子の、この無表情を見てフッと安心したような微笑を一瞬浮かべた。いいわ、朝子、落ち着いてるみたいじゃない。あの無表情が朝子の上手いところなのよね、何考えてるのかこっちは読めなくて、実はこの子、何にも考えてない、思考停止状態じゃないの、なんてつい油断しちゃうのよね。実際にはあの子、冷静にこっちをじっくり観察してカウンターを狙ってるんだけどね。フフ、須崎さん分かるかしら?油断して迂闊に近づくと、朝子の思う壷よ、朝子、後の先の名人なんだからね。まさに玲子の読み通り、須崎は既に朝子の術中に嵌っていた。朝子が無表情の裏側で虎視眈々と須崎の隙を、懐に飛び込むタイミングを図っているなど、全く気づかなかった。「おらチビ、ぼけっとしてねーでさっさと脱ぎな!後がつかえてるんだからよ!」無造作に須崎が両腕を伸ばし、朝子の肩を掴もうとした瞬間、朝子の瞳にキラッと電光が走った。
「ハッ!」裂帛の気合と共に朝子がダンッと鋭く踏み込む。須崎があっと思う間もなく一瞬で間合いを詰めた朝子は左足をグッと踏み込みながら右足で思いっきり地面を蹴る。蹴り足の勢いに腰の回転そして肩の回転を加え、猛スピードに加速された右肘をがら空きの須崎の鳩尾に、アッパーカット気味に突き上げながら思いっきり叩き込んだ。鋭い踏み込みに一瞬、40キロ前半の朝子の体重が大幅に加算されて80キロ台に増幅される。グシャッ・・・うん!手応えバッチリ!内臓に肘がめり込む感触が朝子を興奮させる。猿臂でのフルコンタクトなんて、危険すぎて普段は使えないもんね、一回思いっきりやってみたかったんだ!「カッ・・・ガファッッッッ!!!」内臓が破裂したかのような激痛に須崎は呼吸を失い、口をパクパクさせながら体をくの字に折り、腹を押さえながら真後ろによろけて行く。チャンス!逃がさないわよ!朝子は両腕を上げ、油断なくガードを固めながら追撃する。須崎の顔面はがら空きだ。今打てば入りそうね。だが朝子は慎重だった。直線的に追わず、左右に小刻みに体を揺らしながら軽やかなステップで追い詰める。そして、まだ後退を止められない須崎の右足が上がり、全体重が左足にかかった瞬間を狙って、朝子は得意のローキックを放った。「ハッ!ハイッ!」須崎の腿、膝の外側に朝子の純白のウエスタンブーツが襲い掛かる。「グアダッ!」新たな痛みに須崎は思わずその場に立ち止まり、左足を両手で押さえる。そんな隙を見逃す朝子ではない。隙あり!「エイッ!」須崎を蹴り付けた右脚を繰り戻すと同時に更に追い詰め、動きの止まった須崎の眼前で今度は朝子の左脚が上がる。ぐっ、顔を蹴られるか・・・本能的に須崎は両手を上げ、必死で顔面をガードする。だが朝子がそんな単純な攻めをする訳がない。猫が鼠を弄ぶように、朝子は焦らず、じっくりと須崎にダメージを与え、戦闘能力を奪うつもりだった。焦って止めを刺しに行く、などという不用意をする訳がない。馬鹿ね、須崎さん、あなたたち大柄な人の弱点は足とボディ、身体の下側にあるのよ、知らなかった?須崎のガードが上がりかけるのを嘲笑うように、朝子の左回し蹴りは須崎の左膝を、今度は内側から襲った。「アダッ!」外側に続き、内側からも痛めつけられて須崎の左足全体に耐え難い痛みが走る。こうなるとなまじ大柄でウエイトがある分、却って足にかかる負担は大きい。ヨタヨタとバランスを崩しながら後退した須崎は左足の痛みに耐えかね、思わず全体重を右足にかけ、殆ど片足立ちになりながら左足の腿、膝を押えてしまった。致命的なミスだった。須崎とて十二分に喧嘩慣れしている身、普段だったらこの程度のダメージでひるみはしない。だが相手は女の子、しかもチビのやせっぽち、と完全に油断していた分、心の準備が出来ていなかった。その油断の分、肉体的以上に精神的な動揺が大きく、朝子の、今自分が喧嘩している相手の目の前で片足立ちになり、動けない状態になってその上に両手で足を押えてしまう等という、絶対にやってはいけないミスを犯してしまった。
その隙を冷静な朝子が見逃すわけがない。朝子の右脚が上がる。狙いは・・・須崎の右足だ。今、痛めつけた左足を更に狙うのは素人、全体重が掛かり、動かせない右足を狙うのがプロの選択だ。朝子は一瞬の躊躇もなく、全力で右の前蹴りを放つ。ガッ・・・純白のウエスタンブーツの硬いヒールが自らの体重に固定され、逃げ場のない須崎の右膝に食い込む。やった!手応え十分!私、ローキックは自信あるのよね。それに今日は硬いブーツを履いてるんだし、ヒールで直撃すればローでも十分に一撃必殺になる、と思ったけど、ビンゴね!流石は玲子ね、今日はヒールの硬い、このウエスタンブーツ履いてくるのよ、このブーツが朝子の武器になるんだからね、て言われてたけど、ほんと、玲子の読み通りね。須崎さん、このブーツが凶器だなんて、考え付きもしなかったでしょ?狙い通りだった、只でさえ威力十分な朝子のローキックだ。それに硬いウエスタンブーツのヒールがプラスされれば、これは最早凶器に匹敵する。「ギアアアアッ!!!」膝の皿にヒビでも入ったのか、余りの激痛に須崎は悲鳴を上げながらその場にうずくまってしまった。「あ、あああ・・・!」声にならない悲鳴をあげながら、須崎は片膝をつき、砕かれた右膝を両手で抱え込んだ。だが朝子の時間はここからだ。
5
「OK,行くよ!」朝子は初めて、動きを止めて須崎の正面に立つ。痛みに喘ぎながら須崎は必死で顔を上げる。ついさっきまでは見下ろしていた朝子の顔が、今は自分より遥か上にある。そして無表情だった顔には今や余裕と優越感が満ち溢れ、勝利を確信した残酷な微笑が浮かんでいた。「や、やめ・・グハアッ!!!」須崎が哀願すらできない内に、朝子の鋭い蹴りが襲い掛かる。右の回し蹴り、必死で手を上げガードするが、空中で一旦停止した朝子の右脚はそのまま宙で回転し、下から爪先で須崎の左肘を蹴り上げる。「イダッ!」肘から電流を流されたような、痺れと熱感を伴った痛みが須崎の全身を走る。ブーツの硬い爪先でのトーキックは須崎の腕に激痛を刻み込み、無慈悲にガードを吹き飛ばしてしまった。やった!やっぱブーツ履いてるから、トーキックもOKね!トーキック、これも普段は絶対に使わない技だ。危険、というだけではない。貫手やトーキックのような禁じ手は、いくら威力抜群の危険な技とは言え自らの拳や足を鍛えるのに相当な苦痛と時間がかかる。美貌を誇る朝子にとって、そんな血の出るような努力をしてマニキュアやペディキュアさえできない拳や足を作る気は毛頭なかった。だが今はブーツを履き、硬いトーに自らの柔らかい爪先が守られている。遠慮なく、自らの足を痛める心配なく、心置きなく思いっきり、トーキックを放てた。朝子はブーツを履いているメリットを嫌らしい位、最大限に活用していた。そして一方の須崎の肘は薄いジャケットを着ただけだ。猛スピードで蹴り上げられるウエスタンブーツの爪先に対抗できる訳がない。須崎の左腕は上空に蹴り上げられ、同時にバランスを崩して右のガードも下がってしまう。そして無防備になった顔面に、遂に朝子の蹴りが襲い掛かった。左の回し蹴りが須崎の右頬を捉える。「ゲハッ、ゲフアッッ!」朝子の左脚は八の字を描き、返す刀で須崎の左頬を踵で蹴りつける。ブーツでの往復ビンタに須崎は口からだらしなく涎をたなびかせながら顔を左右に弄ばれる。「いい顔ジャン!ほら行くよ!」そして左脚を引き寄せた朝子は須崎の鼻めがけ、ストレートに前蹴りを繰り出す。朝子の美しい脚線がスッと延びきった瞬間、ヒールにグシャッと気持ちいい感触が走った。「ブギューャァッッッ!!!」鼻を砕かれ、須崎は床をのた打ち回った。うん、やった!最高の感触に朝子は勝利を確信した。だが流石、と言うべきだろうか。暫くのた打ち回っていた須崎がよろよろと立ち上がってきたのだ。「こ、このグァクィャア゛——・・・ぶ、ぶっくぉるぉじでやる・・・」須崎は猛烈に怒っていた。自分にほんの一瞬でこれだけの大ダメージを与えた朝子に。そして油断しきって見事にしてやられた自分自身に。こ、こんなガキに、年下の、しかもチビの女に、やられてたまるか・・・その怒りが須崎の全身に大量のアドレナリンを駆け巡らせていた。右膝、左肘にはヒビが入り、鼻は見事に潰れていた。普通だったら動ける状態ではない。だが極度の興奮が須崎の全身を突き動かしていた。「こ、殺す・・・ぶっ殺してやる・・・」須崎はよろよろと朝子に近づいてくる。いくら興奮により動いている、とはいっても膝にヒビが入っているのだ。そう素早くは動けないし、左手も使えないようだ。完全にKOした、と思った須崎が立ち上がったのを見て一瞬驚いた朝子だったが、須崎がふらついているのを見て直ぐに余裕を取り戻した。なーんだ、やっぱり効いてるじゃん。まあ、しゃーないわね。止めを刺してあげる。
「あーあ、立っちゃって、あんまり無理しない方がいいんじゃない?鼻、きっと折れてるよ?」小首を傾げながらにっこり微笑む朝子の笑顔が、須崎の怒りに更に火を注ぐ。こ、こん畜生!余裕こいてんじゃねえ!!!「ぶ、ブッグォルォズ!!!」全力で須崎は殴りかかった。渾身の右ストレート、女の子の顔面めがけて殴りかかることに何の躊躇もない。だが右足に大ダメージを与えたから蹴りは使えない、更に左手も砕いてある、となればあるのは右のパンチだけ、と朝子は自信を持って読みきっていた。そして須崎のパンチは正に、読みどおりだった。ブーン、それなりのスピードを持ったパンチが迫る。まともに当たれば朝子はひとたまりもない。だが当たれば、の話だ。一歩踏み込んだ朝子は左手を須崎の内側から振り上げて須崎の右手首のあたりに当て、捻りながら左手、更に全身をねじりこんで須崎の起死回生のパンチをいともた易く、受け流していく。そして受け流しながら、朝子が沈み込んでいく。須崎のパンチが沈み込んだ朝子の頭の上を通過していく。朝子の左手は今や須崎の右の二の腕あたりを握り、前方に引き込んでいる。朝子の上体が地面とほぼ平行になる。な、なんだ、何をする気なんだ?次の瞬間、真下から白い影が猛スピードで迫ってきた、と思うと同時に須崎の顎に物凄い衝撃が走った。ガヅッ!!!須崎は声も出せずに首を跳ね上げられ、仰け反りながら昏倒してしまった。朝子は体を倒し、低い位置から180度開脚した右脚を突き上げ、須崎の顎を蹴り上げていたのだ。中国拳法で言う、天空脚に似た技だった。小柄な体を生かして相手の懐に潜り込み、柔軟性を生かして真下から蹴り上げる。両腕で相手を引きずり込んでいるため、相手にとっては朝子の脚は死角になり、見えない。その死角から腕の三倍の力を持つ脚がアッパーカットで襲い掛かるのだ。ましてや硬いブーツのヒールが直撃するのだ、その威力は筆舌に尽くしがたい。須崎は物も言えず、白目を剥いて昏倒してしまった。首が折れなかったのが不思議な位の、凄まじい威力の蹴りだった。
「ケミ!」「須崎!」坊野と奈良村の声が同時に響いた。う、嘘だろ・・・坊野は目の前の光景が信じられなかった。極悪チームとして名を馳せたSNOW CRACK、そのNO2とNO4が一瞬にしてKOされてしまったのだ。しかも相手は自分たちがレイプしようと誘い込んだ相手・・・年下の女の子にだ。俺はラリってるのか?だが検見川と須崎が大の字になって気絶しているこの光景は、紛れもない現実だった。く、糞っ垂れが・・・坊野と奈良村が反射的に富美代たちに襲い掛かろうとした、その時だった。「待ちなさい!」礼子の凛とした声が響いた。「相手が違うわよ。貴方たちの相手は私たちがしてあげる!」フフ、礼子の端正な顔に凄絶な微笑が浮かんだ。「貴方たちも二人、私と玲子も二人、そう、タイマン、てやつ?二対一で苛める、なんてことはしないであげるから、安心してかかって来なさい!」た、タイマン?苛めないでやる?こ、このガキ、舐めやがって!!!坊野は全身の血液が逆流するのを感じた。その時に坊野が頼ったのは自分自身の肉体ではない。武器だった。坊野は何の躊躇いもなく、自分のチェロキーから自らの獲物、金属バットを取り出し、身構えた。最早相手が女の子だろうが、丸腰だろうが関係ない。獲物を使って叩きのめすつもりだった。同時に奈良村も隠し持ったナイフを取り出し、礼子たちを威嚇するように身構えた。だが礼子たちはバットにナイフ、坊野たちが取り出した獲物を見て、彼らの期待に反して大笑いを返してきた。「アハハ!なーんだ、そんなモンしか持ってないんだ!」玲子の嘲るような笑い声は坊野たちを怒らせる、と言うより戸惑わせた。「て、てめえ!こ、このナイフが見えねーのか!ザックリ逝ったろか!」反射的に安っぽい言葉で凄む奈良村に玲子は最早、苦笑を浮べていた。「・・・ハイハイ、私、視力は良いからね、それがナイフだ、てこと位、良く分かるわよ・・・で、私たちの武器が何かは分かってるの?」言いながら玲子はバックルを外し、自らのジーンズからシュルッと黒いベルトを抜き取った。傍らでは礼子もフェイクレザーパンツから茶色いベルトを抜き取っていた。パーン!礼子が二つ折りにしたベルトを鳴らした。「うーん、折角この私たちが相手してあげるって言うんだから、もうちょっと凝った武器出して欲しかったけどね。そんなチープな武器なんかを、まあ得意げに出しちゃって、恥ずかしくない?まあいいわ、貴方たちじゃ所詮、その程度が限界かしらね。さあ、かかって来なさい!」右手にベルトを握り、左手の人差し指でクイクイと挑発する礼子の姿に、坊野たちの頭に血がのぼる。な、何だ、このガキ!か、かかって来なさい、だ?な、舐めやがって!!!坊野も奈良村も、自分たちが切り札のつもりで出した獲物に礼子たちが全くビビらず、却って余裕を見せていることに完全に逆上してしまった。その余裕の根拠は何か?と考える余裕等、全くなかった。礼子たちにとって、坊野と奈良村が取り出した獲物は全く脅威にならなかった。実のところ、礼子たちにとっての心配材料は唯一つ、坊野たちが拳銃を持っている事だけだった。確率は低い。恐らく殆どゼロに近い確率だ。だが、もし持っていたら・・・それに対する備えも一応していたが、それだけが心配だった。だからナイフやバットなどというものは礼子たちにとって、なんの脅威でもない。逆に坊野たちは礼子たちのベルトを余りに過小評価していた。そもそもベルトを武器としてすら認識していなかった。しなやかで強靭な革ベルトが、礼子たちのような熟練者にかかればどれ程強力な武器になるか、身を持って味わうまでは全く想像もつかなかった。
先に動いたのは奈良村だった。「こ、このガキ・・・ベルトが武器だー?てめえは女王様ごっこでもやってんのか、こら!?」右手にナイフを握り、奈良村が間合いを詰めた瞬間、パシーン、痛っ!カラーン、礼子のベルトが一閃し、奈良村の右手を打ち据える音と右手をしたたかに打ち据えられた奈良村の悲鳴、そしてナイフが床に転がる乾いた音が殆ど同時に響いた。打ち落とされたナイフはカラカラと玲子の足元に転がっていった。な、なんだ、何が起こったんだ?玲子が殆どスナップのみで放ったベルト鞭は予備動作が極端に小さく、その癖非常なスピードを兼ね備えていた。奈良村は自分がベルトで鞭打たれた、ということすら、一瞬把握できなかった。ベルトを握った玲子の右手がふっと動いたと思った瞬間、自分の右手に熱を伴った衝撃、今まで全く味わったことのない痛みが走り、頼みの綱のナイフを叩き落していた。玲子のベルトの動きを奈良村のプアな動体視力で捕らえることは到底不可能だった。右手を抑え、思わず呆然とする奈良村に玲子の嘲笑が追い討ちをかける。「アハハ、どうしたのかしら坊や、鞭一発でもうお終いなの?そんなんじゃ、私をレイプするなんて到底無理ね。あ、そうか、鞭一発だけでイタイイタイ、て泣いてる坊やなんか、どうせ根性なしのタマ無しクンだもんね、私をレイプするなんて、端からできっこない見栄っ張りだったのよね。やーいやーい、タマ無し、タマ無し!!!」「て、てめえ!!!な、なめ、舐めんじゃねえー!!!」珍妙なリズムを付けて囃したてる玲子の挑発にすっかり頭に血が上った奈良村は、今にも玲子に飛びかかろうとしていた。だが、辛うじて奈良村の理性を保たせたのは、皮肉なことに自分が落としたナイフだった。奈良村のナイフを玲子はしっかりと黒いブーツで踏みしめ、奈良村が拾えないようにしていた。く、クソ・・・ナイフ、ナイフさえあれば、今度こそぶっ刺してやる・・・なんとか、なんとかナイフを取り戻したい。
一方ナイフを拾いたいのは玲子も同じだった。見たところ奈良村のナイフは軽く、投げナイフとして使えそうだった。間合いを詰めてスナップショットで投げたら、まずは避けられる心配はないわね。だけど・・・玲子は冷静に奈良村との間合いを図った。この間合いじゃ、迂闊にしゃがんだらタックルで突っ込まれる危険があるわね。しゃがんだときに突っ込まれたら、避けられないかも知れないな。玲子は次の一手を慎重に考え、推し量るように奈良村の目を見た。その視線は玲子の方を向いているように見えるが、半分以上はナイフに視線も意識も行っている。ふーん、そんなにナイフに執着するんだ。よし、いいわ。このナイフ、何も私が無理して直接拾う必要はないわね。この手で行こう!奈良村の行動を読みきった玲子は、更に大胆な挑発に出た。「なーに、タマ無しクン?そんなにこの安物ナイフを返して欲しいの?」グリグリとブーツの靴底でナイフを踏み躙りながら玲子が嘲る。「いいわよ、こんな安物、返してあげる。おまけに、お姉さんの唾もつけてあげましょうねー!」玲子は二、三度唇をクチュクチュと動かし、たっぷりと唾を貯めるとブーツをどけ、ナイフの柄にぺっと唾を吐き掛けた。ビチャッと唾がナイフの柄を覆う。「ほーら、お姉さんの唾つきナイフよ、よかったわねー、返して貰えて!」嘲笑りながら玲子はナイフを奈良村の足元に蹴ってよこした。「ぐ、こ、この野郎・・・」奈良村は一瞬躊躇した。唾まみれのナイフ。普段だったら触りたくもない。だが今は・・・悠長に拭いている暇などないことは一目瞭然だ。半ば目をつぶる思いで奈良村はナイフを拾い上げた。ヌルッ・・・右手に玲子の唾の感触が走る。き、汚たねえ、こんな汚たねえもん、触らせやがって!!!「あーら、おっどろいたー!唾掛けられたナイフも拾っちゃうんだー!さっいてー!やっぱ、タマ無しクンは違うわねーえ!ほーらタマ無しクン、そんなに唾が好きだったら、こっちにお顔出してごらん、お姉さんが唾ペッペしてあげるわよーっ!」唇を突き出して白い唾を浮かべ、ここぞとばかりに挑発する玲子に奈良村の僅かな理性は完全に消し飛んでしまった。「て、て、てめえーっっ!こ、殺す、ぶっ殺す、カンペキに殺す!!!」絶叫しながら奈良村は玲子の唾にまみれたナイフを振りかざして襲い掛かった。最早戦術も何もない。闇雲に、ただ力任せにナイフを振り回しながら玲子の顔めがけて切りつけた。愚の骨頂だ。ナイフは日本刀ではない。ナイフの戦闘法はあくまで、刺すのが基本だ。切るのは誉められた使い方ではない。大型のブッシュナイフならともかく、刃渡りが短いジャックナイフでは切りつけようとしたらリーチの短さから、威力半減だ。しかも大振りに大上段から振り下ろしたのでは隙だらけ、玲子のベルトに絶好の標的を提供するだけだった。
フン、かかったわね。馬鹿ね、私がわざわざナイフに唾吐いた理由を考えようともしないなんてね。そんな低脳じゃ、私とやりあうには100億万年と3日は早いわよ!玲子は冷静に奈良村の袈裟懸けの第一撃、バックハンドの第二撃を避けながら完全に間合いとスピードを見切った。そして再び大きく振りかぶった第三撃、奈良村がナイフを振り下ろすと同時に玲子はすっとステップバックした。同時に玲子のベルトが唸る。パシーンッ!今度は下から振り上げた玲子のベルトはまたも見事に、奈良村の右手を打ち据えた。「ッアツ!」いくら固くナイフを握っていても、ベルトで打たれた激痛にはかなわない。しかも奈良村のナイフの柄は玲子の唾まみれだ。まだ濡れている柄はいつもより遥かに滑りやすい。おまけに唾に触る嫌悪感から、半ば無意識に近いが奈良村はナイフのグリップがかなり甘くなっていた。これでは一溜まりもない。右手こそそのまま余勢で振り下ろしたものの、頼みの綱のナイフはいとも簡単に玲子のベルトに弾き出されて跳ね上げられ、クルクルと回転しながら宙を舞った。「ほら、大事なナイフなんでしょ?返してあげるわよ!」動体視力、反射神経においては奈良村を遥かに上回る玲子だ、主の手を離れ、クルクルと宙を回転するナイフに素早く左手を伸ばし、最適の角度でナイフの柄をキャッチする。最適の角度、つまり投げつけるのに最適の角度でだ。ナイフをキャッチすると同時に玲子は左手をしなやかにくねらせ、スナップを効かせてナイフを投げつける。ザビュッ!「ギアアッッッ!!!」玲子のナイフは狙い違わず、奈良村の右足甲に突き刺さった。武道と鞭で鍛えた玲子は完全な両利きだ。左手のスナップも、並みの男を遥かに上回る。銀色の軌跡を描いた玲子のナイフは奈良村の靴を貫き、右足甲を見事に貫通して足の裏に切っ先が顔を覗かせる程、深深と突き刺さった。「ガアッッッ!」野獣のような悲鳴をあげ、奈良村は反射的にナイフを抜こうと蹲ってしまった。深深とナイフを突き刺された衝撃と激痛に、奈良村の頭から玲子は完全に消え去っていた。痛い、痛い、いてえようーーお!!!こんなチャンスを逃がす玲子ではない。奈良村が蹲った瞬間、玲子の長い右脚が閃光のように空を切った。「ハッ!」烈昂の気合と共に玲子は右跳ね蹴りを繰り出した。しかも通常、跳ね蹴りは足の甲の部分で蹴るのだが、今日はブーツを履いている。爪先は硬い皮革に保護されている。朝子と同じく、玲子もブーツを武器としてフルに活用した。無防備に蹲る奈良村の顎に玲子の右脚が迫る。と、命中直前、玲子は足首を思いっきり返し、爪先を立てながら奈良村の顎を蹴りあげた。脚のスピードに足首の返しがプラスされた瞬間的な超高速の蹴り、しかも道場では完全に禁じ手である爪先蹴りを、ブーツの硬い爪先で食らわせるのだ。グジャッ!という、何かを潰すような手応えを感じながら玲子は大きなフォロースルーを取って、右脚をパントキックのように高々と蹴り上げた。「ぶじゃーっ!!!」喉に玲子の爪先を突き立てられ、完全に呼吸を奪われながら奈良村は首をガクン、と真後ろに跳ね上げられ、仰け反るように倒れていった。ゴッ、ドザッ・・・奈良村の後頭部が、ついで全身が床に倒れこんだ。ピクッ、ピクッと全身が痙攣している。辛うじて首が折れるのだけは免れたものの、奈良村の意識は完全に消え失せていた。
6
「な、奈良村!」坊野の目の前で悪夢がまた、繰り返された。検見川、須崎に続いて奈良村までもが倒されてしまった。しかも、奈良村は丸腰ではない。得意のナイフを手にしながら、苦もなく倒されてしまったのだ。ゾク・・・坊野の背筋に悪寒が走った。ま、まさか、俺までやられる、ていうのか?俺たちが、俺たちSNOW CRACKが女にやられただなんて、こ、こんなことが広まったら、俺たちはもう、ストリートを歩けなくなるぞ・・・悪夢と弱気を振り払うかのように、坊野は激しく頭を振った。ば、馬鹿か俺は!俺まで女にやられるなんて、何馬鹿なこと考えてるんだ!弱気になんじゃねえ!ケミたちがやられたのは、女だと思って油断してただけだ!お、俺が、この俺が負けるわけがねえ!大きく息を吸いながら坊野は金属バットを握りなおした。「て、てめーら・・・よくもやってくれやがったな、もういい、輪姦すなんてどうでもいい、そのかわり、てめーら全員、どたまカチ割ってやる!」「アラ大変!ねえ玲子、困ったわ。私たち、頭カチ割られるのなんてごめんよね?」「当たり前でしょ!じゃ、礼子、最後の締めは取っておいてあげたんだから。相手のプレジ、一番おいしい相手は礼子にあげるからね、ごゆっくりどうぞ!」パシーンッ!礼子はベルトを打ち鳴らすと坊野に微笑みかけた。「聞いた?ということで、貴方は私が苛めてあげるわ。さあ、かかってらっしゃい!」い、苛めるだと?そりゃ、こっちのセリフだ!こ、このクソガキ!血圧が上がり過ぎ、目の前が暗くなりかける程の怒りに燃えながら坊野が絶叫した。「て、てめ、そこ動くんじゃねえ!ぶ、ぶ、ぶっ殺してやるーっ!!!オラアッ!」坊野は両手でバットを握ると、礼子めがけて袈裟切りに思いっきり振り下ろした。だが礼子は軽いステップでスッと身をかわす。「オラア!食らえ!待ちやがれ!糞が!」絶叫しながら坊野は立て続けにバットを振り回す。確かに凄いスピードだ。当たれば頭をカチ割ることも出来るだろうし、腕でガードしても骨折程度しかねない。礼子のパワーではうまくベルトで受けても、パワー負けしてガードすることすら困難だろう。だがあくまで、当たれば、の話だ。剣道の高段者でもあり絶対的な見切りを身につけた礼子にとって、坊野のバットの動きは余りに単純過ぎた。何のフェイントもなく、ただ力任せに振り回すだけ。しかもいくら怪力の坊野とは言え、バットはそれなりの重量があり、木刀のように自在に振り回せるわけではない。一旦スイングを開始したら、空中で軌道修正など不可能だ。礼子にとって、そんなバットの動きを見切るのは容易いことだった。
フン、こんなものなの?このレベルならいつでも料理できるわね。礼子の唇の端に嘲るような冷笑が浮かんだ。だが、そうは言っても坊野のパワーは確かに凄まじい。礼子は無理をせず、冷静に待っていた、坊野のスピードが鈍るのを。そんなにフルスイングしちゃって、ご苦労様。でもその元気、いつまで続くかしらね。もう貴方が最後の一人だし、焦ることはないわ。ゆっくり付き合ってあげる。空振りは相手に当たった時の何倍も疲れる。ましてや重いバット、そして酒にタバコにドラッグに、と不摂生な坊野だ。スタミナがあるわけない。礼子の読み通り、僅か10スイング前後外されただけで坊野はもう、肩で息をし始めていた。そろそろいいわね。今まで避けるのに専念していた礼子が、ベルトを握り直した。「に、逃げんじゃねえ・・・」ゼーゼーいいながら坊野がバットを振り上げようとした瞬間、礼子は反撃に転じた。「ハイッ!」気合と共に礼子のベルトが宙を走る。ピシッ、パシッ!バットを顔の前辺りまで振り上げた坊野の両手に強烈にスナップを効かせたベルトの往復ビンタが襲い掛かる。「イデッ!ツッ!」疲れと痛みに坊野は思わずバットを取り落としてしまった。ガラーン、バットが床にバウンドし、転がる。や、やべえ・・・坊野は慌ててバットを拾おうとした。だが、一瞬早くバットを拾い上げたのは、礼子だった。「もーらいっと!」ベルトを右手に握ったまま、礼子は左手にバットを握ると、クルッと一回転させながら坊野に殴りかかった。「く、アウッ!」頭を殴られると思い、坊野は反射的にガードを上げ、必死で頭をカバーした。だが礼子の狙いは違った。わざと外しながらもう一回転、斜めにバットを回転させながら、礼子は坊野の右膝を殴りつけた。ガコーン!骨を殴りつける、いい音が響いた。「ガアッ!」思わず膝を押さえる坊野に、今度は鳩尾への突きを入れる。「グバアッ!」たまらず、坊野はよろけながら後ずさりする。だが礼子は深追いはしない。行ける!いいえ、未だよ。木刀ならいざ知らず、バットとの二刀流じゃ私のスピードも落ちちゃうわ。それに未だ完全に動き、止まってないわね。もう少し疲れさせといた方がやりやすいわね。・・・いいわ、バット、返してあげる。安易に追い詰め、手負いの野獣の反撃を食らったりしてはつまらない。止めを刺すのは完全に坊野の余力を奪ってからで十分だ。「うわ。痛そう・・・大丈夫?このままベルトとバットの二刀流で攻めたら、まるで私が苛めてるみたいね。じゃ、玲子も奈良村さんにチャンスをあげてたみたいだし、私も一度、このバット、坊野さんに返してあげるわ。」カラーン、礼子は無造作に、坊野の足元にバットを転がした。「ぐ、こ、この・・・な、舐めやがって!!!」奈良村と同じく、坊野も完全に礼子の術中にはまってしまった。いくら優勢に戦っていても、やはり相手は男だ。礼子たちにとって、坊野たちが危険な相手であることは変わりない。しかも、自分たちが怪我するなど、真っ平ごめんだ。ではどうするか。挑発し、相手の冷静さを失わせるのが最善の策だった。そしてもう一つ、礼子たちの武器はベルト、鞭だ。拷問ではなく、鞭を武器にして戦う場合の最大のポイントは精神的な優位を保ち、相手を見下し、冷静さを失わせながら攻めることだ。防戦に回ると鞭は弱い。挑発と侮辱により、相手を精神的に追い込みながら戦う、まさに礼子たちの戦術こそが必要不可欠なのだ。
坊野はバットを拾い上げると立ち上がった。右足がふらつくが、立ち上がれない程ではない。「クッ・・・て、てめえ・・・やりやがったな・・・」怒りの余り殆ど顔面蒼白になりながら坊野が迫る。グッ・・・バットを握る手に更に力がこもるのが見て取れる。じりじりと間合いを詰める坊野を、礼子は涼やかな余裕の微笑を浮かべながら待ち構えていた。あらあら坊野さん、そんなに硬くなっちゃ駄目じゃない、それじゃ却ってスピード落ちるし、動きも丸見えよ。「て、てめえ・・・喰らいやがれ!」間合いを詰めた坊野は大きくバットを振りかぶり、反動を付けると思いっきり横なぎに殴りかかった。フン!また力任せに振り回すだけなの?学習効果の無い人ね。礼子は余裕の表情でステップバックし、かわす。だが坊野は空振りの勢いでそのままバットを振り上げ、返す刀で逆袈裟打ちに殴りかかる。礼子はこれもかわす。え?まだあるの?坊野のバットは止まらない。バットを休めず、今度は袈裟打ちに殴りかかる。あらあら、勝負を賭けてきたのね。それにしても・・・オラオラで勝負、とはまた、随分単純に頭を使わない技に頼るものね。坊野さん、貴方本当に偏差値60以上のおつむなの?これじゃ昆虫並みのお馬鹿さんよ?もしかして、脳まで筋肉になってない?日体大にでも逝くつもりなの?「・・・オラオラ!オラオラオラオラオラー!」全身全霊を込めたラッシュだ、礼子にいくらかわされようと構わない。一発、一発当たりさえすれば良いのだ。巧みなスウェー、ステップバック、サイドステップを駆使してかわす礼子を坊野は必死で追い続けた。呼吸すら殆どしていない。無制限の全力ラッシュ、猛烈なスピードで振り回されるバットは、その半径内にある全ての物を粉砕しそうな勢いだ。
確かに坊野はある意味本物、喧嘩のプロだった。これだけの威力のバットの前では多少のテクニックなど、問題にならない。パワーで一気に押し切り、相手が反撃に出る前に叩き潰せる。礼子は苦笑していたが、これはこれで一つの正解、大抵の場合は相手を倒せるし、事実、今まで坊野がこの技を繰り出した時は全ての相手を血の海に沈めてきた。だが坊野は大事な要因を幾つか見落としていた。この工場、自分が礼子たちを連れ込んだこのアジトは充分に広く、礼子が自在にステップを踏み、坊野のラッシュをかわすスペースが充分にあることを。今までの相手はガードしたり、なまじ反撃しようとしたために、兎に角バットを当てることができたが、スピード、身体の柔軟性、動体視力、センス、全てにおいて坊野を遥かに凌駕する礼子が徹底して避けに回ったら、捕まえるのはほとんど不可能であることを。いくら興奮で痛みを忘れているとはいえ、バットで打たれた右膝は深刻なダメージを負っており、追撃のスピードがいつもよりは鈍っていることを。そして人間の活動には限界があり、こんな無酸素運動のマックスは約一分間、それ以上は続かないのが人体の構造だということを。「ゼハッ、ま、待ちやがれ、オラ、チョコマカと・・・」坊野の全身の筋肉の乳酸値が急速に高まっていく。礼子は坊野のバットのスピードが急速に衰え、反比例するかのように呼吸が加速度的に荒くなっていくのを冷静に観察していた。フン、いいわね、そろそろ頃合ね。もう酸素供給能力が追いつかなくなっているようね。アドレナリンが出過ぎて気付いてないかも知れないけど、もうスピードがた落ちよ。スイングが波打っているのも気付いていないの?すっと礼子の足が止まった。チャ、チャンス!!!ガキが、とうとう捕まえたぜ!てめーも疲れて、もう逃げられねーんだろ!?極度の疲労に判断力が鈍った坊野は礼子が自分同様、疲れてもう足が動かなくなったのだ、と勝手に思い込んでしまった。礼子の罠かも知れない、等とは考え付きもしなかった。「く、食らえーッッッ!!!」絶叫と共に頭上高くバットを振り上げると、全身全霊の力を込めて唐竹割に振り下ろした。
フッ・・・坊野が勝利を確信し、両手に礼子の頭蓋骨を陥没させた感触をすら感じた瞬間、礼子はすっと体を右後方に開きながらサイドステップし、当然のように坊野の必殺の一撃をやりすごす。ゴッ・・・全力で床を殴ってしまい、両手に痺れを感じると同時に坊野は一瞬、目の前に黒い蛇が出現したように感じた。ビシッ!「ギアッ!」坊野の悲鳴が響いた。礼子はバットをよけた動きをそのままバックスイングに利用し、カウンターでベルトを見舞っていた。狙いは・・・坊野の目だ。全力でバットを振り下ろし、無防備状態の坊野の両目を礼子のベルトは完璧に捕らえた。「グアッッッ!!!」余りの痛さに坊野は思わずバットを取り落とし、両手で目を押さえてしまった。「あああああ!」だが礼子が悠長に痛みに浸る時間を与えてくれるわけが無い。「ハッ!」礼子は素早くバットを拾い上げると、視界を失い無防備の坊野の鳩尾に鋭い突きを入れる。「グホッ!」目が見えない坊野は、いつどこから攻撃されるのか、まったく分からない。予期せぬ痛みに喘ぐ坊野に、礼子は冷酷に追い討ちをかける。左手に握ったバットを一回転させ、充分なスピードを得ると今度は坊野の右足脛、弁慶の泣き所を思いっきり殴りつけた。ガシッ!バットの芯が的確に坊野の脛の骨を捕らえる、あ、いい感触、骨逝ったかな?素晴らしい感触が礼子の全身を悦ばせる。「ウギャーッッッ!!!」いくら女の子の、片手での一撃とはいえ、脛の骨をバットで思いっきり殴りつけられては溜まらない。「ほ、骨があああっっっ・・・」余りの激痛に坊野はガクンと膝を折ってしまった。最低でも骨にヒビが入ったことは間違いなさそうだった。鳩尾と足の余りの痛さに、無意識の内に両手が下に下がる。目を押さえていた両手は今まで、一応頭部のガードになっていた訳だが、そのガードが完全に外れた。しかも両目は霞んでいて殆ど見えない。礼子はまさに、この隙を待っていた。「隙あり!」気合もろとも、礼子はスナップを思いっきり効かせ、強烈なベルトの一撃を繰り出した。狙いは勿論、先ほどと同じく坊野の目だ。ピシーン!!!「ギァアアッ!め、目が、目があーっっっ!」礼子の熟練の鞭は坊野の目を確実に捉え、完璧に打ち据えていた。「い、いでえ、いでえよーっっっ!!!」先ほどより遥かに強烈な鞭に打ち据えられ、坊野は完全に視力を奪われてしまった。いや、視力どころではない。人体最大の急所の一つである目を革のベルトで思いっきり打ち据えられたのだ、これでは堪ったものではない。余りの痛みに両手で目を押さえ、坊野は床を文字通り、のたうち回っていた。激痛にのたうつ坊野に礼子は慎重に近づいた。大丈夫かな、まだ実は余力を隠しているんじゃないかしら。礼子は焦る気は全くなかった。実際のところ、坊野をいたぶる気すらない。合理的に、自らがリスクを背負うことなく確実に仕留める。そのために最も合理的な方策を取ろうとしているだけだ。但し、いたぶる気もないが礼子の意識には坊野の味わう苦痛に対する配慮も全くない。「い、いでええええ!!!」仰向けに横たわってのたうち回る坊野に近づくと、礼子は左手に握ったバットを振り上げ、坊野のがら空きの鳩尾に再び、深々と突き立てた。「ぐ、ぐげえーっっっ!」坊野の右手が鳩尾を押える。あらあら、右手だけなの、じゃあ、もうワンステップ必要ね。礼子は再びバットを振り上げ、鳩尾を押える坊野の右手に更に突きを入れた。「あ、アデッ!いでーよーっ!!!」手の甲は骨が皮膚のすぐ裏を走る、人体の急所の一つだ。繊細な手の甲の骨をヒビが入るほどバットで突かれ、新鮮な激痛に坊野の左手が反射的に顔から下り、右手に向かう。チャンス!礼子の右手が閃き、ベルトが再び宙を切る。バシーン、ビシーン!礼子の無慈悲なベルトは坊野の左右の耳に往復ビンタを喰らわせる。「あ、アバアッッッ!!!」キーン・・・痛い、と言うより頭の中で爆弾が破裂したかのような衝撃波に脳を揺さぶられる。耳は平手打ちでさえ、的確にヒットすれば重大な衝撃を与えられるポイントだ、そこをベルトで思い切り打ち据えられては堪ったものではない。「・・・!!!」最早声にもならない悲鳴に口を大きく空け、坊野は床をのたうち回る。視力に加え、耳を通して三半規管に加えられた打撃に平衡感覚すら奪われ、最早自分がのたうち回っているのか、ただ痙攣しているだけなのかすら分からない。「グォブォッ!!」鳩尾に鈍い痛みが走る。自分が巨大な虫ピンに貫かれた昆虫のように感じる。そう、確かに礼子は左手に握ったバットを思い切り坊野の鳩尾に突き立て、動きを完全に封じていた。坊野の両手がすがるようにバットを掴む。そうよ。ちゃんと握っていてね。邪魔だから顔をガードなんかしないでね。パシーン、ピシーン!「ひ、ヒギーーーッッッ!!!」坊野の両頬に革ベルトの往復ビンタが炸裂する。両頬が吹き飛ぶような激痛といつ襲い掛かるか想像もつかない鞭の恐怖に坊野は遂にパニック状態に陥ってしまった。「い、イギーーッッ、ヤ、ヤベデグレーーーッッッ!!!」最早SNOW CRACKのプレジ、等という誇りはどこにもない。金切り声を上げながら半ば本能だけで頭を抱えて床をのた打ち回り、泣き叫ぶ坊野を礼子は相変わらず優しい笑顔で微笑みながら見下ろしていた。「痛そうね坊野さん、今止めを刺してあげるわ。」だがその声は、最早坊野には届かない。
「グヴェーーーッッ!」突然、呼吸を奪われ坊野は空気が抜けるような悲鳴を漏らす。絶叫しようにも、喉を突然襲った激痛が悲鳴すらまともにあげさせてくれない。「グギェーーーッ!」止めを刺しにかかった礼子の茶色いブーツを履いた右足が、坊野の喉を踏みつけ、呼吸を封じて意識を刈り取りにかかっていた。激痛と苦しさ、死んだほうがマシな程の苦痛に、断末魔の痙攣のようにもがきながら坊野は必死で礼子のブーツに覆われた足首を掴む。その姿はまるで礼子の足を押し戴いているようだった。一瞬、礼子の顔に戸惑いの影が走る。あら、もう十分にダメージを与えたつもりだったけど、計算が違ったかしら?掴まれたままじゃ厄介ね・・・だが冷静に見下ろすと、自分のブーツに縫い付けられてもがく坊野の顔にあるのは断末魔の苦しみにもがく、苦悶の表情のみだ。・・・うん、大丈夫ね。あと一押しで止めを刺せるわ。じゃ、いいわよ坊野さん、そのまま私のブーツ握ってて。余計なガードなんかしないでね。今、楽にしてあげるから。「ギュァッ!・!・!」坊野の悲鳴が更に苦しそうになる。礼子は坊野にブーツを掴ませたままスット足首を返し、坊野の喉の上に片足立ちしていた。呼吸を完全に封じられた坊野の視界は真っ暗になり、チカチカと星が瞬く。最早自分の喉を踏みつけ、完全に動きを封じた礼子がブーツを履いた左足を高く引き上げている姿など、坊野には全く見えなかった。ドウッ・・・硬いブーツのヒールを纏った礼子のストンピングが坊野の鳩尾深くにめり込む。「ガヴォアッッッ!!!」全身をビクビクと苦痛に痙攣させながら、坊野の意識が急速に消えうせて行く。意識が途切れる最後の一瞬、坊野の脳裏に鮮明な画像が走った。それは・・・相変わらず涼しげに微笑む、礼子の優しげな微笑だった。
ま、まさか、そんな・・・慎治たちは工場で繰り広げられた惨劇を呆然と見つめていた。ま、まさか・・・まさか坊野さんたちがやられるなんて、それも、一矢も報いることができず、一方的にやられちゃうなんて・・・だが、坊野たちSNOW CRACKの幹部四人が全員、血塗れになって大の字に横たわり、気絶しているのは紛れもない現実だった。「ど、どうしよう・・・ねえ、ど、どうしよう???」余りに予想外の展開に言葉を詰まらせながら、慎治は独り言のように問い掛けた。「ど、どうしようったって・・・」たずねられた信次にも、答えなどない。信次が期待していたのは、玲子たち四人がグチャグチャに輪姦され、泣き喚く姿だった。だが、泣き喚いていたのはSNOW CRACKの方だった。「ど、どうしようったって・・・」とその時、信次はとんでもないことに漸く気づいた。輪姦されかけたんだ、玲子さんたち、もしかしたら警察呼ぶかもしれない。で、周りを調べた時に俺たちが見つかったら!!!こ、怖い!警察が怖いのではない。自分たちが依頼主だということが、もし玲子さんにバレタら!!!こ、殺される!!!「し、慎治、や、やばい、やばい!!!」慎治もほぼ同時に気づいていた。「う、うん!!!や、やばいよ、は、早く、早く逃げなくちゃ!!!」だがその時、背後からの声が慎治たちの心臓を凍りつかせた。「駄目じゃん信次、途中で帰っちゃ。ゆっくり最後まで楽しもうよ。」イ゛ッ!思わず悲鳴を上げそうになった二人が振り向くと、後ろには真弓と里美が立っていた。
初めてだった。翌朝目覚めた時、背中、尻、脇腹、慎治たちの全身に礼子たちの鞭の痛みが残っていた。それだけならいつものことだ。だが恨み、富美代と朝子におしっこを引っ掛けられ、馬糞まみれにされた恨みは消えていなかった。いや、一晩置いて尚一層、恨みはつのっていたかもしれない。肉体的な痛みは時間と共に急速に薄れていく。だが精神的な痛みは時間と共に却って増していく。慎治たちはその痛みに駆り立てられるように、復讐の幻想を語り合い、精神の傷口を舐めあっていた。二人は本気だった。本気で,真面目に仕返ししようと必死で知恵を絞って、来る日も来る日も復習計画を練っていた。
それが間違いだった。考えれば考えるほど、礼子たちと自分たちの実力差に思いが至ってしまう。いや、礼子たちどころではない。仮に二人掛かりで行ったとしても、慎治たちの腕力では富美代や朝子にも軽くあしらわれてしまうだろう。そのことは嫌と言うほど思い知らされている。だから慎治たちの企みはとんでもない方向に進んでいってしまった。そう、誰か人を,礼子たちより強い人に頼んで、礼子たちをやっつけてもらう、という考えに。とんでもない考え違いだった。確かに礼子たちは慎治たちより遥かに強い。だが、それがどうしたと言うのだろうか。礼子たちといえども、24時間いつも気を張っているわけではない。慎治たちが本当に自分を捨て,復讐を最優先とするならば、手段などいくらでもある。例えば後ろからナイフで刺すとか闇討ちをかけるとか家に火をつけるとか、極端に言えばヤクザからピストルを買い,撃つという手だってある。いくら礼子たちが強い,と言っても,それは真っ向から向かい合った時の話だ。慎治たちが、自分が犯罪者になったって構わない,という覚悟さえできれば、手段はいくらでもある。突き詰めれば人を殺す,ということはナイフを10センチ前に突き出す,ピストルの引き金を数センチ引く,と言った,僅か数センチの動きを躊躇い無くできるかどうか、に過ぎない。慎治たちはその数センチの覚悟がなかった。本当にもう礼子たちに苛められるのが嫌だ,この地獄から抜け出るためなら,どんなことでもする、自分が犯罪者になるのなんて、全然構わない。礼子たちを殺すか,自分たちが死ぬか,どちらか二つに一つだ。ここまで考え覚悟を固めていれば、おのずと腹も固まり,本当に復讐できたかも知れない。だが慎治たちはそうではなかった。何が何でも復讐してやる,という硬い決意を持てないままに、言葉だけで復讐,という重い覚悟を孕んだ言葉を弄んでいた。逆に言えば,そうやっていつまでたっても覚悟が固まらず,無意味なプチ反抗だけを繰り返してきたからこそ、礼子たちにここまでいいように苛められて来た訳だが。ともあれ、慎治たちはおよそ最悪の選択,自分たちの運命を賭けた復讐を赤の他人に依頼しよう、という致命的なミスをおかしてしまった。赤の他人,慎治たちと違い,礼子たちに別に恨みがあるわけでも何でもないから、失敗しても別にどうということはない人間に復讐を依頼する、というのが何を意味するか。そして、その所詮他人事の依頼が失敗した場合に、礼子たちがどういう行動に出るか,慎治たちは考えを巡らすことができなかった。むしろ、「礼子さんたちよりもっと強い人に頼めばいいんだ!」と何か,自分たちがぶつかっている分厚い壁をブレイクする天啓を得たかのような幻想に酔い,甘い期待に打ち震えてしまっていた。だが復讐を依頼できる相手はなかなか見つらなかった。強く,しかも礼子たちを,女の子を平気でグチャグチャにできる男。もともとワルでもなんでもない慎治たちにそんな知り合いがいるわけない。だが八方手を尽くして探している内に,一本の糸が繋がってしまった。そして慎治たちの運命も、大きく変わろうとしていた。
「なあ慎治、あいつらのこと、先輩に頼んでやっちゃおうぜ・・・」またか、慎治は何の気なしに応じた。先輩、信次が中学の頃、パシリに使われた先輩とやらに頼んで礼子たちをやっつけて貰おう、て話だよな。全く、そんなこと、出来るわけ無いくせに・・・何十回目かの答えだった。「やっちゃうって、誰に?そんな中学の時の先輩に頼む位なら、ヤクザでも雇った方がまだマシじゃない?」いつもだったら、ここでおしまいの話だ。だが今日は違っていた。信次は目をギラつかせながら、身を乗り出してきた。「違うんだよ、慎治、俺の直接の先輩じゃないんだけどさ、紹介してくれる、ていうんだよ。」紹介ね、ふーん、誰を?どうせ、どうでもいい、その辺にたむろってるチンピラだろ?「いや慎治、それが驚けよ、SNOW CRACKだぜ?あそこの坊野さん、あの人と話が繋がる、て言うんだよ!」慎治もこれには些か驚いた。SNOW CRACK、一見テニスサークルかと思うような軟派な名前の彼らは,通称白ギャンとも呼ばれ地元で一目置かれる、いや最悪,札付きのワルだった。専門は名前のとおりドラッグの密売だが、幹部を含め末端に至るまで全員理性が欠片すらない、イカれたメンバー揃いのギャングだった。男は殴る,女はレイプする,金が欲しけりゃ強盗でもなんでもする、狂犬同然の連中だった。いずれあと数年したら全員、ヤクザ、廃人、黒枠の写真に収まっている,のどれかだ、と奄ウれるだけあり手のつけ様が無い、本職のヤクザでさえ関わりあいになるのを嫌がる連中だった。勿論、マジ坊の慎治は名前だけは知っているが、会ったこともない、遠い存在だ。その連中に信次はあたりをつけられる、と言うのだ。「信次、それ、本当か?スノー、て、あのチームだろ?幾らなんでも、あそこに頼めるわけないだろ?僕たちなんか,会っただけで金、せびられるのがオチじゃないの?」「いや、これが本当なんだよ。中学の時の先輩の友達の従兄弟がさ、あそこのプレジの坊野さんなんだよ。でさ、頼めば、カネ次第では坊野さん、力貸してくれそうだっていうんだよ。上手いことにさその人、サブ、ていうより坊野さんとタメの検見川さんって人ともツーカーだっていうんだぜ、どうだい、これ、凄え話じゃないか?」
2
けみがわ・・・けみがわ、検見川・・・慎治の頭の中で引っ掛かるものがあった、検見川、随分珍しい苗字だな・・・「信次、ひょっとしてその検見川さん、て人、僕と中学一緒じゃない?でさ、ホストっぽい、矢鱈と逝けてるルックスの人じゃない?」「あ、そう言えば・・・確かに検見川さん、慎治と同じ中学だよ。うん、確かにあの人、滅茶苦茶鬼畜な癖して,顔は矢鱈と逝けてるけどさ、それがどうかしたのか?」「その検見川さん、僕たちより2年上、丁度僕たちが新入生の頃の最上級生だよね・・・検見川、そんな珍しい苗字の人、あの人しかいないよ、きっと!」「な、なになに慎治、検見川さん、知ってるのか?」「うん・・・いや、僕は殆ど話したことないんだけどさ、富美ちゃんが超お熱だったんだよ。検見川さん、ちょっと危ない感じもする人じゃん?だからさ、富美ちゃん、最後まで告れないまま検見川さんが卒業しちゃってさ、それっきりになっちゃったんだ。だけど、富美ちゃんが超お熱だったのはみんな知ってる、有名な話だよ。」運命の歯車がコトリと不吉な音を立てた。「・・・慎治、プレジの坊野さんだけじゃなくてサブの検見川さんとも話つながりそうじゃん・・・これ、これって・・・俺たちにも、俺たちにもやっと、やっとツキが回ってきたかもしれないぜ!」
早速セットに入った慎治たちに朗報がもたらされたのは、2週間後だった。指定されたファミレスで慎治が会ったのは確かに、中学の時にいた検見川先輩だった。「オウヨ?おまえ、なんか見覚えあるな。もしかして、おまえ、中学の時,俺と被ってなかったか?確か・・・富美代だっけ、あの小うるせーガキとつるんでなかったっけ?」「は、はい。富美ちゃんのこと、覚えていらっしゃいましたか?」「ああ。あいつ、小便臭いガキのくせしてうるさく付きまといやがってよ、結構ウザかったな。あいつ、真面目な子のくせして俺のこと、なんかいい人系と勘違いして付きまとってたろ?笑っちまうよな、こっちは全然その気ないのによ。ウゼーから一回姦っちまうか、と思ってたけどよ、あの頃は俺も人間、丸かったからな、いい人ごっこして遊んでる内に卒業しちまって、それっきりになったけどな。どうよ、あいつも元気してるか?」よかった。覚えていてくれた、しかも富美ちゃんのこと、好意も何も持ってない、じゃあ話は早い。慎治たちは手早く用件を説明した。話は簡単,言葉にすれば僅か1,2行だ。天城礼子,霧島玲子,神崎富美代,萩朝子、この四人を攫ってグチャグチャにレイプして欲しい。できたらレイプ写真も撮って欲しい。そんな写真をばら撒かれたら二度と表を歩けない,という位,恥ずかしい写真を撮って欲しい・・・「ふーん、慎治,何があったかは知らねーけどさ、よっぽど富美代たちのこと、むかついてるんだなー。大方,お前ら高望みしてこいつらに告って派手に振られた、てとこか?ま、別にいいけどよ。坊ちゃん,どうよ?」「おう・・・でもよ,この子たち、マジでいけてねーか?こりゃよ・・・こいつらの依頼抜きでもやっちまいてーよな。こういうお高く止まった女のよ、姦った時の泣き声ってシビレルからな。四人か、全員いい線逝ってるじゃねーか。じゃーよ、奈良村と須崎もこういうタイプ、結構好みだからな、連中も誘ってやろうぜ。・・・OK、おい、おまえ信次、て言ったな、普段はこんな値段じゃ動く気しねーけどな、こいつら上玉揃いだ、出血大サービスしてやるよ。一人十万,四人で四十万積みな。そしたらよ、おまえらの望み通り、グチャグチャに姦ってやるよ。今言った奈良村と須崎な、こいつら、うちのNO.3とNO.4だぜ?それに俺とケミ、うちのNO.1からNO.4揃い踏みの超豪華メンバーで姦ってやるぜ・・・望みどおり姦ってやるぜ。派手に、たっぷりとな。ケミちゃん、この内のこいつ、知り合いなんだろ?だったら、絵は描きやすくねーか?頼むぜ,こいつら上玉揃いじゃん?俺にも楽しませてくれよ!」「オウヨ!ま、その手の絵は俺の専門分野だからな、任せときな。富美代か、よく見ると中坊の時よりグッといい女になってるじゃねーか。中坊の時は食いそびれたけどな、今度は遠慮なく食わしてもらおうか!」
やった、やった、やったーっっっ!!!慎治たちは外に出てから、思わず抱き合って大喜びしてしまった。「や、やった、やったな慎治!」「うん!うん!聞いた?派手に、たっぷりと姦ってくれるんだって!あの人たちが派手に、て言うんだよ!?富美ちゃんも礼子さんたちも、もう終わった、て感じ?」「そうだそうだ!もう四人まとめて終わったよな!キケケケケ!あいつらの泣き顔が目に浮かぶようだぜ!」「イヒ、イヒヒヒヒ!あー、もう早く姦ってくれないかな!富美ちゃんたちが姦られた後、どんな顔して出てくるか、考えただけでも興奮しちゃぅよ!!!」慎治たちは復讐の快感、未だ実際には何も起きていないのに、もう復讐を果たしたかのように束の間、復讐の快感に浸っていた。
検見川は早速、富美代を誘うきっかけを探り始めた。余計な警戒心を持たれずに接触するいい方法を。「よし、慎治、おまえ、富美代たちとよく話すんだろ?そろそろ文化祭シーズンだからよ、連中もどっかの高校の文化祭、行く筈なんだよ。それ聞き出したらよ、俺に報告しな。そこで偶然の再会って奴を演出してやるからよ。」検見川の読み通りだった。人気ブランド校の聖華だ、文化祭シーズンになると各校からの誘いは激しい。そして聖華の中でも有数のハイレベルを誇る礼子たち四人は当然の如く人気抜群だ。慎治が横で聞き耳立てていると、毎週のようにあっちこっちの文化祭に出かけているようだった。慎治たちを毎週末鞭打つ、とは言っても人間の身体だ、土日両日とも鞭打っていたのでは流石に慎治たちの身体が持たない。だから礼子たちの基本的なパターンは土曜に慎治たちを苛め、日曜は自分たちだけでどこかに遊びに行く、というものだった。慎治が礼子たちの予定を逐一、検見川に報告していると、ある一校のところで検見川の目が光った。「うん?来週、二宮義塾か。いいな、ここ坊野の高校だ。ここにするか。」慎治にとっては意外な一言だった。二宮義塾、相当にハイレベルの高校だ。受験偏差値で言えば聖華より高い位、都内でも上位に属する高校だ。実は坊野に限らず、検見川、奈良村、須崎は皆、比較的レベルの高い高校に通っている。彼らは決して馬鹿ではない。彼らに言わせれば工業高校にでも通って族やギャングをやってる連中はサルなみの低脳、時代遅れのパフォーマンスしか出来ない連中だ。今時、気の利いたワルをやるには、少しは頭が必要だろ、と思っている。実際、彼らはレイプ、恐喝、暴行なんでもありの凶悪チームのくせして未だ警察につかまったことはなかった。勿論、警察に相当マークはされているのだが、周到な準備、口封じを徹底し、捕まるにしても精々下っ端、坊野たち四人は今まで全くの無傷だった。
そして日曜日、二宮義塾の文化祭に礼子と富美代が現れた。ブラブラ催し物を見ている二人に次々と誘いがかかる。遠くからでも強烈に目立つ二人だ、誘いは引っ切り無しにかかる。それを適当にあしらいながら回っている二人が漸く一息ついたタイミングを計り、検見川と坊野は行動に移った。「あれ、もしかして富美ちゃん、神崎、富美ちゃんじゃない?」え、誰かしら?知ってる人かな?ベンチに座ってコーヒーを飲んでいるところに後ろから声をかけられ、振り向いた富美代は思わず声を上げそうになった。「あ、け、検見川先輩じゃないですか!え、先輩、この高校なんですか?」そこに立っていたのは中学のとき憧れていた先輩、検見川だった。相変わらずの端正な顔に爽やかな微笑と驚いたような表情を浮べ、両手を広げていた。「いや、俺はここじゃないんだけどさ、友達がここだから遊びに来てたんだよ。あ、紹介するよ、坊野、て言うんだ。」「あ、よろしく、ケミの後輩?」内心のどす黒さを隠しながら、坊野も爽やかな微笑を浮べた。フン、今日は二人だけか。依頼のあったもう二人、霧島玲子と萩朝子は一緒じゃないな。まあいい、今日は仕込みだけにしとくか。食うのは後でゆっくりと楽しめばいいからな・・・それにしても、こいつら二人、マジ上玉だな。後で輪姦すのが楽しみだな。余計な警戒心をもたれないように近くのオープンカフェに二人を誘い、検見川は如何にも嬉しそうに切り出した。「いやー、でも驚いたなあ。こんなとこで富美ちゃんに会うなんてさ。でもほんと、可愛くなったね。今、どこに通ってるの?」「え、せ、聖華です。礼子も聖華のクラスメートなんですよ。」「あ、聖華なんだ。いいねえ。あそこ名門じゃん?」中学の時の憧れ、検見川先輩との思わぬ再会に富美代はすっかり舞い上っていた。高いプライドと十分な警戒心を持っている富美代は普段、ナンパなんぞについていくタイプではない。だが今日ばかりは警戒心がすっかり緩んでいた。横にいる礼子も半ば苦笑していた。あらあら顔真っ赤にしちゃって。クールが売りの富美ちゃんがこんなに顔に出るなんて、初めて見たわ。後で精々冷やかしてやろうっと!検見川たちはしたたかだった。今日、無理してどこかに誘えば余計な警戒心を持たせかねない。だから深追いして無理に誘ったりはせず、携帯ナンバーだけ聞き出すとさっさと話題を切り替え、次に繋ぎながら巧みにリリースに取り掛かった。
「ふう、本当はもっとゆっくりしてたいんだけどさ、俺たちも今日は自分のサークルにも顔出さなくちゃいけないんだ。悪いけど、お先に失礼な。また今度、どこかで会えるといいね。」え、折角再会したのにもう行っちゃうの!?富美代は思わず焦ってしまった。憧れの検見川先輩との予期せぬ再会に舞い上がったところにあっさり終わりを告げられ、すっかり動揺した富美代は普段からは考えられない行動に出てしまった。「え!も、もう行っちゃうんですか!もうちょっといいじゃないですか!せ、折角会えたんだし・・・」フン、バカが、引っ掛かりやがったな。耳まで赤くしている富美代を見ながら、冷酷さを内面に隠しながら検見川はあくまで爽やかそうに、かつ、いかにも残念そうに首を振った。「ああ、ほんと、ごめんな。俺もまさか今日、富美ちゃんと会えるとは思ってなかったからさ、この後、予定びっしり入れちゃったんだよ。ほんと、残念だなあ、もっとゆっくりしてたいんだけどね。なあ、坊野?」「ああ、俺も折角だし、もうちょっとお茶してたいんだけどな。でも、もうマジで行かないと、遅れちゃうぞ!?」え、ええ?本当に行っちゃうの?完全に動転した富美代は思わず、常日頃とは正反対の行動に出てしまった。自分から誘う、という行動に。「せ、先輩!じゃ、じゃあ今度、い、一回どこか、ゆっくり遊びに連れてってくださいよ!」ゲット!検見川が内心、ほくそえんでいるだろうと思い、坊野は笑いを押さえるのに必死だった。ったく、ケミは女引っ掛けるの、上手いよな。この手のお高く止まった女はこっちからいくら誘ったってなびかねーからな、こうやって一度リリースしといて、てめえの方から誘わせるのがコツなんだよな。絶妙の間合いと本日最高の笑顔で検見川は誘い返した。オッケー、一匹ゲット!ったく、この手はよく効くな。「あ、嬉しいな!富美ちゃんもまた、会いたい、て思ってくれたんだ!いや、俺もさ、絶対もう一度会いたいな、て思ったんだけどさ、富美ちゃん、あんまり可愛くなってたんで、ついつい誘いにくくてさ、後でメールでも送ろうか思ってたんだよ。じゃあさ、ほら俺たち、富美ちゃんたちから二個上だろ、丁度四輪の免許取ったとこなんだよ。でさ、坊野と俺、車買ったばかりだからさ、後二人、奈良村と須崎、ていう友達がいるんだけど、そいつらと毎週ドライブ行ってるんだ。どう、富美ちゃんと礼子ちゃんも今度、一緒に行かない?誰か後二人誘ってさ、四対四で行かないかい?」「え、本当ですか!わあ、嬉しい!検見川先輩とドライブできるなんて最高!うん、勿論行きます!ね。礼子、礼子も勿論OKよね?先輩たち四人だから、私たちも後二人、玲子と朝子を誘おうよ!」はいはい、富美ちゃん、もう完全その気ね。玲子と朝子も呼ぶですって?超豪華メンバーじゃない、なんか勝負入ってない?まあ、いいけど。中学の時の憧れの先輩だもんね、いいわよ、ドライブ位、付き合ってあげる。半ば呆れながらも礼子はニッコリと輝くような笑顔でフォローした。「うん、いいわよ。富美ちゃんの先輩とドライブだなんて、私も嬉しいな!私も喜んで行きます!」礼子の返事を聞いて坊野と検見川は内心、ニヤリとほくそ笑んだ。上手く引っ掛かったな。残りの二人、霧島玲子と萩朝子もこれで誘い出せたぜ。バーカ、俺たちにノコノコついて来るなんてよ、一生忘れられないドライブにしてやるぜ・・・余計な警戒を持たれないように、検見川はこの日はこのまま本当に、あっさりと富美代たちを帰した。その代わり、メールを二日おきに入れてメンテを怠らず、富美代の熱を保ちつづけた。一方、その夜富美代は早速、玲子と朝子に誘いの電話を入れていた。「ねえ玲子、お願い!私、先輩と上手く行きそうなんだからさ、協力してよ!」「朝子、絶対付き合って!今度、なんでも好きなの奢るからさ!」全く、富美ちゃんがちょっと笑ってあげれば、向こうから必死で追っかけてくるに決まってるじゃん。あんたの方から追っかけてどうするのよ。富美ちゃんも意外とお子様なんだから・・・礼子と同じく、半ば呆れながらも玲子と朝子もOKした。ま、富美ちゃんがこんだけ言うんだもん、しゃーないわね、ドライブ位、付き合ってあげるわよ。
3
だが、四人の中で唯一、玲子だけは何か妙に引っ掛かるものを感じていた。偶然の再会、ドライブ、今度は四人で行こうよ・・・何か変ね。何か出来すぎてるような気がするな。一つ一つは極めて自然よ。でも・・・まあ検見川さんは富美ちゃんにとって、ずっとお熱の先輩なんだからね、余裕かましてられるかも知れないけど、あの日は礼子も一緒にいたのよね・・・あの二人とお茶して、あんなにあっさり帰るなんて、普通ある?そりゃ、確かに人には好み、ていうものがあるからね、いくら礼子といっても、ああいう真面目でお高いタイプが苦手の男にとってはNOINTかも知れないわ。だけど、だったらわざわざ四対四で、人数増やしてドライブ行こうなんて誘うかしら?メアド交換したのよ、富美ちゃんだけどこかに誘えば十分じゃない?礼子に舞い上がってたならともかく、随分あっさり別れたんでしょ?それでドライブ?何か変ね・・・玲子の直感、礼子たちより少しワルの部分の多い玲子の直感は鋭かった。元々、中学の頃はクラスメートを自殺未遂に追い込むほどの冷酷な苛め常習犯だった玲子だ。今でこそ信次たちという格好のオモチャと、礼子たちといういい友達の両方を得てすっかり更生しているとはいえ、その頃の知り合いで高校ではヤンキー化している連中は何人もいる。早速ツテを辿って調べてみた。結果は・・・ビンゴだった。玲子からその名前を聞いた連中は異口同音にこう答えた。「二宮義塾の坊野、それに検見川だって?そいつら、SNOW CRACKのNO.1とNO.2だぜ?男は殴る、女は輪姦す、最低最悪の連中だよ。で、何?後の二人は奈良村と須崎?そいつらはNO.3とNO.4だぜ。おいおい、SNOW CRACKの幹部揃い踏みじゃん!え、あいつらが中学の時の後輩と健全なお付き合い?するわけないだろ!宅間守が小学校の先生やります、て言ってるようなもんだぜ!?あいつら、野獣以下の連中だぞ、大方、グチャグチャに輪姦してビデオでも撮って裏に流そう、ていう魂胆だろ?玲子、その子が玲子の友達だったら、絶対にやめさせた方がいいぞ。その子に一生取り返しのつかない傷を負わされること、100%保証付きだぜ。悪い事言わねえ、断れないんだったらマジで速攻、警察行ったほうがいいぜ?あいつらが相手だったら、警察だって絶対、何もないうちにだって手、貸してくれるぞ。」
「ふう、やっぱりね。ありがとう、よく分かった、恩に着るわ。」三人目の電話を切り、玲子は軽く溜息をついた。どう見ても罠だ。今なら簡単、誘いを断り逃げればいい。流石にこの段階なら大丈夫、向こうも勘付かれた、と気づいてもう近づいてこないだろう。確かに警察沙汰にする手もある。普通なら警察が未だ何も起きていない今の段階で動くわけないけど、相手はSNOW CRACK、警察も何とかしてくれるだろう。最悪、自分と礼子の両親の名前を出せば、多分助けてくれるわ。だけど・・・問題は富美ちゃんよね。こう盛り上がってる時に水掛けて、あの子止まるかしら。玲子は富美代に直接電話するのを止め、まずは礼子に相談することにした。「ふーん、確かに。言われてみると、やっぱり妙に不自然よね。文化祭で出くわすのはよくあるパターンだとしても、確かに出来すぎよね。ましてや、相手がそういう・・・SNOW CRACKだっけ?そういう極悪の連中だとしたら、尚更よね。ふう、玲子が調べてくれて助かったわ。ありがとう・・・だけど・・・問題はやっぱり、富美ちゃんよね。」流石に検見川たちに何の思い入れもない礼子は冷静だった。玲子の話を素直に受け止め、もう検見川たちのことは全く信用していない。「でしょ?で、どうなの実際?富美ちゃん今の話聞いて、すぐに目を覚まして引きそう?あの手の手合い、一番いいのは関わりあわない事よ。今の段階なら、適当な理由つけて断って、その後二度と合わなければまあ、向こうも諦めて別の獲物探しに行くと思うのよね。だけど富美ちゃん、すんなり引いてくれそう?」
礼子の脳裏に富美代の端正な顔が浮かんだ。富美ちゃん、顔立ちも態度も普段はクール系なのにな、時々、スイッチが入るとやたら熱くのめりこじゃうのよね。のめりこんじゃった富美ちゃんを止めるのって、結構骨だわ・・・「うーん、正直言って、厳しいわね。玲子もそう思ってるんでしょ?富美ちゃん、ああ見えて妙に一途だからさ、未だ何も起きてない今の段階で止める、て言うのは、結構難しいわね。」「やっぱね・・・私もそうじゃないかと思ったんだ。でね、最悪のパターン、て分かる?最悪のパターンはね、私や礼子たちは引いちゃったけど、富美ちゃんは私の言うこと信じられなくて、ズルズル連中の誘いに乗っちゃって一人でついてっちゃうこと。それは・・・お願い、私をレイプして、て、おねだりしに行くようなものよ。連中、人間じゃないわ。野獣同然だからね。そんな連中相手に一人で行くなんて、文字通り自殺行為よ。」「参ったわね、全く。どうしよう・・・玲子、こういう方面は玲子の方が詳しいわ。何かいい考えない?」「そうね・・・礼子、会ったのは二人、坊野と検見川、て言ってたわね。私が聞いた限りじゃ、あの二人がチームのNO.1とNO.2だそうなのよ。で、見た感じどうだった?連中がどの程度の強さなのか、礼子なら分かるんじゃない?」
礼子は二人の姿を思い浮かべてみた。身長は175センチ前後、礼子たちよりやや上だが、大して大柄なわけではない。決して貧弱な体格ではないが、肩幅、体の厚みもそれほどではない。「・・・そうね。確かに悪くない体格だけど、そう特別いいわけではないわ。少なくとも空手とか柔道とか、本格的に格闘技をやり込んだ、プロの格闘家系の体じゃないわね。あんまりじっくり観察したわけじゃないけど、格闘系に限らなくても、とにかく体を鍛えこんでる、ていう感じはしなかったわね。そんなに絶対的なパワーがあるタイプには見えなかったな。極悪チームなんでしょ?喧嘩はし慣れてるんだろうけど、多分、鍛えたのは路上の実戦で、ていうタイプ、腕力よりむしろナイフとか、すぐ武器に頼るタイプだと思うわ。」「そう。じゃ素直に見て、もしやりあったとしたら、どう、勝てそうな相手?」「うーん、まともに一対一、素手対素手でやり合えば、多分勝てると思うわ。だけど、多分ナイフかなんか持ってると思うわ。ナイフなんか出されたら、たとえ勝ててもこっちも無傷じゃ済まないかも知れないよ?」玲子はクスッと笑った。「そこは大丈夫。確かにナイフ対素手だったら、怪我するかも知れないわ。だけど、予め相手がそういう手合いだと分かっていれば、こっちも準備していけるわ。礼子も私も、武器は得意よね。素手で勝てる相手になら、武器を持ったら更にその差は広がるわ。こっちも準備して行けば大丈夫よ!」
礼子たちの見立ては正確だった。坊野たちは確かに極悪チームで有名だし、喧嘩は日常茶飯事だ。だが、彼等が極悪チームと言われる所以は喧嘩の強さそれ自体ではない。むしろ、そのやり口に負うところが大きい。彼等は一言で言って、汚い喧嘩専門だ。一対多数、素手対武器有、といった汚い手を専門としており、得意技は闇討ち、騙まし討ちである。坊野にしろ検見川にしろ、堂々とタイマン張ったことなど、殆どない。タイマンを申し込まれても受けずに逃げ回り、不意討ち、闇討ちで相手を潰すのが常套手段だった。玲子はそれを逆手に取ろうと考えていた。正面から行けば、今度の誘いに敢えて乗ってやれば、向こうは私たちのこと、女の子、と油断してくるはず。チームの他のメンバーを連れてくることはないんじゃないかしら。そうしたら四対四、実質、一対一の勝負に持ち込める。一対一の勝負であれば、なんとかなるんじゃないかしら。そして向こうが襲ってきたところを返り討ちにすれば、後は警察に引き渡せるわ。レイプ未遂、ということで連中をまとめて少年院送りにできる。たとえ勝っても、リターンマッチ代わりに付け狙われたんじゃ、勝ったことにならないものね。一気にカタをつけるには、どうしても連中を少年院送りにしなくちゃならないけど、向こうの誘いに乗ってやっての返り討ちなら、正当防衛と警察に引き渡す理由と、両方一気に条件クリアよ!いくら礼子たちが強い、と言っても流石に女の子の限界はある。肉体、パワーの壁は如何ともし難いものがある。礼子たちをもってしても本格的に鍛えこんだ、たとえば極真の有段者クラスと正面からぶつかっては勝ち目は薄い。そして礼子たちにとって、最もやりにくい相手は鍛え上げ、パワーに溢れたゴリラタイプだ。そういったパワーファイターであれば、極端な話、全く格闘技経験がなくても十二分に脅威だ。例えばラグビーのフォワードやアメラグのラインをやっている連中にフルパワーのタックルだけ、電車道のように往復されれば本当に対処に困ってしまう。だが、幸い坊野たちはそうではない。汚い手が得意、という相手には、こっちも準備さえしっかりしていけば、対応法はいくらでもあるわ。玲子の決断は明快だった。
「礼子、危険はあるけど仕方ないわ。忠告だけして、後は自己責任よ、て言って放っとく考えもあるけど、みすみす富美ちゃんをレイプさせるわけにはいかないわ。そうでしょ?だったら手は一つ、逃げられないなら前に出て、あいつらを叩き潰すしかないわ。向こうは油断してる。一気に向こうのトップ四人を潰して、少年院送りにしちゃえば私たちの勝ちよ。どう、やる?」「そうね。・・・富美ちゃんを見捨てるわけにはいかないわ。玲子、やろう!」礼子の美しい瞳の奥に、青白い炎が燃え上がった。そして礼子たちは朝子にも十分な説明をし、手を貸してくれるよう頼んだ。「うん、分かった。いいよ、富美ちゃんが危ないんじゃ仕方ないよね。私もやるよ!」朝子も腹をくくった。
慎治に待ちに待った連絡が来たのは金曜だった。「オウ、慎治か!?俺だ、検見川だ。例の件な、あさっての日曜にやるぜ!でな、俺たちは寛大だから、特別サービスをつけてやるよ。」「え、さ、サービスって、な、何ですか?」電話の向こうで検見川の笑い声が聞こえる。「オウ、おまえら、富美代たちに恨みがあるんだろ?だったらよ、やつらが輪姦されるとこ、ライブで見たくねーか?」「え、み、見せて貰えるんですか!?」「オウ、俺たちがいつも使ってるアジトに夕方連れ込むからよ、そこの二階からなら、たっぷりと特等席でショーを拝めるぜ。なんなら、俺たちの後でおまえらも姦らせてやろうか?」ひ、そ、そんな!僕たちが関わってるなんてバレタら、間違いなく礼子さんに殺される!「い、いえ、そ、それだけは・・・」「・・・あんだ?度胸のねー奴だな、ったく。ま、いいや、姦りたくねーんなら、好きにしな。で、どうするよ、ショーは見るか?」これには一も二もない。「お、お願いします!ぜ、ぜひ、ぜひお願いします!」慎治たちにとっても、眠れぬ夜のカウントダウンが開始された。そしてドライブの日がきた。集合場所に集まった四人、坊野、検見川、奈良村、須崎の四人は一見、別に普通の高校生と区別はつかない。茶髪でストリート系のファッションだが、実態の凶悪さを感じさせる出で立ちではない。そして三々五々礼子たちが現れた。礼子たちは警戒心を持たせぬよう、一見、普通に振舞っていたがどこか、緊張感を漂わせている。礼子はベージュのレザージャケットに焦茶色のスエードっぽいフェイクレザーパンツ、それに同じく茶色のショートブーツを合わせていた。玲子は黒いレザージャケットに細身のデザイナージーンズ、そして脚の細さを強調するかのように、ジーンズの上に黒いロングブーツを履いている。そして朝子は白いブラウスの上に明るい茶色のレザーベストと同系色のレザースカート、そして白いウエスタンブーツを履いてきた。三人三様、だが奇妙な共通点があった。三人ともブーツを履いているが、ハイヒールではなく、極めて動きやすそうなタイプであること、そしてベルト、がっちりした、如何にも硬そうなバックルのついた革ベルトを締めていることだった。
そして最後に今日の主役、富美代が現れた。「あーっ何、富美ちゃん、随分可愛く極めてきたわね!」礼子が呆れたような声をあげた。富美代は白いブラウスの上に赤いベスト、そして赤をベースにしたタータンチェックのスカート、そして一体どこで探したのか、真っ赤な膝下まであるロングブーツを履いていた。ワインカラーのような落ち着いた色ではない、トマト色、とでも言ったらいいだろうか、極めて明るいイタリアンレッドのブーツ、そしてそのヒールは7センチの高さは良いとして、極めて細いメタルピンヒールだった。鮮烈な赤にメタルの銀色が絶妙のアクセントになっている。「全く、一体どこで買ったの、そんなブーツ、初めて見たわ!」「えへへ、検見川先輩、赤が大好きだ、て言ってたからさ、思わず買っちゃったの!どう、似合う?」「・・・うん、確かに似合うけど・・・」確かにそのブーツは富美代にとてもよく似合っている、だが礼子の心配は別のところにあった。「でも凄いピンヒールね。それ、歩きにくくない?」大丈夫?今日は多分、大立ち回りが控えているのよ?「うん、それがね、このブーツ、意外と歩きやすいんだ。ヒールが上手く重心の位置にあるせいかしらね、ちょっと位なら走っても大丈夫なほどよ!」ふーん・・・まあ、それならいいんだけどね・・・礼子たちは些か不安げに視線を交わした。ドライブは比較的穏やかに進んだ。四人を乗せた二台のチェロキーはアクアラインを通って木更津に渡り、そこから湾岸を一周するようにしてお台場に向かって快適なドライブを続けた。そして日が傾きだしたころ、お約束のレインボーブリッジを渡っていた。ここまでならどうということはない普通のドライブ、礼子たちも些か拍子抜けするほどだった。だがブリッジを渡りながら、検見川が口を開いた。「今日は楽しかったね。富美ちゃんたちとこんなドライブできて、最高だったよ、また誘わせてよ?」富美代は白い頬を赤く上気させながら答えた。「もちろん!私も先輩とドライブできで最高です!ほんと、絶対、絶対また誘って下さいね!」OKOK,誘ってやるともさ、言われなくてもな。嫌だと言っても誘ってやるよ・・「じゃあさ、最後に俺たちのガレージ覗かせてあげるよ!この車、結構いじってあるだろ?これ全部、自分たちでやったんだぜ。でさ、マンションの駐車場は狭いんでガレージ借りたんだ。そこ、見せてあげるよ。俺たちの城だからさ、滅多に人、連れてかないんだぜ?富美ちゃんたちだけ、特別に招待するよ!」
憧れていた検見川先輩が、私を特別に招待してくれる!富美代は天にも昇る気持ちだった。「わー、嬉しい!見せて見せて、先輩のガレージ、連れてって下さい!ね、礼子、もち行くよね!」「・・・うん、喜んで!」はしゃぐ富美代と対照的に礼子はどこかヒリヒリと引き締まった表情になってきた。・・・ガレージね・・・無意識の内に、礼子は両手首をほぐし始めていた。精神の戦闘準備スイッチが入る。いよいよね。背筋を何匹もの虫が這いまわる。自分の目が吊り上っていくのを感じる。礼子にしては珍しく緊張したせいか、ブーツの中で足がじっとりと汗ばむのを感じる。怖い?不快?いや、むしろ心地良い緊張だった。いつ来るかいつ来るか、今日一日、来い、来るなとアンビバレンツな感情に引き裂かれて来た自分が一点に集束していく快感だった。ジリッ・・・ジリッ・・・礼子の脳裏にふとゴングのイメージが走る。もうすぐ鳴るのね、ゴングが。大丈夫、もう十分に心の準備はできてる。いいわよ、いつでも準備OKよ!レインボーブリッジを渡ったチェロキーは直ぐに首都高を降り、芝浦の工場街に向かって行く。そしてある工場の前に止まるとシャッターを開け、中に入っていった。中はガランと広い。既にオーナーは倒産した廃工場だった。二台のチェロキーを中に止め、坊野、検見川、須崎、奈良村の四人は先に車から下りた。そして出口に一番近かった須崎が素早く、厳重に入口をロックした。四人は無言のまま、二台のチェロキーを取り囲むように立っている。暫く、沈黙の時間が流れた。
中にいるのは却って不利ね。このままじゃ思うように戦えないわ。「富美ちゃん、下りるわよ。」礼子に促され富美代も車から下りた。見ると玲子も朝子も既に下りている。冷たい空気が流れる。ついさっきまでの和やかムードはもうどこにもない。礼子たちの表情がどんどん険しくなっていく。「な、なに、みんな、どうしたの、怖い表情して・・・せ、先輩、ここ、なんなんですか?ガレージ?でも、ここ、違いますよね?何かの冗談、そう、冗談なんでしょ?私たちを脅かそうとして、冗談なんでしょ!?」検見川は黙ってラークを取り出すと、火をつけた。「・・・ねえ、先輩!お願い、何とか言ってくださいよ!」検見川はゆっくり富美代の方を振り向き、ゆっくりと近づいてきた。二メートルくらいの距離まで検見川が近づいてきた。「先輩!」富美代の声が祈りにも似た悲鳴に変わって工場に響いた。「アツッ!」検見川は持っていたタバコを指で弾くかのようにして富美代に投げつけた。思わず振り払ったタバコから飛んだ火の粉が富美代の顔をかすめる。「な、なにするんですか!せ、先輩、ま、まさか!?」「うぜーんだよ、いいかげん黙れ、このクソガキ!」さっきまでとはうって変わった検見川の怒声が響いた。その顔にはもう微笑はなく、凶悪な冷笑が浮かんでいた。「バカかおまえ?この俺が本気でお前のこと、気に入ったとでも思ってんのか?タコ!誰がおめーみてーなションベンくせーガキなんか、相手にするかよ!」「そ、そんな・・・せ、先輩、だ、騙したのね!!!」「騙した?人聞きの悪いこと言うんじゃねーよ。お前が勝手にのぼせ上がっただけだろうが、バーカ。今日一日遊んでやっただけでもよ、一生感謝してもらわなくちゃあわねーぜ?なあおい?」ゲヘヘ・・・クックックッ・・・ギャハハハハ・・・下品な声で笑っていた坊野たちが大きく頷きながら近づいてくる。「・・・たくだぜ、俺たちSNOW CRACKを一日中引きずりまわしやがってよ、俺たちゃおめーらのパシリじゃねーっつーの!」「たけ≠コ?俺たちの日当はよ?」「先輩だってよ、いいぜいいぜ、俺たち先輩がたっぷりと人生って奴を指導してやりましょ、体でよ!」下卑た言葉を吐き続ける坊野たちに対し、玲子が妙に冷静に尋ねた。「指導ね。で、こんなところに連れ込んで、私たちをどうするつもりなの?」「決まってるじゃね-か!」坊野が中指を突き立て、お決まりのファックポーズを取った。「てめーら全員、たっぷりと輪姦してやるぜ!?グフフフフ、ここにはビデオも用意してあるからよ、てめーらがよがり狂うとこをたっぷりと撮ってよ、裏ビデオに流してやるぜ!四人分まとめて売りゃ、結構いい値になるだろうぜ?」「オウヨ!でよ、俺たちが十分楽しんだらチームの下の連中にくれてやるぜ。良かったな、てめーら今日から一生、男には不自由しねーぜ!!!」「イヒッ、イヒッ、イヒヒヒヒッッッ!!!」「ヒャハッ、ヒャハハッヒャハハハハハッッッ!!!」二階の小部屋の窓から作業場を見下ろしながら、慎治たちは必死に笑いを噛み殺していた。声を出しちゃいけない、大声出しちゃ、礼子さんたちに気付かれる。だから大声あげて笑い、踊り回って喜びに浸りたいのを必死で抑えていた。「・・・ヒ、ヒヒッ、やった、やった!富美ちゃん、泣いてるよ!ぼ、僕を、僕を苛めたバチが当たったんだ!」「ブヒャヒャヒャヒャーッ!玲子さんも朝子も、もうすぐレイプされちゃうんだ!ざまーみろ!散々人のこと、苛めやがって!他人のことを鞭で叩いたりおしっこ飲ませたりできる女なんて、いつかはこういう目に会うんだーっ!」「ざまー見ろ!礼子さん、いつまで取り澄ましていられるかなー?もうすぐ、礼子さんも、礼子さんもグッチャングッチャンに姦られるんだよーん!!!」顔中に下卑た笑いを浮かべつつ、慎治たちは復讐の喜びに打ち震えていた。
いつ以来だろう、こんなに心の底から笑っているのは。慎治たちは入学後、間もなく礼子たちに苛められ始めていた。毎日毎日、女の子に苛められ、辱められる。いつしか笑顔などというものは忘れてしまっていた。ああ、笑う、ていうのはこういう感覚だったんだ。俺たち、笑うのは鞭を許して、もう苛めないで、て卑屈にお追従笑いを浮かべる時だけだったもんな。笑うって、こんなに楽しいことだったんだ。信次の脳裏を玲子たちに苛められた辛い記憶が走馬灯の様に横切る。引っ叩かれ、蹴られ、唾を吐き掛けられ、靴を舐めさせられ、オカマを掘られ・・・鞭で打たれ、おしっこを飲まされ・・・辛い記憶が次々と甦る。だが不思議といい気分だった。そりゃ当然だよな、だって、俺たちをこんな目に合わせた玲子たちが、これからその報いを受けるんだもんな。ヒッヒッヒ!泣け!喚け!もがき苦しめ!俺たちが味わった苦痛の万分の一でも味わえ!俺たちのこの世界に決定的に足りなかったものは・・・俺たちが心底求めていたものは・・・只一つ、玲子たちの泣き顔だけ・・・ああ、癒される。心の傷が癒えていく・・・お前たちも一緒に地獄に堕ちろーっ!復讐の快感は信次に何とも言えない無上の解放感を与えていた。ああ、最高だ・・・万歳、万歳、復讐万歳!余りのことに富美代は呆然としていた。富美代の頭の中を検見川たちの声が飛び廻る。中学生の頃の検見川の思い出が飛び廻る。今日の楽しい一日が飛び廻る。現実認識を失った富美代の両目から涙がツッと溢れた。「キャハハハハッ!泣いてやんの、このガキ、駄目だぜ、泣いたって許してなんかやらないよーん!」検見川の下卑た声と殆ど同時に、パーンと乾いた音が響いた。礼子が富美代の頬を思い切り平手打ちした音だった。「分かった?富美ちゃん、目、覚めた?」頬を走る痛みにより現実に引き戻された富美代の肩を礼子が激しく揺さぶる。「これが富美ちゃんの憧れていた先輩の正体よ。SNOW CRACK,最悪チームのサブ、女の子を騙して輪姦すのが専門、ていう最低男、それが検見川の正体なのよ!」頬の痛みと礼子の凛とした声が、富美代の意識を現実に引き戻していく。そうよ富美ちゃん、私たちの方に帰って来て!富美代の瞳に意識が戻ってきたのを見て、玲子も続けた。「分かる、富美ちゃん?あいつらはね、富美ちゃんをダシにして、私たちをレイプするために汚い罠を仕掛けたのよ。それでもいいの、富美ちゃん?こんな目にあわされて、黙って泣いている富美ちゃんなの!?まさか、このまま大人しく輪姦されるなんて気、あるわけないよね!?そんな富美ちゃんじゃないよね!?!?!?」
4
無理矢理現実に引き戻された富美代の意識は乾いていた。悲しみ、後悔にすすり泣いて自我を虚空の彼方に失った富美代はもうどこにもいない。乾ききり、ぽっかりと空虚になった富美代の精神を、虚無の暗黒の空間を、唯一つの感情、怒りが満たしていく。玲子の言葉は富美代の精神に満ち満ちたどす黒い感情に、富美代自身形容し難い、強いて言えば只一つの言葉に集約される感情、そう、怒りに炎を灯した。炎は見る見る内に大きく、激しく燃え上がった。ワナワナ・・・下を向いた富美代の肩が小刻みに震え始めた。「・・・先輩・・・ゆる・・・さない・・・」富美代の悲しみは怒りとなり、怒気は闘気となって急速に膨れ上がっていく。日頃クールな、冷たいとも評される富美代の怒り、それは真っ赤を通り越して更に熱気を増し青白い炎となって燃えさかっていく。何、この闘気、殆どオーラじゃない!?こんな闘気、見たことないわ!礼子たちでさえたじろぐほどの勢いで、富美代は闘気を全身から発散させている。俯いていた富美代がゆっくりと顔をあげた。ゾクッ・・・思わず礼子の背筋に寒気が走った。涙を流しながら、美しい顔全てに怒りと憎悪と闘気を満ち溢れさせた富美代の美貌、それは人間の表情ではなかった。それは、そう、夜叉、と呼ぶしかないものだった。
それが検見川には気に入らなかった。なんだ、このガキ、もっと泣き喚きやがれよ、でないと犯りがいがねーだろーがよ?検見川は内心、富美代の余りに凄まじい怒りの表情に半ば気圧されていた。今まで連れ込んだ女たちはみんな、ただ泣いて許しを乞うだけだった。怒りの富美代とクールな礼子たち、予想外の反応に戸惑いながらも、まだ検見川は何も分かっていなかった。あんだ、盛りあがんねーな、ったくよ。まあいいか、どうせ輪姦してやりゃ、嫌でも泣き喚くんだからよ。だからガキは困るんだよ。「何怒ってんだ、コラ?ゆるさねーだと?あ?そりゃこっちのセリフだっつーの、たく、ガキの分際で手焼かすんじゃねーよ。オラ、大人しく服脱げっつんだよ?!それとも、引っぺがしたろーか?」無造作に検見川は手を伸ばしてきた。パシーン!「ハッ!」「グアッ!」富美代は下から検見川の手を跳ね上げると、返す刀で鳩尾に思いっきり当身を叩き込んだ。不意をつかれた検見川は息が詰まり、思わずうずくまるようにして後ずさった。「ヒャハハッ!おいケミ、ダッセーッ!んなチビにやられるなんてよ、焼きがまわったかー?手、貸したろか?」検見川の失態を坊野が指差して大笑いした。検見川の頭に血がのぼる。「るせーよ!?ちと遊んだだけだろーが!おい、富美代、てめー、んなことしてどうなるか、分かってんだろーな、コラ!後悔すんじゃねーぞ?」呼吸を整えると検見川は両腕を広げ、飛び掛るように富美代に掴み掛かっていった。検見川はまさか、富美代が合気道を中心に護身術を本格的に学び、十分な戦闘能力を備えているとは想像もつかなかった。単に不用意に出した手を撥ね退けられ、たまさか何かの弾みでボディーに一発食らった、程度にしか考えていなかった。だから再び富美代に掴み掛かろうとしながらも、未だ十分な気構えは出来ていなかった。検見川は愚かにも、未だ本気の喧嘩ではなく、単なるレイプのオードブルとしか考えていなかった。その油断は全身あちこちに巨大な隙を作っていた。
一方、富美代は不思議な気分だった。怒っている。今までの人生で最高に怒っている。怒りで気も狂いそうなほどだ。だが同時に不思議な位冷静な自分を感じていた。首から下は身の置き場もないほど熱く燃え上がっているのに、頭だけは妙に冷静だった。富美代は検見川が迫るのを見ても、怖くもなんともなかった。許せない・・・私を騙した・・・先輩、私だけじゃない、何人も何人もこうやって騙してレイプしてきたのね・・・最低・・・激しい憎悪と強烈な嫌悪感、軽蔑が富美代の全身を貫く。余りの嫌悪に口の中に自然と唾が涌き出るのを感じた。迫る検見川にどう対応する?ファーストアタックの後の攻撃を有利に進めるために、一番有利な手段は何?コンマ何秒もない、この一瞬の間に富美代の頭はコンピューターのように素早く働いた。うん、これがいい。この攻撃、先輩には予想もつかないはずよ。検見川の手は富美代の間近に迫っていた。「オラッ!」検見川は左手で富美代の髪の毛を掴み、引き摺り回しながら右手で富美代の顔面を殴るつもりだった。女の子の顔面を殴ることに躊躇を覚えるような検見川ではない。だが無造作に伸ばした左手を富美代に下から掴まれ、富美代を引き摺り回すどころか逆に腕を伸ばした自らの勢いそのままに前方に姿勢を崩され、引き摺られていく。「アオッ!」態勢を立て直す余裕もなく、蛇のように絡みついた富美代の手に手首の関節を極められ、更に外側に捻り上げられた。検見川の手首、肘、肩の関節に電流が走る。靭帯が悲鳴を上げる。「アウチッ!」検見川は余りの痛さに思わず悲鳴を上げてしまった。検見川の意識の全てが左手に行き、自由な右手も無意味に宙をさまようだけ、全身無防備状態だ。腕を引き摺られて反射的に腰を屈めた検見川の、戸惑ったような顔が富美代の方を見上げる。富美代はそのタイミングを逃がさなかった。「ペッ!ペッ!」桜色をした富美代の美しい唇が急速に盛り上がり、白い矢のように大きな唾の塊を二発吐き出した。ビチャッペチッ!「アウワッ!」宙を切り裂いた唾は狙い過たず、検見川の両目に見事に命中する。礼子たち四人の中でも富美代はこと、唾に関しては間違いなくNO.1のテクニックを誇っている。射程距離は優に2メートルを超え、更に狙った的にピンポイントで命中させる見事なコントロールと、唾を細かい水滴に分散させず、大きな塊のまま飛ばせる巧みなテクニックを併せ持っている。実戦の最中とは言え検見川との距離は今、1メートル程度に過ぎない。富美代にとっては唾を完璧にコントロールして吐き掛けるのに、何の造作もない間合いだ。左手の痛みに目を大きく見開いていた検見川は視界を完全に富美代の唾に塞がれてしまう。唾の大部分はゆっくりと両目から溢れ出し、頬を伝って流れていくが検見川の視界は泡の多い富美代の唾に白く曇り、霞のかかったような状態になる。屈辱を与え、挑発して頭に血を上らせると同時に視界を奪い、戦闘能力を半減させる。嫌らしい位に合理的な富美代の攻撃だった。唾をも武器として使う、流石に唾吐き名人の富美代らしい創造力に溢れた攻撃だった。精神と肉体と、富美代の唾攻撃は予想以上の、見事な効果を発揮した。
思わぬ、想像もしなかった方法での反撃に検見川は思いっきりたじろいでしまったが次の瞬間、激しい怒りに完全に飲み込まれてしまった。「て、てめえ・・・よ、よくもやりやがったなーっっっ!!!」唾を、女の子に唾を吐き掛けられた、ということに漸く気づいた検見川は凄まじい声で絶叫すると同時に手を捻られた痛みをも忘れ、動きを封じる富美代の腕を力任せに振り払おうとした。愚かな選択だ、唾を吐き掛ける、という富美代の挑発にまんまと乗り、検見川は完全に自分を見失っていた。ビチッ、という破滅的な音を肘が発したのにも気づかない。完全に極められた腕を力任せに振り払ったおかげで検見川の左肘の靭帯は完全に伸び、使い物にならなくなってしまった。ふん、馬鹿な先輩、自分で肘壊しちゃって。ま、いいわ。いずれにせよこの左腕、もう用済みね。富美代は冷静に判断して不要になった検見川の左手を解放し、一旦間合いを取る。左腕を代償としながらも、漸く自由を取り戻した検見川は思いっきり体を後ろに捻り、力任せに右ストレートを繰り出した。視界を塞ぐ唾を拭うのも忘れて大振りな、雑なこと極まりないパンチを。全力でのパンチだ、確かに威力はあるだろう。だがそれは当たれば、の話だ。大振りで簡単に起動が読める上に、唾が目に入り、視界が霞んでターゲットの富美代の姿がぼんやりとしか見えない状態では狙いもいい加減極まりない。富美代は余裕でそのパンチを見切っていた。相手に余裕を持たれる。実戦での必敗パターンだ。富美代は殴りかかる検見川の右手を左手で払いながら右手で肘を掴み、体を捻って勢いを受け流す。「アオッ・・・」唾越しにぼんやり見える富美代の姿が回転すると同時に、ターゲットを失った自らの必殺パンチに引きずられ、検見川はたたらを踏む。そして富美代は検見川を引き摺り回しながら完全に腕を極め、更にその腕を引き込み、自分の背中越しに物の見事に検見川の体を宙に舞わせた。検見川の、ぼんやりと唾に霞んだ視界が急速に回転し、天地が逆転する。教科書のような見事な投げが決まる。だが、そこからが教科書とは違った。道場では相手が怪我しないように、更に相手を回転させて背中から落とす。だが富美代は検見川の体が宙を舞っている、まさにその時に膝を折り、両手の動きを連動させて真下に引きずり落とした。「ガアッ!!」受身の取りようがない。検見川はまともに脳天から、まっさかさまにコンクリートの床に叩きつけられた。頭蓋骨や首はかろうじて折れなかった。だがまともに頭を強打し、意識が掠れる。完全に無防備状態となった検見川に富美代は冷静にとどめを刺した。腕を極めたまま、大の字になってピクピク痙攣している検見川の首、耳の下辺りに再び強烈な当身をめり込ませ、完全に失神させた。
富美代が検見川を打ちのめしているのとほぼタイミングを同じくして、朝子は須崎と対峙していた。須崎はSNOW CRACKではNO.4だが、身長は180センチを超え、四人の中では最も長身だった。一方、朝子は156センチしかない。身長差は30センチ近い。向き合いながら須崎は余裕綽綽だった。喧嘩の際、長身の須崎は基本的に相手を見下ろして戦うことが多い。朝子は自分より遥かに小さい上に、なんと言っても女だ。喧嘩にもなりはしない。ま、多少は抵抗するかもしれないけど、二、三発引っ叩けば大人しくなるわな。どうやって朝子を倒すか、なんて全く考えてすらいない。後のレイプのことだけを考えていた。今日は獲物が四人もいるんだからな。たっぷり楽しめるぜ・・・須崎は朝子が抵抗するとは、想像すらしていなかった。ましてや、自分が身長の低い相手を得意とするのと同様、朝子にとってはむしろ自分より長身の相手とのファイトの方が慣れていて手が合う、等とは想像もつかなかった。油断しきっていた須崎は、小首を傾げ、キョトンと大きな瞳で無表情に自分を見つめる朝子を、いつも自分がレイプしてきた女の子と同じくショックに動転して半失神状態なんだろう、と気軽に考えていた。玲子はチラリと自分の横にいる朝子の、この無表情を見てフッと安心したような微笑を一瞬浮かべた。いいわ、朝子、落ち着いてるみたいじゃない。あの無表情が朝子の上手いところなのよね、何考えてるのかこっちは読めなくて、実はこの子、何にも考えてない、思考停止状態じゃないの、なんてつい油断しちゃうのよね。実際にはあの子、冷静にこっちをじっくり観察してカウンターを狙ってるんだけどね。フフ、須崎さん分かるかしら?油断して迂闊に近づくと、朝子の思う壷よ、朝子、後の先の名人なんだからね。まさに玲子の読み通り、須崎は既に朝子の術中に嵌っていた。朝子が無表情の裏側で虎視眈々と須崎の隙を、懐に飛び込むタイミングを図っているなど、全く気づかなかった。「おらチビ、ぼけっとしてねーでさっさと脱ぎな!後がつかえてるんだからよ!」無造作に須崎が両腕を伸ばし、朝子の肩を掴もうとした瞬間、朝子の瞳にキラッと電光が走った。
「ハッ!」裂帛の気合と共に朝子がダンッと鋭く踏み込む。須崎があっと思う間もなく一瞬で間合いを詰めた朝子は左足をグッと踏み込みながら右足で思いっきり地面を蹴る。蹴り足の勢いに腰の回転そして肩の回転を加え、猛スピードに加速された右肘をがら空きの須崎の鳩尾に、アッパーカット気味に突き上げながら思いっきり叩き込んだ。鋭い踏み込みに一瞬、40キロ前半の朝子の体重が大幅に加算されて80キロ台に増幅される。グシャッ・・・うん!手応えバッチリ!内臓に肘がめり込む感触が朝子を興奮させる。猿臂でのフルコンタクトなんて、危険すぎて普段は使えないもんね、一回思いっきりやってみたかったんだ!「カッ・・・ガファッッッッ!!!」内臓が破裂したかのような激痛に須崎は呼吸を失い、口をパクパクさせながら体をくの字に折り、腹を押さえながら真後ろによろけて行く。チャンス!逃がさないわよ!朝子は両腕を上げ、油断なくガードを固めながら追撃する。須崎の顔面はがら空きだ。今打てば入りそうね。だが朝子は慎重だった。直線的に追わず、左右に小刻みに体を揺らしながら軽やかなステップで追い詰める。そして、まだ後退を止められない須崎の右足が上がり、全体重が左足にかかった瞬間を狙って、朝子は得意のローキックを放った。「ハッ!ハイッ!」須崎の腿、膝の外側に朝子の純白のウエスタンブーツが襲い掛かる。「グアダッ!」新たな痛みに須崎は思わずその場に立ち止まり、左足を両手で押さえる。そんな隙を見逃す朝子ではない。隙あり!「エイッ!」須崎を蹴り付けた右脚を繰り戻すと同時に更に追い詰め、動きの止まった須崎の眼前で今度は朝子の左脚が上がる。ぐっ、顔を蹴られるか・・・本能的に須崎は両手を上げ、必死で顔面をガードする。だが朝子がそんな単純な攻めをする訳がない。猫が鼠を弄ぶように、朝子は焦らず、じっくりと須崎にダメージを与え、戦闘能力を奪うつもりだった。焦って止めを刺しに行く、などという不用意をする訳がない。馬鹿ね、須崎さん、あなたたち大柄な人の弱点は足とボディ、身体の下側にあるのよ、知らなかった?須崎のガードが上がりかけるのを嘲笑うように、朝子の左回し蹴りは須崎の左膝を、今度は内側から襲った。「アダッ!」外側に続き、内側からも痛めつけられて須崎の左足全体に耐え難い痛みが走る。こうなるとなまじ大柄でウエイトがある分、却って足にかかる負担は大きい。ヨタヨタとバランスを崩しながら後退した須崎は左足の痛みに耐えかね、思わず全体重を右足にかけ、殆ど片足立ちになりながら左足の腿、膝を押えてしまった。致命的なミスだった。須崎とて十二分に喧嘩慣れしている身、普段だったらこの程度のダメージでひるみはしない。だが相手は女の子、しかもチビのやせっぽち、と完全に油断していた分、心の準備が出来ていなかった。その油断の分、肉体的以上に精神的な動揺が大きく、朝子の、今自分が喧嘩している相手の目の前で片足立ちになり、動けない状態になってその上に両手で足を押えてしまう等という、絶対にやってはいけないミスを犯してしまった。
その隙を冷静な朝子が見逃すわけがない。朝子の右脚が上がる。狙いは・・・須崎の右足だ。今、痛めつけた左足を更に狙うのは素人、全体重が掛かり、動かせない右足を狙うのがプロの選択だ。朝子は一瞬の躊躇もなく、全力で右の前蹴りを放つ。ガッ・・・純白のウエスタンブーツの硬いヒールが自らの体重に固定され、逃げ場のない須崎の右膝に食い込む。やった!手応え十分!私、ローキックは自信あるのよね。それに今日は硬いブーツを履いてるんだし、ヒールで直撃すればローでも十分に一撃必殺になる、と思ったけど、ビンゴね!流石は玲子ね、今日はヒールの硬い、このウエスタンブーツ履いてくるのよ、このブーツが朝子の武器になるんだからね、て言われてたけど、ほんと、玲子の読み通りね。須崎さん、このブーツが凶器だなんて、考え付きもしなかったでしょ?狙い通りだった、只でさえ威力十分な朝子のローキックだ。それに硬いウエスタンブーツのヒールがプラスされれば、これは最早凶器に匹敵する。「ギアアアアッ!!!」膝の皿にヒビでも入ったのか、余りの激痛に須崎は悲鳴を上げながらその場にうずくまってしまった。「あ、あああ・・・!」声にならない悲鳴をあげながら、須崎は片膝をつき、砕かれた右膝を両手で抱え込んだ。だが朝子の時間はここからだ。
5
「OK,行くよ!」朝子は初めて、動きを止めて須崎の正面に立つ。痛みに喘ぎながら須崎は必死で顔を上げる。ついさっきまでは見下ろしていた朝子の顔が、今は自分より遥か上にある。そして無表情だった顔には今や余裕と優越感が満ち溢れ、勝利を確信した残酷な微笑が浮かんでいた。「や、やめ・・グハアッ!!!」須崎が哀願すらできない内に、朝子の鋭い蹴りが襲い掛かる。右の回し蹴り、必死で手を上げガードするが、空中で一旦停止した朝子の右脚はそのまま宙で回転し、下から爪先で須崎の左肘を蹴り上げる。「イダッ!」肘から電流を流されたような、痺れと熱感を伴った痛みが須崎の全身を走る。ブーツの硬い爪先でのトーキックは須崎の腕に激痛を刻み込み、無慈悲にガードを吹き飛ばしてしまった。やった!やっぱブーツ履いてるから、トーキックもOKね!トーキック、これも普段は絶対に使わない技だ。危険、というだけではない。貫手やトーキックのような禁じ手は、いくら威力抜群の危険な技とは言え自らの拳や足を鍛えるのに相当な苦痛と時間がかかる。美貌を誇る朝子にとって、そんな血の出るような努力をしてマニキュアやペディキュアさえできない拳や足を作る気は毛頭なかった。だが今はブーツを履き、硬いトーに自らの柔らかい爪先が守られている。遠慮なく、自らの足を痛める心配なく、心置きなく思いっきり、トーキックを放てた。朝子はブーツを履いているメリットを嫌らしい位、最大限に活用していた。そして一方の須崎の肘は薄いジャケットを着ただけだ。猛スピードで蹴り上げられるウエスタンブーツの爪先に対抗できる訳がない。須崎の左腕は上空に蹴り上げられ、同時にバランスを崩して右のガードも下がってしまう。そして無防備になった顔面に、遂に朝子の蹴りが襲い掛かった。左の回し蹴りが須崎の右頬を捉える。「ゲハッ、ゲフアッッ!」朝子の左脚は八の字を描き、返す刀で須崎の左頬を踵で蹴りつける。ブーツでの往復ビンタに須崎は口からだらしなく涎をたなびかせながら顔を左右に弄ばれる。「いい顔ジャン!ほら行くよ!」そして左脚を引き寄せた朝子は須崎の鼻めがけ、ストレートに前蹴りを繰り出す。朝子の美しい脚線がスッと延びきった瞬間、ヒールにグシャッと気持ちいい感触が走った。「ブギューャァッッッ!!!」鼻を砕かれ、須崎は床をのた打ち回った。うん、やった!最高の感触に朝子は勝利を確信した。だが流石、と言うべきだろうか。暫くのた打ち回っていた須崎がよろよろと立ち上がってきたのだ。「こ、このグァクィャア゛——・・・ぶ、ぶっくぉるぉじでやる・・・」須崎は猛烈に怒っていた。自分にほんの一瞬でこれだけの大ダメージを与えた朝子に。そして油断しきって見事にしてやられた自分自身に。こ、こんなガキに、年下の、しかもチビの女に、やられてたまるか・・・その怒りが須崎の全身に大量のアドレナリンを駆け巡らせていた。右膝、左肘にはヒビが入り、鼻は見事に潰れていた。普通だったら動ける状態ではない。だが極度の興奮が須崎の全身を突き動かしていた。「こ、殺す・・・ぶっ殺してやる・・・」須崎はよろよろと朝子に近づいてくる。いくら興奮により動いている、とはいっても膝にヒビが入っているのだ。そう素早くは動けないし、左手も使えないようだ。完全にKOした、と思った須崎が立ち上がったのを見て一瞬驚いた朝子だったが、須崎がふらついているのを見て直ぐに余裕を取り戻した。なーんだ、やっぱり効いてるじゃん。まあ、しゃーないわね。止めを刺してあげる。
「あーあ、立っちゃって、あんまり無理しない方がいいんじゃない?鼻、きっと折れてるよ?」小首を傾げながらにっこり微笑む朝子の笑顔が、須崎の怒りに更に火を注ぐ。こ、こん畜生!余裕こいてんじゃねえ!!!「ぶ、ブッグォルォズ!!!」全力で須崎は殴りかかった。渾身の右ストレート、女の子の顔面めがけて殴りかかることに何の躊躇もない。だが右足に大ダメージを与えたから蹴りは使えない、更に左手も砕いてある、となればあるのは右のパンチだけ、と朝子は自信を持って読みきっていた。そして須崎のパンチは正に、読みどおりだった。ブーン、それなりのスピードを持ったパンチが迫る。まともに当たれば朝子はひとたまりもない。だが当たれば、の話だ。一歩踏み込んだ朝子は左手を須崎の内側から振り上げて須崎の右手首のあたりに当て、捻りながら左手、更に全身をねじりこんで須崎の起死回生のパンチをいともた易く、受け流していく。そして受け流しながら、朝子が沈み込んでいく。須崎のパンチが沈み込んだ朝子の頭の上を通過していく。朝子の左手は今や須崎の右の二の腕あたりを握り、前方に引き込んでいる。朝子の上体が地面とほぼ平行になる。な、なんだ、何をする気なんだ?次の瞬間、真下から白い影が猛スピードで迫ってきた、と思うと同時に須崎の顎に物凄い衝撃が走った。ガヅッ!!!須崎は声も出せずに首を跳ね上げられ、仰け反りながら昏倒してしまった。朝子は体を倒し、低い位置から180度開脚した右脚を突き上げ、須崎の顎を蹴り上げていたのだ。中国拳法で言う、天空脚に似た技だった。小柄な体を生かして相手の懐に潜り込み、柔軟性を生かして真下から蹴り上げる。両腕で相手を引きずり込んでいるため、相手にとっては朝子の脚は死角になり、見えない。その死角から腕の三倍の力を持つ脚がアッパーカットで襲い掛かるのだ。ましてや硬いブーツのヒールが直撃するのだ、その威力は筆舌に尽くしがたい。須崎は物も言えず、白目を剥いて昏倒してしまった。首が折れなかったのが不思議な位の、凄まじい威力の蹴りだった。
「ケミ!」「須崎!」坊野と奈良村の声が同時に響いた。う、嘘だろ・・・坊野は目の前の光景が信じられなかった。極悪チームとして名を馳せたSNOW CRACK、そのNO2とNO4が一瞬にしてKOされてしまったのだ。しかも相手は自分たちがレイプしようと誘い込んだ相手・・・年下の女の子にだ。俺はラリってるのか?だが検見川と須崎が大の字になって気絶しているこの光景は、紛れもない現実だった。く、糞っ垂れが・・・坊野と奈良村が反射的に富美代たちに襲い掛かろうとした、その時だった。「待ちなさい!」礼子の凛とした声が響いた。「相手が違うわよ。貴方たちの相手は私たちがしてあげる!」フフ、礼子の端正な顔に凄絶な微笑が浮かんだ。「貴方たちも二人、私と玲子も二人、そう、タイマン、てやつ?二対一で苛める、なんてことはしないであげるから、安心してかかって来なさい!」た、タイマン?苛めないでやる?こ、このガキ、舐めやがって!!!坊野は全身の血液が逆流するのを感じた。その時に坊野が頼ったのは自分自身の肉体ではない。武器だった。坊野は何の躊躇いもなく、自分のチェロキーから自らの獲物、金属バットを取り出し、身構えた。最早相手が女の子だろうが、丸腰だろうが関係ない。獲物を使って叩きのめすつもりだった。同時に奈良村も隠し持ったナイフを取り出し、礼子たちを威嚇するように身構えた。だが礼子たちはバットにナイフ、坊野たちが取り出した獲物を見て、彼らの期待に反して大笑いを返してきた。「アハハ!なーんだ、そんなモンしか持ってないんだ!」玲子の嘲るような笑い声は坊野たちを怒らせる、と言うより戸惑わせた。「て、てめえ!こ、このナイフが見えねーのか!ザックリ逝ったろか!」反射的に安っぽい言葉で凄む奈良村に玲子は最早、苦笑を浮べていた。「・・・ハイハイ、私、視力は良いからね、それがナイフだ、てこと位、良く分かるわよ・・・で、私たちの武器が何かは分かってるの?」言いながら玲子はバックルを外し、自らのジーンズからシュルッと黒いベルトを抜き取った。傍らでは礼子もフェイクレザーパンツから茶色いベルトを抜き取っていた。パーン!礼子が二つ折りにしたベルトを鳴らした。「うーん、折角この私たちが相手してあげるって言うんだから、もうちょっと凝った武器出して欲しかったけどね。そんなチープな武器なんかを、まあ得意げに出しちゃって、恥ずかしくない?まあいいわ、貴方たちじゃ所詮、その程度が限界かしらね。さあ、かかって来なさい!」右手にベルトを握り、左手の人差し指でクイクイと挑発する礼子の姿に、坊野たちの頭に血がのぼる。な、何だ、このガキ!か、かかって来なさい、だ?な、舐めやがって!!!坊野も奈良村も、自分たちが切り札のつもりで出した獲物に礼子たちが全くビビらず、却って余裕を見せていることに完全に逆上してしまった。その余裕の根拠は何か?と考える余裕等、全くなかった。礼子たちにとって、坊野と奈良村が取り出した獲物は全く脅威にならなかった。実のところ、礼子たちにとっての心配材料は唯一つ、坊野たちが拳銃を持っている事だけだった。確率は低い。恐らく殆どゼロに近い確率だ。だが、もし持っていたら・・・それに対する備えも一応していたが、それだけが心配だった。だからナイフやバットなどというものは礼子たちにとって、なんの脅威でもない。逆に坊野たちは礼子たちのベルトを余りに過小評価していた。そもそもベルトを武器としてすら認識していなかった。しなやかで強靭な革ベルトが、礼子たちのような熟練者にかかればどれ程強力な武器になるか、身を持って味わうまでは全く想像もつかなかった。
先に動いたのは奈良村だった。「こ、このガキ・・・ベルトが武器だー?てめえは女王様ごっこでもやってんのか、こら!?」右手にナイフを握り、奈良村が間合いを詰めた瞬間、パシーン、痛っ!カラーン、礼子のベルトが一閃し、奈良村の右手を打ち据える音と右手をしたたかに打ち据えられた奈良村の悲鳴、そしてナイフが床に転がる乾いた音が殆ど同時に響いた。打ち落とされたナイフはカラカラと玲子の足元に転がっていった。な、なんだ、何が起こったんだ?玲子が殆どスナップのみで放ったベルト鞭は予備動作が極端に小さく、その癖非常なスピードを兼ね備えていた。奈良村は自分がベルトで鞭打たれた、ということすら、一瞬把握できなかった。ベルトを握った玲子の右手がふっと動いたと思った瞬間、自分の右手に熱を伴った衝撃、今まで全く味わったことのない痛みが走り、頼みの綱のナイフを叩き落していた。玲子のベルトの動きを奈良村のプアな動体視力で捕らえることは到底不可能だった。右手を抑え、思わず呆然とする奈良村に玲子の嘲笑が追い討ちをかける。「アハハ、どうしたのかしら坊や、鞭一発でもうお終いなの?そんなんじゃ、私をレイプするなんて到底無理ね。あ、そうか、鞭一発だけでイタイイタイ、て泣いてる坊やなんか、どうせ根性なしのタマ無しクンだもんね、私をレイプするなんて、端からできっこない見栄っ張りだったのよね。やーいやーい、タマ無し、タマ無し!!!」「て、てめえ!!!な、なめ、舐めんじゃねえー!!!」珍妙なリズムを付けて囃したてる玲子の挑発にすっかり頭に血が上った奈良村は、今にも玲子に飛びかかろうとしていた。だが、辛うじて奈良村の理性を保たせたのは、皮肉なことに自分が落としたナイフだった。奈良村のナイフを玲子はしっかりと黒いブーツで踏みしめ、奈良村が拾えないようにしていた。く、クソ・・・ナイフ、ナイフさえあれば、今度こそぶっ刺してやる・・・なんとか、なんとかナイフを取り戻したい。
一方ナイフを拾いたいのは玲子も同じだった。見たところ奈良村のナイフは軽く、投げナイフとして使えそうだった。間合いを詰めてスナップショットで投げたら、まずは避けられる心配はないわね。だけど・・・玲子は冷静に奈良村との間合いを図った。この間合いじゃ、迂闊にしゃがんだらタックルで突っ込まれる危険があるわね。しゃがんだときに突っ込まれたら、避けられないかも知れないな。玲子は次の一手を慎重に考え、推し量るように奈良村の目を見た。その視線は玲子の方を向いているように見えるが、半分以上はナイフに視線も意識も行っている。ふーん、そんなにナイフに執着するんだ。よし、いいわ。このナイフ、何も私が無理して直接拾う必要はないわね。この手で行こう!奈良村の行動を読みきった玲子は、更に大胆な挑発に出た。「なーに、タマ無しクン?そんなにこの安物ナイフを返して欲しいの?」グリグリとブーツの靴底でナイフを踏み躙りながら玲子が嘲る。「いいわよ、こんな安物、返してあげる。おまけに、お姉さんの唾もつけてあげましょうねー!」玲子は二、三度唇をクチュクチュと動かし、たっぷりと唾を貯めるとブーツをどけ、ナイフの柄にぺっと唾を吐き掛けた。ビチャッと唾がナイフの柄を覆う。「ほーら、お姉さんの唾つきナイフよ、よかったわねー、返して貰えて!」嘲笑りながら玲子はナイフを奈良村の足元に蹴ってよこした。「ぐ、こ、この野郎・・・」奈良村は一瞬躊躇した。唾まみれのナイフ。普段だったら触りたくもない。だが今は・・・悠長に拭いている暇などないことは一目瞭然だ。半ば目をつぶる思いで奈良村はナイフを拾い上げた。ヌルッ・・・右手に玲子の唾の感触が走る。き、汚たねえ、こんな汚たねえもん、触らせやがって!!!「あーら、おっどろいたー!唾掛けられたナイフも拾っちゃうんだー!さっいてー!やっぱ、タマ無しクンは違うわねーえ!ほーらタマ無しクン、そんなに唾が好きだったら、こっちにお顔出してごらん、お姉さんが唾ペッペしてあげるわよーっ!」唇を突き出して白い唾を浮かべ、ここぞとばかりに挑発する玲子に奈良村の僅かな理性は完全に消し飛んでしまった。「て、て、てめえーっっ!こ、殺す、ぶっ殺す、カンペキに殺す!!!」絶叫しながら奈良村は玲子の唾にまみれたナイフを振りかざして襲い掛かった。最早戦術も何もない。闇雲に、ただ力任せにナイフを振り回しながら玲子の顔めがけて切りつけた。愚の骨頂だ。ナイフは日本刀ではない。ナイフの戦闘法はあくまで、刺すのが基本だ。切るのは誉められた使い方ではない。大型のブッシュナイフならともかく、刃渡りが短いジャックナイフでは切りつけようとしたらリーチの短さから、威力半減だ。しかも大振りに大上段から振り下ろしたのでは隙だらけ、玲子のベルトに絶好の標的を提供するだけだった。
フン、かかったわね。馬鹿ね、私がわざわざナイフに唾吐いた理由を考えようともしないなんてね。そんな低脳じゃ、私とやりあうには100億万年と3日は早いわよ!玲子は冷静に奈良村の袈裟懸けの第一撃、バックハンドの第二撃を避けながら完全に間合いとスピードを見切った。そして再び大きく振りかぶった第三撃、奈良村がナイフを振り下ろすと同時に玲子はすっとステップバックした。同時に玲子のベルトが唸る。パシーンッ!今度は下から振り上げた玲子のベルトはまたも見事に、奈良村の右手を打ち据えた。「ッアツ!」いくら固くナイフを握っていても、ベルトで打たれた激痛にはかなわない。しかも奈良村のナイフの柄は玲子の唾まみれだ。まだ濡れている柄はいつもより遥かに滑りやすい。おまけに唾に触る嫌悪感から、半ば無意識に近いが奈良村はナイフのグリップがかなり甘くなっていた。これでは一溜まりもない。右手こそそのまま余勢で振り下ろしたものの、頼みの綱のナイフはいとも簡単に玲子のベルトに弾き出されて跳ね上げられ、クルクルと回転しながら宙を舞った。「ほら、大事なナイフなんでしょ?返してあげるわよ!」動体視力、反射神経においては奈良村を遥かに上回る玲子だ、主の手を離れ、クルクルと宙を回転するナイフに素早く左手を伸ばし、最適の角度でナイフの柄をキャッチする。最適の角度、つまり投げつけるのに最適の角度でだ。ナイフをキャッチすると同時に玲子は左手をしなやかにくねらせ、スナップを効かせてナイフを投げつける。ザビュッ!「ギアアッッッ!!!」玲子のナイフは狙い違わず、奈良村の右足甲に突き刺さった。武道と鞭で鍛えた玲子は完全な両利きだ。左手のスナップも、並みの男を遥かに上回る。銀色の軌跡を描いた玲子のナイフは奈良村の靴を貫き、右足甲を見事に貫通して足の裏に切っ先が顔を覗かせる程、深深と突き刺さった。「ガアッッッ!」野獣のような悲鳴をあげ、奈良村は反射的にナイフを抜こうと蹲ってしまった。深深とナイフを突き刺された衝撃と激痛に、奈良村の頭から玲子は完全に消え去っていた。痛い、痛い、いてえようーーお!!!こんなチャンスを逃がす玲子ではない。奈良村が蹲った瞬間、玲子の長い右脚が閃光のように空を切った。「ハッ!」烈昂の気合と共に玲子は右跳ね蹴りを繰り出した。しかも通常、跳ね蹴りは足の甲の部分で蹴るのだが、今日はブーツを履いている。爪先は硬い皮革に保護されている。朝子と同じく、玲子もブーツを武器としてフルに活用した。無防備に蹲る奈良村の顎に玲子の右脚が迫る。と、命中直前、玲子は足首を思いっきり返し、爪先を立てながら奈良村の顎を蹴りあげた。脚のスピードに足首の返しがプラスされた瞬間的な超高速の蹴り、しかも道場では完全に禁じ手である爪先蹴りを、ブーツの硬い爪先で食らわせるのだ。グジャッ!という、何かを潰すような手応えを感じながら玲子は大きなフォロースルーを取って、右脚をパントキックのように高々と蹴り上げた。「ぶじゃーっ!!!」喉に玲子の爪先を突き立てられ、完全に呼吸を奪われながら奈良村は首をガクン、と真後ろに跳ね上げられ、仰け反るように倒れていった。ゴッ、ドザッ・・・奈良村の後頭部が、ついで全身が床に倒れこんだ。ピクッ、ピクッと全身が痙攣している。辛うじて首が折れるのだけは免れたものの、奈良村の意識は完全に消え失せていた。
6
「な、奈良村!」坊野の目の前で悪夢がまた、繰り返された。検見川、須崎に続いて奈良村までもが倒されてしまった。しかも、奈良村は丸腰ではない。得意のナイフを手にしながら、苦もなく倒されてしまったのだ。ゾク・・・坊野の背筋に悪寒が走った。ま、まさか、俺までやられる、ていうのか?俺たちが、俺たちSNOW CRACKが女にやられただなんて、こ、こんなことが広まったら、俺たちはもう、ストリートを歩けなくなるぞ・・・悪夢と弱気を振り払うかのように、坊野は激しく頭を振った。ば、馬鹿か俺は!俺まで女にやられるなんて、何馬鹿なこと考えてるんだ!弱気になんじゃねえ!ケミたちがやられたのは、女だと思って油断してただけだ!お、俺が、この俺が負けるわけがねえ!大きく息を吸いながら坊野は金属バットを握りなおした。「て、てめーら・・・よくもやってくれやがったな、もういい、輪姦すなんてどうでもいい、そのかわり、てめーら全員、どたまカチ割ってやる!」「アラ大変!ねえ玲子、困ったわ。私たち、頭カチ割られるのなんてごめんよね?」「当たり前でしょ!じゃ、礼子、最後の締めは取っておいてあげたんだから。相手のプレジ、一番おいしい相手は礼子にあげるからね、ごゆっくりどうぞ!」パシーンッ!礼子はベルトを打ち鳴らすと坊野に微笑みかけた。「聞いた?ということで、貴方は私が苛めてあげるわ。さあ、かかってらっしゃい!」い、苛めるだと?そりゃ、こっちのセリフだ!こ、このクソガキ!血圧が上がり過ぎ、目の前が暗くなりかける程の怒りに燃えながら坊野が絶叫した。「て、てめ、そこ動くんじゃねえ!ぶ、ぶ、ぶっ殺してやるーっ!!!オラアッ!」坊野は両手でバットを握ると、礼子めがけて袈裟切りに思いっきり振り下ろした。だが礼子は軽いステップでスッと身をかわす。「オラア!食らえ!待ちやがれ!糞が!」絶叫しながら坊野は立て続けにバットを振り回す。確かに凄いスピードだ。当たれば頭をカチ割ることも出来るだろうし、腕でガードしても骨折程度しかねない。礼子のパワーではうまくベルトで受けても、パワー負けしてガードすることすら困難だろう。だがあくまで、当たれば、の話だ。剣道の高段者でもあり絶対的な見切りを身につけた礼子にとって、坊野のバットの動きは余りに単純過ぎた。何のフェイントもなく、ただ力任せに振り回すだけ。しかもいくら怪力の坊野とは言え、バットはそれなりの重量があり、木刀のように自在に振り回せるわけではない。一旦スイングを開始したら、空中で軌道修正など不可能だ。礼子にとって、そんなバットの動きを見切るのは容易いことだった。
フン、こんなものなの?このレベルならいつでも料理できるわね。礼子の唇の端に嘲るような冷笑が浮かんだ。だが、そうは言っても坊野のパワーは確かに凄まじい。礼子は無理をせず、冷静に待っていた、坊野のスピードが鈍るのを。そんなにフルスイングしちゃって、ご苦労様。でもその元気、いつまで続くかしらね。もう貴方が最後の一人だし、焦ることはないわ。ゆっくり付き合ってあげる。空振りは相手に当たった時の何倍も疲れる。ましてや重いバット、そして酒にタバコにドラッグに、と不摂生な坊野だ。スタミナがあるわけない。礼子の読み通り、僅か10スイング前後外されただけで坊野はもう、肩で息をし始めていた。そろそろいいわね。今まで避けるのに専念していた礼子が、ベルトを握り直した。「に、逃げんじゃねえ・・・」ゼーゼーいいながら坊野がバットを振り上げようとした瞬間、礼子は反撃に転じた。「ハイッ!」気合と共に礼子のベルトが宙を走る。ピシッ、パシッ!バットを顔の前辺りまで振り上げた坊野の両手に強烈にスナップを効かせたベルトの往復ビンタが襲い掛かる。「イデッ!ツッ!」疲れと痛みに坊野は思わずバットを取り落としてしまった。ガラーン、バットが床にバウンドし、転がる。や、やべえ・・・坊野は慌ててバットを拾おうとした。だが、一瞬早くバットを拾い上げたのは、礼子だった。「もーらいっと!」ベルトを右手に握ったまま、礼子は左手にバットを握ると、クルッと一回転させながら坊野に殴りかかった。「く、アウッ!」頭を殴られると思い、坊野は反射的にガードを上げ、必死で頭をカバーした。だが礼子の狙いは違った。わざと外しながらもう一回転、斜めにバットを回転させながら、礼子は坊野の右膝を殴りつけた。ガコーン!骨を殴りつける、いい音が響いた。「ガアッ!」思わず膝を押さえる坊野に、今度は鳩尾への突きを入れる。「グバアッ!」たまらず、坊野はよろけながら後ずさりする。だが礼子は深追いはしない。行ける!いいえ、未だよ。木刀ならいざ知らず、バットとの二刀流じゃ私のスピードも落ちちゃうわ。それに未だ完全に動き、止まってないわね。もう少し疲れさせといた方がやりやすいわね。・・・いいわ、バット、返してあげる。安易に追い詰め、手負いの野獣の反撃を食らったりしてはつまらない。止めを刺すのは完全に坊野の余力を奪ってからで十分だ。「うわ。痛そう・・・大丈夫?このままベルトとバットの二刀流で攻めたら、まるで私が苛めてるみたいね。じゃ、玲子も奈良村さんにチャンスをあげてたみたいだし、私も一度、このバット、坊野さんに返してあげるわ。」カラーン、礼子は無造作に、坊野の足元にバットを転がした。「ぐ、こ、この・・・な、舐めやがって!!!」奈良村と同じく、坊野も完全に礼子の術中にはまってしまった。いくら優勢に戦っていても、やはり相手は男だ。礼子たちにとって、坊野たちが危険な相手であることは変わりない。しかも、自分たちが怪我するなど、真っ平ごめんだ。ではどうするか。挑発し、相手の冷静さを失わせるのが最善の策だった。そしてもう一つ、礼子たちの武器はベルト、鞭だ。拷問ではなく、鞭を武器にして戦う場合の最大のポイントは精神的な優位を保ち、相手を見下し、冷静さを失わせながら攻めることだ。防戦に回ると鞭は弱い。挑発と侮辱により、相手を精神的に追い込みながら戦う、まさに礼子たちの戦術こそが必要不可欠なのだ。
坊野はバットを拾い上げると立ち上がった。右足がふらつくが、立ち上がれない程ではない。「クッ・・・て、てめえ・・・やりやがったな・・・」怒りの余り殆ど顔面蒼白になりながら坊野が迫る。グッ・・・バットを握る手に更に力がこもるのが見て取れる。じりじりと間合いを詰める坊野を、礼子は涼やかな余裕の微笑を浮かべながら待ち構えていた。あらあら坊野さん、そんなに硬くなっちゃ駄目じゃない、それじゃ却ってスピード落ちるし、動きも丸見えよ。「て、てめえ・・・喰らいやがれ!」間合いを詰めた坊野は大きくバットを振りかぶり、反動を付けると思いっきり横なぎに殴りかかった。フン!また力任せに振り回すだけなの?学習効果の無い人ね。礼子は余裕の表情でステップバックし、かわす。だが坊野は空振りの勢いでそのままバットを振り上げ、返す刀で逆袈裟打ちに殴りかかる。礼子はこれもかわす。え?まだあるの?坊野のバットは止まらない。バットを休めず、今度は袈裟打ちに殴りかかる。あらあら、勝負を賭けてきたのね。それにしても・・・オラオラで勝負、とはまた、随分単純に頭を使わない技に頼るものね。坊野さん、貴方本当に偏差値60以上のおつむなの?これじゃ昆虫並みのお馬鹿さんよ?もしかして、脳まで筋肉になってない?日体大にでも逝くつもりなの?「・・・オラオラ!オラオラオラオラオラー!」全身全霊を込めたラッシュだ、礼子にいくらかわされようと構わない。一発、一発当たりさえすれば良いのだ。巧みなスウェー、ステップバック、サイドステップを駆使してかわす礼子を坊野は必死で追い続けた。呼吸すら殆どしていない。無制限の全力ラッシュ、猛烈なスピードで振り回されるバットは、その半径内にある全ての物を粉砕しそうな勢いだ。
確かに坊野はある意味本物、喧嘩のプロだった。これだけの威力のバットの前では多少のテクニックなど、問題にならない。パワーで一気に押し切り、相手が反撃に出る前に叩き潰せる。礼子は苦笑していたが、これはこれで一つの正解、大抵の場合は相手を倒せるし、事実、今まで坊野がこの技を繰り出した時は全ての相手を血の海に沈めてきた。だが坊野は大事な要因を幾つか見落としていた。この工場、自分が礼子たちを連れ込んだこのアジトは充分に広く、礼子が自在にステップを踏み、坊野のラッシュをかわすスペースが充分にあることを。今までの相手はガードしたり、なまじ反撃しようとしたために、兎に角バットを当てることができたが、スピード、身体の柔軟性、動体視力、センス、全てにおいて坊野を遥かに凌駕する礼子が徹底して避けに回ったら、捕まえるのはほとんど不可能であることを。いくら興奮で痛みを忘れているとはいえ、バットで打たれた右膝は深刻なダメージを負っており、追撃のスピードがいつもよりは鈍っていることを。そして人間の活動には限界があり、こんな無酸素運動のマックスは約一分間、それ以上は続かないのが人体の構造だということを。「ゼハッ、ま、待ちやがれ、オラ、チョコマカと・・・」坊野の全身の筋肉の乳酸値が急速に高まっていく。礼子は坊野のバットのスピードが急速に衰え、反比例するかのように呼吸が加速度的に荒くなっていくのを冷静に観察していた。フン、いいわね、そろそろ頃合ね。もう酸素供給能力が追いつかなくなっているようね。アドレナリンが出過ぎて気付いてないかも知れないけど、もうスピードがた落ちよ。スイングが波打っているのも気付いていないの?すっと礼子の足が止まった。チャ、チャンス!!!ガキが、とうとう捕まえたぜ!てめーも疲れて、もう逃げられねーんだろ!?極度の疲労に判断力が鈍った坊野は礼子が自分同様、疲れてもう足が動かなくなったのだ、と勝手に思い込んでしまった。礼子の罠かも知れない、等とは考え付きもしなかった。「く、食らえーッッッ!!!」絶叫と共に頭上高くバットを振り上げると、全身全霊の力を込めて唐竹割に振り下ろした。
フッ・・・坊野が勝利を確信し、両手に礼子の頭蓋骨を陥没させた感触をすら感じた瞬間、礼子はすっと体を右後方に開きながらサイドステップし、当然のように坊野の必殺の一撃をやりすごす。ゴッ・・・全力で床を殴ってしまい、両手に痺れを感じると同時に坊野は一瞬、目の前に黒い蛇が出現したように感じた。ビシッ!「ギアッ!」坊野の悲鳴が響いた。礼子はバットをよけた動きをそのままバックスイングに利用し、カウンターでベルトを見舞っていた。狙いは・・・坊野の目だ。全力でバットを振り下ろし、無防備状態の坊野の両目を礼子のベルトは完璧に捕らえた。「グアッッッ!!!」余りの痛さに坊野は思わずバットを取り落とし、両手で目を押さえてしまった。「あああああ!」だが礼子が悠長に痛みに浸る時間を与えてくれるわけが無い。「ハッ!」礼子は素早くバットを拾い上げると、視界を失い無防備の坊野の鳩尾に鋭い突きを入れる。「グホッ!」目が見えない坊野は、いつどこから攻撃されるのか、まったく分からない。予期せぬ痛みに喘ぐ坊野に、礼子は冷酷に追い討ちをかける。左手に握ったバットを一回転させ、充分なスピードを得ると今度は坊野の右足脛、弁慶の泣き所を思いっきり殴りつけた。ガシッ!バットの芯が的確に坊野の脛の骨を捕らえる、あ、いい感触、骨逝ったかな?素晴らしい感触が礼子の全身を悦ばせる。「ウギャーッッッ!!!」いくら女の子の、片手での一撃とはいえ、脛の骨をバットで思いっきり殴りつけられては溜まらない。「ほ、骨があああっっっ・・・」余りの激痛に坊野はガクンと膝を折ってしまった。最低でも骨にヒビが入ったことは間違いなさそうだった。鳩尾と足の余りの痛さに、無意識の内に両手が下に下がる。目を押さえていた両手は今まで、一応頭部のガードになっていた訳だが、そのガードが完全に外れた。しかも両目は霞んでいて殆ど見えない。礼子はまさに、この隙を待っていた。「隙あり!」気合もろとも、礼子はスナップを思いっきり効かせ、強烈なベルトの一撃を繰り出した。狙いは勿論、先ほどと同じく坊野の目だ。ピシーン!!!「ギァアアッ!め、目が、目があーっっっ!」礼子の熟練の鞭は坊野の目を確実に捉え、完璧に打ち据えていた。「い、いでえ、いでえよーっっっ!!!」先ほどより遥かに強烈な鞭に打ち据えられ、坊野は完全に視力を奪われてしまった。いや、視力どころではない。人体最大の急所の一つである目を革のベルトで思いっきり打ち据えられたのだ、これでは堪ったものではない。余りの痛みに両手で目を押さえ、坊野は床を文字通り、のたうち回っていた。激痛にのたうつ坊野に礼子は慎重に近づいた。大丈夫かな、まだ実は余力を隠しているんじゃないかしら。礼子は焦る気は全くなかった。実際のところ、坊野をいたぶる気すらない。合理的に、自らがリスクを背負うことなく確実に仕留める。そのために最も合理的な方策を取ろうとしているだけだ。但し、いたぶる気もないが礼子の意識には坊野の味わう苦痛に対する配慮も全くない。「い、いでええええ!!!」仰向けに横たわってのたうち回る坊野に近づくと、礼子は左手に握ったバットを振り上げ、坊野のがら空きの鳩尾に再び、深々と突き立てた。「ぐ、ぐげえーっっっ!」坊野の右手が鳩尾を押える。あらあら、右手だけなの、じゃあ、もうワンステップ必要ね。礼子は再びバットを振り上げ、鳩尾を押える坊野の右手に更に突きを入れた。「あ、アデッ!いでーよーっ!!!」手の甲は骨が皮膚のすぐ裏を走る、人体の急所の一つだ。繊細な手の甲の骨をヒビが入るほどバットで突かれ、新鮮な激痛に坊野の左手が反射的に顔から下り、右手に向かう。チャンス!礼子の右手が閃き、ベルトが再び宙を切る。バシーン、ビシーン!礼子の無慈悲なベルトは坊野の左右の耳に往復ビンタを喰らわせる。「あ、アバアッッッ!!!」キーン・・・痛い、と言うより頭の中で爆弾が破裂したかのような衝撃波に脳を揺さぶられる。耳は平手打ちでさえ、的確にヒットすれば重大な衝撃を与えられるポイントだ、そこをベルトで思い切り打ち据えられては堪ったものではない。「・・・!!!」最早声にもならない悲鳴に口を大きく空け、坊野は床をのたうち回る。視力に加え、耳を通して三半規管に加えられた打撃に平衡感覚すら奪われ、最早自分がのたうち回っているのか、ただ痙攣しているだけなのかすら分からない。「グォブォッ!!」鳩尾に鈍い痛みが走る。自分が巨大な虫ピンに貫かれた昆虫のように感じる。そう、確かに礼子は左手に握ったバットを思い切り坊野の鳩尾に突き立て、動きを完全に封じていた。坊野の両手がすがるようにバットを掴む。そうよ。ちゃんと握っていてね。邪魔だから顔をガードなんかしないでね。パシーン、ピシーン!「ひ、ヒギーーーッッッ!!!」坊野の両頬に革ベルトの往復ビンタが炸裂する。両頬が吹き飛ぶような激痛といつ襲い掛かるか想像もつかない鞭の恐怖に坊野は遂にパニック状態に陥ってしまった。「い、イギーーッッ、ヤ、ヤベデグレーーーッッッ!!!」最早SNOW CRACKのプレジ、等という誇りはどこにもない。金切り声を上げながら半ば本能だけで頭を抱えて床をのた打ち回り、泣き叫ぶ坊野を礼子は相変わらず優しい笑顔で微笑みながら見下ろしていた。「痛そうね坊野さん、今止めを刺してあげるわ。」だがその声は、最早坊野には届かない。
「グヴェーーーッッ!」突然、呼吸を奪われ坊野は空気が抜けるような悲鳴を漏らす。絶叫しようにも、喉を突然襲った激痛が悲鳴すらまともにあげさせてくれない。「グギェーーーッ!」止めを刺しにかかった礼子の茶色いブーツを履いた右足が、坊野の喉を踏みつけ、呼吸を封じて意識を刈り取りにかかっていた。激痛と苦しさ、死んだほうがマシな程の苦痛に、断末魔の痙攣のようにもがきながら坊野は必死で礼子のブーツに覆われた足首を掴む。その姿はまるで礼子の足を押し戴いているようだった。一瞬、礼子の顔に戸惑いの影が走る。あら、もう十分にダメージを与えたつもりだったけど、計算が違ったかしら?掴まれたままじゃ厄介ね・・・だが冷静に見下ろすと、自分のブーツに縫い付けられてもがく坊野の顔にあるのは断末魔の苦しみにもがく、苦悶の表情のみだ。・・・うん、大丈夫ね。あと一押しで止めを刺せるわ。じゃ、いいわよ坊野さん、そのまま私のブーツ握ってて。余計なガードなんかしないでね。今、楽にしてあげるから。「ギュァッ!・!・!」坊野の悲鳴が更に苦しそうになる。礼子は坊野にブーツを掴ませたままスット足首を返し、坊野の喉の上に片足立ちしていた。呼吸を完全に封じられた坊野の視界は真っ暗になり、チカチカと星が瞬く。最早自分の喉を踏みつけ、完全に動きを封じた礼子がブーツを履いた左足を高く引き上げている姿など、坊野には全く見えなかった。ドウッ・・・硬いブーツのヒールを纏った礼子のストンピングが坊野の鳩尾深くにめり込む。「ガヴォアッッッ!!!」全身をビクビクと苦痛に痙攣させながら、坊野の意識が急速に消えうせて行く。意識が途切れる最後の一瞬、坊野の脳裏に鮮明な画像が走った。それは・・・相変わらず涼しげに微笑む、礼子の優しげな微笑だった。
ま、まさか、そんな・・・慎治たちは工場で繰り広げられた惨劇を呆然と見つめていた。ま、まさか・・・まさか坊野さんたちがやられるなんて、それも、一矢も報いることができず、一方的にやられちゃうなんて・・・だが、坊野たちSNOW CRACKの幹部四人が全員、血塗れになって大の字に横たわり、気絶しているのは紛れもない現実だった。「ど、どうしよう・・・ねえ、ど、どうしよう???」余りに予想外の展開に言葉を詰まらせながら、慎治は独り言のように問い掛けた。「ど、どうしようったって・・・」たずねられた信次にも、答えなどない。信次が期待していたのは、玲子たち四人がグチャグチャに輪姦され、泣き喚く姿だった。だが、泣き喚いていたのはSNOW CRACKの方だった。「ど、どうしようったって・・・」とその時、信次はとんでもないことに漸く気づいた。輪姦されかけたんだ、玲子さんたち、もしかしたら警察呼ぶかもしれない。で、周りを調べた時に俺たちが見つかったら!!!こ、怖い!警察が怖いのではない。自分たちが依頼主だということが、もし玲子さんにバレタら!!!こ、殺される!!!「し、慎治、や、やばい、やばい!!!」慎治もほぼ同時に気づいていた。「う、うん!!!や、やばいよ、は、早く、早く逃げなくちゃ!!!」だがその時、背後からの声が慎治たちの心臓を凍りつかせた。「駄目じゃん信次、途中で帰っちゃ。ゆっくり最後まで楽しもうよ。」イ゛ッ!思わず悲鳴を上げそうになった二人が振り向くと、後ろには真弓と里美が立っていた。
1
「な、なんでここに!!!」「い、いつからいたの!!!」慎治たちの金切り声にも似た悲鳴が響く。眼前で繰り広げられた予期せぬ光景に100%の神経を集中していた慎治たちは、背後に迫っていた真弓と里美に全く気付かないでいた。不意に声をかけられ、心臓が飛び出そうな顔をして口をパクパクさせる慎治を真弓は面白そうに見ていた。「なんでここに、ていうのは私たちが聞きたいんだけどな、ねえ里美?」「全くよね。ま、種明かしをしてあげるとね、私たちは玲子に頼まれてたのよ。ほら、玲子たちの家庭教師の良治先生たち、あの二人にランクル出してもらってね、ずっと玲子たちの後を追って、万が一に備えてたのよ。で、玲子の予想通り連中、玲子たちをここへ連れ込んだじゃない?だから私たちも追っかけて、中が見えるポイントを探したって訳よ。」「そう、玲子にはもし連中が予想以上に強くて玲子たちが危ない状況になったら、速攻で警察呼んでくれ、て頼まれてたからね。2階からなら中の様子も見えるかな、て思ってきたら、予期せぬ先客がいた、て訳よ。まあ最も、良治先生たち、表で待ち構えてるけど木刀とかヌンチャク用意してやる気満々みたいだったから、万一の時は警察が来る前に連中、秒殺されてたと思うけどね。」
な、なんてことだ。全て読まれていたんだ。せ、折角ここまで玲子さんたちを誘い込んだのに、はなから無駄だったんだ。玲子さんたちは、自力でSNOW CRACKを潰せればそれでよし、もし負けても即警察呼んで、助けて貰えるようにしてたんだ。どっちに転んでも、僕たちが仕返しなんかできなかったんだ・・・慎治たちの脳裏に良治たちの逞しい肉体が浮かんだ。十二分に鍛え上げた巨体、しかも空手三段、剣道二段だ。大会で入賞できるレベルではないとはいえ、この二人のレベルで木刀やヌンチャクを使えば、ストリートでははっきり言って手のつけようがない。SNOW CRACKだ、なんだと言っても所詮は素人、ナイフやバット程度用意しても全くの無意味、四人ともあっという間に叩きのめされていただろう。玲子の用意周到さは慎治たちの想像を遥かに上回っていた。な、なんてことだ・・・
よく見ると真弓も里美も革ジャンにブルージーンズ、足元はブーツで固め如何にもいざとなれば一緒に参戦するよ、というスタイルだ。だがそんなことはどうでもいい。問題は玲子たちに陰謀が全て露見した、ということだ。慎治たちの心臓が喉からせり上がる。膝がガクガクと震える。胃がキリキリと痛み下腹部が締め上げられるように痛む。恐怖の余り居ても立ってもいられない。「あ、ああ・・・」「ち、ちが、ちがう!!!」反射的に二人はなんとか誤魔化そうとした。「ち、ちが、ちがう・・・ぐ、偶然、ほらね、偶然なんだよ!!!」「そ、そう、ね、僕たちた、たまたまこ、ここ、ここを通りがかったらさ、玲子さんたちが連れ込まれるのがみえて、そ、そう、助けようとしたんだよ!そ、そうだよな、なあ慎治!?」「そ、そうだよ!き、決まってるでしょ?ね、ぼ、ぼくたち、そ、そう、たす、助けようとしたんだよ、ね、そ、ぞでしょ、そうでしょおおおっ!!!」二人の必死の言い訳を真弓たちはクスクス笑いながら眺めていた。馬鹿ね、現行犯逮捕されといて今更言い訳もなにもあったもんじゃないと思うんだけど?
「ふーん、助けようと思ったね。ま、いいわ、そういうことにしといてあげる。じゃあ、ここに白馬の騎士になり損ねた二人組がいるよ、て玲子たちに教えてあげなくちゃね。よりにもよって日頃苛めまくってたあんたたちが助けに来てくれてたただなんて、ちょっとした感動物語じゃない?玲子もきっと喜ぶわよ?もう苛めないでくれるかもね?」里美は革ジャンのポケットから携帯を取り出すと、ストラップを指に引っ掛けてクルクル回す。ひ、そ、それだけは!!!慎治たちは殆どパニック状態になって飛び上がる。玲子さんたちに知られる!それは死刑宣告を意味する。ぼ、僕たちがこ、ここに居たなんて知られたら、こ、殺される、間違いなく殺される!い、いやだ、し、死にたくないーっっ!!!ガバッ・・・信次は反射的に里美の足元に土下座する。「お、お願い、み、見逃してよーっっっ!!!」慎治もはっと我に帰ると真弓のブーツにすがりつく。「た、助けて、お、お願い、な、なんでもするから、だ、黙ってて、僕たちのことは黙ってて、お、お願い、おねがい・・・・こ、殺されちゃう・・・」もう恥も外聞もない。信次たちは二人とも大泣きし、涙と涎で顔中ぐちゃぐちゃだ。真弓たちを倒して逃げよう、等という考えは信次たちの頭を掠めもしない。玲子や朝子よりは一枚劣るとはいえ、空手部で鍛えあげられた真弓も里美も信次たちから見れば雲の上の存在だ。特に信次は組手で毎週のように蹴りのめされている身、真弓たちの強さも自分の弱さも骨身に浸みている。第一、逃げてもどうにもならない。仮にここを逃げおおせたとしても、真弓たちは直ぐに玲子に事情を報告するだろう。そうしたら結果は全く同じだ。信次たちがこの危機を逃げるには、真弓たちを殺す、文字通り殺すしかない。だが、あれだけ苛められた玲子たちをすら殺す決心ができなかった二人に、そんな覚悟ができるわけがない。できるのは唯一つ、哀願だけだった。真弓たちのブーツを舐めんばかりに二人は必死に哀願するが、玲子たちの親友でもある二人が受け入れるわけがない。勿論、信次たちにもその程度は分かっている。分かっていても哀願せずにはいられない。何もできないが何かしていないと気が狂ってしまう。信次たちは真弓たちのブーツにすがり、涙でブーツを濡らしながらひたすら自慰のような無意味な哀願を続けた。
真弓たちはニヤニヤ笑いながら足元に這いつくばる二人を見下ろしていた。バーカ、許して貰えるわけないでしょ?ったく、いつまでこうやってるつもりなのかしらね。フフ、でもここまで惨めに泣き喚く姿を見るのって、ちょっと楽しいわね。このまま、ここでゆっくり苛めてやろうかしら。この調子なら、ちょっと脅せば私たちのおしっこだって飲ませられるんじゃない?だが、ふと階下を見た真弓たち二人の顔に、更に残酷な冷笑が浮かんだ。クイッと里美はブーツの爪先で信次の顎をこじ上げる。「信次、泣いてるのはいいんだけどさ、下でもっと面白いイベントが始まるみたいだよ。フフ、取敢えず、一緒に見物しようよ。・・・玲子に電話するのは後回しにしてあげるからさ。」え、面白いこと?嫌な予感を感じながらも逆らえずに階下を見た信次の視線が凍り付いていく。
2
礼子が坊野に止めを刺し、一階で立っているのは礼子たち四人だけだった。坊野たちは完全に気を失い、あちこちでだらしなく伸びている。「フウッ、片付いたわね。うまくいったわ。」流石にほっとした様子で礼子が皆を振り返る。「お疲れ礼子、いい攻撃だったじゃない、目潰し鞭、とは考えたものね。」「ありがとう、そういう玲子もあのナイフ、いいコントロールね。ナイフ投げの練習もしたことあるの?ま、最も玲子のコンビネーションのポイントは、あのナイフ投げより、その前の唾にあったのは分かってるけどね。玲子も朝子もブーツをフルに活かしたキックで止めを指したけど、あの唾攻撃はいい発想ね。」「あ、分かった?そう、あれは確かに唾がポイント。まあ、唾攻撃は富美ちゃんの十八番だけどね、たまにはいいや、と思って私も使わせてもらったわ。」と言いながら礼子たちの言葉がふと止まる。富美ちゃん・・・視線を投げかけられた富美代の顔に、吹っ切れたような笑顔が浮かぶ。「ううん、もうみんな、気にしないで。もう先輩のことなんか、何とも思ってないから。それより・・・」富美代は言葉を切って礼子たち三人を見まわす。「・・・ありがとう。本当にありがとう。みんなが助けてくれなかったら私、ここで人生終わってたかもしれなかったね。ありがとう!」良かった、富美ちゃん、もう大丈夫ね。礼子たちの顔にもほっとした安堵が浮かぶ。その時、玲子がパンッと手を叩いた。
「さあさあ、休憩はここまで、今日はまだまだやることがあるんだからね。礼子、手を貸して!」「何、どうするの?後は警察呼んで、坊野さんたち引き渡してお終いじゃないの?」「うん、私も最初はそう思ってたんだけどね、よく考えるとこの人たち、なんで四対四にこだわったのかしら?富美ちゃんを狙っただけとは思えないわ。だったら礼子と富美ちゃん、可愛い子二人まとめてゲットしたんだから、礼子たち二人を誘ってレイプしてお終いのはずじゃない?それをなんでわざわざ、四人でドライブしようなんて指定してきたの?輪姦するって言ったって、四人に人数増やしたら却ってやりにくい筈でしょ?何か理由がありそうじゃない?だったら聞いておかないと。単純に警察に引き渡しても、私たちを襲わせた根っ子を叩いておかないと、また別の形で襲われる可能性があるわ。だから、どうしても理由を聞き出さないといけないのよ!」「・・・そうね、確かに変よね。だけど、これだけ派手に痛めつけた私たちが聞いて、素直に答えてくれるかしら?」プフッ!玲子が思わず吹き出した。「礼子、よく考えてごらん。これ、私たちの安全のためだけじゃないわよ・・・ウフフ、当然、こいつら絶対、素直に喋らないわよ。だったら、無理やり聞き出すしかないわよね。違う?それって・・・」ゾクゾクッ!礼子の背中に強烈な電流が走る。「・・・それって・・・拷問・・・ね・・・」「ご名答。フフ、私たち、信次たちを散々痛めつけてきたけど、あれは言ってみれば苛めとかリンチの範疇よ。これは違うわ。正真正銘の拷問よ。どう礼子、本物の拷問、礼子が憧れてきたのはこれじゃない?お遊びじゃない、私たちには拷問する正当な理由があるし、相手も本物の犯罪者、拷問されるのが当然の相手よ。犯罪者を拷問にかけて無理矢理自分の罪を、バックを白状させる、まさに・・・正統派の、これぞまさしく拷問、ていうシチュエーションよ。どう礼子?」礼子の美貌に凄絶な微笑が浮かぶ。嗜虐と冷酷さと残忍さに満ち満ちた微笑だ。「玲子、あなたってほんと、最高ね!本物の拷問、ああ、最高のシチュエーションよ!こんな機会、二度とないわ、やろう、拷問、今日は最高の一日になるわ!富美ちゃん、朝子、あなたたちもやるわよね?あ、もっとも」礼子はクスクス笑う。「嫌なら別にいいわ、無理にとは言わないから遠慮なく言って。代わりにその分、私がいっぱい拷問させて貰うから!」「あ、礼子ずるい!独り占めはよくないよ、ねえ富美ちゃん、私たちだって拷問したいよね!?」「当然よ!大体、一番拷問する権利があるのは私なんだから!」
「OK,話は決まったわね。じゃあ礼子、手伝って。連中が失神している間に下準備をしておこう!」「下準備?どうするの?」「うん。いつも礼子が慎治を苛める時と基本的には同じよ。拷問中に動かれたり、抵抗されたりしたら面倒だからね。完全に動きを封じておくのよ。一応ロープ用意して来たからさ、今のうちにしっかり縛り上げとこう。」ロープで縛る?全く用意周到なんだから。玲子ったら、もしかして拷問まで今日の予定に入れてたんじゃない?もう、この苛めっ子は・・・苦笑しながらも礼子は自分の中で残虐性が抑えきれないくらい高まりつつあるのを感じていた。残虐性、いや破壊衝動、と言った方が正しいだろうか。坊野たちの肉体を痛めつけ、精神を屈服させてやる。慎治たちを苛めるときは一応、一生残るような傷は与えないように気を配っているけど、今はそんな必要更々ない。どうやって痛めつけてやろうかしら。どんな悲鳴をあげるかな。誰の悲鳴が一番大きいかしら。思いっきり手加減なしで痛めつけたら、どんな風に痙攣するのかな。楽しみ・・・ゾクゾクしちゃうわ。肉体が奥深くから燃え上がるのを楽しみながら坊野たちを縛り上げようとした時、ふと礼子の手が止まった。・・・そうよね。今日は拷問をするのよね。普段の苛めなら縛るだけでいいけど、もっと遥かに暴れるんじゃないかしら。それにこの人たち、慎治たちよりはずっとパワーもあるわ。もっと念入りに、抵抗できないように仕込んどかないと集中して拷問を楽しめないわね。「ねえ玲子、拷問にかけたらこいつら、流石に死に物狂いで暴れるんじゃないかしら。ロープで縛るだけじゃちょっと不安よ。どうやっても抵抗できないようにしとこうよ。」どうやっても抵抗できないようにする?確かに礼子の言うとおりね。だけどどうやって?「・・・そうね。確かに縛るだけじゃちょっと不安ね。だけどどうやる?礼子、何かいい考えある?」「うん。要は仮に拷問中にロープが外れても、動けないようにしとけばいいのよ。縛る前にね、連中の肩と股関節、左右両方とも外しちゃおう。その上で縛っちゃえば、腕も脚も力の入れようが無くなるから、絶対にほどけないよ。それに万々が一ほどけちゃったとしても、関節外しておけば立つことすら出来ないからね、怖くも何ともないよ。まあ、本当は関節を外すのも立派な拷問の内だから気絶してる間に外しちゃうのは勿体無い気もするんだけどね、意識を取り戻されてからじゃあ仕事が厄介よ。連中がお寝んねしてる今のうちに、さっさとやっちゃおう!」なるほど、流石は礼子ね!確かに肩と股関節を全部外しちゃえば、連中もう、どうしようも無くなるわね。後は・・・私たちの思うがままよ!「OK,じゃあ私は奈良村さんと須崎さんをやるから、礼子は坊野さんと検見川さんをよろしくね。」
3
ゴキッ・・・バキッ・・・嫌な音が何度も何度も響いた。礼子たち二人は四人の腕を、脚を掴むと無造作に、次々と関節を外していく。いくら武道の達人である礼子たちでも、実戦で相手の関節を外していくのはそう簡単なことではない。相手も生身の人間、必死で抵抗するし逃げもする。だが今は坊野たちは四人とも完全に失神し無防備の状態、これなら仕事は簡単だ。礼子たちはニワトリの羽でも折るかのように、いとも簡単に坊野たちの関節を外し、一人四回、四人合計十六回、関節が外される音を響かせた。全員の関節を外したところで玲子がバッグから四本のロープを取り出し、礼子に二本を渡した。「じゃあ礼子、そっちをお願いね。こんな風に腕と脚をしっかり重ねて縛っちゃって。」肩と股関節を外され、普段より遥かに体が柔軟になった奈良村の両手両足を背中側に回すと手首を膝裏と、肘を足首と重ねて厳重に拘束し、更に左右の腕、脚をびったりと重ねて縛りつけた。玲子たちはヨットにも乗るだけあってロープワークはお手の物だ。絶対にほどけず、緩まない縛り方でしっかりと拘束する。SNOW CRACKが未だ完全に気絶している間に、拷問の準備はすっかり整った。これだけ厳重に縛られては絶対に抵抗できない。第一、手足を四本とも外されているのだ。寝返りを打つことすらままならない。すっかり準備が整ったのを見た朝子が、例によってキョトンとした表情で尋ねた。「ねえ玲子、拷問、ていいんだけどさ、よく考えてみたら今日は私たち、鞭も何も持ってきてないじゃない?どうやろう、道具もなしで、拷問なんてできるのかな?」「チッチッ・・・」玲子が立てた人指指を振った。「朝子、難しく考えないの、そんな大げさな道具がなくても、十分に痛い目にあわせてやるのなんて簡単よ。たとえば連中、ナイフだバットだ、て道具を用意して来てるじゃない?それを使うだけでも十分、拷問できるわよ。ま、単純にナイフで刺すとか切るとかじゃなくて、どう創造的な拷問を考えるか、そこが腕の見せどころよ!」
「そう、朝子も富美ちゃんも頑張ろうね。もう滅多にないチャンスなんだから、精一杯楽しい拷問を考えようね。」ロープの具合を確かめていた礼子が振り返る。「あ、そうだ。拷問を始める前に、少し前振りもしておこうか。」「前振り?何するの?」「うん、折角拷問するのにさ、ちょっと痛めつけただけで直ぐ白状されたら興醒めじゃない?だからさ、こいつらが絶対喋ってたまるか、て私たちに対して目いっぱい反抗的になるようにしとくのよ。そしたらさ、その反抗的な態度を屈服させるのもまた、拷問の最高の楽しみのひとつになるよ!」「いいわね。礼子、乗ってきたジャン!OK,いいわよ、前振りは礼子に任せるわ。私たちも合わせるから。」礼子たちはゆっくりと各々の獲物に近づき、活を入れて意識を取り戻させる。「グッ・・・グブウッッッ・・・」苦しげに大きく息を吐き出しながら坊野が息を吹き返した。「ウグッ・・・」失神していたおかげで忘れられていた痛みが復活する。未だ目も耳も、腹も喉も足も、全身のあちこちが痛い。だが痛みだけではない。全身が何か、不自然に緊張している感じがする。「・・アヅアッ!!!」無意識に腕を動かそうとした坊野の肩に激痛が走る。動かない。腕はまったく動かないのに肩と、何故か分からないが股にも激痛が走る。必死で首を動かすと自分の脚と腕が完全に重なっている。な、なんだ???ロープ?俺は縛られてるのか?
「お目覚めかしら、坊野さん?」コツコツと頬を小突かれ、坊野は上を見た。礼子の美しい顔が自分を見下ろしていた。そして頬を小突いているのは、礼子の茶色いブーツの爪先だった。「随分よく寝てたわね。いい加減、待ちくたびれちゃったわよ。」「て、てめえ、よ、よくもやりやがったな・・・お、覚えてやがれよ、必ず、必ずこの礼はするからな!」「あら怖い怖い、でももう少し、自分の置かれた状況を見てから物を言ったほうがいいわね。」礼子はスッと右足を上げると、ゆっくりと坊野の顔を踏み躙る。頬を、鼻を、口をゆっくりと踏み躙る。「グッ、ブアッ、ゴ、ごの、や、やめろーっ!!!」顔面を女の子のブーツに踏み躙られる屈辱に坊野は絶叫しながら必死で顔をそむけようとする。だが両手を完全に縛り上げられ、しかも全く動けない体では、いくら顔をそむけても却って礼子のブーツに自分の顔をこすりつけているようなものだ。「アハハッ!そんなに私のブーツが好きなの?坊野さん、あなたもしかして変チャン?ギャングだなんて大嘘で、本当は私に苛めて欲しくて後つけてる、ストーカー君なんじゃないの?ねえ、土日はもしかして、秋葉原にでも入り浸ってるんじゃないの?」笑いながら礼子は坊野の顔面を踏み躙り続け、更に嬲る。「ほら白状しなさいよ、僕たちSNOW CRACKはお宅のストーカー集団です、てね!アハハハハハッ!ほらいい子でおねだりしてごらん!お願い、僕ちゃんを苛めてくださーい、てね!アハハハハハハッ!」「ち、畜生、な、舐めんじゃねえ!俺たち、俺たちSNOW CRACKを舐めんじゃねええっっっ!!!」坊野は顔中を口にして必死で絶叫した。四肢の関節を外され、厳重に縛り上げられた坊野にできる唯一の抵抗は唯一つ、空しく叫び続けることだけだった。
「ち、畜生!ほ、解きやがれ、このロープをほどきやがれーっ!グッ・・・」コンコンッ、礼子はブーツの踵の角を立て、坊野の喚き散らす口を軽くノックする。歯や唇は筋肉が無く神経に直結する敏感なポイントだ、いくら軽く、とはいえブーツの踵で小突かれてはかなり痛い。「まあどうでもいいわ、タッキー君、苛めるのは勘弁してあげる。私ね、お宅って趣味じゃないの。どうせ苛めるなら、もうちょっと可愛い坊やを苛めたいわ。」一旦言葉を切った礼子の切れ長の瞳に、妖しい光が輝く。「だから許してあげるわ。但し、私の質問に素直に答えてくれたらね。いい?タッキー君、なんで私たちを襲ったの?貴方たちみたいなお宅のストーカー坊やたちが、私たちを襲おう、なんて勝手に思いつけるわけないわ。誰かに頼まれたんじゃないの?白状しなさい、誰に頼まれたの?白状したら・・・これ以上苛めるのだけは許してあげるわ。」ゆ、許してあげるだ!?た、タッキーだ!?い、苛めるだ!?未だ自分の立場を、そして礼子の性格を理解できない坊野の頭に血が上る。「ざ、ざけんじゃねーっっっ!!!だ、誰がてめえの言いなりになってたまるか!お、俺を誰だと思ってやがる!な、舐めんじゃねーぞ、だ、誰がしゃべるもんか!てめえの質問になんぞ、絶対に答えてやるもんか!」スッと礼子はブーツを坊野の顔から下ろし、地べたに転がされたまま喚く坊野を見下ろした。「随分威勢がいいわね、タッキー君?でもいい?私の質問には素直に答えた方が身のためよ。もし答えたくないなら、お願いです、答えさせてください、て貴方が泣いてお願いしたくなるようにするまでよ。いい?よく聞きなさい。私の質問に素直に答えないなら・・・拷問に掛けるわよ?」拷問・・・一瞬、坊野の目に狼狽と恐怖の色が浮かんだ。礼子はつい先程手酷く痛めつけられた相手、しかも痛めつけるツボを心得ていそうな相手だ。おまけに今、自分は厳重に縛られていて身動き一つ取れない。一体、どんな目に会わされるのか・・・馬鹿野郎、俺は何を弱気になってるんだ!?相手はたかだか女一匹じゃねーか。俺だって何十回も喧嘩してきたんだぜ、殴られたことなんか幾らでもあるわな!こんなクソガキ一匹に何ビビッテんだよ!こんな女程度に殴られる程度、全然怖くねーだろーが!必死で気合を入れ直し、坊野は地べたから礼子を睨み上げた。「あ?それで俺を脅してるつもりかよ!?この坊野を舐めんじゃねーぞ!誰がてめーなんぞに喋ってやるもんか!殴りたきゃ殴りやがれ!てめーに殴られた程度でな、この俺が詫び入れる、とでも思ってんのか?笑わせんじゃねえ!」ゾクッ・・・喚きながら坊野の背筋に悪寒が走った。礼子は笑っていた。その美しい顔に浮かんだ笑みは親しみ、好感を感じさせるものでない。どこかで見たことのある顔だった。そうだ、この顔、俺たちが拉致った奴らにヤキ入れる時の顔じゃねーか。だが礼子の笑みはなまじ美貌の分、より迫力があった。猫が鼠を弄ぶような、残忍、冷酷、無情な笑みだった。
「言ってくれたわね、タッキー君?いいわ、私の警告を無視するなら、勝手にしなさい。拷問に掛けて泣き叫ばせてあげる。その強がりがいつまで続くか、楽しみね。」傍らでは玲子も同じように、奈良村を挑発していた。「どーお、お目々覚めた、タマナシ君?おっきの時間ですよーお?」漸く意識を取り戻した奈良村の頬を、玲子はブーツの爪先で軽く打った。「・・・う、ううっ・・・て、てめえ、さ、刺しやがったな・・・覚えてろよ・・・ぜ、ぜってーこ、殺してやるからな・・・」「うーん、タマナシ君、君、頭軽すぎない?もしかして君の脳みそ、皺が全く無いツルンツルンなのかな?タマナシ君の細腕じゃお姉さんに勝てないって事くらい、未だ分からないの?学習効果のない坊やねえ。それじゃお猿さん以下でちゅよお?幼稚園からやりなおちまちょうかあ?」幼児言葉でおちょくる玲子にまんまと乗せられ、奈良村は逆ギレして喚き散らす。「っせえ、るせえええ!!!ざ、ざけんじゃねえええっ!ぶっ殺す、てめえだけはぜってーにぶっ殺してやっからなあああ!!!ブバッ!」絶叫する奈良村の唇を玲子のブーツが踏み躙る。「はーい、タマナシ君、お部屋の中でおっきな声を出すのはやめまちょうねえ。そんなに喚かなくても、十分に聞こえまちゅよおお。じゃあね、今度はおねえさんからの質問のお時間でちゅよー。」「質問?ざ、ざけんじゃねえー!てめ、この糞ったれの足をどけやがれ!こ、こんなことしやがって、俺がてめーの質問に答えてやるとでも思ってやがるのかーっ!!!グエッ!」玲子は奈良村の顔を踏み躙るブーツにグッと力を込めた。「たっまなっしくーん!きみはほーんっとうに、おバカですねえー!いいですかーっ?君は今、お姉さんにこてんぱんにやっつけられたあげくに、こうやって縛られてなーんの抵抗もできないんですよー?」スッとブーツをどけ、玲子は奈良村の顔を真上から見下ろす。「よーく聞きましょうねえ。大人しくお姉さんの言うことを聞かないと・・・イタイイタイのお時間にしちゃいますよ?」ゾクッ・・・奈良村の背筋に悪寒が走った。下から見上げる玲子の顔は真剣に美しかった、奈良村が今まで会った全ての女の子の中でも一、二を争うのは間違いない。だが玲子の美貌には危険な毒がある。奈良村を見下ろしながら玲子が浮かべている微笑こそが奈良村の背筋を凍りつかせていた。残忍冷酷、弱者をいたぶる事に楽しみを感じる目。だが玲子の視線はそれだけではない、もっと遥かな残酷さ、いや邪悪さと言った方が正しいオーラを発散させていた。見るものの視線を捕らえ、目を逸らすことすら許さない。邪眼、見るものを破滅に引きずりこむ魔性の瞳。切れ長の玲子の瞳に吸い込まれるように、奈良村は釘付けにされていた。な、なんだ、何で俺はこいつの目をじっと見ているんだ。なんでこいつに、たかが女に気圧されているんだ。玲子は奈良村が動揺しているのを当然のように見下ろしていた。玲子にとっては見慣れた光景だ。フン、そうよ。そうやって怯えているのがあなたにはお似合いよ。「いい?頭の悪い君にも分かるように、はっきりと言ってあげるわね。素直に私たちの質問に答えなさい。さもないと・・・拷問にかけるわよ。君たちのやってきたような、子供騙しのリンチなんかじゃない、本物の苦痛、ていうものを味合わせるわよ?」ゾクッとする、という点で言えば、須崎も背筋に悪寒を感じていた。漸く意識を取り戻した須崎を見下ろしていたのは朝子だった。相変わらずキョトンとした顔に無邪気な微笑を浮かべつつ、朝子が小首をかしげた。「大丈夫?お鼻、潰れちゃったみたいだけど、どう?息できる?」如何にも心配しているような素振りと裏腹に、朝子はブーツの爪先でトントンと須崎の顎を小突いた。朝子の天空脚に割られた顎に激痛が走り、須崎は思わず悲鳴をあげる。「いで、イデデデ!て、てめえ、何しやがるんだ!」「アン、そんな怒らないでよ、別にもう、何かするつもりはないんだからさ。顎がどうなったか心配だから確かめてあげてるだけよ。」そう言いながらも朝子は須崎の顎を小突き続ける。
「いで、や、やめろ!!!」声を出しただけで顎の傷に響き、須崎は全身を身悶える。朝子はちょっと足を振り上げただけで、自分の足元で須崎がうめくのを面白そうに眺めていた。玲子たちのように苛めて楽しんでいる、というのとも違った表情だった。面白そう、ある意味、子供のように純真な、邪心のない表情だった。楽しむ、というより興味深く観察している、といった表情だった。苦痛にあえぐ須崎の顔に恐怖の色が浮かんだ。な、なんだ、なんなんだ、こいつは・・・朝子の目は須崎の知らないタイプの目だった。暴力を楽しんでいるのならまだ分かる。俺だってそうだ。だけど、こいつはなんなんだ!?朝子の目に浮かんでいるのは楽しみではない、興味、純粋な興味だけだった。子供が公園に行って、見るもの全てが刺激に満ちあれなに、これなに、と探求する時の目付きだ・・・いや、この目、どこかで・・・そうだ、昆虫採集、いや採集なんてお上品なもんじゃない、ガキの頃、虫やカエルを捕まえて羽や脚をもぎったり解剖して遊んだ時のあの顔、あの目だ・・・須崎は冷や汗がながれるのを感じた。こいつ、俺のことを人間と思っちゃいねえ・・・俺をいじったらどんな反応するか、俺のことをモルモット扱いする気だ・・・拷問、礼子たちは俺たちが質問に答えなかったら、拷問に掛ける、と言いやがった。たかが女、大して痛くもねーだろうが、こいつは・・・何するか分からねえ・・・
だがその時、奈良村と須崎の弱気を吹き飛ばすかのように坊野の怒声が響いた。「て、てめえら!奈良、須崎!イモ引いてんじゃねーぞ!こんなクソガキどもにビビってんじゃねーだろうな!てめえら、こいつらの言いなりに口割りやがったら、後で俺がぶっ殺すぞ!!!」ビンゴ!礼子は心の中で快哉を叫んだ。いいわよ、その調子!そうやってバーをどんどん高くしてね。バーが高いほど・・・拷問のやりがいがあるっていうものよ!両手を叩いて喜びたいのを必死で堪えながら礼子はブーツで坊野の顔を軽く踏みつけた。「後悔するわよ、タッキー君?私の忠告を聞かないと、痛い目に会うのはあなた自身よ。それに・・・」クスクス笑いながら礼子は続けた。「痛いよう、もう止めてよう、なんでも喋るからお願い、許して、て真っ先にピーピー泣きながら白状するのはタッキー君、君だと思うわよ。」「な、何だとー!ざ、ざけんじゃねえ、何でこの俺が真っ先に白状するっつうんだ!」「まだ分からないの?簡単なことよ。」ああ、いいわ、盛り上がってきたわね。礼子は大きく深呼吸した。「あなたを拷問するのは、この私だからよ。」ぐっ・・・完全に頭に血が上った坊野といえども、流石に礼子の宣告には恐怖を禁じえない。だがその恐怖を振り払うかのように坊野は叫んだ。「る、るせええっ!!!だ、誰がてめえの言いなりになってたまるか!SNOWを舐めんじゃねえ!し、死んでもてめえらには何も喋っちゃやらねえぞ!!!」いい、坊野さん、あなたって最高!本当、最高の盛り上げ方よ!KISSしてあげたい位!ああ、夢にまで見た拷問、最高のシチュエーションになったわ。さあ、たっぷりと楽しませてね。私の生涯最初の拷問を!礼子の美貌に凄絶な微笑が浮かんだ。「そう。それなら仕方ないわ。拷問・・・開始よ!」
4
「これ、何か分かる?」坊野の目の前にしゃがみこんだ礼子が見せたのは数本の鉛筆とボールペンだった。坊野たちが気絶している間に、工場の片隅にあったデスクから探してきたものだ。こ、このアマ、な、何を考えてやがる・・・礼子を見上げる坊野の目線に警戒心に混じって微かに恐怖の色が浮かぶのを礼子は満足げに見下ろした。「フフフ・・・見てのとおり、これは鉛筆とボールペン、種も仕掛けもない、ただの鉛筆とボールペンよ。だけどね、この鉛筆とボールペンが今からあなたに、地獄を見せてくれるわ。単純に殴る蹴る、なんてのとは比べ物にならない苦痛をね。」言い放つと礼子は無造作に坊野の背中に腰を下ろした。「グウッ!て、てめえ、どきやがれ!」坊野は必死で礼子を振り落とそうとするが、厳重に縛られ、身動き一つ出来ないのではどうしようもない。
礼子は坊野の右手薬指を握ったかと思うとぐっと引き上げ、薬指の下を通して中指の上に一本の鉛筆を忍び込ませる。続いて人差指を掴み、鉛筆をその下に進ませる。「準備OK,さあこれ、どういう拷問か分かる?ま、古典的な拷問だから知ってるかもしれないわね。子供の頃、おふざけで友達とやったこともあるんじゃない?だけどね、本気でやれば結構、痛い拷問になるわよ。」言いながら礼子は坊野の太い指に優しく掌を重ねた。一瞬、凄絶な微笑を浮かべた礼子がぐっと坊野の指を握り締める。礼子の掌と言うより、自らの人差し指、薬指に押されたボールペンが坊野の中指に食い込む。「ぐ、グウァアアアッッッ!!!」激痛に坊野は必死で抗い、何とか指を開こうと、何とか礼子の手を振り解こうとする。だが、どうにもならない。もともと礼子が握っているのは坊野の指の内、人差し指、中指、薬指の三本だけだ。いくらパワフルな坊野とは言え、指三本だけでは仮に無条件での力比べだったとしても、並みの男性を遥かに上回る握力を誇る礼子に勝つことは不可能だ。ましてや力の支点となる両肩を外され、普段の力の何分の一かしか出せない上に両腕を厳重に縛り上げられていては、指を開くことも腕を動かすことも、どうあがいても絶対に不可能、むしろ必死で指を開こうとする余り、却って中指を自ら余計強く、ボールペンに食い込ませてしまう始末だった。殴る、蹴るとは全く違う局所的な、一点集中の痛み。それも筋肉ではなく、骨に直接食い込み、ゆっくりと全身を蝕む激痛だった。余りの痛さに眼の奥でチカチカと星が瞬くような気がする。錯覚ではない。激痛に血圧が急上昇し、呼吸まで荒くなっている。指なのに、たかが指一本を責められているに過ぎないのに。細身の女の子に手を握られているに過ぎないのに。その激痛は坊野の意識の全てを支配しつつあった。
「グアアッッッ・・・い。イデエェェェッッッ」悲鳴と共に坊野の全身が苦痛と全身の筋肉に無駄に力を込める反動でビクビクと痙攣する。いい、最高・・・礼子は自分の尻の下で坊野がもがき苦しむ様をゆっくりと堪能していた。耳に心地よく響く絶叫に加え、坊野の痙攣が礼子の尻を通して直に体の奥底を揺さぶる。いいわこれ、最高の気分ね。なんだっけ???そう、ボディソニックチェアだったかしら?あれみたいね!昔懐かしいAVツールを連想しながら礼子は坊野の苦悶をじっくりと楽しんでいた。ふふ、なかなかいい悲鳴じゃない?でもね、まだまだ拷問は始まったばかりなのよ。礼子はゆっくりと手を開き、坊野を一旦解放してやる。「くっ、ううぅ・・・」だが解放されたからと言って、坊野の苦しみは直ぐには終わらない。激しく圧迫され、血行障害を起こした中指に再び血が流れると、麻痺しかけた痛覚が蘇り、ジンジンと痺れるような新たな痛みが走る。「う、ううう・・・」坊野が荒い息をつくのをしばし観察していた礼子がゆっくりと拷問の再開を宣告する。「フフ、そろそろ痛覚も復活したようね。じゃ、拷問再開よ!」「ひ、ひいっ・・・や、やめろ、やめろーっっっ・・・い、イデーッッッッ!!!」
再び礼子がゆっくりと坊野の手を握り締め、ボールペンを食い込ませる。礼子はゆっくりと拷問を繰り広げた。締め上げて坊野を絶叫させ、痛覚が麻痺しかけると緩めて感覚を復活させる。更にボールペンの位置も微妙にずらしながら拷問するので、いつまでたっても痛覚が麻痺してくれず、坊野は延々と新鮮な苦痛を味わう羽目になった。5セット程度繰り返しただろうか、「ぎ、イギャーッッッ!」坊野の悲鳴に混じり、パキッと小さな音が響いた。「あら、ボールペン折れちゃったわ。坊野さん、良かったわね、少し休憩できて。私、まだ休ませてあげるつもりはなかったのよ。」礼子は苦笑しながら坊野の鼻先で真っ二つに折れたボールペンをブラブラさせた。「・・・ハッハッハアッッッッ・・・や、やめろ、もうやめでぐれ・・・」「何言ってるのよ、しっかりしなさい、ほらシャンとする!」ピシーンっ!と礼子は坊野の頬を平手打ちし、喝を入れた。「SNOW CRACKの意地を見せてくれるんじゃなかったの?大体大げさに騒いでいるけど、、大して傷なんかついてないじゃない。ほら、よく見てごらんなさいよ、血の一滴すら流れてないわよ!?」坊野はズキズキ痛む中指をピクピクと動かしながら、礼子が突きつけたボールペンを涙目で見た。「う、うそだろ、なんで・・・」確かに礼子の言うとおり、血の一滴すら付いていない。坊野には見えないが、中指の付け根から第一関節にかけてが紫色、というかどす黒く変色しているがそれも極々狭いエリアに留まっている。「あ、あんなに痛かったのに、なんでだ?なんで傷一つついてないんだ?」散々他人に暴力を振るってきたとはいえ、坊野たちの暴力は単純な、殴る蹴るといったストレートな暴力に過ぎない。痛さと傷はほぼ正比例する。長時間激痛を与えながら、なおかつ傷を余りつけない礼子の技術は坊野の想像の埒外、理解を超えていた。当惑は恐怖に変わり、坊野の中で礼子が得体の知れない怪物に変貌していく。背筋を流れる汗を妙に冷たく感じた時、礼子の凛とした声が響いた。
「さあ、もう休憩は終わり、拷問再開よ!」言うなり礼子は、今度は三本のボールペンを同時に手にした。「ヒッ!こ、今度はな、何をする気だ!?」クスクス、と礼子は楽しそうに笑った。「拷問の趣向を変えるのよ。さっきの責めはもう飽きたでしょ?今度は別の拷問で苛めてあげるわ。」あ、新しい拷問!な、何をする気だ!!!坊野は恐怖の余り失禁しそうになった。だが初めての拷問に興奮している礼子は、坊野に考える暇さえ与えない。一本目のボールペンは人差指と中指の間、次いで二本目は中指と薬指の間、三本目は薬指と小指の間、と礼子は立て続けに三本のボールペンを坊野の指に挟んだ。勿論坊野は必死で抵抗しようとするが、指一本の力など知れているし、そうでなくても先程の拷問でかなり消耗している。礼子は難なく抵抗を排除して拷問の準備を整えた。
「さあ準備完了!どう、もう分かった?今度はどういう拷問か。そうよ、こうやって苛めるのよ!」言うなり礼子は坊野の掌側に三分の一程度突き出たボールペンを左手で纏めるように握り、次いで三角形に開いて手の甲側に突き出たボールペンを右手で掴んだ。「逝くわよ、覚悟はいいわね。」礼子はゆっくりと絞るように右手に力を込める。「ぎ、ぎあっ、や、やべ、いだいいいいっ、いだ、いだ、やべでぐれーーーっ!!!」坊野の絶叫が轟く。突き出たボールペンは梃子の原理で礼子の握力をほぼ二倍に拡大し、坊野の指に伝える。指自体にはクッションになる肉は少ないし、第一横からの力に対しては人体の構造上、いくら力を込めようとも抵抗は殆ど不可能だ。中指と薬指の骨にボールペンが食い込む。外側から、そして真中に挟んだボールペンが両指に食い込み苦痛を更に拡大する。頭の中が苦痛で真っ白になっていく。いたいいたいいたい・・・痛み以外何も感じられない。礼子が強く握ると坊野は殆ど自動的に悲鳴をあげ、緩めると荒い息をつく、また握られて喚き散らす、その無限ローテーション、たった三本のボールペンの拷問だけで、礼子は完全に坊野をコントロールしていた。坊野の感覚の全ては礼子の思うがまま、礼子は自由自在に坊野の苦痛をコントロールし、拷問を楽しみ続けていた。
5
礼子が拷問を開始するのとほぼ同時に、玲子も楽しみ始めていた。「さあタマナシ君、覚悟はいいわね?私は十分に警告してあげたはずよ。それを断ったのは君自身。て言うことは君が自分で、私にお願い拷問してください、ておねだりした、て言うことだからね。これから私にどんな酷い目に会わされたって、それは自業自得というものよ?」悠然と微笑む玲子に奈良村は内心のビビリを必死で押し隠しながら絶叫した。「ひ、酷い目、拷問だあー?て、てめえ何をするつもりなんだよ!?」「別に難しいことをするつもりはないわよ。頭の悪い君でも良くわかるように、拷問の定番商品で責めてあげるわ。」言いながら玲子は再び、ウエストからベルトを引き抜いた。パシーンッ!と二つ折りにしたベルトを打ち鳴らす。「礼子は貴方たちのプレジに結構、何発もベルトをお見舞いしてたみたいだけど、タマナシ君はさっき、すぐ伸びちゃったからたった二発しか私の鞭、味わってないでしょ?だからその分、たっぷりと味あわせてあげるわ。」ヒュンッ!バシーンッ!言いながら玲子が振るったベルトが奈良村の背中を打ち据える。「っあっ!」「何演技してるのよ、役者やのおーーーっ。若いのに芸が上手すぎるわよ。ったく、服着たままで、しかもロープまであるのよ、こんな程度のベルトで痛いわけないじゃない。こんなんじゃ拷問はおろか、SMごっこにすらならないわよ?」
玲子は笑いながらブーツの爪先を奈良村の胸の下に差し込むと、グイッと一気に蹴り転がした。「ギアッ・・・イダイ!」関節を外された肩に力がかかり、奈良村の口から悲鳴がもれた。その奈良村の胸を玲子のブーツが踏みしめる。「な、何をする気だ・・・」奈良村の声が妙に弱々しくなっていく。「一本鞭ならともかく、今日はベルトしかないのよ、拷問っていうからには、せめてこれ位はやらなくちゃね。」玲子はベルトの先端でゆっくりと奈良村の顔を撫でた。「さっきの礼子の鞭、見てなかった?拷問、ていうからにはせめてあれ位の鞭にはしてあげたいな、てお姉さん思うのよねえ。あ、そっか、君はあっさりお寝んねしちゃってたものね。見てなかったか。じゃ、教えてあげる。このベルトでね、たっぷりと君の顔を鞭打ってあげる。遠慮しないでいいわよ。一生懸命抵抗してね。ちゃんと逃げないと、いつまでも引っ叩かれちゃうよ?」スッと右足を奈良村の胸から上げた玲子はそのまま奈良村の胸をまたぎ、仁王立ちになる。
か、顔を引っ叩く?しかもベルトで?思わず奈良村が悲鳴をあげそうになる機先を制し、玲子のベルトが唸る。ヒュオッ!バシーンッ!ギアーッ!したたかに打ち据えられた奈良村の頬が乾いた音を立てる。全く、今から拷問楽しむんだから少し静かにしててよ。貴方は一番弱そうだから、ほっといたら何にもしない内に白状しちゃいそうだわ。暫くは声も出ないように苛めてあげないとダメみたいね。玲子のベルトが立て続けに宙を舞い、奈良村の顔面に襲い掛かる。バウッ!パシッ!ビシャッ!パシーンッ!・・・「ヒ、ヒィッイ、イダイ、ブファッヒギーッッッ!!!!!」立て続けに襲い掛かり顔面を打ち据えるベルトに奈良村は恥も外聞もなく悲鳴を上げつづけた。
「アハハッ、何イタイイタイって騒いでるのよ大げさね!」パシーンッ!と一際高い音を立てて奈良村の左頬を打ち据えると、玲子はグイッとブーツでその頬を踏み躙った。「全く、私、礼子と違って君の目も耳も打ってないのよ?私、さっきから君の頬っぺたしか引っ叩いていないわよ?それをまあイタイイタイってこんなに騒いじゃって、ほんと役者よのおー。その根性、叩き直してあげるわね!」何とも楽しげに言い放った玲子は、ブーツをどけるなり再びベルトの往復ビンタを繰り出す。確かに玲子は奈良村の頬しか鞭打たず、より多くの苦痛を与えられる目や耳は敢えて狙っていなかった。当然だろう、それは必要ないからだ。確かに頬をベルトで鞭打たれるだけでも通常の平手打ちの何倍も痛いだろう。だが実のところ、顔面の痛みは玲子の拷問の半分に過ぎない。今、奈良村は仰向けに横たえられている。脱臼させられた肩、股関節を不自然に折り曲げられながら。玲子に鞭打たれる度に、奈良村は反射的に全身に力が入り、身を捩じらせてしまう。その動きが外された肩、股間に無理な力として伝わり、ねじれ、新たな激痛を呼び覚ます。玲子の本当の狙いはそちらだった。
「ヒッ!ヒイッ!!!やべで、ぶぶっ!」虫けらのように地べたに転がされた奈良村を跨ぐように立ち、玲子は思う存分ベルトを振るいつづけた。「アハハッ!ほらタマナシ君、それでも逃げてるつもりなの?ちゃんと逃げないっていうことは、もっとお姉さんの鞭がほしいのかなー?よーし、じゃぁ一杯ご馳走してあげるわね!」腕、足が動かずしかも厳重に縛られた奈良村にできる動きはただ顔を左右に振る程度、転げまわって逃げることなど到底不可能だ。しかも上から見下ろす玲子にとって、奈良村がどう顔を動かそうが顎を引こうが、動きは丸見え、鞭打つ場所には全く困らない。「アハハハハハッ!そんなに顔振っちゃって、あ、そうか、わかった!右を叩かれたら慌ててそっちを下にしてるってことは、今度は左を叩いて欲しいのね!汝、右の頬を打たれたら左の頬を差し出すべし、てわけね!OK!ご要望通り、たっぷりと鞭打ってあげるわね!」パシッ・・・ビシッ・・・玲子のベルトは休むことなく宙を舞い続け、右から左から間断なく奈良村の頬を打ち据える。いくらベルトとはいえ、十分にスナップを効かせた玲子の鞭だ。通常の平手打ちとは比べ物にならない程の威力を発揮する。ひとしきり打ち据えた玲子が漸く手を休めた時、奈良村の頬は既に内出血に見舞われ腫れ上がり始めていた。あらあら、この分だと綺麗に腫れ上がりそうね。いわゆるサッカーボール状態、てやつ?「う、ああ・・・い、びだい・・・グエッ!」脳天にまで響くベルトの連打にまだクラクラしている奈良村の鳩尾を玲子は踵で踏みつけ、喝を入れた。「フフフ、どうタマナシ君、大分効いてるみたいね。もうやめて欲しい?もう顔面鞭は許して欲しい?」玲子に散々苛められてきた信次たちなら、玲子のこの言葉の裏を、隠された毒を感じることも可能だったかも知れない。だが玲子とは初顔あわせの奈良村にそれは無理だ。奈良村は思わず、救いと信じて偽りの命綱を掴んでしまった。更なる泥沼へ誘うロープを。「あ、ああ・・・や。やべで・・・か、顔は、もう・・・ぶたないで・・・くれ・・・・」「いいわ、わかった。私、こう見えても結構優しいのよ。もう顔はぶたないであげる。安心して。」言いながら玲子は左手からベルトの先端を放すとスッとベルトを二つ折りにした。ああ、よかった・・・どうやらこいつも満足したようだ・・・顔の痛みはまだジンジンと残り、更に内出血の気持悪さを伴う痛みは徐々にひどくなっていたが、奈良村はほっとして全身から力を抜いてしまった。その瞬間、玲子は奈良村の鳩尾に乗せていた踵を再び、グッと踏み込んだ。「グボァッ!」「タマナシ君、勘違いしてない?私、リンチを楽しんでるんじゃないの。今は君を拷問に掛けているのよ。約束通り、顔面鞭はもうお終いにしてあげる。でもね、それは拷問の趣向を変える、てことなのよ?」「ひ、ヒッ!い、な、なにをする気・・・」「怖い?知りたい?いいわ、教えてあげる。今度の拷問はこれよ!」玲子はベルトの先端を握ったまま、バックルのみを放した。バックルがブラブラと宙を泳ぐ。「ひ、ひっ・・・ま、まさか・・・」玲子に蹴り転がされ、奈良村は今度はうつ伏せにされた。「そうよ、漸くわかったみたいね。ご名答。だって体は服を着たままだし、背中はロープであちこちガードしてるでしょ?普通にベルトで叩いただけじゃ痛くもなんともないわよ。だから今度は、このバックルで鞭打ってあげるわね!」「ヒ、ヒイーーーッッ!!!や、やべ・・・ギャァーーッ!!!」ブオッ・・・バズッ!奈良村が悲鳴に似た哀願を叫ぶ暇も与えずに玲子は思いっきりベルトを振るった。先端に大き目の、頑丈な鉄のバックルがついたベルトは先程と明らかに違う、重々しい風切り音を伴って奈良村の体に忍び寄り、鈍い音とともに体に食い込む。十分なスピードを得た鋼鉄の一撃が奈良村の腕、丁度力瘤のできる辺りを打ちのめした。「ぐ、グブアアアアア・・・」骨まで響く痛みに奈良村は悲鳴すら上げられずに口をパクパクさせながら痛みに呻吟していた。「アハハハハッ!どう。タマナシ君、結構効いてるみたいじゃん!?やっぱ、この位痛くないと拷問されてる、て気がしないでしょ?さあ、ガンガン逝くわよ!」残忍な笑みを浮かべながら、玲子は全力を開放して立て続けに奈良村にバックルを叩きつける。「ウギャアァッ!ヒグッ、ガッ、ア゛ア゛ッ、イ゛ガア゛ア゛ア゛ッ!!」獣のような、悲鳴とも絶叫ともつかぬ咆哮をあげながら奈良村は玲子の鞭に呻吟しながら床をのた打ち回った。いや、のた打ち回った、と感じているのは本人だけで、実際には縛られた全身をビクビク痙攣させていただけなのだが。
6
ふう、二人ともよくやるわね、もう、ほんと、好きなんだから。玲子たち二人が嬉々として拷問に興じるのを朝子は半ば苦笑しながら眺めていた。朝子の足元には鼻と顎を蹴り潰された須崎が横たわっている。拷問ね・・・じゃ、私はこの人の担当拷問官って役回りか。まあいいけど・・・全く・・・朝子は些か面倒くささを感じていた。拷問が楽しくない訳じゃない。朝子とて玲子に十分に感化された身、他人を痛めつけるのは大好きだ。だが単純に鞭を楽しむならともかく、この場で咄嗟に効果的な拷問を考えろ、と言われては些か困ってしまう。うーん、何したらいいかな。あんま、いい手考えつかないな・・・蹴り潰した鼻や顎でもグリグリしてあげようかな?でも、それもしつこいだけで想像力にかけるわね。なんか、いい手ないかしら?「ねえ須崎さん、成り行き上、私があなたのこと拷問してあげなくちゃいけないみたいなんたけどね、どうしたらいいかな?あんまりいい拷問考えつかないのよね。折角だから一緒に考えてよ。ねえ、どんな拷問して欲しい?何か希望はある?」問われた須崎の方が言葉につまる質問だった。こ、こいつ、何考えてやがるんだ?お、俺の顎、割りやがって、その俺にどう拷問したらいいか考えろだと?お、俺を、自分を拷問する方法を考えろだって?こ、このクソアマ、舐めやがって・・・思わず怒鳴ろうとした須崎だったが、口を動かした途端、顎の激痛に言葉すら発せられずに思わずうめいてしまった。グウウ・・・激痛が須崎の頭に僅かに冷静さを呼び戻す。痛みを堪えながら見上げた朝子の表情を須崎は一生忘れられなかった。
朝子の表情、須崎が想像していたそれは、他人を苛めることを心底楽しんでいる、肉食動物、ネズミを弄ぶネコのような表情だった。だが実際の朝子の表情は先ほどのファイトと同じく、ちょっと小首をかしげ、キョトンとした、どこか困ったような表情だった。楽しむ、といった感じはどこにもない。だが同時に須崎の痛みなど痛みとしてすら認識しない、いや意識すらしなさそうだった。どこかモルモットを見る科学者を連想させる表情だった。得体のしれない、今まで自分が会ったことのないタイプの恐怖に須崎は思わず言葉を失ってしまった。「ねえ、ねえったら!聞いてる?どう拷問したらいいか、一緒に考えてよ!」朝子は少し苛立ったような声をあげた。そ、そんな・・・何を言ったらいいかも分からず呆然としている須崎に苛立ったように、朝子は須崎のポケットに手を突っ込んだ。「もう、須崎さんたちは喧嘩やリンチ、いつもやってるんでしょ?何かいい道具持ってるんじゃないの?貸してよ!」「や、やめろ!い、いや・・・」確かに須崎も獲物を持っていた。朝子に見つかるのを恐れた獲物、それは大型のメリケンサックだった。巨体の須崎に相応しい大型のメリケンサック、それで割られた顎や鼻を殴られたら!だが予想に反し、朝子はメリケンを面白そうにいじくりはしたものの、さして興味を示さなかった。「ふーん、こんなもん持ってたんだあ。ああ怖い。こんなもんで殴られてたら、私の折角の美貌が台無しになるところだったわ。ああ怖い。」折角の美貌、そりゃ確かにてめえツラは綺麗だとしてもよ、自分で言うんじゃねえ!心の中で悪態をついた須崎だが、一瞬後、その顔が凍りついた。朝子が大きな瞳をキラリと輝かせながら、ある物を握り締めたのだ。それは・・・大型のZIPPOライターだった。
「いいもの見つけちゃったっと!」クスクス笑いながら朝子はZIPPOの蓋を開け閉めした。玲子と違って朝子はタバコは吸わないが、ライターの着け方位はわかる。拷問を楽しんでいる玲子たちの方をひょいと見てから再び須崎に向き直った時、朝子はついさっき迄の困ったような表情とは一変し、新しいオモチャを与えられた子供のようにワクワク、ウズウズした笑顔を満面に浮かべていた。「玲子たちは鞭とペンで楽しんでいるみたいだから、私はちょっと趣向を変えようね。だーいじょうーぶよ!こう見えても私、結構優しいんだから、痛い思いはさせないわよ、安心して。」須崎の顔の前にしゃがみこみ、朝子はゆっくりとライターを弄んだ。「やや、やめろ・・・や、やめろよ・・・な、なにするきだよ・・・・」須崎の顔が恐怖に歪んでいく。ウフフ、バカみたい、こんなに怯えちゃって。まだなんにもしてないのにね。シュボッ、ヒッ!朝子がライターを灯した瞬間、須崎の口から思わず悲鳴が漏れた。眼前10センチに灯された炎。今まで無数に見てきたものだし、タバコを吸うときはもっと近くで着ける。だが今はわけがちがう。縛られて身動き一つできない自分。そして自分の目の前でライターを灯し、楽しそうにクスクス笑う美少女。そして、その美少女が可愛いルックスとは裏腹に、他人を傷つけることを何とも思っていないことは先刻、たっぷりと身をもって味合わされたばかりだ。今の須崎にとって目の前のライターの炎は、タバコに火をつけるためのちっぽけな炎ではなくなっていた。それは原始の炎、野獣が本能的に恐れた、克服しようのない恐怖に膨れ上がっていた。「須崎さん、す、ざ、き、さん!ねえ、ねえったら!!!」パンッ!朝子の平手打ちに漸く須崎は現実に引き戻された。まだ何もされていないのに既に全身油汗まみれだ。「ねえ、私、これからどうするかわかる?どうやって拷問するのか、わ、か、るーっ?」わからない訳がない。文字通り火を見るより明らかだ。だが、そんなことを自分の口から言えるわけがない。「や、やべ・・・ゆ、ゆるじで・・・」「あん!そんな泣き声ださないでよ!何言ってるかわからないじゃない!ねえ、私、どうやるかわかる?て聞いてるんだよ!?簡単でしょ、答えてよ!答えてくれないなら・・・火炙りの刑だぞー!」朝子がグッとライターの炎を須崎の鼻先に近づける。「ヒアッ!あ、熱い!や、やめて、火炙りだけは許してくれーっっっ!」もはや恥も外聞もない、須崎は絶叫し、何とか逃れようと必死で全身をくねらせる。
「キャハハハハハッ!わかってるじゃない!そうよ、火責めにしてやるわ!」拷問開始を宣告するや否や、朝子はピョンッとジャンプした。ドスッ!グエッ!見事に須崎の背中のど真ん中にヒップドロップで着地した朝子は須崎の指先にゆっくりと炎を近づけていった。「さあてっと!じゃ、拷問開始っ!朝子の火責め拷問、たっぷりと楽しんでね!」笑いながら朝子はゆっくりとライターの炎を須崎の指先に近づける。「イアッ!ヤ、ヤメ、ア、アヂッ!アヂアヂアヂイイイッッッ!!!」早くも須崎の絶叫が轟いた。「アハハハッ!もう大袈裟なんだからっ!私、まだ近づけただけだよ。直火でもないのに、もう大袈裟ね。」朝子は一旦遠ざけた炎を再び近づけていく。「ねえ、須崎さんって随分毛深いのね。指にまで毛がこんなに生えてるのって、ウザくない?毛焼きしてあげようか?」チリッ、チリッと炎の先端で須崎の指の毛を炙ってみる。「ギャッ、アヂイ、ヤ、ヤベロ、ヤメ゛デグレーーーッッッ!!!」必死の絶叫をあげつつ須崎は何とかのがれようと必死で手を動かそうとするが、しっかりと縛り上げられたロープはびくともしない。須崎にできるのは半ば本能的に、両手を必死で握ったり開いたりとバタバタさせるのみだった。だがその程度の動きは須崎の背中にどっしりと腰を据えて火責めを楽しむ朝子にとって、何の妨げにもならない。手の動きで多少は風が起き、炎を揺らしてはいるものの強風の中でも火が消えないように設計されているZIPPOだ。消える心配など全くない。むしろ手の動きと相俟って須崎の指を不規則に炙り、満遍なく熱を伝えるのには却って好都合だった。熱さに加えて、後手に縛られた手を炙られている須崎は朝子の動きが全く見えない。気まぐれにライターを動かし、指先から手首までのあちこちを炙る朝子の炎が全く見えず、次にどこを炙られるのか全くわからないことが須崎の恐怖を一層掻き立てる。「ヒアッ!アヂイ、アヂイヨーーーッッッ!イアッ!ピギイ゛゛゛゛!!!」
朝子にとっては何とも楽しい拷問だった。殆どなんの労力も使わない、単にライターの炎をちょっと近づけたり遠ざけたりするだけで須崎が全身を痙攣させ、苦悶の絶叫を張り上げる。上から見下ろすと須崎の苦悶の動きは激しい、というよりむしろコミカルとさえ言えた。最高!こんなお手軽拷問なのに効果絶大じゃない!あたし冴えてるーっ!火責めを楽しむ朝子の瞳が、ふと須崎の指の変化を捉えた。あら、これ何かしら?須崎の指のあちこちに半透明というかやや白っぽい水泡ができつつあった。何、この膨らみ、なんか気持ち悪いな・・・一瞬戸惑った朝子だったが、直ぐにその正体に気づいた。あ、なーるほどね、熱が中まで通って水泡が出来てきたって訳なんだ。あーあ、可哀想に。火傷の水泡って痛いのよねえ。なかなか治らないし。クスクス笑いながら朝子は更に炎を近づけてみた。「ギャアッ!アヅ!イヤ!ヤベヤベヤメテグレーーーーッ!!!」チリチリと須崎の指の毛がカールしながら焦げていく。毛が焼け焦げる嫌な臭いと、屈託なく更に楽しそうに笑い転げる朝子の笑い声が須崎の悲鳴に重なっていった。
7
坊野、奈良村、須崎の三人が拷問に呻吟している中、ポツンと未だ静かな一角があった。富美代と検見川の一角だった。坊野たちの方に顔を向けたままうつ伏せに転がされている検見川は恐怖に震えていた。拷問、と聞いても最初は所詮お嬢様連中、単に殴る蹴る程度だろ、とタカをくくっていたが、目の前で繰り広げられているのは本格的、あまりにも本格的な拷問だった。今まで聞いたこともないような三人の絶叫は検見川を震え上がらせるに十分なものだった。そして、自分の目の前にしゃがみ込み、じっと自分の目を見ているのは、自分が騙し、レイプしようとした当の富美代なのだ。どんな目に会わされるのか、検見川は恐怖に震えていた。こんなに怖いのは生まれて初めてと言ってもいいほどだった。富美代が何も言わず、じっと自分を見つめているのが余計に怖かった。
「・・・何震えてるの、先輩・・・」ポツンと富美代が声を発した。「・・・怖いの?坊野さんたちがあんな拷問されてるから?怖いの先輩?私に拷問される、て怯えてるの?」静かな、どこか哀しげな声で富美代は語りかけた。その静かさに検見川は縋り付いた。な、なんでもしてやる!あ、あんな目に会わされる位なら、なんでもしてやる!「あ、ああ、怖い、怖いよ。なあ、許して、許してくれよ。冗談、冗談だったんだよ。なあ、頼む、頼むから・・・ほどいて、ほどいてくれよ・・・頼む、頼むよ・・・俺を、あんな目に、あんな目に合わせないでくれよ・・・なあ・・頼むよ・・・」検見川は必死で哀れみを乞う表情を作り、自分的には一世一代の名演技で何とか富美代を口説き落とそうとした。相変わらず静かに見下ろす富美代の瞳に、微かな悲しみの色が浮かんだ。
「・・・そう、怖いんだ。先輩、怖いんだ・・・だけどね、私だってさっき、とってもとっても怖かったんだよ。でも先輩、私のことなんか全然心配もしてくれなかったね。今だってそう、私のこと傷つけて悪かったなんて、全然考えてもくれてないんでしょ?自分が痛い目に会いたくない、それだけなんだね・・・私のことなんか、何にも考えてくれてないんだよね・・・」「ち、違う、そ、そんな、そんなことない!違う、ちがうーっ!わ、悪かった、悪かったよ、許して、頼む、許してくれよーっ!」「・・・先輩、なんでそんなに必死で叫ぶの?本当は悪かった、なんてこれっぽっちも思ってないんでしょ?なのに何でそうやって謝るの?私が怖いから?私に苛められる、て思うから?私も礼子たちと同じ、他人のこと平気で痛めつけられる女の子だと思うから怖いの?ねえ、何で?要するに先輩、痛い目に会うのが嫌なだけなんでしょ?」図星、ご名答。だがそれを認めるわけにはいかない。検見川は必死で取り繕おうとした。「ち、違う、ほ、本当だよ、し、信じて、信じてくれよーっ!ほ、ほ、本当に悪かったって思ってる!な、何でも、何でもするから、だから、だから頼む、ゆ、許して、許してくれーっっっ!!!」這いつくばったまま半べそをかきながら必死で哀願する検見川を見下ろす富美代の瞳から一滴、大粒の涙がこぼれると同時に耐え難い程の嫌悪感が浮かんだ。「・・・嘘つき・・・未だそうやって嘘をつき続けるんだ・・・私みたいなバカな女の子なら、そうやって舌先三寸でどうとでも言いくるめられる、て未だ思ってるんだ・・・嘘つき・・・最低・・・!」ペッ!富美代は必死で喚き立てる検見川の鼻先に思いっきり唾を吐き掛けた。ベチャッ、ウッ!思わず反射的に睨み返したくなるのを堪えながら検見川は必死で哀願し続ける。つ、唾なら、唾程度ならいい。あ、あんな、あんな拷問される位ならなんでも、なんでもする!「た、頼む、頼むよ富美ちゃん、し、信じてくれよ・・・つ、唾を掛けたくなるのもわ、分かるよ。ひ、酷いことしちゃったからな。それで気がすむんなら、い、いくらでも唾かけてくれ!で、でもし、信じてくれよ、お、俺はな、なんにもするつもりなかったんだよーっっっ!!!」富美代の切れ長の瞳に嫌悪感を通り越し、怒りの色が浮かんできた。「・・・最低・・・未だ言うの・・・じゃあ、これは何なのよ、これは!」
富美代は検見川の尻ポケットに手を突っ込むと、隠し持っていたバタフライナイフを取り出した。「何なのよこれは!?先輩、女の子とのデートにナイフを持ってくのがノーマルだ、とでも言うつもりなの?答えてよ!」あ、アワワ!ま、まずい、まずい!!!な、何とか、何とか誤魔化さなくちゃ!!!検見川は必死で言い訳を探し、頭をフル回転させた。「、それは・・・そう!そうだよ!ほら、最近何かと物騒だろ?だ、だから、誰か悪いやつに襲われたら危ないだろ?だ、だから、そんな時にふ、富美ちゃんを守ってあげるようにって思ってもってたんだよ。な、ほんと、本当だよ!「私のことを守るため?先輩が?私たちをレイプしようとした先輩が?・・・ねえ先輩、言ってて恥ずかしくない?よくもまあ、いけしゃーしゃーとそこまでペラペラと嘘を並べられるわね。」富美代の美貌が青白い炎のような怒りで静かに燃え上がった。「先輩、こんな格好いいイケテル顔してるのに、先輩って最低最悪ね!先輩の中には絶対悪魔がいるのよ。私が悪魔祓いをしてあげる。先輩の腐った根性、私が根本から叩き壊してあげるわ!」富美代はスッと立ち上がると同時に検見川の肩を蹴り上げ、うつ伏せに転がした。外された肩が捩じれ、うめく検見川の顔の横にしゃがみ込むと、富美代は手にした検見川のナイフをカシッと起こし、その刃で検見川の頬をピタピタと叩いた。検見川の全身が恐怖に震える。「ヒッ!ヒッ!な、何を、や、やめて・・・」「怖いの、先輩?これ、先輩のナイフでしょ?自分が散々使ってきたナイフなのに、何をされるかわからないの?じゃあ、私から質問よ。先輩、ナイフはどうやって使うものなの?刺すの?こうやって刺すものなの?」言いながら富美代はナイフの切っ先を検見川の頬に押し当てた。刺さるほどの力は加えていない。だが、チクリとした痛みだけでも検見川の恐怖を更に煽るのには十分だ。「い、イヤーッ!や、やべ、おねがいだーっ!」検見川の絶叫を暫く観察していた富美代は一旦、ナイフをすっと外した。「う、ううっ・・・お、おねがいだ・・・お願いだから刺さないで・・・」すすり泣きながら哀願する検見川を見下ろす富美代の顔に残酷な微笑が浮かんできた。
「フーン、そんなに怖がるってことはどうやら、ナイフは刺すのが正しい使い方なのね。いいわ、先輩、一つ安心させてあげる。私、このナイフで先輩のこと、刺したりしないわよ。約束してあげる。」「ああ、あ、ありがとう・・・」涙と涎で顔中グシャグシャになりながら、検見川は思わず富美代に礼を言ってしまった。「ありがとう?そう、刺されなくて良かったわね。」言いながら富美代は再びナイフを検見川の顔に近づける。「ヒ、ヒイーッッ!さ、刺さないって約束したじゃないかあーっ!!!」「そうよ、先輩、刺さないって約束したわ。だから、刺さないで切り裂いてあげる。先輩のこの顔を。先輩、イケテルこの顔、ご自慢なんでしょ?この顔で私みたいなバカな女の子を何人も騙してきたんでしょ?ウフフ、でも可哀想。今日限りもう二度とそんなこと、できなくなるわね。この顔に二度と消えない傷を刻み込んであげる。思いっきり派手な、隠しようのない傷を刻んであげる。先輩、そんな傷のあるスカーフェイスじゃ、二度と女の子を騙せないわね。」「イ、イヤーッ!や、やめてくれーっっっ、か、顔は、顔だけはやめてくれーっっっ!!!」富美代の見抜いた通り、検見川の最大の自慢はそのルックス、要するに顔だった。だからその自慢の顔を傷つけられる、それも一生消せない傷を刻み込まれる、というのは検見川にとって何よりの苦痛だった。
富美代は必死で叫びながら顔を振り、何とか逃れようとする検見川の髪を鷲づかみにし、次いで膝で額をゴリゴリと音がしそうなほど強く押さえつけた。「ヒッ、イ、イダイ!」「大丈夫、大丈夫。直ぐにこんなの痛いと感じなくなるわよ。だってこうするんだからね!」富美代は握り締めたナイフを検見川の左頬にグッと押し当てると、まるで刺身を引くようにナイフの刃全体を使い、一気に検見川の頬を引き切った。深く、より深く傷を刻もうと手にたっぷりとウェイトをかけ、ナイフを少しでも検見川の顔の奥に食い込ませようとしながら、富美代は検見川の頬を縦に切り裂いた。「ギ!ギアーッッッ!!ヤ、ヤベデーッッッ!!!」ズパッ・・ナイフの先端が検見川の顎の辺りを通過し、顔から離れるのを追いかけるように検見川の顔に赤い線が走り、プツップツッと血の赤い玉が湧き出した。ふーん、これが人を切る感触なんだ。なんかお刺身切る時とあんまり変わらない感じだな。でも、結構いい手応えね。血は直ぐに繋がり、後から後からとめどなく流れ出し、検見川の頬を染めていく。「ビャアーッッッ、か、かおがーっ、お、俺のかおがーっっっ!!!ああ、あぢい、アヂイヨオオオオオッッッ!!!」だが富美代は泣き喚く検見川に一切構わず、今度は鼻の横辺りに、丁度顔を横切るようにナイフを当てる。「アハハハッ!先輩、いい傷じゃない!先輩みたいな人でなしでも、一応血は赤いんだ!私、先輩の血はどす黒いんじゃないか、て思ってたよ!?赤い血で良かったね、先輩、じゃあもっと、もっともっと一杯血を流してあげる!」ズリュッ!「イ、イアーッッッ!!!い、イデエ、イデエヨーッッッ!!!」「アハハッ、アハハハハッ!どう先輩、思い知った?もうこの傷、一生消えないわよ!アハハッ、アハハハハッ、アハハハハハハハハッ!」富美代はゆっくり立ち上がると、左頬に深く長い傷をまるで十文字のように刻まれ、激痛に泣き喚く検見川を見下ろしながら狂ったように高笑いした。「ア、アアアッッッ・・・お、おれの、俺のかおがーっ、い、いでえ、いでーよーっ!あ、あんまりだ、あんまりだあああーっっっ!!!」泣き喚く検見川を暫く楽しんでいた富美代は、やがてゆっくりと右足をあげ、思いっきり蹴り付けるように検見川の血塗れの顔を踏み付けた。「いいザマね、先輩。でもね、まだまだ終わりじゃないのよ。こんなんじゃ拷問にもリンチにもなりはしないわ。先輩、先輩は私の心を踏み躙ったわ。土足で踏み躙ったのよ。こんなちっぽけな傷じゃ、私の心の傷の万分の一にも足りないわ。」「い、いや、もうやべでグブァッ!」検見川の哀願を踏み潰しながら富美代は続けた。
「先輩、このブーツどう?先輩が赤、大好き、て言うから何軒も何軒もはしごして、必死で探してやっと見つけたブーツよ。先輩のために買ったブーツなんだから、先輩の体でたっぷりと味わってね。町で女の子のブーツを見たら、赤い靴を履いている女の子を見かけたら、それだけで体が震える位の、一生消えないトラウマを刻み込んでね。折角の先輩のためのブーツなんだから!」冷たく言い放つと富美代はブーツの銀色に光り輝くメタルピンヒールを検見川の頬の傷、タテヨコの傷が丁度クロスするポイントに押し当てると、一気に全体重を掛けて踏み込んだ。「ブ、ブビャァーッッッ!ビ、ビダイ゛―!ッッ!!ア!アブァバババーッッッ!!!」断末魔のような絶叫がフロアに響く。「ほらほら!たっぷり味わってよ先輩!先輩のためのブーツなのよ!どうなの、おいしい?うれしい?ほらほら!ブーツでピアスしてもらうなんて、一生二度と出来ない経験でしょ?たっぷり楽しんでよ!ほらほら、どう、どうなのよ!何とか言いなさいよ!」富美代は全体重を掛け、ギリギリとブーツのヒールをめり込ませる。「ギャ、ギヒーッッッ!イ゛ア゛―アッッ!!!」検見川の絶叫は悲鳴とも泣き声ともつかぬ、獣の断末魔のような、聞く者の耳から一生消えないような凄まじいものになっていた。無理もない。如何に鋭いピンヒールとは言っても基本的には歩くための、人間の体重を支えるためのものだ。錐や尖針とは違い刺し貫くためのものではない。そのヒールで頬の肉を、如何に深く刻み込んだ傷口だとは言っても、人間の肉体を踏み破ろうというのだ。簡単に刺し貫けるわけがない。針で刺し貫かれるなら数秒で刺し貫かれる分、まだいい。だが富美代は本来、刺さるわけのないブーツのヒールで検見川の頬に穴を開けようというのだ。富美代はヒールに全体重をかけながら、右に左にと激しく足首を捻り、検見川の顔を踏み躙り続けた。刺さるのではない。富美代がブーツで踏み躙る動きに連れ少しずつ、少しずつ、検見川の頬の筋繊維がヒールにこすられ、すり潰され、引き千切られていく。刺されるのより何百倍も痛い。おまけにそう簡単に穴があくわけではないから、たっぷりと時間をかけて検見川は地獄の苦しみを味合わされる。「イヴァッ、イビギャアアアアアッッッ!!!」検見川は間断なく断末魔のような悲鳴を上げ続ける。そうよ、先輩、その声よ。もっともっと、もっともっともっともっと苦しむのよ、泣き喚くのよ!私、さっき一生で一番傷ついたんだから。一番泣いたんだから。だから負けない。先輩なんかに負けない。私よりもっと泣かせてあげる!先輩を私よりもっともっと、100倍たっぷりと泣かせてあげる!
1ミリ、また1ミリ、ゆっくりゆっくりと富美代のブーツは検見川の肉を血管を神経を引き千切りながら進んでいく。やがて富美代はブーツを通して感じる抵抗が少し軽くなったのを感じた。うん?どうしたのかな?構わずブーツを捻じ込み続けると最後にまた少し、固いというより妙に弾力のある抵抗を感じた。ったく、しぶといわね。富美代は一瞬、ブーツを少し持ち上げるとグッと勢いをつけ、思いっきり踏み込んだ.「ギ、ギアーッ!ウ!ウブアッッッ!!!」突然、富美代はブーツのヒールにかかる抵抗がなくなり、検見川の頬をヒールが一気に貫通するのを感じた。同時に、口の中に侵入した富美代のヒールと踵全体が頬にのしかかったことにより、検見川の悲鳴は瞬時にして押し殺された、なんとも苦しげな悲鳴に変えられてしまった「アハハハハハッ!やった、やったわ!どう先輩、少しは思い知った?私のブーツの味は如何?良かったわね、これでほっぺたに特大ピアスを嵌められるわよ。ピアス、通しやすいようにもっと穴を大きくしといてあげるわね。ほら!ほら!ほら!」富美代は高笑いしながら足首を、いや脚全体を使ってブーツを前後左右、円を描くように大きく振り動かした。どう先輩、痛い?苦しい?許して欲しい?でも駄目よ。絶対に許してあげないんだから!私、今日が終わったら先輩のことなんか、ぜーんぶ、綺麗さっぱり忘れてやるわ!先輩なんかよりずっとクールな彼氏も作って、一杯一杯ハッピーになってみせるわ。だけど先輩には私のこと、絶対に忘れさせてあげない!この傷が疼くたびに私のこと、思い出してね。鏡に写るこの傷見る度に、私のこと思い出してね。一生私の影を引きずって生きていってね。醜い傷だらけのスカーフェイスで。先輩、これから一生死ぬまでずっと、思いっきり不幸な人生を送ってね。どうか先輩の一生に、今後いいことなんか一つもありませんように。それが私のことを傷つけた報いよ。一生かけて償ってね!メリ、ミリ、ベリ・・・「ビ!ビア゛ア゛ア゛ア゛!!ヤ、やべで、ざ、ざげるーーっっっ!!!」検見川は自分の顔が引き裂かれる音を確かに聞いたような気がした。痛い、などという言葉では生ぬるい。今まで人生で経験した痛みを全部合計しても遠く及ばない、発狂しないのが不思議な位だった。しかも頬を貫通したヒールに口の中を掻き回され、悲鳴をあげることすらままならない。その悲鳴は富美代の全身に浸み透るようだった。ああ、いい気持ち。ブーツ越しに、検見川の頬を引き裂く感触と全身を間断なく痙攣させる検見川の苦悶が伝わってくる。富美代の耳は断末魔のような検見川の悲鳴に満たされている。そして足元を見下ろすと、自分のブーツに縫い付けられ虫けらのようにのたうち回る検見川の無様な姿と、頬から、口の中から溢れ出る真っ赤な鮮血で床が血の海のようになっているのが見える。ああ、いいわ・・・癒される・・・先輩が私の拷問で苦しんでいる・・・私を傷つけた報いを受けている・・・地獄に堕とされた検見川の苦悶が、富美代の傷ついた心に無上の癒しとなって浸み透っていく。
だが癒し、と言っていられるのは責め手の富美代だけだ。拷問されている検見川にとっては癒しどころではない、凄まじい激痛に間断ない悲鳴をあげるのが精一杯だ。余りの凄まじい悲鳴に、礼子たち三人まで自分の拷問を中断して富美代のところにやってきてしまったほどだ。「ワオッ!すっごーい、完全に貫通してるじゃない、フミちゃん凄い事するわねえ。」「うわ、ほっぺた裂けてるじゃない、いったそー!」「でもさ、なんか綺麗じゃない?だってフミちゃんのブーツ、メタルヒールじゃない?銀色のヒールと血の深紅のコントラストって、なんか綺麗じゃない?」富美代のブーツに踏み貫かれ、床に縫い付けられた検見川の前にしゃがみ込んで礼子たち三人は口々に感心したような声をあげた。「あ゛、あ゛あ゛あああ、だ、だすげで・・」検見川の目は涙でかすみ、もう誰が目の前にしゃがんでいるのかさえはっきりとは見えない。だが必死で哀願せずにはいられなかった。「こ、ごろざれる・・」だが、その哀願は全くの逆効果、検見川本人だけではなく、SNOW CRACK全員をより深い地獄に引きずり込んでしまっただけだった。
「助けてですって?先輩、まだ言ってるの?今更誰が助けてくれる、て言うの?私が許すとでも思ってるの?許してあげるわけなんかないでしょ?まだ思い知ってないようね。ええ、どうなのよ!ほら、もっともっと懲らしめてあげるわ!ほら!ほら!ほら!」「ギ、キヒーッッッ!イア、イダイ゛゛゛゛!!!」富美代が暫く休めていた足首を再び回転させ、検見川の頬を更に引き裂きにかかる。ガッ、ガッ、あん、なによこれ、硬いわね!富美代はイラついたように何度もブーツを蹴り込むような動きをした。「イ゛イ゛アーーーッぼ、ほねぐぁ、お、おれるーーーっ!!!」白い顔を真っ赤に興奮させた富美代も漸く気づいた。ああ、頬骨に当たってたのね、全く邪魔なんだから!ズボッと富美代はブーツのヒールを引き抜いた。銀色のピンヒールに検見川の血がこびり付き、不規則なストライプを描いている。「ひ、ひあっっっ・・」検見川は半失神状態で頬から、口から血を垂れ流している。いくら痛くても、傷口を手で押えることすらできない。止めどもなく血を、涎をだらしなく垂れ流しながらうめくだけしかできない。だが冷酷な拷問官と化した富美代は検見川に僅かな休憩すら与えない。「ほら先輩、誰がもう終わりって言ったのよ!許してなんかあげない、て言ったのが聞こえないの!?さっさと右のほっぺたも出してよ!」ガッ!「ブギャッ!」顔が捻じ曲がる位、思いっきりブーツの爪先で顔を蹴り上げられ、強引に反対側を向かされた検見川の右頬を富美代のブーツが踏み付ける。「フフフ、さあ先輩、片方だけじゃバランス悪いわよ。聖書でも汝、右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ、て言うでしょ?こっちにも大穴、開けてあげるわね!」凄絶な笑みを美貌に湛えながら富美代はナイフを拾い上げた。「・・ねえ礼子、私たち、少しぬるかったようね。」「全くだわ。私たちの拷問なんかフミちゃんの責めに比べたら、ほんの子供だましね。ちょっと手加減しすぎたようね。朝子はどう思う?」「ええー、ぬるかったかなあ?結構熱そうだったけどねえ・・でも、やっぱりもっと、逝くとこまで逝っちゃえ、て感じかな?」玲子たち三人の顔にも富美代と同じ、凄絶な笑みが浮かんだ。小さく頷き合うと、三人の拷問官もクルリと踵を返し、三方に待つそれぞれの担当受刑者へと向かっていった。拷問が再開され、そして過熱する時間が訪れた。
「な、なんでここに!!!」「い、いつからいたの!!!」慎治たちの金切り声にも似た悲鳴が響く。眼前で繰り広げられた予期せぬ光景に100%の神経を集中していた慎治たちは、背後に迫っていた真弓と里美に全く気付かないでいた。不意に声をかけられ、心臓が飛び出そうな顔をして口をパクパクさせる慎治を真弓は面白そうに見ていた。「なんでここに、ていうのは私たちが聞きたいんだけどな、ねえ里美?」「全くよね。ま、種明かしをしてあげるとね、私たちは玲子に頼まれてたのよ。ほら、玲子たちの家庭教師の良治先生たち、あの二人にランクル出してもらってね、ずっと玲子たちの後を追って、万が一に備えてたのよ。で、玲子の予想通り連中、玲子たちをここへ連れ込んだじゃない?だから私たちも追っかけて、中が見えるポイントを探したって訳よ。」「そう、玲子にはもし連中が予想以上に強くて玲子たちが危ない状況になったら、速攻で警察呼んでくれ、て頼まれてたからね。2階からなら中の様子も見えるかな、て思ってきたら、予期せぬ先客がいた、て訳よ。まあ最も、良治先生たち、表で待ち構えてるけど木刀とかヌンチャク用意してやる気満々みたいだったから、万一の時は警察が来る前に連中、秒殺されてたと思うけどね。」
な、なんてことだ。全て読まれていたんだ。せ、折角ここまで玲子さんたちを誘い込んだのに、はなから無駄だったんだ。玲子さんたちは、自力でSNOW CRACKを潰せればそれでよし、もし負けても即警察呼んで、助けて貰えるようにしてたんだ。どっちに転んでも、僕たちが仕返しなんかできなかったんだ・・・慎治たちの脳裏に良治たちの逞しい肉体が浮かんだ。十二分に鍛え上げた巨体、しかも空手三段、剣道二段だ。大会で入賞できるレベルではないとはいえ、この二人のレベルで木刀やヌンチャクを使えば、ストリートでははっきり言って手のつけようがない。SNOW CRACKだ、なんだと言っても所詮は素人、ナイフやバット程度用意しても全くの無意味、四人ともあっという間に叩きのめされていただろう。玲子の用意周到さは慎治たちの想像を遥かに上回っていた。な、なんてことだ・・・
よく見ると真弓も里美も革ジャンにブルージーンズ、足元はブーツで固め如何にもいざとなれば一緒に参戦するよ、というスタイルだ。だがそんなことはどうでもいい。問題は玲子たちに陰謀が全て露見した、ということだ。慎治たちの心臓が喉からせり上がる。膝がガクガクと震える。胃がキリキリと痛み下腹部が締め上げられるように痛む。恐怖の余り居ても立ってもいられない。「あ、ああ・・・」「ち、ちが、ちがう!!!」反射的に二人はなんとか誤魔化そうとした。「ち、ちが、ちがう・・・ぐ、偶然、ほらね、偶然なんだよ!!!」「そ、そう、ね、僕たちた、たまたまこ、ここ、ここを通りがかったらさ、玲子さんたちが連れ込まれるのがみえて、そ、そう、助けようとしたんだよ!そ、そうだよな、なあ慎治!?」「そ、そうだよ!き、決まってるでしょ?ね、ぼ、ぼくたち、そ、そう、たす、助けようとしたんだよ、ね、そ、ぞでしょ、そうでしょおおおっ!!!」二人の必死の言い訳を真弓たちはクスクス笑いながら眺めていた。馬鹿ね、現行犯逮捕されといて今更言い訳もなにもあったもんじゃないと思うんだけど?
「ふーん、助けようと思ったね。ま、いいわ、そういうことにしといてあげる。じゃあ、ここに白馬の騎士になり損ねた二人組がいるよ、て玲子たちに教えてあげなくちゃね。よりにもよって日頃苛めまくってたあんたたちが助けに来てくれてたただなんて、ちょっとした感動物語じゃない?玲子もきっと喜ぶわよ?もう苛めないでくれるかもね?」里美は革ジャンのポケットから携帯を取り出すと、ストラップを指に引っ掛けてクルクル回す。ひ、そ、それだけは!!!慎治たちは殆どパニック状態になって飛び上がる。玲子さんたちに知られる!それは死刑宣告を意味する。ぼ、僕たちがこ、ここに居たなんて知られたら、こ、殺される、間違いなく殺される!い、いやだ、し、死にたくないーっっ!!!ガバッ・・・信次は反射的に里美の足元に土下座する。「お、お願い、み、見逃してよーっっっ!!!」慎治もはっと我に帰ると真弓のブーツにすがりつく。「た、助けて、お、お願い、な、なんでもするから、だ、黙ってて、僕たちのことは黙ってて、お、お願い、おねがい・・・・こ、殺されちゃう・・・」もう恥も外聞もない。信次たちは二人とも大泣きし、涙と涎で顔中ぐちゃぐちゃだ。真弓たちを倒して逃げよう、等という考えは信次たちの頭を掠めもしない。玲子や朝子よりは一枚劣るとはいえ、空手部で鍛えあげられた真弓も里美も信次たちから見れば雲の上の存在だ。特に信次は組手で毎週のように蹴りのめされている身、真弓たちの強さも自分の弱さも骨身に浸みている。第一、逃げてもどうにもならない。仮にここを逃げおおせたとしても、真弓たちは直ぐに玲子に事情を報告するだろう。そうしたら結果は全く同じだ。信次たちがこの危機を逃げるには、真弓たちを殺す、文字通り殺すしかない。だが、あれだけ苛められた玲子たちをすら殺す決心ができなかった二人に、そんな覚悟ができるわけがない。できるのは唯一つ、哀願だけだった。真弓たちのブーツを舐めんばかりに二人は必死に哀願するが、玲子たちの親友でもある二人が受け入れるわけがない。勿論、信次たちにもその程度は分かっている。分かっていても哀願せずにはいられない。何もできないが何かしていないと気が狂ってしまう。信次たちは真弓たちのブーツにすがり、涙でブーツを濡らしながらひたすら自慰のような無意味な哀願を続けた。
真弓たちはニヤニヤ笑いながら足元に這いつくばる二人を見下ろしていた。バーカ、許して貰えるわけないでしょ?ったく、いつまでこうやってるつもりなのかしらね。フフ、でもここまで惨めに泣き喚く姿を見るのって、ちょっと楽しいわね。このまま、ここでゆっくり苛めてやろうかしら。この調子なら、ちょっと脅せば私たちのおしっこだって飲ませられるんじゃない?だが、ふと階下を見た真弓たち二人の顔に、更に残酷な冷笑が浮かんだ。クイッと里美はブーツの爪先で信次の顎をこじ上げる。「信次、泣いてるのはいいんだけどさ、下でもっと面白いイベントが始まるみたいだよ。フフ、取敢えず、一緒に見物しようよ。・・・玲子に電話するのは後回しにしてあげるからさ。」え、面白いこと?嫌な予感を感じながらも逆らえずに階下を見た信次の視線が凍り付いていく。
2
礼子が坊野に止めを刺し、一階で立っているのは礼子たち四人だけだった。坊野たちは完全に気を失い、あちこちでだらしなく伸びている。「フウッ、片付いたわね。うまくいったわ。」流石にほっとした様子で礼子が皆を振り返る。「お疲れ礼子、いい攻撃だったじゃない、目潰し鞭、とは考えたものね。」「ありがとう、そういう玲子もあのナイフ、いいコントロールね。ナイフ投げの練習もしたことあるの?ま、最も玲子のコンビネーションのポイントは、あのナイフ投げより、その前の唾にあったのは分かってるけどね。玲子も朝子もブーツをフルに活かしたキックで止めを指したけど、あの唾攻撃はいい発想ね。」「あ、分かった?そう、あれは確かに唾がポイント。まあ、唾攻撃は富美ちゃんの十八番だけどね、たまにはいいや、と思って私も使わせてもらったわ。」と言いながら礼子たちの言葉がふと止まる。富美ちゃん・・・視線を投げかけられた富美代の顔に、吹っ切れたような笑顔が浮かぶ。「ううん、もうみんな、気にしないで。もう先輩のことなんか、何とも思ってないから。それより・・・」富美代は言葉を切って礼子たち三人を見まわす。「・・・ありがとう。本当にありがとう。みんなが助けてくれなかったら私、ここで人生終わってたかもしれなかったね。ありがとう!」良かった、富美ちゃん、もう大丈夫ね。礼子たちの顔にもほっとした安堵が浮かぶ。その時、玲子がパンッと手を叩いた。
「さあさあ、休憩はここまで、今日はまだまだやることがあるんだからね。礼子、手を貸して!」「何、どうするの?後は警察呼んで、坊野さんたち引き渡してお終いじゃないの?」「うん、私も最初はそう思ってたんだけどね、よく考えるとこの人たち、なんで四対四にこだわったのかしら?富美ちゃんを狙っただけとは思えないわ。だったら礼子と富美ちゃん、可愛い子二人まとめてゲットしたんだから、礼子たち二人を誘ってレイプしてお終いのはずじゃない?それをなんでわざわざ、四人でドライブしようなんて指定してきたの?輪姦するって言ったって、四人に人数増やしたら却ってやりにくい筈でしょ?何か理由がありそうじゃない?だったら聞いておかないと。単純に警察に引き渡しても、私たちを襲わせた根っ子を叩いておかないと、また別の形で襲われる可能性があるわ。だから、どうしても理由を聞き出さないといけないのよ!」「・・・そうね、確かに変よね。だけど、これだけ派手に痛めつけた私たちが聞いて、素直に答えてくれるかしら?」プフッ!玲子が思わず吹き出した。「礼子、よく考えてごらん。これ、私たちの安全のためだけじゃないわよ・・・ウフフ、当然、こいつら絶対、素直に喋らないわよ。だったら、無理やり聞き出すしかないわよね。違う?それって・・・」ゾクゾクッ!礼子の背中に強烈な電流が走る。「・・・それって・・・拷問・・・ね・・・」「ご名答。フフ、私たち、信次たちを散々痛めつけてきたけど、あれは言ってみれば苛めとかリンチの範疇よ。これは違うわ。正真正銘の拷問よ。どう礼子、本物の拷問、礼子が憧れてきたのはこれじゃない?お遊びじゃない、私たちには拷問する正当な理由があるし、相手も本物の犯罪者、拷問されるのが当然の相手よ。犯罪者を拷問にかけて無理矢理自分の罪を、バックを白状させる、まさに・・・正統派の、これぞまさしく拷問、ていうシチュエーションよ。どう礼子?」礼子の美貌に凄絶な微笑が浮かぶ。嗜虐と冷酷さと残忍さに満ち満ちた微笑だ。「玲子、あなたってほんと、最高ね!本物の拷問、ああ、最高のシチュエーションよ!こんな機会、二度とないわ、やろう、拷問、今日は最高の一日になるわ!富美ちゃん、朝子、あなたたちもやるわよね?あ、もっとも」礼子はクスクス笑う。「嫌なら別にいいわ、無理にとは言わないから遠慮なく言って。代わりにその分、私がいっぱい拷問させて貰うから!」「あ、礼子ずるい!独り占めはよくないよ、ねえ富美ちゃん、私たちだって拷問したいよね!?」「当然よ!大体、一番拷問する権利があるのは私なんだから!」
「OK,話は決まったわね。じゃあ礼子、手伝って。連中が失神している間に下準備をしておこう!」「下準備?どうするの?」「うん。いつも礼子が慎治を苛める時と基本的には同じよ。拷問中に動かれたり、抵抗されたりしたら面倒だからね。完全に動きを封じておくのよ。一応ロープ用意して来たからさ、今のうちにしっかり縛り上げとこう。」ロープで縛る?全く用意周到なんだから。玲子ったら、もしかして拷問まで今日の予定に入れてたんじゃない?もう、この苛めっ子は・・・苦笑しながらも礼子は自分の中で残虐性が抑えきれないくらい高まりつつあるのを感じていた。残虐性、いや破壊衝動、と言った方が正しいだろうか。坊野たちの肉体を痛めつけ、精神を屈服させてやる。慎治たちを苛めるときは一応、一生残るような傷は与えないように気を配っているけど、今はそんな必要更々ない。どうやって痛めつけてやろうかしら。どんな悲鳴をあげるかな。誰の悲鳴が一番大きいかしら。思いっきり手加減なしで痛めつけたら、どんな風に痙攣するのかな。楽しみ・・・ゾクゾクしちゃうわ。肉体が奥深くから燃え上がるのを楽しみながら坊野たちを縛り上げようとした時、ふと礼子の手が止まった。・・・そうよね。今日は拷問をするのよね。普段の苛めなら縛るだけでいいけど、もっと遥かに暴れるんじゃないかしら。それにこの人たち、慎治たちよりはずっとパワーもあるわ。もっと念入りに、抵抗できないように仕込んどかないと集中して拷問を楽しめないわね。「ねえ玲子、拷問にかけたらこいつら、流石に死に物狂いで暴れるんじゃないかしら。ロープで縛るだけじゃちょっと不安よ。どうやっても抵抗できないようにしとこうよ。」どうやっても抵抗できないようにする?確かに礼子の言うとおりね。だけどどうやって?「・・・そうね。確かに縛るだけじゃちょっと不安ね。だけどどうやる?礼子、何かいい考えある?」「うん。要は仮に拷問中にロープが外れても、動けないようにしとけばいいのよ。縛る前にね、連中の肩と股関節、左右両方とも外しちゃおう。その上で縛っちゃえば、腕も脚も力の入れようが無くなるから、絶対にほどけないよ。それに万々が一ほどけちゃったとしても、関節外しておけば立つことすら出来ないからね、怖くも何ともないよ。まあ、本当は関節を外すのも立派な拷問の内だから気絶してる間に外しちゃうのは勿体無い気もするんだけどね、意識を取り戻されてからじゃあ仕事が厄介よ。連中がお寝んねしてる今のうちに、さっさとやっちゃおう!」なるほど、流石は礼子ね!確かに肩と股関節を全部外しちゃえば、連中もう、どうしようも無くなるわね。後は・・・私たちの思うがままよ!「OK,じゃあ私は奈良村さんと須崎さんをやるから、礼子は坊野さんと検見川さんをよろしくね。」
3
ゴキッ・・・バキッ・・・嫌な音が何度も何度も響いた。礼子たち二人は四人の腕を、脚を掴むと無造作に、次々と関節を外していく。いくら武道の達人である礼子たちでも、実戦で相手の関節を外していくのはそう簡単なことではない。相手も生身の人間、必死で抵抗するし逃げもする。だが今は坊野たちは四人とも完全に失神し無防備の状態、これなら仕事は簡単だ。礼子たちはニワトリの羽でも折るかのように、いとも簡単に坊野たちの関節を外し、一人四回、四人合計十六回、関節が外される音を響かせた。全員の関節を外したところで玲子がバッグから四本のロープを取り出し、礼子に二本を渡した。「じゃあ礼子、そっちをお願いね。こんな風に腕と脚をしっかり重ねて縛っちゃって。」肩と股関節を外され、普段より遥かに体が柔軟になった奈良村の両手両足を背中側に回すと手首を膝裏と、肘を足首と重ねて厳重に拘束し、更に左右の腕、脚をびったりと重ねて縛りつけた。玲子たちはヨットにも乗るだけあってロープワークはお手の物だ。絶対にほどけず、緩まない縛り方でしっかりと拘束する。SNOW CRACKが未だ完全に気絶している間に、拷問の準備はすっかり整った。これだけ厳重に縛られては絶対に抵抗できない。第一、手足を四本とも外されているのだ。寝返りを打つことすらままならない。すっかり準備が整ったのを見た朝子が、例によってキョトンとした表情で尋ねた。「ねえ玲子、拷問、ていいんだけどさ、よく考えてみたら今日は私たち、鞭も何も持ってきてないじゃない?どうやろう、道具もなしで、拷問なんてできるのかな?」「チッチッ・・・」玲子が立てた人指指を振った。「朝子、難しく考えないの、そんな大げさな道具がなくても、十分に痛い目にあわせてやるのなんて簡単よ。たとえば連中、ナイフだバットだ、て道具を用意して来てるじゃない?それを使うだけでも十分、拷問できるわよ。ま、単純にナイフで刺すとか切るとかじゃなくて、どう創造的な拷問を考えるか、そこが腕の見せどころよ!」
「そう、朝子も富美ちゃんも頑張ろうね。もう滅多にないチャンスなんだから、精一杯楽しい拷問を考えようね。」ロープの具合を確かめていた礼子が振り返る。「あ、そうだ。拷問を始める前に、少し前振りもしておこうか。」「前振り?何するの?」「うん、折角拷問するのにさ、ちょっと痛めつけただけで直ぐ白状されたら興醒めじゃない?だからさ、こいつらが絶対喋ってたまるか、て私たちに対して目いっぱい反抗的になるようにしとくのよ。そしたらさ、その反抗的な態度を屈服させるのもまた、拷問の最高の楽しみのひとつになるよ!」「いいわね。礼子、乗ってきたジャン!OK,いいわよ、前振りは礼子に任せるわ。私たちも合わせるから。」礼子たちはゆっくりと各々の獲物に近づき、活を入れて意識を取り戻させる。「グッ・・・グブウッッッ・・・」苦しげに大きく息を吐き出しながら坊野が息を吹き返した。「ウグッ・・・」失神していたおかげで忘れられていた痛みが復活する。未だ目も耳も、腹も喉も足も、全身のあちこちが痛い。だが痛みだけではない。全身が何か、不自然に緊張している感じがする。「・・アヅアッ!!!」無意識に腕を動かそうとした坊野の肩に激痛が走る。動かない。腕はまったく動かないのに肩と、何故か分からないが股にも激痛が走る。必死で首を動かすと自分の脚と腕が完全に重なっている。な、なんだ???ロープ?俺は縛られてるのか?
「お目覚めかしら、坊野さん?」コツコツと頬を小突かれ、坊野は上を見た。礼子の美しい顔が自分を見下ろしていた。そして頬を小突いているのは、礼子の茶色いブーツの爪先だった。「随分よく寝てたわね。いい加減、待ちくたびれちゃったわよ。」「て、てめえ、よ、よくもやりやがったな・・・お、覚えてやがれよ、必ず、必ずこの礼はするからな!」「あら怖い怖い、でももう少し、自分の置かれた状況を見てから物を言ったほうがいいわね。」礼子はスッと右足を上げると、ゆっくりと坊野の顔を踏み躙る。頬を、鼻を、口をゆっくりと踏み躙る。「グッ、ブアッ、ゴ、ごの、や、やめろーっ!!!」顔面を女の子のブーツに踏み躙られる屈辱に坊野は絶叫しながら必死で顔をそむけようとする。だが両手を完全に縛り上げられ、しかも全く動けない体では、いくら顔をそむけても却って礼子のブーツに自分の顔をこすりつけているようなものだ。「アハハッ!そんなに私のブーツが好きなの?坊野さん、あなたもしかして変チャン?ギャングだなんて大嘘で、本当は私に苛めて欲しくて後つけてる、ストーカー君なんじゃないの?ねえ、土日はもしかして、秋葉原にでも入り浸ってるんじゃないの?」笑いながら礼子は坊野の顔面を踏み躙り続け、更に嬲る。「ほら白状しなさいよ、僕たちSNOW CRACKはお宅のストーカー集団です、てね!アハハハハハッ!ほらいい子でおねだりしてごらん!お願い、僕ちゃんを苛めてくださーい、てね!アハハハハハハッ!」「ち、畜生、な、舐めんじゃねえ!俺たち、俺たちSNOW CRACKを舐めんじゃねええっっっ!!!」坊野は顔中を口にして必死で絶叫した。四肢の関節を外され、厳重に縛り上げられた坊野にできる唯一の抵抗は唯一つ、空しく叫び続けることだけだった。
「ち、畜生!ほ、解きやがれ、このロープをほどきやがれーっ!グッ・・・」コンコンッ、礼子はブーツの踵の角を立て、坊野の喚き散らす口を軽くノックする。歯や唇は筋肉が無く神経に直結する敏感なポイントだ、いくら軽く、とはいえブーツの踵で小突かれてはかなり痛い。「まあどうでもいいわ、タッキー君、苛めるのは勘弁してあげる。私ね、お宅って趣味じゃないの。どうせ苛めるなら、もうちょっと可愛い坊やを苛めたいわ。」一旦言葉を切った礼子の切れ長の瞳に、妖しい光が輝く。「だから許してあげるわ。但し、私の質問に素直に答えてくれたらね。いい?タッキー君、なんで私たちを襲ったの?貴方たちみたいなお宅のストーカー坊やたちが、私たちを襲おう、なんて勝手に思いつけるわけないわ。誰かに頼まれたんじゃないの?白状しなさい、誰に頼まれたの?白状したら・・・これ以上苛めるのだけは許してあげるわ。」ゆ、許してあげるだ!?た、タッキーだ!?い、苛めるだ!?未だ自分の立場を、そして礼子の性格を理解できない坊野の頭に血が上る。「ざ、ざけんじゃねーっっっ!!!だ、誰がてめえの言いなりになってたまるか!お、俺を誰だと思ってやがる!な、舐めんじゃねーぞ、だ、誰がしゃべるもんか!てめえの質問になんぞ、絶対に答えてやるもんか!」スッと礼子はブーツを坊野の顔から下ろし、地べたに転がされたまま喚く坊野を見下ろした。「随分威勢がいいわね、タッキー君?でもいい?私の質問には素直に答えた方が身のためよ。もし答えたくないなら、お願いです、答えさせてください、て貴方が泣いてお願いしたくなるようにするまでよ。いい?よく聞きなさい。私の質問に素直に答えないなら・・・拷問に掛けるわよ?」拷問・・・一瞬、坊野の目に狼狽と恐怖の色が浮かんだ。礼子はつい先程手酷く痛めつけられた相手、しかも痛めつけるツボを心得ていそうな相手だ。おまけに今、自分は厳重に縛られていて身動き一つ取れない。一体、どんな目に会わされるのか・・・馬鹿野郎、俺は何を弱気になってるんだ!?相手はたかだか女一匹じゃねーか。俺だって何十回も喧嘩してきたんだぜ、殴られたことなんか幾らでもあるわな!こんなクソガキ一匹に何ビビッテんだよ!こんな女程度に殴られる程度、全然怖くねーだろーが!必死で気合を入れ直し、坊野は地べたから礼子を睨み上げた。「あ?それで俺を脅してるつもりかよ!?この坊野を舐めんじゃねーぞ!誰がてめーなんぞに喋ってやるもんか!殴りたきゃ殴りやがれ!てめーに殴られた程度でな、この俺が詫び入れる、とでも思ってんのか?笑わせんじゃねえ!」ゾクッ・・・喚きながら坊野の背筋に悪寒が走った。礼子は笑っていた。その美しい顔に浮かんだ笑みは親しみ、好感を感じさせるものでない。どこかで見たことのある顔だった。そうだ、この顔、俺たちが拉致った奴らにヤキ入れる時の顔じゃねーか。だが礼子の笑みはなまじ美貌の分、より迫力があった。猫が鼠を弄ぶような、残忍、冷酷、無情な笑みだった。
「言ってくれたわね、タッキー君?いいわ、私の警告を無視するなら、勝手にしなさい。拷問に掛けて泣き叫ばせてあげる。その強がりがいつまで続くか、楽しみね。」傍らでは玲子も同じように、奈良村を挑発していた。「どーお、お目々覚めた、タマナシ君?おっきの時間ですよーお?」漸く意識を取り戻した奈良村の頬を、玲子はブーツの爪先で軽く打った。「・・・う、ううっ・・・て、てめえ、さ、刺しやがったな・・・覚えてろよ・・・ぜ、ぜってーこ、殺してやるからな・・・」「うーん、タマナシ君、君、頭軽すぎない?もしかして君の脳みそ、皺が全く無いツルンツルンなのかな?タマナシ君の細腕じゃお姉さんに勝てないって事くらい、未だ分からないの?学習効果のない坊やねえ。それじゃお猿さん以下でちゅよお?幼稚園からやりなおちまちょうかあ?」幼児言葉でおちょくる玲子にまんまと乗せられ、奈良村は逆ギレして喚き散らす。「っせえ、るせえええ!!!ざ、ざけんじゃねえええっ!ぶっ殺す、てめえだけはぜってーにぶっ殺してやっからなあああ!!!ブバッ!」絶叫する奈良村の唇を玲子のブーツが踏み躙る。「はーい、タマナシ君、お部屋の中でおっきな声を出すのはやめまちょうねえ。そんなに喚かなくても、十分に聞こえまちゅよおお。じゃあね、今度はおねえさんからの質問のお時間でちゅよー。」「質問?ざ、ざけんじゃねえー!てめ、この糞ったれの足をどけやがれ!こ、こんなことしやがって、俺がてめーの質問に答えてやるとでも思ってやがるのかーっ!!!グエッ!」玲子は奈良村の顔を踏み躙るブーツにグッと力を込めた。「たっまなっしくーん!きみはほーんっとうに、おバカですねえー!いいですかーっ?君は今、お姉さんにこてんぱんにやっつけられたあげくに、こうやって縛られてなーんの抵抗もできないんですよー?」スッとブーツをどけ、玲子は奈良村の顔を真上から見下ろす。「よーく聞きましょうねえ。大人しくお姉さんの言うことを聞かないと・・・イタイイタイのお時間にしちゃいますよ?」ゾクッ・・・奈良村の背筋に悪寒が走った。下から見上げる玲子の顔は真剣に美しかった、奈良村が今まで会った全ての女の子の中でも一、二を争うのは間違いない。だが玲子の美貌には危険な毒がある。奈良村を見下ろしながら玲子が浮かべている微笑こそが奈良村の背筋を凍りつかせていた。残忍冷酷、弱者をいたぶる事に楽しみを感じる目。だが玲子の視線はそれだけではない、もっと遥かな残酷さ、いや邪悪さと言った方が正しいオーラを発散させていた。見るものの視線を捕らえ、目を逸らすことすら許さない。邪眼、見るものを破滅に引きずりこむ魔性の瞳。切れ長の玲子の瞳に吸い込まれるように、奈良村は釘付けにされていた。な、なんだ、何で俺はこいつの目をじっと見ているんだ。なんでこいつに、たかが女に気圧されているんだ。玲子は奈良村が動揺しているのを当然のように見下ろしていた。玲子にとっては見慣れた光景だ。フン、そうよ。そうやって怯えているのがあなたにはお似合いよ。「いい?頭の悪い君にも分かるように、はっきりと言ってあげるわね。素直に私たちの質問に答えなさい。さもないと・・・拷問にかけるわよ。君たちのやってきたような、子供騙しのリンチなんかじゃない、本物の苦痛、ていうものを味合わせるわよ?」ゾクッとする、という点で言えば、須崎も背筋に悪寒を感じていた。漸く意識を取り戻した須崎を見下ろしていたのは朝子だった。相変わらずキョトンとした顔に無邪気な微笑を浮かべつつ、朝子が小首をかしげた。「大丈夫?お鼻、潰れちゃったみたいだけど、どう?息できる?」如何にも心配しているような素振りと裏腹に、朝子はブーツの爪先でトントンと須崎の顎を小突いた。朝子の天空脚に割られた顎に激痛が走り、須崎は思わず悲鳴をあげる。「いで、イデデデ!て、てめえ、何しやがるんだ!」「アン、そんな怒らないでよ、別にもう、何かするつもりはないんだからさ。顎がどうなったか心配だから確かめてあげてるだけよ。」そう言いながらも朝子は須崎の顎を小突き続ける。
「いで、や、やめろ!!!」声を出しただけで顎の傷に響き、須崎は全身を身悶える。朝子はちょっと足を振り上げただけで、自分の足元で須崎がうめくのを面白そうに眺めていた。玲子たちのように苛めて楽しんでいる、というのとも違った表情だった。面白そう、ある意味、子供のように純真な、邪心のない表情だった。楽しむ、というより興味深く観察している、といった表情だった。苦痛にあえぐ須崎の顔に恐怖の色が浮かんだ。な、なんだ、なんなんだ、こいつは・・・朝子の目は須崎の知らないタイプの目だった。暴力を楽しんでいるのならまだ分かる。俺だってそうだ。だけど、こいつはなんなんだ!?朝子の目に浮かんでいるのは楽しみではない、興味、純粋な興味だけだった。子供が公園に行って、見るもの全てが刺激に満ちあれなに、これなに、と探求する時の目付きだ・・・いや、この目、どこかで・・・そうだ、昆虫採集、いや採集なんてお上品なもんじゃない、ガキの頃、虫やカエルを捕まえて羽や脚をもぎったり解剖して遊んだ時のあの顔、あの目だ・・・須崎は冷や汗がながれるのを感じた。こいつ、俺のことを人間と思っちゃいねえ・・・俺をいじったらどんな反応するか、俺のことをモルモット扱いする気だ・・・拷問、礼子たちは俺たちが質問に答えなかったら、拷問に掛ける、と言いやがった。たかが女、大して痛くもねーだろうが、こいつは・・・何するか分からねえ・・・
だがその時、奈良村と須崎の弱気を吹き飛ばすかのように坊野の怒声が響いた。「て、てめえら!奈良、須崎!イモ引いてんじゃねーぞ!こんなクソガキどもにビビってんじゃねーだろうな!てめえら、こいつらの言いなりに口割りやがったら、後で俺がぶっ殺すぞ!!!」ビンゴ!礼子は心の中で快哉を叫んだ。いいわよ、その調子!そうやってバーをどんどん高くしてね。バーが高いほど・・・拷問のやりがいがあるっていうものよ!両手を叩いて喜びたいのを必死で堪えながら礼子はブーツで坊野の顔を軽く踏みつけた。「後悔するわよ、タッキー君?私の忠告を聞かないと、痛い目に会うのはあなた自身よ。それに・・・」クスクス笑いながら礼子は続けた。「痛いよう、もう止めてよう、なんでも喋るからお願い、許して、て真っ先にピーピー泣きながら白状するのはタッキー君、君だと思うわよ。」「な、何だとー!ざ、ざけんじゃねえ、何でこの俺が真っ先に白状するっつうんだ!」「まだ分からないの?簡単なことよ。」ああ、いいわ、盛り上がってきたわね。礼子は大きく深呼吸した。「あなたを拷問するのは、この私だからよ。」ぐっ・・・完全に頭に血が上った坊野といえども、流石に礼子の宣告には恐怖を禁じえない。だがその恐怖を振り払うかのように坊野は叫んだ。「る、るせええっ!!!だ、誰がてめえの言いなりになってたまるか!SNOWを舐めんじゃねえ!し、死んでもてめえらには何も喋っちゃやらねえぞ!!!」いい、坊野さん、あなたって最高!本当、最高の盛り上げ方よ!KISSしてあげたい位!ああ、夢にまで見た拷問、最高のシチュエーションになったわ。さあ、たっぷりと楽しませてね。私の生涯最初の拷問を!礼子の美貌に凄絶な微笑が浮かんだ。「そう。それなら仕方ないわ。拷問・・・開始よ!」
4
「これ、何か分かる?」坊野の目の前にしゃがみこんだ礼子が見せたのは数本の鉛筆とボールペンだった。坊野たちが気絶している間に、工場の片隅にあったデスクから探してきたものだ。こ、このアマ、な、何を考えてやがる・・・礼子を見上げる坊野の目線に警戒心に混じって微かに恐怖の色が浮かぶのを礼子は満足げに見下ろした。「フフフ・・・見てのとおり、これは鉛筆とボールペン、種も仕掛けもない、ただの鉛筆とボールペンよ。だけどね、この鉛筆とボールペンが今からあなたに、地獄を見せてくれるわ。単純に殴る蹴る、なんてのとは比べ物にならない苦痛をね。」言い放つと礼子は無造作に坊野の背中に腰を下ろした。「グウッ!て、てめえ、どきやがれ!」坊野は必死で礼子を振り落とそうとするが、厳重に縛られ、身動き一つ出来ないのではどうしようもない。
礼子は坊野の右手薬指を握ったかと思うとぐっと引き上げ、薬指の下を通して中指の上に一本の鉛筆を忍び込ませる。続いて人差指を掴み、鉛筆をその下に進ませる。「準備OK,さあこれ、どういう拷問か分かる?ま、古典的な拷問だから知ってるかもしれないわね。子供の頃、おふざけで友達とやったこともあるんじゃない?だけどね、本気でやれば結構、痛い拷問になるわよ。」言いながら礼子は坊野の太い指に優しく掌を重ねた。一瞬、凄絶な微笑を浮かべた礼子がぐっと坊野の指を握り締める。礼子の掌と言うより、自らの人差し指、薬指に押されたボールペンが坊野の中指に食い込む。「ぐ、グウァアアアッッッ!!!」激痛に坊野は必死で抗い、何とか指を開こうと、何とか礼子の手を振り解こうとする。だが、どうにもならない。もともと礼子が握っているのは坊野の指の内、人差し指、中指、薬指の三本だけだ。いくらパワフルな坊野とは言え、指三本だけでは仮に無条件での力比べだったとしても、並みの男性を遥かに上回る握力を誇る礼子に勝つことは不可能だ。ましてや力の支点となる両肩を外され、普段の力の何分の一かしか出せない上に両腕を厳重に縛り上げられていては、指を開くことも腕を動かすことも、どうあがいても絶対に不可能、むしろ必死で指を開こうとする余り、却って中指を自ら余計強く、ボールペンに食い込ませてしまう始末だった。殴る、蹴るとは全く違う局所的な、一点集中の痛み。それも筋肉ではなく、骨に直接食い込み、ゆっくりと全身を蝕む激痛だった。余りの痛さに眼の奥でチカチカと星が瞬くような気がする。錯覚ではない。激痛に血圧が急上昇し、呼吸まで荒くなっている。指なのに、たかが指一本を責められているに過ぎないのに。細身の女の子に手を握られているに過ぎないのに。その激痛は坊野の意識の全てを支配しつつあった。
「グアアッッッ・・・い。イデエェェェッッッ」悲鳴と共に坊野の全身が苦痛と全身の筋肉に無駄に力を込める反動でビクビクと痙攣する。いい、最高・・・礼子は自分の尻の下で坊野がもがき苦しむ様をゆっくりと堪能していた。耳に心地よく響く絶叫に加え、坊野の痙攣が礼子の尻を通して直に体の奥底を揺さぶる。いいわこれ、最高の気分ね。なんだっけ???そう、ボディソニックチェアだったかしら?あれみたいね!昔懐かしいAVツールを連想しながら礼子は坊野の苦悶をじっくりと楽しんでいた。ふふ、なかなかいい悲鳴じゃない?でもね、まだまだ拷問は始まったばかりなのよ。礼子はゆっくりと手を開き、坊野を一旦解放してやる。「くっ、ううぅ・・・」だが解放されたからと言って、坊野の苦しみは直ぐには終わらない。激しく圧迫され、血行障害を起こした中指に再び血が流れると、麻痺しかけた痛覚が蘇り、ジンジンと痺れるような新たな痛みが走る。「う、ううう・・・」坊野が荒い息をつくのをしばし観察していた礼子がゆっくりと拷問の再開を宣告する。「フフ、そろそろ痛覚も復活したようね。じゃ、拷問再開よ!」「ひ、ひいっ・・・や、やめろ、やめろーっっっ・・・い、イデーッッッッ!!!」
再び礼子がゆっくりと坊野の手を握り締め、ボールペンを食い込ませる。礼子はゆっくりと拷問を繰り広げた。締め上げて坊野を絶叫させ、痛覚が麻痺しかけると緩めて感覚を復活させる。更にボールペンの位置も微妙にずらしながら拷問するので、いつまでたっても痛覚が麻痺してくれず、坊野は延々と新鮮な苦痛を味わう羽目になった。5セット程度繰り返しただろうか、「ぎ、イギャーッッッ!」坊野の悲鳴に混じり、パキッと小さな音が響いた。「あら、ボールペン折れちゃったわ。坊野さん、良かったわね、少し休憩できて。私、まだ休ませてあげるつもりはなかったのよ。」礼子は苦笑しながら坊野の鼻先で真っ二つに折れたボールペンをブラブラさせた。「・・・ハッハッハアッッッッ・・・や、やめろ、もうやめでぐれ・・・」「何言ってるのよ、しっかりしなさい、ほらシャンとする!」ピシーンっ!と礼子は坊野の頬を平手打ちし、喝を入れた。「SNOW CRACKの意地を見せてくれるんじゃなかったの?大体大げさに騒いでいるけど、、大して傷なんかついてないじゃない。ほら、よく見てごらんなさいよ、血の一滴すら流れてないわよ!?」坊野はズキズキ痛む中指をピクピクと動かしながら、礼子が突きつけたボールペンを涙目で見た。「う、うそだろ、なんで・・・」確かに礼子の言うとおり、血の一滴すら付いていない。坊野には見えないが、中指の付け根から第一関節にかけてが紫色、というかどす黒く変色しているがそれも極々狭いエリアに留まっている。「あ、あんなに痛かったのに、なんでだ?なんで傷一つついてないんだ?」散々他人に暴力を振るってきたとはいえ、坊野たちの暴力は単純な、殴る蹴るといったストレートな暴力に過ぎない。痛さと傷はほぼ正比例する。長時間激痛を与えながら、なおかつ傷を余りつけない礼子の技術は坊野の想像の埒外、理解を超えていた。当惑は恐怖に変わり、坊野の中で礼子が得体の知れない怪物に変貌していく。背筋を流れる汗を妙に冷たく感じた時、礼子の凛とした声が響いた。
「さあ、もう休憩は終わり、拷問再開よ!」言うなり礼子は、今度は三本のボールペンを同時に手にした。「ヒッ!こ、今度はな、何をする気だ!?」クスクス、と礼子は楽しそうに笑った。「拷問の趣向を変えるのよ。さっきの責めはもう飽きたでしょ?今度は別の拷問で苛めてあげるわ。」あ、新しい拷問!な、何をする気だ!!!坊野は恐怖の余り失禁しそうになった。だが初めての拷問に興奮している礼子は、坊野に考える暇さえ与えない。一本目のボールペンは人差指と中指の間、次いで二本目は中指と薬指の間、三本目は薬指と小指の間、と礼子は立て続けに三本のボールペンを坊野の指に挟んだ。勿論坊野は必死で抵抗しようとするが、指一本の力など知れているし、そうでなくても先程の拷問でかなり消耗している。礼子は難なく抵抗を排除して拷問の準備を整えた。
「さあ準備完了!どう、もう分かった?今度はどういう拷問か。そうよ、こうやって苛めるのよ!」言うなり礼子は坊野の掌側に三分の一程度突き出たボールペンを左手で纏めるように握り、次いで三角形に開いて手の甲側に突き出たボールペンを右手で掴んだ。「逝くわよ、覚悟はいいわね。」礼子はゆっくりと絞るように右手に力を込める。「ぎ、ぎあっ、や、やべ、いだいいいいっ、いだ、いだ、やべでぐれーーーっ!!!」坊野の絶叫が轟く。突き出たボールペンは梃子の原理で礼子の握力をほぼ二倍に拡大し、坊野の指に伝える。指自体にはクッションになる肉は少ないし、第一横からの力に対しては人体の構造上、いくら力を込めようとも抵抗は殆ど不可能だ。中指と薬指の骨にボールペンが食い込む。外側から、そして真中に挟んだボールペンが両指に食い込み苦痛を更に拡大する。頭の中が苦痛で真っ白になっていく。いたいいたいいたい・・・痛み以外何も感じられない。礼子が強く握ると坊野は殆ど自動的に悲鳴をあげ、緩めると荒い息をつく、また握られて喚き散らす、その無限ローテーション、たった三本のボールペンの拷問だけで、礼子は完全に坊野をコントロールしていた。坊野の感覚の全ては礼子の思うがまま、礼子は自由自在に坊野の苦痛をコントロールし、拷問を楽しみ続けていた。
5
礼子が拷問を開始するのとほぼ同時に、玲子も楽しみ始めていた。「さあタマナシ君、覚悟はいいわね?私は十分に警告してあげたはずよ。それを断ったのは君自身。て言うことは君が自分で、私にお願い拷問してください、ておねだりした、て言うことだからね。これから私にどんな酷い目に会わされたって、それは自業自得というものよ?」悠然と微笑む玲子に奈良村は内心のビビリを必死で押し隠しながら絶叫した。「ひ、酷い目、拷問だあー?て、てめえ何をするつもりなんだよ!?」「別に難しいことをするつもりはないわよ。頭の悪い君でも良くわかるように、拷問の定番商品で責めてあげるわ。」言いながら玲子は再び、ウエストからベルトを引き抜いた。パシーンッ!と二つ折りにしたベルトを打ち鳴らす。「礼子は貴方たちのプレジに結構、何発もベルトをお見舞いしてたみたいだけど、タマナシ君はさっき、すぐ伸びちゃったからたった二発しか私の鞭、味わってないでしょ?だからその分、たっぷりと味あわせてあげるわ。」ヒュンッ!バシーンッ!言いながら玲子が振るったベルトが奈良村の背中を打ち据える。「っあっ!」「何演技してるのよ、役者やのおーーーっ。若いのに芸が上手すぎるわよ。ったく、服着たままで、しかもロープまであるのよ、こんな程度のベルトで痛いわけないじゃない。こんなんじゃ拷問はおろか、SMごっこにすらならないわよ?」
玲子は笑いながらブーツの爪先を奈良村の胸の下に差し込むと、グイッと一気に蹴り転がした。「ギアッ・・・イダイ!」関節を外された肩に力がかかり、奈良村の口から悲鳴がもれた。その奈良村の胸を玲子のブーツが踏みしめる。「な、何をする気だ・・・」奈良村の声が妙に弱々しくなっていく。「一本鞭ならともかく、今日はベルトしかないのよ、拷問っていうからには、せめてこれ位はやらなくちゃね。」玲子はベルトの先端でゆっくりと奈良村の顔を撫でた。「さっきの礼子の鞭、見てなかった?拷問、ていうからにはせめてあれ位の鞭にはしてあげたいな、てお姉さん思うのよねえ。あ、そっか、君はあっさりお寝んねしちゃってたものね。見てなかったか。じゃ、教えてあげる。このベルトでね、たっぷりと君の顔を鞭打ってあげる。遠慮しないでいいわよ。一生懸命抵抗してね。ちゃんと逃げないと、いつまでも引っ叩かれちゃうよ?」スッと右足を奈良村の胸から上げた玲子はそのまま奈良村の胸をまたぎ、仁王立ちになる。
か、顔を引っ叩く?しかもベルトで?思わず奈良村が悲鳴をあげそうになる機先を制し、玲子のベルトが唸る。ヒュオッ!バシーンッ!ギアーッ!したたかに打ち据えられた奈良村の頬が乾いた音を立てる。全く、今から拷問楽しむんだから少し静かにしててよ。貴方は一番弱そうだから、ほっといたら何にもしない内に白状しちゃいそうだわ。暫くは声も出ないように苛めてあげないとダメみたいね。玲子のベルトが立て続けに宙を舞い、奈良村の顔面に襲い掛かる。バウッ!パシッ!ビシャッ!パシーンッ!・・・「ヒ、ヒィッイ、イダイ、ブファッヒギーッッッ!!!!!」立て続けに襲い掛かり顔面を打ち据えるベルトに奈良村は恥も外聞もなく悲鳴を上げつづけた。
「アハハッ、何イタイイタイって騒いでるのよ大げさね!」パシーンッ!と一際高い音を立てて奈良村の左頬を打ち据えると、玲子はグイッとブーツでその頬を踏み躙った。「全く、私、礼子と違って君の目も耳も打ってないのよ?私、さっきから君の頬っぺたしか引っ叩いていないわよ?それをまあイタイイタイってこんなに騒いじゃって、ほんと役者よのおー。その根性、叩き直してあげるわね!」何とも楽しげに言い放った玲子は、ブーツをどけるなり再びベルトの往復ビンタを繰り出す。確かに玲子は奈良村の頬しか鞭打たず、より多くの苦痛を与えられる目や耳は敢えて狙っていなかった。当然だろう、それは必要ないからだ。確かに頬をベルトで鞭打たれるだけでも通常の平手打ちの何倍も痛いだろう。だが実のところ、顔面の痛みは玲子の拷問の半分に過ぎない。今、奈良村は仰向けに横たえられている。脱臼させられた肩、股関節を不自然に折り曲げられながら。玲子に鞭打たれる度に、奈良村は反射的に全身に力が入り、身を捩じらせてしまう。その動きが外された肩、股間に無理な力として伝わり、ねじれ、新たな激痛を呼び覚ます。玲子の本当の狙いはそちらだった。
「ヒッ!ヒイッ!!!やべで、ぶぶっ!」虫けらのように地べたに転がされた奈良村を跨ぐように立ち、玲子は思う存分ベルトを振るいつづけた。「アハハッ!ほらタマナシ君、それでも逃げてるつもりなの?ちゃんと逃げないっていうことは、もっとお姉さんの鞭がほしいのかなー?よーし、じゃぁ一杯ご馳走してあげるわね!」腕、足が動かずしかも厳重に縛られた奈良村にできる動きはただ顔を左右に振る程度、転げまわって逃げることなど到底不可能だ。しかも上から見下ろす玲子にとって、奈良村がどう顔を動かそうが顎を引こうが、動きは丸見え、鞭打つ場所には全く困らない。「アハハハハハッ!そんなに顔振っちゃって、あ、そうか、わかった!右を叩かれたら慌ててそっちを下にしてるってことは、今度は左を叩いて欲しいのね!汝、右の頬を打たれたら左の頬を差し出すべし、てわけね!OK!ご要望通り、たっぷりと鞭打ってあげるわね!」パシッ・・・ビシッ・・・玲子のベルトは休むことなく宙を舞い続け、右から左から間断なく奈良村の頬を打ち据える。いくらベルトとはいえ、十分にスナップを効かせた玲子の鞭だ。通常の平手打ちとは比べ物にならない程の威力を発揮する。ひとしきり打ち据えた玲子が漸く手を休めた時、奈良村の頬は既に内出血に見舞われ腫れ上がり始めていた。あらあら、この分だと綺麗に腫れ上がりそうね。いわゆるサッカーボール状態、てやつ?「う、ああ・・・い、びだい・・・グエッ!」脳天にまで響くベルトの連打にまだクラクラしている奈良村の鳩尾を玲子は踵で踏みつけ、喝を入れた。「フフフ、どうタマナシ君、大分効いてるみたいね。もうやめて欲しい?もう顔面鞭は許して欲しい?」玲子に散々苛められてきた信次たちなら、玲子のこの言葉の裏を、隠された毒を感じることも可能だったかも知れない。だが玲子とは初顔あわせの奈良村にそれは無理だ。奈良村は思わず、救いと信じて偽りの命綱を掴んでしまった。更なる泥沼へ誘うロープを。「あ、ああ・・・や。やべで・・・か、顔は、もう・・・ぶたないで・・・くれ・・・・」「いいわ、わかった。私、こう見えても結構優しいのよ。もう顔はぶたないであげる。安心して。」言いながら玲子は左手からベルトの先端を放すとスッとベルトを二つ折りにした。ああ、よかった・・・どうやらこいつも満足したようだ・・・顔の痛みはまだジンジンと残り、更に内出血の気持悪さを伴う痛みは徐々にひどくなっていたが、奈良村はほっとして全身から力を抜いてしまった。その瞬間、玲子は奈良村の鳩尾に乗せていた踵を再び、グッと踏み込んだ。「グボァッ!」「タマナシ君、勘違いしてない?私、リンチを楽しんでるんじゃないの。今は君を拷問に掛けているのよ。約束通り、顔面鞭はもうお終いにしてあげる。でもね、それは拷問の趣向を変える、てことなのよ?」「ひ、ヒッ!い、な、なにをする気・・・」「怖い?知りたい?いいわ、教えてあげる。今度の拷問はこれよ!」玲子はベルトの先端を握ったまま、バックルのみを放した。バックルがブラブラと宙を泳ぐ。「ひ、ひっ・・・ま、まさか・・・」玲子に蹴り転がされ、奈良村は今度はうつ伏せにされた。「そうよ、漸くわかったみたいね。ご名答。だって体は服を着たままだし、背中はロープであちこちガードしてるでしょ?普通にベルトで叩いただけじゃ痛くもなんともないわよ。だから今度は、このバックルで鞭打ってあげるわね!」「ヒ、ヒイーーーッッ!!!や、やべ・・・ギャァーーッ!!!」ブオッ・・・バズッ!奈良村が悲鳴に似た哀願を叫ぶ暇も与えずに玲子は思いっきりベルトを振るった。先端に大き目の、頑丈な鉄のバックルがついたベルトは先程と明らかに違う、重々しい風切り音を伴って奈良村の体に忍び寄り、鈍い音とともに体に食い込む。十分なスピードを得た鋼鉄の一撃が奈良村の腕、丁度力瘤のできる辺りを打ちのめした。「ぐ、グブアアアアア・・・」骨まで響く痛みに奈良村は悲鳴すら上げられずに口をパクパクさせながら痛みに呻吟していた。「アハハハハッ!どう。タマナシ君、結構効いてるみたいじゃん!?やっぱ、この位痛くないと拷問されてる、て気がしないでしょ?さあ、ガンガン逝くわよ!」残忍な笑みを浮かべながら、玲子は全力を開放して立て続けに奈良村にバックルを叩きつける。「ウギャアァッ!ヒグッ、ガッ、ア゛ア゛ッ、イ゛ガア゛ア゛ア゛ッ!!」獣のような、悲鳴とも絶叫ともつかぬ咆哮をあげながら奈良村は玲子の鞭に呻吟しながら床をのた打ち回った。いや、のた打ち回った、と感じているのは本人だけで、実際には縛られた全身をビクビク痙攣させていただけなのだが。
6
ふう、二人ともよくやるわね、もう、ほんと、好きなんだから。玲子たち二人が嬉々として拷問に興じるのを朝子は半ば苦笑しながら眺めていた。朝子の足元には鼻と顎を蹴り潰された須崎が横たわっている。拷問ね・・・じゃ、私はこの人の担当拷問官って役回りか。まあいいけど・・・全く・・・朝子は些か面倒くささを感じていた。拷問が楽しくない訳じゃない。朝子とて玲子に十分に感化された身、他人を痛めつけるのは大好きだ。だが単純に鞭を楽しむならともかく、この場で咄嗟に効果的な拷問を考えろ、と言われては些か困ってしまう。うーん、何したらいいかな。あんま、いい手考えつかないな・・・蹴り潰した鼻や顎でもグリグリしてあげようかな?でも、それもしつこいだけで想像力にかけるわね。なんか、いい手ないかしら?「ねえ須崎さん、成り行き上、私があなたのこと拷問してあげなくちゃいけないみたいなんたけどね、どうしたらいいかな?あんまりいい拷問考えつかないのよね。折角だから一緒に考えてよ。ねえ、どんな拷問して欲しい?何か希望はある?」問われた須崎の方が言葉につまる質問だった。こ、こいつ、何考えてやがるんだ?お、俺の顎、割りやがって、その俺にどう拷問したらいいか考えろだと?お、俺を、自分を拷問する方法を考えろだって?こ、このクソアマ、舐めやがって・・・思わず怒鳴ろうとした須崎だったが、口を動かした途端、顎の激痛に言葉すら発せられずに思わずうめいてしまった。グウウ・・・激痛が須崎の頭に僅かに冷静さを呼び戻す。痛みを堪えながら見上げた朝子の表情を須崎は一生忘れられなかった。
朝子の表情、須崎が想像していたそれは、他人を苛めることを心底楽しんでいる、肉食動物、ネズミを弄ぶネコのような表情だった。だが実際の朝子の表情は先ほどのファイトと同じく、ちょっと小首をかしげ、キョトンとした、どこか困ったような表情だった。楽しむ、といった感じはどこにもない。だが同時に須崎の痛みなど痛みとしてすら認識しない、いや意識すらしなさそうだった。どこかモルモットを見る科学者を連想させる表情だった。得体のしれない、今まで自分が会ったことのないタイプの恐怖に須崎は思わず言葉を失ってしまった。「ねえ、ねえったら!聞いてる?どう拷問したらいいか、一緒に考えてよ!」朝子は少し苛立ったような声をあげた。そ、そんな・・・何を言ったらいいかも分からず呆然としている須崎に苛立ったように、朝子は須崎のポケットに手を突っ込んだ。「もう、須崎さんたちは喧嘩やリンチ、いつもやってるんでしょ?何かいい道具持ってるんじゃないの?貸してよ!」「や、やめろ!い、いや・・・」確かに須崎も獲物を持っていた。朝子に見つかるのを恐れた獲物、それは大型のメリケンサックだった。巨体の須崎に相応しい大型のメリケンサック、それで割られた顎や鼻を殴られたら!だが予想に反し、朝子はメリケンを面白そうにいじくりはしたものの、さして興味を示さなかった。「ふーん、こんなもん持ってたんだあ。ああ怖い。こんなもんで殴られてたら、私の折角の美貌が台無しになるところだったわ。ああ怖い。」折角の美貌、そりゃ確かにてめえツラは綺麗だとしてもよ、自分で言うんじゃねえ!心の中で悪態をついた須崎だが、一瞬後、その顔が凍りついた。朝子が大きな瞳をキラリと輝かせながら、ある物を握り締めたのだ。それは・・・大型のZIPPOライターだった。
「いいもの見つけちゃったっと!」クスクス笑いながら朝子はZIPPOの蓋を開け閉めした。玲子と違って朝子はタバコは吸わないが、ライターの着け方位はわかる。拷問を楽しんでいる玲子たちの方をひょいと見てから再び須崎に向き直った時、朝子はついさっき迄の困ったような表情とは一変し、新しいオモチャを与えられた子供のようにワクワク、ウズウズした笑顔を満面に浮かべていた。「玲子たちは鞭とペンで楽しんでいるみたいだから、私はちょっと趣向を変えようね。だーいじょうーぶよ!こう見えても私、結構優しいんだから、痛い思いはさせないわよ、安心して。」須崎の顔の前にしゃがみこみ、朝子はゆっくりとライターを弄んだ。「やや、やめろ・・・や、やめろよ・・・な、なにするきだよ・・・・」須崎の顔が恐怖に歪んでいく。ウフフ、バカみたい、こんなに怯えちゃって。まだなんにもしてないのにね。シュボッ、ヒッ!朝子がライターを灯した瞬間、須崎の口から思わず悲鳴が漏れた。眼前10センチに灯された炎。今まで無数に見てきたものだし、タバコを吸うときはもっと近くで着ける。だが今はわけがちがう。縛られて身動き一つできない自分。そして自分の目の前でライターを灯し、楽しそうにクスクス笑う美少女。そして、その美少女が可愛いルックスとは裏腹に、他人を傷つけることを何とも思っていないことは先刻、たっぷりと身をもって味合わされたばかりだ。今の須崎にとって目の前のライターの炎は、タバコに火をつけるためのちっぽけな炎ではなくなっていた。それは原始の炎、野獣が本能的に恐れた、克服しようのない恐怖に膨れ上がっていた。「須崎さん、す、ざ、き、さん!ねえ、ねえったら!!!」パンッ!朝子の平手打ちに漸く須崎は現実に引き戻された。まだ何もされていないのに既に全身油汗まみれだ。「ねえ、私、これからどうするかわかる?どうやって拷問するのか、わ、か、るーっ?」わからない訳がない。文字通り火を見るより明らかだ。だが、そんなことを自分の口から言えるわけがない。「や、やべ・・・ゆ、ゆるじで・・・」「あん!そんな泣き声ださないでよ!何言ってるかわからないじゃない!ねえ、私、どうやるかわかる?て聞いてるんだよ!?簡単でしょ、答えてよ!答えてくれないなら・・・火炙りの刑だぞー!」朝子がグッとライターの炎を須崎の鼻先に近づける。「ヒアッ!あ、熱い!や、やめて、火炙りだけは許してくれーっっっ!」もはや恥も外聞もない、須崎は絶叫し、何とか逃れようと必死で全身をくねらせる。
「キャハハハハハッ!わかってるじゃない!そうよ、火責めにしてやるわ!」拷問開始を宣告するや否や、朝子はピョンッとジャンプした。ドスッ!グエッ!見事に須崎の背中のど真ん中にヒップドロップで着地した朝子は須崎の指先にゆっくりと炎を近づけていった。「さあてっと!じゃ、拷問開始っ!朝子の火責め拷問、たっぷりと楽しんでね!」笑いながら朝子はゆっくりとライターの炎を須崎の指先に近づける。「イアッ!ヤ、ヤメ、ア、アヂッ!アヂアヂアヂイイイッッッ!!!」早くも須崎の絶叫が轟いた。「アハハハッ!もう大袈裟なんだからっ!私、まだ近づけただけだよ。直火でもないのに、もう大袈裟ね。」朝子は一旦遠ざけた炎を再び近づけていく。「ねえ、須崎さんって随分毛深いのね。指にまで毛がこんなに生えてるのって、ウザくない?毛焼きしてあげようか?」チリッ、チリッと炎の先端で須崎の指の毛を炙ってみる。「ギャッ、アヂイ、ヤ、ヤベロ、ヤメ゛デグレーーーッッッ!!!」必死の絶叫をあげつつ須崎は何とかのがれようと必死で手を動かそうとするが、しっかりと縛り上げられたロープはびくともしない。須崎にできるのは半ば本能的に、両手を必死で握ったり開いたりとバタバタさせるのみだった。だがその程度の動きは須崎の背中にどっしりと腰を据えて火責めを楽しむ朝子にとって、何の妨げにもならない。手の動きで多少は風が起き、炎を揺らしてはいるものの強風の中でも火が消えないように設計されているZIPPOだ。消える心配など全くない。むしろ手の動きと相俟って須崎の指を不規則に炙り、満遍なく熱を伝えるのには却って好都合だった。熱さに加えて、後手に縛られた手を炙られている須崎は朝子の動きが全く見えない。気まぐれにライターを動かし、指先から手首までのあちこちを炙る朝子の炎が全く見えず、次にどこを炙られるのか全くわからないことが須崎の恐怖を一層掻き立てる。「ヒアッ!アヂイ、アヂイヨーーーッッッ!イアッ!ピギイ゛゛゛゛!!!」
朝子にとっては何とも楽しい拷問だった。殆どなんの労力も使わない、単にライターの炎をちょっと近づけたり遠ざけたりするだけで須崎が全身を痙攣させ、苦悶の絶叫を張り上げる。上から見下ろすと須崎の苦悶の動きは激しい、というよりむしろコミカルとさえ言えた。最高!こんなお手軽拷問なのに効果絶大じゃない!あたし冴えてるーっ!火責めを楽しむ朝子の瞳が、ふと須崎の指の変化を捉えた。あら、これ何かしら?須崎の指のあちこちに半透明というかやや白っぽい水泡ができつつあった。何、この膨らみ、なんか気持ち悪いな・・・一瞬戸惑った朝子だったが、直ぐにその正体に気づいた。あ、なーるほどね、熱が中まで通って水泡が出来てきたって訳なんだ。あーあ、可哀想に。火傷の水泡って痛いのよねえ。なかなか治らないし。クスクス笑いながら朝子は更に炎を近づけてみた。「ギャアッ!アヅ!イヤ!ヤベヤベヤメテグレーーーーッ!!!」チリチリと須崎の指の毛がカールしながら焦げていく。毛が焼け焦げる嫌な臭いと、屈託なく更に楽しそうに笑い転げる朝子の笑い声が須崎の悲鳴に重なっていった。
7
坊野、奈良村、須崎の三人が拷問に呻吟している中、ポツンと未だ静かな一角があった。富美代と検見川の一角だった。坊野たちの方に顔を向けたままうつ伏せに転がされている検見川は恐怖に震えていた。拷問、と聞いても最初は所詮お嬢様連中、単に殴る蹴る程度だろ、とタカをくくっていたが、目の前で繰り広げられているのは本格的、あまりにも本格的な拷問だった。今まで聞いたこともないような三人の絶叫は検見川を震え上がらせるに十分なものだった。そして、自分の目の前にしゃがみ込み、じっと自分の目を見ているのは、自分が騙し、レイプしようとした当の富美代なのだ。どんな目に会わされるのか、検見川は恐怖に震えていた。こんなに怖いのは生まれて初めてと言ってもいいほどだった。富美代が何も言わず、じっと自分を見つめているのが余計に怖かった。
「・・・何震えてるの、先輩・・・」ポツンと富美代が声を発した。「・・・怖いの?坊野さんたちがあんな拷問されてるから?怖いの先輩?私に拷問される、て怯えてるの?」静かな、どこか哀しげな声で富美代は語りかけた。その静かさに検見川は縋り付いた。な、なんでもしてやる!あ、あんな目に会わされる位なら、なんでもしてやる!「あ、ああ、怖い、怖いよ。なあ、許して、許してくれよ。冗談、冗談だったんだよ。なあ、頼む、頼むから・・・ほどいて、ほどいてくれよ・・・頼む、頼むよ・・・俺を、あんな目に、あんな目に合わせないでくれよ・・・なあ・・頼むよ・・・」検見川は必死で哀れみを乞う表情を作り、自分的には一世一代の名演技で何とか富美代を口説き落とそうとした。相変わらず静かに見下ろす富美代の瞳に、微かな悲しみの色が浮かんだ。
「・・・そう、怖いんだ。先輩、怖いんだ・・・だけどね、私だってさっき、とってもとっても怖かったんだよ。でも先輩、私のことなんか全然心配もしてくれなかったね。今だってそう、私のこと傷つけて悪かったなんて、全然考えてもくれてないんでしょ?自分が痛い目に会いたくない、それだけなんだね・・・私のことなんか、何にも考えてくれてないんだよね・・・」「ち、違う、そ、そんな、そんなことない!違う、ちがうーっ!わ、悪かった、悪かったよ、許して、頼む、許してくれよーっ!」「・・・先輩、なんでそんなに必死で叫ぶの?本当は悪かった、なんてこれっぽっちも思ってないんでしょ?なのに何でそうやって謝るの?私が怖いから?私に苛められる、て思うから?私も礼子たちと同じ、他人のこと平気で痛めつけられる女の子だと思うから怖いの?ねえ、何で?要するに先輩、痛い目に会うのが嫌なだけなんでしょ?」図星、ご名答。だがそれを認めるわけにはいかない。検見川は必死で取り繕おうとした。「ち、違う、ほ、本当だよ、し、信じて、信じてくれよーっ!ほ、ほ、本当に悪かったって思ってる!な、何でも、何でもするから、だから、だから頼む、ゆ、許して、許してくれーっっっ!!!」這いつくばったまま半べそをかきながら必死で哀願する検見川を見下ろす富美代の瞳から一滴、大粒の涙がこぼれると同時に耐え難い程の嫌悪感が浮かんだ。「・・・嘘つき・・・未だそうやって嘘をつき続けるんだ・・・私みたいなバカな女の子なら、そうやって舌先三寸でどうとでも言いくるめられる、て未だ思ってるんだ・・・嘘つき・・・最低・・・!」ペッ!富美代は必死で喚き立てる検見川の鼻先に思いっきり唾を吐き掛けた。ベチャッ、ウッ!思わず反射的に睨み返したくなるのを堪えながら検見川は必死で哀願し続ける。つ、唾なら、唾程度ならいい。あ、あんな、あんな拷問される位ならなんでも、なんでもする!「た、頼む、頼むよ富美ちゃん、し、信じてくれよ・・・つ、唾を掛けたくなるのもわ、分かるよ。ひ、酷いことしちゃったからな。それで気がすむんなら、い、いくらでも唾かけてくれ!で、でもし、信じてくれよ、お、俺はな、なんにもするつもりなかったんだよーっっっ!!!」富美代の切れ長の瞳に嫌悪感を通り越し、怒りの色が浮かんできた。「・・・最低・・・未だ言うの・・・じゃあ、これは何なのよ、これは!」
富美代は検見川の尻ポケットに手を突っ込むと、隠し持っていたバタフライナイフを取り出した。「何なのよこれは!?先輩、女の子とのデートにナイフを持ってくのがノーマルだ、とでも言うつもりなの?答えてよ!」あ、アワワ!ま、まずい、まずい!!!な、何とか、何とか誤魔化さなくちゃ!!!検見川は必死で言い訳を探し、頭をフル回転させた。「、それは・・・そう!そうだよ!ほら、最近何かと物騒だろ?だ、だから、誰か悪いやつに襲われたら危ないだろ?だ、だから、そんな時にふ、富美ちゃんを守ってあげるようにって思ってもってたんだよ。な、ほんと、本当だよ!「私のことを守るため?先輩が?私たちをレイプしようとした先輩が?・・・ねえ先輩、言ってて恥ずかしくない?よくもまあ、いけしゃーしゃーとそこまでペラペラと嘘を並べられるわね。」富美代の美貌が青白い炎のような怒りで静かに燃え上がった。「先輩、こんな格好いいイケテル顔してるのに、先輩って最低最悪ね!先輩の中には絶対悪魔がいるのよ。私が悪魔祓いをしてあげる。先輩の腐った根性、私が根本から叩き壊してあげるわ!」富美代はスッと立ち上がると同時に検見川の肩を蹴り上げ、うつ伏せに転がした。外された肩が捩じれ、うめく検見川の顔の横にしゃがみ込むと、富美代は手にした検見川のナイフをカシッと起こし、その刃で検見川の頬をピタピタと叩いた。検見川の全身が恐怖に震える。「ヒッ!ヒッ!な、何を、や、やめて・・・」「怖いの、先輩?これ、先輩のナイフでしょ?自分が散々使ってきたナイフなのに、何をされるかわからないの?じゃあ、私から質問よ。先輩、ナイフはどうやって使うものなの?刺すの?こうやって刺すものなの?」言いながら富美代はナイフの切っ先を検見川の頬に押し当てた。刺さるほどの力は加えていない。だが、チクリとした痛みだけでも検見川の恐怖を更に煽るのには十分だ。「い、イヤーッ!や、やべ、おねがいだーっ!」検見川の絶叫を暫く観察していた富美代は一旦、ナイフをすっと外した。「う、ううっ・・・お、おねがいだ・・・お願いだから刺さないで・・・」すすり泣きながら哀願する検見川を見下ろす富美代の顔に残酷な微笑が浮かんできた。
「フーン、そんなに怖がるってことはどうやら、ナイフは刺すのが正しい使い方なのね。いいわ、先輩、一つ安心させてあげる。私、このナイフで先輩のこと、刺したりしないわよ。約束してあげる。」「ああ、あ、ありがとう・・・」涙と涎で顔中グシャグシャになりながら、検見川は思わず富美代に礼を言ってしまった。「ありがとう?そう、刺されなくて良かったわね。」言いながら富美代は再びナイフを検見川の顔に近づける。「ヒ、ヒイーッッ!さ、刺さないって約束したじゃないかあーっ!!!」「そうよ、先輩、刺さないって約束したわ。だから、刺さないで切り裂いてあげる。先輩のこの顔を。先輩、イケテルこの顔、ご自慢なんでしょ?この顔で私みたいなバカな女の子を何人も騙してきたんでしょ?ウフフ、でも可哀想。今日限りもう二度とそんなこと、できなくなるわね。この顔に二度と消えない傷を刻み込んであげる。思いっきり派手な、隠しようのない傷を刻んであげる。先輩、そんな傷のあるスカーフェイスじゃ、二度と女の子を騙せないわね。」「イ、イヤーッ!や、やめてくれーっっっ、か、顔は、顔だけはやめてくれーっっっ!!!」富美代の見抜いた通り、検見川の最大の自慢はそのルックス、要するに顔だった。だからその自慢の顔を傷つけられる、それも一生消せない傷を刻み込まれる、というのは検見川にとって何よりの苦痛だった。
富美代は必死で叫びながら顔を振り、何とか逃れようとする検見川の髪を鷲づかみにし、次いで膝で額をゴリゴリと音がしそうなほど強く押さえつけた。「ヒッ、イ、イダイ!」「大丈夫、大丈夫。直ぐにこんなの痛いと感じなくなるわよ。だってこうするんだからね!」富美代は握り締めたナイフを検見川の左頬にグッと押し当てると、まるで刺身を引くようにナイフの刃全体を使い、一気に検見川の頬を引き切った。深く、より深く傷を刻もうと手にたっぷりとウェイトをかけ、ナイフを少しでも検見川の顔の奥に食い込ませようとしながら、富美代は検見川の頬を縦に切り裂いた。「ギ!ギアーッッッ!!ヤ、ヤベデーッッッ!!!」ズパッ・・ナイフの先端が検見川の顎の辺りを通過し、顔から離れるのを追いかけるように検見川の顔に赤い線が走り、プツップツッと血の赤い玉が湧き出した。ふーん、これが人を切る感触なんだ。なんかお刺身切る時とあんまり変わらない感じだな。でも、結構いい手応えね。血は直ぐに繋がり、後から後からとめどなく流れ出し、検見川の頬を染めていく。「ビャアーッッッ、か、かおがーっ、お、俺のかおがーっっっ!!!ああ、あぢい、アヂイヨオオオオオッッッ!!!」だが富美代は泣き喚く検見川に一切構わず、今度は鼻の横辺りに、丁度顔を横切るようにナイフを当てる。「アハハハッ!先輩、いい傷じゃない!先輩みたいな人でなしでも、一応血は赤いんだ!私、先輩の血はどす黒いんじゃないか、て思ってたよ!?赤い血で良かったね、先輩、じゃあもっと、もっともっと一杯血を流してあげる!」ズリュッ!「イ、イアーッッッ!!!い、イデエ、イデエヨーッッッ!!!」「アハハッ、アハハハハッ!どう先輩、思い知った?もうこの傷、一生消えないわよ!アハハッ、アハハハハッ、アハハハハハハハハッ!」富美代はゆっくり立ち上がると、左頬に深く長い傷をまるで十文字のように刻まれ、激痛に泣き喚く検見川を見下ろしながら狂ったように高笑いした。「ア、アアアッッッ・・・お、おれの、俺のかおがーっ、い、いでえ、いでーよーっ!あ、あんまりだ、あんまりだあああーっっっ!!!」泣き喚く検見川を暫く楽しんでいた富美代は、やがてゆっくりと右足をあげ、思いっきり蹴り付けるように検見川の血塗れの顔を踏み付けた。「いいザマね、先輩。でもね、まだまだ終わりじゃないのよ。こんなんじゃ拷問にもリンチにもなりはしないわ。先輩、先輩は私の心を踏み躙ったわ。土足で踏み躙ったのよ。こんなちっぽけな傷じゃ、私の心の傷の万分の一にも足りないわ。」「い、いや、もうやべでグブァッ!」検見川の哀願を踏み潰しながら富美代は続けた。
「先輩、このブーツどう?先輩が赤、大好き、て言うから何軒も何軒もはしごして、必死で探してやっと見つけたブーツよ。先輩のために買ったブーツなんだから、先輩の体でたっぷりと味わってね。町で女の子のブーツを見たら、赤い靴を履いている女の子を見かけたら、それだけで体が震える位の、一生消えないトラウマを刻み込んでね。折角の先輩のためのブーツなんだから!」冷たく言い放つと富美代はブーツの銀色に光り輝くメタルピンヒールを検見川の頬の傷、タテヨコの傷が丁度クロスするポイントに押し当てると、一気に全体重を掛けて踏み込んだ。「ブ、ブビャァーッッッ!ビ、ビダイ゛―!ッッ!!ア!アブァバババーッッッ!!!」断末魔のような絶叫がフロアに響く。「ほらほら!たっぷり味わってよ先輩!先輩のためのブーツなのよ!どうなの、おいしい?うれしい?ほらほら!ブーツでピアスしてもらうなんて、一生二度と出来ない経験でしょ?たっぷり楽しんでよ!ほらほら、どう、どうなのよ!何とか言いなさいよ!」富美代は全体重を掛け、ギリギリとブーツのヒールをめり込ませる。「ギャ、ギヒーッッッ!イ゛ア゛―アッッ!!!」検見川の絶叫は悲鳴とも泣き声ともつかぬ、獣の断末魔のような、聞く者の耳から一生消えないような凄まじいものになっていた。無理もない。如何に鋭いピンヒールとは言っても基本的には歩くための、人間の体重を支えるためのものだ。錐や尖針とは違い刺し貫くためのものではない。そのヒールで頬の肉を、如何に深く刻み込んだ傷口だとは言っても、人間の肉体を踏み破ろうというのだ。簡単に刺し貫けるわけがない。針で刺し貫かれるなら数秒で刺し貫かれる分、まだいい。だが富美代は本来、刺さるわけのないブーツのヒールで検見川の頬に穴を開けようというのだ。富美代はヒールに全体重をかけながら、右に左にと激しく足首を捻り、検見川の顔を踏み躙り続けた。刺さるのではない。富美代がブーツで踏み躙る動きに連れ少しずつ、少しずつ、検見川の頬の筋繊維がヒールにこすられ、すり潰され、引き千切られていく。刺されるのより何百倍も痛い。おまけにそう簡単に穴があくわけではないから、たっぷりと時間をかけて検見川は地獄の苦しみを味合わされる。「イヴァッ、イビギャアアアアアッッッ!!!」検見川は間断なく断末魔のような悲鳴を上げ続ける。そうよ、先輩、その声よ。もっともっと、もっともっともっともっと苦しむのよ、泣き喚くのよ!私、さっき一生で一番傷ついたんだから。一番泣いたんだから。だから負けない。先輩なんかに負けない。私よりもっと泣かせてあげる!先輩を私よりもっともっと、100倍たっぷりと泣かせてあげる!
1ミリ、また1ミリ、ゆっくりゆっくりと富美代のブーツは検見川の肉を血管を神経を引き千切りながら進んでいく。やがて富美代はブーツを通して感じる抵抗が少し軽くなったのを感じた。うん?どうしたのかな?構わずブーツを捻じ込み続けると最後にまた少し、固いというより妙に弾力のある抵抗を感じた。ったく、しぶといわね。富美代は一瞬、ブーツを少し持ち上げるとグッと勢いをつけ、思いっきり踏み込んだ.「ギ、ギアーッ!ウ!ウブアッッッ!!!」突然、富美代はブーツのヒールにかかる抵抗がなくなり、検見川の頬をヒールが一気に貫通するのを感じた。同時に、口の中に侵入した富美代のヒールと踵全体が頬にのしかかったことにより、検見川の悲鳴は瞬時にして押し殺された、なんとも苦しげな悲鳴に変えられてしまった「アハハハハハッ!やった、やったわ!どう先輩、少しは思い知った?私のブーツの味は如何?良かったわね、これでほっぺたに特大ピアスを嵌められるわよ。ピアス、通しやすいようにもっと穴を大きくしといてあげるわね。ほら!ほら!ほら!」富美代は高笑いしながら足首を、いや脚全体を使ってブーツを前後左右、円を描くように大きく振り動かした。どう先輩、痛い?苦しい?許して欲しい?でも駄目よ。絶対に許してあげないんだから!私、今日が終わったら先輩のことなんか、ぜーんぶ、綺麗さっぱり忘れてやるわ!先輩なんかよりずっとクールな彼氏も作って、一杯一杯ハッピーになってみせるわ。だけど先輩には私のこと、絶対に忘れさせてあげない!この傷が疼くたびに私のこと、思い出してね。鏡に写るこの傷見る度に、私のこと思い出してね。一生私の影を引きずって生きていってね。醜い傷だらけのスカーフェイスで。先輩、これから一生死ぬまでずっと、思いっきり不幸な人生を送ってね。どうか先輩の一生に、今後いいことなんか一つもありませんように。それが私のことを傷つけた報いよ。一生かけて償ってね!メリ、ミリ、ベリ・・・「ビ!ビア゛ア゛ア゛ア゛!!ヤ、やべで、ざ、ざげるーーっっっ!!!」検見川は自分の顔が引き裂かれる音を確かに聞いたような気がした。痛い、などという言葉では生ぬるい。今まで人生で経験した痛みを全部合計しても遠く及ばない、発狂しないのが不思議な位だった。しかも頬を貫通したヒールに口の中を掻き回され、悲鳴をあげることすらままならない。その悲鳴は富美代の全身に浸み透るようだった。ああ、いい気持ち。ブーツ越しに、検見川の頬を引き裂く感触と全身を間断なく痙攣させる検見川の苦悶が伝わってくる。富美代の耳は断末魔のような検見川の悲鳴に満たされている。そして足元を見下ろすと、自分のブーツに縫い付けられ虫けらのようにのたうち回る検見川の無様な姿と、頬から、口の中から溢れ出る真っ赤な鮮血で床が血の海のようになっているのが見える。ああ、いいわ・・・癒される・・・先輩が私の拷問で苦しんでいる・・・私を傷つけた報いを受けている・・・地獄に堕とされた検見川の苦悶が、富美代の傷ついた心に無上の癒しとなって浸み透っていく。
だが癒し、と言っていられるのは責め手の富美代だけだ。拷問されている検見川にとっては癒しどころではない、凄まじい激痛に間断ない悲鳴をあげるのが精一杯だ。余りの凄まじい悲鳴に、礼子たち三人まで自分の拷問を中断して富美代のところにやってきてしまったほどだ。「ワオッ!すっごーい、完全に貫通してるじゃない、フミちゃん凄い事するわねえ。」「うわ、ほっぺた裂けてるじゃない、いったそー!」「でもさ、なんか綺麗じゃない?だってフミちゃんのブーツ、メタルヒールじゃない?銀色のヒールと血の深紅のコントラストって、なんか綺麗じゃない?」富美代のブーツに踏み貫かれ、床に縫い付けられた検見川の前にしゃがみ込んで礼子たち三人は口々に感心したような声をあげた。「あ゛、あ゛あ゛あああ、だ、だすげで・・」検見川の目は涙でかすみ、もう誰が目の前にしゃがんでいるのかさえはっきりとは見えない。だが必死で哀願せずにはいられなかった。「こ、ごろざれる・・」だが、その哀願は全くの逆効果、検見川本人だけではなく、SNOW CRACK全員をより深い地獄に引きずり込んでしまっただけだった。
「助けてですって?先輩、まだ言ってるの?今更誰が助けてくれる、て言うの?私が許すとでも思ってるの?許してあげるわけなんかないでしょ?まだ思い知ってないようね。ええ、どうなのよ!ほら、もっともっと懲らしめてあげるわ!ほら!ほら!ほら!」「ギ、キヒーッッッ!イア、イダイ゛゛゛゛!!!」富美代が暫く休めていた足首を再び回転させ、検見川の頬を更に引き裂きにかかる。ガッ、ガッ、あん、なによこれ、硬いわね!富美代はイラついたように何度もブーツを蹴り込むような動きをした。「イ゛イ゛アーーーッぼ、ほねぐぁ、お、おれるーーーっ!!!」白い顔を真っ赤に興奮させた富美代も漸く気づいた。ああ、頬骨に当たってたのね、全く邪魔なんだから!ズボッと富美代はブーツのヒールを引き抜いた。銀色のピンヒールに検見川の血がこびり付き、不規則なストライプを描いている。「ひ、ひあっっっ・・」検見川は半失神状態で頬から、口から血を垂れ流している。いくら痛くても、傷口を手で押えることすらできない。止めどもなく血を、涎をだらしなく垂れ流しながらうめくだけしかできない。だが冷酷な拷問官と化した富美代は検見川に僅かな休憩すら与えない。「ほら先輩、誰がもう終わりって言ったのよ!許してなんかあげない、て言ったのが聞こえないの!?さっさと右のほっぺたも出してよ!」ガッ!「ブギャッ!」顔が捻じ曲がる位、思いっきりブーツの爪先で顔を蹴り上げられ、強引に反対側を向かされた検見川の右頬を富美代のブーツが踏み付ける。「フフフ、さあ先輩、片方だけじゃバランス悪いわよ。聖書でも汝、右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ、て言うでしょ?こっちにも大穴、開けてあげるわね!」凄絶な笑みを美貌に湛えながら富美代はナイフを拾い上げた。「・・ねえ礼子、私たち、少しぬるかったようね。」「全くだわ。私たちの拷問なんかフミちゃんの責めに比べたら、ほんの子供だましね。ちょっと手加減しすぎたようね。朝子はどう思う?」「ええー、ぬるかったかなあ?結構熱そうだったけどねえ・・でも、やっぱりもっと、逝くとこまで逝っちゃえ、て感じかな?」玲子たち三人の顔にも富美代と同じ、凄絶な笑みが浮かんだ。小さく頷き合うと、三人の拷問官もクルリと踵を返し、三方に待つそれぞれの担当受刑者へと向かっていった。拷問が再開され、そして過熱する時間が訪れた。
1
「さあ坊野さん、少しは休めた?あなたの相棒も目一杯、拷問されているのがわかったでしょ?お待たせしたわね、もうオードブルの時間は終わり。坊野さんにも本格的な拷問をたっぷりと味合わせてあげるわ。」相変わらず静かな、優しげな口調で恐ろしいことを宣告しながら礼子は再び、坊野の背中に腰を下ろした。「ヒ、ヒイッ!ほ、本格的な拷問だなんて・・や、やめてくれ!た、たのむ、や、やめて!」「もう!しっかりしてよ!坊野さん、悪名高いSNOW CRACKのプレジなんでしょ?たかだか女の子の拷問が怖いだなんて、おかしいわよ?」言いながら礼子は坊野の右手を握る。今度はボールペンなしで、そして必死で握り拳を作る坊野の小指だけを握り、無理やり伸ばさせる。既に十分痛めつけられ、握力が極端に低下した坊野の指は最早、礼子に抗することは不可能だった。
「ヒッヒ、イア・・や、やべで・・な、なにを・・」「あら、こうやって指握られてるのに、何されるのか分からないの?案外想像力貧困なのね。難しいことするつもりはないわ。指をへし折ってあげるだけよ。こうやってね。」ニッコリ笑いながら礼子はゆっくりと坊野の指を反らせ、折りにかかる。「ギ、ギアーーッッ!イ、イダイーーーッ!!ヤ、ヤベ、ビギャーアアッッッ!!!」ベギッ、坊野の小指、第三関節があっけなく脱臼する。「イ、イエッッッイ、イデエ、イデエヨーーー・・」余りの痛さにすすり泣く坊野を満足そうに見ながら、礼子は尚も折った指を離さない。
「ウフフッ、どう、痛い?少しは効いたかしら?じゃあね、もっといいこと教えてあげるわ。指の関節っていくつあるか知ってる?そう、人差し指から小指は各三個、親指は二個、両手合計で二十八個もあるのよ。ウフフフフ、全部へし折ってあげる。フフ、フフフフフ、クラゲみたいにしてあげるわ。どう、後二十七回もこの痛みを味合えるのよ。どう、嬉しい?楽しい?感想を聞かせてよ。」
楽しげに笑いながらも礼子はへし折った小指から手を離さない。そして一呼吸置き、坊野が味わっている脱臼の最初の衝撃的な激痛が少し収まった頃を見計らいながら第二関節をゆっくりへし折った。「イ゛!イ゛ギャアアアアッッッ!!!」だがまだ小指一本すら終わっていないのだ。礼子は焦らず、じっくりと坊野の苦痛の波を観察しながら、続いて第一関節を折りにかかった。「ビ、ビギイイイッッッ!」僅かに動かせる首だけをエビのように反らせながら、坊野は断末魔のような悲鳴を三度張り上げた。小指を完全に破壊した礼子が漸く、手を離す。いいな、この感じ。礼子は思わずうっとりと、遠い目になっていた。様々な関節技を使いこなせるといっても、基本的に格闘技として使う関節技は肘、肩、せいぜい手首位しか狙わないものだ。第一、礼子が修行したのはあくまで格闘技であり、相手を責めいたぶるものではない。
相手を脱臼させてしまったことは何回かあるが、それはいずれも事故、流れの中で予想外に技が深く入りすぎ、折ってしまった場合だけだ。
だが今は違う。礼子はゆっくりと指を折る快楽を満喫していた。じっくりと坊野の指を反らして行くと、ミシミシと関節がきしみ、もうこれ以上は無理だと悲鳴をあげるのが伝わってくる。それを更にそらして行くとキシッキシッと軋むような感触に変わっていく。このあたりになると、折られる坊野の絶叫は段々人間離れした悲鳴に変わってくる。そして更にそらすと何かが引っかかたようなブレーキが働き、坊野の関節が最後の抵抗を試みる。その抵抗を踏み躙るかのように更にゆっくりと手に力を込め、止めを刺しにかかるとゴリュッと関節が外れ、骨同士が滑るように擦れあう感触が伝わってくる。抵抗は今までの骨の抵抗と違い、筋が引きずられ、伸びていく柔らかく、どこか弾力のあるものに変わっていく。坊野の休む間のない悲鳴をBGMとして楽しみながら、礼子は極上の快感に、人体を破壊する快感に浸っていた。いつも慎治を鞭打っている時とは違う、再生、治療のことなど何も考えない、純粋な人体破壊。礼子は麻薬のように抵抗しようのない快感を無限に供給する、人体破壊の快楽の完全な虜となっていた。
坊野は小指の関節を三ヶ所ともへし折られ、激痛に肩を震わせながらうめいている。だが休む暇さえ与えずに、今度は薬指に礼子の白魚のような細く長い指がまとわりつく。「い、いや・・・も、もうやめでぐれ・・・」最早完全に涙声になって訴える坊野の哀願に礼子は冷たく答えた。「ダメよ。オードブルは終わり、本格的な拷問の時間だって言ったでしょ?まだ指は9本もあるんだから。どんどん逝くわよ!」
玲子もまた、自分の担当受刑者、奈良村のもとに戻っていた。「・・・さあタマナシ君、検見川さんの悲鳴、聞こえたでしょ?私もお遊びはおしまい。君にもあれ位の悲鳴をあげさせてあげるからね。」言いながら玲子は再びベルトを握り締めた。先ほどと同じく、バックルではなく、ベルトの先端の方を握っている。「フフ、脅かす割には拷問道具は相変わらずベルトなんで一安心してるんじゃない?でもね、私はこう見えても鞭のプロだからさ、色々な打ち方、使いこなせるのよ。さっきとは比べ物にならない位痛くしてあげるわよ。さあ、覚悟はいいわね!」「い、そ、そんな!も、もっと痛くだなんて・・・な、何をする気、ヒッや、やめ!ヒッ!」「煩いわね。何をするかなんて直ぐに分かるんだから、心配いらないわよ。その体にたっぷりと分からせてあげるからさ。さあ!逝くよ!」ビュオッ!と玲子のベルトは風を巻いて襲い掛かり、次の瞬間、ドズッと異様な、鈍い音を立てて奈良村の腕に食い込んだ。
「ギ、グブアーーッッッ!!!」先ほどとは全く次元の違う激痛に奈良村は思わず息が詰まりそうなほどだった。「アハハハハッ!どう、痛いでしょ!もっともっと痛くしてあげるからね、さあ、ガンガン逝くわよ!」ビュオッ、ブオッ・・・ドズッ、ガズッ・・・玲子の振るうベルトが立て続けに奈良村の体に襲い掛かる。
「ギャァァァァァッ!ビア゛―ッ!イダイ!イデエヨーッッッ!!!」余りの激痛に奈良村は喉が張り裂けそうな程の絶叫を上げつづけた。痛い、とにかく痛い。な、なぜだ。なぜこんなに痛いんだ。たかが、たかがベルトなのに。さっきと同じベルトなのに。だがその激痛は先ほどまでとは比較にならない。な、なぜだ、何をされているんだ。床にうつ伏せに転がされた奈良村からは玲子が振り下ろすベルトが見えない。肉体的な激痛に加え、自分が何をされているのかさえ分らない恐怖が奈良村の苦痛を更に倍化させる。
「ヒッ!ヒイッ・・・お、ねがい、もうやめ、ヒギイイイッッッ!!!」奈良村が激痛の余り、哀願すら涙声になるのを確かめて玲子は満足そうに一旦、ベルトを振るう手を休めた。「ウフフフッ、大分効いてるみたいね。じゃあ気分を変えて今度は体の表側を鞭打ってあげるわね。」玲子は言いながら奈良村の体の下にブーツの爪先を潜り込ませ、無造作に蹴り転がす。「ヒッ、か、体の表・・・い、今でも、背中や尻でもこ、こんなに痛いのに腹や胸だなんて!や、やめて、やめでぐれーっっっ!」
「うるさいわね!もう遊びはおしまい、て言ったでしょ?まだまだよ!拷問はこれから佳境に入るんだから!」喚き立てる奈良村の顔をブーツで踏み躙りながら玲子は無慈悲に拷問の続行を宣告する。「フフ、それにタマナシ君、そんなに悪いことばかりじゃないかもよ。こうやって仰向けになってれば、少なくとも自分がどんな拷問を受けているかだけは見られるかもよ。」スッと奈良村の顔からブーツを下ろし、玲子は間合いを取るために2,3歩下がった。「もっとも、君の動体視力で私のベルトの動きを見切れたら、の話だけどね。さあ、逝くわよ!」ビュオッ、ブオッ・・・ドズッ、ガズッ・・・玲子のベルトが再び唸りをあげて奈良村の体、二の腕から胸、腹を襲う。「ビ!ビギイイッ!イ、イダ,ゴブァッ!イ、イダイ!イダイイダイイダイヨーーーーッ!!!」背中とは比べ物にならない痛みに奈良村は獣のような絶叫を張り上げつづける。
自分をこんなに苦しめる玲子の拷問は一体なんなのか、奈良村は激痛の中で必死で見ようとした。だが全く分からない。「アハハハハッどう、痛い?どうなのよ!ほらほらほら!もっともっと!泣くのよ!喚くのよ!もがき苦しむのよ!」玲子は相変わらず高笑いしながらベルトを振り下ろしつづける。だが奈良村にはどう見てもさっきまでと同じく、単にベルトで打ちのめされているようにしか見えない。だがこの激痛、さっきまでとはケタが違うこの激痛は尋常ではない。自分が何をされているのかすら分からない、その恐怖が肉体の激痛に加え、精神的苦痛をも追加サービスしていた。奈良村が分からないのも無理はない。玲子の拷問の正体は僅か90度の手首の捻り、ただそれだけだったのだから。玲子は振り下ろしたベルトが遠心力を十分なスピードに変え、奈良村に命中する寸前に手首を返し、強力なスナップでベルトの威力を倍増させている。だが今はそれだけではない。命中する寸前、スピードが最高点に達したポイントで返した手首を内側に捻りこみ、ベルトの面ではなく、サイドで奈良村を打ち据えていたのだ。ベルトの威力が幅数センチに拡散されず、サイドの数ミリに全て集約される。しかもサイドは硬く、反り返ったりはしないから奈良村の体に命中したベルトは、その威力を肉体の表面に拡散させず、全てを体の奥深くへと食い込ませていた。
打撃の種類は、イメージとしては木刀に近い硬質のものだ。だが木刀よりも質量はない代わりに、より狭い範囲に集中する打撃はむしろ、日本刀による峰打ちに近いものがある。いずれにせよ、こんなもので打ち据えられては堪った物ではない。玲子の責めは筋肉がクッションとして受け止められる限界値を軽く突破している。連続して打ち据えながら、玲子は軽い驚きを感じていた。へえ、ベルトをタテにしたら、こんな感じになるんだ。打ち据える、という感覚とは全く違う、ガツッという手ごたえと共にベルトが奈良村の体に食い込み、急ブレーキがかかる。鞭打ちのように打ち抜く、といった感覚とは全く違う、居合抜きで巻藁等に切りつけた時の感触に似ていた。そして胸、肩など、奈良村の筋肉が薄く、骨が体表に近いところにあたると直接、骨にベルトが食いこむような素晴らしい感触がある。ギシ、ミジッ・・骨が軋み、食い込むベルトに悲鳴をあげ、ヒビが入っていく感触が玲子の手を通じ、全身に強烈な電流のような快感を走らせる。いい、最高・・・打つ、て言うより切りつける感じね・・いいわよ、タマナシ君、おバカな君だけど、私を楽しませるのは上手じゃない!もっと楽しませて頂戴!さあ骨が砕ける音を聞かせて!
玲子はヒユッと小さく息を吐き、気合を入れ直すと体を捻り、大きくバッスイングを取ると自らの全身をも鞭の一部とし、全身の力を込めてベルトを振り下ろした。狙いは・・・奈良村の肋骨、左一番下の肋骨だった。メジッ!「ぎ、きばあああっっ!」一撃で肋骨をへし折られた奈良村が悲痛な叫び声をあげる。「アハハハハッ!どう、今の一撃、気に入った?骨を砕かれる激痛って最高でしょ!ポキッて折られるよりずっとずっと痛いでしょ?ここまでの痛さなんて、そうそう味わえるものじゃないわよ!さあ、この痛み、もっともっとあげるからね!逝くわよ、次に砕くのは・・・ここよ!」玲子のベルトが風を巻いて襲い掛かり、今度は右の鎖骨を直撃する。バギイッ!奈良村は確かに自分の骨が砕ける音を聞いたような気がした。「ぎゃあああっ、あぎっ、ぎゃっ、やべ、やべでぇっ!!!」何か声を発していないと気が狂ってしまいそうな程の激痛だ。死んだほうが遥かにマシ、と思える程の激痛に喘ぎ、のた打ち回りながら奈良村は断末魔のような悲鳴を際限なく上げつづけた。
2
朝子もまた、大張り切りで担当受刑者の須崎のもとに戻っていた。「わあ、この指、どうしたの?真っ赤じゃない!それに何、これ。あちこち水泡ができちゃって、なんかいけない病気にでもかかっちゃったみたいだよ!」朝子の素っ頓狂な声が響いた。須崎自身は見ることができないが、確かに須崎の指は真っ赤に紅潮していた。ズキズキとした痛みが時間を追うごとにひどくなっている。火傷の典型的な症状、体の中に浸透した熱の効果が現れてきていた。「フーン、ああやって遠火で炙っただけでも結構、効くものなのね。どう、痛い?」「ヒッ!アッ!アヒッ!」朝子が指先でツンツンと軽く突っつくだけで、須崎の指に鋭い痛みが走る。「あ、あうっ、た、たのむ、も、もうやめで、あうっ!お、おねがいだから・・・」須崎が必死で哀願するのを朝子は面白そうに眺めていた。既に礼子たちは拷問を再開している。辺りには坊野たちの悲鳴が充満している。「うーん、まあ私としては許してあげてもいいんだけどね。でもね」クスリと朝子は笑った。「あっちでお友達三人とも、お楽しみ中みたいじゃない?一人だけハブにしちゃ可哀想だから、私がちゃんと拷問してあげるね。」
「ひっひーっ、そ、そんな、お、おねがい、や、やめて、たのむ、やめてくれーっっっ!」「うーん、どうしようかなーっと」と口では迷ったように言いながらも朝子は早くもライターを取り出している。「でもね、古今東西、拷問官が途中で受刑者を許しちゃう、ていうのはやっぱ、やっちゃいけないことだと思うのよね。だから・・・やっぱり、これの出番よね!」シュボッ・・・朝子は須崎の鼻先にライターを近づけると、これみよがしに目の前で点火した。それだけで須崎の全身に恐怖と悪寒が走る。
余りの恐怖にガタガタ震えている須崎を見て朝子は楽しそうに微笑んだ。「どうしたの、ガタガタ震えちゃって。あ、もしかして寒いの?まあ無理ないわね。コンクリートに直に転がってるんだもんね。うん、わかった、心配しないで。私があっためてあげるね。じっくりゆっくり、たっぷりとあっためてあげる!」言うなり朝子は一旦立ち上がり、須崎の背中にドスンと座った。「あ、あわわ、お、ねがい・・・」
「大丈夫、安心してよ。さっきみたいな酷いことはしないからさ。」えっ酷いことはしない・・・須崎の頭を一瞬の期待と不安がよぎる。「さっきの程度じゃあんまりあったまんなかったんでしょ?こんなに震えてるんだもんね。じゃ、今度は寒くないように、ちゃんと直火で炙ってあげるね。」
朝子はゆっくりとライターの炎を須崎の指先へと近づける。そして宣告どおり、今度はライターの炎の中に須崎の指を完全に捕らえた。「ひいいいぃっ、熱っ、熱いっ。やめてくれええっ!!!」須崎の悲鳴は先ほどまでとは比べ物にならない。必死で逃れようとするが手首を完全に縛られ、かつ肩は外されているのだ、動ける範囲などごく僅かでしかない。それでも須崎が僅かに動く指を必死で動かすため、炎は乱れ、あちこちになびいている。だが強風の中でも着火可能なZIPPOの炎はその程度では消えはしない。却ってあっちこっちに不規則に動く炎が須崎の指、手のあちこちを炙り、苦痛を増してしまっている。「アハハハハッ!須崎さん、おっきな体の割には結構器用なのね、指、凄い速さじゃない、もしかしてピアノでもやってたの?」
火責めを楽しむ朝子は楽しそうに笑っているが、責められる須崎はそれどころではない。余りの熱さにもがき苦しむので精一杯だ。「嫌ぁっ、いやっ、熱いっ、熱いぃっ。ぎゃあああああぁっ!!!」
ジリジリと炙られる須崎の指のあちこちで皮膚が焼けていく。直火とはいえ、ライターの炎は大した火力ではないから黒焦げ、とはいかないがそれでも皮膚が焼け爛れ、所々に赤い肉が露出している。既に水泡は殆どが熱に炙られ、破れている。炎に炙られ続けている須崎の指から血とも体液ともつかぬ液体が滴り落ちている。最初の内は指の毛が炙られ嫌な臭いを立てていたが、その臭いはもう収まり、別の匂いが立ち始めている。うん?なにかな、この匂い。なんかいい匂いだな。あ、そうか。これ、お肉の焼ける匂いだ!「わあ須崎さん、いい匂い!ねえ須崎さんも嗅げないかなあ、お肉の焼けるいい匂いしてるよ、どう、そっちにも逝ってる?なんか焼き肉食べたくなってこない?」だがそれに対する返事はない。いくら肉が焼ける匂いがする、とは言っても完全に指に、手に火が通り、痛覚が焼け死ぬにはまだまだ至らない、と言うかそこまでの火力はない。だから須崎は延々と苦痛を味わいつづけている。朝子の問いに答えるどころの騒ぎではない。「ぎゃあっ、熱いっ、嫌っ、ぎゃ、あっ、熱いぃっ。嫌あああっ、助けてっ、許してっ、ひいいいっ」
「ねえ私、お肉の焼ける匂いを嗅げてる、て聞いてるんだけどな。ねえ、どうなの、返事してよ?」朝子はライターの炎を手の甲の中心に持っていく。これでは逃げ場がない。須崎の手を一点集中で炎が炙る。「ぎゃああああっ、ぎゃぎゃがああああっ、ひいいいいいいっ!!」須崎の悲鳴がいっそう激しくなる。朝子の尻の下で須崎の体が激しく揺れる。「もう!おっへんじが、あっりませーん!」子供と遊ぶように、おどけながらも朝子は間断なく火責めで須崎を責め苛み続ける。朝子はこの火責めが心底気に入っていた。朝子は指先でライターの位置をキープするだけ。それだけで須崎が際限なく苦しんでくれる。責める朝子にとっては何ともお手軽な、全然疲れない拷問だが責められる須崎にとって、その苦しみは坊野たちに勝るとも劣らない。須崎の皮膚が焼け爛れ、所々ピンクの肉が現れそれも焼けていくところを朝子は特等席でじっくり観察できる。炎で炙られる須崎の全身の痙攣が尻を通して朝子の全身に伝わってくる。その苦悶を、自分は殆ど指先一本動かさずに楽しめるのだ。もともと些かものぐさの気がある朝子にとって、このお手軽な拷問はなんとも性に合うものだった。「もう!お返事してくれないのね!冷たいんだから!いいもん、じゃあ一人で楽しんじゃうから・・・バーベキューパーティーをね!」バーベキュー、そう、須崎は朝子を楽しませる人間バーベキューとなり、延々と焼かれ続けていた。
「グギャアアアアアアアアァァッ!!痛い、痛い痛い痛いぃぃっ!ヤベデェェッ!!」「あ、が、ぎゃあああぁっ。う、うぐぐ……ぎやあぁっ!うぎゃあああああああああああぁっ!!」「ぎゃああああっ、ぎゃっ。許してっ、嫌ぁっ、痛いっ、ぎゃああああああっ!!」「ぎゃあっ、熱いっ、嫌っ、ぎゃ、あっ、熱いぃっ。嫌あああっ、助けてっ、許してっ、ひいいいっ!!」拷問は佳境を呈していた。「アハハッ、アハハハハッ!」「ほらほらほら、どうしたの、もっと叫びなさい!」「どう、楽しい、最高だよね!」「エヘヘヘヘッ、こっちも焼いてあげよっと!」坊野たちの絶叫と礼子たちの笑い声が工場の全空間を満たしていた。人間の声に混じり、微かな音も鳴りつづけていた。ミリッ、ミリリリッ・・・ビキッ、ベシッ・・・ドズッ、バギッ・・・ジリッ、ジジジジッ・・・人間の皮膚が、肉が引き裂かれ、骨が砕かれ、炎に炙られる音が。
礼子たち四人は至福の時間を満喫していた。思う存分坊野たちを痛めつけ、苦しめていた。罪悪感など全く感じない。自分たちをレイプしようとした悪党に対して罪悪感や慈悲心などは全く感じなかった。プロの拷問官のように、礼子たちはより多くの苦痛を、より長時間与えることに全神経、全労力を集中していた。坊野たちにとってはまさに地獄だった。坊野たちとて喧嘩で負け、いいように殴られたりリンチを受けたこともある。常人よりは痛みに慣れているはずだ。だが礼子たちから与えられているような、本格的な拷問に近い痛みを味わったことはない。単なるリンチではない。拷問、プロが発揮する手練の技。常軌を逸した苦痛を長時間与えつづける技。慎治たちを苛めることによって得た経験、知識をフルに活用し、礼子たちはプロの拷問官に近い水準の技術を発揮していた。逃げ道などどこにもない。どう動こうと何をしようと、礼子たちが与える拷問の苦痛から逃れるすべはない。気絶という救いの女神すら、礼子たちの巧みな拷問テクニックに邪魔されて訪れてくれない。坊野たちは延々と、ひたすら愚直に苦痛を味わいつづけた。
「アッ!アヒッ!アヒーーッ!マ、ママーーーッッッ!ママーーーッッッ!!!」「ヒイッ痛い、痛い、いたいよーっ、誰か、誰かたすけてーーっっっ!」「ひぎーーーっもうしません、もうしません、もうしませんんんん!もうしませんからゆるしてーーーっっっ!!!」「ウギーーーッおがあぢゃーん、あづいよーっ、い、いやだ、やだやだ!あっあぢっ、あぢあぢいいいっ!あづいよおおおおおっ!!!」どんなに叫んでも何の救いも訪れない。礼子たちは拷問の手を全く休めない。ヒッヒイッ・・・な、なんでこんな目にあわなくゃいけないんだ、なんでこんな酷い拷問をされなくちゃいけないんだ・・・肉体も精神も崩壊の淵に近づいた時、坊野たち四人は漸く気づいた。救いの道に。拷問をやめてもらうたった一つの方法に。単純な事、拷問官に屈服し、問われるがままの答えを自白すること、それが拷問から逃れる唯一の方法だ。気が狂わんばかりの苦悶の果てに漸くそれに気づいた時、坊野たちの頭は最後の気力を振り絞るようにフル回転した。
な、なんだ、なんだ、なんなんだ。俺たちが聞かれていた尋問はなんだったんだ・・・そうだ、あれだ!四人は殆ど同時に気づくと一斉に絶叫した。「ひっ、や、やめて、しゃ、しゃべる、しゃべるからやめてくれえええええっ!」「た、頼む、や、やめて、少しでいいから、しゃべるあいだだけでもゆるしてえええっ!」「あ、あいつだ、あいつらにたのまれたんだーーっ!」「い、いやっ、しゃ、しゃべる、白状するからおねがい、火を、火をあっちへやってええっ、お願いだあああっ!」礼子たちは一瞬、視線を交わしただけで無言のまま拷問を続行する。だがもうこれしか希望がない坊野たちは必死で喚き立てた。「し、慎治、慎治たちだあああっ!」「た、頼まれただけなんだよ、あいつら、信次たちに頼まれただけなんだああっ!」「あ、あいつ、ほら、慎治、慎治だよおおおっ!」「し、熱い、信次、あのガキがわるいんだーーーっ!」
3
フウッ・・・礼子たちは拷問の手を漸く休め、視線を交わした。礼子の全身を興奮と何とも言えぬ満足感、達成感、俗な言葉でいえば快感が走り抜ける。性的な快感とは違う、精神的な充足をもたらす快感だった。やったわ、私、拷問に成功したのね。
さっきまであんなに反抗的だった坊野さんのこの態度、何?もうすっかり縮み上がっちゃって、私に反抗する気力など、根こそぎにしてやったみたいね。苦痛のみで相手を屈服させた、自分より体も大きく力もある相手を根本的に屈服させた、という快感に礼子は暫く酔いしれていた。横を見ると玲子も自分と同じく、何とも満足げな表情を浮かべている。「フフ、玲子、やっと屈服させたみたいね。」「そうね、どう、初めての拷問のご感想は。礼子も満足した?」「まあね、で、それはそうとして、今白状した依頼人、慎治たちとはね・・・」「そう?私は結構予想通りだったけどな。だってあれだけ苛めてやれば、流石に仕返しの一つや二つ、考えそうじゃない。ねえ朝子?」「うーん、そうねえ。信次たちならまあ、本命筋だけど・・・それにしても、連中にしては随分小ジャレタ仕返しを考えたものねえ・・・」ここまで言って三人は富美代を振り向いた。流石にブーツの動きは止めたが、富美代はまだ検見川の頬を刺し貫いたまま、ブーツを引き抜いていない。どこか遠慮しているかのような目で見ている礼子たち三人に頷きながら、富美代はゆっくりとヒールを検見川の頬から引き抜いた。
「ア、アワアアア・・・」苦しげにうめく検見川を冷たく見下ろしながら、富美代は新たな尋問をした。「・・・先輩、慎治たちに頼まれた、て言ったわね。でも先輩と慎治たちが友達だなんて話、聞いたことないわよ?どうしてこんなこと、引き受けたの?」だが検見川は未だ収まらぬ激痛に即答できなかった。そんなことを許す富美代ではない。一旦下ろしたブーツをすっと上げると、再び検見川の顔を踏み躙る。「どうなのよ!私の質問に答えられないの?さっさと答えないと・・もう一穴開けるわよ!?」もう一穴!検見川の口を開かせるには十分だった。「ヒッヒイッ!や、やめて、やめてくれーっ!は、話す、なんでも喋るからやめてくれーっっ!か、かね、金だよ、俺たちゃ、金で雇われただけなんだーっ!」クスリと傍で聞いていた玲子が笑った。「お金で雇われた、ねえ・・ねえタマナシ君、君もそうなの?」「あ、アウッそ、そう、そうなんだ、お、俺たちは金で頼まれただけなんだ。だから・・・もう、許して・・・」フウッ・・・礼子も小さく溜息をつきながら坊野の顔を軽く蹴りながら尋ねた。「フーン、お金で雇われたの。ところで一体、幾らで雇われたの?」
「じゅ、十万、一人十万円だ・・・」「たったそれだけ?たった十万円で雇われただけで、こんな手の込んだセッティングして私たちのこと、襲ったの!たった十万円で!ご苦労様・・・それでこうやって返り討ちにされて拷問にまで掛けられて・・・随分と高くついたわね?」「あ、ああ・・・た、頼む、もう許して、ぜ、全部話しただろ?いや、か、金も、貰った金だって要らないから、いや、そっくりそのままやるから、頼む、もう許して・・・」「バーカ、私たち別にお金なんか要らないわよ!」笑いながら礼子は軽く坊野の顔面を一蹴りした。
ア、アワワ・・バ、バレタ、バレテしまった・・れ、玲子さんたちに全てバレてしまった・・信次たちは恐怖の余り失禁しそうだった。恐怖、苦痛、絶望・・ありとあらゆる負の感情が二人を包み込む。破滅、僕たち、もう終わりだ・・顔面蒼白で口をパクパクさせる信次たちの目にはもう、何も映っていない。「あーあ、バレちゃった。どうするの信次?」ツンツンと傍らの信次を肘で突っつきながら里美が呆れたような顔をした。「全く、あんたも思い切ったことしたものね・・ああいう連中雇って玲子たちを襲わせるとは、ね・・でもどうするつもりなの。一体?」「うーん、まあ、いくら無事だったとは言っても、結果オーライじゃすまないよ、これ。玲子たちを本気で怒らせちゃったかもね。ねえ、二人ともどうする気?ちょっとこれ、高くつくんじゃない?もしかしたら・・本当に殺されるんじゃない?」殺される!真弓がどこか楽しそうに言い放った恐ろしい言葉に、慎治は反射的に泣き出してしまった。
「そ、そんな・・こ、殺されるでなんて・・ね、ねえ、う、うそでしょ、うそだよね、うそだと言ってよーーっっ!」信次も思わず里美のブーツにすがり付いていた。
「お、おねがい・・た、助けて・・死にたくない・・」
里美と真弓は余りに身勝手な慎治たちの台詞に心底呆れたように、両手を軽く上げた。
「ねえ信次、何か勘違いしてない?」邪険に信次を振り払うと里美が冷たく宣告した。「私たち、玲子の友達だよ。第一、ギャング雇ってクラスメート襲わせようだなんて、あんたたちマジで人間腐ってない?なんで私たちが信次の味方なんかしなくちゃいけないのよ!拷問されようが殺されようが、自業自得でしょ!」大きく頷きながら真弓も続けた。「まったく・・はっきり言って私たち、ここで慎治たちのこと、速攻リンチしてやりたい位なんだからね、あんまり甘ったれたこと、言わないでよね!・・・最も」クスクスっと真弓は楽しそうに笑った。「慎治たちのこと、リンチしたいのは私たちだけじゃないかもね。あそこで寝てるSNOW CRACK、連中も慎治たちのこと、恨んでるんじゃない?なにせ、慎治たちのせいであんな拷問受ける羽目になったんだからさ。」そ、そんな!慎治たちには最悪の悪夢だ。ぼ、坊野さんたちにまで狙われるだなんて、そんな!その時、ふと下をみた里美が少し興奮した声をあげた。「うん?慎治、ちょっとこっち来てごらんよ。下でまた楽しいイベント、再開されるみたいよ。大丈夫、いいからおいでよ。ひょっとしたら慎治たちにとっても、FAVORな展開かもよ?」FAVORな展開?地獄に仏を求めるように、必死で救いを求めながら慎治たちはフロアを見てみた。そこで展開されていたのは、確かにある意味意外、慎治たちの想像を超えた光景だった。
「さーて、と。まあ一応自白もさせたことだし、取り敢えずは警察呼んで引き渡して、今日のところは終わりかしらね。」如何にも疲れたように腕をストレッチングしながら礼子が周りを見回した。富美代も朝子もそうね、という表情をしている。警察に引き渡される、普段だったら絶対マズイ、最悪の展開だが坊野たちにとって今、警察に引き渡される、という礼子の言葉はまさに、地獄に仏だった。け、警察、だったら病院に連れてってもらえるな。なんでもいい。とにかく病院にさえ連れてってもらえれば・・・だがそんな甘い希望を玲子が粉々に打ち砕いた。
「ちょっと待って礼子、まだダメよ!まだやることが残っているわ。」玲子の凛とした、この場の弛緩した雰囲気にそぐわない妙に強いトーンの声が響いた。「やること?未だ拷問続行するの?別にいいけど、一応自白させちゃったし、これ以上やっても単なるリンチじゃない?それもまあ楽しいけど、今日のところはもうご馳走様、て感じするけどな。」「ううん、私も拷問はもうするつもりないよ。だけどね、ここからが最後のツメ、ここをミスっちゃ、折角ここまで上手くやったのに、全部台無しになっちゃうよ。」「ツメ?うーん、分からないな。何を詰めるの?」ああ、礼子も分からないんだ。玲子にとっては少し意外だった。だけど考えてみれば、礼子はこういう方面、やったことないものね。じゃあ仕方ないか。「礼子、フミちゃんも朝子もよく聞いて。そもそも私たち、なんでこの人たちをやっつけて、更には拷問までしたの?お楽しみのため?ううん、確かに思う存分楽しんだけど、それはサブの目的よね。メインの目的は私たちの身の安全を守ることよ。普通の相手だったら、これでお終いでいいわ。もう十二分、お釣りがくる程よ。もう二度と私たちを襲おう、なんて思う訳ないわ。だけどね、こういった最悪のギャングたちはしつこさ命なのよ。これだけ痛めつけても、傷が治ったらリターンマッチでまた狙われかねないわ。そんなの、ご免よ。だからね。」玲子は一呼吸入れた。いつものように痛めつけるのを楽しむための、シチュエーション作りを楽しむ表情ではない、完全に100%真顔だ。「やるからには情け無用、やれる時に徹底的に、相手が再起不能になるまでやらなくちゃダメなのよ!」「確かに玲子の言うとおりだけど・・・でも、具体的にどうやるの?さっきあれだけ拷問したし、もっと痛い目にあわせる、て言ったってさっき以上の痛い目、て中々難しいと思うんだけどな?」小首を傾げながら朝子が言うと、礼子も富美代も確かに、という表情で頷いた。そうよね、朝子の言うとおり、さっき以上に痛い目なんて、一体どうやるの?「ううん、違うのよ、私は別にこれ以上痛めつけよう、て言ってるんじゃないの。原因を取り除きたいのよ。考えてみてよ、この人たちはなんで私たちを襲ったの?お金のため?確かにそれもあるけど、メインはそうじゃないわよね。私たちをレイプするのが目的よね。だったら」「そうか・・・なんか玲子の考えてること、分かったような気がする。」今まで黙っていた富美代が口を開いた。声の調子が妙に冷たい。「要は先輩たちが二度とレイプなんてしたくなくなる、ううん、改心してしたくなくなる、なんてことは絶対にないから、生理的に、と言うか物理的に、と言うか・・・兎に角二度とレイプなんかできない体にしてやろう、て考えてるんじゃないの?」「そう。フミちゃん、よく分かったわね。その通りよ。」礼子と朝子も薄々分かってきた。「そのとおり。この人たちのあそこ、ううん、タマタマね、そこを潰してあげるのよ。そうすればもう二度とレイプなんかできなくなる。もう二度と私たちを狙う理由もなくなるわ。」「ええっ!タマタマを潰すって、玲子、あなたまさか、そんなことまでしてたの!?」流石に驚いた礼子が思わず大声を張り上げた。「まっさかーっ!やだ、やめてよ礼子ったら!いくら何でも、そんなことするわけないじゃん!いくら私でもそこまでしたことなんかないわよ!」半ば笑いながら否定した玲子だが、直ぐ真顔に戻った。「マジで私もタマタマ潰したことなんかないわよ。だけど今は話が別。この人たちだけはキッチリ潰しといた方がいいわ。ここで手加減抜き、完全に再起不能にしとかないと、後で後悔しそうな気がするの。」
「ヒッ!ヒイイイイイッ!!や、やめて、それだけは!」「う、うそだ、うそだーっ!た、頼む、お願い、潰さないでくれえええっ!」「そ、そんな、やめてよして許してええっ!」「イ、イヤ、イャ、イヤアアアッ!!!」金玉を潰される!いくら痛いと言っても、今までの拷問の傷なら時間さえたてば何とか治る。検見川を除いては。
だが睾丸を潰されたらそうはいかない。一生治らないし、大体レイプを生き甲斐にしているような彼らにとって、それは半分殺されたも同然だ。坊野たちは必死で悲鳴を張り上げ哀願し許しを乞うた。哀願されることにすっかり慣れきっている玲子たちは坊野たちの哀願など殆ど気にもとめないが、朝子が少し心配そうに尋ねた。「えっ・・タマタマって、おちんちんの・・あのタマタマでしょ?ねえ玲子、そんなとこ潰して大丈夫?マジで死んだりしないでしょうね?半殺し程度ならいいけどさ、本当に死んだら流石にまずくない?」「うん確かに朝子の言う通りね。流石に死んだらまずいわよ。」富美代も頷く。確かに死んだらまずい、それには玲子も異論はない。「うん、確かにそうよね。で、考えてみたんだけど、タマタマ潰した時に死ぬのって、余りの痛さに自分で舌を噛み切っちゃうのが大半なんだって。だからさ、潰す前に顎を外すか歯をへし折っといてあげれば多分、大丈夫と思うわ。」ア、アワワ・・・こ、こいつら本気だ、本気で潰す気だ・・・坊野たちは殆ど小便を漏らしそうな位、怯えていた。だが追い討ちをかけるように、礼子が更に刑の追加を宣言した。
「ねえ玲子、宦官って知ってる?」「宦官?中国の?知ってるけど、それがどうかしたの?」「うん、宦官もあそこを切り取られたわけだけどさ、金や権力に対する欲望とか執念とか、方向性こそ変わってもそっちの方は消えないって言うか、却ってひどくなったって言うじゃない?だからさ、坊野さんたちもタマタマ潰しただけじゃ足りないかもしれないわね。性欲はなくなってもさ、私たちへの仕返しに一生を捧げます、なんてやられたらかなわないわ。だから、それこそ物理的に、腕力の面でも再起不能にしといた方がよくない?」「腕力も再起不能って、どうやるの?」「うん、折角肩と股関節外してあって仕事しやすいんだからさ、ついでに腱を全部捻じ切っといてあげようよ。そうすればもう、完全に再起不能よ。文字通り、一生女の子以下の力しか出せなくなるわ。」け、腱を捻じ切る!金玉を潰すだけじゃなく腱を捻じ切る!
「そ、そんな・・・や、やめてくれえええっ、ほ、本当に死んじまうよおおおっ!」
「あら大丈夫よ坊野さん、腱を捻じ切った程度で死ぬわけないじゃない?あ、そうか、痛さでショック死すること心配してるのかな?だったら大丈夫、心配いらないわよ。腱を捻じ切るのは最後、タマタマを潰してからにしてあげるから。どうせタマタマ潰したら、痛くて失神しちゃうか激痛でもう何も感じられなくなるわ。その後だったら、今更腱を捻じ切られた所でもう痛いなんて感じられないと思うから心配いらないわよ。」如何にも優しげに微笑みながら、礼子は平然と恐ろしい刑罰を宣告する。
4
「さあ、話はついたわね!と言うことでチャッチャッと逝こうか!」ヒッヒイッ!な、なにも話はついてないよおおっ!坊野たちの悲鳴、哀願など全く無視して四人の美少女は新たな刑罰の執行を開始した。「で、まず誰からいく?」「うーん、まあやっぱり、最初は言い出しっぺの私かな?」と玲子が言った瞬間、富美代の凛とした声が響いた。「待って、玲子!」三人の拷問官と四人の受刑者の視線が富美代に集中する。「今日のこのパーティー、そもそもの発端は私、ううん、私と先輩の二人よね。だったら・・・やっぱり締めも私と先輩からやらせて。」富美代は言いながら検見川の顔を再びブーツで踏み躙る。「そうよね、先輩。やっぱり先輩と私が一番最初にやるべきだと思わない?そうでしょ先輩、ねえどうなのよ!」幾ら踏み躙られても、検見川がハイそうです、と言えるわけがない。「や、やだ、頼む、やめ、やめてくれえええっ!!!やめてよしてたすけてえええっ!」「先輩、別にそんなに嫌がらなくてもいいジャン。どうせ先輩たち、みんな潰されるんだから。順番の違いだけ。それもほんのちょっとの時間の差だけよ。嫌なことは早く済ませた方がまだいいでしょ、ていう私のせめてもの優しさも分からないの?」富美代はブーツにグッと力を込める。グエッ・・・だがここで認めるわけにはいかない。理屈ではない。本能。金玉を潰される、という最悪の事態を少しでも、一秒でもいいから後に引き延ばしたい、そこに何か希望があるわけではない。だが引き延ばさずにはいられない。それは生存本能そのものだった。「や、いや・・・頼むよ、やめて、やめてぐれえええっっっ!」最早恥も外聞も何もない。検見川は涙で顔中グシャグシャにしながら大泣きしていた。「やだよおお、お願いだよおおお、潰さないで、おねがい・・・」
だが検見川を見下ろす富美代の端正な顔には何の変化もない。憐憫の情など、微塵もない。僅かに呆れた、といった感じで唇の端を歪めた富美代はブーツの爪先で検見川の顎をグイッとこじ上げる。「・・・先輩、そんなに潰されるのはいや?」「あ、ああ、お願い、なんでもするから潰すのだけは許して・・・」「フーン、じゃあ一回だけ、最期に一回だけチャンスをあげる。後の三人、坊野さん、奈良村さん、須崎さんの誰かが先輩の代わりになってくれるなら、私はその人のこと、潰すわ。先輩のことは許してあげる。」「ヒッそ、そんな無茶な・・・」出来るわけがない。藁にも縋りたいのは後の三人も同じだ。一分一秒でも長く生き延びたい。富美代の一言を聞いた坊野たち三人は殆ど反射的に顔を背けていた。「あ、ああ・・ぼ、坊野、た、頼む、お、おまえプレジだろ、いい思いもたくさんしてきたじゃねえか!沢山女も回してやったろ?た、頼む、助けてくれよ!な、奈良!お前にも女世話してやったろ?おい、なんで何もいわねえんだよ!おい、こっち向いてくれよ!すざきいいい・・・お、お前なら助けてくれるよな、代わってくれるよな・・・お前をチームに引っ張ったのは俺じゃねえか!な、頼む、今、今こそその借り返してくれよ!なあ、頼む、頼むよ・・・な、なんでだよおおお・・・なんでみんな何も言ってくれないんだよおおお・・・た、頼む、頼むよ・・・潰されたくねえよおおお・・・」当然の如く、三人とも何も言わない。ふ、ふざけるな!何で俺がお前の身代わりにならなくちゃいけねえんだ!三人ともそう叫びたかったが、声に出すことはできなかった。何か言えば富美代たちがどんな反応を示すか分かったものではない。触らぬ神に祟りなし、とばかりに坊野たち三人はひたすらだんまりを決め込んだ。
「・・・先輩、誰も代わってくれないみたいね。じゃあ、処刑始めようか。」「ヒ、ヒイイイイッ!た、頼む、頼むお願い待って、待ってくれえええっ!」「先輩、もう悪あがきやめたら?誰も代わってくれないみたいよ?もう諦めた方がいいんじゃない?後10秒、後10秒で誰も変わってくれなかったら・・・タイムアップね。」富美代は静かに言い放つ。「ヒ、ヒイッ!イ、イヤ、10秒だなんて・・・」「・・・1098・・・」「い、いや、待ってくれえええっ!」だが富美代は無表情でカウントダウンを続ける。「・・・765・・・」「い、いや、坊野、奈良、すざきいいいいい!頼むよ、たのむよおおお!!!」「・・・432・・・」「あ、ああああ・・・み、見捨てないでくれえええええ・・・」「・・・10。・・・先輩、タイムアップよ。」再び検見川の顔をブーツで踏み躙りながら刑の確定を宣告する富美代の声は、氷のように冷たかった。先程までの怒りはもうない。富美代を支配している感情はどちらかと言えば悲しみに近かった。自分が憧れていた先輩が、自分をレイプしようと嵌めたことに対する後悔ではなく、金玉を潰されるという恐怖だけでこんなにみっともなく泣き喚いている。先輩、やっぱり私のことなんかどうでもいいのね。私のためには泣いてくれないのに、自分のタマを潰されるとなったらこんなに泣くんだ・・・先輩、先輩はどこまで逝っても自分の事しか考えてくれないんだね・・・その悲しみはより残酷な刑罰の動機へと変化していった。ふと思いついたように富美代は振り向くと、玲子たちに声をかけた。
「ねえ玲子、私、気が変わったわ。」「何、どうしたのよ急に?」「うん、さっき頬にブーツでピアスしてあげたのは・・・拷問ね。そしてタマタマを潰したり腕、脚を破壊するのは将来に対する保険よね。だったら・・・一つ足りないものがあるわ。」
「足りないもの?何よ一体?」「うん、足りないものはね・・・罰よ。考えても見てよ、先輩たちは私たちをレイプして人生滅茶苦茶にしようとしたのよ?だったら、罪を憎んで人を憎まず、とは言うけど何の罰も与えないで許すわけにはいかないわ。これは先輩たち自身のためでもあるのよ。罪を犯せば必ず罰を与えられる。そのことをしっかり教えこんであげなくちゃ。玲子たちも分かるでしょう?先輩たちは人間じゃない、野獣同然の・・・そう、けだものよ。けだものに教え込むには言葉じゃ駄目、体に教え込まなくちゃ。二度と忘れられないように、厳しい、一生忘れられない位痛い罰を与えて体に教えこんでやらなくちゃ、本能に刻み込まれる程の罰を与えて懲らしめてやらなくちゃ駄目なのよ!」
礼子たち三人は思わず顔を見合わせた。フミちゃん、完全に目が逝っちゃってる。どうする?少し間を置いて玲子が口を開いた。「うーん・・・フミちゃん、気持ちは分かるけどさ、罰はまあ・・・タマタマ潰すだけじゃ足りないかな?それ、メチャメチャ痛いと思うよ。」「駄目よ絶対!絶対駄目!潰すだけじゃなくて、ちゃんと罰も与えないと駄目よ!」色白な、端正な富美代の顔で眼だけが爛々と青白い炎を発するかのように燃えている。それはある種、凄絶と言いたくなる程の美しさだった。フウッ小さく礼子が溜息をついた。「玲子、駄目よ、フミちゃんのこの目、見てごらんよ。フミちゃん、この目の時は止まらないよ・・・いいわ、確かにフミちゃんの言うことにも一理あるわ。罰を与えましょう・・・でもね、あれだけハードに拷問した後よ、あの拷問に匹敵する、ううん、それ以上の苦痛を与える刑罰って、何か考えつく?考えつくんだったらいいけど、ないんだったら玲子の言うとおり、タマタマ潰すので十分、刑罰になるんじゃないかしら?」虚を突かれたように富美代も、困惑したような表情を見せた。だがそれはほんの一瞬だった。どうすれば先輩のことを痛めつけられるかしら、さっきの拷問以上の苦痛を与えるにはどうしたらいいかしら・・・必死で考えながら富美代は自分のブーツの下でうめく検見川を見下ろした。頬はほぼブーツに覆われ、僅かに鼻だけがブーツの下から覗いている。鼻、鼻・・・鼻!富美代の脳裏に、稲妻のようにあるアイデアが閃いた。
「・・・思いついたわ、先輩への刑罰。」「何、どういう刑罰なの?」「聞いたことない?鼻鉛筆、とか鼻割箸って。ほら、両鼻に鉛筆とか割箸突っ込む、ていうリンチよ。昔の朝鮮高校のリンチらしいわね、たまにヤンキー系の雑誌なんかの伝説コーナーで見るけどさ、実際に見た人は多分殆どいない、まあ都市伝説の一種みたいなやつよ・・・ウフフフフ、ねえ先輩、伝説を現実に復活させてあげるわ。イマ風に進化させてね。フフ、ウフフフフ、もう分かったでしょ?鉛筆や割箸じゃなくて、もっともっと痛い、ずっとずっと硬くてよく効くものを突っ込んであげるわ。そう、突っ込むものは勿論・・・私のブーツのピンヒールよ!先輩、先輩への刑を宣告するわ。鼻ブーツの刑、受けてもらうわよ!」
鼻ブーツの刑!検見川も勿論、鼻鉛筆位は知っている。実際に見たことはないし、勿論やったこともない。だが半ば伝説と化した究極のリンチの一つ、恐怖の対象としてヤンキー系の先輩から語り継がれ、存在だけは知っていた。それを我が身で味合わされる。しかもブーツで。富美代のブーツで。両頬に大穴を開けられ、嫌と言うほど苛められ、責め苛まれ、その威力に震え上がらされた富美代のブーツで。そのピンヒールで頬より遥かに弱く、敏感な鼻を、鼻の粘膜を蹂躙され、踏み躙られるのだ。どんな痛みかは全く分からない、だがあれほど残忍冷酷に自分を責め嬲った富美代だ、今度も手加減など一切なし、遠慮会釈なく自分の鼻を責めることは容易に想像できる。ど、どんなに痛いのか・・・想像も出来ないほど痛いことだけは間違いなかった。
「さあみんな、手伝って!まずは場所を変えるわ。先輩をあそこに引き摺ってくわよ!」富美代が指差した先は工場のやや奥の方、階段状に一段低くなっている資材置場だった。「や、嫌だ、や、やめてくれえええええっ!ぎゃぁっ、い、いでえ、いでえええええっ!!!」関節を外された両腕を四人がかりで引き摺られ激痛に絶叫する検見川を委細かまわず、四人は検見川をその段差まで引き摺っていった。「そう、そこ、もうちょっと前、首だけ出るようにして。」富美代は仰向けに転がっている検見川の首だけが段差からはみ出て宙に浮いた状態にセットすると、検見川の顔を跨いで仁王立ちに見下ろした。「さあ先輩、もうすぐ準備完了よ。みんな、ちゃんと押さえてね。」「フフフ、分かったわフミちゃん、こうすればいいのね。さ、検見川さん、上向いてもらえる?」礼子が検見川の髪と顎を掴むと、グイッと強引に後ろにそらせた。「丁度いい高さじゃない、ちょうど検見川さんの頭の天辺が床についてるわよ。ウフフフフ、ここ、まさに鼻ブーツ専用の処刑台、て感じね。」礼子の顔に期待と興奮の彩が浮かんだ。「じゃ、私たちは両手を押さえてあげる。」玲子と朝子が両腕に乗り、検見川の動きを封じると富美代はゆっくりと検見川の胸の上に腰を下ろした。
「さあ先輩、入れるわよ・・・」ツッと右足を上げると富美代はゆっくりとヒールを検見川の鼻へと近づけていく。「や、いや、いやだあああっ、や、やめて、やめてそれだけは、ひっひいいいいいいいっっっ!!!」必死で首を振り何とか逃れようとする検見川の首を礼子がグッと腕に力をこめて押さえつける。「観念するのね、もうこの体勢じゃ絶対逃げられないわよ。下手に動くとヒールが変に刺さって却って危ないわよ。」「ひ、そ、そんな・・・ブギャッ!」恐怖の余り思わず凍りついたように動きを止めた検見川の左の鼻腔に富美代はブーツのヒールを侵入させた。「フンッ、結構きついのね。ギリギリじゃない、だけどまあいいわ。直ぐに拡張してあげるからね。」冷たく笑いながら富美代は左のヒールも鼻に侵入させる。いくら細いピンヒールと言っても女の子一人の体重を支えるのだ、それなりの太さはある。少なくとも直径1センチ程度しかない人間の鼻腔に入れるには、無理矢理こじ入れなければいけない。富美代はゆっくりと両足を左右に回転させ、ヒールがこれからの責めで抜けないように鼻にしっかりと侵入させた。
「さあ準備OK!どう先輩、鼻にブーツを突っ込まれた気分は?無様な姿ね、まるで鼻からブーツが生えてるみたいよ!?」「う、うびっひぎっややべで・・・」鼻に突っ込まれたヒールの圧力を少しでも緩和しようと検見川は必死で首をそらし、ほぼ垂直にまで曲げていた。余りに近すぎ、焦点距離が合わないためぼやけた視界に映るのは、富美代のブーツの銀色のヒールと黒いソールだけだった。視界の殆ど全てが富美代のブーツに塗りつぶされている。「ウフフフフッ、先輩、いい歌思い出したわ。ほら嘉門達夫のあの歌よ、あのフレーズ、チャラリー、鼻から牛乳!て知ってるでしょ?先輩にはこうかしら、チャラリー、鼻からブーツ!てね、どう、ぴったりでしょ、ねえ先輩、ウフ、ウフフ、アハハハハッ!」狂ったように笑いながら富美代は礼子の方を向いた。「ありがとう礼子、もうしっかり入れたから抜けないわ。もう首はいいから体の方、押さえてくれない?」「OK、じゃあ私が腰に乗ってしっかり押さえてあげるね!」腕から肩に玲子と朝子、そして腰に礼子が乗り検見川は完全に、身動き一つできない体勢だ。富美代が検見川の胸の上に腰を下ろしたままだから、未だ何とかブーツは刺さらないでいる。だがもう限界、あと僅か、あとほんの数センチ奥にブーツを押し込まれたら、間違いなく検見川の鼻は富美代のブーツにズタズタに破壊される。自分の足下でうめく検見川を見下ろす富美代の美貌が残酷な笑みに彩られた。「さあ先輩・・・鼻ブーツの刑、執行開始よ!」
「玲子、朝子、肩借りるわよ、それっ!」掛け声と共に富美代は玲子たちの肩に手を置くと、両手の力だけジャンプするように勢いよく立ち上がり、一瞬の反動をつけた次の瞬間、両手を玲子たちの方から離して全体重をヒールにかけ、検見川の鼻腔奥深くへと思いっきり踏み込んだ。「ガバアアアアッ!ビギャアアアアアアアッ!キ゜!ヒイイイイ!イイイッッッ!!!!!」獣の断末魔のような悲鳴が轟き、同時に少しでも富美代のブーツから逃れようとするかのように、検見川は全力で体を、首を仰け反らせた。検見川の腹の上で礼子の体が10センチほどバウンドするが、50キロはある礼子の体を腕も足も使わずに腹筋だけで跳ね飛ばすのは流石に無理だ。「アラッ!検見川さん、頑張るじゃない!だけど私を跳ね飛ばすにはその程度じゃ無理ね!」
両手も必死で動かそうとしたがこちらは肩を外されているからろくに力が入らず、僅かに自由な手首から先をバタバタさせるだけだ。そして検見川の必死の抵抗をあざ笑うかのように富美代は冷酷に鼻ブーツの刑を執行し続ける。「アハ、アハハ、アハハハハハハッ!ほら先輩、どう、どうなのよ!痛い!?苦しい!?でもまだまだよ、もっともっと痛めつけてあげる!これはケダモノへの、先輩への刑罰なんだから!もっともっと泣き喚いてよ!もがき苦しんでよ!ほら!ほら!ほらほらほら!!!」
富美代は高らかに笑いながらも巧みにバランスをコントロールし、転ばないように、鼻からヒールが抜けないように細心の注意を払いながら検見川を責め苛み続けた。
「ほら先輩、先輩のために歌ってあげるわよ!鼻からブーツ、鼻からブーツ、鼻からーー、ブーーーー、ツ!!!」富美代は大声で歌いながら足踏みをするかのように交互に細かくステップを踏みつつ左右のヒールを上下に、かつ腰のツイストも利かせて微妙に鼻の中の責めるポイントを変えながら激しく動かし、検見川の鼻の中をズタズタにしていく。
「ギイイイィッ!ヒギイイィッ!ヒギャアアアアァァッ!!イギャッ!ギヒャアアアアアァァッ!!!」この鼻ブーツの刑に比べれば、鼻鉛筆など子供の悪戯程度のものだ。鼻鉛筆はいくら痛くても一瞬、何度も何度も連続でやられることは殆どない。だが鼻ブーツの刑は違う。富美代は上から責めているのだ。まず力の入り具合が全然違う。鼻鉛筆は下から突き上げる手の力、それも相手も動くし細い鉛筆に力を伝えるため、持てる力のほんの一部しか使えない。だが富美代は全力で、全体重を使って検見川を責められる。しかも基本的には下段蹴り、と言うより足踏み運動に近い動きだから責める富美代はバランスにさえ気をつければ幾らでも責められる。富美代のヒールは繰り返し繰り返しいつまでも検見川の鼻腔を抉り続けた。検見川の鼻は突き抜けて穴を開けられるのだけはなんとか免れていたが、内部はもう滅茶苦茶だった。切れる、鼻血が出る、などという生易しいものではない。情け容赦なく抉り、踏み躙り続ける富美代のブーツは検見川の鼻腔の粘膜を剥ぎ取り、こそげ落し、鼻の肉自体を神経ごと抉り取っていた。
痛い、やめて、許して等という言葉を発する余裕などどこにもない。鼻自体の痛みだけではない、鼻腔の奥、眼球の裏にまでヒールの圧力は及んでいる。鼻の奥、目・・・更には地面に擦り付けられている頭蓋骨、殆ど90度直角に曲げられている首・・・頭部の全てが強烈な痛み、他の全ての感覚を吹き飛ばす程の激痛に塗り潰されている。だが富美代の責めは単純に痛い、だけではない。更にブラスアルファがあった。
「ガアッ!ギギャアアアアアッ!!!・・・」「おぶうぅっ。うぶっ、げぶっ、ごぼぼっえぶうぅっ、おぶっ、うぶぶっ、ごぼぉっ、おごっ、ごあああぁっ・・・」突然、間断なく悲鳴を上げ続けていた検見川が苦しげに咳き込み、全身を苦しげにビクビクと激しく痙攣させ始めた。犯人は血、検見川自身の血だった。鼻血、等という桁ではない。毛細血管が集中している鼻腔の中をグチャグチャに破壊され、検見川の鼻腔は大量の流血に満たされていた。後から後から流れ出る出血のかなりの部分は、富美代のヒールに塞がれた狭い空間から外へと溢れ出て検見川の頬を真っ赤に彩っている。だが鼻の中は血で満杯の状態だ。その血の一部が苦しげに絶叫する検見川が思わず大きく息を吸ってしまった拍子に鼻から逆流し、肺へと入り込んだのだ。検見川の意識に血の鉄臭い味と生臭い匂いが広がる。苦しげに思わず咳き込むがその拍子にまた血を飲み込んでしまった。「がっ、ふっ、あ・・・…あぐが……おごぉっ・・・」
あまりの苦しさに検見川は全身を必死でよじり、更に深く富美代のブーツに鼻の奥深くを抉られる。痛さと苦しさの二重奏、検見川は視界が真っ赤になるのを感じていた。富美代のブーツ、頬から鼻から口から溢れ出る自分の鮮血、そして余りに全身に力を入れすぎて眼球内の毛細血管も切れてしまい、目からは遂に血の涙を流していた。
検見川が咳き込む度に肺に逆流した血と、鼻の奥から口に流れ込んだ血が血泡のように、あるいは飛沫状になって飛び散る。富美代のブーツにより頬に開けられた大穴からも、その傷口自体の出血に加え口中に溢れた血の一部が垂れ流しになっている。目からは血の涙を流し、勿論鼻自体からも大量に出血している。検見川の顔面は大量の鮮血に一面真っ赤に染まっている。そして検見川を責め苛む富美代のブーツも真っ赤に彩られていた。富美代の鮮やかな赤いブーツに同じく赤い、だが明らかに濃淡が違う赤が重なっていく。富美代は満足そうにもがき苦しむ検見川の顔を見下ろした。銀色のメタルピンヒールは検見川の鼻に埋め込まれて見えない。自分の膝から下を覆うブーツの赤と血まみれになった検見川の顔の赤、そして飛び散った血で床一面も真っ赤だ。フフフ、今日の私のファッション、赤で統一してきたけどこれが仕上げね。服だけじゃなくて私の足から先輩の顔、床まで全部真っ赤で統一ね。先輩、悪党の先輩にしちゃ結構、私のこと楽しませてくれるじゃない!これが私への償い?ダメ、まだまだ足りないわ、こんなのほんの手付よ!富美代は漸く一時の興奮は収まりかけていたが、逆に怒りの方は却って激しく燃え上がっていた。まだまだ許してあげないわよ、ほらもっと私のブーツで苦しむのよ!もっともっと、ずっとずっと、一杯苦しむのよ!
富美代は何度も何度もヒールを検見川の鼻腔に思いっきり食い込ませた。グニュッともズリュッともつかぬ、何か柔らかだが丈夫な芯を感じさせる感触、その感触がヒールを伝い富美代の脊椎を駆け上がる。何なのかしら、この感触は。慎治を踏みつけた時の肉を、生身の肉体を踏みつけた時の感触と似ているけど、どこか違うわね。何かこう・・・壊している、削っている、ていう感じかな?うん・・・ヒールが肉をこそぎ落とす感触ね、きっと。この感触、何だか気持ちいいわね。癖になりそうよ。検見川の肉体、それも極めて敏感な、神経の集中している部分を破壊している実感をブーツ越しに感じながら富美代はさらに責め続けた。自分がブーツに力を込める度に、足元で検見川が何種類もの痛みと苦しさに喘ぐ。検見川が流す大量の血がブーツを突き抜け、自分の足全体を浸しているような感覚すらあった。その生温かい血の感覚は富美代にとって嫌悪感ではなく、快感に結びついていた。フフ、ウフフフフッ、アハハハハッ!!!先輩、もう絶対に逃げられないわよ。私が許してあげない限り、先輩はいつまででもこうやって苦しみ続けるのよ。痛い?苦しい?早く気絶したいでしょう?でもダメよ、これだけ痛ければ、簡単には気絶すらできない筈よ、そんな簡単に許してなんかあげないわよ!その通りだった。余りの痛さ、苦しさに検見川は何度も意識を失いかけていたが、そのたびに激痛に意識を叩き起こされ、気絶すらできないでいた。すっと富美代が左のヒールを検見川の鼻から引き抜いた。「ア、アブッ・・・ブバアアッッッ!!!」検見川の右の鼻腔から噴水のように血が噴き出る。「フフフ先輩、まさかもう許して貰える、なんて甘いこと考えてないわよね?まだまだ刑の執行は終わってないわよ。ウフフ、ウフフフフフ、そうよ、片方を抜いてあげたのはこうやって、私がしっかり立てるようにするため。こうすればもっともっと力を込めて先輩を踏み躙ってあげられるからよ!」言うなり富美代は全体重をかけ、全力を込めて右のヒールを更に深く、もっと奥へと蹴り込んだ。「ギ、イギャアアアアアッ!!!ヒッヒギイイイイイッッッ!!!」富美代は自分のヒールが今までよりも更に奥へと侵入するのを確かに感じた。ほんの1-2センチかもしれない。だがその1-2センチの威力は絶大だった。何かコリッとしたわ、今、間違いなく何か踏み潰してあげたわね。ウフフ、きっとこれ、先輩の鼻骨よ。折れたわね、じゃあそこをもっともっと痛めつけてあげる、折れたところをグチャグチャにしてあげる!ほら、ほら、ほらほらほら!「ギッ!ヒアッ!ビギイャアアアアアッ!!!」富美代は巧みにヒールを操り反動をつけながら何度も何度も思いっきり踏み込む、いや踏み込むなどという穏やかな動作ではない、蹴りを、しかも足首の捻りを十分に効かせ全体重をヒールに一点集中させた蹴りを連続して検見川の鼻に叩き込む。唯でさえ破壊力十分なその蹴りだ、弱い鼻の粘膜に対しては破滅的な威力を発揮していた。「アハッアハハハハハッ!どう先輩、最高に痛いでしょ!先輩の鼻、ズタズタにしてあげる!鼻の中の肉も軟骨も神経も、全部削ぎ落としてあげるわよ!これだけメチャメチャにすれば、もう再起不能じゃないの!?嗅覚神経も何もかも全部まとめてバラバラに引き千切ってあげるわよ!もう一生匂いを嗅ぐのは無理なんじゃない?そしたら先輩、一生片輪ね!どんないい匂いも嗅げなくなるわよ!絶対にそうなってね、先輩にはスカーフェイスにしてあげるだけじゃ足りないもの!こうやって嗅覚も一生失って、一生不幸な人生を過ごすようにしてあげるからね!」ゴボッゴボゴボッと際限なく血を噴出しつづける検見川のことを、富美代はいつまでもいつまでも責め続けた。左の鼻腔を完全に破壊し尽くした後、今度は責め足を左に変え、検見川の右の鼻腔も完全に破壊し尽くした。漸く鼻ブーツの刑の執行が終了したとき、検見川は大量の出血と余りに長く続いた苦痛に身動きひとつできず、虫けらのようにピクピクと痙攣していた。もはや痛さの余り声すら出ない。
5
富美代は断末魔のように痙攣し続ける検見川を満足げに見下ろしていたが、やがて玲子たちの方を向き、小さく頷くと横たわった検見川の足を引き摺り、工場の中央へと連れ戻した。ゴリッ、富美代は血塗れのブーツで、同じく血塗れの検見川の顔を踏み躙った。「フフフフフ、先輩、鼻ブーツの刑の味はどうだった?少しは反省したかしら?尤も先輩みたいなけだものに反省、なんて言葉はないでしょうけどね・・・まあいいわ、私は寛大だから、一応罪は償った、として許してあげる。ということでね・・・」ゴリゴリッ、富美代はブーツに更に力を込める。「過去の罪を償ったところで、今度は私たちの将来のための保険、かけさせて貰うわよ!フフ、ウフフフフ、アハハハハッ!先輩のタマタマ、約束どおり潰してあげるわよ!」「・・・あ、あああ・・・ゆ、ゆるして・・・」「なに先輩、なんか言った?よく聞こえなかったんだけど、もうちょっとはっきり言ってくれない!?」「お・・・ねがい、ゆるして・・・し、しんじゃう・・・もう、しんじまうよ・・・」「ああ死んじゃうかもね、うん確かにね。で、それがどうかしたの?別に先輩が死のうが生きようが私の知ったことじゃないわ。私は自分の明るい未来のために先輩のタマタマをここで潰して、腕も足も靭帯を引き千切って再起不能にするだけよ。別に先輩が死んだところで私は痛くも痒くもないわ。と、言うことでお話タイムはお終い、後は痛い痛いのお時間再開よ!じゃあみんな、執行準備を手伝って!」凛とした声を張り上げると富美代は縛り上げた検見川の足だけを解放する。検見川は自由になった足を必死で動かして逃げようとするが、股関節を外されていては不可能と言うものだ。「OK,フミちゃん、じゃあまずは顎、外してあげて!」まずはうつ伏せにした検見川の髪を掴み、礼子が顔を引き摺り起こす。「有難う礼子、じゃあ先輩、武士の情けで顎外してあげるから、口開けて。」「い、いやだあああ、いやだあああああ!」パニック状態に陥った検見川には最早、富美代の声は聞こえない。当然口を開けようともしない。「・・・先輩、あと5秒数える内に開けないと、キックだよ。」「や、いや、やだあああああ・・・」「・・・543・・・」「やめでぐれえええええ・・・」「・・・210。」富美代は検見川の髪を掴む礼子と頷きあった。
礼子は検見川の首の後ろに膝を当て、全体重をかけて押え込みながらそこを支点とし、髪を掴んで顔を固定する。「ア、アワワワワ、ヤベデグレエエエ!!!」カエルのような姿勢で地面に這いつくばらされた検見川の、涙を流しながら哀願の言葉を吐きつづける口めがけて富美代は狙いを定め、大きくバックスイングを取るとサッカーボールキックの要領で真っ赤なブーツの爪先を思いっ切り蹴り込んだ。ぐぎっ、べぎゃっ、ばぎっ・・・富美代のブーツの固い爪先は検見川の下唇に命中し、いとも容易く数本の歯をへし折った。「イア、イギャアアアアア!!!」口から鮮血を迸らせながら絶叫し、何とか逃れようと必死で頭を振る検見川を礼子が全力で押さえつける。ミリッ、ブヂッ・・・検見川の髪が数十本単位で引き抜ける。長くは持たないわね。間髪を入れずに富美代は再び脚を振り上げ、第二撃を繰り出す。今度はやや下から蹴り上げる形で検見川の口を強襲した富美代のブーツが再び数本の歯をへし折る。
「ガッ、ガハッ、ゴバアアアッッッ・・・い、いでえ、いでえよおおおおお・・・」
礼子が解放するなり検見川は頭を床につけてうめいた。床に見る見る鮮血が広がる。
「アハハハハッ!全くバカよね、先輩ったら!折角、痛めつけないで楽に顎を外してあげよう、て言ってあげたのにね!人の好意を無にするからこうなるのよ!」
富美代は狂ったように高笑いする、だがこれで終わった訳ではない。今のは単なるオードブル、刑の執行はこれからなのだ。「・・・さあ先輩、前座は終わり、いよいよ本番、逝くわよ。男、廃業させてあげる。覚悟はいいわね?」富美代が死刑執行宣告をすると同時に礼子は検見川を転がして仰向けにし、腹の上に馬乗りになる。そして玲子は右足、朝子は左足を掴み、検見川の両足を全開脚にする。勿論検見川は必死で足を閉じようとするが、股関節を外されていては力の入れようがない。そして富美代はゆっくりと歩を進め、検見川の無防備に曝け出された男性器の前に仁王立ちした。
「フフフ、さあ先輩、逝くわよ、死刑、執行!」凛とした声で刑の執行を宣告すると同時に富美代は思いっきり右足を後ろに振り上げ、全力でのサッカーボールキックを股間に見舞う。ドゴッ・・・「ブ、ブギャアアアアア!」潰れた手応えはないわ。第二撃。ガズッ・・・「ヒギイイイイイッ!!」アン、中々上手く逝かないわね!金玉をしっかり狙って必殺のトーキックを突き刺したつもりだったが、狙いが微妙に外れた。検見川の股間、恥骨の方にダメージを与えたが肝心の睾丸には命中しなかったようだ。よく考えてみたら、タマタマって丸いのよね。トーキックで蹴れるわけないじゃない。丸くてちっちゃいものを蹴るには・・・しっかり足の甲で蹴らなくちゃね。第三撃。今度はさっきの二発よりややキックの軌道を低くした。命中直前、地表すれすれを飛来した真紅のブーツの爪先は検見川の左睾丸の下に滑り込む。一瞬遅れてブーツに覆われた富美代の足首が睾丸に命中し、そのまま睾丸を検見川自身の恥骨との間に挟み込む。ブヂャッ!先ほどとは明らかに違う、何かが破裂したような感触がブーツ越しに富美代の脚に伝わる。「ギ、ギャアアアアアアアッッッ!!!」全身を仰け反らせながら検見川は絶叫した。痛いいたいイタイ・・・それ以外何も感じられない。全身を貫く激痛と殆ど同時に強烈な悪寒を伴った気持ち悪さが体中の神経を支配する。フフフ、やったやった!先輩、死ぬほど苦しんでるわね。いい気味。その顔見てると、先輩に傷付けられた私の心が癒されるわ。ああいいわ先輩、これだけ癒されたから、そろそろ許してあげる。今止めを刺してあげるわ。もう一個もちゃんと
潰してあげるね!これで先輩、男は廃業ね。これから先輩がどんな人生生きるか知らないけど、全力で不幸な一生でありますように!じゃあね、サヨナラ、先輩!身体の内外からの二重の苦しみに痙攣する検見川に何の憐憫も見せずに真紅のブーツを大きく振り上げ、富美代は止めの一撃を蹴り込んだ。
先ほどの一撃でコツを掴んだ富美代の第四撃は的確に検見川の残された右睾丸を捕らえ、恥骨とのサンドイッチにする。バヅンッ・・・検見川は確かに破滅の音を聞いたような気がした。一生忘れられない音だった。「ガッ!ゴアッッッッッ!!!!!」
余りの激痛に呼吸困難を起こし、全身がビクビク痙攣する。激痛の余り舌が飛びでている。そしてギヂギヂと音が出そうな位強く噛み締めた口のあちこちで、限界以上の力で口内に食い込んだ歯が出血を引き起こす。噛み締めた歯は勿論、はみ出た舌にも食いこんでいるが殆どの歯をへし折られているために舌を噛み切るには至らない。だが残った数本の歯や、折れた歯の残骸が残る歯茎が食い込み、舌もズタズタだ。口一杯に溢れ出る新たな鮮血が真っ赤な血泡となり、検見川の口からブクブク噴き出る。
余りの痛さに失神すら中々出来ない。失神と覚醒とを繰り返しのた打ち回り続けながら、検見川の意識はゆっくりと闇に沈んでいった。
「フーッ・・・フミちゃん、やるときゃやるわね・・・」流石の玲子が些か圧倒されたような声になっていた。「うん。まあ折角のチャンスだからね。私もイヤなこと早く忘れたいから。私は先輩の思い出とバイバイ、先輩は男としての機能とバイバイ、ていうことでまあチャラかな、て思ってさ。」「チャラってフミちゃん・・・これ100倍返しだと思うんだけど。ま、いいか。蹴ろう、ていったのは私だしね。」気を取り直すように2、3回首を振ると玲子は奈良村に向き直った。「と、言うわけでタマナシ君、次は君の番で確定よ。」奈良村の顔から恐怖の余り、サーッと音を立てて血が引いていく。青白い、殆ど死人のような顔になりながら、口をパクパクさせている。「あ、それとね」玲子はその美貌に悪魔の様な残酷な笑いを浮かべながら宣告した。「さっきまでは単に潰すだけのつもりだったんだけどね、私も気が変わったわ。ウフフフフ、そうよ、私も刑罰を追加するわ。たっぷりと楽しませてあげるわよ、覚悟しなさい、思いっきり痛めつけてやるからね!」「ひ、ヒイーッ!い、いや、おねがい!!!もう許してくれえええっ、お、おねがいだあああああっっっ」ボロボロと涙を流して哀願する奈良村を満足気に見下ろしながら、玲子は冷たく宣告した。「ダメよ!タマナシ君、さっき君は私にナイフで切りかかったでしょう?あれがもし私に当たってたら、どうする気だったの?女の子に、特にもし、顔に傷なんかつけられてたら私、一生台無しだったかも知れないのよ?それを思ったら、未遂犯でも罪状は同じよ!やっぱり、そんなことが二度と出来ない様に片輪にしてやらなくちゃ気が済まないわ!」無情な宣告を下しながら玲子は床に転がる奈良村の右手を伸ばすと礼子をその上に座らせた。次に朝子を背中に、富美代を腰に座らせ、奈良村が身動き一つ出来ない様にする。「さあ準備完了!何をされるか分かる?分からない?じゃあ教えてあげる。私、さっきタマナシ君の骨を何本か砕いてあげたわよね?骨ってね、腕や肋骨ならね、きれいに折れれば結構簡単に治るものなのよ。でもね、ああやって砕けばずっと治りにくくなるわ。で、もっと治りにくいのはどこだと思う?」玲子の顔に凄絶な笑みが浮かんだ。
「手の骨よ。指、手の甲、手首・・・細いけど繊細な構造であちこちに関節があるわ。そこを砕かれたらどうなると思う?ましてや手は人体で最も微妙な動きをする所だからね、神経も縦横に通っているのよ。それを破壊したら・・・フフフフフ、もう一生、手は自由に使えなくなるわよ?分かる?どうやるか」玲子はブーツの硬いヒールで奈良村の右手を踏み付けた。「このヒール、硬いでしょう?私の得意技は蹴り、そしてこのヒールを活かした下段蹴りは・・・」玲子がゴリッとブーツに力を込める。「ウフフフフ、君の手の骨なんか、簡単に砕けるわ。そう、指も手も手首も、全部グシャグシャに砕いてあげる。何箇所骨折したか、なんて数えても意味ない位粉々にしてあげるわ。骨も関節も神経も、全部踏み潰してあげる。そう、ドラエモンの手みたく、手首から先が単なる肉球になるまで徹底的に蹴り潰してあげる。フフフ、アハハハハッ!そこまで完全に破壊したら、どんな名医にかかったって絶対に治らないわよ!一生指一本まともに動かせない片輪にしてあげるわ!」
「や、やだ、やべでぐれえええええっ!お、おねがいだ、踏み潰さないでくれえええっ!」奈良村は絶叫しながら必死で右手を固く、全力で握り締めた。肩を外されているから力は入りづらいが今はそんなことを言っている時ではない、全身の力を振り絞って握り締めた。だがそんな奈良村の必死の悪あがきを玲子はあっさりと鼻でせせら笑った。「フフ、タマナシ君どうしたの、そんなに固くお手て握っちゃって。もしかして、固く拳を固めたら私が踏み潰せなくなる、とでも思っているの?馬鹿ねえ、そんなことしても、何の役にも立たないわよ。」玲子はツッとブーツを奈良村の手からどけるとカッカッとヒールで床をつついた。「分かる、この音。この床、コンクリートなのよね。上から加えられる力を下へ逃がしちゃうことはないわ。て、言うことはね、要するに上から私が下段蹴りを加えるとね、力学的にはコンクリートで君の拳を殴りつけているのと同じことになるのよ。分かる?ガードなんて無意味、そうやって握り締めれば石の拳になる、と言うのなら話は別だけどね。果たして君の手、コンクリートよりも硬いかどうか、試してあげるわ!」
玲子はニヤリと笑いながらゆっくりと右足を引き上げた。「さあ、右手にお別れは言えたかしら?覚悟はいいわね、逝くわよ、ハッ!」気合もろとも玲子は全身のウエイトを掛けながら、捻りを効かせた凄まじい蹴りを奈良村の右拳に叩き込んだ。バギッ・・・「ギャアアアッ!」瓦数枚を蹴り割る必殺の下段蹴り、しかも玲子は巧みに角度を調節し、ヒールの角が奈良村の拳に食い込むように蹴り付けていた。これでは人間の骨など一たまりもない。早くも人差し指の付け根から手の甲を走る骨をへし折られた奈良村の悲鳴が響く。「アハハハハッ!何回聞いても君の悲鳴はいいわね、その情けない声、私結構好きよ、ゾクゾクしちゃう!もっとその声、聞かせてよ!ほら!ほら!ほらほらほら!」ガッ、ドガッ、ベジャッ、バギッ・・・ギャアッ!ヒッヒギイイイッ!イ、イデエ、イデエエエエエッ!!!玲子が立て続けに蹴りを叩き込む毎に奈良村の悲鳴が轟く。僅か数発で既に奈良村の手の力は完全に失われ、拳はだらしなく開いていた。まずは手の甲から手首にかけて数箇所をへし折られ、奈良村は最早拳を握る力すら奪われていた。「ウフフフフ、どうタマナシ君、私の言った通りでしょ?拳を握ったところで無駄だって。さあ、じゃあチューリップが開いたところで、今度はその指を潰してあげる!」ガギイッ・・・ギアアアアッッッ!一段と高い悲鳴が轟いた。玲子の黒いブーツのヒールが奈良村の親指を覆い隠している。そして玲子がグリッと一躙りした後ヒールを持ち上げた。「アハハハハッ!ほらタマナシ君、見てご覧よ!君の親指、潰れちゃったみたいよ!」涙にボヤケた目で自分の親指、ズキズキ、と言うよりズシンズシンと体の奥底へと響く痛みを送りつける自分の指を見て、奈良村は思わず我が目を疑ってしまった。な、なんだこりゃ!?!?そこにあったのは見慣れた自分の親指ではなかった。ほぼ丸い、筒状の親指が明らかに扁平な楕円形に変形していた。何箇所もの骨折から来るズキズキとした鈍い、体の奥底から響いてくる痛みすら一瞬忘れさせる、自分の体が変形させられてしまった、という衝撃が奈良村に絶望的な悲しみとなった。「う、ううっ・・・あ、あんまりだ、あんまりだ・・・つ、つぶすなんて・・・ひ、ひどい・・・」全身を震わせてすすり泣く奈良村の頭上から玲子の嘲笑が降り注いだ。
「アハハッ!泣いてるの、タマナシ君?そんなに指潰されたのが悲しいの?大丈夫、心配いらないわよ、そんな悲しみ、お姉さんが吹き飛ばしてあげるからね!直ぐに残りの指四本もお手ても手首も、全部砕いてあげるから!悲しいなんて感じている暇なんかなくなるから安心してね!」言うなり玲子は再びブーツを振り上げ、奈良村の人差し指に思いっきりヒールを叩き込んだ。「ギギャアアアアアッッッ!」ああ、この感触最高よ!ヒールを踏み込む度に、ブーツの中の玲子の踵にミジッというような、硬い芯のあるものを砕く感触が伝わってくる。単に硬いっていうのとは違うのよね。硬いくせして、砕けると今度は小砂利を踏んだような感触と言うか、なんか粘りがあるって言うか・・・兎に角気持ちいいわね、この感触!しかも私が踏み潰したところ、どんどん内出血してくるじゃん!鞭の内出血とも全然違う感じの出血ね、こう、なんかブワッと膨れて腫れ上がる、ていう感じじゃない?なんかこのままグシャグシャにしてあげたら、タマナシ君の手、冗談抜きでグローブみたいに大きくなっちゃうかもね!玲子といえども他人の骨を折った経験は殆どない。だがこうやってコンクリートの床で逃げ場がない奈良村の指を固いブーツのヒールで責めると、面白い位簡単に骨がポキポキと折れていく。折れる、と言うより潰され、砕け、骨としての機能を失ってバラバラの骨片に分解されていく。ふーん、人の骨って案外もろいのね。こんなに簡単に砕けるものなんだ。玲子は不思議な気分だった。流石に人の骨を砕くなんて、考えてもみなかったな。だけど・・・気持ちいい!楽しいわよこれ!練習中、まともに蹴りが入って相手の骨にヒビが入ったことはあったけど、その時は結構罪悪感あったのに不思議ね、こうやってブーツを履いて骨を蹴り砕くのって、全然罪悪感なんて感じないわ。骨を砕く感触がブーツで濾過されて快感に変わっていくみたい・・・最高ね、この感覚。でも残念、流石にこんな経験、一生二度と出来ないかもしれないわよね。だったら・・・今、このチャンスに精一杯、目一杯楽しんどかなくちゃ嘘よね!ほら逝くわよ!もっと感じさせて頂戴、骨の砕ける感触を!聞かせて頂戴、骨を砕かれて片輪になっていく君の悲鳴を!見せて頂戴、崩壊していく君の手が内出血で変形していく様を!
涙に曇った奈良村の視界の中で、玲子の漆黒のブーツは天上界から降り注がれる神々の大槌のように、視界の上方に消えては再び振り下ろされ、奈良村に新たな苦痛を刻んではまた上方に消えて行った。神々を怒らせた愚かな虫けらのように、奈良村には唯ひたすら玲子の責めを受け泣き叫び続ける以外に道はない。最早首を上げる気力すらない奈良村の視界に映るものは一つだけ、一定の周期で降り注ぎ、自分の指を、手を破壊していく玲子の漆黒のブーツだけだった。玲子はこまめに丁寧に、満遍なく奈良村の手を砕いていった。指一本につき十回近くも蹴りを叩き込み、文字通り粉々に砕いていった。「ウフフフフ、さあもう指は全部、粉々に砕けたみたいね。じゃあ仕上をしてあげるわ!」玲子はブーツ全体を使って奈良村の指を踏みつけると、全体重をかけながらゆっくりゆっくりと丁寧に踏み躙っていく。「アッアギギギッイイ!イアアアアアッ!!イデエエエエエエエッッッ!!!」なら村が一段と高い悲鳴をあげた。「アハハハハハハッ!どうタマナシ君、最高に痛いでしょ!?そりゃそうよね、だってあっちこっちでグシャグシャに砕けた骨を踏みつけてあげてるんだものね。痛いでしょう?こうやって踏み躙ってあげると、砕けた骨の欠片が君の指の中であっちこっちに散らばって神経に刺さりまくっているはずよ!アハハ、アハハハハハハッ!気が狂いそうに痛いでしょう?もう死んじゃいたいんじゃないの?でもダメよ、そう簡単に死ねるわけないでしょ。いくら痛くてもたかが指なんだからね。死ねるわけないわよね!覚悟しなさい、もっともっと痛くしてあげるからね、たっぷりと味わうのよ!そして思い知りなさい、女の子にナイフで切りつけた罪の重さを!ほら!ほら!ほらほらほら!」玲子は指全体を、五本の指全てを一本一本満遍なく破壊し、骨を文字通りバラバラに崩壊させていった。次いで手の甲、更には手首、と順次砕き、踏み躙り、徹底的に破壊していった。延々と続いた破壊作業が終了した時、悲鳴を上げ続けていた奈良村は精魂尽き果てたようにグッタリしていた。「ウフフフフ、どうタマナシ君、踏み潰し刑、随分効いたみたいね。さあ、じゃあ君のお手てがどうなったかみせて頂戴。」処刑が一段落したところで礼子たちは一旦奈良村の上から降りたのだが、最早動く気力は全くない。肩を震わせて荒い息をする奈良村の右手を礼子は無造作に持ち上げた。「ワ~ッほらみんな見てご覧よ!これおもしろーい!」玲子の言うとおり、奈良村の手は中々の見物だった。何箇所と数えるのも馬鹿らしいほど沢山の複雑骨折、そして内出血で手はパンパンに腫れ上がって来ていた。そして何よりも、その柔軟性は誰も見たことがないものだった。「ほら、これこれ!どこでも、どの方向にでも曲がるよ!ほらタマナシ君の手、まるでタコみたいじゃん!」玲子がクイクイッと適当なポイントを掴みながら曲げると奈良村の手はどこでも、殆ど何の抵抗もなく有り得ない角度に曲がっていく。勿論、骨が折れた所だ、そんな傷口を更に抉られて痛くないわけがない。「ひっひぎああっい、いでえええっや、やべで、さわらないで・・・ひいいい!!!」「あら冷たいじゃない、そんなに嫌わなくてもいいでしょ、私、別に手荒な真似なんかしてないよ。単に握手したいだけよ。ほら、握手しよ!」玲子が無理矢理奈良村の右手を握る。指、手の甲、手首、砕かれた骨があちこちで神経を刺激し奈良村に爆発的な激痛を与える。どこが痛い、等というのは無意味だ。手全体の神経が一斉に悲鳴をあげる。「ギャアアアアアッ!ヒッヒイイイイイッッッッ!」「あら、そんなに嬉しいの?うん、分かる分かる!この霧島玲子さんに握手して貰えるなんて、君には身に余る光栄だものね、泣いて喜ぶのも当然よね!じゃあお姉さん、今日は機嫌いいから特別サービスもしてあげるわ。ほら、両手一緒に握手してあげる。但し・・・左のお手ても砕いてからね!」「ひっそ、そんな、そんなあああっやべでぐれええええっ、や、やべでえええええっっっ!!!」奈良村は甲高い声で泣き叫び続けた。だが玲子の言うとおり、まだ片手なのだ。もう一回、もう一回奈良村はこの激痛の処刑を受けなければならないのだ。漸く処刑が終わった時、奈良村は半ば意識を失いかけていた。だが玲子の恐ろしい宣告が失神、という救いの女神を一瞬にして遠ざけてしまった。「さあタマナシ君、これで踏み潰し刑は執行完了よ。良かったわね、大負けに負けて、一応罪は償った、てことにしておいてあげるわ。・・・と言う事で、そろそろ仕上、タマタマ潰しに移ってあげるわね!」
あ、あああ・・・奈良村の口から絶望の嗚咽が漏れた。だが余りに体力を消耗し、その声は虫の息程度のものだった。
6
「ウン?何言ってるの?全然聞こえないよ、もうちょっと大きな声で言ってよ?」玲子は奈良村の口元に耳を近づけた。「・・・た、たすけて・・・つぶ、さ・ない・・で・・・」
「ああ、それはダメよ。諦めなさい。どうせ潰されるのが早いか遅いかだけの違いなんだからさ、イヤな事は早く済ませた方がいいんじゃない?」玲子の拒絶に合わせるように、礼子が奈良村の髪を掴み、顔を引き摺り起こす。「さあ、ここで最後の選択よ。顎外して貰うのがいい?それとも、検見川さんみたく、歯を蹴り砕かれるのがいい?お好きなほうを選んで頂戴。あ、念のため逝っとくけど、どっちもイヤ、とか、やめて、とかいう返事は歯をへし折られる方をチョイスした、と見なすからね。」玲子は漆黒のブーツの爪先でコツコツと奈良村の口をノックしながら最後の選択を迫った。「あ、ああ・・・」奈良村は恐怖と絶望の余り、口をパクパクさせるだけで何も言えない。だが目の前で検見川が歯を蹴り砕かれるのを見せ付けられたのだ、選択の余地はない。奈良村は涙を流しながらも口をダラリと開け放った。フンッと玲子は冷笑を浮べながらブーツを更に突き出す。「あ、やっぱ顎を外される方がいいのね。まあ賢明な選択と思うわよ。じゃあ、私が仕事しやすいように、ちゃんと咥えこんで頂戴!」
クイッと玲子がブーツをしゃくる動きにつられるように、奈良村は玲子のブーツの爪先を自ら咥えこんだ。自分の両手を粉々に砕き、再起不能の片輪にしたブーツを。自分のことを際限なく責め苛んだ漆黒のブーツ、苦痛と屈辱の象徴、元凶とも言える玲子のブーツを自らの意思で咥える。靴を舐める、等というレベルではない屈辱だ。激痛に頭の中が真っ白になった中でもその屈辱は決して掻き消されずに奈良村の精神を責め苛む。だがいくら悔しくても玲子に逆らうことはできない。その気になれば玲子はいつでも自分の歯を蹴り砕けるのだ。これだけの苦痛を味わった後、しかもこの後は睾丸を砕かれる責めが待ち受けているのだ。その前に受ける苦痛は少しでも、ほんの僅かでも減らしておきたい。奈良村は屈辱を必死で堪えながら玲子のブーツを、咥えこんだ。土埃と皮革の匂いが奈良村の口の中一杯に広がる。目の前には玲子の漆黒のブーツが聳えている。信次たちが味あわされたのと同じ、屈辱の情景だ。フフフフフ、タマナシ君、泣いてるのね、いいザマよ。自分でブーツを咥えに来るなんて、もう精神もズタズタに踏み躙ってあげられたみたいね。その屈服して怯えた目、私を見上げるその目、最高よ。いつまでもずっとずっと、その目で見上げさせていたいわ!玲子は奈良村が涙を流しながら、自分のブーツを咥えたまま見上げているのをゆっくりと楽しんだ後、おもむろに刑を執行した。「いいわ、じゃあ、逝くわよ?」玲子の宣告に合わせるように、礼子が奈良村の首を支えたまま指を耳の下、頬骨と頭蓋骨の付け根に食い込ませて上に持ち上げ、力の支点とする。「せーの、それ!」玲子は奈良村の口に押し込んだブーツを一気に踏み下げる。ガックーン・・・あっけないほど簡単に奈良村の顎が外れる。「ア、アワワ・・・」奈良村は顎が外れるのは初体験だった。いたい、と言うより疲労感を伴うような、時間と共に痛み、不快感が増す、何とも形容し難い苦痛だ、これだけでも十二分に苦しい。だが今はこの程度の痛み、ほんの前座に過ぎない。本物の苦痛はこれからやって来るのだ。
「OK・・・さあ準備完了ね。さ、タマナシ君、これで君も名実共に、本物のタマナシ君になるのよ。」仰向けにひっくり返した奈良村の股間にしゃがみ込みながら、玲子は拳を固め、片膝をついて下段正拳突きの姿勢を取る。言葉は相変わらず奈良村を嘲っているものの、眼は笑っていない、むしろどこか緊張感すら漂わせている。検見川の時と同じく礼子は腹の上、そして今度は富美代が右足、朝子が左足を広げながら押さえ込む。「い、いや、ヒック、ウエッ・・・やめて・・・イアッ・・・」奈良村は最早絶叫する気力すらなく、ひたすら泣いている。「タマナシ君、ダメよ、泣いても許してあげない・・・だけど君をいたぶるつもりも、もうないのよ。余計な苦しみを味あわなくて済むように、一発で決めてあげるわね!」玲子は右拳を引き付け、ゆっくりと呼吸を整えた。「ヒュウウウッッッ・・・ハッ!」列昂の気合と共に、玲子は必殺の下段突きを繰り出した。ドグジャッ!瓦数枚を砕く玲子の下段突き、しかも睾丸はコンクリートの床にくっついている。これでは力の逃げ場所が全くない。奈良村の左の睾丸があっけなく潰れた。「ギギャアアアアアッッッ!ギア゛ッ、イ、イデエ、イデエヨオオオオオッ!!!」奈良村の全身に鉛の塊で殴りつけられたような重い衝撃が走る。イタイ、それ以外は何も感じられない。殴る蹴る、といった体の表面から来る痛みではない。内臓を傷つけられる感覚、生命の危機を本能が感じ取り、最大限の警報を鳴らしているようだ。
奈良村は全身を苦悶にのた打ち回らせるが肩、股関節を外された上に礼子たち三人掛かりで押さえつけられていては満足にのた打ち回ることすらできない。その奈良村の股間を触った玲子の美貌に満足そうな、そして見るものを震え上がらせる残酷な冷笑が浮かんだ。「ウフフフフッ、我ながら完璧にヒットしたわね。タマナシ君、左は潰してあげたから・・・今度は右よ!」「いあ゛、あべておしえおえあいいいいいいっっっ!!!い、いっあつ、いっあつ!」玲子の余りに無慈悲な宣告に、激痛にのた打ち回っていた奈良村の口から断末魔のような悲鳴が迸る。だが顎を外されているから殆ど言葉にすらならない、「うん?!一発だけ、とでも言ってるのかな?確かに私、一発、て言ったわよね。だけど、それは左を一発で潰してあげる、て言っただけよ。両方一辺に潰すだなんて、一体誰が言ったの?」玲子にとって、この刑罰は確かに必要に迫られての刑罰だ。だが、玲子の中では必要だから仕方ない、というドライな判断と折角の金玉潰し初体験をたっぷり堪能したい、という加虐の慶びの二つの感情が全く矛盾なく共存していた。思ったよりあっけなく潰れるものね・・・だけど潰した瞬間のこの絶叫、ゾクゾクするじゃない?いいわよタマナシ君、私、君にこんなに私をゾクゾクさせる才能があるなんて知らなかったわ。今は右の拳で極めたから・・・今度は左の拳にこの感触、焼き付けておかなくちゃ!さあ、もう一度楽しませて頂戴!
玲子がゆっくりと左拳を巻き上げる。「さあ、逝くわよ・・・覚悟はいいわね!?ハヤッ!」ビュオッ・・・グジャッ・・・「ギャビイイイイイッッッ!!!ギブアアアアアアッッッッ」未だ先ほどの激痛が抜けない、というより痛みが余計激しくなっている奈良村の全神経を、新たな苦痛がパニック状態に陥れる。冷たい氷のような感覚、身体の奥底にズシンと氷の巨弾を打ち込まれたような感覚だった。「グヴエッ・・・オゲブァアアアッッッ!!!」奈良村の全身を押え様のない吐き気が貫き、胃液がこみ上げてくる。「ヴベバッ、ガハッゲバアッッッッ!!!」だが胃液を吐き出すほどの力さえ出ない。余りの痛さに呼吸困難に陥った奈良村の喉を胃液が上下し、それが新たな咳き込みを誘って苦痛を更に増していく。股間の痛みと呼吸困難と内臓の反乱と。奈良村は全身の神経の暴走に延々と苛まされつづけながら、長い時間をかけてのたうち回ったあげくに白目を剥いて気絶していった。
残り二人。未だ意識があるのは須崎と坊野の二人だけだった。「さあ、残るは二人、後半戦ね。で、どっちが先に逝く?」完全に気絶した奈良村の背中から降りた礼子が、冷たい微笑を浮べながら尋ねた。「い、いやだあああ!ぼ、坊野、坊野さああああん!お、お願いだあああ、助けて、先に逝って、いやだよおおお!!!」「ば、ばかやろおおお、お、おれだって、おれだっていやだ、お、おまえだ、おまえが先いけ、め、めいれい、命令だ、おまえが先逝け、言うこと聞かねえとぶっ殺すぞ!」もう仲間意識などどこにもない。あるのは唯一つ、生存本能。助かりたい、自分が、自分だけは助かりたい。坊野も須崎も、頭の中にあるのはそれだけだ。二人の醜い罵りあいに些か辟易としたように朝子が肩をすぼめた。「あーあ、最凶のギャング、といってもタマタマ潰すよ、ていうだけでこんなになっちゃうんだ・・・なんか、もううんざりだな。もうこんな連中に付き合うの、そろそろ終わりにしたいな。ねえ礼子、チャッチャッとすませちゃおうよ。まあトリは一応この人たちのプレジ、ということで坊野さんと礼子にしてさ、次、私が片付けちゃっていい?」礼子にも否やはない。早速四人は須崎を取り囲んだ。「い、いや、いやだあああああ、やめてくれえええええっ!」「・・・全く五月蝿いわね、何よ、そんなに涙流して情けない声で・・・貴方たち一応、最凶ギャングを名乗ってるんでしょ?恥ずかしくないの?ペッ!」須崎の髪を掴んで引き上げた朝子が軽蔑と嫌悪感を露骨にその愛くるしい美貌に浮かべながら、思いっきり唾を吐き掛けた。「ホラ今何されたかわかんないの?唾吐き掛けられたんだよ?女の子に、自分の顎を蹴り砕いて、手を焼いて拷問した女の子に。自分よりずっと小っちゃくてしかも年下の女の子に。須崎さん今、唾吐き掛けられたんだよ?ねえ、悔しくないの?顔に唾吐き掛けられるなんて、人間最大の屈辱じゃないの?ほら、そんなことされたのに睨み返す位できないの?よく唾吐き掛けられて、悔しいとも思わずにいられるわねえ。最低!ねえ、そんな意気地なしだったら、もう一回唾吐き掛けちゃうよ?ほら!こっち見て、私の口を見てよ、自分が唾吐き掛けられるところをたっぷりと見なさいよ、ほら逝くよ、ペッ!」朝子は須崎のことを嬲りながら再度、唾を吐き掛けた。朝子は他人に唾を吐き掛けることが大好きだった。自分の優位性、他人を屈辱させられる強さの象徴と思っていた。うーん、気持ちいい!こうやって唾吐き掛けるのって、何度やっても最高に気持ちいいよね。唾掛けられた相手が悔しそうに私のこと見て、だけど怖くて逆らうことすらできない、ていうの最高よね。ゾクゾクしちゃう!なんかさ、唾吐く度に唇がこう、フワーッとあったかくなるような感じがしてほんと、気持ちいいのよね。私、フミちゃんほど唾吐くのは上手じゃないけど、それでもこうやって唾吐き掛けるのって大好き。ほんとこれ、最高に楽しいのよね・・・だが須崎はもう反抗する気力も何もない。悔しそうに朝子を睨むことさえできない。唯々怯えるだけだった。「・・あ、あわわわわ・・・ゆるして、やめて・・・つぶさないで・・・・・」うわ言のように呟き続ける須崎に、呆れた、というように朝子が両手を広げて肩をすぼめた。
「ふう、全く情けないわね・・・じゃあ須崎さん、いいこと教えてあげる。私ね、男の人の好みは結構男っぽい人が好みなんだ。逆に意気地なし君は大っ嫌いなの。今の今までね、まあこれ以上苛めたら可哀想だから、あっさり潰して終わりにしてあげよう、て思ってたんだけどね」ニヤリと朝子が残酷な笑みを浮かべた。「須崎さん、大っきいだけで実はとんでもない意気地なし君だったみたいね。だって唾吐き掛けられたのに悔しくもないんだものね。そんな意気地なし君の分際で私を襲おうとしたなんて、図に乗るのにも程っていうものがあるわ!やっぱり・・・懲らしめてあげなくちゃいけないわね、たーーっ、ぷりと!」やれやれ、玲子は思わず苦笑してしまった。朝子ったらはなからすっかりやる気だった癖して。睨み返したら反抗的だ、とか反省が足りないとか言って結局絶対に苛めるつもりの癖してね。変に希望を持たせたり前振りしてる間に自分で勝手に盛り上がっていくから朝子って怖いのよね。そんな玲子の苦笑に気付かないかのように、朝子は嬉々として刑の宣告をした。
「さあ、どうやって懲らしめられるかは、もう分かっているわよね。そう。も・ち・ろ・ん・・・火焙りの刑よ!」ひ、ひあぶりーーー!須崎にとっては最も聞きたくない言葉だった。「そ、そんな!ひ、火焙りだけは、それだけは許してくれえええっ!」「だーめ!須崎さん、さっきあれだけいい声で叫んでたんだから。よっぽど私の火責め、効いたんでしょ?だったら刑罰は勿論、火焙りよ!覚悟しなさい、拷問の火責めじゃないんだからね、火焙り、これは刑罰なのよ。さっきよりも・・・ずーっとずーっと、熱ーくしてあげるからね!」必死で泣き喚く須崎に構わず、朝子は須崎をうつ伏せにするとパンツとトランクスを一気に引き摺り下ろし、尻を剥き出しにした。玲子と富美代が両腕を、礼子が両足に乗って押さえつける。「アハハハハッ、須崎さん随分とお尻が白いのね、ちょっと不健康なんじゃない?」ピシャピシャと須崎の尻を叩きながら朝子が笑った。「でも安心してね、直ぐに色をつけてあげるわ・・・そう、真っ赤にしてあげるからね!」恐怖で震える須崎の眼前に朝子は四個のライターを突きつけた。須崎のライターと同じ大型のZIPPO、そう、須崎たちSNOW CRACKの幹部が一緒に特注したものだった。気絶した須崎たちを縛り上げている間に、朝子は抜け目なくそのライターを四人全員から集めていたのだ。「ウフフフフ、ねえどうするか分かる?まさか、さっきまでと同じ、単純に炙るだけ、なんて思ってないわよねえ?」カチッと音を立てて朝子はZIPPOのオイル注入口を空け、中のオイルを須崎の尻に垂らした。「あっあわわわわわっ・・・・ま、まさか・・・・」「ウフフ、そうよ、分かったみたいね、ビンゴよ。ライターのちっぽけな火で炙る、なんて手温いわ。そんなんじゃ刑罰にはならないでしょ。だから今度は・・・直火で焼いてあげる!」恐ろしい宣告をしながら朝子は四つのライターから次々にオイルを須崎の尻に垂らしていく。そしてそのオイルを尻一面に満遍なく伸ばした。
「さあ準備完了。覚悟はいいわね、オイルでの直火焼き、これきっと熱いわよー!足自由にできないのが残念ね。文字通り尻に火が着く、てやつかしら。ウフフフフ、自由にしてたらきっと、100メートル3秒で走れるんじゃない?残念だわ、世界新記録を見損ねちゃったわね。」
「や、やべ、やべやべやめてぐれえええええっ!」須崎が必死で絶叫するのを楽しそうに眺めながら、朝子は問い返す。「ねえ須崎さん、ところでひとつ質問なんだけど。そうやって絶叫するのは須崎さんの勝手なんだけどさ、叫んでいたら許してもらえる、て本気で思ってるの?」グウッ・・・須崎が思わず返答に詰まるのを見て朝子は大きく頷いた。「あ、そっか!自分でも無駄だ、て分かってるんだ!だったらいいわね。私、もしかして須崎さんが本気で許してもらえる、て本心から信じているんだったら、悪いからやめようかな、て思ってたのよ。だけど須崎さん自身が信じていないんだったら遠慮はいらないわよね!じゃ、遠慮なく火焙りの刑、執行よ!」シュボッと朝子がライターに点火した。オイルを抜いても暫くの間は芯に染み込んだオイルで十分に火はつく。わざと須崎の鼻先を掠めるようにしながら、朝子はゆっくりとライターの火を須崎の尻に近づけていく。
「あっああっや、やめて・・・おねがい・・・」恐怖の余り微かな泣き声しか出なくなった須崎を嘲笑うかのように、朝子はゆっくりと炎で尻を掠める。「ヒイッ!」ライターの熱を感じると同時に甲高い悲鳴をあげ、須崎の尻が跳ね上がる。「アハハハハッ!やーねえ、大袈裟なんだから!未だ火は付いてないわよ。今のはほんの予告編。本番はこれからよ、さあ、本当に・・・火をつけてあげるわね。逝くわよ・・・ファイヤーーーー!」「あ、ああっや、やべ・・・ギッアヂイイイイッッッ!」朝子が今度はしっかりと須崎の尻にライターの火を押し付ける。と、一瞬の間を置いて須崎の尻に擦り込まれたオイルがポッと赤い炎をあげた。炎はあっと言う間に広がり須崎の尻を覆い尽くす。「ギアッ!熱いっ、熱いぃっ!グウギャアアアアアアァァァギイイイイイィッ!!」四肢の関節を外された上で縛られ、身動きのとれない須崎の体がその場で30センチ近くも飛び上がった。「アハハハハッ!須崎さん凄い腹筋力じゃない!その調子よ、もっと踊って踊って!」笑い転げる朝子にかまう余裕などどこにもない。炎で我が身を焼かれる苦痛、意思の力で制御できるような苦痛ではない。殆ど原始の本能、野獣の本能というべきか、なんとか、なんとか逃れようと須崎は凄まじい悲鳴をあげながら飛び跳ねつづけた。なんとか、なんとか引っ繰り返って尻を床につけ、火を消そうと必死でもがき続けた。だが周りを囲んでいる朝子たち四人はそんなこと、百も承知だ。須崎がヒコヒコと腰を突き出すように必死で飛び跳ね、なんとか引っ繰り返ろうとしてもしっかり全身を押さえつけ、、あえなく腹から着地させてしまう。体を捻ろうとしても、手足をしっかりと固定されていては無理というものだ。あらゆる動きを封じられ、須崎は尻を焼かれつづけた。
「ひギアあああっ、熱いっ、くああアアあぁっ、アッ、アギイイィィッ!!」須崎は狂ったように叫び続けた。手を炙られた時の苦痛の比ではない。体の奥底にまで熱が伝わってくるのが分かる。まさに命そのものを燃やされているような苦痛だ。これほどまでの苦痛は未だかって味わったことがない。須崎がのた打ち回るのを見下ろしながら朝子は大笑いしていた。「アハ、アハハ、アハハハハッ!いい動きよ!ほらもっとお尻を動かして!そんなんじゃいつまで経っても火は消えないよ!」笑い転げながら朝子はふとオイルが燃える匂いに混じって異臭を感じた。なんだろ、この匂い。余り記憶にない、ツンと刺激的な匂いだった。どこから漂ってるのかな?匂いの源を探してニ、三回鼻をクンクンと鳴らした朝子がポンッと手をたたいた。「あ、そうか!この匂い、須崎さんのお尻が焼ける匂いなんだ!」そう分かった瞬間、朝子はその匂いを何とも言えずいい香り、と感じた。人間が焼ける匂いは耐え難い悪臭、と聞いていたけど、全然そんなことないじゃん!いい匂い・・・うっとりしちゃうわ、なんか焼肉食べたくなってくるような匂いじゃない!それを職業としている軍人でも、初めて敵の焼け焦げた死体の匂いを嗅いだ時は生理的嫌悪感に耐えられない、と言う。だが須崎を責め苛むことに、特に長時間火責めを続け、火で責め苛むことに耽溺してきた朝子にとって、その匂いは自らの拷問、処刑の成功を祝福する香り、自らの勝利と須崎の苦悶を象徴する至上の芳香となっていた。「ああ、いい匂い!うっとりしちゃう・・・ねえ須崎さんも感じない?自分の体が焼ける匂い。最高の香りだと思うんだけど、どう?」朝子は大きく息を吸い、須崎の尻が焼けていく匂いを満喫した。だが問い掛けられた須崎に答える余裕などあるわけがない。我が身を焼かれている最中なのだ、ひたすら絶叫をあげ、悶え苦しむ以外のことが出来ようはずがない。
須崎にとっては無限とも思える時間が流れた。実際には高々10ccかそこらのオイルしかない。燃える、と言っても何分も燃えつづけるわけではない、一分かそこらのものだ。だが須崎の精神も肉体も全てを焼き尽くすには十二分な長さだった。漸くオイルが燃える炎が須崎の尻の上で小さくなり、一条の煙を残して燃え尽きても須崎は全身をピクピクと痙攣させたまま精根尽き果てて横たわり、啜り泣いていた。だが朝子が与えた休息時間はほんの僅かしかなかった。「うん、結構いい色に焼けてきたじゃない!もう触っても熱くないかな?」満面に笑みを浮かべながら、朝子は焼け爛れた須崎の尻を平手でピシャピシャと叩いた。「ぎ、ぎあっや、やべ、さわらないで!!!」火は消えたとは言え重度の火傷を負った尻を叩かれては堪らない。痛い、というより不快感、悪寒のような苦痛が全身を駆け巡る。「アハハハハッ!そんなに痛いんだ!そう、可哀想にねえ。この火傷、果たして治るかしら?一生痕が残るかもね!」笑いながら朝子は須崎の眼前にしゃがみこんだ。「でもね、これはあくまで刑罰、須崎さんを懲らしめる火焙りの刑だ、て言ったでしょ?唯のリンチ程度ならもうこれでお終いにしてあげてもいいんだけどね、刑罰、て言ったらこれじゃまだまだ手温いわ。いい?これは刑罰、火焙りの刑よ。今のはほんのオードブル、本物の火焙り刑の執行は・・・これからよ!」
楽しげに笑いながら朝子は奥の機械が置かれている作業場にあるテーブルへと歩いていき、上に置いてあった缶を持ってきた。その缶を須崎の目の前で揺り動かすとチャポチャポと音がする。何だろう、と涙で曇った目で見た須崎が声にならない悲鳴をあげる。その缶にはこう書いてあった。「潤滑用オイル」「・・・ひっひいいいいっ!そ、そんな!!!」「あら何そんなに驚くのよ、ここは廃業したとは言っても工場なんでしょ、オイル位残ってたって不思議はないでしょ?そんなことより、この量・・・ウフフフフ、100CC以上は入ってるわね。さっきお尻を焼いてあげたオイルの十倍はあるんじゃない?ねえ、もうこの先の展開、流石に分かるわよね?ウフ、ウフフ、ウフフフフフ、このオイル、ぜーんぶ使って焼いてあげるからね!あっついわよー、どうするの、さっきみたく直ぐには火、消えてくれないわよ。ウフフフフ、須崎さんのお尻、真っ赤になるとか皮が剥ける、じゃすまないかもね。お尻、黒焦げになっちゃうんじゃない?どんな悲鳴とダンスを見せてくれるかな?たのしみー!たっぷりと堪能させてね!」朝子は蓋を開け、須崎の尻にゆっくりと黒ずんだオイルを垂らしていく。「ヒッ、ヒイッ!」「あら冷たかった?ごめんねー、直ぐにあったかくしてあげるからさ、ちょっと待っててね!」先ほどよりも遥かにたっぷりとオイルを垂らしたところで朝子はふと手を休めた。「あっ、そう言えば一つ忘れてたわ。玲子もフミちゃんも、一生再起不能、絶対に消えない痕が残るような刑を執行したわよね。うーん、こうやってお尻を焼くだけじゃちょっと物足りないわね。・・・お顔でも焼く?」「や、やだああああっや、やべでぐれえええええっそ、それだけは、それだけはやめてくれえええええっっっ!!!」朝子が目の前にオイル缶を突きつけると須崎は死に物狂いで泣き喚き、激しく首を振り回して何とかオイルから逃れようとする。クスッ、馬鹿ね須崎さん、流石に顔面ケロイドにしたんじゃ後始末が厄介すぎるわよ。でもこんなに恐がっちゃって、何だか可愛いわね。「アハハハハッ、よっぽど顔面焼きは怖いみたいね。いいわ、じゃあ勘弁してあげようか?」「あ、ああっお、おねがい、なんでも、なんでもするから顔だけは許して・・・」「ふーん、じゃ、顔以外だったらどこを焼かれてもいいね?」朝子はグイッと須崎の尻の割れ目を広げると、その割れ目の中、特に肛門周辺にたっぷりとオイルをかけた。「さっきはオイル少なかったから、中までしっかりと焼けなかったでしょ?でも本当にバッチクテ臭いのはここだもんね。ここもこんがり焼いてあげるわね!」ヒイイイイッ再び須崎の悲鳴が上がる。「そ、そんな酷い・・・」「あ、何?やめて欲しいの?いいわよ、やめても。じゃ顔面ケロイドがいい?どっちか好きな方選んでいいよ。でもどっちか一つよ。あれも嫌これも嫌、どっちも嫌だなんて言うのは、そりゃ無理よ?どっちがいい?お尻、お顔、はーい、ファイナルアンサーのお時間でーす!ラストカウント終了までにチョイスしてくださーい!あ、念のため、アンサーがなかった場合には、両方まとめて焼いちゃいますからねー!」りょ、両方!そ、そんな・・・と言おうとして朝子を仰ぎ見た須崎は絶望に言葉も出ない。こ、こいつなら・・・こいつなら本当にやる・・・お、俺を絶対に焼く・・・「5,4,」答えなければりょ、両方とも「3,2,」・・・ど、どうする・・・「1,0!はーい、ではファイナルアンサーをどうぞ!」流石に顔か尻かで、顔を焼いてくれ、と言えるわけがない。「・・・け、けつ・・・」「うん、なんですかあ?はっきり答えてくださーい!」「・・・あ、ああ・・・け、けつ・・・尻にしてくれ・・・」「はあい、お尻がファイナルアンサーですね!ではお望み通り、しっかり焼いてあげましょう!焼き加減は・・・ウェルダンでよろしいですね!」
朝子がゆっくりとライターの炎を近づけ、再び須崎の尻に点火する。ボッ・・・純度が低い潤滑用オイルはやや黒い煙をあげながら燃え始め、あっと言う間に須崎の尻全体を炎が舐めつくす。「「ギャアアアアアアアァッ!!熱いッ、熱いいぃっ!ウギャアアアアアアアアァッ!!」「いやあああああぁっ、助けてえぇっ、誰、誰かっ、火を消してぇっ。いやああああぁっ」先ほどとは比べ物にならない位の絶叫が須崎の口から迸りる。相変わらず引っ繰り返ろうとしては朝子たちに押さえつけられるので、せめて唯一自由にできる動きを、少しでもオイルを振り落とそうと尻をヒコヒコと上下左右に振り回し、必死で珍妙なダンスを踊りつづける。だが揮発性が高く、サラッとした燃料用オイルと違い潤滑用オイルはある程度の粘性を持つ。その粘性はオイルを下に垂れ落とさず、須崎の尻にしっかりとこびり付かせている。そして純度の低さも須崎を責め苛むのに寄与していた。潤滑用オイルは燃料用オイルよりは純度が低い分、燃える速度もかなりゆっくりである。勿論燃焼温度も若干低いのだが、そんなことは須崎にとってなんの慰めにもならない。少なくとも人体を焼くには十二分な温度だ、皮膚に密着して中々床に垂れず、しかも延々と燃えつづける。潤滑用オイルは本来の意図とはまったく関係ない用途、火焙り刑にその威力を、須崎を責め苛むには遥かに適した特性を発揮してゆっくりと燃え続けた。「ああっ、熱いっ、ひいっ、あっ、あっ、ああああ---っ!熱いっ、やめてっ、お願いぃっ!」やっと少し炎が下火になり、かつ表皮の神経が焼け死んだせいであろうか、須崎の悲鳴が若干とはいえ何か多少は意味のある、言葉らしきものになってきた。その様子をゆっくりと鑑賞していた朝子の美貌に更に悪戯っぽい笑みが浮かんだ。
「ウフフフフフ、須崎さん少しは余裕出てきたみたいじゃん?火も大分弱くなっちゃったしね、もう終わりだ、やっと終わった、て思ってるんでしょ?・・・ブーッ!ざーんねんでーしたっと!誰がもう終わり、だなんて言ったの?ほらよく見てご覧、まだオイル残ってるよね?聞こえる、ほらまだこーんなにチャポチャポって言ってるじゃん?全部須崎さんにあげる、て言ったでしょ?私、約束守る人なんだ。だから約束通り、須崎さんにこのオイル、全部あげるね!と、いうことでオイル追加いっきまーす!」「ヒッ!イッ!!ヒイイイイイッ!!!きゃああああああああぁっ!やべてっ、も、もうっ、じんじゃううぅっ!ぎゃああああああああぁっ!!」処刑が漸く終わる、と思って神経が緩んだところに処刑再開を告げられ、苦痛が全て振り出しに戻りまた一から焼かれ直す。肉体面だけではない、この朝子の巧みな緩急自在の処刑は須崎の精神までも焼き尽くし、幼児退行に追い込んでいく。須崎の精神は錯乱一歩手前だった。いや、いっそ錯乱してしまえたら、気が狂ってしまえたら、どんなに楽なことだろうか。だが発狂することすらできなかった。
泣き喚く須崎を満足そうに見下ろしながら朝子は追加のオイルを降り注ぐ。しかも今度は既にかなり焼けた尻だけではなく、太腿から膝裏の方にまでオイルを降り注いだ。弱まりかけた炎が新たな燃料補給により勢いを取り戻し、そして炎が脚に、今まで焼かれていなくて未だ神経が生きている脚へと伸びていく。「ギャッ、アッ、あ、あ、熱いっ、熱、っ、ぎゃあああっ!ひいぃっ、ひいっ、ひいいいいいっ!!嫌ああああぁっ!!!えーん、マ、ママ、ママァッ!!!熱い、熱いようっ!た、たすけてえええっ!!!やべでえええっ!!!」だが幾ら泣いても喚いても助けなど来るわけがない。須崎にできることはひたすら苦しむこと、朝子が手にするオイルが全て燃え尽きるまでもがき苦しむこと以外には何もない。漸く全てのオイルが燃え尽きた時、須崎の尻から膝裏にかけては悲惨な状況になっていた。皮膚はべろりと剥け、下の筋肉組織も焼け爛れていた。特に長時間焼かれた尻の一部などは黒焦げに炭化している。一目で分かる。面積に直せば人体全体の1/10程度だから生命に別状はないが、一生ケロイドが残るのは間違いない。須崎は巨体に似合わない女の子のような声でウエッウエッと啜り泣き続けていた。だが未だ終わってはいない。朝子はもう一つの処刑を忘れてはいない。そう、須崎の睾丸を潰すことを。
7
いかにも楽しそうに須崎を見下ろしていた朝子がやがて立ち上がり、ゆっくりと須崎を蹴り転がす。「ギアッ!ヒヅウッ!!」焼け爛れた尻が床につく刺激に須崎が悲鳴をあげる。その悲鳴に朝子が微かに眉をしかめる。「ああもう!ったくうるさいんだから!それくらいで一々悲鳴あげないの!しっかりしなさい!ペッ!」朝子は再度、須崎に唾を吐き掛けた。そして唾を吐き掛けた朝子の唇が残酷な微笑に歪む。「須崎さん、男の子でしょう?未だ刑は終わっていないのよ・・・そう、これから須崎さんのタマタマ、潰してあげるんだから!あ、そっか、潰したら須崎さん、男の子じゃなくなっちゃうんだね!そうか、じゃあ男らしくないのも仕方ないわね、アハハハハッ!」ケラケラと朝子は楽しそうに笑った。「あっあぐううううう、そ、そんな・・・もうやべで・・・し、死んじゃう・・・」「アン、ほらそんな情けないこと言わないで!大丈夫よ、検見川さんも奈良村さんも潰されたけど、一応生きてるみたいよ。だから須崎さんも多分きっと・・・上手くいけば命は助かるわよ、うん!」「そ、そんな・・・ひ、他人事だと思って気軽に言わないでよお・・・」「他人事?気軽?何バカ言ってるのよ、あったりまえじゃん!他人事に決まってるでしょ?分かってるの?須崎さんは犯罪者、私たちをレイプしようとした罪人よ。私たちはその罪に対する刑を執行しているだけじゃない!当然のことでしょ?それをなんで私が須崎さんみたいな最低の犯罪者のことを親身になって心配してあげなくちゃいけないの?なんで被害者の私が、加害者の須崎さんに同情してあげなくちゃいけないのよ、バカ言わないでよ!」朝子の顔に怒気が浮かんでいた。
「やっぱり須崎さんって全然反省してないのね!あれだけ焼いてあげたのに未だ反省してないなんて、本当に人間の屑、筋金入りの屑ね。須崎さん、骨の髄まで腐ってるわよ・・・いいわ、たっぷりと懲らしめてやる。須崎さんのタマタマ、両方ともペシャンコに潰してあげるから覚悟しなさいね!」罵りながらペッ、ペッと二度、三度と朝子は須崎に唾を吐き掛ける。そして腰に手を当て須崎を見下ろしながらブーツの爪先で須崎の顎を小突いた。「ほら、武士の情けよ、顎は外してあげるから、口開けて!」だが朝子を怒らせてしまった恐怖にパニック状態に陥った須崎は朝子のイラついた声すら聞こえず、ますます大声で叫びたてた。「ひ、ひいいいいった、たすけでぐでえええええっ!つぶさないでくれえええええっ!」「ああもう!うるさい!だったら・・・こうよ!」日頃はどちらかというと脳天気な、やや天然ボケっぽいところさえあり、決してキツイ印象を与えない朝子の可愛い顔立ちが、夜叉のような憤怒に彩られた。
スッと純白のウエスタンブーツを上げた朝子は委細構わず、大口を開けて泣き喚く須崎の口に強引にブーツの爪先をねじ込んだ。「ウ、ウグッ・・・ぐえっ!」悲鳴を封じられ、苦しそうにのたうつ須崎を憎々しげに見下ろしながら、朝子は一気にブーツを踏みこむ。ガグッ・・・呆気なく須崎のあごが外れる。「アガッ、アガガガガッッ・・・」恐怖に顎の苦痛が加わり須崎的には一層激しく絶叫しているつもりだが、顎を外されたせいで悲鳴の音量は急低下している。「ああ清々した。もう須崎さんの悲鳴はうんざり、聞き飽きたわ。さあ止めよ、須崎さんの大事なとこ、潰してあげる。フフフッ、こんな大きな身体でオカマちゃんになるなんて、なんか結構、キモイわね。」
言うなり朝子はクルリと須崎に背を向け、須崎の左足を跨ぐように立ち、位置を極めると振り向いて冷たく宣告した。「さあ準備できた、と。須崎さんは私のブーツ、特にヒールが大好きみたいだから、やっぱりここもヒールで潰してあげるわね。フフフ、思い出した?私のブーツのヒールの堅さ。お鼻と顎でたっぷりと味わったんでしょ?今度はここにも味合わせてあげる!」
「ギビイイイッ、ヤベ・・・ア゛ビイ゛イイイイイッ!!」刑の執行を宣言した朝子は須崎の哀願を完全に無視して前に振り向き、ブーツを振り上げると一気に股間めがけ、踏み込んだ。グヂャッ・・・堅いウエスタンブーツのヒールで踏まれては一たまりもない。須崎の右睾丸が呆気なく潰れる。検見川が、奈良村が味わったのと同じ激痛が須崎を襲う。「ギベエエエエエッ!イ゛ダイ゛イイイ、イデエエエエエエ!!」
須崎にとって不運だったのは、朝子は一気に二つとも潰すつもりで踏み込んだのに、実際には右しか潰れなかったことだ。堅いブーツ越しでも一つしか潰せなかったのは朝子にも分かる。「ったく、しぶといんだから!全くホント、バカよねえ。人が折角、ちゃんと両方一辺に潰してあげよう、ていうのに変に動くんだから!片方しか潰せなかったじゃない、余計な手間、かけさせないでよね!ほら、今度こそ止め、逝くわよ!」激痛に全身をビクビク痙攣させる須崎に何の憐憫の情も見せずに朝子は再びブーツを振り上げ、再度踏みつける。ベヂッ・・・狙い違わず、須崎の左睾丸も完全に潰れた。念入りに止めを刺すように、そのままブーツで踏み躙る朝子の足の動きが須崎の激痛を更に高めていく。「イ゛、イビイイイイイイ、ブブァッ、オゴグゲエエエエエッ!!!」激痛、吐き気、貧血、ありとあらゆる苦痛が須崎の全身を走る。
「キャッ、もう汚いんだから!」こみ上げてくる胃液を、顎を外されているから吐き出すことすらできずに垂れ流しのように噴出す須崎に朝子たちが一斉に飛びのく。その胃液が逆流し、半ば溺れるように咳き込みながら須崎は意識を失っていった。
吐瀉物と鮮血とに塗れてボロ雑巾のようになった検見川以下、SNOW CRACKの幹部三人が意識を失い、床に断末魔の様相を呈しながら横たわっている。廃工場を奇妙な沈黙が支配していた。佇む美少女四人と縛られて転がる男一人。この場で唯一意識のある男、坊野にとって現状はおよそ考えうる最悪の状況だった。もう自分しかいない。自分しか・・・そして自分を担当するであろう美少女、未だ役割を果たしていない美少女は唯一人、自分の指をバラバラにした礼子だった。物心ついて以来勝手気侭に振舞ってきた坊野にとって、礼子は生まれて初めて本能的な恐怖を覚えた相手だった。肉体的、と言うより精神的に屈服させられた唯一の相手だ。その礼子がスッと自分の方に一歩を踏み出した時、坊野は柄にもなく泣きながら哀願してしまった。
「ヒッウッウェッッッッ・・・お、ねがい、許して、たすけて・・・」その時礼子が浮べた表情は嘲笑、侮蔑といった当たり前のものではなかった。聖母のような慈愛に満ちた弱者に対する憐憫の表情と、強い決意に満ち満ちた戦士の表情が同居していた。「・・・私が恐いの、坊野さん?」フウッと礼子は軽いため息をついた。「まあ無理もないかもね。あれだけ坊野さんの指を痛めつけて、挙句にクラゲにした私だものね。もういい加減に許して欲しい、て思うのも無理ないわね。私ももういい加減、今日一日の暴力の応酬にうんざりしてきてはいるのよ。」一瞬坊野は淡い期待を、礼子が許してくれるのでは、という期待を抱いた。だがその幻想はものの五秒も持たなかった。「でもね、坊野さんのお仲間はみんな逝っちゃったみたいだし、おまけに坊野さんはそちらのプレジでしょ?だったら成り行き上、私もこっちの代表として恥ずかしくないパフォーマンスをしなくちゃいけない、と思うの。」「ヒッヒイッッッそ、そんな、や、やめて・・・」「ねえ坊野さん、障害者プロレス、て知ってる?」
障害者プロレス?坊野も名前だけは聞いたことがあるが、どういうものか見たことはない。「読んで字の如し、文字通り身体障害者のプロレスよ。一見色物、て思うでしょ?ところがどうして、グラウンドや関節技中心の、結構ガチガチのシュート系に近い、セメント勝負のプロレスよ。でね、そのキャッチフレーズがいいの。曰く、
「俺たちは命懸けでやっているんだ、だからお前たちも命懸けで見ろ!」ってね。どう、痺れるフレーズだと思わない?」ゴクッと坊野は息を呑んだ。嫌な、喩えようもなく嫌な予感がする。「そう。坊野さん、私、心を鬼にするわ。今から暫く血も涙もない、残忍冷酷な鬼になって坊野さんのことを責めてあげる。私の全てを、頭も力も技も、全てを使って坊野さんのことを全力で、一切の手加減なしで苛めてあげる。私が本当に全力で苛めたら、坊野さん掛け値なし、命懸けで苦しむことになるわね。だから私もその分、命懸けで苛めてあげる。これから私が坊野さんにする責め、坊野さんにとっては一生忘れられなくなるはずよ。だからせめて、私にとっても一生忘れられなくなるように、他人に対してあんな酷いことをしたのはあの時だけ、て一生記憶に残るように全力で、命懸けで苛めてあげるわね。」
静かな、奇妙なほど静かな口調で礼子は恐ろしい宣告を口にした。そ、そんな・・・やめてくれ!!!余りのことに反射的に絶叫しようとした坊野は自分の身体の異変にぞっとした。声が出ないのだ。余りの恐怖に、自分を散々責め苛んだ美少女の静かな死刑宣告に坊野の肉体自体が恐怖し、機能を停止しつつあった。カエルのように口をパクパクさせている坊野を床に横たえると、礼子はゆっくりとブーツの爪先で坊野の口をなぞった。「さあ、もう分かるわね?須崎さんと奈良村さんは顎を外してもらえたけど・・・坊野さんはどうなるのかしら?」言いながら礼子はブーツをゆっくり動かし、爪先を上に滑らせ、ヒールを坊野の口に当てて軽くノックする。「・・・分かるわね、次の展開は?」礼子はそのままヒールをゆっくりと持ち上げる。焦らすように、ゆっくり、ゆっくりと。そしてついにヒールが止まる。横たえられた坊野の視界に礼子のブーツのヒールだけが妙に大きく映る。ひいっ、せ、せめて顎を外してくれ!坊野の目に声にならない哀願が浮かぶのを見て取った礼子が静かに答える。「そう、ご想像のとおりよ。坊野さんには選択の自由はあげないわ。余りの苦痛に舌を噛み切って自殺する自由も、顎を外して貰って一段階、楽をする自由も。歯をへし折られる苦痛と潰される苦痛、両方フルに味合わせてあげる。それがプレジの務めでしょ?」
坊野の返答を待たずに、礼子は一気に全体重をヒールに掛けながら思いっきり踏み込んだ。グギャベギッバギッ!!!「ギ、ブギギャアアアアアッッッ!!!!!」全体重をかけた礼子の蹴りは当然の如く、坊野の上の歯を数本、一瞬にしてへし折る。更にブーツのソールは坊野の上顎と鼻を踏み潰し、鼻骨もへし折っている。礼子がブーツのヒールを持ち上げると殆ど同時に鮮血が噴き出る。へし折られた歯茎から、口の中に侵入した堅いヒールに傷つけられた口の内部から、そして鼻骨を砕かれた両方の鼻の穴から。「イデエ、イデエヨオオオ、イデエエエエエ!!!」絶叫とともに坊野が必死で頭を左右に振る動きに連れ、飛び散った鮮血が床一面に降り注ぐ。噴水のような勢いはないが、汲めどもつきぬ泉のように鮮血が後から後から止め処もなく溢れ出る。「どう、痛い?でもまだまだよ。今のは上の歯だけ。まだ下の歯が残っているでしょ?」そう、礼子は巧みに蹴りをコントロールし、わざと上の歯だけをへし折っていた。下の歯を残し、もう一度歯をへし折られる苦痛を坊野に味合わせるために。
「さあ、下の歯も行くわよ?上と下、どっちが痛いかしらね?」トントンと予告するかのようにブーツのヒールで下の前歯をノックした。「さあ、逝くわよ?」スーッと持ち上げられた礼子のブーツが再び踏み下ろされる。「ギギャァァァァァッ!」下の歯を数本へし折られた上に、下顎の骨まで砕かれた。「痛いでしょう?でも未だ終わっていないわよ。」礼子は更に坊野の頬を蹴り、横を向かせると上顎、下顎それぞれに更に蹴りを入れ、上下の顎を完全に蹴り砕いた。丁寧に、左から、右からと二セット繰り返し、完全に坊野の鼻と顎を粉砕する。「アラアラ、これで一生総入れ歯確定ね。まあ歯はまだいいとしてもね、きっと今ので顎の骨も砕けたわよ?しっかり踏み砕いたから多分、もう顎の骨、くっつくのは無理よ。あーあ、可哀想に。これで一生、硬いものは食べられないわよ。ステーキもフライドチキンも、美味しいものは殆ど諦めるしかないわね。これからのお供はお粥やお豆腐だけ。ウフフフフッ、つまらない人生になったわね。文字通り味気ない、ていう所かしら?」「あがが・・・あぎひいいい・・・ガボッ、グガアッッッッッ・・・」相変わらず優しい表情で嬲る礼子に反応もできずに喘いでいた坊野だが、不意に苦しげに咳き込みながら全身をビクビクと痙攣させた。「ウン?どうしたの、急に静かになっちゃって、ねえったら!」礼子は砕いた顎を爪先で小突いてみたが坊野の反応はない。指の関節を殆ど全て外された上に歯を10本以上もまとめてへし折られ、おまけに鼻、顎まで砕かれたのだ。言葉にすらできないほどの激痛に喘いでいる上に自分の出血を肺に飲み込んでしまった坊野は遂に痛みの限界値を超え、白目を剥いて気絶してしまっていた。
普通だったらこれで流石の礼子も拷問・リンチ終了だ。だが今日の礼子に対しては気絶など、何の救いにもならない。ゴロリと坊野を蹴り転がし、うつ伏せにさせると礼子は坊野の口に指を突っ込み、飲んだ血を吐かせた。「ゲッ、ゲバアッッッ・・・」
失神したまま坊野が肺に入った血を吐き出すのを確認すると、礼子は坊野の背中に右膝をあて、更に両肩を掴んだ。「・・・ハッ!」「・・ガッ、グハアッッッ・・・」
礼子に巧みな活を入れられた坊野が弱々しい声と共に息を吹き返す。「どう、目覚めた?気絶したらもう終わり、と思ってたでしょ?フフフ、駄目よ。今日は気絶なんかしても絶対に許してあげない。好きなだけ気絶していいわよ。何回でも活を入れてあげるから。」「…して…」「何、何か言った?もうちょっとはっきり言ってくれないかしら?」「・・ゆる・・して…お・ねがい…」消え入りそうな声で坊野は哀願した。その目は涙でうるみ、視線は弱々しい負け犬のものだ。最早最凶ギャングの誇りも何もない。余りに圧倒的な礼子の暴力の前に坊野の精神は完全に打ち砕かれてしまった。
あるのは唯一つ、目の前にいる礼子に対する恐怖だけ。礼子が女の子、自分より年下の美少女であることすら、もう関係ない。目の前にいる礼子は残酷な、余りに残酷な支配者、冷酷な拷問官、純粋な恐怖の対象そのものである、破壊の女神の化身、人間を超えた存在だった。そして、その残酷な女神は許す、等という言葉とは無縁の存在だった。
「許して?残念だけど無理ね。言ったはずでしょう?命懸けで苛めてあげる、て。こんなんじゃあ、まだまだ終わらないわよ。」そ、そんな・・・坊野が必死で口を動かそうとするより早く、礼子が問い掛けてきた。「さてと、ここで一つ質問よ。私の次の責めは何かしら。当ててご覧なさい。当たったら・・・そうね、少しは痛くないようにしてあげるかもよ?」い、痛くなくしてくれる!坊野にとってその言葉は何よりのカンフル剤となった。「まあ結構簡単な質問だと思うわよ。」内心で舌を出しながら、礼子はヒントらしきものを与えた。かすれている意識を必死で叩き起こしながら、坊野は必死で考えた。そして、その必死さは当然のように礼子の仕掛けた罠にはまり込んでしまった。か、簡単・・・み、みんながやられたのは・・・「つ、潰す・・んです・・・か・・・」フフ、こうも簡単に引っかかるとはね。「潰す?タマタマを潰す、て思うの?それが坊野さんのファイナルアンサーでOK?」「・・・は、はい・・・」「ブーーッ!外れよ。坊野さん、結構頭悪いわね。簡単だ、て言ったでしょ?私、さっき言ったはずよ。あなた達の肩と股関節、四箇所全部の靭帯を引き千切って再起不能にしてあげる、て。他の三人はもう失神してるから後回しにして、坊野さん、あなただけは特別扱い。あなただけは潰すより先、意識がある内に、痛みを十分に感じられる内に引き千切ってあげるわ。」
凄絶な微笑を浮かべながら、礼子は坊野の右腕を掴むとグルグル回して見せた。「どうかしら?普段だったらこんな角度では肩、回らないはずよ。関節外したおかげでこんな回転ができるんだけどね、生憎これじゃ、いくらやっても靭帯、千切れないのよ。まずは下拵えをしないとね!」楽しそうに言いながら、礼子は掴んだ腕を反時計回りにほぼ一回転ねじ上げる。「い、いでえええっ!」早くも坊野の悲鳴があがる。
「痛い?でもこれからもっともっと痛くなるわよ。」礼子は腕をもうこれ以上絞り上げられない、というところまでねじ上げると膝を坊野の肩に当てて力の支点とした。
「ウフフフフッ、さあ準備OK!私も結構何人もの靭帯を伸ばしたり、関節を外しちゃったことはあるけど、流石にこうやって意図的に靭帯を引き千切るのは初めてよ。どう、怖い?私がこの腕絞り切ったら、坊野さんの靭帯、ブチブチ、て音立てて千切れる筈よ。そうしたら・・・多分、もう一生直らないわね。可哀想、一生片輪、確定ね。」「い、いやだ、いやだあああああっ、やめ、やめでぐれえええええっ!」
坊野は必死に腕を振り解こうとするが、礼子の束縛はびくともしない。「無駄よ。肩は外してあるんだから、坊野さんの力は半減以下よ。それに第一、これだけねじ上げてあれば、力を出すどころじゃないわよ。嘘だと思うなら試してご覧なさい。ほら、振り解いてもいいのよ、できるものならね!」笑いながら礼子は坊野の腕を前後左右に小刻みに揺り動かした。「あひっ!あいつっ!いだっ、いたいいい!」礼子に翻弄される度に坊野の肩に様々な角度から痛みが走る。痛みにあえぎながらも坊野は必死でなんとか自由になろうともがくが、礼子の言うとおり、肩には殆ど力が入らない。
力を入れる度に却って肩に痛みが走るのだが単に余計痛いだけで、力が入り自分の思うように腕を動かせる感触は全くない
「どう?もういい?じゃ、処刑開始よ!」礼子は腕をギリギリと絞り上げながらゆっくりと前方向に坊野の腕を倒していく。ギジッ、ミジッ・・・既に限界値まで伸ばされていた靭帯に更に負荷がかかる。人間の靭帯は丈夫だ、そう簡単には千切れるものではない。だが礼子は手首と肘を極めながら梃子の原理で絞り上げ、坊野の肩に強烈な負荷をかけている。「ひぎっ、ひきいいいっ!ぐふぁっ!?」坊野の声が甲高くなっていく。靭帯が伸び、千切れかけていく音、実際には音などしないのだが、責めている礼子と責められている坊野の二人だけは、その音を確かに感じていた。耳ではない、全身で感じていた。ち、千切れる!!!「・・・感じるわ、坊野さんの腕が壊れていく音を。全身が悲鳴を上げているわね。もうやめて、もう限界だ、て。これ以上逝ったら本当に千切れる、て言ってるわ。フフフ、坊野さんの全ては今、私のものよ・・・」礼子の全身にゾクゾクするほどの快感が走った。この快感を直ぐに終わらせるのは勿体無いわ。礼子は二度、三度と坊野の肩を絞り上げたり緩めたりして弄んだ。うん?さっきより少し前まで倒せるみたいね。「あら坊野さん、肩の可動域、少し広がったみたいよ。ストレッチング効果、といったとこかしら。よかったわね、少し希望が出てきたじゃない、このままもっともっと柔かくなれば、引き千切られないで済むかもよ?」「あ、あぎぎぎっっっ!ひ、いでえええええっっっ!そ、そんな、いだい!も、もうだめだあああ、いや、やめて、放してくれえええっ!」礼子の美貌に満足げな笑みが浮かぶ。「駄目よ、あきらめちゃ!人間は無限の可能性を持ってる、て言うでしょ?それを信じなさい!自分の限界を認めちゃったら・・・その時は靭帯を引き千切られちゃう、てことを忘れないでね。さあ、逝くわよ!」「ヂ、ヂギレルウウゥッ!ヂギレジャウッ!ギャビャアアアアアアアアアアアアァッ!!!」
ゆっくりゆっくりと礼子は坊野の肩を絞り続けた。ゆっくりゆっくりと、坊野の靭帯が千切れる限界ギリギリまで負荷をかけては少し緩め、また絞り上げ、延々と激痛を味あわせ続けた。「い、いや、ビギャァァァァッッ、は、はな、しゃべ、な、なんでもしゃべるよ、しゃべるがら、アギアッ!いや、ゆるめで、ギャヒイッ!ちょっと、ちょっどでいいいいいからあああっ!!ゆ、ゆるめで、はなじでぐれえええええっ!しゃべるあいだだけでもおおお!ゆ、ゆるめでぐれえええええっっっ!!!」だが礼子は坊野の悲鳴などどこ吹く風で相変わらず涼しい顔だ。「あら坊野さん、もう拷問は終わったのよ。別にもう、これ以上喋ってもらうことなんかないわ。聞くべきことはもう十分に聞かせて貰ったわよ。後はあなたを処刑するだけなの。だから安心してゆっくり苦しんで頂戴。いいってことよ、遠慮はいらないわ、坊野さんと私の仲じゃないの!」ヒイッ!そ、そんな!拷問ではない、礼子のその言葉は坊野の救いを全て断ち切るものだった。もう白状しようが何をしようが、この激痛から救われることはない。本当に片輪にされる・・・坊野の精神は恐怖と絶望に崩壊一歩手前だった。
だが坊野自身より早く、礼子は坊野の自我が崩壊しようとしているのを見取っていた。フン、そろそろ限界のようね。いいわ、まずは一本、引き千切ってあげる。発狂なんかさせてあげないわよ、フフフ、この激痛で意識を叩き起こしてあげる。最強のカンフル剤になるわよ!礼子は大きく息を吸った。「だいぶ痛そうね、ウフフフフッ、さあ、じゃあこの腕、そろそろ引き千切ってあげるわね。いーち、にーの・・・さん!」「ビッビアアアアアッ!あぎゃっ、アギイイイイイッ!!!」断末魔のような坊野の絶叫が響き渡る中、礼子はゆっくりと最後の一線を超えていった。既に限界に達して伸びきり、筋繊維が脆くなっていた坊野の肩の靭帯が遂に抵抗不能となった。ブツッ・・・ビヂッブヂッ・・・バッヅッ・・・その音は周りにいる玲子たちには聞こえなかった。その音を聞いたのは処刑官の礼子と受刑者の坊野の二人だけだった。いや、聞いたというのは不正確かもしれない、感じたと言った方が正確だろう。
最後の一線で抵抗していた靭帯が遂に限界を超えてこれ以上持ちこたえる力を失い、一本、また一本と筋繊維が断裂し、千切れていった。
「ひっひぎいいいいいっ!いだい!いいいいっ!!ああああっ!!!」坊野の悲鳴は完全に裏返り、金切り声となって響き渡る。「いぎゃあああああっ!い・だ・いいいいいいっっっ!!!」ああ、本当にいい声。ゆっくりゆっくりと坊野の肩を破壊しながら礼子は今まで味わったことのない程の快感に浸っていた。礼子が少し、また少しと締め上げる度に坊野の断末魔が響く。ああ坊野さん、あなたって最高・・・私の精神とあなたの精神、今完全にシンクロしてるわね。私の動きとあなたの叫び、私の快感とあなたの苦痛、今完全に一つに溶け合っているわ・・・もう少し、もう少しよ・・・もうすぐ一緒になれるわ・・・礼子がまた少し絞る。ミジッ、また一本坊野の筋繊維が断裂する。「ウ、ウギャアアアアアーーーッ!」ああ、そうよ、その反応、私の責めにリアルタイムのその絶叫、最高よ・・・礼子は最早坊野のことを憎んでなどいなかった。リターンマッチを挑まれては面倒、という恐怖心すらもうない。礼子の心を占めているのはいとおしさ、坊野のことを限りなくいとおしく思う心だった。ああ、私と坊野さん、今完全に理解しあっているわ・・・同じ時間を共有している・・・いつまでも、こうやってずっと二人で、二人だけでいられたらいいのに・・・さあ、一緒に昇り詰めましょう・・・愛情、と言ったほうがふさわしいかもしれない穏やかな、優しい感情だった。勿論坊野の側にそんな感情は毛頭ない。想像を絶する苦痛に喘ぎ、絶望に打ちひしがれている坊野に愛だの何だのを語る余裕など全くない。
一方的な、完全に一方通行の愛情。だが礼子の愛情は坊野の全てを、肉体も精神も全てを奪い尽くし焼き尽くす激情だった。
プヂッ・・・「ギアアアアアッ!ア!ギギギイイイイーーーッッッ!!!」ああ、切れたのね・・・最高・・・痛いでしょう?最高に痛いでしょう?気が狂いそうな位の痛さでしょう?私もよ・・・私が坊野さんを破壊し尽くしたのね・・・最高・・・最高に気持ちいい・・・私もこんな気持ちいいの、生まれて初めてよ・・・遂に坊野の右肩の靭帯、最後の一本が断裂する破滅の音が響いた。力が全く入らなくなった坊野の右腕を漸く解放した礼子は暫しの間、全身に満ち溢れる快感の余韻に浸りながら苦痛に喘ぐ坊野を見下ろしていた。その視線に先ほどまでの鋭さ、残酷さはもうない。相変わらず微笑を浮かべていたが、その微笑は慈愛に満ちた、何とも優しげな微笑だった。満面に優しさを湛えながら、礼子は坊野の左腕を取った。「あ、や、やだ、ひいっ、お・・ねがいだ・・・やめて・・・くれ・・・」虫の息で涙を流して哀願する坊野に礼子は相変わらず微笑みながら首を振った。「そんなこと言わないで、坊野さん。私とあなたの二人だけの時間、もっともっとたっぷりと楽しみましょうよ。時間は十分あるわ。腕一本と足二本、ゆっくりと楽しみましょう?」「や、いや、いやだあああっ!だ、だれか、誰か助けて、たすげでぐれええええっ!こ、ころされるううううっっっっ!!!」「心配しないで、私が坊野さんのこと、殺したりするわけないじゃない?だって私のことを世界で一番分かってくれているのは坊野さんなんだから。そうでしょう?」確かにその通りだった。他人の肉体を、精神をなんら良心の呵責を感じずに完膚なきまでに破壊し尽くし、相手の自我の崩壊を無常の喜びとする礼子。その礼子の本質を骨の髄まで叩き込まれたのは坊野だけだ。慎治たちだってここまではやられていない。魅入られた者を最悪の破滅に追い込む破壊の女神、拷問室の天使。その女神に魅入られた坊野に許されることはただ一つ、苦痛を味わい続けることだけだ。「坊野さん、私を分かってくれて嬉しいわ・・・私も坊野さんを世界で一番理解しているわ・・・坊野さんの苦痛、嘆き、悲しみ、後悔・・・全部分かっているわ・・・さあ、もっともっと理解しあいましょう・・・もっともっと感じさせて、坊野さんの全てを・・坊野さんの今までの人生は全て、私に会う今日のための準備に過ぎなかったんだから・・・私が坊野さんの今までの人生に意味を与えてあげるわ・・・」恐怖に蒼ざめ、全身を震わせる坊野の左手を礼子が優しく、しっかりと握り締めた。
たっぷりと時間をかけて礼子は坊野の左肩、そして両足を破壊していった。何回となく坊野は気絶しては活を入れられて無理矢理意識を取り戻させられ、再び靭帯が引き千切られる苦痛を味合わされた。漸く礼子の人体破壊が一段落した時、床に転がっている坊野は自力では殆ど動くことすらできなくなっていた。四肢の関節を全て外され、靭帯を引き千切られ、指の関節も何箇所も何箇所もへし折られていた。想像を絶する苦痛に全身の筋肉は痙攣するほど緊張し、間断なく悲鳴を上げ続けた喉も破れて血が流れていた。全身の全てのエネルギーを使い果たし、ボロ雑巾の様になって坊野は床に転がっていた。「あ・・・あぎぎぎ・・・」関節を破壊された痛みは一過性のものではない。体内で進む内出血、炎症に坊野の痛みは全くと言っていいほど軽くならない。激痛から嘔吐感を伴う鈍痛に変わりつつあるが、痛みの程度としてはむしろ余計ひどくなっているような感じさえする。礼子はそんな坊野を満足そうに見下ろしていたが、やがてゆっくりと坊野を仰向けに引っくり返した。先ほどまでのように、乱暴に蹴り転がすのではない。優しく慈しむかの様に坊野を抱きしめながら、礼子は仰向けに坊野の体を横たえた。
8
「がっ!いだい・・・」礼子がいくら優しく転がした、とはいっても関節に力が加わり、坊野の全身に新たな激痛が走る。「痛い?大丈夫よ、直ぐに次の責めに移ってあげるから。その痛みは暫く、忘れられるわ。」暫く!?忘れる!?ま、まさか・・・怖くてその先を言葉にすることは流石にできない。「そう。これが今日の私と坊野さん、二人のデートの仕上げ、クライマックスよ。さあ、精一杯楽しみましょう。」
「ヒ、ヒッ、ヒイッ!そ、そんな、まさか、つ、つぶす・・・の?やめて・・・もう許して・・・し、死ぬ、ほ、本当に死んじまう・・・」絞り出すような声で、両目一杯に涙を浮かべて哀願する坊野の髪を優しく撫でながら、礼子は何とも穏やかに微笑んだ。
「死ぬ?大丈夫よ、ちゃんと歯は折ってあげたでしょう?痛さの余りショック死、ていう可能性はあるけど、人間そう簡単には死ねないものよ。交通事故かなんかで潰れちゃったけど生きてる人っていうのは結構いるんだから。坊野さんも多分、助かるわよ。」柔らかい声で恐ろしい宣告をしながら、礼子は坊野のチノパンとトランクスを脱がせた。坊野の一物は哀れなほど縮み上がっていた。その一物をそっと持ち上げながら、礼子は坊野の睾丸を両手に一つずつ、優しく包み込んだ。「坊野さん、私、男性の玉を触るのなんて初めてなのよ。うん、ちょっぴり恥ずかしいわ・・・だけど大丈夫、安心して。あなたのなら私、大丈夫よ。私の初体験、坊野さんにあげるわ。坊野さんも女の子に潰されるのは勿論初めてでしょう?」
礼子はゆっくりと、まずは右手に力を入れていく。「ぐっ・・あはっ・・・おばっ、い、いいいいい!!!」先程までの痛みとは異質の、体の奥底にズシリと重く響くような痛みに坊野は溜息をつくような、押し殺された悲鳴を漏らした。フーン、潰される時ってこういう声になるのね。さっきまでの金切り声の絶叫とはずいぶん違う悲鳴ね。「ねえ坊野さん、いいこと教えてあげようか?私ね、こう見えても握力には結構自信があるのよ。大抵の男の子には負けたことないわ。いくつだと思う?私ね、両手とも60キロあるわ。どう、驚いた?もしかしたら坊野さんより上なんじゃない?」
ろ、60キロ?激痛にボヤケた意識の中で坊野の頭の中を、その非現実的とも言える数値が飛び回った。ろ、60キロだって!?お、おれでさえ50キロそこそこだぞ、それをこんな細い女の子が出すなんて、マジかよ。怪力自慢の須崎といい勝負じゃねえか・・・こ、こいつ化け物か?坊野が怯えるのも無理はない。普通、かなり鍛えた運動部系の女の子でも握力の平均値は30キロ台前半だ。40キロあれば相当に強い方、柔道、空手等、格闘技系の男でも50キロ台なら通常、十分な握力だ。勿論、怪力自慢のプロレスラーや力士等、100キロを超える人間もいるが、それは基本的には異常値の世界であり、一般的には男でも、60キロと言えば十分、握力自慢で通用するレベルだ。そ、それをこんな細い女の子が出すなんて・・・坊野は涙で曇った目で改めて礼子の腕を、肩を見てしまった。確かに細いとはいえ、引き締まった腕には十分な、鞭のような強靭かつしなやかな筋肉が秘められていそうだ、だがどう見てもそんな怪力型、ゴリラタイプには見えない。ま、マジかよ・・・こいつ、化け物か・・・化け物、その言葉を坊野は何度も何度も反芻した。急速に礼子が人間を超えた何か、非現実的な存在に思えてきた。ゾクッ・・・坊野の背筋になんとも言えない悪寒が走った。目の前にいる、自分を責め苛み続ける美少女が想像を超える怪物、悪魔に思えてきた。坊野の精神が感じる礼子は強大な悪魔だ、だがその目に映る現実の礼子は美しい、天使、とさえ言いたくなる程の美少女だ。そのギャップが坊野の恐怖を余計に掻き立てる。し、信じられねえ・・・坊野は何度となくその言葉を歯をへし折られた口で呟き続けた。だがそれも束の間、礼子は優雅に呟いてなどいられないレベルに責めをアップし始めた。
坊野の目に怯えの影が浮かんだのを見て礼子は微かに微笑みながら右手を緩めた。
「ゼッ・・ゼハッガッ・・・」坊野が荒い息をつくタイミングを礼子はじっと見ていた。「ゼハッ・・・グブアアアアアッ!」坊野が息を吐ききったまさにその瞬間を狙って礼子は今度は左手に力を込める。たちまち先ほどまでと同じ、内臓を鷲掴みにされたような痛み、苦しみが坊野の全身を支配する。いや、先ほどまでと同じではない。礼子に睾丸を締め上げられた坊野は余りの苦しさに息が詰まり、半ば呼吸困難状態だ。だが今度は息を吐き切った瞬間に締め上げられているのだ、肺に空気は殆どない。「グウ、ウウウッ・・・グヘッ、ゲグッ、ゲハッ!ゲハアアッ!!!」苦しさに喘ぐ坊野は空気を貪るように必死で口をパクパクさせ、その拍子にへし折られた歯茎から未だ止めどもなく溢れつづけている自分の血を肺に吸い込んでしまったからたまらない。たちまちの内に抑えようのない、止め処もない咳が重症の喘息患者の発作のように坊野の全身を痙攣させる。
喘息患者が酷い発作に襲われると、しまいに呼吸困難からチアノーゼ症状を起こすように、坊野もまた空気を奪われる苦しみ、そこに、目の前にいくらでも空気はあるのに殆どそれを吸えない苦しみに全身を痙攣させてもがき苦しみ続けた。礼子は巧みにインターバルをおき、責める睾丸を時々変え、痛みが新鮮さを失わないように最新の注意を払いながら坊野を責め苛みつづけた。
「ウフフフフッ・・・その調子よ坊野さん、人生で最高の痛みでしょ?私も最高。こんな楽しいのは初めてよ。さあ、もっともっと聞かせて頂戴、坊野さんの最高の声を!魂の叫びを!」礼子は満面に笑みを湛えながら両手で同時に左右の睾丸をしっかりと握り締めた。「さあ、今度は両方いっぺんに苛めてあげるわ。お楽しみも二倍よ!」ギシッ・・・礼子が両手に力を込めると同時に坊野の全身を更に倍加された激痛が抱きしめる。「ガアッ、ギ、ギアッ!ギャアアアアアッッッ!!!」坊野は必死で身をよじり、何とかこの地獄から逃げ出そうとした。だが四肢を全て砕かれ、更に最大の急所である睾丸をしっかりと抑えられていてはどうしようもない。逃げるは愚か、腰を浮かすことすらできない。動かない手足を波打たせ、それが神経を余計に刺激して更に坊野を苦しめる。「嬉しい・・・坊野さん、こんなに喜んでくれているのね。そんなに全身が震えるほど嬉しいのね!私もよ、私も最高に嬉しいわ!喜んで、また新しい責めを考えついたわよ!もっともっと苦しんでね、ほら、今度はこうやって苛めてあげる!」白い頬を上気させながら、礼子はまるで揉み洗いをするかの如く、両手に握り締めた坊野の睾丸を激しくこすり合わせ、睾丸同士をグニグニと押し付け、こねくり回した。「イヤアアアアアッ、イ、イダイ、デエ、イデエヨオオオオッ!ヤ、ヤベ・・・グバアアアッ、ゲ、ゲバッ!ヒッ!ピギイイイイイッッッ!!!」激痛の余り目の前が真っ暗になっていくようだった。痛い、苦しい・・・その極限点、礼子の両手が自分の体内に侵入し、内臓を鷲掴みにされているようだった。礼子が睾丸同士を打ちつけ、こすり合わせ、相互に潰し合わせる動き、僅か数ミリ、数センチ単位に過ぎない睾丸の変形が坊野の全身に悪寒と強烈な嘔吐感を伴った激痛を駆け巡らせる。体の表面や筋肉、骨といった組織ではない、生命維持に直接関わる内蔵そのものを礼子に破壊されているかのような激痛に、坊野の生物としての本能が全力で悲鳴をあげ、警告を最大音量で発している。これ以上責められるのは生命に関わる、と。「グッ、グボアアアッッッ・・・」坊野は内臓そのものが飛び出てくるかのような強烈な嘔吐に見舞われた。だが既に激痛の余り、本人が気づかないうちに何度も何度も嘔吐していた坊野の胃袋には内容物など最早ない。吐き出された僅かな胃液と空気、それは口の中に溢れ続ける血と混じりあい、ブクブクとカニのような泡となって口の端から零れ落ちた。真っ赤に染まった血泡を吹き出しながら、激痛に半ば錯乱状態に陥りつつある坊野は白目を剥いて気絶しかけていた。だが礼子が気絶などという救いを許してくれるわけがない。
坊野を責め続けた両手を一旦休め、痛みの余韻に痙攣し続ける坊野の胸を、まるで赤ん坊でもあやすかのように礼子は掌で優しく、トントンと叩いた。「ひっひあっっっっっ・・も、もう・・・や、べ・・・て・・・」坊野の哀願はもはや微かな独り言並みのボリューム、よっぽど注意深く耳を傾けないと聞こえないレベルにまで落ちていた。礼子はそのまま坊野の心臓の上にそっと手を置いた。
早鐘のように凄まじい速さで鼓動を打っているが、なんとなく鼓動が弱々しくなってきたような気がした。フウッ・・・礼子は小さく溜息をついた。楽しい時って本当にあっという間ね。もう坊野さん、本当に限界が来ちゃったみたい。仕方ないわね・・・「フウッ・・・坊野さん楽しかった?とのデート。私は最高だったわ。生涯最高に楽しいデートだったわよ。でもどうやらお別れの時間が来たようね。私とのデート、坊野さんにとっても一生の思い出になったかしら?でもね、デートは別れ間際が一番盛り上がるのよね。さあ、最期にとびっきりの思い出を刻み込んであげるわ!」礼子は最早虫の息の坊野の睾丸、左の睾丸をしっかりと右の手掌に包み込み、更に上から左手を添えた。「さあ・・・逝くわよ・・・」礼子はゆっくりと両手に力を込めていった。「・・・イ、ガッッッ!ギッヒイイイイッッ!ア、アウウウウッッッ!!!」激痛が坊野の意識を蹴り起こす。睾丸を、いや体の中心、はらわた全てを握り潰されるような激痛に坊野が全身を痙攣させながら苦しげに喘ぐ。「うん、そうよ・・・いい表情・・・最高よ・・・こっちを向いて・・・坊野さんの表情、よく見せて頂戴・・・そう、そうよ・・・いいわ・・・さあ、いよいよよ・・・逝かせてあげる!」礼子は60キロの握力全てを一気に解放した。「アッ!アアッ!ギ、ヤ、ベデエエエエエッ!ツ!ツブ、ギャアアアアアアアッッッ!!!」ブヂュッ・・・聞く者の耳に一生こびりついて離れないような凄まじい悲鳴の影で、微かな音を立てながら坊野の左睾丸が潰された。ブクブクと口から血泡を吹きながら坊野が全身を痙攣させている。痛い、等という言葉は生温い。腹の中に無理矢理巨大な鉛の塊を詰め込まれたかのような圧迫感を伴った鈍痛、そしてその鉛の塊は氷のように冷たく、はらわたを、全身の熱をあっという間に奪い尽くすかのようだった。そして全身の血液がそこに流れ込んでいくかのように、坊野の左睾丸が急速に腫れ上がり、ボールのように膨れ上がっていく。「ウ、ウグアアアアッ・・・ゴブアアアアッ・・・」何度目かの嘔吐に全身を震わせながら、随意筋、不随意筋を含め全身の筋肉を最早自分では全くコントロールできなくなった坊野は礼子の足元でついに失禁してしまった。
素早く手を引っ込めた礼子は、坊野の失禁が止まると今度は右の睾丸を左手で握り、上から右手を添えた。「ウフフフフッ!坊野さんったら!そんなに気持ちよかったの?おしっこ漏らしちゃう位気持ち良かったのね。嬉しい、そんなに喜んで貰えるなんて、私も最高に幸せよ。でもね、もう正真正銘、お別れの時間が来たようね。さあ、こっちも潰してあげるわ。この玉が潰れたら・・・私と坊野さんもお別れね。楽しかったわ坊野さん、あなたのことは一生忘れないわ。坊野さんもでしょ?」礼子が徐々に握力を解放していく。「ギッ!ヒッ!ヒヒャッ!ヒギッ!ハヒャアッ!!!」坊野の悲鳴はどこか、笑っているような響きがあった。「ハッ!ハヒッ!ハヒッ!ハヒヒッ!ハヒヒヒヒッ!ハヒヒヒヒイイイッ!!!」坊野の目は裏返り、完全に白目を剥いている、口はだらしなく開き、血泡を垂れ流している。痛い、苦しい、という感覚すらどこかに飛び、他人事のようになっていた。視界が暗くなり真っ暗な中、目の前でチカチカと星が瞬いた。「さようなら、坊野さん!」ブヂュウッ!!!「アッ!アビイイイイイッッッ!!!」礼子が全てのパワーを解放し、坊野の右睾丸をペチャンコに潰すと同時に坊野の喉から断末魔の悲鳴があがった。完全に意識を失った坊野の体から、永久に失われた男の機能とプライドの名残かのように、白い精液がドクドクと流れ出していた。通常の何倍もの量の放出、いつもなら快感に震えたであろう坊野だが、今は射精の喜びに何百倍も勝る喜びに浸っていた。やっと失神できる、全身を支配する苦痛から束の間とは言え解放してくれる、失神という喜びに咽び泣きながら、坊野の意識は何もない、暗黒の虚無に堕ちていった。
あ、ああ・・・慎治たちは呆然と眼下に広がる地獄絵図を眺めていた。ついさっきまで最凶を誇っていたSNOW CRACKの四人がボロ雑巾のように横たわっていた。全身血塗れ、手足はあらぬ方向に折れ曲がっていた。今は玲子たちが最後の後始末、奈良村たち三人の靭帯をねじ切っているところだった。普通だったら想像を絶する激痛を伴う筈だ。だが睾丸を潰され、人生最大の激痛に悶絶しながら気絶していった奈良村たちはピクリともせずに為すがままにされていた。そ、そんな・・・坊野さんたちがやられるなんて・・・慎治たちは未だに自分たちが見ている光景を信じられなかった。礼子たちが強いのは分かっていた。残酷なのも身をもって味合わされている。だがこれほどまでとは・・・全てのリミッターを取り払った礼子たちの恐怖は底無しだった。復讐、固く心に誓ったつもりでも上っ面だけ、所詮は他人を雇う、という程度の覚悟しかできなかった自分たちと傷つくリスクを省みずに前に出て危機を乗り切った礼子たち。しかも闇雲に前に出るのではなく、礼子たちは慎重な計算と何重もの安全確保も図っていた。差が、余りにも差があり過ぎた。そして今、時は満ちた。坊野たちは礼子たちの拷問に屈し、慎治たちに端金で雇われたことを洗いざらい白状していた。
あ、ああ・・・ど、どうしよう・・・もう逃げ道はどこにもない。呆然と涙を流しながら思考停止に陥っていた二人に真弓が声を掛けた。「さあ信次、下も終わったようだし、そろそろ玲子に電話して降りていこうか。」恐怖の、死刑宣告に等しい一言だった。「・・・あ、ああ・・・や、やめて・・・」「何言ってるのよ!信次も見てたでしょ?坊野さんたち、玲子たちに拷問されてあんたたちのこと、全部喋っちゃったじゃない。今更やめても何もないでしょ?」笑いながら真弓が携帯のコールボタンを押すのを信次たちは呆けたように見つめていた。「あ、玲子?私、真弓よ。うん、今ここの二階にいるのよ。里美もいるわ。でね、まあ玲子も察しがついてるとは思うけど、スペシャルゲストも一緒よ。そう、信次たち。二人ともいるわよ。どうする?うん、下に連れてけばいいのね。OK、直ぐ行くわ。」携帯を切った真弓が信次に微笑みかけた。「信次、玲子が一緒に下に来て、てさ。じゃ、行こうか。」信次たちは半ば腰が抜けかけていたが、最早真弓たちに逆らう気力もなかった。されるがまま、半ば抱きかかえられるようにして立ち上がると階下へ引き摺られていった。
「あっ、来たわね信次!この!」待ち構えていた玲子が真弓から信次を受け取ると軽く頭を小突いた。「全く、ギャングを雇って私たちを襲わせるとは、随分と小ジャレタ真似をしてくれるものじゃない?ねえ礼子?」礼子もにこやかに笑いながら答えた。「全くよ。あんなに毎日、私たち美女軍団がたっぷりと遊んであげてた、て言うのに、この仕打ちなんだもんねえ。何か、飼い犬に手を噛まれた、ていう感じかな?」にこやか、礼子たちが妙ににこやかなのが慎治たちにとって却って恐ろしかった。きっといきなり殴りかかられる、蹴りつけられて坊野たちと同じような拷問に掛けられる、と思っていた。それが礼子たちは妙にフレンドリーだった。な、なに、なにを企んでいるの・・・信次が怯えているさまを楽しんでいた玲子の口元が緩んだ。
「信次、信次が何考えてるかは分かるわよ。私たちに拷問されるか処刑されるか、兎に角死ぬほど痛い目に会わされる、て怯えてるんでしょ?フフ、バカねえ、そんなことする訳ないじゃない。罪を憎んで人を憎まず、て言うでしょ?だから私たち、信次たちのことを憎んではいないのよ。」礼子も大きく頷いた。「そうよ。私たちがそんな鬼だと思う?可愛い可愛い、大事な慎治たちを処刑するなんて思ってるの?そんな訳ないでしょ。悲しいわ、私たちの優しさが未だ分かってないのね?」予想だにしない展開に戸惑う慎治たちを見て朝子がケラケラと笑った。「バッカねえ信次ったら!玲子たちが何て言ってるか分からないの?要するにね、許してあげる、て言ってるのよ!全く鈍いんだからもう!最も」クスクスと笑いながら朝子は続けた。「本当に許してあげるかどうかはフミちゃん次第かしらね。なにせ今日の最大の被害者はフミちゃんだからね、最終判決を下すのはやっぱりフミちゃんだと思うわよ?」
フ、フミちゃん・・・ごくりと息を飲みながら慎治は富美代の方を怯えためで見た。
フ、フミちゃん・・・あの気性の激しい富美代が、自分を嵌めようとした慎治たちを許せるとは思えなかった。だが富美代は意外なほど明るい声で笑った。「アハハ、最終判決ね。そうね・・・まあついさっきまでは慎治たちのこと、絶対許さない、て思ってたんだけどね。先輩のこと踏み付けながら、慎治も絶対私のヒールでズタズタにしてやる、体中穴だらけにしてやる、て思ってたんだけどね。だけどまあ・・・先輩の鼻グチャグチャにして、タマタマも潰しちゃったら何か、スッキリした、て感じかな。いいよ慎治、私も許してあげるわ。飼い主の礼子たちがいい、て言うなら、私も文句言わないよ。」「お、おおおっっっ・・・」「あ、ああ、あああああっっっ・・・」慎治たちの口から歓喜とも嗚咽ともつかぬ声が漏れた。た、助かった・・・こ、殺されないですむ・・絶望、絶体絶命、絶対に助からない、と思っていただけに、生き残れる、殺されないですむ、という嬉しさは想像を絶するものだった。
「あ、あ、ありがとう・・・」「ご。ごめんなさい。ごめんなさい・・・」慎治たちは殆ど無意識の内に礼子たちの足許に跪き、ブーツにキスしていた。血に塗れ、幾多の悲鳴を吸ったブーツに。
そんな二人を見下ろしながら礼子たちは満足げに頷きあった。礼子が小さく頷くのを合図に、玲子がブーツにキスしている信次を小突き起こした。「さあ二人とも、許してもらった喜びに浸りたいのはわかるけど、今日はもうお開きよ。私たちはこれから後始末、この人たちを警察に引き渡さなくちゃいけないから、まだ一仕事あるの。だから今日は信次たちと遊んであげられないのよ。今日のところはこのまま、真弓たちと一緒に帰りなさい。」か、帰れる!生きてここから帰れる!は、早く、早くここから逃げ出さなくちゃ、玲子たちの気が変わらない内に・・・未だ力がうまく入らない足を絡ませフラフラしながら信次たちは工場から逃げだそうとした。だが工場を出る直前、礼子が発した言葉は二人の心臓を一瞬にして凍りつかせてしまった。「慎治、あなたたちの罪は確かに許してあげるわよ。でも罪と罰、て言うでしょ?罪は許すけど、罰はキチンと与えるからね。どういう罰を与えるかは月曜に学校で宣告するわ。楽しみにしていなさいね!」
「さあ坊野さん、少しは休めた?あなたの相棒も目一杯、拷問されているのがわかったでしょ?お待たせしたわね、もうオードブルの時間は終わり。坊野さんにも本格的な拷問をたっぷりと味合わせてあげるわ。」相変わらず静かな、優しげな口調で恐ろしいことを宣告しながら礼子は再び、坊野の背中に腰を下ろした。「ヒ、ヒイッ!ほ、本格的な拷問だなんて・・や、やめてくれ!た、たのむ、や、やめて!」「もう!しっかりしてよ!坊野さん、悪名高いSNOW CRACKのプレジなんでしょ?たかだか女の子の拷問が怖いだなんて、おかしいわよ?」言いながら礼子は坊野の右手を握る。今度はボールペンなしで、そして必死で握り拳を作る坊野の小指だけを握り、無理やり伸ばさせる。既に十分痛めつけられ、握力が極端に低下した坊野の指は最早、礼子に抗することは不可能だった。
「ヒッヒ、イア・・や、やべで・・な、なにを・・」「あら、こうやって指握られてるのに、何されるのか分からないの?案外想像力貧困なのね。難しいことするつもりはないわ。指をへし折ってあげるだけよ。こうやってね。」ニッコリ笑いながら礼子はゆっくりと坊野の指を反らせ、折りにかかる。「ギ、ギアーーッッ!イ、イダイーーーッ!!ヤ、ヤベ、ビギャーアアッッッ!!!」ベギッ、坊野の小指、第三関節があっけなく脱臼する。「イ、イエッッッイ、イデエ、イデエヨーーー・・」余りの痛さにすすり泣く坊野を満足そうに見ながら、礼子は尚も折った指を離さない。
「ウフフッ、どう、痛い?少しは効いたかしら?じゃあね、もっといいこと教えてあげるわ。指の関節っていくつあるか知ってる?そう、人差し指から小指は各三個、親指は二個、両手合計で二十八個もあるのよ。ウフフフフ、全部へし折ってあげる。フフ、フフフフフ、クラゲみたいにしてあげるわ。どう、後二十七回もこの痛みを味合えるのよ。どう、嬉しい?楽しい?感想を聞かせてよ。」
楽しげに笑いながらも礼子はへし折った小指から手を離さない。そして一呼吸置き、坊野が味わっている脱臼の最初の衝撃的な激痛が少し収まった頃を見計らいながら第二関節をゆっくりへし折った。「イ゛!イ゛ギャアアアアッッッ!!!」だがまだ小指一本すら終わっていないのだ。礼子は焦らず、じっくりと坊野の苦痛の波を観察しながら、続いて第一関節を折りにかかった。「ビ、ビギイイイッッッ!」僅かに動かせる首だけをエビのように反らせながら、坊野は断末魔のような悲鳴を三度張り上げた。小指を完全に破壊した礼子が漸く、手を離す。いいな、この感じ。礼子は思わずうっとりと、遠い目になっていた。様々な関節技を使いこなせるといっても、基本的に格闘技として使う関節技は肘、肩、せいぜい手首位しか狙わないものだ。第一、礼子が修行したのはあくまで格闘技であり、相手を責めいたぶるものではない。
相手を脱臼させてしまったことは何回かあるが、それはいずれも事故、流れの中で予想外に技が深く入りすぎ、折ってしまった場合だけだ。
だが今は違う。礼子はゆっくりと指を折る快楽を満喫していた。じっくりと坊野の指を反らして行くと、ミシミシと関節がきしみ、もうこれ以上は無理だと悲鳴をあげるのが伝わってくる。それを更にそらして行くとキシッキシッと軋むような感触に変わっていく。このあたりになると、折られる坊野の絶叫は段々人間離れした悲鳴に変わってくる。そして更にそらすと何かが引っかかたようなブレーキが働き、坊野の関節が最後の抵抗を試みる。その抵抗を踏み躙るかのように更にゆっくりと手に力を込め、止めを刺しにかかるとゴリュッと関節が外れ、骨同士が滑るように擦れあう感触が伝わってくる。抵抗は今までの骨の抵抗と違い、筋が引きずられ、伸びていく柔らかく、どこか弾力のあるものに変わっていく。坊野の休む間のない悲鳴をBGMとして楽しみながら、礼子は極上の快感に、人体を破壊する快感に浸っていた。いつも慎治を鞭打っている時とは違う、再生、治療のことなど何も考えない、純粋な人体破壊。礼子は麻薬のように抵抗しようのない快感を無限に供給する、人体破壊の快楽の完全な虜となっていた。
坊野は小指の関節を三ヶ所ともへし折られ、激痛に肩を震わせながらうめいている。だが休む暇さえ与えずに、今度は薬指に礼子の白魚のような細く長い指がまとわりつく。「い、いや・・・も、もうやめでぐれ・・・」最早完全に涙声になって訴える坊野の哀願に礼子は冷たく答えた。「ダメよ。オードブルは終わり、本格的な拷問の時間だって言ったでしょ?まだ指は9本もあるんだから。どんどん逝くわよ!」
玲子もまた、自分の担当受刑者、奈良村のもとに戻っていた。「・・・さあタマナシ君、検見川さんの悲鳴、聞こえたでしょ?私もお遊びはおしまい。君にもあれ位の悲鳴をあげさせてあげるからね。」言いながら玲子は再びベルトを握り締めた。先ほどと同じく、バックルではなく、ベルトの先端の方を握っている。「フフ、脅かす割には拷問道具は相変わらずベルトなんで一安心してるんじゃない?でもね、私はこう見えても鞭のプロだからさ、色々な打ち方、使いこなせるのよ。さっきとは比べ物にならない位痛くしてあげるわよ。さあ、覚悟はいいわね!」「い、そ、そんな!も、もっと痛くだなんて・・・な、何をする気、ヒッや、やめ!ヒッ!」「煩いわね。何をするかなんて直ぐに分かるんだから、心配いらないわよ。その体にたっぷりと分からせてあげるからさ。さあ!逝くよ!」ビュオッ!と玲子のベルトは風を巻いて襲い掛かり、次の瞬間、ドズッと異様な、鈍い音を立てて奈良村の腕に食い込んだ。
「ギ、グブアーーッッッ!!!」先ほどとは全く次元の違う激痛に奈良村は思わず息が詰まりそうなほどだった。「アハハハハッ!どう、痛いでしょ!もっともっと痛くしてあげるからね、さあ、ガンガン逝くわよ!」ビュオッ、ブオッ・・・ドズッ、ガズッ・・・玲子の振るうベルトが立て続けに奈良村の体に襲い掛かる。
「ギャァァァァァッ!ビア゛―ッ!イダイ!イデエヨーッッッ!!!」余りの激痛に奈良村は喉が張り裂けそうな程の絶叫を上げつづけた。痛い、とにかく痛い。な、なぜだ。なぜこんなに痛いんだ。たかが、たかがベルトなのに。さっきと同じベルトなのに。だがその激痛は先ほどまでとは比較にならない。な、なぜだ、何をされているんだ。床にうつ伏せに転がされた奈良村からは玲子が振り下ろすベルトが見えない。肉体的な激痛に加え、自分が何をされているのかさえ分らない恐怖が奈良村の苦痛を更に倍化させる。
「ヒッ!ヒイッ・・・お、ねがい、もうやめ、ヒギイイイッッッ!!!」奈良村が激痛の余り、哀願すら涙声になるのを確かめて玲子は満足そうに一旦、ベルトを振るう手を休めた。「ウフフフッ、大分効いてるみたいね。じゃあ気分を変えて今度は体の表側を鞭打ってあげるわね。」玲子は言いながら奈良村の体の下にブーツの爪先を潜り込ませ、無造作に蹴り転がす。「ヒッ、か、体の表・・・い、今でも、背中や尻でもこ、こんなに痛いのに腹や胸だなんて!や、やめて、やめでぐれーっっっ!」
「うるさいわね!もう遊びはおしまい、て言ったでしょ?まだまだよ!拷問はこれから佳境に入るんだから!」喚き立てる奈良村の顔をブーツで踏み躙りながら玲子は無慈悲に拷問の続行を宣告する。「フフ、それにタマナシ君、そんなに悪いことばかりじゃないかもよ。こうやって仰向けになってれば、少なくとも自分がどんな拷問を受けているかだけは見られるかもよ。」スッと奈良村の顔からブーツを下ろし、玲子は間合いを取るために2,3歩下がった。「もっとも、君の動体視力で私のベルトの動きを見切れたら、の話だけどね。さあ、逝くわよ!」ビュオッ、ブオッ・・・ドズッ、ガズッ・・・玲子のベルトが再び唸りをあげて奈良村の体、二の腕から胸、腹を襲う。「ビ!ビギイイッ!イ、イダ,ゴブァッ!イ、イダイ!イダイイダイイダイヨーーーーッ!!!」背中とは比べ物にならない痛みに奈良村は獣のような絶叫を張り上げつづける。
自分をこんなに苦しめる玲子の拷問は一体なんなのか、奈良村は激痛の中で必死で見ようとした。だが全く分からない。「アハハハハッどう、痛い?どうなのよ!ほらほらほら!もっともっと!泣くのよ!喚くのよ!もがき苦しむのよ!」玲子は相変わらず高笑いしながらベルトを振り下ろしつづける。だが奈良村にはどう見てもさっきまでと同じく、単にベルトで打ちのめされているようにしか見えない。だがこの激痛、さっきまでとはケタが違うこの激痛は尋常ではない。自分が何をされているのかすら分からない、その恐怖が肉体の激痛に加え、精神的苦痛をも追加サービスしていた。奈良村が分からないのも無理はない。玲子の拷問の正体は僅か90度の手首の捻り、ただそれだけだったのだから。玲子は振り下ろしたベルトが遠心力を十分なスピードに変え、奈良村に命中する寸前に手首を返し、強力なスナップでベルトの威力を倍増させている。だが今はそれだけではない。命中する寸前、スピードが最高点に達したポイントで返した手首を内側に捻りこみ、ベルトの面ではなく、サイドで奈良村を打ち据えていたのだ。ベルトの威力が幅数センチに拡散されず、サイドの数ミリに全て集約される。しかもサイドは硬く、反り返ったりはしないから奈良村の体に命中したベルトは、その威力を肉体の表面に拡散させず、全てを体の奥深くへと食い込ませていた。
打撃の種類は、イメージとしては木刀に近い硬質のものだ。だが木刀よりも質量はない代わりに、より狭い範囲に集中する打撃はむしろ、日本刀による峰打ちに近いものがある。いずれにせよ、こんなもので打ち据えられては堪った物ではない。玲子の責めは筋肉がクッションとして受け止められる限界値を軽く突破している。連続して打ち据えながら、玲子は軽い驚きを感じていた。へえ、ベルトをタテにしたら、こんな感じになるんだ。打ち据える、という感覚とは全く違う、ガツッという手ごたえと共にベルトが奈良村の体に食い込み、急ブレーキがかかる。鞭打ちのように打ち抜く、といった感覚とは全く違う、居合抜きで巻藁等に切りつけた時の感触に似ていた。そして胸、肩など、奈良村の筋肉が薄く、骨が体表に近いところにあたると直接、骨にベルトが食いこむような素晴らしい感触がある。ギシ、ミジッ・・骨が軋み、食い込むベルトに悲鳴をあげ、ヒビが入っていく感触が玲子の手を通じ、全身に強烈な電流のような快感を走らせる。いい、最高・・・打つ、て言うより切りつける感じね・・いいわよ、タマナシ君、おバカな君だけど、私を楽しませるのは上手じゃない!もっと楽しませて頂戴!さあ骨が砕ける音を聞かせて!
玲子はヒユッと小さく息を吐き、気合を入れ直すと体を捻り、大きくバッスイングを取ると自らの全身をも鞭の一部とし、全身の力を込めてベルトを振り下ろした。狙いは・・・奈良村の肋骨、左一番下の肋骨だった。メジッ!「ぎ、きばあああっっ!」一撃で肋骨をへし折られた奈良村が悲痛な叫び声をあげる。「アハハハハッ!どう、今の一撃、気に入った?骨を砕かれる激痛って最高でしょ!ポキッて折られるよりずっとずっと痛いでしょ?ここまでの痛さなんて、そうそう味わえるものじゃないわよ!さあ、この痛み、もっともっとあげるからね!逝くわよ、次に砕くのは・・・ここよ!」玲子のベルトが風を巻いて襲い掛かり、今度は右の鎖骨を直撃する。バギイッ!奈良村は確かに自分の骨が砕ける音を聞いたような気がした。「ぎゃあああっ、あぎっ、ぎゃっ、やべ、やべでぇっ!!!」何か声を発していないと気が狂ってしまいそうな程の激痛だ。死んだほうが遥かにマシ、と思える程の激痛に喘ぎ、のた打ち回りながら奈良村は断末魔のような悲鳴を際限なく上げつづけた。
2
朝子もまた、大張り切りで担当受刑者の須崎のもとに戻っていた。「わあ、この指、どうしたの?真っ赤じゃない!それに何、これ。あちこち水泡ができちゃって、なんかいけない病気にでもかかっちゃったみたいだよ!」朝子の素っ頓狂な声が響いた。須崎自身は見ることができないが、確かに須崎の指は真っ赤に紅潮していた。ズキズキとした痛みが時間を追うごとにひどくなっている。火傷の典型的な症状、体の中に浸透した熱の効果が現れてきていた。「フーン、ああやって遠火で炙っただけでも結構、効くものなのね。どう、痛い?」「ヒッ!アッ!アヒッ!」朝子が指先でツンツンと軽く突っつくだけで、須崎の指に鋭い痛みが走る。「あ、あうっ、た、たのむ、も、もうやめで、あうっ!お、おねがいだから・・・」須崎が必死で哀願するのを朝子は面白そうに眺めていた。既に礼子たちは拷問を再開している。辺りには坊野たちの悲鳴が充満している。「うーん、まあ私としては許してあげてもいいんだけどね。でもね」クスリと朝子は笑った。「あっちでお友達三人とも、お楽しみ中みたいじゃない?一人だけハブにしちゃ可哀想だから、私がちゃんと拷問してあげるね。」
「ひっひーっ、そ、そんな、お、おねがい、や、やめて、たのむ、やめてくれーっっっ!」「うーん、どうしようかなーっと」と口では迷ったように言いながらも朝子は早くもライターを取り出している。「でもね、古今東西、拷問官が途中で受刑者を許しちゃう、ていうのはやっぱ、やっちゃいけないことだと思うのよね。だから・・・やっぱり、これの出番よね!」シュボッ・・・朝子は須崎の鼻先にライターを近づけると、これみよがしに目の前で点火した。それだけで須崎の全身に恐怖と悪寒が走る。
余りの恐怖にガタガタ震えている須崎を見て朝子は楽しそうに微笑んだ。「どうしたの、ガタガタ震えちゃって。あ、もしかして寒いの?まあ無理ないわね。コンクリートに直に転がってるんだもんね。うん、わかった、心配しないで。私があっためてあげるね。じっくりゆっくり、たっぷりとあっためてあげる!」言うなり朝子は一旦立ち上がり、須崎の背中にドスンと座った。「あ、あわわ、お、ねがい・・・」
「大丈夫、安心してよ。さっきみたいな酷いことはしないからさ。」えっ酷いことはしない・・・須崎の頭を一瞬の期待と不安がよぎる。「さっきの程度じゃあんまりあったまんなかったんでしょ?こんなに震えてるんだもんね。じゃ、今度は寒くないように、ちゃんと直火で炙ってあげるね。」
朝子はゆっくりとライターの炎を須崎の指先へと近づける。そして宣告どおり、今度はライターの炎の中に須崎の指を完全に捕らえた。「ひいいいぃっ、熱っ、熱いっ。やめてくれええっ!!!」須崎の悲鳴は先ほどまでとは比べ物にならない。必死で逃れようとするが手首を完全に縛られ、かつ肩は外されているのだ、動ける範囲などごく僅かでしかない。それでも須崎が僅かに動く指を必死で動かすため、炎は乱れ、あちこちになびいている。だが強風の中でも着火可能なZIPPOの炎はその程度では消えはしない。却ってあっちこっちに不規則に動く炎が須崎の指、手のあちこちを炙り、苦痛を増してしまっている。「アハハハハッ!須崎さん、おっきな体の割には結構器用なのね、指、凄い速さじゃない、もしかしてピアノでもやってたの?」
火責めを楽しむ朝子は楽しそうに笑っているが、責められる須崎はそれどころではない。余りの熱さにもがき苦しむので精一杯だ。「嫌ぁっ、いやっ、熱いっ、熱いぃっ。ぎゃあああああぁっ!!!」
ジリジリと炙られる須崎の指のあちこちで皮膚が焼けていく。直火とはいえ、ライターの炎は大した火力ではないから黒焦げ、とはいかないがそれでも皮膚が焼け爛れ、所々に赤い肉が露出している。既に水泡は殆どが熱に炙られ、破れている。炎に炙られ続けている須崎の指から血とも体液ともつかぬ液体が滴り落ちている。最初の内は指の毛が炙られ嫌な臭いを立てていたが、その臭いはもう収まり、別の匂いが立ち始めている。うん?なにかな、この匂い。なんかいい匂いだな。あ、そうか。これ、お肉の焼ける匂いだ!「わあ須崎さん、いい匂い!ねえ須崎さんも嗅げないかなあ、お肉の焼けるいい匂いしてるよ、どう、そっちにも逝ってる?なんか焼き肉食べたくなってこない?」だがそれに対する返事はない。いくら肉が焼ける匂いがする、とは言っても完全に指に、手に火が通り、痛覚が焼け死ぬにはまだまだ至らない、と言うかそこまでの火力はない。だから須崎は延々と苦痛を味わいつづけている。朝子の問いに答えるどころの騒ぎではない。「ぎゃあっ、熱いっ、嫌っ、ぎゃ、あっ、熱いぃっ。嫌あああっ、助けてっ、許してっ、ひいいいっ」
「ねえ私、お肉の焼ける匂いを嗅げてる、て聞いてるんだけどな。ねえ、どうなの、返事してよ?」朝子はライターの炎を手の甲の中心に持っていく。これでは逃げ場がない。須崎の手を一点集中で炎が炙る。「ぎゃああああっ、ぎゃぎゃがああああっ、ひいいいいいいっ!!」須崎の悲鳴がいっそう激しくなる。朝子の尻の下で須崎の体が激しく揺れる。「もう!おっへんじが、あっりませーん!」子供と遊ぶように、おどけながらも朝子は間断なく火責めで須崎を責め苛み続ける。朝子はこの火責めが心底気に入っていた。朝子は指先でライターの位置をキープするだけ。それだけで須崎が際限なく苦しんでくれる。責める朝子にとっては何ともお手軽な、全然疲れない拷問だが責められる須崎にとって、その苦しみは坊野たちに勝るとも劣らない。須崎の皮膚が焼け爛れ、所々ピンクの肉が現れそれも焼けていくところを朝子は特等席でじっくり観察できる。炎で炙られる須崎の全身の痙攣が尻を通して朝子の全身に伝わってくる。その苦悶を、自分は殆ど指先一本動かさずに楽しめるのだ。もともと些かものぐさの気がある朝子にとって、このお手軽な拷問はなんとも性に合うものだった。「もう!お返事してくれないのね!冷たいんだから!いいもん、じゃあ一人で楽しんじゃうから・・・バーベキューパーティーをね!」バーベキュー、そう、須崎は朝子を楽しませる人間バーベキューとなり、延々と焼かれ続けていた。
「グギャアアアアアアアアァァッ!!痛い、痛い痛い痛いぃぃっ!ヤベデェェッ!!」「あ、が、ぎゃあああぁっ。う、うぐぐ……ぎやあぁっ!うぎゃあああああああああああぁっ!!」「ぎゃああああっ、ぎゃっ。許してっ、嫌ぁっ、痛いっ、ぎゃああああああっ!!」「ぎゃあっ、熱いっ、嫌っ、ぎゃ、あっ、熱いぃっ。嫌あああっ、助けてっ、許してっ、ひいいいっ!!」拷問は佳境を呈していた。「アハハッ、アハハハハッ!」「ほらほらほら、どうしたの、もっと叫びなさい!」「どう、楽しい、最高だよね!」「エヘヘヘヘッ、こっちも焼いてあげよっと!」坊野たちの絶叫と礼子たちの笑い声が工場の全空間を満たしていた。人間の声に混じり、微かな音も鳴りつづけていた。ミリッ、ミリリリッ・・・ビキッ、ベシッ・・・ドズッ、バギッ・・・ジリッ、ジジジジッ・・・人間の皮膚が、肉が引き裂かれ、骨が砕かれ、炎に炙られる音が。
礼子たち四人は至福の時間を満喫していた。思う存分坊野たちを痛めつけ、苦しめていた。罪悪感など全く感じない。自分たちをレイプしようとした悪党に対して罪悪感や慈悲心などは全く感じなかった。プロの拷問官のように、礼子たちはより多くの苦痛を、より長時間与えることに全神経、全労力を集中していた。坊野たちにとってはまさに地獄だった。坊野たちとて喧嘩で負け、いいように殴られたりリンチを受けたこともある。常人よりは痛みに慣れているはずだ。だが礼子たちから与えられているような、本格的な拷問に近い痛みを味わったことはない。単なるリンチではない。拷問、プロが発揮する手練の技。常軌を逸した苦痛を長時間与えつづける技。慎治たちを苛めることによって得た経験、知識をフルに活用し、礼子たちはプロの拷問官に近い水準の技術を発揮していた。逃げ道などどこにもない。どう動こうと何をしようと、礼子たちが与える拷問の苦痛から逃れるすべはない。気絶という救いの女神すら、礼子たちの巧みな拷問テクニックに邪魔されて訪れてくれない。坊野たちは延々と、ひたすら愚直に苦痛を味わいつづけた。
「アッ!アヒッ!アヒーーッ!マ、ママーーーッッッ!ママーーーッッッ!!!」「ヒイッ痛い、痛い、いたいよーっ、誰か、誰かたすけてーーっっっ!」「ひぎーーーっもうしません、もうしません、もうしませんんんん!もうしませんからゆるしてーーーっっっ!!!」「ウギーーーッおがあぢゃーん、あづいよーっ、い、いやだ、やだやだ!あっあぢっ、あぢあぢいいいっ!あづいよおおおおおっ!!!」どんなに叫んでも何の救いも訪れない。礼子たちは拷問の手を全く休めない。ヒッヒイッ・・・な、なんでこんな目にあわなくゃいけないんだ、なんでこんな酷い拷問をされなくちゃいけないんだ・・・肉体も精神も崩壊の淵に近づいた時、坊野たち四人は漸く気づいた。救いの道に。拷問をやめてもらうたった一つの方法に。単純な事、拷問官に屈服し、問われるがままの答えを自白すること、それが拷問から逃れる唯一の方法だ。気が狂わんばかりの苦悶の果てに漸くそれに気づいた時、坊野たちの頭は最後の気力を振り絞るようにフル回転した。
な、なんだ、なんだ、なんなんだ。俺たちが聞かれていた尋問はなんだったんだ・・・そうだ、あれだ!四人は殆ど同時に気づくと一斉に絶叫した。「ひっ、や、やめて、しゃ、しゃべる、しゃべるからやめてくれえええええっ!」「た、頼む、や、やめて、少しでいいから、しゃべるあいだだけでもゆるしてえええっ!」「あ、あいつだ、あいつらにたのまれたんだーーっ!」「い、いやっ、しゃ、しゃべる、白状するからおねがい、火を、火をあっちへやってええっ、お願いだあああっ!」礼子たちは一瞬、視線を交わしただけで無言のまま拷問を続行する。だがもうこれしか希望がない坊野たちは必死で喚き立てた。「し、慎治、慎治たちだあああっ!」「た、頼まれただけなんだよ、あいつら、信次たちに頼まれただけなんだああっ!」「あ、あいつ、ほら、慎治、慎治だよおおおっ!」「し、熱い、信次、あのガキがわるいんだーーーっ!」
3
フウッ・・・礼子たちは拷問の手を漸く休め、視線を交わした。礼子の全身を興奮と何とも言えぬ満足感、達成感、俗な言葉でいえば快感が走り抜ける。性的な快感とは違う、精神的な充足をもたらす快感だった。やったわ、私、拷問に成功したのね。
さっきまであんなに反抗的だった坊野さんのこの態度、何?もうすっかり縮み上がっちゃって、私に反抗する気力など、根こそぎにしてやったみたいね。苦痛のみで相手を屈服させた、自分より体も大きく力もある相手を根本的に屈服させた、という快感に礼子は暫く酔いしれていた。横を見ると玲子も自分と同じく、何とも満足げな表情を浮かべている。「フフ、玲子、やっと屈服させたみたいね。」「そうね、どう、初めての拷問のご感想は。礼子も満足した?」「まあね、で、それはそうとして、今白状した依頼人、慎治たちとはね・・・」「そう?私は結構予想通りだったけどな。だってあれだけ苛めてやれば、流石に仕返しの一つや二つ、考えそうじゃない。ねえ朝子?」「うーん、そうねえ。信次たちならまあ、本命筋だけど・・・それにしても、連中にしては随分小ジャレタ仕返しを考えたものねえ・・・」ここまで言って三人は富美代を振り向いた。流石にブーツの動きは止めたが、富美代はまだ検見川の頬を刺し貫いたまま、ブーツを引き抜いていない。どこか遠慮しているかのような目で見ている礼子たち三人に頷きながら、富美代はゆっくりとヒールを検見川の頬から引き抜いた。
「ア、アワアアア・・・」苦しげにうめく検見川を冷たく見下ろしながら、富美代は新たな尋問をした。「・・・先輩、慎治たちに頼まれた、て言ったわね。でも先輩と慎治たちが友達だなんて話、聞いたことないわよ?どうしてこんなこと、引き受けたの?」だが検見川は未だ収まらぬ激痛に即答できなかった。そんなことを許す富美代ではない。一旦下ろしたブーツをすっと上げると、再び検見川の顔を踏み躙る。「どうなのよ!私の質問に答えられないの?さっさと答えないと・・もう一穴開けるわよ!?」もう一穴!検見川の口を開かせるには十分だった。「ヒッヒイッ!や、やめて、やめてくれーっ!は、話す、なんでも喋るからやめてくれーっっ!か、かね、金だよ、俺たちゃ、金で雇われただけなんだーっ!」クスリと傍で聞いていた玲子が笑った。「お金で雇われた、ねえ・・ねえタマナシ君、君もそうなの?」「あ、アウッそ、そう、そうなんだ、お、俺たちは金で頼まれただけなんだ。だから・・・もう、許して・・・」フウッ・・・礼子も小さく溜息をつきながら坊野の顔を軽く蹴りながら尋ねた。「フーン、お金で雇われたの。ところで一体、幾らで雇われたの?」
「じゅ、十万、一人十万円だ・・・」「たったそれだけ?たった十万円で雇われただけで、こんな手の込んだセッティングして私たちのこと、襲ったの!たった十万円で!ご苦労様・・・それでこうやって返り討ちにされて拷問にまで掛けられて・・・随分と高くついたわね?」「あ、ああ・・・た、頼む、もう許して、ぜ、全部話しただろ?いや、か、金も、貰った金だって要らないから、いや、そっくりそのままやるから、頼む、もう許して・・・」「バーカ、私たち別にお金なんか要らないわよ!」笑いながら礼子は軽く坊野の顔面を一蹴りした。
ア、アワワ・・バ、バレタ、バレテしまった・・れ、玲子さんたちに全てバレてしまった・・信次たちは恐怖の余り失禁しそうだった。恐怖、苦痛、絶望・・ありとあらゆる負の感情が二人を包み込む。破滅、僕たち、もう終わりだ・・顔面蒼白で口をパクパクさせる信次たちの目にはもう、何も映っていない。「あーあ、バレちゃった。どうするの信次?」ツンツンと傍らの信次を肘で突っつきながら里美が呆れたような顔をした。「全く、あんたも思い切ったことしたものね・・ああいう連中雇って玲子たちを襲わせるとは、ね・・でもどうするつもりなの。一体?」「うーん、まあ、いくら無事だったとは言っても、結果オーライじゃすまないよ、これ。玲子たちを本気で怒らせちゃったかもね。ねえ、二人ともどうする気?ちょっとこれ、高くつくんじゃない?もしかしたら・・本当に殺されるんじゃない?」殺される!真弓がどこか楽しそうに言い放った恐ろしい言葉に、慎治は反射的に泣き出してしまった。
「そ、そんな・・こ、殺されるでなんて・・ね、ねえ、う、うそでしょ、うそだよね、うそだと言ってよーーっっ!」信次も思わず里美のブーツにすがり付いていた。
「お、おねがい・・た、助けて・・死にたくない・・」
里美と真弓は余りに身勝手な慎治たちの台詞に心底呆れたように、両手を軽く上げた。
「ねえ信次、何か勘違いしてない?」邪険に信次を振り払うと里美が冷たく宣告した。「私たち、玲子の友達だよ。第一、ギャング雇ってクラスメート襲わせようだなんて、あんたたちマジで人間腐ってない?なんで私たちが信次の味方なんかしなくちゃいけないのよ!拷問されようが殺されようが、自業自得でしょ!」大きく頷きながら真弓も続けた。「まったく・・はっきり言って私たち、ここで慎治たちのこと、速攻リンチしてやりたい位なんだからね、あんまり甘ったれたこと、言わないでよね!・・・最も」クスクスっと真弓は楽しそうに笑った。「慎治たちのこと、リンチしたいのは私たちだけじゃないかもね。あそこで寝てるSNOW CRACK、連中も慎治たちのこと、恨んでるんじゃない?なにせ、慎治たちのせいであんな拷問受ける羽目になったんだからさ。」そ、そんな!慎治たちには最悪の悪夢だ。ぼ、坊野さんたちにまで狙われるだなんて、そんな!その時、ふと下をみた里美が少し興奮した声をあげた。「うん?慎治、ちょっとこっち来てごらんよ。下でまた楽しいイベント、再開されるみたいよ。大丈夫、いいからおいでよ。ひょっとしたら慎治たちにとっても、FAVORな展開かもよ?」FAVORな展開?地獄に仏を求めるように、必死で救いを求めながら慎治たちはフロアを見てみた。そこで展開されていたのは、確かにある意味意外、慎治たちの想像を超えた光景だった。
「さーて、と。まあ一応自白もさせたことだし、取り敢えずは警察呼んで引き渡して、今日のところは終わりかしらね。」如何にも疲れたように腕をストレッチングしながら礼子が周りを見回した。富美代も朝子もそうね、という表情をしている。警察に引き渡される、普段だったら絶対マズイ、最悪の展開だが坊野たちにとって今、警察に引き渡される、という礼子の言葉はまさに、地獄に仏だった。け、警察、だったら病院に連れてってもらえるな。なんでもいい。とにかく病院にさえ連れてってもらえれば・・・だがそんな甘い希望を玲子が粉々に打ち砕いた。
「ちょっと待って礼子、まだダメよ!まだやることが残っているわ。」玲子の凛とした、この場の弛緩した雰囲気にそぐわない妙に強いトーンの声が響いた。「やること?未だ拷問続行するの?別にいいけど、一応自白させちゃったし、これ以上やっても単なるリンチじゃない?それもまあ楽しいけど、今日のところはもうご馳走様、て感じするけどな。」「ううん、私も拷問はもうするつもりないよ。だけどね、ここからが最後のツメ、ここをミスっちゃ、折角ここまで上手くやったのに、全部台無しになっちゃうよ。」「ツメ?うーん、分からないな。何を詰めるの?」ああ、礼子も分からないんだ。玲子にとっては少し意外だった。だけど考えてみれば、礼子はこういう方面、やったことないものね。じゃあ仕方ないか。「礼子、フミちゃんも朝子もよく聞いて。そもそも私たち、なんでこの人たちをやっつけて、更には拷問までしたの?お楽しみのため?ううん、確かに思う存分楽しんだけど、それはサブの目的よね。メインの目的は私たちの身の安全を守ることよ。普通の相手だったら、これでお終いでいいわ。もう十二分、お釣りがくる程よ。もう二度と私たちを襲おう、なんて思う訳ないわ。だけどね、こういった最悪のギャングたちはしつこさ命なのよ。これだけ痛めつけても、傷が治ったらリターンマッチでまた狙われかねないわ。そんなの、ご免よ。だからね。」玲子は一呼吸入れた。いつものように痛めつけるのを楽しむための、シチュエーション作りを楽しむ表情ではない、完全に100%真顔だ。「やるからには情け無用、やれる時に徹底的に、相手が再起不能になるまでやらなくちゃダメなのよ!」「確かに玲子の言うとおりだけど・・・でも、具体的にどうやるの?さっきあれだけ拷問したし、もっと痛い目にあわせる、て言ったってさっき以上の痛い目、て中々難しいと思うんだけどな?」小首を傾げながら朝子が言うと、礼子も富美代も確かに、という表情で頷いた。そうよね、朝子の言うとおり、さっき以上に痛い目なんて、一体どうやるの?「ううん、違うのよ、私は別にこれ以上痛めつけよう、て言ってるんじゃないの。原因を取り除きたいのよ。考えてみてよ、この人たちはなんで私たちを襲ったの?お金のため?確かにそれもあるけど、メインはそうじゃないわよね。私たちをレイプするのが目的よね。だったら」「そうか・・・なんか玲子の考えてること、分かったような気がする。」今まで黙っていた富美代が口を開いた。声の調子が妙に冷たい。「要は先輩たちが二度とレイプなんてしたくなくなる、ううん、改心してしたくなくなる、なんてことは絶対にないから、生理的に、と言うか物理的に、と言うか・・・兎に角二度とレイプなんかできない体にしてやろう、て考えてるんじゃないの?」「そう。フミちゃん、よく分かったわね。その通りよ。」礼子と朝子も薄々分かってきた。「そのとおり。この人たちのあそこ、ううん、タマタマね、そこを潰してあげるのよ。そうすればもう二度とレイプなんかできなくなる。もう二度と私たちを狙う理由もなくなるわ。」「ええっ!タマタマを潰すって、玲子、あなたまさか、そんなことまでしてたの!?」流石に驚いた礼子が思わず大声を張り上げた。「まっさかーっ!やだ、やめてよ礼子ったら!いくら何でも、そんなことするわけないじゃん!いくら私でもそこまでしたことなんかないわよ!」半ば笑いながら否定した玲子だが、直ぐ真顔に戻った。「マジで私もタマタマ潰したことなんかないわよ。だけど今は話が別。この人たちだけはキッチリ潰しといた方がいいわ。ここで手加減抜き、完全に再起不能にしとかないと、後で後悔しそうな気がするの。」
「ヒッ!ヒイイイイイッ!!や、やめて、それだけは!」「う、うそだ、うそだーっ!た、頼む、お願い、潰さないでくれえええっ!」「そ、そんな、やめてよして許してええっ!」「イ、イヤ、イャ、イヤアアアッ!!!」金玉を潰される!いくら痛いと言っても、今までの拷問の傷なら時間さえたてば何とか治る。検見川を除いては。
だが睾丸を潰されたらそうはいかない。一生治らないし、大体レイプを生き甲斐にしているような彼らにとって、それは半分殺されたも同然だ。坊野たちは必死で悲鳴を張り上げ哀願し許しを乞うた。哀願されることにすっかり慣れきっている玲子たちは坊野たちの哀願など殆ど気にもとめないが、朝子が少し心配そうに尋ねた。「えっ・・タマタマって、おちんちんの・・あのタマタマでしょ?ねえ玲子、そんなとこ潰して大丈夫?マジで死んだりしないでしょうね?半殺し程度ならいいけどさ、本当に死んだら流石にまずくない?」「うん確かに朝子の言う通りね。流石に死んだらまずいわよ。」富美代も頷く。確かに死んだらまずい、それには玲子も異論はない。「うん、確かにそうよね。で、考えてみたんだけど、タマタマ潰した時に死ぬのって、余りの痛さに自分で舌を噛み切っちゃうのが大半なんだって。だからさ、潰す前に顎を外すか歯をへし折っといてあげれば多分、大丈夫と思うわ。」ア、アワワ・・・こ、こいつら本気だ、本気で潰す気だ・・・坊野たちは殆ど小便を漏らしそうな位、怯えていた。だが追い討ちをかけるように、礼子が更に刑の追加を宣言した。
「ねえ玲子、宦官って知ってる?」「宦官?中国の?知ってるけど、それがどうかしたの?」「うん、宦官もあそこを切り取られたわけだけどさ、金や権力に対する欲望とか執念とか、方向性こそ変わってもそっちの方は消えないって言うか、却ってひどくなったって言うじゃない?だからさ、坊野さんたちもタマタマ潰しただけじゃ足りないかもしれないわね。性欲はなくなってもさ、私たちへの仕返しに一生を捧げます、なんてやられたらかなわないわ。だから、それこそ物理的に、腕力の面でも再起不能にしといた方がよくない?」「腕力も再起不能って、どうやるの?」「うん、折角肩と股関節外してあって仕事しやすいんだからさ、ついでに腱を全部捻じ切っといてあげようよ。そうすればもう、完全に再起不能よ。文字通り、一生女の子以下の力しか出せなくなるわ。」け、腱を捻じ切る!金玉を潰すだけじゃなく腱を捻じ切る!
「そ、そんな・・・や、やめてくれえええっ、ほ、本当に死んじまうよおおおっ!」
「あら大丈夫よ坊野さん、腱を捻じ切った程度で死ぬわけないじゃない?あ、そうか、痛さでショック死すること心配してるのかな?だったら大丈夫、心配いらないわよ。腱を捻じ切るのは最後、タマタマを潰してからにしてあげるから。どうせタマタマ潰したら、痛くて失神しちゃうか激痛でもう何も感じられなくなるわ。その後だったら、今更腱を捻じ切られた所でもう痛いなんて感じられないと思うから心配いらないわよ。」如何にも優しげに微笑みながら、礼子は平然と恐ろしい刑罰を宣告する。
4
「さあ、話はついたわね!と言うことでチャッチャッと逝こうか!」ヒッヒイッ!な、なにも話はついてないよおおっ!坊野たちの悲鳴、哀願など全く無視して四人の美少女は新たな刑罰の執行を開始した。「で、まず誰からいく?」「うーん、まあやっぱり、最初は言い出しっぺの私かな?」と玲子が言った瞬間、富美代の凛とした声が響いた。「待って、玲子!」三人の拷問官と四人の受刑者の視線が富美代に集中する。「今日のこのパーティー、そもそもの発端は私、ううん、私と先輩の二人よね。だったら・・・やっぱり締めも私と先輩からやらせて。」富美代は言いながら検見川の顔を再びブーツで踏み躙る。「そうよね、先輩。やっぱり先輩と私が一番最初にやるべきだと思わない?そうでしょ先輩、ねえどうなのよ!」幾ら踏み躙られても、検見川がハイそうです、と言えるわけがない。「や、やだ、頼む、やめ、やめてくれえええっ!!!やめてよしてたすけてえええっ!」「先輩、別にそんなに嫌がらなくてもいいジャン。どうせ先輩たち、みんな潰されるんだから。順番の違いだけ。それもほんのちょっとの時間の差だけよ。嫌なことは早く済ませた方がまだいいでしょ、ていう私のせめてもの優しさも分からないの?」富美代はブーツにグッと力を込める。グエッ・・・だがここで認めるわけにはいかない。理屈ではない。本能。金玉を潰される、という最悪の事態を少しでも、一秒でもいいから後に引き延ばしたい、そこに何か希望があるわけではない。だが引き延ばさずにはいられない。それは生存本能そのものだった。「や、いや・・・頼むよ、やめて、やめてぐれえええっっっ!」最早恥も外聞も何もない。検見川は涙で顔中グシャグシャにしながら大泣きしていた。「やだよおお、お願いだよおおお、潰さないで、おねがい・・・」
だが検見川を見下ろす富美代の端正な顔には何の変化もない。憐憫の情など、微塵もない。僅かに呆れた、といった感じで唇の端を歪めた富美代はブーツの爪先で検見川の顎をグイッとこじ上げる。「・・・先輩、そんなに潰されるのはいや?」「あ、ああ、お願い、なんでもするから潰すのだけは許して・・・」「フーン、じゃあ一回だけ、最期に一回だけチャンスをあげる。後の三人、坊野さん、奈良村さん、須崎さんの誰かが先輩の代わりになってくれるなら、私はその人のこと、潰すわ。先輩のことは許してあげる。」「ヒッそ、そんな無茶な・・・」出来るわけがない。藁にも縋りたいのは後の三人も同じだ。一分一秒でも長く生き延びたい。富美代の一言を聞いた坊野たち三人は殆ど反射的に顔を背けていた。「あ、ああ・・ぼ、坊野、た、頼む、お、おまえプレジだろ、いい思いもたくさんしてきたじゃねえか!沢山女も回してやったろ?た、頼む、助けてくれよ!な、奈良!お前にも女世話してやったろ?おい、なんで何もいわねえんだよ!おい、こっち向いてくれよ!すざきいいい・・・お、お前なら助けてくれるよな、代わってくれるよな・・・お前をチームに引っ張ったのは俺じゃねえか!な、頼む、今、今こそその借り返してくれよ!なあ、頼む、頼むよ・・・な、なんでだよおおお・・・なんでみんな何も言ってくれないんだよおおお・・・た、頼む、頼むよ・・・潰されたくねえよおおお・・・」当然の如く、三人とも何も言わない。ふ、ふざけるな!何で俺がお前の身代わりにならなくちゃいけねえんだ!三人ともそう叫びたかったが、声に出すことはできなかった。何か言えば富美代たちがどんな反応を示すか分かったものではない。触らぬ神に祟りなし、とばかりに坊野たち三人はひたすらだんまりを決め込んだ。
「・・・先輩、誰も代わってくれないみたいね。じゃあ、処刑始めようか。」「ヒ、ヒイイイイッ!た、頼む、頼むお願い待って、待ってくれえええっ!」「先輩、もう悪あがきやめたら?誰も代わってくれないみたいよ?もう諦めた方がいいんじゃない?後10秒、後10秒で誰も変わってくれなかったら・・・タイムアップね。」富美代は静かに言い放つ。「ヒ、ヒイッ!イ、イヤ、10秒だなんて・・・」「・・・1098・・・」「い、いや、待ってくれえええっ!」だが富美代は無表情でカウントダウンを続ける。「・・・765・・・」「い、いや、坊野、奈良、すざきいいいいい!頼むよ、たのむよおおお!!!」「・・・432・・・」「あ、ああああ・・・み、見捨てないでくれえええええ・・・」「・・・10。・・・先輩、タイムアップよ。」再び検見川の顔をブーツで踏み躙りながら刑の確定を宣告する富美代の声は、氷のように冷たかった。先程までの怒りはもうない。富美代を支配している感情はどちらかと言えば悲しみに近かった。自分が憧れていた先輩が、自分をレイプしようと嵌めたことに対する後悔ではなく、金玉を潰されるという恐怖だけでこんなにみっともなく泣き喚いている。先輩、やっぱり私のことなんかどうでもいいのね。私のためには泣いてくれないのに、自分のタマを潰されるとなったらこんなに泣くんだ・・・先輩、先輩はどこまで逝っても自分の事しか考えてくれないんだね・・・その悲しみはより残酷な刑罰の動機へと変化していった。ふと思いついたように富美代は振り向くと、玲子たちに声をかけた。
「ねえ玲子、私、気が変わったわ。」「何、どうしたのよ急に?」「うん、さっき頬にブーツでピアスしてあげたのは・・・拷問ね。そしてタマタマを潰したり腕、脚を破壊するのは将来に対する保険よね。だったら・・・一つ足りないものがあるわ。」
「足りないもの?何よ一体?」「うん、足りないものはね・・・罰よ。考えても見てよ、先輩たちは私たちをレイプして人生滅茶苦茶にしようとしたのよ?だったら、罪を憎んで人を憎まず、とは言うけど何の罰も与えないで許すわけにはいかないわ。これは先輩たち自身のためでもあるのよ。罪を犯せば必ず罰を与えられる。そのことをしっかり教えこんであげなくちゃ。玲子たちも分かるでしょう?先輩たちは人間じゃない、野獣同然の・・・そう、けだものよ。けだものに教え込むには言葉じゃ駄目、体に教え込まなくちゃ。二度と忘れられないように、厳しい、一生忘れられない位痛い罰を与えて体に教えこんでやらなくちゃ、本能に刻み込まれる程の罰を与えて懲らしめてやらなくちゃ駄目なのよ!」
礼子たち三人は思わず顔を見合わせた。フミちゃん、完全に目が逝っちゃってる。どうする?少し間を置いて玲子が口を開いた。「うーん・・・フミちゃん、気持ちは分かるけどさ、罰はまあ・・・タマタマ潰すだけじゃ足りないかな?それ、メチャメチャ痛いと思うよ。」「駄目よ絶対!絶対駄目!潰すだけじゃなくて、ちゃんと罰も与えないと駄目よ!」色白な、端正な富美代の顔で眼だけが爛々と青白い炎を発するかのように燃えている。それはある種、凄絶と言いたくなる程の美しさだった。フウッ小さく礼子が溜息をついた。「玲子、駄目よ、フミちゃんのこの目、見てごらんよ。フミちゃん、この目の時は止まらないよ・・・いいわ、確かにフミちゃんの言うことにも一理あるわ。罰を与えましょう・・・でもね、あれだけハードに拷問した後よ、あの拷問に匹敵する、ううん、それ以上の苦痛を与える刑罰って、何か考えつく?考えつくんだったらいいけど、ないんだったら玲子の言うとおり、タマタマ潰すので十分、刑罰になるんじゃないかしら?」虚を突かれたように富美代も、困惑したような表情を見せた。だがそれはほんの一瞬だった。どうすれば先輩のことを痛めつけられるかしら、さっきの拷問以上の苦痛を与えるにはどうしたらいいかしら・・・必死で考えながら富美代は自分のブーツの下でうめく検見川を見下ろした。頬はほぼブーツに覆われ、僅かに鼻だけがブーツの下から覗いている。鼻、鼻・・・鼻!富美代の脳裏に、稲妻のようにあるアイデアが閃いた。
「・・・思いついたわ、先輩への刑罰。」「何、どういう刑罰なの?」「聞いたことない?鼻鉛筆、とか鼻割箸って。ほら、両鼻に鉛筆とか割箸突っ込む、ていうリンチよ。昔の朝鮮高校のリンチらしいわね、たまにヤンキー系の雑誌なんかの伝説コーナーで見るけどさ、実際に見た人は多分殆どいない、まあ都市伝説の一種みたいなやつよ・・・ウフフフフ、ねえ先輩、伝説を現実に復活させてあげるわ。イマ風に進化させてね。フフ、ウフフフフ、もう分かったでしょ?鉛筆や割箸じゃなくて、もっともっと痛い、ずっとずっと硬くてよく効くものを突っ込んであげるわ。そう、突っ込むものは勿論・・・私のブーツのピンヒールよ!先輩、先輩への刑を宣告するわ。鼻ブーツの刑、受けてもらうわよ!」
鼻ブーツの刑!検見川も勿論、鼻鉛筆位は知っている。実際に見たことはないし、勿論やったこともない。だが半ば伝説と化した究極のリンチの一つ、恐怖の対象としてヤンキー系の先輩から語り継がれ、存在だけは知っていた。それを我が身で味合わされる。しかもブーツで。富美代のブーツで。両頬に大穴を開けられ、嫌と言うほど苛められ、責め苛まれ、その威力に震え上がらされた富美代のブーツで。そのピンヒールで頬より遥かに弱く、敏感な鼻を、鼻の粘膜を蹂躙され、踏み躙られるのだ。どんな痛みかは全く分からない、だがあれほど残忍冷酷に自分を責め嬲った富美代だ、今度も手加減など一切なし、遠慮会釈なく自分の鼻を責めることは容易に想像できる。ど、どんなに痛いのか・・・想像も出来ないほど痛いことだけは間違いなかった。
「さあみんな、手伝って!まずは場所を変えるわ。先輩をあそこに引き摺ってくわよ!」富美代が指差した先は工場のやや奥の方、階段状に一段低くなっている資材置場だった。「や、嫌だ、や、やめてくれえええええっ!ぎゃぁっ、い、いでえ、いでえええええっ!!!」関節を外された両腕を四人がかりで引き摺られ激痛に絶叫する検見川を委細かまわず、四人は検見川をその段差まで引き摺っていった。「そう、そこ、もうちょっと前、首だけ出るようにして。」富美代は仰向けに転がっている検見川の首だけが段差からはみ出て宙に浮いた状態にセットすると、検見川の顔を跨いで仁王立ちに見下ろした。「さあ先輩、もうすぐ準備完了よ。みんな、ちゃんと押さえてね。」「フフフ、分かったわフミちゃん、こうすればいいのね。さ、検見川さん、上向いてもらえる?」礼子が検見川の髪と顎を掴むと、グイッと強引に後ろにそらせた。「丁度いい高さじゃない、ちょうど検見川さんの頭の天辺が床についてるわよ。ウフフフフ、ここ、まさに鼻ブーツ専用の処刑台、て感じね。」礼子の顔に期待と興奮の彩が浮かんだ。「じゃ、私たちは両手を押さえてあげる。」玲子と朝子が両腕に乗り、検見川の動きを封じると富美代はゆっくりと検見川の胸の上に腰を下ろした。
「さあ先輩、入れるわよ・・・」ツッと右足を上げると富美代はゆっくりとヒールを検見川の鼻へと近づけていく。「や、いや、いやだあああっ、や、やめて、やめてそれだけは、ひっひいいいいいいいっっっ!!!」必死で首を振り何とか逃れようとする検見川の首を礼子がグッと腕に力をこめて押さえつける。「観念するのね、もうこの体勢じゃ絶対逃げられないわよ。下手に動くとヒールが変に刺さって却って危ないわよ。」「ひ、そ、そんな・・・ブギャッ!」恐怖の余り思わず凍りついたように動きを止めた検見川の左の鼻腔に富美代はブーツのヒールを侵入させた。「フンッ、結構きついのね。ギリギリじゃない、だけどまあいいわ。直ぐに拡張してあげるからね。」冷たく笑いながら富美代は左のヒールも鼻に侵入させる。いくら細いピンヒールと言っても女の子一人の体重を支えるのだ、それなりの太さはある。少なくとも直径1センチ程度しかない人間の鼻腔に入れるには、無理矢理こじ入れなければいけない。富美代はゆっくりと両足を左右に回転させ、ヒールがこれからの責めで抜けないように鼻にしっかりと侵入させた。
「さあ準備OK!どう先輩、鼻にブーツを突っ込まれた気分は?無様な姿ね、まるで鼻からブーツが生えてるみたいよ!?」「う、うびっひぎっややべで・・・」鼻に突っ込まれたヒールの圧力を少しでも緩和しようと検見川は必死で首をそらし、ほぼ垂直にまで曲げていた。余りに近すぎ、焦点距離が合わないためぼやけた視界に映るのは、富美代のブーツの銀色のヒールと黒いソールだけだった。視界の殆ど全てが富美代のブーツに塗りつぶされている。「ウフフフフッ、先輩、いい歌思い出したわ。ほら嘉門達夫のあの歌よ、あのフレーズ、チャラリー、鼻から牛乳!て知ってるでしょ?先輩にはこうかしら、チャラリー、鼻からブーツ!てね、どう、ぴったりでしょ、ねえ先輩、ウフ、ウフフ、アハハハハッ!」狂ったように笑いながら富美代は礼子の方を向いた。「ありがとう礼子、もうしっかり入れたから抜けないわ。もう首はいいから体の方、押さえてくれない?」「OK、じゃあ私が腰に乗ってしっかり押さえてあげるね!」腕から肩に玲子と朝子、そして腰に礼子が乗り検見川は完全に、身動き一つできない体勢だ。富美代が検見川の胸の上に腰を下ろしたままだから、未だ何とかブーツは刺さらないでいる。だがもう限界、あと僅か、あとほんの数センチ奥にブーツを押し込まれたら、間違いなく検見川の鼻は富美代のブーツにズタズタに破壊される。自分の足下でうめく検見川を見下ろす富美代の美貌が残酷な笑みに彩られた。「さあ先輩・・・鼻ブーツの刑、執行開始よ!」
「玲子、朝子、肩借りるわよ、それっ!」掛け声と共に富美代は玲子たちの肩に手を置くと、両手の力だけジャンプするように勢いよく立ち上がり、一瞬の反動をつけた次の瞬間、両手を玲子たちの方から離して全体重をヒールにかけ、検見川の鼻腔奥深くへと思いっきり踏み込んだ。「ガバアアアアッ!ビギャアアアアアアアッ!キ゜!ヒイイイイ!イイイッッッ!!!!!」獣の断末魔のような悲鳴が轟き、同時に少しでも富美代のブーツから逃れようとするかのように、検見川は全力で体を、首を仰け反らせた。検見川の腹の上で礼子の体が10センチほどバウンドするが、50キロはある礼子の体を腕も足も使わずに腹筋だけで跳ね飛ばすのは流石に無理だ。「アラッ!検見川さん、頑張るじゃない!だけど私を跳ね飛ばすにはその程度じゃ無理ね!」
両手も必死で動かそうとしたがこちらは肩を外されているからろくに力が入らず、僅かに自由な手首から先をバタバタさせるだけだ。そして検見川の必死の抵抗をあざ笑うかのように富美代は冷酷に鼻ブーツの刑を執行し続ける。「アハ、アハハ、アハハハハハハッ!ほら先輩、どう、どうなのよ!痛い!?苦しい!?でもまだまだよ、もっともっと痛めつけてあげる!これはケダモノへの、先輩への刑罰なんだから!もっともっと泣き喚いてよ!もがき苦しんでよ!ほら!ほら!ほらほらほら!!!」
富美代は高らかに笑いながらも巧みにバランスをコントロールし、転ばないように、鼻からヒールが抜けないように細心の注意を払いながら検見川を責め苛み続けた。
「ほら先輩、先輩のために歌ってあげるわよ!鼻からブーツ、鼻からブーツ、鼻からーー、ブーーーー、ツ!!!」富美代は大声で歌いながら足踏みをするかのように交互に細かくステップを踏みつつ左右のヒールを上下に、かつ腰のツイストも利かせて微妙に鼻の中の責めるポイントを変えながら激しく動かし、検見川の鼻の中をズタズタにしていく。
「ギイイイィッ!ヒギイイィッ!ヒギャアアアアァァッ!!イギャッ!ギヒャアアアアアァァッ!!!」この鼻ブーツの刑に比べれば、鼻鉛筆など子供の悪戯程度のものだ。鼻鉛筆はいくら痛くても一瞬、何度も何度も連続でやられることは殆どない。だが鼻ブーツの刑は違う。富美代は上から責めているのだ。まず力の入り具合が全然違う。鼻鉛筆は下から突き上げる手の力、それも相手も動くし細い鉛筆に力を伝えるため、持てる力のほんの一部しか使えない。だが富美代は全力で、全体重を使って検見川を責められる。しかも基本的には下段蹴り、と言うより足踏み運動に近い動きだから責める富美代はバランスにさえ気をつければ幾らでも責められる。富美代のヒールは繰り返し繰り返しいつまでも検見川の鼻腔を抉り続けた。検見川の鼻は突き抜けて穴を開けられるのだけはなんとか免れていたが、内部はもう滅茶苦茶だった。切れる、鼻血が出る、などという生易しいものではない。情け容赦なく抉り、踏み躙り続ける富美代のブーツは検見川の鼻腔の粘膜を剥ぎ取り、こそげ落し、鼻の肉自体を神経ごと抉り取っていた。
痛い、やめて、許して等という言葉を発する余裕などどこにもない。鼻自体の痛みだけではない、鼻腔の奥、眼球の裏にまでヒールの圧力は及んでいる。鼻の奥、目・・・更には地面に擦り付けられている頭蓋骨、殆ど90度直角に曲げられている首・・・頭部の全てが強烈な痛み、他の全ての感覚を吹き飛ばす程の激痛に塗り潰されている。だが富美代の責めは単純に痛い、だけではない。更にブラスアルファがあった。
「ガアッ!ギギャアアアアアッ!!!・・・」「おぶうぅっ。うぶっ、げぶっ、ごぼぼっえぶうぅっ、おぶっ、うぶぶっ、ごぼぉっ、おごっ、ごあああぁっ・・・」突然、間断なく悲鳴を上げ続けていた検見川が苦しげに咳き込み、全身を苦しげにビクビクと激しく痙攣させ始めた。犯人は血、検見川自身の血だった。鼻血、等という桁ではない。毛細血管が集中している鼻腔の中をグチャグチャに破壊され、検見川の鼻腔は大量の流血に満たされていた。後から後から流れ出る出血のかなりの部分は、富美代のヒールに塞がれた狭い空間から外へと溢れ出て検見川の頬を真っ赤に彩っている。だが鼻の中は血で満杯の状態だ。その血の一部が苦しげに絶叫する検見川が思わず大きく息を吸ってしまった拍子に鼻から逆流し、肺へと入り込んだのだ。検見川の意識に血の鉄臭い味と生臭い匂いが広がる。苦しげに思わず咳き込むがその拍子にまた血を飲み込んでしまった。「がっ、ふっ、あ・・・…あぐが……おごぉっ・・・」
あまりの苦しさに検見川は全身を必死でよじり、更に深く富美代のブーツに鼻の奥深くを抉られる。痛さと苦しさの二重奏、検見川は視界が真っ赤になるのを感じていた。富美代のブーツ、頬から鼻から口から溢れ出る自分の鮮血、そして余りに全身に力を入れすぎて眼球内の毛細血管も切れてしまい、目からは遂に血の涙を流していた。
検見川が咳き込む度に肺に逆流した血と、鼻の奥から口に流れ込んだ血が血泡のように、あるいは飛沫状になって飛び散る。富美代のブーツにより頬に開けられた大穴からも、その傷口自体の出血に加え口中に溢れた血の一部が垂れ流しになっている。目からは血の涙を流し、勿論鼻自体からも大量に出血している。検見川の顔面は大量の鮮血に一面真っ赤に染まっている。そして検見川を責め苛む富美代のブーツも真っ赤に彩られていた。富美代の鮮やかな赤いブーツに同じく赤い、だが明らかに濃淡が違う赤が重なっていく。富美代は満足そうにもがき苦しむ検見川の顔を見下ろした。銀色のメタルピンヒールは検見川の鼻に埋め込まれて見えない。自分の膝から下を覆うブーツの赤と血まみれになった検見川の顔の赤、そして飛び散った血で床一面も真っ赤だ。フフフ、今日の私のファッション、赤で統一してきたけどこれが仕上げね。服だけじゃなくて私の足から先輩の顔、床まで全部真っ赤で統一ね。先輩、悪党の先輩にしちゃ結構、私のこと楽しませてくれるじゃない!これが私への償い?ダメ、まだまだ足りないわ、こんなのほんの手付よ!富美代は漸く一時の興奮は収まりかけていたが、逆に怒りの方は却って激しく燃え上がっていた。まだまだ許してあげないわよ、ほらもっと私のブーツで苦しむのよ!もっともっと、ずっとずっと、一杯苦しむのよ!
富美代は何度も何度もヒールを検見川の鼻腔に思いっきり食い込ませた。グニュッともズリュッともつかぬ、何か柔らかだが丈夫な芯を感じさせる感触、その感触がヒールを伝い富美代の脊椎を駆け上がる。何なのかしら、この感触は。慎治を踏みつけた時の肉を、生身の肉体を踏みつけた時の感触と似ているけど、どこか違うわね。何かこう・・・壊している、削っている、ていう感じかな?うん・・・ヒールが肉をこそぎ落とす感触ね、きっと。この感触、何だか気持ちいいわね。癖になりそうよ。検見川の肉体、それも極めて敏感な、神経の集中している部分を破壊している実感をブーツ越しに感じながら富美代はさらに責め続けた。自分がブーツに力を込める度に、足元で検見川が何種類もの痛みと苦しさに喘ぐ。検見川が流す大量の血がブーツを突き抜け、自分の足全体を浸しているような感覚すらあった。その生温かい血の感覚は富美代にとって嫌悪感ではなく、快感に結びついていた。フフ、ウフフフフッ、アハハハハッ!!!先輩、もう絶対に逃げられないわよ。私が許してあげない限り、先輩はいつまででもこうやって苦しみ続けるのよ。痛い?苦しい?早く気絶したいでしょう?でもダメよ、これだけ痛ければ、簡単には気絶すらできない筈よ、そんな簡単に許してなんかあげないわよ!その通りだった。余りの痛さ、苦しさに検見川は何度も意識を失いかけていたが、そのたびに激痛に意識を叩き起こされ、気絶すらできないでいた。すっと富美代が左のヒールを検見川の鼻から引き抜いた。「ア、アブッ・・・ブバアアッッッ!!!」検見川の右の鼻腔から噴水のように血が噴き出る。「フフフ先輩、まさかもう許して貰える、なんて甘いこと考えてないわよね?まだまだ刑の執行は終わってないわよ。ウフフ、ウフフフフフ、そうよ、片方を抜いてあげたのはこうやって、私がしっかり立てるようにするため。こうすればもっともっと力を込めて先輩を踏み躙ってあげられるからよ!」言うなり富美代は全体重をかけ、全力を込めて右のヒールを更に深く、もっと奥へと蹴り込んだ。「ギ、イギャアアアアアッ!!!ヒッヒギイイイイイッッッ!!!」富美代は自分のヒールが今までよりも更に奥へと侵入するのを確かに感じた。ほんの1-2センチかもしれない。だがその1-2センチの威力は絶大だった。何かコリッとしたわ、今、間違いなく何か踏み潰してあげたわね。ウフフ、きっとこれ、先輩の鼻骨よ。折れたわね、じゃあそこをもっともっと痛めつけてあげる、折れたところをグチャグチャにしてあげる!ほら、ほら、ほらほらほら!「ギッ!ヒアッ!ビギイャアアアアアッ!!!」富美代は巧みにヒールを操り反動をつけながら何度も何度も思いっきり踏み込む、いや踏み込むなどという穏やかな動作ではない、蹴りを、しかも足首の捻りを十分に効かせ全体重をヒールに一点集中させた蹴りを連続して検見川の鼻に叩き込む。唯でさえ破壊力十分なその蹴りだ、弱い鼻の粘膜に対しては破滅的な威力を発揮していた。「アハッアハハハハハッ!どう先輩、最高に痛いでしょ!先輩の鼻、ズタズタにしてあげる!鼻の中の肉も軟骨も神経も、全部削ぎ落としてあげるわよ!これだけメチャメチャにすれば、もう再起不能じゃないの!?嗅覚神経も何もかも全部まとめてバラバラに引き千切ってあげるわよ!もう一生匂いを嗅ぐのは無理なんじゃない?そしたら先輩、一生片輪ね!どんないい匂いも嗅げなくなるわよ!絶対にそうなってね、先輩にはスカーフェイスにしてあげるだけじゃ足りないもの!こうやって嗅覚も一生失って、一生不幸な人生を過ごすようにしてあげるからね!」ゴボッゴボゴボッと際限なく血を噴出しつづける検見川のことを、富美代はいつまでもいつまでも責め続けた。左の鼻腔を完全に破壊し尽くした後、今度は責め足を左に変え、検見川の右の鼻腔も完全に破壊し尽くした。漸く鼻ブーツの刑の執行が終了したとき、検見川は大量の出血と余りに長く続いた苦痛に身動きひとつできず、虫けらのようにピクピクと痙攣していた。もはや痛さの余り声すら出ない。
5
富美代は断末魔のように痙攣し続ける検見川を満足げに見下ろしていたが、やがて玲子たちの方を向き、小さく頷くと横たわった検見川の足を引き摺り、工場の中央へと連れ戻した。ゴリッ、富美代は血塗れのブーツで、同じく血塗れの検見川の顔を踏み躙った。「フフフフフ、先輩、鼻ブーツの刑の味はどうだった?少しは反省したかしら?尤も先輩みたいなけだものに反省、なんて言葉はないでしょうけどね・・・まあいいわ、私は寛大だから、一応罪は償った、として許してあげる。ということでね・・・」ゴリゴリッ、富美代はブーツに更に力を込める。「過去の罪を償ったところで、今度は私たちの将来のための保険、かけさせて貰うわよ!フフ、ウフフフフ、アハハハハッ!先輩のタマタマ、約束どおり潰してあげるわよ!」「・・・あ、あああ・・・ゆ、ゆるして・・・」「なに先輩、なんか言った?よく聞こえなかったんだけど、もうちょっとはっきり言ってくれない!?」「お・・・ねがい、ゆるして・・・し、しんじゃう・・・もう、しんじまうよ・・・」「ああ死んじゃうかもね、うん確かにね。で、それがどうかしたの?別に先輩が死のうが生きようが私の知ったことじゃないわ。私は自分の明るい未来のために先輩のタマタマをここで潰して、腕も足も靭帯を引き千切って再起不能にするだけよ。別に先輩が死んだところで私は痛くも痒くもないわ。と、言うことでお話タイムはお終い、後は痛い痛いのお時間再開よ!じゃあみんな、執行準備を手伝って!」凛とした声を張り上げると富美代は縛り上げた検見川の足だけを解放する。検見川は自由になった足を必死で動かして逃げようとするが、股関節を外されていては不可能と言うものだ。「OK,フミちゃん、じゃあまずは顎、外してあげて!」まずはうつ伏せにした検見川の髪を掴み、礼子が顔を引き摺り起こす。「有難う礼子、じゃあ先輩、武士の情けで顎外してあげるから、口開けて。」「い、いやだあああ、いやだあああああ!」パニック状態に陥った検見川には最早、富美代の声は聞こえない。当然口を開けようともしない。「・・・先輩、あと5秒数える内に開けないと、キックだよ。」「や、いや、やだあああああ・・・」「・・・543・・・」「やめでぐれえええええ・・・」「・・・210。」富美代は検見川の髪を掴む礼子と頷きあった。
礼子は検見川の首の後ろに膝を当て、全体重をかけて押え込みながらそこを支点とし、髪を掴んで顔を固定する。「ア、アワワワワ、ヤベデグレエエエ!!!」カエルのような姿勢で地面に這いつくばらされた検見川の、涙を流しながら哀願の言葉を吐きつづける口めがけて富美代は狙いを定め、大きくバックスイングを取るとサッカーボールキックの要領で真っ赤なブーツの爪先を思いっ切り蹴り込んだ。ぐぎっ、べぎゃっ、ばぎっ・・・富美代のブーツの固い爪先は検見川の下唇に命中し、いとも容易く数本の歯をへし折った。「イア、イギャアアアアア!!!」口から鮮血を迸らせながら絶叫し、何とか逃れようと必死で頭を振る検見川を礼子が全力で押さえつける。ミリッ、ブヂッ・・・検見川の髪が数十本単位で引き抜ける。長くは持たないわね。間髪を入れずに富美代は再び脚を振り上げ、第二撃を繰り出す。今度はやや下から蹴り上げる形で検見川の口を強襲した富美代のブーツが再び数本の歯をへし折る。
「ガッ、ガハッ、ゴバアアアッッッ・・・い、いでえ、いでえよおおおおお・・・」
礼子が解放するなり検見川は頭を床につけてうめいた。床に見る見る鮮血が広がる。
「アハハハハッ!全くバカよね、先輩ったら!折角、痛めつけないで楽に顎を外してあげよう、て言ってあげたのにね!人の好意を無にするからこうなるのよ!」
富美代は狂ったように高笑いする、だがこれで終わった訳ではない。今のは単なるオードブル、刑の執行はこれからなのだ。「・・・さあ先輩、前座は終わり、いよいよ本番、逝くわよ。男、廃業させてあげる。覚悟はいいわね?」富美代が死刑執行宣告をすると同時に礼子は検見川を転がして仰向けにし、腹の上に馬乗りになる。そして玲子は右足、朝子は左足を掴み、検見川の両足を全開脚にする。勿論検見川は必死で足を閉じようとするが、股関節を外されていては力の入れようがない。そして富美代はゆっくりと歩を進め、検見川の無防備に曝け出された男性器の前に仁王立ちした。
「フフフ、さあ先輩、逝くわよ、死刑、執行!」凛とした声で刑の執行を宣告すると同時に富美代は思いっきり右足を後ろに振り上げ、全力でのサッカーボールキックを股間に見舞う。ドゴッ・・・「ブ、ブギャアアアアア!」潰れた手応えはないわ。第二撃。ガズッ・・・「ヒギイイイイイッ!!」アン、中々上手く逝かないわね!金玉をしっかり狙って必殺のトーキックを突き刺したつもりだったが、狙いが微妙に外れた。検見川の股間、恥骨の方にダメージを与えたが肝心の睾丸には命中しなかったようだ。よく考えてみたら、タマタマって丸いのよね。トーキックで蹴れるわけないじゃない。丸くてちっちゃいものを蹴るには・・・しっかり足の甲で蹴らなくちゃね。第三撃。今度はさっきの二発よりややキックの軌道を低くした。命中直前、地表すれすれを飛来した真紅のブーツの爪先は検見川の左睾丸の下に滑り込む。一瞬遅れてブーツに覆われた富美代の足首が睾丸に命中し、そのまま睾丸を検見川自身の恥骨との間に挟み込む。ブヂャッ!先ほどとは明らかに違う、何かが破裂したような感触がブーツ越しに富美代の脚に伝わる。「ギ、ギャアアアアアアアッッッ!!!」全身を仰け反らせながら検見川は絶叫した。痛いいたいイタイ・・・それ以外何も感じられない。全身を貫く激痛と殆ど同時に強烈な悪寒を伴った気持ち悪さが体中の神経を支配する。フフフ、やったやった!先輩、死ぬほど苦しんでるわね。いい気味。その顔見てると、先輩に傷付けられた私の心が癒されるわ。ああいいわ先輩、これだけ癒されたから、そろそろ許してあげる。今止めを刺してあげるわ。もう一個もちゃんと
潰してあげるね!これで先輩、男は廃業ね。これから先輩がどんな人生生きるか知らないけど、全力で不幸な一生でありますように!じゃあね、サヨナラ、先輩!身体の内外からの二重の苦しみに痙攣する検見川に何の憐憫も見せずに真紅のブーツを大きく振り上げ、富美代は止めの一撃を蹴り込んだ。
先ほどの一撃でコツを掴んだ富美代の第四撃は的確に検見川の残された右睾丸を捕らえ、恥骨とのサンドイッチにする。バヅンッ・・・検見川は確かに破滅の音を聞いたような気がした。一生忘れられない音だった。「ガッ!ゴアッッッッッ!!!!!」
余りの激痛に呼吸困難を起こし、全身がビクビク痙攣する。激痛の余り舌が飛びでている。そしてギヂギヂと音が出そうな位強く噛み締めた口のあちこちで、限界以上の力で口内に食い込んだ歯が出血を引き起こす。噛み締めた歯は勿論、はみ出た舌にも食いこんでいるが殆どの歯をへし折られているために舌を噛み切るには至らない。だが残った数本の歯や、折れた歯の残骸が残る歯茎が食い込み、舌もズタズタだ。口一杯に溢れ出る新たな鮮血が真っ赤な血泡となり、検見川の口からブクブク噴き出る。
余りの痛さに失神すら中々出来ない。失神と覚醒とを繰り返しのた打ち回り続けながら、検見川の意識はゆっくりと闇に沈んでいった。
「フーッ・・・フミちゃん、やるときゃやるわね・・・」流石の玲子が些か圧倒されたような声になっていた。「うん。まあ折角のチャンスだからね。私もイヤなこと早く忘れたいから。私は先輩の思い出とバイバイ、先輩は男としての機能とバイバイ、ていうことでまあチャラかな、て思ってさ。」「チャラってフミちゃん・・・これ100倍返しだと思うんだけど。ま、いいか。蹴ろう、ていったのは私だしね。」気を取り直すように2、3回首を振ると玲子は奈良村に向き直った。「と、言うわけでタマナシ君、次は君の番で確定よ。」奈良村の顔から恐怖の余り、サーッと音を立てて血が引いていく。青白い、殆ど死人のような顔になりながら、口をパクパクさせている。「あ、それとね」玲子はその美貌に悪魔の様な残酷な笑いを浮かべながら宣告した。「さっきまでは単に潰すだけのつもりだったんだけどね、私も気が変わったわ。ウフフフフ、そうよ、私も刑罰を追加するわ。たっぷりと楽しませてあげるわよ、覚悟しなさい、思いっきり痛めつけてやるからね!」「ひ、ヒイーッ!い、いや、おねがい!!!もう許してくれえええっ、お、おねがいだあああああっっっ」ボロボロと涙を流して哀願する奈良村を満足気に見下ろしながら、玲子は冷たく宣告した。「ダメよ!タマナシ君、さっき君は私にナイフで切りかかったでしょう?あれがもし私に当たってたら、どうする気だったの?女の子に、特にもし、顔に傷なんかつけられてたら私、一生台無しだったかも知れないのよ?それを思ったら、未遂犯でも罪状は同じよ!やっぱり、そんなことが二度と出来ない様に片輪にしてやらなくちゃ気が済まないわ!」無情な宣告を下しながら玲子は床に転がる奈良村の右手を伸ばすと礼子をその上に座らせた。次に朝子を背中に、富美代を腰に座らせ、奈良村が身動き一つ出来ない様にする。「さあ準備完了!何をされるか分かる?分からない?じゃあ教えてあげる。私、さっきタマナシ君の骨を何本か砕いてあげたわよね?骨ってね、腕や肋骨ならね、きれいに折れれば結構簡単に治るものなのよ。でもね、ああやって砕けばずっと治りにくくなるわ。で、もっと治りにくいのはどこだと思う?」玲子の顔に凄絶な笑みが浮かんだ。
「手の骨よ。指、手の甲、手首・・・細いけど繊細な構造であちこちに関節があるわ。そこを砕かれたらどうなると思う?ましてや手は人体で最も微妙な動きをする所だからね、神経も縦横に通っているのよ。それを破壊したら・・・フフフフフ、もう一生、手は自由に使えなくなるわよ?分かる?どうやるか」玲子はブーツの硬いヒールで奈良村の右手を踏み付けた。「このヒール、硬いでしょう?私の得意技は蹴り、そしてこのヒールを活かした下段蹴りは・・・」玲子がゴリッとブーツに力を込める。「ウフフフフ、君の手の骨なんか、簡単に砕けるわ。そう、指も手も手首も、全部グシャグシャに砕いてあげる。何箇所骨折したか、なんて数えても意味ない位粉々にしてあげるわ。骨も関節も神経も、全部踏み潰してあげる。そう、ドラエモンの手みたく、手首から先が単なる肉球になるまで徹底的に蹴り潰してあげる。フフフ、アハハハハッ!そこまで完全に破壊したら、どんな名医にかかったって絶対に治らないわよ!一生指一本まともに動かせない片輪にしてあげるわ!」
「や、やだ、やべでぐれえええええっ!お、おねがいだ、踏み潰さないでくれえええっ!」奈良村は絶叫しながら必死で右手を固く、全力で握り締めた。肩を外されているから力は入りづらいが今はそんなことを言っている時ではない、全身の力を振り絞って握り締めた。だがそんな奈良村の必死の悪あがきを玲子はあっさりと鼻でせせら笑った。「フフ、タマナシ君どうしたの、そんなに固くお手て握っちゃって。もしかして、固く拳を固めたら私が踏み潰せなくなる、とでも思っているの?馬鹿ねえ、そんなことしても、何の役にも立たないわよ。」玲子はツッとブーツを奈良村の手からどけるとカッカッとヒールで床をつついた。「分かる、この音。この床、コンクリートなのよね。上から加えられる力を下へ逃がしちゃうことはないわ。て、言うことはね、要するに上から私が下段蹴りを加えるとね、力学的にはコンクリートで君の拳を殴りつけているのと同じことになるのよ。分かる?ガードなんて無意味、そうやって握り締めれば石の拳になる、と言うのなら話は別だけどね。果たして君の手、コンクリートよりも硬いかどうか、試してあげるわ!」
玲子はニヤリと笑いながらゆっくりと右足を引き上げた。「さあ、右手にお別れは言えたかしら?覚悟はいいわね、逝くわよ、ハッ!」気合もろとも玲子は全身のウエイトを掛けながら、捻りを効かせた凄まじい蹴りを奈良村の右拳に叩き込んだ。バギッ・・・「ギャアアアッ!」瓦数枚を蹴り割る必殺の下段蹴り、しかも玲子は巧みに角度を調節し、ヒールの角が奈良村の拳に食い込むように蹴り付けていた。これでは人間の骨など一たまりもない。早くも人差し指の付け根から手の甲を走る骨をへし折られた奈良村の悲鳴が響く。「アハハハハッ!何回聞いても君の悲鳴はいいわね、その情けない声、私結構好きよ、ゾクゾクしちゃう!もっとその声、聞かせてよ!ほら!ほら!ほらほらほら!」ガッ、ドガッ、ベジャッ、バギッ・・・ギャアッ!ヒッヒギイイイッ!イ、イデエ、イデエエエエエッ!!!玲子が立て続けに蹴りを叩き込む毎に奈良村の悲鳴が轟く。僅か数発で既に奈良村の手の力は完全に失われ、拳はだらしなく開いていた。まずは手の甲から手首にかけて数箇所をへし折られ、奈良村は最早拳を握る力すら奪われていた。「ウフフフフ、どうタマナシ君、私の言った通りでしょ?拳を握ったところで無駄だって。さあ、じゃあチューリップが開いたところで、今度はその指を潰してあげる!」ガギイッ・・・ギアアアアッッッ!一段と高い悲鳴が轟いた。玲子の黒いブーツのヒールが奈良村の親指を覆い隠している。そして玲子がグリッと一躙りした後ヒールを持ち上げた。「アハハハハッ!ほらタマナシ君、見てご覧よ!君の親指、潰れちゃったみたいよ!」涙にボヤケた目で自分の親指、ズキズキ、と言うよりズシンズシンと体の奥底へと響く痛みを送りつける自分の指を見て、奈良村は思わず我が目を疑ってしまった。な、なんだこりゃ!?!?そこにあったのは見慣れた自分の親指ではなかった。ほぼ丸い、筒状の親指が明らかに扁平な楕円形に変形していた。何箇所もの骨折から来るズキズキとした鈍い、体の奥底から響いてくる痛みすら一瞬忘れさせる、自分の体が変形させられてしまった、という衝撃が奈良村に絶望的な悲しみとなった。「う、ううっ・・・あ、あんまりだ、あんまりだ・・・つ、つぶすなんて・・・ひ、ひどい・・・」全身を震わせてすすり泣く奈良村の頭上から玲子の嘲笑が降り注いだ。
「アハハッ!泣いてるの、タマナシ君?そんなに指潰されたのが悲しいの?大丈夫、心配いらないわよ、そんな悲しみ、お姉さんが吹き飛ばしてあげるからね!直ぐに残りの指四本もお手ても手首も、全部砕いてあげるから!悲しいなんて感じている暇なんかなくなるから安心してね!」言うなり玲子は再びブーツを振り上げ、奈良村の人差し指に思いっきりヒールを叩き込んだ。「ギギャアアアアアッッッ!」ああ、この感触最高よ!ヒールを踏み込む度に、ブーツの中の玲子の踵にミジッというような、硬い芯のあるものを砕く感触が伝わってくる。単に硬いっていうのとは違うのよね。硬いくせして、砕けると今度は小砂利を踏んだような感触と言うか、なんか粘りがあるって言うか・・・兎に角気持ちいいわね、この感触!しかも私が踏み潰したところ、どんどん内出血してくるじゃん!鞭の内出血とも全然違う感じの出血ね、こう、なんかブワッと膨れて腫れ上がる、ていう感じじゃない?なんかこのままグシャグシャにしてあげたら、タマナシ君の手、冗談抜きでグローブみたいに大きくなっちゃうかもね!玲子といえども他人の骨を折った経験は殆どない。だがこうやってコンクリートの床で逃げ場がない奈良村の指を固いブーツのヒールで責めると、面白い位簡単に骨がポキポキと折れていく。折れる、と言うより潰され、砕け、骨としての機能を失ってバラバラの骨片に分解されていく。ふーん、人の骨って案外もろいのね。こんなに簡単に砕けるものなんだ。玲子は不思議な気分だった。流石に人の骨を砕くなんて、考えてもみなかったな。だけど・・・気持ちいい!楽しいわよこれ!練習中、まともに蹴りが入って相手の骨にヒビが入ったことはあったけど、その時は結構罪悪感あったのに不思議ね、こうやってブーツを履いて骨を蹴り砕くのって、全然罪悪感なんて感じないわ。骨を砕く感触がブーツで濾過されて快感に変わっていくみたい・・・最高ね、この感覚。でも残念、流石にこんな経験、一生二度と出来ないかもしれないわよね。だったら・・・今、このチャンスに精一杯、目一杯楽しんどかなくちゃ嘘よね!ほら逝くわよ!もっと感じさせて頂戴、骨の砕ける感触を!聞かせて頂戴、骨を砕かれて片輪になっていく君の悲鳴を!見せて頂戴、崩壊していく君の手が内出血で変形していく様を!
涙に曇った奈良村の視界の中で、玲子の漆黒のブーツは天上界から降り注がれる神々の大槌のように、視界の上方に消えては再び振り下ろされ、奈良村に新たな苦痛を刻んではまた上方に消えて行った。神々を怒らせた愚かな虫けらのように、奈良村には唯ひたすら玲子の責めを受け泣き叫び続ける以外に道はない。最早首を上げる気力すらない奈良村の視界に映るものは一つだけ、一定の周期で降り注ぎ、自分の指を、手を破壊していく玲子の漆黒のブーツだけだった。玲子はこまめに丁寧に、満遍なく奈良村の手を砕いていった。指一本につき十回近くも蹴りを叩き込み、文字通り粉々に砕いていった。「ウフフフフ、さあもう指は全部、粉々に砕けたみたいね。じゃあ仕上をしてあげるわ!」玲子はブーツ全体を使って奈良村の指を踏みつけると、全体重をかけながらゆっくりゆっくりと丁寧に踏み躙っていく。「アッアギギギッイイ!イアアアアアッ!!イデエエエエエエエッッッ!!!」なら村が一段と高い悲鳴をあげた。「アハハハハハハッ!どうタマナシ君、最高に痛いでしょ!?そりゃそうよね、だってあっちこっちでグシャグシャに砕けた骨を踏みつけてあげてるんだものね。痛いでしょう?こうやって踏み躙ってあげると、砕けた骨の欠片が君の指の中であっちこっちに散らばって神経に刺さりまくっているはずよ!アハハ、アハハハハハハッ!気が狂いそうに痛いでしょう?もう死んじゃいたいんじゃないの?でもダメよ、そう簡単に死ねるわけないでしょ。いくら痛くてもたかが指なんだからね。死ねるわけないわよね!覚悟しなさい、もっともっと痛くしてあげるからね、たっぷりと味わうのよ!そして思い知りなさい、女の子にナイフで切りつけた罪の重さを!ほら!ほら!ほらほらほら!」玲子は指全体を、五本の指全てを一本一本満遍なく破壊し、骨を文字通りバラバラに崩壊させていった。次いで手の甲、更には手首、と順次砕き、踏み躙り、徹底的に破壊していった。延々と続いた破壊作業が終了した時、悲鳴を上げ続けていた奈良村は精魂尽き果てたようにグッタリしていた。「ウフフフフ、どうタマナシ君、踏み潰し刑、随分効いたみたいね。さあ、じゃあ君のお手てがどうなったかみせて頂戴。」処刑が一段落したところで礼子たちは一旦奈良村の上から降りたのだが、最早動く気力は全くない。肩を震わせて荒い息をする奈良村の右手を礼子は無造作に持ち上げた。「ワ~ッほらみんな見てご覧よ!これおもしろーい!」玲子の言うとおり、奈良村の手は中々の見物だった。何箇所と数えるのも馬鹿らしいほど沢山の複雑骨折、そして内出血で手はパンパンに腫れ上がって来ていた。そして何よりも、その柔軟性は誰も見たことがないものだった。「ほら、これこれ!どこでも、どの方向にでも曲がるよ!ほらタマナシ君の手、まるでタコみたいじゃん!」玲子がクイクイッと適当なポイントを掴みながら曲げると奈良村の手はどこでも、殆ど何の抵抗もなく有り得ない角度に曲がっていく。勿論、骨が折れた所だ、そんな傷口を更に抉られて痛くないわけがない。「ひっひぎああっい、いでえええっや、やべで、さわらないで・・・ひいいい!!!」「あら冷たいじゃない、そんなに嫌わなくてもいいでしょ、私、別に手荒な真似なんかしてないよ。単に握手したいだけよ。ほら、握手しよ!」玲子が無理矢理奈良村の右手を握る。指、手の甲、手首、砕かれた骨があちこちで神経を刺激し奈良村に爆発的な激痛を与える。どこが痛い、等というのは無意味だ。手全体の神経が一斉に悲鳴をあげる。「ギャアアアアアッ!ヒッヒイイイイイッッッッ!」「あら、そんなに嬉しいの?うん、分かる分かる!この霧島玲子さんに握手して貰えるなんて、君には身に余る光栄だものね、泣いて喜ぶのも当然よね!じゃあお姉さん、今日は機嫌いいから特別サービスもしてあげるわ。ほら、両手一緒に握手してあげる。但し・・・左のお手ても砕いてからね!」「ひっそ、そんな、そんなあああっやべでぐれええええっ、や、やべでえええええっっっ!!!」奈良村は甲高い声で泣き叫び続けた。だが玲子の言うとおり、まだ片手なのだ。もう一回、もう一回奈良村はこの激痛の処刑を受けなければならないのだ。漸く処刑が終わった時、奈良村は半ば意識を失いかけていた。だが玲子の恐ろしい宣告が失神、という救いの女神を一瞬にして遠ざけてしまった。「さあタマナシ君、これで踏み潰し刑は執行完了よ。良かったわね、大負けに負けて、一応罪は償った、てことにしておいてあげるわ。・・・と言う事で、そろそろ仕上、タマタマ潰しに移ってあげるわね!」
あ、あああ・・・奈良村の口から絶望の嗚咽が漏れた。だが余りに体力を消耗し、その声は虫の息程度のものだった。
6
「ウン?何言ってるの?全然聞こえないよ、もうちょっと大きな声で言ってよ?」玲子は奈良村の口元に耳を近づけた。「・・・た、たすけて・・・つぶ、さ・ない・・で・・・」
「ああ、それはダメよ。諦めなさい。どうせ潰されるのが早いか遅いかだけの違いなんだからさ、イヤな事は早く済ませた方がいいんじゃない?」玲子の拒絶に合わせるように、礼子が奈良村の髪を掴み、顔を引き摺り起こす。「さあ、ここで最後の選択よ。顎外して貰うのがいい?それとも、検見川さんみたく、歯を蹴り砕かれるのがいい?お好きなほうを選んで頂戴。あ、念のため逝っとくけど、どっちもイヤ、とか、やめて、とかいう返事は歯をへし折られる方をチョイスした、と見なすからね。」玲子は漆黒のブーツの爪先でコツコツと奈良村の口をノックしながら最後の選択を迫った。「あ、ああ・・・」奈良村は恐怖と絶望の余り、口をパクパクさせるだけで何も言えない。だが目の前で検見川が歯を蹴り砕かれるのを見せ付けられたのだ、選択の余地はない。奈良村は涙を流しながらも口をダラリと開け放った。フンッと玲子は冷笑を浮べながらブーツを更に突き出す。「あ、やっぱ顎を外される方がいいのね。まあ賢明な選択と思うわよ。じゃあ、私が仕事しやすいように、ちゃんと咥えこんで頂戴!」
クイッと玲子がブーツをしゃくる動きにつられるように、奈良村は玲子のブーツの爪先を自ら咥えこんだ。自分の両手を粉々に砕き、再起不能の片輪にしたブーツを。自分のことを際限なく責め苛んだ漆黒のブーツ、苦痛と屈辱の象徴、元凶とも言える玲子のブーツを自らの意思で咥える。靴を舐める、等というレベルではない屈辱だ。激痛に頭の中が真っ白になった中でもその屈辱は決して掻き消されずに奈良村の精神を責め苛む。だがいくら悔しくても玲子に逆らうことはできない。その気になれば玲子はいつでも自分の歯を蹴り砕けるのだ。これだけの苦痛を味わった後、しかもこの後は睾丸を砕かれる責めが待ち受けているのだ。その前に受ける苦痛は少しでも、ほんの僅かでも減らしておきたい。奈良村は屈辱を必死で堪えながら玲子のブーツを、咥えこんだ。土埃と皮革の匂いが奈良村の口の中一杯に広がる。目の前には玲子の漆黒のブーツが聳えている。信次たちが味あわされたのと同じ、屈辱の情景だ。フフフフフ、タマナシ君、泣いてるのね、いいザマよ。自分でブーツを咥えに来るなんて、もう精神もズタズタに踏み躙ってあげられたみたいね。その屈服して怯えた目、私を見上げるその目、最高よ。いつまでもずっとずっと、その目で見上げさせていたいわ!玲子は奈良村が涙を流しながら、自分のブーツを咥えたまま見上げているのをゆっくりと楽しんだ後、おもむろに刑を執行した。「いいわ、じゃあ、逝くわよ?」玲子の宣告に合わせるように、礼子が奈良村の首を支えたまま指を耳の下、頬骨と頭蓋骨の付け根に食い込ませて上に持ち上げ、力の支点とする。「せーの、それ!」玲子は奈良村の口に押し込んだブーツを一気に踏み下げる。ガックーン・・・あっけないほど簡単に奈良村の顎が外れる。「ア、アワワ・・・」奈良村は顎が外れるのは初体験だった。いたい、と言うより疲労感を伴うような、時間と共に痛み、不快感が増す、何とも形容し難い苦痛だ、これだけでも十二分に苦しい。だが今はこの程度の痛み、ほんの前座に過ぎない。本物の苦痛はこれからやって来るのだ。
「OK・・・さあ準備完了ね。さ、タマナシ君、これで君も名実共に、本物のタマナシ君になるのよ。」仰向けにひっくり返した奈良村の股間にしゃがみ込みながら、玲子は拳を固め、片膝をついて下段正拳突きの姿勢を取る。言葉は相変わらず奈良村を嘲っているものの、眼は笑っていない、むしろどこか緊張感すら漂わせている。検見川の時と同じく礼子は腹の上、そして今度は富美代が右足、朝子が左足を広げながら押さえ込む。「い、いや、ヒック、ウエッ・・・やめて・・・イアッ・・・」奈良村は最早絶叫する気力すらなく、ひたすら泣いている。「タマナシ君、ダメよ、泣いても許してあげない・・・だけど君をいたぶるつもりも、もうないのよ。余計な苦しみを味あわなくて済むように、一発で決めてあげるわね!」玲子は右拳を引き付け、ゆっくりと呼吸を整えた。「ヒュウウウッッッ・・・ハッ!」列昂の気合と共に、玲子は必殺の下段突きを繰り出した。ドグジャッ!瓦数枚を砕く玲子の下段突き、しかも睾丸はコンクリートの床にくっついている。これでは力の逃げ場所が全くない。奈良村の左の睾丸があっけなく潰れた。「ギギャアアアアアッッッ!ギア゛ッ、イ、イデエ、イデエヨオオオオオッ!!!」奈良村の全身に鉛の塊で殴りつけられたような重い衝撃が走る。イタイ、それ以外は何も感じられない。殴る蹴る、といった体の表面から来る痛みではない。内臓を傷つけられる感覚、生命の危機を本能が感じ取り、最大限の警報を鳴らしているようだ。
奈良村は全身を苦悶にのた打ち回らせるが肩、股関節を外された上に礼子たち三人掛かりで押さえつけられていては満足にのた打ち回ることすらできない。その奈良村の股間を触った玲子の美貌に満足そうな、そして見るものを震え上がらせる残酷な冷笑が浮かんだ。「ウフフフフッ、我ながら完璧にヒットしたわね。タマナシ君、左は潰してあげたから・・・今度は右よ!」「いあ゛、あべておしえおえあいいいいいいっっっ!!!い、いっあつ、いっあつ!」玲子の余りに無慈悲な宣告に、激痛にのた打ち回っていた奈良村の口から断末魔のような悲鳴が迸る。だが顎を外されているから殆ど言葉にすらならない、「うん?!一発だけ、とでも言ってるのかな?確かに私、一発、て言ったわよね。だけど、それは左を一発で潰してあげる、て言っただけよ。両方一辺に潰すだなんて、一体誰が言ったの?」玲子にとって、この刑罰は確かに必要に迫られての刑罰だ。だが、玲子の中では必要だから仕方ない、というドライな判断と折角の金玉潰し初体験をたっぷり堪能したい、という加虐の慶びの二つの感情が全く矛盾なく共存していた。思ったよりあっけなく潰れるものね・・・だけど潰した瞬間のこの絶叫、ゾクゾクするじゃない?いいわよタマナシ君、私、君にこんなに私をゾクゾクさせる才能があるなんて知らなかったわ。今は右の拳で極めたから・・・今度は左の拳にこの感触、焼き付けておかなくちゃ!さあ、もう一度楽しませて頂戴!
玲子がゆっくりと左拳を巻き上げる。「さあ、逝くわよ・・・覚悟はいいわね!?ハヤッ!」ビュオッ・・・グジャッ・・・「ギャビイイイイイッッッ!!!ギブアアアアアアッッッッ」未だ先ほどの激痛が抜けない、というより痛みが余計激しくなっている奈良村の全神経を、新たな苦痛がパニック状態に陥れる。冷たい氷のような感覚、身体の奥底にズシンと氷の巨弾を打ち込まれたような感覚だった。「グヴエッ・・・オゲブァアアアッッッ!!!」奈良村の全身を押え様のない吐き気が貫き、胃液がこみ上げてくる。「ヴベバッ、ガハッゲバアッッッッ!!!」だが胃液を吐き出すほどの力さえ出ない。余りの痛さに呼吸困難に陥った奈良村の喉を胃液が上下し、それが新たな咳き込みを誘って苦痛を更に増していく。股間の痛みと呼吸困難と内臓の反乱と。奈良村は全身の神経の暴走に延々と苛まされつづけながら、長い時間をかけてのたうち回ったあげくに白目を剥いて気絶していった。
残り二人。未だ意識があるのは須崎と坊野の二人だけだった。「さあ、残るは二人、後半戦ね。で、どっちが先に逝く?」完全に気絶した奈良村の背中から降りた礼子が、冷たい微笑を浮べながら尋ねた。「い、いやだあああ!ぼ、坊野、坊野さああああん!お、お願いだあああ、助けて、先に逝って、いやだよおおお!!!」「ば、ばかやろおおお、お、おれだって、おれだっていやだ、お、おまえだ、おまえが先いけ、め、めいれい、命令だ、おまえが先逝け、言うこと聞かねえとぶっ殺すぞ!」もう仲間意識などどこにもない。あるのは唯一つ、生存本能。助かりたい、自分が、自分だけは助かりたい。坊野も須崎も、頭の中にあるのはそれだけだ。二人の醜い罵りあいに些か辟易としたように朝子が肩をすぼめた。「あーあ、最凶のギャング、といってもタマタマ潰すよ、ていうだけでこんなになっちゃうんだ・・・なんか、もううんざりだな。もうこんな連中に付き合うの、そろそろ終わりにしたいな。ねえ礼子、チャッチャッとすませちゃおうよ。まあトリは一応この人たちのプレジ、ということで坊野さんと礼子にしてさ、次、私が片付けちゃっていい?」礼子にも否やはない。早速四人は須崎を取り囲んだ。「い、いや、いやだあああああ、やめてくれえええええっ!」「・・・全く五月蝿いわね、何よ、そんなに涙流して情けない声で・・・貴方たち一応、最凶ギャングを名乗ってるんでしょ?恥ずかしくないの?ペッ!」須崎の髪を掴んで引き上げた朝子が軽蔑と嫌悪感を露骨にその愛くるしい美貌に浮かべながら、思いっきり唾を吐き掛けた。「ホラ今何されたかわかんないの?唾吐き掛けられたんだよ?女の子に、自分の顎を蹴り砕いて、手を焼いて拷問した女の子に。自分よりずっと小っちゃくてしかも年下の女の子に。須崎さん今、唾吐き掛けられたんだよ?ねえ、悔しくないの?顔に唾吐き掛けられるなんて、人間最大の屈辱じゃないの?ほら、そんなことされたのに睨み返す位できないの?よく唾吐き掛けられて、悔しいとも思わずにいられるわねえ。最低!ねえ、そんな意気地なしだったら、もう一回唾吐き掛けちゃうよ?ほら!こっち見て、私の口を見てよ、自分が唾吐き掛けられるところをたっぷりと見なさいよ、ほら逝くよ、ペッ!」朝子は須崎のことを嬲りながら再度、唾を吐き掛けた。朝子は他人に唾を吐き掛けることが大好きだった。自分の優位性、他人を屈辱させられる強さの象徴と思っていた。うーん、気持ちいい!こうやって唾吐き掛けるのって、何度やっても最高に気持ちいいよね。唾掛けられた相手が悔しそうに私のこと見て、だけど怖くて逆らうことすらできない、ていうの最高よね。ゾクゾクしちゃう!なんかさ、唾吐く度に唇がこう、フワーッとあったかくなるような感じがしてほんと、気持ちいいのよね。私、フミちゃんほど唾吐くのは上手じゃないけど、それでもこうやって唾吐き掛けるのって大好き。ほんとこれ、最高に楽しいのよね・・・だが須崎はもう反抗する気力も何もない。悔しそうに朝子を睨むことさえできない。唯々怯えるだけだった。「・・あ、あわわわわ・・・ゆるして、やめて・・・つぶさないで・・・・・」うわ言のように呟き続ける須崎に、呆れた、というように朝子が両手を広げて肩をすぼめた。
「ふう、全く情けないわね・・・じゃあ須崎さん、いいこと教えてあげる。私ね、男の人の好みは結構男っぽい人が好みなんだ。逆に意気地なし君は大っ嫌いなの。今の今までね、まあこれ以上苛めたら可哀想だから、あっさり潰して終わりにしてあげよう、て思ってたんだけどね」ニヤリと朝子が残酷な笑みを浮かべた。「須崎さん、大っきいだけで実はとんでもない意気地なし君だったみたいね。だって唾吐き掛けられたのに悔しくもないんだものね。そんな意気地なし君の分際で私を襲おうとしたなんて、図に乗るのにも程っていうものがあるわ!やっぱり・・・懲らしめてあげなくちゃいけないわね、たーーっ、ぷりと!」やれやれ、玲子は思わず苦笑してしまった。朝子ったらはなからすっかりやる気だった癖して。睨み返したら反抗的だ、とか反省が足りないとか言って結局絶対に苛めるつもりの癖してね。変に希望を持たせたり前振りしてる間に自分で勝手に盛り上がっていくから朝子って怖いのよね。そんな玲子の苦笑に気付かないかのように、朝子は嬉々として刑の宣告をした。
「さあ、どうやって懲らしめられるかは、もう分かっているわよね。そう。も・ち・ろ・ん・・・火焙りの刑よ!」ひ、ひあぶりーーー!須崎にとっては最も聞きたくない言葉だった。「そ、そんな!ひ、火焙りだけは、それだけは許してくれえええっ!」「だーめ!須崎さん、さっきあれだけいい声で叫んでたんだから。よっぽど私の火責め、効いたんでしょ?だったら刑罰は勿論、火焙りよ!覚悟しなさい、拷問の火責めじゃないんだからね、火焙り、これは刑罰なのよ。さっきよりも・・・ずーっとずーっと、熱ーくしてあげるからね!」必死で泣き喚く須崎に構わず、朝子は須崎をうつ伏せにするとパンツとトランクスを一気に引き摺り下ろし、尻を剥き出しにした。玲子と富美代が両腕を、礼子が両足に乗って押さえつける。「アハハハハッ、須崎さん随分とお尻が白いのね、ちょっと不健康なんじゃない?」ピシャピシャと須崎の尻を叩きながら朝子が笑った。「でも安心してね、直ぐに色をつけてあげるわ・・・そう、真っ赤にしてあげるからね!」恐怖で震える須崎の眼前に朝子は四個のライターを突きつけた。須崎のライターと同じ大型のZIPPO、そう、須崎たちSNOW CRACKの幹部が一緒に特注したものだった。気絶した須崎たちを縛り上げている間に、朝子は抜け目なくそのライターを四人全員から集めていたのだ。「ウフフフフ、ねえどうするか分かる?まさか、さっきまでと同じ、単純に炙るだけ、なんて思ってないわよねえ?」カチッと音を立てて朝子はZIPPOのオイル注入口を空け、中のオイルを須崎の尻に垂らした。「あっあわわわわわっ・・・・ま、まさか・・・・」「ウフフ、そうよ、分かったみたいね、ビンゴよ。ライターのちっぽけな火で炙る、なんて手温いわ。そんなんじゃ刑罰にはならないでしょ。だから今度は・・・直火で焼いてあげる!」恐ろしい宣告をしながら朝子は四つのライターから次々にオイルを須崎の尻に垂らしていく。そしてそのオイルを尻一面に満遍なく伸ばした。
「さあ準備完了。覚悟はいいわね、オイルでの直火焼き、これきっと熱いわよー!足自由にできないのが残念ね。文字通り尻に火が着く、てやつかしら。ウフフフフ、自由にしてたらきっと、100メートル3秒で走れるんじゃない?残念だわ、世界新記録を見損ねちゃったわね。」
「や、やべ、やべやべやめてぐれえええええっ!」須崎が必死で絶叫するのを楽しそうに眺めながら、朝子は問い返す。「ねえ須崎さん、ところでひとつ質問なんだけど。そうやって絶叫するのは須崎さんの勝手なんだけどさ、叫んでいたら許してもらえる、て本気で思ってるの?」グウッ・・・須崎が思わず返答に詰まるのを見て朝子は大きく頷いた。「あ、そっか!自分でも無駄だ、て分かってるんだ!だったらいいわね。私、もしかして須崎さんが本気で許してもらえる、て本心から信じているんだったら、悪いからやめようかな、て思ってたのよ。だけど須崎さん自身が信じていないんだったら遠慮はいらないわよね!じゃ、遠慮なく火焙りの刑、執行よ!」シュボッと朝子がライターに点火した。オイルを抜いても暫くの間は芯に染み込んだオイルで十分に火はつく。わざと須崎の鼻先を掠めるようにしながら、朝子はゆっくりとライターの火を須崎の尻に近づけていく。
「あっああっや、やめて・・・おねがい・・・」恐怖の余り微かな泣き声しか出なくなった須崎を嘲笑うかのように、朝子はゆっくりと炎で尻を掠める。「ヒイッ!」ライターの熱を感じると同時に甲高い悲鳴をあげ、須崎の尻が跳ね上がる。「アハハハハッ!やーねえ、大袈裟なんだから!未だ火は付いてないわよ。今のはほんの予告編。本番はこれからよ、さあ、本当に・・・火をつけてあげるわね。逝くわよ・・・ファイヤーーーー!」「あ、ああっや、やべ・・・ギッアヂイイイイッッッ!」朝子が今度はしっかりと須崎の尻にライターの火を押し付ける。と、一瞬の間を置いて須崎の尻に擦り込まれたオイルがポッと赤い炎をあげた。炎はあっと言う間に広がり須崎の尻を覆い尽くす。「ギアッ!熱いっ、熱いぃっ!グウギャアアアアアアァァァギイイイイイィッ!!」四肢の関節を外された上で縛られ、身動きのとれない須崎の体がその場で30センチ近くも飛び上がった。「アハハハハッ!須崎さん凄い腹筋力じゃない!その調子よ、もっと踊って踊って!」笑い転げる朝子にかまう余裕などどこにもない。炎で我が身を焼かれる苦痛、意思の力で制御できるような苦痛ではない。殆ど原始の本能、野獣の本能というべきか、なんとか、なんとか逃れようと須崎は凄まじい悲鳴をあげながら飛び跳ねつづけた。なんとか、なんとか引っ繰り返って尻を床につけ、火を消そうと必死でもがき続けた。だが周りを囲んでいる朝子たち四人はそんなこと、百も承知だ。須崎がヒコヒコと腰を突き出すように必死で飛び跳ね、なんとか引っ繰り返ろうとしてもしっかり全身を押さえつけ、、あえなく腹から着地させてしまう。体を捻ろうとしても、手足をしっかりと固定されていては無理というものだ。あらゆる動きを封じられ、須崎は尻を焼かれつづけた。
「ひギアあああっ、熱いっ、くああアアあぁっ、アッ、アギイイィィッ!!」須崎は狂ったように叫び続けた。手を炙られた時の苦痛の比ではない。体の奥底にまで熱が伝わってくるのが分かる。まさに命そのものを燃やされているような苦痛だ。これほどまでの苦痛は未だかって味わったことがない。須崎がのた打ち回るのを見下ろしながら朝子は大笑いしていた。「アハ、アハハ、アハハハハッ!いい動きよ!ほらもっとお尻を動かして!そんなんじゃいつまで経っても火は消えないよ!」笑い転げながら朝子はふとオイルが燃える匂いに混じって異臭を感じた。なんだろ、この匂い。余り記憶にない、ツンと刺激的な匂いだった。どこから漂ってるのかな?匂いの源を探してニ、三回鼻をクンクンと鳴らした朝子がポンッと手をたたいた。「あ、そうか!この匂い、須崎さんのお尻が焼ける匂いなんだ!」そう分かった瞬間、朝子はその匂いを何とも言えずいい香り、と感じた。人間が焼ける匂いは耐え難い悪臭、と聞いていたけど、全然そんなことないじゃん!いい匂い・・・うっとりしちゃうわ、なんか焼肉食べたくなってくるような匂いじゃない!それを職業としている軍人でも、初めて敵の焼け焦げた死体の匂いを嗅いだ時は生理的嫌悪感に耐えられない、と言う。だが須崎を責め苛むことに、特に長時間火責めを続け、火で責め苛むことに耽溺してきた朝子にとって、その匂いは自らの拷問、処刑の成功を祝福する香り、自らの勝利と須崎の苦悶を象徴する至上の芳香となっていた。「ああ、いい匂い!うっとりしちゃう・・・ねえ須崎さんも感じない?自分の体が焼ける匂い。最高の香りだと思うんだけど、どう?」朝子は大きく息を吸い、須崎の尻が焼けていく匂いを満喫した。だが問い掛けられた須崎に答える余裕などあるわけがない。我が身を焼かれている最中なのだ、ひたすら絶叫をあげ、悶え苦しむ以外のことが出来ようはずがない。
須崎にとっては無限とも思える時間が流れた。実際には高々10ccかそこらのオイルしかない。燃える、と言っても何分も燃えつづけるわけではない、一分かそこらのものだ。だが須崎の精神も肉体も全てを焼き尽くすには十二分な長さだった。漸くオイルが燃える炎が須崎の尻の上で小さくなり、一条の煙を残して燃え尽きても須崎は全身をピクピクと痙攣させたまま精根尽き果てて横たわり、啜り泣いていた。だが朝子が与えた休息時間はほんの僅かしかなかった。「うん、結構いい色に焼けてきたじゃない!もう触っても熱くないかな?」満面に笑みを浮かべながら、朝子は焼け爛れた須崎の尻を平手でピシャピシャと叩いた。「ぎ、ぎあっや、やべ、さわらないで!!!」火は消えたとは言え重度の火傷を負った尻を叩かれては堪らない。痛い、というより不快感、悪寒のような苦痛が全身を駆け巡る。「アハハハハッ!そんなに痛いんだ!そう、可哀想にねえ。この火傷、果たして治るかしら?一生痕が残るかもね!」笑いながら朝子は須崎の眼前にしゃがみこんだ。「でもね、これはあくまで刑罰、須崎さんを懲らしめる火焙りの刑だ、て言ったでしょ?唯のリンチ程度ならもうこれでお終いにしてあげてもいいんだけどね、刑罰、て言ったらこれじゃまだまだ手温いわ。いい?これは刑罰、火焙りの刑よ。今のはほんのオードブル、本物の火焙り刑の執行は・・・これからよ!」
楽しげに笑いながら朝子は奥の機械が置かれている作業場にあるテーブルへと歩いていき、上に置いてあった缶を持ってきた。その缶を須崎の目の前で揺り動かすとチャポチャポと音がする。何だろう、と涙で曇った目で見た須崎が声にならない悲鳴をあげる。その缶にはこう書いてあった。「潤滑用オイル」「・・・ひっひいいいいっ!そ、そんな!!!」「あら何そんなに驚くのよ、ここは廃業したとは言っても工場なんでしょ、オイル位残ってたって不思議はないでしょ?そんなことより、この量・・・ウフフフフ、100CC以上は入ってるわね。さっきお尻を焼いてあげたオイルの十倍はあるんじゃない?ねえ、もうこの先の展開、流石に分かるわよね?ウフ、ウフフ、ウフフフフフ、このオイル、ぜーんぶ使って焼いてあげるからね!あっついわよー、どうするの、さっきみたく直ぐには火、消えてくれないわよ。ウフフフフ、須崎さんのお尻、真っ赤になるとか皮が剥ける、じゃすまないかもね。お尻、黒焦げになっちゃうんじゃない?どんな悲鳴とダンスを見せてくれるかな?たのしみー!たっぷりと堪能させてね!」朝子は蓋を開け、須崎の尻にゆっくりと黒ずんだオイルを垂らしていく。「ヒッ、ヒイッ!」「あら冷たかった?ごめんねー、直ぐにあったかくしてあげるからさ、ちょっと待っててね!」先ほどよりも遥かにたっぷりとオイルを垂らしたところで朝子はふと手を休めた。「あっ、そう言えば一つ忘れてたわ。玲子もフミちゃんも、一生再起不能、絶対に消えない痕が残るような刑を執行したわよね。うーん、こうやってお尻を焼くだけじゃちょっと物足りないわね。・・・お顔でも焼く?」「や、やだああああっや、やべでぐれえええええっそ、それだけは、それだけはやめてくれえええええっっっ!!!」朝子が目の前にオイル缶を突きつけると須崎は死に物狂いで泣き喚き、激しく首を振り回して何とかオイルから逃れようとする。クスッ、馬鹿ね須崎さん、流石に顔面ケロイドにしたんじゃ後始末が厄介すぎるわよ。でもこんなに恐がっちゃって、何だか可愛いわね。「アハハハハッ、よっぽど顔面焼きは怖いみたいね。いいわ、じゃあ勘弁してあげようか?」「あ、ああっお、おねがい、なんでも、なんでもするから顔だけは許して・・・」「ふーん、じゃ、顔以外だったらどこを焼かれてもいいね?」朝子はグイッと須崎の尻の割れ目を広げると、その割れ目の中、特に肛門周辺にたっぷりとオイルをかけた。「さっきはオイル少なかったから、中までしっかりと焼けなかったでしょ?でも本当にバッチクテ臭いのはここだもんね。ここもこんがり焼いてあげるわね!」ヒイイイイッ再び須崎の悲鳴が上がる。「そ、そんな酷い・・・」「あ、何?やめて欲しいの?いいわよ、やめても。じゃ顔面ケロイドがいい?どっちか好きな方選んでいいよ。でもどっちか一つよ。あれも嫌これも嫌、どっちも嫌だなんて言うのは、そりゃ無理よ?どっちがいい?お尻、お顔、はーい、ファイナルアンサーのお時間でーす!ラストカウント終了までにチョイスしてくださーい!あ、念のため、アンサーがなかった場合には、両方まとめて焼いちゃいますからねー!」りょ、両方!そ、そんな・・・と言おうとして朝子を仰ぎ見た須崎は絶望に言葉も出ない。こ、こいつなら・・・こいつなら本当にやる・・・お、俺を絶対に焼く・・・「5,4,」答えなければりょ、両方とも「3,2,」・・・ど、どうする・・・「1,0!はーい、ではファイナルアンサーをどうぞ!」流石に顔か尻かで、顔を焼いてくれ、と言えるわけがない。「・・・け、けつ・・・」「うん、なんですかあ?はっきり答えてくださーい!」「・・・あ、ああ・・・け、けつ・・・尻にしてくれ・・・」「はあい、お尻がファイナルアンサーですね!ではお望み通り、しっかり焼いてあげましょう!焼き加減は・・・ウェルダンでよろしいですね!」
朝子がゆっくりとライターの炎を近づけ、再び須崎の尻に点火する。ボッ・・・純度が低い潤滑用オイルはやや黒い煙をあげながら燃え始め、あっと言う間に須崎の尻全体を炎が舐めつくす。「「ギャアアアアアアアァッ!!熱いッ、熱いいぃっ!ウギャアアアアアアアアァッ!!」「いやあああああぁっ、助けてえぇっ、誰、誰かっ、火を消してぇっ。いやああああぁっ」先ほどとは比べ物にならない位の絶叫が須崎の口から迸りる。相変わらず引っ繰り返ろうとしては朝子たちに押さえつけられるので、せめて唯一自由にできる動きを、少しでもオイルを振り落とそうと尻をヒコヒコと上下左右に振り回し、必死で珍妙なダンスを踊りつづける。だが揮発性が高く、サラッとした燃料用オイルと違い潤滑用オイルはある程度の粘性を持つ。その粘性はオイルを下に垂れ落とさず、須崎の尻にしっかりとこびり付かせている。そして純度の低さも須崎を責め苛むのに寄与していた。潤滑用オイルは燃料用オイルよりは純度が低い分、燃える速度もかなりゆっくりである。勿論燃焼温度も若干低いのだが、そんなことは須崎にとってなんの慰めにもならない。少なくとも人体を焼くには十二分な温度だ、皮膚に密着して中々床に垂れず、しかも延々と燃えつづける。潤滑用オイルは本来の意図とはまったく関係ない用途、火焙り刑にその威力を、須崎を責め苛むには遥かに適した特性を発揮してゆっくりと燃え続けた。「ああっ、熱いっ、ひいっ、あっ、あっ、ああああ---っ!熱いっ、やめてっ、お願いぃっ!」やっと少し炎が下火になり、かつ表皮の神経が焼け死んだせいであろうか、須崎の悲鳴が若干とはいえ何か多少は意味のある、言葉らしきものになってきた。その様子をゆっくりと鑑賞していた朝子の美貌に更に悪戯っぽい笑みが浮かんだ。
「ウフフフフフ、須崎さん少しは余裕出てきたみたいじゃん?火も大分弱くなっちゃったしね、もう終わりだ、やっと終わった、て思ってるんでしょ?・・・ブーッ!ざーんねんでーしたっと!誰がもう終わり、だなんて言ったの?ほらよく見てご覧、まだオイル残ってるよね?聞こえる、ほらまだこーんなにチャポチャポって言ってるじゃん?全部須崎さんにあげる、て言ったでしょ?私、約束守る人なんだ。だから約束通り、須崎さんにこのオイル、全部あげるね!と、いうことでオイル追加いっきまーす!」「ヒッ!イッ!!ヒイイイイイッ!!!きゃああああああああぁっ!やべてっ、も、もうっ、じんじゃううぅっ!ぎゃああああああああぁっ!!」処刑が漸く終わる、と思って神経が緩んだところに処刑再開を告げられ、苦痛が全て振り出しに戻りまた一から焼かれ直す。肉体面だけではない、この朝子の巧みな緩急自在の処刑は須崎の精神までも焼き尽くし、幼児退行に追い込んでいく。須崎の精神は錯乱一歩手前だった。いや、いっそ錯乱してしまえたら、気が狂ってしまえたら、どんなに楽なことだろうか。だが発狂することすらできなかった。
泣き喚く須崎を満足そうに見下ろしながら朝子は追加のオイルを降り注ぐ。しかも今度は既にかなり焼けた尻だけではなく、太腿から膝裏の方にまでオイルを降り注いだ。弱まりかけた炎が新たな燃料補給により勢いを取り戻し、そして炎が脚に、今まで焼かれていなくて未だ神経が生きている脚へと伸びていく。「ギャッ、アッ、あ、あ、熱いっ、熱、っ、ぎゃあああっ!ひいぃっ、ひいっ、ひいいいいいっ!!嫌ああああぁっ!!!えーん、マ、ママ、ママァッ!!!熱い、熱いようっ!た、たすけてえええっ!!!やべでえええっ!!!」だが幾ら泣いても喚いても助けなど来るわけがない。須崎にできることはひたすら苦しむこと、朝子が手にするオイルが全て燃え尽きるまでもがき苦しむこと以外には何もない。漸く全てのオイルが燃え尽きた時、須崎の尻から膝裏にかけては悲惨な状況になっていた。皮膚はべろりと剥け、下の筋肉組織も焼け爛れていた。特に長時間焼かれた尻の一部などは黒焦げに炭化している。一目で分かる。面積に直せば人体全体の1/10程度だから生命に別状はないが、一生ケロイドが残るのは間違いない。須崎は巨体に似合わない女の子のような声でウエッウエッと啜り泣き続けていた。だが未だ終わってはいない。朝子はもう一つの処刑を忘れてはいない。そう、須崎の睾丸を潰すことを。
7
いかにも楽しそうに須崎を見下ろしていた朝子がやがて立ち上がり、ゆっくりと須崎を蹴り転がす。「ギアッ!ヒヅウッ!!」焼け爛れた尻が床につく刺激に須崎が悲鳴をあげる。その悲鳴に朝子が微かに眉をしかめる。「ああもう!ったくうるさいんだから!それくらいで一々悲鳴あげないの!しっかりしなさい!ペッ!」朝子は再度、須崎に唾を吐き掛けた。そして唾を吐き掛けた朝子の唇が残酷な微笑に歪む。「須崎さん、男の子でしょう?未だ刑は終わっていないのよ・・・そう、これから須崎さんのタマタマ、潰してあげるんだから!あ、そっか、潰したら須崎さん、男の子じゃなくなっちゃうんだね!そうか、じゃあ男らしくないのも仕方ないわね、アハハハハッ!」ケラケラと朝子は楽しそうに笑った。「あっあぐううううう、そ、そんな・・・もうやべで・・・し、死んじゃう・・・」「アン、ほらそんな情けないこと言わないで!大丈夫よ、検見川さんも奈良村さんも潰されたけど、一応生きてるみたいよ。だから須崎さんも多分きっと・・・上手くいけば命は助かるわよ、うん!」「そ、そんな・・・ひ、他人事だと思って気軽に言わないでよお・・・」「他人事?気軽?何バカ言ってるのよ、あったりまえじゃん!他人事に決まってるでしょ?分かってるの?須崎さんは犯罪者、私たちをレイプしようとした罪人よ。私たちはその罪に対する刑を執行しているだけじゃない!当然のことでしょ?それをなんで私が須崎さんみたいな最低の犯罪者のことを親身になって心配してあげなくちゃいけないの?なんで被害者の私が、加害者の須崎さんに同情してあげなくちゃいけないのよ、バカ言わないでよ!」朝子の顔に怒気が浮かんでいた。
「やっぱり須崎さんって全然反省してないのね!あれだけ焼いてあげたのに未だ反省してないなんて、本当に人間の屑、筋金入りの屑ね。須崎さん、骨の髄まで腐ってるわよ・・・いいわ、たっぷりと懲らしめてやる。須崎さんのタマタマ、両方ともペシャンコに潰してあげるから覚悟しなさいね!」罵りながらペッ、ペッと二度、三度と朝子は須崎に唾を吐き掛ける。そして腰に手を当て須崎を見下ろしながらブーツの爪先で須崎の顎を小突いた。「ほら、武士の情けよ、顎は外してあげるから、口開けて!」だが朝子を怒らせてしまった恐怖にパニック状態に陥った須崎は朝子のイラついた声すら聞こえず、ますます大声で叫びたてた。「ひ、ひいいいいった、たすけでぐでえええええっ!つぶさないでくれえええええっ!」「ああもう!うるさい!だったら・・・こうよ!」日頃はどちらかというと脳天気な、やや天然ボケっぽいところさえあり、決してキツイ印象を与えない朝子の可愛い顔立ちが、夜叉のような憤怒に彩られた。
スッと純白のウエスタンブーツを上げた朝子は委細構わず、大口を開けて泣き喚く須崎の口に強引にブーツの爪先をねじ込んだ。「ウ、ウグッ・・・ぐえっ!」悲鳴を封じられ、苦しそうにのたうつ須崎を憎々しげに見下ろしながら、朝子は一気にブーツを踏みこむ。ガグッ・・・呆気なく須崎のあごが外れる。「アガッ、アガガガガッッ・・・」恐怖に顎の苦痛が加わり須崎的には一層激しく絶叫しているつもりだが、顎を外されたせいで悲鳴の音量は急低下している。「ああ清々した。もう須崎さんの悲鳴はうんざり、聞き飽きたわ。さあ止めよ、須崎さんの大事なとこ、潰してあげる。フフフッ、こんな大きな身体でオカマちゃんになるなんて、なんか結構、キモイわね。」
言うなり朝子はクルリと須崎に背を向け、須崎の左足を跨ぐように立ち、位置を極めると振り向いて冷たく宣告した。「さあ準備できた、と。須崎さんは私のブーツ、特にヒールが大好きみたいだから、やっぱりここもヒールで潰してあげるわね。フフフ、思い出した?私のブーツのヒールの堅さ。お鼻と顎でたっぷりと味わったんでしょ?今度はここにも味合わせてあげる!」
「ギビイイイッ、ヤベ・・・ア゛ビイ゛イイイイイッ!!」刑の執行を宣言した朝子は須崎の哀願を完全に無視して前に振り向き、ブーツを振り上げると一気に股間めがけ、踏み込んだ。グヂャッ・・・堅いウエスタンブーツのヒールで踏まれては一たまりもない。須崎の右睾丸が呆気なく潰れる。検見川が、奈良村が味わったのと同じ激痛が須崎を襲う。「ギベエエエエエッ!イ゛ダイ゛イイイ、イデエエエエエエ!!」
須崎にとって不運だったのは、朝子は一気に二つとも潰すつもりで踏み込んだのに、実際には右しか潰れなかったことだ。堅いブーツ越しでも一つしか潰せなかったのは朝子にも分かる。「ったく、しぶといんだから!全くホント、バカよねえ。人が折角、ちゃんと両方一辺に潰してあげよう、ていうのに変に動くんだから!片方しか潰せなかったじゃない、余計な手間、かけさせないでよね!ほら、今度こそ止め、逝くわよ!」激痛に全身をビクビク痙攣させる須崎に何の憐憫の情も見せずに朝子は再びブーツを振り上げ、再度踏みつける。ベヂッ・・・狙い違わず、須崎の左睾丸も完全に潰れた。念入りに止めを刺すように、そのままブーツで踏み躙る朝子の足の動きが須崎の激痛を更に高めていく。「イ゛、イビイイイイイイ、ブブァッ、オゴグゲエエエエエッ!!!」激痛、吐き気、貧血、ありとあらゆる苦痛が須崎の全身を走る。
「キャッ、もう汚いんだから!」こみ上げてくる胃液を、顎を外されているから吐き出すことすらできずに垂れ流しのように噴出す須崎に朝子たちが一斉に飛びのく。その胃液が逆流し、半ば溺れるように咳き込みながら須崎は意識を失っていった。
吐瀉物と鮮血とに塗れてボロ雑巾のようになった検見川以下、SNOW CRACKの幹部三人が意識を失い、床に断末魔の様相を呈しながら横たわっている。廃工場を奇妙な沈黙が支配していた。佇む美少女四人と縛られて転がる男一人。この場で唯一意識のある男、坊野にとって現状はおよそ考えうる最悪の状況だった。もう自分しかいない。自分しか・・・そして自分を担当するであろう美少女、未だ役割を果たしていない美少女は唯一人、自分の指をバラバラにした礼子だった。物心ついて以来勝手気侭に振舞ってきた坊野にとって、礼子は生まれて初めて本能的な恐怖を覚えた相手だった。肉体的、と言うより精神的に屈服させられた唯一の相手だ。その礼子がスッと自分の方に一歩を踏み出した時、坊野は柄にもなく泣きながら哀願してしまった。
「ヒッウッウェッッッッ・・・お、ねがい、許して、たすけて・・・」その時礼子が浮べた表情は嘲笑、侮蔑といった当たり前のものではなかった。聖母のような慈愛に満ちた弱者に対する憐憫の表情と、強い決意に満ち満ちた戦士の表情が同居していた。「・・・私が恐いの、坊野さん?」フウッと礼子は軽いため息をついた。「まあ無理もないかもね。あれだけ坊野さんの指を痛めつけて、挙句にクラゲにした私だものね。もういい加減に許して欲しい、て思うのも無理ないわね。私ももういい加減、今日一日の暴力の応酬にうんざりしてきてはいるのよ。」一瞬坊野は淡い期待を、礼子が許してくれるのでは、という期待を抱いた。だがその幻想はものの五秒も持たなかった。「でもね、坊野さんのお仲間はみんな逝っちゃったみたいだし、おまけに坊野さんはそちらのプレジでしょ?だったら成り行き上、私もこっちの代表として恥ずかしくないパフォーマンスをしなくちゃいけない、と思うの。」「ヒッヒイッッッそ、そんな、や、やめて・・・」「ねえ坊野さん、障害者プロレス、て知ってる?」
障害者プロレス?坊野も名前だけは聞いたことがあるが、どういうものか見たことはない。「読んで字の如し、文字通り身体障害者のプロレスよ。一見色物、て思うでしょ?ところがどうして、グラウンドや関節技中心の、結構ガチガチのシュート系に近い、セメント勝負のプロレスよ。でね、そのキャッチフレーズがいいの。曰く、
「俺たちは命懸けでやっているんだ、だからお前たちも命懸けで見ろ!」ってね。どう、痺れるフレーズだと思わない?」ゴクッと坊野は息を呑んだ。嫌な、喩えようもなく嫌な予感がする。「そう。坊野さん、私、心を鬼にするわ。今から暫く血も涙もない、残忍冷酷な鬼になって坊野さんのことを責めてあげる。私の全てを、頭も力も技も、全てを使って坊野さんのことを全力で、一切の手加減なしで苛めてあげる。私が本当に全力で苛めたら、坊野さん掛け値なし、命懸けで苦しむことになるわね。だから私もその分、命懸けで苛めてあげる。これから私が坊野さんにする責め、坊野さんにとっては一生忘れられなくなるはずよ。だからせめて、私にとっても一生忘れられなくなるように、他人に対してあんな酷いことをしたのはあの時だけ、て一生記憶に残るように全力で、命懸けで苛めてあげるわね。」
静かな、奇妙なほど静かな口調で礼子は恐ろしい宣告を口にした。そ、そんな・・・やめてくれ!!!余りのことに反射的に絶叫しようとした坊野は自分の身体の異変にぞっとした。声が出ないのだ。余りの恐怖に、自分を散々責め苛んだ美少女の静かな死刑宣告に坊野の肉体自体が恐怖し、機能を停止しつつあった。カエルのように口をパクパクさせている坊野を床に横たえると、礼子はゆっくりとブーツの爪先で坊野の口をなぞった。「さあ、もう分かるわね?須崎さんと奈良村さんは顎を外してもらえたけど・・・坊野さんはどうなるのかしら?」言いながら礼子はブーツをゆっくり動かし、爪先を上に滑らせ、ヒールを坊野の口に当てて軽くノックする。「・・・分かるわね、次の展開は?」礼子はそのままヒールをゆっくりと持ち上げる。焦らすように、ゆっくり、ゆっくりと。そしてついにヒールが止まる。横たえられた坊野の視界に礼子のブーツのヒールだけが妙に大きく映る。ひいっ、せ、せめて顎を外してくれ!坊野の目に声にならない哀願が浮かぶのを見て取った礼子が静かに答える。「そう、ご想像のとおりよ。坊野さんには選択の自由はあげないわ。余りの苦痛に舌を噛み切って自殺する自由も、顎を外して貰って一段階、楽をする自由も。歯をへし折られる苦痛と潰される苦痛、両方フルに味合わせてあげる。それがプレジの務めでしょ?」
坊野の返答を待たずに、礼子は一気に全体重をヒールに掛けながら思いっきり踏み込んだ。グギャベギッバギッ!!!「ギ、ブギギャアアアアアッッッ!!!!!」全体重をかけた礼子の蹴りは当然の如く、坊野の上の歯を数本、一瞬にしてへし折る。更にブーツのソールは坊野の上顎と鼻を踏み潰し、鼻骨もへし折っている。礼子がブーツのヒールを持ち上げると殆ど同時に鮮血が噴き出る。へし折られた歯茎から、口の中に侵入した堅いヒールに傷つけられた口の内部から、そして鼻骨を砕かれた両方の鼻の穴から。「イデエ、イデエヨオオオ、イデエエエエエ!!!」絶叫とともに坊野が必死で頭を左右に振る動きに連れ、飛び散った鮮血が床一面に降り注ぐ。噴水のような勢いはないが、汲めどもつきぬ泉のように鮮血が後から後から止め処もなく溢れ出る。「どう、痛い?でもまだまだよ。今のは上の歯だけ。まだ下の歯が残っているでしょ?」そう、礼子は巧みに蹴りをコントロールし、わざと上の歯だけをへし折っていた。下の歯を残し、もう一度歯をへし折られる苦痛を坊野に味合わせるために。
「さあ、下の歯も行くわよ?上と下、どっちが痛いかしらね?」トントンと予告するかのようにブーツのヒールで下の前歯をノックした。「さあ、逝くわよ?」スーッと持ち上げられた礼子のブーツが再び踏み下ろされる。「ギギャァァァァァッ!」下の歯を数本へし折られた上に、下顎の骨まで砕かれた。「痛いでしょう?でも未だ終わっていないわよ。」礼子は更に坊野の頬を蹴り、横を向かせると上顎、下顎それぞれに更に蹴りを入れ、上下の顎を完全に蹴り砕いた。丁寧に、左から、右からと二セット繰り返し、完全に坊野の鼻と顎を粉砕する。「アラアラ、これで一生総入れ歯確定ね。まあ歯はまだいいとしてもね、きっと今ので顎の骨も砕けたわよ?しっかり踏み砕いたから多分、もう顎の骨、くっつくのは無理よ。あーあ、可哀想に。これで一生、硬いものは食べられないわよ。ステーキもフライドチキンも、美味しいものは殆ど諦めるしかないわね。これからのお供はお粥やお豆腐だけ。ウフフフフッ、つまらない人生になったわね。文字通り味気ない、ていう所かしら?」「あがが・・・あぎひいいい・・・ガボッ、グガアッッッッッ・・・」相変わらず優しい表情で嬲る礼子に反応もできずに喘いでいた坊野だが、不意に苦しげに咳き込みながら全身をビクビクと痙攣させた。「ウン?どうしたの、急に静かになっちゃって、ねえったら!」礼子は砕いた顎を爪先で小突いてみたが坊野の反応はない。指の関節を殆ど全て外された上に歯を10本以上もまとめてへし折られ、おまけに鼻、顎まで砕かれたのだ。言葉にすらできないほどの激痛に喘いでいる上に自分の出血を肺に飲み込んでしまった坊野は遂に痛みの限界値を超え、白目を剥いて気絶してしまっていた。
普通だったらこれで流石の礼子も拷問・リンチ終了だ。だが今日の礼子に対しては気絶など、何の救いにもならない。ゴロリと坊野を蹴り転がし、うつ伏せにさせると礼子は坊野の口に指を突っ込み、飲んだ血を吐かせた。「ゲッ、ゲバアッッッ・・・」
失神したまま坊野が肺に入った血を吐き出すのを確認すると、礼子は坊野の背中に右膝をあて、更に両肩を掴んだ。「・・・ハッ!」「・・ガッ、グハアッッッ・・・」
礼子に巧みな活を入れられた坊野が弱々しい声と共に息を吹き返す。「どう、目覚めた?気絶したらもう終わり、と思ってたでしょ?フフフ、駄目よ。今日は気絶なんかしても絶対に許してあげない。好きなだけ気絶していいわよ。何回でも活を入れてあげるから。」「…して…」「何、何か言った?もうちょっとはっきり言ってくれないかしら?」「・・ゆる・・して…お・ねがい…」消え入りそうな声で坊野は哀願した。その目は涙でうるみ、視線は弱々しい負け犬のものだ。最早最凶ギャングの誇りも何もない。余りに圧倒的な礼子の暴力の前に坊野の精神は完全に打ち砕かれてしまった。
あるのは唯一つ、目の前にいる礼子に対する恐怖だけ。礼子が女の子、自分より年下の美少女であることすら、もう関係ない。目の前にいる礼子は残酷な、余りに残酷な支配者、冷酷な拷問官、純粋な恐怖の対象そのものである、破壊の女神の化身、人間を超えた存在だった。そして、その残酷な女神は許す、等という言葉とは無縁の存在だった。
「許して?残念だけど無理ね。言ったはずでしょう?命懸けで苛めてあげる、て。こんなんじゃあ、まだまだ終わらないわよ。」そ、そんな・・・坊野が必死で口を動かそうとするより早く、礼子が問い掛けてきた。「さてと、ここで一つ質問よ。私の次の責めは何かしら。当ててご覧なさい。当たったら・・・そうね、少しは痛くないようにしてあげるかもよ?」い、痛くなくしてくれる!坊野にとってその言葉は何よりのカンフル剤となった。「まあ結構簡単な質問だと思うわよ。」内心で舌を出しながら、礼子はヒントらしきものを与えた。かすれている意識を必死で叩き起こしながら、坊野は必死で考えた。そして、その必死さは当然のように礼子の仕掛けた罠にはまり込んでしまった。か、簡単・・・み、みんながやられたのは・・・「つ、潰す・・んです・・・か・・・」フフ、こうも簡単に引っかかるとはね。「潰す?タマタマを潰す、て思うの?それが坊野さんのファイナルアンサーでOK?」「・・・は、はい・・・」「ブーーッ!外れよ。坊野さん、結構頭悪いわね。簡単だ、て言ったでしょ?私、さっき言ったはずよ。あなた達の肩と股関節、四箇所全部の靭帯を引き千切って再起不能にしてあげる、て。他の三人はもう失神してるから後回しにして、坊野さん、あなただけは特別扱い。あなただけは潰すより先、意識がある内に、痛みを十分に感じられる内に引き千切ってあげるわ。」
凄絶な微笑を浮かべながら、礼子は坊野の右腕を掴むとグルグル回して見せた。「どうかしら?普段だったらこんな角度では肩、回らないはずよ。関節外したおかげでこんな回転ができるんだけどね、生憎これじゃ、いくらやっても靭帯、千切れないのよ。まずは下拵えをしないとね!」楽しそうに言いながら、礼子は掴んだ腕を反時計回りにほぼ一回転ねじ上げる。「い、いでえええっ!」早くも坊野の悲鳴があがる。
「痛い?でもこれからもっともっと痛くなるわよ。」礼子は腕をもうこれ以上絞り上げられない、というところまでねじ上げると膝を坊野の肩に当てて力の支点とした。
「ウフフフフッ、さあ準備OK!私も結構何人もの靭帯を伸ばしたり、関節を外しちゃったことはあるけど、流石にこうやって意図的に靭帯を引き千切るのは初めてよ。どう、怖い?私がこの腕絞り切ったら、坊野さんの靭帯、ブチブチ、て音立てて千切れる筈よ。そうしたら・・・多分、もう一生直らないわね。可哀想、一生片輪、確定ね。」「い、いやだ、いやだあああああっ、やめ、やめでぐれえええええっ!」
坊野は必死に腕を振り解こうとするが、礼子の束縛はびくともしない。「無駄よ。肩は外してあるんだから、坊野さんの力は半減以下よ。それに第一、これだけねじ上げてあれば、力を出すどころじゃないわよ。嘘だと思うなら試してご覧なさい。ほら、振り解いてもいいのよ、できるものならね!」笑いながら礼子は坊野の腕を前後左右に小刻みに揺り動かした。「あひっ!あいつっ!いだっ、いたいいい!」礼子に翻弄される度に坊野の肩に様々な角度から痛みが走る。痛みにあえぎながらも坊野は必死でなんとか自由になろうともがくが、礼子の言うとおり、肩には殆ど力が入らない。
力を入れる度に却って肩に痛みが走るのだが単に余計痛いだけで、力が入り自分の思うように腕を動かせる感触は全くない
「どう?もういい?じゃ、処刑開始よ!」礼子は腕をギリギリと絞り上げながらゆっくりと前方向に坊野の腕を倒していく。ギジッ、ミジッ・・・既に限界値まで伸ばされていた靭帯に更に負荷がかかる。人間の靭帯は丈夫だ、そう簡単には千切れるものではない。だが礼子は手首と肘を極めながら梃子の原理で絞り上げ、坊野の肩に強烈な負荷をかけている。「ひぎっ、ひきいいいっ!ぐふぁっ!?」坊野の声が甲高くなっていく。靭帯が伸び、千切れかけていく音、実際には音などしないのだが、責めている礼子と責められている坊野の二人だけは、その音を確かに感じていた。耳ではない、全身で感じていた。ち、千切れる!!!「・・・感じるわ、坊野さんの腕が壊れていく音を。全身が悲鳴を上げているわね。もうやめて、もう限界だ、て。これ以上逝ったら本当に千切れる、て言ってるわ。フフフ、坊野さんの全ては今、私のものよ・・・」礼子の全身にゾクゾクするほどの快感が走った。この快感を直ぐに終わらせるのは勿体無いわ。礼子は二度、三度と坊野の肩を絞り上げたり緩めたりして弄んだ。うん?さっきより少し前まで倒せるみたいね。「あら坊野さん、肩の可動域、少し広がったみたいよ。ストレッチング効果、といったとこかしら。よかったわね、少し希望が出てきたじゃない、このままもっともっと柔かくなれば、引き千切られないで済むかもよ?」「あ、あぎぎぎっっっ!ひ、いでえええええっっっ!そ、そんな、いだい!も、もうだめだあああ、いや、やめて、放してくれえええっ!」礼子の美貌に満足げな笑みが浮かぶ。「駄目よ、あきらめちゃ!人間は無限の可能性を持ってる、て言うでしょ?それを信じなさい!自分の限界を認めちゃったら・・・その時は靭帯を引き千切られちゃう、てことを忘れないでね。さあ、逝くわよ!」「ヂ、ヂギレルウウゥッ!ヂギレジャウッ!ギャビャアアアアアアアアアアアアァッ!!!」
ゆっくりゆっくりと礼子は坊野の肩を絞り続けた。ゆっくりゆっくりと、坊野の靭帯が千切れる限界ギリギリまで負荷をかけては少し緩め、また絞り上げ、延々と激痛を味あわせ続けた。「い、いや、ビギャァァァァッッ、は、はな、しゃべ、な、なんでもしゃべるよ、しゃべるがら、アギアッ!いや、ゆるめで、ギャヒイッ!ちょっと、ちょっどでいいいいいからあああっ!!ゆ、ゆるめで、はなじでぐれえええええっ!しゃべるあいだだけでもおおお!ゆ、ゆるめでぐれえええええっっっ!!!」だが礼子は坊野の悲鳴などどこ吹く風で相変わらず涼しい顔だ。「あら坊野さん、もう拷問は終わったのよ。別にもう、これ以上喋ってもらうことなんかないわ。聞くべきことはもう十分に聞かせて貰ったわよ。後はあなたを処刑するだけなの。だから安心してゆっくり苦しんで頂戴。いいってことよ、遠慮はいらないわ、坊野さんと私の仲じゃないの!」ヒイッ!そ、そんな!拷問ではない、礼子のその言葉は坊野の救いを全て断ち切るものだった。もう白状しようが何をしようが、この激痛から救われることはない。本当に片輪にされる・・・坊野の精神は恐怖と絶望に崩壊一歩手前だった。
だが坊野自身より早く、礼子は坊野の自我が崩壊しようとしているのを見取っていた。フン、そろそろ限界のようね。いいわ、まずは一本、引き千切ってあげる。発狂なんかさせてあげないわよ、フフフ、この激痛で意識を叩き起こしてあげる。最強のカンフル剤になるわよ!礼子は大きく息を吸った。「だいぶ痛そうね、ウフフフフッ、さあ、じゃあこの腕、そろそろ引き千切ってあげるわね。いーち、にーの・・・さん!」「ビッビアアアアアッ!あぎゃっ、アギイイイイイッ!!!」断末魔のような坊野の絶叫が響き渡る中、礼子はゆっくりと最後の一線を超えていった。既に限界に達して伸びきり、筋繊維が脆くなっていた坊野の肩の靭帯が遂に抵抗不能となった。ブツッ・・・ビヂッブヂッ・・・バッヅッ・・・その音は周りにいる玲子たちには聞こえなかった。その音を聞いたのは処刑官の礼子と受刑者の坊野の二人だけだった。いや、聞いたというのは不正確かもしれない、感じたと言った方が正確だろう。
最後の一線で抵抗していた靭帯が遂に限界を超えてこれ以上持ちこたえる力を失い、一本、また一本と筋繊維が断裂し、千切れていった。
「ひっひぎいいいいいっ!いだい!いいいいっ!!ああああっ!!!」坊野の悲鳴は完全に裏返り、金切り声となって響き渡る。「いぎゃあああああっ!い・だ・いいいいいいっっっ!!!」ああ、本当にいい声。ゆっくりゆっくりと坊野の肩を破壊しながら礼子は今まで味わったことのない程の快感に浸っていた。礼子が少し、また少しと締め上げる度に坊野の断末魔が響く。ああ坊野さん、あなたって最高・・・私の精神とあなたの精神、今完全にシンクロしてるわね。私の動きとあなたの叫び、私の快感とあなたの苦痛、今完全に一つに溶け合っているわ・・・もう少し、もう少しよ・・・もうすぐ一緒になれるわ・・・礼子がまた少し絞る。ミジッ、また一本坊野の筋繊維が断裂する。「ウ、ウギャアアアアアーーーッ!」ああ、そうよ、その反応、私の責めにリアルタイムのその絶叫、最高よ・・・礼子は最早坊野のことを憎んでなどいなかった。リターンマッチを挑まれては面倒、という恐怖心すらもうない。礼子の心を占めているのはいとおしさ、坊野のことを限りなくいとおしく思う心だった。ああ、私と坊野さん、今完全に理解しあっているわ・・・同じ時間を共有している・・・いつまでも、こうやってずっと二人で、二人だけでいられたらいいのに・・・さあ、一緒に昇り詰めましょう・・・愛情、と言ったほうがふさわしいかもしれない穏やかな、優しい感情だった。勿論坊野の側にそんな感情は毛頭ない。想像を絶する苦痛に喘ぎ、絶望に打ちひしがれている坊野に愛だの何だのを語る余裕など全くない。
一方的な、完全に一方通行の愛情。だが礼子の愛情は坊野の全てを、肉体も精神も全てを奪い尽くし焼き尽くす激情だった。
プヂッ・・・「ギアアアアアッ!ア!ギギギイイイイーーーッッッ!!!」ああ、切れたのね・・・最高・・・痛いでしょう?最高に痛いでしょう?気が狂いそうな位の痛さでしょう?私もよ・・・私が坊野さんを破壊し尽くしたのね・・・最高・・・最高に気持ちいい・・・私もこんな気持ちいいの、生まれて初めてよ・・・遂に坊野の右肩の靭帯、最後の一本が断裂する破滅の音が響いた。力が全く入らなくなった坊野の右腕を漸く解放した礼子は暫しの間、全身に満ち溢れる快感の余韻に浸りながら苦痛に喘ぐ坊野を見下ろしていた。その視線に先ほどまでの鋭さ、残酷さはもうない。相変わらず微笑を浮かべていたが、その微笑は慈愛に満ちた、何とも優しげな微笑だった。満面に優しさを湛えながら、礼子は坊野の左腕を取った。「あ、や、やだ、ひいっ、お・・ねがいだ・・・やめて・・・くれ・・・」虫の息で涙を流して哀願する坊野に礼子は相変わらず微笑みながら首を振った。「そんなこと言わないで、坊野さん。私とあなたの二人だけの時間、もっともっとたっぷりと楽しみましょうよ。時間は十分あるわ。腕一本と足二本、ゆっくりと楽しみましょう?」「や、いや、いやだあああっ!だ、だれか、誰か助けて、たすげでぐれええええっ!こ、ころされるううううっっっっ!!!」「心配しないで、私が坊野さんのこと、殺したりするわけないじゃない?だって私のことを世界で一番分かってくれているのは坊野さんなんだから。そうでしょう?」確かにその通りだった。他人の肉体を、精神をなんら良心の呵責を感じずに完膚なきまでに破壊し尽くし、相手の自我の崩壊を無常の喜びとする礼子。その礼子の本質を骨の髄まで叩き込まれたのは坊野だけだ。慎治たちだってここまではやられていない。魅入られた者を最悪の破滅に追い込む破壊の女神、拷問室の天使。その女神に魅入られた坊野に許されることはただ一つ、苦痛を味わい続けることだけだ。「坊野さん、私を分かってくれて嬉しいわ・・・私も坊野さんを世界で一番理解しているわ・・・坊野さんの苦痛、嘆き、悲しみ、後悔・・・全部分かっているわ・・・さあ、もっともっと理解しあいましょう・・・もっともっと感じさせて、坊野さんの全てを・・坊野さんの今までの人生は全て、私に会う今日のための準備に過ぎなかったんだから・・・私が坊野さんの今までの人生に意味を与えてあげるわ・・・」恐怖に蒼ざめ、全身を震わせる坊野の左手を礼子が優しく、しっかりと握り締めた。
たっぷりと時間をかけて礼子は坊野の左肩、そして両足を破壊していった。何回となく坊野は気絶しては活を入れられて無理矢理意識を取り戻させられ、再び靭帯が引き千切られる苦痛を味合わされた。漸く礼子の人体破壊が一段落した時、床に転がっている坊野は自力では殆ど動くことすらできなくなっていた。四肢の関節を全て外され、靭帯を引き千切られ、指の関節も何箇所も何箇所もへし折られていた。想像を絶する苦痛に全身の筋肉は痙攣するほど緊張し、間断なく悲鳴を上げ続けた喉も破れて血が流れていた。全身の全てのエネルギーを使い果たし、ボロ雑巾の様になって坊野は床に転がっていた。「あ・・・あぎぎぎ・・・」関節を破壊された痛みは一過性のものではない。体内で進む内出血、炎症に坊野の痛みは全くと言っていいほど軽くならない。激痛から嘔吐感を伴う鈍痛に変わりつつあるが、痛みの程度としてはむしろ余計ひどくなっているような感じさえする。礼子はそんな坊野を満足そうに見下ろしていたが、やがてゆっくりと坊野を仰向けに引っくり返した。先ほどまでのように、乱暴に蹴り転がすのではない。優しく慈しむかの様に坊野を抱きしめながら、礼子は仰向けに坊野の体を横たえた。
8
「がっ!いだい・・・」礼子がいくら優しく転がした、とはいっても関節に力が加わり、坊野の全身に新たな激痛が走る。「痛い?大丈夫よ、直ぐに次の責めに移ってあげるから。その痛みは暫く、忘れられるわ。」暫く!?忘れる!?ま、まさか・・・怖くてその先を言葉にすることは流石にできない。「そう。これが今日の私と坊野さん、二人のデートの仕上げ、クライマックスよ。さあ、精一杯楽しみましょう。」
「ヒ、ヒッ、ヒイッ!そ、そんな、まさか、つ、つぶす・・・の?やめて・・・もう許して・・・し、死ぬ、ほ、本当に死んじまう・・・」絞り出すような声で、両目一杯に涙を浮かべて哀願する坊野の髪を優しく撫でながら、礼子は何とも穏やかに微笑んだ。
「死ぬ?大丈夫よ、ちゃんと歯は折ってあげたでしょう?痛さの余りショック死、ていう可能性はあるけど、人間そう簡単には死ねないものよ。交通事故かなんかで潰れちゃったけど生きてる人っていうのは結構いるんだから。坊野さんも多分、助かるわよ。」柔らかい声で恐ろしい宣告をしながら、礼子は坊野のチノパンとトランクスを脱がせた。坊野の一物は哀れなほど縮み上がっていた。その一物をそっと持ち上げながら、礼子は坊野の睾丸を両手に一つずつ、優しく包み込んだ。「坊野さん、私、男性の玉を触るのなんて初めてなのよ。うん、ちょっぴり恥ずかしいわ・・・だけど大丈夫、安心して。あなたのなら私、大丈夫よ。私の初体験、坊野さんにあげるわ。坊野さんも女の子に潰されるのは勿論初めてでしょう?」
礼子はゆっくりと、まずは右手に力を入れていく。「ぐっ・・あはっ・・・おばっ、い、いいいいい!!!」先程までの痛みとは異質の、体の奥底にズシリと重く響くような痛みに坊野は溜息をつくような、押し殺された悲鳴を漏らした。フーン、潰される時ってこういう声になるのね。さっきまでの金切り声の絶叫とはずいぶん違う悲鳴ね。「ねえ坊野さん、いいこと教えてあげようか?私ね、こう見えても握力には結構自信があるのよ。大抵の男の子には負けたことないわ。いくつだと思う?私ね、両手とも60キロあるわ。どう、驚いた?もしかしたら坊野さんより上なんじゃない?」
ろ、60キロ?激痛にボヤケた意識の中で坊野の頭の中を、その非現実的とも言える数値が飛び回った。ろ、60キロだって!?お、おれでさえ50キロそこそこだぞ、それをこんな細い女の子が出すなんて、マジかよ。怪力自慢の須崎といい勝負じゃねえか・・・こ、こいつ化け物か?坊野が怯えるのも無理はない。普通、かなり鍛えた運動部系の女の子でも握力の平均値は30キロ台前半だ。40キロあれば相当に強い方、柔道、空手等、格闘技系の男でも50キロ台なら通常、十分な握力だ。勿論、怪力自慢のプロレスラーや力士等、100キロを超える人間もいるが、それは基本的には異常値の世界であり、一般的には男でも、60キロと言えば十分、握力自慢で通用するレベルだ。そ、それをこんな細い女の子が出すなんて・・・坊野は涙で曇った目で改めて礼子の腕を、肩を見てしまった。確かに細いとはいえ、引き締まった腕には十分な、鞭のような強靭かつしなやかな筋肉が秘められていそうだ、だがどう見てもそんな怪力型、ゴリラタイプには見えない。ま、マジかよ・・・こいつ、化け物か・・・化け物、その言葉を坊野は何度も何度も反芻した。急速に礼子が人間を超えた何か、非現実的な存在に思えてきた。ゾクッ・・・坊野の背筋になんとも言えない悪寒が走った。目の前にいる、自分を責め苛み続ける美少女が想像を超える怪物、悪魔に思えてきた。坊野の精神が感じる礼子は強大な悪魔だ、だがその目に映る現実の礼子は美しい、天使、とさえ言いたくなる程の美少女だ。そのギャップが坊野の恐怖を余計に掻き立てる。し、信じられねえ・・・坊野は何度となくその言葉を歯をへし折られた口で呟き続けた。だがそれも束の間、礼子は優雅に呟いてなどいられないレベルに責めをアップし始めた。
坊野の目に怯えの影が浮かんだのを見て礼子は微かに微笑みながら右手を緩めた。
「ゼッ・・ゼハッガッ・・・」坊野が荒い息をつくタイミングを礼子はじっと見ていた。「ゼハッ・・・グブアアアアアッ!」坊野が息を吐ききったまさにその瞬間を狙って礼子は今度は左手に力を込める。たちまち先ほどまでと同じ、内臓を鷲掴みにされたような痛み、苦しみが坊野の全身を支配する。いや、先ほどまでと同じではない。礼子に睾丸を締め上げられた坊野は余りの苦しさに息が詰まり、半ば呼吸困難状態だ。だが今度は息を吐き切った瞬間に締め上げられているのだ、肺に空気は殆どない。「グウ、ウウウッ・・・グヘッ、ゲグッ、ゲハッ!ゲハアアッ!!!」苦しさに喘ぐ坊野は空気を貪るように必死で口をパクパクさせ、その拍子にへし折られた歯茎から未だ止めどもなく溢れつづけている自分の血を肺に吸い込んでしまったからたまらない。たちまちの内に抑えようのない、止め処もない咳が重症の喘息患者の発作のように坊野の全身を痙攣させる。
喘息患者が酷い発作に襲われると、しまいに呼吸困難からチアノーゼ症状を起こすように、坊野もまた空気を奪われる苦しみ、そこに、目の前にいくらでも空気はあるのに殆どそれを吸えない苦しみに全身を痙攣させてもがき苦しみ続けた。礼子は巧みにインターバルをおき、責める睾丸を時々変え、痛みが新鮮さを失わないように最新の注意を払いながら坊野を責め苛みつづけた。
「ウフフフフッ・・・その調子よ坊野さん、人生で最高の痛みでしょ?私も最高。こんな楽しいのは初めてよ。さあ、もっともっと聞かせて頂戴、坊野さんの最高の声を!魂の叫びを!」礼子は満面に笑みを湛えながら両手で同時に左右の睾丸をしっかりと握り締めた。「さあ、今度は両方いっぺんに苛めてあげるわ。お楽しみも二倍よ!」ギシッ・・・礼子が両手に力を込めると同時に坊野の全身を更に倍加された激痛が抱きしめる。「ガアッ、ギ、ギアッ!ギャアアアアアッッッ!!!」坊野は必死で身をよじり、何とかこの地獄から逃げ出そうとした。だが四肢を全て砕かれ、更に最大の急所である睾丸をしっかりと抑えられていてはどうしようもない。逃げるは愚か、腰を浮かすことすらできない。動かない手足を波打たせ、それが神経を余計に刺激して更に坊野を苦しめる。「嬉しい・・・坊野さん、こんなに喜んでくれているのね。そんなに全身が震えるほど嬉しいのね!私もよ、私も最高に嬉しいわ!喜んで、また新しい責めを考えついたわよ!もっともっと苦しんでね、ほら、今度はこうやって苛めてあげる!」白い頬を上気させながら、礼子はまるで揉み洗いをするかの如く、両手に握り締めた坊野の睾丸を激しくこすり合わせ、睾丸同士をグニグニと押し付け、こねくり回した。「イヤアアアアアッ、イ、イダイ、デエ、イデエヨオオオオッ!ヤ、ヤベ・・・グバアアアッ、ゲ、ゲバッ!ヒッ!ピギイイイイイッッッ!!!」激痛の余り目の前が真っ暗になっていくようだった。痛い、苦しい・・・その極限点、礼子の両手が自分の体内に侵入し、内臓を鷲掴みにされているようだった。礼子が睾丸同士を打ちつけ、こすり合わせ、相互に潰し合わせる動き、僅か数ミリ、数センチ単位に過ぎない睾丸の変形が坊野の全身に悪寒と強烈な嘔吐感を伴った激痛を駆け巡らせる。体の表面や筋肉、骨といった組織ではない、生命維持に直接関わる内蔵そのものを礼子に破壊されているかのような激痛に、坊野の生物としての本能が全力で悲鳴をあげ、警告を最大音量で発している。これ以上責められるのは生命に関わる、と。「グッ、グボアアアッッッ・・・」坊野は内臓そのものが飛び出てくるかのような強烈な嘔吐に見舞われた。だが既に激痛の余り、本人が気づかないうちに何度も何度も嘔吐していた坊野の胃袋には内容物など最早ない。吐き出された僅かな胃液と空気、それは口の中に溢れ続ける血と混じりあい、ブクブクとカニのような泡となって口の端から零れ落ちた。真っ赤に染まった血泡を吹き出しながら、激痛に半ば錯乱状態に陥りつつある坊野は白目を剥いて気絶しかけていた。だが礼子が気絶などという救いを許してくれるわけがない。
坊野を責め続けた両手を一旦休め、痛みの余韻に痙攣し続ける坊野の胸を、まるで赤ん坊でもあやすかのように礼子は掌で優しく、トントンと叩いた。「ひっひあっっっっっ・・も、もう・・・や、べ・・・て・・・」坊野の哀願はもはや微かな独り言並みのボリューム、よっぽど注意深く耳を傾けないと聞こえないレベルにまで落ちていた。礼子はそのまま坊野の心臓の上にそっと手を置いた。
早鐘のように凄まじい速さで鼓動を打っているが、なんとなく鼓動が弱々しくなってきたような気がした。フウッ・・・礼子は小さく溜息をついた。楽しい時って本当にあっという間ね。もう坊野さん、本当に限界が来ちゃったみたい。仕方ないわね・・・「フウッ・・・坊野さん楽しかった?とのデート。私は最高だったわ。生涯最高に楽しいデートだったわよ。でもどうやらお別れの時間が来たようね。私とのデート、坊野さんにとっても一生の思い出になったかしら?でもね、デートは別れ間際が一番盛り上がるのよね。さあ、最期にとびっきりの思い出を刻み込んであげるわ!」礼子は最早虫の息の坊野の睾丸、左の睾丸をしっかりと右の手掌に包み込み、更に上から左手を添えた。「さあ・・・逝くわよ・・・」礼子はゆっくりと両手に力を込めていった。「・・・イ、ガッッッ!ギッヒイイイイッッ!ア、アウウウウッッッ!!!」激痛が坊野の意識を蹴り起こす。睾丸を、いや体の中心、はらわた全てを握り潰されるような激痛に坊野が全身を痙攣させながら苦しげに喘ぐ。「うん、そうよ・・・いい表情・・・最高よ・・・こっちを向いて・・・坊野さんの表情、よく見せて頂戴・・・そう、そうよ・・・いいわ・・・さあ、いよいよよ・・・逝かせてあげる!」礼子は60キロの握力全てを一気に解放した。「アッ!アアッ!ギ、ヤ、ベデエエエエエッ!ツ!ツブ、ギャアアアアアアアッッッ!!!」ブヂュッ・・・聞く者の耳に一生こびりついて離れないような凄まじい悲鳴の影で、微かな音を立てながら坊野の左睾丸が潰された。ブクブクと口から血泡を吹きながら坊野が全身を痙攣させている。痛い、等という言葉は生温い。腹の中に無理矢理巨大な鉛の塊を詰め込まれたかのような圧迫感を伴った鈍痛、そしてその鉛の塊は氷のように冷たく、はらわたを、全身の熱をあっという間に奪い尽くすかのようだった。そして全身の血液がそこに流れ込んでいくかのように、坊野の左睾丸が急速に腫れ上がり、ボールのように膨れ上がっていく。「ウ、ウグアアアアッ・・・ゴブアアアアッ・・・」何度目かの嘔吐に全身を震わせながら、随意筋、不随意筋を含め全身の筋肉を最早自分では全くコントロールできなくなった坊野は礼子の足元でついに失禁してしまった。
素早く手を引っ込めた礼子は、坊野の失禁が止まると今度は右の睾丸を左手で握り、上から右手を添えた。「ウフフフフッ!坊野さんったら!そんなに気持ちよかったの?おしっこ漏らしちゃう位気持ち良かったのね。嬉しい、そんなに喜んで貰えるなんて、私も最高に幸せよ。でもね、もう正真正銘、お別れの時間が来たようね。さあ、こっちも潰してあげるわ。この玉が潰れたら・・・私と坊野さんもお別れね。楽しかったわ坊野さん、あなたのことは一生忘れないわ。坊野さんもでしょ?」礼子が徐々に握力を解放していく。「ギッ!ヒッ!ヒヒャッ!ヒギッ!ハヒャアッ!!!」坊野の悲鳴はどこか、笑っているような響きがあった。「ハッ!ハヒッ!ハヒッ!ハヒヒッ!ハヒヒヒヒッ!ハヒヒヒヒイイイッ!!!」坊野の目は裏返り、完全に白目を剥いている、口はだらしなく開き、血泡を垂れ流している。痛い、苦しい、という感覚すらどこかに飛び、他人事のようになっていた。視界が暗くなり真っ暗な中、目の前でチカチカと星が瞬いた。「さようなら、坊野さん!」ブヂュウッ!!!「アッ!アビイイイイイッッッ!!!」礼子が全てのパワーを解放し、坊野の右睾丸をペチャンコに潰すと同時に坊野の喉から断末魔の悲鳴があがった。完全に意識を失った坊野の体から、永久に失われた男の機能とプライドの名残かのように、白い精液がドクドクと流れ出していた。通常の何倍もの量の放出、いつもなら快感に震えたであろう坊野だが、今は射精の喜びに何百倍も勝る喜びに浸っていた。やっと失神できる、全身を支配する苦痛から束の間とは言え解放してくれる、失神という喜びに咽び泣きながら、坊野の意識は何もない、暗黒の虚無に堕ちていった。
あ、ああ・・・慎治たちは呆然と眼下に広がる地獄絵図を眺めていた。ついさっきまで最凶を誇っていたSNOW CRACKの四人がボロ雑巾のように横たわっていた。全身血塗れ、手足はあらぬ方向に折れ曲がっていた。今は玲子たちが最後の後始末、奈良村たち三人の靭帯をねじ切っているところだった。普通だったら想像を絶する激痛を伴う筈だ。だが睾丸を潰され、人生最大の激痛に悶絶しながら気絶していった奈良村たちはピクリともせずに為すがままにされていた。そ、そんな・・・坊野さんたちがやられるなんて・・・慎治たちは未だに自分たちが見ている光景を信じられなかった。礼子たちが強いのは分かっていた。残酷なのも身をもって味合わされている。だがこれほどまでとは・・・全てのリミッターを取り払った礼子たちの恐怖は底無しだった。復讐、固く心に誓ったつもりでも上っ面だけ、所詮は他人を雇う、という程度の覚悟しかできなかった自分たちと傷つくリスクを省みずに前に出て危機を乗り切った礼子たち。しかも闇雲に前に出るのではなく、礼子たちは慎重な計算と何重もの安全確保も図っていた。差が、余りにも差があり過ぎた。そして今、時は満ちた。坊野たちは礼子たちの拷問に屈し、慎治たちに端金で雇われたことを洗いざらい白状していた。
あ、ああ・・・ど、どうしよう・・・もう逃げ道はどこにもない。呆然と涙を流しながら思考停止に陥っていた二人に真弓が声を掛けた。「さあ信次、下も終わったようだし、そろそろ玲子に電話して降りていこうか。」恐怖の、死刑宣告に等しい一言だった。「・・・あ、ああ・・・や、やめて・・・」「何言ってるのよ!信次も見てたでしょ?坊野さんたち、玲子たちに拷問されてあんたたちのこと、全部喋っちゃったじゃない。今更やめても何もないでしょ?」笑いながら真弓が携帯のコールボタンを押すのを信次たちは呆けたように見つめていた。「あ、玲子?私、真弓よ。うん、今ここの二階にいるのよ。里美もいるわ。でね、まあ玲子も察しがついてるとは思うけど、スペシャルゲストも一緒よ。そう、信次たち。二人ともいるわよ。どうする?うん、下に連れてけばいいのね。OK、直ぐ行くわ。」携帯を切った真弓が信次に微笑みかけた。「信次、玲子が一緒に下に来て、てさ。じゃ、行こうか。」信次たちは半ば腰が抜けかけていたが、最早真弓たちに逆らう気力もなかった。されるがまま、半ば抱きかかえられるようにして立ち上がると階下へ引き摺られていった。
「あっ、来たわね信次!この!」待ち構えていた玲子が真弓から信次を受け取ると軽く頭を小突いた。「全く、ギャングを雇って私たちを襲わせるとは、随分と小ジャレタ真似をしてくれるものじゃない?ねえ礼子?」礼子もにこやかに笑いながら答えた。「全くよ。あんなに毎日、私たち美女軍団がたっぷりと遊んであげてた、て言うのに、この仕打ちなんだもんねえ。何か、飼い犬に手を噛まれた、ていう感じかな?」にこやか、礼子たちが妙ににこやかなのが慎治たちにとって却って恐ろしかった。きっといきなり殴りかかられる、蹴りつけられて坊野たちと同じような拷問に掛けられる、と思っていた。それが礼子たちは妙にフレンドリーだった。な、なに、なにを企んでいるの・・・信次が怯えているさまを楽しんでいた玲子の口元が緩んだ。
「信次、信次が何考えてるかは分かるわよ。私たちに拷問されるか処刑されるか、兎に角死ぬほど痛い目に会わされる、て怯えてるんでしょ?フフ、バカねえ、そんなことする訳ないじゃない。罪を憎んで人を憎まず、て言うでしょ?だから私たち、信次たちのことを憎んではいないのよ。」礼子も大きく頷いた。「そうよ。私たちがそんな鬼だと思う?可愛い可愛い、大事な慎治たちを処刑するなんて思ってるの?そんな訳ないでしょ。悲しいわ、私たちの優しさが未だ分かってないのね?」予想だにしない展開に戸惑う慎治たちを見て朝子がケラケラと笑った。「バッカねえ信次ったら!玲子たちが何て言ってるか分からないの?要するにね、許してあげる、て言ってるのよ!全く鈍いんだからもう!最も」クスクスと笑いながら朝子は続けた。「本当に許してあげるかどうかはフミちゃん次第かしらね。なにせ今日の最大の被害者はフミちゃんだからね、最終判決を下すのはやっぱりフミちゃんだと思うわよ?」
フ、フミちゃん・・・ごくりと息を飲みながら慎治は富美代の方を怯えためで見た。
フ、フミちゃん・・・あの気性の激しい富美代が、自分を嵌めようとした慎治たちを許せるとは思えなかった。だが富美代は意外なほど明るい声で笑った。「アハハ、最終判決ね。そうね・・・まあついさっきまでは慎治たちのこと、絶対許さない、て思ってたんだけどね。先輩のこと踏み付けながら、慎治も絶対私のヒールでズタズタにしてやる、体中穴だらけにしてやる、て思ってたんだけどね。だけどまあ・・・先輩の鼻グチャグチャにして、タマタマも潰しちゃったら何か、スッキリした、て感じかな。いいよ慎治、私も許してあげるわ。飼い主の礼子たちがいい、て言うなら、私も文句言わないよ。」「お、おおおっっっ・・・」「あ、ああ、あああああっっっ・・・」慎治たちの口から歓喜とも嗚咽ともつかぬ声が漏れた。た、助かった・・・こ、殺されないですむ・・絶望、絶体絶命、絶対に助からない、と思っていただけに、生き残れる、殺されないですむ、という嬉しさは想像を絶するものだった。
「あ、あ、ありがとう・・・」「ご。ごめんなさい。ごめんなさい・・・」慎治たちは殆ど無意識の内に礼子たちの足許に跪き、ブーツにキスしていた。血に塗れ、幾多の悲鳴を吸ったブーツに。
そんな二人を見下ろしながら礼子たちは満足げに頷きあった。礼子が小さく頷くのを合図に、玲子がブーツにキスしている信次を小突き起こした。「さあ二人とも、許してもらった喜びに浸りたいのはわかるけど、今日はもうお開きよ。私たちはこれから後始末、この人たちを警察に引き渡さなくちゃいけないから、まだ一仕事あるの。だから今日は信次たちと遊んであげられないのよ。今日のところはこのまま、真弓たちと一緒に帰りなさい。」か、帰れる!生きてここから帰れる!は、早く、早くここから逃げ出さなくちゃ、玲子たちの気が変わらない内に・・・未だ力がうまく入らない足を絡ませフラフラしながら信次たちは工場から逃げだそうとした。だが工場を出る直前、礼子が発した言葉は二人の心臓を一瞬にして凍りつかせてしまった。「慎治、あなたたちの罪は確かに許してあげるわよ。でも罪と罰、て言うでしょ?罪は許すけど、罰はキチンと与えるからね。どういう罰を与えるかは月曜に学校で宣告するわ。楽しみにしていなさいね!」

Bo
bootslover
Re: 【转载·日语原文】レイコとシンジ リベンジ編 と 復讐するは我にあり編
感谢大神分享!不知有没有大神愿意翻译一二?
1
恐怖に震えながら、それでも漸く慎治たちは家に辿り着いた。復讐の無残な失敗、そして礼子たちによる「罰」の宣告。一体どういう目に合わされるのか、坊野たちが想像を絶する、ある意味で非現実的ともいえる程の責めを味あわされるのをたっぷりと見せ付けられただけに、慎治たちの恐怖は気も狂わんばかりのものだった。そんな慎治たちにとっての希望はたった一つ、礼子たちが警察を呼ぶ、と言っていたことだった。確かに坊野さんたちは礼子さんたちをレイプしようとした、だけど・・・だけどあそこまで無茶苦茶やったんだよ・・・坊野さんたち、全員片輪にされちゃったんだ・・・あの怪我、隠しようもないよね・・・だったら、幾らなんでも礼子さんたちも罪に問われるわね、過剰防衛どころじゃない、拷問まで楽しんでたんだから・・・流石に警察だって礼子さんたちのこと、調べるよね、そうしたら、少なくとも暫くは礼子さんたちだって、僕たちに関わりあう暇はないはずだよね・・・
だが現実は慎治たちの淡い期待に冷たく背を向けていた。冷静沈着かつ用意周到な玲子の用意は単に戦闘だけには留まらなかった。玲子たちは慎治たちを送り出すと、落ち着き払ってかねてからの手筈通り、まずは自分たちの両親に電話を入れた。可愛い娘とその親友がレイプされかかり、辛うじて相手をKOしたものの恐怖に怯えて涙ながらの電話を入れてきたのだ。玲子たちの両親は直ちに持てる力、人脈の全てを駆使して愛娘の力になる手配をした。警察、弁護士、そして政治家に至るまで。地元の有力者である玲子たちの両親がダブルで動いたのだ、その影響力は強力なものだった。
そしてもう一つ、極めて強力な別ルートも作動した。それは良治たちのルートだった。良治たち自身は別に、有力者の一族ではない。だが体育会、東大でいうところの運動会ルートは礼子たちの利による?がりとは別の、先輩-後輩ラインという極めてウエットかつ緊密な?がりを持っていた。無論、警察上部にもOBはいる。所属部の中核選手であり、OB間にも極めて顔の広い良治たちが自分の教え子がトラブルに巻き込まれて危機に瀕している、お願いします先輩、助けて下さい、と泣き付いたのだ。この威力は即効的だった。なまじ利によるところがなく純粋なお願いベースの分、受けたOBも極めて気軽に、速攻で対応してくれていた。手配を終え、一呼吸したところで玲子たちは警察に電話を入れた。勿論、攫われてレイプされかけた哀れな犠牲者として。全ては計算通りだった、たった一つの誤算を除いては。玲子たちにとって意外だったのは、これらの手配は結果的に不要だった、ということだった。
通報を受けた所轄警察の少年課担当刑事、池上は色めきたった。「なに、SNOW CRACKの連中がレイプ未遂をやらかした?で、しかも襲おうとした女の子たちに抵抗されてのされちまっただって!?こいつは・・・チャンスだ、課長、私が直ぐに行きます、あいつら、中々シッポを出さないがいつか絶対に検挙してやろうとてぐすね引いてたんですよ!このチャンスに連中を徹底的に締め上げて、余罪も何もかも全部白状させて一挙に奴等を壊滅させてやりますよ!」少年課の中でも最も敏腕の池上が完全にやる気になっているのだ、課長の五反田としても異論はない。「よし、すぐに行ってくれ、頼むぞ、奴等を一気に追い込んでくれ!」現場に到着した池上は工場の惨状を見て、一瞬躊躇したのは確かだった。こ、これは・・・ボロ雑巾のように、半死半生で転がっている坊野たち四人と床一面の血塗れの修羅場は海千山千の池上をしても驚きを禁じえなかった。だが、切り替えは素早かった。まあいい、カス共がどうなっていようが俺の知ったことか。いや、こいつは却ってツイてるかも知れないぞ。こいつらこんな重傷だったら、手当てをエサにすりゃ何でも自白させられるかも知れないな。驚きを直ぐに心の奥底にしまい、いかにも柔和な笑顔を浮かべながら池上は玲子たちに近づいてきた。「やあ君たち、今日は災難だったね。僕は池上、この事件を担当させてもらうことになるからね、一つよろしく頼むよ。」さあ、ここが勝負どころよ・・・玲子たちの目にも流石に緊張の色が走る。それに素早く気づいた池上は礼子たちの不安をかき消すように、声を立てて笑った。「いやみんな、そんなに緊張しなくていいんだよ。僕は君たちの味方だからね。いいかい、はっきり言っておくが君たちを攫ってレイプしようとしたこいつら、SNOW CRACKは最悪のギャング、街のクズだ。君たちはそいつらに襲われたんだよ、本当に無事でよかった。いや、必死で抵抗したんだろう、多少は過剰防衛もあったかもしれないが、そんなの全く関係ないよ。後は僕に任せてくれれば大丈夫、君たちに不利になるようなことは間違ってもしないから。僕の仕事は君たちを守り、こいつらを少年院にできるだけ長く送ることなんだ。僕は、いや警察はみんな君たちの味方だからね、大船に乗ったつもりで安心していてくれ!」池上の指揮下現場の警官は全員、端から完全に玲子たちの味方と化して玲子たちに不利な証拠を全て抹消し、ただひたすら、坊野たちの罪を問うことに全力をあげていた。玲子たちが拍子抜けする程だった。
傑作だったのはその後の、所轄署にかかってきた一本の電話だった。礼子たちの両親、そして良治たちの根回しは奇しくもある一人の所でバッティングしていた。何と本庁の部長、目黒のところで。利、情両面からの懇請を受けて目黒は所轄に直接、電話をかけてきたのだ。「お、おい池上君・・・部長、本庁の目黒部長から直接、電話が入っているぞ・・・」電話を回してきた五反田の声は明らかに動転していた。無理もない、階級社会の警察内部において、キャリア、それも出世階段まっしぐらの目黒の威光は絶大だ。池上のように現場叩き上げ、出世には興味ないタイプならともかく、所轄の課長クラスと言う守りたいポストがある五反田にとって、目黒からの直接の電話はまさに腫れ物に触るような慎重な対応を要求するものだ。チッ、参ったな・・・SNOW CRACKの連中に政治家絡みの奴でもいたのか?大体において本庁のお偉いさんからの電話はろくな事がないからな。これを揉み潰せ、て言うのかよ?苦虫を噛み潰したような表情で電話口に出た池上だったが、その電話の内容は池上の予想と正反対のものだった。
「ああ、君が担当の池上君かね、君も忙しい身だろうから単刀直入に言おう、君が担当している事件だがね、被害者の女の子たちが実は私も色々と縁がある子たちなんだよ。で、その子たちが事件に巻き込まれて酷く怯えているんだ。難を逃れたはいいが、必死だったからやり過ぎたんじゃないか、過剰防衛で自分たちも罪に問われるんじゃないか、とね。でね、そのまあ、なんだ、私としては君に方向性を間違えて欲しくないんだよ、分かる・・・よな?相手は凶悪なギャングだっていうじゃないか、被害者の女の子たちにこれ以上、傷を負わせることがないようにして貰いたいんだよ。」「え・・・?ということは・・・要は被害者の女の子たちが過剰防衛その他で訴えられたりしないように、私にSNOW CRACKの捜査だけに専念しろ、と・・・こう仰りたい訳でしょうか?」「いや、そうはっきり言われても困るんだが・・・まあそういうことだ。」「アハハハハッ!なんだ、そういうことですか!部長、それでしたら何の心配もございません。私も元々目標は只一つ、SNOW CRACKの壊滅です。被害者の女の子たちも確かに、若干やり過ぎはあったかも知れませんが、そんなこと全く、何の問題にもなりません。過剰防衛だなんだだなんて・・・そんなの、あんなクズども相手に成立するわけないじゃありませんか!いや私以下現場全員、そんなこと全く考えついてもおりませんでしたよ!連中相手だったら何をやってもOK,そう・・・過剰どころか過小防衛ですよ!はい、過剰防衛があった、なんて証拠は私たちの誰一人、何一つ見ておりません!」思わず電話口で大笑いしてしまった池上につられるように、目黒も笑い出してしまった。「ハハハハハッ、いやなんだ、そうか、君も私と同じ事を考えていたのか、うんそりゃそうだ、まあ当たり前だよな。あの手のクズどもに悩まされている君たち現場としては、あいつらを壊滅できるこんな絶好のチャンス、逃がすわけがないよな。あ、いかんいかん、もしかして私は変な圧力でも掛けてしまったかな?誤解しないでくれよ。」「圧力?いや部長、私は今、圧力など掛けられていないと思いますが。圧力とはそう・・・やりたい事をやるな、とかやりたくない事をやれ、と命じられることでしょう?私はまさに、部長の仰ることをその通りにやりたい、と思っておりました。ですからこれは、そう、言うなれば激励を頂いたものかと?」「おおそうだ、そうだ!君の言う通り、君と私の意見は完全に一致しているんだからな。うん、確かに私は圧力など全くかけていないな。そう、君の言うとおり、私は君を激励したかったんだ。いやすまんすまん、余計な時間を取らせてしまったな。後で何か差し入れを贈っておくよ、頑張ってあのクズどもを壊滅させて、思う存分手柄を立ててくれたまえ!」
幾ら出世に興味がない池上でも、上層部に激励されて悪い気はしない。強制されてではなく自分の意思で、受身と自発では全く勢いが違う。自らの意思と上層部の支持が一致したことを見て取った池上は一気に突っ走った。坊野たちを立件し、少しでも長く少年院に送り込むためには手段を選ばなかった。礼子たちの暴走はきれいさっぱり無視され、SNOW CRACK内部のリンチ、ということであっさり片付けられてしまった。そして民間の中立的な病院ではなく、わざわざ警察病院に運び込まれた坊野たちを待っていたのは連日の過酷な取り調べだった。流石に拷問に掛けられるわけではない、だがそれは法律を遵守して、というわけではない。単純に必要ないからだった。全身の傷でうめき続け、鎮痛剤を、休息を懇願する坊野たちに池上は情け容赦なく、自白を迫った。鎮痛剤なし、休憩無しの長時間尋問はそれだけで半死半生の坊野たちにとって、拷問同然のものだった。僅かな、ほんの一時しか持たない量の鎮痛剤、ごく短時間の休憩と引き換えに次から次へと坊野たちは余罪を白状させられ、仲間の罪も売らされていった。
単に肉体の痛みだけではない。玲子たちの過酷な拷問に精神も肉体もボロボロにされ、あげくに睾丸まで潰された坊野たちに抵抗する気力など全くない。敏腕の池上は坊野たちから手に入れた情報をもとにSNOW CRACKのメンバーを次々と検挙し、あっという間に彼らを壊滅へと追い込んでしまった。勿論、幹部である坊野たちについてはたっぷりと長期刑を、検察逆送となるに十分の証拠を固めてめでたく塀の向こうに叩き込んでしまった。玲子たちへの配慮も十分だった。池上はこっそりと玲子たちの家の顧問弁護士に調書を事前に見せていたが、玲子たちの不利になることなど何一つ、影も形もなく消え失せていた。
かくして坊野たちは塀の向こうに消え、残ったSNOW CRACKの残党も殆どが検挙された。玲子たちの暴走も全て、無かったことに抹消された。全ては片付いた。残るは・・・慎治たちへの罰だけだった。
2
玲子たちは早くも、日曜日には池上からの電話で全て安心するように、過剰防衛等、礼子たちにとって不利になることは一切捜査しない、警察にとって興味があるのはあくまで坊野たちを処罰することだけであり、玲子たちの身の安全、経歴に全く傷がつかないようにする配慮には万全を期す、との連絡を受けていた。フウッ・・・これで安心ね。フフフ、私たちはこれでスッキリだけど、信次たちは果たして、どんな顔で登校してくるのかしら。全てを片付けた玲子は早くも、信次たちをどう処罰するか、ワクワクしていた。そして月曜の朝がきた。
「お、おはよう・・・ございます・・・」れ、玲子さんたちがもう来ている・・・信次は朝から上機嫌の玲子たちを見て胃がシクシクと泣き出した。上機嫌、玲子さん、上機嫌だ。玲子の笑顔を見ただけで、信次は自分の淡い期待、幻想など粉々に打ち砕かれていることを悟った。こ、こんなに上機嫌だってことは・・・もう警察沙汰はすっかり片付いちゃったんだな・・・駄目か・・・もう駄目だ・・・もう俺たちの最後の希望も無くなった、もうどうにもならないんだ・・・絶望の中、信次の脳裏を忌まわしい、考えたくもない言葉が侵食していく。罰・・・玲子さん、罰を与える、て言ってたな・・・どんな、どんな罰を与えられるんだ、鞭?いや、鞭なんかじゃ済まないかも・・・じゃ、じゃあどんな???信次の中で恐怖が勝手に一人歩きしていく。信次の顔が見る見る泣きべそ顔になっていくのを見て玲子は楽しそうにケラケラと明るい笑い声を立てた。「もう信次ったら!何朝一から思いっきりブルー入ってるのよ、やあねえ。ほら、朝くらいもう少し楽しそうな顔してご覧よ!・・・ねえ信次、大体、この週末は色々あったじゃない、土曜のパーティー、楽しかったよね?」ヒッ、ヒイッ!き、来たか!!!悲鳴をあげそうになる信次を片手で制して玲子は続けた。「信次、そんなに怯えないの。私、今信次をどうこうするつもりは全くないよ。もう時間もないしね・・・例の件は後でゆっくりとね。そう、お昼休みにしようか?」信次は心臓が縮み上がる思いだった。あ、後で・・・これじゃあ蛇の生殺しだ、や、やるならいっそ一思いにさっさとやってくれ・・・だがあまりの恐怖に言葉を発することもできずに口をパクパクさせている信次に軽くウィンクしながら、玲子はさっさと席に戻ってしまった。
そして昼休み、さっさと弁当を食べ終えた礼子たちは慎治を急き立てた。「ほら慎治、早く食べてよ、今日は予定がつかえてるんだからさ。慎治たちも楽しみにしてたんでしょ?どういう罰を与えられるか。今日のメインイベント、早く始めたいんだからさ、さっさと食べてよ!」砂を噛むような思いでただ機械的に、味わう余裕すらなく弁当を飲み込んでいた慎治たちの手が凍りついた。ば、ばつ、バツ、罰…もう食事どころではない。「ああもう!信次、礼子が早く、て言ったのが聞こえなかったの?早く、て言われたのに何で信次は手を止めちゃうのよ!」玲子が些かいらついた声をあげた。「あ、ああ、ご、ごめんなさい…で、でも、でももう、食べられない…」実際、手だけではない、口も喉も胃も、信次たちの全身が凍り付き、もう食べることなど到底できなかった。「うーん、まあ仕方ないか。じゃあ信次、二人とももうご馳走様でいいわね?いいの、本当に?午後私たちのせいでお腹すいた、なんて文句言わないでよ?」礼子は念を押すように尋ねると、ゆっくりと教壇に向かって歩いていった。
「ハーイ、皆さん、そのまま食べながら聞いてくださーい。臨時ホームルームを開きます!」礼子の凛とした声にクラスメートの視線が集中した。「実はこの週末、私たち四人、それに矢作慎治君、川内信次君との間で、非常に大きな事件が発生しました。そのご報告をしたいと思います。では当事者のお二人に、自分の口から報告して貰いましょう。矢作君、川内君、前に出てきなさい!」あ、ああ…そんな、じ、自分の口で喋らされるの…だが抵抗などできない。フラフラと夢遊病者のように前にさまよい出た二人は、ぼそ、ぼそと途切れ途切れに告白、懺悔を始めさせられた。「あ、あの、、、ぼ、ぼくたちは…お、おそわせました…礼子さん、たちを…」「や、やとった、んです…坊野さん、たちを…SNOW CRACKを…」一瞬、教室がシーンとした後、一斉に声が上がった。「何、何よそれ、全然わかんないよ!」「襲わせたって信次たちが?ねえ一体あんたたち、何やらかしたのよ!」「ちょっと、SNOW CRACKて何よ、ちゃんと分かるように説明してよ!?」蜂の巣を突付いたような騒ぎを暫く楽しんでいた礼子がパンパンッと手を叩いて皆を制した。「ハイハイ、みなさんお静かに!気持ちはよく分かりますが、少しご静聴願いまーす!矢作君、川内君、君たちの告白も全くなっていませんよ。もっときちんと、順を追ってしっかりと説明してください。はい、では一からやり直し!」
礼子の巧みな誘導と質問により、慎治たちは自分が何をしたか、逐一白状させられた。
礼子たちを恨みに思ってギャングを雇ったこと。そのギャングに礼子たちをレイプさせようとしたこと。礼子たちが襲われた廃工場で、ギャングが礼子たちを襲うのを見物していたこと。全てを白状させられた。慎治たちの告白の間、シーンと静まり返っていた教室は一瞬の静寂の後、怒号に包まれた。「なによそれ!慎治、あんたそれでも人間なの!?」「さ、最低!ギャング雇って礼子たちをレイプさせようだなんて・・・信次、あんた気でも狂ったの!?」「クラスメートをレイプさせようとしたの?女の子の一生狂わせようとしたなんて・・・慎治、あんたいますぐ死んで、この場で死になさいよ!」「全く、ふざけるにも程ってもんがあるわよね!信次、どうする気なのよ、ええ、あんた・・・生きてる値打ちなんかないわよ!」「ったく、ああ穢らわしい!こんな最低男が一緒にいただなんて・・・今すぐ死んで、二度とその顔、私たちの前に見せないでよ!」洪水のような罵声に圧倒されながら、慎治たちは呆然と何も言えずに立ちすくんでいた。その態度が女の子達の一層の怒りを買った。「慎治、何とか言いなさいよ、このケダモノ!」誰かが投げつけたのを皮切りに、一斉に慎治たちに物が、シャープペン、紙くず、その他ありとあらゆる手近な物が投げつけられた。「みんな、こいつ・・・許せない!みんなでやっちゃおうよ!」誰言うともなく発せられたその声に、全員が立ち上がりかけたその時、礼子の声が響いた。
「ハイ、みんなそこまで!みんなストップ、そこまでよ!落ち着いて、みんな、それじゃリンチよ。そんなことをしたら、みんなも慎治と同じレベルに堕ちちゃうわよ。ストップ、落ち着いて、兎に角一旦座って!」礼子の声には有無を言わせぬ迫力があった。「礼子、でもこいつら、どうするのよ、礼子たちは被害者なんでしょ?こいつらを、こいつらをこのまま許してやる気なの?」「許す、とは言ってないわ。でもね、ここは日本、法治国家よ。どんな極悪非道の罪人にも裁判を受ける権利は保証されているわ。だから、私たちも慎治たちに、せめて裁判は受けさせてやろうと思うのよ。裁判を受けさせて、そして判決として下された事を刑罰として執行するのよ。そうじゃなくちゃ、ただのリンチよ。それじゃあ慎治たちと同じレベルに堕ちちゃうわ。そんなの嫌よ。今、みんなに話を聞いてもらったのは、慎治たちを裁判にかけるためよ!」
裁判・・・なるほどね、そういう趣向ね・・・何となくクラスに納得したような空気が広がる。「みんな分かってくれたみたいね。じゃあ早速始めましょう!裁判長は玲子、検察官は私がやるわ。原告はフミちゃんよ。それと慎治、安心していいわよ、ちゃんと弁護人もつけてあげるから。我ながら甘すぎる、とは思うけど人民裁判にはしないであげるわ、感謝しなさいよ。で、弁護人は・・・そうね、土曜一日付き合ってもらって事情が分かっているから、真弓と里美にお願いするわ。あ、それと裁判進行に際しての廷吏は朝子に頼むわね。それとこの裁判、玲子が判決下したんじゃどうせ慎治たち、納得しないで文句言いそうでしょ?アメリカンスタイルで陪審員制とするわ。陪審員は、そう、みんなにお願いするわね。」な、なんてことだ・・・慎治たちは思わず言葉を失ってしまった。裁判、聞こえはいいがこれは単に慎治たちに屈辱を味あわせるための手段、罰を与えるためのワンステップ過ぎない。だが文句を言う暇すら与えられずに、裁判が開始されたまずは法廷のレイアウト、とばかりに教壇上に裁判官席として玲子の椅子が中央に、そして検察官席として礼子の席、そして原告である富美代の席が左側、弁護人席として真弓、里美の席が右側にセットされた。そして慎治たちは被告席、教壇の下の床に土下座させられ、その横に威圧するかのように朝子が陣取っていた。そして周りを取り囲むように陪審員席としてクラス中の女子生徒が椅子を移動させて取り囲んだ。床に土下座させられた慎治たちにとって、それだけで十二分に屈辱的なシチュエーションだった。礼子たちは一段高いところに、しかも椅子に腰掛けているのに対し、自分たちは床に、しかも土下座させられている。裁判、というより江戸時代のお裁き、平伏する身分が低いものにお上が裁きを下す、といったシチュエーションだった。「ではこれよりクラス裁判を開始します。まずは検察官より訴状を読み上げます。被告人はその間、そのままの姿勢で平伏していなさい。」玲子の凛とした声が響いた。屈辱の涙をこらえながら平伏する慎治たちを一瞥すると、礼子が口を開いた。
「原告、神崎富美代は被告、矢作慎治と幼馴染であります。本学、聖華学園に進級してからも幼馴染ではありますが極めて出来の悪い被告に対し、なにくれと面倒をみてやっていたのに対し、被告はあろうことか原告を理不尽にも逆恨みし、もう一人の被告、川内信次と共謀し、神崎富美代とその友人である3名を陥れようとしたのであります。そして一昨日、被告人両名は被告および原告双方が面識ある学外のギャングを雇い、原告を襲わせたのであります。幸いにして原告は虎口を脱し、無事であったものの心身双方に大きな苦痛を受け、その治療には相当の時間を要するものと思われます。か弱い女性を襲わせ、一生の傷を負わせようとした被告人両名に対し、検察は厳罰をもって臨むべきだと考えます。」め、面倒をみてやった!り、理不尽!逆恨み!屈辱に耐えながら礼子の冒頭陳述を聞かされていた慎治たちの両手がブルブルと震えた。な、なにが理不尽だ、逆恨みだ、し、心身双方の苦痛、そ、そんな、ぼ、僕たちの苦痛に比べたら!!!「ひ、ひどい、あんまりだ!!!」「そ、そうだ、じ、自分たちは、自分たちはもっと、もっとめちゃくちゃに僕たちを苛めてたくせに、あ、あんまりだ!!!」思わず顔をあげ、悔し涙を流しながら嗚咽のような声をあげる慎治たちを、玲子は冷たく睨み付けた。
「被告人は裁判長の許可なく発言しないように。不規則発言には法廷侮辱罪を適用します。只今の不規則発言について、当法廷は被告人の有罪を宣告し、略式命令を下します。廷吏、被告人両名を鞭打ち各10回の刑に処しなさい。」ああ成る程ね、礼子が私に廷吏やれ、て言ったときは何の必要があるかよく分からなかったけど、こういうことね。「了解しました、裁判長。被告人を鞭打ち10回の刑に処します。二人とも、シャツを脱いで背中を出しなさい!」カチャカチャ、とわざと音を立てながらバックルを外すと、朝子はベルトをウエストから引き抜いて二つ折りにし、パシッと打ち鳴らした。「ヒッ、そ、そんな!」「や、やめて、ぶたないで・・・」朝子がベルトを構えただけで、鞭に対する恐怖を本能に近いレベルまで刷り込まれている慎治たちは心底怯え切った泣き声になってしまった。だがそんなことで許す玲子ではない。「被告人は直ちにシャツを脱ぎ、廷吏が鞭打ちやすいように四つん這いになりなさい。命令に従わない場合、刑を倍加します。」そ、そんな!!!抗議の声をあげたくなるのを必死で堪えながら慎治たちはシャツを脱ぎ、四つん這いになった。逆らえばどうなるか、考えるまでもなかった。上半身裸になり、犬のように四つん這いになった慎治の横に朝子が立ち、ベルトを高々と構えた。「これより、法廷侮辱罪として鞭打ち10回の刑を執行します。ハッ!」ビュオッ・・・パッシーン!「ヒッヒイッ!」ヒュオッ、パシッ、ビシッ・・・朝子は情け容赦なく慎治を打ち据えると踵を返し、今度は信次の傍らに立った。「鞭打ち刑、執行!」ヒュオッ・・・パシッ、ビシッ!「い、イツッ、イタイイイッ!」朝子が一切の手加減抜きで、全力でベルトを振り下ろす度に慎治たちの悲鳴があがる。フンッ、なによ大げさね。私たちに散々本物の鞭で打ち据えられているんでしょ?慎治たちにとって、高々この程度のベルトなんて、ハタキで撫でられてる程度のものじゃないの?大げさに騒がないでよ。朝子の考えている通り、確かに鞭の痛みに比べれば遥かに軽い。だがベルトはベルト、痛いものは痛い。慎治たちにとって、この悲鳴は演技でもなんでもない。
10回ずつ打たれた慎治たちが泣きながら正座し、のろのろとシャツを着ようとするのを、玲子がピシャリと制した。「シャツを着ることは許可しません。今後不規則発言の際、直ちに鞭打ち刑を加えられるように被告人はそのまま裸でいなさい。」そ、そんな・・・あ、あんまりだ・・・思わず口を開きかけた信次は玲子の射るような視線に凍りついた。いいわよ信次、何か言いたいのかしら?言ってごらんなさいよ。口を開く勇気があるならね。玲子の視線は一瞬にして信次を圧し、すべての言葉を凍りつかせてしまう。フン、何も言えないのね、まあ賢明な選択だけど。「では裁判を再開します。被告人、罪状認否を行います。只今の検察官の告発に対し、事実と認めますか?事実と認めるか否かのみを答えなさい。」
そ、そんな、イエスかノーか。と答えろだなんて!「そ、そんなムチャな、イエスかノーかだなんて・・・」「そ、そうだ、だってどうしようもなかったんだから・・・」バカな連中・・・フッと礼子が失笑するのと同時に玲子が再び刑を宣告する。「只今の被告の発言は当法廷の命令を無視するものです。よって被告人に対し、当法廷の命令を無視した罪により法廷侮辱罪を宣告します。廷吏、直ちに鞭打ち刑10回を執行しなさい!」アッ、アヒイッ!そ、そんな!だが今度は泣き言を言う暇さえない。ベルトを手にしたまま信次たちの横に立っていた朝子は、直ちに手近にいた信次の首根っ子を捕まえると床に押さえつけて土下座させ、そのまま首根っ子を足で踏み付けながら思いっきり、背中を打ち据えた。次いで慎治も打ち据えると朝子は無言のまま、ベルトをパシッと打ち鳴らしながら信次のすぐ横に再び構える。
「再度質問します。被告人は事実と認めますか?」もう選択の余地はない。「・・・み、認めます・・・」「・・・は、はい・・・みと、めます・・・」弱々しく答える二人を見て玲子は微かに笑いながら里美、真弓の方を向いた。「弁護人の陳述を認めます。」里美と真弓は何やらコソコソと相談していたが、やがて代表する形で真弓が口を開いた。「一昨日、原告が襲われた場所に実は我々弁護人も居合わせておりました。そこには被告人もおりましたため、状況については弁護人も把握しております。被告人は起訴事実については既に認めておりますので、弁護人も事実関係については争いません。しかしながら、被告人は自らが雇ったギャングが倒された後、非常なる恐怖を感じておりましたことを指摘します。被告人が既に、罰への恐怖には怯えていたこと、罪への呵責はないと言えども十分なる恐怖は味わってきたことに免じ、寛大なる処罰をお願いするものです。」な、なんだこれは・・・こ、これが、これが弁護、こ、これじゃ、これじゃ検察側の証言じゃないか!!!動きかけた信次はビクッと思わず震え、横を盗み見た。そこには朝子がいた、そしてその手、ベルトを握った手が確かにビクッと動いていた。信次、その調子よ、早く何か言いなさいよ。また思いっきり引っ叩いてあげるから。確かに朝子の手はそう語りかけていた。
玲子も信次たちが何か言うのを待っていたが、二人が肩を震わせながらも黙っているのを見てフッと小さく笑った。まあ流石に学習効果、ていうものが少しは出るわよね。まあいいわ。「では次に原告に意見陳述を認めます。原告、自由な発言を認めます。」玲子が頷くのを見て富美代が陳述する。「検察官の告発はすべて真実です。私、および私の友人が被告の陰謀により如何に恐怖し、如何に傷ついたかは言葉にしようもありません。何卒、被告を厳罰に処すようにお願いします。」げ、厳罰・・・厳罰という言葉に恐怖する信次たちを一瞥すると、玲子が宣告した。「では以上をもって結審します。陪審員、表決をお願いします。被告人を無罪とする陪審員、挙手願います。」シーンと静まり返ったまま、誰の手も上がらない。「有罪とする陪審員、挙手願います。」バッ、と一斉に女子生徒全員が挙手する。「全陪審員一致をもって、被告人を有罪と認めます。」
3
あ、あああっそ、そんな!!!もう限界だった。「ひ、ひどい、あんまりだ、こんなの裁判じゃないよ!」「そ、そうだ、ふ、不公平だ!インチキだあああっ!」必死で絶叫する二人をニヤニヤと笑いながら見ていた玲子がやがて、スッと手をあげた。玲子が手をあげる、僅かそれだけの動作であれだけ喚いていた慎治たちが恐怖に声を失ってしまった。「廷吏、被告人を法廷侮辱罪により、鞭打ち刑10回に処しなさい。」直ちに朝子のベルトが唸る。そし鞭打ち刑が終了したとき、玲子が質した。「被告人、当法廷を不公平、インチキと称しましたが、その理由を述べなさい。」り、理由・・・思わず慎治たちは息を呑んだ。「起訴事実を認めたのは被告自身です。そして表決を下したのはクラスの女子生徒全員、しかも裁判官、検察官、原告は共に投票権を有していません。それを不公平と言うからには何か根拠があるはず。その根拠を聞きましょう。」り、理由、根拠・・・確かに明らかな不正、とは言いにくい。数の暴力ではあるが、それを不正、とは言えない。「もし根拠がない、というのであれば、重篤なる法廷侮辱罪を適用します。」じゅ、重篤な!い、いけない、なにか、なにかないか、何か根拠は・・・あ、あった!信次たちの脳裏を同じ考えが走った。
「そ、そうだ、あ、ある、あるよ理由は!」「お、男、男がいないじゃないかあああっ!陪審員が女の子だけだなんて、ふ、不公平だ、お、男、男子も投票しなくちゃ、こ、公平じゃないよおおおっ!」フウッ・・・呆れたように玲子は失笑を漏らした。何、男子にも投票させろ?何を言い出すかと思ったら・・・もうちょっとマシな文句、考えなさいよね、まあどうでもいいけど。「男子にも陪審員として投票させるべき、それが被告人の主張ですね?」「そ、そうだ!」「そうだよ。その通りだ!」バカねえ本当に。玲子は最早あからさまに侮蔑の笑いを浮かべていた。「いいでしょう、その主張を認め、表決を追加します。男子生徒の皆さん、各員の陳述は聞こえていましたよね?聞こえていれば、表決のみを執り行うこととしたいのですが、異議のある方はいますか?」誰も挙手しない。オイオイ、ッタク俺たちまで巻き込むなよな、という顔で男子生徒は互いを見回している。「では被告人が無罪と思う方、挙手願います。」誰も挙手しない。当然だ、玲子たちに敢えて逆らおうとする者がいるわけがない。「被告人、これでいいですか?」「や、やだ、やだやだあああっ!」「そ、そうだ、む、無罪、とは言ってないけど、有罪とも言ってないじゃないかあっ!ゆ、有罪じゃない、だったら無罪と同じになるはずだあああっ!」「・・・いいでしょう。では有罪と認める陪審員は挙手してください。」パラッ、パラッと手が挙がり始める。「被告人が納得するよう、棄権はなしとしましょう、全員がどちらかに挙手するまで、何回でも表決します。有罪と積極的に認める陪審員のみ、挙手してください。後で無罪に挙手しなおしたい、という陪審員は遠慮なく、挙手しないでそのままにしていてください。」
こう言われて有罪としない男子生徒など、いるわけがない。玲子たちの想像を絶する強さと残酷さは全員、目の当たりに見ている。信次たちという生贄がいてよかった、自分がああなるのだけは死んでもご免だ、この思いは全員共通だ。加えて、玲子たちは信次たち以外には極めて人気が高い。美貌と明るい性格に加え、面倒見も極めていいし成績も最高レベルだ。だからテスト前にノートをコピーさせて貰ったり、宿題を教えて貰った連中も多い。彼女を紹介して貰った男さえいる。おまけに近隣に名高い美少女軍団の玲子たちだ、玲子たち四人の誰か一人でも参加する合コンをセットしたらそれだけで仲間内で大きな貸しを作れる。ショップ情報にしろ何にしろ、玲子たちから得ているものは非常に多いが玲子たちに何かを返せる男子生徒など殆どいない。従って大部分の男子生徒は玲子たちに対して借りは相当にあるが貸しはない。翻って、慎治たちに味方して得るものは・・・何もなかった。入学早々、玲子たちに苛められ始めた慎治たちは、男子の間でも友達と言える存在はいない。特に仲がいいわけでもない慎治たちを庇って得られるものなど何がある?得られるリターンとして唯一可能性があるのは、我と我が身を玲子たちの苛めターゲットに提供することだけ。クラスの内外を問わず人気と人望の厚い玲子たちの苛めターゲットになること、それは高校生活を、人生で最も楽しい時期の一つを丸ごと、地獄に変えてしまうことを意味する。そんな危ない、超ハイリスクノーリターンの賭けに乗るものがいるわけがない。
それでも自分一人の責任で慎治たちを突き落とすのならまだ躊躇するものもあるが今日は多数決、一人一人の責任は軽い、という格好の言い訳がある。ワリーな慎治、別にお前たちに恨みはないんだけどな、でも別にお前らに何かしてやる義理もないしな。天城さんには宿題見せてもらったりしてるからね。俺、霧島さんの隠れファンなんだよ。ま、自分で何とかしてくれよ。別にいいじゃん、天城さんたち四人と遊んで貰えるなんてラッキーだろ?バラッ、パラッと男子生徒の手が挙がり、あっという間に全員の手がしっかりと挙手されてしまった。「あ、あああ・・・そ、そんな・・・」「み、みんなお願い、見捨てないでよおぉぉぉ・・・」弱々しい、消え入りそうな声で慎治たちは涙ながらに哀願したが誰一人、手を下ろすものはいない。当然でしょ、信次たちに味方するのがいたら、お目にかかってみたいものだわ。全くバカなんだから。信次、あんたたちが男子からも苛められないのは何故だと思っているの?私たちの専用オモチャにしてるから、みんな手出ししないだけなんだよ。それをまあ、男子も表決に参加させれば助かるかもしれないだなんて、相変わらず現実認識がなってないわね。嘲りの微笑を浮かべながら玲子は判決を下す。
「被告人、希望通り男子全員も表決に参加しましたが、全員一致で有罪の評決に達しました。以上をもって、当法廷は被告人両名に有罪を宣告します。では検察官、刑を求刑してください。」「はい、検察は被告人両名の卑怯卑劣な行為に対し、公衆便所の刑を求刑します。」「わかりました。判決を下します。被告人矢作慎治、川内信次の両名を無期公衆便所の刑に処します。被告人両名はこれより、全ての授業間の休み時間、昼休みの間、女子トイレにて固定されて利用を希望する女子生徒全員の便器となり、おしっこを飲むことを命じます。刑期は無期、当法廷が被告人に顕著なる改悛の情が認められた、と判断するまで刑を執行し続けます。尚、刑は直ちに執行します。これにて閉廷、被告人を女子トイレに引き立てなさい。」「い、いやたああああっ、や、やめてくれええええっ!!!」「そ、そんな、べ、便器、みんなの便器だなんて、そ、そんな、そんなのないよおおおっっっ!!!」
いやだ、やめてと泣き叫ぶ慎治の両手を礼子と富美代、信次を玲子と朝子が掴み、女子トイレに引きずっていく。泣き喚く信次にクスクスと笑いながら玲子が小声で囁いた。「フフフ、何そんなに恐がってるのよ、バカねえ信次ったら。安心しなさい、そんなに酷いことするつもりはないんだからさ。大して痛くも何ともないわよ、ほんの軽いお遊びみたいなものよ、そんなに怖がることないわよ。」ひ、酷いことはしない?だ、だけどトイレに連れてかれるんでしょ・・・公衆便所の刑、そしてトイレに引き立てられる、と来ればどういう運命が待っているかは信次でなくとも直ぐに分かる。こ、これが酷いことでなくて何だって言うの・・・信次の涙も止まらぬうちに一行は女子トイレに到着した。そのトイレは入ると左右に個室が5室ずつ並んでいる。手前側四室は洋式便器だが、一番奥の一室ずつのみは和式便器になっている。しかも好都合なことに、その便器は個室の入り口から見て縦、つまり奥に金隠しが位置していた。女子生徒の大半が一緒についてくる中、刑場に到着した玲子たちは早速、設営にとりかかった。「さあ信次、ここが今日からの信次たちの居場所よ。フフフ、信次たちにまさにお似合いの場所ね。朝子、あれ持ってきた?」「もちろん!はい!」朝子が差し出したのは二本のやや太目の木の棒と大型の透明な漏斗だった。カラン、と乾いた音をたてながら玲子は二本の棒を便器の上、金隠しに近い位置に置くと信次の手を引いた。「信次、便器、といっても支えがないと疲れちゃうでしょ?優しい私が枕を用意してあげたわよ、感謝してね。さあ、ここに寝なさい!」「ね、寝なさいって・・・こ、ここに?と、トイレ、便器の上じゃないの!」信次が思わず金切り声で悲鳴を上げるのをよそに、礼子は慎治を向かい側の個室に連れて行く。「慎治、あんたはこっちよ。慎治の便器はここ、アハハッ、違ったわね、便器は慎治の口だったわよね、じゃあここは・・・そう、慎治のベッドかしら?」「そ、そんな!べ、便器を、トイレをベッドだなんてあんまりだあああっ!」信次たちは必死で抗議の声を上げるが、玲子たちが許してくれるわけがない。「さあ信次、さっさとそこに寝なさい!」玲子の声が鞭のように響くともう、二人の抵抗の意欲などあっさりと吹き飛ばされてしまう。う、ううう・・・屈辱に咽びながらトイレの床に横たわる。コンクリートの硬く冷たい感触が背中から熱を奪うと同時に信次たちの精神を凍りつかせる。トイレの床に横たわり、玲子たち女子生徒の姿を足元から見上げているとそれだけで例え様もない屈辱だ。
「朝子、ここのセッティングよろしくね。」「OK,任せといて!」横たわった信次の口に朝子が手にした漏斗を差し込んだ。「ウフフフ信次、まるでフォアグラ用のガチョウみたいよ。楽しみにしててね、本物のガチョウ見たくお腹パンパンにしてあげるから。アハハハッ、私たちのおしっこでね!」朝子と富美代は信次たちの口に漏斗を差し込むと、次いで顔の両脇に高さ20センチ程度の踏み台を置いた。「高さはどうかな?」朝子が踏み台の上に乗り、しゃがんでみる。スカートを穿いたままの朝子の股間が信次の顔の上に降りてきて、止まった位置は漏斗の口から5センチ程度上の位置だった。「OK,丁度いい高さみたいね。」口が広めの漏斗、透明のプラスチック越に朝子のブレザーのスカートが遠ざかっていく。向かい側のトイレでも、慎治が富美代の手により便器と化せられていた。そしてガタガタッと音を立てながら、玲子たちがトイレへ何かを運び込む音がした。便器の上に寝かされたまま上目遣いに見てみると、玲子たちが真弓、和枝らに手伝わせて三枚の衝立を持ち込んでいた。
「玲子、何なのそれ?なんでトイレにパネルなんか持ち込むの?」里美が不思議そうに尋ねた。「えっ、分からない?だって里美ももう、何するかは分かってるでしょ?そう、慎治たちを公衆便所にしてみんなでおしっこ飲ませてやるわけじゃない、だけど慎治たちを寝かせとくんだからどうやったって足がはみ出ちゃうでしょ?トイレのドア、閉められないわよ。流石にドア開けたまま、後ろから丸見えとか隣りからひょいと顔覗かせたら丸見え、ていう状態でおしっこするのなんか嫌じゃない?だからこうやって、パネルで仕切っとくのよ。」言いながら玲子は信次側、手前の洋式便器個室との仕切りに1枚目の衝立を立て、次いで2枚目を信次たちが寝かされている、両側の和式便器個室の真ん中に立てた。そして三枚目を同様に慎治側の洋式便器個室との仕切りにする。「さあこれでOK。これでトイレに入るところもおしっこするところも、誰からも見えないわよ。ああ、もっとも信次たちは別ね、二人は特等席で見ていいわよ、私たちがおしっこするところをたっぷりとね。」
4
すべてのセッティングが完了したのをチェックすると、礼子がパンパンッ、と手を打った。「はいみんな、準備完了したところで説明するわね。無期公衆便所の刑、まあ刑の名前とこのセッティングを見ればどういう刑かは一目瞭然、説明の必要はないわね?そう、今まで私たち四人が慎治たちをトイレとして独占してきたけど、今から慎治たちの口、公衆便所として無料開放します!」わあっすっごーい!ほんと、ほんとに慎治たちにおしっこ飲ませていいの?トイレを埋めた女の子たちから一斉に歓声が上がる。「勿論よ!学校に居る間中、全ての休み時間、慎治たちを公衆便所として解放します。慎治、あなたたち二人は朝、登校したら直ぐこのトイレに直行よ。そしてこの姿勢でみんなが来るのを待って、おしっこしてもらいなさい。勿論、拒否権なんか一切ないわよ。みんな、慎治たちがもし少しでも反抗的な素振りを見せたら遠慮なく言ってね、即、罰を与えるから。そう、気絶するまで鞭で打ちのめしてやるからね!」きゃあっ鞭で打ちのめすだって、すっごーい!また歓声が上がる。礼子は満足げに頷きながら更に続けた。「で、私たちはもう毎日飲ませてるから慣れてるけど、みんなはおしっこ飲ませるの初めてでしょ?上手く飲ませられなくて慎治たちが零しちゃったら興醒めだし、床が汚れるのも嫌よね。だから取り敢えず、こうやって漏斗をセットしておくわ。この漏斗だったら口も広いし量もたっぷり入るから、何も考えないで思いっきりおしっこしても零れる心配は全然ないし、もし零れちゃったとしても下は便器、本物の便器だからね、流してそれでお終い、後始末する必要なんかないわ。あ、それとねみんな、これはあくまで慎治たちに対する刑罰なんだからね、ちゃんと慎治たちが飲むように、ズルして口から溢れさせたりしないようにしっかりチェックしてね。」「ああ礼子、これを用意しといたわよ。」横から富美代がノート、紐を付けトイレの壁に打ち込んだ釘に引っ掛けられるようにしたノートを渡す。そのノートの最初の数ページは上に日付を記入し、その下を四列、左から0、S,M,Lと四列、縦に罫線を引いて区切ってあった。「みんな、おしっこしたら必ず、このノートにチェックを入れてね。零した量がゼロなら0の列、以下少しならS,結構零したらM,一杯零したらLの列にチェックして、夕方のホームルームでそれを集計するから。慎治、よく聞いとくのよ、L一個につき3発、Mなら2発、Sなら1発で計算して、その数を今日一日の零した罰、ということで、ホームルームの時にみんなの目の前で思いっきりベルトで引っ叩いてやるからね!」
わあっ流石は礼子、きびしいーっ、ほんとよねえ、じゃあ慎治たち、一生懸命飲まなくっちゃねえっ、え、でもさ、面白くない、意地悪するのも楽しくない?全部きれいに飲んだのにさ、Lにチェックしちゃうとか!どっと女の子たちは盛り上がった。いい、それいいかも!流石に当の礼子が苦笑しながら一応、フォローを入れた。「ハイハイ、みんな一応良識をもって刑を執行してくださいね。フフフフフ、あんまり慎治を苛めないようにね!あ、それと一つ、これだけは絶対に守ってね。いい、飲ませていいのはおしっこだけよ。おっきいほう、うーん、そう、うんちは・・・絶対に食べさせちゃ駄目よ!うんちの方は私たちがいずれ食べさせてやろうって思って大事に取ってあるんだからね!抜け駆け禁止よ!食べさせたら・・・恨むわよ!?」再びどっと場が盛り上がる。苛めないようにだって!それ礼子が言うのーっ!?思わず笑いが漏れたところで礼子が再び、パンパンッと手を打ち鳴らした。「ハイハイみんな、何か質問はありますか?ない?それじゃあ最後に私から一言、トイレの順番、基本的には予約制とするわね。なるべく多くの人におしっこ飲ませて貰いたいから、一応原則として、一日一人一回とするわね。勿論、空いていたら自由に飲ませて頂戴。あと、まあ飼い主特権、ということで私とフミちゃんは慎治に対して、玲子と朝子は信次に対しては予約なしでいつでも飲ませてOK、順番待ちなし割込み可の優先権を貰うわよ。ズルイ、というご意見もあるでしょうけど、まあそのくらいは勘弁してね。」チラリと腕時計を覗き込むと、昼休みは未だ10分ほどあった。「さあ、じゃあ無期公衆便所刑、執行開始を宣告します!最初に飲ませるのは誰!?」
ハイハイハイッ!勢いよく何人かの手が上がった。わたしわたし、私が飲ませたい!皮切りは予想通り、礼子たちのグループのメンバーだった。結局、慎治の個室に残ったのは和枝、そして信次の個室には真弓が残った。「じゃあね、ゆっくりおしっこ楽しんでね!」ぞろぞろとクラスメートが衝立の向こうに去り、各々の個室には二人だけが残った。「ウフフフフ、ねえ慎治、私がトップバッターになつたけど、どう?慎治の予想通りだった?それとも誰か別の子に飲ませられると思った?」笑いながら和枝が慎治の顔を覗き込む。「フフフ、本当にいいざま、お似合いよね。なんかこうやってみると慎治、便器が板についてるよ。やっぱり礼子やフミちゃんたちにたっぷりと飲ませられた成果かしら?」笑いながら和枝は踏み台に登った。「慎治、やっと、て感じかな?フミちゃんたちが毎日おしっこ飲ませるの見ててさ、本当は私も飲ませたいな、て思ってたんだよ。覚えてないかな?小学校の頃、私も慎治のこと、蹴っ飛ばして泣かせたことあったでしょ?あの時にもっと苛めて慎治のこと、私のオモチャにしちゃえばよかったな、てずっと思ってたんだよ。そしたら今ごろは礼子じゃなくて、私が慎治のこと、毎日苛めてたのにな、て残念だったのよ。せめてあの時、泣かせるだけで許してなんかやらないでおしっこ飲ませてやれば良かったな、そしたら慎治の口、私が一番乗りだったのにな、てね、結構悔しく思ってたのよ。フフフ、漸く思いがかなうわ、慎治、フミちゃん程しょっちゅうじゃないけど、昔泣かされた私におしっこ飲ませられるのよ、どう悔しい?それとも慎治にとってはもう嬉しいのかな?まあどっちでもいいわ、たっぷり飲ませてあげるからね。」和枝はスカートをたくし上げると、パンティを下ろし、慎治の顔の上にゆっくりとしゃがみ込んだ。「・・・さあ慎治、覚悟はいいわね?私のおしっこ、飲ませてあげる。これから私も毎日、飲ませてあげるからね!」
その頃、真弓も信次の顔をゆっくりと見下ろしていた。「うん信次、よくお似合いのポーズよ。私、漏斗咥えた人間なんて見るの初めてだけど、信次にはよく似合っているわよ。」笑いながら真弓は二,三回咳払いをした。「ああ信次、最初に言っとくけど、これおしっこする時の私の癖だからね。別に信次を苛めるためにわざとやってるんじゃないのよ。信次みたいな痰壷がない限り、女の子が外で唾吐くことなんてまずないでしょ?だからトイレに入ったとき、こうやって痰切っとくのよ。フフ、普通の男の子じゃ分からない、信次みたいな便器君にしか分からない女の子の秘密、てやつかしら?遠慮しないでいいわよ、たっぷりと見せてあげるから。」オヤジのようにカアーッと下品に喉を鳴らすわけではない、女の子が普通に咳払いするのと同じ要領でンンッ、ンッ!と短く喉を鳴らすと真弓はペッと勢いよく漏斗に痰を吐き捨てた。風邪を引いているわけではないから黄色くはない。だが白いと言っても唾とは明らかに違う、よりドロッと密度が高い、ゲル状の塊が真弓の狙い通り漏斗の底部、信次の口に差し込まれた嘴の部分への縁に着地する。そして真弓の痰唾は自らの意思を持つアメーバのようにゆっくりと漏斗の嘴を伝い、信次の口中へと流れ込んでいった。ジュルッとした感触、塩気を感じる汚辱の味が信次の舌を支配する。「クックウウッ・・・」ひ、ひでえ・・・た、痰唾だなんて、き、きたねえ、きたねえよ・・・信次の顔が屈辱に歪むのを見て真弓は満足そうに声を立てて笑った。「アハハハハッ!どう、私の痰唾の味は!いつも飲まされている唾とは一味違うでしょ、どんな味なの?私、痰唾の味なんて考えたことないし、ましてや他人の痰唾なんて絶対に口にする機会はないからね、想像もつかないわ。後でどんな味か教えてね、じゃあ私の痰唾の味、ちゃんと分かるようにもう一つお代わりあげるわね、ンンッ、ンッ、ペッ!」唾をいつも飲まされている、というのは些か事実とは異なる。確かに信次は毎日のように誰かに唾を吐き掛けられている。だが玲子を始め女の子たちは信次を辱しめるために、軽蔑の象徴として唾を吐き掛けているのだ。だから別に信次に唾を飲ませたいわけではない。結果的に信次の口中に唾が飛び込むことはあるが、それはあくまで例外、殆どの唾は顔に吐き掛けられたものだ。こうやってたっぷりと唾、しかも痰唾の味を味合わされたことなどない。ひどい屈辱だった。「さあ信次、後もつかえているし、そろそろ飲ませてあげるわね。」ガタッと真弓は踏み台の上に上ると、パンティを下ろしながらゆっくりとしゃがみ込んだ。
「フフフ慎治、覚悟はいいわね?」「さあ信次、いい、出すわよ・・・ちゃんと飲まないと大変よ、後で玲子の鞭が待ってるわよ。」信次たちの視界は透明のプラスチック越しに和枝、真弓の尻と白いパンティに支配されている。そしてその上、パンティの端あたりの遥か高みから二人の顔が慎治たちを見下ろしている。クラスメート、同じ部の同期。本来だったら一番仲良くならなければならない存在は今、慎治たちに人間として最大の屈辱、他人の排泄物を飲ませる、という人格を一切無視した刑罰を加える執行官となっていた。自分の尻の、足元の更に下に置き、情け容赦なくおしっこを飲ませる。ああ、礼子さんたちと同じだ。和枝も真弓も美少女揃いの聖華の生徒に相応しく、礼子たち程ではないとはいえ、かなりのレベルの美少女だ。その二人がパンティをおろし、自分の顔のすぐ上にしゃがみ込んでいる。余りに当然のように、和枝も真弓も罪悪感とか可哀想は愚か、自分たちが苛めている、慎治たちを傷つけ酷い屈辱を与えようとしている、という意識すらない。二人の心を支配しているのは楽しい、この最高に楽しい遊びを思う存分満喫する、ということだけだった。慎治たちがどうなるかなど、全く眼中にない。まさに礼子たち、天使のような微笑を湛えながら無邪気に悪鬼のような苛めを加え、慎治たちを地獄に突き落とす美少女が増殖していた。
和枝と真弓は慎治たちの顔を見下ろしながら、やがて尿意が十分に高まってくるのを感じた。うん、出そう。「・・ンッ・・・」「フッ・・」ほぼ同時に括約筋を緩めた二人の尿道口から奔流が迸り出た。ジャアアーーッ、コポポポポ・・・二人の小便は勢いよく漏斗に注がれた。漏斗の側面に当たった小便が渦を巻き、そして底部の穴に吸い込まれていく。わあっ一杯でる、随分溜まってたのね。和枝は我ながら驚く程の量の小便を排泄しながら、自分が排泄した小便が漏斗に溜まっていくのを楽しげに見下ろしている。アハハハハッ、なんか渦巻いてるじゃない、しかも穴というか慎治の口に吸い込まれていって、ほんとトイレそのものね。アハハハハッ、なんか私のおしっこ、泡立っちゃってるし!見上げる慎治は和枝が放尿を開始した瞬間、思わず一瞬目をつぶってしまった。礼子たちが無意識の内に、全部飲ませるためにある程度勢いをコントロールしながら放尿するのに対し、和枝は全力で、何のブレーキもかけずに勢いよく放尿していた。慎治の目の前で、透明な漏斗にはねた和枝の小便が勢いよく渦を巻きながら蓄積していく。最初は無色だったその小便は溜まるにつれおしっこの色、吐き気を催す薄いレモンイエローになっていく。ぐうっ・・・き、汚い・・・自分がおしっこを、他人の排泄物を飲まされているんだ、と否応なく認識させられる屈辱の色だった。味覚嗅覚聴覚だけではなく、慎治は視覚でも和枝のおしっこを飲まされていた。
シャアアアアッッ、漏斗で響くせいかしら、何かおしっこの音が随分響くわね。ちょっと驚いた真弓だったが、次の瞬間にはその唇に笑みが浮かんだ。シャアアッという音に混じり、ゴポポポ、という水がパイプに吸い込まれていく音がしたからだ。その音はごく短い間、慎治が咥える漏斗の嘴に真弓の小便が満たされるまでの間しかしないが、真弓にとってはそれで十分だった。ウフフフフッ、行った逝った、私のおしっこが信次の口に届いたのね。ウフフフフ、これで信次を汚してやった、これで私も玲子や朝子と一緒、信次を一生取り返しがつかないように汚してやったのね!真弓は溜まっていく自分の小便と漏斗の透明なプラスチックの向こうで、信次の顔が微妙に動くのを、口に流れ込む自分の小便を飲み干そうと信次が必死で嚥下するのを飽くことなく眺めていた。いいわ、この光景、ほんとに最高!玲子たちったらずるいよ、こんな楽しいことを独り占めしてたなんて!漏斗に注がれた真弓の小便はほんの一瞬のタイムラグを置いて、信次の口に流れ込んでくる。ウグゴエッ・・・飲み慣れた味、他人の小便の味が信次の口いっぱいに広がる。飲みやすい、といえば飲みやすい。玲子たちに放尿される時は口を一杯に空けたまま、喉を鳴らすようにして飲み干さねばならない。使えるスペースは自分の口腔の中しかないのだから、急いで全力で飲み下さないと直ぐに口から溢れ出てしまう。そして溢れさせてしまったら、玲子たちからたっぷりと鞭打たれてしまう。だが今は漏斗を咥えさせられている、要は大型のストローを付けてもらったようなものだ、格段に飲みやすい。しかしその分、口に注がれる真弓の小便は一旦、口中に滞留し、信次の舌に小便の味を刻み込んでいく。玲子たちの小便は口中に殆ど溜まることなく喉の奥へ、そして食道へ胃袋へと直行するからその汚辱の味を味わうまでには至らない、精々温かさとうっすらとした塩辛さ、そして飲み終わってからの残り香に苛まれるだけだ。だが今、信次の口腔は真弓の小便に満たされている、信次の全ての味覚細胞が真弓の小便に浸されている。それは信次の口の中でゆっくりと舌に絡みつき、たっぷりと小便の味を信次に焼き付けていく。生温かい、薄目の麦茶にたっぷりと塩を入れたような、何ともいえないえぐみと不快感を伴う味。玲子たちに毎日飲まされている以上に強烈に、自分は今、女の子のおしっこを飲まされているんだ、自分の口は女の子の便器にされているんだ、と否応なく認識させられる味だった。普通の人間が一生味わうことのない味、汚辱に満ちた人生最悪の飲み物の味を。美少女の体内で濾過され、濃縮された純粋な侮辱と軽蔑の雫、相手を僅かでも人間扱いしているなら、飲ませるなど想像することすらできない筈の、他人にとっては最も汚い液体の味を。それはまさに拷問具そのもの、肉体的には痛みも苦しみも伴わないが、信次の精神をズタズタに、一生二度と修復不可能な程に破壊する天然の拷問具だった。そしてその拷問具は目の前、いや自分の顔の上に君臨する美少女の体内で精製されているのだ。今日だけではない、明日も明後日も明々後日も。毎日毎日、いつまででもこの美少女、いや玲子を始めとするクラスメートすべての体内でこの拷問具が精製され続けるのだ。信次は屈辱を通り越し、絶望の余り気が狂いそうだった。
無限とも思える時間の後、漸く二人の体内から迸る奔流は弱まり、やがて完全にストップした。だが漏斗にはまだまだ二人のおしっこがたっぷりと溜まっていた。ペーパーで軽く性器を拭き、パンティを履きながら和枝たちは立ち上がると、慎治たちが自分のおしっこを飲み干すのをしっかりと監視していた。ングッングッ・・・慎治たちが必死でおしっこを飲み込む音が響き、やがて漏斗の中は空になった。「ハアッハアッ・・・」「ンガッ、グハッ・・・」二人の荒い息遣いが聞こえる。ウフフ、飲ませてやった、本当に楽しいわね、これ!あっそうだ出る前にお漏らしチェックもしなくちゃいけないのよね。和枝は少しかがみこんで慎治の頬を見た。二筋三筋、自分のおしっこが伝わった跡がある。慎治、生意気よ私のおしっこを溢すなんて!ええと、お溢しの罰は何回だったっけ?Lでも・・・たったの3発かあ。じゃ、これは当然、3発よね!上履きの白い爪先で慎治の顔を小突きながら和枝は当然の如く、宣告する。「慎治、だめじゃないそんなに溢しちゃ!当然Lにチェックしたからね、後で玲子に鞭3発、叩いて貰うのね!」ヒッ、そ、そんな!ぜ、全然溢してないじゃない、ほ、ほんのちょっとだけじゃない、そんなこれだけで鞭3発だなんて!グエッ!」思わず漏斗を口から出して抗議する慎治の口を和枝は乱暴に踏み付ける。「うるさいよ慎治、大体生意気なのよ、私の折角のおしっこを溢すだなんて!私のおしっこをそれだけ溢したらLに決まってるでしょ!礼子にこれ以上叩かれるのが嫌だったら、次の子のおしっこは精々一生懸命溢さずに全部飲むことね!」真弓も同じく、信次が僅かに溢したのを遠慮会釈なく、Lにチェックしてトイレを後にしていた。トイレから出ることを許されない、信次を残して。
「ああ気持ちよかった!」「ほんと、最高よね、信次の口!あれ本物のナチュラルボーン便器、て感じね!玲子いいなあ、あんな便器をいつでも使えるなんて!」興奮した面持ちで和枝と真弓がパネルの向こうから出てくるのを、玲子たちが待ち構えていた。「そうでしょ、最高でしょ慎治の口って。」「妬かない妬かない、順番で明日からもずっと使わせてあげるからさ。明日は慎治の口を使ってごらんよ、また一味違うわよ。」フフフ、二人ともすっかり興奮しちゃって、可愛いんだから。まあ当然よね、私たちも最初におしっこ飲ませた時って、本当にゾクゾクしちゃったものね。チラリと腕時計に目をやった礼子が声をあげた。「さあ昼休みはまだ5分あるわ、もう一人ずついけるわよ、次は誰が行く!?」勢いよく手があがった。
5
5時間目の授業の間、慎治たちは未だ屈辱に震えていた。流石に教室におしっこの臭いを漂わせられては迷惑、ということで口をゆすぎ、顔を洗うことは許されたものの全身に浸み込んでいる汚辱の味はそんなもので消えはしない。授業など、先生が何を言っているかなどまったく頭に入らないでいる内に、あっという間に5時間目が終了し10分休憩となった。チャイムが鳴り、教師が退室するや否や玲子が、そしてクラス中の女の子が立ち上がった。「さあ信次、トイレ行くよ!」「え、ええっそ、そんな、ま、またなのおおおっ!?!?」「当たり前でしょ、無期公衆便所の刑、全ての休み時間、信次はトイレになる、て判決したでしょ?当然この休みもトイレに決まってるじゃない、ほらさっさと立ちなさい!」「慎治、慎治も当然、速攻便器よ。全く二人とも余計な手間かけさせないでよね、休み時間になったら何も言われなくてもさっさとトイレにダッシュして、誰かがおしっこしに来るのを待ってなさいよね!」あ、あああ・・・10分休み、その僅かといえば僅かな時間に慎治たちはそれぞれクラスメート二人ずつのトイレにされた。
そして6時間目、悪夢だ、これは悪い夢だ、なんでまたおしっこを飲まされたんだ・・・慎治たちが現実を直視できずにいる間にあっという間に授業は終わり担任の夕礼も終了、後は生徒だけのホームルームとなった。あ、あああ・・・呆然と座り込んでいる慎治たちを尻目に、礼子がホームルームの開始を告げた。通常の連絡事項等を淡々とこなし、一呼吸置いて礼子が宣言する。「以上、他に何かありますか?・・・何もないですね、では最後に神崎さん、矢作慎治と川内信次、二人の公衆便所刑受刑者が今日どれだけ溢したか、および懲戒の鞭打刑執行回数を発表して下さい。」「ハイ、では発表します。」富美代がトイレから回収した二冊のノートを手に発表する。「矢作慎治、L2回、M1回につき計8発、川内信次、L3回につき計9発、懲戒として鞭を受けなければなりません!」「ハイ、分かりました。では両名、前に出なさい、本日分の懲戒として、鞭打刑を執行します。」「ヒイッ、イヤアアアッ!」「ひ、ひでえ、ひどすぎるうううっ!」泣き喚く慎治たちを富美代と朝子が素早く取り押さえ、教壇に引き立てる。「ほら慎治、しっかり自分で立ちなさい、手間かけさせないの、ちゃんと立たないと、礼子の後で私も引っ叩くよ!」富美代の一言は効果抜群だった。教壇を抱きかかえるように、うつぶせになって皆に尻を向ける慎治のズボンとパンツを富美代が一気に引き下ろす。「キャアッ、きったなーい!」「もう慎治、そんなばっちいお尻こっちに向けないでよ!」「やだ、なんか臭いんじゃない、あんた!ちゃんと洗ってるの!?」笑い転げながら嘲るクラス中の女の子の嘲笑に、慎治は顔から火が出る思いで必死で耐えている。その顔をグイッと礼子がこじ上げる。「さあ慎治、刑を執行するわよ。」カチャカチャ、と聞きなれた音を立てながら手馴れた仕草で礼子はベルトのバックルを外し、シュルッとウエストから引き抜いて両手に構える。礼子の手の中でベルトが、服飾品が一瞬にして鞭に、拷問具に変化する。「さあ逝くよ、ハイッ!」ピシーン、パシーン・・・礼子の鞭の音が教室中に響く。8発打ち据えられた慎治が引き下ろされると、次いで信次が引き立てられる。同じくベルトを構えた玲子が9発打ち据える。刑の執行が終わった時、慎治たちは剥き出しの尻、未だ鞭の余韻が残る尻を抑えながら床に転がり、屈辱と苦痛に咽び泣いていた。そんな信次たちを呆れたように玲子は見下ろしていた。「全く大袈裟なんだからもう!たった9発、しかもベルトじゃない?今更信次たちにはこんな程度の鞭なんて、ほんのお遊びみたいなもんでしょ?本当は全然痛くなんかないくせに大袈裟に泣いちゃったりして!」礼子も大きく頷く。「ほんとよね。こんな程度でメソメソ泣いて辛いフリするんだからねえ、全くもう!まだまだ反省が足りないみたいね・・・まあいいわ、二人とも公衆便所の刑は無期だからね、ゆっくりとその腐った根性、叩きなおしてやるわよ。さあみんな、こんな連中にいつまでも付きあってられないわよね、部活もあるし、解散しよう!」礼子の閉会宣言でクラスメートは三々五々、部活に、或いは帰宅の途につく。ほぼ全員が教室を後にしても、慎治たちは未だ泣いていた。そんな慎治たちに構わず、礼子もさっさと自分の机を片付け、帰り支度を整えると未だ泣いている慎治の頭を踏み付ける。「じゃあね慎治、明日は一日フルにみんなのトイレにしてもらうのよ。ちゃんと早く来なさいよ、朝一は私のトイレにしてあげるからね。楽しみにしてなさいね。アハハ、アハハハハッ!じゃあね、泣き虫便器ちゃん、ま・た・あ・し・た、ペッ!」口中一杯にたっぷりと溜めた唾を思いっきり吐き掛けると、礼子は慎治たちを残したまま笑いながら富美代たちと一緒に帰っていく。教室の電気も消し、薄暗くなった教室で惨めにすすり泣く慎治たちにはもう一瞥もくれずに、礼子たちは帰っていった。
恐怖に震えながら、それでも漸く慎治たちは家に辿り着いた。復讐の無残な失敗、そして礼子たちによる「罰」の宣告。一体どういう目に合わされるのか、坊野たちが想像を絶する、ある意味で非現実的ともいえる程の責めを味あわされるのをたっぷりと見せ付けられただけに、慎治たちの恐怖は気も狂わんばかりのものだった。そんな慎治たちにとっての希望はたった一つ、礼子たちが警察を呼ぶ、と言っていたことだった。確かに坊野さんたちは礼子さんたちをレイプしようとした、だけど・・・だけどあそこまで無茶苦茶やったんだよ・・・坊野さんたち、全員片輪にされちゃったんだ・・・あの怪我、隠しようもないよね・・・だったら、幾らなんでも礼子さんたちも罪に問われるわね、過剰防衛どころじゃない、拷問まで楽しんでたんだから・・・流石に警察だって礼子さんたちのこと、調べるよね、そうしたら、少なくとも暫くは礼子さんたちだって、僕たちに関わりあう暇はないはずだよね・・・
だが現実は慎治たちの淡い期待に冷たく背を向けていた。冷静沈着かつ用意周到な玲子の用意は単に戦闘だけには留まらなかった。玲子たちは慎治たちを送り出すと、落ち着き払ってかねてからの手筈通り、まずは自分たちの両親に電話を入れた。可愛い娘とその親友がレイプされかかり、辛うじて相手をKOしたものの恐怖に怯えて涙ながらの電話を入れてきたのだ。玲子たちの両親は直ちに持てる力、人脈の全てを駆使して愛娘の力になる手配をした。警察、弁護士、そして政治家に至るまで。地元の有力者である玲子たちの両親がダブルで動いたのだ、その影響力は強力なものだった。
そしてもう一つ、極めて強力な別ルートも作動した。それは良治たちのルートだった。良治たち自身は別に、有力者の一族ではない。だが体育会、東大でいうところの運動会ルートは礼子たちの利による?がりとは別の、先輩-後輩ラインという極めてウエットかつ緊密な?がりを持っていた。無論、警察上部にもOBはいる。所属部の中核選手であり、OB間にも極めて顔の広い良治たちが自分の教え子がトラブルに巻き込まれて危機に瀕している、お願いします先輩、助けて下さい、と泣き付いたのだ。この威力は即効的だった。なまじ利によるところがなく純粋なお願いベースの分、受けたOBも極めて気軽に、速攻で対応してくれていた。手配を終え、一呼吸したところで玲子たちは警察に電話を入れた。勿論、攫われてレイプされかけた哀れな犠牲者として。全ては計算通りだった、たった一つの誤算を除いては。玲子たちにとって意外だったのは、これらの手配は結果的に不要だった、ということだった。
通報を受けた所轄警察の少年課担当刑事、池上は色めきたった。「なに、SNOW CRACKの連中がレイプ未遂をやらかした?で、しかも襲おうとした女の子たちに抵抗されてのされちまっただって!?こいつは・・・チャンスだ、課長、私が直ぐに行きます、あいつら、中々シッポを出さないがいつか絶対に検挙してやろうとてぐすね引いてたんですよ!このチャンスに連中を徹底的に締め上げて、余罪も何もかも全部白状させて一挙に奴等を壊滅させてやりますよ!」少年課の中でも最も敏腕の池上が完全にやる気になっているのだ、課長の五反田としても異論はない。「よし、すぐに行ってくれ、頼むぞ、奴等を一気に追い込んでくれ!」現場に到着した池上は工場の惨状を見て、一瞬躊躇したのは確かだった。こ、これは・・・ボロ雑巾のように、半死半生で転がっている坊野たち四人と床一面の血塗れの修羅場は海千山千の池上をしても驚きを禁じえなかった。だが、切り替えは素早かった。まあいい、カス共がどうなっていようが俺の知ったことか。いや、こいつは却ってツイてるかも知れないぞ。こいつらこんな重傷だったら、手当てをエサにすりゃ何でも自白させられるかも知れないな。驚きを直ぐに心の奥底にしまい、いかにも柔和な笑顔を浮かべながら池上は玲子たちに近づいてきた。「やあ君たち、今日は災難だったね。僕は池上、この事件を担当させてもらうことになるからね、一つよろしく頼むよ。」さあ、ここが勝負どころよ・・・玲子たちの目にも流石に緊張の色が走る。それに素早く気づいた池上は礼子たちの不安をかき消すように、声を立てて笑った。「いやみんな、そんなに緊張しなくていいんだよ。僕は君たちの味方だからね。いいかい、はっきり言っておくが君たちを攫ってレイプしようとしたこいつら、SNOW CRACKは最悪のギャング、街のクズだ。君たちはそいつらに襲われたんだよ、本当に無事でよかった。いや、必死で抵抗したんだろう、多少は過剰防衛もあったかもしれないが、そんなの全く関係ないよ。後は僕に任せてくれれば大丈夫、君たちに不利になるようなことは間違ってもしないから。僕の仕事は君たちを守り、こいつらを少年院にできるだけ長く送ることなんだ。僕は、いや警察はみんな君たちの味方だからね、大船に乗ったつもりで安心していてくれ!」池上の指揮下現場の警官は全員、端から完全に玲子たちの味方と化して玲子たちに不利な証拠を全て抹消し、ただひたすら、坊野たちの罪を問うことに全力をあげていた。玲子たちが拍子抜けする程だった。
傑作だったのはその後の、所轄署にかかってきた一本の電話だった。礼子たちの両親、そして良治たちの根回しは奇しくもある一人の所でバッティングしていた。何と本庁の部長、目黒のところで。利、情両面からの懇請を受けて目黒は所轄に直接、電話をかけてきたのだ。「お、おい池上君・・・部長、本庁の目黒部長から直接、電話が入っているぞ・・・」電話を回してきた五反田の声は明らかに動転していた。無理もない、階級社会の警察内部において、キャリア、それも出世階段まっしぐらの目黒の威光は絶大だ。池上のように現場叩き上げ、出世には興味ないタイプならともかく、所轄の課長クラスと言う守りたいポストがある五反田にとって、目黒からの直接の電話はまさに腫れ物に触るような慎重な対応を要求するものだ。チッ、参ったな・・・SNOW CRACKの連中に政治家絡みの奴でもいたのか?大体において本庁のお偉いさんからの電話はろくな事がないからな。これを揉み潰せ、て言うのかよ?苦虫を噛み潰したような表情で電話口に出た池上だったが、その電話の内容は池上の予想と正反対のものだった。
「ああ、君が担当の池上君かね、君も忙しい身だろうから単刀直入に言おう、君が担当している事件だがね、被害者の女の子たちが実は私も色々と縁がある子たちなんだよ。で、その子たちが事件に巻き込まれて酷く怯えているんだ。難を逃れたはいいが、必死だったからやり過ぎたんじゃないか、過剰防衛で自分たちも罪に問われるんじゃないか、とね。でね、そのまあ、なんだ、私としては君に方向性を間違えて欲しくないんだよ、分かる・・・よな?相手は凶悪なギャングだっていうじゃないか、被害者の女の子たちにこれ以上、傷を負わせることがないようにして貰いたいんだよ。」「え・・・?ということは・・・要は被害者の女の子たちが過剰防衛その他で訴えられたりしないように、私にSNOW CRACKの捜査だけに専念しろ、と・・・こう仰りたい訳でしょうか?」「いや、そうはっきり言われても困るんだが・・・まあそういうことだ。」「アハハハハッ!なんだ、そういうことですか!部長、それでしたら何の心配もございません。私も元々目標は只一つ、SNOW CRACKの壊滅です。被害者の女の子たちも確かに、若干やり過ぎはあったかも知れませんが、そんなこと全く、何の問題にもなりません。過剰防衛だなんだだなんて・・・そんなの、あんなクズども相手に成立するわけないじゃありませんか!いや私以下現場全員、そんなこと全く考えついてもおりませんでしたよ!連中相手だったら何をやってもOK,そう・・・過剰どころか過小防衛ですよ!はい、過剰防衛があった、なんて証拠は私たちの誰一人、何一つ見ておりません!」思わず電話口で大笑いしてしまった池上につられるように、目黒も笑い出してしまった。「ハハハハハッ、いやなんだ、そうか、君も私と同じ事を考えていたのか、うんそりゃそうだ、まあ当たり前だよな。あの手のクズどもに悩まされている君たち現場としては、あいつらを壊滅できるこんな絶好のチャンス、逃がすわけがないよな。あ、いかんいかん、もしかして私は変な圧力でも掛けてしまったかな?誤解しないでくれよ。」「圧力?いや部長、私は今、圧力など掛けられていないと思いますが。圧力とはそう・・・やりたい事をやるな、とかやりたくない事をやれ、と命じられることでしょう?私はまさに、部長の仰ることをその通りにやりたい、と思っておりました。ですからこれは、そう、言うなれば激励を頂いたものかと?」「おおそうだ、そうだ!君の言う通り、君と私の意見は完全に一致しているんだからな。うん、確かに私は圧力など全くかけていないな。そう、君の言うとおり、私は君を激励したかったんだ。いやすまんすまん、余計な時間を取らせてしまったな。後で何か差し入れを贈っておくよ、頑張ってあのクズどもを壊滅させて、思う存分手柄を立ててくれたまえ!」
幾ら出世に興味がない池上でも、上層部に激励されて悪い気はしない。強制されてではなく自分の意思で、受身と自発では全く勢いが違う。自らの意思と上層部の支持が一致したことを見て取った池上は一気に突っ走った。坊野たちを立件し、少しでも長く少年院に送り込むためには手段を選ばなかった。礼子たちの暴走はきれいさっぱり無視され、SNOW CRACK内部のリンチ、ということであっさり片付けられてしまった。そして民間の中立的な病院ではなく、わざわざ警察病院に運び込まれた坊野たちを待っていたのは連日の過酷な取り調べだった。流石に拷問に掛けられるわけではない、だがそれは法律を遵守して、というわけではない。単純に必要ないからだった。全身の傷でうめき続け、鎮痛剤を、休息を懇願する坊野たちに池上は情け容赦なく、自白を迫った。鎮痛剤なし、休憩無しの長時間尋問はそれだけで半死半生の坊野たちにとって、拷問同然のものだった。僅かな、ほんの一時しか持たない量の鎮痛剤、ごく短時間の休憩と引き換えに次から次へと坊野たちは余罪を白状させられ、仲間の罪も売らされていった。
単に肉体の痛みだけではない。玲子たちの過酷な拷問に精神も肉体もボロボロにされ、あげくに睾丸まで潰された坊野たちに抵抗する気力など全くない。敏腕の池上は坊野たちから手に入れた情報をもとにSNOW CRACKのメンバーを次々と検挙し、あっという間に彼らを壊滅へと追い込んでしまった。勿論、幹部である坊野たちについてはたっぷりと長期刑を、検察逆送となるに十分の証拠を固めてめでたく塀の向こうに叩き込んでしまった。玲子たちへの配慮も十分だった。池上はこっそりと玲子たちの家の顧問弁護士に調書を事前に見せていたが、玲子たちの不利になることなど何一つ、影も形もなく消え失せていた。
かくして坊野たちは塀の向こうに消え、残ったSNOW CRACKの残党も殆どが検挙された。玲子たちの暴走も全て、無かったことに抹消された。全ては片付いた。残るは・・・慎治たちへの罰だけだった。
2
玲子たちは早くも、日曜日には池上からの電話で全て安心するように、過剰防衛等、礼子たちにとって不利になることは一切捜査しない、警察にとって興味があるのはあくまで坊野たちを処罰することだけであり、玲子たちの身の安全、経歴に全く傷がつかないようにする配慮には万全を期す、との連絡を受けていた。フウッ・・・これで安心ね。フフフ、私たちはこれでスッキリだけど、信次たちは果たして、どんな顔で登校してくるのかしら。全てを片付けた玲子は早くも、信次たちをどう処罰するか、ワクワクしていた。そして月曜の朝がきた。
「お、おはよう・・・ございます・・・」れ、玲子さんたちがもう来ている・・・信次は朝から上機嫌の玲子たちを見て胃がシクシクと泣き出した。上機嫌、玲子さん、上機嫌だ。玲子の笑顔を見ただけで、信次は自分の淡い期待、幻想など粉々に打ち砕かれていることを悟った。こ、こんなに上機嫌だってことは・・・もう警察沙汰はすっかり片付いちゃったんだな・・・駄目か・・・もう駄目だ・・・もう俺たちの最後の希望も無くなった、もうどうにもならないんだ・・・絶望の中、信次の脳裏を忌まわしい、考えたくもない言葉が侵食していく。罰・・・玲子さん、罰を与える、て言ってたな・・・どんな、どんな罰を与えられるんだ、鞭?いや、鞭なんかじゃ済まないかも・・・じゃ、じゃあどんな???信次の中で恐怖が勝手に一人歩きしていく。信次の顔が見る見る泣きべそ顔になっていくのを見て玲子は楽しそうにケラケラと明るい笑い声を立てた。「もう信次ったら!何朝一から思いっきりブルー入ってるのよ、やあねえ。ほら、朝くらいもう少し楽しそうな顔してご覧よ!・・・ねえ信次、大体、この週末は色々あったじゃない、土曜のパーティー、楽しかったよね?」ヒッ、ヒイッ!き、来たか!!!悲鳴をあげそうになる信次を片手で制して玲子は続けた。「信次、そんなに怯えないの。私、今信次をどうこうするつもりは全くないよ。もう時間もないしね・・・例の件は後でゆっくりとね。そう、お昼休みにしようか?」信次は心臓が縮み上がる思いだった。あ、後で・・・これじゃあ蛇の生殺しだ、や、やるならいっそ一思いにさっさとやってくれ・・・だがあまりの恐怖に言葉を発することもできずに口をパクパクさせている信次に軽くウィンクしながら、玲子はさっさと席に戻ってしまった。
そして昼休み、さっさと弁当を食べ終えた礼子たちは慎治を急き立てた。「ほら慎治、早く食べてよ、今日は予定がつかえてるんだからさ。慎治たちも楽しみにしてたんでしょ?どういう罰を与えられるか。今日のメインイベント、早く始めたいんだからさ、さっさと食べてよ!」砂を噛むような思いでただ機械的に、味わう余裕すらなく弁当を飲み込んでいた慎治たちの手が凍りついた。ば、ばつ、バツ、罰…もう食事どころではない。「ああもう!信次、礼子が早く、て言ったのが聞こえなかったの?早く、て言われたのに何で信次は手を止めちゃうのよ!」玲子が些かいらついた声をあげた。「あ、ああ、ご、ごめんなさい…で、でも、でももう、食べられない…」実際、手だけではない、口も喉も胃も、信次たちの全身が凍り付き、もう食べることなど到底できなかった。「うーん、まあ仕方ないか。じゃあ信次、二人とももうご馳走様でいいわね?いいの、本当に?午後私たちのせいでお腹すいた、なんて文句言わないでよ?」礼子は念を押すように尋ねると、ゆっくりと教壇に向かって歩いていった。
「ハーイ、皆さん、そのまま食べながら聞いてくださーい。臨時ホームルームを開きます!」礼子の凛とした声にクラスメートの視線が集中した。「実はこの週末、私たち四人、それに矢作慎治君、川内信次君との間で、非常に大きな事件が発生しました。そのご報告をしたいと思います。では当事者のお二人に、自分の口から報告して貰いましょう。矢作君、川内君、前に出てきなさい!」あ、ああ…そんな、じ、自分の口で喋らされるの…だが抵抗などできない。フラフラと夢遊病者のように前にさまよい出た二人は、ぼそ、ぼそと途切れ途切れに告白、懺悔を始めさせられた。「あ、あの、、、ぼ、ぼくたちは…お、おそわせました…礼子さん、たちを…」「や、やとった、んです…坊野さん、たちを…SNOW CRACKを…」一瞬、教室がシーンとした後、一斉に声が上がった。「何、何よそれ、全然わかんないよ!」「襲わせたって信次たちが?ねえ一体あんたたち、何やらかしたのよ!」「ちょっと、SNOW CRACKて何よ、ちゃんと分かるように説明してよ!?」蜂の巣を突付いたような騒ぎを暫く楽しんでいた礼子がパンパンッと手を叩いて皆を制した。「ハイハイ、みなさんお静かに!気持ちはよく分かりますが、少しご静聴願いまーす!矢作君、川内君、君たちの告白も全くなっていませんよ。もっときちんと、順を追ってしっかりと説明してください。はい、では一からやり直し!」
礼子の巧みな誘導と質問により、慎治たちは自分が何をしたか、逐一白状させられた。
礼子たちを恨みに思ってギャングを雇ったこと。そのギャングに礼子たちをレイプさせようとしたこと。礼子たちが襲われた廃工場で、ギャングが礼子たちを襲うのを見物していたこと。全てを白状させられた。慎治たちの告白の間、シーンと静まり返っていた教室は一瞬の静寂の後、怒号に包まれた。「なによそれ!慎治、あんたそれでも人間なの!?」「さ、最低!ギャング雇って礼子たちをレイプさせようだなんて・・・信次、あんた気でも狂ったの!?」「クラスメートをレイプさせようとしたの?女の子の一生狂わせようとしたなんて・・・慎治、あんたいますぐ死んで、この場で死になさいよ!」「全く、ふざけるにも程ってもんがあるわよね!信次、どうする気なのよ、ええ、あんた・・・生きてる値打ちなんかないわよ!」「ったく、ああ穢らわしい!こんな最低男が一緒にいただなんて・・・今すぐ死んで、二度とその顔、私たちの前に見せないでよ!」洪水のような罵声に圧倒されながら、慎治たちは呆然と何も言えずに立ちすくんでいた。その態度が女の子達の一層の怒りを買った。「慎治、何とか言いなさいよ、このケダモノ!」誰かが投げつけたのを皮切りに、一斉に慎治たちに物が、シャープペン、紙くず、その他ありとあらゆる手近な物が投げつけられた。「みんな、こいつ・・・許せない!みんなでやっちゃおうよ!」誰言うともなく発せられたその声に、全員が立ち上がりかけたその時、礼子の声が響いた。
「ハイ、みんなそこまで!みんなストップ、そこまでよ!落ち着いて、みんな、それじゃリンチよ。そんなことをしたら、みんなも慎治と同じレベルに堕ちちゃうわよ。ストップ、落ち着いて、兎に角一旦座って!」礼子の声には有無を言わせぬ迫力があった。「礼子、でもこいつら、どうするのよ、礼子たちは被害者なんでしょ?こいつらを、こいつらをこのまま許してやる気なの?」「許す、とは言ってないわ。でもね、ここは日本、法治国家よ。どんな極悪非道の罪人にも裁判を受ける権利は保証されているわ。だから、私たちも慎治たちに、せめて裁判は受けさせてやろうと思うのよ。裁判を受けさせて、そして判決として下された事を刑罰として執行するのよ。そうじゃなくちゃ、ただのリンチよ。それじゃあ慎治たちと同じレベルに堕ちちゃうわ。そんなの嫌よ。今、みんなに話を聞いてもらったのは、慎治たちを裁判にかけるためよ!」
裁判・・・なるほどね、そういう趣向ね・・・何となくクラスに納得したような空気が広がる。「みんな分かってくれたみたいね。じゃあ早速始めましょう!裁判長は玲子、検察官は私がやるわ。原告はフミちゃんよ。それと慎治、安心していいわよ、ちゃんと弁護人もつけてあげるから。我ながら甘すぎる、とは思うけど人民裁判にはしないであげるわ、感謝しなさいよ。で、弁護人は・・・そうね、土曜一日付き合ってもらって事情が分かっているから、真弓と里美にお願いするわ。あ、それと裁判進行に際しての廷吏は朝子に頼むわね。それとこの裁判、玲子が判決下したんじゃどうせ慎治たち、納得しないで文句言いそうでしょ?アメリカンスタイルで陪審員制とするわ。陪審員は、そう、みんなにお願いするわね。」な、なんてことだ・・・慎治たちは思わず言葉を失ってしまった。裁判、聞こえはいいがこれは単に慎治たちに屈辱を味あわせるための手段、罰を与えるためのワンステップ過ぎない。だが文句を言う暇すら与えられずに、裁判が開始されたまずは法廷のレイアウト、とばかりに教壇上に裁判官席として玲子の椅子が中央に、そして検察官席として礼子の席、そして原告である富美代の席が左側、弁護人席として真弓、里美の席が右側にセットされた。そして慎治たちは被告席、教壇の下の床に土下座させられ、その横に威圧するかのように朝子が陣取っていた。そして周りを取り囲むように陪審員席としてクラス中の女子生徒が椅子を移動させて取り囲んだ。床に土下座させられた慎治たちにとって、それだけで十二分に屈辱的なシチュエーションだった。礼子たちは一段高いところに、しかも椅子に腰掛けているのに対し、自分たちは床に、しかも土下座させられている。裁判、というより江戸時代のお裁き、平伏する身分が低いものにお上が裁きを下す、といったシチュエーションだった。「ではこれよりクラス裁判を開始します。まずは検察官より訴状を読み上げます。被告人はその間、そのままの姿勢で平伏していなさい。」玲子の凛とした声が響いた。屈辱の涙をこらえながら平伏する慎治たちを一瞥すると、礼子が口を開いた。
「原告、神崎富美代は被告、矢作慎治と幼馴染であります。本学、聖華学園に進級してからも幼馴染ではありますが極めて出来の悪い被告に対し、なにくれと面倒をみてやっていたのに対し、被告はあろうことか原告を理不尽にも逆恨みし、もう一人の被告、川内信次と共謀し、神崎富美代とその友人である3名を陥れようとしたのであります。そして一昨日、被告人両名は被告および原告双方が面識ある学外のギャングを雇い、原告を襲わせたのであります。幸いにして原告は虎口を脱し、無事であったものの心身双方に大きな苦痛を受け、その治療には相当の時間を要するものと思われます。か弱い女性を襲わせ、一生の傷を負わせようとした被告人両名に対し、検察は厳罰をもって臨むべきだと考えます。」め、面倒をみてやった!り、理不尽!逆恨み!屈辱に耐えながら礼子の冒頭陳述を聞かされていた慎治たちの両手がブルブルと震えた。な、なにが理不尽だ、逆恨みだ、し、心身双方の苦痛、そ、そんな、ぼ、僕たちの苦痛に比べたら!!!「ひ、ひどい、あんまりだ!!!」「そ、そうだ、じ、自分たちは、自分たちはもっと、もっとめちゃくちゃに僕たちを苛めてたくせに、あ、あんまりだ!!!」思わず顔をあげ、悔し涙を流しながら嗚咽のような声をあげる慎治たちを、玲子は冷たく睨み付けた。
「被告人は裁判長の許可なく発言しないように。不規則発言には法廷侮辱罪を適用します。只今の不規則発言について、当法廷は被告人の有罪を宣告し、略式命令を下します。廷吏、被告人両名を鞭打ち各10回の刑に処しなさい。」ああ成る程ね、礼子が私に廷吏やれ、て言ったときは何の必要があるかよく分からなかったけど、こういうことね。「了解しました、裁判長。被告人を鞭打ち10回の刑に処します。二人とも、シャツを脱いで背中を出しなさい!」カチャカチャ、とわざと音を立てながらバックルを外すと、朝子はベルトをウエストから引き抜いて二つ折りにし、パシッと打ち鳴らした。「ヒッ、そ、そんな!」「や、やめて、ぶたないで・・・」朝子がベルトを構えただけで、鞭に対する恐怖を本能に近いレベルまで刷り込まれている慎治たちは心底怯え切った泣き声になってしまった。だがそんなことで許す玲子ではない。「被告人は直ちにシャツを脱ぎ、廷吏が鞭打ちやすいように四つん這いになりなさい。命令に従わない場合、刑を倍加します。」そ、そんな!!!抗議の声をあげたくなるのを必死で堪えながら慎治たちはシャツを脱ぎ、四つん這いになった。逆らえばどうなるか、考えるまでもなかった。上半身裸になり、犬のように四つん這いになった慎治の横に朝子が立ち、ベルトを高々と構えた。「これより、法廷侮辱罪として鞭打ち10回の刑を執行します。ハッ!」ビュオッ・・・パッシーン!「ヒッヒイッ!」ヒュオッ、パシッ、ビシッ・・・朝子は情け容赦なく慎治を打ち据えると踵を返し、今度は信次の傍らに立った。「鞭打ち刑、執行!」ヒュオッ・・・パシッ、ビシッ!「い、イツッ、イタイイイッ!」朝子が一切の手加減抜きで、全力でベルトを振り下ろす度に慎治たちの悲鳴があがる。フンッ、なによ大げさね。私たちに散々本物の鞭で打ち据えられているんでしょ?慎治たちにとって、高々この程度のベルトなんて、ハタキで撫でられてる程度のものじゃないの?大げさに騒がないでよ。朝子の考えている通り、確かに鞭の痛みに比べれば遥かに軽い。だがベルトはベルト、痛いものは痛い。慎治たちにとって、この悲鳴は演技でもなんでもない。
10回ずつ打たれた慎治たちが泣きながら正座し、のろのろとシャツを着ようとするのを、玲子がピシャリと制した。「シャツを着ることは許可しません。今後不規則発言の際、直ちに鞭打ち刑を加えられるように被告人はそのまま裸でいなさい。」そ、そんな・・・あ、あんまりだ・・・思わず口を開きかけた信次は玲子の射るような視線に凍りついた。いいわよ信次、何か言いたいのかしら?言ってごらんなさいよ。口を開く勇気があるならね。玲子の視線は一瞬にして信次を圧し、すべての言葉を凍りつかせてしまう。フン、何も言えないのね、まあ賢明な選択だけど。「では裁判を再開します。被告人、罪状認否を行います。只今の検察官の告発に対し、事実と認めますか?事実と認めるか否かのみを答えなさい。」
そ、そんな、イエスかノーか。と答えろだなんて!「そ、そんなムチャな、イエスかノーかだなんて・・・」「そ、そうだ、だってどうしようもなかったんだから・・・」バカな連中・・・フッと礼子が失笑するのと同時に玲子が再び刑を宣告する。「只今の被告の発言は当法廷の命令を無視するものです。よって被告人に対し、当法廷の命令を無視した罪により法廷侮辱罪を宣告します。廷吏、直ちに鞭打ち刑10回を執行しなさい!」アッ、アヒイッ!そ、そんな!だが今度は泣き言を言う暇さえない。ベルトを手にしたまま信次たちの横に立っていた朝子は、直ちに手近にいた信次の首根っ子を捕まえると床に押さえつけて土下座させ、そのまま首根っ子を足で踏み付けながら思いっきり、背中を打ち据えた。次いで慎治も打ち据えると朝子は無言のまま、ベルトをパシッと打ち鳴らしながら信次のすぐ横に再び構える。
「再度質問します。被告人は事実と認めますか?」もう選択の余地はない。「・・・み、認めます・・・」「・・・は、はい・・・みと、めます・・・」弱々しく答える二人を見て玲子は微かに笑いながら里美、真弓の方を向いた。「弁護人の陳述を認めます。」里美と真弓は何やらコソコソと相談していたが、やがて代表する形で真弓が口を開いた。「一昨日、原告が襲われた場所に実は我々弁護人も居合わせておりました。そこには被告人もおりましたため、状況については弁護人も把握しております。被告人は起訴事実については既に認めておりますので、弁護人も事実関係については争いません。しかしながら、被告人は自らが雇ったギャングが倒された後、非常なる恐怖を感じておりましたことを指摘します。被告人が既に、罰への恐怖には怯えていたこと、罪への呵責はないと言えども十分なる恐怖は味わってきたことに免じ、寛大なる処罰をお願いするものです。」な、なんだこれは・・・こ、これが、これが弁護、こ、これじゃ、これじゃ検察側の証言じゃないか!!!動きかけた信次はビクッと思わず震え、横を盗み見た。そこには朝子がいた、そしてその手、ベルトを握った手が確かにビクッと動いていた。信次、その調子よ、早く何か言いなさいよ。また思いっきり引っ叩いてあげるから。確かに朝子の手はそう語りかけていた。
玲子も信次たちが何か言うのを待っていたが、二人が肩を震わせながらも黙っているのを見てフッと小さく笑った。まあ流石に学習効果、ていうものが少しは出るわよね。まあいいわ。「では次に原告に意見陳述を認めます。原告、自由な発言を認めます。」玲子が頷くのを見て富美代が陳述する。「検察官の告発はすべて真実です。私、および私の友人が被告の陰謀により如何に恐怖し、如何に傷ついたかは言葉にしようもありません。何卒、被告を厳罰に処すようにお願いします。」げ、厳罰・・・厳罰という言葉に恐怖する信次たちを一瞥すると、玲子が宣告した。「では以上をもって結審します。陪審員、表決をお願いします。被告人を無罪とする陪審員、挙手願います。」シーンと静まり返ったまま、誰の手も上がらない。「有罪とする陪審員、挙手願います。」バッ、と一斉に女子生徒全員が挙手する。「全陪審員一致をもって、被告人を有罪と認めます。」
3
あ、あああっそ、そんな!!!もう限界だった。「ひ、ひどい、あんまりだ、こんなの裁判じゃないよ!」「そ、そうだ、ふ、不公平だ!インチキだあああっ!」必死で絶叫する二人をニヤニヤと笑いながら見ていた玲子がやがて、スッと手をあげた。玲子が手をあげる、僅かそれだけの動作であれだけ喚いていた慎治たちが恐怖に声を失ってしまった。「廷吏、被告人を法廷侮辱罪により、鞭打ち刑10回に処しなさい。」直ちに朝子のベルトが唸る。そし鞭打ち刑が終了したとき、玲子が質した。「被告人、当法廷を不公平、インチキと称しましたが、その理由を述べなさい。」り、理由・・・思わず慎治たちは息を呑んだ。「起訴事実を認めたのは被告自身です。そして表決を下したのはクラスの女子生徒全員、しかも裁判官、検察官、原告は共に投票権を有していません。それを不公平と言うからには何か根拠があるはず。その根拠を聞きましょう。」り、理由、根拠・・・確かに明らかな不正、とは言いにくい。数の暴力ではあるが、それを不正、とは言えない。「もし根拠がない、というのであれば、重篤なる法廷侮辱罪を適用します。」じゅ、重篤な!い、いけない、なにか、なにかないか、何か根拠は・・・あ、あった!信次たちの脳裏を同じ考えが走った。
「そ、そうだ、あ、ある、あるよ理由は!」「お、男、男がいないじゃないかあああっ!陪審員が女の子だけだなんて、ふ、不公平だ、お、男、男子も投票しなくちゃ、こ、公平じゃないよおおおっ!」フウッ・・・呆れたように玲子は失笑を漏らした。何、男子にも投票させろ?何を言い出すかと思ったら・・・もうちょっとマシな文句、考えなさいよね、まあどうでもいいけど。「男子にも陪審員として投票させるべき、それが被告人の主張ですね?」「そ、そうだ!」「そうだよ。その通りだ!」バカねえ本当に。玲子は最早あからさまに侮蔑の笑いを浮かべていた。「いいでしょう、その主張を認め、表決を追加します。男子生徒の皆さん、各員の陳述は聞こえていましたよね?聞こえていれば、表決のみを執り行うこととしたいのですが、異議のある方はいますか?」誰も挙手しない。オイオイ、ッタク俺たちまで巻き込むなよな、という顔で男子生徒は互いを見回している。「では被告人が無罪と思う方、挙手願います。」誰も挙手しない。当然だ、玲子たちに敢えて逆らおうとする者がいるわけがない。「被告人、これでいいですか?」「や、やだ、やだやだあああっ!」「そ、そうだ、む、無罪、とは言ってないけど、有罪とも言ってないじゃないかあっ!ゆ、有罪じゃない、だったら無罪と同じになるはずだあああっ!」「・・・いいでしょう。では有罪と認める陪審員は挙手してください。」パラッ、パラッと手が挙がり始める。「被告人が納得するよう、棄権はなしとしましょう、全員がどちらかに挙手するまで、何回でも表決します。有罪と積極的に認める陪審員のみ、挙手してください。後で無罪に挙手しなおしたい、という陪審員は遠慮なく、挙手しないでそのままにしていてください。」
こう言われて有罪としない男子生徒など、いるわけがない。玲子たちの想像を絶する強さと残酷さは全員、目の当たりに見ている。信次たちという生贄がいてよかった、自分がああなるのだけは死んでもご免だ、この思いは全員共通だ。加えて、玲子たちは信次たち以外には極めて人気が高い。美貌と明るい性格に加え、面倒見も極めていいし成績も最高レベルだ。だからテスト前にノートをコピーさせて貰ったり、宿題を教えて貰った連中も多い。彼女を紹介して貰った男さえいる。おまけに近隣に名高い美少女軍団の玲子たちだ、玲子たち四人の誰か一人でも参加する合コンをセットしたらそれだけで仲間内で大きな貸しを作れる。ショップ情報にしろ何にしろ、玲子たちから得ているものは非常に多いが玲子たちに何かを返せる男子生徒など殆どいない。従って大部分の男子生徒は玲子たちに対して借りは相当にあるが貸しはない。翻って、慎治たちに味方して得るものは・・・何もなかった。入学早々、玲子たちに苛められ始めた慎治たちは、男子の間でも友達と言える存在はいない。特に仲がいいわけでもない慎治たちを庇って得られるものなど何がある?得られるリターンとして唯一可能性があるのは、我と我が身を玲子たちの苛めターゲットに提供することだけ。クラスの内外を問わず人気と人望の厚い玲子たちの苛めターゲットになること、それは高校生活を、人生で最も楽しい時期の一つを丸ごと、地獄に変えてしまうことを意味する。そんな危ない、超ハイリスクノーリターンの賭けに乗るものがいるわけがない。
それでも自分一人の責任で慎治たちを突き落とすのならまだ躊躇するものもあるが今日は多数決、一人一人の責任は軽い、という格好の言い訳がある。ワリーな慎治、別にお前たちに恨みはないんだけどな、でも別にお前らに何かしてやる義理もないしな。天城さんには宿題見せてもらったりしてるからね。俺、霧島さんの隠れファンなんだよ。ま、自分で何とかしてくれよ。別にいいじゃん、天城さんたち四人と遊んで貰えるなんてラッキーだろ?バラッ、パラッと男子生徒の手が挙がり、あっという間に全員の手がしっかりと挙手されてしまった。「あ、あああ・・・そ、そんな・・・」「み、みんなお願い、見捨てないでよおぉぉぉ・・・」弱々しい、消え入りそうな声で慎治たちは涙ながらに哀願したが誰一人、手を下ろすものはいない。当然でしょ、信次たちに味方するのがいたら、お目にかかってみたいものだわ。全くバカなんだから。信次、あんたたちが男子からも苛められないのは何故だと思っているの?私たちの専用オモチャにしてるから、みんな手出ししないだけなんだよ。それをまあ、男子も表決に参加させれば助かるかもしれないだなんて、相変わらず現実認識がなってないわね。嘲りの微笑を浮かべながら玲子は判決を下す。
「被告人、希望通り男子全員も表決に参加しましたが、全員一致で有罪の評決に達しました。以上をもって、当法廷は被告人両名に有罪を宣告します。では検察官、刑を求刑してください。」「はい、検察は被告人両名の卑怯卑劣な行為に対し、公衆便所の刑を求刑します。」「わかりました。判決を下します。被告人矢作慎治、川内信次の両名を無期公衆便所の刑に処します。被告人両名はこれより、全ての授業間の休み時間、昼休みの間、女子トイレにて固定されて利用を希望する女子生徒全員の便器となり、おしっこを飲むことを命じます。刑期は無期、当法廷が被告人に顕著なる改悛の情が認められた、と判断するまで刑を執行し続けます。尚、刑は直ちに執行します。これにて閉廷、被告人を女子トイレに引き立てなさい。」「い、いやたああああっ、や、やめてくれええええっ!!!」「そ、そんな、べ、便器、みんなの便器だなんて、そ、そんな、そんなのないよおおおっっっ!!!」
いやだ、やめてと泣き叫ぶ慎治の両手を礼子と富美代、信次を玲子と朝子が掴み、女子トイレに引きずっていく。泣き喚く信次にクスクスと笑いながら玲子が小声で囁いた。「フフフ、何そんなに恐がってるのよ、バカねえ信次ったら。安心しなさい、そんなに酷いことするつもりはないんだからさ。大して痛くも何ともないわよ、ほんの軽いお遊びみたいなものよ、そんなに怖がることないわよ。」ひ、酷いことはしない?だ、だけどトイレに連れてかれるんでしょ・・・公衆便所の刑、そしてトイレに引き立てられる、と来ればどういう運命が待っているかは信次でなくとも直ぐに分かる。こ、これが酷いことでなくて何だって言うの・・・信次の涙も止まらぬうちに一行は女子トイレに到着した。そのトイレは入ると左右に個室が5室ずつ並んでいる。手前側四室は洋式便器だが、一番奥の一室ずつのみは和式便器になっている。しかも好都合なことに、その便器は個室の入り口から見て縦、つまり奥に金隠しが位置していた。女子生徒の大半が一緒についてくる中、刑場に到着した玲子たちは早速、設営にとりかかった。「さあ信次、ここが今日からの信次たちの居場所よ。フフフ、信次たちにまさにお似合いの場所ね。朝子、あれ持ってきた?」「もちろん!はい!」朝子が差し出したのは二本のやや太目の木の棒と大型の透明な漏斗だった。カラン、と乾いた音をたてながら玲子は二本の棒を便器の上、金隠しに近い位置に置くと信次の手を引いた。「信次、便器、といっても支えがないと疲れちゃうでしょ?優しい私が枕を用意してあげたわよ、感謝してね。さあ、ここに寝なさい!」「ね、寝なさいって・・・こ、ここに?と、トイレ、便器の上じゃないの!」信次が思わず金切り声で悲鳴を上げるのをよそに、礼子は慎治を向かい側の個室に連れて行く。「慎治、あんたはこっちよ。慎治の便器はここ、アハハッ、違ったわね、便器は慎治の口だったわよね、じゃあここは・・・そう、慎治のベッドかしら?」「そ、そんな!べ、便器を、トイレをベッドだなんてあんまりだあああっ!」信次たちは必死で抗議の声を上げるが、玲子たちが許してくれるわけがない。「さあ信次、さっさとそこに寝なさい!」玲子の声が鞭のように響くともう、二人の抵抗の意欲などあっさりと吹き飛ばされてしまう。う、ううう・・・屈辱に咽びながらトイレの床に横たわる。コンクリートの硬く冷たい感触が背中から熱を奪うと同時に信次たちの精神を凍りつかせる。トイレの床に横たわり、玲子たち女子生徒の姿を足元から見上げているとそれだけで例え様もない屈辱だ。
「朝子、ここのセッティングよろしくね。」「OK,任せといて!」横たわった信次の口に朝子が手にした漏斗を差し込んだ。「ウフフフ信次、まるでフォアグラ用のガチョウみたいよ。楽しみにしててね、本物のガチョウ見たくお腹パンパンにしてあげるから。アハハハッ、私たちのおしっこでね!」朝子と富美代は信次たちの口に漏斗を差し込むと、次いで顔の両脇に高さ20センチ程度の踏み台を置いた。「高さはどうかな?」朝子が踏み台の上に乗り、しゃがんでみる。スカートを穿いたままの朝子の股間が信次の顔の上に降りてきて、止まった位置は漏斗の口から5センチ程度上の位置だった。「OK,丁度いい高さみたいね。」口が広めの漏斗、透明のプラスチック越に朝子のブレザーのスカートが遠ざかっていく。向かい側のトイレでも、慎治が富美代の手により便器と化せられていた。そしてガタガタッと音を立てながら、玲子たちがトイレへ何かを運び込む音がした。便器の上に寝かされたまま上目遣いに見てみると、玲子たちが真弓、和枝らに手伝わせて三枚の衝立を持ち込んでいた。
「玲子、何なのそれ?なんでトイレにパネルなんか持ち込むの?」里美が不思議そうに尋ねた。「えっ、分からない?だって里美ももう、何するかは分かってるでしょ?そう、慎治たちを公衆便所にしてみんなでおしっこ飲ませてやるわけじゃない、だけど慎治たちを寝かせとくんだからどうやったって足がはみ出ちゃうでしょ?トイレのドア、閉められないわよ。流石にドア開けたまま、後ろから丸見えとか隣りからひょいと顔覗かせたら丸見え、ていう状態でおしっこするのなんか嫌じゃない?だからこうやって、パネルで仕切っとくのよ。」言いながら玲子は信次側、手前の洋式便器個室との仕切りに1枚目の衝立を立て、次いで2枚目を信次たちが寝かされている、両側の和式便器個室の真ん中に立てた。そして三枚目を同様に慎治側の洋式便器個室との仕切りにする。「さあこれでOK。これでトイレに入るところもおしっこするところも、誰からも見えないわよ。ああ、もっとも信次たちは別ね、二人は特等席で見ていいわよ、私たちがおしっこするところをたっぷりとね。」
4
すべてのセッティングが完了したのをチェックすると、礼子がパンパンッ、と手を打った。「はいみんな、準備完了したところで説明するわね。無期公衆便所の刑、まあ刑の名前とこのセッティングを見ればどういう刑かは一目瞭然、説明の必要はないわね?そう、今まで私たち四人が慎治たちをトイレとして独占してきたけど、今から慎治たちの口、公衆便所として無料開放します!」わあっすっごーい!ほんと、ほんとに慎治たちにおしっこ飲ませていいの?トイレを埋めた女の子たちから一斉に歓声が上がる。「勿論よ!学校に居る間中、全ての休み時間、慎治たちを公衆便所として解放します。慎治、あなたたち二人は朝、登校したら直ぐこのトイレに直行よ。そしてこの姿勢でみんなが来るのを待って、おしっこしてもらいなさい。勿論、拒否権なんか一切ないわよ。みんな、慎治たちがもし少しでも反抗的な素振りを見せたら遠慮なく言ってね、即、罰を与えるから。そう、気絶するまで鞭で打ちのめしてやるからね!」きゃあっ鞭で打ちのめすだって、すっごーい!また歓声が上がる。礼子は満足げに頷きながら更に続けた。「で、私たちはもう毎日飲ませてるから慣れてるけど、みんなはおしっこ飲ませるの初めてでしょ?上手く飲ませられなくて慎治たちが零しちゃったら興醒めだし、床が汚れるのも嫌よね。だから取り敢えず、こうやって漏斗をセットしておくわ。この漏斗だったら口も広いし量もたっぷり入るから、何も考えないで思いっきりおしっこしても零れる心配は全然ないし、もし零れちゃったとしても下は便器、本物の便器だからね、流してそれでお終い、後始末する必要なんかないわ。あ、それとねみんな、これはあくまで慎治たちに対する刑罰なんだからね、ちゃんと慎治たちが飲むように、ズルして口から溢れさせたりしないようにしっかりチェックしてね。」「ああ礼子、これを用意しといたわよ。」横から富美代がノート、紐を付けトイレの壁に打ち込んだ釘に引っ掛けられるようにしたノートを渡す。そのノートの最初の数ページは上に日付を記入し、その下を四列、左から0、S,M,Lと四列、縦に罫線を引いて区切ってあった。「みんな、おしっこしたら必ず、このノートにチェックを入れてね。零した量がゼロなら0の列、以下少しならS,結構零したらM,一杯零したらLの列にチェックして、夕方のホームルームでそれを集計するから。慎治、よく聞いとくのよ、L一個につき3発、Mなら2発、Sなら1発で計算して、その数を今日一日の零した罰、ということで、ホームルームの時にみんなの目の前で思いっきりベルトで引っ叩いてやるからね!」
わあっ流石は礼子、きびしいーっ、ほんとよねえ、じゃあ慎治たち、一生懸命飲まなくっちゃねえっ、え、でもさ、面白くない、意地悪するのも楽しくない?全部きれいに飲んだのにさ、Lにチェックしちゃうとか!どっと女の子たちは盛り上がった。いい、それいいかも!流石に当の礼子が苦笑しながら一応、フォローを入れた。「ハイハイ、みんな一応良識をもって刑を執行してくださいね。フフフフフ、あんまり慎治を苛めないようにね!あ、それと一つ、これだけは絶対に守ってね。いい、飲ませていいのはおしっこだけよ。おっきいほう、うーん、そう、うんちは・・・絶対に食べさせちゃ駄目よ!うんちの方は私たちがいずれ食べさせてやろうって思って大事に取ってあるんだからね!抜け駆け禁止よ!食べさせたら・・・恨むわよ!?」再びどっと場が盛り上がる。苛めないようにだって!それ礼子が言うのーっ!?思わず笑いが漏れたところで礼子が再び、パンパンッと手を打ち鳴らした。「ハイハイみんな、何か質問はありますか?ない?それじゃあ最後に私から一言、トイレの順番、基本的には予約制とするわね。なるべく多くの人におしっこ飲ませて貰いたいから、一応原則として、一日一人一回とするわね。勿論、空いていたら自由に飲ませて頂戴。あと、まあ飼い主特権、ということで私とフミちゃんは慎治に対して、玲子と朝子は信次に対しては予約なしでいつでも飲ませてOK、順番待ちなし割込み可の優先権を貰うわよ。ズルイ、というご意見もあるでしょうけど、まあそのくらいは勘弁してね。」チラリと腕時計を覗き込むと、昼休みは未だ10分ほどあった。「さあ、じゃあ無期公衆便所刑、執行開始を宣告します!最初に飲ませるのは誰!?」
ハイハイハイッ!勢いよく何人かの手が上がった。わたしわたし、私が飲ませたい!皮切りは予想通り、礼子たちのグループのメンバーだった。結局、慎治の個室に残ったのは和枝、そして信次の個室には真弓が残った。「じゃあね、ゆっくりおしっこ楽しんでね!」ぞろぞろとクラスメートが衝立の向こうに去り、各々の個室には二人だけが残った。「ウフフフフ、ねえ慎治、私がトップバッターになつたけど、どう?慎治の予想通りだった?それとも誰か別の子に飲ませられると思った?」笑いながら和枝が慎治の顔を覗き込む。「フフフ、本当にいいざま、お似合いよね。なんかこうやってみると慎治、便器が板についてるよ。やっぱり礼子やフミちゃんたちにたっぷりと飲ませられた成果かしら?」笑いながら和枝は踏み台に登った。「慎治、やっと、て感じかな?フミちゃんたちが毎日おしっこ飲ませるの見ててさ、本当は私も飲ませたいな、て思ってたんだよ。覚えてないかな?小学校の頃、私も慎治のこと、蹴っ飛ばして泣かせたことあったでしょ?あの時にもっと苛めて慎治のこと、私のオモチャにしちゃえばよかったな、てずっと思ってたんだよ。そしたら今ごろは礼子じゃなくて、私が慎治のこと、毎日苛めてたのにな、て残念だったのよ。せめてあの時、泣かせるだけで許してなんかやらないでおしっこ飲ませてやれば良かったな、そしたら慎治の口、私が一番乗りだったのにな、てね、結構悔しく思ってたのよ。フフフ、漸く思いがかなうわ、慎治、フミちゃん程しょっちゅうじゃないけど、昔泣かされた私におしっこ飲ませられるのよ、どう悔しい?それとも慎治にとってはもう嬉しいのかな?まあどっちでもいいわ、たっぷり飲ませてあげるからね。」和枝はスカートをたくし上げると、パンティを下ろし、慎治の顔の上にゆっくりとしゃがみ込んだ。「・・・さあ慎治、覚悟はいいわね?私のおしっこ、飲ませてあげる。これから私も毎日、飲ませてあげるからね!」
その頃、真弓も信次の顔をゆっくりと見下ろしていた。「うん信次、よくお似合いのポーズよ。私、漏斗咥えた人間なんて見るの初めてだけど、信次にはよく似合っているわよ。」笑いながら真弓は二,三回咳払いをした。「ああ信次、最初に言っとくけど、これおしっこする時の私の癖だからね。別に信次を苛めるためにわざとやってるんじゃないのよ。信次みたいな痰壷がない限り、女の子が外で唾吐くことなんてまずないでしょ?だからトイレに入ったとき、こうやって痰切っとくのよ。フフ、普通の男の子じゃ分からない、信次みたいな便器君にしか分からない女の子の秘密、てやつかしら?遠慮しないでいいわよ、たっぷりと見せてあげるから。」オヤジのようにカアーッと下品に喉を鳴らすわけではない、女の子が普通に咳払いするのと同じ要領でンンッ、ンッ!と短く喉を鳴らすと真弓はペッと勢いよく漏斗に痰を吐き捨てた。風邪を引いているわけではないから黄色くはない。だが白いと言っても唾とは明らかに違う、よりドロッと密度が高い、ゲル状の塊が真弓の狙い通り漏斗の底部、信次の口に差し込まれた嘴の部分への縁に着地する。そして真弓の痰唾は自らの意思を持つアメーバのようにゆっくりと漏斗の嘴を伝い、信次の口中へと流れ込んでいった。ジュルッとした感触、塩気を感じる汚辱の味が信次の舌を支配する。「クックウウッ・・・」ひ、ひでえ・・・た、痰唾だなんて、き、きたねえ、きたねえよ・・・信次の顔が屈辱に歪むのを見て真弓は満足そうに声を立てて笑った。「アハハハハッ!どう、私の痰唾の味は!いつも飲まされている唾とは一味違うでしょ、どんな味なの?私、痰唾の味なんて考えたことないし、ましてや他人の痰唾なんて絶対に口にする機会はないからね、想像もつかないわ。後でどんな味か教えてね、じゃあ私の痰唾の味、ちゃんと分かるようにもう一つお代わりあげるわね、ンンッ、ンッ、ペッ!」唾をいつも飲まされている、というのは些か事実とは異なる。確かに信次は毎日のように誰かに唾を吐き掛けられている。だが玲子を始め女の子たちは信次を辱しめるために、軽蔑の象徴として唾を吐き掛けているのだ。だから別に信次に唾を飲ませたいわけではない。結果的に信次の口中に唾が飛び込むことはあるが、それはあくまで例外、殆どの唾は顔に吐き掛けられたものだ。こうやってたっぷりと唾、しかも痰唾の味を味合わされたことなどない。ひどい屈辱だった。「さあ信次、後もつかえているし、そろそろ飲ませてあげるわね。」ガタッと真弓は踏み台の上に上ると、パンティを下ろしながらゆっくりとしゃがみ込んだ。
「フフフ慎治、覚悟はいいわね?」「さあ信次、いい、出すわよ・・・ちゃんと飲まないと大変よ、後で玲子の鞭が待ってるわよ。」信次たちの視界は透明のプラスチック越しに和枝、真弓の尻と白いパンティに支配されている。そしてその上、パンティの端あたりの遥か高みから二人の顔が慎治たちを見下ろしている。クラスメート、同じ部の同期。本来だったら一番仲良くならなければならない存在は今、慎治たちに人間として最大の屈辱、他人の排泄物を飲ませる、という人格を一切無視した刑罰を加える執行官となっていた。自分の尻の、足元の更に下に置き、情け容赦なくおしっこを飲ませる。ああ、礼子さんたちと同じだ。和枝も真弓も美少女揃いの聖華の生徒に相応しく、礼子たち程ではないとはいえ、かなりのレベルの美少女だ。その二人がパンティをおろし、自分の顔のすぐ上にしゃがみ込んでいる。余りに当然のように、和枝も真弓も罪悪感とか可哀想は愚か、自分たちが苛めている、慎治たちを傷つけ酷い屈辱を与えようとしている、という意識すらない。二人の心を支配しているのは楽しい、この最高に楽しい遊びを思う存分満喫する、ということだけだった。慎治たちがどうなるかなど、全く眼中にない。まさに礼子たち、天使のような微笑を湛えながら無邪気に悪鬼のような苛めを加え、慎治たちを地獄に突き落とす美少女が増殖していた。
和枝と真弓は慎治たちの顔を見下ろしながら、やがて尿意が十分に高まってくるのを感じた。うん、出そう。「・・ンッ・・・」「フッ・・」ほぼ同時に括約筋を緩めた二人の尿道口から奔流が迸り出た。ジャアアーーッ、コポポポポ・・・二人の小便は勢いよく漏斗に注がれた。漏斗の側面に当たった小便が渦を巻き、そして底部の穴に吸い込まれていく。わあっ一杯でる、随分溜まってたのね。和枝は我ながら驚く程の量の小便を排泄しながら、自分が排泄した小便が漏斗に溜まっていくのを楽しげに見下ろしている。アハハハハッ、なんか渦巻いてるじゃない、しかも穴というか慎治の口に吸い込まれていって、ほんとトイレそのものね。アハハハハッ、なんか私のおしっこ、泡立っちゃってるし!見上げる慎治は和枝が放尿を開始した瞬間、思わず一瞬目をつぶってしまった。礼子たちが無意識の内に、全部飲ませるためにある程度勢いをコントロールしながら放尿するのに対し、和枝は全力で、何のブレーキもかけずに勢いよく放尿していた。慎治の目の前で、透明な漏斗にはねた和枝の小便が勢いよく渦を巻きながら蓄積していく。最初は無色だったその小便は溜まるにつれおしっこの色、吐き気を催す薄いレモンイエローになっていく。ぐうっ・・・き、汚い・・・自分がおしっこを、他人の排泄物を飲まされているんだ、と否応なく認識させられる屈辱の色だった。味覚嗅覚聴覚だけではなく、慎治は視覚でも和枝のおしっこを飲まされていた。
シャアアアアッッ、漏斗で響くせいかしら、何かおしっこの音が随分響くわね。ちょっと驚いた真弓だったが、次の瞬間にはその唇に笑みが浮かんだ。シャアアッという音に混じり、ゴポポポ、という水がパイプに吸い込まれていく音がしたからだ。その音はごく短い間、慎治が咥える漏斗の嘴に真弓の小便が満たされるまでの間しかしないが、真弓にとってはそれで十分だった。ウフフフフッ、行った逝った、私のおしっこが信次の口に届いたのね。ウフフフフ、これで信次を汚してやった、これで私も玲子や朝子と一緒、信次を一生取り返しがつかないように汚してやったのね!真弓は溜まっていく自分の小便と漏斗の透明なプラスチックの向こうで、信次の顔が微妙に動くのを、口に流れ込む自分の小便を飲み干そうと信次が必死で嚥下するのを飽くことなく眺めていた。いいわ、この光景、ほんとに最高!玲子たちったらずるいよ、こんな楽しいことを独り占めしてたなんて!漏斗に注がれた真弓の小便はほんの一瞬のタイムラグを置いて、信次の口に流れ込んでくる。ウグゴエッ・・・飲み慣れた味、他人の小便の味が信次の口いっぱいに広がる。飲みやすい、といえば飲みやすい。玲子たちに放尿される時は口を一杯に空けたまま、喉を鳴らすようにして飲み干さねばならない。使えるスペースは自分の口腔の中しかないのだから、急いで全力で飲み下さないと直ぐに口から溢れ出てしまう。そして溢れさせてしまったら、玲子たちからたっぷりと鞭打たれてしまう。だが今は漏斗を咥えさせられている、要は大型のストローを付けてもらったようなものだ、格段に飲みやすい。しかしその分、口に注がれる真弓の小便は一旦、口中に滞留し、信次の舌に小便の味を刻み込んでいく。玲子たちの小便は口中に殆ど溜まることなく喉の奥へ、そして食道へ胃袋へと直行するからその汚辱の味を味わうまでには至らない、精々温かさとうっすらとした塩辛さ、そして飲み終わってからの残り香に苛まれるだけだ。だが今、信次の口腔は真弓の小便に満たされている、信次の全ての味覚細胞が真弓の小便に浸されている。それは信次の口の中でゆっくりと舌に絡みつき、たっぷりと小便の味を信次に焼き付けていく。生温かい、薄目の麦茶にたっぷりと塩を入れたような、何ともいえないえぐみと不快感を伴う味。玲子たちに毎日飲まされている以上に強烈に、自分は今、女の子のおしっこを飲まされているんだ、自分の口は女の子の便器にされているんだ、と否応なく認識させられる味だった。普通の人間が一生味わうことのない味、汚辱に満ちた人生最悪の飲み物の味を。美少女の体内で濾過され、濃縮された純粋な侮辱と軽蔑の雫、相手を僅かでも人間扱いしているなら、飲ませるなど想像することすらできない筈の、他人にとっては最も汚い液体の味を。それはまさに拷問具そのもの、肉体的には痛みも苦しみも伴わないが、信次の精神をズタズタに、一生二度と修復不可能な程に破壊する天然の拷問具だった。そしてその拷問具は目の前、いや自分の顔の上に君臨する美少女の体内で精製されているのだ。今日だけではない、明日も明後日も明々後日も。毎日毎日、いつまででもこの美少女、いや玲子を始めとするクラスメートすべての体内でこの拷問具が精製され続けるのだ。信次は屈辱を通り越し、絶望の余り気が狂いそうだった。
無限とも思える時間の後、漸く二人の体内から迸る奔流は弱まり、やがて完全にストップした。だが漏斗にはまだまだ二人のおしっこがたっぷりと溜まっていた。ペーパーで軽く性器を拭き、パンティを履きながら和枝たちは立ち上がると、慎治たちが自分のおしっこを飲み干すのをしっかりと監視していた。ングッングッ・・・慎治たちが必死でおしっこを飲み込む音が響き、やがて漏斗の中は空になった。「ハアッハアッ・・・」「ンガッ、グハッ・・・」二人の荒い息遣いが聞こえる。ウフフ、飲ませてやった、本当に楽しいわね、これ!あっそうだ出る前にお漏らしチェックもしなくちゃいけないのよね。和枝は少しかがみこんで慎治の頬を見た。二筋三筋、自分のおしっこが伝わった跡がある。慎治、生意気よ私のおしっこを溢すなんて!ええと、お溢しの罰は何回だったっけ?Lでも・・・たったの3発かあ。じゃ、これは当然、3発よね!上履きの白い爪先で慎治の顔を小突きながら和枝は当然の如く、宣告する。「慎治、だめじゃないそんなに溢しちゃ!当然Lにチェックしたからね、後で玲子に鞭3発、叩いて貰うのね!」ヒッ、そ、そんな!ぜ、全然溢してないじゃない、ほ、ほんのちょっとだけじゃない、そんなこれだけで鞭3発だなんて!グエッ!」思わず漏斗を口から出して抗議する慎治の口を和枝は乱暴に踏み付ける。「うるさいよ慎治、大体生意気なのよ、私の折角のおしっこを溢すだなんて!私のおしっこをそれだけ溢したらLに決まってるでしょ!礼子にこれ以上叩かれるのが嫌だったら、次の子のおしっこは精々一生懸命溢さずに全部飲むことね!」真弓も同じく、信次が僅かに溢したのを遠慮会釈なく、Lにチェックしてトイレを後にしていた。トイレから出ることを許されない、信次を残して。
「ああ気持ちよかった!」「ほんと、最高よね、信次の口!あれ本物のナチュラルボーン便器、て感じね!玲子いいなあ、あんな便器をいつでも使えるなんて!」興奮した面持ちで和枝と真弓がパネルの向こうから出てくるのを、玲子たちが待ち構えていた。「そうでしょ、最高でしょ慎治の口って。」「妬かない妬かない、順番で明日からもずっと使わせてあげるからさ。明日は慎治の口を使ってごらんよ、また一味違うわよ。」フフフ、二人ともすっかり興奮しちゃって、可愛いんだから。まあ当然よね、私たちも最初におしっこ飲ませた時って、本当にゾクゾクしちゃったものね。チラリと腕時計に目をやった礼子が声をあげた。「さあ昼休みはまだ5分あるわ、もう一人ずついけるわよ、次は誰が行く!?」勢いよく手があがった。
5
5時間目の授業の間、慎治たちは未だ屈辱に震えていた。流石に教室におしっこの臭いを漂わせられては迷惑、ということで口をゆすぎ、顔を洗うことは許されたものの全身に浸み込んでいる汚辱の味はそんなもので消えはしない。授業など、先生が何を言っているかなどまったく頭に入らないでいる内に、あっという間に5時間目が終了し10分休憩となった。チャイムが鳴り、教師が退室するや否や玲子が、そしてクラス中の女の子が立ち上がった。「さあ信次、トイレ行くよ!」「え、ええっそ、そんな、ま、またなのおおおっ!?!?」「当たり前でしょ、無期公衆便所の刑、全ての休み時間、信次はトイレになる、て判決したでしょ?当然この休みもトイレに決まってるじゃない、ほらさっさと立ちなさい!」「慎治、慎治も当然、速攻便器よ。全く二人とも余計な手間かけさせないでよね、休み時間になったら何も言われなくてもさっさとトイレにダッシュして、誰かがおしっこしに来るのを待ってなさいよね!」あ、あああ・・・10分休み、その僅かといえば僅かな時間に慎治たちはそれぞれクラスメート二人ずつのトイレにされた。
そして6時間目、悪夢だ、これは悪い夢だ、なんでまたおしっこを飲まされたんだ・・・慎治たちが現実を直視できずにいる間にあっという間に授業は終わり担任の夕礼も終了、後は生徒だけのホームルームとなった。あ、あああ・・・呆然と座り込んでいる慎治たちを尻目に、礼子がホームルームの開始を告げた。通常の連絡事項等を淡々とこなし、一呼吸置いて礼子が宣言する。「以上、他に何かありますか?・・・何もないですね、では最後に神崎さん、矢作慎治と川内信次、二人の公衆便所刑受刑者が今日どれだけ溢したか、および懲戒の鞭打刑執行回数を発表して下さい。」「ハイ、では発表します。」富美代がトイレから回収した二冊のノートを手に発表する。「矢作慎治、L2回、M1回につき計8発、川内信次、L3回につき計9発、懲戒として鞭を受けなければなりません!」「ハイ、分かりました。では両名、前に出なさい、本日分の懲戒として、鞭打刑を執行します。」「ヒイッ、イヤアアアッ!」「ひ、ひでえ、ひどすぎるうううっ!」泣き喚く慎治たちを富美代と朝子が素早く取り押さえ、教壇に引き立てる。「ほら慎治、しっかり自分で立ちなさい、手間かけさせないの、ちゃんと立たないと、礼子の後で私も引っ叩くよ!」富美代の一言は効果抜群だった。教壇を抱きかかえるように、うつぶせになって皆に尻を向ける慎治のズボンとパンツを富美代が一気に引き下ろす。「キャアッ、きったなーい!」「もう慎治、そんなばっちいお尻こっちに向けないでよ!」「やだ、なんか臭いんじゃない、あんた!ちゃんと洗ってるの!?」笑い転げながら嘲るクラス中の女の子の嘲笑に、慎治は顔から火が出る思いで必死で耐えている。その顔をグイッと礼子がこじ上げる。「さあ慎治、刑を執行するわよ。」カチャカチャ、と聞きなれた音を立てながら手馴れた仕草で礼子はベルトのバックルを外し、シュルッとウエストから引き抜いて両手に構える。礼子の手の中でベルトが、服飾品が一瞬にして鞭に、拷問具に変化する。「さあ逝くよ、ハイッ!」ピシーン、パシーン・・・礼子の鞭の音が教室中に響く。8発打ち据えられた慎治が引き下ろされると、次いで信次が引き立てられる。同じくベルトを構えた玲子が9発打ち据える。刑の執行が終わった時、慎治たちは剥き出しの尻、未だ鞭の余韻が残る尻を抑えながら床に転がり、屈辱と苦痛に咽び泣いていた。そんな信次たちを呆れたように玲子は見下ろしていた。「全く大袈裟なんだからもう!たった9発、しかもベルトじゃない?今更信次たちにはこんな程度の鞭なんて、ほんのお遊びみたいなもんでしょ?本当は全然痛くなんかないくせに大袈裟に泣いちゃったりして!」礼子も大きく頷く。「ほんとよね。こんな程度でメソメソ泣いて辛いフリするんだからねえ、全くもう!まだまだ反省が足りないみたいね・・・まあいいわ、二人とも公衆便所の刑は無期だからね、ゆっくりとその腐った根性、叩きなおしてやるわよ。さあみんな、こんな連中にいつまでも付きあってられないわよね、部活もあるし、解散しよう!」礼子の閉会宣言でクラスメートは三々五々、部活に、或いは帰宅の途につく。ほぼ全員が教室を後にしても、慎治たちは未だ泣いていた。そんな慎治たちに構わず、礼子もさっさと自分の机を片付け、帰り支度を整えると未だ泣いている慎治の頭を踏み付ける。「じゃあね慎治、明日は一日フルにみんなのトイレにしてもらうのよ。ちゃんと早く来なさいよ、朝一は私のトイレにしてあげるからね。楽しみにしてなさいね。アハハ、アハハハハッ!じゃあね、泣き虫便器ちゃん、ま・た・あ・し・た、ペッ!」口中一杯にたっぷりと溜めた唾を思いっきり吐き掛けると、礼子は慎治たちを残したまま笑いながら富美代たちと一緒に帰っていく。教室の電気も消し、薄暗くなった教室で惨めにすすり泣く慎治たちにはもう一瞥もくれずに、礼子たちは帰っていった。
1
翌日、未だ目覚めたくない、このまま永久に夜が続いてくれたらな、という願いとは裏腹に慎治たちは妙に早く目覚めてしまった。
もう朝か・・・今日は一日公衆便所・・・鉛を飲み込んだような気分で重い足を引きずりながら登校すると、礼子たちはもう登校していた。女の子たちも既に2/3以上登校している。「あっ慎治、やっと来たわね、遅かったじゃない!」「あ、ああ、ご、ごめんなさい、あ、お、はよう、ございます・・・」慎治の挨拶が終わらぬうちに、礼子はすっと立ち上がり、歩き出した。「別にどうこう言ってるわけじゃないじゃない、そう一々ビクツカないでよ。まるで朝っぱらから私が苛めてるみたいじゃない!まあどうでもいいけどさ、ほら慎治、さっさとおいで!おトイレ我慢して待っててあげたんだからね、早く来なさいよ!」ああ、本当に朝一からトイレかよ・・・礼子の後ろをうなだれ、とぼとぼ付いていく慎治の姿に失笑があちこちから漏れる。当然のように、信次も玲子に引き立てられている。
そしてトイレにつくと、礼子は顎をしゃくった。「ほら早く横になりなさい!」慎治がノロノロと踏み台と漏斗をセットしようとしていると、向かいの個室から玲子の声が響いた。
「信次、あんたバカア?私が今更漏斗とか踏み台とか使うと思ってるの?全く便器にすら満足になれないのね、信次は!この低脳!ペッ!」「あっああっごめんなさい、許して・・・」「ほらさっさとそこなさいよ!」玲子の声に弾かれるように、慎治は礼子の顔色を伺った。「慎治、聞こえたでしょ、私も漏斗や踏み台はいらないわ。それより・・・さっさとしてくれないか・し・ら?」礼子の声音に苛つきの影が見える。慌てて慎治は便器の上に、自らの汚辱と安住の地に横たわり精一杯口を開けた。「そうそう慎治、その口よ。今度スムーズにこうできなかったら、分かるわね、鞭よ。」「ふうっ、信次、私のおしっこ飲むの一体何回目だと思ってるの?いい加減、もう何も言わなくても私が気持ちよくおしっこできるようにしなさいよね!」シャアアアアッッッ・・・礼子たちはほぼ同時に放尿を開始した。
その日、慎治たちは昨日の宣告通り休み時間毎にトイレに引き立てられた。聖華の休み時間は1-4,5-6の各時限の合間に10分ずつの休みが入り、また昼休みは一時間となっている。都合4回の10分休みには平均して各二人ずつに飲まされた。そして昼休みは最初の20分間で食事、後片付け等を全て終えさせられ、残り40分間フルにトイレに逝かされた。その間におしっこを飲まされた女の子は実に8人、殆ど休みなし、一人が出たと思ったら直ぐに次の子が入ってくる、といった具合だった。最初は確かに和枝や真弓といった空手部員、合気道部員やココタマ等、礼子たちと親しいクラスメートが中心になって便器化した慎治たちのいわば皮切りをしていた。だが皮切りはそこまで、極く僅かで十分だった。多数派のクラスメートたち、お付き合いで慎治たちに唾を吐き掛けたり靴を舐めさせたり程度はするが積極的に苛めようとはしなかった女の子たち、実際には多数派のこの子たちの中からポツリポツリと、慎治たちにおしっこを飲ませる子が出始めたのだ。
不思議と言えば不思議なものだ。礼子たちも最初はそうだったのだが、お嬢様校である聖華の女子生徒は皆決して苛めっ子等ではない。自分が他人におしっこを飲ませる、なんて想像したことは誰一人ない。だが慎治たちは特別、毎日毎日礼子たちに唾を吐き掛けられ、鞭で打たれ、踏み躙られている。いくら苛められてもひたすら許して許して、と泣き喚くだけの慎治たち。いつしかクラスメート皆にとって、慎治たちが苛められていること、慎治たちが泣いていること、通常滅多に見ることができない男の子が女の子に苛められて泣いている光景、それがこのクラスの中だけでは一つの極ありふれた日常になっていた。
加えて今の刑、無差別にみんなのおしっこを飲まされる公衆便所の刑、これは余りに日常から懸け離れすぎていた。これが仮に全員で毎日、慎治をビンタ、あるいは鞭で打つ、という刑だったら却って容易に慎治たちの痛みを想像できる分、どこかで誰かが、或いは集団的な無意識がブレーキを掛けたかもしれない。だがおしっこを飲ませる、これは余りに想像を絶していた。想像を絶する分、どこか興味をそそられかつ慎治たちの苦痛を想像しにくい物であることも確かだった。
ええ、おしっこを飲ませる!?そんなのできるわけないじゃん!・・・でも、もう一生そんなことする機会、あるわけないよね・・・今を逃したら絶対、二度とそんな機会はないよね・・・そういえば飲尿健康法なんてのもあったわね。ああいうのがあるってことは、おしっこって飲んでも病気になったり体に悪いものじゃないのよね・・・そうよね、もう礼子たちに散々飲まされてるんだし・・・フミちゃんや朝子も飲ませてるのよね・・・もう四人のおしっこ飲んだんでしょ?あ、今また慎治、新たな一人のおしっこ飲んだのね。だったらもう、私一人位増えてもどうっていうことないよね・・・なんか、面白そう・・・一生の記念になるかもね・・・慎治、別に慎治を鞭で叩いたり蹴っ飛ばしたりしたいとは思わないんだけどさ、おしっこ飲ませる、ていうのはなんか惹かれちゃうのよ・・・こういうのって、お祭よね、のらないのって却って変じゃない・・・私もやってみようか・・・
一人、また一人と好奇心、嗜虐心というより好奇心に負けてトイレの予約リストに名前を連ねていった。一人、また一人と参加者が増えるにつれ、群集心理も働いていき罪悪感、抵抗感は加速度的になくなっていく。そして礼子たちのトイレセッティングがまた絶妙だった。これが礼子たちがいつもやっているように直接慎治たちの口におしっこをするとか、或いは手軽に底を抜いたペットボトルか何かを咥えさせてその中におしっこを出す、といった程度のセッティングではおしっこの狙いを定める、勢いをコントロールする、或いは腰を浮かせて中腰の状態で放尿する、といった通常の排泄と相当に違うシチュエーションとなりクラスメートの心理的抵抗も大きかっただろう。ことに直接排泄するパターンでは間近に慎治たちの顔がある分、恥ずかしさも感じたかもしれない。だが慎治たちは透明とはいえ大きな漏斗を咥えさせられているから自分と慎治たちの間には大きな壁があり、自分の秘所を直接見られることはない。この一枚のプラスチック板があるだけで自分の性器を、排泄の瞬間を見られるという心理的な抵抗は相当に少なくなる。しかも踏み台もあるからいつもと同じく完全に腰を下ろしてゆっくりと放尿できる。そして漏斗は大きく、十分に口が広いから何も考えずに一気に放尿しても溢れたり便器の外に飛び散る心配、特に自分にかかってしまう心配は全くない。要は排泄する側のクラスメートから見れば、普段のトイレと全く変わらない要領で、いつもの、生まれてこの方何千回となくやってきた通りに放尿するだけでいいのだ。それだけで他人の口を便器にする、他人に自分のおしっこを飲ませる、という一生二度とできない経験ができるのだ。この魅力には勝てない。その日の夕方、一日の終わりには既に飲ませた方が多数派になっていた。おそらく明日には殆どの女の子が飲ませ、まだ飲ませていない子は圧倒的に少数派になっているだろう。
や、やっと今日が終わった・・・夕方のホームルーム、慎治たちにとって長い長い一日が漸く終わろうとしていた。今日一日で何人に飲まされたんだ?信次は指折り数えてみる。朝一に玲子さん、朝子、そして・・・休み時間毎に二人だから八人、昼休みも八人だったから・・・合計・・・じゅう、はちにん、十八人!?は、はは、ははははは・・・・・信次は力なく笑った。じゅ、じゅうはちにんか・・・そんなに飲まされたのか、俺、そんなにたくさんの女の子のおしっこ、飲まされたんだ・・・す、すげえ、すげえよなあああ・・・腹もガボガボの筈だよな、一体俺、どれ位の量のおしっこ、飲まされたんだ???信次が笑ってしまうのも無理はない。一人一回当たり、仮に平均200ccのおしっこを排泄したとしても全部で3,600cc,平均300ccだとしたらなんと、5,400ccにもなる。1.5リットル入りの大型ペットボトル二、三本、事によるともっと、というとんでもない量を飲まされたのだ。信じられねえ、そんなに飲まされたんだ・・・あまりに大量のおしっこを飲まされたため信次たちは今日一日、他の水分を全く飲む気にならなかった。それだけ飲めば、そりゃ今日一日、他に何も飲む気にならなかった筈だよな。そう、信次たちが今日一日に飲んだ水分は全て、クラスメートのおしっこだけだった。ははは、あれだけ一杯飲まされたせいか、俺もなんども小便しちゃったけど、あれ全部、みんなのおしっこなんだ。みんなのおしっこが俺の体を通り抜けてったんだな。お、俺の、俺の体を、じゃあ・・・ははははは、俺の体の中、みんなのおしっこで一杯、体中、みんなのおしっこが浸み通っていった、てことかよ。は、はは、ははははは・・・・・でも明日も明後日も、まだまだこれが続くんだろ?ということは・・・ははははは、俺の体の中、全身の細胞全部、水分全てみんなのおしっこに置きかえられちまうな・・・へ・へへ・へへへへへ・・・便器人間、おしっこ男信次、の誕生か?へ・へへ・へへへへへ・・・・・べんきまーーーん!じょぼおおおおおっ!力なく自嘲的に笑っている信次に玲子が追い討ちをかける。
「さあ、今日の懲戒は何回かしら?信次、私や朝子はチェックしないであげたんだから、少しは得したじゃない、良かったわね!」殆どのクラスメートはLにチェックしていた。玲子たち以外の延べ14人に対し、L12人、M2人だった。「じゃあ・・・計40発ね!信次、今日の懲戒は私が執行するわ!」教壇に引き据えられた信次の目の前で、朝子がウェストからベルトを引き抜き構える。「逝くわよ、ハイッ!」次いで慎治の番、予想通り慎治の前では富美代がベルトを構える。慎治はL11人M3人、計39発だった。「慎治、毎日の懲戒は私と礼子が毎日、交代で執行するからね、今日の鞭は私、明日は礼子よ。さあ逝くわよ、それっ!」教室に二人の悲鳴が再び木霊した。
2
水曜、木曜と公衆便所の刑は執行され続けた。毎日毎日慎治たちは朝登校するや否やトイレに引き立てられ、礼子たちを皮切りにクラスメートのおしっこを延々と飲まされ続けた。10分休み、昼休みと飲まされ続け、そして夕刻のホームルームではベルトで鞭打たれる。毎日繰り返される刑罰に慎治たちの精神は確実に蝕まれていった。
ひどい、こんな酷い刑罰ってないよ・・・みんなの、みんなの公衆便所だなんて・・・毎日毎日みんなの目の前でお尻を出されて鞭打たれるなんて・・・そ、それを毎日、無期限で続けられるだなんて・・・もう、耐え切れない・・・不幸な、慎治たちにとっては不幸なすれ違いが発生していた。実のところ、刑罰を執行している礼子たちにしてみれば酷いことをしている、という意識は全くなかった。いやそれどころか私たちも甘いな、この程度で済ましてやってるんだから、慎治たちもさぞかしほっとしているでしょうね。まあいいけど、慎治たちも感謝しなさいよ、私たちの寛大さに!と本気で考えていた。当然と言えば当然だ。礼子たちにとっては慎治たちを便器にし、おしっこを飲ませているのは公衆便所の刑の執行以前からやっている日常生活の一部に過ぎない。だから礼子たちからしてみれば、この刑はほんの軽いお遊びのつもりだった。
二人とも私たち四人からそうね・・・大体毎日、最低でも四回ずつは飲まされてるでしょ?それが若干回数増えただけじゃない。別に飲みきれない量を北京ダックよろしく無理矢理飲ませて水責めにしているわけじゃないし、おしっこは無害だって言うじゃない?慎治たちはどうせ私たちのおしっこを毎日飲んでたんだから、高々その回数が増えるだけ、全然大したことないよね。懲戒の鞭にしてもベルトで許してやってるし、回数も50発にもいかないわよ。第一そんなに思いっきり引っ叩いてるわけどもないし、たったあれだけのベルトなんてお尻がちょっと赤くなるだけよね。私たちの本物の鞭であれだけ打たれてる慎治たちにとってはほんのお遊び程度のものよね。大袈裟に悲鳴上げてるけど、ほんとはハタキではたかれてる程度にしか感じてないんじゃない?大体、今までだってみんなに唾吐き掛けられたり靴舐めさせられたりして十分苛められてるじゃない?今まで散々私たちにやられたことが多少回数増えるだけよ、クラス裁判、ていう恥じかきシチュエーションはあったにしてもさ、今更慎治たち、恥ずかしいでもないでしょ?
礼子たちは本心でこの無期公衆便所の刑をほんのお遊び、形式的な、罰とも言えない軽いお遊び程度のもの、としか考えていなかった。そして慎治たちもそう思っていると、ああこの程度の罰ですんでよかった、礼子さんたちがこの程度の罰で許してくれるなんて本当に良かった、と自分たちの寛大さに心の底から感謝しているに違いない、と純粋に信じ切っていた。
一方、飲まされる側の慎治たちは全く事情が異なっていた。慎治たちのひ弱な精神が耐えられる最後の一線は、僕たちを人間扱いしないで酷い苛めをしているのは礼子さんたちだけだ、他のクラスメートたちは苛めるにしても、唾を吐き掛けたり平手打ちで引っ叩いたりはするけど、僕たちのことを人間扱いはしている、一線を超えて苛めてはいない、と思い込むことだった。
物理的な苛めで言えば鞭、本物の鞭、礼子たちが振るうような牛馬にしか使われることがない人間が鞭打たれることなど決してない筈の鞭で打たれることがそれに当たる。そして・・・おしっこを飲まされること、それも慎治たちにとっては最後の一線だった。人間が人間におしっこを飲ませるなんて、絶対にありえない、絶対に・・・礼子さんたちが僕たちに飲ませているのは、僕たちのせいじゃない、僕たちが悪いんじゃない。礼子さんが、礼子さんたちがおかしいんだ、あんなの人間ができることじゃない、礼子さんたち、人間じゃないよ・・・
そう思い込むこと、自分たちが異常なんじゃない、礼子たちこそ異常なんだ、と思い込むことが慎治たちにとっての唯一の心の支えだった。それを礼子たちはいとも簡単に打ち砕いてしまった。礼子たちの誘いに応じ、クラスメート全員が公衆便所の刑に参加していた。全員、そう全員に飲まされたのだ。自分を誤魔化すことさえさせてもらえない。
クラスメート全員におしっこを飲まされた男。礼子たちだけにではない、全員に飲まされたのだ。こんなことされた奴、一生二度と会えないだろうな・・・俺たち、俺たちが異常なんだ・・・俺たちみたいな奴、クラス中の女の子に朝から晩までおしっこ飲まされてる奴なんて、日本中探したって絶対にいないんだ・・・単におしっこを飲ませる人間が増えた、という問題ではない。他の子にだって唾を吐き掛けられてるんだから、おしっこ飲む位どうということないでしょ?というのは責める側の言い分だ。慎治たちにとってはそうではない。おしっこを、おしっこを集団で飲まされる、というのはある意味、鞭で半死半生になるまで打ちのめされるよりも遥かに辛いものだった。我慢の限界だった。坊野たちのように肉体的に破壊されたわけではない、だが精神的な拷問、と言う意味では慎治たちはまさしく延々と拷問を味合わされていたのだ。僅かに残っていたプライドを、自分が人間だ、という最後の誇りをズタズタに破壊され、永遠に奪われる痛みと屈辱と喪失感を。
実際にはあと少し、あと少し耐えていれば良かったのだ。礼子たちはほんの軽いお遊びのつもりだったたから、みんなに慎治たちにおしっこを飲ませることを強制などしていない。そしてみんなも最初こそ興味本位で全員が参加したものの、徐々に参加者は限定されていた。和枝、真弓たちのような合気道部、空手部仲間を中心とする礼子たちのコアなグループ以外は徐々に慎治たちに飲ませる頻度が減っていた。いくら群集心理とは言っても、自ら積極的に苛めを楽しむ女の子はやはり限定されてしまう。そして礼子たちも、段々トイレに立つクラスメートが減ってきた事に気づいていた。だから四人の間ではこんな会話が交わされていたのだ。
みんな一巡したみたいだし、そろそろ新鮮味も薄れてきたみたいね。そうね、マンネリ化しても面白くないしいい加減許してやる?うん、別にいいんじゃない?まあ飲ませたい、ていう子がいたらいつでもご自由にトイレに連れてって、ていう感じで。そうね、じゃあ一応、来週一杯位で公衆便所の刑は終了、ていうことでまあ、トイレからは解放してあげようか。
礼子たちと慎治たち、責める側と責められる側の捩れは拡大しつつ金曜を迎えた。その日、昨日までと同じく朝からトイレに引き立てられた慎治たちはいつものように、まずは礼子たち四人のトイレにされて一日をスタートした。一時間目二時間目三時間目と授業は進み、休み時間毎にクラスメートが慎治たちに次々とおしっこを飲ませていく。そして昼休み、急いで食べさせられた慎治たちがトイレに追いやられてから暫くして、仕切りを越えて二人のクラスメートがやってきた。青葉陽子と古鷹有希子だった。二人とも空手部、合気道部といったコアなグループではないが礼子たちとは仲がよい真面目系の女の子だった。特に陽子は富美代と仲が良く、そのツテで礼子とも非常に仲がよかった。別に慎治たちを率先して積極的に苛めてはいなかったが、二人とも慎治たちに対しては軽蔑しか感じていない。
無論、今回の公衆便所の刑に対しても慎治たちには何の同情もしていない。だが二人とも、まだ一回ずつしか飲ませていなかった。大した理由があったわけではない。単純に面倒くさかったからに過ぎない。おしっこするのに何で一々順番待ちしたり予約したりしなくちゃいけないの?そりゃ慎治たちに飲ませたい気もするけどさ、そんなことまでして飲ませることないわよね。もっと空いてから飲ませてやればいいじゃん、もし刑期が終わったとしてもさ、どうせ礼子たちに頼めば何時だって貸してもらえるわよ。
そのため、やっと空いて来た昨日に陽子は信次、有希子は慎治にそれぞれ飲ませたばかりだった。そしてこの昼休み、ふと見ると予約表はブランクになっていた。
「有希子、なんか今、トイレ空いてるみたいよ?」「ああ本当だ、やっぱりみんな一巡して空いて来たみたいね。どうする?昨日飲ませたばっかだけど、いく?」「・・・うん、そうね。まあ昨日一回飲ませただけだから、一応行っとこうか。だってさ、昨日気が付いたんだけど、ほらもうみんな飲ませちゃってさ、未だ二人両方に飲ませてないのって、私たちだけみたいだよ?私たちも昨日一人ずつ飲ませたでしょ?今もう片方に飲ませれば、これで一応クラス全員、一巡はしたことになるみたいよ?」「へえ、私たちで一巡達成なんだ、じゃあやるしかないわね・・・じゃあ今日は私が信次、陽子が慎治ね。」連れ立ってトイレに現れた二人は左右に別れ、各々の便器の待つ個室に入っていった。
「慎治、ねえ今日は私で何人目なの?もうすっかり便器が板に付いたみたいね。でも私は信次に飲ませるの、これか初めてなのよ、分かる?まあこうやってみんなに飲まされ続けたんだもんね、一々誰に飲まされたか、誰が未だかなんて覚えていないか。」陽子は踏み台に上り、白いパンティを下ろして慎治の顔の上にしゃがみ込みつつ話し掛けた。「ハイ慎治、今度は私の番よ・・・ねえ慎治、ちょっと聞いてみたかったんだけどさ、みんなのおしっこ飲んでて味に違いってあるの?だってさ、私で慎治に飲ませるの丁度20人目だからさ、記念に聞いときたいんだ。」ウン、20人目?・・・慎治はその意味を一瞬、理解できないでいた。20人目・・・その時向かいの個室から有希子の声が聞こえてきた。
「信次、気が付いていないかも知れないけど、私で最後なのよ?私で20人目、これでクラス全員が信次におしっこ飲ませた、てなるわけ。今陽子も慎治に飲ませるとこだからさ、これで二人ともめでたく、クラス全員制覇、全員のおしっこ完飲、てなるわけよ。・・・凄いわねえ、20人のおしっこ完飲、てそうそう出来ることじゃないわよ。玲子たちのことだもん、多分志津子たちみたいな部活仲間の、よそのクラスの子のおしっこもそのうち飲まされるわよ?ウフフ、信次、あんたたちがおしっこ飲んだ女の子の数、そうそう破られることないんじゃない?そのうち学校中の女の子のおしっこ完全制覇したりさ、ううん、もっと頑張ればおしっこ千人切りとか言っててギネスブック狙えるかもよ?」
ぜ、全員!クラス全員!有希子のその言葉は慎治たちの心臓に深々と突き刺さった。全員・・・俺たちこいつで最後、クラス中の女の子全員のおしっこ飲まされちゃったのか?う、嘘だろ!今まで目の前の、いや目の上の女の子のおしっこを飲むだけで精一杯だったから気付かないで済んでいた現実、自分がクラス中の女の子の公衆便所にされたこと、玲子が宣告した公衆便所の刑が完全に執行され、自分たちの口が喉が胃が、そして全身がクラスメート全員の便器にされてしまったのだ、という逃れ様のない現実が二人の精神にグッサリ深々と付き刺さった。そして有希子の洩らした何気ない一言、志津子たちのような玲子たちの部活仲間、中学の同期系、更にはその子たちのクラスメート、と自分たちにおしっこを飲ませよう、という女の子のリングが際限なく広がっていく、その光景がリアルな現実、それも直ぐにでも始まりそうな現実として二人に襲い掛かっていた。学校中の女の子のおしっこ完全制覇・・・今まで飲んだ女の子は大体20人、その20倍近い数の女の子におしっこを飲まされる、それすら大いに有りそうなことに思えてきた。
慎治が半ばパニック状態に近い狼狽を顔に浮べるのを陽子は面白そうに見下ろしていた。フーン、こうやって見下ろしていると、慎治が何考えてるのかなんて、一目瞭然ね。あ、でもこんなお話してる間に、本当におしっこしたくなってきちゃったわ!「さあ慎治、じゃあクラス完全制覇おめでとう!完全制覇達成記念のお祝いよ、私からささやかなプレゼントあげるね、思いっきり、たっぷり私のおしっこ飲ませてあげる、有難く受け取ってね!」
チョロロ・・・シャアア・・・ジャアアアアアッ!陽子が括約筋を緩めるや否や、たっぷりと溜まっていたおしっこが陽子の体内から溢れ出し、それはあっという間に勢いを増して太い水流となって慎治が咥えさせられている漏斗に満ちていく。そしてその薄黄色の液体は信次の口に流れ込み、慎治の舌に慣れ親しんだ味を、他人のおしっこの味を刻み付ける。
「アハハハハッ、完全制覇達成記念のおしっこよ、たっぷりと召し上がれ!」陽子の笑い声が降って来る。「アハハハハッ、飲んでる飲んでる!これでクラス制覇達成ね、おめでとう!記念のおしっこの味、たっぷりと味わってね!夕方のホームルームで報告してあげるね、深,燭舛・・・実匸ラス制覇達成したことを!」向かいの個室から有希子の笑い声も聞こえてくる。信次も飲まされてるのか、これで俺たち二人とも・・・クラス全員のおしっこ・・・飲んじまったのか・・・全員の・・・みんなの・・・お、おしっこを・・・の、飲んだ、みんなのをの・ん・だ・・・
慎治たちの頭の中にこの4日間の記憶がフラッシュバックする。笑いながらおしっこした子、いかにも軽蔑に耐えない、といった顔で見下ろしながらおしっこした子、何の表情も浮かべずに単純に普通の便器にするようにおしっこして一言も発せずに立ち去った子・・・様々な顔が、お尻が自分の上に現われそしておしっこをしていった。それを・・・飲んだんだ・・・みんなのを・・・一人残らず・・・20人・・・分を・・・のんだんだ!!!
慎治の頭の中に浮かんだ、自分におしっこを飲ませていったクラスメートの映像は消えずにグルグルと駆け巡る。アハハ、アハハハハ、アハハハハハッ!嘲笑の声が聞こえてきた。その筈がない、ここはトイレだ、みんなの笑い声なんか聞こえる筈がない!!!だがいくら打ち消そうとしても、慎治の頭の中に響く嘲笑の声、礼子の富美代の和枝の・・・そして陽子の声は止むことなく却って増幅し拡大していく。現実には陽子一人が慎治におしっこを飲ませながら嘲笑の声を上げているだけなのだが、慎治の頭の中は全員の、クラスメート全員の自分を見下ろす顔、嘲笑う声に支配されていた。や、いや、いやだあああああっ!や、やめ、やめろおおおっ、!!わ、笑うな、笑うな、笑わないでくれえええええっっっっ!!!慎治の目の前が赤黒く染まり意識が混濁していく。自分が完全に発狂寸前、パニック状態に陥り精神も肉体も制御できなくなっていくのを微かに感じた。
「ウッギィャラオオオオオッッッ!!!!!」突然獣のような、声とも咆哮ともつかぬ訳のわからない絶叫と共に慎治の全身がビクンビクンと痙攣した。「キャッ、な、何よ!」陽子が叫ぶと同時に「ギッヒャアアアアアアアッッッッッ!!!!!」漏斗を咥えたまま慎治が突然跳ね起きた。「キャアッ、何するのよ!」慎治の顔に漏斗でお尻を下から突き上げられ、バランスを崩した陽子を慎治は更に両手で突き飛ばす。
ドザッ、ゴッ!「い、いったーい!」排泄中の無防備な所を思いっきり突き飛ばされては堪らない。陽子は踏み台から後ろ向きに転げ落ち、半回転して頭を床にしたたか打ち付けてしまった。「ウガアアアアアッ!!!」その陽子に一目もくれず、慎治は絶叫しながら個室、公衆便所の刑を執行されていた個室から走り出し、パネルを突き倒すとトイレから走り出ようとした。
「な、何よ!」慎治の絶叫に有希子が驚いて振り向いた瞬間、有希子の股間の下からも絶叫が響いた。「イイイイアアアアアッッッ!!!!!」
あっと思う間もない、絶叫と共にガバッと体を起こした深,力嚇佑鵬・・実匸されてバランスを崩した有希子を更に信次が突き飛ばす。
「キャアアアアアアッ!やめてよ!」悲鳴と共に半身のまま下から押された有希子は体の捻りそのままに前向きに飛び込む様に床にダイブしてしまった。ザウッ、ガッ!「いったああああ・・・な、なんなのよ・・・」有希子の呻き声が漏れる。
興奮の余り目の前が真っ暗になった慎治たち二人は闇雲に個室から飛び出るとガッシャアーン!とパネルを勢いよく突き倒し、勢い余って自らも転びながらトイレの中央に転がり出る。「キャッ、な、なによ!」「何なの、どうしたって言うのよ!」トイレに居たクラスメート数人の悲鳴が上がる。その中を四つん這いになり、たたらを踏みながら立ち上がった慎治たちが奇声を発しつつ駆け抜けようとする。
「アギャラアアアアアッッッ!!!」「イギイイイイイイッッッ!!!」だが運の悪いことにトイレには丁度、富美代と朝子が来ていた。二人とも流石に驚いたものの慎治たちの逆切れはしょっちゅう見ている二人だ、リカバリーは速い。一瞬にして冷静さを取り戻し慎治たちに襲い掛かった。
「アアアアアッッッ!」「ハッ!」絶叫しながら駆け出そうとする信次の足元を朝子のローキックが掃腿の要領で払う。「ハイッ!」「グハアッ!」富美代も慎治を避けるどころか逆に反射的に、機先を制するかのように一歩踏み込み駆け出そうとする慎治が未だスピードに乗れないでふらついているところを、素早く右腕を掴んで極める。「ハヤッ!」極められた右手首を中心に慎治の体が宙を舞い、コンクリートの床に叩き付けられる。「ゲッバアッ!」そして富美代も朝子も素早く慎治たちの腕を極めながら頭を踏みつけて動きを封じる。「ほら慎治、何やってるのよ!」「信次、一体どういうつもりよ!何の真似なのよこれは!」富美代と朝子の一喝が慎治たちの精神の昂ぶりを鞭のように打ち据え、一瞬にして萎えさせる。
その時、倒れたパネルの向こうから呻き声が聞こえてきた。「イタタタタ、ひ、酷いわ・・・」「な、なによ、何で私が突き飛ばされるの・・・」陽子と有希子の声だった。声の方を振り向いた富美代たちの顔が怒りに彩られる。「・・・慎治、あんた一体どういうつもりなのよ!?」グイッとさらに一捻り腕を捩じ上げつつ、朝子が横にいた真弓に声をかけた。「ったく信次、あんた分かってるの?こんなことしてどうなるか・・・真弓、玲子たち呼んできて!」「OK!」朝子に頼まれた真弓は教室に書け戻り、玲子たちに急を告げた。
「玲子!大変よ信次が、信次がね、有希子をトイレで突き飛ばして転ばせちゃったのよ!慎治も陽子のことを転ばせてたわよ!兎に角速く来て!二人とも怪我しちゃってるみたいよ!」「な、何だって!?マジそれ?真弓、ホントなの!?」「本当よ!いいから二人とも速く来てよ!」ガタッと椅子が引っ繰り返るほど勢いよく、礼子が立ち上がった。「で真弓、慎治たちは?連中はどうしたの?」「丁度トイレには朝子とフミちゃんがいたわ。だからあの二人が慎治たちのこと、取り押さえてるわよ。」「礼子、行こう!」一声かけると玲子は全力で走り出した。そしてトイレに着くと思わぬ光景に息を呑んでしまった。
富美代と朝子に取り押さえられ、トイレの床に押さえつけられている信次たちには目もくれずに玲子は有希子たちに走りよった。「有希子!陽子!大丈夫?一体・・・一体どうしたの、何があったのよ!?」「・・・知らないわよ、こっちが聞きたい位よ!私がおしっこ飲ませてたら、突然信次が暴れだして私のこと突き飛ばしたのよ・・・アツツ、ああ痛いな、もう・・・」「ちょ、ちょっと見せて・・・ああ有希子、血が出てるよ・・・」玲子が言うまでもなく、床に転がされた有希子は二の腕を擦り剥いて血を滲ませていた。「礼子、陽子はどう?」玲子は陽子の方を振り向いて礼子に声をかけた。「頭は軽く打っただけみたいだけど・・・転んだときに膝を切っちゃったみたいね、血が出てるわ。兎に角二人とも、早く保健室に連れてかなくちゃ。転んだ場所が場所だし、化膿したら面倒よ。」礼子の声に頷いた富美代と朝子が反対側から陽子と有希子を助け起こす。「いいわよ礼子、保健室には私たちが一緒に行くから・・・それより礼子たちはここをお願い。大丈夫、陽子?歩ける?」「ありがとう・・・大丈夫、骨がどうにかなった訳じゃないから、歩けるわよ・・・でも」富美代の手を借りて軽く足を引きずりながら歩き出した陽子は涙を溢しながら礼子を振り向いた。
「・・・ねえ礼子、なんで、なんでなの?なんで私がこんな目にあわなくちゃいけないの?トイレの床に突き飛ばされて、転ばされるなんて・・・トイレ、トイレにだよ?わたし・・・悔しい、なんで私が慎治に、慎治なんかに怪我させられなくちゃいけないのよ・・・しかもトイレで・・・あんまりよ、あんまりだわ!」有希子も余りのことに涙を流していた。「そうよ・・・そうよ・・・玲子、ひどい、ひどすぎるわよ!こんなのないわよ・・・私・・・私、トイレに、トイレの床に・・・顔打ち付けられたのよ・・・なんで、なんで私がこんな目に会わなくちゃいけないの?私が何したって言うのよ?あんまりよ!絶対・・・絶対許せない!」
陽子たちが保健室に連れて行かれた後、トイレを一瞬の静寂が支配していた。やがてその静寂を破るように低い声が響いた。「・・・慎治・・・慎治・・・」顔をやや伏せたまま、礼子が呪文のように慎治の名前を唱えていた。「・・・慎治・・・あんたよくも・・・やってくれたわね・・・・・」ゆっくりと顔を上げた礼子と視線が合った時、慎治は思わず恐怖の余り全身が凍りついてしまった。礼子の整った顔立ちは紅潮し、大粒のダイヤのように光り輝く美しい瞳は激しい怒りの炎に燃え上がっていた。信次が初めて見る表情、それは礼子の本気の怒りの表情だった。礼子は本気で怒っていた。あれだけの大罪を犯した慎治たちをこの程度の、ほんのおしるしだけの罰で許してやろうっていうんだからね。ほんと私も甘やかし過ぎよね、慎治、感謝しなさいよ。礼子は慎治たちが自分に感謝していると信じて疑っていなかった。それを・・・よくも裏切ったわね。私がこれだけ優しくしてあげたのに、慎治はそれを裏切りで返すのね。陽子に、私の友達に、女の子に怪我させるなんて・・・許さない・・・・・
日頃慎治を苛める時、礼子は楽しそうな輝くばかりの笑顔を浮べ、決して怒りの表情を見せたことはない。どんなに理不尽に責め苛みながらも常に楽しそうな遊びの表情であり、怒ったことなど殆どない。慎治にとって礼子の本気の怒りの表情は久し振り、初めて唾を吐き掛けられた時以来の、本当に久し振りに見るものだった。なまじ整った文句の付けようのない美貌だから余計に恐ろしい。柳眉を逆立てるといった言い方が最も相応しい、見るものの血を凍らせる夜叉、悪鬼羅刹の類いの表情だった。「・・・慎治、許さないよ・・・」
礼子はゆっくりと慎治に近づいていく。ヒッ・・・慎治は後ずさりしようとするが礼子の本気の余りに激しい怒りに半ば腰が抜けてしまい、満足に動くことすらできない。「・・・慎治・・・」その美しい瞳をカーミラの邪眼の様に燃え上がらせながら礼子はゆっくりと慎治の胸倉を鷲掴みにする。ヒッ・・・慎治は悲鳴をあげたつもりだが、実際には恐怖の余りかすれ声すら発していない。「許さないよ・・・」アアアアアアッ!慎治の悲鳴と共に激痛が襲い掛かった。「ハッ!」烈昂の気合と共に礼子の右当身が信次の鳩尾に食い込む。「ゲバアッ・・・ビギャアッ!」悲鳴を上げる隙すらなく、腰をくの字にかがめようとする慎治の顎を礼子の肘打ちが叩き起こす。そして間髪を入れず、礼子の全開の右前蹴りが慎治の胸に炸裂する。「グハアッ!」蹴り飛ばされてトイレの壁に叩き付けられた慎治にずいずいと礼子は近づいていく。
「ヒッ!ヒイッ!!」「この手・・・邪魔よ!」礼子は一瞬の躊躇もなく、反射的に頭部を庇った慎治の右腕を強引に捩じ上げる。お、折られる!そう慎治が思うのより早く、礼子は捩じ上げ脱臼させるなんてもどかしい、とばかりに完全に極めた慎治の肩に凄まじい手刀を叩き込んだ。バギッ・・・・・「ギヒイイイイイッ!」半ばへし折り、打ち砕くかのように肩を一瞬にして脱臼させられた慎治の悲鳴に委細構わず、礼子は慎治の左腕も捩じ上げ同様に破壊する。「ギ、ギアアアアアッ、ヘアッ・・・」両肩を破壊された激痛に絶叫する慎治の喉下に礼子の純白の上履きが食い込む。右上段前蹴りで慎治をトイレの壁に昆虫採集のように釘付けにしながら、礼子は怒りに震えた声で言い放った。「慎治・・・よくも陽子を・・・よくも私を裏切ったわね・・・許さないわよ・・殺・・・す・・・」恐ろしいほどの殺気がこもった声を発しながら礼子は慎治を捕らえた右足にグッと力をこめると、一旦その足を引き戻した。
礼子の右足が引かれたその瞬間、玲子の声が響いた。「待って礼子、それまでよ!」怒りに顔を紅潮させながら礼子が振り向いた。「何よ玲子、邪魔する気!?ほっといてよ!慎治を庇いだてする気なら、聞く耳持たないわよ!誰が何と言おうと私、慎治のことは・・・殺す!」「礼子、少しは落ち着いてよ!私が慎治たちの事を庇いだてするわけないでしょ!私だって有希子の仇を討ちたいわよ!だけど今はタイムアップよ。もう昼休みはおしまい、今からじゃ慎治たちの事殺す、て言ったって大したことする時間はないわ。蹴り倒して骨何本かへし折ってそれでお終い?そしたら病院送りで万事終了?礼子、あんたそんな温いんでいいの?こいつらに・・・こんな大それた事をしでかした慎治たちを簡単に、一思いに殺しちゃってそんなんでいいの?私はいやよ!礼子、こいつらの罪は・・・後でたっぷりと時間をかけて、たっぷりと痛めつけてやらなくちゃ許せないわよ!礼子、礼子はどうなのよ!?慎治たちを・・・この最低の連中をそんな簡単に罰してそれでOK、て済ましちゃう気なの?」
フウッ、フウーーーッ・・・ウウウーーーーー・・・全身を怒りに総毛立たせた猛獣のように小刻みに全身を震わせながら、慎治を壁に縫いつけた姿勢のままで礼子は暫く玲子のことを睨みつけていた。やがて大きく一回、深呼吸をすると口を開いた。「・・・そうね・・・玲子の言うのも一理あるわね・・・いいわ慎治、この場はここまでよ。慎治の命、ひとまず預けておくわ。だけど」すっと長く伸びた足を下ろしながら礼子は宣告する。「慎治、あんたのことは絶対許さないからね。後で・・・リンチよ!」
ドスッ!グエエッ・・・礼子は慎治を絶望に突き落とす言葉を吐き捨てると信次の鳩尾に掌底をめり込ませ、うずくまる慎治をその場に残してクルリと踵を返し、トイレから足音高く出ていってしまった。
礼子たち二人の殺気立ったやりとりにトイレの中はシーンと静まり返っていた。フウッ、残された玲子は小さく溜息をつくと慎治に近づいてきた。「・・・たく礼子ったら、やりっぱなしで行っちゃうんだから・・・」ブチブチとぼやきつつ玲子は慎治の右腕を掴んだ。「ヒッ!な、何するの!!!」「・・・ったくうざいわね、肩を入れてあげるだけよ、ほら静かにしなさい、動くとよけい痛いよ!」グッ・・・ゴギッ、ヒイイイッ!肩を外された時と変わらないほどの苦痛が慎治を襲った。その悲鳴に委細構わず玲子は慎治の左腕も嵌める。ゴリッ、ギャアアアッ!「ほら慎治、嵌ったわよ、肩動かしてごらん?」痛みが少し治まったところで玲子が声をかけた。その声に促され、慎治は恐る恐る肩を動かしてみる。動く・・・もう痛みも大分引いている。ああよかった・・・僕の腕、大丈夫みたいだ・・・「どうやら動くみたいね。」立ったまま見下ろす玲子を、慎治はトイレの床から見上げる。「あ、は、はい・・・動く、動きます・・・あ、あ・・・」「何?何か用?」「あ、はい・・・あ、あの・・・あり、がとう・・・」
「ハアアッ?ありがとう?慎治、あんた本物のバカア!?私が怒ってないとでも、慎治が肩外されて可哀想だから手当てしてやった、とでも思ってるの?」玲子は呆れて物も言えない、というように大きく首を振った。「慎治、言ったでしょ?礼子に負けず劣らず、私だって今、滅茶苦茶怒ってるのよ。今応急手当してあげたのは後で慎治をゆっくりと嬲り殺しにしてやるため、それだけ、そのためだけなのよ?それをまあ、ありがとう、だなんて・・・慎治、あんた本当にバカなのね!・・・まあいいわ。慎治がバカだろうと何だろうともうどうでもいいわ。一つだけ、幾らおバカな慎治でも分かるようにハッキリと言っておいてあげる。信次もしっかり聞いときなさい!慎治、あんたたち二人とも・・・放課後、リンチよ!」
3
リ、リンチ・・・リンチ・・・一体何を、何をされるんだろう・・・5時間目、恐怖にガタガタ震えていた慎治はふと、教室を一枚の紙片が回覧されていることを、それを読んだ女の子たちがクスクス笑いながら自分と信次の方を見ていることに気づいた。な、なんだ、なんなんだ・・・信次も同じことに気づいていた。そして5時間目終了後の休み時間、その紙片はたまたま信次の隣席である里美に回ってきていた。クスクス笑いながら顔をあげた里美の視線が信次とあう。「フフフどうしたの信次、なんか心配そうな顔しちゃって。ああそうか、これになんて書いてあるか知りたいのね。いいわよ、そんなに知りたいなら見せてあげる、ほら。」その紙片を見た信次の顔から見る見る血の気が引いていく。紙片にはこう書かれていた。
シンジをリンチにかける会 緊急開催のご案内
本日の昼休み、矢作慎治および川内信次の両名が女子トイレにて暴力を奮い、女子生徒に怪我を負わせる、という大事件を起こしました。
両名に対しては時間をかけゆっくり、じっくり、たっぷりと厳刑を加える方針ですが、取り急ぎ本日放課後、両名を第一陣のリンチにかけたいと思います。
皆様万障お繰り合わせの上、一人でも多くのご出席をお願いします。
シンジをリンチにかける会
代表 天城 礼子 霧島 玲子
幹事 神埼 富美代 萩 朝子
シンジをリンチにかける会!ほ、本当なんだ、本当に僕たち、リンチに掛けられるんだ・・・それも放課後、もうあと僅か一時間後に・・・あまりの恐怖に二人が呆然としている間に、あっという間に6時間目の授業は終わり放課後になってしまった。
ホームルームもそこそこに礼子が宣告する。「今日の連絡事項は以上です。何か他にありますか?無いようでしたら先ほどご連絡したとおり、これより矢作慎治、川内信次の両名をリンチに掛けたいと思います。皆さん第三体育館に移動してください。」
第三体育館、それは予備の講堂、ミニホールとして使用できるように小規模ではあるが舞台をしつらえ、防音設備を施した体育館だった。礼子さんたち、5時間目の休み時間にいない、と思ったらここを取りに行ってたんだ。
「ヒッヒイイイイッ・・・」「り、リンチだなんて、そんな・・・」半べそをかきながら腰が抜けてしまった二人をクラスメートが取り囲む。「さあ信次、行こうか!」信次の両側からは朝子と真弓が、慎治には富美代と和枝が無理やり引きずり起こすように立たせると、信次たちを取り囲むように殆どのクラスメートが一緒になって第三体育館に連行する。
「あ、あああ・・・」まるで死刑場に引き立てられる受刑者のように、信次たちは泣きながらフラフラと引き立てられていく。「信次、陽子たちをよくも怪我させたわね!」「もう、絶対許さないからね!」「フフフ、この人数で苛められるんだよ、どう、楽しみ?」「あ、私今日、何か弾けちゃいそう!」「全くよね!礼子たちのことだから、きっと凄いリンチ考えてるわよ?ウフフ、ねえ慎治、今日生きておうちに帰れるかしら?」
歩きながら女の子たちは口々に慎治たちを罵り、小突き回す。どの顔も妙に楽しそうな、ある種の祭りの高揚感に似たハイな笑顔になっていた。お、同じだ・・・慎治たちの嫌な記憶、白馬で、奥多摩で体育館に引き立てられ、たっぷりと責め苛まれた記憶が甦る。慎治たちを刑場に引き立てながら礼子たちが浮かべていた心底楽しそうな笑顔、それをクラスメート全員が浮かべていた。
「あ、あああ・・・おねがい、たすけて・・・」誰に言うともなく力なく慎治は呟いた。だが都合よく助けが現れるのは安っぽいハリウッドムービーだけだ、現実世界で助けなど現れるはずがない。あっという間に慎治たちは体育館に到着した。
ガラガラ、と和枝が体育館のドアを開けると中には既に玲子たちが一足先に来ていた。「あ、来たわね。朝子、中に入ったらしっかり鍵かけてね。ほかのドアはみんなロックしたから、後はそこだけ閉めればもう邪魔は入らないわ。」邪魔は入らない・・・その言葉がなにを意味するか、考える必要などない。朝子が入り口をしっかり閉めると、慎治たちは体育館の真ん中に引き立てられ正座させられた。
「さあ慎治、どうなるか分かってるわよね。お昼休みは時間切れ、て言うことで終わっちゃったけど、今度はそうは行かないわよ?覚悟はいいわね?」慎治を土下座させ、後頭部をグリグリと踏み躙りながら礼子がリンチ開始を宣告する。「そうよ慎治、私たちがあれだけ優しくしてあげたのに、慎治たちの大罪をあんな軽い罰で許してあげたのに、よくもまああれだけ堂々と恩を仇で返してくれたものね?勿論、只で済むとは思ってないわよね?」「あ、ああ、あああああ・・・お、お願い、許して・・・」ガッ!ヒッ!慎治の哀願に苛立ったかのように礼子は足を上げたかと思うと慎治の頭を蹴り付けるかのように踏み躙った。「許して?ふざけるんじゃないわよ!あんな軽い罰で許してやった私たちを裏切っておいていまさら許してですって?そんなのが通用するとでも思ってるの!?」
「礼子、ストップストップ、冷静に!こいつらにとって今、一番の救いは礼子や私が切れて一気に気絶させてくれることでしょ?落ち着いて、ゆっくり一回深呼吸して!・・・どう、少しは落ち着いた?」妙に静かな玲子の声に我を取り戻した礼子は言われるままにゆっくりと深呼吸をし、玲子にニッコリと微笑みかけた。「フウウ・・・そうよね、こいつらのその手に危うく乗せられるところだったわ。折角5時間目、6時間目とリンチのプランをじっくり練ってたんだもんね。一気に潰しちゃ勿体無さ過ぎるわ。慎治、時間はたっぷりあるわ。じっくりと苛めてあげるからね。」礼子の声も冷静さを取り戻した。礼子の冷静な声は先ほどの怒声の数倍も恐ろしい、慎治たちの背筋をゾクリと震え上がらせる、破滅へと誘うセイレーンの歌声のような魔力があった。
「そう、折角プランを練って場所取って、みんなも忙しい時間を割いてリンチに駆けつけてくれたんだからね。たっぷりと泣き叫ばせてやらなくちゃ元が取れないわ・・・さあ、そろそろリンチ、開始しましょうか。信次、二人とも覚悟するのね。ゆっくりと苛めてやるからね!」
あ、あああ・・・・・恐怖に半ば腰が抜けている二人を裸にさせ並ばせて正座させると、玲子はクイッと二人の顎を上げ、自分を仰ぎ見させた。「二人とも、この姿勢絶対に崩しちゃ駄目よ。崩したらもっと酷いリンチに会わせるからね!」刑の開始を宣告すると、玲子は信次たちの目の前でカチャカチャとわざと音を立てながらベルトのバックルを外し、シュルッと細いウエストから引き抜いた。ヒッヒイイイイイッ・・・玲子の手の中でベルトが、服飾品が一本の鞭に変化する。「分かるわね、どういう目に会うか。でも安心しなさい、まずは二人とも、一発ずつだけよ。一発ずつしか鞭打たないわ、どう、安心した?」これまで散々苛め抜かれてきた信次たちが安心などするわけがない、だが一発だけ、という玲子の思いがけない言葉に信次は思わず反射的に微かにほっとしたような顔色を浮かべた。
「このブタ!鞭が一発だけ、て聞いただけでほっとするなんてね。この最低男!」ペッ!玲子は自分を見上げる信次の顔に思いっきり唾を吐き掛けた。「慎治、慎治も今、ほっとしていたでしょ?バーカ!」ペッ!玲子は返す刀で慎治にも唾を吐き掛ける。「さあ、行くよ!」手にしたベルトを翻らせると玲子は袈裟切りに振り下ろすように信次を一撃し、そのままバックハンドで慎治も打ち据える。
「ヒッ!」「アウッ!」信次たちの悲鳴が上がるのを冷たく見下ろすと玲子はゆっくりと二人の前から離れた。間を置かずに今度は礼子が二人の前に立つ。「どう二人とも、何をされるのか分かったかしら?簡単なセレモニーよ、本格的なリンチの前のほんのご挨拶、ていうところ。これからたっぷりとリンチしてあげるからね、まずは手付よ!」ゆっくりとベルトをウエストから引き抜くと、礼子も二人に唾を吐き掛け、一撃ずつ鞭打つと二人の前を離れていく。続いて朝子が、そして富美代が同じように二人の前でベルトを引き抜き、唾を、鞭を一撃ずつ加えていく。
な、なんだ、なんなんだ・・・富美代の次に和枝が目の前に立った時、漸く慎治は礼子たちの企みを理解した。
「フフフ慎治、分かったみたいね。でも私だけじゃないのよ。フフ、フフフフフ、ペッ!」和枝は笑いながら二人に唾を吐き掛けるとベルトを大きく振りかぶった。「礼子たちほど上手じゃないけどね、私のファースト鞭、逝くよ!」ピシッ!パシッ!慎治たちの肩のあたりを鞭打つと和枝は笑いながら場所を譲る。そして次に真弓が二人の前でベルトを引き抜いた。「そうよ信次、いい顔色に怯えてきたじゃない、ご名答。次は誰が信次たちのことを鞭打つのかしら?みんなよみんな、全員で鞭打ってあげるわ!どう、楽しいでしょ、アハハ、アハハハハッ!」笑いながら真弓も唾を吐き掛け、一発ずつ鞭を振るうと場を空ける。
クラスメート全員が一人一人、慎治たちの目の前でベルトを引き抜き、唾を吐き掛けて一鞭ずつ打ち据えていく。慎治たちの当惑は直ぐに屈辱と恐怖に変わっていった。フフフ、慎治、怯えてるわね。精々怖がりなさい。今日のリンチだけじゃないわよ、これから先、明日以降の自分たちがどうなるか、たっぷりと怯えるがいいわ。礼子たちの狙いどおり、このセレモニーは慎治たちの精神を強烈に蝕んでいた。流石にいくら苛めを蔓延させる、と言ってもクラスメート全員が鞭を購入し慎治たちを苛める、等ということはまず有り得ない。だがベルトなら話は別だ。別に責め具としてではなく制服の一部として全員が毎日身につけている、そのベルトで鞭打たれる。痛さだけの問題ではない。むしろ痛さだけで言えばたかがベルト、本物の一本鞭で数え切れないほど鞭打たれている慎治たちにとっては痛いとはいえ、十分に耐えられるレベルだ。だがベルトで鞭打たれるのは本物の鞭以上の屈辱感を二人に刻み込んでいた。
慎治たちの目の前で一人、また一人とベルトをウエストから引き抜く。その瞬間、ベルトが意思を持たない制服の一部から残酷な責め具へと変化していく。そして同時にクラスメートが、今まで苛められたとは言えクラスメートであった女の子が礼子たちと同じ、残酷な拷問官へと変化していく。順番を待つ他のクラスメートも全員がウエストに鞭を、慎治たちを打ち据え泣き喚かせる責め具を締めている。隠すこともなく、誰に咎められることもなく。
それは慎治たち以外の誰にとっても単なるベルト、単なる制服の一部に過ぎない。慎治たち以外の男子生徒は誰も、女の子たちが締めているベルトを全く意識にも止めずに見ているだろう。だが慎治たちにとっては全てのクラスメートが常に鞭を携えているのと同じ、もし慎治たちが何か少しでも気に入らないことをすれば、いつでも鞭打てる、いつでも跪かせ、苦痛と屈辱にのた打ち回らせることができるのよ、と言う事を一人、また一人と宣言していくようだった。明日も明後日も女の子たちはみんな、制服を着てベルトを締めてくるだろう。そしてその女の子たちの誰に対しても二度と、対等な立場にはなり得ない。例え相手が普通に話しかけてきても、慎治たちにとっては剥き出しの鞭を構えられているのと同じなのだから、常に怯え、卑屈に追従と愛想笑いを浮かべ、必死でご機嫌取りをするしかない。玲子たちだけではなく、クラスメート全員との間に鞭を持つ支配者と打ち据えられる隷属者の関係が自然に、だが確固として確立されていくのを誰よりも、慎治たち自身が最も深く明確に逃れようもなく認識していた。
玲子は信次たちの怯えと屈辱をゆっくりと楽しんでいた。そうよ、その顔よ。フフフ、信次、あなた私と話す時、私が何もしなくても私のベルトをチラチラと見ているわよね。殆ど無意識にだろうけど、私の手がベルトに伸びやしないかっていつも怯えているのよ。勿論慎治も同じ、礼子やフミちゃんの前ではいつも、ベルトで打たれやしないか、唾を吐き掛けられるんじゃないか、ていつも怯えているわ。信次、私信次のその怯えた顔、大好き。だからしょっちゅうベルトで鞭打ったり唾を吐き掛けてあげてトラウマをたっぷりと植付けてきてあげたのよ。フフフ、その刷り込みがこんなに効いてくるとはね。信次、あなた私たち女の子の制服姿にもう一生、消し去りようのないトラウマを植え付けられているのよ。いい気味ね。
玲子たちが見守る中、次々とクラスメートは信次たちの前を通り過ぎていく。そして残るは二人、陽子と有希子だけになっていた。「信次、なによその顔!もうみんなの唾でベトベトじゃない!あらあら顔中から糸引いて唾垂らしちゃって・・・いい気味。少しは思い知った?」涙とクラスメートの唾に霞んだ目で見上げると、勝ち誇ったように笑いながら陽子が見下ろしていた。「どう、なんか言うことないの?」「あ、あああ・・・ご、ごめんなさい・・・ごめんなさい・・・だから、お願い、許して・・・」唾をボタボタと顔から床に垂らしながら、半ば反射的に土下座する信次の顎を陽子は白い上履きの爪先でクイッと小突きあげた。「許して?何馬鹿言ってるのよ、ダメに決まってるでしょ!?覚悟しなさいよ、私もこのリンチ、燃えてるんだからね。トイレの床に突き転ばされた恨み、きっちりと晴らさせてもらうわよ!?」陽子はクチュクチュと口中一杯に唾を溜めると、信次たちに思いっきり吐き掛け、そしてベルトを引き抜くと力任せに肩の辺りを打ち据えた。「ヒイッ・・・」「じゃあまた・・・あとでね!」
そして取りは有希子だった。信次の前に立った有希子は冷笑を浮かべながら慎治を見下ろしていた。不思議ね、いつもは信次が苛められるのを見てると、少しは可哀想、ていう気になるのに今日はそんな気、全く起きないわね。ま、当然か、トイレで転ばされて怪我させられて、それでも許してやろうなんて考える子、いるわけないよね!みんなに倣い、有希子もゆっくりとベルトを引き抜いた。「信次・・・私で二十人目、最後ね。じゃあ最後に一つお願いして貰おうかしら。どうか僕の汚い顔に唾を吐き掛けてください、そしてどうかみんなで腐りきった人間のクズである僕を鞭打って罰してください、てね。」「あ、あうううう、そ、そんな、そんなこと・・・」唾まみれの顔に新たな涙を流しながら咽ぶ信次に有希子は冷たく言い放った。「そう、言いたくないのね、私の言うことは聞けない、て言うのね?」グッとベルトを握る右手に力を込める有希子の仕草に信次は震え上がって叫んだ。「い、い、いえ、そ、そんな!逆らうだなんてそしな!お、おねがい、おねがいですうううううっ!ど、どうか、どうか唾を、唾を吐き掛けて下さいいい、そしてどうか、どうかぼ、僕を鞭打って罰してくださいいい、お、お願い、おねがいですううううう!!!」信次の必死の哀願を有希子は鼻でせせら笑った。馬鹿ね信次、哀願しようが何しようが結果は同じ、みんなに死ぬほど鞭打たれるのは変わらないんだからね。でもまあいいわ。ご希望には応えてあげるわよ。「そう、そんなに私の唾が欲しいの?そんなに唾が欲しいなら、望み通り吐き掛けてやるわよ!この・・・ゴキブリ!ブタ!ぺっ!」思いっきり唾を吐き掛けると手にしたベルトを大きく振りかぶり、真っ直ぐに振り下ろした。ピシッ!ヒイッ!「まずはご挨拶。あとでたっぷりとまた鞭打ってあげるからね。」
4
漸く全員が慎治たちに唾を吐き掛け、ベルトで打ち据え終わった。だがこれで終わったのではない。今日の責めは、リンチはこれからが本番なのだ。精神をグチャグチャに破壊され、屈辱に全身を責め苛まれた今から漸く、肉体の苦痛が始まる。絶望と恐怖におびえた目で信次は視線を彷徨わせた。前後左右、どこを見てもクラスメートの女の子がいる。みんな手にはベルトを、今さっき自分を打ち据えたベルトを握り締めて今や遅しとリンチの開始を待っている。ああ、あああああ・・・な、なにをされるんだろう・・・みんなに打ち据えられるんだよな・・・でもどうやって?慎治の脳裏に潰れた大学のグラウンドで玲子たち四人掛りで鞭打たれた苦い記憶が蘇る。だけど・・・だけどいくらなんでも、全員同時に鞭なんてさすがに無理だよな・・・精々二、三人同時が限界だよな、だったらなんとか大丈夫かな・・・でも、でも・・・!慎治は大きく息を吐いた。礼子さんたちがそんなに甘いわけないよ。きっと、きっと何か凄い、酷いリンチを考えているに決まってるんだ!でも、でもいったいどうやって・・・慎治たちの頭の中で恐怖が無限に増殖していく。その時、パシーン!と玲子が手にしたベルトを鳴らした。
「ハーイみんな!信次たちに挨拶は済んだわね?じゃあいよいよ・・・リンチ開始と逝くわよ!」「待ってましたあっ!」「うん、やろうやろう!今の一発ずつなんて全然物足りないよ!」「ほんとほんと!もっと思いっ切り引っ叩きたーいっ!」一斉に上がる歓声に苦笑しながら、礼子がパンパンッと手を叩いた。「ハイハイ、みんな安心してね、心配しなくても・・・思う存分引っ叩かせてあげるわよ!じゃあみんな、さっきメモに書いといたように整列してね!」礼子の声を合図にまず玲子、富美代、朝子が歩き出した。玲子は信次を四つん這いのまま連れて行き、慎治だけが取り残される。そして四人で体育館の横幅一杯を使い、対角線10メートルの、やや横長のダイアモンドを形作った。すると他の女の子たちも一斉に動き始め、玲子たち四人の間に互い違いで2-3メートル程度の間隔をおいて並び始めた。向かい合う女の子通しの幅は1-2メートルある。完成したそのフォームはやや横長の楕円、互い違いに二重の輪に並んだ女の子通しの間にチューブのように通路がある楕円形だった。
全員が位置に付き、間隔を調整し終えたのを確認すると玲子は信次の顎に二つ折りにしたベルトを引っ掛けて持ち上げた。「信次、もう自分がどうリンチされるのか、大体は分かったでしょ?そう、信次には私たちの輪の中をゆっくりと四つん這いで行進して貰うわよ。そして歩きながらみんなの鞭を受けるのよ!」「ヒッヒイイイイッ!そ、そんな、みんなに、みんなに鞭打たれるだなんて!!!」
反対側では慎治も礼子から刑を宣告されていた。「慎治、玲子の説明は聞こえたわね?二人ともスタートしたら時計回りに行進するのよ。ああそれとね、止まりたければ勝手に止まりなさい。どこで潰れようと慎治の勝手よ。但し、私たちの許しも無しに止まったりしたら、そこの地点でみんなから集中攻撃されることになるからそのつもりでね。」「しゅ、集中・・・攻撃だなんてそんな・・・」「フフフ、痛そうでしょ?集中攻撃だなんて真っ平よね?だったら精々しっかり行進することね。」礼子は笑いながらパシンッとベルトを打ち鳴らした。「玲子、そっちはOK?みんな、用意はいいかな?しっかりベルトは構えましたかあ?」「ハーイ、いつでもOKよ!」「早く早く!早く慎治のこと、引っ叩きたーい!」パシンッ、パーンッ!そこかしこでベルトを打ち鳴らす音が体育館に響く。「や、やだ、やめて・・・」「ひっひどい、そんな・・・」慎治たちのか細い哀願には一瞥もくれずに礼子はベルトを高く振り上げた。「さあ慎治、逝くわよ・・・リンチ・・・開始よ!」
ビュオッという音と共に礼子のベルトが振り下ろされた。バシーンッ!ヒイッ!礼子は慎治の背中に立て続けにベルトを振り下ろす。ビシッ!パシッ!「ヒッヒイッ!い、痛いいい!」あ、あああ、に、逃げなくちゃ、兎に角逃げなくちゃ、礼子さんのベルトの届かないところに・・・
信次も玲子のベルトに追い立てられ、必死で這い始めた。い、痛い!痛い!痛い!い、いやだ、いやだあああ!必死で信次が這いずるにつれ、最初は肩の辺りに炸裂していたベルトが徐々に背中の中心に移り、次いで尻にと移動していく。ハアハア、もう少し、もう少しで逃げられる・・・痛いっ!名残を惜しむかのように横にスイングされたベルトが信次の太腿の裏を打ち据える。思わず反射的に右手でそこを抑えてしまい、バランスを崩しながらも何とか必死で前に進んだ。ハアハアハア、こ、これで玲子さんの鞭からは何とか逃げ、パシッ!ヒイッ!逃げおおせたと思った瞬間、再び肩にベルトが食い込んだ。反射的に顔を上げた信次が見たものは、信次を打ち据えたベルトを再び振り上げ、今まさに二撃目を振り下ろそうとしている有希子の姿だった。
「来たわね信次!私をトイレで突き飛ばした罪・・・今こそ思い知らせてあげる!」バシッ、ビシッ、パンッ・・・力任せに有希子が振り回すベルトが信次の背中に次々と炸裂する。鞭は初めての有希子だが長さもそんなにないベルトは振り回しやすく、力任せに振り回すだけで十分に鞭として機能する。「い、いたっいたいたいたいいいいっ!や、やめてお願い許してえええ!!」信次は必死で有希子のベルトの制空圏を通り過ぎたが、息つく間もなく三人目のベルトが肩に降り注ぐ。「いいだ、いだいよおおおっ、やめて、もう・・・ひいいいいっ、ごめんなさいごめんなさいいいいっ!!!」慎治も間断なく鞭打たれながら必死で這い続けていた。礼子さん、陽子さん・・・三人、四人と鞭打たれながらも這い続けた慎治の悲鳴が急に甲高くなった。
「ヒッ、ヒギャァッ!」バッシーンッ!背中を襲うベルトの音が急に凶悪さを増し、背中に一段と酷い激痛を刻み込んだ。「い、いたあああああ・・・」仰け反るように仰ぎ見た慎治が見たものは、笑いながら高々とベルトを振りかざす富美代の姿だった。
「アハハハハッ!どう慎治、私のベルトの味は!みんなのベルトよりちょっとは効いてるかしら?それ!」ビシーーーンッ!富美代が思いっきり振り下ろしたベルトが慎治の背中に深々と食い込んだ。「ヒギイイイッ!」「アギャアアアアアッ!」殆ど同じタイミングで信次も金切り声を上げていた。「ア、アウッ、や、やべ、ギャヒイイイイッ!」信次に悲鳴を上げさせていたのは朝子のベルトだった。「キャハハハハッ!信次、痛い?みんなの時よりいい悲鳴じゃない!そんなに私の鞭痛いの?プロの腕ってやつかしら?じゃあたっぷりと手練の技を見せてあげるね!」
富美代も朝子もいつもの一本鞭ではなくベルト、しかもそんなに数多くは鞭打てない、とあって遠慮会釈なく全力を解放して二人を打ち据えた。半歩下げた右足の蹴りを効かせながら十二分に腰を入れ、体重をしっかりとベルトに乗せながら打ち下ろす。しかも肩、肘、と順に回転させ最大限しなりを効かせてスピードを得たベルトが慎治たちの肉体に当たる最後の瞬間、ピッと鋭く手首を返して威力を倍増させる。何百発何千発と鞭を振るって体得した、受刑者により多くの苦痛を与えるテクニックを富美代も朝子も情け容赦なく振るっていた。やっとの思いで二人の前を慎治たちは通り過ぎた。
だが決して休みなど与えられない。富美代、朝子のベルトよりは多少痛くない、とはいえ他のクラスメートのベルトも十二分に痛い。そして・・・更に五人進むと礼子たちが待ち構えていた。「信次、よく来たわね、中間ポイントよ、ちゃんとハンコを押してあげるわね、ソレッ!」「慎治、私でちょうど半分よ、良かったわね、おめでとう!」ビシーッッッ、バシーッッッ・・・「グギイイイイッ!!!」「イヤアアアアアッッッ!」
富美代や朝子のベルトをも上回る激痛に二人とも思わず背中を仰け反らせ、その場に止まってしまった。反射的な行動とは言え、最悪の選択だった。「あら信次、そんなに私の鞭が欲しいの?いいわよ、遠慮はいらないわ、だって私と信次の仲だものね!」「ああそうなの慎治、やっぱりこの位痛くないと慎治には物足りないのね。いいわよ、お望みどおり引っ叩いてあげる!」バシッ、ビシッ、パウッ、パーンッ!!!ギャアアアッ!イ、イタイイイイイッ!ア、アベ、アベデエエエッ!ユルジデエエエエエッ!!!余りの激痛に涙と涎を垂れ流し、何を言っているのかすら分からない悲鳴をあげつつ慎治たちは何とかこの場を逃れようと必死で這いずった。漸く礼子たちの制空圏から脱した慎治たちだが、次のベルトを受けながら暗い閃きに思わず絶望してしまった。
礼子さんのところは過ぎたけど、こ、この先にはフミちゃん・・・あ、あと五人、あと五人先にはあ、朝子さんが、朝子さんが待っている・・・残酷な配置だった。礼子たちは熟練した鞭の使い手四人のポイントを散りばめることで、慎治たちにあと何人でまた激痛ポイント、と怯えさせ、精神的にも苦しめることを狙っていた。精神面だけではない。礼子たち四人が連続して並んでしまうと激痛のため慎治たちの痛覚がマヒしてしまい、痛みがフレッシュでなくなってしまうかもしれない。他のクラスメートの鞭が十分な苦痛を与えられなくなってしまうかも知れない。位置を分散したのはそれに対する配慮も兼ねていた。鞭打ち初体験のクラスメートを前後に挟むことで、自分たちの強烈な鞭をより新鮮な激痛として慎治たちに味合わせる事ができる。更に四人が散らばることで前後のクラスメートが礼子たちのフォームを真似しやすくなる、少なくとも礼子たちの鞭音につられ、遠慮なく思いっきり引っ叩けるようにすることも狙っていた。礼子たちの配慮は狙い通り、何重もの効果を上げて慎治たちの苦痛をいや増していた。
「アウッ、アウウウウッ・・・」「ヒッ、ヒック、ウエッウエエエエッ・・・」苦痛と恐怖と屈辱を際限なく味合わされながら、慎治たちは必死で這いずり続けた。そして漸くゴール地点、一周して礼子たちの下に辿り着くと二人とも、その場に突っ伏してしまった。200発近く打たれたであろうか、幅のあるベルトだから蚯蚓腫れになったり皮膚が切れたりはしていなかったが、二人の肩から尻にかけては真っ赤に腫れ上がり、所々は内出血のため青痣になっていた。
「フフフ慎治、いいザマね。少しは懲りたかしら?」「あ、あああ、ご、めんなさい・・・もう、許して、お、願い・・・」礼子に頭を踏み躙られながら、慎治は呻き声で哀願した。
「信次、少しは反省した?どうなの、少しは自分の罪深さを思い知ったかしら?」玲子も信次の頬を踏み躙りながら尋ねていた。「あ、あううう・・・は、はい・・・は、はんせい、反省しました・・・だから、どうか・・・許して・・・くだ、さい・・・」消え入りそうな声で呟く信次を玲子は満足そうに、だが冷ややかな目で見下ろしていた。「そう、信次みたいなカスでも流石にこれだけ鞭打たれれば少しは反省、らしきものを言えるのね。だけど」玲子は信次を踏み付ける足にグッと力を込めた。「まだまだ足りないわ。この程度で許してあげるわけにはいかないわ!」「えっえええええっ、そ、そんな!!!」礼子も慎治にリンチの続行を宣告していた。
「許す?ダメよ慎治、まだまだ足りない、慎治のことはもっともっと、いっぱい懲らしめてあげるわ。さあ、少しは休ませてあげたのよ、感謝しなさい!リンチ、再開よ!」礼子はパンッとベルトを打ち鳴らすと同時に足をどけた。「あ、あひいいいいっ!そ、そんな、そんなあああああっ!」「あら慎治、別に動きたくなければいいのよ、そのままそこに蹲ってなさい!そうやって・・・私の鞭をずっと受け続けなさい!」ビュオッ・・・ブオッ!礼子たちのベルトがリンチ再開を待ちかねたかのように唸り始めた。
「あ、ああ、あああああ・・・・・」「は、はひっはひっひっひっひっ・・・」二周目が終わった時、慎治たちはもはや気絶寸前だった。数え切れないほど打ち据えられた背中は赤を通り過ぎ青黒くなっていた。肉体以上に精神も崩壊寸前だった。動く気力もなく倒れ伏した二人をクラスメートが取り囲んだ。「どうみんな、鞭は堪能した?」礼子の声が響いた。「もうちょっと懲らしめたい気もするけど、流石に今日はこれまでね。もう多分、痛覚殆どマヒしちゃってるから、これ以上苛めても余り面白くないわ。と、言うことで今日はこれまで、解散にしよう!お疲れ様!」礼子の声を合図に、心地よい疲労を楽しみながらクラスメートがゾロゾロと帰っていく。後には礼子たち四人と慎治たちだけが残っていた。
「信次、正座。」玲子が静かに命令した。玲子の命令に突き動かされ、最後の気力を振り絞るように二人はのろのろと正座する。「どうかしら、少しは骨身に沁みた?反省したかしら?」「・・・は、はい・・・はん、せい・・・しまし、た・・・」消え入るような声で呟く信次を満足げに見下ろしながら玲子は冷笑した。「そう、それは良かった。だけどね、もう遅いのよ。信次、あんたたちは超えてはならない一線を飛び越えちゃったのよ。いくら反省しても、もう絶対に許してあげない。信次、あんたたちにはこれから、本物の苛め、ていうものを教えてあげるわ。私たちの全力で、本気で苛め尽くしてあげるからね・・・辛いわよ、覚悟しておくことね。」
ほ、本物の苛め・・・そ、そんな・・・い、一体なにをする気なの?ま、まさか、これから一本鞭で・・・
恐怖に引きつる二人に、後を引き取った礼子が告げる。「二人とも安心していいわ。今日これから鞭を追加する、なんてことはしないから。今日はもう、何もする気はないわ。ううん、それどころかこの週末は解放してあげる。ゆっくりと休んでいいわよ。」な、なにもしない?い、いやそれより、週末休ませてくれる?い、一体なぜ、どうして???予想外の礼子の言葉に、慎治たちは安堵よりも戸惑いと不安に包まれる。その困惑の表情を見て玲子が冷笑を浮かべた。
「信次、不安?怖い?自分がどうされるのか知りたい?ダメ、教えてあげないわよ。」礼子の美貌にも残酷な冷笑が浮かぶ。
「まあこれだけは教えといてあげるわ。玲子が本物の苛め、て言ったでしょ?念のため言っとくけど、今までみたいに単純に鞭で打ちのめすのが本物の苛めじゃないからね。鞭100発が200発になる、なんていう単純な責めを考えられたら困るわよ。ウフフフフ、血塗れになるまで鞭打たれたのが軽いお遊びに思えるような目に会わせてあげるわ。フフフ、週明け、楽しみにしていなさい、どういう目に会わされるのか・・・精々ゆっくりと想像してみることね。」「そ、そんな・・・な、なにを、なにをされるんですか・・・」「ど、どうするの、ぼくたちを・・・どうするつもりなの・・・おしえて・・・」涙を流しながら必死で尋ねる二人に冷笑を投げかけながら礼子たちは解散を宣言した。「それでは良い週末を!」「また来週!」
翌日、未だ目覚めたくない、このまま永久に夜が続いてくれたらな、という願いとは裏腹に慎治たちは妙に早く目覚めてしまった。
もう朝か・・・今日は一日公衆便所・・・鉛を飲み込んだような気分で重い足を引きずりながら登校すると、礼子たちはもう登校していた。女の子たちも既に2/3以上登校している。「あっ慎治、やっと来たわね、遅かったじゃない!」「あ、ああ、ご、ごめんなさい、あ、お、はよう、ございます・・・」慎治の挨拶が終わらぬうちに、礼子はすっと立ち上がり、歩き出した。「別にどうこう言ってるわけじゃないじゃない、そう一々ビクツカないでよ。まるで朝っぱらから私が苛めてるみたいじゃない!まあどうでもいいけどさ、ほら慎治、さっさとおいで!おトイレ我慢して待っててあげたんだからね、早く来なさいよ!」ああ、本当に朝一からトイレかよ・・・礼子の後ろをうなだれ、とぼとぼ付いていく慎治の姿に失笑があちこちから漏れる。当然のように、信次も玲子に引き立てられている。
そしてトイレにつくと、礼子は顎をしゃくった。「ほら早く横になりなさい!」慎治がノロノロと踏み台と漏斗をセットしようとしていると、向かいの個室から玲子の声が響いた。
「信次、あんたバカア?私が今更漏斗とか踏み台とか使うと思ってるの?全く便器にすら満足になれないのね、信次は!この低脳!ペッ!」「あっああっごめんなさい、許して・・・」「ほらさっさとそこなさいよ!」玲子の声に弾かれるように、慎治は礼子の顔色を伺った。「慎治、聞こえたでしょ、私も漏斗や踏み台はいらないわ。それより・・・さっさとしてくれないか・し・ら?」礼子の声音に苛つきの影が見える。慌てて慎治は便器の上に、自らの汚辱と安住の地に横たわり精一杯口を開けた。「そうそう慎治、その口よ。今度スムーズにこうできなかったら、分かるわね、鞭よ。」「ふうっ、信次、私のおしっこ飲むの一体何回目だと思ってるの?いい加減、もう何も言わなくても私が気持ちよくおしっこできるようにしなさいよね!」シャアアアアッッッ・・・礼子たちはほぼ同時に放尿を開始した。
その日、慎治たちは昨日の宣告通り休み時間毎にトイレに引き立てられた。聖華の休み時間は1-4,5-6の各時限の合間に10分ずつの休みが入り、また昼休みは一時間となっている。都合4回の10分休みには平均して各二人ずつに飲まされた。そして昼休みは最初の20分間で食事、後片付け等を全て終えさせられ、残り40分間フルにトイレに逝かされた。その間におしっこを飲まされた女の子は実に8人、殆ど休みなし、一人が出たと思ったら直ぐに次の子が入ってくる、といった具合だった。最初は確かに和枝や真弓といった空手部員、合気道部員やココタマ等、礼子たちと親しいクラスメートが中心になって便器化した慎治たちのいわば皮切りをしていた。だが皮切りはそこまで、極く僅かで十分だった。多数派のクラスメートたち、お付き合いで慎治たちに唾を吐き掛けたり靴を舐めさせたり程度はするが積極的に苛めようとはしなかった女の子たち、実際には多数派のこの子たちの中からポツリポツリと、慎治たちにおしっこを飲ませる子が出始めたのだ。
不思議と言えば不思議なものだ。礼子たちも最初はそうだったのだが、お嬢様校である聖華の女子生徒は皆決して苛めっ子等ではない。自分が他人におしっこを飲ませる、なんて想像したことは誰一人ない。だが慎治たちは特別、毎日毎日礼子たちに唾を吐き掛けられ、鞭で打たれ、踏み躙られている。いくら苛められてもひたすら許して許して、と泣き喚くだけの慎治たち。いつしかクラスメート皆にとって、慎治たちが苛められていること、慎治たちが泣いていること、通常滅多に見ることができない男の子が女の子に苛められて泣いている光景、それがこのクラスの中だけでは一つの極ありふれた日常になっていた。
加えて今の刑、無差別にみんなのおしっこを飲まされる公衆便所の刑、これは余りに日常から懸け離れすぎていた。これが仮に全員で毎日、慎治をビンタ、あるいは鞭で打つ、という刑だったら却って容易に慎治たちの痛みを想像できる分、どこかで誰かが、或いは集団的な無意識がブレーキを掛けたかもしれない。だがおしっこを飲ませる、これは余りに想像を絶していた。想像を絶する分、どこか興味をそそられかつ慎治たちの苦痛を想像しにくい物であることも確かだった。
ええ、おしっこを飲ませる!?そんなのできるわけないじゃん!・・・でも、もう一生そんなことする機会、あるわけないよね・・・今を逃したら絶対、二度とそんな機会はないよね・・・そういえば飲尿健康法なんてのもあったわね。ああいうのがあるってことは、おしっこって飲んでも病気になったり体に悪いものじゃないのよね・・・そうよね、もう礼子たちに散々飲まされてるんだし・・・フミちゃんや朝子も飲ませてるのよね・・・もう四人のおしっこ飲んだんでしょ?あ、今また慎治、新たな一人のおしっこ飲んだのね。だったらもう、私一人位増えてもどうっていうことないよね・・・なんか、面白そう・・・一生の記念になるかもね・・・慎治、別に慎治を鞭で叩いたり蹴っ飛ばしたりしたいとは思わないんだけどさ、おしっこ飲ませる、ていうのはなんか惹かれちゃうのよ・・・こういうのって、お祭よね、のらないのって却って変じゃない・・・私もやってみようか・・・
一人、また一人と好奇心、嗜虐心というより好奇心に負けてトイレの予約リストに名前を連ねていった。一人、また一人と参加者が増えるにつれ、群集心理も働いていき罪悪感、抵抗感は加速度的になくなっていく。そして礼子たちのトイレセッティングがまた絶妙だった。これが礼子たちがいつもやっているように直接慎治たちの口におしっこをするとか、或いは手軽に底を抜いたペットボトルか何かを咥えさせてその中におしっこを出す、といった程度のセッティングではおしっこの狙いを定める、勢いをコントロールする、或いは腰を浮かせて中腰の状態で放尿する、といった通常の排泄と相当に違うシチュエーションとなりクラスメートの心理的抵抗も大きかっただろう。ことに直接排泄するパターンでは間近に慎治たちの顔がある分、恥ずかしさも感じたかもしれない。だが慎治たちは透明とはいえ大きな漏斗を咥えさせられているから自分と慎治たちの間には大きな壁があり、自分の秘所を直接見られることはない。この一枚のプラスチック板があるだけで自分の性器を、排泄の瞬間を見られるという心理的な抵抗は相当に少なくなる。しかも踏み台もあるからいつもと同じく完全に腰を下ろしてゆっくりと放尿できる。そして漏斗は大きく、十分に口が広いから何も考えずに一気に放尿しても溢れたり便器の外に飛び散る心配、特に自分にかかってしまう心配は全くない。要は排泄する側のクラスメートから見れば、普段のトイレと全く変わらない要領で、いつもの、生まれてこの方何千回となくやってきた通りに放尿するだけでいいのだ。それだけで他人の口を便器にする、他人に自分のおしっこを飲ませる、という一生二度とできない経験ができるのだ。この魅力には勝てない。その日の夕方、一日の終わりには既に飲ませた方が多数派になっていた。おそらく明日には殆どの女の子が飲ませ、まだ飲ませていない子は圧倒的に少数派になっているだろう。
や、やっと今日が終わった・・・夕方のホームルーム、慎治たちにとって長い長い一日が漸く終わろうとしていた。今日一日で何人に飲まされたんだ?信次は指折り数えてみる。朝一に玲子さん、朝子、そして・・・休み時間毎に二人だから八人、昼休みも八人だったから・・・合計・・・じゅう、はちにん、十八人!?は、はは、ははははは・・・・・信次は力なく笑った。じゅ、じゅうはちにんか・・・そんなに飲まされたのか、俺、そんなにたくさんの女の子のおしっこ、飲まされたんだ・・・す、すげえ、すげえよなあああ・・・腹もガボガボの筈だよな、一体俺、どれ位の量のおしっこ、飲まされたんだ???信次が笑ってしまうのも無理はない。一人一回当たり、仮に平均200ccのおしっこを排泄したとしても全部で3,600cc,平均300ccだとしたらなんと、5,400ccにもなる。1.5リットル入りの大型ペットボトル二、三本、事によるともっと、というとんでもない量を飲まされたのだ。信じられねえ、そんなに飲まされたんだ・・・あまりに大量のおしっこを飲まされたため信次たちは今日一日、他の水分を全く飲む気にならなかった。それだけ飲めば、そりゃ今日一日、他に何も飲む気にならなかった筈だよな。そう、信次たちが今日一日に飲んだ水分は全て、クラスメートのおしっこだけだった。ははは、あれだけ一杯飲まされたせいか、俺もなんども小便しちゃったけど、あれ全部、みんなのおしっこなんだ。みんなのおしっこが俺の体を通り抜けてったんだな。お、俺の、俺の体を、じゃあ・・・ははははは、俺の体の中、みんなのおしっこで一杯、体中、みんなのおしっこが浸み通っていった、てことかよ。は、はは、ははははは・・・・・でも明日も明後日も、まだまだこれが続くんだろ?ということは・・・ははははは、俺の体の中、全身の細胞全部、水分全てみんなのおしっこに置きかえられちまうな・・・へ・へへ・へへへへへ・・・便器人間、おしっこ男信次、の誕生か?へ・へへ・へへへへへ・・・・・べんきまーーーん!じょぼおおおおおっ!力なく自嘲的に笑っている信次に玲子が追い討ちをかける。
「さあ、今日の懲戒は何回かしら?信次、私や朝子はチェックしないであげたんだから、少しは得したじゃない、良かったわね!」殆どのクラスメートはLにチェックしていた。玲子たち以外の延べ14人に対し、L12人、M2人だった。「じゃあ・・・計40発ね!信次、今日の懲戒は私が執行するわ!」教壇に引き据えられた信次の目の前で、朝子がウェストからベルトを引き抜き構える。「逝くわよ、ハイッ!」次いで慎治の番、予想通り慎治の前では富美代がベルトを構える。慎治はL11人M3人、計39発だった。「慎治、毎日の懲戒は私と礼子が毎日、交代で執行するからね、今日の鞭は私、明日は礼子よ。さあ逝くわよ、それっ!」教室に二人の悲鳴が再び木霊した。
2
水曜、木曜と公衆便所の刑は執行され続けた。毎日毎日慎治たちは朝登校するや否やトイレに引き立てられ、礼子たちを皮切りにクラスメートのおしっこを延々と飲まされ続けた。10分休み、昼休みと飲まされ続け、そして夕刻のホームルームではベルトで鞭打たれる。毎日繰り返される刑罰に慎治たちの精神は確実に蝕まれていった。
ひどい、こんな酷い刑罰ってないよ・・・みんなの、みんなの公衆便所だなんて・・・毎日毎日みんなの目の前でお尻を出されて鞭打たれるなんて・・・そ、それを毎日、無期限で続けられるだなんて・・・もう、耐え切れない・・・不幸な、慎治たちにとっては不幸なすれ違いが発生していた。実のところ、刑罰を執行している礼子たちにしてみれば酷いことをしている、という意識は全くなかった。いやそれどころか私たちも甘いな、この程度で済ましてやってるんだから、慎治たちもさぞかしほっとしているでしょうね。まあいいけど、慎治たちも感謝しなさいよ、私たちの寛大さに!と本気で考えていた。当然と言えば当然だ。礼子たちにとっては慎治たちを便器にし、おしっこを飲ませているのは公衆便所の刑の執行以前からやっている日常生活の一部に過ぎない。だから礼子たちからしてみれば、この刑はほんの軽いお遊びのつもりだった。
二人とも私たち四人からそうね・・・大体毎日、最低でも四回ずつは飲まされてるでしょ?それが若干回数増えただけじゃない。別に飲みきれない量を北京ダックよろしく無理矢理飲ませて水責めにしているわけじゃないし、おしっこは無害だって言うじゃない?慎治たちはどうせ私たちのおしっこを毎日飲んでたんだから、高々その回数が増えるだけ、全然大したことないよね。懲戒の鞭にしてもベルトで許してやってるし、回数も50発にもいかないわよ。第一そんなに思いっきり引っ叩いてるわけどもないし、たったあれだけのベルトなんてお尻がちょっと赤くなるだけよね。私たちの本物の鞭であれだけ打たれてる慎治たちにとってはほんのお遊び程度のものよね。大袈裟に悲鳴上げてるけど、ほんとはハタキではたかれてる程度にしか感じてないんじゃない?大体、今までだってみんなに唾吐き掛けられたり靴舐めさせられたりして十分苛められてるじゃない?今まで散々私たちにやられたことが多少回数増えるだけよ、クラス裁判、ていう恥じかきシチュエーションはあったにしてもさ、今更慎治たち、恥ずかしいでもないでしょ?
礼子たちは本心でこの無期公衆便所の刑をほんのお遊び、形式的な、罰とも言えない軽いお遊び程度のもの、としか考えていなかった。そして慎治たちもそう思っていると、ああこの程度の罰ですんでよかった、礼子さんたちがこの程度の罰で許してくれるなんて本当に良かった、と自分たちの寛大さに心の底から感謝しているに違いない、と純粋に信じ切っていた。
一方、飲まされる側の慎治たちは全く事情が異なっていた。慎治たちのひ弱な精神が耐えられる最後の一線は、僕たちを人間扱いしないで酷い苛めをしているのは礼子さんたちだけだ、他のクラスメートたちは苛めるにしても、唾を吐き掛けたり平手打ちで引っ叩いたりはするけど、僕たちのことを人間扱いはしている、一線を超えて苛めてはいない、と思い込むことだった。
物理的な苛めで言えば鞭、本物の鞭、礼子たちが振るうような牛馬にしか使われることがない人間が鞭打たれることなど決してない筈の鞭で打たれることがそれに当たる。そして・・・おしっこを飲まされること、それも慎治たちにとっては最後の一線だった。人間が人間におしっこを飲ませるなんて、絶対にありえない、絶対に・・・礼子さんたちが僕たちに飲ませているのは、僕たちのせいじゃない、僕たちが悪いんじゃない。礼子さんが、礼子さんたちがおかしいんだ、あんなの人間ができることじゃない、礼子さんたち、人間じゃないよ・・・
そう思い込むこと、自分たちが異常なんじゃない、礼子たちこそ異常なんだ、と思い込むことが慎治たちにとっての唯一の心の支えだった。それを礼子たちはいとも簡単に打ち砕いてしまった。礼子たちの誘いに応じ、クラスメート全員が公衆便所の刑に参加していた。全員、そう全員に飲まされたのだ。自分を誤魔化すことさえさせてもらえない。
クラスメート全員におしっこを飲まされた男。礼子たちだけにではない、全員に飲まされたのだ。こんなことされた奴、一生二度と会えないだろうな・・・俺たち、俺たちが異常なんだ・・・俺たちみたいな奴、クラス中の女の子に朝から晩までおしっこ飲まされてる奴なんて、日本中探したって絶対にいないんだ・・・単におしっこを飲ませる人間が増えた、という問題ではない。他の子にだって唾を吐き掛けられてるんだから、おしっこ飲む位どうということないでしょ?というのは責める側の言い分だ。慎治たちにとってはそうではない。おしっこを、おしっこを集団で飲まされる、というのはある意味、鞭で半死半生になるまで打ちのめされるよりも遥かに辛いものだった。我慢の限界だった。坊野たちのように肉体的に破壊されたわけではない、だが精神的な拷問、と言う意味では慎治たちはまさしく延々と拷問を味合わされていたのだ。僅かに残っていたプライドを、自分が人間だ、という最後の誇りをズタズタに破壊され、永遠に奪われる痛みと屈辱と喪失感を。
実際にはあと少し、あと少し耐えていれば良かったのだ。礼子たちはほんの軽いお遊びのつもりだったたから、みんなに慎治たちにおしっこを飲ませることを強制などしていない。そしてみんなも最初こそ興味本位で全員が参加したものの、徐々に参加者は限定されていた。和枝、真弓たちのような合気道部、空手部仲間を中心とする礼子たちのコアなグループ以外は徐々に慎治たちに飲ませる頻度が減っていた。いくら群集心理とは言っても、自ら積極的に苛めを楽しむ女の子はやはり限定されてしまう。そして礼子たちも、段々トイレに立つクラスメートが減ってきた事に気づいていた。だから四人の間ではこんな会話が交わされていたのだ。
みんな一巡したみたいだし、そろそろ新鮮味も薄れてきたみたいね。そうね、マンネリ化しても面白くないしいい加減許してやる?うん、別にいいんじゃない?まあ飲ませたい、ていう子がいたらいつでもご自由にトイレに連れてって、ていう感じで。そうね、じゃあ一応、来週一杯位で公衆便所の刑は終了、ていうことでまあ、トイレからは解放してあげようか。
礼子たちと慎治たち、責める側と責められる側の捩れは拡大しつつ金曜を迎えた。その日、昨日までと同じく朝からトイレに引き立てられた慎治たちはいつものように、まずは礼子たち四人のトイレにされて一日をスタートした。一時間目二時間目三時間目と授業は進み、休み時間毎にクラスメートが慎治たちに次々とおしっこを飲ませていく。そして昼休み、急いで食べさせられた慎治たちがトイレに追いやられてから暫くして、仕切りを越えて二人のクラスメートがやってきた。青葉陽子と古鷹有希子だった。二人とも空手部、合気道部といったコアなグループではないが礼子たちとは仲がよい真面目系の女の子だった。特に陽子は富美代と仲が良く、そのツテで礼子とも非常に仲がよかった。別に慎治たちを率先して積極的に苛めてはいなかったが、二人とも慎治たちに対しては軽蔑しか感じていない。
無論、今回の公衆便所の刑に対しても慎治たちには何の同情もしていない。だが二人とも、まだ一回ずつしか飲ませていなかった。大した理由があったわけではない。単純に面倒くさかったからに過ぎない。おしっこするのに何で一々順番待ちしたり予約したりしなくちゃいけないの?そりゃ慎治たちに飲ませたい気もするけどさ、そんなことまでして飲ませることないわよね。もっと空いてから飲ませてやればいいじゃん、もし刑期が終わったとしてもさ、どうせ礼子たちに頼めば何時だって貸してもらえるわよ。
そのため、やっと空いて来た昨日に陽子は信次、有希子は慎治にそれぞれ飲ませたばかりだった。そしてこの昼休み、ふと見ると予約表はブランクになっていた。
「有希子、なんか今、トイレ空いてるみたいよ?」「ああ本当だ、やっぱりみんな一巡して空いて来たみたいね。どうする?昨日飲ませたばっかだけど、いく?」「・・・うん、そうね。まあ昨日一回飲ませただけだから、一応行っとこうか。だってさ、昨日気が付いたんだけど、ほらもうみんな飲ませちゃってさ、未だ二人両方に飲ませてないのって、私たちだけみたいだよ?私たちも昨日一人ずつ飲ませたでしょ?今もう片方に飲ませれば、これで一応クラス全員、一巡はしたことになるみたいよ?」「へえ、私たちで一巡達成なんだ、じゃあやるしかないわね・・・じゃあ今日は私が信次、陽子が慎治ね。」連れ立ってトイレに現れた二人は左右に別れ、各々の便器の待つ個室に入っていった。
「慎治、ねえ今日は私で何人目なの?もうすっかり便器が板に付いたみたいね。でも私は信次に飲ませるの、これか初めてなのよ、分かる?まあこうやってみんなに飲まされ続けたんだもんね、一々誰に飲まされたか、誰が未だかなんて覚えていないか。」陽子は踏み台に上り、白いパンティを下ろして慎治の顔の上にしゃがみ込みつつ話し掛けた。「ハイ慎治、今度は私の番よ・・・ねえ慎治、ちょっと聞いてみたかったんだけどさ、みんなのおしっこ飲んでて味に違いってあるの?だってさ、私で慎治に飲ませるの丁度20人目だからさ、記念に聞いときたいんだ。」ウン、20人目?・・・慎治はその意味を一瞬、理解できないでいた。20人目・・・その時向かいの個室から有希子の声が聞こえてきた。
「信次、気が付いていないかも知れないけど、私で最後なのよ?私で20人目、これでクラス全員が信次におしっこ飲ませた、てなるわけ。今陽子も慎治に飲ませるとこだからさ、これで二人ともめでたく、クラス全員制覇、全員のおしっこ完飲、てなるわけよ。・・・凄いわねえ、20人のおしっこ完飲、てそうそう出来ることじゃないわよ。玲子たちのことだもん、多分志津子たちみたいな部活仲間の、よそのクラスの子のおしっこもそのうち飲まされるわよ?ウフフ、信次、あんたたちがおしっこ飲んだ女の子の数、そうそう破られることないんじゃない?そのうち学校中の女の子のおしっこ完全制覇したりさ、ううん、もっと頑張ればおしっこ千人切りとか言っててギネスブック狙えるかもよ?」
ぜ、全員!クラス全員!有希子のその言葉は慎治たちの心臓に深々と突き刺さった。全員・・・俺たちこいつで最後、クラス中の女の子全員のおしっこ飲まされちゃったのか?う、嘘だろ!今まで目の前の、いや目の上の女の子のおしっこを飲むだけで精一杯だったから気付かないで済んでいた現実、自分がクラス中の女の子の公衆便所にされたこと、玲子が宣告した公衆便所の刑が完全に執行され、自分たちの口が喉が胃が、そして全身がクラスメート全員の便器にされてしまったのだ、という逃れ様のない現実が二人の精神にグッサリ深々と付き刺さった。そして有希子の洩らした何気ない一言、志津子たちのような玲子たちの部活仲間、中学の同期系、更にはその子たちのクラスメート、と自分たちにおしっこを飲ませよう、という女の子のリングが際限なく広がっていく、その光景がリアルな現実、それも直ぐにでも始まりそうな現実として二人に襲い掛かっていた。学校中の女の子のおしっこ完全制覇・・・今まで飲んだ女の子は大体20人、その20倍近い数の女の子におしっこを飲まされる、それすら大いに有りそうなことに思えてきた。
慎治が半ばパニック状態に近い狼狽を顔に浮べるのを陽子は面白そうに見下ろしていた。フーン、こうやって見下ろしていると、慎治が何考えてるのかなんて、一目瞭然ね。あ、でもこんなお話してる間に、本当におしっこしたくなってきちゃったわ!「さあ慎治、じゃあクラス完全制覇おめでとう!完全制覇達成記念のお祝いよ、私からささやかなプレゼントあげるね、思いっきり、たっぷり私のおしっこ飲ませてあげる、有難く受け取ってね!」
チョロロ・・・シャアア・・・ジャアアアアアッ!陽子が括約筋を緩めるや否や、たっぷりと溜まっていたおしっこが陽子の体内から溢れ出し、それはあっという間に勢いを増して太い水流となって慎治が咥えさせられている漏斗に満ちていく。そしてその薄黄色の液体は信次の口に流れ込み、慎治の舌に慣れ親しんだ味を、他人のおしっこの味を刻み付ける。
「アハハハハッ、完全制覇達成記念のおしっこよ、たっぷりと召し上がれ!」陽子の笑い声が降って来る。「アハハハハッ、飲んでる飲んでる!これでクラス制覇達成ね、おめでとう!記念のおしっこの味、たっぷりと味わってね!夕方のホームルームで報告してあげるね、深,燭舛・・・実匸ラス制覇達成したことを!」向かいの個室から有希子の笑い声も聞こえてくる。信次も飲まされてるのか、これで俺たち二人とも・・・クラス全員のおしっこ・・・飲んじまったのか・・・全員の・・・みんなの・・・お、おしっこを・・・の、飲んだ、みんなのをの・ん・だ・・・
慎治たちの頭の中にこの4日間の記憶がフラッシュバックする。笑いながらおしっこした子、いかにも軽蔑に耐えない、といった顔で見下ろしながらおしっこした子、何の表情も浮かべずに単純に普通の便器にするようにおしっこして一言も発せずに立ち去った子・・・様々な顔が、お尻が自分の上に現われそしておしっこをしていった。それを・・・飲んだんだ・・・みんなのを・・・一人残らず・・・20人・・・分を・・・のんだんだ!!!
慎治の頭の中に浮かんだ、自分におしっこを飲ませていったクラスメートの映像は消えずにグルグルと駆け巡る。アハハ、アハハハハ、アハハハハハッ!嘲笑の声が聞こえてきた。その筈がない、ここはトイレだ、みんなの笑い声なんか聞こえる筈がない!!!だがいくら打ち消そうとしても、慎治の頭の中に響く嘲笑の声、礼子の富美代の和枝の・・・そして陽子の声は止むことなく却って増幅し拡大していく。現実には陽子一人が慎治におしっこを飲ませながら嘲笑の声を上げているだけなのだが、慎治の頭の中は全員の、クラスメート全員の自分を見下ろす顔、嘲笑う声に支配されていた。や、いや、いやだあああああっ!や、やめ、やめろおおおっ、!!わ、笑うな、笑うな、笑わないでくれえええええっっっっ!!!慎治の目の前が赤黒く染まり意識が混濁していく。自分が完全に発狂寸前、パニック状態に陥り精神も肉体も制御できなくなっていくのを微かに感じた。
「ウッギィャラオオオオオッッッ!!!!!」突然獣のような、声とも咆哮ともつかぬ訳のわからない絶叫と共に慎治の全身がビクンビクンと痙攣した。「キャッ、な、何よ!」陽子が叫ぶと同時に「ギッヒャアアアアアアアッッッッッ!!!!!」漏斗を咥えたまま慎治が突然跳ね起きた。「キャアッ、何するのよ!」慎治の顔に漏斗でお尻を下から突き上げられ、バランスを崩した陽子を慎治は更に両手で突き飛ばす。
ドザッ、ゴッ!「い、いったーい!」排泄中の無防備な所を思いっきり突き飛ばされては堪らない。陽子は踏み台から後ろ向きに転げ落ち、半回転して頭を床にしたたか打ち付けてしまった。「ウガアアアアアッ!!!」その陽子に一目もくれず、慎治は絶叫しながら個室、公衆便所の刑を執行されていた個室から走り出し、パネルを突き倒すとトイレから走り出ようとした。
「な、何よ!」慎治の絶叫に有希子が驚いて振り向いた瞬間、有希子の股間の下からも絶叫が響いた。「イイイイアアアアアッッッ!!!!!」
あっと思う間もない、絶叫と共にガバッと体を起こした深,力嚇佑鵬・・実匸されてバランスを崩した有希子を更に信次が突き飛ばす。
「キャアアアアアアッ!やめてよ!」悲鳴と共に半身のまま下から押された有希子は体の捻りそのままに前向きに飛び込む様に床にダイブしてしまった。ザウッ、ガッ!「いったああああ・・・な、なんなのよ・・・」有希子の呻き声が漏れる。
興奮の余り目の前が真っ暗になった慎治たち二人は闇雲に個室から飛び出るとガッシャアーン!とパネルを勢いよく突き倒し、勢い余って自らも転びながらトイレの中央に転がり出る。「キャッ、な、なによ!」「何なの、どうしたって言うのよ!」トイレに居たクラスメート数人の悲鳴が上がる。その中を四つん這いになり、たたらを踏みながら立ち上がった慎治たちが奇声を発しつつ駆け抜けようとする。
「アギャラアアアアアッッッ!!!」「イギイイイイイイッッッ!!!」だが運の悪いことにトイレには丁度、富美代と朝子が来ていた。二人とも流石に驚いたものの慎治たちの逆切れはしょっちゅう見ている二人だ、リカバリーは速い。一瞬にして冷静さを取り戻し慎治たちに襲い掛かった。
「アアアアアッッッ!」「ハッ!」絶叫しながら駆け出そうとする信次の足元を朝子のローキックが掃腿の要領で払う。「ハイッ!」「グハアッ!」富美代も慎治を避けるどころか逆に反射的に、機先を制するかのように一歩踏み込み駆け出そうとする慎治が未だスピードに乗れないでふらついているところを、素早く右腕を掴んで極める。「ハヤッ!」極められた右手首を中心に慎治の体が宙を舞い、コンクリートの床に叩き付けられる。「ゲッバアッ!」そして富美代も朝子も素早く慎治たちの腕を極めながら頭を踏みつけて動きを封じる。「ほら慎治、何やってるのよ!」「信次、一体どういうつもりよ!何の真似なのよこれは!」富美代と朝子の一喝が慎治たちの精神の昂ぶりを鞭のように打ち据え、一瞬にして萎えさせる。
その時、倒れたパネルの向こうから呻き声が聞こえてきた。「イタタタタ、ひ、酷いわ・・・」「な、なによ、何で私が突き飛ばされるの・・・」陽子と有希子の声だった。声の方を振り向いた富美代たちの顔が怒りに彩られる。「・・・慎治、あんた一体どういうつもりなのよ!?」グイッとさらに一捻り腕を捩じ上げつつ、朝子が横にいた真弓に声をかけた。「ったく信次、あんた分かってるの?こんなことしてどうなるか・・・真弓、玲子たち呼んできて!」「OK!」朝子に頼まれた真弓は教室に書け戻り、玲子たちに急を告げた。
「玲子!大変よ信次が、信次がね、有希子をトイレで突き飛ばして転ばせちゃったのよ!慎治も陽子のことを転ばせてたわよ!兎に角速く来て!二人とも怪我しちゃってるみたいよ!」「な、何だって!?マジそれ?真弓、ホントなの!?」「本当よ!いいから二人とも速く来てよ!」ガタッと椅子が引っ繰り返るほど勢いよく、礼子が立ち上がった。「で真弓、慎治たちは?連中はどうしたの?」「丁度トイレには朝子とフミちゃんがいたわ。だからあの二人が慎治たちのこと、取り押さえてるわよ。」「礼子、行こう!」一声かけると玲子は全力で走り出した。そしてトイレに着くと思わぬ光景に息を呑んでしまった。
富美代と朝子に取り押さえられ、トイレの床に押さえつけられている信次たちには目もくれずに玲子は有希子たちに走りよった。「有希子!陽子!大丈夫?一体・・・一体どうしたの、何があったのよ!?」「・・・知らないわよ、こっちが聞きたい位よ!私がおしっこ飲ませてたら、突然信次が暴れだして私のこと突き飛ばしたのよ・・・アツツ、ああ痛いな、もう・・・」「ちょ、ちょっと見せて・・・ああ有希子、血が出てるよ・・・」玲子が言うまでもなく、床に転がされた有希子は二の腕を擦り剥いて血を滲ませていた。「礼子、陽子はどう?」玲子は陽子の方を振り向いて礼子に声をかけた。「頭は軽く打っただけみたいだけど・・・転んだときに膝を切っちゃったみたいね、血が出てるわ。兎に角二人とも、早く保健室に連れてかなくちゃ。転んだ場所が場所だし、化膿したら面倒よ。」礼子の声に頷いた富美代と朝子が反対側から陽子と有希子を助け起こす。「いいわよ礼子、保健室には私たちが一緒に行くから・・・それより礼子たちはここをお願い。大丈夫、陽子?歩ける?」「ありがとう・・・大丈夫、骨がどうにかなった訳じゃないから、歩けるわよ・・・でも」富美代の手を借りて軽く足を引きずりながら歩き出した陽子は涙を溢しながら礼子を振り向いた。
「・・・ねえ礼子、なんで、なんでなの?なんで私がこんな目にあわなくちゃいけないの?トイレの床に突き飛ばされて、転ばされるなんて・・・トイレ、トイレにだよ?わたし・・・悔しい、なんで私が慎治に、慎治なんかに怪我させられなくちゃいけないのよ・・・しかもトイレで・・・あんまりよ、あんまりだわ!」有希子も余りのことに涙を流していた。「そうよ・・・そうよ・・・玲子、ひどい、ひどすぎるわよ!こんなのないわよ・・・私・・・私、トイレに、トイレの床に・・・顔打ち付けられたのよ・・・なんで、なんで私がこんな目に会わなくちゃいけないの?私が何したって言うのよ?あんまりよ!絶対・・・絶対許せない!」
陽子たちが保健室に連れて行かれた後、トイレを一瞬の静寂が支配していた。やがてその静寂を破るように低い声が響いた。「・・・慎治・・・慎治・・・」顔をやや伏せたまま、礼子が呪文のように慎治の名前を唱えていた。「・・・慎治・・・あんたよくも・・・やってくれたわね・・・・・」ゆっくりと顔を上げた礼子と視線が合った時、慎治は思わず恐怖の余り全身が凍りついてしまった。礼子の整った顔立ちは紅潮し、大粒のダイヤのように光り輝く美しい瞳は激しい怒りの炎に燃え上がっていた。信次が初めて見る表情、それは礼子の本気の怒りの表情だった。礼子は本気で怒っていた。あれだけの大罪を犯した慎治たちをこの程度の、ほんのおしるしだけの罰で許してやろうっていうんだからね。ほんと私も甘やかし過ぎよね、慎治、感謝しなさいよ。礼子は慎治たちが自分に感謝していると信じて疑っていなかった。それを・・・よくも裏切ったわね。私がこれだけ優しくしてあげたのに、慎治はそれを裏切りで返すのね。陽子に、私の友達に、女の子に怪我させるなんて・・・許さない・・・・・
日頃慎治を苛める時、礼子は楽しそうな輝くばかりの笑顔を浮べ、決して怒りの表情を見せたことはない。どんなに理不尽に責め苛みながらも常に楽しそうな遊びの表情であり、怒ったことなど殆どない。慎治にとって礼子の本気の怒りの表情は久し振り、初めて唾を吐き掛けられた時以来の、本当に久し振りに見るものだった。なまじ整った文句の付けようのない美貌だから余計に恐ろしい。柳眉を逆立てるといった言い方が最も相応しい、見るものの血を凍らせる夜叉、悪鬼羅刹の類いの表情だった。「・・・慎治、許さないよ・・・」
礼子はゆっくりと慎治に近づいていく。ヒッ・・・慎治は後ずさりしようとするが礼子の本気の余りに激しい怒りに半ば腰が抜けてしまい、満足に動くことすらできない。「・・・慎治・・・」その美しい瞳をカーミラの邪眼の様に燃え上がらせながら礼子はゆっくりと慎治の胸倉を鷲掴みにする。ヒッ・・・慎治は悲鳴をあげたつもりだが、実際には恐怖の余りかすれ声すら発していない。「許さないよ・・・」アアアアアアッ!慎治の悲鳴と共に激痛が襲い掛かった。「ハッ!」烈昂の気合と共に礼子の右当身が信次の鳩尾に食い込む。「ゲバアッ・・・ビギャアッ!」悲鳴を上げる隙すらなく、腰をくの字にかがめようとする慎治の顎を礼子の肘打ちが叩き起こす。そして間髪を入れず、礼子の全開の右前蹴りが慎治の胸に炸裂する。「グハアッ!」蹴り飛ばされてトイレの壁に叩き付けられた慎治にずいずいと礼子は近づいていく。
「ヒッ!ヒイッ!!」「この手・・・邪魔よ!」礼子は一瞬の躊躇もなく、反射的に頭部を庇った慎治の右腕を強引に捩じ上げる。お、折られる!そう慎治が思うのより早く、礼子は捩じ上げ脱臼させるなんてもどかしい、とばかりに完全に極めた慎治の肩に凄まじい手刀を叩き込んだ。バギッ・・・・・「ギヒイイイイイッ!」半ばへし折り、打ち砕くかのように肩を一瞬にして脱臼させられた慎治の悲鳴に委細構わず、礼子は慎治の左腕も捩じ上げ同様に破壊する。「ギ、ギアアアアアッ、ヘアッ・・・」両肩を破壊された激痛に絶叫する慎治の喉下に礼子の純白の上履きが食い込む。右上段前蹴りで慎治をトイレの壁に昆虫採集のように釘付けにしながら、礼子は怒りに震えた声で言い放った。「慎治・・・よくも陽子を・・・よくも私を裏切ったわね・・・許さないわよ・・殺・・・す・・・」恐ろしいほどの殺気がこもった声を発しながら礼子は慎治を捕らえた右足にグッと力をこめると、一旦その足を引き戻した。
礼子の右足が引かれたその瞬間、玲子の声が響いた。「待って礼子、それまでよ!」怒りに顔を紅潮させながら礼子が振り向いた。「何よ玲子、邪魔する気!?ほっといてよ!慎治を庇いだてする気なら、聞く耳持たないわよ!誰が何と言おうと私、慎治のことは・・・殺す!」「礼子、少しは落ち着いてよ!私が慎治たちの事を庇いだてするわけないでしょ!私だって有希子の仇を討ちたいわよ!だけど今はタイムアップよ。もう昼休みはおしまい、今からじゃ慎治たちの事殺す、て言ったって大したことする時間はないわ。蹴り倒して骨何本かへし折ってそれでお終い?そしたら病院送りで万事終了?礼子、あんたそんな温いんでいいの?こいつらに・・・こんな大それた事をしでかした慎治たちを簡単に、一思いに殺しちゃってそんなんでいいの?私はいやよ!礼子、こいつらの罪は・・・後でたっぷりと時間をかけて、たっぷりと痛めつけてやらなくちゃ許せないわよ!礼子、礼子はどうなのよ!?慎治たちを・・・この最低の連中をそんな簡単に罰してそれでOK、て済ましちゃう気なの?」
フウッ、フウーーーッ・・・ウウウーーーーー・・・全身を怒りに総毛立たせた猛獣のように小刻みに全身を震わせながら、慎治を壁に縫いつけた姿勢のままで礼子は暫く玲子のことを睨みつけていた。やがて大きく一回、深呼吸をすると口を開いた。「・・・そうね・・・玲子の言うのも一理あるわね・・・いいわ慎治、この場はここまでよ。慎治の命、ひとまず預けておくわ。だけど」すっと長く伸びた足を下ろしながら礼子は宣告する。「慎治、あんたのことは絶対許さないからね。後で・・・リンチよ!」
ドスッ!グエエッ・・・礼子は慎治を絶望に突き落とす言葉を吐き捨てると信次の鳩尾に掌底をめり込ませ、うずくまる慎治をその場に残してクルリと踵を返し、トイレから足音高く出ていってしまった。
礼子たち二人の殺気立ったやりとりにトイレの中はシーンと静まり返っていた。フウッ、残された玲子は小さく溜息をつくと慎治に近づいてきた。「・・・たく礼子ったら、やりっぱなしで行っちゃうんだから・・・」ブチブチとぼやきつつ玲子は慎治の右腕を掴んだ。「ヒッ!な、何するの!!!」「・・・ったくうざいわね、肩を入れてあげるだけよ、ほら静かにしなさい、動くとよけい痛いよ!」グッ・・・ゴギッ、ヒイイイッ!肩を外された時と変わらないほどの苦痛が慎治を襲った。その悲鳴に委細構わず玲子は慎治の左腕も嵌める。ゴリッ、ギャアアアッ!「ほら慎治、嵌ったわよ、肩動かしてごらん?」痛みが少し治まったところで玲子が声をかけた。その声に促され、慎治は恐る恐る肩を動かしてみる。動く・・・もう痛みも大分引いている。ああよかった・・・僕の腕、大丈夫みたいだ・・・「どうやら動くみたいね。」立ったまま見下ろす玲子を、慎治はトイレの床から見上げる。「あ、は、はい・・・動く、動きます・・・あ、あ・・・」「何?何か用?」「あ、はい・・・あ、あの・・・あり、がとう・・・」
「ハアアッ?ありがとう?慎治、あんた本物のバカア!?私が怒ってないとでも、慎治が肩外されて可哀想だから手当てしてやった、とでも思ってるの?」玲子は呆れて物も言えない、というように大きく首を振った。「慎治、言ったでしょ?礼子に負けず劣らず、私だって今、滅茶苦茶怒ってるのよ。今応急手当してあげたのは後で慎治をゆっくりと嬲り殺しにしてやるため、それだけ、そのためだけなのよ?それをまあ、ありがとう、だなんて・・・慎治、あんた本当にバカなのね!・・・まあいいわ。慎治がバカだろうと何だろうともうどうでもいいわ。一つだけ、幾らおバカな慎治でも分かるようにハッキリと言っておいてあげる。信次もしっかり聞いときなさい!慎治、あんたたち二人とも・・・放課後、リンチよ!」
3
リ、リンチ・・・リンチ・・・一体何を、何をされるんだろう・・・5時間目、恐怖にガタガタ震えていた慎治はふと、教室を一枚の紙片が回覧されていることを、それを読んだ女の子たちがクスクス笑いながら自分と信次の方を見ていることに気づいた。な、なんだ、なんなんだ・・・信次も同じことに気づいていた。そして5時間目終了後の休み時間、その紙片はたまたま信次の隣席である里美に回ってきていた。クスクス笑いながら顔をあげた里美の視線が信次とあう。「フフフどうしたの信次、なんか心配そうな顔しちゃって。ああそうか、これになんて書いてあるか知りたいのね。いいわよ、そんなに知りたいなら見せてあげる、ほら。」その紙片を見た信次の顔から見る見る血の気が引いていく。紙片にはこう書かれていた。
シンジをリンチにかける会 緊急開催のご案内
本日の昼休み、矢作慎治および川内信次の両名が女子トイレにて暴力を奮い、女子生徒に怪我を負わせる、という大事件を起こしました。
両名に対しては時間をかけゆっくり、じっくり、たっぷりと厳刑を加える方針ですが、取り急ぎ本日放課後、両名を第一陣のリンチにかけたいと思います。
皆様万障お繰り合わせの上、一人でも多くのご出席をお願いします。
シンジをリンチにかける会
代表 天城 礼子 霧島 玲子
幹事 神埼 富美代 萩 朝子
シンジをリンチにかける会!ほ、本当なんだ、本当に僕たち、リンチに掛けられるんだ・・・それも放課後、もうあと僅か一時間後に・・・あまりの恐怖に二人が呆然としている間に、あっという間に6時間目の授業は終わり放課後になってしまった。
ホームルームもそこそこに礼子が宣告する。「今日の連絡事項は以上です。何か他にありますか?無いようでしたら先ほどご連絡したとおり、これより矢作慎治、川内信次の両名をリンチに掛けたいと思います。皆さん第三体育館に移動してください。」
第三体育館、それは予備の講堂、ミニホールとして使用できるように小規模ではあるが舞台をしつらえ、防音設備を施した体育館だった。礼子さんたち、5時間目の休み時間にいない、と思ったらここを取りに行ってたんだ。
「ヒッヒイイイイッ・・・」「り、リンチだなんて、そんな・・・」半べそをかきながら腰が抜けてしまった二人をクラスメートが取り囲む。「さあ信次、行こうか!」信次の両側からは朝子と真弓が、慎治には富美代と和枝が無理やり引きずり起こすように立たせると、信次たちを取り囲むように殆どのクラスメートが一緒になって第三体育館に連行する。
「あ、あああ・・・」まるで死刑場に引き立てられる受刑者のように、信次たちは泣きながらフラフラと引き立てられていく。「信次、陽子たちをよくも怪我させたわね!」「もう、絶対許さないからね!」「フフフ、この人数で苛められるんだよ、どう、楽しみ?」「あ、私今日、何か弾けちゃいそう!」「全くよね!礼子たちのことだから、きっと凄いリンチ考えてるわよ?ウフフ、ねえ慎治、今日生きておうちに帰れるかしら?」
歩きながら女の子たちは口々に慎治たちを罵り、小突き回す。どの顔も妙に楽しそうな、ある種の祭りの高揚感に似たハイな笑顔になっていた。お、同じだ・・・慎治たちの嫌な記憶、白馬で、奥多摩で体育館に引き立てられ、たっぷりと責め苛まれた記憶が甦る。慎治たちを刑場に引き立てながら礼子たちが浮かべていた心底楽しそうな笑顔、それをクラスメート全員が浮かべていた。
「あ、あああ・・・おねがい、たすけて・・・」誰に言うともなく力なく慎治は呟いた。だが都合よく助けが現れるのは安っぽいハリウッドムービーだけだ、現実世界で助けなど現れるはずがない。あっという間に慎治たちは体育館に到着した。
ガラガラ、と和枝が体育館のドアを開けると中には既に玲子たちが一足先に来ていた。「あ、来たわね。朝子、中に入ったらしっかり鍵かけてね。ほかのドアはみんなロックしたから、後はそこだけ閉めればもう邪魔は入らないわ。」邪魔は入らない・・・その言葉がなにを意味するか、考える必要などない。朝子が入り口をしっかり閉めると、慎治たちは体育館の真ん中に引き立てられ正座させられた。
「さあ慎治、どうなるか分かってるわよね。お昼休みは時間切れ、て言うことで終わっちゃったけど、今度はそうは行かないわよ?覚悟はいいわね?」慎治を土下座させ、後頭部をグリグリと踏み躙りながら礼子がリンチ開始を宣告する。「そうよ慎治、私たちがあれだけ優しくしてあげたのに、慎治たちの大罪をあんな軽い罰で許してあげたのに、よくもまああれだけ堂々と恩を仇で返してくれたものね?勿論、只で済むとは思ってないわよね?」「あ、ああ、あああああ・・・お、お願い、許して・・・」ガッ!ヒッ!慎治の哀願に苛立ったかのように礼子は足を上げたかと思うと慎治の頭を蹴り付けるかのように踏み躙った。「許して?ふざけるんじゃないわよ!あんな軽い罰で許してやった私たちを裏切っておいていまさら許してですって?そんなのが通用するとでも思ってるの!?」
「礼子、ストップストップ、冷静に!こいつらにとって今、一番の救いは礼子や私が切れて一気に気絶させてくれることでしょ?落ち着いて、ゆっくり一回深呼吸して!・・・どう、少しは落ち着いた?」妙に静かな玲子の声に我を取り戻した礼子は言われるままにゆっくりと深呼吸をし、玲子にニッコリと微笑みかけた。「フウウ・・・そうよね、こいつらのその手に危うく乗せられるところだったわ。折角5時間目、6時間目とリンチのプランをじっくり練ってたんだもんね。一気に潰しちゃ勿体無さ過ぎるわ。慎治、時間はたっぷりあるわ。じっくりと苛めてあげるからね。」礼子の声も冷静さを取り戻した。礼子の冷静な声は先ほどの怒声の数倍も恐ろしい、慎治たちの背筋をゾクリと震え上がらせる、破滅へと誘うセイレーンの歌声のような魔力があった。
「そう、折角プランを練って場所取って、みんなも忙しい時間を割いてリンチに駆けつけてくれたんだからね。たっぷりと泣き叫ばせてやらなくちゃ元が取れないわ・・・さあ、そろそろリンチ、開始しましょうか。信次、二人とも覚悟するのね。ゆっくりと苛めてやるからね!」
あ、あああ・・・・・恐怖に半ば腰が抜けている二人を裸にさせ並ばせて正座させると、玲子はクイッと二人の顎を上げ、自分を仰ぎ見させた。「二人とも、この姿勢絶対に崩しちゃ駄目よ。崩したらもっと酷いリンチに会わせるからね!」刑の開始を宣告すると、玲子は信次たちの目の前でカチャカチャとわざと音を立てながらベルトのバックルを外し、シュルッと細いウエストから引き抜いた。ヒッヒイイイイイッ・・・玲子の手の中でベルトが、服飾品が一本の鞭に変化する。「分かるわね、どういう目に会うか。でも安心しなさい、まずは二人とも、一発ずつだけよ。一発ずつしか鞭打たないわ、どう、安心した?」これまで散々苛め抜かれてきた信次たちが安心などするわけがない、だが一発だけ、という玲子の思いがけない言葉に信次は思わず反射的に微かにほっとしたような顔色を浮かべた。
「このブタ!鞭が一発だけ、て聞いただけでほっとするなんてね。この最低男!」ペッ!玲子は自分を見上げる信次の顔に思いっきり唾を吐き掛けた。「慎治、慎治も今、ほっとしていたでしょ?バーカ!」ペッ!玲子は返す刀で慎治にも唾を吐き掛ける。「さあ、行くよ!」手にしたベルトを翻らせると玲子は袈裟切りに振り下ろすように信次を一撃し、そのままバックハンドで慎治も打ち据える。
「ヒッ!」「アウッ!」信次たちの悲鳴が上がるのを冷たく見下ろすと玲子はゆっくりと二人の前から離れた。間を置かずに今度は礼子が二人の前に立つ。「どう二人とも、何をされるのか分かったかしら?簡単なセレモニーよ、本格的なリンチの前のほんのご挨拶、ていうところ。これからたっぷりとリンチしてあげるからね、まずは手付よ!」ゆっくりとベルトをウエストから引き抜くと、礼子も二人に唾を吐き掛け、一撃ずつ鞭打つと二人の前を離れていく。続いて朝子が、そして富美代が同じように二人の前でベルトを引き抜き、唾を、鞭を一撃ずつ加えていく。
な、なんだ、なんなんだ・・・富美代の次に和枝が目の前に立った時、漸く慎治は礼子たちの企みを理解した。
「フフフ慎治、分かったみたいね。でも私だけじゃないのよ。フフ、フフフフフ、ペッ!」和枝は笑いながら二人に唾を吐き掛けるとベルトを大きく振りかぶった。「礼子たちほど上手じゃないけどね、私のファースト鞭、逝くよ!」ピシッ!パシッ!慎治たちの肩のあたりを鞭打つと和枝は笑いながら場所を譲る。そして次に真弓が二人の前でベルトを引き抜いた。「そうよ信次、いい顔色に怯えてきたじゃない、ご名答。次は誰が信次たちのことを鞭打つのかしら?みんなよみんな、全員で鞭打ってあげるわ!どう、楽しいでしょ、アハハ、アハハハハッ!」笑いながら真弓も唾を吐き掛け、一発ずつ鞭を振るうと場を空ける。
クラスメート全員が一人一人、慎治たちの目の前でベルトを引き抜き、唾を吐き掛けて一鞭ずつ打ち据えていく。慎治たちの当惑は直ぐに屈辱と恐怖に変わっていった。フフフ、慎治、怯えてるわね。精々怖がりなさい。今日のリンチだけじゃないわよ、これから先、明日以降の自分たちがどうなるか、たっぷりと怯えるがいいわ。礼子たちの狙いどおり、このセレモニーは慎治たちの精神を強烈に蝕んでいた。流石にいくら苛めを蔓延させる、と言ってもクラスメート全員が鞭を購入し慎治たちを苛める、等ということはまず有り得ない。だがベルトなら話は別だ。別に責め具としてではなく制服の一部として全員が毎日身につけている、そのベルトで鞭打たれる。痛さだけの問題ではない。むしろ痛さだけで言えばたかがベルト、本物の一本鞭で数え切れないほど鞭打たれている慎治たちにとっては痛いとはいえ、十分に耐えられるレベルだ。だがベルトで鞭打たれるのは本物の鞭以上の屈辱感を二人に刻み込んでいた。
慎治たちの目の前で一人、また一人とベルトをウエストから引き抜く。その瞬間、ベルトが意思を持たない制服の一部から残酷な責め具へと変化していく。そして同時にクラスメートが、今まで苛められたとは言えクラスメートであった女の子が礼子たちと同じ、残酷な拷問官へと変化していく。順番を待つ他のクラスメートも全員がウエストに鞭を、慎治たちを打ち据え泣き喚かせる責め具を締めている。隠すこともなく、誰に咎められることもなく。
それは慎治たち以外の誰にとっても単なるベルト、単なる制服の一部に過ぎない。慎治たち以外の男子生徒は誰も、女の子たちが締めているベルトを全く意識にも止めずに見ているだろう。だが慎治たちにとっては全てのクラスメートが常に鞭を携えているのと同じ、もし慎治たちが何か少しでも気に入らないことをすれば、いつでも鞭打てる、いつでも跪かせ、苦痛と屈辱にのた打ち回らせることができるのよ、と言う事を一人、また一人と宣言していくようだった。明日も明後日も女の子たちはみんな、制服を着てベルトを締めてくるだろう。そしてその女の子たちの誰に対しても二度と、対等な立場にはなり得ない。例え相手が普通に話しかけてきても、慎治たちにとっては剥き出しの鞭を構えられているのと同じなのだから、常に怯え、卑屈に追従と愛想笑いを浮かべ、必死でご機嫌取りをするしかない。玲子たちだけではなく、クラスメート全員との間に鞭を持つ支配者と打ち据えられる隷属者の関係が自然に、だが確固として確立されていくのを誰よりも、慎治たち自身が最も深く明確に逃れようもなく認識していた。
玲子は信次たちの怯えと屈辱をゆっくりと楽しんでいた。そうよ、その顔よ。フフフ、信次、あなた私と話す時、私が何もしなくても私のベルトをチラチラと見ているわよね。殆ど無意識にだろうけど、私の手がベルトに伸びやしないかっていつも怯えているのよ。勿論慎治も同じ、礼子やフミちゃんの前ではいつも、ベルトで打たれやしないか、唾を吐き掛けられるんじゃないか、ていつも怯えているわ。信次、私信次のその怯えた顔、大好き。だからしょっちゅうベルトで鞭打ったり唾を吐き掛けてあげてトラウマをたっぷりと植付けてきてあげたのよ。フフフ、その刷り込みがこんなに効いてくるとはね。信次、あなた私たち女の子の制服姿にもう一生、消し去りようのないトラウマを植え付けられているのよ。いい気味ね。
玲子たちが見守る中、次々とクラスメートは信次たちの前を通り過ぎていく。そして残るは二人、陽子と有希子だけになっていた。「信次、なによその顔!もうみんなの唾でベトベトじゃない!あらあら顔中から糸引いて唾垂らしちゃって・・・いい気味。少しは思い知った?」涙とクラスメートの唾に霞んだ目で見上げると、勝ち誇ったように笑いながら陽子が見下ろしていた。「どう、なんか言うことないの?」「あ、あああ・・・ご、ごめんなさい・・・ごめんなさい・・・だから、お願い、許して・・・」唾をボタボタと顔から床に垂らしながら、半ば反射的に土下座する信次の顎を陽子は白い上履きの爪先でクイッと小突きあげた。「許して?何馬鹿言ってるのよ、ダメに決まってるでしょ!?覚悟しなさいよ、私もこのリンチ、燃えてるんだからね。トイレの床に突き転ばされた恨み、きっちりと晴らさせてもらうわよ!?」陽子はクチュクチュと口中一杯に唾を溜めると、信次たちに思いっきり吐き掛け、そしてベルトを引き抜くと力任せに肩の辺りを打ち据えた。「ヒイッ・・・」「じゃあまた・・・あとでね!」
そして取りは有希子だった。信次の前に立った有希子は冷笑を浮かべながら慎治を見下ろしていた。不思議ね、いつもは信次が苛められるのを見てると、少しは可哀想、ていう気になるのに今日はそんな気、全く起きないわね。ま、当然か、トイレで転ばされて怪我させられて、それでも許してやろうなんて考える子、いるわけないよね!みんなに倣い、有希子もゆっくりとベルトを引き抜いた。「信次・・・私で二十人目、最後ね。じゃあ最後に一つお願いして貰おうかしら。どうか僕の汚い顔に唾を吐き掛けてください、そしてどうかみんなで腐りきった人間のクズである僕を鞭打って罰してください、てね。」「あ、あうううう、そ、そんな、そんなこと・・・」唾まみれの顔に新たな涙を流しながら咽ぶ信次に有希子は冷たく言い放った。「そう、言いたくないのね、私の言うことは聞けない、て言うのね?」グッとベルトを握る右手に力を込める有希子の仕草に信次は震え上がって叫んだ。「い、い、いえ、そ、そんな!逆らうだなんてそしな!お、おねがい、おねがいですうううううっ!ど、どうか、どうか唾を、唾を吐き掛けて下さいいい、そしてどうか、どうかぼ、僕を鞭打って罰してくださいいい、お、お願い、おねがいですううううう!!!」信次の必死の哀願を有希子は鼻でせせら笑った。馬鹿ね信次、哀願しようが何しようが結果は同じ、みんなに死ぬほど鞭打たれるのは変わらないんだからね。でもまあいいわ。ご希望には応えてあげるわよ。「そう、そんなに私の唾が欲しいの?そんなに唾が欲しいなら、望み通り吐き掛けてやるわよ!この・・・ゴキブリ!ブタ!ぺっ!」思いっきり唾を吐き掛けると手にしたベルトを大きく振りかぶり、真っ直ぐに振り下ろした。ピシッ!ヒイッ!「まずはご挨拶。あとでたっぷりとまた鞭打ってあげるからね。」
4
漸く全員が慎治たちに唾を吐き掛け、ベルトで打ち据え終わった。だがこれで終わったのではない。今日の責めは、リンチはこれからが本番なのだ。精神をグチャグチャに破壊され、屈辱に全身を責め苛まれた今から漸く、肉体の苦痛が始まる。絶望と恐怖におびえた目で信次は視線を彷徨わせた。前後左右、どこを見てもクラスメートの女の子がいる。みんな手にはベルトを、今さっき自分を打ち据えたベルトを握り締めて今や遅しとリンチの開始を待っている。ああ、あああああ・・・な、なにをされるんだろう・・・みんなに打ち据えられるんだよな・・・でもどうやって?慎治の脳裏に潰れた大学のグラウンドで玲子たち四人掛りで鞭打たれた苦い記憶が蘇る。だけど・・・だけどいくらなんでも、全員同時に鞭なんてさすがに無理だよな・・・精々二、三人同時が限界だよな、だったらなんとか大丈夫かな・・・でも、でも・・・!慎治は大きく息を吐いた。礼子さんたちがそんなに甘いわけないよ。きっと、きっと何か凄い、酷いリンチを考えているに決まってるんだ!でも、でもいったいどうやって・・・慎治たちの頭の中で恐怖が無限に増殖していく。その時、パシーン!と玲子が手にしたベルトを鳴らした。
「ハーイみんな!信次たちに挨拶は済んだわね?じゃあいよいよ・・・リンチ開始と逝くわよ!」「待ってましたあっ!」「うん、やろうやろう!今の一発ずつなんて全然物足りないよ!」「ほんとほんと!もっと思いっ切り引っ叩きたーいっ!」一斉に上がる歓声に苦笑しながら、礼子がパンパンッと手を叩いた。「ハイハイ、みんな安心してね、心配しなくても・・・思う存分引っ叩かせてあげるわよ!じゃあみんな、さっきメモに書いといたように整列してね!」礼子の声を合図にまず玲子、富美代、朝子が歩き出した。玲子は信次を四つん這いのまま連れて行き、慎治だけが取り残される。そして四人で体育館の横幅一杯を使い、対角線10メートルの、やや横長のダイアモンドを形作った。すると他の女の子たちも一斉に動き始め、玲子たち四人の間に互い違いで2-3メートル程度の間隔をおいて並び始めた。向かい合う女の子通しの幅は1-2メートルある。完成したそのフォームはやや横長の楕円、互い違いに二重の輪に並んだ女の子通しの間にチューブのように通路がある楕円形だった。
全員が位置に付き、間隔を調整し終えたのを確認すると玲子は信次の顎に二つ折りにしたベルトを引っ掛けて持ち上げた。「信次、もう自分がどうリンチされるのか、大体は分かったでしょ?そう、信次には私たちの輪の中をゆっくりと四つん這いで行進して貰うわよ。そして歩きながらみんなの鞭を受けるのよ!」「ヒッヒイイイイッ!そ、そんな、みんなに、みんなに鞭打たれるだなんて!!!」
反対側では慎治も礼子から刑を宣告されていた。「慎治、玲子の説明は聞こえたわね?二人ともスタートしたら時計回りに行進するのよ。ああそれとね、止まりたければ勝手に止まりなさい。どこで潰れようと慎治の勝手よ。但し、私たちの許しも無しに止まったりしたら、そこの地点でみんなから集中攻撃されることになるからそのつもりでね。」「しゅ、集中・・・攻撃だなんてそんな・・・」「フフフ、痛そうでしょ?集中攻撃だなんて真っ平よね?だったら精々しっかり行進することね。」礼子は笑いながらパシンッとベルトを打ち鳴らした。「玲子、そっちはOK?みんな、用意はいいかな?しっかりベルトは構えましたかあ?」「ハーイ、いつでもOKよ!」「早く早く!早く慎治のこと、引っ叩きたーい!」パシンッ、パーンッ!そこかしこでベルトを打ち鳴らす音が体育館に響く。「や、やだ、やめて・・・」「ひっひどい、そんな・・・」慎治たちのか細い哀願には一瞥もくれずに礼子はベルトを高く振り上げた。「さあ慎治、逝くわよ・・・リンチ・・・開始よ!」
ビュオッという音と共に礼子のベルトが振り下ろされた。バシーンッ!ヒイッ!礼子は慎治の背中に立て続けにベルトを振り下ろす。ビシッ!パシッ!「ヒッヒイッ!い、痛いいい!」あ、あああ、に、逃げなくちゃ、兎に角逃げなくちゃ、礼子さんのベルトの届かないところに・・・
信次も玲子のベルトに追い立てられ、必死で這い始めた。い、痛い!痛い!痛い!い、いやだ、いやだあああ!必死で信次が這いずるにつれ、最初は肩の辺りに炸裂していたベルトが徐々に背中の中心に移り、次いで尻にと移動していく。ハアハア、もう少し、もう少しで逃げられる・・・痛いっ!名残を惜しむかのように横にスイングされたベルトが信次の太腿の裏を打ち据える。思わず反射的に右手でそこを抑えてしまい、バランスを崩しながらも何とか必死で前に進んだ。ハアハアハア、こ、これで玲子さんの鞭からは何とか逃げ、パシッ!ヒイッ!逃げおおせたと思った瞬間、再び肩にベルトが食い込んだ。反射的に顔を上げた信次が見たものは、信次を打ち据えたベルトを再び振り上げ、今まさに二撃目を振り下ろそうとしている有希子の姿だった。
「来たわね信次!私をトイレで突き飛ばした罪・・・今こそ思い知らせてあげる!」バシッ、ビシッ、パンッ・・・力任せに有希子が振り回すベルトが信次の背中に次々と炸裂する。鞭は初めての有希子だが長さもそんなにないベルトは振り回しやすく、力任せに振り回すだけで十分に鞭として機能する。「い、いたっいたいたいたいいいいっ!や、やめてお願い許してえええ!!」信次は必死で有希子のベルトの制空圏を通り過ぎたが、息つく間もなく三人目のベルトが肩に降り注ぐ。「いいだ、いだいよおおおっ、やめて、もう・・・ひいいいいっ、ごめんなさいごめんなさいいいいっ!!!」慎治も間断なく鞭打たれながら必死で這い続けていた。礼子さん、陽子さん・・・三人、四人と鞭打たれながらも這い続けた慎治の悲鳴が急に甲高くなった。
「ヒッ、ヒギャァッ!」バッシーンッ!背中を襲うベルトの音が急に凶悪さを増し、背中に一段と酷い激痛を刻み込んだ。「い、いたあああああ・・・」仰け反るように仰ぎ見た慎治が見たものは、笑いながら高々とベルトを振りかざす富美代の姿だった。
「アハハハハッ!どう慎治、私のベルトの味は!みんなのベルトよりちょっとは効いてるかしら?それ!」ビシーーーンッ!富美代が思いっきり振り下ろしたベルトが慎治の背中に深々と食い込んだ。「ヒギイイイッ!」「アギャアアアアアッ!」殆ど同じタイミングで信次も金切り声を上げていた。「ア、アウッ、や、やべ、ギャヒイイイイッ!」信次に悲鳴を上げさせていたのは朝子のベルトだった。「キャハハハハッ!信次、痛い?みんなの時よりいい悲鳴じゃない!そんなに私の鞭痛いの?プロの腕ってやつかしら?じゃあたっぷりと手練の技を見せてあげるね!」
富美代も朝子もいつもの一本鞭ではなくベルト、しかもそんなに数多くは鞭打てない、とあって遠慮会釈なく全力を解放して二人を打ち据えた。半歩下げた右足の蹴りを効かせながら十二分に腰を入れ、体重をしっかりとベルトに乗せながら打ち下ろす。しかも肩、肘、と順に回転させ最大限しなりを効かせてスピードを得たベルトが慎治たちの肉体に当たる最後の瞬間、ピッと鋭く手首を返して威力を倍増させる。何百発何千発と鞭を振るって体得した、受刑者により多くの苦痛を与えるテクニックを富美代も朝子も情け容赦なく振るっていた。やっとの思いで二人の前を慎治たちは通り過ぎた。
だが決して休みなど与えられない。富美代、朝子のベルトよりは多少痛くない、とはいえ他のクラスメートのベルトも十二分に痛い。そして・・・更に五人進むと礼子たちが待ち構えていた。「信次、よく来たわね、中間ポイントよ、ちゃんとハンコを押してあげるわね、ソレッ!」「慎治、私でちょうど半分よ、良かったわね、おめでとう!」ビシーッッッ、バシーッッッ・・・「グギイイイイッ!!!」「イヤアアアアアッッッ!」
富美代や朝子のベルトをも上回る激痛に二人とも思わず背中を仰け反らせ、その場に止まってしまった。反射的な行動とは言え、最悪の選択だった。「あら信次、そんなに私の鞭が欲しいの?いいわよ、遠慮はいらないわ、だって私と信次の仲だものね!」「ああそうなの慎治、やっぱりこの位痛くないと慎治には物足りないのね。いいわよ、お望みどおり引っ叩いてあげる!」バシッ、ビシッ、パウッ、パーンッ!!!ギャアアアッ!イ、イタイイイイイッ!ア、アベ、アベデエエエッ!ユルジデエエエエエッ!!!余りの激痛に涙と涎を垂れ流し、何を言っているのかすら分からない悲鳴をあげつつ慎治たちは何とかこの場を逃れようと必死で這いずった。漸く礼子たちの制空圏から脱した慎治たちだが、次のベルトを受けながら暗い閃きに思わず絶望してしまった。
礼子さんのところは過ぎたけど、こ、この先にはフミちゃん・・・あ、あと五人、あと五人先にはあ、朝子さんが、朝子さんが待っている・・・残酷な配置だった。礼子たちは熟練した鞭の使い手四人のポイントを散りばめることで、慎治たちにあと何人でまた激痛ポイント、と怯えさせ、精神的にも苦しめることを狙っていた。精神面だけではない。礼子たち四人が連続して並んでしまうと激痛のため慎治たちの痛覚がマヒしてしまい、痛みがフレッシュでなくなってしまうかもしれない。他のクラスメートの鞭が十分な苦痛を与えられなくなってしまうかも知れない。位置を分散したのはそれに対する配慮も兼ねていた。鞭打ち初体験のクラスメートを前後に挟むことで、自分たちの強烈な鞭をより新鮮な激痛として慎治たちに味合わせる事ができる。更に四人が散らばることで前後のクラスメートが礼子たちのフォームを真似しやすくなる、少なくとも礼子たちの鞭音につられ、遠慮なく思いっきり引っ叩けるようにすることも狙っていた。礼子たちの配慮は狙い通り、何重もの効果を上げて慎治たちの苦痛をいや増していた。
「アウッ、アウウウウッ・・・」「ヒッ、ヒック、ウエッウエエエエッ・・・」苦痛と恐怖と屈辱を際限なく味合わされながら、慎治たちは必死で這いずり続けた。そして漸くゴール地点、一周して礼子たちの下に辿り着くと二人とも、その場に突っ伏してしまった。200発近く打たれたであろうか、幅のあるベルトだから蚯蚓腫れになったり皮膚が切れたりはしていなかったが、二人の肩から尻にかけては真っ赤に腫れ上がり、所々は内出血のため青痣になっていた。
「フフフ慎治、いいザマね。少しは懲りたかしら?」「あ、あああ、ご、めんなさい・・・もう、許して、お、願い・・・」礼子に頭を踏み躙られながら、慎治は呻き声で哀願した。
「信次、少しは反省した?どうなの、少しは自分の罪深さを思い知ったかしら?」玲子も信次の頬を踏み躙りながら尋ねていた。「あ、あううう・・・は、はい・・・は、はんせい、反省しました・・・だから、どうか・・・許して・・・くだ、さい・・・」消え入りそうな声で呟く信次を玲子は満足そうに、だが冷ややかな目で見下ろしていた。「そう、信次みたいなカスでも流石にこれだけ鞭打たれれば少しは反省、らしきものを言えるのね。だけど」玲子は信次を踏み付ける足にグッと力を込めた。「まだまだ足りないわ。この程度で許してあげるわけにはいかないわ!」「えっえええええっ、そ、そんな!!!」礼子も慎治にリンチの続行を宣告していた。
「許す?ダメよ慎治、まだまだ足りない、慎治のことはもっともっと、いっぱい懲らしめてあげるわ。さあ、少しは休ませてあげたのよ、感謝しなさい!リンチ、再開よ!」礼子はパンッとベルトを打ち鳴らすと同時に足をどけた。「あ、あひいいいいっ!そ、そんな、そんなあああああっ!」「あら慎治、別に動きたくなければいいのよ、そのままそこに蹲ってなさい!そうやって・・・私の鞭をずっと受け続けなさい!」ビュオッ・・・ブオッ!礼子たちのベルトがリンチ再開を待ちかねたかのように唸り始めた。
「あ、ああ、あああああ・・・・・」「は、はひっはひっひっひっひっ・・・」二周目が終わった時、慎治たちはもはや気絶寸前だった。数え切れないほど打ち据えられた背中は赤を通り過ぎ青黒くなっていた。肉体以上に精神も崩壊寸前だった。動く気力もなく倒れ伏した二人をクラスメートが取り囲んだ。「どうみんな、鞭は堪能した?」礼子の声が響いた。「もうちょっと懲らしめたい気もするけど、流石に今日はこれまでね。もう多分、痛覚殆どマヒしちゃってるから、これ以上苛めても余り面白くないわ。と、言うことで今日はこれまで、解散にしよう!お疲れ様!」礼子の声を合図に、心地よい疲労を楽しみながらクラスメートがゾロゾロと帰っていく。後には礼子たち四人と慎治たちだけが残っていた。
「信次、正座。」玲子が静かに命令した。玲子の命令に突き動かされ、最後の気力を振り絞るように二人はのろのろと正座する。「どうかしら、少しは骨身に沁みた?反省したかしら?」「・・・は、はい・・・はん、せい・・・しまし、た・・・」消え入るような声で呟く信次を満足げに見下ろしながら玲子は冷笑した。「そう、それは良かった。だけどね、もう遅いのよ。信次、あんたたちは超えてはならない一線を飛び越えちゃったのよ。いくら反省しても、もう絶対に許してあげない。信次、あんたたちにはこれから、本物の苛め、ていうものを教えてあげるわ。私たちの全力で、本気で苛め尽くしてあげるからね・・・辛いわよ、覚悟しておくことね。」
ほ、本物の苛め・・・そ、そんな・・・い、一体なにをする気なの?ま、まさか、これから一本鞭で・・・
恐怖に引きつる二人に、後を引き取った礼子が告げる。「二人とも安心していいわ。今日これから鞭を追加する、なんてことはしないから。今日はもう、何もする気はないわ。ううん、それどころかこの週末は解放してあげる。ゆっくりと休んでいいわよ。」な、なにもしない?い、いやそれより、週末休ませてくれる?い、一体なぜ、どうして???予想外の礼子の言葉に、慎治たちは安堵よりも戸惑いと不安に包まれる。その困惑の表情を見て玲子が冷笑を浮かべた。
「信次、不安?怖い?自分がどうされるのか知りたい?ダメ、教えてあげないわよ。」礼子の美貌にも残酷な冷笑が浮かぶ。
「まあこれだけは教えといてあげるわ。玲子が本物の苛め、て言ったでしょ?念のため言っとくけど、今までみたいに単純に鞭で打ちのめすのが本物の苛めじゃないからね。鞭100発が200発になる、なんていう単純な責めを考えられたら困るわよ。ウフフフフ、血塗れになるまで鞭打たれたのが軽いお遊びに思えるような目に会わせてあげるわ。フフフ、週明け、楽しみにしていなさい、どういう目に会わされるのか・・・精々ゆっくりと想像してみることね。」「そ、そんな・・・な、なにを、なにをされるんですか・・・」「ど、どうするの、ぼくたちを・・・どうするつもりなの・・・おしえて・・・」涙を流しながら必死で尋ねる二人に冷笑を投げかけながら礼子たちは解散を宣言した。「それでは良い週末を!」「また来週!」
1?
シンジをリンチにかける会緊急開催のご案内本日の昼休み、矢作慎治および川内信次の両名が女子トイレにて暴力を奮い、女子生徒に怪我を負わせる、という大事件を起こしました。両名に対しては時間をかけゆっくり、じっくり、たっぷりと厳刑を加える方針ですが、取り急ぎ本日放課後、両名を第一陣のリンチにかけたいと思います。皆様万障お繰り合わせの上、一人でも多くのご出席をお願いします。シンジをリンチにかける会代表天城礼子霧島玲子幹事神埼富美代萩朝子
シンジをリンチにかける会!ほ、本当なんだ、本当に僕たち、リンチに掛けられるんだ・・・それも放課後、もうあと僅か一時間後に・・・あまりの恐怖に二人が呆然としている間に、あっという間に6時間目の授業は終わり放課後になってしまった。
ホームルームもそこそこに礼子が宣告する。「今日の連絡事項は以上です。何か他にありますか?無いようでしたら先ほどご連絡したとおり、これより矢作慎治、川内信次の両名をリンチに掛けたいと思います。皆さん第三体育館に移動してください。」
第三体育館、それは予備の講堂、ミニホールとして使用できるように小規模ではあるが舞台をしつらえ、防音設備を施した体育館だった。礼子さんたち、5時間目の休み時間にいない、と思ったらここを取りに行ってたんだ。
「ヒッヒイイイイッ・・・」「り、リンチだなんて、そんな・・・」半べそをかきながら腰が抜けてしまった二人をクラスメートが取り囲む。「さあ信次、行こうか!」信次の両側からは朝子と真弓が、慎治には富美代と和枝が無理やり引きずり起こすように立たせると、信次たちを取り囲むように殆どのクラスメートが一緒になって第三体育館に連行する。
「あ、あああ・・・」まるで死刑場に引き立てられる受刑者のように、信次たちは泣きながらフラフラと引き立てられていく。「信次、陽子たちをよくも怪我させたわね!」「もう、絶対許さないからね!」「フフフ、この人数で苛められるんだよ、どう、楽しみ?」「あ、私今日、何か弾けちゃいそう!」「全くよね!礼子たちのことだから、きっと凄いリンチ考えてるわよ?ウフフ、ねえ慎治、今日生きておうちに帰れるかしら?」
歩きながら女の子たちは口々に慎治たちを罵り、小突き回す。どの顔も妙に楽しそうな、ある種の祭りの高揚感に似たハイな笑顔になっていた。お、同じだ・・・慎治たちの嫌な記憶、白馬で、奥多摩で体育館に引き立てられ、たっぷりと責め苛まれた記憶が甦る。慎治たちを刑場に引き立てながら礼子たちが浮かべていた心底楽しそうな笑顔、それをクラスメート全員が浮かべていた。
「あ、あああ・・・おねがい、たすけて・・・」誰に言うともなく力なく慎治は呟いた。だが都合よく助けが現れるのは安っぽいハリウッドムービーだけだ、現実世界で助けなど現れるはずがない。あっという間に慎治たちは体育館に到着した。
ガラガラ、と和枝が体育館のドアを開けると中には既に玲子たちが一足先に来ていた。「あ、来たわね。朝子、中に入ったらしっかり鍵かけてね。ほかのドアはみんなロックしたから、後はそこだけ閉めればもう邪魔は入らないわ。」邪魔は入らない・・・その言葉がなにを意味するか、考える必要などない。朝子が入り口をしっかり閉めると、慎治たちは体育館の真ん中に引き立てられ正座させられた。
「さあ慎治、どうなるか分かってるわよね。お昼休みは時間切れ、て言うことで終わっちゃったけど、今度はそうは行かないわよ?覚悟はいいわね?」慎治を土下座させ、後頭部をグリグリと踏み躙りながら礼子がリンチ開始を宣告する。「そうよ慎治、私たちがあれだけ優しくしてあげたのに、慎治たちの大罪をあんな軽い罰で許してあげたのに、よくもまああれだけ堂々と恩を仇で返してくれたものね?勿論、只で済むとは思ってないわよね?」「あ、ああ、あああああ・・・お、お願い、許して・・・」ガッ!ヒッ!慎治の哀願に苛立ったかのように礼子は足を上げたかと思うと慎治の頭を蹴り付けるかのように踏み躙った。「許して?ふざけるんじゃないわよ!あんな軽い罰で許してやった私たちを裏切っておいていまさら許してですって?そんなのが通用するとでも思ってるの!?」
「礼子、ストップストップ、冷静に!こいつらにとって今、一番の救いは礼子や私が切れて一気に気絶させてくれることでしょ?落ち着いて、ゆっくり一回深呼吸して!・・・どう、少しは落ち着いた?」妙に静かな玲子の声に我を取り戻した礼子は言われるままにゆっくりと深呼吸をし、玲子にニッコリと微笑みかけた。「フウウ・・・そうよね、こいつらのその手に危うく乗せられるところだったわ。折角5時間目、6時間目とリンチのプランをじっくり練ってたんだもんね。一気に潰しちゃ勿体無さ過ぎるわ。慎治、時間はたっぷりあるわ。じっくりと苛めてあげるからね。」礼子の声も冷静さを取り戻した。礼子の冷静な声は先ほどの怒声の数倍も恐ろしい、慎治たちの背筋をゾクリと震え上がらせる、破滅へと誘うセイレーンの歌声のような魔力があった。
「そう、折角プランを練って場所取って、みんなも忙しい時間を割いてリンチに駆けつけてくれたんだからね。たっぷりと泣き叫ばせてやらなくちゃ元が取れないわ・・・さあ、そろそろリンチ、開始しましょうか。信次、二人とも覚悟するのね。ゆっくりと苛めてやるからね!」
あ、あああ・・・・・恐怖に半ば腰が抜けている二人を裸にさせ並ばせて正座させると、玲子はクイッと二人の顎を上げ、自分を仰ぎ見させた。「二人とも、この姿勢絶対に崩しちゃ駄目よ。崩したらもっと酷いリンチに会わせるからね!」刑の開始を宣告すると、玲子は信次たちの目の前でカチャカチャとわざと音を立てながらベルトのバックルを外し、シュルッと細いウエストから引き抜いた。ヒッヒイイイイイッ・・・玲子の手の中でベルトが、服飾品が一本の鞭に変化する。「分かるわね、どういう目に会うか。でも安心しなさい、まずは二人とも、一発ずつだけよ。一発ずつしか鞭打たないわ、どう、安心した?」これまで散々苛め抜かれてきた信次たちが安心などするわけがない、だが一発だけ、という玲子の思いがけない言葉に信次は思わず反射的に微かにほっとしたような顔色を浮かべた。
「このブタ!鞭が一発だけ、て聞いただけでほっとするなんてね。この最低男!」ペッ!玲子は自分を見上げる信次の顔に思いっきり唾を吐き掛けた。「慎治、慎治も今、ほっとしていたでしょ?バーカ!」ペッ!玲子は返す刀で慎治にも唾を吐き掛ける。「さあ、行くよ!」手にしたベルトを翻らせると玲子は袈裟切りに振り下ろすように信次を一撃し、そのままバックハンドで慎治も打ち据える。
「ヒッ!」「アウッ!」信次たちの悲鳴が上がるのを冷たく見下ろすと玲子はゆっくりと二人の前から離れた。間を置かずに今度は礼子が二人の前に立つ。「どう二人とも、何をされるのか分かったかしら?簡単なセレモニーよ、本格的なリンチの前のほんのご挨拶、ていうところ。これからたっぷりとリンチしてあげるからね、まずは手付よ!」ゆっくりとベルトをウエストから引き抜くと、礼子も二人に唾を吐き掛け、一撃ずつ鞭打つと二人の前を離れていく。続いて朝子が、そして富美代が同じように二人の前でベルトを引き抜き、唾を、鞭を一撃ずつ加えていく。
な、なんだ、なんなんだ・・・富美代の次に和枝が目の前に立った時、漸く慎治は礼子たちの企みを理解した。
「フフフ慎治、分かったみたいね。でも私だけじゃないのよ。フフ、フフフフフ、ペッ!」和枝は笑いながら二人に唾を吐き掛けるとベルトを大きく振りかぶった。「礼子たちほど上手じゃないけどね、私のファースト鞭、逝くよ!」ピシッ!パシッ!慎治たちの肩のあたりを鞭打つと和枝は笑いながら場所を譲る。そして次に真弓が二人の前でベルトを引き抜いた。「そうよ信次、いい顔色に怯えてきたじゃない、ご名答。次は誰が信次たちのことを鞭打つのかしら?みんなよみんな、全員で鞭打ってあげるわ!どう、楽しいでしょ、アハハ、アハハハハッ!」笑いながら真弓も唾を吐き掛け、一発ずつ鞭を振るうと場を空ける。
クラスメート全員が一人一人、慎治たちの目の前でベルトを引き抜き、唾を吐き掛けて一鞭ずつ打ち据えていく。慎治たちの当惑は直ぐに屈辱と恐怖に変わっていった。フフフ、慎治、怯えてるわね。精々怖がりなさい。今日のリンチだけじゃないわよ、これから先、明日以降の自分たちがどうなるか、たっぷりと怯えるがいいわ。礼子たちの狙いどおり、このセレモニーは慎治たちの精神を強烈に蝕んでいた。流石にいくら苛めを蔓延させる、と言ってもクラスメート全員が鞭を購入し慎治たちを苛める、等ということはまず有り得ない。だがベルトなら話は別だ。別に責め具としてではなく制服の一部として全員が毎日身につけている、そのベルトで鞭打たれる。痛さだけの問題ではない。むしろ痛さだけで言えばたかがベルト、本物の一本鞭で数え切れないほど鞭打たれている慎治たちにとっては痛いとはいえ、十分に耐えられるレベルだ。だがベルトで鞭打たれるのは本物の鞭以上の屈辱感を二人に刻み込んでいた。
慎治たちの目の前で一人、また一人とベルトをウエストから引き抜く。その瞬間、ベルトが意思を持たない制服の一部から残酷な責め具へと変化していく。そして同時にクラスメートが、今まで苛められたとは言えクラスメートであった女の子が礼子たちと同じ、残酷な拷問官へと変化していく。順番を待つ他のクラスメートも全員がウエストに鞭を、慎治たちを打ち据え泣き喚かせる責め具を締めている。隠すこともなく、誰に咎められることもなく。
それは慎治たち以外の誰にとっても単なるベルト、単なる制服の一部に過ぎない。慎治たち以外の男子生徒は誰も、女の子たちが締めているベルトを全く意識にも止めずに見ているだろう。だが慎治たちにとっては全てのクラスメートが常に鞭を携えているのと同じ、もし慎治たちが何か少しでも気に入らないことをすれば、いつでも鞭打てる、いつでも跪かせ、苦痛と屈辱にのた打ち回らせることができるのよ、と言う事を一人、また一人と宣言していくようだった。明日も明後日も女の子たちはみんな、制服を着てベルトを締めてくるだろう。そしてその女の子たちの誰に対しても二度と、対等な立場にはなり得ない。例え相手が普通に話しかけてきても、慎治たちにとっては剥き出しの鞭を構えられているのと同じなのだから、常に怯え、卑屈に追従と愛想笑いを浮かべ、必死でご機嫌取りをするしかない。玲子たちだけではなく、クラスメート全員との間に鞭を持つ支配者と打ち据えられる隷属者の関係が自然に、だが確固として確立されていくのを誰よりも、慎治たち自身が最も深く明確に逃れようもなく認識していた。
玲子は信次たちの怯えと屈辱をゆっくりと楽しんでいた。そうよ、その顔よ。フフフ、信次、あなた私と話す時、私が何もしなくても私のベルトをチラチラと見ているわよね。殆ど無意識にだろうけど、私の手がベルトに伸びやしないかっていつも怯えているのよ。勿論慎治も同じ、礼子やフミちゃんの前ではいつも、ベルトで打たれやしないか、唾を吐き掛けられるんじゃないか、ていつも怯えているわ。信次、私信次のその怯えた顔、大好き。だからしょっちゅうベルトで鞭打ったり唾を吐き掛けてあげてトラウマをたっぷりと植付けてきてあげたのよ。フフフ、その刷り込みがこんなに効いてくるとはね。信次、あなた私たち女の子の制服姿にもう一生、消し去りようのないトラウマを植え付けられているのよ。いい気味ね。
玲子たちが見守る中、次々とクラスメートは信次たちの前を通り過ぎていく。そして残るは二人、陽子と有希子だけになっていた。「信次、なによその顔!もうみんなの唾でベトベトじゃない!あらあら顔中から糸引いて唾垂らしちゃって・・・いい気味。少しは思い知った?」涙とクラスメートの唾に霞んだ目で見上げると、勝ち誇ったように笑いながら陽子が見下ろしていた。「どう、なんか言うことないの?」「あ、あああ・・・ご、ごめんなさい・・・ごめんなさい・・・だから、お願い、許して・・・」唾をボタボタと顔から床に垂らしながら、半ば反射的に土下座する信次の顎を陽子は白い上履きの爪先でクイッと小突きあげた。「許して?何馬鹿言ってるのよ、ダメに決まってるでしょ!?覚悟しなさいよ、私もこのリンチ、燃えてるんだからね。トイレの床に突き転ばされた恨み、きっちりと晴らさせてもらうわよ!?」陽子はクチュクチュと口中一杯に唾を溜めると、信次たちに思いっきり吐き掛け、そしてベルトを引き抜くと力任せに肩の辺りを打ち据えた。「ヒイッ・・・」「じゃあまた・・・あとでね!」
そして取りは有希子だった。信次の前に立った有希子は冷笑を浮かべながら慎治を見下ろしていた。不思議ね、いつもは信次が苛められるのを見てると、少しは可哀想、ていう気になるのに今日はそんな気、全く起きないわね。ま、当然か、トイレで転ばされて怪我させられて、それでも許してやろうなんて考える子、いるわけないよね!みんなに倣い、有希子もゆっくりとベルトを引き抜いた。「信次・・・私で二十人目、最後ね。じゃあ最後に一つお願いして貰おうかしら。どうか僕の汚い顔に唾を吐き掛けてください、そしてどうかみんなで腐りきった人間のクズである僕を鞭打って罰してください、てね。」「あ、あうううう、そ、そんな、そんなこと・・・」唾まみれの顔に新たな涙を流しながら咽ぶ信次に有希子は冷たく言い放った。「そう、言いたくないのね、私の言うことは聞けない、て言うのね?」グッとベルトを握る右手に力を込める有希子の仕草に信次は震え上がって叫んだ。「い、い、いえ、そ、そんな!逆らうだなんてそしな!お、おねがい、おねがいですうううううっ!ど、どうか、どうか唾を、唾を吐き掛けて下さいいい、そしてどうか、どうかぼ、僕を鞭打って罰してくださいいい、お、お願い、おねがいですううううう!!!」信次の必死の哀願を有希子は鼻でせせら笑った。馬鹿ね信次、哀願しようが何しようが結果は同じ、みんなに死ぬほど鞭打たれるのは変わらないんだからね。でもまあいいわ。ご希望には応えてあげるわよ。「そう、そんなに私の唾が欲しいの?そんなに唾が欲しいなら、望み通り吐き掛けてやるわよ!この・・・ゴキブリ!ブタ!ぺっ!」思いっきり唾を吐き掛けると手にしたベルトを大きく振りかぶり、真っ直ぐに振り下ろした。ピシッ!ヒイッ!「まずはご挨拶。あとでたっぷりとまた鞭打ってあげるからね。」
2?
漸く全員が慎治たちに唾を吐き掛け、ベルトで打ち据え終わった。だがこれで終わったのではない。今日の責めは、リンチはこれからが本番なのだ。精神をグチャグチャに破壊され、屈辱に全身を責め苛まれた今から漸く、肉体の苦痛が始まる。絶望と恐怖におびえた目で信次は視線を彷徨わせた。前後左右、どこを見てもクラスメートの女の子がいる。みんな手にはベルトを、今さっき自分を打ち据えたベルトを握り締めて今や遅しとリンチの開始を待っている。ああ、あああああ・・・な、なにをされるんだろう・・・みんなに打ち据えられるんだよな・・・でもどうやって?慎治の脳裏に潰れた大学のグラウンドで玲子たち四人掛りで鞭打たれた苦い記憶が蘇る。だけど・・・だけどいくらなんでも、全員同時に鞭なんてさすがに無理だよな・・・精々二、三人同時が限界だよな、だったらなんとか大丈夫かな・・・でも、でも・・・!慎治は大きく息を吐いた。礼子さんたちがそんなに甘いわけないよ。きっと、きっと何か凄い、酷いリンチを考えているに決まってるんだ!でも、でもいったいどうやって・・・慎治たちの頭の中で恐怖が無限に増殖していく。その時、パシーン!と玲子が手にしたベルトを鳴らした。
「ハーイみんな!信次たちに挨拶は済んだわね?じゃあいよいよ・・・リンチ開始と逝くわよ!」「待ってましたあっ!」「うん、やろうやろう!今の一発ずつなんて全然物足りないよ!」「ほんとほんと!もっと思いっ切り引っ叩きたーいっ!」一斉に上がる歓声に苦笑しながら、礼子がパンパンッと手を叩いた。「ハイハイ、みんな安心してね、心配しなくても・・・思う存分引っ叩かせてあげるわよ!じゃあみんな、さっきメモに書いといたように整列してね!」礼子の声を合図にまず玲子、富美代、朝子が歩き出した。玲子は信次を四つん這いのまま連れて行き、慎治だけが取り残される。そして四人で体育館の横幅一杯を使い、対角線10メートルの、やや横長のダイアモンドを形作った。すると他の女の子たちも一斉に動き始め、玲子たち四人の間に互い違いで2-3メートル程度の間隔をおいて並び始めた。向かい合う女の子通しの幅は1-2メートルある。完成したそのフォームはやや横長の楕円、互い違いに二重の輪に並んだ女の子通しの間にチューブのように通路がある楕円形だった。
全員が位置に付き、間隔を調整し終えたのを確認すると玲子は信次の顎に二つ折りにしたベルトを引っ掛けて持ち上げた。「信次、もう自分がどうリンチされるのか、大体は分かったでしょ?そう、信次には私たちの輪の中をゆっくりと四つん這いで行進して貰うわよ。そして歩きながらみんなの鞭を受けるのよ!」「ヒッヒイイイイッ!そ、そんな、みんなに、みんなに鞭打たれるだなんて!!!」
反対側では慎治も礼子から刑を宣告されていた。「慎治、玲子の説明は聞こえたわね?二人ともスタートしたら時計回りに行進するのよ。ああそれとね、止まりたければ勝手に止まりなさい。どこで潰れようと慎治の勝手よ。但し、私たちの許しも無しに止まったりしたら、そこの地点でみんなから集中攻撃されることになるからそのつもりでね。」「しゅ、集中・・・攻撃だなんてそんな・・・」「フフフ、痛そうでしょ?集中攻撃だなんて真っ平よね?だったら精々しっかり行進することね。」礼子は笑いながらパシンッとベルトを打ち鳴らした。「玲子、そっちはOK?みんな、用意はいいかな?しっかりベルトは構えましたかあ?」「ハーイ、いつでもOKよ!」「早く早く!早く慎治のこと、引っ叩きたーい!」パシンッ、パーンッ!そこかしこでベルトを打ち鳴らす音が体育館に響く。「や、やだ、やめて・・・」「ひっひどい、そんな・・・」慎治たちのか細い哀願には一瞥もくれずに礼子はベルトを高く振り上げた。「さあ慎治、逝くわよ・・・リンチ・・・開始よ!」
ビュオッという音と共に礼子のベルトが振り下ろされた。バシーンッ!ヒイッ!礼子は慎治の背中に立て続けにベルトを振り下ろす。ビシッ!パシッ!「ヒッヒイッ!い、痛いいい!」あ、あああ、に、逃げなくちゃ、兎に角逃げなくちゃ、礼子さんのベルトの届かないところに・・・
信次も玲子のベルトに追い立てられ、必死で這い始めた。い、痛い!痛い!痛い!い、いやだ、いやだあああ!必死で信次が這いずるにつれ、最初は肩の辺りに炸裂していたベルトが徐々に背中の中心に移り、次いで尻にと移動していく。ハアハア、もう少し、もう少しで逃げられる・・・痛いっ!名残を惜しむかのように横にスイングされたベルトが信次の太腿の裏を打ち据える。思わず反射的に右手でそこを抑えてしまい、バランスを崩しながらも何とか必死で前に進んだ。ハアハアハア、こ、これで玲子さんの鞭からは何とか逃げ、パシッ!ヒイッ!逃げおおせたと思った瞬間、再び肩にベルトが食い込んだ。反射的に顔を上げた信次が見たものは、信次を打ち据えたベルトを再び振り上げ、今まさに二撃目を振り下ろそうとしている有希子の姿だった。
「来たわね信次!私をトイレで突き飛ばした罪・・・今こそ思い知らせてあげる!」バシッ、ビシッ、パンッ・・・力任せに有希子が振り回すベルトが信次の背中に次々と炸裂する。鞭は初めての有希子だが長さもそんなにないベルトは振り回しやすく、力任せに振り回すだけで十分に鞭として機能する。「い、いたっいたいたいたいいいいっ!や、やめてお願い許してえええ!!」信次は必死で有希子のベルトの制空圏を通り過ぎたが、息つく間もなく三人目のベルトが肩に降り注ぐ。「いいだ、いだいよおおおっ、やめて、もう・・・ひいいいいっ、ごめんなさいごめんなさいいいいっ!!!」慎治も間断なく鞭打たれながら必死で這い続けていた。礼子さん、陽子さん・・・三人、四人と鞭打たれながらも這い続けた慎治の悲鳴が急に甲高くなった。
「ヒッ、ヒギャァッ!」バッシーンッ!背中を襲うベルトの音が急に凶悪さを増し、背中に一段と酷い激痛を刻み込んだ。「い、いたあああああ・・・」仰け反るように仰ぎ見た慎治が見たものは、笑いながら高々とベルトを振りかざす富美代の姿だった。
「アハハハハッ!どう慎治、私のベルトの味は!みんなのベルトよりちょっとは効いてるかしら?それ!」ビシーーーンッ!富美代が思いっきり振り下ろしたベルトが慎治の背中に深々と食い込んだ。「ヒギイイイッ!」「アギャアアアアアッ!」殆ど同じタイミングで信次も金切り声を上げていた。「ア、アウッ、や、やべ、ギャヒイイイイッ!」信次に悲鳴を上げさせていたのは朝子のベルトだった。「キャハハハハッ!信次、痛い?みんなの時よりいい悲鳴じゃない!そんなに私の鞭痛いの?プロの腕ってやつかしら?じゃあたっぷりと手練の技を見せてあげるね!」
富美代も朝子もいつもの一本鞭ではなくベルト、しかもそんなに数多くは鞭打てない、とあって遠慮会釈なく全力を解放して二人を打ち据えた。半歩下げた右足の蹴りを効かせながら十二分に腰を入れ、体重をしっかりとベルトに乗せながら打ち下ろす。しかも肩、肘、と順に回転させ最大限しなりを効かせてスピードを得たベルトが慎治たちの肉体に当たる最後の瞬間、ピッと鋭く手首を返して威力を倍増させる。何百発何千発と鞭を振るって体得した、受刑者により多くの苦痛を与えるテクニックを富美代も朝子も情け容赦なく振るっていた。やっとの思いで二人の前を慎治たちは通り過ぎた。
だが決して休みなど与えられない。富美代、朝子のベルトよりは多少痛くない、とはいえ他のクラスメートのベルトも十二分に痛い。そして・・・更に五人進むと礼子たちが待ち構えていた。「信次、よく来たわね、中間ポイントよ、ちゃんとハンコを押してあげるわね、ソレッ!」「慎治、私でちょうど半分よ、良かったわね、おめでとう!」ビシーッッッ、バシーッッッ・・・「グギイイイイッ!!!」「イヤアアアアアッッッ!」
富美代や朝子のベルトをも上回る激痛に二人とも思わず背中を仰け反らせ、その場に止まってしまった。反射的な行動とは言え、最悪の選択だった。「あら信次、そんなに私の鞭が欲しいの?いいわよ、遠慮はいらないわ、だって私と信次の仲だものね!」「ああそうなの慎治、やっぱりこの位痛くないと慎治には物足りないのね。いいわよ、お望みどおり引っ叩いてあげる!」バシッ、ビシッ、パウッ、パーンッ!!!ギャアアアッ!イ、イタイイイイイッ!ア、アベ、アベデエエエッ!ユルジデエエエエエッ!!!余りの激痛に涙と涎を垂れ流し、何を言っているのかすら分からない悲鳴をあげつつ慎治たちは何とかこの場を逃れようと必死で這いずった。漸く礼子たちの制空圏から脱した慎治たちだが、次のベルトを受けながら暗い閃きに思わず絶望してしまった。
礼子さんのところは過ぎたけど、こ、この先にはフミちゃん・・・あ、あと五人、あと五人先にはあ、朝子さんが、朝子さんが待っている・・・残酷な配置だった。礼子たちは熟練した鞭の使い手四人のポイントを散りばめることで、慎治たちにあと何人でまた激痛ポイント、と怯えさせ、精神的にも苦しめることを狙っていた。精神面だけではない。礼子たち四人が連続して並んでしまうと激痛のため慎治たちの痛覚がマヒしてしまい、痛みがフレッシュでなくなってしまうかもしれない。他のクラスメートの鞭が十分な苦痛を与えられなくなってしまうかも知れない。位置を分散したのはそれに対する配慮も兼ねていた。鞭打ち初体験のクラスメートを前後に挟むことで、自分たちの強烈な鞭をより新鮮な激痛として慎治たちに味合わせる事ができる。更に四人が散らばることで前後のクラスメートが礼子たちのフォームを真似しやすくなる、少なくとも礼子たちの鞭音につられ、遠慮なく思いっきり引っ叩けるようにすることも狙っていた。礼子たちの配慮は狙い通り、何重もの効果を上げて慎治たちの苦痛をいや増していた。
「アウッ、アウウウウッ・・・」「ヒッ、ヒック、ウエッウエエエエッ・・・」苦痛と恐怖と屈辱を際限なく味合わされながら、慎治たちは必死で這いずり続けた。そして漸くゴール地点、一周して礼子たちの下に辿り着くと二人とも、その場に突っ伏してしまった。200発近く打たれたであろうか、幅のあるベルトだから蚯蚓腫れになったり皮膚が切れたりはしていなかったが、二人の肩から尻にかけては真っ赤に腫れ上がり、所々は内出血のため青痣になっていた。
「フフフ慎治、いいザマね。少しは懲りたかしら?」「あ、あああ、ご、めんなさい・・・もう、許して、お、願い・・・」礼子に頭を踏み躙られながら、慎治は呻き声で哀願した。
「信次、少しは反省した?どうなの、少しは自分の罪深さを思い知ったかしら?」玲子も信次の頬を踏み躙りながら尋ねていた。「あ、あううう・・・は、はい・・・は、はんせい、反省しました・・・だから、どうか・・・許して・・・くだ、さい・・・」消え入りそうな声で呟く信次を玲子は満足そうに、だが冷ややかな目で見下ろしていた。「そう、信次みたいなカスでも流石にこれだけ鞭打たれれば少しは反省、らしきものを言えるのね。だけど」玲子は信次を踏み付ける足にグッと力を込めた。「まだまだ足りないわ。この程度で許してあげるわけにはいかないわ!」「えっえええええっ、そ、そんな!!!」礼子も慎治にリンチの続行を宣告していた。
「許す?ダメよ慎治、まだまだ足りない、慎治のことはもっともっと、いっぱい懲らしめてあげるわ。さあ、少しは休ませてあげたのよ、感謝しなさい!リンチ、再開よ!」礼子はパンッとベルトを打ち鳴らすと同時に足をどけた。「あ、あひいいいいっ!そ、そんな、そんなあああああっ!」「あら慎治、別に動きたくなければいいのよ、そのままそこに蹲ってなさい!そうやって・・・私の鞭をずっと受け続けなさい!」ビュオッ・・・ブオッ!礼子たちのベルトがリンチ再開を待ちかねたかのように唸り始めた。
「あ、ああ、あああああ・・・・・」「は、はひっはひっひっひっひっ・・・」二周目が終わった時、慎治たちはもはや気絶寸前だった。数え切れないほど打ち据えられた背中は赤を通り過ぎ青黒くなっていた。肉体以上に精神も崩壊寸前だった。動く気力もなく倒れ伏した二人をクラスメートが取り囲んだ。「どうみんな、鞭は堪能した?」礼子の声が響いた。「もうちょっと懲らしめたい気もするけど、流石に今日はこれまでね。もう多分、痛覚殆どマヒしちゃってるから、これ以上苛めても余り面白くないわ。と、言うことで今日はこれまで、解散にしよう!お疲れ様!」礼子の声を合図に、心地よい疲労を楽しみながらクラスメートがゾロゾロと帰っていく。後には礼子たち四人と慎治たちだけが残っていた。
「信次、正座。」玲子が静かに命令した。玲子の命令に突き動かされ、最後の気力を振り絞るように二人はのろのろと正座する。「どうかしら、少しは骨身に沁みた?反省したかしら?」「・・・は、はい・・・はん、せい・・・しまし、た・・・」消え入るような声で呟く信次を満足げに見下ろしながら玲子は冷笑した。「そう、それは良かった。だけどね、もう遅いのよ。信次、あんたたちは超えてはならない一線を飛び越えちゃったのよ。いくら反省しても、もう絶対に許してあげない。信次、あんたたちにはこれから、本物の苛め、ていうものを教えてあげるわ。私たちの全力で、本気で苛め尽くしてあげるからね・・・辛いわよ、覚悟しておくことね。」
ほ、本物の苛め・・・そ、そんな・・・い、一体なにをする気なの?ま、まさか、これから一本鞭で・・・
恐怖に引きつる二人に、後を引き取った礼子が告げる。「二人とも安心していいわ。今日これから鞭を追加する、なんてことはしないから。今日はもう、何もする気はないわ。ううん、それどころかこの週末は解放してあげる。ゆっくりと休んでいいわよ。」な、なにもしない?い、いやそれより、週末休ませてくれる?い、一体なぜ、どうして???予想外の礼子の言葉に、慎治たちは安堵よりも戸惑いと不安に包まれる。その困惑の表情を見て玲子が冷笑を浮かべた。
「信次、不安?怖い?自分がどうされるのか知りたい?ダメ、教えてあげないわよ。」礼子の美貌にも残酷な冷笑が浮かぶ。
「まあこれだけは教えといてあげるわ。玲子が本物の苛め、て言ったでしょ?念のため言っとくけど、今までみたいに単純に鞭で打ちのめすのが本物の苛めじゃないからね。鞭100発が200発になる、なんていう単純な責めを考えられたら困るわよ。ウフフフフ、血塗れになるまで鞭打たれたのが軽いお遊びに思えるような目に会わせてあげるわ。フフフ、週明け、楽しみにしていなさい、どういう目に会わされるのか・・・精々ゆっくりと想像してみることね。」「そ、そんな・・・な、なにを、なにをされるんですか・・・」「ど、どうするの、ぼくたちを・・・どうするつもりなの・・・おしえて・・・」涙を流しながら必死で尋ねる二人に冷笑を投げかけながら礼子たちは解散を宣言した。「それでは良い週末を!」「また来週!」
シンジをリンチにかける会緊急開催のご案内本日の昼休み、矢作慎治および川内信次の両名が女子トイレにて暴力を奮い、女子生徒に怪我を負わせる、という大事件を起こしました。両名に対しては時間をかけゆっくり、じっくり、たっぷりと厳刑を加える方針ですが、取り急ぎ本日放課後、両名を第一陣のリンチにかけたいと思います。皆様万障お繰り合わせの上、一人でも多くのご出席をお願いします。シンジをリンチにかける会代表天城礼子霧島玲子幹事神埼富美代萩朝子
シンジをリンチにかける会!ほ、本当なんだ、本当に僕たち、リンチに掛けられるんだ・・・それも放課後、もうあと僅か一時間後に・・・あまりの恐怖に二人が呆然としている間に、あっという間に6時間目の授業は終わり放課後になってしまった。
ホームルームもそこそこに礼子が宣告する。「今日の連絡事項は以上です。何か他にありますか?無いようでしたら先ほどご連絡したとおり、これより矢作慎治、川内信次の両名をリンチに掛けたいと思います。皆さん第三体育館に移動してください。」
第三体育館、それは予備の講堂、ミニホールとして使用できるように小規模ではあるが舞台をしつらえ、防音設備を施した体育館だった。礼子さんたち、5時間目の休み時間にいない、と思ったらここを取りに行ってたんだ。
「ヒッヒイイイイッ・・・」「り、リンチだなんて、そんな・・・」半べそをかきながら腰が抜けてしまった二人をクラスメートが取り囲む。「さあ信次、行こうか!」信次の両側からは朝子と真弓が、慎治には富美代と和枝が無理やり引きずり起こすように立たせると、信次たちを取り囲むように殆どのクラスメートが一緒になって第三体育館に連行する。
「あ、あああ・・・」まるで死刑場に引き立てられる受刑者のように、信次たちは泣きながらフラフラと引き立てられていく。「信次、陽子たちをよくも怪我させたわね!」「もう、絶対許さないからね!」「フフフ、この人数で苛められるんだよ、どう、楽しみ?」「あ、私今日、何か弾けちゃいそう!」「全くよね!礼子たちのことだから、きっと凄いリンチ考えてるわよ?ウフフ、ねえ慎治、今日生きておうちに帰れるかしら?」
歩きながら女の子たちは口々に慎治たちを罵り、小突き回す。どの顔も妙に楽しそうな、ある種の祭りの高揚感に似たハイな笑顔になっていた。お、同じだ・・・慎治たちの嫌な記憶、白馬で、奥多摩で体育館に引き立てられ、たっぷりと責め苛まれた記憶が甦る。慎治たちを刑場に引き立てながら礼子たちが浮かべていた心底楽しそうな笑顔、それをクラスメート全員が浮かべていた。
「あ、あああ・・・おねがい、たすけて・・・」誰に言うともなく力なく慎治は呟いた。だが都合よく助けが現れるのは安っぽいハリウッドムービーだけだ、現実世界で助けなど現れるはずがない。あっという間に慎治たちは体育館に到着した。
ガラガラ、と和枝が体育館のドアを開けると中には既に玲子たちが一足先に来ていた。「あ、来たわね。朝子、中に入ったらしっかり鍵かけてね。ほかのドアはみんなロックしたから、後はそこだけ閉めればもう邪魔は入らないわ。」邪魔は入らない・・・その言葉がなにを意味するか、考える必要などない。朝子が入り口をしっかり閉めると、慎治たちは体育館の真ん中に引き立てられ正座させられた。
「さあ慎治、どうなるか分かってるわよね。お昼休みは時間切れ、て言うことで終わっちゃったけど、今度はそうは行かないわよ?覚悟はいいわね?」慎治を土下座させ、後頭部をグリグリと踏み躙りながら礼子がリンチ開始を宣告する。「そうよ慎治、私たちがあれだけ優しくしてあげたのに、慎治たちの大罪をあんな軽い罰で許してあげたのに、よくもまああれだけ堂々と恩を仇で返してくれたものね?勿論、只で済むとは思ってないわよね?」「あ、ああ、あああああ・・・お、お願い、許して・・・」ガッ!ヒッ!慎治の哀願に苛立ったかのように礼子は足を上げたかと思うと慎治の頭を蹴り付けるかのように踏み躙った。「許して?ふざけるんじゃないわよ!あんな軽い罰で許してやった私たちを裏切っておいていまさら許してですって?そんなのが通用するとでも思ってるの!?」
「礼子、ストップストップ、冷静に!こいつらにとって今、一番の救いは礼子や私が切れて一気に気絶させてくれることでしょ?落ち着いて、ゆっくり一回深呼吸して!・・・どう、少しは落ち着いた?」妙に静かな玲子の声に我を取り戻した礼子は言われるままにゆっくりと深呼吸をし、玲子にニッコリと微笑みかけた。「フウウ・・・そうよね、こいつらのその手に危うく乗せられるところだったわ。折角5時間目、6時間目とリンチのプランをじっくり練ってたんだもんね。一気に潰しちゃ勿体無さ過ぎるわ。慎治、時間はたっぷりあるわ。じっくりと苛めてあげるからね。」礼子の声も冷静さを取り戻した。礼子の冷静な声は先ほどの怒声の数倍も恐ろしい、慎治たちの背筋をゾクリと震え上がらせる、破滅へと誘うセイレーンの歌声のような魔力があった。
「そう、折角プランを練って場所取って、みんなも忙しい時間を割いてリンチに駆けつけてくれたんだからね。たっぷりと泣き叫ばせてやらなくちゃ元が取れないわ・・・さあ、そろそろリンチ、開始しましょうか。信次、二人とも覚悟するのね。ゆっくりと苛めてやるからね!」
あ、あああ・・・・・恐怖に半ば腰が抜けている二人を裸にさせ並ばせて正座させると、玲子はクイッと二人の顎を上げ、自分を仰ぎ見させた。「二人とも、この姿勢絶対に崩しちゃ駄目よ。崩したらもっと酷いリンチに会わせるからね!」刑の開始を宣告すると、玲子は信次たちの目の前でカチャカチャとわざと音を立てながらベルトのバックルを外し、シュルッと細いウエストから引き抜いた。ヒッヒイイイイイッ・・・玲子の手の中でベルトが、服飾品が一本の鞭に変化する。「分かるわね、どういう目に会うか。でも安心しなさい、まずは二人とも、一発ずつだけよ。一発ずつしか鞭打たないわ、どう、安心した?」これまで散々苛め抜かれてきた信次たちが安心などするわけがない、だが一発だけ、という玲子の思いがけない言葉に信次は思わず反射的に微かにほっとしたような顔色を浮かべた。
「このブタ!鞭が一発だけ、て聞いただけでほっとするなんてね。この最低男!」ペッ!玲子は自分を見上げる信次の顔に思いっきり唾を吐き掛けた。「慎治、慎治も今、ほっとしていたでしょ?バーカ!」ペッ!玲子は返す刀で慎治にも唾を吐き掛ける。「さあ、行くよ!」手にしたベルトを翻らせると玲子は袈裟切りに振り下ろすように信次を一撃し、そのままバックハンドで慎治も打ち据える。
「ヒッ!」「アウッ!」信次たちの悲鳴が上がるのを冷たく見下ろすと玲子はゆっくりと二人の前から離れた。間を置かずに今度は礼子が二人の前に立つ。「どう二人とも、何をされるのか分かったかしら?簡単なセレモニーよ、本格的なリンチの前のほんのご挨拶、ていうところ。これからたっぷりとリンチしてあげるからね、まずは手付よ!」ゆっくりとベルトをウエストから引き抜くと、礼子も二人に唾を吐き掛け、一撃ずつ鞭打つと二人の前を離れていく。続いて朝子が、そして富美代が同じように二人の前でベルトを引き抜き、唾を、鞭を一撃ずつ加えていく。
な、なんだ、なんなんだ・・・富美代の次に和枝が目の前に立った時、漸く慎治は礼子たちの企みを理解した。
「フフフ慎治、分かったみたいね。でも私だけじゃないのよ。フフ、フフフフフ、ペッ!」和枝は笑いながら二人に唾を吐き掛けるとベルトを大きく振りかぶった。「礼子たちほど上手じゃないけどね、私のファースト鞭、逝くよ!」ピシッ!パシッ!慎治たちの肩のあたりを鞭打つと和枝は笑いながら場所を譲る。そして次に真弓が二人の前でベルトを引き抜いた。「そうよ信次、いい顔色に怯えてきたじゃない、ご名答。次は誰が信次たちのことを鞭打つのかしら?みんなよみんな、全員で鞭打ってあげるわ!どう、楽しいでしょ、アハハ、アハハハハッ!」笑いながら真弓も唾を吐き掛け、一発ずつ鞭を振るうと場を空ける。
クラスメート全員が一人一人、慎治たちの目の前でベルトを引き抜き、唾を吐き掛けて一鞭ずつ打ち据えていく。慎治たちの当惑は直ぐに屈辱と恐怖に変わっていった。フフフ、慎治、怯えてるわね。精々怖がりなさい。今日のリンチだけじゃないわよ、これから先、明日以降の自分たちがどうなるか、たっぷりと怯えるがいいわ。礼子たちの狙いどおり、このセレモニーは慎治たちの精神を強烈に蝕んでいた。流石にいくら苛めを蔓延させる、と言ってもクラスメート全員が鞭を購入し慎治たちを苛める、等ということはまず有り得ない。だがベルトなら話は別だ。別に責め具としてではなく制服の一部として全員が毎日身につけている、そのベルトで鞭打たれる。痛さだけの問題ではない。むしろ痛さだけで言えばたかがベルト、本物の一本鞭で数え切れないほど鞭打たれている慎治たちにとっては痛いとはいえ、十分に耐えられるレベルだ。だがベルトで鞭打たれるのは本物の鞭以上の屈辱感を二人に刻み込んでいた。
慎治たちの目の前で一人、また一人とベルトをウエストから引き抜く。その瞬間、ベルトが意思を持たない制服の一部から残酷な責め具へと変化していく。そして同時にクラスメートが、今まで苛められたとは言えクラスメートであった女の子が礼子たちと同じ、残酷な拷問官へと変化していく。順番を待つ他のクラスメートも全員がウエストに鞭を、慎治たちを打ち据え泣き喚かせる責め具を締めている。隠すこともなく、誰に咎められることもなく。
それは慎治たち以外の誰にとっても単なるベルト、単なる制服の一部に過ぎない。慎治たち以外の男子生徒は誰も、女の子たちが締めているベルトを全く意識にも止めずに見ているだろう。だが慎治たちにとっては全てのクラスメートが常に鞭を携えているのと同じ、もし慎治たちが何か少しでも気に入らないことをすれば、いつでも鞭打てる、いつでも跪かせ、苦痛と屈辱にのた打ち回らせることができるのよ、と言う事を一人、また一人と宣言していくようだった。明日も明後日も女の子たちはみんな、制服を着てベルトを締めてくるだろう。そしてその女の子たちの誰に対しても二度と、対等な立場にはなり得ない。例え相手が普通に話しかけてきても、慎治たちにとっては剥き出しの鞭を構えられているのと同じなのだから、常に怯え、卑屈に追従と愛想笑いを浮かべ、必死でご機嫌取りをするしかない。玲子たちだけではなく、クラスメート全員との間に鞭を持つ支配者と打ち据えられる隷属者の関係が自然に、だが確固として確立されていくのを誰よりも、慎治たち自身が最も深く明確に逃れようもなく認識していた。
玲子は信次たちの怯えと屈辱をゆっくりと楽しんでいた。そうよ、その顔よ。フフフ、信次、あなた私と話す時、私が何もしなくても私のベルトをチラチラと見ているわよね。殆ど無意識にだろうけど、私の手がベルトに伸びやしないかっていつも怯えているのよ。勿論慎治も同じ、礼子やフミちゃんの前ではいつも、ベルトで打たれやしないか、唾を吐き掛けられるんじゃないか、ていつも怯えているわ。信次、私信次のその怯えた顔、大好き。だからしょっちゅうベルトで鞭打ったり唾を吐き掛けてあげてトラウマをたっぷりと植付けてきてあげたのよ。フフフ、その刷り込みがこんなに効いてくるとはね。信次、あなた私たち女の子の制服姿にもう一生、消し去りようのないトラウマを植え付けられているのよ。いい気味ね。
玲子たちが見守る中、次々とクラスメートは信次たちの前を通り過ぎていく。そして残るは二人、陽子と有希子だけになっていた。「信次、なによその顔!もうみんなの唾でベトベトじゃない!あらあら顔中から糸引いて唾垂らしちゃって・・・いい気味。少しは思い知った?」涙とクラスメートの唾に霞んだ目で見上げると、勝ち誇ったように笑いながら陽子が見下ろしていた。「どう、なんか言うことないの?」「あ、あああ・・・ご、ごめんなさい・・・ごめんなさい・・・だから、お願い、許して・・・」唾をボタボタと顔から床に垂らしながら、半ば反射的に土下座する信次の顎を陽子は白い上履きの爪先でクイッと小突きあげた。「許して?何馬鹿言ってるのよ、ダメに決まってるでしょ!?覚悟しなさいよ、私もこのリンチ、燃えてるんだからね。トイレの床に突き転ばされた恨み、きっちりと晴らさせてもらうわよ!?」陽子はクチュクチュと口中一杯に唾を溜めると、信次たちに思いっきり吐き掛け、そしてベルトを引き抜くと力任せに肩の辺りを打ち据えた。「ヒイッ・・・」「じゃあまた・・・あとでね!」
そして取りは有希子だった。信次の前に立った有希子は冷笑を浮かべながら慎治を見下ろしていた。不思議ね、いつもは信次が苛められるのを見てると、少しは可哀想、ていう気になるのに今日はそんな気、全く起きないわね。ま、当然か、トイレで転ばされて怪我させられて、それでも許してやろうなんて考える子、いるわけないよね!みんなに倣い、有希子もゆっくりとベルトを引き抜いた。「信次・・・私で二十人目、最後ね。じゃあ最後に一つお願いして貰おうかしら。どうか僕の汚い顔に唾を吐き掛けてください、そしてどうかみんなで腐りきった人間のクズである僕を鞭打って罰してください、てね。」「あ、あうううう、そ、そんな、そんなこと・・・」唾まみれの顔に新たな涙を流しながら咽ぶ信次に有希子は冷たく言い放った。「そう、言いたくないのね、私の言うことは聞けない、て言うのね?」グッとベルトを握る右手に力を込める有希子の仕草に信次は震え上がって叫んだ。「い、い、いえ、そ、そんな!逆らうだなんてそしな!お、おねがい、おねがいですうううううっ!ど、どうか、どうか唾を、唾を吐き掛けて下さいいい、そしてどうか、どうかぼ、僕を鞭打って罰してくださいいい、お、お願い、おねがいですううううう!!!」信次の必死の哀願を有希子は鼻でせせら笑った。馬鹿ね信次、哀願しようが何しようが結果は同じ、みんなに死ぬほど鞭打たれるのは変わらないんだからね。でもまあいいわ。ご希望には応えてあげるわよ。「そう、そんなに私の唾が欲しいの?そんなに唾が欲しいなら、望み通り吐き掛けてやるわよ!この・・・ゴキブリ!ブタ!ぺっ!」思いっきり唾を吐き掛けると手にしたベルトを大きく振りかぶり、真っ直ぐに振り下ろした。ピシッ!ヒイッ!「まずはご挨拶。あとでたっぷりとまた鞭打ってあげるからね。」
2?
漸く全員が慎治たちに唾を吐き掛け、ベルトで打ち据え終わった。だがこれで終わったのではない。今日の責めは、リンチはこれからが本番なのだ。精神をグチャグチャに破壊され、屈辱に全身を責め苛まれた今から漸く、肉体の苦痛が始まる。絶望と恐怖におびえた目で信次は視線を彷徨わせた。前後左右、どこを見てもクラスメートの女の子がいる。みんな手にはベルトを、今さっき自分を打ち据えたベルトを握り締めて今や遅しとリンチの開始を待っている。ああ、あああああ・・・な、なにをされるんだろう・・・みんなに打ち据えられるんだよな・・・でもどうやって?慎治の脳裏に潰れた大学のグラウンドで玲子たち四人掛りで鞭打たれた苦い記憶が蘇る。だけど・・・だけどいくらなんでも、全員同時に鞭なんてさすがに無理だよな・・・精々二、三人同時が限界だよな、だったらなんとか大丈夫かな・・・でも、でも・・・!慎治は大きく息を吐いた。礼子さんたちがそんなに甘いわけないよ。きっと、きっと何か凄い、酷いリンチを考えているに決まってるんだ!でも、でもいったいどうやって・・・慎治たちの頭の中で恐怖が無限に増殖していく。その時、パシーン!と玲子が手にしたベルトを鳴らした。
「ハーイみんな!信次たちに挨拶は済んだわね?じゃあいよいよ・・・リンチ開始と逝くわよ!」「待ってましたあっ!」「うん、やろうやろう!今の一発ずつなんて全然物足りないよ!」「ほんとほんと!もっと思いっ切り引っ叩きたーいっ!」一斉に上がる歓声に苦笑しながら、礼子がパンパンッと手を叩いた。「ハイハイ、みんな安心してね、心配しなくても・・・思う存分引っ叩かせてあげるわよ!じゃあみんな、さっきメモに書いといたように整列してね!」礼子の声を合図にまず玲子、富美代、朝子が歩き出した。玲子は信次を四つん這いのまま連れて行き、慎治だけが取り残される。そして四人で体育館の横幅一杯を使い、対角線10メートルの、やや横長のダイアモンドを形作った。すると他の女の子たちも一斉に動き始め、玲子たち四人の間に互い違いで2-3メートル程度の間隔をおいて並び始めた。向かい合う女の子通しの幅は1-2メートルある。完成したそのフォームはやや横長の楕円、互い違いに二重の輪に並んだ女の子通しの間にチューブのように通路がある楕円形だった。
全員が位置に付き、間隔を調整し終えたのを確認すると玲子は信次の顎に二つ折りにしたベルトを引っ掛けて持ち上げた。「信次、もう自分がどうリンチされるのか、大体は分かったでしょ?そう、信次には私たちの輪の中をゆっくりと四つん這いで行進して貰うわよ。そして歩きながらみんなの鞭を受けるのよ!」「ヒッヒイイイイッ!そ、そんな、みんなに、みんなに鞭打たれるだなんて!!!」
反対側では慎治も礼子から刑を宣告されていた。「慎治、玲子の説明は聞こえたわね?二人ともスタートしたら時計回りに行進するのよ。ああそれとね、止まりたければ勝手に止まりなさい。どこで潰れようと慎治の勝手よ。但し、私たちの許しも無しに止まったりしたら、そこの地点でみんなから集中攻撃されることになるからそのつもりでね。」「しゅ、集中・・・攻撃だなんてそんな・・・」「フフフ、痛そうでしょ?集中攻撃だなんて真っ平よね?だったら精々しっかり行進することね。」礼子は笑いながらパシンッとベルトを打ち鳴らした。「玲子、そっちはOK?みんな、用意はいいかな?しっかりベルトは構えましたかあ?」「ハーイ、いつでもOKよ!」「早く早く!早く慎治のこと、引っ叩きたーい!」パシンッ、パーンッ!そこかしこでベルトを打ち鳴らす音が体育館に響く。「や、やだ、やめて・・・」「ひっひどい、そんな・・・」慎治たちのか細い哀願には一瞥もくれずに礼子はベルトを高く振り上げた。「さあ慎治、逝くわよ・・・リンチ・・・開始よ!」
ビュオッという音と共に礼子のベルトが振り下ろされた。バシーンッ!ヒイッ!礼子は慎治の背中に立て続けにベルトを振り下ろす。ビシッ!パシッ!「ヒッヒイッ!い、痛いいい!」あ、あああ、に、逃げなくちゃ、兎に角逃げなくちゃ、礼子さんのベルトの届かないところに・・・
信次も玲子のベルトに追い立てられ、必死で這い始めた。い、痛い!痛い!痛い!い、いやだ、いやだあああ!必死で信次が這いずるにつれ、最初は肩の辺りに炸裂していたベルトが徐々に背中の中心に移り、次いで尻にと移動していく。ハアハア、もう少し、もう少しで逃げられる・・・痛いっ!名残を惜しむかのように横にスイングされたベルトが信次の太腿の裏を打ち据える。思わず反射的に右手でそこを抑えてしまい、バランスを崩しながらも何とか必死で前に進んだ。ハアハアハア、こ、これで玲子さんの鞭からは何とか逃げ、パシッ!ヒイッ!逃げおおせたと思った瞬間、再び肩にベルトが食い込んだ。反射的に顔を上げた信次が見たものは、信次を打ち据えたベルトを再び振り上げ、今まさに二撃目を振り下ろそうとしている有希子の姿だった。
「来たわね信次!私をトイレで突き飛ばした罪・・・今こそ思い知らせてあげる!」バシッ、ビシッ、パンッ・・・力任せに有希子が振り回すベルトが信次の背中に次々と炸裂する。鞭は初めての有希子だが長さもそんなにないベルトは振り回しやすく、力任せに振り回すだけで十分に鞭として機能する。「い、いたっいたいたいたいいいいっ!や、やめてお願い許してえええ!!」信次は必死で有希子のベルトの制空圏を通り過ぎたが、息つく間もなく三人目のベルトが肩に降り注ぐ。「いいだ、いだいよおおおっ、やめて、もう・・・ひいいいいっ、ごめんなさいごめんなさいいいいっ!!!」慎治も間断なく鞭打たれながら必死で這い続けていた。礼子さん、陽子さん・・・三人、四人と鞭打たれながらも這い続けた慎治の悲鳴が急に甲高くなった。
「ヒッ、ヒギャァッ!」バッシーンッ!背中を襲うベルトの音が急に凶悪さを増し、背中に一段と酷い激痛を刻み込んだ。「い、いたあああああ・・・」仰け反るように仰ぎ見た慎治が見たものは、笑いながら高々とベルトを振りかざす富美代の姿だった。
「アハハハハッ!どう慎治、私のベルトの味は!みんなのベルトよりちょっとは効いてるかしら?それ!」ビシーーーンッ!富美代が思いっきり振り下ろしたベルトが慎治の背中に深々と食い込んだ。「ヒギイイイッ!」「アギャアアアアアッ!」殆ど同じタイミングで信次も金切り声を上げていた。「ア、アウッ、や、やべ、ギャヒイイイイッ!」信次に悲鳴を上げさせていたのは朝子のベルトだった。「キャハハハハッ!信次、痛い?みんなの時よりいい悲鳴じゃない!そんなに私の鞭痛いの?プロの腕ってやつかしら?じゃあたっぷりと手練の技を見せてあげるね!」
富美代も朝子もいつもの一本鞭ではなくベルト、しかもそんなに数多くは鞭打てない、とあって遠慮会釈なく全力を解放して二人を打ち据えた。半歩下げた右足の蹴りを効かせながら十二分に腰を入れ、体重をしっかりとベルトに乗せながら打ち下ろす。しかも肩、肘、と順に回転させ最大限しなりを効かせてスピードを得たベルトが慎治たちの肉体に当たる最後の瞬間、ピッと鋭く手首を返して威力を倍増させる。何百発何千発と鞭を振るって体得した、受刑者により多くの苦痛を与えるテクニックを富美代も朝子も情け容赦なく振るっていた。やっとの思いで二人の前を慎治たちは通り過ぎた。
だが決して休みなど与えられない。富美代、朝子のベルトよりは多少痛くない、とはいえ他のクラスメートのベルトも十二分に痛い。そして・・・更に五人進むと礼子たちが待ち構えていた。「信次、よく来たわね、中間ポイントよ、ちゃんとハンコを押してあげるわね、ソレッ!」「慎治、私でちょうど半分よ、良かったわね、おめでとう!」ビシーッッッ、バシーッッッ・・・「グギイイイイッ!!!」「イヤアアアアアッッッ!」
富美代や朝子のベルトをも上回る激痛に二人とも思わず背中を仰け反らせ、その場に止まってしまった。反射的な行動とは言え、最悪の選択だった。「あら信次、そんなに私の鞭が欲しいの?いいわよ、遠慮はいらないわ、だって私と信次の仲だものね!」「ああそうなの慎治、やっぱりこの位痛くないと慎治には物足りないのね。いいわよ、お望みどおり引っ叩いてあげる!」バシッ、ビシッ、パウッ、パーンッ!!!ギャアアアッ!イ、イタイイイイイッ!ア、アベ、アベデエエエッ!ユルジデエエエエエッ!!!余りの激痛に涙と涎を垂れ流し、何を言っているのかすら分からない悲鳴をあげつつ慎治たちは何とかこの場を逃れようと必死で這いずった。漸く礼子たちの制空圏から脱した慎治たちだが、次のベルトを受けながら暗い閃きに思わず絶望してしまった。
礼子さんのところは過ぎたけど、こ、この先にはフミちゃん・・・あ、あと五人、あと五人先にはあ、朝子さんが、朝子さんが待っている・・・残酷な配置だった。礼子たちは熟練した鞭の使い手四人のポイントを散りばめることで、慎治たちにあと何人でまた激痛ポイント、と怯えさせ、精神的にも苦しめることを狙っていた。精神面だけではない。礼子たち四人が連続して並んでしまうと激痛のため慎治たちの痛覚がマヒしてしまい、痛みがフレッシュでなくなってしまうかもしれない。他のクラスメートの鞭が十分な苦痛を与えられなくなってしまうかも知れない。位置を分散したのはそれに対する配慮も兼ねていた。鞭打ち初体験のクラスメートを前後に挟むことで、自分たちの強烈な鞭をより新鮮な激痛として慎治たちに味合わせる事ができる。更に四人が散らばることで前後のクラスメートが礼子たちのフォームを真似しやすくなる、少なくとも礼子たちの鞭音につられ、遠慮なく思いっきり引っ叩けるようにすることも狙っていた。礼子たちの配慮は狙い通り、何重もの効果を上げて慎治たちの苦痛をいや増していた。
「アウッ、アウウウウッ・・・」「ヒッ、ヒック、ウエッウエエエエッ・・・」苦痛と恐怖と屈辱を際限なく味合わされながら、慎治たちは必死で這いずり続けた。そして漸くゴール地点、一周して礼子たちの下に辿り着くと二人とも、その場に突っ伏してしまった。200発近く打たれたであろうか、幅のあるベルトだから蚯蚓腫れになったり皮膚が切れたりはしていなかったが、二人の肩から尻にかけては真っ赤に腫れ上がり、所々は内出血のため青痣になっていた。
「フフフ慎治、いいザマね。少しは懲りたかしら?」「あ、あああ、ご、めんなさい・・・もう、許して、お、願い・・・」礼子に頭を踏み躙られながら、慎治は呻き声で哀願した。
「信次、少しは反省した?どうなの、少しは自分の罪深さを思い知ったかしら?」玲子も信次の頬を踏み躙りながら尋ねていた。「あ、あううう・・・は、はい・・・は、はんせい、反省しました・・・だから、どうか・・・許して・・・くだ、さい・・・」消え入りそうな声で呟く信次を玲子は満足そうに、だが冷ややかな目で見下ろしていた。「そう、信次みたいなカスでも流石にこれだけ鞭打たれれば少しは反省、らしきものを言えるのね。だけど」玲子は信次を踏み付ける足にグッと力を込めた。「まだまだ足りないわ。この程度で許してあげるわけにはいかないわ!」「えっえええええっ、そ、そんな!!!」礼子も慎治にリンチの続行を宣告していた。
「許す?ダメよ慎治、まだまだ足りない、慎治のことはもっともっと、いっぱい懲らしめてあげるわ。さあ、少しは休ませてあげたのよ、感謝しなさい!リンチ、再開よ!」礼子はパンッとベルトを打ち鳴らすと同時に足をどけた。「あ、あひいいいいっ!そ、そんな、そんなあああああっ!」「あら慎治、別に動きたくなければいいのよ、そのままそこに蹲ってなさい!そうやって・・・私の鞭をずっと受け続けなさい!」ビュオッ・・・ブオッ!礼子たちのベルトがリンチ再開を待ちかねたかのように唸り始めた。
「あ、ああ、あああああ・・・・・」「は、はひっはひっひっひっひっ・・・」二周目が終わった時、慎治たちはもはや気絶寸前だった。数え切れないほど打ち据えられた背中は赤を通り過ぎ青黒くなっていた。肉体以上に精神も崩壊寸前だった。動く気力もなく倒れ伏した二人をクラスメートが取り囲んだ。「どうみんな、鞭は堪能した?」礼子の声が響いた。「もうちょっと懲らしめたい気もするけど、流石に今日はこれまでね。もう多分、痛覚殆どマヒしちゃってるから、これ以上苛めても余り面白くないわ。と、言うことで今日はこれまで、解散にしよう!お疲れ様!」礼子の声を合図に、心地よい疲労を楽しみながらクラスメートがゾロゾロと帰っていく。後には礼子たち四人と慎治たちだけが残っていた。
「信次、正座。」玲子が静かに命令した。玲子の命令に突き動かされ、最後の気力を振り絞るように二人はのろのろと正座する。「どうかしら、少しは骨身に沁みた?反省したかしら?」「・・・は、はい・・・はん、せい・・・しまし、た・・・」消え入るような声で呟く信次を満足げに見下ろしながら玲子は冷笑した。「そう、それは良かった。だけどね、もう遅いのよ。信次、あんたたちは超えてはならない一線を飛び越えちゃったのよ。いくら反省しても、もう絶対に許してあげない。信次、あんたたちにはこれから、本物の苛め、ていうものを教えてあげるわ。私たちの全力で、本気で苛め尽くしてあげるからね・・・辛いわよ、覚悟しておくことね。」
ほ、本物の苛め・・・そ、そんな・・・い、一体なにをする気なの?ま、まさか、これから一本鞭で・・・
恐怖に引きつる二人に、後を引き取った礼子が告げる。「二人とも安心していいわ。今日これから鞭を追加する、なんてことはしないから。今日はもう、何もする気はないわ。ううん、それどころかこの週末は解放してあげる。ゆっくりと休んでいいわよ。」な、なにもしない?い、いやそれより、週末休ませてくれる?い、一体なぜ、どうして???予想外の礼子の言葉に、慎治たちは安堵よりも戸惑いと不安に包まれる。その困惑の表情を見て玲子が冷笑を浮かべた。
「信次、不安?怖い?自分がどうされるのか知りたい?ダメ、教えてあげないわよ。」礼子の美貌にも残酷な冷笑が浮かぶ。
「まあこれだけは教えといてあげるわ。玲子が本物の苛め、て言ったでしょ?念のため言っとくけど、今までみたいに単純に鞭で打ちのめすのが本物の苛めじゃないからね。鞭100発が200発になる、なんていう単純な責めを考えられたら困るわよ。ウフフフフ、血塗れになるまで鞭打たれたのが軽いお遊びに思えるような目に会わせてあげるわ。フフフ、週明け、楽しみにしていなさい、どういう目に会わされるのか・・・精々ゆっくりと想像してみることね。」「そ、そんな・・・な、なにを、なにをされるんですか・・・」「ど、どうするの、ぼくたちを・・・どうするつもりなの・・・おしえて・・・」涙を流しながら必死で尋ねる二人に冷笑を投げかけながら礼子たちは解散を宣言した。「それでは良い週末を!」「また来週!」
1
最低の週末、文字通り最低の週末を慎治たちは送っていた。許さない・・・礼子たちの言葉が重く重くのしかかっていた。あの目・・・礼子さんのあの目・・・真剣に、本気で怒っていたな・・・苛めを楽しむ様子すらなかったよ・・・どうしよう・・・完全解放の久々の週末、鞭で打たれずに済むのは本当に久しぶりだな。この2日間だけはおしっこを飲まされずに済むんだな。だけど・・・ちっとも嬉しくなかった。どんな目に遭わされるんだろう・・・鉛のように重い心を抱えながら慎治は机上の携帯を見た。今までの週末、不意に呼び出されるんじゃないか、体育館に、グラウンドに、さあ今から鞭打ってあげるからおいで!と慎治の都合など一切お構いなしに呼び出されたことを思い出す。友達など殆どいない慎治、携帯が鳴るのは礼子たちからの呼び出し以外には滅多にない。だから普段は携帯が鳴る度にギクッとするが今日ばかりは何故か、鳴ってほしいような気もする。とその時、いきなり着信音が鳴り響いた。
「ヒッ!」そ、そんな!鳴って欲しいなとは思ったけど、やっぱり鞭はいや!だが出るのが遅いとまた怒られる。震える手で慎治は携帯を掴んだ。「も、も、もしもし・・・」
「あ、慎治、ごめん・・・俺、信次だけど・・・」「何だ信次か・・・脅かさないでよ!」フウウッと安堵とも失望ともつかぬため息をつきながら慎治は座り込んだ。「どうしたの、何か用?」「ああ・・・慎治も考えてると思うんだけど・・・俺たち、どうなるんだろう・・・」「そ、そんなこと!ぼ、僕が、僕が知ってるわけないじゃない!そんなこと!!!・・・やめてよ・・・それ考えるともう、気が狂いそうだよ・・・」「そ、そんな、俺に怒るなよ!俺だって・・・俺だって死にたいよ・・・」「ああ・・・そうだよね・・・こんなとこで罵り合ってもしょうがないよね・・・で、どうされるんだろう・・・やっぱり・・・鞭かな?みんな・・・クラスみんなが鞭を買ってくるとか・・・」「みんなで鞭!?痛そうだな・・・だけどなんか、鞭じゃないような気がしないか?もっと何か・・・もっとずっと酷い目に遭わされそうな気が・・・」「・・・僕も・・・だけど、なんなんだろう?おしっこも飲まされたし、鞭よりも酷いことなんて・・・何???」
二人は際限なく愚痴と嘆きと自己憐憫を零しながら延々と自分たちを待ち受けるであろう悲惨な運命を、僅かでもいいから予想しようとした。なんとなくの予想は坊野たちが味合わされた拷問、あんな一生片輪にまではされないだろうが、死ぬほど痛い拷問をされるんじゃないか、それが二人の貧困な想像力の及ぶ限界だった。だが現実は二人の予想とは全く異なっていた。
無限とも思える精神的拷問の時間、遅々として動かない時計は針の音だけが矢鱈に耳障りに響く。まるで自分だけが時の流れから切り離され永遠の牢獄に閉じ込められたようだった。だが一歩また一歩と時はゆっくりとその時に近づいていく。恐怖が現実となる時へ。月曜の朝へと。
一睡もできないまま悶々と朝を迎えた慎治は足枷を嵌められたかのように重い足を引き摺りながら登校してきた。フウウウッ・・・来ちゃった・・・正門前で立ち竦んでいると、反対から信次が来るのが見えた。俯きながら歩いてきた信次がため息をつきながら顔を上げたとき、慎治は思わずギョッとしてしまった。酷い顔色・・・土気色じゃない?生気も全くないし、病人みたいだよ・・・気がつくと信次も自分のことを驚いたような顔で見ている。ハハハそうか、僕もなのか・・・僕も酷い顔色なんだね・・・死人みたいなんだろ?生きている死人、僕たちゾンビみたいなもんだね・・・
フラフラと教室に入っていくと二人は強烈な違和感を感じた。何、何か変・・・何なの?いつもは慎治たちが登校してくると早速クラスメートがクスクスと指を指して笑っていたり、或いは待ち構えていたかのように「さあトイレ行こう!」と声がかかったりする。だが今日は何もなかった。じっと見つめるクラスメートはいるが、直ぐに見てはいけない物を見てしまったかのように目を逸らしてしまう。
な、なんだ・・・何なの一体?こたえを求めるかのように必死できょろきょろする慎治はふと富美代と視線があった。「あ、ああ・・・フミちゃん・・・おはよう・・・ございます・・・」「・・・ああおはよう。」気のない返事を返して富美代はプイとそっぽを向いてしまった。え、えええ!?慎治たちは毎朝礼子、富美代、玲子、朝子に朝の挨拶をし、合格のハンコ代わりに唾を吐き掛けて貰うよう命じられていた。誰からも唾を吐き掛けて貰えなかったら、不合格の罰として放課後、ベルトで鞭打たれる。だが富美代は合格不合格以前に慎治の挨拶に全く興味がなさそうだった。恒例の朝一のおしっこすら命じる気配はない。
「ふ、フミちゃん・・・あの、その・・・」「何よ慎治、何か用?ああそうか・・・唾吐き掛けて貰ってないから気になるの?いいわよ別に、今日は合格、ていうことでいいんじゃない?」それに・・・と言いかけた富美代は口を閉ざして慎治の事をじっと見詰めていた。ゾクッ!慎治の背筋に何とも言えない悪寒が走る。富美代の視線、それはいつもの冷たい視線でも責め嬲る楽しみにふける残忍な眼差しでもなかった。その視線は・・・哀れみの視線だった。苛めの相手ではなく、幼馴染としての慎治の破滅を悼む憐憫の眼差しだった。
可哀想に慎治、私の幼馴染・・・その慎治がもう直ぐ破滅させられるのね。可哀想に・・・う、うそだ!こんなの、こんなことありえない!慎治の脳裏に富美代の残酷な笑顔が甦る。サイボーグとも言われるほど整った冷たい美貌に、冷笑を浮かべながら自分を散々責め苛んだ富美代の姿が。この美しい唇に何度唾を吐き掛けられたことだろう。引き締まった腕が振るう鞭でどれだけ泣き喚かされたことだろう。細く長い脚、白ブーツを履いたその脚でどれだけ踏み躙られたことだろう。そしてキュッと締まった形のよいお尻、そこから排泄されるおしっこを何回飲まされたことか・・・僕がどんなに泣き叫んでも絶対に許してくれなかった、それどころか楽しそうに笑いながらいつまでもいつまでも苛め続けたフミちゃんだよ?礼子さんにも負けず劣らずの、超の字がつく苛めっ子のフミちゃんだよ?そのフミちゃんが僕を憐れむだなんて・・・そんなことがある訳ないいいいっ!
「そ、そんな・・・ど、どうする気なの・・・僕たち一体・・・どうなるの・・・」フウッと富美代は小さく溜息をついた。「いいじゃん別に。どうなるかなんて、どうせ直ぐに分かるわよ。今聞いたとこで何の役にも立たないじゃない?」そ、そんなあああああっ!慎治は思わず富美代の足元に縋り付こうとしたが、丁度その時ホームルーム開始のチャイムが鳴った。そして授業開始、だが慎治たちは二人とも授業なんか全く聞こえてはいない。ひたすら恐怖に怯えるだけだ。そして一限が終了し、休み時間となったが、誰もトイレに引き立てようともしない。あああ・・・泣きべそを掻いている二人をおいて二限が始まった。そして終了間際、突然慎治は強烈な黒雲のような不安感、邪悪な違和感が襲い掛かってくるのを感じた。息が詰まるような嫌な感じだ。こ、この感じ、いつかどこかで・・・そうだ、あの時、礼子さんやフミちゃんが鞭を買った時の感じだ!と言う事は!!!
丁度その時チャイムが鳴り授業が終わった。教師が出て行ったのとほぼ同時に校内放送のチャイムが鳴った。「一年一組の川内信次、矢作慎治の両名は直ちに校長室まで来るように、繰り返します、一年一組の川内信次、矢作慎治の両名は直ちに校長室まで来るように。」こ、こ、校長室!!!な、何で僕たちが呼び出されるの!?予想外の展開に凍り付いた二人は必死に答えを求めるかのように辺りをキョロキョロと見回した。その二人に朝子が相変わらずキョトンとした表情で近づいてきた。「ほら二人とも早く行きなさいよ、みんな待ってるわよ。」無理やり引きずり出されるかのように廊下に連れ出された二人は夢遊病者のようにフラフラと歩いて行った。
校長室のドアの前でノックもできずに佇んでいると、気配を察したのか内側からドアが開けられた。何と校長の秋月自身だった。「ああ二人とも遅いじゃないか!呼びに行こうかとしていたところだったよ!さあ早く入って!」急かされて入った二人は中にいるメンバーを見て思わず呻いてしまった。礼子、陽子、玲子、有希子、担任の若月、そして二人の妙齢の女性がいた。日向怜と日向舞の二人だった。
2?
日向怜と日向舞、この二人は聖華において特別な存在だった。私立の聖華は法的には理事長個人の所有であり、怜と舞はその理事長の姪だった。独身で子供のいない理事長は怜と舞を我が子同然に可愛がり、理事長の財産である聖華は唯一の血縁である二人の母を経由して怜と舞、一卵性双生児の二人の美女が相続することも民法的にも既に確定している、と言ってよい。だが特別なのはその血縁だけではなかった。幼い頃より才媛の双子で有名だった二人は敢えて聖華へは進学せず、小学校から高校までを都内でも数少ない国立大学の付属校で過ごし、二人とも東大に進学した。怜は教育心理学、舞は経営学を学んだがそこでも才能を如何なく発揮した二人は今年、30歳という異例の若さで母校の助教授に抜擢され、1-2年後の教授退官時には二人が次期教授となるのはほぼ確実、と言われていた。
既に結婚し戸籍上は榛名怜、長門舞となっていたが、仕事上では継続して日向怜、舞と名乗っている二人は聖華においても旧姓を使用していた。仕事を引き受けたのは無論単なる根負けだけではない、有能な研究者である二人だが自らの教育、経営に関する知識を実践する、いわばフィールドワークとしての興味をそそられたこともあった。このため肩書き上は常任理事、と言うことでNO.2だが実質的にはトップとして学園経営に関する全ての決定を二人だけで下す権限を得た上で二人は聖華に着任した。
二人が外部の専門家としての視点で冷静に分析した聖華の現状、将来は決して明るいものではなかった。お嬢様学校とは言っても超ブランド校ではない聖華はその分野ではトップになれず、中の上のレベルを超えることはできない。一方、完全な受験校にシフトするのもまた、長年受験教育に注力してきたライバル校が数多い中では余り勝算が高いとは思えなかった。また教員の質についても極めて評価が低かった。お嬢様学校という美名に隠れて微温湯にどっぷりと浸り切り、自己研鑽を怠った教員が余りにも多過ぎた。
大体良妻賢母教育を目指しております、だなんて何時の時代の話をしているのよ?英語もパソコンもろくに出来ないで、十年一日の変わり映えのしない授業を惰性でやってるだけじゃない?じゃあクラブ活動に力をいれてるのか、と思えばお嬢様学校ですからクラブ活動などは程々が一番です?要するに何もやる気がないだけじゃない!怜の評価ではおよそ半分は教員としてのレベルは平均以下、不適格だった。些か八方ふさがり、とは言っても仕方ないわね、で片付けてしまうわけにはいかない。
「フウウッ・・・予想以上に酷いわね。ちょっとやそっとのことじゃ立て直せないわよ。」参った、というように舞は天井を見上げていた。「何か抜本的な事を考えないとね・・・」先程から黙って何か考えていた怜が舞の方に向き直り、口を開いた。「ねえ舞、いっそ思い切ってさ、聖華を共学校にしてみない?定員は今のままで増やさないで、男女各半々の完全共学校に変えるのよ。」「共学に変える?それはまた・・・随分思い切った、というか凄い提案ね。それ・・・真剣に言っているの?冗談でなく?」「うん、真面目も真面目、100%真剣よ。考えてもみてよ、お嬢様学校でも生き残れない、進学校にも成り切れない、となればこのまま女子校でいれば単なる中堅私立に埋没してしまうだけよ。だけど共学ならどう?私立の進学校は大体、男子校と女子校に分かれていて共学の進学校、というのは私立では数少ないのよ。多分レベルで言えば私たちの母校とか都立のトップとか、共学は公立の方が優勢よ。だからこそ、勝負できる可能性があると思うの、共学志向で優秀な生徒を集められれば結構展望開けるんじゃないかしら?」「・・・そうか!定員維持で共学化、となれは必然的に女子の倍率は上がって優秀な生徒に絞れるかも知れないわね。問題は男子だけど・・・どうなの?聖華を男子が受けるかしら?」「大丈夫よ!いい、男子校の伝統校は例え名門校でも、どこか荒っぽさが多少はあるものよ。大人しい系の男子でそういう雰囲気は嫌だ、もっと穏やかな柔らかい雰囲気がいい、ていう子も少なからずいる筈よ。そういう子たちにとっては元女子校、それも伝統あるお嬢様学校の聖華は格好の進学先になるはずよ!」「そうね・・・怜、そのプランいいわ、きっと行けるわよ!それに、多分もう一つ、いい効果が期待できるわよ。」「もう一つ?どういう事?」
「女子校から共学校への転換、この上ない大改革じゃない?だから聖華のもう一つの問題、無能な教員連中への踏み絵にもなるわよ。ずっと微温湯に浸りきっていたい、ていう連中がこの改革に賛成するわけないでしょう?きっと猛反対するわよ。フフフ、これからの聖華に不要な連中を焙り出して片付ける格好の踏み絵になるわよ、これ。大体考えて見れば、今はこの不景気じゃない?有能なのに勤務先がないとか、実力派なのに安い待遇で我慢している先生たちなんて幾らでもいるわ。無能な連中をカットしてそういう埋もれかけた有能な先生たちに入れ替えるには、今が絶好のチャンスよ!」「流石は舞ね、そこまでは私も気付かなかったけど、言われてみればその通りじゃない!まさに一石二鳥とはこのことね!じゃあ早速動き始めよう!」「ええ早速!じっとしている時間が勿体無いわ!」
この提案には怜と舞の学歴も大いに関係していた。怜と舞は小学校から大学まで一貫して共学育ち、しかも日本でもトップレベルの共学校育ちだ。従って少なくとも成績面においては男女全くハンディなく同一条件で競争することが当たり前、男女を分ける意味など全くない、と考えていた。また新世代の女性運動、特にジェンダー論にも詳しい二人にとっては良妻賢母教育のような役割分担に基づく教育は僻咾發痢・軌蕕諒鉸・⊆・僻歡蠅剖瓩ざ鬚砲發弔・覆こ鞠阿世辰拭・・・・隍苳・ぢ今時時代錯誤もいい加減にしなさいよね。体育とかで体力面のハンディがあるからクラス分け、種目分けするのは当然だけどあとは一々男だ女だ、て分けること自体がナンセンスよ。そんなことを今だに言っている教員は、自分の不勉強、怠慢をカモフラージュする隠れ蓑に使っている怠け者か本物のバカかのどちらかよ。いずれにせよそんな連中、要らないわ。無論女性否定的な面のある旧式なウーマンリブ運動と違い、怜も舞も女性としての自分を否定する気やユニセックス志向は毛頭ない。170センチの長身と引き締まったスリムなプロポーション、加えて溢れるばかりの知性をたたえながら何処か親しみやすい美貌。学生時代はモデルのバイトすらしていたほどの二人だ。ファッションにしろメイクにしろ、女性としての楽しみもフルに満喫しているし男性関係もかってはかなり派手な方だった。むしろそういった女性としての魅力を磨こうとしない、仕事とか学校の成績、点数しか興味のない古典的なガリ勉系の女性については心底軽蔑していた。ついでに言えば二人の夫もキャリア、知性、ルックス共に申し分のないエリートだ。一言で言って怜と舞は礼子たちと考え方、育ち共に極めて近い、ポジティブではあるが強烈な上昇志向の権化のような美女であった。
共学化の提案、それには当然のことながら猛反発が相次いだ。大まかに言って反対の根源は三団体、OG会、理事会、そして教員だった。このうちOG会は怜と舞が有力者に直談判し、呆気なく説得してしまった。同性から見ても人間的魅力に溢れた二人に説得されて、反対を貫く人間などそうはいない。理事会はもっと簡単だった。もともと理事長の個人的諮問機関の性格が強く、二人の母、何より自分たち自身も理事なのだ、何でも出来る。反対派の理事についてはさっさと解任してしまった。残るは教員たちだけだ。教員全員を集めて共学化方針を説明したときのリアクションは中々見物だった。反対意見、怒号、金切り声に近いヒステリックな声での反対意見一色だった。
「共学化?せ、せ、聖華の・・・伝統ある聖華の伝統をいったいなんだと思っているんですか!」「そ、そんな重大な決定をなんで、なんで我々教員に、聖華の全てを担う我々教員の意見も聞かずに決めようとするんですか!そ、そんなの絶対に認められませんんんん!」「大体受験だとか成績とかを考えること自体、お嬢様学校のメッカであるこの聖華にふさわしくないいいい!!!」愚にもつかない反対意見をヒステリックに喚き散らすのは大部分、怜が不適格と判定した無能教師、怠慢教師だった。中にはまともな教員もいるのだが、ヒステリックな反対意見に圧倒避けて賛成意見など到底言える雰囲気ではなかった。
全く呆れたものね・・・よくもまあ、自分たちのバカさ加減を棚にあげてそれだけ好き勝手に喚き散らせるものね。呆れ果てた二人は適当なところで打ち切り、適当に放って置いてから全教員に対して自由に意見表明させる記名アンケートを実施した。アンケートが配られた時の反対派教員の反応は後々まで二人の嘲笑のネタとなった。「おおアンケートか。やっとあのお嬢様方も、我々現場の意見を聞かないと何もできないということが少しはわかったようじゃないか。」「全くね、聖華を動かしているのは私たち教員だ、ていうことが今度のことで思い知ったでしょうよ。」「そうそう、まあ、あの世間知らずの小娘どもも、少しは世の中というものが分かったんじゃないの?いい薬になったでしょうよ。」そのアンケートは予想通り、反対意見が過半数を占めた。バカなことだった。怜と舞が着々とOG会、PTA、理事会と説得工作を終了させ新教員についても既に面接は一通り終了し殆ど目途がつきつつあることに、反対派は全く気付いていなかった。いや学園内、教員内部でさえ、心ある教員、有能な教員はさっさと賛成意見に転じていたことに気づいていなかった。そしてアンケートを回収した怜と舞は反対派の中から数人、指導力に優れた教員のみを選び出すと個別に呼び出して説得に当たった。知的な、そして人間的魅力に溢れた二人のたっての要請だ、心動かされない訳がない。加えて二人は共学化の大方針は譲らないが、それ以外の面、移行に伴う様々な問題点への対応については十分に教員の意見に耳を傾け、取り入れることを約していた。更には改革後の待遇改善まで約束されていた。これで転向しないわけがない。外堀、内堀は全て埋め尽くされた。後は無能教員に引導を渡すだけだった。そしてその日ももう間もなくだった。
遂にその日がやってきた。二人は既に新たに採用する有能な教員軍団を確定し正式契約も結んでいた。そして解雇する無能教員のリスト、アンケートの反対派および賛成としたが指導力不足著しく、今後の聖華には不要と判断した教員のリストも作成済だった。その朝、怜が切り出した。「さてと・・・今日、解雇通知するんだったわよね?もうリストも出来てるし、あのまま最終発表でいいわよね?」「勿論よ。じゃあ事務長に連絡しておくわね。」舞は内線電話を取り事務長を呼び出した。「ああ舞です、この前お渡ししたリストの件ですけど、今日正式に通告しますので、3時に対象者を常任理事室に出頭させてください。」そして3時、授業終了後に呼び出された教員がゾロゾロと常任理事室に入ってきた。全教員の半分強が呼び出されていた。大部分は自分たちより遥かに年上の教員たちを立たせたまま、自分たちは座ったままで先ず怜が単刀直入に用件を切り出した。
「今日来てもらったのは他でもありません、先日のアンケートに基づく理事会決定を通知するためです。皆さんは聖華の共学化、という大方針に反対意見を表明しました。無論、どういう意見を持とうと皆さんの自由です。しかしながら学園をどう運営するかの方針は私たち理事会が決定する事であり、皆さんはその執行機関に過ぎません、従ってあなた方は運営方針についてあれこれ口出しできる立場ではありません。それを勘違いしている皆さんは今後の聖華に不要な人材です。反対意見の方の中でも一部、指導力豊かな先生には今後の聖華のため、私たちからお願いして残って頂きましたが、ここにいる皆さんについては敢えて聖華に残って頂く必要はございません。従って、雇用契約が切れる今年度末、つまり来年三月末をもって皆さんを全員、解雇します。」
「か、かかかかか、かいこおおおおおっ!?!?!?」「そ、それって・・・クビっていうことかあああああっ?」「う、うそだろおおおおおっっっ!」金切り声に近い悲鳴に全く動ずることなく怜が答える。「そうですね、平たく言えばクビ、ということです。」声色一つ変えない怜の無情な宣告に悲鳴と怒号が木霊する。「そ、そんなそんなそんなあああああっ!お、横暴だ滅茶苦茶だあああっ!」「そ、そうだそうだあああっ!だ、断じてみとめないぞおおおおっ!と、とりけせええええええっ!!!」「ひ、酷いわ酷いわあんまりよおおおっ!こんなの絶対にみとめないわよおおおおおっっっ!!!」
一しきり悲鳴が木霊するのを舞は苦笑しながら眺めていた。・・・全く、自分たちの無能と馬鹿さ加減を棚にあげて、今更滅茶苦茶も何もあったもんじゃないわよね。大体認めないって、聖華には組合すらないのにどうやって私たちに反撃するつもりなのかしら?貴方たち低脳集団にはそんなことも分からないのかしらね。いい加減バカどもにはうんざりした、と言うように舞はバーン、と机を大きな音を立てて叩き教員たちを黙らせた。「皆さん何か勘違いしていませんか?私たちは今日、あなた方に解雇通知をする為に呼び出したんですよ?皆さんと話し合いをする為に呼び出したのではありません。もう一度言います。これは通知、私たちから皆さんへの通告です。どう言おうと勝手ですけど、私たちは皆さんと話し合いをするつもり等毛頭ありません。」
冷たく突き放す舞の言葉に毒気を抜かれたように教員たちは静まり返ったが、やがて再び騒ぎ出した。「そ、そんな・・・一方的な!」「そ、そうだ!俺たちの、俺たちの権利はどうなるんだ、こ、これは・・・そ、そうだ、ふ、ふと、不当・・・不当解雇だあああっ!」「そ、そうよそうよおおおっ!聖華を、私たちの聖華をどうするのよおおおっ!」呆れたかのように舞は首を振りながら答えた。「一方的?不当解雇?もう少し勉強してから物を言いなさい。いいですか、皆さんの契約は一年毎の年度更新契約なんですよ?長期雇用契約、ましてや終身雇用だなんていうのは皆さんの勝手な思い込みです。一度きちんと契約書を読んでごらんなさい?そしたら今みたいなバカなことは言えない筈ですよ。いいですか、もう一度いいます。これは皆さんを今年度末で解雇する、という通知です。法律上の通知義務期限より相当に早く通知して上げている訳ですから、私たちには何ら法的な問題はありません。もし皆さんがこれ以上、不当解雇だ何だと言うのでしたら別に構いません、遠慮なく裁判を起こしてください。当学園の顧問弁護士はご存知ですね?必要なやりとりは弁護士を通じてお願いします。あとは法廷でお会いしましょう。」
法廷で会いましょう、と言いながら舞は絶対に裁判になどならない、という確信を持っていた。全くバカよね、今更、事ここに至ってからで打つ手なんかあるわけないでしょう?私たちはリーガルチェックやらなんやら十分に手を打っておいたのに、あなたたちは何にもしないで只寝てただけじゃない?そんなんで勝負になるとでも思っているのかしら?舞の毅然とした宣告に黙り込んでしまった教員たちに、怜が追い討ちをかけた。「用件は以上です。皆さん、期日までに身辺整理をきちんとしておいてくださいね。ではさっさと退室してください。」それ以上抗議することさえできずに解雇された教員たちは廊下に追い出されてしまった。う、うううう・・・誰からともなく啜り泣きが広がっていく。う、ううう・・・その声は常任理事室の中にも聞こえてきた。
「・・・ったく!今更泣いたってなんか意味があるとでも思っているのかしら・・・大体今の聖華は給料も安いじゃない?馬鹿野郎、首にするなら勝手にしやがれ、俺みたいな有能な人間を首にしたらそっちが損するだけだぞ!て啖呵の一つも切れないのかしら・・・それをまあ、首にされてグズグズ泣いてるだなんて・・・私ああいうクズって大嫌い!ああいう連中見てるとムカムカする、思わず唾を吐き掛けてやりたくなっちゃうわ!」イライラしたように吐き捨てる怜に舞も大きく頷いた。「本当よねえ・・・自己研鑽なんて言葉とは全く縁のないクズどものくせして・・・連中きっと今、私たちの事をグチグチと呪っているわよ、自分たちの無能さを棚にあげてね。怜がさっさと連中を追い出してくれて良かったわよ。あんなカス共が目の前でグチグチ泣いてるのを見たら、ほんと思いっきり唾吐き掛けずにはいられないわよね。」「全く、大体連中、無能な癖に言うことだけは一人前の癖して、いざとなったらいい歳して泣くだけでろくすぽ反論もできないだなんて、本当に情けないわよね。フフ、首にされたくない人は私の靴を舐めなさい、なんて言ったら、全員が舐めちゃったりしてね!」「アハハハハッ!言えてるそれ、絶対に全員が舐めにきたわよ。でもまあ良かったわよ、あんな穢らわしい連中に舐められたら、私たちの靴が腐っちゃうわ!」フウウッ!と二人は大きく深呼吸をして気分を入れ替えた。「まあどうでもいいか、あんなクズども。どうせここをクビになったら自力で就職先探す度量もない能無しどもばかりだものね。プーになるかホームレスになるか、いずれどこかの吹き溜まりに落ちぶれていく連中がどうなろうと私たちの知った事じゃないわよね。あんな連中、唾を吐き掛けてやる値打ちもないわ。」「全く怜の言うとおりよね。あんなクズどもに吐き掛けたら、私たちの唾が勿体無い、て言うものよ!それより・・・やらなくちゃいけない仕事はまだまだ山積みよ。さあ仕事仕事!」未だ啜り泣き続ける教員たちを完全に頭の片隅からも消し去り、二人は仕事に戻っていった。そして4月、予定通り新生聖華は共学校に生まれ変わりその第一期生を迎えた。礼子たち、そして慎治たちだった。
3?
無論、この事は慎治たちの入学前の出来事だから彼らにとっては知る由もない。二人が怜と舞を見て呻いたのは別の理由からだった。怜と舞もまた礼子たち同様、あまりの美少女振りに護身術を学ぶ必要がある、と考えた両親の意見により幼いころから怜は合気道、舞は空手を学び大学では女子部の主将を務めた二人はインカレでも大活躍した程の腕前だった。二人は聖華の教員ではないので顧問ではないが、多忙な中での体調維持を兼ねて時折、生徒たちに交じって乱取り中心に汗を流し、礼子たちとも何回も拳を交えていた。礼子たちは部内では群を抜く実力者であるため本気になれば殆ど誰も相手にならない、だが怜と舞は些かレベルが違った。若い分、スタミナを含めた肉体的パワーでは玲子たちが勝るが怜と舞は豊富な実戦経験が磨いた多彩な技、そして冷静な状況判断と適応力を持っていた。若さに任せた礼子たちの力攻めに対応しきれないこともあるが、僅かでも隙ができれば直ぐに反撃される。子供の頃から通っていた道場でも女子の部では強すぎ、男性を相手にすることの方が多い礼子たちにとって、女性同士で全力で戦い五分がやっと、という相手は滅多にいなかった。加えて本物の知性と抜群のルックス、そして女性らしさと超一流のキャリアを併せ持つ怜と舞だ、礼子たちは珍しく一致して二人のことを心から尊敬していた。自分たちも将来ああなるわ、と言った身近な目標、と言ってもよい。怜と舞もまた、礼子たちのことを非常に気に入り可愛がっていた。優秀な成績と抜群の身体能力、そして活発な性格で周囲を明るくする性格。負けず嫌いで競争大好きだけどゲームのようなものと割り切り、明るく楽しくオープンに競い合うのでついつい周囲も私も負けない!と競争に参加してしまうから礼子たちの周囲は自然と優秀な生徒が、男女を問わず多い。まさに怜と舞が求めていた新生聖華の理想を体現するような存在だった。だから言ったでしょう、お嬢様学校なんてカビの生えたような建前は早く捨てましょう、て。これからはこういう、明るく強気の生徒を集めていかなくちゃいけないのよ!
それなのに慎治たちは致命的なミスを犯してしまったのだ。毎日毎日礼子たちに苛められる生活、そして教員も慎治たちの両親でさえも優等生の礼子たちに取り込まれ、誰も助けてくれない。誰か・・・誰か助けて!誰でもいい、礼子さんたちを止められる人はいないの!・・・いた!礼子さんたちよりもっと強い人が。「し、慎治・・・もう・・・もう駄目だ・・・俺もう・・・耐えられない・・・」玲子たちに週末、いつものように体育館に連れて行かれ死ぬほど鞭打たれた帰り、信次が思いつめたように呟いた。「ぼ、僕もだよ・・・誰か、誰か助けてよ・・・誰か・・・」ふと信次が何かを思いついたように顔をあげた。「慎治、舞先生なら、舞先生ならもしかして・・・」慎治もあっと言う様な顔をした。「そ、そうだ・・・怜先生、怜先生なら確かに・・・礼子さんたちも、怜先生と舞先生のことは尊敬している、て言ってたよね。だったら・・・怜先生たちに言って貰えばもしかして、礼子さんたちも聞いてくれるかもしれないよ!」この二人なら玲子さんたちも尊敬している、この二人なら・・・怜先生と舞先生に注意して貰えば礼子さんたちも言うこと聞くかも知れない!馬鹿な考え、馬鹿と言うより妄想に近いほど愚かな考えだった。慎治たちは怜と舞の本質を完全に誤解していた。意を決した二人は週明け、理事室のドアをノックした。「ハイ?どうぞ、開いてますよ。」怜の澄んだ声が聞こえた。「し、失礼します・・・」学園の最高実力者の二人に直訴しようというのだ、緊張からおどおどとしながら二人は理事室に入った。「あら君たちは・・・確か川内・・・信次君、だったかしら?空手部にいたんじゃなかった?そちらは矢作慎治君ね、確か一年一組だったかしら?」と舞が如何にも何の用かしら、忙しいんだけどな、と言う様に少し苛ついた声をあげた。「ああ・・・そういえばどこかで見たことあるな、と思ったわ。矢作君は確か、合気道部にいたわね。で、どうしたのかしら今日は急に。呼び出した覚えはないと思うけど、何か急ぎの用件でもあるのかしら?」怜も訝しげにしていた。
無理もない、教員ではなく理事である二人に対し一生徒に過ぎない慎治たちが何か用件がある、とは思えなかった。い、いけない・・・早く、早く言わなくちゃ、お願いしなくちゃ!二人の苛立った声に急かされたように、慎治が口を開いた。「すすす・・・す、すみません・・・お、お忙しいところ・・・そ、その・・・礼子さん、天城、礼子さんのことで・・・・お、願いにきたんです!」信次も急いで付け加える。「そそそ、そう、そうなんです!霧島・・・玲子さんのことです!」天城さんと霧島さんのこと?一体どういうこと?「まあ兎に角、立ったままって言うのも何だから、そちらに座りなさい。」怜が部屋の片隅の応接コーナーを指し示し、慎治たちを座らせ、自分たちも席を移した。全く何の用なのかしら・・・苦笑しながら舞が尋ねた。「天城さんと霧島さんのことで私たちにお願いですって?一体何なのかしら?あ、もしかして二人に告りたいから応援してくれ、とかいうことかしら?」常識的にはこんな所としか思えない。フフフ、と怜も苦笑した。「・・・まあそういうところかしら?でもそういうことだったら、あなたたちクラスも部活も一緒なんだから私たちなんかを経由しないで直接口説けばいいじゃない?・・・まあ勝算はちょっと低いかな、とは思うけど、たまには玉砕してみるのもいいものよ。」怜も苦笑しながらフォローする。く、口説く!告る!ぼ、僕たちが礼子さんたちに!飛び上がらんばかりに驚いた二人は反射的に金切り声で絶叫してしまった。「そ、そそ、そんな!れ、玲子さんに告るだなんて!そ、そんな!」「そ、そうですうっ!逆、逆逆!ぼ、僕たち・・・礼子さんたちに苛められているんですうううっっっ!」苛められている?一体どういうこと?流石に二人とも当惑を隠せなかったが、怜が静かな声で尋ねた。「今・・・苛められてる、て言ったわね?どういうこと、落ち着いて話して頂戴。」
は、話を聞いて貰える!慎治たちは急いで争うように話し始めた。礼子たちに蹴りのめされ打ちのめされたことを。唾を吐き掛けられブーツで踏み躙られたことを。鞭で打ちのめされたことを。そして・・・おしっこを飲まされたことも。慎治たちの告白が一段落した時、信じられない、といった表情で首を振りながら舞が呟いた。「フウウッ・・・些か信じられない話ね・・・」し、信じられない!「そ、そんなお願い信じてくださいいっ!ほ、本当なんです、そ、そうだ証拠、証拠もあります!こ、この背中、この背中を見てください!き、昨日、昨日玲子さんたちに・・・玲子さんたちに鞭打たれたんです・・・こ、この傷、この傷を見てくださいいいっ!」信次はボタンを引き千切らんばかりの勢いでシャツを脱ぎ、背中を二人に向けた。「そそそ。そうですううっ!ぼ、僕も・・・僕も死ぬほど鞭で叩かれたんですうううっ!こ、この背中を・・・見てくださいいいいっ!」慎治も急いでシャツを脱ぎ鞭跡だらけ、蚯蚓腫れと青痣に彩られた背中を二人に向けた。「う、ううう・・・全部、全部玲子さんたちに・・・やられたんです・・・」「ヒッヒック・・・僕たち・・・何もしてないのに・・・死ぬほど鞭打たれたんです・・・」自分たちの言葉に、行為に酔ったかのように慎治たちは泣きながら涙ながらに訴えた。きっとわかって貰えると、この凄惨な鞭跡を見ればきっと僕たちのことを何て可哀想に、と同情してくれるに違いない、助けてくれるに違いない、と慎治たちは信じて疑っていなかった。そして愚かな二人は未だ気付いていなかった。怜と舞が同情ではなく、軽蔑と嫌悪の表情を浮かべていることに。「・・・もういいわ、二人とも早くシャツを着なさい。」怜が嫌悪感を露にしつつ冷たい声で言った。シャツを着終えた二人を座らせ、舞が静かに尋ねた。「言ってることは良く分かったわ。どうやら苛められてる、ていうことは本当みたいね。多分・・・おしっこまで飲まされている、ていうのも本当なんでしょうね。で、それで?私たちにどうして欲しいの?何を言いにここに来たのかしら?」舞の声も静かだが剣呑なトーンになりつつあることに、信次は全く気付いていなかった。「そ、それはもちろん・・・お願いです、玲子さんに、玲子さんに言ってください!こんなことはもうやめろって!こんな苛めはもうするなって言ってください!お願い・・・します・・・」「矢作君、あなたのお願いも同じなの?」怜も静かに尋ねた。「そそそ、そうです!そうですそうですうううっ!せ、先生の・・・先生の言うことなら礼子さんたちもきっと聞いてくれます、お、お願い、お願いです助けて・・・くださいいっ!」必死で涙を流しながら縋るように哀願する慎治たち、そんな二人を静かに見据えていた怜がゆっくりと口を開いた。「そう、あなたたちのお願い事は分かったわ。じゃあ答えてあげる。これが私の返事よ・・・ペッ!」鮮紅のルージュを引いた怜の唇が急速に盛り上がったかと思うと、慎治にとっては見慣れたもの、唾が吐き出され慎治に襲い掛かった。ペチャッ!あ、あああ・・・予想外の展開に驚いた信次が顔を上げると舞が冷たい眼差しで自分を睨み付けていた。こ、この目・・・玲子さんたちと同じだ、そ、そんな何故!?「私の返事も同じ。川内君、これが答えよ・・・ペッ!」信次が言葉を発するよりも早く、舞もピンクのルージュを塗った唇を二、三回クチュクチュと動かしたっぷりと唾を溜めると思いっきり信次の顔に吐き掛けた。ペチャッ!既に数え切れないほど味合わされた汚辱の感触、女性に唾を吐き掛けられた感触が信次の顔面を走る。「あ、あああ・・・そんな・・・」「な、なんで・・・」余りのことに吐き掛けられた唾を拭うことも忘れ、顔に今吐き掛けられたばかりの怜と舞の唾を滴らせながら慎治たちは呆けたような声で呟いた。
「なぜ?なぜ唾を吐き掛けられたか分からないの?」怜が軽蔑に満ちた声で問い詰める。「全く・・・よくもまあ恥ずかしげもなく、こんなことをお願いできたものね!そんな男、いえ男なんて言えないわね、そんなクズはこうやって唾を吐き掛けられるのがお似合いでしょう?」舞も心底呆れたというように、信次のことを見据える。「川内君、あなた一応男の子でしょう?それが女の子に苛められてるんです、先生助けてくださいいい?言ってて恥ずかしいと思わないの?この・・・意気地なし!ペッ!」唾を吐き掛けた唇を軽蔑に歪めながら舞が続ける。「何のつもりでそのみっともない鞭跡だらけの、汚らしい背中を私たちに見せたのか知らないけど、そんなに嫌だったら何で嫌と言わないの!?何で毅然と断らないの!?霧島さんたちの方が強いから、なんて言い訳にもならないわ。負けても何でも本当に嫌なら100回でも200回でも戦えばいいじゃない!それをあなたたちは毎週のこのこと体育館やグラウンドについて行って・・・挙句の果てにおしっこを、霧島さんたちのだけではなく萩さんや神崎さんのおしっこまで飲んでます?ふざけるのもいい加減にしなさい!ペッ!」舞の一喝に怜も大きく頷いた。「舞の言うとおりよ。いい、二人ともよく聞きなさい、戦いもしないで苛められてる、て言うのはね、あなたたち自身がお願い苛めてください、て天城さんたちにお願いしているのと同じことよ!そうやって苛めてくださいおねがいしますうう、てやっておいて、何が僕たち鞭で打たれて泣かされてるんです、助けてくださいよ!甘ったれるのもいい加減にしなさい!ペッ!」情け容赦なく断罪しながら、怜と舞は慎治たちに何回も何回も唾を吐き掛けた。「このクズ!落ちこぼれ!君たちみたいな情けない連中はね、一生こうやって唾を吐き掛けられているのがお似合いよ!ペッ!」憎々しげに言い放ちながら思いっきり唾を吐き掛けた怜の後を引き取るように、舞も信次をこの上ない軽蔑と共に睨み付ける。「全く、よくもまあこんな情けないお願いに来れたものね!そんな情けない人間、生きている資格なんかないわ!さっさと死になさい!ペッ!」あ、あああ・・・慎治は余りに峻厳とした怜と舞の拒絶に愕然としながら、同時に無限の絶望を感じていた。だが、どうしても怜と舞の言葉を受け入れることはできなかった。鞭打たれおしっこを飲まされて毎日苛められている自分たち、それは全て自分自身の情けなさのせい、それは恐らく真実だろう。だがその真実を受け入れる事はどうしても出来なかった。そして面罵され心底蔑まれて挙句の果てに唾まで吐き掛けられてもそれでも尚、慎治たちは怜と舞にすがらずにはいられなかった。「そ・・・そんな・・・せんせい・・・」「ひ・・・どい・・・お願い、見捨てないで・・・ください・・・」そんな慎治たちの哀願は怜と舞の怒りの炎に油を注ぐだけだった。「・・・まだ言うの・・・この・・・クズ!ペッ!」「どうしようもないカスね、あなたたちは・・・何で自殺しないのよ!ペッ!」最早軽蔑を通り越し憎悪も露に怜と舞は再度、思いっきり唾を吐き掛けた。ああ、あああ・・・慎治たちは涙を流し、だらしなく口を開けて嗚咽を漏らしながら怜と舞の唾を浴び続けた。鮮紅のルージュを塗った怜の唇、ピンクのルージュに彩られた舞の唇は際限なく、慎治たちの全人格を否定する罵倒と侮蔑の言葉を吐き出した。凛とした鞭のように厳しい二人の声で浴びせられるそれらの言葉は、まともな男ならば一言浴びせられただけでも恥辱に打ち震えてしまう程のものばかりだった。そして罵倒の言葉の合間、一瞬沈黙を入れると二人は唇をクチュクチュと動かし唾を溜め、次の瞬間思いっきり吐き掛ける。急速に盛り上がる唇、吐き出され宙を切り裂く白い矢、そしてビチャッと汚辱の液体が顔を汚す感触。既に数え切れないほど味合わされた屈辱の儀式が再現され、慎治たちの惰弱な精神をズタズタに引き裂いていく。
何なのよこの子たちは。唾を吐き掛けながら、面罵しながら怜と舞は強烈な違和感、嫌悪を通り越した一種異様な不気味さを感じていた。いくら罵っても唾を吐き掛けても、慎治たちは涙を流し必死で哀願して許しを請いながらも、顔を伏せたり背けたりもせずに怜と舞の顔から視線を逸らそうとしないのだ。何度唾を吐き掛けても吐き掛けても、飛んでくる唾を手で避けようともしないのだ。あたかも唾をおねだりするかのように、慎治たちは泣きながら汚い顔を怜と舞に向け続けていた。その不気味なほどに惨めな様は怜と舞を余計に苛立たせた。何なのよ君たちは・・・これでもまだ足りないって言うの!ペッ!怜は自分の唾が慎治の眉間に炸裂し、ゆっくりと頬を伝っていくのを、慎治の顔面が自分の唾で醜く彩られて行くのを嫌悪感も露に睨み付けていた。軽蔑侮蔑嫌悪焦燥憎悪・・・吐き気を催しそうな程、慎治たちは気味が悪かった。あらゆる黒い衝動が怜と舞の全身を貫く。吐き掛けても吐き掛けても、止め処もなく唾が口の中に湧き出してくる。唾を吐き掛け罵り続けていないと、怜と舞の方が正気を失いそうだった。一体どういうつもりなのよ・・・何ぼうっとしているのよ!ペッ!痴呆のようにだらしなく口を開けたまま泣いている信次の顔に舞は思いっきり唾を吐き掛けた。もう何回唾を吐き掛けられたと思っているの?何で唾を吐き掛けられているのに私のことを見続けていられるのよ、このキチガイ!いい加減にしなさいよ!聞いているの!
不意に怜が黙り、慎治の顔を覗き込んだ。「アウッ、ヒッヒック・・・許して・・・」泣きながら哀願する慎治、自分の吐いた唾に塗れた顔で哀願する慎治を怜は氷のように冷たい表情で睨み付ける。「何なのよ君は、一体どういうつもりなの?さっきから何回唾を吐き掛けられても避けもせず顔を背けもしないでバカみたいに私のことを見詰めちゃって。まさか喜んでいるの?罵られて唾を吐き掛けられるのが嬉しいとでも言うの?この・・・変態!」そ、そんな違ううううっ!だ、だってだって・・・「何よ何か言いたいの?言いたいことあるならはっきり言いなさい!」言いたい、僕だって言いたい・・・だけど、だけど・・・口ごもる慎治に苛ついたかのように、舞が信次の胸倉をグイッと掴み引きずり寄せる。「アウッ、ウウウ・・・」引っ叩かれる!思わず下を向いてしまった信次の顔を邪険に跳ね上げながら舞は更に引きずり寄せる。あああ・・・目の前30センチに舞の美貌があった。知的な美貌を怒りに燃え上がらせた舞、夜叉のような怒りの形相はなまじ美人な分、余計に恐ろしい。だが同時に色白な頬を上気させた舞はゾクッとするほど美しかった。その凄絶な美貌と大きな瞳に射抜かれたように、信次は身動きひとつできない。「矢作君はどうやら口が訊けなくなったみたいだから、君に聞くわ。一体なんで?どうして君たちは避けもしないで唾を吐き掛けられ続けているの?はっきり答えなさい!」あう、あうう・・・恐怖に怯え、痴呆のように呻きながら信次は反射的に答えた。「れ、れいこ、玲子さんが・・・」「玲子さん?霧島さんのこと?霧島さんがどうしたって言うのよ、私に分かるように、はっきり言いなさい!」鞭のように厳しい舞の声に信次の全身がビクッと痙攣する。ヒイイイッお、怒ってる、舞先生怒ってる、言わなくちゃ、言わなくちゃ・・・「玲子さんに・・・命令された、んです・・・唾を吐き掛けられる時は絶対避けるな、顔を背けるなって・・・」「ハアッ?唾を避けるな、て命令されている?矢作君、君もそうなの?天城さんに命令されているから、それで大人しく唾を吐き掛けられている、ていうわけ?」呆れたように尋ねる怜に、消え入りそうな声で慎治が答える。「・・・はい・・・絶対に避けるな、て。避けたら鞭で叩くよ、て・・・自分たちだけじゃない、クラスの誰が唾を吐き掛けた時でも絶対に避けるな、て、避けたって聞いたら泣くまで鞭で引っ叩くわよ、て言われたんです・・・」ハアッ?一体何を言っているの?信じられない、という面持ちで首を振りながら怜が尋ねた。「ねえ矢作君、君自分が何言っているか分かっているの?唾吐き掛けられても何の抵抗もしないだなんて・・・唾を吐き掛けられるなんて人生最大の侮辱よ、大抵の人間は唾を他人に吐き掛けられるなんて、一生縁がない話よ。それを怒るは愚か避けもしないで視線も逸らさずにいるなんて・・・君それで本当にいいの?君はそれでも本当に人間なの?」フウウッ・・・舞の深い溜息が漏れた。「君たち・・・信じられない位腐り果てているのね。私だったら、唾を吐き掛けられたりしたら絶対許さない、一生許さないわよ。それが普通の人間でしょう?それを君たちは・・・呆れて物も言えないわ。」「だって、だつて・・・」「そ、そんな・・・唾なんて僕たちも嫌・・・だけど、だけど・・・」泣きながら慎治たちは必死で言いすがった。怜先生たち、少し声が静かだ、もしかしたら、もしかしたら僕たちを少しでも哀れんでくれるかも・・・淡い幻想に縋りながら慎治たちは消え入りそうな声で縋りついた。「でも・・・礼子さんたちに逆らったら・・・死ぬほど苛められるから・・・」「だって鞭で・・・鞭で叩かれたら誰だって・・・」
胸がむかつく程の嫌悪感を必死で抑えながら、声だけは努めて冷静に保ちながら舞は信次の顔を上げさせた。「川内君、しっかり目を開けて私のことをご覧なさい。」ヒック、ウエック・・・咽び泣きながら信次が顔を上げるのを舞はじっと待っていた。のろのろと顔を上げた信次の、生気がない怯え切った惨めなネズミのような目を舞の鋭い視線が射抜く。「川内君・・・もう君たちの顔なんか見たくもないんだけど、一回だけ教育を施してあげるわよ。」「きょ、教育?な、何です・・・か?」また、苛められるの、と怯えながら信次がオドオドと尋ねる。「別に大したことじゃないわよ。少しは君に自分の意志というものを教えてあげようというだけよ。いい、今から私は君にもう一度唾を吐き掛けるわ。だけど避けていいわよ。手で顔を覆うなり顔を背けるなり、この場から逃げ出すなり、どうとでも好きにしていいわ。私が許可してあげる。いい?避けていいからね、私の唾をちゃんと避けるのよ!」「えっええっ、そ、そんな・・・」「そんな?何がそんなよ。吐き掛ける私が許可してあげているのよ、それでも唾を避けられない理由があるとでも言うの?自分は人間です、と言いたいなら、せめて唾くらい避けてご覧なさい!行くわよ!」あ、あああ・・・信次は目の前で舞が美しい唇をクチュクチュと動かし唾を溜めるのを震えながら見ていた。よよよ、避けなくちゃ避けなくちゃ・・・いいって言った、舞先生、避けていいって言った・・・嫌だ、唾掛けられるのなんて嫌、大嫌い!よ、避ける避ける、手を上げて顔を下ろして・・・だけど、だけど・・・だが思い出したくない、今この時は絶対に思い出したくないイメージが信次の脳裏に鮮明に浮かび上がる。玲子の美しい顔が信次を見下ろしている。凛とした声が、まるで玲子がここのいるかのように響く。「信次、唾を避けたら・・・分っているわね?鞭で死ぬほど引っ叩くわよ。」ああ、あああ!い、嫌、いやあああああ!や、やだ、唾、舞先生の唾を避けるんだああああっ!信次は必死で玲子のイメージを掻き消そうとした。だが玲子の呪縛は信次が抗えば抗うほど強くなっていく。
目の前では舞が既に、口の中に十分唾を溜め終わっていた。大きく息を吸いながら、舞が反動を付けるかのように首を僅かに後ろに引く。ああ、あああ・・・先生、唾を吐き掛ける準備完了したんだ・・・く、来る!よ、避けるううう!手を上げるううう!だが信次の両手は鉛の手錠を嵌められたかのように重く、ピクリとも持ち上がらない。か、顔を・・・曲げるううう・・・首はギブスで固定されたかのように硬直し、僅かに震えるだけだ。そして目は舞の冷たい魔眼に魅入られたように吸い寄せられ、視線を逸らすことさえできない。クッ、舞の顔が前に動く、と同時にピンクの唇が急速に盛り上がり、たっぷりと溜められた唾を猛スピードで吐き掛けた。ペッ!ビチャッ!先ほどまでに何度となく響いた音、舞が唾を吐き掛ける音と唾が信次の顔面を直撃する音がまた響いた。「避けていい、て言ったでしょう?何故避けないの?もう一度行くわよ・・・ペッ!」二度、三度と舞は唾を吐き掛け続けた。目の前で繰り広げられる光景を舞は到底信じられなかった。「何でなのよ・・・避けていい、て言ったでしょう?それを何でそうやって平然と唾を吐き掛けられ続けているのよ・・・このクズ!ペッ!」舞はああもう!と言わんばかりに激しく首を振りながら怜の方を振り向いた。「怜、私もう頭が変になりそうよ!何なのよこの子たちは!」苛立ちを露に舞は険しい声を上げた。これ以上信次の顔を見ていたら、自分の抑えが効かなくなりそうだった。目の前で薄汚い泣き声を上げている惨めな化物を無性に張り倒し蹴り倒し、踏み潰してやりたかった。駄目、もう殺したくなっちゃうわ・・・「私もよ。本当にもう、絞め殺してやりたいわ・・・」怜の顔色も怒りの余り蒼白になっていた。「信じられないわ、こんな連中が本当にこの世に存在していたなんて。ああもう!」大きく息を吸いながら怜は慎治を睨み付けた。「ヒッ!」殴られる!反射的に慎治は両手を跳ね上げ、頭を庇った。だが打撃はこない。ぶ、ぶたないの?両手の合間から覗き見ると怜が少しほっとしたような目で見ていた。「ああ良かった、どうやら矢作君の手は動くみたいじゃない。いいわよ、ぶったりはしないから、安心しなさい。」フウッと溜め息を吐きながら怜が言った。「そうよ、怖かったら、嫌だったらせめてそうやって固まっていればいいのよ。そうやって自分を庇えばいいのよ。」吐き捨てるように言う怜の言葉に慎治は少しだけほっとした。だが怜の次の言葉に慎治は呻いてしまった。「いい矢作君、そのまま聞きなさい。こんな言い方、バカらしくて有り得ないんだけど、君たちにはどうやらこのレベルからじゃないと駄目みたいだからね。いい?今から私も唾を吐き掛けるわ、だから君はそのまま固まっていなさい。そうすれば私の唾は避けられるんだから。それとこれも約束してあげる。天城さんたちには絶対に言わないわ。君が私の唾を避けたことは絶対に言わないであげる。私が黙っていれば、天城さんたちにバレル心配はないわね?バレなければ鞭でお仕置きされる心配もないわよね。どう、これなら安心でしょう?安心して唾を避けられるでしょう?」「えっええっ、そ、そんな・・・お、お願いです、もう唾掛けないで・・・」「ああもう掛けないであげるわよ!私だって君たちにはもううんざり!だから君が一回でいいから私の唾を避けられたらそれでお終いよ!一回でいいから避けなさい、そしてさっさと私たちの目の前から消えうせて頂戴!」吐き捨てるように言いながら怜は口に唾を溜めていく。この蛆虫は・・・でもいくらなんでもこれなら避けられるでしょう?そのまま凍りついていればいいんだから。慎治も同じだった。ヒッ、動いちゃ、動いちゃ駄目、怜先生をもっと怒らせちゃう・・・礼子の美しくも恐ろしい幻影は勿論慎治の脳裏にも浮かんでいた。れ、礼子さん、礼子さんの命令を破っちゃう・・・だけど、だけど怜先生も怖い・・・それに約束してくれた、礼子さんには言わない、て約束してくれた、だから、だから大丈夫、礼子さんにはぶたれないはず・・・だが礼子の呪縛は慎治の精神の深層、殆どリビドーに至るまでに及んでいた。十分に唾を溜めた怜が鮮紅の唇、散々慎治に唾を吐き掛けたためしっとりと湿った唇を突き出した時、慎治の精神を瞬時に三つの映像が同時に埋め尽くした。
一つ目は鞭を携えた礼子だった。「慎治、いい、よく聞きなさい。今から先、私にも他の誰にも、唾を吐き掛けられる時には絶対に避けちゃ駄目よ。顔を背けるのも手で避けるのも絶対禁止。唾を吐き掛けられる時は必ず、相手の顔をしっかりと見なさい。自分が唾を吐き掛けられるところをしっかり見ておくのよ。もし避けたらどうなるか・・・この鞭で教えてあげるわ!」言い終えると同時に礼子の鞭が宙を舞った。ヒュオッ、バシーンッ、ヒイイイイッ!鞭の音と慎治の悲鳴がクロスする。「い、痛いいいいっ!よ、避けてない、避けてないじゃないいいいっ!」「何言っているのよ、当たり前じゃない!今私、唾引っ掛けたりしていないでしょう?今はね、唾を避けたらどうなるかを教えてあげているのよ、この鞭でね!唾を避けたらどうなるかたっぷりと学習しなさい!それっ!」そのまま何十発打たれたか、ピクリとも動けなくなるまで鞭打たれた映像だった。二つ目は唇を突き出して今まさに唾を吐き掛けようとする和枝の顔だった。「慎治、お早う!」明るい和枝の声に何気なく「あ、お早う」と言いながら振り向いた慎治に、和枝はペッと朝の挨拶代わりに唾を吐き掛けた。「アッ、な、何を!」予期せぬ唾に慎治は思わず手を上げて和枝の唾を避けてしまった。その瞬間、ガタッと礼子が立ち上がる音がした。あ、あああっっっ振り向いた慎治が目にしたものはベルトをウエストから引き抜いている礼子の姿だった。「慎治、今和枝の唾を避けたわね、お仕置きよ、お尻を出しなさい!」たったそれだけの理由でクラスメートたちに取り囲まれながらたっぷりと鞭打たれた映像だった。そして三つ目は眼前に迫り来る礼子の漆黒のブーツだった。いつものように週末、体育館に呼び出されて死ぬほど鞭打たれた後、帰り間際になって慎治は礼子の前に正座させられた。「慎治、これで今日の私の鞭はおしまいよ。」フウウッ・・・鞭の激痛の余韻に啜り泣きながら慎治は緊張の意図が途切れたかのようにがっくりとうな垂れた。その顎を礼子のブーツがこじ上げる。「ところで和枝から聞いたんだけど、あんた水曜に陽子が唾掛けた時、顔を伏せて避けたそうじゃない?」「そ、そんな、そんなあああ!あれはち、違う、避けただなんて!アガッ!」顎をこじ上げていた礼子のブーツが一閃し、慎治の顔面を蹴り倒す。アウッ、アウウウウ・・・痛さに呻く慎治に礼子がゆっくりと近づいてくる。「ヒイイッ!ガハアッ!」逃げようと必死で上半身を起こした慎治を強烈な回し蹴りで叩き伏せた礼子は仁王立ちのまま顔面をブーツで踏み躙る。「ヒイイッヒイイイイッ!だ、だじげでえええええっ!」「慎治、未だ私の命令が守れていない様じゃない?いいわよ、命令に背いたらどうなるか、骨の髄まで叩き込んであげる!」慎治の顔面を踏み付けた礼子は、足首をクイッと返すとブーツの爪先に全体重を掛けながら無理矢理慎治の口中奥深くへと捻じ込む。「アゴオオオオッガガアアアアアッ・・・」口一杯にブーツを咥えさせられ、余りの苦しさと顎が外れそうな激痛に耐えかねた慎治は必死で礼子のブーツを押し頂くように支える。喉の奥に爪先が当たり気道を殆ど塞いでしまっている。ソールの幅広な部分と優美な甲の曲線が慎治の口を張り裂けんばかりに、限界ギリギリまで押し広げている。これだけで、ブーツだけで十二分な苦痛だ。だが見下ろす礼子の瞳は更に残酷な炎に燃え上がっていた。フフフ慎治、無様な姿ね、お似合いよ。涙目で縋り付いちゃって、みっともないったらありゃしない。だけどダーメ、泣いたって何したって許してあげないわよ!そうやって慎治が泣けば泣くほど、ウフフフフ、もっと泣き叫ばせてやりたくなるわ!ブーツを咥えた惨めな慎治を冷たく見下ろしながら、礼子はシュルッと肩から鞭を外すと柄と先端を握り、二つ折りにする。「さあ逝くよ、私の命令に背くとどうなるか、たっぷりと思い知らせてやるからね!」ビュオッバシイッヒュンッビシイイイッ!礼子は全体重を慎治の口に掛けながら後ろ手で慎治の柔らかい脇腹、全く腹筋のない弛んだ腹から太腿に掛けて強烈な鞭を浴びせた。「びいいいいっ!びだいいいいいっ!ゆるじでえええええっ!!!」「アンッ?何言ってるの、全然分かんないわよ、許して欲しいなら許して欲しいで、ちゃんとお願いしなさい!」
だが口一杯にブーツを押し込まれてまともに言葉など発せられる訳がない。フフフ、クックックッ、アハハハハハッ!礼子はこみ上げてくる楽しさを押えきれないかのように高らかに笑っていた。ああ最高!こうやってブーツ咥えさせるのってほんと、楽しいわよね。爪先を無理矢理捻じ込んでやっている時の慎治の惨めな顔!もう最高!惨めな虫ケラ、私のブーツで地べたに縫い付けられているみたいじゃない!どう慎治、痛い?苦しい?顎を外してあげようか?簡単よ、私が足首一つ返せば、慎治の顎なんか簡単に外せるのよ?アハハハハッ!必死で私のブーツを押し頂いちゃって!そうしないと苦しいものね、窒息しちゃうものね、だけどそうやって両手塞がってたら、鞭はど・う・す・る・の・か・な・あ?あっやっぱり痛くて手をブーツから放したわね、じゃあいいわ、そーれっと!ほーら、もっと喉の奥までいれてあげる、私のブーツ、たーっぷりと苦しめてあげる!どう?突っ込まれるだけじゃ変化が足りない?じゃあこうやって足首を捻ってあげようか?苦悶と激痛の二重奏、鞭を振るう腕とブーツで踏み躙る脚、自分の体がフルに慎治を苦しめ地獄を味あわせるのを礼子は心ゆくまで堪能していた。ウンッ?何かしら?不意に礼子は、慎治の口に押し込んだブーツ越しに何か締め付けられるように感じた。ガギイイイイイッ・・・余りの苦痛に慎治は馬のハミよろしく礼子のブーツに必死で噛り付いていた。クックックッ、礼子の顔に楽しそうな笑顔が浮かぶ。「慎治、どうしたの私のブーツ齧っちゃって。そんなにおいしい?いいわよ遠慮しなくて、もっともっとたーっぷりと味あわせてあげる。そら!そら!そら!ほらそんなんじゃ噛んでるのかどうか、私に全然伝わらないよ!ブーツに噛み付きたいんでしょう?私に痛い思いをさせたいんでしょう?だったらもっとしっかり齧んなくちゃ全然効かないわよ。ほらほらほらどうしたのかなあ?マッサージでもしてくれてるつもりなの?駄目じゃん慎治、もっとしっかり抵抗しなくちゃ!気合の鞭を入れてあげようか?そら!そら!そら!」ビシッバシッパーーンッ!礼子は慎治の反撃ともつかぬあがきさえ、新たな愉しみに変えてしまった。バカね慎治、顎の力程度で私のウェイトに勝てるわけないじゃない。むしろそうやって力を込めてくれた方がしっかり体重かけられて都合がいいっていうものよ。第一ブーツの厚い革越しよ、ソールもあるのよ、どうやったって歯が立つ硬さじゃないわよ。まあ精々頑張りなさい、その分、ゆっくりと苛めさせてもらうから。やがて精根尽き果てたように慎治の歯から力が抜けていく。腹を庇っていた手も殆ど力が抜けガードしている、というより単に腹に置かれただけになっていた。痛い苦しい・・・そして何より疲れ果てていた。痛くても苦しくてももう、何をすることもできなかった。唯々礼子の鞭に打たれ続ける人形に成り果てていた。漸く礼子が許した時、慎治の弛んだ腹は真っ赤に彩られ、ボロ雑巾のようにあちこちで皮膚が打ち破られて血が幾筋も流れていた。
「うう、ううう・・・ウエッ、ヒック・・・痛いよううう・・・」礼子の鞭の余りの痛さに泣き続ける慎治の目の前に、玲子がしゃがみ込んだ。クスクス笑いながら意味ありげな視線を礼子と交わしつつ、「あーあ慎治、可哀想に。こんなボロボロになっちゃって、痛かったでしょう?」クックッと小さく笑いながら玲子は慎治の全身の傷をチョンチョンと爪の先で突っつく。「アウッ!い、痛い!お願いやめて・・・」玲子が傷口を突っつく度に慎治の悲鳴が上がる。「そんなに痛いの慎治?可哀想に、全く礼子ったら酷いわよね、こんなにボロボロになるまで鞭打っちゃってさ。安心して、私は何もしやしないわよ。それどころか、優しい私は傷口を消毒してあげるからね。」ニッコリと微笑んだ玲子がやや厚みのある、美しく肉感的な唇をクチュクチュと動かす。と次の瞬間、玲子はペッと慎治の目に目掛け、思いっ切り唾を吐き掛けた。「アヒッ!」目に向かって一直線に飛んでくる唾に慎治は反射的に目をつぶってしまった。「あっ慎治、今目つぶったでしょ!」クルッと礼子に向き直った玲子はわざとらしく、如何にも怒ったような口調で言う。「礼子、今慎治ったら私の唾、目をつぶって避けたじゃない!全くもう、ちょっと教育が足りないんじゃない!?」ニヤリと礼子は満面に残酷な笑みを浮かべると、パンッと鞭を打ち鳴らした。「ご免ね玲子、確かに私の躾が甘かったようね。慎治、いい度胸しているじゃない、言われた傍から私の命令無視するなんてさ。いいわよ、お望み通りたっぷりと私の鞭、味合わせてやろうじゃないの。」「そ、そんなあああっ!ち、違う、違うよおおおっ!お、思わず閉じちゃっただけだよおおおっ!ヒイイイイッ!」必死で絶叫する慎治を礼子の鞭が情け容赦なく打ち据える。慎治は泣き喚きながら床をのた打ち回るが、礼子はいつまでもいつまでも鞭打ち続けた。ウフフフフ慎治、いい声よ、折角だから、今日はとことん逝ってみようかしら?ボロクズにしてあげる!のた打ち回ることさえ出来なくしてあげるわ!漸く出血が止まった傷口の上を狙うかのように打ち据える礼子の鞭に、慎治は全身から血を霧のように噴出していた。大した出血ではない、鞭で血が弾き飛ばされるから派手に見えるが出血自体は多くない。だが丸一日苛められたあとのこの鞭、傷口を抉る礼子の鞭だ、痛いなどという言葉は生温い。強烈な嘔吐感すら催すほどの、全身に不快な寒気が走るほどの激痛だ。慎治は文字通りオールアウトになるまで打ちのめされていた。ビシイッ!アウウッ・・・パシイイイッ!アグウウッ・・・最早慎治はのた打ち回ることさえできずに、うつぶせに倒れ付したまま礼子の鞭を浴び続けていた。礼子の鞭が背中に炸裂する度に、断末魔のように全身を痙攣させ虚空を掴むかのように片手を宙に上げていたが、遂に全身を鞭跡と血で真っ赤に彩りながら慎治はスイッチを切られたかのように動けなくなった。半死半生、鞭で、礼子の鞭で文字通り半殺しにされていた。慎治の一生の中でも最悪の映像の一つだった。
怜が今まさに唾を吐き掛けようと首をそらし反動をつけた瞬間、慎治の全身は礼子に刻み込まれた最悪の記憶に、全行動を規定する強烈なトラウマに支配されてしまった。ああ、あああああ・・・両手が鉛のように重くなっていく。持ち上げて・・・いられない・・・駄目・・・意思とは全く関係なく慎治の両手はダラリと下がっていく。その両手で抱え込むようにして下を向いていた首が、硬直するように震えながら上がっていく。虚ろな視線を彷徨わせ、慎治の目は怜の顔を、今まさに自分に唾を吐き掛けんとする美貌に釘付けになる。ペッ!ベチャッ・・・怜の唾が慎治の鼻先に着弾した。「どういうつもりなのよ!避けていいって言ったでしょう?そのまま凍り付いていればいいって言ったでしょう?何なのよ一体!さっさと避けなさいよ!ペッ!ペッ!」信じられない、どういうことなのよ一体!怒りに全身を震わせながら怜は何度も何度も激しく唾を吐き掛けた。だが何度吐き掛けられても慎治は情けない声ですすり泣くだけだ。ザッ・・終いに疲れ果てたかのように怜は大きく仰け反ってソファにもたれ掛かった。天を仰ぎながら呟く。「もういいわこんな連中・・・こんなのと付き合ってたら私の方が気が変になっちゃう・・・矢作君、川内君、あなたたち・・・今すぐ死になさい。自分の意思を持たないのなら、生きていても仕方ないでしょう?ここを出たら今すぐどこかのビルの屋上に行って飛び降りなさい。唾を吐き掛けられても黙って掛けられるがままの人生なんて、生きてる意味ないでしょう?」暫くの間、疲れ切ったかのように怜も舞も押し黙っていた。聞こえる物音は唾まみれになった慎治たちの嗚咽だけだった。やがて怜がゆっくりと立ち上がり、慎治の腕を掴んだ。「本当に見果てたクズねあなたたちは・・・いい、この先あなたたちが天城さんたちに苛められようが殺されようが、私たちの知ったことじゃないわ!勝手にどうにでもされなさい!もうその顔、見ているだけでも穢らわしいわ、さっさと私たちの前から消え失せなさい!」舞も信次の腕を掴み引き摺り上げながら言い放った。「本当よ・・・あなたたちみたいなクズは、勝手に好きなだけ苛められて苛め殺されるのがお似合いよ!ああもう!君たちと同じ空気を吸っているだけでも最悪の気分よ!」酷い・・・怜先生も舞先生も・・・礼子さんたちと同じだ・・・慎治たちは漸く気付いた。怜と舞の本質に。二人とも完全に持って生まれた強者、礼子たちと同じく強者である事を。慎治たち弱者のことなど虫けら以下にしか思っていないことを。そして自分の手を煩わせた虫けらなど、純粋に怒りの対象でしかないことを。だがどうしても認めたくはなかった。いや認めるわけにはいかなかった。「おね・・・がいです・・・」「見捨て・・・ないで・・・」二人の最後の願いは怜と舞のより激しい怒りを買っただけだった。「・・・未だ言うの・・・このクズは!」「いい加減に・・・しなさいよ!」怜と舞の美貌は今や激しい怒りに燃え上がっていた。「これ以上・・・私の貴重な時間を下らない世迷い言で潰さないで頂戴!ペッ!」「いい、今度こんな下らないことを言いに来たら・・・只じゃおかないわよ!ペッ!」美しい悪鬼、夜叉羅刹のような見る者の血も心も凍り付かせる激しい怒りに美貌を燃え上がらせながら二人は慎治たちを突き放した。蹴り倒してやろうかしら、それとも腕をへし折ってやろうかしら。だけどこんな穢らわしい連中には、触るのも嫌よ。だったら・・・怜と舞の頭に残酷な攻撃方法が浮かんだ。こいつらに最も相応しいやり方で、こいつらが一番嫌な、一番屈辱的な方法で追い出してやる!怜と舞の脳裏に同じプランが浮かんだ。散々唾を吐き掛けられている癖して、生意気にも唾を吐き掛けられるのは嫌みたいじゃない?だったら・・・唾だけで追い出してやる!天城さんや霧島さんのように鞭を使う必要すらないわ、こいつらには唾だけで十分よ!唾だけで何の抵抗もできずに叩き出される屈辱を刻み込んでやる!「出ていかないんだったら、こうやって追い出してやるわよ!ペッ!」ダンッ!鋭く踏み込みながら怜は思いっきり慎治に唾を吐き掛ける。「アウッ!」怜の鋭い視線と唾に気圧されるように慎治は一歩ずり下がる。「穢らわしい!私の目の前から消え失せなさい!このクズ!ペッ!」見る者の血を凍り付かせるような、メドゥーサの邪眼のような眼力で睨み据えながら舞も唾を吐き掛ける。信次はブオッと顔に芳しい舞の吐息を感じた次の瞬間。吐き掛けられた唾に突き飛ばされるようによろけた。吐き掛けられた唾、殆ど質量すらない舞の唾が玲子のフルスイングの鞭に匹敵するほどの威力で信次を突き飛ばす。「このクズ!ペッ!ゴミ虫!ペッ!ゴキブリの方が100億万倍マシよ!ペッ!」「この穀潰し!ペッ!役立たず!ペッ!生きているだけで罪悪よ!ペッ!」怜と舞は普通の男、いやまともな人間ならば一生一度たりとも言われないであろう侮蔑と憎悪に満ちた罵倒を浴びせながら唾を吐き掛け続けた。ダンッ!一歩踏み込んで唾を吐き掛ける度に慎治たちが一歩後退していく。このゴミクズ!ウジムシ!怜と舞は知的な美貌を阿修羅の形相に変幻させて唾を吐き掛け続けた。ダンッ!ペッ!穢らわしい!寄生虫!踏み込み唾を吐きかける度に慎治たちが一歩後退して行く。そうよ二人共、その調子よ・・・唾で追い出してやる、君たち如きには触るのすら穢らわしいわ、唾だけで、唾だけで追い出してやる!指一本触れられずに、唾だけで追い出された男なんて、見たことも聞いたこともないわよ。さぞ屈辱でしょうね、君たちみたいなクズでも、悔しくて悔しくて夜も眠れなくなるでしょうね!お似合いの罰よ、ペッ!「この穢らわしいクズ!ペッ!無駄飯食い!ペッ!」「腐ったゴミよ君たちは!ペッ!臭い、ああ臭いこの生ゴミ!ペッ!」ひ、ひどい、ひどい・・・なんで僕たちを・・・慎治たちは泣きながら後退し続けた。怜と舞の唾に追い払われる屈辱、指一本触れられていないのに追い払われる屈辱。痛くない、ぶたれてもいないし首を絞められてもいない、苦痛は何も無い筈なのに慎治たちは無限の苦痛を感じていた。怜と舞の唾が着弾する度に、顔に思いっきり殴りつけられたような痛みが走る。芳しい吐息が暴風のように体を吹き飛ばす。殆ど質量もない筈なのに怜と舞の唾に、吐息に顔面を、全身を突き飛ばされる感触が確固としたリアルな実感として意識を支配する。慎治たちは為す術もなく、怜と舞の唾に駆り立てられながらドアへ、出口へと追いやられていく。カウボーイが牛を追い込むように、牧羊犬が羊を駆り立てるように、怜と舞は唾だけで慎治たちをドアへと駆り立てていった。
ドンッ、背中が固いものにぶつかる感触に慎治は思わず後ろを振り向いた。ど、ドア、ドアにぶつかった・・・じゃ、じゃあ・・・その通り、ソファからドアまで、三メートル近い距離を怜と舞の唾に駆り立てられて来ていたのだ。縋るように、パニック状態の空ろな視線を彷徨わせる慎治に怜の凛とした声が響く。「何をグズグズしているのよ!さっさと出て行け、ていうのが分からないの!それともこうやってずっと唾を吐き掛けられていたいって言うの!?唾が大好きです、もっと下さい、とでも言う気なの!この変態!ペッ!」ああ、あああ・・・慎治たちは必死でドアを開けようとする、だが半身の逃げ腰になりながらも、相変わらず唾を受けられるよう顔は前に向けたままだ。しかも二人が同時にノブに手を伸ばしたものだから手と手がぶつかりあい、ノブを奪いあうようになってしまって中々開けられない。苛立ちを露わに舞が怒鳴りつける。「何をやっているのよこのバカ!ドアを開けることすらできないの、そんなこと三歳児でもできるわよ!どこまで役立たずなのよ君たちは!さっさとしなさいよ、この精薄!ペッ!うすのろ!ペッ!グズグズしていたら、出て行くまで唾よ!ペッ!」ひいいっい、いやあああっ!矢のように降り注ぐ怜と舞の唾を浴びつつ、やっとのことで慎治たちはドアをあけた。「あわっ」「あうううっ」不意に開いたドアからよろめき出た二人はそのまま廊下の反対側の壁までつんのめるようにふらつき、そして壁とお互いにぶつかって絡み合うように転んでしまった。唾だけで本当に追い出されてしまった・・・唾に霞んだ慎治たちの目に、理事室の中が遥か遠い世界のように見える。だが悠長に屈辱にむせび泣いている暇などなかった。慎治たちはまだまだ、怜と舞の唾地獄から這い出ていなかったのだ。
ウウウ・・・アツツ・・・呻く二人を怜と舞は冷ややかに見下ろしている。「何よ、今度はそうやってそこに居座ろう、ていう気?ふざけるんじゃないわよ、目障りよ!ペッ!」漸く四つんばいになった慎治に怜の罵声が、そして唾が降り注ぐ。「アヒイッ!」バランスを崩した慎治はそのまま半身を捻り、腰が抜けたように座り込んでしまった。仰向けの姿勢で慎治の下敷きになっていた信次が上半身を起こすと、丁度信次たち二人は足を投げ出したまま怜と舞に向かってだらしなく座り込んでいるような格好だった。「何をしているのよ、誰がそんなところで寛いでいい、て言ったのよ!?さっさと消え失せなさい!ペッ!」舞が体を反らしたかと思うと、全力で唾を吐き掛けた。唾責めの再開だった。そんな、そんなあああ・・・も、もう部屋から追い出したじゃないですかああああっ!?なのに、なのにまた唾責めですかあああっ!そう、唾責めはまだまだ終わりではなかったのだ。最早立ち上がる気力もなく、へたり込んでいる慎治たちに怜と舞は情け容赦なく唾を吐き掛け続ける。「無様な姿!その姿が君たちにはお似合いよ!ペッ!」「よく恥ずかしくないわね、こんな生き恥さらして何で自殺しないのよ!この恥知らず!ペッ!さっさと死になさいよ!ペッ!」二人が唾を吐きかける度に、慎治たちは呆けたように一歩、また一歩とずり下がっていく。そんな慎治たちを見下ろしながら、怜と舞は漸く人心地を取り戻しつつあった。ペッと唾を吐いた感触、着弾した唾が慎治たちの顔面を穢していく様子、そして屈辱に塗れながらずり下がっていく慎治たち。その何とも無様な姿が怜と舞の怒りを癒していくようだった。いい気味、一生トラウマになるがいいわ、君たちに相応しい罰よね。もっともっと屈辱を与えてやるわよ、私たちの貴重な時間を何分浪費させたと思っているの?私たちを苛立たせたゴミクズには、そうやって泣き叫んで貰わないと割りが合わないわよ、ああいい気味!怜と舞はふと、自分たちの顔が綻んできていることに気づいた。フフフ、何か少し、楽しくなってきたわね。唾だけで二人を部屋から追い出したことに、微かな達成感すらあった。「廊下に座り込んじゃいけませんよ!全くお行儀が悪い犬ね!ペッ!」「ほーらほらほら、赤ん坊以下の無様な姿ね、そうやって這い蹲ってるのが君たちクズどもにはお似合いよ!ペッ!」ウフフフフ、牛追い鞭や羊飼いの犬、ていうのはあるけど、唾で人間追い立てるなんて、考えてみたこともなかったわ。
怜はゾクリとするような凄絶な微笑を浮かべながら唾を吐き掛け続ける。怒りの余り唾を吐き掛ける、ていうのはまあ分かるけど、こうやって他人を唾で追い立てるなんて想像したこともなかったわ。ウフフ、私ゴジラか何か、強い怪獣になったみたいね、私の口から聖なる炎を吐いているみたいじゃない?ウフフフフ、そうよ虫けらどもを滅ぼす炎よ、私の唾で君たちの心を焼き尽くしてやるわよ、ペッ!舞も残酷な愉悦の笑みを浮かべながら唾を吐き掛けている。そして慎治たち虫けらと怜たち女神の間に初めて、コミュニケーションが成立していた。慎治たちは屈辱だけではない、恐怖に満ち満ちた目で怜と舞の唇を見詰め続けていた。美しい唇の奥から間断なく、止め処もなく大量の唾が湧き上がり、自分たちに向かって吐き掛けられる。唾、消化液の一種に過ぎない唾、本当は慎治たちの体内にもあるものだ。だが慎治たちにとって唾は別のもの、美しい女性が自分を責め苛むための残酷な責め具だ。鞭にも匹敵する威力のその責め具は怜と舞の体内で次々と生産され、慎治たちを間断なく責め苛む。ヒッ、ヒイイッ、アヒイイイッ・・・残酷な、苦痛に満ち満ちた責め具を口から吐き出せる怜と舞。同じ人間に唾を吐き掛けられて辱められている、といったレベルはとうの昔に通り過ぎていた。慎治たちにとっても怜と舞は最早同じ人間ではなかった。口から自分たちを焼き尽くす炎を吐き出す人間を遥かに超えた存在だった。ああ、お願いです・・・どうか・・・やめて・・・ください・・・や、やめて、あつい・・・とけちゃう・・・慎治たちにとって怜と舞は人間を超越した女神に、唾一つで自分たちに最悪の苦痛を与えられる残酷な女神に昇華してしまっていた。慎治たちに間断なく降り注ぐ怜と舞の唾、そして決して顔を逸らすな、という礼子たちの呪縛。二重に縛られた慎治たちは屈辱の嗚咽を漏らしながら追い立てられていく。破局へと、奈落の底へと。余りに激しい唾責めに、慎治たちはすっかり忘れてしまっていた。ここが二階であることを。怜と舞の唾で追い立てられた慎治たちはいつの間にか、階段の縁まで追い込まれていた。ウフフ、あと少しね、もうあと一メートルもないわよ。ここまで来て振り向かれたりしたら興醒めもいいところだわ。二人ともしっかりこっちを向いているのよ。ペッペッペッペッ・・・怜と舞は唾を吐き掛けるスピードをアップし、最後の詰めに出る。ああ、あああ・・・や、やめて・・・慎治たちの意識は全て、怜と舞の唾のみに占領されている。そして突然、破局がきた。チラッと怜と舞は頷きあった。もう縁ギリギリ、後一歩で転落ね。そうね、止めを刺すわよ。怜と舞はニヤリと残酷な笑いを浮かべながら大きく息を吸い込んだ。「止めよ!ペッ!」「地獄に・・・墜ちなさい!ペッ!」ヒッ!アウッ!思いっ切り吐き掛けられた唾に押しやられてずり下がった二人の手が突然、ガクンッと落ちていく。「わっわあああっ!」「あああああああっ!」あると思っていた廊下が突然消えた恐怖、何が起こったのか考える暇もない。「あぐっがっわああああっ!」真後ろにでんぐり返しするように慎治は転げ落ちていく。「うぶっひっひぎゃあああああっ!」バランスを崩し、半身からうつ伏せになった信次はガンガンと何度も何度も激しく顔面を階段に叩き付けながら滑るように落ちていく。ドザアッ、ダダンッ!「うぐうううっ、うううううっ・・・」「いいい、いだあああああ・・・」階下に激しく叩き付けられた慎治たちは全身を襲う激痛に呻いていた。その時、天上から女神の笑い声が響いてきた。怜が高らかに勝利の凱歌を上げていた。「アハハハハッ!いいザマよ二人とも、君たちはそうやって虫けらみたいに呻いているのがお似合いよ!ペッ!」舞も楽しげに笑っていた。「いい、二人とも二度とこの階段を登ってくるんじゃないわよ。君たちみたいなクズが上ってきていい場所じゃないのよここは!もし上ってきたら、また唾で叩き落してやるからね!ペッ!」遠距離攻撃、とばかりに怜と舞は斜め上に向かって、放物線を描くように最後の唾を吐き出した。ビチャッ、ベチャッ、最後は殆ど垂直に落下した唾が見事に慎治たちの顔面で跳ねた。アハハハッ、アハハハハッ!ああさっぱりした、とばかりに笑いながら天上の女神は踵を返して去っていった。奈落の底で呻く亡者、女神の唾にまみれて泣き続けている慎治たちのことなど全く構いもせずに。階下に叩きつけられた慎治たちは何時までも何時までも、呆然と咽び泣き続けていた。微かな望みが絶たれたことに。そして学園の最高権力者に絶対的な怒りと軽蔑を買ってしまったことに。
4?
勿論、礼子たちは翌日にはこの事を怜と舞から聞かされていた。「ああ天城さん、今日これから予定ある?少しお茶でもしていかない?」翌日部活が終わった後に怜から誘われた礼子は何なのか不思議に思いながらも付いていった。そして連れて行かれた理事室には既に、舞と玲子が来ていた。あ、この面子・・・もしかして慎治たちのこと?あーあ、もしかして苛めてるのがバレちゃったのかな?そう思いながらも不思議と嫌な予感は全くしなかった。「遅かったわね、二人も同じのでいいかしら?」香り高い紅茶を入れ直した舞が待ちかねたように、ニヤニヤと楽しげに笑いながら切り出した。「ウフフ、勘のいい霧島さんたちのことだからもう気付いているとは思うんだけどね、今日来て貰ったのは勿論、川内君たちのことよ。」怜も妙に楽しげにクスクス笑っている。「そうなのよ、昨日は参ったわよ。いきなりあの二人、矢作君と川内君が私たちの部屋に押しかけてきてね、先生、天城さんと霧島さんに苛められているんです、先生から言って苛めを止めさせてください、て泣いてお願いしてきたのよ。」紅茶で唇を湿らせると舞が後を引き取った。「傑作だったわよ、いきなりシャツを脱いじゃってこの鞭跡、霧島さんたちに鞭打たれたんです、とか毎日毎日おしっこ飲まされてるんです、とか言いながら泣き出しちゃったんだから。」怜も紅茶を啜りながら尋ねた。「で、天城さん、私たちがどう答えたと思う?まあ貴方なら直ぐに分かっちゃいそうだけどね?」怜先生も舞先生も楽しそうね、ということは・・・「そうですね、怜先生たちのことですから、甘ったれるんじゃないわよ!と一喝して追い返したんじゃないですか?」怜と舞は手を叩いて大笑いしていた。「ご名答!流石ね、その通り。女の子に苛められてます、なんて言うだけでも恥ずかしいのに、鞭で叩かれてます?おしっこ飲まされてます?まあよく恥ずかしげもなくそんなこといえるものね!て私たち心底呆れ果てちゃったわよ。だから唾を吐き掛けて追い返してやったわ!」「え?怜先生と舞先生が唾を吐き掛けたんですか?信次たちに?」流石に驚いた玲子が聞き返したのに対し、舞は大きく頷いた。「そうよ!もう思いっきり唾を吐き掛けて叩き出してやったわ!そんなに驚くことないでしょう?本当に心底軽蔑したら唾を吐き掛けてやりたくなるのって当然でしょう?そこは私たちも霧島さんたちと同じよ。」やっぱりね・・・そりゃそうよね、怜先生と舞先生が信次たちの味方するわけないわよね。顔を見合わせて頷きあった礼子たちを見て、怜と舞は満足そうに微笑んだ。
「そう言えばそうですよね。最近は何かにつけ唾を吐き掛けてやってるけど、やっぱり最初に吐き掛けた時は侮蔑と言うか・・・怒りと軽蔑の極致で思わず吐き掛けてしまった、て感じでしたね。」礼子が少し感慨に耽るように言うのを怜は穏やかに笑いながら頷いた。「そうね、私たちもまあ子供の頃に喧嘩してペッとやったとか言うのを別にすると、そうね、本気で他人に唾を吐き掛けたのはやはり貴方たち位の時かしらね。多分天城さんと同じようなシチュエーションかな、余りに情けない男に苛ついて思わず吐き掛けたのが最初よ。」「最も霧島さんは少し違うかもね。」舞が笑いながら引き取った。「霧島さんはもう少し純粋に苛めっ子が入っていそうね。多分、唾を吐き掛けられて屈辱に歪む顔みたさに、誰かを苛めながら吐き掛けたのが最初じゃないかしら?」「あ、やっぱり・・・分っちゃいますう?ついでに言うと、フミちゃん、神崎さんが私タイプで朝子、萩さんが礼子タイプですね!」おどけたように玲子はペロリと舌を出した。舞先生、全てお見通しのようね、だったら隠したりとぼけたりするのは逆効果ね。「あらあら堂々たるカミングアウトね!四人揃って全くもう、全員苛めっ子なんだから!」四人そろって一しきり大笑いしたところで、怜が切り出した。
「ああ二人とも気にしないでいいのよ、最初に言っとくけど、私たち別に貴方たちに注意するとか苛めを止めなさい、とか言うために呼んだんじゃないからね。単に矢作君たちがバカなお願いをしに来たけど、追い返してやったわ、ていうことを教えてあげるためだけよ。じゃないと、まあそんな知恵が回るとも思えないけどあの二人、私たちに苛めを相談しに行ったぞ、とか言って少しでもあなたたちに苛められないようにしよう、とかするかも知れないからね。まあどうでもいいけど、あんなクズに名前を使われるだけでも不愉快だから予めあなたたちに教えておいてあげよう、ていうことよ。」「そう、怜の言うとおり単にそれだけよ。大体ちょっと見れば分かるけど、あなたたちが苛めているのはあの二人だけ、他のみんなとは男女を問わずとても仲いいじゃない?だったら・・・まああなたたちなら分かるだろうからストレートに言うわね、教員というより学園の経営者である私たちが、落ちこぼれのクズでしかないあの二人と優等生で人気者のあなたたちと、どちらを取るかは言うまでもないでしょう?」極めて分かりやすい、ストレートと言うよりあけすけな怜と舞の説明だった。好き嫌いという単純明快な感情論と、教育論だ人生観だのの綺麗事など一切入らない単純明快な利益考量。礼子たちも直感的に理解出来るものだった。最後の紅茶を飲み干しながら怜が言った。「あなたたちが矢作君たちをどう苛めようと、私たちの関与せざるところ、よ。好きにやっていいわ。」そして舞が最後に一本、釘を刺すのも忘れなかった。「但し、やはり学園の枠組みはあるからね、何か面倒なことになりそうな時は事前に私たちに一報入れてね。」
礼子たちは当初、怜と舞を巻き込む気はなかった。単にクラスメートを怪我させた慎治たちをリンチにかけるにあたり、クラス全員参加の大規模リンチを加えようと思いそれだけの大規模リンチとなれば舞に釘を刺されたこともあるし、一応事前に知らせておく必要はある、と思っただけだった。「さてと、やっぱり怜先生と舞先生には言っておかなくちゃいけないわよね・・・どう言ったらいいかしら?」礼子の問いかけに暫く考え込んだ玲子だったが、小さく頷くと答えた。「あの二人は信次たちの両親なんかとはレベルが違うからね、下手な誤魔化しは通用しないと思うわ。て言うより、小細工する必要ないんじゃない?だって唾吐き掛けて追い払う位信次たちを軽蔑しているのよ?だったらストレートにさ、あの二人が逆ギレして陽子と有希子をケガさせたからみんなでリンチする、て有りのままに言ったほうがいいと思うよ?」そして土曜日、怜と舞に金曜の件を報告し、更に来週クラスみんなで信次たちをリンチにかける、と打ち明けた玲子たちに二人は意外な反応を返してきた。「ちょっと待って!今の話、本当?本当に矢作君と川内君が青葉さんと古鷹さんを突き飛ばして怪我させたの?」話を聞いた怜の顔から笑いが消え、真剣な表情に一変した。あらら・・・まずいかな・・・一瞬、玲子は嫌な予感がした。やりすぎよ、て怒っているのかな?だが続く舞の言葉は玲子たちの予想とは正反対だった。「霧島さん、途中経過はどうでもいいわ。この前言ったとおり、あなたたちが川内君たちをどう苛めようとどうみんなでリンチしようと構わないわ。病院送りにしようが自殺させようがどうでもいいの、そんな事は全然問題ないわ。そんなことより本当なの?あの二人が古鷹さんたちに怪我をさせた、て言うのは本当なの?イエスかノーかだけで答えて!」え、苛めたりリンチはどうでもいい?一瞬反応に詰まりながらも玲子が答えた。「・・・ええ、本当です。信次たちが有希子たちを突き飛ばして怪我をさせたこと、これは間違いありません。」フウウウウッ・・・怜と舞が大きく溜息をついた。暫く沈黙がその場を支配したが、やがて怜が口を開いた。「・・・ったくあの二人は・・・やってくれるわね・・・」怒りを押えきれないように呟く怜と同様、舞も吐き捨てるように呟いた。「よりにもよって女の子をトイレで突き飛ばすとはね・・・クズが!」美しい、大きな瞳を怒りに燃え上がらせながら怜が礼子を見据えながら静かに言った。「天城さん、聖華で・・・と言うより共学校でおよそ一番してはいけないことってなんだと思う?それはね、男の子が女の子に暴力をふるうことよ。」舞の白い頬も怒りに上気していた。「そう、理由なんか関係ない、苛められてたから、リンチされてたから反撃しました、なんて情状酌量の対象にすらならないわ。男の子が女の子に暴力を振るう事、これだけは絶対のタブーなのよ。」
怜と舞が直感的に思い出したのは体育科の主任、大井との会話だった。大井は日体大出の典型的な体育教師、時に乱暴な印象すら与える古典的な体育教員だが抜群の指導力と豊かな人間味を持ち、運動部の生徒を中心に極めて人気が高かった。聖華の共学化にあたっては頑強な反対派であったがその指導力に惚れ込んでいた怜と舞は文字通り三願の礼をもって翻意を促し、遂に説得に成功したときは思わず快哉を叫んだ程だった。大井が反対したのは単に改革反対、ということではない。共学化に際し万が一の事故、特に有体に言えば男子生徒が女子生徒に肉体的、特に性的な暴力を振るった場合、聖華のブランドが回復不能なまでに傷付く事を恐れたのが最大の理由だった。その心配は怜と舞にも良く分かった。いや二人が最も恐れ、防止に全力をあげねばならないと考えていたのも、まさにその点だった。「大井先生の仰るとおり、私たちもその問題は一番重視しています。だからこそ・・・もしそんな問題が発生した場合は、犯人は絶対に許しませんよ。」断言する怜に対し、大井は試すかのように質問した。「許さない、それはよく分かるが・・・具体的にどうするつもりなのかな?」舞が断言するかのように答えた。「最大限厳しい罰を与えます。そう・・・体罰を含む、ある種見せしめ的な、ここまでやる必要はないだろう、と言う位の厳しい罰を与えるつもりです。」ほう、と言う顔で大井は更に突っ込んだ。「体罰ねえ・・・まあ口でいうのは簡単だけど、実際に誰がそんなことやるのかな?聖華の今の教員でそこまでやる熱意がある奴は少ないし、となると結局は体育科の俺たちにお鉢が回ってくるのかな?暴力教師の役割もやれ、と言うことですかな?」ニヤリと怜は微笑を、凄絶な笑みを浮べた。「そんなことはしませんわ。大井先生たち体育科の先生方に汚れ仕事を押し付けて自分たちだけ澄ました顔でいるつもりは毛頭ありません。約束します、最初、少なくとも最初にそんなことをしでかした生徒には、私たち自らが罰を与えます。」本気か?大井は驚きを隠せなかった。「・・・本当ですか?本気で・・・本気であなたたち、理事の、いや東大の助教授で、汚れ仕事なんかは他人に押し付けて余計な事には首を突っ込まないほうが楽なはずのあんたたちが、自ら体罰までやる、ていうんですか?」自然に口調も丁寧になっていた。ここが勝負所、大井先生に私たちが本当に本気だ、て分かってもらえるラストチャンスよ。舞は大きく頷きながら断言した。「怜の言ったことは本当ですよ。約束します、最初に女子生徒に暴力を振るった男子生徒には、私と怜とで罰を、体罰を含む厳罰を加えます。大井先生たちには頼りません、私たち、私たち自身の手で罰を与えます。」大井の目を見据えながら舞は静かに宣言した。「大井先生、これでも私たち、一応は空手と合気道の黒帯ですよ?そこいらの男の子を懲らしめる位、簡単ですよ!」怜の言葉に頷きながら暫く腕組みをしてじっと考えていた大井は、やがて破顔一笑して右手を差し出した。「分かりました、そこまで言うのなら、あなたたちを信じましょう!そこまで本気ならもう何も言う事はありません、俺は全力であなたたちの改革を支持しますよ!」
そして今・・・恐れていた事態が現実になった。怜も舞も自分のテンションが上がってくるのを感じていた。いいわ、私たちは自分の言葉に責任を持つ、ということを見せてあげる。怜は礼子を正面から見据えながら言った。「天城さん、事は重大よ。言葉遊びや腹の探り合いなんかしている場合じゃないわ、私たちからのお願い、ストレートに言うわね。」怜の本気がヒリヒリと伝わってくるだけに礼子たちはゴクリと唾を飲んだ。何だろう、怜先生たちのお願いって。一瞬の沈黙の後、舞が口を開いた。「心配いらないわよ、霧島さんたちに不利とか負担を掛けることは何もないわ。クラスでどんなリンチを加えようとあなたたちの自由よ、あの二人をどんな酷い目にあわせてもいいわ。だけどね、その前に先ず私たちからも罰を加えさせて欲しいのよ。そう・・・学校としての処罰、体罰を含む厳罰をね。」体罰を含む厳罰?思わず顔を見合わせる二人の緊張を解そうとするかのように、怜が明るい笑い声を上げた。「アハハハハッ!二人ともそんなに驚かないでよ、単純なこと、頭のいいあなたたちならすぐ分かる話よ。天城さんたちがここに来たのは、矢作君たちをリンチする、て私たちに事前連絡に来たわけでしょう?それを邪魔する気はないから、学校としての処罰を私たちも執行するわよ、ていうだけの話、単に取引をしましょう、ていう話よ!」舞も笑いながら続けた。「そうそう、別に困った話じゃないでしょう?それどころか学校を、私たちを敵に回す、て言う意味で川内君たちにとっては極めて厳しい責めになるはずよ。だって私たちはここの理事よ?当然、肉体的な苦痛だけじゃなくて家庭を巻き込んだ最大限屈辱的、しかも一生後を引くような責め苦を味あわせてやるわよ。ウフフどう、正直ベース、あ、それいいな、て思ったんじゃない?立場が違う私たちが責め手に加われば、あの二人に全く新たな苦痛を味あわせてやれる、て?」
思いもかけない展開に流石の玲子たちも驚きを隠せなかった。確かに怜と舞が信次たちへの制裁に参加してくれれば最高だ、朝子や富美代たちと同じく、新たな発想の苛めで信次たちをたっぷりと泣かせてくれるだろう。いや肉体的な責めに留まらない、この二人はなんと言っても学園の理事、最高権力者だ、怜と舞がその気になれば信次たちの学園生活を滅茶苦茶にしてしまうことなどた易いだろう。しかも自分たちがどんなリンチを加えてもよい、学校公認で苛めさせてあげる、とのおまけつきだ。学校公認の苛め、傷跡や周囲の目など、多少は働いていたリミッターを全部解除できる。どんな苛めをしても良いフリーパス、喜んで飛びつきたいオファーだ。だが玲子には一つだけ気懸かりがあった。怜先生と舞先生が加わる、それって物凄くよく効く薬みたいなものよね。よく効く分・・・副作用も怖いわ。「舞先生、すごく嬉しいお話で大喜びなんですけど・・・一つだけお願いが・・・」アハハハハッ!と大笑いしながら舞が手を振った。「分かった!霧島さんが何を言いたいか当ててみましょうか?あの二人を退学にはしないで下さいね、てことでしょう?」流石!「分かりました?その通りです。だって退学にされたらあの二人を苛めにくくなっちゃいますもん!」エヘッと明るく笑いながら舌を出し、少しブリっ子を入れながら玲子は肩をすくめた。笑いながら舞が答えた。「心配しなくていいわよ二人とも、退学は愚か停学にもしないわ。理由はあなたたちと同じよ、だって退学や停学にしたらそれ以上責められないでしょう?単に罰を加えるだけじゃないわ、あの二人には見せしめになって貰うのよ。今後聖華で女子生徒に暴力を振るった男子がどういう目にあうのかっていうね。」ニヤリと凄絶な冷笑を浮かべながら怜が言った。「考えてみれば丁度よかったわ。他の前途ある生徒には余り手荒な真似や酷いことはできないけど、あの二人みたいなクズなら何の未来もないでしょう?一生の心の傷を負わせてやっても全然問題ないわ。連中も光栄というものじゃない?せめて見せしめ、生贄としてであれ他人様のお役に立てるんだから!泣いて喜んで貰いたいわね。」余りに悲惨、余りに残酷な会談だった。慎治たちの全く知らない所で、信次たちが全く手出しも出来ないところで二人の運命が決められていた。更に深いどん底へ、二度と這い上がれない地獄へと突き落とされることが。
5?
校長室に入った慎治たちを待ち構えていたのは校長の秋月と担任の若月、礼子と陽子、玲子と有希子、そして怜と舞の8人だった。敵意に満ちた16個の視線が慎治たちに突き刺さる。うう・・・刺すような視線に二人の背中に早くも冷たい汗が吹き出てくる。校長室の中央に置かれたテーブルの周りのソファーと椅子に8人が陣取っていた。口を切ったのはこの部屋の主、そして慎治たち以外では唯一の男性である秋月だった。「来たか・・・まあ兎に角座りなさい。」秋月は打ち合わせ時用に壁に立てかけてあるパイプ椅子を指し示した。と、その時怜の凛とした声が響いた。「校長先生、何を甘いことを言ってるんですか!この二人を座らせる必要などありません。二人ともそこに正座していなさい!」せ、正座、床に正座、そんな、みんな座っているのに僕たちだけ正座・・・慎治は微かに声を出しそうになった、だが怜の燃えるような視線に射すくめられ、何も言えない。「さあ青葉さん、古鷹さん、嫌な記憶を蒸し返して申し訳ないんだけれど、加害者の二人が来たところでもう一度だけ、さっきの話を聞かせて貰えないかしら。」慎治たちに対してとは打って変わった優しい口調で怜が陽子と有希子に微笑みかけた。ゲッ・・・陽子と有希子に視線を向けた信次は、二人の手と膝に大袈裟に包帯が巻かれているのを見て悲鳴を上げそうになった。ふと見るとテーブルの上には二枚のÅ4サイズの紙が置かれている。内容までは見えないが、そのタイトルには確かに「診断書」とあった。玲子さんたち・・・酷い陰謀を・・・な、何とか、何とか先生たちの誤解を解かなくちゃ・・・玲子たちの陰謀、信次の想像が及ぶのはそこまでだった。よもや怜と舞が決定的に自分たちの敵に回っている、とまでは予想もつかなかった。
「は、はい・・・金曜の放課後なんです、私がトイレに入ったら、奥の一つ手前の個室に入ったんですけど、隣の個室で何かゴソゴソと変な物音がしたんです。でふと下を見たら・・・隣の個室から鏡が突き出ていたんです・・・」啜り泣きながら訴える陽子に続いて有希子も訴えた。「私も・・・青葉さんの向かいの個室に入ったんですけど、同じように鏡が・・・それでビックリして飛び出たら丁度、向かいから青葉さんも飛び出てきたんです。で、二人で何なの、何なのあれ、て驚いちゃって、それで外から見ると隣の個室、一番奥の個室のドアが閉まってて誰か入ってるみたいだったけど、物音一つ立てないで凄く不気味だったんです・・・だって普通トイレだったら、何か音の一つもするじゃないですか?」「そうなんです、だから古鷹さんと二人でこれ絶対変、絶対おかしい、て思ってドアをノックしてみたんです。誰、誰か入ってるの!?変な音がしたんだけど誰が入ってるの、て・・・」「でも返事がなかったんです。必死で息を潜めているような感じで、なんの返事もなかったんです。それでもうすっかり怖くなっちゃって青葉さんに、これ絶対変、誰か呼んでこようよ、て言った時にいきなり・・・」「バターン、て凄い勢いでドアがあいて中から矢作君が飛び出してきて私のことを突き飛ばして転ばせて・・・」「えっ、と驚いて振り向いたら私の方のドアも急に開いて中から川内君が・・・飛び出てきて後ろから私のことを突き飛ばして、転んだ私のことを飛び越えて・・・逃げて行ったんです・・・」そ、そんな!で、でたらめだ!抗議の声を上げようとする信次の機先を舞が制する。「川内君、誰もあなたになんか聞いていないわ、黙っていなさい!」ピシリと鞭のように厳しい舞の声に押さえ込まれ、信次はアウウ・・・と声にならない呻き声だけを漏らした。そんな信次を一瞥すると舞は玲子たちに穏やかに問い掛けた。「霧島さん、天城さん、あなたたちの話ももう一回聞かせて頂戴。」「はい、私と天城さんがトイレに入った時、奥で青葉さんと古鷹さんがトイレのドアをガンガンノックしていたんです。誰なの、開けてよ、返事してよ、て大声上げていたんです。」「そうです、それで私もびっくりして青葉さんたちにどうしたの、何かあったの、て声をかけたんです、そしたらその瞬間に・・・トイレのドアがバーン、と凄い勢いで開いて中から矢作君と川内君が飛び出してきたんです!」礼子の言葉に頷きながら玲子が証言を続ける。「えっ、て私も天城さんも本当にびっくりしちゃって・・・でも青葉さんと古鷹さんが転ばされて悲鳴を上げたんで我に返って駆け寄ろうとしたんです。その間に川内君と矢作君は・・・」「私と霧島さんの横を駆け抜けてトイレから飛び出して逃げていったんです。一瞬でしたけど、絶対に見間違えなんかじゃありません。間違いなく矢作君と川内君でした。」
ああ、あああ・・・慎治たちは全身の血が恐怖で凍りつきそうだった。ひ、酷い!!!僕たち、女子トイレを覗いて、しかもそれがバレて逃げる時に青葉さんたちに怪我させた犯人に仕立て上げられている!!!礼子たちの証言が終わったところで溜息を突きながら秋月が慎治たちに尋ねた。「・・・どうなんだね・・・青葉さんたちの話の通りで間違いないのかね?全く・・・何でこんな事をしでかしたんだ?」い、今だ、今言わなくちゃ、今言わなくちゃアアアッ!「ち、違う違うちがいますうううううっ!ぼ、僕たち、僕たちが被害者なんですうううううっ!」「そそそ、そうですそうです!ぼ、僕たち、僕たちの方が、僕たちがリンチされてたんですうううっ!」「あ、あ、天城さんや霧島さんたちにいいいい、苛め、苛められているんですうううっ!きき、金曜も、金曜もりりり、リンチされてたんですよおおおおおっ!トト、トイレで、トイレで無理やりみんなのおしっこを飲まされてたんですううううっ!」「そ、そうですそうです!そ、それに、そのリンチに青葉さんたちも加わってたんです!青葉さんたちも僕たちに・・・おしっこ飲ませてたんです!だから・・・だから僕たち、必死で逃げ出しただけなんですううう、お願い、信じてください・・・」「フウウウウ・・・全く・・・」慎治たちの涙ながらの絶叫にうんざりとした表情を露骨に浮かべながら秋月が眉間を押えながら呟いた。「私は情けないよ、この期に及んで未だそんな嘘を付くとは・・・古臭い言い方だけど、君たち男としてのプライドというものは欠片もないのか?よりによって女の子たちにトイレでリンチされていた?それもおしっこを飲まされてた?君たち・・・嘘を付くなら・・・せめてもう少しはマシな嘘を付いたらどうかね・・・」怜と舞は慎治たちに敢えて自由に弁明させながらフン、と鼻で笑っていた。別に秋月に対して事前に根回ししてあったわけでも自分たちに同調することを強要したわけでもない。だが秋月は常識人、だからこそ自分の中での一般常識の範囲内でしか判断するわけがない。しかも校長にまで登りつめた十分に優秀な、怜と舞から見ても評価に値するレベルの男だ。その秋月にとって男子が女子にトイレでリンチされていた、しかも場末の商業高校じゃない、名門のここ聖華でだ、そんなことが信用できるわけがない。信用できないならばそれは嘘、慎治たちが我が身可愛さに必死に嘘を付いているとしか思えない、と考えるのが自然な論理だ。慎治たちの弁明はこの場で唯一、僅かに中立的な秋月をも完全に敵に回しただけだった。フフフ思った通りじゃない、大体秋月先生レベルのまともな男、大人の男性があなたたちみたいなカスの味方をするとでも思っているの?本当にとことんバカね。まあどうでもいいけど、秋月先生はもう完全に私たちサイドね、じゃあ次、行こうかしら。秋月が呆れ果てたように首を振っているのを満足げに見ながら、怜が口を開いた。「校長先生、彼らの話を到底信用できない、ていうのは私たちも同じですけど、一応担任の若月先生にも話を聞いてみませんか?」舞も大きく頷いた。「そうですね。私たちも是非、伺いたいですわ。若月先生は一体どうお考えなのか・・・こんな酷い生徒が私たちの聖華にいるだなんて、担任として一体どういう教育を施してきたのか是非、お伺いしたいですわ。」ヒッ、ヒイイッ!必死で隅に縮こまっていた若月は話を振られた途端、ビクッと電気を流されたかのように全身を震わせた。無理もない。若月はここ聖華のOGということで採用されていたが教員としては可もなし不可もなし、のレベルだった。ルックス、性格、頭のよさ、そして教師としての技量、全てが可もなし不可もなしだった。自分でも限界をわきまえていた若月は共学化にあたり、私なんかが学園の方針に賛成だ反対だ、ていうのもおこがましいわ、と自己規制したおかげで辛うじて残留組に入れたが、内心聖華に残れるかどうか相当にヒヤヒヤしていたことも確かだった。私ももう35歳なのに未だ独身だし・・・この年で聖華をクビになったら行く当てなんかどこにもないわ。何とかここに残れて良かった・・・実のところ怜と舞の評価も毒にも薬にもならないレベル、いてもいなくてもどちらでもいいわね、と言った程度の評価だった。契約更新に当り舞はそのことを若月にはっきりと伝えていた。「若月先生、ではあなたとの契約を来年も更新します。だけど一つ、覚えておいて下さいね。今年ほどの大規模ではないにしろ、聖華では今後も毎年、私たちが求めるレベルに達しない先生たちには遠慮なく、辞めて頂きます。若月先生、あなたは現時点では下位10位以内に入っています。今後相当に頑張らないと・・・来年以降、契約を更新できるという保証はありませんよ?」「はは、はいいいっ!が、がんばります、がんばりますから・・・どうかよろしくお願いしますっ!」遥かに年下の舞にテーブルに頭をこすりつけんばかりの勢いで平身低頭しながら、若月は心底怯えながら心に固く誓っていた。「たたた、大変だ・・・がんばらなくゃ、何とかしなくちゃクビにされちゃう・・・そしたら私・・・どこにも行くところなんかないんだから!!!」その若月にとって、舞の冷たい言葉は匕首を喉元に突きつけられたようなものだった。そそそ、そんなあああっ!わ、私まで、私まで巻き添えにしないでよおおおおっ!自己保身以外に考えられなくなった若月は大慌てで上ずった声で証言した。「はは、はいいっ!そそ、そんな、苛めだなんて、苛めだなんて見たことも聞いたこともありませんんんっ!ぜ、絶対、絶対です!わ、私のクラスで苛めだなんて、絶対にありませんんんっ!」あらあら舞、薬が効きすぎよ、今日は若月先生を苛める趣旨じゃないでしょ、そんなに苛めちゃ逆効果よ。苦笑しながら怜が穏やかな声で若月に問い掛けた。「まあまあ若月先生、落ち着いてください、舞がどういう指導をしてるんですか、なんて言いましたけど、大した意味はないんですから。それより先生も大変なんじゃないですか?こんな問題児を二人も担任に抱えていらして。若月先生も本当に大変でしょうね、て私たちもむしろ同情しているんですよ?如何ですか、普段の彼等は?授業態度とか友達付き合いとか、先生の目から見てどうだか教えて頂けませんか?心配いりません、幾ら先生が努力しても限界があるのは承知していますわ。先生の責任だなんて誰も思いませんから、遠慮なく教えて頂けませんか?」
鞭のように厳しい舞の言葉の後だ、怜の甘い飴の威力は絶大だった。もとよりクラス一の劣等生、しかも礼子たちの姦計により授業を真面目に受ける事を禁じられ殆どの教員から態度最悪の烙印を押されている慎治たち。その担任という事で散々嫌な思いをさせられ下げたくない頭を下げさせられてきた若月だ、慎治たちに対する嫌悪はあっても庇ってやる義理など毛頭ない。ましてや自分の生殺与奪の全権を握る怜と舞の前だ、二人の意図に逆らうような発言をするはずがない。「は、はい!二人とも、二人とも授業態度は本当に最悪、殆どの先生方から叱られていて、私のところにもよく先生方から文句がきていますうっ!」そうそう、その調子よ。怜が優しげに微笑みながら問い掛けた。「授業態度については私たちも聞いていますが、苛めについては如何ですか?そんな現場を目撃されたとか、苛められている、という話を聞いたことはありますか?」「あああ、ありませんんっ!・・・い、いえ逆に、こんな落ちこぼれだから男子生徒にからかわれているのを、天城さんたちに助けてもらっているのを見たこともありますっ!あああ、天城さんや霧島さんが二人を庇っているのは何回も見ましたけど、天城さんたちが苛めているだなんて、断じてありませんんんんっ!」ビンゴ!怜と舞は内心、思わず手を叩いていた。若月先生も満更バカじゃないじゃん!ちゃんとこの場を読んでどう答えれば私たちが満足するか位は分かるのね、よしよしお利口お利口、少しは見直したわよ。満足そうに頷きながら怜は秋月の方に向き直った。「秋月先生、もう十分ですよね?彼等は頑として自分の非を認めないつもりのようですが、これだけ証拠が揃えば彼等の自白がなくても十分だと思いますが?」「全くですな・・・私も教員生活は長いが、これだけ酷い事件は初めてですよ。どう見ても疑う余地はありませんな。」はいOK,これで外堀は埋まったわよ。「では若月先生、お手数ですが彼等の自宅に連絡して至急、ご両親に来て頂くよう伝えてください。ああ勿論、彼等が何をしたかも伝えて下さいね。女子トイレに忍び込んだ挙句に見つかってクラスメートに怪我をさせた、ていうことを。」「はは、はいいっ!た、ただいま直ぐに!」怜の指示に若月は大慌てで転びそうな勢いで駆け出していく。慎治たちの両親が揃うまでの間、一旦散会となったが慎治たちはそのまま昼食も抜きで校長室に軟禁されていた。そして二時間後、慎治たちの両親が血相変えて飛び込んできた。辛い査問の再開だった。
事情を説明された慎治たちの両親は茫然自失の呈だった。母親二人は泣き崩れ、父親二人は余りのショックに、息子が変態性欲者だったという宣告に顔面蒼白となりながらワナワナと唇を震わせていた。長い沈黙の後、信次の父が必死で声を搾り出した。「・・・信次・・・どうしてだ、なんでこんなことをしでかしたんだ・・・」そ、そんなあああっ!ち、違う、ちがうんだああああっ!信次は必死で絶叫した。「ち、ちがう、ちがうんだよおおおっ!嵌められた、俺は嵌められたんだよおおおっ!苛められてたのは、トイレでリンチされてたのは俺のほうなんだよおおおっ!!!」だが信次の父も中小企業とはいえ一つの会社を経営できるまともな男だ、仮にも男である信次、障害者でも何でもない五体満足な男である信次が女の子にトイレでリンチされる、なんて信じられるわけがない。覗きをしでかして捕まえられそうになり、逃げ出した、との話の方が100万倍は信じられる。「おまえは・・・まだそんな嘘を・・・つくのかああああっ!このばかやろおおおおおっっっ!!!」ガターンッ!ドガッ!怒りに我を忘れた信次の父はいきなり立ち上がると力任せに信次を殴り倒した。「俺は・・・俺は情けないいっ!死ね、死ね、お前など今すぐ死んでしまえええっ!」「慎治・・・お前はどうなんだ・・・何か言う事はないのか・・・」慎治の父も俯いて拳を握り締めたまま、押し殺したような声で呟いた。「あああああ・・・と、とうさん・・・信じて・・・違う、違うんだよ・・・僕たちじゃない・・・悪いのは礼子さんたち・・・」「黙れっ!いい加減にしろ!」慎治の父も怒りを全身からぶちまけながら立ち上がった。「未だ言うのか・・・それも言うに事欠いて天城さんの、落ちこぼれのお前に何かと世話を焼いてくれた天城さんのせいにしようとは・・・このばかものおおおっ!土下座しろ、土下座して皆さんに謝れえええっっっ!!!」床に正座させられている慎治の首根っこを引っつかむと、慎治の父は泣きながら何度も何度も慎治の頭を床に叩き付けた。「何でだ・・・何で俺の息子がこんなクズになってしまったんだ・・・お前は本当に慎治なのか?俺の息子なのか?」礼子の父のサポートもあり、出世街道を順調に歩んでいる慎治の父にとっても慎治の言う事は、いくら実の息子の言う事だとは言っても到底信じる事はできなかった。信用できない、即ち追い詰められて嘘を言っている。女子トイレの覗き、クラスメートへの暴行。最低の破廉恥行為をしでかしたのに、何とか言い逃れをしようとしているとしか思えない。卑劣な・・・何と卑劣な・・・加えて礼子たちは慎治たちの自宅を足繁く訪れ、慎治たちの両親とも何回も会っている。美しく知的で明るい礼子たち、大人から見て最高の、理想の女の子像を巧みに演じきっていた。その礼子たちが実は慎治たちを苛めていた、そんな話を信じられるわけがない。しかも苛めなど全くなかったと、担任の若月が明確に否定しているのだ。そして高校入学以来、慎治たちの成績が急低下し更に授業態度、生活態度などで両親も父母会、個別面談などで再三学校から注意を受けている。これでは・・・どんなに慎治たちが叫んでも信用してもらえるわけがない。いや、言えば言うほど両親の怒りと絶望と嘆きを掻き立てるだけだった。なまじ肉親の分、余計絶望は、嘆きは深い。そしてその怒りは骨肉憎悪、赤の他人に対する何倍もの憎悪へと膨れ上がっていく。憎悪、という点で言えば慎治たちの両親の憎悪の方が怜、舞よりも、いや礼子たちよりも遥かに激しく膨れ上がっていた。今や両親、慎治たちの最後の望みの綱も明確に敵側に回っていた。
一仕切り慎治たちの両親が爆発したタイミングを見計らって怜が声を掛けた。「お父さん、お二人ともお怒りになったり嘆かれるお気持ちは良く分かりますが、取り敢えずその辺りでストップして頂けませんか?兎に角どうぞ落ち着いて、お坐り下さい。」怒りで顔面を紅潮させつつ、同時に余りの恥辱に身の置き場もないように震えながら慎治たちの父は椅子に座り込んだ。二人が一呼吸ついたのを見計らうと怜が静かに語りかけた。「どうやら事情はお分かり頂けたようですね?慎治くんたちはこの期に及んでも未だ、とんでもない嘘を付いて誤魔化そうとしていますが、流石にそんなことは信じていらっしゃらない、ということでよろしいでしょうか?」弱々しく二人が頷くのを見て怜は言葉を続けた。「今、お父さん方が慎治くんたちを殴りつけていらっしゃいましたが、それはとても正しい事だと思います。人間として絶対にやってはならないこと、それを犯したら罰を受けねばならない、そういう毅然とした態度を示された事は正に尊敬に値します。しかしながら、幾らお父さん方に罰せられた、といっても、私たち学園としてはそれだけで許す、というわけには行きません。お分かり頂けますね?」「・・・はい、分かります・・・申し訳ありません・・・覚悟は・・・できています・・・」慎治の父が呻くように言った。「当然・・・退学、でしょうね・・・仕方ない・・・ですね・・・信次、お前もう、学校には行かないでいい、明日から直ぐに仕事を探せ、さっさとどこかで仕事見つけて働くんだ、いいな!」信次の父も悄然としながら同意した。母親二人も泣きながら頷いていた。予想通りの反応に内心、怜も舞もニヤリとしていた。その横で未だ痛みの余韻を味わいながら、慎治たちは呆然としていた。退学・・・退学にされるのか・・・未だ現実味が全く沸かなかった。だけど・・・まあいいのかも知れないな・・・退学になれば、兎に角礼子さんたちからは離れられるもんな・・・毎日毎日鞭やおしっこで苛められてる位なら、いっそ退学になっちゃった方がまだマシかもな・・・だが二人の淡い喜びは舞の一言であっさりと踏み潰された。「そうですね、確かに慎治君たちの振舞いは十二分に、退学に値します。だけど、私たちは今回敢えて、敢えて二人を退学にするのは留保したいと思います。」「えっええっ!ほ、本当ですか!?」「そ、そんな!退学に・・・しないで頂けるんですか!」仰天した父親たちが大声をあげた。「そうです。決して・・・決して今回の罪を許す事はできません。けれど聖華も共学化した以上、今後もこのようなことが絶対に、二度と起きないとは言い切れません。その度に犯人を退学にするのは簡単ですが、敢えて最も困難な更生への道を探る事もまた、大事な教育だと思います。だから、ご両親が私たちの条件を了承して頂けるなら、今回は退学処分だけは留保しようと思います。」父親二人が喜んだ声をあげた。「あ、ありがとうございます!」「退学は、退学だけは許して頂けるなら、どんな条件でも結構です!お願い・・・します!」
あらあら簡単に乗って来たわね。内心舌なめずりをしながら怜がつなぐ。「ありがとうございます、て些か気が早すぎますわ。この条件、かなり厳しいですよ。と言いますか、滅茶苦茶理不尽な条件ですよ。」厳しい条件・・・な、なんだなんだ、先生たち、一体何を企んでるの?恐怖に震える慎治たちをチラリと見た怜が説明する。「お父さん方も、ここ聖華が古くからの女子高だということはご存知ですね?今でこそ、そんな習慣は全く廃れましたが戦前のここではイギリスのパブリックスクール式で、躾の名のもとに相当な体罰が恒常的に行われていたんですよ。今でも地下に、そういうお仕置き部屋が残っています。そう・・・慎治君たちを更生させるために、体罰を認めて欲しいのです。」げっげえええええっ!!!思わず仰け反る慎治たちにチラリと冷たい視線を投げかけた舞は、次の瞬間、慎治たちの両親に如何にも困ったような、何とも言えない慈悲と誠実さを溢れ出させたような微笑を投げかけた。「体罰をさせて下さいなんて、酷いお願いをしている、と言うこと位は私たち自身、よく分かっています。だけど・・・これが私たちの限界なんですよ。徳の高い高僧ならば言葉の力だけで慎治君たちを更生させることもできるかも知れません。だけど、申し訳ないんですが私たちにはそれ程の力はありません。だから・・・だから普通の指導も勿論全力を尽くしますが、体罰を併用する位しか考えつけないんですよ。」如何にも誠意に満ち溢れた舞の言葉に、慎治たちの両親は躊躇せずに飛びついてきた。「も、も、勿論です!勿論構いません!な、なあ矢作さん、当然、当然お願いするしかないですよね!」「と、当然です!体罰程度で慎治を見捨てないでご指導頂けるなら、幾らでもぶん殴ってやってください!骨が折れようが片輪になろうが構いません!遠慮なく、遠慮なくビシビシやってください、お願いします!」そ、そんな、そんなあああああっっっ!体罰を了承する、それが何を意味するか、流石に鈍い慎治たちにも直ぐに分かった。どんな傷がつこうと、痣だらけ、蚯蚓腫れだらけにされても体罰の一言で全て片付けられる。苛めの免罪符、何をやってもどう苛めてもいい、というフリーパスを怜と舞に、そして礼子たちに与えるようなものだった。「ああ、そんな酷い・・・」「父さん・・・助けて・・・」だが帰ってきた返事は罵倒だけだった。「馬鹿者!お前はもう黙っていろ!」「二度とそんなふざけた口を叩けないように、根本から叩き直して貰ってこい!」闇、更に深い地獄への口が慎治たちの足元に広がっていた。
6?
屈辱と口惜しさに満ち満ちた悪夢のような保護者面談が終わり、慎治たちの両親が帰っていった後、校長室は奇妙な静寂が支配していた。その静寂に耐えかねたかのように、若月がおずおずと口を開いた。「あの・・・体罰もありで指導、となったんですが、どう・・・やりましょうか?」体罰のなくなった教育を受けた世代である若月にとって、体罰といってもどういうものか想像もつかない。精々がビンタ程度のものだ。だが怜と舞が考えているのはそんなレベルではない。怜が凄絶な冷笑を浮べながら答えた。「心配しなくてもいいですわ、若月先生。どういう罰を加えるかは私と舞とで考えて、後でご連絡しますから。基本的には体罰の執行も私たちがやるつもりです。秋月先生もそれでよろしいですよね?」流石に秋月は薄々と舞台裏に勘付いたかのようだったが、敢えて慎治たちを庇う義理など何もない。それに校長職は激務、正直言って余計な面倒事は背負い込みたくない。「ええ、お二人にお任せできるのであれば、私としても助かります。」ある意味で大人の秋月はそれっきり、慎治たちのことを脳裏から消し去ってしまうことにした。もし復活するとすれば、また何か問題が発した時だけだ。「ではお言葉に甘えて、この二人の処分については理事会にお任せしましょうか。若月先生も異論ないですな?」秋月の言葉に未だ事情を飲み込めないまま若月が頷くのを見ると、怜は早速切り出した。「ありがとうございます。では矢作君、川内君、部屋を変えるわよ、ついていらっしゃい。」二人が慎治たちに礼子、陽子、玲子、有希子の6人を連れて出た後、疑問を抑え切れない若月は秋月に尋ねた。「・・・校長先生、これでいいのでしょうか・・・私は何かしなくても・・・」えっ、未だ分かっていないのか君は、と呆れたように秋月は振り返った。「うん・・・君はもういい、このことは忘れたまえ。これは理事マターだからね、君がタッチする必要はない。必要ない事、関わりあう必要がない事には・・・首を突っ込まない方が身のためだよ。」
一方、六人を引き連れて廊下に出た舞は陽子と有希子に声を掛けた。「ご苦労様。二人ともいい出来だったわよ。じゃあ後は私たちでやっておくから、教室に戻っていいわよ。」「ハイ先生、じゃあ後はお願いします!」明るく言いながら陽子は憎々しげに慎治を睨みつけた。「思い知った、慎治?後は・・・ゆっくりと礼子や怜先生に苛めて貰うのね、ペッ!」思いっきり唾を吐き掛けた陽子の隣で有希子も勝利の笑顔を浮かべていた。「ざまあみろ!てところよね、信次。もうあんたの人生滅茶苦茶よね、当然の報いでしょう?いい気味よ!ペッ!」心底楽しそうに、復讐成就の快感に酔いしれながら有希子も思いっきり唾を吐き掛けると、二人は意気揚々と去って行った。クラスメートの唾を頬に滴らせながら呆然としている慎治たちに、怜の凛とした声が響いた。「何ぼうっとしているの!さっさと来なさい、愚図愚図していると罰を追加するわよ!」恐怖にもつれる足を半ば絡ませながら慎治たちは必死でついていった。怜と舞が降りて行ったのは慎治たちにとって恐怖と屈辱に満ちた、視聴覚室へと通じる階段だった。「あ、もしかしてお仕置き部屋って・・・」閃いたように言った礼子に怜が答えた。「流石は天城さんね、その通りよ。お仕置き部屋って言ったら完全防音じゃないといけないでしょう?昔の技術じゃ完全防音の部屋なんて地下に作るしかなかったんでしょうね。」視聴覚室の横、何のためにあるか誰も知らずにいたドアの前に着くと、舞がポケットから鍵を取り出した。ガチャッと音を立てて開いたドアのすぐ奥には、更に下へと降りる階段があった。生まれて初めて本物の鞭で打ち据えられた視聴覚室、ココタマにまで苛められ屈辱に咽び泣いた視聴覚室、慎治たちにとっては悪夢のような部屋だ。だがお仕置き部屋はその視聴覚室の更に下にある。その階段は地獄の奥底へと続いているかのようだった。降りきったところにもう一つドアがあった。そのドアを舞が開け、壁際のスイッチを入れた。天井に設置された蛍光灯に照らし出された部屋は意外なほど広かった。見たところ視聴覚室とほぼ同じくらいの広さだ。入ってすぐに広いスペースがあり、奥は二つの小部屋への入り口となっていた。長年使われていないため厚く埃をかぶった部屋のよどんだ空気に顔をしかめた怜が換気扇のスイッチを入れた。広い室内にはあちこちに何台もの器具、見慣れない器具が置いてあった。そのうちの一台、木馬のように足を伸ばし、その上に跳び箱の背のような台が乗り何本かの皮ベルトが伸びた器具の前で怜が立ち止まった。「フフフ、二人とも聖華学園自慢のお仕置き部屋へようこそ。これからあなた達がたっぷりと、長い時間を過ごすことになる部屋よ。遠慮なく寛いでいいわよ。」陰惨な雰囲気、映画の中でしか見たことのない拷問部屋のような雰囲気に慎治たちは恐怖に全身が凍りつきそうだ。「ウフフフフ、怖いの?そんなに震えちゃって。まあ当然でしょうね、このお仕置き部屋、昔は一体どれだけの数の生徒たちの悲鳴を聞いていたことかしらね。その子たちの恐怖、悲鳴、苦痛、後悔・・・フフフ、部屋中にたっぷりと浸み込んでいるみたいじゃない?今日からはあなたたちの悲鳴をたっぷりと浸み込ませてあげるわ。男の子の悲鳴は初めてだからね、この部屋もさぞ喜ぶでしょうね。」怜が凄惨な冷笑を浮かべながら言い放った。震え上がる慎治たちの肩に手を回した舞が、奥の小部屋、ベッドのような奇妙な台、を置いた小部屋に二人を連れて行く。古びた責め具が多いこの部屋でその台だけが妙に新しい。「フフフ、何で小部屋があるか分かる?元々は女子高だからね、お仕置きのメニューで浣腸もあったのよ。幾らお仕置きとはいっても何人も纏めてお仕置きする時に、お互いのお尻やうんちを見るのもお下品でしょう?だから小部屋も用意してあるわけ。ウフフ、でもね、小部屋に一人ずつ入れられてお仕置きされていると、隣の部屋からも悲鳴が聞こえてきてとても盛り上がったそうよ。」
大部屋に戻ると怜がスッと傍らの器具を撫でた。「ここにある道具は基本的に拘束具よ。例えばこれは、君たちを背中に四つんばい状態に寝かせて固定し、お尻を鞭打つための台ね。」、とジャラッと舞が天井から下りた鎖に取り付けられた皮ベルト付の横棒を手にした。「これも拘束具よ。天井から降りたバーに君たちの手を固定して、ここにある足枷で両足も固定するわけよ。そのまま鞭を加えてもいいし、反省するまで立たせたままにしておくこともできるわね。」ああ、あああ・・・慎治たちは恐怖のため膝がガクガクとし、全身がブルブルと激しく震えていた。「せ、先生・・・そんな・・・許して・・・」「こ、こんな・・・ひどすぎます・・・」涙と鼻水を垂れ流しながら、二人は泣きながら土下座して哀願した。体育館、廃グラウンド、視聴覚室・・・いずれとも違う本格的な拷問室の陰惨な雰囲気は二人の精神を何もせずとも既にズタズタに踏み躙っていた。美女二人に美少女二人、そして土下座して泣いている無力な男が二人。責める側、責められる側がこの上なく明確に分かれていた。「フフフ、もう無理よ矢作君、さっきのお父さんたちの言葉を聞いたでしょう?」ゴリッと高級な黒いパンプスを履いた脚で怜は慎治の頭を踏みつけた。「もうあなたたちは両親にも見捨てられたのよ。どんな体罰を加えても構わないってね。しっかりお墨付きは頂いたわ、遠慮はしない、たっぷりと指導してあげるわね。」ガリッと舞のヒールも信次の後頭部に食い込んだ。「さあてと、あなたたちの泣き言に付き合っている暇はないから、取り敢えずやることを命令しておくわね。」怜がクイッとパンプスの爪先で慎治の顎を小突き上げた。「この部屋はずっと使っていなかったから大分汚れてるでしょう?お仕置きも清潔な環境でやりたいからね、綺麗に掃除しておいて頂戴。今日はもう授業に出なくていいから、あそこの隅においてある掃除用具を使って綺麗に掃除しておきなさい。」そ、掃除!自分たちが痛めつけられる場所を自分たちで掃除!ひ、酷い・・・だが何も言えなかった。信次の頬を爪先で軽く突きながら舞が冷笑した。「放課後にくるわね、その時にチェックして未だ汚れていたら、フフフ分かるわね、体罰を増やすわよ?」体罰を増やす!その一言は慎治たちを震え上がらせるのに十分だった。「さあ、じゃあ私たちは行きましょうか、仕事もあるし授業もあるし、何より綺麗になってからじゃないと苛める気にもならないわよね!」アハハハハッと楽しげに笑いながら、四人は階段を上がりお仕置き部屋から出て行った。後には・・・嫌々ながらものそのそと掃除にとりかかる慎治たちだけが取り残されていた。
そして三時過ぎ、必死で働き続けた慎治たちが漸く掃除を終えたころに一行が戻ってきた。今度は怜と舞、礼子たちの他に富美代と朝子も一緒だった。「フーン、ここがお仕置き部屋なんだあ?」のんびりした声で朝子が面白そうに部屋の中を見て回る。「いつもの視聴覚室の地下にこんな部屋があるとはね・・・知らなかったわ。」いつもクールな富美代も流石に驚いた様子だった。お仕置き部屋を初めて見る富美代と朝子は部屋自体に興味を奪われていたが、礼子たちは怜と舞の服装に目を奪われていた。午前中と違う服だが別に突飛な服を着ているわけではない。アルマーニの濃紺のスーツの上下にインナーは純白のブラウスと見るからに知的なキャリアウーマンファッション、悪く言えばある種、キャリアウーマン用の制服に近いフアッションだ。違うといえば足元をパンプスから漆黒のジョルダンのロングブーツに履き替えているのが若干違和感といえば違和感だが、一人一人で見れば全くおかしなところはない、むしろ長身でスタイル抜群、内面から知性か溢れ出ている二人にとってはある意味、最も着慣れたよく似合うフアッションだ。違和感があるのは二人、怜と舞が全く同じ服装、かつヘアスタイルもメイクも完全に同じにし、殆ど全く見分けが付かないようにしていることだった。興味津々、と言う目で見ていた礼子が遂に口を開いた。「・・・しかし怜先生と舞先生、一卵性というだけあって本当に似てますね。普段は服とかメイクとかを分けてるから分かりますけど、そうやって完璧に同じにすると、殆ど区別つきませんね。」玲子も、私もそれ聞きたかったんだ、と言うように頷いた。「そうですよね、先生・・・でも午前は別の着ていらしたし、何故ですか?先生たちが無意味にそんな事するとは思えないし、何か楽しい企みがあるんじゃないですか?教えてくださいよ!?」あけすけに尋ねる玲子に苦笑しつつ舞が答えた。「全く霧島さんは勘がいいんだから・・・苛めっ子の直感、というやつかしら?確かにこうやって私と怜が完全同じ服着てるのは、後のお仕置きで楽しい趣向を用意してあるからよ。」クックックッと怜も楽しそうに笑った。「まあブーツは少し悪乗り、あなたたちが矢作君たちを本気で苛める時はブーツを履くことが多い、て聞いたからね、この二人にはブーツがとても怖いんじゃないかな、て思って用意したのよ。ウフフフフ、でもスーツとメイクの方は折角双子なんだからね、それを責めにも活かしたいでしょう?フフフ、ご指摘の通り、楽しい趣向を用意してあるわよ!」もう!先生ったらー!慎治たちを除く全員が一頻り笑ったところで礼子が口を開いた。「じゃあ先生・・・心残りもありますけど、今日は部活もあるし私たち、これで失礼します!じゃあね慎治、しっかりお仕置きして貰うのよ!」えっ、まさか今日は怜先生たちと一対一で苛められるの?予想外の展開に戸惑う慎治たちを見て玲子がクスクスと笑った。
「アハハハハッ!信次、あんた今日は私たちも入って集団リンチされると思ったんでしょう?ブーー、残念でした。今日は舞先生たちにゆーっくりと、お仕置きしてもらいなさい!ウフフフフフ、きっと楽しいわよお?あ、そうだ、行く前に一つね、いいことを教えてあげる。」「い、いいこと?な、なんなの!?」甲高い声を上げる信次を嘲笑いながら玲子が答えた。「金曜のことよ。あの時、信次たちは陽子と有希子のおしっこ飲まされて逆ギレしたでしょう?だけどね、本当は私たち、公衆便所の刑は金曜で、あの日一杯で終わりにしてあげようね、て言ってたのよ。」「えっえええっ!そ、そんなあああ・・・」玲子の言葉に思わず絶句する信次に冷笑を浴びせながら礼子も続けた。「玲子の言ったことは本当よ。取り敢えず全員飲ませ終わったみたいだから、じゃあもう許してやろうか、て言ってたのよ。ううん、もっといいこと教えてあげるわ。あの日、トイレの予約はもう、陽子と有希子までしか入っていなかったのよ。ウフフフフ、分かる、私の言ってること?要するにね、陽子たちのおしっこさえ我慢して大人しく飲んでいれば、慎治たちは助かっていたのよ!」「あああ、あああああ・・・そんな・・・馬鹿な・・・う、嘘だ嘘だあああっっっ!うっうううっ、嘘だと・・・嘘だと言ってよおおおっ!おね・・・がいいいいっ!」慎治は思わず大声で泣き出してしまった。な、なんていうことだ・・・後一人だったなんて・・・後一人、後一人のおしっこさえ飲んでいれば助かっただなんて!!!「ひ、ひどい・・・なんで今更そんなことをいうんだよおおおおおっ!せめて・・・せめてそんなこと、聞きたくなかったよおおおおおっ!!!」涙をボロボロ零しながら絶叫する信次の無様な姿を、玲子は心底楽しそうに嘲笑っていた。「アハハハハハッ!アーッハッハッハッ!どう信次、悔しい?後悔先に立たず、とはよく言ったものでしょう?でもだーめ、もう遅いのよ!信次は破滅しちゃったの!たーっぷりと、惨めな気分を味わいなさい!自分の馬鹿さ加減を悔やみなさい!そしたら・・・舞先生のお仕置きも何倍にも辛くなるわよね!アハハハッ、アハハハハハッ!いい気味、まさに自業自得よね!」
最低の週末、文字通り最低の週末を慎治たちは送っていた。許さない・・・礼子たちの言葉が重く重くのしかかっていた。あの目・・・礼子さんのあの目・・・真剣に、本気で怒っていたな・・・苛めを楽しむ様子すらなかったよ・・・どうしよう・・・完全解放の久々の週末、鞭で打たれずに済むのは本当に久しぶりだな。この2日間だけはおしっこを飲まされずに済むんだな。だけど・・・ちっとも嬉しくなかった。どんな目に遭わされるんだろう・・・鉛のように重い心を抱えながら慎治は机上の携帯を見た。今までの週末、不意に呼び出されるんじゃないか、体育館に、グラウンドに、さあ今から鞭打ってあげるからおいで!と慎治の都合など一切お構いなしに呼び出されたことを思い出す。友達など殆どいない慎治、携帯が鳴るのは礼子たちからの呼び出し以外には滅多にない。だから普段は携帯が鳴る度にギクッとするが今日ばかりは何故か、鳴ってほしいような気もする。とその時、いきなり着信音が鳴り響いた。
「ヒッ!」そ、そんな!鳴って欲しいなとは思ったけど、やっぱり鞭はいや!だが出るのが遅いとまた怒られる。震える手で慎治は携帯を掴んだ。「も、も、もしもし・・・」
「あ、慎治、ごめん・・・俺、信次だけど・・・」「何だ信次か・・・脅かさないでよ!」フウウッと安堵とも失望ともつかぬため息をつきながら慎治は座り込んだ。「どうしたの、何か用?」「ああ・・・慎治も考えてると思うんだけど・・・俺たち、どうなるんだろう・・・」「そ、そんなこと!ぼ、僕が、僕が知ってるわけないじゃない!そんなこと!!!・・・やめてよ・・・それ考えるともう、気が狂いそうだよ・・・」「そ、そんな、俺に怒るなよ!俺だって・・・俺だって死にたいよ・・・」「ああ・・・そうだよね・・・こんなとこで罵り合ってもしょうがないよね・・・で、どうされるんだろう・・・やっぱり・・・鞭かな?みんな・・・クラスみんなが鞭を買ってくるとか・・・」「みんなで鞭!?痛そうだな・・・だけどなんか、鞭じゃないような気がしないか?もっと何か・・・もっとずっと酷い目に遭わされそうな気が・・・」「・・・僕も・・・だけど、なんなんだろう?おしっこも飲まされたし、鞭よりも酷いことなんて・・・何???」
二人は際限なく愚痴と嘆きと自己憐憫を零しながら延々と自分たちを待ち受けるであろう悲惨な運命を、僅かでもいいから予想しようとした。なんとなくの予想は坊野たちが味合わされた拷問、あんな一生片輪にまではされないだろうが、死ぬほど痛い拷問をされるんじゃないか、それが二人の貧困な想像力の及ぶ限界だった。だが現実は二人の予想とは全く異なっていた。
無限とも思える精神的拷問の時間、遅々として動かない時計は針の音だけが矢鱈に耳障りに響く。まるで自分だけが時の流れから切り離され永遠の牢獄に閉じ込められたようだった。だが一歩また一歩と時はゆっくりとその時に近づいていく。恐怖が現実となる時へ。月曜の朝へと。
一睡もできないまま悶々と朝を迎えた慎治は足枷を嵌められたかのように重い足を引き摺りながら登校してきた。フウウウッ・・・来ちゃった・・・正門前で立ち竦んでいると、反対から信次が来るのが見えた。俯きながら歩いてきた信次がため息をつきながら顔を上げたとき、慎治は思わずギョッとしてしまった。酷い顔色・・・土気色じゃない?生気も全くないし、病人みたいだよ・・・気がつくと信次も自分のことを驚いたような顔で見ている。ハハハそうか、僕もなのか・・・僕も酷い顔色なんだね・・・死人みたいなんだろ?生きている死人、僕たちゾンビみたいなもんだね・・・
フラフラと教室に入っていくと二人は強烈な違和感を感じた。何、何か変・・・何なの?いつもは慎治たちが登校してくると早速クラスメートがクスクスと指を指して笑っていたり、或いは待ち構えていたかのように「さあトイレ行こう!」と声がかかったりする。だが今日は何もなかった。じっと見つめるクラスメートはいるが、直ぐに見てはいけない物を見てしまったかのように目を逸らしてしまう。
な、なんだ・・・何なの一体?こたえを求めるかのように必死できょろきょろする慎治はふと富美代と視線があった。「あ、ああ・・・フミちゃん・・・おはよう・・・ございます・・・」「・・・ああおはよう。」気のない返事を返して富美代はプイとそっぽを向いてしまった。え、えええ!?慎治たちは毎朝礼子、富美代、玲子、朝子に朝の挨拶をし、合格のハンコ代わりに唾を吐き掛けて貰うよう命じられていた。誰からも唾を吐き掛けて貰えなかったら、不合格の罰として放課後、ベルトで鞭打たれる。だが富美代は合格不合格以前に慎治の挨拶に全く興味がなさそうだった。恒例の朝一のおしっこすら命じる気配はない。
「ふ、フミちゃん・・・あの、その・・・」「何よ慎治、何か用?ああそうか・・・唾吐き掛けて貰ってないから気になるの?いいわよ別に、今日は合格、ていうことでいいんじゃない?」それに・・・と言いかけた富美代は口を閉ざして慎治の事をじっと見詰めていた。ゾクッ!慎治の背筋に何とも言えない悪寒が走る。富美代の視線、それはいつもの冷たい視線でも責め嬲る楽しみにふける残忍な眼差しでもなかった。その視線は・・・哀れみの視線だった。苛めの相手ではなく、幼馴染としての慎治の破滅を悼む憐憫の眼差しだった。
可哀想に慎治、私の幼馴染・・・その慎治がもう直ぐ破滅させられるのね。可哀想に・・・う、うそだ!こんなの、こんなことありえない!慎治の脳裏に富美代の残酷な笑顔が甦る。サイボーグとも言われるほど整った冷たい美貌に、冷笑を浮かべながら自分を散々責め苛んだ富美代の姿が。この美しい唇に何度唾を吐き掛けられたことだろう。引き締まった腕が振るう鞭でどれだけ泣き喚かされたことだろう。細く長い脚、白ブーツを履いたその脚でどれだけ踏み躙られたことだろう。そしてキュッと締まった形のよいお尻、そこから排泄されるおしっこを何回飲まされたことか・・・僕がどんなに泣き叫んでも絶対に許してくれなかった、それどころか楽しそうに笑いながらいつまでもいつまでも苛め続けたフミちゃんだよ?礼子さんにも負けず劣らずの、超の字がつく苛めっ子のフミちゃんだよ?そのフミちゃんが僕を憐れむだなんて・・・そんなことがある訳ないいいいっ!
「そ、そんな・・・ど、どうする気なの・・・僕たち一体・・・どうなるの・・・」フウッと富美代は小さく溜息をついた。「いいじゃん別に。どうなるかなんて、どうせ直ぐに分かるわよ。今聞いたとこで何の役にも立たないじゃない?」そ、そんなあああああっ!慎治は思わず富美代の足元に縋り付こうとしたが、丁度その時ホームルーム開始のチャイムが鳴った。そして授業開始、だが慎治たちは二人とも授業なんか全く聞こえてはいない。ひたすら恐怖に怯えるだけだ。そして一限が終了し、休み時間となったが、誰もトイレに引き立てようともしない。あああ・・・泣きべそを掻いている二人をおいて二限が始まった。そして終了間際、突然慎治は強烈な黒雲のような不安感、邪悪な違和感が襲い掛かってくるのを感じた。息が詰まるような嫌な感じだ。こ、この感じ、いつかどこかで・・・そうだ、あの時、礼子さんやフミちゃんが鞭を買った時の感じだ!と言う事は!!!
丁度その時チャイムが鳴り授業が終わった。教師が出て行ったのとほぼ同時に校内放送のチャイムが鳴った。「一年一組の川内信次、矢作慎治の両名は直ちに校長室まで来るように、繰り返します、一年一組の川内信次、矢作慎治の両名は直ちに校長室まで来るように。」こ、こ、校長室!!!な、何で僕たちが呼び出されるの!?予想外の展開に凍り付いた二人は必死に答えを求めるかのように辺りをキョロキョロと見回した。その二人に朝子が相変わらずキョトンとした表情で近づいてきた。「ほら二人とも早く行きなさいよ、みんな待ってるわよ。」無理やり引きずり出されるかのように廊下に連れ出された二人は夢遊病者のようにフラフラと歩いて行った。
校長室のドアの前でノックもできずに佇んでいると、気配を察したのか内側からドアが開けられた。何と校長の秋月自身だった。「ああ二人とも遅いじゃないか!呼びに行こうかとしていたところだったよ!さあ早く入って!」急かされて入った二人は中にいるメンバーを見て思わず呻いてしまった。礼子、陽子、玲子、有希子、担任の若月、そして二人の妙齢の女性がいた。日向怜と日向舞の二人だった。
2?
日向怜と日向舞、この二人は聖華において特別な存在だった。私立の聖華は法的には理事長個人の所有であり、怜と舞はその理事長の姪だった。独身で子供のいない理事長は怜と舞を我が子同然に可愛がり、理事長の財産である聖華は唯一の血縁である二人の母を経由して怜と舞、一卵性双生児の二人の美女が相続することも民法的にも既に確定している、と言ってよい。だが特別なのはその血縁だけではなかった。幼い頃より才媛の双子で有名だった二人は敢えて聖華へは進学せず、小学校から高校までを都内でも数少ない国立大学の付属校で過ごし、二人とも東大に進学した。怜は教育心理学、舞は経営学を学んだがそこでも才能を如何なく発揮した二人は今年、30歳という異例の若さで母校の助教授に抜擢され、1-2年後の教授退官時には二人が次期教授となるのはほぼ確実、と言われていた。
既に結婚し戸籍上は榛名怜、長門舞となっていたが、仕事上では継続して日向怜、舞と名乗っている二人は聖華においても旧姓を使用していた。仕事を引き受けたのは無論単なる根負けだけではない、有能な研究者である二人だが自らの教育、経営に関する知識を実践する、いわばフィールドワークとしての興味をそそられたこともあった。このため肩書き上は常任理事、と言うことでNO.2だが実質的にはトップとして学園経営に関する全ての決定を二人だけで下す権限を得た上で二人は聖華に着任した。
二人が外部の専門家としての視点で冷静に分析した聖華の現状、将来は決して明るいものではなかった。お嬢様学校とは言っても超ブランド校ではない聖華はその分野ではトップになれず、中の上のレベルを超えることはできない。一方、完全な受験校にシフトするのもまた、長年受験教育に注力してきたライバル校が数多い中では余り勝算が高いとは思えなかった。また教員の質についても極めて評価が低かった。お嬢様学校という美名に隠れて微温湯にどっぷりと浸り切り、自己研鑽を怠った教員が余りにも多過ぎた。
大体良妻賢母教育を目指しております、だなんて何時の時代の話をしているのよ?英語もパソコンもろくに出来ないで、十年一日の変わり映えのしない授業を惰性でやってるだけじゃない?じゃあクラブ活動に力をいれてるのか、と思えばお嬢様学校ですからクラブ活動などは程々が一番です?要するに何もやる気がないだけじゃない!怜の評価ではおよそ半分は教員としてのレベルは平均以下、不適格だった。些か八方ふさがり、とは言っても仕方ないわね、で片付けてしまうわけにはいかない。
「フウウッ・・・予想以上に酷いわね。ちょっとやそっとのことじゃ立て直せないわよ。」参った、というように舞は天井を見上げていた。「何か抜本的な事を考えないとね・・・」先程から黙って何か考えていた怜が舞の方に向き直り、口を開いた。「ねえ舞、いっそ思い切ってさ、聖華を共学校にしてみない?定員は今のままで増やさないで、男女各半々の完全共学校に変えるのよ。」「共学に変える?それはまた・・・随分思い切った、というか凄い提案ね。それ・・・真剣に言っているの?冗談でなく?」「うん、真面目も真面目、100%真剣よ。考えてもみてよ、お嬢様学校でも生き残れない、進学校にも成り切れない、となればこのまま女子校でいれば単なる中堅私立に埋没してしまうだけよ。だけど共学ならどう?私立の進学校は大体、男子校と女子校に分かれていて共学の進学校、というのは私立では数少ないのよ。多分レベルで言えば私たちの母校とか都立のトップとか、共学は公立の方が優勢よ。だからこそ、勝負できる可能性があると思うの、共学志向で優秀な生徒を集められれば結構展望開けるんじゃないかしら?」「・・・そうか!定員維持で共学化、となれは必然的に女子の倍率は上がって優秀な生徒に絞れるかも知れないわね。問題は男子だけど・・・どうなの?聖華を男子が受けるかしら?」「大丈夫よ!いい、男子校の伝統校は例え名門校でも、どこか荒っぽさが多少はあるものよ。大人しい系の男子でそういう雰囲気は嫌だ、もっと穏やかな柔らかい雰囲気がいい、ていう子も少なからずいる筈よ。そういう子たちにとっては元女子校、それも伝統あるお嬢様学校の聖華は格好の進学先になるはずよ!」「そうね・・・怜、そのプランいいわ、きっと行けるわよ!それに、多分もう一つ、いい効果が期待できるわよ。」「もう一つ?どういう事?」
「女子校から共学校への転換、この上ない大改革じゃない?だから聖華のもう一つの問題、無能な教員連中への踏み絵にもなるわよ。ずっと微温湯に浸りきっていたい、ていう連中がこの改革に賛成するわけないでしょう?きっと猛反対するわよ。フフフ、これからの聖華に不要な連中を焙り出して片付ける格好の踏み絵になるわよ、これ。大体考えて見れば、今はこの不景気じゃない?有能なのに勤務先がないとか、実力派なのに安い待遇で我慢している先生たちなんて幾らでもいるわ。無能な連中をカットしてそういう埋もれかけた有能な先生たちに入れ替えるには、今が絶好のチャンスよ!」「流石は舞ね、そこまでは私も気付かなかったけど、言われてみればその通りじゃない!まさに一石二鳥とはこのことね!じゃあ早速動き始めよう!」「ええ早速!じっとしている時間が勿体無いわ!」
この提案には怜と舞の学歴も大いに関係していた。怜と舞は小学校から大学まで一貫して共学育ち、しかも日本でもトップレベルの共学校育ちだ。従って少なくとも成績面においては男女全くハンディなく同一条件で競争することが当たり前、男女を分ける意味など全くない、と考えていた。また新世代の女性運動、特にジェンダー論にも詳しい二人にとっては良妻賢母教育のような役割分担に基づく教育は僻咾發痢・軌蕕諒鉸・⊆・僻歡蠅剖瓩ざ鬚砲發弔・覆こ鞠阿世辰拭・・・・隍苳・ぢ今時時代錯誤もいい加減にしなさいよね。体育とかで体力面のハンディがあるからクラス分け、種目分けするのは当然だけどあとは一々男だ女だ、て分けること自体がナンセンスよ。そんなことを今だに言っている教員は、自分の不勉強、怠慢をカモフラージュする隠れ蓑に使っている怠け者か本物のバカかのどちらかよ。いずれにせよそんな連中、要らないわ。無論女性否定的な面のある旧式なウーマンリブ運動と違い、怜も舞も女性としての自分を否定する気やユニセックス志向は毛頭ない。170センチの長身と引き締まったスリムなプロポーション、加えて溢れるばかりの知性をたたえながら何処か親しみやすい美貌。学生時代はモデルのバイトすらしていたほどの二人だ。ファッションにしろメイクにしろ、女性としての楽しみもフルに満喫しているし男性関係もかってはかなり派手な方だった。むしろそういった女性としての魅力を磨こうとしない、仕事とか学校の成績、点数しか興味のない古典的なガリ勉系の女性については心底軽蔑していた。ついでに言えば二人の夫もキャリア、知性、ルックス共に申し分のないエリートだ。一言で言って怜と舞は礼子たちと考え方、育ち共に極めて近い、ポジティブではあるが強烈な上昇志向の権化のような美女であった。
共学化の提案、それには当然のことながら猛反発が相次いだ。大まかに言って反対の根源は三団体、OG会、理事会、そして教員だった。このうちOG会は怜と舞が有力者に直談判し、呆気なく説得してしまった。同性から見ても人間的魅力に溢れた二人に説得されて、反対を貫く人間などそうはいない。理事会はもっと簡単だった。もともと理事長の個人的諮問機関の性格が強く、二人の母、何より自分たち自身も理事なのだ、何でも出来る。反対派の理事についてはさっさと解任してしまった。残るは教員たちだけだ。教員全員を集めて共学化方針を説明したときのリアクションは中々見物だった。反対意見、怒号、金切り声に近いヒステリックな声での反対意見一色だった。
「共学化?せ、せ、聖華の・・・伝統ある聖華の伝統をいったいなんだと思っているんですか!」「そ、そんな重大な決定をなんで、なんで我々教員に、聖華の全てを担う我々教員の意見も聞かずに決めようとするんですか!そ、そんなの絶対に認められませんんんん!」「大体受験だとか成績とかを考えること自体、お嬢様学校のメッカであるこの聖華にふさわしくないいいい!!!」愚にもつかない反対意見をヒステリックに喚き散らすのは大部分、怜が不適格と判定した無能教師、怠慢教師だった。中にはまともな教員もいるのだが、ヒステリックな反対意見に圧倒避けて賛成意見など到底言える雰囲気ではなかった。
全く呆れたものね・・・よくもまあ、自分たちのバカさ加減を棚にあげてそれだけ好き勝手に喚き散らせるものね。呆れ果てた二人は適当なところで打ち切り、適当に放って置いてから全教員に対して自由に意見表明させる記名アンケートを実施した。アンケートが配られた時の反対派教員の反応は後々まで二人の嘲笑のネタとなった。「おおアンケートか。やっとあのお嬢様方も、我々現場の意見を聞かないと何もできないということが少しはわかったようじゃないか。」「全くね、聖華を動かしているのは私たち教員だ、ていうことが今度のことで思い知ったでしょうよ。」「そうそう、まあ、あの世間知らずの小娘どもも、少しは世の中というものが分かったんじゃないの?いい薬になったでしょうよ。」そのアンケートは予想通り、反対意見が過半数を占めた。バカなことだった。怜と舞が着々とOG会、PTA、理事会と説得工作を終了させ新教員についても既に面接は一通り終了し殆ど目途がつきつつあることに、反対派は全く気付いていなかった。いや学園内、教員内部でさえ、心ある教員、有能な教員はさっさと賛成意見に転じていたことに気づいていなかった。そしてアンケートを回収した怜と舞は反対派の中から数人、指導力に優れた教員のみを選び出すと個別に呼び出して説得に当たった。知的な、そして人間的魅力に溢れた二人のたっての要請だ、心動かされない訳がない。加えて二人は共学化の大方針は譲らないが、それ以外の面、移行に伴う様々な問題点への対応については十分に教員の意見に耳を傾け、取り入れることを約していた。更には改革後の待遇改善まで約束されていた。これで転向しないわけがない。外堀、内堀は全て埋め尽くされた。後は無能教員に引導を渡すだけだった。そしてその日ももう間もなくだった。
遂にその日がやってきた。二人は既に新たに採用する有能な教員軍団を確定し正式契約も結んでいた。そして解雇する無能教員のリスト、アンケートの反対派および賛成としたが指導力不足著しく、今後の聖華には不要と判断した教員のリストも作成済だった。その朝、怜が切り出した。「さてと・・・今日、解雇通知するんだったわよね?もうリストも出来てるし、あのまま最終発表でいいわよね?」「勿論よ。じゃあ事務長に連絡しておくわね。」舞は内線電話を取り事務長を呼び出した。「ああ舞です、この前お渡ししたリストの件ですけど、今日正式に通告しますので、3時に対象者を常任理事室に出頭させてください。」そして3時、授業終了後に呼び出された教員がゾロゾロと常任理事室に入ってきた。全教員の半分強が呼び出されていた。大部分は自分たちより遥かに年上の教員たちを立たせたまま、自分たちは座ったままで先ず怜が単刀直入に用件を切り出した。
「今日来てもらったのは他でもありません、先日のアンケートに基づく理事会決定を通知するためです。皆さんは聖華の共学化、という大方針に反対意見を表明しました。無論、どういう意見を持とうと皆さんの自由です。しかしながら学園をどう運営するかの方針は私たち理事会が決定する事であり、皆さんはその執行機関に過ぎません、従ってあなた方は運営方針についてあれこれ口出しできる立場ではありません。それを勘違いしている皆さんは今後の聖華に不要な人材です。反対意見の方の中でも一部、指導力豊かな先生には今後の聖華のため、私たちからお願いして残って頂きましたが、ここにいる皆さんについては敢えて聖華に残って頂く必要はございません。従って、雇用契約が切れる今年度末、つまり来年三月末をもって皆さんを全員、解雇します。」
「か、かかかかか、かいこおおおおおっ!?!?!?」「そ、それって・・・クビっていうことかあああああっ?」「う、うそだろおおおおおっっっ!」金切り声に近い悲鳴に全く動ずることなく怜が答える。「そうですね、平たく言えばクビ、ということです。」声色一つ変えない怜の無情な宣告に悲鳴と怒号が木霊する。「そ、そんなそんなそんなあああああっ!お、横暴だ滅茶苦茶だあああっ!」「そ、そうだそうだあああっ!だ、断じてみとめないぞおおおおっ!と、とりけせええええええっ!!!」「ひ、酷いわ酷いわあんまりよおおおっ!こんなの絶対にみとめないわよおおおおおっっっ!!!」
一しきり悲鳴が木霊するのを舞は苦笑しながら眺めていた。・・・全く、自分たちの無能と馬鹿さ加減を棚にあげて、今更滅茶苦茶も何もあったもんじゃないわよね。大体認めないって、聖華には組合すらないのにどうやって私たちに反撃するつもりなのかしら?貴方たち低脳集団にはそんなことも分からないのかしらね。いい加減バカどもにはうんざりした、と言うように舞はバーン、と机を大きな音を立てて叩き教員たちを黙らせた。「皆さん何か勘違いしていませんか?私たちは今日、あなた方に解雇通知をする為に呼び出したんですよ?皆さんと話し合いをする為に呼び出したのではありません。もう一度言います。これは通知、私たちから皆さんへの通告です。どう言おうと勝手ですけど、私たちは皆さんと話し合いをするつもり等毛頭ありません。」
冷たく突き放す舞の言葉に毒気を抜かれたように教員たちは静まり返ったが、やがて再び騒ぎ出した。「そ、そんな・・・一方的な!」「そ、そうだ!俺たちの、俺たちの権利はどうなるんだ、こ、これは・・・そ、そうだ、ふ、ふと、不当・・・不当解雇だあああっ!」「そ、そうよそうよおおおっ!聖華を、私たちの聖華をどうするのよおおおっ!」呆れたかのように舞は首を振りながら答えた。「一方的?不当解雇?もう少し勉強してから物を言いなさい。いいですか、皆さんの契約は一年毎の年度更新契約なんですよ?長期雇用契約、ましてや終身雇用だなんていうのは皆さんの勝手な思い込みです。一度きちんと契約書を読んでごらんなさい?そしたら今みたいなバカなことは言えない筈ですよ。いいですか、もう一度いいます。これは皆さんを今年度末で解雇する、という通知です。法律上の通知義務期限より相当に早く通知して上げている訳ですから、私たちには何ら法的な問題はありません。もし皆さんがこれ以上、不当解雇だ何だと言うのでしたら別に構いません、遠慮なく裁判を起こしてください。当学園の顧問弁護士はご存知ですね?必要なやりとりは弁護士を通じてお願いします。あとは法廷でお会いしましょう。」
法廷で会いましょう、と言いながら舞は絶対に裁判になどならない、という確信を持っていた。全くバカよね、今更、事ここに至ってからで打つ手なんかあるわけないでしょう?私たちはリーガルチェックやらなんやら十分に手を打っておいたのに、あなたたちは何にもしないで只寝てただけじゃない?そんなんで勝負になるとでも思っているのかしら?舞の毅然とした宣告に黙り込んでしまった教員たちに、怜が追い討ちをかけた。「用件は以上です。皆さん、期日までに身辺整理をきちんとしておいてくださいね。ではさっさと退室してください。」それ以上抗議することさえできずに解雇された教員たちは廊下に追い出されてしまった。う、うううう・・・誰からともなく啜り泣きが広がっていく。う、ううう・・・その声は常任理事室の中にも聞こえてきた。
「・・・ったく!今更泣いたってなんか意味があるとでも思っているのかしら・・・大体今の聖華は給料も安いじゃない?馬鹿野郎、首にするなら勝手にしやがれ、俺みたいな有能な人間を首にしたらそっちが損するだけだぞ!て啖呵の一つも切れないのかしら・・・それをまあ、首にされてグズグズ泣いてるだなんて・・・私ああいうクズって大嫌い!ああいう連中見てるとムカムカする、思わず唾を吐き掛けてやりたくなっちゃうわ!」イライラしたように吐き捨てる怜に舞も大きく頷いた。「本当よねえ・・・自己研鑽なんて言葉とは全く縁のないクズどものくせして・・・連中きっと今、私たちの事をグチグチと呪っているわよ、自分たちの無能さを棚にあげてね。怜がさっさと連中を追い出してくれて良かったわよ。あんなカス共が目の前でグチグチ泣いてるのを見たら、ほんと思いっきり唾吐き掛けずにはいられないわよね。」「全く、大体連中、無能な癖に言うことだけは一人前の癖して、いざとなったらいい歳して泣くだけでろくすぽ反論もできないだなんて、本当に情けないわよね。フフ、首にされたくない人は私の靴を舐めなさい、なんて言ったら、全員が舐めちゃったりしてね!」「アハハハハッ!言えてるそれ、絶対に全員が舐めにきたわよ。でもまあ良かったわよ、あんな穢らわしい連中に舐められたら、私たちの靴が腐っちゃうわ!」フウウッ!と二人は大きく深呼吸をして気分を入れ替えた。「まあどうでもいいか、あんなクズども。どうせここをクビになったら自力で就職先探す度量もない能無しどもばかりだものね。プーになるかホームレスになるか、いずれどこかの吹き溜まりに落ちぶれていく連中がどうなろうと私たちの知った事じゃないわよね。あんな連中、唾を吐き掛けてやる値打ちもないわ。」「全く怜の言うとおりよね。あんなクズどもに吐き掛けたら、私たちの唾が勿体無い、て言うものよ!それより・・・やらなくちゃいけない仕事はまだまだ山積みよ。さあ仕事仕事!」未だ啜り泣き続ける教員たちを完全に頭の片隅からも消し去り、二人は仕事に戻っていった。そして4月、予定通り新生聖華は共学校に生まれ変わりその第一期生を迎えた。礼子たち、そして慎治たちだった。
3?
無論、この事は慎治たちの入学前の出来事だから彼らにとっては知る由もない。二人が怜と舞を見て呻いたのは別の理由からだった。怜と舞もまた礼子たち同様、あまりの美少女振りに護身術を学ぶ必要がある、と考えた両親の意見により幼いころから怜は合気道、舞は空手を学び大学では女子部の主将を務めた二人はインカレでも大活躍した程の腕前だった。二人は聖華の教員ではないので顧問ではないが、多忙な中での体調維持を兼ねて時折、生徒たちに交じって乱取り中心に汗を流し、礼子たちとも何回も拳を交えていた。礼子たちは部内では群を抜く実力者であるため本気になれば殆ど誰も相手にならない、だが怜と舞は些かレベルが違った。若い分、スタミナを含めた肉体的パワーでは玲子たちが勝るが怜と舞は豊富な実戦経験が磨いた多彩な技、そして冷静な状況判断と適応力を持っていた。若さに任せた礼子たちの力攻めに対応しきれないこともあるが、僅かでも隙ができれば直ぐに反撃される。子供の頃から通っていた道場でも女子の部では強すぎ、男性を相手にすることの方が多い礼子たちにとって、女性同士で全力で戦い五分がやっと、という相手は滅多にいなかった。加えて本物の知性と抜群のルックス、そして女性らしさと超一流のキャリアを併せ持つ怜と舞だ、礼子たちは珍しく一致して二人のことを心から尊敬していた。自分たちも将来ああなるわ、と言った身近な目標、と言ってもよい。怜と舞もまた、礼子たちのことを非常に気に入り可愛がっていた。優秀な成績と抜群の身体能力、そして活発な性格で周囲を明るくする性格。負けず嫌いで競争大好きだけどゲームのようなものと割り切り、明るく楽しくオープンに競い合うのでついつい周囲も私も負けない!と競争に参加してしまうから礼子たちの周囲は自然と優秀な生徒が、男女を問わず多い。まさに怜と舞が求めていた新生聖華の理想を体現するような存在だった。だから言ったでしょう、お嬢様学校なんてカビの生えたような建前は早く捨てましょう、て。これからはこういう、明るく強気の生徒を集めていかなくちゃいけないのよ!
それなのに慎治たちは致命的なミスを犯してしまったのだ。毎日毎日礼子たちに苛められる生活、そして教員も慎治たちの両親でさえも優等生の礼子たちに取り込まれ、誰も助けてくれない。誰か・・・誰か助けて!誰でもいい、礼子さんたちを止められる人はいないの!・・・いた!礼子さんたちよりもっと強い人が。「し、慎治・・・もう・・・もう駄目だ・・・俺もう・・・耐えられない・・・」玲子たちに週末、いつものように体育館に連れて行かれ死ぬほど鞭打たれた帰り、信次が思いつめたように呟いた。「ぼ、僕もだよ・・・誰か、誰か助けてよ・・・誰か・・・」ふと信次が何かを思いついたように顔をあげた。「慎治、舞先生なら、舞先生ならもしかして・・・」慎治もあっと言う様な顔をした。「そ、そうだ・・・怜先生、怜先生なら確かに・・・礼子さんたちも、怜先生と舞先生のことは尊敬している、て言ってたよね。だったら・・・怜先生たちに言って貰えばもしかして、礼子さんたちも聞いてくれるかもしれないよ!」この二人なら玲子さんたちも尊敬している、この二人なら・・・怜先生と舞先生に注意して貰えば礼子さんたちも言うこと聞くかも知れない!馬鹿な考え、馬鹿と言うより妄想に近いほど愚かな考えだった。慎治たちは怜と舞の本質を完全に誤解していた。意を決した二人は週明け、理事室のドアをノックした。「ハイ?どうぞ、開いてますよ。」怜の澄んだ声が聞こえた。「し、失礼します・・・」学園の最高実力者の二人に直訴しようというのだ、緊張からおどおどとしながら二人は理事室に入った。「あら君たちは・・・確か川内・・・信次君、だったかしら?空手部にいたんじゃなかった?そちらは矢作慎治君ね、確か一年一組だったかしら?」と舞が如何にも何の用かしら、忙しいんだけどな、と言う様に少し苛ついた声をあげた。「ああ・・・そういえばどこかで見たことあるな、と思ったわ。矢作君は確か、合気道部にいたわね。で、どうしたのかしら今日は急に。呼び出した覚えはないと思うけど、何か急ぎの用件でもあるのかしら?」怜も訝しげにしていた。
無理もない、教員ではなく理事である二人に対し一生徒に過ぎない慎治たちが何か用件がある、とは思えなかった。い、いけない・・・早く、早く言わなくちゃ、お願いしなくちゃ!二人の苛立った声に急かされたように、慎治が口を開いた。「すすす・・・す、すみません・・・お、お忙しいところ・・・そ、その・・・礼子さん、天城、礼子さんのことで・・・・お、願いにきたんです!」信次も急いで付け加える。「そそそ、そう、そうなんです!霧島・・・玲子さんのことです!」天城さんと霧島さんのこと?一体どういうこと?「まあ兎に角、立ったままって言うのも何だから、そちらに座りなさい。」怜が部屋の片隅の応接コーナーを指し示し、慎治たちを座らせ、自分たちも席を移した。全く何の用なのかしら・・・苦笑しながら舞が尋ねた。「天城さんと霧島さんのことで私たちにお願いですって?一体何なのかしら?あ、もしかして二人に告りたいから応援してくれ、とかいうことかしら?」常識的にはこんな所としか思えない。フフフ、と怜も苦笑した。「・・・まあそういうところかしら?でもそういうことだったら、あなたたちクラスも部活も一緒なんだから私たちなんかを経由しないで直接口説けばいいじゃない?・・・まあ勝算はちょっと低いかな、とは思うけど、たまには玉砕してみるのもいいものよ。」怜も苦笑しながらフォローする。く、口説く!告る!ぼ、僕たちが礼子さんたちに!飛び上がらんばかりに驚いた二人は反射的に金切り声で絶叫してしまった。「そ、そそ、そんな!れ、玲子さんに告るだなんて!そ、そんな!」「そ、そうですうっ!逆、逆逆!ぼ、僕たち・・・礼子さんたちに苛められているんですうううっっっ!」苛められている?一体どういうこと?流石に二人とも当惑を隠せなかったが、怜が静かな声で尋ねた。「今・・・苛められてる、て言ったわね?どういうこと、落ち着いて話して頂戴。」
は、話を聞いて貰える!慎治たちは急いで争うように話し始めた。礼子たちに蹴りのめされ打ちのめされたことを。唾を吐き掛けられブーツで踏み躙られたことを。鞭で打ちのめされたことを。そして・・・おしっこを飲まされたことも。慎治たちの告白が一段落した時、信じられない、といった表情で首を振りながら舞が呟いた。「フウウッ・・・些か信じられない話ね・・・」し、信じられない!「そ、そんなお願い信じてくださいいっ!ほ、本当なんです、そ、そうだ証拠、証拠もあります!こ、この背中、この背中を見てください!き、昨日、昨日玲子さんたちに・・・玲子さんたちに鞭打たれたんです・・・こ、この傷、この傷を見てくださいいいっ!」信次はボタンを引き千切らんばかりの勢いでシャツを脱ぎ、背中を二人に向けた。「そそそ。そうですううっ!ぼ、僕も・・・僕も死ぬほど鞭で叩かれたんですうううっ!こ、この背中を・・・見てくださいいいいっ!」慎治も急いでシャツを脱ぎ鞭跡だらけ、蚯蚓腫れと青痣に彩られた背中を二人に向けた。「う、ううう・・・全部、全部玲子さんたちに・・・やられたんです・・・」「ヒッヒック・・・僕たち・・・何もしてないのに・・・死ぬほど鞭打たれたんです・・・」自分たちの言葉に、行為に酔ったかのように慎治たちは泣きながら涙ながらに訴えた。きっとわかって貰えると、この凄惨な鞭跡を見ればきっと僕たちのことを何て可哀想に、と同情してくれるに違いない、助けてくれるに違いない、と慎治たちは信じて疑っていなかった。そして愚かな二人は未だ気付いていなかった。怜と舞が同情ではなく、軽蔑と嫌悪の表情を浮かべていることに。「・・・もういいわ、二人とも早くシャツを着なさい。」怜が嫌悪感を露にしつつ冷たい声で言った。シャツを着終えた二人を座らせ、舞が静かに尋ねた。「言ってることは良く分かったわ。どうやら苛められてる、ていうことは本当みたいね。多分・・・おしっこまで飲まされている、ていうのも本当なんでしょうね。で、それで?私たちにどうして欲しいの?何を言いにここに来たのかしら?」舞の声も静かだが剣呑なトーンになりつつあることに、信次は全く気付いていなかった。「そ、それはもちろん・・・お願いです、玲子さんに、玲子さんに言ってください!こんなことはもうやめろって!こんな苛めはもうするなって言ってください!お願い・・・します・・・」「矢作君、あなたのお願いも同じなの?」怜も静かに尋ねた。「そそそ、そうです!そうですそうですうううっ!せ、先生の・・・先生の言うことなら礼子さんたちもきっと聞いてくれます、お、お願い、お願いです助けて・・・くださいいっ!」必死で涙を流しながら縋るように哀願する慎治たち、そんな二人を静かに見据えていた怜がゆっくりと口を開いた。「そう、あなたたちのお願い事は分かったわ。じゃあ答えてあげる。これが私の返事よ・・・ペッ!」鮮紅のルージュを引いた怜の唇が急速に盛り上がったかと思うと、慎治にとっては見慣れたもの、唾が吐き出され慎治に襲い掛かった。ペチャッ!あ、あああ・・・予想外の展開に驚いた信次が顔を上げると舞が冷たい眼差しで自分を睨み付けていた。こ、この目・・・玲子さんたちと同じだ、そ、そんな何故!?「私の返事も同じ。川内君、これが答えよ・・・ペッ!」信次が言葉を発するよりも早く、舞もピンクのルージュを塗った唇を二、三回クチュクチュと動かしたっぷりと唾を溜めると思いっきり信次の顔に吐き掛けた。ペチャッ!既に数え切れないほど味合わされた汚辱の感触、女性に唾を吐き掛けられた感触が信次の顔面を走る。「あ、あああ・・・そんな・・・」「な、なんで・・・」余りのことに吐き掛けられた唾を拭うことも忘れ、顔に今吐き掛けられたばかりの怜と舞の唾を滴らせながら慎治たちは呆けたような声で呟いた。
「なぜ?なぜ唾を吐き掛けられたか分からないの?」怜が軽蔑に満ちた声で問い詰める。「全く・・・よくもまあ恥ずかしげもなく、こんなことをお願いできたものね!そんな男、いえ男なんて言えないわね、そんなクズはこうやって唾を吐き掛けられるのがお似合いでしょう?」舞も心底呆れたというように、信次のことを見据える。「川内君、あなた一応男の子でしょう?それが女の子に苛められてるんです、先生助けてくださいいい?言ってて恥ずかしいと思わないの?この・・・意気地なし!ペッ!」唾を吐き掛けた唇を軽蔑に歪めながら舞が続ける。「何のつもりでそのみっともない鞭跡だらけの、汚らしい背中を私たちに見せたのか知らないけど、そんなに嫌だったら何で嫌と言わないの!?何で毅然と断らないの!?霧島さんたちの方が強いから、なんて言い訳にもならないわ。負けても何でも本当に嫌なら100回でも200回でも戦えばいいじゃない!それをあなたたちは毎週のこのこと体育館やグラウンドについて行って・・・挙句の果てにおしっこを、霧島さんたちのだけではなく萩さんや神崎さんのおしっこまで飲んでます?ふざけるのもいい加減にしなさい!ペッ!」舞の一喝に怜も大きく頷いた。「舞の言うとおりよ。いい、二人ともよく聞きなさい、戦いもしないで苛められてる、て言うのはね、あなたたち自身がお願い苛めてください、て天城さんたちにお願いしているのと同じことよ!そうやって苛めてくださいおねがいしますうう、てやっておいて、何が僕たち鞭で打たれて泣かされてるんです、助けてくださいよ!甘ったれるのもいい加減にしなさい!ペッ!」情け容赦なく断罪しながら、怜と舞は慎治たちに何回も何回も唾を吐き掛けた。「このクズ!落ちこぼれ!君たちみたいな情けない連中はね、一生こうやって唾を吐き掛けられているのがお似合いよ!ペッ!」憎々しげに言い放ちながら思いっきり唾を吐き掛けた怜の後を引き取るように、舞も信次をこの上ない軽蔑と共に睨み付ける。「全く、よくもまあこんな情けないお願いに来れたものね!そんな情けない人間、生きている資格なんかないわ!さっさと死になさい!ペッ!」あ、あああ・・・慎治は余りに峻厳とした怜と舞の拒絶に愕然としながら、同時に無限の絶望を感じていた。だが、どうしても怜と舞の言葉を受け入れることはできなかった。鞭打たれおしっこを飲まされて毎日苛められている自分たち、それは全て自分自身の情けなさのせい、それは恐らく真実だろう。だがその真実を受け入れる事はどうしても出来なかった。そして面罵され心底蔑まれて挙句の果てに唾まで吐き掛けられてもそれでも尚、慎治たちは怜と舞にすがらずにはいられなかった。「そ・・・そんな・・・せんせい・・・」「ひ・・・どい・・・お願い、見捨てないで・・・ください・・・」そんな慎治たちの哀願は怜と舞の怒りの炎に油を注ぐだけだった。「・・・まだ言うの・・・この・・・クズ!ペッ!」「どうしようもないカスね、あなたたちは・・・何で自殺しないのよ!ペッ!」最早軽蔑を通り越し憎悪も露に怜と舞は再度、思いっきり唾を吐き掛けた。ああ、あああ・・・慎治たちは涙を流し、だらしなく口を開けて嗚咽を漏らしながら怜と舞の唾を浴び続けた。鮮紅のルージュを塗った怜の唇、ピンクのルージュに彩られた舞の唇は際限なく、慎治たちの全人格を否定する罵倒と侮蔑の言葉を吐き出した。凛とした鞭のように厳しい二人の声で浴びせられるそれらの言葉は、まともな男ならば一言浴びせられただけでも恥辱に打ち震えてしまう程のものばかりだった。そして罵倒の言葉の合間、一瞬沈黙を入れると二人は唇をクチュクチュと動かし唾を溜め、次の瞬間思いっきり吐き掛ける。急速に盛り上がる唇、吐き出され宙を切り裂く白い矢、そしてビチャッと汚辱の液体が顔を汚す感触。既に数え切れないほど味合わされた屈辱の儀式が再現され、慎治たちの惰弱な精神をズタズタに引き裂いていく。
何なのよこの子たちは。唾を吐き掛けながら、面罵しながら怜と舞は強烈な違和感、嫌悪を通り越した一種異様な不気味さを感じていた。いくら罵っても唾を吐き掛けても、慎治たちは涙を流し必死で哀願して許しを請いながらも、顔を伏せたり背けたりもせずに怜と舞の顔から視線を逸らそうとしないのだ。何度唾を吐き掛けても吐き掛けても、飛んでくる唾を手で避けようともしないのだ。あたかも唾をおねだりするかのように、慎治たちは泣きながら汚い顔を怜と舞に向け続けていた。その不気味なほどに惨めな様は怜と舞を余計に苛立たせた。何なのよ君たちは・・・これでもまだ足りないって言うの!ペッ!怜は自分の唾が慎治の眉間に炸裂し、ゆっくりと頬を伝っていくのを、慎治の顔面が自分の唾で醜く彩られて行くのを嫌悪感も露に睨み付けていた。軽蔑侮蔑嫌悪焦燥憎悪・・・吐き気を催しそうな程、慎治たちは気味が悪かった。あらゆる黒い衝動が怜と舞の全身を貫く。吐き掛けても吐き掛けても、止め処もなく唾が口の中に湧き出してくる。唾を吐き掛け罵り続けていないと、怜と舞の方が正気を失いそうだった。一体どういうつもりなのよ・・・何ぼうっとしているのよ!ペッ!痴呆のようにだらしなく口を開けたまま泣いている信次の顔に舞は思いっきり唾を吐き掛けた。もう何回唾を吐き掛けられたと思っているの?何で唾を吐き掛けられているのに私のことを見続けていられるのよ、このキチガイ!いい加減にしなさいよ!聞いているの!
不意に怜が黙り、慎治の顔を覗き込んだ。「アウッ、ヒッヒック・・・許して・・・」泣きながら哀願する慎治、自分の吐いた唾に塗れた顔で哀願する慎治を怜は氷のように冷たい表情で睨み付ける。「何なのよ君は、一体どういうつもりなの?さっきから何回唾を吐き掛けられても避けもせず顔を背けもしないでバカみたいに私のことを見詰めちゃって。まさか喜んでいるの?罵られて唾を吐き掛けられるのが嬉しいとでも言うの?この・・・変態!」そ、そんな違ううううっ!だ、だってだって・・・「何よ何か言いたいの?言いたいことあるならはっきり言いなさい!」言いたい、僕だって言いたい・・・だけど、だけど・・・口ごもる慎治に苛ついたかのように、舞が信次の胸倉をグイッと掴み引きずり寄せる。「アウッ、ウウウ・・・」引っ叩かれる!思わず下を向いてしまった信次の顔を邪険に跳ね上げながら舞は更に引きずり寄せる。あああ・・・目の前30センチに舞の美貌があった。知的な美貌を怒りに燃え上がらせた舞、夜叉のような怒りの形相はなまじ美人な分、余計に恐ろしい。だが同時に色白な頬を上気させた舞はゾクッとするほど美しかった。その凄絶な美貌と大きな瞳に射抜かれたように、信次は身動きひとつできない。「矢作君はどうやら口が訊けなくなったみたいだから、君に聞くわ。一体なんで?どうして君たちは避けもしないで唾を吐き掛けられ続けているの?はっきり答えなさい!」あう、あうう・・・恐怖に怯え、痴呆のように呻きながら信次は反射的に答えた。「れ、れいこ、玲子さんが・・・」「玲子さん?霧島さんのこと?霧島さんがどうしたって言うのよ、私に分かるように、はっきり言いなさい!」鞭のように厳しい舞の声に信次の全身がビクッと痙攣する。ヒイイイッお、怒ってる、舞先生怒ってる、言わなくちゃ、言わなくちゃ・・・「玲子さんに・・・命令された、んです・・・唾を吐き掛けられる時は絶対避けるな、顔を背けるなって・・・」「ハアッ?唾を避けるな、て命令されている?矢作君、君もそうなの?天城さんに命令されているから、それで大人しく唾を吐き掛けられている、ていうわけ?」呆れたように尋ねる怜に、消え入りそうな声で慎治が答える。「・・・はい・・・絶対に避けるな、て。避けたら鞭で叩くよ、て・・・自分たちだけじゃない、クラスの誰が唾を吐き掛けた時でも絶対に避けるな、て、避けたって聞いたら泣くまで鞭で引っ叩くわよ、て言われたんです・・・」ハアッ?一体何を言っているの?信じられない、という面持ちで首を振りながら怜が尋ねた。「ねえ矢作君、君自分が何言っているか分かっているの?唾吐き掛けられても何の抵抗もしないだなんて・・・唾を吐き掛けられるなんて人生最大の侮辱よ、大抵の人間は唾を他人に吐き掛けられるなんて、一生縁がない話よ。それを怒るは愚か避けもしないで視線も逸らさずにいるなんて・・・君それで本当にいいの?君はそれでも本当に人間なの?」フウウッ・・・舞の深い溜息が漏れた。「君たち・・・信じられない位腐り果てているのね。私だったら、唾を吐き掛けられたりしたら絶対許さない、一生許さないわよ。それが普通の人間でしょう?それを君たちは・・・呆れて物も言えないわ。」「だって、だつて・・・」「そ、そんな・・・唾なんて僕たちも嫌・・・だけど、だけど・・・」泣きながら慎治たちは必死で言いすがった。怜先生たち、少し声が静かだ、もしかしたら、もしかしたら僕たちを少しでも哀れんでくれるかも・・・淡い幻想に縋りながら慎治たちは消え入りそうな声で縋りついた。「でも・・・礼子さんたちに逆らったら・・・死ぬほど苛められるから・・・」「だって鞭で・・・鞭で叩かれたら誰だって・・・」
胸がむかつく程の嫌悪感を必死で抑えながら、声だけは努めて冷静に保ちながら舞は信次の顔を上げさせた。「川内君、しっかり目を開けて私のことをご覧なさい。」ヒック、ウエック・・・咽び泣きながら信次が顔を上げるのを舞はじっと待っていた。のろのろと顔を上げた信次の、生気がない怯え切った惨めなネズミのような目を舞の鋭い視線が射抜く。「川内君・・・もう君たちの顔なんか見たくもないんだけど、一回だけ教育を施してあげるわよ。」「きょ、教育?な、何です・・・か?」また、苛められるの、と怯えながら信次がオドオドと尋ねる。「別に大したことじゃないわよ。少しは君に自分の意志というものを教えてあげようというだけよ。いい、今から私は君にもう一度唾を吐き掛けるわ。だけど避けていいわよ。手で顔を覆うなり顔を背けるなり、この場から逃げ出すなり、どうとでも好きにしていいわ。私が許可してあげる。いい?避けていいからね、私の唾をちゃんと避けるのよ!」「えっええっ、そ、そんな・・・」「そんな?何がそんなよ。吐き掛ける私が許可してあげているのよ、それでも唾を避けられない理由があるとでも言うの?自分は人間です、と言いたいなら、せめて唾くらい避けてご覧なさい!行くわよ!」あ、あああ・・・信次は目の前で舞が美しい唇をクチュクチュと動かし唾を溜めるのを震えながら見ていた。よよよ、避けなくちゃ避けなくちゃ・・・いいって言った、舞先生、避けていいって言った・・・嫌だ、唾掛けられるのなんて嫌、大嫌い!よ、避ける避ける、手を上げて顔を下ろして・・・だけど、だけど・・・だが思い出したくない、今この時は絶対に思い出したくないイメージが信次の脳裏に鮮明に浮かび上がる。玲子の美しい顔が信次を見下ろしている。凛とした声が、まるで玲子がここのいるかのように響く。「信次、唾を避けたら・・・分っているわね?鞭で死ぬほど引っ叩くわよ。」ああ、あああ!い、嫌、いやあああああ!や、やだ、唾、舞先生の唾を避けるんだああああっ!信次は必死で玲子のイメージを掻き消そうとした。だが玲子の呪縛は信次が抗えば抗うほど強くなっていく。
目の前では舞が既に、口の中に十分唾を溜め終わっていた。大きく息を吸いながら、舞が反動を付けるかのように首を僅かに後ろに引く。ああ、あああ・・・先生、唾を吐き掛ける準備完了したんだ・・・く、来る!よ、避けるううう!手を上げるううう!だが信次の両手は鉛の手錠を嵌められたかのように重く、ピクリとも持ち上がらない。か、顔を・・・曲げるううう・・・首はギブスで固定されたかのように硬直し、僅かに震えるだけだ。そして目は舞の冷たい魔眼に魅入られたように吸い寄せられ、視線を逸らすことさえできない。クッ、舞の顔が前に動く、と同時にピンクの唇が急速に盛り上がり、たっぷりと溜められた唾を猛スピードで吐き掛けた。ペッ!ビチャッ!先ほどまでに何度となく響いた音、舞が唾を吐き掛ける音と唾が信次の顔面を直撃する音がまた響いた。「避けていい、て言ったでしょう?何故避けないの?もう一度行くわよ・・・ペッ!」二度、三度と舞は唾を吐き掛け続けた。目の前で繰り広げられる光景を舞は到底信じられなかった。「何でなのよ・・・避けていい、て言ったでしょう?それを何でそうやって平然と唾を吐き掛けられ続けているのよ・・・このクズ!ペッ!」舞はああもう!と言わんばかりに激しく首を振りながら怜の方を振り向いた。「怜、私もう頭が変になりそうよ!何なのよこの子たちは!」苛立ちを露に舞は険しい声を上げた。これ以上信次の顔を見ていたら、自分の抑えが効かなくなりそうだった。目の前で薄汚い泣き声を上げている惨めな化物を無性に張り倒し蹴り倒し、踏み潰してやりたかった。駄目、もう殺したくなっちゃうわ・・・「私もよ。本当にもう、絞め殺してやりたいわ・・・」怜の顔色も怒りの余り蒼白になっていた。「信じられないわ、こんな連中が本当にこの世に存在していたなんて。ああもう!」大きく息を吸いながら怜は慎治を睨み付けた。「ヒッ!」殴られる!反射的に慎治は両手を跳ね上げ、頭を庇った。だが打撃はこない。ぶ、ぶたないの?両手の合間から覗き見ると怜が少しほっとしたような目で見ていた。「ああ良かった、どうやら矢作君の手は動くみたいじゃない。いいわよ、ぶったりはしないから、安心しなさい。」フウッと溜め息を吐きながら怜が言った。「そうよ、怖かったら、嫌だったらせめてそうやって固まっていればいいのよ。そうやって自分を庇えばいいのよ。」吐き捨てるように言う怜の言葉に慎治は少しだけほっとした。だが怜の次の言葉に慎治は呻いてしまった。「いい矢作君、そのまま聞きなさい。こんな言い方、バカらしくて有り得ないんだけど、君たちにはどうやらこのレベルからじゃないと駄目みたいだからね。いい?今から私も唾を吐き掛けるわ、だから君はそのまま固まっていなさい。そうすれば私の唾は避けられるんだから。それとこれも約束してあげる。天城さんたちには絶対に言わないわ。君が私の唾を避けたことは絶対に言わないであげる。私が黙っていれば、天城さんたちにバレル心配はないわね?バレなければ鞭でお仕置きされる心配もないわよね。どう、これなら安心でしょう?安心して唾を避けられるでしょう?」「えっええっ、そ、そんな・・・お、お願いです、もう唾掛けないで・・・」「ああもう掛けないであげるわよ!私だって君たちにはもううんざり!だから君が一回でいいから私の唾を避けられたらそれでお終いよ!一回でいいから避けなさい、そしてさっさと私たちの目の前から消えうせて頂戴!」吐き捨てるように言いながら怜は口に唾を溜めていく。この蛆虫は・・・でもいくらなんでもこれなら避けられるでしょう?そのまま凍りついていればいいんだから。慎治も同じだった。ヒッ、動いちゃ、動いちゃ駄目、怜先生をもっと怒らせちゃう・・・礼子の美しくも恐ろしい幻影は勿論慎治の脳裏にも浮かんでいた。れ、礼子さん、礼子さんの命令を破っちゃう・・・だけど、だけど怜先生も怖い・・・それに約束してくれた、礼子さんには言わない、て約束してくれた、だから、だから大丈夫、礼子さんにはぶたれないはず・・・だが礼子の呪縛は慎治の精神の深層、殆どリビドーに至るまでに及んでいた。十分に唾を溜めた怜が鮮紅の唇、散々慎治に唾を吐き掛けたためしっとりと湿った唇を突き出した時、慎治の精神を瞬時に三つの映像が同時に埋め尽くした。
一つ目は鞭を携えた礼子だった。「慎治、いい、よく聞きなさい。今から先、私にも他の誰にも、唾を吐き掛けられる時には絶対に避けちゃ駄目よ。顔を背けるのも手で避けるのも絶対禁止。唾を吐き掛けられる時は必ず、相手の顔をしっかりと見なさい。自分が唾を吐き掛けられるところをしっかり見ておくのよ。もし避けたらどうなるか・・・この鞭で教えてあげるわ!」言い終えると同時に礼子の鞭が宙を舞った。ヒュオッ、バシーンッ、ヒイイイイッ!鞭の音と慎治の悲鳴がクロスする。「い、痛いいいいっ!よ、避けてない、避けてないじゃないいいいっ!」「何言っているのよ、当たり前じゃない!今私、唾引っ掛けたりしていないでしょう?今はね、唾を避けたらどうなるかを教えてあげているのよ、この鞭でね!唾を避けたらどうなるかたっぷりと学習しなさい!それっ!」そのまま何十発打たれたか、ピクリとも動けなくなるまで鞭打たれた映像だった。二つ目は唇を突き出して今まさに唾を吐き掛けようとする和枝の顔だった。「慎治、お早う!」明るい和枝の声に何気なく「あ、お早う」と言いながら振り向いた慎治に、和枝はペッと朝の挨拶代わりに唾を吐き掛けた。「アッ、な、何を!」予期せぬ唾に慎治は思わず手を上げて和枝の唾を避けてしまった。その瞬間、ガタッと礼子が立ち上がる音がした。あ、あああっっっ振り向いた慎治が目にしたものはベルトをウエストから引き抜いている礼子の姿だった。「慎治、今和枝の唾を避けたわね、お仕置きよ、お尻を出しなさい!」たったそれだけの理由でクラスメートたちに取り囲まれながらたっぷりと鞭打たれた映像だった。そして三つ目は眼前に迫り来る礼子の漆黒のブーツだった。いつものように週末、体育館に呼び出されて死ぬほど鞭打たれた後、帰り間際になって慎治は礼子の前に正座させられた。「慎治、これで今日の私の鞭はおしまいよ。」フウウッ・・・鞭の激痛の余韻に啜り泣きながら慎治は緊張の意図が途切れたかのようにがっくりとうな垂れた。その顎を礼子のブーツがこじ上げる。「ところで和枝から聞いたんだけど、あんた水曜に陽子が唾掛けた時、顔を伏せて避けたそうじゃない?」「そ、そんな、そんなあああ!あれはち、違う、避けただなんて!アガッ!」顎をこじ上げていた礼子のブーツが一閃し、慎治の顔面を蹴り倒す。アウッ、アウウウウ・・・痛さに呻く慎治に礼子がゆっくりと近づいてくる。「ヒイイッ!ガハアッ!」逃げようと必死で上半身を起こした慎治を強烈な回し蹴りで叩き伏せた礼子は仁王立ちのまま顔面をブーツで踏み躙る。「ヒイイッヒイイイイッ!だ、だじげでえええええっ!」「慎治、未だ私の命令が守れていない様じゃない?いいわよ、命令に背いたらどうなるか、骨の髄まで叩き込んであげる!」慎治の顔面を踏み付けた礼子は、足首をクイッと返すとブーツの爪先に全体重を掛けながら無理矢理慎治の口中奥深くへと捻じ込む。「アゴオオオオッガガアアアアアッ・・・」口一杯にブーツを咥えさせられ、余りの苦しさと顎が外れそうな激痛に耐えかねた慎治は必死で礼子のブーツを押し頂くように支える。喉の奥に爪先が当たり気道を殆ど塞いでしまっている。ソールの幅広な部分と優美な甲の曲線が慎治の口を張り裂けんばかりに、限界ギリギリまで押し広げている。これだけで、ブーツだけで十二分な苦痛だ。だが見下ろす礼子の瞳は更に残酷な炎に燃え上がっていた。フフフ慎治、無様な姿ね、お似合いよ。涙目で縋り付いちゃって、みっともないったらありゃしない。だけどダーメ、泣いたって何したって許してあげないわよ!そうやって慎治が泣けば泣くほど、ウフフフフ、もっと泣き叫ばせてやりたくなるわ!ブーツを咥えた惨めな慎治を冷たく見下ろしながら、礼子はシュルッと肩から鞭を外すと柄と先端を握り、二つ折りにする。「さあ逝くよ、私の命令に背くとどうなるか、たっぷりと思い知らせてやるからね!」ビュオッバシイッヒュンッビシイイイッ!礼子は全体重を慎治の口に掛けながら後ろ手で慎治の柔らかい脇腹、全く腹筋のない弛んだ腹から太腿に掛けて強烈な鞭を浴びせた。「びいいいいっ!びだいいいいいっ!ゆるじでえええええっ!!!」「アンッ?何言ってるの、全然分かんないわよ、許して欲しいなら許して欲しいで、ちゃんとお願いしなさい!」
だが口一杯にブーツを押し込まれてまともに言葉など発せられる訳がない。フフフ、クックックッ、アハハハハハッ!礼子はこみ上げてくる楽しさを押えきれないかのように高らかに笑っていた。ああ最高!こうやってブーツ咥えさせるのってほんと、楽しいわよね。爪先を無理矢理捻じ込んでやっている時の慎治の惨めな顔!もう最高!惨めな虫ケラ、私のブーツで地べたに縫い付けられているみたいじゃない!どう慎治、痛い?苦しい?顎を外してあげようか?簡単よ、私が足首一つ返せば、慎治の顎なんか簡単に外せるのよ?アハハハハッ!必死で私のブーツを押し頂いちゃって!そうしないと苦しいものね、窒息しちゃうものね、だけどそうやって両手塞がってたら、鞭はど・う・す・る・の・か・な・あ?あっやっぱり痛くて手をブーツから放したわね、じゃあいいわ、そーれっと!ほーら、もっと喉の奥までいれてあげる、私のブーツ、たーっぷりと苦しめてあげる!どう?突っ込まれるだけじゃ変化が足りない?じゃあこうやって足首を捻ってあげようか?苦悶と激痛の二重奏、鞭を振るう腕とブーツで踏み躙る脚、自分の体がフルに慎治を苦しめ地獄を味あわせるのを礼子は心ゆくまで堪能していた。ウンッ?何かしら?不意に礼子は、慎治の口に押し込んだブーツ越しに何か締め付けられるように感じた。ガギイイイイイッ・・・余りの苦痛に慎治は馬のハミよろしく礼子のブーツに必死で噛り付いていた。クックックッ、礼子の顔に楽しそうな笑顔が浮かぶ。「慎治、どうしたの私のブーツ齧っちゃって。そんなにおいしい?いいわよ遠慮しなくて、もっともっとたーっぷりと味あわせてあげる。そら!そら!そら!ほらそんなんじゃ噛んでるのかどうか、私に全然伝わらないよ!ブーツに噛み付きたいんでしょう?私に痛い思いをさせたいんでしょう?だったらもっとしっかり齧んなくちゃ全然効かないわよ。ほらほらほらどうしたのかなあ?マッサージでもしてくれてるつもりなの?駄目じゃん慎治、もっとしっかり抵抗しなくちゃ!気合の鞭を入れてあげようか?そら!そら!そら!」ビシッバシッパーーンッ!礼子は慎治の反撃ともつかぬあがきさえ、新たな愉しみに変えてしまった。バカね慎治、顎の力程度で私のウェイトに勝てるわけないじゃない。むしろそうやって力を込めてくれた方がしっかり体重かけられて都合がいいっていうものよ。第一ブーツの厚い革越しよ、ソールもあるのよ、どうやったって歯が立つ硬さじゃないわよ。まあ精々頑張りなさい、その分、ゆっくりと苛めさせてもらうから。やがて精根尽き果てたように慎治の歯から力が抜けていく。腹を庇っていた手も殆ど力が抜けガードしている、というより単に腹に置かれただけになっていた。痛い苦しい・・・そして何より疲れ果てていた。痛くても苦しくてももう、何をすることもできなかった。唯々礼子の鞭に打たれ続ける人形に成り果てていた。漸く礼子が許した時、慎治の弛んだ腹は真っ赤に彩られ、ボロ雑巾のようにあちこちで皮膚が打ち破られて血が幾筋も流れていた。
「うう、ううう・・・ウエッ、ヒック・・・痛いよううう・・・」礼子の鞭の余りの痛さに泣き続ける慎治の目の前に、玲子がしゃがみ込んだ。クスクス笑いながら意味ありげな視線を礼子と交わしつつ、「あーあ慎治、可哀想に。こんなボロボロになっちゃって、痛かったでしょう?」クックッと小さく笑いながら玲子は慎治の全身の傷をチョンチョンと爪の先で突っつく。「アウッ!い、痛い!お願いやめて・・・」玲子が傷口を突っつく度に慎治の悲鳴が上がる。「そんなに痛いの慎治?可哀想に、全く礼子ったら酷いわよね、こんなにボロボロになるまで鞭打っちゃってさ。安心して、私は何もしやしないわよ。それどころか、優しい私は傷口を消毒してあげるからね。」ニッコリと微笑んだ玲子がやや厚みのある、美しく肉感的な唇をクチュクチュと動かす。と次の瞬間、玲子はペッと慎治の目に目掛け、思いっ切り唾を吐き掛けた。「アヒッ!」目に向かって一直線に飛んでくる唾に慎治は反射的に目をつぶってしまった。「あっ慎治、今目つぶったでしょ!」クルッと礼子に向き直った玲子はわざとらしく、如何にも怒ったような口調で言う。「礼子、今慎治ったら私の唾、目をつぶって避けたじゃない!全くもう、ちょっと教育が足りないんじゃない!?」ニヤリと礼子は満面に残酷な笑みを浮かべると、パンッと鞭を打ち鳴らした。「ご免ね玲子、確かに私の躾が甘かったようね。慎治、いい度胸しているじゃない、言われた傍から私の命令無視するなんてさ。いいわよ、お望み通りたっぷりと私の鞭、味合わせてやろうじゃないの。」「そ、そんなあああっ!ち、違う、違うよおおおっ!お、思わず閉じちゃっただけだよおおおっ!ヒイイイイッ!」必死で絶叫する慎治を礼子の鞭が情け容赦なく打ち据える。慎治は泣き喚きながら床をのた打ち回るが、礼子はいつまでもいつまでも鞭打ち続けた。ウフフフフ慎治、いい声よ、折角だから、今日はとことん逝ってみようかしら?ボロクズにしてあげる!のた打ち回ることさえ出来なくしてあげるわ!漸く出血が止まった傷口の上を狙うかのように打ち据える礼子の鞭に、慎治は全身から血を霧のように噴出していた。大した出血ではない、鞭で血が弾き飛ばされるから派手に見えるが出血自体は多くない。だが丸一日苛められたあとのこの鞭、傷口を抉る礼子の鞭だ、痛いなどという言葉は生温い。強烈な嘔吐感すら催すほどの、全身に不快な寒気が走るほどの激痛だ。慎治は文字通りオールアウトになるまで打ちのめされていた。ビシイッ!アウウッ・・・パシイイイッ!アグウウッ・・・最早慎治はのた打ち回ることさえできずに、うつぶせに倒れ付したまま礼子の鞭を浴び続けていた。礼子の鞭が背中に炸裂する度に、断末魔のように全身を痙攣させ虚空を掴むかのように片手を宙に上げていたが、遂に全身を鞭跡と血で真っ赤に彩りながら慎治はスイッチを切られたかのように動けなくなった。半死半生、鞭で、礼子の鞭で文字通り半殺しにされていた。慎治の一生の中でも最悪の映像の一つだった。
怜が今まさに唾を吐き掛けようと首をそらし反動をつけた瞬間、慎治の全身は礼子に刻み込まれた最悪の記憶に、全行動を規定する強烈なトラウマに支配されてしまった。ああ、あああああ・・・両手が鉛のように重くなっていく。持ち上げて・・・いられない・・・駄目・・・意思とは全く関係なく慎治の両手はダラリと下がっていく。その両手で抱え込むようにして下を向いていた首が、硬直するように震えながら上がっていく。虚ろな視線を彷徨わせ、慎治の目は怜の顔を、今まさに自分に唾を吐き掛けんとする美貌に釘付けになる。ペッ!ベチャッ・・・怜の唾が慎治の鼻先に着弾した。「どういうつもりなのよ!避けていいって言ったでしょう?そのまま凍り付いていればいいって言ったでしょう?何なのよ一体!さっさと避けなさいよ!ペッ!ペッ!」信じられない、どういうことなのよ一体!怒りに全身を震わせながら怜は何度も何度も激しく唾を吐き掛けた。だが何度吐き掛けられても慎治は情けない声ですすり泣くだけだ。ザッ・・終いに疲れ果てたかのように怜は大きく仰け反ってソファにもたれ掛かった。天を仰ぎながら呟く。「もういいわこんな連中・・・こんなのと付き合ってたら私の方が気が変になっちゃう・・・矢作君、川内君、あなたたち・・・今すぐ死になさい。自分の意思を持たないのなら、生きていても仕方ないでしょう?ここを出たら今すぐどこかのビルの屋上に行って飛び降りなさい。唾を吐き掛けられても黙って掛けられるがままの人生なんて、生きてる意味ないでしょう?」暫くの間、疲れ切ったかのように怜も舞も押し黙っていた。聞こえる物音は唾まみれになった慎治たちの嗚咽だけだった。やがて怜がゆっくりと立ち上がり、慎治の腕を掴んだ。「本当に見果てたクズねあなたたちは・・・いい、この先あなたたちが天城さんたちに苛められようが殺されようが、私たちの知ったことじゃないわ!勝手にどうにでもされなさい!もうその顔、見ているだけでも穢らわしいわ、さっさと私たちの前から消え失せなさい!」舞も信次の腕を掴み引き摺り上げながら言い放った。「本当よ・・・あなたたちみたいなクズは、勝手に好きなだけ苛められて苛め殺されるのがお似合いよ!ああもう!君たちと同じ空気を吸っているだけでも最悪の気分よ!」酷い・・・怜先生も舞先生も・・・礼子さんたちと同じだ・・・慎治たちは漸く気付いた。怜と舞の本質に。二人とも完全に持って生まれた強者、礼子たちと同じく強者である事を。慎治たち弱者のことなど虫けら以下にしか思っていないことを。そして自分の手を煩わせた虫けらなど、純粋に怒りの対象でしかないことを。だがどうしても認めたくはなかった。いや認めるわけにはいかなかった。「おね・・・がいです・・・」「見捨て・・・ないで・・・」二人の最後の願いは怜と舞のより激しい怒りを買っただけだった。「・・・未だ言うの・・・このクズは!」「いい加減に・・・しなさいよ!」怜と舞の美貌は今や激しい怒りに燃え上がっていた。「これ以上・・・私の貴重な時間を下らない世迷い言で潰さないで頂戴!ペッ!」「いい、今度こんな下らないことを言いに来たら・・・只じゃおかないわよ!ペッ!」美しい悪鬼、夜叉羅刹のような見る者の血も心も凍り付かせる激しい怒りに美貌を燃え上がらせながら二人は慎治たちを突き放した。蹴り倒してやろうかしら、それとも腕をへし折ってやろうかしら。だけどこんな穢らわしい連中には、触るのも嫌よ。だったら・・・怜と舞の頭に残酷な攻撃方法が浮かんだ。こいつらに最も相応しいやり方で、こいつらが一番嫌な、一番屈辱的な方法で追い出してやる!怜と舞の脳裏に同じプランが浮かんだ。散々唾を吐き掛けられている癖して、生意気にも唾を吐き掛けられるのは嫌みたいじゃない?だったら・・・唾だけで追い出してやる!天城さんや霧島さんのように鞭を使う必要すらないわ、こいつらには唾だけで十分よ!唾だけで何の抵抗もできずに叩き出される屈辱を刻み込んでやる!「出ていかないんだったら、こうやって追い出してやるわよ!ペッ!」ダンッ!鋭く踏み込みながら怜は思いっきり慎治に唾を吐き掛ける。「アウッ!」怜の鋭い視線と唾に気圧されるように慎治は一歩ずり下がる。「穢らわしい!私の目の前から消え失せなさい!このクズ!ペッ!」見る者の血を凍り付かせるような、メドゥーサの邪眼のような眼力で睨み据えながら舞も唾を吐き掛ける。信次はブオッと顔に芳しい舞の吐息を感じた次の瞬間。吐き掛けられた唾に突き飛ばされるようによろけた。吐き掛けられた唾、殆ど質量すらない舞の唾が玲子のフルスイングの鞭に匹敵するほどの威力で信次を突き飛ばす。「このクズ!ペッ!ゴミ虫!ペッ!ゴキブリの方が100億万倍マシよ!ペッ!」「この穀潰し!ペッ!役立たず!ペッ!生きているだけで罪悪よ!ペッ!」怜と舞は普通の男、いやまともな人間ならば一生一度たりとも言われないであろう侮蔑と憎悪に満ちた罵倒を浴びせながら唾を吐き掛け続けた。ダンッ!一歩踏み込んで唾を吐き掛ける度に慎治たちが一歩後退していく。このゴミクズ!ウジムシ!怜と舞は知的な美貌を阿修羅の形相に変幻させて唾を吐き掛け続けた。ダンッ!ペッ!穢らわしい!寄生虫!踏み込み唾を吐きかける度に慎治たちが一歩後退して行く。そうよ二人共、その調子よ・・・唾で追い出してやる、君たち如きには触るのすら穢らわしいわ、唾だけで、唾だけで追い出してやる!指一本触れられずに、唾だけで追い出された男なんて、見たことも聞いたこともないわよ。さぞ屈辱でしょうね、君たちみたいなクズでも、悔しくて悔しくて夜も眠れなくなるでしょうね!お似合いの罰よ、ペッ!「この穢らわしいクズ!ペッ!無駄飯食い!ペッ!」「腐ったゴミよ君たちは!ペッ!臭い、ああ臭いこの生ゴミ!ペッ!」ひ、ひどい、ひどい・・・なんで僕たちを・・・慎治たちは泣きながら後退し続けた。怜と舞の唾に追い払われる屈辱、指一本触れられていないのに追い払われる屈辱。痛くない、ぶたれてもいないし首を絞められてもいない、苦痛は何も無い筈なのに慎治たちは無限の苦痛を感じていた。怜と舞の唾が着弾する度に、顔に思いっきり殴りつけられたような痛みが走る。芳しい吐息が暴風のように体を吹き飛ばす。殆ど質量もない筈なのに怜と舞の唾に、吐息に顔面を、全身を突き飛ばされる感触が確固としたリアルな実感として意識を支配する。慎治たちは為す術もなく、怜と舞の唾に駆り立てられながらドアへ、出口へと追いやられていく。カウボーイが牛を追い込むように、牧羊犬が羊を駆り立てるように、怜と舞は唾だけで慎治たちをドアへと駆り立てていった。
ドンッ、背中が固いものにぶつかる感触に慎治は思わず後ろを振り向いた。ど、ドア、ドアにぶつかった・・・じゃ、じゃあ・・・その通り、ソファからドアまで、三メートル近い距離を怜と舞の唾に駆り立てられて来ていたのだ。縋るように、パニック状態の空ろな視線を彷徨わせる慎治に怜の凛とした声が響く。「何をグズグズしているのよ!さっさと出て行け、ていうのが分からないの!それともこうやってずっと唾を吐き掛けられていたいって言うの!?唾が大好きです、もっと下さい、とでも言う気なの!この変態!ペッ!」ああ、あああ・・・慎治たちは必死でドアを開けようとする、だが半身の逃げ腰になりながらも、相変わらず唾を受けられるよう顔は前に向けたままだ。しかも二人が同時にノブに手を伸ばしたものだから手と手がぶつかりあい、ノブを奪いあうようになってしまって中々開けられない。苛立ちを露わに舞が怒鳴りつける。「何をやっているのよこのバカ!ドアを開けることすらできないの、そんなこと三歳児でもできるわよ!どこまで役立たずなのよ君たちは!さっさとしなさいよ、この精薄!ペッ!うすのろ!ペッ!グズグズしていたら、出て行くまで唾よ!ペッ!」ひいいっい、いやあああっ!矢のように降り注ぐ怜と舞の唾を浴びつつ、やっとのことで慎治たちはドアをあけた。「あわっ」「あうううっ」不意に開いたドアからよろめき出た二人はそのまま廊下の反対側の壁までつんのめるようにふらつき、そして壁とお互いにぶつかって絡み合うように転んでしまった。唾だけで本当に追い出されてしまった・・・唾に霞んだ慎治たちの目に、理事室の中が遥か遠い世界のように見える。だが悠長に屈辱にむせび泣いている暇などなかった。慎治たちはまだまだ、怜と舞の唾地獄から這い出ていなかったのだ。
ウウウ・・・アツツ・・・呻く二人を怜と舞は冷ややかに見下ろしている。「何よ、今度はそうやってそこに居座ろう、ていう気?ふざけるんじゃないわよ、目障りよ!ペッ!」漸く四つんばいになった慎治に怜の罵声が、そして唾が降り注ぐ。「アヒイッ!」バランスを崩した慎治はそのまま半身を捻り、腰が抜けたように座り込んでしまった。仰向けの姿勢で慎治の下敷きになっていた信次が上半身を起こすと、丁度信次たち二人は足を投げ出したまま怜と舞に向かってだらしなく座り込んでいるような格好だった。「何をしているのよ、誰がそんなところで寛いでいい、て言ったのよ!?さっさと消え失せなさい!ペッ!」舞が体を反らしたかと思うと、全力で唾を吐き掛けた。唾責めの再開だった。そんな、そんなあああ・・・も、もう部屋から追い出したじゃないですかああああっ!?なのに、なのにまた唾責めですかあああっ!そう、唾責めはまだまだ終わりではなかったのだ。最早立ち上がる気力もなく、へたり込んでいる慎治たちに怜と舞は情け容赦なく唾を吐き掛け続ける。「無様な姿!その姿が君たちにはお似合いよ!ペッ!」「よく恥ずかしくないわね、こんな生き恥さらして何で自殺しないのよ!この恥知らず!ペッ!さっさと死になさいよ!ペッ!」二人が唾を吐きかける度に、慎治たちは呆けたように一歩、また一歩とずり下がっていく。そんな慎治たちを見下ろしながら、怜と舞は漸く人心地を取り戻しつつあった。ペッと唾を吐いた感触、着弾した唾が慎治たちの顔面を穢していく様子、そして屈辱に塗れながらずり下がっていく慎治たち。その何とも無様な姿が怜と舞の怒りを癒していくようだった。いい気味、一生トラウマになるがいいわ、君たちに相応しい罰よね。もっともっと屈辱を与えてやるわよ、私たちの貴重な時間を何分浪費させたと思っているの?私たちを苛立たせたゴミクズには、そうやって泣き叫んで貰わないと割りが合わないわよ、ああいい気味!怜と舞はふと、自分たちの顔が綻んできていることに気づいた。フフフ、何か少し、楽しくなってきたわね。唾だけで二人を部屋から追い出したことに、微かな達成感すらあった。「廊下に座り込んじゃいけませんよ!全くお行儀が悪い犬ね!ペッ!」「ほーらほらほら、赤ん坊以下の無様な姿ね、そうやって這い蹲ってるのが君たちクズどもにはお似合いよ!ペッ!」ウフフフフ、牛追い鞭や羊飼いの犬、ていうのはあるけど、唾で人間追い立てるなんて、考えてみたこともなかったわ。
怜はゾクリとするような凄絶な微笑を浮かべながら唾を吐き掛け続ける。怒りの余り唾を吐き掛ける、ていうのはまあ分かるけど、こうやって他人を唾で追い立てるなんて想像したこともなかったわ。ウフフ、私ゴジラか何か、強い怪獣になったみたいね、私の口から聖なる炎を吐いているみたいじゃない?ウフフフフ、そうよ虫けらどもを滅ぼす炎よ、私の唾で君たちの心を焼き尽くしてやるわよ、ペッ!舞も残酷な愉悦の笑みを浮かべながら唾を吐き掛けている。そして慎治たち虫けらと怜たち女神の間に初めて、コミュニケーションが成立していた。慎治たちは屈辱だけではない、恐怖に満ち満ちた目で怜と舞の唇を見詰め続けていた。美しい唇の奥から間断なく、止め処もなく大量の唾が湧き上がり、自分たちに向かって吐き掛けられる。唾、消化液の一種に過ぎない唾、本当は慎治たちの体内にもあるものだ。だが慎治たちにとって唾は別のもの、美しい女性が自分を責め苛むための残酷な責め具だ。鞭にも匹敵する威力のその責め具は怜と舞の体内で次々と生産され、慎治たちを間断なく責め苛む。ヒッ、ヒイイッ、アヒイイイッ・・・残酷な、苦痛に満ち満ちた責め具を口から吐き出せる怜と舞。同じ人間に唾を吐き掛けられて辱められている、といったレベルはとうの昔に通り過ぎていた。慎治たちにとっても怜と舞は最早同じ人間ではなかった。口から自分たちを焼き尽くす炎を吐き出す人間を遥かに超えた存在だった。ああ、お願いです・・・どうか・・・やめて・・・ください・・・や、やめて、あつい・・・とけちゃう・・・慎治たちにとって怜と舞は人間を超越した女神に、唾一つで自分たちに最悪の苦痛を与えられる残酷な女神に昇華してしまっていた。慎治たちに間断なく降り注ぐ怜と舞の唾、そして決して顔を逸らすな、という礼子たちの呪縛。二重に縛られた慎治たちは屈辱の嗚咽を漏らしながら追い立てられていく。破局へと、奈落の底へと。余りに激しい唾責めに、慎治たちはすっかり忘れてしまっていた。ここが二階であることを。怜と舞の唾で追い立てられた慎治たちはいつの間にか、階段の縁まで追い込まれていた。ウフフ、あと少しね、もうあと一メートルもないわよ。ここまで来て振り向かれたりしたら興醒めもいいところだわ。二人ともしっかりこっちを向いているのよ。ペッペッペッペッ・・・怜と舞は唾を吐き掛けるスピードをアップし、最後の詰めに出る。ああ、あああ・・・や、やめて・・・慎治たちの意識は全て、怜と舞の唾のみに占領されている。そして突然、破局がきた。チラッと怜と舞は頷きあった。もう縁ギリギリ、後一歩で転落ね。そうね、止めを刺すわよ。怜と舞はニヤリと残酷な笑いを浮かべながら大きく息を吸い込んだ。「止めよ!ペッ!」「地獄に・・・墜ちなさい!ペッ!」ヒッ!アウッ!思いっ切り吐き掛けられた唾に押しやられてずり下がった二人の手が突然、ガクンッと落ちていく。「わっわあああっ!」「あああああああっ!」あると思っていた廊下が突然消えた恐怖、何が起こったのか考える暇もない。「あぐっがっわああああっ!」真後ろにでんぐり返しするように慎治は転げ落ちていく。「うぶっひっひぎゃあああああっ!」バランスを崩し、半身からうつ伏せになった信次はガンガンと何度も何度も激しく顔面を階段に叩き付けながら滑るように落ちていく。ドザアッ、ダダンッ!「うぐうううっ、うううううっ・・・」「いいい、いだあああああ・・・」階下に激しく叩き付けられた慎治たちは全身を襲う激痛に呻いていた。その時、天上から女神の笑い声が響いてきた。怜が高らかに勝利の凱歌を上げていた。「アハハハハッ!いいザマよ二人とも、君たちはそうやって虫けらみたいに呻いているのがお似合いよ!ペッ!」舞も楽しげに笑っていた。「いい、二人とも二度とこの階段を登ってくるんじゃないわよ。君たちみたいなクズが上ってきていい場所じゃないのよここは!もし上ってきたら、また唾で叩き落してやるからね!ペッ!」遠距離攻撃、とばかりに怜と舞は斜め上に向かって、放物線を描くように最後の唾を吐き出した。ビチャッ、ベチャッ、最後は殆ど垂直に落下した唾が見事に慎治たちの顔面で跳ねた。アハハハッ、アハハハハッ!ああさっぱりした、とばかりに笑いながら天上の女神は踵を返して去っていった。奈落の底で呻く亡者、女神の唾にまみれて泣き続けている慎治たちのことなど全く構いもせずに。階下に叩きつけられた慎治たちは何時までも何時までも、呆然と咽び泣き続けていた。微かな望みが絶たれたことに。そして学園の最高権力者に絶対的な怒りと軽蔑を買ってしまったことに。
4?
勿論、礼子たちは翌日にはこの事を怜と舞から聞かされていた。「ああ天城さん、今日これから予定ある?少しお茶でもしていかない?」翌日部活が終わった後に怜から誘われた礼子は何なのか不思議に思いながらも付いていった。そして連れて行かれた理事室には既に、舞と玲子が来ていた。あ、この面子・・・もしかして慎治たちのこと?あーあ、もしかして苛めてるのがバレちゃったのかな?そう思いながらも不思議と嫌な予感は全くしなかった。「遅かったわね、二人も同じのでいいかしら?」香り高い紅茶を入れ直した舞が待ちかねたように、ニヤニヤと楽しげに笑いながら切り出した。「ウフフ、勘のいい霧島さんたちのことだからもう気付いているとは思うんだけどね、今日来て貰ったのは勿論、川内君たちのことよ。」怜も妙に楽しげにクスクス笑っている。「そうなのよ、昨日は参ったわよ。いきなりあの二人、矢作君と川内君が私たちの部屋に押しかけてきてね、先生、天城さんと霧島さんに苛められているんです、先生から言って苛めを止めさせてください、て泣いてお願いしてきたのよ。」紅茶で唇を湿らせると舞が後を引き取った。「傑作だったわよ、いきなりシャツを脱いじゃってこの鞭跡、霧島さんたちに鞭打たれたんです、とか毎日毎日おしっこ飲まされてるんです、とか言いながら泣き出しちゃったんだから。」怜も紅茶を啜りながら尋ねた。「で、天城さん、私たちがどう答えたと思う?まあ貴方なら直ぐに分かっちゃいそうだけどね?」怜先生も舞先生も楽しそうね、ということは・・・「そうですね、怜先生たちのことですから、甘ったれるんじゃないわよ!と一喝して追い返したんじゃないですか?」怜と舞は手を叩いて大笑いしていた。「ご名答!流石ね、その通り。女の子に苛められてます、なんて言うだけでも恥ずかしいのに、鞭で叩かれてます?おしっこ飲まされてます?まあよく恥ずかしげもなくそんなこといえるものね!て私たち心底呆れ果てちゃったわよ。だから唾を吐き掛けて追い返してやったわ!」「え?怜先生と舞先生が唾を吐き掛けたんですか?信次たちに?」流石に驚いた玲子が聞き返したのに対し、舞は大きく頷いた。「そうよ!もう思いっきり唾を吐き掛けて叩き出してやったわ!そんなに驚くことないでしょう?本当に心底軽蔑したら唾を吐き掛けてやりたくなるのって当然でしょう?そこは私たちも霧島さんたちと同じよ。」やっぱりね・・・そりゃそうよね、怜先生と舞先生が信次たちの味方するわけないわよね。顔を見合わせて頷きあった礼子たちを見て、怜と舞は満足そうに微笑んだ。
「そう言えばそうですよね。最近は何かにつけ唾を吐き掛けてやってるけど、やっぱり最初に吐き掛けた時は侮蔑と言うか・・・怒りと軽蔑の極致で思わず吐き掛けてしまった、て感じでしたね。」礼子が少し感慨に耽るように言うのを怜は穏やかに笑いながら頷いた。「そうね、私たちもまあ子供の頃に喧嘩してペッとやったとか言うのを別にすると、そうね、本気で他人に唾を吐き掛けたのはやはり貴方たち位の時かしらね。多分天城さんと同じようなシチュエーションかな、余りに情けない男に苛ついて思わず吐き掛けたのが最初よ。」「最も霧島さんは少し違うかもね。」舞が笑いながら引き取った。「霧島さんはもう少し純粋に苛めっ子が入っていそうね。多分、唾を吐き掛けられて屈辱に歪む顔みたさに、誰かを苛めながら吐き掛けたのが最初じゃないかしら?」「あ、やっぱり・・・分っちゃいますう?ついでに言うと、フミちゃん、神崎さんが私タイプで朝子、萩さんが礼子タイプですね!」おどけたように玲子はペロリと舌を出した。舞先生、全てお見通しのようね、だったら隠したりとぼけたりするのは逆効果ね。「あらあら堂々たるカミングアウトね!四人揃って全くもう、全員苛めっ子なんだから!」四人そろって一しきり大笑いしたところで、怜が切り出した。
「ああ二人とも気にしないでいいのよ、最初に言っとくけど、私たち別に貴方たちに注意するとか苛めを止めなさい、とか言うために呼んだんじゃないからね。単に矢作君たちがバカなお願いをしに来たけど、追い返してやったわ、ていうことを教えてあげるためだけよ。じゃないと、まあそんな知恵が回るとも思えないけどあの二人、私たちに苛めを相談しに行ったぞ、とか言って少しでもあなたたちに苛められないようにしよう、とかするかも知れないからね。まあどうでもいいけど、あんなクズに名前を使われるだけでも不愉快だから予めあなたたちに教えておいてあげよう、ていうことよ。」「そう、怜の言うとおり単にそれだけよ。大体ちょっと見れば分かるけど、あなたたちが苛めているのはあの二人だけ、他のみんなとは男女を問わずとても仲いいじゃない?だったら・・・まああなたたちなら分かるだろうからストレートに言うわね、教員というより学園の経営者である私たちが、落ちこぼれのクズでしかないあの二人と優等生で人気者のあなたたちと、どちらを取るかは言うまでもないでしょう?」極めて分かりやすい、ストレートと言うよりあけすけな怜と舞の説明だった。好き嫌いという単純明快な感情論と、教育論だ人生観だのの綺麗事など一切入らない単純明快な利益考量。礼子たちも直感的に理解出来るものだった。最後の紅茶を飲み干しながら怜が言った。「あなたたちが矢作君たちをどう苛めようと、私たちの関与せざるところ、よ。好きにやっていいわ。」そして舞が最後に一本、釘を刺すのも忘れなかった。「但し、やはり学園の枠組みはあるからね、何か面倒なことになりそうな時は事前に私たちに一報入れてね。」
礼子たちは当初、怜と舞を巻き込む気はなかった。単にクラスメートを怪我させた慎治たちをリンチにかけるにあたり、クラス全員参加の大規模リンチを加えようと思いそれだけの大規模リンチとなれば舞に釘を刺されたこともあるし、一応事前に知らせておく必要はある、と思っただけだった。「さてと、やっぱり怜先生と舞先生には言っておかなくちゃいけないわよね・・・どう言ったらいいかしら?」礼子の問いかけに暫く考え込んだ玲子だったが、小さく頷くと答えた。「あの二人は信次たちの両親なんかとはレベルが違うからね、下手な誤魔化しは通用しないと思うわ。て言うより、小細工する必要ないんじゃない?だって唾吐き掛けて追い払う位信次たちを軽蔑しているのよ?だったらストレートにさ、あの二人が逆ギレして陽子と有希子をケガさせたからみんなでリンチする、て有りのままに言ったほうがいいと思うよ?」そして土曜日、怜と舞に金曜の件を報告し、更に来週クラスみんなで信次たちをリンチにかける、と打ち明けた玲子たちに二人は意外な反応を返してきた。「ちょっと待って!今の話、本当?本当に矢作君と川内君が青葉さんと古鷹さんを突き飛ばして怪我させたの?」話を聞いた怜の顔から笑いが消え、真剣な表情に一変した。あらら・・・まずいかな・・・一瞬、玲子は嫌な予感がした。やりすぎよ、て怒っているのかな?だが続く舞の言葉は玲子たちの予想とは正反対だった。「霧島さん、途中経過はどうでもいいわ。この前言ったとおり、あなたたちが川内君たちをどう苛めようとどうみんなでリンチしようと構わないわ。病院送りにしようが自殺させようがどうでもいいの、そんな事は全然問題ないわ。そんなことより本当なの?あの二人が古鷹さんたちに怪我をさせた、て言うのは本当なの?イエスかノーかだけで答えて!」え、苛めたりリンチはどうでもいい?一瞬反応に詰まりながらも玲子が答えた。「・・・ええ、本当です。信次たちが有希子たちを突き飛ばして怪我をさせたこと、これは間違いありません。」フウウウウッ・・・怜と舞が大きく溜息をついた。暫く沈黙がその場を支配したが、やがて怜が口を開いた。「・・・ったくあの二人は・・・やってくれるわね・・・」怒りを押えきれないように呟く怜と同様、舞も吐き捨てるように呟いた。「よりにもよって女の子をトイレで突き飛ばすとはね・・・クズが!」美しい、大きな瞳を怒りに燃え上がらせながら怜が礼子を見据えながら静かに言った。「天城さん、聖華で・・・と言うより共学校でおよそ一番してはいけないことってなんだと思う?それはね、男の子が女の子に暴力をふるうことよ。」舞の白い頬も怒りに上気していた。「そう、理由なんか関係ない、苛められてたから、リンチされてたから反撃しました、なんて情状酌量の対象にすらならないわ。男の子が女の子に暴力を振るう事、これだけは絶対のタブーなのよ。」
怜と舞が直感的に思い出したのは体育科の主任、大井との会話だった。大井は日体大出の典型的な体育教師、時に乱暴な印象すら与える古典的な体育教員だが抜群の指導力と豊かな人間味を持ち、運動部の生徒を中心に極めて人気が高かった。聖華の共学化にあたっては頑強な反対派であったがその指導力に惚れ込んでいた怜と舞は文字通り三願の礼をもって翻意を促し、遂に説得に成功したときは思わず快哉を叫んだ程だった。大井が反対したのは単に改革反対、ということではない。共学化に際し万が一の事故、特に有体に言えば男子生徒が女子生徒に肉体的、特に性的な暴力を振るった場合、聖華のブランドが回復不能なまでに傷付く事を恐れたのが最大の理由だった。その心配は怜と舞にも良く分かった。いや二人が最も恐れ、防止に全力をあげねばならないと考えていたのも、まさにその点だった。「大井先生の仰るとおり、私たちもその問題は一番重視しています。だからこそ・・・もしそんな問題が発生した場合は、犯人は絶対に許しませんよ。」断言する怜に対し、大井は試すかのように質問した。「許さない、それはよく分かるが・・・具体的にどうするつもりなのかな?」舞が断言するかのように答えた。「最大限厳しい罰を与えます。そう・・・体罰を含む、ある種見せしめ的な、ここまでやる必要はないだろう、と言う位の厳しい罰を与えるつもりです。」ほう、と言う顔で大井は更に突っ込んだ。「体罰ねえ・・・まあ口でいうのは簡単だけど、実際に誰がそんなことやるのかな?聖華の今の教員でそこまでやる熱意がある奴は少ないし、となると結局は体育科の俺たちにお鉢が回ってくるのかな?暴力教師の役割もやれ、と言うことですかな?」ニヤリと怜は微笑を、凄絶な笑みを浮べた。「そんなことはしませんわ。大井先生たち体育科の先生方に汚れ仕事を押し付けて自分たちだけ澄ました顔でいるつもりは毛頭ありません。約束します、最初、少なくとも最初にそんなことをしでかした生徒には、私たち自らが罰を与えます。」本気か?大井は驚きを隠せなかった。「・・・本当ですか?本気で・・・本気であなたたち、理事の、いや東大の助教授で、汚れ仕事なんかは他人に押し付けて余計な事には首を突っ込まないほうが楽なはずのあんたたちが、自ら体罰までやる、ていうんですか?」自然に口調も丁寧になっていた。ここが勝負所、大井先生に私たちが本当に本気だ、て分かってもらえるラストチャンスよ。舞は大きく頷きながら断言した。「怜の言ったことは本当ですよ。約束します、最初に女子生徒に暴力を振るった男子生徒には、私と怜とで罰を、体罰を含む厳罰を加えます。大井先生たちには頼りません、私たち、私たち自身の手で罰を与えます。」大井の目を見据えながら舞は静かに宣言した。「大井先生、これでも私たち、一応は空手と合気道の黒帯ですよ?そこいらの男の子を懲らしめる位、簡単ですよ!」怜の言葉に頷きながら暫く腕組みをしてじっと考えていた大井は、やがて破顔一笑して右手を差し出した。「分かりました、そこまで言うのなら、あなたたちを信じましょう!そこまで本気ならもう何も言う事はありません、俺は全力であなたたちの改革を支持しますよ!」
そして今・・・恐れていた事態が現実になった。怜も舞も自分のテンションが上がってくるのを感じていた。いいわ、私たちは自分の言葉に責任を持つ、ということを見せてあげる。怜は礼子を正面から見据えながら言った。「天城さん、事は重大よ。言葉遊びや腹の探り合いなんかしている場合じゃないわ、私たちからのお願い、ストレートに言うわね。」怜の本気がヒリヒリと伝わってくるだけに礼子たちはゴクリと唾を飲んだ。何だろう、怜先生たちのお願いって。一瞬の沈黙の後、舞が口を開いた。「心配いらないわよ、霧島さんたちに不利とか負担を掛けることは何もないわ。クラスでどんなリンチを加えようとあなたたちの自由よ、あの二人をどんな酷い目にあわせてもいいわ。だけどね、その前に先ず私たちからも罰を加えさせて欲しいのよ。そう・・・学校としての処罰、体罰を含む厳罰をね。」体罰を含む厳罰?思わず顔を見合わせる二人の緊張を解そうとするかのように、怜が明るい笑い声を上げた。「アハハハハッ!二人ともそんなに驚かないでよ、単純なこと、頭のいいあなたたちならすぐ分かる話よ。天城さんたちがここに来たのは、矢作君たちをリンチする、て私たちに事前連絡に来たわけでしょう?それを邪魔する気はないから、学校としての処罰を私たちも執行するわよ、ていうだけの話、単に取引をしましょう、ていう話よ!」舞も笑いながら続けた。「そうそう、別に困った話じゃないでしょう?それどころか学校を、私たちを敵に回す、て言う意味で川内君たちにとっては極めて厳しい責めになるはずよ。だって私たちはここの理事よ?当然、肉体的な苦痛だけじゃなくて家庭を巻き込んだ最大限屈辱的、しかも一生後を引くような責め苦を味あわせてやるわよ。ウフフどう、正直ベース、あ、それいいな、て思ったんじゃない?立場が違う私たちが責め手に加われば、あの二人に全く新たな苦痛を味あわせてやれる、て?」
思いもかけない展開に流石の玲子たちも驚きを隠せなかった。確かに怜と舞が信次たちへの制裁に参加してくれれば最高だ、朝子や富美代たちと同じく、新たな発想の苛めで信次たちをたっぷりと泣かせてくれるだろう。いや肉体的な責めに留まらない、この二人はなんと言っても学園の理事、最高権力者だ、怜と舞がその気になれば信次たちの学園生活を滅茶苦茶にしてしまうことなどた易いだろう。しかも自分たちがどんなリンチを加えてもよい、学校公認で苛めさせてあげる、とのおまけつきだ。学校公認の苛め、傷跡や周囲の目など、多少は働いていたリミッターを全部解除できる。どんな苛めをしても良いフリーパス、喜んで飛びつきたいオファーだ。だが玲子には一つだけ気懸かりがあった。怜先生と舞先生が加わる、それって物凄くよく効く薬みたいなものよね。よく効く分・・・副作用も怖いわ。「舞先生、すごく嬉しいお話で大喜びなんですけど・・・一つだけお願いが・・・」アハハハハッ!と大笑いしながら舞が手を振った。「分かった!霧島さんが何を言いたいか当ててみましょうか?あの二人を退学にはしないで下さいね、てことでしょう?」流石!「分かりました?その通りです。だって退学にされたらあの二人を苛めにくくなっちゃいますもん!」エヘッと明るく笑いながら舌を出し、少しブリっ子を入れながら玲子は肩をすくめた。笑いながら舞が答えた。「心配しなくていいわよ二人とも、退学は愚か停学にもしないわ。理由はあなたたちと同じよ、だって退学や停学にしたらそれ以上責められないでしょう?単に罰を加えるだけじゃないわ、あの二人には見せしめになって貰うのよ。今後聖華で女子生徒に暴力を振るった男子がどういう目にあうのかっていうね。」ニヤリと凄絶な冷笑を浮かべながら怜が言った。「考えてみれば丁度よかったわ。他の前途ある生徒には余り手荒な真似や酷いことはできないけど、あの二人みたいなクズなら何の未来もないでしょう?一生の心の傷を負わせてやっても全然問題ないわ。連中も光栄というものじゃない?せめて見せしめ、生贄としてであれ他人様のお役に立てるんだから!泣いて喜んで貰いたいわね。」余りに悲惨、余りに残酷な会談だった。慎治たちの全く知らない所で、信次たちが全く手出しも出来ないところで二人の運命が決められていた。更に深いどん底へ、二度と這い上がれない地獄へと突き落とされることが。
5?
校長室に入った慎治たちを待ち構えていたのは校長の秋月と担任の若月、礼子と陽子、玲子と有希子、そして怜と舞の8人だった。敵意に満ちた16個の視線が慎治たちに突き刺さる。うう・・・刺すような視線に二人の背中に早くも冷たい汗が吹き出てくる。校長室の中央に置かれたテーブルの周りのソファーと椅子に8人が陣取っていた。口を切ったのはこの部屋の主、そして慎治たち以外では唯一の男性である秋月だった。「来たか・・・まあ兎に角座りなさい。」秋月は打ち合わせ時用に壁に立てかけてあるパイプ椅子を指し示した。と、その時怜の凛とした声が響いた。「校長先生、何を甘いことを言ってるんですか!この二人を座らせる必要などありません。二人ともそこに正座していなさい!」せ、正座、床に正座、そんな、みんな座っているのに僕たちだけ正座・・・慎治は微かに声を出しそうになった、だが怜の燃えるような視線に射すくめられ、何も言えない。「さあ青葉さん、古鷹さん、嫌な記憶を蒸し返して申し訳ないんだけれど、加害者の二人が来たところでもう一度だけ、さっきの話を聞かせて貰えないかしら。」慎治たちに対してとは打って変わった優しい口調で怜が陽子と有希子に微笑みかけた。ゲッ・・・陽子と有希子に視線を向けた信次は、二人の手と膝に大袈裟に包帯が巻かれているのを見て悲鳴を上げそうになった。ふと見るとテーブルの上には二枚のÅ4サイズの紙が置かれている。内容までは見えないが、そのタイトルには確かに「診断書」とあった。玲子さんたち・・・酷い陰謀を・・・な、何とか、何とか先生たちの誤解を解かなくちゃ・・・玲子たちの陰謀、信次の想像が及ぶのはそこまでだった。よもや怜と舞が決定的に自分たちの敵に回っている、とまでは予想もつかなかった。
「は、はい・・・金曜の放課後なんです、私がトイレに入ったら、奥の一つ手前の個室に入ったんですけど、隣の個室で何かゴソゴソと変な物音がしたんです。でふと下を見たら・・・隣の個室から鏡が突き出ていたんです・・・」啜り泣きながら訴える陽子に続いて有希子も訴えた。「私も・・・青葉さんの向かいの個室に入ったんですけど、同じように鏡が・・・それでビックリして飛び出たら丁度、向かいから青葉さんも飛び出てきたんです。で、二人で何なの、何なのあれ、て驚いちゃって、それで外から見ると隣の個室、一番奥の個室のドアが閉まってて誰か入ってるみたいだったけど、物音一つ立てないで凄く不気味だったんです・・・だって普通トイレだったら、何か音の一つもするじゃないですか?」「そうなんです、だから古鷹さんと二人でこれ絶対変、絶対おかしい、て思ってドアをノックしてみたんです。誰、誰か入ってるの!?変な音がしたんだけど誰が入ってるの、て・・・」「でも返事がなかったんです。必死で息を潜めているような感じで、なんの返事もなかったんです。それでもうすっかり怖くなっちゃって青葉さんに、これ絶対変、誰か呼んでこようよ、て言った時にいきなり・・・」「バターン、て凄い勢いでドアがあいて中から矢作君が飛び出してきて私のことを突き飛ばして転ばせて・・・」「えっ、と驚いて振り向いたら私の方のドアも急に開いて中から川内君が・・・飛び出てきて後ろから私のことを突き飛ばして、転んだ私のことを飛び越えて・・・逃げて行ったんです・・・」そ、そんな!で、でたらめだ!抗議の声を上げようとする信次の機先を舞が制する。「川内君、誰もあなたになんか聞いていないわ、黙っていなさい!」ピシリと鞭のように厳しい舞の声に押さえ込まれ、信次はアウウ・・・と声にならない呻き声だけを漏らした。そんな信次を一瞥すると舞は玲子たちに穏やかに問い掛けた。「霧島さん、天城さん、あなたたちの話ももう一回聞かせて頂戴。」「はい、私と天城さんがトイレに入った時、奥で青葉さんと古鷹さんがトイレのドアをガンガンノックしていたんです。誰なの、開けてよ、返事してよ、て大声上げていたんです。」「そうです、それで私もびっくりして青葉さんたちにどうしたの、何かあったの、て声をかけたんです、そしたらその瞬間に・・・トイレのドアがバーン、と凄い勢いで開いて中から矢作君と川内君が飛び出してきたんです!」礼子の言葉に頷きながら玲子が証言を続ける。「えっ、て私も天城さんも本当にびっくりしちゃって・・・でも青葉さんと古鷹さんが転ばされて悲鳴を上げたんで我に返って駆け寄ろうとしたんです。その間に川内君と矢作君は・・・」「私と霧島さんの横を駆け抜けてトイレから飛び出して逃げていったんです。一瞬でしたけど、絶対に見間違えなんかじゃありません。間違いなく矢作君と川内君でした。」
ああ、あああ・・・慎治たちは全身の血が恐怖で凍りつきそうだった。ひ、酷い!!!僕たち、女子トイレを覗いて、しかもそれがバレて逃げる時に青葉さんたちに怪我させた犯人に仕立て上げられている!!!礼子たちの証言が終わったところで溜息を突きながら秋月が慎治たちに尋ねた。「・・・どうなんだね・・・青葉さんたちの話の通りで間違いないのかね?全く・・・何でこんな事をしでかしたんだ?」い、今だ、今言わなくちゃ、今言わなくちゃアアアッ!「ち、違う違うちがいますうううううっ!ぼ、僕たち、僕たちが被害者なんですうううううっ!」「そそそ、そうですそうです!ぼ、僕たち、僕たちの方が、僕たちがリンチされてたんですうううっ!」「あ、あ、天城さんや霧島さんたちにいいいい、苛め、苛められているんですうううっ!きき、金曜も、金曜もりりり、リンチされてたんですよおおおおおっ!トト、トイレで、トイレで無理やりみんなのおしっこを飲まされてたんですううううっ!」「そ、そうですそうです!そ、それに、そのリンチに青葉さんたちも加わってたんです!青葉さんたちも僕たちに・・・おしっこ飲ませてたんです!だから・・・だから僕たち、必死で逃げ出しただけなんですううう、お願い、信じてください・・・」「フウウウウ・・・全く・・・」慎治たちの涙ながらの絶叫にうんざりとした表情を露骨に浮かべながら秋月が眉間を押えながら呟いた。「私は情けないよ、この期に及んで未だそんな嘘を付くとは・・・古臭い言い方だけど、君たち男としてのプライドというものは欠片もないのか?よりによって女の子たちにトイレでリンチされていた?それもおしっこを飲まされてた?君たち・・・嘘を付くなら・・・せめてもう少しはマシな嘘を付いたらどうかね・・・」怜と舞は慎治たちに敢えて自由に弁明させながらフン、と鼻で笑っていた。別に秋月に対して事前に根回ししてあったわけでも自分たちに同調することを強要したわけでもない。だが秋月は常識人、だからこそ自分の中での一般常識の範囲内でしか判断するわけがない。しかも校長にまで登りつめた十分に優秀な、怜と舞から見ても評価に値するレベルの男だ。その秋月にとって男子が女子にトイレでリンチされていた、しかも場末の商業高校じゃない、名門のここ聖華でだ、そんなことが信用できるわけがない。信用できないならばそれは嘘、慎治たちが我が身可愛さに必死に嘘を付いているとしか思えない、と考えるのが自然な論理だ。慎治たちの弁明はこの場で唯一、僅かに中立的な秋月をも完全に敵に回しただけだった。フフフ思った通りじゃない、大体秋月先生レベルのまともな男、大人の男性があなたたちみたいなカスの味方をするとでも思っているの?本当にとことんバカね。まあどうでもいいけど、秋月先生はもう完全に私たちサイドね、じゃあ次、行こうかしら。秋月が呆れ果てたように首を振っているのを満足げに見ながら、怜が口を開いた。「校長先生、彼らの話を到底信用できない、ていうのは私たちも同じですけど、一応担任の若月先生にも話を聞いてみませんか?」舞も大きく頷いた。「そうですね。私たちも是非、伺いたいですわ。若月先生は一体どうお考えなのか・・・こんな酷い生徒が私たちの聖華にいるだなんて、担任として一体どういう教育を施してきたのか是非、お伺いしたいですわ。」ヒッ、ヒイイッ!必死で隅に縮こまっていた若月は話を振られた途端、ビクッと電気を流されたかのように全身を震わせた。無理もない。若月はここ聖華のOGということで採用されていたが教員としては可もなし不可もなし、のレベルだった。ルックス、性格、頭のよさ、そして教師としての技量、全てが可もなし不可もなしだった。自分でも限界をわきまえていた若月は共学化にあたり、私なんかが学園の方針に賛成だ反対だ、ていうのもおこがましいわ、と自己規制したおかげで辛うじて残留組に入れたが、内心聖華に残れるかどうか相当にヒヤヒヤしていたことも確かだった。私ももう35歳なのに未だ独身だし・・・この年で聖華をクビになったら行く当てなんかどこにもないわ。何とかここに残れて良かった・・・実のところ怜と舞の評価も毒にも薬にもならないレベル、いてもいなくてもどちらでもいいわね、と言った程度の評価だった。契約更新に当り舞はそのことを若月にはっきりと伝えていた。「若月先生、ではあなたとの契約を来年も更新します。だけど一つ、覚えておいて下さいね。今年ほどの大規模ではないにしろ、聖華では今後も毎年、私たちが求めるレベルに達しない先生たちには遠慮なく、辞めて頂きます。若月先生、あなたは現時点では下位10位以内に入っています。今後相当に頑張らないと・・・来年以降、契約を更新できるという保証はありませんよ?」「はは、はいいいっ!が、がんばります、がんばりますから・・・どうかよろしくお願いしますっ!」遥かに年下の舞にテーブルに頭をこすりつけんばかりの勢いで平身低頭しながら、若月は心底怯えながら心に固く誓っていた。「たたた、大変だ・・・がんばらなくゃ、何とかしなくちゃクビにされちゃう・・・そしたら私・・・どこにも行くところなんかないんだから!!!」その若月にとって、舞の冷たい言葉は匕首を喉元に突きつけられたようなものだった。そそそ、そんなあああっ!わ、私まで、私まで巻き添えにしないでよおおおおっ!自己保身以外に考えられなくなった若月は大慌てで上ずった声で証言した。「はは、はいいっ!そそ、そんな、苛めだなんて、苛めだなんて見たことも聞いたこともありませんんんっ!ぜ、絶対、絶対です!わ、私のクラスで苛めだなんて、絶対にありませんんんっ!」あらあら舞、薬が効きすぎよ、今日は若月先生を苛める趣旨じゃないでしょ、そんなに苛めちゃ逆効果よ。苦笑しながら怜が穏やかな声で若月に問い掛けた。「まあまあ若月先生、落ち着いてください、舞がどういう指導をしてるんですか、なんて言いましたけど、大した意味はないんですから。それより先生も大変なんじゃないですか?こんな問題児を二人も担任に抱えていらして。若月先生も本当に大変でしょうね、て私たちもむしろ同情しているんですよ?如何ですか、普段の彼等は?授業態度とか友達付き合いとか、先生の目から見てどうだか教えて頂けませんか?心配いりません、幾ら先生が努力しても限界があるのは承知していますわ。先生の責任だなんて誰も思いませんから、遠慮なく教えて頂けませんか?」
鞭のように厳しい舞の言葉の後だ、怜の甘い飴の威力は絶大だった。もとよりクラス一の劣等生、しかも礼子たちの姦計により授業を真面目に受ける事を禁じられ殆どの教員から態度最悪の烙印を押されている慎治たち。その担任という事で散々嫌な思いをさせられ下げたくない頭を下げさせられてきた若月だ、慎治たちに対する嫌悪はあっても庇ってやる義理など毛頭ない。ましてや自分の生殺与奪の全権を握る怜と舞の前だ、二人の意図に逆らうような発言をするはずがない。「は、はい!二人とも、二人とも授業態度は本当に最悪、殆どの先生方から叱られていて、私のところにもよく先生方から文句がきていますうっ!」そうそう、その調子よ。怜が優しげに微笑みながら問い掛けた。「授業態度については私たちも聞いていますが、苛めについては如何ですか?そんな現場を目撃されたとか、苛められている、という話を聞いたことはありますか?」「あああ、ありませんんっ!・・・い、いえ逆に、こんな落ちこぼれだから男子生徒にからかわれているのを、天城さんたちに助けてもらっているのを見たこともありますっ!あああ、天城さんや霧島さんが二人を庇っているのは何回も見ましたけど、天城さんたちが苛めているだなんて、断じてありませんんんんっ!」ビンゴ!怜と舞は内心、思わず手を叩いていた。若月先生も満更バカじゃないじゃん!ちゃんとこの場を読んでどう答えれば私たちが満足するか位は分かるのね、よしよしお利口お利口、少しは見直したわよ。満足そうに頷きながら怜は秋月の方に向き直った。「秋月先生、もう十分ですよね?彼等は頑として自分の非を認めないつもりのようですが、これだけ証拠が揃えば彼等の自白がなくても十分だと思いますが?」「全くですな・・・私も教員生活は長いが、これだけ酷い事件は初めてですよ。どう見ても疑う余地はありませんな。」はいOK,これで外堀は埋まったわよ。「では若月先生、お手数ですが彼等の自宅に連絡して至急、ご両親に来て頂くよう伝えてください。ああ勿論、彼等が何をしたかも伝えて下さいね。女子トイレに忍び込んだ挙句に見つかってクラスメートに怪我をさせた、ていうことを。」「はは、はいいっ!た、ただいま直ぐに!」怜の指示に若月は大慌てで転びそうな勢いで駆け出していく。慎治たちの両親が揃うまでの間、一旦散会となったが慎治たちはそのまま昼食も抜きで校長室に軟禁されていた。そして二時間後、慎治たちの両親が血相変えて飛び込んできた。辛い査問の再開だった。
事情を説明された慎治たちの両親は茫然自失の呈だった。母親二人は泣き崩れ、父親二人は余りのショックに、息子が変態性欲者だったという宣告に顔面蒼白となりながらワナワナと唇を震わせていた。長い沈黙の後、信次の父が必死で声を搾り出した。「・・・信次・・・どうしてだ、なんでこんなことをしでかしたんだ・・・」そ、そんなあああっ!ち、違う、ちがうんだああああっ!信次は必死で絶叫した。「ち、ちがう、ちがうんだよおおおっ!嵌められた、俺は嵌められたんだよおおおっ!苛められてたのは、トイレでリンチされてたのは俺のほうなんだよおおおっ!!!」だが信次の父も中小企業とはいえ一つの会社を経営できるまともな男だ、仮にも男である信次、障害者でも何でもない五体満足な男である信次が女の子にトイレでリンチされる、なんて信じられるわけがない。覗きをしでかして捕まえられそうになり、逃げ出した、との話の方が100万倍は信じられる。「おまえは・・・まだそんな嘘を・・・つくのかああああっ!このばかやろおおおおおっっっ!!!」ガターンッ!ドガッ!怒りに我を忘れた信次の父はいきなり立ち上がると力任せに信次を殴り倒した。「俺は・・・俺は情けないいっ!死ね、死ね、お前など今すぐ死んでしまえええっ!」「慎治・・・お前はどうなんだ・・・何か言う事はないのか・・・」慎治の父も俯いて拳を握り締めたまま、押し殺したような声で呟いた。「あああああ・・・と、とうさん・・・信じて・・・違う、違うんだよ・・・僕たちじゃない・・・悪いのは礼子さんたち・・・」「黙れっ!いい加減にしろ!」慎治の父も怒りを全身からぶちまけながら立ち上がった。「未だ言うのか・・・それも言うに事欠いて天城さんの、落ちこぼれのお前に何かと世話を焼いてくれた天城さんのせいにしようとは・・・このばかものおおおっ!土下座しろ、土下座して皆さんに謝れえええっっっ!!!」床に正座させられている慎治の首根っこを引っつかむと、慎治の父は泣きながら何度も何度も慎治の頭を床に叩き付けた。「何でだ・・・何で俺の息子がこんなクズになってしまったんだ・・・お前は本当に慎治なのか?俺の息子なのか?」礼子の父のサポートもあり、出世街道を順調に歩んでいる慎治の父にとっても慎治の言う事は、いくら実の息子の言う事だとは言っても到底信じる事はできなかった。信用できない、即ち追い詰められて嘘を言っている。女子トイレの覗き、クラスメートへの暴行。最低の破廉恥行為をしでかしたのに、何とか言い逃れをしようとしているとしか思えない。卑劣な・・・何と卑劣な・・・加えて礼子たちは慎治たちの自宅を足繁く訪れ、慎治たちの両親とも何回も会っている。美しく知的で明るい礼子たち、大人から見て最高の、理想の女の子像を巧みに演じきっていた。その礼子たちが実は慎治たちを苛めていた、そんな話を信じられるわけがない。しかも苛めなど全くなかったと、担任の若月が明確に否定しているのだ。そして高校入学以来、慎治たちの成績が急低下し更に授業態度、生活態度などで両親も父母会、個別面談などで再三学校から注意を受けている。これでは・・・どんなに慎治たちが叫んでも信用してもらえるわけがない。いや、言えば言うほど両親の怒りと絶望と嘆きを掻き立てるだけだった。なまじ肉親の分、余計絶望は、嘆きは深い。そしてその怒りは骨肉憎悪、赤の他人に対する何倍もの憎悪へと膨れ上がっていく。憎悪、という点で言えば慎治たちの両親の憎悪の方が怜、舞よりも、いや礼子たちよりも遥かに激しく膨れ上がっていた。今や両親、慎治たちの最後の望みの綱も明確に敵側に回っていた。
一仕切り慎治たちの両親が爆発したタイミングを見計らって怜が声を掛けた。「お父さん、お二人ともお怒りになったり嘆かれるお気持ちは良く分かりますが、取り敢えずその辺りでストップして頂けませんか?兎に角どうぞ落ち着いて、お坐り下さい。」怒りで顔面を紅潮させつつ、同時に余りの恥辱に身の置き場もないように震えながら慎治たちの父は椅子に座り込んだ。二人が一呼吸ついたのを見計らうと怜が静かに語りかけた。「どうやら事情はお分かり頂けたようですね?慎治くんたちはこの期に及んでも未だ、とんでもない嘘を付いて誤魔化そうとしていますが、流石にそんなことは信じていらっしゃらない、ということでよろしいでしょうか?」弱々しく二人が頷くのを見て怜は言葉を続けた。「今、お父さん方が慎治くんたちを殴りつけていらっしゃいましたが、それはとても正しい事だと思います。人間として絶対にやってはならないこと、それを犯したら罰を受けねばならない、そういう毅然とした態度を示された事は正に尊敬に値します。しかしながら、幾らお父さん方に罰せられた、といっても、私たち学園としてはそれだけで許す、というわけには行きません。お分かり頂けますね?」「・・・はい、分かります・・・申し訳ありません・・・覚悟は・・・できています・・・」慎治の父が呻くように言った。「当然・・・退学、でしょうね・・・仕方ない・・・ですね・・・信次、お前もう、学校には行かないでいい、明日から直ぐに仕事を探せ、さっさとどこかで仕事見つけて働くんだ、いいな!」信次の父も悄然としながら同意した。母親二人も泣きながら頷いていた。予想通りの反応に内心、怜も舞もニヤリとしていた。その横で未だ痛みの余韻を味わいながら、慎治たちは呆然としていた。退学・・・退学にされるのか・・・未だ現実味が全く沸かなかった。だけど・・・まあいいのかも知れないな・・・退学になれば、兎に角礼子さんたちからは離れられるもんな・・・毎日毎日鞭やおしっこで苛められてる位なら、いっそ退学になっちゃった方がまだマシかもな・・・だが二人の淡い喜びは舞の一言であっさりと踏み潰された。「そうですね、確かに慎治君たちの振舞いは十二分に、退学に値します。だけど、私たちは今回敢えて、敢えて二人を退学にするのは留保したいと思います。」「えっええっ!ほ、本当ですか!?」「そ、そんな!退学に・・・しないで頂けるんですか!」仰天した父親たちが大声をあげた。「そうです。決して・・・決して今回の罪を許す事はできません。けれど聖華も共学化した以上、今後もこのようなことが絶対に、二度と起きないとは言い切れません。その度に犯人を退学にするのは簡単ですが、敢えて最も困難な更生への道を探る事もまた、大事な教育だと思います。だから、ご両親が私たちの条件を了承して頂けるなら、今回は退学処分だけは留保しようと思います。」父親二人が喜んだ声をあげた。「あ、ありがとうございます!」「退学は、退学だけは許して頂けるなら、どんな条件でも結構です!お願い・・・します!」
あらあら簡単に乗って来たわね。内心舌なめずりをしながら怜がつなぐ。「ありがとうございます、て些か気が早すぎますわ。この条件、かなり厳しいですよ。と言いますか、滅茶苦茶理不尽な条件ですよ。」厳しい条件・・・な、なんだなんだ、先生たち、一体何を企んでるの?恐怖に震える慎治たちをチラリと見た怜が説明する。「お父さん方も、ここ聖華が古くからの女子高だということはご存知ですね?今でこそ、そんな習慣は全く廃れましたが戦前のここではイギリスのパブリックスクール式で、躾の名のもとに相当な体罰が恒常的に行われていたんですよ。今でも地下に、そういうお仕置き部屋が残っています。そう・・・慎治君たちを更生させるために、体罰を認めて欲しいのです。」げっげえええええっ!!!思わず仰け反る慎治たちにチラリと冷たい視線を投げかけた舞は、次の瞬間、慎治たちの両親に如何にも困ったような、何とも言えない慈悲と誠実さを溢れ出させたような微笑を投げかけた。「体罰をさせて下さいなんて、酷いお願いをしている、と言うこと位は私たち自身、よく分かっています。だけど・・・これが私たちの限界なんですよ。徳の高い高僧ならば言葉の力だけで慎治君たちを更生させることもできるかも知れません。だけど、申し訳ないんですが私たちにはそれ程の力はありません。だから・・・だから普通の指導も勿論全力を尽くしますが、体罰を併用する位しか考えつけないんですよ。」如何にも誠意に満ち溢れた舞の言葉に、慎治たちの両親は躊躇せずに飛びついてきた。「も、も、勿論です!勿論構いません!な、なあ矢作さん、当然、当然お願いするしかないですよね!」「と、当然です!体罰程度で慎治を見捨てないでご指導頂けるなら、幾らでもぶん殴ってやってください!骨が折れようが片輪になろうが構いません!遠慮なく、遠慮なくビシビシやってください、お願いします!」そ、そんな、そんなあああああっっっ!体罰を了承する、それが何を意味するか、流石に鈍い慎治たちにも直ぐに分かった。どんな傷がつこうと、痣だらけ、蚯蚓腫れだらけにされても体罰の一言で全て片付けられる。苛めの免罪符、何をやってもどう苛めてもいい、というフリーパスを怜と舞に、そして礼子たちに与えるようなものだった。「ああ、そんな酷い・・・」「父さん・・・助けて・・・」だが帰ってきた返事は罵倒だけだった。「馬鹿者!お前はもう黙っていろ!」「二度とそんなふざけた口を叩けないように、根本から叩き直して貰ってこい!」闇、更に深い地獄への口が慎治たちの足元に広がっていた。
6?
屈辱と口惜しさに満ち満ちた悪夢のような保護者面談が終わり、慎治たちの両親が帰っていった後、校長室は奇妙な静寂が支配していた。その静寂に耐えかねたかのように、若月がおずおずと口を開いた。「あの・・・体罰もありで指導、となったんですが、どう・・・やりましょうか?」体罰のなくなった教育を受けた世代である若月にとって、体罰といってもどういうものか想像もつかない。精々がビンタ程度のものだ。だが怜と舞が考えているのはそんなレベルではない。怜が凄絶な冷笑を浮べながら答えた。「心配しなくてもいいですわ、若月先生。どういう罰を加えるかは私と舞とで考えて、後でご連絡しますから。基本的には体罰の執行も私たちがやるつもりです。秋月先生もそれでよろしいですよね?」流石に秋月は薄々と舞台裏に勘付いたかのようだったが、敢えて慎治たちを庇う義理など何もない。それに校長職は激務、正直言って余計な面倒事は背負い込みたくない。「ええ、お二人にお任せできるのであれば、私としても助かります。」ある意味で大人の秋月はそれっきり、慎治たちのことを脳裏から消し去ってしまうことにした。もし復活するとすれば、また何か問題が発した時だけだ。「ではお言葉に甘えて、この二人の処分については理事会にお任せしましょうか。若月先生も異論ないですな?」秋月の言葉に未だ事情を飲み込めないまま若月が頷くのを見ると、怜は早速切り出した。「ありがとうございます。では矢作君、川内君、部屋を変えるわよ、ついていらっしゃい。」二人が慎治たちに礼子、陽子、玲子、有希子の6人を連れて出た後、疑問を抑え切れない若月は秋月に尋ねた。「・・・校長先生、これでいいのでしょうか・・・私は何かしなくても・・・」えっ、未だ分かっていないのか君は、と呆れたように秋月は振り返った。「うん・・・君はもういい、このことは忘れたまえ。これは理事マターだからね、君がタッチする必要はない。必要ない事、関わりあう必要がない事には・・・首を突っ込まない方が身のためだよ。」
一方、六人を引き連れて廊下に出た舞は陽子と有希子に声を掛けた。「ご苦労様。二人ともいい出来だったわよ。じゃあ後は私たちでやっておくから、教室に戻っていいわよ。」「ハイ先生、じゃあ後はお願いします!」明るく言いながら陽子は憎々しげに慎治を睨みつけた。「思い知った、慎治?後は・・・ゆっくりと礼子や怜先生に苛めて貰うのね、ペッ!」思いっきり唾を吐き掛けた陽子の隣で有希子も勝利の笑顔を浮かべていた。「ざまあみろ!てところよね、信次。もうあんたの人生滅茶苦茶よね、当然の報いでしょう?いい気味よ!ペッ!」心底楽しそうに、復讐成就の快感に酔いしれながら有希子も思いっきり唾を吐き掛けると、二人は意気揚々と去って行った。クラスメートの唾を頬に滴らせながら呆然としている慎治たちに、怜の凛とした声が響いた。「何ぼうっとしているの!さっさと来なさい、愚図愚図していると罰を追加するわよ!」恐怖にもつれる足を半ば絡ませながら慎治たちは必死でついていった。怜と舞が降りて行ったのは慎治たちにとって恐怖と屈辱に満ちた、視聴覚室へと通じる階段だった。「あ、もしかしてお仕置き部屋って・・・」閃いたように言った礼子に怜が答えた。「流石は天城さんね、その通りよ。お仕置き部屋って言ったら完全防音じゃないといけないでしょう?昔の技術じゃ完全防音の部屋なんて地下に作るしかなかったんでしょうね。」視聴覚室の横、何のためにあるか誰も知らずにいたドアの前に着くと、舞がポケットから鍵を取り出した。ガチャッと音を立てて開いたドアのすぐ奥には、更に下へと降りる階段があった。生まれて初めて本物の鞭で打ち据えられた視聴覚室、ココタマにまで苛められ屈辱に咽び泣いた視聴覚室、慎治たちにとっては悪夢のような部屋だ。だがお仕置き部屋はその視聴覚室の更に下にある。その階段は地獄の奥底へと続いているかのようだった。降りきったところにもう一つドアがあった。そのドアを舞が開け、壁際のスイッチを入れた。天井に設置された蛍光灯に照らし出された部屋は意外なほど広かった。見たところ視聴覚室とほぼ同じくらいの広さだ。入ってすぐに広いスペースがあり、奥は二つの小部屋への入り口となっていた。長年使われていないため厚く埃をかぶった部屋のよどんだ空気に顔をしかめた怜が換気扇のスイッチを入れた。広い室内にはあちこちに何台もの器具、見慣れない器具が置いてあった。そのうちの一台、木馬のように足を伸ばし、その上に跳び箱の背のような台が乗り何本かの皮ベルトが伸びた器具の前で怜が立ち止まった。「フフフ、二人とも聖華学園自慢のお仕置き部屋へようこそ。これからあなた達がたっぷりと、長い時間を過ごすことになる部屋よ。遠慮なく寛いでいいわよ。」陰惨な雰囲気、映画の中でしか見たことのない拷問部屋のような雰囲気に慎治たちは恐怖に全身が凍りつきそうだ。「ウフフフフ、怖いの?そんなに震えちゃって。まあ当然でしょうね、このお仕置き部屋、昔は一体どれだけの数の生徒たちの悲鳴を聞いていたことかしらね。その子たちの恐怖、悲鳴、苦痛、後悔・・・フフフ、部屋中にたっぷりと浸み込んでいるみたいじゃない?今日からはあなたたちの悲鳴をたっぷりと浸み込ませてあげるわ。男の子の悲鳴は初めてだからね、この部屋もさぞ喜ぶでしょうね。」怜が凄惨な冷笑を浮かべながら言い放った。震え上がる慎治たちの肩に手を回した舞が、奥の小部屋、ベッドのような奇妙な台、を置いた小部屋に二人を連れて行く。古びた責め具が多いこの部屋でその台だけが妙に新しい。「フフフ、何で小部屋があるか分かる?元々は女子高だからね、お仕置きのメニューで浣腸もあったのよ。幾らお仕置きとはいっても何人も纏めてお仕置きする時に、お互いのお尻やうんちを見るのもお下品でしょう?だから小部屋も用意してあるわけ。ウフフ、でもね、小部屋に一人ずつ入れられてお仕置きされていると、隣の部屋からも悲鳴が聞こえてきてとても盛り上がったそうよ。」
大部屋に戻ると怜がスッと傍らの器具を撫でた。「ここにある道具は基本的に拘束具よ。例えばこれは、君たちを背中に四つんばい状態に寝かせて固定し、お尻を鞭打つための台ね。」、とジャラッと舞が天井から下りた鎖に取り付けられた皮ベルト付の横棒を手にした。「これも拘束具よ。天井から降りたバーに君たちの手を固定して、ここにある足枷で両足も固定するわけよ。そのまま鞭を加えてもいいし、反省するまで立たせたままにしておくこともできるわね。」ああ、あああ・・・慎治たちは恐怖のため膝がガクガクとし、全身がブルブルと激しく震えていた。「せ、先生・・・そんな・・・許して・・・」「こ、こんな・・・ひどすぎます・・・」涙と鼻水を垂れ流しながら、二人は泣きながら土下座して哀願した。体育館、廃グラウンド、視聴覚室・・・いずれとも違う本格的な拷問室の陰惨な雰囲気は二人の精神を何もせずとも既にズタズタに踏み躙っていた。美女二人に美少女二人、そして土下座して泣いている無力な男が二人。責める側、責められる側がこの上なく明確に分かれていた。「フフフ、もう無理よ矢作君、さっきのお父さんたちの言葉を聞いたでしょう?」ゴリッと高級な黒いパンプスを履いた脚で怜は慎治の頭を踏みつけた。「もうあなたたちは両親にも見捨てられたのよ。どんな体罰を加えても構わないってね。しっかりお墨付きは頂いたわ、遠慮はしない、たっぷりと指導してあげるわね。」ガリッと舞のヒールも信次の後頭部に食い込んだ。「さあてと、あなたたちの泣き言に付き合っている暇はないから、取り敢えずやることを命令しておくわね。」怜がクイッとパンプスの爪先で慎治の顎を小突き上げた。「この部屋はずっと使っていなかったから大分汚れてるでしょう?お仕置きも清潔な環境でやりたいからね、綺麗に掃除しておいて頂戴。今日はもう授業に出なくていいから、あそこの隅においてある掃除用具を使って綺麗に掃除しておきなさい。」そ、掃除!自分たちが痛めつけられる場所を自分たちで掃除!ひ、酷い・・・だが何も言えなかった。信次の頬を爪先で軽く突きながら舞が冷笑した。「放課後にくるわね、その時にチェックして未だ汚れていたら、フフフ分かるわね、体罰を増やすわよ?」体罰を増やす!その一言は慎治たちを震え上がらせるのに十分だった。「さあ、じゃあ私たちは行きましょうか、仕事もあるし授業もあるし、何より綺麗になってからじゃないと苛める気にもならないわよね!」アハハハハッと楽しげに笑いながら、四人は階段を上がりお仕置き部屋から出て行った。後には・・・嫌々ながらものそのそと掃除にとりかかる慎治たちだけが取り残されていた。
そして三時過ぎ、必死で働き続けた慎治たちが漸く掃除を終えたころに一行が戻ってきた。今度は怜と舞、礼子たちの他に富美代と朝子も一緒だった。「フーン、ここがお仕置き部屋なんだあ?」のんびりした声で朝子が面白そうに部屋の中を見て回る。「いつもの視聴覚室の地下にこんな部屋があるとはね・・・知らなかったわ。」いつもクールな富美代も流石に驚いた様子だった。お仕置き部屋を初めて見る富美代と朝子は部屋自体に興味を奪われていたが、礼子たちは怜と舞の服装に目を奪われていた。午前中と違う服だが別に突飛な服を着ているわけではない。アルマーニの濃紺のスーツの上下にインナーは純白のブラウスと見るからに知的なキャリアウーマンファッション、悪く言えばある種、キャリアウーマン用の制服に近いフアッションだ。違うといえば足元をパンプスから漆黒のジョルダンのロングブーツに履き替えているのが若干違和感といえば違和感だが、一人一人で見れば全くおかしなところはない、むしろ長身でスタイル抜群、内面から知性か溢れ出ている二人にとってはある意味、最も着慣れたよく似合うフアッションだ。違和感があるのは二人、怜と舞が全く同じ服装、かつヘアスタイルもメイクも完全に同じにし、殆ど全く見分けが付かないようにしていることだった。興味津々、と言う目で見ていた礼子が遂に口を開いた。「・・・しかし怜先生と舞先生、一卵性というだけあって本当に似てますね。普段は服とかメイクとかを分けてるから分かりますけど、そうやって完璧に同じにすると、殆ど区別つきませんね。」玲子も、私もそれ聞きたかったんだ、と言うように頷いた。「そうですよね、先生・・・でも午前は別の着ていらしたし、何故ですか?先生たちが無意味にそんな事するとは思えないし、何か楽しい企みがあるんじゃないですか?教えてくださいよ!?」あけすけに尋ねる玲子に苦笑しつつ舞が答えた。「全く霧島さんは勘がいいんだから・・・苛めっ子の直感、というやつかしら?確かにこうやって私と怜が完全同じ服着てるのは、後のお仕置きで楽しい趣向を用意してあるからよ。」クックックッと怜も楽しそうに笑った。「まあブーツは少し悪乗り、あなたたちが矢作君たちを本気で苛める時はブーツを履くことが多い、て聞いたからね、この二人にはブーツがとても怖いんじゃないかな、て思って用意したのよ。ウフフフフ、でもスーツとメイクの方は折角双子なんだからね、それを責めにも活かしたいでしょう?フフフ、ご指摘の通り、楽しい趣向を用意してあるわよ!」もう!先生ったらー!慎治たちを除く全員が一頻り笑ったところで礼子が口を開いた。「じゃあ先生・・・心残りもありますけど、今日は部活もあるし私たち、これで失礼します!じゃあね慎治、しっかりお仕置きして貰うのよ!」えっ、まさか今日は怜先生たちと一対一で苛められるの?予想外の展開に戸惑う慎治たちを見て玲子がクスクスと笑った。
「アハハハハッ!信次、あんた今日は私たちも入って集団リンチされると思ったんでしょう?ブーー、残念でした。今日は舞先生たちにゆーっくりと、お仕置きしてもらいなさい!ウフフフフフ、きっと楽しいわよお?あ、そうだ、行く前に一つね、いいことを教えてあげる。」「い、いいこと?な、なんなの!?」甲高い声を上げる信次を嘲笑いながら玲子が答えた。「金曜のことよ。あの時、信次たちは陽子と有希子のおしっこ飲まされて逆ギレしたでしょう?だけどね、本当は私たち、公衆便所の刑は金曜で、あの日一杯で終わりにしてあげようね、て言ってたのよ。」「えっえええっ!そ、そんなあああ・・・」玲子の言葉に思わず絶句する信次に冷笑を浴びせながら礼子も続けた。「玲子の言ったことは本当よ。取り敢えず全員飲ませ終わったみたいだから、じゃあもう許してやろうか、て言ってたのよ。ううん、もっといいこと教えてあげるわ。あの日、トイレの予約はもう、陽子と有希子までしか入っていなかったのよ。ウフフフフ、分かる、私の言ってること?要するにね、陽子たちのおしっこさえ我慢して大人しく飲んでいれば、慎治たちは助かっていたのよ!」「あああ、あああああ・・・そんな・・・馬鹿な・・・う、嘘だ嘘だあああっっっ!うっうううっ、嘘だと・・・嘘だと言ってよおおおっ!おね・・・がいいいいっ!」慎治は思わず大声で泣き出してしまった。な、なんていうことだ・・・後一人だったなんて・・・後一人、後一人のおしっこさえ飲んでいれば助かっただなんて!!!「ひ、ひどい・・・なんで今更そんなことをいうんだよおおおおおっ!せめて・・・せめてそんなこと、聞きたくなかったよおおおおおっ!!!」涙をボロボロ零しながら絶叫する信次の無様な姿を、玲子は心底楽しそうに嘲笑っていた。「アハハハハハッ!アーッハッハッハッ!どう信次、悔しい?後悔先に立たず、とはよく言ったものでしょう?でもだーめ、もう遅いのよ!信次は破滅しちゃったの!たーっぷりと、惨めな気分を味わいなさい!自分の馬鹿さ加減を悔やみなさい!そしたら・・・舞先生のお仕置きも何倍にも辛くなるわよね!アハハハッ、アハハハハハッ!いい気味、まさに自業自得よね!」
1?
高笑いを響かせながら礼子たちが立ち去った後も、慎治たちは暫くの間泣き続けていた。余りの絶望、坊野たちの件といい陽子たちの件といい、自分たちの全ての選択、全ての行動が悉く裏目、それも最悪の目を出し続けていることに。そしてその裏目の連続は慎治たちをのっぴきならぬ状況に追い込んでいた。苦痛と屈辱だけではない、未来までも全て奪い尽くされようとしていた。単純な苛めだけではない、学校、家庭・・・全てが慎治たちを拒絶し、苦しめ辱める側へとはっきりと回っていた。そして今、床に突っ伏して泣いている慎治たちを冷笑しながら見下ろしているのは怜と舞、女教師を遥かに超えた学園理事の二人だった。ありとあらゆる権力を駆使して慎治たちを罰せられる二人、そして部活で礼子たちと互角に渡り合える力を発揮する二人は腕力の面でも慎治たちを遥かに凌駕している。だから女性二人に男子生徒二人、ということによると危険なシチュエーションにも関わらず二人は余裕綽々だった。最も精神を殆どボロボロになるまで破壊されつくした慎治たちに、反抗の元気などあるわけもないが。「さてと、天城さんたちも行ったことだし、そろそろ体罰を始めるわね。」怜の無慈悲な宣告に合わせるように舞が入り口近くに置いてあった細長い袋から二本の棒状の物を取り出した。ヒッ、乗馬鞭!玲子たちも大好きな乗馬鞭を直感的に想像した信次の口から悲鳴が漏れる。「ウフフフフッ、残念、外れよ。これは乗馬鞭じゃないわ。よく見てご覧なさい。」舞が信次の目の前に手にした拷問具を差し出す。それは長さ1メートル程度の細い木製の棒だった。太さは1センチ程度であろうか、先端にかけてやや細くなっているようだが太さはほぼ均一、そして根元に黒いグリップが嵌められていた。「CANEていうのよ、日本では樺鞭ともいうわね。鞭というより笞と言った方がいいかも知れないわ。」一本を舞から受け取った怜がスナップを効かせて軽く振った。ヒュンッ!金属質ともいいたくなる、凶悪な風切り音がした。ヒッ!思わず悲鳴を漏らす慎治、その怯えを見た怜の美貌に残酷な笑みが浮かんだ。「フフフどう、痛そうでしょう?あなたたちは毎週のように天城さんたちに革鞭で打たれている、ていうからね、違う種類の鞭を用意してあげたのよ。ウフフフフッ、こっちの鞭も・・・痛いわよお?」ギュッギュッと怜は二、三回、鞭を撓らせる。ガタガタ震える信次の頬に舞が手にした鞭を近づける。「ヒイイイッ!や、やめて!」悲鳴をあげる信次を舞は笑い飛ばした。「アハハハハッ!大丈夫よ、何もしやしないわよ。ほら手をどけなさい!」恐怖に怯えながら手を下ろした信次の頬に舞は鞭の先端を押し当て、グッと力を込めた。舞の手と信次の頬の間で鞭がギュッギュッと撓る。「どう?この撓り具合は?あなたたち、乗馬鞭でも鞭打たれたことはあったわよね?でも乗馬鞭よりも大分硬い感じじゃないかしら?」
その通りだった。それは鞭と棒との中間、乗馬鞭がより鞭に近い存在とするならば、怜と舞が手にしている樺鞭はより棒に近い、細身の棍棒とも思えた。「さあ、お仕置きの始まりは・・・まず鞭よ、二人ともさっさと服を脱いで、この台に両足と左手を固定しなさい。右手は私たちが縛ってあげるから!」ピッと怜は大部屋の中心に置かれた、木馬型の拘束台を鞭で指し示した。「あっ・・・いやっ、そんな!!!」「せ、先生・・・許して・・・ヒッ!」涙を流しながら哀願する二人の眼前を舞の鞭がヒュオッと鋭い音を立てて切り裂いた。「霧島さんたちに教えてもらっているでしょう?余計な事を言わないでさっさと言われた通りにしなさい!それとも・・・腕ずくでその台に縛り付けて欲しいの?動けなくなるほど痛めつけられてから?別にそうしてあげてもいいのよ?何の苦労もいらない話だからね。」動けなくなるほど痛めつける!玲子たちと五分に渡り合える強さを部活で見せ付けられている信次たちだ、怜と舞がその気になれば一瞬で叩きのめされてしまうこと位は流石に分かる。ああ・・・あああ・・・い、嫌だ・・・蹴り倒されたくない、投げ飛ばされたくない・・・魂を抜かれたかのようにガタガタと全身を震わせ、顔面蒼白になりながらのろのろと二人は服を脱ぎ始めた。「ホラ、何愚図愚図しているの!さっさとしなさい!」ヒュンッ!ヒイッ!「・・・ったくとろいわねえ・・・鞭がないと動けないの!?」ヒュオッ!アヒイイッ!鞭音に追われながら慎治たちは服を脱ぎ捨てて一糸纏わぬ無防備な裸になり、そして拘束台に我と我が身を縛り付けた。木馬型の拘束台の背中を抱え込み、その脚に自らの足首をがっちりと固定してしまった。最後に残った右手を台から生える革ベルトに拘束されると、身動き一つできない。平行に並べられた拘束台、そして慎治の横には怜が、信次の横には舞が鞭を手に寄り添っている。拘束台を抱え込み、尻を突き出した慎治たち、背中と尻を無防備に曝け出した二人と高級なスーツとブーツに身を固めた怜と舞。鞭を手にした美女と全裸で縛り付けられた無力な男。いつもながらの余りに対照的、余りに屈辱的なシチュエーションだ。「フフフ、何なのよこのザマは。裸になりなさい、台に自分を縛り付けなさい、なんて理不尽な命令にも反論一つ出来ない意気地なしなのね、君たちは。そうそう、天城さんたちにいつも唾を吐き掛けられているんだったわね、今日は私たちが吐き掛けてあげるわよ、ペッ!」怜が真紅のルージュを纏った唇を軽蔑に歪めながら嘲笑い、唾を吐き掛けた。「本当に役立たずのクズよね。そんなクズの分際でよくもまあ、私たちの手を煩わせてくれたわね・・・まあいいわ、君たちにはいくら説教してあげても無駄でしょうからね、体に分からせてあげるわよ。先ずは霧島さんたち同じく、私も君たちのことを軽蔑しきっているんだ、ていうことを分からせてあげるわ。この唾でね!ペッ!」ギュウウッ、鞭を尻に食い込むほど押し付けながら舞が非情な宣告をし、同時に処刑開始の唾を吐き掛ける。頷きあった怜と舞が鞭をスッと慎治たちの尻から離し、ゆっくりとテイクバックしていく。「ああ、あああ先生・・・」「おねが、い・・・許して・・・」二人の哀願を掻き消すかのように、不気味な音が響いた。
ヒョオッ!ビシイイイッ!「ギッハアアアッ!」「ガッハアアアッ!」慎治たちの尻に樺鞭が食い込む。乗馬鞭より固い樺鞭は鞭のピリッとした軽質な、皮膚表面から筋肉組織の浅い部分に留まる痛みとは違い、強烈な衝撃を、体の内部へと貫くような激痛を刻み込む。思わず仰け反る慎治たち、だが拘束台に完全に固定されて身を捩ることさえままならない。一拍間合いを置き、二人の痛覚が第一波を過ぎ、鋭敏さを取り戻すのを見計らうかのように怜と舞は再び鞭を振り上げた。ビュオッ!バジイイイッ!「ガッギイイイッ!」「ゲヒイイイイッ!」再び鞭音と悲鳴がお仕置部屋に轟く。いい感触ね。古い本でイギリスのお仕置は読んだ事があったけど、その時はああ体罰がない時代で良かった、て思っただけだったけどね。自分が叩かれるのは真っ平だけど、こうやって罰を加える側なら大歓迎よ!怜の手に知らず知らずの内に力が入る。気持ちいいじゃない、これ。こんなに楽しいんじゃ、世界中で拷問が無くならない筈よね。法律で厳しく取り締まられない限り、こんな楽しい事を止められるわけないものね。ウフフ、でも今、君たちは法律の保護の外にいるのよ、だから・・・思う存分、打ち据えてあげるわ!舞の手にも力がこもっていく。ヒュンッ!バシィンッ!ヒギイイイイイッ!ヒュオッ!ピシイイイイッ!ギャアアアアアッ!怜と舞は双子らしく、息のあった鞭を打ち続ける。慎治の尻に炸裂した怜の鞭が慎治の悲鳴を迸らせる。その悲鳴が静まりかけた瞬間、舞の鞭が唸り信次を泣き叫ばせる。スナップを思いっきり利かせて打ち据えた次の瞬間、反動と鞭自身の撓りを利用して素早く振り上げられた鞭はそのまま中で二、三回上下に振られて恐ろしげな音を立てながら慎治たちを脅しつける。そんなに強く打っているわけではない、だが慎治たちは耐え難いほどの、礼子たちの鞭にも匹敵するほどの痛さに泣き叫んでいた。鞭の音と悲鳴がお仕置き部屋に間断なく木霊し続けた。10発ずつ打ったところで、二人は一旦鞭を休めて慎治たちの前に歩み寄った。「ウフフフフ、どう私たちの鞭は?少しは反省したかしら?」鞭の先端でうな垂れる慎治の顎を小突き上げながら怜が尋ねた。「あううう・・・先生・・・もう・・・許して・・・」傍らで舞に嬲るかのように、軽く頬を叩かれていた信次も必死で哀願した。「せ、せんせい・・・おねがい・・・はんせい、反省しましたから・・・もう許して・・・ください・・・」「そう、反省したの。それは偉いわね、反省することは大事よ。だけどね、この程度じゃまだまだ、お仕置きは足りないわ。」「そ、そんなあああああっ!アウッ!」「い、いやあああああっ!ヒッ!」二人の悲鳴を怜と舞の鞭が掻き消す。
「ウフフフフ、舞の鞭は堪能したでしょう?今度は私の鞭を味あわせてあげるわ。」「そうよ、今度は私の鞭を矢作君に味合わせてあげるわね。川内君は怜の鞭を味わいなさい。」あああ!そ、そんな!二人の必死の哀願を嘲笑いながら怜と舞は立ち位置を交換し、ヒールの乾いた音を響かせながら今度は舞が慎治の、怜が信次の傍らに立つ。「さあ行くわよ・・・ペッ!それっ!」「お仕置き再開よ・・・ペッ!ハッ!」再び唾を吐き掛けたのを合図にビュオッバシイイインッと地下室に再び鞭音と慎治たちの悲鳴が木霊する。再び10発ずつ鞭打ったところで二人は鞭打つ手を休め、今度は慎治たちの前方に並んで立った。ウフフフフ、思いっきり涙流しちゃって。そりゃそうよね、これだけ鞭打ったんだもの、痛いでしょうねえ。それに・・・ウフフ、こんなところで拘束台に縛り付けられて、惨めよねえ。すすり泣く慎治たちを満足げに見下ろす怜に、二人の尻を見てきた舞が言った。「フフフ、怜、二人のお尻を見てご覧よ。中々いい色になってるわよ。」「いい色?見せて見せて!」後ろに回った怜は思わず歓声をあげた。「ワアッ!本当じゃない、いい色!矢作君も見てご覧なさいよ、自分のお尻。いい色になってるわよ!」い、いい色!?まだジンジンと全く引かない痛みにうめき続ける慎治の顔が微かに上がる。「アハハッ、怜ったら!縛り付けているんだもの、見えるわけがないじゃない!二人とも、自分のお尻がどうなっているかは後のお楽しみにとっておきなさいね・・・でもまあ可哀想だから、お互いのお尻を見せてあげる。二人とも似たり寄ったりだからね、自分のお尻もこうなっている、と思えばいいわよ。」舞は拘束台を交互に回転させ、交互にお知りを見させてやった。見せ付けられた相手の尻に、慎治たちは思わず息を呑んだ。「ひ、ひどい・・・」「あんまりだ・・・」二人の尻は酷い内出血に腫れ上がっていた。未だ白い箇所も多いが近いが見ている間にも尻のあちこちが急速に赤く腫れ上がり始めていた。鞭が直撃した所を中心に、交点、鞭跡、そして鞭跡の狭間と微妙なグラデーションがついていた。
ウフフフフ・・・そろそろ逝っちゃおうか・・・すすり泣き続ける慎治たちの頭上で、怜と舞は熱にうなされたような視線を交わしていた。久しぶりね、この感覚。そうね、折角貴重な時間を割いていることだし、思いっきり逝ってみようか?二人のクールな美貌に凄絶な冷笑が浮かんだ。グッと鞭を握る手にも力がこもってくる。「さあ、お尻の鑑賞会は終わり、お仕置き再開よ。」怜が慎治の拘束台を戻す。「ヒイイイイッ!そ、そんなあああああっ!ゆ、ゆるしてえええええっ!」ガタッと舞も信次の拘束台を回転させる。「い、いや、いやだあああああっ!もう、もう十分でしょ、お願い、許してえええええっ!」「煩いわね!未だ軽くしか叩いていないんだから、本当のお仕置きはこれからに決まってるでしょう!?」ほ、本当のお仕置き・・・い、いったい何を・・・聞きたい、だが余りの恐ろしさにそれを聞くことすらできない。思わず黙ってしまった慎治の頬を鞭でグリグリと小突きながら怜が微笑んだ。「本当のお仕置きがどんなものか知りたい?いいわよ、教えてあげる。だけどその前に、私の質問にも答えてね。矢作君は今、私と舞の両方に鞭打たれた訳だけど、どっちの鞭が痛かった?」ピシャピシャと信次の頬を軽く打ちながら舞も信次に尋ねた。「そう、私もそれを聞きたいのよ。怜の鞭と私の鞭、どっちが効いたの?怒らないから正直に答えてご覧なさい?」えっそ、そんな・・・思わず慎治たちは答えに詰まってしまった。どっちの鞭も死ぬほど痛かった。だけど・・・どっち、なんて言ったら、もう一人に鞭打たれるんじゃないだろうか・・・いや、それとも先生たちの事だから、痛い、て言った方に鞭打たれるんじゃ・・・答えに詰まったまま黙ってしまった慎治の尻を怜が鋭く打ち据えた。ピシインッ!ヒイッ!「聞こえなかったの、それとも答えたくない、ていう意思表示なのかしら?」慎治の悲鳴に身をすくめた信次の頬から舞が鞭を離した。「川内君も素直に答える気はないみたいね。こうやれば答える気になるかしら?」ビシイッ!アウッ!信次の尻にも激痛が走る。「答えるまで鞭で打ってあげようかしら?」怜が鞭を撓らせながら宣告する。ヒイッ、答えるまで鞭打つなんて!慎治は必死で叫んだ。「れ、怜先生の方が!!!痛いですううううっ!」ほぼ同時に信次も絶叫する。「ま、ま、舞先生の鞭の方が・・・痛いいいいっ!」ニヤリと残酷な微笑を浮かべながら二人の美女は鞭を撓らせビーンと弾いた。「そう矢作君、怜の方が痛いのね、私の鞭はまだまだ温いというわけね。」「川内君、よく言ったわね、舞の鞭より私の方が痛くない、甘い、て言うのね君は。」ヒッヒイイイッ!そ、そんなあああっ!「いいわよ矢作君、私の鞭が温い、て言うのならもう手加減してあげない。本当に痛い鞭の打ち方でお仕置きしてあげるわよ。覚悟しなさい!ペッ!」「川内君、少し優しくしてあげたら図に乗るのね、君は。どうやら本気で鞭打ってあげなくちゃ反省できないようね。このクズが!ペッ!」慎治の傍らには舞が、信次の傍らには怜が立ち鞭を高々と構えて処刑の唾を吐き掛けた。
ビュオッ!ヒュオッ!バシイイインッ!ビシイイイイッ!「ギャッヒイイイイイッ!!」「ウギャアアアアッ!!」一段と凄まじい音を立てて鞭が炸裂した瞬間、慎治たちの尻に信じられないほどの激痛が走った。皮膚を肉を貫き骨にまで達するかのような衝撃、いや尻から背骨を直通して脳天直撃、と言いたくなるほどの激痛だった。「ウフフ、どう矢作君、本物の鞭打ちの味は?お望みどおり手加減なしの鞭を味あわせてあげるわね、それっ!」「川内君、どうかしら?私の本気の鞭はお気に召した?たっぷりと味わいなさいね、それっ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ギャッ、ギャアアアアッ!ウギイイイッ!ガウウッ!ハヒイイイイッ!ガハアアアアッ!凄まじい音と悲鳴が地下室に響き渡る。痛いのも当然だ、怜と舞は十分に腰を入れスナップを利かせた鞭が炸裂した瞬間、グッとリストを返し捻るようにして反動を押さえ込み、慎治たちの尻に鞭を食い込ませたまま静止させていた。堅い鞭は二人の尻の肉に食い込み、めり込むようにして止まりその衝撃の全てを慎治たちの体内へと送り込んでいた。先程までのように鞭を直ぐに、反動とともに跳ね上げてくれれば少しは威力を逃がせるが食い込ませ、静止されればそんなことは到底不可能、怜と舞の凄絶な鞭の威力を全て我が身で味あわなければならないのだ。とめどもなく絶叫し続ける二人に10発ずつ鞭を見舞った怜と舞は一旦鞭を休め、二人の前に戻る。
「ウフフフフ、どう矢作君、これでもまだ、私の鞭の方が痛くない?」「フフフ、川内君、もう一度聞くわね、どっちの鞭が痛いの?」「あああ・・・舞先生の方が・・・痛いです・・・」「ううう・・・怜先生が・・・痛い・・・です・・・」かかったわね、おバカさんたち。「あら矢作君、舞の方が痛いですって?私の鞭の痛さを忘れちゃったみたいね、思い出させてあげる。舞、チェンジよ。」「怜の方が痛いですって?川内君、さっき私の方が痛い、て言ったばかりじゃない。また嘘をつくのね君は。いいわ怜、チェンジよ。」すっと交代して今度は怜が慎治の、舞が信次の横に来る。「さあ逝くわよ・・・ペッ!ハイッ!」「この嘘つきが・・・ペッ!ホラッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・凄まじい音と悲鳴が再び地下室に響き渡る。アヒイイイイッ!イヤッイタイイイイッ!ヤ、ヤベデ!ユルジデエエエエエッッッ!慎治たちの哀願を一切無視して更に10発ずつ鞭打った怜と舞は再び、二人の前に立ちはだかる。「さあもう一度聞くわね矢作君、どっちの鞭が痛かった?」「さあ川内君、素直に答えてご覧なさい、私の鞭と怜の鞭、どっちが痛いの?」ひ、ひどい・・・あんまりだ・・・怜先生の鞭も・・・舞先生の鞭も・・・死ぬほど・・・痛い・・・「あああ、うえええ・・・ど、どっちも・・・同じ位・・・痛いです・・・」「二人とも痛すぎますううう・・・どっちも・・・痛すぎますううう・・・」フンッやっぱりそう来たわね。全く、少しは予想を外して欲しいものよね。「同じ位?そんなの答えにならないわね、どっちが痛いのか、はっきり分かるようにもう一回鞭打ってあげましょうね。逝くわよ!ペッ!」「どっちも痛すぎる?要するにどっちが痛いか、未だ分からないのね、じゃあはっきり分かるまで鞭打ってあげるわ!ペッ!」「そ、そんなそんなそんなあああああっ!キャアアアッ!」「ややややめてよしてゆるしてえええええっ!ヒイイイッ!」哀願すら出来ないうちに二人に唾が吐き掛けられ、怜と舞は再び鞭を振るい始めた。お尻が、お尻があああああっ!痛いいいいっ、さ、裂けちゃううううううっ!絶叫する二人を情け容赦なく更に10発打ち据えた怜と舞は再び二人の前に立ちはだかる。「さあもう一回聞くわね。私と舞の鞭、どっちが痛い?」「もうはっきり分かったでしょう?じゃあ教えて頂戴、私と怜の鞭、どちらが痛いの?」怜といえば舞、舞と言えば怜に鞭打たれる。だけど分からないとも・・・答えに窮した慎治たちは思わず黙り込んでしまった。バーカ、もうちょっと頭を使いなさいよ、だんまりが私たちに通用するわけないでしょう?「そう矢作君、答えたくない、て言うわけね。随分と挑発的な態度じゃない?当然、鞭よ!ペッ!」「そう、よく分かったわ。お前なんかの質問には答えてやらないぞ、ていう意思表示ね。いいわ川内君、そのだんまりがどこまで続けられるか、この鞭で試してあげる!ペッ!」「い、いやああああっ!やめでえええええっっっ!ヒギャアアアッ!」「ちちち、ちがうちがうちがいますうううううっ!アウウッ!」慌てて絶叫する二人に委細構わず怜と舞は無慈悲に鞭打ちを再開する。今度もきっちり10発ずつ打ち据えたスーツを纏った女神がまた二人の前に舞い降りる。
「ウフフフフ、ちゃんと答えないと矢作君のお尻、ズタズタになっちゃうわよ?はっきり答えなさい、私と舞の鞭、どっちが痛いの?」「アハハハハッ!随分といい声で泣いたわね。どうやらだんまりは無理だ、て分かったみたいじゃない?じゃあもう一度聞くわね、怜と私、どっちの鞭が痛いの?」慎治たちは答えられなかった。怜と舞は尻だけを集中して鞭打っていた。威力十分の鞭を尻に集中して炸裂させた集中破壊力は慎治たちの尻をとっくに内出血で真っ赤、いや赤を通り越して赤紫青紫、場所によってはどす黒いほどの凄まじい痣で覆い尽くしていた。そして体内部からの圧力と外から加えられる鞭の衝撃に耐え切れなくなった皮膚があちこちで破れ始め、慎治たちの尻から腿にかけて幾筋もの血の帯が滴り落ちていた。鞭で流血させられたことは何度もある。だが礼子たちの鞭が引き鞭で切り裂くようにして出血させたのと違い、怜と舞の鞭は皮膚を叩き破る、と言った感覚だった。痛い、兎に角痛い。皮膚、尻の肉を通り越して骨にまで達するほどの激痛に身を震わせながら慎治たちは半ばパニック状態に陥りつつあった。痛いいたいイタイ・・・激痛以外何も感じられない。怜と舞の質問に答える余力すら無くなっていた。「お・・ねが・い・・・もう・・ゆ、るし・て・・・」「あああ・・・いたい・・・もうやめて・・・」消え入りそうな声で慎治たちは涙をボロボロこぼし泣きながら哀願した。二人の質問にも答えずに。そんな事を残酷な美神が許すわけがない。「答えになってないわね、分かったわ。矢作君は答える気がない、てことね。いい度胸じゃない、そんなに私には答えたくないって言うわけね。じゃあいいわ、好きなだけ鞭を味わいなさい!?ペッ!」「フウッ、川内君は心底バカなのね。ちゃんと答えないと鞭打たれる、て未だ分からないの?学習効果ゼロね。まあいいわ、答える気がないなら、いつまででも鞭打たれるがいいわ!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・唾を吐き掛けた怜と舞が腕を振り上げ、鞭打ちは直ちに再開された。
そして再度10発打ち終えた時、怜がアラッと声をあげた。「どうしたの?」「うん、この鞭見てよ、折れちゃったわ。丈夫な鞭だと思ったのにね、案外簡単に折れるものなのね。舞の鞭は大丈夫?」確かに怜の鞭は真ん中から二つに折れかけていた。「そう言えば私の鞭も、最後何か変な手応えだったな・・・あ、やっぱりそうだ、罅が入ってる!」怜も覗き込んで見た。舞の鞭はほぼ真ん中に10センチ近い罅が走っていた。もう二、三発も打てばへし折れてしまいそうだった。あああ、良かった・・・ラッキー、これでやっと終わったな、それにしても・・・痛かった、鞭が折れるなんて・・・酷い、折れるまで鞭打つなんて・・・慎治たちは思わず安堵の溜息を漏らし、がっくりと顔を拘束台に埋めていた。もう流石に終わりだよね・・・鞭は壊れたんだから、もうお仕置きできないよな、良かった・・・二人は全く気付いていなかった。自分たちが安心し喜んでいる姿を見下ろしている怜と舞が嘲笑っていることを。クスクスと笑い声を漏らしながら、本当にバカよねえ、と言った表情で慎治たちを見下ろしていることを。「フフフフフッ、矢作君も川内君も何を喜んでいるのかしら?ひょっとして私たちの鞭が壊れて良かった、ああこれでお仕置き終わりだ、なんて勘違いしているんじゃないでしょうね?」二人の拘束台の間に入り、怜は両手で慎治たちの髪の毛を掴みグイッと引き摺り上げた。涙で曇った二人の視線の先には舞がいた。「ウフフフフ、バカねえ君たちは!ここはお仕置き部屋よ、鞭の替え位、幾らでも用意してあるわよ。ホラッ!」手にした袋を舞が破ると、中には何本もの鞭が束ねられていた。アワワ、アワワワワ・・・そそそそそんなそんなそんな・・・恐怖に青ざめる慎治たちの表情を楽しみながら舞はスッと二本の新しい鞭を取り出し、二刀流よろしく左右の手に一本ずつ握って同時に空を切った。ヒュオッヒョオッ!「さあ、新しい鞭でお仕置き再開よ。質問を続けるわね。どっちの鞭が痛かった?」
どう答えたらいいの・・・怜先生と言っても、舞先生と言っても、どっちも痛いも答えないも全て通用しない、どう答えても全て鞭打ちで返される。じゃあせめてもの抵抗で答えない、それも不可能だった。連続で50発、100発と鞭打たれるなら感覚は殆どマヒ状態、それ故質問に対しても上の空でいられるが10発ずつと区切られては意識が飛んでくれない。意識が鮮明な状態では怜と舞の質問に答えないでいる勇気を持つことは到底不可能だ。慎治たちが半ばパニック状態に陥りつつあるのを見て怜と舞は残酷な目配せを交わした。そろそろ次のステップに行こうか。そうね、そろそろ頃合ね。慎治の尻に鞭を食い込ませつつ、怜が尋ねた。「どっちの鞭が痛いか、そんなに答えたくないなら質問を変えてあげましょうか?今度矢作君を鞭打つのは怜と舞のどちらかしら?」舞も同時に信次に尋ねる。「そう、君にはわかるかしら?私は怜?それとも舞?」えっえええっ・・・慎治たちは一瞬、考え込んでしまった。今僕を叩こうとしているのは怜先生・・・だよね?と慎治。た、多分・・・横にいるのは舞先生・・・だよね?と信次。「れ、怜先生・・・です」「舞先生・・・舞先生です・・・」「本当に?本当にそう思うの?じゃあこの鞭と唾で確かめてみるといいわ!それっ!ペッ!」「正解かどうか、顔と体で確かめなさい!それっ!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・再び鞭が唸る。ああああ、あわわわわ、お、怒ってる!!!ち、ちがったんだ、ちがったんだあああっっっ!!!きっちり10発ずつ鞭打つと、怜と舞は再び尋ねた。「さあ、私は怜?それとも舞?」「もう一度聞くわね、この鞭は怜の鞭?それとも舞の鞭?」反射的に慎治たちは答えた。「ま、舞先生・・です・・・」と慎治。信次もうめくように呟いた。「怜・・・先生です・・・」怜と舞の美しい横顔が残酷な笑みに歪む。「私が舞?これだけ鞭打たれてるのに、その程度の区別すらつかないのね君は!じゃあもう一度鞭をあげるから、しっかり学習しなさい!ペッ!」「失礼ね!私が怜だって!この鞭が怜の鞭だって言うのこの鞭が!えええっ?!この鞭とこの唾が私の、舞の鞭と唾よ!よく覚えておきなさい!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ヒギイイイイイッ!アヒイイイイイッ!10発を打ち終えた怜と舞が再び二人の前に戻る。「さあ今度こそ分かるわね、今の鞭は私?それとも舞の鞭?」「いくらおバカな川内君でもいいかげん分かったでしょう?私は舞?それとも怜?」ハヒッハヒッハヒッ、イウッククク・・・激痛にうめきながら慎治たちは必死で答えた。「れ、れい・・・先生です・・・」「舞、先生・・・です・・・」確かにそのとおり、慎治を鞭打ったのは怜、信次を鞭打ったのは舞だった。だが残酷な美女は冷笑とともに鞭を撓らせる。「今の鞭が怜?何言ってるの、今のは私、舞の鞭よ。」平然と言い放つ怜に合わせ、舞も頷く。「私が舞?失礼ね、私は怜よ!」「えええっっっ!そ、そんな馬鹿な・・・」「う、うそ、うそだああああっ!」弱々しく悲鳴をあげる二人を見下ろしながら怜と舞は冷酷に宣告する。「馬鹿?失礼ね、馬鹿とは何よ馬鹿とは!君ごときに馬鹿なんて言われる覚えはないわよ!当然鞭よ!ペッ!」「嘘?私が嘘をついたって言うの!?失礼にも程って言うものがあるでしょう?懲らしめてあげる、この鞭でね!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ヒギイイイイイッ!アヒイイイイイッ!そ、そんなそんなそんなあああ・・・慎治たちは絶望と恐怖と苦痛、そして屈辱に頭の中が真っ白になっていく。今のは確かに怜先生・・今のは絶対舞先生だよ・・・どう答えても答えなくても鞭打たれる恐怖、必ず答えさせられ必ず罰せられる絶望。余りに横暴な怜と舞、だが鞭を握り全知全能の二人は自由自在にルールを定め、後出しで勝手にルールを変更できる。縛り付けられ尻を無防備に曝け出した信次たちにできることなど何もない。只ひたすら横暴な女神の鞭に耐え忍ぶしかない。学習性無力感、という言葉を遥かに通りこした極限の絶望と屈辱が信次たちの精神をズタズタにし、意識を、現実認識を蝕んでいく。絶対、絶対間違ってない・・・ひどいよ今のは合ってるよ・・・だが目の前にいるのは同じ顔、同じ声、同じスタイルの二人だ。同じ服、同じブーツを身に纏い同じ鞭を握り締めている。そして鞭の痛さも唾の感触すら殆ど同じだ。ほとんど見分けもつかない二人、その姿が慎治たちの脆い精神を内部から蝕んでいく。だけど・・・だけど怜先生、後ろで代わっているんじゃ・・・まさか今、舞先生交代した???あああ、どっちなんだあああああ!何もかも分からなくなっていく、自我が崩壊していくようだった。世界がグニャアッと音を立てて歪んでいくようだ、単純に鞭打たれるだけより何倍も辛い、肉体と精神を同時に責め苛む怜と舞の責めに慎治たちはひたすら泣き叫び続けた。ああ早く気絶してしまいたい。だが10発ずつしか鞭打たれないのでは気絶することすらできない。ああお願い先生・・・いっそ、いっそ一思いに責め潰してえええっっっ・・・
そんな必死の願いを弄ぶかのように怜と舞はまた問いかける。「さあもう一度聞くわね。私は誰?怜?それとも舞?」「いい加減分かったわよね?今の鞭は舞?それとも怜?」半ば意識朦朧としながら慎治は答えた。さっきは怜先生・・・じゃなくて舞先生だったんだから・・・「怜・・・先生です・・・」涙にむせて一瞬、答えるのが遅れた信次は思わずあっ!と声を上げそうになった。そ、そうだ・・・慎治と同じ答えなら・・・もしかして大丈夫じゃ・・・50%は望みがありそう・・・どっちかは助かるはず・・・「怜先生・・・です・・・」チラッと怜と舞を盗み見た信次は思わず背筋に悪寒が走った。二人は確かに笑っていた。チッと舌打ちするでもなくやられた、という当惑を見せるでもなく馬鹿にしたような、完全に余裕綽々の冷笑を浮かべていたのだ。「私が怜?違うって教えてあげたばかりでしょう?この低脳!鞭でお仕置きよ!ペッ!」「怜先生?矢作君と同じ答えを言うなんて、人の答え真似するなんて、そんなズルが通用するとでも思っているの!?懲らしめてあげる、私の鞭でね!ペッ!」ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ヒギイイイイイッ!アヒイイイイイッ!そんな、そんなそんなあああああっ!ひ、ひどいひどいひどすぎるうううううっ!馬鹿ね、同じ答えを言えばどっちかは助かるなんて、そんな甘い考えが通用するとでも思っているの?全くよね、そんな簡単な手口を私たちが予想しないとでも思っていたのかしら、本当に馬鹿ね。怜と舞は満面に侮蔑の嘲笑を浮かべながら鞭を振るった。
あああ、あああああ・・・ど、どうすれば・・・どうすればいいんだあああああっっっっ!!!怜といえば舞、舞といえば怜、同じ答えは反則。答えなければ反抗と看做す。どう答えても鞭と唾が襲ってくる。そしてめまぐるしく立ち位置を替え慎治たちの死角からブーツの足音を響かせて光臨する二人。ああ、あああ・・・今のは怜先生・・・あううううっ!いや舞先生?ひいいいいっ!ど、どっち、本当にどっちなのおおおおおっ!極限まで追い詰められ完全にパニック状態となった二人を怜と舞は更に追い詰めていく。5回、10回と積み重ねられていく拷問。完全に閉ざされ逃げ道など全くない言葉の迷宮、そして果てしなく続く苦痛。いつしか慎治たちは自分を鞭打っているのが怜なのか舞なのか本当に分からなくなっていった。はは、ひゃはははは、ヒギイイイイイッ!いへ、いへへへへ、アヒイイイイイッ!慎治たちの世界がグルグルと回転し始める。現実認識が狂い自分の声も怜と舞の声も、全てが分からなくなっていく。時折顔を濡らす唾の感触を前触れとして襲ってくる鞭の苦痛、それだけが慎治たちの全てだ。ひゃはははっひゃはははははっここは・・・どこだ・・・イヘ、イヘヘヘヘヘ、ぼくはだれなにをしているの・・・パニック状態から更にとことん追い詰められた二人は半狂乱状態となっていく。そろそろかしらね?そうね、第一段階終了ね。半狂乱状態となり口から泡を吹きながらだらしなく笑い始めた慎治たちを見下ろしながら怜と舞は軽く頷きあった。「さてと、半狂乱はいいけど本当に発狂されたら困るからね、一旦ストップよ。」「そうそう、どの道もう痛覚もマヒして来たみたいだしね、鞭は終わりよ。」笑いながら慎治たちの首に腕を回した二人はスリーパーの要領で頚動脈を絞め上げ、一気に慎治たちを失神させた。良かったわね、鞭が終わって。少し休ませてあげるわね、元気を回復させてあげる。尻を痣と血で染め上げたままだらしなく失神している二人を見下ろしながら、怜と舞は満足そうに笑っていた。
2
ジンジンと疼くような尻の痛みに呻きながら、慎治たちは殆ど同時に目を覚ました。殺風景なコンクリート打ちっ放しの天井が蛍光灯の無機質な光に照らされている。ああここは・・・お仕置き部屋、僕たちはここで散々鞭打たれていたんだったな。拘束台からは下ろされ、床に転がされていたがせめてもの慈悲だろうか、体には毛布が掛けられていた。う、うう・・・隣で信次が呻いているのが聞こえる。ああ信次も目を覚ましたんだな。ふと尻に手をやるともう出血は止まっているようだった。ツンと刺激臭のある軟膏のようなものが塗られていた。カタカタ、カタカタカタ、とパソコンを打つ音が聞こえてくる。
ううう・・・痛む体を引きずり起こすとお仕置き部屋の奥で怜と舞は持ち込んだノートブックPCに何かを打ち込んでいる最中だった。「あら二人ともお目覚め?ちょっと待っていてね、もう少しで切りがつくから。」10分位経つと、パタンとノートブックを閉じて二人は大きく伸びをした。「ふう、一服入れましょうか。」立ち上がった舞は部屋の片隅のポットから紙コップに湯気の立つ液体を注いだ。怜に一つを渡し、慎治たちにも一つずつ配った。「ミルクティーよ、お砂糖たっぷりと入れてあるから、疲れが取れるわよ。」湯気の立つ甘く芳しい液体は激しい鞭打ちに疲れ果てた慎治たちの体に沁み込んでいくようだった。がっつくように飲む二人に苦笑しながら舞が尋ねた。「そんなに急いで飲むと火傷するわよ。もう一杯飲む?」「は、はい・・・お願いします」「く、ください、お願いです・・・」もう一杯ずつ飲んで漸く二人が人心地着くのを待ってから怜が尋ねた。
「どう二人とも、私たちの鞭は効いた?痛かった?」ビクッと恐怖に震えながら慎治は答えた。「は、はい・・・とっても、痛かったです・・・」信次もまた鞭打たれるんじゃないか、と恐怖に怯えながら答える。「い、痛かったです・・・とても・・・もう反省、しましたから許して・・・ください・・・」
クスクスッと笑いながら舞が答える。「フフフ、随分応えたみたいね、よかった。私たちも鞭で人を打つのなんて初めてだからね、ちゃんと痛いかどうか心配だったのよ、まあ十分効いたみたいだし、良かったわ。ああ心配要らないわよ、もう鞭打つ気はないから。お尻、触ってみたんでしょう?一応止血と消毒はしておいたわよ。消炎剤も打っておいたけど、今日はかなり腫れてくると思うわ。そのくらいは我慢しなさいね。」にこやかに語る舞に、信次たちはほっと胸を撫で下ろす思いだった。よかった、ああよかった・・・もう鞭はお終い?ああよかった・・・信次たちがほっとするのを見た怜も笑いながら言った。「本当のことを言うとね、どういう体罰にしようか、て私たちも随分頭を悩ませたのよ。痛いだけじゃちょっと趣旨にそぐわないし、少し精神的にダメージを与える責めにしなくちゃいけないでしょう?真っ先に思い浮かんだのは唾を吐き掛けることだけど、それはもうやったし第一、矢作君たちは天城さんたちに毎日、唾を吐き掛けられるのは愚かおしっこまで飲まされている、ていうものね。」
そんなこと、本気で考えないでよ!どうやって責めようかなんて!慎治は喉まで出かかった言葉を必死で飲み込む。舞が後を引き取る。「そうなのよ。じゃあ単純にエスカレートさせてうんちを食べさせる、ていうのも勿論考えたわよ。」う、うんち!ま、まさか!緊張する信次たちを楽しげに見ながら舞は続けた。「でも折角霧島さんたちが、じっくりと君たちを苛めているんだものね。分かっているとは思うけど、いずれ近いうちに君たちは霧島さんたちにうんちを食べさせられるわ。彼女たちが大事に取っておいたお楽しみを奪っちゃ悪いものね、それでうんち責めも没、となったのよ。」う、うんち!うんちを食べさせられる!最悪の未来として恐怖に怯えながら必死で考えまい考えまいとしてきた悪夢を突きつけられ、信次はグッと胃の辺りに鈍痛が走る。そ、そんな・・・分かっているんだったら止めてよ!そんな酷い苛めはするなって・・・だが絶対無理、怜も舞も完全に玲子たちの味方だ、言うだけ無駄、いや却って怒らせるようなものだ。
押し黙ってしまう二人を見て、怜がフッと小さな笑いをもらした。「ねえ矢作君、ところで今のお仕置きなんだけどね、鞭が痛いのはまあ当然として、私たちの質問責め、どうだった?ああいう答えがない質問で苛められる、ていうのも結構厳しかったんじゃないかしら?」ぐううっ・・・慎治の脳裏についさっきまでの苦痛と焦燥が蘇る。どう答えても鞭、答えなくても鞭。だが答えないわけにはいかない。ただ打たれるよりも数段辛い責めだった。「は、はい・・・とっても辛かったです・・・単純に引っ叩かれるのよりずっと・・・辛かったです・・・」満足げに頷きながら舞が尋ねる。「そう、やっぱり鞭だけの責めよりずっと辛かったのね。じゃあ川内君、もう一つ質問。責められていた君にはそんな余裕なかったかも知れないけど、何か変だと思わなかった?私たち、鞭は初めてだから多少ぎこちなかったと思うんだけど、この質問責めは妙にスムーズ、慣れた責め口だな、と思わなかった?」「そ、そんな・・・辛くて痛くてそれどころじゃ・・・でも・・・」「でも?何?」「確かに・・・どう答えても全部先生の予想通り・・・罠に掛けられたみたいに・・・どうにも逃げるも言い訳も何もできませんでした・・・」あら随分と素直じゃない、よろしいよろしい。満足そうに舞が頷く。
「そう、やっぱり上手だったかしら?じゃあいいこと教えてあげるわね。私たち、鞭は確かに今日が初体験よ。だけどね、質問責めは前にもやったことがあるのよ。」え、やったことがある?まさかこんな酷くじゃないよな、子供のころ、誰かを苛めて泣かせた程度のことだろうな。半ば聞き流そうとした慎治たちは怜の言葉に耳を疑った。「フフフ、今日のなんかまだまだ生温いわよ。私たちね、責め殺したことがあるの。二人の男性、大人の男性をね。」ええ、ほ、本当に!?せ、責め殺した・・・殺したの!?流石に仰天した慎治たちは言葉を失ってしまい、暫しの間呆けたように怜と舞の知的な美貌をまじまじと見つめてしまう。せ、責め殺す・・・殺した、殺した・・・まさか・・・でも怜先生と舞先生、あんなに残酷なんだから、もしかしたら・・・絶句している二人を見て怜が可笑しそうに笑う。「アハハ、二人とも何凍りついているのよ、責め殺したって、私たちがナイフか何かで刺し殺して死体を山に埋めたか海に沈めたかでもしたか、と思っているの?」舞もケラケラと笑っている。「アハハハハ、二人ともいい加減バカな事考えないの!そんな本当に二人も殺したら今頃、私たち刑務所入りよ。責め殺した、ていうのは比喩に決まっているでしょう?そう、前置詞をつけて置くわね、精神的に、責め殺したのよ。」ああ良かった、本当に殺人を犯したんじゃなかったんだ・・・でも精神的に責め殺したって、どういうこと・・・一瞬ほっとした二人だったが、怜と舞の話を聞くにつれ、急速に青ざめていった。
「あれは今から丁度一年前ね。」怜が語り始めた。「私も舞も当時は未だ大学では講師でね、教授に来年助教授に昇進する、そして自分が定年退官したら次期教授を頼む、て言われたばかりだったのよ。分からないかも知れないけど大学は閉鎖的な社会でね、教授、助教授、講師、助手っていう階級制度は結構絶対的なものなの。私も舞も最年少助教授になるわけだけど、私たちが昇進する、ていうことは他の講師の人たちは教授になる目がほぼ確実になくなった、て言うことなの。もう精々が助教授、つまり遥かに年下の私たちにずっと仕えるしかないっていうことなの。まあ東大は傘下の大学が多いからね、他所に行けば幾らでも教授の口はあるんだけど、女の私たちに負けた、て言うのがどうしても納得できない人たちはいるのよ。」
舞も大きく頷いた。「そう。大部分の人はまあしょうがないや、てそれなりに納得するんだけどね。中にはどうしても納得できない人もいるのよ。まともに喧嘩ふっかけてくるとか辞表叩きつけるとかならいいんだけどね、閉鎖社会の大学にしかいない人たちって、中には結構変に歪んじゃう人もいるのよ。」フッとどこか遠い目をした怜が小さな笑いを漏らした。「私の方は最古参の講師、名取さん、ていう当時もう40才なのに独身の人ね。もともと私にかなり気があったらしくて私が結婚する前は大分お誘いがあったんだけど、好みじゃなかったからお断りしてたら一時はストーカーまがいの行為に走って大変だったのよ。まあ私が結婚したら諦めたようだったけど、私の助教授内定を機に再発しちゃってね、結構ディープなストーカーになっちゃったのよ。」
「私の方も似たようなものね。」舞もどこか懐かしそうに話し出した。「その人も40才独身、那珂さんといってね、講師としてはベテランだったけど研究者としては今一歩だったのよ。教育者としてはまあまあだったから、教授はどこか別の大学の一般教養なら十分に教授が勤まる、と考えたのよ。それで教授に頼まれて、箔付けに私の論文の何本かに共同執筆者として入れさせてやったのよ。そうしたらその人、何を誤解したのか逆恨みしちゃったの。私みたいな小娘にお情けで共同執筆者に名前だけ加えさせてもらうなんて、俺様のプライドが許さない、て言う訳ね。その私が助教授に昇進する、女の尻に敷かれるなんてやってられるか、てね。で、私の論文をパクッて盗作したり、挙句の果てにそれがバレるのを恐れて私の論文データをパソコンから消去しちゃったりと、酷い妨害工作に走り始めたのよ。」
怜が苦笑しながら続ける。「矢作君たちには一生関係ない世界だろうけどね、学者の世界、て狭い上にドロドロした伏魔殿なのよ。講師間でストーカーが発生しているなんて、格好の汚bのネタね、当然、それを利用して私や私の講座の足を引っ張ろうとする輩は多いのよ。」舞も頷く。「そう、盗作騒ぎは学者の世界、日常茶飯事だけどそれを同じ講座内でやって、しかも派手に妨害工作までしているなんて、講座内の管理能力を疑われちゃうわ。私たちの助教授昇進は愚か、研究者としての生命に関わることなのよ。どうしても、早急に排除しないといけなかったわけ。」
「でもね、早急に片付ける、といってもどうすればいいと思う?まさか君たち相手にするように、体罰を加えるわけにもいかないでしょう?第一、一応大学出で頭はいいんだから、迂闊に暴力に訴えたら逆にこっちが加害者にされかねないわ。」「そう、それに盗作うんぬんも、何年もかかって延々と論争しているケースなんて幾らでもあるわ。そんなのに巻き込まれて余計なエネルギーを使わされるのは真っ平ごめんよ。」「だからね、舞と相談して実力で彼らを排除することにしたの。二度と私たちに近づけなくなるように、大学からも学界からも永久追放されて、絶対に戻ってこれないようにしてやろう、てね。」「ほんと、正直言うと殺してやろうかと思ったわよ、でも肉体的に殺すわけにはいかないでしょう?私たちが手を汚したなんて言われたら困るからね、だから絶対に証拠が残らないようにやる必要もあったのよ。それで色々考えた末にね、怜とこう決めたのよ。肉体的に殺せないなら精神的に抹殺してやろう、再起不能になるまで精神を破壊してやろう、てね。分かる?どういうことだか。平たく言うとね、彼らを精神崩壊するまで責めて責めて責め嬲り抜いて、発狂させてやったのよ。」
ウフフフフ、怜が残酷な笑みを浮かべた。「そう、あの二人をね、キチガイにしてやったのよ。キチガイになるまで苛めてやったの。殺しはしないわ、発狂させた後は自由に解放してあげたわよ、それだったら元々犯罪行為の匂いすらないからね、警察が乗り出すまでもなく、事件にすらならずにおしまいになったわ。」舞も懐かしげな表情に楽しそうな笑みを浮かべた。「あの二人、どうしているかなあ。一応精神病院に入院はしたみたいだけど、治療は不可能、ていうことで退院したあと実家に引き取られていったわ。東大出の自慢の息子がキチガイになっちゃった、てご両親、泣いていたわねえ。」
言い終えた舞がじっと信次を見詰めた。「フフフ、川内君、どうやって発狂させたか教えてあげようか?」ヒッ!そ、そんなこと、聞きたくない!だがそうは言えない。舞に対してイエス以外の返事をする気にはなれなかった。「は、はい・・・教えて・・・ください・・・」うんうん、いい子ね、というように舞はニコリと笑うと話し始めた。「川内君、あなたは霧島さんたちに散々苛められていたんだったわよね。何回も何回も、失神するまで苛められたんでしょう?じゃあ聞くけど、一番苦しい失神の仕方はどういう失神だった?」「そ、それは・・・」信次は思わず口ごもってしまった。玲子に、朝子に失神させられた苦い記憶が甦る。踵落とし、ブーツキック・・・だけど一番はやっぱり鞭かな。
「鞭で・・・気絶するまで打ちのめされた時です・・・二人掛り、四人掛りで・・・」「うーん川内君、私の質問の意味が分からなかったみたいね。私は苦しい、て言ったのよ?鞭での失神は苦しい、ていうより痛いじゃないの?」「まあまあ舞、もしかしたら川内君は経験ないかもしれないわよ、矢作君、君はどう?苦しい失神はどんな失神だった?」苦しい、苦しい・・・慎治は必死で怜と舞の意に沿う答えを考えた。苦しい・・・やっぱり、あれかな・・・「首を・・・ブーツで絞められた時、かな・・・礼子さんのブーツが喉に食い込んで息ができなくて、もがき苦しんだ挙句にちょっとだけ息吸わせて貰えて・・・中々気絶すらさせて貰えなくて延々と苛められた時とか、フミちゃんに唾を鼻に入れられて窒息させられた時、です・・・」「うん、そうビンゴ、正解よ!」怜が楽しそうに両手を叩いて笑った。
「窒息責め、て苦しいでしょう?長い時間をかけてジワジワと苦しめられて中々気絶すらできないし、脳震盪のように一瞬で気絶したり脳貧血のように痛覚が麻痺してくれないからね、最後の一瞬まで延々と苦しみを味わい続けるのよね。」舞も大きく頷いていた。「そう、それと窒息責めにはもう一つ、とてもいい長所があるのよ。それはね、拷問を加えたという証拠が残らないこと。勿論、肺や心臓、気管、更には脳と全身に蒙るダメージは大きいわよ。だけど少なくとも体の表面には殆ど傷は残らないわ。責める私たちにはそれがまたいいのよ。例えば今みたいに鞭で追い込むのもいいけど、それだとあなたたちみたいに全身傷だらけになっちゃうでしょう?それじゃあ折角発狂させても、解放した時に全身の傷を見て警察沙汰になるリスクがあるわ。それは困るからね。」
恐ろしいことを平然と言い放つ怜と舞に、慎治たちは心底恐怖していた。ま、まさか・・・でも先生たちならやりかねない・・・思わず礼子たちの姿を思い浮かべた。礼子さんたちも、僕たちの命に関わるような責めはしないけど、残酷なことはどんな酷い事でも平然とやるよね・・・殺しはしない、その一線さえ守れば玲子さんと同じ、却ってどんな残酷なことにも抵抗がなくなっちゃうかもしれない・・・思わず絶句する二人を面白そうに眺めながら怜が続ける。「じゃあ具体的にどうやって拷問したか、教えてあげるわね。最初は名取さんの方を攫ってきたのよ。夏休みで講義が休みの時を狙ったから、独身男性が何日か行方不明になったってどこか旅行にでも行ったんだろう、としか思われないわね。それでね、私たちの別荘に監禁したのよ。そこで3日3晩責め続けたの。どうやってか、ていうとね、名取さんは私をストーカーしていた、て言ったでしょう?つまり私のお尻を追い掛け回していた訳よね。ウフフフフ、単に窒息責めだけなら水に漬けるとか、ガムテープで口や鼻を塞ぐとか簡単で有効な方法は幾らでも考え付くけど、それじゃあ恐怖と屈辱を与え続ける、ていう目的を達成できないでしょう?だから、名取さんの希望を、夢を叶えてあげることにしたのよ。」「ゆ、夢?か、叶える?」余りの恐怖に慎治は尋ねずにはいられなかった。
「フフフフフ、もう薄々と分かっているんじゃない?そう、散々追っかけまわした私のお尻をたっぷりと味合わせてあげることにしたのよ。簡易ベッドを改造して拘束台を作ってね、それに縛り付けて私と舞のお尻の下敷きにして窒息させたのよ。」舞も残酷な笑いを浮かべながら言う。「アハハハハ、怜のお尻を追い掛け回した名取さんが怜のお尻で苦しめられる、正に因果応報、て奴でしょう?名取さんが発狂した後ね、今度は那珂さんを攫って来たのよ。そして名取さんと同じく、私たちのお尻の下で窒息責めに合わせたの。楽しかったわよお?だって女の私の尻に敷かれるのが死ぬほど嫌だった那珂さんが、私のお尻に敷かれて泣き喚いているんですものね。最高だったわ。面白いことにね、名取さんと同じく丁度3日3晩責め続けたところで発狂したわ。」
アハハハハ、と心底楽しそうに笑いながら怜が尋ねる。「ところで矢作君、一つ不思議なんじゃない?本当に窒息責めで発狂するのか、て。僕たちも鞭やブーツで何回も失神しているけど、発狂はしていないぞ、て?」怜の言うとおりだった。尻に敷かれて窒息責め、確かに苦しそうだ。だがそれで気絶させられた程度で本当に人間は発狂するものなのだろうか。信次も同じ事を感じているのに気づいた舞が言った。「川内君も同じ疑問を感じているようね。まあ当然でしょうね、何回か失神させられた程度じゃあ、確かに人間は発狂なんかしないわよ。だけどね、さっきの私たちの鞭を思い出して貰える?あなたたちも言ってたわよね、ああやって答えのない質問を繰り返されながら苛められるのは、単純に鞭で打ち続けられるよりもずっと辛い、て。」う、信次は微かな声で呻いた。
「そう、私と怜はね、さっきと同じように責めたのよ。答えのない質問責め、それだけじゃあないわ。君たちはさっき、間違えても鞭で10発ずつ鞭打たれただけよ。だけど名取さんと那珂さんはね、一回間違えるごとに窒息責めで気絶させられたのよ、全身を苦痛で痙攣させて散々もがき苦しんだ挙句にね。」「それだけじゃないわ、今は矢作君たちと私たち、二対二でしょう?だけど名取さんたちは一人だからね、私たちは二人掛りで苛められるのよ。分かる?私と舞と交代でね、夜も昼もないわ、一日24時間、ノンストップで責め続けたのよ。拷問する側の私たちは交代で休憩もするし食事もする、睡眠も取れるわ、だけど名取さんたちはそうはいかない。拘束台に縛り付けられたまま、ノンストップで責め続けられて、漸く失神しても休憩なんかさせてあげない、直ぐに活を入れて息を吹き返させ、直ちに拷問再開よ。勿論、水の一滴も飲ませないし食べ物なんか一切与えないわ。文字通り飲まず食わずで責め苛み続けたのよ。」「ううん、私も怜も拷問、てさっきから言ってるけど、拷問よりも酷いわよね。だって拷問ならば自白すればいいんだけど、自白することなんか何もないんだもの。単なる苛めにしても、気絶したら、とか時間の制約とかいろいろとリミッターはあるわよね?だけどあの時は完全無制限だもの、発狂に追い込む、ていう目的を知っているのは私たちだけ、那珂さんたちは何も教えて貰えずに、ゴールがどこにあるかも分からずにひたすら苦しみ続けるだけだったのよ。大体ね、3日3晩一睡もさせない、しかも完全に飲まず食わずなんだからそれだけでも十二分に苦しいわよ。」
少し間をおいた怜が楽しそうに話し続ける。「面白かったわよお?散々私を悩ませた名取さんがね、私のお尻の下で泣き喚いて、必死で哀願して許しを乞い続けるんだから!バカよねえ、許してなんか貰えるわけないのに。」「怜の言うとおり、本当に楽しかったわ。那珂さんもね、攫われてきた当初は強気で「何をするんだ!さっさと放せ!」とか喚いているのよね。ウフフ、だけど一回気絶させてやるともう泣き声で「お願い許して・・・もう日向さんの邪魔は決してしませんから・・・」とか言い出しちゃってね。」「そうそう!」怜も手を叩いて笑っている。「でもそれも無視して責め続けるじゃない、そうすると今度は逆ギレしてくるのよね。「ち、畜生!う、訴えてやる!絶対復讐してやる!」とか言っちゃってね。」「アハハハハ、そうだったそうだった!」舞も大笑いしている。「そうそう、その反抗期を過ぎるともう、自我が崩壊寸前になっていくのよね!声も弱々しくなっちゃって、「おねがい・・・ゆるして・・・」とか殆ど切れ切れにしか哀願できなくなっていくのよね。それも過ぎるといよいよ最終段階。」
怜が頷く。「先ずは言葉がでなくなるのよね。いくら責めても出てくるのはアアア・・・ウウウ・・・とかいう弱々しい悲鳴というか嗚咽だけ。苦痛に体は反応するけど、意識が混濁して頭が現実を認識できなくなっていくのよね。」舞が床を指差した。「拷問した部屋はワインセラーになっている地下室でね、外の光が一切入らないし音も殆ど聞こえないのよ。明るさも常に変わらない蛍光灯だけだから時間の感覚も直ぐに消滅しちゃってね、一体いつから自分がここにいるのかいつまでいるのかも分からなくなって、時間の流れも認識できなくなっていくのよ。」
にっこりと笑いながら怜が問い掛ける。「矢作君、天城さんたちに苛められた時、夜はどうしてる?死んだように眠りこけてるんじゃない?一日中責められたら全身ボロボロ、精も根も尽き果てて泥のように眠っちゃうでしょう?」確かにそう、怜の言うとおりだった。「は、はい・・・もう眠らずには・・・いられません・・・」慎治の答えに頷きながら舞が言った。「そうでしょう?眠らずにはいられない筈よね。全身が休息を要求するでしょう?だけどね、私たちは一睡もさせなかったのよ。さっきも言ったとおり、気絶したら直ぐに息を吹き返させて即刻拷問再開よ。だけど時計もないし光も音も、全てが一日中変わらない。ううん、それだけじゃあないわ。私と怜は交代で苛めた、て言ったでしょう?だからそれぞれの休憩時間を利用してね、服も下着に至るまで大急ぎで洗濯して、ずっと同じ服装、香水やメイクに至るまで全て同じにして責め続けたのよ。フフフ分かる?同じ顔、同じ体格同じ声の私たちがずっと同じ服装で責めるの。どれ位責められ続けたか今誰に責められているのか全く分からなくしてあげたのよ。疲労と肉体的ダメージでボロボロになった那珂さんたちをそうやって、錯乱状態に追い込んでいってあげたの、フフフ、効果抜群だったわよ?」
うう、ううう・・・信次は恐怖に思わず呻いてしまった。全く同じ顔の二人の責め。しかも休息なし、自分がどれだけ気絶したかも分からず、責めのゴールすら想像できない。恐ろしい責めだった。まさに地獄、永遠に苦痛のみが続く究極の煉獄だ。ま、まさか・・・まさか・・・怖い、余りにも怖い想像が信次の脳裏から離れない。なんでこんな事を俺たちに教えるんだ・・・まさか、慎治と俺をそうやって拷問するつもりじゃ・・・ふと横を見ると慎治も同じ恐怖に怯えていた。そ、そんな!は、発狂だなんて嫌!今さっき飲んだミルクティーの温かさもどこへやら、二人は余りの恐怖にガタガタと震えていた。怜先生も舞先生も・・・二人とも同じスーツを着ている・・・同じブーツを履いている・・・香水の香りも同じだ・・・ま、まさか・・・
怜と舞は恐怖に震え、怯えきった二人を穏やかに微笑を浮かべながら見詰めていた。優雅な手つきで、ゆっくりとミルクティーを飲み干していく。カップの中の液体はもうあと僅かのようだった。グッと最後の一口を飲み干した二人は静かにカップをテーブルに置いた。「フフフ、どうしたの?そんなに怯えちゃって。」怜の微笑は残酷な冷笑に変わっている。「さあ休憩はおしまい。少しは人心地ついたでしょう?良かったわね、今話した那珂さんたちには、こんな休憩タイムは全然なかったのよ。」ゆっくりと舞が立ち上がった。「ねえ二人とも、ここには今鞭打たれたこの大部屋の他に奥に二つ、小部屋があったわよね?部屋の中、もう一度よく見せてあげるわ。いらっしゃい。」ガチャッと扉が開けられ、怜が小部屋の蛍光灯のスイッチを入れた。「ヒッ!ヒイイイイッッッッ!」「そ、そんな・・・そんなあああ・・・」真ん中に設置された台を改めて見た慎治たちの口から悲鳴が漏れた。そこに設置されていたのはクッションを取り外され骨組みだけとなったスチールベッドだった。しかも上部には首、真ん中には両手および腰、そして下部には両足を固定するための頑丈な革ベルトが骨組みから伸びている。上から1/3程度の所には起倒式の背もたれ、フレームのみで間に犠牲者が潜り込む形となる、拘束具兼用の背もたれもついていた。しかも上部ベルトの更に上には万力のような、可動式らしい留め具が二本突き出ていた。留め具は顔面に添う形で30センチ近い長さがあった。奇妙なことに頭を横たえる最上部は大分幅が狭くなっており、かつ首が台から落ちないように縁が高くなっていた。
こ、拘束台!!!間違いない、どうみても怜と舞が邪魔者を処刑した拘束台、名取と那珂という二人の男が発狂させられた拷問台に間違いなかった。「フフフどう矢作君、もうわかったでしょう?そう、これが今教えてあげた拷問台よ。土曜日に天城さんたちから君たちの犯罪を聞いてね、大急ぎで別荘から運んで来たのよ。軽井沢日帰り往復なんて結構疲れるんだからね、感謝しなさいよ?」「そ、そんな・・・怜先生、感謝だなんて・・・」「ウフフ、川内君、心配しないでもいいわ、君用の拘束台はちゃんと隣に用意してあるからね。那珂さんたちを拷問した時に、壊れたら面倒、と思って予備を作っておいて良かったわ。二人で一台なんてケチな事は言わないわ、二人とも専用のベッドを用意してあげたから。遠慮なく苦しんで頂戴ね。」「い、嫌だ・・・舞先生・・・お願いやめて・・・狂いたく・・・ない・・・」信次がボロボロ涙を溢しながら哀願するのを見て舞はカラカラと手を叩いて大笑いした。「アハハハハッ!何深刻な顔して泣いているのよ!少しは展開考えなさいよ!いい、さっき言ったでしょう?川内君たちはその内、霧島さんたちにうんち食べさせられる、て。そのお楽しみを邪魔しちゃ悪い、とも言ったわよね?そうやって気を使っている私たちが、君たちを発狂まで追い込むわけないじゃない!」苦笑しながら怜も頷いた。「全く・・・大体考えてみなさいよ、私たちは3日3晩責め嬲って名取さんたちを発狂させたのよ?いくらなんでも今から3日間、君たちを責め続けるほどの時間を取れるわけないじゃない!これでも私たち忙しい身なのよ、君たちにそんなにずっと付き合うことはできないわ。」
ああ良かった・・・発狂させられないで済む・・・信次たちがホッとするのを見澄ましたように舞が言い放った。「フフフ、どうしたの二人とも安心しちゃって?いい、確かに私たちはもう責める気はないわ、だって君たちを責める適役は他にいるものね。ウフフ、君たちにとって最も怖い女性が。君たちを責めるのはその子たちの役目よ。アハハハハッ!彼女たちのお尻の下でたっぷりと苦しみなさい!」「ああ、あああああ、そ、そんな・・・まさか・・・」怜の瞳にも残酷な光が浮かんでいた。「君たちを責めるのが誰かなんて、もう言わなくてもわかっているわね?君たちが一番怖いのは誰かしら?アハハハハッ、そうよ天城さんと霧島さんよ!あの二人にはたっぷりと窒息責めのやり方もこの拘束台の使い方もレクチャーしておいたわ。張り切ってたわよ二人とも、女の子に暴力ふるって怪我させた最低男の君たちに、女性の怖さをたっぷりと思い知らせてやるってね。フフフフフ、女の子のお尻を見ただけで条件反射で震え上がる位、苦しい目に会わせてやるってね!」「い、いや、いやあああああ!!!」床に崩れ落ちて泣き喚く二人の無様な姿に怜と舞は大笑いしていた。丁度その時、タンタンタン、と階段を下りる軽い足音が聞こえてきた。「ヒッヒイイイイッ!」「ああ、あああああ・・・・・」部活を終えた礼子たちがやってきたのだ、慎治たちに窒息責めを加えるために、地獄の苦悶を味合わせるために。
高笑いを響かせながら礼子たちが立ち去った後も、慎治たちは暫くの間泣き続けていた。余りの絶望、坊野たちの件といい陽子たちの件といい、自分たちの全ての選択、全ての行動が悉く裏目、それも最悪の目を出し続けていることに。そしてその裏目の連続は慎治たちをのっぴきならぬ状況に追い込んでいた。苦痛と屈辱だけではない、未来までも全て奪い尽くされようとしていた。単純な苛めだけではない、学校、家庭・・・全てが慎治たちを拒絶し、苦しめ辱める側へとはっきりと回っていた。そして今、床に突っ伏して泣いている慎治たちを冷笑しながら見下ろしているのは怜と舞、女教師を遥かに超えた学園理事の二人だった。ありとあらゆる権力を駆使して慎治たちを罰せられる二人、そして部活で礼子たちと互角に渡り合える力を発揮する二人は腕力の面でも慎治たちを遥かに凌駕している。だから女性二人に男子生徒二人、ということによると危険なシチュエーションにも関わらず二人は余裕綽々だった。最も精神を殆どボロボロになるまで破壊されつくした慎治たちに、反抗の元気などあるわけもないが。「さてと、天城さんたちも行ったことだし、そろそろ体罰を始めるわね。」怜の無慈悲な宣告に合わせるように舞が入り口近くに置いてあった細長い袋から二本の棒状の物を取り出した。ヒッ、乗馬鞭!玲子たちも大好きな乗馬鞭を直感的に想像した信次の口から悲鳴が漏れる。「ウフフフフッ、残念、外れよ。これは乗馬鞭じゃないわ。よく見てご覧なさい。」舞が信次の目の前に手にした拷問具を差し出す。それは長さ1メートル程度の細い木製の棒だった。太さは1センチ程度であろうか、先端にかけてやや細くなっているようだが太さはほぼ均一、そして根元に黒いグリップが嵌められていた。「CANEていうのよ、日本では樺鞭ともいうわね。鞭というより笞と言った方がいいかも知れないわ。」一本を舞から受け取った怜がスナップを効かせて軽く振った。ヒュンッ!金属質ともいいたくなる、凶悪な風切り音がした。ヒッ!思わず悲鳴を漏らす慎治、その怯えを見た怜の美貌に残酷な笑みが浮かんだ。「フフフどう、痛そうでしょう?あなたたちは毎週のように天城さんたちに革鞭で打たれている、ていうからね、違う種類の鞭を用意してあげたのよ。ウフフフフッ、こっちの鞭も・・・痛いわよお?」ギュッギュッと怜は二、三回、鞭を撓らせる。ガタガタ震える信次の頬に舞が手にした鞭を近づける。「ヒイイイッ!や、やめて!」悲鳴をあげる信次を舞は笑い飛ばした。「アハハハハッ!大丈夫よ、何もしやしないわよ。ほら手をどけなさい!」恐怖に怯えながら手を下ろした信次の頬に舞は鞭の先端を押し当て、グッと力を込めた。舞の手と信次の頬の間で鞭がギュッギュッと撓る。「どう?この撓り具合は?あなたたち、乗馬鞭でも鞭打たれたことはあったわよね?でも乗馬鞭よりも大分硬い感じじゃないかしら?」
その通りだった。それは鞭と棒との中間、乗馬鞭がより鞭に近い存在とするならば、怜と舞が手にしている樺鞭はより棒に近い、細身の棍棒とも思えた。「さあ、お仕置きの始まりは・・・まず鞭よ、二人ともさっさと服を脱いで、この台に両足と左手を固定しなさい。右手は私たちが縛ってあげるから!」ピッと怜は大部屋の中心に置かれた、木馬型の拘束台を鞭で指し示した。「あっ・・・いやっ、そんな!!!」「せ、先生・・・許して・・・ヒッ!」涙を流しながら哀願する二人の眼前を舞の鞭がヒュオッと鋭い音を立てて切り裂いた。「霧島さんたちに教えてもらっているでしょう?余計な事を言わないでさっさと言われた通りにしなさい!それとも・・・腕ずくでその台に縛り付けて欲しいの?動けなくなるほど痛めつけられてから?別にそうしてあげてもいいのよ?何の苦労もいらない話だからね。」動けなくなるほど痛めつける!玲子たちと五分に渡り合える強さを部活で見せ付けられている信次たちだ、怜と舞がその気になれば一瞬で叩きのめされてしまうこと位は流石に分かる。ああ・・・あああ・・・い、嫌だ・・・蹴り倒されたくない、投げ飛ばされたくない・・・魂を抜かれたかのようにガタガタと全身を震わせ、顔面蒼白になりながらのろのろと二人は服を脱ぎ始めた。「ホラ、何愚図愚図しているの!さっさとしなさい!」ヒュンッ!ヒイッ!「・・・ったくとろいわねえ・・・鞭がないと動けないの!?」ヒュオッ!アヒイイッ!鞭音に追われながら慎治たちは服を脱ぎ捨てて一糸纏わぬ無防備な裸になり、そして拘束台に我と我が身を縛り付けた。木馬型の拘束台の背中を抱え込み、その脚に自らの足首をがっちりと固定してしまった。最後に残った右手を台から生える革ベルトに拘束されると、身動き一つできない。平行に並べられた拘束台、そして慎治の横には怜が、信次の横には舞が鞭を手に寄り添っている。拘束台を抱え込み、尻を突き出した慎治たち、背中と尻を無防備に曝け出した二人と高級なスーツとブーツに身を固めた怜と舞。鞭を手にした美女と全裸で縛り付けられた無力な男。いつもながらの余りに対照的、余りに屈辱的なシチュエーションだ。「フフフ、何なのよこのザマは。裸になりなさい、台に自分を縛り付けなさい、なんて理不尽な命令にも反論一つ出来ない意気地なしなのね、君たちは。そうそう、天城さんたちにいつも唾を吐き掛けられているんだったわね、今日は私たちが吐き掛けてあげるわよ、ペッ!」怜が真紅のルージュを纏った唇を軽蔑に歪めながら嘲笑い、唾を吐き掛けた。「本当に役立たずのクズよね。そんなクズの分際でよくもまあ、私たちの手を煩わせてくれたわね・・・まあいいわ、君たちにはいくら説教してあげても無駄でしょうからね、体に分からせてあげるわよ。先ずは霧島さんたち同じく、私も君たちのことを軽蔑しきっているんだ、ていうことを分からせてあげるわ。この唾でね!ペッ!」ギュウウッ、鞭を尻に食い込むほど押し付けながら舞が非情な宣告をし、同時に処刑開始の唾を吐き掛ける。頷きあった怜と舞が鞭をスッと慎治たちの尻から離し、ゆっくりとテイクバックしていく。「ああ、あああ先生・・・」「おねが、い・・・許して・・・」二人の哀願を掻き消すかのように、不気味な音が響いた。
ヒョオッ!ビシイイイッ!「ギッハアアアッ!」「ガッハアアアッ!」慎治たちの尻に樺鞭が食い込む。乗馬鞭より固い樺鞭は鞭のピリッとした軽質な、皮膚表面から筋肉組織の浅い部分に留まる痛みとは違い、強烈な衝撃を、体の内部へと貫くような激痛を刻み込む。思わず仰け反る慎治たち、だが拘束台に完全に固定されて身を捩ることさえままならない。一拍間合いを置き、二人の痛覚が第一波を過ぎ、鋭敏さを取り戻すのを見計らうかのように怜と舞は再び鞭を振り上げた。ビュオッ!バジイイイッ!「ガッギイイイッ!」「ゲヒイイイイッ!」再び鞭音と悲鳴がお仕置部屋に轟く。いい感触ね。古い本でイギリスのお仕置は読んだ事があったけど、その時はああ体罰がない時代で良かった、て思っただけだったけどね。自分が叩かれるのは真っ平だけど、こうやって罰を加える側なら大歓迎よ!怜の手に知らず知らずの内に力が入る。気持ちいいじゃない、これ。こんなに楽しいんじゃ、世界中で拷問が無くならない筈よね。法律で厳しく取り締まられない限り、こんな楽しい事を止められるわけないものね。ウフフ、でも今、君たちは法律の保護の外にいるのよ、だから・・・思う存分、打ち据えてあげるわ!舞の手にも力がこもっていく。ヒュンッ!バシィンッ!ヒギイイイイイッ!ヒュオッ!ピシイイイイッ!ギャアアアアアッ!怜と舞は双子らしく、息のあった鞭を打ち続ける。慎治の尻に炸裂した怜の鞭が慎治の悲鳴を迸らせる。その悲鳴が静まりかけた瞬間、舞の鞭が唸り信次を泣き叫ばせる。スナップを思いっきり利かせて打ち据えた次の瞬間、反動と鞭自身の撓りを利用して素早く振り上げられた鞭はそのまま中で二、三回上下に振られて恐ろしげな音を立てながら慎治たちを脅しつける。そんなに強く打っているわけではない、だが慎治たちは耐え難いほどの、礼子たちの鞭にも匹敵するほどの痛さに泣き叫んでいた。鞭の音と悲鳴がお仕置き部屋に間断なく木霊し続けた。10発ずつ打ったところで、二人は一旦鞭を休めて慎治たちの前に歩み寄った。「ウフフフフ、どう私たちの鞭は?少しは反省したかしら?」鞭の先端でうな垂れる慎治の顎を小突き上げながら怜が尋ねた。「あううう・・・先生・・・もう・・・許して・・・」傍らで舞に嬲るかのように、軽く頬を叩かれていた信次も必死で哀願した。「せ、せんせい・・・おねがい・・・はんせい、反省しましたから・・・もう許して・・・ください・・・」「そう、反省したの。それは偉いわね、反省することは大事よ。だけどね、この程度じゃまだまだ、お仕置きは足りないわ。」「そ、そんなあああああっ!アウッ!」「い、いやあああああっ!ヒッ!」二人の悲鳴を怜と舞の鞭が掻き消す。
「ウフフフフ、舞の鞭は堪能したでしょう?今度は私の鞭を味あわせてあげるわ。」「そうよ、今度は私の鞭を矢作君に味合わせてあげるわね。川内君は怜の鞭を味わいなさい。」あああ!そ、そんな!二人の必死の哀願を嘲笑いながら怜と舞は立ち位置を交換し、ヒールの乾いた音を響かせながら今度は舞が慎治の、怜が信次の傍らに立つ。「さあ行くわよ・・・ペッ!それっ!」「お仕置き再開よ・・・ペッ!ハッ!」再び唾を吐き掛けたのを合図にビュオッバシイイインッと地下室に再び鞭音と慎治たちの悲鳴が木霊する。再び10発ずつ鞭打ったところで二人は鞭打つ手を休め、今度は慎治たちの前方に並んで立った。ウフフフフ、思いっきり涙流しちゃって。そりゃそうよね、これだけ鞭打ったんだもの、痛いでしょうねえ。それに・・・ウフフ、こんなところで拘束台に縛り付けられて、惨めよねえ。すすり泣く慎治たちを満足げに見下ろす怜に、二人の尻を見てきた舞が言った。「フフフ、怜、二人のお尻を見てご覧よ。中々いい色になってるわよ。」「いい色?見せて見せて!」後ろに回った怜は思わず歓声をあげた。「ワアッ!本当じゃない、いい色!矢作君も見てご覧なさいよ、自分のお尻。いい色になってるわよ!」い、いい色!?まだジンジンと全く引かない痛みにうめき続ける慎治の顔が微かに上がる。「アハハッ、怜ったら!縛り付けているんだもの、見えるわけがないじゃない!二人とも、自分のお尻がどうなっているかは後のお楽しみにとっておきなさいね・・・でもまあ可哀想だから、お互いのお尻を見せてあげる。二人とも似たり寄ったりだからね、自分のお尻もこうなっている、と思えばいいわよ。」舞は拘束台を交互に回転させ、交互にお知りを見させてやった。見せ付けられた相手の尻に、慎治たちは思わず息を呑んだ。「ひ、ひどい・・・」「あんまりだ・・・」二人の尻は酷い内出血に腫れ上がっていた。未だ白い箇所も多いが近いが見ている間にも尻のあちこちが急速に赤く腫れ上がり始めていた。鞭が直撃した所を中心に、交点、鞭跡、そして鞭跡の狭間と微妙なグラデーションがついていた。
ウフフフフ・・・そろそろ逝っちゃおうか・・・すすり泣き続ける慎治たちの頭上で、怜と舞は熱にうなされたような視線を交わしていた。久しぶりね、この感覚。そうね、折角貴重な時間を割いていることだし、思いっきり逝ってみようか?二人のクールな美貌に凄絶な冷笑が浮かんだ。グッと鞭を握る手にも力がこもってくる。「さあ、お尻の鑑賞会は終わり、お仕置き再開よ。」怜が慎治の拘束台を戻す。「ヒイイイイッ!そ、そんなあああああっ!ゆ、ゆるしてえええええっ!」ガタッと舞も信次の拘束台を回転させる。「い、いや、いやだあああああっ!もう、もう十分でしょ、お願い、許してえええええっ!」「煩いわね!未だ軽くしか叩いていないんだから、本当のお仕置きはこれからに決まってるでしょう!?」ほ、本当のお仕置き・・・い、いったい何を・・・聞きたい、だが余りの恐ろしさにそれを聞くことすらできない。思わず黙ってしまった慎治の頬を鞭でグリグリと小突きながら怜が微笑んだ。「本当のお仕置きがどんなものか知りたい?いいわよ、教えてあげる。だけどその前に、私の質問にも答えてね。矢作君は今、私と舞の両方に鞭打たれた訳だけど、どっちの鞭が痛かった?」ピシャピシャと信次の頬を軽く打ちながら舞も信次に尋ねた。「そう、私もそれを聞きたいのよ。怜の鞭と私の鞭、どっちが効いたの?怒らないから正直に答えてご覧なさい?」えっそ、そんな・・・思わず慎治たちは答えに詰まってしまった。どっちの鞭も死ぬほど痛かった。だけど・・・どっち、なんて言ったら、もう一人に鞭打たれるんじゃないだろうか・・・いや、それとも先生たちの事だから、痛い、て言った方に鞭打たれるんじゃ・・・答えに詰まったまま黙ってしまった慎治の尻を怜が鋭く打ち据えた。ピシインッ!ヒイッ!「聞こえなかったの、それとも答えたくない、ていう意思表示なのかしら?」慎治の悲鳴に身をすくめた信次の頬から舞が鞭を離した。「川内君も素直に答える気はないみたいね。こうやれば答える気になるかしら?」ビシイッ!アウッ!信次の尻にも激痛が走る。「答えるまで鞭で打ってあげようかしら?」怜が鞭を撓らせながら宣告する。ヒイッ、答えるまで鞭打つなんて!慎治は必死で叫んだ。「れ、怜先生の方が!!!痛いですううううっ!」ほぼ同時に信次も絶叫する。「ま、ま、舞先生の鞭の方が・・・痛いいいいっ!」ニヤリと残酷な微笑を浮かべながら二人の美女は鞭を撓らせビーンと弾いた。「そう矢作君、怜の方が痛いのね、私の鞭はまだまだ温いというわけね。」「川内君、よく言ったわね、舞の鞭より私の方が痛くない、甘い、て言うのね君は。」ヒッヒイイイッ!そ、そんなあああっ!「いいわよ矢作君、私の鞭が温い、て言うのならもう手加減してあげない。本当に痛い鞭の打ち方でお仕置きしてあげるわよ。覚悟しなさい!ペッ!」「川内君、少し優しくしてあげたら図に乗るのね、君は。どうやら本気で鞭打ってあげなくちゃ反省できないようね。このクズが!ペッ!」慎治の傍らには舞が、信次の傍らには怜が立ち鞭を高々と構えて処刑の唾を吐き掛けた。
ビュオッ!ヒュオッ!バシイイインッ!ビシイイイイッ!「ギャッヒイイイイイッ!!」「ウギャアアアアッ!!」一段と凄まじい音を立てて鞭が炸裂した瞬間、慎治たちの尻に信じられないほどの激痛が走った。皮膚を肉を貫き骨にまで達するかのような衝撃、いや尻から背骨を直通して脳天直撃、と言いたくなるほどの激痛だった。「ウフフ、どう矢作君、本物の鞭打ちの味は?お望みどおり手加減なしの鞭を味あわせてあげるわね、それっ!」「川内君、どうかしら?私の本気の鞭はお気に召した?たっぷりと味わいなさいね、それっ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ギャッ、ギャアアアアッ!ウギイイイッ!ガウウッ!ハヒイイイイッ!ガハアアアアッ!凄まじい音と悲鳴が地下室に響き渡る。痛いのも当然だ、怜と舞は十分に腰を入れスナップを利かせた鞭が炸裂した瞬間、グッとリストを返し捻るようにして反動を押さえ込み、慎治たちの尻に鞭を食い込ませたまま静止させていた。堅い鞭は二人の尻の肉に食い込み、めり込むようにして止まりその衝撃の全てを慎治たちの体内へと送り込んでいた。先程までのように鞭を直ぐに、反動とともに跳ね上げてくれれば少しは威力を逃がせるが食い込ませ、静止されればそんなことは到底不可能、怜と舞の凄絶な鞭の威力を全て我が身で味あわなければならないのだ。とめどもなく絶叫し続ける二人に10発ずつ鞭を見舞った怜と舞は一旦鞭を休め、二人の前に戻る。
「ウフフフフ、どう矢作君、これでもまだ、私の鞭の方が痛くない?」「フフフ、川内君、もう一度聞くわね、どっちの鞭が痛いの?」「あああ・・・舞先生の方が・・・痛いです・・・」「ううう・・・怜先生が・・・痛い・・・です・・・」かかったわね、おバカさんたち。「あら矢作君、舞の方が痛いですって?私の鞭の痛さを忘れちゃったみたいね、思い出させてあげる。舞、チェンジよ。」「怜の方が痛いですって?川内君、さっき私の方が痛い、て言ったばかりじゃない。また嘘をつくのね君は。いいわ怜、チェンジよ。」すっと交代して今度は怜が慎治の、舞が信次の横に来る。「さあ逝くわよ・・・ペッ!ハイッ!」「この嘘つきが・・・ペッ!ホラッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・凄まじい音と悲鳴が再び地下室に響き渡る。アヒイイイイッ!イヤッイタイイイイッ!ヤ、ヤベデ!ユルジデエエエエエッッッ!慎治たちの哀願を一切無視して更に10発ずつ鞭打った怜と舞は再び、二人の前に立ちはだかる。「さあもう一度聞くわね矢作君、どっちの鞭が痛かった?」「さあ川内君、素直に答えてご覧なさい、私の鞭と怜の鞭、どっちが痛いの?」ひ、ひどい・・・あんまりだ・・・怜先生の鞭も・・・舞先生の鞭も・・・死ぬほど・・・痛い・・・「あああ、うえええ・・・ど、どっちも・・・同じ位・・・痛いです・・・」「二人とも痛すぎますううう・・・どっちも・・・痛すぎますううう・・・」フンッやっぱりそう来たわね。全く、少しは予想を外して欲しいものよね。「同じ位?そんなの答えにならないわね、どっちが痛いのか、はっきり分かるようにもう一回鞭打ってあげましょうね。逝くわよ!ペッ!」「どっちも痛すぎる?要するにどっちが痛いか、未だ分からないのね、じゃあはっきり分かるまで鞭打ってあげるわ!ペッ!」「そ、そんなそんなそんなあああああっ!キャアアアッ!」「ややややめてよしてゆるしてえええええっ!ヒイイイッ!」哀願すら出来ないうちに二人に唾が吐き掛けられ、怜と舞は再び鞭を振るい始めた。お尻が、お尻があああああっ!痛いいいいっ、さ、裂けちゃううううううっ!絶叫する二人を情け容赦なく更に10発打ち据えた怜と舞は再び二人の前に立ちはだかる。「さあもう一回聞くわね。私と舞の鞭、どっちが痛い?」「もうはっきり分かったでしょう?じゃあ教えて頂戴、私と怜の鞭、どちらが痛いの?」怜といえば舞、舞と言えば怜に鞭打たれる。だけど分からないとも・・・答えに窮した慎治たちは思わず黙り込んでしまった。バーカ、もうちょっと頭を使いなさいよ、だんまりが私たちに通用するわけないでしょう?「そう矢作君、答えたくない、て言うわけね。随分と挑発的な態度じゃない?当然、鞭よ!ペッ!」「そう、よく分かったわ。お前なんかの質問には答えてやらないぞ、ていう意思表示ね。いいわ川内君、そのだんまりがどこまで続けられるか、この鞭で試してあげる!ペッ!」「い、いやああああっ!やめでえええええっっっ!ヒギャアアアッ!」「ちちち、ちがうちがうちがいますうううううっ!アウウッ!」慌てて絶叫する二人に委細構わず怜と舞は無慈悲に鞭打ちを再開する。今度もきっちり10発ずつ打ち据えたスーツを纏った女神がまた二人の前に舞い降りる。
「ウフフフフ、ちゃんと答えないと矢作君のお尻、ズタズタになっちゃうわよ?はっきり答えなさい、私と舞の鞭、どっちが痛いの?」「アハハハハッ!随分といい声で泣いたわね。どうやらだんまりは無理だ、て分かったみたいじゃない?じゃあもう一度聞くわね、怜と私、どっちの鞭が痛いの?」慎治たちは答えられなかった。怜と舞は尻だけを集中して鞭打っていた。威力十分の鞭を尻に集中して炸裂させた集中破壊力は慎治たちの尻をとっくに内出血で真っ赤、いや赤を通り越して赤紫青紫、場所によってはどす黒いほどの凄まじい痣で覆い尽くしていた。そして体内部からの圧力と外から加えられる鞭の衝撃に耐え切れなくなった皮膚があちこちで破れ始め、慎治たちの尻から腿にかけて幾筋もの血の帯が滴り落ちていた。鞭で流血させられたことは何度もある。だが礼子たちの鞭が引き鞭で切り裂くようにして出血させたのと違い、怜と舞の鞭は皮膚を叩き破る、と言った感覚だった。痛い、兎に角痛い。皮膚、尻の肉を通り越して骨にまで達するほどの激痛に身を震わせながら慎治たちは半ばパニック状態に陥りつつあった。痛いいたいイタイ・・・激痛以外何も感じられない。怜と舞の質問に答える余力すら無くなっていた。「お・・ねが・い・・・もう・・ゆ、るし・て・・・」「あああ・・・いたい・・・もうやめて・・・」消え入りそうな声で慎治たちは涙をボロボロこぼし泣きながら哀願した。二人の質問にも答えずに。そんな事を残酷な美神が許すわけがない。「答えになってないわね、分かったわ。矢作君は答える気がない、てことね。いい度胸じゃない、そんなに私には答えたくないって言うわけね。じゃあいいわ、好きなだけ鞭を味わいなさい!?ペッ!」「フウッ、川内君は心底バカなのね。ちゃんと答えないと鞭打たれる、て未だ分からないの?学習効果ゼロね。まあいいわ、答える気がないなら、いつまででも鞭打たれるがいいわ!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・唾を吐き掛けた怜と舞が腕を振り上げ、鞭打ちは直ちに再開された。
そして再度10発打ち終えた時、怜がアラッと声をあげた。「どうしたの?」「うん、この鞭見てよ、折れちゃったわ。丈夫な鞭だと思ったのにね、案外簡単に折れるものなのね。舞の鞭は大丈夫?」確かに怜の鞭は真ん中から二つに折れかけていた。「そう言えば私の鞭も、最後何か変な手応えだったな・・・あ、やっぱりそうだ、罅が入ってる!」怜も覗き込んで見た。舞の鞭はほぼ真ん中に10センチ近い罅が走っていた。もう二、三発も打てばへし折れてしまいそうだった。あああ、良かった・・・ラッキー、これでやっと終わったな、それにしても・・・痛かった、鞭が折れるなんて・・・酷い、折れるまで鞭打つなんて・・・慎治たちは思わず安堵の溜息を漏らし、がっくりと顔を拘束台に埋めていた。もう流石に終わりだよね・・・鞭は壊れたんだから、もうお仕置きできないよな、良かった・・・二人は全く気付いていなかった。自分たちが安心し喜んでいる姿を見下ろしている怜と舞が嘲笑っていることを。クスクスと笑い声を漏らしながら、本当にバカよねえ、と言った表情で慎治たちを見下ろしていることを。「フフフフフッ、矢作君も川内君も何を喜んでいるのかしら?ひょっとして私たちの鞭が壊れて良かった、ああこれでお仕置き終わりだ、なんて勘違いしているんじゃないでしょうね?」二人の拘束台の間に入り、怜は両手で慎治たちの髪の毛を掴みグイッと引き摺り上げた。涙で曇った二人の視線の先には舞がいた。「ウフフフフ、バカねえ君たちは!ここはお仕置き部屋よ、鞭の替え位、幾らでも用意してあるわよ。ホラッ!」手にした袋を舞が破ると、中には何本もの鞭が束ねられていた。アワワ、アワワワワ・・・そそそそそんなそんなそんな・・・恐怖に青ざめる慎治たちの表情を楽しみながら舞はスッと二本の新しい鞭を取り出し、二刀流よろしく左右の手に一本ずつ握って同時に空を切った。ヒュオッヒョオッ!「さあ、新しい鞭でお仕置き再開よ。質問を続けるわね。どっちの鞭が痛かった?」
どう答えたらいいの・・・怜先生と言っても、舞先生と言っても、どっちも痛いも答えないも全て通用しない、どう答えても全て鞭打ちで返される。じゃあせめてもの抵抗で答えない、それも不可能だった。連続で50発、100発と鞭打たれるなら感覚は殆どマヒ状態、それ故質問に対しても上の空でいられるが10発ずつと区切られては意識が飛んでくれない。意識が鮮明な状態では怜と舞の質問に答えないでいる勇気を持つことは到底不可能だ。慎治たちが半ばパニック状態に陥りつつあるのを見て怜と舞は残酷な目配せを交わした。そろそろ次のステップに行こうか。そうね、そろそろ頃合ね。慎治の尻に鞭を食い込ませつつ、怜が尋ねた。「どっちの鞭が痛いか、そんなに答えたくないなら質問を変えてあげましょうか?今度矢作君を鞭打つのは怜と舞のどちらかしら?」舞も同時に信次に尋ねる。「そう、君にはわかるかしら?私は怜?それとも舞?」えっえええっ・・・慎治たちは一瞬、考え込んでしまった。今僕を叩こうとしているのは怜先生・・・だよね?と慎治。た、多分・・・横にいるのは舞先生・・・だよね?と信次。「れ、怜先生・・・です」「舞先生・・・舞先生です・・・」「本当に?本当にそう思うの?じゃあこの鞭と唾で確かめてみるといいわ!それっ!ペッ!」「正解かどうか、顔と体で確かめなさい!それっ!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・再び鞭が唸る。ああああ、あわわわわ、お、怒ってる!!!ち、ちがったんだ、ちがったんだあああっっっ!!!きっちり10発ずつ鞭打つと、怜と舞は再び尋ねた。「さあ、私は怜?それとも舞?」「もう一度聞くわね、この鞭は怜の鞭?それとも舞の鞭?」反射的に慎治たちは答えた。「ま、舞先生・・です・・・」と慎治。信次もうめくように呟いた。「怜・・・先生です・・・」怜と舞の美しい横顔が残酷な笑みに歪む。「私が舞?これだけ鞭打たれてるのに、その程度の区別すらつかないのね君は!じゃあもう一度鞭をあげるから、しっかり学習しなさい!ペッ!」「失礼ね!私が怜だって!この鞭が怜の鞭だって言うのこの鞭が!えええっ?!この鞭とこの唾が私の、舞の鞭と唾よ!よく覚えておきなさい!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ヒギイイイイイッ!アヒイイイイイッ!10発を打ち終えた怜と舞が再び二人の前に戻る。「さあ今度こそ分かるわね、今の鞭は私?それとも舞の鞭?」「いくらおバカな川内君でもいいかげん分かったでしょう?私は舞?それとも怜?」ハヒッハヒッハヒッ、イウッククク・・・激痛にうめきながら慎治たちは必死で答えた。「れ、れい・・・先生です・・・」「舞、先生・・・です・・・」確かにそのとおり、慎治を鞭打ったのは怜、信次を鞭打ったのは舞だった。だが残酷な美女は冷笑とともに鞭を撓らせる。「今の鞭が怜?何言ってるの、今のは私、舞の鞭よ。」平然と言い放つ怜に合わせ、舞も頷く。「私が舞?失礼ね、私は怜よ!」「えええっっっ!そ、そんな馬鹿な・・・」「う、うそ、うそだああああっ!」弱々しく悲鳴をあげる二人を見下ろしながら怜と舞は冷酷に宣告する。「馬鹿?失礼ね、馬鹿とは何よ馬鹿とは!君ごときに馬鹿なんて言われる覚えはないわよ!当然鞭よ!ペッ!」「嘘?私が嘘をついたって言うの!?失礼にも程って言うものがあるでしょう?懲らしめてあげる、この鞭でね!ペッ!」ヒュンッ、ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ヒギイイイイイッ!アヒイイイイイッ!そ、そんなそんなそんなあああ・・・慎治たちは絶望と恐怖と苦痛、そして屈辱に頭の中が真っ白になっていく。今のは確かに怜先生・・今のは絶対舞先生だよ・・・どう答えても答えなくても鞭打たれる恐怖、必ず答えさせられ必ず罰せられる絶望。余りに横暴な怜と舞、だが鞭を握り全知全能の二人は自由自在にルールを定め、後出しで勝手にルールを変更できる。縛り付けられ尻を無防備に曝け出した信次たちにできることなど何もない。只ひたすら横暴な女神の鞭に耐え忍ぶしかない。学習性無力感、という言葉を遥かに通りこした極限の絶望と屈辱が信次たちの精神をズタズタにし、意識を、現実認識を蝕んでいく。絶対、絶対間違ってない・・・ひどいよ今のは合ってるよ・・・だが目の前にいるのは同じ顔、同じ声、同じスタイルの二人だ。同じ服、同じブーツを身に纏い同じ鞭を握り締めている。そして鞭の痛さも唾の感触すら殆ど同じだ。ほとんど見分けもつかない二人、その姿が慎治たちの脆い精神を内部から蝕んでいく。だけど・・・だけど怜先生、後ろで代わっているんじゃ・・・まさか今、舞先生交代した???あああ、どっちなんだあああああ!何もかも分からなくなっていく、自我が崩壊していくようだった。世界がグニャアッと音を立てて歪んでいくようだ、単純に鞭打たれるだけより何倍も辛い、肉体と精神を同時に責め苛む怜と舞の責めに慎治たちはひたすら泣き叫び続けた。ああ早く気絶してしまいたい。だが10発ずつしか鞭打たれないのでは気絶することすらできない。ああお願い先生・・・いっそ、いっそ一思いに責め潰してえええっっっ・・・
そんな必死の願いを弄ぶかのように怜と舞はまた問いかける。「さあもう一度聞くわね。私は誰?怜?それとも舞?」「いい加減分かったわよね?今の鞭は舞?それとも怜?」半ば意識朦朧としながら慎治は答えた。さっきは怜先生・・・じゃなくて舞先生だったんだから・・・「怜・・・先生です・・・」涙にむせて一瞬、答えるのが遅れた信次は思わずあっ!と声を上げそうになった。そ、そうだ・・・慎治と同じ答えなら・・・もしかして大丈夫じゃ・・・50%は望みがありそう・・・どっちかは助かるはず・・・「怜先生・・・です・・・」チラッと怜と舞を盗み見た信次は思わず背筋に悪寒が走った。二人は確かに笑っていた。チッと舌打ちするでもなくやられた、という当惑を見せるでもなく馬鹿にしたような、完全に余裕綽々の冷笑を浮かべていたのだ。「私が怜?違うって教えてあげたばかりでしょう?この低脳!鞭でお仕置きよ!ペッ!」「怜先生?矢作君と同じ答えを言うなんて、人の答え真似するなんて、そんなズルが通用するとでも思っているの!?懲らしめてあげる、私の鞭でね!ペッ!」ヒョオッ、ビシイイイッ、バシイイイイッ・・・ヒギイイイイイッ!アヒイイイイイッ!そんな、そんなそんなあああああっ!ひ、ひどいひどいひどすぎるうううううっ!馬鹿ね、同じ答えを言えばどっちかは助かるなんて、そんな甘い考えが通用するとでも思っているの?全くよね、そんな簡単な手口を私たちが予想しないとでも思っていたのかしら、本当に馬鹿ね。怜と舞は満面に侮蔑の嘲笑を浮かべながら鞭を振るった。
あああ、あああああ・・・ど、どうすれば・・・どうすればいいんだあああああっっっっ!!!怜といえば舞、舞といえば怜、同じ答えは反則。答えなければ反抗と看做す。どう答えても鞭と唾が襲ってくる。そしてめまぐるしく立ち位置を替え慎治たちの死角からブーツの足音を響かせて光臨する二人。ああ、あああ・・・今のは怜先生・・・あううううっ!いや舞先生?ひいいいいっ!ど、どっち、本当にどっちなのおおおおおっ!極限まで追い詰められ完全にパニック状態となった二人を怜と舞は更に追い詰めていく。5回、10回と積み重ねられていく拷問。完全に閉ざされ逃げ道など全くない言葉の迷宮、そして果てしなく続く苦痛。いつしか慎治たちは自分を鞭打っているのが怜なのか舞なのか本当に分からなくなっていった。はは、ひゃはははは、ヒギイイイイイッ!いへ、いへへへへ、アヒイイイイイッ!慎治たちの世界がグルグルと回転し始める。現実認識が狂い自分の声も怜と舞の声も、全てが分からなくなっていく。時折顔を濡らす唾の感触を前触れとして襲ってくる鞭の苦痛、それだけが慎治たちの全てだ。ひゃはははっひゃはははははっここは・・・どこだ・・・イヘ、イヘヘヘヘヘ、ぼくはだれなにをしているの・・・パニック状態から更にとことん追い詰められた二人は半狂乱状態となっていく。そろそろかしらね?そうね、第一段階終了ね。半狂乱状態となり口から泡を吹きながらだらしなく笑い始めた慎治たちを見下ろしながら怜と舞は軽く頷きあった。「さてと、半狂乱はいいけど本当に発狂されたら困るからね、一旦ストップよ。」「そうそう、どの道もう痛覚もマヒして来たみたいだしね、鞭は終わりよ。」笑いながら慎治たちの首に腕を回した二人はスリーパーの要領で頚動脈を絞め上げ、一気に慎治たちを失神させた。良かったわね、鞭が終わって。少し休ませてあげるわね、元気を回復させてあげる。尻を痣と血で染め上げたままだらしなく失神している二人を見下ろしながら、怜と舞は満足そうに笑っていた。
2
ジンジンと疼くような尻の痛みに呻きながら、慎治たちは殆ど同時に目を覚ました。殺風景なコンクリート打ちっ放しの天井が蛍光灯の無機質な光に照らされている。ああここは・・・お仕置き部屋、僕たちはここで散々鞭打たれていたんだったな。拘束台からは下ろされ、床に転がされていたがせめてもの慈悲だろうか、体には毛布が掛けられていた。う、うう・・・隣で信次が呻いているのが聞こえる。ああ信次も目を覚ましたんだな。ふと尻に手をやるともう出血は止まっているようだった。ツンと刺激臭のある軟膏のようなものが塗られていた。カタカタ、カタカタカタ、とパソコンを打つ音が聞こえてくる。
ううう・・・痛む体を引きずり起こすとお仕置き部屋の奥で怜と舞は持ち込んだノートブックPCに何かを打ち込んでいる最中だった。「あら二人ともお目覚め?ちょっと待っていてね、もう少しで切りがつくから。」10分位経つと、パタンとノートブックを閉じて二人は大きく伸びをした。「ふう、一服入れましょうか。」立ち上がった舞は部屋の片隅のポットから紙コップに湯気の立つ液体を注いだ。怜に一つを渡し、慎治たちにも一つずつ配った。「ミルクティーよ、お砂糖たっぷりと入れてあるから、疲れが取れるわよ。」湯気の立つ甘く芳しい液体は激しい鞭打ちに疲れ果てた慎治たちの体に沁み込んでいくようだった。がっつくように飲む二人に苦笑しながら舞が尋ねた。「そんなに急いで飲むと火傷するわよ。もう一杯飲む?」「は、はい・・・お願いします」「く、ください、お願いです・・・」もう一杯ずつ飲んで漸く二人が人心地着くのを待ってから怜が尋ねた。
「どう二人とも、私たちの鞭は効いた?痛かった?」ビクッと恐怖に震えながら慎治は答えた。「は、はい・・・とっても、痛かったです・・・」信次もまた鞭打たれるんじゃないか、と恐怖に怯えながら答える。「い、痛かったです・・・とても・・・もう反省、しましたから許して・・・ください・・・」
クスクスッと笑いながら舞が答える。「フフフ、随分応えたみたいね、よかった。私たちも鞭で人を打つのなんて初めてだからね、ちゃんと痛いかどうか心配だったのよ、まあ十分効いたみたいだし、良かったわ。ああ心配要らないわよ、もう鞭打つ気はないから。お尻、触ってみたんでしょう?一応止血と消毒はしておいたわよ。消炎剤も打っておいたけど、今日はかなり腫れてくると思うわ。そのくらいは我慢しなさいね。」にこやかに語る舞に、信次たちはほっと胸を撫で下ろす思いだった。よかった、ああよかった・・・もう鞭はお終い?ああよかった・・・信次たちがほっとするのを見た怜も笑いながら言った。「本当のことを言うとね、どういう体罰にしようか、て私たちも随分頭を悩ませたのよ。痛いだけじゃちょっと趣旨にそぐわないし、少し精神的にダメージを与える責めにしなくちゃいけないでしょう?真っ先に思い浮かんだのは唾を吐き掛けることだけど、それはもうやったし第一、矢作君たちは天城さんたちに毎日、唾を吐き掛けられるのは愚かおしっこまで飲まされている、ていうものね。」
そんなこと、本気で考えないでよ!どうやって責めようかなんて!慎治は喉まで出かかった言葉を必死で飲み込む。舞が後を引き取る。「そうなのよ。じゃあ単純にエスカレートさせてうんちを食べさせる、ていうのも勿論考えたわよ。」う、うんち!ま、まさか!緊張する信次たちを楽しげに見ながら舞は続けた。「でも折角霧島さんたちが、じっくりと君たちを苛めているんだものね。分かっているとは思うけど、いずれ近いうちに君たちは霧島さんたちにうんちを食べさせられるわ。彼女たちが大事に取っておいたお楽しみを奪っちゃ悪いものね、それでうんち責めも没、となったのよ。」う、うんち!うんちを食べさせられる!最悪の未来として恐怖に怯えながら必死で考えまい考えまいとしてきた悪夢を突きつけられ、信次はグッと胃の辺りに鈍痛が走る。そ、そんな・・・分かっているんだったら止めてよ!そんな酷い苛めはするなって・・・だが絶対無理、怜も舞も完全に玲子たちの味方だ、言うだけ無駄、いや却って怒らせるようなものだ。
押し黙ってしまう二人を見て、怜がフッと小さな笑いをもらした。「ねえ矢作君、ところで今のお仕置きなんだけどね、鞭が痛いのはまあ当然として、私たちの質問責め、どうだった?ああいう答えがない質問で苛められる、ていうのも結構厳しかったんじゃないかしら?」ぐううっ・・・慎治の脳裏についさっきまでの苦痛と焦燥が蘇る。どう答えても鞭、答えなくても鞭。だが答えないわけにはいかない。ただ打たれるよりも数段辛い責めだった。「は、はい・・・とっても辛かったです・・・単純に引っ叩かれるのよりずっと・・・辛かったです・・・」満足げに頷きながら舞が尋ねる。「そう、やっぱり鞭だけの責めよりずっと辛かったのね。じゃあ川内君、もう一つ質問。責められていた君にはそんな余裕なかったかも知れないけど、何か変だと思わなかった?私たち、鞭は初めてだから多少ぎこちなかったと思うんだけど、この質問責めは妙にスムーズ、慣れた責め口だな、と思わなかった?」「そ、そんな・・・辛くて痛くてそれどころじゃ・・・でも・・・」「でも?何?」「確かに・・・どう答えても全部先生の予想通り・・・罠に掛けられたみたいに・・・どうにも逃げるも言い訳も何もできませんでした・・・」あら随分と素直じゃない、よろしいよろしい。満足そうに舞が頷く。
「そう、やっぱり上手だったかしら?じゃあいいこと教えてあげるわね。私たち、鞭は確かに今日が初体験よ。だけどね、質問責めは前にもやったことがあるのよ。」え、やったことがある?まさかこんな酷くじゃないよな、子供のころ、誰かを苛めて泣かせた程度のことだろうな。半ば聞き流そうとした慎治たちは怜の言葉に耳を疑った。「フフフ、今日のなんかまだまだ生温いわよ。私たちね、責め殺したことがあるの。二人の男性、大人の男性をね。」ええ、ほ、本当に!?せ、責め殺した・・・殺したの!?流石に仰天した慎治たちは言葉を失ってしまい、暫しの間呆けたように怜と舞の知的な美貌をまじまじと見つめてしまう。せ、責め殺す・・・殺した、殺した・・・まさか・・・でも怜先生と舞先生、あんなに残酷なんだから、もしかしたら・・・絶句している二人を見て怜が可笑しそうに笑う。「アハハ、二人とも何凍りついているのよ、責め殺したって、私たちがナイフか何かで刺し殺して死体を山に埋めたか海に沈めたかでもしたか、と思っているの?」舞もケラケラと笑っている。「アハハハハ、二人ともいい加減バカな事考えないの!そんな本当に二人も殺したら今頃、私たち刑務所入りよ。責め殺した、ていうのは比喩に決まっているでしょう?そう、前置詞をつけて置くわね、精神的に、責め殺したのよ。」ああ良かった、本当に殺人を犯したんじゃなかったんだ・・・でも精神的に責め殺したって、どういうこと・・・一瞬ほっとした二人だったが、怜と舞の話を聞くにつれ、急速に青ざめていった。
「あれは今から丁度一年前ね。」怜が語り始めた。「私も舞も当時は未だ大学では講師でね、教授に来年助教授に昇進する、そして自分が定年退官したら次期教授を頼む、て言われたばかりだったのよ。分からないかも知れないけど大学は閉鎖的な社会でね、教授、助教授、講師、助手っていう階級制度は結構絶対的なものなの。私も舞も最年少助教授になるわけだけど、私たちが昇進する、ていうことは他の講師の人たちは教授になる目がほぼ確実になくなった、て言うことなの。もう精々が助教授、つまり遥かに年下の私たちにずっと仕えるしかないっていうことなの。まあ東大は傘下の大学が多いからね、他所に行けば幾らでも教授の口はあるんだけど、女の私たちに負けた、て言うのがどうしても納得できない人たちはいるのよ。」
舞も大きく頷いた。「そう。大部分の人はまあしょうがないや、てそれなりに納得するんだけどね。中にはどうしても納得できない人もいるのよ。まともに喧嘩ふっかけてくるとか辞表叩きつけるとかならいいんだけどね、閉鎖社会の大学にしかいない人たちって、中には結構変に歪んじゃう人もいるのよ。」フッとどこか遠い目をした怜が小さな笑いを漏らした。「私の方は最古参の講師、名取さん、ていう当時もう40才なのに独身の人ね。もともと私にかなり気があったらしくて私が結婚する前は大分お誘いがあったんだけど、好みじゃなかったからお断りしてたら一時はストーカーまがいの行為に走って大変だったのよ。まあ私が結婚したら諦めたようだったけど、私の助教授内定を機に再発しちゃってね、結構ディープなストーカーになっちゃったのよ。」
「私の方も似たようなものね。」舞もどこか懐かしそうに話し出した。「その人も40才独身、那珂さんといってね、講師としてはベテランだったけど研究者としては今一歩だったのよ。教育者としてはまあまあだったから、教授はどこか別の大学の一般教養なら十分に教授が勤まる、と考えたのよ。それで教授に頼まれて、箔付けに私の論文の何本かに共同執筆者として入れさせてやったのよ。そうしたらその人、何を誤解したのか逆恨みしちゃったの。私みたいな小娘にお情けで共同執筆者に名前だけ加えさせてもらうなんて、俺様のプライドが許さない、て言う訳ね。その私が助教授に昇進する、女の尻に敷かれるなんてやってられるか、てね。で、私の論文をパクッて盗作したり、挙句の果てにそれがバレるのを恐れて私の論文データをパソコンから消去しちゃったりと、酷い妨害工作に走り始めたのよ。」
怜が苦笑しながら続ける。「矢作君たちには一生関係ない世界だろうけどね、学者の世界、て狭い上にドロドロした伏魔殿なのよ。講師間でストーカーが発生しているなんて、格好の汚bのネタね、当然、それを利用して私や私の講座の足を引っ張ろうとする輩は多いのよ。」舞も頷く。「そう、盗作騒ぎは学者の世界、日常茶飯事だけどそれを同じ講座内でやって、しかも派手に妨害工作までしているなんて、講座内の管理能力を疑われちゃうわ。私たちの助教授昇進は愚か、研究者としての生命に関わることなのよ。どうしても、早急に排除しないといけなかったわけ。」
「でもね、早急に片付ける、といってもどうすればいいと思う?まさか君たち相手にするように、体罰を加えるわけにもいかないでしょう?第一、一応大学出で頭はいいんだから、迂闊に暴力に訴えたら逆にこっちが加害者にされかねないわ。」「そう、それに盗作うんぬんも、何年もかかって延々と論争しているケースなんて幾らでもあるわ。そんなのに巻き込まれて余計なエネルギーを使わされるのは真っ平ごめんよ。」「だからね、舞と相談して実力で彼らを排除することにしたの。二度と私たちに近づけなくなるように、大学からも学界からも永久追放されて、絶対に戻ってこれないようにしてやろう、てね。」「ほんと、正直言うと殺してやろうかと思ったわよ、でも肉体的に殺すわけにはいかないでしょう?私たちが手を汚したなんて言われたら困るからね、だから絶対に証拠が残らないようにやる必要もあったのよ。それで色々考えた末にね、怜とこう決めたのよ。肉体的に殺せないなら精神的に抹殺してやろう、再起不能になるまで精神を破壊してやろう、てね。分かる?どういうことだか。平たく言うとね、彼らを精神崩壊するまで責めて責めて責め嬲り抜いて、発狂させてやったのよ。」
ウフフフフ、怜が残酷な笑みを浮かべた。「そう、あの二人をね、キチガイにしてやったのよ。キチガイになるまで苛めてやったの。殺しはしないわ、発狂させた後は自由に解放してあげたわよ、それだったら元々犯罪行為の匂いすらないからね、警察が乗り出すまでもなく、事件にすらならずにおしまいになったわ。」舞も懐かしげな表情に楽しそうな笑みを浮かべた。「あの二人、どうしているかなあ。一応精神病院に入院はしたみたいだけど、治療は不可能、ていうことで退院したあと実家に引き取られていったわ。東大出の自慢の息子がキチガイになっちゃった、てご両親、泣いていたわねえ。」
言い終えた舞がじっと信次を見詰めた。「フフフ、川内君、どうやって発狂させたか教えてあげようか?」ヒッ!そ、そんなこと、聞きたくない!だがそうは言えない。舞に対してイエス以外の返事をする気にはなれなかった。「は、はい・・・教えて・・・ください・・・」うんうん、いい子ね、というように舞はニコリと笑うと話し始めた。「川内君、あなたは霧島さんたちに散々苛められていたんだったわよね。何回も何回も、失神するまで苛められたんでしょう?じゃあ聞くけど、一番苦しい失神の仕方はどういう失神だった?」「そ、それは・・・」信次は思わず口ごもってしまった。玲子に、朝子に失神させられた苦い記憶が甦る。踵落とし、ブーツキック・・・だけど一番はやっぱり鞭かな。
「鞭で・・・気絶するまで打ちのめされた時です・・・二人掛り、四人掛りで・・・」「うーん川内君、私の質問の意味が分からなかったみたいね。私は苦しい、て言ったのよ?鞭での失神は苦しい、ていうより痛いじゃないの?」「まあまあ舞、もしかしたら川内君は経験ないかもしれないわよ、矢作君、君はどう?苦しい失神はどんな失神だった?」苦しい、苦しい・・・慎治は必死で怜と舞の意に沿う答えを考えた。苦しい・・・やっぱり、あれかな・・・「首を・・・ブーツで絞められた時、かな・・・礼子さんのブーツが喉に食い込んで息ができなくて、もがき苦しんだ挙句にちょっとだけ息吸わせて貰えて・・・中々気絶すらさせて貰えなくて延々と苛められた時とか、フミちゃんに唾を鼻に入れられて窒息させられた時、です・・・」「うん、そうビンゴ、正解よ!」怜が楽しそうに両手を叩いて笑った。
「窒息責め、て苦しいでしょう?長い時間をかけてジワジワと苦しめられて中々気絶すらできないし、脳震盪のように一瞬で気絶したり脳貧血のように痛覚が麻痺してくれないからね、最後の一瞬まで延々と苦しみを味わい続けるのよね。」舞も大きく頷いていた。「そう、それと窒息責めにはもう一つ、とてもいい長所があるのよ。それはね、拷問を加えたという証拠が残らないこと。勿論、肺や心臓、気管、更には脳と全身に蒙るダメージは大きいわよ。だけど少なくとも体の表面には殆ど傷は残らないわ。責める私たちにはそれがまたいいのよ。例えば今みたいに鞭で追い込むのもいいけど、それだとあなたたちみたいに全身傷だらけになっちゃうでしょう?それじゃあ折角発狂させても、解放した時に全身の傷を見て警察沙汰になるリスクがあるわ。それは困るからね。」
恐ろしいことを平然と言い放つ怜と舞に、慎治たちは心底恐怖していた。ま、まさか・・・でも先生たちならやりかねない・・・思わず礼子たちの姿を思い浮かべた。礼子さんたちも、僕たちの命に関わるような責めはしないけど、残酷なことはどんな酷い事でも平然とやるよね・・・殺しはしない、その一線さえ守れば玲子さんと同じ、却ってどんな残酷なことにも抵抗がなくなっちゃうかもしれない・・・思わず絶句する二人を面白そうに眺めながら怜が続ける。「じゃあ具体的にどうやって拷問したか、教えてあげるわね。最初は名取さんの方を攫ってきたのよ。夏休みで講義が休みの時を狙ったから、独身男性が何日か行方不明になったってどこか旅行にでも行ったんだろう、としか思われないわね。それでね、私たちの別荘に監禁したのよ。そこで3日3晩責め続けたの。どうやってか、ていうとね、名取さんは私をストーカーしていた、て言ったでしょう?つまり私のお尻を追い掛け回していた訳よね。ウフフフフ、単に窒息責めだけなら水に漬けるとか、ガムテープで口や鼻を塞ぐとか簡単で有効な方法は幾らでも考え付くけど、それじゃあ恐怖と屈辱を与え続ける、ていう目的を達成できないでしょう?だから、名取さんの希望を、夢を叶えてあげることにしたのよ。」「ゆ、夢?か、叶える?」余りの恐怖に慎治は尋ねずにはいられなかった。
「フフフフフ、もう薄々と分かっているんじゃない?そう、散々追っかけまわした私のお尻をたっぷりと味合わせてあげることにしたのよ。簡易ベッドを改造して拘束台を作ってね、それに縛り付けて私と舞のお尻の下敷きにして窒息させたのよ。」舞も残酷な笑いを浮かべながら言う。「アハハハハ、怜のお尻を追い掛け回した名取さんが怜のお尻で苦しめられる、正に因果応報、て奴でしょう?名取さんが発狂した後ね、今度は那珂さんを攫って来たのよ。そして名取さんと同じく、私たちのお尻の下で窒息責めに合わせたの。楽しかったわよお?だって女の私の尻に敷かれるのが死ぬほど嫌だった那珂さんが、私のお尻に敷かれて泣き喚いているんですものね。最高だったわ。面白いことにね、名取さんと同じく丁度3日3晩責め続けたところで発狂したわ。」
アハハハハ、と心底楽しそうに笑いながら怜が尋ねる。「ところで矢作君、一つ不思議なんじゃない?本当に窒息責めで発狂するのか、て。僕たちも鞭やブーツで何回も失神しているけど、発狂はしていないぞ、て?」怜の言うとおりだった。尻に敷かれて窒息責め、確かに苦しそうだ。だがそれで気絶させられた程度で本当に人間は発狂するものなのだろうか。信次も同じ事を感じているのに気づいた舞が言った。「川内君も同じ疑問を感じているようね。まあ当然でしょうね、何回か失神させられた程度じゃあ、確かに人間は発狂なんかしないわよ。だけどね、さっきの私たちの鞭を思い出して貰える?あなたたちも言ってたわよね、ああやって答えのない質問を繰り返されながら苛められるのは、単純に鞭で打ち続けられるよりもずっと辛い、て。」う、信次は微かな声で呻いた。
「そう、私と怜はね、さっきと同じように責めたのよ。答えのない質問責め、それだけじゃあないわ。君たちはさっき、間違えても鞭で10発ずつ鞭打たれただけよ。だけど名取さんと那珂さんはね、一回間違えるごとに窒息責めで気絶させられたのよ、全身を苦痛で痙攣させて散々もがき苦しんだ挙句にね。」「それだけじゃないわ、今は矢作君たちと私たち、二対二でしょう?だけど名取さんたちは一人だからね、私たちは二人掛りで苛められるのよ。分かる?私と舞と交代でね、夜も昼もないわ、一日24時間、ノンストップで責め続けたのよ。拷問する側の私たちは交代で休憩もするし食事もする、睡眠も取れるわ、だけど名取さんたちはそうはいかない。拘束台に縛り付けられたまま、ノンストップで責め続けられて、漸く失神しても休憩なんかさせてあげない、直ぐに活を入れて息を吹き返させ、直ちに拷問再開よ。勿論、水の一滴も飲ませないし食べ物なんか一切与えないわ。文字通り飲まず食わずで責め苛み続けたのよ。」「ううん、私も怜も拷問、てさっきから言ってるけど、拷問よりも酷いわよね。だって拷問ならば自白すればいいんだけど、自白することなんか何もないんだもの。単なる苛めにしても、気絶したら、とか時間の制約とかいろいろとリミッターはあるわよね?だけどあの時は完全無制限だもの、発狂に追い込む、ていう目的を知っているのは私たちだけ、那珂さんたちは何も教えて貰えずに、ゴールがどこにあるかも分からずにひたすら苦しみ続けるだけだったのよ。大体ね、3日3晩一睡もさせない、しかも完全に飲まず食わずなんだからそれだけでも十二分に苦しいわよ。」
少し間をおいた怜が楽しそうに話し続ける。「面白かったわよお?散々私を悩ませた名取さんがね、私のお尻の下で泣き喚いて、必死で哀願して許しを乞い続けるんだから!バカよねえ、許してなんか貰えるわけないのに。」「怜の言うとおり、本当に楽しかったわ。那珂さんもね、攫われてきた当初は強気で「何をするんだ!さっさと放せ!」とか喚いているのよね。ウフフ、だけど一回気絶させてやるともう泣き声で「お願い許して・・・もう日向さんの邪魔は決してしませんから・・・」とか言い出しちゃってね。」「そうそう!」怜も手を叩いて笑っている。「でもそれも無視して責め続けるじゃない、そうすると今度は逆ギレしてくるのよね。「ち、畜生!う、訴えてやる!絶対復讐してやる!」とか言っちゃってね。」「アハハハハ、そうだったそうだった!」舞も大笑いしている。「そうそう、その反抗期を過ぎるともう、自我が崩壊寸前になっていくのよね!声も弱々しくなっちゃって、「おねがい・・・ゆるして・・・」とか殆ど切れ切れにしか哀願できなくなっていくのよね。それも過ぎるといよいよ最終段階。」
怜が頷く。「先ずは言葉がでなくなるのよね。いくら責めても出てくるのはアアア・・・ウウウ・・・とかいう弱々しい悲鳴というか嗚咽だけ。苦痛に体は反応するけど、意識が混濁して頭が現実を認識できなくなっていくのよね。」舞が床を指差した。「拷問した部屋はワインセラーになっている地下室でね、外の光が一切入らないし音も殆ど聞こえないのよ。明るさも常に変わらない蛍光灯だけだから時間の感覚も直ぐに消滅しちゃってね、一体いつから自分がここにいるのかいつまでいるのかも分からなくなって、時間の流れも認識できなくなっていくのよ。」
にっこりと笑いながら怜が問い掛ける。「矢作君、天城さんたちに苛められた時、夜はどうしてる?死んだように眠りこけてるんじゃない?一日中責められたら全身ボロボロ、精も根も尽き果てて泥のように眠っちゃうでしょう?」確かにそう、怜の言うとおりだった。「は、はい・・・もう眠らずには・・・いられません・・・」慎治の答えに頷きながら舞が言った。「そうでしょう?眠らずにはいられない筈よね。全身が休息を要求するでしょう?だけどね、私たちは一睡もさせなかったのよ。さっきも言ったとおり、気絶したら直ぐに息を吹き返させて即刻拷問再開よ。だけど時計もないし光も音も、全てが一日中変わらない。ううん、それだけじゃあないわ。私と怜は交代で苛めた、て言ったでしょう?だからそれぞれの休憩時間を利用してね、服も下着に至るまで大急ぎで洗濯して、ずっと同じ服装、香水やメイクに至るまで全て同じにして責め続けたのよ。フフフ分かる?同じ顔、同じ体格同じ声の私たちがずっと同じ服装で責めるの。どれ位責められ続けたか今誰に責められているのか全く分からなくしてあげたのよ。疲労と肉体的ダメージでボロボロになった那珂さんたちをそうやって、錯乱状態に追い込んでいってあげたの、フフフ、効果抜群だったわよ?」
うう、ううう・・・信次は恐怖に思わず呻いてしまった。全く同じ顔の二人の責め。しかも休息なし、自分がどれだけ気絶したかも分からず、責めのゴールすら想像できない。恐ろしい責めだった。まさに地獄、永遠に苦痛のみが続く究極の煉獄だ。ま、まさか・・・まさか・・・怖い、余りにも怖い想像が信次の脳裏から離れない。なんでこんな事を俺たちに教えるんだ・・・まさか、慎治と俺をそうやって拷問するつもりじゃ・・・ふと横を見ると慎治も同じ恐怖に怯えていた。そ、そんな!は、発狂だなんて嫌!今さっき飲んだミルクティーの温かさもどこへやら、二人は余りの恐怖にガタガタと震えていた。怜先生も舞先生も・・・二人とも同じスーツを着ている・・・同じブーツを履いている・・・香水の香りも同じだ・・・ま、まさか・・・
怜と舞は恐怖に震え、怯えきった二人を穏やかに微笑を浮かべながら見詰めていた。優雅な手つきで、ゆっくりとミルクティーを飲み干していく。カップの中の液体はもうあと僅かのようだった。グッと最後の一口を飲み干した二人は静かにカップをテーブルに置いた。「フフフ、どうしたの?そんなに怯えちゃって。」怜の微笑は残酷な冷笑に変わっている。「さあ休憩はおしまい。少しは人心地ついたでしょう?良かったわね、今話した那珂さんたちには、こんな休憩タイムは全然なかったのよ。」ゆっくりと舞が立ち上がった。「ねえ二人とも、ここには今鞭打たれたこの大部屋の他に奥に二つ、小部屋があったわよね?部屋の中、もう一度よく見せてあげるわ。いらっしゃい。」ガチャッと扉が開けられ、怜が小部屋の蛍光灯のスイッチを入れた。「ヒッ!ヒイイイイッッッッ!」「そ、そんな・・・そんなあああ・・・」真ん中に設置された台を改めて見た慎治たちの口から悲鳴が漏れた。そこに設置されていたのはクッションを取り外され骨組みだけとなったスチールベッドだった。しかも上部には首、真ん中には両手および腰、そして下部には両足を固定するための頑丈な革ベルトが骨組みから伸びている。上から1/3程度の所には起倒式の背もたれ、フレームのみで間に犠牲者が潜り込む形となる、拘束具兼用の背もたれもついていた。しかも上部ベルトの更に上には万力のような、可動式らしい留め具が二本突き出ていた。留め具は顔面に添う形で30センチ近い長さがあった。奇妙なことに頭を横たえる最上部は大分幅が狭くなっており、かつ首が台から落ちないように縁が高くなっていた。
こ、拘束台!!!間違いない、どうみても怜と舞が邪魔者を処刑した拘束台、名取と那珂という二人の男が発狂させられた拷問台に間違いなかった。「フフフどう矢作君、もうわかったでしょう?そう、これが今教えてあげた拷問台よ。土曜日に天城さんたちから君たちの犯罪を聞いてね、大急ぎで別荘から運んで来たのよ。軽井沢日帰り往復なんて結構疲れるんだからね、感謝しなさいよ?」「そ、そんな・・・怜先生、感謝だなんて・・・」「ウフフ、川内君、心配しないでもいいわ、君用の拘束台はちゃんと隣に用意してあるからね。那珂さんたちを拷問した時に、壊れたら面倒、と思って予備を作っておいて良かったわ。二人で一台なんてケチな事は言わないわ、二人とも専用のベッドを用意してあげたから。遠慮なく苦しんで頂戴ね。」「い、嫌だ・・・舞先生・・・お願いやめて・・・狂いたく・・・ない・・・」信次がボロボロ涙を溢しながら哀願するのを見て舞はカラカラと手を叩いて大笑いした。「アハハハハッ!何深刻な顔して泣いているのよ!少しは展開考えなさいよ!いい、さっき言ったでしょう?川内君たちはその内、霧島さんたちにうんち食べさせられる、て。そのお楽しみを邪魔しちゃ悪い、とも言ったわよね?そうやって気を使っている私たちが、君たちを発狂まで追い込むわけないじゃない!」苦笑しながら怜も頷いた。「全く・・・大体考えてみなさいよ、私たちは3日3晩責め嬲って名取さんたちを発狂させたのよ?いくらなんでも今から3日間、君たちを責め続けるほどの時間を取れるわけないじゃない!これでも私たち忙しい身なのよ、君たちにそんなにずっと付き合うことはできないわ。」
ああ良かった・・・発狂させられないで済む・・・信次たちがホッとするのを見澄ましたように舞が言い放った。「フフフ、どうしたの二人とも安心しちゃって?いい、確かに私たちはもう責める気はないわ、だって君たちを責める適役は他にいるものね。ウフフ、君たちにとって最も怖い女性が。君たちを責めるのはその子たちの役目よ。アハハハハッ!彼女たちのお尻の下でたっぷりと苦しみなさい!」「ああ、あああああ、そ、そんな・・・まさか・・・」怜の瞳にも残酷な光が浮かんでいた。「君たちを責めるのが誰かなんて、もう言わなくてもわかっているわね?君たちが一番怖いのは誰かしら?アハハハハッ、そうよ天城さんと霧島さんよ!あの二人にはたっぷりと窒息責めのやり方もこの拘束台の使い方もレクチャーしておいたわ。張り切ってたわよ二人とも、女の子に暴力ふるって怪我させた最低男の君たちに、女性の怖さをたっぷりと思い知らせてやるってね。フフフフフ、女の子のお尻を見ただけで条件反射で震え上がる位、苦しい目に会わせてやるってね!」「い、いや、いやあああああ!!!」床に崩れ落ちて泣き喚く二人の無様な姿に怜と舞は大笑いしていた。丁度その時、タンタンタン、と階段を下りる軽い足音が聞こえてきた。「ヒッヒイイイイッ!」「ああ、あああああ・・・・・」部活を終えた礼子たちがやってきたのだ、慎治たちに窒息責めを加えるために、地獄の苦悶を味合わせるために。
1
「遅くなりましたあっ!どう慎治、怜先生にしっかりお仕置きしてもらった?」明るい声をあげながら礼子たちが入ってきた。「お帰りなさい、丁度いいタイミングだったわ、鞭でのお仕置きで一回お寝んねしてね、今二人とも起きたことろよ。一息ついてフフフ、丁度いい責め頃よ。」ヒッ!せ。責め頃だなんて・・・怯える二人の事など全く意に介さず、舞が玲子たちに椅子を指した。「まあ二人とも、座って一服しなさいよ、紅茶でもいれるわ。」「あ、有難うございます!舞先生、どんなお仕置きしたんですか、教えて下さいよ!」腰掛けるや否や、興味津々と言った様子で玲子が尋ねた。「はいはい、全くウキウキしちゃって霧島さんは、もう根っからの苛めっ子ね!」カラカラと楽しそうに笑いながら舞が答える。「取りあえず二人とも、鞭でお尻ズタズタにしてあげたわ。ウフフフフ、楽しかったわよ、色々言葉でも追い詰めながらね。あんまり楽しくて私も怜もついついお仕置きに力が入っちゃったわ。川内君、二人とも立って霧島さんたちにお尻、見せてあげなさい。」穏やかな口調だが信次たちが逆らえるわけがない。「は、はい・・・」のろのろと立ち上がった二人は全裸の惨めな姿のまま、怜と舞にズタズタにされた尻を玲子たちに向けた。「わあっすっごーい!」「流石は怜先生!もう血塗れに引き裂いた、て感じですねえ!」美貌のクラスメート、自分たちを地獄に突き落とした張本人に惨めな傷跡を嘲笑われる、それだけで十二分な恥辱だ。だが恥辱などほんの始まりに過ぎない。もう間もなく礼子たちに苛められるのだ。窒息責め、怜たちが邪魔な男を発狂させたという恐怖の責めを味合わされるのだ。クックッと礼子たちはゆっくりと香り高い紅茶を飲み干していく。まるで死への砂時計を刻まれているようだ。あの紅茶を飲み終えたら・・・窒息責めをされる!逃げ出したい、どこかに逃げ出したい!でもどこへ?両親さえもう敵に回ってしまったのだ、「慎治くんたちがお仕置きから逃げました、連れ戻してください。」と言われれば慎治たちの両親は何の躊躇もなく二人を学校に、残酷な美女たちの鞭の下に連れ戻すだろう。絶望、ただそれだけが二人の全てを支配していた。
コクッと最後の一口を飲み終えた礼子がカチャッと小さな音を立ててカップをソーサーに戻した。ビクッと震える慎治を一瞥しながら礼子はフッと小さく息をついた。「ごちそうさまでした。おいしかったです。」「そう、良かったわね。じゃあっと」ウン、と小さく伸びをしながら怜と舞が立ち上がった。「じゃあ天城さん、霧島さん、後はよろしくね。ええと、鍵はもう渡したわよね?施錠だけはよろしくね。」い、行ってしまう!怜先生が・・・そしてその後は・・・礼子さんに窒息責めされる!「ああ、あああ・・・先生・・・行かないで・・・」涙声で哀願する慎治に、怜は一瞬キョトンとした表情を浮かべた後、何とも言えない苦笑と嘲笑の入り混じった笑いを浮かべた。「全く・・・矢作君、あなた一体どういうつもりで今、私に行かないで、なんてお願いしたの?いい、君は今、私にお尻を鞭でズタズタに引き裂かれたばかりでしょう?分かってるの?君にとって私は、天城さんたちと同じ責め手、拷問官でしょう?その私に行かないでなんて、正気で言っているの?」呆れた、というように首をすくめながら舞も苦笑する。「まあどうしても行かないで、て言うなら残ってあげてもいいけど、それは君たちにとって窒息責めの責め手が一人から二人に増えるだけだと思うわよ?全く・・・君たち本当に・・・おバカね!」ぐうっ・・・何も言えなくなった二人を一瞥すると舞は玲子に言った。「まあ霧島さんたちも、先は長いんだから余り無茶しないようにね。あ、それと例の件、予定決まったら簡単にメモにして頂戴ね。急がせて悪いんだけど根回しもあるからなるべく早め、できたら今週中に貰えないかしら?」「あ、あれでしたらもう大体やること、もう決めたんです、明日にはメモ、お渡しします。」打てば響くような玲子の答えに二人は満足そうに頷いた。「流石は霧島さん、ほんとクイックレスポンスで気持ちいいわね。じゃあよろしくね。」な、なになになになんなんだ?例の件って?怜と舞が出て行き一瞬静かになったお仕置き部屋、その重苦しい空気に怯えながらも信次は聞きたくて聞きたくて仕方がなかった。「フフフ信次、どうしたのよモジモジしちゃって、どうせこのことでしょ?例の件って何、て聞きたいんでしょ?」「あ、は、ハイ・・・聞かせてお願い・・・」ニヤリと玲子の口元に残忍な笑みが浮かぶ。「いいわ、教えてあげる。私と礼子はね、舞先生たちに信次たちのお仕置き計画を頼まれたのよ。今日この場でのお仕置きなんかじゃないわよ。ウフフフフ、全校に恥を晒して、女の子に暴力振るった男はこうなるのよ、それだけは聖華では絶対に許されないことなのよ、ていうことを知らしめるお仕置きよ。ああそう怯えなくてもいいわ、痛い、という意味では多少は痛いけど安心していい、信次たちにとっては十分耐えられる筈よ、肉体的にはね。だけど、フフフフフ、精神的には辛いわよ?たっぷりと生き恥を晒させてやるからね?」「ひいいいいいっ、そ、そんな・・・、何をさせる気なの・・・」傍らで慎治が思わず呟くのを礼子は聞き逃さなかった。「慎治、心配しなくてもいいわよ、もう何日かすればどうせ嫌でも分かるんだからね。それより慎治が心配しなくちゃいけないのは他のことよ。フフフ、窒息責め、たっぷりと苦しめてあげるからね!」ああ、あああ・・・完全防音のお仕置き部屋に礼子と慎治、そして玲子と信次。責める側の礼子たちにとっては最高の環境、そして犠牲者の慎治たちにとってはこれから先、まさに地獄を味わい続ける場所だった。
「さあ、私たちもブーツに履き替えようかしら。」えっブーツ!?慎治たちの背筋にゾクッと寒気が走る。お仕置き部屋の片隅に置かれた大型のバッグに向かって礼子たちが歩いていく。見覚えのあるバッグだった、あれは確か・・・週末、レンタル体育館に連れて行かれる時に礼子さんたちが鞭やブーツを入れてくるバッグだ!「怜先生たちもわざわざブーツを履いて慎治たちをお仕置きしてくれたそうじゃない?流石は怜先生よね、慎治たちがどうやれば怯えるか、よくご存知よね。だったら私たちがこれからどうすると思う?ウフフ慎治、どうやら分かっているみたいじゃない?そうよ、あのブーツを持ってきてあげたのよ。黒ブーツをね!」礼子が取り出したのはまさに、慎治たちの血と涙をたっぷりと吸った漆黒のブーツだった。礼子たちの黒ブーツと富美代たちの白ブーツ、このブーツにどれだけ苛められたことだろう。「ウフフフフ信次、どういうことか分かるわよね?このブーツを私たちが履いたらどうなるか?」ヒッ、ヒイイイイッッッ!信次は声にならない悲鳴を上げた。ブ、ブブブブ、ブーツ!黒ブーツ!れ、玲子さんたち、このブーツ履くと残酷さ100倍増じゃないかあああっ!「あああ、お、お願い、ブーツは、ブーツだけは許してえええっ!」必死で絶叫する信次を見据える玲子が嗜虐の楽しみを満喫するかの如く、ゆっくりとブーツに脚を入れていく。「フフフフフ、分かっているみたいじゃない信次、そうよ、このブーツ履いちゃったら私たち、リミッター全解除よ!」ブーツを履いた礼子たちはまさに残酷さ全開、慎治たちにとっては地獄の悪鬼と化してしまう。例え僅かであっても手加減してくれる望みが全く絶たれてしまう。「そ、そんなあああ・・・」「やめてお願い・・・履かないで・・・」哀願する二人の情けない顔を楽しみながら礼子たちはチーッとゆっくりとブーツのチャックを上げていく。ピタッと細身のブーツが脚に吸い付く感触が二人の心を燃え立たせる。「さあ信次、戦闘準備完了よ!覚悟はいいわね?」玲子が勢いよく立ち上がった。
「さあ慎治は礼子と一緒に左の部屋、信次は私と右の部屋よ。ウフフフフ大丈夫、心配しないでいわ、壁は防音じゃないからね、ちゃんと慎治の苦しむ悲鳴は聞こえるわよ。勿論、信次の悲鳴もあっちに届くからね、二人で仲良く苦しみなさい。あ、もっとも苦しすぎてお互いの悲鳴なんか聞いてる余裕ないと思うけどね。アハハハハッ!」楽しそうに笑いながら信次を引き立てて玲子が隣の部屋に移動し、後には礼子と慎治だけが取り残された。「フフフ、丁度小部屋が二つあって良かったわ。」礼子が口を開いた。「お尻の下で窒息させる、と言ってもね、私たちも服が乱れるでしょう?玲子も私も、お互い自分のお尻を見られるのは嫌だからね、おトイレと同じでちゃんと個室があって良かったわ。そう言えば慎治は中学の頃から私に憧れていたのよね。ウフフフフ、今でも憧れているかしら?」そ、そんな・・・憧れの感情などとうに消え失せている。だが慎治の中で礼子がかって憧れの存在、文字通り偶像に近い、言葉の真の意味でアイドルであったことは確固として刻み込まれている。だからこそ、その憧れの存在、礼子に責め苛まれるのは他の女の子に苛められる何倍も辛い。礼子は慎治のそんな感情を読み尽し、手玉に取って弄んでいた。「鞭で打ちのめされ唾を吐き掛けられ、おしっこまで飲まされても未だ、私に憧れている?流石にもう無理かしら?アハハハハッ!でも私のお尻にも憧れていたんでしょう?いいお尻だなあ、触りたいなあ、て散々妄想していたんじゃない?望みをかなえてあげるわよ、今日は慎治にたっぷりと私のお尻を堪能させてあげる!心行くまで私のお尻を堪能するがいいわ。憧れの私のお尻を、この天城礼子のお尻をね!遠慮はいらないわ、嫌といっても無理矢理堪能させてあげる。ウフフフフ、責め終わったらどうなっているかしら、私のお尻、憧れから恐怖の象徴に変わっているかもね!」
隣室に連れ込まれた信次も死刑宣告を受けていた。「ねえ信次一つ聞かせて、信次、私のこと大嫌いでしょう?憎くて憎くて堪らないでしょう?殺したくて仕方ないでしょう?正直に言いなさい!」と、当然だろう!ぶ、ぶっ殺してやりたい・・・だがそんなことを口に出せるわけがない。「そ、そんなこと・・・ないです・・・」消え入りそうな声で答える信次を玲子は嘲った。「嘘言いなさい!毎日毎日こんなことされて悔しくないわけないでしょう?ほらこんなことされても?ペッ!ほら!ペッ!」二度三度と玲子は唾を吐き掛けた。ち、畜生、気軽に唾吐き掛けやがって・・・信次の顔が屈辱に歪むのを玲子は楽しそうに見下ろしている。「ウフフフフ、こうやって毎日毎日唾吐き掛けられているんだものね、信次、私の唇もう怖くて怖くて仕方ないでしょう?」ヒッ!突然玲子が平手打ちをするかのように手を振り上げ、信次の悲鳴が漏れる。「アハハハハハッ、いい反応よ。当然よね、ビンタに鞭にと、私の手に散々痛めつけられたんだものね。ウフフフフ、私の足も当然怖いでしょう?ブーツで踏み躙られて蹴り倒されたんだものね、怖くて怖くて堪らないでしょう?ウフフフフ信次、今からもう一つトラウマを植えつけてあげる。そうよ、私のお尻。フフフフフ、私のお尻を見ただけで震え上がるほど、苦しめてあげるからね!」「い、いや、いやああああっ、そんなそんな、いやだあああああっ!」必死で首を振り泣き喚く信次を見下ろしながら、玲子はゆっくりと立ち上がった。「さあ信次、お仕置き後半戦よ。ウフフフフ、私のお尻、たっぷりと味合わせてあげるわ。」「そ、そんな・・・玲子さん・・・お願い、もう・・・苛めないで・・・」「苛める?何を言ってるのよ失礼ね!これは信次に対する正当な処罰、ご両親も公認の体罰よ!苛めだなんて、全く失礼ね!どうやらまだまだ反省が足りないみたいね、たっぷりと懲らしめてあげるわ!」「ヒッ、ヒイイイッ!こ、懲らしめるだなんて、そ、そんなああああ・・・」「怖い?当然よね、窒息責め苦しいわよ?多分さっきの舞先生たちの鞭よりも辛いんじゃないかしら。だけどね」玲子の美貌にも冷酷な笑いが浮かぶ。「そんなに嘆き悲しむことはないんじゃないかしら?」「そ、そんな・・・窒息させられるのに・・・悲しいに決まってるじゃないか・・・」座り込んで泣きながら抗議する信次を玲子は楽しそうに見下ろしている。「あらそうかしら?例え窒息責めと言っても信次、私のお尻をたっぷりと味わえるのよ?こう見えても私、もてるのよ?顔面騎乗なんて言葉もある位なんだから、私に座られたい、ていう男は幾らでもいるわよ。嘘だと思ったら沖あたりにでも聞いてご覧よ、霧島玲子が僕の顔面に座る、て言ってるけど代わってくれないか、てね。きっと沖、大喜びで代わってくれるわよ。私が座ってあげたら泣いて喜ぶんじゃない?沖だけじゃないわ、多分クラスの男の子の殆どみんな、私か礼子に座られたい人手を上げて、て言ったら一斉に手をあげるわよ。ウフフフフ、信次みたいなクズが私に座ってもらえるなんて、光栄と思いなさい!」
「そんなあああ・・・」「い、いやだあああああ!!!」二人の悲鳴と哀願を楽しんでいた礼子たちの美しい唇から、遂に処刑開始の宣告が発せられた。「さあ、拘束台に登りなさい!」「はい、泣き言はもういいから、さっさと拘束台に寝るのよ!」泣きながら慎治たちは拘束台に登り、横たわった。手馴れた手つきで礼子たちは慎治たちの手足を、首を、腰を固定していく。あっという間に慎治たちは完全に身動き一つ出来なくされた。二人にももう分かっていた、礼子たちのような冷酷な拷問官の前で身動き一つできなく拘束され、抵抗の術を完全に奪われることが何を意味するかを。これから加えられるであろう責め苦の苦しさの予感に慎治たちは止め処もなく涙を流し続けていた。首のベルトをグッと締め上げた礼子が、締め具合を確認する。喉に食いこんではいないが頭を全く持ち上げられない、絶妙の締め具合だ。「さあ最後はこれよ。」キリキリキリ、と拘束台のサイドに取り付けられたハンドルを回すと、慎治の顔面の両側から万力の留め具が迫ってくる。「あああ・・・やめてえええええっ!」慎治の悲鳴を無視して礼子はハンドルを回し続ける。留め具は慎治の両耳の辺りにがっちりと食い込み、最早首を上下左右、どの方向に動かすこともできない。隣室でも同じく万力に締め上げられた信次に玲子が声をかけた。「聞こえる信次、耳を塞がれても私の言うこと位は聞こえるでしょう?」「あうううう・・・玲子さん・・・お願い外して・・・」「何、万力外して欲しいの?」「お願いですううう・・・外してくださいいいいいい!」「アハハハハッ!へーえ、そうなんだ、万力外して欲しいんだ!いいわよ、後で外してあげるわ。ウフフだけどね、きっと信次、万力外して貰ったことを後悔するわよ?」「こ、後悔?な、なんで・・・」信次が言えたのはそれまでだった。
「逝くわよ・・・」礼子がゆっくりと慎治を跨ぐように立ち、腰を下ろし始めた。紺ブレのスカートがゆっくりと降りてくる。視界の全てが礼子のスカートに覆い尽され、尻がもう間近に迫った最後の瞬間、礼子はスッとスカートの裾を後方に捲り上げた。スカートの中には純白の薄いパンティに包まれた美しい尻が双丘のように聳え立っていた。「ぐぶうううううっっっ!」礼子の張りのある、鞠のように弾力のある美尻が着地した瞬間、慎治の口から何とも言えない悲鳴が漏れた。顔に布の感触を感じた次の瞬間、鼻、目、額、そして口と顔中全てに加速度的に強烈な重みが掛かってきた。「グフィイイイイイッ!」悲鳴を上げながら慎治は必死で逃れようと反射的に全身に力を込めた。ギシッとベルトが軋む音がする。だが頑丈な革ベルトは全く緩まず、大型万力でしっかりと固定された頭は左右に動かすことなど全くできない。首を思いっきり前に起こせば顔がスポッと万力から抜け出られるかも知れないが、礼子が顔の上に座り込んでいるのだ、首の力だけで跳ね飛ばすのはプロレスラーでも難しい、ましてや慎治になど逆立ちしても不可能だ。「グウッ、グウウウッ、グブウウウウウッッッ・・・」「フフフどう慎治、苦しい?重い?ウフフフフ、でもね、未だ私は全体重をかけてはいないのよ、重くなるのは・・・これからよ!」楽しげに笑いながら礼子は僅かに伸ばしていた膝から力を抜いて全体重を尻に、椅子に、即ち慎治の顔面へと掛けていく。グギュウウウ・・・顔面全体への圧迫が一層強まり慎治は悲鳴を上げることすら困難な状況だ。慎治の上顎あたりに腰を下ろした礼子はそのまま太腿を慎治の顔面にピタリと密着させ50キロ強の全体重を顔面の狭いエリアに集中させる。見えない、慎治の目は礼子の太腿の下敷きにされ殆ど何も見えない。耳は万力に塞がれ何も聞こえない。そして鼻は礼子の股間に押し当てられピタリとパンティが張り付いたような状態だ、呼吸をすることすら困難を極めた。ぐ、ぐ、ぐぐぐ・・・ぐるじい・・・いだい・・・苦しいだけではない、手で僅かでも礼子の体を支えて苦痛を軽減することすらできない、一切の支えなしで顔面に全体重を受けているのだ。しかも慎治が寝かされている拘束台はクッションなど全くない硬い板でできている。礼子の全体重を掛けられている後頭部は骨がミシミシいっているかのようだ。余りの痛さと苦しさに慎治は目の前がクラクラしてきた。頭が・・・頭が割れるうううっ!ナットクラッカーに挟まれたクルミのように、自分の頭が礼子の尻にグシャリと押し潰されてしまう映像が頭に浮かんだその時、礼子がスッと僅かに腰を浮かした。「ぐはっくはあああっ・・・あっあっあっ・・・」必死で荒い息をする慎治を満足気に見下ろしながら礼子は笑っていた。「アハハハハッ!苦しいでしょう?痛いでしょう?でもね、まだまだほんの序の口よ。私はこの責め、単に座っているだけだもの、全然疲れないわ。ウフフフフ、たっぷりと時間をかけて苦しめてあげるわね!」「あっ!そんなあああああっ!や、やめてえええええっ!!やべ、ぐひいいいいいっ!!!」慎治の悲鳴を嘲笑いながら礼子は再び腰を下ろす。ぐうううっくぶぶぶぶ・・・いいわこの感触、本当に楽しいわね、これ。礼子は自分の尻の下でもがき苦しむ慎治の痙攣を心の底から楽しんでいた。間断なくビクビクと痙攣のように慎治がもがく。いいわいいわ、もっともっと苦しみなさい。いくらでも好きなだけもがきなさい、そんなもの何の役にも立たないけどね。礼子は僅かに尻を前に動かし、慎治の鼻腔に股間を押し当てた。「ぐぷううう・・・くかあああああ・・・」苦しげな悲鳴が漏れる。ウフフどう、苦しい?息をするのも大変でしょう?でも完全に塞がってるわけじゃないからね、少しずつは息も吸えるはずよ。窒息する心配はないわ慎治。ウフフフフ、だってそんなに簡単に気絶させちゃ面白くないものね、さあもっともっともがき苦しみなさい!グッグッと礼子は前後左右に捻るように腰を揺り動かす。「ぎがあああああっっっ・・・」慎治の潰れた悲鳴が礼子の尻の下から漏れる。無理もない、尻は決して肉と脂肪のみで出来ているわけではない、中には硬い尾?骨が走っている。その先端は普段は肉の中に隠れているが、全体重をかけて慎治を潰している礼子の尾?骨は今、慎治の顔面に食い込んでいる。それを前後左右に揺り動かされては溜まったものではない。柔らかい尻の肉の中に隠された硬い尾?骨、それはまるで美貌と明るい性格の中に無限の残酷さを隠し持つ礼子の象徴のようだった。ゴリッ、グリュッ・・・顔面を硬い棒でこねくり回されるような苦痛に慎治は悲鳴を上げ続けた。痛いいたいイタイ・・・痛いよおおおおおっっっ!!!苦痛は時間とともに無制限に拡大していく。鞭のような激痛ではないが瞬時の休みもない責め苦、しかも礼子の無情な圧迫は顔面全体、さらには後頭部に鬱血を引き起こし等比級数的に苦痛を増大させていく。目は見えず耳も聞こえない。暗闇と耳を圧迫されたゴーッという轟音の中でひたすら苦痛のみを味わい続ける。他人の、美しいクラスメートの尻の下に敷かれるという屈辱、他人に顔面に座られるという屈辱。それすら今の慎治にとっては何の問題でもない。屈辱を味わっている暇などない。あるのは苦痛、ただ苦痛の二文字のみしかなかった。そして隣室では同じく信次も玲子の尻の下で呻き続けていた。
どれくらいの時間がたっただろうか、意識朦朧とした信次の顔面から玲子がすっと下りて泣き疲れたように醜く歪んだ信次を見下ろしていた。「信次、信次!聞こえる?聞こえたら返事くらいしなさい!」ピシーンと鞭のようによくしなる玲子のビンタが信次の頬を打ち据えた。「ほら万力はもう外してあげたわよ、耳は自由になったんだから聞こえるでしょう!?」玲子の凛とした声に叩き起こされ、信次は優しい救いの手、失神の一歩手前から連れ戻されてしまう。焦点があわずボヤケていた目に徐々にはっきりと、見下ろす玲子の美貌が見えてきた。「目が覚めた?どう、私のお尻の味は、たっぷりと堪能したかしら?」「あぐうううう・・・もう・・・ゆるして・・・」「許して欲しい?苦しかった?それとも痛かったかしら?私にたっぷりと座られたんだもの、さぞ痛いでしょうね。もう許して、ていうのもわかるわ。でも」玲子は満面に冷酷な笑みを浮かべて言い放った。「女の子に暴力振るうような男はね、この程度じゃ絶対に許して貰えないのよ。これからが本番よ、ウフフ、今までのはほんのオードブル、これからもっともっと苦しめてあげる!さあ万力を締め直しましょうね、キリキリと!」愉しげに笑いながら玲子は万力に手をかけ、回し始めた。「い、いやあああああっ!いやだあああああっ!」「何をそんなに騒ぐのよ、煩いわね。」ふと手を止めて玲子が尋ねた。「信次、万力で締められるのはそんなに嫌?もしかして締めないで欲しいの?」「いやあああああ・・・お願い・・・万力は許して・・・ください・・・」涙を溢れさせながら信次は必死で哀願した。せめて万力さえ、万力さえなければ頭を横に回せる、そうすれば少しは・・・少しは楽になれるはず、息は自由に吸えるはず・・・でも玲子さんが許してくれるわけない・・・だが玲子の唇から漏れた言葉は意外なものだった。「フーンそう、信次はそんなに万力が嫌なんだ。じゃあいいわ、万力はしないであげるわよ。」「えっ・・・ほ、ほんと、本当ですか???」「嘘は言わないわよ、ほらこうやって万力、しまってあげる。」玲子は収納式になっているアームを一杯に下げて拘束台に埋め込んだ。首を固定されているとはいえ、頭の動きはかなり自由になった。ある程度は左右に捻じったり、上下にも動かせる。ああ良かった・・・だけどなぜ・・・なんで万力を許してくれたんだ・・・不安げな信次の怯えを楽しむかのように玲子が嘲笑った。「お望み通り万力は許してあげるわ。ウフフフフ、でもね、いいこと教えてあげるわ。万力がなくなるとね、もっともっと、ずっとずーーーっと、苦しくなるのよ。でも仕方ないわね、万力を取ってくれ、て言ったのは信次自身だものね!余計苦しくなっても自業自得というものよね、アハハハハ、アハハハハッ!」えっええっ、そ、そんなあああ・・・でもなぜ、なぜ万力がないと余計苦しくなるの???その疑問はすぐに氷解した。「さあ信次、万力がなくなるとどうなるか、たっぷりと教えてあげるわね。ウフフフフ、心いくまで苦しみなさい!」玲子は再び信次の顔を跨ぎ腰を下ろしてきた。「ひっ、ひいいいいっっっ!ブギイッ!」信次の顔面に玲子の尻が着地し、そのままグウッと体重が掛かってくる。「ぐっぷううううっ・・・」悲鳴にもならない信次の苦悶の喘ぎが小さく響いた。あが、あがあっ・・・な、なんで、なぜえええええっ!重いいいい・・・さっきより全然重いいいい!責められている信次には理由は分からなかったが、苦痛が増したのも当然だ。信次の顔面を固定していた万力は確かに顔面を真上に固定する責め具ではあったが、同時に玲子が腰を下ろした時、その体重の一部を支える役目も果たしていたのだ。その支えが無くなった今、玲子の文字通り全体重が信次の顔面にかかってくる。だが玲子の責めはそれだけではない。更に厳しい責め苦が待っていた。「うばっ、うぶぶぶぶ・・・」信次の苦しげな悲鳴が響く。「アハハハハッ!どうしたの信次、随分悶えているじゃない、こうやって揺すって欲しいの?私も協力してあげようか?ほら!ほら!ほらほらほら!」玲子が愉しげに笑いながら腰を前後左右に揺り動かす度に、全身を苦悶に痙攣させる信次の苦しみ様は只事ではなかった。ギシッ、ギシギシギシッと拘束台を激しく軋ませながら信次は苦悶に全身を痙攣させていた。「どうしたのよ、何をそんなに悶えているの?ぴったり密着している分、さっきと違ってお尻の骨は食い込んでいない筈よ。痛いのは大分軽くなったんじゃないの?」確かにその通りであった。玲子の尻、太腿は信次の顔面にぴったりと密着している、そのため尾?骨の角度が変わり、先ほどまでとは違って信次の顔に余り食い込んではいないから痛みはかなり軽減されている。適度に肉と脂肪のついた熟成しつつある美少女の肢体、玲子のお尻は適度な柔らかさとハードトレーニングの賜物である十分な弾力を併せ持つ、最高の双丘だった。だがその柔らかさこそが信次を地獄のどん底に突き落としていたのだ。「くはっくはあああっ、ぐ、ぐふううううっっっ、い、いぎがあああ・・・」玲子の尻の下で信次は声も碌に出せないままもがき苦しんでいた。万力という抵抗から解放された玲子の柔らかい尻の肉は、信次の顔面にぴったりと密着していた。勿論、口にも鼻にも。柔らかい分密着の度合いは大きく、信次が呼吸しようにもほんの僅かの隙間しかない。く、ぐるじいいい・・・このままじゃ窒息するううう・・・横、横を向かなくちゃ・・・信次は必死で顔を左右に動かし、なんとか横を向いて口と鼻を自由にしようと抗った。フフフ、苦しんでる苦しんでる、そうよね、私のお尻に口も鼻も塞がれてさぞ苦しいでしょうね。ウフフフフ、でもそう簡単に横を向けるわけないでしょう?精々頑張ることね、まるでお尻の下で踊っているみたい!アハハハハッ、さあ踊りなさい!お尻の下で。頑張んないと・・・窒息しちゃうわよ!?玲子は冷酷な笑みを浮かべながらグッと太腿に力を入れ、乗馬の要領で締めつけた。万力こそないものの信次の顔面は玲子の太腿に両側から締め付けられ、全く自由はない。いくら必死で動かしても首の可動範囲は極く僅か、玲子の尻の下から抜け出るには程遠い。それに僅かばかり首が動いたところで、上に乗っている玲子の尻も一緒に動くのだからどう足掻いても息は吸えない。「うっぐううううう・・・くっかああああ・・・」楽になるどころか必死で全身に力を込めるものだから酸素をより多く消費してしまい、息苦しさは増すばかりだ。「あひっあひいいいいっっっひっぎいいいいっっっ」信次の全身が凄まじい苦悶に激しく震えている。ぐ、ぐるじいいい・・・
呼吸困難、だが口も鼻も僅かな隙間は残されている。その隙間から時折、若干とはいえ空気が肺に入ってくるから中々失神することすらできない。蛇の生殺しのように、呼吸困難のチアノーゼ症状にゆっくりと全身を責め苛まれながら信次は延々と苦しみ続けた。「ぐぎいいいいい・・・ゆるじでえええ・・・く、くうき、くうきいいい・・・いきが、いきがあああ・・・・・」哀願の言葉すら碌に言えない。玲子が腰を上げてくれない限り信次はいつまででも際限なく苦しみ続けるのだ。信次の苦悶を玲子は心の底から楽しんでいた。フフフ、楽しいわこの窒息責め、私のお尻に信次の苦悶がストレートに流れ込んでくるわ。必死のあがき、痙攣、苦しげに吐き出す僅かな息、それにほんの少ししか流れ込んでこない空気を必死で吸い込もうとする無駄な努力。ああ楽しい、私の手を煩わせたクズを罰しているんだ、ていう実感が本当に気持ちいいわ、窒息責め最高!玲子が拷問の悦楽を満喫している間も信次の全身は間断なく痙攣し続け、口と鼻の前に僅かな空間ができるたびに必死で空気を貪る。ズッ、ズズウッッッ・・・だらしない音を立てながら必死で空気を貪る。フフフフフ、頑張ってるじゃない信次、信次の喘ぎでお尻がくすぐったいわ。玲子は薄いパンティ越しに伝わる信次の苦悶を何ともいえない快感と共にゆっくりと堪能していた。「ウフフフフ信次、どう私のお尻の下の居心地は?女の子のお尻を追い掛け回してトイレにまで忍び込んだ信次でしょう、お望み通りの居場所じゃないの?天国に昇るような気分じゃないの?アハハハハッ!ゆっくりと楽しみなさい!ああそうだ、私は宿題片付けちゃうから、あんまり暴れないでよ、やりにくいからね。」「ぞ、ぞんなあああああ・・・」しゅ、宿題?じゃ、じゃあ・・・いったいどれだけ俺の上に座っている気なんだあああああっ!その通り、玲子は時折僅かに腰を浮かせて信次に息継ぎをさせながらたっぷりと座り続けた。
一時間近くがたち、慢性的な酸欠、呼吸困難と顔面に絶え間なく座られ続けた圧迫で意識朦朧となった頃、漸く信次たち二人はお尻の下から解放された。ゼハアッ、ゼハアアアアッッッ・・・荒い息を吐き続ける慎治の頬を礼子が優しく撫でた。「ウフフフフ、どう効いたかしら今の責め、苦しかった?」「あうっあああ・・・・く、るしい・・・ねがい・・・もう、許して・・・」隣室では信次も束の間の休息を貪っていた。ハアッハアハアハアハアッッッ、ゲホッグハアッ、ハアハアゼイゼイ・・・「アハハハハ、やあねえ咳き込んじゃって、そんなに急いで息するからよ!そんなに苦しかった、私のお仕置き?もう十分反省した?」「アウッヒッヒックウエッッッッ・・・し、ました・・・反省・・・・しました・・・・から、どうかおねがい、許して・・・ください・・・・もう・・・しませんから・・・」それぞれのお仕置き部屋で礼子たちは満足そうに頷いていた。「そう、そんなに許して欲しい?ウフフ、じゃあ一つ質問よ、慎治、今の私の責めは・・・どういう責め?責めの名前は何かしら?」「あらあら信次、ずいぶん素直じゃない、よろしいよろしい、大分お仕置きの効果があがったようね、嬉しいわ。じゃあ一つ質問するわね、今の私の責め、何ていう責めかしら?」え、今の責めの名前???慎治たちは一瞬躊躇した、さっき言ってたけど、そのままでいいんだろうか・・・また引っ掛けじゃ?だが考えている時間はない。「わからないのかしら?」「どうしたの、答えは?」微かな棘を感じさせるだけで十分だった。「ヒッ、ち、窒息責めです・・・」「ち、ち、窒息・・・責めだと思いますっ!」引っ掛かったわね、礼子の冷たい美貌が嗜虐の予感に綻ぶ。「窒息責め?まあ散々苦しんだ慎治としては当然の答えでしょうけどね、残念ながら外れよ!」「えっえええっっっそ、そんな・・・ちがうんですかあああ!?」「そう、違うわ。大体さっき怜先生、窒息責めを慎治に説明してくれた時になんて言ったかしら?名取さんたちを何百回となく失神させたって言ったでしょう?だけど慎治は未だ一度も失神していない筈よ。と言うことは、窒息責めには程遠い、只の顔面椅子の刑がさっきのお仕置きの名前よ。」「あわわ・・・あわわわわわ・・・ま、まさか、そんな・・・」「ウフフフフそうよ、ご想像の通り。いよいよ本物の窒息責めを味合わせてあげる。フフフフフ、辛いわよお?慎治が本当に失神するまで苛めてあげるわね。」「ヒッヒイイイイイイッ!!!そ、そんなそんないやだあああああっ!ゆるしてえええええええっっっ!!!」慎治が必死で絶叫するのを礼子は面白そうに眺めていた。一しきり慎治が叫んだところで礼子が尋ねる。「ねえ慎治、そうやって絶叫するのは勝手だけどね、私にはどうしても理解できないな。慎治は今、拘束台に縛られているのよ?やめて許して、て幾ら叫んだって私に許してあげる気がない以上、無駄なんじゃないかしら?そんなに大声出して余計な体力使うと、後で却って余計ニ苦しむのは慎治自身だと思うんだけどな?」ああ、あああああ・・・・・そんな・・・慎治が恐怖と絶望の余り、思わず絶句してしまったのを見て礼子はいよいよ刑の執行を宣告する。「ウフフフフ、所で窒息責め、逝く前に二つ準備があるのよ。」部屋の隅から礼子が持ってきたものはガムテープ、紙ではない布テープだった。「これは只のガムテープ、どうするか分かる?分からない、いいわ教えてあげる、こうするのよ。」言うや否や礼子はピッとガムテープを伸ばし慎治の口に唐阨tけるとそのまま何重にもグルグル巻きにし、口を完全に塞いでしまった。鼻は塞がれていないから呼吸はできるものの、最早悲鳴をあげることすらできない。
2
「大丈夫、息はできるわね?それでもう一つの準備はね、これよ。」言いながら礼子はブーツを履いたまま純白のパンティを脱いで椅子の背にかけた。「パンティを脱いだ理由は簡単よ、パンティは幾ら薄いとは言っても布だから私の体から少しは浮いているし、慎治が必死で首を振れば少しは滑って息をする隙間もできるわ。だけどね、今度はそうは逝かないわよ?私のお尻の肉がぴたりと慎治の鼻を塞ぐわ、逃げ道なくね。ウフフ分かる?今度はどう抵抗しても無駄、私が腰を浮かせてあげない限り、絶対に呼吸できないわよ?」「えっおおっうんおおお・・・」「無駄よ、口を塞がれているんだからね、何も言えるわけないじゃない。そしてそのガムテープはね、二つの役割があるわ。一つはね、そうやって口を塞いでしまい、呼吸を鼻だけにしてしまうこと。そしてもう一つはね、抵抗を完全に封じることよ。怜先生たちは無理矢理監禁した、て言ったでしょう?窮鼠猫を噛むじゃないけど、口を自由にしたまま座ってお尻を齧られたら痛いからね、こうやって口を塞いで絶対に抵抗できないようにしたそうよ。うん、何?僕は絶対噛んだりしません、絶対抵抗しないからガムテープ剥がしてください、と言いたいの?」「うう、ううんうん、うん!」慎治は必死で頷いた。「ダメに決まってるじゃん、バカねえ!幾ら抵抗しない、て口約束したって失神寸前、生きるか死ぬかなんてシチュエーションだったら、反射的に何をするか分かったもんじゃないわ!第一、お鼻だけにしておいた方が私が責めやすいじゃない!?」交渉決裂であった。ゆっくりと礼子が慎治の顔を跨ぐ。「ウフフ、さあ逝くわよ、覚悟はいいわね?散々おしっこを飲まされた私のお尻で今度は窒息させてあげる。アハハハハッ!おしっこなんて苛めとしては生温く感じるまで苦しめてやるわ!」
礼子は慎治の顔を跨いだまま暫しの間、勝ち誇った笑みを満面に浮かべながら見下ろしていたが、やがてゆっくりと腰を下ろし始めた。慎治の目にどんどん礼子の尻、というより女性器が迫ってくる。慎治を責め嬲る喜びに上気しているかのように、ピンク色に艶やかに濡れ輝いている。いつもは顔の上10センチ程度で静止し、汚辱のおしっこを噴出する礼子の性器、だが今日は静止せず、そのまま近づいてくる。一瞬大アップになった礼子の性器は、近づきすぎて最早見ることもできない。呆然と見詰めていた慎治はハッと吾に返って必死で鼻から息を吸い込む。
い、息、今のうちに少しでも息を吸っておかなくちゃ!必死で吸った空気に微かな異臭が混じっていた。艶やかだがどこか野生を感じさせる、生々しい肉の匂い。これから慎治を責め苛む礼子の女性器の芳香だった。クラクラするような濃密な芳香、そしてその源が慎治の鼻にピトリと着地した。ピチャッと湿った感触に続いて慎治の顔面に礼子の体重がのしかかる。痛い重い・・・だが数秒を経ずしてそんな苦痛など物の数ではない、と嘲笑うかのような苦痛が襲い掛かってきた。
プッ、プッ、ウプウウッ!息が・・・吐けないいいいっ!慎治の鼻、口を塞がれた慎治にとって唯一の呼吸器官は礼子の女性器にめり込むかのように包み込まれ、完全に空気から遮断されていた。吸った息は吐かなければ次の呼吸はできない。だが必死で肺一杯に溜め込んだ息を吐くことすらままならない。クウッ、クウウウッッッッッ!慎治の体内一杯に溜め込まれた空気は出口を失い、慎治の鼻から肺を空しく行き来する。だがその空気は最早呼吸には何の役にも立たない。
ぐぐぐ・・・ぐるじいいいい・・・最後の力を振り絞るかのように必死で慎治が息を吐き出そうとした瞬間、礼子はほんの一瞬だけ僅かに腰をあげてやった。ブビイッ、みっともない異音を立てて慎治の鼻から空気が吐き出された瞬間、礼子は素早く全体重を掛けなおし慎治の鼻を完全に塞ぐ。「アハハハハッ、良かったわね慎治、お望みどおり息を吐き出せて!でも吐くことは出来ても、吸うことはできるかしら?まあ精々頑張ってみることね!」
「グウッ、グウウウウウッ、ググブブブブウウウウウッッッ!!!」慎治の腹が、胸がベルトを引き千切らんばかりの勢いで激しく上下する。空っぽになり縮んだ肺、だがその肺を膨らませてくれる空気は全く入ってこない。礼子の女性器、パンティを脱ぎ捨てて柔らかい肉を剥き出しにした女性器はその柔らかさを恐怖の拷問具と化し、慎治の鼻に密着して空気を完全に遮断していた。br>ブバアアアアッ、クヒュウウウウウッ・・・待ちかねた新鮮な空気が慎治の体内に流入する。必死で空気を貪る慎治を見下ろしていた礼子が不意に腰を下ろす。「うぎいいいいいいいっっっ・・・」窒息責めの再開だ。再び窒息寸前まで慎治を追い込んだ礼子が腰をあげると、慎治は必死で空気を貪る。グハッ、カハッ、フヒュッフヒュッ、フヒイッッッ・・・漸く自分の尻から解放されて苦しげに喘ぐ慎治を、礼子は満足そうに微笑みながら見下ろしていた。
「フフフフフどう慎治、苦しい?息をする自由すら奪われた感想は如何?ウフフフフ、許して欲しい?もう勘弁して欲しい?でも駄目よ、この程度じゃ陽子たちにケガさせた償いにも満たないわ。ましてや私の顔に泥を塗った償いは・・・未だ始まってもいないのよ。さあもっともっと苦しめてあげる!」高らかに笑いながら礼子は慎治の顔に体重をかける。
礼子は慎治の顔面を騎乗のように、太腿でしっかりと挟みつけて固定しながら鼻を自分の性器でピッタリと塞いでいる。だが塞いでいるのは鼻だけだから慎治の目は自由だ。言葉を、呼吸を奪われた慎治が窒息の苦痛と死の恐怖に怯えながら必死で哀願しているのを礼子は満足気に見下ろしていた。涙を両目一杯に溢れさせながら自分を見上げ必死に哀願している慎治、だが言葉すら発せられない。動くことも泣き喚くこともできずにただただ自分の尻の下で悶絶している。フフフ、慎治には泣きながらのたうつ以外何もできないわよね。息をすることすら、普段無意識にしている呼吸ひとつですら私の許可なしにはできないのよ。ウフフフフ、慎治の全ては私のもの、私のお尻の下で、無力な自分を嘆き悲しむがいいわ!自分の犯した罪の重さを思い知るがいいわ!でも幾ら後悔してももう遅いのよ、地獄に堕ちてからじゃね!思う存分苦しめてやるからね!礼子は例えようもない勝利と蹂躙の味を思う存分満喫していた。そして満喫していたのは精神的な満足感だけではない。
ああ気持ちいい・・・最高!慎治の苦悶が、礼子の両腿での締め付けから何とか逃れようとする慎治の無駄な足掻きが、絶妙の振動となって礼子の女性器を震わせ、素晴らしい快感をもたらす。慎治の生殺与奪の全て、息をするという基本的人権以前の、生きるための文字通り必要最小限のことまで私のお尻が支配しているのね!私自身の象徴、私の性器が慎治を苦しめているのね。ああもう最高!鞭を通して、ブーツを通して慎治の苦悶を散々楽しんできたけど、この責めストレート、慎治の苦痛が全部私に直結して伝わってくる!慎治、そう簡単には解放してあげないわよ、限界まで、とことん苦しめてあげる!慎治、憧れの私とデートして愛し合いたかったんでしょう?私の体を心行くまで堪能したかったんでしょう?いいわよ、心行くまで堪能させてあげる、最高の苦痛と一緒に心行くまで味わいなさい!フフフ、折角窒息寸前までいっても、こうしたらどう?礼子は限界まで呼吸を奪われ全身を断末魔のように痙攣させている慎治の鼻からすっとお尻を持ち上げた。「プヒューーーッ、グヒュウウウウウッッッ・・・」待ちわびた空気、欲しくて欲しくて堪らなかった空気を必死で貪る慎治の喘ぎを礼子は素晴らしい快感を味わいながら見下ろす。フフフ、それだけ苦しいんだものね、私がお尻をあげたら思わず空気を吸っちゃうでしょう?吸わせてあげる、失神できないようにね、失神寸前まで追い込んでから少しだけ吸わせてあげる。いつまでもいつまでも、私が窒息責めを楽しめるようにね!
グビイイイイイッ、クハッゲハッ、ブッヒイイイイイッッッッッ・・・慎治は礼子の尻の下で果てしない責め苦にもがき苦しみ続けた。涙を両目から溢れさせながら慎治は礼子のことだけを見上げていた。色白の頬をピンク色に上気させ、楽しそうに笑いながら礼子は慎治のことを見下ろしている。ああ・・・お、お願い息を、息を吸わせてえええ・・・だが言葉を発することはできない。余りの苦しさに意識が暗転しかけた瞬間、フッと礼子が腰を浮かせてくれた。ああ空気、くうきいいい・・・必死で空気を貪るがあっという間に礼子の尻が再び慎治の鼻を塞ぐ。
あぐううううう・・・喘ぎながら慎治は必死で礼子を縋り付くような眼差しで見上げる。おねがいいい・・・ゆるして・・・だが見下ろす礼子の美しい瞳に憐憫は影も形もない。ああ礼子さん、楽しんでいる、熱中している、僕を苦しめることに・・・礼子さんの瞳・・・僕の苦痛を推し量っている、どこまでなら責められるか観察している・・・お願い、やめてえええ・・・こんなの酷すぎるよおおおっ、あ、あんまりだあああああっっっ!
だが慎治にも分かっていた、礼子は決して許してくれないことが。ブーツを履いた礼子、リミッターを解除した礼子の残酷さは嫌というほど身にしみていた。だがそれでも許しを乞わずにはいられない。声も僅かな身の動きも、全てを奪われた慎治に唯一可能なことは願うことだけだった。それは願いと言うより空しい祈りに近かった。
おねがいいい礼子さんんんん!許してえええええ、息を、息をすわせてええええええ・・・慎治は必死で祈り続けた。幾ら祈りを捧げても女神から見れば所詮は取るに足らない虫けら一匹、その祈りを聞き入れる義理などさらさらない。決して叶わぬ祈り、それ位は慎治にも分かる。だが今できることはそれしかない。慎治の頭の中全て、意識の全ては礼子への祈りに塗り潰される。礼子・・・さんんんんんっっっ・・・礼子さんんんんんん!自分を地獄に突き落とした美少女への祈り、それだけに慎治の全てが捧げられている。礼子さん礼子さん礼子さん礼子さん礼子さん礼子さんんんんんんんんんん・・・残酷な女神、全てを奪いつくす大地神に僅かな恵みの慈悲を乞うかのように、慎治はひたすら礼子に哀願し祈り続けた。慎治の目に浮かぶ自分への哀願が礼子には手に取るようによく分かった。いい子ね慎治、もう私のことしか考えられなくなったみたいね。きっと慎治、今私に必死で祈っているでしょう?許して下さいお慈悲を掛けて下さい、て祈っているでしょう?私に祈る以外、慎治にできることは何もないものね。いい気分よ、祈りを捧げられるのはとってもいい気分。その調子よ、私のことだけを思いながら苦しみなさい、私に祈りを捧げながら苦しみなさい、さあもっともっと苦しみなさい!礼子は更にしっかりと慎治の上に体重をかけていった。
3
隣室では信次も地獄を味わっていた。「ウフフフフさあ信次、いよいよ尻地獄の本番よ。」ツッと信次の顎の下を撫でながら玲子は獲物を弄ぶ女猫のように残酷な笑みを浮かべる。既に信次も口にガムテープを巻かれ、哀願することすらできない。「さあてと、今日は特別のお仕置きだからね、私も特別の準備をしてきてあげたのよ。」特別の準備?い、一体何を?怯える信次の表情を楽しみながら玲子は言った。「信次、もう信次にも分かっているでしょう?いずれ近い将来、私にうんちを食べさせられる、ていうことはね。ウフフ安心していいわ、それは今日じゃないから、もう少し先の話よ。だけどねフフフ、今日は手付けをあげるわ。」て、手付け?ど、とうするつもり・・・「今日ね、私うんちした後、ペーパーで拭いただけなのよ、ウオシュレット使ってないの。それに今部活終えた後もね、シャワー浴びたいのを我慢してここに来てあげたのよ。フフフ、感謝しなさいよ、この霧島玲子が信次如きを苛めるために、気持ち悪いのを我慢してきてあげたんだからね。100倍返しで償ってもらうわよ!ハハハ、アハハハハッ!」あ、洗ってない、シャワーも浴びてない・・・ま、まさか、まさかああああっ!!!「分かったみたいじゃない。そう、そのとおりよ。うんちを食べさせて信次の口を冒す前にね、まずは信次の鼻を穢してあげる!アハハハハハッ!私の汚れたままのお尻で窒息させてやるわよ、さぞ臭いことでしょうねえ、アハハハハッ、アハハハハハッ!」ムウッムグッブギュウウウウウッッッ!ガムテープの下から信次の必死の抗議が漏れる。「何よ信次、そんなに嫌なの?そりゃそうよねえ、洗ってないお尻で潰されるなんて、おしっこ飲まされるのなんか比べ物にならない位の屈辱よね。ねえ分かる?信次はだいだいだーいっきらいな私、この世で一番嫌いで憎くて憎くて堪らない私の、信次を地獄に突き落としたこの私のお尻の穴を嗅がされるのよ!?アハハハハッ!毎日毎日、自分を死ぬほど苛め続けるこの私の一番汚いところ、お尻の穴の臭いを嗅がされるのよ?ねえどんな気分?私も苛めにかけては年季の入ったプロだけど、流石にお尻の穴を人に嗅がせたことはないわ。だからもうワクワクしちゃって、早くこの汚れたお尻を嗅がせてやりたい、信次の顔に押し付けてやりたい、てもうウズウズしちゃっているのよ。ねえ信次はどうなのよ、悔しい?止めて欲しい?嫌で嫌で堪らないでしょう?どうかお願い、それだけは許して下さい?だけど・・・ダーメ、信次は私の一番汚いところ、私の肛門で窒息させられるのよ!有希子を怪我させたクズに相応しい罰よね!たっぷりと苦しめてやる!アハハハハハッアハハハハッ!」スッと漆黒のパンティを脱ぎ捨てた玲子が後ろ向きになって信次の顔を跨ぐ。「あっそうそう、せめてもの慈悲よ、ひとつだけいいことを教えておいてあげる。」振り向きながら玲子は嘲笑を浮かべつつ言った。「いい、窒息責めの合間に何回かは息を吸わせてあげるけどね、息を吸ったら、フフフ、私のお尻の臭いをもろに嗅ぐことになるわよ。ウフフフフ、私のお尻の臭いを嗅がされるのが嫌だったらね、どんなに苦しくても息を吸うのはやめることね。」そ、そんなあああ!息をしなけりゃいいだなんてええええっ、し、死んじゃうじゃないかあああああっ!
だが玲子は信次の必死の叫びなど全く無視しながらゆっくりと信次の顔面を今度は後ろ向きに、横たえられた信次の体の方を向くように跨いだ。「どう信次、私のお尻を味わうにはこっちの向きの方がいいでしょう?さあたっぷりと味わいなさい!」見せ付けるかのように、玲子はゆっくりゆっくりと腰を下ろしていく。ああ、あああああ・・・や、やだいやだあああああっっっっっ!!!信次の視界を玲子の美しい尻が覆いつくしていく。優美なラインを描く双丘、そしてその真ん中を分断する割れ目の中に短い細いラインのような割れ目があった。あ、あそこ・・・あそこが玲子さんの・・・肛門!信次は他人のは愚か自分の肛門すら見たことはなかった。だがそれが玲子の肛門であること、そして玲子がそれを信次の鼻めがけて一直線に降下させていることはすぐにわかった。ひ、ひでえええええっ、お、お尻で、肛門で潰すなんて酷すぎるうううううっ!信次の呻き声など委細構わず玲子は信次の顔面にお尻を着地させた。フフフ、直ぐには潰してあげない、少し苛めてあげる。玲子はわざと信次の鼻の前にほんの少しだけ空間をあけてやった。だがその空間は1センチもない、ほんの数ミリだ。鼻の前に自分の肛門を押し付けられた信次が息をしまいと必死で堪えているのが良くわかる。「フフフ信次、その調子よ。私の肛門、信次のお鼻の目の前だからね、息を吸ったら・・・アハハハハッ!私のお尻の臭いが直撃よ!頑張ってね信次ちゃーん、そのまま失神するまで息を止めていたら、私のお尻の臭い、嗅がなくてすむわよお!ほーらガンバレ信次、ガンバレ信次!」楽しそうに笑いながら玲子は確信していた。信次が失神するまで頑張れるわけなどないことを。グウッ、グウウッ、グフウウウウウッッッ・・・自分の尻の下から込みあがって来る信次の苦しげな喘ぎ声を楽しみながら、玲子は限界点が来るのをゆっくりと待っていた。
い、いやだいやだあああ・・・お、お尻の臭いを嗅ぐだなんて絶対にいやあああ・・・あああ、で、でも・・・く、苦しいいいい・・・息が・・・もうだめええええ・・・余りに残酷な玲子の責めだった。完全に鼻を塞がれてしまえばどの道呼吸はできないのだから、単純に苦しんでいればいい。だがこうやって一応、息はできるようにされていれば、自分の意志で我慢などできるものではない。強制されてではない、自分の意志で玲子のお尻を嗅がなくてはならないのだ。憎い憎い玲子、自分をとことん責め苛む残酷な美少女のお尻の臭いを嗅がなくてはならないのだ。余りの屈辱、想像を絶する恥辱。だが肉体の苦痛、空気に対する欲求にこれ以上抗うことは不可能だった。遂に限界に達した信次は堪えていた息を一気に噴き出した。玲子の肛門を信次の鼻息がくすぐる。アハハハハッ、いよいよ来たわね、さあたっぷりと嗅ぎなさい!一陣の風の後、信次が空気を吸い込む気配を玲子は無上の慶びを楽しみながら感じていた。「ブッ、ブヒュウウウウウッ・・・ムグウウウウウッ!!!」信次の悲痛な呻き声が湧き上がる。ヒイイイイイッ、く、臭いいいいいいっ!清冽な汗の香りに混じった饐えたような異臭、微かにトイレ臭いと感じさせる異臭、それは確かに排泄物、玲子のおしっことうんちの残り香、それも時間を経て発酵したような異臭だった。異臭といってもきちんとペーパーで拭いているし前夜は風呂にも入っている、本当は大して臭いわけではないのだが鼻の直前に肛門を押し付けられているのだ、僅かな臭いでも十二分な破壊力だった。
「グヒイイイイイッ、クギイイイイイッ!」悪臭と屈辱に咽び泣く信次の嗚咽を暫く堪能した後、玲子はスッと腰を後ろにずらしていく。「フフフフフ信次、いい声で泣くじゃない、だけど今のは臭いだけ、苦しいのは・・・これからよ!」玲子の尻が最後の数ミリを移動し、肛門が完全に信次の鼻を塞いだ。「グプウウウウウッ、クヒイイイイイッ!!!」ぐ、ぐるじいいいいい・・・玲子の双丘の割れ目、美尻の真ん中に信次の鼻は完全にキャッチされてしまった。玲子の肛門に鼻の先端をめり込ませ、両頬をガッチリと玲子のカモシカのように引き締まった太腿に捕らえられ、信次の鼻は完全に空気と遮断されている。い、いやあああああああっ!信次は声にならない絶叫を張り上げた。柔らかい尻の肉の中でやや異質な感触、若干硬く皺のある襞のような感触が鼻に覆いかぶさる。それは間違いなく玲子の肛門だった。いやいやいやいやいやあああああああっ!ど、どいてどいて・・・お願いどいてえええええっ!全身を生まれてこの方経験したことがないほどの屈辱と嫌悪感が貫く。不潔、汚い・・・想像できる全ての言葉を超越した汚辱、朝子たちに馬糞の上に落とされたのなどとは比べ物にならない程の屈辱だった。ぐう、ぐうう、ぐひいいいいいっっっ!!!何とか玲子の肛門から逃れようとするがガッチリと玲子の太腿で固定されたそれは、蛸のように信次の鼻に吸い付いて離れない。必死で空しい抵抗を続ける信次、だがその抵抗は貴重な空気を浪費させ、玲子の尻に汚された空気への抑えがたい渇望を高めさせるだけだった。「グッグッグフウウウウウッッッッッ・・・」信次の悲鳴が奇妙に甲高くなっていく。そろそろかしら?スッと玲子が尻を微かにずらすや否や、待ちかねたように信次は必死で息を吸い込む、玲子の尻の臭いを肺一杯に吸い込みながら。ウヒイイイッ、く、臭いいいいいいっ・・・だが贅沢を言っている場合ではない、兎に角少しでも多く空気を吸わなくちゃ・・・必死で信次が自分のお尻で穢された空気を吸い込むのを玲子は満足そうに見下ろしている。
4
いい顔よ信次、その屈辱に歪んだ顔、最高よ。余りの恥辱で死にたい位でしょう?肛門を信次の鼻に押し付けた瞬間、玲子の全身をビクンと電気のような快感が貫いた。やった・・・信次をここまで穢しつくしてやった・・・私のこの手で、ううん、このお尻で。中学の時の苛め相手に、靴を舐めさせたりトイレの水を飲ませた時の事を思い出した。信次に最初におしっこを飲ませた時の、屈辱に歪んだ顔を思い出した。だけどそのどれも・・・この顔には敵わないわ。丁寧に時間をかけていたぶり尽してやった成果よね。全てを奪った私、毎日毎日苛めて泣き喚かせる私、大嫌いな私のお尻の臭いなんていうこの世で最悪の臭いを嗅がされているのになんの抵抗もできない自分。フフフ、ウフフフフフ、アハハハハハハッ!信次、さぞ悔しいでしょうねえ!私は最高の気分よ、もっともっと辱しめてあげる!一杯お尻を嗅ぎたくなるように、また窒息させてあげる!グッと玲子の尻が再び信次から空気を奪い去る。「ヒイイイイイッッッ・・・」何回も何回も、玲子は狂ったように笑いながら信次を責め続けた。十回以上責めただろうか、不意に玲子はスッと立ち上がって咽び泣き続ける信次を見下ろした。
「ウフフフフ信次、私のお尻の臭い、堪能した?だけどもう、お鼻バカになってきちゃったんじゃない?お尻の臭いも最初ほどのインパクトはなくなっちゃったんじゃない?」確かにそうだった、人間の鼻は動物界ではかなりバカな方、更に大抵の悪臭は嗅ぎ続ければすぐ慣れてしまう。事実信次ももう、玲子の尻の臭いに対する抵抗は薄れつつあった。「安心しなさい、信次が退屈しないように拷問の趣向を変えてあげる。ここからは・・・シンプルな窒息責めよ!アハハハハッ!信次、徹底的に苦しめてやるわよ?ピストルズはNO FUTURE FORYOUて歌ってたけど、信次の場合はNO AIR FOR YOUよね!さあ・・・逝くわよ!」笑いながら玲子は再び腰を下ろし信次の鼻を完全に塞いでしまう。そのまま30秒ほどすると、早くも信次の呻き声が漏れ始めた。うう、ううううっ、うぐううう・・・・・ぐ、ぐるじいいいいい・・・だが玲子は唇の端にニヤリと残酷な笑みを浮かべたまま、全く体重を浮かせない。「アハハハハ信次、苦しい?最高?じゃあ信次のために歌ってあげるわね!NO AIR NO AIR NO AIR FOR YOU!ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、フォーユー!NO AIR NO AIR NO AIR FOR YOU!ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、フォーユー!」玲子は楽しそうに尻を揺り動かしながら何度も何度も歌い続けた。ワンフレーズ終わるごとに信次の苦しみは等比級数的に急上昇していく。グ、グルジイイイイイ!!!ジ、ジヌウウウウウ・・・信次の全身の痙攣が断末魔のように激しくなったころ、玲子は漸く腰を上げて息を吸わせてやる。
「クックッブッフウッッッッッ・・・」待ちかねた空気が肺に流れ込む。必死で空気を貪る信次を玲子は残酷な笑みを浮かべながら見下ろしていた。「アハハハハ、よかったね信次、やっと吸えて!少し時間をあげるからさ、一杯吸っときなさいよ、もうすぐ・・・またNO AIRだからね!」ひっひいいいっそんなあああああ!!!声にならない悲鳴をあげめ信次の頭上から女神の聖託が降臨する。「さあ信次、窒息責め再開よ、息を大きく吸いなさい!」玲子はわざとゆっくりと腰を下ろす。空気空気くうきいいい!一杯吸わなくちゃあああああ!信次は必死で肺一杯に大きく空気を吸い込む。フフフバカね信次、一杯吸ったところでそんなもの、何十秒かの差に過ぎないのにね、まあ精々頑張ることね。玲子は信次が限界まで空気を吸い込んだところで鼻を塞いだ。10秒、20秒・・・ブシュシュシュシュ・・・微かに吐き出す空気が漏れて玲子の尻をくすぐる。フフフ、別にいいわよ信次、必死で吐けば少しずつは吐けるかも知れないけど、吸うのは絶対に無理よ。ビクッビクビクッ・・・信次の全身が苦しげに震え始める。痙攣は直ぐに激しくなり、信次は玲子の尻の下で窒息の苦しみに延々と責め苛まされた。ウウ、ウウウ、ウウウウウウウウ・・・・・だずげでえええええ・・・必死で信次はもがきながら玲子を仰ぎ見た、だが信次に見えるのは後ろ向きに座った玲子の背中だけだった。地獄の苦悶に喘ぐ信次の必死の哀願すら拒絶するように、玲子は振り向きもせずに信次を責め続ける。クラスメート、学校、家族・・・世界の全てが信次に背中を向けていた。玲子の背中はこの世の全てからの拒否の象徴のようだった。そして信次が唯一縋り付けるのは、信次に唯一構ってくれるのは自分を地獄に突き落とした張本人、玲子だけなのだ。背中を向け信次の哀願に知らん振りをして責め苛む玲子、その玲子に縋り付いて慈悲を乞う以外、信次にできることは何も無い。れ、玲子さんんんん・・・お、ねがいいいい、だずげでえええええ・・・必死ですがりつく信次、だが玲子は振り向きもしない。信次を拒絶するかのように背中を向けたままの玲子、信次を地獄から救い出せる唯一神、残酷な女神は信次を振り向きもせずに座り続けていた。
一体どれ位の時間が経ったのだろうか。女神たちの饗宴と亡者たちの苦悶の宴はいつ果てるともなく続いていた。カヒッカハッハヒッヒッヒッ、ガハアッゼッゼバアアアッ、グハックパックハアアアアッ、ブッブビッブビイイイイイッ・・・慎治たちの苦しげな悲鳴、口を塞がれているから声すら出せない悲鳴が地下室に充満する。残酷な美少女たちは延々と慎治たちを責め続けた。「ほーら慎治、一杯空気吸わせてあげるわよ、大丈夫よ、直ぐには座らないから安心して一杯吸いなさい・・・さあ一杯吸った?じゃあゆっくりと座るからね、いい、ちゃんと頑張って私に座られる直前まで一杯吸い込むんだよ。」礼子はわざと慎治に充分呼吸させ、息を整えさせてから座った。だが一旦座ったらしっかりと慎治の頭を挟み込み、いつまでもいつまでも呼吸をさせてやらない。必死に肺に蓄えた空気、命綱のような貴重な空気だが慎治の肉体が求める量に比べれば余りに僅か、直ぐに尽きていく。「むうっ、むうううっ、むううううっ!」限界に達した慎治の全身がビク、ビクビク、ビクビクビク、と窒息の苦しみに震えだす。なまじ一杯に空気を吸い込んだものだから限界に達する時間が長く、それだけ苦しみも持続する。地獄、まさに地獄だった。美しいクラスメートの尻の下、大部分の男にとっては天国にも等しい礼子たちの尻の下、そこは慎治たちにとっては息をする自由さえ奪われた地獄だった。
完全に抵抗を封じた二人の女神は僅かに尻を上げ下げするだけで、太腿に力を入れたり抜いたりするだけで、尻を前後に数ミリ動かすだけで、自由自在に慎治たちに地獄の苦しみを与えつづけていた。内臓、特に心臓、肺には深刻なダメージが刻み込まれている。寿命すら縮めかねないほどの責め苦だ。だが血は一滴も流れない、だから礼子たちは責めながら全く疲労しないだけでなく、罪悪感も何も感じないし手加減してやろうという気持ちも全く起きなかった。し、しぬ・・・数え切れぬほど何度となく、慎治たちは窒息寸前まで追い込まれまた蘇生させられた。慎治たちの視界は礼子たちの美しい尻に奪われていたが、礼子たちからはもがき苦しむ慎治たちの全身がよく見える。痙攣の激しさ、早さ、そして限界に達し動きが鈍くなっていくところも。ダメよ慎治、勝手に失神なんかさせないわよ。苦悶の果てに漸く意識を失いかけたところで僅かな空気が与えられる。信次、意識が飛んじゃったみたいね、だけど許さない、こっちに帰っていらっしゃい、もっと苦しむためにね!意識が飛びかけた信次の鼻先に玲子はアンモニアを染み込ませたガーゼを当てる。うっううう・・・ツンとしたアンモニアの臭いが信次の意識を失神という楽園から無情にも連れ戻す。底知れぬ無間地獄を彷徨い続ける慎治たち、だが漸く最終的な限界が近づきつつあった。胸、腹、そして僅かに見える顔面、それらにチアノーゼの累積したダメージ、紫色の鬱血が急速に増加しつつあるのを礼子たちは見逃さなかった。これ以上同じ責めを続ければ間も無く、限界に達し失神してしまうことは確実だった。いいわ、そろそろ止めを刺してあげる。今日のところはこれで解放してあげるわ。
スッと礼子は立ち上がると慎治の顔を見下ろした。涙でビショビショに濡れた惨めな顔一杯に疲労と絶望が浮かんでいる。「慎治、どうかしら私の窒息責め、もう十分反省した?心底、私に申し訳ないことをしたと思っている?心の底からお詫びしたいと思ってる?」「うう、ううう・・・うーん、うーん・・・」なけなしの力を振り絞り、必死で首を動かしながら慎治は必死で許しを乞うた。お願いです・・・許してください・・・もう十分・・・反省しましたから・・・「そう慎治、今度こそ本当に反省した、ていうのね。いいわ、もし本当に慎治が反省した、て言うなら、今日のところは許してあげる。」ああ、あああ・・・よかった・・・慎治の顔に安堵の色が広がるのを見た礼子の美貌に、凄絶な冷笑が浮かぶ。「ちょっと慎治、何か勘違いしていない?私はね、慎治が本当に反省したなら許してあげる、て言ったのよ。慎治の言葉なんかはいらないわ、きちんと行動で示して頂戴、本当に、心の底から反省した、ていうことをね。」こ、行動?行動で示す?ど、どうやって・・・慎治の顔に困惑と恐怖が広がる。「簡単よ、本当に反省した、心の底から申し訳ない、て思っているんだったらね、自分を罰しないではいられないはずよ。怜先生に鞭打たれた?私に窒息させられた?そんなのは他人に罰せられただけじゃない、自分を罰したことにはならないわ。いい、よく聞きなさい、慎治が自分で自分をきちんと罰せられたら、十分反省したって認めて許してあげる。」そ、そんな・・・そんなあああ・・・怜先生や礼子さんにもう十分苛められたじゃないですかあああ・・・大体、自分を罰しろって言ったって一体どうやって・・・僕は身動きひとつ出来ないじゃないですか・・・
5
慎治の困惑を満足げに見下ろしながら、礼子は残酷な宣告を下した。「ウフフフフ慎治、心配することはないわよ、そうやって縛られたままじゃ自分を罰するのも大変でしょう?私が手伝ってあげるわよ。責めは今までと同じ窒息責めでいいわ。だけどね、今度は私、脚で慎治の顔面を固定しないから。私は慎治の顔面に座ってあげるだけ。慎治が自分の意志で私のお尻に顔を埋めて窒息しなさい。そのまま気絶したら、自分を罰したと認めてあげる。どう、簡単なことでしょう?」「うう、うううううっ、うぶううううっっっ!!!」そ、そんな、そんな、そんなあああああ!!!じ、自分で窒息しろだなんて、幾らなんでも無理だよおおおおおっ!慎治の声にならない抗議を礼子は一笑に付した。「どうしたのよ慎治、無理だとでも言うの?自分にその程度の罰すら与えられないようなら、反省したことになんかならないわ。それじゃあ許してあげるわけにはいかないわね。いい慎治、私、慎治が心の底から反省するまで絶対に許さないからね。慎治が顔を背けたら、何度でも何度でもその顔を私のお尻の下に引き戻してやるわ、ウフフフフ、慎治がイヤだと言っても、無理矢理にでも反省させてやるわ。慎治が本当に反省するまで、私のお尻の下で失神するまで絶対にどかないからね!」い、いやあああ、そんなのいやあああああ!慎治の悲鳴はムグウウウッ、ムクウウウウウ!と声にすらならない。必死で嫌々する慎治に委細構わず、礼子はゆっくりと慎治の顔面、鼻の真上に腰を下ろした。座るときこそ位置決めのため両手で慎治の顔面を固定していたが、しっかり座ると礼子はおもむろに宣告した。「さあ慎治、ちゃんと自分で反省するところを見せて頂戴。いい、手を放すわよ。」スッと礼子の白魚のような指が慎治の頬から離れる。約束どおり、太ももで締め上げてもいない、単純に慎治の顔面に座り鼻を塞いでいるだけだ。
フフフさあ慎治、どうするかしら?苦痛を少しでも少なくしたいなら、頑張って一回で失神することだけど、果たして慎治にそれができるかしら?まず無理よね。ウフフフフ、どうせ慎治のことだから絶対に我慢できなくて顔そらして息ついちゃうわよね。そうやったら私に引き戻されてまた一から苦しみ直しなのにね。絶対そうするわよね慎治、そうやって・・・たっぷりと私を楽しませてね!礼子の読み通りだった。慎治にもそれくらいのことは分かっていた。なんとか・・・なんとか一回で気絶しなくちゃ、一回、一回我慢すればいいんだから・・・だが自らの意志で窒息するには並大抵ではない意志力が必要だ。例えば壁に頭を打ち付けるとかのように一撃で気絶できるやり方ならば、慎治にもできるかもしれない。しかし窒息は長い苦しみに耐えなければならないのだ。慎治の意志力程度では到底不可能、ましてや礼子に拘束されていない状況、何時でも顔を背けられる状況では逃げないでいられるわけがない。確かに礼子は慎治の顔面に座っている。だが礼子の性器は慎治を責め嬲る快感と慎治の必死の足掻きによる刺激で豊潤な蜜を溢れさせ、極めて滑りやすくなっている。ちょっとでも首のバランスがずれれば鼻が礼子の性器からはみでてしまい、息ができるのだ。この状況、息をしないでいる方が遥かに難しいこの状況を乗り越える意志力が慎治にある訳がない。
クッ、クウウッ、クウウウウッ、息苦しさが加速する、それでも必死で耐えようとする慎治だが絶対の生理的欲求には敵わない。だ、だめ!くるしいいいい、もうだめえええっ!半ば無意識の内に慎治は首を右へ傾けようとした。ニュルッと最高品質の潤滑油、礼子の甘い蜜を鼻から頬に塗り伸ばしながら慎治は横を向き、息を付いてしまった。ハアハア、プフップフウウウッ・・・バーカ慎治、やっぱり我慢できなかったわね。多分最初のこの一回が勝負よ、ここで我慢できなかったんだから後はもうアリ地獄、慎治、もうとことん苦しむしかないわね。「慎治、息しちゃったじゃない、ダメねえ、さあ、私の下にお・も・ど・り・な・さ・い!」クックックッと楽しげに笑いながら礼子は慎治の鼻を再び塞ぐ。うう、ううう、ううううう・・・あっという間に再び息苦しさに襲われる慎治、だが礼子の読み通り、一度逃げてしまった慎治にもう耐える事はできない。ぷ、ぷぷぷ・・・ぷっはあっ・・・横を向いた慎治が一息二息吸ったところで礼子はまた慎治を引き戻す。アリ地獄へようこそ慎治!ウフフフフ、慎治が横向く度にお鼻で刺激するから、私は結構気持ちいいよ。まあ精々頑張って私を楽しませてね、疲れてもう動けなくなるまで。
礼子は慎治が横を向くのは許すがほんの一呼吸二呼吸しかさせない。だから慎治は徐々に慢性的な酸素不足、蓄積していく窒息の苦しみに喘ぎながら体力を消耗していった。ぐううう、れ、礼子さん・・・重い・・・ぐっぐううううう・・・何回窒息地獄からの逃亡を図ったことだろうか、顔面にのしかかる礼子の重みに耐えながら必死で首を回す肉体的疲労、すぐまた窒息地獄に連れ戻される精神的疲労の相乗効果に慎治の体力は限界に達しつつあった。あらあらもう限界かしら?礼子は散々楽しんだオモチャが電池切れとなったように、慎治の動きが鈍くなるのを天上の高みから見下ろしていた。まあ仕方ないか、これだけ苦しめたんだものね、ああ楽しかった!礼子は大いなる満足感と共に慎治の断末魔の様相を見下ろしていた。自分の股間、お尻の下で人間一人を完膚なきまでに責め嬲り、窒息責めで生死の境目を彷徨わせている。全ての精力を搾り取ってやった快感、極限の苦しみを味あわせてやった満足感を全身で噛み締めていた。さあ慎治、最後までちゃんと見せてね、わたしのお尻の下で逝くところを。頚動脈を締めてなんかあげないわ、最後の一瞬まで苦しい窒息責めで逝かせてあげる!苦しめ苦しめ苦しめ!最後の最後まで・・・苦しみぬくのよ!アハハ、アハハハハ、アハハハハハハハッ!精魂尽き果てた慎治が蝋燭の最後の炎が燃え尽きるように、弱々しく痙攣しながら動かなくなるのを礼子は高笑いと共に見下ろしていた。
一方、玲子の美尻の下で信次も最期の瞬間を迎えようとしていた。「ブハッブフウップフウウウッ・・・」玲子が時折僅かに尻を持ち上げてくれるや否や、信次は必死で空気を貪る。例え玲子の尻臭を嗅がされながらでも何でもいい、吸わずにはいられなかった。だが空気を吸うには一旦、肺の中の古い空気を吐き出さねばならない。信次は唯ひたすら純粋に苦しみ続けているだけだったが玲子は、苛めのプロを自任する玲子は信次の苦悶を楽しみながらも冷静に信次を観察し、タイミングを計っていた。玲子は単純に尻を上げ下げして責めているだけではなかった。信次の呼吸のタイミングを計り、尻をどれ位上げたら信次が息をできるのか、吐息を吐き切るまで何秒かかるのかを正確に推し量っていたのだ。コンマ数秒の単位、だが玲子はそのタイミングを完全に把握しきっていた。どの程度尻を浮かせてやれば信次が息を吸えるか、その限界点も数ミリの単位で見切っていた。思ったよりスペースいらないみたいね、信次、あんた私のお尻の穴が殆ど鼻にくっついたままでも吸えるのね。フフフグッドね、あの攻撃、とーっても効きそうじゃない!玲子はニヤリと残酷な冷笑を浮かべるとスッと尻をあげた。分かったわよ信次のリズム、もう自由に信次の呼吸、コントロールできるわよ。例えばこんなのはどう?玲子がスッと尻を上げるや否や、信次は必死で汚れた息を吹き出した、と次の瞬間、信次が全く息を吸えない内に玲子の尻が下り、信次の鼻を塞いでしまった。「むぎゅううううううううう・・・ふんがふんがぁぁぁぁぁ・・・」ビタリと鼻の穴を塞がれた信次、肺の中は完全に空っぽになってしまったのに新たな空気は全く入ってこない。「アハハハハハッ!いつでも息をさせてもらえると思ったら大間違いよ!さあその空っぽの肺でいつまで持つかしら?試してあげる!」ぐ、ぐるじいいいいい・・・苦しいだけではない、空っぽに潰れた肺に横隔膜が引き上げられ、胸に、腹に激痛が走る。いだいいいい・・・ぐるじいいいいい・・・目の前が真っ暗になるほどの苦しさだった。信次の目は殆ど引っ繰り返り白目が剥き出しになっている。ヒコヒコヒコヒコ・・・胸が腹が苦しげに上下する、だがそんなことをしても求める唯一つのもの、空気は玲子のお尻に遮断され全く入ってこない。じ、じぬううううう・・・信次の眼前で星がチカチカ瞬く、失神か死か分からない、もう臨界点を超える、と思ったその瞬間、玲子はすっと尻をあげてやる。
ぶひゅっぶひゅうううううううっっっ必死で空気を貪る信次、だが人間の呼吸だ、吸った息は吐かねばならない。トントントン・・・玲子は膝頭を指で叩きながら信次の呼吸のリズムを図る。トントントン、今よ!グッと玲子が座りなおした瞬間、それは信次がまさにすべての息を吐き切った瞬間、玲子に座られない内に必死で空気を吸おうとした瞬間だった。ブヒッブヒイイイイイッッッッッ!!!ぐるじいいいいいいいっっっ!信次の全身が余りの苦痛にビクンビクンと大きく痙攣する。ギシギシッと頑丈な革ベルトが軋む。だが玲子の美尻は信次の必死の足掻きをものともせずに空気を奪い続ける。「アハハハハッ!信次、いい苦しみ方じゃない!そうそう、そうこなくっちゃね、せめてこの位は苦しんで貰わないと罰にはならないわよね!ぽーらほらほら、苦しめ苦しめー!」楽しげに笑いながら玲子は、自らの体内で最後の処刑用具が整ったことを感じていた。あ、やっときた、ウフフフフ、信次良かったわね、そろそろ止めを刺してあげるわ。信次の鼻頭での刺激、そして鼻息に刺激され玲子は直腸内にガスが溜まってきたのを感じていたのだ。ウフフフフ信次、感謝しなさいよ。昨日からお芋とか繊維質の多いもの一杯食べて、おならが出やすいようにしといてあげたんだからね。私みたいな美女のおならを直接嗅げるなんて、信次の一生の記念になる経験でしょ?たーっぷりと楽しんでね!
玲子の尻の下で地獄の苦しみにのた打ち回る信次には、玲子の企みを推測する余裕など全くない。信次が感じられることはただ一つ、苦痛レベルの飛躍的な上昇だけだった。余りに的確に息を吐き切ったタイミングで鼻を塞ぐ玲子、その巧みな責めに信次は涙を流し目を白黒させながらもがき苦しんでいた。ぐ、ぐるじいいいいいっ!だ、だれがあああっっっだずげでえええええっ!ぐげえええええっっっ、い、いっそ・・・いっそごろじでえええええっ!!!その瞬間、スッと玲子が尻を上げた。正確には尻を上げた内に入らないだろう、僅かに尻の位置をずらした程度だ、だがそれでも辛うじて空気が移動するスペースはある。ぶぶっ、ほんの僅かな空気を信次は鼻から吹き出した、そして信次が必死で息を吸い込もうとしたその瞬間、玲子はピタッと信次の鼻を肛門で完全に塞いだ。今よ・・・尻地獄、これが止めよ!プッスウウウウウッ・・・玲子は直腸内に溜まったガスを一気に放出した。必死で息を吸う信次、空っぽになった肺の陰圧に引かれて放出された玲子のガスの全てが信次の鼻へ、肺へと吸い込まれていく。ぐっげえええええええっ!ぐ、ぐざいいいいいいっっっ!至近距離どころではない、ゼロ距離での毒ガス攻撃。放出したばかりのおなら全てを吸わされたのだ、溜まったものではない。普通おならが臭い、と言ってもそれは空気で相当に拡散されたものを吸って臭いだなんだと言っているだけだ、この一撃とは比べ物にならない。臭い、等という言葉は生ぬるい、鼻から肺にかけてガーン、と殴られたような衝撃が走る。目の前が黄色くなるような衝撃、激痛すら感じる衝撃だった。ぐっぶうううううううっっっ、ぐごげえええええええっっっ!玲子のおならに体の中から全身を侵され、腐り果てさせられるようだった。ひ、ひでえええええ、は、鼻先でおならだなんてえええええ・・・
アハハハハッ、アハハハハハッ!苦しんでる苦しんでる!玲子は想像以上の信次の苦しみように手を叩いて喜んでいた。やったやったーっ!どうよ信次、少しは思い知った?もう私の全身、信次にとって凶器よね。口も手も足もお尻も、私の全身どこでも見ただけで苛められた辛い辛―いトラウマに直結でしょう?でも体の外側だけじゃないわよね。私の体から出るものも信次にとってはトラウマ直結よね。唾を吐き掛けられる気分はどう?おしっこ飲まされるのも辛くて辛くて堪らないでしょう?挙句の果てにウフフフフ、おならで窒息だって!もう最高!おならで窒息させられた人間なんて、そんなの私聞いたことないわよ。私の体の外も中もぜーんぶ、信次にとっては最高の拷問具ね!さぞ私が怖いことでしょうね!あはは、あははははっ!信次、あんたもう精神ボロボロでしょう?ざまーみろ、て感じよね!もう一生その臭い、忘れられないわよ、アハハッ、アハハハハハッ!ああ最高、何かまたおならしてやりたくなってきたわ!ウフフフフ、もう一回苦しめてあげる!私のおならを嗅がせてあげる!そして・・・私のおならで窒息するのよ信次!さあ成仏しなさい、ほら逝くわよ!玲子は再び微かに尻をずらした。ぶぶうっ、待ちかねたかのように信次は必死で汚辱の毒ガスを、玲子のおなら混じりの息を吹き出す。フフフ信次、ほんと信次ってバカね、学習能力皆無じゃない、こうされるってことくらい分からないの?玲子は信次が息を吸うタイミングを読み切って止めのおならを信次の鼻に注入した。
プスウウウウウッ、静かな音とともに吐き出された玲子の毒ガスを信次は再び肺の奥深くまで吸い込んでしまった。ぐえええええええっひいいいいいいいいいいいっ・・・ぐざいいいいいいい・・・先程よりもより濃密な玲子のおならの臭いに、信次はピクピクと断末魔のように痙攣する。無理も無い、幾ら全力で肺の中の空気を吐き出しても人体の構造上、全てを吐き出すことはできない。一定割合は、つまり最初に吸わされた玲子のおならの一部は肺の中に残っている。そこに第二陣の毒ガスが襲い掛かったのだ。確実に濃度を増した玲子のおならに鼻から肺を全て満たされた信次は汚辱と苦悶の極みに突き落とされた。臭いだけ、苦しいだけではない。ぐげえええええっい、痛いいいいいい!酷い頭痛に頭が割れそうだ、心臓がバクバクと激しく動悸し殆ど不整脈状態となり、全身の血管から血が吹き出てきそうだ。全身が反乱を起こしたかのような苦痛のオンパレードに信次は殆どパニック状態に陥っていた。おならは決して肛門から空気が逆流しているわけではない。口、鼻から入った空気の一部であり、それは腸内の発酵作用により酸素の大部分を消費された、一種の酸欠ガスだ。一回に放出されるおならは体積にすれば少量、ごく少量だが玲子はその全てを信次に吸わせ、信次の肺の殆ど全てを自らのおならで満たしてしまったのだ。それは決して比喩ではなく、毒ガス同然の威力があった。酸欠ガス、純度は低いが悪臭に満ち満ちた汚辱の毒ガス、しかも玲子はピタリと信次の鼻を塞ぎそのガスを決して外に出させない。ぐ、ぐるじいいいいい・・・ひ、ひでえええ・・・あんまり、あんまりだあああああ・・・お、ならで・・・おならで・・・責め潰すなんて・・・あんまり・・・だあああああ・・・・・ククク、ウフフフフフ、アハハハハハッ!玲子は肛門の下で信次の痙攣が徐々にか細くなっていくのを、自分のおならを吸わされ悶絶させられた信次の断末魔を楽しそうに笑いながらいつまでもいつまでも楽しんでいた。
「遅くなりましたあっ!どう慎治、怜先生にしっかりお仕置きしてもらった?」明るい声をあげながら礼子たちが入ってきた。「お帰りなさい、丁度いいタイミングだったわ、鞭でのお仕置きで一回お寝んねしてね、今二人とも起きたことろよ。一息ついてフフフ、丁度いい責め頃よ。」ヒッ!せ。責め頃だなんて・・・怯える二人の事など全く意に介さず、舞が玲子たちに椅子を指した。「まあ二人とも、座って一服しなさいよ、紅茶でもいれるわ。」「あ、有難うございます!舞先生、どんなお仕置きしたんですか、教えて下さいよ!」腰掛けるや否や、興味津々と言った様子で玲子が尋ねた。「はいはい、全くウキウキしちゃって霧島さんは、もう根っからの苛めっ子ね!」カラカラと楽しそうに笑いながら舞が答える。「取りあえず二人とも、鞭でお尻ズタズタにしてあげたわ。ウフフフフ、楽しかったわよ、色々言葉でも追い詰めながらね。あんまり楽しくて私も怜もついついお仕置きに力が入っちゃったわ。川内君、二人とも立って霧島さんたちにお尻、見せてあげなさい。」穏やかな口調だが信次たちが逆らえるわけがない。「は、はい・・・」のろのろと立ち上がった二人は全裸の惨めな姿のまま、怜と舞にズタズタにされた尻を玲子たちに向けた。「わあっすっごーい!」「流石は怜先生!もう血塗れに引き裂いた、て感じですねえ!」美貌のクラスメート、自分たちを地獄に突き落とした張本人に惨めな傷跡を嘲笑われる、それだけで十二分な恥辱だ。だが恥辱などほんの始まりに過ぎない。もう間もなく礼子たちに苛められるのだ。窒息責め、怜たちが邪魔な男を発狂させたという恐怖の責めを味合わされるのだ。クックッと礼子たちはゆっくりと香り高い紅茶を飲み干していく。まるで死への砂時計を刻まれているようだ。あの紅茶を飲み終えたら・・・窒息責めをされる!逃げ出したい、どこかに逃げ出したい!でもどこへ?両親さえもう敵に回ってしまったのだ、「慎治くんたちがお仕置きから逃げました、連れ戻してください。」と言われれば慎治たちの両親は何の躊躇もなく二人を学校に、残酷な美女たちの鞭の下に連れ戻すだろう。絶望、ただそれだけが二人の全てを支配していた。
コクッと最後の一口を飲み終えた礼子がカチャッと小さな音を立ててカップをソーサーに戻した。ビクッと震える慎治を一瞥しながら礼子はフッと小さく息をついた。「ごちそうさまでした。おいしかったです。」「そう、良かったわね。じゃあっと」ウン、と小さく伸びをしながら怜と舞が立ち上がった。「じゃあ天城さん、霧島さん、後はよろしくね。ええと、鍵はもう渡したわよね?施錠だけはよろしくね。」い、行ってしまう!怜先生が・・・そしてその後は・・・礼子さんに窒息責めされる!「ああ、あああ・・・先生・・・行かないで・・・」涙声で哀願する慎治に、怜は一瞬キョトンとした表情を浮かべた後、何とも言えない苦笑と嘲笑の入り混じった笑いを浮かべた。「全く・・・矢作君、あなた一体どういうつもりで今、私に行かないで、なんてお願いしたの?いい、君は今、私にお尻を鞭でズタズタに引き裂かれたばかりでしょう?分かってるの?君にとって私は、天城さんたちと同じ責め手、拷問官でしょう?その私に行かないでなんて、正気で言っているの?」呆れた、というように首をすくめながら舞も苦笑する。「まあどうしても行かないで、て言うなら残ってあげてもいいけど、それは君たちにとって窒息責めの責め手が一人から二人に増えるだけだと思うわよ?全く・・・君たち本当に・・・おバカね!」ぐうっ・・・何も言えなくなった二人を一瞥すると舞は玲子に言った。「まあ霧島さんたちも、先は長いんだから余り無茶しないようにね。あ、それと例の件、予定決まったら簡単にメモにして頂戴ね。急がせて悪いんだけど根回しもあるからなるべく早め、できたら今週中に貰えないかしら?」「あ、あれでしたらもう大体やること、もう決めたんです、明日にはメモ、お渡しします。」打てば響くような玲子の答えに二人は満足そうに頷いた。「流石は霧島さん、ほんとクイックレスポンスで気持ちいいわね。じゃあよろしくね。」な、なになになになんなんだ?例の件って?怜と舞が出て行き一瞬静かになったお仕置き部屋、その重苦しい空気に怯えながらも信次は聞きたくて聞きたくて仕方がなかった。「フフフ信次、どうしたのよモジモジしちゃって、どうせこのことでしょ?例の件って何、て聞きたいんでしょ?」「あ、は、ハイ・・・聞かせてお願い・・・」ニヤリと玲子の口元に残忍な笑みが浮かぶ。「いいわ、教えてあげる。私と礼子はね、舞先生たちに信次たちのお仕置き計画を頼まれたのよ。今日この場でのお仕置きなんかじゃないわよ。ウフフフフ、全校に恥を晒して、女の子に暴力振るった男はこうなるのよ、それだけは聖華では絶対に許されないことなのよ、ていうことを知らしめるお仕置きよ。ああそう怯えなくてもいいわ、痛い、という意味では多少は痛いけど安心していい、信次たちにとっては十分耐えられる筈よ、肉体的にはね。だけど、フフフフフ、精神的には辛いわよ?たっぷりと生き恥を晒させてやるからね?」「ひいいいいいっ、そ、そんな・・・、何をさせる気なの・・・」傍らで慎治が思わず呟くのを礼子は聞き逃さなかった。「慎治、心配しなくてもいいわよ、もう何日かすればどうせ嫌でも分かるんだからね。それより慎治が心配しなくちゃいけないのは他のことよ。フフフ、窒息責め、たっぷりと苦しめてあげるからね!」ああ、あああ・・・完全防音のお仕置き部屋に礼子と慎治、そして玲子と信次。責める側の礼子たちにとっては最高の環境、そして犠牲者の慎治たちにとってはこれから先、まさに地獄を味わい続ける場所だった。
「さあ、私たちもブーツに履き替えようかしら。」えっブーツ!?慎治たちの背筋にゾクッと寒気が走る。お仕置き部屋の片隅に置かれた大型のバッグに向かって礼子たちが歩いていく。見覚えのあるバッグだった、あれは確か・・・週末、レンタル体育館に連れて行かれる時に礼子さんたちが鞭やブーツを入れてくるバッグだ!「怜先生たちもわざわざブーツを履いて慎治たちをお仕置きしてくれたそうじゃない?流石は怜先生よね、慎治たちがどうやれば怯えるか、よくご存知よね。だったら私たちがこれからどうすると思う?ウフフ慎治、どうやら分かっているみたいじゃない?そうよ、あのブーツを持ってきてあげたのよ。黒ブーツをね!」礼子が取り出したのはまさに、慎治たちの血と涙をたっぷりと吸った漆黒のブーツだった。礼子たちの黒ブーツと富美代たちの白ブーツ、このブーツにどれだけ苛められたことだろう。「ウフフフフ信次、どういうことか分かるわよね?このブーツを私たちが履いたらどうなるか?」ヒッ、ヒイイイイッッッ!信次は声にならない悲鳴を上げた。ブ、ブブブブ、ブーツ!黒ブーツ!れ、玲子さんたち、このブーツ履くと残酷さ100倍増じゃないかあああっ!「あああ、お、お願い、ブーツは、ブーツだけは許してえええっ!」必死で絶叫する信次を見据える玲子が嗜虐の楽しみを満喫するかの如く、ゆっくりとブーツに脚を入れていく。「フフフフフ、分かっているみたいじゃない信次、そうよ、このブーツ履いちゃったら私たち、リミッター全解除よ!」ブーツを履いた礼子たちはまさに残酷さ全開、慎治たちにとっては地獄の悪鬼と化してしまう。例え僅かであっても手加減してくれる望みが全く絶たれてしまう。「そ、そんなあああ・・・」「やめてお願い・・・履かないで・・・」哀願する二人の情けない顔を楽しみながら礼子たちはチーッとゆっくりとブーツのチャックを上げていく。ピタッと細身のブーツが脚に吸い付く感触が二人の心を燃え立たせる。「さあ信次、戦闘準備完了よ!覚悟はいいわね?」玲子が勢いよく立ち上がった。
「さあ慎治は礼子と一緒に左の部屋、信次は私と右の部屋よ。ウフフフフ大丈夫、心配しないでいわ、壁は防音じゃないからね、ちゃんと慎治の苦しむ悲鳴は聞こえるわよ。勿論、信次の悲鳴もあっちに届くからね、二人で仲良く苦しみなさい。あ、もっとも苦しすぎてお互いの悲鳴なんか聞いてる余裕ないと思うけどね。アハハハハッ!」楽しそうに笑いながら信次を引き立てて玲子が隣の部屋に移動し、後には礼子と慎治だけが取り残された。「フフフ、丁度小部屋が二つあって良かったわ。」礼子が口を開いた。「お尻の下で窒息させる、と言ってもね、私たちも服が乱れるでしょう?玲子も私も、お互い自分のお尻を見られるのは嫌だからね、おトイレと同じでちゃんと個室があって良かったわ。そう言えば慎治は中学の頃から私に憧れていたのよね。ウフフフフ、今でも憧れているかしら?」そ、そんな・・・憧れの感情などとうに消え失せている。だが慎治の中で礼子がかって憧れの存在、文字通り偶像に近い、言葉の真の意味でアイドルであったことは確固として刻み込まれている。だからこそ、その憧れの存在、礼子に責め苛まれるのは他の女の子に苛められる何倍も辛い。礼子は慎治のそんな感情を読み尽し、手玉に取って弄んでいた。「鞭で打ちのめされ唾を吐き掛けられ、おしっこまで飲まされても未だ、私に憧れている?流石にもう無理かしら?アハハハハッ!でも私のお尻にも憧れていたんでしょう?いいお尻だなあ、触りたいなあ、て散々妄想していたんじゃない?望みをかなえてあげるわよ、今日は慎治にたっぷりと私のお尻を堪能させてあげる!心行くまで私のお尻を堪能するがいいわ。憧れの私のお尻を、この天城礼子のお尻をね!遠慮はいらないわ、嫌といっても無理矢理堪能させてあげる。ウフフフフ、責め終わったらどうなっているかしら、私のお尻、憧れから恐怖の象徴に変わっているかもね!」
隣室に連れ込まれた信次も死刑宣告を受けていた。「ねえ信次一つ聞かせて、信次、私のこと大嫌いでしょう?憎くて憎くて堪らないでしょう?殺したくて仕方ないでしょう?正直に言いなさい!」と、当然だろう!ぶ、ぶっ殺してやりたい・・・だがそんなことを口に出せるわけがない。「そ、そんなこと・・・ないです・・・」消え入りそうな声で答える信次を玲子は嘲った。「嘘言いなさい!毎日毎日こんなことされて悔しくないわけないでしょう?ほらこんなことされても?ペッ!ほら!ペッ!」二度三度と玲子は唾を吐き掛けた。ち、畜生、気軽に唾吐き掛けやがって・・・信次の顔が屈辱に歪むのを玲子は楽しそうに見下ろしている。「ウフフフフ、こうやって毎日毎日唾吐き掛けられているんだものね、信次、私の唇もう怖くて怖くて仕方ないでしょう?」ヒッ!突然玲子が平手打ちをするかのように手を振り上げ、信次の悲鳴が漏れる。「アハハハハハッ、いい反応よ。当然よね、ビンタに鞭にと、私の手に散々痛めつけられたんだものね。ウフフフフ、私の足も当然怖いでしょう?ブーツで踏み躙られて蹴り倒されたんだものね、怖くて怖くて堪らないでしょう?ウフフフフ信次、今からもう一つトラウマを植えつけてあげる。そうよ、私のお尻。フフフフフ、私のお尻を見ただけで震え上がるほど、苦しめてあげるからね!」「い、いや、いやああああっ、そんなそんな、いやだあああああっ!」必死で首を振り泣き喚く信次を見下ろしながら、玲子はゆっくりと立ち上がった。「さあ信次、お仕置き後半戦よ。ウフフフフ、私のお尻、たっぷりと味合わせてあげるわ。」「そ、そんな・・・玲子さん・・・お願い、もう・・・苛めないで・・・」「苛める?何を言ってるのよ失礼ね!これは信次に対する正当な処罰、ご両親も公認の体罰よ!苛めだなんて、全く失礼ね!どうやらまだまだ反省が足りないみたいね、たっぷりと懲らしめてあげるわ!」「ヒッ、ヒイイイッ!こ、懲らしめるだなんて、そ、そんなああああ・・・」「怖い?当然よね、窒息責め苦しいわよ?多分さっきの舞先生たちの鞭よりも辛いんじゃないかしら。だけどね」玲子の美貌にも冷酷な笑いが浮かぶ。「そんなに嘆き悲しむことはないんじゃないかしら?」「そ、そんな・・・窒息させられるのに・・・悲しいに決まってるじゃないか・・・」座り込んで泣きながら抗議する信次を玲子は楽しそうに見下ろしている。「あらそうかしら?例え窒息責めと言っても信次、私のお尻をたっぷりと味わえるのよ?こう見えても私、もてるのよ?顔面騎乗なんて言葉もある位なんだから、私に座られたい、ていう男は幾らでもいるわよ。嘘だと思ったら沖あたりにでも聞いてご覧よ、霧島玲子が僕の顔面に座る、て言ってるけど代わってくれないか、てね。きっと沖、大喜びで代わってくれるわよ。私が座ってあげたら泣いて喜ぶんじゃない?沖だけじゃないわ、多分クラスの男の子の殆どみんな、私か礼子に座られたい人手を上げて、て言ったら一斉に手をあげるわよ。ウフフフフ、信次みたいなクズが私に座ってもらえるなんて、光栄と思いなさい!」
「そんなあああ・・・」「い、いやだあああああ!!!」二人の悲鳴と哀願を楽しんでいた礼子たちの美しい唇から、遂に処刑開始の宣告が発せられた。「さあ、拘束台に登りなさい!」「はい、泣き言はもういいから、さっさと拘束台に寝るのよ!」泣きながら慎治たちは拘束台に登り、横たわった。手馴れた手つきで礼子たちは慎治たちの手足を、首を、腰を固定していく。あっという間に慎治たちは完全に身動き一つ出来なくされた。二人にももう分かっていた、礼子たちのような冷酷な拷問官の前で身動き一つできなく拘束され、抵抗の術を完全に奪われることが何を意味するかを。これから加えられるであろう責め苦の苦しさの予感に慎治たちは止め処もなく涙を流し続けていた。首のベルトをグッと締め上げた礼子が、締め具合を確認する。喉に食いこんではいないが頭を全く持ち上げられない、絶妙の締め具合だ。「さあ最後はこれよ。」キリキリキリ、と拘束台のサイドに取り付けられたハンドルを回すと、慎治の顔面の両側から万力の留め具が迫ってくる。「あああ・・・やめてえええええっ!」慎治の悲鳴を無視して礼子はハンドルを回し続ける。留め具は慎治の両耳の辺りにがっちりと食い込み、最早首を上下左右、どの方向に動かすこともできない。隣室でも同じく万力に締め上げられた信次に玲子が声をかけた。「聞こえる信次、耳を塞がれても私の言うこと位は聞こえるでしょう?」「あうううう・・・玲子さん・・・お願い外して・・・」「何、万力外して欲しいの?」「お願いですううう・・・外してくださいいいいいい!」「アハハハハッ!へーえ、そうなんだ、万力外して欲しいんだ!いいわよ、後で外してあげるわ。ウフフだけどね、きっと信次、万力外して貰ったことを後悔するわよ?」「こ、後悔?な、なんで・・・」信次が言えたのはそれまでだった。
「逝くわよ・・・」礼子がゆっくりと慎治を跨ぐように立ち、腰を下ろし始めた。紺ブレのスカートがゆっくりと降りてくる。視界の全てが礼子のスカートに覆い尽され、尻がもう間近に迫った最後の瞬間、礼子はスッとスカートの裾を後方に捲り上げた。スカートの中には純白の薄いパンティに包まれた美しい尻が双丘のように聳え立っていた。「ぐぶうううううっっっ!」礼子の張りのある、鞠のように弾力のある美尻が着地した瞬間、慎治の口から何とも言えない悲鳴が漏れた。顔に布の感触を感じた次の瞬間、鼻、目、額、そして口と顔中全てに加速度的に強烈な重みが掛かってきた。「グフィイイイイイッ!」悲鳴を上げながら慎治は必死で逃れようと反射的に全身に力を込めた。ギシッとベルトが軋む音がする。だが頑丈な革ベルトは全く緩まず、大型万力でしっかりと固定された頭は左右に動かすことなど全くできない。首を思いっきり前に起こせば顔がスポッと万力から抜け出られるかも知れないが、礼子が顔の上に座り込んでいるのだ、首の力だけで跳ね飛ばすのはプロレスラーでも難しい、ましてや慎治になど逆立ちしても不可能だ。「グウッ、グウウウッ、グブウウウウウッッッ・・・」「フフフどう慎治、苦しい?重い?ウフフフフ、でもね、未だ私は全体重をかけてはいないのよ、重くなるのは・・・これからよ!」楽しげに笑いながら礼子は僅かに伸ばしていた膝から力を抜いて全体重を尻に、椅子に、即ち慎治の顔面へと掛けていく。グギュウウウ・・・顔面全体への圧迫が一層強まり慎治は悲鳴を上げることすら困難な状況だ。慎治の上顎あたりに腰を下ろした礼子はそのまま太腿を慎治の顔面にピタリと密着させ50キロ強の全体重を顔面の狭いエリアに集中させる。見えない、慎治の目は礼子の太腿の下敷きにされ殆ど何も見えない。耳は万力に塞がれ何も聞こえない。そして鼻は礼子の股間に押し当てられピタリとパンティが張り付いたような状態だ、呼吸をすることすら困難を極めた。ぐ、ぐ、ぐぐぐ・・・ぐるじい・・・いだい・・・苦しいだけではない、手で僅かでも礼子の体を支えて苦痛を軽減することすらできない、一切の支えなしで顔面に全体重を受けているのだ。しかも慎治が寝かされている拘束台はクッションなど全くない硬い板でできている。礼子の全体重を掛けられている後頭部は骨がミシミシいっているかのようだ。余りの痛さと苦しさに慎治は目の前がクラクラしてきた。頭が・・・頭が割れるうううっ!ナットクラッカーに挟まれたクルミのように、自分の頭が礼子の尻にグシャリと押し潰されてしまう映像が頭に浮かんだその時、礼子がスッと僅かに腰を浮かした。「ぐはっくはあああっ・・・あっあっあっ・・・」必死で荒い息をする慎治を満足気に見下ろしながら礼子は笑っていた。「アハハハハッ!苦しいでしょう?痛いでしょう?でもね、まだまだほんの序の口よ。私はこの責め、単に座っているだけだもの、全然疲れないわ。ウフフフフ、たっぷりと時間をかけて苦しめてあげるわね!」「あっ!そんなあああああっ!や、やめてえええええっ!!やべ、ぐひいいいいいっ!!!」慎治の悲鳴を嘲笑いながら礼子は再び腰を下ろす。ぐうううっくぶぶぶぶ・・・いいわこの感触、本当に楽しいわね、これ。礼子は自分の尻の下でもがき苦しむ慎治の痙攣を心の底から楽しんでいた。間断なくビクビクと痙攣のように慎治がもがく。いいわいいわ、もっともっと苦しみなさい。いくらでも好きなだけもがきなさい、そんなもの何の役にも立たないけどね。礼子は僅かに尻を前に動かし、慎治の鼻腔に股間を押し当てた。「ぐぷううう・・・くかあああああ・・・」苦しげな悲鳴が漏れる。ウフフどう、苦しい?息をするのも大変でしょう?でも完全に塞がってるわけじゃないからね、少しずつは息も吸えるはずよ。窒息する心配はないわ慎治。ウフフフフ、だってそんなに簡単に気絶させちゃ面白くないものね、さあもっともっともがき苦しみなさい!グッグッと礼子は前後左右に捻るように腰を揺り動かす。「ぎがあああああっっっ・・・」慎治の潰れた悲鳴が礼子の尻の下から漏れる。無理もない、尻は決して肉と脂肪のみで出来ているわけではない、中には硬い尾?骨が走っている。その先端は普段は肉の中に隠れているが、全体重をかけて慎治を潰している礼子の尾?骨は今、慎治の顔面に食い込んでいる。それを前後左右に揺り動かされては溜まったものではない。柔らかい尻の肉の中に隠された硬い尾?骨、それはまるで美貌と明るい性格の中に無限の残酷さを隠し持つ礼子の象徴のようだった。ゴリッ、グリュッ・・・顔面を硬い棒でこねくり回されるような苦痛に慎治は悲鳴を上げ続けた。痛いいたいイタイ・・・痛いよおおおおおっっっ!!!苦痛は時間とともに無制限に拡大していく。鞭のような激痛ではないが瞬時の休みもない責め苦、しかも礼子の無情な圧迫は顔面全体、さらには後頭部に鬱血を引き起こし等比級数的に苦痛を増大させていく。目は見えず耳も聞こえない。暗闇と耳を圧迫されたゴーッという轟音の中でひたすら苦痛のみを味わい続ける。他人の、美しいクラスメートの尻の下に敷かれるという屈辱、他人に顔面に座られるという屈辱。それすら今の慎治にとっては何の問題でもない。屈辱を味わっている暇などない。あるのは苦痛、ただ苦痛の二文字のみしかなかった。そして隣室では同じく信次も玲子の尻の下で呻き続けていた。
どれくらいの時間がたっただろうか、意識朦朧とした信次の顔面から玲子がすっと下りて泣き疲れたように醜く歪んだ信次を見下ろしていた。「信次、信次!聞こえる?聞こえたら返事くらいしなさい!」ピシーンと鞭のようによくしなる玲子のビンタが信次の頬を打ち据えた。「ほら万力はもう外してあげたわよ、耳は自由になったんだから聞こえるでしょう!?」玲子の凛とした声に叩き起こされ、信次は優しい救いの手、失神の一歩手前から連れ戻されてしまう。焦点があわずボヤケていた目に徐々にはっきりと、見下ろす玲子の美貌が見えてきた。「目が覚めた?どう、私のお尻の味は、たっぷりと堪能したかしら?」「あぐうううう・・・もう・・・ゆるして・・・」「許して欲しい?苦しかった?それとも痛かったかしら?私にたっぷりと座られたんだもの、さぞ痛いでしょうね。もう許して、ていうのもわかるわ。でも」玲子は満面に冷酷な笑みを浮かべて言い放った。「女の子に暴力振るうような男はね、この程度じゃ絶対に許して貰えないのよ。これからが本番よ、ウフフ、今までのはほんのオードブル、これからもっともっと苦しめてあげる!さあ万力を締め直しましょうね、キリキリと!」愉しげに笑いながら玲子は万力に手をかけ、回し始めた。「い、いやあああああっ!いやだあああああっ!」「何をそんなに騒ぐのよ、煩いわね。」ふと手を止めて玲子が尋ねた。「信次、万力で締められるのはそんなに嫌?もしかして締めないで欲しいの?」「いやあああああ・・・お願い・・・万力は許して・・・ください・・・」涙を溢れさせながら信次は必死で哀願した。せめて万力さえ、万力さえなければ頭を横に回せる、そうすれば少しは・・・少しは楽になれるはず、息は自由に吸えるはず・・・でも玲子さんが許してくれるわけない・・・だが玲子の唇から漏れた言葉は意外なものだった。「フーンそう、信次はそんなに万力が嫌なんだ。じゃあいいわ、万力はしないであげるわよ。」「えっ・・・ほ、ほんと、本当ですか???」「嘘は言わないわよ、ほらこうやって万力、しまってあげる。」玲子は収納式になっているアームを一杯に下げて拘束台に埋め込んだ。首を固定されているとはいえ、頭の動きはかなり自由になった。ある程度は左右に捻じったり、上下にも動かせる。ああ良かった・・・だけどなぜ・・・なんで万力を許してくれたんだ・・・不安げな信次の怯えを楽しむかのように玲子が嘲笑った。「お望み通り万力は許してあげるわ。ウフフフフ、でもね、いいこと教えてあげるわ。万力がなくなるとね、もっともっと、ずっとずーーーっと、苦しくなるのよ。でも仕方ないわね、万力を取ってくれ、て言ったのは信次自身だものね!余計苦しくなっても自業自得というものよね、アハハハハ、アハハハハッ!」えっええっ、そ、そんなあああ・・・でもなぜ、なぜ万力がないと余計苦しくなるの???その疑問はすぐに氷解した。「さあ信次、万力がなくなるとどうなるか、たっぷりと教えてあげるわね。ウフフフフ、心いくまで苦しみなさい!」玲子は再び信次の顔を跨ぎ腰を下ろしてきた。「ひっ、ひいいいいっっっ!ブギイッ!」信次の顔面に玲子の尻が着地し、そのままグウッと体重が掛かってくる。「ぐっぷううううっ・・・」悲鳴にもならない信次の苦悶の喘ぎが小さく響いた。あが、あがあっ・・・な、なんで、なぜえええええっ!重いいいい・・・さっきより全然重いいいい!責められている信次には理由は分からなかったが、苦痛が増したのも当然だ。信次の顔面を固定していた万力は確かに顔面を真上に固定する責め具ではあったが、同時に玲子が腰を下ろした時、その体重の一部を支える役目も果たしていたのだ。その支えが無くなった今、玲子の文字通り全体重が信次の顔面にかかってくる。だが玲子の責めはそれだけではない。更に厳しい責め苦が待っていた。「うばっ、うぶぶぶぶ・・・」信次の苦しげな悲鳴が響く。「アハハハハッ!どうしたの信次、随分悶えているじゃない、こうやって揺すって欲しいの?私も協力してあげようか?ほら!ほら!ほらほらほら!」玲子が愉しげに笑いながら腰を前後左右に揺り動かす度に、全身を苦悶に痙攣させる信次の苦しみ様は只事ではなかった。ギシッ、ギシギシギシッと拘束台を激しく軋ませながら信次は苦悶に全身を痙攣させていた。「どうしたのよ、何をそんなに悶えているの?ぴったり密着している分、さっきと違ってお尻の骨は食い込んでいない筈よ。痛いのは大分軽くなったんじゃないの?」確かにその通りであった。玲子の尻、太腿は信次の顔面にぴったりと密着している、そのため尾?骨の角度が変わり、先ほどまでとは違って信次の顔に余り食い込んではいないから痛みはかなり軽減されている。適度に肉と脂肪のついた熟成しつつある美少女の肢体、玲子のお尻は適度な柔らかさとハードトレーニングの賜物である十分な弾力を併せ持つ、最高の双丘だった。だがその柔らかさこそが信次を地獄のどん底に突き落としていたのだ。「くはっくはあああっ、ぐ、ぐふううううっっっ、い、いぎがあああ・・・」玲子の尻の下で信次は声も碌に出せないままもがき苦しんでいた。万力という抵抗から解放された玲子の柔らかい尻の肉は、信次の顔面にぴったりと密着していた。勿論、口にも鼻にも。柔らかい分密着の度合いは大きく、信次が呼吸しようにもほんの僅かの隙間しかない。く、ぐるじいいい・・・このままじゃ窒息するううう・・・横、横を向かなくちゃ・・・信次は必死で顔を左右に動かし、なんとか横を向いて口と鼻を自由にしようと抗った。フフフ、苦しんでる苦しんでる、そうよね、私のお尻に口も鼻も塞がれてさぞ苦しいでしょうね。ウフフフフ、でもそう簡単に横を向けるわけないでしょう?精々頑張ることね、まるでお尻の下で踊っているみたい!アハハハハッ、さあ踊りなさい!お尻の下で。頑張んないと・・・窒息しちゃうわよ!?玲子は冷酷な笑みを浮かべながらグッと太腿に力を入れ、乗馬の要領で締めつけた。万力こそないものの信次の顔面は玲子の太腿に両側から締め付けられ、全く自由はない。いくら必死で動かしても首の可動範囲は極く僅か、玲子の尻の下から抜け出るには程遠い。それに僅かばかり首が動いたところで、上に乗っている玲子の尻も一緒に動くのだからどう足掻いても息は吸えない。「うっぐううううう・・・くっかああああ・・・」楽になるどころか必死で全身に力を込めるものだから酸素をより多く消費してしまい、息苦しさは増すばかりだ。「あひっあひいいいいっっっひっぎいいいいっっっ」信次の全身が凄まじい苦悶に激しく震えている。ぐ、ぐるじいいい・・・
呼吸困難、だが口も鼻も僅かな隙間は残されている。その隙間から時折、若干とはいえ空気が肺に入ってくるから中々失神することすらできない。蛇の生殺しのように、呼吸困難のチアノーゼ症状にゆっくりと全身を責め苛まれながら信次は延々と苦しみ続けた。「ぐぎいいいいい・・・ゆるじでえええ・・・く、くうき、くうきいいい・・・いきが、いきがあああ・・・・・」哀願の言葉すら碌に言えない。玲子が腰を上げてくれない限り信次はいつまででも際限なく苦しみ続けるのだ。信次の苦悶を玲子は心の底から楽しんでいた。フフフ、楽しいわこの窒息責め、私のお尻に信次の苦悶がストレートに流れ込んでくるわ。必死のあがき、痙攣、苦しげに吐き出す僅かな息、それにほんの少ししか流れ込んでこない空気を必死で吸い込もうとする無駄な努力。ああ楽しい、私の手を煩わせたクズを罰しているんだ、ていう実感が本当に気持ちいいわ、窒息責め最高!玲子が拷問の悦楽を満喫している間も信次の全身は間断なく痙攣し続け、口と鼻の前に僅かな空間ができるたびに必死で空気を貪る。ズッ、ズズウッッッ・・・だらしない音を立てながら必死で空気を貪る。フフフフフ、頑張ってるじゃない信次、信次の喘ぎでお尻がくすぐったいわ。玲子は薄いパンティ越しに伝わる信次の苦悶を何ともいえない快感と共にゆっくりと堪能していた。「ウフフフフ信次、どう私のお尻の下の居心地は?女の子のお尻を追い掛け回してトイレにまで忍び込んだ信次でしょう、お望み通りの居場所じゃないの?天国に昇るような気分じゃないの?アハハハハッ!ゆっくりと楽しみなさい!ああそうだ、私は宿題片付けちゃうから、あんまり暴れないでよ、やりにくいからね。」「ぞ、ぞんなあああああ・・・」しゅ、宿題?じゃ、じゃあ・・・いったいどれだけ俺の上に座っている気なんだあああああっ!その通り、玲子は時折僅かに腰を浮かせて信次に息継ぎをさせながらたっぷりと座り続けた。
一時間近くがたち、慢性的な酸欠、呼吸困難と顔面に絶え間なく座られ続けた圧迫で意識朦朧となった頃、漸く信次たち二人はお尻の下から解放された。ゼハアッ、ゼハアアアアッッッ・・・荒い息を吐き続ける慎治の頬を礼子が優しく撫でた。「ウフフフフ、どう効いたかしら今の責め、苦しかった?」「あうっあああ・・・・く、るしい・・・ねがい・・・もう、許して・・・」隣室では信次も束の間の休息を貪っていた。ハアッハアハアハアハアッッッ、ゲホッグハアッ、ハアハアゼイゼイ・・・「アハハハハ、やあねえ咳き込んじゃって、そんなに急いで息するからよ!そんなに苦しかった、私のお仕置き?もう十分反省した?」「アウッヒッヒックウエッッッッ・・・し、ました・・・反省・・・・しました・・・・から、どうかおねがい、許して・・・ください・・・・もう・・・しませんから・・・」それぞれのお仕置き部屋で礼子たちは満足そうに頷いていた。「そう、そんなに許して欲しい?ウフフ、じゃあ一つ質問よ、慎治、今の私の責めは・・・どういう責め?責めの名前は何かしら?」「あらあら信次、ずいぶん素直じゃない、よろしいよろしい、大分お仕置きの効果があがったようね、嬉しいわ。じゃあ一つ質問するわね、今の私の責め、何ていう責めかしら?」え、今の責めの名前???慎治たちは一瞬躊躇した、さっき言ってたけど、そのままでいいんだろうか・・・また引っ掛けじゃ?だが考えている時間はない。「わからないのかしら?」「どうしたの、答えは?」微かな棘を感じさせるだけで十分だった。「ヒッ、ち、窒息責めです・・・」「ち、ち、窒息・・・責めだと思いますっ!」引っ掛かったわね、礼子の冷たい美貌が嗜虐の予感に綻ぶ。「窒息責め?まあ散々苦しんだ慎治としては当然の答えでしょうけどね、残念ながら外れよ!」「えっえええっっっそ、そんな・・・ちがうんですかあああ!?」「そう、違うわ。大体さっき怜先生、窒息責めを慎治に説明してくれた時になんて言ったかしら?名取さんたちを何百回となく失神させたって言ったでしょう?だけど慎治は未だ一度も失神していない筈よ。と言うことは、窒息責めには程遠い、只の顔面椅子の刑がさっきのお仕置きの名前よ。」「あわわ・・・あわわわわわ・・・ま、まさか、そんな・・・」「ウフフフフそうよ、ご想像の通り。いよいよ本物の窒息責めを味合わせてあげる。フフフフフ、辛いわよお?慎治が本当に失神するまで苛めてあげるわね。」「ヒッヒイイイイイイッ!!!そ、そんなそんないやだあああああっ!ゆるしてえええええええっっっ!!!」慎治が必死で絶叫するのを礼子は面白そうに眺めていた。一しきり慎治が叫んだところで礼子が尋ねる。「ねえ慎治、そうやって絶叫するのは勝手だけどね、私にはどうしても理解できないな。慎治は今、拘束台に縛られているのよ?やめて許して、て幾ら叫んだって私に許してあげる気がない以上、無駄なんじゃないかしら?そんなに大声出して余計な体力使うと、後で却って余計ニ苦しむのは慎治自身だと思うんだけどな?」ああ、あああああ・・・・・そんな・・・慎治が恐怖と絶望の余り、思わず絶句してしまったのを見て礼子はいよいよ刑の執行を宣告する。「ウフフフフ、所で窒息責め、逝く前に二つ準備があるのよ。」部屋の隅から礼子が持ってきたものはガムテープ、紙ではない布テープだった。「これは只のガムテープ、どうするか分かる?分からない、いいわ教えてあげる、こうするのよ。」言うや否や礼子はピッとガムテープを伸ばし慎治の口に唐阨tけるとそのまま何重にもグルグル巻きにし、口を完全に塞いでしまった。鼻は塞がれていないから呼吸はできるものの、最早悲鳴をあげることすらできない。
2
「大丈夫、息はできるわね?それでもう一つの準備はね、これよ。」言いながら礼子はブーツを履いたまま純白のパンティを脱いで椅子の背にかけた。「パンティを脱いだ理由は簡単よ、パンティは幾ら薄いとは言っても布だから私の体から少しは浮いているし、慎治が必死で首を振れば少しは滑って息をする隙間もできるわ。だけどね、今度はそうは逝かないわよ?私のお尻の肉がぴたりと慎治の鼻を塞ぐわ、逃げ道なくね。ウフフ分かる?今度はどう抵抗しても無駄、私が腰を浮かせてあげない限り、絶対に呼吸できないわよ?」「えっおおっうんおおお・・・」「無駄よ、口を塞がれているんだからね、何も言えるわけないじゃない。そしてそのガムテープはね、二つの役割があるわ。一つはね、そうやって口を塞いでしまい、呼吸を鼻だけにしてしまうこと。そしてもう一つはね、抵抗を完全に封じることよ。怜先生たちは無理矢理監禁した、て言ったでしょう?窮鼠猫を噛むじゃないけど、口を自由にしたまま座ってお尻を齧られたら痛いからね、こうやって口を塞いで絶対に抵抗できないようにしたそうよ。うん、何?僕は絶対噛んだりしません、絶対抵抗しないからガムテープ剥がしてください、と言いたいの?」「うう、ううんうん、うん!」慎治は必死で頷いた。「ダメに決まってるじゃん、バカねえ!幾ら抵抗しない、て口約束したって失神寸前、生きるか死ぬかなんてシチュエーションだったら、反射的に何をするか分かったもんじゃないわ!第一、お鼻だけにしておいた方が私が責めやすいじゃない!?」交渉決裂であった。ゆっくりと礼子が慎治の顔を跨ぐ。「ウフフ、さあ逝くわよ、覚悟はいいわね?散々おしっこを飲まされた私のお尻で今度は窒息させてあげる。アハハハハッ!おしっこなんて苛めとしては生温く感じるまで苦しめてやるわ!」
礼子は慎治の顔を跨いだまま暫しの間、勝ち誇った笑みを満面に浮かべながら見下ろしていたが、やがてゆっくりと腰を下ろし始めた。慎治の目にどんどん礼子の尻、というより女性器が迫ってくる。慎治を責め嬲る喜びに上気しているかのように、ピンク色に艶やかに濡れ輝いている。いつもは顔の上10センチ程度で静止し、汚辱のおしっこを噴出する礼子の性器、だが今日は静止せず、そのまま近づいてくる。一瞬大アップになった礼子の性器は、近づきすぎて最早見ることもできない。呆然と見詰めていた慎治はハッと吾に返って必死で鼻から息を吸い込む。
い、息、今のうちに少しでも息を吸っておかなくちゃ!必死で吸った空気に微かな異臭が混じっていた。艶やかだがどこか野生を感じさせる、生々しい肉の匂い。これから慎治を責め苛む礼子の女性器の芳香だった。クラクラするような濃密な芳香、そしてその源が慎治の鼻にピトリと着地した。ピチャッと湿った感触に続いて慎治の顔面に礼子の体重がのしかかる。痛い重い・・・だが数秒を経ずしてそんな苦痛など物の数ではない、と嘲笑うかのような苦痛が襲い掛かってきた。
プッ、プッ、ウプウウッ!息が・・・吐けないいいいっ!慎治の鼻、口を塞がれた慎治にとって唯一の呼吸器官は礼子の女性器にめり込むかのように包み込まれ、完全に空気から遮断されていた。吸った息は吐かなければ次の呼吸はできない。だが必死で肺一杯に溜め込んだ息を吐くことすらままならない。クウッ、クウウウッッッッッ!慎治の体内一杯に溜め込まれた空気は出口を失い、慎治の鼻から肺を空しく行き来する。だがその空気は最早呼吸には何の役にも立たない。
ぐぐぐ・・・ぐるじいいいい・・・最後の力を振り絞るかのように必死で慎治が息を吐き出そうとした瞬間、礼子はほんの一瞬だけ僅かに腰をあげてやった。ブビイッ、みっともない異音を立てて慎治の鼻から空気が吐き出された瞬間、礼子は素早く全体重を掛けなおし慎治の鼻を完全に塞ぐ。「アハハハハッ、良かったわね慎治、お望みどおり息を吐き出せて!でも吐くことは出来ても、吸うことはできるかしら?まあ精々頑張ってみることね!」
「グウッ、グウウウウウッ、ググブブブブウウウウウッッッ!!!」慎治の腹が、胸がベルトを引き千切らんばかりの勢いで激しく上下する。空っぽになり縮んだ肺、だがその肺を膨らませてくれる空気は全く入ってこない。礼子の女性器、パンティを脱ぎ捨てて柔らかい肉を剥き出しにした女性器はその柔らかさを恐怖の拷問具と化し、慎治の鼻に密着して空気を完全に遮断していた。br>ブバアアアアッ、クヒュウウウウウッ・・・待ちかねた新鮮な空気が慎治の体内に流入する。必死で空気を貪る慎治を見下ろしていた礼子が不意に腰を下ろす。「うぎいいいいいいいっっっ・・・」窒息責めの再開だ。再び窒息寸前まで慎治を追い込んだ礼子が腰をあげると、慎治は必死で空気を貪る。グハッ、カハッ、フヒュッフヒュッ、フヒイッッッ・・・漸く自分の尻から解放されて苦しげに喘ぐ慎治を、礼子は満足そうに微笑みながら見下ろしていた。
「フフフフフどう慎治、苦しい?息をする自由すら奪われた感想は如何?ウフフフフ、許して欲しい?もう勘弁して欲しい?でも駄目よ、この程度じゃ陽子たちにケガさせた償いにも満たないわ。ましてや私の顔に泥を塗った償いは・・・未だ始まってもいないのよ。さあもっともっと苦しめてあげる!」高らかに笑いながら礼子は慎治の顔に体重をかける。
礼子は慎治の顔面を騎乗のように、太腿でしっかりと挟みつけて固定しながら鼻を自分の性器でピッタリと塞いでいる。だが塞いでいるのは鼻だけだから慎治の目は自由だ。言葉を、呼吸を奪われた慎治が窒息の苦痛と死の恐怖に怯えながら必死で哀願しているのを礼子は満足気に見下ろしていた。涙を両目一杯に溢れさせながら自分を見上げ必死に哀願している慎治、だが言葉すら発せられない。動くことも泣き喚くこともできずにただただ自分の尻の下で悶絶している。フフフ、慎治には泣きながらのたうつ以外何もできないわよね。息をすることすら、普段無意識にしている呼吸ひとつですら私の許可なしにはできないのよ。ウフフフフ、慎治の全ては私のもの、私のお尻の下で、無力な自分を嘆き悲しむがいいわ!自分の犯した罪の重さを思い知るがいいわ!でも幾ら後悔してももう遅いのよ、地獄に堕ちてからじゃね!思う存分苦しめてやるからね!礼子は例えようもない勝利と蹂躙の味を思う存分満喫していた。そして満喫していたのは精神的な満足感だけではない。
ああ気持ちいい・・・最高!慎治の苦悶が、礼子の両腿での締め付けから何とか逃れようとする慎治の無駄な足掻きが、絶妙の振動となって礼子の女性器を震わせ、素晴らしい快感をもたらす。慎治の生殺与奪の全て、息をするという基本的人権以前の、生きるための文字通り必要最小限のことまで私のお尻が支配しているのね!私自身の象徴、私の性器が慎治を苦しめているのね。ああもう最高!鞭を通して、ブーツを通して慎治の苦悶を散々楽しんできたけど、この責めストレート、慎治の苦痛が全部私に直結して伝わってくる!慎治、そう簡単には解放してあげないわよ、限界まで、とことん苦しめてあげる!慎治、憧れの私とデートして愛し合いたかったんでしょう?私の体を心行くまで堪能したかったんでしょう?いいわよ、心行くまで堪能させてあげる、最高の苦痛と一緒に心行くまで味わいなさい!フフフ、折角窒息寸前までいっても、こうしたらどう?礼子は限界まで呼吸を奪われ全身を断末魔のように痙攣させている慎治の鼻からすっとお尻を持ち上げた。「プヒューーーッ、グヒュウウウウウッッッ・・・」待ちわびた空気、欲しくて欲しくて堪らなかった空気を必死で貪る慎治の喘ぎを礼子は素晴らしい快感を味わいながら見下ろす。フフフ、それだけ苦しいんだものね、私がお尻をあげたら思わず空気を吸っちゃうでしょう?吸わせてあげる、失神できないようにね、失神寸前まで追い込んでから少しだけ吸わせてあげる。いつまでもいつまでも、私が窒息責めを楽しめるようにね!
グビイイイイイッ、クハッゲハッ、ブッヒイイイイイッッッッッ・・・慎治は礼子の尻の下で果てしない責め苦にもがき苦しみ続けた。涙を両目から溢れさせながら慎治は礼子のことだけを見上げていた。色白の頬をピンク色に上気させ、楽しそうに笑いながら礼子は慎治のことを見下ろしている。ああ・・・お、お願い息を、息を吸わせてえええ・・・だが言葉を発することはできない。余りの苦しさに意識が暗転しかけた瞬間、フッと礼子が腰を浮かせてくれた。ああ空気、くうきいいい・・・必死で空気を貪るがあっという間に礼子の尻が再び慎治の鼻を塞ぐ。
あぐううううう・・・喘ぎながら慎治は必死で礼子を縋り付くような眼差しで見上げる。おねがいいい・・・ゆるして・・・だが見下ろす礼子の美しい瞳に憐憫は影も形もない。ああ礼子さん、楽しんでいる、熱中している、僕を苦しめることに・・・礼子さんの瞳・・・僕の苦痛を推し量っている、どこまでなら責められるか観察している・・・お願い、やめてえええ・・・こんなの酷すぎるよおおおっ、あ、あんまりだあああああっっっ!
だが慎治にも分かっていた、礼子は決して許してくれないことが。ブーツを履いた礼子、リミッターを解除した礼子の残酷さは嫌というほど身にしみていた。だがそれでも許しを乞わずにはいられない。声も僅かな身の動きも、全てを奪われた慎治に唯一可能なことは願うことだけだった。それは願いと言うより空しい祈りに近かった。
おねがいいい礼子さんんんん!許してえええええ、息を、息をすわせてええええええ・・・慎治は必死で祈り続けた。幾ら祈りを捧げても女神から見れば所詮は取るに足らない虫けら一匹、その祈りを聞き入れる義理などさらさらない。決して叶わぬ祈り、それ位は慎治にも分かる。だが今できることはそれしかない。慎治の頭の中全て、意識の全ては礼子への祈りに塗り潰される。礼子・・・さんんんんんっっっ・・・礼子さんんんんんん!自分を地獄に突き落とした美少女への祈り、それだけに慎治の全てが捧げられている。礼子さん礼子さん礼子さん礼子さん礼子さん礼子さんんんんんんんんんん・・・残酷な女神、全てを奪いつくす大地神に僅かな恵みの慈悲を乞うかのように、慎治はひたすら礼子に哀願し祈り続けた。慎治の目に浮かぶ自分への哀願が礼子には手に取るようによく分かった。いい子ね慎治、もう私のことしか考えられなくなったみたいね。きっと慎治、今私に必死で祈っているでしょう?許して下さいお慈悲を掛けて下さい、て祈っているでしょう?私に祈る以外、慎治にできることは何もないものね。いい気分よ、祈りを捧げられるのはとってもいい気分。その調子よ、私のことだけを思いながら苦しみなさい、私に祈りを捧げながら苦しみなさい、さあもっともっと苦しみなさい!礼子は更にしっかりと慎治の上に体重をかけていった。
3
隣室では信次も地獄を味わっていた。「ウフフフフさあ信次、いよいよ尻地獄の本番よ。」ツッと信次の顎の下を撫でながら玲子は獲物を弄ぶ女猫のように残酷な笑みを浮かべる。既に信次も口にガムテープを巻かれ、哀願することすらできない。「さあてと、今日は特別のお仕置きだからね、私も特別の準備をしてきてあげたのよ。」特別の準備?い、一体何を?怯える信次の表情を楽しみながら玲子は言った。「信次、もう信次にも分かっているでしょう?いずれ近い将来、私にうんちを食べさせられる、ていうことはね。ウフフ安心していいわ、それは今日じゃないから、もう少し先の話よ。だけどねフフフ、今日は手付けをあげるわ。」て、手付け?ど、とうするつもり・・・「今日ね、私うんちした後、ペーパーで拭いただけなのよ、ウオシュレット使ってないの。それに今部活終えた後もね、シャワー浴びたいのを我慢してここに来てあげたのよ。フフフ、感謝しなさいよ、この霧島玲子が信次如きを苛めるために、気持ち悪いのを我慢してきてあげたんだからね。100倍返しで償ってもらうわよ!ハハハ、アハハハハッ!」あ、洗ってない、シャワーも浴びてない・・・ま、まさか、まさかああああっ!!!「分かったみたいじゃない。そう、そのとおりよ。うんちを食べさせて信次の口を冒す前にね、まずは信次の鼻を穢してあげる!アハハハハハッ!私の汚れたままのお尻で窒息させてやるわよ、さぞ臭いことでしょうねえ、アハハハハッ、アハハハハハッ!」ムウッムグッブギュウウウウウッッッ!ガムテープの下から信次の必死の抗議が漏れる。「何よ信次、そんなに嫌なの?そりゃそうよねえ、洗ってないお尻で潰されるなんて、おしっこ飲まされるのなんか比べ物にならない位の屈辱よね。ねえ分かる?信次はだいだいだーいっきらいな私、この世で一番嫌いで憎くて憎くて堪らない私の、信次を地獄に突き落としたこの私のお尻の穴を嗅がされるのよ!?アハハハハッ!毎日毎日、自分を死ぬほど苛め続けるこの私の一番汚いところ、お尻の穴の臭いを嗅がされるのよ?ねえどんな気分?私も苛めにかけては年季の入ったプロだけど、流石にお尻の穴を人に嗅がせたことはないわ。だからもうワクワクしちゃって、早くこの汚れたお尻を嗅がせてやりたい、信次の顔に押し付けてやりたい、てもうウズウズしちゃっているのよ。ねえ信次はどうなのよ、悔しい?止めて欲しい?嫌で嫌で堪らないでしょう?どうかお願い、それだけは許して下さい?だけど・・・ダーメ、信次は私の一番汚いところ、私の肛門で窒息させられるのよ!有希子を怪我させたクズに相応しい罰よね!たっぷりと苦しめてやる!アハハハハハッアハハハハッ!」スッと漆黒のパンティを脱ぎ捨てた玲子が後ろ向きになって信次の顔を跨ぐ。「あっそうそう、せめてもの慈悲よ、ひとつだけいいことを教えておいてあげる。」振り向きながら玲子は嘲笑を浮かべつつ言った。「いい、窒息責めの合間に何回かは息を吸わせてあげるけどね、息を吸ったら、フフフ、私のお尻の臭いをもろに嗅ぐことになるわよ。ウフフフフ、私のお尻の臭いを嗅がされるのが嫌だったらね、どんなに苦しくても息を吸うのはやめることね。」そ、そんなあああ!息をしなけりゃいいだなんてええええっ、し、死んじゃうじゃないかあああああっ!
だが玲子は信次の必死の叫びなど全く無視しながらゆっくりと信次の顔面を今度は後ろ向きに、横たえられた信次の体の方を向くように跨いだ。「どう信次、私のお尻を味わうにはこっちの向きの方がいいでしょう?さあたっぷりと味わいなさい!」見せ付けるかのように、玲子はゆっくりゆっくりと腰を下ろしていく。ああ、あああああ・・・や、やだいやだあああああっっっっっ!!!信次の視界を玲子の美しい尻が覆いつくしていく。優美なラインを描く双丘、そしてその真ん中を分断する割れ目の中に短い細いラインのような割れ目があった。あ、あそこ・・・あそこが玲子さんの・・・肛門!信次は他人のは愚か自分の肛門すら見たことはなかった。だがそれが玲子の肛門であること、そして玲子がそれを信次の鼻めがけて一直線に降下させていることはすぐにわかった。ひ、ひでえええええっ、お、お尻で、肛門で潰すなんて酷すぎるうううううっ!信次の呻き声など委細構わず玲子は信次の顔面にお尻を着地させた。フフフ、直ぐには潰してあげない、少し苛めてあげる。玲子はわざと信次の鼻の前にほんの少しだけ空間をあけてやった。だがその空間は1センチもない、ほんの数ミリだ。鼻の前に自分の肛門を押し付けられた信次が息をしまいと必死で堪えているのが良くわかる。「フフフ信次、その調子よ。私の肛門、信次のお鼻の目の前だからね、息を吸ったら・・・アハハハハッ!私のお尻の臭いが直撃よ!頑張ってね信次ちゃーん、そのまま失神するまで息を止めていたら、私のお尻の臭い、嗅がなくてすむわよお!ほーらガンバレ信次、ガンバレ信次!」楽しそうに笑いながら玲子は確信していた。信次が失神するまで頑張れるわけなどないことを。グウッ、グウウッ、グフウウウウウッッッ・・・自分の尻の下から込みあがって来る信次の苦しげな喘ぎ声を楽しみながら、玲子は限界点が来るのをゆっくりと待っていた。
い、いやだいやだあああ・・・お、お尻の臭いを嗅ぐだなんて絶対にいやあああ・・・あああ、で、でも・・・く、苦しいいいい・・・息が・・・もうだめええええ・・・余りに残酷な玲子の責めだった。完全に鼻を塞がれてしまえばどの道呼吸はできないのだから、単純に苦しんでいればいい。だがこうやって一応、息はできるようにされていれば、自分の意志で我慢などできるものではない。強制されてではない、自分の意志で玲子のお尻を嗅がなくてはならないのだ。憎い憎い玲子、自分をとことん責め苛む残酷な美少女のお尻の臭いを嗅がなくてはならないのだ。余りの屈辱、想像を絶する恥辱。だが肉体の苦痛、空気に対する欲求にこれ以上抗うことは不可能だった。遂に限界に達した信次は堪えていた息を一気に噴き出した。玲子の肛門を信次の鼻息がくすぐる。アハハハハッ、いよいよ来たわね、さあたっぷりと嗅ぎなさい!一陣の風の後、信次が空気を吸い込む気配を玲子は無上の慶びを楽しみながら感じていた。「ブッ、ブヒュウウウウウッ・・・ムグウウウウウッ!!!」信次の悲痛な呻き声が湧き上がる。ヒイイイイイッ、く、臭いいいいいいっ!清冽な汗の香りに混じった饐えたような異臭、微かにトイレ臭いと感じさせる異臭、それは確かに排泄物、玲子のおしっことうんちの残り香、それも時間を経て発酵したような異臭だった。異臭といってもきちんとペーパーで拭いているし前夜は風呂にも入っている、本当は大して臭いわけではないのだが鼻の直前に肛門を押し付けられているのだ、僅かな臭いでも十二分な破壊力だった。
「グヒイイイイイッ、クギイイイイイッ!」悪臭と屈辱に咽び泣く信次の嗚咽を暫く堪能した後、玲子はスッと腰を後ろにずらしていく。「フフフフフ信次、いい声で泣くじゃない、だけど今のは臭いだけ、苦しいのは・・・これからよ!」玲子の尻が最後の数ミリを移動し、肛門が完全に信次の鼻を塞いだ。「グプウウウウウッ、クヒイイイイイッ!!!」ぐ、ぐるじいいいいい・・・玲子の双丘の割れ目、美尻の真ん中に信次の鼻は完全にキャッチされてしまった。玲子の肛門に鼻の先端をめり込ませ、両頬をガッチリと玲子のカモシカのように引き締まった太腿に捕らえられ、信次の鼻は完全に空気と遮断されている。い、いやあああああああっ!信次は声にならない絶叫を張り上げた。柔らかい尻の肉の中でやや異質な感触、若干硬く皺のある襞のような感触が鼻に覆いかぶさる。それは間違いなく玲子の肛門だった。いやいやいやいやいやあああああああっ!ど、どいてどいて・・・お願いどいてえええええっ!全身を生まれてこの方経験したことがないほどの屈辱と嫌悪感が貫く。不潔、汚い・・・想像できる全ての言葉を超越した汚辱、朝子たちに馬糞の上に落とされたのなどとは比べ物にならない程の屈辱だった。ぐう、ぐうう、ぐひいいいいいっっっ!!!何とか玲子の肛門から逃れようとするがガッチリと玲子の太腿で固定されたそれは、蛸のように信次の鼻に吸い付いて離れない。必死で空しい抵抗を続ける信次、だがその抵抗は貴重な空気を浪費させ、玲子の尻に汚された空気への抑えがたい渇望を高めさせるだけだった。「グッグッグフウウウウウッッッッッ・・・」信次の悲鳴が奇妙に甲高くなっていく。そろそろかしら?スッと玲子が尻を微かにずらすや否や、待ちかねたように信次は必死で息を吸い込む、玲子の尻の臭いを肺一杯に吸い込みながら。ウヒイイイッ、く、臭いいいいいいっ・・・だが贅沢を言っている場合ではない、兎に角少しでも多く空気を吸わなくちゃ・・・必死で信次が自分のお尻で穢された空気を吸い込むのを玲子は満足そうに見下ろしている。
4
いい顔よ信次、その屈辱に歪んだ顔、最高よ。余りの恥辱で死にたい位でしょう?肛門を信次の鼻に押し付けた瞬間、玲子の全身をビクンと電気のような快感が貫いた。やった・・・信次をここまで穢しつくしてやった・・・私のこの手で、ううん、このお尻で。中学の時の苛め相手に、靴を舐めさせたりトイレの水を飲ませた時の事を思い出した。信次に最初におしっこを飲ませた時の、屈辱に歪んだ顔を思い出した。だけどそのどれも・・・この顔には敵わないわ。丁寧に時間をかけていたぶり尽してやった成果よね。全てを奪った私、毎日毎日苛めて泣き喚かせる私、大嫌いな私のお尻の臭いなんていうこの世で最悪の臭いを嗅がされているのになんの抵抗もできない自分。フフフ、ウフフフフフ、アハハハハハハッ!信次、さぞ悔しいでしょうねえ!私は最高の気分よ、もっともっと辱しめてあげる!一杯お尻を嗅ぎたくなるように、また窒息させてあげる!グッと玲子の尻が再び信次から空気を奪い去る。「ヒイイイイイッッッ・・・」何回も何回も、玲子は狂ったように笑いながら信次を責め続けた。十回以上責めただろうか、不意に玲子はスッと立ち上がって咽び泣き続ける信次を見下ろした。
「ウフフフフ信次、私のお尻の臭い、堪能した?だけどもう、お鼻バカになってきちゃったんじゃない?お尻の臭いも最初ほどのインパクトはなくなっちゃったんじゃない?」確かにそうだった、人間の鼻は動物界ではかなりバカな方、更に大抵の悪臭は嗅ぎ続ければすぐ慣れてしまう。事実信次ももう、玲子の尻の臭いに対する抵抗は薄れつつあった。「安心しなさい、信次が退屈しないように拷問の趣向を変えてあげる。ここからは・・・シンプルな窒息責めよ!アハハハハッ!信次、徹底的に苦しめてやるわよ?ピストルズはNO FUTURE FORYOUて歌ってたけど、信次の場合はNO AIR FOR YOUよね!さあ・・・逝くわよ!」笑いながら玲子は再び腰を下ろし信次の鼻を完全に塞いでしまう。そのまま30秒ほどすると、早くも信次の呻き声が漏れ始めた。うう、ううううっ、うぐううう・・・・・ぐ、ぐるじいいいいい・・・だが玲子は唇の端にニヤリと残酷な笑みを浮かべたまま、全く体重を浮かせない。「アハハハハ信次、苦しい?最高?じゃあ信次のために歌ってあげるわね!NO AIR NO AIR NO AIR FOR YOU!ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、フォーユー!NO AIR NO AIR NO AIR FOR YOU!ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、ノーーーー、エーーーア、フォーユー!」玲子は楽しそうに尻を揺り動かしながら何度も何度も歌い続けた。ワンフレーズ終わるごとに信次の苦しみは等比級数的に急上昇していく。グ、グルジイイイイイ!!!ジ、ジヌウウウウウ・・・信次の全身の痙攣が断末魔のように激しくなったころ、玲子は漸く腰を上げて息を吸わせてやる。
「クックッブッフウッッッッッ・・・」待ちかねた空気が肺に流れ込む。必死で空気を貪る信次を玲子は残酷な笑みを浮かべながら見下ろしていた。「アハハハハ、よかったね信次、やっと吸えて!少し時間をあげるからさ、一杯吸っときなさいよ、もうすぐ・・・またNO AIRだからね!」ひっひいいいっそんなあああああ!!!声にならない悲鳴をあげめ信次の頭上から女神の聖託が降臨する。「さあ信次、窒息責め再開よ、息を大きく吸いなさい!」玲子はわざとゆっくりと腰を下ろす。空気空気くうきいいい!一杯吸わなくちゃあああああ!信次は必死で肺一杯に大きく空気を吸い込む。フフフバカね信次、一杯吸ったところでそんなもの、何十秒かの差に過ぎないのにね、まあ精々頑張ることね。玲子は信次が限界まで空気を吸い込んだところで鼻を塞いだ。10秒、20秒・・・ブシュシュシュシュ・・・微かに吐き出す空気が漏れて玲子の尻をくすぐる。フフフ、別にいいわよ信次、必死で吐けば少しずつは吐けるかも知れないけど、吸うのは絶対に無理よ。ビクッビクビクッ・・・信次の全身が苦しげに震え始める。痙攣は直ぐに激しくなり、信次は玲子の尻の下で窒息の苦しみに延々と責め苛まされた。ウウ、ウウウ、ウウウウウウウウ・・・・・だずげでえええええ・・・必死で信次はもがきながら玲子を仰ぎ見た、だが信次に見えるのは後ろ向きに座った玲子の背中だけだった。地獄の苦悶に喘ぐ信次の必死の哀願すら拒絶するように、玲子は振り向きもせずに信次を責め続ける。クラスメート、学校、家族・・・世界の全てが信次に背中を向けていた。玲子の背中はこの世の全てからの拒否の象徴のようだった。そして信次が唯一縋り付けるのは、信次に唯一構ってくれるのは自分を地獄に突き落とした張本人、玲子だけなのだ。背中を向け信次の哀願に知らん振りをして責め苛む玲子、その玲子に縋り付いて慈悲を乞う以外、信次にできることは何も無い。れ、玲子さんんんん・・・お、ねがいいいい、だずげでえええええ・・・必死ですがりつく信次、だが玲子は振り向きもしない。信次を拒絶するかのように背中を向けたままの玲子、信次を地獄から救い出せる唯一神、残酷な女神は信次を振り向きもせずに座り続けていた。
一体どれ位の時間が経ったのだろうか。女神たちの饗宴と亡者たちの苦悶の宴はいつ果てるともなく続いていた。カヒッカハッハヒッヒッヒッ、ガハアッゼッゼバアアアッ、グハックパックハアアアアッ、ブッブビッブビイイイイイッ・・・慎治たちの苦しげな悲鳴、口を塞がれているから声すら出せない悲鳴が地下室に充満する。残酷な美少女たちは延々と慎治たちを責め続けた。「ほーら慎治、一杯空気吸わせてあげるわよ、大丈夫よ、直ぐには座らないから安心して一杯吸いなさい・・・さあ一杯吸った?じゃあゆっくりと座るからね、いい、ちゃんと頑張って私に座られる直前まで一杯吸い込むんだよ。」礼子はわざと慎治に充分呼吸させ、息を整えさせてから座った。だが一旦座ったらしっかりと慎治の頭を挟み込み、いつまでもいつまでも呼吸をさせてやらない。必死に肺に蓄えた空気、命綱のような貴重な空気だが慎治の肉体が求める量に比べれば余りに僅か、直ぐに尽きていく。「むうっ、むうううっ、むううううっ!」限界に達した慎治の全身がビク、ビクビク、ビクビクビク、と窒息の苦しみに震えだす。なまじ一杯に空気を吸い込んだものだから限界に達する時間が長く、それだけ苦しみも持続する。地獄、まさに地獄だった。美しいクラスメートの尻の下、大部分の男にとっては天国にも等しい礼子たちの尻の下、そこは慎治たちにとっては息をする自由さえ奪われた地獄だった。
完全に抵抗を封じた二人の女神は僅かに尻を上げ下げするだけで、太腿に力を入れたり抜いたりするだけで、尻を前後に数ミリ動かすだけで、自由自在に慎治たちに地獄の苦しみを与えつづけていた。内臓、特に心臓、肺には深刻なダメージが刻み込まれている。寿命すら縮めかねないほどの責め苦だ。だが血は一滴も流れない、だから礼子たちは責めながら全く疲労しないだけでなく、罪悪感も何も感じないし手加減してやろうという気持ちも全く起きなかった。し、しぬ・・・数え切れぬほど何度となく、慎治たちは窒息寸前まで追い込まれまた蘇生させられた。慎治たちの視界は礼子たちの美しい尻に奪われていたが、礼子たちからはもがき苦しむ慎治たちの全身がよく見える。痙攣の激しさ、早さ、そして限界に達し動きが鈍くなっていくところも。ダメよ慎治、勝手に失神なんかさせないわよ。苦悶の果てに漸く意識を失いかけたところで僅かな空気が与えられる。信次、意識が飛んじゃったみたいね、だけど許さない、こっちに帰っていらっしゃい、もっと苦しむためにね!意識が飛びかけた信次の鼻先に玲子はアンモニアを染み込ませたガーゼを当てる。うっううう・・・ツンとしたアンモニアの臭いが信次の意識を失神という楽園から無情にも連れ戻す。底知れぬ無間地獄を彷徨い続ける慎治たち、だが漸く最終的な限界が近づきつつあった。胸、腹、そして僅かに見える顔面、それらにチアノーゼの累積したダメージ、紫色の鬱血が急速に増加しつつあるのを礼子たちは見逃さなかった。これ以上同じ責めを続ければ間も無く、限界に達し失神してしまうことは確実だった。いいわ、そろそろ止めを刺してあげる。今日のところはこれで解放してあげるわ。
スッと礼子は立ち上がると慎治の顔を見下ろした。涙でビショビショに濡れた惨めな顔一杯に疲労と絶望が浮かんでいる。「慎治、どうかしら私の窒息責め、もう十分反省した?心底、私に申し訳ないことをしたと思っている?心の底からお詫びしたいと思ってる?」「うう、ううう・・・うーん、うーん・・・」なけなしの力を振り絞り、必死で首を動かしながら慎治は必死で許しを乞うた。お願いです・・・許してください・・・もう十分・・・反省しましたから・・・「そう慎治、今度こそ本当に反省した、ていうのね。いいわ、もし本当に慎治が反省した、て言うなら、今日のところは許してあげる。」ああ、あああ・・・よかった・・・慎治の顔に安堵の色が広がるのを見た礼子の美貌に、凄絶な冷笑が浮かぶ。「ちょっと慎治、何か勘違いしていない?私はね、慎治が本当に反省したなら許してあげる、て言ったのよ。慎治の言葉なんかはいらないわ、きちんと行動で示して頂戴、本当に、心の底から反省した、ていうことをね。」こ、行動?行動で示す?ど、どうやって・・・慎治の顔に困惑と恐怖が広がる。「簡単よ、本当に反省した、心の底から申し訳ない、て思っているんだったらね、自分を罰しないではいられないはずよ。怜先生に鞭打たれた?私に窒息させられた?そんなのは他人に罰せられただけじゃない、自分を罰したことにはならないわ。いい、よく聞きなさい、慎治が自分で自分をきちんと罰せられたら、十分反省したって認めて許してあげる。」そ、そんな・・・そんなあああ・・・怜先生や礼子さんにもう十分苛められたじゃないですかあああ・・・大体、自分を罰しろって言ったって一体どうやって・・・僕は身動きひとつ出来ないじゃないですか・・・
5
慎治の困惑を満足げに見下ろしながら、礼子は残酷な宣告を下した。「ウフフフフ慎治、心配することはないわよ、そうやって縛られたままじゃ自分を罰するのも大変でしょう?私が手伝ってあげるわよ。責めは今までと同じ窒息責めでいいわ。だけどね、今度は私、脚で慎治の顔面を固定しないから。私は慎治の顔面に座ってあげるだけ。慎治が自分の意志で私のお尻に顔を埋めて窒息しなさい。そのまま気絶したら、自分を罰したと認めてあげる。どう、簡単なことでしょう?」「うう、うううううっ、うぶううううっっっ!!!」そ、そんな、そんな、そんなあああああ!!!じ、自分で窒息しろだなんて、幾らなんでも無理だよおおおおおっ!慎治の声にならない抗議を礼子は一笑に付した。「どうしたのよ慎治、無理だとでも言うの?自分にその程度の罰すら与えられないようなら、反省したことになんかならないわ。それじゃあ許してあげるわけにはいかないわね。いい慎治、私、慎治が心の底から反省するまで絶対に許さないからね。慎治が顔を背けたら、何度でも何度でもその顔を私のお尻の下に引き戻してやるわ、ウフフフフ、慎治がイヤだと言っても、無理矢理にでも反省させてやるわ。慎治が本当に反省するまで、私のお尻の下で失神するまで絶対にどかないからね!」い、いやあああ、そんなのいやあああああ!慎治の悲鳴はムグウウウッ、ムクウウウウウ!と声にすらならない。必死で嫌々する慎治に委細構わず、礼子はゆっくりと慎治の顔面、鼻の真上に腰を下ろした。座るときこそ位置決めのため両手で慎治の顔面を固定していたが、しっかり座ると礼子はおもむろに宣告した。「さあ慎治、ちゃんと自分で反省するところを見せて頂戴。いい、手を放すわよ。」スッと礼子の白魚のような指が慎治の頬から離れる。約束どおり、太ももで締め上げてもいない、単純に慎治の顔面に座り鼻を塞いでいるだけだ。
フフフさあ慎治、どうするかしら?苦痛を少しでも少なくしたいなら、頑張って一回で失神することだけど、果たして慎治にそれができるかしら?まず無理よね。ウフフフフ、どうせ慎治のことだから絶対に我慢できなくて顔そらして息ついちゃうわよね。そうやったら私に引き戻されてまた一から苦しみ直しなのにね。絶対そうするわよね慎治、そうやって・・・たっぷりと私を楽しませてね!礼子の読み通りだった。慎治にもそれくらいのことは分かっていた。なんとか・・・なんとか一回で気絶しなくちゃ、一回、一回我慢すればいいんだから・・・だが自らの意志で窒息するには並大抵ではない意志力が必要だ。例えば壁に頭を打ち付けるとかのように一撃で気絶できるやり方ならば、慎治にもできるかもしれない。しかし窒息は長い苦しみに耐えなければならないのだ。慎治の意志力程度では到底不可能、ましてや礼子に拘束されていない状況、何時でも顔を背けられる状況では逃げないでいられるわけがない。確かに礼子は慎治の顔面に座っている。だが礼子の性器は慎治を責め嬲る快感と慎治の必死の足掻きによる刺激で豊潤な蜜を溢れさせ、極めて滑りやすくなっている。ちょっとでも首のバランスがずれれば鼻が礼子の性器からはみでてしまい、息ができるのだ。この状況、息をしないでいる方が遥かに難しいこの状況を乗り越える意志力が慎治にある訳がない。
クッ、クウウッ、クウウウウッ、息苦しさが加速する、それでも必死で耐えようとする慎治だが絶対の生理的欲求には敵わない。だ、だめ!くるしいいいい、もうだめえええっ!半ば無意識の内に慎治は首を右へ傾けようとした。ニュルッと最高品質の潤滑油、礼子の甘い蜜を鼻から頬に塗り伸ばしながら慎治は横を向き、息を付いてしまった。ハアハア、プフップフウウウッ・・・バーカ慎治、やっぱり我慢できなかったわね。多分最初のこの一回が勝負よ、ここで我慢できなかったんだから後はもうアリ地獄、慎治、もうとことん苦しむしかないわね。「慎治、息しちゃったじゃない、ダメねえ、さあ、私の下にお・も・ど・り・な・さ・い!」クックックッと楽しげに笑いながら礼子は慎治の鼻を再び塞ぐ。うう、ううう、ううううう・・・あっという間に再び息苦しさに襲われる慎治、だが礼子の読み通り、一度逃げてしまった慎治にもう耐える事はできない。ぷ、ぷぷぷ・・・ぷっはあっ・・・横を向いた慎治が一息二息吸ったところで礼子はまた慎治を引き戻す。アリ地獄へようこそ慎治!ウフフフフ、慎治が横向く度にお鼻で刺激するから、私は結構気持ちいいよ。まあ精々頑張って私を楽しませてね、疲れてもう動けなくなるまで。
礼子は慎治が横を向くのは許すがほんの一呼吸二呼吸しかさせない。だから慎治は徐々に慢性的な酸素不足、蓄積していく窒息の苦しみに喘ぎながら体力を消耗していった。ぐううう、れ、礼子さん・・・重い・・・ぐっぐううううう・・・何回窒息地獄からの逃亡を図ったことだろうか、顔面にのしかかる礼子の重みに耐えながら必死で首を回す肉体的疲労、すぐまた窒息地獄に連れ戻される精神的疲労の相乗効果に慎治の体力は限界に達しつつあった。あらあらもう限界かしら?礼子は散々楽しんだオモチャが電池切れとなったように、慎治の動きが鈍くなるのを天上の高みから見下ろしていた。まあ仕方ないか、これだけ苦しめたんだものね、ああ楽しかった!礼子は大いなる満足感と共に慎治の断末魔の様相を見下ろしていた。自分の股間、お尻の下で人間一人を完膚なきまでに責め嬲り、窒息責めで生死の境目を彷徨わせている。全ての精力を搾り取ってやった快感、極限の苦しみを味あわせてやった満足感を全身で噛み締めていた。さあ慎治、最後までちゃんと見せてね、わたしのお尻の下で逝くところを。頚動脈を締めてなんかあげないわ、最後の一瞬まで苦しい窒息責めで逝かせてあげる!苦しめ苦しめ苦しめ!最後の最後まで・・・苦しみぬくのよ!アハハ、アハハハハ、アハハハハハハハッ!精魂尽き果てた慎治が蝋燭の最後の炎が燃え尽きるように、弱々しく痙攣しながら動かなくなるのを礼子は高笑いと共に見下ろしていた。
一方、玲子の美尻の下で信次も最期の瞬間を迎えようとしていた。「ブハッブフウップフウウウッ・・・」玲子が時折僅かに尻を持ち上げてくれるや否や、信次は必死で空気を貪る。例え玲子の尻臭を嗅がされながらでも何でもいい、吸わずにはいられなかった。だが空気を吸うには一旦、肺の中の古い空気を吐き出さねばならない。信次は唯ひたすら純粋に苦しみ続けているだけだったが玲子は、苛めのプロを自任する玲子は信次の苦悶を楽しみながらも冷静に信次を観察し、タイミングを計っていた。玲子は単純に尻を上げ下げして責めているだけではなかった。信次の呼吸のタイミングを計り、尻をどれ位上げたら信次が息をできるのか、吐息を吐き切るまで何秒かかるのかを正確に推し量っていたのだ。コンマ数秒の単位、だが玲子はそのタイミングを完全に把握しきっていた。どの程度尻を浮かせてやれば信次が息を吸えるか、その限界点も数ミリの単位で見切っていた。思ったよりスペースいらないみたいね、信次、あんた私のお尻の穴が殆ど鼻にくっついたままでも吸えるのね。フフフグッドね、あの攻撃、とーっても効きそうじゃない!玲子はニヤリと残酷な冷笑を浮かべるとスッと尻をあげた。分かったわよ信次のリズム、もう自由に信次の呼吸、コントロールできるわよ。例えばこんなのはどう?玲子がスッと尻を上げるや否や、信次は必死で汚れた息を吹き出した、と次の瞬間、信次が全く息を吸えない内に玲子の尻が下り、信次の鼻を塞いでしまった。「むぎゅううううううううう・・・ふんがふんがぁぁぁぁぁ・・・」ビタリと鼻の穴を塞がれた信次、肺の中は完全に空っぽになってしまったのに新たな空気は全く入ってこない。「アハハハハハッ!いつでも息をさせてもらえると思ったら大間違いよ!さあその空っぽの肺でいつまで持つかしら?試してあげる!」ぐ、ぐるじいいいいい・・・苦しいだけではない、空っぽに潰れた肺に横隔膜が引き上げられ、胸に、腹に激痛が走る。いだいいいい・・・ぐるじいいいいい・・・目の前が真っ暗になるほどの苦しさだった。信次の目は殆ど引っ繰り返り白目が剥き出しになっている。ヒコヒコヒコヒコ・・・胸が腹が苦しげに上下する、だがそんなことをしても求める唯一つのもの、空気は玲子のお尻に遮断され全く入ってこない。じ、じぬううううう・・・信次の眼前で星がチカチカ瞬く、失神か死か分からない、もう臨界点を超える、と思ったその瞬間、玲子はすっと尻をあげてやる。
ぶひゅっぶひゅうううううううっっっ必死で空気を貪る信次、だが人間の呼吸だ、吸った息は吐かねばならない。トントントン・・・玲子は膝頭を指で叩きながら信次の呼吸のリズムを図る。トントントン、今よ!グッと玲子が座りなおした瞬間、それは信次がまさにすべての息を吐き切った瞬間、玲子に座られない内に必死で空気を吸おうとした瞬間だった。ブヒッブヒイイイイイッッッッッ!!!ぐるじいいいいいいいっっっ!信次の全身が余りの苦痛にビクンビクンと大きく痙攣する。ギシギシッと頑丈な革ベルトが軋む。だが玲子の美尻は信次の必死の足掻きをものともせずに空気を奪い続ける。「アハハハハッ!信次、いい苦しみ方じゃない!そうそう、そうこなくっちゃね、せめてこの位は苦しんで貰わないと罰にはならないわよね!ぽーらほらほら、苦しめ苦しめー!」楽しげに笑いながら玲子は、自らの体内で最後の処刑用具が整ったことを感じていた。あ、やっときた、ウフフフフ、信次良かったわね、そろそろ止めを刺してあげるわ。信次の鼻頭での刺激、そして鼻息に刺激され玲子は直腸内にガスが溜まってきたのを感じていたのだ。ウフフフフ信次、感謝しなさいよ。昨日からお芋とか繊維質の多いもの一杯食べて、おならが出やすいようにしといてあげたんだからね。私みたいな美女のおならを直接嗅げるなんて、信次の一生の記念になる経験でしょ?たーっぷりと楽しんでね!
玲子の尻の下で地獄の苦しみにのた打ち回る信次には、玲子の企みを推測する余裕など全くない。信次が感じられることはただ一つ、苦痛レベルの飛躍的な上昇だけだった。余りに的確に息を吐き切ったタイミングで鼻を塞ぐ玲子、その巧みな責めに信次は涙を流し目を白黒させながらもがき苦しんでいた。ぐ、ぐるじいいいいいっ!だ、だれがあああっっっだずげでえええええっ!ぐげえええええっっっ、い、いっそ・・・いっそごろじでえええええっ!!!その瞬間、スッと玲子が尻を上げた。正確には尻を上げた内に入らないだろう、僅かに尻の位置をずらした程度だ、だがそれでも辛うじて空気が移動するスペースはある。ぶぶっ、ほんの僅かな空気を信次は鼻から吹き出した、そして信次が必死で息を吸い込もうとしたその瞬間、玲子はピタッと信次の鼻を肛門で完全に塞いだ。今よ・・・尻地獄、これが止めよ!プッスウウウウウッ・・・玲子は直腸内に溜まったガスを一気に放出した。必死で息を吸う信次、空っぽになった肺の陰圧に引かれて放出された玲子のガスの全てが信次の鼻へ、肺へと吸い込まれていく。ぐっげえええええええっ!ぐ、ぐざいいいいいいっっっ!至近距離どころではない、ゼロ距離での毒ガス攻撃。放出したばかりのおなら全てを吸わされたのだ、溜まったものではない。普通おならが臭い、と言ってもそれは空気で相当に拡散されたものを吸って臭いだなんだと言っているだけだ、この一撃とは比べ物にならない。臭い、等という言葉は生ぬるい、鼻から肺にかけてガーン、と殴られたような衝撃が走る。目の前が黄色くなるような衝撃、激痛すら感じる衝撃だった。ぐっぶうううううううっっっ、ぐごげえええええええっっっ!玲子のおならに体の中から全身を侵され、腐り果てさせられるようだった。ひ、ひでえええええ、は、鼻先でおならだなんてえええええ・・・
アハハハハッ、アハハハハハッ!苦しんでる苦しんでる!玲子は想像以上の信次の苦しみように手を叩いて喜んでいた。やったやったーっ!どうよ信次、少しは思い知った?もう私の全身、信次にとって凶器よね。口も手も足もお尻も、私の全身どこでも見ただけで苛められた辛い辛―いトラウマに直結でしょう?でも体の外側だけじゃないわよね。私の体から出るものも信次にとってはトラウマ直結よね。唾を吐き掛けられる気分はどう?おしっこ飲まされるのも辛くて辛くて堪らないでしょう?挙句の果てにウフフフフ、おならで窒息だって!もう最高!おならで窒息させられた人間なんて、そんなの私聞いたことないわよ。私の体の外も中もぜーんぶ、信次にとっては最高の拷問具ね!さぞ私が怖いことでしょうね!あはは、あははははっ!信次、あんたもう精神ボロボロでしょう?ざまーみろ、て感じよね!もう一生その臭い、忘れられないわよ、アハハッ、アハハハハハッ!ああ最高、何かまたおならしてやりたくなってきたわ!ウフフフフ、もう一回苦しめてあげる!私のおならを嗅がせてあげる!そして・・・私のおならで窒息するのよ信次!さあ成仏しなさい、ほら逝くわよ!玲子は再び微かに尻をずらした。ぶぶうっ、待ちかねたかのように信次は必死で汚辱の毒ガスを、玲子のおなら混じりの息を吹き出す。フフフ信次、ほんと信次ってバカね、学習能力皆無じゃない、こうされるってことくらい分からないの?玲子は信次が息を吸うタイミングを読み切って止めのおならを信次の鼻に注入した。
プスウウウウウッ、静かな音とともに吐き出された玲子の毒ガスを信次は再び肺の奥深くまで吸い込んでしまった。ぐえええええええっひいいいいいいいいいいいっ・・・ぐざいいいいいいい・・・先程よりもより濃密な玲子のおならの臭いに、信次はピクピクと断末魔のように痙攣する。無理も無い、幾ら全力で肺の中の空気を吐き出しても人体の構造上、全てを吐き出すことはできない。一定割合は、つまり最初に吸わされた玲子のおならの一部は肺の中に残っている。そこに第二陣の毒ガスが襲い掛かったのだ。確実に濃度を増した玲子のおならに鼻から肺を全て満たされた信次は汚辱と苦悶の極みに突き落とされた。臭いだけ、苦しいだけではない。ぐげえええええっい、痛いいいいいい!酷い頭痛に頭が割れそうだ、心臓がバクバクと激しく動悸し殆ど不整脈状態となり、全身の血管から血が吹き出てきそうだ。全身が反乱を起こしたかのような苦痛のオンパレードに信次は殆どパニック状態に陥っていた。おならは決して肛門から空気が逆流しているわけではない。口、鼻から入った空気の一部であり、それは腸内の発酵作用により酸素の大部分を消費された、一種の酸欠ガスだ。一回に放出されるおならは体積にすれば少量、ごく少量だが玲子はその全てを信次に吸わせ、信次の肺の殆ど全てを自らのおならで満たしてしまったのだ。それは決して比喩ではなく、毒ガス同然の威力があった。酸欠ガス、純度は低いが悪臭に満ち満ちた汚辱の毒ガス、しかも玲子はピタリと信次の鼻を塞ぎそのガスを決して外に出させない。ぐ、ぐるじいいいいい・・・ひ、ひでえええ・・・あんまり、あんまりだあああああ・・・お、ならで・・・おならで・・・責め潰すなんて・・・あんまり・・・だあああああ・・・・・ククク、ウフフフフフ、アハハハハハッ!玲子は肛門の下で信次の痙攣が徐々にか細くなっていくのを、自分のおならを吸わされ悶絶させられた信次の断末魔を楽しそうに笑いながらいつまでもいつまでも楽しんでいた。

We
weixiefashi
Re: 【转载·日语原文】レイコとシンジ リベンジ編·復讐するは我にあり編·罪と罰編·らせん編
我记得螺旋篇站内有人翻译过了,就是后半部分坐脸那些。
七八年前的了吧,我当时看得血脉贲张啊,算是我早期的启蒙作之一了
七八年前的了吧,我当时看得血脉贲张啊,算是我早期的启蒙作之一了

Bo
bootslover
Re: 【转载·日语原文】レイコとシンジ リベンジ編·復讐するは我にあり編·罪と罰編·らせん編
还有大佬愿意翻译此文吗?