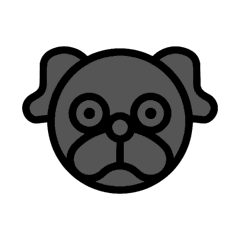《小日向凪と奴隷先輩》(日文原版)
添加标签
作者:墓荒らし
目录:
奴隷先輩のプロローグ
奴隷先輩の日常風景
奴隷先輩の失態
奴隷先輩の上履きオナニー
奴隷先輩の初調教
奴隷先輩の腋オナニー
奴隷先輩の立場
奴隷先輩の人間椅子
奴隷先輩のおなら責め
小日向凪の先輩観察日記
奴隷先輩の尋問
奴隷先輩の昼食風景
奴隷先輩の放置プレイ
奴隷先輩の入浴タイム
奴隷先輩のお泊り
小日向凪の先輩観察日記その2
奴隷先輩の転機
奴隷先輩の本懐
奴隷先輩の初デート
奴隷先輩のクリスマス
奴隷先輩のエピローグ
小日向凪の奴隷先輩
目录:
奴隷先輩のプロローグ
奴隷先輩の日常風景
奴隷先輩の失態
奴隷先輩の上履きオナニー
奴隷先輩の初調教
奴隷先輩の腋オナニー
奴隷先輩の立場
奴隷先輩の人間椅子
奴隷先輩のおなら責め
小日向凪の先輩観察日記
奴隷先輩の尋問
奴隷先輩の昼食風景
奴隷先輩の放置プレイ
奴隷先輩の入浴タイム
奴隷先輩のお泊り
小日向凪の先輩観察日記その2
奴隷先輩の転機
奴隷先輩の本懐
奴隷先輩の初デート
奴隷先輩のクリスマス
奴隷先輩のエピローグ
小日向凪の奴隷先輩
奴隷先輩のプロローグ
この小説はM男向け小説です。
逆転は無いです。
稚拙な文章ですが、どうか楽しんでください
小日向凪こひなた なぎと俺が最初に出会った時、彼女はいつものように、屋上で一人、本を読んでいた。
青空の下、小日向はフェンスにもたれかかって、ブックカバーの掛かった文庫本に目線を落としていた。
まん丸で子猫のような瞳。小さく整った鼻筋。薄く艶やかな唇。
短めの黒髪と、対照的に真っ白な肌は日の光を受けて輝いて見えた。
小柄な体形、細い手足、人形のように怜悧な童顔……それが小日向凪という美少女の詳細である。
彼女はひどく無表情で、眉一つ動かさずにこちらに視線を移した。
水晶のように澄んだ瞳の中に、俺の顔が映る。
まるで作り物めいた彼女の美しさに、俺の動きは完全に止まった。
「……何か用ですか?」
その一声で俺はやっと我にかえった。外見にぴったりの涼やかでハスキーな声だった。
「あ、いや、その……」
俺は完全にしどろもどろになってしまった。何せ目の前にいる彼女は、ありえないほどの美少女。
実は精巧に創られた等身大のアンティーク・ドールと言われても、信じてしまいそうなほどだ。
「用が無いなら出ていってもらえます?」
俺が悶々としていると、彼女は少しだけ不機嫌そうな声色でそう言うと、再び持っていた文庫本に目を落とし、二度と口を開くことは無かった。
俺は何も言うことが出来ず、黙って彼女を見つめ続けるしか無かった。
――それから一ヵ月後。
彼女は同じ場所で同じ顔をしながら同じ本を呼んでいた。
相変わらず小日向は小っちゃくて可愛らしく、物静かで可憐であった。
だが、一週間前と違う所もある。
それは、
「動かないでください、先輩。気が散ります」
「…………」
俺が彼女の椅子になっているということだった。
俺達が初めて会った場所で、俺は仰向けになっている。そして俺の顔面に、小日向はどっかりと腰を下ろしていた。
柔らかい尻肉が俺の顔全体を包み込むように押し付けられる。
小柄な彼女であるが、やはり高校生なだけあって適度に重い。顔に貼り付く下着と相まって、上手く呼吸が出来ず、荒い息を放ってしまう。
さらに甘いような酸っぱいような生々しい臭いが、鼻孔をくすぐり、背徳的な興奮を駆り立てた。
恐ろしいほどの無表情で、小日向はページをめくってゆく。
下に敷いている俺のことなど全く眼中にないようで、読書に没頭している。
俺は声を発するどころか動くことすら出来ず、ただその感触と体臭を味わう事しか出来なかった。
「……もうこんな時間ですね」
そう言って小日向は腰を上げた。スカートを掃い本を閉じると、冷たい視線で俺を見下ろす。
「勃起してますね、先輩」
すっ……と小日向の目線が俺の下半身に集中する。
彼女の言う通り俺の肉棒は、ズボン越しでもはっきりとわかる位、怒張していた。
「た、頼む、小日向……さ、触ってくれ……射精させてくれ……」
俺はそのゴミを見るような双眸に向かって、懇願した。
今の俺は小日向によって、射精どころか自分の性器に触ることすら禁止されているのだ。
「私はただ座ってただけですよ。それなのに先輩は興奮しちゃってるんですか?」
「う……」
「先輩は本当に変態ですね」
「うう……」
「私のお尻、そんなに気持ちがよかったですか? 後輩の一年生に顔の上に乗られて、先輩として恥ずかしくないんですか?」
「ううう……」
文字通り年下の少女の尻に敷かれ、興奮した挙句勃起し、今や彼女に媚びている。
そんな最低な俺を小日向は一瞥すると、無表情のまま思いっきり固くなったペニスを蹴りあげた。
「あーーーーーーーッ!!」
股間を襲う激痛と衝撃と共に頭がスパークし、快感の波が押し寄せ、精液が一気に噴出する。
頭の中が真っ白になり、体から力がごっそり抜けていく。ズボンの股の部分に染みが出来、異臭を放ち始めた。
「……屋上を汚さないでくださいね」
それだけ言うと小日向は振り返りもせずに、屋上から出ていってしまった。
残された俺の頭上を白い雲がゆったりと流れていく。
――俺は何をしているのだろう。
小日向凪と出会ってから一週間。
俺達の関係は学校の先輩後輩から、ご主人様と奴隷にへと変わっていった。
彼女は常に氷のような表情で俺を嬲った。そして俺もそんな彼女の責めに興奮し、隷属するようになっていった。
だが、会ったばかりの俺達は絶対にこんな関係では無かった。
とりあえず……一ヵ月前の話から詳しくしよう。
俺、山崎省吾やまざき しょうごが小日向凪の奴隷となっていく、その原因と顛末を……
この小説はM男向け小説です。
逆転は無いです。
稚拙な文章ですが、どうか楽しんでください
小日向凪こひなた なぎと俺が最初に出会った時、彼女はいつものように、屋上で一人、本を読んでいた。
青空の下、小日向はフェンスにもたれかかって、ブックカバーの掛かった文庫本に目線を落としていた。
まん丸で子猫のような瞳。小さく整った鼻筋。薄く艶やかな唇。
短めの黒髪と、対照的に真っ白な肌は日の光を受けて輝いて見えた。
小柄な体形、細い手足、人形のように怜悧な童顔……それが小日向凪という美少女の詳細である。
彼女はひどく無表情で、眉一つ動かさずにこちらに視線を移した。
水晶のように澄んだ瞳の中に、俺の顔が映る。
まるで作り物めいた彼女の美しさに、俺の動きは完全に止まった。
「……何か用ですか?」
その一声で俺はやっと我にかえった。外見にぴったりの涼やかでハスキーな声だった。
「あ、いや、その……」
俺は完全にしどろもどろになってしまった。何せ目の前にいる彼女は、ありえないほどの美少女。
実は精巧に創られた等身大のアンティーク・ドールと言われても、信じてしまいそうなほどだ。
「用が無いなら出ていってもらえます?」
俺が悶々としていると、彼女は少しだけ不機嫌そうな声色でそう言うと、再び持っていた文庫本に目を落とし、二度と口を開くことは無かった。
俺は何も言うことが出来ず、黙って彼女を見つめ続けるしか無かった。
――それから一ヵ月後。
彼女は同じ場所で同じ顔をしながら同じ本を呼んでいた。
相変わらず小日向は小っちゃくて可愛らしく、物静かで可憐であった。
だが、一週間前と違う所もある。
それは、
「動かないでください、先輩。気が散ります」
「…………」
俺が彼女の椅子になっているということだった。
俺達が初めて会った場所で、俺は仰向けになっている。そして俺の顔面に、小日向はどっかりと腰を下ろしていた。
柔らかい尻肉が俺の顔全体を包み込むように押し付けられる。
小柄な彼女であるが、やはり高校生なだけあって適度に重い。顔に貼り付く下着と相まって、上手く呼吸が出来ず、荒い息を放ってしまう。
さらに甘いような酸っぱいような生々しい臭いが、鼻孔をくすぐり、背徳的な興奮を駆り立てた。
恐ろしいほどの無表情で、小日向はページをめくってゆく。
下に敷いている俺のことなど全く眼中にないようで、読書に没頭している。
俺は声を発するどころか動くことすら出来ず、ただその感触と体臭を味わう事しか出来なかった。
「……もうこんな時間ですね」
そう言って小日向は腰を上げた。スカートを掃い本を閉じると、冷たい視線で俺を見下ろす。
「勃起してますね、先輩」
すっ……と小日向の目線が俺の下半身に集中する。
彼女の言う通り俺の肉棒は、ズボン越しでもはっきりとわかる位、怒張していた。
「た、頼む、小日向……さ、触ってくれ……射精させてくれ……」
俺はそのゴミを見るような双眸に向かって、懇願した。
今の俺は小日向によって、射精どころか自分の性器に触ることすら禁止されているのだ。
「私はただ座ってただけですよ。それなのに先輩は興奮しちゃってるんですか?」
「う……」
「先輩は本当に変態ですね」
「うう……」
「私のお尻、そんなに気持ちがよかったですか? 後輩の一年生に顔の上に乗られて、先輩として恥ずかしくないんですか?」
「ううう……」
文字通り年下の少女の尻に敷かれ、興奮した挙句勃起し、今や彼女に媚びている。
そんな最低な俺を小日向は一瞥すると、無表情のまま思いっきり固くなったペニスを蹴りあげた。
「あーーーーーーーッ!!」
股間を襲う激痛と衝撃と共に頭がスパークし、快感の波が押し寄せ、精液が一気に噴出する。
頭の中が真っ白になり、体から力がごっそり抜けていく。ズボンの股の部分に染みが出来、異臭を放ち始めた。
「……屋上を汚さないでくださいね」
それだけ言うと小日向は振り返りもせずに、屋上から出ていってしまった。
残された俺の頭上を白い雲がゆったりと流れていく。
――俺は何をしているのだろう。
小日向凪と出会ってから一週間。
俺達の関係は学校の先輩後輩から、ご主人様と奴隷にへと変わっていった。
彼女は常に氷のような表情で俺を嬲った。そして俺もそんな彼女の責めに興奮し、隷属するようになっていった。
だが、会ったばかりの俺達は絶対にこんな関係では無かった。
とりあえず……一ヵ月前の話から詳しくしよう。
俺、山崎省吾やまざき しょうごが小日向凪の奴隷となっていく、その原因と顛末を……
奴隷先輩の日常風景
まだエロはないです
「ごめんなさい、山崎君。私……好きな人がいるんです……」
俺の目の前で、音無遥おとなし はるかさんは丁寧に頭を下げた。それは俺の恋がまた一つ、消滅した瞬間であった。
「ご、ごめんなさい……!」
そう言って走り去る音無さんの背中を見ながら、俺はその場に崩れ落ちていった。
俺、山崎省吾は最近焦っていた。
俺はどこにでもある普通の家庭に長男として生を受けた。
普通に学校に行って、普通に勉強して、普通に生きていた俺だったが高校に進学して、ある考えに目覚めた。
――彼女が欲しい。
それは思春期の少年にとって、当り前の思想だった。
だが俺はどうやって彼女をつくるかなんて分からなかった。なにせ十七年間童貞を守り通した男だ。
まずは告白かな、それとも運命的な出会いからのゴールインだろうか? 待て待て、急に自宅に美少女が押しかけてくるかも……
なんてライトノベルも真っ青な妄想ばかりしてたら、青春時代の約半分近くを独り身で過ごしてしまった。
気付けば高校二年生。あと少しで花の高校生活は終わってしまう。
駄目だ。そんなのは寂しすぎる!
そう考えて俺は、密かに想いを寄せていた音無遥さんに告白を試みたが、結果は轟沈。
待ち合わせに指定した校舎の裏で、俺はがっくりと膝を屈した。
たしかに音無さんは美人で人当たりが良くて巨乳で学園のアイドルで、俺なんて日陰者が告白するなんておこがましいかもしれないけどさ。あの美貌とスタイルで彼氏無しなんて、一発逆転コース狙うしかないじゃん!
そう考えていた時期が俺にもありました……
ああ、ウキウキでラブレター書いて、告白の言葉考えて、デートのシュミレーションまでしてた俺って一体……
「まあ、そう気を落とすなよ。世の中、女なんて腐るほどいるし」
そう言って俺を肩をポンポンと叩くのは、同じ学年で同じクラスの青木一馬あおき かずま。
俺と同じ帰宅部のエースで、一年からの腐れ縁だったりする。
俺同様、容姿も性格も成績も運動神経も平凡なはずなのに、何故か美人の幼馴染みと美少女の妹がいるという、完全なリア充だ。
こいつは俺と同じで「彼女欲しい」と言っているが、いつも一緒にいる幼馴染みの間宮鈴まみや すずさんが一馬のことを好きなのは一目瞭然なので、さっさと手を出して責任を取ればいいと、俺は思っている。
リア充爆発しろ。
「そんなこと言ってもよ……もう五人目だぜ。五人目……なんで一回も告白が成就しないんだ」
「節操が無いからじゃないか?」
「う……」
まあ、確かに気のある女の子に手当たり次第、声をかけてちゃそう思われてもしかたないか……
「もう帰ろうぜ。音無さんはしょうがないって」
そう言って帰路に着き始める一馬。
一馬だって音無さんの事好きなんだろ……と心の中で考えながら、俺は言った。
「いや、別々に帰ろうぜ。穂乃花ちゃんも待ってるだろうし」
穂乃花ちゃんとは中等部に通う一馬の妹で、ほんわかした容姿に、ゆったりとした巨乳と長髪がトレードマークの美少女だ。
この一馬の血の繋がった妹とは思えない程の美少女で、中等部はおろか高等部にもファンが多い。
もっとも彼女自身は強烈なブラコンで、一馬のことしか頭にないようだが……リア充爆発しろ。
「穂乃花ちゃん、俺が一馬と一緒にいると何か機嫌悪いんだよ……」
お兄ちゃんとの下校時間を邪魔しないで! って感じだ。あのいたたまれなさはヤバい。
「そ、そうか。わかった」
一馬も実妹のヤバさを知っているのか、すぐに了承してそそくさと俺から離れていった。
そして俺は一人、その場に残された。
「はあ……」
溜息まじりに俺は歩き始めた。
ごめんなさい、ごめんさい、ごめんなさい……先程の音無さんの言葉が脳内でリピートされる。
足取りは重く、気分も憂鬱だ。
俺はそのままの状態で、ふらふらと屋上へ向かった。
俺の通う私立若葉高等学校の屋上は、基本的に解放されている。
昼時は女子たちやカップルが一緒に昼食をとるベストスポットと化しているが、今は放課後。人は少ない。
だから俺はそこでおもいっきり叫ぼうと思ったのだ。
この心の底から湧き上がる鬱憤を無人の屋上で吐き出したい。空の中へこの惨めな気持ちを投げつけて、心機一転したい。
そう考えていたのだ。
俺は屋上へと繋がるドアを開け、辺りを見回して誰か人がいないかを確認する。
――そして俺は彼女に出会った。
初めて彼女を見た時、俺は失恋のショックどころか、全ての理性と感情が吹っ飛んだ。
うなじまで伸びた黒髪が。細く薄い眉が。大きく輝く両目が。スッと伸びた鼻が。桜色の唇が。
全て俺の網膜に焼き付き、脳内をスパークさせた。
透き通るように白い肌と、触れれば壊れてしまいそうな華奢な肢体。それが彼女の怜悧な童顔と完璧にマッチしていて、ある種の神秘性を醸し出していた。
制服に付いているリボンの色で彼女が一年生……後輩で年下であると分かった。
極上の美少女。俺の頭にそんな言葉が横切った。
俺は結局、当初の目的を果たすどころか、正気を取り戻すまでずっと彼女の姿を見つめ続けていた……
「はあ~」
翌日、朝のショートホームルーム俺は自分の机に突っ伏し、深く深く溜息をついた。
昨日見た少女の姿が忘れられない。寝ても覚めてもあの子一色なのだ。
音無さんに告白し玉砕したばかりでこんな感情を抱くのは、節操が無いかもと思ったが、それでも湧き出るリビドーは抑えられないのだ。
「まだ引きずってるのかよ、省吾」
そう言って学生鞄を降ろし、どっかりと隣の席に座ったのは一馬だった。その後ろには間宮さんが鞄を持って座る。
こいつ、今日も幼馴染と妹と登校かよ……
「いや、もう音無さんは吹っ切れた……」
「そ、そうか。だったら何で……」
「なあ、一馬」
「な、なんだ?」
俺はシリアスな面持ちで一馬に問うた。
「年下……後輩の女の子ってさ、お前どう思う?」
「はあ?」
心配そうに俺の顔を覗き込んでいた一馬の顔が、一気に引いていく。そしてなんだか胡散臭いモノをみるような視線で、俺を見つめる。
「お前……まさかもう新しい子を見つけたのか?」
一馬は重く溜息をつくと、苦笑して言った。
「お前はすぐに落ち込むが、立ち直るのはそれ以上に早いな」
「ほっとけ。それにまだ惚れたって決まったわけじゃねぇ」
俺がそう言うと一馬は不思議そうに首を傾げた。でも本当にそうだからしょうがないのだ。
今まで俺は色んな女の子に告白してきたが、そこにはいつも、告白する少女に対する情熱と情欲があった。
しかし、彼女……昨日屋上であった少女は、そのような気持ちが湧かないのだ。
あるのは純粋な好奇心。とにかく彼女に興味があるのだ。
そこにいつものような熱さや、激しい鼓動の高鳴りは無く、静かに彼女に対する関心が深まってゆき、何もかもをその感情が埋め尽くしてしまった。そんな感じであった。
「せめて名前くらい知りたいなぁ……」
あの後、正気を取り戻した俺は、すぐにその場から退散した。彼女を見続ける精神状態ではなかったのだ。
「思い立ったらすぐ動く山崎にしては、珍しいわね」
間宮さんが話に入ってくる。
間宮鈴さんは一馬の幼馴染みで、俺とは一年生の時からのクラスメイトだ。俺が一馬と仲良くなったため、間宮さんとも不通に世間話が出来る位には、仲良くなったのだ。
「そんなこと言われても、言葉じゃ表せないんだよ。この妙な感覚はさ」
そんな俺の机の端に、間宮さんは腰掛けた。
カモシカのような美脚が目の前に迫る。間宮さんは健康的な肢体と、勝気な表情にしなやかなポニーテールが目印の美少女で、今までは彼女が近くに迫るたび、ドキドキしていた。
しかし、今やそんなことは全くない。
それほどまでにあの屋上の少女に心を奪われてしまったというのか。
「……とりあえず、話しかけてみることから始めるか」
俺はそんなことを考えながら一日中、ぼーっと過ごした。
そして、放課後。
穂乃花ちゃんに連行されてゆく親友の姿を見送ってから、俺は逸る鼓動を抑えつつ、屋上へ伸びる階段へと足を運んだ。
屋上の入り口の扉の前で深呼吸。そしてドアノブを握り、一気に開け放った。
「…………」
彼女は昨日と同じ場所で、同じ格好をしながら、同じ本を読んでいた。
「…………」
相変わらず可愛らしい顔立ちをしている。童顔に小柄な体格も相まって、触れれば壊れてしまいそうな可憐さを感じる。
「う……」
その神々しい姿を見て、俺は思わず恐縮してしまう。
どうやってしゃべりかけようか、色々と考えていたのに、それらは全てふっとんでしまった。
ただただ頭の中が空っぽになっていき、彼女から視線が離せなくなる。
ああ……本当に可愛いな。
真ん丸のお目々といい、細い手足といい、艶のある黒髪といい……
なんだろう、小動物のような子だな……子猫とかリスとか、そんな感じかな。
俺が彼女に見惚れながら、お花畑な妄想をしていると、パタンという音がした。
気が付くと、彼女は読んでいた本を閉じ、立ち上がっていた。そして俺の方に近づいてくる。
さっきまで眺めていた少女が目の前に迫ってくる。いきなりの事に、心臓は高鳴り、俺は固まってしまう。
ど、どうしよう。見てたのがバレたか?
「……どいてください」
恐ろしいほど無表情のまま、彼女は言い放った。
見た目によく似合うハスキーな声で、一瞬その声色に俺は聞き惚れた。
が、
「あ、ああ……」
俺は何も言えず、そこをどく事しか出来なかった。
それから数日。
俺は自分の持つ人脈を使って彼女のことを調べた。
彼女は名前を小日向凪といい、一年B組の生徒らしい。
外見通り大人しく無表情な子で、仲の良い友人もあまりいないらしく、クラスでも一人で本を読んでいることがほとんどらしい。
その可憐さから彼女に告白しようとした猛者も多くいるらしいが、彼女の氷のような視線の前に全て撃沈していったという。
そしてそれらの事を知った俺は、毎日放課後になると屋上に行き、小日向をひたすら眺め続ける生活を始めていた。
読書をしている彼女を夕暮れまで見つめ、帰り支度を始めると俺も帰る。
見方によっては完全にストーカー、訴えられたら完敗するレベルだ。
でもそれでいいと思っている自分がここにいる。今まで惚れた女の子には、なりふり構わず告白し続けた俺にとって、それは異常なことだった。あの可愛らしい少女を眺めるだけで満足……そんな今までにない考えを持っている俺であった。
あの子も初日以来、俺に目もくれず読書にふけっていた。相変わらず彼女の存在は神が勝った可憐さで。俺はそれを眺めるだけだった。
……でもその平和な時間も永遠には続かなかった。
まだエロはないです
「ごめんなさい、山崎君。私……好きな人がいるんです……」
俺の目の前で、音無遥おとなし はるかさんは丁寧に頭を下げた。それは俺の恋がまた一つ、消滅した瞬間であった。
「ご、ごめんなさい……!」
そう言って走り去る音無さんの背中を見ながら、俺はその場に崩れ落ちていった。
俺、山崎省吾は最近焦っていた。
俺はどこにでもある普通の家庭に長男として生を受けた。
普通に学校に行って、普通に勉強して、普通に生きていた俺だったが高校に進学して、ある考えに目覚めた。
――彼女が欲しい。
それは思春期の少年にとって、当り前の思想だった。
だが俺はどうやって彼女をつくるかなんて分からなかった。なにせ十七年間童貞を守り通した男だ。
まずは告白かな、それとも運命的な出会いからのゴールインだろうか? 待て待て、急に自宅に美少女が押しかけてくるかも……
なんてライトノベルも真っ青な妄想ばかりしてたら、青春時代の約半分近くを独り身で過ごしてしまった。
気付けば高校二年生。あと少しで花の高校生活は終わってしまう。
駄目だ。そんなのは寂しすぎる!
そう考えて俺は、密かに想いを寄せていた音無遥さんに告白を試みたが、結果は轟沈。
待ち合わせに指定した校舎の裏で、俺はがっくりと膝を屈した。
たしかに音無さんは美人で人当たりが良くて巨乳で学園のアイドルで、俺なんて日陰者が告白するなんておこがましいかもしれないけどさ。あの美貌とスタイルで彼氏無しなんて、一発逆転コース狙うしかないじゃん!
そう考えていた時期が俺にもありました……
ああ、ウキウキでラブレター書いて、告白の言葉考えて、デートのシュミレーションまでしてた俺って一体……
「まあ、そう気を落とすなよ。世の中、女なんて腐るほどいるし」
そう言って俺を肩をポンポンと叩くのは、同じ学年で同じクラスの青木一馬あおき かずま。
俺と同じ帰宅部のエースで、一年からの腐れ縁だったりする。
俺同様、容姿も性格も成績も運動神経も平凡なはずなのに、何故か美人の幼馴染みと美少女の妹がいるという、完全なリア充だ。
こいつは俺と同じで「彼女欲しい」と言っているが、いつも一緒にいる幼馴染みの間宮鈴まみや すずさんが一馬のことを好きなのは一目瞭然なので、さっさと手を出して責任を取ればいいと、俺は思っている。
リア充爆発しろ。
「そんなこと言ってもよ……もう五人目だぜ。五人目……なんで一回も告白が成就しないんだ」
「節操が無いからじゃないか?」
「う……」
まあ、確かに気のある女の子に手当たり次第、声をかけてちゃそう思われてもしかたないか……
「もう帰ろうぜ。音無さんはしょうがないって」
そう言って帰路に着き始める一馬。
一馬だって音無さんの事好きなんだろ……と心の中で考えながら、俺は言った。
「いや、別々に帰ろうぜ。穂乃花ちゃんも待ってるだろうし」
穂乃花ちゃんとは中等部に通う一馬の妹で、ほんわかした容姿に、ゆったりとした巨乳と長髪がトレードマークの美少女だ。
この一馬の血の繋がった妹とは思えない程の美少女で、中等部はおろか高等部にもファンが多い。
もっとも彼女自身は強烈なブラコンで、一馬のことしか頭にないようだが……リア充爆発しろ。
「穂乃花ちゃん、俺が一馬と一緒にいると何か機嫌悪いんだよ……」
お兄ちゃんとの下校時間を邪魔しないで! って感じだ。あのいたたまれなさはヤバい。
「そ、そうか。わかった」
一馬も実妹のヤバさを知っているのか、すぐに了承してそそくさと俺から離れていった。
そして俺は一人、その場に残された。
「はあ……」
溜息まじりに俺は歩き始めた。
ごめんなさい、ごめんさい、ごめんなさい……先程の音無さんの言葉が脳内でリピートされる。
足取りは重く、気分も憂鬱だ。
俺はそのままの状態で、ふらふらと屋上へ向かった。
俺の通う私立若葉高等学校の屋上は、基本的に解放されている。
昼時は女子たちやカップルが一緒に昼食をとるベストスポットと化しているが、今は放課後。人は少ない。
だから俺はそこでおもいっきり叫ぼうと思ったのだ。
この心の底から湧き上がる鬱憤を無人の屋上で吐き出したい。空の中へこの惨めな気持ちを投げつけて、心機一転したい。
そう考えていたのだ。
俺は屋上へと繋がるドアを開け、辺りを見回して誰か人がいないかを確認する。
――そして俺は彼女に出会った。
初めて彼女を見た時、俺は失恋のショックどころか、全ての理性と感情が吹っ飛んだ。
うなじまで伸びた黒髪が。細く薄い眉が。大きく輝く両目が。スッと伸びた鼻が。桜色の唇が。
全て俺の網膜に焼き付き、脳内をスパークさせた。
透き通るように白い肌と、触れれば壊れてしまいそうな華奢な肢体。それが彼女の怜悧な童顔と完璧にマッチしていて、ある種の神秘性を醸し出していた。
制服に付いているリボンの色で彼女が一年生……後輩で年下であると分かった。
極上の美少女。俺の頭にそんな言葉が横切った。
俺は結局、当初の目的を果たすどころか、正気を取り戻すまでずっと彼女の姿を見つめ続けていた……
「はあ~」
翌日、朝のショートホームルーム俺は自分の机に突っ伏し、深く深く溜息をついた。
昨日見た少女の姿が忘れられない。寝ても覚めてもあの子一色なのだ。
音無さんに告白し玉砕したばかりでこんな感情を抱くのは、節操が無いかもと思ったが、それでも湧き出るリビドーは抑えられないのだ。
「まだ引きずってるのかよ、省吾」
そう言って学生鞄を降ろし、どっかりと隣の席に座ったのは一馬だった。その後ろには間宮さんが鞄を持って座る。
こいつ、今日も幼馴染と妹と登校かよ……
「いや、もう音無さんは吹っ切れた……」
「そ、そうか。だったら何で……」
「なあ、一馬」
「な、なんだ?」
俺はシリアスな面持ちで一馬に問うた。
「年下……後輩の女の子ってさ、お前どう思う?」
「はあ?」
心配そうに俺の顔を覗き込んでいた一馬の顔が、一気に引いていく。そしてなんだか胡散臭いモノをみるような視線で、俺を見つめる。
「お前……まさかもう新しい子を見つけたのか?」
一馬は重く溜息をつくと、苦笑して言った。
「お前はすぐに落ち込むが、立ち直るのはそれ以上に早いな」
「ほっとけ。それにまだ惚れたって決まったわけじゃねぇ」
俺がそう言うと一馬は不思議そうに首を傾げた。でも本当にそうだからしょうがないのだ。
今まで俺は色んな女の子に告白してきたが、そこにはいつも、告白する少女に対する情熱と情欲があった。
しかし、彼女……昨日屋上であった少女は、そのような気持ちが湧かないのだ。
あるのは純粋な好奇心。とにかく彼女に興味があるのだ。
そこにいつものような熱さや、激しい鼓動の高鳴りは無く、静かに彼女に対する関心が深まってゆき、何もかもをその感情が埋め尽くしてしまった。そんな感じであった。
「せめて名前くらい知りたいなぁ……」
あの後、正気を取り戻した俺は、すぐにその場から退散した。彼女を見続ける精神状態ではなかったのだ。
「思い立ったらすぐ動く山崎にしては、珍しいわね」
間宮さんが話に入ってくる。
間宮鈴さんは一馬の幼馴染みで、俺とは一年生の時からのクラスメイトだ。俺が一馬と仲良くなったため、間宮さんとも不通に世間話が出来る位には、仲良くなったのだ。
「そんなこと言われても、言葉じゃ表せないんだよ。この妙な感覚はさ」
そんな俺の机の端に、間宮さんは腰掛けた。
カモシカのような美脚が目の前に迫る。間宮さんは健康的な肢体と、勝気な表情にしなやかなポニーテールが目印の美少女で、今までは彼女が近くに迫るたび、ドキドキしていた。
しかし、今やそんなことは全くない。
それほどまでにあの屋上の少女に心を奪われてしまったというのか。
「……とりあえず、話しかけてみることから始めるか」
俺はそんなことを考えながら一日中、ぼーっと過ごした。
そして、放課後。
穂乃花ちゃんに連行されてゆく親友の姿を見送ってから、俺は逸る鼓動を抑えつつ、屋上へ伸びる階段へと足を運んだ。
屋上の入り口の扉の前で深呼吸。そしてドアノブを握り、一気に開け放った。
「…………」
彼女は昨日と同じ場所で、同じ格好をしながら、同じ本を読んでいた。
「…………」
相変わらず可愛らしい顔立ちをしている。童顔に小柄な体格も相まって、触れれば壊れてしまいそうな可憐さを感じる。
「う……」
その神々しい姿を見て、俺は思わず恐縮してしまう。
どうやってしゃべりかけようか、色々と考えていたのに、それらは全てふっとんでしまった。
ただただ頭の中が空っぽになっていき、彼女から視線が離せなくなる。
ああ……本当に可愛いな。
真ん丸のお目々といい、細い手足といい、艶のある黒髪といい……
なんだろう、小動物のような子だな……子猫とかリスとか、そんな感じかな。
俺が彼女に見惚れながら、お花畑な妄想をしていると、パタンという音がした。
気が付くと、彼女は読んでいた本を閉じ、立ち上がっていた。そして俺の方に近づいてくる。
さっきまで眺めていた少女が目の前に迫ってくる。いきなりの事に、心臓は高鳴り、俺は固まってしまう。
ど、どうしよう。見てたのがバレたか?
「……どいてください」
恐ろしいほど無表情のまま、彼女は言い放った。
見た目によく似合うハスキーな声で、一瞬その声色に俺は聞き惚れた。
が、
「あ、ああ……」
俺は何も言えず、そこをどく事しか出来なかった。
それから数日。
俺は自分の持つ人脈を使って彼女のことを調べた。
彼女は名前を小日向凪といい、一年B組の生徒らしい。
外見通り大人しく無表情な子で、仲の良い友人もあまりいないらしく、クラスでも一人で本を読んでいることがほとんどらしい。
その可憐さから彼女に告白しようとした猛者も多くいるらしいが、彼女の氷のような視線の前に全て撃沈していったという。
そしてそれらの事を知った俺は、毎日放課後になると屋上に行き、小日向をひたすら眺め続ける生活を始めていた。
読書をしている彼女を夕暮れまで見つめ、帰り支度を始めると俺も帰る。
見方によっては完全にストーカー、訴えられたら完敗するレベルだ。
でもそれでいいと思っている自分がここにいる。今まで惚れた女の子には、なりふり構わず告白し続けた俺にとって、それは異常なことだった。あの可愛らしい少女を眺めるだけで満足……そんな今までにない考えを持っている俺であった。
あの子も初日以来、俺に目もくれず読書にふけっていた。相変わらず彼女の存在は神が勝った可憐さで。俺はそれを眺めるだけだった。
……でもその平和な時間も永遠には続かなかった。
奴隷先輩の失態
いつも通りの超展開です
「お、音無さん! ずっと前からあなたのことが好きでした! つ、付き合って下さい!」
放課後の屋上にその声は響いた。
青木一馬……俺の親友はそう高らかに宣言すると、勢いよく頭を下げた。
その先にいるのは約一週間目に俺が告白して撃沈した、音無遥さん。
そして俺は屋上へ繋がる校舎の裏に隠れて二人を見守っていた。
事の発端は、数分前。
いつものように屋上に来た俺だったが、小日向が定位置にいないことに気が付いた。
まだ来てないのか……と少し落胆し、小日向が来るまで待とうと思った矢先、入り口のドアが開いた。
咄嗟に身を隠し校舎の陰に潜み様子を窺う。
そこに現れたのは。
「音無さん!」
間違いない。腰まで伸びた黒髪に、豊満な巨乳。白い肌に麗しい美貌。
約一週間前に俺が告白して見事にフラれた音無遥さんに相違ない。
でも何故ここに?
さらに追い打ちをかけるように、一馬も後ろから現れた。
――そして冒頭に戻る。
俺の眼前では自分の親友がかつて俺がフラれた子に告白していた。
え? 何これ? なんで一馬が音無さんに?
俺はいきなりのことに混乱していた。
しかし一馬、俺と同じで本気で音無さんを狙っていたのか……
一馬が音無さんに対して好意を抱いているのは薄々わかっていたが、告白するまでとは思っていなかった。
一馬の告白を聞いた音無さんは恥ずかしそうにモジモジし始める。顔は真っ赤だし、息も少しだけ荒れている。
あれ? 俺が告白した時と反応が全然違うぞ?
そして暫く静寂が続いた後……
「……はい」
消え入りそうな細い声で音無さんは答えた……ってええええええええええええええ!?
思わず叫びそうになるも、何とか声を押さえ込む。
だが俺の頭の中は完全に混乱してしまっていた。
一体これはどういうことだ? 一馬が告白して音無さんがOKした? 俺をフッた時に音無さんは「他に好きな人がいる」と言った。その相手は一馬だったのか?
放心状態寸前になってしまった俺とは対照的に、一馬は狂喜乱舞し、音無さんは顔を赤くしながら恥ずかしげに俯いている。
そして一馬は音無さんの手を取ると、そのまま二人で屋上から出ていった。
一方、一人残された俺はただただ茫然と立ち尽くしていた。
もう吹っ切れたとはいえ、かつてフラれた女生徒と親友が目の前でくっついたのだ。器が小さいと我ながら感じるが、それでもショックなものはショックだった。
……今日はもう帰ろう。
たっぷりと時間をかけて落ち込んだ後、ふらふらとおぼつかない足取りで俺は屋上から出た。
うつろな面持ちで下駄箱まで降りると、そこで俺は見慣れた顔を見かけた。
「あ……」
黒のセミロングに白い肌。小動物を思わせる可憐な顔に華奢な体。
見間違えるはずも無い。俺の現在の片思い相手、小日向凪だ。
一年生の下駄箱の前で上履きを脱いで白いスニーカーに履き替えている。
今日は屋上で読書しないのか、そのまま校舎から出ていってしまった。
……ちょっと姿が見えただけだったけど、やっぱり可愛いな。
去ってゆく小日向を目で追いながら俺はふと、とあるものが目に入った。
俺の視線の先には一年生の下駄箱。その中でも先程彼女が脱いだ上履きがあった。
不意に俺の中で何かどす黒いものが胎動しはじめていた。
周囲を見渡し誰もいないことを確認すると、俺は一年の下駄箱に接近する。目の前には小さく「小日向」と書かれた上履きがあった。
「…………」
俺はまるで宝物に触れるような厳かさで、両手を受け皿のようにして上履きを持ち上げた。
激しく心臓が脈動し、掌に汗が滲む。
再び周りを確認し、俺はそのまま上履きを傍から見えないように抱えると、屋上に向かって走り出した。
段をかっ飛ばしながら階段を駆けあがり、再び屋上に上がる。
そして屋上に俺以外の生徒がいないのを確認すると、校舎の陰に移動し腰を降ろす。
そして俺は下駄箱から拝借してきた小日向のちっちゃな上履きを取り出した。
「…………」
目の前にずっと一方的にしたっていた彼女の私物がある。
今自分がしていることは最低の行為だと分かっていながら、俺は体の芯から迸る感情の奔流を押えきれないでいた。
俺は小日向の上履きの中身に鼻を近づける。そして思いっきり鼻から空気を吸い込んだ。
「……ッ」
可愛らしい小日向からは考えられないような、動物的な香りが俺の鼻孔を突いた。
酸っぱいような上手く表現できない臭いに、俺の体は上気し、頭の中が小日向の体臭に埋め尽くされてゆく。
別に俺は臭いフェチでも脚フェチでもない。
ただ小日向の物なら何でもよかった。
気が付くと俺は下半身を露出させ、いきり立った肉棒を片手で握りしめていた。
何度も何度も深呼吸し、小日向の臭いを吸い込み続ける。
ただ自棄になっているだけかもしれない。親友ばかりがモテて自分がモテないという現実に、耐えられなくなっただけなのかもしれない。
とにかく俺は何もかも忘れて、この背徳的な行為に没頭していた。
だからこそ、気が付かなかったのだろう。
「……何してるのですか?」
後ろから抑揚のない声が投げかけられる、その時まで。
いつも通りの超展開です
「お、音無さん! ずっと前からあなたのことが好きでした! つ、付き合って下さい!」
放課後の屋上にその声は響いた。
青木一馬……俺の親友はそう高らかに宣言すると、勢いよく頭を下げた。
その先にいるのは約一週間目に俺が告白して撃沈した、音無遥さん。
そして俺は屋上へ繋がる校舎の裏に隠れて二人を見守っていた。
事の発端は、数分前。
いつものように屋上に来た俺だったが、小日向が定位置にいないことに気が付いた。
まだ来てないのか……と少し落胆し、小日向が来るまで待とうと思った矢先、入り口のドアが開いた。
咄嗟に身を隠し校舎の陰に潜み様子を窺う。
そこに現れたのは。
「音無さん!」
間違いない。腰まで伸びた黒髪に、豊満な巨乳。白い肌に麗しい美貌。
約一週間前に俺が告白して見事にフラれた音無遥さんに相違ない。
でも何故ここに?
さらに追い打ちをかけるように、一馬も後ろから現れた。
――そして冒頭に戻る。
俺の眼前では自分の親友がかつて俺がフラれた子に告白していた。
え? 何これ? なんで一馬が音無さんに?
俺はいきなりのことに混乱していた。
しかし一馬、俺と同じで本気で音無さんを狙っていたのか……
一馬が音無さんに対して好意を抱いているのは薄々わかっていたが、告白するまでとは思っていなかった。
一馬の告白を聞いた音無さんは恥ずかしそうにモジモジし始める。顔は真っ赤だし、息も少しだけ荒れている。
あれ? 俺が告白した時と反応が全然違うぞ?
そして暫く静寂が続いた後……
「……はい」
消え入りそうな細い声で音無さんは答えた……ってええええええええええええええ!?
思わず叫びそうになるも、何とか声を押さえ込む。
だが俺の頭の中は完全に混乱してしまっていた。
一体これはどういうことだ? 一馬が告白して音無さんがOKした? 俺をフッた時に音無さんは「他に好きな人がいる」と言った。その相手は一馬だったのか?
放心状態寸前になってしまった俺とは対照的に、一馬は狂喜乱舞し、音無さんは顔を赤くしながら恥ずかしげに俯いている。
そして一馬は音無さんの手を取ると、そのまま二人で屋上から出ていった。
一方、一人残された俺はただただ茫然と立ち尽くしていた。
もう吹っ切れたとはいえ、かつてフラれた女生徒と親友が目の前でくっついたのだ。器が小さいと我ながら感じるが、それでもショックなものはショックだった。
……今日はもう帰ろう。
たっぷりと時間をかけて落ち込んだ後、ふらふらとおぼつかない足取りで俺は屋上から出た。
うつろな面持ちで下駄箱まで降りると、そこで俺は見慣れた顔を見かけた。
「あ……」
黒のセミロングに白い肌。小動物を思わせる可憐な顔に華奢な体。
見間違えるはずも無い。俺の現在の片思い相手、小日向凪だ。
一年生の下駄箱の前で上履きを脱いで白いスニーカーに履き替えている。
今日は屋上で読書しないのか、そのまま校舎から出ていってしまった。
……ちょっと姿が見えただけだったけど、やっぱり可愛いな。
去ってゆく小日向を目で追いながら俺はふと、とあるものが目に入った。
俺の視線の先には一年生の下駄箱。その中でも先程彼女が脱いだ上履きがあった。
不意に俺の中で何かどす黒いものが胎動しはじめていた。
周囲を見渡し誰もいないことを確認すると、俺は一年の下駄箱に接近する。目の前には小さく「小日向」と書かれた上履きがあった。
「…………」
俺はまるで宝物に触れるような厳かさで、両手を受け皿のようにして上履きを持ち上げた。
激しく心臓が脈動し、掌に汗が滲む。
再び周りを確認し、俺はそのまま上履きを傍から見えないように抱えると、屋上に向かって走り出した。
段をかっ飛ばしながら階段を駆けあがり、再び屋上に上がる。
そして屋上に俺以外の生徒がいないのを確認すると、校舎の陰に移動し腰を降ろす。
そして俺は下駄箱から拝借してきた小日向のちっちゃな上履きを取り出した。
「…………」
目の前にずっと一方的にしたっていた彼女の私物がある。
今自分がしていることは最低の行為だと分かっていながら、俺は体の芯から迸る感情の奔流を押えきれないでいた。
俺は小日向の上履きの中身に鼻を近づける。そして思いっきり鼻から空気を吸い込んだ。
「……ッ」
可愛らしい小日向からは考えられないような、動物的な香りが俺の鼻孔を突いた。
酸っぱいような上手く表現できない臭いに、俺の体は上気し、頭の中が小日向の体臭に埋め尽くされてゆく。
別に俺は臭いフェチでも脚フェチでもない。
ただ小日向の物なら何でもよかった。
気が付くと俺は下半身を露出させ、いきり立った肉棒を片手で握りしめていた。
何度も何度も深呼吸し、小日向の臭いを吸い込み続ける。
ただ自棄になっているだけかもしれない。親友ばかりがモテて自分がモテないという現実に、耐えられなくなっただけなのかもしれない。
とにかく俺は何もかも忘れて、この背徳的な行為に没頭していた。
だからこそ、気が付かなかったのだろう。
「……何してるのですか?」
後ろから抑揚のない声が投げかけられる、その時まで。
奴隷先輩の上履きオナニー
「……何してるのですか?」
背中に投げつけられた一言に俺の体は完全に停止した。
そのままゆっ……くりと首を後ろに向けると、そこには携帯電話を持った小日向が、冷たい視線で俺を見下ろしていた。
いつも通りの無表情で小日向は問うた。まるで何の感情も無いかのように、その瞳には一切の揺らぎが感じられなかった。
一方、俺はいきなりの出来事に目を白黒させていた。
何故だ!? 小日向はもう帰ったはず。それに俺は何度も周りを確認し、人がいないことを前提に情事に及んだというのに……
なんとか弁解を試みようとするも、小日向の有無を言わせない迫力が俺の口を開かせない。
「……ずっと先輩が私を見ていたのは知っていました」
静寂を切り裂き、最初に言葉を発したのは小日向だった。
「見てるだけで何もしないので放っておきましたが……今日は何か思い詰めたような顔で私を見ていたのでもしやと思いましたが」
小日向の視線が俺の持っている彼女の上履きに向けられる。
「……こういうことだったんですね」
「ち、ちがっ……」
「何が違うんですか?」
ナイフのように怜悧な声が俺に突き刺さる。
確かに今の俺は右手に下駄箱から拝借した小日向の上履き。左手には露出させた自分の性器が握られている。
完全に不審者の風貌だ。通報されたら一発で御用だ。
しかも彼女の手にはピンク色のスマートフォンが。恐らく俺の痴態はあれで撮影されていると見ていいだろう。
万事休す。俺がそう覚悟した時だった。
「……気になります」
「え?」
「先輩は上履きが好きなんですか?」
小日向は顔をピクリとも動かさず尋ねた。
「上履きに性的興奮を覚えるのですか?」
そう聞いてくる小日向の瞳は、真っ直ぐ輝いていた。
彼女は純粋に興味があるような口ぶりだった。
「答えて下さい」
俺が黙っていると、小日向はちょっとだけ不機嫌そうな口調で催促する。
今の俺に彼女に逆らう術は無い。それに小日向の目の前では、あらゆる嘘も通用しない。そんな気もした。
「……ちがう」
「……違う、ですか。でしたら何故、上履きで勃起したのですか? 匂いですか? 汚れですか?」
「…………小日向の」
湖畔のように澄んだ瞳に晒されると、俺は自然と本当の気持ちが胸の内から湧き出てきた。
「小日向のモノだから……興奮したんだ」
消え入りそうな声で自分の気持ちを絞り出した時、小日向は少しだけ驚いたように目を見開いたが、すぐにもとのビスクドールのような表情に戻った。
「……私、だから。ですか?」
「あ、ああ……」
「……それは先輩が私の事が、好き。ということですか?」
「ッ!」
はっきりそう聞かれるとさすがに恥ずかしくなる。だが、これ以上俺の気持ちが隠し通せるとは思えなかった。
「お、俺は……」
体を震わせ俯いたまま俺は絞り出すように告白した。
「俺は、小日向の事が好きだ……」
屋上を爽やかな風が吹き抜けていった。そして訪れる無音の時間。
無言のまま俺を見下ろし続ける小日向に俺はただ顔を真っ赤にして震える事しか出来なかった。
永遠に続くように感じられる静寂の末、ついに小日向は口を開いた。
「……私の事が、好き、ですか」
小日向は暫くその言葉を反芻すると、一瞬だけ唇の端を吊り上げた。が、すぐに元の鉄面皮に戻ると再び抑揚の無い声で言った。
「成程、それで私の持ち物に欲情したですね」
「あ、ああ……」
「そして我慢できず私の上履きを盗んで……」
「…………」
「ここでオナニーしてたですね」
「…………」
その通りなんだがこうも真正面から事実を突きつけられると恥ずかしくて何も言えない。
「……怒らないのか?」
「何がです?」
「そ、その、お前の上履きで……おっ、オナニーしようとしたこと……」
しかしこのまま黙っていても埒が明かない。当然の疑問をとりあえずぶつけてみる。
ほとんど見知らぬ男子生徒が勝手に自分の私物でいかがわしいことをしていたのだ。
普通の女子なら怒るに決まっている。
俺の社会的地位は地に堕ち、最悪退学処分になるだろう。
俺は絶望に染まった未来を想像し、自業自得だと考え、小日向に全ての判断を任せた。
「こっちを見て下さい」
しかし、小日向はそう言って両手で顎を掴んで、スッと顔を上げた。
少し前に姿勢を傾ければ触れられそうな程、小日向の顔が近くに迫る。
あれほど見つめた端麗な顔立ちが目の前に迫り、甘い香りが鼻孔をくすぐった。
俺は唾をゴクリと飲み込んだ。そしてしばし俺達は互いの顔を見つめ合った。
「……続けて下さい」
沈黙を破ったのは小日向だった。
彼女は俺の顎から両手を離すと、いつも以上に冷淡な声で言った。
「え?」
「続きです。先輩がさっきしてたことの続きを、ここでして下さい」
「……ちょ、ちょっと、それって!」
いきなりの事に、俺も一瞬彼女が何を言っているのか理解できなかった。
しかしすぐに小日向の言わんとしていることは分かった。しかし、それを実行するこどうかは別だ。
「そ、そんなことできねえよ……」
小日向はここで俺にさっきの続きをしろと言っている。つまりオナニーをしろと言っているのだ。彼女の目の前で。
しかし小日向は眉一つ動かさず、持っているスマートフォンを掲げた。
「これはお願いではありません。命令です、先輩」
「…………」
「私の命令通りにしてくれたら、皆には内緒にしてあげますよ」
「……!」
あのスマートフォンの中には先程の俺の痴態が撮られている。どう考えても俺は不利だ。
しかも彼女のいう事をきけば、少なくともバラされることはないらしい。
「ほ、本当か?」
「ほんとです」
「…………」
「私の上履きなら、好きに使ってもいいですよ」
その一言と同時に俺は再び小日向の上靴を自分の鼻に押し当て、思いっきり彼女の足臭を吸い込んだ。
湿り気の帯びた動物的な香りが俺の脳を麻痺させてゆく。
最悪の事態を回避したことの刹那的な安心感。後輩の少女に命令されるという背徳感。そしてなにより小日向の私物で自慰行為が出来るという事実に俺は抗う事が出来なかった。
もしかしたらこれが彼女の体臭を嗅げる最後の機会かもしれない。そう思うと俺は何も考えられなくなり、ただただ小日向のむせかえるように香る上靴でオナニーするしか無かった。
少しでも小日向の足臭を脳に染みつけようと何度も何度も呼吸し、それに合わせて己の分身をしごく手も動きを加速させてゆく。
「…………」
小日向はそんな醜態を晒す俺を感情の読み取れない瞳で見下ろしていた。
そんな彼女の視線にも俺は興奮してしまう。
そして、
「ッ~~~!」
声にならない嬌声を上げ、俺は絶頂を迎えた。ペニスの先端から白い精液が勢いよく飛び出し、屋上を汚した。
少しの間、俺は痙攣しながら精液を絞り出し、そして一気に虚脱感に襲われ、がっくりと体勢を崩した。あたりには精液独特の生臭い香りが漂った。
小日向は暫く賢者状態の俺を胡乱な瞳で見つめていたが、ふっ……と溜息をつくと俺の片手に握られていた上履きを回収する。
「……先輩。これからは私の命令を何でも聞いて下さい」
小日向はそう言うと踵を返すと屋上の出口に向かって歩き出した。そしてドアノブを握るのと同時に振り向いて言った。
「明日もここに来てください」
そして小日向は屋上から出ていった。
残された俺はこれからの生活に不満を覚えながらも、ずっと思い続けていた後輩の少女と間に生まれた奇妙な関係に、少しばかりの高揚を感じていた。
「……何してるのですか?」
背中に投げつけられた一言に俺の体は完全に停止した。
そのままゆっ……くりと首を後ろに向けると、そこには携帯電話を持った小日向が、冷たい視線で俺を見下ろしていた。
いつも通りの無表情で小日向は問うた。まるで何の感情も無いかのように、その瞳には一切の揺らぎが感じられなかった。
一方、俺はいきなりの出来事に目を白黒させていた。
何故だ!? 小日向はもう帰ったはず。それに俺は何度も周りを確認し、人がいないことを前提に情事に及んだというのに……
なんとか弁解を試みようとするも、小日向の有無を言わせない迫力が俺の口を開かせない。
「……ずっと先輩が私を見ていたのは知っていました」
静寂を切り裂き、最初に言葉を発したのは小日向だった。
「見てるだけで何もしないので放っておきましたが……今日は何か思い詰めたような顔で私を見ていたのでもしやと思いましたが」
小日向の視線が俺の持っている彼女の上履きに向けられる。
「……こういうことだったんですね」
「ち、ちがっ……」
「何が違うんですか?」
ナイフのように怜悧な声が俺に突き刺さる。
確かに今の俺は右手に下駄箱から拝借した小日向の上履き。左手には露出させた自分の性器が握られている。
完全に不審者の風貌だ。通報されたら一発で御用だ。
しかも彼女の手にはピンク色のスマートフォンが。恐らく俺の痴態はあれで撮影されていると見ていいだろう。
万事休す。俺がそう覚悟した時だった。
「……気になります」
「え?」
「先輩は上履きが好きなんですか?」
小日向は顔をピクリとも動かさず尋ねた。
「上履きに性的興奮を覚えるのですか?」
そう聞いてくる小日向の瞳は、真っ直ぐ輝いていた。
彼女は純粋に興味があるような口ぶりだった。
「答えて下さい」
俺が黙っていると、小日向はちょっとだけ不機嫌そうな口調で催促する。
今の俺に彼女に逆らう術は無い。それに小日向の目の前では、あらゆる嘘も通用しない。そんな気もした。
「……ちがう」
「……違う、ですか。でしたら何故、上履きで勃起したのですか? 匂いですか? 汚れですか?」
「…………小日向の」
湖畔のように澄んだ瞳に晒されると、俺は自然と本当の気持ちが胸の内から湧き出てきた。
「小日向のモノだから……興奮したんだ」
消え入りそうな声で自分の気持ちを絞り出した時、小日向は少しだけ驚いたように目を見開いたが、すぐにもとのビスクドールのような表情に戻った。
「……私、だから。ですか?」
「あ、ああ……」
「……それは先輩が私の事が、好き。ということですか?」
「ッ!」
はっきりそう聞かれるとさすがに恥ずかしくなる。だが、これ以上俺の気持ちが隠し通せるとは思えなかった。
「お、俺は……」
体を震わせ俯いたまま俺は絞り出すように告白した。
「俺は、小日向の事が好きだ……」
屋上を爽やかな風が吹き抜けていった。そして訪れる無音の時間。
無言のまま俺を見下ろし続ける小日向に俺はただ顔を真っ赤にして震える事しか出来なかった。
永遠に続くように感じられる静寂の末、ついに小日向は口を開いた。
「……私の事が、好き、ですか」
小日向は暫くその言葉を反芻すると、一瞬だけ唇の端を吊り上げた。が、すぐに元の鉄面皮に戻ると再び抑揚の無い声で言った。
「成程、それで私の持ち物に欲情したですね」
「あ、ああ……」
「そして我慢できず私の上履きを盗んで……」
「…………」
「ここでオナニーしてたですね」
「…………」
その通りなんだがこうも真正面から事実を突きつけられると恥ずかしくて何も言えない。
「……怒らないのか?」
「何がです?」
「そ、その、お前の上履きで……おっ、オナニーしようとしたこと……」
しかしこのまま黙っていても埒が明かない。当然の疑問をとりあえずぶつけてみる。
ほとんど見知らぬ男子生徒が勝手に自分の私物でいかがわしいことをしていたのだ。
普通の女子なら怒るに決まっている。
俺の社会的地位は地に堕ち、最悪退学処分になるだろう。
俺は絶望に染まった未来を想像し、自業自得だと考え、小日向に全ての判断を任せた。
「こっちを見て下さい」
しかし、小日向はそう言って両手で顎を掴んで、スッと顔を上げた。
少し前に姿勢を傾ければ触れられそうな程、小日向の顔が近くに迫る。
あれほど見つめた端麗な顔立ちが目の前に迫り、甘い香りが鼻孔をくすぐった。
俺は唾をゴクリと飲み込んだ。そしてしばし俺達は互いの顔を見つめ合った。
「……続けて下さい」
沈黙を破ったのは小日向だった。
彼女は俺の顎から両手を離すと、いつも以上に冷淡な声で言った。
「え?」
「続きです。先輩がさっきしてたことの続きを、ここでして下さい」
「……ちょ、ちょっと、それって!」
いきなりの事に、俺も一瞬彼女が何を言っているのか理解できなかった。
しかしすぐに小日向の言わんとしていることは分かった。しかし、それを実行するこどうかは別だ。
「そ、そんなことできねえよ……」
小日向はここで俺にさっきの続きをしろと言っている。つまりオナニーをしろと言っているのだ。彼女の目の前で。
しかし小日向は眉一つ動かさず、持っているスマートフォンを掲げた。
「これはお願いではありません。命令です、先輩」
「…………」
「私の命令通りにしてくれたら、皆には内緒にしてあげますよ」
「……!」
あのスマートフォンの中には先程の俺の痴態が撮られている。どう考えても俺は不利だ。
しかも彼女のいう事をきけば、少なくともバラされることはないらしい。
「ほ、本当か?」
「ほんとです」
「…………」
「私の上履きなら、好きに使ってもいいですよ」
その一言と同時に俺は再び小日向の上靴を自分の鼻に押し当て、思いっきり彼女の足臭を吸い込んだ。
湿り気の帯びた動物的な香りが俺の脳を麻痺させてゆく。
最悪の事態を回避したことの刹那的な安心感。後輩の少女に命令されるという背徳感。そしてなにより小日向の私物で自慰行為が出来るという事実に俺は抗う事が出来なかった。
もしかしたらこれが彼女の体臭を嗅げる最後の機会かもしれない。そう思うと俺は何も考えられなくなり、ただただ小日向のむせかえるように香る上靴でオナニーするしか無かった。
少しでも小日向の足臭を脳に染みつけようと何度も何度も呼吸し、それに合わせて己の分身をしごく手も動きを加速させてゆく。
「…………」
小日向はそんな醜態を晒す俺を感情の読み取れない瞳で見下ろしていた。
そんな彼女の視線にも俺は興奮してしまう。
そして、
「ッ~~~!」
声にならない嬌声を上げ、俺は絶頂を迎えた。ペニスの先端から白い精液が勢いよく飛び出し、屋上を汚した。
少しの間、俺は痙攣しながら精液を絞り出し、そして一気に虚脱感に襲われ、がっくりと体勢を崩した。あたりには精液独特の生臭い香りが漂った。
小日向は暫く賢者状態の俺を胡乱な瞳で見つめていたが、ふっ……と溜息をつくと俺の片手に握られていた上履きを回収する。
「……先輩。これからは私の命令を何でも聞いて下さい」
小日向はそう言うと踵を返すと屋上の出口に向かって歩き出した。そしてドアノブを握るのと同時に振り向いて言った。
「明日もここに来てください」
そして小日向は屋上から出ていった。
残された俺はこれからの生活に不満を覚えながらも、ずっと思い続けていた後輩の少女と間に生まれた奇妙な関係に、少しばかりの高揚を感じていた。
奴隷先輩の初調教
俺と小日向の奇妙な関係は、こうして始まったのであった。
そして翌日。放課後の喧噪の中、俺は重い足取りで屋上へ向かっていた。
理由は明快だ。
「……先輩。これからは私の命令を何でも聞いて下さい」
無機質にそう言い放った小日向の命令に従い、俺は指定された場所に足を運んでいたのであった。
あの後、屋上に飛び散った己の精液の後始末をしながら、俺は自身の犯した過ちを猛省した。
どんなに自暴自棄になっていたとしても女子の私物を盗んで、あまつさえそれを自分の欲求を解消する道具にするなど、最低の行為に他ならない。
本来ならどんな罰を受けても文句の言えない重罪だろう。だが小日向はそれを許した。
……彼女に絶対服従をするという条件付き、であるが。
かくして俺は彼女に平伏する以外の道を失ったのであった。
一方、年下の少女の前であられもない姿を晒すという行為に、俺が興奮したのも事実である。
一目見た時から心に焼き付いて離れなかった後輩の美少女。そんな小日向に冷たい目で見られながら、彼女の上履きをオカズにオナニーをする背徳感に、俺は興奮したのだ。
俺はマゾの気は無かったはずだが、そんな感情を押しつぶすほど、あの快楽は強烈であった。
その後帰宅した俺は、その時の事を思い出しながら何度も自慰に耽った。
小日向の蔑むような視線を。絶対零度の声色を。すっぱいような甘いような上履きにこべりついた体臭を脳内で再現し、狂ったように射精を繰り返した。
それでも夕方に味わったあの湧き上がるような快感を得ることは出来なかった。
もう一度小日向に会いたい。会ってまたあの甘露を味わいたい……そんな願望も俺の中に生まれていた。
そんなことを考えていると、いつの間にか俺は屋上へ続く扉の前にいた。
この扉の向こうには小日向がいる。俺は2、3回深呼吸をして気持ちを落ち着かせると、ドアノブを捻った……
「…………」
いつもの場所で小日向は無表情のまま本を読んでいた。
相変わらず可憐な少女だ。
透き通るような白い肌は日に光を浴びてキラキラと輝いており、うなじまで伸びた黒髪は柔らかみを帯び、艶やかだった。
精巧に創られたアンティーク・ドールと言われても信じてしまいそうだ。
「…………」
小日向はカバーの掛かった文庫本から目線を上げ、俺が入ってきたのを確認する。だが何の反応も起こさず、すぐに興味なさそうに目線を文庫本に落とした。
俺は気まずい空気に尻込みしつつも、小日向にゆっくりと近づいていった。
「よ、よお。約束通り来たぞ……」
昨日の事があるので少しおっかなびっくりで話かけてみる。
「…………」
小日向は無反応だった。眉をピクリとも動かさず、じっと印刷された活字を目で追っている。
俺はその後、暫く彼女に色々と話しかけたが、小日向は全く無視の構えだったので、とりあえず彼女の近くに腰を降ろすことにした。
しかし、
「……脱いでください」
「え?」
「服、全部脱いでください」
俺が胡坐をかいた直後、小日向は初めて口を開いたかと思うと、絶対零度の声色でそう命令してきた。読んでいる本から一切目を逸らさずに言えるのが、恐ろしい。
「こ、ここでか?」
俺の問いに小日向は何も言わず、コクンと頷いただけだった。
「で、でもさすがにここで全裸になるのは……」
「先輩」
俺の弁明を遮って、小日向は今日初めて俺の目を見ると、背筋が凍りつくような冷たい声で言った。
「命令です」
「…………」
それは有無を言わせぬ、絶対王者の言葉だった。
彼女の透き通るような声音が、俺の全身から体内に侵入し、内部から凍結させていくような感覚が一瞬、体中を襲う。
小日向が再び本に視線を向けたところでようやく正気に戻った俺は、黙って身につけている制服に手をかけるしかなかった。
上着を脱ぎネクタイを緩め、靴と靴下を脱いでズボンを降ろす。
「……パンツも脱ぐのか?」
小日向は再び無言で頷く。
抵抗してもしょうがないので、俺は黙って自身に残された最後の装束に手をかけた。
一糸纏わぬ姿となった俺を小日向はチラリと横目で見て確認すると、新しい命令を出した。
「正座してください」
「え?」
思わず聞き直した俺に小日向は無言のまま顎で床を指す。
釈然としない命令だったが、俺はとりあえず屋上の床に正座した。ひんやりと冷たい無機物が剥き出しの肌に触れ、何だか落ち着かない。
これから何をやらされるんだろう。昨日の件があるので俺は今からどんなことをされるのか。俺は不安半分、好奇心半分で小日向を見つめた。
暫くすると小日向は器用に足だけを動かし、上履きを脱ぎ始めた。
そして彼女も足から二足の上履きが、床に落とされる。
転がされた上履きが俺の目に入る。それと同時に昨日の匂いが脳裏に浮かび、言いようも無い興奮が体の奥底から湧き上がってくる。
気が付くと俺は、食い入るように彼女の上履きを見ていた。
「……嗅ぎたいですか?」
小日向のその一言に俺は咄嗟に顔を上げた。小日向は未だ文庫本から目を離さずに、淡々と言葉を紡いでいく。
「……それ、嗅いでいいですよ」
「! ほ、ほんとか!?」
あの香しい小日向の足臭を再び味わえる。そう考えただけで俺の気分は一気に高揚し、情けないほどに狼狽してしまう。
「ただし、条件があるです」
小日向は顔を上げてまっすぐ俺の方を見た。
「……オナニーは禁止です」
「……!」
「それでもいいなら好きなだけ嗅いでください」
それだけ言うと、小日向は再びいつもの体勢に戻る。
一方俺は息を荒らげながら、上履きに視線を固定したまま硬直してしまっていた。
彼女の出した命令は、俺にとっては残酷な命令だ。昨晩俺は小日向の体臭を妄想し、自慰行為を繰り返した。なので渇望していた小日向の臭いがついた物を手にしながら、自分を慰められないのは拷問に等しかった。
しかし……
「わ、わかった。それでもいいから嗅がせてくれ……」
それでも本物のもつ魔力に俺は叶わなかった。
進物を捧げるように上履きを持ち上げた俺は、そのままその中に鼻を突っ込み、一気に空気を吸い上げた。
むせかえるような彼女の足臭が鼻の奥底まで浸透し、澄み渡ってゆく。
酸っぱいようなむせかえるような……あ、ああ……これだ。これが小日向の香りだ。
本来なら悪臭ともいえる動物的な臭いだが、可愛らしい小日向の分泌物から成る臭いだと思うと、甘美な香りにも感じてくる。
俺は何度も何度も小日向の汗や靴下の入り混じった臭いを吸いこんだ。甘ったるい快楽に全身が支配されてゆき、小日向のことしか考えられなくなってゆく。
完全に戦闘態勢に入った我が愚息は、いきり立ちながらもその先端から先走り汁を溢れさせている。
だがいくら興奮していても、オナニーを禁止されている身では、触ることすら敵わない。
そのジレンマが己の惨めさを醸し出し、背徳的な興奮が無限に溢れ身を捩った。
一方、小日向はそんな俺など完全に無視し、読書に没頭していた。
まるで俺など彼女にとっては取るに取らない存在であるという事を、示しているようだ。
ああ、小日向……俺はずっとこの快楽を味わっていたい。
出来る事なら、小日向のその細い足でこの香りごと踏みにじって貰いたい……あるいは小日向の靴の中敷きになって、全身に足臭を行き渡らせたい……
あまりにも情けなく、そして淫靡な妄想の中に俺は溺れていった……
「……もうこんな時間ですね」
小日向がそう言ってパタンと本を閉じた時、ようやく俺は我に返った。
もうどの位、小日向の臭いに没頭していたのだろうか。空はすでに紅に染まっていた。
小日向は立ち上がってスカートをパンパンと叩くと、俺から上靴を無言で取り上げた。
「あ……」
俺は名残惜しげにそれを見つめた。その様はまるで母親に大事な玩具を取られた児童のようだ。
小日向はそのまま上履きを履くと、全裸で正座する俺を見据えた。
「……勃起してますね」
その鋭利な視線が俺の股間に移動する。
俺は咄嗟に両手でそそり立った肉棒を隠す。
「隠さないでください」
が、小日向にそう命令され、しぶしぶながらも手をどけた。
「…………」
小日向は俺の勃起したペニスをしばし、見つめていた。後輩の少女に無言で性器を凝視されるのは、思った以上に恥ずかった。命令があるので隠すわけにもいかず、俺は顔を真っ赤にしながら耐えTるしかなかった。
「……射精したいですか?」
「え?」
唐突に小日向は言った。
「射精したいのですか、先輩?」
首を少しだけ傾けて小日向は尋ねた。俺は無言で首を縦に振る。
「そうですか。射精したいですか」
ずいっ、と顔を寄せてくる小日向。冷酷な瞳が目の前に迫り、赤面する俺の顔を映した。
「しゃ……射精したい。射精させてくれ、小日向……」
俺は恥も外聞も投げ捨て、小日向に懇願した。
小日向の命令など無視して勝手に自分でオナニーすることもやろうと思えば出来ただろう。
だが、今の俺は小日向の許可を得なければ自分の肉棒を触っていけない……そんな気がしていた。
俺の気持ちを見抜いたかのように、小日向は舐るように俺の全身を見渡す。
「……先輩、恥ずかしくないんですか?」
「う……」
「年下の女の子に、えっちなお願いして、懇願して」
「うう……」
「射精させて欲しいなんて……先輩は変態さんなんですか?」
淡々と言われ、俺はあまりの恥ずかしさに俯いてしまう。しかし小日向は俺の顎を掴むと、無理に顔を上げさせる。
「あ……」
小日向の顔がすぐ目の前に迫る。
やっぱり現実離れしてる可愛さだな……
俺がそんな風に呆けていると、小日向は唐突に顎を掴んでいた手を離した。
「条件です、先輩」
「え?」
「私の条件を受けてくれれば、射精させてあげてもいいですよ」
「ッ! ほ、本当か!?」」
俺はまるで砂漠の真ん中でオアシスを見つけた迷い人のように、目を輝かせた。
今の俺に彼女の要求を断れる胆力は無かった。
「何でもする……何でも受け入れる。だから!」
「……わかりました」
「!」
片足をおもむろに上げると、俺の顔面を上靴に包まれた足で踏みつけた。
顔に上履き特有のむせかえるような臭いと感触が彼女のかける体重と共に襲いかかる。
「あ、ああ……」
「……踏んであげます、先輩」
そのままぐりっと俺の顔の上で足を捻る。
「あ、ああああああああああああああああああああああ!」
甲高い嬌声と共に、俺の全身が弾け、ペニスから大量の精液が噴出した。
今まで感じたこのの無い快感に体が溺れ、歓喜に震える。
俺は暫くの間、その圧倒的な享楽に身を委ねた。
「……条件ですが」
冷静な小日向の一言で俺はようやく我に返った。そして射精を条件に彼女と取引をしたことも思い出した。
一体どんな要求なんだろう。俺は不安で胸がいっぱいになっていく。
「簡単な条件です」
小日向は俺の不安を切り捨てるかの如く、端的に言い放った。
「先輩の射精はこれから私が管理します」
「……え?」
「先輩は今後、私の前で私の許可が出た時だけ、私の指示した方法で射精してください」
小日向はそういうと口角をほんの少しだけ上げた。
「……それ以外の射精は一切認めないです」
そこでようやく俺は、後輩の少女に自分の性器を完全に掌握されたことに気が付いた。
俺を焦らして強引に契約を交わし、今まで以上に支配を強める……思った以上に小日向という少女は狡猾なようだ。
だが、これもまだ序の口。
小日向の俺に対する責めはまだ始まったばかりだった。
俺と小日向の奇妙な関係は、こうして始まったのであった。
そして翌日。放課後の喧噪の中、俺は重い足取りで屋上へ向かっていた。
理由は明快だ。
「……先輩。これからは私の命令を何でも聞いて下さい」
無機質にそう言い放った小日向の命令に従い、俺は指定された場所に足を運んでいたのであった。
あの後、屋上に飛び散った己の精液の後始末をしながら、俺は自身の犯した過ちを猛省した。
どんなに自暴自棄になっていたとしても女子の私物を盗んで、あまつさえそれを自分の欲求を解消する道具にするなど、最低の行為に他ならない。
本来ならどんな罰を受けても文句の言えない重罪だろう。だが小日向はそれを許した。
……彼女に絶対服従をするという条件付き、であるが。
かくして俺は彼女に平伏する以外の道を失ったのであった。
一方、年下の少女の前であられもない姿を晒すという行為に、俺が興奮したのも事実である。
一目見た時から心に焼き付いて離れなかった後輩の美少女。そんな小日向に冷たい目で見られながら、彼女の上履きをオカズにオナニーをする背徳感に、俺は興奮したのだ。
俺はマゾの気は無かったはずだが、そんな感情を押しつぶすほど、あの快楽は強烈であった。
その後帰宅した俺は、その時の事を思い出しながら何度も自慰に耽った。
小日向の蔑むような視線を。絶対零度の声色を。すっぱいような甘いような上履きにこべりついた体臭を脳内で再現し、狂ったように射精を繰り返した。
それでも夕方に味わったあの湧き上がるような快感を得ることは出来なかった。
もう一度小日向に会いたい。会ってまたあの甘露を味わいたい……そんな願望も俺の中に生まれていた。
そんなことを考えていると、いつの間にか俺は屋上へ続く扉の前にいた。
この扉の向こうには小日向がいる。俺は2、3回深呼吸をして気持ちを落ち着かせると、ドアノブを捻った……
「…………」
いつもの場所で小日向は無表情のまま本を読んでいた。
相変わらず可憐な少女だ。
透き通るような白い肌は日に光を浴びてキラキラと輝いており、うなじまで伸びた黒髪は柔らかみを帯び、艶やかだった。
精巧に創られたアンティーク・ドールと言われても信じてしまいそうだ。
「…………」
小日向はカバーの掛かった文庫本から目線を上げ、俺が入ってきたのを確認する。だが何の反応も起こさず、すぐに興味なさそうに目線を文庫本に落とした。
俺は気まずい空気に尻込みしつつも、小日向にゆっくりと近づいていった。
「よ、よお。約束通り来たぞ……」
昨日の事があるので少しおっかなびっくりで話かけてみる。
「…………」
小日向は無反応だった。眉をピクリとも動かさず、じっと印刷された活字を目で追っている。
俺はその後、暫く彼女に色々と話しかけたが、小日向は全く無視の構えだったので、とりあえず彼女の近くに腰を降ろすことにした。
しかし、
「……脱いでください」
「え?」
「服、全部脱いでください」
俺が胡坐をかいた直後、小日向は初めて口を開いたかと思うと、絶対零度の声色でそう命令してきた。読んでいる本から一切目を逸らさずに言えるのが、恐ろしい。
「こ、ここでか?」
俺の問いに小日向は何も言わず、コクンと頷いただけだった。
「で、でもさすがにここで全裸になるのは……」
「先輩」
俺の弁明を遮って、小日向は今日初めて俺の目を見ると、背筋が凍りつくような冷たい声で言った。
「命令です」
「…………」
それは有無を言わせぬ、絶対王者の言葉だった。
彼女の透き通るような声音が、俺の全身から体内に侵入し、内部から凍結させていくような感覚が一瞬、体中を襲う。
小日向が再び本に視線を向けたところでようやく正気に戻った俺は、黙って身につけている制服に手をかけるしかなかった。
上着を脱ぎネクタイを緩め、靴と靴下を脱いでズボンを降ろす。
「……パンツも脱ぐのか?」
小日向は再び無言で頷く。
抵抗してもしょうがないので、俺は黙って自身に残された最後の装束に手をかけた。
一糸纏わぬ姿となった俺を小日向はチラリと横目で見て確認すると、新しい命令を出した。
「正座してください」
「え?」
思わず聞き直した俺に小日向は無言のまま顎で床を指す。
釈然としない命令だったが、俺はとりあえず屋上の床に正座した。ひんやりと冷たい無機物が剥き出しの肌に触れ、何だか落ち着かない。
これから何をやらされるんだろう。昨日の件があるので俺は今からどんなことをされるのか。俺は不安半分、好奇心半分で小日向を見つめた。
暫くすると小日向は器用に足だけを動かし、上履きを脱ぎ始めた。
そして彼女も足から二足の上履きが、床に落とされる。
転がされた上履きが俺の目に入る。それと同時に昨日の匂いが脳裏に浮かび、言いようも無い興奮が体の奥底から湧き上がってくる。
気が付くと俺は、食い入るように彼女の上履きを見ていた。
「……嗅ぎたいですか?」
小日向のその一言に俺は咄嗟に顔を上げた。小日向は未だ文庫本から目を離さずに、淡々と言葉を紡いでいく。
「……それ、嗅いでいいですよ」
「! ほ、ほんとか!?」
あの香しい小日向の足臭を再び味わえる。そう考えただけで俺の気分は一気に高揚し、情けないほどに狼狽してしまう。
「ただし、条件があるです」
小日向は顔を上げてまっすぐ俺の方を見た。
「……オナニーは禁止です」
「……!」
「それでもいいなら好きなだけ嗅いでください」
それだけ言うと、小日向は再びいつもの体勢に戻る。
一方俺は息を荒らげながら、上履きに視線を固定したまま硬直してしまっていた。
彼女の出した命令は、俺にとっては残酷な命令だ。昨晩俺は小日向の体臭を妄想し、自慰行為を繰り返した。なので渇望していた小日向の臭いがついた物を手にしながら、自分を慰められないのは拷問に等しかった。
しかし……
「わ、わかった。それでもいいから嗅がせてくれ……」
それでも本物のもつ魔力に俺は叶わなかった。
進物を捧げるように上履きを持ち上げた俺は、そのままその中に鼻を突っ込み、一気に空気を吸い上げた。
むせかえるような彼女の足臭が鼻の奥底まで浸透し、澄み渡ってゆく。
酸っぱいようなむせかえるような……あ、ああ……これだ。これが小日向の香りだ。
本来なら悪臭ともいえる動物的な臭いだが、可愛らしい小日向の分泌物から成る臭いだと思うと、甘美な香りにも感じてくる。
俺は何度も何度も小日向の汗や靴下の入り混じった臭いを吸いこんだ。甘ったるい快楽に全身が支配されてゆき、小日向のことしか考えられなくなってゆく。
完全に戦闘態勢に入った我が愚息は、いきり立ちながらもその先端から先走り汁を溢れさせている。
だがいくら興奮していても、オナニーを禁止されている身では、触ることすら敵わない。
そのジレンマが己の惨めさを醸し出し、背徳的な興奮が無限に溢れ身を捩った。
一方、小日向はそんな俺など完全に無視し、読書に没頭していた。
まるで俺など彼女にとっては取るに取らない存在であるという事を、示しているようだ。
ああ、小日向……俺はずっとこの快楽を味わっていたい。
出来る事なら、小日向のその細い足でこの香りごと踏みにじって貰いたい……あるいは小日向の靴の中敷きになって、全身に足臭を行き渡らせたい……
あまりにも情けなく、そして淫靡な妄想の中に俺は溺れていった……
「……もうこんな時間ですね」
小日向がそう言ってパタンと本を閉じた時、ようやく俺は我に返った。
もうどの位、小日向の臭いに没頭していたのだろうか。空はすでに紅に染まっていた。
小日向は立ち上がってスカートをパンパンと叩くと、俺から上靴を無言で取り上げた。
「あ……」
俺は名残惜しげにそれを見つめた。その様はまるで母親に大事な玩具を取られた児童のようだ。
小日向はそのまま上履きを履くと、全裸で正座する俺を見据えた。
「……勃起してますね」
その鋭利な視線が俺の股間に移動する。
俺は咄嗟に両手でそそり立った肉棒を隠す。
「隠さないでください」
が、小日向にそう命令され、しぶしぶながらも手をどけた。
「…………」
小日向は俺の勃起したペニスをしばし、見つめていた。後輩の少女に無言で性器を凝視されるのは、思った以上に恥ずかった。命令があるので隠すわけにもいかず、俺は顔を真っ赤にしながら耐えTるしかなかった。
「……射精したいですか?」
「え?」
唐突に小日向は言った。
「射精したいのですか、先輩?」
首を少しだけ傾けて小日向は尋ねた。俺は無言で首を縦に振る。
「そうですか。射精したいですか」
ずいっ、と顔を寄せてくる小日向。冷酷な瞳が目の前に迫り、赤面する俺の顔を映した。
「しゃ……射精したい。射精させてくれ、小日向……」
俺は恥も外聞も投げ捨て、小日向に懇願した。
小日向の命令など無視して勝手に自分でオナニーすることもやろうと思えば出来ただろう。
だが、今の俺は小日向の許可を得なければ自分の肉棒を触っていけない……そんな気がしていた。
俺の気持ちを見抜いたかのように、小日向は舐るように俺の全身を見渡す。
「……先輩、恥ずかしくないんですか?」
「う……」
「年下の女の子に、えっちなお願いして、懇願して」
「うう……」
「射精させて欲しいなんて……先輩は変態さんなんですか?」
淡々と言われ、俺はあまりの恥ずかしさに俯いてしまう。しかし小日向は俺の顎を掴むと、無理に顔を上げさせる。
「あ……」
小日向の顔がすぐ目の前に迫る。
やっぱり現実離れしてる可愛さだな……
俺がそんな風に呆けていると、小日向は唐突に顎を掴んでいた手を離した。
「条件です、先輩」
「え?」
「私の条件を受けてくれれば、射精させてあげてもいいですよ」
「ッ! ほ、本当か!?」」
俺はまるで砂漠の真ん中でオアシスを見つけた迷い人のように、目を輝かせた。
今の俺に彼女の要求を断れる胆力は無かった。
「何でもする……何でも受け入れる。だから!」
「……わかりました」
「!」
片足をおもむろに上げると、俺の顔面を上靴に包まれた足で踏みつけた。
顔に上履き特有のむせかえるような臭いと感触が彼女のかける体重と共に襲いかかる。
「あ、ああ……」
「……踏んであげます、先輩」
そのままぐりっと俺の顔の上で足を捻る。
「あ、ああああああああああああああああああああああ!」
甲高い嬌声と共に、俺の全身が弾け、ペニスから大量の精液が噴出した。
今まで感じたこのの無い快感に体が溺れ、歓喜に震える。
俺は暫くの間、その圧倒的な享楽に身を委ねた。
「……条件ですが」
冷静な小日向の一言で俺はようやく我に返った。そして射精を条件に彼女と取引をしたことも思い出した。
一体どんな要求なんだろう。俺は不安で胸がいっぱいになっていく。
「簡単な条件です」
小日向は俺の不安を切り捨てるかの如く、端的に言い放った。
「先輩の射精はこれから私が管理します」
「……え?」
「先輩は今後、私の前で私の許可が出た時だけ、私の指示した方法で射精してください」
小日向はそういうと口角をほんの少しだけ上げた。
「……それ以外の射精は一切認めないです」
そこでようやく俺は、後輩の少女に自分の性器を完全に掌握されたことに気が付いた。
俺を焦らして強引に契約を交わし、今まで以上に支配を強める……思った以上に小日向という少女は狡猾なようだ。
だが、これもまだ序の口。
小日向の俺に対する責めはまだ始まったばかりだった。
奴隷先輩の腋オナニー
「ああ……」
自室のベッドの上で俺は最早何度目になるかも分からない、深い溜息を吐きだした。
自らの射精権を小日向に譲渡してから早三日。俺は毎晩自室のベッドで小日向の上履きの臭いを思い出し、悶々としていた。
あの日から俺は小日向の言いつけを守り、一切オナニーをしていなかった。
ただでさえ性にアグレッシブな年頃であり、尚且つ小日向の体臭という今までにない衝撃を体験したばかりの俺には、とても辛い事であった。
正直、何度も言いつけを破ってこっそりオナニーしようと考えた。しかし小日向のあの全てを見透かすような瞳に晒されると、俺は心の底まで丸裸にされたような感覚に陥ってしまうのだ。
――隠そうとしても無駄ですよ。先輩の事なんて、すぐにわかりますから。
そんなセリフが浮かんでくるほど、小日向の目は俺を支配下に置く眼力があった。
放課後の屋上通いも続いていた。
小日向は自分が履いている上履きを俺に渡すと、「嗅いでいいですよ」とだけ言った。
そしてそのままいつもの読書タイムに突入する。
射精を許されていないため極力、自分の性器に触りたくない。いやそれ以上に勃起もしたくない。しかし小日向の上履きの魅力には抗えない俺は、黙って上履きを己の顔に押し付け、香りを堪能しながら必死に射精願望を抑えるしかなかった。
小日向は絶対に射精許可を出さない。
俺がどんなに懇願しても、氷のような表情で俺を見下ろす。
そして何も言わず、俺を残して帰ってしまうのだった。
「ああ……」
でも小日向との関係が壊れるのが嫌で逆らえない自分もいる。
結局俺は小日向の掌で転がされているのか……
ベッドの上で情欲に身を焼かれながら、俺はただのた打ち回るしか出来なかった。
「どうもです。先輩」
射精禁止から一週間目の放課後が訪れた。
いつも通り小日向は文庫本片手に、屋上に現れた。
今日も変わらず、小っちゃくて可愛らしい。
だが俺にはそんな感傷に浸る暇も無かった。
禁欲と小日向の上靴を臭うだけの一週間。
それは俺の平常心を破壊し、淫猥な癖を覚えさせるのに最適な環境だった。
今の俺は小日向の姿を見ただけで、彼女の上履きのむせかえりそうな臭いが脳裏に甦ってくる。
そして条件反射的に勃起してしまう自分の性器の存在も……
すでに息を荒くし股にテントを張る俺の姿を、小日向は残酷に見下ろすとすぐに視線を写し、定位置に腰を降ろした。
ペラッと頁を捲りながら、小日向はいつものように足先だけを動かし、上履きを器用に脱いだ。
「ああ……」
思わずため息が漏れる。もはや彼女の履物は俺の中で絶対の存在へと昇華していた。
一刻も早くあれを手にしたい。顔を埋めたいというどうしようもない欲求が脳を駆け巡る。
射精の快感が得られない今、俺の最高の快楽はあの香りを嗅ぐことだけ……
そう思い俺が彼女の上履きを手に取った瞬間だった。
「駄目ですよ、先輩」
唐突に放たれた小日向の一言に、俺の手は止まった。
「今日からここで、上履きを嗅ぐのは禁止です」
「ッ……そんな!」
小日向の無情な命令に、俺は自分の体が闇の中に一人落ちて浮くような感覚に陥った。
もうすでに小日向の足臭無しじゃあ、満足できない体になってしまった。だというのに、それを禁止されるなんて……
「辛そうな顔ですね、先輩」
俺の心の底を見透かすように、小日向は俺の顔を覗き込んできた。
「……実は新しい上履きを買ったんです」
「……え?」
小日向は本を閉じて横に置くと、俺を正面から見ると言った。
「だからその古くて汚くて臭い上履きは先輩にあげます」
「!!」
俺は思わず固唾を呑みこんだ。
そして王様から勲章を貰うかの如く厳かな姿勢で、目の前の上履きを持ち上げた。
「私にとってはゴミですが……変態の先輩にとっては宝物ですよね」
恍惚の表情で上履きを見つめる俺に、小日向は軽蔑しきった声で言った。
「……でも屋上でそれを嗅ぐのは駄目です」
小日向は何処からともなく新品の上靴を取り出すと、それを履いて立ち上がった。
「それは先輩の家で好きなだけ嗅いでください。勿論オナニーは禁止ですが……」
小日向はそのままふっ、と完全に見下した笑みを浮かべ、
「先輩は私の上靴があるだけで幸せですもんね」
と言って俺の頭をまるで飼い犬にやるような仕草で撫でた。
「あ、ああ……」
普通、こんなことを年下の少女に言われたら、烈火の如く怒るのが普通の男だろう。
だが俺は心の底から喜びに震えていた。今までどんなに渇望しても手に入らなかった小日向の私物。それが手に入ったのだから……
「それと……今日は特別に射精させてあげます」
「!? マ、マジで!?」
コクン、と可愛らしく頷くと、小日向はいきなり首元のリボンを緩め、制服のボタンを外し始めた。
いきなりの脱衣に俺が目を見開いて驚いていると、小日向は上半身に身につけていた制服を脱ぎ捨てた。
そして目に入ってきたのは上だけであるが小日向の下着姿。
ほぼゼロと言ってもいい平坦なバストに、それを包み込む薄桃色のシンプルなブラジャー。
染み一つない真っ白な肌に、ちっちゃなおへそ。
それらは完璧な美しさと清純さをもって日に光の元で鎮座していた。
俺は初めて目の当たりにした小日向の柔肌に釘付けとなる。
そんな俺を横目に、小日向はゆっくりと片腕を上げた。
「これからはここの臭いです」
小日向にそう支持され、ようやく俺は彼女の言わんとしていることを理解できた。
「わ、腋か……」
腋毛一本生えてない綺麗な色の腋を小日向は俺に差し出した。
気が付くと俺は彼女の腋に顔を埋め、鼻を擦りつけていた。
すぐに鼻に入り込んでくるのは、小日向の汗の臭い。
上履きとは違い、瑞々しい小日向の汗の萌芽が体温と共に直に伝わってくる。
女の子は体臭を気にする生き物だと俺は思っていた。だから体は常に清潔にするし、こまめに消臭もする。
しかし小日向の腋からは彼女の可憐さと見た目の清潔さからは考えられない程、生々しい動物的な香りが発されていた。
「……今日は体育があったです。いっぱい汗もかきました」
小日向は少しだけ声を上気させながら告白する。
「だから臭いと思うです。でも……」
一瞬、間を置いて小日向は言った。
「先輩はそれがいいんですよね?」
「ああっ……」
まるで犬のように鼻を小日向の腋に這わせ、臭いを嗅いでゆく。
上履きとは違う小日向の体臭に、俺は早くも心を奪われていた。
「……オナニーしてもいいですよ」
「!」
「この臭いをオカズにして下さい。先輩」
新鮮な汗の香りに加え、一週間ぶりの射精許可。俺がその快楽に逆らえるわけなかった。
無我夢中で臭いを嗅ぎ、勃起したペニスをしごいてゆく。
「ん……先輩の鼻息。ちょっとくすぐったいです」
悩ましい吐息でささやかな不満を漏らす小日向。
それさえ、今の俺には性的興奮への最良のスパイスでしかない。
「……舐めてもいいですよ」
それが決定打だった。
俺は躊躇なく小日向の可愛らしい腋に下を伸ばした。
ぬるっとした脇汗の感触と柔らかい小日向の腋の肉質。そして適度にしょっぱい汗の味に、甘酸っぱい香り。
俺の脳の容量はたちまちいっぱいになった。
「ッ――!」
声にならない嬌声と共に頭が真っ白になり、代わりに大量の快感が流れ込む。
そして溜まりに溜まった一週間分の精液が肉棒から噴出する。
それは間違いなく。今まで生きてきた中で一番気持ちよい射精に相違なかった……
紅に空が染まる中、俺はあまりの快楽に脱力し、仰向けのままの体を冷たい屋上の床に投げ出していた。
その横では小日向が上着を直していた。
彼女はいつも格好に戻り本を抱えると、未だ立てずにいる俺を見下ろしながら言った。
「……今日からはこれだけで射精できるようになってもらいます」
小日向はそのままポケットティッシュを一枚取り出すと、腋をそれで拭き、そのティッシュを俺の顔に被せた。
「家に帰ってからも、この臭いを思い出してください」
顔面に貼り付く小日向の脇汗ティッシュ。それだけでも興奮モノだが……
「でも上履きの臭いも忘れちゃダメですよ……」
それだけ言うと小日向は振り返りもせず、屋上から出ていった。
俺は彼女から貰った使い古しの上履きを握りしめながら、しばし彼女の腋の香りを脳内に繰り出していた……
「ああ……」
自室のベッドの上で俺は最早何度目になるかも分からない、深い溜息を吐きだした。
自らの射精権を小日向に譲渡してから早三日。俺は毎晩自室のベッドで小日向の上履きの臭いを思い出し、悶々としていた。
あの日から俺は小日向の言いつけを守り、一切オナニーをしていなかった。
ただでさえ性にアグレッシブな年頃であり、尚且つ小日向の体臭という今までにない衝撃を体験したばかりの俺には、とても辛い事であった。
正直、何度も言いつけを破ってこっそりオナニーしようと考えた。しかし小日向のあの全てを見透かすような瞳に晒されると、俺は心の底まで丸裸にされたような感覚に陥ってしまうのだ。
――隠そうとしても無駄ですよ。先輩の事なんて、すぐにわかりますから。
そんなセリフが浮かんでくるほど、小日向の目は俺を支配下に置く眼力があった。
放課後の屋上通いも続いていた。
小日向は自分が履いている上履きを俺に渡すと、「嗅いでいいですよ」とだけ言った。
そしてそのままいつもの読書タイムに突入する。
射精を許されていないため極力、自分の性器に触りたくない。いやそれ以上に勃起もしたくない。しかし小日向の上履きの魅力には抗えない俺は、黙って上履きを己の顔に押し付け、香りを堪能しながら必死に射精願望を抑えるしかなかった。
小日向は絶対に射精許可を出さない。
俺がどんなに懇願しても、氷のような表情で俺を見下ろす。
そして何も言わず、俺を残して帰ってしまうのだった。
「ああ……」
でも小日向との関係が壊れるのが嫌で逆らえない自分もいる。
結局俺は小日向の掌で転がされているのか……
ベッドの上で情欲に身を焼かれながら、俺はただのた打ち回るしか出来なかった。
「どうもです。先輩」
射精禁止から一週間目の放課後が訪れた。
いつも通り小日向は文庫本片手に、屋上に現れた。
今日も変わらず、小っちゃくて可愛らしい。
だが俺にはそんな感傷に浸る暇も無かった。
禁欲と小日向の上靴を臭うだけの一週間。
それは俺の平常心を破壊し、淫猥な癖を覚えさせるのに最適な環境だった。
今の俺は小日向の姿を見ただけで、彼女の上履きのむせかえりそうな臭いが脳裏に甦ってくる。
そして条件反射的に勃起してしまう自分の性器の存在も……
すでに息を荒くし股にテントを張る俺の姿を、小日向は残酷に見下ろすとすぐに視線を写し、定位置に腰を降ろした。
ペラッと頁を捲りながら、小日向はいつものように足先だけを動かし、上履きを器用に脱いだ。
「ああ……」
思わずため息が漏れる。もはや彼女の履物は俺の中で絶対の存在へと昇華していた。
一刻も早くあれを手にしたい。顔を埋めたいというどうしようもない欲求が脳を駆け巡る。
射精の快感が得られない今、俺の最高の快楽はあの香りを嗅ぐことだけ……
そう思い俺が彼女の上履きを手に取った瞬間だった。
「駄目ですよ、先輩」
唐突に放たれた小日向の一言に、俺の手は止まった。
「今日からここで、上履きを嗅ぐのは禁止です」
「ッ……そんな!」
小日向の無情な命令に、俺は自分の体が闇の中に一人落ちて浮くような感覚に陥った。
もうすでに小日向の足臭無しじゃあ、満足できない体になってしまった。だというのに、それを禁止されるなんて……
「辛そうな顔ですね、先輩」
俺の心の底を見透かすように、小日向は俺の顔を覗き込んできた。
「……実は新しい上履きを買ったんです」
「……え?」
小日向は本を閉じて横に置くと、俺を正面から見ると言った。
「だからその古くて汚くて臭い上履きは先輩にあげます」
「!!」
俺は思わず固唾を呑みこんだ。
そして王様から勲章を貰うかの如く厳かな姿勢で、目の前の上履きを持ち上げた。
「私にとってはゴミですが……変態の先輩にとっては宝物ですよね」
恍惚の表情で上履きを見つめる俺に、小日向は軽蔑しきった声で言った。
「……でも屋上でそれを嗅ぐのは駄目です」
小日向は何処からともなく新品の上靴を取り出すと、それを履いて立ち上がった。
「それは先輩の家で好きなだけ嗅いでください。勿論オナニーは禁止ですが……」
小日向はそのままふっ、と完全に見下した笑みを浮かべ、
「先輩は私の上靴があるだけで幸せですもんね」
と言って俺の頭をまるで飼い犬にやるような仕草で撫でた。
「あ、ああ……」
普通、こんなことを年下の少女に言われたら、烈火の如く怒るのが普通の男だろう。
だが俺は心の底から喜びに震えていた。今までどんなに渇望しても手に入らなかった小日向の私物。それが手に入ったのだから……
「それと……今日は特別に射精させてあげます」
「!? マ、マジで!?」
コクン、と可愛らしく頷くと、小日向はいきなり首元のリボンを緩め、制服のボタンを外し始めた。
いきなりの脱衣に俺が目を見開いて驚いていると、小日向は上半身に身につけていた制服を脱ぎ捨てた。
そして目に入ってきたのは上だけであるが小日向の下着姿。
ほぼゼロと言ってもいい平坦なバストに、それを包み込む薄桃色のシンプルなブラジャー。
染み一つない真っ白な肌に、ちっちゃなおへそ。
それらは完璧な美しさと清純さをもって日に光の元で鎮座していた。
俺は初めて目の当たりにした小日向の柔肌に釘付けとなる。
そんな俺を横目に、小日向はゆっくりと片腕を上げた。
「これからはここの臭いです」
小日向にそう支持され、ようやく俺は彼女の言わんとしていることを理解できた。
「わ、腋か……」
腋毛一本生えてない綺麗な色の腋を小日向は俺に差し出した。
気が付くと俺は彼女の腋に顔を埋め、鼻を擦りつけていた。
すぐに鼻に入り込んでくるのは、小日向の汗の臭い。
上履きとは違い、瑞々しい小日向の汗の萌芽が体温と共に直に伝わってくる。
女の子は体臭を気にする生き物だと俺は思っていた。だから体は常に清潔にするし、こまめに消臭もする。
しかし小日向の腋からは彼女の可憐さと見た目の清潔さからは考えられない程、生々しい動物的な香りが発されていた。
「……今日は体育があったです。いっぱい汗もかきました」
小日向は少しだけ声を上気させながら告白する。
「だから臭いと思うです。でも……」
一瞬、間を置いて小日向は言った。
「先輩はそれがいいんですよね?」
「ああっ……」
まるで犬のように鼻を小日向の腋に這わせ、臭いを嗅いでゆく。
上履きとは違う小日向の体臭に、俺は早くも心を奪われていた。
「……オナニーしてもいいですよ」
「!」
「この臭いをオカズにして下さい。先輩」
新鮮な汗の香りに加え、一週間ぶりの射精許可。俺がその快楽に逆らえるわけなかった。
無我夢中で臭いを嗅ぎ、勃起したペニスをしごいてゆく。
「ん……先輩の鼻息。ちょっとくすぐったいです」
悩ましい吐息でささやかな不満を漏らす小日向。
それさえ、今の俺には性的興奮への最良のスパイスでしかない。
「……舐めてもいいですよ」
それが決定打だった。
俺は躊躇なく小日向の可愛らしい腋に下を伸ばした。
ぬるっとした脇汗の感触と柔らかい小日向の腋の肉質。そして適度にしょっぱい汗の味に、甘酸っぱい香り。
俺の脳の容量はたちまちいっぱいになった。
「ッ――!」
声にならない嬌声と共に頭が真っ白になり、代わりに大量の快感が流れ込む。
そして溜まりに溜まった一週間分の精液が肉棒から噴出する。
それは間違いなく。今まで生きてきた中で一番気持ちよい射精に相違なかった……
紅に空が染まる中、俺はあまりの快楽に脱力し、仰向けのままの体を冷たい屋上の床に投げ出していた。
その横では小日向が上着を直していた。
彼女はいつも格好に戻り本を抱えると、未だ立てずにいる俺を見下ろしながら言った。
「……今日からはこれだけで射精できるようになってもらいます」
小日向はそのままポケットティッシュを一枚取り出すと、腋をそれで拭き、そのティッシュを俺の顔に被せた。
「家に帰ってからも、この臭いを思い出してください」
顔面に貼り付く小日向の脇汗ティッシュ。それだけでも興奮モノだが……
「でも上履きの臭いも忘れちゃダメですよ……」
それだけ言うと小日向は振り返りもせず、屋上から出ていった。
俺は彼女から貰った使い古しの上履きを握りしめながら、しばし彼女の腋の香りを脳内に繰り出していた……
奴隷先輩の立場
「……なあ、小日向……」
「……………」
「こ、こひな……」
「黙ってください、先輩」
俺の必死の懇願は、小さな後輩に一刀両断された。
現在俺は、青空の下で全裸のまま正座している。無論小日向の命令でだ。
一応公共の場である屋上で全裸を晒しているという背徳感からか、それとも小日向の前だからかは分からないが、俺はすでに息を荒くし、性器も勃起させていた。
一方小日向は今日も今日とて、屋上にぺたんと座り込み、読書に耽っている。
自然に風景に溶け込む可愛らしい小日向と、屋上にいるにはあまりにも不自然な俺。それは明らかに不自然な光景だった。
そして俺がいつも通り放課後にここを訪れて小日向と合流し、そのまま彼女が出した命令に従い、服を脱ぎ正座してから既に一時間が経過していた。
それなら今までの調教と同じなのだが、これまで受けた一週間の調教と決定的に違う場所があった。
……小日向の上履きが無い。
思えば一昨日まで、俺はここにいる時は常に小日向の上履きを肌身離さず持ち、その香りを胸がいっぱいになるまで吸い込んでいた。
だから射精できなくても小日向から基本的には無視されようと、胸のもやもやさえあれど、ある程度は満ち足りていた。
しかし今は違う。
こんなに近くにいるのに小日向に触れられないという焦燥感。そして脳裏に甦ってくる彼女の上履きと腋の香り。
二つのスパイスが混ざり合い、何とも言えない背徳的な興奮が俺の胸の奥からふつふつと湧き上がってくる。
結果的に俺はギンギンに発情しながら、小日向に少しでも何かしてくれないかと懇願することしか出来なかった。
しかし肝心の小日向は完全に拒否。読書に集中したいようで、さっきから俺の願いを冷たくあしらっている。
ヘビの生殺しのようで、非常につらい。けど日が暮れる頃には昨日みたいにまた腋を嗅がせてもらえる。舐めさせてもくれるかも……俺はそんな期待に胸を膨らませながら、ひたすら耐えるしかなかった。
……
…………
………………
「……今日はここまでですね」
本を閉じて可愛く腕を伸ばすと、小日向は立ち上がった。
俺はようやく小日向に構ってもらえると思い、顔を上げた。
しかし小日向は俺に一瞥もくれず、そのままそそくさと屋上から出ようとする。
「あっ! こ、小日向、待って!」
俺は咄嗟に小日向の足元に縋り付く。
「……何ですか先輩?」
小日向はそんな俺を汚いものを見るような目で見下ろすと、人形のように細い足で俺を小突いた。
「……毎日嗅がせてあげるわけではないですよ」
「うそ……」
「しかも……そんな恰好で後輩に引っ付くなんて、恥ずかしくないんですか?」
「で、でも……」
「……そんなに嗅ぎたいですか?」
「え……?」
小日向は俺の目を真っ直ぐ見ながら尋ねた。
「私の腋、そんなに嗅ぎたいですか?」
「……ッ」
無表情であるが明らかに馬鹿にした態度で尋ねてくる小日向。
俺の中にほんの少しだけ、年下に蔑まれていることからくる怒りの炎が宿る。
が、それ以上に小日向の足元に情けなく縋り付き、恥ずかしい願いを懇願するという状況。そしてそこからくる言いようのない興奮が俺の全身を覆い尽くした。
それに必死に頼めばもしかしたら腋を嗅がしてもらえるかも……
「そんなに必死になって……どれだけ私の腋を臭いたいんですか?」
「う、うう……」
顔が熱くなってくる。恐らく羞恥心で真っ赤になっているんだろう。
そんな俺の顔を無理やり上げると小日向は囁くように言った。
「……だったら、お願いしてください」
「……え?」
「私の腋が臭いたいなら、ちゃんとお願いしてください。そしたら考えてあげますよ」
「う……」
彼女の言わんとしていることは分かった。
一瞬戸惑ったが、目の前にある誘惑には勝てず、俺はその場で這いつくばる。
そして体を震わせながら土下座の体勢に入る。
「こ、小日向……わ、腋を……」
「敬語ですよ、先輩」
「ッ……こ、小日向様……わ、腋を……嗅がせてください……」
絞り出すように出したお願い。
それから少しだけ間が開いて、
「……顔を上げて下さい」
小日向の冷淡な声が耳元に届いた。
顔を上げると、いつの間にか彼女はしゃがんでおり、すぐ目の前に小日向の童顔があった。
「そこまでして、私の腋の臭いを嗅ぎたいですか?」
「え……」
「後輩の女の子に土下座して頼んじゃう位、私の腋を臭いたいですか」
「…………」
辱めるような質問に、俺は再び顔を降ろす。
もはやプライドなど微塵もなかった。落ちるとこまで堕ちた感のある俺に、小日向は言った。
「……特別ですよ」
シュルっと生地が擦れる音が聞こえた。
慌てて顔を上げると、そこにはリボンを外し、上着のボタンを外してゆく小日向の姿があった。
驚く俺を尻目に、彼女は上着を脱ぎ去ると、そのまま白い肌と共に汗ばんだ腋を日の元に晒した。
「……先輩が頼んだんですから、自分で嗅ぎに来てください」
その言葉を聞き終わるやいなや、俺はすぐに自身の鼻を鬼日向の腋に押し付けた。
「……舐めちゃ駄目ですよ、先輩。臭うだけです。勿論、オナニーも禁止です」
伸ばそうとした舌を彼女の命令で止める。ここで小日向に逆らって、折角のお情けを取り上げられては堪らない。
俺は射精と汗の味への欲求を何とか我慢しながら、小日向の臭いを少しでも鼻に残そうと何度も腋臭を吸い込む。
酸っぱくて何とも言えない香りに俺の脳は刺激され、麻薬のようにそれを欲してゆく。
「鼻息荒いですよ、先輩」
小馬鹿にしたような小日向の一言も、俺を興奮させる要因の一つに過ぎない。
「分かりましたか、先輩。先輩は私に『嗅がせてもらう』立場なんです」
夢中で情事に及ぶ俺に、小日向は諭すように囁く。
「これからも先輩が腋を臭えるかは、私の気分次第です」
「…………」
「なのでこれからは……もっと私に媚を売るですよ」
それは小日向の新たな脅迫だった。
前の脅迫は俺の痴態を皆に暴露されたくなかったら、言う事をきけというものだった。
だが今回のはこれからも小日向の体臭を嗅ぎたければ、言う事をきけというものだ。
前者は絶対に従わなければ、社会的に抹殺されてしまうものであった。だから屈服してもしょうがない。
だが後者は……それは俺が小日向のアブノーマルな魅力に屈服したことを意味する。
客観的に見れば、それは男のプライドを捨てた最低の行為である。
しかし……
「わ、わかった……小日向……小日向様に従います……どんな命令にも従います……だから!」
「だから?」
わざとらしく聞き返す小日向に、俺ははっきりと言った。
「小日向様の臭い……嗅がせて下さい……」
静寂が屋上を覆った。
まるで最後の審判のような緊張感が俺の五体を覆う。
やがて小日向はクスリ、と小さく笑った。
「先輩は本当に私の匂いが好きですね。変態さん、です」
彼女の独特な言い回しに、ますます俺の興奮のボルテージは上がってゆく。
射精は出来ないものの、俺の心は小日向の体臭で満ち溢れていた……
「先輩、今日はこのへんでおしまいです」
どれくらいの時が経っただろうか。
小日向はそう言って俺を引きはがした。そして素早く着衣すると、物欲しげに見る俺を尻目にちょっと咎めるように言った。
「……先輩の敬語は何か嫌です。これからも前と同じ口調でお願いします」
そう言って小日向は出ていった。
俺は小日向の香りを思い出しながら、一人屋上で空を見上げる事しか出来なかった。
「……なあ、小日向……」
「……………」
「こ、こひな……」
「黙ってください、先輩」
俺の必死の懇願は、小さな後輩に一刀両断された。
現在俺は、青空の下で全裸のまま正座している。無論小日向の命令でだ。
一応公共の場である屋上で全裸を晒しているという背徳感からか、それとも小日向の前だからかは分からないが、俺はすでに息を荒くし、性器も勃起させていた。
一方小日向は今日も今日とて、屋上にぺたんと座り込み、読書に耽っている。
自然に風景に溶け込む可愛らしい小日向と、屋上にいるにはあまりにも不自然な俺。それは明らかに不自然な光景だった。
そして俺がいつも通り放課後にここを訪れて小日向と合流し、そのまま彼女が出した命令に従い、服を脱ぎ正座してから既に一時間が経過していた。
それなら今までの調教と同じなのだが、これまで受けた一週間の調教と決定的に違う場所があった。
……小日向の上履きが無い。
思えば一昨日まで、俺はここにいる時は常に小日向の上履きを肌身離さず持ち、その香りを胸がいっぱいになるまで吸い込んでいた。
だから射精できなくても小日向から基本的には無視されようと、胸のもやもやさえあれど、ある程度は満ち足りていた。
しかし今は違う。
こんなに近くにいるのに小日向に触れられないという焦燥感。そして脳裏に甦ってくる彼女の上履きと腋の香り。
二つのスパイスが混ざり合い、何とも言えない背徳的な興奮が俺の胸の奥からふつふつと湧き上がってくる。
結果的に俺はギンギンに発情しながら、小日向に少しでも何かしてくれないかと懇願することしか出来なかった。
しかし肝心の小日向は完全に拒否。読書に集中したいようで、さっきから俺の願いを冷たくあしらっている。
ヘビの生殺しのようで、非常につらい。けど日が暮れる頃には昨日みたいにまた腋を嗅がせてもらえる。舐めさせてもくれるかも……俺はそんな期待に胸を膨らませながら、ひたすら耐えるしかなかった。
……
…………
………………
「……今日はここまでですね」
本を閉じて可愛く腕を伸ばすと、小日向は立ち上がった。
俺はようやく小日向に構ってもらえると思い、顔を上げた。
しかし小日向は俺に一瞥もくれず、そのままそそくさと屋上から出ようとする。
「あっ! こ、小日向、待って!」
俺は咄嗟に小日向の足元に縋り付く。
「……何ですか先輩?」
小日向はそんな俺を汚いものを見るような目で見下ろすと、人形のように細い足で俺を小突いた。
「……毎日嗅がせてあげるわけではないですよ」
「うそ……」
「しかも……そんな恰好で後輩に引っ付くなんて、恥ずかしくないんですか?」
「で、でも……」
「……そんなに嗅ぎたいですか?」
「え……?」
小日向は俺の目を真っ直ぐ見ながら尋ねた。
「私の腋、そんなに嗅ぎたいですか?」
「……ッ」
無表情であるが明らかに馬鹿にした態度で尋ねてくる小日向。
俺の中にほんの少しだけ、年下に蔑まれていることからくる怒りの炎が宿る。
が、それ以上に小日向の足元に情けなく縋り付き、恥ずかしい願いを懇願するという状況。そしてそこからくる言いようのない興奮が俺の全身を覆い尽くした。
それに必死に頼めばもしかしたら腋を嗅がしてもらえるかも……
「そんなに必死になって……どれだけ私の腋を臭いたいんですか?」
「う、うう……」
顔が熱くなってくる。恐らく羞恥心で真っ赤になっているんだろう。
そんな俺の顔を無理やり上げると小日向は囁くように言った。
「……だったら、お願いしてください」
「……え?」
「私の腋が臭いたいなら、ちゃんとお願いしてください。そしたら考えてあげますよ」
「う……」
彼女の言わんとしていることは分かった。
一瞬戸惑ったが、目の前にある誘惑には勝てず、俺はその場で這いつくばる。
そして体を震わせながら土下座の体勢に入る。
「こ、小日向……わ、腋を……」
「敬語ですよ、先輩」
「ッ……こ、小日向様……わ、腋を……嗅がせてください……」
絞り出すように出したお願い。
それから少しだけ間が開いて、
「……顔を上げて下さい」
小日向の冷淡な声が耳元に届いた。
顔を上げると、いつの間にか彼女はしゃがんでおり、すぐ目の前に小日向の童顔があった。
「そこまでして、私の腋の臭いを嗅ぎたいですか?」
「え……」
「後輩の女の子に土下座して頼んじゃう位、私の腋を臭いたいですか」
「…………」
辱めるような質問に、俺は再び顔を降ろす。
もはやプライドなど微塵もなかった。落ちるとこまで堕ちた感のある俺に、小日向は言った。
「……特別ですよ」
シュルっと生地が擦れる音が聞こえた。
慌てて顔を上げると、そこにはリボンを外し、上着のボタンを外してゆく小日向の姿があった。
驚く俺を尻目に、彼女は上着を脱ぎ去ると、そのまま白い肌と共に汗ばんだ腋を日の元に晒した。
「……先輩が頼んだんですから、自分で嗅ぎに来てください」
その言葉を聞き終わるやいなや、俺はすぐに自身の鼻を鬼日向の腋に押し付けた。
「……舐めちゃ駄目ですよ、先輩。臭うだけです。勿論、オナニーも禁止です」
伸ばそうとした舌を彼女の命令で止める。ここで小日向に逆らって、折角のお情けを取り上げられては堪らない。
俺は射精と汗の味への欲求を何とか我慢しながら、小日向の臭いを少しでも鼻に残そうと何度も腋臭を吸い込む。
酸っぱくて何とも言えない香りに俺の脳は刺激され、麻薬のようにそれを欲してゆく。
「鼻息荒いですよ、先輩」
小馬鹿にしたような小日向の一言も、俺を興奮させる要因の一つに過ぎない。
「分かりましたか、先輩。先輩は私に『嗅がせてもらう』立場なんです」
夢中で情事に及ぶ俺に、小日向は諭すように囁く。
「これからも先輩が腋を臭えるかは、私の気分次第です」
「…………」
「なのでこれからは……もっと私に媚を売るですよ」
それは小日向の新たな脅迫だった。
前の脅迫は俺の痴態を皆に暴露されたくなかったら、言う事をきけというものだった。
だが今回のはこれからも小日向の体臭を嗅ぎたければ、言う事をきけというものだ。
前者は絶対に従わなければ、社会的に抹殺されてしまうものであった。だから屈服してもしょうがない。
だが後者は……それは俺が小日向のアブノーマルな魅力に屈服したことを意味する。
客観的に見れば、それは男のプライドを捨てた最低の行為である。
しかし……
「わ、わかった……小日向……小日向様に従います……どんな命令にも従います……だから!」
「だから?」
わざとらしく聞き返す小日向に、俺ははっきりと言った。
「小日向様の臭い……嗅がせて下さい……」
静寂が屋上を覆った。
まるで最後の審判のような緊張感が俺の五体を覆う。
やがて小日向はクスリ、と小さく笑った。
「先輩は本当に私の匂いが好きですね。変態さん、です」
彼女の独特な言い回しに、ますます俺の興奮のボルテージは上がってゆく。
射精は出来ないものの、俺の心は小日向の体臭で満ち溢れていた……
「先輩、今日はこのへんでおしまいです」
どれくらいの時が経っただろうか。
小日向はそう言って俺を引きはがした。そして素早く着衣すると、物欲しげに見る俺を尻目にちょっと咎めるように言った。
「……先輩の敬語は何か嫌です。これからも前と同じ口調でお願いします」
そう言って小日向は出ていった。
俺は小日向の香りを思い出しながら、一人屋上で空を見上げる事しか出来なかった。
奴隷先輩の人間椅子
「ああ、小日向……」
自室のベッドの上で、何度目になるかも分からない溜息を、俺は吐いた。
その手には彼女から恵んでもらった使い古しの上履きがあった。
所々が黒く変色し、中身にいたっては凄まじい異臭を放っている二足の上履きを、俺は何度もしゃぶり、臭いを嗅いでいた。
小日向の体臭を嗅ぐことで俺の体は火照り、ペニスはギンギンに勃起してしまっていた。
勿論、オナニーは禁止されているので射精は出来ないが、それでも小日向の私物が手の中にあるだけで俺は満足してしまっていた。
小日向に骨抜きにされてしまっている。そんな事実が脳裏を過った。
が、しかし。
――それでも小日向と一緒にいたい。
小日向への思慕が理性を上回った。
彼女の調教は、着実と俺自身を飲み込みつつあったのだ。
「……こんにちわです、先輩」
小日向の腋を初めて嗅いだ日から一週間。
俺は毎日、小日向の腋の香りを嗅がせてもらっていた。
上靴とはまた一味違う、若く動物的な香りに俺はすっかりハマってしまっていた。
そして今日も俺は小日向の体臭を妄想しながら屋上の扉を叩いたのであった。
一方、小日向はいつも通りの無表情と抑揚の無い声で俺に挨拶してきた。
彼女の顔を見るだけで俺は正気じゃいられなくなるほどドキドキするというのに、小日向の方はまるで俺なんて眼中にないような振る舞いだ。
でもそんな小日向に俺は惚れてるんだよな……と悶々とした気持ちになってしまった。
「どうしたですか、先輩?」
「あ、いや……いやなんでもない」
俺の心を見透かしたように尋ねる小日向に、俺は慌てて平静を取り繕う。
小日向は暫く間を置いてから「そうですか」とだけ言うと、そのままいつものように命令を出してきた。
「先輩、今日から腋はおあずけです」
「え……ええっ!?」
突然の宣告に狼狽してしまう。
もう俺は小日向の腋の虜だというのに、おあずけとは……
絶望する俺に向かって、小日向は淡々と告げた。
「……今日から、先輩は椅子になってもらいます」
「……え?」
「先輩は今日から私専用の椅子になってもらいます」
小日向は真顔だった。どうやら本気で俺を椅子替わりにするつもりらしい。でもどうやって……
「……仰向けになってください」
問答無用な小日向の命令に、俺は従うしか術が無い。
俺は大人しく屋上の床に仰向けになった。これからどんな事をされるのだろう。恐れ半分期待半分といった面持ちで俺は小日向を待つ。
「ではそのままですよ、先輩」
人形のように端正な顔が俺を見下ろす。そのあまりの美麗さに、俺は思わず息を呑んだ。
が、それは一瞬の事で、小日向はすぐに体を翻すと、俺を跨るような体勢をとった。
「あ!!」
小日向の細い足が俺を視界を横切り、次に視界に飛び込んできたのは彼女のスカートの中。
純白の下着に包まれた、形のよい小ぶりのお尻。
肉質はそんなにないものの、張りがよさそうな健康的なヒップ。
パンティにうっすらと滲み出るラインがとても魅力的だ。
俺が小日向の尻に見惚れているのも束の間、その美しい臀部は俺の顔面に向けて急降下してきた。
「!!」
俺が何か言う前に、小日向は俺の顔面に腰を降ろした。躊躇いなど皆無のようで、思いっきり体重の乗ったお尻が俺の顔を直撃した。
「……動かないでください」
そう言って小日向は下の俺などお構いなしに、下半身をグイグイ動かした。
「ふもっ……」
その内に、俺の鼻がちょうど尻の割れ目にすっぽりと挟まれる。
「これでよしです」
そう言うと小日向はそのまま文庫本を取りだし、パラパラめくり始めた。
一方俺は彼女の尻肉にキャッチされ、完全に身動きが取れなくなってしまう。
顔いっぱいを柔らかい、そして張りのある小日向のお尻で覆われ、押しつぶされるような感触に夢中になる。
また白い布地が顔面をぴっちりと密着している為、上手く呼吸が出来ない。必死になって空気を吸い込もうとすると湿っぽい汗の香りが下着越しに伝わってきた。
今までの上靴や腋とはまた違った臭い。汗だけでなくほのかな温かさと淫猥な香りが鼻を突いた。
その香りに俺は熱中してしまう。
もはや生きるためではなく、小日向の体臭を嗅ぐために必死に呼吸をしているような感じだ。
すでに俺の興奮度はマックスで、下半身の分身は直立していた。
文字通り小日向の尻に敷かれ、俺はすっかり彼女の臀部の虜になってしまったわけだ。
ああ……小日向。このままずっと……彼女に座られていたい。押しつぶして欲しい。
そんなどうしようもない願望が、俺の頭の中をグルグルと回っていた。
――そしてプロローグへと繋がる。
「……もうこんな時間ですね」
そう言って小日向は腰を上げた。スカートを掃い本を閉じると、冷たい視線で俺を見下ろす。
「勃起してますね、先輩」
すっ……と小日向の目線が俺の下半身に集中する。
彼女の言う通り俺の肉棒は、ズボン越しでもはっきりとわかる位、怒張していた。
「た、頼む、小日向……さ、触ってくれ……射精させてくれ……」
俺はそのゴミを見るような双眸に向かって、懇願した。
今の俺は小日向によって、射精どころか自分の性器に触ることすら禁止されているのだ。
「私はただ座ってただけですよ。それなのに先輩は興奮しちゃってるんですか?」
「う……」
「先輩は本当に変態ですね」
「うう……」
「私のお尻、そんなに気持ちがよかったですか? 後輩の一年生に顔の上に乗られて、先輩として恥ずかしくないんですか?」
「ううう……」
文字通り年下の少女の尻に敷かれ、興奮した挙句勃起し、今や彼女に媚びている。
そんな最低な俺を小日向は一瞥すると、無表情のまま思いっきり固くなったペニスを蹴りあげた。
「あーーーーーーーッ!!」
股間を襲う激痛と衝撃と共に頭がスパークし、快感の波が押し寄せ、精液が一気に噴出する。
頭の中が真っ白になり、体から力がごっそり抜けていく。ズボンの股の部分に染みが出来、異臭を放ち始めた。
「……屋上を汚さないでくださいね」
それだけ言うと小日向は振り返りもせずに、屋上から出ていってしまった。
残された俺の頭上を白い雲がゆったりと流れていく。
――俺は何をしているのだろう。
小日向凪と出会ってから数週間。
俺達の関係は学校の先輩後輩から、ご主人様と奴隷にへと変わっていった。
彼女は常に氷のような表情で俺を嬲った。そして俺もそんな彼女の責めに興奮し、隷属するようになっていった。
そして今日もまた……
だが小日向の調教はまだまだ始まったばかりだということを、この時の俺は知らなかった。
「ああ、小日向……」
自室のベッドの上で、何度目になるかも分からない溜息を、俺は吐いた。
その手には彼女から恵んでもらった使い古しの上履きがあった。
所々が黒く変色し、中身にいたっては凄まじい異臭を放っている二足の上履きを、俺は何度もしゃぶり、臭いを嗅いでいた。
小日向の体臭を嗅ぐことで俺の体は火照り、ペニスはギンギンに勃起してしまっていた。
勿論、オナニーは禁止されているので射精は出来ないが、それでも小日向の私物が手の中にあるだけで俺は満足してしまっていた。
小日向に骨抜きにされてしまっている。そんな事実が脳裏を過った。
が、しかし。
――それでも小日向と一緒にいたい。
小日向への思慕が理性を上回った。
彼女の調教は、着実と俺自身を飲み込みつつあったのだ。
「……こんにちわです、先輩」
小日向の腋を初めて嗅いだ日から一週間。
俺は毎日、小日向の腋の香りを嗅がせてもらっていた。
上靴とはまた一味違う、若く動物的な香りに俺はすっかりハマってしまっていた。
そして今日も俺は小日向の体臭を妄想しながら屋上の扉を叩いたのであった。
一方、小日向はいつも通りの無表情と抑揚の無い声で俺に挨拶してきた。
彼女の顔を見るだけで俺は正気じゃいられなくなるほどドキドキするというのに、小日向の方はまるで俺なんて眼中にないような振る舞いだ。
でもそんな小日向に俺は惚れてるんだよな……と悶々とした気持ちになってしまった。
「どうしたですか、先輩?」
「あ、いや……いやなんでもない」
俺の心を見透かしたように尋ねる小日向に、俺は慌てて平静を取り繕う。
小日向は暫く間を置いてから「そうですか」とだけ言うと、そのままいつものように命令を出してきた。
「先輩、今日から腋はおあずけです」
「え……ええっ!?」
突然の宣告に狼狽してしまう。
もう俺は小日向の腋の虜だというのに、おあずけとは……
絶望する俺に向かって、小日向は淡々と告げた。
「……今日から、先輩は椅子になってもらいます」
「……え?」
「先輩は今日から私専用の椅子になってもらいます」
小日向は真顔だった。どうやら本気で俺を椅子替わりにするつもりらしい。でもどうやって……
「……仰向けになってください」
問答無用な小日向の命令に、俺は従うしか術が無い。
俺は大人しく屋上の床に仰向けになった。これからどんな事をされるのだろう。恐れ半分期待半分といった面持ちで俺は小日向を待つ。
「ではそのままですよ、先輩」
人形のように端正な顔が俺を見下ろす。そのあまりの美麗さに、俺は思わず息を呑んだ。
が、それは一瞬の事で、小日向はすぐに体を翻すと、俺を跨るような体勢をとった。
「あ!!」
小日向の細い足が俺を視界を横切り、次に視界に飛び込んできたのは彼女のスカートの中。
純白の下着に包まれた、形のよい小ぶりのお尻。
肉質はそんなにないものの、張りがよさそうな健康的なヒップ。
パンティにうっすらと滲み出るラインがとても魅力的だ。
俺が小日向の尻に見惚れているのも束の間、その美しい臀部は俺の顔面に向けて急降下してきた。
「!!」
俺が何か言う前に、小日向は俺の顔面に腰を降ろした。躊躇いなど皆無のようで、思いっきり体重の乗ったお尻が俺の顔を直撃した。
「……動かないでください」
そう言って小日向は下の俺などお構いなしに、下半身をグイグイ動かした。
「ふもっ……」
その内に、俺の鼻がちょうど尻の割れ目にすっぽりと挟まれる。
「これでよしです」
そう言うと小日向はそのまま文庫本を取りだし、パラパラめくり始めた。
一方俺は彼女の尻肉にキャッチされ、完全に身動きが取れなくなってしまう。
顔いっぱいを柔らかい、そして張りのある小日向のお尻で覆われ、押しつぶされるような感触に夢中になる。
また白い布地が顔面をぴっちりと密着している為、上手く呼吸が出来ない。必死になって空気を吸い込もうとすると湿っぽい汗の香りが下着越しに伝わってきた。
今までの上靴や腋とはまた違った臭い。汗だけでなくほのかな温かさと淫猥な香りが鼻を突いた。
その香りに俺は熱中してしまう。
もはや生きるためではなく、小日向の体臭を嗅ぐために必死に呼吸をしているような感じだ。
すでに俺の興奮度はマックスで、下半身の分身は直立していた。
文字通り小日向の尻に敷かれ、俺はすっかり彼女の臀部の虜になってしまったわけだ。
ああ……小日向。このままずっと……彼女に座られていたい。押しつぶして欲しい。
そんなどうしようもない願望が、俺の頭の中をグルグルと回っていた。
――そしてプロローグへと繋がる。
「……もうこんな時間ですね」
そう言って小日向は腰を上げた。スカートを掃い本を閉じると、冷たい視線で俺を見下ろす。
「勃起してますね、先輩」
すっ……と小日向の目線が俺の下半身に集中する。
彼女の言う通り俺の肉棒は、ズボン越しでもはっきりとわかる位、怒張していた。
「た、頼む、小日向……さ、触ってくれ……射精させてくれ……」
俺はそのゴミを見るような双眸に向かって、懇願した。
今の俺は小日向によって、射精どころか自分の性器に触ることすら禁止されているのだ。
「私はただ座ってただけですよ。それなのに先輩は興奮しちゃってるんですか?」
「う……」
「先輩は本当に変態ですね」
「うう……」
「私のお尻、そんなに気持ちがよかったですか? 後輩の一年生に顔の上に乗られて、先輩として恥ずかしくないんですか?」
「ううう……」
文字通り年下の少女の尻に敷かれ、興奮した挙句勃起し、今や彼女に媚びている。
そんな最低な俺を小日向は一瞥すると、無表情のまま思いっきり固くなったペニスを蹴りあげた。
「あーーーーーーーッ!!」
股間を襲う激痛と衝撃と共に頭がスパークし、快感の波が押し寄せ、精液が一気に噴出する。
頭の中が真っ白になり、体から力がごっそり抜けていく。ズボンの股の部分に染みが出来、異臭を放ち始めた。
「……屋上を汚さないでくださいね」
それだけ言うと小日向は振り返りもせずに、屋上から出ていってしまった。
残された俺の頭上を白い雲がゆったりと流れていく。
――俺は何をしているのだろう。
小日向凪と出会ってから数週間。
俺達の関係は学校の先輩後輩から、ご主人様と奴隷にへと変わっていった。
彼女は常に氷のような表情で俺を嬲った。そして俺もそんな彼女の責めに興奮し、隷属するようになっていった。
そして今日もまた……
だが小日向の調教はまだまだ始まったばかりだということを、この時の俺は知らなかった。
奴隷先輩のおなら責め
「よいしょっ……と」
ドスン! と小日向は容赦なく俺の顔に腰を降ろした。
そして器用に俺の顔を尻肉の谷間に挟むと、そのまま読書を開始した。
一方俺も柔らかい感触を顔いっぱいで味わいながら、小日向の体臭を必死になって吸い込んでいた。
初めて小日向の椅子になってからもう三日たった。
今まで味わう事の出来なかった小日向の尻の臭いに、彼女の体に長時間触れていられるという喜び。
そんな風に俺はすっかり彼女の人間椅子に魅せられてしまっていたのだった。
「さてと、今日はここまでですね」
幸せな時間はあっという間に過ぎ、終わりの時がきてしまう。
「……先輩、今日も勃起してますね」
俺の戦闘態勢になりっぱなしの愚息に、小日向の視線が注がれる。
いつもなら読書を終えたらすぐに顏からどくのに、今日は座ったままだ。
「年下の女の子のお尻に敷かれて、気持ちいいですか?」
「…………」
「蒸れた下着の臭いはそんなにいいですか?」
「…………」
抑揚の無い声で、それでいて責めるような雰囲気を纏いながら小日向は続ける。
さらにわざと下半身を動かし、ぐりぐりと俺の顔面に柔らかい桃尻をこすりつける。
張りのあるヒップをむにむにと押し付けられ、その極上の感触と官能的な香りが相まって酔いそうになってしまう。
「……答えてください」
そう言いながら小日向は再び尻の谷間に俺の顔を挟んだ。
「先輩はマゾヒストなんですか?」
顔で小日向の全身の体重を受け止めながら、俺は彼女の問いを聞いた。
「マゾだから、こんなことされて喜んじゃうですか」
「…………」
「女の子に虐められて喜んじゃう変態さんですから、こんなに勃起しちゃうですか?」
「…………」
「答えて下さい、先輩」
「……俺は」
彼女の下着で顔を覆われ、うまくしゃべれない。
だが、それでも小日向の問いには答えなくてはいけない。
「俺は……小日向だから興奮するんだ。小日向が相手だから……こんなに……興奮しちゃうんだ」
俺のどうしようもない告白を聞いて、小日向は暫く黙ってしまう。
……軽蔑されてしまっただろうか。いやでもこれ以上俺の心証は下がることないだろうし……
俺がそう考えていると、小日向はふっ、と笑った……気がした。
「そうですか、つまり先輩は女の子に虐められるのが好きなのではなく」
再び下半身をぐりぐり動かすと小日向はいつもよりちょっとだけ嬉しそうに言った。
「私に虐められるのが好きなのですね……」
「…………うう」
改めてそう確認されると何だか気恥ずかしい。前に一度、初めて小日向に同じことを言ったが、あの時はまだ小日向とも出会ったばかりで、小日向とコミュニケーションがとれるなら何でもいいと思っていた。
でも今はそれ以上に、小日向に蔑まれ、体臭を嗅がされることが。数週間に渡って行ってきた小日向との密会が。自分の中でかけがえのないモノへと昇華していった。
――もっと小日向に嬲られたい。臭いを吸いたい!
それが俺の全てであった。
「じゃあ……確かめさせて貰いますね」
すると小日向はん……っと小さく吐息を吐きだすと、
――ぷぅっ!
「!!」
可愛らしい音と共に、校門から生暖かいガスを噴き出した。
ふわっとした生ぬるい空気がダイレクトに顔に直撃し、鼻を突くような異臭が肺にまで届く。
……これっ……もしかしなくても……小日向のおなら……!
こんなに温かくて臭くて……こんなものが小日向の体から出てくるなんて……
「どうですか、先輩?」
それから小日向は再び、ぷ……っとおならをくり出した。
「……っ!」
「おならなんて……普通、嫌がりますよね。いくら好きな人のだったとしても……」
明らかに小馬鹿にした口調で語りかける小日向。それは明らかに怒張した俺のペニスを確認したからであろう。小日向のおならを嗅がされてもなお、いやそれでさらに膨らみガマン汁を漏らしているペニスを。
「どうしました、先輩? おちんちんが辛そうですよ?」
「…………」
「もしかして……私のおならでも興奮しちゃいました?」
「……ッ」
「……図星だったですね」
小日向がくすくすと笑いを漏らす。
でも彼女の言う通り、俺は可憐な少女から放たれた臭気に、一発で心を奪われてしまっていた。
「私の出すモノなら何でもいいんですか、先輩?」
「…………」
「答えて下さい」
「…………」
もはや隠し通せるものではあるまい。
俺は覚悟を決めて、言った。
「ああ。こ、小日向の臭いなら……どんなものでも……ドキドキしてしまう」
「……最低です、先輩」
「あ……ああ……」
はっきりと自身の気持ちを言葉にしたことで、自分の全ての変態性が白日の元に晒されてしまったような気持ちになり、より一層背徳的な興奮が湧き上がる。
「そんな先輩に、プレゼントです」
そう言うと小日向は力をこめ……
「んっ……」
ぶぅ~~~~~っと、盛大に最後の一発を放った。
今までので一番大きく強いおなら。それをモロに浴びた俺は。
「ッ~~~!」
言葉になっていない歓喜の悲鳴をあげ、勢いよく三日ぶりの精液を噴出させた。
今までに感じたことの無い快楽が体の奥底から流れ、全身をしならせる。
そのまま眠りについてしまいたいほどの倦怠感が体を襲い、意識がぼうっとしてきた。
「……本当に、先輩は変態ですね」
小日向は軽蔑したような態度で立ち上がると、頭上から俺を見下ろした。
「そんなに私が好きですか?」
目の前が徐々に霞んでくる。小日向の怜悧な童顔が薄くなってゆく。
「……でしたら、もっともっと汚してあげますね……」
確かに俺はそう聞いた。
そして、そこで俺の意識はぷっつりと途絶えた。
「よいしょっ……と」
ドスン! と小日向は容赦なく俺の顔に腰を降ろした。
そして器用に俺の顔を尻肉の谷間に挟むと、そのまま読書を開始した。
一方俺も柔らかい感触を顔いっぱいで味わいながら、小日向の体臭を必死になって吸い込んでいた。
初めて小日向の椅子になってからもう三日たった。
今まで味わう事の出来なかった小日向の尻の臭いに、彼女の体に長時間触れていられるという喜び。
そんな風に俺はすっかり彼女の人間椅子に魅せられてしまっていたのだった。
「さてと、今日はここまでですね」
幸せな時間はあっという間に過ぎ、終わりの時がきてしまう。
「……先輩、今日も勃起してますね」
俺の戦闘態勢になりっぱなしの愚息に、小日向の視線が注がれる。
いつもなら読書を終えたらすぐに顏からどくのに、今日は座ったままだ。
「年下の女の子のお尻に敷かれて、気持ちいいですか?」
「…………」
「蒸れた下着の臭いはそんなにいいですか?」
「…………」
抑揚の無い声で、それでいて責めるような雰囲気を纏いながら小日向は続ける。
さらにわざと下半身を動かし、ぐりぐりと俺の顔面に柔らかい桃尻をこすりつける。
張りのあるヒップをむにむにと押し付けられ、その極上の感触と官能的な香りが相まって酔いそうになってしまう。
「……答えてください」
そう言いながら小日向は再び尻の谷間に俺の顔を挟んだ。
「先輩はマゾヒストなんですか?」
顔で小日向の全身の体重を受け止めながら、俺は彼女の問いを聞いた。
「マゾだから、こんなことされて喜んじゃうですか」
「…………」
「女の子に虐められて喜んじゃう変態さんですから、こんなに勃起しちゃうですか?」
「…………」
「答えて下さい、先輩」
「……俺は」
彼女の下着で顔を覆われ、うまくしゃべれない。
だが、それでも小日向の問いには答えなくてはいけない。
「俺は……小日向だから興奮するんだ。小日向が相手だから……こんなに……興奮しちゃうんだ」
俺のどうしようもない告白を聞いて、小日向は暫く黙ってしまう。
……軽蔑されてしまっただろうか。いやでもこれ以上俺の心証は下がることないだろうし……
俺がそう考えていると、小日向はふっ、と笑った……気がした。
「そうですか、つまり先輩は女の子に虐められるのが好きなのではなく」
再び下半身をぐりぐり動かすと小日向はいつもよりちょっとだけ嬉しそうに言った。
「私に虐められるのが好きなのですね……」
「…………うう」
改めてそう確認されると何だか気恥ずかしい。前に一度、初めて小日向に同じことを言ったが、あの時はまだ小日向とも出会ったばかりで、小日向とコミュニケーションがとれるなら何でもいいと思っていた。
でも今はそれ以上に、小日向に蔑まれ、体臭を嗅がされることが。数週間に渡って行ってきた小日向との密会が。自分の中でかけがえのないモノへと昇華していった。
――もっと小日向に嬲られたい。臭いを吸いたい!
それが俺の全てであった。
「じゃあ……確かめさせて貰いますね」
すると小日向はん……っと小さく吐息を吐きだすと、
――ぷぅっ!
「!!」
可愛らしい音と共に、校門から生暖かいガスを噴き出した。
ふわっとした生ぬるい空気がダイレクトに顔に直撃し、鼻を突くような異臭が肺にまで届く。
……これっ……もしかしなくても……小日向のおなら……!
こんなに温かくて臭くて……こんなものが小日向の体から出てくるなんて……
「どうですか、先輩?」
それから小日向は再び、ぷ……っとおならをくり出した。
「……っ!」
「おならなんて……普通、嫌がりますよね。いくら好きな人のだったとしても……」
明らかに小馬鹿にした口調で語りかける小日向。それは明らかに怒張した俺のペニスを確認したからであろう。小日向のおならを嗅がされてもなお、いやそれでさらに膨らみガマン汁を漏らしているペニスを。
「どうしました、先輩? おちんちんが辛そうですよ?」
「…………」
「もしかして……私のおならでも興奮しちゃいました?」
「……ッ」
「……図星だったですね」
小日向がくすくすと笑いを漏らす。
でも彼女の言う通り、俺は可憐な少女から放たれた臭気に、一発で心を奪われてしまっていた。
「私の出すモノなら何でもいいんですか、先輩?」
「…………」
「答えて下さい」
「…………」
もはや隠し通せるものではあるまい。
俺は覚悟を決めて、言った。
「ああ。こ、小日向の臭いなら……どんなものでも……ドキドキしてしまう」
「……最低です、先輩」
「あ……ああ……」
はっきりと自身の気持ちを言葉にしたことで、自分の全ての変態性が白日の元に晒されてしまったような気持ちになり、より一層背徳的な興奮が湧き上がる。
「そんな先輩に、プレゼントです」
そう言うと小日向は力をこめ……
「んっ……」
ぶぅ~~~~~っと、盛大に最後の一発を放った。
今までので一番大きく強いおなら。それをモロに浴びた俺は。
「ッ~~~!」
言葉になっていない歓喜の悲鳴をあげ、勢いよく三日ぶりの精液を噴出させた。
今までに感じたことの無い快楽が体の奥底から流れ、全身をしならせる。
そのまま眠りについてしまいたいほどの倦怠感が体を襲い、意識がぼうっとしてきた。
「……本当に、先輩は変態ですね」
小日向は軽蔑したような態度で立ち上がると、頭上から俺を見下ろした。
「そんなに私が好きですか?」
目の前が徐々に霞んでくる。小日向の怜悧な童顔が薄くなってゆく。
「……でしたら、もっともっと汚してあげますね……」
確かに俺はそう聞いた。
そして、そこで俺の意識はぷっつりと途絶えた。
小日向凪の先輩観察日記
誤字脱字があったらすいません
私――小日向凪は本が友達でした。
いやそりゃあまあクラスメイトとはちゃんと話せますし、いじめられているとかそういうことはありませんが、単に多くの人と関わるより一人でいることの方が好きなのです。
特に年頃の女の子は群れを成すのが好きで、皆特定のグループに分かれ独自のコミュニティを作っています。私はそんな同性たちの煩わしい人間関係が嫌でした。
だから私は高校に入学してから、自然と読書三昧の日々が始まりました。
朝のホームルーム。授業の合間の休み時間。お昼休み。そして放課後。学校にいる中で自由でいれる時間には、いつも本を開いていました。
確かにほとんど他の人と交流せず、読書に耽るのは周りから見れば特異なことかもしれません。ですがもうこの位の年だと表立って悪く言う者はクラスにほとんどいません。勿論変わった子というレッテルは貼られましたがそれだけです。私の生活に支障はありません。
多分共働きの両親の元に生まれ、幼少時自宅で一人お留守番をしていた時に、今の性格が形成されたのだと私は思っています。
だから私は周りからどう思われようと、今の読書生活を辞める気はありませんでした。
私にはお気に入りのスポットがありました。放課後の屋上です。
昼間は昼食をとるために多くの生徒が訪れますが、放課後はここに訪れる生徒など酔狂なカップルくらいしかいません。
広くて静かで心地よいこの空間は、私のベスト読書ポイントとなりました。
様々なジャンルの本を読みました。
著名な近代文学作品や荒唐無稽な大衆小説。小難しい論説や古典。恋愛小説からライトノベルまで貪欲にチャレンジしました。
特に最近は恋愛小説。その中でも普通の純愛小説でなく、とりわけ歪んだ……偏愛や異常性癖を持つ者たちの恋愛劇を見るのが好きでした。
そんな中、私は先輩……山崎省吾先輩に出会いました。
先輩と最初に顔を合わせたのは私がいつものように屋上で読書している時でした。
どうやら先輩は何か理由があってここにきたようでした。しかし私の姿を確認するとポカンと呆けてしまいました。
そしてそのままじーっと私の方を見てきました。暫くしたら出ていくかな……と最初は放っておきましたが、いつまでも見てくるので私は先輩に要件を聞きました。しかし、先輩はしどろもどろで答えなかったため、私は無視することに決めました。
きっと偶然ここに来て出会っただけですし、もう関わることもないでしょう……私はそう思っていました。
しかし、それから先輩は毎日、屋上にやってきました。しかも特に何かするわけでもなく、遠くから私を見ていました。実害は無いので特になにも言いませんでしたが、ちょっとうざかったです。
先輩はそこそこ有名な人でした。
何でも惚れっぽい性格のようで今まで色んな女の人に告白しては、フラれてきた人のようです。
じゃあ先輩が毎日屋上にくるのは、私に恋してしまったからなのでしょうか……
ですが先輩は遠目で私を見つめるだけで何もしませんでした。惚れたらすぐに告白すると聞いていたので、意外でした。
なので私も何もしないならと放置していましたが、ある日思い詰めたような顔をしながら、ふらふら歩く先輩を発見しました。
気になったので様子をこっそり窺って見ると、なんと先輩は私の上履きを懐に入れ、屋上へと向かったんのです。
私はすぐに追いました。そして、屋上で私の上履きを嗅いでいる先輩を発見しました。
これには私も驚きました。何せ毎日少しとはいえ顔を合わせていた先輩が、私の私物。しかもよりにもよって汚れて異臭を放つ上履きを嗅いでいるんて……
私はまず何故先輩がこんなことをしたのか、その理由を尋ねました。
「小日向のモノだから……興奮したんだ」
震えながら先輩はそう言いました。
それを聞いた時、私は前に読んだ小説を思い出しまた。
その小説の主人公はとある女性を心底惚れこみ、彼女の私物を盗んでしまいます。そしてその女性の体臭を嗅いで、喜んでしまうのです。彼の行動はどんどんエスカレートしていき、ついに意中の人にその行為がばれてしまいます。
その女性は自分の私物を必死で集める主人公を笑い、玩具として扱います。そして段々とその扱いは乱暴になってゆき……といった内容でした。
私は目の前の先輩をその小説の主人公と重ねました。
そして、試すことにしました。
本当に私が好きなのか。そして私の私物でこの人がどこまで堕ちるのか……
私がオナニーをしなさいと命令すると、先輩は必死になって上履きを嗅ぎながら人目も憚らずオナニーしました。
どうやら本気で上履きの臭いに興奮しているようでした。
では次に射精を制限してみましょう。
実行してるかしていないかはすぐにわかりました。先輩は顔や態度に本音が出やすい人でしたので、辛そうな顔をする先輩を見てちゃんと言いつけを守ってるのだなと思いました。
上履きの次は腋、その次はおしりと、私の主観でどんどん汚い所の臭いを先輩に与えました。
そして先輩はその全てを受け入れました。
おならで射精した時は、さすがの私も驚きました。
そして同時に、先輩が本気で私を愛している事。私の共にいるためなら、どんな命令にも従うことが分かりました。
私は先輩をもっとぐちゃぐちゃにしてやりたいという願望が芽生えました。
この私に心酔する彼を、この上なく酷く汚いもので支配したいと考えました。
きっと私も異常なのでしょう。ですが辞める気はありません。
先輩……本当の調教はこれからですよ。
脱落なんて許しませんから。
精々もがいて私を楽しませてくださいね、先輩。
誤字脱字があったらすいません
私――小日向凪は本が友達でした。
いやそりゃあまあクラスメイトとはちゃんと話せますし、いじめられているとかそういうことはありませんが、単に多くの人と関わるより一人でいることの方が好きなのです。
特に年頃の女の子は群れを成すのが好きで、皆特定のグループに分かれ独自のコミュニティを作っています。私はそんな同性たちの煩わしい人間関係が嫌でした。
だから私は高校に入学してから、自然と読書三昧の日々が始まりました。
朝のホームルーム。授業の合間の休み時間。お昼休み。そして放課後。学校にいる中で自由でいれる時間には、いつも本を開いていました。
確かにほとんど他の人と交流せず、読書に耽るのは周りから見れば特異なことかもしれません。ですがもうこの位の年だと表立って悪く言う者はクラスにほとんどいません。勿論変わった子というレッテルは貼られましたがそれだけです。私の生活に支障はありません。
多分共働きの両親の元に生まれ、幼少時自宅で一人お留守番をしていた時に、今の性格が形成されたのだと私は思っています。
だから私は周りからどう思われようと、今の読書生活を辞める気はありませんでした。
私にはお気に入りのスポットがありました。放課後の屋上です。
昼間は昼食をとるために多くの生徒が訪れますが、放課後はここに訪れる生徒など酔狂なカップルくらいしかいません。
広くて静かで心地よいこの空間は、私のベスト読書ポイントとなりました。
様々なジャンルの本を読みました。
著名な近代文学作品や荒唐無稽な大衆小説。小難しい論説や古典。恋愛小説からライトノベルまで貪欲にチャレンジしました。
特に最近は恋愛小説。その中でも普通の純愛小説でなく、とりわけ歪んだ……偏愛や異常性癖を持つ者たちの恋愛劇を見るのが好きでした。
そんな中、私は先輩……山崎省吾先輩に出会いました。
先輩と最初に顔を合わせたのは私がいつものように屋上で読書している時でした。
どうやら先輩は何か理由があってここにきたようでした。しかし私の姿を確認するとポカンと呆けてしまいました。
そしてそのままじーっと私の方を見てきました。暫くしたら出ていくかな……と最初は放っておきましたが、いつまでも見てくるので私は先輩に要件を聞きました。しかし、先輩はしどろもどろで答えなかったため、私は無視することに決めました。
きっと偶然ここに来て出会っただけですし、もう関わることもないでしょう……私はそう思っていました。
しかし、それから先輩は毎日、屋上にやってきました。しかも特に何かするわけでもなく、遠くから私を見ていました。実害は無いので特になにも言いませんでしたが、ちょっとうざかったです。
先輩はそこそこ有名な人でした。
何でも惚れっぽい性格のようで今まで色んな女の人に告白しては、フラれてきた人のようです。
じゃあ先輩が毎日屋上にくるのは、私に恋してしまったからなのでしょうか……
ですが先輩は遠目で私を見つめるだけで何もしませんでした。惚れたらすぐに告白すると聞いていたので、意外でした。
なので私も何もしないならと放置していましたが、ある日思い詰めたような顔をしながら、ふらふら歩く先輩を発見しました。
気になったので様子をこっそり窺って見ると、なんと先輩は私の上履きを懐に入れ、屋上へと向かったんのです。
私はすぐに追いました。そして、屋上で私の上履きを嗅いでいる先輩を発見しました。
これには私も驚きました。何せ毎日少しとはいえ顔を合わせていた先輩が、私の私物。しかもよりにもよって汚れて異臭を放つ上履きを嗅いでいるんて……
私はまず何故先輩がこんなことをしたのか、その理由を尋ねました。
「小日向のモノだから……興奮したんだ」
震えながら先輩はそう言いました。
それを聞いた時、私は前に読んだ小説を思い出しまた。
その小説の主人公はとある女性を心底惚れこみ、彼女の私物を盗んでしまいます。そしてその女性の体臭を嗅いで、喜んでしまうのです。彼の行動はどんどんエスカレートしていき、ついに意中の人にその行為がばれてしまいます。
その女性は自分の私物を必死で集める主人公を笑い、玩具として扱います。そして段々とその扱いは乱暴になってゆき……といった内容でした。
私は目の前の先輩をその小説の主人公と重ねました。
そして、試すことにしました。
本当に私が好きなのか。そして私の私物でこの人がどこまで堕ちるのか……
私がオナニーをしなさいと命令すると、先輩は必死になって上履きを嗅ぎながら人目も憚らずオナニーしました。
どうやら本気で上履きの臭いに興奮しているようでした。
では次に射精を制限してみましょう。
実行してるかしていないかはすぐにわかりました。先輩は顔や態度に本音が出やすい人でしたので、辛そうな顔をする先輩を見てちゃんと言いつけを守ってるのだなと思いました。
上履きの次は腋、その次はおしりと、私の主観でどんどん汚い所の臭いを先輩に与えました。
そして先輩はその全てを受け入れました。
おならで射精した時は、さすがの私も驚きました。
そして同時に、先輩が本気で私を愛している事。私の共にいるためなら、どんな命令にも従うことが分かりました。
私は先輩をもっとぐちゃぐちゃにしてやりたいという願望が芽生えました。
この私に心酔する彼を、この上なく酷く汚いもので支配したいと考えました。
きっと私も異常なのでしょう。ですが辞める気はありません。
先輩……本当の調教はこれからですよ。
脱落なんて許しませんから。
精々もがいて私を楽しませてくださいね、先輩。
奴隷先輩の尋問
「はあ……」
六限終了後のホームルーム前にある小さな自由時間。机に突っ伏しながら俺は何度目か分からない溜息をついた。
屋上でのおなら責めから翌日、俺の頭の中は小日向でいっぱいになっていた。
今日もあと少しで放課後になる。そうすればまた小日向に虐めてもらえる……
そう思うともうそれ以外のことは考えられなくなってしまい、何も手につかなくなってしまっていた。
「何気の抜けた顔してんだよ、省吾」
横から聞きなれた声がしたので、ふいっと顔を上げる。
「なんだ、一馬か……」
「何だとは何だ、何だとは」
俺が顔を上げた先には嘆息する親友の顔があった。
「最近、全然元気ないじゃないか。例の後輩と何かあったのか?」
「え、ああ、まあな……」
まさかその後輩に骨抜きにされたとは言えまい。
「そう言うお前こそ、最近音無さんとべったりじゃねえか、クズが……」
「く、くずとは酷い言いようだな……」
学園のアイドルを彼女にしているんだから、これ位は言われても仕方なかろう。
まあ今の俺には小日向がいるから別に何とも思わないのであるが……
「そろそろ先生が来るぜ、席つけよ」
「あ、ああ……」
釈然としない顔をしながら一馬は席に戻っていった。そしてタイミングよく、担任が教室に入ってきた……
ショートホームルームが終わり、俺はすぐに鞄を掴んで席を立つ。勿論、屋上に向かうためだ。
一馬に軽い挨拶をし教室を出ようとしたその時であった。
「あ……先輩」
「こ、小日向!」
突然視界に入ってきたのは、俺の心のオアシスともいえる少女。見間違えるはずもなく、小日向凪その人だった。
すぐに急ブレーキをかけ、小日向の前に止まる。
「どうもです、先輩」
「な、何で二年生の教室に小日向が……?」
「迎えにきたです」
いつもの無表情で小日向は涼しげに答えた。その小さな手には学校指定の通学鞄が握られている。
「え、どういうことだ?」
「先輩を迎えに来たのです」
少しだけむっとしながら、小日向は俺の腕を掴んだ。
「え、何この子?」
「可愛い子だな……」
「あのリボンの色、一年生じゃない?」
「何で山崎と一緒にいんの?」
「まさか付き合ってるとか……?」
突然現れた一年生の少女に、クラスメイト達が騒ぎ始める。
今まで小日向と俺が会うのは屋上だけだった。俺も小日向との関係は一馬以外には全く話していない。
だからこそ他の奴らにとって、小日向は突然現れた謎の美少女。そりゃ気になるだろう。
「え、えーとこの子はな……」
「先輩、行きますよ」
俺がとりあえず何か言い訳しようとするがそれを遮って小日向が俺の腕を掴んで、廊下へ連れ出した。
「お、おいっ! 小日向!」
彼女に手を引かれながら俺は校舎を進んで行く。後ろの方からは同級生らの困惑に満ちた声が聞こえてきていた。
「何ですか、先輩?」
「い、いきなり何で教室に来たんだ? それに行くってどこに?」
「今日は私の家に来てください、先輩」
「……何だって?」
「今日は私の家に来てください、先輩」
小日向はその場に止まり、俺の方を向いてそう言いなおした。硝子細工のように大きい瞳が、真っ直ぐに俺を見つめていた。
小日向の家は学校から歩いて20分程で辿り着いた。
閑静な住宅街。その中に『小日向』と書かれた標識の一軒家があった。
「どうぞです」
小日向は懐から合鍵を取り出して玄関を開けると、俺を招き入れた。
「お、お邪魔します……」
いたって普通の玄関なのだが、妙に緊張してしまう。やっぱり一人で女の子の家に来たのが初めてだからであろうか……
「あ、先輩。今日は父も母も仕事で帰りが遅いですよ」
「えっ?」
靴を脱ぎながら小日向は告げた。そ、それってつまり……
「……たっぷり遊びましょうね、先輩」
俺は唾を飲み込むと、微笑する小日向の背中を追いかけた。
階段を上るとすぐに小日向の自室に辿り着いた。木製のドアには「NAGI」と書かれたネームプレートがかけられている。
小日向に促され中へ入ると、そこには今まで見たこととの無い『女の子の部屋』があった。
フローリングの床に白いカーペット。小さな勉強机にシンプルなデザインのベッド。何個も並べられた本棚には、様々な種類の本がパンパンに詰まっている。
そして……何だか甘いような臭いが俺の鼻孔をくすぐった。
「……家族以外を入れるのは初めてです」
「え? マジで?」
コクリと無表情で頷く小日向だが、ひょっとして俺は今、とんでもない状況に足を突っ込んでいるのではないか?
冷静に考えると女子の部屋に二人っきりだ。間違いが起きてもおかしくない……いや、もしかして小日向は間違いが起こってもいいと思っている? 一ヵ月近い交流を通して遂に俺を受け入れることを決意したのか……? まてまて、そんなこと、でも……
「えい」
可愛らしい掛け声と共に俺の眉間に小日向のチョップが直撃する。
「いてっ!」
「変な事、考えちゃ駄目です」
そう言うと小日向は冷たい目で俺を見つめながら鞄をベッドに降ろし、そのままベッドに腰掛けた。
「正座してください」
「…………」
まあ、そんないい話のわけないよな……ちょっと期待をした俺が馬鹿だ。でも小日向の自室に入っているという事実は変わらない。さっきから微妙に小日向のの臭いが香ってくるし。
そんな馬鹿な事を考えながら、俺はカーペットの上に正座した。
「今日は先輩を尋問するです」
小日向の冷淡な声が聞こえた瞬間、俺の視界が黒で覆われた。直後柔らかい感触が俺の顔面を塞ぎ、同時にもわっとした温もりと懐かしい香りが襲いくる。
「ふごっ……」
「先輩の大好きなモノですよ……」
それが靴下に包まれた小日向の足の裏だと気が付くのに時間はかからなかった。
そして小日向の足臭だと分かった瞬間、俺はすぐに鼻でめいいっぱい息を吸い込んだ。
「……ッ!」
脳天を貫く程に香る小日向の足。毎晩使い古しの上靴を嗅いでいるとはいえ、やはり本人の足に直接触れながら臭いを吸えるのは最高だ……
「私の蒸れた足はどうです?」
ぐりぐりと足の裏を押し付けながら小日向は言った。
「変態の先輩にとってはご褒美ですね」
小馬鹿にしたような小日向の言い方に俺は鼻息を荒くしてしまう。
「もっと臭いたいですか?」
小日向の問いに俺は迷わず頷いた。
「……だったら私の質問に素直に答えてください」
俺の顔に密着していた足が少しずらされ、口の部分が外気に触れる。
「わ、わかった……」
質問って何だろう……? そういえばさっき尋問するって言ってたような……
「私はまだ、先輩の事をよく知りません」
「…………」
確かに俺と小日向は一ヵ月近く屋上で秘密の逢瀬を繰り返してきたが、お互いのことはそんなに知らない。
良く考えれば二人の接点は屋上しかないのだ。しかもそこでも俺達はほとんどしゃべっていない。
「先輩の事、もっとよく知りたいです」
「……ッ!」
今まで俺に対してほとんど無関心に見えた小日向がそんな事を言うなんて……
「嘘ついたら、おあずけですから」
きゅっと足の指で鼻を摘ままれる。それだけでまるで小日向に完全に体を掌握されたような気持ちになる。
「あ、ああ……わかった」
すでに俺は小日向の体臭の虜だ。この香りを一分でも長く嗅ぎ続けたいと思ってしまう。
それに嘘をついても小日向が相手ならすぐにばれてしまいそうでもある。
こうしてお互いの利害が一致し、小日向による尋問が始まった。
自分の名前から始まり生年月日、身長体重から好きな食べ物まで根掘り葉掘り小日向は質問してくる。
俺は足の香りを嗅ぎたい一心で小日向の質問に答えていったが、まるで一枚ずつ自分を構成する皮を剥がされていくような感覚に陥ってくる。心まで丸裸にされてしまうような感じだった。
そして段々と質問の内容も偏った感じになってくる。
「……先輩は巨乳の女の子と貧乳の女の子、どっちがタイプですか?」
「そりゃ勿論巨乳……」
そう答えた瞬間、ぐりぃ! と小日向は俺の顔を強く踏みにじる。
「で、でも、小日向に胸は関係ないぞ! 俺は小日向が好きなんだし……」
咄嗟にそう取り繕うと、足の力が少しばかり緩められた。そうか胸のこと気にしていたのか……
「……では次の質問です」
「……おう」
「何で私を好きになったんですか?」
……いきなり直球な問いかけが来たな……
「一目ぼれじゃ、駄目か?」
「……先輩は今まで多くの女の人に告白してきたらしいですね」
「あ、ああ……」
「その方々も一目ぼれですか?」
「…………」
「……そうですか」
小日向はいつもの抑揚の無い声でそう言った。しかしその声色はいつも以上に冷たく感じられた。
「私も、他の人たちと同じ。ということですか」
「違う」
俺は迷わず反論した。驚いたのか、小日向の足の力が若干弱まる。
「確かに俺は惚れっぽいし、好みの女性のタイプは巨乳で明るい性格の人だけど……」
「…………」
「でも俺は小日向が一番好きだ。小日向を一目見た時から、小日向のことしか考えれないんだ。小日向だけなんだ。こんな気持ちになったのは」
俺は正直に彼女への思いを告白した。本当にどうしようもない感情だが、今は素直にこの感情を伝えることが大事だと思った。
それを聞いた小日向は暫く黙っていたが、
「……そうですか」
と消えそうな程の小声で呟くと足を上下に動かし顔面に足の裏を擦りつけた。
「そんなに私が好きですか?」
「あ、ああ……」
「先輩は本当に私が好きなんですね」
「ああ……ずっとそう言ってると思うが……」
「そうですか……だったら先輩は私でえっちな妄想もするのですか?」
「ふぇっ?」
唐突な質問の変化に思わず変な声が出てしまう。
「どうなんです?」
「……ま、まあそりゃするさ。好きな子なんだからさ」
「では私に教えてください」
「え?」
「どんな風に妄想していたのか、全部教えてください」
「そ、それってさ……」
「私でどんなえっちぃ妄想をしていたのですか? 全部教えてください」
「…………」
どうしよう、正直言って話せるような代物じゃない。でもちゃんと話さないと、小日向の足の臭いがおあずけになってしまうかも……
「……聞いても引かない?」
「いえ、ドン引きすると思います。でもそれで先輩を捨てたりしません」
「……本当?」
「本当です」
「……わかった」
俺は覚悟を決めて、小日向を使ったオナニーネタ(実際に射精はしてないので違うかもしれんが)を挙げていった。
「こ、小日向が踏んだ食べ物を食べさせられたり……」
「…………」
「小日向の汗を全部舐めとらされたり……」
「…………」
俺の独白が始ってから既に10分以上が経過していた。俺は妄想の内容を1つず口に出す。それに対し小日向は無言のまま、聞いている。
やがてストックが尽きてくる。そこでようやく小日向は口を開いた。
「……本当に最低ですね、先輩」
「う、うう」
「そんな変態的な妄想を私でしていたですね……」
「あ、ああ」
「……ふふ」
俺の顔を圧迫していた両足がどかされ、塞がれていた視界が晴れた。ぼんやりとしか見えないが、微笑する小日向が見える。
「これで尋問は終わりです。お疲れ様でした、先輩」
小日向はそう言うと、俺の髪を掴むとそのまま自分の方へ引き寄せた。
「先輩のこと、今日でたくさん知りました」
「…………」
「これは頑張ったご褒美です」
そう言うと小日向は俺の顔を自身の股に押し付けた。
薄い布の感触が俺の顔を包むと同時に、汗の酸っぱい香りと性器独特の発酵したような香りが鼻についた。
布越しであるが伝わってくる小日向の体温と肉の感触。間違いない、これが小日向の性器……
「ッああああぁぁぁぁぁぁぁ~!」
そう理解した瞬間、快楽が体を貫き体が弓のようにしなる。そして情けない声と共に尋問されていた時からずっと勃起していたペニスから精液が噴出した。
今回はちゃんと服を着ていたので、パンツの中で爆発してしまう結果となった。
「……射精したですね。許可してないのに……」
冷めたような声が頭上から聞こえた。
「全く、駄目ですね先輩」
そう言うと小日向は俺の顔を上にあげさせた。
「マゾで早漏で臭いフェチなんて、先輩は最低の人間です」
小日向の端正な顔が目の前に迫る。
「今日はここまでです。……明日からもっともっと虐めてあげますからね」
そんな小日向を見上げながら、俺は射精の解放感と明日からの彼女との行為に思いを馳せていた。
「はあ……」
六限終了後のホームルーム前にある小さな自由時間。机に突っ伏しながら俺は何度目か分からない溜息をついた。
屋上でのおなら責めから翌日、俺の頭の中は小日向でいっぱいになっていた。
今日もあと少しで放課後になる。そうすればまた小日向に虐めてもらえる……
そう思うともうそれ以外のことは考えられなくなってしまい、何も手につかなくなってしまっていた。
「何気の抜けた顔してんだよ、省吾」
横から聞きなれた声がしたので、ふいっと顔を上げる。
「なんだ、一馬か……」
「何だとは何だ、何だとは」
俺が顔を上げた先には嘆息する親友の顔があった。
「最近、全然元気ないじゃないか。例の後輩と何かあったのか?」
「え、ああ、まあな……」
まさかその後輩に骨抜きにされたとは言えまい。
「そう言うお前こそ、最近音無さんとべったりじゃねえか、クズが……」
「く、くずとは酷い言いようだな……」
学園のアイドルを彼女にしているんだから、これ位は言われても仕方なかろう。
まあ今の俺には小日向がいるから別に何とも思わないのであるが……
「そろそろ先生が来るぜ、席つけよ」
「あ、ああ……」
釈然としない顔をしながら一馬は席に戻っていった。そしてタイミングよく、担任が教室に入ってきた……
ショートホームルームが終わり、俺はすぐに鞄を掴んで席を立つ。勿論、屋上に向かうためだ。
一馬に軽い挨拶をし教室を出ようとしたその時であった。
「あ……先輩」
「こ、小日向!」
突然視界に入ってきたのは、俺の心のオアシスともいえる少女。見間違えるはずもなく、小日向凪その人だった。
すぐに急ブレーキをかけ、小日向の前に止まる。
「どうもです、先輩」
「な、何で二年生の教室に小日向が……?」
「迎えにきたです」
いつもの無表情で小日向は涼しげに答えた。その小さな手には学校指定の通学鞄が握られている。
「え、どういうことだ?」
「先輩を迎えに来たのです」
少しだけむっとしながら、小日向は俺の腕を掴んだ。
「え、何この子?」
「可愛い子だな……」
「あのリボンの色、一年生じゃない?」
「何で山崎と一緒にいんの?」
「まさか付き合ってるとか……?」
突然現れた一年生の少女に、クラスメイト達が騒ぎ始める。
今まで小日向と俺が会うのは屋上だけだった。俺も小日向との関係は一馬以外には全く話していない。
だからこそ他の奴らにとって、小日向は突然現れた謎の美少女。そりゃ気になるだろう。
「え、えーとこの子はな……」
「先輩、行きますよ」
俺がとりあえず何か言い訳しようとするがそれを遮って小日向が俺の腕を掴んで、廊下へ連れ出した。
「お、おいっ! 小日向!」
彼女に手を引かれながら俺は校舎を進んで行く。後ろの方からは同級生らの困惑に満ちた声が聞こえてきていた。
「何ですか、先輩?」
「い、いきなり何で教室に来たんだ? それに行くってどこに?」
「今日は私の家に来てください、先輩」
「……何だって?」
「今日は私の家に来てください、先輩」
小日向はその場に止まり、俺の方を向いてそう言いなおした。硝子細工のように大きい瞳が、真っ直ぐに俺を見つめていた。
小日向の家は学校から歩いて20分程で辿り着いた。
閑静な住宅街。その中に『小日向』と書かれた標識の一軒家があった。
「どうぞです」
小日向は懐から合鍵を取り出して玄関を開けると、俺を招き入れた。
「お、お邪魔します……」
いたって普通の玄関なのだが、妙に緊張してしまう。やっぱり一人で女の子の家に来たのが初めてだからであろうか……
「あ、先輩。今日は父も母も仕事で帰りが遅いですよ」
「えっ?」
靴を脱ぎながら小日向は告げた。そ、それってつまり……
「……たっぷり遊びましょうね、先輩」
俺は唾を飲み込むと、微笑する小日向の背中を追いかけた。
階段を上るとすぐに小日向の自室に辿り着いた。木製のドアには「NAGI」と書かれたネームプレートがかけられている。
小日向に促され中へ入ると、そこには今まで見たこととの無い『女の子の部屋』があった。
フローリングの床に白いカーペット。小さな勉強机にシンプルなデザインのベッド。何個も並べられた本棚には、様々な種類の本がパンパンに詰まっている。
そして……何だか甘いような臭いが俺の鼻孔をくすぐった。
「……家族以外を入れるのは初めてです」
「え? マジで?」
コクリと無表情で頷く小日向だが、ひょっとして俺は今、とんでもない状況に足を突っ込んでいるのではないか?
冷静に考えると女子の部屋に二人っきりだ。間違いが起きてもおかしくない……いや、もしかして小日向は間違いが起こってもいいと思っている? 一ヵ月近い交流を通して遂に俺を受け入れることを決意したのか……? まてまて、そんなこと、でも……
「えい」
可愛らしい掛け声と共に俺の眉間に小日向のチョップが直撃する。
「いてっ!」
「変な事、考えちゃ駄目です」
そう言うと小日向は冷たい目で俺を見つめながら鞄をベッドに降ろし、そのままベッドに腰掛けた。
「正座してください」
「…………」
まあ、そんないい話のわけないよな……ちょっと期待をした俺が馬鹿だ。でも小日向の自室に入っているという事実は変わらない。さっきから微妙に小日向のの臭いが香ってくるし。
そんな馬鹿な事を考えながら、俺はカーペットの上に正座した。
「今日は先輩を尋問するです」
小日向の冷淡な声が聞こえた瞬間、俺の視界が黒で覆われた。直後柔らかい感触が俺の顔面を塞ぎ、同時にもわっとした温もりと懐かしい香りが襲いくる。
「ふごっ……」
「先輩の大好きなモノですよ……」
それが靴下に包まれた小日向の足の裏だと気が付くのに時間はかからなかった。
そして小日向の足臭だと分かった瞬間、俺はすぐに鼻でめいいっぱい息を吸い込んだ。
「……ッ!」
脳天を貫く程に香る小日向の足。毎晩使い古しの上靴を嗅いでいるとはいえ、やはり本人の足に直接触れながら臭いを吸えるのは最高だ……
「私の蒸れた足はどうです?」
ぐりぐりと足の裏を押し付けながら小日向は言った。
「変態の先輩にとってはご褒美ですね」
小馬鹿にしたような小日向の言い方に俺は鼻息を荒くしてしまう。
「もっと臭いたいですか?」
小日向の問いに俺は迷わず頷いた。
「……だったら私の質問に素直に答えてください」
俺の顔に密着していた足が少しずらされ、口の部分が外気に触れる。
「わ、わかった……」
質問って何だろう……? そういえばさっき尋問するって言ってたような……
「私はまだ、先輩の事をよく知りません」
「…………」
確かに俺と小日向は一ヵ月近く屋上で秘密の逢瀬を繰り返してきたが、お互いのことはそんなに知らない。
良く考えれば二人の接点は屋上しかないのだ。しかもそこでも俺達はほとんどしゃべっていない。
「先輩の事、もっとよく知りたいです」
「……ッ!」
今まで俺に対してほとんど無関心に見えた小日向がそんな事を言うなんて……
「嘘ついたら、おあずけですから」
きゅっと足の指で鼻を摘ままれる。それだけでまるで小日向に完全に体を掌握されたような気持ちになる。
「あ、ああ……わかった」
すでに俺は小日向の体臭の虜だ。この香りを一分でも長く嗅ぎ続けたいと思ってしまう。
それに嘘をついても小日向が相手ならすぐにばれてしまいそうでもある。
こうしてお互いの利害が一致し、小日向による尋問が始まった。
自分の名前から始まり生年月日、身長体重から好きな食べ物まで根掘り葉掘り小日向は質問してくる。
俺は足の香りを嗅ぎたい一心で小日向の質問に答えていったが、まるで一枚ずつ自分を構成する皮を剥がされていくような感覚に陥ってくる。心まで丸裸にされてしまうような感じだった。
そして段々と質問の内容も偏った感じになってくる。
「……先輩は巨乳の女の子と貧乳の女の子、どっちがタイプですか?」
「そりゃ勿論巨乳……」
そう答えた瞬間、ぐりぃ! と小日向は俺の顔を強く踏みにじる。
「で、でも、小日向に胸は関係ないぞ! 俺は小日向が好きなんだし……」
咄嗟にそう取り繕うと、足の力が少しばかり緩められた。そうか胸のこと気にしていたのか……
「……では次の質問です」
「……おう」
「何で私を好きになったんですか?」
……いきなり直球な問いかけが来たな……
「一目ぼれじゃ、駄目か?」
「……先輩は今まで多くの女の人に告白してきたらしいですね」
「あ、ああ……」
「その方々も一目ぼれですか?」
「…………」
「……そうですか」
小日向はいつもの抑揚の無い声でそう言った。しかしその声色はいつも以上に冷たく感じられた。
「私も、他の人たちと同じ。ということですか」
「違う」
俺は迷わず反論した。驚いたのか、小日向の足の力が若干弱まる。
「確かに俺は惚れっぽいし、好みの女性のタイプは巨乳で明るい性格の人だけど……」
「…………」
「でも俺は小日向が一番好きだ。小日向を一目見た時から、小日向のことしか考えれないんだ。小日向だけなんだ。こんな気持ちになったのは」
俺は正直に彼女への思いを告白した。本当にどうしようもない感情だが、今は素直にこの感情を伝えることが大事だと思った。
それを聞いた小日向は暫く黙っていたが、
「……そうですか」
と消えそうな程の小声で呟くと足を上下に動かし顔面に足の裏を擦りつけた。
「そんなに私が好きですか?」
「あ、ああ……」
「先輩は本当に私が好きなんですね」
「ああ……ずっとそう言ってると思うが……」
「そうですか……だったら先輩は私でえっちな妄想もするのですか?」
「ふぇっ?」
唐突な質問の変化に思わず変な声が出てしまう。
「どうなんです?」
「……ま、まあそりゃするさ。好きな子なんだからさ」
「では私に教えてください」
「え?」
「どんな風に妄想していたのか、全部教えてください」
「そ、それってさ……」
「私でどんなえっちぃ妄想をしていたのですか? 全部教えてください」
「…………」
どうしよう、正直言って話せるような代物じゃない。でもちゃんと話さないと、小日向の足の臭いがおあずけになってしまうかも……
「……聞いても引かない?」
「いえ、ドン引きすると思います。でもそれで先輩を捨てたりしません」
「……本当?」
「本当です」
「……わかった」
俺は覚悟を決めて、小日向を使ったオナニーネタ(実際に射精はしてないので違うかもしれんが)を挙げていった。
「こ、小日向が踏んだ食べ物を食べさせられたり……」
「…………」
「小日向の汗を全部舐めとらされたり……」
「…………」
俺の独白が始ってから既に10分以上が経過していた。俺は妄想の内容を1つず口に出す。それに対し小日向は無言のまま、聞いている。
やがてストックが尽きてくる。そこでようやく小日向は口を開いた。
「……本当に最低ですね、先輩」
「う、うう」
「そんな変態的な妄想を私でしていたですね……」
「あ、ああ」
「……ふふ」
俺の顔を圧迫していた両足がどかされ、塞がれていた視界が晴れた。ぼんやりとしか見えないが、微笑する小日向が見える。
「これで尋問は終わりです。お疲れ様でした、先輩」
小日向はそう言うと、俺の髪を掴むとそのまま自分の方へ引き寄せた。
「先輩のこと、今日でたくさん知りました」
「…………」
「これは頑張ったご褒美です」
そう言うと小日向は俺の顔を自身の股に押し付けた。
薄い布の感触が俺の顔を包むと同時に、汗の酸っぱい香りと性器独特の発酵したような香りが鼻についた。
布越しであるが伝わってくる小日向の体温と肉の感触。間違いない、これが小日向の性器……
「ッああああぁぁぁぁぁぁぁ~!」
そう理解した瞬間、快楽が体を貫き体が弓のようにしなる。そして情けない声と共に尋問されていた時からずっと勃起していたペニスから精液が噴出した。
今回はちゃんと服を着ていたので、パンツの中で爆発してしまう結果となった。
「……射精したですね。許可してないのに……」
冷めたような声が頭上から聞こえた。
「全く、駄目ですね先輩」
そう言うと小日向は俺の顔を上にあげさせた。
「マゾで早漏で臭いフェチなんて、先輩は最低の人間です」
小日向の端正な顔が目の前に迫る。
「今日はここまでです。……明日からもっともっと虐めてあげますからね」
そんな小日向を見上げながら、俺は射精の解放感と明日からの彼女との行為に思いを馳せていた。
奴隷先輩の昼食風景
「はぁ……」
あの小日向の尋問から翌日。俺は憂鬱な面持ちで制服に着替えていた。
あの後、小日向の家から出てすぐに自宅に帰ったが、思い出すのは小日向の足臭と部屋の香り。
その日はずっとそのことで頭がいっぱいだった。そして今日もその事が頭から離れなかった。
「ああ、小日向……」
人間離れした美貌を持つ彼女のことを想いながら、俺は上の空で玄関を開けた。
「おはようございます。先輩」
「ファッ!?」
玄関の先には、学生鞄を抱えた後輩が立っていた。
白くて健康的な肌。小動物を思わせる可愛らしい容姿に小っちゃい肢体。間違いなく小日向凪その人だった。
「な、なんでここに小日向が?」
「昨日、先輩から聞いた住所を頼りに来たです」
ちょっと得意げに胸を張る小日向。その仕草に少しだけ可愛いと思ってしまった。
「今日から一緒に登下校するですよ、先輩」
「え、あ、ああ……」
「……嫌ですか?」
上目使いで俺の腕を掴む小日向。相変わらず顔は無表情だが、胸に来るような可憐さがそこにはあった。
「い、いや、嫌じゃないけど何でいきなりなんだろうってさ」
「……先輩を管理するためです」
そう言うと小日向は俺の腕を引っ張って歩き出した。
「こ、小日向! 早いって!」
俺の言葉を無視し、どんどん速度を速める小日向。俺は戸惑いながらも、これはこれでいいなと思って素直に付いていった。
この時、俺は日常生活までどんどん小日向に侵略されていることに、まだ気が付いていなかった。
「どうもです、先輩」
4時間目の授業が終了し昼休憩が始まってすぐに、小日向は俺の教室に現れた。
上級生の教室に堂々と入ってくる小日向にクラスの奴らは皆、驚いていた。無論俺もだ。
一方、小日向本人はそんな先輩方の視線を一身に受けながら、いつもの涼しい表情で俺の元へ一直線にやってきた。
「こ、小日向。どうした一体?」
「お昼を一緒に食べましょう、先輩」
そう言う小日向の手には可愛らしい柄の布に包まれた、小さなお弁当箱が握られていた。
突然の小日向来襲後、俺は自分の弁当を持って小日向の後ろに付いていった。そして辿り着いたのいつもの屋上ではなく、校舎の隅にある倉庫の裏だった。
外履きに履き替え、校舎と倉庫に挟まれた小さなスペースに、俺達は腰を降ろす。下がコンクリートだったのが若干気になったが、小日向は全く気にせずに座ったので俺もそれに倣った。
「で、何で倉庫の裏なんだ?」
「……昼休みの屋上は人気なので」
確かに毎日俺達が使っている放課後の屋上と違って、昼休みの屋上はカップルの溜まり場だ。元々人ごみが嫌いなイメージのある小日向には、行きづらい場所だろう。
一方、今いるここは完全に校舎から死角になっており、人もほとんど寄り付かないだろう。
「ここなら人がいないです」
弁当の包みを広げながら小日向は言った。
「先輩と二人っきりで、色んなことができるです」
「ふ、二人っきり……」
小日向の言い回しにちょっとドキってしてしまう。
「まずはご飯です」
弁当箱の蓋を開け、箸を取り出すと小日向は言った。俺もそれに倣い、弁当箱を開ける。
「あ、先輩。ちょっと待って下さい」
「え?」
早速飯にありつこうとした俺を制止すると、小日向はいきなり靴を脱ぎだした。
学校指定の革靴が小日向の足から外れ、紺色の靴下に包まれた足が、熱気を帯びて露わになる。
「どうぞです。先輩」
「え? どういうことだ?」
「……先輩のオカズです」
眉をほんのちょっとだけ不快そうに歪めながら、小日向は履いていた革靴を差し出した。
「今日から先輩は毎日私とお昼を食べるです……私の足の匂いを嗅ぎながら」
「……ッ」
さすがの俺も戦慄した。食事の時にあの匂いを嗅がせるなんて、予想もしなかった。
いくら小日向の体臭中毒者ともいえる俺でも、さすがに口に食べ物を含んでる時にきついあの匂いを嗅ぐのは……
「どっちですか?」
しかし有無を言わせず小日向は靴を差し出してくる。所詮俺は小日向の奴隷。拒否権など無いのだ。
「で、でもどうやってそれを嗅ぎながら飯を食うんだ? 弁当と箸を持ったら、両手が塞がっちゃって、靴を持てないぜ」
「それは大丈夫です。少し手間がかかりますが……」
そう言った瞬間、小日向は懐から紙テープを取り出した。
「これで靴を先輩の顔に直接くっつけるです」
「…………」
ふふん、と得意げな感じの小日向だったが、正直俺はどうにも釈然としなかった。しかしそれと同時に、未だ味わったことの無い小日向の革靴に興奮し、ズボンにテントが張り始めたのも事実だった。
「いきますよ、先輩」
小日向はそう言うと脱いだ革靴を掴むとそれを俺の鼻に押し当て、一気にテープで固定する。
「んがっ!」
鼻を突くような激臭が俺を襲う。履きならしているというだけあって、かなり蒸れており強烈な臭気を放っている。
よく嗅いでいる上靴の臭いに革独特の臭いを足したかのような香り。俺にはたまらない代物だった。
「……目、とろんとしてるですよ。先輩」
冷ややかな小日向の一言で我に返る。しかしすぐに彼女の香りに心を奪われてしまう。
「早く食べないと、休み時間終わっちゃうですよ」
いつの間にか食事を始めていた小日向は、冷ややかにそう言った。だが俺は小日向の靴に夢中になり始めていた。
しかし小日向は許さなかった。
「先輩、命令です。さっさと食べて下さい」
『命令』とあれば絶対従わなければならない。俺は懸命に理性を呼び起こし、弁当と箸を持った。
そして彼女の靴の香りと共に、無言で昼食を口に入れてゆく。
「よく噛んで食べないとダメですよ」
小日向に注意されるも、小日向の靴を嗅ぎながら食事をとるという行為自体に俺は酔い始めていた。
普通ならこんな激臭を臭いながら食事なんて出来ないだろう。だがすでに彼女の虜となっている俺は、むしろこの動物的な香りによって食欲すら湧いてくる始末だ。
「美味しそうに食べますね、先輩」
小日向もそれに気付いたのか、若干うれしそうな声色で嘲笑する。
「私が言うのも何ですが、相当臭いと思うですよ」
もきゅもきゅとリスみたいに小日向は頬を膨らませ、弁当を咀嚼していた。そしてそれをごくりと飲み込むと、唇を少しだけ歪ませる。
「今日から毎日、先輩はその状態でご飯を食べるですよ。そうすればいつか……」
小日向が最後まで言い終わる前に俺は、弁当を口に詰め込んだ。
「……私の靴を嗅ぐだけで、お腹が空いちゃう体になっちゃうですよ」
淡々にそういう小日向だったが、俺はその可能性を否定できなかった。
表情をほとんど変えないまま、楽しそうな雰囲気を出す小日向。
俺はどんどん泥沼に沈んでいく感覚を、革靴の香りの余韻と共に浸っていった……
「はぁ……」
あの小日向の尋問から翌日。俺は憂鬱な面持ちで制服に着替えていた。
あの後、小日向の家から出てすぐに自宅に帰ったが、思い出すのは小日向の足臭と部屋の香り。
その日はずっとそのことで頭がいっぱいだった。そして今日もその事が頭から離れなかった。
「ああ、小日向……」
人間離れした美貌を持つ彼女のことを想いながら、俺は上の空で玄関を開けた。
「おはようございます。先輩」
「ファッ!?」
玄関の先には、学生鞄を抱えた後輩が立っていた。
白くて健康的な肌。小動物を思わせる可愛らしい容姿に小っちゃい肢体。間違いなく小日向凪その人だった。
「な、なんでここに小日向が?」
「昨日、先輩から聞いた住所を頼りに来たです」
ちょっと得意げに胸を張る小日向。その仕草に少しだけ可愛いと思ってしまった。
「今日から一緒に登下校するですよ、先輩」
「え、あ、ああ……」
「……嫌ですか?」
上目使いで俺の腕を掴む小日向。相変わらず顔は無表情だが、胸に来るような可憐さがそこにはあった。
「い、いや、嫌じゃないけど何でいきなりなんだろうってさ」
「……先輩を管理するためです」
そう言うと小日向は俺の腕を引っ張って歩き出した。
「こ、小日向! 早いって!」
俺の言葉を無視し、どんどん速度を速める小日向。俺は戸惑いながらも、これはこれでいいなと思って素直に付いていった。
この時、俺は日常生活までどんどん小日向に侵略されていることに、まだ気が付いていなかった。
「どうもです、先輩」
4時間目の授業が終了し昼休憩が始まってすぐに、小日向は俺の教室に現れた。
上級生の教室に堂々と入ってくる小日向にクラスの奴らは皆、驚いていた。無論俺もだ。
一方、小日向本人はそんな先輩方の視線を一身に受けながら、いつもの涼しい表情で俺の元へ一直線にやってきた。
「こ、小日向。どうした一体?」
「お昼を一緒に食べましょう、先輩」
そう言う小日向の手には可愛らしい柄の布に包まれた、小さなお弁当箱が握られていた。
突然の小日向来襲後、俺は自分の弁当を持って小日向の後ろに付いていった。そして辿り着いたのいつもの屋上ではなく、校舎の隅にある倉庫の裏だった。
外履きに履き替え、校舎と倉庫に挟まれた小さなスペースに、俺達は腰を降ろす。下がコンクリートだったのが若干気になったが、小日向は全く気にせずに座ったので俺もそれに倣った。
「で、何で倉庫の裏なんだ?」
「……昼休みの屋上は人気なので」
確かに毎日俺達が使っている放課後の屋上と違って、昼休みの屋上はカップルの溜まり場だ。元々人ごみが嫌いなイメージのある小日向には、行きづらい場所だろう。
一方、今いるここは完全に校舎から死角になっており、人もほとんど寄り付かないだろう。
「ここなら人がいないです」
弁当の包みを広げながら小日向は言った。
「先輩と二人っきりで、色んなことができるです」
「ふ、二人っきり……」
小日向の言い回しにちょっとドキってしてしまう。
「まずはご飯です」
弁当箱の蓋を開け、箸を取り出すと小日向は言った。俺もそれに倣い、弁当箱を開ける。
「あ、先輩。ちょっと待って下さい」
「え?」
早速飯にありつこうとした俺を制止すると、小日向はいきなり靴を脱ぎだした。
学校指定の革靴が小日向の足から外れ、紺色の靴下に包まれた足が、熱気を帯びて露わになる。
「どうぞです。先輩」
「え? どういうことだ?」
「……先輩のオカズです」
眉をほんのちょっとだけ不快そうに歪めながら、小日向は履いていた革靴を差し出した。
「今日から先輩は毎日私とお昼を食べるです……私の足の匂いを嗅ぎながら」
「……ッ」
さすがの俺も戦慄した。食事の時にあの匂いを嗅がせるなんて、予想もしなかった。
いくら小日向の体臭中毒者ともいえる俺でも、さすがに口に食べ物を含んでる時にきついあの匂いを嗅ぐのは……
「どっちですか?」
しかし有無を言わせず小日向は靴を差し出してくる。所詮俺は小日向の奴隷。拒否権など無いのだ。
「で、でもどうやってそれを嗅ぎながら飯を食うんだ? 弁当と箸を持ったら、両手が塞がっちゃって、靴を持てないぜ」
「それは大丈夫です。少し手間がかかりますが……」
そう言った瞬間、小日向は懐から紙テープを取り出した。
「これで靴を先輩の顔に直接くっつけるです」
「…………」
ふふん、と得意げな感じの小日向だったが、正直俺はどうにも釈然としなかった。しかしそれと同時に、未だ味わったことの無い小日向の革靴に興奮し、ズボンにテントが張り始めたのも事実だった。
「いきますよ、先輩」
小日向はそう言うと脱いだ革靴を掴むとそれを俺の鼻に押し当て、一気にテープで固定する。
「んがっ!」
鼻を突くような激臭が俺を襲う。履きならしているというだけあって、かなり蒸れており強烈な臭気を放っている。
よく嗅いでいる上靴の臭いに革独特の臭いを足したかのような香り。俺にはたまらない代物だった。
「……目、とろんとしてるですよ。先輩」
冷ややかな小日向の一言で我に返る。しかしすぐに彼女の香りに心を奪われてしまう。
「早く食べないと、休み時間終わっちゃうですよ」
いつの間にか食事を始めていた小日向は、冷ややかにそう言った。だが俺は小日向の靴に夢中になり始めていた。
しかし小日向は許さなかった。
「先輩、命令です。さっさと食べて下さい」
『命令』とあれば絶対従わなければならない。俺は懸命に理性を呼び起こし、弁当と箸を持った。
そして彼女の靴の香りと共に、無言で昼食を口に入れてゆく。
「よく噛んで食べないとダメですよ」
小日向に注意されるも、小日向の靴を嗅ぎながら食事をとるという行為自体に俺は酔い始めていた。
普通ならこんな激臭を臭いながら食事なんて出来ないだろう。だがすでに彼女の虜となっている俺は、むしろこの動物的な香りによって食欲すら湧いてくる始末だ。
「美味しそうに食べますね、先輩」
小日向もそれに気付いたのか、若干うれしそうな声色で嘲笑する。
「私が言うのも何ですが、相当臭いと思うですよ」
もきゅもきゅとリスみたいに小日向は頬を膨らませ、弁当を咀嚼していた。そしてそれをごくりと飲み込むと、唇を少しだけ歪ませる。
「今日から毎日、先輩はその状態でご飯を食べるですよ。そうすればいつか……」
小日向が最後まで言い終わる前に俺は、弁当を口に詰め込んだ。
「……私の靴を嗅ぐだけで、お腹が空いちゃう体になっちゃうですよ」
淡々にそういう小日向だったが、俺はその可能性を否定できなかった。
表情をほとんど変えないまま、楽しそうな雰囲気を出す小日向。
俺はどんどん泥沼に沈んでいく感覚を、革靴の香りの余韻と共に浸っていった……
奴隷先輩の放置プレイ
誤字脱字があったらすいません
「どうしたの、省吾。全然、食べてないじゃない」
夜の食卓で母さんが呆れたように言った。その眼下には三分の二ほど残っている夕食があった。
「ごめん、何だか食欲なくってよ」
俺はそう言って早々と席を立つと、そそくさと自室に籠った。そしてそのままベッドに倒れこむ。
小日向との昼食が始まってから二週間近くが経過していた。その間俺は毎日、小日向の靴を嗅ぎながら弁当を食べた。
最初はそのどぎつい臭いに戸惑いつつも満更でも無い感じだったのだが、今では小日向の靴無しでは食欲が湧かないようにまでなっていた。
それに最近は登下校もずっと小日向と一緒だ。そのこと自体はとても嬉しいのだが、段々と日常生活全てを小日向に侵略されているようでたまにゾっとすることもある。
放課後の調教も続いている。あいかわらず俺は小日向の香りを嗅ぎながら放置され、小日向は読書をしているだけだ。だがもはやこの時間は俺にとって無くてはならない日常となっていた。
俺はそんな事を考えながら、日課になっている小日向の上履き嗅ぎをするために、机の下に隠していた小日向の上履きを手に取った。
「先輩、今週の土日は暇ですか?」
それはいつもの調教が終わってから、唐突に小日向の口から放たれた言葉だった。
「え?」
俺はいきなり投げかけられた台詞に少なからず動揺した。今まで小日向と土日に会ったことは無かった。だからこそ、小日向の発言にびっくりしたのだ。
「……今週の土日は学校も休みです。だから」
そのまま上目使いで小日向は尋ねた。
「私の家で、遊びませんか?」
無表情ながらもどこか期待するような小日向の佇まいは、俺の心を掴むのに十分な破壊力があった。
日が落ちかける屋上で、俺は無言で首を縦に振ったのだった。
そしてあっという間に土曜日がやってきた。
休日に小日向に会うという初めてのビックイベントということで、出来るだけ見た目に気を付ける。
何せわざわざ前日に私服を新調したのだ。無難なデザインのシャツとジーンズ。一応、下着も新品のモノを着用した。
勿論髪型も念入りにチェックだ。もしかしたら今日で小日向との距離が一気に縮まるかもしれない。そう思いシャワーも浴びた。
体の隅々まできっちりと清潔かどうか確認し、俺は高鳴る胸を感じながら家を出たのであった。
午前11時に小日向の家に集合。それが彼女との約束だった。
事前に小日向に電話して行くことを伝えてから小日向邸に向かう。約束を快諾した後、小日向は両親がその日は家にいないということを告げた。
やっぱり誘ってるとしか思えない。そう思いながら、俺は期待に胸を膨らませ、ドアホンを押したのだった。
「おはようです。先輩」
「お、おお……」
玄関のドアを開いて現れた小日向に、俺は息を呑んだ。
それは初めて見る小日向の私服だった。
上は半袖の白いTシャツ一枚、下はラフなデザインのホットパンツというシンプル且つ露出度の多い服装だった。
完全に部屋着といった印象で、大胆に露出した白く細い腕と生足が艶めかしい。
新鮮な彼女の姿に、俺は暫くフリーズした。
「えいっ」
「はっ!」
小日向の眉間チョップで俺は意識を取り戻す。最近、こんなことばっかだな。
「ぽーっとしてちゃダメですよ、先輩。さっさと入ってください」
「あ、ああ……お邪魔します……」
彼女に先導さえれて、家に入る。小日向に持ってきたお土産(母さんに持たされた菓子)を渡すと、小日向は彼女の部屋に行くように支持した。
一度来ているので多少は間取りが分かる。とりあえず記憶をたどって2階に向かい、『NAGI』と書かれたネームプレートのかかった部屋のドアを開ける。
床に置いてあるクッションに腰を降ろし、暫くほのかに香る小日向の匂いを堪能していると、麦茶の入ったコップを2つ持って、小日向が部屋に入ってきた。
茶を飲んで一息つくと小日向は俺真っ直ぐに見ていった。
「さてと、先輩。今日はここでたっぷりと遊ぶですよ」
「お、おう」
……まあ、小日向と二人っきりの時点でこうなることはわかっていたから、俺もそんなに驚かない。
ちょっとだけ彼女との甘い時間なんて妄想したが、しょうがない。それに小日向の調教も俺にとっては他には得難い時間でもある。
「では先輩、ここに座ってください」
小日向がそう言って指を指した先には、小さな椅子が1つあった。四足で背もたれ付きの何処にでもありそうなデザインの椅子だ。
「わかった」
とりあえず小日向の命に従い、腰を降ろす。すると小日向は懐からガムテープを取り出した。
「じっとしてて下さいね」
そう言うと小日向は俺の両腕を椅子の後ろにグルグル巻きで固定する。さらに足を開かせ、左右の椅子の足に縛り付ける。
完全に椅子に縛り付けられてしまった。あまりにきっちり縛られてしまったため、身動きが全く取れない状態になってしまう。
「どうです? 動けないですよ?」
ちょっと得意げに聞いてくる小日向。だが当の俺は今まで無かったシチュレーションに少し困惑してしまっていた。
「ちょっと待っててください」
そう言うと小日向は一度部屋から出て、一階に降りた。少し間を置いて戻ってきた彼女の手には俺にとって見慣れたモノが握られていた。
「小日向……それっ!」
「はい。先輩の大好きな一日中履いたパンツと靴下です」
それを見せつけるように目の前に差し出す。そのせいで早くも俺は勃起してしまう。
「……勃起してますね」
「あ、うん……」
「これを見ただけでおちんちんをおっきくしちゃうなんて、先輩は本当に変態さんですね」
愉快そうに嘲笑する小日向、一方俺は全く反論できないでいた。
「では、いくですよ。じっとしててくださいね」
小日向はそのまま靴下を丸めると、俺の鼻を摘まんで口を強引に開けさせると、二足の靴下を無理やり俺の口に突っ込んだ。
「むがっ……」
熟成された汗の香りが鼻を突き、同時に布の何とも言えない触感と、香ばしい味が口いっぱいに広がった。
「お味はどうですか?」
小首を傾げ可愛らしく尋ねる小日向。いつもの感情が欠落したような顔であったが、どこか馬鹿にされているような気はした。
だがすでにこの香りや感触に慣れてしまっている俺にとって、この行為はより興奮するだけであった。
「……次はこれですよ」
小日向はそう言って次にパンツを取り出した。
純白の生地のシンプルなパンティーだった。余りにも飾り気のないその外観は、確かに小日向らしい下着であった。
「見て下さい」
そう言うと小日向は両手でパンツを広げ、中身を見せるように掲げた。
純白のパンツ、しかし性器とダイレクトに触れている部分は黄色と茶色が混ざったような色彩で、変色していた。
「今日はこれを嗅いでもらうです」
「……!」
今まで小日向のパンツを嗅ぐことはあった。しかしその時は顔面騎乗の時であり、臭うのはパンツの外側であり、それにどちらかというと尻の匂いを嗅いでいる感じだった。
しかし今回はパンツの中身。しかもよく熟成された使用済み……すでに幾度とない調教ですっかり小日向の匂いフェチになってしまった俺にとって、それはとても魅力的なものに見えた。
「どうぞです」
俺が彼女の下着に見惚れていると、小日向はそのまま下着を俺の顔に被せてきた。
「むぐう!」
ちょうど鼻の部分が汚れている部分がぴったりとくっつけるように、俺の頭に被せてきた。
現在俺は口を小日向の靴下で塞がれているため、鼻で呼吸するしかない。
だが、鼻の部分は小日向のパンティーに密着している。つまり呼吸のたびに俺はこの小日向の下着及びそれに付着した汚れの匂いを嗅がなくてはならない。
つまり呼吸するたびに小日向の局部の香りがダイレクトに伝わってくるのだ。
今の俺にとって、これ以上のご褒美は無かった。
「……嬉しそうですね、先輩」
そう言う小日向も嬉しそうに頬を緩める。そのまま小日向は真っ赤になった俺の顔を暫し眺めた後、学生鞄から本を取りだしベッドに腰掛けた。
「じゃあ大人しくしててくださいね、先輩」
それだけ言うと、小日向はベッドに寝っころがって、読書を開始した。
顔も完全にそっぽを向いており、俺のことなど眼中に無いようだ。
それでも俺はよかった。放置されることなどいつものことだ。このまま小日向に解放されるまで、じっくりとこの耽美な萌芽を楽しむとしよう……
……
…………
………………
……既に一時間近くが経とうとしていた。
ずっと下着の一番汚れた部分を臭い続けているからか、未だに俺の息子は怒張しっぱなしである。
さすがにそろそろ貧血になってしまいそうだったが、ある意味ずっとこの状態を維持できるのは、それだけ小日向に入れ込んでいる証でもあろう。
しかし、いつも以上の放置プレイはちょっと……小日向は俺の方など全く見ずに、読書に没頭していた。
……椅子に固定されてから二時間の時が流れた。
未だに我が愚息は臨戦態勢だ。そしてそれからくる血の巡りの悪さによって、頭がぼーっとしてきた。
しかしそれと同時に尿意がむくむくと腹の下あたりから湧き上がってきていた。
カラカラになった喉から何とか声を絞り出し、小日向に救いを乞う。だが小日向は、ずっと文庫本に目を落としたままだった。
遂に三時間が経過しようとしていた。
もう勃起も尿意も限界だ。体中から汗が滝のように流れてゆく。
パンパンに膨らんだ風船のように膀胱は破裂しそうになっている。さらに長きにわたる勃起のせいで、意識も朦朧と仕掛けている。
俺は何度も唸り声をあげ、体を動かして小日向に訴えたが、彼女はずっと無視していた。
「んーっ! んーっ!」
俺は必死になってアピールしたが、小日向は足をパタパタさせながら読書の虫だ。
「んーっ! んんんーっ!」
「……うるさいですね」
さすがに無視できなくなったのか、めんどくさそうに小日向は立ち上がった。
「読書の邪魔ですよ、先輩」
そう告げる小日向の視線は氷のように冷たかった。
ようやくこっちを向いてくれた小日向に対し、俺は必死に今の窮状を訴える。
「苦しそうですね、一体どうしたんですか?」
「んんーっ! んんん!」
「……何を言ってるかわかりませんよ」
そこで小日向はニヤリと意地悪げに唇の端を吊り上げた。
それで俺は悟った。小日向は俺がこうなることを知っていて、ここに拘束したのだ。
「んんんんんんんんんんんんんんんんんんっ!」
遂に俺は限界を迎えた。
昨日買ったばかりのジーンズの股の部分が黒く染まっていき、ダムの堰を切ったように尿が溢れ出す。
一度溢れてしまったものはもう戻すことは出来ない。
好きな女の子の前で失禁してしまったという現実に羞恥心で体が熱くなってゆく。それと同時に排尿の解放感と、言いようの無い興奮が体を突き抜けていった。
「……お漏らしなんて恥ずかしいですね、先輩」
小日向の容赦ない言葉にも心が抉られる。
「ほんと、最低です」
「――ッ!」
その瞬間、体がピンと張ったのと同時に、溜まっていた精液が一気に噴出した。
いままでに味わったことの無いような凄まじい快感に襲われ、意識が持って行かれそうになる。
やがて体中から力が抜けていき、徐々に湿りきった股の部分が気持ち悪く感じてくる。
「カーペット、洗わなきゃいけませんね」
そう言うと小日向は俺の拘束を解き始めた。
「う、ううう……」
一方、あまりの情けなさに俺は涙を溢れさせていた。そんな俺の顎を掴んで、上に向けると小日向は耳元で囁いた。
「こんなことで興奮しちゃう先輩は、本当に変態さんです」
「あ、ああ……」
「そんな、先輩にはこれからもっと恥ずかしい事が待っているですよ」
小日向の冷酷な宣言。しかし俺はそれにすら、興奮し始めていた。
小日向家での調教は、まだ始まったばかりであった……
誤字脱字があったらすいません
「どうしたの、省吾。全然、食べてないじゃない」
夜の食卓で母さんが呆れたように言った。その眼下には三分の二ほど残っている夕食があった。
「ごめん、何だか食欲なくってよ」
俺はそう言って早々と席を立つと、そそくさと自室に籠った。そしてそのままベッドに倒れこむ。
小日向との昼食が始まってから二週間近くが経過していた。その間俺は毎日、小日向の靴を嗅ぎながら弁当を食べた。
最初はそのどぎつい臭いに戸惑いつつも満更でも無い感じだったのだが、今では小日向の靴無しでは食欲が湧かないようにまでなっていた。
それに最近は登下校もずっと小日向と一緒だ。そのこと自体はとても嬉しいのだが、段々と日常生活全てを小日向に侵略されているようでたまにゾっとすることもある。
放課後の調教も続いている。あいかわらず俺は小日向の香りを嗅ぎながら放置され、小日向は読書をしているだけだ。だがもはやこの時間は俺にとって無くてはならない日常となっていた。
俺はそんな事を考えながら、日課になっている小日向の上履き嗅ぎをするために、机の下に隠していた小日向の上履きを手に取った。
「先輩、今週の土日は暇ですか?」
それはいつもの調教が終わってから、唐突に小日向の口から放たれた言葉だった。
「え?」
俺はいきなり投げかけられた台詞に少なからず動揺した。今まで小日向と土日に会ったことは無かった。だからこそ、小日向の発言にびっくりしたのだ。
「……今週の土日は学校も休みです。だから」
そのまま上目使いで小日向は尋ねた。
「私の家で、遊びませんか?」
無表情ながらもどこか期待するような小日向の佇まいは、俺の心を掴むのに十分な破壊力があった。
日が落ちかける屋上で、俺は無言で首を縦に振ったのだった。
そしてあっという間に土曜日がやってきた。
休日に小日向に会うという初めてのビックイベントということで、出来るだけ見た目に気を付ける。
何せわざわざ前日に私服を新調したのだ。無難なデザインのシャツとジーンズ。一応、下着も新品のモノを着用した。
勿論髪型も念入りにチェックだ。もしかしたら今日で小日向との距離が一気に縮まるかもしれない。そう思いシャワーも浴びた。
体の隅々まできっちりと清潔かどうか確認し、俺は高鳴る胸を感じながら家を出たのであった。
午前11時に小日向の家に集合。それが彼女との約束だった。
事前に小日向に電話して行くことを伝えてから小日向邸に向かう。約束を快諾した後、小日向は両親がその日は家にいないということを告げた。
やっぱり誘ってるとしか思えない。そう思いながら、俺は期待に胸を膨らませ、ドアホンを押したのだった。
「おはようです。先輩」
「お、おお……」
玄関のドアを開いて現れた小日向に、俺は息を呑んだ。
それは初めて見る小日向の私服だった。
上は半袖の白いTシャツ一枚、下はラフなデザインのホットパンツというシンプル且つ露出度の多い服装だった。
完全に部屋着といった印象で、大胆に露出した白く細い腕と生足が艶めかしい。
新鮮な彼女の姿に、俺は暫くフリーズした。
「えいっ」
「はっ!」
小日向の眉間チョップで俺は意識を取り戻す。最近、こんなことばっかだな。
「ぽーっとしてちゃダメですよ、先輩。さっさと入ってください」
「あ、ああ……お邪魔します……」
彼女に先導さえれて、家に入る。小日向に持ってきたお土産(母さんに持たされた菓子)を渡すと、小日向は彼女の部屋に行くように支持した。
一度来ているので多少は間取りが分かる。とりあえず記憶をたどって2階に向かい、『NAGI』と書かれたネームプレートのかかった部屋のドアを開ける。
床に置いてあるクッションに腰を降ろし、暫くほのかに香る小日向の匂いを堪能していると、麦茶の入ったコップを2つ持って、小日向が部屋に入ってきた。
茶を飲んで一息つくと小日向は俺真っ直ぐに見ていった。
「さてと、先輩。今日はここでたっぷりと遊ぶですよ」
「お、おう」
……まあ、小日向と二人っきりの時点でこうなることはわかっていたから、俺もそんなに驚かない。
ちょっとだけ彼女との甘い時間なんて妄想したが、しょうがない。それに小日向の調教も俺にとっては他には得難い時間でもある。
「では先輩、ここに座ってください」
小日向がそう言って指を指した先には、小さな椅子が1つあった。四足で背もたれ付きの何処にでもありそうなデザインの椅子だ。
「わかった」
とりあえず小日向の命に従い、腰を降ろす。すると小日向は懐からガムテープを取り出した。
「じっとしてて下さいね」
そう言うと小日向は俺の両腕を椅子の後ろにグルグル巻きで固定する。さらに足を開かせ、左右の椅子の足に縛り付ける。
完全に椅子に縛り付けられてしまった。あまりにきっちり縛られてしまったため、身動きが全く取れない状態になってしまう。
「どうです? 動けないですよ?」
ちょっと得意げに聞いてくる小日向。だが当の俺は今まで無かったシチュレーションに少し困惑してしまっていた。
「ちょっと待っててください」
そう言うと小日向は一度部屋から出て、一階に降りた。少し間を置いて戻ってきた彼女の手には俺にとって見慣れたモノが握られていた。
「小日向……それっ!」
「はい。先輩の大好きな一日中履いたパンツと靴下です」
それを見せつけるように目の前に差し出す。そのせいで早くも俺は勃起してしまう。
「……勃起してますね」
「あ、うん……」
「これを見ただけでおちんちんをおっきくしちゃうなんて、先輩は本当に変態さんですね」
愉快そうに嘲笑する小日向、一方俺は全く反論できないでいた。
「では、いくですよ。じっとしててくださいね」
小日向はそのまま靴下を丸めると、俺の鼻を摘まんで口を強引に開けさせると、二足の靴下を無理やり俺の口に突っ込んだ。
「むがっ……」
熟成された汗の香りが鼻を突き、同時に布の何とも言えない触感と、香ばしい味が口いっぱいに広がった。
「お味はどうですか?」
小首を傾げ可愛らしく尋ねる小日向。いつもの感情が欠落したような顔であったが、どこか馬鹿にされているような気はした。
だがすでにこの香りや感触に慣れてしまっている俺にとって、この行為はより興奮するだけであった。
「……次はこれですよ」
小日向はそう言って次にパンツを取り出した。
純白の生地のシンプルなパンティーだった。余りにも飾り気のないその外観は、確かに小日向らしい下着であった。
「見て下さい」
そう言うと小日向は両手でパンツを広げ、中身を見せるように掲げた。
純白のパンツ、しかし性器とダイレクトに触れている部分は黄色と茶色が混ざったような色彩で、変色していた。
「今日はこれを嗅いでもらうです」
「……!」
今まで小日向のパンツを嗅ぐことはあった。しかしその時は顔面騎乗の時であり、臭うのはパンツの外側であり、それにどちらかというと尻の匂いを嗅いでいる感じだった。
しかし今回はパンツの中身。しかもよく熟成された使用済み……すでに幾度とない調教ですっかり小日向の匂いフェチになってしまった俺にとって、それはとても魅力的なものに見えた。
「どうぞです」
俺が彼女の下着に見惚れていると、小日向はそのまま下着を俺の顔に被せてきた。
「むぐう!」
ちょうど鼻の部分が汚れている部分がぴったりとくっつけるように、俺の頭に被せてきた。
現在俺は口を小日向の靴下で塞がれているため、鼻で呼吸するしかない。
だが、鼻の部分は小日向のパンティーに密着している。つまり呼吸のたびに俺はこの小日向の下着及びそれに付着した汚れの匂いを嗅がなくてはならない。
つまり呼吸するたびに小日向の局部の香りがダイレクトに伝わってくるのだ。
今の俺にとって、これ以上のご褒美は無かった。
「……嬉しそうですね、先輩」
そう言う小日向も嬉しそうに頬を緩める。そのまま小日向は真っ赤になった俺の顔を暫し眺めた後、学生鞄から本を取りだしベッドに腰掛けた。
「じゃあ大人しくしててくださいね、先輩」
それだけ言うと、小日向はベッドに寝っころがって、読書を開始した。
顔も完全にそっぽを向いており、俺のことなど眼中に無いようだ。
それでも俺はよかった。放置されることなどいつものことだ。このまま小日向に解放されるまで、じっくりとこの耽美な萌芽を楽しむとしよう……
……
…………
………………
……既に一時間近くが経とうとしていた。
ずっと下着の一番汚れた部分を臭い続けているからか、未だに俺の息子は怒張しっぱなしである。
さすがにそろそろ貧血になってしまいそうだったが、ある意味ずっとこの状態を維持できるのは、それだけ小日向に入れ込んでいる証でもあろう。
しかし、いつも以上の放置プレイはちょっと……小日向は俺の方など全く見ずに、読書に没頭していた。
……椅子に固定されてから二時間の時が流れた。
未だに我が愚息は臨戦態勢だ。そしてそれからくる血の巡りの悪さによって、頭がぼーっとしてきた。
しかしそれと同時に尿意がむくむくと腹の下あたりから湧き上がってきていた。
カラカラになった喉から何とか声を絞り出し、小日向に救いを乞う。だが小日向は、ずっと文庫本に目を落としたままだった。
遂に三時間が経過しようとしていた。
もう勃起も尿意も限界だ。体中から汗が滝のように流れてゆく。
パンパンに膨らんだ風船のように膀胱は破裂しそうになっている。さらに長きにわたる勃起のせいで、意識も朦朧と仕掛けている。
俺は何度も唸り声をあげ、体を動かして小日向に訴えたが、彼女はずっと無視していた。
「んーっ! んーっ!」
俺は必死になってアピールしたが、小日向は足をパタパタさせながら読書の虫だ。
「んーっ! んんんーっ!」
「……うるさいですね」
さすがに無視できなくなったのか、めんどくさそうに小日向は立ち上がった。
「読書の邪魔ですよ、先輩」
そう告げる小日向の視線は氷のように冷たかった。
ようやくこっちを向いてくれた小日向に対し、俺は必死に今の窮状を訴える。
「苦しそうですね、一体どうしたんですか?」
「んんーっ! んんん!」
「……何を言ってるかわかりませんよ」
そこで小日向はニヤリと意地悪げに唇の端を吊り上げた。
それで俺は悟った。小日向は俺がこうなることを知っていて、ここに拘束したのだ。
「んんんんんんんんんんんんんんんんんんっ!」
遂に俺は限界を迎えた。
昨日買ったばかりのジーンズの股の部分が黒く染まっていき、ダムの堰を切ったように尿が溢れ出す。
一度溢れてしまったものはもう戻すことは出来ない。
好きな女の子の前で失禁してしまったという現実に羞恥心で体が熱くなってゆく。それと同時に排尿の解放感と、言いようの無い興奮が体を突き抜けていった。
「……お漏らしなんて恥ずかしいですね、先輩」
小日向の容赦ない言葉にも心が抉られる。
「ほんと、最低です」
「――ッ!」
その瞬間、体がピンと張ったのと同時に、溜まっていた精液が一気に噴出した。
いままでに味わったことの無いような凄まじい快感に襲われ、意識が持って行かれそうになる。
やがて体中から力が抜けていき、徐々に湿りきった股の部分が気持ち悪く感じてくる。
「カーペット、洗わなきゃいけませんね」
そう言うと小日向は俺の拘束を解き始めた。
「う、ううう……」
一方、あまりの情けなさに俺は涙を溢れさせていた。そんな俺の顎を掴んで、上に向けると小日向は耳元で囁いた。
「こんなことで興奮しちゃう先輩は、本当に変態さんです」
「あ、ああ……」
「そんな、先輩にはこれからもっと恥ずかしい事が待っているですよ」
小日向の冷酷な宣言。しかし俺はそれにすら、興奮し始めていた。
小日向家での調教は、まだ始まったばかりであった……
奴隷先輩の入浴タイム
「これでよし、です」
洗濯機のスイッチを押すと、ぱんぱんと小日向は手を叩いた。
音を立てて起動する洗濯機の中には、小便で汚れてしまった俺の衣服が入っていた。
好きな後輩の自室で、その子を目の前にしながら失禁&射精という情けないにも程がある醜態を晒した俺に対し、小日向はまず脱衣を命じた。
汚れてしまったズボンと下着と靴下を脱ぐと、次にカーペットをどかし、床にこぼれた小便を雑巾(俺の上着)で拭くことを命令された。
そして汚れを全て拭き取ると、小日向は汚物まみれとなった俺の衣服を没収し、軽く風呂場で汚れを流した後、洗濯機に放り込んだのであった。
ちなみにカーペットは風呂場で俺が洗わされた。雑巾で汚れを吸い取った後に水で流し、外に干した。
その後、着る服など用意されていない俺は全裸のまま脱衣場の床に正座していた。
「それにしても、酷い恰好ですね」
小日向は作り物めいた無表情さで俺を見下ろしながら、俺の額を小突いた。
「人の家でこんな恰好するなんて、恥ずかしくないんですか?」
「う、うう……」
「しかもお漏らしまで……先輩は本当に高校生ですか?」
「う、うあ……」
小日向に嵌められたとはいえ、後輩の部屋で失禁した挙句、彼女に衣服を洗ってもらっていることは事実なので、俺はあまりにも情けなくて、マジ泣き一歩手前まで追い込まれる。
「……そう泣かないでください」
小日向は先程の鉄面皮から少しだけ頬を緩めると、まるで赤子をあやすかのように、俺の頭を撫でた。
「服の次は体を綺麗にしますよ」
「ふえ?」
俺が聞き返すと、小日向はニコッと笑うと、風呂場の入り口を開いた。
「先に入って待ってて下さい。勝手にお湯に浸かっちゃ駄目ですよ」
そう言うと小日向は脱衣場から出ていった。一方、残された俺は喜びに体を震わせていた。
小日向と一緒にお風呂! 好きな女の子と一緒に入浴は、男なら一度は夢見るシチュレーションだろう。
今からそれが実現するかもしれないのである。男として興奮しないわけがあろうか。いや、ない。
そういえば小日向と今まで色んなプレイをしてきたが、彼女が服を脱いだ姿は見たことないなぁ……なんてことを考えながら、風呂場のタイルの上に座って待っていると、がちゃりと後ろのドアが開いた。
「……お待たせです」
「う、うおっ……」
はにかみながら現れた小日向の姿に、俺は釘づけとなった。
小日向は水着を着ていた。しかも紺色のスクール水着だ。
幼児体型の小日向にはとても似合っており、陶器のように白い手足が艶めかしかった。
「さ、綺麗にするですよ」
俺が小日向に見惚れていると、小日向はそれを察したように微笑しながら、そう言って俺を横に寝かした。
軽くシャワーで俺の全身を流し、小日向はボディーソープの容器を手に取る。そしてそのまま俺の体に中身を垂らした。
ぬるりと生暖かい液体が俺の体の上で広がってゆく。しかしそんな感触も束の間だった。
「えいっ」
可愛らしい掛け声と共に鬼日向の細く白いおみ足が、俺の体に振り下ろされたのである。
足の裏の柔らかい感触が俺の体の上で動かされ、下半身を蹂躙してゆく。
彼女の足が動くたびにボディーソープが泡立ち、くちゅくちゅという卑猥な音が聞こえてくる。
「小日向特製の、足たわしですよ、先輩」
ごしごしと足で俺の体を磨いていく小日向。一方小日向の足が前進を這う感覚に、俺はすっかり興奮してしまっていた。
「どうしたですか先輩。おちんちん、大きくなってるですよ」
俺の肉棒の変化に目敏く気付いた小日向が、意地悪げにそう指摘する。
「お漏らしした所は徹底的に洗わないと、駄目ですね」
ぐちゅっ! と小日向は泡だらけの足で勃起した肉棒を踏みにじる。
「臭くて汚いここは……念入りに、です」
「あ、あああああっ!」
足の指で玉を転がし、竿を足の裏で包み上下する。
泡と足の絶妙な柔らかさが、絶妙な快楽を与えてくれる。
「どんどん固くなっていくですよ。本当に節操が無いですね」
サディスティックな笑みを浮かべ、足に力を入れる小日向。俺はその蹂躙劇に身を任せるままであった。
そして、
「ッううううう!」
俺はまたしても絶頂を迎えてしまった。
「あらら、せっかく綺麗にしてるのにまたお漏らしちゃうなんて、先輩は本当に堪え性が無いですね」
溢れ出る精液で己を汚しながら痙攣する俺を見下ろしながら、小日向はシャワーを手に取った。
「一日に二回もお漏らしするなんて……先輩は赤ちゃんみたいですね」
「う、うう……」
「洗い流してあげますよ、先輩。ふふふ、感謝してくださいね」
適度に暖かい湯がかけられ、石鹸の泡と出したばかりの精液が流されてゆく。
その光景を見ながら何だか惨めに思えてくる。だが小日向の方はそれが嬉しいのか、はにかみながら俺を上から見下ろしている。
そういえば小日向って俺を責めている時、普段より饒舌になるような……
「えいっ」
「ぷっ! ぶわわっ! な、何するんだ!」
突然顔にお湯をかけられ、思わずびっくりしてしまう。
「何時まで呆けている気ですか?」
「あ、いや……」
小日向はそのまま俺の顔の目の前に腰を降ろした。
紺色の薄布に包まれた小日向の股が迫り、思わず俺は息を呑む。
「私の足を汚した罰ですよ……口を開けるです」
「え、え」
「先輩、早くあーんするです」
小日向の異様な迫力に押され、俺は有無を言わず口を開けた。
「んっ……」
すると小日向は艶めかしい吐息を吐いたと思うと、ぶるっと体を振るわす。
水着の股の部分が徐々に黒く染まってゆく。そこで俺は彼女の真意に気付いたが、既に遅かった。
じょろろろろろろ……
水着から溢れた小日向の聖水が俺の口に直接降り注ぐ。
ほのかに香る独特の臭いと、生暖かい小便が口内に溢れる。
一瞬俺はフリーズしてしまうが、小日向の尿だと思うと頭より先に体が動いた。
喉を鳴らしながら一滴も零さないように降り注ぐ小日向の小水を飲んでゆく。
「……先輩にとってはご褒美でしたか」
呆れたような小日向の声を聞きながら、俺はゴクゴクと小日向の小便を飲み干してゆく。
何とも言えない味が口の中いっぱいに広がってゆく。これが小日向の体から出た排泄物であると思うと、不思議と嫌悪感は湧かなかった。いやむしろそれを口にしているという事実に、堪らなく興奮してしまう。
「ふぅ……」
ぶるっと震えると小日向は最後の一滴を絞り出す。
「どうでした? 先輩? 私のおしっこの味は?」
顔を上気させながら俺を嘲笑うと小日向はそう尋ねた。
正直、絶妙にぬるくて苦くてしょっぱい味というあんまりおいしくない味であったが、小日向の聖水だと思うとその不味さも究極の甘露に思えてしまう。
「あ、ああ……」
その余韻に浸る俺を確認すると、小日向はクスッと笑い声を漏らした。
「恍惚の表情まで浮かべて……そんなにおいしかったですか?」
そのまま小日向は、小便でぐっちょりと濡れた股の部分を俺の顔の押し付けた。
「吸っていいですよ。私もこのまま濡れっぱなしじゃ嫌ですし」
「ッ……!」
俺はその言葉の意味を理解すると同時に、小便まみれになった小日向のスク水の股部分に口を付け、一気に水分を吸い上げた。
異臭を放つ紺色の布をチューチューと吸い、染みていた小水を残らないように搾り取る。
スク水独特の感触と小便の味が絶妙なハーモニーを奏で、俺から残された理性を刈り取ってゆく。
「必死で吸ってますね……ふふ、本当に惨めな姿です」
頭の中が小日向の尿に支配されていく中、俺は夢中で彼女の水着にしゃぶりついていた……
「これでよし、です」
洗濯機のスイッチを押すと、ぱんぱんと小日向は手を叩いた。
音を立てて起動する洗濯機の中には、小便で汚れてしまった俺の衣服が入っていた。
好きな後輩の自室で、その子を目の前にしながら失禁&射精という情けないにも程がある醜態を晒した俺に対し、小日向はまず脱衣を命じた。
汚れてしまったズボンと下着と靴下を脱ぐと、次にカーペットをどかし、床にこぼれた小便を雑巾(俺の上着)で拭くことを命令された。
そして汚れを全て拭き取ると、小日向は汚物まみれとなった俺の衣服を没収し、軽く風呂場で汚れを流した後、洗濯機に放り込んだのであった。
ちなみにカーペットは風呂場で俺が洗わされた。雑巾で汚れを吸い取った後に水で流し、外に干した。
その後、着る服など用意されていない俺は全裸のまま脱衣場の床に正座していた。
「それにしても、酷い恰好ですね」
小日向は作り物めいた無表情さで俺を見下ろしながら、俺の額を小突いた。
「人の家でこんな恰好するなんて、恥ずかしくないんですか?」
「う、うう……」
「しかもお漏らしまで……先輩は本当に高校生ですか?」
「う、うあ……」
小日向に嵌められたとはいえ、後輩の部屋で失禁した挙句、彼女に衣服を洗ってもらっていることは事実なので、俺はあまりにも情けなくて、マジ泣き一歩手前まで追い込まれる。
「……そう泣かないでください」
小日向は先程の鉄面皮から少しだけ頬を緩めると、まるで赤子をあやすかのように、俺の頭を撫でた。
「服の次は体を綺麗にしますよ」
「ふえ?」
俺が聞き返すと、小日向はニコッと笑うと、風呂場の入り口を開いた。
「先に入って待ってて下さい。勝手にお湯に浸かっちゃ駄目ですよ」
そう言うと小日向は脱衣場から出ていった。一方、残された俺は喜びに体を震わせていた。
小日向と一緒にお風呂! 好きな女の子と一緒に入浴は、男なら一度は夢見るシチュレーションだろう。
今からそれが実現するかもしれないのである。男として興奮しないわけがあろうか。いや、ない。
そういえば小日向と今まで色んなプレイをしてきたが、彼女が服を脱いだ姿は見たことないなぁ……なんてことを考えながら、風呂場のタイルの上に座って待っていると、がちゃりと後ろのドアが開いた。
「……お待たせです」
「う、うおっ……」
はにかみながら現れた小日向の姿に、俺は釘づけとなった。
小日向は水着を着ていた。しかも紺色のスクール水着だ。
幼児体型の小日向にはとても似合っており、陶器のように白い手足が艶めかしかった。
「さ、綺麗にするですよ」
俺が小日向に見惚れていると、小日向はそれを察したように微笑しながら、そう言って俺を横に寝かした。
軽くシャワーで俺の全身を流し、小日向はボディーソープの容器を手に取る。そしてそのまま俺の体に中身を垂らした。
ぬるりと生暖かい液体が俺の体の上で広がってゆく。しかしそんな感触も束の間だった。
「えいっ」
可愛らしい掛け声と共に鬼日向の細く白いおみ足が、俺の体に振り下ろされたのである。
足の裏の柔らかい感触が俺の体の上で動かされ、下半身を蹂躙してゆく。
彼女の足が動くたびにボディーソープが泡立ち、くちゅくちゅという卑猥な音が聞こえてくる。
「小日向特製の、足たわしですよ、先輩」
ごしごしと足で俺の体を磨いていく小日向。一方小日向の足が前進を這う感覚に、俺はすっかり興奮してしまっていた。
「どうしたですか先輩。おちんちん、大きくなってるですよ」
俺の肉棒の変化に目敏く気付いた小日向が、意地悪げにそう指摘する。
「お漏らしした所は徹底的に洗わないと、駄目ですね」
ぐちゅっ! と小日向は泡だらけの足で勃起した肉棒を踏みにじる。
「臭くて汚いここは……念入りに、です」
「あ、あああああっ!」
足の指で玉を転がし、竿を足の裏で包み上下する。
泡と足の絶妙な柔らかさが、絶妙な快楽を与えてくれる。
「どんどん固くなっていくですよ。本当に節操が無いですね」
サディスティックな笑みを浮かべ、足に力を入れる小日向。俺はその蹂躙劇に身を任せるままであった。
そして、
「ッううううう!」
俺はまたしても絶頂を迎えてしまった。
「あらら、せっかく綺麗にしてるのにまたお漏らしちゃうなんて、先輩は本当に堪え性が無いですね」
溢れ出る精液で己を汚しながら痙攣する俺を見下ろしながら、小日向はシャワーを手に取った。
「一日に二回もお漏らしするなんて……先輩は赤ちゃんみたいですね」
「う、うう……」
「洗い流してあげますよ、先輩。ふふふ、感謝してくださいね」
適度に暖かい湯がかけられ、石鹸の泡と出したばかりの精液が流されてゆく。
その光景を見ながら何だか惨めに思えてくる。だが小日向の方はそれが嬉しいのか、はにかみながら俺を上から見下ろしている。
そういえば小日向って俺を責めている時、普段より饒舌になるような……
「えいっ」
「ぷっ! ぶわわっ! な、何するんだ!」
突然顔にお湯をかけられ、思わずびっくりしてしまう。
「何時まで呆けている気ですか?」
「あ、いや……」
小日向はそのまま俺の顔の目の前に腰を降ろした。
紺色の薄布に包まれた小日向の股が迫り、思わず俺は息を呑む。
「私の足を汚した罰ですよ……口を開けるです」
「え、え」
「先輩、早くあーんするです」
小日向の異様な迫力に押され、俺は有無を言わず口を開けた。
「んっ……」
すると小日向は艶めかしい吐息を吐いたと思うと、ぶるっと体を振るわす。
水着の股の部分が徐々に黒く染まってゆく。そこで俺は彼女の真意に気付いたが、既に遅かった。
じょろろろろろろ……
水着から溢れた小日向の聖水が俺の口に直接降り注ぐ。
ほのかに香る独特の臭いと、生暖かい小便が口内に溢れる。
一瞬俺はフリーズしてしまうが、小日向の尿だと思うと頭より先に体が動いた。
喉を鳴らしながら一滴も零さないように降り注ぐ小日向の小水を飲んでゆく。
「……先輩にとってはご褒美でしたか」
呆れたような小日向の声を聞きながら、俺はゴクゴクと小日向の小便を飲み干してゆく。
何とも言えない味が口の中いっぱいに広がってゆく。これが小日向の体から出た排泄物であると思うと、不思議と嫌悪感は湧かなかった。いやむしろそれを口にしているという事実に、堪らなく興奮してしまう。
「ふぅ……」
ぶるっと震えると小日向は最後の一滴を絞り出す。
「どうでした? 先輩? 私のおしっこの味は?」
顔を上気させながら俺を嘲笑うと小日向はそう尋ねた。
正直、絶妙にぬるくて苦くてしょっぱい味というあんまりおいしくない味であったが、小日向の聖水だと思うとその不味さも究極の甘露に思えてしまう。
「あ、ああ……」
その余韻に浸る俺を確認すると、小日向はクスッと笑い声を漏らした。
「恍惚の表情まで浮かべて……そんなにおいしかったですか?」
そのまま小日向は、小便でぐっちょりと濡れた股の部分を俺の顔の押し付けた。
「吸っていいですよ。私もこのまま濡れっぱなしじゃ嫌ですし」
「ッ……!」
俺はその言葉の意味を理解すると同時に、小便まみれになった小日向のスク水の股部分に口を付け、一気に水分を吸い上げた。
異臭を放つ紺色の布をチューチューと吸い、染みていた小水を残らないように搾り取る。
スク水独特の感触と小便の味が絶妙なハーモニーを奏で、俺から残された理性を刈り取ってゆく。
「必死で吸ってますね……ふふ、本当に惨めな姿です」
頭の中が小日向の尿に支配されていく中、俺は夢中で彼女の水着にしゃぶりついていた……
奴隷先輩のお泊り
こんなにも心臓が高鳴ることが俺の人生において、他にあったであろうか。小日向の背中の感触を味わいながら、俺はそんな事を考えていた。
現在、俺は小日向とお風呂に入っていた。まるで抱き抱えるような形で密着しながら、狭い浴槽の中で二人で丸くなっている。
スクール水着を着ているとはいえ、小日向と肌を合わせながら入浴しているという状況。体が火照ってしょうがないのはきっとお湯に浸かっているからだけじゃあるまい。
「ふう……いいお湯ですね、先輩」
「! あ、ああ……」
正直小日向の軟肉に夢中で、湯加減なんて気にしている余裕がない。思わず頭がクラっとしてしまう。
「そろそろ上がりますか……どうしたです、先輩? 上を向いたりして」
「い、いや、何でもない、何でもない」
あとちょっとで溢れ出しそうな鼻血を抑えつつ、俺は浴槽から体を起こした。
風呂から出て体を拭くと、俺はそのまま居間に通される。勿論、全裸のままであるが、もう慣れてしまったのか違和感や羞恥心は無かった。
「さ、ご飯にするですよ」
いつの間にか私服姿に戻っていた小日向が、料理の乗った皿を持ってくる。
ほかほかと湯気が立ち上る料理がテーブルに並べられる。鶏のからあげ、青野菜中心のサラダにクリームシチュー……豪華な料理が俺の目の前に並べられている……
「す、すげえ! これ全部小日向が作ったのか!?」
「……はいです」
少し恥ずかしそうに顔を赤らめる小日向。エプロン姿がものすごく可愛らしい。
しかも食卓に並ぶ料理の見た目がすごい。普通にプロみたいな盛り付けというか見た目である。
「ほ、本当にこれ食っていいのか……?」
「はいです。先輩のために作ったんですから、食べてくれないと困ります」
……その小日向の言葉に俺は雷に打たれたような衝撃を憶えた。
女の子の手料理! しかも好きな子が自分のために作ってくれた手料理! これに感動しない男なんていないだろう。
「いただきます!」
俺は小日向と神に感謝し、ほかほかの料理に箸をつける。
「……う、うまい!」
からあげを口に入れた瞬間、美味しさが口いっぱいに広がった。
焼き加減、味付け、全てが絶妙で溢れ出る肉汁が堪らない。
「うまい! うまいぜ、小日向!」
他の料理もめちゃくちゃ美味しく作られており、俺は小日向の料理の腕に脱帽した。
「そ、それはよかったです」
顔を赤くしながら小さい口でもにゅもにゅと料理を咀嚼する小日向は小動物みたいで可愛かった。
食事が終わると食器を小日向と一緒に片づける。まるで同棲しているみたいだ。これで俺が全裸でなきゃ、最高なんだがな……
洗い物が終わると、小日向は再び俺を自室に招いた。
「先輩、今日はここで寝るですよ」
「え!? ここって……」
小日向が示した場所はこの部屋に一つしかない、小さなベッドだった。つ、つまり……」
「私と一緒に寝るです」
……これはもう。決まった……というやつではないか?
女の子の家で女の子の部屋に泊まり女の子と一緒のベッドで眠る。もう小日向が誘っているとしか思えない。ああ、ようやく俺の愛が伝わって二人は一つに……
「先輩はこれを着て寝るですよ」
俺の甘い幻想は小日向が取り出したある物によって破壊された。
「お、お前、これ……」
「はい。私がさっき着てたやつです」
それは先程、小日向が入浴時に身につけていたスクール水着だった。
「こ、小日向これは俺にはちょっと小さいんじゃ……あとまだ乾ききってない……」
「着るですよ、先輩」
ずいっ……と半乾きのスクール水着片手に迫ってくる後輩の圧力に、俺は言葉を飲んだ。
渡された水着に無言で袖を通してゆく。
元々小日向が着るものであるため、俺には一回り以上小さい。無理に体を通すが、ぴっちぴっちに体に貼り付いて、いまにもはちきれそうな風貌となってしまう。もちろん股間のもっこりも強調される。
後やっぱり若干湿ってて気持ち悪い。
「似合ってますよ、先輩」
小日向がそう言って親指を立てる。本当にそう思ってるんなら、噴き出すのを我慢するんじゃない。
「それに……ここも」
「うっ!」
浮き出ている睾丸を小日向は握りしめる。ただでさえぴちぴちの感触と小日向が身につけたものを着ているというせいで興奮していたペニスが、それをきっかけに戦闘態勢に入ってしまう。
「勃起しちゃいましたね」
淡々とそう言って小日向は狭い水着に中で怒張する肉棒を指で弾いた。
「本当に変態です。そんなの着て、気持ち悪くないんですか?」
ぴしっぴしっと股間にデコピンする小日向。
「さてと、次はこれです」
そう言って小日向は昼に俺を縛り上げたガムテープを再び取り出した。
「こ、小日向。一体何を……」
「黙ってください」
そのまま小日向は俺の手をグルグル巻きにして縛ると、仰向けの状態でベッドに転がした。
さらに足もガムテープで縛られてしまう。
「先輩は今晩、私専用の抱き枕になるです。動いたら駄目ですし喋っても駄目です」
……え、そういうこと? てっきり俺との初夜を解禁してくれたのかと思ったのに、また拘束プレイか……ちょっと残念だ。
俺がそんな事を考えていると、小日向は唐突に着ていたTシャツを脱ぎだした。
「こ、小日向! 何で脱いでんだよ!」
「? パジャマに着替えるですよ」
不思議そうに首を傾げながら小日向はさらにショートパンツも脱ぎ捨て、下着姿になった。
白いスポーツタイプのブラジャーは、ぺったんこな小日向にはとてもマッチしていて、同じく真っ白なパンティーは童顔幼児体型の彼女には似合いすぎている。
細い手足が。純白の下着が。小さなおへそが。俺の眼前に晒される。無防備な彼女の下着姿に俺は完全に目が釘付けになってしまう。
そんなこと知らない小日向はそのままパジャマを取りだし、袖を通し始める。
半袖長ズボンの薄い水色のパジャマは可愛らしく、シンプルなデザインは涼しげにも感じられる。
「さて、と」
上着のボタンを留め終わると、電気を消した。
「おやすみなさいです、先輩」
そのまま俺の横に寝転がり掛け布団をかけて、か細い手足で俺の体を挟み込む。
「お、おい小日向」
「喋っちゃ駄目です先輩。先輩は抱き枕。モノなんですから」
ぴしゃりと小日向に言われ、俺は思わず黙ってしまう。今回はこういうプレイか……
だがそれでも小日向の柔らかい体が、ほのかな体臭が、俺の五感を刺激する。
「ふみゅ……」
「ッ!」
甘い吐息と共に小日向の膝が俺の股間にぐりっと押し付けられる。
「こ、小日向……」
「黙ってください」
そう言われても現在進行形で小日向のおみ足が俺の性器を刺激してくるんだから、どうしようもない。
「…………!」
必死で快感によって声が漏れそうになるのを耐える。しかし耐えれば耐えるほど小日向の足は動きを増してゆく。
「はあっ……んん……」
次第に喘ぎ声が漏れ始める。
「……うるさいですよ先輩」
ぎりっ……と乳首を抓られる。痛みとそれによる快楽が俺の体に染み込んでゆく。
「……射精したら駄目ですよ。一週間靴下おあずけの刑です」
「……!」
それは駄目だ。すでに小日向の匂いジャンキーと化している俺にとって、彼女の靴下はもはや生活必需品といってもよい」
だから俺は必死に耐えることにした。それを嘲笑うかの如く小日向は足による攻撃を強めてゆく。
あ、これはわざとだ。俺を苦しめる小日向のプレイだと理解するまでしばらくかかった。
責めは小日向が眠りにつくまで続けられた。
刺激から解放された俺だったが、今度はすぐ近くで小日向が眠っているという状況に興奮してしまい、眠れなくなってしまった。
俺の肉棒のギンギンが収まるのは明け方近くの事であった。
こんなにも心臓が高鳴ることが俺の人生において、他にあったであろうか。小日向の背中の感触を味わいながら、俺はそんな事を考えていた。
現在、俺は小日向とお風呂に入っていた。まるで抱き抱えるような形で密着しながら、狭い浴槽の中で二人で丸くなっている。
スクール水着を着ているとはいえ、小日向と肌を合わせながら入浴しているという状況。体が火照ってしょうがないのはきっとお湯に浸かっているからだけじゃあるまい。
「ふう……いいお湯ですね、先輩」
「! あ、ああ……」
正直小日向の軟肉に夢中で、湯加減なんて気にしている余裕がない。思わず頭がクラっとしてしまう。
「そろそろ上がりますか……どうしたです、先輩? 上を向いたりして」
「い、いや、何でもない、何でもない」
あとちょっとで溢れ出しそうな鼻血を抑えつつ、俺は浴槽から体を起こした。
風呂から出て体を拭くと、俺はそのまま居間に通される。勿論、全裸のままであるが、もう慣れてしまったのか違和感や羞恥心は無かった。
「さ、ご飯にするですよ」
いつの間にか私服姿に戻っていた小日向が、料理の乗った皿を持ってくる。
ほかほかと湯気が立ち上る料理がテーブルに並べられる。鶏のからあげ、青野菜中心のサラダにクリームシチュー……豪華な料理が俺の目の前に並べられている……
「す、すげえ! これ全部小日向が作ったのか!?」
「……はいです」
少し恥ずかしそうに顔を赤らめる小日向。エプロン姿がものすごく可愛らしい。
しかも食卓に並ぶ料理の見た目がすごい。普通にプロみたいな盛り付けというか見た目である。
「ほ、本当にこれ食っていいのか……?」
「はいです。先輩のために作ったんですから、食べてくれないと困ります」
……その小日向の言葉に俺は雷に打たれたような衝撃を憶えた。
女の子の手料理! しかも好きな子が自分のために作ってくれた手料理! これに感動しない男なんていないだろう。
「いただきます!」
俺は小日向と神に感謝し、ほかほかの料理に箸をつける。
「……う、うまい!」
からあげを口に入れた瞬間、美味しさが口いっぱいに広がった。
焼き加減、味付け、全てが絶妙で溢れ出る肉汁が堪らない。
「うまい! うまいぜ、小日向!」
他の料理もめちゃくちゃ美味しく作られており、俺は小日向の料理の腕に脱帽した。
「そ、それはよかったです」
顔を赤くしながら小さい口でもにゅもにゅと料理を咀嚼する小日向は小動物みたいで可愛かった。
食事が終わると食器を小日向と一緒に片づける。まるで同棲しているみたいだ。これで俺が全裸でなきゃ、最高なんだがな……
洗い物が終わると、小日向は再び俺を自室に招いた。
「先輩、今日はここで寝るですよ」
「え!? ここって……」
小日向が示した場所はこの部屋に一つしかない、小さなベッドだった。つ、つまり……」
「私と一緒に寝るです」
……これはもう。決まった……というやつではないか?
女の子の家で女の子の部屋に泊まり女の子と一緒のベッドで眠る。もう小日向が誘っているとしか思えない。ああ、ようやく俺の愛が伝わって二人は一つに……
「先輩はこれを着て寝るですよ」
俺の甘い幻想は小日向が取り出したある物によって破壊された。
「お、お前、これ……」
「はい。私がさっき着てたやつです」
それは先程、小日向が入浴時に身につけていたスクール水着だった。
「こ、小日向これは俺にはちょっと小さいんじゃ……あとまだ乾ききってない……」
「着るですよ、先輩」
ずいっ……と半乾きのスクール水着片手に迫ってくる後輩の圧力に、俺は言葉を飲んだ。
渡された水着に無言で袖を通してゆく。
元々小日向が着るものであるため、俺には一回り以上小さい。無理に体を通すが、ぴっちぴっちに体に貼り付いて、いまにもはちきれそうな風貌となってしまう。もちろん股間のもっこりも強調される。
後やっぱり若干湿ってて気持ち悪い。
「似合ってますよ、先輩」
小日向がそう言って親指を立てる。本当にそう思ってるんなら、噴き出すのを我慢するんじゃない。
「それに……ここも」
「うっ!」
浮き出ている睾丸を小日向は握りしめる。ただでさえぴちぴちの感触と小日向が身につけたものを着ているというせいで興奮していたペニスが、それをきっかけに戦闘態勢に入ってしまう。
「勃起しちゃいましたね」
淡々とそう言って小日向は狭い水着に中で怒張する肉棒を指で弾いた。
「本当に変態です。そんなの着て、気持ち悪くないんですか?」
ぴしっぴしっと股間にデコピンする小日向。
「さてと、次はこれです」
そう言って小日向は昼に俺を縛り上げたガムテープを再び取り出した。
「こ、小日向。一体何を……」
「黙ってください」
そのまま小日向は俺の手をグルグル巻きにして縛ると、仰向けの状態でベッドに転がした。
さらに足もガムテープで縛られてしまう。
「先輩は今晩、私専用の抱き枕になるです。動いたら駄目ですし喋っても駄目です」
……え、そういうこと? てっきり俺との初夜を解禁してくれたのかと思ったのに、また拘束プレイか……ちょっと残念だ。
俺がそんな事を考えていると、小日向は唐突に着ていたTシャツを脱ぎだした。
「こ、小日向! 何で脱いでんだよ!」
「? パジャマに着替えるですよ」
不思議そうに首を傾げながら小日向はさらにショートパンツも脱ぎ捨て、下着姿になった。
白いスポーツタイプのブラジャーは、ぺったんこな小日向にはとてもマッチしていて、同じく真っ白なパンティーは童顔幼児体型の彼女には似合いすぎている。
細い手足が。純白の下着が。小さなおへそが。俺の眼前に晒される。無防備な彼女の下着姿に俺は完全に目が釘付けになってしまう。
そんなこと知らない小日向はそのままパジャマを取りだし、袖を通し始める。
半袖長ズボンの薄い水色のパジャマは可愛らしく、シンプルなデザインは涼しげにも感じられる。
「さて、と」
上着のボタンを留め終わると、電気を消した。
「おやすみなさいです、先輩」
そのまま俺の横に寝転がり掛け布団をかけて、か細い手足で俺の体を挟み込む。
「お、おい小日向」
「喋っちゃ駄目です先輩。先輩は抱き枕。モノなんですから」
ぴしゃりと小日向に言われ、俺は思わず黙ってしまう。今回はこういうプレイか……
だがそれでも小日向の柔らかい体が、ほのかな体臭が、俺の五感を刺激する。
「ふみゅ……」
「ッ!」
甘い吐息と共に小日向の膝が俺の股間にぐりっと押し付けられる。
「こ、小日向……」
「黙ってください」
そう言われても現在進行形で小日向のおみ足が俺の性器を刺激してくるんだから、どうしようもない。
「…………!」
必死で快感によって声が漏れそうになるのを耐える。しかし耐えれば耐えるほど小日向の足は動きを増してゆく。
「はあっ……んん……」
次第に喘ぎ声が漏れ始める。
「……うるさいですよ先輩」
ぎりっ……と乳首を抓られる。痛みとそれによる快楽が俺の体に染み込んでゆく。
「……射精したら駄目ですよ。一週間靴下おあずけの刑です」
「……!」
それは駄目だ。すでに小日向の匂いジャンキーと化している俺にとって、彼女の靴下はもはや生活必需品といってもよい」
だから俺は必死に耐えることにした。それを嘲笑うかの如く小日向は足による攻撃を強めてゆく。
あ、これはわざとだ。俺を苦しめる小日向のプレイだと理解するまでしばらくかかった。
責めは小日向が眠りにつくまで続けられた。
刺激から解放された俺だったが、今度はすぐ近くで小日向が眠っているという状況に興奮してしまい、眠れなくなってしまった。
俺の肉棒のギンギンが収まるのは明け方近くの事であった。
小日向凪の先輩観察日記その2
遅くなってすいません
今日は今までにない最高の朝を迎えることが出来ました。
理由は勿論、現在進行形で私の隣で眠っている先輩の存在です。手足をガムテープで縛られ、私のスクール水着を着ながらすやすやと眠る光景は、とても滑稽でした。
私のスクール水着は小さいため、先輩が着るとピチピチに突っ張ってしまっています。その中で股の部分に目をやると、大きく膨らんでいるのがすぐにわかります。朝勃ち、というやつでしょうか。
「…………」
私は無言で固くなった先輩のイチモツを指ですーっと、撫でます。
「んっ……」
寝息を立てながら悶える先輩の顔を見て、思わずクスリと笑いが漏れます。
先輩を私が独占している――この事実を実感します。
先輩初めて屋上で会ってから既に一ヵ月以上の月日が流れていました。
その中で私の先輩への思いはどんどん変化していきました。
最初は興味本位でした。私の事を好きという先輩が、私の私物に興奮しているのを見て、この人がどこまで堕ちてゆくかを試してみたいと言う思いがありました。
上靴、靴下、腋、お尻、おなら……先輩は私の私物や分泌物で興奮する変態さんでした。
私はそんな先輩の浅ましい姿を見るのがいつの間にか楽しみとなり、様々な調教を行いました。
そんな中、私に新しい疑問が生まれました。
先輩はただのマゾヒスト、もしくは臭いフェチでそういったプレイが出来るなら誰でもいいんじゃないのか、と。
実際に先輩は惚れっぽい人として有名で、色んな女の人に告白していると聞きます。
本当は私じゃなくても、マニアックなプレイが出来れば誰でもいいんじゃないかと、そんな考えが私の頭をぐるぐると回りました。
それではまるで私が都合のいい道具と同じではないか。そう思った私は先輩を自宅に呼んで尋問を行いました。
臭い責めで正気を失わせながらゆっくりと尋問を行いました。じっくりと時間をかけて先輩の精神を弱らせた後、私の事が好きなのかと尋ねました。
先輩は弱々しくも、私の事が好き、といってくれました。そこに嘘は無く、真実の気持ちを打ちあけてくれたのだと、直感的に感じました。
その瞬間、私は自身の胸が高鳴るのを肌で感じていました。
この先輩は心の底から私を崇拝している。そのことが分かった時、私は確かに先輩への歪んだ愛情が生まれるのを感じました。
もっとこの人を貶めたい。この人が滅茶苦茶になっていく様を見たいと思いました。
それと同時に、この人を独占したいという思いも、心の底から湧き上がってきました。
もしも先輩が私以外の女の子と仲良くしたら……そんなことは絶対にないと思うのですが、それでもそんな考えが浮かんでしまいます。そして腸が煮えくり返りそうになるほどの怒りが湧くのです。
だから私はあらゆる手を使って先輩を支配することに決めました。
登下校・休み時間・放課後は常に寄り添い、多くの人々に私と先輩の仲を認知させました。
さらに責めもどんどんマニアックにしていきました。もう先輩は私以外では興奮しない体になっているでしょう。勿論、それが狙いなのですが……
このまま私は先輩をどんどん駄目にしてゆく予定です。気付いた時には、もう手遅れ。先輩は私無しでは生きられない体になっているでしょう。
……二日目最初の調教は、朝一番の聖水を飲ませてあげる予定です。その後もたっぷりと調教メニューを考えています。
今だけはゆっくり寝かせてあげますよ先輩。もっともっと、私を楽しませてくださいね。
遅くなってすいません
今日は今までにない最高の朝を迎えることが出来ました。
理由は勿論、現在進行形で私の隣で眠っている先輩の存在です。手足をガムテープで縛られ、私のスクール水着を着ながらすやすやと眠る光景は、とても滑稽でした。
私のスクール水着は小さいため、先輩が着るとピチピチに突っ張ってしまっています。その中で股の部分に目をやると、大きく膨らんでいるのがすぐにわかります。朝勃ち、というやつでしょうか。
「…………」
私は無言で固くなった先輩のイチモツを指ですーっと、撫でます。
「んっ……」
寝息を立てながら悶える先輩の顔を見て、思わずクスリと笑いが漏れます。
先輩を私が独占している――この事実を実感します。
先輩初めて屋上で会ってから既に一ヵ月以上の月日が流れていました。
その中で私の先輩への思いはどんどん変化していきました。
最初は興味本位でした。私の事を好きという先輩が、私の私物に興奮しているのを見て、この人がどこまで堕ちてゆくかを試してみたいと言う思いがありました。
上靴、靴下、腋、お尻、おなら……先輩は私の私物や分泌物で興奮する変態さんでした。
私はそんな先輩の浅ましい姿を見るのがいつの間にか楽しみとなり、様々な調教を行いました。
そんな中、私に新しい疑問が生まれました。
先輩はただのマゾヒスト、もしくは臭いフェチでそういったプレイが出来るなら誰でもいいんじゃないのか、と。
実際に先輩は惚れっぽい人として有名で、色んな女の人に告白していると聞きます。
本当は私じゃなくても、マニアックなプレイが出来れば誰でもいいんじゃないかと、そんな考えが私の頭をぐるぐると回りました。
それではまるで私が都合のいい道具と同じではないか。そう思った私は先輩を自宅に呼んで尋問を行いました。
臭い責めで正気を失わせながらゆっくりと尋問を行いました。じっくりと時間をかけて先輩の精神を弱らせた後、私の事が好きなのかと尋ねました。
先輩は弱々しくも、私の事が好き、といってくれました。そこに嘘は無く、真実の気持ちを打ちあけてくれたのだと、直感的に感じました。
その瞬間、私は自身の胸が高鳴るのを肌で感じていました。
この先輩は心の底から私を崇拝している。そのことが分かった時、私は確かに先輩への歪んだ愛情が生まれるのを感じました。
もっとこの人を貶めたい。この人が滅茶苦茶になっていく様を見たいと思いました。
それと同時に、この人を独占したいという思いも、心の底から湧き上がってきました。
もしも先輩が私以外の女の子と仲良くしたら……そんなことは絶対にないと思うのですが、それでもそんな考えが浮かんでしまいます。そして腸が煮えくり返りそうになるほどの怒りが湧くのです。
だから私はあらゆる手を使って先輩を支配することに決めました。
登下校・休み時間・放課後は常に寄り添い、多くの人々に私と先輩の仲を認知させました。
さらに責めもどんどんマニアックにしていきました。もう先輩は私以外では興奮しない体になっているでしょう。勿論、それが狙いなのですが……
このまま私は先輩をどんどん駄目にしてゆく予定です。気付いた時には、もう手遅れ。先輩は私無しでは生きられない体になっているでしょう。
……二日目最初の調教は、朝一番の聖水を飲ませてあげる予定です。その後もたっぷりと調教メニューを考えています。
今だけはゆっくり寝かせてあげますよ先輩。もっともっと、私を楽しませてくださいね。
奴隷先輩の転機
小日向の家でのお泊り会が終了した翌日。俺はいつもどおり迎えに来た小日向と合流して、学校に向かった。
俺に腕を絡めながら涼しげに歩く小日向を横目で眺める。あいかわらず無表情のままで、俺にべったりとくっついている。
こんな小柄で大人しそうな少女が、二日間俺を監禁してマニアックな調教を施すとは思えまい。そう思うと小日向の秘密を俺だけが知っているということになり、それはそれで優越感が湧いてくるのだが……
それでも最近の調教はどんどんエスカレートしていると思う。
昨日は起きた後、小日向の濃い聖水を飲まされそのまま小便まみれになった性器を舐めさせられた。その後は拘束されたまま一日中、小日向の尻に敷かれていた。勿論オナニーは禁止で、俺は彼女の刺激的な体臭に悶えながら一日を終えたのだった。
しかもまだ射精は許可されていないのに、小日向にこんなに密着されているので、落ち着かなくってしょうがない。
「先輩、どうしたですか? 息が荒いですよ?」
「えっ、いや、別に何ともないぞ」
「そうですか……ふふっ」
俺の内心を見透かしたのか、小日向はちょっとだけ嘲笑すると、より一層その柔らかい体を擦りつけてくる。
その後、俺は教室に到着するまでずっと密着してくる小日向の肉質に耐え続けた。
「今日も小日向の家でか?」
そして放課後。俺は小日向と共に彼女の自宅へと進んでいた。
「そうですよ。何か問題でも?」
「いや……ただ、毎日お邪魔してるからさ。迷惑にならないのかなーって。ご家族もいるだろうし……」
「……今日も両親はいないから大丈夫です」
少し暗い声色で小日向は答えた。
そういえば俺はよく小日向の家で調教を受けているが、今まで一度も彼女の両親と出会っていない。
仕事柄で俺が家にいる時間には帰って来れないという可能性もあったが、小日向の家にはどうにも生活感が感じられないのだ。
だがさすがに他人の家庭の事情をきくのは憚られる。
「大丈夫ですよ。いくら先輩が変態なことをしようと両親にばれることはありませんから」
俺の心を覗き込むかのように、小日向はにやりと笑うのであった。
いつも通り玄関をくぐり小日向の自室に入る。通学鞄を置いて俺は床に正座し、小日向はベッドに腰掛けた。
「今日は体育はバレーボールだったです」
そう言って小日向は紺色のソックスに包まれた右足を俺の顔に近づける。
「体育館シューズ履いてたから、すっごく蒸れてるです」
そのまま彼女はむわっとしたソックスの中で、足の指を上下に動かして俺を挑発する。
「……嗅ぎたいですか?」
足先に釘付けになっている俺を嘲笑うように、小日向は聞いてくる。俺は無言で頷いた。
「だったら……自分から臭いに来てください」
俺のすぐ目の前で足を固定した小日向はそうやって俺を焦らしてくる。すでに昨日から生殺しを喰らっている俺は、まるでオアシスを求める旅人のように、小日向の足に吸い寄せられてゆく。
足の裏の部分に顔を引っ付けて大きく息を吸う。たちまち熟成された布と汗と皮のような香りが、鼻の奥まで入り込んでゆく。
「……そんなにふがふがして……まるで豚みたいですよ、先輩」
「んぐっ……」
「それにズボンがもうパンパンになってます。そんなに興奮するような臭いですか?」
俺の顔面に足を押し付けながら、もう片方の足で大きくなった俺の性器をぐりぐりする小日向。
呼吸のたびに小日向の足臭が肺まで届き、血液が沸騰するほどの高揚感が体に現れる。そして息が荒くなり、より強く小日向の体臭を吸い込んでしまう。
一方、盛り上がった性器は踵で踏みつけられたかと思うと、指で軽く摘ままれ上下に強く擦られたりする。
「こんなに硬くして……やっぱり先輩は変態さんです」
明らかに馬鹿にした口調でそう言う小日向に対し、俺は怒りが湧くどころかむしろ興奮してしまっていた。
「あ……小日向……も、もっと……」
恥も外聞もなく小日向におねだりする。むせかえるような小日向の体臭は、今や俺にとって性的興奮を得るために必要不可欠なモノとなっていた。
「……しょうがないですね。変態の先輩を構ってあげるのも私の仕事……ですっ」
指先が鼻の穴を覆う。濃厚な香りが澄み渡るように体内へ吸収されてゆく。
「おちんちんもどんどん大きくなってますね。こんな臭い足でここまで勃起させるなんて、気持ち悪いことこの上ないですが……」
小日向はそう言うと、ギンギンになったペニスをズボン越しにしごいてゆく。指でペニスを摘まみながら緩急をつけて刺激してくる。
ぐにぐに、しゅっしゅ。ぐにぐに、しゅっしゅ。
俺の感じるところをすでに把握しているのか、小日向の足は的確に急所を責めたててくる。
「……先輩。今日は特別に足を舐めてもいいですよ」
「!?」
唐突に小日向が言い放った一言に、俺の思考は停止した。
「お、おい、小日向、今なんて……」
「生の足を舐めさせてあげる、と言ったですよ」
まるで全身が総毛立ったような感覚に襲われた。
今までの調教で小日向の体を舐めたことは何度もあった。腋と性器だ。汗まみれとなった柔らかい腋。小便まみれとなった無駄毛一本無いピンク色の性器。どちらも俺にとっては最高のご褒美だった。
だが、足にはそれをはるかに上回る魅力を俺は感じていた。初めて触れた小日向の私物は彼女の上靴だったし、足の香りは貰った上靴で毎日のように臭っている。
昼食時にも足を嗅がされ今ではすっかりそれ無しじゃ食欲が湧かない体になってしまったし、何度もその白く細い足で嬲りものにされる妄想をした。
つまり俺にとって小日向の足は一種の聖域であり、それを舐めさせて貰えるなんて光栄極まりないことなのである。
「ほ、本当か、小日向?」
「はい。ほんとです」
小日向は顔から少しだけ足を離す。そして頬を僅かに染めると、俺の口元につま先を差し出した。
「脱がせて下さい。どうやればいいかは……分かりますね?」
「ああ……」
小日向はなんて魅力的な提案をしてくるのだろう。この蒸れた靴下を口で咥えて脱がせろと彼女は言うのだ。
震える唇で目の前の靴下の布地に歯をたてる。小日向の指を噛んでしまわないよう慎重に口で紺色の布を挟むと、そのままゆっくりと引いてゆく。
蠱惑的な香りに何度も意識が飛びかけながら、俺は何度か引っかけてしまいつつも、何とか最後まで靴下を脱がすことに成功した。
「よく頑張りましたね先輩。はい、ご褒美です」
その途端、露わになった小日向の白い足が、目の前で艶めかしく躍動する。ちっちゃな指が食虫植物のように動き、俺の舌を捕食するかの如く迫ってくる。
俺はその淫靡な光景に酔ってしまい、意識を朦朧とさせながらつま先に舌を這わせた。
「――!」
小日向の足に舌を接触させた瞬間、体に電撃が走ったかのような衝撃が襲いかかった。
長時間靴下に包まれていたためか、小日向の足は汗で湿っており、ほのかにしょっぱい味がした。
臭いも強烈で脳まで蕩けてしまうような感覚に陥ってしまう。
「……指の間も舐めていいですよ」
「!!」
小日向のその言葉と同時に俺は彼女の指の隙間に舌をねじ込んでいた。
より湿っぽく、少量の埃とカスのようなものが舌に付着する。それを舌でなめとるたびに、自分が今小日向の足を舐めているという事実を実感する。
「そんなに必死に舐めて……浅ましいですよ、先輩」
心底見下した小日向の声が聞こえてくる。それすらも俺を興奮させる甘味料となって体中に染み込んでゆく。
ちゅぱちゅぱと音を立てて、小日向の生足にむしゃぶりつく。指に吸い付き、土踏まずにまで舌を伸ばす。
「まるで犬です。人間のプライドは無いんですか?」
唇をにやりと歪めながら、小日向は俺の口の中につま先を突っ込み、指を舌に絡ませる。それはまるで小日向の足とディープキスをしているようであった。
「おちんちんも限界ですね。ほら、イってください」
そう言うと小日向は、ズボン越しでペニスをいじっていたもう片方の足に力を入れた。
「――っっッ!!」
そして俺の目の前は真っ白になった。
全身が一気に痙攣し、波のような快楽が流れ込んでゆく。そのまま体が大きく反り返り、一気に力が抜けてゆく。
「ふふ、イッたですね」
征服者の微笑みを浮かべながら、小日向は足を離した。
「女の子の足は美味しかったですか?」
「ぁ……」
放心状態の俺は力なく頷いた。
「後輩の足はそんなに美味でしたか……本当に変態さんです」
「うあ……」
俺はそう呟くとパンツの中で俺は大量の精液を吹き出したまま、意識をブラックアウトさせていった。
「……なあ小日向」
「何ですか、先輩」
「……パンツを脱いじゃ駄目か?」
「駄目です」
その後意識を取り戻した俺は、自分のパンツの中が精液まみれでどろどろになっていたことに、軽く絶望した。
しかもそのままの状態で帰宅を命じられ、玄関まで連れて行かれてしまう。
「お漏らししたまま帰るなんて、先輩にはお似合いの格好です」
俺の要望を無慈悲に却下すると、小日向は上機嫌で俺の背中を押した。
「明日もいっぱい虐めてあげますからね、先輩」
そうやっていつも通り俺が小日向家から出ようとした、まさにその時だった。
いつもは開かない玄関のドアが開き、外から開いた。
突然の事に固まる、俺と小日向の前でゆっくりとドアは開き、人影が一つ現れた。
それを見て俺の後ろで小日向が息を呑んだ。
そこに現れたのは高級そうなスーツに身を包んだ、中年らしき男性だった。背は高く、年相応の皺顔に刻まれているが、若々しさを残す外見をしていた。
「……おお、凪。帰ってたのか」
その男は小日向の姿を見ると、淡白にそう言った。
「…………」
小日向はただ彼を見つめながら、黙っているだけだった。
「君は……娘の友達かね?」
そこでようやく我に返った俺は、彼がずっと会う事のなかった小日向の父親であることに気が付いた。
「あ……はい! 娘さんとは仲良くさせていただいてます!」
すぐに俺はその場を取り繕う。小日向のお父さんは俺を興味深げに見つめた後、
「そうか。娘をよろしく頼むぞ」
とだけ言うとそのまま家に上がった。そして硬直する俺達の横をお父さんは素通りし、居間に向かう。
そして引きだしから何かを取り出すと、再び玄関に戻ってきた。
「じゃあ父さんはもう行くから、家の事を頼むぞ、凪」
そのままお父さんは本当に家を出ていった。本当に一瞬で、嵐のような出来事だった。
「…………」
沈黙が続く。
まさかずっと出会う事の無かった小日向の親とこんな風に遭遇するとは……
「……先輩」
きゅ、と弱々しくと背中を摘ままれる。
「……もうちょっと、いっしょにいて貰っても、いいですか?」
そこにいつもの淡々とした口調はなかった。
俺は小日向の家の事情は分からない。だが不安そうに震える彼女を放っておけなかった。
……今になって思えば。
この出来事が後の俺と小日向の運命を決定づけた出来事だったのかもしれない。
小日向の家でのお泊り会が終了した翌日。俺はいつもどおり迎えに来た小日向と合流して、学校に向かった。
俺に腕を絡めながら涼しげに歩く小日向を横目で眺める。あいかわらず無表情のままで、俺にべったりとくっついている。
こんな小柄で大人しそうな少女が、二日間俺を監禁してマニアックな調教を施すとは思えまい。そう思うと小日向の秘密を俺だけが知っているということになり、それはそれで優越感が湧いてくるのだが……
それでも最近の調教はどんどんエスカレートしていると思う。
昨日は起きた後、小日向の濃い聖水を飲まされそのまま小便まみれになった性器を舐めさせられた。その後は拘束されたまま一日中、小日向の尻に敷かれていた。勿論オナニーは禁止で、俺は彼女の刺激的な体臭に悶えながら一日を終えたのだった。
しかもまだ射精は許可されていないのに、小日向にこんなに密着されているので、落ち着かなくってしょうがない。
「先輩、どうしたですか? 息が荒いですよ?」
「えっ、いや、別に何ともないぞ」
「そうですか……ふふっ」
俺の内心を見透かしたのか、小日向はちょっとだけ嘲笑すると、より一層その柔らかい体を擦りつけてくる。
その後、俺は教室に到着するまでずっと密着してくる小日向の肉質に耐え続けた。
「今日も小日向の家でか?」
そして放課後。俺は小日向と共に彼女の自宅へと進んでいた。
「そうですよ。何か問題でも?」
「いや……ただ、毎日お邪魔してるからさ。迷惑にならないのかなーって。ご家族もいるだろうし……」
「……今日も両親はいないから大丈夫です」
少し暗い声色で小日向は答えた。
そういえば俺はよく小日向の家で調教を受けているが、今まで一度も彼女の両親と出会っていない。
仕事柄で俺が家にいる時間には帰って来れないという可能性もあったが、小日向の家にはどうにも生活感が感じられないのだ。
だがさすがに他人の家庭の事情をきくのは憚られる。
「大丈夫ですよ。いくら先輩が変態なことをしようと両親にばれることはありませんから」
俺の心を覗き込むかのように、小日向はにやりと笑うのであった。
いつも通り玄関をくぐり小日向の自室に入る。通学鞄を置いて俺は床に正座し、小日向はベッドに腰掛けた。
「今日は体育はバレーボールだったです」
そう言って小日向は紺色のソックスに包まれた右足を俺の顔に近づける。
「体育館シューズ履いてたから、すっごく蒸れてるです」
そのまま彼女はむわっとしたソックスの中で、足の指を上下に動かして俺を挑発する。
「……嗅ぎたいですか?」
足先に釘付けになっている俺を嘲笑うように、小日向は聞いてくる。俺は無言で頷いた。
「だったら……自分から臭いに来てください」
俺のすぐ目の前で足を固定した小日向はそうやって俺を焦らしてくる。すでに昨日から生殺しを喰らっている俺は、まるでオアシスを求める旅人のように、小日向の足に吸い寄せられてゆく。
足の裏の部分に顔を引っ付けて大きく息を吸う。たちまち熟成された布と汗と皮のような香りが、鼻の奥まで入り込んでゆく。
「……そんなにふがふがして……まるで豚みたいですよ、先輩」
「んぐっ……」
「それにズボンがもうパンパンになってます。そんなに興奮するような臭いですか?」
俺の顔面に足を押し付けながら、もう片方の足で大きくなった俺の性器をぐりぐりする小日向。
呼吸のたびに小日向の足臭が肺まで届き、血液が沸騰するほどの高揚感が体に現れる。そして息が荒くなり、より強く小日向の体臭を吸い込んでしまう。
一方、盛り上がった性器は踵で踏みつけられたかと思うと、指で軽く摘ままれ上下に強く擦られたりする。
「こんなに硬くして……やっぱり先輩は変態さんです」
明らかに馬鹿にした口調でそう言う小日向に対し、俺は怒りが湧くどころかむしろ興奮してしまっていた。
「あ……小日向……も、もっと……」
恥も外聞もなく小日向におねだりする。むせかえるような小日向の体臭は、今や俺にとって性的興奮を得るために必要不可欠なモノとなっていた。
「……しょうがないですね。変態の先輩を構ってあげるのも私の仕事……ですっ」
指先が鼻の穴を覆う。濃厚な香りが澄み渡るように体内へ吸収されてゆく。
「おちんちんもどんどん大きくなってますね。こんな臭い足でここまで勃起させるなんて、気持ち悪いことこの上ないですが……」
小日向はそう言うと、ギンギンになったペニスをズボン越しにしごいてゆく。指でペニスを摘まみながら緩急をつけて刺激してくる。
ぐにぐに、しゅっしゅ。ぐにぐに、しゅっしゅ。
俺の感じるところをすでに把握しているのか、小日向の足は的確に急所を責めたててくる。
「……先輩。今日は特別に足を舐めてもいいですよ」
「!?」
唐突に小日向が言い放った一言に、俺の思考は停止した。
「お、おい、小日向、今なんて……」
「生の足を舐めさせてあげる、と言ったですよ」
まるで全身が総毛立ったような感覚に襲われた。
今までの調教で小日向の体を舐めたことは何度もあった。腋と性器だ。汗まみれとなった柔らかい腋。小便まみれとなった無駄毛一本無いピンク色の性器。どちらも俺にとっては最高のご褒美だった。
だが、足にはそれをはるかに上回る魅力を俺は感じていた。初めて触れた小日向の私物は彼女の上靴だったし、足の香りは貰った上靴で毎日のように臭っている。
昼食時にも足を嗅がされ今ではすっかりそれ無しじゃ食欲が湧かない体になってしまったし、何度もその白く細い足で嬲りものにされる妄想をした。
つまり俺にとって小日向の足は一種の聖域であり、それを舐めさせて貰えるなんて光栄極まりないことなのである。
「ほ、本当か、小日向?」
「はい。ほんとです」
小日向は顔から少しだけ足を離す。そして頬を僅かに染めると、俺の口元につま先を差し出した。
「脱がせて下さい。どうやればいいかは……分かりますね?」
「ああ……」
小日向はなんて魅力的な提案をしてくるのだろう。この蒸れた靴下を口で咥えて脱がせろと彼女は言うのだ。
震える唇で目の前の靴下の布地に歯をたてる。小日向の指を噛んでしまわないよう慎重に口で紺色の布を挟むと、そのままゆっくりと引いてゆく。
蠱惑的な香りに何度も意識が飛びかけながら、俺は何度か引っかけてしまいつつも、何とか最後まで靴下を脱がすことに成功した。
「よく頑張りましたね先輩。はい、ご褒美です」
その途端、露わになった小日向の白い足が、目の前で艶めかしく躍動する。ちっちゃな指が食虫植物のように動き、俺の舌を捕食するかの如く迫ってくる。
俺はその淫靡な光景に酔ってしまい、意識を朦朧とさせながらつま先に舌を這わせた。
「――!」
小日向の足に舌を接触させた瞬間、体に電撃が走ったかのような衝撃が襲いかかった。
長時間靴下に包まれていたためか、小日向の足は汗で湿っており、ほのかにしょっぱい味がした。
臭いも強烈で脳まで蕩けてしまうような感覚に陥ってしまう。
「……指の間も舐めていいですよ」
「!!」
小日向のその言葉と同時に俺は彼女の指の隙間に舌をねじ込んでいた。
より湿っぽく、少量の埃とカスのようなものが舌に付着する。それを舌でなめとるたびに、自分が今小日向の足を舐めているという事実を実感する。
「そんなに必死に舐めて……浅ましいですよ、先輩」
心底見下した小日向の声が聞こえてくる。それすらも俺を興奮させる甘味料となって体中に染み込んでゆく。
ちゅぱちゅぱと音を立てて、小日向の生足にむしゃぶりつく。指に吸い付き、土踏まずにまで舌を伸ばす。
「まるで犬です。人間のプライドは無いんですか?」
唇をにやりと歪めながら、小日向は俺の口の中につま先を突っ込み、指を舌に絡ませる。それはまるで小日向の足とディープキスをしているようであった。
「おちんちんも限界ですね。ほら、イってください」
そう言うと小日向は、ズボン越しでペニスをいじっていたもう片方の足に力を入れた。
「――っっッ!!」
そして俺の目の前は真っ白になった。
全身が一気に痙攣し、波のような快楽が流れ込んでゆく。そのまま体が大きく反り返り、一気に力が抜けてゆく。
「ふふ、イッたですね」
征服者の微笑みを浮かべながら、小日向は足を離した。
「女の子の足は美味しかったですか?」
「ぁ……」
放心状態の俺は力なく頷いた。
「後輩の足はそんなに美味でしたか……本当に変態さんです」
「うあ……」
俺はそう呟くとパンツの中で俺は大量の精液を吹き出したまま、意識をブラックアウトさせていった。
「……なあ小日向」
「何ですか、先輩」
「……パンツを脱いじゃ駄目か?」
「駄目です」
その後意識を取り戻した俺は、自分のパンツの中が精液まみれでどろどろになっていたことに、軽く絶望した。
しかもそのままの状態で帰宅を命じられ、玄関まで連れて行かれてしまう。
「お漏らししたまま帰るなんて、先輩にはお似合いの格好です」
俺の要望を無慈悲に却下すると、小日向は上機嫌で俺の背中を押した。
「明日もいっぱい虐めてあげますからね、先輩」
そうやっていつも通り俺が小日向家から出ようとした、まさにその時だった。
いつもは開かない玄関のドアが開き、外から開いた。
突然の事に固まる、俺と小日向の前でゆっくりとドアは開き、人影が一つ現れた。
それを見て俺の後ろで小日向が息を呑んだ。
そこに現れたのは高級そうなスーツに身を包んだ、中年らしき男性だった。背は高く、年相応の皺顔に刻まれているが、若々しさを残す外見をしていた。
「……おお、凪。帰ってたのか」
その男は小日向の姿を見ると、淡白にそう言った。
「…………」
小日向はただ彼を見つめながら、黙っているだけだった。
「君は……娘の友達かね?」
そこでようやく我に返った俺は、彼がずっと会う事のなかった小日向の父親であることに気が付いた。
「あ……はい! 娘さんとは仲良くさせていただいてます!」
すぐに俺はその場を取り繕う。小日向のお父さんは俺を興味深げに見つめた後、
「そうか。娘をよろしく頼むぞ」
とだけ言うとそのまま家に上がった。そして硬直する俺達の横をお父さんは素通りし、居間に向かう。
そして引きだしから何かを取り出すと、再び玄関に戻ってきた。
「じゃあ父さんはもう行くから、家の事を頼むぞ、凪」
そのままお父さんは本当に家を出ていった。本当に一瞬で、嵐のような出来事だった。
「…………」
沈黙が続く。
まさかずっと出会う事の無かった小日向の親とこんな風に遭遇するとは……
「……先輩」
きゅ、と弱々しくと背中を摘ままれる。
「……もうちょっと、いっしょにいて貰っても、いいですか?」
そこにいつもの淡々とした口調はなかった。
俺は小日向の家の事情は分からない。だが不安そうに震える彼女を放っておけなかった。
……今になって思えば。
この出来事が後の俺と小日向の運命を決定づけた出来事だったのかもしれない。
奴隷先輩の本懐
今回はエロなしです
「…………」
ついさっき足責めを受けた小日向の部屋に俺はいた。
シーツについたであろう精液はきれいに掃除されており、ベッドは清潔そのものだ。そのベッドの上に俺と小日向は腰を降ろしていた。
「…………」
小日向はずっと喋らない。
俯きながら俺の腕にぴったりとくっついて、袖をきゅっと握っている。
その小さな姿は、いつも感情の起伏が少ない顔で俺を嬲ってくる彼女と同じには見えなかった。
「…………」
このままほっとくわけにはいけない。
俺のすぐそばで震えるこの少女を慰めてあげたい。
彼女が悲しそうだと俺も悲しくなるから……
「なあ、小日向」
俺がそう切り出すと、小日向は体をビクッと震わせ、より体を密着させてくる。
「…………」
小日向は何も言わない。
ただ俺に身体を預けるだけで、何もアクションを起こそうとしない。
……そんなにショックだったのか。
おそらく小日向とあの父親には何か確執めいたものがあるのだろう。だが今はそれを詮索する時じゃない。
といってもかける言葉が見つからない。
だから、
「あっ……」
俺はほとんど衝動的に小日向を抱きしめた。
小日向は驚いたように吐息を漏らすと少しだけ震えた後、俺の胸に顔を埋めた。
――ああ、こんなに小さかったのか。
腕の中で縮こまる小日向を直に感じながら、俺はそう思った。
いつも俺を惑わせ夢中にさせる小日向だけど、やっぱり年頃の女の子であることには変わりない。
せめて少しでも元気になってくれれば……そう考えながら俺は小日向を抱きしめ続けるのだった。
「……ありがとうございます。先輩」
しばらく経ってから小日向はそう言って、俺の胸を離れた。
すぐ目の前で俺を見上げる小日向は、ほんの少しだけ瞳を潤ませていた。
「少しだけ取り乱してしまいました」
目元を手でごしごしすると、小日向はいつもの表情に戻った。
「先輩にこんな姿を見られてしまいました……恥ずかしいです」
そのまま俯いてしまう小日向の肩を掴むと、彼女は顔を上げた。
「そんなことないぞ、小日向。俺、小日向に頼って貰えて嬉しかった」
「先輩……」
父親が家を出ていった後、小日向は俺の背中を摘まんで弱々しく聞いてきた。もうちょっとだけここにいて欲しい、と。
今まで背徳的な行為を行ってきた俺と小日向だが、いつもは俺が小日向に恥ずかしいことをねだるか、小日向が俺に命令することがほとんどだった。
だが今回は小日向が俺を頼ってくれた。突然の出来事に困惑して俺を頼っただけかもしれないが、それでも彼女に必要されたことに喜びを感じていた。
「それに……小日向が悲しそうにしてると、俺も悲しい」
俺は胸の内を正直に話した。それが一番いいと思ったから。
「…………」
すると小日向は再び俯いてしまう。
「……先輩はずるいです」
「え?」
「そんな台詞、今言うなんて先輩はずるいです」
そのまま顔を上げた小日向の頬はうっすらと朱色に染まっていた。
「……ありがとうございます。先輩」
そして小日向は、俺の目の前で。子猫のようににっこりと笑ったのだった。
「……両親は私が中学生の時に離婚しました」
そう言うと小日向はコップに入ったお茶をずずずと啜った。
小日向はベッドの上で暫く俺にくっついて離れなかったが、少し落ち着いたのか一階のリビングに降りた。その際、俺の精液まみれになったパンツを手で洗ってくれた。おかげで俺は乾くまでは下半身全裸だが。
「それ以来、母から連絡はないです。父も……他の女の人の家に泊まるようになって……」
コトン、とコップを置くと小日向は寂しげに微笑んだ。
「この家には私しかいなくなったです」
「…………」
ずっと疑問に思っていた。
俺は何度も小日向の家を訪れたが、そこに彼女の両親はいなかった。何度も通い、一泊したこともあるのに一度も顔を合わせたことが無いのだ。
考えないようにしてきたが、やはり疑問はあった。
「もうあの人たちにとって、私はどうでもいい存在なんだと思います。娘が男の人を家に連れ込んでるのに、あの態度ですから」
小日向は極めて冷静に言った。しかしその瞳は哀しげに揺れており、その姿は痛々しかった。
きっと表面上は平静を保っているが、やっぱりお父さんの態度がショックだったんだろう。
「でも少しだけ取り乱してしまいました。先輩、迷惑をおかけしてすいませんです」
ぺこりと頭を下げる小日向。その姿はいじらしく、小さかった。
想像してみる。
誰もいない家に帰っていく小日向を。一人ぼっちで広い家にいる小日向を。
……それを考えるだけで俺は胸が苦しくなって。
「……なあ、小日向」
「なんですか、先輩」
「またこれからも、この家に来ていいか?」
「…………」
小日向は一瞬驚いた顔をした後、柔らかい笑みを浮かべて答えた。
「……はい」
その後俺達は何だか恥ずかしくなって、暫く静かにお茶を啜り合った。
「そろそろ乾いたですかね」
唐突に小日向はそう言うと席を立った。
そういえば小日向に洗ってもらったパンツがそろそろ乾く頃だ。
そんな事を考えていると、小日向は部屋の出入り口前で俺に向かって振り返った。
「……先輩」
「ん?」
「……好きです」
ほんのりと頬を染めた小日向はそう告げると、部屋を出ていった。
「…………」
俺は後頭部をハンマーで殴られたような衝撃を受けて、そのまま固まってしまっていた。
この日、俺は本当の意味で小日向と繋がりあえたような気がした。
「ふぁ……」
カーテンから差し込む朝日で俺は目を覚ました。欠伸交じりに横の時計を見ると針は7時を指している。まだ時間の余裕があるので、俺はゆっくりとベッドから起き上がった。
ぐっと腕を伸ばしながら俺は昨日の事を思い起こす。
俺を必要としてくれた小日向の笑顔が脳裏に浮かび、思わず笑いがこぼれてしまう。
最初はツンとして俺のことなど歯牙にもかけなかった小日向が、『好き』と言ってくれたのだ。小日向に一目惚れし、彼女の持ち物や臭いにまで執着した俺からすれば、まさに本懐を遂げたといっていいだろう。
俺は軽い足取りで階段を下り、洗顔を済ませてリビングに向かった。
「おはようございます、先輩」
「ええっ!?」
あまりの光景に俺は言葉を失った。
見慣れた食卓にいたのは俺の想い人・小日向凪その人である。
人形のように整った容姿と氷のような表情。小動物を連想させる小柄な体躯と白い肌。間違いなく小日向本人だ。
「な、なんで小日向がここに?」
「朝ごはんの準備をしてるです」
よく見ると彼女はいつもの制服の上にエプロンをつけて、キッチンに立っていた。そのちっちゃな手には包丁が握られている。
「いや、そうじゃなくて何でこの家に……」
「ああ、私が入れてあげたのよ」
横からそう言ったのは母さんだった。
「小日向ちゃん、毎日家まで迎えに来てくれるでしょ。それで今日はいつもより早く来てたから、家に入れてあげたのよ」
母さんはにこにこしながら言った。
「そしたら小日向ちゃん、朝食の準備を手伝ってくれてね。本当にいい子だわ、小日向ちゃん」
毎日家の前までやってくる小日向の事は、母さんも父さんも知っていた。だがこうして直に会って話すのは初めての事だろう。
「聞いてみたらまだ朝ご飯食べてないみたいだから、一緒に食べていかないって誘ったのよ」
だがどうやら母さんは小日向を気に入ったようで、さっきから笑顔で応対している。
「駄目じゃない。彼女を待たせたりしちゃ」
母さんはそう言って俺の肩を叩いた。俺は目の端に少しだけ顔を赤らめる小日向の姿を確認した。
「……これからは先輩のご家族とも仲良くしたいと思いまして」
そう耳打ちするとそのまま小日向は作業に戻っていった。
やがてトーストの小日向が刻んだサラダが登場した所で父さんが姿を現した。
小日向の姿を確認すると父さんは目を丸くし驚いていたが、小日向がすぐに頭を下げて自己紹介すると、笑顔で彼女を受け入れてくれた。
そして俺と両親、小日向を入れた四人の朝食が始ったのだった。
「小日向ちゃんは省吾の彼女なのかい?」
いっきなりぶっこんできた父親の発言に、俺は危うく牛乳を噴きかけた。
「…………」
小日向はもきゅもきゅとトーストを咀嚼すると、少し赤らんで俯いた後、
「……はい。せんぱ……省吾さんとお付き合いさせてもらってるです」
とか細い声で答えた。
一揆に俺の体温が上がる。それは両親も同じだったようだ。小日向の初々しい反応に、揃いも揃って赤面してしまう。
「お義父さんとお義母さん、とてもいい人ですね。先輩が羨ましいです」
固まる俺達を尻目に、小日向はそっと耳元で言った。
……あれ、今『お父さん』と『お母さん』の発音、おかしくなかったか?
そんな事を考えながら俺は小日向と共に朝食を胃袋に入れていったのであった。
今回はエロなしです
「…………」
ついさっき足責めを受けた小日向の部屋に俺はいた。
シーツについたであろう精液はきれいに掃除されており、ベッドは清潔そのものだ。そのベッドの上に俺と小日向は腰を降ろしていた。
「…………」
小日向はずっと喋らない。
俯きながら俺の腕にぴったりとくっついて、袖をきゅっと握っている。
その小さな姿は、いつも感情の起伏が少ない顔で俺を嬲ってくる彼女と同じには見えなかった。
「…………」
このままほっとくわけにはいけない。
俺のすぐそばで震えるこの少女を慰めてあげたい。
彼女が悲しそうだと俺も悲しくなるから……
「なあ、小日向」
俺がそう切り出すと、小日向は体をビクッと震わせ、より体を密着させてくる。
「…………」
小日向は何も言わない。
ただ俺に身体を預けるだけで、何もアクションを起こそうとしない。
……そんなにショックだったのか。
おそらく小日向とあの父親には何か確執めいたものがあるのだろう。だが今はそれを詮索する時じゃない。
といってもかける言葉が見つからない。
だから、
「あっ……」
俺はほとんど衝動的に小日向を抱きしめた。
小日向は驚いたように吐息を漏らすと少しだけ震えた後、俺の胸に顔を埋めた。
――ああ、こんなに小さかったのか。
腕の中で縮こまる小日向を直に感じながら、俺はそう思った。
いつも俺を惑わせ夢中にさせる小日向だけど、やっぱり年頃の女の子であることには変わりない。
せめて少しでも元気になってくれれば……そう考えながら俺は小日向を抱きしめ続けるのだった。
「……ありがとうございます。先輩」
しばらく経ってから小日向はそう言って、俺の胸を離れた。
すぐ目の前で俺を見上げる小日向は、ほんの少しだけ瞳を潤ませていた。
「少しだけ取り乱してしまいました」
目元を手でごしごしすると、小日向はいつもの表情に戻った。
「先輩にこんな姿を見られてしまいました……恥ずかしいです」
そのまま俯いてしまう小日向の肩を掴むと、彼女は顔を上げた。
「そんなことないぞ、小日向。俺、小日向に頼って貰えて嬉しかった」
「先輩……」
父親が家を出ていった後、小日向は俺の背中を摘まんで弱々しく聞いてきた。もうちょっとだけここにいて欲しい、と。
今まで背徳的な行為を行ってきた俺と小日向だが、いつもは俺が小日向に恥ずかしいことをねだるか、小日向が俺に命令することがほとんどだった。
だが今回は小日向が俺を頼ってくれた。突然の出来事に困惑して俺を頼っただけかもしれないが、それでも彼女に必要されたことに喜びを感じていた。
「それに……小日向が悲しそうにしてると、俺も悲しい」
俺は胸の内を正直に話した。それが一番いいと思ったから。
「…………」
すると小日向は再び俯いてしまう。
「……先輩はずるいです」
「え?」
「そんな台詞、今言うなんて先輩はずるいです」
そのまま顔を上げた小日向の頬はうっすらと朱色に染まっていた。
「……ありがとうございます。先輩」
そして小日向は、俺の目の前で。子猫のようににっこりと笑ったのだった。
「……両親は私が中学生の時に離婚しました」
そう言うと小日向はコップに入ったお茶をずずずと啜った。
小日向はベッドの上で暫く俺にくっついて離れなかったが、少し落ち着いたのか一階のリビングに降りた。その際、俺の精液まみれになったパンツを手で洗ってくれた。おかげで俺は乾くまでは下半身全裸だが。
「それ以来、母から連絡はないです。父も……他の女の人の家に泊まるようになって……」
コトン、とコップを置くと小日向は寂しげに微笑んだ。
「この家には私しかいなくなったです」
「…………」
ずっと疑問に思っていた。
俺は何度も小日向の家を訪れたが、そこに彼女の両親はいなかった。何度も通い、一泊したこともあるのに一度も顔を合わせたことが無いのだ。
考えないようにしてきたが、やはり疑問はあった。
「もうあの人たちにとって、私はどうでもいい存在なんだと思います。娘が男の人を家に連れ込んでるのに、あの態度ですから」
小日向は極めて冷静に言った。しかしその瞳は哀しげに揺れており、その姿は痛々しかった。
きっと表面上は平静を保っているが、やっぱりお父さんの態度がショックだったんだろう。
「でも少しだけ取り乱してしまいました。先輩、迷惑をおかけしてすいませんです」
ぺこりと頭を下げる小日向。その姿はいじらしく、小さかった。
想像してみる。
誰もいない家に帰っていく小日向を。一人ぼっちで広い家にいる小日向を。
……それを考えるだけで俺は胸が苦しくなって。
「……なあ、小日向」
「なんですか、先輩」
「またこれからも、この家に来ていいか?」
「…………」
小日向は一瞬驚いた顔をした後、柔らかい笑みを浮かべて答えた。
「……はい」
その後俺達は何だか恥ずかしくなって、暫く静かにお茶を啜り合った。
「そろそろ乾いたですかね」
唐突に小日向はそう言うと席を立った。
そういえば小日向に洗ってもらったパンツがそろそろ乾く頃だ。
そんな事を考えていると、小日向は部屋の出入り口前で俺に向かって振り返った。
「……先輩」
「ん?」
「……好きです」
ほんのりと頬を染めた小日向はそう告げると、部屋を出ていった。
「…………」
俺は後頭部をハンマーで殴られたような衝撃を受けて、そのまま固まってしまっていた。
この日、俺は本当の意味で小日向と繋がりあえたような気がした。
「ふぁ……」
カーテンから差し込む朝日で俺は目を覚ました。欠伸交じりに横の時計を見ると針は7時を指している。まだ時間の余裕があるので、俺はゆっくりとベッドから起き上がった。
ぐっと腕を伸ばしながら俺は昨日の事を思い起こす。
俺を必要としてくれた小日向の笑顔が脳裏に浮かび、思わず笑いがこぼれてしまう。
最初はツンとして俺のことなど歯牙にもかけなかった小日向が、『好き』と言ってくれたのだ。小日向に一目惚れし、彼女の持ち物や臭いにまで執着した俺からすれば、まさに本懐を遂げたといっていいだろう。
俺は軽い足取りで階段を下り、洗顔を済ませてリビングに向かった。
「おはようございます、先輩」
「ええっ!?」
あまりの光景に俺は言葉を失った。
見慣れた食卓にいたのは俺の想い人・小日向凪その人である。
人形のように整った容姿と氷のような表情。小動物を連想させる小柄な体躯と白い肌。間違いなく小日向本人だ。
「な、なんで小日向がここに?」
「朝ごはんの準備をしてるです」
よく見ると彼女はいつもの制服の上にエプロンをつけて、キッチンに立っていた。そのちっちゃな手には包丁が握られている。
「いや、そうじゃなくて何でこの家に……」
「ああ、私が入れてあげたのよ」
横からそう言ったのは母さんだった。
「小日向ちゃん、毎日家まで迎えに来てくれるでしょ。それで今日はいつもより早く来てたから、家に入れてあげたのよ」
母さんはにこにこしながら言った。
「そしたら小日向ちゃん、朝食の準備を手伝ってくれてね。本当にいい子だわ、小日向ちゃん」
毎日家の前までやってくる小日向の事は、母さんも父さんも知っていた。だがこうして直に会って話すのは初めての事だろう。
「聞いてみたらまだ朝ご飯食べてないみたいだから、一緒に食べていかないって誘ったのよ」
だがどうやら母さんは小日向を気に入ったようで、さっきから笑顔で応対している。
「駄目じゃない。彼女を待たせたりしちゃ」
母さんはそう言って俺の肩を叩いた。俺は目の端に少しだけ顔を赤らめる小日向の姿を確認した。
「……これからは先輩のご家族とも仲良くしたいと思いまして」
そう耳打ちするとそのまま小日向は作業に戻っていった。
やがてトーストの小日向が刻んだサラダが登場した所で父さんが姿を現した。
小日向の姿を確認すると父さんは目を丸くし驚いていたが、小日向がすぐに頭を下げて自己紹介すると、笑顔で彼女を受け入れてくれた。
そして俺と両親、小日向を入れた四人の朝食が始ったのだった。
「小日向ちゃんは省吾の彼女なのかい?」
いっきなりぶっこんできた父親の発言に、俺は危うく牛乳を噴きかけた。
「…………」
小日向はもきゅもきゅとトーストを咀嚼すると、少し赤らんで俯いた後、
「……はい。せんぱ……省吾さんとお付き合いさせてもらってるです」
とか細い声で答えた。
一揆に俺の体温が上がる。それは両親も同じだったようだ。小日向の初々しい反応に、揃いも揃って赤面してしまう。
「お義父さんとお義母さん、とてもいい人ですね。先輩が羨ましいです」
固まる俺達を尻目に、小日向はそっと耳元で言った。
……あれ、今『お父さん』と『お母さん』の発音、おかしくなかったか?
そんな事を考えながら俺は小日向と共に朝食を胃袋に入れていったのであった。
奴隷先輩の初デート
小日向の家で俺と彼女がお互いの気持ちを確かめ合ってから、すでに二週間近くが経とうとしていた。
しかし相思相愛になった俺達だが、普段の生活にそう変化はなかった。
朝は毎日小日向が俺の家までやってきて、腕を組んで一緒に登校する。昼は人気のない校舎の影で、小日向の体臭を嗅ぎながら昼食。放課後は彼女の家で気のすむまで臭いプレイを行う。
……よく考えてみると、前とあんまり変わってないな。そういう意味では俺と小日向はずっと前から恋人同士……だったのだろうか?
勿論、変わったこともあった。
小日向は、よく我が家にご飯を食べに来るようになった。小日向を気に入った両親が、彼女が一人暮らしに近い生活をしていることを知り、頻繁に食事に誘うようになったからだ。
今や俺の家の食卓は両親と俺、そして小日向がデフォだ。小日向はすっかり両親と仲良くなり、母さんの料理や食器洗いを手伝っている。
キッチンでエプロンをつけて家事をする小日向の姿は、まるで新妻のようで俺は落ち着かなかった。
「凪ちゃんが省吾のお嫁さんのなってくれればいいのにねー」
母さんがそんな冗談を言うたびに、小日向は無表情のまま耳を真っ赤に染めた。
両親は小日向を気に入り、名前で呼ぶようになった。そして、小日向がいない所で、頻繁に俺達の進展を聞いてくる。
「なあ、省吾。凪ちゃんはいい子だぞ。お前には勿体ない位の子だ。大切にしろよ」
「そうよ、省吾。凪ちゃんを悲しませたりしたら、お母さん許さないわよ」
両親は完全に小日向の味方だった。そして小日向も俺の両親を慕い始めていた。
そんな中だった。
「そういえば、省吾。あんた凪ちゃんとデートしたことあるの?」
母が爆弾を投下したのは。
それから一週間近く経った日曜日。
俺は駅前の広場で小日向を待っていた。
時刻は間もなく11時を回る。俺は腕時計とにらめっこしながら、自分の格好を再度、確認する。普通のシャツにジーパン。きっと大丈夫なはずだ。変じゃないはず……
「先輩」
その声に俺はがばっと顔を上げた。そして目の前には天使がいた。
透き通るような白い肌に子猫を思わせる大きな瞳と体躯。短めに整った黒髪に、表情が掴み辛い童顔。
俺の待ち人であり一目ぼれの相手でありご主人様である、小日向凪だった。
今日の小日向は白地のTシャツの上に半袖の女性向けGジャンを羽織り、デニムのミニを身につけ黒のストッキングに茶色のブーツを履いている。
俺も初めて見る、小日向の余所行きの私服姿だった。
「…………」
俺は言葉を失った。あまりにも小日向の私服姿が可愛らしかったから……
「待ちました?」
小日向は俺の元にぱたぱたと駆け寄ってきて尋ねた。俺はようやくそこで正気を取り戻した。
「い、いや、別に」
俺は少しだけ小日向から目を逸らす。小日向の可愛さと緊張から、彼女を直視できないのだ。
「そうですか」
そう淡白に言うと小日向は俺の腕に手を回す。
「行きましょうか、先輩」
「あ、ああ……」
お互い何かとぎくしゃくしながら、俺達は初めてのデートを開始するのだった。
母の一言の後、俺は小日向と何だかんだで恋人らしいことをまるでやっていないことに気が付いた。
なんせそんなものをすっ飛ばして、マニアックな臭いプレイに勤しんでいたのだから。
勿論プレイ自体に文句はないが、小日向と普通の恋人みたいなデートをしてみたいという気持ちが俺にもあった。
だから誘ってみた。『週末に二人でどこか遊びに行かないか』と。それを聞いた小日向は最初驚いたように目を見開いたが、やがて顔を赤くしながらコクンと頷いた。
そして俺達は約束を交わし、今にいたる。
「…………」
小日向はいつも通り無表情――少しだけ頬を染めていたが――で一言も喋らない。元々無口な子だが、今日はいつにも増して喋らない。そしていつも以上に緊張する。
「な、なあ……」
続く沈黙に耐えきれず、俺は口火を切った。小日向は黙ったままだ。
「きょ、今日は温かいな」
「……そうですね」
「き、昨日はそんなにだったのにな」
「……そうですね」
「…………」
駄目だ。全く会話が続かない。それに緊張してしまう。小日向の些細な表情に自然と注目し、一挙一動が気になってしょうがない。
「……先輩」
「あっ……なんだ、小日向?」
小日向は不意に顔を上げると、上目使いで言った。
「今日は何処に行くですか?」
「え……ああ、まずは映画を見て……それから昼飯食ってからカラオケかゲーセンかな……」
これは昨日一馬に音無さんとどんなデートをしているかを聞いて考えた、俺のデートプランだ。割とスタンダードなデートだと思う……多分。
「そうですか……」
それっきり小日向は再び俯いて黙ってしまう。俺も中々会話を切り出せず、無言のまま俺達は映画館に向かうのだった。
二人で券を買い、映画館内へ。とりあえずデートに無難そうな、一般向けの恋愛映画をチョイス。最近売れたらしい恋愛小説を実写化したもので、女子の間でかなり人気があるらしい。
色んな小説を読んで目の肥えた小日向に受けるかどうかは心配だったけど、割とベタな内容で中々面白かった。小日向も最後まで普通に見てたので多分、大丈夫だと思う。
その後は音無さんから教えてもらったお洒落でちょっと高めのレストランで、昼食を取った。取り放題のサラダバーを気にいったのか、皿に山盛りにされた野菜を瞳を輝かせながら咀嚼する小日向が見れて、俺はひとまず安心した。
食後は小日向の提案で、近くにある大型のショッピングモールへ。様々な店が立ち並び、ゲームセンターやレストラン街もあるため、非常に便利が良い場所だ。賑やかで歩くだけでも楽しい。
その中にある、本屋へ小日向は向かった。小日向が贔屓にしている小説家の新作を二人で探し、面白い本はないかと店内を散策した。
気が付くと既に時計の針は三時を指していた。
休憩も兼ねてショッピングモールから離れ、近くの広い公園へ向かった。休日ということもあり、家族連れやカップルが多くて賑やかだった。そんな公園の芝生の上に腰を降ろす。
「…………」
隣りにちょこんと座る小日向を横目で窺う。今日一日小日向はぴったりと俺にくっついていたが、普段以上に口を開かなかった。表情も時折頬を染める程度で、俯いてることも多かった。もしかしてつまらなかったのか、それとも俺と同じで緊張していたのか……分からないから不安になってしまう。
「……先輩」
「え、ああ、な、何?」
俺はそんな風に悩んでいると、小日向はそれを見透かすような澄んだ瞳で、俺を見据えてきた。
「どうしたですか?」
「い、いや、なんでもないぞ」
まさか自分のデートに自信が持てなくなってきたとはいえまい。あまりにも情けないし、恥ずかしい。
そう思っていた俺の心中を察したのか、小日向はふっと微笑した。
「先輩。私、男の人とデートするのは今日が初めてでした」
「お、おう」
「先輩と二人で映画を見て、ご飯食べて……」
「…………」
「……今日は楽しかったです」
「!」
はにかみながら小日向は俺の手をぎゅっと握る。小さく温かな掌が俺の手を優しく包み込む。小日向のその一言で、俺は今まで胸の内にあったもやもやが一気に霧散してゆく。
「だから、また一緒に遊ぶです」
「こ、小日向!」
思わず抱きしめたくなる。そんな俺の気持ちを見透かしたのか、小日向は両手を伸ばした。恥も外聞も投げ捨て、小日向を抱きしめる。周りの目など知ったことか。小さな体をぎゅっと抱き寄せる。柔らかい感触とほのかな温かみが、腕の中すっぽりと収まった。
そんな俺の耳元で。小日向は静かに囁いた。
「だから……今日はご褒美をあげますね」
「ほ、ほんとにいいのか?」
小日向に手を引かれて辿り着いた先は、駅の裏にある静かなホテル街。その中でもビジネスホテルとは違った装飾の、ホテルの前で俺は小日向に尋ねた。
「はいですよ……それとも嫌ですか?」
「そっそんなわけないだろ!」
狼狽する俺を小日向はくすりと笑った。そして俺の手をぎゅっと握ると、ホテルの入り口へと赴く。
「たっぷりとご褒美をあげますからね」
個室に入り、小日向はベッドに腰を降ろす。俺はその足元に正座した。
「先輩も自分の身分が分かってきたようですね」
憐れむような微笑を湛えて小日向は俺の頭を軽く撫でると、ブーツを履いた足を突き出した。俺はその動作だけで彼女の真意を悟り、手で丁寧にブーツを脱がしてゆく。
黒いストッキングに包まれた小さな足が晒される。皮の籠った臭いがほのかに香った。
「……今日はいっぱい歩きましたからね……きっとすごく臭うですよ。ブーツだから尚更です」
突き出された足をゆらゆらと揺らしながら、小日向は俺を誘惑する。薄いパンストの生地からは彼女の白い足が透けて見えていた。
「……釘付けですね。そんなに足を臭いたいですか?」
俺は無言で頷く。小日向はそれを馬鹿にしたような目で見下ろした後、
「では、どうぞ。好きなだけ嗅いでいいですよ」
ぐい、と俺の顔を踏みにじった。
「~~~~ッ!」
その瞬間、いつもの靴下をはるかに超える、強烈な臭いが俺の鼻腔に充満した。
ブーツで蒸れて染みだした汗の湿気が、パンストをほんのりと温め、湿ったような感触を与えてくれる。
俺は我を忘れて小日向の足裏で呼吸を繰り返す。少しでも多く彼女の足臭を味わうべく、何度も何度も鼻で空気を吸い込む。
「…………全く、相変わらず気持ち悪いですね」
足をぐりぐりと動かしながら、小日向は軽蔑しきった声色で言った。
「そんなに必死になって……普段以上に発酵した足はおいしいですか?」
顔面をストッキングで蹂躙しながら小日向は問いかける。俺は肯定の意を込めて、彼女の足裏に軽く口づけをした。
「――ッ! そうですか。こんなに臭そうで汚そうで、汗まみれの足がそんなに好きですか」
一瞬、息を呑んだ小日向は、より乱暴に俺の顔面を踏みにじる。その声は少し上ずっており、罵倒の言葉にも熱がこもった。
「……そんなに嗅ぎたいなら、もっと嗅がせてあげますよ」
小日向は不意に足を引込めた。
「あっ……」
麗しのストッキングが視界から消え、代わりに現れたのは頬を上気させ、サディスティックに瞳を輝かせる小日向の顔があった。
「服を脱ぐですよ、先輩」
小日向の命令に、俺はすぐに来ていた服を手にかけた。俺が全裸になったことを確認すると、小日向は自身が座っているベッドの横を軽くポンポンと叩いた。
「きてください」
俺は興奮を抑えながら、小日向の隣に正座する。小日向は視線を俺の下半身に視線を移す。そして既に勃起していることを確認したのか、満足げに口を吊り上げた。
「もう勃起してますね……でも勝手に射精しちゃ駄目ですよ」
そう言いながら小日向は、履いていたストッキングをするすると脱いでゆく。たちまち白い小日向の生足が露わになり、その艶めかしさに俺は釘付けとなる。
そんな俺を尻目に、小日向は脱いだストッキングを丸めると俺の口元に差し出した。
「はい、先輩。あーん、です」
その言葉で反射的に開いた俺の口に、小日向はストッキングをねじ入れた。
「先輩が大好きな私の匂いの染みついたモノですよ。いっぱい味わってくださいね」
それはまさに未知の味だった。布の感触が口いっぱいに広がり、香ばしい香りが口内に満たされる。
思わず噛むと、小日向の汗が布から染みだし、舌の上に流れ込んだ。
まるで小日向の足の臭いと感触を凝縮したような味。俺は出来るだけこの甘露を味わえるように、ゆっくりとストッキングを舐めはじめた。
「……油断してたら駄目ですよ」
耳元で小日向の声がした。気が付くと、彼女は俺の後ろに回っていた。
小日向はそのまま後ろから俺を抱き抱える様に密着すると、細い足で俺の体を挟み、そのつま先を俺の股間へ向けた。
「先輩のおちんちん、捕まえちゃいますね」
そう言った瞬間、小日向の足が俺の怒張したペニスを捕えた。そしてちっちゃな足指で肉棒を摘まむと、上下に扱き始める。
その足は汗で少し湿っており、既に染みだしていたガマン汁と混ざり合って、くちゅくちゅと卑猥な音が漏れ始めた。
「どうです、先輩? 変態の先輩には天国だと思うですが」
耳元で甘い吐息を吹きかけながら、小日向はそう囁いた。体が密着している為、背中に否応が無しに小日向の柔らかい感触を感じてしまう。
そして彼女によってねじ込まれたストッキングは俺の唾液を吸って、より強い臭いを出すようになり、汗とカウパーでドロドロになった肉棒は爆発寸前であった。
確かにこれは天国だ。
小日向の臭いにまみれながら、小日向の体を直に感じることが出来るなんて……
「段々息があがってるですよ」
片方の指で竿を、片方の指で玉を。小日向は弄りはじめる。
淫液まみれのペニスをぐちゅぐちゅとしごきながら、パンパンになった睾丸を踏みにじるかの如く弄繰り回す。
もう駄目だ。射精する……しかし俺の射精は小日向によって掌握されている。彼女の許可なしで射精するわけにはいかない。そう思い、俺はぐっと耐える。だが我慢すれば我慢するほど、小日向の責めはより苛烈になってゆく。
「ガマンしてるですか、先輩」
小日向が俺の苦しそうな顔に気が付いたのか、そう呟く。
「……好きなだけイっていいですよ、先輩。今日はご褒美です」
そう言うと小日向は俺の耳たぶを甘噛みした。
「――ッ~~~~~~~!!」
唐突に襲いかかった甘美な痛覚に、俺の体は弓のようにしなり、快楽の波が一気に全身を駆け巡った。塞き止めていた精液が一気に噴出し、目の前が激しくスパークする。
溜まりに溜まった精液が止めどなく溢れ、小日向の足とベッドのシーツを汚してゆく。
やがて絶頂の痙攣が収まってゆき、上がった息が徐々に落ち着いてゆく。
が、
「んんんんんんんんーッ!!」
精液を出し尽くし、萎びはじめていた肉棒を小日向の足指が挟みこむ。
「まだですよ、先輩。中のザーメン、全部出すです」
意地悪げに小日向は言うと、再び指を上下に動かし始める。
既に精液まみれぐちゅぐちゅに汚れた肉棒を、足でさらにぐちゅぐちゅにしながら、小日向は足コキを再開する。
「こ、小日向! まだ俺、出したばかり……」
「はい。でも暫く我慢させてたので、いっぱい溜まってるですね?」
確かに俺は小日向と恋人になって以来、射精を禁止されていた。恋人同士になったが、奴隷という扱いは変わらず、俺は小日向に射精を制限されていたのだ。
「だから……好きなだけ射精して下さい。初デート記念……ですっ」
ぎゅーっと玉を抓られる。その瞬間、俺は再び絶頂を迎えた。
しかし小さな支配者は奴隷の休息を許さない。
俺は射精するたびに何度も性器を扱かれた。時に耳たぶを舐められたり、時に乳首を弄られたりして、また勃起させられ絶頂まで導かれる。意識が何度も飛びかけるも、その度に睾丸を抓られたりして強制的に意識を取り戻される。
その拷問じみた搾精は俺のタンクが空になるまで続くのだった。
すっかり日が暮れた頃、俺達はホテルと出た。
小日向に散々射精させられ、精根尽き果てた俺は小日向の腕を引かれながら帰路に着いていた。
「先輩、辛いなら送ってくれなくても大丈夫ですよ?」
「いや、さすがに彼女は送らないと駄目だろ……」
「強がりですね……ふふ」
互いに軽口を叩きつつ、のんびりと薄暗い街並みを歩く。今日は一日いろいろあったが、俺はとても充実していたと思えた。
チラリと小日向を見る。口ではああ言っていたが、彼女は本当に楽しかったのだろうか。
そんな風に考えていると、気が付けば小日向の自宅前に到着していた。
「ここまでありがとうございます」
腕から離れ、俺に向き合うと、小日向はそう言った。
「……先輩、ここでお別れですね」
「ああ、そうだな」
名残惜しいが、楽しい時間はいつか終わる。俺は寂しさを感じながら、小日向と別れた――その時だった。
「先輩」
「え?」
突如後ろから呼び止められ、後ろを振り返る。その一瞬、俺の頬に柔らかい衝撃が走った。
すぐそばに小日向の可愛らしい童顔が迫る。閉じられた眼が迫る。小ぶりな鼻が迫る。そして桜色の唇が限界まで迫り、そして離れてゆく。
「……今日のお礼ですよ」
はにかみながらそれだけ言うと、小日向は小走りで家に入っていった。
「…………」
残された俺は。
状況を理解するのに数秒を要し。そして一気に体温が上がるのだった。
小日向の家で俺と彼女がお互いの気持ちを確かめ合ってから、すでに二週間近くが経とうとしていた。
しかし相思相愛になった俺達だが、普段の生活にそう変化はなかった。
朝は毎日小日向が俺の家までやってきて、腕を組んで一緒に登校する。昼は人気のない校舎の影で、小日向の体臭を嗅ぎながら昼食。放課後は彼女の家で気のすむまで臭いプレイを行う。
……よく考えてみると、前とあんまり変わってないな。そういう意味では俺と小日向はずっと前から恋人同士……だったのだろうか?
勿論、変わったこともあった。
小日向は、よく我が家にご飯を食べに来るようになった。小日向を気に入った両親が、彼女が一人暮らしに近い生活をしていることを知り、頻繁に食事に誘うようになったからだ。
今や俺の家の食卓は両親と俺、そして小日向がデフォだ。小日向はすっかり両親と仲良くなり、母さんの料理や食器洗いを手伝っている。
キッチンでエプロンをつけて家事をする小日向の姿は、まるで新妻のようで俺は落ち着かなかった。
「凪ちゃんが省吾のお嫁さんのなってくれればいいのにねー」
母さんがそんな冗談を言うたびに、小日向は無表情のまま耳を真っ赤に染めた。
両親は小日向を気に入り、名前で呼ぶようになった。そして、小日向がいない所で、頻繁に俺達の進展を聞いてくる。
「なあ、省吾。凪ちゃんはいい子だぞ。お前には勿体ない位の子だ。大切にしろよ」
「そうよ、省吾。凪ちゃんを悲しませたりしたら、お母さん許さないわよ」
両親は完全に小日向の味方だった。そして小日向も俺の両親を慕い始めていた。
そんな中だった。
「そういえば、省吾。あんた凪ちゃんとデートしたことあるの?」
母が爆弾を投下したのは。
それから一週間近く経った日曜日。
俺は駅前の広場で小日向を待っていた。
時刻は間もなく11時を回る。俺は腕時計とにらめっこしながら、自分の格好を再度、確認する。普通のシャツにジーパン。きっと大丈夫なはずだ。変じゃないはず……
「先輩」
その声に俺はがばっと顔を上げた。そして目の前には天使がいた。
透き通るような白い肌に子猫を思わせる大きな瞳と体躯。短めに整った黒髪に、表情が掴み辛い童顔。
俺の待ち人であり一目ぼれの相手でありご主人様である、小日向凪だった。
今日の小日向は白地のTシャツの上に半袖の女性向けGジャンを羽織り、デニムのミニを身につけ黒のストッキングに茶色のブーツを履いている。
俺も初めて見る、小日向の余所行きの私服姿だった。
「…………」
俺は言葉を失った。あまりにも小日向の私服姿が可愛らしかったから……
「待ちました?」
小日向は俺の元にぱたぱたと駆け寄ってきて尋ねた。俺はようやくそこで正気を取り戻した。
「い、いや、別に」
俺は少しだけ小日向から目を逸らす。小日向の可愛さと緊張から、彼女を直視できないのだ。
「そうですか」
そう淡白に言うと小日向は俺の腕に手を回す。
「行きましょうか、先輩」
「あ、ああ……」
お互い何かとぎくしゃくしながら、俺達は初めてのデートを開始するのだった。
母の一言の後、俺は小日向と何だかんだで恋人らしいことをまるでやっていないことに気が付いた。
なんせそんなものをすっ飛ばして、マニアックな臭いプレイに勤しんでいたのだから。
勿論プレイ自体に文句はないが、小日向と普通の恋人みたいなデートをしてみたいという気持ちが俺にもあった。
だから誘ってみた。『週末に二人でどこか遊びに行かないか』と。それを聞いた小日向は最初驚いたように目を見開いたが、やがて顔を赤くしながらコクンと頷いた。
そして俺達は約束を交わし、今にいたる。
「…………」
小日向はいつも通り無表情――少しだけ頬を染めていたが――で一言も喋らない。元々無口な子だが、今日はいつにも増して喋らない。そしていつも以上に緊張する。
「な、なあ……」
続く沈黙に耐えきれず、俺は口火を切った。小日向は黙ったままだ。
「きょ、今日は温かいな」
「……そうですね」
「き、昨日はそんなにだったのにな」
「……そうですね」
「…………」
駄目だ。全く会話が続かない。それに緊張してしまう。小日向の些細な表情に自然と注目し、一挙一動が気になってしょうがない。
「……先輩」
「あっ……なんだ、小日向?」
小日向は不意に顔を上げると、上目使いで言った。
「今日は何処に行くですか?」
「え……ああ、まずは映画を見て……それから昼飯食ってからカラオケかゲーセンかな……」
これは昨日一馬に音無さんとどんなデートをしているかを聞いて考えた、俺のデートプランだ。割とスタンダードなデートだと思う……多分。
「そうですか……」
それっきり小日向は再び俯いて黙ってしまう。俺も中々会話を切り出せず、無言のまま俺達は映画館に向かうのだった。
二人で券を買い、映画館内へ。とりあえずデートに無難そうな、一般向けの恋愛映画をチョイス。最近売れたらしい恋愛小説を実写化したもので、女子の間でかなり人気があるらしい。
色んな小説を読んで目の肥えた小日向に受けるかどうかは心配だったけど、割とベタな内容で中々面白かった。小日向も最後まで普通に見てたので多分、大丈夫だと思う。
その後は音無さんから教えてもらったお洒落でちょっと高めのレストランで、昼食を取った。取り放題のサラダバーを気にいったのか、皿に山盛りにされた野菜を瞳を輝かせながら咀嚼する小日向が見れて、俺はひとまず安心した。
食後は小日向の提案で、近くにある大型のショッピングモールへ。様々な店が立ち並び、ゲームセンターやレストラン街もあるため、非常に便利が良い場所だ。賑やかで歩くだけでも楽しい。
その中にある、本屋へ小日向は向かった。小日向が贔屓にしている小説家の新作を二人で探し、面白い本はないかと店内を散策した。
気が付くと既に時計の針は三時を指していた。
休憩も兼ねてショッピングモールから離れ、近くの広い公園へ向かった。休日ということもあり、家族連れやカップルが多くて賑やかだった。そんな公園の芝生の上に腰を降ろす。
「…………」
隣りにちょこんと座る小日向を横目で窺う。今日一日小日向はぴったりと俺にくっついていたが、普段以上に口を開かなかった。表情も時折頬を染める程度で、俯いてることも多かった。もしかしてつまらなかったのか、それとも俺と同じで緊張していたのか……分からないから不安になってしまう。
「……先輩」
「え、ああ、な、何?」
俺はそんな風に悩んでいると、小日向はそれを見透かすような澄んだ瞳で、俺を見据えてきた。
「どうしたですか?」
「い、いや、なんでもないぞ」
まさか自分のデートに自信が持てなくなってきたとはいえまい。あまりにも情けないし、恥ずかしい。
そう思っていた俺の心中を察したのか、小日向はふっと微笑した。
「先輩。私、男の人とデートするのは今日が初めてでした」
「お、おう」
「先輩と二人で映画を見て、ご飯食べて……」
「…………」
「……今日は楽しかったです」
「!」
はにかみながら小日向は俺の手をぎゅっと握る。小さく温かな掌が俺の手を優しく包み込む。小日向のその一言で、俺は今まで胸の内にあったもやもやが一気に霧散してゆく。
「だから、また一緒に遊ぶです」
「こ、小日向!」
思わず抱きしめたくなる。そんな俺の気持ちを見透かしたのか、小日向は両手を伸ばした。恥も外聞も投げ捨て、小日向を抱きしめる。周りの目など知ったことか。小さな体をぎゅっと抱き寄せる。柔らかい感触とほのかな温かみが、腕の中すっぽりと収まった。
そんな俺の耳元で。小日向は静かに囁いた。
「だから……今日はご褒美をあげますね」
「ほ、ほんとにいいのか?」
小日向に手を引かれて辿り着いた先は、駅の裏にある静かなホテル街。その中でもビジネスホテルとは違った装飾の、ホテルの前で俺は小日向に尋ねた。
「はいですよ……それとも嫌ですか?」
「そっそんなわけないだろ!」
狼狽する俺を小日向はくすりと笑った。そして俺の手をぎゅっと握ると、ホテルの入り口へと赴く。
「たっぷりとご褒美をあげますからね」
個室に入り、小日向はベッドに腰を降ろす。俺はその足元に正座した。
「先輩も自分の身分が分かってきたようですね」
憐れむような微笑を湛えて小日向は俺の頭を軽く撫でると、ブーツを履いた足を突き出した。俺はその動作だけで彼女の真意を悟り、手で丁寧にブーツを脱がしてゆく。
黒いストッキングに包まれた小さな足が晒される。皮の籠った臭いがほのかに香った。
「……今日はいっぱい歩きましたからね……きっとすごく臭うですよ。ブーツだから尚更です」
突き出された足をゆらゆらと揺らしながら、小日向は俺を誘惑する。薄いパンストの生地からは彼女の白い足が透けて見えていた。
「……釘付けですね。そんなに足を臭いたいですか?」
俺は無言で頷く。小日向はそれを馬鹿にしたような目で見下ろした後、
「では、どうぞ。好きなだけ嗅いでいいですよ」
ぐい、と俺の顔を踏みにじった。
「~~~~ッ!」
その瞬間、いつもの靴下をはるかに超える、強烈な臭いが俺の鼻腔に充満した。
ブーツで蒸れて染みだした汗の湿気が、パンストをほんのりと温め、湿ったような感触を与えてくれる。
俺は我を忘れて小日向の足裏で呼吸を繰り返す。少しでも多く彼女の足臭を味わうべく、何度も何度も鼻で空気を吸い込む。
「…………全く、相変わらず気持ち悪いですね」
足をぐりぐりと動かしながら、小日向は軽蔑しきった声色で言った。
「そんなに必死になって……普段以上に発酵した足はおいしいですか?」
顔面をストッキングで蹂躙しながら小日向は問いかける。俺は肯定の意を込めて、彼女の足裏に軽く口づけをした。
「――ッ! そうですか。こんなに臭そうで汚そうで、汗まみれの足がそんなに好きですか」
一瞬、息を呑んだ小日向は、より乱暴に俺の顔面を踏みにじる。その声は少し上ずっており、罵倒の言葉にも熱がこもった。
「……そんなに嗅ぎたいなら、もっと嗅がせてあげますよ」
小日向は不意に足を引込めた。
「あっ……」
麗しのストッキングが視界から消え、代わりに現れたのは頬を上気させ、サディスティックに瞳を輝かせる小日向の顔があった。
「服を脱ぐですよ、先輩」
小日向の命令に、俺はすぐに来ていた服を手にかけた。俺が全裸になったことを確認すると、小日向は自身が座っているベッドの横を軽くポンポンと叩いた。
「きてください」
俺は興奮を抑えながら、小日向の隣に正座する。小日向は視線を俺の下半身に視線を移す。そして既に勃起していることを確認したのか、満足げに口を吊り上げた。
「もう勃起してますね……でも勝手に射精しちゃ駄目ですよ」
そう言いながら小日向は、履いていたストッキングをするすると脱いでゆく。たちまち白い小日向の生足が露わになり、その艶めかしさに俺は釘付けとなる。
そんな俺を尻目に、小日向は脱いだストッキングを丸めると俺の口元に差し出した。
「はい、先輩。あーん、です」
その言葉で反射的に開いた俺の口に、小日向はストッキングをねじ入れた。
「先輩が大好きな私の匂いの染みついたモノですよ。いっぱい味わってくださいね」
それはまさに未知の味だった。布の感触が口いっぱいに広がり、香ばしい香りが口内に満たされる。
思わず噛むと、小日向の汗が布から染みだし、舌の上に流れ込んだ。
まるで小日向の足の臭いと感触を凝縮したような味。俺は出来るだけこの甘露を味わえるように、ゆっくりとストッキングを舐めはじめた。
「……油断してたら駄目ですよ」
耳元で小日向の声がした。気が付くと、彼女は俺の後ろに回っていた。
小日向はそのまま後ろから俺を抱き抱える様に密着すると、細い足で俺の体を挟み、そのつま先を俺の股間へ向けた。
「先輩のおちんちん、捕まえちゃいますね」
そう言った瞬間、小日向の足が俺の怒張したペニスを捕えた。そしてちっちゃな足指で肉棒を摘まむと、上下に扱き始める。
その足は汗で少し湿っており、既に染みだしていたガマン汁と混ざり合って、くちゅくちゅと卑猥な音が漏れ始めた。
「どうです、先輩? 変態の先輩には天国だと思うですが」
耳元で甘い吐息を吹きかけながら、小日向はそう囁いた。体が密着している為、背中に否応が無しに小日向の柔らかい感触を感じてしまう。
そして彼女によってねじ込まれたストッキングは俺の唾液を吸って、より強い臭いを出すようになり、汗とカウパーでドロドロになった肉棒は爆発寸前であった。
確かにこれは天国だ。
小日向の臭いにまみれながら、小日向の体を直に感じることが出来るなんて……
「段々息があがってるですよ」
片方の指で竿を、片方の指で玉を。小日向は弄りはじめる。
淫液まみれのペニスをぐちゅぐちゅとしごきながら、パンパンになった睾丸を踏みにじるかの如く弄繰り回す。
もう駄目だ。射精する……しかし俺の射精は小日向によって掌握されている。彼女の許可なしで射精するわけにはいかない。そう思い、俺はぐっと耐える。だが我慢すれば我慢するほど、小日向の責めはより苛烈になってゆく。
「ガマンしてるですか、先輩」
小日向が俺の苦しそうな顔に気が付いたのか、そう呟く。
「……好きなだけイっていいですよ、先輩。今日はご褒美です」
そう言うと小日向は俺の耳たぶを甘噛みした。
「――ッ~~~~~~~!!」
唐突に襲いかかった甘美な痛覚に、俺の体は弓のようにしなり、快楽の波が一気に全身を駆け巡った。塞き止めていた精液が一気に噴出し、目の前が激しくスパークする。
溜まりに溜まった精液が止めどなく溢れ、小日向の足とベッドのシーツを汚してゆく。
やがて絶頂の痙攣が収まってゆき、上がった息が徐々に落ち着いてゆく。
が、
「んんんんんんんんーッ!!」
精液を出し尽くし、萎びはじめていた肉棒を小日向の足指が挟みこむ。
「まだですよ、先輩。中のザーメン、全部出すです」
意地悪げに小日向は言うと、再び指を上下に動かし始める。
既に精液まみれぐちゅぐちゅに汚れた肉棒を、足でさらにぐちゅぐちゅにしながら、小日向は足コキを再開する。
「こ、小日向! まだ俺、出したばかり……」
「はい。でも暫く我慢させてたので、いっぱい溜まってるですね?」
確かに俺は小日向と恋人になって以来、射精を禁止されていた。恋人同士になったが、奴隷という扱いは変わらず、俺は小日向に射精を制限されていたのだ。
「だから……好きなだけ射精して下さい。初デート記念……ですっ」
ぎゅーっと玉を抓られる。その瞬間、俺は再び絶頂を迎えた。
しかし小さな支配者は奴隷の休息を許さない。
俺は射精するたびに何度も性器を扱かれた。時に耳たぶを舐められたり、時に乳首を弄られたりして、また勃起させられ絶頂まで導かれる。意識が何度も飛びかけるも、その度に睾丸を抓られたりして強制的に意識を取り戻される。
その拷問じみた搾精は俺のタンクが空になるまで続くのだった。
すっかり日が暮れた頃、俺達はホテルと出た。
小日向に散々射精させられ、精根尽き果てた俺は小日向の腕を引かれながら帰路に着いていた。
「先輩、辛いなら送ってくれなくても大丈夫ですよ?」
「いや、さすがに彼女は送らないと駄目だろ……」
「強がりですね……ふふ」
互いに軽口を叩きつつ、のんびりと薄暗い街並みを歩く。今日は一日いろいろあったが、俺はとても充実していたと思えた。
チラリと小日向を見る。口ではああ言っていたが、彼女は本当に楽しかったのだろうか。
そんな風に考えていると、気が付けば小日向の自宅前に到着していた。
「ここまでありがとうございます」
腕から離れ、俺に向き合うと、小日向はそう言った。
「……先輩、ここでお別れですね」
「ああ、そうだな」
名残惜しいが、楽しい時間はいつか終わる。俺は寂しさを感じながら、小日向と別れた――その時だった。
「先輩」
「え?」
突如後ろから呼び止められ、後ろを振り返る。その一瞬、俺の頬に柔らかい衝撃が走った。
すぐそばに小日向の可愛らしい童顔が迫る。閉じられた眼が迫る。小ぶりな鼻が迫る。そして桜色の唇が限界まで迫り、そして離れてゆく。
「……今日のお礼ですよ」
はにかみながらそれだけ言うと、小日向は小走りで家に入っていった。
「…………」
残された俺は。
状況を理解するのに数秒を要し。そして一気に体温が上がるのだった。