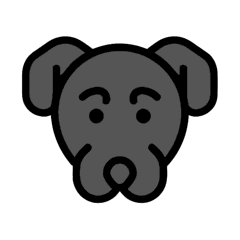笛地静恵さんの新・第三次性徴世界シリーズ
添加标签
千城醉歌笔耕不辍发布于 ,编辑于 2016-09-16 22:47
笛地静恵さんの新・第三次性徴世界シリーズ
新・第三次性徴世界シリーズ・1
天女中学校野球部部室の巻
Text by 笛地静恵
中学二年生のマリヤは、夏休みになってから、髪を赤毛に染めていた。夕日がそれを、さらに
炎のように赤く染め上げていた。今日は、ポニーテールにしていた。赤のゴムのバンドでまとめ
ている。それを、ばさりと振ってみた。
野球部のグラウンドは、天女中学校の本校舎から、十五分間ほど歩いた田畑の中にあった。
付近は人家がなくて静かだった。せみしぐれだけが、喧しかった。
無人のグラウンドに、整地用のローラーだけが、中央に放置されていた。
普通は、野球部員が、二人がかりで全力で、ひっぱる。マリヤは、中指一本だけを鉄棒に掛
けた。無造作にごろごろと移動していった。練習の邪魔にならない端の位置にまで、回転させ
ていった。
まもなく、野球部員が、遠征試合から野球部専用のバスで帰ってくる。彼らの予定は、きちん
と調べ上げていた。部員の中に、彼女が好きな子がいるのだった。しかし、告白はできなかっ
た。全員を、相手にするかたちにするしかなかった。
マリヤは、顔も身体も、どこもかしこも、肉がぱっつんぱっつんに、はちきれそうな女の子だっ
た。胸も腰も、肉感的に熟した果実だった。食べれば果汁がしたたりそうな肉体だった。男なら
ば、よだれを垂らす肉体だった。
童顔で、どこかに幼さの残るふくよかな丸顔だった。凝視がのったふくよかな頬にも、夕陽が
光っていた。
セーラー服の上は、急速な成長のために、サイズが小さくなっているようだった。サッカーボ
ールのような巨乳に押し上げられた胸元は、見るからにきつそうだった。限界まで生地が張り
詰めていた。ブラジャーの形と、その下の大きめの乳首の形までを、くっきりと浮き上がらせて
いた。自分でも少し勃起しているのが、わかっていた。これからおこることを予想して、興奮して
いるのだった。
野球部の、無人の部室に入り込んでいった。
三メートル十センチの身長の彼女は、天井が三メートルの男子野球部の部室には、背を屈め
て入っていかなければならない。狭苦しかった。頭の赤い髪の毛が、蜘蛛の巣と埃だらけの天
井を、モップのように掃除してしまいそうだった。
猛烈に男臭かった。可愛い顔を顰めていた。暑い。ただでさえ、むんむんとするような一日だ
った。不快指数が高いだろう。野球部の部室の温度も、マリヤ一人が発散する体熱で、数度は
上昇しているだろう。
肩にかついでいたビールの入った段ボールの箱を、床に置いた。中身を出して三リットル缶
のプルトップを、ブッシュと開けた。本数には、ゆとりがあるのだ。
本人が、どこもかしこも暑苦しい身体だったのだ。天井の蛍光灯の光が、上を向いた白い喉
の皮膚に、てらてらと照り返していた。
ビールのせいか、悪臭も気にならなくなっていた。彼女の周囲、数メートルの空間は、マリヤ
という女の匂いに染められていた。
本人は意識もしていないが、二十二世紀になって、もっとも大きく変化した日本の女性の美意
識は、体臭に関する認識なのかもしれなかった。過去の、日本人の女性は、それを恥として隠
していた。消臭スプレーというものが、販売されていた時代もあった。それが、欧米と同じように、
体臭も自分の個性だとして、積極的にアピールするように変化していったのだった。
マリヤは、中学生だから、大人のように香水を付けているわけではない。高価なものは、買え
なかった。それでも、彼女は、周囲の空間を、自分という個性の色に、はっきりと染めていた。
そのことを、恥ずかしいとも何とも思っていなかった。
無人の部室の中央にあぐらをかいた。そのために、少し、中を掃除してあげた。不精もののマ
リヤとしては、大サービスだった。床に散らかったものは、部室の脇に怪力で寄せておいた。机
だけは残して、ビールを乗せた。後で、使用する予定もある。両手を乗せて、耐久性を試してみ
た。スチール製のどこにでもある事務机だった。悲鳴を上げて軋んだが、潰れはしなかった。当
座の目的には、充分に使えそうだった。
ずしんと、女の大仏のように座っていた。小人の家に入り込んだ白雪姫というのは、こんな気
分がしたのだろうか。ロッカーや、壁のシャワーが、おもちゃの家具のように小さかった。
肩膝を立てているので、短くしたセーラー服のプリーツスカートから、白い太腿が付け根まで
むっちりとのぞいていた。そのさらに奥には、髪と同じような、情熱的な色の小さな下着がのぞ
けていた。かろうじて股間の陰毛だけを、隠すような小さなサイズだった。これも、マリヤの巨大
な尻から、いまにも、はち切れそうに緊張している。股間の割れ目に、食い込んでいるのだった。
少しきついが、気にしなかった。親も、洋服代がかかって困るとぼやいている。破れるまでは着
ていた。
やがて、彼らが帰ってきた。九人の男たちは、侵入者の女にびっくりしていた。周囲を丸く取り
囲んで来た。話によっては、ただでは帰さないという険悪な雰囲気があった。どうやら、逃がさ
ないためのような布陣をしているつもりのようだった。大きさといい、形といい、こけし人形のよ
うだった。野球部の全員は、坊主頭である。あのざらりした髪の感触を、味わってみたかった。
マリヤは、それを敏感な粘膜に擦らせる時のことを考えていた。あそこが、じゅんと濡れるのが
わかった。
マリヤは、心の中でくすりと笑っていた。まだ、しばらくは力づくで、事態を進行させるつもりは
なかった。乱暴をするつもりもなかった。穏便に済むならば、その方が好ましかった。彼女が好
きなタイプの男性も、そこに交じっていた。
マリヤは、そこに座っている。けれども、男子としてはいずれも平均身長を上回る屈強な野球
部員の選手たちと、それで、だいたい目線の高さが、同じになるぐらいだった。
ユニホームから汗の臭いがした。顔に光るものは塩の粒なのだろう。ワイルドで可愛らしい連
中だった。野良犬の群れのようだった。
彼らは炎天下で、朝の五時から苛酷な練習をしていたはずだった。少人数だが、天女中学の
野球部は、この地区では強豪として名を馳せていた。秋の全国大会に向けて、九人の部員は、
夏休みを返上して練習に励んでいた。健気な連中なのだ。マリヤは、軟弱な男に飽きていた。
彼らの醸す険悪な雰囲気にも、好感が持てた。
今日も、隣の市の野球部と、練習試合をしてきたのだった。
日が暮れてから戻ってくると、鍵のかかっていない部室の中に、マリヤが座っていたのだった。
さぞかし驚いたことだろう。
彼女は、自分が、この中学二年生の中でも、札付きの不良少女という烙印を、押されている
ことを知っていた。悪い噂は、みんなが知っているはずだった。半分以上が本当だった。
彼らの表情は緊張していた。野球部の試合のズボンの股間も、明らかに緊張していた。男子
の中での、マリヤのあだ名のひとつは、「公衆便所」だった。だれにでもやらせるという評判だっ
た。ひどい誤解だった。男子を便器にして使ってやったことはあるが、自分が便所になったこと
は一度もない。
マリヤは、野球部の部室に、缶ビールの一ダース入りの段ボール箱を、肩にかついで持ち込
んでいた。それを、差し入れだといった。
水分だけで計算しても、女性用の三リットル缶は、一本が三キロある。それが一ダースだから、
三十六キログラムのお荷物だ。それをマリヤは、重さのないもののように、飄々と、男の足では、
徒歩で十五分はかかる酒屋からかついできたのだった。
すぐにマリヤが差し入れてくれた、その一ダースの缶入りの発砲酒のビールは、すべて中身
が空になって、床に転がっていた。喉が渇いていた彼らは、あっというまに、ごくごくと飲み干し
てしまっていた。マリヤの狡猾な罠の中に、填まりこんでいた。
女性用の三リットル缶は、マリヤには、片手に持って一口の分量である。でも、中学生の男子
には、かなりの呑みでがあった。全員、耳までを赤くしていた。真っ黒に陽に焼けた首筋まで、
赤くなっているのがわかった。
「もし、あたしに腕相撲で、一人でも勝てる人がいたら、全員に、一時間だけあたしの身体で何
でもしていいけどなあ。サービスしてあげるよ」
マリヤは、アルコールが行き渡った彼らに条件を出した。自分でも、九リットルのビールを飲
み干していた。
「なんでもか?」
監督は、大きな高い鼻の細長い穴を、すんと膨らましていた。前任の監督がやめた後で、今
年から監督に就任した男だった。天女中学出身で、高校時代には、甲子園に出場した。まだ三
十歳にはなっていない。なかなかの色男なのだった。
「なんでもよ。そのかわり、一時間だけよ。やあね、どこを、何を見てるのよ。監督。あたしに、虫
歯でもあるの?」
「い、いや」
監督は、アルコールのせいで赤くなった首を、左右に大きく振った。
事実、マリヤの歯は真っ白で、虫歯など一本もなかった。健康そのものだった。
「あたし、酔っちゃったから、横にならせてね」
マリヤは、部室の床の汚れも気にせずに、巨大な肉体をのばしながら横たわっていった。部
室の全体が、彼女の身体に占領されたような光景だった。二メートル近いヒップが、小山のよう
に盛り上がっていた。圧倒的な量感があった。
マリヤは、ここが自分の部屋のベッドの上だというように、すっかりリラックスしていた。床に両
肘をついていた。監督の方に、顔を向けるようにしていた。
彼が目を下に下げると、彼女の胸元が顕になっていた。二分の一カップの真紅のレースのブ
ラからあらわになった、乳房の上半球の皮膚が、汗にてかてかと光っているのが見えたことだ
ろう。腹筋の引き締まった腹部の方まで、のぞくことができたかもしれない。
若い女特有の甘い体臭が、鼻孔を刺激するはずだ。マリヤは、自分の体臭のフェロモンが、
男子に与える催淫効果については自信を持っていた。彼女は、両腕の内側で胸を左右から挟
んで、圧迫するようにしてやった。ぎゅっと力を入れた。乳房の谷間を、狭めるようにしていた。
男は、このポーズに弱いのだ。女としては、扱い易いサイズと思っているだろう。事実、全員が、
目を皿のようにしていた。
「ねえ、いいでしょ。ほんとの遊びなのよ」
そうして、上半身をくねらせた。
胸の左右の脂肪の塊が、ぎゅうぎゅうと音を立てるようにして、熱く擦れあっていた。
「……ううん、そうだな」
監督は、喉をごくりと鳴らしていた。大きな喉仏が、上下にごくんと動いた。
「条件は、なんだ?」
さすがは、大人だった。判断が早い。
「もちろん、イーヴンよ。もし、あたしが勝ったら、あたしが、野球部のみんなを、一時間だけ、好
きにしてもいいということね」
監督は、マリヤの良く動く口の中の、赤い舌の動きを観察しているようだった。何を考えてい
るか分かっている。マリヤは、口の中で舌をねっとりとした動きで、ゆっくりと回転させてやった。
にちゃにちゃと、唾液の音がした。
もし、あそこにつっこんでやったら、この生意気なスケは、どんな悲鳴をあげて哀願することだ
ろうか。吸引力は強そうだ。
そんなことを考えているのだろう。男は、みんな同じだった。
いくら、大きくたって、男子野球部員の九人の力の敵ではない。力ならば負けていない。いま
だって、この女を、力づくで自由にできるだろう。女としては手ごろなサイズだった。
ただ、抵抗はされるだろう。それよりは、賭けに負けて、従順になったところを従わせた方が、
いろいろと楽しいしことも、容易に運ぶことだろう。
監督の表情からは、彼の心の中が手に取るように、マリヤには読み取れていた。
この大きな胸を、持て余しているようなマリヤとかいう不良の女は、男にかまってもらいたくて、
うずうずしているのだ。男の手で揉んでもらいたいのだろう。それで、こうして夜の部室にも、単
身で、遊びに来ているのだ。
この女の高慢な顔と、あのあたたかそうな胸に、溜りに貯まった精液を、思いっきりぶちまけ
てやりたかった。
監督の嫌らしい視線は、そう告白していた。
「いいだろう」
監督は、そう答えてしまっていた。マリヤの待望の一言だった。部員たちからも別に異論はな
かった。みんな監督と同じ気持ちなのだ。
九人で、一人に勝てばいいのだ。
「右手だけだな」
監督は、そうマリヤに確認してきた。
「そうよオ」
マリヤは、歌うような節を付けて、手のひらをひらひらさせた。内輪のように風が起こった。面
積が広いのだった。
監督は、綿密に計算を立てて、順番を組んでいった。
部屋のゴミの積み上がった隅で、円陣を組んでいた。できるだけ長期戦に持ち込んで、マリ
ヤの筋肉を疲労させていくという、作戦のようだった。
彼女は、たしかにでかいが、筋肉質ではない。力は、そんなにないはずだ。全身には、脂肪
の層が厚くのっている。特に、あそこにはだ。監督の目が、マリヤの胸元に吸い寄せられてい
った。セーラー服の胸元を、横目の視線でなめるように、ちらりとなぞっていた。
マリヤは、自然に身体の向きを変えて、彼らに見えやすいようにしてやっていた。手団扇で胸
元に、空気を送り込んだ。真珠のような大粒の汗の玉が、つうっと流れて、奥に吸い込まれて
いくのを、監督は、見逃さなかったことだろう。
一番手は、俊足の次郎長だった。反射神経が鋭い男だった。
部室の中央の机の上で、二人は向かい合っていた。
彼女が先に、肘をその上に乗せた。セーラー服は、半袖なのだった。彼女の二の腕は、脚に
自身のある次郎長の太腿と同じぐらいの直径があるのだ。ぎしっと古い机が軋んだ。マリヤは、
かなり背を丸くして、屈まなければならなかった。胸元がのぞいた。計算通りだった。次郎長は、
そこを見ないようにしようとしている。集中力を乱されそうだったからだ。真面目で可愛らしい男
なのだった。
彼は、彼女と手を合わせた。大きかった。女子の手など毎日、見慣れているが、こうして直接
に手を組む機会は、中学生ともなると少ない。すっぽりと彼の手を覆い隠してしまう。明らかに
不利だと分かったのだろう。マリヤにも、それは分かった。これでは、ハンディがありすぎるのだ。
勝負を拒否されてはたいへんだった。
「いいわ、これだけで相手してあげる」
マリヤは、指を人差し指と中指の二本だけ、立てて見せた。
「いいのか」
監督は念を押していた。
部員たちが、ざわついていた。マリヤが、自分たちをバカにしているように感じているのだ。
いいのさ。監督は、心で笑っていた。勝てばいいのだ。それに、このスケは、負けて、おれた
ちに玩ばれたいだけなのだ。簡単に、勝負はつくだろう。
マリヤの作戦通りだった。
次郎長は、マリヤの指二本と健闘した。マリヤの長い健康なピンクの爪の先端が、机の落書
だらけの表面につきそうだった。
「ああん、いたあ~い」
マリヤは、色っぽい声で、悲鳴を上げてやった。それだけで、真面目で優しい、次郎長君は、
はっと力を緩めてくれていた。その瞬間、マリヤが巻き返していた。
次郎長の手の甲が机の表面に、そっと軟着陸してしまっていた。
「女だからと思って、気を抜くな」
監督は、次郎長を激しく叱った。が、良い気分だったことだろう。あの非力な次郎長で、これだ
け善戦できるなら結果は見えている。マリヤは、痛そうに指を曲げたりのばしたりしていた。
「長期戦に持ち込め。マリヤを疲労させればいい」
そう円陣を組んで、マリヤには聞こえないように、再度、小声で指示を与えていた。監督の知
恵など、そんなものだった。
しかし、二番手、三番手まで、手も無く捻られていた。三番手の犬田は、頭がいいので、奇策
を使うかと思った。女性には優しいので、あくまで正攻法だった。甘い容貌だった。マリヤは逆
に、苦しさに身悶えるようにした。胸を大きく揺らしたのだった。その隙を、つかれた形で犬田も
負けた。
四番手は、サードのゴリラだった。怪獣という異名を持っている。にきびだらけのあばた面をし
ていた。力のある男で、特大のホームランをかっ飛ばすこともあった。監督も期待していただろ
う。試合では、頼れる男なのだった。彼と五番手で、決めてもらいたかったことだろう。だが、そ
うは問屋が卸さないのだった。マリヤは、心の中で、にたりとしていた。たしかに、表面的には、
長期戦になった。しかし、結局は、先に力尽きたのは、ゴリラだった。
「ひゃあ、つええ、つええ」
彼は、興奮した時の癖で、妙に甲高い声で、真っ赤になった手を振っていた。
五番手が、番長だった。最近は、怪我で欠場することが多かったが、肉体トレーニングで、筋
肉を付けている。無言で、マリヤの前に立った。
「きゃあん、番長さん、こわい!」
マリヤの挑発にものらない。気合いが入っている証拠だった。すごい目で睨み付けてくれた。
「よし、清、行け」
監督も一言だけ、応援した。大一番だった。マリヤも、玩んでやった。マリヤの手が震えたよう
に男どもに見えたのは、この時だけだっただろう。しかし、番長は、疲弊した肉体に力を入れす
ぎたのだ。いきなり右のふくらはぎに激痛が走ったようだった。肉離れを起こしてしまった。
マリヤの不戦勝だった。
六番手は、他の学校から、転向してきた大福という太った男だった。天女中学が強いのは、
金の力で、優秀な選手を引き抜いてくるからだ、という噂があった。そうなのかもしれないと、マ
リヤも思っている。しかし、こいつも、凡退だった。
七番手は、曲者だった。何かしてくれるかもしれないという、一縷の望みが監督にも選手にも
あっただろう。しかし、マリヤの胸元にふっと息を吹き込んでくるのがせいぜいだった。マリヤを、
くすぐったいと、けらけら笑わせてくれただけだった。失礼な男の手を、怪我しない程度に、握り
潰してやった。簡単に捻られてしった。
八番手の、キャッチャーと、九番手のピッチャーも倒れた。
残るは、監督だけになってしまった。
「うふふ、もうすぐよね。みんな、用意はいいかしら。一時間だけ。あたしの思い通りに、なって
くれるのよね」
マリヤは、机から上半身をのばした。三メートル十センチの巨体を、できるかぎりまっすぐ大き
くなるように、背伸びさせていった。思わず、口元のよだれを手の甲で、ずるっと拭っていた。妖
艶な魔女のような目だった。天井に近い高処から、足元の男どもを見下ろしてやっていた。彼ら
は、罠にかかった鼠だった。もう逃げられないのだ。みんな、なんてちっちゃくて、可愛らしいの
だろう。そして、おいしそうだった。あの坊主頭を撫でて、キスしてやりたかった。たっぷりと唾液
を付けてやって、そして、それから、うふふふ……。笑みがこぼれていた。
監督は、罠にかかったのが、わかったのだろう。すでに現役を退いている彼に、マリヤを倒せ
る見込みはなかった。彼の、判断ミスだった。
「あのビールに、何か薬でもいれたな」
そうでなければ、天女中学野球部が、中学二年生の不良少女ひとりに、こんなに惨めな敗戦
はありえなかった。そう信じたかったのだろう。
「このスケ、おれをだましたな」
監督は、怒りの表情を癇性の額の血管に顕にしていた。手元にあったバットで殴りかかって
いった。かつては、天女中学を地区優勝に導いた、チーム随一のホームランバッターの、必殺
の一撃だった。
マリヤは、動かなかった。弁慶の泣き所と言われる、マリヤの臑に命中していた。白いルーズ
ソックスに包まれている。足の直径は、電信柱ぐらいに膨張してみえただろう。
彼の身長では、立ち上がった彼女の、膝の下にしかヒットしなかったのだ。それでも、苦痛の
あまり倒れこんだところを、さらに腹部を攻撃するという計画のようだった。
しかし、鈍い音がしただけだった。臑でも、野球部監督の鍛えぬいた太腿よりも直径が太かっ
た。
「足元で何しているの。くすぐったいわよ」
監督は、わが目を疑ったことだろう。
マリヤは、セーラー服の高い胸元の向こうから、彼を冷たい目で見下ろしてやっていた。口調
は笑っていたが、目は笑っていなかった。蛍光灯の光背に、髪の毛が黒い雲のようだった。そ
の下に太い腕を組んでいた。
彼女の黒のローヒールの革靴は、部室のコンクリートの床の上で、根が生えたように、まった
く位置も変化させていなかった。恐怖が彼の中に、わずかに残っていた自制心を吹き飛ばした。
再度、全力でスイングした。
男にとっては、鋼鉄の電信柱を、急襲したようなものなのだろうか。鈍い音がした。バットが折
れた。部室のブロックの壁に、ばしんとぶつかっていた。白い抉ったような傷跡を、深く残してい
た。破片が、ぱらぱらと四方に飛び散っていた。
マリヤは、「くすぐったいわ」というと、巨大な身体を折り曲げていた。その動きで起こった風を、
監督は汗で濡れた顔に感じていた。長い手で臑の彼が強打した部分を、指でぼりぼりと音をた
てて掻いていた。皮膚は、変色してもいなかった。
「今度は、あたしの番ね」
部員全員が、バットを持って。マリヤに襲いかかってきていた。それから、部室の中を、マリヤ
という名前の紺色の大きな台風が荒れ狂った。紺色のスカートが、彼らの頭上で黒い雲のよう
に暴れていた。ルーズソックスに包まれた白い足が、純白の750ccのオートバイのように襲来
した。次々に空中に、はねとばされていった。
ロッカーが倒れた。
各自の侍の剣のように大事なバットは、ぐしゃぐしゃに握りつぶされていた。割り箸のような木
切れになっていた。マリヤの握力は、それほどのものだった。踏み潰されたものもあった。彼女
としては、男子と遊んでやったつもりだった。
監督の嫌な脂汗に濡れていた男の顔面は、マリヤのローヒールの靴底に踏みつぶされて、
泥まみれにいた。打撃のショックで、手がなお肘まで痺れている状態だった。
抵抗した部員たちは、血を流して床や壁に倒れていた。ぴくりとも動かなかった。
マリヤの両の脇の下と、脚の太腿の間に挟まれて、番長と曲者とキャッチャーが、失神してい
た。彼女は、息も切らしていなかった。
「どう、強い男と、か弱い女の実力のちがいが、わかったかしら」
そして、監督と九人の部員は、マリヤの性の奴隷にされたのだった。
マリヤは男子野球部の部室で、思う様に、快感に豊満な白い姿態を、巨大な蛇のようにくね
らせて揺らしていた。
痴態を、見ているのは、窓から差し込む月光だけだった。何をしても良かったし、何をすること
も可能だった。マリヤの力に逆らって、それを止めることができるものは、だれもいなかった。
裏庭の草原からは、虫のすだく声がかまびすしかった。
いずれも、坊主頭の全裸の中学生の男子九名に、奉仕させていた。
両方の盛り上がった乳房の山頂に、一人ずつを黒い小鳥のように留まらせていた。ゴリラと
犬田だった。乳首を愛撫させていた。脇の下も一人ずつに念入りに舐めさせていた。汗が溜ま
って気持ちが悪かった。
腹の上の番長は、マリヤの奔放な動きに、跳ねとばされそうになっては、必死にしがみついて
いた。嵐の海の大船の甲板に、のっているような気分だったろう。このタイタニック号は、人間
の肉で出来ているのだった。
股間に、髪の短い坊主頭の男の頭部があって、激しく蠢いていた。監督だった。巨大な下腹
部と黒い密林の影になって、小さな男の顔はマリヤにも見えなかった。しかし、大人の男のテク
ニックだった。充分に満足させてくれた。監督よりも、女の紐になった方が向いているのではな
いだろうか。
監督にこうしてもらいたかったのだ。ああん、好きよ。彼女は、心の中で、彼の名前を呼ぶと、
彼の坊主頭をいとおしそうに撫でていた。同世代のガキよりも、大人を服従させることで、性欲
がより燃えあがるのだった。
長い長い白い脚にも、一人ずつがまとわりついていた。舌で奉仕させていた。足の裏に一人
がいて、これも舌で、一日のルーズソックスの中で蒸れていた汚れと臭いを、掃除させていた。
足の指の間まで入念にやらせた。
総勢九人。王女さまのような、豪華な夜だった。
思うままに、大きな声を出して暴れて、喘いだ。男子の、はあはあぜいぜいという、激しい吐
息もしていた。巨大な女体を感じさせるという重労働の重圧に、喘いでいた。無理もないマリヤ
の肉体の各部の重量だけでも、数百キログラムはあっただろう。苦しげな肉体労働者の呼吸
音がしていた。それもマリヤの快感を高める美酒だった。この責め苦は、きっかり一時間続い
た。
「ああ、おいしかったなあ」
マリヤは帰り道で、星のきらめく銀河を見上げながら、背伸びをしていた。まだ、野球部の部
室では、大人一人と九人の少年全員が、疲労困憊して、意識を回復せずに、引っ繰り返ってい
ることだろう。長い一日だった。彼らのミルクは、すっかり飲み干してやった。あと、三日間は、
足腰が立たないだろう。野球の練習も、出来ないかもしれなかった。なにしろ玉がないもの。マ
リヤは、口元のよだれを拭って、笑った。
帰りの道は、暗くなっていた。道のところには、ところどころに街灯の明かりがあったが、その
まわりは闇に包まれていた。前世紀の隕石ガイアの衝突の際に壊滅した廃墟が、ほとんどそ
のままに、緑の中に放置されていた。日本は大災害の傷跡から、ほとんど回復していなかった。
雨の夜には、鬼火が燃えるという噂があった。マリヤは、別に恐いとも思わなかった。前世紀の
街は、マリヤにとっては、小人の住む世界だった。小人の幽霊など恐くはなかった。
それでも、後から追い付いてくる長身の人影に出会った時には、ほっとしていた。クラスの委
員長の松本貴子だった。紺色のセーラー服が、彼女が着ていると、王女の正装のように、気品
のあるものに見える。不思議だった。
クラスでも、一番の長身の部類である。三メートル六十センチ以上は、あった。眉毛が濃い。
意志の強そうな端正な顔だちをしていた。黒目勝ちの瞳に力があった。夜の中でも、きらきらと
光っている。
三メートル十センチと、女子の中では小柄なマリヤは、並んで歩くと見下ろされてしまうのだっ
た。頭一つ分の相違があった。
松本貴子は、試験も学年で五位以内をつねにキープしていた。ガリ勉タイプではない。運動
の方も、バレー部のエース・アタッカーだった。腕力もマリヤの比ではないだろう。今も、練習を
終わって帰るところだという。駅まで同じ方向だった。
マリヤは、男子の運動部を次々と襲っては、いたずらを繰り返しているのも、自分の身体が女
子としては小さいという、劣等感のせいなのかもしれないと思っていた。自分の大きさと強さを、
せめて男子を相手にして、誇示したいだけなのだろうか。
横幅と胸の丸さでは、貴子にも負けていなかった。それでも、バレーの試合で、委員長がアタ
ックをするために、ネットぎわで体操服の胸元を、ぐいっと反らすようにしたきなどは、相当に大
きいことがわかった。いつもは、何となく猫背で俯くようにして歩いているので、目立たないの
だ。
貴子は友達は多いのに、休み時間は自分の席で、一人で文庫本を静かに読んでいることの
方を好んでいた。明らかに文学少女である。隠れ読書家であるマリヤは、好感を持っていた。
前世紀までの、男性と女性が同じ大きさであった時代の、恋愛小説を愛読していた。
松本貴子は、中学三年生の光史郎と、高校三年生の二人の兄貴がいたはずだった。マリヤ
のような不良にも、別け隔てせずに、気軽に話し掛けてくれた。彼女にだけは、マリヤも気を許
して、自然に付き合えたのだった。
駅の前に新しい甘味処が開店した。冷たいお汁粉を、飲ませてくれる店がある。大きなお餅
が入っている。食べにいかない。そんな誘いだった。貴子の頬もぷくぷくとして丸かった。笑み
を浮かべていた。マリヤのセーラー服の下で、お腹が、ぐうっと鳴った。そういえば放課後は、
ビール三本と、男子のミルクちょっぴりしか、腹にいれていなかったのだ。ちょっとした運動もし
た。「行きます」そう気軽に、委員長の顔を見上げて答えていた。同級生なのに、貴子にだけは、
敬語になるのが、自分でも不思議だった。年上のお姉さんと、話をしているような気分になるの
だった。「あたし、お代わりをするかも、しれなくてよ」松本貴子がそういうので、「あたしもです」
と、これも丁寧に答えていた。
新・第三次性徴世界シリーズ・1
天女中学校野球部部室の巻 了
【作者後記】はじめまして。笛地静恵と申します。ネットに巨大な女の子を主人公とする、小説を
発表しているものです。「妹の部屋」の作品を記憶している方も、何人か、いらっしゃると思いま
す。「The darkside of the moon」と「Peter Panty」の二編は、改稿の上で、こちらで再度、
発表して頂く予定に なっています。これは、「第三次性徴世界」という、環境ホルモンの影響で
女性が男性よりも、二倍以上に大きくなった世界での、長編の物語の一部です。クロさんのHPに
掲載していただいていた、「巨大女子高生百物語」の姉妹編になります。こちらは、「巨大女子中
学生」が活躍します。評判がよければ、続編を書いていこうと思っています。よろしくお願い申し
上げます。拙作の、発表の場所を提供していただいた、伊藤一蔵さんに深く感謝いたします。
天女中学校野球部部室の巻
Text by 笛地静恵
中学二年生のマリヤは、夏休みになってから、髪を赤毛に染めていた。夕日がそれを、さらに
炎のように赤く染め上げていた。今日は、ポニーテールにしていた。赤のゴムのバンドでまとめ
ている。それを、ばさりと振ってみた。
野球部のグラウンドは、天女中学校の本校舎から、十五分間ほど歩いた田畑の中にあった。
付近は人家がなくて静かだった。せみしぐれだけが、喧しかった。
無人のグラウンドに、整地用のローラーだけが、中央に放置されていた。
普通は、野球部員が、二人がかりで全力で、ひっぱる。マリヤは、中指一本だけを鉄棒に掛
けた。無造作にごろごろと移動していった。練習の邪魔にならない端の位置にまで、回転させ
ていった。
まもなく、野球部員が、遠征試合から野球部専用のバスで帰ってくる。彼らの予定は、きちん
と調べ上げていた。部員の中に、彼女が好きな子がいるのだった。しかし、告白はできなかっ
た。全員を、相手にするかたちにするしかなかった。
マリヤは、顔も身体も、どこもかしこも、肉がぱっつんぱっつんに、はちきれそうな女の子だっ
た。胸も腰も、肉感的に熟した果実だった。食べれば果汁がしたたりそうな肉体だった。男なら
ば、よだれを垂らす肉体だった。
童顔で、どこかに幼さの残るふくよかな丸顔だった。凝視がのったふくよかな頬にも、夕陽が
光っていた。
セーラー服の上は、急速な成長のために、サイズが小さくなっているようだった。サッカーボ
ールのような巨乳に押し上げられた胸元は、見るからにきつそうだった。限界まで生地が張り
詰めていた。ブラジャーの形と、その下の大きめの乳首の形までを、くっきりと浮き上がらせて
いた。自分でも少し勃起しているのが、わかっていた。これからおこることを予想して、興奮して
いるのだった。
野球部の、無人の部室に入り込んでいった。
三メートル十センチの身長の彼女は、天井が三メートルの男子野球部の部室には、背を屈め
て入っていかなければならない。狭苦しかった。頭の赤い髪の毛が、蜘蛛の巣と埃だらけの天
井を、モップのように掃除してしまいそうだった。
猛烈に男臭かった。可愛い顔を顰めていた。暑い。ただでさえ、むんむんとするような一日だ
った。不快指数が高いだろう。野球部の部室の温度も、マリヤ一人が発散する体熱で、数度は
上昇しているだろう。
肩にかついでいたビールの入った段ボールの箱を、床に置いた。中身を出して三リットル缶
のプルトップを、ブッシュと開けた。本数には、ゆとりがあるのだ。
本人が、どこもかしこも暑苦しい身体だったのだ。天井の蛍光灯の光が、上を向いた白い喉
の皮膚に、てらてらと照り返していた。
ビールのせいか、悪臭も気にならなくなっていた。彼女の周囲、数メートルの空間は、マリヤ
という女の匂いに染められていた。
本人は意識もしていないが、二十二世紀になって、もっとも大きく変化した日本の女性の美意
識は、体臭に関する認識なのかもしれなかった。過去の、日本人の女性は、それを恥として隠
していた。消臭スプレーというものが、販売されていた時代もあった。それが、欧米と同じように、
体臭も自分の個性だとして、積極的にアピールするように変化していったのだった。
マリヤは、中学生だから、大人のように香水を付けているわけではない。高価なものは、買え
なかった。それでも、彼女は、周囲の空間を、自分という個性の色に、はっきりと染めていた。
そのことを、恥ずかしいとも何とも思っていなかった。
無人の部室の中央にあぐらをかいた。そのために、少し、中を掃除してあげた。不精もののマ
リヤとしては、大サービスだった。床に散らかったものは、部室の脇に怪力で寄せておいた。机
だけは残して、ビールを乗せた。後で、使用する予定もある。両手を乗せて、耐久性を試してみ
た。スチール製のどこにでもある事務机だった。悲鳴を上げて軋んだが、潰れはしなかった。当
座の目的には、充分に使えそうだった。
ずしんと、女の大仏のように座っていた。小人の家に入り込んだ白雪姫というのは、こんな気
分がしたのだろうか。ロッカーや、壁のシャワーが、おもちゃの家具のように小さかった。
肩膝を立てているので、短くしたセーラー服のプリーツスカートから、白い太腿が付け根まで
むっちりとのぞいていた。そのさらに奥には、髪と同じような、情熱的な色の小さな下着がのぞ
けていた。かろうじて股間の陰毛だけを、隠すような小さなサイズだった。これも、マリヤの巨大
な尻から、いまにも、はち切れそうに緊張している。股間の割れ目に、食い込んでいるのだった。
少しきついが、気にしなかった。親も、洋服代がかかって困るとぼやいている。破れるまでは着
ていた。
やがて、彼らが帰ってきた。九人の男たちは、侵入者の女にびっくりしていた。周囲を丸く取り
囲んで来た。話によっては、ただでは帰さないという険悪な雰囲気があった。どうやら、逃がさ
ないためのような布陣をしているつもりのようだった。大きさといい、形といい、こけし人形のよ
うだった。野球部の全員は、坊主頭である。あのざらりした髪の感触を、味わってみたかった。
マリヤは、それを敏感な粘膜に擦らせる時のことを考えていた。あそこが、じゅんと濡れるのが
わかった。
マリヤは、心の中でくすりと笑っていた。まだ、しばらくは力づくで、事態を進行させるつもりは
なかった。乱暴をするつもりもなかった。穏便に済むならば、その方が好ましかった。彼女が好
きなタイプの男性も、そこに交じっていた。
マリヤは、そこに座っている。けれども、男子としてはいずれも平均身長を上回る屈強な野球
部員の選手たちと、それで、だいたい目線の高さが、同じになるぐらいだった。
ユニホームから汗の臭いがした。顔に光るものは塩の粒なのだろう。ワイルドで可愛らしい連
中だった。野良犬の群れのようだった。
彼らは炎天下で、朝の五時から苛酷な練習をしていたはずだった。少人数だが、天女中学の
野球部は、この地区では強豪として名を馳せていた。秋の全国大会に向けて、九人の部員は、
夏休みを返上して練習に励んでいた。健気な連中なのだ。マリヤは、軟弱な男に飽きていた。
彼らの醸す険悪な雰囲気にも、好感が持てた。
今日も、隣の市の野球部と、練習試合をしてきたのだった。
日が暮れてから戻ってくると、鍵のかかっていない部室の中に、マリヤが座っていたのだった。
さぞかし驚いたことだろう。
彼女は、自分が、この中学二年生の中でも、札付きの不良少女という烙印を、押されている
ことを知っていた。悪い噂は、みんなが知っているはずだった。半分以上が本当だった。
彼らの表情は緊張していた。野球部の試合のズボンの股間も、明らかに緊張していた。男子
の中での、マリヤのあだ名のひとつは、「公衆便所」だった。だれにでもやらせるという評判だっ
た。ひどい誤解だった。男子を便器にして使ってやったことはあるが、自分が便所になったこと
は一度もない。
マリヤは、野球部の部室に、缶ビールの一ダース入りの段ボール箱を、肩にかついで持ち込
んでいた。それを、差し入れだといった。
水分だけで計算しても、女性用の三リットル缶は、一本が三キロある。それが一ダースだから、
三十六キログラムのお荷物だ。それをマリヤは、重さのないもののように、飄々と、男の足では、
徒歩で十五分はかかる酒屋からかついできたのだった。
すぐにマリヤが差し入れてくれた、その一ダースの缶入りの発砲酒のビールは、すべて中身
が空になって、床に転がっていた。喉が渇いていた彼らは、あっというまに、ごくごくと飲み干し
てしまっていた。マリヤの狡猾な罠の中に、填まりこんでいた。
女性用の三リットル缶は、マリヤには、片手に持って一口の分量である。でも、中学生の男子
には、かなりの呑みでがあった。全員、耳までを赤くしていた。真っ黒に陽に焼けた首筋まで、
赤くなっているのがわかった。
「もし、あたしに腕相撲で、一人でも勝てる人がいたら、全員に、一時間だけあたしの身体で何
でもしていいけどなあ。サービスしてあげるよ」
マリヤは、アルコールが行き渡った彼らに条件を出した。自分でも、九リットルのビールを飲
み干していた。
「なんでもか?」
監督は、大きな高い鼻の細長い穴を、すんと膨らましていた。前任の監督がやめた後で、今
年から監督に就任した男だった。天女中学出身で、高校時代には、甲子園に出場した。まだ三
十歳にはなっていない。なかなかの色男なのだった。
「なんでもよ。そのかわり、一時間だけよ。やあね、どこを、何を見てるのよ。監督。あたしに、虫
歯でもあるの?」
「い、いや」
監督は、アルコールのせいで赤くなった首を、左右に大きく振った。
事実、マリヤの歯は真っ白で、虫歯など一本もなかった。健康そのものだった。
「あたし、酔っちゃったから、横にならせてね」
マリヤは、部室の床の汚れも気にせずに、巨大な肉体をのばしながら横たわっていった。部
室の全体が、彼女の身体に占領されたような光景だった。二メートル近いヒップが、小山のよう
に盛り上がっていた。圧倒的な量感があった。
マリヤは、ここが自分の部屋のベッドの上だというように、すっかりリラックスしていた。床に両
肘をついていた。監督の方に、顔を向けるようにしていた。
彼が目を下に下げると、彼女の胸元が顕になっていた。二分の一カップの真紅のレースのブ
ラからあらわになった、乳房の上半球の皮膚が、汗にてかてかと光っているのが見えたことだ
ろう。腹筋の引き締まった腹部の方まで、のぞくことができたかもしれない。
若い女特有の甘い体臭が、鼻孔を刺激するはずだ。マリヤは、自分の体臭のフェロモンが、
男子に与える催淫効果については自信を持っていた。彼女は、両腕の内側で胸を左右から挟
んで、圧迫するようにしてやった。ぎゅっと力を入れた。乳房の谷間を、狭めるようにしていた。
男は、このポーズに弱いのだ。女としては、扱い易いサイズと思っているだろう。事実、全員が、
目を皿のようにしていた。
「ねえ、いいでしょ。ほんとの遊びなのよ」
そうして、上半身をくねらせた。
胸の左右の脂肪の塊が、ぎゅうぎゅうと音を立てるようにして、熱く擦れあっていた。
「……ううん、そうだな」
監督は、喉をごくりと鳴らしていた。大きな喉仏が、上下にごくんと動いた。
「条件は、なんだ?」
さすがは、大人だった。判断が早い。
「もちろん、イーヴンよ。もし、あたしが勝ったら、あたしが、野球部のみんなを、一時間だけ、好
きにしてもいいということね」
監督は、マリヤの良く動く口の中の、赤い舌の動きを観察しているようだった。何を考えてい
るか分かっている。マリヤは、口の中で舌をねっとりとした動きで、ゆっくりと回転させてやった。
にちゃにちゃと、唾液の音がした。
もし、あそこにつっこんでやったら、この生意気なスケは、どんな悲鳴をあげて哀願することだ
ろうか。吸引力は強そうだ。
そんなことを考えているのだろう。男は、みんな同じだった。
いくら、大きくたって、男子野球部員の九人の力の敵ではない。力ならば負けていない。いま
だって、この女を、力づくで自由にできるだろう。女としては手ごろなサイズだった。
ただ、抵抗はされるだろう。それよりは、賭けに負けて、従順になったところを従わせた方が、
いろいろと楽しいしことも、容易に運ぶことだろう。
監督の表情からは、彼の心の中が手に取るように、マリヤには読み取れていた。
この大きな胸を、持て余しているようなマリヤとかいう不良の女は、男にかまってもらいたくて、
うずうずしているのだ。男の手で揉んでもらいたいのだろう。それで、こうして夜の部室にも、単
身で、遊びに来ているのだ。
この女の高慢な顔と、あのあたたかそうな胸に、溜りに貯まった精液を、思いっきりぶちまけ
てやりたかった。
監督の嫌らしい視線は、そう告白していた。
「いいだろう」
監督は、そう答えてしまっていた。マリヤの待望の一言だった。部員たちからも別に異論はな
かった。みんな監督と同じ気持ちなのだ。
九人で、一人に勝てばいいのだ。
「右手だけだな」
監督は、そうマリヤに確認してきた。
「そうよオ」
マリヤは、歌うような節を付けて、手のひらをひらひらさせた。内輪のように風が起こった。面
積が広いのだった。
監督は、綿密に計算を立てて、順番を組んでいった。
部屋のゴミの積み上がった隅で、円陣を組んでいた。できるだけ長期戦に持ち込んで、マリ
ヤの筋肉を疲労させていくという、作戦のようだった。
彼女は、たしかにでかいが、筋肉質ではない。力は、そんなにないはずだ。全身には、脂肪
の層が厚くのっている。特に、あそこにはだ。監督の目が、マリヤの胸元に吸い寄せられてい
った。セーラー服の胸元を、横目の視線でなめるように、ちらりとなぞっていた。
マリヤは、自然に身体の向きを変えて、彼らに見えやすいようにしてやっていた。手団扇で胸
元に、空気を送り込んだ。真珠のような大粒の汗の玉が、つうっと流れて、奥に吸い込まれて
いくのを、監督は、見逃さなかったことだろう。
一番手は、俊足の次郎長だった。反射神経が鋭い男だった。
部室の中央の机の上で、二人は向かい合っていた。
彼女が先に、肘をその上に乗せた。セーラー服は、半袖なのだった。彼女の二の腕は、脚に
自身のある次郎長の太腿と同じぐらいの直径があるのだ。ぎしっと古い机が軋んだ。マリヤは、
かなり背を丸くして、屈まなければならなかった。胸元がのぞいた。計算通りだった。次郎長は、
そこを見ないようにしようとしている。集中力を乱されそうだったからだ。真面目で可愛らしい男
なのだった。
彼は、彼女と手を合わせた。大きかった。女子の手など毎日、見慣れているが、こうして直接
に手を組む機会は、中学生ともなると少ない。すっぽりと彼の手を覆い隠してしまう。明らかに
不利だと分かったのだろう。マリヤにも、それは分かった。これでは、ハンディがありすぎるのだ。
勝負を拒否されてはたいへんだった。
「いいわ、これだけで相手してあげる」
マリヤは、指を人差し指と中指の二本だけ、立てて見せた。
「いいのか」
監督は念を押していた。
部員たちが、ざわついていた。マリヤが、自分たちをバカにしているように感じているのだ。
いいのさ。監督は、心で笑っていた。勝てばいいのだ。それに、このスケは、負けて、おれた
ちに玩ばれたいだけなのだ。簡単に、勝負はつくだろう。
マリヤの作戦通りだった。
次郎長は、マリヤの指二本と健闘した。マリヤの長い健康なピンクの爪の先端が、机の落書
だらけの表面につきそうだった。
「ああん、いたあ~い」
マリヤは、色っぽい声で、悲鳴を上げてやった。それだけで、真面目で優しい、次郎長君は、
はっと力を緩めてくれていた。その瞬間、マリヤが巻き返していた。
次郎長の手の甲が机の表面に、そっと軟着陸してしまっていた。
「女だからと思って、気を抜くな」
監督は、次郎長を激しく叱った。が、良い気分だったことだろう。あの非力な次郎長で、これだ
け善戦できるなら結果は見えている。マリヤは、痛そうに指を曲げたりのばしたりしていた。
「長期戦に持ち込め。マリヤを疲労させればいい」
そう円陣を組んで、マリヤには聞こえないように、再度、小声で指示を与えていた。監督の知
恵など、そんなものだった。
しかし、二番手、三番手まで、手も無く捻られていた。三番手の犬田は、頭がいいので、奇策
を使うかと思った。女性には優しいので、あくまで正攻法だった。甘い容貌だった。マリヤは逆
に、苦しさに身悶えるようにした。胸を大きく揺らしたのだった。その隙を、つかれた形で犬田も
負けた。
四番手は、サードのゴリラだった。怪獣という異名を持っている。にきびだらけのあばた面をし
ていた。力のある男で、特大のホームランをかっ飛ばすこともあった。監督も期待していただろ
う。試合では、頼れる男なのだった。彼と五番手で、決めてもらいたかったことだろう。だが、そ
うは問屋が卸さないのだった。マリヤは、心の中で、にたりとしていた。たしかに、表面的には、
長期戦になった。しかし、結局は、先に力尽きたのは、ゴリラだった。
「ひゃあ、つええ、つええ」
彼は、興奮した時の癖で、妙に甲高い声で、真っ赤になった手を振っていた。
五番手が、番長だった。最近は、怪我で欠場することが多かったが、肉体トレーニングで、筋
肉を付けている。無言で、マリヤの前に立った。
「きゃあん、番長さん、こわい!」
マリヤの挑発にものらない。気合いが入っている証拠だった。すごい目で睨み付けてくれた。
「よし、清、行け」
監督も一言だけ、応援した。大一番だった。マリヤも、玩んでやった。マリヤの手が震えたよう
に男どもに見えたのは、この時だけだっただろう。しかし、番長は、疲弊した肉体に力を入れす
ぎたのだ。いきなり右のふくらはぎに激痛が走ったようだった。肉離れを起こしてしまった。
マリヤの不戦勝だった。
六番手は、他の学校から、転向してきた大福という太った男だった。天女中学が強いのは、
金の力で、優秀な選手を引き抜いてくるからだ、という噂があった。そうなのかもしれないと、マ
リヤも思っている。しかし、こいつも、凡退だった。
七番手は、曲者だった。何かしてくれるかもしれないという、一縷の望みが監督にも選手にも
あっただろう。しかし、マリヤの胸元にふっと息を吹き込んでくるのがせいぜいだった。マリヤを、
くすぐったいと、けらけら笑わせてくれただけだった。失礼な男の手を、怪我しない程度に、握り
潰してやった。簡単に捻られてしった。
八番手の、キャッチャーと、九番手のピッチャーも倒れた。
残るは、監督だけになってしまった。
「うふふ、もうすぐよね。みんな、用意はいいかしら。一時間だけ。あたしの思い通りに、なって
くれるのよね」
マリヤは、机から上半身をのばした。三メートル十センチの巨体を、できるかぎりまっすぐ大き
くなるように、背伸びさせていった。思わず、口元のよだれを手の甲で、ずるっと拭っていた。妖
艶な魔女のような目だった。天井に近い高処から、足元の男どもを見下ろしてやっていた。彼ら
は、罠にかかった鼠だった。もう逃げられないのだ。みんな、なんてちっちゃくて、可愛らしいの
だろう。そして、おいしそうだった。あの坊主頭を撫でて、キスしてやりたかった。たっぷりと唾液
を付けてやって、そして、それから、うふふふ……。笑みがこぼれていた。
監督は、罠にかかったのが、わかったのだろう。すでに現役を退いている彼に、マリヤを倒せ
る見込みはなかった。彼の、判断ミスだった。
「あのビールに、何か薬でもいれたな」
そうでなければ、天女中学野球部が、中学二年生の不良少女ひとりに、こんなに惨めな敗戦
はありえなかった。そう信じたかったのだろう。
「このスケ、おれをだましたな」
監督は、怒りの表情を癇性の額の血管に顕にしていた。手元にあったバットで殴りかかって
いった。かつては、天女中学を地区優勝に導いた、チーム随一のホームランバッターの、必殺
の一撃だった。
マリヤは、動かなかった。弁慶の泣き所と言われる、マリヤの臑に命中していた。白いルーズ
ソックスに包まれている。足の直径は、電信柱ぐらいに膨張してみえただろう。
彼の身長では、立ち上がった彼女の、膝の下にしかヒットしなかったのだ。それでも、苦痛の
あまり倒れこんだところを、さらに腹部を攻撃するという計画のようだった。
しかし、鈍い音がしただけだった。臑でも、野球部監督の鍛えぬいた太腿よりも直径が太かっ
た。
「足元で何しているの。くすぐったいわよ」
監督は、わが目を疑ったことだろう。
マリヤは、セーラー服の高い胸元の向こうから、彼を冷たい目で見下ろしてやっていた。口調
は笑っていたが、目は笑っていなかった。蛍光灯の光背に、髪の毛が黒い雲のようだった。そ
の下に太い腕を組んでいた。
彼女の黒のローヒールの革靴は、部室のコンクリートの床の上で、根が生えたように、まった
く位置も変化させていなかった。恐怖が彼の中に、わずかに残っていた自制心を吹き飛ばした。
再度、全力でスイングした。
男にとっては、鋼鉄の電信柱を、急襲したようなものなのだろうか。鈍い音がした。バットが折
れた。部室のブロックの壁に、ばしんとぶつかっていた。白い抉ったような傷跡を、深く残してい
た。破片が、ぱらぱらと四方に飛び散っていた。
マリヤは、「くすぐったいわ」というと、巨大な身体を折り曲げていた。その動きで起こった風を、
監督は汗で濡れた顔に感じていた。長い手で臑の彼が強打した部分を、指でぼりぼりと音をた
てて掻いていた。皮膚は、変色してもいなかった。
「今度は、あたしの番ね」
部員全員が、バットを持って。マリヤに襲いかかってきていた。それから、部室の中を、マリヤ
という名前の紺色の大きな台風が荒れ狂った。紺色のスカートが、彼らの頭上で黒い雲のよう
に暴れていた。ルーズソックスに包まれた白い足が、純白の750ccのオートバイのように襲来
した。次々に空中に、はねとばされていった。
ロッカーが倒れた。
各自の侍の剣のように大事なバットは、ぐしゃぐしゃに握りつぶされていた。割り箸のような木
切れになっていた。マリヤの握力は、それほどのものだった。踏み潰されたものもあった。彼女
としては、男子と遊んでやったつもりだった。
監督の嫌な脂汗に濡れていた男の顔面は、マリヤのローヒールの靴底に踏みつぶされて、
泥まみれにいた。打撃のショックで、手がなお肘まで痺れている状態だった。
抵抗した部員たちは、血を流して床や壁に倒れていた。ぴくりとも動かなかった。
マリヤの両の脇の下と、脚の太腿の間に挟まれて、番長と曲者とキャッチャーが、失神してい
た。彼女は、息も切らしていなかった。
「どう、強い男と、か弱い女の実力のちがいが、わかったかしら」
そして、監督と九人の部員は、マリヤの性の奴隷にされたのだった。
マリヤは男子野球部の部室で、思う様に、快感に豊満な白い姿態を、巨大な蛇のようにくね
らせて揺らしていた。
痴態を、見ているのは、窓から差し込む月光だけだった。何をしても良かったし、何をすること
も可能だった。マリヤの力に逆らって、それを止めることができるものは、だれもいなかった。
裏庭の草原からは、虫のすだく声がかまびすしかった。
いずれも、坊主頭の全裸の中学生の男子九名に、奉仕させていた。
両方の盛り上がった乳房の山頂に、一人ずつを黒い小鳥のように留まらせていた。ゴリラと
犬田だった。乳首を愛撫させていた。脇の下も一人ずつに念入りに舐めさせていた。汗が溜ま
って気持ちが悪かった。
腹の上の番長は、マリヤの奔放な動きに、跳ねとばされそうになっては、必死にしがみついて
いた。嵐の海の大船の甲板に、のっているような気分だったろう。このタイタニック号は、人間
の肉で出来ているのだった。
股間に、髪の短い坊主頭の男の頭部があって、激しく蠢いていた。監督だった。巨大な下腹
部と黒い密林の影になって、小さな男の顔はマリヤにも見えなかった。しかし、大人の男のテク
ニックだった。充分に満足させてくれた。監督よりも、女の紐になった方が向いているのではな
いだろうか。
監督にこうしてもらいたかったのだ。ああん、好きよ。彼女は、心の中で、彼の名前を呼ぶと、
彼の坊主頭をいとおしそうに撫でていた。同世代のガキよりも、大人を服従させることで、性欲
がより燃えあがるのだった。
長い長い白い脚にも、一人ずつがまとわりついていた。舌で奉仕させていた。足の裏に一人
がいて、これも舌で、一日のルーズソックスの中で蒸れていた汚れと臭いを、掃除させていた。
足の指の間まで入念にやらせた。
総勢九人。王女さまのような、豪華な夜だった。
思うままに、大きな声を出して暴れて、喘いだ。男子の、はあはあぜいぜいという、激しい吐
息もしていた。巨大な女体を感じさせるという重労働の重圧に、喘いでいた。無理もないマリヤ
の肉体の各部の重量だけでも、数百キログラムはあっただろう。苦しげな肉体労働者の呼吸
音がしていた。それもマリヤの快感を高める美酒だった。この責め苦は、きっかり一時間続い
た。
「ああ、おいしかったなあ」
マリヤは帰り道で、星のきらめく銀河を見上げながら、背伸びをしていた。まだ、野球部の部
室では、大人一人と九人の少年全員が、疲労困憊して、意識を回復せずに、引っ繰り返ってい
ることだろう。長い一日だった。彼らのミルクは、すっかり飲み干してやった。あと、三日間は、
足腰が立たないだろう。野球の練習も、出来ないかもしれなかった。なにしろ玉がないもの。マ
リヤは、口元のよだれを拭って、笑った。
帰りの道は、暗くなっていた。道のところには、ところどころに街灯の明かりがあったが、その
まわりは闇に包まれていた。前世紀の隕石ガイアの衝突の際に壊滅した廃墟が、ほとんどそ
のままに、緑の中に放置されていた。日本は大災害の傷跡から、ほとんど回復していなかった。
雨の夜には、鬼火が燃えるという噂があった。マリヤは、別に恐いとも思わなかった。前世紀の
街は、マリヤにとっては、小人の住む世界だった。小人の幽霊など恐くはなかった。
それでも、後から追い付いてくる長身の人影に出会った時には、ほっとしていた。クラスの委
員長の松本貴子だった。紺色のセーラー服が、彼女が着ていると、王女の正装のように、気品
のあるものに見える。不思議だった。
クラスでも、一番の長身の部類である。三メートル六十センチ以上は、あった。眉毛が濃い。
意志の強そうな端正な顔だちをしていた。黒目勝ちの瞳に力があった。夜の中でも、きらきらと
光っている。
三メートル十センチと、女子の中では小柄なマリヤは、並んで歩くと見下ろされてしまうのだっ
た。頭一つ分の相違があった。
松本貴子は、試験も学年で五位以内をつねにキープしていた。ガリ勉タイプではない。運動
の方も、バレー部のエース・アタッカーだった。腕力もマリヤの比ではないだろう。今も、練習を
終わって帰るところだという。駅まで同じ方向だった。
マリヤは、男子の運動部を次々と襲っては、いたずらを繰り返しているのも、自分の身体が女
子としては小さいという、劣等感のせいなのかもしれないと思っていた。自分の大きさと強さを、
せめて男子を相手にして、誇示したいだけなのだろうか。
横幅と胸の丸さでは、貴子にも負けていなかった。それでも、バレーの試合で、委員長がアタ
ックをするために、ネットぎわで体操服の胸元を、ぐいっと反らすようにしたきなどは、相当に大
きいことがわかった。いつもは、何となく猫背で俯くようにして歩いているので、目立たないの
だ。
貴子は友達は多いのに、休み時間は自分の席で、一人で文庫本を静かに読んでいることの
方を好んでいた。明らかに文学少女である。隠れ読書家であるマリヤは、好感を持っていた。
前世紀までの、男性と女性が同じ大きさであった時代の、恋愛小説を愛読していた。
松本貴子は、中学三年生の光史郎と、高校三年生の二人の兄貴がいたはずだった。マリヤ
のような不良にも、別け隔てせずに、気軽に話し掛けてくれた。彼女にだけは、マリヤも気を許
して、自然に付き合えたのだった。
駅の前に新しい甘味処が開店した。冷たいお汁粉を、飲ませてくれる店がある。大きなお餅
が入っている。食べにいかない。そんな誘いだった。貴子の頬もぷくぷくとして丸かった。笑み
を浮かべていた。マリヤのセーラー服の下で、お腹が、ぐうっと鳴った。そういえば放課後は、
ビール三本と、男子のミルクちょっぴりしか、腹にいれていなかったのだ。ちょっとした運動もし
た。「行きます」そう気軽に、委員長の顔を見上げて答えていた。同級生なのに、貴子にだけは、
敬語になるのが、自分でも不思議だった。年上のお姉さんと、話をしているような気分になるの
だった。「あたし、お代わりをするかも、しれなくてよ」松本貴子がそういうので、「あたしもです」
と、これも丁寧に答えていた。
新・第三次性徴世界シリーズ・1
天女中学校野球部部室の巻 了
【作者後記】はじめまして。笛地静恵と申します。ネットに巨大な女の子を主人公とする、小説を
発表しているものです。「妹の部屋」の作品を記憶している方も、何人か、いらっしゃると思いま
す。「The darkside of the moon」と「Peter Panty」の二編は、改稿の上で、こちらで再度、
発表して頂く予定に なっています。これは、「第三次性徴世界」という、環境ホルモンの影響で
女性が男性よりも、二倍以上に大きくなった世界での、長編の物語の一部です。クロさんのHPに
掲載していただいていた、「巨大女子高生百物語」の姉妹編になります。こちらは、「巨大女子中
学生」が活躍します。評判がよければ、続編を書いていこうと思っています。よろしくお願い申し
上げます。拙作の、発表の場所を提供していただいた、伊藤一蔵さんに深く感謝いたします。
千城醉歌笔耕不辍发布于 2016-09-16 23:01
Re: 笛地静恵さんの新・第三次性徴世界シリーズ
话说有翻译的吗

Mo
moonlighte发布于 2016-09-17 06:34
Re: 笛地静恵さんの新・第三次性徴世界シリーズ
这是什么?
千城醉歌笔耕不辍发布于 2016-09-17 14:55
Re: 笛地静恵さんの新・第三次性徴世界シリーズ
"moonlighte":这是什么?这是一条神奇的天路~埃