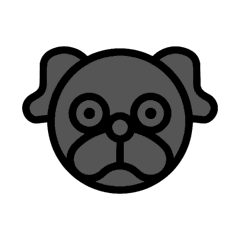正当自白拷问法(已全部转载 长篇日文求大神随意翻译几段)
外文原文
我一口气全部转载过来了 求大神随意翻译其中几段让大家鉴赏
1:「決意」
新人が目の当たりにする凄惨な拷問。正義の代行者として、人はどこまで情をなくせるのか。
ペンを持つ手が震えた。
薄暗い拷問部屋には数々の器具が取り揃えられている。施してきた拷問の歴史を表すように、それらは冷たく、無機質に、その血塗られた姿を晒していた。どれも目を覆いたくなるような品ばかりだ。
幸い、今日の器具使用は必要最低限のものに留められていた。
違反者の男の両手足を拘束するための磔台――それ以上のものを使用することはないと、由香利先輩から事前に聞かされていた。実践見学研修の初日では刺激が強すぎるという理由から、先輩がそのように取り計らってくれたのだろう。
もちろん、いずれそれらを使用しなければならないことも、そのための勉強を欠かせないこともわかっていた。でも、私は少し安心していた。今日だけは、その使用を見なくて済むのだから。
「ご気分はいかがですか?」
そう問いかける先輩の拳は、男の弛んだ腹に延々と叩き付けられていた。彼の名は神沼誠次。歳は二十九。正当拷問自白法の違反者だ。だぶついた大きな身体だが、身長は低い。呻き声を上げながら、彼は、
「苦し、い……です。お願……す。もう――」
と、必死で懇願している。私は、彼の様子を事細かに書類に書き綴っていった。
自白のための拷問を認める法律が正式に制定されたのは、もう何年も前のことだ。そして、その法に違反した者は、拒否罪に問われる。ある者は幾年、ある者は一生、死よりも辛い拷問を受け続けることになる。但し、その刑に服して社会復帰できた者の話は、未だ聞かない。私はその処刑人として、ここに配属された。
受刑者の顔を見るのがきつい――それが正直な気持ちだった。受刑者の取りがちな行動や、それへの対処法などは、もちろん研修講義の段階で一通り学んでいた。内容が頭に入るまで、マニュアルに何度も目を通した。しかし、実践見学となると話は別だ。私は平静な表情を繕うのがやっとだった。
手の震えが止まらない。足が竦んでいる。凄惨な場面に、思わず目を逸らしてしまうこともある。
しかし由香利先輩は、そんな私の行動を敏感に察知する。その時には必ず、
「新村さん」
と、厳しい声が飛んでくる。叱られるのも当然だ。先輩が実践を見せてくれているのは、他ならぬ私のためなのだから。
しっかりと見て、学習し、できるだけ多くのことを吸収する。それが、今日の私の義務だ。
私は「はい!」と返事をして気を引き締め、再び、先輩と受刑者に視線を向ける。
男は涙を浮かべ、決して叶うことのない願いを叫んでいる。その声は既に掠れていた。目が虚ろだ。時々、激しく咳き込む。喉から荒い息音を発し、口の端から胃液を垂れ流している。
私はペンを握り直し、書類にその様子を書き留めていった。
「苦しいですか?」
「うぐうっ!……はひぃ……」
「もっと抉りますからね」
「っ……はぐうっ!」
「潰れるまでの我慢ですので」
「っはっ!……ぐふうぉ!」
先輩は嬉々とした表情を湛え、男の腹を殴り続けた。彼の苦痛を労わる言葉をかけながら、さらなる苦痛を躊躇なく与えている、といった印象だ。
プロの世界――。私は肌でそう感じていた。
受刑者――神沼誠次の口から鮮血が溢れ出した頃、唐突に由香利先輩から声をかけられた。
「新村さん、交代ね」
その言葉に、私は耳を疑った。
「えっ……!?」
素っ頓狂な声と同時に、私は再びペンを落としてしまう。思わぬ指示に、戸惑いを隠せなかった。先輩は私に一度にっこりと微笑むと、痙攣し始めている彼に、
「こちら、研修生の新村明菜です。実践経験の一貫として、ここで交代させていただきます」
と呼びかけると、私に手招きをした。
足の震えが止まらなかった。
見ているだけでもこんなに恐ろしいのだ。実際に拷問を行うなんて、できるはずがない。しかし、先輩の瞳は真剣そのものだった。私の手を引き、
「失礼のないように、ね」
と、優しい口調で私に囁く。
私は困惑していた。
――できるわけ、ないじゃん……
その思いだけが、私の中に広がっていく。男がゴボゴボと喉から異様な音を立て始めるのを見ながら、私は無意識に首を横に振っていた。
その時、バシッという音とともに、私の首が大きく横に振られた。頬を張られたのだ。じわじわと熱を帯びてくるのがわかる。無意識に涙が溢れる。霞んで見える先輩の表情には、鋭い眼光が湛えられていた。
「遊びじゃないの」
冷然とした口調で言い放った先輩の言葉が、私の全身を貫いた。
先輩はそっと私の手を取り、男の前へと立たせる。私の手からペンと書類を抜き取り、先輩がそれに目を通す。そして、極めて事務的な口調で、
「内臓損傷終了です。残るメニューは――」
と、確認するように内容を読み上げる。もちろんメニューは頭に入っていた。だからこそ、こんなにも震えが止まらないというのに……どうして……?
「真剣にね」
そう言葉を加えられ、トンと背中を軽く押される。私は覚悟が決まらないまま、
「た……担当代理の、に、新村明菜です。よろしくお願いします」
と挨拶をする。
声が上擦ってしまう。逃げ出したい衝動に駆られる。そんな私の肩に、先輩がそっと手を置いた。
私は勢いに任せ、恐る恐る男の指に手を伸ばす。それに反応し、彼は触れる前から耳を劈くような悲鳴を上げた。目を大きく見開き、涎を撒き散らしながら声を上げ続ける。
狂人的なその反応が恐ろしくなり、私はその場で腰を抜かしてしまう。自然と涙が溢れてくる。しかし、先輩は態度を変えなかった。私を見ながら、なおも立つように指示する。
――どうして? 私をいじめて、楽しんでるの?
徐々に、先輩に対する不信感が芽を出してくる。先輩の微笑が鬱陶しい。
私は深く息を吸い込み、ゆっくりと立ち上がった。怒りが開き直った気持ちとなって、私の動揺を鎮めていった。
あらためて男の前に立ち、非礼を詫びる。同時に、横目でちらりと由香利先輩の顔を睨みつける。
――やってやる。……見てなさいよ。
私は再度、視線を目の前の男に向けた。
男の様子に目立った変化はない。相変わらず、時に怒号を上げ、時に弱々しい目を向ける。私は同情心を振りきり、再びその指に手を伸ばした。
「ひ、ひぃ! ひいぃ!……助け……おね、お願いします……」
男のその言葉に、私はつい手をピクリと反応させてしまう。彼は咳き込み、目を真っ赤に腫らし、後から後から涙を零し続けていた。嗚咽を漏らし、存分に顔を崩した彼の姿は、とても哀れに思えた。
手が動かない。
男は私の触れている指を懸命に動かし、抵抗の意思を表す。あまりにも非力だ。人間は、手首を拘束されているだけで、こんなにも力を無くしてしまうものなのか。例え、それが大の男であっても。
私は男の手をしっかりと捕らえ、小指を掴む。それは容易いことだった。しかし――
「や、……やめ……。ゆる、やべでぇええ!」
……彼の悲鳴が、私にとっての歯止めとなってしまう。
無駄な抵抗。それは自明なことだった。私にとっても、もちろん、この制度を知っているであろう彼にとっても。ここで公務をきちんと執行することが、今の私に課せられた義務なのだということも、十分承知していた。それなのに……
自分の額に汗が滲んでくるのがわかった。男の手を辛うじて掴んだまま、私は困惑する。理性と感情が鬩ぎ合い、葛藤を起こす。無意識に先輩に視線を送ってしまう。
「ゆ、由香利先輩……あの……」
喉から出たのは、紛れもない怯声だった。私は救いを待った。しかし、先輩は毅然とした態度を崩さない。その瞳は凛とした光を湛え、ただ男と私をじっと見つめていた。そして、
「甘えないで」
と、毅然とした表情のままで言い放つだけだった。その態度に、私は再び感情を逆撫でされる。
――別に、甘えてなんかない! 言われなくたって……
意を決し、私は男の小指の関節に親指を宛がう。手を添え、ぐいと力を込める。
「ひっ……、いや……嫌だあっ!」
彼の懇願の声が痛々しい。それを振り払うように目を瞑り、さらに力を加える。しかし、想像していた以上に関節の骨は硬かった。じわじわと力を強めていくにつれて、彼の叫びも大きくなる。
「やめえええぇ!……ぎぃ、があっ! いいいいっ!……ああああっ!!」
――黙って! お願い。もう少し……
その時、ボキッという鈍い音が鳴った。ようやく男の小指の骨が折れたのだ。しかしそれは、私の本意ではなかった。当然だ。それは私の手による骨折ではなかったのだから。
男の絶叫が鳴り響く中、私は目を開いた。先輩の瞳が、私を貫いていた。
「酷い! 私、頑張ってたのに……最後までやらせてくれないなんて!」
私は無意識に、感情を先輩にぶつけてしまう。しかし先輩は、無言のままだった。すぐに私から目を逸らし、男に視線を戻す。そして、
「本当に、ごめんなさい」
と、彼に頭を下げた。先輩の瞳には、うっすらと涙が浮かんでいた。
理解できなかった。
――どうして? なぜ、先輩が泣いて……?
先輩は男の手をしっかりと握り、自分の胸元に固定する。そして――
「ぐあああああぁっ!」
……もう片方の手で、彼の薬指の関節を躊躇なく折る。
「も、もうだ、……ダメ、やめ……」
と、枯れ果てた声で叫ぶ男の声を聞きながら、手際よく中指の関節も手懸ける。
「ぎぃ……いぃやああああっ!」
聞くに堪えない絶叫に、私は思わず耳を塞いでしまう。身体が震える。渡されたペンと書類を拾うことも忘れ、ただ目だけをしっかりと開いていた。正確には、その光景に目を奪われてしまっていたのだろう。職務を忠実に執行する、先輩の手腕に見惚れるかのように。
しかし先輩は、さらに私に無言の指示を重ねた。横目で私を見ながら、自分の耳を二、三度指差す。耳を塞ぐことすら許されないのだ。両耳から手を放した私の耳に「ちゃんと聴くのが礼儀だよ」という先輩の声が響いてきた。
再び男をしっかりと見据えた先輩は、
「痛いですよね」
と、問いかける。そして、
「も、もう、……本当に……ぐがああああっ!!」
と懇願し、断末魔の声を上げる彼をにこやかに見ながら、手際よく指を折っていった。気付けば、既に残った指は親指だけになっていた。拷問を施す先輩の瞳からは、不思議と慈愛のようなものが感じられる。
「ひぃ……ひ……お願い……」
「最後の一本ですね」
そう囁き、先輩は微笑んだ。もはや抵抗する気力も失ったのか、既に男が手を動かすことはなかった。青ざめた表情のまま目を大きく見開き、ただ先輩を見ていた。先輩はその笑みを崩すことなく、彼の親指の関節に手をかける。
「ぐっ……ああああああっ!!」
拷問部屋を覆う男の悲鳴とともに、第二のメニューである『片手全指骨折』が幕を閉じた。
男の絶叫が響く中、先輩は私へとその視線を注いだ。目が自然と泳いでしまう。先輩は私の肩をポンと叩くと、穏やかな口調で話し始めた。
「私たちは、警察官なの。法に従って職務を遂行する。それが仕事だよ」
そう言うと、再び彼の方へと視線を向ける。
――そんなこと、わかってる。でも……
私は、躊躇なく違反者を痛めつける先輩に対する反感を、どうしても拭い去ることができなかった。
確かに先輩が言っていることは正論だ。法律に背くことは許されない。しかし、だからと言って、あんなにも事務的に……。いや、それも違う。だからこそ、余計にわからない。先輩は、決して冷酷な人間でもないのだ。むしろ人一倍、情深くも見える。
拷問を行う際の笑顔。慈愛に満ちた瞳。何より、さっきのあの涙の意味――
考えれば考えるほどわからなくなっていった。
そして、今まさに、先輩は男を抱きしめている。震える背中を優しく擦り、耳元に唇を寄せていた。
「次で最後です」
先輩の囁く声を聴き、私はあらためて書類とペンを拾い上げた。おそらく、先輩はソツなくこなしてしまうのだろう。しかし、本当にそれでよいのかという懸念が、私を突き動かしていた。
「由香利先輩……」
思わず、私は先輩に声をかけていた。
「もう。……もう終わりにしては、ダメですか?」
私がそう言葉を重ねた時、男の表情がにわかに精気を帯びてくるのがわかった。しかし同時に、先輩の表情はみるみるうちに険しくなっていった。
先輩は男に一礼し、私の元へと歩を進めた。しかし、私もまた毅然とした態度を崩さなかった。先輩が私の目の前で立ち止まった時、私は、
「先輩、酷すぎます!」
と、半ば感情的に、内に溜めていた思いを吐き出した。先輩は私の言葉を聞き、ふっと穏やかな笑みを私に向ける。
「さっきも言ったでしょ? 私たちは法律の――」
「わかってます。でも先輩は、その、冷たい……と思うんです」
「冷たい?」
「そうです。容赦も躊躇もない。手加減も一切しない」
「……その考えは違うよ」
そう言った先輩の表情は、少し寂しさを感じさせるものだった。先輩がさらに口を開く。
「さっきの執行中、あなたは手加減してたの?」
「いえ。……一生懸命やりました。でも、痛がったら躊躇する。それが人間だと思います」
「違う。どんな過程を経ても、刑は実行する。あなたの過程がもたらしたのは、何だった?」
そう訊かれ、私は答えに窮する。先輩は微笑し、言葉を重ねた。
「恐怖と痛み、苦しみの継続。……違う?」
「っ……」
「それはじわじわと甚振る行為と同じ。それは優しさじゃない。苦しみを長引かせるだけなの」
「……で、でも、頑張ってたんです。情を捨てようと、必死で――」
「一生懸命なのはわかってたよ。だけどね……」
そこで一呼吸置き、先輩はあらためてじっと私の瞳を見つめた。そして、
「違反者は実験道具じゃない。人間なの。尊厳を損ねる行為は……許されない」
と、言葉を紡いだ。
私の価値観が壊れていくのを、はっきりと感じた。
私は、踵を返した先輩の横を通り抜けた。
横目でちらりと見た先輩の顔には、とても穏やかな笑みが浮かんでいた。
「頑張ってね」
その言葉を背中で聞きながら、私は男の方へと真っ直ぐに進んでいった。
彼の表情は、若干和らいでいるように見えた。その縋るような瞳を見た時、私はようやく心から微笑むことができた。私の中で彼が、受刑者――神沼誠次から、人間――神沼誠次へと変わった瞬間だった。
拳を固く握りしめ、神沼さんの睾丸を凝視する。
振り下ろす拳――。私はもう迷わなかった。
1:「決意」
新人が目の当たりにする凄惨な拷問。正義の代行者として、人はどこまで情をなくせるのか。
ペンを持つ手が震えた。
薄暗い拷問部屋には数々の器具が取り揃えられている。施してきた拷問の歴史を表すように、それらは冷たく、無機質に、その血塗られた姿を晒していた。どれも目を覆いたくなるような品ばかりだ。
幸い、今日の器具使用は必要最低限のものに留められていた。
違反者の男の両手足を拘束するための磔台――それ以上のものを使用することはないと、由香利先輩から事前に聞かされていた。実践見学研修の初日では刺激が強すぎるという理由から、先輩がそのように取り計らってくれたのだろう。
もちろん、いずれそれらを使用しなければならないことも、そのための勉強を欠かせないこともわかっていた。でも、私は少し安心していた。今日だけは、その使用を見なくて済むのだから。
「ご気分はいかがですか?」
そう問いかける先輩の拳は、男の弛んだ腹に延々と叩き付けられていた。彼の名は神沼誠次。歳は二十九。正当拷問自白法の違反者だ。だぶついた大きな身体だが、身長は低い。呻き声を上げながら、彼は、
「苦し、い……です。お願……す。もう――」
と、必死で懇願している。私は、彼の様子を事細かに書類に書き綴っていった。
自白のための拷問を認める法律が正式に制定されたのは、もう何年も前のことだ。そして、その法に違反した者は、拒否罪に問われる。ある者は幾年、ある者は一生、死よりも辛い拷問を受け続けることになる。但し、その刑に服して社会復帰できた者の話は、未だ聞かない。私はその処刑人として、ここに配属された。
受刑者の顔を見るのがきつい――それが正直な気持ちだった。受刑者の取りがちな行動や、それへの対処法などは、もちろん研修講義の段階で一通り学んでいた。内容が頭に入るまで、マニュアルに何度も目を通した。しかし、実践見学となると話は別だ。私は平静な表情を繕うのがやっとだった。
手の震えが止まらない。足が竦んでいる。凄惨な場面に、思わず目を逸らしてしまうこともある。
しかし由香利先輩は、そんな私の行動を敏感に察知する。その時には必ず、
「新村さん」
と、厳しい声が飛んでくる。叱られるのも当然だ。先輩が実践を見せてくれているのは、他ならぬ私のためなのだから。
しっかりと見て、学習し、できるだけ多くのことを吸収する。それが、今日の私の義務だ。
私は「はい!」と返事をして気を引き締め、再び、先輩と受刑者に視線を向ける。
男は涙を浮かべ、決して叶うことのない願いを叫んでいる。その声は既に掠れていた。目が虚ろだ。時々、激しく咳き込む。喉から荒い息音を発し、口の端から胃液を垂れ流している。
私はペンを握り直し、書類にその様子を書き留めていった。
「苦しいですか?」
「うぐうっ!……はひぃ……」
「もっと抉りますからね」
「っ……はぐうっ!」
「潰れるまでの我慢ですので」
「っはっ!……ぐふうぉ!」
先輩は嬉々とした表情を湛え、男の腹を殴り続けた。彼の苦痛を労わる言葉をかけながら、さらなる苦痛を躊躇なく与えている、といった印象だ。
プロの世界――。私は肌でそう感じていた。
受刑者――神沼誠次の口から鮮血が溢れ出した頃、唐突に由香利先輩から声をかけられた。
「新村さん、交代ね」
その言葉に、私は耳を疑った。
「えっ……!?」
素っ頓狂な声と同時に、私は再びペンを落としてしまう。思わぬ指示に、戸惑いを隠せなかった。先輩は私に一度にっこりと微笑むと、痙攣し始めている彼に、
「こちら、研修生の新村明菜です。実践経験の一貫として、ここで交代させていただきます」
と呼びかけると、私に手招きをした。
足の震えが止まらなかった。
見ているだけでもこんなに恐ろしいのだ。実際に拷問を行うなんて、できるはずがない。しかし、先輩の瞳は真剣そのものだった。私の手を引き、
「失礼のないように、ね」
と、優しい口調で私に囁く。
私は困惑していた。
――できるわけ、ないじゃん……
その思いだけが、私の中に広がっていく。男がゴボゴボと喉から異様な音を立て始めるのを見ながら、私は無意識に首を横に振っていた。
その時、バシッという音とともに、私の首が大きく横に振られた。頬を張られたのだ。じわじわと熱を帯びてくるのがわかる。無意識に涙が溢れる。霞んで見える先輩の表情には、鋭い眼光が湛えられていた。
「遊びじゃないの」
冷然とした口調で言い放った先輩の言葉が、私の全身を貫いた。
先輩はそっと私の手を取り、男の前へと立たせる。私の手からペンと書類を抜き取り、先輩がそれに目を通す。そして、極めて事務的な口調で、
「内臓損傷終了です。残るメニューは――」
と、確認するように内容を読み上げる。もちろんメニューは頭に入っていた。だからこそ、こんなにも震えが止まらないというのに……どうして……?
「真剣にね」
そう言葉を加えられ、トンと背中を軽く押される。私は覚悟が決まらないまま、
「た……担当代理の、に、新村明菜です。よろしくお願いします」
と挨拶をする。
声が上擦ってしまう。逃げ出したい衝動に駆られる。そんな私の肩に、先輩がそっと手を置いた。
私は勢いに任せ、恐る恐る男の指に手を伸ばす。それに反応し、彼は触れる前から耳を劈くような悲鳴を上げた。目を大きく見開き、涎を撒き散らしながら声を上げ続ける。
狂人的なその反応が恐ろしくなり、私はその場で腰を抜かしてしまう。自然と涙が溢れてくる。しかし、先輩は態度を変えなかった。私を見ながら、なおも立つように指示する。
――どうして? 私をいじめて、楽しんでるの?
徐々に、先輩に対する不信感が芽を出してくる。先輩の微笑が鬱陶しい。
私は深く息を吸い込み、ゆっくりと立ち上がった。怒りが開き直った気持ちとなって、私の動揺を鎮めていった。
あらためて男の前に立ち、非礼を詫びる。同時に、横目でちらりと由香利先輩の顔を睨みつける。
――やってやる。……見てなさいよ。
私は再度、視線を目の前の男に向けた。
男の様子に目立った変化はない。相変わらず、時に怒号を上げ、時に弱々しい目を向ける。私は同情心を振りきり、再びその指に手を伸ばした。
「ひ、ひぃ! ひいぃ!……助け……おね、お願いします……」
男のその言葉に、私はつい手をピクリと反応させてしまう。彼は咳き込み、目を真っ赤に腫らし、後から後から涙を零し続けていた。嗚咽を漏らし、存分に顔を崩した彼の姿は、とても哀れに思えた。
手が動かない。
男は私の触れている指を懸命に動かし、抵抗の意思を表す。あまりにも非力だ。人間は、手首を拘束されているだけで、こんなにも力を無くしてしまうものなのか。例え、それが大の男であっても。
私は男の手をしっかりと捕らえ、小指を掴む。それは容易いことだった。しかし――
「や、……やめ……。ゆる、やべでぇええ!」
……彼の悲鳴が、私にとっての歯止めとなってしまう。
無駄な抵抗。それは自明なことだった。私にとっても、もちろん、この制度を知っているであろう彼にとっても。ここで公務をきちんと執行することが、今の私に課せられた義務なのだということも、十分承知していた。それなのに……
自分の額に汗が滲んでくるのがわかった。男の手を辛うじて掴んだまま、私は困惑する。理性と感情が鬩ぎ合い、葛藤を起こす。無意識に先輩に視線を送ってしまう。
「ゆ、由香利先輩……あの……」
喉から出たのは、紛れもない怯声だった。私は救いを待った。しかし、先輩は毅然とした態度を崩さない。その瞳は凛とした光を湛え、ただ男と私をじっと見つめていた。そして、
「甘えないで」
と、毅然とした表情のままで言い放つだけだった。その態度に、私は再び感情を逆撫でされる。
――別に、甘えてなんかない! 言われなくたって……
意を決し、私は男の小指の関節に親指を宛がう。手を添え、ぐいと力を込める。
「ひっ……、いや……嫌だあっ!」
彼の懇願の声が痛々しい。それを振り払うように目を瞑り、さらに力を加える。しかし、想像していた以上に関節の骨は硬かった。じわじわと力を強めていくにつれて、彼の叫びも大きくなる。
「やめえええぇ!……ぎぃ、があっ! いいいいっ!……ああああっ!!」
――黙って! お願い。もう少し……
その時、ボキッという鈍い音が鳴った。ようやく男の小指の骨が折れたのだ。しかしそれは、私の本意ではなかった。当然だ。それは私の手による骨折ではなかったのだから。
男の絶叫が鳴り響く中、私は目を開いた。先輩の瞳が、私を貫いていた。
「酷い! 私、頑張ってたのに……最後までやらせてくれないなんて!」
私は無意識に、感情を先輩にぶつけてしまう。しかし先輩は、無言のままだった。すぐに私から目を逸らし、男に視線を戻す。そして、
「本当に、ごめんなさい」
と、彼に頭を下げた。先輩の瞳には、うっすらと涙が浮かんでいた。
理解できなかった。
――どうして? なぜ、先輩が泣いて……?
先輩は男の手をしっかりと握り、自分の胸元に固定する。そして――
「ぐあああああぁっ!」
……もう片方の手で、彼の薬指の関節を躊躇なく折る。
「も、もうだ、……ダメ、やめ……」
と、枯れ果てた声で叫ぶ男の声を聞きながら、手際よく中指の関節も手懸ける。
「ぎぃ……いぃやああああっ!」
聞くに堪えない絶叫に、私は思わず耳を塞いでしまう。身体が震える。渡されたペンと書類を拾うことも忘れ、ただ目だけをしっかりと開いていた。正確には、その光景に目を奪われてしまっていたのだろう。職務を忠実に執行する、先輩の手腕に見惚れるかのように。
しかし先輩は、さらに私に無言の指示を重ねた。横目で私を見ながら、自分の耳を二、三度指差す。耳を塞ぐことすら許されないのだ。両耳から手を放した私の耳に「ちゃんと聴くのが礼儀だよ」という先輩の声が響いてきた。
再び男をしっかりと見据えた先輩は、
「痛いですよね」
と、問いかける。そして、
「も、もう、……本当に……ぐがああああっ!!」
と懇願し、断末魔の声を上げる彼をにこやかに見ながら、手際よく指を折っていった。気付けば、既に残った指は親指だけになっていた。拷問を施す先輩の瞳からは、不思議と慈愛のようなものが感じられる。
「ひぃ……ひ……お願い……」
「最後の一本ですね」
そう囁き、先輩は微笑んだ。もはや抵抗する気力も失ったのか、既に男が手を動かすことはなかった。青ざめた表情のまま目を大きく見開き、ただ先輩を見ていた。先輩はその笑みを崩すことなく、彼の親指の関節に手をかける。
「ぐっ……ああああああっ!!」
拷問部屋を覆う男の悲鳴とともに、第二のメニューである『片手全指骨折』が幕を閉じた。
男の絶叫が響く中、先輩は私へとその視線を注いだ。目が自然と泳いでしまう。先輩は私の肩をポンと叩くと、穏やかな口調で話し始めた。
「私たちは、警察官なの。法に従って職務を遂行する。それが仕事だよ」
そう言うと、再び彼の方へと視線を向ける。
――そんなこと、わかってる。でも……
私は、躊躇なく違反者を痛めつける先輩に対する反感を、どうしても拭い去ることができなかった。
確かに先輩が言っていることは正論だ。法律に背くことは許されない。しかし、だからと言って、あんなにも事務的に……。いや、それも違う。だからこそ、余計にわからない。先輩は、決して冷酷な人間でもないのだ。むしろ人一倍、情深くも見える。
拷問を行う際の笑顔。慈愛に満ちた瞳。何より、さっきのあの涙の意味――
考えれば考えるほどわからなくなっていった。
そして、今まさに、先輩は男を抱きしめている。震える背中を優しく擦り、耳元に唇を寄せていた。
「次で最後です」
先輩の囁く声を聴き、私はあらためて書類とペンを拾い上げた。おそらく、先輩はソツなくこなしてしまうのだろう。しかし、本当にそれでよいのかという懸念が、私を突き動かしていた。
「由香利先輩……」
思わず、私は先輩に声をかけていた。
「もう。……もう終わりにしては、ダメですか?」
私がそう言葉を重ねた時、男の表情がにわかに精気を帯びてくるのがわかった。しかし同時に、先輩の表情はみるみるうちに険しくなっていった。
先輩は男に一礼し、私の元へと歩を進めた。しかし、私もまた毅然とした態度を崩さなかった。先輩が私の目の前で立ち止まった時、私は、
「先輩、酷すぎます!」
と、半ば感情的に、内に溜めていた思いを吐き出した。先輩は私の言葉を聞き、ふっと穏やかな笑みを私に向ける。
「さっきも言ったでしょ? 私たちは法律の――」
「わかってます。でも先輩は、その、冷たい……と思うんです」
「冷たい?」
「そうです。容赦も躊躇もない。手加減も一切しない」
「……その考えは違うよ」
そう言った先輩の表情は、少し寂しさを感じさせるものだった。先輩がさらに口を開く。
「さっきの執行中、あなたは手加減してたの?」
「いえ。……一生懸命やりました。でも、痛がったら躊躇する。それが人間だと思います」
「違う。どんな過程を経ても、刑は実行する。あなたの過程がもたらしたのは、何だった?」
そう訊かれ、私は答えに窮する。先輩は微笑し、言葉を重ねた。
「恐怖と痛み、苦しみの継続。……違う?」
「っ……」
「それはじわじわと甚振る行為と同じ。それは優しさじゃない。苦しみを長引かせるだけなの」
「……で、でも、頑張ってたんです。情を捨てようと、必死で――」
「一生懸命なのはわかってたよ。だけどね……」
そこで一呼吸置き、先輩はあらためてじっと私の瞳を見つめた。そして、
「違反者は実験道具じゃない。人間なの。尊厳を損ねる行為は……許されない」
と、言葉を紡いだ。
私の価値観が壊れていくのを、はっきりと感じた。
私は、踵を返した先輩の横を通り抜けた。
横目でちらりと見た先輩の顔には、とても穏やかな笑みが浮かんでいた。
「頑張ってね」
その言葉を背中で聞きながら、私は男の方へと真っ直ぐに進んでいった。
彼の表情は、若干和らいでいるように見えた。その縋るような瞳を見た時、私はようやく心から微笑むことができた。私の中で彼が、受刑者――神沼誠次から、人間――神沼誠次へと変わった瞬間だった。
拳を固く握りしめ、神沼さんの睾丸を凝視する。
振り下ろす拳――。私はもう迷わなかった。
二:「由香利ノート -強制自白編-」
由香利は己が信念を突き進む。拷問は正義の名の下に。ノートは全てを記録する。
冷えた空気が火照った身体に心地よかった。
思った以上に疲れていたらしい。ゆっくりとお湯に浸かったことで、手足が幾分軽くなっているのが分かった。
浴室の照明を切って部屋に入り、すぐさまドレッサーへと向かう。ちょっと前までは、こんなバスローブ一枚の姿では寒くてたまらなかった。あらためて、季節の移り変わりの早さを実感する。
髪を頭の上で軽くまとめ、化粧水を手に取る。それをコットンに多めに含ませ、頬を丹念に撫でていく。化粧台の前には、たくさんの美容液や化粧品が並んでいる。それらを使ってお肌のケアに勤しむ。
一通り終わって顔のお肌チェックをしている頃、小さなケータイが私を呼んだ。掌の半分ほどの大きさのそれを手に取る。着信表示には大切な先輩の名前が浮かんでいた。
「はい!」
喜びと期待でつい大きな声を出してしまう。
「もしもし、由香利――」
甘くて優しい声が身を包む。
さっきまで感じていた疲れがまるで嘘だったかのように、身体中に元気が漲ってくる。
「凛先輩、こんばんは! おつかれさまです!」
「うん。今日は本当におつかれさま。正直、疲れたでしょ?」
「はい。でも、先輩から電話をもらったら急に元気になっちゃいました。」
通話口の向こう側から、苦笑にも似た笑い声が聞こえる。
「……どうだった?」
「そうですね。初めての仕事だったので、いろいろと新しい発見がありました。」
「どんな?」
凛先輩のその言葉を聞き、あらためて今日の出来事をふり返ってみる。その時になって初めて、今日の日記をまだつけていなかったことに気が付いた。そのことを考え込み、しばし沈黙してしまう。
再度、先輩の言葉が通話口から聞こえてきた。
「あ、いきなりそんなこと聞かれても困っちゃうね。ごめん。」
黙り込んでしまったことで心配をかけてしまったのかもしれない。慌てて口を開く。
「ごめんなさい。いろいろとあったんですけど。」
「一口では言えないよね。本当、無理しなくていいから。またゆっくり聞かせてね。」
「ありがとうございます。これからも頑張ります!」
「――ん……あの、さ……。……あまり気張らなくていいからね。」
「ご心配、ありがとうございます! 嬉しいです!」
「もし辛かったら――」
「全然! 今日もすごく楽しかったので!」
「……そう。……それならいい。これから一緒に仕事をする機会もあると思うから、よろしくね。」
「はい。こちらこそです。どうぞよろしくお願いします!」
そこで通話は途切れた。
凛先輩から直接電話してもらえたことで、心までリラックスできていることに気付く。あらためて先輩に対する感謝の気持ちが膨れ上がってくる。心地よい気分で机に向かい、私は一冊のノートを手に取った。新しく買った分厚いノートの表紙には『由香利ノート』と記してある。表ページの見開きに書いた『正当拷問自白法 執行記録』という大きな文字を見ていると、今日の仕事の光景がまざまざと脳裏に浮かんでくる。私は夢中になってノートにペンを走らせた。
ノートを書き終えた時、私の胸はなぜか大きな高鳴りを見せていた。
ふと時計を見上げる。針は深夜一時を指していた。
――こんなにドキドキして、眠れるのかな?……でも明日も仕事! 寝不足は美容の敵!
そんなことを考えながら、私はベッドに潜り込んだ。
人事異動が終わって、新しい部署に回された。私は今年度、晴れて『正当拷問自白法違反者処刑人』から『正当拷問自白法取調執行人』へと昇格になった。
刑事としてのランクアップはもちろん嬉しいけど、それについては正直まだ実感がない。それよりも私が何より嬉しかったのは、憧れの凛先輩と同じ部署で働くことができるようになったということ。
さっきも私を気遣って電話までしてくれた。本当に素敵な先輩だと思う。先輩も言ってたけど、これから一緒に仕事をすることもあるんだろうなぁ。そう考えると、すごく楽しみ!
今日は初日だから本当に緊張したし、正直疲れたけど、でもやっぱりやり甲斐のある素晴らしい仕事だと思った。
私の手で一人でも多くの悪人を自白させてみせる。そしていつか、全ての悪人をこの世から消してみせる。何より私は今、刑事として働けることがすごく嬉しい。悪人を懲らしめることがすごく楽しい。
この気持ちを持ち続けている限り、私はこれからも仕事を続けていけると思う。
容疑者 嶺岸秀一 二十四歳
取調室の前に立った途端、すごく荒っぽい声が聞こえてきた。
「違う……。違う! 俺はやってねえ! やってねえんだよ!」
私は気を引き締め、身に着けたミニスカートの裾を整える。この白のプリーツスカートは、買ったばかりのお気に入り。動きやすさを考えて、上半身には淡い黄緑の半袖Tシャツを選んだ。高めのヒールのついた薄いブラウンのブーツは膝丈サイズ。このコーディネートは、春を意識したものだ。アクセサリにも気を遣って、今日はネックレスとダイヤの指輪を身に着けてみた。
案内係の警官の「よろしくお願いします」という言葉に「はい!」と短く元気に返事をした後、私はドキドキしながら取調室の扉を開いた。
室内を覆う煙の臭いがきつかった。机上の灰皿の上には火のついたままのタバコが適当に置かれていて、煙がモクモクと出ていた。正直ケムかった……
紫煙の向こう側に、うっすらと男性二人の姿が見える。どちらも取り調べに当たっていた先輩刑事さんだ。でも、まだ部署に配属されたばかりで顔を見ても名前が浮かんでこない。後で勉強しておかないと……。次いで、その二人の刑事さんが、必死で取り押さえようとしている人物の姿が目に入った。
白んだ狭い部屋の中で目を凝らしてその顔を確認する。彼の第一印象は、私の想像とは全く違っていた。茶髪でもなければロン毛でもない。顔立ちには幼さが残り、純真な雰囲気を感じさせる。細身の身体に普段着をまとった彼は、真面目を絵に描いたような青年だった。
正直、私にはとても罪を犯すような人間には見えなかった。
刑事さん二人は私が入室したことを確認すると、
「後藤くん! こいつを取り押さえてくれ!」
と、私に声をかけてくる。その声はとても切迫したものだった。
私は表情を引きしめ、彼らのいる方へと急いだ。
机に置かれた火のついたタバコを手に取る。
私は刑事さん二人をかき分け、暴れる嶺岸さんの首筋にタバコの先をぐいと押し当ててみた。
「ぐああああっ!」
叫び声とともに、彼がエビみたいに大きく身体をのけぞらせる。その反動で彼は刑事さん二人の手を離れる。私はすかさず持っていたタバコを捨て、同時に彼のお腹に力いっぱい拳を叩き込んだ。
彼は呻き声を上げ、そのまま床に倒れ込んで悶絶した。
……バタバタしてる姿がちょっと可愛い。
刑事さん二人は「ふうっ」と大きく息を吐きながら呼吸を整え、襟元を正し始めていた。
私は転げ回る彼の喉元をブーツの底で踏み付けて押さえ込みながら、
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
と、自己紹介をする。
取調執行人としての仕事がこれから始まるのだと思うと、胸のドキドキが収まらない。私は自分の緊張を解すように、大きめの声で彼に告げたつもりだった。けれど彼はその言葉がまるで聞こえていないかのように、目を大きく見開いたまま、顔を真っ赤にして痙攣し始めていた。
……せっかくの自己紹介なのに、タイミング悪いな。
一呼吸ついた刑事さん二人は、まるで何事もなかったかのように彼に背を向け、
「では、ひとつよろしく頼むよ。」
「お願いしますね。」
と、私に声をかけた。私が「はい」とだけ答えると、彼らは無言のまま取調室を出て行った。
ドアの閉まる音を背中で聞きながら、私は嶺岸さんの喉仏にさらに体重を乗せる。彼はやがて口から泡を吹き、ぐったりと全身の力を抜いた。失禁し、ズボンの下半身がじわじわと濡れていく。
……ちょっとやりすぎちゃったかな。これから尋問しなきゃいけないし。
私は足を彼の喉元から放す。周囲を見回すと、ちょうど刑事さんが残していったライターが目に入った。手に取り、彼の耳を炙る。肉がじりじりと焦げる音を立て始めた頃、彼は悲鳴を上げて飛び起きた。何が起こったのか分からないといった様子で耳を押さえている彼の姿が滑稽で面白い。
私は再度、自己紹介をした。今度はちゃんと聞いてくれたと思う。
「じゃあ、早速質問させていただきますね。」
呆然としている彼に向かって、私はさらに言葉を続ける。
「あなたは京握区内で、無差別に罪のない多くの人たちを殺傷した爆弾魔ですね。」
その言葉を聞いても彼は無言のままだった。相変わらず耳を押さえたまま、身体を震わせ始める。
私がさらに「答えてください」と言った時、彼が突然私に飛びかかってきた。
「ふざけんな! 俺はやってねえ!」
と怒声を吐きながら、私に掴みかかる。
とてもそんなことをするような人には見えなかったので、すごくびっくりした。何より、私はこの時あらためて、処刑人と取調執行人の違いを実感していた。私が今まで拷問してきた人たちは皆『違反者』という肩書きをもった人たちだった。そんな彼らには法の下、適切なメニューが与えられていた。態度も基本的には従順だった。私はそういう人たちに、メニューの一つ一つを与えていただけ。でも、今は違う。目の前の彼もそうだけど、ここに来る人たちは皆、まだ自白もしていない容疑者なのだ。こうやって襲いかかってくることも多々あるのだろう。
彼のお陰で、私はまた一つ勉強することができた。
嶺岸さんの必死な形相が可愛かった。
大きな声で何かを訴える様子は、駄々をこねる子どもみたいで愛しかった。思わずぎゅってしたい衝動に駆られる。……反省。でも、自分の罪を認めない態度はやっぱりよくない。自白をしない悪い子にはお仕置きが必要だよね。
私は彼の左手をぐいと捻り上げる。
小指の骨を第二関節から折ると、彼は絶叫した。その時点で私を掴む力は緩んだけど、念のため薬指の骨も同じように折ってあげた。再び彼は絶叫して私から身体を離す。彼は蹲ったままで呻き声を上げていた。
何とか落ち着いてくれたみたいでまずは一安心、かな。
彼は左手を押さえ、床に膝をついたままで涙を零していた。心なしか、さっきよりも元気がなくなっているような気がする。怯えた目で私をじっと見つめている。私が近付こうとすっと足を前へ出すと、彼は「ひっ」と声を上げて後ずさる。その行動がすごく可愛くて、私はつい何度かその仕草を繰り返す。その度に、彼もまた同じ仕草を繰り返す。
……この人ならきっと、ちゃんと自白して反省できるはず。
でも彼は、それを認めることができなかった。私の問いに対しては「やってないんです。信じてください」の一点張りだった。
……まだちゃんとしたいい人にはなれてないみたい。少しがっかりしたけど、私がちゃんと自白できるようにお手伝いしなくちゃ……
私はそう心に決め、彼につかつかと近付いていった。
側に寄ると、彼は身を縮めて肩を震わせた。弱々しい声を上げながら嗚咽を漏らす様子を見ていると、また身体が火照ってくる。怯える様子に興奮してしまうこの癖は、未だに治っていない。私は思わず笑みを零していた。
「ちゃんと素直な人になれるまで、しっかり痛めつけさせてもらいますね。」
そう言って私は再び彼の左手を持ち上げ、中指にも手をかける。彼は絶叫した。声が震えている。
「や、やめろ!」
と言いながら私の手を振り払い、まるで芋虫のように這いながら壁際へと向かう。彼の足はガクガクと震えていた。恐怖のあまり足に力が入らなくなっているようだった。そんなに自分の犯した罪に怯えるなら、最初からやらなければいいのに。
……もう、困った人。
私は彼を見下ろしながら、その後をゆっくりと歩いて追った。
彼が必死で声を絞る。
「く、来るな!」
「ダメです。ちゃんと自白するまでは。」
「俺はやってないんだ。」
「あっ。まだそういう態度なんですか? そういうのよくないです。」
「信じてくれ……ください! こんなことしても、俺……僕は本当に――」
その時、彼に追いついた私は、彼の髪を掴んで強制的に立たせた。力が入らないのか、手を放すとすぐに膝から崩れ落ちてしまう。なかなか自分で立ってくれない。
私はチェーンネックレスを外して彼の首にかけ、同時にそれを窓にある格子に潜らせて彼の身体を固定した。少し爪先立ちをしてやっと首回りに余裕ができる高さだ。
崩れたら首を吊ってしまうその姿勢になって、ようやく彼は震えながらも足に力を入れ始めた。
嶺岸さんは再び失禁したようだった。乾き始めたズボンの前部が再び湿ってくる。
「ゆ、許してください。本当に――」
と泣きながら訴える彼の言葉をかき消し、私は再度、彼に問う。
「あなたは京握区内で、無差別に罪のない多くの人たちを殺傷した爆弾魔――」
「違う!」
彼の声もまた、私の言葉を途中で遮った。きっとこの人は小さい頃から、こうやってなかなか素直になれなかったんだと思う。私は一つ大きなため息を吐き、それから彼の湿ったズボンのベルトを外す。
「や、やめ……何を?」
と言いながら彼は身を捩って無駄な抵抗をする。私はその問いかけには答えず、力ずくで彼のズボンを下げた。彼は恥ずかしいのか、その両足を精一杯内股にしていた。彼のモノの先にはまだ少し黄色い液体が残っていた。
「こ……こんなこと……」
彼は脱力したようにふらつく。そして首のチェーンを意識してまた頑張って立ち上がる。そんなことを何回か繰り返していた。私はその様子をじっと見つめていた。彼の必死な行動になぜか色気を感じる。
……彼は本当は純粋ないい人。ただ、なかなか素直になれないだけ……
私は自分に言い聞かせた。彼がきちんと自分の口で自白できるまで、私も精一杯やらなくちゃ!
「もう一度聞きますね。あなたは――」
「何度聞いても答えは同じなんです。やってない。やって……あぐぅ!」
私は彼の睾丸をしっかりと握り締め、その手をぐいと下に引いた。睾丸の痛みで彼が身体を下げると、首回りのチェーンがギシギシと音を響かせて彼の首を絞める。
「ちゃんと言えるまでやり直しです。あなたが犯人ですね?」
「ぅ……だから、それはちが……うぐうっ……」
「はい。もう一度。あなたが犯人ですよね?」
「はぁ……。はぁ……お願いですから……ぐあっ!」
何度か繰り返したけど、彼はやはりなかなか素直になれない。それがすごく切なかった。態度も従順になってきたし、言葉遣いも最初に比べて随分と丁寧になった。でも、認めることだけができない。
彼は息遣いを荒くし、涙を流して訴える。気付くと彼の睾丸は赤く充血し、首回りも傷だらけになっていた。そこまでして隠さなければいけないのなら、最初から犯罪なんて考えちゃダメなのに……
「嶺岸さん。」
私は努めて優しい口調で彼に問いかける。でも彼はガタガタと身を震わせるだけで、返事をすることができない。私は睾丸を握る力を少し強めた。そして再度呼びかけると、彼は震える声を振り絞って「はいぃぃ……」と力なく返事をした。
「私が最近、素敵だなって思った言葉があるんです。」
と、私が言葉を続けると、彼はまた「はひぃ」と弱々しい声で答える。私は続ける。
「"隠していいのは、自分の行った善事だけ" 意味は、分かりますよね。」
私は彼の顎を持ち上げ、瞳を覗き込んだ。彼は怯えた犬のような目で私を見ながら、しきりに首を縦に振る。でも、私がそれから再び自白を促した時には、彼はやはりその首を横に振った。
脱力した。悔しさが込み上げてくる。
私は睾丸を握る力を一層強め、彼の身体を思いきり下へと引っ張った。彼がもがく。悲鳴を上げる。でも今は絶対に彼を許してはいけないと思った。
彼はやがて口から泡を吹き、失神した。
私が嶺岸さんの身体を殴ると、彼は絶叫とともに目を覚ました。
寝ている間に上着を捲っておいたので、彼の上半身は半裸だった。本当は剥ぎ取ってしまおうと思ったけど、チェーンで首を通すことができなかった。そのため、上着は彼の首元にマフラーのように巻きついていた。
「おはようございます。」
元気な声で挨拶をしたけど、彼は私の顔を見るなり驚愕の声を上げて震えた。そしてうわ言のように、
「やってない……やってない……やってない……やってない……」
と、絶え間なく口にする。
"良薬口に苦し"、"冷酒と親父の言葉は後で効く"
知っているいろいろな言葉を思い出しながら自分を励ましてみる。でもやっぱり、心を開いてくれないことは正直辛い。けれど……
……彼を絶対に見捨てたりしない。
その決意だけが、今の自分の気持ちを奮い立たせてくれていた。
彼は殴られたお腹の肉に大きな引っ掻き傷ができているのに気付くと、再度怯えた声を上げた。傷口からは血が滲んできていた。
彼は貧血を起こしたのか、足元がふらつく。当然、首にかかったチェーンは、彼が倒れることを許さなかった。
私はふらふらと立っている彼のお腹を再度、思いきり殴った。捻りを加えて内蔵に衝撃を与えるようにする。彼は「ぐぶっ……」という呻き声を漏らす。身体を少しくの字に曲げ、再びチェーンに引き留められる。彼の身体に二つ目の傷ができた。そこからも血がじわじわと滲み出していた。
私は拳を握り締め、中指に付けたダイヤの指輪をじっと見つめた。指輪にはハートの形を模した小さなダイヤが散りばめられていて、それぞれ先の方が鋭利になっている。あらためて近くで見るととても綺麗だ。私はしばらくその輝きに見惚れる。
「このダイヤ……結構、威力あるんですよ……」
言いながら、再度彼のお腹を殴る。彼は呻き、呼吸を荒げる。でも、私の言葉は彼の頭には届いていない様子だった。
……こんなに辛い思いをしてまで、どうして意地を張るんだろう?
私は何度も何度も彼のお腹を殴った。やがて胃液と思われる液体が、糸を引くように地面に零れてきた。ふと顔を上げると、まるで精気を失ったかのようにやつれた彼の表情が見えた。
ドクンと私の中で何かが反応する。いつもの悪い癖だろうか……
それから私は無我夢中で、彼のお腹のあらゆる箇所を殴った。おそらくその度に、彼は地獄に瀕した亡者のような声を上げていたんだと思う。でも、私の耳にはそれは聞こえてこなかった。ただ夢中で、彼の腹部を殴り続けた。
やがて私の腕に赤い液体が勢いよく流れてきた。そこで私ははっと我に返ったような気がした。再び目を上げると、彼は咳き込み、口から大量の血液を噴き出していた。ふと彼の腹部を見ると、私が抉った傷痕は彼のお腹に大きなハート模様を象っていた。
……無意識に、彼のお腹に絵を描いてしまってたみたい。
「見てください。可愛い絵ができましたよ。」
私の声を聞いた彼は、虚ろな目のままビクリと身体を震わせた。私はその大きなハート模様の内側に、もう一つの小さなハート模様もサービスで付け加えておいた。
私は再度、嶺岸さんの左手を掴む。彼は条件反射のように身体を震わせ、
「ご、ごめんな……さいぃ……。許して……くださいぃ……」
と、今にも消え入りそうな声で訴えた。その姿は本当に弱々しかった。彼を愛しいと思う心が、私の中で膨れ上がってくる。
……私がこの人を素直にさせてあげないと……
そういった気持ちがどんどん込み上げてくる。きちんと躾ければ、きっと素直になれる。そう信じて、私は彼に自分のできる限りのことはしてあげたいと思った。
「早く自白しましょうね。」
言いながら私は、既に小指と薬指の折れた彼の左手を持ち上げ、中指を折った。「ぎゃああああ!」という絶叫が取調室を覆う。そして再び罪を問うが、彼の答えはやはりNoだった。今度は彼の人差し指に手をかける。
「やめ……やめて……。お願いします――」
「――自白したらすぐに終わりますよ。」
努めて優しく声をかけ、私は人差し指を折る。
「ぎぃや……っあああっ……」
彼の絶叫を聞きながら残った親指に両手をかける。
「自白してください。」
私は彼の左手の親指の関節に力を込める。彼は顔面蒼白になり、その口からはもはや言葉すら出てこなかった。ただじっと目を瞑り、その時が来るのを待っているような感じがした。
バキッと乾いた音が室内に響く。
「ぐううああああっ!……あぐぅ……ぐぅぅ……」
左手の全指の骨を折っても、彼の答えは変わらなかった。
彼はぐったりと身体の力を抜いて気を失った。当然足に力が入らないから、チェーンが彼の首を持ち上げる形になる。チェーンがミシミシと音を立て、彼の口からは泡が吹き零れてきていた。
私は脱力したまま、彼の首からチェーンを外した。
彼に気持ちが伝わらないことが悔しくて仕方がなかった。やりきれなさが込み上げてくる。
チェーンから解放された彼は、潰れるように床に倒れ込んだ。彼の口から流れ出す血液が床にじわじわと広がっていった。
ふと気付くと、私の白いプリーツスカートにも彼の血が付着していた。購入したてだったから、すごく残念だった。でも、これも仕事だから仕方がない……。そう自分に言い聞かせるけど、やっぱりそのショックはとても大きかった。
私はぐったりと倒れ込んだ彼を背負い、取調室の隅に置かれた拷問器具に固定した。彼が気を失っている間に着々と準備を進める。
凛先輩なら、肉体一つできっと自白させられるのに。私はまだまだ力不足みたい。
……自分の力の無さが恥ずかしい。私の思いを彼に伝えられないことがもどかしい。
私がライターで彼の睾丸をしばらく炙ると、彼は悲鳴を上げて飛び起きた。手足が拘束されていることに驚いたのか、彼は不安そうに、キョロキョロと目だけで周りを見回していた。
ちょうど背凭れに寄りかかって座っているような姿勢だ。全裸の彼がもがく。しかし拘束具は彼の身体をがっちりと固定しているため、身動きを取ることはできない。
彼が再び悲鳴を上げたのは、自分の睾丸をしっかりと挟み込んでいる万力を見た時だった。
嶺岸さんの表情からは血の気が完全に引いていた。
震える口から声を絞る。
「こ、これ……」
信じられないような顔つきで私を見る。その瞳は潤み、奥歯は絶えずガタガタと音を立てていた。
私は満面の笑みを彼へと向けるが、彼は一層大きく震えるばかりだった。落ち着いてもらおうと必死で微笑んだけど、彼は笑わない。もしかしたら私の顔が引き攣っているのかもしれない。だって……
私は再度、諸所が赤く染まったプリーツスカートに目を遣った。悔しい気持ちがじわじわと込み上げてくるのが分かった。ついポツリと声を漏らしてしまう。
「これ……昨日買ったばかりなんです。」
「え?」
彼が素っ頓狂な声を上げる。予想だにしなかった言葉だったからかもしれない。でも、私はその後も言葉を続けずにはいられなかった。
「お気に入りなんです。」
私が目線を下へと落とす。彼もまた私と同じように視線を下げる。そして彼はさらに大きく震えた。
自分の血でまだら模様になった私のスカートに気付いてくれたのだろう。彼の反応を見て、私は内心ホッとした。彼はちゃんと罪悪感を抱ける人なんだ。そう思うと、すごく嬉しくなった。
……彼が本当はいい人だという考えは、間違っていなかった。ただ、素直になれないだけ……
私はそっと彼の瞳を覗き込み、努めて優しく声をかける。
「他人の大事にしてる物を台無しにした時は、どうすればいいと思いますか?」
「あ……うぅ……」
「責任……取るべきですよね……」
「ひぃ……ひいぃ……」
「嶺岸さんの大事にしてるもの――」
そこまで言った後、私は万力に手をかけた。ギリギリと彼の右側の睾丸を圧迫する。
「ぎゃああああっ!」
と彼は絶叫し、「ごめ……いぃ……。ごめんな……さいぃ!」と涙を流しながら訴えた。
彼が苦痛の声を大きくする度、私は嬉しくて仕方がなかった。
……彼はちゃんと痛みが理解できる人。ちゃんと反省もできる人。私がしっかりと……
「素直ないい人にして差し上げます……」
「や、やめ……」
――グチャッという鈍い音とともに鮮血が舞った。亀頭から噴き出す血液が再び私を覆う。彼はピクピクと全身を痙攣させながら断末魔の声を上げた。
「ぎゃああああっ! があああああっ!」
彼は今にも拷問器具から身体を振り解きそうな勢いで暴れた。彼を拘束している枷がギシギシと音を立て、彼の肌を傷つけていった。やがて傷痕は深くなり、そこからも血がポタリポタリと滴り始めた。
しばらく暴れた後、彼は身体を震わせたままぐったりと項垂れた。その瞳は涙で覆い尽くされ、口は半開きのまま涎を垂れ流し続けていた。
私は彼の頭をそっと撫でた後、彼のもう片方の睾丸に手をかけた。
嶺岸さんは表情を失い、その額には脂汗がびっしりと浮かんでいた。そんな状態の中、彼は声を振り絞る。
「……ごめ……さい……。めん……なさぃ……」
彼の視線は自分の股間へと注がれていた。私は彼に問う。
「ちゃんと、反省できましたね。」
「は……いっ……。ですからもう……もう……」
「でも、もう一つ残って――」
「おね……します……。お……ます……」
呼吸困難を引き起こしているのか、彼の息が激しい音を立てている。その目はまるで、母親の愛の手を求める赤ちゃんのようだった。その姿がとても愛らしく、私のサービス精神をくすぐる。
「もう一つも、潰しておきましょうね。」
私が彼のもう片方の睾丸を万力に挟み込む。彼はとうとう言葉が出せなくなってしまったのか、喉からヒューヒューという擦れた音だけを漏らしていた。彼の身体が激しく震えている。涙を流し、必死で何かを訴えかけている。
彼は準備を進める私の顔や身体、手などあらゆる箇所を見ては、尋常でない震えを見せた。
「よっぽど、怖いんですね。」
私のその言葉を聞き、彼は何度も首を大きく縦に振った。犯罪が怖いものだということを、彼は自覚しているのだろう。私は震える彼の瞳をじっと見つめた。
「じゃあ……せめて……」
その後は言葉にできなかった。
私は右手の二本の指を勢いよく突き出した。彼の両目に向けて。
彼がとっさに身体を捩る。狙いが少しずれ、人差し指の方は目を捉えることができなかった。中指は彼の右目の結膜内に突き刺さっていく。ヌルリとした円蓋部結膜に指の先を挿入し、私は彼の眼球を強く抉った。ドロドロと血液が流れてくる。
「ぐあ……あああ……! いぎゃ……あぁ!」
と、彼が喉の奥から声を振り絞る。右目から血を滴らせながら、彼が激しく悶える。私は、片方の目しか潰すことができなかったことを悔やんだ。彼にもう一度痛い思いをさせなければいけないのだと思うと、とてもかわいそうだった。
……でも、彼がこれ以上怖いものを見なくてすむのなら。
私は再度、人差し指を彼の左目へと向ける。
「ごめんなさい。もう一度刺します。動かないでくださいね。」
私がそう言った時、彼の口からその言葉が聞こえてきた。
「……や……した。……犯……人……ぼく……」
彼の言葉を聞き、私の目からは自然と涙が溢れた。やっぱり一生懸命やれば心を開いてくれるんだ。心が通じるって、こんなにも嬉しいことなんだ。私はそれを、この時初めて知った。私は思わず拘束台の上の彼に手を差し伸べ、強く抱きしめていた。
「嶺岸さん。素敵です。本当によく言えましたね。」
そう言いながら私は、彼の頭を優しく撫で続けた。彼はまだ自分が素直になったことに慣れていないためか、きちんと自白できた後も身体を強張らせ、小刻みに震わせていた。
そして私は最後のけじめとして、彼の左側の睾丸もしっかりと潰した。
……これで彼は、自分のしたことを素直に認めること、そして、他人の大事な物は大切に扱わなければいけないこと、どっちも理解してくれたはず。
私は、絶叫の末に再び気絶した彼を前に、とても清々しい気持ちでいっぱいになっていた。
再び取調室に先輩刑事さん二人が入って来たのは、私が物言わぬ嶺岸さんを強く抱きしめている時だった。
ほっとしたからかもしれない。嶺岸さんに気持ちが伝わったことに感極まったからかもしれない。原因は分からなかった。私は、後から後から溢れ出てくる涙をどうしても止めることができなかった。
「自白終了、ですよね。」
一人の刑事さんに言われ、私は虚をつかれたような思いがした。この仕事は自白報告があって初めて終了になることを、あらためて思い出す。処刑人だった頃にこんな失敗をすることなんてなかった。自分の単純なミスを自覚し、少し自己嫌悪に陥る。
「ご苦労様。」
もう一人の刑事さんに優しく声をかけてもらい、私は感傷に浸っていた自分を戒める。涙を拭い、刑事さん二人に向き直る。嶺岸さんに背を向けながら私は、
「自白終了です!」
と、元気を振り絞って声を出した。
***
署内は朝から慌しかった。
昨日と同じように取調執行人としての準備を整える。着替えを終え、チェーンネックレスに手を伸ばす。その時、更衣室の前から凛先輩の声が聞こえてきた。
挨拶をしようとドアの方へ向かったが、男性の声が聞こえてきて立ち止まった。声の主は、署長のものらしかった。どうやら凛先輩と会話をしているようだ。
「署長もミラー越しにご覧になっていましたよね。彼女のやり方は――」
凛先輩の声色はいつになく厳しかった。普段の甘くて優しい響きはそこにはない。
何となく出辛くて、更衣室のドアの前で足を止めてしまった。
盗み聞きをするつもりはなくとも、自然と耳にその会話が入ってくる。
「初めてとは思えないほど素晴らしい活躍だったね。」
対する署長の声は、とても明るいものだった。
それでも凛先輩は、厳しい口調を崩さない。
「素晴らしいと……署長は思われたのですね。」
「容疑者はちゃんと自白したよ。あの短時間で随分とおとなしくもなった。」
そう言って署長が高らかに笑う。
「……でも、特に……自白後のあの行為は、明らかに彼女個人の――」
そう言いかけた先輩を遮り、署長は高圧的に言い放った。
「後藤くんはよく頑張った。犯人は自白した。必要なのは、それだけだ。」
「…………」
「これからも後藤くんの教育、よろしく頼むよ。」
二人が歩き去る音が聞こえ、会話は途絶えた。
私は項垂れたまま、自分のロッカーの前へと戻った。準備したネックレスをそっとロッカー内へ戻す。
――今のままじゃ駄目なんだ……
凛先輩に認められたい。その思いだけがどんどん強くなっていった。
本日の容疑者資料に目を通す。彼は世間を騒がせた通り魔殺人の容疑者だ。
私はアイスピックを手に取り、上着のポケットに入れた。
由香利は己が信念を突き進む。拷問は正義の名の下に。ノートは全てを記録する。
冷えた空気が火照った身体に心地よかった。
思った以上に疲れていたらしい。ゆっくりとお湯に浸かったことで、手足が幾分軽くなっているのが分かった。
浴室の照明を切って部屋に入り、すぐさまドレッサーへと向かう。ちょっと前までは、こんなバスローブ一枚の姿では寒くてたまらなかった。あらためて、季節の移り変わりの早さを実感する。
髪を頭の上で軽くまとめ、化粧水を手に取る。それをコットンに多めに含ませ、頬を丹念に撫でていく。化粧台の前には、たくさんの美容液や化粧品が並んでいる。それらを使ってお肌のケアに勤しむ。
一通り終わって顔のお肌チェックをしている頃、小さなケータイが私を呼んだ。掌の半分ほどの大きさのそれを手に取る。着信表示には大切な先輩の名前が浮かんでいた。
「はい!」
喜びと期待でつい大きな声を出してしまう。
「もしもし、由香利――」
甘くて優しい声が身を包む。
さっきまで感じていた疲れがまるで嘘だったかのように、身体中に元気が漲ってくる。
「凛先輩、こんばんは! おつかれさまです!」
「うん。今日は本当におつかれさま。正直、疲れたでしょ?」
「はい。でも、先輩から電話をもらったら急に元気になっちゃいました。」
通話口の向こう側から、苦笑にも似た笑い声が聞こえる。
「……どうだった?」
「そうですね。初めての仕事だったので、いろいろと新しい発見がありました。」
「どんな?」
凛先輩のその言葉を聞き、あらためて今日の出来事をふり返ってみる。その時になって初めて、今日の日記をまだつけていなかったことに気が付いた。そのことを考え込み、しばし沈黙してしまう。
再度、先輩の言葉が通話口から聞こえてきた。
「あ、いきなりそんなこと聞かれても困っちゃうね。ごめん。」
黙り込んでしまったことで心配をかけてしまったのかもしれない。慌てて口を開く。
「ごめんなさい。いろいろとあったんですけど。」
「一口では言えないよね。本当、無理しなくていいから。またゆっくり聞かせてね。」
「ありがとうございます。これからも頑張ります!」
「――ん……あの、さ……。……あまり気張らなくていいからね。」
「ご心配、ありがとうございます! 嬉しいです!」
「もし辛かったら――」
「全然! 今日もすごく楽しかったので!」
「……そう。……それならいい。これから一緒に仕事をする機会もあると思うから、よろしくね。」
「はい。こちらこそです。どうぞよろしくお願いします!」
そこで通話は途切れた。
凛先輩から直接電話してもらえたことで、心までリラックスできていることに気付く。あらためて先輩に対する感謝の気持ちが膨れ上がってくる。心地よい気分で机に向かい、私は一冊のノートを手に取った。新しく買った分厚いノートの表紙には『由香利ノート』と記してある。表ページの見開きに書いた『正当拷問自白法 執行記録』という大きな文字を見ていると、今日の仕事の光景がまざまざと脳裏に浮かんでくる。私は夢中になってノートにペンを走らせた。
ノートを書き終えた時、私の胸はなぜか大きな高鳴りを見せていた。
ふと時計を見上げる。針は深夜一時を指していた。
――こんなにドキドキして、眠れるのかな?……でも明日も仕事! 寝不足は美容の敵!
そんなことを考えながら、私はベッドに潜り込んだ。
人事異動が終わって、新しい部署に回された。私は今年度、晴れて『正当拷問自白法違反者処刑人』から『正当拷問自白法取調執行人』へと昇格になった。
刑事としてのランクアップはもちろん嬉しいけど、それについては正直まだ実感がない。それよりも私が何より嬉しかったのは、憧れの凛先輩と同じ部署で働くことができるようになったということ。
さっきも私を気遣って電話までしてくれた。本当に素敵な先輩だと思う。先輩も言ってたけど、これから一緒に仕事をすることもあるんだろうなぁ。そう考えると、すごく楽しみ!
今日は初日だから本当に緊張したし、正直疲れたけど、でもやっぱりやり甲斐のある素晴らしい仕事だと思った。
私の手で一人でも多くの悪人を自白させてみせる。そしていつか、全ての悪人をこの世から消してみせる。何より私は今、刑事として働けることがすごく嬉しい。悪人を懲らしめることがすごく楽しい。
この気持ちを持ち続けている限り、私はこれからも仕事を続けていけると思う。
容疑者 嶺岸秀一 二十四歳
取調室の前に立った途端、すごく荒っぽい声が聞こえてきた。
「違う……。違う! 俺はやってねえ! やってねえんだよ!」
私は気を引き締め、身に着けたミニスカートの裾を整える。この白のプリーツスカートは、買ったばかりのお気に入り。動きやすさを考えて、上半身には淡い黄緑の半袖Tシャツを選んだ。高めのヒールのついた薄いブラウンのブーツは膝丈サイズ。このコーディネートは、春を意識したものだ。アクセサリにも気を遣って、今日はネックレスとダイヤの指輪を身に着けてみた。
案内係の警官の「よろしくお願いします」という言葉に「はい!」と短く元気に返事をした後、私はドキドキしながら取調室の扉を開いた。
室内を覆う煙の臭いがきつかった。机上の灰皿の上には火のついたままのタバコが適当に置かれていて、煙がモクモクと出ていた。正直ケムかった……
紫煙の向こう側に、うっすらと男性二人の姿が見える。どちらも取り調べに当たっていた先輩刑事さんだ。でも、まだ部署に配属されたばかりで顔を見ても名前が浮かんでこない。後で勉強しておかないと……。次いで、その二人の刑事さんが、必死で取り押さえようとしている人物の姿が目に入った。
白んだ狭い部屋の中で目を凝らしてその顔を確認する。彼の第一印象は、私の想像とは全く違っていた。茶髪でもなければロン毛でもない。顔立ちには幼さが残り、純真な雰囲気を感じさせる。細身の身体に普段着をまとった彼は、真面目を絵に描いたような青年だった。
正直、私にはとても罪を犯すような人間には見えなかった。
刑事さん二人は私が入室したことを確認すると、
「後藤くん! こいつを取り押さえてくれ!」
と、私に声をかけてくる。その声はとても切迫したものだった。
私は表情を引きしめ、彼らのいる方へと急いだ。
机に置かれた火のついたタバコを手に取る。
私は刑事さん二人をかき分け、暴れる嶺岸さんの首筋にタバコの先をぐいと押し当ててみた。
「ぐああああっ!」
叫び声とともに、彼がエビみたいに大きく身体をのけぞらせる。その反動で彼は刑事さん二人の手を離れる。私はすかさず持っていたタバコを捨て、同時に彼のお腹に力いっぱい拳を叩き込んだ。
彼は呻き声を上げ、そのまま床に倒れ込んで悶絶した。
……バタバタしてる姿がちょっと可愛い。
刑事さん二人は「ふうっ」と大きく息を吐きながら呼吸を整え、襟元を正し始めていた。
私は転げ回る彼の喉元をブーツの底で踏み付けて押さえ込みながら、
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
と、自己紹介をする。
取調執行人としての仕事がこれから始まるのだと思うと、胸のドキドキが収まらない。私は自分の緊張を解すように、大きめの声で彼に告げたつもりだった。けれど彼はその言葉がまるで聞こえていないかのように、目を大きく見開いたまま、顔を真っ赤にして痙攣し始めていた。
……せっかくの自己紹介なのに、タイミング悪いな。
一呼吸ついた刑事さん二人は、まるで何事もなかったかのように彼に背を向け、
「では、ひとつよろしく頼むよ。」
「お願いしますね。」
と、私に声をかけた。私が「はい」とだけ答えると、彼らは無言のまま取調室を出て行った。
ドアの閉まる音を背中で聞きながら、私は嶺岸さんの喉仏にさらに体重を乗せる。彼はやがて口から泡を吹き、ぐったりと全身の力を抜いた。失禁し、ズボンの下半身がじわじわと濡れていく。
……ちょっとやりすぎちゃったかな。これから尋問しなきゃいけないし。
私は足を彼の喉元から放す。周囲を見回すと、ちょうど刑事さんが残していったライターが目に入った。手に取り、彼の耳を炙る。肉がじりじりと焦げる音を立て始めた頃、彼は悲鳴を上げて飛び起きた。何が起こったのか分からないといった様子で耳を押さえている彼の姿が滑稽で面白い。
私は再度、自己紹介をした。今度はちゃんと聞いてくれたと思う。
「じゃあ、早速質問させていただきますね。」
呆然としている彼に向かって、私はさらに言葉を続ける。
「あなたは京握区内で、無差別に罪のない多くの人たちを殺傷した爆弾魔ですね。」
その言葉を聞いても彼は無言のままだった。相変わらず耳を押さえたまま、身体を震わせ始める。
私がさらに「答えてください」と言った時、彼が突然私に飛びかかってきた。
「ふざけんな! 俺はやってねえ!」
と怒声を吐きながら、私に掴みかかる。
とてもそんなことをするような人には見えなかったので、すごくびっくりした。何より、私はこの時あらためて、処刑人と取調執行人の違いを実感していた。私が今まで拷問してきた人たちは皆『違反者』という肩書きをもった人たちだった。そんな彼らには法の下、適切なメニューが与えられていた。態度も基本的には従順だった。私はそういう人たちに、メニューの一つ一つを与えていただけ。でも、今は違う。目の前の彼もそうだけど、ここに来る人たちは皆、まだ自白もしていない容疑者なのだ。こうやって襲いかかってくることも多々あるのだろう。
彼のお陰で、私はまた一つ勉強することができた。
嶺岸さんの必死な形相が可愛かった。
大きな声で何かを訴える様子は、駄々をこねる子どもみたいで愛しかった。思わずぎゅってしたい衝動に駆られる。……反省。でも、自分の罪を認めない態度はやっぱりよくない。自白をしない悪い子にはお仕置きが必要だよね。
私は彼の左手をぐいと捻り上げる。
小指の骨を第二関節から折ると、彼は絶叫した。その時点で私を掴む力は緩んだけど、念のため薬指の骨も同じように折ってあげた。再び彼は絶叫して私から身体を離す。彼は蹲ったままで呻き声を上げていた。
何とか落ち着いてくれたみたいでまずは一安心、かな。
彼は左手を押さえ、床に膝をついたままで涙を零していた。心なしか、さっきよりも元気がなくなっているような気がする。怯えた目で私をじっと見つめている。私が近付こうとすっと足を前へ出すと、彼は「ひっ」と声を上げて後ずさる。その行動がすごく可愛くて、私はつい何度かその仕草を繰り返す。その度に、彼もまた同じ仕草を繰り返す。
……この人ならきっと、ちゃんと自白して反省できるはず。
でも彼は、それを認めることができなかった。私の問いに対しては「やってないんです。信じてください」の一点張りだった。
……まだちゃんとしたいい人にはなれてないみたい。少しがっかりしたけど、私がちゃんと自白できるようにお手伝いしなくちゃ……
私はそう心に決め、彼につかつかと近付いていった。
側に寄ると、彼は身を縮めて肩を震わせた。弱々しい声を上げながら嗚咽を漏らす様子を見ていると、また身体が火照ってくる。怯える様子に興奮してしまうこの癖は、未だに治っていない。私は思わず笑みを零していた。
「ちゃんと素直な人になれるまで、しっかり痛めつけさせてもらいますね。」
そう言って私は再び彼の左手を持ち上げ、中指にも手をかける。彼は絶叫した。声が震えている。
「や、やめろ!」
と言いながら私の手を振り払い、まるで芋虫のように這いながら壁際へと向かう。彼の足はガクガクと震えていた。恐怖のあまり足に力が入らなくなっているようだった。そんなに自分の犯した罪に怯えるなら、最初からやらなければいいのに。
……もう、困った人。
私は彼を見下ろしながら、その後をゆっくりと歩いて追った。
彼が必死で声を絞る。
「く、来るな!」
「ダメです。ちゃんと自白するまでは。」
「俺はやってないんだ。」
「あっ。まだそういう態度なんですか? そういうのよくないです。」
「信じてくれ……ください! こんなことしても、俺……僕は本当に――」
その時、彼に追いついた私は、彼の髪を掴んで強制的に立たせた。力が入らないのか、手を放すとすぐに膝から崩れ落ちてしまう。なかなか自分で立ってくれない。
私はチェーンネックレスを外して彼の首にかけ、同時にそれを窓にある格子に潜らせて彼の身体を固定した。少し爪先立ちをしてやっと首回りに余裕ができる高さだ。
崩れたら首を吊ってしまうその姿勢になって、ようやく彼は震えながらも足に力を入れ始めた。
嶺岸さんは再び失禁したようだった。乾き始めたズボンの前部が再び湿ってくる。
「ゆ、許してください。本当に――」
と泣きながら訴える彼の言葉をかき消し、私は再度、彼に問う。
「あなたは京握区内で、無差別に罪のない多くの人たちを殺傷した爆弾魔――」
「違う!」
彼の声もまた、私の言葉を途中で遮った。きっとこの人は小さい頃から、こうやってなかなか素直になれなかったんだと思う。私は一つ大きなため息を吐き、それから彼の湿ったズボンのベルトを外す。
「や、やめ……何を?」
と言いながら彼は身を捩って無駄な抵抗をする。私はその問いかけには答えず、力ずくで彼のズボンを下げた。彼は恥ずかしいのか、その両足を精一杯内股にしていた。彼のモノの先にはまだ少し黄色い液体が残っていた。
「こ……こんなこと……」
彼は脱力したようにふらつく。そして首のチェーンを意識してまた頑張って立ち上がる。そんなことを何回か繰り返していた。私はその様子をじっと見つめていた。彼の必死な行動になぜか色気を感じる。
……彼は本当は純粋ないい人。ただ、なかなか素直になれないだけ……
私は自分に言い聞かせた。彼がきちんと自分の口で自白できるまで、私も精一杯やらなくちゃ!
「もう一度聞きますね。あなたは――」
「何度聞いても答えは同じなんです。やってない。やって……あぐぅ!」
私は彼の睾丸をしっかりと握り締め、その手をぐいと下に引いた。睾丸の痛みで彼が身体を下げると、首回りのチェーンがギシギシと音を響かせて彼の首を絞める。
「ちゃんと言えるまでやり直しです。あなたが犯人ですね?」
「ぅ……だから、それはちが……うぐうっ……」
「はい。もう一度。あなたが犯人ですよね?」
「はぁ……。はぁ……お願いですから……ぐあっ!」
何度か繰り返したけど、彼はやはりなかなか素直になれない。それがすごく切なかった。態度も従順になってきたし、言葉遣いも最初に比べて随分と丁寧になった。でも、認めることだけができない。
彼は息遣いを荒くし、涙を流して訴える。気付くと彼の睾丸は赤く充血し、首回りも傷だらけになっていた。そこまでして隠さなければいけないのなら、最初から犯罪なんて考えちゃダメなのに……
「嶺岸さん。」
私は努めて優しい口調で彼に問いかける。でも彼はガタガタと身を震わせるだけで、返事をすることができない。私は睾丸を握る力を少し強めた。そして再度呼びかけると、彼は震える声を振り絞って「はいぃぃ……」と力なく返事をした。
「私が最近、素敵だなって思った言葉があるんです。」
と、私が言葉を続けると、彼はまた「はひぃ」と弱々しい声で答える。私は続ける。
「"隠していいのは、自分の行った善事だけ" 意味は、分かりますよね。」
私は彼の顎を持ち上げ、瞳を覗き込んだ。彼は怯えた犬のような目で私を見ながら、しきりに首を縦に振る。でも、私がそれから再び自白を促した時には、彼はやはりその首を横に振った。
脱力した。悔しさが込み上げてくる。
私は睾丸を握る力を一層強め、彼の身体を思いきり下へと引っ張った。彼がもがく。悲鳴を上げる。でも今は絶対に彼を許してはいけないと思った。
彼はやがて口から泡を吹き、失神した。
私が嶺岸さんの身体を殴ると、彼は絶叫とともに目を覚ました。
寝ている間に上着を捲っておいたので、彼の上半身は半裸だった。本当は剥ぎ取ってしまおうと思ったけど、チェーンで首を通すことができなかった。そのため、上着は彼の首元にマフラーのように巻きついていた。
「おはようございます。」
元気な声で挨拶をしたけど、彼は私の顔を見るなり驚愕の声を上げて震えた。そしてうわ言のように、
「やってない……やってない……やってない……やってない……」
と、絶え間なく口にする。
"良薬口に苦し"、"冷酒と親父の言葉は後で効く"
知っているいろいろな言葉を思い出しながら自分を励ましてみる。でもやっぱり、心を開いてくれないことは正直辛い。けれど……
……彼を絶対に見捨てたりしない。
その決意だけが、今の自分の気持ちを奮い立たせてくれていた。
彼は殴られたお腹の肉に大きな引っ掻き傷ができているのに気付くと、再度怯えた声を上げた。傷口からは血が滲んできていた。
彼は貧血を起こしたのか、足元がふらつく。当然、首にかかったチェーンは、彼が倒れることを許さなかった。
私はふらふらと立っている彼のお腹を再度、思いきり殴った。捻りを加えて内蔵に衝撃を与えるようにする。彼は「ぐぶっ……」という呻き声を漏らす。身体を少しくの字に曲げ、再びチェーンに引き留められる。彼の身体に二つ目の傷ができた。そこからも血がじわじわと滲み出していた。
私は拳を握り締め、中指に付けたダイヤの指輪をじっと見つめた。指輪にはハートの形を模した小さなダイヤが散りばめられていて、それぞれ先の方が鋭利になっている。あらためて近くで見るととても綺麗だ。私はしばらくその輝きに見惚れる。
「このダイヤ……結構、威力あるんですよ……」
言いながら、再度彼のお腹を殴る。彼は呻き、呼吸を荒げる。でも、私の言葉は彼の頭には届いていない様子だった。
……こんなに辛い思いをしてまで、どうして意地を張るんだろう?
私は何度も何度も彼のお腹を殴った。やがて胃液と思われる液体が、糸を引くように地面に零れてきた。ふと顔を上げると、まるで精気を失ったかのようにやつれた彼の表情が見えた。
ドクンと私の中で何かが反応する。いつもの悪い癖だろうか……
それから私は無我夢中で、彼のお腹のあらゆる箇所を殴った。おそらくその度に、彼は地獄に瀕した亡者のような声を上げていたんだと思う。でも、私の耳にはそれは聞こえてこなかった。ただ夢中で、彼の腹部を殴り続けた。
やがて私の腕に赤い液体が勢いよく流れてきた。そこで私ははっと我に返ったような気がした。再び目を上げると、彼は咳き込み、口から大量の血液を噴き出していた。ふと彼の腹部を見ると、私が抉った傷痕は彼のお腹に大きなハート模様を象っていた。
……無意識に、彼のお腹に絵を描いてしまってたみたい。
「見てください。可愛い絵ができましたよ。」
私の声を聞いた彼は、虚ろな目のままビクリと身体を震わせた。私はその大きなハート模様の内側に、もう一つの小さなハート模様もサービスで付け加えておいた。
私は再度、嶺岸さんの左手を掴む。彼は条件反射のように身体を震わせ、
「ご、ごめんな……さいぃ……。許して……くださいぃ……」
と、今にも消え入りそうな声で訴えた。その姿は本当に弱々しかった。彼を愛しいと思う心が、私の中で膨れ上がってくる。
……私がこの人を素直にさせてあげないと……
そういった気持ちがどんどん込み上げてくる。きちんと躾ければ、きっと素直になれる。そう信じて、私は彼に自分のできる限りのことはしてあげたいと思った。
「早く自白しましょうね。」
言いながら私は、既に小指と薬指の折れた彼の左手を持ち上げ、中指を折った。「ぎゃああああ!」という絶叫が取調室を覆う。そして再び罪を問うが、彼の答えはやはりNoだった。今度は彼の人差し指に手をかける。
「やめ……やめて……。お願いします――」
「――自白したらすぐに終わりますよ。」
努めて優しく声をかけ、私は人差し指を折る。
「ぎぃや……っあああっ……」
彼の絶叫を聞きながら残った親指に両手をかける。
「自白してください。」
私は彼の左手の親指の関節に力を込める。彼は顔面蒼白になり、その口からはもはや言葉すら出てこなかった。ただじっと目を瞑り、その時が来るのを待っているような感じがした。
バキッと乾いた音が室内に響く。
「ぐううああああっ!……あぐぅ……ぐぅぅ……」
左手の全指の骨を折っても、彼の答えは変わらなかった。
彼はぐったりと身体の力を抜いて気を失った。当然足に力が入らないから、チェーンが彼の首を持ち上げる形になる。チェーンがミシミシと音を立て、彼の口からは泡が吹き零れてきていた。
私は脱力したまま、彼の首からチェーンを外した。
彼に気持ちが伝わらないことが悔しくて仕方がなかった。やりきれなさが込み上げてくる。
チェーンから解放された彼は、潰れるように床に倒れ込んだ。彼の口から流れ出す血液が床にじわじわと広がっていった。
ふと気付くと、私の白いプリーツスカートにも彼の血が付着していた。購入したてだったから、すごく残念だった。でも、これも仕事だから仕方がない……。そう自分に言い聞かせるけど、やっぱりそのショックはとても大きかった。
私はぐったりと倒れ込んだ彼を背負い、取調室の隅に置かれた拷問器具に固定した。彼が気を失っている間に着々と準備を進める。
凛先輩なら、肉体一つできっと自白させられるのに。私はまだまだ力不足みたい。
……自分の力の無さが恥ずかしい。私の思いを彼に伝えられないことがもどかしい。
私がライターで彼の睾丸をしばらく炙ると、彼は悲鳴を上げて飛び起きた。手足が拘束されていることに驚いたのか、彼は不安そうに、キョロキョロと目だけで周りを見回していた。
ちょうど背凭れに寄りかかって座っているような姿勢だ。全裸の彼がもがく。しかし拘束具は彼の身体をがっちりと固定しているため、身動きを取ることはできない。
彼が再び悲鳴を上げたのは、自分の睾丸をしっかりと挟み込んでいる万力を見た時だった。
嶺岸さんの表情からは血の気が完全に引いていた。
震える口から声を絞る。
「こ、これ……」
信じられないような顔つきで私を見る。その瞳は潤み、奥歯は絶えずガタガタと音を立てていた。
私は満面の笑みを彼へと向けるが、彼は一層大きく震えるばかりだった。落ち着いてもらおうと必死で微笑んだけど、彼は笑わない。もしかしたら私の顔が引き攣っているのかもしれない。だって……
私は再度、諸所が赤く染まったプリーツスカートに目を遣った。悔しい気持ちがじわじわと込み上げてくるのが分かった。ついポツリと声を漏らしてしまう。
「これ……昨日買ったばかりなんです。」
「え?」
彼が素っ頓狂な声を上げる。予想だにしなかった言葉だったからかもしれない。でも、私はその後も言葉を続けずにはいられなかった。
「お気に入りなんです。」
私が目線を下へと落とす。彼もまた私と同じように視線を下げる。そして彼はさらに大きく震えた。
自分の血でまだら模様になった私のスカートに気付いてくれたのだろう。彼の反応を見て、私は内心ホッとした。彼はちゃんと罪悪感を抱ける人なんだ。そう思うと、すごく嬉しくなった。
……彼が本当はいい人だという考えは、間違っていなかった。ただ、素直になれないだけ……
私はそっと彼の瞳を覗き込み、努めて優しく声をかける。
「他人の大事にしてる物を台無しにした時は、どうすればいいと思いますか?」
「あ……うぅ……」
「責任……取るべきですよね……」
「ひぃ……ひいぃ……」
「嶺岸さんの大事にしてるもの――」
そこまで言った後、私は万力に手をかけた。ギリギリと彼の右側の睾丸を圧迫する。
「ぎゃああああっ!」
と彼は絶叫し、「ごめ……いぃ……。ごめんな……さいぃ!」と涙を流しながら訴えた。
彼が苦痛の声を大きくする度、私は嬉しくて仕方がなかった。
……彼はちゃんと痛みが理解できる人。ちゃんと反省もできる人。私がしっかりと……
「素直ないい人にして差し上げます……」
「や、やめ……」
――グチャッという鈍い音とともに鮮血が舞った。亀頭から噴き出す血液が再び私を覆う。彼はピクピクと全身を痙攣させながら断末魔の声を上げた。
「ぎゃああああっ! があああああっ!」
彼は今にも拷問器具から身体を振り解きそうな勢いで暴れた。彼を拘束している枷がギシギシと音を立て、彼の肌を傷つけていった。やがて傷痕は深くなり、そこからも血がポタリポタリと滴り始めた。
しばらく暴れた後、彼は身体を震わせたままぐったりと項垂れた。その瞳は涙で覆い尽くされ、口は半開きのまま涎を垂れ流し続けていた。
私は彼の頭をそっと撫でた後、彼のもう片方の睾丸に手をかけた。
嶺岸さんは表情を失い、その額には脂汗がびっしりと浮かんでいた。そんな状態の中、彼は声を振り絞る。
「……ごめ……さい……。めん……なさぃ……」
彼の視線は自分の股間へと注がれていた。私は彼に問う。
「ちゃんと、反省できましたね。」
「は……いっ……。ですからもう……もう……」
「でも、もう一つ残って――」
「おね……します……。お……ます……」
呼吸困難を引き起こしているのか、彼の息が激しい音を立てている。その目はまるで、母親の愛の手を求める赤ちゃんのようだった。その姿がとても愛らしく、私のサービス精神をくすぐる。
「もう一つも、潰しておきましょうね。」
私が彼のもう片方の睾丸を万力に挟み込む。彼はとうとう言葉が出せなくなってしまったのか、喉からヒューヒューという擦れた音だけを漏らしていた。彼の身体が激しく震えている。涙を流し、必死で何かを訴えかけている。
彼は準備を進める私の顔や身体、手などあらゆる箇所を見ては、尋常でない震えを見せた。
「よっぽど、怖いんですね。」
私のその言葉を聞き、彼は何度も首を大きく縦に振った。犯罪が怖いものだということを、彼は自覚しているのだろう。私は震える彼の瞳をじっと見つめた。
「じゃあ……せめて……」
その後は言葉にできなかった。
私は右手の二本の指を勢いよく突き出した。彼の両目に向けて。
彼がとっさに身体を捩る。狙いが少しずれ、人差し指の方は目を捉えることができなかった。中指は彼の右目の結膜内に突き刺さっていく。ヌルリとした円蓋部結膜に指の先を挿入し、私は彼の眼球を強く抉った。ドロドロと血液が流れてくる。
「ぐあ……あああ……! いぎゃ……あぁ!」
と、彼が喉の奥から声を振り絞る。右目から血を滴らせながら、彼が激しく悶える。私は、片方の目しか潰すことができなかったことを悔やんだ。彼にもう一度痛い思いをさせなければいけないのだと思うと、とてもかわいそうだった。
……でも、彼がこれ以上怖いものを見なくてすむのなら。
私は再度、人差し指を彼の左目へと向ける。
「ごめんなさい。もう一度刺します。動かないでくださいね。」
私がそう言った時、彼の口からその言葉が聞こえてきた。
「……や……した。……犯……人……ぼく……」
彼の言葉を聞き、私の目からは自然と涙が溢れた。やっぱり一生懸命やれば心を開いてくれるんだ。心が通じるって、こんなにも嬉しいことなんだ。私はそれを、この時初めて知った。私は思わず拘束台の上の彼に手を差し伸べ、強く抱きしめていた。
「嶺岸さん。素敵です。本当によく言えましたね。」
そう言いながら私は、彼の頭を優しく撫で続けた。彼はまだ自分が素直になったことに慣れていないためか、きちんと自白できた後も身体を強張らせ、小刻みに震わせていた。
そして私は最後のけじめとして、彼の左側の睾丸もしっかりと潰した。
……これで彼は、自分のしたことを素直に認めること、そして、他人の大事な物は大切に扱わなければいけないこと、どっちも理解してくれたはず。
私は、絶叫の末に再び気絶した彼を前に、とても清々しい気持ちでいっぱいになっていた。
再び取調室に先輩刑事さん二人が入って来たのは、私が物言わぬ嶺岸さんを強く抱きしめている時だった。
ほっとしたからかもしれない。嶺岸さんに気持ちが伝わったことに感極まったからかもしれない。原因は分からなかった。私は、後から後から溢れ出てくる涙をどうしても止めることができなかった。
「自白終了、ですよね。」
一人の刑事さんに言われ、私は虚をつかれたような思いがした。この仕事は自白報告があって初めて終了になることを、あらためて思い出す。処刑人だった頃にこんな失敗をすることなんてなかった。自分の単純なミスを自覚し、少し自己嫌悪に陥る。
「ご苦労様。」
もう一人の刑事さんに優しく声をかけてもらい、私は感傷に浸っていた自分を戒める。涙を拭い、刑事さん二人に向き直る。嶺岸さんに背を向けながら私は、
「自白終了です!」
と、元気を振り絞って声を出した。
***
署内は朝から慌しかった。
昨日と同じように取調執行人としての準備を整える。着替えを終え、チェーンネックレスに手を伸ばす。その時、更衣室の前から凛先輩の声が聞こえてきた。
挨拶をしようとドアの方へ向かったが、男性の声が聞こえてきて立ち止まった。声の主は、署長のものらしかった。どうやら凛先輩と会話をしているようだ。
「署長もミラー越しにご覧になっていましたよね。彼女のやり方は――」
凛先輩の声色はいつになく厳しかった。普段の甘くて優しい響きはそこにはない。
何となく出辛くて、更衣室のドアの前で足を止めてしまった。
盗み聞きをするつもりはなくとも、自然と耳にその会話が入ってくる。
「初めてとは思えないほど素晴らしい活躍だったね。」
対する署長の声は、とても明るいものだった。
それでも凛先輩は、厳しい口調を崩さない。
「素晴らしいと……署長は思われたのですね。」
「容疑者はちゃんと自白したよ。あの短時間で随分とおとなしくもなった。」
そう言って署長が高らかに笑う。
「……でも、特に……自白後のあの行為は、明らかに彼女個人の――」
そう言いかけた先輩を遮り、署長は高圧的に言い放った。
「後藤くんはよく頑張った。犯人は自白した。必要なのは、それだけだ。」
「…………」
「これからも後藤くんの教育、よろしく頼むよ。」
二人が歩き去る音が聞こえ、会話は途絶えた。
私は項垂れたまま、自分のロッカーの前へと戻った。準備したネックレスをそっとロッカー内へ戻す。
――今のままじゃ駄目なんだ……
凛先輩に認められたい。その思いだけがどんどん強くなっていった。
本日の容疑者資料に目を通す。彼は世間を騒がせた通り魔殺人の容疑者だ。
私はアイスピックを手に取り、上着のポケットに入れた。
三:「罪には罰を」
彼女は職務に忠実だった。犯罪者には拷問を。例え誰が相手でも。
「ぼ……僕じゃない……僕じゃ……」
凛の瞳がキラリと光る。握りしめた拳を男の目の前に翳し、下目でじっと男を見下ろしていた。ただそれだけでも、男の戦意を喪失させるには十分すぎるほどの威圧感だった。
「まだ、続けますか?」
凛が冷たくそう言い放つ。男は身体を震わせ、その言葉に大きく反応した。
男の顔は既に見る影もなく潰れていた。血の混じった吐瀉物が床一杯に広がり、男は身体を小さく丸めてその場に蹲っていた。激しく咳き込み、既に声を出すことも困難である様子だった。剥き出しにされた上半身には至る所に痣ができ、所々に血が滲んでいた。
「わ……分かった。分かりました。ご……ゴホッ……。すみません。僕が……やりました。」
必死で声を絞り出す。
凛は安堵の溜息を漏らし、救護担当への連絡のベルを鳴らした。立ち会っていた刑事二人も思わずニヤリと笑みを零す。
「自白終了です。手当てを急いで。」
受話口から凛は冷静にそう告げた。
間もなく救護担当の人間が担架を持ってやってきた。無言のまま男を担架へ乗せると、そのまま取調室から飛び出すように出ていった。
静寂に包まれた取調室をあらためて見回し、再び凛は大きく溜息をついた。
「ごくろうさん。これから詳細を吐かせんとな。後は我々が引き継ぐ。」
事務的な言葉を聞き流し、凛は二人に一礼すると取調室を後にした。
仮眠室へと足を運んだ凛は、おもむろにベッドへと身体を投げ出した。
――今日は少し疲れた――
凛は目を閉じて仮眠を取る。ここのところ昼夜を問わず仕事に追われる日々が続いている。
新法案「正当拷問自白法」が成立してからというもの、警察内部はそれに関わる対策本部の立ち上げや連日の会議で急激に慌しくなっていた。それに伴って管理システムや担当、そして人間関係までもが急速に変化していった。警察署内の忙しさから、警察関係者には次第に余裕がなくなっていった。
容疑者自白担当は人選が厳しい。そこに係る労力や精神力は半端なものではない。人選にはそれに加えて格闘の才能や努力を惜しまない姿勢、責任感など、あらゆる素質が要求される。凛は、その基準を全てクリアしたものと上層部に判断された。
任務についてからというもの、凛にとっては毎日が激務の連続だった。それでも彼女は自分に与えられた使命を果たそうと、日々努力していた。
――身体が重い。
全く疲れが取れていないように凛は感じた。
少し身体を起こす。
交代の時間が迫っている。凛は胸元が四角く開いた薄手のTシャツとミニスカートに着替える。動く仕事なので、破れやすいストッキングは身に着けなかった。シンプルでヒールが低めのパンプスを履く。髪を梳かしながら、今日の仕事内容を確認しようと、書類を手に取った。
そこに書かれた容疑者の名前を見て、凛は凍りついた。
「担当の瀬川凛です。よろしくお願いします。」
取調室で俯いている男は、凛の声を聞くと過敏に反応した。
容疑者と対面するのがこれほど嫌だと思ったのは、彼女にとって初めてのことだった。
男がゆっくりと顔を上げる。その顔が歪むのを見て、凛は思わず目を逸らしそうになった。
凛のやるせない思いは、表情には出なかった。
「凛。凛……だよな。」
凛は返事をしなかった。ただじっと、容疑者である男の顔を見つめていた。
――古嶋隼人、二十八歳。職業はエンジニア。
凛は彼のことをよく知っていた。
――水瓶座のB型。好きな食べ物はアンチョビパスタ。動物嫌い。想い出の場所は映画館。二人の初デートの場所は……
「良かった! 助けてくれ。俺は何もしていない。凛なら、分かってくれるだろ?」
彼女は運命を呪った。同情の念を押し込め、凛は己の職務を開始した。
男は口から胃液を吐き出しながら、無様に倒れ込んだ。
「お……俺じゃないんだ。本当に、何も知らないんだよ……」
床に這い蹲りながら、男は咳き込みながら必死で凛に訴える。
「もう一度聞きます。先日、区内で起きた路上殺人事件。犯人はあなたですね?」
凛は足元に縋りついた男の顔面を、容赦なく蹴り上げる。男の身体が勢いよく壁に叩きつけられる。哀願する男の顔は、涙と鼻血でグシャグシャに汚れていた。
「凛……。凛……。」
男は質問には応えず、ただ凛の名を呟き続けていた。まるで信じられないものを見る目で、彼女を見据えながら……。
凛は無表情のまま、男との距離をじわじわと詰める。
男は怯え、腰を抜かしていた。立つことすらままならず、部屋の隅へと後ずさる。身体を小さく丸め、ブルブルと震えていた。
「やめてくれ……やめてくれ……」
訴えかける男の顔からは、もはや精気は感じられなかった。まるで母親に許しを乞い、その愛を信じ求める子供のように、男は何度も言葉を続けた。
「お願いだ……やめてくれ……許してくれ……」
凛は蹲っている男の身体を、再び勢いよく蹴り上げた。もんどりうって倒れた男を追い詰め、何度も何度も蹴り上げた。その度に男は苦悶の声を上げ、嗚咽を漏らす。怯えきった男にはもはや抵抗する意志はなく、ただその攻撃に耐えることしかできなかった。
「正直に言ってください。これ以上、痛い思いをしますか? それとも……」
彼女はそこで言葉を一度呑み込む。脅迫でも威圧でもない。ただ純粋に、早く自白してほしいという思いが、その言葉には込められていた。
男の身体がふいに持ち上がる。凛が男の襟首を掴み上げたからだ。彼女がじっとその瞳を覗き込むと、男はたまらず視線を逸らす。凛はそれを許さず、顎を掴んで顔を自分の方へと向ける。彼女は男の瞳の奥をさらに強い眼光で睨みつけると、その拳を勢いよく男の腹へと捻じ込んだ。
「う……ぐえっ……」
男の身体がくの字に曲がる。そのままの体勢で凛はさらに二発、三発と膝を男の鳩尾に叩き込んだ。男の呻き声が取調室を包む。それでも彼女はその攻撃の手を止めようとはしなかった。
「うええええっ……ごふうううっ……」
鈍い呻き声が響き渡り、男は吐瀉物を吐いて倒れ込んだ。口の端からは胃液が糸を引きながら零れてきていた。
凛は即座に、突っ伏した男の睾丸をしっかりと握り、その手の中で擦り合わせた。
「ぎ……あああっ……がっ……」
たまらず男は悲鳴を上げる。
「気を失わないでくださいね。あなたには、真実を話していただきます。」
「ううっ……うううっ……」
凛は相変わらず無表情のままだった。いや、正確には表情を作れずにいたのだ。凛は内心に渦巻く葛藤と、常に闘っていたのだから。
睾丸を握りしめられた男は、悲鳴を上げながらも身動きが取れない状態となっていた。怯える男をじっと見つめながら、彼女は睾丸をさらに強く握りしめる。
「あ! がああぁ……。い! 痛い!……い……」
悲痛な叫びを上げる男の目をしっかりと見つめながら、凛は静かに告げる。
「自白、しますか?」
男は必死で首を横に振る。黙って、凛の瞳を喰い入るように見つめていた。
「自白してください……!」
凛の中に焦りが生まれる。自白しない限り、この拷問は終わらないからだ。
男はまた首を振り、息を吸い込んだ。呼吸を整え、口を開いた。
「……信じてくれ、凛……」
静かな声。男の瞳には、強い意志が映し出されていた。
凛はその眼光に動揺を隠し切ることができなくなっていた。愛する者に向けられた真摯な瞳。ほんのわずか、迷いが生まれる。
しかし彼女は、そんな自分の弱い心に負ける訳にはいかなかった。
「残念です……」
そう呟き、睾丸を握った手の平に再び力を込めた。
男の額に脂汗が滲む。しかしそれでも自白する気配は感じられなかった。
凛は無念そうに、わずかに瞳を伏せた。溜息を吐き、拳の力を大きくしていく。
万力のようにじわじわと、しかし確実に睾丸への圧力が増えていく。
最初は我慢していた男も、少しずつまた声が漏れてくるようになった。
「う……うぐぅ…! が……か……」
男の睾丸が風船のようにぷっくりと膨れ上がる。
「ぐわあああああ!!……ううぅあっ……ぎぃやああああっ!!」
限界までギリギリと締め付ける。睾丸が破裂するかと思えた時、凛がふいに手を放した。
男は慌てて身体を後ろに引き、股間を両手で押さえた。狂ったように地面をのた打ち回り、やがてぐったりと動かなくなった。
凛はゆっくりと男の元へと歩を進めた。その無様な姿を見下ろし、顔をパンプスで踏みつける。
「話してください、古嶋さん。でないと……」
凛の瞳が鋭く光る。
「一つずつ潰していきますよ……。」
男はその言葉に大きく震えた。身体を丸めたままガタガタと震えている。
凛の無言の圧力が男に圧し掛かる。
やがて男は、身体から絞り出すようにして言葉を吐いた。
「……お前は、俺の知ってる凛じゃない……!」
その瞳には、恐怖とも嫌悪ともつかぬ感情が溢れていた。
「別人……なんだろ? 見た目は凛そっくりだけど、お前は別人なんだろ?」
男は祈るような顔で、凛の足元に縋り付いて叫んだ。
言葉に確信はなかった。
そうであってほしい。そうであったら、どんなに救われるだろう。そんなわずかな期待と願望が、男の口から零れてきているようだった。
「なぁ……そうだと言ってくれよ。」
男の目が潤む。
凛はそんな男の口を塞ごうとするかのように、顔を踏みつける力をさらに強めた。男は圧迫に耐え切れず、その言葉はやがてただの呻き声へと変わっていた。
凛は答えなかった。
わずかに瞳を伏せ、凛は男の顔を蹴り飛ばした。男の身体は舞うように反転し、床に強く叩きつけられた。衝撃で鼻血を噴き出し、うつ伏せになって倒れ込む。
凛の冷たい視線は、男の少しの希望を容赦なく切り捨てた。
男は腑抜けのように口を開いたまま、涎を垂らしている。凛に与えられた攻撃とショックは、肉体的にも、精神的にも彼を打ちのめしていたのだ。
凛は倒れ込んだ男に近付くと、身体中を蹴り続けた。男はまるで死んでいるかのように、彼女の蹴りに対して全く抵抗しなかった。
しばらく蹴り続けた後、凛は男が上半身に身に着けているシャツを剥ぎ取り、背中に両手の爪を立てた。ギリギリとその背中を引っ掻いていく。男の背中の皮膚が徐々に破れ、そこから血が滲んできていた。
「ぐ……あああぁ……」
男は強制的に意識を覚醒させられ、たまらず声を上げる。爪痕はまるで編目のように、その背中を赤く彩っていた。
「意識をしっかりともっていてください。放心されては困ります。」
凛の言葉は淡白なものだった。
「凛……凛……」
男の縋るような目や言葉を全て拒否するかのように、凛は男の上半身を無心で引っ掻き続けた。それは、凛にとって一つの決意を貫かんとする行為であったのかもしれない。
職務を全うすること。
その強い意志が信念となって、まるで凛の身体を支配しているようであった。
凛はパンプスの先を男の股へと近付ける。
男は全く抵抗しなかった。例え抵抗しようにも、身体はほとんど動かなかったであろう。凛は男の睾丸を思い切り蹴り上げた。
「うぐぅああ……」
鈍い痛みとともに男は悶絶し、無意識に股を押さえようとする。しかし凛はそれを許さなかった。男の両手をしっかりと掴み、足を蹴って股を開かせる。そして再度、睾丸を蹴り上げた。
「ぎぃああぁ!……ああ……」
何度も何度も、凛は男の睾丸を蹴り続けた。男は鈍い痛みに必死で耐えることしかできなかった。
やがて男は口から泡を吹き始めた。
凛はそれを見ると、男の脇に腕を入れた。強制的に立ち上がらせると、男の身体を壁に立てかけた。
男は既に一人では立つこともできないほどになっていた。膝から崩れ落ちないように、凛は男の首を左手で掴む。次の瞬間、凛の拳が男の腹に突き刺さった。
「ぐううええっ……」
鈍い音とともに男はくの字になる。凛は首を掴んで壁へとその身体を押し戻す。そして再び男の腹を殴る。蹴る。時には膝で内臓を抉る。
凛の攻撃は繰り返された。執拗な腹責めに、男の腹はどんどんと赤く腫れていった。男は次第に白目を向き、頬を大きく膨らませた。
「げええええっ……ぐうえええっ…………」
男はとうとう吐血した。口一杯に溜めた血を吐き出し、それが床一面を彩った。凛の顔は彼から吐き出された返り血で所々が赤く染まっていた。
凛が首にかけた手を放すと、男は膝を折ってふわりと前のめりに倒れ込む。凛はその顔を目がけて、容赦なく強烈な蹴りを見舞った。壁に叩きつけられ、壁と足の間に顔が挟まったまま男は動かなくなった。ゆっくりと凛がその足を下ろすと同時に、男は血の海に沈んだ。
「うぅ……」
男には、もう気力も体力も残っていなかった。
ただ、凛への思いだけが、彼を支えているようだった。ボロボロになった身体に鞭打ちながら、必死で彼女に呼びかけ続けていた。
「凛……凛……」
男の顔は腫れ上がり、口の端からは血が流れていた。瞼が切れ、ほとんど開かなくなった片方の目の上からも血が滲んでいる。
凛は男の呟きを無視するかのように、顔を、腹を、手足を、淡々と殴り続けた。
男が凛の顔に向かって、よろよろと手を伸ばす。反撃かと思い凛は警戒したが、彼の手は凛に害を為すつもりはないようだった。指先を凛の耳の側にまで伸ばす。
虫の息で、男は言葉を絞り出した。
「……覚えてるか? 去年のクリスマスに買ったプレゼントを……」
凛の瞳が、一瞬大きく揺れた。
彼女の耳に付いたプラチナのピアスがキラリと光る。
「大切にしてくれてるんだな……。ありがとう。」
男は本当に嬉しそうに微笑んだ。身体の痛みや苦しみを忘れたかのように清々しい笑顔だった。それは、凛が一番よく知っている彼の、古嶋隼人の顔だった。
凛は攻撃の手を緩めた。そして、静かに男に語りかけた。
「私は……」
声が震える。
「……私は、あなたの恋人である瀬川凛です。ただ、同時に私は警察官でもあります。」
凛は彼に対し、真っ直ぐな視線を向けていた。淡々と彼女は言葉を続けた。
「容疑者に自白をさせるのが、私の仕事です。それが……私の正義です。」
男は項垂れた。しばらくの間、沈黙が二人を支配した。
どのくらいの時が経ったのだろう。
男がポツリと呟いた。
「殺すしか……なかったんだ……。」
「あいつは……ずっと凛をストーカーしてたんだから……。」
「…………」
「俺もずっと嫌がらせを受けてた。本当にしつこくて、陰湿な……。」
「…………」
「あんなやつ……死んで当然なんだ……。」
男がとうとうと言葉を吐き続ける間、凛は口を挟まなかった。
ただ、哀れみにも似た目で彼を見つめていた。
ずっと冷静な顔だった凛の瞳に、涙が溜まっていく。
男の頬にそっと手を沿え、彼の口を自らの唇で塞いだ。
突然の出来事に男は言葉を失う。途惑いつつ、彼は目を閉じた。おそらく最後のキスだろう。口付けを交わす二人の姿は、愛し合う恋人同士そのものであった。
唇を離した時、そこには柔らかい笑顔の凛の姿があった。
凛はしばし彼を優しく見つめた後、表情を引き締めた。
「それでも……殺人は、罪です。」
男は顔を歪め、やがて泣き崩れた。
男の刑事二人が取調室に入ってきたのは、その時だった。
「お、終わったんか。自白はしたんかいな?」
「終了なら、報告せないかんな。」
二人の言葉は凛の頭にはしばらく入ってこなかった。ぼうっと気が抜けたように立ち尽くす。それは、これまで凛が見せたことのない、気力を失った表情であった。
「……自白……終了です。」
そう一言だけ告げる。凛は涙を拭い、男の身体をそっと抱きしめた。
刑事たちは何が何やら分からず、ただしばらくの間、凛と男を交互に見回すことしかできなかった。
人を愛するということ。己の中の正義を守るということ。
プライベートの時間。職務を全うする使命。
凛は自分の中のさまざまな思いと向き合い、心に深く刻んだ。
この世に犯罪は尽きない。
本日も、また新たな容疑者が連れて来られている。彼女の仕事は、拷問し、自白させること。
凛は、取調室の扉を開けた。
容疑者に対し、淡々と挨拶した。
「担当の瀬川凛です。よろしくお願いします。」
深々と頭を下げる。
容疑者は凛を見て、驚きの声を上げた。
「あ…あれ? お前、凛じゃないか! わかるだろ、兄貴だよ。助けてくれよ!」
凛はそれには答えず、男の喉元に手をかけた。
「なぁ、凛……冗談だよな?」
凛には既に迷いはなかった。
彼女は職務に忠実だった。犯罪者には拷問を。例え誰が相手でも。
「ぼ……僕じゃない……僕じゃ……」
凛の瞳がキラリと光る。握りしめた拳を男の目の前に翳し、下目でじっと男を見下ろしていた。ただそれだけでも、男の戦意を喪失させるには十分すぎるほどの威圧感だった。
「まだ、続けますか?」
凛が冷たくそう言い放つ。男は身体を震わせ、その言葉に大きく反応した。
男の顔は既に見る影もなく潰れていた。血の混じった吐瀉物が床一杯に広がり、男は身体を小さく丸めてその場に蹲っていた。激しく咳き込み、既に声を出すことも困難である様子だった。剥き出しにされた上半身には至る所に痣ができ、所々に血が滲んでいた。
「わ……分かった。分かりました。ご……ゴホッ……。すみません。僕が……やりました。」
必死で声を絞り出す。
凛は安堵の溜息を漏らし、救護担当への連絡のベルを鳴らした。立ち会っていた刑事二人も思わずニヤリと笑みを零す。
「自白終了です。手当てを急いで。」
受話口から凛は冷静にそう告げた。
間もなく救護担当の人間が担架を持ってやってきた。無言のまま男を担架へ乗せると、そのまま取調室から飛び出すように出ていった。
静寂に包まれた取調室をあらためて見回し、再び凛は大きく溜息をついた。
「ごくろうさん。これから詳細を吐かせんとな。後は我々が引き継ぐ。」
事務的な言葉を聞き流し、凛は二人に一礼すると取調室を後にした。
仮眠室へと足を運んだ凛は、おもむろにベッドへと身体を投げ出した。
――今日は少し疲れた――
凛は目を閉じて仮眠を取る。ここのところ昼夜を問わず仕事に追われる日々が続いている。
新法案「正当拷問自白法」が成立してからというもの、警察内部はそれに関わる対策本部の立ち上げや連日の会議で急激に慌しくなっていた。それに伴って管理システムや担当、そして人間関係までもが急速に変化していった。警察署内の忙しさから、警察関係者には次第に余裕がなくなっていった。
容疑者自白担当は人選が厳しい。そこに係る労力や精神力は半端なものではない。人選にはそれに加えて格闘の才能や努力を惜しまない姿勢、責任感など、あらゆる素質が要求される。凛は、その基準を全てクリアしたものと上層部に判断された。
任務についてからというもの、凛にとっては毎日が激務の連続だった。それでも彼女は自分に与えられた使命を果たそうと、日々努力していた。
――身体が重い。
全く疲れが取れていないように凛は感じた。
少し身体を起こす。
交代の時間が迫っている。凛は胸元が四角く開いた薄手のTシャツとミニスカートに着替える。動く仕事なので、破れやすいストッキングは身に着けなかった。シンプルでヒールが低めのパンプスを履く。髪を梳かしながら、今日の仕事内容を確認しようと、書類を手に取った。
そこに書かれた容疑者の名前を見て、凛は凍りついた。
「担当の瀬川凛です。よろしくお願いします。」
取調室で俯いている男は、凛の声を聞くと過敏に反応した。
容疑者と対面するのがこれほど嫌だと思ったのは、彼女にとって初めてのことだった。
男がゆっくりと顔を上げる。その顔が歪むのを見て、凛は思わず目を逸らしそうになった。
凛のやるせない思いは、表情には出なかった。
「凛。凛……だよな。」
凛は返事をしなかった。ただじっと、容疑者である男の顔を見つめていた。
――古嶋隼人、二十八歳。職業はエンジニア。
凛は彼のことをよく知っていた。
――水瓶座のB型。好きな食べ物はアンチョビパスタ。動物嫌い。想い出の場所は映画館。二人の初デートの場所は……
「良かった! 助けてくれ。俺は何もしていない。凛なら、分かってくれるだろ?」
彼女は運命を呪った。同情の念を押し込め、凛は己の職務を開始した。
男は口から胃液を吐き出しながら、無様に倒れ込んだ。
「お……俺じゃないんだ。本当に、何も知らないんだよ……」
床に這い蹲りながら、男は咳き込みながら必死で凛に訴える。
「もう一度聞きます。先日、区内で起きた路上殺人事件。犯人はあなたですね?」
凛は足元に縋りついた男の顔面を、容赦なく蹴り上げる。男の身体が勢いよく壁に叩きつけられる。哀願する男の顔は、涙と鼻血でグシャグシャに汚れていた。
「凛……。凛……。」
男は質問には応えず、ただ凛の名を呟き続けていた。まるで信じられないものを見る目で、彼女を見据えながら……。
凛は無表情のまま、男との距離をじわじわと詰める。
男は怯え、腰を抜かしていた。立つことすらままならず、部屋の隅へと後ずさる。身体を小さく丸め、ブルブルと震えていた。
「やめてくれ……やめてくれ……」
訴えかける男の顔からは、もはや精気は感じられなかった。まるで母親に許しを乞い、その愛を信じ求める子供のように、男は何度も言葉を続けた。
「お願いだ……やめてくれ……許してくれ……」
凛は蹲っている男の身体を、再び勢いよく蹴り上げた。もんどりうって倒れた男を追い詰め、何度も何度も蹴り上げた。その度に男は苦悶の声を上げ、嗚咽を漏らす。怯えきった男にはもはや抵抗する意志はなく、ただその攻撃に耐えることしかできなかった。
「正直に言ってください。これ以上、痛い思いをしますか? それとも……」
彼女はそこで言葉を一度呑み込む。脅迫でも威圧でもない。ただ純粋に、早く自白してほしいという思いが、その言葉には込められていた。
男の身体がふいに持ち上がる。凛が男の襟首を掴み上げたからだ。彼女がじっとその瞳を覗き込むと、男はたまらず視線を逸らす。凛はそれを許さず、顎を掴んで顔を自分の方へと向ける。彼女は男の瞳の奥をさらに強い眼光で睨みつけると、その拳を勢いよく男の腹へと捻じ込んだ。
「う……ぐえっ……」
男の身体がくの字に曲がる。そのままの体勢で凛はさらに二発、三発と膝を男の鳩尾に叩き込んだ。男の呻き声が取調室を包む。それでも彼女はその攻撃の手を止めようとはしなかった。
「うええええっ……ごふうううっ……」
鈍い呻き声が響き渡り、男は吐瀉物を吐いて倒れ込んだ。口の端からは胃液が糸を引きながら零れてきていた。
凛は即座に、突っ伏した男の睾丸をしっかりと握り、その手の中で擦り合わせた。
「ぎ……あああっ……がっ……」
たまらず男は悲鳴を上げる。
「気を失わないでくださいね。あなたには、真実を話していただきます。」
「ううっ……うううっ……」
凛は相変わらず無表情のままだった。いや、正確には表情を作れずにいたのだ。凛は内心に渦巻く葛藤と、常に闘っていたのだから。
睾丸を握りしめられた男は、悲鳴を上げながらも身動きが取れない状態となっていた。怯える男をじっと見つめながら、彼女は睾丸をさらに強く握りしめる。
「あ! がああぁ……。い! 痛い!……い……」
悲痛な叫びを上げる男の目をしっかりと見つめながら、凛は静かに告げる。
「自白、しますか?」
男は必死で首を横に振る。黙って、凛の瞳を喰い入るように見つめていた。
「自白してください……!」
凛の中に焦りが生まれる。自白しない限り、この拷問は終わらないからだ。
男はまた首を振り、息を吸い込んだ。呼吸を整え、口を開いた。
「……信じてくれ、凛……」
静かな声。男の瞳には、強い意志が映し出されていた。
凛はその眼光に動揺を隠し切ることができなくなっていた。愛する者に向けられた真摯な瞳。ほんのわずか、迷いが生まれる。
しかし彼女は、そんな自分の弱い心に負ける訳にはいかなかった。
「残念です……」
そう呟き、睾丸を握った手の平に再び力を込めた。
男の額に脂汗が滲む。しかしそれでも自白する気配は感じられなかった。
凛は無念そうに、わずかに瞳を伏せた。溜息を吐き、拳の力を大きくしていく。
万力のようにじわじわと、しかし確実に睾丸への圧力が増えていく。
最初は我慢していた男も、少しずつまた声が漏れてくるようになった。
「う……うぐぅ…! が……か……」
男の睾丸が風船のようにぷっくりと膨れ上がる。
「ぐわあああああ!!……ううぅあっ……ぎぃやああああっ!!」
限界までギリギリと締め付ける。睾丸が破裂するかと思えた時、凛がふいに手を放した。
男は慌てて身体を後ろに引き、股間を両手で押さえた。狂ったように地面をのた打ち回り、やがてぐったりと動かなくなった。
凛はゆっくりと男の元へと歩を進めた。その無様な姿を見下ろし、顔をパンプスで踏みつける。
「話してください、古嶋さん。でないと……」
凛の瞳が鋭く光る。
「一つずつ潰していきますよ……。」
男はその言葉に大きく震えた。身体を丸めたままガタガタと震えている。
凛の無言の圧力が男に圧し掛かる。
やがて男は、身体から絞り出すようにして言葉を吐いた。
「……お前は、俺の知ってる凛じゃない……!」
その瞳には、恐怖とも嫌悪ともつかぬ感情が溢れていた。
「別人……なんだろ? 見た目は凛そっくりだけど、お前は別人なんだろ?」
男は祈るような顔で、凛の足元に縋り付いて叫んだ。
言葉に確信はなかった。
そうであってほしい。そうであったら、どんなに救われるだろう。そんなわずかな期待と願望が、男の口から零れてきているようだった。
「なぁ……そうだと言ってくれよ。」
男の目が潤む。
凛はそんな男の口を塞ごうとするかのように、顔を踏みつける力をさらに強めた。男は圧迫に耐え切れず、その言葉はやがてただの呻き声へと変わっていた。
凛は答えなかった。
わずかに瞳を伏せ、凛は男の顔を蹴り飛ばした。男の身体は舞うように反転し、床に強く叩きつけられた。衝撃で鼻血を噴き出し、うつ伏せになって倒れ込む。
凛の冷たい視線は、男の少しの希望を容赦なく切り捨てた。
男は腑抜けのように口を開いたまま、涎を垂らしている。凛に与えられた攻撃とショックは、肉体的にも、精神的にも彼を打ちのめしていたのだ。
凛は倒れ込んだ男に近付くと、身体中を蹴り続けた。男はまるで死んでいるかのように、彼女の蹴りに対して全く抵抗しなかった。
しばらく蹴り続けた後、凛は男が上半身に身に着けているシャツを剥ぎ取り、背中に両手の爪を立てた。ギリギリとその背中を引っ掻いていく。男の背中の皮膚が徐々に破れ、そこから血が滲んできていた。
「ぐ……あああぁ……」
男は強制的に意識を覚醒させられ、たまらず声を上げる。爪痕はまるで編目のように、その背中を赤く彩っていた。
「意識をしっかりともっていてください。放心されては困ります。」
凛の言葉は淡白なものだった。
「凛……凛……」
男の縋るような目や言葉を全て拒否するかのように、凛は男の上半身を無心で引っ掻き続けた。それは、凛にとって一つの決意を貫かんとする行為であったのかもしれない。
職務を全うすること。
その強い意志が信念となって、まるで凛の身体を支配しているようであった。
凛はパンプスの先を男の股へと近付ける。
男は全く抵抗しなかった。例え抵抗しようにも、身体はほとんど動かなかったであろう。凛は男の睾丸を思い切り蹴り上げた。
「うぐぅああ……」
鈍い痛みとともに男は悶絶し、無意識に股を押さえようとする。しかし凛はそれを許さなかった。男の両手をしっかりと掴み、足を蹴って股を開かせる。そして再度、睾丸を蹴り上げた。
「ぎぃああぁ!……ああ……」
何度も何度も、凛は男の睾丸を蹴り続けた。男は鈍い痛みに必死で耐えることしかできなかった。
やがて男は口から泡を吹き始めた。
凛はそれを見ると、男の脇に腕を入れた。強制的に立ち上がらせると、男の身体を壁に立てかけた。
男は既に一人では立つこともできないほどになっていた。膝から崩れ落ちないように、凛は男の首を左手で掴む。次の瞬間、凛の拳が男の腹に突き刺さった。
「ぐううええっ……」
鈍い音とともに男はくの字になる。凛は首を掴んで壁へとその身体を押し戻す。そして再び男の腹を殴る。蹴る。時には膝で内臓を抉る。
凛の攻撃は繰り返された。執拗な腹責めに、男の腹はどんどんと赤く腫れていった。男は次第に白目を向き、頬を大きく膨らませた。
「げええええっ……ぐうえええっ…………」
男はとうとう吐血した。口一杯に溜めた血を吐き出し、それが床一面を彩った。凛の顔は彼から吐き出された返り血で所々が赤く染まっていた。
凛が首にかけた手を放すと、男は膝を折ってふわりと前のめりに倒れ込む。凛はその顔を目がけて、容赦なく強烈な蹴りを見舞った。壁に叩きつけられ、壁と足の間に顔が挟まったまま男は動かなくなった。ゆっくりと凛がその足を下ろすと同時に、男は血の海に沈んだ。
「うぅ……」
男には、もう気力も体力も残っていなかった。
ただ、凛への思いだけが、彼を支えているようだった。ボロボロになった身体に鞭打ちながら、必死で彼女に呼びかけ続けていた。
「凛……凛……」
男の顔は腫れ上がり、口の端からは血が流れていた。瞼が切れ、ほとんど開かなくなった片方の目の上からも血が滲んでいる。
凛は男の呟きを無視するかのように、顔を、腹を、手足を、淡々と殴り続けた。
男が凛の顔に向かって、よろよろと手を伸ばす。反撃かと思い凛は警戒したが、彼の手は凛に害を為すつもりはないようだった。指先を凛の耳の側にまで伸ばす。
虫の息で、男は言葉を絞り出した。
「……覚えてるか? 去年のクリスマスに買ったプレゼントを……」
凛の瞳が、一瞬大きく揺れた。
彼女の耳に付いたプラチナのピアスがキラリと光る。
「大切にしてくれてるんだな……。ありがとう。」
男は本当に嬉しそうに微笑んだ。身体の痛みや苦しみを忘れたかのように清々しい笑顔だった。それは、凛が一番よく知っている彼の、古嶋隼人の顔だった。
凛は攻撃の手を緩めた。そして、静かに男に語りかけた。
「私は……」
声が震える。
「……私は、あなたの恋人である瀬川凛です。ただ、同時に私は警察官でもあります。」
凛は彼に対し、真っ直ぐな視線を向けていた。淡々と彼女は言葉を続けた。
「容疑者に自白をさせるのが、私の仕事です。それが……私の正義です。」
男は項垂れた。しばらくの間、沈黙が二人を支配した。
どのくらいの時が経ったのだろう。
男がポツリと呟いた。
「殺すしか……なかったんだ……。」
「あいつは……ずっと凛をストーカーしてたんだから……。」
「…………」
「俺もずっと嫌がらせを受けてた。本当にしつこくて、陰湿な……。」
「…………」
「あんなやつ……死んで当然なんだ……。」
男がとうとうと言葉を吐き続ける間、凛は口を挟まなかった。
ただ、哀れみにも似た目で彼を見つめていた。
ずっと冷静な顔だった凛の瞳に、涙が溜まっていく。
男の頬にそっと手を沿え、彼の口を自らの唇で塞いだ。
突然の出来事に男は言葉を失う。途惑いつつ、彼は目を閉じた。おそらく最後のキスだろう。口付けを交わす二人の姿は、愛し合う恋人同士そのものであった。
唇を離した時、そこには柔らかい笑顔の凛の姿があった。
凛はしばし彼を優しく見つめた後、表情を引き締めた。
「それでも……殺人は、罪です。」
男は顔を歪め、やがて泣き崩れた。
男の刑事二人が取調室に入ってきたのは、その時だった。
「お、終わったんか。自白はしたんかいな?」
「終了なら、報告せないかんな。」
二人の言葉は凛の頭にはしばらく入ってこなかった。ぼうっと気が抜けたように立ち尽くす。それは、これまで凛が見せたことのない、気力を失った表情であった。
「……自白……終了です。」
そう一言だけ告げる。凛は涙を拭い、男の身体をそっと抱きしめた。
刑事たちは何が何やら分からず、ただしばらくの間、凛と男を交互に見回すことしかできなかった。
人を愛するということ。己の中の正義を守るということ。
プライベートの時間。職務を全うする使命。
凛は自分の中のさまざまな思いと向き合い、心に深く刻んだ。
この世に犯罪は尽きない。
本日も、また新たな容疑者が連れて来られている。彼女の仕事は、拷問し、自白させること。
凛は、取調室の扉を開けた。
容疑者に対し、淡々と挨拶した。
「担当の瀬川凛です。よろしくお願いします。」
深々と頭を下げる。
容疑者は凛を見て、驚きの声を上げた。
「あ…あれ? お前、凛じゃないか! わかるだろ、兄貴だよ。助けてくれよ!」
凛はそれには答えず、男の喉元に手をかけた。
「なぁ、凛……冗談だよな?」
凛には既に迷いはなかった。
四:「由香利ノート」
一冊のノートに綴られた拷問の記録。無邪気さこそが本当の恐怖。
夜になっても署内は慌しかった。
夜勤との引き継ぎが終わってもなお、日勤の人間が残務に励んでいる。彼女もまた、そんな忙しい人間の一人であった。疲れのせいもあろうか、彼女からは溜息が絶えない。
事務処理が一段落ついた頃、彼女は休憩を兼ねて座席を離れると、仮眠室に向かった。
仮眠室は署内の騒がしい様子とは打って変わった静けさを漂わせている。
堅いベッドの脇には一冊のノートが置かれていた。彼女はそのノートに手を伸ばす。
五百ページはあろうかという分厚いノートの表紙には、大きく『由香利ノート』と記されている。
表ページの見開きに大きく書かれた文字。
『正当拷問自白法 違反者記録』
新法案、正当拷問自白法成立から早二年が過ぎようとしている。
連日のように起こる凶悪犯罪件数は未だ衰えるところを知らない。しかしそれとは裏腹にその自白率は年々右肩上がりの良傾向を見せている。
彼女は複雑な思いを胸にノートを開いた。そこには丁寧な文字で仕事の記録が残っている。二年分の文字の量は膨大だ。
最初のページには由香利の思いが切々と込められていた。
今日から仕事が始まった。なかなか就職先が見つからなかった私にとっては、願ってもない話だった。
全ての悪人がこの世からいなくなったら、どんなに幸せな世界ができるんだろう。
生きてる間に悪人に地獄を見せてやれたら、相手の気持ちが少しは分かるんじゃないか。
そんな風に考えていた私にとって、この仕事はまさに天職であるかのような思いがした。
正義の処刑人として働くことができるようになれて、私は今心底幸せを感じている。
正当な拷問を受けても自白しないような悪人は…私がこの手で処刑してあげる。
彼女はおもむろにパラパラとページをめくっていった。
***
受刑者番号五十番 横山菅生 二十三歳
彼は強盗殺人の罪を最後まで否認し続けた。正当拷問に対しても反抗的な態度だったため、自白法違反で拷問刑が確定した。
私はタンクトップにデニムスカートを履いた服装で拷問部屋に入る。罪人との初対面であるこの瞬間はいつも緊張する。私は中にいるその人物の様子を観察した。
今時の若者って感じですごくイキがいい。彼は法律違反者となって今日が初めての拷問の日だった。
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
私は形式的な挨拶をする。彼は私を見るといきなり私の胸を触ろうとしてきた。
「俺に気持ちいいことしてくれるのかな。」
…ずいぶんと笑わせてくれる…
私は笑顔のままその腕を捻り上げ、背中の後ろで固定する。彼は苦痛の声を上げて抵抗をやめた。
「い…いだだ…くあっ…」
「ふふ…変な抵抗しちゃ駄目ですよ…」
そのまま背後に回りこみ、もう片方の腕で首を絞める。声帯を絞められたことで声が出せなくなっている。
私は抵抗をやめた彼をそのまま仰向けに倒し、首を絞めたままお腹を思いきり殴り続けた。
「ごほおっ!…ご…ごめんなさ…いぐっ…げほおっ!…」
こういう男性はとにかく芯が脆い。ちょっと本気出すとすぐこれだから…。
私はつい感情的になり、そのまま彼が泡を吹くまでやってしまった。
ここからが私の仕事。
「今日のメニューは股裂きと片側の睾丸潰しです。」
私は既にぐったりと倒れ込んだ彼にそう告げる。
彼は私の言葉を冗談だと思ったのか、半信半疑の面持ちで不安そうに私を見つめる。
無理もないか…今日は彼にとっての『初体験』だもんね…「お…おいおい…ちょ…待ってくれ。まさか本気でやるわけじゃないんだろ?」
彼は脂汗を垂らしながら私を見つめる。その怯えた表情に、私は若干のエクスタシーを覚えた。
…ふふ…本気じゃなかったらこんなところに来ないでしょ…
私は心の中で笑った。心の奥底が急激に冷えていく感覚が私を覆う。
無表情のまま備え付けの手枷を手際よく彼の両腕に付け、磔台の低い位置に固定する。
腰を床につけたままの姿勢でいる彼の足を持ち、限界まで股を開かせる。彼は悲痛の声を上げた。
そのままの形で部屋の両脇についているリングと彼の両足をチェーンで繋ぐ。
片方のリングには車輪がついていた。事態を察知した彼は予想通り悲鳴を上げる。
「や…やめてくれ!…たのむ…やめて…」
「それじゃいきますね。声はいくら出しても大丈夫ですからね。」
優しく彼にそう告げる。それから私はリングの車輪を少しずつ少しずつ巻いていくのだ。
ギリギリと音を立て、彼の股がどんどんと開かれていく。この瞬間が本当に楽しい。
「ぎいいっやああああああ!!た…助けて!!…助けて!!」
「はい、痛いですねー。これからもっともっと痛くなりますからねー。」
私はさらに車輪を巻く。だんだんと車輪が重くなってくる。私はそれに合わせて力いっぱい車輪を回さなければならないのだ。これが結構な重労働。
「ぐが…あ…あああああああああああああ!!!」
絶叫が部屋の中いっぱいにこだまする。私の力が限界に達した頃、彼の股関節が音を立てて外れた。
彼は絶叫し、気を失った。私は一息つくと、彼の裂けた股の間から垂れ下がっている睾丸を強く握りしめ、強制的に意識を取り戻させる。
「ぎゃあっ!!…はぁ…はぁ…いいいいいい…痛い…痛い…ごめんなさい。助けて…」
泣きながら訴える彼の姿がとても可愛らしく感じた。
「今日のメニューはあと一つで終わりです。もう少しですからね。」
私はまた優しくそう答える。
「ま…待ってくれ…あと一つって…だってそれは…たのむから!それだけは!」
この部屋は最新の技術が駆使してあり、防音は完璧だ。こんなに叫ぶんだから当然必要なシステムだよね。
ただ…近くにいる私はすごく耳が痛くなる。最初にメニューを伝えてあるんだからその瞬間になってそんなに叫ばなくたっていいのに…。
彼は狂ったように身体を捩り、必死でもがいている。しかし完全に身体を固定されているため、それは無駄な足掻きにしかなっていない。
私は彼のズボンのチャックの中から睾丸を引き出す。
「それじゃ、いきますね。」
「や…やめて…やめ…やめーーー!!!」
私は片方の睾丸の皮膚を持って床に押し付けた。片方の足で皮膚を押さえつけ、もう片方の足を振り上げる。
……!!!!!…
私は彼の睾丸を足で力いっぱい踏み潰すと、亀頭から血が噴出してくるのを確認した。彼の断末魔の声が響き渡る。
今日の仕事はこれで終了。再び気を失った彼を見つめながら私はほっと肩を撫で下ろした。
明日もまた仕事だ。頑張らなくちゃ!
受刑者番号七十九番 定岡直人 三十五歳
この緊張感からいつかは解放されるのだろうか。
まだまだ仕事に対する不安は大きいけど、しっかりと頑張っていこうと思う。
彼はお年寄りの家に次々と放火してまわった、いわゆる愉快犯。彼もやっぱり容疑を否認し続けて自白法違反となった人だ。
許せない…。罪もない、しかも…か弱いお年寄りだけを狙うなんて…
だからと言うわけじゃないけど、処刑メニューはしっかりとこなそうとあらためて心に誓った。
今日はキャミソールにフリルのついたミニスカート。これらの服は買ったばかりなので私のお気に入りだ。気を引き締めて拷問部屋に入る。
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
彼の第一印象は、暗く、疲れ果てた老人のようで、とても三十五には見えなかった。
入所してから何日も経っていたためか、ずいぶんと元気がなかったように思う。
「最初は身体全体への刺針です。」
彼は諦めきった様子で、指示に対しては大きなリアクションをしない。
「はい…」
叫び声を上げるのが得意な罪人はすごく多いけど、彼は驚くほど無抵抗だった。
ここでのやり方を既に理解し、無駄な抵抗をしないようにしているのかもしれない。
もっともその方が私は仕事がしやすくてとても助かるのだけれど。
自らベッドに横たわった彼の身体中に、16Gの針を一つ一つ刺していく。
胸、腕、顔、腿、そして陰茎。至る所に穴を開けていく。刺し傷から血が滴る。
彼は俯きながら一生懸命耐えていた。
「次は鞭打ちです。」
「はい。」
私は皮製の乗馬鞭で、ついたばかりの傷跡が目立つその身体全体に鞭を振り下ろしていく。
「ぐ…あぁっ…がああああ…」
彼は声を押し殺しながら必死で耐える。その姿が私を高揚させる。これは私の悪い癖だ。
私は、男が苦痛に耐える姿に言い知れぬ興奮を覚えることを既に自覚していた。
ついつい鞭を持つ手に力が入る。
「ほら。痛いですね。ふふ…一生懸命我慢してるんですね。たくさん痛めつけてあげますからね。」
何度も…何度も…何度も…何度も…
私は自分の欲望の赴くままに鞭を振り下ろす。自制が効かなくなっていく自分が少し怖かった。
さすが、年の功といった感じだった。本当に我慢強い。その強さが私の感情をさらに高ぶらせていくことに、私自身この時は気付いていなかったのかもしれない。
「…処刑人さん…ちょっと、いいですか。」
鞭打ちを終わらせた頃、彼が私に話しかけてきた。
「あの…普段はメニューを先に教えてもらっていたはずです。方針が変わったのでしょうか。」
…あ…しまった…
うっかりしていた。最初にメニューを告げるのは処刑人マニュアルの基本であった。
私自身これまでしっかりと行ってきたことであったはずだが、この時はすっかり忘れてしまっていた。
「申し訳ありませんでした。最初にお伝えするところを…」
「いえ…」
私は慌てて最後のメニューを彼に告げた。しかしその途端、彼の態度が豹変した。
これまでの落ち着いた雰囲気とはうってかわり、明らかに取り乱した様子を見せた。
その姿に驚いた反面、何故か私は彼に親しみを感じたような気がした。
「ほ…本当にか…本当にそれが…。あ…あ…やめ…やめて…」
人間同士の心と心が触れ合う時…それはお互いが素の自分を曝け出した時なのかもしれない…
そんな思いがふと私の頭を過った。相手が憎むべき違反者であることも忘れ、私は彼に魅かれる自分を感じた。
「最後の仕上げ…精一杯行わせていただきますね。」
それは私の心からの言葉だった。しっかりと真心をもって最後の作業を行わなければ失礼だ。そんな風に考えていた。
「た…頼むーーー!それだけは…それだけは勘弁してくれ!!お願いしますーー!!」
私は彼に微笑むと抵抗する彼の首を絞めて気絶させた。変形型の拘束具を着せてベッドに縛り付けて固定する。
彼の左の手首から上だけが剥き出しになり、残りの全てが拘束具で包まれている。
しばらくすると彼は目覚めた。目は大きく見開かれ、彼は恐怖のためか絶叫をあげ続けた。
「やめてくれーー!!助けてくれーーー!!」
「これが最後のメニューです。」
彼の親指にナイフを突きつける。彼の息を呑む音が耳元で大きく聞こえる。
私は片手で彼の手をしっかりと押さえつけると、反対の手で力いっぱいナイフを叩きつけ、親指を切断した。
「ぎぃやあああああああああああああ!!!」
絶叫が部屋全体に響き渡る。そして彼は失禁し、気絶した。
…ちょっとだけかっこよく感じちゃった。私って駄目な女。相手は法律違反者なのに…
とにかく、今日の仕事も完了。
私は今まで以上に、この仕事が楽しいと思えるようになってきている。
今日は私の担当する処刑業務はなかった。その代わりに、別室でトレーニングを行うことになった。
私を指導してくださったのは瀬川凛先輩だ。スレンダーな美しい肢体。
訓練のことなんて忘れて、その身体にしばらく見惚れてしまっていた。互いに向き合い、素手でぶつかり合う。凛先輩との格闘は私にとって幸せそのものだ。
殴りかかる私の腕を掴み、鮮やかに身体を腕の下にくぐらせる。
私は身体を倒され、腕拉ぎをかけられた。完全に関節を決められている。
う…くうう…
「ふふ…まだまだ指導が必要ね…」
…かっこいい…
胸の高鳴りが治まらなかった。先輩の姿が未だに目に焼きついて離れない。
いつかは私も先輩のようにかっこいい人間になりたい。
「ねぇ、あなたはどうしてこの仕事に就こうと思ったの?」
凛先輩が私に問いかける。トレーニングを終えたばかりの私は倒れ込み、身体を起こすこともできない。天井を見上げながら私は答えた。
「悪人をこの世から全て消したいんです。」
息を荒げながら答える私の顔を凛先輩はそっと覗き込み、微笑を浮かべていた。
「そう…。これからのトレーニングもしばらく私が付き合うから。そのつもりでいなさいね。」
笑顔のまま私のおでこに軽くキスをする。
彼女の言葉やその行為の意味は、正直なところ私にはまだ分からない。でも、憧れの凛先輩からこれから先も指導していただけるのだと思うと、私の胸はさらに大きく高鳴った。
「先輩…」
私はかろうじて身体を起こして凛先輩の方に向き直った。彼女は既に汗を拭うとその場でスーツに着替え始めていた。その後ろ姿に再び私は見惚れてしまい、背中の汗を拭う先輩から目が離せなくなっていた。
「執行人としての誇りと自覚をもって、これからも頑張っていきます。」
その言葉を聞いた私の憧れの人は涼やかな笑顔を見せ、優しく私に言葉をかけた。
「ふふ…頑張ってね。」
受刑者番号百十一番 光村隆介 二十九歳
思えばたくさんの人を処刑してきた。
どうして犯罪は無くならないんだろう。どうしてきちんと自白しないんだろう。
私にはどうしても理解することができなかった。
彼は一家全員を皆殺しにした凶悪犯だ。絶対に許すことはできない。
先日デパートで購入したばかりのチュニックにスキニージーンズ姿で部屋に入る。ネイルサロンで塗ってもらったばかりの爪が私の気分をわくわくさせる。
私が部屋に入るなり、男は喚いた。
「頼むよ!頼むから!俺をここから出してくれ、な?お願いだ。」
どうしてここに来る人たちは皆、こんな感じなんだろう。結局は自分で選んで来た道でしょ?
私は彼の言葉に反応することなく、言葉を発した。
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
「頼む!もう許してくれ!頼む!俺は本当に、何もしてないんだから。」
…さっきからくだらないことばかり言ってる…
私は言葉を続けた。
「今日のメニューは、左手全指骨折と内臓損傷です。」
男は私の言葉など聞いている様子はなかった。
「た…助けてくれ…助けてください…」
こういう受刑者には、まず自分の置かれている立場をしっかりと理解してもらわなければいけない。
私は黙って男に近付くと、その首を掴んで床に勢いよく倒した。
「抵抗は無意味です。刑はしっかりと受けていただきます。それが、あなたの務めですよ。」
にっこりと微笑みながら語りかける私の目を見て、男は涙を溢れさせた。
彼はぐったりと脱力し、肩に全く力が入らなくなっているようだった。
迅速にその腕を取り、股の間に挟みこむと相手と一緒に倒れ込んだ。腕拉ぎをかける。
男はそれでもなお絶叫を上げ、じたばたと抵抗しようとする。
「では、一つ目のメニューです。」
私は関節を決めた左腕をがっちりと固めたまま、彼の手をそっと握る。
そして彼の指を小指から順番に、関節とは逆の方向に折り曲げて一本一本丁寧に折っていった。
「ぐあああああ!!ぎぃやいやあああああ!!うっぐあああああああ!!!」
骨折と同時に彼の絶叫が小部屋に大きく響き渡る。既に彼の喉は枯れ果て、かすれた、声にならない声がその部屋全体を覆い尽くしていた。
左手の全ての指の機能を奪われた彼は、完全に生気を失っていた。その目に光はなく、ただただ小刻みにその身体を震わせながら小さく身体を丸めていた。
「今日のメニューは次で最後になります。頑張ってくださいね。」
私の言葉に、彼はまたも返答しようとはしなかった。虚ろな目をしながら、うわ言のように同じ言葉を繰り返しながら天井を見つめていた。
「た…す…け……助けて…助けて…。俺はやってない…やってない…。」
この人は本当に同じ言葉しか言わない。私はその姿が何となく滑稽に思え、笑いが込み上げてきてしまっていた。
ぼうっと立ち尽くす彼をしばらくじっと見つめ、それから私は勢いよく彼に向かって走った。
…!!…
渾身の力を込めたボディブローを彼のお腹に叩きつける。
その瞬間彼は我に返ったのか、目を大きく見開き、頬を膨らませた。強制的にその瞳に光が戻される。
「うぐううえええええっ!!!」
彼はお腹を抱えて蹲った。必死で押さえるその手を引き剥がすようにしながら、私はなおもボディブローを彼に何度も突き刺していった。
「はううっ!おえええっ!!げほおおお!!」
拳を叩きつける度にまた搾り出すように声を上げる。私は彼に馬乗りになり、さらに何度もパンチを入れる。
「げえっ!もう…くるし…く…がはあああ!!うぐはあああ!!」
私はその後立ち上がると、今度はそのお腹を踏みつけた。徐々に体重を乗せていく。
「う…お…おおぉぉ…」
力を緩め、そしてまた体重を乗せることを繰り返す。彼は顔を真っ赤にして苦しみに耐えている。
しばらく踏みつけを行うと、彼は脱力して動かなくなった。
私はその無防備になったお腹に全体重をかけてニードロップをした。
「ぐうえあああああああああ!!げおおおお…お…」
絶叫とともに彼は悶絶し、やがて嘔吐した。顔面は蒼白になり、すでに半分白目をむいていた。
変な感じ…やっぱり、何となくだけど…
私は男を甚振る度に高揚していく自分の気持ちに少しずつ気付いていた。不思議な感覚…
お腹を抱えて蹲る彼を蹴り上げ、再び身体を仰向けにさせると、そのお腹を力いっぱい踏みつけた。ぐりぐりと踏みにじる。
私は自分の行為にまた言いようもないエクスタシーを感じていた。
しばらく弄んだ後、再びお腹を思いきり踏みつける。何度も…何度も…
その度に男は苦悶の声を上げ、心地よい悲鳴を上げる。
「げほぉぉぉ!…う…うぇ…うげぇ…がはああああ!!!」
とうとう彼は白目を向き、ぐったりとしたまま口から血を噴き出した。床が彼の血で染まる。
彼はかろうじて呼吸をしているようだった。私はその姿を見ながら必死で笑いを堪えていた。
「今日のメニューは終了です。おつかれさまでした。」
虫の息で倒れ込んだ彼を担いでベッドに寝かせる。私はいつものように救護担当にコールした。
今日の仕事も無事終了。
私は毎日楽しく仕事を頑張っている。
これまでたくさんの人を処刑してきたけど、やっぱり一番緊張したのは最初の仕事の時だったと思う。あの人の名前は今でも忘れない。
大谷悟さん二十七歳。
今考えると、あの日は私にとってすごく重要な意味をもつ日だったんだと思う。
何と言っても、初任務でいきなり新法案「正当拷問自白法」の違反一件目の人の担当に当たったんだから。
気を引き締めていかなくちゃ!ってドキドキしてた。
…任務前にサインもらっておけばよかった…なんて後で思ったりもした。
『俺は八人の女を強姦した後、殺したんだ!』ってしきりに叫んでたのを覚えてる。
だったらどうして自白しなかったんだろう?
それがすごく不思議…。
極刑を免れてよかったじゃない。結果的に拷問刑を選択したのは自分自身なのにね…
***
彼女は、そこで一度ノートを置いた。
仕事の疲れからか眠気がピークに達してきている。
少しでも身体をほぐそうと片方の手で肩や腰を叩き、ぐっと背伸びをした。
床に寝転んだまま、しばしぼうっと天井を見上げる。
その瞳には、どこか悲しげな表情が見て取れた。
彼女はふと、思いついたかのように受刑者記録の最初のページを開いた。
受刑者番号一番 大谷悟 二十七歳
「今日のメニューは爪剥ぎと抜歯、それから右腕の骨折です。担当刑事の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
婦警のかっちりとした制服に身を包んだ私は、内心の緊張を抑えながら告げた。
怯えきった様子の彼は私が挨拶をするなり突然叫び出した。
「お…俺は八人の女を強姦して殺したんだよ!死刑にしてくれ!死刑にしてくれ!!」
「そうですよね、分かってますよ。ただ大谷さんの刑は死刑じゃなくて拷問刑なんです。今日は私が担当させていただきますので、よろしくお願いしますね。」
「い…嫌だ!俺は…」
私は言葉を待たずに彼に跳びかかり、首を掴んで壁に押しつけた。苦しそうな声が喉から漏れる。
「ちょっと静かにしてもらいますね。すぐに終わりますから。」
笑顔でそう告げると私は彼の鳩尾を拳で一突きして気絶させた。押さえつけていた手を離し、床に寝かせる。
用意していたペンチで慎重に彼の小指の爪を掴む。私は力いっぱい彼の爪を引き抜いた。
あっと言う間に血が滲む。彼は痛みのあまり意識を取り戻し、同時に絶叫をあげた。
「ぎやああああああああ!痛い!!があああああああああ!!」
彼の目に涙が浮かぶ。
「やめて…やめ…」
私の側を離れ、彼は壁にもたれかかるようにして縮こまった。その姿が不思議と私を魅了する。
…可愛い…
それが私の正直な感想だった。小さく身体を丸めながら許しを乞う姿がこんなに可愛らしいなんて…。
私はついその姿がもっと見たくなってしまった。
もっともっと可愛らしいあなたを…見せて…
口元が緩んでしまう。笑顔のまま私は彼に一歩一歩近付く。
「ひぃぃぃ…」
怯える様子を見て、私は意気を高める。
「サービスしてあげましょうか…。全部抜いちゃってもいいんですよ…ふふふ…」
彼はその言葉に大きく反応すると、再び気を失った。
私は彼の反対の手の小指を掴むと、再度その爪を引き抜いた。彼はまた意識を取り戻し、絶叫した。
「ぐあああああああああああああ!!!ああああああああああああ!!!」
ついついサービスで三つも抜いてあげてしまった。そろそろ抜歯に移らないとね…
最初の仕事であると同時に、その相手が正当拷問自白法成立以来初めての違反者だったということもあり、正直最初は緊張して仕方がなかった。
しかし彼に刑を執行しているうちに、私は確実にこの仕事を楽しく思えてきていた。
こんなに楽しいなら、これから先もやっていけると思う。
私は彼の顔をじっと見つめた。彼が弱い小動物のように見えた。
身体をぶるぶる震わせながら小さくなっていた。
彼の取調べを担当した凛先輩は、『強情を絵に描いたような人だった』って言ってたけど…正直、全く印象が違っていた。
今の彼は…ただ怯えるだけの小動物。絶対的な力に服従するだけの…ふふ…
私は可笑しくて仕方がなかった。今にも笑い出しそうになるのを堪えながら、私は彼に堂々と近付いた。
「お…お願いします…もう…もう…」
私は彼の顎を指先で優しく撫でた。こんなにも愛しさを感じるなんて思ってもみなかった。
許し難い大犯罪者…それなのに…
私は彼の口を片手で掴み、無理矢理口を開けさせた。無抵抗な彼の前歯をペンチでゆっくりと挟み込む。
「は…や…や…」
我慢できずに彼の頭を撫でる。身体を摺り寄せる。
…この感動をいつまでも覚えていたい…
そんな思いを胸に私は彼の前歯を勢いよく引き抜いた。涙目の彼の口から血が溢れ出す。
「がああああああああああああああああ!!!!」
ふふ…よく叫ぶ人…
すかさず私は彼の背後に回り、右腕を捻りあげる。
彼には既に抵抗する意志はない様子だった。泣きながら何かを呟いている。
私はそんな彼を目に焼き付けるように見ながら、その関節を痛打した。骨が折れる感触が伝わってくる。
「ぐうあああああああああああ!!ああああああああああああ!!」
彼は声を搾り出すかのように叫んだ。
「これで今日のメニューは終了です。おつかれさまでした。」
私の目からは何故か涙が溢れていた。感動で今にも胸が張り裂けそうになっていたのかもしれない。
これからも頑張っていきたい。この時私は、そう思わせてくれた大谷さんへの感謝の思いでいっぱいだった。
***
いくつかのページを読み終えた時、彼女の唇からは自然と笑みが零れていた。
彼女はその忘れ物のノートを閉じ、由香利のロッカーに返してあげるべく仮眠室を後にした。
「ふふ…まだまだ指導が必要みたいね。」
そう小声で呟いた彼女は、瀬川凛その人であった。
一冊のノートに綴られた拷問の記録。無邪気さこそが本当の恐怖。
夜になっても署内は慌しかった。
夜勤との引き継ぎが終わってもなお、日勤の人間が残務に励んでいる。彼女もまた、そんな忙しい人間の一人であった。疲れのせいもあろうか、彼女からは溜息が絶えない。
事務処理が一段落ついた頃、彼女は休憩を兼ねて座席を離れると、仮眠室に向かった。
仮眠室は署内の騒がしい様子とは打って変わった静けさを漂わせている。
堅いベッドの脇には一冊のノートが置かれていた。彼女はそのノートに手を伸ばす。
五百ページはあろうかという分厚いノートの表紙には、大きく『由香利ノート』と記されている。
表ページの見開きに大きく書かれた文字。
『正当拷問自白法 違反者記録』
新法案、正当拷問自白法成立から早二年が過ぎようとしている。
連日のように起こる凶悪犯罪件数は未だ衰えるところを知らない。しかしそれとは裏腹にその自白率は年々右肩上がりの良傾向を見せている。
彼女は複雑な思いを胸にノートを開いた。そこには丁寧な文字で仕事の記録が残っている。二年分の文字の量は膨大だ。
最初のページには由香利の思いが切々と込められていた。
今日から仕事が始まった。なかなか就職先が見つからなかった私にとっては、願ってもない話だった。
全ての悪人がこの世からいなくなったら、どんなに幸せな世界ができるんだろう。
生きてる間に悪人に地獄を見せてやれたら、相手の気持ちが少しは分かるんじゃないか。
そんな風に考えていた私にとって、この仕事はまさに天職であるかのような思いがした。
正義の処刑人として働くことができるようになれて、私は今心底幸せを感じている。
正当な拷問を受けても自白しないような悪人は…私がこの手で処刑してあげる。
彼女はおもむろにパラパラとページをめくっていった。
***
受刑者番号五十番 横山菅生 二十三歳
彼は強盗殺人の罪を最後まで否認し続けた。正当拷問に対しても反抗的な態度だったため、自白法違反で拷問刑が確定した。
私はタンクトップにデニムスカートを履いた服装で拷問部屋に入る。罪人との初対面であるこの瞬間はいつも緊張する。私は中にいるその人物の様子を観察した。
今時の若者って感じですごくイキがいい。彼は法律違反者となって今日が初めての拷問の日だった。
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
私は形式的な挨拶をする。彼は私を見るといきなり私の胸を触ろうとしてきた。
「俺に気持ちいいことしてくれるのかな。」
…ずいぶんと笑わせてくれる…
私は笑顔のままその腕を捻り上げ、背中の後ろで固定する。彼は苦痛の声を上げて抵抗をやめた。
「い…いだだ…くあっ…」
「ふふ…変な抵抗しちゃ駄目ですよ…」
そのまま背後に回りこみ、もう片方の腕で首を絞める。声帯を絞められたことで声が出せなくなっている。
私は抵抗をやめた彼をそのまま仰向けに倒し、首を絞めたままお腹を思いきり殴り続けた。
「ごほおっ!…ご…ごめんなさ…いぐっ…げほおっ!…」
こういう男性はとにかく芯が脆い。ちょっと本気出すとすぐこれだから…。
私はつい感情的になり、そのまま彼が泡を吹くまでやってしまった。
ここからが私の仕事。
「今日のメニューは股裂きと片側の睾丸潰しです。」
私は既にぐったりと倒れ込んだ彼にそう告げる。
彼は私の言葉を冗談だと思ったのか、半信半疑の面持ちで不安そうに私を見つめる。
無理もないか…今日は彼にとっての『初体験』だもんね…「お…おいおい…ちょ…待ってくれ。まさか本気でやるわけじゃないんだろ?」
彼は脂汗を垂らしながら私を見つめる。その怯えた表情に、私は若干のエクスタシーを覚えた。
…ふふ…本気じゃなかったらこんなところに来ないでしょ…
私は心の中で笑った。心の奥底が急激に冷えていく感覚が私を覆う。
無表情のまま備え付けの手枷を手際よく彼の両腕に付け、磔台の低い位置に固定する。
腰を床につけたままの姿勢でいる彼の足を持ち、限界まで股を開かせる。彼は悲痛の声を上げた。
そのままの形で部屋の両脇についているリングと彼の両足をチェーンで繋ぐ。
片方のリングには車輪がついていた。事態を察知した彼は予想通り悲鳴を上げる。
「や…やめてくれ!…たのむ…やめて…」
「それじゃいきますね。声はいくら出しても大丈夫ですからね。」
優しく彼にそう告げる。それから私はリングの車輪を少しずつ少しずつ巻いていくのだ。
ギリギリと音を立て、彼の股がどんどんと開かれていく。この瞬間が本当に楽しい。
「ぎいいっやああああああ!!た…助けて!!…助けて!!」
「はい、痛いですねー。これからもっともっと痛くなりますからねー。」
私はさらに車輪を巻く。だんだんと車輪が重くなってくる。私はそれに合わせて力いっぱい車輪を回さなければならないのだ。これが結構な重労働。
「ぐが…あ…あああああああああああああ!!!」
絶叫が部屋の中いっぱいにこだまする。私の力が限界に達した頃、彼の股関節が音を立てて外れた。
彼は絶叫し、気を失った。私は一息つくと、彼の裂けた股の間から垂れ下がっている睾丸を強く握りしめ、強制的に意識を取り戻させる。
「ぎゃあっ!!…はぁ…はぁ…いいいいいい…痛い…痛い…ごめんなさい。助けて…」
泣きながら訴える彼の姿がとても可愛らしく感じた。
「今日のメニューはあと一つで終わりです。もう少しですからね。」
私はまた優しくそう答える。
「ま…待ってくれ…あと一つって…だってそれは…たのむから!それだけは!」
この部屋は最新の技術が駆使してあり、防音は完璧だ。こんなに叫ぶんだから当然必要なシステムだよね。
ただ…近くにいる私はすごく耳が痛くなる。最初にメニューを伝えてあるんだからその瞬間になってそんなに叫ばなくたっていいのに…。
彼は狂ったように身体を捩り、必死でもがいている。しかし完全に身体を固定されているため、それは無駄な足掻きにしかなっていない。
私は彼のズボンのチャックの中から睾丸を引き出す。
「それじゃ、いきますね。」
「や…やめて…やめ…やめーーー!!!」
私は片方の睾丸の皮膚を持って床に押し付けた。片方の足で皮膚を押さえつけ、もう片方の足を振り上げる。
……!!!!!…
私は彼の睾丸を足で力いっぱい踏み潰すと、亀頭から血が噴出してくるのを確認した。彼の断末魔の声が響き渡る。
今日の仕事はこれで終了。再び気を失った彼を見つめながら私はほっと肩を撫で下ろした。
明日もまた仕事だ。頑張らなくちゃ!
受刑者番号七十九番 定岡直人 三十五歳
この緊張感からいつかは解放されるのだろうか。
まだまだ仕事に対する不安は大きいけど、しっかりと頑張っていこうと思う。
彼はお年寄りの家に次々と放火してまわった、いわゆる愉快犯。彼もやっぱり容疑を否認し続けて自白法違反となった人だ。
許せない…。罪もない、しかも…か弱いお年寄りだけを狙うなんて…
だからと言うわけじゃないけど、処刑メニューはしっかりとこなそうとあらためて心に誓った。
今日はキャミソールにフリルのついたミニスカート。これらの服は買ったばかりなので私のお気に入りだ。気を引き締めて拷問部屋に入る。
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
彼の第一印象は、暗く、疲れ果てた老人のようで、とても三十五には見えなかった。
入所してから何日も経っていたためか、ずいぶんと元気がなかったように思う。
「最初は身体全体への刺針です。」
彼は諦めきった様子で、指示に対しては大きなリアクションをしない。
「はい…」
叫び声を上げるのが得意な罪人はすごく多いけど、彼は驚くほど無抵抗だった。
ここでのやり方を既に理解し、無駄な抵抗をしないようにしているのかもしれない。
もっともその方が私は仕事がしやすくてとても助かるのだけれど。
自らベッドに横たわった彼の身体中に、16Gの針を一つ一つ刺していく。
胸、腕、顔、腿、そして陰茎。至る所に穴を開けていく。刺し傷から血が滴る。
彼は俯きながら一生懸命耐えていた。
「次は鞭打ちです。」
「はい。」
私は皮製の乗馬鞭で、ついたばかりの傷跡が目立つその身体全体に鞭を振り下ろしていく。
「ぐ…あぁっ…がああああ…」
彼は声を押し殺しながら必死で耐える。その姿が私を高揚させる。これは私の悪い癖だ。
私は、男が苦痛に耐える姿に言い知れぬ興奮を覚えることを既に自覚していた。
ついつい鞭を持つ手に力が入る。
「ほら。痛いですね。ふふ…一生懸命我慢してるんですね。たくさん痛めつけてあげますからね。」
何度も…何度も…何度も…何度も…
私は自分の欲望の赴くままに鞭を振り下ろす。自制が効かなくなっていく自分が少し怖かった。
さすが、年の功といった感じだった。本当に我慢強い。その強さが私の感情をさらに高ぶらせていくことに、私自身この時は気付いていなかったのかもしれない。
「…処刑人さん…ちょっと、いいですか。」
鞭打ちを終わらせた頃、彼が私に話しかけてきた。
「あの…普段はメニューを先に教えてもらっていたはずです。方針が変わったのでしょうか。」
…あ…しまった…
うっかりしていた。最初にメニューを告げるのは処刑人マニュアルの基本であった。
私自身これまでしっかりと行ってきたことであったはずだが、この時はすっかり忘れてしまっていた。
「申し訳ありませんでした。最初にお伝えするところを…」
「いえ…」
私は慌てて最後のメニューを彼に告げた。しかしその途端、彼の態度が豹変した。
これまでの落ち着いた雰囲気とはうってかわり、明らかに取り乱した様子を見せた。
その姿に驚いた反面、何故か私は彼に親しみを感じたような気がした。
「ほ…本当にか…本当にそれが…。あ…あ…やめ…やめて…」
人間同士の心と心が触れ合う時…それはお互いが素の自分を曝け出した時なのかもしれない…
そんな思いがふと私の頭を過った。相手が憎むべき違反者であることも忘れ、私は彼に魅かれる自分を感じた。
「最後の仕上げ…精一杯行わせていただきますね。」
それは私の心からの言葉だった。しっかりと真心をもって最後の作業を行わなければ失礼だ。そんな風に考えていた。
「た…頼むーーー!それだけは…それだけは勘弁してくれ!!お願いしますーー!!」
私は彼に微笑むと抵抗する彼の首を絞めて気絶させた。変形型の拘束具を着せてベッドに縛り付けて固定する。
彼の左の手首から上だけが剥き出しになり、残りの全てが拘束具で包まれている。
しばらくすると彼は目覚めた。目は大きく見開かれ、彼は恐怖のためか絶叫をあげ続けた。
「やめてくれーー!!助けてくれーーー!!」
「これが最後のメニューです。」
彼の親指にナイフを突きつける。彼の息を呑む音が耳元で大きく聞こえる。
私は片手で彼の手をしっかりと押さえつけると、反対の手で力いっぱいナイフを叩きつけ、親指を切断した。
「ぎぃやあああああああああああああ!!!」
絶叫が部屋全体に響き渡る。そして彼は失禁し、気絶した。
…ちょっとだけかっこよく感じちゃった。私って駄目な女。相手は法律違反者なのに…
とにかく、今日の仕事も完了。
私は今まで以上に、この仕事が楽しいと思えるようになってきている。
今日は私の担当する処刑業務はなかった。その代わりに、別室でトレーニングを行うことになった。
私を指導してくださったのは瀬川凛先輩だ。スレンダーな美しい肢体。
訓練のことなんて忘れて、その身体にしばらく見惚れてしまっていた。互いに向き合い、素手でぶつかり合う。凛先輩との格闘は私にとって幸せそのものだ。
殴りかかる私の腕を掴み、鮮やかに身体を腕の下にくぐらせる。
私は身体を倒され、腕拉ぎをかけられた。完全に関節を決められている。
う…くうう…
「ふふ…まだまだ指導が必要ね…」
…かっこいい…
胸の高鳴りが治まらなかった。先輩の姿が未だに目に焼きついて離れない。
いつかは私も先輩のようにかっこいい人間になりたい。
「ねぇ、あなたはどうしてこの仕事に就こうと思ったの?」
凛先輩が私に問いかける。トレーニングを終えたばかりの私は倒れ込み、身体を起こすこともできない。天井を見上げながら私は答えた。
「悪人をこの世から全て消したいんです。」
息を荒げながら答える私の顔を凛先輩はそっと覗き込み、微笑を浮かべていた。
「そう…。これからのトレーニングもしばらく私が付き合うから。そのつもりでいなさいね。」
笑顔のまま私のおでこに軽くキスをする。
彼女の言葉やその行為の意味は、正直なところ私にはまだ分からない。でも、憧れの凛先輩からこれから先も指導していただけるのだと思うと、私の胸はさらに大きく高鳴った。
「先輩…」
私はかろうじて身体を起こして凛先輩の方に向き直った。彼女は既に汗を拭うとその場でスーツに着替え始めていた。その後ろ姿に再び私は見惚れてしまい、背中の汗を拭う先輩から目が離せなくなっていた。
「執行人としての誇りと自覚をもって、これからも頑張っていきます。」
その言葉を聞いた私の憧れの人は涼やかな笑顔を見せ、優しく私に言葉をかけた。
「ふふ…頑張ってね。」
受刑者番号百十一番 光村隆介 二十九歳
思えばたくさんの人を処刑してきた。
どうして犯罪は無くならないんだろう。どうしてきちんと自白しないんだろう。
私にはどうしても理解することができなかった。
彼は一家全員を皆殺しにした凶悪犯だ。絶対に許すことはできない。
先日デパートで購入したばかりのチュニックにスキニージーンズ姿で部屋に入る。ネイルサロンで塗ってもらったばかりの爪が私の気分をわくわくさせる。
私が部屋に入るなり、男は喚いた。
「頼むよ!頼むから!俺をここから出してくれ、な?お願いだ。」
どうしてここに来る人たちは皆、こんな感じなんだろう。結局は自分で選んで来た道でしょ?
私は彼の言葉に反応することなく、言葉を発した。
「担当の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
「頼む!もう許してくれ!頼む!俺は本当に、何もしてないんだから。」
…さっきからくだらないことばかり言ってる…
私は言葉を続けた。
「今日のメニューは、左手全指骨折と内臓損傷です。」
男は私の言葉など聞いている様子はなかった。
「た…助けてくれ…助けてください…」
こういう受刑者には、まず自分の置かれている立場をしっかりと理解してもらわなければいけない。
私は黙って男に近付くと、その首を掴んで床に勢いよく倒した。
「抵抗は無意味です。刑はしっかりと受けていただきます。それが、あなたの務めですよ。」
にっこりと微笑みながら語りかける私の目を見て、男は涙を溢れさせた。
彼はぐったりと脱力し、肩に全く力が入らなくなっているようだった。
迅速にその腕を取り、股の間に挟みこむと相手と一緒に倒れ込んだ。腕拉ぎをかける。
男はそれでもなお絶叫を上げ、じたばたと抵抗しようとする。
「では、一つ目のメニューです。」
私は関節を決めた左腕をがっちりと固めたまま、彼の手をそっと握る。
そして彼の指を小指から順番に、関節とは逆の方向に折り曲げて一本一本丁寧に折っていった。
「ぐあああああ!!ぎぃやいやあああああ!!うっぐあああああああ!!!」
骨折と同時に彼の絶叫が小部屋に大きく響き渡る。既に彼の喉は枯れ果て、かすれた、声にならない声がその部屋全体を覆い尽くしていた。
左手の全ての指の機能を奪われた彼は、完全に生気を失っていた。その目に光はなく、ただただ小刻みにその身体を震わせながら小さく身体を丸めていた。
「今日のメニューは次で最後になります。頑張ってくださいね。」
私の言葉に、彼はまたも返答しようとはしなかった。虚ろな目をしながら、うわ言のように同じ言葉を繰り返しながら天井を見つめていた。
「た…す…け……助けて…助けて…。俺はやってない…やってない…。」
この人は本当に同じ言葉しか言わない。私はその姿が何となく滑稽に思え、笑いが込み上げてきてしまっていた。
ぼうっと立ち尽くす彼をしばらくじっと見つめ、それから私は勢いよく彼に向かって走った。
…!!…
渾身の力を込めたボディブローを彼のお腹に叩きつける。
その瞬間彼は我に返ったのか、目を大きく見開き、頬を膨らませた。強制的にその瞳に光が戻される。
「うぐううえええええっ!!!」
彼はお腹を抱えて蹲った。必死で押さえるその手を引き剥がすようにしながら、私はなおもボディブローを彼に何度も突き刺していった。
「はううっ!おえええっ!!げほおおお!!」
拳を叩きつける度にまた搾り出すように声を上げる。私は彼に馬乗りになり、さらに何度もパンチを入れる。
「げえっ!もう…くるし…く…がはあああ!!うぐはあああ!!」
私はその後立ち上がると、今度はそのお腹を踏みつけた。徐々に体重を乗せていく。
「う…お…おおぉぉ…」
力を緩め、そしてまた体重を乗せることを繰り返す。彼は顔を真っ赤にして苦しみに耐えている。
しばらく踏みつけを行うと、彼は脱力して動かなくなった。
私はその無防備になったお腹に全体重をかけてニードロップをした。
「ぐうえあああああああああ!!げおおおお…お…」
絶叫とともに彼は悶絶し、やがて嘔吐した。顔面は蒼白になり、すでに半分白目をむいていた。
変な感じ…やっぱり、何となくだけど…
私は男を甚振る度に高揚していく自分の気持ちに少しずつ気付いていた。不思議な感覚…
お腹を抱えて蹲る彼を蹴り上げ、再び身体を仰向けにさせると、そのお腹を力いっぱい踏みつけた。ぐりぐりと踏みにじる。
私は自分の行為にまた言いようもないエクスタシーを感じていた。
しばらく弄んだ後、再びお腹を思いきり踏みつける。何度も…何度も…
その度に男は苦悶の声を上げ、心地よい悲鳴を上げる。
「げほぉぉぉ!…う…うぇ…うげぇ…がはああああ!!!」
とうとう彼は白目を向き、ぐったりとしたまま口から血を噴き出した。床が彼の血で染まる。
彼はかろうじて呼吸をしているようだった。私はその姿を見ながら必死で笑いを堪えていた。
「今日のメニューは終了です。おつかれさまでした。」
虫の息で倒れ込んだ彼を担いでベッドに寝かせる。私はいつものように救護担当にコールした。
今日の仕事も無事終了。
私は毎日楽しく仕事を頑張っている。
これまでたくさんの人を処刑してきたけど、やっぱり一番緊張したのは最初の仕事の時だったと思う。あの人の名前は今でも忘れない。
大谷悟さん二十七歳。
今考えると、あの日は私にとってすごく重要な意味をもつ日だったんだと思う。
何と言っても、初任務でいきなり新法案「正当拷問自白法」の違反一件目の人の担当に当たったんだから。
気を引き締めていかなくちゃ!ってドキドキしてた。
…任務前にサインもらっておけばよかった…なんて後で思ったりもした。
『俺は八人の女を強姦した後、殺したんだ!』ってしきりに叫んでたのを覚えてる。
だったらどうして自白しなかったんだろう?
それがすごく不思議…。
極刑を免れてよかったじゃない。結果的に拷問刑を選択したのは自分自身なのにね…
***
彼女は、そこで一度ノートを置いた。
仕事の疲れからか眠気がピークに達してきている。
少しでも身体をほぐそうと片方の手で肩や腰を叩き、ぐっと背伸びをした。
床に寝転んだまま、しばしぼうっと天井を見上げる。
その瞳には、どこか悲しげな表情が見て取れた。
彼女はふと、思いついたかのように受刑者記録の最初のページを開いた。
受刑者番号一番 大谷悟 二十七歳
「今日のメニューは爪剥ぎと抜歯、それから右腕の骨折です。担当刑事の後藤由香利です。よろしくお願いします。」
婦警のかっちりとした制服に身を包んだ私は、内心の緊張を抑えながら告げた。
怯えきった様子の彼は私が挨拶をするなり突然叫び出した。
「お…俺は八人の女を強姦して殺したんだよ!死刑にしてくれ!死刑にしてくれ!!」
「そうですよね、分かってますよ。ただ大谷さんの刑は死刑じゃなくて拷問刑なんです。今日は私が担当させていただきますので、よろしくお願いしますね。」
「い…嫌だ!俺は…」
私は言葉を待たずに彼に跳びかかり、首を掴んで壁に押しつけた。苦しそうな声が喉から漏れる。
「ちょっと静かにしてもらいますね。すぐに終わりますから。」
笑顔でそう告げると私は彼の鳩尾を拳で一突きして気絶させた。押さえつけていた手を離し、床に寝かせる。
用意していたペンチで慎重に彼の小指の爪を掴む。私は力いっぱい彼の爪を引き抜いた。
あっと言う間に血が滲む。彼は痛みのあまり意識を取り戻し、同時に絶叫をあげた。
「ぎやああああああああ!痛い!!があああああああああ!!」
彼の目に涙が浮かぶ。
「やめて…やめ…」
私の側を離れ、彼は壁にもたれかかるようにして縮こまった。その姿が不思議と私を魅了する。
…可愛い…
それが私の正直な感想だった。小さく身体を丸めながら許しを乞う姿がこんなに可愛らしいなんて…。
私はついその姿がもっと見たくなってしまった。
もっともっと可愛らしいあなたを…見せて…
口元が緩んでしまう。笑顔のまま私は彼に一歩一歩近付く。
「ひぃぃぃ…」
怯える様子を見て、私は意気を高める。
「サービスしてあげましょうか…。全部抜いちゃってもいいんですよ…ふふふ…」
彼はその言葉に大きく反応すると、再び気を失った。
私は彼の反対の手の小指を掴むと、再度その爪を引き抜いた。彼はまた意識を取り戻し、絶叫した。
「ぐあああああああああああああ!!!ああああああああああああ!!!」
ついついサービスで三つも抜いてあげてしまった。そろそろ抜歯に移らないとね…
最初の仕事であると同時に、その相手が正当拷問自白法成立以来初めての違反者だったということもあり、正直最初は緊張して仕方がなかった。
しかし彼に刑を執行しているうちに、私は確実にこの仕事を楽しく思えてきていた。
こんなに楽しいなら、これから先もやっていけると思う。
私は彼の顔をじっと見つめた。彼が弱い小動物のように見えた。
身体をぶるぶる震わせながら小さくなっていた。
彼の取調べを担当した凛先輩は、『強情を絵に描いたような人だった』って言ってたけど…正直、全く印象が違っていた。
今の彼は…ただ怯えるだけの小動物。絶対的な力に服従するだけの…ふふ…
私は可笑しくて仕方がなかった。今にも笑い出しそうになるのを堪えながら、私は彼に堂々と近付いた。
「お…お願いします…もう…もう…」
私は彼の顎を指先で優しく撫でた。こんなにも愛しさを感じるなんて思ってもみなかった。
許し難い大犯罪者…それなのに…
私は彼の口を片手で掴み、無理矢理口を開けさせた。無抵抗な彼の前歯をペンチでゆっくりと挟み込む。
「は…や…や…」
我慢できずに彼の頭を撫でる。身体を摺り寄せる。
…この感動をいつまでも覚えていたい…
そんな思いを胸に私は彼の前歯を勢いよく引き抜いた。涙目の彼の口から血が溢れ出す。
「がああああああああああああああああ!!!!」
ふふ…よく叫ぶ人…
すかさず私は彼の背後に回り、右腕を捻りあげる。
彼には既に抵抗する意志はない様子だった。泣きながら何かを呟いている。
私はそんな彼を目に焼き付けるように見ながら、その関節を痛打した。骨が折れる感触が伝わってくる。
「ぐうあああああああああああ!!ああああああああああああ!!」
彼は声を搾り出すかのように叫んだ。
「これで今日のメニューは終了です。おつかれさまでした。」
私の目からは何故か涙が溢れていた。感動で今にも胸が張り裂けそうになっていたのかもしれない。
これからも頑張っていきたい。この時私は、そう思わせてくれた大谷さんへの感謝の思いでいっぱいだった。
***
いくつかのページを読み終えた時、彼女の唇からは自然と笑みが零れていた。
彼女はその忘れ物のノートを閉じ、由香利のロッカーに返してあげるべく仮眠室を後にした。
「ふふ…まだまだ指導が必要みたいね。」
そう小声で呟いた彼女は、瀬川凛その人であった。
五:「正当拷問自白法」
合法の名の下に施される執拗な拷問。女刑事と凶悪殺人犯の根比べの行方は……
新法案を巡り、国会では連日、与野党間の激しい攻防が行われていた。
「大臣はこの法案についていったいどうお考えなんでしょうか?」
「『目には目を、歯には歯を』――ハムラビ法典を知らないわけではありますまい。現代は猟奇殺人や愉快犯、放火など実に嘆かわしい事件が相次ぐ時代となってしまっているのです。この時代を立て直すには、もはや古代に学ぶより他はありません」
「この法案が現代にどのような影響を与えるのか。この法案を成立させることによるメリットをお聞かせいただきたいのです」
「犯罪者による、自白率の増加ですよ」
「新法案『正当拷問自白法』与野党合意の上、成立」
新聞の一面に大きく記事が載っていた。諦めかけてはいたが、それでも俺は少しの希望をもってこの議論を見つめてきた。が、結果は可決。
現実にこの法案が成立してしまったことは大きな問題だ。
なぜなら俺は、犯罪者だから。
事実は、紙切れ一枚で決まる。だったら俺が、黙秘を突き通せばいい。自信は十分あった。
この法案が可決するまでは……
俺が警察に目を付けられるのに、それほど時間はかからなかった。
世間で言うところの凶悪犯罪だ。証拠の全てを隠滅することなんて到底無理だった。だが……、だが俺は、絶対に逃げ延びてみせる。
連れて来られたのは、警察署の取調室だった。
ここの構造は、刑事もののドラマなどで見るものとさほど変わらない。ドラマの演出もなまじっか嘘ではないのだと感じる。制作者側の人間もきちんと取材しているのだろう。装飾の一つもなければ、面白い置物すら置いてない。全くもってそっけない部屋だ。机が一つ置いてあり、俺と刑事は向かい合って座らされる。
刑事は表情が読み取られないよう、そして、刑事が容疑者の少しの表情の変化も読み取ることができるよう、容疑者の顔を照らすライトや窓の位置の工夫がしてあるらしい、と、どこかで聞いたのを思い出した。
「もう調べはついてるんだよ、大谷さん」
取調室には刑事が二人。俺と向かい合ったその「黒いほう」が俺に話を切り出した。体格はレスラーのようであり、見ているだけで暑苦しい。
もう一人の刑事は窓際に立って遠くを見つめ、何やら黄昏ている。そちらの「白いほう」は、肌だけでなく髪も白い。定年間際の刑事といった感じだ。だが見た目とは裏腹に、目の前で怒鳴るこいつよりも幾分貫禄が感じられる。
「女八人か。ハッ……しっかし、ようこんなにもやったなぁ。惨いこっちゃ」
色黒は容疑者である俺に対して、まるで犯人扱いだ。まぁ、それに間違いがないことは、俺自身がよく分かっているんだが。
「これ以上シラを切るようであれば、致し方ありませんかな……」
それまで口を閉ざして黄昏ていたもう一人の刑事が、静かに口を開く。
――来たか。
予想通りの結果に、俺は驚きもしなかった。なぜなら、ここからが俺の勝負……
政府の確立したクソ法案、『正当拷問自白法』との対決なのだから。
連れてこられたのは、窓一つ無い小部屋だった。
いや、小部屋という洒落た名前をやるにはあまりにも役者不足か。壁はコンクリート丸出しで、テーブル一つ無い。
俺たちの人権はいったいどうなってるんだ? 弁護士を雇う権利くらいあって当然だろうに。全く、嫌な世の中になったもんだ。
そんなことを考えながら、狭い部屋の隅々を探るように見回す。その時、ひとりの人物が俺の前に姿を現した。
――お……、女?
驚いたことに、そこに現れたのは、こんな薄汚く狭い部屋とは到底不似合いな美しい女だった。ノースリーブ一枚の上半身。デニムのスカートに短めのブーツ。
露出度の高い服装を纏ったその女に、俺は思わず性欲を掻き立てられる。
俺は驚きの反面、期待の外れた嬉しさからその美しい女を舐めるように見回した。
「あんた、来るとこ間違ってねーか? それとも、お姉ちゃまがボクを自白させてくだちゃるんでちょうか?」
俺はふざけて笑い飛ばした。可笑しくて仕方がなかった。
容疑者を拷問にかけることを許容し、自白を促す政府のクソ新法案。表向きはどうあれ、犯罪を防ぐための見せしめ法案に間違いはないだろう。俺は腹を括り、この法案に対してどう対決するか、これまで考えてきた。
絶対に、服従などしない。
この間違った政治に警鐘を鳴らすとかそんな格好いいものではない。ただ俺のプライドが、決してそのような悪法に屈することを許さなかっただけのこと。それが――、それが?
俺は再び笑った。馬鹿馬鹿しくて仕方がなかったのだ。
女は依然、俺の方を見ながら真顔でじっと俺を見つめていた。そして次の瞬間――
「……っ!」
俺の視線は強制的に上へ向けられた。
どうやら、彼女が繰り出したアッパーカットが俺の顎にジャストミートし、俺は宙に浮かんでいた。――ようだ。
――ば、馬鹿な……、そんな……?
きっと今の俺は素っ頓狂な表情をしているのだろう。無理もない。突如現れたか細い女に突然パンチを喰らわされた挙句、こうして仰向けになって無様な姿を晒しているのだから。
女は黙ったまま真顔で俺をまっすぐに見つめている。
「……へっ、愛想、笑いの、一つもなしに……いきなりこれかよ」
俺のふざけた態度を見ても、彼女の姿勢は変わらない。
「申し遅れました。担当の瀬川凛です。よろしくお願いします」
眉一つ動かすことなく、形式的な挨拶をする。
「ふん。っ……、気の強え姉ちゃんだな」
俺は、内心どうしたものかと考えを巡らせていた。予想はしていたが、油断しすぎたようだ。ただの女を間違えてこんなところに連れて来た、なんてことになれば、笑い話の一つにもなりはしない。露出の多い服装は、おそらく動きやすさ重視。決しておふざけではないのだ。
このまま黙ってこんなのを受け続けたら身がもたない。
絶対に服従しない。それが俺の最大の目標なのだ。
……どう出て来る?
目の前の女を注視しながら身構える。
さっき受けた一撃でこの女が只者でないことが分からないほど、俺も馬鹿ではない。俺から目線を外さず、なおも微動だにひとつしない女。
「言っておくが……、俺は強えぜ。甘く見てると、寝首をかかれることになるかもな」
この挑発が果たしてどういう結果をもたらすか。神経を張り詰める。
次の瞬間、女の身体がふっと横に揺れた。
――来る!!
俺は構えを解かぬまま、目だけで女を追う。
――右か!!
予想は的中した。しかし――
ガードをしようと右腕を上げた隙を突き、がら空きになった鳩尾めがけて彼女の蹴りが鋭く突き刺さった。
「が……、く、っはっ!」
俺はたまらず蹲る。女はすかさず、続けざまに俺の背中に踵落としを見舞う。
「ぐがああああ!!」
俺はその場に突っ伏し、それでも目線を女から逸らさないように、キッと睨みを効かせていた。
「こ、これが新しいクソ法案の結果かよ。これが、正しい方法なのかよ……。お前は、政府の飼い犬か? 奴隷か? あ? 答えてみろよ」
女は挑発に乗ることなく、依然として黙って俺を見つめているだけだ。
「この……アマが!」
高ぶる感情で、俺は自制が効かなくなっていた。気が付くと俺は、女に向かって頭から体ごと跳びかかっていた。ドスンという鈍い音が響き、俺と女は絡みつきながら地面に倒れ込んだ。すかさず俺は、精一杯の力を込めて女に馬乗りになる。
「はっ、っははははは!」
俺は笑った。こうなったら、この雌をめちゃくちゃに痛めつけてやる! 俺は八人も殺した大犯罪者だ。罪を認めてしまったら死刑は確実なんだ。絶対自白はしない。この場を、絶対切り抜けてみせる!
俺は馬乗りのまま、女の顔面を力一杯殴りつけた。女は鋭い目で俺を睨みつけている。
「お前も、あの女たちと同……」
途中で言葉を切る。進んで自らの立場を悪くする必要はない。俺のこの行為の理由はただ一つ。そう、正当防衛だ。俺はまだ容疑者だ。自衛権があるはずだ。
自分自身を納得させると同時に、俺はさらに何度も女の顔を殴りつけていく。もう一発、もう一発――
その時、女は腰を力強く突き上げた。その衝撃で俺はバランスを崩し、前のめりに倒れ込む。
あっという間の出来事だった。
女はそのまま身をよじり、するりと俺の左腕を取ると、すぐさま腕拉ぎをかけてきた。あまりに滑らかな動きに、俺は何も抵抗することができなかった。女が絞め付けを強くする。
「が、あああああ!!」
突然、小部屋の戸が徐に開き、さっき俺を取り調べた刑事二人が入ってきた。
「おうおう。瀬川刑事、派手にやっとるなぁ。ほな、ちょっと手伝いましょか」
色黒のレスラー刑事が、楽しそうにもう一人に話しかける。
「ふむ、そうだな。このお方は、なかなか強情なようだ」
色白の貫禄ジジイがそう答えると、二人は俺を女から引き剥がし、互いに俺の右腕、左腕をそれぞれ押さえ込み、壁に押し付けた。
「な、何の真似だ?」
女は口から一筋の血を流し、なおも俺を睨みつけている。その口元には、少しだけ笑みがこぼれているようにも見えた。
刑事達に押さえつけられ、身動きが取れず、訳も分からないまま、俺はしばしそこに立ち尽くす。見かけによらず、この二人は力がある。
――腐っても刑事だな。……微塵も動けねえ。
そんな俺の目の前に、女が立ちはだかる。一瞬、背筋が凍りつくような感覚を覚えた。
――まさかな? 国家権力の名の下で、そんなこと。
「お、おいおい。何をしようが、俺は無実なんだよ! 俺からは何も聴き出せやしない。早いとこその手を離せよ」
俺は自分の心境を隠そうと、刑事二人に啖呵を切った。
「おやおや、これは威勢のいい」
「ふざけやがってこのガキが! その空元気がいつまでもつか楽しみだな」
刑事二人が、俺の言葉に反応する。それから、貫禄ジジイの方が女に命じた。
「では、瀬川刑事。やってしまってください。くれぐれも、殺してしまわないように」
――やってしまって? 殺し……? おいおい、マジで何言ってんだよ。こいつら正気か?
女は、じわじわと俺との距離を縮めてくる。
「おい……冗談だろ? なぁ?」
しかし女は眉一つ動かさず、それこそ真剣な眼差しを俺に向ける。額には若干の汗が滲んでいるように見えた。
――冷や汗? まさかな。まさか……、冗談なんかじゃないのか?
俺は恐怖を覚えた。何より、この女の真剣な表情が「本気」であることを物語っているように見えた。女は身動きの取れない俺の腹に向け、強烈なボディブローを入れた。
「うぐうっ!……く」
女が口を開く。
「正直に言ってください。あなたは、串田区内で若い女性計八人を襲った連続殺人犯に間違いありませんね」
若干緊張しているように思えたものの、落ち着いた口調で女はそう話した。俺は一瞬戸惑ったが、すぐに嘘の返事をする。
「だか……ら、……違う、って言ってんだろ。何度言えば……、っ! がはああ!!」
言葉の途中で、さらに女のボディブローが入る。鳩尾を抉るように、拳で内部を捻ってくる。
「正直にお願いします。これ以上、苦しみたいですか?」
「じょ……、冗談じゃねえ。嘘、じゃねえ、って、何度も……、ぐうえええ!!」
「正確に」
「違うっ……、ぐはあああ!!! ち、ちが……っは! ぐうおおお! ぐぶうぅ!!」
容赦ない腹パンチの嵐が俺を襲う。俺は内部の苦しみに、今にも吐き出しそうになっていた。
苦しみが絶頂に達した頃、俺を押さえつけていた二人が女を手で制す。
「はい。とりあえずそこまでで」
貫禄ジジイが、そう女に語りかける。
俺は、ほとんど虫の息だった。しかし、休む暇もなく俺を襲ってくる地獄のような苦しみから一時的にでも解放され、俺は内心ほっとしていた。
「はぁ、っ、はぁ……ごほっ! ごぼおっ!!」
俺は咳き込み、息遣いも荒くなる。継続的に繰り出されてきた女のパンチに跪きそうになりながら、それでもここまで必死で耐えた自分を褒めたかった。だが――
「さて、と。……そろそろ、認める気になりましたか?」
貫禄ジジイが、今にも笑い出しそうな顔で俺の顔を覗き込む。俺はそのジジイの表情に心底腹が立った。
「へっ、馬鹿……言ってんじゃねーよ、この……、クソジジイが」
「貴様! 犯罪者が偉そうな口を叩くんじゃない!」
啖呵を切った俺に、色黒が罵声を浴びせる。
――本音が出やがった。
最初からこいつらは、俺を犯罪者だと決めつけてやがる。その態度がどうしても気に入らなかった。
絶対に口は割らない。それは、既に俺の信念となって、俺自身を包み込んでいた。
当然と言えば当然のこと。
俺に対する拷問は、ここで終わりではなかった。
「仕方がありませんね。では、例のアレ、いきましょうか」
――例の、アレ?
引っかかる言い方だ。俺は内心怯えていた。
しかし、自白を強要するこの方法は、絶対に許すべからざる行為だ。……クソ政府が。その思いが俺を常に支え続けていた。
女が俺に近付く。刑事二人は、先ほどと同じように俺を両脇から支える。
――今度は、何をする気だ?
そんな不安を他所に、女はまた俺に近付く。さきほどよりも、さらに緊張の観を高めているようだ。
――何を?
女は、俺の首に鎖を巻きつけ、喉元で交差させて両手で先端をしっかりと握った。少しずつ、少しずつ……、じわじわと絞め付けられていくのが分かる。
――っ! く、苦し……
俺は、既に声を出すことが出来なくなっていた。
――くそ……このアマ……
しばらくすると、女は力を緩める。
「がはっ!……はぁ……はぁ……」
俺の喉元に詰まっていた二酸化炭素が一気に吐き出され、同時に多量の酸素を欲して自然と呼吸が荒くなる。
「ご、ほっ……、て、てめえ……、はぁ……な、何しやがる!」
俺は、怒りを抑えきることができなかった。そんな俺に、女は真剣な表情で言葉を発する。
「正直に言えば、ここで終わりにします。白状するまでは続けます」
両脇の二人は、そんな俺たちのやり取りを笑みを堪えながら見ている。
――く……どこまで非道なんだ、こいつら。一生、許さねえからな。
「どうしますか? 正直に言いますか? それとも、もっと苦しい思いをしますか?」
女は無機質に、そう俺に問いかける。
「ふざけるな! このクソアマが! 俺は最初から本当のことを言ってるんだよ。白状もなにもあるか!」
落胆した表情を見せ、一時女は肩を落とす。そして、すぐにまた真剣な表情で俺に向き直る。再び、俺の首は女の手で絞め上げられる。さっきよりも多少絞める力が強くなっている。
――苦しい……、くそっ、こいつ……
また力が緩まる。女は俺に問いかける。俺は咳き込みながらシラを切る。再び絞め付けられる。
我慢比べ。
――これは忍耐勝負だ。俺は……絶対負けない!!
しかし俺は、自分の体が次第に衰弱していくのが分かっていた。このままでは埒が明かない。
{ 2007/04/17(火) }
そんな時、色黒がまた馬鹿げたことを言い始めた。
「同時に『男』も責めてやれや。くく、分かるだろ? 金玉だよ、金玉。はははは」
――何言ってるんだこいつ……。マジで、マジで正気か?
今さらだが俺は、こいつは本当に、生理的に受け付けない。汚らしい上にゴツイしオヤジ臭がきつい。それにこの下品な言い方。俺は憎しみから、思わず横にいる色黒に唾を吐きかけていた。
「こいつ! 馬鹿な奴だ! おい、やってほしいってよ。ほら、やれよ! 命令だ!」
女は少し頬を朱に染めながら、それでも命令と聞くと、その視線を鋭くした。
「分かりました。絶対、白状させますから」
そう気丈に応える。
「ちょ……、本気か? ま、待……」
女が、脚を思いきり後ろに引いた。そしてその膝が、俺めがけて飛んできた。
――はぐうっ!!
下半身に衝撃が走る。内臓を揺さぶられるような感覚が俺を襲う。激しい痛みが俺の内部に響いてくる。
「ぐああああああ!!」
痛い。……痛い。
俺は股を閉じて腰を引き、情けない格好で押さえつけられたまま飛び跳ねる。その間にも、女は俺の首を再び絞めあげる。
「ぐ、くう……」
また膝蹴り。
「ぐっ! こ、おおおお……あ」
両手に握った鎖で首を絞めながら、俺の下半身に膝蹴りを何度も叩き込む。その度に俺は苦悶の声を上げ、そしてその声は絞められることで抑えられる。
俺は痛みと苦しみを同時に与えられ、もはや息をするのも困難な状態になっていた。両脇の馬鹿二人は、そんな俺を見てニヤニヤとした気持ち悪い表情を浮かべている。
「こんなこと、いつまで続けるんだ? いくら痛めつけたって、俺からは何も出ない」
俺の必死の叫びには、誰も応えない。しかしその瞬間、俺は感じた。
そう。色黒が腰に装備している、――銃。気持ち悪い表情で、明らかに気を抜いている二人。俺の体もいつかは尽きるだろう。チャンスは今しかないのだ。
俺は渾身の力を両腕に込めて、両脇の二人を目の前に引き合わせた。二人は虚をつかれたためか、意外にあっさりと体をふらつかせ、お互いに頭をぶつける。同時に、俺は女を力いっぱい蹴り飛ばした。女はよろけ、後ろの壁に体を叩き付けた。
「ぐあっ! 何を?」
「こ、この……」
「う……」
ふらつく三人の隙をつき、俺は色黒の腰から素早く銃を引き抜く。少し離れて銃を構え、三人に対峙する。
股間に激痛が走る。俺は腹の中にまで込み上げてくるその痛みに必死で耐えた。
一瞬の油断が命取りになる。俺は固唾を呑んで、三人を凝視し続けた。
刑事二人は突然のことにあっけにとられたのか、しばし無言のままで戸惑っている様子だった。
「き、きき貴様、こんなことして……」
言葉を言いかけた色黒を、ジジイが手で制する。
「大谷さん。暴力はいけません。さぁ、その銃を、とりあえずこちらに。穏便に、ね」
こいつは本当の馬鹿だ。さっきまで暴力でカタをつけようとしてたのはどこのどいつだ。俺はこの刑事二人に対する蔑みの気持ちをいっそう強くした。
――こんなやつら……、殺してやる、殺してやる……
「おいおい。さっきまでの威勢はどうしたんだよ、え? 刑事さんよ!」
俺は躊躇いなく、色黒の右足の太腿を撃ち抜いた。
「ぐあああああああ!!」
色黒の絶叫が心地よく響き渡る。
――くくっ、俺を馬鹿にするからこうなるんだよ。
「お、落ち着け。私たちは、何も君を殺そうとかね、そんなことを考えているわけじゃ……、っ!」
俺は、ジジイの頭を撃ち抜いた。目を大きく見開き、ジジイは絶命した。
――くくくく。
「あ、……ああ、た、助けてくれ……ください。おおお願いです、た……」
俺は薄ら笑いを浮かべながら、銃口を色黒に向けなおし、その胸を撃ち抜いた。
「ふ、ふふふふふふ……、はははははは!」
俺は可笑しくて仕方がなかった。
――俺の報復はきついだろ? ざまーみやがれ。
女は壁に寄りかかり、じっと俺を見つめている。その瞳には光が感じられなかった。目の前で人が二人も殺されたんだ。無理もない。俺は勝利を確信し、銃口を今度は女に向けた。
「最後に言い残したことはあるか? 婦警さんよ」
俺は余裕の笑みで、ゆっくりと女に近付いた。
しかし女は、そんな俺を見つめながら、落ち着いた声で言った。
「殺人および公務執行妨害の現行犯で、あなたを逮捕します」
――ふん、今更何を。これは正当防衛だ。俺はこれからも逃げ延びて見せるからな。
「だったらどうだって言うんだ? お前に俺は捕まえられねーよ」
俺は、ニヤけながら女を見つめる。よく見ると本当にいい女だ。
――できるならこいつもレイプしてやりたいものだがな……くくくくく。
「正直、口実ができて安心しました。これで私もあなたを捕らえるために、本気を出せますからね」
意外にも女には安堵の表情が浮かび、肩の力が抜けたような仕草を見せている。
――こいつ、手加減してたとでも言うつもりなのか? 全く、どいつもこいつも……
「ふん。あんたは、まだ状況が分かってないらしいな」
女は黙って俺の目を見つめている。さっきまでの緊張した感じではなく、むしろリラックスした雰囲気が女から読み取れた。その仕草が俺の癪に障る。
――こいつ……、俺が怖くないのか?
俺は再び銃を握りなおすと、銃口の焦点をしっかりと女に向けた。
「ほら、命乞いしてみろよ。泣き叫んで許しを乞うなら、犯すだけで許してやるからよ」
言葉とは裏腹に、俺のこめかみ辺りから汗が滴ってくる。
――どうしてだ? 女一人に、俺がびびっているとでも?……馬鹿な!
立場は圧倒的に俺が有利。しかし不思議と女から滲み出る自信や威圧感が、俺に言いようもない不安を与えているのも事実だった。
――不快だ。こんな女一人に……、何をしてるんだ俺は。
その不安を振り払いたくて、女の足元に向けて威嚇射撃をしようとする。その時――
「あっ!」
一瞬の出来事だった。女は俺が引き金を引く瞬間に身を屈めて俺との距離を縮め、銃を握った俺の右手を左手でしっかりと握って銃口を上に向けさせていた。放たれた弾丸は宙を舞い、天井に突き刺さっていた。
女は反対の右腕を俺の首に当て、壁との間に俺の首を挟みこんで俺を押さえつけた。こんな状況にも関わらず落ち着いた表情を浮かべ、また俺をじっと見つめている。
――このアマが……くそっ、くそおっ!
俺は状況の変化に焦った。しかし、このチャンスを逃すわけにはいかない。女を何とか押しのけようと渾身の力を入れる。しかし驚いたことに、女の体はびくともしなかった。
――何て馬鹿力なんだ、この女は?
焦りが焦りを呼ぶ。お互いに身動きが取れないまま、相反する力が均衡を保つ。いや……。俺は気付いていた。わずかながら、いや、きっと、相当な力の差があることを。
女は銃を持った俺の腕を捻り上げ、俺の背中の後ろに持っていく。
――銃は、絶対離さない!……ぐ、あああああああ!
鈍い音が、狭い室内に響き渡った。
俺の右腕は、女に捻り上げられたことで折れてしまったのだ。激しい痛みが俺を襲う。
「うわああああああああ!!!」
俺は絶叫した。
今まで体験したことのない痛みだ。痛い。痛い。当然、銃は俺の手を離れ、空しく地面に落ちた。俺は反対の手で女の脇の下から手を入れ、女の首を押し返すように力を入れた。
――何とか、この状況を打開しなくては。
「うぐっ!!」
だが、女は隙を見せなかった。脚を大きく後ろに引き、俺の腹に膝蹴りを入れてきたのだ。俺はたまらず身体をくの字に曲げる。俺の頭が下がった瞬間を見計らい、女は続けて俺の顔面に膝蹴りを入れた。
「がああああっ!!」
弾かれたように俺の身体は宙に舞い、仰向けに倒れ込む。それと同時に女は俺に馬乗りになり、今度は両手で俺の首をしっかりと掴んで絞め始めた。
――く、くそっ。こんなところで……、こんなところで!
「さぁ、白状してください。串田区連続凶悪殺人犯はあなたですね」
こんな状況下でも、こいつは冷静に仕事をしてやがる。くそっ、気にくわねえ!! 絶対に口は割らない、……割らない!
俺は沈黙を守っていた。
――屈したら負けだ。俺は、絶対に逃げ果せてみせる。
「し……しらね、っつってん、だろうが……」
絞められたまま、擦り切れるような声を上げる。しかし女は、そこでまた力を強くする。
俺は、左手で女の顔面に殴りかかった――が、寸でのところでかわされる。そして女は、右手で俺の左腕を押さえる。
「その危ない左腕も、壊しておきましょうか」
冷静な女の口調に寒気を覚えた。
――まさか……まさか……
「ぐ!」
女は俺の手首を掴んで捻り上げ、膝で俺の腕の関節を思いきり強打した。関節とは逆の方向に。俺はもう片方の手の機能も奪われた。またも激しい痛みが俺を襲う。
「ぎゃあああああああああ!!!」
再び絶叫が響き渡る。両手を奪われた俺には、もはや抵抗する余力はなくなってしまった。
「ふぅ……。さ、続けましょうか」
あまりに淡々とした女の言葉。まるで単純作業に取り組んでいるように、残酷な行為を平然と行う。
俺はこの時、この女の底知れぬ恐ろしさを垣間見たような気がした。
俺に馬乗りになったまま、女は俺の首を絞め続ける。
「そろそろ自白してください。私もあなたを殺したくはありませんから」
「ばかな。刑事が、人殺しなんて……」
「分かっていませんね。あなたは刑事二人を殺したんですよ? 私の目の前で。これを本当の正当防衛と言うんです」
俺の目の前には、二体の死体がまだ先ほどと同じ形で転がっている。
――確かに、俺はこの刑事二人を……。いや、それは違う。俺だって、さっきまで拷問を受けていたんだ。俺の方こそ、正当防衛じゃないのか?
そんな俺の考えを見透かしたように、女は続ける。
「刑事による拷問は、今や『合法』なんです。あなたは列記とした殺人犯、公務執行妨害現行犯。それ以外の何者でもありません」
女はさらに絞める力をじわじわと強くしてくる。苦しい……
――畜生。俺たちには、もはや自衛権もないのか。……絶対に間違ってる。こんなやり方、絶対に間違ってる!
仰向けになったまま両足を振り上げ、女の身体を背後から掴もうとする。しかし、女はその度に身をかわし、さらに力強く俺を絞め上げる。
「む、ぐぐ……ぐ」
苦しさから、声もまともに出すことが出来ない。
「足がうっとおしいですね。その足も――」
背筋が凍りついた。
――これは、恐怖心? この俺が? まさかこんな女一人に、恐怖を感じているというのか?
女は力を緩めた。それから女は身体を反対方向に向け、俺の足に目線を落とした。
「ひ……ひっ、ひぃぃ!」
自分でも驚くほどの情けない声が漏れる。
――やめてくれ。もう折るのは……やめてくれ!
女はふり返り、俺の顔を見て笑みを浮かべる。
「怖いんですか? 大谷さん。ふふ、顔が怯えてますよ?」
――っ!……馬鹿にするな! こ、この俺を……。こ、殺してやる!
俺は無我夢中で身体を起こし、女に頭突きを見舞った。一瞬怯んだ女の隙を逃がさず、俺は背後から女に覆いかぶさるように倒れ込んだ。うつ伏せになった女の上に、今度は俺が馬乗りになる形になった。
――くく……。形勢逆転、だ。
俺は半分我を見失っていたのかもしれない。恐怖心がそうさせたのか、それとも別の原因があるのかそれは俺自身にも分からなかった。ただ、俺の中の声がしきりに叫んでいた。
『殺せ! こいつを殺せ!』
俺は馬乗りの体勢のまま、唯一使える足で女の身体を力いっぱい絞めつけた。
「うっ……ぅ……」
女が呻き声を上げる。その声が、持て余していた俺の性欲を結果的に高ぶらせることになった。
「お前を殺してから、たっぷりと犯してやるよ。へへ、すぐに楽にしてやる」
俺は、女の身体をさらに強く絞め上げながら、その上で跳びはねて女を何度も踏みつけた。女は苦しそうにまた声を漏らす。俺は我慢ができなくなり、女の尻に自分のモノを擦りつけた。デニムのミニスカートから覗く白い下着が、俺の欲情をいっそう掻き立てる。
「な、何を――」
戸惑いの声が心地いい。そしてまた女を絞め上げる。女が苦痛の声を上げる。その循環に俺は興奮し、激しくモノを擦りつけながら……、やがて果てた。
――ふふ、お楽しみはこれからだ。
俺は、片足で女の背中を踏みつけたまま立ち上がった。そして、思いきり女の腹に蹴りを入れた。
「ぐふっ!……う、ごほっ!」
「お前もこれから殺してやるよ。めちゃくちゃに暴行してな。はははは!」
「あなた……。こんなことして、ただでは済みませんよ」
心なしか、女の声には余裕が感じられる。それがいっそう、俺の破壊願望に火をつける。
――あの女どもと同じように、お前も、……死姦してやるからな。
心の中で呟きながら、俺は何度も女の腹を蹴り続けた。
「ほら、苦しいだろ? さっきの俺の痛みだよ。くくくく」
女は苦しみながら、しかしどこか余裕の表情で俺を見上げて言った。
「ちょっと、あなたを甘く見すぎていたみたいです。殺されても、文句は言わないでくださいね……」
――ちっ、口の減らない女だ。まあいい。これから存分に甚振って……
「っ!」
華麗な躍動が目前に見えた。女は俺の足の下からするりと身を脱し、俺の両足を自分の両足で挟み込んで力を加えたのだ。俺は意表を突かれ、もんどりうってその場に仰向けに倒れ込んだ。
――し、しまっ……
気付くと女は手に銃を握りしめ、再び俺に馬乗りになり、もう片方の手で俺の首を押さえ込んでいた。
「あなたは私を怒らせました。覚悟は……できていますね……?」
――く、くそ、くそおおっ!
女は俺の方を向いたまま、銃を持った手を後ろに向ける。
「ま、まさ、か。や、やめ……」
地味な銃の音が二発。銃弾は俺の両方の太腿を打ち抜いていた。この世のものとは思えない痛みがまたしても俺を襲う。
「ぎゃあああああああ!!!」
四肢崩壊。
もはや俺は自分で身体を動かすことすら出来なくなっていた。女は俺の太腿に出来た穴に手を突っ込み、ぐりぐりと弄ぶようにそこを甚振る。その度に俺は絶叫し、気付くと俺の喉は枯れ果て、まともな声も出せないほどになっていた。
「もう時間がありません。このままでは、あなたは出血多量でいずれ死亡してしまうでしょう。最後にもう一度、聴きます。串田区連続凶悪殺人犯は、あなたですね」
あまりの痛みに、女の問いかけは耳の奥の方でかすかに聞こえる程度だった。しかし絶対に自白はしない。そう誓ったことは忘れてはいなかった。
――こうなったら、意地を張り通してやるからな。そして……、こんな拷問では何も解決しないことを、世に訴えてやる。そして俺は……無罪放免だ。世間の同情、というおまけつきでな……あぁ、ぐっ!
「事実は、変わらない。俺は……無罪だ」
太腿の痛みは、和らぐことなく俺に襲いかかる。俺は出血のためか、だんだんと意識が朦朧としてきていた。
女は俺の変わらない態度に呆れ果てていた様子だったが、俺への拷問はその後も止むことはなかった。左の腕で俺の喉を押さえ込み、今度は執拗に腹を責め続ける。
「ぐ、え……おえええ! うぐぅ……! は、ぐううっ!……あうぅぅ、……ぐぶぅ!」
内臓に響くほどの強烈なパンチを何度も腹に受け、その度に俺は声にならない声を上げた。鳴り止まないパンチの音が室内に響き渡り、とうとう俺は血の混じったゲロを吐き出した。
「あなたが悪いんですよ。本当に……こんな強情な人、初めてです」
感心だろうか。それとも呆れ返りだろうか。女の言葉は、俺の脳をかすめて消えていった。
腹責めの苦しみは想像をはるかに超え、俺は次第に壊されていく内部の感触を味わわされていた。
「ごほっ……、うええっ! げえええええ!!」
搾り出すように、俺は吐血を繰り返す。破壊された内部の苦しみは俺から戦意そのものを奪っていた。
――もう、抵抗できない……
仰向けに倒れ込んだまま、しばらく天井を見上げる。女は立ち上がり、何やら道具を取り出している様子だった。
――いったい、今度は何を……?
無表情のまま、女は倒れている俺の目の前に立ちはだかり、俺の腹を足で踏みつける。それと同時に凄まじい激痛が再び俺を襲う。
「もう諦めてくださいね。あなたは反抗的すぎました。とても残念です」
そう言うと女は、既に無抵抗を余儀なくされた俺の身包みを全て引き剥がす。俺は羞恥心から自然に身体を縮こめた。その時、女の手にしているものが目の端に映った。警棒だ。しかし、単なる警棒ではないことは遠目にも明らかだった。
そこには有刺鉄線が万遍なく施されていた。世にも恐ろしい武器が、俺の恐怖心を煽る。
「ま、まさか、まさか……、や……」
女の目は据わっていた。俺を直視しながら、その警棒を俺の身体めがけて思いきり振り下ろした。
「ぎぃやぁああああ!!!」
とてつもない痛みに一瞬我を忘れる。しかし女の手は休まることを知らなかった。
頭、肩、腕、腹、腰、太腿、脛。あらゆる部位に凶器が振り下ろされる。心持ち、女の表情に狂気にも似た笑みらしきものが浮かんでいるように見える。痛い! 痛い!!
俺は必死で身体を丸めた。殴打を続けられ、俺の身体のどこからともなく鮮血がほとばしる。
――殺される!
直感的にそう感じた。
倒れた俺の目の前には、死んだ刑事の顔があった。少し開いた目からは、既に光は感じられない。
――死んだら俺も、こいつらと同じような姿に……。嫌だ!! この女には……、この女にはもう、逆らってはいけないんだ。従う……、従う!!
女はそれから俺の身体に再び馬乗りになり、体中を鉄線でチクチクと甚振り、抉り始めた。反対の手で喉元は完全に押さえつけられ、声も出すことができない。
俺はこの時初めて後悔を知った。この女には、逆らってはいけなかったのだ。
「体全体を抉っていきますね。あなたは、どこまで耐え切れるのかしら……。ふふふふ」
身体中のいたるところに有刺鉄線が突き刺さり、俺の皮膚は鉄線に抗うことなく裂けていく。
「ここ、痛いんでしょうね。男性が、一番感じる部分ですものね」
女は、俺の陰部にまで鉄線を近付ける。そして――
「ぐ、ぎぃやああああ! ああああ、がああああ! うああああああ!!」
――待ってくれ、許してくれ! もうやめてくれ! 話す! もう何でも話すから……
そう考えた俺の口からは、もう既に言葉は発せられなかった。出せるのは、叫びだけ。身体の全てが崩壊していく。
俺は、とうとうその場で気を失った。
気付くと俺は独房に入れられていた。
――俺は、どうなったんだ?
体中が痛むが、傷の手当てがしてある。
――生きてるんだ。い、生きて……、はははははははは。
腹の底から笑いがこみ上げてきた。声も出さずに、心の中で大声で笑った。
――俺は生きてる。生きてる! クソ刑事どもに、俺は勝ったんだ。はっ、ざまーみやがれ! あはははははは!! うっ……
まだ体中の痛みはチクチクと俺を襲う。有刺鉄線の傷は一部治りかけていた。
気絶してから数日は経っているらしい。だが今俺は、自白しなかった自分が誇らしくて仕方がなかった。
――絶対、ここから逃げ出してみせる。逃げ出してみせる!
ぼんやりと独房の天井を眺めていた。証拠は絶対に不十分だ。確かに全てを隠しきることは不可能だった。だが、俺は自白をしなかった。刑事を二人も殺したが、それは身を守るために仕方なくしたこと。情状酌量の余地は十分にあるはずだ。
「くくくく」
笑いが声となって漏れる。
――政府のクソ野郎ども。国家権力の奴隷ども。俺を裁くことは不可能なんだよ。あははははははは!!
しばらくすると刑事が二人、独房の鍵を開けに来た。俺の両脇を抱え、またあの小部屋に連れて行く。
――ま、まさかまだ、続けるのか?
あの女の拷問を思い出し、身震いをする。恐怖心が、再び芽を出す。
――だが俺は、絶対に言わない。絶対に……
そんなことを考えている矢先、一人の刑事が口を開いた。
「まだ続くと思ってますか?」
虚をつかれた。心の奥を見透かされたようで不快だった。
「いくら拷問されたって、俺は本当のことしか話せねえよ」
俺の言葉に、刑事はやっぱりといった顔つきで俺に語りかけてきた。
「あなたの裁判は終わりましたよ。何日も気絶していたので略式裁判となりましたがね」
刑事は淡々と俺に告げた。
――略式、裁判?
「あなたは、新法案発足後、初めての違反者となります。よって、正当拷問自白法拒否罪が適用されることになりました」
――こいつは何を言ってるんだ? どういう意味だ?
何が何だかさっぱり分からない。俺は混乱し、戸惑いを隠すことができなかった。
「あなたがまだよくご存知ないのは仕方がないことです」
刑事はそう前置きし、言葉を続けた。
「あなたの犯した罪は、殺人および公務執行妨害、加えて……正当拷問自白法拒否罪だということです。適用される刑罰は、こちらも新法案である拷問刑です。執行猶予はもちろんつきません」
「な、何? 拷問……刑、だと?」
「運がいいですね。あれだけの凶悪殺人を犯しておきながら、死刑は免れたわけですから」
意味が分からない。自白しなかったんだから、証拠不十分で免罪じゃないのか?
「要するに、あなたは合法である『正当拷問自白法』違反により、これから一生、拷問を受け続けることになった。そういう刑罰だとご理解ください」
――な、な……そんな、馬鹿な……
「ま、法律違反ですからね。刑罰はきちんと受けていただきます」
――う、あああああああああ!!!!
--------------------------数年後--------------------------
「お、俺がやったんだ。俺が、女八人を強姦した挙句に殺したんだよ!」
「そうですよね。分かりました。さて、それでは早速、今日の拷問を始めます。来なさい」
――嫌だ。嫌だ。もう、こんな風に毎日拷問される生活は……嫌だ!
――誰か! 誰か助けてくれ!……もう死んでしまいたい。こ、殺してくれ! 死刑にしてくれ!!
またいつものように、女と二人きりで小部屋に閉じ込められる。
「今日のメニューは爪剥ぎと抜歯、それから右腕の骨折です。担当刑事の後藤由香利です。よろしくお願いします」
それはまさに、俺にとって死を超える恐怖。この世に見る地獄であった。
合法の名の下に施される執拗な拷問。女刑事と凶悪殺人犯の根比べの行方は……
新法案を巡り、国会では連日、与野党間の激しい攻防が行われていた。
「大臣はこの法案についていったいどうお考えなんでしょうか?」
「『目には目を、歯には歯を』――ハムラビ法典を知らないわけではありますまい。現代は猟奇殺人や愉快犯、放火など実に嘆かわしい事件が相次ぐ時代となってしまっているのです。この時代を立て直すには、もはや古代に学ぶより他はありません」
「この法案が現代にどのような影響を与えるのか。この法案を成立させることによるメリットをお聞かせいただきたいのです」
「犯罪者による、自白率の増加ですよ」
「新法案『正当拷問自白法』与野党合意の上、成立」
新聞の一面に大きく記事が載っていた。諦めかけてはいたが、それでも俺は少しの希望をもってこの議論を見つめてきた。が、結果は可決。
現実にこの法案が成立してしまったことは大きな問題だ。
なぜなら俺は、犯罪者だから。
事実は、紙切れ一枚で決まる。だったら俺が、黙秘を突き通せばいい。自信は十分あった。
この法案が可決するまでは……
俺が警察に目を付けられるのに、それほど時間はかからなかった。
世間で言うところの凶悪犯罪だ。証拠の全てを隠滅することなんて到底無理だった。だが……、だが俺は、絶対に逃げ延びてみせる。
連れて来られたのは、警察署の取調室だった。
ここの構造は、刑事もののドラマなどで見るものとさほど変わらない。ドラマの演出もなまじっか嘘ではないのだと感じる。制作者側の人間もきちんと取材しているのだろう。装飾の一つもなければ、面白い置物すら置いてない。全くもってそっけない部屋だ。机が一つ置いてあり、俺と刑事は向かい合って座らされる。
刑事は表情が読み取られないよう、そして、刑事が容疑者の少しの表情の変化も読み取ることができるよう、容疑者の顔を照らすライトや窓の位置の工夫がしてあるらしい、と、どこかで聞いたのを思い出した。
「もう調べはついてるんだよ、大谷さん」
取調室には刑事が二人。俺と向かい合ったその「黒いほう」が俺に話を切り出した。体格はレスラーのようであり、見ているだけで暑苦しい。
もう一人の刑事は窓際に立って遠くを見つめ、何やら黄昏ている。そちらの「白いほう」は、肌だけでなく髪も白い。定年間際の刑事といった感じだ。だが見た目とは裏腹に、目の前で怒鳴るこいつよりも幾分貫禄が感じられる。
「女八人か。ハッ……しっかし、ようこんなにもやったなぁ。惨いこっちゃ」
色黒は容疑者である俺に対して、まるで犯人扱いだ。まぁ、それに間違いがないことは、俺自身がよく分かっているんだが。
「これ以上シラを切るようであれば、致し方ありませんかな……」
それまで口を閉ざして黄昏ていたもう一人の刑事が、静かに口を開く。
――来たか。
予想通りの結果に、俺は驚きもしなかった。なぜなら、ここからが俺の勝負……
政府の確立したクソ法案、『正当拷問自白法』との対決なのだから。
連れてこられたのは、窓一つ無い小部屋だった。
いや、小部屋という洒落た名前をやるにはあまりにも役者不足か。壁はコンクリート丸出しで、テーブル一つ無い。
俺たちの人権はいったいどうなってるんだ? 弁護士を雇う権利くらいあって当然だろうに。全く、嫌な世の中になったもんだ。
そんなことを考えながら、狭い部屋の隅々を探るように見回す。その時、ひとりの人物が俺の前に姿を現した。
――お……、女?
驚いたことに、そこに現れたのは、こんな薄汚く狭い部屋とは到底不似合いな美しい女だった。ノースリーブ一枚の上半身。デニムのスカートに短めのブーツ。
露出度の高い服装を纏ったその女に、俺は思わず性欲を掻き立てられる。
俺は驚きの反面、期待の外れた嬉しさからその美しい女を舐めるように見回した。
「あんた、来るとこ間違ってねーか? それとも、お姉ちゃまがボクを自白させてくだちゃるんでちょうか?」
俺はふざけて笑い飛ばした。可笑しくて仕方がなかった。
容疑者を拷問にかけることを許容し、自白を促す政府のクソ新法案。表向きはどうあれ、犯罪を防ぐための見せしめ法案に間違いはないだろう。俺は腹を括り、この法案に対してどう対決するか、これまで考えてきた。
絶対に、服従などしない。
この間違った政治に警鐘を鳴らすとかそんな格好いいものではない。ただ俺のプライドが、決してそのような悪法に屈することを許さなかっただけのこと。それが――、それが?
俺は再び笑った。馬鹿馬鹿しくて仕方がなかったのだ。
女は依然、俺の方を見ながら真顔でじっと俺を見つめていた。そして次の瞬間――
「……っ!」
俺の視線は強制的に上へ向けられた。
どうやら、彼女が繰り出したアッパーカットが俺の顎にジャストミートし、俺は宙に浮かんでいた。――ようだ。
――ば、馬鹿な……、そんな……?
きっと今の俺は素っ頓狂な表情をしているのだろう。無理もない。突如現れたか細い女に突然パンチを喰らわされた挙句、こうして仰向けになって無様な姿を晒しているのだから。
女は黙ったまま真顔で俺をまっすぐに見つめている。
「……へっ、愛想、笑いの、一つもなしに……いきなりこれかよ」
俺のふざけた態度を見ても、彼女の姿勢は変わらない。
「申し遅れました。担当の瀬川凛です。よろしくお願いします」
眉一つ動かすことなく、形式的な挨拶をする。
「ふん。っ……、気の強え姉ちゃんだな」
俺は、内心どうしたものかと考えを巡らせていた。予想はしていたが、油断しすぎたようだ。ただの女を間違えてこんなところに連れて来た、なんてことになれば、笑い話の一つにもなりはしない。露出の多い服装は、おそらく動きやすさ重視。決しておふざけではないのだ。
このまま黙ってこんなのを受け続けたら身がもたない。
絶対に服従しない。それが俺の最大の目標なのだ。
……どう出て来る?
目の前の女を注視しながら身構える。
さっき受けた一撃でこの女が只者でないことが分からないほど、俺も馬鹿ではない。俺から目線を外さず、なおも微動だにひとつしない女。
「言っておくが……、俺は強えぜ。甘く見てると、寝首をかかれることになるかもな」
この挑発が果たしてどういう結果をもたらすか。神経を張り詰める。
次の瞬間、女の身体がふっと横に揺れた。
――来る!!
俺は構えを解かぬまま、目だけで女を追う。
――右か!!
予想は的中した。しかし――
ガードをしようと右腕を上げた隙を突き、がら空きになった鳩尾めがけて彼女の蹴りが鋭く突き刺さった。
「が……、く、っはっ!」
俺はたまらず蹲る。女はすかさず、続けざまに俺の背中に踵落としを見舞う。
「ぐがああああ!!」
俺はその場に突っ伏し、それでも目線を女から逸らさないように、キッと睨みを効かせていた。
「こ、これが新しいクソ法案の結果かよ。これが、正しい方法なのかよ……。お前は、政府の飼い犬か? 奴隷か? あ? 答えてみろよ」
女は挑発に乗ることなく、依然として黙って俺を見つめているだけだ。
「この……アマが!」
高ぶる感情で、俺は自制が効かなくなっていた。気が付くと俺は、女に向かって頭から体ごと跳びかかっていた。ドスンという鈍い音が響き、俺と女は絡みつきながら地面に倒れ込んだ。すかさず俺は、精一杯の力を込めて女に馬乗りになる。
「はっ、っははははは!」
俺は笑った。こうなったら、この雌をめちゃくちゃに痛めつけてやる! 俺は八人も殺した大犯罪者だ。罪を認めてしまったら死刑は確実なんだ。絶対自白はしない。この場を、絶対切り抜けてみせる!
俺は馬乗りのまま、女の顔面を力一杯殴りつけた。女は鋭い目で俺を睨みつけている。
「お前も、あの女たちと同……」
途中で言葉を切る。進んで自らの立場を悪くする必要はない。俺のこの行為の理由はただ一つ。そう、正当防衛だ。俺はまだ容疑者だ。自衛権があるはずだ。
自分自身を納得させると同時に、俺はさらに何度も女の顔を殴りつけていく。もう一発、もう一発――
その時、女は腰を力強く突き上げた。その衝撃で俺はバランスを崩し、前のめりに倒れ込む。
あっという間の出来事だった。
女はそのまま身をよじり、するりと俺の左腕を取ると、すぐさま腕拉ぎをかけてきた。あまりに滑らかな動きに、俺は何も抵抗することができなかった。女が絞め付けを強くする。
「が、あああああ!!」
突然、小部屋の戸が徐に開き、さっき俺を取り調べた刑事二人が入ってきた。
「おうおう。瀬川刑事、派手にやっとるなぁ。ほな、ちょっと手伝いましょか」
色黒のレスラー刑事が、楽しそうにもう一人に話しかける。
「ふむ、そうだな。このお方は、なかなか強情なようだ」
色白の貫禄ジジイがそう答えると、二人は俺を女から引き剥がし、互いに俺の右腕、左腕をそれぞれ押さえ込み、壁に押し付けた。
「な、何の真似だ?」
女は口から一筋の血を流し、なおも俺を睨みつけている。その口元には、少しだけ笑みがこぼれているようにも見えた。
刑事達に押さえつけられ、身動きが取れず、訳も分からないまま、俺はしばしそこに立ち尽くす。見かけによらず、この二人は力がある。
――腐っても刑事だな。……微塵も動けねえ。
そんな俺の目の前に、女が立ちはだかる。一瞬、背筋が凍りつくような感覚を覚えた。
――まさかな? 国家権力の名の下で、そんなこと。
「お、おいおい。何をしようが、俺は無実なんだよ! 俺からは何も聴き出せやしない。早いとこその手を離せよ」
俺は自分の心境を隠そうと、刑事二人に啖呵を切った。
「おやおや、これは威勢のいい」
「ふざけやがってこのガキが! その空元気がいつまでもつか楽しみだな」
刑事二人が、俺の言葉に反応する。それから、貫禄ジジイの方が女に命じた。
「では、瀬川刑事。やってしまってください。くれぐれも、殺してしまわないように」
――やってしまって? 殺し……? おいおい、マジで何言ってんだよ。こいつら正気か?
女は、じわじわと俺との距離を縮めてくる。
「おい……冗談だろ? なぁ?」
しかし女は眉一つ動かさず、それこそ真剣な眼差しを俺に向ける。額には若干の汗が滲んでいるように見えた。
――冷や汗? まさかな。まさか……、冗談なんかじゃないのか?
俺は恐怖を覚えた。何より、この女の真剣な表情が「本気」であることを物語っているように見えた。女は身動きの取れない俺の腹に向け、強烈なボディブローを入れた。
「うぐうっ!……く」
女が口を開く。
「正直に言ってください。あなたは、串田区内で若い女性計八人を襲った連続殺人犯に間違いありませんね」
若干緊張しているように思えたものの、落ち着いた口調で女はそう話した。俺は一瞬戸惑ったが、すぐに嘘の返事をする。
「だか……ら、……違う、って言ってんだろ。何度言えば……、っ! がはああ!!」
言葉の途中で、さらに女のボディブローが入る。鳩尾を抉るように、拳で内部を捻ってくる。
「正直にお願いします。これ以上、苦しみたいですか?」
「じょ……、冗談じゃねえ。嘘、じゃねえ、って、何度も……、ぐうえええ!!」
「正確に」
「違うっ……、ぐはあああ!!! ち、ちが……っは! ぐうおおお! ぐぶうぅ!!」
容赦ない腹パンチの嵐が俺を襲う。俺は内部の苦しみに、今にも吐き出しそうになっていた。
苦しみが絶頂に達した頃、俺を押さえつけていた二人が女を手で制す。
「はい。とりあえずそこまでで」
貫禄ジジイが、そう女に語りかける。
俺は、ほとんど虫の息だった。しかし、休む暇もなく俺を襲ってくる地獄のような苦しみから一時的にでも解放され、俺は内心ほっとしていた。
「はぁ、っ、はぁ……ごほっ! ごぼおっ!!」
俺は咳き込み、息遣いも荒くなる。継続的に繰り出されてきた女のパンチに跪きそうになりながら、それでもここまで必死で耐えた自分を褒めたかった。だが――
「さて、と。……そろそろ、認める気になりましたか?」
貫禄ジジイが、今にも笑い出しそうな顔で俺の顔を覗き込む。俺はそのジジイの表情に心底腹が立った。
「へっ、馬鹿……言ってんじゃねーよ、この……、クソジジイが」
「貴様! 犯罪者が偉そうな口を叩くんじゃない!」
啖呵を切った俺に、色黒が罵声を浴びせる。
――本音が出やがった。
最初からこいつらは、俺を犯罪者だと決めつけてやがる。その態度がどうしても気に入らなかった。
絶対に口は割らない。それは、既に俺の信念となって、俺自身を包み込んでいた。
当然と言えば当然のこと。
俺に対する拷問は、ここで終わりではなかった。
「仕方がありませんね。では、例のアレ、いきましょうか」
――例の、アレ?
引っかかる言い方だ。俺は内心怯えていた。
しかし、自白を強要するこの方法は、絶対に許すべからざる行為だ。……クソ政府が。その思いが俺を常に支え続けていた。
女が俺に近付く。刑事二人は、先ほどと同じように俺を両脇から支える。
――今度は、何をする気だ?
そんな不安を他所に、女はまた俺に近付く。さきほどよりも、さらに緊張の観を高めているようだ。
――何を?
女は、俺の首に鎖を巻きつけ、喉元で交差させて両手で先端をしっかりと握った。少しずつ、少しずつ……、じわじわと絞め付けられていくのが分かる。
――っ! く、苦し……
俺は、既に声を出すことが出来なくなっていた。
――くそ……このアマ……
しばらくすると、女は力を緩める。
「がはっ!……はぁ……はぁ……」
俺の喉元に詰まっていた二酸化炭素が一気に吐き出され、同時に多量の酸素を欲して自然と呼吸が荒くなる。
「ご、ほっ……、て、てめえ……、はぁ……な、何しやがる!」
俺は、怒りを抑えきることができなかった。そんな俺に、女は真剣な表情で言葉を発する。
「正直に言えば、ここで終わりにします。白状するまでは続けます」
両脇の二人は、そんな俺たちのやり取りを笑みを堪えながら見ている。
――く……どこまで非道なんだ、こいつら。一生、許さねえからな。
「どうしますか? 正直に言いますか? それとも、もっと苦しい思いをしますか?」
女は無機質に、そう俺に問いかける。
「ふざけるな! このクソアマが! 俺は最初から本当のことを言ってるんだよ。白状もなにもあるか!」
落胆した表情を見せ、一時女は肩を落とす。そして、すぐにまた真剣な表情で俺に向き直る。再び、俺の首は女の手で絞め上げられる。さっきよりも多少絞める力が強くなっている。
――苦しい……、くそっ、こいつ……
また力が緩まる。女は俺に問いかける。俺は咳き込みながらシラを切る。再び絞め付けられる。
我慢比べ。
――これは忍耐勝負だ。俺は……絶対負けない!!
しかし俺は、自分の体が次第に衰弱していくのが分かっていた。このままでは埒が明かない。
{ 2007/04/17(火) }
そんな時、色黒がまた馬鹿げたことを言い始めた。
「同時に『男』も責めてやれや。くく、分かるだろ? 金玉だよ、金玉。はははは」
――何言ってるんだこいつ……。マジで、マジで正気か?
今さらだが俺は、こいつは本当に、生理的に受け付けない。汚らしい上にゴツイしオヤジ臭がきつい。それにこの下品な言い方。俺は憎しみから、思わず横にいる色黒に唾を吐きかけていた。
「こいつ! 馬鹿な奴だ! おい、やってほしいってよ。ほら、やれよ! 命令だ!」
女は少し頬を朱に染めながら、それでも命令と聞くと、その視線を鋭くした。
「分かりました。絶対、白状させますから」
そう気丈に応える。
「ちょ……、本気か? ま、待……」
女が、脚を思いきり後ろに引いた。そしてその膝が、俺めがけて飛んできた。
――はぐうっ!!
下半身に衝撃が走る。内臓を揺さぶられるような感覚が俺を襲う。激しい痛みが俺の内部に響いてくる。
「ぐああああああ!!」
痛い。……痛い。
俺は股を閉じて腰を引き、情けない格好で押さえつけられたまま飛び跳ねる。その間にも、女は俺の首を再び絞めあげる。
「ぐ、くう……」
また膝蹴り。
「ぐっ! こ、おおおお……あ」
両手に握った鎖で首を絞めながら、俺の下半身に膝蹴りを何度も叩き込む。その度に俺は苦悶の声を上げ、そしてその声は絞められることで抑えられる。
俺は痛みと苦しみを同時に与えられ、もはや息をするのも困難な状態になっていた。両脇の馬鹿二人は、そんな俺を見てニヤニヤとした気持ち悪い表情を浮かべている。
「こんなこと、いつまで続けるんだ? いくら痛めつけたって、俺からは何も出ない」
俺の必死の叫びには、誰も応えない。しかしその瞬間、俺は感じた。
そう。色黒が腰に装備している、――銃。気持ち悪い表情で、明らかに気を抜いている二人。俺の体もいつかは尽きるだろう。チャンスは今しかないのだ。
俺は渾身の力を両腕に込めて、両脇の二人を目の前に引き合わせた。二人は虚をつかれたためか、意外にあっさりと体をふらつかせ、お互いに頭をぶつける。同時に、俺は女を力いっぱい蹴り飛ばした。女はよろけ、後ろの壁に体を叩き付けた。
「ぐあっ! 何を?」
「こ、この……」
「う……」
ふらつく三人の隙をつき、俺は色黒の腰から素早く銃を引き抜く。少し離れて銃を構え、三人に対峙する。
股間に激痛が走る。俺は腹の中にまで込み上げてくるその痛みに必死で耐えた。
一瞬の油断が命取りになる。俺は固唾を呑んで、三人を凝視し続けた。
刑事二人は突然のことにあっけにとられたのか、しばし無言のままで戸惑っている様子だった。
「き、きき貴様、こんなことして……」
言葉を言いかけた色黒を、ジジイが手で制する。
「大谷さん。暴力はいけません。さぁ、その銃を、とりあえずこちらに。穏便に、ね」
こいつは本当の馬鹿だ。さっきまで暴力でカタをつけようとしてたのはどこのどいつだ。俺はこの刑事二人に対する蔑みの気持ちをいっそう強くした。
――こんなやつら……、殺してやる、殺してやる……
「おいおい。さっきまでの威勢はどうしたんだよ、え? 刑事さんよ!」
俺は躊躇いなく、色黒の右足の太腿を撃ち抜いた。
「ぐあああああああ!!」
色黒の絶叫が心地よく響き渡る。
――くくっ、俺を馬鹿にするからこうなるんだよ。
「お、落ち着け。私たちは、何も君を殺そうとかね、そんなことを考えているわけじゃ……、っ!」
俺は、ジジイの頭を撃ち抜いた。目を大きく見開き、ジジイは絶命した。
――くくくく。
「あ、……ああ、た、助けてくれ……ください。おおお願いです、た……」
俺は薄ら笑いを浮かべながら、銃口を色黒に向けなおし、その胸を撃ち抜いた。
「ふ、ふふふふふふ……、はははははは!」
俺は可笑しくて仕方がなかった。
――俺の報復はきついだろ? ざまーみやがれ。
女は壁に寄りかかり、じっと俺を見つめている。その瞳には光が感じられなかった。目の前で人が二人も殺されたんだ。無理もない。俺は勝利を確信し、銃口を今度は女に向けた。
「最後に言い残したことはあるか? 婦警さんよ」
俺は余裕の笑みで、ゆっくりと女に近付いた。
しかし女は、そんな俺を見つめながら、落ち着いた声で言った。
「殺人および公務執行妨害の現行犯で、あなたを逮捕します」
――ふん、今更何を。これは正当防衛だ。俺はこれからも逃げ延びて見せるからな。
「だったらどうだって言うんだ? お前に俺は捕まえられねーよ」
俺は、ニヤけながら女を見つめる。よく見ると本当にいい女だ。
――できるならこいつもレイプしてやりたいものだがな……くくくくく。
「正直、口実ができて安心しました。これで私もあなたを捕らえるために、本気を出せますからね」
意外にも女には安堵の表情が浮かび、肩の力が抜けたような仕草を見せている。
――こいつ、手加減してたとでも言うつもりなのか? 全く、どいつもこいつも……
「ふん。あんたは、まだ状況が分かってないらしいな」
女は黙って俺の目を見つめている。さっきまでの緊張した感じではなく、むしろリラックスした雰囲気が女から読み取れた。その仕草が俺の癪に障る。
――こいつ……、俺が怖くないのか?
俺は再び銃を握りなおすと、銃口の焦点をしっかりと女に向けた。
「ほら、命乞いしてみろよ。泣き叫んで許しを乞うなら、犯すだけで許してやるからよ」
言葉とは裏腹に、俺のこめかみ辺りから汗が滴ってくる。
――どうしてだ? 女一人に、俺がびびっているとでも?……馬鹿な!
立場は圧倒的に俺が有利。しかし不思議と女から滲み出る自信や威圧感が、俺に言いようもない不安を与えているのも事実だった。
――不快だ。こんな女一人に……、何をしてるんだ俺は。
その不安を振り払いたくて、女の足元に向けて威嚇射撃をしようとする。その時――
「あっ!」
一瞬の出来事だった。女は俺が引き金を引く瞬間に身を屈めて俺との距離を縮め、銃を握った俺の右手を左手でしっかりと握って銃口を上に向けさせていた。放たれた弾丸は宙を舞い、天井に突き刺さっていた。
女は反対の右腕を俺の首に当て、壁との間に俺の首を挟みこんで俺を押さえつけた。こんな状況にも関わらず落ち着いた表情を浮かべ、また俺をじっと見つめている。
――このアマが……くそっ、くそおっ!
俺は状況の変化に焦った。しかし、このチャンスを逃すわけにはいかない。女を何とか押しのけようと渾身の力を入れる。しかし驚いたことに、女の体はびくともしなかった。
――何て馬鹿力なんだ、この女は?
焦りが焦りを呼ぶ。お互いに身動きが取れないまま、相反する力が均衡を保つ。いや……。俺は気付いていた。わずかながら、いや、きっと、相当な力の差があることを。
女は銃を持った俺の腕を捻り上げ、俺の背中の後ろに持っていく。
――銃は、絶対離さない!……ぐ、あああああああ!
鈍い音が、狭い室内に響き渡った。
俺の右腕は、女に捻り上げられたことで折れてしまったのだ。激しい痛みが俺を襲う。
「うわああああああああ!!!」
俺は絶叫した。
今まで体験したことのない痛みだ。痛い。痛い。当然、銃は俺の手を離れ、空しく地面に落ちた。俺は反対の手で女の脇の下から手を入れ、女の首を押し返すように力を入れた。
――何とか、この状況を打開しなくては。
「うぐっ!!」
だが、女は隙を見せなかった。脚を大きく後ろに引き、俺の腹に膝蹴りを入れてきたのだ。俺はたまらず身体をくの字に曲げる。俺の頭が下がった瞬間を見計らい、女は続けて俺の顔面に膝蹴りを入れた。
「がああああっ!!」
弾かれたように俺の身体は宙に舞い、仰向けに倒れ込む。それと同時に女は俺に馬乗りになり、今度は両手で俺の首をしっかりと掴んで絞め始めた。
――く、くそっ。こんなところで……、こんなところで!
「さぁ、白状してください。串田区連続凶悪殺人犯はあなたですね」
こんな状況下でも、こいつは冷静に仕事をしてやがる。くそっ、気にくわねえ!! 絶対に口は割らない、……割らない!
俺は沈黙を守っていた。
――屈したら負けだ。俺は、絶対に逃げ果せてみせる。
「し……しらね、っつってん、だろうが……」
絞められたまま、擦り切れるような声を上げる。しかし女は、そこでまた力を強くする。
俺は、左手で女の顔面に殴りかかった――が、寸でのところでかわされる。そして女は、右手で俺の左腕を押さえる。
「その危ない左腕も、壊しておきましょうか」
冷静な女の口調に寒気を覚えた。
――まさか……まさか……
「ぐ!」
女は俺の手首を掴んで捻り上げ、膝で俺の腕の関節を思いきり強打した。関節とは逆の方向に。俺はもう片方の手の機能も奪われた。またも激しい痛みが俺を襲う。
「ぎゃあああああああああ!!!」
再び絶叫が響き渡る。両手を奪われた俺には、もはや抵抗する余力はなくなってしまった。
「ふぅ……。さ、続けましょうか」
あまりに淡々とした女の言葉。まるで単純作業に取り組んでいるように、残酷な行為を平然と行う。
俺はこの時、この女の底知れぬ恐ろしさを垣間見たような気がした。
俺に馬乗りになったまま、女は俺の首を絞め続ける。
「そろそろ自白してください。私もあなたを殺したくはありませんから」
「ばかな。刑事が、人殺しなんて……」
「分かっていませんね。あなたは刑事二人を殺したんですよ? 私の目の前で。これを本当の正当防衛と言うんです」
俺の目の前には、二体の死体がまだ先ほどと同じ形で転がっている。
――確かに、俺はこの刑事二人を……。いや、それは違う。俺だって、さっきまで拷問を受けていたんだ。俺の方こそ、正当防衛じゃないのか?
そんな俺の考えを見透かしたように、女は続ける。
「刑事による拷問は、今や『合法』なんです。あなたは列記とした殺人犯、公務執行妨害現行犯。それ以外の何者でもありません」
女はさらに絞める力をじわじわと強くしてくる。苦しい……
――畜生。俺たちには、もはや自衛権もないのか。……絶対に間違ってる。こんなやり方、絶対に間違ってる!
仰向けになったまま両足を振り上げ、女の身体を背後から掴もうとする。しかし、女はその度に身をかわし、さらに力強く俺を絞め上げる。
「む、ぐぐ……ぐ」
苦しさから、声もまともに出すことが出来ない。
「足がうっとおしいですね。その足も――」
背筋が凍りついた。
――これは、恐怖心? この俺が? まさかこんな女一人に、恐怖を感じているというのか?
女は力を緩めた。それから女は身体を反対方向に向け、俺の足に目線を落とした。
「ひ……ひっ、ひぃぃ!」
自分でも驚くほどの情けない声が漏れる。
――やめてくれ。もう折るのは……やめてくれ!
女はふり返り、俺の顔を見て笑みを浮かべる。
「怖いんですか? 大谷さん。ふふ、顔が怯えてますよ?」
――っ!……馬鹿にするな! こ、この俺を……。こ、殺してやる!
俺は無我夢中で身体を起こし、女に頭突きを見舞った。一瞬怯んだ女の隙を逃がさず、俺は背後から女に覆いかぶさるように倒れ込んだ。うつ伏せになった女の上に、今度は俺が馬乗りになる形になった。
――くく……。形勢逆転、だ。
俺は半分我を見失っていたのかもしれない。恐怖心がそうさせたのか、それとも別の原因があるのかそれは俺自身にも分からなかった。ただ、俺の中の声がしきりに叫んでいた。
『殺せ! こいつを殺せ!』
俺は馬乗りの体勢のまま、唯一使える足で女の身体を力いっぱい絞めつけた。
「うっ……ぅ……」
女が呻き声を上げる。その声が、持て余していた俺の性欲を結果的に高ぶらせることになった。
「お前を殺してから、たっぷりと犯してやるよ。へへ、すぐに楽にしてやる」
俺は、女の身体をさらに強く絞め上げながら、その上で跳びはねて女を何度も踏みつけた。女は苦しそうにまた声を漏らす。俺は我慢ができなくなり、女の尻に自分のモノを擦りつけた。デニムのミニスカートから覗く白い下着が、俺の欲情をいっそう掻き立てる。
「な、何を――」
戸惑いの声が心地いい。そしてまた女を絞め上げる。女が苦痛の声を上げる。その循環に俺は興奮し、激しくモノを擦りつけながら……、やがて果てた。
――ふふ、お楽しみはこれからだ。
俺は、片足で女の背中を踏みつけたまま立ち上がった。そして、思いきり女の腹に蹴りを入れた。
「ぐふっ!……う、ごほっ!」
「お前もこれから殺してやるよ。めちゃくちゃに暴行してな。はははは!」
「あなた……。こんなことして、ただでは済みませんよ」
心なしか、女の声には余裕が感じられる。それがいっそう、俺の破壊願望に火をつける。
――あの女どもと同じように、お前も、……死姦してやるからな。
心の中で呟きながら、俺は何度も女の腹を蹴り続けた。
「ほら、苦しいだろ? さっきの俺の痛みだよ。くくくく」
女は苦しみながら、しかしどこか余裕の表情で俺を見上げて言った。
「ちょっと、あなたを甘く見すぎていたみたいです。殺されても、文句は言わないでくださいね……」
――ちっ、口の減らない女だ。まあいい。これから存分に甚振って……
「っ!」
華麗な躍動が目前に見えた。女は俺の足の下からするりと身を脱し、俺の両足を自分の両足で挟み込んで力を加えたのだ。俺は意表を突かれ、もんどりうってその場に仰向けに倒れ込んだ。
――し、しまっ……
気付くと女は手に銃を握りしめ、再び俺に馬乗りになり、もう片方の手で俺の首を押さえ込んでいた。
「あなたは私を怒らせました。覚悟は……できていますね……?」
――く、くそ、くそおおっ!
女は俺の方を向いたまま、銃を持った手を後ろに向ける。
「ま、まさ、か。や、やめ……」
地味な銃の音が二発。銃弾は俺の両方の太腿を打ち抜いていた。この世のものとは思えない痛みがまたしても俺を襲う。
「ぎゃあああああああ!!!」
四肢崩壊。
もはや俺は自分で身体を動かすことすら出来なくなっていた。女は俺の太腿に出来た穴に手を突っ込み、ぐりぐりと弄ぶようにそこを甚振る。その度に俺は絶叫し、気付くと俺の喉は枯れ果て、まともな声も出せないほどになっていた。
「もう時間がありません。このままでは、あなたは出血多量でいずれ死亡してしまうでしょう。最後にもう一度、聴きます。串田区連続凶悪殺人犯は、あなたですね」
あまりの痛みに、女の問いかけは耳の奥の方でかすかに聞こえる程度だった。しかし絶対に自白はしない。そう誓ったことは忘れてはいなかった。
――こうなったら、意地を張り通してやるからな。そして……、こんな拷問では何も解決しないことを、世に訴えてやる。そして俺は……無罪放免だ。世間の同情、というおまけつきでな……あぁ、ぐっ!
「事実は、変わらない。俺は……無罪だ」
太腿の痛みは、和らぐことなく俺に襲いかかる。俺は出血のためか、だんだんと意識が朦朧としてきていた。
女は俺の変わらない態度に呆れ果てていた様子だったが、俺への拷問はその後も止むことはなかった。左の腕で俺の喉を押さえ込み、今度は執拗に腹を責め続ける。
「ぐ、え……おえええ! うぐぅ……! は、ぐううっ!……あうぅぅ、……ぐぶぅ!」
内臓に響くほどの強烈なパンチを何度も腹に受け、その度に俺は声にならない声を上げた。鳴り止まないパンチの音が室内に響き渡り、とうとう俺は血の混じったゲロを吐き出した。
「あなたが悪いんですよ。本当に……こんな強情な人、初めてです」
感心だろうか。それとも呆れ返りだろうか。女の言葉は、俺の脳をかすめて消えていった。
腹責めの苦しみは想像をはるかに超え、俺は次第に壊されていく内部の感触を味わわされていた。
「ごほっ……、うええっ! げえええええ!!」
搾り出すように、俺は吐血を繰り返す。破壊された内部の苦しみは俺から戦意そのものを奪っていた。
――もう、抵抗できない……
仰向けに倒れ込んだまま、しばらく天井を見上げる。女は立ち上がり、何やら道具を取り出している様子だった。
――いったい、今度は何を……?
無表情のまま、女は倒れている俺の目の前に立ちはだかり、俺の腹を足で踏みつける。それと同時に凄まじい激痛が再び俺を襲う。
「もう諦めてくださいね。あなたは反抗的すぎました。とても残念です」
そう言うと女は、既に無抵抗を余儀なくされた俺の身包みを全て引き剥がす。俺は羞恥心から自然に身体を縮こめた。その時、女の手にしているものが目の端に映った。警棒だ。しかし、単なる警棒ではないことは遠目にも明らかだった。
そこには有刺鉄線が万遍なく施されていた。世にも恐ろしい武器が、俺の恐怖心を煽る。
「ま、まさか、まさか……、や……」
女の目は据わっていた。俺を直視しながら、その警棒を俺の身体めがけて思いきり振り下ろした。
「ぎぃやぁああああ!!!」
とてつもない痛みに一瞬我を忘れる。しかし女の手は休まることを知らなかった。
頭、肩、腕、腹、腰、太腿、脛。あらゆる部位に凶器が振り下ろされる。心持ち、女の表情に狂気にも似た笑みらしきものが浮かんでいるように見える。痛い! 痛い!!
俺は必死で身体を丸めた。殴打を続けられ、俺の身体のどこからともなく鮮血がほとばしる。
――殺される!
直感的にそう感じた。
倒れた俺の目の前には、死んだ刑事の顔があった。少し開いた目からは、既に光は感じられない。
――死んだら俺も、こいつらと同じような姿に……。嫌だ!! この女には……、この女にはもう、逆らってはいけないんだ。従う……、従う!!
女はそれから俺の身体に再び馬乗りになり、体中を鉄線でチクチクと甚振り、抉り始めた。反対の手で喉元は完全に押さえつけられ、声も出すことができない。
俺はこの時初めて後悔を知った。この女には、逆らってはいけなかったのだ。
「体全体を抉っていきますね。あなたは、どこまで耐え切れるのかしら……。ふふふふ」
身体中のいたるところに有刺鉄線が突き刺さり、俺の皮膚は鉄線に抗うことなく裂けていく。
「ここ、痛いんでしょうね。男性が、一番感じる部分ですものね」
女は、俺の陰部にまで鉄線を近付ける。そして――
「ぐ、ぎぃやああああ! ああああ、がああああ! うああああああ!!」
――待ってくれ、許してくれ! もうやめてくれ! 話す! もう何でも話すから……
そう考えた俺の口からは、もう既に言葉は発せられなかった。出せるのは、叫びだけ。身体の全てが崩壊していく。
俺は、とうとうその場で気を失った。
気付くと俺は独房に入れられていた。
――俺は、どうなったんだ?
体中が痛むが、傷の手当てがしてある。
――生きてるんだ。い、生きて……、はははははははは。
腹の底から笑いがこみ上げてきた。声も出さずに、心の中で大声で笑った。
――俺は生きてる。生きてる! クソ刑事どもに、俺は勝ったんだ。はっ、ざまーみやがれ! あはははははは!! うっ……
まだ体中の痛みはチクチクと俺を襲う。有刺鉄線の傷は一部治りかけていた。
気絶してから数日は経っているらしい。だが今俺は、自白しなかった自分が誇らしくて仕方がなかった。
――絶対、ここから逃げ出してみせる。逃げ出してみせる!
ぼんやりと独房の天井を眺めていた。証拠は絶対に不十分だ。確かに全てを隠しきることは不可能だった。だが、俺は自白をしなかった。刑事を二人も殺したが、それは身を守るために仕方なくしたこと。情状酌量の余地は十分にあるはずだ。
「くくくく」
笑いが声となって漏れる。
――政府のクソ野郎ども。国家権力の奴隷ども。俺を裁くことは不可能なんだよ。あははははははは!!
しばらくすると刑事が二人、独房の鍵を開けに来た。俺の両脇を抱え、またあの小部屋に連れて行く。
――ま、まさかまだ、続けるのか?
あの女の拷問を思い出し、身震いをする。恐怖心が、再び芽を出す。
――だが俺は、絶対に言わない。絶対に……
そんなことを考えている矢先、一人の刑事が口を開いた。
「まだ続くと思ってますか?」
虚をつかれた。心の奥を見透かされたようで不快だった。
「いくら拷問されたって、俺は本当のことしか話せねえよ」
俺の言葉に、刑事はやっぱりといった顔つきで俺に語りかけてきた。
「あなたの裁判は終わりましたよ。何日も気絶していたので略式裁判となりましたがね」
刑事は淡々と俺に告げた。
――略式、裁判?
「あなたは、新法案発足後、初めての違反者となります。よって、正当拷問自白法拒否罪が適用されることになりました」
――こいつは何を言ってるんだ? どういう意味だ?
何が何だかさっぱり分からない。俺は混乱し、戸惑いを隠すことができなかった。
「あなたがまだよくご存知ないのは仕方がないことです」
刑事はそう前置きし、言葉を続けた。
「あなたの犯した罪は、殺人および公務執行妨害、加えて……正当拷問自白法拒否罪だということです。適用される刑罰は、こちらも新法案である拷問刑です。執行猶予はもちろんつきません」
「な、何? 拷問……刑、だと?」
「運がいいですね。あれだけの凶悪殺人を犯しておきながら、死刑は免れたわけですから」
意味が分からない。自白しなかったんだから、証拠不十分で免罪じゃないのか?
「要するに、あなたは合法である『正当拷問自白法』違反により、これから一生、拷問を受け続けることになった。そういう刑罰だとご理解ください」
――な、な……そんな、馬鹿な……
「ま、法律違反ですからね。刑罰はきちんと受けていただきます」
――う、あああああああああ!!!!
--------------------------数年後--------------------------
「お、俺がやったんだ。俺が、女八人を強姦した挙句に殺したんだよ!」
「そうですよね。分かりました。さて、それでは早速、今日の拷問を始めます。来なさい」
――嫌だ。嫌だ。もう、こんな風に毎日拷問される生活は……嫌だ!
――誰か! 誰か助けてくれ!……もう死んでしまいたい。こ、殺してくれ! 死刑にしてくれ!!
またいつものように、女と二人きりで小部屋に閉じ込められる。
「今日のメニューは爪剥ぎと抜歯、それから右腕の骨折です。担当刑事の後藤由香利です。よろしくお願いします」
それはまさに、俺にとって死を超える恐怖。この世に見る地獄であった。