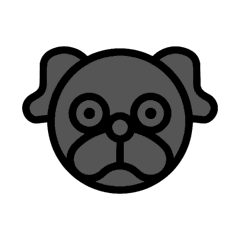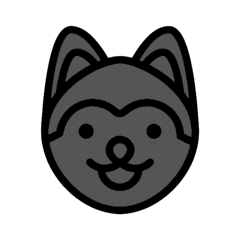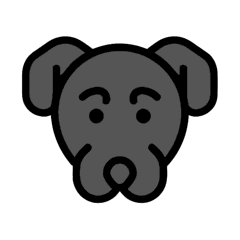(转)魔妃(日文)
添加标签
PS:请注意,该文转自p站,作者为 本
「はぁ…はぁ…」
「…ここまで勇者が強くなっているとはな…!」
荘厳な装飾品の並ぶ大きな広間にその二人は対峙していた。
一方は洗練された闘気を纏い、勇者の紋章の刻まれた聖剣を構える。
一方は凄まじい威圧感を放ち、魔王の証である魔剣を振り上げた。
「これで…終わりだっ!!」
聖剣を構えるその青年は勇者オルト。魔王を倒し、世界に平和をもたらす存在と天命を受けた世界でただ一人の男であった。精悍な顔立ち、細身であるが一切の無駄のない引き締まった身体、数々の戦いで鍛えられた技の冴え、その全てが勇者として相応しい者と言える。そして聖剣を構えた勇者オルトは今まさに魔王を討ち果そうとしていた。
「ふ、ふははははっ!!!!面白いっ!私を打ち倒してみろ勇者オルト!」
対するはオルトの2倍はありそうなほどの巨躯、天に逆巻く角、人目見ただけで呪い殺されそうな悪魔の相貌、光を飲み込むような漆黒の翼、全てを切り裂くような爪、大地を割るかの如き蹄をもつ異形の存在、すべての魔物を統一する魔王と呼ばれる者だった。魔王がこの世界に現れてから数十年、長きに渡り人間を苦しめてきたその存在は全身に傷を負い、左腕は切断され、片角が折られ今まさに命を散らそうとしていた。ただその状態であってもなお、魔王の放つ威圧感は変わらない、むしろさらに増しているように見えた。
「…光よ!俺に力をっ!!!」
オルトは構えた剣にすべての力を込めた。勇者の力を込められた聖剣はから光が溢れ、刀身を聖なる気が纏っていく。そして光は収束し、凄まじい輝きとなって剣全体を太陽のように発光させた。徐々に光は炎となり、ついに勇者の全身の鎧までもが白き炎に包まれた。
「奥義…白炎!!!」
「来い、勇者っ!!!」
オルトが叫んだ瞬間、勇者から立ち上った陽炎が揺れた。魔王もそれを迎え撃つように魔剣を構え、魔力を剣へと集中させる。闇の魔力を纏った魔剣が今まさに勇者を両断しようと剣を振り下ろした。その瞬間、白炎を纏った勇者の姿が一瞬にして消え去った。
「…ふははっ!見事…!!」
闇を裂くように白い光が一閃した。そして魔剣を振り下ろした姿のまま、魔王は満足したかのように笑った。その胴体に3つの線が入り、切り口に小さく白き炎が揺らめいく。
「終わりだ…魔王」
オルトは超高速の斬撃から魔王の背後で剣を振りぬいたまま静止した。次の瞬間、背後で白い爆炎が全てを浄化させるかのように包み込み、魔王の身体は灰燼とかした。爆炎が収まった時、燃え残った魔剣以外、何もなかったかのようであった。
「…くっ!…はぁ…はぁ…」
力を使い果たしたかのようにオルトは膝をついた。ギリギリの戦いだった。実力は均衡しており、一歩間違えればこちらがやられていた。奥義白炎によって全気力を使い果たし、現在のオルトには戦う力がほとんど残っていなかった。
「…終わったよ、皆…」
勇者は仲間を想い、涙を流して呟いた。この魔王の間まで来るまでに仲間はその身を捧げて勇者をほぼ無傷で魔王の間まで送り届けたのだった。魔王軍幹部と相打ちになった者、幾千の魔物相手に一人で囮になった者、生命力を全て使い果たし、最後は身を呈して勇者を庇った者、彼らの力がなければ勇者が魔王を倒すことは不可能だった。
(くっ…魔力が無くなる前に通信魔法で王に報告を…)
最後の魔力で最大国家である中央王国の王に「魔王、討伐」とだけ通信を送る。
「…今帰るからな」
戦いの前に送るはずだった結婚指輪を撫で、故郷に置いてきた妻を想う。元々旅の仲間であった彼女は最後の戦いには連れて行かなかった。もし自分に何かあったときに彼女だけは守ろうと思ったためだ。仲間たちと勇者は結託し、彼女を説得したのだった。そして戦いが終わった暁にこの指輪を渡すつもりだったのだ。
(これで…帰れるんだ…やっとこの指輪を…)
オルトは自分の指にはまっている指輪と同じ指輪を握り締める。力の入らない手足を無理矢理動かしてその場から立ち上がろうとした。
ギィ……
その時、扉の軋む音が背後から聞こえた。オルトの入ってきた正面の荘厳な扉は開かれておらず、オルトは反射的に振り返った。
「…あら、騒がしいと思ったら…」
ねっとりとした甘い女の声が魔王の間に響いた。その人物は勇者のいる魔王の玉座から少し離れた場所から現れた。物陰でありシルエットしか見えなかったが、頭から生える悪魔の角、細長いエルフのような耳と腰付近から生える悪魔の羽、背後に見える尻尾の影がその者を人間でないことを表している。勇者は手に力の入らない手に無理矢理力を込めて聖剣を構えた。
「この魔力の残滓…魔王様を倒したのはそこのお方?」
「誰だっ!」
ゆっくりとその人物がこちらに近づいていくる。影が消え、その姿が明らかになったとき…オルトはただ、単純にその人物に見惚れた。いや正しくは見惚れることを強要されたかのようだった。
「名前も名乗らず申し訳ありません、私の名前はリリトゥと申しますわ、呼びづらい名前ですからリリとお呼びくださいませ」
それは間違いなく誰もが見惚れ、心を奪われるような絶世の美女であった。少女のような可愛らしさから女性の色香まで全てをを併せ持ったその顔貌は正に完璧としか言えなかった。しかしその美しさは彫像や女神のような美しさでは決してない。潤んだ大きな瞳、雪のように美しい白い肌、ピンク色の潤った艶かしい唇が、ただひたすらにオルトの情欲を掻き立てる。その魔性の美しさはまるで娼婦のように妖艶な雰囲気を纏っていた。
「それで…魔王さまを倒したあなた様はどなたでしょう?」
「…っ!!」
煌めくような長い美しい金髪が歩くたびにさらさらと揺れる。問いに対してオルトは何も答える事ができなかった。リリトゥと名乗った女性の全身から目を離せず、ただ引きこまれていた。
(なんだ…これは…!)
そのあまりに現実離れした美しすぎる顔貌もそうだったが、それと同等、いやそれ以上に眼の前の女性の身体は凄まじいものだった。美しく淫靡に揺れる乳房から煽情的に曲線を描く、くびれた腰、レオタードがぴったりと張り付き、その形と割れ目を強調する股間、黒いストッキングがぴったりと張り付くむっちりとした太ももから美しい足先。リリの全身からあふれる凄まじい色気にオルトの股間は反応してしまいそうになる。
「あら答えてくださらないの…?わたくしの魅了に逆らえるなんて…魔王様を倒した実力は本物のようですわね」
何も答えないオルトに感心するようにリリは微笑む。実際、オルトはまだリリの肢体から目を離すことができなかった。
(これはサキュバスの魅了…!?こここまで強力なものが…!?)
オルトはこの感覚を知っていた。サキュバスという希少な魔物が使用する魅了魔法の効果だ。この独特の甘い匂いとその肉体で獲物の理性を崩壊させ、意のままにしてしまうものだが、勇者の魔法耐性の前にはほとんどが無効化されるはずだった。しかし不意打ちのようだったとは言え、目の前の女から感じる尋常ではない魅了の魔力は勇者であるオルトすら飲み込みそうなほどであった。
(…耐えろ…っ!!)
勇者は理性が崩壊しそうになるのを必死に耐えた。全力で片方の手もう片方の手を握りしめた瞬間、自分の指に嵌めた結婚指輪が目に入った。その瞬間、脳内に故郷で待つ妻の笑顔が浮かんだ。
(絶対帰ってきてくれ…オルトっ!)
リリの身体を食い入るように見つめていたオルトはそこで電撃が走ったように我に返った。勇者の魔法耐性が魅了の効果を上回り、オルトは正気を取り戻す。知らぬ間にオルトまであと10歩程度の距離まで迫ったリリに魅了を吹き飛ばすように名乗りを上げる。
「…俺は勇者オルト、魔王を打ち倒したものだ!」
「あら…やはりあなたが勇者オルト様ですのね…♡」
「お前は誰だ!なぜ魔王の間にいる!」
リリトゥの一挙手一投足にオルトの視線は奪われそうになるが、オルトの精神力はなんとかそれを上回っていた。一時的に魅了を打ち消し、油断なく聖剣を構えてオルトは問う。
(魔王の間までの魔物は仲間たちが命を賭して倒した…この部屋にいるはずの魔物は本来、魔王だけだ…!)
魔王軍の幹部は全て勇者一行に魔王の間までの戦いで倒されているはずだった。そもそも高位の魔物でなければ魔王の間に入ることは許されないはず…つまりこの魔物は相当に高位の魔物であるということだ。
「先ほども申しました通り、名はリリトゥ、あなたが倒された魔王様の第三夫人ですわ」
「第三…?魔王の妻は魔王軍幹部に二人だけじゃ…!?」
「私は表に出ることはほとんどありませんでしたから…彼女達はとても聡明でお強かった。それに比べて私はただ一族の代表として嫁がされただけ…戦いは苦手なのですわ」
オルト達人間の掴んでいた情報では魔王の第一、第二夫人は双方とも魔王軍の幹部であった。そしたここにくるまでの戦いで仲間たちが自分の命と引き換えに倒した相手でもあった。
(魔王の妻ならこの部屋にいることも納得できる…くそっ…!今の体力でこの女に勝てるのか…?)
眼の前にいるリリトゥと名乗った魔物は戦闘は苦手といっているがあの魔王の第三夫人だ。恐らく相当の戦闘能力、もしくは特殊な力を持っているだろう。内心に焦りを見せながら聖剣を構える勇者にリリはさらに近づき言葉を続ける。
「うふふ…それにしても魔王さまを倒してしまわれるなんてとてもお強いなのですね」
「…お前も魔王の後を追いたくなかったらさっさと消えるんだな」
勇者は聖剣を向けるとそう言ったが、ほとんどはったりに近かった。実際のところ勇者の身体は魔王との戦いで力を使い果たしていたのだ。
「あら…怖いこと仰らないで、わたくしは勇者様を恨んでなどいませんのに…」
「…なに?どういう…」
そう言った瞬間、リリは背の羽をゆっくりと広げた。その瞬間、彼女の周囲に魔力が可視できるほどの濃度で集まり始めた。
(…来るか!)
聖剣を構えて勇者はリリを迎え撃とうとした。しかし何故かリリが襲い掛かってくることはない。それどころかその場所から動こうともしなかった。
「構えなくても結構ですわ勇者さま?わたくしは戦う気などないのですから」
リリは凄まじい魔力を纏いながら、その場で言葉を続ける。リリの意図が分かりかねたオルトは黙ってリリの隙を伺い続けた。
「勇者オルト様、わたくしはあなた様に興味がありましたの」
「なに…?」
「わたくしは淫魔、殿方と交わり、愛し合うことを生業としています」
「…ふん、それで相手の男は最後は生命力を吸い取って殺してしまうんだろう、淫魔とはそういう生物だ」
「あら、それは軟弱な殿方が悪いのです…ともかくわたくしは淫魔である限り、殿方と交わらなければなりません」
リリは悲しみの表情を浮かべ、自らの身を両手で抱きしめる。突然語り始めたリリに困惑しながらも緊張をゆるめないオルトだったが、リリが自らを抱きしめることで腕の間で潰れる乳肉と太ももが絡み合う様子が目に入ってしまい、さりげなく目をそらす。
「魔王様はあなた様との戦いのことばかり…世継ぎのことも考えずわたくし達の誰とも交わりませんでしたわ…城内の魔物ではわたくしとの交わりに耐えられる者は中々居らず…稀に現れても一度きりで力尽きてしまう者ばかり」
オルトにさらに一歩近づきながらリリは話し続ける。思わず一歩後ろにさがりながらもオルトはなおも油断なくリリを注視し続ける。
「わかりますか…?淫魔としての性…ひたすらに狂おしく、身を焦がすほどの情欲がわたくしを捉えて離さないのです」
「そんな下劣な考えは分からないな…!」
「うふふ…本当につれないお方…わたくしは思いました、魔王さまに匹敵する器を持った方ならばわたくしを満たしてくれると」
「どういう…ことだ」
魔王と戦っているときに感じた圧倒的なプレッシャーとも違う、生ぬるい、包み込むような異様な感覚をオルトは味わう。リリの言葉から嫌な予感をひしひしと感じた。
「ついに…見つけました、精悍な顔立ちと肉体、世界で一人の選ばれし者、そして…」
「魔王様すら打ち倒したお方を」
紅潮した頬に上品に片手を当て、リリは潤んだ瞳で舐めるようにオルトの全身を眺めた。ぞくっとした感覚がオルトの背中を走る。情欲にまみれたその視線は動物が餌となる獲物を見定めるようだった。
「わたくしを満たしてくれるのは…もうあなた様しか考えられませんわ…勇者オルト様♡」
「…っ!」
微笑みを浮かべオルトを見つめるリリの姿に一瞬、オルトは言葉を失う。
「…何が目的だ…!」
「うふふ…端的に申し上げますとわたくしの目的はあなた様の身体と心ですわ…♡」
「なっ…!」
リリの口から紡がれた言葉にオルトは驚きを隠せず、一瞬固まってしまう。この女の狙いが自分だということに一瞬理解が追いつかない。
「あなた様のような素晴らしい殿方との、激しく、獣のように、溶け合うように、濃密な交じり合いをわたくしは…夢見ておりました♡」
(この女は…魔王の代わりに俺で自分の下劣な欲を満たそうというのか…!)
サキュバスという魔物の本質をそのまま具現化したような存在、それが眼の前の女ということだ。夫の敵であろうとも、自らが満たされるためならば何も気にしない、人間とは全く異なる考え方。異常な考えを持つリリの姿に恐れを感じながらもオルトは真っ向からリリの言葉を拒絶する。
「悪いがお前のような売女と交わるほど女には困ってないんでな…!」
「うふふ…なるほど、そのようですわね♡勇者さまにはお相手がいらっしゃるようで…その指輪、婚約されているのでしょうか?」
リリに指摘され、いつまにか握りしめていた指輪を見る。懐にあるもう一対の指輪を渡すまでオルトは死ぬことができないのだ。その想いが体力の尽きたオルトを突き動かす原動力となっていた。
「そうですね、人間の女がこんなに素敵な勇者様を放っておくはずありませんもの…うふふ…でもそれなら簡単なことですわね」
優雅な足取りで魔王の玉座の肘掛けに手をおいたリリは凄まじい魔力を纏ったままこちらを見つめる。吸い込まれるような瞳がオルトの視線を捉える。
「何が簡単だって…!?」
「あなた様を私のものにする方法…ですわ」
肘掛けから移動し、玉座の座面を撫でてからリリは玉座に腰掛ける。魔王の座った姿とはまた違う得も言われぬ威圧感がリリから放たれる。
「俺に勝てる自信でもあるのか…?例え俺が今弱っていたとしてもお前程度なら倒すことはできるぞ!」
「あら真正面から勇者様と戦うなんて恐れ多いことはいたしませんわ。魔王さまが負けてしまった相手にわたくしが勝てるはずありませんもの…」
眼を瞑り首を振ってリリはそう言うと、足を組み、玉座から見惚れるようにオルトを眺める。
「ですが例えあなた様が選ばれし勇者であっても…男性である限り、肉欲には逆らえぬもの」
リリの甘ったるい声がオルトの耳から脳に伝わるように響く。部屋に充満する甘い匂いがさらに濃度を増し、むせ返るようなほど強くなっていく。
(魅了魔法がさらに強くなっている…!この力…こいつただのサキュバスじゃ…!)
魅了魔法は本来、格上の相手には全く意味を成さない魔法である。そもそも勇者の魔法耐性の上から状態異常を発現させるなど今までただの一度もなかった。
「…ましては魔王さまとの戦いの後、体力も気力も限界でしょう。その状態でわたくしの魅了に耐えられますか…?」
「ちっ…!」
確かにオルト自信、魔王との戦いで限界が近かった。今もなんとか魅了に耐え切っているがこのまま長時間耐えられる保証はない。
「あなた様がわたくしの魅了に負け、わたくしを自ら求めた時、それがあなた様の心と肉体がわたくしのものになるときですわ」
(それならば魅了に完全に掛かる前にこの女を倒してしまえば…っ!)
確かに勇者は押され始めていたがこの女自体の戦闘力は高くない。魅了自体もまだ耐えられる。まらばその前にこの女を斬り倒せばいいだけの話だ。
「勇者様も理解されたようですね?そう、わたくしがあなた様を魅了するか、あなた様がわたくしをその剣で斬るかどちらが先かということですわ」
リリは未だに余裕の態度を崩さない。無防備な状態のままオルトは眺めるのみだ。それだけこの女には勝算があるということだろう。
「サキュバスクイーンたるわたくしに男性である勇者様がいつまで抵抗できるか…楽しみですわ♡」
挑発的に微笑むリリは腕を組み、その豊満な胸を主張しながらオルトと対峙する。オルトは何も言わず剣を抜き、いつでも突進できるように構える。
「では…簡単に堕ちないでくださいね?苦労して手に入れたものほど…魅力は増すものですし…ね♡」
リリの瞳が一瞬、ピンク色に輝いた。つぎの瞬間今までの倍以上の魅了の魔力が魔王の間を包む。
(…っ!?な、なんだこれはっ…!)
思わずオルトは自分の指輪を握りしめた。そうしなければ自分の理性が崩壊してしまいそうだったのだ。それほどまでに一瞬でリリの姿が淫靡であり魅力的に見えてしまった。突然の強大な力にオルトに隙が生まれる。
「んっ♡…見てください、私の胸、あなた様を想ってもうこんなに…あんっ♡」
そこに畳み掛けるようにリリは玉座に座ったまま自らの乳房を揉みしだき、嬌声を上げた。白く滑らかな肌が踊り、大きな乳房がリリの手の形に自由自在に形を変える。張りのある乳房は揉みしだかれるたびに揺れ、さら服の上からでも分かるくらいに乳首がその形を主張していた。その淫猥な光景とともにリリの魅了の効果がますます強くなる。視界に霧がかかったように景色が薄れるが、何故かリリの姿だけはさらに鮮明になっていく。
(こ、こいつ、まさか…いままでっ!!)
「それともお尻がよろしいですか…?恥ずかしながら少し大きいのですが…それでも人間のものとは比べ物にならないでしょう?」
リリは玉座の背もたれに垂れかかるように後ろを向くと尻をつき出しこちらに向かって淫らに、いやらしく動かす。尻尾と共にゆらゆらと揺れる豊満な尻に女性的な魅力を感じられずにはいられなかった。尻から腰のラインの浮き出た服装によってさらにその魅力を増している。オルトは虜になったように尻を見つめてしまう。
(こいつ、さっきまで魅了を…使って、いなかったのか…!!)
明確な恐怖がオルトを襲う。リリが現れた時からその魅了に耐えてきたと思っていたオルトだが実際は違った…リリは魅了など行なっていなかったのだ。オルトが魅了だと感じていたのは、ただリリから溢れだすその残滓のみ、今オルトが受けているこれこそ紛れも無い【魅了】だということだ。
「さぁもっと近づいてわたくしを見てください、情欲に身を任せ、勇者ということも忘れてわたくしを求めてくださいませ♡」
「ぐっ…くそっ…!」
意識が朦朧とし、身体が段々と火照り出す。視界から入る興奮と部屋に充満する匂いは確実にオルトの身を犯し、侵食していた。オルトはよろよろと吸い寄せられるようにリリに向かって一歩踏み出してしまう。意識とは別に身体が操られていく感覚――紛れも無い魅了だった。
「あらあら…その様子だとどうやらお尻はお好きなようですね…♡では、足はどうでしょうか?」
そう言ったリリは微笑んで再び正面を向くと脚を組み太ももを見せつけるように撫でる。絡み合ったことでむちむちとしていて、それでいて美しい絶妙なバランスを持った太ももが強調され、オルトの視線が惹きつけられる。さらにスラっとした下腿から爪先まで黒いタイツによってさらに美しく魅せつける。
「…っ…はぁ…はぁ…」
「うふふ…興奮してらっしゃるようですわね、サキュバスの肉体は男の願望から生まれた至高の肉体、サキュバスクイーンたるわたしはすべての男性の願望を遥かに超えた肉体を持っているのです…♡」
リリの肉体、言葉、仕草、全てが男性の願望を超えたもの。オルトが男性である限り、リリの肉体はオルトの想像する最高の女性の肉体を超えたものとなる。オルトが知っている女の身体など一人しか知らない。すなわちリリの肉体はオルトの妻以上の肉体であるということだった。
「ねぇ勇者様…?私のものとなれば何時でも、この身体を好きにしていいんですよ?」
サキュバスクイーン――すべてのサキュバスの頂点に立つ女王。その圧倒的な力に勇者の理性と意識は敗れそうになってしまっていた。たとえ万全の状態であってもこの力に対抗できたか定かではない。それほどまでの強力な力に体力も精神力も底をついていたオルトが対抗できるはずもなかった。一歩また一歩とオルトは自らリリに近づいていく。
「それとも…やはり、男性ですもの…ここを御消耗でしょうか?」
「なに…を…!?」
ゆっくりとリリは組んだ脚を解くと右脚を椅子に乗せるように上げた。膝を曲げて椅子の上に脚を乗せたことで必然的にオルトの視線はその美しい足先からむちむちとした太ももへ、そして最後に脚を組んでいた時には見えなかったリリの股間へ視線が固定される。
「…ぁ…っ」
それをちらりと見た瞬間、今まで抑えていたものが一気に溢れだすようにオルトの中の何かが決壊した。半勃ちだったペニスは一度にその硬度を増し、口を半開きにして食い入るようにそれを見つめる。
「うふふ…服の上からでもわかるくらい、蜜が溢れてれているでしょう…?もっとしっかり見つめてくださいませ…わたくしのここもあなた様が欲しくてたまらないのです…♡」
脚椅子の背もたれからずり落ちるような姿勢になったリリはもう片方の脚も上げ両脚を自らの手で支えながらその股間を惜しげも無く晒した。完全に開かれたそれは薄いレオタードとストッキングしか着けていないためか、恥丘の形が鮮明に浮かび上がり、ヒクヒクと動くその様子までがオルトに伝わる。すでにレオタードは湿り気を帯びており、濃厚な香りがオルトの嗅覚を侵食する。
(く…っ…い、しきが…)
目の前に存在するあまりにも淫猥なそれはオルトの意識までも奪おうとしていた。握った剣を放り出し、すぐにでもむしゃぶりつきたい衝動がオルトを駆け巡る。
(…お、れは…かえ…るんだ)
何のために帰るのか、誰のために帰るのかすら今のオルトが意識していたかはさだかではないが、オルトは無意識のうちにポケットにある妻に渡す指輪を握り締める。溢れ出る欲望を最後の最後でせき止めながら一歩一歩とリリに迫る。玉座との距離はあと5歩ほどだった。
「もっと、もっと近くにいらして…、一度サキュバスの蜜壺を味わったら二度と人間の女では満足できませんから…♡」
微笑みながら誘惑を続けるリリは完全に余裕を見せて油断していた。無意識のうちに勇者の勘がその好機を告げる。リリまでの距離はあと3歩、既に勇者の剣は届く距離だった。
「さぁ勇者さ…っ!?」
その瞬間、オルトは剣を両手で構え一気に振り上げた。リリが一瞬余裕の微笑みを崩し、驚愕の表情を浮かべ、その動きが止まる。
「おれは…帰るんだぁぁっ!!!」
その好機を逃さず、戦士は全力でその手の剣を振り降ろした。
「はぁ…はぁ…」
「…ここまで勇者が強くなっているとはな…!」
荘厳な装飾品の並ぶ大きな広間にその二人は対峙していた。
一方は洗練された闘気を纏い、勇者の紋章の刻まれた聖剣を構える。
一方は凄まじい威圧感を放ち、魔王の証である魔剣を振り上げた。
「これで…終わりだっ!!」
聖剣を構えるその青年は勇者オルト。魔王を倒し、世界に平和をもたらす存在と天命を受けた世界でただ一人の男であった。精悍な顔立ち、細身であるが一切の無駄のない引き締まった身体、数々の戦いで鍛えられた技の冴え、その全てが勇者として相応しい者と言える。そして聖剣を構えた勇者オルトは今まさに魔王を討ち果そうとしていた。
「ふ、ふははははっ!!!!面白いっ!私を打ち倒してみろ勇者オルト!」
対するはオルトの2倍はありそうなほどの巨躯、天に逆巻く角、人目見ただけで呪い殺されそうな悪魔の相貌、光を飲み込むような漆黒の翼、全てを切り裂くような爪、大地を割るかの如き蹄をもつ異形の存在、すべての魔物を統一する魔王と呼ばれる者だった。魔王がこの世界に現れてから数十年、長きに渡り人間を苦しめてきたその存在は全身に傷を負い、左腕は切断され、片角が折られ今まさに命を散らそうとしていた。ただその状態であってもなお、魔王の放つ威圧感は変わらない、むしろさらに増しているように見えた。
「…光よ!俺に力をっ!!!」
オルトは構えた剣にすべての力を込めた。勇者の力を込められた聖剣はから光が溢れ、刀身を聖なる気が纏っていく。そして光は収束し、凄まじい輝きとなって剣全体を太陽のように発光させた。徐々に光は炎となり、ついに勇者の全身の鎧までもが白き炎に包まれた。
「奥義…白炎!!!」
「来い、勇者っ!!!」
オルトが叫んだ瞬間、勇者から立ち上った陽炎が揺れた。魔王もそれを迎え撃つように魔剣を構え、魔力を剣へと集中させる。闇の魔力を纏った魔剣が今まさに勇者を両断しようと剣を振り下ろした。その瞬間、白炎を纏った勇者の姿が一瞬にして消え去った。
「…ふははっ!見事…!!」
闇を裂くように白い光が一閃した。そして魔剣を振り下ろした姿のまま、魔王は満足したかのように笑った。その胴体に3つの線が入り、切り口に小さく白き炎が揺らめいく。
「終わりだ…魔王」
オルトは超高速の斬撃から魔王の背後で剣を振りぬいたまま静止した。次の瞬間、背後で白い爆炎が全てを浄化させるかのように包み込み、魔王の身体は灰燼とかした。爆炎が収まった時、燃え残った魔剣以外、何もなかったかのようであった。
「…くっ!…はぁ…はぁ…」
力を使い果たしたかのようにオルトは膝をついた。ギリギリの戦いだった。実力は均衡しており、一歩間違えればこちらがやられていた。奥義白炎によって全気力を使い果たし、現在のオルトには戦う力がほとんど残っていなかった。
「…終わったよ、皆…」
勇者は仲間を想い、涙を流して呟いた。この魔王の間まで来るまでに仲間はその身を捧げて勇者をほぼ無傷で魔王の間まで送り届けたのだった。魔王軍幹部と相打ちになった者、幾千の魔物相手に一人で囮になった者、生命力を全て使い果たし、最後は身を呈して勇者を庇った者、彼らの力がなければ勇者が魔王を倒すことは不可能だった。
(くっ…魔力が無くなる前に通信魔法で王に報告を…)
最後の魔力で最大国家である中央王国の王に「魔王、討伐」とだけ通信を送る。
「…今帰るからな」
戦いの前に送るはずだった結婚指輪を撫で、故郷に置いてきた妻を想う。元々旅の仲間であった彼女は最後の戦いには連れて行かなかった。もし自分に何かあったときに彼女だけは守ろうと思ったためだ。仲間たちと勇者は結託し、彼女を説得したのだった。そして戦いが終わった暁にこの指輪を渡すつもりだったのだ。
(これで…帰れるんだ…やっとこの指輪を…)
オルトは自分の指にはまっている指輪と同じ指輪を握り締める。力の入らない手足を無理矢理動かしてその場から立ち上がろうとした。
ギィ……
その時、扉の軋む音が背後から聞こえた。オルトの入ってきた正面の荘厳な扉は開かれておらず、オルトは反射的に振り返った。
「…あら、騒がしいと思ったら…」
ねっとりとした甘い女の声が魔王の間に響いた。その人物は勇者のいる魔王の玉座から少し離れた場所から現れた。物陰でありシルエットしか見えなかったが、頭から生える悪魔の角、細長いエルフのような耳と腰付近から生える悪魔の羽、背後に見える尻尾の影がその者を人間でないことを表している。勇者は手に力の入らない手に無理矢理力を込めて聖剣を構えた。
「この魔力の残滓…魔王様を倒したのはそこのお方?」
「誰だっ!」
ゆっくりとその人物がこちらに近づいていくる。影が消え、その姿が明らかになったとき…オルトはただ、単純にその人物に見惚れた。いや正しくは見惚れることを強要されたかのようだった。
「名前も名乗らず申し訳ありません、私の名前はリリトゥと申しますわ、呼びづらい名前ですからリリとお呼びくださいませ」
それは間違いなく誰もが見惚れ、心を奪われるような絶世の美女であった。少女のような可愛らしさから女性の色香まで全てをを併せ持ったその顔貌は正に完璧としか言えなかった。しかしその美しさは彫像や女神のような美しさでは決してない。潤んだ大きな瞳、雪のように美しい白い肌、ピンク色の潤った艶かしい唇が、ただひたすらにオルトの情欲を掻き立てる。その魔性の美しさはまるで娼婦のように妖艶な雰囲気を纏っていた。
「それで…魔王さまを倒したあなた様はどなたでしょう?」
「…っ!!」
煌めくような長い美しい金髪が歩くたびにさらさらと揺れる。問いに対してオルトは何も答える事ができなかった。リリトゥと名乗った女性の全身から目を離せず、ただ引きこまれていた。
(なんだ…これは…!)
そのあまりに現実離れした美しすぎる顔貌もそうだったが、それと同等、いやそれ以上に眼の前の女性の身体は凄まじいものだった。美しく淫靡に揺れる乳房から煽情的に曲線を描く、くびれた腰、レオタードがぴったりと張り付き、その形と割れ目を強調する股間、黒いストッキングがぴったりと張り付くむっちりとした太ももから美しい足先。リリの全身からあふれる凄まじい色気にオルトの股間は反応してしまいそうになる。
「あら答えてくださらないの…?わたくしの魅了に逆らえるなんて…魔王様を倒した実力は本物のようですわね」
何も答えないオルトに感心するようにリリは微笑む。実際、オルトはまだリリの肢体から目を離すことができなかった。
(これはサキュバスの魅了…!?こここまで強力なものが…!?)
オルトはこの感覚を知っていた。サキュバスという希少な魔物が使用する魅了魔法の効果だ。この独特の甘い匂いとその肉体で獲物の理性を崩壊させ、意のままにしてしまうものだが、勇者の魔法耐性の前にはほとんどが無効化されるはずだった。しかし不意打ちのようだったとは言え、目の前の女から感じる尋常ではない魅了の魔力は勇者であるオルトすら飲み込みそうなほどであった。
(…耐えろ…っ!!)
勇者は理性が崩壊しそうになるのを必死に耐えた。全力で片方の手もう片方の手を握りしめた瞬間、自分の指に嵌めた結婚指輪が目に入った。その瞬間、脳内に故郷で待つ妻の笑顔が浮かんだ。
(絶対帰ってきてくれ…オルトっ!)
リリの身体を食い入るように見つめていたオルトはそこで電撃が走ったように我に返った。勇者の魔法耐性が魅了の効果を上回り、オルトは正気を取り戻す。知らぬ間にオルトまであと10歩程度の距離まで迫ったリリに魅了を吹き飛ばすように名乗りを上げる。
「…俺は勇者オルト、魔王を打ち倒したものだ!」
「あら…やはりあなたが勇者オルト様ですのね…♡」
「お前は誰だ!なぜ魔王の間にいる!」
リリトゥの一挙手一投足にオルトの視線は奪われそうになるが、オルトの精神力はなんとかそれを上回っていた。一時的に魅了を打ち消し、油断なく聖剣を構えてオルトは問う。
(魔王の間までの魔物は仲間たちが命を賭して倒した…この部屋にいるはずの魔物は本来、魔王だけだ…!)
魔王軍の幹部は全て勇者一行に魔王の間までの戦いで倒されているはずだった。そもそも高位の魔物でなければ魔王の間に入ることは許されないはず…つまりこの魔物は相当に高位の魔物であるということだ。
「先ほども申しました通り、名はリリトゥ、あなたが倒された魔王様の第三夫人ですわ」
「第三…?魔王の妻は魔王軍幹部に二人だけじゃ…!?」
「私は表に出ることはほとんどありませんでしたから…彼女達はとても聡明でお強かった。それに比べて私はただ一族の代表として嫁がされただけ…戦いは苦手なのですわ」
オルト達人間の掴んでいた情報では魔王の第一、第二夫人は双方とも魔王軍の幹部であった。そしたここにくるまでの戦いで仲間たちが自分の命と引き換えに倒した相手でもあった。
(魔王の妻ならこの部屋にいることも納得できる…くそっ…!今の体力でこの女に勝てるのか…?)
眼の前にいるリリトゥと名乗った魔物は戦闘は苦手といっているがあの魔王の第三夫人だ。恐らく相当の戦闘能力、もしくは特殊な力を持っているだろう。内心に焦りを見せながら聖剣を構える勇者にリリはさらに近づき言葉を続ける。
「うふふ…それにしても魔王さまを倒してしまわれるなんてとてもお強いなのですね」
「…お前も魔王の後を追いたくなかったらさっさと消えるんだな」
勇者は聖剣を向けるとそう言ったが、ほとんどはったりに近かった。実際のところ勇者の身体は魔王との戦いで力を使い果たしていたのだ。
「あら…怖いこと仰らないで、わたくしは勇者様を恨んでなどいませんのに…」
「…なに?どういう…」
そう言った瞬間、リリは背の羽をゆっくりと広げた。その瞬間、彼女の周囲に魔力が可視できるほどの濃度で集まり始めた。
(…来るか!)
聖剣を構えて勇者はリリを迎え撃とうとした。しかし何故かリリが襲い掛かってくることはない。それどころかその場所から動こうともしなかった。
「構えなくても結構ですわ勇者さま?わたくしは戦う気などないのですから」
リリは凄まじい魔力を纏いながら、その場で言葉を続ける。リリの意図が分かりかねたオルトは黙ってリリの隙を伺い続けた。
「勇者オルト様、わたくしはあなた様に興味がありましたの」
「なに…?」
「わたくしは淫魔、殿方と交わり、愛し合うことを生業としています」
「…ふん、それで相手の男は最後は生命力を吸い取って殺してしまうんだろう、淫魔とはそういう生物だ」
「あら、それは軟弱な殿方が悪いのです…ともかくわたくしは淫魔である限り、殿方と交わらなければなりません」
リリは悲しみの表情を浮かべ、自らの身を両手で抱きしめる。突然語り始めたリリに困惑しながらも緊張をゆるめないオルトだったが、リリが自らを抱きしめることで腕の間で潰れる乳肉と太ももが絡み合う様子が目に入ってしまい、さりげなく目をそらす。
「魔王様はあなた様との戦いのことばかり…世継ぎのことも考えずわたくし達の誰とも交わりませんでしたわ…城内の魔物ではわたくしとの交わりに耐えられる者は中々居らず…稀に現れても一度きりで力尽きてしまう者ばかり」
オルトにさらに一歩近づきながらリリは話し続ける。思わず一歩後ろにさがりながらもオルトはなおも油断なくリリを注視し続ける。
「わかりますか…?淫魔としての性…ひたすらに狂おしく、身を焦がすほどの情欲がわたくしを捉えて離さないのです」
「そんな下劣な考えは分からないな…!」
「うふふ…本当につれないお方…わたくしは思いました、魔王さまに匹敵する器を持った方ならばわたくしを満たしてくれると」
「どういう…ことだ」
魔王と戦っているときに感じた圧倒的なプレッシャーとも違う、生ぬるい、包み込むような異様な感覚をオルトは味わう。リリの言葉から嫌な予感をひしひしと感じた。
「ついに…見つけました、精悍な顔立ちと肉体、世界で一人の選ばれし者、そして…」
「魔王様すら打ち倒したお方を」
紅潮した頬に上品に片手を当て、リリは潤んだ瞳で舐めるようにオルトの全身を眺めた。ぞくっとした感覚がオルトの背中を走る。情欲にまみれたその視線は動物が餌となる獲物を見定めるようだった。
「わたくしを満たしてくれるのは…もうあなた様しか考えられませんわ…勇者オルト様♡」
「…っ!」
微笑みを浮かべオルトを見つめるリリの姿に一瞬、オルトは言葉を失う。
「…何が目的だ…!」
「うふふ…端的に申し上げますとわたくしの目的はあなた様の身体と心ですわ…♡」
「なっ…!」
リリの口から紡がれた言葉にオルトは驚きを隠せず、一瞬固まってしまう。この女の狙いが自分だということに一瞬理解が追いつかない。
「あなた様のような素晴らしい殿方との、激しく、獣のように、溶け合うように、濃密な交じり合いをわたくしは…夢見ておりました♡」
(この女は…魔王の代わりに俺で自分の下劣な欲を満たそうというのか…!)
サキュバスという魔物の本質をそのまま具現化したような存在、それが眼の前の女ということだ。夫の敵であろうとも、自らが満たされるためならば何も気にしない、人間とは全く異なる考え方。異常な考えを持つリリの姿に恐れを感じながらもオルトは真っ向からリリの言葉を拒絶する。
「悪いがお前のような売女と交わるほど女には困ってないんでな…!」
「うふふ…なるほど、そのようですわね♡勇者さまにはお相手がいらっしゃるようで…その指輪、婚約されているのでしょうか?」
リリに指摘され、いつまにか握りしめていた指輪を見る。懐にあるもう一対の指輪を渡すまでオルトは死ぬことができないのだ。その想いが体力の尽きたオルトを突き動かす原動力となっていた。
「そうですね、人間の女がこんなに素敵な勇者様を放っておくはずありませんもの…うふふ…でもそれなら簡単なことですわね」
優雅な足取りで魔王の玉座の肘掛けに手をおいたリリは凄まじい魔力を纏ったままこちらを見つめる。吸い込まれるような瞳がオルトの視線を捉える。
「何が簡単だって…!?」
「あなた様を私のものにする方法…ですわ」
肘掛けから移動し、玉座の座面を撫でてからリリは玉座に腰掛ける。魔王の座った姿とはまた違う得も言われぬ威圧感がリリから放たれる。
「俺に勝てる自信でもあるのか…?例え俺が今弱っていたとしてもお前程度なら倒すことはできるぞ!」
「あら真正面から勇者様と戦うなんて恐れ多いことはいたしませんわ。魔王さまが負けてしまった相手にわたくしが勝てるはずありませんもの…」
眼を瞑り首を振ってリリはそう言うと、足を組み、玉座から見惚れるようにオルトを眺める。
「ですが例えあなた様が選ばれし勇者であっても…男性である限り、肉欲には逆らえぬもの」
リリの甘ったるい声がオルトの耳から脳に伝わるように響く。部屋に充満する甘い匂いがさらに濃度を増し、むせ返るようなほど強くなっていく。
(魅了魔法がさらに強くなっている…!この力…こいつただのサキュバスじゃ…!)
魅了魔法は本来、格上の相手には全く意味を成さない魔法である。そもそも勇者の魔法耐性の上から状態異常を発現させるなど今までただの一度もなかった。
「…ましては魔王さまとの戦いの後、体力も気力も限界でしょう。その状態でわたくしの魅了に耐えられますか…?」
「ちっ…!」
確かにオルト自信、魔王との戦いで限界が近かった。今もなんとか魅了に耐え切っているがこのまま長時間耐えられる保証はない。
「あなた様がわたくしの魅了に負け、わたくしを自ら求めた時、それがあなた様の心と肉体がわたくしのものになるときですわ」
(それならば魅了に完全に掛かる前にこの女を倒してしまえば…っ!)
確かに勇者は押され始めていたがこの女自体の戦闘力は高くない。魅了自体もまだ耐えられる。まらばその前にこの女を斬り倒せばいいだけの話だ。
「勇者様も理解されたようですね?そう、わたくしがあなた様を魅了するか、あなた様がわたくしをその剣で斬るかどちらが先かということですわ」
リリは未だに余裕の態度を崩さない。無防備な状態のままオルトは眺めるのみだ。それだけこの女には勝算があるということだろう。
「サキュバスクイーンたるわたくしに男性である勇者様がいつまで抵抗できるか…楽しみですわ♡」
挑発的に微笑むリリは腕を組み、その豊満な胸を主張しながらオルトと対峙する。オルトは何も言わず剣を抜き、いつでも突進できるように構える。
「では…簡単に堕ちないでくださいね?苦労して手に入れたものほど…魅力は増すものですし…ね♡」
リリの瞳が一瞬、ピンク色に輝いた。つぎの瞬間今までの倍以上の魅了の魔力が魔王の間を包む。
(…っ!?な、なんだこれはっ…!)
思わずオルトは自分の指輪を握りしめた。そうしなければ自分の理性が崩壊してしまいそうだったのだ。それほどまでに一瞬でリリの姿が淫靡であり魅力的に見えてしまった。突然の強大な力にオルトに隙が生まれる。
「んっ♡…見てください、私の胸、あなた様を想ってもうこんなに…あんっ♡」
そこに畳み掛けるようにリリは玉座に座ったまま自らの乳房を揉みしだき、嬌声を上げた。白く滑らかな肌が踊り、大きな乳房がリリの手の形に自由自在に形を変える。張りのある乳房は揉みしだかれるたびに揺れ、さら服の上からでも分かるくらいに乳首がその形を主張していた。その淫猥な光景とともにリリの魅了の効果がますます強くなる。視界に霧がかかったように景色が薄れるが、何故かリリの姿だけはさらに鮮明になっていく。
(こ、こいつ、まさか…いままでっ!!)
「それともお尻がよろしいですか…?恥ずかしながら少し大きいのですが…それでも人間のものとは比べ物にならないでしょう?」
リリは玉座の背もたれに垂れかかるように後ろを向くと尻をつき出しこちらに向かって淫らに、いやらしく動かす。尻尾と共にゆらゆらと揺れる豊満な尻に女性的な魅力を感じられずにはいられなかった。尻から腰のラインの浮き出た服装によってさらにその魅力を増している。オルトは虜になったように尻を見つめてしまう。
(こいつ、さっきまで魅了を…使って、いなかったのか…!!)
明確な恐怖がオルトを襲う。リリが現れた時からその魅了に耐えてきたと思っていたオルトだが実際は違った…リリは魅了など行なっていなかったのだ。オルトが魅了だと感じていたのは、ただリリから溢れだすその残滓のみ、今オルトが受けているこれこそ紛れも無い【魅了】だということだ。
「さぁもっと近づいてわたくしを見てください、情欲に身を任せ、勇者ということも忘れてわたくしを求めてくださいませ♡」
「ぐっ…くそっ…!」
意識が朦朧とし、身体が段々と火照り出す。視界から入る興奮と部屋に充満する匂いは確実にオルトの身を犯し、侵食していた。オルトはよろよろと吸い寄せられるようにリリに向かって一歩踏み出してしまう。意識とは別に身体が操られていく感覚――紛れも無い魅了だった。
「あらあら…その様子だとどうやらお尻はお好きなようですね…♡では、足はどうでしょうか?」
そう言ったリリは微笑んで再び正面を向くと脚を組み太ももを見せつけるように撫でる。絡み合ったことでむちむちとしていて、それでいて美しい絶妙なバランスを持った太ももが強調され、オルトの視線が惹きつけられる。さらにスラっとした下腿から爪先まで黒いタイツによってさらに美しく魅せつける。
「…っ…はぁ…はぁ…」
「うふふ…興奮してらっしゃるようですわね、サキュバスの肉体は男の願望から生まれた至高の肉体、サキュバスクイーンたるわたしはすべての男性の願望を遥かに超えた肉体を持っているのです…♡」
リリの肉体、言葉、仕草、全てが男性の願望を超えたもの。オルトが男性である限り、リリの肉体はオルトの想像する最高の女性の肉体を超えたものとなる。オルトが知っている女の身体など一人しか知らない。すなわちリリの肉体はオルトの妻以上の肉体であるということだった。
「ねぇ勇者様…?私のものとなれば何時でも、この身体を好きにしていいんですよ?」
サキュバスクイーン――すべてのサキュバスの頂点に立つ女王。その圧倒的な力に勇者の理性と意識は敗れそうになってしまっていた。たとえ万全の状態であってもこの力に対抗できたか定かではない。それほどまでの強力な力に体力も精神力も底をついていたオルトが対抗できるはずもなかった。一歩また一歩とオルトは自らリリに近づいていく。
「それとも…やはり、男性ですもの…ここを御消耗でしょうか?」
「なに…を…!?」
ゆっくりとリリは組んだ脚を解くと右脚を椅子に乗せるように上げた。膝を曲げて椅子の上に脚を乗せたことで必然的にオルトの視線はその美しい足先からむちむちとした太ももへ、そして最後に脚を組んでいた時には見えなかったリリの股間へ視線が固定される。
「…ぁ…っ」
それをちらりと見た瞬間、今まで抑えていたものが一気に溢れだすようにオルトの中の何かが決壊した。半勃ちだったペニスは一度にその硬度を増し、口を半開きにして食い入るようにそれを見つめる。
「うふふ…服の上からでもわかるくらい、蜜が溢れてれているでしょう…?もっとしっかり見つめてくださいませ…わたくしのここもあなた様が欲しくてたまらないのです…♡」
脚椅子の背もたれからずり落ちるような姿勢になったリリはもう片方の脚も上げ両脚を自らの手で支えながらその股間を惜しげも無く晒した。完全に開かれたそれは薄いレオタードとストッキングしか着けていないためか、恥丘の形が鮮明に浮かび上がり、ヒクヒクと動くその様子までがオルトに伝わる。すでにレオタードは湿り気を帯びており、濃厚な香りがオルトの嗅覚を侵食する。
(く…っ…い、しきが…)
目の前に存在するあまりにも淫猥なそれはオルトの意識までも奪おうとしていた。握った剣を放り出し、すぐにでもむしゃぶりつきたい衝動がオルトを駆け巡る。
(…お、れは…かえ…るんだ)
何のために帰るのか、誰のために帰るのかすら今のオルトが意識していたかはさだかではないが、オルトは無意識のうちにポケットにある妻に渡す指輪を握り締める。溢れ出る欲望を最後の最後でせき止めながら一歩一歩とリリに迫る。玉座との距離はあと5歩ほどだった。
「もっと、もっと近くにいらして…、一度サキュバスの蜜壺を味わったら二度と人間の女では満足できませんから…♡」
微笑みながら誘惑を続けるリリは完全に余裕を見せて油断していた。無意識のうちに勇者の勘がその好機を告げる。リリまでの距離はあと3歩、既に勇者の剣は届く距離だった。
「さぁ勇者さ…っ!?」
その瞬間、オルトは剣を両手で構え一気に振り上げた。リリが一瞬余裕の微笑みを崩し、驚愕の表情を浮かべ、その動きが止まる。
「おれは…帰るんだぁぁっ!!!」
その好機を逃さず、戦士は全力でその手の剣を振り降ろした。
カンッ!…カラン…カラン
オルトの振り下ろした剣は、床に落ち、転がった。
「勇者様ぁ…どうですか?サキュバスクイーンの生のここは…♡」
「あ…あぁ…っ!!」
今、オルトの目の前には想像を遥かに凌駕する、「女性」そのものが広がっていた。ただ綺麗で、美しく、淫らな「それ」を前にオルトの理性、意識、感情までもが飲みこまれるように消え去った。もはや勇者の人格というものすら消え入りそうなオルトにリリは変わらぬ調子で話しかける。
「うふふ…サキュバスの服はわたくし達の魔力で作られているのです、どこを消すのも自由自在ですわ」
オルトが斬りかかった瞬間、リリの股間部分の布だけが消失し、それが姿を現した。その瞬間、オルトは剣を握る指を緩めた。その結果、剣は転げ落ちオルトは動きを止めたのだった。
「ご覧になって?人間の物とは比べ物にならないでしょう…サキュバスのここは殿方のあそこを受け入れるため、そして天上の快楽に導いて差し上げるためにあるのです♡」
その声はもはやオルトには届いていない。オルトは今、目の前にある至宝に全ての感覚を使い集中していた。視界で美しい陰唇を、宝石のような陰核を、ヒクヒクと開閉する生々しい淫らな肉色の腟口を、聴覚でクチュクチュと愛液が混ざり合う音を、そして嗅覚でリリの放つ濃厚で甘美な香りを味わっていた。
「あら…勇者様のおちんちんはとっても素直ですわ…♡」
ペニスははちきれんばかりに勃起し、今にも精が溢れそうだった。しかしオルトはその場から動かない、完全に魅了された彼には命令が必要だった。その魅了した相手であるサキュバスクイーンからの命令が。
「さぁ…もっと近づいて、わたくしを…たっぷり味わってくださいませ♡」
開脚して自らその膣口を広げて魅せつけた姿勢のまま、リリがそう言った瞬間、オルトは跪いた。膝立ちになりだらしなく口を開けて涎を垂らしながらその秘部に近づいていく。完全に魅了によって囚われたオルトは自分の欲望に忠実に、素直にただ舌を出してリリの秘裂に顔を埋めていった。
「いらっしゃいませ、勇者様♡」
「はぁ…はぁ…はぁ…ちゅ…れろぉ」
濃密な香りに荒い息を吐きながらオルトはヒクヒクと動く、その蜜壺に口をつけた。その瞬間、オルトの口内にあふれたその味はなにものにも表せない至福の味であった。あまりに甘美な味からそれだけで射精しそうなほどだ。舌の先だけで味わった状態から少しずつ少しずつ舐めるようにねぶるように舌を動かし始める。
「んっ♡…うふふ…どうですか?わたくしのここは美味しいですか?」
「あぁ…っちゅ…れろ…れろぉ…」
オルトは頷きながら夢中でそこを味わい続ける。奥から次々と溢れ出る愛液を舌先で舐めとるように必死に動かして甘酸っぱい至高の味を味わい続ける。もうそこに勇者の姿はなく、誘惑に屈した憐れな一人の男の姿があるのみだった。
「お気に召していただいてなによりです♡…口元をびちゃびちゃにして、まるで子供みたいですわ…可愛い…♡」
「ん…レロ…ちゅ…ちゅ…じゅる…!」
「あんっ…♡もっと味わってわたくしの味を染み込ませてくださいませ」
膣口をなぞり、陰核に吸い付く。思う存分味わった後、溢れ出る愛液を秘裂に唇をつけて吸い尽くすように味わう。リリの汗、愛液の濃密な香りによって視界は眩み、うつろな目になりながらも夢中で吸い続ける。リリはその様子を微笑みながら見つめ、開脚していた脚を徐々に閉じ始める。
「じゅる…じゅるる…ぁ…れろ、れろぉ…」
「さぁもっと味あわせて差し上げます、ほぉら♡」
むぎゅぅぅぅ…
「んむっ!…んっ…はぁ…ぐっ」
夢中で秘裂に舌を這わせていたオルトは顔面を両側から柔らかい太ももで押さえつけられた。そしてそのまま首に下腿をかけられ、さらに秘部へと顔面を押し付けられる。さらに後頭部に手を当てられ抱きすくめるように固定されてしまう。ただ息をすることすらままならず、顔全体にリリの蜜を塗りこまれるようだった。
「あんっ♡鼻息が掛かってますわ…わたくしもそろそろ我慢が…んっ♡」
鼻までもが秘裂に押し込まれ、もはや空気などなくひたすらに甘酸っぱい淫臭に肺と脳が満たされる。
「ん…♡あぁっ、ぁぁっ♡」
「はぁ…ぐっ…じゅるるる…ぁ…じゅる…じゅるるる…」
リリの嬌声が聞こえた瞬間、今までと比べ物もならないくらいの愛液が溢れだし、オルトは溺れそうになりながらもひたすらに吸い付き、舐めとり、愛液を味わった。凄まじいくらいの蜜はオルトの脳をとろかし、心を溶かした。
「はぁ…♡はぁ…あら、もしかして…イっちゃいましたか…?」
オルトの股間から、ズボンから染み出すように白い液体が溢れていた。あまりに強力な催淫効果と媚薬効果のアルサキュバスクイーンの愛液は、意思を失ったオルトを簡単に射精させてしまったのだった。
「…ぁ、ぁ、くっ…」
長い間、その愛液を味わってしまったオルトは、人間としての精神が耐えることができず、肺と脳をリリの愛液ろ匂いに溶かされて…意識を失った。
「…気を失ってしまわれましたか…丁度よろしいですね、場所を移しましょうか、勇者様…♡」
気を失い、床に倒れこむ勇者の股間から溢れる精液を見て、舌舐めずりをしながらリリは微笑んだ。
―――
――――ここは
「気が付かれましたか?」
オルトが意識を取り戻すとそこは見知らぬ部屋だった。美しい装飾品が彩る小奇麗な部屋で、自分はベッドの上で仰向けに寝ているようだった。
「おれは…一体…」
「あなた様は気を失って、倒れこんでしまいましたのでわたくしの部屋にお招きいたしました」
ぼうっとした頭で斜め上を見るとぼやけた輪郭の中でなんとなく女性ということがわかった。靄がかかったように回らない頭でなんとか何があったのかを思い出そうとする。
「まだしっかり起きていらっしゃらないのですか?…思い出してくださいませ」
その言葉を聞いた瞬間、今までの旅、勇者、仲間、魔王、妻、そしてさきほどの出来事がすべて一瞬で頭に走馬灯のように鮮明に現れた。覚醒した勇者は自分が何をしたかを思い出し、羞恥心と屈辱感から顔を真っ赤にしてリリに怒鳴る。
「お前っ!!、よくも…!!」
「あんっ…怒鳴らないでください、これから愛し会う身だというのに…」
「な…なにっ!どういう…」
そこまで言った時にようやくリリの服装に気づいた。さきほどと違い、リリはベビードールのような姿であり、その肌が大胆に露出されていた。なめらかな白い肌、大きく美しい乳房、絶妙な腰からヒップまでのライン、それが目に入った瞬間、オルト一瞬動きを止めてしまう。
(不味い…!あれは魅了を強くするための…!)
先ほどのまでの出来事を鑑みれば、リリの行動は全てが魅了魔法を増強するものに繋がっているはずだ。つまりこの服装も魅了の一種なのだろう。目を背けようとするがどうも先ほどまでと様子が違う。
(…魅了の魔力自体は感じない…どういうことだ?)
疑問を浮かべるオルトを尻目にリリはベッドの上に四つ這いになって上がってくる。そのまま寝そべるオルトの上にゆっくりと這うように近づいてくる。
「っ…!ち…近づくな…」
「言葉に力がありませんわね…ふふっ…」
今すぐにでも眼の前の憎らしい女を殺したい…そう思わなければならないはずなのに、オルトはリリが近づくだけで極度に興奮していた。リリの姿を見るだけで簡単に硬化したペニスは天井に向かってそそり立っている。
「…あぁ…勇者様のおちんちんがこんなに近くに…わたくしはこの時を夢に見ておりました…♡」
寝そべるオルトに覆いかぶさるようにリリは四つ這いになり、見下ろす。下から見上げると揺れる乳房によってリリの顔が隠れてしまい、その表情は窺い知れない。
「な、にを勝手に…っぁ!」
「おちんちんは準備万端のようですわね…わたくしももう我慢出来ませんわ」
再びリリに向かって怒鳴ろうとした瞬間、膨らんだペニスの先端をショーツ越しにリリが股間を押し付け擦りつけた。硬化していたペニスはその刺激から逃れるようにビクンと動くがそれを逃がすことなくリリは巧みに腰を動かす。布一枚越しにすりすりと押し付けられる柔らかな感触に耐えることができず、リリを突き飛ばして逃げ出そうとする…しかしその意思は身体に反映されなかった。
「…くっ…なんでっ、身体が…ぐあっ!」
「気づきましたか…?勇者様の肉体はもう…わたくしの魅了に完全に取り込まれていますもの♡」
「…っ!?」
淫らに動かしていた腰を一旦止めたリリは笑顔でそう言った。言葉の意味が一瞬理解できず、オルトは石化したように表情を固める。魅了にかかっている?自分が?
(それならば何故オレは自分の意思で話せて…)
「今、勇者様がご自分の意思を保てているのかはわたくしが命令したから…あなた様自身の自由意志は既にないということですわ」
「…な、ならなんでわざわざオレの意思を戻した!そんなことに意味は…」
オルトはリリの言葉が信じることができず、青ざめた顔でリリに問う。冷静になることができず、意味のない問いをかけてしまうオルトだが自らに魅了がかかっていることなど信じることができなかった。それが現実だった倍、それは実質、勇者が敗北したということだ。
「うふふ…それは、あなた様の心を本当の意味でわたくしのものにするため…♡」
そう言ったリリはオルトの服のポケットを弄る。そこは恋人への婚約指輪が入っているところだった。
「くっ…!そこは…!!!」
「…♪ありましたわ」
リリはポケットの中から指輪の箱を探り出し、抜き出した。絶対に渡してはならないものを奪われ、オルトの心に怒りが灯る。しかし無情にもその身体は動かず、オルトはその様子を歯噛みをしながらリリを睨みつけることしかできなかった。
「返せっ!!それは…」
「恋人…奥様なる方へあてたものですか?うふふ…やはりそうですのね」
「…っ!?」
オルトの腹部の上に座り込んだリリは箱を開けて勝手に指輪を取り出し、値踏みをするように覗きこんだ。簡単に言い当てられオルトは二の句を継げなくなってしまう。
「良い物ですわね…先ほどから気になっていました、勇者様があまりにわたくしの魅了に逆らうものですから不思議でしたが…その理由がこれですね♡」
「お前…何をするつもりだ!?」
「何を?…勇者様の妻になるのはこのわたくしですもの、これはわたくしがいただきますわ♡」
「ふ…ふざけるなぁぁっ!!!」
リリはさも当然のように笑ってオルトにそう言った。リリの意図を理解したオルトは自分の上に乗るリリに向かい全力の殺意を向けた。身体が沸騰しそうなほどの怒りによって視界が赤くなる。この指輪が奪われたらオルトと妻のすべてが否定されるようだった。そして奪われてしまう自分の不甲斐なさがオルトの怒りを生んだ。
「く…ぉぉっ!!」
その怒りが魅了の力を超えたのか、オルトの左手が動き、リリの腕を握ろうと手を伸ばす。妻の笑顔が頭にうかび、オルトの最後の力がリリにまで届こうとした瞬間、
「確かにいただきました…サイズもぴったりですわ♡」
リリは自らの左手の薬指に指輪をはめてしまった。伸ばしたオルトの薬指に輝く指輪とリリがつけた同じ指輪が重なるように煌めいた。
「あ、ぁ、ぁぁぁぁぁっ!!!」
その姿を見た瞬間、オルトの中で何かが壊れた。動かないはずの身体を動かし、起き上がって、リリに殴りかかろうとした…はずだった。
「落ち着いてくださいませ、勇者様」
その言葉を聞いた瞬間、オルトの身体から完全に力が抜け、ふたたびベッドに仰向けに倒れる。
「くそ…許さないぞ…!!!絶対に…!!」
「もう、自分の妻を睨まないでください…人間の結婚は指輪を渡したらまだすることがあるでしょう?」
「これ以上…なにをっ!!!」
「誓いのキ・スに決まってますわ♡」
仰向けのオルトに垂れかかるようにリリは倒れこんだ。首元にリリの頭が来るような形になり、絡みつくように抱きついてくる。潰れる乳房の柔らかな感触が怒り心頭なはずのオルトの力を強制的に抜いてくる。
「こうして身を寄せ合うだけで、身体が1つになったかのよう…わたくし達の身体の相性はやはり抜群なのでしょうか…♡」
「…っ」
リリはほとんど唇が触れ合う距離でそう囁いた。熱いリリの吐息が感じられるほどの距離にそのあまり美しい顔があるためか、オルトは息を呑んで声を出すことができなかった。そして――リリの言葉は確かだった。リリが抱きついた瞬間、溶け合うような満たされるような感覚がオルトの身を包んだ、そう妻と抱き合ったときには感じられなかった感覚を。
(おれは…おれはっ!!)
今感じた感覚を嘘だと、あり得ないと困惑するオルトに微笑んだリリはゆっくりとその潤ったピンク色の唇を近づける。
「さぁ永遠の愛を誓いましょう…ん…ちゅっ♡」
「ん…ぐっ」
力が抜けた瞬間、リリが滑らかに、しかし素早くオルトの唇を奪った。重なりあう唇から直接リリの体温と唾液の味が伝わり、怒りで火照っていたはずの身体が別の感覚…快楽によって火照り出す。
(く、そ…こんな、もの、で、)
「ちゅ、ちゅ…ん~っ、んっ、ぁむ♡…んんっ」
リリはオルトの唇を完全に塞ぎこみ自らの唾液を流しこむ。歯を閉じようとしても敏感な部分を察知したリリのい舌が這いずり回り、その快楽により強制的に口を開けられる。
「ん…んっ♡れろぉ…れろ…じゅぷ…」
逃さずに唾液とともに侵入したリリの舌がオルトの口内を蹂躙し、オルトの舌を絡めとるかのように動く。口内の犯されるような濃厚なキスにオルトの脳内に靄がかかったかのように意識が快楽に呑まれていく。
「んっ…まぁだ…♡…ぁむっ♡れろっ…ん~っ、ちゅ、くちゅ…んっ♡」
「はぁ…はぁ…んむっ!、んっ、んっ、はぁ、ぁ…っ」
空気を求める息を吸おうとするオルトに容赦なく口を覆うようにリリが唇を塞ぐ。そして再びぬるりとリリの舌が口内に侵入する。オルトの舌に蛇のように巻きついたリリの舌を絡めとり強制的にリリの口内へ吸い取られるように運ばれる。舌が溶かされたような、蕩けるような甘い甘い感覚がオルトを襲い、はちきれんばかりに勃起したペニスも震える。
「ちゅっ、れろぉ…ぅん…ぁむ…じゅ…じゅるっ♡」
(おぼれ、る)
じゅぷじゅぷと唾液が絡みつく水音が聞こえるほど、激しく甘いキスによってオルトは完全にその虜になてしまっていた。先ほどのまでの激しい怒りを快楽で塗りつぶされ、リリから与えれる濃厚なその甘さを身体をビクビクと小刻みに震わせる。酸素を与えらず、代わりにリリの甘い唾液で口内を満たされたオルトはただそのキスに溺れていった。
「ん…ぷはっ♡なんて甘く…心地良い感覚なんでしょう…♡わたくしこのような気持ちになるのは初めてですわ…人間の恋とはこのような感覚なのでしょうか…♡」
「はぁ…はぁ…はぁ…!」
唾液で糸を引きながらお互いの唇がゆっくりと離れる。口元の唾液を舐めとりながらリリは起き上がってオルトに跨るように座った。長い長いキスの末、やっと開放されたオルトはぼやけた視界の中、必死に酸素を取り込む。
「うふふ…儀式は終わりました、後は1つになるだけですね…♡」
そう言ったリリを跨るような姿勢から立ち上がった。ベッドに上でオルトを見下ろすような形になったリリは、微笑みながら自らのショーツに両手をかける。
「ん…♡もうこんなに…これでは下着の意味がありませんわ…♡」
リリはゆっくりと自らの愛液でびしょびしょに濡れた可愛らしいショーツをずり下げていく、片足ずつショーツから脚を引きぬき、用済みとばかりにベッドに投げ捨てる。再び目の前に現れたリリの蜜壺はヒクヒクと淫らに蠢きながら、太ももまで伝うほどの蜜を垂らしていた。
「わたくしも、わたくしのここももう我慢出来ませんの♡…さぁ交わりましょう勇者様」
パチッ
リリが指を鳴らすと勇者のズボンは消失し、完全に勃起したペニスが白昼にさらされた。興奮に興奮を重ねたペニスは亀頭を真っ赤に染め、我慢汁が溢れ出し、ペニス全体を滑らせていた。鈍く輝く勃起したペニスを見つめてリリは恍惚の笑みを浮かべる。
「あぁ…♡こんなに立派に大きく、いやらしいお汁で濡れて…勇者様もわたくしと同じ気持ちなのですね♡」
「…やめ…ろ…!」
オルトは力無く言葉を吐く。これからされようとしていることは妻に対する明確な裏切りだった。しかしそれを期待し、興奮し、待ち焦がれるオルトの身体が徐々にその意思までも侵食しているようだった。言葉では否定しようと、オルトの視線はリリの秘裂に釘付けであった。
(かえる…か、えるんだ、おれは…)
奥底の意識だけが今だに残る。帰りを待つ妻に会うために、その気持ちだけが魅了され、墜落したオルトの最後の一線を守っていた。
(かえって…指輪を…?)
しかし脳にかかった靄が、リリから与えられた快楽がその最後の想いすら絡みとる。指輪を思い出し、そして目の前に立つリリの指にはまっている指輪を見て、そして妻の姿がリリに重なった。似ても似つかないその姿が何故か徐々に鮮明に重なり始める。
「後はこの腰を沈めるだけ…勇者さま?わたくしのここを味わったら…人間の粗悪なそれでは二度と達することはできなくなりますが…もう人間と交わることなど永久にないですから、良いですね♡」
オルトが自らの想いが蝕まれている間に、リリはオルトの股間の上に自らの秘裂を合わせるようにしゃがみこんでいた。その距離はもうほとんど0に近い。
(ゆびわ…はめた、妻、誰が)
妻であるはずの女とリリの姿が二重になり、重なり、再び二重になり…どちらがどちらか、徐々に理解出来なくなっていたオルトは混乱とともに眼の前の景色を認識した。
「ではわたくしの膣内に…いらっしゃいませ…♡」
そうだ、リリと妻であるはずの女を間違えるはずがない。オルトが愛する女はただ一人だ。ぎりぎりのところで意識を保ったオルトが我に返った瞬間、見えたのはリリの幸せそうな笑顔だった。
ぬぷっ…ずにゅ…じゅぷぅっ…
「あぁぁっ!!」
「…あっ♡入って…まいりました…♡」
ゆっくり、ゆっくりとリリが腰を降ろした。亀頭がはリリの秘裂をかき分けその蜜壺へと飲み込まれていく。ぬめったその感触、つぎの瞬間、ペニスに訪れたのはこの世のものとは思えない快楽だった。かつて感じたことのある膣の感触とは比べ物にならない、構造自体が違う淫魔の膣は幾十にも重ねたヒダでオルトのペニスを包み込み、密着し、快楽を与えながら奥へ奥へと飲み込む。
「あ…はぁ…♡この時を、待ちわびておりました…♡」
「…っは…あぁ…」
ずぷん…
膣内の複雑な構造をした淫肉が絡みつきながらもペニスをゆっくりと奥へ運び、最後には根本まで全てを飲み込んだ。腰を完全に下ろしきったリリは快楽に顔を蕩けさせて両手をオルトの胸板に置く。
「だ、めだ、もう…」
リリの蜜壺に飲み込まれたペニスはただ包まれているだけなのに、もう我慢の限界だった。締め付けれているわけでもないのに、動いてるわけでもないのに、快楽をあたえるためだけにあるこの器官は…包み込むだけでオルトを敗北させた。
「ん…イキそう…ですか?駄目ですよ…♡」
「くっ、あぁぁっ…!」
びくんっと一度、リリに組み伏せられたオルトの身体が跳ねた。しかしそのペニスから何故か精液は放出されず、オルトは絶頂に至るギリギリで生殺しのような感覚を味わう。
「んっ、ぐっ、なん、で」
「勇者様は、魅了されていますから…わたくしの命令が無い限りもう勝手に射精することができませんわ」
勇者に跨るリリがそう言った瞬間、膣内がゆっくりと収縮しはじめた。とろとろだった膣内は一ミリの隙間もなく、赤子を抱くように優しく、そして確実に、リリの淫肉が勇者のペニスを締め付け始める。
「っあ!…あ、ぐぅぅっ」
包み込まれているだけで絶頂を迎えているはずのオルトが、その収縮に耐えられるはずもなかった。身体を小刻みに震わせて射精したくでもできない、頭のおかしくなりそうな感覚を味わわせられる。
「後は勇者様の心をわたくしのものにするだけ…勇者様が自分から望んでくだされば、わたくしの膣内で射精させてさしあげます」
オルトの胸に手を置いたリリは胸板を幸せそうに場で回しながら微笑んだ。
「それでは、勇者様が素直になるまで…ゆっくり優しく焦らしてあげます…♡」
じゅぷっ…
リリの腰がゆっくり、ゆっくりと持ち上がっていく。ペニスに絡みつく淫肉は決して強く締め付けるようには収縮せず、あくまで優しく包み込むようだった。淫肉は生き物のようにペニスの表面を愛撫しながら再び膣口まで輸送される。
「ぅ…くっ…あ」
「あっ…はぁ…♡うふふ…お顔が蕩けていますよ」
熱い、溶けそうだ、耐えられるはずがない、しかし達することができない。
体全体が震え、絶頂を求める。はやくイきたいと急き立てる。目の前の女が誰であろうとどうでもいい。この蜜壺にすべてを吐き出してしまいたいと思ってしまう。
「勇者も…んっ…いけない人ですわね。恋人がいらっしゃるのに、他の女でこんなに興奮して…あんっ♡」
淫らに腰を焦らすようにくねらせながら、リリはオルトを挑発するように言葉をかける。その言葉すらオルトにはもう快楽に変換されてしまう。恋人がいるという身でありながら魔王の妻と性交をしているという事実、この背徳の極みとも思える行為に興奮を覚えてしまっていたのだ。
ずぷん…
「うぅ…!あっ…」
「早く素直になりましょう…ね勇者様?もっと気持ちよくなりたいでしょう?」
再びオルトのペニスは膣内に飲み込まれていく。1往復の間にオルトの限界はとっくに超えていた。快楽にオルトの自身の意識が上書きされ、リリを求めてしまいそうになる。魅了の影響でない、オルト自身が、自らリリを求めようとしていた。
(だめだ…おれには、あい、つが…)
妻の姿を思いそうとする、しかし靄がかかったようにその鮮明な姿を思い出せない。
考えようとしてもペニスから与えられる快楽が全てを塗りつぶす。絶頂を求める身体が…心が、恋心を打ち消していく。目の目の快楽を求めるようになってしまう。
(…イきたいっイきたいっイきたいっ!!)
結局、
「…したい」
「…なにか申しましたか勇者様?」
オルトの口から零れた言葉はリリには届かなかった。しかしもうオルトは、我慢することはできなかった。
「…射精、したい」
求めてしまった。
「うふ…うふふっ♡求めてしまいましたのね…勇者様が…魔王の妻であるこのわたくしを」
歓喜の表情を浮かべたリリは両手をオルトの顔の横について、見下ろすような形になった。
「わたくしの膣内で射精してしまったら、二度と人間の女で…勇者様の恋人でイくことは出来なくなります…それでもよろしいでしょうか?」
…こくっ
オルトは朦朧とした意識の中で頷いた。我慢出来るはずもなかったのだ。そもそも、魅了された時点でオルトはリリの身体にどうしようもなく惹かれていたのだから。気持ちだけがリリを否定していた、いや否定しようとしていた。しかし狂おしいほど、壊れるほどの射精欲はオルトを本能のまま動かしてしまった。リリの膣内ひたすらに焦らされたペニスは今にも破裂してしまいそうだ。
「わかりました…♡そんなに切ないお顔をされてはわたくしも意地悪できませんわ…♡」
愛おしそうにオルトの頬を撫でたリリはそのまま身をおろし、オルトを抱きしめた。潰れる乳房とリリの体温がさらに興奮を誘う。リリの膣内がどんどんと密を増し、一ミリの隙間もなく淫肉がペニスに纏わりつき、絡みつき根本から搾り出すように収縮しはじめた。そして
「射精してくださいませ…勇者様」
耳元でリリが囁いた。
どくっ、どぴゅ、どぴゅ、どぴゅ…
止めどなく精液が漏れだした。全てを吐き出すように、リリの膣内を満たすように、白い液体が溢れだす。ビクビクと身体を震わせてオルトは快楽の果てを味わっていた。
「あっ…はぁ…♡なんて、上質で、美味しい精…こんなものがあっていいんでしょうか…♡」
恍惚の表情を浮かべ、リリはその精を味わいながら膣を蠢かせて精液を1滴残らず搾り出そうとする。ペニスに残る精はその膣の収縮によって止まることなく溢れ続ける。
「あぁぁぁぁぁっ…!!」
どぴゅ…どぴゅ…
いつまでも終わらないかのような長い射精がそこで止まった。妻を裏切り、宿敵の妻への射精は、今まで感じた中で一番の絶頂だった。
「ん…♡いただきました…あら、ふふっまだまだ射精したりないようですね…♡」
「も、もっと…」
射精の終わったペニスは萎えることなく、リリの膣内でその硬度を保っていた。オルトはタガの外れたようにリリの膣内での射精を求める。
「あらあら…おねだりしてしまうほど、気持よかったですか?うふふっ少しお待ちくださいませ」
ぎゅ…ぐにゅ
リリをの膣内が生き物のように胎動し、オルトのペニスを包み込み、その形を変えていく。イかせるような動きではなく、ただその形を覚えるような動き。
「今、勇者様を、わたくしの膣が記憶しています。勇者様だけを気持ちよくするために、勇者様だけの蜜壺に形を変えるのですよ」
ぐにゅ…ぐにゅ…ぎゅっ!
「あぁっ!、くっ、あ、」
「はい、出来ました…これでわたくしは勇者様だけのものです…あぁん♡」
「くっ、あぁぁっ!!」
どぴゅ、どぴゅ、どぴゅ…
その形となった瞬間、射精した。オルトのペニスに最適化した膣内はこれ以上に締り、締め付け射精したばかりの敏感なペニスには耐えられるはずもなかった。射精している間も淫肉がひたすらにペニスに纏わりつき、愛撫し、搾りだし続ける。
「あんっ♡もう…おもらししてるみたいですわ…まだ動いていませんのに」
「はぁ…はぁ…はぁ…」
(気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい)
そこにあるのは圧倒的な快楽だった。オルトは今人生で一番幸せなときを味わっているのだ。よく考えたらなぜ自分があんなにも否定していたのかが不思議だった。
「では…サキュバスクイーンの腰使い、ご堪能下さいませ」
ずぷっ、ずぷっ、じゅぷっ、ずちゅ…
股間にまたがったリリが淫らなダンスを踊る。跳ねる乳房、淫らな香り、膣の感触、腰の動き全てがオルトを簡単に絶頂へ導く。腰が1振りするたびに精液と愛液が交じり合った液体が結合したリリの膣口から漏れだす。
(そうだ、なぜあの女に固執していたんだろう…)
今なら恋人の顔も思い出せた。いやもう恋人ではない、あんな女などリリに比べたら取るに足らない存在だ。
(リリの方が美しい、可愛らしい、淫らだ、いい匂いがする、気持ちがいい)
激しくなっていくリリの腰振りに、オルトのペニスは壊れた蛇口のように精液を放出し続けた。魅了の効果だろうとなんだろうともうどうでもいい。眼の前の愛おしい女から与えられる快楽が今のオルトの全てだった。
ぐちゅ、ぐっちゅ、ずちゅ、じゅぷ、じゅぷぷっ!、
淫らな水音を響かせながら繋がり合う、二人はお互いの目を見つめ合い、愛しあいながら1つの生物のように絡み合う。
「ん…♡はっ…どうですか?人間なんかよりもとっても気持ちがいいでしょう?」
「あ…あ…」
「…オルト様、わたくしと、毎日こうして愛しあいましょう…ね♡」
「ああ…」
「結婚…いたしましょう…♡」
「ああ」
繋がりながら、リリははめていた指輪をはずして、一度オルトに返した。そしてその左手を差し出す。オルトはそれを受け取り、リリの指に再び、優しくゆっくりとはめた。
「嬉しい…♡んっ♡わたくしも、そろそろ…一緒に」
「あ…あ、あ、くっ」
じゅぷっ、じゅぷっ、じゅぷぅぅっ!!
さらに動きが激しくなり、水音も響き渡る。いつのまにか下にいるオルトも腰を突き上げ、お互いが激しく互いの身体を貪るように求め合っていた。
「あっ♡、あっ♡…あぁぁぁぁぁんっ♡」
「くっ、は、あぁぁぁぁぁっ!!」
どぴゅぅぅぅぅぅっ…
オルトは腰を思いっきり突き入れて、子宮口に精液を注ぎ込んだ、リリは反り返って歓喜の表情を浮かべて嬌声を上げながら絶頂に達した。限界を遥かに越えて精液を放出したオルトはその瞬間、完全に意識を失ってしまった。
「はぁ…はぁ…これからよろしくお願いしますね、オルト様…♡ちゅっ♡」
オルトの胸にすがりつくように倒れこんだリリは、心底、愛おしそうにオルトにキスをした。
…
1年後
「魔妃リリトゥ!!世界のため…死んでもらうっ!!」
荘厳な魔王の間の扉を押し通りながら勢いよく女がそう言った。
相当な美人だがその険しい表情のせいで冷く見えた、長い金髪を1つにまとめ軽い鎧をまとった女騎士は薄暗いその部屋を見回す。
(誰もいない…!?…いや何か音が…それにこの匂い…)
何か規則的な水音のようなものが聞こえた。そして部屋中に溢れる甘いような、そしてどこか淫靡な香りが鼻につく。よく見渡すと薄暗い部屋の中心、玉座のようなところに誰かが居るのがわかった。
「…誰だっ!リリトゥかっ!!」
女騎士は玉座に一気に近づいた。そこで見たものは男女二人が性交をしている様子だった。玉座に座る男の上に、この世のものとは思えないほどの絶世の美女…おそらくその羽と角、尻尾からサキュバスと思われる女性が乗り、部屋中に水音を響かせるほどに激しく、淫猥に交わっていたのだった。
「あら…んっ♡お客様?表の魔物は何をしていたのかし…らっ♡」
この世のものとは思えない美貌、特徴的なサキュバスの羽と尻尾とむせ返るような甘い香り、そしてこのあまりに淫らで下賎な様子…
「城内の魔物はあらかた掃討した、噂通り、下劣な趣味のようだな魔妃リリトゥ!!」
騎士剣を突きつけて女騎士は声を荒げた。この眼の前にいる存在こそ、魔族の頂点、自らの夫の仇…魔妃リリトゥであると判断したのだ。
「オルトの…夫の仇、討たせてもらう!!」
この女騎士こそ、勇者オルトのパーティーメンバーにして婚約するはずだった女だった。半年前、オルトから中王国へ魔王を倒したと連絡があった。しかしオルトは帰ってこなかった。その後、魔王城に新たな城主、魔王の妻、魔妃リリトゥが現れ、再び魔王軍の残党とともに人間と戦い始めたのだ。
(あれから私は復讐のために、力をつけた)
その話を聞いた女騎士はひたすらに自分を鍛え、磨き強さを求めた。愛した人の仇をとるためだけに。そして今人間の軍隊とともに魔王城へ攻め入ったのだ。
(目の前に仇がいるっ!!今なら…)
女騎士はリリトゥの喉元を狙って騎士剣を構え、突進しようとした。その瞬間、リリトゥが体勢を変えて、その背後にいる男の顔が女騎士に見えてしまった。
「んっ♡…困りました…どうしましょうか?オルトさま、ぁあんっ♡」
「っ!?」
その瞬間、女騎士は驚きのあまり、完全に硬直してしまった。顔は青ざめ、動悸が早まり、目の前の様子が信じられないかのように、その場にへたりと座り込んでしまう。
「なっ…!!、な、なん…で、あなたが…」
リリトゥと交わっていたのは、見知った、いや自分が世界で一番愛した男だった。虚ろな目をしたままリリトゥと交わり続ける男は、死んだと思われていた勇者オルトだったのだ。
「…オルト様お知り合いですか?」
「俺の…昔の仲間で、婚約者だった女だ…」
交わりながら、背後を向いて愛おしそうにオルトの頬を撫でてリリトゥは問う。オルトはリリトゥの瞳を見つめながらなんの感情も持たずにそう言った。
「オルト…!!あなた…どうしてっ!」
女騎士はもう平静を保っていられなかった。再開できた嬉しさよりも――自分の愛した人が魔妃と交わっていることが理解不能で、頭がおかしくなりそうだった。
「あらあら♡…それは、しっかり挨拶しなければなりませんね、私はオルト様の妻、リリトゥと申しますわ」
笑顔でこちらを見るリリトゥの言っていることが意味不明だった。何がどうなっているのか全く理解できない。
「嘘…嘘だといってくれ、オルトっ!!」
涙を浮かべて女騎士は叫んだ。この光景が女騎士の思った通りのままならば、それは――
「嘘じゃない。俺が、愛しているのは、リリだ」
オルトは声色を全く変えず、愛おしそうにリリの頭を優しく撫でた。オルト本人の言葉を聞いてもなお信じられず女騎士はリリトゥに叫ぶ。
「お前…!私のオルトに何をしたぁっ!!!」
「何を…?確かに、わたくしの魅了で一度はオルト様を虜にしました」
それを聞いた瞬間、女騎士はリリトゥを殺せばオルトは解放される…と一瞬考えた。しかし――
「ですが、その後わたくしに本心から愛を誓ってくださいました。この指輪が見えますか?これはオルト様がわたくしにくださったものです…1年間、毎日わたくしの膣内に愛の証を下さいましたわ…♡もちろん今も…こんなに♡あんっ♡」
その指にはめられた指輪を見せつけられ、絶望に突き落とされた女騎士は剣を握り落とした。変わらず交わり続けるオルトとリリトゥに永遠の愛の証である指輪と、二人が繋がっている結合部を見せつけられているようで気が狂いそうだった。
「…こんなにも、わたくしを求めてくださいます…♡」
オルトは女騎士など目もくれず、一心不乱にリリトゥに腰を打ち付ける。結合部から溢れだす精液と愛液と交じり合った白濁とした液体がポタポタと音を立てて床に落ちる。
「う、嘘だ…こんなの嘘だ…」
絶望の表情を浮かべ、床にへたり込む女騎士を尻目にリリトゥとオルトは変わらず交わり続ける。
「あら、そんなに落ち込んでしまわれて…あなたも混ぜてあげましょうか?もちろんオルト様がよろしければ…ですが?」
「いや、おれは、リリだけでいい…」
1年の間、リリに毎日、ひたすら犯され続け、完全に思考を快楽だけに支配されたオルトは、今交わっているリリと呆然と座り込む女騎士…どちらが快楽を与えてくれるか理解していた。当然、貧相な身体の人間の女など選ぶはずもなかった。
「あら残念です、振られてしまいましたね女騎士様♡、代わりに城内の魔物でしたらお貸ししますわよ、汚らしいオークなどがお似合いでしょうか?うふふっ、あははははははっ♡」
本来の主など既にいなくなった魔王城に、美しく、残酷な魔妃の笑いが響き渡った
オルトの振り下ろした剣は、床に落ち、転がった。
「勇者様ぁ…どうですか?サキュバスクイーンの生のここは…♡」
「あ…あぁ…っ!!」
今、オルトの目の前には想像を遥かに凌駕する、「女性」そのものが広がっていた。ただ綺麗で、美しく、淫らな「それ」を前にオルトの理性、意識、感情までもが飲みこまれるように消え去った。もはや勇者の人格というものすら消え入りそうなオルトにリリは変わらぬ調子で話しかける。
「うふふ…サキュバスの服はわたくし達の魔力で作られているのです、どこを消すのも自由自在ですわ」
オルトが斬りかかった瞬間、リリの股間部分の布だけが消失し、それが姿を現した。その瞬間、オルトは剣を握る指を緩めた。その結果、剣は転げ落ちオルトは動きを止めたのだった。
「ご覧になって?人間の物とは比べ物にならないでしょう…サキュバスのここは殿方のあそこを受け入れるため、そして天上の快楽に導いて差し上げるためにあるのです♡」
その声はもはやオルトには届いていない。オルトは今、目の前にある至宝に全ての感覚を使い集中していた。視界で美しい陰唇を、宝石のような陰核を、ヒクヒクと開閉する生々しい淫らな肉色の腟口を、聴覚でクチュクチュと愛液が混ざり合う音を、そして嗅覚でリリの放つ濃厚で甘美な香りを味わっていた。
「あら…勇者様のおちんちんはとっても素直ですわ…♡」
ペニスははちきれんばかりに勃起し、今にも精が溢れそうだった。しかしオルトはその場から動かない、完全に魅了された彼には命令が必要だった。その魅了した相手であるサキュバスクイーンからの命令が。
「さぁ…もっと近づいて、わたくしを…たっぷり味わってくださいませ♡」
開脚して自らその膣口を広げて魅せつけた姿勢のまま、リリがそう言った瞬間、オルトは跪いた。膝立ちになりだらしなく口を開けて涎を垂らしながらその秘部に近づいていく。完全に魅了によって囚われたオルトは自分の欲望に忠実に、素直にただ舌を出してリリの秘裂に顔を埋めていった。
「いらっしゃいませ、勇者様♡」
「はぁ…はぁ…はぁ…ちゅ…れろぉ」
濃密な香りに荒い息を吐きながらオルトはヒクヒクと動く、その蜜壺に口をつけた。その瞬間、オルトの口内にあふれたその味はなにものにも表せない至福の味であった。あまりに甘美な味からそれだけで射精しそうなほどだ。舌の先だけで味わった状態から少しずつ少しずつ舐めるようにねぶるように舌を動かし始める。
「んっ♡…うふふ…どうですか?わたくしのここは美味しいですか?」
「あぁ…っちゅ…れろ…れろぉ…」
オルトは頷きながら夢中でそこを味わい続ける。奥から次々と溢れ出る愛液を舌先で舐めとるように必死に動かして甘酸っぱい至高の味を味わい続ける。もうそこに勇者の姿はなく、誘惑に屈した憐れな一人の男の姿があるのみだった。
「お気に召していただいてなによりです♡…口元をびちゃびちゃにして、まるで子供みたいですわ…可愛い…♡」
「ん…レロ…ちゅ…ちゅ…じゅる…!」
「あんっ…♡もっと味わってわたくしの味を染み込ませてくださいませ」
膣口をなぞり、陰核に吸い付く。思う存分味わった後、溢れ出る愛液を秘裂に唇をつけて吸い尽くすように味わう。リリの汗、愛液の濃密な香りによって視界は眩み、うつろな目になりながらも夢中で吸い続ける。リリはその様子を微笑みながら見つめ、開脚していた脚を徐々に閉じ始める。
「じゅる…じゅるる…ぁ…れろ、れろぉ…」
「さぁもっと味あわせて差し上げます、ほぉら♡」
むぎゅぅぅぅ…
「んむっ!…んっ…はぁ…ぐっ」
夢中で秘裂に舌を這わせていたオルトは顔面を両側から柔らかい太ももで押さえつけられた。そしてそのまま首に下腿をかけられ、さらに秘部へと顔面を押し付けられる。さらに後頭部に手を当てられ抱きすくめるように固定されてしまう。ただ息をすることすらままならず、顔全体にリリの蜜を塗りこまれるようだった。
「あんっ♡鼻息が掛かってますわ…わたくしもそろそろ我慢が…んっ♡」
鼻までもが秘裂に押し込まれ、もはや空気などなくひたすらに甘酸っぱい淫臭に肺と脳が満たされる。
「ん…♡あぁっ、ぁぁっ♡」
「はぁ…ぐっ…じゅるるる…ぁ…じゅる…じゅるるる…」
リリの嬌声が聞こえた瞬間、今までと比べ物もならないくらいの愛液が溢れだし、オルトは溺れそうになりながらもひたすらに吸い付き、舐めとり、愛液を味わった。凄まじいくらいの蜜はオルトの脳をとろかし、心を溶かした。
「はぁ…♡はぁ…あら、もしかして…イっちゃいましたか…?」
オルトの股間から、ズボンから染み出すように白い液体が溢れていた。あまりに強力な催淫効果と媚薬効果のアルサキュバスクイーンの愛液は、意思を失ったオルトを簡単に射精させてしまったのだった。
「…ぁ、ぁ、くっ…」
長い間、その愛液を味わってしまったオルトは、人間としての精神が耐えることができず、肺と脳をリリの愛液ろ匂いに溶かされて…意識を失った。
「…気を失ってしまわれましたか…丁度よろしいですね、場所を移しましょうか、勇者様…♡」
気を失い、床に倒れこむ勇者の股間から溢れる精液を見て、舌舐めずりをしながらリリは微笑んだ。
―――
――――ここは
「気が付かれましたか?」
オルトが意識を取り戻すとそこは見知らぬ部屋だった。美しい装飾品が彩る小奇麗な部屋で、自分はベッドの上で仰向けに寝ているようだった。
「おれは…一体…」
「あなた様は気を失って、倒れこんでしまいましたのでわたくしの部屋にお招きいたしました」
ぼうっとした頭で斜め上を見るとぼやけた輪郭の中でなんとなく女性ということがわかった。靄がかかったように回らない頭でなんとか何があったのかを思い出そうとする。
「まだしっかり起きていらっしゃらないのですか?…思い出してくださいませ」
その言葉を聞いた瞬間、今までの旅、勇者、仲間、魔王、妻、そしてさきほどの出来事がすべて一瞬で頭に走馬灯のように鮮明に現れた。覚醒した勇者は自分が何をしたかを思い出し、羞恥心と屈辱感から顔を真っ赤にしてリリに怒鳴る。
「お前っ!!、よくも…!!」
「あんっ…怒鳴らないでください、これから愛し会う身だというのに…」
「な…なにっ!どういう…」
そこまで言った時にようやくリリの服装に気づいた。さきほどと違い、リリはベビードールのような姿であり、その肌が大胆に露出されていた。なめらかな白い肌、大きく美しい乳房、絶妙な腰からヒップまでのライン、それが目に入った瞬間、オルト一瞬動きを止めてしまう。
(不味い…!あれは魅了を強くするための…!)
先ほどのまでの出来事を鑑みれば、リリの行動は全てが魅了魔法を増強するものに繋がっているはずだ。つまりこの服装も魅了の一種なのだろう。目を背けようとするがどうも先ほどまでと様子が違う。
(…魅了の魔力自体は感じない…どういうことだ?)
疑問を浮かべるオルトを尻目にリリはベッドの上に四つ這いになって上がってくる。そのまま寝そべるオルトの上にゆっくりと這うように近づいてくる。
「っ…!ち…近づくな…」
「言葉に力がありませんわね…ふふっ…」
今すぐにでも眼の前の憎らしい女を殺したい…そう思わなければならないはずなのに、オルトはリリが近づくだけで極度に興奮していた。リリの姿を見るだけで簡単に硬化したペニスは天井に向かってそそり立っている。
「…あぁ…勇者様のおちんちんがこんなに近くに…わたくしはこの時を夢に見ておりました…♡」
寝そべるオルトに覆いかぶさるようにリリは四つ這いになり、見下ろす。下から見上げると揺れる乳房によってリリの顔が隠れてしまい、その表情は窺い知れない。
「な、にを勝手に…っぁ!」
「おちんちんは準備万端のようですわね…わたくしももう我慢出来ませんわ」
再びリリに向かって怒鳴ろうとした瞬間、膨らんだペニスの先端をショーツ越しにリリが股間を押し付け擦りつけた。硬化していたペニスはその刺激から逃れるようにビクンと動くがそれを逃がすことなくリリは巧みに腰を動かす。布一枚越しにすりすりと押し付けられる柔らかな感触に耐えることができず、リリを突き飛ばして逃げ出そうとする…しかしその意思は身体に反映されなかった。
「…くっ…なんでっ、身体が…ぐあっ!」
「気づきましたか…?勇者様の肉体はもう…わたくしの魅了に完全に取り込まれていますもの♡」
「…っ!?」
淫らに動かしていた腰を一旦止めたリリは笑顔でそう言った。言葉の意味が一瞬理解できず、オルトは石化したように表情を固める。魅了にかかっている?自分が?
(それならば何故オレは自分の意思で話せて…)
「今、勇者様がご自分の意思を保てているのかはわたくしが命令したから…あなた様自身の自由意志は既にないということですわ」
「…な、ならなんでわざわざオレの意思を戻した!そんなことに意味は…」
オルトはリリの言葉が信じることができず、青ざめた顔でリリに問う。冷静になることができず、意味のない問いをかけてしまうオルトだが自らに魅了がかかっていることなど信じることができなかった。それが現実だった倍、それは実質、勇者が敗北したということだ。
「うふふ…それは、あなた様の心を本当の意味でわたくしのものにするため…♡」
そう言ったリリはオルトの服のポケットを弄る。そこは恋人への婚約指輪が入っているところだった。
「くっ…!そこは…!!!」
「…♪ありましたわ」
リリはポケットの中から指輪の箱を探り出し、抜き出した。絶対に渡してはならないものを奪われ、オルトの心に怒りが灯る。しかし無情にもその身体は動かず、オルトはその様子を歯噛みをしながらリリを睨みつけることしかできなかった。
「返せっ!!それは…」
「恋人…奥様なる方へあてたものですか?うふふ…やはりそうですのね」
「…っ!?」
オルトの腹部の上に座り込んだリリは箱を開けて勝手に指輪を取り出し、値踏みをするように覗きこんだ。簡単に言い当てられオルトは二の句を継げなくなってしまう。
「良い物ですわね…先ほどから気になっていました、勇者様があまりにわたくしの魅了に逆らうものですから不思議でしたが…その理由がこれですね♡」
「お前…何をするつもりだ!?」
「何を?…勇者様の妻になるのはこのわたくしですもの、これはわたくしがいただきますわ♡」
「ふ…ふざけるなぁぁっ!!!」
リリはさも当然のように笑ってオルトにそう言った。リリの意図を理解したオルトは自分の上に乗るリリに向かい全力の殺意を向けた。身体が沸騰しそうなほどの怒りによって視界が赤くなる。この指輪が奪われたらオルトと妻のすべてが否定されるようだった。そして奪われてしまう自分の不甲斐なさがオルトの怒りを生んだ。
「く…ぉぉっ!!」
その怒りが魅了の力を超えたのか、オルトの左手が動き、リリの腕を握ろうと手を伸ばす。妻の笑顔が頭にうかび、オルトの最後の力がリリにまで届こうとした瞬間、
「確かにいただきました…サイズもぴったりですわ♡」
リリは自らの左手の薬指に指輪をはめてしまった。伸ばしたオルトの薬指に輝く指輪とリリがつけた同じ指輪が重なるように煌めいた。
「あ、ぁ、ぁぁぁぁぁっ!!!」
その姿を見た瞬間、オルトの中で何かが壊れた。動かないはずの身体を動かし、起き上がって、リリに殴りかかろうとした…はずだった。
「落ち着いてくださいませ、勇者様」
その言葉を聞いた瞬間、オルトの身体から完全に力が抜け、ふたたびベッドに仰向けに倒れる。
「くそ…許さないぞ…!!!絶対に…!!」
「もう、自分の妻を睨まないでください…人間の結婚は指輪を渡したらまだすることがあるでしょう?」
「これ以上…なにをっ!!!」
「誓いのキ・スに決まってますわ♡」
仰向けのオルトに垂れかかるようにリリは倒れこんだ。首元にリリの頭が来るような形になり、絡みつくように抱きついてくる。潰れる乳房の柔らかな感触が怒り心頭なはずのオルトの力を強制的に抜いてくる。
「こうして身を寄せ合うだけで、身体が1つになったかのよう…わたくし達の身体の相性はやはり抜群なのでしょうか…♡」
「…っ」
リリはほとんど唇が触れ合う距離でそう囁いた。熱いリリの吐息が感じられるほどの距離にそのあまり美しい顔があるためか、オルトは息を呑んで声を出すことができなかった。そして――リリの言葉は確かだった。リリが抱きついた瞬間、溶け合うような満たされるような感覚がオルトの身を包んだ、そう妻と抱き合ったときには感じられなかった感覚を。
(おれは…おれはっ!!)
今感じた感覚を嘘だと、あり得ないと困惑するオルトに微笑んだリリはゆっくりとその潤ったピンク色の唇を近づける。
「さぁ永遠の愛を誓いましょう…ん…ちゅっ♡」
「ん…ぐっ」
力が抜けた瞬間、リリが滑らかに、しかし素早くオルトの唇を奪った。重なりあう唇から直接リリの体温と唾液の味が伝わり、怒りで火照っていたはずの身体が別の感覚…快楽によって火照り出す。
(く、そ…こんな、もの、で、)
「ちゅ、ちゅ…ん~っ、んっ、ぁむ♡…んんっ」
リリはオルトの唇を完全に塞ぎこみ自らの唾液を流しこむ。歯を閉じようとしても敏感な部分を察知したリリのい舌が這いずり回り、その快楽により強制的に口を開けられる。
「ん…んっ♡れろぉ…れろ…じゅぷ…」
逃さずに唾液とともに侵入したリリの舌がオルトの口内を蹂躙し、オルトの舌を絡めとるかのように動く。口内の犯されるような濃厚なキスにオルトの脳内に靄がかかったかのように意識が快楽に呑まれていく。
「んっ…まぁだ…♡…ぁむっ♡れろっ…ん~っ、ちゅ、くちゅ…んっ♡」
「はぁ…はぁ…んむっ!、んっ、んっ、はぁ、ぁ…っ」
空気を求める息を吸おうとするオルトに容赦なく口を覆うようにリリが唇を塞ぐ。そして再びぬるりとリリの舌が口内に侵入する。オルトの舌に蛇のように巻きついたリリの舌を絡めとり強制的にリリの口内へ吸い取られるように運ばれる。舌が溶かされたような、蕩けるような甘い甘い感覚がオルトを襲い、はちきれんばかりに勃起したペニスも震える。
「ちゅっ、れろぉ…ぅん…ぁむ…じゅ…じゅるっ♡」
(おぼれ、る)
じゅぷじゅぷと唾液が絡みつく水音が聞こえるほど、激しく甘いキスによってオルトは完全にその虜になてしまっていた。先ほどのまでの激しい怒りを快楽で塗りつぶされ、リリから与えれる濃厚なその甘さを身体をビクビクと小刻みに震わせる。酸素を与えらず、代わりにリリの甘い唾液で口内を満たされたオルトはただそのキスに溺れていった。
「ん…ぷはっ♡なんて甘く…心地良い感覚なんでしょう…♡わたくしこのような気持ちになるのは初めてですわ…人間の恋とはこのような感覚なのでしょうか…♡」
「はぁ…はぁ…はぁ…!」
唾液で糸を引きながらお互いの唇がゆっくりと離れる。口元の唾液を舐めとりながらリリは起き上がってオルトに跨るように座った。長い長いキスの末、やっと開放されたオルトはぼやけた視界の中、必死に酸素を取り込む。
「うふふ…儀式は終わりました、後は1つになるだけですね…♡」
そう言ったリリを跨るような姿勢から立ち上がった。ベッドに上でオルトを見下ろすような形になったリリは、微笑みながら自らのショーツに両手をかける。
「ん…♡もうこんなに…これでは下着の意味がありませんわ…♡」
リリはゆっくりと自らの愛液でびしょびしょに濡れた可愛らしいショーツをずり下げていく、片足ずつショーツから脚を引きぬき、用済みとばかりにベッドに投げ捨てる。再び目の前に現れたリリの蜜壺はヒクヒクと淫らに蠢きながら、太ももまで伝うほどの蜜を垂らしていた。
「わたくしも、わたくしのここももう我慢出来ませんの♡…さぁ交わりましょう勇者様」
パチッ
リリが指を鳴らすと勇者のズボンは消失し、完全に勃起したペニスが白昼にさらされた。興奮に興奮を重ねたペニスは亀頭を真っ赤に染め、我慢汁が溢れ出し、ペニス全体を滑らせていた。鈍く輝く勃起したペニスを見つめてリリは恍惚の笑みを浮かべる。
「あぁ…♡こんなに立派に大きく、いやらしいお汁で濡れて…勇者様もわたくしと同じ気持ちなのですね♡」
「…やめ…ろ…!」
オルトは力無く言葉を吐く。これからされようとしていることは妻に対する明確な裏切りだった。しかしそれを期待し、興奮し、待ち焦がれるオルトの身体が徐々にその意思までも侵食しているようだった。言葉では否定しようと、オルトの視線はリリの秘裂に釘付けであった。
(かえる…か、えるんだ、おれは…)
奥底の意識だけが今だに残る。帰りを待つ妻に会うために、その気持ちだけが魅了され、墜落したオルトの最後の一線を守っていた。
(かえって…指輪を…?)
しかし脳にかかった靄が、リリから与えられた快楽がその最後の想いすら絡みとる。指輪を思い出し、そして目の前に立つリリの指にはまっている指輪を見て、そして妻の姿がリリに重なった。似ても似つかないその姿が何故か徐々に鮮明に重なり始める。
「後はこの腰を沈めるだけ…勇者さま?わたくしのここを味わったら…人間の粗悪なそれでは二度と達することはできなくなりますが…もう人間と交わることなど永久にないですから、良いですね♡」
オルトが自らの想いが蝕まれている間に、リリはオルトの股間の上に自らの秘裂を合わせるようにしゃがみこんでいた。その距離はもうほとんど0に近い。
(ゆびわ…はめた、妻、誰が)
妻であるはずの女とリリの姿が二重になり、重なり、再び二重になり…どちらがどちらか、徐々に理解出来なくなっていたオルトは混乱とともに眼の前の景色を認識した。
「ではわたくしの膣内に…いらっしゃいませ…♡」
そうだ、リリと妻であるはずの女を間違えるはずがない。オルトが愛する女はただ一人だ。ぎりぎりのところで意識を保ったオルトが我に返った瞬間、見えたのはリリの幸せそうな笑顔だった。
ぬぷっ…ずにゅ…じゅぷぅっ…
「あぁぁっ!!」
「…あっ♡入って…まいりました…♡」
ゆっくり、ゆっくりとリリが腰を降ろした。亀頭がはリリの秘裂をかき分けその蜜壺へと飲み込まれていく。ぬめったその感触、つぎの瞬間、ペニスに訪れたのはこの世のものとは思えない快楽だった。かつて感じたことのある膣の感触とは比べ物にならない、構造自体が違う淫魔の膣は幾十にも重ねたヒダでオルトのペニスを包み込み、密着し、快楽を与えながら奥へ奥へと飲み込む。
「あ…はぁ…♡この時を、待ちわびておりました…♡」
「…っは…あぁ…」
ずぷん…
膣内の複雑な構造をした淫肉が絡みつきながらもペニスをゆっくりと奥へ運び、最後には根本まで全てを飲み込んだ。腰を完全に下ろしきったリリは快楽に顔を蕩けさせて両手をオルトの胸板に置く。
「だ、めだ、もう…」
リリの蜜壺に飲み込まれたペニスはただ包まれているだけなのに、もう我慢の限界だった。締め付けれているわけでもないのに、動いてるわけでもないのに、快楽をあたえるためだけにあるこの器官は…包み込むだけでオルトを敗北させた。
「ん…イキそう…ですか?駄目ですよ…♡」
「くっ、あぁぁっ…!」
びくんっと一度、リリに組み伏せられたオルトの身体が跳ねた。しかしそのペニスから何故か精液は放出されず、オルトは絶頂に至るギリギリで生殺しのような感覚を味わう。
「んっ、ぐっ、なん、で」
「勇者様は、魅了されていますから…わたくしの命令が無い限りもう勝手に射精することができませんわ」
勇者に跨るリリがそう言った瞬間、膣内がゆっくりと収縮しはじめた。とろとろだった膣内は一ミリの隙間もなく、赤子を抱くように優しく、そして確実に、リリの淫肉が勇者のペニスを締め付け始める。
「っあ!…あ、ぐぅぅっ」
包み込まれているだけで絶頂を迎えているはずのオルトが、その収縮に耐えられるはずもなかった。身体を小刻みに震わせて射精したくでもできない、頭のおかしくなりそうな感覚を味わわせられる。
「後は勇者様の心をわたくしのものにするだけ…勇者様が自分から望んでくだされば、わたくしの膣内で射精させてさしあげます」
オルトの胸に手を置いたリリは胸板を幸せそうに場で回しながら微笑んだ。
「それでは、勇者様が素直になるまで…ゆっくり優しく焦らしてあげます…♡」
じゅぷっ…
リリの腰がゆっくり、ゆっくりと持ち上がっていく。ペニスに絡みつく淫肉は決して強く締め付けるようには収縮せず、あくまで優しく包み込むようだった。淫肉は生き物のようにペニスの表面を愛撫しながら再び膣口まで輸送される。
「ぅ…くっ…あ」
「あっ…はぁ…♡うふふ…お顔が蕩けていますよ」
熱い、溶けそうだ、耐えられるはずがない、しかし達することができない。
体全体が震え、絶頂を求める。はやくイきたいと急き立てる。目の前の女が誰であろうとどうでもいい。この蜜壺にすべてを吐き出してしまいたいと思ってしまう。
「勇者も…んっ…いけない人ですわね。恋人がいらっしゃるのに、他の女でこんなに興奮して…あんっ♡」
淫らに腰を焦らすようにくねらせながら、リリはオルトを挑発するように言葉をかける。その言葉すらオルトにはもう快楽に変換されてしまう。恋人がいるという身でありながら魔王の妻と性交をしているという事実、この背徳の極みとも思える行為に興奮を覚えてしまっていたのだ。
ずぷん…
「うぅ…!あっ…」
「早く素直になりましょう…ね勇者様?もっと気持ちよくなりたいでしょう?」
再びオルトのペニスは膣内に飲み込まれていく。1往復の間にオルトの限界はとっくに超えていた。快楽にオルトの自身の意識が上書きされ、リリを求めてしまいそうになる。魅了の影響でない、オルト自身が、自らリリを求めようとしていた。
(だめだ…おれには、あい、つが…)
妻の姿を思いそうとする、しかし靄がかかったようにその鮮明な姿を思い出せない。
考えようとしてもペニスから与えられる快楽が全てを塗りつぶす。絶頂を求める身体が…心が、恋心を打ち消していく。目の目の快楽を求めるようになってしまう。
(…イきたいっイきたいっイきたいっ!!)
結局、
「…したい」
「…なにか申しましたか勇者様?」
オルトの口から零れた言葉はリリには届かなかった。しかしもうオルトは、我慢することはできなかった。
「…射精、したい」
求めてしまった。
「うふ…うふふっ♡求めてしまいましたのね…勇者様が…魔王の妻であるこのわたくしを」
歓喜の表情を浮かべたリリは両手をオルトの顔の横について、見下ろすような形になった。
「わたくしの膣内で射精してしまったら、二度と人間の女で…勇者様の恋人でイくことは出来なくなります…それでもよろしいでしょうか?」
…こくっ
オルトは朦朧とした意識の中で頷いた。我慢出来るはずもなかったのだ。そもそも、魅了された時点でオルトはリリの身体にどうしようもなく惹かれていたのだから。気持ちだけがリリを否定していた、いや否定しようとしていた。しかし狂おしいほど、壊れるほどの射精欲はオルトを本能のまま動かしてしまった。リリの膣内ひたすらに焦らされたペニスは今にも破裂してしまいそうだ。
「わかりました…♡そんなに切ないお顔をされてはわたくしも意地悪できませんわ…♡」
愛おしそうにオルトの頬を撫でたリリはそのまま身をおろし、オルトを抱きしめた。潰れる乳房とリリの体温がさらに興奮を誘う。リリの膣内がどんどんと密を増し、一ミリの隙間もなく淫肉がペニスに纏わりつき、絡みつき根本から搾り出すように収縮しはじめた。そして
「射精してくださいませ…勇者様」
耳元でリリが囁いた。
どくっ、どぴゅ、どぴゅ、どぴゅ…
止めどなく精液が漏れだした。全てを吐き出すように、リリの膣内を満たすように、白い液体が溢れだす。ビクビクと身体を震わせてオルトは快楽の果てを味わっていた。
「あっ…はぁ…♡なんて、上質で、美味しい精…こんなものがあっていいんでしょうか…♡」
恍惚の表情を浮かべ、リリはその精を味わいながら膣を蠢かせて精液を1滴残らず搾り出そうとする。ペニスに残る精はその膣の収縮によって止まることなく溢れ続ける。
「あぁぁぁぁぁっ…!!」
どぴゅ…どぴゅ…
いつまでも終わらないかのような長い射精がそこで止まった。妻を裏切り、宿敵の妻への射精は、今まで感じた中で一番の絶頂だった。
「ん…♡いただきました…あら、ふふっまだまだ射精したりないようですね…♡」
「も、もっと…」
射精の終わったペニスは萎えることなく、リリの膣内でその硬度を保っていた。オルトはタガの外れたようにリリの膣内での射精を求める。
「あらあら…おねだりしてしまうほど、気持よかったですか?うふふっ少しお待ちくださいませ」
ぎゅ…ぐにゅ
リリをの膣内が生き物のように胎動し、オルトのペニスを包み込み、その形を変えていく。イかせるような動きではなく、ただその形を覚えるような動き。
「今、勇者様を、わたくしの膣が記憶しています。勇者様だけを気持ちよくするために、勇者様だけの蜜壺に形を変えるのですよ」
ぐにゅ…ぐにゅ…ぎゅっ!
「あぁっ!、くっ、あ、」
「はい、出来ました…これでわたくしは勇者様だけのものです…あぁん♡」
「くっ、あぁぁっ!!」
どぴゅ、どぴゅ、どぴゅ…
その形となった瞬間、射精した。オルトのペニスに最適化した膣内はこれ以上に締り、締め付け射精したばかりの敏感なペニスには耐えられるはずもなかった。射精している間も淫肉がひたすらにペニスに纏わりつき、愛撫し、搾りだし続ける。
「あんっ♡もう…おもらししてるみたいですわ…まだ動いていませんのに」
「はぁ…はぁ…はぁ…」
(気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい)
そこにあるのは圧倒的な快楽だった。オルトは今人生で一番幸せなときを味わっているのだ。よく考えたらなぜ自分があんなにも否定していたのかが不思議だった。
「では…サキュバスクイーンの腰使い、ご堪能下さいませ」
ずぷっ、ずぷっ、じゅぷっ、ずちゅ…
股間にまたがったリリが淫らなダンスを踊る。跳ねる乳房、淫らな香り、膣の感触、腰の動き全てがオルトを簡単に絶頂へ導く。腰が1振りするたびに精液と愛液が交じり合った液体が結合したリリの膣口から漏れだす。
(そうだ、なぜあの女に固執していたんだろう…)
今なら恋人の顔も思い出せた。いやもう恋人ではない、あんな女などリリに比べたら取るに足らない存在だ。
(リリの方が美しい、可愛らしい、淫らだ、いい匂いがする、気持ちがいい)
激しくなっていくリリの腰振りに、オルトのペニスは壊れた蛇口のように精液を放出し続けた。魅了の効果だろうとなんだろうともうどうでもいい。眼の前の愛おしい女から与えられる快楽が今のオルトの全てだった。
ぐちゅ、ぐっちゅ、ずちゅ、じゅぷ、じゅぷぷっ!、
淫らな水音を響かせながら繋がり合う、二人はお互いの目を見つめ合い、愛しあいながら1つの生物のように絡み合う。
「ん…♡はっ…どうですか?人間なんかよりもとっても気持ちがいいでしょう?」
「あ…あ…」
「…オルト様、わたくしと、毎日こうして愛しあいましょう…ね♡」
「ああ…」
「結婚…いたしましょう…♡」
「ああ」
繋がりながら、リリははめていた指輪をはずして、一度オルトに返した。そしてその左手を差し出す。オルトはそれを受け取り、リリの指に再び、優しくゆっくりとはめた。
「嬉しい…♡んっ♡わたくしも、そろそろ…一緒に」
「あ…あ、あ、くっ」
じゅぷっ、じゅぷっ、じゅぷぅぅっ!!
さらに動きが激しくなり、水音も響き渡る。いつのまにか下にいるオルトも腰を突き上げ、お互いが激しく互いの身体を貪るように求め合っていた。
「あっ♡、あっ♡…あぁぁぁぁぁんっ♡」
「くっ、は、あぁぁぁぁぁっ!!」
どぴゅぅぅぅぅぅっ…
オルトは腰を思いっきり突き入れて、子宮口に精液を注ぎ込んだ、リリは反り返って歓喜の表情を浮かべて嬌声を上げながら絶頂に達した。限界を遥かに越えて精液を放出したオルトはその瞬間、完全に意識を失ってしまった。
「はぁ…はぁ…これからよろしくお願いしますね、オルト様…♡ちゅっ♡」
オルトの胸にすがりつくように倒れこんだリリは、心底、愛おしそうにオルトにキスをした。
…
1年後
「魔妃リリトゥ!!世界のため…死んでもらうっ!!」
荘厳な魔王の間の扉を押し通りながら勢いよく女がそう言った。
相当な美人だがその険しい表情のせいで冷く見えた、長い金髪を1つにまとめ軽い鎧をまとった女騎士は薄暗いその部屋を見回す。
(誰もいない…!?…いや何か音が…それにこの匂い…)
何か規則的な水音のようなものが聞こえた。そして部屋中に溢れる甘いような、そしてどこか淫靡な香りが鼻につく。よく見渡すと薄暗い部屋の中心、玉座のようなところに誰かが居るのがわかった。
「…誰だっ!リリトゥかっ!!」
女騎士は玉座に一気に近づいた。そこで見たものは男女二人が性交をしている様子だった。玉座に座る男の上に、この世のものとは思えないほどの絶世の美女…おそらくその羽と角、尻尾からサキュバスと思われる女性が乗り、部屋中に水音を響かせるほどに激しく、淫猥に交わっていたのだった。
「あら…んっ♡お客様?表の魔物は何をしていたのかし…らっ♡」
この世のものとは思えない美貌、特徴的なサキュバスの羽と尻尾とむせ返るような甘い香り、そしてこのあまりに淫らで下賎な様子…
「城内の魔物はあらかた掃討した、噂通り、下劣な趣味のようだな魔妃リリトゥ!!」
騎士剣を突きつけて女騎士は声を荒げた。この眼の前にいる存在こそ、魔族の頂点、自らの夫の仇…魔妃リリトゥであると判断したのだ。
「オルトの…夫の仇、討たせてもらう!!」
この女騎士こそ、勇者オルトのパーティーメンバーにして婚約するはずだった女だった。半年前、オルトから中王国へ魔王を倒したと連絡があった。しかしオルトは帰ってこなかった。その後、魔王城に新たな城主、魔王の妻、魔妃リリトゥが現れ、再び魔王軍の残党とともに人間と戦い始めたのだ。
(あれから私は復讐のために、力をつけた)
その話を聞いた女騎士はひたすらに自分を鍛え、磨き強さを求めた。愛した人の仇をとるためだけに。そして今人間の軍隊とともに魔王城へ攻め入ったのだ。
(目の前に仇がいるっ!!今なら…)
女騎士はリリトゥの喉元を狙って騎士剣を構え、突進しようとした。その瞬間、リリトゥが体勢を変えて、その背後にいる男の顔が女騎士に見えてしまった。
「んっ♡…困りました…どうしましょうか?オルトさま、ぁあんっ♡」
「っ!?」
その瞬間、女騎士は驚きのあまり、完全に硬直してしまった。顔は青ざめ、動悸が早まり、目の前の様子が信じられないかのように、その場にへたりと座り込んでしまう。
「なっ…!!、な、なん…で、あなたが…」
リリトゥと交わっていたのは、見知った、いや自分が世界で一番愛した男だった。虚ろな目をしたままリリトゥと交わり続ける男は、死んだと思われていた勇者オルトだったのだ。
「…オルト様お知り合いですか?」
「俺の…昔の仲間で、婚約者だった女だ…」
交わりながら、背後を向いて愛おしそうにオルトの頬を撫でてリリトゥは問う。オルトはリリトゥの瞳を見つめながらなんの感情も持たずにそう言った。
「オルト…!!あなた…どうしてっ!」
女騎士はもう平静を保っていられなかった。再開できた嬉しさよりも――自分の愛した人が魔妃と交わっていることが理解不能で、頭がおかしくなりそうだった。
「あらあら♡…それは、しっかり挨拶しなければなりませんね、私はオルト様の妻、リリトゥと申しますわ」
笑顔でこちらを見るリリトゥの言っていることが意味不明だった。何がどうなっているのか全く理解できない。
「嘘…嘘だといってくれ、オルトっ!!」
涙を浮かべて女騎士は叫んだ。この光景が女騎士の思った通りのままならば、それは――
「嘘じゃない。俺が、愛しているのは、リリだ」
オルトは声色を全く変えず、愛おしそうにリリの頭を優しく撫でた。オルト本人の言葉を聞いてもなお信じられず女騎士はリリトゥに叫ぶ。
「お前…!私のオルトに何をしたぁっ!!!」
「何を…?確かに、わたくしの魅了で一度はオルト様を虜にしました」
それを聞いた瞬間、女騎士はリリトゥを殺せばオルトは解放される…と一瞬考えた。しかし――
「ですが、その後わたくしに本心から愛を誓ってくださいました。この指輪が見えますか?これはオルト様がわたくしにくださったものです…1年間、毎日わたくしの膣内に愛の証を下さいましたわ…♡もちろん今も…こんなに♡あんっ♡」
その指にはめられた指輪を見せつけられ、絶望に突き落とされた女騎士は剣を握り落とした。変わらず交わり続けるオルトとリリトゥに永遠の愛の証である指輪と、二人が繋がっている結合部を見せつけられているようで気が狂いそうだった。
「…こんなにも、わたくしを求めてくださいます…♡」
オルトは女騎士など目もくれず、一心不乱にリリトゥに腰を打ち付ける。結合部から溢れだす精液と愛液と交じり合った白濁とした液体がポタポタと音を立てて床に落ちる。
「う、嘘だ…こんなの嘘だ…」
絶望の表情を浮かべ、床にへたり込む女騎士を尻目にリリトゥとオルトは変わらず交わり続ける。
「あら、そんなに落ち込んでしまわれて…あなたも混ぜてあげましょうか?もちろんオルト様がよろしければ…ですが?」
「いや、おれは、リリだけでいい…」
1年の間、リリに毎日、ひたすら犯され続け、完全に思考を快楽だけに支配されたオルトは、今交わっているリリと呆然と座り込む女騎士…どちらが快楽を与えてくれるか理解していた。当然、貧相な身体の人間の女など選ぶはずもなかった。
「あら残念です、振られてしまいましたね女騎士様♡、代わりに城内の魔物でしたらお貸ししますわよ、汚らしいオークなどがお似合いでしょうか?うふふっ、あははははははっ♡」
本来の主など既にいなくなった魔王城に、美しく、残酷な魔妃の笑いが響き渡った

We
weixiefashi
Re: (转)魔妃(日文)
看完了一遍,木有血腥,木有残杀,撸点对不上,我就不翻译了

Ho
howlingblade
Re: (转)魔妃(日文)
日語盲看完感覺好像很贊啊!