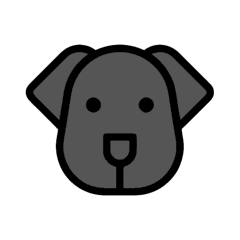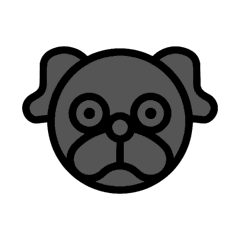ギロチン少女マジカル☆ギヨたん1-12全
添加标签
這個是我覺得看過相當不錯的日文BF小說
之前曾在版上貼過一部分
最近因為原網站封閉了 所以在這裡將全文貼上供同好欣賞
ちゅ……ちゅっ……。
夜の路地裏に、水がピチャピチャと跳ねるような音がした。
路地に人通りのまったくないほどの夜更け、その裏には下半身を突き出した男が恍惚とした表情でだらしなく涎を垂らしている。
「んっ、ふうっ……ちゅっ」
男の股の間で屹立した肉棒を幼い少女が銜えていた。黒いドレスに白いフリル。黒と白のコントラストが印象的な、まだ十代の半ばにも達していないような少女だ。
ぺたんと地面に座りこんでいる少女は、がくがくと震える男の腰に抱きついて、根本まで呑み込んだペニスにねっとりと舌を絡みつかせている。
情熱的なわけでもなく――作業的に男の弱点を丹念に、まるで玩具でも愛でるようにカリ首の合間に滑り込ませてじゅるりと舐めていた。
「あむ……ちゅじゅっ、ぢゅ……んちゅっ」
そのまま舌は亀頭の頭を撫でていき、尿道をマッサージしていく。少女とは別の生き物みたいに動く血のように赤い舌に、男は背筋を震わせた。
その執拗な舌責めは幼い外観からは想像も付かない淫らさで、奉仕される男は少女の頭に手を添えて立っているのが精一杯だった。
「あ、あああ……もう駄目だっ、出――!」
言い終わるまで男は耐える事ができず、少女の口の中で肉棒がスペルマを間欠泉みたいに噴き出した。
「んぐ……っ」
どくんどくんっと心臓みたいに激しく脈打ちながらペニスが放出した口内から溢れ出そうなほどの白濁とした精液を、少女は嫌な顔すらせずに無表情で呑み込む。小さな喉が何度も上下に動いて、精液は胃に流れ落ちていった。
少女は熱い吐息をついて男性器から口を離すと、肉棒に絡みついた精液を舌ですくい取る。かわいらしい真っ赤な舌が敏感になった亀頭を舐めて、男はがくがくと足を震わせると腰を抜かして路地裏にへたり込んでしまった。
それでもむき出しになった男の陰茎は屹立としていて、少女は無言で下着を脱いで男の躯に跨ると、ドレスのスカートをたくし上げた。毛も生えていない未成熟 な女性器が眼前で恥ずかしげもなく晒されて、男は顔を紅潮させた。どんなに女性として成熟した者の性器よりも、そのいやらしさと可憐さが奇妙なバランスを 持った花弁のような少女のヴァギナは淫靡だったのである。
見とれて一言も口をきけない男のペニスに向けて、少女は見せつけるかのようにして腰を下ろした。
亀頭が入り口に触れる。
だが、期待していた感覚は男にはやってこなかった。
挿入されるのかと思いきや、愛液で滑ったペニスは少女の性器をなぞっただけであった。男は入れてくれ、と懇願するように少女を見上げる。
そこには蔑むような冷たい視線があった。
自分よりもずっと年下からの冷罵でありながら、男は既に蛇に睨まれた蛙になってしまっていた。
男が硬直しているうちに、少女は男の下腹部の上に座った。しかし挿入はされておらず、未熟な性器で陰茎を押しつぶす。
少女がじっと男を見て、腰を肉棒にそって動かした。ずるり、ずるり、と性器の口で射精したばかりのペニスを擦りあげると、男は女性みたいな高い嬌声をあげた。
裏筋をなぞる女性器は蛸の吸盤のように吸い付き、そのままペニスを横笛みたいになぞるのだ。愛液でびしょびしょにされた肉棒の根本から裏筋をなぞって亀頭の筋まで。ぐちゅり、ぐりゅりと音を立てて刺激する。
女性器によるマッサージ。少女は男のペニスを挿れるわけでもなく、寸止めして弄んでいた。だが男は異を唱えられない。裏筋を集中的に滑るヴァギナはそれだけの快楽を与えた。
少女の腰の動きが速くなる。短いスパンで何度も何度も陰茎が摩擦し、カリを入り口でなぞってはまた筋を舐めていく少女の下半身に、男の性欲はまたもや解放のときを迎えた。
「あああ、あああ――ッ!
どぷっ! とひねり出される精液。
少女の白い太腿に飛び散りながら、子種は男自身の身体に降り注いだ。なにも身に着けていない下半身と服を着たままだった上半身が青臭い液体でべっとりと汚れてしまった。
はあ、はあ、と肩で息をする男から少女は立ち上がり、またペニスに口を寄せる。どろどろと白濁にコーティングされた亀頭を銜えた。
「あがっ!?」
稲妻のような快楽に男の腰が浮き上がる。
「も、もうやめて……」
少女は答えることなく、男の精液を吸い上げた。
ちゅっ、と一際大きな音を立てて亀頭を吸うと、少女は陰茎から口を離して喉を大きく上下させて口の中の白濁とした液体を呑み込んだ。
あとに残されたのは、自分の精子で濡れた哀れな男の死体だけだった。
少女の耳に、足音が聞こえてくる。
新たな獲物を見つけた。
その方向へ顔を向けて、少女は路地裏を後にする――。
*
ある時代、ある日の広間。
人を焼き殺すような熱気、目を潰すほどに燦爛と輝く日輪。
声だけで人を圧壊するような熱狂の渦の中で、
――ひとつの首が宙を舞った。
断頭台が落ちたのだ。幾多の人の血を吸った忌まわしき鈍重なる刃が、また無慈悲に人の首を狩り落とした。
だが、果たして。無慈悲だったのはギロチンなのか。それとも、刃を落とした人間だったのか。
舞う首の金髪が光を反射する、それはまるで金粉をまき散らしているようで。その生首は、神々しい死の煌めきをまき散らしながら、広間の石畳に転げ落ちた。
その男の生前を語るのならば、ただかつて処刑の執行人をしていたというだけで事足りる。それ以外に、なにもないような男だった。血縁などいなかったが、そ れはこの時代において悲劇たり得なかったろうし、なにより本人がそれを当然と受け入れていた。幸いにも食事は毎日ありつけていたし、鍛えた躯は健康そのも のだった。
処刑人という陰惨な、人からの畏怖と憎悪を買う仕事をしていながら、本人は至って素朴な男だった。たいして言葉を知らぬから、口数は 少ないうえ人と親密な関係になることもなかった。劣悪な生活環境は改善しようとするが、上昇思考があったわけではない。本当に、素朴という言葉がよく似合 う。
ああ、知っている――とソレは嘆いた。
けして、殺されていいようなものではなかった。
こんなことで、死んでしまっていいようなものではなかった。
命に区別はない。ひとしく同義だ。それは、ソレが一番理解していた。己の用途が故に。
だが。その男の首が舞って、地面を転げて、その首を笑いながら蹴るものたちを見ながら、ソレは思う。
このような愚劣極まりない行為をおこなう連中が、彼と同じ命とでも云うのか?
――何を、馬鹿なことを。
ふつふつと、自分の中で燃え上がる感情が、最初なにかソレは判りかねた。やがて、自分が奴らにしてやりたい行為のことを分析して、判明した。これは憎悪だ。憤怒だ。――殺意だ。
自分に今まで向けられていた感情を、今は晴天の広間を覆い尽くしている、蟻のような人間に注いでいた。
民衆が、処刑された元・処刑人を罵倒していた。
悪魔。人殺し。屑。
犬野郎、狂人、お前なんて人の子じゃない――。
なにを云っているのだ。その男を殺したのは、なにもここにいる別の処刑人でも、ましてや〝私〟だけでもない。お前らだ。お前らの総意が、彼を殺したのだ――。
――ある日、革命が起きた。
王は殺された。女王も殺された。公開処刑であった。
民衆は娯楽と、そして自分たちを苦しめたと想像する総ての悪徳を彼らに押しつけて、新たなる秩序の名の下に断罪し、歓喜していた。
しかし、自分たちの生活の改善を願って蜂起したものの、生活は一向に上向くことはなく、むしろ以前より困窮していく始末だ。自分たちはいったいなんのため に支配者を打倒し、無様な死をくれてやったのだろうか。この混迷たる世の中で、自分たちの幸福を願って戦ったはずなのに。
そうした不満を抱き、追い詰められ、影響を露わにするのは、社会的が地位の低い者たちだった。
その日は、街の広場で公開処刑がおこなわれていない日であった。どんな不平や不満も、自分たちを追い詰めたものたちの死によって一時、熱狂という水で洗い流されていたわけだが、それがないとあっては虫の居所が良くはない。
特に。陽が地平線の彼方に消えてからかなりの時間が経つ夜更けに、頼りない街灯の明かりに照らされた路地を肩を怒らせて歩く男三人の機嫌はすこぶる悪かった。
「なんでだ……なんで、あの王も死んだっていうのに、オレたちの生活はすこぶる不調のままなんだ。こっから先は祝福された人生が待ってるんじゃなかったのかよ」
三人の中では一番大柄な男が云った。過酷な肉体労働でもしているのか、肩幅は広く、腕の太さも少年の胴回りくらいはある。手入れもまったくされていない、 単に無精で映え放題になった髭がみっともないが、誰もそれに苦言を呈すことができないほどに凶暴な猛獣を彷彿とさせる男だった。
「仕方ないですよ。王様が死んだからって、わたしどもの仕事が楽になるわけじゃないんですからね。王様が死んだら、そのまま食事がわたしたちの前に並ぶような、そんな単純な問題だったらよかったんですけどね」
大男の言葉に、一番小柄な男が応えた。背丈は他の男性と比べると低いが、そこはやはり大男の同業者、肉体に恵まれてはいないものの筋肉だけはついていた。それで腕っ節、喧嘩が強いなんてわけではないようだと判るくらいに、その男の肩身は狭そうであったが。
「おいおい、テメェは今更全部わかってましたって面で諦観かよ。さすが自称知性派はご慧眼の持ち主なんだなぁ、ええ?」
最後のひとり、眉が薄いせいか眼窩の骨が目立つせいで酷く乱暴者な印象を抱かせる男が、小柄な男を睨み付けた。先程からずっと眉間には皺が寄っていて、眉がなくても男が苛立っていることは誰から見ても明らかだった。
「そんなつもりで云ったのでは……」
「じゃあどういうつもりで云ったんだよ、あァ?」
「ったく、うるせぇぞ、テメエら! その顔血まみれにされたくなかったら黙ってろ!」
大男は自分の背後で騒ぎ出すふたりを怒鳴ると、たちまち静かになる。一喝に萎縮したふたりに、大男は苛立ちを隠さぬ口調で独白した。
「オ ヤジはのんだくれでよぉ、オフクロは男共に股を開く売女だった。今に至っては、お前らみたいな馬鹿な奴らがオレの後ろで騒ぎたてやがる。ホントに、うまく いかねえ……。王とか、女王だとか、あのときの……そうだ、陰気な処刑人が死んだときみたいな……大笑いできる見せ物がないってのも、おかしな話だ、 よ!」
大男は足下に転がっていた石ころを蹴り飛ばした。カンッ、と耳に刺さる音を立てて石畳の上で跳ねた石ころは、誰かの足に当たって地面に落ちた。
「お?」
大男は声をあげた。その街灯の明かりが途切れる境界線に、この中の三人の誰よりも小柄な女の子が立っていたのだ。
奇妙な少女だった。
黒いドレス。それも、お城に住んでいる人間が着ていそうな――ほとんど男の偏見であったが――豪奢なフリルをあしらったものを着ていたのだ。黒を基調にし て、白いフリルに飾られた衣装は影絵のようなコントラストを作っている。もしかしたら、このまま歩いていては気付かずにぶつかっていたかもしれない。
男たちのそこそこに長い人生の中で、その服装は見たことがなかった。自分たちがこの国でふつうに生活していては、お目にかかることはない。しかし、他国の人間が革命をおこした最中にある国へと足を伸ばそうなどと酔狂なことを考えるものだろうか。
自分たちが立ち入れない場所といえば、この国ではお城しか考えられない。つまり、あの少女は――処刑されるのが怖くて、逃げ出した王族、あるいは貴族の人間なのだ。
そうとわかると、まず大男がその髭だらけの口の端を持ち上げた。笑ったのであろうが、端から見れば獲物を前にして牙を剥いた獣にしか見えなかったし、事実大男は少女を獲物と見ていた。
街灯の明かりが届く限界にいるため、少女の姿は曖昧にしか見えず、躯の輪郭もふわふわとした衣装のせいで判らない。けれど、その顔がとびきりの上玉であることだけは目聡く把握していた。
成熟した女性のような情欲を抱かせる顔つきではない。躯の方も、貧相なのは脱がせなくても判る。けれども、ある程度の幼さを残した少女だけが持つ、年頃の危うさ――脱皮をしようしている蝶のような、触れては無くなってしまいそうなバランスで保たれた色香があった。
特に、大男は少女と同じくらいの年代のときはいつも両親にこき使われて労働を強制されていた。とてもではないが、異性と懇意になる余裕などなく。娼婦を抱いても、若い肉体への憧憬が常に胸の中で燻っていた。
だからこそ、その少女は大男にとって、即獲物と判断されたのだ。
大男は他の男たちの倍はあるのではないかと思う歩幅であっという間に少女に近づくと、その肩を掴んだ。あと少し強く力を入れれば肩をもぎ取ってしまえるのではないかと思うくらい、少女は大男と比べると小さかった。
「こんな夜中に街を出歩くとは良い度胸じゃねえか。それとも、箱入りのお嬢さんは夜の街の礼儀もしらねえのかい?」
「兄貴ー、そんな餓鬼になにするつもりなんです? 素人娼婦潰したみたいにすぐ壊れちゃいますぜ」
「馬鹿、それがいいんだよ。それにな……何事も、新鮮さってのは大事だ」
「そいつァはまったくもって真理ってやつっスね」
ふたりは下品に笑った。夜の街に、それが染みいって消えていく。人通りのまったくない夜だった。誰にも邪魔されることはない。もっとも、貴族の娘が乱暴されるのを止めるような者が、この国に今もいるなんてことはないだろう。
大男と眉無しが少女の腕を掴んで、強引に路地裏へと引きずり込む。それを見て困惑気味だった小柄な男は、仕方なしにふたりの後に付いていった。
その間、少女はずっと無表情に男の下卑た表情を見つめていた。
街灯の明かりがまったく届かない路地裏は、天に輝く月明かりすら差し込まない。
それでも、夜目に慣れていた三人の目は、至近距離なら少女の姿 を捉えるのに支障はなかった。顔と白いフリルだけが闇の中に浮いているように見えるのを小柄な男は不気味と思い一歩退いたが、他のふたりは完全に火がつい ていた。興奮したふたりは、目的以外の感覚が完全に鈍化していて、気付かない。広場で公開処刑に熱狂していたときのように、ふたりは高ぶっていた。
「へへっ、怖くて声も出せないってか。出しても誰も来ないだろうがな。お前が今も着てる服がオレたちの犠牲の下で作られてることの傲慢さの報いってやつを、たっぷり躯で教えてやるよ」
よく見ると、少女の服は所々はだけていた。脱がせ方など判らず、元より破くつもりだった大男は思いきり引くだけで上半身のドレスが脱げたことに驚く。まさ か、もう既に誰かの手で汚されていたのだろうか。あり得ないことではない。むしろ、こんな少女が歩き回っていれば、当然といえた。
誰の手にも触れていない果実を貪る――その想像に胸を躍らせていただけに、別の男によって弄ばれた後というのは酷く落胆した。それでも、少女は魅力的だった。止める理由はない。
暗い路地裏で露出された胸は、予想通り薄かった。ふっくらと膨らんだ胸は発酵を始めたばかりのパン生地のようで、柔らかいが膨らみはたいしたことはない。けれど乳首の淡い色も、肌の白さも、男慣れした娼婦とは比べものにもならない背徳感を抱かせた。
大男は少女の黒髪の上から頭を掴んで、ぐいっと自分の股間へと顔を近づけさせた。下着ごとズボンを降ろすと、刺激臭を放ちながらもぱんぱんに膨らんだ肉棒が少女の頬を叩いた。
その肉棒は、大男の体格と合ってふつうの男のものとは一回り以上も大きかった。女性の手首くらいの太さはある。それはもう性器というより、女性にしてみれば凶器だった。
「ここのところ風呂なんて入ってねえからな……まずはお前の口で綺麗にしろ」
少女は黙って、大男の陰茎を見つめていた。大男が自慢する一物に度肝を抜かれたのか、それとも、なにをすればいいのか理解していないのか。
大男は焦れて、少女のぷにぷにと柔らかい唇を親指でこじ開けて、無理矢理陰茎を突き入れた。上顎の凹凸を亀頭がなぞり、裏筋をなぞる舌を押しのけながら喉 の奥を突くと少女が初めて呻き声を上げた。口が裂けそうなほど大きなものを銜えさせられた少女は今にも顎が外れてしまいそうで、目を大きく見開いた。
「うっ……っっっ……」
少女の反応に気をよくして、大男は少女の黒髪を掴んで無理矢理引くと、腰を思い切り少女の美貌に叩きつける。
「ふっ!?」
悲鳴を喉の奥で上げる少女に、大男は嗜虐心を煽られた。陰茎は、少女の口の中で今も大きさを増していた。
「ほら、綺麗にしねえか!」
大男は何度も少女の顔に腰を振った。
真っ赤に膨れあがった亀頭が少女の涎を絡みとって、じゅっじゅっと上顎にこすりつけられる。何層にも重なった垢が少女の口を汚し、赤々とした舌は大男の裏筋を強制的に舐め上げさせられる。
「んんっ! じゅ……ふう……んぐっ、んんんっ」
少女の口の中は一言でいってしまえば、これまで大男が相手にしてきた娼婦など比ではないほどにいやらしく、心地よく、刺激的にペニスを舐めあげた。
幼気な、そして憎き貴族の娘であるからだけではない。この少女の口は、まさしく大男の精液を搾り取るために作り上げられた産物のようにペニスに纏わり付いていた。
大男はいつの間にか息を荒くしていた。快感が腹部にこみ上げてくる。
もう我慢できなかった。
少女の頭を両手で掴み、ぐっと腰を奥まで押しつける。喉の奥の奥へと思い切り突き入れ、少女が反射的に大男のペニスに歯を立てるが、唇に親指をねじ込んでそれを押しとどめた。
「ぐ……出るぞォ!」
猛獣のように咆えて、大男はペニスから精液を噴出した。
どくんっ、どくどくっ、どくんっっ!
がくがくと腰が震えるほどの快感が大男の下腹部を走り抜けた。
何度も震えながら、数週間にわたって発散していなかった精液が少女の細い喉に直接流し込まれる。
「あ……うううう……っ、んー! んー!」
小刻みに震える大男のペニスのように少女の躯も驚きでまた震えた。大男から逃れようとするが、少女の腕力では屈強な躯を一ミリたりとも押しかえすことができない。
「ああ、ぐう……全部飲み干せ! でなけりゃ喉に詰まって死んじまうぞ?」
にたりと笑って、大男はまだわずかに射精しながら脈動するペニスで少女の喉を擦った。
「んん……ん、んん……んくっ、んくっ……」
何度も少女の小さな喉が上下する。それでも、ゲルのように粘性の高い大男のはき出した精液を喉の奥に出されたのでは少女には飲み下せなかった。
大男は少女が窒息しそうになる寸前で陰茎を抜くと、少女は咳き込みながら自分のドレスの上に精液をはき出した。
「けほっ、けほっ!」
どろりとした白濁が少女の口から流れて黒いドレスを白く彩る。少女を犯した実感が大男を高ぶらせた。
「兄貴、早すぎですよ。こんな餓鬼に」
「うるせえ、お前もやってみろ……こいつは魔性だぜ……」
大男のペニスは少女の口に精液を流し込んだばかりにもかかわらず、涎と精液で濡れた赤黒い姿で天を指していた。
元より、一発程度で満足するような男ではなかったが――全然、収まらないのは初めてだった。
大男は路地裏に座り込むと、咳き込む少女の腰を掴んで自分の下半身の上までもってきた。咳き込み、まだ虚ろな目の少女のスカートを掴み、はぎ取る。ボタンでも千切れたのか、スカートはあっさりと脱げ、まだ毛も生えていない無垢な下半身を獣の前に晒させた。
「おお……」
思わず声を洩らす。つるりとした卵のような下半身と、小さな突起に、亀裂から覗くわずかな赤み。
大男は生唾を飲んでいた。これは、熟れた女の性器よりも、ずっと淫蕩だ。
ペニスははち切れんばかりに大きくなっている。大男は少女の腰を掴んで浮き上がらせると、屹立したペニスに宛がった。
入り口に亀頭を押しつける。どう見ても少女の躯に入る大きさではない。けれど大男は躊躇せずに力を込めた。ずるりと、亀頭が小さな穴に力尽くでねじ込まれた。
「あ――!?」
びくんっ、と一際大きく少女の躯が跳ねた。亀頭が入っただけだというのに、それでも小柄な少女の躯には大きすぎた。
「まだ頭が入っただけだぞ? たっぷり味わえ……!」
大男はその反応に気をよくして――一息に少女の躯をペニスに打ち下ろした。
ずんっ、と少女は下半身を貫いた槍の衝撃で、ずっと胡乱だった目を見開く。少女の腹部は見ただけで判るくらい、大男のペニスが存在を主張していた。
「おお……っ」
大男はペニスを締め付ける膣の快感に声を洩らす。
膣は大男の一物を押しつぶそうとするほどに密着し、挿入の際にそのひだで亀頭をなで上げた。予想外に愛液でたっぷりと濡れた少女の未熟な性器は、それだけで大男を絶頂させるところだった。
ぐっぐっ、と動かさなくても何度も膣が収縮し、ペニスを刺激する。それだけで大男は亀頭で押し込んでいる子宮に精液をぶちまけてしまいそうになる。
「ぐっ、そんなみっともない真似してたまるか!」
大男が少女の腰を掴んで浮かせると、また玩具みたいに腰へと落とす。少女の体重を乗せたピストンがまた少女の子宮を突き上げた。
「うあっ! ……あああっ」
「見た目と違って煩く鳴くじゃねえか、そんなにオレのが良いか、おい!」
大男は少女の躯をくるりと半回転させると、地面に四つん這いにさせた。そのままバックで少女のお尻に腰を叩きつける。ピストンする度に、赤い血が流れた。それは破瓜の血なのか、それともあまりに大きい陰茎故に性器が裂けたのか。
亀頭はぐちゅっ、ぐちゅっと膣内を何度も突いて竿は少女の柔肉が丹念になで上げる。大男は全財産を払っても買えないような高級な布のように白くなめらかな少女の背中に涎を垂らす。そして乱暴され赤くなっている少女のふっくらとしたお尻に腰を叩きつけた。
そのたびに少女の性器は年らしからぬいやらしいぐちゃぐちゃとした音を立てて、男のペニスに蹂躙される。
「ああっ、あ……ああっ……!」
「おおおおおお、おおおおおお!」
大男は咆えて、ぱんっぱんっぱんっと叩き込む。
もう再度の射精感を押しとどめることは出来なかった。
腰を引く――亀頭のエラをずりゅずりゅっと膣が舐めて、大男は達した。少女の腰を指が食い込むほど掴んで腰を押し込んだ。
――びゅっ、びゅる――っ!
肉棒が爆発して、そんな音が少女の肉越しに聞こえてきそうな勢いで精液を吐きだした。躯の中身ごと総て捻り出そうな射精感が大男を襲った。
がっちりと大男の汚い剛直を銜え込んだ小さな性器から、精液が勢いよく噴き出した。少女の痩躯には大男の欲望はあまりにも大きく暴力的すぎた。
「あ、はあ……っ、んあ……」
ぐったりと上半身を地面に横たえて、少女は未発達な胸を上下させていた。
大男は乱暴に陵辱された少女よりも疲労していた。睾丸から精液を吸い出されただけではなく、体力まで少女の中に放出してしまったような錯覚すらした。これまで何人かも覚えていない量の女と寝てきた大男であったが、この少女の性器の快楽はそれらとは桁違いだった。
しかも、大男の肉棒はまだおさまらず、ぱんぱんに腫れ上がっている。鋭敏になった神経をひくひくと圧迫する少女の性器のせいで萎えることさえできない。
「な、なんて名器だ……」
赤くなった少女の丸々としたお尻と接合部をマジマジと見る。未成熟な、けれど男の味を知って女にさせられた少女の躯は、再び大男の性欲に火をつけた。
ゆっくりと腰を引き、大男は思いきり腰を突き出す。
「ひゃっ」
大男の手では片手で持ち上げられそうなほど小さな躯に暴力を叩きつける。陰部から泡立った精液と愛液が掻き出され、少女の躯は意志とは裏腹に大男のペニスを受け入れさせられていた。
三回戦に突入した大男を見て、眉無しの男は笑った。
「大げさだなァ、兄貴は。そんなにきつめが好きなんすかィ? こういう小綺麗な子供よりも、胸のでかい女の方がこっちとしては好みなんすがね……お?」
眉無しが片方の眉を持ち上げる。よろよろと上半身を起こした少女が、バックから突かれながらも眉無しの下腹部に顔を寄せていたのだ。
にやりと眉無しは笑って、ズボン越しにはち切れんばかりになっているペニス突き出すと、少女はたどたどしい手つきで眉無しのズボンを脱がせた。
「なんだ、そんなに気持ちいい理由がわかりましたぜ。こいつ、見かけと違ってこういうことに手慣れてやがるんだ。それとも、夜の礼儀ってのを教え込まれたのかな?」
少女はふわふわとした手でペニスを握ると、亀頭をぺろりと撫でた。ぴくっと反応するペニスを見つめて、少女は目を細める。
つい先程まで軽口を叩いていた眉無しは背筋にぞくりと走るものを感じた。とても少女がするような目ではなかった。あまり色気があって――自分の欲望を総て見透かされているような錯覚を抱かせる。
「あむ……」
少女が口を開けて、眉無しの赤い肉の塊を口に含んだ。ちろちろと口の中で尿道を舐めると、眉無しは反射的に腰が引けた。けれども、少女は腰が下がった分だけ身を乗り出して、そのペニスを離さなかった。
「うおおおっ」
大男のペニスを精液まみれの下半身で銜えたまま、少女は銜えた陰茎を根本まで簡単に食べてしまった。頬をすぼめて、口の中の柔らかい肉で茎を締め付けて、舌で亀頭の下の裏筋を丹念に舐めあげた。
ぐちゅ、ぐちゅっ、じゅるっと、下品な音を隠しもしない。上品な姿と裏腹の淫靡な振る舞いに男の中で急速に射精の欲求が高まっていく。
「お、おい、ちょっと待て。やめろっ」
「ん……んんっ……ふ……っ」
少女は聞こえていないのか、無視しているのか。銜えたペニスは離さない。むしろより一層激しくフェラの勢いを高める。じゅ、じゅじゅじゅ、と高まるテンポに、男は意識を奪われた。止めようなどという考えが吹き飛んだ。
混みあがる快感に、男は下腹部をみっともなく突き出して――
びゅくっ、びゅくっ!
陸に打ち上げられた魚のように背筋を振るわせて、男は溜め込んだ白く濃厚な精液を少女の口内に洩らした。
「……んくっ」
さっき大男の精液を飲み下すことができなかったのが嘘のように、少女は新たな精液を唾液で攪拌すると総て喉に流し込んだ。
ペニスに纏わり付いた精液一滴惜しむように吸い付いて、眉無しに追い打ちの快感を与えながら、少女は男の陰茎を悩ましげな吐息と共に離れた。
亀頭と唇の間に出来た唾液の糸を指で払うと、口元についた精液を拭って舌で舐めとる。
「お、おおおおおおっ」
大男が三度目の絶頂を迎えていた。陶然としただらしない顔で、大男は自分より一回りも二回りも小さい、子猫のような少女の性器に欲望を流し込む。いいや、吸い取られている。
犬のように男たちに犯されている体勢でありながら、少女はいつの間にか男たちを手玉にとっていた。
少女と、唯一この狂乱に参加していなかった三人目の男の目があう。少女の目は、やはり表情を写していない。性の興奮に身を焦がしているわけでもなかった。 けれど、そこには憎しみの感情が見え隠れし――それは普通とは違う妖しい煌めきとなって、男たちの目を釘付けにして離さない。
矮躯の男はまだなにもされていない状態でありながら、あることをこの場の誰よりも強く理解していた。
路地裏の暗がりに転がった、人の躯を見つけてしまったから。それは水分を抜き取られたように渇いていて、惨めに下腹部をさらけ出して死んでいる誰かの死体。
そうして、ああ、あれが自分の末路なのだと思った。恐怖におののいても、逃げることも声をあげることさえ、できない。
何故なら。本来ならば少女を犯すなどと考えられないこの男でさえ、あの少女のアンバランスな魅力に、既に虜になってしまっていた。香るほどの死の臭い。それは男たちの頭を胡乱にして――。
大男が仰向けになり、少女が大きな躯に跨る。大男に頭を掴まれればたちまち握り潰されそうなほどの体格差がありながら、もう大男は肉食の野生動物に馬乗りにされたようなものだった。
眉無しが少女のお尻を掴み、親指をねじ込んでアナルを押し広げる。そこに吸い込まれるように、いきり立った肉棒を挿入した。
また狂乱が再開する。
肉がぶつかり合い、淫らな水が音を立てる。
ここは狩猟現場。けれど、最初に獲物だったはずの存在に、獣は無惨に貪られる。そんな凄惨な、夜の食人祭だった――。
そこには乾涸らびた何かだけが残り。
そうして誰もいなくなった。
白目を剥いて動かなくなった巨漢の男を一瞥すると、少女は靴下だけになった足で立ち上がった。
ぬぽっ、と音を立てて大男の一物が下半身から抜け落ちた。硬さを失っていても、そのペニスは平均的な男性が勃起したものと同じくらいの大きさがあった。
ふらりと物言わぬ屍となった男から離れると、股と後ろの穴から白い液体が汚い路地裏の地面にシミを作った。
どれほどの間、こうして男三人とまぐわっていたのか。躯に渇いた精液と汗、涎がこびり付いていて少女は不快だった。下着をはこうと思ったが、路地裏の隅にボロ切れとなって発見されたので諦めた。
自分のブーツを見つけると、一緒に拾ったドレス――ゴシックロリータという衣装らしいことを少女は聞かされていた――ごと身に着ける。服が汚れることを気にはしなかった。どうせ、もらい物だ。
合計四人にもなる男の亡骸を少女はもう一顧だにしなかった。平然と路地に出る。
街灯の下に、人影があった。
こんな夜更けにまた獲物が迷い出たかと少女は思ったが、胸を大きく開いた扇情的なローブを纏った女性を見て、すぐに怒りを鎮めた。
その女性は娼婦と云われればそうだったが、大きな帽子と長いローブを身に纏った姿を一言で表すなら、魔女という言葉が一番よく似合った。
魔女。――そう、まさしく、その魔女だ。
腰まで届く銀の髪は、色が抜けたなんて間抜けな想像はさせない。銀塊を熱で溶かして細工したように美しい。ここが人通りの多い時間ならキラキラと光るその 髪に手を伸ばそうとする者がほとんどであっただろう。目は切れ長で見つめられるだけで誘われているような色香があり、露わになった胸元は豊満。
少女を言葉であらわすならば幼さと成長間近のアンバランスな肢体が背徳感を刺激する抗いがたい魅了の美であり、魔女は男ならば抱かずにはいられないと躍起にさせる女性的な魅力で溢れていた。
大きな帽子を被った魔女が、少女に微笑んだ。
「どうだい、その躯の使い心地は。すこぶる良好だったろう。今の君にかかれば、男なんて猿と同じだよ。その気になれば躯ひとつでどんな権力者でも虜にできるだろうさ」
「興味ない」
魔女のつかみ所のない物言いを、少女はばっさりと切って捨てた。刃物のような切れ味だった。
「男を籠絡して、混沌に落ちる様を眺めるのも遊びとしては楽しいものだと思うけどねえ。いやしかし、キミがそれほど美しくなるとは私としても予想外だったよ。純粋なモノほど、見た目に現れ易いということかな。キミほど美しく洗練されたモノは見たことがない」
少女は魔女の会話に付き合うつもりはなかった。自分に躯を与えてくれたことには感謝しているが、わざわざ恩を返そうとは考えていない。何故なら魔女はおの れの娯楽のために少女を少女たらしめたのであり、そこに利害があるのなら、特別、少女から何か恩を抱く必要はないと思ったのだ。
「自分では判らないけど、その美しさがわたしの役に立つのなら――好都合だわ」
「へえ、本当にやるつもりなのかい。キミは」
魔女は自分が少女と邂逅した日のことを脳裏で再生しながら、云った。
「あの処刑人の復讐を。――処刑道具であるギロチンのキミが」
少女は黙っていたが、沈黙は即ち肯定だった。
くくっ、と魔女は喉を鳴らして笑う。
「自分の手入れをしてくれていた処刑人が、自分を使って殺された。その復讐をしようとは畏れ入る。素敵に一途だ。しかしだね、私は判らないのだが、キミは誰に復讐をするつもりなのだね。さっきの男たちは処刑人の死に直接関わったようには見えなかったのだけど」
「復讐の相手? わかりきったことね」
少女は憎悪を込めて、うそぶく。
「わたしの復讐する相手は〝この国の総ての人間〟。この国自体がわたしの敵。――わたしは彼を殺した総意に報復する」
広場の熱狂が少女の裡で蘇る。
誰もが、何もかもが、処刑人の男の死を望んでいた。頭のネジがとんでいるみたいに喚き散らして、ギロチンである自分の刃が震えるほどに叫ぶ。あれは狂気の嵐だった。
彼らは直接殺していない? なんてことをいうのか。人の死に興奮し、狂い、望んだのなら、彼らも等しく殺人者だ。少なくとも、処刑道具として産まれ、人間のエゴで人を殺し続けてきた少女はそう確信していた。
「それにあの大きな男は、あの日、彼の生首を持ち上げて石畳に叩きつけていたの。額が割れて血が流れていたわ。そんな人を見つけたら、もう殺すしかないでしょう?」
「ほうっ、では何故わざわざ男たちに快感を与えて殺したんだい? キミならもっと効率的に殺せるじゃないか。慈悲のつもりかい?」
「慈悲?」
少女はそのとき、初めて笑った。暗い暗い、井戸の底のような笑み。
「まさか……。ギロチンは、人を楽に殺してあげるための人道的な処刑道具として作られたんだから……。あっさり首を狩っちゃったら、苦しくないでしょう?」
そうだ。自分が処刑人を殺す道具として使われたことに唯一感謝することがあるなら、彼を苦しませずに逝かせてあげられたことだ。
「それに、快楽は……一度与えられた至福は、やがて来る絶望を引き立てるもの。わたしが彼という幸福を奪われたときのように、快感が絶望へと変わる感情の墜落――それを味わわせることなく殺すなんて、わたしにはできないわ」
少女が口数も多く、滔々と語った内容は魔女の心を満足させた。喉を鳴らして笑った魔女は、夜闇の元で手を叩いた。
「すばらしい! それでこそ、だ。見せてもらおうじゃないか。キミの人と国ひとつを堕落させる復讐を。しかし、それならキミにも名前がいる。そうでなくては、存在としての重みが違う。人もモノも名を持つことで存在として一段強くなるのだよ」
「名前……?」
自分の名前。そう云われても、少女は断頭台。人を殺す道具としての名前はこれだけで充分だった。けど、そうだ。少女の脳裏に引っかかっているものがある。それはいったい……、と引き出そうと悩む少女を尻目に魔女はいった。
「よし、キミの名前はギヨたんだ」
「…………はっ?」
少女は目を丸くした。人としての躯を得てからの少女の表情では、とびきり間抜けな顔になっている。
「なんだい、そんなに私を見て。そんなに気に入ったかギヨたん。良い名前だよギヨたん。うん、我ながら素晴らしいネーミングセンスというやつだ」
「…………」
「どうした、ギヨたん。感動で声もでないのかい」
「その呼び方をやめないと真っ二つにしてやる」
溜息をついて少女は魔女に背を向けた。
「アンナマリア」
「うん?」
「アンナマリア――そういえば彼はわたしをそう呼んでいた」
処刑道具に聖母の名前。そうだった。寡黙な男だったけれど、彼はロマンチストだったことをアンナマリアは思い出した。
街灯が転々と続く、どこまでも続いていきそうな真っ暗な路地をアンナマリアは歩き出した。
名前のことを意識したら、洪水のように処刑人のことが脳裏に浮かぶ。そして、それがもう二度と手に入らないことに気付く。
ああ、そうか。と深い闇を睨んだ。
ここから、わたしの復讐が始まるんだ――。
序章/了
魔女とは、その名の通りに魔法を操る女性のことである。けれど、魔法使いではない。魔女と魔法使いを区別する最大の要因は悪魔と契約したか、そうでないかである。
魔法使いは一概に悪しき存在とはされない。もちろん、自我を持っている生物であるから邪念を持った者もいるだろうが、それはただの人間とて同じことだ。一 方、魔女の全員は悪魔との契約を結んでいる。彼らの交換条件を受け入れているのだから、それは間違いなく人に仇をなす。そのために、魔女狩りが各地で勃発 したのである。
何より、人は魔女に恐怖していた。実際に魔女を目にした者は少なかろうし、実在を信じぬものもいる。だが、魔女の恐怖とは常に身近なところにあった。
「――ふむ」
自宅の壁に寄りかかり、窓から日中の人通りを眺めている銀髪の女は、紛う事なきその実在する魔女の証明であった。
今は魔女のトレードマークたる両手で抱えるくらいの大きなハットを帽子掛けに預けて、悩ましい胸を押し上げて腕を組んでいる。
断頭台を人に変えてしまった、この魔女の尋常ならざる力は、やはり人が見れば畏怖する対象になるのも納得であった。
「いよいよもって、騒ぎになってきたね。理由のわからない結果による不安が、街の中に溢れている。この押し殺したようなざわめきは、火薬庫牢獄への襲撃による革命を控えていたときを思い出すよ」
唇の端を持ち上げて微笑する魔女に、奥の方にある扉の向こう側からの声が答えた。
「そんなこと云って、今回の騒ぎは先生の仕業じゃないですかぁ」
間延びした、甘えている猫みたいな少女の声。
扉が開く。足で扉を蹴って出てきたものは、大量の紙――ではなく、大量の紙束を抱えた女の子である。
彼女は部屋の隅で本を乱暴に手放す。人がジャンプしたみたいな地響きがして、積もっていた埃が大量に舞った。それに少女は口を押さえて咳をする。
「うひゃあ、……もうっ、先生がお掃除しないから埃がこんなにたまるんですよぉ! たまるのは性欲だけにしてほしいですぅ」
「掃除の必要性を感じないのだよ、私はね。だって、考えてもみたまえよ。私は流浪の魔女、いつここを離れるともしれない身だ。家の整理などして何になる」
「暮らしやすくなるんですってば! それに住むからには少しでも楽しく気持ちよく生活できた方が素敵じゃないですかぁ」
「一理あるね。じゃあ言い出しっぺが頑張ってくれるんだろうね?」
「うっ、墓穴でしたかも……なに云っても先生は動かないんでしょうけど……」
にこりと魔女が微笑んだ。
「よくわかってるね。さすが、私の助手だよ、レリア・キッス」
「奴隷の間違いじゃないですかぁ?」
助手と呼ばれた少女、レリア・キッスは、露出している、まるで雲みたいに白い肩を落として嘆息した。
レリアは炎みたいな色をしたショートヘアが印象的な少女だ。炎といっても単純な赤ではない。火がもっとも情熱的に燃えるときの色は、透き通ったマリンブルーみたいな蒼である。レリアの頭髪は、赤と蒼の見事なグラデーションの幻想的な色合いだった。
服もキャミソールか、それに類したもので薄着だ。下は裾を短くつめたスカートである。激しい動きをすると中のものが見えてしまいそうだが、きっとこの少女のことだから下着を隠すようなものはないのだろう。
魔女のものぐさな態度に呆れたレリアはまた家の奥へと戻ろうとすると、タイミングよく玄関の扉がノックされた。
木を叩く小気味良いリズムに魔女が返事もせずに扉を開ける。そこには紙袋一杯にパンを抱えた金髪の少年がにこにこと嫌みのない笑顔を浮かべていた。
「こんにちは、魔女先生! 今日もパンを届けに来ましたよ」
元気の良い挨拶に、魔女も歓迎するように腕を広げる。劇でも演じるような大仰な動作であっても、これが魔女にとっては自然体だった。
「おや、ジョゼフか。いつもよく来てくれるね」
「いえいえ、魔女先生は命の恩人ですから。こんなことで遠慮なんてしないでくださいよ」
「そうかい。ところで、魔女先生というのはいい加減やめてくれないかな。あんまり知られると困るんだ」
「あ……そうですね、イザベラ先生、の方がいいですよね」
「偽名だけどね。はい、いつもわざわざ来てくれて助かるよ」
魔女イザベラの言葉に、レリアは「そう思うなら自分で買いに行けばいいのに……」と呟く。わざわざ宅配してもらっているのは彼女だけなのである。
それでも、ジョゼフと呼ばれた少年は嫌な顔ひとつしておらず、はっきりとした口調で否定した。
「いえ、好きでやってることですから」
「そういってくれると胸が痛まなくて助かるよ」
ジョゼフに銅貨を渡してパンを受け取っているイザベラをレリアが胡散臭そうな顔で見ていたが、すぐに表情を切り替えてジョゼフの方へと走り出す。イザベラの躯を抱きつくように押しのけた。
「ジョゼフくん、ジョゼフくん! いつものやつもちゃんと入ってるよね」
「ぼくの作ったパンのことなら、うん、入ってるよ。でも、いいのかな。こんなのまで買い取ってもらって。ぼく、まだ見習いだし、恥ずかしい話だけど美味しくないよ」
ジョゼフはパン屋に住み込みで働いている少年で、熱心な働き者として客からの評判はよかった。屈託のない芯の通った性格と子供っぽい笑みのために、今では パン屋の看板娘ならぬ看板男と云われるほどである。欠点をあげるなら、パンを焼くのがお世辞にも上手ではないことだった。
「ううん、いいの。あたしはジョゼフくんのパンが食べたいの。これからも一杯もってきてよ?」
「そう云ってくれると作ってよかったって気分になるね……。今度はもっと美味しくできるように頑張るよ。それじゃあ、ぼくはこれで!」
魔女イザベラに小さく頭を下げると、ジョゼフは家に背を向けて小走りに大通りへ消えていった。
ジョゼフの背中が人混みの中へ完全に消えるまで、レリアは恋い焦がれる乙女の顔でじっと見つめていた。イザベラに抱きついたまま、見た目に合わぬ悩ましげに息をついた。
「はあああ……美味しそうだなあ」
目はパンに――ではなく、ジョゼフが去った方に向いたままである。
「先生ぇ、ジョゼフくんはきっと美味しいですよぉ。食べていいでしょう?」
「駄目だ。さすがの私も自分の助けた相手が片手間にあの世へ送り返されるのは黙ってられないぞ。キミはパンでも食べてなさい」
「ふがっ」
パンを口の中に突っ込まれて、レリアは呻いてイザベラから離れる。そのパンは不格好でお世辞にも綺麗な見た目とは云えなかったが、レリアはそのままパンを平らげてしまった。
「うーん、いつ食べてもジョゼフくんのパンは不味いなあ」
言葉とは裏腹にレリアは満面の笑顔である。
イザベラは机の上にパンの詰まった紙袋を置くと椅子に躯を預けて、レリアの方に皮肉めいた笑みを向けた。
「レリア、キミは社交辞令をよくわかってるんだね。関心するよ」
フランスパンを小さく千切って口の中に放り込む。今朝焼いたばかりのパンは表面こそ硬いものの香ばしく、反面、中身は柔らかい。スープにつけて食べると 益々味が引き立つだろうが、イザベラは料理をするのが好きではなかったし、レリアにとっては本来の食事とは異なる代換え行為に過ぎなかった。
「へ、社交辞令なんて云ってないですよぉ? あたし、ジョゼフくんの前でこのパンが美味しいなんて一言もいってないですもん」
「余計タチが悪いと思うよ。それが不味いのには同意だけど」
「あ、でも、あたしはこの味の方が好きなんですよ? 人が美味しいと感じるものより、こういった不味いものの方が口にあいますからねぇ」
「なら美味しいって云ってあげたらいいんじゃないかな」
「やだなぁ、そんなこと云ったらジョゼフくんが勘違いして色んな人に食べさせちゃうじゃないですかぁ。そうしたら、後で悲しむのはジョゼフくんですよ? 言葉の意味は気をつけないといけないのです、混乱しちゃいます」
「笑顔で不味いというのも充分に人を混乱させるよ」
フランスパンを半分ほど食べてから、イザベラはまた外を見る。行き交う人を目で追って、ジョゼフがやってくる前の話を振り返った。
「さて、ギヨたんはこれからどうするかな。このまま国の人間を皆殺しにできるのなら、見物なんだけどね」
「そのことなんですけどぉ、その、ギヨたん、ですか? 面倒なのに目をつけられてますよ」
「ほう、やはり彼女たちのシマを荒らしているからかい。まるで狩り場を取られた獲物だね」
「そんなに暢気でいいんですか? きっと殺されちゃいますよ」
「今のままなら――そうだろうね。あっさりと負けてしまうはずさ」
剣呑な指摘に、イザベラはあっさりと頷いた。
「だ けどギヨたんはね、その辺にいる悪魔だとかの範疇からは逸脱しているよ。なにせ元が無機物だ。どこかの国では長い年月を経た道具には魂が宿るとされている が、ギヨたんは誕生してまだ数年。この時点でも既にギヨたんが並外れた素質を持っていることは明かだ。私が手を加えたといっても異常だよ、これはね」
「でも、今は人間の姿って話じゃないですか。そんなに凄いとは思えないけどなぁ」
「なんだい、もしかして私が褒めるものだからって、嫉妬してる?」
「し、してませんよ! どうしてそうなるんですかぁ!」
むっ、と顔をしかめて、パンを総て呑み込んだレリアは小走りに玄関へ急いだ。
「どこに行くつもり?」
「ご飯です!」
無神経に訊ねてくるイザベラにレリアは肩を怒らせて答えると、扉を吹き飛ばす勢いで家を飛び出していった。
「やれやれ。……殺さないように気をつけたまえよ、なんて、もう遅いか」
自分の言葉をさして気にした様子もなく、イザベラは食事に戻ることにした。
*
ギヨたんこと、断頭台アンナマリアは夜の街で途方に暮れていた。
石畳をブーツで叩いて歩きながら、街を見渡す。
陽が落ちて久しい時刻、街灯が転々と道を照らしている。小さなスポットライトが列を作っているように見えた。アンナマリアが道を歩くと何度も何度もその灯りに照らされて、まるで劇の主演女優のようである。
ただし、他の出演者は誰もいない。
「……誰も、いない」
夜の街には人通りがまったくなかった。
闇に覆われた時刻なのだから、人が少ないのは当然である。それに不思議はなかったが、まったくいないのだけは異常だった。夜は太陽の代わりに月が昇る。そうして月の魔力に誘われるように、娼婦と男たちが街でうごめき始めるのだ。
なのに、今日と来たら、この有様である。
いや、以前よりこの兆候はあった。あまり気に止めていなかったが、日に日に人通りは少なくなっていた。
「わたしの、せいかな」
アンナマリアは連日、夜に出歩いた。朝には広間で断頭台に姿を戻している。それは、自分で人を処刑させるためだ。何故なら、アンナマリア以外の処刑機具で はいたずらに人を痛め付けた末に殺してしまう。苦しめずに人を処刑する思想で作られたアンナマリアは、それが許せなかった。
どうせ、全員苦しめて殺すのに――とアンナマリアは自分でも不思議に思うものの、性分なのだから仕方ない。きっと、自分の作った人たちの意志がそうさせるのだろう。
なので、自然と出歩くのは人が寝静まった夜になってしまう。アンナマリアは知らないが、街では夜の衰弱死体の大量発生で話題は持ちきりになっていた。さすがに毎晩そんな死体が見つかっていれば、怖れて外出を控えるのも当然だった。
街灯の下で途方にくれた。風評を気にしない無神経さか、よっぽどのもの好きでなければ通りがかることなどない。これでは目的が果たせない。いっそ、家に乗り込んでみようか。そうすれば、人の数に悩まされることもないし――。
そこで、アンナマリアは見つけた。
風評を気にしない無神経さを持っていて、もの好きな男が通りかかるのを。
金髪碧眼の、この国の者とは少しばかり顔の彫りも違う少年だった。彼の名は、ジョゼフといった。
かつては勉学や剣の道に励み、今はパン屋に住み込みで働いている快活な少年だった。それはもう脳天気だと云われるレベルであったが、本人は気にしていない。元気なのは、良いことだ。が彼の座右の銘であった。
客商売故に、ジョゼフも夜の街に関して流れる噂話は耳に挟んでいた。怖くなかったのかといえば、怖かった。けれど、遠くにある仕入れ先まで行って、小麦粉 などの買い取りの交渉をおこなわなくてはいけなかったのである。店主たちは夜の噂を懸念していたので、代役をジョゼフが買って出たのだ。
この分だと、無事に帰れそうだ。とジョゼフは胸をなで下ろす。誰もいない街を歩くのは、さすがに元気が取り柄のジョゼフといえども薄気味悪かった。
安心した矢先に、街灯の下に誰かがいることに気付く。
思わず足を止めて、小さな影を凝視した。
「女の子?」
思い浮かべていた人を襲う悪魔みたいなイメージが一気に霧散して、ジョゼフは肩の力を抜いた。
こんな夜更けに出歩く女の子がいるのも奇妙な話だ。首をかしげるが、深く事情を詮索するようなことはしなかった。ただ、こんな時間に子供が出歩くのは危ない。
「おーい、こんな時間に出歩いていたら危ないよ。最近、夜は特に物騒なんだからね」
声をかけるとジョゼフのことを女の子は見返した。けれど、彼女はとてとてと路地裏へと入っていく。
「あっ、ちょっと!」
ジョゼフが声をあげて、女の子が消えた方へと近づいていく。
「これじゃあ、ぼくが不審者みたいじゃないか……」
見間違えられてないといいなあ、と期待しつつ、路地裏を覗き込む。黒く煤汚れた地面に一歩踏み込むと、ジョゼフに背中を向けて闇に同化している女の子がいた。
黒いドレスは、ジョゼフも見たことはない。ふわふわしていて、気持ちよさそうだ、が第一印象だった。
女の子が振り返る。さらさらと黒髪が川となって空を流れた。ジョゼフは揺れる髪を自然と目で追っていた。この地域では滅多に見ない髪の色で、服装と相まって、その女の子は闇の妖精といわれても信じてしまいそうだった。
髪に見とれていて、ジョゼフは女の子が自分をじっと見ていることに遅れて気付いた。顔を近くで見てみると、自分よりもずっと幼い顔立ちをしている。小さな女の子に見とれていたことに恥ずかしくなって顔を羞恥で熱くしながら、なんとか注意の言葉を絞りだした。
「えっと、夜に出歩くのはやめておいた方が良いよ。ただでさえ、最近は恐怖政治で騒ぎがすごいから……あっ、いや、こんなこと云っちゃいけないんだけど。……それとも、帰れないのかな?」
家を無くしてしまった子だったら、帰れというのも酷な話だ。ひとりで悩んでしまうが、女の子がなにも云ってくれないのだから、しょうがない。
ただし、口を開いていない間も、女の子はずっとジョゼフの顔を見ていた。
「あの、ぼくの顔がどうかしたかな?」
「アンナマリア」
「え?」
「わたし、アンナマリア」
「あ、ああ、きみの名前か。良い名前だね。マリア様のお母さんと、その娘の名前か。きっと、この名前をつけてくれた人は素敵な人だったんだね」
素直な感想をジョゼフは口にした。この思ったことをすぐ口にしてしまうところが、今だに少年と呼ばれてしまう一番の要因なのかもしれない。けれど、嘘のない笑みは人を信用させるものだ。
しばらくアンナマリアはそのままじっとしていたものの、突然地面を蹴って駆けだす。
そしてジョゼフに思い切り体当たりをすると、そのまま唇を奪った。
勢いのままに唇を奪われ、ジョゼフは押し倒された。
いきなりの行動で躱すことも受け止めることもできない。そのせいで頭を地面に打ち付けてしまったが、ジョゼフの思考を乱すのは痛みではなく唇に触れている女の子の感触だった。
アンナマリアは相手の首に腕をまわして捕まえると、深く深く自分のそれを押しつける。
赤い眼と碧眼が合う。まるで地球と太陽のような対比。
そしてジョゼフはその赤い眼に釘付けになった。赤は赤でも、これは血の色だ。血で固められた赤い宝石(カーネリアン)。見つめているだけで心奪われる背徳の色。
熱い吐息を漏らしながら、アンナマリアは舌をいれて相手のものと絡みつかせた。そのままつるつるとした頬肉を内側からなめ、歯茎をなぞり、相手の舌をついばむ。
彼女の舌がそうやって口腔を情熱的に責めると、ジョゼフは口の中が火傷したみたいに熱くなって、同時に頭がクラクラと熱に魘された。
ジョゼフの舌の裏側に小さな舌が侵入して、浮き上がっている青い血管をなで上げる。ジンジンとした快感が喉元から下半身までを駆け抜けた。
口内をいやらしくくすぐった舌が抜ける。アンナマリアが顔を離していた。
キスをされているときは近すぎて見えなかった彼女の顔の全貌が、この距離だとよく見えた。
日頃こねてるパン生地のような柔らかそうな輪郭。大きな眼とぷっくりとした唇は赤々としていて、白と赤のコントラストは彼女がこの世のものではないようだった。
アンナマリアの肩にかかっていた黒髪が流れ落ちて、ジョゼフの顔をくすぐる。その黒は闇より深い暗黒だ。
確かに黒と呼べる髪。けれど、こんな黒をジョゼフは見たことがない。知らないのに、黒と認識できる。ジョゼフは昔、自分たち人間の世界にあるものは全部模 造品であり、真なる万物が存在する世界があると学んだことを思いだす。その世界にある本物の個体を知っているから、歪んだ図形を見れば間違っていると認識 できるのだ、と。
では、見たこともないはずの深いこの髪の色を黒と断定できるのは、これが本物だと云う経験にない記憶が想起しているからで――そうだ、この世ならざるものなら、この女の子の浮世離れしている美しさも道理であった。
まだ成熟していない躯でありながら、悪魔のように心を掴んで離さないのだから――。
「……あ」
ジョゼフが声をあげる。自分よりもずっと幼い少女からのキスで膨張していた愚息を、彼女が服の上から触っていた。
「ちょっと、駄目だったら……」
自分で云ってから、ジョゼフは本気で止めようとしていない自分がいることに気がついてしまった。キスのせいで酸素が不足しているからではない。ドレス姿の少女から漂う色香に期待して、はち切れそうになっている。
女性経験のなかったジョゼフは、たった一度のキスで魅了されてしまっていた。
細い指先がジョゼフの下半身の布を手慣れた動作で剥ぐ。勃起した男根がジョゼフのお腹を叩いた。
つぅ――、とアンナマリアの爪が裏筋を根本からなぞる。
「ふあっ!?」
快楽の稲妻が背筋を走り抜けて、ジョゼフは情けない声をあげてしまった。
刺激でゆがんだジョゼフの表情をちらりと覗き見て、アンナマリアは陰嚢を優しく撫でる。少しの衝撃で痛みを訴えるほどに敏感は睾丸は、快感に対しても忠実だった。まるで全身を愛撫されていると錯覚させる少女の手つきに、少年は肩をびくつかせた。
睾丸が甘やかされるにつれて、ペニスの方は激しく脈打つ。数々の行為によって破裂しそうになっているのに、直接触ってもらえていないせいで焦れていた。
物欲しげに脈動する情けない様で、アンナマリアも何をしてほしいのかを察する。男がどうして欲しいか、そんなことは連日連夜の性行で把握できるようになっていた。それこそ、本当にそのままの意味で手に取るように。
「これ、触って欲しいんだ」
アンナマリアが囁く。蔑みはなく、どちらかといえば、珍しくからかうような声音。
「ち、違っ」
「それじゃあ、このままで良いんだよね」
「それは……」
言いよどむジョゼフには言及せずに、アンナマリアは睾丸をさする手を止めない。男性器には指すら伸ばさなかった。
「あ、うあ」
「どうして欲しいの?」
「ぼくはっ、別に……」
アンナマリアは黙して語らない。無表情のまま、焦らされて切なそうにしているジョゼフを見つめるだけだった。
心を見透かすような目と、与え続けられる生殺しの刺激が、ついにジョゼフの羞恥心を上回る。
「下を、触って」
「下って、どこ? ……足?」
「そうじゃなくて! 云わなくてもわかるでしょうっ」
「ちゃんと、云って」
「……っ! ペニスだよ、お願いだから、もうっ」
「そうだよ……云ってくれないと、わからないよ?」
くすくすとアンナマリアが笑い、両手で陰茎を掴んだ。左手は亀頭に添えられ、右手は竿をゆっくりと上下させる。
これまでと比較にならない甘美な感触にジョゼフの腰が跳ねた。今までお預けをくらい、さらには女の子に懇願してしまったせいで、いつもよりもずっと快感が増幅されていた。
ジョゼフの穏和な顔立ちからは想像できないグロテスクな陰茎に、アンナマリアは息がかかる距離まで近づく。けれど亀頭はピンク色で、それが今まで自分の犯してきた男たちと違ってかわいらしかった。
アンナマリアははっとなる。憎き国に所属する男のペニスをかわいいと表現してしまって、アンナマリアは自分自身を疑った。
なにを考えているのだろう。
子供をあやすみたいな手つきを一変させて、アンナマリアは陰茎を握る手に思い切り力を込めた。
「うっ!」
突然の強い刺激に呻き声をあげたジョゼフに、アンナマリアは冷たく告げる。
「無様」
さっきまでの優しげな態度はどこへやら、小さな手は強い力で竿を擦り始めた。もう片方の手は我慢汁を亀頭に馴染ませるように円を描く。
激しい手淫に声をあげるジョゼフを無視して、アンナマリアの手は機械的にペニスを責めていた。我慢汁でぐっしょりと濡れた指先を雁首に這わせて、弾く。
「!?」
竿をしごく手はまったく止めずに、今度は親指と人差し指で作った輪で雁首を引っかけて、擦りあげる。
じゅっ、じゅっ、じゅっ、と我慢汁が気泡を作って音をたてた。
その間も、別の手が熱く滾った肉棒を扱う。ふたつの独立した手技に、高ぶっていた性欲が一気に限界を迎えた。
「う、うわあああっ」
ドクンッ、ドクッ、ドクッ、ドクッ……!
幼い手の中で欲棒が爆発した。
だが、熱く生臭い白濁とした精液を勢いよく掌に発射されても、アンナマリアは手の動きを止めなかった。
ジョゼフの腰が震えて、本来なら出なかったはずの精子がアンナマリアに飛び散った。犯しがたい黒の髪を、情欲の白濁が彩った。
何十秒もドクドクと出し続けていた射精の勢いが収まると、ようやくペニスをしごく手の動きも止まった。
容赦ない手つきに責められて息も絶え絶えなジョゼフとは対照的に、アンナマリアは息ひとつ乱していなかった。腐った下水道のぬめりのようにネバネバとした精液で真っ白に汚れた自分の手とペニスに視線を落とす。
「うぐっ!」
ジョゼフが悲鳴じみた声をあげた。
夜風に晒されていたペニスが生暖かいものに包まれていた。アンナマリアが口で銜えたのだ。
彼女の唾液が精液に濡れた肉棒を包み込んで、攪拌された精子を小さな喉を使って呑み込んでいる。喉が動くたびに上顎と舌が性器を圧迫して、萎えそうになっていたペニスに血液が集まった。
出してから一分も経っていないのに、ジョゼフの股間が熱くなっていく。それも少女の見た目とかけ離れた振る舞いのせいだった。
ペニスにむしゃぶりつくアンナマリアの頬は赤く上気していて、口淫で夢中になっているように見えた。ぴちゃぴちゃと音を隠しもせずに、少女の舌が剛直にこびりついた精子を呑み込む。
ジョゼフの腰が自然と浮き上がった。
再びペニスに集まり出す射精感。
しかし、それが放出されることはなかった。
「え?」
アンナマリアがジョゼフのモノから口を離していた。精液の代わりに唾液漬けにされたペニスが切なげに大きく脈打っている。
不思議な顔で視線を自分の陰部とアンナマリアの顔で行ったり来たりさせるジョゼフに、アンナマリアは嗜虐的な心理を覗かせた。
「どうかした?」
「い、いや、だって、また……」
「イかせて貰えると思ってたの?」
「で、でも、あともう少しだけは」
ジョゼフは股間に広がる射精したいという欲求を少しでも誤魔化すために、足をもじもじと動かす。ぱんぱんになったペニスは胸をかきむしりたくなるほどに射精への期待で一杯だった。
情けない懇願の声に、アンナマリアは感情を窺わせない冷徹なままで、けれど声だけは愉悦に満ちている。
「自分でやればいい。わたしの目の前で」
「そんな……」
突き放す少女に抗議の声をあげるが、アンナマリアは本当にそのつもりのようで、一切動こうとしない。ジョゼフがどうするかじっと観察していた。
こんな女の子に見られてる前で、自慰をするなんて――想像しただけでジョゼフの顔は真っ赤になる。既に少女の手の中で果ててしまった事実があっても、その痴態を晒すのには抵抗があった。
ふつうなら、女の子の前で自慰なんて絶対にしない。けれど、頭がおかしくなりそうなほど陰嚢の中で精子がはき出してくれと暴れ回っているのだ。
「う……っ」
真っ赤なトマトみたいに赤面して、ジョゼフは自分の肉棒を握った。自分の手で触れたのに、それはいつもよりもずっと心地よい快感を伴って陰茎を走った。
アンナマリアの唾液で濡れたペニスを上下にしごく。彼女の口内から分泌された透明のぬるぬるとした粘液を性器に刷り込んでいるような倒錯的な気分になってしまう。我慢汁と唾液が混ざって、気泡を立てる。
息を切らしながらの醜態をアンナマリアの感情を写さない目が見つめていた。ジョゼフの目がその目に吸い込まれる。目は口より雄弁に感情を語るという。けれ ども、無口無表情な彼女の目は前述したように感情を感じさせない。なのにジョゼフは小さな女の子に蔑まれているように思えた。
少女の手よりもずっと大きな掌の中で、肉棒はさらに硬さを増して膨れあがる。
アンナマリアの視線がジョゼフの切なげな表情から、下半身に移動した。
「オナニー見られて、興奮してる……」
「これは、その、そういうわけじゃ」
「変態」
「うぐっ」
「だって、今も手だけは止めないんだから」
アンナマリアの云う通りだった。自慰をおこなう手の上下運動はおさまるどころか激しさを増していた。
「わたしの見てる前で、出しちゃえばいいんだ」
耳元で囁かれたみたいに、その声は敏感になった神経に突き刺さり。
しごいたペニスは限界に達した。
「ううううううっ」
――ドクン! ドクンッドクンッビュクンッ!
尿道を駆け抜けて精液が噴出した。
ぐっと目をつぶって快感を受け止めるジョゼフの手がペニスを動かしてしまう。射精された白濁液が飛び散った先にはアンナマリアがいた。
アンナマリアの黒いドレスがぐっしょりと白で汚れた。胸元から、糸を引きつつスカートへ。グラスから牛乳をこぼしたみたいに、精液がみっともなくかかっている。
自分の服を汚した精液を黙って見つめる少女に気がついて、ジョゼフはペニスを握り締めたまま肩を震わせた。
「あっ、ごめん!」
ドレスに飛び散った精液をアンナマリアは指で掬いとると、なんとか上半身を起こそうとしているジョゼフを見下ろした。
「駄目。許さない」
起き上がろうとする肩を掴んで路地裏の地面に叩きつけると、アンナマリアはそのまま馬乗りになった。
痛みに目を閉じたジョゼフが呻きながらまぶたを開くと、眼前の光景に息を飲んだ。
ドレスのスカートをたくし上げて口に銜え、下半身を扇情的に晒したアンナマリアがそこにいた。
アンナマリアはスカートを口にしたまま、片手でレースのついた真っ白いショーツをずらすと、もう片方の手でジョゼフの剛直をつまんで秘所へと導く。
男の性器を受け入れられるとは到底思えない小さな亀裂と亀頭がキスをした。
「ん……」
熱っぽい息を吐いて、アンナマリアは腰を落とす。
愛液に濡れそぼっていた秘所が亀頭を呑み込んだ。
ぬるりと滑って入った少女の膣は、やはり狭い。ぎゅうぎゅうと真っ赤にふくれた亀頭を全方位から押しつぶしてくる。まるでクッションで包まれているようだった。
細い、抱きしめたら折れてしまいそうなアンナマリアの腰が落ちていくのに合わせて、幼い膣が陰茎をなで回しながら奥へと誘っていく。亀頭を、雁首を、竿と裏の筋を無数のひだにマッサージされ、今日一番の衝撃にジョゼフはたまらず声をあげた。
「あっ、あああああっ!」
二度の射精で神経がむき出しになったように敏感になったペニスから伝わる快感は、肉体的にも過酷な生活を送ってきたジョゼフすら絶叫するほどに淫蕩だっ た。しかし、連続で精液を出したペニスはすぐには射精をしない。もし一回も出さずにいれていたら、すぐに達していたことだろう。
既に達していたから雷に打たれたみたいな快感に翻弄され、既に達していたから中々射精ができない。そのふたつが合わさって、アンナマリアの膣はまるで嵐のようにジョゼフを襲った。
ずんっ、と少女の小ぶりなお尻がジョゼフの下半身に座る。アンナマリアの小柄な躯が男を根本まで銜えていた。
スカートを噛む力が強くなり、全身から絞り出した呼気がアンナマリアの喉の奥から洩れる。
「は、ん、ああああ……あ」
ぎゅぅううう、っと膣が締まり、剛直が柔らかい肉の感触に震えた。
浅い呼吸にあわせて、膣肉が蠕動を繰り返して銜えたものを情熱的に抱擁する。瑞々しく愛液をしたたらせる性器は、肉を雁首の合間にねじ込んでは舐めあげる。亀頭の表面はまるで無数の舌が這い回っているようで。膣肉の締め付けに肉棒は押しつぶされそうだった。
少女の意志とは関係なく、その未熟な躯は招き入れた男の精を貪欲に求めてペニスに食らい付いて離さない。
汚く穢れた大男の凶器じみた肉棒で処女を散らし、多くの男たちとの肉欲にふけり続けたアンナマリアの性器は、男の肉棒を快楽に昇らせる術を刻み込まれていた。精液が全身から染みこむのと一緒に、淫らな技もまたその身で覚えていた。
男を知って淫靡に染まった少女の柔肉に、女を知らぬ少年のペニスがもつわけもなかった。
「あ、ああああああああ!」
ドプッ、ドプッ、ドクドク。無意識に少女の腰を掴んでペニスを突き入れたジョゼフは、三度目ともなるのに一向に衰えない勢いでの射精をした。背筋を駆け上る悦楽で涎を垂らしながら、アンナマリアの子宮に若い精子を流し込む。
「ふ、くっ……出てる……っ」
虚ろな目で胸を上下させるジョゼフを頬を紅潮させたアンナマリアが楽しげに見つめる。口からスカートを離して、少年の胸の上に手をついた。
「あは……まだ動いてもないのにイっちゃうなんて、早漏なんだ」
そう云って、自分の腹部をさする。中にある肉棒が未だに存在を主張している。三度もの射精で出し尽くしているはずなのに、こうしている間にも少女の膣は蠢いて萎えるさせることはなかった。
「……動くよ」
聞いているとも判らない相手に告げて、アンナマリアは獣みたいな浅い息を吐いて、腰を持ち上げると――ずんっ、と体重を乗せてペニスを押し込む。
アンナマリアが美しい黒髪を揺らしながら腰を振るたびに、組み敷かれたジョゼフは快感と苦しみの入り交じったような声を発した。
「あっ、あっ、あああ……っ」
陸に打ち上げられた魚みたいに口をぱくぱくとさせる金髪の少年の顔を眺めていると、アンナマリアの中でこれまでにない嗜虐心と充実感がわき上がる。復讐心と嫌悪感だけで男を貪っていたときとは違う、不思議な感覚だった。
自分の中に産まれたものについて、アンナマリアは深く考えられなかった。彼女もまた、自分の中で暴れる肉棒によって興奮していた。脳髄が蕩けそうになって、黒曜の目を情欲に濡らしながら激しく、より激しく陰茎を性器に出し入れする。
ぷっ、くちゅっと泡立った白濁液が掻き出されて、生臭い鼻につく臭いが香る。汗に混じった、普段なら気持ち悪いはずの臭いが、今は興奮を助長させた。
「ふっ、ふっ、んんんっ!」
髪を振り乱して、玉のような汗を散らしながら腰を振れば、その白い肌からは性欲を刺激しそうな甘い香りが発散される。
「あはっ、またビクビクしてる……。ねえ、出したいの?」
気分が高揚しているアンナマリアは饒舌になって訊ねる。けれど、当のジョゼフはと云えば、少女の腰の動きによって与え続けられる心地よさで今にも意識を失いそうになっていた。
「答えられないの? いいよ……それでも今度はイかせてあげる」
アンナマリアの動きが激しさを増した。
ずちゅっずちゅっずちゅ! いやらしい少女の腰遣いが、肉棒を高みへと上り詰めさせ――
「う、出、ぁあ、あああああああ!!」
膣に愛撫され続け、四度目ともなる射精。
アンナマリアの膣の中にドクドクドクッと、洪水のように精子が押し寄せた。なんと今日一番の異常な量の精液が子宮と膣をぱんぱんになるまで犯し、それでも止まらない射精でペニスと秘部の接合部から精液がおもらしみたいに流れ出した。
「すごい、わたしの中が一杯……」
陶然とした表情で、アンナマリアは至福のときだと云うように無防備な顔を晒す。男のまぐわいで、これほどの幸福感を味わったのは初めての経験だった。
ガクガクと全身を震わせて、ジョゼフの首から力が抜ける。あまりの快感に少年は白目を剥いて失神していた。
その頬を小さな指がなぞる。
「まだ寝ちゃ駄目……もっと、がんばろ?」
そう云って、アンナマリアは再び腰を浮かせて無理矢理起こそうと――
「ちょぉぉぉぉぉっと待ったぁぁぁ――っ!」
――しようとして、夜闇に高い声が木霊した。
「はえ?」
不意打ちに、アンナマリアは彼女のイメージからでは想像できないほどかわいらしい声をあげてしまった。
その声は女の子の声で、真上から聞こえてきた。ジョゼフと繋がったまま、アンナマリアは声の主の方を見上げた。
上空――夜天にかかる満月を背後にして、大きな蝙蝠の翼が浮いている。ボロ切れみたいに解れた陰を揺らす翼、それを持つものはもちろん蝙蝠などではなかった。
人である。それも、小柄な少女だった。
一対の翼を広げて中空に浮遊しているのは、焔のような髪をした少女である。赤と蒼の不可思議なグラデーションの頭髪は風に揺られ、月明かりを受けてこの世のものとは思えぬ色彩を放っていた。オーロラを見たことのある者がいれば、まさしくそれだと断言しただろう。
健康的な色の肩を露出する下着みたいな服に、アンナマリアのドレスとは違い簡単に中が覗けそうな短いスカート。どれもが少女の性格を象徴しているようで、快活な力に溢れていた。
「正義の淫魔レリア・キッス参上! トウッ」
落下する勢いで急降下して、レリア・キッスと名乗った少女が路地裏に舞い降りた。
すたんっ、とポーズを決めて華麗に着地した少女は、呆然としているアンナマリアに柳眉を怒らせながら人差し指を突き付けた。
「ジョゼフくんはっ! あたしのっ! 獲物っ! なんですっ! 即刻離れなさーい!」
それが淫魔レリア・キッスと断頭台アンナマリアの邂逅だった。
レリア・キッスと名乗った少女に指をさされ、今まで呆気にとられていたアンナマリアはようやく平静を取り戻しかけていた。といっても、未だに下半身は男と繋がったままである。
初めて興が乗っていた情事を邪魔されて、憤懣がアンナマリアの胸の裡にわき上がっていた。レリアの背にある羽根は飾り物ではないようだし、只者でないこと は確かであったが、アンナマリアにしてみれば性行を妨害された一点のみが問題だった。そもそもアンナマリアとて只者ではない。
「……この人の知り合い? 目障りだから、どこかに消えてよ」
「むっか! 人の話ちゃんと聞いてました? あたしの方が先に退いてくださいっていったんですよぉ! それとも言葉がわかりませんかギヨたん」
「ギヨ、たん?」
そんな名前を口にした覚えはアンナマリアにはなく、ただしその名前で自分のことを呼ぶ者にはひとりだけ心当たりがあった。
「あの魔女の知り合いなのね」
「ええ、そうです。あたしは不本意ながらも先生の助手をしているのです。だから、貴女のこともよぉーく知ってますよ、ギヨた――」
言い終わる前にレリアは地面に伏せる。
瞬間、先程まで彼女の頭があった場所を疾風が駆け抜けた。
まるで刃を震ったような寒々しい風切り音。
レリアがおそるおそる顔を上げると、両脇の建物の壁に鋭い亀裂が走っていた。谷底のように亀裂の奥は闇が続いている。刃物でつけられたとしか思えない。け れど、その傷痕はどこまでも続いているように深い。どれほどの刃渡りがあれば、こんな痕が刻み込めるのか。それ以前に、建物を両断できる刃物がどこにある のだろうか――。
「その名で呼ぶなら、次は殺す。わたしにはアンナマリアっていう名前があるんだから」
アンナマリアがレリアに向かって細腕を突き出していた。その手は何も握っていないが、レリアは凶器を喉に突き付けられる心地だった。
「そうでしたね……貴女、元はギロチンでしたもんね」
どうしてこんな傷痕ができたのか理解して、レリアは呟いた。
そして驚きは既に消え、焔色の髪を夜風に揺らす少女の相貌には妖しい笑みが浮かんだ。
「それならぁ、こっちの方が……効果的ですよね」
レリアが地面を蹴って、アンナマリアに抱きついた。
「えっ」
ジョゼフと繋がったままで避けることもできなかったアンナマリアは抵抗できなかった。
もし性行中でなかったにしても、敵対心の感じない抱擁は避けようとすることができなかっただろう。
そのまま押し倒されて、アンナマリアの秘所からずるりと肉棒が抜けた。ずっと躯の奥で感じていたモノがなくなって物足りなさを覚えるが、今はいきなりレリアに抱きつかれたことに脳内が一杯になっていた。
「ちょ、ちょっと、いきなり何するのっ」
「貴女がいつもしてることですよぉ?」
ゴシックドレスの裾をはためかしながらジタバタと暴れるアンナマリアの目を見て笑うと、レリアは唐突に相手の唇を奪った。
「んー!?」
女性にキスをされて目を瞠り、抵抗が止まる。男相手になら慣れたものだったが、同性――ギロチンに性別をつけるならだが――からキスをされるという状況に酷く驚いた。
先程まで男の腰に跨って腰を振っていたとは思えない初心な反応を返すアンナマリアにレリアは愉しげに目を細めると、舌を相手の口の中にねじ込む。レリアのものより幼く、小さいぷっくりとした唇の合間に滑り込んで歯茎を舐めた。
「ひうっ」
口の中に入ってきた舌の感触にアンナマリアが肩を震わせる。必死に舌で押し返そうとするが、レリアはその舌に自分のものを絡ませた。
レリアの舌がアンナマリアの舌をなめ回し、くちゅくちゅと唾液が混ざり合う。
少女に舌で舌を愛撫されて、アンナマリアは背筋に甘い刺激が走るのを抑えられなかった。背中に蜂蜜を塗りたくられているみたいな、男と躯を重ねていたときには与えられていなかった快感に痺れてしまう。
「ふ、うぅぅ……」
目を恍惚に蕩けさせて、アンナマリアは反抗の意志を手放していた。自分の口の中を犯すレリアの舌に何も考えられなくなる。
涎の糸を引きながら、レリアの顔が離れる。舌が抜かれてしまったときに寂しさを覚えたのは、アンナマリアの気のせいではなかった。
唾液まみれになった自分の唇に指を這わせながら、レリアがアンナマリアの虚ろな目を覗き込んだ。
「あははっ、お口が弱点なんですかぁ、ギヨたん? それとも、あたしのキスがそんなによかったんですかぁ?」
「ぎ、ギヨたんって……いうなぁ」
息を荒くしながらアンナマリアはなんとか言葉を返すものの、それ以上のことはできない。神経一本一本に甘い蜜が染みこんでいるようで、躯がいうことをきかなかったのである。
「そんなに甘い声で囁かれたら、誘ってるみたいですよ? 女の子のキスでそこまで感じちゃうなんて、かわいいんですから」
「そ、そんなこと――ひゃっ!」
レリアが秘部に触れて、アンナマリアは無防備な声をあげてしまった。赤子の頭を撫でるような手つきで精液と愛液に濡れた女性器を撫でられて、ぎゅっと拳を作ってしまう。そのまま二本の指がぬるりと小さな性器に滑り込んだ。
「わっ、すごい。こんなに小さいのに二本も一気に入っちゃいましたよ? こんなにヒクヒクと指を締め付けて……かわいいですよ、ギヨたん」
レリアがアンナマリアの首もとに顔を近づけて、熱い吐息を吹きかけながら囁く。
「や、やっ! やめっ、そんなとこにいれないで……あうっ」
「何いってるんですかぁ、あんなにしっかりジョゼフくんのおちんちん銜え込んでたくせに。今更恥ずかしがっちゃ駄目ですよ」
レリアの口がアンナマリアの首もとに吸い付いた。首筋を舌で舐められながら吸い上げられて、びくんっと背中が跳ね上がる。
さらに秘所に入り込んだレリアの指先が何度も出し入れされて、その度に愛液と精液が掻き出される。肉襞を内側から指先が刺激された。それは男の剛直でかき 回されるのとは違った鋭い刺激で、声を抑えることができない。まるでどこで気持ちよくなるのか知っているような指先の動きは、的確にアンナマリアの弱いと ころを責めていた。
「ほらほらぁ、気持ちいいですかぁ?」
「そ、そんなわけ、ないっ!」
「強情ですねぇ。じゃあ、そろそろこっちも触っちゃいましょうか」
今まで一度として触られていなかったアンナマリアの陰核に、レリアの親指が触れた。
ジョゼフとの性行中も刺激を受けていなかった陰核に親指が触れると、快楽の電流にアンナマリアは口を大きく開いて嬌声をあげた。
「ひゃ、あああああぅ!?」
小柄ながらも膨れあがった少女の陰核を、レリアは親指の腹でマッサージするような優しい手つきで刺激する。今まで触れられていなかった陰核は、勃起していたのに触れられていなかったペニスと同じで、アンナマリアは流し込まれる快感に抗うことができずに痩躯を震わせた。
「ほらほら、まだここが残ってますよー?」
くすりと笑って、レリアはアンナマリアのドレスをはだける。片手しか使っていないにも関わらず、あっさりと白い肌を露出させた。
わずかな膨らみしかない薄い胸をレリアは下から押し上げる動きで撫でる。そして、最後に乳輪を人差し指でなぞった。
「や、やあ!」
「そんなこといってー、乳首はこんなに硬くなってますよぉ?」
レリアが首もとから口を離して、アンナマリアの薄い胸で硬くなっている乳首を舌先で突いた。
そうやって焔色の髪の毛を持ったレリアから与えられる刺激は、総て躯に触れたと同時にぴりぴりとした快楽をアンナマリアに与える。男に犯されて強引に弄られたときは気持ちよさを感じなくとも、レリアの繊細な手腕には逃れがたい快感を叩きつけられていた。
「な、なにこれ、どうしてこんなに……っ」
「どうしてこんなに気持ちいいか、ですよねぇ?」
「……っ」
アンナマリアの顔が羞恥心で真っ赤になる。嘘をついて突っぱねることができないほどに、躯は正直にレリアの手によって悶えさせられていた。
レリアが乳首を甘噛みすれば、ずっと弄られ続けているアンナマリアの秘所からは愛液があふれ出す。
「あっ、ああう……はぁっ! ああ……」
虚ろな目で小刻みに痙攣を繰り返す。その有様に、レリアが微笑んだ。
「あれ、イっちゃいましたぁ?」
「はっ、あ、うあ……」
ふわふわとした浮遊感にアンナマリアは戸惑っていた。肉体を得て地上を徘徊し始めてから与えられる初めての経験に、自分がどうしたのかわかっていなかった。
だから、レリアに訊ねられてこれが絶頂なのだと理解した。
「イった……?」
今までは知識としか知らないものだった。それはいつでもアンナマリアと躯を重ねる男が死の間際まで幾度となく繰り返す感覚であったのだ。ジョゼフと繋がったときこそは奇妙な充足感があったものの、これほど衝撃的なものではなかった。
「そうですよぉ、ギヨたんはイっちゃったんです。あたしに舐められてぇ、性器を撫でられてぇ、気持ちよさのあまりに昇天しちゃったんですよ。もしかして、イクのは初めてでした?」
全身を弛緩させたアンナマリアの下半身から指を抜いて、愛液と精液の絡み合った指を口に運ぶ。レリアは自分の指に舌を這わせて、その混合液を嚥下した。
「んふっ、これがジョゼフくんの精液と、ギヨたんの味なんですか。久しぶりの精だから夢中になっちゃいそうですよ。結局、今日もパンしか食べませんでしたから」
「こんなこと、今までなかったのに……これが……」
「そんなに衝撃的なんですかぁ? それとも、不思議ですか? どうしてあたしの行為でこんなに気持ちよくなっちゃうのか」
アンナマリアはのろのろとした動きで後者の言葉に首肯した。疲労がたまってぐったりすることはあっても、今みたいに全身に快楽が染みわたるようなことは経 験がない。男たちに技量が足りなかったといえばそれまでかもしれないが、アンナマリアが心的に充足していたジョゼフとの性行ですら起こりえなかったこと だ。
もしかするとあの充足感はわずかに達していたために起こったものかもしれなかったが、どちらにしろ今の感覚よりはずっと易しい。
だから、レリアに原因があるとしかアンナマリアには思えなかった。
「それはですねぇ、あたしが淫魔だからですよ」
「淫魔?」
「そ う、淫魔です。あたしたちの唾液とか、分泌される体液には精力を増幅させる要素があってですね。えっちする人をより性的に興奮させることができるのです。 なので、感度も上がってしまうわけなんですね。そういうわけで、今も自分が得意な状況にしたんですよぉ? まともに戦ったらギヨたんには敵いませんから」
淫魔――そういった種族がいることくらいならアンナマリアも朧気にではあるものの知っていた。魔女に教わった記憶はないので、恐らく制作者たちによって断頭台として生を受ける前に刻まれたものなのだろう。
「で もこれくらいは人が呼吸をするように、淫魔なら全員が持ってる生態なんですけどね。実際は、あたしのえっちが上手だからなんですよ。ギヨたんも女の子だか ら、どこで感じるかなんてもう手に取るように判っちゃうんだから。あ、淫魔には女の人しかいないんですけどね。とにかく、乱暴に男の人に突かれてるだけ じゃ、こうはならなかったでしょー?」
ちゅっ、とレリアが胸にキスをすると、はふっ、とアンナマリアは甘い吐息を洩らす。この薄い胸を滅茶苦茶に揉まれたことは何度かあったが、脳髄が蕩けだしそうになることはなかった。
「ギヨたんったら、ホントにイジメがいがあるんですからっ! もっと食べたくなっちゃった。人間じゃないから先生も文句をいうことはないでしょうし……あっ」
レリアがあるものを見つけて、目を輝かせた。
「そうだ……じゃあ、ギヨたん、次はこうしましょうね」
「え……?」
ようやく頭の回転が戻ってきたアンナマリアを起こすと、レリアはそれの方へと近づいていった。
ふたりはジョゼフの股の間に躯を滑り込ませる。そこには勃起しているペニスがむき出しになっていた。
「ジョゼフくんったら、ギヨたんの喘ぎ声で目を覚ましちゃってたんですよ」
「あ、いや、これはその、盗み聞きをしていたつもりじゃ!」
意識があったといっても夢に微睡んでいるような状態だったジョゼフは、レリアとアンナマリアが動いたことでようやく完全に覚醒した。どうしてこうなっているのか理解はできていないようだったが、現状の認識はできている。
ジョゼフの弁明をレリアは聞く耳すら持たなかった。その目は爛々と輝いて、大きくなっている肉棒に注がれていた。
「ふふっ、おしおきしてないとあげませんよね?」
レリアが竿を握ると、押し殺した呻き声がする。
「さあ、ギヨたん。……一緒に、舐めちゃいましょ?」
アンナマリアの目も、大きくなった性器に釘付けだった。さっき自分が銜えこんでいた陰茎を前にして、あの愉しげな感情が再び胸に戻ってくる。
レリアが舌を伸ばすと、釣られてアンナマリアも舌を伸ばす。ふたりの少女の真っ赤な舌がジョゼフのペニスを舐めあげた。
「うっ!?」
ふたりの口が茎に吸い付いて、肉棒が激しく脈打つ。既に何度もアンナマリアに射精していたにも関わらず亀頭を真っ赤に膨らませたペニスに、レリアが歓声を上げた。
「あはっ、ジョゼフのおちんちんってこうなってたんですねえ。こんなに震えちゃって……」
レリアが眼を細めて、感極まったとでもいうように云った。魔女から止められていたが、ジョゼフのことはこの国にやってきたときからずっと目をつけていたの である。今まで狙った相手はすぐに食べていたレリアとしては、お預けされ続けてきた末に食べることを許されたごちそうであった。
「はむっ」
レリアが亀頭を呑み込む。
ぷちゅっ、と唾液が亀頭に絡んでいやらしい音を立てた。赤く膨れあがった先端に何度も情熱的なキスをする。柔らかく膨れた唇が亀頭を這い回って、舌先が尿道をなぞっていく。その甘美な快感にペニスの射精へのカウントダウンが始まった。
「んー、こっちにキスされる感覚はどうですかぁ? いっぱい愛でてあげちゃいますよー……わっ」
押し寄せる快楽に耐えているジョゼフの顔を眺めながら亀頭にキスしていたレリアの唇に、アンナマリアの唇が触れた。
「ん……」
アンナマリアがレリアの目を一瞥して、彼女の唇を巻き込んで亀頭を愛撫する。ふたつの舌に責められて、切なげな声があがった。
知らずのうちに、アンナマリアは対抗意識に駆られていた。それを見て取ったレリアは面白いと鼻を鳴らす。
「んふっ、そっちがその気ならぁ、こうですよ」
ずぷんっ、とアンナマリアの秘所になにかが突き込まれた。
「ひあっ!」
喉の奥からしゃっくりみたいに声をあげたアンナマリアは、自分の膣に入り込んでいるものを見る。そこにあったのはレリアの手ではなく、彼女の尾骨の辺りからスカートを押し上げつつ現れた黒い尻尾であった。
先端がハート型になった――見ようによっては、男性器に見えなくもない尻尾が、アンナマリアの愛液に濡れながら奥へ奥へと突き進む。男性器と違って膣内で蛇みたいにのたうち回る尻尾に、アンナマリアは快感で足をぴんと伸ばした。
「あっ、ひゃあっ、入って、る!」
「おちんちんとは違いますけどぉ、これなら色んな所も責めてあげられますよ?」
アンナマリアの耳に息を吹きかけて、レリアはさらに尻尾を暴れさせる。男のモノを銜え込み続けていたとはいっても、快感を与えられることに慣れていなかった少女の躯の弱点を探りあてるなどレリアには造作もないことだった。
ずぽっ、ずぽっ、と尻尾のピストン運動にアンナマリアは口淫をしていたことも忘れ、涎を垂らしながら喘ぐ。
「や、やあ……っ、これ以上、されたら……お、おかしくっ」
「はいはーい、お口がお留守ですよぉ」
レリアがアンナマリアの頭を掴んで、ぐっとジョゼフの一物へと近づける。
「あ……」
焦点を失った目でアンナマリアは目の前でそそり立つペニスを銜えた。
尻尾に突かれ、抑えきれぬ喘ぎ声をあげながらも一心不乱に男性器に食らい付くゴシックドレスの少女にレリアは満足そうに頷いて、だらしない顔になっているジョゼフを見上げた。
「それじゃあ、ジョゼフくぅん……たっぷり気持ちよくなってくださいね」
アンナマリアと唇を重ねるように、レリアもまた逞しく勃起した陰茎に口づけをした。
天性の肉体に任せて男を絶頂させていたアンナマリアと違い、レリアの口は染みついた技巧が伴っている。男性の一番敏感なところを熱っぽく幾度とキスする手際に、男は全身を一斉に愛撫されているような錯覚を起こすのだ。
小さな口で涎を垂らしながら一生懸命にペニスを出し入れするアンナマリアに、恵まれた肉体だけでなく経験によって培われた性技を披露するレリア。
奥歯を噛んで脳内で神経が切れてしまっているのではないかと思うくらい我慢していたジョゼフにも限界は目前に迫っていた。
アンナマリアも、また天に向かって上り詰める。躯を突く、乱暴に見えても実は繊細に弱いところを突き上げてくる尻尾に抗うことはできない。きっとジョゼフがイクと同時に彼女も達してしまうだろう。
自身の幼い躯を弄ばれて快楽に苛まれながらも美味しそうにペニスを舐めるアンナマリアは、正気を手放しそうになりながらもわずかに残った脳の片隅で考える。
このまま、イっていいものか――。
でも、我慢することはできない。下半身をがくがくと痙攣させて、アンナマリアの躯はレリアが与えてくれる刺激に陶酔していた。
ただ。このままイかされるのは、嫌だ。
きっと、このままイってしまえば、あまりの気持ちよさに意識を失ってしまうことをアンナマリアは自覚していた。それは、くやしい。
復讐のためにこんなことをしてきて、街を徘徊してきたのに、こんなところで出会ってしまった淫魔を証する少女にあっさりと折られてしまう。そんなの、くやしいに決まっている。
なら、せめて一矢報いてやる――。
アンナマリアはレリアのスカートの中に手を伸ばした。
下着に触れると、そこは興奮のためか愛液でぐっしょりと濡れていた。その合間から、アンナマリアはレリアの秘所に指を差し込んだ。
レリアの膣肉は指を強く締め付け、幾重にも波打つ襞に擦られる。くちゅくちゅと音を鳴らしながら掴まれた指先は、それだけで背筋を走る快感を覚えさせられた。
くふっ、と唇とペニスの合間から息を洩らして、レリアが微笑む。
「ギヨたんったらぁ、その気になっちゃって……うふふ、気持ちいいですよ?」
男のモノなら何度も握ったことはあったが、アンナマリアも他人の女性器を弄るのは初めてだった。そのせいで手つきはたどたどしく、手探りにレリアの下半身をまさぐっている。
「ほら、頑張ってくださいよぉ」
「んぐっ!?」
嗜虐的に云って、レリアは尻尾でアンナマリアの子宮口をぐっと押した。内臓を押し上げられてえづくが、それ以上の快感が躯を浸食する。
「あ、ひゃう」
肺が引きつって、変な声をあげてしまった。涙で視界が歪むのは、悲しいからではなく心地よすぎたからに他ならない。
鼻先のペニスから漂う精と唾液の香りに、激しい挿入でひくひくと痙攣する陰部。
止まりそうになる指先に意識を集中させて、アンナマリアは指の根本までレリアの秘部に挿入した。アンナマリアと同じか、それ以上に小さいレリアの性器は淫らにうごめき、二本も三本も指を銜え込む。
「そうですよぉ、その調子です。ふふっ、少し気持ちよくなってきまし……はうっ!?」
アンナマリアの指の動きに、余裕綽々だったレリアは艶っぽい声をあげた。自分で自分の反応に驚いて、レリアは股をむずむずと動かす。そうすると膣内にある指の感触がより鮮明に感じられた。間違いなく、そこにあるのはアンナマリアの手業に慣れていない細い指先。
「な、なんで? ……ひゃっ! えっ、うそ、なんであたしが感じてるんですかっ」
その反応は奇しくもレリアに責められたときのアンナマリアのそれと似ていた。
アンナマリアは汗ばんだ顔で、眠たそうにした目をレリアに向ける。それは快楽に酔いしれている目であったが、胡乱ではなく――どこまでも続いていきそうな深遠なる闇が垣間見えた。
レリアの中に焦燥感がわき上がる。続いて、対抗心。人になって数日か数週間した経たぬ者に性技で負けるわけにはいかない。ムキになって、尻尾のピストンを跳ね上げた。
「うぐっ」
アンナマリアの腰が跳ね上がる。愛液が比喩ではなしに滝のようにこぼれ落ちた。口からは喘ぎを洩らす。それでも指だけは止めなかった。
ぎこちなかった指の動きは今やよどみないものとなり、女性の――レリアが弱いところを探し当てようと膣内をこねくりまわし、責める。そのたびに少女の躯が反応を返した。
性技に長けたレリアは、もちろん人から受ける快感への耐性も強かった。性技自慢の男たちとまぐわろうとも、相手を搾り殺すことこそすれ、感じることはそう そうない。二度、三度、人間がレリアの躯に経験を積めば話は違うかもしれなかったが、それでも気持ちいいと感じさせるだけに留まるのみだろう。そもそも、 一度目で死んでしまうのだから二度目が来ることすらないのである。
よって、レリアは性行を楽しみこそしても、躯をビクビクと震わせるほどに快感を感じたのは魔女と寝ているときを除いて数百年ぶりだった。
「そ、そんな、どうしてこんなに早くっ」
「だって、教えてくれたでしょう? さっき、わたしの躯で……」
「まっ、まさか! あたしに責められただけで、覚えちゃったんですかぁ!?」
驚くべき事実でも、そうとしか説明のしようがなかった。アンナマリアはレリアの技に身をもって溺れたことで、一気にやり方を吸収してしまったのである。
「で、でも……先にあたしがイかせちゃえばっ! このままならもうジョゼフくんとギヨたんだって限界のはずっ」
その通りだった。アンナマリアの覚えた技は、所詮はレリアの付け焼き刃。いくら驚異的学習能力だとしても、この逆境を跳ね返すだけの力はない。
――そう、この力、だけなら。
はあ、はあっ、と肩で息をして快感に意識を手放しそうになりながら、アンナマリアはレリアの耳元で呟く。
「ねえ……この、ジョゼフって人のこと、好きなの!?」
「はいぃ!? なっ、なにを云ってるんですか! あたしは淫魔ですよ、サキュバスですよ? 人なんて食料に決まってるじゃないですか! ステーキに欲情する人間がいますか? いないでしょう!」
「慌ててる……かわいい」
自分を苦しめたレリアが顔を真っ赤にして否定したものだから、アンナマリアは素直にそう思ってしまった。その言葉が益々レリアに羞恥心を抱かせ、心の隙にアンナマリアの指が入り込み――こじ開ける。
「ひゃっ、あっ、しまっ……だ、駄目です、もう……っ」
うっとりとした表情で、レリアは興奮のままに尻尾を上下させながら、涎まみれの口で陰茎にむしゃぶりつく。
「ひっ、いやぁっ!」
アンナマリアもレリアも限界だった。
ふたりは目の前の肉棒に激しく唇を這わせながら、指と尻尾の勢いを増して――。
「ふぁ、ああああああ――!」
同時に絶頂を迎えた。
びくんっ、と躯を仰け反らせて、口は亀頭に吸い付く。それで肉棒も頂点に達した。
激しく脈打つペニスから飛び出す精の塊。アンナマリアとレリアの顔を熱いスペルマが真っ白に彩った。
むせかえるような精の香り。再度の射精にまたもや意識を手放したジョゼフの下半身に顔を寄せて、口の中に入り込む精子の味に酔いながらふたりも意識を手放した。
路地裏には半裸の三人が倒れていた。それをすぐ近くでひとりの女が見下ろしている。
魔女イザベラは呆れて嘆息した。そこにいたのは、全員彼女の顔見知りであったからだ。云うまでもなく、ジョゼフ、アンナマリア、レリアの三人である。
「まったく、運ぶ身にもなってくれたまえよ。まあ、こうなることは予想できてたんだけど」
ローブをまとい、扇情的に胸元をはだけているイザベラは、呆れはしたものの驚くことはない。今回の出来事はイザベラにとっては想定内のことであったからだ。
「ジョゼフが生き残っていることくらいかな、意外なことは。てっきりギヨたんかレリアに搾り殺されると思ってたけど、その前にダブルノックダウンとはね」
運の良い子だな、と肩を竦める。そこに罪悪感は欠片もない。それを追求すれば、結局生き残っているのだから感じる意味もないとイザベラは断じることだろう。かといって、死んでいても悪びれるかと云えば、そうは思えない様子が彼女にはあった。
例え自分が助けた命でも、死ぬときがくれば死ぬ。それをわざわざ能動的に払ってやろうと行動しない程度に、魔女イザベラはやはり魔女と云える思考の持ち主だった。
けれど、生き残ったのなら、せめて助手共々面倒を見てやらなくては――とイザベラは億劫ながらも腕を突き出し、動作をやめる。
「おや……」
遠くから足音がしていた。それはひとりによるものではない。人が群れをなし、夜闇の中で闊歩していた。
「おい、こっちから声が聞こえてきたよな」
「ああ、もしかすると最近噂の殺人犯かもしれないぞ」
魔女はトレードマークの帽子を手で抑えながら、彼らが何者であるか検討をつけていた。
夜の街を巡回している男たちだ。アンナマリアの所業によって行われた殺人の数々で、ついに重い腰をあげて警邏を強化したのであろう。
どうやら、三人の情事を嗅ぎつけてきたらしい。
「声が大きすぎるよ、君たち……」
三人には届かないと判っていても、イザベラは面倒が増えたことに対する不満を口にするのを抑えられなかった。
そうしているうちに、路地裏を覗く幾つもの影がイザベラの背後に現れた。
「おい、誰かいるぞ」
男のひとりがランプを路地裏に向けた。背中に光の熱を感じて、イザベラはローブを揺らして振り返る。
そこにいたのは四人の男たちだ。腰には鋳型にはめられて作られた安物の剣を下げ、頭部を守るメットとなめし革の鎧を身に着けている。
もし、彼らの想定していた殺人犯が単独犯なら、なるほど、その程度の装備でもなんとかなったかもしれない。相手が人間であるなら、四方を囲めばそれで事が済む。
ただ、それも相手が常人であった場合を想定していたらの話である。イザベラからしてみれば、酷くお粗末な身なりだった。イザベラでなくとも、相応の使い手 ――今まで悟られずに街中で人殺しをおこない続けることができるほどの者となれば、問題なく皆殺しにできてしまえそうである。
「なんだ、娼婦か?」
イザベラとその背後に半裸で倒れる三人を見て、男たちのひとりが疑問の声をあげる。
下半身をむき出しにしたジョゼフと、男性器に纏わり付く少女がふたり。誰が見ても、路上で激しい一夜を過ごしている者たちにしか見えなかった。
さらに、イザベラの格好はおよそ街中を歩く淑女に相応しい身なりではない。ふわふわとした布で躯の線こそ隠れているものの、たわわに実る豊満な胸元は外気 に晒されていた。くわえて、美貌である。月光を受けて輝く銀髪も、その氷像然としていながら飄々と揺れる柳のような相貌も、総ての要素が黄金比率を保って いた。
高級娼婦。否、それ以上。男たちの全財産を叩いても抱けないほどの上玉――。
警邏隊の関心はイザベラと、倒れる少女の裸体にだけ注がれていた。彼女たちこそが警戒しなければいけない集団であるとはまったく考えていなかった。。
「へえ、良い女じゃないか……。そっちのガキ共も、相当手慣れてるみたいだな。男共々気絶してやがる。しかしなあ、俺たちの手を煩わせたんだ……勿論、責任は躯でとってくれるんだろうな?」
警邏隊のひとりがイザベラの腰に腕を回す。色事を前にしただらしない男の顔が息もかかるほどイザベラの顔に近づく。
どうやらこの男がリーダーのようで、他の三人は遠巻きにイザベラたちを見ているだけだった。それでも顔はだらしなく緩んでいる。情事の現場を目撃して興奮したのか、彼らも浮き足だっていた。
イザベラは口元に笑みを浮かべて、自分の腰を抱く男を流し目で見た。それだけで漂う色香が男の胸をくすぐる。
「どうやら、随分たまっているようだね……。ふふ、激務で女を抱く暇もないのかい?」
「ああ、そうさ。それに、誰のために俺たちが働いてやってると思ってる? 国民のためさ……なら、お前たちも俺たちに奉仕する義務がある。そうだろう?」
男は布越しに膨らんだペニスをイザベラのふとももに押しつけながら、彼女の乳房を乱暴に掴んだ。
小さく嬌声をあげてると、イザベラは指先で男の顎をなぞる。
「強引だね。でも、そういう男は嫌いじゃない。私も久方ぶりでね……男が欲しかったところなんだ」
「へえ、話がわかるじゃねえか……。後ろの連中の相手はそっちのガキどもがやってくれるんだろうな? 俺ひとりでってのも気が引けるんでねえ」
「ああ、それは駄目だね。彼女たちは疲れているし……そもそも、キミひとりじゃ私が満足できない」
「なに?」
片眉をあげて問い返す男に、イザベラは妖艶に微笑んで右手を掲げた。
「私がキミたち全員の相手をしてあげよう」
パチン――、と指を弾く音。
それを合図に、世界は変貌した。
*
警邏をしていた四人の中で一番肩身の狭い思いをしていたのが誰かと云えば、もっとも年若い少年だった。
年齢は一六歳で、人と喧嘩をしたことこそあれども殺し合い染みたやりとりはしたことはないという、そこそこに恵まれた少年である。
革命が起きたことで、そんな少年にも剣を持たなければいけないときがきた。王を処刑したのだし、戦時なのだから今まで戦いをしたことのない者でも武器を手にしなければいけないのは考えてみれば当然のことである。
もっとも、少年が警邏に従事しているのは、なにも革命やそれに伴う使命感などではなかった。もし、徴兵を断ったりしたら逆賊として殺されるに決まっている。それが革命によって生まれ変わった国家の選択だった。
これじゃあ、僕たちの戦いに意味などないじゃないか――。
少年は革命を望まなかったが、それを時代は許さなかった。群衆の総意は、いつだって少年みたいな人間を小石のように流れへ巻き込んだ。
少数派を呑み込んで、一丸となって戦いに挑む。それ自体に間違いはないのだろう。統一性がなければ、争いに足を取られてしまう。
呑み込まれた少数派はいつだって不平を洩らすが、所詮、それは大多数から見れば弱者の戯言にすぎない。少数派である彼らの主張が正しくとも、それを他人と 共有できなければ、そこまでの主張であったに過ぎない。少数派が大多数の人間を罵るのは、結局のところそれしかできないから責任と無力感を押しつけている だけなのだ。
そう、革命が、民衆の総意が嫌なら、不平を云うのではなく、立ち上がって声も高らかに宣言しなければならない。リスクを恐れずに総意へ立ち向かわなければいけない。それができないのなら、そもそも見苦しく自身の思想なぞまき散らすべきではないのだ。
だから少年は口を閉じた。
自分にそんな力がないことも、見苦しく不平を垂れることすらもできない小心者であることをよくわかっていたからだ。
「――そう、キミは疲れているんだね」
「え?」
優しい声が少年に語りかけてきて、声をあげる。
いつの間にか、少年はベッドの上にいた。淡いピンク色のシーツが敷かれた、甘い香りが漂うふかふかのベッドだ。
少年の頬に柔らかい手が触れる。ベッドにはもうひとり座っていた。
身を乗り出して手を伸ばしていたのは、少年と同い年くらいの少女である。長い銀髪に、見つめられると背筋が撫でられたみたいな心地になる鋭利な眼が印象的だった。
魅力的な瞳が、少年をいたわるように細められている。頬に触れている手の感触に心奪われて、少年は革命によって荒んでいた精神の海が凪いでいくのを感じた。
「君は誰――そういえば、僕はさっきまで警邏を――」
少年の唇を少女の人差し指が塞いだ。
「何も考えなくて良いよ。私に身も心も任せるといい。大丈夫、優しくエスコートしてあげるよ……天国まで」
少女が少年の肩を押して、唇を奪いながらベッドに寝かせた。
抵抗しようという気持ちはついぞ浮かんでこなくて、少年はこの麗しい少女になにもかも任せることにした。もう、考えるのは疲れていた。この甘い芳香で、悩みがどうでもよくなった。
そういえば、ここはどこなのだろう。ベッドしか見あたらない、よくわからない場所。
――まあ、どうでもいいか。
そう切り捨てて、少年は口の中に入ってくる少女の舌に意識を集中させた。
長い長い全身を包み込むようなキスが終わる。真上で微笑む少女に、少年はひとつだけ訊ねてみた。
「君の、名前は?」
少女は囁く。
「――イザベラ」
リーダー格の男は困惑していた。
自分は先程まで、汚物まみれで臭気漂う路地裏で女の腰を抱いていたはずである。
「なのに、どうして」
悪夢の中に迷い込んだ心地でつぶやいた。
そこはピンク色のシーツが引かれたベッドの上だった。こんなところにやってきた記憶が、男にはまったくない。飲酒もしていなかったし、前後不覚になる理由はなかった。
なによりも、ここにはベッドしかないのが問題だった。周囲を見渡しても、果てが見えない。大海原に放り出されても、こんな不安は抱かないだろう。なにせ、海には海水と空があるのに、ここは文字通りベッド以外の存在が皆無なのである。
「へえ、変化なしか。この私の躯が理想的だったとは、いやはや、女としては誇りに思うね。キミに恋愛感情が抱けていたのなら、きっと心底愛してあげられたはずだよ」
いつの間にか、魔女イザベラがベッドに腰掛けていた。大きな帽子も、ローブも、そのままである。この空間にあって、その姿は異様だった。
「お、おい、いったいここはなんだ。お前がなにかしたのか!」
「その通り。総てが私の思いのままになる、ここが一番好都合なのさ。なにより、ベッドの上の方がムードがあるだろう? それとも、陵辱願望をお持ちだったかな」
イザベラがベッドに引きずり倒された。破れたローブから、片手では覆いきれない乳房が漏れ出る。
「お前、俺をおちょくってんのか!」
「あれ、そのつもりだったんだけど……判らなかったかな?」
男の頭の中が怒りで沸騰した。もう、ここがどこだかなんて考えるのはやめた。今は、この女の躯に後悔の味を刻みつけることに執心した。
ズボンを降ろし、男は勃起した一物をむき出しにする。例えいかに腹の立つ女であったとしても、目の前にいるイザベラは男にとって理想的な肉体をもっていた。
彼女の銀髪を乱暴に掴むと、男はペニスを口の中にねじ込む。魅惑的な赤い唇と白い歯を押しのけ、一気に喉の奥を亀頭で突き上げた。
そのまま髪を引いて、口の中で剛直をピストンさせる。人肌の生ぬるい温度でしめった口腔を犯せば、背徳感と快感が合わさってぞくぞくっと全身を駆け巡った。
夢中になってイザベラの顔を腰に叩きつけ、口蓋と舌を汚れたペニスで蹂躙する。
男性器を慰める気持ちよさに涎を垂らしながら息を乱していることに、当の本人である男は気付いていなかった。
イザベラが髪の毛を掴んでいる男の手首に触れると、軽い衝撃がそこに走る。痛みはなくとも、腱を刺激されたせいで男の手は勝手に開き、銀髪を手放してしまった。
ぬるりと涎まみれの男性器を口から抜いて、イザベラは男相手に上目遣いとなる。
「口よりも、もっと気持ち良いところがあるよ」
そう云って、自身の胸に剛直を挟み込んだ。
異論を唱えるより先に自分自身が胸に包まれたことで、男は情けなく声を洩らしてしまった。
仰向けの体勢で豊満な、それでいてマシュマロみたいに柔らかい乳房で男のペニスを捉えれば、イザベラは胸を上下させた。
ぬちゅっ、ぬちゅっ、と音がして、胸の中で肉棒が暴れる。胸があがれば亀頭まですっぽりと胸に押し包まれる。胸が下がれば、亀頭が胸肉を掻き分けながら顔を出した。
「本物の亀みたいに頭を出したり隠したり……随分とかわいらしいペニスじゃないか」
「はが、あがががが……」
男は腰砕けになりそうなのを必死に堪えていて、イザベラの言葉は耳に入ってこなかった。
彼女の唾液が潤滑液となり、スムーズに胸の谷間を往復する。
鉄のように硬くなったペニスを押しつつむ豊かで柔らかな感触は、まさに天にも昇る心地よさ。
ふつう、女性の乳房は子供にミルクを与える供給器官であるはずなのに、イザベラのそれは男の肉棒からミルクを搾りだすための搾精器官だった。
「熱い、焼けるように熱いな……そんなによがって、よほど私の胸が気持ちいいらしいね」
淫蕩に微笑み、イザベラは自分の乳房を揉みしだきながらペニスを圧迫する。自分で自分の胸を慰めながら男の肉棒を擦り挙げる仕草は目眩がするほどに妖しい。
「我慢する必要はない。たっぷりと玉袋にたまった精子を吐きだしたまえ。この胸の中でね……」
云われるまでもなく、男の脳裏に我慢の二文字はなくなっていた。それ以前に、優しくも無慈悲にペニスを搾る乳房に抗えるとは思えなかった。
亀頭に鮮烈な快感が走る。魔女が目一杯舌を伸ばして、その先端で亀頭を舐めていた。胸の谷間から顔を出したペニスをちろちろと舐めながら、ぎゅっと左右から胸で茎を圧迫する。
尿道にイザベラの舌が入り込んだ瞬間、男のペニスが震えた。
「あ、あ、出る……うわおおおおおおお!」
ぶしゅっ、と白濁の噴水が飛び出した。
イザベラの美麗な顔へ大量に男の子種がまき散らされる。
目を閉じて精子を受け止める。まだ射精は留まることを知らず、乳房の中でのたうち回り黄ばんだ精液を吐きだしていた。
イザベラの顎から細い喉までを真っ白く濡らし、あまりの快感に男が腰を引くと胸の中でも爆発を続けた。ぶわっと乳房から溢れだした精液が谷間に白濁の池を作る。
陰嚢の中にあったものを一度に総て吐きだしたのではないかと思うほどの量がイザベラを汚し、むせかえるほどの青臭さが溢れた。
腰が砕けたのか、男はイザベラに覆い被さる形でベッドに倒れ込む。何十分も全力疾走をしたのかと思うほどに息を荒くする男は、ペニスに再度くわえられる刺激に情けなく呻いた。
イザベラが精液に濡れた乳房で、射精したばかりのペニスをしごいていたのだ。
「ほらほら、どうしたんだい? 男なんだから、まさか一回出しただけで満足なんてことあるわけないよね? 遠慮しなくていいっていったじゃないか……出したまえよ」
男にはそれが悪魔の囁きにしか思えなかった。性欲は旺盛だと自負していた男も、たった一度胸に搾られただけで総ての精子を吐きだしていた。
嗜虐的に笑いながら、イザベラは精液を利用してぬるぬると胸でペニスを責め立てる。いやらしく精子で気泡をたてながら、柔らかい胸が絡みついた。
「はぐっ、ごっぐげっ……ああああああ……っ」
ベッドのシーツに顔を押しつけながら内臓を吐き出しかねない形相で男が悶える。射精した直後のペニスを責める温かくも柔らかい胸は冷酷なまでの快楽を流し込んでいた。
男の苦しみようとは裏腹に限界まで勃起したペニスは白い飛沫を飛ばしながら乳房を堪能している。イザベラが首を傾けて、胸から飛び出た亀頭に吸い付いた。 ずずっ、と精液をすすりながら亀頭にキスをする。精液に口元を濡らしながら亀頭を這い回る唇。イザベラの唇に刻まれている皺のひとつひとつが感じ取れるほ ど、亀頭の感覚ははりつめていた。
「やめ、やめてくれ、出る、また出るっもう出ないのにっやめろ! やめてくれ!」
「嘘はよくないな……キミはまだまだ出せるよ。だって、ほぅら。今だってこんなに膨らんでいる」
聞く耳もたずにイザベラは乳房を操る速度を速め――
「だあああああああああああああああああ――――!?」
男の絶叫と共に、乳房から頭を突き出したペニスが爆発した。
一回目と変わらぬ、むしろそれ以上の勢いで真っ白な液体が溢れる。イザベラの美しい銀髪にもべっとりとかかり、さらに顔と胸に子種を振りかけた。
「おやおや、これでは胸が妊娠してしまうじゃないか」
くっくっ、と喉を鳴らして、胸を白くデコレーションしたペニスに向かって云った。
威勢のよかった男は既に無く、あとには虚ろな目でベッドに横たわる哀れな犠牲者がいるだけだ。
躯を起こしたイザベラは、今にも息絶えそうな男に――そのペニスに手を伸ばした。精液まみれの萎えかけたペニスを掴むと、男の躯が跳ね上がって嬌声をあげた。
「あがぁ……っ」
「まさか、本当にこれで終わりってわけじゃないだろうね。私はまだ胸に挟んだだけで、膣に挿入すらしていないのだよ? それはあまりにも自分本位な性行じゃないか。さあ、本番と行こう」
イザベラが萎えかけたペニスをしごくと、掌の中でむくむくと首をもたげ始める。精液でぬるぬると指を滑らせる手つきに、男は意志と反して挿入可能の状態になるしかなかった。
「な、なんで……なんで、まだ立つんだ……」
けれど、数週間、数ヶ月分の精液を一度に吐きだしたにも関わらず勃起するというのはさすがに異常だった。自分の躯が自分のものではないようで、男は快感ではなく恐怖で震え出す。
「ああ、それはね。ちょっとキミに細工をしただけだよ。私は淫魔と違って人間だからね、精力を刺激する体液を分泌なんてできなくてね。自前のテクニックと魔法でどうにかするしかないのさ」
「ま、魔法? まさか、魔女……!」
男は悲鳴をあげるようにその名を口にした。
魔女について、今更説明するまでもない。悪魔と契約したことにより力を手にした背信者、その総称が魔女である。
魔法使いを恐れる人間は少ない。むしろその力に憧憬すら抱く。だが、魔女は別なのだ。悪魔が無償で契約することは、人が呼吸をしないで生活するのと同じく らいにあり得ない。彼らは必ず、人に交換条件を持って契約を結ぶのだ。より正しく云うなら、人は悪魔に従属することで魔女となる。そもそもの力が違うのだ から対等な契約が結べるわけもない。
そして、悪魔の契約とは常に人間を追い詰めるものである。力を与える代わりに生け贄を寄越せ、なんてものがポピュラーなものだろう。
だからこその魔女狩り。異端なるモノ共の放逐。
人はみな、魔女を恐れていた。彼らは自分たちと同じ人の姿をしているから、隣にいる人が魔女かもしれない。そんな恐怖が常につきまとっていたのだ。
「そ、そんな……魔女狩りがあったはずなのに……」
「魔女狩りか。あれは不味かったね。キミたちが魔女として狩っていたのは、大抵がただの人か淫魔だったんだから。あんなことをおこなわなければ、淫魔が国を支配しようだなんて考えなかったのに」
「い、淫魔……? さ、さっきからそれはなんだ……」
「うーん」
唸って、イザベラが男のペニスを握る手に力を込める。元気さを取り戻したそれにイザベラは舌を寄せた。亀頭を舐めあげ、舌にこびり付いた精液を呑み込む。
「今の私みたいな生き物、かな?」
淫蕩に微笑むイザベラに、男は自分の末路を悟った。
なんて、悪夢だ――。
「悪夢じゃない。淫夢さ」
男の思考に声で応え、イザベラは相手に騎乗すると肉棒を膣に埋めた。
魔女イザベラの扱う魔法の体系は多岐にわたる。それもこれも、無数の悪魔と契約を結ぶという荒技をおこなったがために会得できたものだ。
魔法と一言にいってしまうのは、世界中の食物を総て料理として括ってしまう程度には乱暴な区分であったが、魔女イザベラに対してだけは話が別である。魔法というおおざっぱな区別をしなければいけないほどに彼女の能力は膨大だった。
今、おこなわれているこれも、イザベラの特異な能力故であった。
「なんだ、キミは私みたいな幼子が好きなのかい? それは変態性癖と云わざるを得ないな」
魔女イザベラの声――しかし、幼い。
舌っ足らずな、イザベラに似た声を発したのは一二、一三歳くらいの幼子である。その女の子はピンク色のシーツがひかれたベッドの上に仁王立ちして、ベッドに寝転がる男を見下していた。
警邏隊の四人組、そのうちのひとりである。
男の股間は布越しでも膨れあがっているのが目に見えて判るほどで、幼子は不愉快そうに鼻を鳴らした。
「変態と云われて喜ぶ人種がいるのは知っているが、いつ見ても理解に苦しむな、ペドフィリアめ。さすがにそんなもの、触ってやりたくもないよ」
太腿まで届く靴下を穿いた足で、幼子が男の股間を勢いよく踏みつけた。例え幼子といえども蹴られれば痛みがあったはずだが、男が洩らした声は苦悶ではなく嬌声である。
「あ、ああ……!」
「喘ぐな、耳の毒だ。このまま踏み潰してあげようか?」
男性器を踏む足に力がこもる。ぐりぐり、と足を捻った。
土踏まずの下で余計に膨れあがっていくペニスに、銀髪の幼子は未成熟ながらも美しくなることを予想させる顔をしかめた。
「小さくなるどころか、大きくなるとはね……。こうも欲望に忠実だと逆に関心するよ。よくもそこまで興奮できるものだよ」
変声期も迎えていない幼い喉から発せられる言葉は知的にして老獪で、その差違が彼女を異質たらしめていた。
その追求に、男は上擦った声をあげながら首を振った。
「こっ、興奮なんてしてないぞっ」
慌てて取り繕われると、幼子は足の力を強めて強制的に黙らせる。
「嘘をつくならもっとマシな嘘をつきたまえよ。幼女に踏まれてペニスを勃起させながら云っても説得力なんて皆無だ。ああ、幼女趣味ならおちんちんと云った方が興奮するかな。……するようだね」
足の裏に伝わる感触がさらに硬くなり、幼子は吐き捨てる。男は羞恥で顔を真っ赤にしていた。
「こうしていても仕方のないことだし……まずは一度楽にしてあげよう。……このままね」
幼子が足の指先を器用に使って男のズボンから性器を露出させた。
ぼろんっ、と半分ほどまで皮を被ったペニスがこぼれ出てくる。足先で裏筋を撫でながら皮を引っ張ると、汚臭漂う亀頭が姿を現した。
「うぐ……っ」
「まだ皮を剥かれただけだろうに、どうしてそんなに息を荒くしているのだか。ふふ……童女の足がそんなに好きかね」
すりすりと靴下越しに足がペニスを撫でる。幼子の汗で湿った靴下が亀頭の根本から裏筋を何度も往復して、男は情けなく身を快感でよじった。
尿道から湧き出す我慢汁が幼子の靴下に染みこむ。そして精子混じりの分泌液で濡れた足はペニス全体に我慢汁を塗布した。
濡れて動きやすくなったことで、足の動きが激しくなる。技術もなにもない、精を搾るためではなく汚物を踏みにじる乱雑な足責め。だからこそ男は被虐的な心を刺激された。
額に汗しながらペニスを踏みつける幼子は、真っ白い頬を紅潮させて亀頭を踵でグリグリと捩る。
「はあっ、……ははっ! 踏まれてるだけでおちんちんビクビクさせて、今にもイってしまいそうじゃないか。ほら、出してしまいなよ。無様に悶えて精液を足にかけてしまえばいい」
ぐぎゅっ、と足がはち切れそうになっていた肉棒全体を踏みつけた。
押し潰されそうな強い刺激が我慢という名の理性を蹴破った。
「う、うわあああああ――っ!」
どくっ! どくっ! どくんっ!
ペニスが弾けた。幼い少女の足によって射精に導かれた肉棒は、脈打って濁流のような白濁を噴出する。
真っ白い精液が幼子の足にべったりと降りかかった。純白の樹液が肉感に乏しい太腿からふくらはぎまで垂れて、黒い靴下も精子でてらてらと光る。生殖活動のために精製される子種は幼子の未熟な足を精の色で汚したのだ。
足の裏から伝わってくる大きく熱い肉棒の脈動に幼子は酷薄に笑む。
「あっははっ、本当に足で出すなんて……それも、こんな小さな私に踏まれて精を漏らしてしまうだなんて。ねえ、恥ずかしくないの?」
幼子の言葉が男の胸に突き刺さり、顔は羞恥で真っ赤になる。何も云い返せないほどの恥ずかしさと屈辱に頭が沸騰していた。けれど、その感情さえもゾクゾク とした快感となって背筋を走り抜ける。今も幼子の足で踏みつけられている自分のモノを見下ろして、男は押しとどめ難い疼きを覚えていた。
「あれ、また硬くなってきたね。まさか、踏まれているペニスを見て興奮したのかい? 度し難い性癖だねっ」
一際強く幼子の足が肉棒を踏む。イったばかりなところへ叩きつけられる刺激。
「はうっ」
「小さい女の子に虐められるのが好きなんて……なら、これがお望みなんだろう?」
幼子が自分の下半身を覆っていた布をはぎ取ると、そこには毛すら生えていない秘所があった。
男の視線を釘付けにして、ゆっくりと腰をペニスへと降ろす。亀頭が小さな亀裂を押し広げ――。
ずんっ、と女性器が裂けんばかりにねじ込まれるペニス。だが、悲鳴をあげたのは男の方だった。無数の襞で陰茎をなで回す狭い狭い女陰に、男は一瞬で限界を迎えた。
幼子の躯を突き抜ける勢いで放出される精液。
男に跨った幼子は、自分の下腹部を撫でる。掌には、止まることのない射精に狂ったペニスの感触が伝わってきた。
「はは、出すといい……死ぬまで、私の性器に抱かれて……」
艶然と笑う姿は、幼い姿からは想像できぬほどに淫らだった。
無数の女体が躯に絡みつく。柔らかく、細い腕が男の上半身を抱きしめる。豹のようにしなやかな足が、男の足に纏わり付く。絶世の美女たちが、ひとりの男を全身で愛撫していた。
ピンク色のシーツ、ふかふかのベッド、そしてどこまで続くかもわからない空間――。
ここには世界中のあらゆる快楽が混在していた。
大きな肉の果実が男の背中に押しつけられ、のの字を書くように動き回る。背筋をなぞる乳房の感触に男は脳髄が溶け出して耳から溢れてしまいそうになっていた。
男の股の間には三人の女性が躯を滑り込ませて、熱心にペニスを銜えている。その三人に、それと背後にいる女性も、総て同じ顔をしていた。
それは路地裏であった女性だと男は曖昧になっていく脳で思い出したが、間断なく与え続けられる快楽にそれ以上の思考を働かせることはできない。陰茎をなぞる舌と唇の感触は、女体に溺れる以外の選択肢を奪い去っていた。
だから、どうして警邏で路地裏に立ち寄っていたはずなのに、こんな場所にいるのか――なんて疑問に答えを見つけることもできなかった。
「キミの場合はハーレム願望か――実に判りやすくて健全だね」
背中から男を抱きしめている女性、イザベラが耳元で囁いた。言葉に揺らぎはなく、一定のリズムを保っているのに、耳にかかる息だけは溶岩のように熱い。
「なにが……なにが起こってるんだ……」
熱い吐息に意識がわずかに引き戻され、男はようやく意味のある言葉を発することができた。
イザベラはからかうような声音でそれに答える。
「私はね、相手の嗜好にもっとも適した姿を知ることができるんだよ……欲望っていうのは、あまりに輝きが強すぎるから、手に取るように判るのさ」
「で、でも……なんで、こんなに、人が……」
「そうだね……」
優しく、些細な質問の問いを伝えた。
「私が魔女だから、かな?」
男のペニスに群がっていた三人のイザベラが口淫の速度を速めた。ぴちゃぴちゃと涎を垂らしながら、男の欲望を限界まで導く。
そうして、何度目かも判らなくなるくらいの射精。
イザベラたちは顔を汚す精子を気にせずに、精液を出し続ける肉棒を貪る。射精中に与えられる快感に、男は絶叫する。あまりの快感で脳内の神経がいくつも千切れ飛んだ感覚。
粘度の高い白濁液で顔を汚しながらも奉仕を続ける三人の自分自身を見下ろして、イザベラはもう言葉を理解することもできないであろう男に語りかけた。
「さあ……もっと、楽しもうか――?」
*
夜の路地裏には四つの死体が転がっていた。
全身の水分を吸い取られたミイラのような有様は、吸血鬼に血でも抜き取られたのかと思ってしまうほどに凄惨だった。
「しまったな、少し調子に乗りすぎてしまったか」
その横には、衣服ひとつ乱れていない魔女イザベラの姿がある。悩ましく胸を押し上げる形で腕を組んだ彼女はばつが悪そうな顔になったものの、すぐに頷いて気を取り直すことにした。
「一応、殺すつもりはなかったんだけど……まあ、いいよね。顔を見られていたし、四人分ギヨたんの代わりをしてあげたと思えば逆に感謝されて然るべきだろう」
自分なりの理屈で納得するとイザベラは彼らから視線を外して、未だに意識を失っているジョゼフたちの方へと向かって行く。
実際は、ジョゼフたちが気絶してからまだ五分と経っていなかった。だから、未だにという表現は相応しくない。けれど、男たちの死体は無限とも云える時間の中で朽ちたようにも見える。大事なものがイザベラの周りで噛み合っていなかった。
魔女――。
悪魔と契約し、超常の力を得た人を超えし者。
このとき、イザベラが何をおこなったのか。知る術を持つものは誰ひとりとしていなかった。
第二章/了
目覚めは暗闇の中だった。
アンナマリアが意識を取り戻したとき、外にはまだ闇の帳が降りていた。そう長くないうちに陽が空に昇るのであろうことはなんとなく躯の調子でわかるものの、それでも人が目覚めるにはまだ早い。
天井の木目を見つめて、どうしてこんなところにいるのだろうか、とアンナマリアはぼんやりと思考する。
「……あっ」
意識をなくす直前のことを思い出して、アンナマリアは躯を起こした。何故か彼女はベッドの上で寝ていたが、もちろん見覚えはない。そもそも、ベッドで寝た経験など断頭台であるアンナマリアにはないことだった。
「あの後、どうなったんだろう……?」
レリア・キッスとの戦いで疲弊のあまり、今まで眠ってしまっていたのだ。
「お目覚めかい、ギヨたん」
声をかけられて、アンナマリアは弾かれたようにその方へと振り向く。もし誰かの家に運び込まれていたとしたら面倒だと思ったのだが、そこにいたのは魔女イザベラだった。
「……ギヨたんいうな」
見覚えのある人物でアンナマリアはほっと胸をなで下ろして毒づいた。好意を抱くような人物ではなかったが、今は安心できる。
「ここが貴方の家?」
アンナマリアは部屋の中を見渡す。断頭台として過ごしてきたために人の家がどうなっているかの知識はなかったが、殺風景だと感じることはできた。
寝室だからなのか、目立つ家具は置かれていない。それにしてもベッド以外には本の山しかないのは少々異常だった。イザベラのことだから、そのようなものには頓着していないのだろう。
「そうだよ。まあ、家というよりは、寝床といった方が正しいかもしれないけど。別に愛着はないからね」
「そういうものなんだ」
「少なくとも、私の方はね」
イザベラの言葉には、自分以外の者も住んでいることをほのめかしていた。
「もしかして、あのレリア・キッスっていう子もここにいるの?」
「ああ、私の助手だからね。今はジョゼフと一緒に別の部屋で寝ているよ。ギヨたんは流石に起床が早かったね。断頭台の朝は早いということかな」
「茶化さないで。……酷い目にあったんだから」
後半の文句は羞恥心で小さくなっていた。同性に感じさせられて、最後には気絶してしまったのだ。初めての経験に頬が恥ずかしさで熱くなるのをアンナマリアは抑えることができなかった。
初心な反応にイザベラは笑みを浮かべてアンナマリアに答える。
「仕方ないじゃないか。キミがジョゼフに手を出さなければレリアも襲いかかることはなかったんだ」
「……せっかく、楽しんでたのに」
アンナマリアはベッドで足を抱えて、膝に顔を埋める。レリアによって与えられた感覚は確かに得難いものであったものの、ジョゼフとの性行を邪魔されたことはまだアンナマリアの心の中で尾を引いていた。
「本当、貴方の知り合いに関わると碌なことにならない」
「私はなにもしてないじゃないか。そんなに詰られる謂われはないよ? そもそも、私がこうやって助けていなかったら、ギヨたんたちは今頃詰め所にお持ち帰りされて乱交パーティーでも開かれていただろうさ。それに、キミはレリアに感謝した方がいいかもしれない」
「……なんで?」
むすっ、とした不機嫌さを隠そうともせずに、アンナマリアはイザベラを睨み付けた。レリアに感謝することなどまったく見あたらない。むしろ、愚痴を申したい気分だった。
「彼はジョゼフと云ってね。キミとしては因縁を感じずにはいられない名前だろう、ギヨたん」
「ジョゼフ・ギヨたんとでも云いたいの? それよりも質問に答えて」
その視線を何処吹く風で受け流し、イザベラは逆に問い返した。
「キミ、ジョゼフを見て不思議な気分にはならなかったかね」
「不思議な気分……」
そういえば、どうして自分はあんなにも熱中して行為に耽っていたのだろうか?
イザベラの云うことに心当たりはあったが、理由は思い浮かんでこない。
「ううむ。わからないか。ならストレートに答えを云うとだね。ジョゼフはキミの世話をしていた処刑人の弟だ」
「……え?」
あまりにもあっさりと告げられて、アンナマリアは目を丸くした。なにを云われたのか理解できなかったのである。
「処刑になんて興味のない私がキミを見つけたことを、そもそも不思議には思わなかったのかい? ジョゼフの兄が処刑されるからと聞いて、その日だけ足を運んだんだよ。そうでなければ、キミは今でも断頭台のままさ」
「そ、それ、どういうこと!? だって、あの人は自分に血縁はいないって……」
「そ うだね、彼は弟が死んだと思っていただろう。なにせ、ジョゼフは一度森の中で死にかけたんだ。右腕をばっさりと持って行かれてね。そこを私が通りがかって 助けてあげたのさ。ジョゼフはその後、兄には会わなかったようだから、残された血痕だけを見て死んだと判断したのだろうね」
「そんな……」
アンナマリアの体温が一気に下がり、考えたくもないことが胸の裡で膨れあがった。
もしかして、わたしは彼の家族を、殺すところだった?
処刑人を殺した総意に反逆すると決めた。ならば、国家に所属する総ての人間を自らの手で殺すとアンナマリアは決心を固めていた。
あのときの行為とて例外ではない。如何に愉しんでいたとしても、逃がす気など毛頭なかった。事実、レリアが妨害していなければ間違いなくジョゼフを殺していた。
命とは常に平等だ。生き方、人生に違いがあれど、命の重さ自体に違いはない。聖人も、奴隷も、殺せば死ぬ。よって等価値である。断頭台として産まれて、幾多の首をはねてきたアンナマリアの中に血と共に染みこんだ思想だ。
にも関わらず、処刑人の弟を後一歩で殺すところだったこと、殺してしまっていたときのことを考えると、足が竦んでしまった。
躯を硬直するアンナマリアにイザベラが声をかける。魔女はいつでも冷静にして冷徹だった。
「別に、考えなかったわけじゃないんだろう? 国をひとりで総て滅ぼすということは、自分に関わった関係者だろうが、彼らの家族だろうが、区別なく殺すことだって。それとも、殺す人間を選ぶのかい、断頭台であるキミが。命を分別なく刈り取る断頭台のキミが」
「……やめて」
「もし自分の気に入る人間だけを残して殺戮をおこなうというなら、それはなんて傲慢な行為だろう。そもそも、人殺しの処刑道具に命を測って分ける自由など元よりありはしないのに」
「やめてって云ってるの!」
ぶんっとアンナマリアは枕を投げつける。
真っ直ぐに飛んできた枕をイザベラは身を逸らして簡単に避けてしまった。
すっかり機嫌を悪くして蹲ったアンナマリアを見て、イザベラは大仰に肩を竦めた。
「別 に虐めるつもりで云ったわけではないんだけどね。ただ、キミが当初語っていた国家惨殺の理念と相容れないから、こうして忠告してみたというわけさ。中途半 端な気持ちで国民を皆殺しにするなんて、そう出来るわけがないだろう? 彼らだって生きているんだから死にものぐるいで抵抗する。それこそ、あらゆる手段 でね」
今度は黙ってイザベラの話を聞いていた。
アンナマリアの中には、今も弱まることのない国民への怒りがある。自分に処刑人を殺させた者たちの意志を許すことはできない。
見せ物として、娯楽として、殺されてしまった実直な彼。この世は弱肉強食と誰もが嘯く。そうして、国民の精神の安寧を維持するために弱者である彼は殺され た。殺される方が悪いのだ、と云ってしまえばそれまでのことだ。アンナマリアもその生まれからして、死に対して感傷を抱くわけではない。生死の哲学をおこ なうこともしない。
けれど、大切だった人が奪われたことに対する怒りはどうすればいいのだ。
仕方がないと割り切らなければいけないのか。殺された方が悪いのだと死を許容しなければいけないのだろうか。
国民がそういうならば、その総意ごと斬って捨てる。
そうして歩み出した道であったはずなのに。その過程で、彼が大切にしていたであろう人を殺さなければいけないとしたら――。
「どうすればいいの……」
アンナマリアは声の震えを隠すほどの余裕すらなかった。明確な自意識を持って活動してからの日が浅い彼女に、この問いは重すぎた。
割り切って殺してしまえばいいのか。――けれどそれはただの思考放棄だ。
割り切るということは、なにかを捨てることだ。悩みを解消するために、悩みを捨てることだ。思考を削り落とすことだ。苦悩するのは美徳ではないが、悩まないで愚直に猛進するということは、考える葦であるところの人を止めたということに他ならない。
人を殺すように、こんなものすら斬れたらいいのに。そう思っても、彼女の鎌は思慮を両断することはできなかった。
「どうすればいいか悩むというなら、なにもしないという選択肢もあるよ。ここで止めてしまえばいい。復讐劇はここでお終いだ」
「それは……」
それが、一番いいのではないか、とアンナマリアは思った。
彼のために、彼が好きだったものを壊すのは、本末転倒も良いところだ。処刑人のために復讐する、聞こえはいいが、それは自らのやり場がない怒りを放出するための手段である。自己の充足のために、大切な人の大切なものを殺す。どこまで云っても満たされるのは自分だけだ。
死んだ人に操を立てても、仕方のないことである。
でも……けれど……、そんな風に思考がぐるぐると少女の小さな頭の中で回っていた。
「もうすぐ朝だよ。ギヨたん、広間に戻っておかなければならないんじゃないかな」
イザベラに声をかけられて、窓の外が白み始めていることに気がついた。いつもならばどうでもいい人殺しの仕事が始まる夜明けなのに、今は太陽を無くしてしまいたくなるほどに恨めしい夜明けだった。
でも、いかないと、処刑は凄惨なものに取って代わるだろうことは判っていた。一枚一枚爪を剥がし、肉を抉り、生きながらに内臓を引きずりだし、あらゆる苦痛を罪人――あるいは罪人のレッテルを貼られた人が受けるのだ。使命感などなかったが、それでも許したくはなかった。
アンナマリアは無言でベッドから抜け出すと、イザベラの横を通り抜けて扉のノブに手をかける。
「広間の方へ行きたいなら、ここから北に真っ直ぐと進むと良い」
答えるのも億劫で、アンナマリアは小さく頷くと扉を開けた。
「……あっ」
少年が驚いて声をあげて、アンナマリアもびっくりして立ち止まった。
扉を開けた先には、あの金髪の少年――ジョゼフがいたのである。
改めて、アンナマリアは目の前の少年の顔をまじまじと見つめた。金髪碧眼、それは処刑人と同じで、云われて見れば彼の面影がジョゼフにはある。高い鼻に、彫りの深い精悍は顔立ち。どれもが処刑人を彷彿とさせた。
ただ、処刑人はお世辞にも明るいとは云えない寡黙な男だったのに対し、ジョゼフは溢れんばかりの快活さを持った少年だった。そのせいで、このふたりに血の繋がりがあると想像できなかったのである。見た目は似ているが、中身は正反対だ。
アンナマリアにじっと見つめられて、ジョゼフは顔を赤くする。少ししか見ていないつもりでも、それなりに長い間眺めていたらしい。
「えーと、さっきはどうも」
恥ずかしそうにもじもじとしているジョゼフがアンナマリアには不思議だったが、自分が彼と何度も性行していたことを思い出して納得した。そういえば、自分 と寝た男と話すのはこれが初めての経験だった。そう考えるとアンナマリアも急に居心地が悪くなる。しかも相手が処刑人と同じ顔をしているものだから、その 恥ずかしさも大きい。
表情には出すまいと気を払っていたからだろうか。アンナマリアはおかしなことを口にしてしまう。
「気持ちよかった?」
「え!?」
「なんでもない。忘れて……お願いだから」
本当に、なにを訊ねてしまったのだか。意味を自覚してアンナマリアは顔から火を噴きそうになってしまった。無表情を必死に守っていても、顔だけ真っ赤になっていればやせ我慢だとは誰の目にも明かである。
「あはは、ジョゼフは童貞だからそういうこと云ってもまともなことは返ってこないと思うよ」
「ちょっと! どうしてそんなこと知ってるんですか、魔女先生!」
「それは私が魔女だからさ」
「説得力凄いですよね、それ」
イザベラに云われて恥ずかしさに顔を手で覆ったジョゼフだったが、咳払いをして膝を曲げるとアンナマリアに目線を合わせた。
「えっと、アンナマリアちゃん、だよね。魔女先生に聞いたんだけど兄さんの大事な子なんだよね」
「それは……」
「ジョゼフはギヨたんよりほんの少し早く目が覚めたんでね。ちょっとだけなら話してあげたんだよ。大丈夫、肝心なことは云ってないから」
つまり、アンナマリアが断頭台であるということは話していないのだろう。もっとも、話したところで信じるかどうかは別のことだったが。
「肝心のこと?」
「女の子には男の子に秘密があるのさ。それで、なにか用があったんじゃないの?」
「あ、そうでした」ジョゼフは改めてアンナマリアに向き直る。「えっとね、兄さんはあんなことになっちゃったけど……きみまで自棄にはならないでね」
「自棄?」
「いや……ほら、さっきみたいなこと」
「別に、自棄でやってるわけじゃない」
自分が悩んでいた事柄にずけずけと入り込まれて、アンナマリアは眉間に眉を寄せる。気分を害したのがジョゼフにも伝わったのか、青年は困った顔になった。それでも、ぶれるような気配はない。
「わたしは、わたしの好きでやってるの。他人にとやかく云われる筋合いはないんだから」
「なんであんなことやってるかなんて、そりゃ聞かないけど……。兄さんなら絶対に止めるはずだよ」
ジョゼフの口から処刑人のことがでてくると、どうしてかアンナマリアは平静でいられなかった。自分は産まれてからずっと彼のことを見てきたのに、いきなり出てきたジョゼフが知った風な口を聞くのが、許せない。
脳裏に浮かんでくるのは、いつも寂しげな顔でアンナマリアの刃を拭う処刑人の姿。ついぞ最後までアンナマリアはそれ以外の表情を見ることは叶わなかった。
いつだって、自分はひとりだと呟いていた。本当は、弟が生きているのに。彼がずっとそう思い込んでいたのは、どうしてだか知らないが、ジョゼフが自身の生存を隠していたからだ。明かしていたら、少なくとも死の間際まで嘆きすらしないなんてことはなかった。
「うるさいっ、その兄に自分のことを隠してたくせに!」
「それは……」
予想外の追求にジョゼフは瞠目する。口を何度か開くが、それは水面に浮かんだ魚のように動くだけだ。
肩を怒らせてアンナマリアが玄関の方へ向き、ジョゼフに背を向ける。
「あ、待って! 危ないから送っていくよ!」
「あんなによがってたくせに指図なんてしないでよ!」
「ちょっとぉ!?」
顔を赤くして慌てふためくジョゼフには目もくれずアンナマリアは廊下を早足に歩き出す。
咄嗟にジョゼフは彼女の肩に手を伸ばすが――空を掴むだけだった。
避けられたのではない。途中で、伸ばす手がとまってしまった。ジョゼフの耳の奥には、アンナマリアの台詞がずっとこびり付いていて、彼女を捕まえることをためらわせた。
玄関が乱暴に開かれる音でジョゼフは放心状態から復帰する。もう彼女は家にはいなかった。
未だに腕を伸ばしたままだったことに気付いて、ジョゼフは苦笑しながら腕を降ろす。それは一度森の奥で切り落とされた右腕だった。
「嫌われちゃったな」
自嘲気味にジョゼフは洩らす。普段のまぶしいくらいに浮かべている笑顔はそこにはない。もしアンナマリアがまだここにいたのなら、その顔は処刑人にそっくりだと思っただろう。
一部始終を見ていた魔女が部屋から出てきて、廊下の壁に寄りかかる。
「あれは嫉妬だよ、嫉妬。そんなに気に病む必要はないと思うよ」
「嫉妬、ですか?」
嫉妬される心当たりがなく、ジョゼフは首を捻る。リスみたいな動作にイザベラは微笑した。
「あ あ、嫉妬だよ。彼女がこの世で一番長い時間一緒にいたのは、キミのお兄さんだ。それはね、つまり彼が世界の中心だったというわけだよ。どんなものでも、自 分の一番大切なものを中心としてグルグルと世界を回すのさ。だから、自分よりも処刑人と絆の深い者がいることを許せなかった」
「そんな、嫉妬されるようなことなんてぼくにはないんだけどな。兄さんとの繋がりは、血縁であるってことくらいですよ」
「それが彼女にとっては誰よりも重いのさ。彼女は誰とも血が繋がっていない」
「孤児ってことですか?」
「そんなところだよ」
断頭台だから、とはイザベラも云わなかった。
それでも、どれだけアンナマリアが血の繋がりを重く見ているかはジョゼフにも伝わっただろう。自分と血を分けた存在がいない、その重圧に。
血縁が誰ひとりといないとしても、所詮は他人と呼ぶ者もいる。確かに、人がこの世に生まれ落ちた時点で主観は自分ひとりのものであるし、母との縁もへその 緒を切れば目に見えなくなる。親と子、兄妹の繋がりなんて、結局は自己防衛のために必要とされる最小のコミュニティでしかない。
人間にとってはそうでも、アンナマリアにとっては違った。便宜上、自分を作った者を親とするなら、いる。だが、血は繋がっていない。
人は遺伝子を連綿と受け継ぎ、継続性を持っているものの、アンナマリアは違う。突如としてこの国に生まれた、誰との繋がりも持たない正真正銘の新しい子供。
彼女は産まれたときから庇護してくれる者すらおらず、復讐に身を焦がすだけの、孤独な人だった。
そんな彼女にとっては、血縁という繋がりは誰とも得ることができない。空に手を伸ばしても太陽を掴めないように願ってやまない渇望だったのだ。
ひとりだと悲しそうに云っていた彼にも、弟がいた。それが、彼女には複雑だったのである。処刑人が世界の総てだったのに、血の繋がりという自分では絶対に得られない絆で彼と結ばれている者がいることは。
「あの子にとって、血縁っていうのは本当に特別なんだ。なのに、自分が生きていることを黙っていた。それも許せないんじゃないかな」
「まさか。ぼくはいない方が兄さんも楽だったと思いますよ」
ジョゼフは笑みを浮かべながら首を振って否定した。
「そういえば、あの子はどこに住んでるんですか? 兄さんの代わり……なんておこがましくて云えませんけど、そんな話を聞いたら尚更心配ですよ」
「広間の辺りにいると思うけど、見つからないと思うよ。夜になればまた会えるんじゃないかな」
「そんなに街角に立ってるんですか。珍しい話じゃないですけどね」
そういうわけではなかったが、イザベラもわざわざ訂正して余計ややこしくする気はなかった。夜になればアンナマリアが必ず街を徘徊しているのだから、嘘は云っていない。
「じゃあ、ぼくはそろそろお暇させてもらいます。店長たちも心配してると思いますし、営業準備を手伝わないといけないんで。あっ、レリアちゃんにもよろしく云っておいてください!」
「ああ、気をつけたまえよ。なんだか嫌な気配がするんでね」
「あはは、魔女先生らしい忠告ですね。肝に銘じておきますよ!」
そういって、ジョゼフは騒がしく廊下を駆けていく。その背中を見送って、イザベラは溜息を吐いた。
「さて、今日は助手の機嫌が悪そうだ」
ずっと部屋の扉に寄りかかって廊下の話を聞いていたレリアは特徴的な頭髪を弄りながら、呟いた。
「最後の最後で思い出したように云うんだから」
こつん、と踵で壁を蹴った。
「ジョゼフくんの、ばか」
*
時刻は数刻ほど遡る。まだ深い夜がこの国を覆っていたときの王城、その一角で密やかに狂乱の幕が開かれようとしていた。
入浴行為は、躯に水を浸透させ脆弱にする行為とされた。
少なくとも、この国では風呂に入ることで躯を清潔にするという発想はなかった。それは自らを貶めてしまう悪しきおこないであるとされてきたのである。
それでも、湯で躯を洗うことは何よりも清潔さを保てるものだ。よって、一部のものだけは密かなる楽しみとして入浴していた。
王族、貴族たちである。
湯を沸かし、湯船に溜めるなど、入浴には手間がかかった。それを問題とせずに躯を流せる者は、そのような権力者たちだけの特権であった。
つまり、入浴とは庶民にとって禁忌であり――権力の象徴だったのだ。
ここに、革命後現在の指導権を握った派閥の幹部がいる。彼は今や誰もが認めるこの国の権力者である。市民からここまで成り上がった者が入浴行為に嫌悪と同時に羨望を持っていたのは、まったくおかしなことではなかった。
男は脱衣所で服を脱ぐと、城にあった浴場へと入る。湯船は優に数十人もの人が同時に浸かれそうなほど大きく、当然市民であった頃には親しみはまったくないものだ。
男の分厚い胸板はこの上ない優越感で膨らむ。何故なら、今この瞬間、大浴場はふたりだけのものなのである。
大浴場には、既にひとりの女がいた。
髪の長い女である。椅子に座っていると、世にも珍しい蒼い髪は浴場の床に毛布のように広がっている。男はこの王宮に来てからも、彼女の髪よりも美しい毛皮は見たことがなかった。
一糸まとわぬ姿の女性は振り返り、艶めかしく瑞々しい肌を惜しげもなく男の前に晒す。ピンと上を向く、果実のような胸はいつ見ても男の情欲を掻き立てた。 母性もあり、それに勝る淫靡さがあった。アダムとイブが手にした果実は、きっと彼女の乳房のように手にしなくてはたまらないものであったのだろう。
「お待ちしておりましたわ。さあ、お背中を清めさせていただきます」
「アワリティア」
男は女の名を呼ぶ。その目は夢見るように虚ろだった。
「いつもと同じように頼むよ」
「いつもと同じ、ですね。受けたまわりましたわ」
蒼い髪のアワリティアは物静かな顔立ちに、蕩けてしまいそうになるくらいに蠱惑的な笑みを浮かべた。
湯で濡らした躯に石鹸を塗り込み、アワリティアは自らの乳房を擦り合わせて泡を立てる。悩ましげな声を洩らしながら躯を泡立てると、乳房を男の大きな背中に押しつけた。
躯を上下させ、泡で真っ白になっている胸で背中を擦る。
「おお……」
泡で滑る胸が背中をなぞっていく感覚に男は満足気な溜息を吐いた。筋肉で角張った背中に柔らかな胸肉が入り込んで洗い流していく。時折皮膚を引っ掻いていく乳首の硬さが心地よかった。
「はあっ、どうですか、旦那様。痒い所はございませんか?」
相手の耳を吐息で撫でながら、アワリティアが訊ねる。その間も胸での背中への奉仕は止むことがなく、彼女の乳房は背中を往復していた。
「ああ……前の方が痒いな」
「前……あらあら」
おっとりとした笑み。それでいて含みのあるいやらしい微笑み方。
アワリティアは男の背中に抱きついたまま、その両手を相手の股ぐらへと伸ばした。石鹸の泡で滑って入り込んだ手はそそり立つ陰茎に指を絡ませる。
「こんなにしてらして、掻痒をお感じになられるわけですわ。今、綺麗にして差し上げますね……」
云うと、アワリティアは自分の蒼い長髪を引き寄せて男の一物に絡みつかせる。泡だらけになっている蒼い髪に包み込まれて、それは女の手の中で強く跳ねた。
「こちらも今、綺麗にして差し上げますね」
胸の動きを緩くして、アワリティアは髪越しに男性器を擦り始めた。
これほどの長髪でありながら傷みの見えない毛並みが亀頭を刺激する。アワリティアの手の動きで髪はさらさらと流れ、高級な絹にペニスをなすりつけているような快感と倒錯感を与えられる。
雁首に幾房の髪が絡みつき、彼女の繊細な手ですりすりと亀頭へと滑っていく。その視覚的にも触覚的にも経験のないものに、男は暑い浴場の中でありながら身を震わせた。
「どうかいたしました? 私はただ洗っているだけですのに」
からかう声に男は胸の裡をぞくぞくと這い回る蛇の存在を感じた。耳朶を舐める言葉は脳がマヒしてしまいそうになるほどに甘い。
ある時代、民衆用の風呂屋には入浴以外の用途がもうひとつだけあった。それは、売春である。風呂場とは躯を洗い流すためと、そして女性が春を売る場所なのだ。
男のペニスに髪の毛を巻き付けて、その上から握り締めてくるふたつの手。左手は竿を髪と一緒にしごき――洗い上げ、右手は髪と一緒に亀頭へと添えられてグ リグリと動いている。さらに、背中に押しつけられる泡まみれの乳房も動きを止めてはいなかった。三つの刺激が別々に男を苛んで、意味のない言葉が口から漏 れ出す。たるんだ顔には権力者としての面影は微塵もなかった。
髪の毛がアワリティアの手によってペニスを擦るたびに泡が立ち、もう男の下半身は泡まみれになっている。石鹸が手と髪の動きを円滑にして、粘膜を刺激する無数の髪は膣のようだった。
ぎゅっと左手が陰茎を握り締めて、上下に洗う。適度な締め付けと亀頭を覆う長髪は、男を心地よく高めていた。
躯の神経が鋭敏になっていき、乳房が動き回るだけで背中も性感帯であるかのような快感を訴え出す。無意識に男は股を開いて腰を突き出した。アワリティアの両手と長髪が絡みつくペニスを雄々しく天に掲げて、夢の世界に落ちていこうとしていた。
「ああ――」
女性の膣に挿入したものとは異質な快楽。我慢の限界に達して苦悶の表情で精を吐き出すのと、この心地よさはまったく違っていた。
まるで、全身をマッサージされて疲れをこそぎ落とされていくときの心地だ。
石鹸とアワリティアの混ざり合った香りが肺一杯になって、麻薬みたいに頭蓋骨の中身を溶かしていく。
躯が軽くなって浮いてしまいそうになる浮遊感。
静かに、やさしく。子守歌を聴かされて眠りに落ちそうになる、そんな安らかさが男を押し上げている。
「さあ、気持ちよくなってくださいな、旦那様。だって、お風呂は気持ちの良いものなんですから――」
アワリティアが手の動きを徐々に早めていく。髪の感触と、掌の緩やかな力加減。
髪の房を縫ってモグラのように何度も亀頭を出し入れさせながら与えられる快感に、男は絶頂を迎えた。
「あああ――――」
髪の中でペニスが射精した。
文字通り、天にも昇る安らかな心地。どこまでも飛んでいってしまいそうになる感覚のままに精を放った。
どくどくどくと髪の中でペニスは精液を吐き出して、蒼い髪の中で行き場のなくなった精子が陰茎に纏わりつく。
そして髪の間から何度も白濁とした液体が溢れだした。アワリティアの幻想的な蒼い髪は情欲の液体で白く穢され、指先は泥のような精液でべとべとである。
アワリティアは手足を投げ出している男の肩口から顔を出して、その陶然としている顔を覗き見た。
「旦那様、今はお風呂の時間なのですから……汚してしまっては駄目ではありませんか。私の髪の毛と手も、石鹸より真っ白くされてしまいましたわ」
精液が付着して固まった房を指で梳いて、掌に精液をこそぎ落とすと、アワリティアはそれを自分の口へと運んだ。手に唇が吸い付いて、物静かな顔立ちからは想像できない舌遣いで精子を舐めとると、嚥下する。
「さすが旦那様……こんなに濃くて喉に引っかかる精子は飲んだことがありませんわ。でも、前の方は念入りにお掃除してあげないといけませんね」
アワリティアが男の前へと回り込むと、その胸板に乳房を押しつけながら抱きつく。
その体勢で躯を上下に動かすと、乳房が胸板の上でパン生地のように形を変えた。
うっ、と男が呻く。アワリティアが動く度に彼女のお腹がペニスに擦れていた。引き締まった腹筋の上についた柔らかい脂肪が、勃起したままだったペニスの裏筋を圧迫する。
「どうかしましたか、旦那様」
訊ねながらも笑みを浮かべた彼女の動きは止まらない。
その間にも、アワリティアのおへそに亀頭が引っかかって男は声を洩らす。お腹のくぼみに性器でキスをするのは、男の性欲を掻き立てるには充分すぎた。
硬さを増したペニスの感触にアワリティアは目を丸くすると、男に悪戯小僧を見るような視線を向けた。
「もう、躯を洗っているだけですのに……このままではもっと汚されてしまいそうですわ。そうですね、こちらもたっぷり泡一杯のおっぱいで洗って差し上げますね」
アワリティアは男の股の間にぺたんっと座ると、泡だらけのペニスを乳房に押しつけた。
器用に乳房の間で肉棒を挟み込むと、アワリティアは両手で胸を動かす。
石鹸の泡を羽毛みたいに纏わり付かせた胸がペニスを撫で上げた。陰茎にこびり付いていた精液がふたつの胸に洗い流されていく。
精液と泡は混じりあっていき、ペニスは確かに綺麗にされていた。
けれど、胸での奉仕はまたもや男を絶頂に導く。
ただでさえむしゃぶりついて滅茶苦茶にしてしまいたいほどに魅力的な乳房であるのに、それで男自身を挟み込まれてしまっては肉体的にも精神的にも我慢できるわけがなかった。
アワリティアは搾精の動きではない。本当に胸でペニスを洗うつもりで泡を刷り込んでいた。それが包容力となって男の心を急速に満たしていく。アワリティアに胸でペニスを包まれている感覚は、疲労してベッドに潜り込んだときの充足感と同じだった。
乳房に挟まれて窮屈そうなペニスは、しかしタイトな快感に脈打つ。
「私の胸の中で震えていらっしゃるのがわかりますわ……さあ、ご遠慮なさらず吐き出してしまってくださいな。今度は汚れてしまわぬよう、私の口で受け止めさせていただきます」
乳房でペニスを扱く淫らな姿とはかけ離れた聖母のような笑みをアワリティアは男に向けた。慈愛に満ちた瞳を向けられた男は全身を愛撫されている多幸感に支配される。この女性からの穏やかな手管に逆らえる男などいようはずがなかった。
「ああっ、わかった……飲め、飲み干してくれっ」
男が腰を振って乳房から肉棒を突き出すと、アワリティアの口が亀頭を一口で呑み込む。その生暖かい口腔の感触で男は絶頂を迎えた。
ただの射精ではない。全身が弛緩して魂が口から抜け出てしまいそうになる、リラックスの果てにある空を飛ぶような快感――。
陰嚢が収縮し、一気に男は精液をアワリティアの口内へと放った。
「んふっ」
喉の奥に精液がぶつかってアワリティアが恍惚とした表情のままに唸る。口の中から溢れそうになるほどの精液が砂漠で乾涸らびていた所に見つけたオアシスの水とでもいうように、喉を鳴らして呑み込む。
ごくっ、ごくっ、ごくん……。
長い射精が終わって、男は脱力して椅子から転げ落ちそうになる。
そしてアワリティアがペニスから口を離すと、そこに精液は見あたらず、糸を引く彼女の唾液しか付着していなかった。
唇の端に白い糸を垂らしながら、アワリティアは男にまぶしい笑顔を向けた。
「綺麗になりましたよ、旦那様。さあ……あとは私にお情けをくださいませ」
男はふらふらと頭を左右に揺らしながら、辛うじて彼女の言葉に頷いた。
大浴場の広大な浴場に浸かると、その中でアワリティアは股を開く。彼女の性器は揺れるお湯で波打って見えた。
ゆらゆらと波を作るお湯越しであったとしても、その陰部の美しさに男は生唾を呑み込んでしまう。
何度見ても、目の前の秘所は昔を思い出させた。初めて女を抱いたとき、女性器を直視できなかった記憶である。じっと見つめ続けることで恥ずかしさを覚えて しまうほど、男はアワリティアの女性の部分に釘づけだった。彼だけではない。世にいる男性ならば、等しくこの蒼い陰毛が薄く生えた丘を目の前して平静では いられないのだ。
彼女の男を喜ばせるためだけに削り出された女体の、彫刻に似た優美さが合わさって、その陰部は完成していた。
「さあ、焦らさず……早く、お願いします」
男は答えることも忘れて湯船に入ると彼女の腰を掴み、ペニスを秘部へとあてがう。お湯の中で入り口に亀頭ねじ込まれ、アワリティアが背筋を伸ばして艶のある声を洩らした。
「はあっ、そうです……そのまま、来てください」
云われるまでもなく。男は腰に力を込める。お湯の中だからか、それともアワリティアが濡れていたのか。ペニスは一息に膣を貫いた。
アワリティアの中に挿入して、男は堪らず声を上げる。肉棒に絡みついてくる膣は名器と呼ぶのすら躊躇ってしまうほど、貪欲に精を求めて蠢く搾精機関だった。
自分は膣ではなく、別の生き物に挿入してしまったのではないかと不安になるくらい、アワリティアの中は自在に蠕動していた。ペニスを擦り上げ、捻り、圧迫し、玉袋に溜まった精液を捻りだそうとする肉食動物のごとき活動。
自分と膣の境がわからなくなるほどにぴっちりと張り付いてくる膣に二度も射精して性感を高められていた男が耐えられるわけもなかった。
「男の人なんですから、かっこいいところ見せてくださいね?」
奥歯を噛んで耐えていなければすぐにでも射精してしまいそうな中、アワリティアは悪魔のように男へ囁いた。そうされてしまえば、男は反射的に腰を動かしてしまった。
「うぐ……っ」
歯を食いしばって腰を引き――叩きつける。
肉と肉がぶつかり合う音の代わりに、湯船がばしゃりと盛大に弾けた。
そのまま何度も男はピストン運動を繰り返す。その度にお湯は弾け跳び、獣のような激しさで肉欲に耽る男はアワリティアの肢体を貪った。
「そう、そうよ……そのまま私に精を吐き出してしまうのです……」
だが、貪っているのは男ではなくアワリティアの方だった。彼女の酷薄な笑みに男は気付く余裕すらなく、腰を動かすこととペニスにじゅくじゅくと吸い付く膣の感触に心囚われていた。
「あ、ああああ゛あ゛あ゛――ッ!」
男が絶叫する。アワリティアに一際強く腰を叩きつけ――
ドクン、ドクン、ドクン――。
ありったけの精子をアワリティアの奥に流し込んだ。
「ああ、出ていますよ、旦那様……あなたの子種が私の中を満たしています。本当……素敵……」
人の躯では受け止めきれるとは思えない量の射精。それでもアワリティアはお湯の中でがっちりとペニスを銜え込んで一滴たりとも逃さなかった。
「旦那様、さあ、もっと私に――あら」
アワリティアが目を丸くする。男が自分に倒れかかってきたのだ。
あやうくお湯の中に沈みそうになりながらも男を引き剥がすと、アワリティアは柳眉を寄せた。
「死んで……ますね。困りました、この人にはもっと働いて貰わなくてはいけなかったのですけど――構いませんか。代わりはいくらでもいるのですからね……ふふっ」
絶頂のうちに死亡した男の亡骸を抱いたまま、アワリティアは穏和な顔に底知れぬ笑みを浮かべたのだった。
男たちに死体を処理させたあと、アワリティアは街を歩いていた。
露出の少ない清楚な衣装である。服に過剰な装飾は一切施されておらず、質素な印象を抱かせた。
黒色に近い紺色と純白のみで構成された服装は、アワリティアをシスターのように見せていた。シスター服と違うことがあるといえば、太腿が見えるほどに深く 刻まれたスカートのスリットだろうか。それでも、顔と手以外は露出していないために下品ではない。そのスリットから垣間見える太腿は雨雲から顔を出した太 陽のようだった。
アワリティアが歩いていた場所は街の外れだ。最近、夜に人が死ぬという噂話が氾濫しているせいか誰ともすれ違うことはない。しかし彼女はその噂にはまったく意を介してはいなかった。
平然と街を歩くアワリティアはひとつの施設の前で足を止めた。
シスターのように控えめな服装の彼女とは対照的に、目の前の建物は過剰な装飾が施されていた。優雅さはなく、目が痛くなる派手さは資金がかかっていない見た目だけのものであることを如実に示している。
そこは娼館だった。
とてもではないが、女の訪れるような場所ではない。かといってアワリティアが娼婦かと云えば、彼女の淫蕩な行為を目の当たりにした者でなければそんな発想はでてこないだろう。
その立ち姿には静かな気品が漂っていた。自分を誇り、胸を張ることができて、なおかつそれに伴う生活を過ごしてきた者だけが放つ気品である。前者だけでも、後者だけでも、この手の香るほどに漂う上品さは演出できない。
娼館の扉を両手で押し開くと、アワリティアは誰もいない玄関を進んだ。階段を使って二階に昇ると廊下の奥にある扉の前で足を止めた。
大きな扉である。アワリティアふたり分、いや三人分ほどの大きさがある。この娼館では一番の大部屋だ。
それをノックもせずに開いた。
途端、熱気が肌に纏わり付く。香ってくるのは芳醇で濃厚な蜜の芳香だ。
最後に、狂ったみたいに発せられる女の嬌声。
「あはっ! 良いよ、ボクの奥におちんちん一杯感じてるのっ! もっと突いて、もっと出して……ほら! がんばって……」
七人はいただろうか。その男達はベッドの上で腰を振るひとりの女に群がっていた。
ベッドに寝転がった男に騎乗位で腰を振る女のアナルには別の男のペニスが突き入れられ、両手には別々の勃起した肉棒がある。さらに彼女の目の前には三つの剛直が並んでいた。
髪の短い、ボーイッシュな少女である。
乳房はアワリティアよりも控えめだが、そこには大量の渇いた精液がこびり付いていて、男性を虜にする機能では劣っていないことを示していた。
鍛えられて引き締まったお尻は男の大きなペニスを根本まで銜え込み、括約筋でぎゅうぎゅうと締め付けている。
ボーイッシュといっても、少女としての魅力はまったく損なわれていなかった。
「ルクスリア」
狂乱中の少女にアワリティアは冷たい声をかけた。
「〝もう死んでます〟」
「ふぇ?」
夢中になって腰を振っていたルクスリアと呼ばれたボーイッシュな少女は我に返り、自分がのしかかっている男を見下ろした。
その男は白目を剥き、口を半開きにしてだらしなく舌を垂らし、絶命していた。
息をしていない男はひとりだけではない。この場にいる全員が既にこの世の者ではなかった。
自分の下にいる男の肩を何度か揺すって、ルクスリアは意気消沈する。
「そんなぁー! せっかくこれから楽しくなりそうだったのにぃ……。おちんちんはこんなにカチカチなのにっ」
「それは貴女の躯のせいですよ。死んでいる人間のものですら立たせたままにしてしまうなんて、いったいどれだけ淫乱なんですか」
「アワリティアには云われたくないよー」
七つの死体に囲まれたまま、ルクスリアはくすくすと微笑んだ。少女の様子にアワリティアは渋い顔をしていたが、すぐに苦笑にかわった。
「まったく……もう慣れましたけどね。ちゃんと仕事をしてくれれば私は構いませんよ。ところで貴女が殺した彼らは、権力者ではないでしょうね」
「あ、それは大丈夫だよ。ただの下っ端騎士さんたちだから」
「……ならいいですが、それはそれで今度はスペルビアが怒りそうですね」
そうやってぼやいたものの、アワリティアはすぐにそれはいいか、と思考を切り替えた。やはり、物言わぬ男たちには興味を示さない。
「それよりも、最近、私たち以外でこの街の夜を惑わしている者がいるようです」
「ああ、知ってる知ってる。結局、どうするつもりなの?」
「決まっているでしょう。始末します」
まるで世間話でもするようにアワリティアはよどみなく断言した。
「私たち以外、夜の王は不要ですから。もっとも、こちらの軍門にくだるというなら考えなくもありませんが……それでも事の重大さを理解させるためにも、見せしめは必要です」
「もー、まどろっこしいなあ。早く云ってよ、ボクは他の男と遊んできたいんだから」
「さすが、色欲のルクスリア。性欲は他の淫魔の比ではありませんね」
「強欲のアワリティアがそれを云うかな?」
「いいではないですか。まあ、貴女が飽きてしまわないよう簡潔に云ってしまえば。今日の明朝、対象との関与が疑わしい男を逮捕し、処刑します。ちょうど広場に断頭台がありますからね」
「見せしめってこと? アワリティアって、やってることはホントえげつないよねー」
ルクスリアの言葉に応えるのは酷薄な、寒気すらする笑み。
「ええ、私は――強欲ですから」
この国の人間は知らない。
淫魔と呼ばれる種族に、自分たちが影ながら支配されているという現実を――。
*
ジョゼフが自分の働いているパン屋へとたどりついたときには、既に空からまばゆい日差しが降りかかっている時間だった。
「仕込みの時間に間に合わなかったなあ……どうせ手伝えないんだけど」
怒られないといいな、と淡い期待を抱きながら、ジョゼフはパン屋の入り口に到着する。店名の書かれた木彫りの看板が目印の、この辺りでは珍しい小綺麗な店だ。
表のドアから入ろうとして、ジョゼフはまだ開店時間ではないのでこちらは開いているわけがないことを思い出す。だが、ノブを回してみると鍵は開いていた。
不思議に思って中を覗くと、既に何人かの男性客がパン屋には入っていた。けれど、まだパンは店頭に並べられていない。
ジョゼフに背中を向けていた男たちが、物音で振り返る。
屈強な男たちだった。全員、ただの肉体労働者ではない。人を害するために戦闘訓練を受けた者特有のしっかりとした立ち方だ、とジョゼフは一目で見抜いた。
わけもわからず、キモが冷える。
男たちの肩口から、真っ青になった店主の男の顔が現れた。
「ジョ、ジョゼフ! 逃げろ!」
「え?」
男のひとりが店主の顔を殴った。カウンターの小物を引き倒しながら店主が床に倒れる。
それでジョゼフは逃げるのを躊躇した。このまま逃げたら店主はどうなるのか、それよりも店主は大丈夫なのか案じてしまったのである。
逡巡の時間は数秒。事態を確定させるには充分すぎた。
男がジョゼフの腕を掴み、背中に回して拘束する。その手際は乱暴であったがあっという間で、最早抵抗の余地はなかった。
別の男が眼前にやってくる。ジョゼフの体格は中々のものであったが、その男は更に大きかった。
「貴様を反逆罪、及び犯罪幇助の疑いで逮捕――処刑する」
感情を写さない人形のような双眸が、呆然とするジョゼフを射貫いた。
「そんな、いったいなんで――」
とっさに意義を申し立てようと口を開き、鳩尾に拳を叩き込まれてねじ伏せられた。
息が止まり、床に涎が吐き出される。急速に視野が狭窄していく。
呼吸すらできない激痛の中、ジョゼフは男を見上げた。
その顔を見て、
――まるで、誰かに操られてるみたいだ。
そんな不気味な感想を抱いて、意識を失った。
もう今日だけで三回目だ、などというとりとめのないことも思い浮かべながら。
革命が起こったとはいえ、既存の軍事力がなくなるわけではない。
王に仕えていた軍隊は、そのまま革命者たちの配下となる。そうしなければ国も兵士たちも、破綻してしまう。
もっとも、王を欠いた軍の士気が高いのかといえば、無論その限りではない。
士気のない軍隊の敗北は必至である。
逆に云えば、その戦う動機に火をつけてやれば良いだけのこと。
兵士、男たちに火をつける有用な手段は、古来からたったひとつに決まっていた。
「だ、団長……っ」
まだ垢抜けない少年が切なげな声をあげた。
そばかすが頬に残る少年は軍服をはだけさせられていた。棒立ちになってしまっている少年の下半身を覆う布は剥かれていて、少年の屹立した男性器を隠す物はなにひとつとしてない。
あるとすれば、それは女性の手だった。
床に両膝をついて、少年の股間に顔を寄せている女性がいる。きらきらと黄金のように輝く金髪を紐で馬の尻尾のように纏めた女性だ。ポニーテールの女性の顔 つきは凜としていて、目は意志の強さを感じさせる鋭さがあった。冷徹そうであり、並の人の比ではない力強さが滲みでている。
女性の肢体はしなやかな豹のようであった。躯は引き締まっていて、武術の心得がある者なら相当鍛えていると一目でわかる。しかし、筋肉によってなめらかな躯のラインが損なわれてしまっているかと問われれば、否である。むしろ、その逆だった。
女性は自身がまとっている革製の防具に手をかけると、留め具を外す。音を立てて防具を降ろすと、胸が姿を現した。まだ服で全貌を明らかにしていないもの の、ずっと解かれることのなかった防具がなくなったことで禁断の聖域を目の当たりにしてしまったかのような錯覚を人に抱かせる。
胸にいやらしさなど皆無。なのに、目が自然と谷間に吸い寄せられてしまう。薄手の服の胸元から見える汗ばんだ胸元に、少年は息を飲んだ。
さらに女性は衣服を脱いで、上半身を無造作にさらけ出す。裸になって、躯の線はよりはっきりと見えた。女豹――その印象に狂いはなかった。
鍛えられた筋肉がしっかりと躯を引き締めていて、そこにスタミナを維持するための脂肪がうっすらとついている。腹筋、へそのラインのなめらかさは健康的すぎて逆に妖しさを漂わせていた。
女性の手が少年の男性自身に触れると、か細い声があがった。切れ長な女性の目が少年を見上げる。
「どうした、そう力むな。力を抜け」
「で、ですが……」
「云う通りにしろ。これも訓練と同じだ。それとも、嫌でも力が入らないようにしてやろうか」
云うなり、女性は少年のペニスを一口で呑み込んでしまった。
「ああっ!」
女性の口技は、彼女の顔立ちに反して淫らだった。
ぐちゅっ、ぐちゅっと音を鳴らしながら首を上下に動かし、肉棒を舐めしごく。根本から亀頭まで下がり、亀頭から一気に根本まで呑み込んだ。唾液で濡れた頬肉と舌がねっとりと陰茎にからみつく。
「んっ、ちゅっ……どうした、まだ一〇秒も経っていないぞ?」
ペニスを口から抜き、笛でも吹くように竿に唇を這わせて、女性が笑う。それに答えるだけの余力のない少年は、ただこみ上げてくる快感を堪えるのに必死だった。
早くに限界を迎えるのは恥ずかしいという感情が少年にはあったが、墓穴を掘るとわかっていても、少年は自分の性器に舌を這わせる女性から目を離すことができない。
「スペルビア団長……っ」
少年は荒く息をはきながら、女性の名を口にする。
スペルビアという女性は国の騎士を統括する団長だった。軍隊にいる少年とは所属が違ったが、その卓越した技量から軍の人間はよく稽古をつけてもらっていた。女だてらに騎士の頂点に立った技術と力に敵う男はこの国にはひとりとしていなかった。
くわえて、その美貌である。清廉な厳格さをまとった容姿は見ているだけで気が引き締まるくらいで、誰もが憧れたものだ。幾人もの男を虜にしたが、ずっと高 嶺の花で有り続けたのは彼女の力故である。男に自信を喪失させるほど、スペルビアは強かった。そんな彼女へ無神経にも手を出そうとする愚か者は、この時代 にはいなかったという話だ。
なのに、そんな誰の手にも汚されていないような女性がペニスをしゃぶっている――その光景から目を離すことなんて少年には考えられなかった。
スペルビアは自分の涎と少年の我慢汁で口元をぐちゃぐちゃに汚しながら、首を振りって熱心に少年の亀頭に食らい付く。赤々とした粘膜を這う舌と唇の感触――
「あ、ああ、もうだめ……あああああっ!」
未熟な少年はついに我慢の限界に達した。
あの騎士団長の口の中に射精してしまう、その事実に云いようのない背徳感を感じながら少年は精液をぶちまけた。
スペルビアは顔色ひとつ変えずに、少年の精液を呑み込む。けれど、その口はスペルビアとは独立した存在であるかのように精液を絞り取る機関と化していた。無表情に精液をペニスから吸い出されて、少年は腰が抜けるほどの快感に震える。
がくり、と少年は足から力を抜いて床に倒れる。兵舎の一室の床は冷たかったが、熱を感じることができないほど頭の中に甘い快楽が充満していた。
「これで力は抜けたな」
精子の糸を引きながら少年のペニスから口を離したスペルビアは、膝立ちになって少年の腰に跨った。
既にスペルビアの下半身にはショーツ一枚しかなかった。黒い布地にレースをあしらったもので、スペルビアの印象とあわないような、それとも酷く合致しているような、不思議な感慨を少年に与える。
スペルビアはショーツをずらすと、秘所を相手に見せつけた。
「お前が前線に行く褒美だ……忘れられぬよう脳髄にまで焼き付けるがいい」
愛液で濡れていた女性器に少年のペニスが宛がわれ、一息にスペルビアは腰を落とした。
ずぷんっ、と少年の経験不足なペニスが女性騎士たるスペルビアの躯を貫いた。
子供の陰茎は、未成熟といっても男性としての機能という点においては欲望に忠実な獣。
だが――欲望に忠実という点においては、スペルビアの方が一枚も二枚も上手だった。
「ははっ、この我の中でお前のペニスがどんどん膨らんでいるぞ。物足りぬかもしれぬと懸念していたが、やればできるではないか!」
歓声をあげて、スペルビアは淫らに腰を振る。騎乗位で少年を馬のように扱いながら、結んだ髪を尻尾のように振り乱す。尻尾を振って悦ぶ姿はまるで交尾に夢中の犬かなにかのようだった。
頬を上気させて腰を振り乱せば、スペルビアの膣が少年のペニスをきつく締め付ける。鍛えられた括約筋でしまる膣圧は強く、少年のペニスは押しつぶされてしまいそうだった。けれどスペルビアの膣肉は極上の霜降り肉よりも柔らかい。
「あ、駄目、もうっ」
スペルビアが腰を三回も振らぬうちに、少年の我慢は限界に達した。射精したばかりだったというのに少年は精を騎士団長の秘部にぶちまける。
「手加減してやったというのに……早漏め。ならばしっかりと訓練をつけてやらんとな!」
少年が射精していても、スペルビアは腰の動きを止めることはなかった。むしろ、余計に腰の激しさは増す。肌に珠のような汗を浮かべながら、冷静沈着な騎士団長は愉悦に顔を歪めて少年のペニスを弄んだ。
「あ、ああああ……!!」
彼はもう、悲鳴をあげてスペルビアの中に射精することしかできなかった。
*
事を済ませたスペルビアが向かったのは、この国の牢獄のひとつだった。
「まったく、いきなり人を呼び出すとはどういう了見だ……我は忙しいのだぞ」
愚痴をこぼして腰にはいた剣の石突きを叩く。
現在この国は、革命者たちが指揮する軍で他国と戦争の真っ最中だった。もっとも、戦争の原因は革命軍の方にある。彼らが国の主権を握り、その勢いで他国に まで攻め立てたのだ。問題は、軍は既存のものであるということだ。王に仕えていた者たちがそれを殺した者にすんなり従うわけがない。よって、戦線は酷い有 様である。兵士の士気など最悪である。
そんな状況なので、スペルビアは前線に赴く羽目になった少年の筆卸をしていたのだ。もう二度と祖国の土を踏めない哀れな少年への手向けに。
もっとも、革命の要因を作ったのは他でもないスペルビアを含む三人の高位淫魔であるが。そんなことまで気にしない辺り、騎士とは云えやはりスペルビアも淫魔のひとりだ。
牢獄に到着すると衛兵に声をかけて中に入れて貰う。スペルビアは女官に扮しているアワリティアと高級娼婦を名乗っているルクスリアとは知名度が違うので、ほとんど顔だけで入れて貰えた。
案内を断ってスペルビアはアワリティアとルクスリアに呼ばれた牢獄の一室にやってきた。
そこは牢獄の最奥にある檻だ。
鍵のかかっていない檻の中にアワリティアとルクスリアの姿を確認した。
「おい、こんなところに呼び出して、いったいなんの用だ。お前たちと違って、我には表の仕事があるのだから、わざわざ呼び出すな」
不機嫌さを隠しもしない言葉だったが、檻の中で振り返ったふたりは気を悪くした様子もない。スペルビアは誰に対してもこんな性格なのだと知っているのである。
スペルビアの顔はぞっとするくらい端正であるものだから、必要以上に苛立っている風に見えるのだ。そのため、並の肝っ玉の持ち主なら竦みあがってしまう。その性格が熟知できるくらいに付き合いが長ければ、彼女の表情の変化に戸惑うこともない。
もっとも、実力ある淫魔は己の力に絶対の自信を持っている。例え怒らせても自分が負けるとは考えていないのが恐れない最大の要因だった。
「つれないなあ、スペルビアは。せっかくボクに男を貸してくれたお礼をしてあげようと思ったのに」
ニコニコとしているボーイッシュな褐色の少女にスペルビアは溜息を吐く。
「あれは貸したのではなく、奪われたの間違いだ。貴重な労働力を浪費するな、淫売め」
「もうっ! スペルビアは人間に甘いんだから」
「何を云っている。蟻程度の力しか出せぬ猿も人海戦術には必要だからな。ものは使い用だ。それと、何度も云わせるな。何故我を呼んだ?」
「彼に見覚えがあるでしょう?」
いい加減本当に苛立ってきたスペルビアに答えたのは、長髪を揺らす穏和な顔つきのアワリティアである。
アワリティアが牢の中を手で示すが、丁度灯りの影になっていて何がいるか窺えない。
スペルビアも牢の中に入ってそこにいる人物を見た。
「――ほう」
自分の姿を見て萎縮した青年を見て、苛立ちもどこへやら、スペルビアは口の端をつり上げる。
「まさかまたお前に会うことになるとは思わなかったな、ジョゼフ」
「スペルビア団長……」
両手を背中で拘束されているジョゼフは、呆然とスペルビアを見上げた。
「えっと、この子はスペルビアの知り合いなんだよね? ボクはアワリティアからの又聞きだから良く知らないけど」
「ああ、昔騎士団に居た奴でな。てっきり死んだと思っていた。いや――」
こつん、と人差し指が腰にはいた剣の石突きを叩く。
「我が殺したはずだと思っていたのだがな。壮健そうでなによりだ。切り落としたはずの右腕もどうやら繋がっているらしい」
「……っ」
ぐっ、とジョゼフが奥歯を噛みしめる。怒りはなく、睨むわけでもなかった。それは自分の無力さに打ちひしがれているようだった。
「へえ、殺したってどういうこと?」
「こいつは我が剣を教えていた騎士のひとりでな。その中でも剣の才は飛び抜けていた。まあ、あくまで見習い共の中での話だが……。これの最も優れた才は状況の判断能力でな、革命の機運をいち早く察知して騎士団を脱退したのだよ」
「……そして、ぼくは貴女に斬られた」
「ああ、我がお前の右腕を切り落とした」
悪びれもせず、スペルビアは云った。
「少しでも我の興味を惹いた男は試さずにはいられない。だから斬った。騎士を突然止めたのだから、殺しても適当な理由をでっち上げればそこそこの正当性も得られたからな」
「変なの。気に入ったなら食べちゃえばいいのに」
「お前と一緒にするな。そんなに腰ばかり振っていては脳髄が溶ける。それに今から食べさせてもらう。崖に突き落として這い上がってきた相手ほど虐め甲斐があるからな。どうせ、そうさせるために我を呼んだのだろう、アワリティア」
「ええ。人質ですが、別に殺してしまって構わないでしょう。どうせ相手をおびき寄せるための餌にすぎないのですから、死んでいても悟られなければ仔細問題ありません」
アワリティアは一切言葉を詰まらせることなく云いきった。
ジョゼフを逮捕して処刑を敢行すると宣言したのは、彼が夜を騒がせている者と関連性があると踏んだためである。
危険人物としてアワリティアは魔女イザベラを斥候にマークさせていた。あれほどの力の持ち主、七つの大罪の名を冠するほどの上位淫魔なら気付かぬわけがな い。その家に三人の人物が担ぎ込まれ、うちひとりがジョゼフだった。ふたりいた小柄な少女のうち、片方はイザベラと同居している者であったから、自然と夜 の犯人は見慣れない黒いドレスの少女に絞られてくる。
どうやらジョゼフは夜に吸われた者で唯一の生還者、相手が特別な思い入れをしている可能性は高い。こうすれば、なんらかのアクションがあると踏んだわけだ。
当てが外れたところで特に問題もない。そのときは、国民を満足させるために処刑される哀れな少年がひとり増えるだけの話だ。
「ふふっ、なら遠慮なく頂くとするか」
「な、なにを……」
「なにを? わかり切ったことを聞くのだな」
ジョゼフを鼻で笑って、スペルビアは服を脱いだ。身を守るための鎧を無造作に放り捨てて、仁王立ちになる。
「淫魔がすることなど、ひとつしかあるまい」
「淫魔って、まさか団長が!?」
「ボクたちもそうだよ-」
驚愕しているジョゼフをせせら笑うようにルクスリアが補足した。
ジョゼフは気絶している間にここへ連れてこられて、意識を取り戻したときに見ず知らずのふたりがいたのだ。彼女たちがどんな素性の者達か判っていなかった のも無理からぬ話である。しかも、一度殺されかけたとはいえ、かつて自分の上司であったスペルビアまでもが人ではなかったと云われれば、思考も停止してし まう。
「さて、いつまでそうしているつもりだ。頭が高いぞ、ささっとかしずかんか」
スペルビアはジョゼフの頭を踵で思い切り蹴り飛ばした。
靴底が額を殴打し視界が真っ白に弾ける。ジョゼフは声をあげる暇すらなく床に頭をたたきつけられ、鶏の首を絞めたときのような苦しい声を洩らした。
「ガ……っ」
「苦痛で歪む、いい顔だ……これだから殴り甲斐があるのだよ。あのときも本当に愉しかった、この腕を切り落とした時も!」
ジョゼフの右肩をスペルビアが容赦なく踏みつける。骨が軋む音が聞こえてきそうなほどの力強さのまま、足が捩られてジョゼフは悲鳴をあげた。
「ア、ギ、ッアアア……ッ」
「はっはは! 古傷が痛むか? そうだろうなあ、あのとき我が切り落としたところは丁度ここのはずだ。痛かろうさ。けれど、まだあのときよりはマシであろう? もう一度ここを外してやったら、さぞや懐かしい気分に浸れるだろうな」
傷みを快楽に変えるような手管の女性というのもいるが、スペルビアの場合、そこに加えられた力には一切の加減がなかった。本当にこのままジョゼフの右肩を外して、ちぎり取ってやろうという意気込みを感じるくらいの力が足にこめられている。
「ふふ……意地悪もこれくらいにしてやろうか。お前を苦痛で鳴かせた回数などもう数えることもできんのだ。次はこっちで鳴いてもらおうか」
そういうとスペルビアは下半身を覆っていたショーツを脱ぎ捨てて、ジョゼフの顔の上に腰を落とした。鼻と口に押しつけられた熱く濡れる柔肉に、ジョゼフは目を見開く。視界に広がるのは鼻をこりこりと刺激する陰核とスペルビアの金の平原だけだ。
「ほら、ここがお前の肉棒を銜え込む搾精器だ……たっぷり味わうがいい。なにもしないと、窒息してしまうぞ?」
鼻を塞がれて呼吸ができないジョゼフはスペルビアの云う通りにするしかなかった。
例えそんなリスクがなかったとしても、この甘い液体で濡れた秘部に舌を這わせていたことだろう。人間にとって、スペルビアの愛液に濡れた秘所は昆虫にとっての樹液で濡れた木々同然だった。
アンナマリアの薄い線のようなものではなく、ぱっくりと口を開いた性器に舌を伸ばす。女性の陰部を舐めるなんてジョゼフは初経験だったが、そのことを忘れてしまうほど鼻と口を押さえつけるそれは魅力的。
舌が亀裂をゆるく舐めると、スペルビアの背筋がびくんっと跳ねる。
「あはっ、いいぞ……そのまま中に……んんっ」
舌先が膣の入り口をノックし、肉の道を掻き分けていく。すると舌先から、ジョゼフは全身が震えそうになる快感を流し込まれた。膣肉が侵入してきた舌をペニ スと同じように締め付ける。波打った襞が左右共に別々のうねった動きでもって舌を責め立てる。性器を舐めて感じさせているのはジョゼフのはずなのに、舌を 入れただけでジョゼフの攻守は完全に逆転してしまっていた。
「はっ、ああ……」
ジョゼフの口内から唾液が大量に溢れて口元を赤ん坊のように濡らす。それでも舌を引き抜けないのほどの快感がジョゼフを襲っていた。
口の中に流れ込む愛液を喉が動いて呑み込めば、さらに痺れるような快楽が全身に染みこんでいく。頭がクラクラするのは、なにも酸素が欠乏しているだけではなかった。
「いいぞ、慣れてないにしては上出来だ。我の中でお前の舌が性器みたいにのたうちまわっておるぞ」
舌を膣にいれただけでペニスを触られたように感じてしまったジョゼフを笑う。
「では、お待ちかねだ。そんなに触って欲しいのなら我が喰らってやろう」
スペルビアが躯を捻って体勢を変える。ジョゼフの顔に女性器を押しつけながら、ズボンの中で膨らむペニスに顔を寄せた。
手際良くズボンを脱がせると、がちがちに勃起したペニスがこぼれる。
「ふん、我の性器を舐めさせられただけでこうも硬くするとはな」
スペルビアの舌が陰茎を根本から尿道までぬるりとなぞった。
そのまま亀頭を包み込み、口をすぼめて頬肉と舌を密着させる。鍛えられた騎士団長といえどその口内は柔らかく、亀頭に吸い付く肉の感触は男の躯を悦ばせてあまりあった。
「は……ああ……」
「だらしない声をあげおって……淫魔の愛液をそんなに呑んだのだから当然か」
「そこにスペルビアの唾液をペニスにすり込まれれば、どのような男も正気でいられるわけもありませんね」
淫魔の分泌する体液には精力増強の他にも、媚薬のように性欲を刺激する効果がある。それはもう麻薬と同じで、口に含んでしまえば最後、正常な思考能力を 失ってしまう。たとえどんなに屈強な強者であっても、力を生かすための思考を奪われてしまえば赤子も同然であった。しかも、高位の淫魔たるアワリティア、 ルクスリア、そしてスペルビアの体液は他の淫魔の比ではない。彼女たちと寝てしまった時点で、人は性欲という三大欲求のひとつに執着する精液袋と成り下が るしかないのだ。
「ねえねえ、スペルビアを見てたらボクも欲しくなっちゃったよ。仲間にはいってもいいよね?」
にこりと笑って、スペルビアはジョゼフの股の間に寝転がってペニスに顔を近づけた。ペニスに浮き上がる裏筋へ挨拶代わりに舌を這わせる。
ペニスは熱された鉄のようで、力を込めて無理矢理射精を堪えていた。そんな男の儚い抵抗は淫魔たちには筒抜けで、逆に嗜虐心を煽るだけだ。
「これは今、我の所有物だ。ならぬ。あとにせよ」
「スペルビアの後なんて絶対回ってこないよ。だってずっとやめないんだもん。それにー、もしボクがこの子イかせたら、この躯の方が気に入ってるってことだよね。道具はより上手く使える人に渡るべきだと思いまーす」
「ほう、この我に勝負を挑むか……面白い。なら我より先にジョゼフをイかせることができたならば譲ってやろう」
「やった! じゃあ、いただきまーす」
スペルビアの反対側からルクスリアがペニスに吸い付いた。
ふたりの淫魔の舌と唇にペニスを責め立てられて、ジョゼフにはもう正常な思考能力は残されていなかった。下半身へ反射的に力が集まって辛うじて射精を堪えているだけで、もう天上の快楽から逃れようとする抵抗の意志は根こそぎ取られていた。
「んふっ、ちゅ……あはっ、まだまだ大きくなってるね。ふたりの淫魔に責められたら、どんな短小包茎なおちんちんでもおっきくなっちゃうからね……。こうやってボクたちみたいなすっごく強い淫魔に舐められてるんだから……こんな幸せなこと、滅多にないんだよ?」
牢屋の中はむせかえりそうになるほどの甘い香気が漂っている。ルクスリアとスペルビアの汗ばんだ躯から漂った色香だ。その匂いは嗅がなくとも、肌に触れた だけで男は勃起を抑えることはできないほどの淫蕩な気である。さらにその原液とも云える愛液を呑み、唾液を粘膜にすりつけられれば、男の精神を崩壊させて しまうには充分だった。
「ねえ、スペルビア。お口だけじゃなくて、おっぱいも使おうよ。きっと夢心地であっという間にイっちゃうから」
「胸? ……我の胸はあまり大きくはないが」
「淫魔なのにそんなこといわないの! その胸が逆に男を悩殺しちゃうんだからさ」
「ふむ、そんなものか」
ルクスリアとスペルビアが胸元をはだけると、褐色の美乳と純白の微乳が揺れた。後者はささやかな揺れでも、それが男の背徳感を刺激する。
勃起して天上を指していたペニスを、ルクスリアとスペルビアの胸がサンドイッチにした。ふたりの乳房に亀頭以外を包まれて、ジョゼフはスペルビアの秘所に口を押しつけたまま嬌声をあげる。
「ボクの胸の中でビクビクしてる……亀頭が触られてないからイけないんだね。すっごい苦しそうに膨らんでるよ」
褐色の胸で脈打つペニスを見下ろすと、くふっ、と喉を鳴らしてルクスリアが微笑み、亀頭に舌を伸ばした。
八の字を描くようにして亀頭を舐めると、舌先を尿道に滑り込ませる。
「は、あああっ!?」
「む……このままお前にイかさせてなるものか。我の胸で……」
一生懸命に胸を中央に寄せたスペルビアが躯を揺する。控えめな胸がペニスにこすりつけられて、硬い乳首が雁首を弾いた。
「このおちんちん、もうイっちゃいそうだよ? これはボクの勝ちかな」
「抜かせ、我の胸が良いのだ! ……はむ」
むっちりと肉のついたふとももでジョゼフの顔を挟んで自らの女陰をなめさせながら、スペルビアは胸から顔を出す亀頭を銜える。ルクスリアの唇とスペルビアの唇がひとつのペニスを取り合っていた。
竿にくわえられるふたりの胸の極上な感触と亀頭を這う熱い塊の刺激は、淫魔の気に当てられ昂ぶっていたジョゼフを限界へ引きずり上げた。
「ぁ……ッ、ああああ゛あ゛あ゛あ゛あ゛――――!」
ドクンッ! ドクンッ、ドクドクンッ……!
噴火した火山のごとく白濁とした精液がペニスから噴き出した。
ルクスリアとスペルビアの口で受け止めきれなかったほどの精がふたりの顔にぶち当たり、ペニスを挟んだ乳房の上にだらだらと降りかかる。口に入り込んだ濃い、ぷるぷるとした大量の精液をふたりは舌の上で転がし、呑み込む。
チーズみたいに唇を汚した精液を舌で舐めて、ルクスリアは喉の奥から青臭い吐息を吐いた。
「はあっ、すっごい濃い精液! これだけ出させたんだから、ボクの勝ちだね」
褐色の胸を白くデコレーションした精液を見せつけながら、ルクスリアが得意げにいった。
「戯け、我の躯にこやつが感じたのだ。その証拠に我の女性器に夢中でむしゃぶりついている」
スペルビアが躯を起こして、ジョゼフの顔の上に騎乗する。太腿で頭を固定させたまま腰で円を描いて、男の顔に何度も陰部もなすりつけた。
「くくっ、そのペニスはたっぷり濡れた我が抱きしめてやる予定なのだ」
ようやくスペルビアが立ち上がると、腰の下から現れたジョゼフは虚ろな目で浅い呼吸を繰り返していた。口を解放されたにも関わらず、もう意味のある言葉を出せなかった。
スペルビアが牢の壁に背中を預けて、股を開く。秘部が花弁のように開いて男自身を誘っていた。
「さあ、来い。ここにお前のペニスを突き刺すがいい。抱きしめてやろう……天の果てまでな」
騎士団長の誘惑に乗るほどの理性すらジョゼフには残されていない。それでも、ジョゼフはルクスリアを押しのけて、スペルビアと向かい合う。街灯に群がる蛾のように、抗いがたい誘いに引き寄せられて。
あれだけ盛大に爆発したペニスは淫魔の気、そしてふたりによる暴力的なまでのテクニックで未だに萎えていなかった。
ジョゼフはスペルビアに覆い被さり、ペニスを女性器に近づけていく。
スペルビアの、武器を握ってきたせいで肌がささくれ立った手が肉棒に添えられた。細く綺麗という女性の指の印象からかけ離れていながらも、その指で触れられれば声を洩らしてしまうほどの快楽が染みこんでくる。
男根を期待して、スペルビアの女性器が涎を垂らした。ジョゼフの意志とは裏腹に、肉棒はそこへ吸い寄せられる。
くちゅ、と音を立てて亀頭が秘部に埋まる。瞬間、無数の襞が蠕動した。
亀頭を幾重もの襞はまるで何十、何百という舌を同時に押しつけられたような圧力と快感。
「あ、ああああああッ!」
亀頭の隅々に愛液をすり込もうと蠢く膣の感触に男が耐えられるわけもなかった。
ペニスが膣の入り口で暴発する。どこにそれだけの精があるのか。どう見ても陰嚢に入りきらない量の精液が接合部から溢れだした。
「なんだ……先端をいれただけで達してしまったのか?」
陰茎に添えていたせいで精液まみれになった手を眺めながら、スペルビアが鼻で笑った。
「少し本気になりすぎてしまったか。……さて、お前は奥まで入るうちに幾度射精するのだ?」
精液で汚れた指を口で銜えて綺麗にすると、艶然と微笑むスペルビアはジョゼフの腰に足を絡みつかせた。足に力を入れて、まだ射精の余韻さめやらぬ肉棒を自分の中に押し込んでいく。
ず……ずる……っ。
竿に絡みつく濡れた膣肉は容赦がなかった。きゅっとしまった膣は手で握られているようだが、与えられる無数の襞による感触は明かに手のそれではない。
この圧力はアンナマリアのような小さい膣にいれた時の狭いからきつい、というものではなかった。鍛えられた括約筋による締め付けは緩めるのも強めるのも自由自在で、精を絞りだそうと常に新しい刺激を与えてくるのだ――。
「駄目……これ以上は、無理……!」
ペニスに与えられる感覚はジョゼフの正気すら取り戻させるほどだった。
けれど、膣からペニスを抜くことは叶わない。腰はスペルビアががっちりと足で捕まえていたし、なによりジョゼフは逃げようと思うことができなかった。
これ以上の快楽を拒絶しているのに、不思議とジョゼフの腰はペニスを押し込もうとしている。陰嚢の中はもう空になっているはずなのにだ。
「ど、どうして……っ、止まらない……!?」
「くくっ、わからないようだな、ジョゼフ」
汗で前髪を額に吸い付かせているスペルビアがその動揺を見抜いた。
「我 の気は少々特殊でな……。なに、たいしたことはない。ただ、我の発する気を受けた者は危機に対して愚鈍になってしまってな……逃げようだとか、後退だと か、そういったことが一切できなくなるのだ。逃走本能の鎮圧だな。普段は戦場で自軍の兵士を従えるために使っているが……この状況でも、ありだろう?」
「そんな――」
「以前、お前が我に腕を切り落とされたのも同じ理由だ……お前は逃げようとする意志を知らず破壊されていたのだよ。そうでなければ、力及ばぬと判っている相手を迎撃なぞしないだろう?」
スペルビアの前に立った時点で。あらゆる者は逃げ出すことができなくなる。出会ってしまったときに人は死を覚悟しなければならないのだ。
まさに、恐怖の権化と呼ぶにふさわしい理不尽の象徴。
「さあ、……来い」
「う、うわあああああああっ!」
ぐっ、と引き寄せられ、ジョセフは再び膣の中で射精した。
量は衰えることを知らない。多量の精液がスペルビアの膣に注ぎ込まれていく。なのに、ジョゼフの腰は前進を続けていた。
「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛ァァァ――――!!!」
精を噴き出しても止まらない刺激に絶叫した。脈打っているペニスに纏わり付く襞、その中を突き進むことによって倍増する快感に脳内で神経がいくつもはじけ飛んだ。眼窩の奥で火花が散る。
「ほぅら、ようやく半分! まだまだ行くぞ、そぉれ!」
吐き出した精液のせいで滑りのよくなった膣をペニスが一気に突き進む。
射精が終わらぬうちに、ジョゼフはまた絶頂する。最早止まることなく噴き出し続ける精液。
「あっはっはっはっは! 命諸共総て吐き出してしまえ!」
哄笑を上げて、ついにスペルビアがペニスを根本まで呑み込む。子宮と亀頭がキスをして――生きているように子宮が亀頭に食らい付いた。
「あ、ああ゛あ゛あ゛あ゛あ゛ ――――――!!!」
ドプンッ! ドクッドクッドクン! ドッ、ドッ、ドプッ――!
声にならない声を上げて、ジョゼフは何度目とも思い出せない限界に達した。
「ああ、出てる、すごい精の量だ――」
スペルビアの顔が至福で緩んだ。膣内は注がれる精液を吸収しようと何度も収縮を繰り返す。そうやって精を啜る動作すら、中のペニスを弄ぶ暴力的な動きだった。
「あ、あ……」
ジョゼフの躯から力が抜けた。
がくり、とスペルビアの上にジョゼフが倒れる。自分の上にいる白目を剥いた青年の顔を覗き込んだ。
「ん……ああ、死んでしまったか……」
少年は呼吸を止め、事切れていた。動かなくなったジョゼフを見て、スペルビアは残念だと顔をしかめる。
「もうっ! スペルビアはいっつも早いんだからー!」
「貴女が云うことですか、ルクスリア」
頬を膨らませて怒るルクスリアに、ずっと情事を眺めていたアワリティアが呆れて溜息を吐いた。
そんなふたりには目もくれず、スペルビアはジョゼフの首に手を回す。
「死んでしまったか……」
半開きになった唇を自分の方へと引き寄せた。
「〝なら、天国から引きずり降ろさないとな〟」
スペルビアがジョゼフの唇に唇を重ねた。
熱い、濃厚なキス。
吐息を洩らしながら、長い長いキスの末――
「――!?」
ジョゼフが目を覚ました。
それに気付いて、スペルビアが顔を離す。
「え、いったい、なにが……」
意識を取り戻し、眼前にあるスペルビアの顔にジョゼフが動揺した。何が起こったのか理解していない表情を見て、スペルビアは端正な顔に悪戯を成功させた子供の茶目っ気ある笑みを浮かべる。
「くくっ、自分が死んでいたことも気付かなかったか」
「死ん……!?」
「ああ、お前はさっき我に精を総て吐き出して死んだのだ。当たり前であろう。人にあれほど精液を出すことなどできぬ……。お前の命ごと喰らってやったのよ。そして、それをお前に返してやったのだ……」
事態が飲み込めていないジョゼフだったが、ともかく自分の躯が軽くなっていることに気付く。体力が戻っていることは事実だった。
「わざわざ、助けて……?」
しかし、どうしてそのようなことをしたのかは判らずに、ジョゼフは無垢に首をかしげる。人の好意を信じているようなジョゼフの言葉。確かにスペルビアはそれに好意でもって応じた。ただし、スペルビアの最大の愛情表現での好意。
「ああ、そうとも。――さあ、続きをしようではないか。また、〝最初から〟な」
そして、スペルビアの膣がまた搾精を開始した。
「え、あ、――あぐっ!?」
あれだけ出したというのに、スペルビアに生命力を返還されたジョゼフのペニスは最初の硬度を完全に取り戻していた。体調は、万全だった。精神は度重なる快楽の電流で疲弊したままなのに。
「先程は、奥まで入れることしかできなかったからな……きちんと腰を振ってもらおう」
「そ、んな……団長、これ以上は無理です……っ」
「我ら淫魔にとって精液はごちそうでな……淫魔の躯を構成する必須の栄養がたんまりと含まれているのだ。最高の餌を前にお預けを許容できるほど、我が謙虚に見えるか? 我は傲慢のスペルビアぞ」
押し倒されているのはスペルビアの方であるのに、生殺与奪は体勢とまったくの逆だった。
「そ れにの、よく聞くがいい。我ら淫魔は搾精という一点において進化を続けてきた。中には、我の生命返還のように特異な能力を持った個体も生まれている。つま り、今お前は淫魔の生物として何千、何万、いや、何億年という進化の歴史の頂点と交わっているのだ。光栄に思い、快感に翻弄されるがいい」
「や、やめ……うあああっ」
拒絶の言葉に逆らって、ジョゼフは自分から腰を振っていた。精神はもう疲れ切って快感が苦痛でしかないというのに、復活した躯の方からしてみればスペルビ アの中はまさに極楽浄土だったのだ。それに、スペルビアの躯が無意識にジョゼフの腰を振らせるほどに魔性じみているのである。
ずんっずんっ、と ジョゼフのペニスがスペルビアを突き上げる。手加減されているのか、ジョゼフは少なくとも三回までの挿入運動には辛うじて耐えきった。それでも、一瞬気が 緩んだだけで総てを放出してしまいそうになるほど、淫蕩に濡れた蜜壺の熱い膣肉はペニスを貪っている。
三回は耐えても、四回目は下半身に集う射精感を抑えることはできない。このまま腰を打ち込んで復活一回目の射精をしようとしたとき、ジョゼフの背中に柔らかいものが押しつけられる。
「ふたりだけの正真正銘の二回戦だなんてボクが許さないぞー。見てるだけで濡れちゃったんだから、ボクも混ぜてもらわないとね」
褐色の美乳に渇いた精液をこびりつかせたルクスリアが、ジョゼフの背中に抱きついていた。
「なにをいうかと思えば、二回戦? 最低でも一〇回戦はするつもりなのだが」
スペルビアの言いぐさにジョゼフは顔を強ばらせた。最初の一度ですら脳をミンチにされたように疲弊してしまったのに、それを最低でも一〇回は繰り返す?
きっとその頃には、腰を動かすことしかできない肉の人形が転がっているだろう。その未来にジョゼフは背中を粟だたせた。
「そういうわけだ。邪魔をするな」
「邪魔はしないよ。安心して、ボクはこっちの穴を借りるだけだから」
突然、ルクスリアの人差し指がジョゼフのお尻の穴に侵入した。
「あぐぁっ!?」
「わっ、かわいい声をあげるんだね……こっちは初めてかな」
排泄以外のことに使われていなかったアナルをルクスリアの指がこねくり回した。繊細な指という異物がアナルの中でのたうち回る未知の感覚にジョゼフはあられもない声を上げる。
「んふふ、いい具合。これならボクを受け止められそうだね」
ルクスリアがアナルから指を引っこ抜く。穴から指が出て行く時に排泄と似た甘い感覚が背筋を走り抜け、ジョゼフは男とは思えない無防備な喘ぎ越えを洩らした。
ルクスリアの背中でなにかが揺れる。
黒い、ボロボロなマフラー状の物体。それは鎖骨の辺りからでているようにも見えたし、肩胛骨から翼のように生えているとも見えた。マフラーが一気に広がると、蝙蝠の翼のような姿になる。
「淫魔の翼……こうした方がやりやすいから、ね!」
ルクスリアの尾骨から出た尻尾が、彼女の女性器に入り込む。中で捩れ、膣から漆黒の剛直が飛び出した。
黒一色であることを除けば、ルクスリアの秘部から映えたのは立派なペニスだ。小柄な躯には不釣り合いなほどに大きい。
「やっぱり男女の快楽を両方堪能しなきゃだよね、色欲なんて名前を襲名したんだから。それじゃ……ボクも混ぜて貰うよ?」
ルクスリア自身の愛液で濡れて凶悪な光を反射した黒いペニスがジョゼフのアナルに添えられ――貫いた。
「がはっ」
肛門を無理矢理に押し広げるペニスにジョゼフは咳き込む。内臓が中から押し上げられたような不快さと、アナルの中にあるペニスの存在感に頭の中が真っ白なり――
あと少しでスペルビアの中で達してしまいそうなときにアナルに挿入されたせいで、ジョゼフの堤防は一気に崩壊した。
「あ、あああ、駄目、た、耐えられないっ!」
ジョゼフのアナルがぎゅっと締まってルクスリアのペニスを圧迫しつつ、自分のペニスから精をスペルビアの中に流し込んだ。
「うふ、ボクのおちんちんがアナルに挿入されてイっちゃったね。そんなにお尻好きなんだ……じゃあ、もっとやってあげるっ」
射精の余韻さめやらぬままに、ルクスリアがジョゼフのお尻に腰を叩きつけた。何度も何度もアナルを貫かれる。肛門を前後するペニスの異様な感覚とお尻に触 れるルクスリアのお腹の感触ににジョゼフは身もだえた。その間にも、ジョゼフの躯はスペルビアに夢中で腰を振っている。
前と後ろで別々に与えられる快楽。永遠と続きそうな時間に、ジョゼフは世界が自分から遠退いて行くような錯覚を覚えながら、また射精を繰り返す――。
「さて……そろそろのようですね」
唯一狂乱に参加せず、鑑賞していただけのアワリティアが牢屋の外を振り返る。なにやら牢獄の中はにわかに騒がしくなっていた。
「どうやら、来たようですね」
牢屋がこれほどに騒がしくなることは滅多にない。この監獄にいる犯罪者は既に処刑が決まった者ばかりだ。今更抵抗しようとする者はいないのだから、異分子が紛れ込んだと見て間違いはない。
「お相手さしあげますわ……私たちの愛すべき愚か者よ」
牢屋を襲撃した侵入者たちに向けて、アワリティアはひとりつぶやいた。
「――はあ!? じょ、ジョゼフくんが……拉致されたぁ!?」
閉店中のパン屋の中で、少女の絶叫がこだました。
それは牢獄での拷問から数時間遡る。
アンナマリアが広間で断頭台としての使命を果たし、夕暮れが街を血のような朱色で染め上げているとき。
ジョゼフの勤務するパン屋で聞いた事実は、レリアを驚かせるには充分なものだった。
体当たりで勢いよく扉を開けて魔女の家に転がり込んだレリアは、バンッとテーブルを叩いた。
「ど、どどどどういうことなんですかっ」
帰ってくるなり声を張り上げるレリアに、イザベラはうるさそうに片耳を塞いだ。
「どういうことと云われても、なんの話だい?」
「ジョゼフくんのことですよぉ! 軍人に逮捕されたって……どうしてジョゼフくんが?」
「……ああ、しまった。それはきっと淫魔たちの差し金だね。この家、彼女たちに監視されてるんだよ」
「そんなことは知ってますよ! まさか、なんの対策もしてなかったんですか?」
「だって、する必要もないだろう? 別に見られて困ることもしてないし」
「ああっ、もう! 先生はなんでそんなに肝心なところでずぼらなんですか!」
「そんな視線をいつまでも気にしていられるほどの繊細な神経は当の昔にかすれて消えたのだよ。むしろ、そんなに私の躯は美しいかと照れてしまうね」
「だ、駄目だこの変態……」
云って、皺のよった眉間をレリアは抑えた。
ジョゼフ拉致の一報を知ったのは、ついさっきのことである。
最初におかしいと思ったのは、いつもこの家にパンを配達に来ているジョゼフが一向に姿を現さなかったときだった。昼を過ぎてもやってくることはなく、夕刻にさしかかろうしていてもそれは変わらなかった。
夜が明けてから帰宅したものだからパン屋の主人に怒られて配達に行かせてもらえないのではないか、とレリアは考えてみたものの、あの几帳面なジョゼフがそんな簡単に折れるとは思えない。
イザベラは特に気にしておらず調べる気配がまったくなかったので、レリアは不安になって直接パン屋に出向いたのだ。
そうすれば、案の定その不安は的中した。暴行をくわえられて怪我をした店主から、ジョゼフが捕まったと聞かされたのである。
反逆罪、犯罪幇助。どれもジョゼフには似合わぬ罪状だった。あの人なつっこい子犬みたいな顔をした青年が決起するなんて本気で考えているのだろうか。い や、例え反乱の意志などなくとも捕まえてるのが今のこの国である。不安定な国家情勢、少しでも方針に異を唱える者がいればそれが不和となって国内が分裂し てしまう。戦時下においては疑問を口にしただけで、悪なのだ。
そんな体制に、レリアはあきれかえってなにも云えなかった。人間はレリアにとって 愛すべき食料であるが、それでも彼らの不合理さと個人の意識レベルの低さにはほとほと幻滅する。この国を動かしている人間が悉く高位淫魔によって傀儡とさ れていることはレリアも知っていたが、それにしても、ここまで悪辣だとは。
「なまじ自我があるから衝突や主張なんてするんですね……。あたしたちみたいに、個人主義にもなれなくて、しかも数が多いんだから……これだから人間は……!」
「キミの心配しているジョゼフも人間だってことを忘れちゃ駄目だよ? まあ、今回も淫魔が絡んでいるんじゃないかな。多分、ギヨたんに関してだ」
「あ……もしかして」
「そ う、ジョゼフはギヨたんに襲われて唯一生き残った人間だ。だから、そこに何かあると踏んだのだろう。彼女たちにとって、ギヨたんは目の上のたんこぶだ。な にせ、自分たちの狩場に土足で入り込んだ異分子だからね。ギヨたんをどうにかできるなら、そこにつけ込みたいわけだよ」
「だったら、あたしみたいに直接ギヨたんと戦えばいいのに……」
「こ れまでは、ギヨたんの正体すらわからなかったんだよ。だけど、昨日ここに連れ込んだとき、監視の目がギヨたんを捉えて……そうしてようやく誰か判明したん じゃないかな。ほら、ギヨたんって淫魔じゃなくて無機物だろう? 探そうと思っても見つけられないんだよ。人海戦術をとっても人間じゃギヨたんに殺される だけだからね」
「それで、ギヨたんと接点があるかもしれない子を捕まえて、餌にした……ですか。さすが、一国を簡単に手中に収めただけはある……姑息な手段ですね」
この国はわずか三人の淫魔によって支配されている。支配されているという自覚を誰にも与えず、水が土に染みこむようにしてこの国を支配下においた。水の味を知った土は、もうそれなしでは生きていけない。
個人や、極限られた数人に国家という単位が支配されるのは、別段そこまで珍しいことでもない。人間の中にも独裁者なんていくらでもいた。そして、恋に狂っ て破滅した支配者も。淫魔たちも、それと変わらない。いや、そうやって人を狂わせてきた存在こそが淫魔たちなのだ。彼女たちに気づけないのは、そう、影だ からであり、肉欲によって人を虜にするからである。性欲に支配された者は、もう人ではなく動物なのだから。動物を優しく手なずけることは、淫魔にとって苦 でもなんでもなかった。
「さて、そうやってジョゼフは捕まってしまったわけだが……キミはどうするつもりなんだい、レリア」
「決まってるじゃないですかぁ、助けに行くんですよ!」
「キミも随分と甘くなったものだねえ」
「自分の獲物を同族に奪い取られると、淫魔は誰だってこうなりますよ。吸い殺しちゃったらそれまでですけど、自分以外にされるのは癪なんです」
「なんとも重くて軽い愛だことで。で、ひとりで行くつもり? 云っておくが、私は手伝わないよ。面倒だから」
「最初から期待していません。あたしひとりで充分です。監獄の男なんて、全員食べちゃうんですから!」
「そうかい。では無事帰ってこれるよう期待しておこう――」
バンッ、とそのとき扉が勢いよく開けられた。
ふたりの目がそちらを向く。そこには漆黒のドレスを着た少女が息を切らして立っていた。
「……わたしも行く」
夕焼けが沈んで訪れた闇を背にして、アンナマリアはふたりに宣言した。
*
月明かりを受けて、牢獄が黄金色に染まった輪郭を闇夜に浮き上がらせていた。
煉瓦材の不揃いなおうとつによって複雑なパズルの形をした影を作る牢獄。その門には、ふたりの見張りが槍を携え立っている。彼らはこの牢獄の門番だった。
と、いっても。昨今、この牢獄はほとんど利用されていない国立刑務所である。要塞として使用することを視野に入れて建造されただけに堅牢なものの、囚人も大半が出所していた。
そう、大半が、である。
まだこの牢獄には何人かの囚人が投獄されていた。そのために、このふたりのような門番がいるのだ。
しかし、門番のふたりはどんな人物がここに投獄されているのか知らなかった。おそらく、この牢獄を担当している兵士たちで囚人がいる理由を知っている者の方が少ないだろう。囚人たちの世話は専属の人間たちが行っているのである。
専属の人間は、何故か豪勢な料理を囚人たちに振る舞う。その理由を兵士たちは知らない。多分、追求しない方がいいのだろうと兵士たちは弁えていた。もし、 そんなことを知ろうとしてしまったら、きっと次の日には国に搬送されて広場で生首を晒すことになる。断頭台の一刀でもって。
「交代の時間は、まだなのか?」
兵士である若い男のひとりが、隣にいる同僚に尋ねた。
「まだまだ先だぞ。どうせ敵なんて来ることはない、そう肩肘張るなよ。立ってるだけで飯が食える楽な仕事だと思え」
同僚も兵士で、屈強な男だ。年の頃は四〇を過ぎており、無精髭を生やしている角張った顔は、眠そうにしかめられている。落ち着かない様子で訊ねた男とは正反対で、この男にとっては廃棄されたはずの牢獄の警護などという胡散臭い仕事は雑務と変わらないようだった。
「んなこと云っても……」
「むしろ、どうしてそんなにそわそわしているんだ? おれにはそっちの方が不思議なわけだが」
「いや、今日は珍しく人の出入りが多かっただろ」
「多いといっても、近々処刑される予定の囚人がひとりに……女中と高級娼婦に、騎士団長様じゃないか」
「おかしいだろ。組み合わせがバラバラだ。娼婦は囚人が呼んだとして、女中さんはこの牢獄の専属人たちのご同輩だって考えても……囚人を連れてくる組み合わせじゃない。それに、どうして後から騎士団長がやってくる?」
「おれに訊かれてもな」
「なんだか、嫌な予感がする。嫌な予感が……」
年老いた同僚とは対照的に、若い兵士は冷や汗を流し出す。
そのとき、枯れ草が擦れる音がした。
ふたりは弾かれて音の方を向く。不穏な話をしていたためか、門番の槍を構える動きは俊敏。
賊の集団がでたとしてもふたりだけで拮抗できそうなほどに完璧に訓練された所作。
だが、そこにいる者を見て躯から力を抜く。
枯れ草を踏んだのは、幼い少女のふたりだった。
薄着で肌を大胆に晒した焔色の髪をした少女と、腰まで届く漆黒の長髪と黒いドレスを着た少女。ふたりは太陽と月のように対照的で、そしてこの場にはまったくもって似つかわしくない組み合わせだった。
こんな時間でなくとも、この牢獄は街の人間が近づくような場所ではない。そんな場所にふたりの少女がやってきて、門番は戸惑った。
そこへ、にこり、と短髪の少女の方が兵士に微笑んで明るく声をかける。
「あのー、あたしたち、ここの人に呼ばれてお仕事に来たんですけどぉ」
「し、仕事?」
若い門番が反応すると、彼女は頷いた。
「そうですよぉ。あたしはレリアっていうんですけど、夜の相手をしろって云われて来ました」
「ああ、そういえば、今日はひとり娼婦がやってきてたな……」
「あ、それは先輩ですねー。あたしたちも同じ所から呼ばれてきたんですよぉ」
もうひとりの門番が頷いた。
「なるほど……」
確かに、夜中にこんな格好で出歩く女の子など、そういう仕事をしている者くらいだろう。しかも、こんな所までくるのは。
大方、囚人か他の兵士が呼びつけたに違いない。この刑務所には、娼婦とおぼしき者が何人も出入りしていた。兵士たちが控え、囚人たちを捕らえる牢獄としては実に規則の緩い場所だったのである。
レリアを見てそう判断した年老いた門番が黒いドレスの少女の方へと向く。
「そっちの子もか?」
「はい、そうですよー。ほら、ギヨたん、挨拶して」
「……ギヨたんじゃない、アンナマリア」
ぼそっ、と少女が呟いた。小さいが、よく通る声だ。隣の少女と比べて見た目は暗いが、声はどもることもなく自然と耳朶に吸い込まれる。
「ちょっと無愛想な子ですけど、仕事はちゃーんとこなせますからね」
「へえ、なるほど。それじゃあとっとと中に……」
「ま、待てよ。それは無防備すぎないか? さすがに、証明書でも見せて貰わなきゃ信用できないだろ」
臆病な気質から出た言葉だったが、至極当然の意見だった。表向きは閉鎖され、正式な刑務所としての機能を果たしていない場所だとしても、簡単に訪問者を受 け入れることはできない。今日やってきた者たちは全員が身分を証明できるものを持っていたから立ち入りを許可されたのである。
それにレリアは目を大げさに見開いた。
「ええっ、あたしたちそんなの貰ってませんよ!」
「あー、そりゃ仕方ないな。で、誰が君たちを呼んだんだ? そいつを連れてきてやるよ」
「うーん、それよりもぉ……」
レリアは顎に指を当て、年に似合わぬ妖艶な目つきを兵士に送る。
「躯で証明した方がはやいですよね?」
老いた方の兵士に、そういってレリアは抱きついた。
「へえ、それはまた奉仕の精神が旺盛なことで……」
上目遣いのレリアと目があって、ささくれた頬が薄く笑みを形作る。相変わらず余裕のある仕草だったが、目の奥には淫魔の香りによって火をつけられた情欲の炎が燃え上がっていた。
「おいおい、こんなところで……」
突然のことに、残された門番のひとりが慌てて上擦った声を発する。ふたりの兵士に槍を構えたときの名残は最早なかった。
その兵士の服の裾を、アンナマリアが掴む。思わずふりほどこうとして、兵士は少女と目があう。
それだけで、アンナマリアの深淵な瞳に、兵士の意識は吸い込まれるように魅了されていた。
レリアは膝をつくと、男のズボンを脱がしにかかった。細い指先は慣れた手つきで動くと、あっという間にペニスを月夜の下に導き出す。両手の指が絡みついて、芋虫のような柔らかさだった陰茎は膨張した。
両手からはみ出るほどに大きくなった男のペニスにレリアが興奮で頬を赤らめる。
「あはっ、おじさんのおっきい……。娘さんと同じくらいの女の子でもこんなにガチガチにしちゃうんですね」
両手でペニスをゆっくりと擦り、エラばったグロテスクな亀頭を見つめながら訊いた。
男の一物は体格に見劣りしないもので、レリアの小さな手では握っている手の親指と中指が触れられないほどである。しばらく洗っていないのか鼻につく刺激臭 を発するペニスは年相応に使い込まれているようだった。今まで何人の女性の膣をかき回してきたのかわからぬペニスが、レリアの丁寧な手淫によって掌の中で 脈打つ。
「いや、おれに家族はいないんでな。娘なんてこさえる前にかみさんも死んじまった。確かに、子供がいたらお前くらいの年頃か……」
「へえ、じゃあ遠慮も罪悪感もいらないですね」
にこりとして、レリアが亀頭を一度舐めてからそれを口で銜え込んだ。口内に広がる臭いに喉を鳴らして、舌を思い切り亀頭にこすりつける。
ずるり、と力強く尿道ごとなぞる舌。
唾液をまぶしながら亀頭に累積した垢を舐めとるレリアの舌の動きに、溜まらず男も唸った。余裕のあった表情が快感でこわばる。
「う……っ、娼婦も遠慮なんてするんだな……」
「そりゃ、しますよ? だってぇ、もうおじさんはあたし以外ではイけない躯にされちゃうんですから」
「なに……」
何事か言い返そうとするが、直後に下腹部へと与えられた刺激で二の句を紡げなくなった。
唾液をたっぷりと含んだレリアの口が、男の凶器じみたペニスを呑み込んでいた。顎は外れそうなほど開かれ、亀頭が喉の奥を突いている。それでも入りきらないほど、男のペニスは大きかった。
しかし、レリアは苦悶の表情は浮かべない。大好物を頬張っているように、一心不乱に舌を動かした。
「んっ、んふっ! ちゅ……はぅ、あん……んっ」
亀頭を締め付ける喉奥の感触は膣と同じで、舌と頬肉、口蓋は女性器にはない感触でペニスを責め立てた。くるくると陰茎をなめ回す舌と、唾液で濡れたすべすべの頬肉が雁首を愛撫する。上顎の細かいくぼみはまるで襞となってペニスを擦った。
「お、おおおお……っ」
「ほら、気持ちいいれしょう? もっとあたしで感じてね、――お父さん」
男のペニスを口から離さずに、レリアは茶目っ気たっぷりに云った。
少女は何度も何度も頭を上下させてペニスを刺激する。上目遣いに男を見る目は献身的で、介護されているような気分を相手に与えた。
「ここ、こんなに膨らんで苦しそう……早くレリアで気持ちよくなってね」
髪を揺らしながら、少女は陰茎に唇を這わせ、肉の間に隠れた汚れひとつとして見逃さんとする執拗な丁寧さでペニスに吸い付く。
「娘……娘……」
「そうだよ、レリア、お父さんのためにがんばるよ?」
くすっ、と微笑んでレリアは我慢汁でだらしなく濡れたペニスをしゃぶる。
男は徐々に快感で意識が朦朧としてきた。靄がかった視界はレリア以外なにも見えなくなる。
「お父さん……お父さん……」
何度も呼びかけられる、淫靡に巨大な魔羅をなめ回す娼婦。――いや、愛娘。
急激に男の中で背徳感という名の快楽がわき上がった。
何度も女性を鳴かせたペニスを一生懸命に気持ちよくしようとする娘であるレリアの姿と与えられる快楽の凄まじさに、男はこみ上げるものをとめることができない。
「ああ、駄目だ、駄目だ、レリア……それ以上はもう……っ」
「我慢しちゃう方が躯に毒だよ。だから、ねえ。早く苦しいの全部出しちゃって……この中にあるの全部レリアに」
小さな手が男の陰嚢を包み込む。人肌のぬくもりが冷え切ったそこを暖める。娘に抱きしめられたと錯覚するぬくもりが躯を包み込み、男は親身な奉仕によって絶頂を迎えようとしていた。
「ここにある精液、全部あたしに頂戴……他の人にあげてた精子、全部」
ペニスを銜えながら淫蕩に誘惑してくる娘に、男は理性を忘れた。
「イって……お父さん?」
「う、うおおおおおおおおおおおおおっ」
びんっ、と跳ねてレリアの口から飛び出したペニスはその勢いのままに射精した。
溜まっていた白濁が鉄砲水のようにレリアの顔にぶちあたった。
「あふっ」
眉間に当たって鼻をなぞり落ちていく白い粘液。青臭い精液を男は何度も娘の顔に吐き出した。
熱い白濁液に顔を汚されながら、レリアは陶然とする。
「すごい……一杯でてる」
顎からしたたり落ちる精液を手で受け止めながら、レリアは口元にたれてきた精液を舌で掬いとると喉を鳴らして呑み込んだ。
「臭いも味も、とっても濃いよ……娘のあたしに興奮してくれたんだね? うれしい……」
肩で息をしながら呆然と見下ろしてくる男に、レリアはほほえみかける。
「でも、こっちはまだこんなに元気だね」
唾液をすり込まれてマスケット銃のように光るペニスにレリアが触れた。指の刺激に男は息を呑む。
「じゃあ、まだまだしてあげる……」
そういって、レリアは男の腰に体重をかける。射精直後で気が抜けていた男はあっさりと地面に尻餅をついた。
レリアは立ち上がると、スカートをつまんで下着姿を男に見せつける。ショーツはじんわりと湿っていた。
指をショーツの間にいれて、ずり降ろす。すると、片足を上げて脱いだショーツを男のペニスに落とした。
レリアがショーツの上からペニスを握り締める。想定外の光景に、男は釘付けになった。
「うふ……女の子の下着って布がすべすべして気持ちいいんだよ?」
その手がショーツごとペニスを掴んだまま、ぬるく動き出す。
しゅっ、しゅっ、と先程までレリアの着ていたショーツがペニスを包み込んでなで上げる。上等なきめの細かい布の縫い目ひとつひとつが、敏感となったペニスにはわかった。
娘の愛液でしめったショーツが男の精液を吸い取りながら、ペニスを拭っていく。その倒錯的な状況は、ますます男のペニスを大きくさせた。
「ああ、そんなこと……娘の下着でなんか……」
「いいんだよ、遠慮しなくても。お父さんがあたしの下着に興奮したって……嫌だなんて思わないよ? だって、こすりつけられただけで、こんなに気持ちよさそうなんだから」
わざわざ口に出すレリアに、男は嫌が応にもその異常な状況を脳裏に刻みつけてしまう。
気持ちよくなってはいけない、と理性が歯止めをかける。その焦りが、男の性感をよりいっそう高めた。
「お父さんのおちんちん、あたしのパンツの中でどんどん硬くなってるよ。やっぱり、気持ちいいんだよね、娘のパンツでこすられちゃうのが」
「あ、あああ……!」
絶望的な表情になる男に、レリアは一押しとなる悪魔の誘惑をした。
「あたしのパンツの中で、|射精|(だし)しちゃえ」
「う、うおおおおおっ!?」
ショーツの中でペニスが爆発した。
どぷんっ、どぷんっ、とペニスが射精する。
娘の下着の中での射精の快感が、男の脳天からつま先までに背徳の稲妻となって駆け抜けた。下半身が震えて、精嚢が作り出したありったけの精液を吐き出す。その激しい精液の勢いに、愛液に濡れていたショーツが風船のように何度も膨らんだ。
心ここにあらずといった雰囲気で射精の快感に酔っている男から、レリアはショーツを取り上げる。
人差し指と親指でつまんだショーツは精液をたっぷりと吸い込んでいて、最初とは比べものにならないくらいに重い。精液をしたたり落ちさせるショーツをレリアは顔を赤らめた。
「もうっ、こんなに出しちゃって……。これじゃあ、あたしのパンツが妊娠しちゃうよ」
はむっ、とショーツを銜えて精液を吸うと、すぐに放り出す。
「どうせ妊娠させるなら、こっち……だよ?」
膝立ちになったレリアは両手でスカートをまくると、うっすらと産毛のような毛しか生えていない未成熟な女性器を男の前に見せつけた。そうやって成長しきっていないものであるのに、赤々とした秘所は男欲しさに濡れた口を開いている。
レリアは男の首に腕を絡みつかせながら抱きつく。お互いの息がかかる距離で見つめ合いながら、ゆっくりと腰を下ろした。
二度の射精を経ても頂点を向いたペニスに女陰が触れる。
「ん……っ」
吐息を洩らしながら、レリアはそのまま腰を沈めていく。
幼い少女の躯が受け止めるにはあまりに大きなペニスは、少女の躯を引き裂いてしまいそうだった。男は止めようとしても、亀頭を圧迫する膣口の刺激によって声が詰まった。
「ん……んっ!」
ぐっ、とレリアが腰に力を込める。そうすれば、愛液に濡れた膣が亀頭を呑み込んだ。
「あ、ひゃあっ!」
「うぐっ、ああ……っ」
「お父さん、苦しい? でも、入ったよ……おちんちん。もっと、奥まで、きて……」
痩躯を揺らして、レリアはさらに腰を埋めていく。一度入り口に入れば、後は奥へ奥へとペニスを導いた。
全身に珠の汗を浮かび上がらせて、レリアの躯がペニスを奥まで呑み込む。
「ああっ! 入った……奥まで、お父さんが来てるよ……すっごくおっきいのがっ」
男の首に抱きついたまま、レリアは苦しげな顔で嬌声をあげた。
己の一物によって目と鼻の先で悶える娘の姿に男の中で完全に箍が外れた。
レリアと唇を重ねる。舌と舌を絡める蕩けるほどの深いキス。
ふたりは興奮に昂ぶって、向かい合いながら獣みたいに相手の口を求める。その対面して座り込んだ状態のまま、ふたりは腰を振った。
「ふっ、んっ、ああっ!」
レリアの白い肌が何度も何度も男の腰を叩きつけられ、赤く腫れ上がる。その痛みすら感じないのか、レリアも夢中になって腰を振っていた。
ぎゅうぎゅうにペニスを締め付ける膣は、その襞を余すところなく肉棒に絡みつかせる。愛娘の熟れた蜜壺の心地に、男の頭の中は完全に真っ白になっていた。 もう、娘のこと以外なにも考えられなかった。自分のペニスから子種を絞り取ろうとする女としてのいやらしさに意識は埋もれていった。
「お父さん……頂戴! お父さんの精子頂戴! いっぱい、いっぱい精液注いで!」
狂ったような懇願は興奮を衰えることのない速度で空へと誘っていく。
男はレリアの、娘の腰を掴んで突き上げる。ペニスに絡みついてくる膣の感触は今まで抱いたどの女よりも、妻よりも遙かに馴染んでいた。このまま肉棒と一緒に躯が溶け出してしまいそうな暴力的な快感。
「ああ……っ、あああああああがああああああ――――ッ?!」
耐えられようわけもなかった。
娘の膣内で男のペニスが精液を吐き出した。精子をたっぷりと含んだ精の塊を子宮に撃ち出しながら、男は腰を止められない。この娘の躯が何よりも愛おしい。
射精しながら与えられる快楽に狂った男のペニスは止まることのなく射精を続かせる。
男はとっくに人間らしい思考を放棄していた。今はもう娘の躯が与えてくる極上の快楽を享受するだけだった。
「あは……ごちそうさま……お父さん?」
全身に広がっていく精を満喫して、レリアは動かなくなった男に妖しく語りかけた。
「ふう、まずひとりっと」
ん、と息を吐きながら腰をあげたレリアは満足気に深呼吸をして男から離れた。門番の男は地面に倒れ、もう身動きひとつとらなかった。
「ギヨたーん、そっちは……」
レリアはアンナマリアたちの方へと振り返り、一度言葉を詰まらせる。
「……大丈夫、だったみたいですね」
漆黒のゴシックドレスをまったく乱していないアンナマリアがそこに立っていた。彼女の足下にはもうひとりの門番が倒れている。レリアに弄ばれた門番と同じ末路をたどったことは想像に難くなかった。
衣服をまったく乱さずに相手を倒す、その手際の良さは以前のアンナマリアにはなかったものである。これまでは躯の並外れたスペックで相手を圧倒していただ けなのに、そこへ技量が追従している。行為に慣れた、という言葉だけでは済まされない。前日と今日では、まさに別人だ。
成長というよりは、並外れた環境適応能力による技能の吸収と云った方が正しい。その生態にレリアは期待と不安がない交ぜになった感情を抱く。続いて、嫉妬。
「……って、なに考えてるんですか、あたし」
頭を振って感情を追い払う。別に、アンナマリアに嫉妬する要素はない。そのはずだ。
レリアは淫魔で、だからひとりの男に執着しすぎるといったこともないのである。だから、断じて嫉妬する原因は彼が原因ではない。自分に言い聞かせながら、アンナマリアに声をかけた。
「この門番の人から鍵見つけましたよ。ホント、管理がずさんですねぇ……だから、はやく行きますよぉ」
「……わかった」
口を尖らせたレリアに声をかけられてうなずき、足を踏み出す。
それが、急激に力を失う。足から力が抜けて、アンナマリアは地面に膝をついていた。
「――っ」
アンナマリアは頭を抑えて苦悶に声を洩らす。
「ちょ、ちょっとギヨたん? どうかしたんです?」
さっきまでの不機嫌さはどこへやら。いきなり倒れたアンナマリアに、レリアは慌てて駆け寄った。
しかし、アンナマリアは首を振って差し出される手を断ると、おぼつかない足取りで立ち上がった。
「別に、なんでもない。ちょっとつまずいただけ」
「つまずいたって、そんな感じじゃ……」
それに、とレリアは指摘できないことを心の中で呟く。
――顔、真っ青じゃないですか。
「なんでもない……本当になんでもないの」
顔を背けて、アンナマリアは門へと歩き出す。その言葉が嘘であることは誰の目にも明かだったが、頑なに否定する彼女にレリアはこれ以上追求することができなかった。黙ってアンナマリアの背中に続く。
レリアが門の錠前に鍵を差し込むと、カチリと音を立てて解錠を知らせる金属音が落ちる。ふたりが分厚い木の門を押せば、蝶番を軋ませながら門は開いた。
壁にかけられたランプの明かりで橙色に照らされた、闇の沈殿する牢獄の中。
門の開く音に反応したのか。通路に人の気配が集まってくるのをレリアは感じた。
牢の見た目に反して、思ったよりも常駐している人の数はずっと少ないようだ。それでも、牢獄ひとつを相手どるのは並大抵のことではない。
男たちの気配に、レリアは興奮で唇をなめる。
「なにもないっていうなら……行きますよ、ギヨたん。全員、吸い取っちゃいましょう」
「やってみせる」
こうして牢獄ひとつを陥落させるべく、レリアとアンナマリアは通路の奥から現れる男たちに向かっていった。
牢獄といっても、ここは既に廃棄目前の場所であるようだった。
「ふう……これで、えっと、何十人目でしたっけ」
まあいいか。と自分のつぶやきに結論づけて、レリアは自分の掌で果てて倒れた男から離れる。彼女の背後にある通路には死屍累々と精液を吐き出した男たちが床に伏せていた。
乱れた服装を直そうともせず、控えめに膨らんだ胸を露出したまま、レリアは手についた白濁液を舐めとる。精液に含まれた多量の栄養素は、淫魔の躯に馴染み易い。そのため、摂取するだけで全身に活力が漲った。
「こんなに精液を搾ったのは何年ぶりですかねぇ……質より量も悪くないです」
レリアは秘所から床に流れおちる精液を手で受け止めて、舌で舐める。幼い躯を精液まみれにしてのそんな仕草は、男を妖艶で幼い魅力の虜とするにはあまりあった。
「ん……んっ」
声の方にレリアが振り返ると、そこでは四つん這いになったアンナマリアが後ろから男に突かれていた。
フリルをあしらった黒いドレスのスカートをはしたなく捲り上げられたアンナマリアは、白い臀部が赤くなるまで男に腰を叩きつけられている。何かに取り憑かれたように男が少女の膣にペニスを出し入れすると、漆黒の長髪が揺れて甘い芳香が漂った。
「おおあ……ぅあああああっ!」
絶叫して男がアンナマリアの中に精液を吐き出した。
そうして、糸が切れたマリオネットのように男は仰け反って倒れる。白目を剥いた男の下半身は痙攣しながらアンナマリアの膣に精液を一滴残らず吐き出した。
「は、あぁ……んんっ」
アンナマリアは立ち上がりながら男の一物を引き抜く。成長しきっていない未成熟な性器には渇く間すら許されない愛液と精液の混じりあう混合液がべったりと付着していた。
さすがに体力のある兵士たち、それも砦兼牢獄にいる全員を相手にしてしまえば、急激に成長しているアンナマリアですら消耗を余儀なくされた。これが国にい るただの市民であるならいくらでも相手にできるのだが、そこは戦闘訓練を受けた人間であるだけのことはある。なにをするにも力強い限りだ。
さらにアンナマリアが不利な点をあげるとするなら、淫魔であるレリアと違って精液での体力回復が望めない点だ。栄養源にはある程度なるものの、淫魔のような急激な回復ではない。人間のそれの範疇である。
「そろそろ限界ですかぁ、ギヨたん」
「……まだまだ、問題ない」
からかう声音のレリアの言葉を突っぱねて、アンナマリアは廊下の先を行く。レリアもその一歩後を続いた。
ふたりがこの牢獄にやってきてどれほどの時間が経ったのか。疲労はしているものの、ふたりの手腕は男なら舌を巻いて手も足も出せないほどで、既にほとんどの兵士らしき者たちを撃退していた。
レリアとアンナマリアの靴音が廊下に反響する。人数を狂わせそうな跳ね回る音は不気味だ。
そこでふと、レリアがアンナマリアの背中を見る。
ここまでは休むことなく男を手玉にとっていたためになにも聞くことができなかったものの、こうして小休止を置いてみるとレリアの中で疑問が首をもたげ始めた。
どうして、アンナマリアはここにやってきたのだろう?
レリアがこの牢獄に来たのは、云うまでもなくジョゼフが捕まってしまったからである。彼に対してどんな感情があるかは一先ず置いておくとしても、知り合いが同族に不当な拉致を受けたとあっては納得いくわけがない。
ただ、アンナマリアにはどんな理由があってここにいるのか。国家殲滅の復讐をかかげるほどの断頭台である彼女が、人を助ける道理がいったいどこにあるのだろう。
「どうして」
「ん……?」
「どうして貴女はここに来たんです?」
返答はなかった。云いあぐねてでもいるのか、アンナマリアは沈黙している。
「貴女がジョゼフくんに執着する理由が、あたしにはわかりませんよ」
答えが返ってくるのを待たずに、レリアは踏み込む。
「今朝だって、別れるときに喧嘩してたじゃないですか。しかも、原因はジョゼフくんにも結構ありますし。わざわざ自分を危険に晒してまで来るようなことじゃないでしょう」
「レリアもここに来てる。どうして?」
「あたしの話はしてません」
聞き返されてもレリアは動揺しなかった。心が巌のように硬くなっていた。
だから、遠慮無くアンナマリアに踏み込める。
「もしかして、自分の好きな人の弟だったから、なんて。そんなことのためだけなんです?」
「……っ」
何事か言い返そうとして、結局アンナマリアは意味のある言葉を紡ぐことができなかった。図星だったのか、どう返せばいいのかわからなかったのか。レリアの追求にアンナマリアは無力だった。
「まあ、淫魔のあたしが云うのもなんですけど。もし別の男のためにジョゼフくんを助けて満足しようっていうんなら、今すぐ帰って欲しいですね。正直云って、目障りです」
「それは、その」
初対面からしてふたりは良好な関係とは言い難かったが、こうしてはっきりと拒絶の意志を見せられたのは初めてだった。アンナマリアは人と仲良くしようだなんて一切考えていなかったが、こうして面と向かって宣言されると予想以上に衝撃を受けてしまう。
それとも、衝撃を受けてしまうほどに今の自分は心に隙があったのか。
「……教えて。レリアがジョゼフを助けにきたのは、なんで」
今度は話を逸らすためのものではなく、純粋に知りたかったからアンナマリアは訊ねた。それがレリアにも伝わって、彼女も誤魔化すことはしなかった。
「そうですね……えっと、うん、……もうっ、どうしてあたしまでこんなに恥ずかしいこと思わなきゃいけないんですか」
「なに?」
「彼を、あー……放っておけないからです! これ以上云わせないでください!」
さっきまで平気で男たちを弄んでいた様子からは想像もつかない初心な反応をレリアは見せた。そんな様子だけで、アンナマリアにも充分意図することは伝わった。
「そっか……」
頷いて、またしばらくアンナマリアは黙った。といっても、いつ誰がやってくるかわからない状況である。黙っていたと云ってもものの数秒程度だ。
「わたしが来たのは、レリアの云ったような理由もあるの。もういないあの人の面影を見たから、それで、ここまで来ちゃった」
「なら……」
「でもね、それだけじゃないよ」
アンナマリアはレリアの言葉を遮る。
「あんなことを云ってくれたのは、初めてだったから。迷惑だと反発しちゃっても、あんなに優しい言葉をかけてくれたのは……本当に初めてだったから。しかも、わたしのせいかもしれないなんて知ったら、もういてもたってもいられなかったの」
アンナマリアはジョゼフとの口論を思い出す。なにも知らないで、という怒りは今もある。一言どころかもっと文句をいってやりたいと思う心情はずっと残って いる。けど、それを伝えられないでずっと胸にわだかまらせておくのは嫌だったし、それに、嬉しくなかったと云えばそれも嘘になるのだ。
断頭台か ら人になれるようになったとき、アンナマリアに味方と呼べる人はいなかった。気を一時でも許せる相手もおらず、愚痴や不安をこぼせる場所もない。自身の裡 に溜まるフラストレーションを発散させる手段を一切持っていなかったのだ。箱の鼠と一緒で、暗い世界でひとり蹲っているしかない。
自身を実体化 させた魔女イザベラとて、面識があるだけで味方と呼ぶには分不相応である。彼女はトリックスターで、観察者だ。舞台の仕込みをする機械仕掛けの神であり、 自分の用意した世界で役者がなにを演じるか楽しむ観客なのだ。人の形をしていながら、雲の上にいるような存在。頼ろうなどと安易に思えるわけがない。
国家殲滅なんていう思想がそれに拍車をかけて、アンナマリアはいつだって孤独で、自分だけが唯一信用できる存在だった。
なのに、あんな言葉を。あんな顔でかけられてしまったら。どうしたらいいのか判らなくなってしまったのだ。
「わたしのやっていることとか、相容れない相手だっていうのは判ってるの。でも、このまま何も出来ないで終わってしまう方が……ずっと嫌だった」
「まったく、断頭台っていうのはそんなに不器用でつとまる仕事なんですか? 呆れちゃいますよ、ホントにもう……」
レリアは苦笑いを浮かべた。ただ、今までのように含みはない、清々しさすらある苦笑だ。
「それともうひとつだけある」
「へえ、それはなんです?」
「直接わたしを狙ってこない腰抜けたちの腰を本当に抜かしてやろうかなって」
アンナマリアがレリアを振り返って、愉快気に微笑んだ。そんな彼女が面白くて、レリアもつられて噴き出した。
「あっはは! 意外と大胆なこと考えてるんですね、ギヨたん。いいですよ……ならそれにあたしも乗らせてもらいます。人の獲物に手を出す奴は、馬に蹴られて地獄に落ちろ、です」
「勝手にすればいい。あと、最後にひとつだけ」
「はい?」
「ギヨたんいうな」
ふたりはさらに奥へ奥へと進んでいく。兵士たちは粗方蹴散らしてしまったのか、あとは静かなものだった。
「それにしても、これはいったいなんなんです?」
歩みを止めないで、レリアは左右にある牢屋を見回した。
鉄格子の中はほとんどが空だったが、たまに囚人が投獄されているものがある。
真新しいシーツのベッドと、敷居で隔離されたトイレ。しかも牢の中はそこそこの清潔さを保っている。この国の人間はあまり清潔にしようという意識の薄い人種である、とレリアは認識していたので、きちんと掃除されている囚人の居住環境には違和感があった。
牢の中にいる囚人たちは、どれも大人しい。場に似つかわしくないふたりを見かけても眉ひとつ動かさなかった。ただただぼんやりとしている。
「……まるで、ペットの小屋みたい」
アンナマリアが、その不気味な光景の感想をつぶやく。
「あながち、それ、正解かもしれませんね」
周囲を見渡しながら、レリアは賛同した。
「おおかた、淫魔たちが廃棄予定の牢獄を使って食料庫としているんでしょう。生かさず殺さずの愛玩具。まさしくペットですね」
「悪趣味」
「その通りで……って、なんでそんな目であたしを見るんですかぁ!? 同じ淫魔でもしませんよ、こんなこと!」
疑いの眼差しで見られて、レリアは慌てて反論する。
ガチャッ、とそのとき金属が擦れる音が弛緩した空気を震わせた。
ふたりが身構える。
周囲にあった牢屋の鉄格子が開いていた。
中から、おぼつかない足取りの男たちが現れる。
虚ろな目をした男たちだったが、どれも躯つきは囚人とは思えないほどしっかりとしている。
現れた囚人の数は、八人。ここまで兵士たちを打ち破ってきたふたりにしてみればたいした数字ではない。
「伏兵、ってところでしょうか。この程度で止められると思われるなんて、あたしたちも舐められたものですね」
「関係ない……結局、吸い殺しちゃうんだから」
「あはっ、それもそうですね!」
自分へと手を伸ばしてきた男の腕を掴んで引き寄せると、レリアはそのまま唇を奪った。柔らかい唇を触れさせ、舌を入り込ませる。口の中で動き回る小さな舌に、男の背筋がビクンと震えた。
「キスは得意なんですよ。みんな、すぐにイってがっかりさせないでくださいね?」
くすりと笑って男を誘うと、四人の男がふらふらと蜜へ近づく蝶のようにレリアに群がっていく。
残りの四人は、なにもせずともアンナマリアの方へと吸い寄せられていた。
「……瞬殺してあげる」
挑発的な笑みを浮かべて、アンナマリアも男たちを受け入れるように両腕をゆるゆると開く。例え妖しげな者たちであっても、相手が男ならもう負ける気がしていなかった。
男のひとりがアンナマリアを背中から抱きしめる。手がドレスの上から薄い胸を撫でて、お腹の方へと降りていく。意識があるのかどうかも端から見れば定かではない男の手の動きは、それでも女性に慣れたものだった。
アンナマリアの口から吐息が洩れる。
「えっ?」
躯が反応したことに、彼女は自分でも驚いた。男からの愛撫で感じたことは今までなかったのである。
動揺している間に、三人の男の手もアンナマリアを捕まえていた。
男たちの手のひとつが下半身にのびた。スカートの中にいれられた手が秘部をなぞる。ショーツ越しに這っていく指の手つきに、肩が跳ね上がった。
「ひゃっ!? な、なにこれ……」
その疑問に、同じく快感で躯をよじらせるレリアが答えた。
「う……ちょっと油断してました。この人たちは淫魔たちのペットなんです……彼女たちを悦ばせるための方法を骨の髄まで叩き込まれているんでした! それこそ、性技以外のことは忘れてしまうくらいの勢いで!」
アンナマリアのショーツを下げて、男の指が小さな割れ目に入り込む。与えられた刺激に、躯が前に傾いだ。
「ふぁっ! そ、そんな……それだけでこんなに簡単に……?」
「い、 淫魔と何度も交わったら嫌でも巧くなりますよ、しかも覚えさせることを前提にしていたら。快感に耐性までできちゃって、生半可な刺激じゃ感じなくも……ふ つうは淫魔と一回もすれば死んでしまうから考慮外ですけ、ど……ひゃっ、ちょ、ちょっと人が話してるときに手が早……っ」
淫魔であるレリアも頬を紅くして、男の愛撫に声をあげた。
予想外の伏兵だった。ふたりにとっての敵は、あくまでも他の淫魔たち。牢獄攻略の際に躯を重ねる男たちのことは単なる障害であり、いかに時間と体力を温存して突破するか、の計算にいれているものであったのだ。
アンナマリアを囲う男たちが、虚ろな目のままに下半身を露出する。現れた一物はどれも既に勃起していた。使い込まれた凶悪な代物を向けられて、思わずアンナマリアは躯を震わせる。
長い髪の毛を掴まれて、顔をペニスに近づけられた。汚臭を漂わせる肉棒にアンナマリアの視線が集中すると、男は小さな少女の口の中に亀頭を押し込んだ。
「んぐ……っ」
いきなり口内にいれられたモノの大きさで、苦しさに目を細める。その間に、背中側からアンナマリアに抱きついていた男がそのドレスに手をかけていた。ずるり、と果物の皮でも剥ぐようにドレスが降ろされる。ぴんと淡い色の突起をもった、新鮮な裸身がさらけ出された。
わずかな膨らみの胸を男の手が撫でる。正気を保っていないように見えながら、一番敏感なところには触れない動き。今まで無理矢理するか、されるかしてきたアンナマリアにとって、男から焦らされるのもまた初めての経験だった。
「んんっ、ふ……じゅう……っ」
口の中で暴れるペニスと胸を這う手つきに脳が痺れる。アンナマリアが反撃しようする前に、今度は残りのふたりが動いた。
ひとりがアンナマリアの下で寝転がると、その細い腰のくびれを掴む。腕によって引き寄せられる先には、物欲しげに脈打つペニス。
亀頭と女性器が触れて、濡れたアンナマリアのそこは容易く男自身を呑み込んだ。
「んぐっ、んっ、んーっ!」
熱く、硬くなったペニスに跨らされて、アンナマリアの目が大きく開く。口と、腰の下から突き上げられてくるペニス。ここに至るまで相手にしてきた屈強な兵士たちの肉棒とは違った動き。そして、二本だけでは終わらない。
ずっと後ろから抱きついていた男がアンナマリアの小さなお尻の谷間に陰茎をこすりつけた。臀部に触れた熱い肉の感触にきゅっと穴がしまる。そこへ男は亀頭を押しつけ――力尽くで押し込んだ。
「んあふ……っ」
アンナマリアの秘所から流れ出した愛液と、ここに来るまでに受け止めた兵士の精液で濡れていたアナルは男の肉棒を受け入れた。すぐに腰が動き出して、お尻に男の腰がぶつかる。
穴という穴を塞がれたアンナマリアの躯を男の肉棒が暴力的に突き上げた。
自分より一回りも二回りも大きな男に挟まれて腰を振らされ、口内をペニスに蹂躙される。いやらしい粘液の混ざる音と肉と肉がぶつかる音が牢獄の中で反響した。
男の腰の上で跳ねまわる少女の躯に、最後の一本が押しつけられる。いれる穴がなくなったペニスは、亀頭をアンナマリアの小さな胸にこすりつけた。
我慢汁を胸にすり込むペニスを見て、アンナマリアはゆっくりと手を伸ばす。そのペニスを掴むと、首を振って口内の肉棒を吐き出した。
「どうせなら、二本とも……」
ふたつのペニスを掴んで、アンナマリアは一度に両方の亀頭を口にくわえた。
熱に浮かされて口の周りを唾液まみれにしながら、アンナマリアは長髪を振り乱して熱心に亀頭に吸い付く。陰茎の部分は手でしごきあげると少女から与えられる快感にペニスがさらに膨れあがった。
レリアの方も、状況は似たようなものだった。こちらは仰向けの体勢にされて膣とアナルにペニスをねじ込まれ、口で肉棒を慰めている。男の腰が動いて亀頭が膣を掻き分ける度に幼い躯が激しく揺れた。
「う、動きが速すぎますよぉ……そ、そんなんじゃ……」
かすれ気味の声は男たちに届いていないのか、理不尽にも益々腰のペースは増していく。膣肉を太いペニスが掻き分けていき。
「そんなのじゃ……あっという間にイっちゃいますよ?」
レリアがくすりと笑って、口をすぼめながら腰を捻った。頬肉が中のペニスを圧迫し、膣とアナルは捩れて中のペニスを思い切り締め付けた。
瞬間、
どぷっ、どくっ、どくん、と四本のペニスがそれだけの動きで一気に限界へ達した。
二本のペニスが弾丸のように吐き出した精液がレリアの口から飛び出して口周りを生クリームみたいに汚し、顎から首もとへと流れ落ちる。秘部とアナルはきゅっと締まって、ペニスから吐き出され続ける精液を一滴たりとも逃さなかった。
「あはっ、ほらほら、一杯出してくださいね……ペットちゃん?」
淫魔たちに鍛えられた男たち。
忘れてはいけないのは、淫魔によって性に耐性ができているといっても所詮ペットとしてしか使われていないという点だ。
性技が多少巧くとも、飼い主からしてみればかわいいかわいい愛玩動物でしかなく、よって男たちは少女たちにペニスを挿入した時点で既に勝負は決していた。
「ん……イく? ならイかせてあげる……死ぬまで」
アンナマリアはペニスをくわえたまま上目遣いで男たちに微笑むと、陰茎を扱く手の動きを早める。少女の小ぶりな手はマッサージでもされているような適切な力加減でペニスを握り締めて、亀頭を舐める舌と唇は膣と同じ吸い付きで、それに男が耐えられるわけもなかった。
「はい……終わり」
悪戯な口調で、思い切りペニスを握り締め、
二本のペニスが跳ね上がり、アンナマリアの顔に向けて思い切り精子を噴き出した。
目を細めたアンナマリアのからかうような、それでいて冷ややかな面立ちを白濁とした子種が汚す。熱い粘液を顔に吐き出されながら、陰部とアナルを掻き分けているペニスに意識を移す。
今まで適度に緩めていた力を、一息に腰へと込める。急激に高まった締め付けの力は、気付かぬうちに限界付近で留まっていた男たちを簡単に天へと引き上げた。
「イっちゃえ」
騎乗位で腰を振っていたアンナマリアの中に、男たちは精液を注ぎ込まされる。精液を呑ませる側だと思っていた男たちは、いつの間にか精液を捧げる側へと堕ちていた。
「それで……ペットって何回くらいイけるのかな」
「さあ、試してみるしかないんじゃないですかね? ……時間もないので、手早く、ね」
アンナマリアとレリアが目を合わせて、口元を持ち上げる。
いくら女を悦ばせる知恵を身に着けていたとしても、ペニスを相手に許した時点で、男たちはただ搾取されるだけの存在となっていた。いつも、淫魔たちにされているように。
あとには吸い尽くされて乾涸らびた死体が残るのみだった。
服を整えたふたりは牢獄の中を駆け抜けていた。
ランプで照らされた廊下に長い影を作りながら、アンナマリアとレリアは奥へと向かって足を動かす。
「倒すのは難しくありませんでしたけど、絶倫すぎて時間とられちゃいましたよぉ……ほら、ギヨたんももっと急いで!」
淫魔たちの愛玩動物は徹底された体調管理でもされていたのか、吸っても吸っても精が尽きなかったのだ。ただ搾精されて、しかも長い間淫魔たちを悦ばせるた めの状態。まさしくペットと呼んで相違ない。質の良い精を放つものだから、レリアは時間があればもっと楽しみたいくらいだった。
「わたし、運動、苦手なの……!」
息を切らせながらアンナマリアは走っていた。額には汗が浮かび、男たちと交わっているときよりもよっぽど大変そうに見える。
「男の人とはあんなに運動してる子がどの口で云ってるんですか。あたしみたいに早く走れないんですかぁ?」
「それはっ、走ってるっ、じゃなくてっ、飛んでるって云うの!」
レリアが背中から生やしたボロ布のような羽根を指さして声を荒げた。アンナマリアの云う通りで、レリアは宙に浮いて滑空していた。
「あたしたちの業界では、これを走っていると云うのです」
「なんだか釈然としない……」
ない胸を張ってふんぞり返るレリアに、アンナマリアは非難を込めた視線を送った。けど、どんなに不満だろうともレリアの云う通りで、時間がないのだから走 るしかない。断頭台から人の身に変化したアンナマリアは、ひとつの事柄を除き身体能力は人間並なのだ。レリアのような便利能力はない。
急にレリアの顔付きが変わる。むっ、と眉を寄せて、この先の闇を睨んだ。
「この甘い匂いは……ご同輩の気配! ここを抜ければ、きっとジョゼフくんもそこにいるはずですっ!」
闇の奥には大きな扉があった。
ふたりは勢いに任せて同時に扉を蹴り飛ばした。
音を立てて開いた両開きの扉から中へとなだれ込む。
そこは開けた空間だった。廊下が狭いわけではなかったが、ここは壁際に並べられたランプだけでは全貌を照らすことができないくらいに、広い。
アンナマリアとレリアの目に飛び込んで来たのは、広間の中央に立っているひとりの女性だ。
髪の長い、物静かな女性である。露出を恥じるように肌を隠した衣装は聖職者のようで、牢獄には不釣り合いな姿だった。その姿にアンナマリアは意表を突かれたが、レリアはその女性の正体を一目で見抜いていた。
「絶対に気を抜いちゃ駄目ですよ、ギヨたん。あれは淫魔……かなり高位の淫魔、強欲のアワリティア……七大淫魔の、アワリティアです!」」
今までにないほど真剣な表情で警戒心を露わにするレリアに、女性は柔らかい表情で頭をさげる。
「あら、名乗るまでもありませんでしたか。さすがに、同じ淫魔ともなれば名も知られてしまっているのですね。ええ、その通り。私がアワリティアです」
ジョゼフはどうなっているのか気になってアンナマリアは早く動きたくて仕方なかったが、目の前の女性がそれをさせなかった。アワリティアと名乗った彼女の 一挙手一投足、それはゆったりとした遅さであるはずなのに、迂闊に動けないほどの威圧感があったのだ。レリアの云う通り油断をすれば、そのときにはなんら かの勝敗が決している。先程の男たちのような虚仮威しではない恐ろしさがアンナマリアにもわかるほどにアワリティアから発せられていた。
「そして、奥にいるのが色欲のルクスリアと傲慢のスペルビアです。貴方たちが中々やってこないものですから、ふたりとも奥で盛ってますわ」
アワリティアの浮かべた笑みは寒気がするほどに凄惨で、アンナマリアは胸の内側が急激に凍り付いて行くのを感じた。
広間の奥に目を懲らす。暗闇に慣れていた目が、奥の牢で動く人影を捉えた。
「ジョゼフ……っ」
その光景に目を瞠った。
男ひとりと、女性ふたりが絡み合って乱れていた。男はジョゼフで、その顔に生気はない。白目を剥いた男の躯に女性ふたりが群がっている形である。
ジョゼフの上で凜とした整った顔立ちの女性が腰を振っていた。もうひとりの女性はジョゼフの腕にしがみつきながら、胸板に舌を這わせている。
組み敷かれた逞しい躯が震える。女性の中で果てていた。離れていても香ってくるほどの精子の臭い。よく見れば、その牢にいる女性ふたりは精液まみれだった。いったい、何百回と射精すればあそこまで精子で汚れることができるのか、検討もつかない。
「いったい彼も何度目でしょうか、絶頂してしまうのは。もう痛覚どころか、全身の感覚さえあるかどうか。脳の神経も全部引きちぎれてしまっているかもしれませんね」
「離して……はやく離して!」
「そうです、ジョゼフくんを離しなさい! ただの人間を捕まえる理由もないでしょう?」
ふたりの要求に、アワリティアは笑顔のまま応えた。
「それは聞けない要求ですね。彼にはこの場にて、見せしめのためにも果てていただきます。ええ、正しい意味で果ててもらうのです」
「見せ、しめ……?」
アンナマリアの問いに首肯する。
「え え。貴女が、最近この辺りで男を吸い殺している方ですね? 困るのですよ……そういうことを勝手になされるのは。この国はどの施設も組織も掌握しました が、外国の教会に悟られると面倒なことになってしまうのです。負ける気はしませんが、対異端者用の騎士団というのもありますからね」
「だからって、なんでジョゼフを?」
「貴女にとっては、なにがしかの意味がある相手かと思いまして。どうやら、正解だったようですね?」
アンナマリアは答えられなかった。こうして危険をおかしてまで助けに来たのは事実であるし、否定するような理由はない。それに違うと云っても、ジョゼフが解放されることは万に一つも考えられなかった。
「なに、そう睨まないでください。なにも私たちは争おうという訳ではありません。貴女と……そうですね、そちらの同族さんにも提案があるだけなのです」
「あたしたちに提案、ですか?」
アンナマリアとレリアの顔を見て、アワリティアは背後の狂乱には一切目を向けずに会話を進める。
「はい。どうです、私共と手を組みませんか? そうすれば、精を啜るなとはもうしませんよ。ちょうど、この国をまわすのには三人だけでは面倒になっていたところだったので」
予想外の提案に、ふたりは押し黙った。口を開かないアンナマリアとレリアに、アワリティアは言葉を続ける。
「悪い条件ではないと思いますよ。そちらの淫魔も、どうやらあの魔女に下僕として使役されている様子。これを機に下克上でもどうです?」
「それはそれは……魅力的なお誘いですね」
レリアが薄く笑った。その表情を見て、まさか、とアンナマリアは躯を強ばらせる。しかし、そんなアンナマリアにレリアは片目をつむった。
「でも生憎と、あたしは自分の力だけで先生を屈服させてあげるのが夢なんですよ。他人の力を借りて勝っても消化不良で死ぬまで胃が痛くなっちゃいますからねー。だから、お断りさせてもらいます」
そうやって、レリアは笑顔で高位淫魔の誘いを一蹴した。
返ってきた答えに、アワリティアはわずかに表情を曇らせた。
「そうですか、それは残念です。では、ご自身がここでどうなるか……わかっていますね?」
「わかりませーん、なにされちゃうんです?」
明かに格上の同族を相手に、レリアは臆せず挑発する。
「いいでしょう。では、そちらの貴女は?」
アワリティアの目がアンナマリアの方へと向いた。
「その前に、ひとつだけ」
「なんでしょう?」
「さっき〝見せしめ〟と云った。……どうせわたしたちが承諾しても、ジョゼフは殺すつもりだったのね?」
断頭台として生まれてから数年の間、破格の人数を処刑してきたアンナマリアは悪意には特に鋭敏な触覚を持っていた。だから、ずっとアワリティアの言葉が引っかかっていたのである。
その追求に、アワリティアは一切動じずに頷いた。
「ええ、おっしゃる通りです。どちらにしろ、彼はここで死んで貰うつもりでした。たかが人ひとり、わざわざ特別視して生かしておく必要もないでしょう? 彼の代わりもまた、沢山この世にはいますから」
「じゃあ、わたしの返事も決まってる。……お断りよ、貴女のくだらない口車に乗ってやるつもりは微塵もないわ」
「そうですか、それは残念です。……スペルビア! ルクスリア!」
アワリティアが大きな声をあげて淫蕩に耽るふたりの名を呼んだ。
「もう遊びはいいでしょう? 実行させなさい」
「まったく、我はまだ楽しみ足りないというのに……」
「えー! 結局ボクは入れさせてもらってないんだよ!? こんなのあんまりだー!」
文句を云いながらも、ふたりはジョゼフから離れた。スペルビアとルクスリアが離れると、ジョゼフの躯は床に投げ出されて動かない。もうあの状態で生きていると呼ぶことすら正しいのか、言葉の定義が混乱しそうになる。
スペルビアが文句をいいつつも、指を鳴らした。すると、広間の奥から兵士がひとりやってくる。その手には抜き身の剣が握られていた。
スペルビアが、兵士に命令した。
「首をはね、殺せ。苦しませぬよう一刀でな」
さっ、とアンナマリアとレリアの顔から血の気が引いた。
「やっぱりそう来ますよね……! でも、素直にそんなこと許すと思ってるんですかっ!?」
「貴女の方こそ、私たちが素直に邪魔させると思っているのですか?」
アワリティアが酷薄な笑みを刻む。
アワリティア、スペルビア、ルクスリア。どれもこれも一目見ただけで只者でないことはわかった。全員がアンナマリアとレリアよりも強く、そしてそれが三人 も立ちふさがっている。どれもこれも、飛び抜けた淫魔有数の実力者。その三人を突破して人ひとりを助けられるかといえば――そんなの、無理に決まってい た。
抜き身の剣を掲げて虚ろ目でジョゼフへと近づいていく兵士。ひとりだけ残っていたらしい淫魔たちのペットはジョゼフの横に立つと、剣を振り上げた。
このまま振り下ろせば、無防備はジョゼフは躱すこともできずあっさりと首をはねられる。
首を――。
心臓がうるさい、とアンナマリアは思った。
さっきからなにも云えていなかった。まるで言葉を忘れてしまったようだ。人の姿になってまだ日も浅い、人間らしい機能を忘れてしまうのも、らしいといえばらしいな、とくだらないことを考える。
どうしよう――。
汗が全身から噴き出す。興奮からでも、運動したからでもない。ただただどうしようもなく不安で、怖くて、恐ろしくて、躯が涙を流すように汗を噴出している。
嫌な汗だ。こんな機能が人の躯にあるなんて体験するまで忘れていた。こんなに気持ちの悪いものとは思わなかった。
今から駆けだして、間に合うだろうか。
……間に合うかもしれない。
けれど、それも邪魔が入らなければの話。淫魔三人が見逃してくれるわけもないし、そもそも真っ向から戦って勝てる相手ではないと対面して身に染みるほど自覚した。
人間である限り、もうジョゼフを救うことはできない。
首がはねられる。処刑人のように、彼のように。弟もその末路をたどるのだ。他でもない自分の目の前で、そして弟は自分のせいで。
剣が振り下ろされる。
刃は首に向かって一直線に落ちていく。
鋭い振り下ろし。
ああ、でも――自分ならもっと美しく刃を打ち下ろせるのに、とアンナマリアはうそぶく。
人であっても、断頭台であっても、結局人を目の前で失ってしまうのなら、自分の刃で綺麗に殺してあげたいのに。
――断頭台?
ふと気がついて、アンナマリアは笑いそうになった。
そうだ、断頭台だ。
自分がなんであったかを思い出した。
わたしは――断頭台なのだ。
グキッ、と関節の軋む音。アンナマリアは右手の指をかぎ爪のように曲げる。それをレリアが見て、あっ、と声を出した。
そうである。今も人の姿をしていても、アンナマリアは断頭台であり、処刑機具であり、絶対的な死を宣告する理不尽の象徴なのだ。
レリアはアンナマリアと邂逅したときのことをすぐに思い出した。
あのとき、突然建物に亀裂が走った。
まるで、斬撃のような。
まるで、大きな刃物で切ったような。
では、それが刃であったと過程して――その刃はどこにあって、どこにいったのか?
答えは簡単だ。凶刃は常に目の前にあった。誰も気がつかなかっただけで。
レリアは一瞬、アンナマリアの腕が巨大な刃になるのを幻視した。陽炎のように揺れる刃が腕に纏わり付く姿を幻想した。
だが、それは幻覚などではなかった。それこそが、最初から、彼女の真の姿。
アワリティアが息を呑んだ。
その瞬間、アンナマリアは虚空に向かって腕を振るっていた。
一迅の疾風が空を裂いた。
あらゆるものを引き裂いて、一切の命を区別なく処罰して、その名において安楽の死を与える刃が疾った。
剣を振り下ろしていた兵士が異変に気付いて振り向こうとして、躯が動かないことに気付く。
それもそのはずである。
兵士には、既に躯と呼べるものはなく。上半身だけの姿になって、自分の下半身を見上げ――それが最後に見たものだった。
「あ……」
急にアンナマリアの躯から力が抜けて、床に倒れた。
「ぎ、ギヨたん!?」
呆然としていたレリアははっと我に返り、慌ててアンナマリアを助け起こした。
アンナマリアの顔色は悪い。浅く呼吸を繰り返し、目を見開いて自分の躯を抱きしめていた。
「なんだ……今のは?」
スペルビアが怪訝な表情で死体となった兵士とアンナマリアを交互に見る。武闘派として名高いスペルビアは空気の歪みひとつとして見逃さずに一部始終を見届 けていた。故に、アンナマリアが腕を振るった瞬間に斬撃としか呼べないものが空を疾駆して兵士を切り裂いたと正しく認識していた。だが、それがどうして起 こったのかは理解できない。彼女はアンナマリアの正体を知らなかった。
「これは――いけません。ああ、まさか、まだこんなところにまで王の栄光がちらついているだなんて……! 確かに、この私が殺したはずなのに! 息の根を止めたはずなのに! 死者の分際でまだこの私を虚仮にするだなんて……!」
一度も余裕を崩さなかったアワリティアが、頭を抱えて取り乱していた。もうレリアやアンナマリア、ジョゼフのことなど頭の中にはないようだった。
滅多にないアワリティアの豹変に、ルクスリアが目を丸くする。
「ど、どうしたのアワリティア? そんなに血相変えて……おかしいよ?」
「これが驚かずに居られますか! とにかく、一時退却です!」
「えっ、でもあの娘たちは?」
「今はいいのです、ともかく一刻も速く離れなければ……」
「ジョゼフはどうするのだ?」
「置いておきなさい、今追ってこられたらこちらが困ります」
スペルビアとルクスリアは怪訝な顔をしたが、それでもアワリティアの珍しい様子のために頷いた。
三人は他の者に目もくれず舞い上がると、はめ殺しの窓を叩きわって夜空へと消えていく。レリアはそれをなにもせずに見送って、小刻みに躯を震わせるアンナマリアの背中を撫でた。
「ホント、ギヨたんと一緒だと退屈しませんね……」
レリアの軽口に返ってくる言葉はない。いつの間にか、アンナマリアは目を閉じて眠っていた。
「……ギヨたん云うなって、返してくださいよ」
急に不安になって、レリアはアンナマリアの手を握りしめた。
気絶したジョゼフとアンナマリア。逃げ出した高位淫魔たち。
どうやら、自分の知らぬことがあるらしい――。
ただひとつ判ることは、なにやら嫌な予感がするということ。なにかが始まり、終わろうとしていること。
レリアが頭を上げると、窓の向こうに月が見えた。窓という額縁に切り取られたような三日月。
「月は無慈悲な夜の女王……なんて、ね」
三日月は、地上の人々を笑っているように見えた。
第三章/了
「――拙いな」
窓越しに夜空を見上げて、銀髪の女性は物憂げに呟く。
雨が降っていた。
いきなりの豪雨である。
地面を間断なく叩く雨音は家の壁を貫いて、激しく人の鼓膜を叩いた。目に見えぬ不吉なものの存在を信じてしまいそうになるほどの不気味さで、暴力的な雨脚は掃射された矢が地面で跳ねているような音だった。
そんな中でも夜空で輝く三日月は空が笑っているようで、魔女イザベラは眉を顰めた。
「嵐の中を、青ざめた馬が闊歩する。騎手は死の御使いで、人は震えて頭(こうべ)を隠す」魔女は帽子掛けからハットを取って深くかぶった。「そろそろこの隠遁生活も終わりかな。お節介なちびすけもいなくて案外気に入っていたのだけど……」
珍しく感慨深そうにイザベラは溜息を吐く。
突然、家の扉が弾かれた。
蝶番が壊れそうなくらい勢いよく開かれた扉。それにイザベラは驚かなかった。
イザベラは、玄関の向こう側に向かって微笑む。
「おかえり、三人とも」
玄関の前には、全身で雨を受けながら人を背負ったレリアの小さな姿があった。
終章/夢の終わり La fin du reve...
夢を見ていた。
なんでこれが夢だとすぐに気づけたのか、それは簡単な話で。
もうこの世にはいない人がいたから、だからこれは幸せな夢なのだと思ったのだ。
アンナマリアはぼんやりと目の前にいる男を見ていた。
口の周りにだらしなく無精髭を生やしている、くたびれた金髪の男だ。服を油で汚した男は、アンナマリアに背中を向けて熱心に仕事をこなしている。
油を染みこませた布で、刃にこびり付いた血糊を拭っていた。
娘を愛でるように。恋人を撫でるように。大事な機械を手入れするように。何度も何度も布で断頭台の刃を布で拭く。
その男がアンナマリアを見ることはない。だってこれは夢で、アンナマリアは劇を見る観客に過ぎないから。
いや、男はアンナマリアを見ていなかったが、確かにアンナマリアを見ていた。
――あれは、わたしだ。
あの刃は、断頭台はわたしだ、と理解する。そして、自分の手入れをしている男の背中をアンナマリアはよく知っていた。
男の名前を呼ぼうとして、困惑する。
例えこれが夢の中だとしても。過去の再現だったとしても。断頭台の自分ではなく、人間になった自分の方に振り向いて欲しかった。自分から自分へと視線を奪い去りたい、矛盾した嫉妬心に身を焦がされた。
おかしいのはアンナマリアも自覚していたが、それでも気持ちを押しとどめることはできない。できるわけがない。
自分が殺した男だ。もう二度と会えないことは知っている。その理不尽さにせめて反抗しようと、人の身となって人間に報復しようと決めたのだ。
想い焦がれていた、二度と会えないその姿。
だから、自分に目を向けさせなかった。ずっと大事にしてくれたから、こんな姿で生まれることができたと伝えたかった。
なのに。
「 !」
声は意味をなさない。
ああ、そうだ。――私は彼の名前すら知らなかった。
アンナマリアは背中に駆け寄ろうとした。なのに、どんどんと男の姿は遠くなる。
真っ白な光の彼方に消えていく男の背中へ、必死になって手を伸ばす。かすれていく男に手は届かない。
夢から覚めたくない。せめて、せめて、また声だけは、聞かせて欲しいのに。
男の姿はアンナマリアの視界から薄れていく。
その間際。男がアンナマリアを振り返った。
消えゆく姿で、顔すら霞みに隠されている。
「 」
唇が動いた。
なんといったのだろう。
わからない――。
アンナマリアは夢から覚める。
イザベラがレリアにタオルを渡し、三人の水気を取って風邪をひかないように暖め、落ち着いたときには既に夜明けが間近となっていた。
簡単にイザベラが作った暖かいスープをレリアがすする。調理した人間のせいでスープに具はない。味も水よりはマシという程度だったが、冷え切った躯にはそれでも暖かく染みいった。
毛布を被って両手でカップに入ったスープをレリアが飲んでいると、横のソファに寝かされていたアンナマリアが目を覚ました。
濡れたドレスを脱がされて裸に毛布をかぶせられた状態のアンナマリアは、頭を抑えながらゆっくりと上半身を起こす。
「ここは……帰ってきたの……?」
「レリアがひとりで運んできたんだよ」
まだ状況をうまく飲み込めていないアンナマリアに、イザベラが答えた。
カップの縁から口を離して、レリアは頷く。
「ええ、いきなり、ギヨたんは倒れたんですよ。兵士の首を切り落とした途端に。……びっくりしたんですからね」
「ごめん」
「謝られても困ります」
「……ありがとう」
「それでいいんです」
レリアが表情を緩めたのを見て、アンナマリアは恥ずかしくなって毛布に顔を埋めた。よくよく考えてみると誰かに対して素直に礼をいったのは初めてだった気がして、所在なくなり胸がむずむずとした。
落ち着かなくてきょろきょろと辺りを見ていたアンナマリアは、恥ずかしさを誤魔化すためにふたりへ訊ねた。
「ジョゼフは、どうしたの?」
アンナマリアは夢の中に出てきた男のことを脳裏に浮かべて、云ってから唐突に不安で胸がいっぱいになった。
もしかして、結局助けることはできなかったのではないだろうか?
毛布に爪を立てて握り締めるアンナマリアに、イザベラは奥の扉を示した。
「別の部屋で寝ているよ。一番衰弱していたから、ベッドの上さ」
それを聞いて、アンナマリアは自分自身でも驚くほどに安堵してしまった。胸につっかえていた重りがすとんと落ちて、ほっと息を吐く。
「そう、よかった」
ジョゼフは助けることができた。そのことにアンナマリアは表情が緩むことを抑えられなかった。
「……だけど」
と、そこで口を開いたのはレリアだ。
「淫魔の毒気に当てられています」
「毒?」
「前 にも云いましたよね、あたしたち淫魔は精力を増進する体液を分泌できるって。でも、それには副作用がありまして……連続して長時間その体液を吸収すると、 正常な身体機能を損なってしまうんです。麻薬みたいなものですからね。しかも、ジョゼフくんはそれをたっぷりと躯に取り込んでしまったようで……」
「つまり、どうなってるの?」
「ジョゼフくんは、脳機能に障害を負いました。思考能力がなくなってます。生きてはいても、なにも考えられなくなったんです」
弛緩していたところを力の限り殴られたような心地だった。
それでは、まるで――
「生きた、屍……」
レリアは無言で、スープに口をつける。アンナマリアの言葉を否定する者は誰もいなかった。
「そんな……治らない、の?」
「いや、治るよ」
愕然としているアンナマリアの言葉をイザベラが平然と否定した。
「な、治るの?」
「うん。ふつうなら治らないんだけどね。そこはほら、この偉大な魔法使いの力にかかればなんとでもなるよ」
いつもなら悪態のひとつでも突くところだが、今はアンナマリアの目には本当にイザベラが偉大な人物のように映った。
「ただ、それにはひとつ条件があるんですよ」
レリアが云いにくそうに言葉を濁したので、またもやアンナマリアは不安になる。それもまた、なにか副作用でもあるのだろうか。
「なに、簡単なことじゃないか。ジョゼフと性行して淫魔の毒がたっぷりの精液を搾るだけだ」
「そ、そんな方法で?」
「そんな方法とは心外な。いいかい、精液というモノは欲望の原液であり塊なのだから、そこに邪なものを関連づけて一緒に引きづり出すのは実に正当な方法なのだよ。私の術のお陰でそうやって毒気の摘出ができるのだから、むしろ称讃してほしいくらいだね」
方法が意外だったので驚いたものの、悪い方向の話ではなかったのでアンナマリアは胸をなで下ろした。それでも、レリアの表情は依然としてまだ暗い。
アンナマリアがその理由を訊ねようとすると、イザベラが先に口を開いた。
「で、問題は誰がジョゼフの精を搾るかだ」
「……あ」
ようやく、気まずい雰囲気が流れているのかがわかった。
アンナマリアは口をつぐんでしまう。
誰がジョゼフを搾りとればいいのか。別に、アンナマリア以外でもできることだ。イザベラはなんでも出来そうなものだから性技も余裕であろうし、レリアに至っては淫魔だ。どちらも完璧に仕事をこなしてみせるに違いない。
けれど、とアンナマリアば憮然としてしまう。ジョゼフが自分以外の女に搾精されているのを想像するのは、なんというか、気分が悪かった。
自分以外がするのは嫌なのに、だからといって志願するのは躊躇われる。それもこれも牢獄でレリアに告白されたことを思い出してしまうからだ。
レリアはジョゼフに好意を持っている。一方アンナマリアといえば、兄の面影をジョゼフに見ていないといえば嘘になる。訊ねられれば、それ以外の感情もあると断言するが、代換のように見てしまっている節がないわけではなかった。
その後ろめたさのせいで声をあげることができない。
アンナマリアが黙っていると、案の定レリアが沈黙を破った。
「あたしは辞退します」
「え!?」
びっくりして、アンナマリアは思わず声をあげていた。
「ちょっとギヨたん、声が大きいですよ!」
「ど、どうして!? だって、レリアは……」
「忘れたんですか、あたしは淫魔ですよ」
レリアは寂しげに笑った。
「淫魔の毒気を抜かなきゃいけないのに、また淫魔の体液をすり込んじゃったら何があるかわからないじゃないですか……。だから、あたしは駄目なんですよ」
だから、と云ってレリアはアンナマリアの方を見た。
「ギヨたんにお願いします。大変不本意ですけど」
「あれ、私でもいいんだよ?」
「先生はもっと駄目です。色々と駄目です。駄目駄目です」
「やれやれ、手厳しい助手だ」
腕を組んで肩を竦めるイザベラには目もくれず、アンナマリアはレリアのことを注視していた。
「わたしで、いいの?」
「もうっ、いいって云ってるじゃないですか。あたしの気が変わらないうちにとっとと行ってきちゃってくださいよ!」
「……わかった」
アンナマリアは頷いて、毛布を引きずりながら立ち上がった。
そうして、廊下の方へと出て行き扉が閉まると、レリアは糸が切れたように躯から力を抜いてソファに寝転んだ。
「うー、もう、ホントに……」
毛布を抱きかかえて、もどかしそうに足をばたばたとさせた。そんなレリアをイザベラは笑った。
「いやあ、難儀だねえ。珍しくいじらしくて微笑ましいよ、レリア」
「茶化さないでくださいよぉ……。これでも結構本気で悔しがってるんですから」
「ふむ、そうか。ではこういう趣向はどうだい?」
「はい?」
と、イザベラが何事かを耳打ちすると、レリアの表情がみるみると驚きに変わっていく。
そうして、イザベラは悪戯っぽく笑った。
アンナマリアは人の気配のする部屋の前に立つと、一度息を大きく吸い込んでから扉を開いた。
ベッドの上で起き上がっているジョゼフの姿が目に入り、少しだけ動きを止めた。
ジョゼフがアンナマリアを見る。その目には意志の光はない。ただ、音に反応しただけだ。自分がなにをしているのか、自分がなにを見ているのか、そういったことは一切考えられていない。
雨が地面を叩く音だけが暗い部屋の中で響く。アンナマリアはしばらくジョゼフと目を合わせた後、ベッドの方へと歩き出した。
雨雲の切れ目から覗く月の灯りがアンナマリアとジョゼフをほのかに照らし出す。
ベッドの前まで来ると、アンナマリアは自身の躯を包む毛布をするりと床に落とした。
少女の細い裸体が白銀色の灯りを受けて、暗闇の中で浮かび上がる。控えめな胸の膨らみからすべすべとして柔らかそうなお腹、そこからへこんだへそに、まだ毛も生えていない秘部。それらすべては隠されることもなく、月明かりを受けて浮かび上がっていた。
幻想的な姿だった。
アンナマリアは四つん這いでベッドにあがり、ジョゼフへ抱きつくように身を寄せた。
何が起こっているのかも理解していない、赤ん坊のような瞳を覗き込む。息がかかるほど近くから目を合わせて、アンナマリアはささやいた。
「今、楽に……気持ちよく、してあげるね」
急にわき上がってきた嗜虐心のままに唇を奪う。
アンナマリアは相手をベッドの上に押し倒した。いつの間にか、路地裏で押し倒してたときと同じ嗜虐的な思考がアンナマリアの裡にわき上がっていた。
いつもなら惨めに喘がせて果てさせてやろう、と思うのに、今はみっともなく虐めてやろうと思っている。似ているようで、それは相反するものだった。
男を相手にしている淫魔が抱いている感情と同じものだとはまったく自覚しないまま、アンナマリアは衝動に突き動かされるままに相手の舌に自分のものを絡みつかせる。
「んっ……っ……」
獲物に食らい付く獣のように荒くなった熱い吐息が洩れる。アンナマリアの小さな唇は情熱的に吸い付いて、相手の全身を抱擁するように深く繋がる。
いったいキスだけでどれくらいの時間繋がっていたのか。長く長く繋がっていたふたりは、アンナマリアが躯を起こしたことでようやく離れた。
小さな躯で精一杯献身するように、しかしその実相手を虜にする舌技をこなしたアンナマリアの唇はふたりの混じり合った唾液で濡れていて、細い糸が残滓となってお互いの唇を繋いでいた。
ジョゼフに馬乗りになったアンナマリアは、ついに切れてしまった唾液の糸が名残惜しく、自分の唇を人差し指でなぞる。
自然とアンナマリアの小さな口元が持ち上がった。
心臓がドキドキとしていた。胸の中心に火の塊でも現れたのかのように、そこからジンジンと熱が広がっていた。苦しくも、ましてや不快でもない。なにかが物足りない切なさと、全身をほてらせる満足感があった。
頬が紅潮していることが、アンナマリア自身にもわかる。熱くなっているのが自覚できるくらい、その華奢な肉体は興奮していた。
頭の中には、相手を自分のものにしたいという欲求で満ちている。アンナマリアは本来なら断頭台であり、道具が担い手を決めるなど本来ならあり得ざることだ。
いや、道具だからこそ、自分にふさわしい担い手を決めたくもなる。ただ、今まではそれができるような状況でないがために誰もわからなかっただけのこと。
熱く、強く、深く、抱きしめて――自分だけのものにしたい――。
アンナマリアは今まで自分が感じたことのない想いで頭がパンクしそうだった。クラクラと揺れる頭では、自分でもおかしいと思えるほどに正常な判断がつかな い。なんでこんなことを、と動揺する。けれど、そんな冷静な思考もやがて水に溶けるようにして消えていく。人で例えるなら、アンナマリアはアルコールに 酔っているも同然だった。
ふと、自分のお尻の下で存在を主張するものに気付く。
ジョゼフの下半身に座り込んでいたアンナマリアは躯をずらすと、相手の股間部分が大きく膨らんでいるのを布越しに見た。
それでアンナマリアは、自分は直接ここから毒気に染まった精子を搾り取らなければいけないことを思い出した。
大きく膨らんだペニスを服の上から指でなぞる。亀頭の辺りから根本まで細い指が流れ落ち、ペニスが小刻みに震えた。その素直な反応に、くすりと笑う。
「相変わらず、こっちは素直なままなんだね……男の人って」
服の上から肉棒を握って、上下に扱く。アンナマリアの手の動きで雁首を行ったり来たりする皮と亀頭全体を撫でる布の感触にペニスはますます硬さを増した。
「ふふ……じゃあ、一度このまま出しちゃえ」
自分の手で為す術なく感じてしまうペニスが面白くて、アンナマリアは嗜虐心に従って手の動きを早める。直接陰茎に触れられたわけでもなく、服を脱がされる こともなく続けられる手淫。布も合わせて与えられる快楽はその躯にとって未知のもので、意志を失ったジョゼフが我慢できるわけもない。
白い肩を何度も揺らしながらパン生地でもこねるように両手でペニスを扱き上げるアンナマリアの動きに、性感は瞬く間に高められていき。
ぐぎゅっ、と強く掴まれたままに雁首をなで上げられたとき、ジョゼフは限界を迎えた。
どぷんっ、どぷんっ、と内側から何度もノックされてズボンが膨れあがる。熱く滾った精液が布に染みこんでいき、ペニスを握ったままだったアンナマリアの掌にも熱い精の感触が伝わってきた。
「まず一回目……」
まるでゲームの回数を数えるような気軽な口調ながら、その顔は夜空に浮かぶ月のように妖しく笑っていた。
「それじゃあ、二回目……行こうか?」
アンナマリアがジョゼフのズボンを下げる。すると、自分の出した白濁とした液体でたっぷりと濡れたペニスが姿を現した。大きさも硬さも衰えずに、今にもま た爆発しそうなくらいパンパンに膨らんだ陰茎をアンナマリアは優しく握り込む。熱く、粘っこい精液の感触。指に絡みつく感触を不快とは思わず逆に楽しみな がら、ペニスに精液を塗り込むように指を動かす。
精液を潤滑液代わりにして別々の生き物のようにペニスを這い回る繊細な指先の動きに、達したばかりにも関わらずペニスは射精感を高め出した。
人差し指の腹が尿道口を広げながら撫でる。敏感になっている亀頭の上を指が滑っていく度にペニスは激しく脈打った。
その反応と砂糖のデコレーションでもされたようにたっぷりの精液で濡れた亀頭を見て、アンナマリアは唇を舌で舐める。そして、自身の黒い長髪を手で背中に流しながら亀頭を口で呑み込んだ。
口内に広がる苦々しい精液の味と独特の鼻をつく臭いに、アンナマリアは目を陶然と細める。見た目の錯覚通り、それが砂糖菓子の飾りであるとでも云うように頬をすぼめながらペニスに付着した精液を舐めた。
「んっ、ちゅっ、……ん、ふぅうう、じゅ……んふっ」
根本まで呑み込みながら、一回目にたっぷりと吐き出された精液を呑み込む。口を亀頭の辺りまで引くと今度は陰茎を手で責めながら、亀頭を執拗になめ回す。
いつの間にか、ペニスを濡らすのは精液ではなくアンナマリアの唾液になっていた。ジョゼフの体温も熱くなり、息はアンナマリアよりもずっと激しくなる。
アンナマリアの口淫は搾り取るためだけの動きではなかった。もちろん、それもあるが、なによりも相手に気持ちよくなってもらおうという感情が行為を通して現れていた。
アンナマリアは自分の持っている技量の限りを込めて口の中を蠢かせる。幾多の男たちを絶頂させてきた少女が心から行為に没頭しているのだから、それに男が搾り取られないわけもなく。
幼い少女の口から強制的に与えられる快楽の前に、ジョゼフの躯はまたもや屈服した。
バネで弾かれたように腰を浮かせてアンナマリアの喉を突き、ペニスは精嚢に溜まった欲望を噴出した。
「んっ!?」
最初、アンナマリアは驚いて目を見開いたものの、すぐに眼を細める。妖艶な目つきのままに喉を鳴らした。
どくっ、どくっ、どくっ……。
「んくっ、んくっ……はあ……っ」
一分は続いただろうか。長い射精が終わると、アンナマリアはペニスを口から抜いて満足気な吐息を吐いた。
この二回でジョゼフが射精した精子は、既に精嚢に溜まる量を易々と超過していた。それもこれも、淫魔の体液による精力増進効果の賜である。射精を続けれ ば、やがて精子過剰生産と体力の喪失による死が待っている。もっとも、それ以前にショック死してしまう場合もあるが――その毒気に当てられたジョゼフは、 体液に触れていなくとも同等の効果が躯に現れているのだ。
精力を絶やさぬ力により、ペニスは未だに衰えを知らない。高位淫魔による体液の力と躯ひとつで男たちを搾り殺してきたアンナマリアの肉体があわされば、ペニスが萎えることすら許されないのは当然の結果だった。
それに、今やアンナマリアは躯に頼るだけではなくなっていた。
「淫魔の力ってすごいんだ……ここ、こんなにしちゃって。それとも、そんなに気持ちよかったの?」
クスクスと笑いながら囁く。思考能力を失ってしまっているはずのジョゼフの躯が羞恥に悶えるように身じろいだ。言葉に反応したのか、それとも単なる偶然なのか。定かではないが、アンナマリアは面白くなってペニスを指で弾いた。
「次はどんな風にしてあげようかな……、男の人なんだから。きっと、変態的なこと、考えてるんだよね?」
ペニスを刺激されて背筋を震わせているジョゼフを尻目に、アンナマリアはどうやって気持ちよくしてあげようかと考えを巡らせていた。
「そうだ……。自分からしたことはないけど、こういうのは、どう?」
云うなり、アンナマリアは自分の胸を両手で撫でた。ふっくらと控えめに膨れた胸にたっぷりと精液と唾液の混合液を塗りつけて、ジョゼフの腰に腕を回して抱きつく。そうして、てらてらと光る胸をペニスに押しつけた。
胸は成長途上の未成熟なものということもあり、手で包み隠せるほどの慎ましやかな山でしかなかった。そんな乳房でも、弾力がないわけではない。小さいながらもペニスに押しつけられた胸は柔らかい弾力を敏感な神経に伝えていた。
「ん……おっきくないから挟めない、けど……こういうの、好きな人もいるんでしょう?」
少し自分の胸の大きさを気にしながらも、アンナマリアは躯をゆっくりと動かしてペニスを乳房で撫でる。
豊満な胸で挟んだときのような柔らかい胸の圧力はない。
代わりに、未熟な胸を擦りつけるというのはそれとはまた別の快感をジョゼフに与えていた。
アンナマリアの胸は小さいながらも非常に柔らかく、ペニスが沈み込む。さらに、雁首を何度も刺激する乳首。アンナマリアが息を乱しながら躯を揺する度に擦 りつけられる肌は高級な布で撫でられているようで、ぬるぬると少女の胸元を往復するペニスに伝わる感覚に、ジョゼフの躯は何度も腰を小刻みに震えさせた。
「やっぱり、こういうの好きなんだ。ん、でも、そんなに動くと巧く捕まえてられない……」
辛うじてある谷間から滑って外れそうになるペニスを押しとどめようと、アンナマリアはジョゼフの腰に回した腕に力を込める。きつく抱きついてなんとか固定 できたものの、アンナマリアの胸では精液を塗りつけすぎたせいもあり、いつ滑って溢れ出るかわかったものではなかった。
「う……どうして、ちゃんと止められないの……」
別にアンナマリアは人間体の胸にコンプレックスを抱いていたわけではないのだが、こうして乳房による責めで苦戦してしまうといたく自尊心を傷つけられた。さっきまでの余裕がわずかに崩れ、声は焦りで上擦ってしまう。
「もう、駄目ですよー、ギヨたん。力を入れすぎたら逆にこぼれちゃいますよ」
「え?」
唐突なレリアの忠告に、アンナマリアは目を丸くした。声のした隣を見ると、先程までまったく気配も感じなかったレリアの姿があった。月明かりに照らされたレリアはどうしてかわずかに透けてみえるものの、ゆらゆらと燃える焔色のショートヘアは見間違えようがなかった。
「え、え、なんで?」
いくら行為に夢中だったとはいえ、背後で扉が開く音くらい聞き逃すわけはない。そんな音がした覚えはなかったのにレリアが隣にいて、アンナマリアは驚いた。
「ほらほら、それよりもギヨたんは向かい側にいってください。やっぱり独り占めしようだなんて許しませんよ、あたしにだってご褒美はあってしかるべきなんです。はい」
ひとりで納得しているレリアに急かされながら肩を押され、アンナマリアは股の間から無理矢理退けられた。服をはだけ出すレリアを見て、アンナマリアは慌てた。
「ちょっと待って。どうしてここにいるの!? だって……」
自分じゃなにがあるかわからないからって、と続ける前に別の声がアンナマリアの問いに答えた。
「それはなにを隠そう、この私のお陰というわけさ」
いつの間にか、魔女イザベラがベッドに腰掛けていた。ジョゼフの足先に座ったイザベラ、今度も扉の開く音は聞こえていない。しかも、イザベラの姿も透明な 膜が間にあるかのように輪郭がぼやけて見える。さらにいえば、アンナマリアはレリアに押し出されたときにそちらを見たが間違いなく誰もいなかったはずだ。
しかし、イザベラの姿が見えて余計混乱するということもなく、むしろアンナマリアはいくらか平静を取り戻した。
「……貴方がなにかしたんだ。驚くのも飽きたくらいなんだけど」
断頭台であった自分を人間に変えた魔女のことである。イザベラに関しては、なにができても不思議ではない。おそらく、彼女にできないことなどほとんどないのだろう。もし彼女がなにかをおこなわなかったら、それはできないのではなくやろうとしていないだけのことだ。
なので、イザベラには常識的な思考で相手をしていては混乱するだけなのである。元が人ではないアンナマリアは常識など最初から持ち合わせてはおらず、よって短い付き合いながらイザベラの相手の仕方は心得ていた。
「うむ、その通りだよ。いやあ、このままだとかわいいかわいい助手が不憫でならなくてね。けれどレリアがジョゼフくんの相手をするとうっかり悪化で元に戻れなくなるかもしれない。淫魔の毒に犯された躯に淫魔の躯はきつすぎる」
「それで、どうしてレリアがこれるようになったの?」
「はっはっは、なに、問題なのはレリアの躯なわけだ。つまり、躯がなければなんの問題もないわけでね。今ここにいるレリアは精神思念体……判りやすく云えば生き霊かな?」
「ちょっと先生! なんですかその言いぐさは! 大体今は先生だってそうじゃないですか」
よりにもよって生き霊呼ばわりされたことにレリアが怒る横で、アンナマリアはやっていることの理屈はわからないもののどういう結果になったかは漠然と呑み込んだ。
「それはわかったけど、そもそも躯が無くて触れるの? あ、でも今……?」
云いながら、アンナマリアはさっきレリアに押しのけられたことを思い出す。実体がない霊体のはずなのに、レリアと確かに触れあえていた。
「大丈夫大丈夫、ふつうは触れないものだけど、今回は触りたいと思った相手の五感に作用し、錯覚させて正確な感覚を再現しつつ、大気を操り人体の動きをエミュレートして圧縮させることで押しつけるなどといった行動も可能にしたからね」
「なんでもありなんだから……」
イザベラに順応した、とアンナマリアも思っていたが、いざ事も無げにこういった内容を語られるとつくづく非常識な存在であると再確認してしまう。
驚きを通り越してあきれ果てたアンナマリアは、目を細めてイザベラに抗議した。
「それで、なんで貴方までそっちの姿で……」
「ほらほらギヨたん、そんなことはもういいじゃないですか。そんなに待たせたらこっちがかわいそうですよ?」
レリアがそういって、ふたりが来るまではアンナマリアの胸で押さえつけられていたペニスを撫でた。実体のないレリアの手がジョゼフのモノに触れると、本物の手が触ったかのようにペニスは反応した。
「じゃあ、胸の続きをしましょうか。ギヨたんはそっちから、こっちからあたしで……こんな感じに……」
「ん、こう……?」
レリアに云われるがままにアンナマリアが動くと、ちょうどふたりの胸でひとつのペニスがサンドイッチされる形になった。
胸が控えめなふたりは自然と抱き合うような形で、互いに興奮した吐息の熱を感じた。
レリアはアンナマリアの手をとって握り合うと、自分たちの胸から顔をだす亀頭を見下ろして笑った。
「わー、ホントにこの躯でも挟めてますよ……。たまには先生も良い仕事するんですから」
「たまには余計だ、たまには」
そんなイザベラの軽口も耳には届いていないようで、レリアは目と目が触れそうなほど近くでアンナマリアを見た。
「ほら、ギヨたんはおっぱい小さいからあたしもいた方がいいですよね。こうしたら、もう絶対こぼれませんよ」
「それは大きなお世話で! ……んんっ」
怒ろうとしたアンナマリアの口をレリアが口で塞ぐ。唇に伝わってくる暖かさは確かにレリアのもので、感触もまるで本物の肉体としているようにリアルだった。
びっくりしているアンナマリアからレリアは顔を離した。
「そんなに怒っちゃダメですよ……ね、一緒に楽しませてください。やっぱり仲間外れはくやしいし、さみしいんですよ」
じっとレリアが瞳を見つめる。そこにはいつもの活発な力強さと、茶化していない真摯な感情が込められていた。
さっきまで、アンナマリアはジョゼフを独占してしまいたいと思っていたし、今でもそれは変わらない。独占欲が、じりじりと胸の奥で燻っている。
「……わかった。じゃあ、一緒に」
けれどレリアの気持ちも知っていて、だからアンナマリアは断らなかった。
それとこのままふたりでするということに、アンナマリアは少なからず興奮していた。
――こっちの方が、もっと沢山虐められる。
一度ぞくぞくとした嗜虐心に火がつけば、もう止める術はなかった。
もう一度アンナマリアとレリアは口づけをして、躯を揺らし始める。
ふたりの乳房は押しつけ合って潰れ、その谷間に挟まれたペニスは胸で擦り上げられる。
大きな胸とは違い、陰茎総てを包み込むようなものではなかった。左右は少女たちの胸で柔らかく擦られているが、同時にふたりの躯で締め付けられてもいた。
抱き合うふたりの躯はほどよい圧力で肉棒を締め付け、緩め、精液と愛液の潤滑液で愛撫する。
にゅち、にゅち、と粘っこい音を立てて頭を出したり下げたりする亀頭は快楽で紅く膨れあがり、先端から透明の液体を涙のように流していた。
「ふふっ、我慢汁がいっぱいですよ。舐めとってあげないと」
レリアは尿道口へと舌を伸ばす。途絶えることなくどくどくと流れる透明の液体を綺麗に拭ってしまうと、そのまま亀頭にキスをする。胸で抑えながら、唇を亀頭に吸い付かせた。
「わたしも、混ぜて」
アンナマリアも亀頭に口づけをすると、舌先で雁首を舐めた。レリアと唇が触れあい、ふたりは互いにキスしあうように亀頭をついばむ。
はあ、はあ、と白い靄混じりの吐息を吐きながら、ふたりは精の臭いを漂わせる肉棒で夢中になった。
「ちゅ……ふっ、んはっ! ギヨたんも上手になりましたね……このおちんちん、またイっちゃうみたいですよ」
「こらえ性がないペニスだから……もう、イっちゃえ」
ふたりは悪戯に笑って、亀頭を銜え込む。そのまま、思い切り胸で締め付け――
「ん……あ、あああああ!」
反射的に、ジョゼフの口から絶叫が洩れた。
もう何度も撃ったとは思えない勢いで、ペニスはふたりの口内に射精した。
精液はふたりの口を押し返して胸に溢れ出た。まるで小さな胸から母乳でも出たかのように白濁液が胸をべっとりと濡らす。それでもまだペニスは脈打ち、精液で少女たちの細い輪郭を蹂躙した。
レリアとアンナマリアは互いに相手の頬を伝い落ちる精液を舐める。まるで、猫同士が顔についた食べ残しを拭うように。
そう、蹂躙されているのはこのふたりではなく、目をつけられた男の方がまさしく獲物なのだ。
「えへへ、ギヨたん、精液でびちゃびちゃですよー。って、あたしもですね」
「これなら……満足できるまで、がんばれ」
精液に濡れたふたりの少女は淫蕩に笑って、まだ萎えることも許されないペニスを指で突いた。
いつの間にかふたりの頭の中から淫魔の毒のことは綺麗さっぱり消え失せてしまっていた。
ジョゼフが目を覚ましたとき、目の前は不自然なくらい真っ暗だった。
「んん……あう?」
あれ、と声を出そうとして、なにかに口が塞がれていることに気付く。そうして口を動かすと、塞いでいるものがビクンと痙攣してもっと強く押しつけられる。柔らかい何かで鼻も塞がれて、ジョゼフはびっくりして声をあげた。
「んー!? ぶはっ」
じたばたと暴れると、顔に押しつけられていたものが離れた。何故か顔中が水浸しになっているジョゼフは咳き込みながら大きく息を吸い込んだ。
「な、なに?」
「あっ、ようやくお目覚めですかぁ、ジョゼフくん」
「え……うわっ」
聞き慣れた声が話しかけてきて、ジョゼフはようやく今の状況を認識できるだけの余裕ができた。そして、自分に与えられている刺激にも。
ジョゼフの顔を塞いでいたのは女陰だった。それを顔に押しつけていた女性がベッドの上に膝で立ち上がったために、股の間からジョゼフは自分の下半身を見ることができた。
「え、れ、レリアちゃん、なにを!?」
そこには、ジョゼフのペニスを性器で根本まで銜え込んだレリアの姿があった。
窓から差し込む茜色の朝日が、わずかに透けているレリアの躯を照らしている。全身が燃えるように揺らめく幼い裸体は神聖なものであるようで、同時に酷くいやらしく見えた。自分のペニスに跨っているレリアの姿に、ジョゼフの心臓は大きく脈打った。
「なにってぇ、見て判らないんですかぁ?」
レリアの間延びした口調が、いつにも増して艶っぽいものになっている。騎乗位で繋がっているのに、まるで耳元にささやきかけられたかのような熱さがジョゼフの汗ばんだ首もとを撫でた。
「それは判るけど……ああっ」
ジョゼフの言葉を、レリアが腰を捻って黙らせた。ガチガチに勃起した肉棒を銜え込む狭い秘所が捩られて、刺すような抗いがたい快感がペニスに走る。
「判るんなら、男の人がやらなきゃいけないことはひとつだけですよぉ。――子種、いっぱい注いでくださいね」
「あ、あああああ――!?」
悪戯っぽい笑みのままに愛液で濡れた極上の肉壁が締め付けてきて、いきり立った肉棒は限界に達した。
ぶびゅ! びゅくっ、どくっ! そんな音が鼓膜を震わせる勢いで、ペニスが精液をレリアの子宮に注ぎ込む。もう何度目かもわからない射精でペニスが鈍痛を訴えるものの、それを遙かに上回る快感がジョゼフの脳内を占領した。
「あはっ、でてる、でてる……ホントにあたしの子宮に射精されてるみたいですよ」
「もう淫魔の毒はないはずなのに、こんなに出しちゃうんだから。根っからの変態みたいね」
「う……っ、あ、アンナマリアちゃん?」
息を荒げながら、ジョゼフは自分の目の前にある細い躯を見上げた。白く、ぷにぷにと柔らかそうなお腹をなぞり、渇いた大量の精液を付着させた控えめな胸を通り、黒髪を揺らす少女の顔に行き着く。それは、あのアンナマリアだった。
目が覚めたばかりにこの状況で、ジョゼフは夢でも見ているような心地になる。
「い、いったいなにが……あうっ」
ここに至るまで自分はなにをしていたのかと思い出そうとするが、絶え間なく蠢くレリアの膣に思考を桃色に染め上げられた。
何日も水分をとっていないかのように渇いた喉を震わせて嬌声をあげるしかできないジョゼフに、ひとりの女性が近づいた。
「説明すると話は長くなるのだけどね。それもこれも最初はキミを助けるためだったのだよ、ジョゼフ。まあ、今となっては彼女たち自身が満足するためと目的は変わってしまったがね」
「い、イザベラ先生……って、どうして裸なんですか!」
ベッドの脇に、一糸まとわぬ姿で豊満な胸をさらけだすイザベラが立っていた。手で掴んでもこぼれてしまうくらいの胸はぴんっと張っていて美しく、腰のくび れは腕を回して抱きしめたくなるくらいに引き締まっている。肉感的で、しかしだらしなくない肉体。アンナマリアとレリアとはまったく違う成熟した女性の 瑞々しい肢体に、ジョゼフは生唾を飲んだ。
「いやあ、それはだね。見ていたら私もむらむらとしてきてしまってね。どうせだから仲間に入れて貰おうと思ったのさ。なに、こんなときのために私もレリアと同じ方法でこちらに来たのだ、搾り殺さないように加減はできているはずだよ」
「そ、そういう問題じゃむぐっ!?」
「ほら、喉渇いてるんでしょう? ……いっぱい、呑んじゃえばいいよ」
ジョゼフの顔にまたアンナマリアの性器が押しつけられる。鼻には陰核と肌が強く押しつけられて、また呼吸が苦しくなった。手足を振って暴れても、弱った ジョゼフの躯には少女たちに抵抗するだけの力すら残されてはいなかった。アンナマリアが離してくれる様子もなく、ジョゼフは小さな少女の言葉に従って性器 を舐めて、愛液を掻き出す。
必死になってアンナマリアの亀裂に舌を入り込ませると、無数の肉襞に出迎えられた。奥へ奥へと導くように動く膣内の動きに、ぴりぴりと痺れるのに似た快感が舌をなぶる。
その舌を伝って、愛液が流れ落ちてきた。透明な液体が口の中に入り込むと、強烈な水への欲求がわき上がった。衝動のままに喉を鳴らして、アンナマリアの性器から流れ出した愛液を嚥下していく。
愛液を呑み、そこに酸素不足も相まって、ジョゼフは頭がクラクラとした。倒錯的な行為にふわふわと躯が浮き上がっていくように感じる。
「ふふっ、そう、その調子……息もかかって気持ち良いよ。もっと、はげしく……んっ」
アンナマリアがジョセフの頭の上に両手を置いて、自分で腰を動かし始める。ぴちゃぴちゃと愛液を淫らに鳴らし、アンナマリアはうっとりとした表情で舌の感触を楽しんだ。
「ジョゼフくーん、そっちの方だけに気を取られちゃ、ダメですよ?」
「うぐっ!?」
舌での愛撫だけに持って行かれていたジョゼフの意識を、レリアがペニスを思い切り締め付けて引き寄せた。
「おっと、それだけじゃないのだよ。実体じゃないから、こんなこともできるのさ」
レリアが繋がっているにも関わらず、イザベラがジョゼフの下半身に躯を近づける。すると、その躯はレリアをすり抜けてジョゼフのペニスまで達した。
「同時に与えられる胸と膣内の世にも奇妙な快楽……存分に楽しみたまえ」
そうして、豊満な乳房を手で押さえつけ、肉棒を挟み込んだ。
「ふ、んぐぅっ!」
イザベラの胸に挟まれた快楽は、ジョゼフの想像を絶するものだった。痛いくらいに勃起した肉棒は全体をすっぽりと乳房に呑み込まれ、あらゆる角度から柔らかい締め付けに襲われた。
さらに、ぎゅっとペニスを情熱的に呑み込んだレリアの膣の感触も襲いかかってくる。胸の柔らかすぎない弾力的な感触と、肉襞に締め上げられる快感。本来なら同時に起こりえるはずのない快楽の波に、ジョゼフの目の前は真っ白になった。
「あ、ぐ、ひあっ! あ、あ゛あ゛、あ゛……」
「さらに、これはどうかな?」
イザベラが笑って、乳房から顔を出させた亀頭を口に銜えた。雁首に吸い付く紅い唇のぷるりとした感触と、尿道口を滑る舌。もし口をアンナマリアに塞がれていなかったら、ジョゼフは甲高い嬌声をあげていた。
「ちょっと、先生ばっかり! あたしももっといただくんですっ!」
むっと眉を寄せたレリアが、強く力を込めて腰を落とす。子宮口が亀頭に押しつけられ――ずぶっ、と亀頭が子宮の中へと半分ほど埋まった。
子宮の入り口が、亀頭を思い切り締める。淫魔のそこはまるでもうひとつの唇のように繊細に動いた。
「――――!?!?!?」
精液をほしがって口をぱくぱくと開き亀頭を刺激する子宮口とイザベラの口内に、ジョゼフの脳内回路がいくつもの快楽で混線した。
「次は、もっと躯を動かしてぇ……」
レリアが腰を上げ――落とす。
ずんっ、とまた一気に奥までペニスが導かれる。肉棒をなで上げる膣に、ジョゼフは意識を失っていたときとはまた別の意味で思考できなくなっていく。
「ああっ、おっきいっ、おちんちんがっ、中で暴れてますよ!」
「ん……これで、終わり……っ」
目を蕩けさせたアンナマリアが女性器をより強くジョゼフに押しつける。その背後で、レリアの上下運動は激しさを増していた。
「ふふ……ではイってしまうといい……」
肉棒を乳房で扱きながら亀頭にむしゃぶりつき、イザベラは微笑んだ。
顔を圧迫する愛液にまみれたアンナマリアの女性器に、ペニスへ絶え間なく食らい付くレリアの膣。そして、イザベラの乳房による愛撫――
「あ、あ、――――!!!」
それに男が耐えられるわけもなかった。
「はあっ、あああ!」
そして、アンナマリアとレリアも下半身から上り詰める刺激に嬌声をあげて。
躯の中身ごと総て吐き出しなほどの快感に貫かれながら、肉棒は勢いよく精液を噴出した。
嵐の中で荒れ狂う川のように白濁とした本流がレリアの膣とイザベラの口内にぶちまけられた。膣内と口内を生臭い精子で染め上げても射精の勢いは止まらず、ふたりの霊体を貫通してアンナマリアの背中を熱く滾った精液で白く汚した。
朝日で真っ赤に染まった部屋の中には、男女の荒い吐息の音だけが静かに響いていた。
――数年前。王宮にて。
王宮の玉座にてひとりの男性が組んだ手に額を押し当て、唸っていた。
豪奢な服装の男性であった。肌触りの良さそうな生地で仕立てられた貴族服には絵画に描かれているような模様が編み込まれていて、それは庶民の薄給では一生かかっても手に入りそうにないものだ。
身なりだけではない。それを身に着けた男性にも、余人にはない気品があった。一朝一夕ではけして身に着けることのできない、生まれたときより染みこんだ風格である。喉を鳴らして悩んでいる仕草ひとつとっても、上等な生まれのものでなければ身につかない貫禄があった。
男性が浮世離れした風格を持っているのも当然で、彼こそがこの国の王なのだ。
国家を統べる場所であり、大勢の兵士がつめ、貴族が集まる国の最高機関である王宮の頂点に君臨する最高の権力者。
しかし、普段ならば王の周りにいるはずの兵士も、貴族も、玉座の周りにはひとりとしていなかった。
王は顔をあげて、がらんとした玉座の間に目をやる。キラキラと星のように輝くシャンデリアが灯火を幻想的に揺らしていたが、常ならば絢爛な灯りも今となっ ては薄ら寒いものにしか見えない。消えてしまいしまいそうになりながら頼りなくゆらゆらと揺れる灯に不安を覚えて、王は天井の絵画へと目を向けた。
かつての王が巨額の費用を投じて芸術家に描かせた太陽神の天井画である。そこに描き込まれた太陽神と人々の絵にはこの瞬間にでも動き出しそうな脈動感があった。見ているだけで活力を漲らせてくれるようなその絵画だけが王に残された最後の心のよりどころであった。
王は目を閉じて、耳を澄ます。それでも、本当に遠くの方から人の声がかすかに聞こえる程度だった。王が大声をあげても誰の耳にも届かないくらいに、兵士たちは玉座の間より引き離されていた。
王宮の警護を手薄にしろなどと、王は命じた覚えもない。なのに、どうしてか王宮は腹を見せて寝転んだ獅子のように無防備を晒している。
争いをおこなわずに、対象を無力化する。
そういう手段を得意とした連中を、王は知っていた。そしてなにより懸念し、警戒していたはずなのだ。
連中に対抗する手段を模索し、国家より駆逐する――そのお膳立てを、王はつい最近終えたばかりであった。
その認識が敵につけ込まれる隙を生んでしまったのだろう。王宮の中での出来事で王が認識できないものが増えていったことに気付いたときには、もはや手遅れだった。
これより自身へと降りかかるであろうことを考え、顔が悲壮に歪んだ。
「逃げずに残っているだなんて、その勇気には敬意を表したいですね、王」
王にかけるものとは思えない不遜な女性の物言いが玉座の間に響いた。
扉を開けて入ってきたのは侍女の格好をした女性だ。それでも、王には見覚えのない顔である。王宮に仕えている者たちの顔を全員把握しているというわけではないものの、王は王宮で起こっている異常の元凶が彼女であると判断した。
「例え逃げても、無駄なことなのはわかっている。そうだろう、淫魔よ」
「察しがよくて助かります。ああ、そういえば、名乗りが遅れてしまいましたね。高位淫魔、七柱が一柱、強欲のアワリティア――あなたを果てさせる者です」
「昔、聞いたことがある。淫魔の中でも特に優れた七人の者たちがいると……そうか、そのひとりが入り込んだとあってはこうもなろうな」
「正確には、私だけではありません。騎士団を掌握している騎士団長のスペルビアも七柱のひとりですし、あとひとり、貴族御用達の娼館で働いていますよ。いずれも」
「高位淫魔が三人……この手際のよさも頷ける。これは命運が尽きるのも道理だ」
冷や汗を流しながら、王は毒でも飲まされたように苦しげに頷いた。それでも口調から威厳を手放していないのは、さすがは王といったところか。
「あなたがいけないのですよ。おとなしく人の王として君臨していればよかったのです。そうすれば、私たちも市民に紛れて人間を搾取するだけで干渉は致しませんでしたのに」
王はアワリティアの口ぶりに生唾を呑み込んだ。
自分がやろうとしていたことを淫魔に知られているとは思わなかったのである。
「お前たちも他の淫魔と同じく、魔女狩りのときの報復で人に害をなそうとしているかと思っていたが……よもや、知られていようとはな」
かつて、淫魔は人に紛れて何食わぬ顔で生活をしていた。気ままに人と戯れ、思い付きのままに人を虜にする。迷惑な限りであったが、淫魔たち個人個人の気分 で完結されていたために大きな問題もおきていなかった。それなのに、一部の人間が自分たちとは違う淫魔たちを見抜いてしまった。しかも厄介なことに、彼ら は彼女たちを淫魔ではなく魔女と勘違いしたのだ。
世界中に広まった魔女狩り、それによって処刑された魔女の中には多くの淫魔たちも含まれてい た。これを契機に淫魔たちは人間への態度を家畜に対するそれに変更し、襲うようになった。そのため王は、アワリティアたちが国を支配しようと暗躍していた のは魔女狩りの報復だと思っていたのだ。
そう訊ねられて、アワリティアは笑い話でも聞かされたようにくすくすと笑う。
「何故、私たちが 人に捕まって処刑されてしまうような淫魔たちの復讐をしてあげなくてはいけないのですか? 所詮、彼女たちは自分が弱かったから処刑された……弱肉強食と いうものですよ。私は常に相手を喰らう強者ですので、彼女たちのことも、そしてこれから喰べられてしまうあなたのことも顧みる気などありません」
「……死は覚悟していた。今なら人も来るまい。しかし、ただで殺されるつもりはない」
王は玉座の陰に隠していたマスケット銃の銃把を掴んで構える。こういう日が来ることを予期して手入れを怠ることはなかったものであり、撃てば淫魔といえども無傷ではすむまい。
マスケット銃はアワリティアへと向けられた。銃口が自分をじっと見つめていても、アワリティアの笑みは消えなかった。
「あら、殿方が女性に銃を向けるのですか? ノブレス・オブリージュはどうなっているのでしょう」
「お前たちを排除することこそが、王としての高貴なる義務のひとつだ」
「私たちは人に仇など成してはいないのですけどね。むしろ、悦ばせてあげているのですから、感謝されることはあっても謗られる覚えはありませんよ」
「浅はかな……己の口でそうも語るか。お前たちの毒牙にかかるくらいならば、自害の道を選ぼう」
「強情ですのね。あなたの奥様はあんなにも悦んでくださいましたのに」
「な、なに……?」
王が動揺すると、アワリティアの背後にある扉から褐色の少女が現れた。
王宮にはおよそ似つかわしくない露出の多い服を着ており、腹部や瑞々しいふとももをおしげもなく晒した姿はジプシーかなにかのようで、躯を売り物にしているような相手なのは一目でわかった。
「きましたか、ルクスリア」
「きましたか、じゃないよー。せっかく貴族の男の人たちと遊ぼうと思ってたのに。まあ、新しい玩具も楽しかったからいいけどね」
にこにこと笑っているルクスリアという褐色の少女の言動で、彼女も淫魔なのだと王は理解した。おそらく、先程の話にできてた娼館に勤めている淫魔とやらだ。そして、言いようのない悪寒に襲われる。
「お前たち、まさか……」
「そのまさかですよ。さあ、妃様に入ってきて貰いなさい」
ルクスリアが、扉の外からひとりの女性を引っ張ってきた。思わず、王は声をあげていた。
「そんな、お前たち……妻になんてことを!」
淫魔たちに連れてこられた女性は、王の妃その人であった。
いつもは気丈に、傲岸不遜、傍若無人と振る舞っていた妃――が、その瞳は色欲で濡れていた。焦点を結ばない目は与えられた快楽で意識が朦朧としているためだ。
ひとりで立っていられなくてルクスリアに寄りかかった妃のドレスはスカートの部分が大きく引き裂かれており、むき出しになった股からは放尿でもしたのかと思うほどの愛液が流れ出していた。
「あはっ、妃様とえっちするなんて初めてだったから、つい張り切っちゃって。すっごい抵抗してくれたから、調教のし甲斐があってボクは楽しかったよ?」
「妻から、離れろ!」
無邪気な物言いが癪に障って王はマスケット銃をルクスリアへと向け、すぐにアワリティアが視界から消えていることに気がついた。
どこへ消えた――?
さっと血の気が引き、怒りで熱く燃えていた頭が一気に冷める。マスケット銃を右へ左へと振るもアワリティアは見あたらない。
直後、頭上で鳥が羽ばたくような羽音がした。
はっ、と王はマスケット銃を天井へ向けた――が、急降下してきたアワリティアの足に勢いよく蹴り飛ばされて銃は床を跳ねていった。
衝撃に痛む手に呻く間もなく、王は降ってきたアワリティアによって床へと押し倒された。
「ぐ……っ!?」
「油断大敵ですよ、王。これで、あなたは私たちを殺すことも自害することも選べません」
王へ馬乗りになったアワリティアの背中からは、蝙蝠のものに似た羽根が一対生えていた。男である王の躯すら包み込めそうなほどに大きな羽根は、淫魔が普段は体内に隠しているトレードマークのひとつである。
「ここで死なれては困るのです。あなたは、革命派によって殺されて貰わねばならないのですからね。それらが完了したとき、この国は私たちのものとなるのですよ」
「ならば、舌を噛み切ってでも……」
「させませんよ……そんなこと、考えられなくさせてしまうんですから」
そういって、アワリティアは王へと顔を近づけると相手のそれへと自分の唇を押しつけた。
「んふ……っ、ちゅ……」
しっとりと濡れた赤い唇を重ねて、アワリティアは己の舌を相手の中へとねじ込む。
王はその舌を噛み切ってやろうかと思ったが、アワリティアに歯茎を舐められると快楽で意識が胡乱になった。じんじんと痺れるように浸透する快感で顎に力が入らない。
「う……」
「先程までの威勢はどうなさいましたか? そんなに目を蕩けさせてしまって……奥様も見ていますのよ?」
「こ、殺せ……ひと思いに……」
「そんな無粋なことはしませんよ。私たちの手を煩わせたことに敬意を表して……与えるのは苦痛ではなく、快楽です」
アワリティアは上品な顔で妖しく淫蕩に微笑んで、王の服を留め具をひとつひとつ器用に外していく。服の下から現れた胸板をアワリティアの人差し指がなぞるとそれだけで性器に触れられたような快感があった。
「や、やめろ……。淫魔なぞに犯されるなどと、人としての恥……!」
「その強情が、いつまで続くのでしょうね?」
くすくすと笑み、アワリティアは腰を揺らす。柔らかい尻の肉を押しつけられて、敷かれていた王の股間はあっという間に最高硬度へと到達した。
「それに、こちらをこうも膨らませていては説得力もありませんね」
王の顔が羞恥と怒りに歪む。その表情をアワリティアは愉しんでいた。
「本当は、このまま私の中で果てていただくつもりでしたが……そうですね。機会をあげましょう。もしあなたが私をイかせることができたら、この国から手を引いてあげます。どうします、自分に自信がありませんか?」
見え透いた挑発だった。しかし、このままアワリティアのされるがままになっていても事態が好転しないのは間違いなく、屈辱的な提案だとしても受けざるを得なかった。
「いいだろう……その生意気な口を二度と聞けぬようにしてやろうではないか……!」
「ふふ、楽しみにさせてもらいますわ」
アワリティアは王の上から退くと、床に座り込んで股を広げ、自分の服をはだける。侍女用の服がほどかれ、露わになった胸元は見る者の目を釘付けにするほどに扇情的だった。王も、その姿には思わず生唾を呑む。
「さあ、いらしてくださいな」
アワリティアが手を差し出して指で誘う。無言のままに王はアワリティアの躯に覆い被さった。
妻が、すぐ側にいる。そのことで罪悪感が沸き、それでも抑えきれないほどに淫魔の美しい躯から目が離せない。無意識のうちに露出した一物はガチガチに堅くなったままだった。
そして、王は男のもっとも無防備なところをアワリティアの秘部に押しつける。亀頭に愛液で濡れた膣肉が触れた。亀頭に吸い付く感触に、まだ挿入すらしていないにも関わらず刺激で腰を引いてしまいそうになる。
女を知らぬ少年のように胸を高鳴らせた王はアワリティアの細い腰に腕を回すと、ペニスを彼女の中へと挿入した。
ぬぷっ、と準備万端だった膣の中にペニスが突き入れられる。
「は、っああ……!」
喉の奥から声を洩らしたのはアワリティアではなく王の方であった。
熱く濡れた膣はまるで精液を搾りとろうとする意志でもあるかのようにずるずると肉棒に絡みつく。その感触に王の頭の中からはこの場を切り抜けようと巡らせていた思考が吹き飛んでしまった。
「声などあげてしまわれて、そんなにも私の中は心地よかったのですか? そんな姿を奥様の目の前で晒されるなんて……男性として恥ずかしくはないのですか?」
「お前が、しろとっ」
「ふふっ、私はこの躯をイかせられたら、といったのですよ。それだけなら入れる必要なんてないのです。そうやって腰を動かしているのは……ご自分がなさりたかったことだからでしょう?」
云われてみれば、確かにその通りだった。本当にやりたくないことならば、それを出来るだけ避けて目的を遂行しようとする。それをせずに、この方法を即決し たのは、ひとえに王がアワリティアを抱いてしまいたかったために過ぎない。自分の妻を目の前にしているという状況においてでも。
戸惑う王に、アワリティアは膣に力を込めてペニスを締め付けた。ぎゅるっ、と力強く膣肉が陰茎全体を滑りながら愛撫する。
「ぬ、おおおっ」
「さあ、もっと突いてくださいな。もっと突いて、私を気持ちよくしてくださいね、王様?」
アワリティアは足を王の腰に絡みつかせ、動けなくすると、淫蕩に微笑んだ。
今まで抱いてきたどのような女性よりも心地良い暴力的な膣の感触に、王は既に果ててしまいそうになっていた。アワリティアの躯は自分から一切動いていない のに、膣はうごめいて精液を搾り取ろうとむしゃぶりついてくる。愛液という涎でびしょ濡れになった秘所の食い付きになにもかも吐き出してしまいそうだっ た。
それでも、イってはならない。相手を先にイかせなければ……。わずかに残ったその目的だけを頼りに、王は歯を食いしばって腰をアワリティアに叩きつけた。
ぱんっ、ぱんっ、とアワリティアの躯に男の躯がぶつかる。
「あんっ」
柔らかい肉を叩きながら膣を貫く剛直に、アワリティアはわかりやすい嬌声をあげた。
「ああっ、良いですよ、王様……いつもこうやって奥様を喘がせていたのですね? さあ、もっと、もっと……」
さらに強く懇願するアワリティアに、王は腰の動きを早めた。すぐにでも限界を迎えてしまいそうな快楽の中、王は先に相手をイかせようと何度も子宮を亀頭で突き上げる。
「そんなに激しく突かれては、私はもう……我慢できなくなってしまいますっ」
あと一息……、と頭の片隅で確信して、王はアワリティアの豊満な胸を両手で乱暴に掴んで、一気にペニスで膣を掻き分け。
「精液を、味わいたくて――ですが」
いきなりアワリティアの膣の動きが変わった。たっぷりと愛液に濡れた膣は締め付けを強め、ぐちゅぐちゅと音を立てながらペニスを呑み込んだ。
「お、おお!?」
「では、これでお終いにしてあげますね。さあ、私の中で果ててください」
くいっ、とアワリティアが腰を一度捻り、
「あ、ああああああ!」
一瞬で王の我慢を超えた快楽に、ペニスは為す術なくアワリティアの中に白濁を噴出した。
肉棒から噴き出した白濁とした男臭い精液が子宮に流れ込み、アワリティアは自分の下腹部を撫でながら唇を舌で舐めた。
「王様の精子、いっぱいいただきました。でも、このくらいでは足りませんから……もっと、搾り取らせていただきますね? さあ、王様、精液を全部私の子宮に出し切るか、それより前に私をイかせることができるか……勝負しようではありませんか」
達した衝撃で倒れ込み、アワリティアの胸に顔を埋めている王の頭を撫でて、微笑む。
「もっとも、その様子では……もう私の躯の虜でしょうけれど」
「えー、もう勝負着いちゃったのの? つまんないよー、まだこっちは始まったばかりなのに」
アワリティアがルクスリアの声がした方へと向くと、彼女は股間から生やしたペニスで壁に手を着かせた妃を突いていた。こうして喋っている間にも、ルクスリアはお尻を無防備に突きだしている妃を突くことを忘れなかった。
「あ、あひぅ! ひっ、いやっ、も、もうこんなに……」
「はいはーい、また一緒にイこうねー? ボクの精液たくさん味わってねっ」
ルクスリアは妃に囁いて、ずっ、とペニスで奥まで入れると白濁を妃の中に流し込む。それが子宮を叩くと、妃は一際高い声を発した。
「ひ、い、いやああああああっ」
妃の膝ががくがくと震え、股から溢れた愛液と精液がぴちゃぴちゃと床に大きな水たまりを作った。
もう何度イかされたかも判らぬ妃が腰砕けになって倒れそうになったところを、ルクスリアが腰を支えて押しとどめた。
「まだダーメ、もう一回最初からいこーねー?」
「あ、あああ……ああ……」
口から涎を垂らしながら虚ろな目になっていく妃に、ルクスリアは精液だらけになったペニスで掻き分けはじめだしたのだった。
そんなふたりの様子を見て、アワリティアは膣を一度きゅっと捻り、満足気に王の顔を胸に押しつける。
「これで、あなたがたも、この国も――私たちの、虜です」
それは、国がひとつ淫魔に掌握された瞬間だった。
*
「それで、進行状況はどのようになっていますか?」
不遜にも玉座に腰を降ろしているアワリティアが、正面に立っている騎士スペルビアに訊ねる。その顔色に余裕はなく、追い詰められた鼠のように暗かった。
革製の防具を身に着け、凜として立つスペルビアは、アワリティアが哀れに見えるほどの平静さで返答する。
「なんの問題もない。云われた通り、兵を手配し、魔女狩りと称しての襲撃をおこなう手筈も整った」
淫魔――その名前から連想させる淫蕩な気配は、スペルビアからは一切伺えない。清廉な、騎士たる高貴さを感じさせる立ち姿だった。しかし、鎧の下には淫ら に男を惑わす柔肉が隠されていることは実際に躯を重ねて魅了された男たちしか知らぬことである。もっとも、その大半は帰らぬ人となっているが。
「国の兵を挙げて討伐しようなどと、お前らしからぬ優雅さの欠片もない行為だ」
男を狂わせる肉体を持ちながらそれをおくびにも出さないスペルビアは、それと同じくらいに平静で、動揺もなにも見せていなかった。
アワリティアは疲れを吐き出すように溜息をついて、首を振る。
「貴女に優雅さをとかれるとは思いませんでしたよ。剣などという無粋極まりないものを振り回す貴女に」
「剣が無粋ならば、この世の総ては品性の欠片もない下劣な創造物であろうよ。剣と力ほど洗練された美しいものはない」
「武力に拘るとは、淫魔らしくもない……いえ、知力に拘るのも、淫魔らしくはないのでしょうけれど。それでもやはり自ら力を振るうより、蟲みたいに争う人間相手に高みの見物をする方が性にはあっています」
「ようやく調子がでてきたな。で、いい加減話して貰おうか。何故、兵を挙げて彼奴らを潰そうとする? お前が以前からあの魔女らの存在を危険視していたのは知ってはいたが、一国を手に入れた今、ここまで大事にする意味はあるまい」
アワリティアたちは、この国に革命を起こした。国王に反感を抱く勢力と貴族たちを抱え込んで籠絡し、争いの火種を造り、発火させた。ひとりだったなら苦労 もしたであろうが、高位淫魔が三人も揃えば国家を転覆させることなど造作もなく。王を革命派に処刑させ、誰にも知られることなくアワリティアたちは国を 盗った。
国を盗ることにさえ一度として表舞台に立たず、人を操ることはあっても指示をすることはなかったアワリティアが、今、たった三人を暴力によって潰そうとしていた。それがスペルビアには疑問だった。
「いいえ、違うのですよ……問題は魔女ではない。あの黒いドレスの少女です」
「どういうことだ?」
「私がこの国を落とそうと企てた理由を、知っていますか?」
「そんなものがあったことすら初耳だ。魔女狩りで我等淫魔が虐げられた腹いせで、どこでも良いと思っていたが」
その昔、魔女狩りがおこなわれた。多数の人々が魔女とされ、処刑された儀式である。しかし、魔女とされた中には人に紛れていた淫魔も含まれていたのだ。そ れまでは人とある程度もちつもたれつのような関係で過ごしていた淫魔たちは、それに激怒した。あの出来事以来、淫魔たちの大半は人間を純粋な家畜として見 ており、スペルビアはアワリティアの行動も魔女狩りの報復としてのおこないであると思っていた。
「どうして、私が殺された者たちの報復などしてや らなくてはいけないのですか。腰を振ってあげるだけで悦んで死んでいくような相手に殺されたなんて、淫魔の恥さらしですよ。……私は、単にこの国が驚異 だったからこそ潰そうとしたのです。あの国王は、私たちにとって最悪の天敵でした」
「その国王も、お前の腰の下で果てて処刑台に送られたはずだが……」
「そう、それです。処刑台! あの王が残した遺物。まさか、もう人の形をとれるようになっていたとは思いもしませんでした。一心不乱に私の中へと精を注ぎ込むしかできなかったあの男が、ここにきてこんな隠し球を残していたなんて……」
不安に駆られて強く玉座の肘掛けを握り締めたアワリティアは、いてもたってもいられなくなって立ち上がった。
「スペルビア、戦いの用意を。ルクスリアにもいつなにがあっても良いように伝達しておいてください。今回で、今度こそ総ての憂いを断ちます」
「よかろう。どちらにせよ、横取りされた獲物も取り返してやらねばならぬしな……」
ちろっ、とスペルビアの舌が唇を舐める。その一瞬だけ、女性騎士の本性が垣間見えた。
こうして、自分たちが淫魔たちに操られているとは露とも思わぬ兵士たちはアンナマリアたちを狙って行動を開始した。
*
夜が明け、アンナマリア、イザベラ、レリア、そしてジョゼフはリビングに集まっていた。
「さて、無事ジョゼフを救出することができたわけだ」
ソファに座ったイザベラは周囲にいる全員を見渡しながら、皆の労をねぎらうように口を開く。それに、対面で座っていたジョゼフの顔が引きつった。
「いや、まあ、助けてもらったことはありがたいんですけど……せめて方法というものはなかったんですかね……」
アンナマリア、レリア、イザベラによるジョゼフの体内に溜まった淫魔の毒気を駆除する作業は無事成功していた。一時期は自我を喪失していたジョゼフも、あれから数時間が経過した現在はすっかり以前の状態を取り戻している。
これまでの間に、ジョゼフは淫魔の毒気に当てられていたことの説明を受けていたが、それでも三人におそわれていたときのことを思い出すと恥ずかしさで顔が熱くなるのは止められなかった。
「やだなー、ジョゼフくんったら。みんなで楽しんだんだから良いじゃないですか」
「楽しんでなかったとは、たしかに云えないんだけど……」
にこやかに笑顔を浮かべて躯を寄せてくるレリアにジョゼフは立ち上がってしまいそうな勢いで肩を跳ね上げると、すぐに情けなさで萎縮してしまった。
「元はと言えば、巻き込んだのはわたしの責任だから……責めるなら、いくらでも甘んじて受ける」
三人とは少し離れ、彼らに背を向けて木製の椅子に座っているアンナマリアが呟くと、ジョゼフは慌てて弁明した。
「い、いや! あそこにいた、その、スペルビアって騎士の女の人はぼくの知り合いだったわけでね。だからぼくも無関係ってわけでもなかったから、アンナマリアちゃんだけのせいってわけでもないよ」
「そうだぞ、ギヨたん。物事を気にしすぎて沈んでいたらつまらないじゃないか。そこはもう開き直って捕まる方が悪いと云いきってしまえばいいのだよ」
「……それはそれでどうかと思うんですよ、魔女先生」
あきれ果てるジョゼフにイザベラは笑い、しかしすぐにその表情から珍しく笑みを消した。
「今回ばかりは、いつまでも落ち込んでいられる暇はないということさ」
「え、それってどういうことなんですかぁ、先生」
「そうやっていつまでも余韻に浸ってジョゼフに抱きついているのは結構だけど、それで注意力が散漫になってしまうのは、まるで恋する乙女のようだよ、レリア」
「余計なお世話です!? もうっ、もったいぶらずに早く云ってくださいよ」
「ではまずひとつ。何故、朝なのにギヨたんはいつまでもここに留まっていると思う?」
「……あ」
そういえば、アンナマリアはいつも朝には広場に戻って、断頭台へと姿を変えていた。本来なら広間にあるはずの断頭台がいつまでもなければ、大騒ぎになって しまうからだ。それに、アンナマリアは処刑という行為を自分がおこなうことに一種の義務感までも覚えていた。一番楽に人を殺せ、さらに民衆を満足させる視 覚効果を演出する処刑道具としてはアンナマリアが一番優れていた。
だというのに、この話を聞いていてもアンナマリアには動こうという気配すらなかった。
「えっと、ギヨたん、なんで……?」
「わたしも、行けることなら行きたいけど。今日はその必要もないみたいだから」
「そう、今日は処刑がおこなわれない。何故だかわかるかい? 街中に兵を配置するために人員を割いているから、そんなことをする時間もないのさ。そう、この国を支配しているあの淫魔たちは、とうとう私たちを武力行使で排除しようとしているわけだよ」
「な、なんだか、すごい大事になってますね、魔女先生」
「その一翼を担っているのは、キミのお師匠様だけどね。いや、ジョゼフもえらい淫魔に目をつけられていたものだ」
「淫魔ってだけでも驚きですけどね……そんなのがいるなんて思いもしませんでしたよ」
目が覚めてから、淫魔という種族が人間に混じって生活をしていることをジョゼフは初めて聞かされた。牢屋でスペルビアらに云われたときは驚きで頭がいっぱいであり疑念を抱く余裕もなかったが、改めて聞かされるとそれもまた驚くことばかりである。
「もー、そんなのって酷いですよ、ジョゼフくん」
「え、ああ、ごめん、悪気はなかったんだ……」
「えへへー、わかってますけどねー」
イザベラに敵の動向も聞かされても、レリアはすっかりジョゼフにのぼせ上がった笑顔のままに相手の腕に抱きつく力を強めた。直接の躯でなくとも、狙っていた意中の相手と繋がったことはそれだけレリアにとっては悦びであったのである。
「っていうか、レリア、くっつきすぎ。ジョゼフも、鼻の下伸ばしすぎ」
「伸ばしてないよ! こ、これはただドキドキして……」
「やだー、ギヨたんったら嫉妬ですかっ? こわーい」
「……死なす」
「ちょっとアンナマリアちゃん、落ち着いて! 椅子に座って! 魔女先生もなんとか云ってくださいよ!」
背後に黒い影を背負って立ち上がるアンナマリアに慌てながらジョゼフはイザベラに訴えるが、彼女は面白そうににやにやとしているだけだった。
「いいじゃないか、こんな状況でも普段通りでいられるのは良いことだよ。そもそも私たちにしんみりとした空気は似合わない。そうは思わないか、ジョゼフ」
「そりゃ明るい方がいいですけど」
「ははは、まあ仕方がない。ふたりとも、その辺りにしておきなさい。さすがに時間的な猶予も少なくてね。もう数刻もせずに兵士たちはここに踏み込んでくるだろう。さすがに一国の軍隊ひとつを真正面から相手にするのはきついだろう?」
「そもそも、あたしたちの戦う場所はそこじゃないですからねえ。ジョゼフくんならわかるよねー?」
意味深に笑ってレリアがジョゼフの胸に頭を乗っけると、ジョゼフはビクンと躯を震わせ、アンナマリアの視線がきつくなったことに頬を引きつらせた。
助手の期待通りの返答に、イザベラは満足げに頷く。
「その通り。だから、君たちの戦場で決着をつけようじゃないか」
「……まさか、国の人間全員を一斉にあっちの方で相手をする、なんてこと云い出すつもりなの?」
「ギヨたんの目的はそれだったろう? ちょうどいいじゃないか」
「あ、あはは、先生……そういう力押しも一度はやってみたいことではありますけど……」
数十万、数百万の男女を相手に性技でねじ伏せるようなことは淫魔であるレリアもさすがに考えておらず、ずっと明るかった笑みが引きつった。
「なんて、それは冗談だよ。面白くはあるけど、あとに控えた淫魔たちを続けて相手になんてしたら保たないだろう? だから、取り巻きは無視してしまおうじゃないか。直接、その淫魔たちを叩こう」
「な るほど、あのアワリティアとかいう淫魔たちがいなくなれば、あたしたちは大丈夫ですね。表だって権力を持っているのは騎士団長だけで、他のふたりのことな んて兵士たちは知らないでしょうし。淫魔の虜にされてた人たちも彼女たちが消えてしまえば、総力を挙げてあたしたちを潰せー、なんて命令取り下げますもん ね」
そこで、元騎士団所属だったジョゼフが口を挟む。
「でも、魔女先生。その、あの牢屋から出してくれるくらいだからこのふたりがすご いのは判りますけど、もしその淫魔さんたちが城に立て籠もっていたら接触するのは難しいですよ。ぼくがいたときでさえ、スペルビア団長と軍の人間たちが決 めた警備に穴はなかったんですから、籠城を決めるつもりなら、さらに頑強になっているに決まってます」
「もうっ、ジョゼフくんはあたしたちのこと信用してないんですかぁ? 大丈夫、男の兵隊さんなんて物の数じゃないですよ。ジョゼフくんだって今朝までじっくり体験したじゃないですかぁ」
「そ、そうだけど……」
「まあ、たしかに利口なやり方とは云えないですけどねー。人がどんどん来ちゃいますし、槍とか銃でぐさっぱーんっ、もあり得ますから」
「あ、城攻めの方は大丈夫だよ。私が魔法で直接敵のところへ転送してあげるから」
「……ジョゼフを助けに行く時、それを使ってくれればよかったのに」
「ごめんごめん。これは行ったことのある場所にしか転送できないんだよ。生憎と私は牢獄に入れられるようなことはしてないんでね」
「司法の目をかいくぐってきたって意味でしかないですよねぇ、先生の場合」
レリアの追求もイザベラは微笑で受け流して話を続ける。
「で、 高位淫魔三人……アワリティア、ルクスリア、スペルビアだったかな。この全員を負かしてしまえばいいわけだけど、淫魔の根城にこちらから飛び込もうってい うんだから、力尽くの戦いはできないわけだ。どっちにしろ、レリアもギヨたんも一番得意な戦いは相手と同じだろうから関係ないけど――」
そこでイザベラはジョゼフの方へと向いた。
いつも見ているはずの笑顔なのに、ジョゼフは嫌な予感に胃の入り口がきゅっと絞まるのを感じた。
「問題はジョゼフだね。いやあ、人間の男が淫魔と戦って勝つなんてよっぽどのことがないと無理だけど、まあ、がんばってね」
「え、え、えええええ、ぼくですか!?」
素っ頓狂な声をあげてジョゼフが驚く。イザベラの言葉はアンナマリアとレリアも聞かされていなかったため寝耳に水で、ずっとジョゼフに躯を預けていたレリアも飛び上がってしまうほどの驚きだった。
「ちょっ、先生!? てっきり、あたし、ギヨたん、先生の頭数で淫魔を相手にするつもりだったんですけど!」
「え、私はなにも手伝わないって云わなかったっけ」
「あれってジョゼフくん助けに行くときだけの話じゃなかったんですか!?」
「残念ながら私は世俗に関与しない主義なんだ。さして結果の変わらぬ小事にならともかくとして、介入次第で歴史が変わってしまうようなことに関わるつもりはない。城への手助けをするのだって最大限の協力なんだから。本当は自分たちで方法を探してほしいくらいだよ」
「ぼ、ぼくがまたあの人たちと……」
ジョゼフは牢屋での出来事を思い出して、雨に触れた犬のように身震いした。淫魔たちに与えられた快楽が全身に甦り、脳髄が溶け出しそうな蜜月の記憶に躯が 熱くなる。ただ、同じくらいに、生と死を強制的に繰り返させられて終わることない渦の中に引きずり込まれた畏怖も強かった。
「先生、あたしとギヨたんのふたりで三人を相手にしちゃえばいいじゃないですか。厳しいですけど、できないことは……」
「いや、それが間違いなく無理なんだ。キミとギヨたんはアワリティアとルクスリア相手ならともかく、スペルビア相手では万に一つの勝目もない」
「……それは、どうして?」
絶対に勝てないと断言されて、アンナマリアは無表情の中に不愉快さを覗かせた。牢獄で淫魔たちと出会ったとき、圧倒的な力の差を見せつけられて愕然としたことは記憶に新しいが、それでも一瞬の迷いもなく云われては腹も立ってしまう。
「簡単なことだ。彼女だけは淫魔でもあり、そして騎士であるからだ。スペルビアを押し倒して性技の方で相対するには、まず、暴力的な戦いの方で勝たなければいけないのさ。淫魔の異端であり、そして淫魔が一番敵に回したくないのが傲慢のスペルビアというわけだね」
「うぐっ、あたしたち淫魔はそういう戦いはあんまり必要としませんもんね……。人間相手なら早々負ける気はしませんけど……」
「そういうこと。あとギヨたんもダメな理由は一緒だからね」
「……なんで? わたしは淫魔じゃないし、それに、戦う力なら……」
ある、と続けようとしたアンナマリアの言葉をイザベラは手で制した。
「ああ、キミは優れた殺戮能力を持っている。けど、キミは効率的に首を刎ねることはできても、それを実行するだけの能力がない。起源が道具なんだ、あくまで身体能力が人間と同じなキミじゃ荷が重い」
そこまで云われて、アンナマリアも重く口を噤む。それに、アンナマリアの――断頭台としての本来の――力は、牢獄で一度淫魔たちに目撃されている。もしアンナマリアがスペルビアと相対したとしても、初撃を見切られたら勝つ見込みはない。
「えーと、魔女先生、今のはアンナマリアちゃんが、その、元はギロチンってあることに関係してるんですか? よくわかりませんでしたけど」
「そうだね。まあ、関係のない話だよ。ともかく、スペルビアにはジョゼフが当たって貰う。なに、勝算がないわけじゃない。なんといっても今のジョゼフなら淫魔の快楽にもある程度耐えられるだろうからね」
「あ、そうですね、ジョゼフくんは淫魔といっぱいえっちしましたからね」
ぶっ、とジョゼフはレリアの取り繕い一切なしの言葉に噴き出した。
「そ うそう。レリアだけじゃない、あれだけの高位淫魔と生死の境を何度もさまよいながら交わい続けたんだよ? 躯だって耐えやすくなっているさ。ふつうなら、 慣れる前に死ぬか精神が崩壊するんだけど、ジョゼフの場合は両方乗り越えられているし。そこにギヨたんもいるんだ、多分もうふつうの女の子相手じゃジョゼ フも感じられないんじゃないかな」
「喜んで良いのやら、悪いのやら……。でも、そのお陰でぼくも頭数に加われるんだから、そこには感謝ですけど」
「え、ジョゼフくんそんなにまたスペルビアとしたいんですか?」
「違うよ!?」
「さて、これでジョゼフがスペルビアを相手にすることは納得してもらえたと思うけど、残りはアワリティアとルクスリアだね」
「あ、先生、ルクスリアはあたしが相手をしまーす。スペルビアと一緒にずっとジョゼフくんと絡み合っていたのが許せません」
「はい決定。じゃあアワリティアはギヨたんに任せるよ」
「う、うわあ……適当だなあ……」
「いいじゃないか。とっても妥当で宿命的な組み合わせだと思うよ。特にこの国を転覆させた首謀者を断頭台のギヨたんが相手にするのが特に」
「関係ない。わたしは降りかかる火の粉を払うだけだもの。……それと、別に今すぐしかけるわけじゃないんでしょ? 少し、ひとりで休んでる」
返答を待たずにアンナマリアは立ち上がると廊下の方へと歩き出してしまう。
イザベラは手を叩いて、それを合図にして場に張り詰めていた空気を払った。
「じゃあ、そういうわけで私たちも休もう。じゃ、こっちも準備があるから」
レリアとジョゼフに言い残して、イザベラはアンナマリアの後を追うように部屋を出て行った。
適当な部屋のひとつに入って扉を閉めた瞬間、全身の筋肉が弛緩した。傾く躯に驚いて棚の天板に手をかけても力が入らず、小物を薙ぎ倒しながら床に尻を付いた。
緊張の糸が途切れると、一気に汗が噴き出す。来ている服は汗でぐっしょりと濡れて、額には髪が鬱陶しく張り付いた。
もう我慢する必要はないのに、強く手を握りしめる。掌に突き刺さる爪の感触が辛うじて判り、そのことだけがこの状況においての救いだった。
大丈夫……まだ大丈夫……まだ、わたしは……。
「随分と辛そうだね、ギヨたん」
「……っ!」
熱病に苛まれたように胡乱としていた思考が、一声で覚醒する。
アンナマリアは弾かれたように、声のした方へと顔を上げた。ベッドに腰を下ろしているイザベラの姿に驚愕で目を見開く。
「どうして……ドアは閉めたのに……それに、わたしの方が早く……」
「だからね、私は魔女なんだよ。既存の法則で括ってもらっては困る。そんなことより、よくもまあそんなになるまで隠し通せていたものだね」
「別に、足がもつれて転んだだけ。まだ人間の躯になれきってないから……」
「見え見えの嘘はやめなさい。キミが今どんな状況にあるのか、私は全部わかっているんだよ」
イザベラはベッドから離れて、アンナマリアの前で膝をついた。
「キミがあと少しで死んでしまうこともね」
アンナマリアは息を呑んだ。誰にも悟られまいとしていたことが簡単に見抜かれていて、その事実に声を出すことすら忘れてしまった。
「どう、して」
「レリアに担がれて帰ってきてきたときにね、一発で悟ったよ。そもそもキミに命を与えたのは私だよ、それが消えかかっているくらいわかるさ。それに、死にかかっているかの原因と解決方法すらも判ってる」
「……死なない? 生きられる、方法……。それは、なんなの? 教えて!」
イザベラの肩を掴んで、アンナマリアは掠れた声で懇願した。
「簡単だ。人を殺せばいい」
「……え」
「キミは、処刑道具が人と成ったものだ。だから、己の意志で人を殺せばキミは世界に生存を許される」
「云っている意味が、わからない」
「そ うか、じゃあまず前提条件から話そう。器物が意志を持つには九十九年はかかるものなんだよ。それが人の形を成そうとするなら、倍以上の時間が必要になって しまうわけだ。人を殺す物には呪詛的な力が宿って期間が短縮されるものであるけど、それにしたってたかだか数年で人間になるなんて不可能なんだ」
「でもわたしは貴方の力で……」
「そ う、私はキミを人間にした。ただし、それはキミの存在価値と目的が合一を果たしていたから、その呪詛の力を増幅して所用期間を誤魔化すだけの力を生み出し てあげたに過ぎないんだ。……わかるかな? キミの存在価値と目的がずれた時点で、増幅できる力の源がなくなる。あとは先細りで衰えていくだけだ」
――人を殺せばいい。その言葉がアンナマリアの頭蓋骨の中で反響していた。
「わたしの存在価値……人殺し。それで、人になりたいと願ったのは……」
「そう、復讐。殺害欲求。ほら、ぴったりだろう。けれど、今のキミは復讐をしてやろうだなんて気概が薄れてしまっている」
「そ、そんなこと……」
「存在価値は生まれたときから移り変わることなんて滅多にない。特に、断頭台なんてものの存在価値が殺害以外に変わるとは思えないね」
自分の目的を果たせば、人の形を保っていられる。どちらもアンナマリアの望みで、叶える分にはなんのデメリットもない。
そのはずだ。そのはずだった。
やりたいようにすれば生きられる。最初、男を殺したときと同じで残虐に、冷酷に、嘲笑を持って搾り殺してやればいい。あの彼を殺した国の総意に報復するためにも。
むざむざ彼の処刑を執行させられたときの屈辱は忘れていない。何度も何度も、広場のゴミみたいな民衆に呪詛を投げかけた。
殺してやる、殺してやる、殺してやる……。
お前たちもわたしで殺してやる……。
殺して、殺して、殺し尽くして。
最後には――。
――彼の弟すらも手にかけるか。
「なんで……」
イザベラの肩を掴んでいた手が、落ちる。
「なんで、ないの……どこに行っちゃったの……ずっと、あったはずなのに……殺したいって、思ってたのに……」
狂おしく燃えたぎっていた憎悪の炎が、いつの間にか遠くにあった。他人の記憶でも覗き込んでいるように、まるで余所事でもを眺めるように、その感情は自分のものではなくなってしまっていた。
冷静になって考えてしまえば。
こんな復讐など、ただの八つ当たりでしかなかった。
現実が許せなかった。こんなのは嘘だと思いたかった。けれど、それは叶わない。いくら目を背けようと、残酷な速度で大切な人を欠落させた世界は回り続ける。
彼を殺したのは世界だ。なのに、どうしてそうも無関心でいられるの?
たかだか処刑人ひとりの人生、鑑みる方がどうかしているのだろう。でも、彼を殺した奴が、それに歓喜している奴らがのうのうと生を謳歌しているのは――どうしても気に喰わなかった。
そんなことをして、死者が喜ぶとは思わない。
悲しむことさえ、死者にはできないのだ。
それにアンナマリアは納得できなかった。だからこその復讐である。復讐とは、理不尽に対する裡なる衝動の発露に他ならないのだ。怒りや哀しみといった感情に整理をつけるためにおこなう精神活動なのだ。
アンナマリアの場合、そこに矛盾が生まれてしまった。
国の人間を総て殺してやりたい、願望。それは彼の弟さえも手にかけると云うことだ。
彼のために、彼の弟を殺す――。
否。自分が彼を失った悲しみの穴を忘れるための復讐で、彼の弟を殺すのだ。
断じて復讐は誰の為でもない。総て自分の為にするものなのである。
だからそれは、アンナマリアにとって最大の自己矛盾だった。
――なによりも。
ジョゼフにかけられた優しい言葉が、胸の奥で引っかかっている。
好きとか、嫌いとか、そんな感情ではない。ただ、うれしかった。人を殺してされる感謝は、いつも悲しみか下卑た笑みで満ちていたから。
彼の弟だからではない。ジョゼフだから殺したくなかった。
あんなに殺したじゃないか、とアンナマリアの中でまた別のアンナマリアが囁いた。今更、善人を気取るつもりなのかと。えり好みするのかと。
そんなつもりはなかった。でも、殺そうだなんて思えなかった。
もう、胸の奥の炎は戻ってきてはくれないようだから。
「……判ったようだね、アンナマリア」
一瞬、誰に呼びかけられたのか判らなかった。虚ろだった目でイザベラに焦点を合わせると、どうやら彼女がいったらしいと判る。それくらい、聞いた事のない真剣な声だった。
「も うキミは、人は殺せても復讐心はほとんどない。キミが人間でいられる時間は、保ってあと数日だろう。こればっかりは、残念ながら私でも変えてやることはで きない。しかも残りの時間を自由に使おうにも、兵士たちのせいでそれも難しいだろう。なら最後に、できるだけやり残したことは潰さないかい」
「……ひとつ、きかせて。わたしは死んだらどうなるの?」
「本当は、死ぬという表現は正しくないんだ。キミは人の形を失って、また断頭台に戻ってしまうだけで、正確には眠りにつくといった方が正しい。そしてまた力を蓄えれば、再び人の姿も取り戻せる。しかし……」
「ならいい。そんな、なんでもかんでも身の回りの整理してたら、ホントに死んじゃうみたい。だから、あの淫魔たちを蹴散らしちゃった後に考える。それでいい」
「……よし。キミがそういうなら、私もこれ以上云うまい。それじゃあ、時間になったら声をかけるから、それまではゆっくりとしているんだよ」
「うん、わかってる」
イザベラが立ち上がり、今度はふつうにアンナマリアの背後にある扉を開けた。
すると、廊下側に立っていた者が声をあげた。
「あ……」
そこには、ジョゼフが立っていた。
イザベラと入れ違いで部屋に入ったジョゼフは、アンナマリアをベッドへと移動させて一息ついた。
ふたりはお互い相手に背中を向けてベッドに座っている。これといった理由があるわけではなく、なんとなくの行動だった。
口が重くなる気まずい沈黙が流れ、それを最初に壊したのは落ち着きのない様子のジョゼフではなく、憮然としていたアンナマリアだった。
「全部、聞いてたんだ」
「えっと、死なないでいる方法、って君が訊いてた辺りから」
「やっぱり全部だ」
「……ごめん、盗み聞きするつもりはなかったんだけど」
申し訳なさで肩を落としているジョゼフの姿がアンナマリアには容易く想像できて、つい微笑を洩らしてしまった。
「別に怒ってないよ。誰に知られたって何かが変わるわけでもないから。ただ、恥ずかしいこと、知られちゃったなあ、って」
「ぼくの方ばかり、聞いちゃってるね」
「じゃあ、そっちも何か話して。恥ずかしい話」
「恥ずかしい話? は、恥ずかしい話……」
顎に手を当て、短く唸る。しばし躊躇しながらも、ジョゼフは意を決して話を切り出した。
「それじゃあ、ぼくと兄さんの話を聞いてくれるかな」
そういわれて、アンナマリアの胸が一度だけ大きく跳ねる。
「……うん」
アンナマリアが緊張しながら頷くと、ジョゼフは一呼吸置いてから滔々と語り出した。
「兄は……ぼくが知る中でもっとも働き者で、もっとも立派な人で、そしてもっとも不器用な人だった」
振り向いたわけではなかったが、アンナマリアの脳裏にジョゼフの寂しそうな顔が浮かんでくるくらいに、その声には陰りがあった。
「ぼ くたちの両親は早くに死んでしまって、だからふたりで自立しなきゃいけなかった。でも困ったことにぼくは今よりもずっと小さくて、無力で……だから兄さん はぼくの分まで頑張ってしまったんだ。あの仕事に就いてたのもそういうわけで、他人がやりたがらない仕事を率先してやらなければ子供に人を養うことはでき なかった。でも、兄さんは余計にお金を稼ごうとした……ぼくに教育を受けさせるために」
「教育……」
「学があれば自分ほど苦労しなくてすむ、って。お陰でぼくは勉強ができたし、武芸の稽古まですることができた。けど、兄さんはそのひとつだって受けちゃいない。絶対に、ぼくよりも兄さんの方が優れていたのに……ぼくがいたせいでね」
ジョゼフの声には後悔の感情が色濃くにじんでいた。普段の温厚な性格からは考えられないくらいの重く沈んだ声に、アンナマリアも慎重に言葉を選ぶ。
「でも、それはそのときのジョゼフにはどうしようもなかった。だから、ジョゼフがいなくたって大変なことに代わりは……あ」
口にしていて、思考が整理されたことにより論理のパズルが急速に組み上がっていくのを感じた。頭の中でぐるぐるとしていたものがひとつの答えを導き出し、現れたのは単純で明瞭なパズルの絵面だ。
「ジョゼフは、もしかして、自分が重荷になっていると思ったから」
「そう、兄さんにぼくが生きていることは伝えなかったんだ」
処刑人である彼が孤独に死んでいったことをアンナマリアは覚えている。それで彼に血縁者なんていないと思っていたし、だからこそジョゼフが大怪我を負って生死の境をさまよったとき、処刑人の彼に対して生存を隠していたことをアンナマリアは憤った。
「腕 を切り落とされて、死にかけたとき……良い機会だな、ってね。ぼんやりとしながら思ったんだ。このまま死んでしまえば、兄さんは自由になる、って。結果的 には魔女先生に助けられて、けどぼくは死んだということにしてもらったんだ。でも……きみがあんなに怒ってたんだ、きっと逆効果だったんだろうね」
「うん」アンナマリアは即答した。「逆効果だった。余計なお世話だった。全力で裏目になってた」
「きついなあ」
遠慮のない言葉にジョゼフは苦笑した。けれど、それには不快そうな様子はなくむしろ清々しさすらあった。
「でも、その通り。ぼくもただ、人にいつまでも保護されているのが嫌で、それから逃れたかったんだ。……ね、恥ずかしい話だろう?」
「予想以上に恥ずかしい話で困惑するくらい恥ずかしい話だった」
「う、うん。まったくもって面目次第もなく……」
「本当に、許すとか許さないとかそういうのもわからないくらい、嫌な話だけど……。でも、わたしは断頭台だから、弾劾する方法は首を刎ねることしかできないし。どうにもしてやれないのがくやしい」
ふう、とアンナマリアは疲労を熱い溜息として吐き出した。
「だから、彼が死んでしまうほどに尽くした価値が貴方にあるのか、わたしに見せて」
「それは、どうやって?」
「……パンでも、焼いてくれればいい。もし不味かったら、そのときは首を切り落とすから」
「な、なにそれ、そんなことで!?」
パンを焼くだけで価値を示せるのか、そしてパンの不出来で生死が決まるのか。アンナマリアの不条理な要求にはそんなふたつの驚きがあって、ジョゼフは思わず背後を向く。
すると、同じく振り返っていたアンナマリアとジョゼフの目が合った。小さな少女は、刃のように真っ直ぐな瞳で相手を見つめていた。
「でも、彼にはパンは焼けなかった。彼にできなかったことをできるっていうなら、充分じゃない」
ジョゼフは口を噤む。兄ならばパンくらいすぐに焼けるようになるはずだ、と思う。きっと、自分のよりも美味しいに違いない、とそこまで考えてもジョゼフは 兄が作ったパンの味を想像できなかった。それは兄がパンを焼いたことなど一度もなかったのだから、当然である。作っていたということもなく、もちろんそれ を食べた経験もないジョゼフには、兄の作ったパンというものは空想上の産物にすぎない。
元より。ジョゼフが劣等感を抱いていた兄の姿は、ほとん どが勝手に作り出された虚像だったのだ。自分のために苦心してくれて、身を削ってくれた兄の強さは、ジョゼフの中で誇張されていったのである。それ故に ジョゼフの方が兄より学力や知能もあるのは間違いないのに、それは兄の環境が酷いものだったからそうなっただけだ、といつも思い込んでいた。事実、そう だったかもしれない。けれど、そうでなかったかもしれない。
どちらにしろ、今ある結果が変わるわけでもないのに。いつだって、勝手に作り上げたイメージに負け続けていただけだ。
「そっか、そうだね。……わかった、明日にでも、つくって持ってくるよ」
兄への負い目はジョゼフの中に沈澱して、なくなることはなかった。今でも、もし兄も自分のようにしていたらどうだったのか、との疑問は消えない。けれど、アンナマリアがパンを焼け、といった相手はジョゼフだった。それは、例え兄が生きていたとしてもできなかったことだ。
アンナマリアにパンを焼いてあげるのは、実にやりがいのある仕事に思えた。
「うん、また明日。その前に……少し、眠い」
しょぼしょぼとした目を擦るアンナマリアに、ジョゼフは相好を崩した。
「ぼくも……。時間になるまで、寝てようか」
「うん」
そうして、ふたりはくすくす笑いながらベッドに倒れて、微睡みへと落ちていく。
目覚めたときには、淫魔たちと争うことになる。
それなのに、ふたりの中には不安はない。意識を手放す寸前まで、総ての事が終わったときへと思いを馳せていた。
だから、廊下で聞き耳を立てているレリアには最後まで気付くことはなかった。
数刻が流れ、時刻は昼にさしかかろうとしていた頃、アンナマリアたちはリビングに集まっていた。
イザベラは腕を組んで悩ましい胸を押し上げながら、首を回してアンナマリア、レリア、ジョゼフの三人の顔を見渡す。ひとりは無表情、かたや笑顔に、緊張した様子の者もいると反応は三者三様であった。
「さて、いよいよ時間的猶予もなくなってきた。今はこの家全体に人払いの魔法をかけて隠匿しているが、それもそろそろ限界……。いい加減、こちらから仕掛けようじゃないか」
声を弾ませて陽気に魔女が謳うと、勢いよくレリアが手を挙げた。
「待ってましたぁ! はーいっ、先生、それじゃあ一番手はあたしが行きまーすっ! やっぱり、何事も一番っていうのが大事ですからね。あたしがサクッと勝利を掴んで、ギヨたんとジョゼフくんにお手本を見せてあげますよ」
ふふんっ、とレリアは得意げに鼻を鳴らすとイザベラは苦笑した。
「やれやれ、レリアも威勢がいいなあ。最初からキミに一番手を頼むつもりではあったけどね。この中で唯一の純粋な淫魔であるキミが一番手には適任だ」
「先生もよくわかってますねえ。初見では遅れをとりましたが、今度はあの小生意気な淫魔たちをあひあひ云わせてあげますよ! もうギヨたんたちの出番なんていらないくらいなんですから」
不敵にレリアが笑えば、アンナマリアは怪訝な顔になった。
「……レリア、どうかしたの?」
「へ?」
「なんだか、様子が変」
「べ、別にそんなことないですよ! あたしは普通ですっ」
「そうは見えないけど……」
「ともかく!」とレリアはアンナマリアの言葉を遮った。「最初はあたしがもらいますから! ギヨたんとジョゼフくんはそこで大人しくしててください!」
レリアの強気な言葉に押し切られて、アンナマリアは釈然としていないまま口を噤む。ただ、引っかかっていたのはアンナマリアだけでなくジョゼフも同じだった。
「れ、レリアちゃん、なにをムキになってるの?」
「ムキになんかなってないですっ」
首を傾げるジョゼフに声を荒げたレリアの頬は、心なしか紅くなっているように見えた。
レリアはこれ以上の追求を拒絶するように大股でイザベラの方へと歩み寄る。
「さあ、先生。そういうことですから、あたしを転送してください。ばっちり敵を仕留めてみせますからね!」
「……難儀な性格してるよね、レリアは」
イザベラが眼を細めて頬を緩めると、レリアはますます取り乱した。
「な、なんの話ですか? もうこれ以上待たせないでください!」
「はいはい。……ああ、そうだ、レリア。その前に」
何事かを思い出したイザベラはレリアに躯を寄せる。
「まだなにかあるんですか?」
むすっ、とレリアは頬を膨らませて怒ると、イザベラは身をかがめてその額にキスをした。
「……へ?」
「いってらっしゃいのキス。たまにはこういうのもいいだろう?」
「ば、ばかなことしてないで早くしてくださいっ!」
イザベラの突然の行動に驚いて、レリアは顔を真っ赤にしてイザベラを何度も叩く。ただ、少女の小さな手で叩かれてもイザベラは痛くも痒いもないようだった。
「ははは、――それでは、武運を祈るよ、レリア」
そういって、イザベラはレリアの目の前で指を弾いた。
*
大々的な儀式は必要ない。
余計な呪文も必要なく、
起こった動作は一挙動。
それだけで、レリアの躯は一秒前までいた空間とは別の場所に跳ばされている。
距離を無視するという通常あり得ざる行為が容易であるわけもない。あらかじめ周到に準備を完了させていたのか、それとも魔女にしてみれば造作もないことだったのか。
どちらにしろ、レリアはわかり切っている事実を胸の中で吐き出した。
――そういえば、先生は化け物なのでした。
一瞬、レリアは暗闇に包まれた。その闇が払われたとき、既に周囲は見知らぬものになっていた。
鼻の奥に纏わり付く匂いがして、レリアは深呼吸してみる。甘い、香の匂いだ。そして、それに混じって、肺をねっとりと熱く満たして蹂躙しようとする匂いがあった。それはとても馴染みのあるものだ。
そこは石造りの部屋で、兵士が十人、二十人いても窮屈さを感じさせないだろうと思うほどに広い。壁にかけられている獅子の描かれた立派な絵画といい、王宮の一室であるのは間違いないだろう。
レリアの前で、ひとりの女が踊っていた。服としての役割も真っ当できそうにない薄い生地の服をはだけて、褐色の肌を震わせて腰を激しく振っている。
突然やってきたレリアに気付いているのか、それとも目に入らぬほど夢中になっているのか。女は甘い声をあげて、床の敷物に寝転んだ男の上で踊っていた。
「あっはあっ! いいよっ、おっきなのがボクの中で暴れてる! ほら、またイちゃって? そっちのキミたちもっ」
女の両脇にはペニスを突き出した男がおり、ふたりのペニスは女の手で扱かれていた。我慢汁と唾液にまみれた肉棒を男たちは女のすべすべとした頬に押しつけると、女はふたつの亀頭を一緒に呑み込んだ。
首を振って、ぷるぷるとした赤黒い肉を激しく唇と舌でなめ回しながら、竿を手で握りしめる。
まるで女が犯されているような構図だった。それでも、レリアにはどちらが事の主導権を握っているのか、悩むまでもなく判っていた。
「ん……っ、ほらっ、ほらっ、ほらっ、……イっちゃえ!」
しなやかなの腰を振りながら、女郎蜘蛛の笑みを浮かべて女は二本のペニスに吸い付く。膣と手で思い切り握りしめられたペニスは、それで決壊した。
男たちは唸り声を開けて腰を女に突きだし、その褐色の肌を白濁とした精液で真っ白に染め上げる。勢いよく飛び出した精液は女の口から溢れて胸に流れ落ちると、ナメクジの這ったような跡を残しながら谷間を滑り落ちて腹筋をなぞり、おへその小さなくぼみに流れていった。
「んくっ、んく……っ」
それ以上こぼさないように手で受け皿を作りながら、女はうっとりとした表情で喉を鳴らして男たちの子種を飲み干していく。その間にも女の女陰はぴくぴくと痙攣し、組み敷いた男のペニスから精液を吸い上げていた。
どさっ、と音を立てて男ふたりが倒れた。女の口へ精を放出していたふたりである。
より正しく云うなら、放出していたのではない。女の手管によって搾り取られたのだ。
ふたりには目も向けず、女は唇をてらてらと濡らす精液の残滓を舌で舐めとる。
「あーっ、 満足っ! やっぱり盛りのついた戦場の男は精液の濃さが違うよね。いつ死ぬかわからないと、女の人をいっぱい孕ませようとして沢山精子作っちゃうのか なぁ? そんなに張り切ってもボクたちがおいしく食べちゃうだけで、なーんにもならないのに。人間ってなんでこう、哀れなんだろう。ね、キミもそう思うで しょ?」
中性的な、それでも女らしいかしましさを感じさせる少女はレリアに笑いかけた。
当の昔に事切れていた男の肉棒を膣から引き抜いて立ち上がる少女に、レリアは頷く。
「そうですねぇ。あたしたちにしてみたら、卵を産んでくれる鶏みたいなものです。結局、人間なんてがんばったって自分ごと全部あたしたちに食べられる程度の存在ですよ」
「だよね、だよね! 必死な顔でボクに腰を振って、感じさせてくれて、妊娠させようと精液を流し込んできて……。そんな子たちを堕落させて、引きずり落としちゃうなんて、とっても刺激的な遊びだよね。キミも淫魔だから、やっぱりそういうこと大好きなんだ、うれしいな」
「そうですねぇ、大好きです。特に気に入った男の子の上で腰を振ってあげたときのもどかしそうな顔なんて、思い出しただけでむずむずするくらいですよ。でも、あなたはちょっと勘違いしてますね」
「え、なに?」
「人間が家畜だけじゃなくて人間すら食い物にしてしまうようにですね。あたしはあなたみたいな身の程知らずな淫魔に躯で現実を教え込んであげるのが大好きなんですよ」
挑発的にレリアが微笑むと、少女は目を丸くした。
喘ぎ声がずっと反響していた部屋に流れるわずかは沈黙は、やはり少女によって破られた。
「面白いねぇ、キミ! 牢獄で会ったときは話せなかったから判らなかったや。いいよ、いいね、そういうの! うんっ、ボクも気持ちいいことは大好きだよ。だから、教えてくれるとうれしいかな、……ええと、キミの名前はなんていうの?」
相手の名を呼ぼうとして、少女はレリアの名前すら知らないことに気がついたのか、そう訊ねた。
「レリア。レリア・キッスです。あと、自分が名乗らないのに人に訊ねるのは失礼じゃないですか」
「あ、そうだったね。ごめんごめん、怒らないで。申し遅れましたっ、ボクは淫蕩のルクスリア。いっぱい楽しもうね、レリアちゃんっ!」
「……淫蕩というより、淫乱の間違いですよね。それに、色欲の間違いじゃないですか?」
溜息をついて、レリアは呆れた。
兵士のような荒々しさのない、踊りを生業とする者特有のしなやかな筋肉の付き方をした肢体にはランジェリーのような透けて見える服しか身に着けられていな い。さらに、褐色の肌には精液が塗りたくられて、どこもかしこも壁際で揺れる灯を受けていやらしい光沢を放っている。ここで事切れている男三人以外にも、 ルクスリアが躯を洗う手間すら惜しんで男と行為に没頭していたのは明かだった。
レリアの云いように、ルクスリアは訝しげに眉を寄せた。
「色欲より、淫蕩の方がえっちっぽいよね! ……ええと、淫蕩と淫乱って、なにか違うの?」
「淫乱は、ただ淫蕩に乱されて、振り回されてるんですよ。淫蕩は、人を惑わす現象そのものなのです。持論ですけどね」
「うーん、やっぱりわかんないや。だから、レリアちゃんの躯で教えてね。……そうだ、それならもっと人がいた方がいいよね! おーい、みんなこっちに入って来てー!」
ルクスリアが声を上げると、レリアの背後にある荘厳な装飾の施された扉が開かれる。
レリアが扉を振り返ると、五人ほどの男たちが入ってきたところだった。屈強な肉体を持った、レリアと比べたらクマみたいな大きさの男たちである。腰に剣を はいていることから兵士なのだろうが、それにしては口周りにみっともなく生えた髭といい、煤けた髪といい、あまりに粗野である。まるで手入れをしていな い。
そこまで見て、レリアは男たちの目が虚ろなことで昨日のことを思い出していた。牢獄で襲いかかってきた淫魔のペットに似ているのだ。
「なるほど、あの牢獄の兵士たちはあなたが食べた残り滓だったというわけですね。それと、この人たちも」
道理で見た目が汚いわけである。何故なら、男たちはもう快楽を受けることしか頭には残っていないのだ。放っておいたら食事すらするかどうか。
「残り滓だなんて人聞きが悪いよぉ。あれはね、ただ、多めに手をつけておかないと数がすぐに減っちゃうからだもん」
「加減ができないなんて、さすが淫乱ですね。その性欲には淫魔でも脱帽しますよ。きっと、その淫らさだけで七つの大罪の位を名乗ることを許されたんでしょうねー」
「むむっ、ちゃんと他の淫魔たちをメロメロにして、淫蕩って呼ばれて良い? って聞いたもんっ! まあ、あんまり興味なかったんだけど……みんな涎を垂らしながら頷いてくれたよ。それでね、今からキミもそうなるんだよ」
にこっ、とルクスリアは場にそぐわぬほどの天真爛漫な笑顔を浮かべた。
「それじゃ、みんなー、えっちの時間だよっ」
緩慢だった男たちの動きが速くなる。レリアという見たこともない新しい少女に男は一斉に群がった。リンゴなんて軽々と潰せてしまえるであろう大きな手でレリアの腕を掴むと、男のひとりが床に放り出した。
レリアは尻餅をついて痛みに声をあげると、ルクスリアを睨み付けた。
「ちょっと、女の子はもっと乱暴に扱ってくれなきゃ困りますよ! それとも、激しくされるのがあなたの好みだったんですか?」
「うんっ、やっぱり男は活きがないとダメだよね。そういう人たちから搾ってあげるのが楽しいんだから」
「それは動感ですけどね」
賛同を示したレリアの前で、男のひとりが下半身を露出した。既に臨戦態勢となった垢まみれの剛直が目の前に突き出されて、レリアは目を丸くする。
「うわあ……お馬さんみたいな太さですね」
「ボクが選りすぐった兵隊さんだもん。たっぷり味わってね!」
ルクスリアの言葉を待っていたわけではないだろうが、ちょうどそれを合図にして男はレリアの髪を掴むと口へと乱暴にペニスをねじ込んだ。
「もがっ」
明かに口よりも大きな肉棒を押し込まれて、顎を外れそうになるくらいに開けたレリアは目を丸くした。
男は両手で頭を掴むと、腰ではなくレリアの頭を激しく動かした。蟲でも沸いていそうなくらいに茂った陰毛でレリアの顔を撫でながら、馬並みのペニスは舌と口内の肉を蹂躙する。
その間に別の男が背後に回っていた。尻餅をついたレリアの細い腰を掴むと易々と持ち上げて床の上で四つん這いにさせる。無防備に突き出された白いお尻に、意識のないはずである男は生唾を呑み込んでいた。
こちらもまた馬のように逞しい肉棒を取り出すと、幼い菊座に宛がい、一息で貫く。
「んー!?」
前戯もなにもなしでアナルにペニスを突き込まれて、別のペニスで口を塞がれたレリアは喉で悲鳴をあげた。
男がレリアのお尻に腰をぶつけると、ぱちんっぱちんっ、と柔肉が甲高い音を立てる。男はレリアの腰を掴む手の力を強めるとますますペースをあげてペニスでアナルを貫く。
ドリルのような亀頭に肛門を掻き分けられて、レリアの目が情欲に濡れる。地面につかされていた腕を目の前にいる男の腰に回すと、自分からペニスにむしゃぶりついた。
「じゅ……んんんっ! ん! ふっ、んぐ……あっ、はぁあああ……っ!」
呼吸をするのも忘れて獣のように男の肉棒を舐め上げれば、おおきな男の躯は面白いくらいに震えていた。クマと幼女といったほどに体格差があるというのに、少女の華奢な躯に、男はまるで戦場で命の危機に瀕しているときのように震えているのである。
それはレリアの菊の穴を犯す男とて同じことだった。
性欲を満たすためだけに腰を振る男は、いつしか腰を止めることすらままならなくなっている。例え腰が痛くなろうとも、休むことさえできないのだ。脳内の神 経を巡る快楽に、男は逆に犯されていた。それが少しでも衰えてしまうと気が狂ってしまいそうになっている。もっとも、この快楽が既に男の気を狂わせている からこうもなってしまうわけだが――。
「ふっ……ふふっ」
レリアは妖しい笑みを浮かべて、男を上目遣いで見上げた。目と目が合い、男は心臓を鷲づかみにされたような錯覚に陥る。視界から脳内を犯されているような、甘く蕩ける視線。
そして、レリアは括約筋に力を込める。手で握りしめられたような強い締め付けに、アナルにペニスを突き入れていた男が呻いた。
「ひゃあ……おふぁりです」
終わりです、と宣言して、レリアは頬をすぼめてペニスに吸い付くと同時にかわいらしいお尻を捻った。
舌が蛇みたいに雁首へ絡みつくぬめりとした感覚と、ペニスを襞だらけな肉で締め付ける快楽に選りすぐりの兵士たちといえども耐えることはできなかった。
「んふ……っ、んっ!」
どぷっ! どぷんっ! どぷどぷっ!
男たちの精液が、レリアの口とお尻の穴に注ぎ込まれる。それでもレリアは休むことなく肉棒に吸い付き、お尻をふりふりと振った。
止まらぬ刺激に、男たちの射精もまたとどまる事はなかった。地盤を破って噴き出した間欠泉のように、男たちは尽きることない射精の快楽に声をあげた。
それが一分以上は続いたか。ついに男たちの射精は収まる。
同時に、男たちが力をなくして床に倒れた。そんな中でも、レリアは何事もなかったかのように立ち上がる。指についた精液を淫靡に舐めとるレリアの背中には、一対の羽根がマフラーみたいに揺れていた。
「今日はのんびり男の人と遊ぶつもりなんてないんですよ。――ただの性欲自慢な精液袋に用はありません」
高位淫魔であるルクスリアの躯に慣れさせられた男たちを瞬殺して、レリアは傲岸不遜に言い放った。
「さあ、あなたも遊んでないで付き合って貰いますよ」
そう、男三人の肉棒と戯れているルクスリアに言い放った。
レリアが男二人の相手をしていたときから、ずっとルクスリアは残りの男たちと性行をしていたのである。
最初からルクスリアに男でレリアを犯し尽くして屈服させようなどという肚はなく、楽しむための玩具として呼び出していたのだ。
後座位で男に性器を突かせて、残りふたりのペニスから口で精を啜っていたルクスリアは、にこにこと笑みを浮かべている。
「えへへ、そうだね。そんな、ふたりだけじゃ満足なんてできないよね。うん、わかった。じゃあ……ボクが気持ちよくしてあげるよ」
振っていた腰を止めて、ルクスリアは立ち上がった。ぬぷっ、と秘所から勃起したペニスが抜け落ちる。
「おっと。はい、ご褒美」
名残惜しげにビクビクと震えるペニスに眼を細めて、ルクスリアは足の指でその裏筋をなで上げる。
それだけで、どぷっ! と男の肉棒から精液が溢れだした。
足の裏を汚す暖かい子種の感触に満足して、ルクスリアはレリアの方へと向かう。白目を剥いて射精を続ける男にはもう目を向けなかった。
「それじゃあ、楽しくえっちしようね? うんと、やっぱり沢山気持ちよくなるなら、これがいるよね」
そういって、ルクスリアは愛液と精液に塗れた陰部に手をかけると、陰核をきゅっとつまんだ。すると、陰核は膨張をはじめる。指先ほどの大きさだったもの は、あっという間に勃起した男のペニスへと変貌していた。愛液でべとべとになったペニスは、先程レリアが銜え込んだ男と同等の迫力がある。
「これくらいで、いいかな?」
「立派なものですねぇ。ええ、構いませんよ。あたしの中でたっぷり気持ちよくしてあげますから……」
レリアは自信満々に云いきって、昂揚で乾いた唇を舐めると床に座ってM字に股を開いた。
ルクスリアはレリアに覆い被さり、ペニスの先端をまだ精液で汚れていない性器に押し当てる。野良猫みたいに目を細めて、ルクスリアは相手の目を覗き込んだ。
「それじゃ、行くよ」
つぷっ、と亀頭が女陰に沈み込む。レリアの躯には大きすぎるペニスは、濡れていた愛液で驚くほど簡単に入り込んだ。けれど、簡単に挿入できたのはなにも濡 れていたからではない。初々しい見た目に反して使い込まれたレリアの躯が、むしろその男性自身を淫らに求めていたからだ。
陰核が膨れあがってできた肉棒がレリアの膣肉を掻き分けて、ずんっと奥へと入り込んでいく。竿に加わる甘美な締め付けに、ルクスリアの頬が緩んだ。
「ああっ、すごい……こんな締め付け、久しぶり……っ」
「あたしの中にいれたのが運の尽きでしたね。あはっ、逃がしませんから覚悟してくださいね?」
捉えた獲物に微笑みながら、レリアは足を相手の腰に回してがっちりと捕まえる。そのまま力を込めて、一気にルクスリアを自分の方に引き寄せた。自分の意志とは関係なしに深く挿入されて、褐色の肉体は快楽に打ち震えた。
胸を反らせ、ぴんっと張った淡い色の乳首を突き出したルクスリアは熱く吐息を洩らす。肌を流れ落ちる汗は部屋に焚かれた香よりもなお甘い香りで、精の青臭さと香に汗が交わって、胸を焦がす淫蕩な芳香となって部屋に充満した。
レリアが腰を捻る度に、ルクスリアは面白いほどに喘いだ。膣をねじって襞で雁首を抉り舐めると、口の端から涎を垂らして快感に震えていた。
今にも流れ出すのではないかというほど瞳を蕩けさせたルクスリアの胸に唇を寄せて、レリアは乳首をついばんだ。
「ひゃっ、やっ、そんなとこ吸っちゃダメだよぉ」
それを無視して腰を揺すると、すぐにルクスリアの抗議は嬌声へと変わった。
胸越しに相手の鼓動を感じながら、レリアはルクスリアが本気でよがっていることを確信してほくそ笑む。
ルクスリアの敗因は慢心だった。
淫魔が持つ陰核の役割は、人間の女性と変わらない。性感を高め、快楽を得るために発達したものである。当然、他の部位に比べ殊更に敏感だ。
レリアに挿入されたペニスは、元はと言えばその陰核が強制的に発達させられたものである。膨張した陰核は、通常の男性が持っている肉棒よりもずっと鋭敏な神経を持っていた。例えるなら、ルクスリアの疑似ペニスは総て亀頭と同じ性感なのである。
それでも挿入した相手が人間の女であったなら、ルクスリアはなんの苦もなく犯しぬいていただろう。淫魔で一番敏感な部位といっても、精を搾るために生まれ たような肉体である。生殖の付随機能として快感を覚えるようになった人間の躯程度に快楽で溺れさせられるようなことはない。
けれど、ルクスリアが挿入した相手は人間の女ではなかった。自分と同じ、男を籠絡して精液を搾り取り、天国へと導く搾精器官を持った淫魔なのである。
なのにそんな一物を淫魔の蜜壺に突き入れて、無事で済むわけがなかった。
「あたし、えっちを楽しむのは良いことだって思うんですけど。でも、相手を間違えちゃいましたねぇ?」
ぐちゅっ、ぐちゅっ、とレリアの腰を掴みながらルクスリアは必死になって肉棒で膣を突く。与えられる電流のような快感で、今にもその腰は砕けてしまいそうだった。
「ふぁ、ああ……すごい……こ、腰が止まらないよぉ」
「こんなに気持ちよくなったのは初めてですか? 男の人たちにいっぱい突かれても、こんなに気持ちよくなんてならなかったんですよね? いいですよ、あたしの中に全部出しちゃって。お布団に包まれて眠っちゃうような、そんな心地良さの中で果ててください……」
レリアは足に力を込めて相手と深く深く密着すると、トドメとばかりに膣の力を強める。
ねっとりとした蜜に塗れた膣肉が肉棒を包み込み、ルクスリアは一際高い嬌声をあげた。
「はあっ、だ、ダメ、イク……イっちゃ……ひゃ、あ、ひゃああああああああっ!」
レリアは自分の勝利に勝ち誇った笑みを浮かべて、ルクスリアの精を子宮で受け止めた。
どぷぅうう――っ! どくんっ、どくどくぅ――っ! びゅっ、びゅ――びゅ――っ!
「これで、あなたもあたしのとり、こ……にひゃう!? な、なんですか? や、やだ、来ちゃ……来ちゃうぅううううにゃああああああ!」
ルクスリアの元気が良い射精を受け止めた、そう思ったときにはレリアの頭からつま先にかけて稲妻のような快楽の衝撃が走っている。
それは、レリアが絶頂したことを意味していた。
肉棒から流し込まれる熱い、それこそマグマのようにぐつぐつと煮えたぎった濃厚な精。それはレリアがこれまで搾り取ってきた男たちとは比べものにならない射精の勢いと量、質があった。
その濃厚と云う言葉では足りないほどに濃い精子は拒むこともできずに子宮に流し込まれ、レリアの小さな躯では受け止めきれない精液がふたりの結合部から噴き出した。
「や、やだ、なんなんですか、これ……射精させて、射精されてるだけなのに、なんで……なんでこんなに躯が……ひゃああああっ!」
それでもルクスリアの射精は止まらない。快楽で緩んだ表情のまま腰を突き出して、何度も何度も精液をレリアに流し込む。ねっとりとした白いゲル状の液体に犯されて、レリアの小さな躯は幾度も跳ねて絶頂した。
びゅくっ! とペニスが震えて精を吐くと、ビクンッ! とレリアの躯は震えて達することを繰り返す。
「あ、あ、あ……っ」
目を大きく見開いて、半開きになった口から唾液を垂らすのはルクスリアではなくレリアだ。連続でいったい何回、何十回とイかされたのか。既にその口は肺が痙攣して出す喘ぎ声しか洩らすことはできなくなっていた。
そんなレリアの頬を褐色の手が撫でる。ルクスリアの表情には、まるで我が子を慈しむ母親のような包容力があったが、その仕草はどこまでも淫ら。
「えへへ……どう、気持ちよかったよね、ボクの精子。ホントはこんなに出すつもりはなかったんだけど……レリアちゃんの中が気持ち良いのがいけないんだよ? そうじゃなかったら、こんなにイかなかったんだから……って、聞こえてる?」
ルクスリアが腰を引いて、一気に奥まで突く。
「ひゃう!?」
「あはっ、聞こえてるね?」
「あ、ああ……」
反射的に涙を流しながら呆然としているレリアに、ルクスリアはくすくすと笑った。
「そ んなに味わってくれると、ボクも出した甲斐があるなあ。実はね、ボクの精液にはすっごく強い催淫効果があるんだよ。なんでもね、ボクが呑んできた精気が凝 縮されてるんだってさ。それがこんなに効果覿面なんておかしいよねえ、だってボク、このお城に入る人たちよりちょっと多いかなってくらいの人たちからしか 搾り取ってないのに」
王宮ひとつに入りきらないほどの男の精液を飲み干してきた――。そんな途方もない言葉を、快感に朦朧となったレリアの頭で理解するには長い時間を必要とした。
「どうしたの、レリアちゃん。淫乱と淫蕩の違いを教えてくれるんだよね? ほら、続き、しよっ」
無邪気に笑って、ルクスリアがレリアと唇を重ねた。
「や、やめ……ひゃあっ!?」
キスしたまま、ルクスリアはずんっ、とレリアの子宮口を亀頭でノックした。絶頂の余韻さめやらぬレリアの躯にはあまりにも刺激的すぎて、また軽く達してしまった。
「やめてって、またなんで? ……あ、そっか。ずっと同じ体勢じゃつまらないもんね!」
「そういう意味じゃ……っ」
レリアの文句はルクスリアには届かず、あっという間にふたりの体位は変わっていた。
ルクスリアは背中を床に預けて仰向けになり、その上にレリアが跨る、所謂騎乗位となる。淫魔が男を犯すときによく使う格好だったが、今の主導権は跨っているレリアではなくペニスを銜え込まれたルクスリアにあった。
「あ、これだけじゃ物足りないかな? じゃあ、ふたりとも、レリアちゃんを楽しませてあげてっ」
ルクスリアが呼びかけると、ずっと棒立ちになっていた男ふたりが蜜に群がる蟲のようにふらふらと寄ってきた。屈強な男のペニスはルクスリアにおあずけを喰らっていたためか、既に臨戦態勢をとっていた。
「え、だ、ダメですよ、今は……はうっ」
レリアの言葉は男たちに届かず、無理矢理ペニスを口の中に入れられて頬肉に亀頭を押しつけられた。同時にふたつの馬並みペニスをねじ込まれて、レリアの顎は外れそうなくらいに開かれる。
「ほらほら、下からもっ、行くよ!」
リズミカルに突き上げてくる肉棒にレリアの華奢な躯はバネで押し出されるように跳ねる。
今まで感じたことのないほどの膣をペニスでかき混ぜられる快感。それ故にレリアは咄嗟に快感を受け流すことができない。
「んーっ! んーっ、んーっ、んーっ! んんんん――――っ!」
膣の締め付けが強くなる。それはレリアがまた絶頂を迎えた証拠だった。
男たちはレリアの髪の毛を掴むと、強引に腰を動かして口内を蹂躙する。頬肉に垢を擦りつけ、歯茎をなぞり、舌に竿を扱かせる。
強制される口淫と、突き上げてくる快感。それに文字通りレリアの頭の中は真っ白になっていた。
「ああっ、レリアちゃんの中って最高だよぉ! ボク、またイっちゃうねっ」
何度イっても疲れた様子のないルクスリアの叫びに、レリアは子宮が疼くのを感じた。
もっと、もっと精液が呑みたい――。
気持ちよくなりたい――。
漠然とそう思っていたとき、またしても濃厚な精子が子宮に飛び込んできた。
びゅっ、びゅっ、と勢いは衰えを知らずに膣内を白濁とした淫液で満たしていく。それに遅れて、口内で男たちのペニスが爆発した。
口の中に広がるむせかえりそうになる精の青臭さと、窒息しそうになる精液の量にレリアは目眩を覚えた。
「はう……は、ああ……」
イきすぎて躯に力の入らなくなったレリアは、男の汚い太腿に寄りかかって掠れ声を発するのが精一杯になっていた。
なのに、ルクスリアはまた思い切り下からレリアを突いて無理矢理たたき起こす。
ひゃうっ、と悲鳴をあげる少女に、ルクスリアは笑いかけた。
「……ね? まだ、お終いじゃ、ないよね?」
「あ……ああ……」
底なしの性欲に、レリアはしばし呆然とした。
「こんな程度じゃ、レリアちゃんも満足できないよね? だって、そうでしょ。ボクたち七罪を冠した淫魔は世襲でもなんでもなくて、実力で前任の人をたおしてなるものなんだから……。それに挑もうって淫魔が、こんな簡単に倒れちゃうわけ、ないよね?」
淫魔の社会は、人に比べると穏やかなものだ。彼女たちの社会には明確な競争はないのである。勿論、上昇思考は持っているが、それを最優先事項にすることはまずない。淫魔は淫らでふしだらにして怠惰な生き物なのである。
それは男に頼れば、彼女たちは何不自由なく生活をできるからだ。もし寄生している男が息絶えれば、また別の男のところへ。淫魔の美貌と床の技術は、どんな名家の子息にでも取り入れるだけの力があったのである。
その中での例外が七罪の名を冠する淫魔たちである。
それは高位淫魔として一級の実力があると認められる名誉の称号なのだ。そんな称号をとるためには、前任者を退ける必要がある。淫魔と淫魔で床の勝負である。
故に七罪だけは競争意識があった。さらに、七罪は挑戦者を拒めない、実力主義の頂点。
それだけの競争を勝ち抜いた淫魔の中の淫魔が、そう簡単に倒れるわけもなかったのだ。
「そんな……こ、このままじゃ……っ、あたし、頭がおかしくなっちゃ……」
にこにことルクスリアはボーイッシュな顔で笑った。
「なら、一緒におかしくなっちゃお?」
下から突き上げられて、レリアの口内で溜まっていた男たちの精液が溢れだし躯を真っ白く汚していく。
「ひゃっ!? あ、ああ……っ、あうぅうう……」
もう四肢に力は入らず、レリアの下半身はルクスリア、口は男たちの好きなようにされるだけだった。
レリアの躯に注ぎ込まれる精気は、既に数千、いや、万にも届こうかという男から搾った精と同じ量があった。ルクスリアの肉棒から溢れる精液の密度はそれだ け法外だったのである。いくらアルコールに強い者でも度数が百もあるものを摂取すれば倒れるように、いくら淫魔といえどもこれだけの濃さの精液を一度に叩 きつければ無事では済まない。
そんな精気を溜め込んで平然としていたルクスリアはレリアとは比べものにならない精気の許容量があるということで、基本スペックからして差は歴然だったのだ。
レリアの躯ではルクスリアには遠く及ばない。
そのことを拒みようがないほどに躯へ刻み込まれた。
「レリアちゃんはかわいい声で鳴いてくれるねっ! そんなにボクのおちんちんが気に入ったのかな。それじゃ、もっとイってもらおうかな」
このままでは、犯されてルクスリアの餌となってしまう。
レリアの躯では勝てない。
しかし、ここにきても、まだ揺るがないひとつの事実があった。
ルクスリアの敗因は慢心である。
小さく揺れるレリアの胸に伸ばされたルクスリアの腕が掴まれる。押しとどめたのは他ならないレリアだ。
「あれれ、まだがんばってくれるの?」
「はい……あと三分間だけ、付き合って貰おうかと」
汗と精液に濡れた顔で笑うレリアに、ルクスリアは不思議さで目を丸くした。
「ええ、あと三分だけ……」
レリアの背中から生えていた一対の翼が窓もない部屋の中でゆらゆらと揺れはじめた。
風が吹いていた。
最初は微風。どんどんと風は強くなっていき、前髪が持ち上がって額が見えるほどになっていく。
その風の中心にはレリアの躯があった。
口の中からぬるりと男たちのペニスを離すと、レリアは唇を蛇のように舐めた。
「……付き合って貰います。あたしの本気よりも、もっとすごいものを感じさせてあげますよ」
そうして、少女の躯に変化が生じた。
胸が膨らんでいく。見た目相応の控え目な胸が、ふっくらと姿を変える。
現れるのは、片手で掴んでもこぼれおちてしまうほどに大きな乳房。
変化はそれだけではなかった。
胸の変化に同調して、レリアの躯が大きく変化していた。
手足は長く、舞台の女優のように細く、逞しく、優雅な肉つきのそれに。お尻は思わずむしゃぶりつきたくなるほどの曲線を描く。
数年かけての成長を数秒の間に圧縮すればこうなるのか。短く切られていたオーロラ色の頭髪は腰の位置よりも低く、座っていれば床に落ちるほどに長い。オーロラを夜空から切り取って編んだ帯のようだ――そう幻想を抱かせる、超常的な美しさだった。
いつの間にか、ルクスリアの肉棒を膣で銜え込んでいるのはレリアではなく、彼女の変化した情熱的な美女になっていた。
唖然としているルクスリアに、美女はくすりとほほえみかけた。
「――さて。この躯を使うのは久しぶりなのだけど。改めて挨拶をした方がいいかしら、ルクスリア?」
「え、え、レリアちゃん、だよね……?」
「そうよ。もっとも、この躯のときは襲名した名前を名乗っていたのだけど……そうね。ややこしいから、あたしのことはレリアと呼んで貰って構わないわ。ルクスリアがふたりいては面倒だものね」
「る、ルクスリア? それって、ボクと同じ……もしかして!?」
思いの外察しの良いルクスリアに、レリア――と自称した女性はほほえんだ。
「ええ、お察しの通り。先代の色欲――淫蕩のルクスリアよ。あなたとは初見だけどね」
先程、ルクスリアは自分が淫蕩と呼ばれるために淫魔たちと戦ったと口にしていた。だが、それはおかしい。七つの大罪の襲名は、襲名者を倒すことで得られるものである。他の淫魔たちにわざわざ認めさせる必要はない。
「まあ、それも当然よね。あたしは何年も前に行方をくらましてしまったんだもの。人間にでも倒されたんじゃないかって、騒動にでもなっていたかしら?」
「そ、そりゃすごい大騒ぎになって……って、なんでそんな人がレリアちゃんになってたの!? しかも、敵になってるし!」
「別に称号があったとしても、あたしたちは味方というわけではないでしょう? 利害が違えば敵にだってなるわ。それに、あんなちっちゃい姿になっていたのは……ふふ、あなたたちの思っていた通り。あたしが人間に負けたからよ」
「嘘……」
「あ ら、ホントよ。もっとも、あれは人というより魔女だけど。しかも、その上で力を封印されて、あんなに小さな躯にされて助手としてこき使われたんだか ら……。でも、ちゃんとあのときはあの人をイかせてみせたけどね。あんなに気持ちよさそうにしてる顔を見たのはあれが最初で最後だったわ……」
頬に手をあててうっとりとするレリアを呆けながら見ていたが、はっと我に返るとルクスリアは豊満になったレリアの胸を掴んだ。
うなじを撫でてくるように色っぽい声をあげるレリアを前に、ルクスリアは完全に調子を取り戻していた。
「よく考えたら、レリアちゃんが誰だったかなんて関係ないよね。だって、もっと楽しめることには変わりないんだもんっ」
舌なめずりをして、ルクスリアはまた下からレリアの躯を突き上げる。幼い見た目のためにふわふわと軽かった前までのレリアと違って、今のレリアは十代後半 の完全に成熟した躯。そのため、ペニスに加わる感触もまた違ったものになっている。レリアが重くなって、より奥までペニスがねじ込めるのだ。
両手でレリアの乳房を揉みしだいて、膣の中で肉棒を暴れさせる。ぐちゅぐちゅと蜜壺をかき回す音とレリアの喘ぎ声が卑猥な合唱となって石壁に反響していた。
「んあっ! ああ……っ、まったく、人の話くらい最後まで聞いてから動きなさいな。これだから堪え性のない淫乱はっ」
「レリアちゃんだって、ボクの精液と愛液で中がぐちゅぐちゅだよ? イきたくてイきたくて、我慢できないんだよね! ほら、君たちもぼーっとしてないで……お尻とかおっぱいとか、使ってあげて!」
ルクスリアがレリアの乳房から手を離すと、男のひとりが前に回り込んだ。ルクスリアをまたいで、男は肉棒を正面からレリアの胸へと押し当てる。
ぷにっ、と亀頭に伝わる感触にペニスが射精する間際のように脈打つ。乳房を乱暴に掴むと、そのままペニスを挟み込ませた。
レリアの口から溢れ出た精液で濡れた胸の谷間に極太の肉棒が潜り込む。すっかり大きくなった乳房は、しっかりと男性自身を銜え込んで離さない。
ペニスを包み込む極上のクッションのような乳房の圧力に、男は腰をがくがくと震わせながらレリアの胸を突き上げる。
「んっ、久しぶりのおっぱいなんだから、もっと丁寧に扱ってほしいわ……んあっ」
白濁塗れになって泡を立てながらじゅぽじゅぽと胸の間から顔を出す亀頭を眺めていると、レリアの菊座にもう一人の男のペニスが宛がわれた。
躯が小さかったときに別の男に射精させた精子が、まだ後ろの穴にも残っていた。レリアのアナルは簡単に男のペニスを受け入れる。
ずんっ、と一気に奥までペニスを突き入れられた。その衝撃にレリアは躯を仰け反らせて喉の奥から嬌声を洩らす。
「あっはぁ! 淫魔と男のおちんちんで一緒にされると……すごいわね……っ」
「それがボクにも伝わってくるよ……レリアちゃんの中もきゅんきゅんって締め付けてくる! ボクも気持ちよくて……またイっちゃうね!」
乳房と膣とアナル。同時に三つをかき回さす肉棒の速度はフィニッシュとばかりに動きを早める。
「イくよ、イくよ、レリアちゃん! 全部受け止めてね!」
「んんっ、ああ……あたしも……っ! あああんっ」
レリアの腰を両手で掴んで何度も突き上げていたルクスリアは、形の良いお尻に力をいれて思い切り肉棒を押し込んだ。
大量に出された白濁と愛液の混じり合った混合液で濡れた膣に締め付けられる感覚に酔いしれながら、また精液をレリアの中にぶちまける――。
「あは……出てる、沢山レリアちゃんの中にでてるよっ」
どく……どく、どく……っ! 放出される精液は今日一番の量で、子供を育てる子宮の中をあっという間に白濁とした子種だけで満たしてしまう。
「あ……ああん……っ」
同時に達したレリアの膣が甘くペニスを締め付ける。きゅっ、きゅっ、とまだイっている最中の肉棒を刺激して、それがさらにルクスリアの射精を助長した。
たっぷりと放出される媚薬のような精液に、レリアの美しい顔が艶美に蕩ける。その顔を目掛けて、レリアの胸でペニスを刺激した男も射精した。
胸が変形するほど力を込めて肉棒を圧迫すると、男のペニスから飛び出した精子がレリアの顔を真っ白に染め上げる。ドロドロの砂糖細工でデコレーションされ ていくレリアは、射精を続けるペニスに唇を押しつける。ぷにぷにと弾力のある唇で亀頭に吸い付き、夢中になって精液を呑み込む。
「んん……っ、んー! んふ……っ!」
獣のような激しさで首を振り、ペニスから一滴残らず精子を搾りだそうと自らの手で胸を圧迫する。
そして、レリアの臀部に腰を寄せながら、最後の男もまた限界を迎えていた。
アナルの中に流れ込んでくる、汚らしい男の精子。直腸に直接叩き込まれるどろりとした粘液の感触に、アナルはきゅっと勢いよく絞まった。
性器と、排泄器と、口。レリアはその三つへ同時に子種という白濁を注ぎ込まれていた。
「あはは……これで、ちゃんと先代の淫蕩も堕としちゃったんだ……。これで、誰もボクに文句なんて云わないんだね……」
射精をしながら、ルクスリアは頬を緩ませたまま自分の成した行為の結果に酔いしれる。
「あら、それはどうかしらね……」
「え?」
そういったのは、胸に挟んだペニスから顔を上げたレリアだった。
胸に精液を注いでいた男が直立不動になったまま動かなくなっていた。それをレリアが横に押すと、抵抗なく地面に倒れる。自我をなくした肉人形は精を搾り尽くされて息絶えていた。
もうひとつの何かが倒れるどさり、とした音。レリアの菊座に挿入したまま、最後の男も力尽きていた。
「射精、まだ止まらないみたいだけど?」
「あ、あれ……そんな、おかしいな……なんで、ずっと止まらな……あぁあうっ」
戸惑っているルクスリアのペニスを膣が締め付ける。
「止まらないわよねえ。だって、そうしているんだもの」
「ふぇ……?」
「だってあなた、淫魔としての力はあたしよりも凄いのだけれど。技巧もなにもないじゃない。大方、周りの淫魔たちもこのおちんちんだけで喘がせてただけなんでしょう?」
「そうだけどっ」
「格下ならそれで瞬殺できたでしょうけどね。自分と同等の相手にこんな敏感でかわいらしいもの挿入しちゃったら……それこそ淫魔と人間くらい差が出るに決まってるじゃないの」
レリアが唇についた精液を舌で舐めとる。高位淫魔であるルクスリアですらぞくりとするほどに艶然な仕草だった。
「光栄に思ってね……これが、人間と同じ立場で感じられる、淫魔の妙技よ」
ぐにぐにとレリアの膣が動き出す。襞が上下に、左右に、あるいは捩るように、包み込むように、ぐにぐに、ぐりぐり、ぐにぐに、ぐりぐり……。
「や、や、やめ……っ! だめぇ……しゃ、射精がとまらないよぉ……!」
「止めて欲しいの?」
レリアが首を傾げて、腰を持ち上げる。膣から開放されていくペニスに、ルクスリアは胸を上下させて荒く呼吸を繰り返した。
「ひあ、あ……や、やめ……」
「うふふ、だーめっ」
体重を乗せてレリアは一気に腰を落とした。
ずぷんっ! とルクスリアの肉棒が襞に擦られながら呑み込まれる。とまらない射精で神経がむき出しになったも同然なペニスに与えられる刺激は淫魔をも狂わせた。
「や、あ、あああああああああっ! 頭っ、ボクの頭っ、飛んじゃうよぉおおおお!!」
どくんっ! どくんっ! どくんっ!
びゅくっ! びゅるるっ、びゅるっ!
どぷっ、どぷどぷ……っ、どぷんっ!
「あ、あう、ああ……」
大きくなったレリアの膣内にも入りきらなくなった精液が結合部から流れ出す。床の敷物も吸収しきれないほどの白濁液が水をぶちまけたように床に広がっていった。
「あ、ああ……」
「ふふ……」
終わらない快楽で気絶したルクスリアの頬をレリアの指先が撫でる。それは自分の跡継ぎに向ける賞賛のような行為だった。
「あなたが油断してくれなければ、この姿でも負けていたでしょうね。力を封じた状態で仕掛けて、正解だったわ……」
んっ、と声を出して足に力を込めるとレリアは立ち上がって膣からペニスをぬく。そこで躯に力が入らなくなった。
床に尻餅をつく――そのときには、もう少女の姿に戻っていた。
本来の姿に戻ってちょうど三分が経過していた。
「先生ったら……キスするついでに封印を緩めてくれるんなら、もっと長い間動けるようにしてくださいよね」
不満を零して、レリアは床に大の字になって寝転がる。もう起き上がることすら億劫だった。
レリアは自分に失望していた。
ひとりで他の全員も相手をする。そう啖呵を切ったくせにルクスリアひとりを倒したくらいでこうも疲れて果てている自分自身が、どうしようもなく情けなくなかった。
――あたしが無理をすれば、ギヨたんは何もしなくて済んで、寿命は少しでも延びるかもしれない。
魔が差したと表現のできる思考だった。
レリアも自分らしくない考え方だと自覚していた。
しかも、アンナマリアはいうなれば自分の獲物を奪おうとする敵である。それこそ、この高位淫魔たちよりもレリアにとっては脅威度の高い敵である。
なのに、どうしてだろう。
友情? 同情? 愛情?
考える。
……どれも、違う気がした。
友情と云えるほど綺麗なものはふたりの間にはなかったし、同情に至ってはそんな感情を抱く理由がない。アンナマリアは自分の意志で決断した。その道を哀れ むのは、なによりも彼女を冒涜することだとレリアは思っていた。愛情は論外で、それに類した感情は一切持っていない。躯を重ねたことはあっても、あれは淫 魔にしてみればじゃれているようなもので、スキンシップの一環なのだ。
では、他になにがあるか。
レリアは目を閉じる。
自分を駆り立てた感情がなんであるのか、やはり名前をつけることはできなかった。もやもやと、ぐるぐると、胸の裡で巡る霞みのような気持ちの揺らぎは掴もうとしても指の間をすり抜けていってしまった。
掴もうとしても、逃がしてしまう。それが大切なものであるはずなのに、自分では理解できない。
胸に喪失感が浮かぶ。判るはずの感情、掴めなければおかしいはずの感情を取り逃してしまったが故の悲しみ。
ふと、抱いた感情がアンナマリアに向けている感情と同じであることに気付いた。
ああ、そうだ、とレリアは笑う。ようやくちぐはぐだったパズルのピースが揃った。
――あたしは、寂しかったんだ。
たとえ、出会ってから数日としか経っていなくても。アンナマリアがいなくなってしまうことが寂しいのだ。
安心したら、レリアにどっと疲れによる眠気が押し寄せた。
少し、眠ろう――睡魔に身を委ねる。
意識が闇に落ちる寸前になって、レリアは自分とアンナマリアの関係を表す言葉を思いついた。
そう、ふたりは――くだらないことでも争うような。
そんな、悪友だ。
first battle.
レリア・キッス VS. ルクスリア
Winner レリア・キッス
To be continued Second battle...
之前曾在版上貼過一部分
最近因為原網站封閉了 所以在這裡將全文貼上供同好欣賞
ちゅ……ちゅっ……。
夜の路地裏に、水がピチャピチャと跳ねるような音がした。
路地に人通りのまったくないほどの夜更け、その裏には下半身を突き出した男が恍惚とした表情でだらしなく涎を垂らしている。
「んっ、ふうっ……ちゅっ」
男の股の間で屹立した肉棒を幼い少女が銜えていた。黒いドレスに白いフリル。黒と白のコントラストが印象的な、まだ十代の半ばにも達していないような少女だ。
ぺたんと地面に座りこんでいる少女は、がくがくと震える男の腰に抱きついて、根本まで呑み込んだペニスにねっとりと舌を絡みつかせている。
情熱的なわけでもなく――作業的に男の弱点を丹念に、まるで玩具でも愛でるようにカリ首の合間に滑り込ませてじゅるりと舐めていた。
「あむ……ちゅじゅっ、ぢゅ……んちゅっ」
そのまま舌は亀頭の頭を撫でていき、尿道をマッサージしていく。少女とは別の生き物みたいに動く血のように赤い舌に、男は背筋を震わせた。
その執拗な舌責めは幼い外観からは想像も付かない淫らさで、奉仕される男は少女の頭に手を添えて立っているのが精一杯だった。
「あ、あああ……もう駄目だっ、出――!」
言い終わるまで男は耐える事ができず、少女の口の中で肉棒がスペルマを間欠泉みたいに噴き出した。
「んぐ……っ」
どくんどくんっと心臓みたいに激しく脈打ちながらペニスが放出した口内から溢れ出そうなほどの白濁とした精液を、少女は嫌な顔すらせずに無表情で呑み込む。小さな喉が何度も上下に動いて、精液は胃に流れ落ちていった。
少女は熱い吐息をついて男性器から口を離すと、肉棒に絡みついた精液を舌ですくい取る。かわいらしい真っ赤な舌が敏感になった亀頭を舐めて、男はがくがくと足を震わせると腰を抜かして路地裏にへたり込んでしまった。
それでもむき出しになった男の陰茎は屹立としていて、少女は無言で下着を脱いで男の躯に跨ると、ドレスのスカートをたくし上げた。毛も生えていない未成熟 な女性器が眼前で恥ずかしげもなく晒されて、男は顔を紅潮させた。どんなに女性として成熟した者の性器よりも、そのいやらしさと可憐さが奇妙なバランスを 持った花弁のような少女のヴァギナは淫靡だったのである。
見とれて一言も口をきけない男のペニスに向けて、少女は見せつけるかのようにして腰を下ろした。
亀頭が入り口に触れる。
だが、期待していた感覚は男にはやってこなかった。
挿入されるのかと思いきや、愛液で滑ったペニスは少女の性器をなぞっただけであった。男は入れてくれ、と懇願するように少女を見上げる。
そこには蔑むような冷たい視線があった。
自分よりもずっと年下からの冷罵でありながら、男は既に蛇に睨まれた蛙になってしまっていた。
男が硬直しているうちに、少女は男の下腹部の上に座った。しかし挿入はされておらず、未熟な性器で陰茎を押しつぶす。
少女がじっと男を見て、腰を肉棒にそって動かした。ずるり、ずるり、と性器の口で射精したばかりのペニスを擦りあげると、男は女性みたいな高い嬌声をあげた。
裏筋をなぞる女性器は蛸の吸盤のように吸い付き、そのままペニスを横笛みたいになぞるのだ。愛液でびしょびしょにされた肉棒の根本から裏筋をなぞって亀頭の筋まで。ぐちゅり、ぐりゅりと音を立てて刺激する。
女性器によるマッサージ。少女は男のペニスを挿れるわけでもなく、寸止めして弄んでいた。だが男は異を唱えられない。裏筋を集中的に滑るヴァギナはそれだけの快楽を与えた。
少女の腰の動きが速くなる。短いスパンで何度も何度も陰茎が摩擦し、カリを入り口でなぞってはまた筋を舐めていく少女の下半身に、男の性欲はまたもや解放のときを迎えた。
「あああ、あああ――ッ!
どぷっ! とひねり出される精液。
少女の白い太腿に飛び散りながら、子種は男自身の身体に降り注いだ。なにも身に着けていない下半身と服を着たままだった上半身が青臭い液体でべっとりと汚れてしまった。
はあ、はあ、と肩で息をする男から少女は立ち上がり、またペニスに口を寄せる。どろどろと白濁にコーティングされた亀頭を銜えた。
「あがっ!?」
稲妻のような快楽に男の腰が浮き上がる。
「も、もうやめて……」
少女は答えることなく、男の精液を吸い上げた。
ちゅっ、と一際大きな音を立てて亀頭を吸うと、少女は陰茎から口を離して喉を大きく上下させて口の中の白濁とした液体を呑み込んだ。
あとに残されたのは、自分の精子で濡れた哀れな男の死体だけだった。
少女の耳に、足音が聞こえてくる。
新たな獲物を見つけた。
その方向へ顔を向けて、少女は路地裏を後にする――。
*
ある時代、ある日の広間。
人を焼き殺すような熱気、目を潰すほどに燦爛と輝く日輪。
声だけで人を圧壊するような熱狂の渦の中で、
――ひとつの首が宙を舞った。
断頭台が落ちたのだ。幾多の人の血を吸った忌まわしき鈍重なる刃が、また無慈悲に人の首を狩り落とした。
だが、果たして。無慈悲だったのはギロチンなのか。それとも、刃を落とした人間だったのか。
舞う首の金髪が光を反射する、それはまるで金粉をまき散らしているようで。その生首は、神々しい死の煌めきをまき散らしながら、広間の石畳に転げ落ちた。
その男の生前を語るのならば、ただかつて処刑の執行人をしていたというだけで事足りる。それ以外に、なにもないような男だった。血縁などいなかったが、そ れはこの時代において悲劇たり得なかったろうし、なにより本人がそれを当然と受け入れていた。幸いにも食事は毎日ありつけていたし、鍛えた躯は健康そのも のだった。
処刑人という陰惨な、人からの畏怖と憎悪を買う仕事をしていながら、本人は至って素朴な男だった。たいして言葉を知らぬから、口数は 少ないうえ人と親密な関係になることもなかった。劣悪な生活環境は改善しようとするが、上昇思考があったわけではない。本当に、素朴という言葉がよく似合 う。
ああ、知っている――とソレは嘆いた。
けして、殺されていいようなものではなかった。
こんなことで、死んでしまっていいようなものではなかった。
命に区別はない。ひとしく同義だ。それは、ソレが一番理解していた。己の用途が故に。
だが。その男の首が舞って、地面を転げて、その首を笑いながら蹴るものたちを見ながら、ソレは思う。
このような愚劣極まりない行為をおこなう連中が、彼と同じ命とでも云うのか?
――何を、馬鹿なことを。
ふつふつと、自分の中で燃え上がる感情が、最初なにかソレは判りかねた。やがて、自分が奴らにしてやりたい行為のことを分析して、判明した。これは憎悪だ。憤怒だ。――殺意だ。
自分に今まで向けられていた感情を、今は晴天の広間を覆い尽くしている、蟻のような人間に注いでいた。
民衆が、処刑された元・処刑人を罵倒していた。
悪魔。人殺し。屑。
犬野郎、狂人、お前なんて人の子じゃない――。
なにを云っているのだ。その男を殺したのは、なにもここにいる別の処刑人でも、ましてや〝私〟だけでもない。お前らだ。お前らの総意が、彼を殺したのだ――。
――ある日、革命が起きた。
王は殺された。女王も殺された。公開処刑であった。
民衆は娯楽と、そして自分たちを苦しめたと想像する総ての悪徳を彼らに押しつけて、新たなる秩序の名の下に断罪し、歓喜していた。
しかし、自分たちの生活の改善を願って蜂起したものの、生活は一向に上向くことはなく、むしろ以前より困窮していく始末だ。自分たちはいったいなんのため に支配者を打倒し、無様な死をくれてやったのだろうか。この混迷たる世の中で、自分たちの幸福を願って戦ったはずなのに。
そうした不満を抱き、追い詰められ、影響を露わにするのは、社会的が地位の低い者たちだった。
その日は、街の広場で公開処刑がおこなわれていない日であった。どんな不平や不満も、自分たちを追い詰めたものたちの死によって一時、熱狂という水で洗い流されていたわけだが、それがないとあっては虫の居所が良くはない。
特に。陽が地平線の彼方に消えてからかなりの時間が経つ夜更けに、頼りない街灯の明かりに照らされた路地を肩を怒らせて歩く男三人の機嫌はすこぶる悪かった。
「なんでだ……なんで、あの王も死んだっていうのに、オレたちの生活はすこぶる不調のままなんだ。こっから先は祝福された人生が待ってるんじゃなかったのかよ」
三人の中では一番大柄な男が云った。過酷な肉体労働でもしているのか、肩幅は広く、腕の太さも少年の胴回りくらいはある。手入れもまったくされていない、 単に無精で映え放題になった髭がみっともないが、誰もそれに苦言を呈すことができないほどに凶暴な猛獣を彷彿とさせる男だった。
「仕方ないですよ。王様が死んだからって、わたしどもの仕事が楽になるわけじゃないんですからね。王様が死んだら、そのまま食事がわたしたちの前に並ぶような、そんな単純な問題だったらよかったんですけどね」
大男の言葉に、一番小柄な男が応えた。背丈は他の男性と比べると低いが、そこはやはり大男の同業者、肉体に恵まれてはいないものの筋肉だけはついていた。それで腕っ節、喧嘩が強いなんてわけではないようだと判るくらいに、その男の肩身は狭そうであったが。
「おいおい、テメェは今更全部わかってましたって面で諦観かよ。さすが自称知性派はご慧眼の持ち主なんだなぁ、ええ?」
最後のひとり、眉が薄いせいか眼窩の骨が目立つせいで酷く乱暴者な印象を抱かせる男が、小柄な男を睨み付けた。先程からずっと眉間には皺が寄っていて、眉がなくても男が苛立っていることは誰から見ても明らかだった。
「そんなつもりで云ったのでは……」
「じゃあどういうつもりで云ったんだよ、あァ?」
「ったく、うるせぇぞ、テメエら! その顔血まみれにされたくなかったら黙ってろ!」
大男は自分の背後で騒ぎ出すふたりを怒鳴ると、たちまち静かになる。一喝に萎縮したふたりに、大男は苛立ちを隠さぬ口調で独白した。
「オ ヤジはのんだくれでよぉ、オフクロは男共に股を開く売女だった。今に至っては、お前らみたいな馬鹿な奴らがオレの後ろで騒ぎたてやがる。ホントに、うまく いかねえ……。王とか、女王だとか、あのときの……そうだ、陰気な処刑人が死んだときみたいな……大笑いできる見せ物がないってのも、おかしな話だ、 よ!」
大男は足下に転がっていた石ころを蹴り飛ばした。カンッ、と耳に刺さる音を立てて石畳の上で跳ねた石ころは、誰かの足に当たって地面に落ちた。
「お?」
大男は声をあげた。その街灯の明かりが途切れる境界線に、この中の三人の誰よりも小柄な女の子が立っていたのだ。
奇妙な少女だった。
黒いドレス。それも、お城に住んでいる人間が着ていそうな――ほとんど男の偏見であったが――豪奢なフリルをあしらったものを着ていたのだ。黒を基調にし て、白いフリルに飾られた衣装は影絵のようなコントラストを作っている。もしかしたら、このまま歩いていては気付かずにぶつかっていたかもしれない。
男たちのそこそこに長い人生の中で、その服装は見たことがなかった。自分たちがこの国でふつうに生活していては、お目にかかることはない。しかし、他国の人間が革命をおこした最中にある国へと足を伸ばそうなどと酔狂なことを考えるものだろうか。
自分たちが立ち入れない場所といえば、この国ではお城しか考えられない。つまり、あの少女は――処刑されるのが怖くて、逃げ出した王族、あるいは貴族の人間なのだ。
そうとわかると、まず大男がその髭だらけの口の端を持ち上げた。笑ったのであろうが、端から見れば獲物を前にして牙を剥いた獣にしか見えなかったし、事実大男は少女を獲物と見ていた。
街灯の明かりが届く限界にいるため、少女の姿は曖昧にしか見えず、躯の輪郭もふわふわとした衣装のせいで判らない。けれど、その顔がとびきりの上玉であることだけは目聡く把握していた。
成熟した女性のような情欲を抱かせる顔つきではない。躯の方も、貧相なのは脱がせなくても判る。けれども、ある程度の幼さを残した少女だけが持つ、年頃の危うさ――脱皮をしようしている蝶のような、触れては無くなってしまいそうなバランスで保たれた色香があった。
特に、大男は少女と同じくらいの年代のときはいつも両親にこき使われて労働を強制されていた。とてもではないが、異性と懇意になる余裕などなく。娼婦を抱いても、若い肉体への憧憬が常に胸の中で燻っていた。
だからこそ、その少女は大男にとって、即獲物と判断されたのだ。
大男は他の男たちの倍はあるのではないかと思う歩幅であっという間に少女に近づくと、その肩を掴んだ。あと少し強く力を入れれば肩をもぎ取ってしまえるのではないかと思うくらい、少女は大男と比べると小さかった。
「こんな夜中に街を出歩くとは良い度胸じゃねえか。それとも、箱入りのお嬢さんは夜の街の礼儀もしらねえのかい?」
「兄貴ー、そんな餓鬼になにするつもりなんです? 素人娼婦潰したみたいにすぐ壊れちゃいますぜ」
「馬鹿、それがいいんだよ。それにな……何事も、新鮮さってのは大事だ」
「そいつァはまったくもって真理ってやつっスね」
ふたりは下品に笑った。夜の街に、それが染みいって消えていく。人通りのまったくない夜だった。誰にも邪魔されることはない。もっとも、貴族の娘が乱暴されるのを止めるような者が、この国に今もいるなんてことはないだろう。
大男と眉無しが少女の腕を掴んで、強引に路地裏へと引きずり込む。それを見て困惑気味だった小柄な男は、仕方なしにふたりの後に付いていった。
その間、少女はずっと無表情に男の下卑た表情を見つめていた。
街灯の明かりがまったく届かない路地裏は、天に輝く月明かりすら差し込まない。
それでも、夜目に慣れていた三人の目は、至近距離なら少女の姿 を捉えるのに支障はなかった。顔と白いフリルだけが闇の中に浮いているように見えるのを小柄な男は不気味と思い一歩退いたが、他のふたりは完全に火がつい ていた。興奮したふたりは、目的以外の感覚が完全に鈍化していて、気付かない。広場で公開処刑に熱狂していたときのように、ふたりは高ぶっていた。
「へへっ、怖くて声も出せないってか。出しても誰も来ないだろうがな。お前が今も着てる服がオレたちの犠牲の下で作られてることの傲慢さの報いってやつを、たっぷり躯で教えてやるよ」
よく見ると、少女の服は所々はだけていた。脱がせ方など判らず、元より破くつもりだった大男は思いきり引くだけで上半身のドレスが脱げたことに驚く。まさ か、もう既に誰かの手で汚されていたのだろうか。あり得ないことではない。むしろ、こんな少女が歩き回っていれば、当然といえた。
誰の手にも触れていない果実を貪る――その想像に胸を躍らせていただけに、別の男によって弄ばれた後というのは酷く落胆した。それでも、少女は魅力的だった。止める理由はない。
暗い路地裏で露出された胸は、予想通り薄かった。ふっくらと膨らんだ胸は発酵を始めたばかりのパン生地のようで、柔らかいが膨らみはたいしたことはない。けれど乳首の淡い色も、肌の白さも、男慣れした娼婦とは比べものにもならない背徳感を抱かせた。
大男は少女の黒髪の上から頭を掴んで、ぐいっと自分の股間へと顔を近づけさせた。下着ごとズボンを降ろすと、刺激臭を放ちながらもぱんぱんに膨らんだ肉棒が少女の頬を叩いた。
その肉棒は、大男の体格と合ってふつうの男のものとは一回り以上も大きかった。女性の手首くらいの太さはある。それはもう性器というより、女性にしてみれば凶器だった。
「ここのところ風呂なんて入ってねえからな……まずはお前の口で綺麗にしろ」
少女は黙って、大男の陰茎を見つめていた。大男が自慢する一物に度肝を抜かれたのか、それとも、なにをすればいいのか理解していないのか。
大男は焦れて、少女のぷにぷにと柔らかい唇を親指でこじ開けて、無理矢理陰茎を突き入れた。上顎の凹凸を亀頭がなぞり、裏筋をなぞる舌を押しのけながら喉 の奥を突くと少女が初めて呻き声を上げた。口が裂けそうなほど大きなものを銜えさせられた少女は今にも顎が外れてしまいそうで、目を大きく見開いた。
「うっ……っっっ……」
少女の反応に気をよくして、大男は少女の黒髪を掴んで無理矢理引くと、腰を思い切り少女の美貌に叩きつける。
「ふっ!?」
悲鳴を喉の奥で上げる少女に、大男は嗜虐心を煽られた。陰茎は、少女の口の中で今も大きさを増していた。
「ほら、綺麗にしねえか!」
大男は何度も少女の顔に腰を振った。
真っ赤に膨れあがった亀頭が少女の涎を絡みとって、じゅっじゅっと上顎にこすりつけられる。何層にも重なった垢が少女の口を汚し、赤々とした舌は大男の裏筋を強制的に舐め上げさせられる。
「んんっ! じゅ……ふう……んぐっ、んんんっ」
少女の口の中は一言でいってしまえば、これまで大男が相手にしてきた娼婦など比ではないほどにいやらしく、心地よく、刺激的にペニスを舐めあげた。
幼気な、そして憎き貴族の娘であるからだけではない。この少女の口は、まさしく大男の精液を搾り取るために作り上げられた産物のようにペニスに纏わり付いていた。
大男はいつの間にか息を荒くしていた。快感が腹部にこみ上げてくる。
もう我慢できなかった。
少女の頭を両手で掴み、ぐっと腰を奥まで押しつける。喉の奥の奥へと思い切り突き入れ、少女が反射的に大男のペニスに歯を立てるが、唇に親指をねじ込んでそれを押しとどめた。
「ぐ……出るぞォ!」
猛獣のように咆えて、大男はペニスから精液を噴出した。
どくんっ、どくどくっ、どくんっっ!
がくがくと腰が震えるほどの快感が大男の下腹部を走り抜けた。
何度も震えながら、数週間にわたって発散していなかった精液が少女の細い喉に直接流し込まれる。
「あ……うううう……っ、んー! んー!」
小刻みに震える大男のペニスのように少女の躯も驚きでまた震えた。大男から逃れようとするが、少女の腕力では屈強な躯を一ミリたりとも押しかえすことができない。
「ああ、ぐう……全部飲み干せ! でなけりゃ喉に詰まって死んじまうぞ?」
にたりと笑って、大男はまだわずかに射精しながら脈動するペニスで少女の喉を擦った。
「んん……ん、んん……んくっ、んくっ……」
何度も少女の小さな喉が上下する。それでも、ゲルのように粘性の高い大男のはき出した精液を喉の奥に出されたのでは少女には飲み下せなかった。
大男は少女が窒息しそうになる寸前で陰茎を抜くと、少女は咳き込みながら自分のドレスの上に精液をはき出した。
「けほっ、けほっ!」
どろりとした白濁が少女の口から流れて黒いドレスを白く彩る。少女を犯した実感が大男を高ぶらせた。
「兄貴、早すぎですよ。こんな餓鬼に」
「うるせえ、お前もやってみろ……こいつは魔性だぜ……」
大男のペニスは少女の口に精液を流し込んだばかりにもかかわらず、涎と精液で濡れた赤黒い姿で天を指していた。
元より、一発程度で満足するような男ではなかったが――全然、収まらないのは初めてだった。
大男は路地裏に座り込むと、咳き込む少女の腰を掴んで自分の下半身の上までもってきた。咳き込み、まだ虚ろな目の少女のスカートを掴み、はぎ取る。ボタンでも千切れたのか、スカートはあっさりと脱げ、まだ毛も生えていない無垢な下半身を獣の前に晒させた。
「おお……」
思わず声を洩らす。つるりとした卵のような下半身と、小さな突起に、亀裂から覗くわずかな赤み。
大男は生唾を飲んでいた。これは、熟れた女の性器よりも、ずっと淫蕩だ。
ペニスははち切れんばかりに大きくなっている。大男は少女の腰を掴んで浮き上がらせると、屹立したペニスに宛がった。
入り口に亀頭を押しつける。どう見ても少女の躯に入る大きさではない。けれど大男は躊躇せずに力を込めた。ずるりと、亀頭が小さな穴に力尽くでねじ込まれた。
「あ――!?」
びくんっ、と一際大きく少女の躯が跳ねた。亀頭が入っただけだというのに、それでも小柄な少女の躯には大きすぎた。
「まだ頭が入っただけだぞ? たっぷり味わえ……!」
大男はその反応に気をよくして――一息に少女の躯をペニスに打ち下ろした。
ずんっ、と少女は下半身を貫いた槍の衝撃で、ずっと胡乱だった目を見開く。少女の腹部は見ただけで判るくらい、大男のペニスが存在を主張していた。
「おお……っ」
大男はペニスを締め付ける膣の快感に声を洩らす。
膣は大男の一物を押しつぶそうとするほどに密着し、挿入の際にそのひだで亀頭をなで上げた。予想外に愛液でたっぷりと濡れた少女の未熟な性器は、それだけで大男を絶頂させるところだった。
ぐっぐっ、と動かさなくても何度も膣が収縮し、ペニスを刺激する。それだけで大男は亀頭で押し込んでいる子宮に精液をぶちまけてしまいそうになる。
「ぐっ、そんなみっともない真似してたまるか!」
大男が少女の腰を掴んで浮かせると、また玩具みたいに腰へと落とす。少女の体重を乗せたピストンがまた少女の子宮を突き上げた。
「うあっ! ……あああっ」
「見た目と違って煩く鳴くじゃねえか、そんなにオレのが良いか、おい!」
大男は少女の躯をくるりと半回転させると、地面に四つん這いにさせた。そのままバックで少女のお尻に腰を叩きつける。ピストンする度に、赤い血が流れた。それは破瓜の血なのか、それともあまりに大きい陰茎故に性器が裂けたのか。
亀頭はぐちゅっ、ぐちゅっと膣内を何度も突いて竿は少女の柔肉が丹念になで上げる。大男は全財産を払っても買えないような高級な布のように白くなめらかな少女の背中に涎を垂らす。そして乱暴され赤くなっている少女のふっくらとしたお尻に腰を叩きつけた。
そのたびに少女の性器は年らしからぬいやらしいぐちゃぐちゃとした音を立てて、男のペニスに蹂躙される。
「ああっ、あ……ああっ……!」
「おおおおおお、おおおおおお!」
大男は咆えて、ぱんっぱんっぱんっと叩き込む。
もう再度の射精感を押しとどめることは出来なかった。
腰を引く――亀頭のエラをずりゅずりゅっと膣が舐めて、大男は達した。少女の腰を指が食い込むほど掴んで腰を押し込んだ。
――びゅっ、びゅる――っ!
肉棒が爆発して、そんな音が少女の肉越しに聞こえてきそうな勢いで精液を吐きだした。躯の中身ごと総て捻り出そうな射精感が大男を襲った。
がっちりと大男の汚い剛直を銜え込んだ小さな性器から、精液が勢いよく噴き出した。少女の痩躯には大男の欲望はあまりにも大きく暴力的すぎた。
「あ、はあ……っ、んあ……」
ぐったりと上半身を地面に横たえて、少女は未発達な胸を上下させていた。
大男は乱暴に陵辱された少女よりも疲労していた。睾丸から精液を吸い出されただけではなく、体力まで少女の中に放出してしまったような錯覚すらした。これまで何人かも覚えていない量の女と寝てきた大男であったが、この少女の性器の快楽はそれらとは桁違いだった。
しかも、大男の肉棒はまだおさまらず、ぱんぱんに腫れ上がっている。鋭敏になった神経をひくひくと圧迫する少女の性器のせいで萎えることさえできない。
「な、なんて名器だ……」
赤くなった少女の丸々としたお尻と接合部をマジマジと見る。未成熟な、けれど男の味を知って女にさせられた少女の躯は、再び大男の性欲に火をつけた。
ゆっくりと腰を引き、大男は思いきり腰を突き出す。
「ひゃっ」
大男の手では片手で持ち上げられそうなほど小さな躯に暴力を叩きつける。陰部から泡立った精液と愛液が掻き出され、少女の躯は意志とは裏腹に大男のペニスを受け入れさせられていた。
三回戦に突入した大男を見て、眉無しの男は笑った。
「大げさだなァ、兄貴は。そんなにきつめが好きなんすかィ? こういう小綺麗な子供よりも、胸のでかい女の方がこっちとしては好みなんすがね……お?」
眉無しが片方の眉を持ち上げる。よろよろと上半身を起こした少女が、バックから突かれながらも眉無しの下腹部に顔を寄せていたのだ。
にやりと眉無しは笑って、ズボン越しにはち切れんばかりになっているペニス突き出すと、少女はたどたどしい手つきで眉無しのズボンを脱がせた。
「なんだ、そんなに気持ちいい理由がわかりましたぜ。こいつ、見かけと違ってこういうことに手慣れてやがるんだ。それとも、夜の礼儀ってのを教え込まれたのかな?」
少女はふわふわとした手でペニスを握ると、亀頭をぺろりと撫でた。ぴくっと反応するペニスを見つめて、少女は目を細める。
つい先程まで軽口を叩いていた眉無しは背筋にぞくりと走るものを感じた。とても少女がするような目ではなかった。あまり色気があって――自分の欲望を総て見透かされているような錯覚を抱かせる。
「あむ……」
少女が口を開けて、眉無しの赤い肉の塊を口に含んだ。ちろちろと口の中で尿道を舐めると、眉無しは反射的に腰が引けた。けれども、少女は腰が下がった分だけ身を乗り出して、そのペニスを離さなかった。
「うおおおっ」
大男のペニスを精液まみれの下半身で銜えたまま、少女は銜えた陰茎を根本まで簡単に食べてしまった。頬をすぼめて、口の中の柔らかい肉で茎を締め付けて、舌で亀頭の下の裏筋を丹念に舐めあげた。
ぐちゅ、ぐちゅっ、じゅるっと、下品な音を隠しもしない。上品な姿と裏腹の淫靡な振る舞いに男の中で急速に射精の欲求が高まっていく。
「お、おい、ちょっと待て。やめろっ」
「ん……んんっ……ふ……っ」
少女は聞こえていないのか、無視しているのか。銜えたペニスは離さない。むしろより一層激しくフェラの勢いを高める。じゅ、じゅじゅじゅ、と高まるテンポに、男は意識を奪われた。止めようなどという考えが吹き飛んだ。
混みあがる快感に、男は下腹部をみっともなく突き出して――
びゅくっ、びゅくっ!
陸に打ち上げられた魚のように背筋を振るわせて、男は溜め込んだ白く濃厚な精液を少女の口内に洩らした。
「……んくっ」
さっき大男の精液を飲み下すことができなかったのが嘘のように、少女は新たな精液を唾液で攪拌すると総て喉に流し込んだ。
ペニスに纏わり付いた精液一滴惜しむように吸い付いて、眉無しに追い打ちの快感を与えながら、少女は男の陰茎を悩ましげな吐息と共に離れた。
亀頭と唇の間に出来た唾液の糸を指で払うと、口元についた精液を拭って舌で舐めとる。
「お、おおおおおおっ」
大男が三度目の絶頂を迎えていた。陶然としただらしない顔で、大男は自分より一回りも二回りも小さい、子猫のような少女の性器に欲望を流し込む。いいや、吸い取られている。
犬のように男たちに犯されている体勢でありながら、少女はいつの間にか男たちを手玉にとっていた。
少女と、唯一この狂乱に参加していなかった三人目の男の目があう。少女の目は、やはり表情を写していない。性の興奮に身を焦がしているわけでもなかった。 けれど、そこには憎しみの感情が見え隠れし――それは普通とは違う妖しい煌めきとなって、男たちの目を釘付けにして離さない。
矮躯の男はまだなにもされていない状態でありながら、あることをこの場の誰よりも強く理解していた。
路地裏の暗がりに転がった、人の躯を見つけてしまったから。それは水分を抜き取られたように渇いていて、惨めに下腹部をさらけ出して死んでいる誰かの死体。
そうして、ああ、あれが自分の末路なのだと思った。恐怖におののいても、逃げることも声をあげることさえ、できない。
何故なら。本来ならば少女を犯すなどと考えられないこの男でさえ、あの少女のアンバランスな魅力に、既に虜になってしまっていた。香るほどの死の臭い。それは男たちの頭を胡乱にして――。
大男が仰向けになり、少女が大きな躯に跨る。大男に頭を掴まれればたちまち握り潰されそうなほどの体格差がありながら、もう大男は肉食の野生動物に馬乗りにされたようなものだった。
眉無しが少女のお尻を掴み、親指をねじ込んでアナルを押し広げる。そこに吸い込まれるように、いきり立った肉棒を挿入した。
また狂乱が再開する。
肉がぶつかり合い、淫らな水が音を立てる。
ここは狩猟現場。けれど、最初に獲物だったはずの存在に、獣は無惨に貪られる。そんな凄惨な、夜の食人祭だった――。
そこには乾涸らびた何かだけが残り。
そうして誰もいなくなった。
白目を剥いて動かなくなった巨漢の男を一瞥すると、少女は靴下だけになった足で立ち上がった。
ぬぽっ、と音を立てて大男の一物が下半身から抜け落ちた。硬さを失っていても、そのペニスは平均的な男性が勃起したものと同じくらいの大きさがあった。
ふらりと物言わぬ屍となった男から離れると、股と後ろの穴から白い液体が汚い路地裏の地面にシミを作った。
どれほどの間、こうして男三人とまぐわっていたのか。躯に渇いた精液と汗、涎がこびり付いていて少女は不快だった。下着をはこうと思ったが、路地裏の隅にボロ切れとなって発見されたので諦めた。
自分のブーツを見つけると、一緒に拾ったドレス――ゴシックロリータという衣装らしいことを少女は聞かされていた――ごと身に着ける。服が汚れることを気にはしなかった。どうせ、もらい物だ。
合計四人にもなる男の亡骸を少女はもう一顧だにしなかった。平然と路地に出る。
街灯の下に、人影があった。
こんな夜更けにまた獲物が迷い出たかと少女は思ったが、胸を大きく開いた扇情的なローブを纏った女性を見て、すぐに怒りを鎮めた。
その女性は娼婦と云われればそうだったが、大きな帽子と長いローブを身に纏った姿を一言で表すなら、魔女という言葉が一番よく似合った。
魔女。――そう、まさしく、その魔女だ。
腰まで届く銀の髪は、色が抜けたなんて間抜けな想像はさせない。銀塊を熱で溶かして細工したように美しい。ここが人通りの多い時間ならキラキラと光るその 髪に手を伸ばそうとする者がほとんどであっただろう。目は切れ長で見つめられるだけで誘われているような色香があり、露わになった胸元は豊満。
少女を言葉であらわすならば幼さと成長間近のアンバランスな肢体が背徳感を刺激する抗いがたい魅了の美であり、魔女は男ならば抱かずにはいられないと躍起にさせる女性的な魅力で溢れていた。
大きな帽子を被った魔女が、少女に微笑んだ。
「どうだい、その躯の使い心地は。すこぶる良好だったろう。今の君にかかれば、男なんて猿と同じだよ。その気になれば躯ひとつでどんな権力者でも虜にできるだろうさ」
「興味ない」
魔女のつかみ所のない物言いを、少女はばっさりと切って捨てた。刃物のような切れ味だった。
「男を籠絡して、混沌に落ちる様を眺めるのも遊びとしては楽しいものだと思うけどねえ。いやしかし、キミがそれほど美しくなるとは私としても予想外だったよ。純粋なモノほど、見た目に現れ易いということかな。キミほど美しく洗練されたモノは見たことがない」
少女は魔女の会話に付き合うつもりはなかった。自分に躯を与えてくれたことには感謝しているが、わざわざ恩を返そうとは考えていない。何故なら魔女はおの れの娯楽のために少女を少女たらしめたのであり、そこに利害があるのなら、特別、少女から何か恩を抱く必要はないと思ったのだ。
「自分では判らないけど、その美しさがわたしの役に立つのなら――好都合だわ」
「へえ、本当にやるつもりなのかい。キミは」
魔女は自分が少女と邂逅した日のことを脳裏で再生しながら、云った。
「あの処刑人の復讐を。――処刑道具であるギロチンのキミが」
少女は黙っていたが、沈黙は即ち肯定だった。
くくっ、と魔女は喉を鳴らして笑う。
「自分の手入れをしてくれていた処刑人が、自分を使って殺された。その復讐をしようとは畏れ入る。素敵に一途だ。しかしだね、私は判らないのだが、キミは誰に復讐をするつもりなのだね。さっきの男たちは処刑人の死に直接関わったようには見えなかったのだけど」
「復讐の相手? わかりきったことね」
少女は憎悪を込めて、うそぶく。
「わたしの復讐する相手は〝この国の総ての人間〟。この国自体がわたしの敵。――わたしは彼を殺した総意に報復する」
広場の熱狂が少女の裡で蘇る。
誰もが、何もかもが、処刑人の男の死を望んでいた。頭のネジがとんでいるみたいに喚き散らして、ギロチンである自分の刃が震えるほどに叫ぶ。あれは狂気の嵐だった。
彼らは直接殺していない? なんてことをいうのか。人の死に興奮し、狂い、望んだのなら、彼らも等しく殺人者だ。少なくとも、処刑道具として産まれ、人間のエゴで人を殺し続けてきた少女はそう確信していた。
「それにあの大きな男は、あの日、彼の生首を持ち上げて石畳に叩きつけていたの。額が割れて血が流れていたわ。そんな人を見つけたら、もう殺すしかないでしょう?」
「ほうっ、では何故わざわざ男たちに快感を与えて殺したんだい? キミならもっと効率的に殺せるじゃないか。慈悲のつもりかい?」
「慈悲?」
少女はそのとき、初めて笑った。暗い暗い、井戸の底のような笑み。
「まさか……。ギロチンは、人を楽に殺してあげるための人道的な処刑道具として作られたんだから……。あっさり首を狩っちゃったら、苦しくないでしょう?」
そうだ。自分が処刑人を殺す道具として使われたことに唯一感謝することがあるなら、彼を苦しませずに逝かせてあげられたことだ。
「それに、快楽は……一度与えられた至福は、やがて来る絶望を引き立てるもの。わたしが彼という幸福を奪われたときのように、快感が絶望へと変わる感情の墜落――それを味わわせることなく殺すなんて、わたしにはできないわ」
少女が口数も多く、滔々と語った内容は魔女の心を満足させた。喉を鳴らして笑った魔女は、夜闇の元で手を叩いた。
「すばらしい! それでこそ、だ。見せてもらおうじゃないか。キミの人と国ひとつを堕落させる復讐を。しかし、それならキミにも名前がいる。そうでなくては、存在としての重みが違う。人もモノも名を持つことで存在として一段強くなるのだよ」
「名前……?」
自分の名前。そう云われても、少女は断頭台。人を殺す道具としての名前はこれだけで充分だった。けど、そうだ。少女の脳裏に引っかかっているものがある。それはいったい……、と引き出そうと悩む少女を尻目に魔女はいった。
「よし、キミの名前はギヨたんだ」
「…………はっ?」
少女は目を丸くした。人としての躯を得てからの少女の表情では、とびきり間抜けな顔になっている。
「なんだい、そんなに私を見て。そんなに気に入ったかギヨたん。良い名前だよギヨたん。うん、我ながら素晴らしいネーミングセンスというやつだ」
「…………」
「どうした、ギヨたん。感動で声もでないのかい」
「その呼び方をやめないと真っ二つにしてやる」
溜息をついて少女は魔女に背を向けた。
「アンナマリア」
「うん?」
「アンナマリア――そういえば彼はわたしをそう呼んでいた」
処刑道具に聖母の名前。そうだった。寡黙な男だったけれど、彼はロマンチストだったことをアンナマリアは思い出した。
街灯が転々と続く、どこまでも続いていきそうな真っ暗な路地をアンナマリアは歩き出した。
名前のことを意識したら、洪水のように処刑人のことが脳裏に浮かぶ。そして、それがもう二度と手に入らないことに気付く。
ああ、そうか。と深い闇を睨んだ。
ここから、わたしの復讐が始まるんだ――。
序章/了
魔女とは、その名の通りに魔法を操る女性のことである。けれど、魔法使いではない。魔女と魔法使いを区別する最大の要因は悪魔と契約したか、そうでないかである。
魔法使いは一概に悪しき存在とはされない。もちろん、自我を持っている生物であるから邪念を持った者もいるだろうが、それはただの人間とて同じことだ。一 方、魔女の全員は悪魔との契約を結んでいる。彼らの交換条件を受け入れているのだから、それは間違いなく人に仇をなす。そのために、魔女狩りが各地で勃発 したのである。
何より、人は魔女に恐怖していた。実際に魔女を目にした者は少なかろうし、実在を信じぬものもいる。だが、魔女の恐怖とは常に身近なところにあった。
「――ふむ」
自宅の壁に寄りかかり、窓から日中の人通りを眺めている銀髪の女は、紛う事なきその実在する魔女の証明であった。
今は魔女のトレードマークたる両手で抱えるくらいの大きなハットを帽子掛けに預けて、悩ましい胸を押し上げて腕を組んでいる。
断頭台を人に変えてしまった、この魔女の尋常ならざる力は、やはり人が見れば畏怖する対象になるのも納得であった。
「いよいよもって、騒ぎになってきたね。理由のわからない結果による不安が、街の中に溢れている。この押し殺したようなざわめきは、火薬庫牢獄への襲撃による革命を控えていたときを思い出すよ」
唇の端を持ち上げて微笑する魔女に、奥の方にある扉の向こう側からの声が答えた。
「そんなこと云って、今回の騒ぎは先生の仕業じゃないですかぁ」
間延びした、甘えている猫みたいな少女の声。
扉が開く。足で扉を蹴って出てきたものは、大量の紙――ではなく、大量の紙束を抱えた女の子である。
彼女は部屋の隅で本を乱暴に手放す。人がジャンプしたみたいな地響きがして、積もっていた埃が大量に舞った。それに少女は口を押さえて咳をする。
「うひゃあ、……もうっ、先生がお掃除しないから埃がこんなにたまるんですよぉ! たまるのは性欲だけにしてほしいですぅ」
「掃除の必要性を感じないのだよ、私はね。だって、考えてもみたまえよ。私は流浪の魔女、いつここを離れるともしれない身だ。家の整理などして何になる」
「暮らしやすくなるんですってば! それに住むからには少しでも楽しく気持ちよく生活できた方が素敵じゃないですかぁ」
「一理あるね。じゃあ言い出しっぺが頑張ってくれるんだろうね?」
「うっ、墓穴でしたかも……なに云っても先生は動かないんでしょうけど……」
にこりと魔女が微笑んだ。
「よくわかってるね。さすが、私の助手だよ、レリア・キッス」
「奴隷の間違いじゃないですかぁ?」
助手と呼ばれた少女、レリア・キッスは、露出している、まるで雲みたいに白い肩を落として嘆息した。
レリアは炎みたいな色をしたショートヘアが印象的な少女だ。炎といっても単純な赤ではない。火がもっとも情熱的に燃えるときの色は、透き通ったマリンブルーみたいな蒼である。レリアの頭髪は、赤と蒼の見事なグラデーションの幻想的な色合いだった。
服もキャミソールか、それに類したもので薄着だ。下は裾を短くつめたスカートである。激しい動きをすると中のものが見えてしまいそうだが、きっとこの少女のことだから下着を隠すようなものはないのだろう。
魔女のものぐさな態度に呆れたレリアはまた家の奥へと戻ろうとすると、タイミングよく玄関の扉がノックされた。
木を叩く小気味良いリズムに魔女が返事もせずに扉を開ける。そこには紙袋一杯にパンを抱えた金髪の少年がにこにこと嫌みのない笑顔を浮かべていた。
「こんにちは、魔女先生! 今日もパンを届けに来ましたよ」
元気の良い挨拶に、魔女も歓迎するように腕を広げる。劇でも演じるような大仰な動作であっても、これが魔女にとっては自然体だった。
「おや、ジョゼフか。いつもよく来てくれるね」
「いえいえ、魔女先生は命の恩人ですから。こんなことで遠慮なんてしないでくださいよ」
「そうかい。ところで、魔女先生というのはいい加減やめてくれないかな。あんまり知られると困るんだ」
「あ……そうですね、イザベラ先生、の方がいいですよね」
「偽名だけどね。はい、いつもわざわざ来てくれて助かるよ」
魔女イザベラの言葉に、レリアは「そう思うなら自分で買いに行けばいいのに……」と呟く。わざわざ宅配してもらっているのは彼女だけなのである。
それでも、ジョゼフと呼ばれた少年は嫌な顔ひとつしておらず、はっきりとした口調で否定した。
「いえ、好きでやってることですから」
「そういってくれると胸が痛まなくて助かるよ」
ジョゼフに銅貨を渡してパンを受け取っているイザベラをレリアが胡散臭そうな顔で見ていたが、すぐに表情を切り替えてジョゼフの方へと走り出す。イザベラの躯を抱きつくように押しのけた。
「ジョゼフくん、ジョゼフくん! いつものやつもちゃんと入ってるよね」
「ぼくの作ったパンのことなら、うん、入ってるよ。でも、いいのかな。こんなのまで買い取ってもらって。ぼく、まだ見習いだし、恥ずかしい話だけど美味しくないよ」
ジョゼフはパン屋に住み込みで働いている少年で、熱心な働き者として客からの評判はよかった。屈託のない芯の通った性格と子供っぽい笑みのために、今では パン屋の看板娘ならぬ看板男と云われるほどである。欠点をあげるなら、パンを焼くのがお世辞にも上手ではないことだった。
「ううん、いいの。あたしはジョゼフくんのパンが食べたいの。これからも一杯もってきてよ?」
「そう云ってくれると作ってよかったって気分になるね……。今度はもっと美味しくできるように頑張るよ。それじゃあ、ぼくはこれで!」
魔女イザベラに小さく頭を下げると、ジョゼフは家に背を向けて小走りに大通りへ消えていった。
ジョゼフの背中が人混みの中へ完全に消えるまで、レリアは恋い焦がれる乙女の顔でじっと見つめていた。イザベラに抱きついたまま、見た目に合わぬ悩ましげに息をついた。
「はあああ……美味しそうだなあ」
目はパンに――ではなく、ジョゼフが去った方に向いたままである。
「先生ぇ、ジョゼフくんはきっと美味しいですよぉ。食べていいでしょう?」
「駄目だ。さすがの私も自分の助けた相手が片手間にあの世へ送り返されるのは黙ってられないぞ。キミはパンでも食べてなさい」
「ふがっ」
パンを口の中に突っ込まれて、レリアは呻いてイザベラから離れる。そのパンは不格好でお世辞にも綺麗な見た目とは云えなかったが、レリアはそのままパンを平らげてしまった。
「うーん、いつ食べてもジョゼフくんのパンは不味いなあ」
言葉とは裏腹にレリアは満面の笑顔である。
イザベラは机の上にパンの詰まった紙袋を置くと椅子に躯を預けて、レリアの方に皮肉めいた笑みを向けた。
「レリア、キミは社交辞令をよくわかってるんだね。関心するよ」
フランスパンを小さく千切って口の中に放り込む。今朝焼いたばかりのパンは表面こそ硬いものの香ばしく、反面、中身は柔らかい。スープにつけて食べると 益々味が引き立つだろうが、イザベラは料理をするのが好きではなかったし、レリアにとっては本来の食事とは異なる代換え行為に過ぎなかった。
「へ、社交辞令なんて云ってないですよぉ? あたし、ジョゼフくんの前でこのパンが美味しいなんて一言もいってないですもん」
「余計タチが悪いと思うよ。それが不味いのには同意だけど」
「あ、でも、あたしはこの味の方が好きなんですよ? 人が美味しいと感じるものより、こういった不味いものの方が口にあいますからねぇ」
「なら美味しいって云ってあげたらいいんじゃないかな」
「やだなぁ、そんなこと云ったらジョゼフくんが勘違いして色んな人に食べさせちゃうじゃないですかぁ。そうしたら、後で悲しむのはジョゼフくんですよ? 言葉の意味は気をつけないといけないのです、混乱しちゃいます」
「笑顔で不味いというのも充分に人を混乱させるよ」
フランスパンを半分ほど食べてから、イザベラはまた外を見る。行き交う人を目で追って、ジョゼフがやってくる前の話を振り返った。
「さて、ギヨたんはこれからどうするかな。このまま国の人間を皆殺しにできるのなら、見物なんだけどね」
「そのことなんですけどぉ、その、ギヨたん、ですか? 面倒なのに目をつけられてますよ」
「ほう、やはり彼女たちのシマを荒らしているからかい。まるで狩り場を取られた獲物だね」
「そんなに暢気でいいんですか? きっと殺されちゃいますよ」
「今のままなら――そうだろうね。あっさりと負けてしまうはずさ」
剣呑な指摘に、イザベラはあっさりと頷いた。
「だ けどギヨたんはね、その辺にいる悪魔だとかの範疇からは逸脱しているよ。なにせ元が無機物だ。どこかの国では長い年月を経た道具には魂が宿るとされている が、ギヨたんは誕生してまだ数年。この時点でも既にギヨたんが並外れた素質を持っていることは明かだ。私が手を加えたといっても異常だよ、これはね」
「でも、今は人間の姿って話じゃないですか。そんなに凄いとは思えないけどなぁ」
「なんだい、もしかして私が褒めるものだからって、嫉妬してる?」
「し、してませんよ! どうしてそうなるんですかぁ!」
むっ、と顔をしかめて、パンを総て呑み込んだレリアは小走りに玄関へ急いだ。
「どこに行くつもり?」
「ご飯です!」
無神経に訊ねてくるイザベラにレリアは肩を怒らせて答えると、扉を吹き飛ばす勢いで家を飛び出していった。
「やれやれ。……殺さないように気をつけたまえよ、なんて、もう遅いか」
自分の言葉をさして気にした様子もなく、イザベラは食事に戻ることにした。
*
ギヨたんこと、断頭台アンナマリアは夜の街で途方に暮れていた。
石畳をブーツで叩いて歩きながら、街を見渡す。
陽が落ちて久しい時刻、街灯が転々と道を照らしている。小さなスポットライトが列を作っているように見えた。アンナマリアが道を歩くと何度も何度もその灯りに照らされて、まるで劇の主演女優のようである。
ただし、他の出演者は誰もいない。
「……誰も、いない」
夜の街には人通りがまったくなかった。
闇に覆われた時刻なのだから、人が少ないのは当然である。それに不思議はなかったが、まったくいないのだけは異常だった。夜は太陽の代わりに月が昇る。そうして月の魔力に誘われるように、娼婦と男たちが街でうごめき始めるのだ。
なのに、今日と来たら、この有様である。
いや、以前よりこの兆候はあった。あまり気に止めていなかったが、日に日に人通りは少なくなっていた。
「わたしの、せいかな」
アンナマリアは連日、夜に出歩いた。朝には広間で断頭台に姿を戻している。それは、自分で人を処刑させるためだ。何故なら、アンナマリア以外の処刑機具で はいたずらに人を痛め付けた末に殺してしまう。苦しめずに人を処刑する思想で作られたアンナマリアは、それが許せなかった。
どうせ、全員苦しめて殺すのに――とアンナマリアは自分でも不思議に思うものの、性分なのだから仕方ない。きっと、自分の作った人たちの意志がそうさせるのだろう。
なので、自然と出歩くのは人が寝静まった夜になってしまう。アンナマリアは知らないが、街では夜の衰弱死体の大量発生で話題は持ちきりになっていた。さすがに毎晩そんな死体が見つかっていれば、怖れて外出を控えるのも当然だった。
街灯の下で途方にくれた。風評を気にしない無神経さか、よっぽどのもの好きでなければ通りがかることなどない。これでは目的が果たせない。いっそ、家に乗り込んでみようか。そうすれば、人の数に悩まされることもないし――。
そこで、アンナマリアは見つけた。
風評を気にしない無神経さを持っていて、もの好きな男が通りかかるのを。
金髪碧眼の、この国の者とは少しばかり顔の彫りも違う少年だった。彼の名は、ジョゼフといった。
かつては勉学や剣の道に励み、今はパン屋に住み込みで働いている快活な少年だった。それはもう脳天気だと云われるレベルであったが、本人は気にしていない。元気なのは、良いことだ。が彼の座右の銘であった。
客商売故に、ジョゼフも夜の街に関して流れる噂話は耳に挟んでいた。怖くなかったのかといえば、怖かった。けれど、遠くにある仕入れ先まで行って、小麦粉 などの買い取りの交渉をおこなわなくてはいけなかったのである。店主たちは夜の噂を懸念していたので、代役をジョゼフが買って出たのだ。
この分だと、無事に帰れそうだ。とジョゼフは胸をなで下ろす。誰もいない街を歩くのは、さすがに元気が取り柄のジョゼフといえども薄気味悪かった。
安心した矢先に、街灯の下に誰かがいることに気付く。
思わず足を止めて、小さな影を凝視した。
「女の子?」
思い浮かべていた人を襲う悪魔みたいなイメージが一気に霧散して、ジョゼフは肩の力を抜いた。
こんな夜更けに出歩く女の子がいるのも奇妙な話だ。首をかしげるが、深く事情を詮索するようなことはしなかった。ただ、こんな時間に子供が出歩くのは危ない。
「おーい、こんな時間に出歩いていたら危ないよ。最近、夜は特に物騒なんだからね」
声をかけるとジョゼフのことを女の子は見返した。けれど、彼女はとてとてと路地裏へと入っていく。
「あっ、ちょっと!」
ジョゼフが声をあげて、女の子が消えた方へと近づいていく。
「これじゃあ、ぼくが不審者みたいじゃないか……」
見間違えられてないといいなあ、と期待しつつ、路地裏を覗き込む。黒く煤汚れた地面に一歩踏み込むと、ジョゼフに背中を向けて闇に同化している女の子がいた。
黒いドレスは、ジョゼフも見たことはない。ふわふわしていて、気持ちよさそうだ、が第一印象だった。
女の子が振り返る。さらさらと黒髪が川となって空を流れた。ジョゼフは揺れる髪を自然と目で追っていた。この地域では滅多に見ない髪の色で、服装と相まって、その女の子は闇の妖精といわれても信じてしまいそうだった。
髪に見とれていて、ジョゼフは女の子が自分をじっと見ていることに遅れて気付いた。顔を近くで見てみると、自分よりもずっと幼い顔立ちをしている。小さな女の子に見とれていたことに恥ずかしくなって顔を羞恥で熱くしながら、なんとか注意の言葉を絞りだした。
「えっと、夜に出歩くのはやめておいた方が良いよ。ただでさえ、最近は恐怖政治で騒ぎがすごいから……あっ、いや、こんなこと云っちゃいけないんだけど。……それとも、帰れないのかな?」
家を無くしてしまった子だったら、帰れというのも酷な話だ。ひとりで悩んでしまうが、女の子がなにも云ってくれないのだから、しょうがない。
ただし、口を開いていない間も、女の子はずっとジョゼフの顔を見ていた。
「あの、ぼくの顔がどうかしたかな?」
「アンナマリア」
「え?」
「わたし、アンナマリア」
「あ、ああ、きみの名前か。良い名前だね。マリア様のお母さんと、その娘の名前か。きっと、この名前をつけてくれた人は素敵な人だったんだね」
素直な感想をジョゼフは口にした。この思ったことをすぐ口にしてしまうところが、今だに少年と呼ばれてしまう一番の要因なのかもしれない。けれど、嘘のない笑みは人を信用させるものだ。
しばらくアンナマリアはそのままじっとしていたものの、突然地面を蹴って駆けだす。
そしてジョゼフに思い切り体当たりをすると、そのまま唇を奪った。
勢いのままに唇を奪われ、ジョゼフは押し倒された。
いきなりの行動で躱すことも受け止めることもできない。そのせいで頭を地面に打ち付けてしまったが、ジョゼフの思考を乱すのは痛みではなく唇に触れている女の子の感触だった。
アンナマリアは相手の首に腕をまわして捕まえると、深く深く自分のそれを押しつける。
赤い眼と碧眼が合う。まるで地球と太陽のような対比。
そしてジョゼフはその赤い眼に釘付けになった。赤は赤でも、これは血の色だ。血で固められた赤い宝石(カーネリアン)。見つめているだけで心奪われる背徳の色。
熱い吐息を漏らしながら、アンナマリアは舌をいれて相手のものと絡みつかせた。そのままつるつるとした頬肉を内側からなめ、歯茎をなぞり、相手の舌をついばむ。
彼女の舌がそうやって口腔を情熱的に責めると、ジョゼフは口の中が火傷したみたいに熱くなって、同時に頭がクラクラと熱に魘された。
ジョゼフの舌の裏側に小さな舌が侵入して、浮き上がっている青い血管をなで上げる。ジンジンとした快感が喉元から下半身までを駆け抜けた。
口内をいやらしくくすぐった舌が抜ける。アンナマリアが顔を離していた。
キスをされているときは近すぎて見えなかった彼女の顔の全貌が、この距離だとよく見えた。
日頃こねてるパン生地のような柔らかそうな輪郭。大きな眼とぷっくりとした唇は赤々としていて、白と赤のコントラストは彼女がこの世のものではないようだった。
アンナマリアの肩にかかっていた黒髪が流れ落ちて、ジョゼフの顔をくすぐる。その黒は闇より深い暗黒だ。
確かに黒と呼べる髪。けれど、こんな黒をジョゼフは見たことがない。知らないのに、黒と認識できる。ジョゼフは昔、自分たち人間の世界にあるものは全部模 造品であり、真なる万物が存在する世界があると学んだことを思いだす。その世界にある本物の個体を知っているから、歪んだ図形を見れば間違っていると認識 できるのだ、と。
では、見たこともないはずの深いこの髪の色を黒と断定できるのは、これが本物だと云う経験にない記憶が想起しているからで――そうだ、この世ならざるものなら、この女の子の浮世離れしている美しさも道理であった。
まだ成熟していない躯でありながら、悪魔のように心を掴んで離さないのだから――。
「……あ」
ジョゼフが声をあげる。自分よりもずっと幼い少女からのキスで膨張していた愚息を、彼女が服の上から触っていた。
「ちょっと、駄目だったら……」
自分で云ってから、ジョゼフは本気で止めようとしていない自分がいることに気がついてしまった。キスのせいで酸素が不足しているからではない。ドレス姿の少女から漂う色香に期待して、はち切れそうになっている。
女性経験のなかったジョゼフは、たった一度のキスで魅了されてしまっていた。
細い指先がジョゼフの下半身の布を手慣れた動作で剥ぐ。勃起した男根がジョゼフのお腹を叩いた。
つぅ――、とアンナマリアの爪が裏筋を根本からなぞる。
「ふあっ!?」
快楽の稲妻が背筋を走り抜けて、ジョゼフは情けない声をあげてしまった。
刺激でゆがんだジョゼフの表情をちらりと覗き見て、アンナマリアは陰嚢を優しく撫でる。少しの衝撃で痛みを訴えるほどに敏感は睾丸は、快感に対しても忠実だった。まるで全身を愛撫されていると錯覚させる少女の手つきに、少年は肩をびくつかせた。
睾丸が甘やかされるにつれて、ペニスの方は激しく脈打つ。数々の行為によって破裂しそうになっているのに、直接触ってもらえていないせいで焦れていた。
物欲しげに脈動する情けない様で、アンナマリアも何をしてほしいのかを察する。男がどうして欲しいか、そんなことは連日連夜の性行で把握できるようになっていた。それこそ、本当にそのままの意味で手に取るように。
「これ、触って欲しいんだ」
アンナマリアが囁く。蔑みはなく、どちらかといえば、珍しくからかうような声音。
「ち、違っ」
「それじゃあ、このままで良いんだよね」
「それは……」
言いよどむジョゼフには言及せずに、アンナマリアは睾丸をさする手を止めない。男性器には指すら伸ばさなかった。
「あ、うあ」
「どうして欲しいの?」
「ぼくはっ、別に……」
アンナマリアは黙して語らない。無表情のまま、焦らされて切なそうにしているジョゼフを見つめるだけだった。
心を見透かすような目と、与え続けられる生殺しの刺激が、ついにジョゼフの羞恥心を上回る。
「下を、触って」
「下って、どこ? ……足?」
「そうじゃなくて! 云わなくてもわかるでしょうっ」
「ちゃんと、云って」
「……っ! ペニスだよ、お願いだから、もうっ」
「そうだよ……云ってくれないと、わからないよ?」
くすくすとアンナマリアが笑い、両手で陰茎を掴んだ。左手は亀頭に添えられ、右手は竿をゆっくりと上下させる。
これまでと比較にならない甘美な感触にジョゼフの腰が跳ねた。今までお預けをくらい、さらには女の子に懇願してしまったせいで、いつもよりもずっと快感が増幅されていた。
ジョゼフの穏和な顔立ちからは想像できないグロテスクな陰茎に、アンナマリアは息がかかる距離まで近づく。けれど亀頭はピンク色で、それが今まで自分の犯してきた男たちと違ってかわいらしかった。
アンナマリアははっとなる。憎き国に所属する男のペニスをかわいいと表現してしまって、アンナマリアは自分自身を疑った。
なにを考えているのだろう。
子供をあやすみたいな手つきを一変させて、アンナマリアは陰茎を握る手に思い切り力を込めた。
「うっ!」
突然の強い刺激に呻き声をあげたジョゼフに、アンナマリアは冷たく告げる。
「無様」
さっきまでの優しげな態度はどこへやら、小さな手は強い力で竿を擦り始めた。もう片方の手は我慢汁を亀頭に馴染ませるように円を描く。
激しい手淫に声をあげるジョゼフを無視して、アンナマリアの手は機械的にペニスを責めていた。我慢汁でぐっしょりと濡れた指先を雁首に這わせて、弾く。
「!?」
竿をしごく手はまったく止めずに、今度は親指と人差し指で作った輪で雁首を引っかけて、擦りあげる。
じゅっ、じゅっ、じゅっ、と我慢汁が気泡を作って音をたてた。
その間も、別の手が熱く滾った肉棒を扱う。ふたつの独立した手技に、高ぶっていた性欲が一気に限界を迎えた。
「う、うわあああっ」
ドクンッ、ドクッ、ドクッ、ドクッ……!
幼い手の中で欲棒が爆発した。
だが、熱く生臭い白濁とした精液を勢いよく掌に発射されても、アンナマリアは手の動きを止めなかった。
ジョゼフの腰が震えて、本来なら出なかったはずの精子がアンナマリアに飛び散った。犯しがたい黒の髪を、情欲の白濁が彩った。
何十秒もドクドクと出し続けていた射精の勢いが収まると、ようやくペニスをしごく手の動きも止まった。
容赦ない手つきに責められて息も絶え絶えなジョゼフとは対照的に、アンナマリアは息ひとつ乱していなかった。腐った下水道のぬめりのようにネバネバとした精液で真っ白に汚れた自分の手とペニスに視線を落とす。
「うぐっ!」
ジョゼフが悲鳴じみた声をあげた。
夜風に晒されていたペニスが生暖かいものに包まれていた。アンナマリアが口で銜えたのだ。
彼女の唾液が精液に濡れた肉棒を包み込んで、攪拌された精子を小さな喉を使って呑み込んでいる。喉が動くたびに上顎と舌が性器を圧迫して、萎えそうになっていたペニスに血液が集まった。
出してから一分も経っていないのに、ジョゼフの股間が熱くなっていく。それも少女の見た目とかけ離れた振る舞いのせいだった。
ペニスにむしゃぶりつくアンナマリアの頬は赤く上気していて、口淫で夢中になっているように見えた。ぴちゃぴちゃと音を隠しもせずに、少女の舌が剛直にこびりついた精子を呑み込む。
ジョゼフの腰が自然と浮き上がった。
再びペニスに集まり出す射精感。
しかし、それが放出されることはなかった。
「え?」
アンナマリアがジョゼフのモノから口を離していた。精液の代わりに唾液漬けにされたペニスが切なげに大きく脈打っている。
不思議な顔で視線を自分の陰部とアンナマリアの顔で行ったり来たりさせるジョゼフに、アンナマリアは嗜虐的な心理を覗かせた。
「どうかした?」
「い、いや、だって、また……」
「イかせて貰えると思ってたの?」
「で、でも、あともう少しだけは」
ジョゼフは股間に広がる射精したいという欲求を少しでも誤魔化すために、足をもじもじと動かす。ぱんぱんになったペニスは胸をかきむしりたくなるほどに射精への期待で一杯だった。
情けない懇願の声に、アンナマリアは感情を窺わせない冷徹なままで、けれど声だけは愉悦に満ちている。
「自分でやればいい。わたしの目の前で」
「そんな……」
突き放す少女に抗議の声をあげるが、アンナマリアは本当にそのつもりのようで、一切動こうとしない。ジョゼフがどうするかじっと観察していた。
こんな女の子に見られてる前で、自慰をするなんて――想像しただけでジョゼフの顔は真っ赤になる。既に少女の手の中で果ててしまった事実があっても、その痴態を晒すのには抵抗があった。
ふつうなら、女の子の前で自慰なんて絶対にしない。けれど、頭がおかしくなりそうなほど陰嚢の中で精子がはき出してくれと暴れ回っているのだ。
「う……っ」
真っ赤なトマトみたいに赤面して、ジョゼフは自分の肉棒を握った。自分の手で触れたのに、それはいつもよりもずっと心地よい快感を伴って陰茎を走った。
アンナマリアの唾液で濡れたペニスを上下にしごく。彼女の口内から分泌された透明のぬるぬるとした粘液を性器に刷り込んでいるような倒錯的な気分になってしまう。我慢汁と唾液が混ざって、気泡を立てる。
息を切らしながらの醜態をアンナマリアの感情を写さない目が見つめていた。ジョゼフの目がその目に吸い込まれる。目は口より雄弁に感情を語るという。けれ ども、無口無表情な彼女の目は前述したように感情を感じさせない。なのにジョゼフは小さな女の子に蔑まれているように思えた。
少女の手よりもずっと大きな掌の中で、肉棒はさらに硬さを増して膨れあがる。
アンナマリアの視線がジョゼフの切なげな表情から、下半身に移動した。
「オナニー見られて、興奮してる……」
「これは、その、そういうわけじゃ」
「変態」
「うぐっ」
「だって、今も手だけは止めないんだから」
アンナマリアの云う通りだった。自慰をおこなう手の上下運動はおさまるどころか激しさを増していた。
「わたしの見てる前で、出しちゃえばいいんだ」
耳元で囁かれたみたいに、その声は敏感になった神経に突き刺さり。
しごいたペニスは限界に達した。
「ううううううっ」
――ドクン! ドクンッドクンッビュクンッ!
尿道を駆け抜けて精液が噴出した。
ぐっと目をつぶって快感を受け止めるジョゼフの手がペニスを動かしてしまう。射精された白濁液が飛び散った先にはアンナマリアがいた。
アンナマリアの黒いドレスがぐっしょりと白で汚れた。胸元から、糸を引きつつスカートへ。グラスから牛乳をこぼしたみたいに、精液がみっともなくかかっている。
自分の服を汚した精液を黙って見つめる少女に気がついて、ジョゼフはペニスを握り締めたまま肩を震わせた。
「あっ、ごめん!」
ドレスに飛び散った精液をアンナマリアは指で掬いとると、なんとか上半身を起こそうとしているジョゼフを見下ろした。
「駄目。許さない」
起き上がろうとする肩を掴んで路地裏の地面に叩きつけると、アンナマリアはそのまま馬乗りになった。
痛みに目を閉じたジョゼフが呻きながらまぶたを開くと、眼前の光景に息を飲んだ。
ドレスのスカートをたくし上げて口に銜え、下半身を扇情的に晒したアンナマリアがそこにいた。
アンナマリアはスカートを口にしたまま、片手でレースのついた真っ白いショーツをずらすと、もう片方の手でジョゼフの剛直をつまんで秘所へと導く。
男の性器を受け入れられるとは到底思えない小さな亀裂と亀頭がキスをした。
「ん……」
熱っぽい息を吐いて、アンナマリアは腰を落とす。
愛液に濡れそぼっていた秘所が亀頭を呑み込んだ。
ぬるりと滑って入った少女の膣は、やはり狭い。ぎゅうぎゅうと真っ赤にふくれた亀頭を全方位から押しつぶしてくる。まるでクッションで包まれているようだった。
細い、抱きしめたら折れてしまいそうなアンナマリアの腰が落ちていくのに合わせて、幼い膣が陰茎をなで回しながら奥へと誘っていく。亀頭を、雁首を、竿と裏の筋を無数のひだにマッサージされ、今日一番の衝撃にジョゼフはたまらず声をあげた。
「あっ、あああああっ!」
二度の射精で神経がむき出しになったように敏感になったペニスから伝わる快感は、肉体的にも過酷な生活を送ってきたジョゼフすら絶叫するほどに淫蕩だっ た。しかし、連続で精液を出したペニスはすぐには射精をしない。もし一回も出さずにいれていたら、すぐに達していたことだろう。
既に達していたから雷に打たれたみたいな快感に翻弄され、既に達していたから中々射精ができない。そのふたつが合わさって、アンナマリアの膣はまるで嵐のようにジョゼフを襲った。
ずんっ、と少女の小ぶりなお尻がジョゼフの下半身に座る。アンナマリアの小柄な躯が男を根本まで銜えていた。
スカートを噛む力が強くなり、全身から絞り出した呼気がアンナマリアの喉の奥から洩れる。
「は、ん、ああああ……あ」
ぎゅぅううう、っと膣が締まり、剛直が柔らかい肉の感触に震えた。
浅い呼吸にあわせて、膣肉が蠕動を繰り返して銜えたものを情熱的に抱擁する。瑞々しく愛液をしたたらせる性器は、肉を雁首の合間にねじ込んでは舐めあげる。亀頭の表面はまるで無数の舌が這い回っているようで。膣肉の締め付けに肉棒は押しつぶされそうだった。
少女の意志とは関係なく、その未熟な躯は招き入れた男の精を貪欲に求めてペニスに食らい付いて離さない。
汚く穢れた大男の凶器じみた肉棒で処女を散らし、多くの男たちとの肉欲にふけり続けたアンナマリアの性器は、男の肉棒を快楽に昇らせる術を刻み込まれていた。精液が全身から染みこむのと一緒に、淫らな技もまたその身で覚えていた。
男を知って淫靡に染まった少女の柔肉に、女を知らぬ少年のペニスがもつわけもなかった。
「あ、ああああああああ!」
ドプッ、ドプッ、ドクドク。無意識に少女の腰を掴んでペニスを突き入れたジョゼフは、三度目ともなるのに一向に衰えない勢いでの射精をした。背筋を駆け上る悦楽で涎を垂らしながら、アンナマリアの子宮に若い精子を流し込む。
「ふ、くっ……出てる……っ」
虚ろな目で胸を上下させるジョゼフを頬を紅潮させたアンナマリアが楽しげに見つめる。口からスカートを離して、少年の胸の上に手をついた。
「あは……まだ動いてもないのにイっちゃうなんて、早漏なんだ」
そう云って、自分の腹部をさする。中にある肉棒が未だに存在を主張している。三度もの射精で出し尽くしているはずなのに、こうしている間にも少女の膣は蠢いて萎えるさせることはなかった。
「……動くよ」
聞いているとも判らない相手に告げて、アンナマリアは獣みたいな浅い息を吐いて、腰を持ち上げると――ずんっ、と体重を乗せてペニスを押し込む。
アンナマリアが美しい黒髪を揺らしながら腰を振るたびに、組み敷かれたジョゼフは快感と苦しみの入り交じったような声を発した。
「あっ、あっ、あああ……っ」
陸に打ち上げられた魚みたいに口をぱくぱくとさせる金髪の少年の顔を眺めていると、アンナマリアの中でこれまでにない嗜虐心と充実感がわき上がる。復讐心と嫌悪感だけで男を貪っていたときとは違う、不思議な感覚だった。
自分の中に産まれたものについて、アンナマリアは深く考えられなかった。彼女もまた、自分の中で暴れる肉棒によって興奮していた。脳髄が蕩けそうになって、黒曜の目を情欲に濡らしながら激しく、より激しく陰茎を性器に出し入れする。
ぷっ、くちゅっと泡立った白濁液が掻き出されて、生臭い鼻につく臭いが香る。汗に混じった、普段なら気持ち悪いはずの臭いが、今は興奮を助長させた。
「ふっ、ふっ、んんんっ!」
髪を振り乱して、玉のような汗を散らしながら腰を振れば、その白い肌からは性欲を刺激しそうな甘い香りが発散される。
「あはっ、またビクビクしてる……。ねえ、出したいの?」
気分が高揚しているアンナマリアは饒舌になって訊ねる。けれど、当のジョゼフはと云えば、少女の腰の動きによって与え続けられる心地よさで今にも意識を失いそうになっていた。
「答えられないの? いいよ……それでも今度はイかせてあげる」
アンナマリアの動きが激しさを増した。
ずちゅっずちゅっずちゅ! いやらしい少女の腰遣いが、肉棒を高みへと上り詰めさせ――
「う、出、ぁあ、あああああああ!!」
膣に愛撫され続け、四度目ともなる射精。
アンナマリアの膣の中にドクドクドクッと、洪水のように精子が押し寄せた。なんと今日一番の異常な量の精液が子宮と膣をぱんぱんになるまで犯し、それでも止まらない射精でペニスと秘部の接合部から精液がおもらしみたいに流れ出した。
「すごい、わたしの中が一杯……」
陶然とした表情で、アンナマリアは至福のときだと云うように無防備な顔を晒す。男のまぐわいで、これほどの幸福感を味わったのは初めての経験だった。
ガクガクと全身を震わせて、ジョゼフの首から力が抜ける。あまりの快感に少年は白目を剥いて失神していた。
その頬を小さな指がなぞる。
「まだ寝ちゃ駄目……もっと、がんばろ?」
そう云って、アンナマリアは再び腰を浮かせて無理矢理起こそうと――
「ちょぉぉぉぉぉっと待ったぁぁぁ――っ!」
――しようとして、夜闇に高い声が木霊した。
「はえ?」
不意打ちに、アンナマリアは彼女のイメージからでは想像できないほどかわいらしい声をあげてしまった。
その声は女の子の声で、真上から聞こえてきた。ジョゼフと繋がったまま、アンナマリアは声の主の方を見上げた。
上空――夜天にかかる満月を背後にして、大きな蝙蝠の翼が浮いている。ボロ切れみたいに解れた陰を揺らす翼、それを持つものはもちろん蝙蝠などではなかった。
人である。それも、小柄な少女だった。
一対の翼を広げて中空に浮遊しているのは、焔のような髪をした少女である。赤と蒼の不可思議なグラデーションの頭髪は風に揺られ、月明かりを受けてこの世のものとは思えぬ色彩を放っていた。オーロラを見たことのある者がいれば、まさしくそれだと断言しただろう。
健康的な色の肩を露出する下着みたいな服に、アンナマリアのドレスとは違い簡単に中が覗けそうな短いスカート。どれもが少女の性格を象徴しているようで、快活な力に溢れていた。
「正義の淫魔レリア・キッス参上! トウッ」
落下する勢いで急降下して、レリア・キッスと名乗った少女が路地裏に舞い降りた。
すたんっ、とポーズを決めて華麗に着地した少女は、呆然としているアンナマリアに柳眉を怒らせながら人差し指を突き付けた。
「ジョゼフくんはっ! あたしのっ! 獲物っ! なんですっ! 即刻離れなさーい!」
それが淫魔レリア・キッスと断頭台アンナマリアの邂逅だった。
レリア・キッスと名乗った少女に指をさされ、今まで呆気にとられていたアンナマリアはようやく平静を取り戻しかけていた。といっても、未だに下半身は男と繋がったままである。
初めて興が乗っていた情事を邪魔されて、憤懣がアンナマリアの胸の裡にわき上がっていた。レリアの背にある羽根は飾り物ではないようだし、只者でないこと は確かであったが、アンナマリアにしてみれば性行を妨害された一点のみが問題だった。そもそもアンナマリアとて只者ではない。
「……この人の知り合い? 目障りだから、どこかに消えてよ」
「むっか! 人の話ちゃんと聞いてました? あたしの方が先に退いてくださいっていったんですよぉ! それとも言葉がわかりませんかギヨたん」
「ギヨ、たん?」
そんな名前を口にした覚えはアンナマリアにはなく、ただしその名前で自分のことを呼ぶ者にはひとりだけ心当たりがあった。
「あの魔女の知り合いなのね」
「ええ、そうです。あたしは不本意ながらも先生の助手をしているのです。だから、貴女のこともよぉーく知ってますよ、ギヨた――」
言い終わる前にレリアは地面に伏せる。
瞬間、先程まで彼女の頭があった場所を疾風が駆け抜けた。
まるで刃を震ったような寒々しい風切り音。
レリアがおそるおそる顔を上げると、両脇の建物の壁に鋭い亀裂が走っていた。谷底のように亀裂の奥は闇が続いている。刃物でつけられたとしか思えない。け れど、その傷痕はどこまでも続いているように深い。どれほどの刃渡りがあれば、こんな痕が刻み込めるのか。それ以前に、建物を両断できる刃物がどこにある のだろうか――。
「その名で呼ぶなら、次は殺す。わたしにはアンナマリアっていう名前があるんだから」
アンナマリアがレリアに向かって細腕を突き出していた。その手は何も握っていないが、レリアは凶器を喉に突き付けられる心地だった。
「そうでしたね……貴女、元はギロチンでしたもんね」
どうしてこんな傷痕ができたのか理解して、レリアは呟いた。
そして驚きは既に消え、焔色の髪を夜風に揺らす少女の相貌には妖しい笑みが浮かんだ。
「それならぁ、こっちの方が……効果的ですよね」
レリアが地面を蹴って、アンナマリアに抱きついた。
「えっ」
ジョゼフと繋がったままで避けることもできなかったアンナマリアは抵抗できなかった。
もし性行中でなかったにしても、敵対心の感じない抱擁は避けようとすることができなかっただろう。
そのまま押し倒されて、アンナマリアの秘所からずるりと肉棒が抜けた。ずっと躯の奥で感じていたモノがなくなって物足りなさを覚えるが、今はいきなりレリアに抱きつかれたことに脳内が一杯になっていた。
「ちょ、ちょっと、いきなり何するのっ」
「貴女がいつもしてることですよぉ?」
ゴシックドレスの裾をはためかしながらジタバタと暴れるアンナマリアの目を見て笑うと、レリアは唐突に相手の唇を奪った。
「んー!?」
女性にキスをされて目を瞠り、抵抗が止まる。男相手になら慣れたものだったが、同性――ギロチンに性別をつけるならだが――からキスをされるという状況に酷く驚いた。
先程まで男の腰に跨って腰を振っていたとは思えない初心な反応を返すアンナマリアにレリアは愉しげに目を細めると、舌を相手の口の中にねじ込む。レリアのものより幼く、小さいぷっくりとした唇の合間に滑り込んで歯茎を舐めた。
「ひうっ」
口の中に入ってきた舌の感触にアンナマリアが肩を震わせる。必死に舌で押し返そうとするが、レリアはその舌に自分のものを絡ませた。
レリアの舌がアンナマリアの舌をなめ回し、くちゅくちゅと唾液が混ざり合う。
少女に舌で舌を愛撫されて、アンナマリアは背筋に甘い刺激が走るのを抑えられなかった。背中に蜂蜜を塗りたくられているみたいな、男と躯を重ねていたときには与えられていなかった快感に痺れてしまう。
「ふ、うぅぅ……」
目を恍惚に蕩けさせて、アンナマリアは反抗の意志を手放していた。自分の口の中を犯すレリアの舌に何も考えられなくなる。
涎の糸を引きながら、レリアの顔が離れる。舌が抜かれてしまったときに寂しさを覚えたのは、アンナマリアの気のせいではなかった。
唾液まみれになった自分の唇に指を這わせながら、レリアがアンナマリアの虚ろな目を覗き込んだ。
「あははっ、お口が弱点なんですかぁ、ギヨたん? それとも、あたしのキスがそんなによかったんですかぁ?」
「ぎ、ギヨたんって……いうなぁ」
息を荒くしながらアンナマリアはなんとか言葉を返すものの、それ以上のことはできない。神経一本一本に甘い蜜が染みこんでいるようで、躯がいうことをきかなかったのである。
「そんなに甘い声で囁かれたら、誘ってるみたいですよ? 女の子のキスでそこまで感じちゃうなんて、かわいいんですから」
「そ、そんなこと――ひゃっ!」
レリアが秘部に触れて、アンナマリアは無防備な声をあげてしまった。赤子の頭を撫でるような手つきで精液と愛液に濡れた女性器を撫でられて、ぎゅっと拳を作ってしまう。そのまま二本の指がぬるりと小さな性器に滑り込んだ。
「わっ、すごい。こんなに小さいのに二本も一気に入っちゃいましたよ? こんなにヒクヒクと指を締め付けて……かわいいですよ、ギヨたん」
レリアがアンナマリアの首もとに顔を近づけて、熱い吐息を吹きかけながら囁く。
「や、やっ! やめっ、そんなとこにいれないで……あうっ」
「何いってるんですかぁ、あんなにしっかりジョゼフくんのおちんちん銜え込んでたくせに。今更恥ずかしがっちゃ駄目ですよ」
レリアの口がアンナマリアの首もとに吸い付いた。首筋を舌で舐められながら吸い上げられて、びくんっと背中が跳ね上がる。
さらに秘所に入り込んだレリアの指先が何度も出し入れされて、その度に愛液と精液が掻き出される。肉襞を内側から指先が刺激された。それは男の剛直でかき 回されるのとは違った鋭い刺激で、声を抑えることができない。まるでどこで気持ちよくなるのか知っているような指先の動きは、的確にアンナマリアの弱いと ころを責めていた。
「ほらほらぁ、気持ちいいですかぁ?」
「そ、そんなわけ、ないっ!」
「強情ですねぇ。じゃあ、そろそろこっちも触っちゃいましょうか」
今まで一度として触られていなかったアンナマリアの陰核に、レリアの親指が触れた。
ジョゼフとの性行中も刺激を受けていなかった陰核に親指が触れると、快楽の電流にアンナマリアは口を大きく開いて嬌声をあげた。
「ひゃ、あああああぅ!?」
小柄ながらも膨れあがった少女の陰核を、レリアは親指の腹でマッサージするような優しい手つきで刺激する。今まで触れられていなかった陰核は、勃起していたのに触れられていなかったペニスと同じで、アンナマリアは流し込まれる快感に抗うことができずに痩躯を震わせた。
「ほらほら、まだここが残ってますよー?」
くすりと笑って、レリアはアンナマリアのドレスをはだける。片手しか使っていないにも関わらず、あっさりと白い肌を露出させた。
わずかな膨らみしかない薄い胸をレリアは下から押し上げる動きで撫でる。そして、最後に乳輪を人差し指でなぞった。
「や、やあ!」
「そんなこといってー、乳首はこんなに硬くなってますよぉ?」
レリアが首もとから口を離して、アンナマリアの薄い胸で硬くなっている乳首を舌先で突いた。
そうやって焔色の髪の毛を持ったレリアから与えられる刺激は、総て躯に触れたと同時にぴりぴりとした快楽をアンナマリアに与える。男に犯されて強引に弄られたときは気持ちよさを感じなくとも、レリアの繊細な手腕には逃れがたい快感を叩きつけられていた。
「な、なにこれ、どうしてこんなに……っ」
「どうしてこんなに気持ちいいか、ですよねぇ?」
「……っ」
アンナマリアの顔が羞恥心で真っ赤になる。嘘をついて突っぱねることができないほどに、躯は正直にレリアの手によって悶えさせられていた。
レリアが乳首を甘噛みすれば、ずっと弄られ続けているアンナマリアの秘所からは愛液があふれ出す。
「あっ、ああう……はぁっ! ああ……」
虚ろな目で小刻みに痙攣を繰り返す。その有様に、レリアが微笑んだ。
「あれ、イっちゃいましたぁ?」
「はっ、あ、うあ……」
ふわふわとした浮遊感にアンナマリアは戸惑っていた。肉体を得て地上を徘徊し始めてから与えられる初めての経験に、自分がどうしたのかわかっていなかった。
だから、レリアに訊ねられてこれが絶頂なのだと理解した。
「イった……?」
今までは知識としか知らないものだった。それはいつでもアンナマリアと躯を重ねる男が死の間際まで幾度となく繰り返す感覚であったのだ。ジョゼフと繋がったときこそは奇妙な充足感があったものの、これほど衝撃的なものではなかった。
「そうですよぉ、ギヨたんはイっちゃったんです。あたしに舐められてぇ、性器を撫でられてぇ、気持ちよさのあまりに昇天しちゃったんですよ。もしかして、イクのは初めてでした?」
全身を弛緩させたアンナマリアの下半身から指を抜いて、愛液と精液の絡み合った指を口に運ぶ。レリアは自分の指に舌を這わせて、その混合液を嚥下した。
「んふっ、これがジョゼフくんの精液と、ギヨたんの味なんですか。久しぶりの精だから夢中になっちゃいそうですよ。結局、今日もパンしか食べませんでしたから」
「こんなこと、今までなかったのに……これが……」
「そんなに衝撃的なんですかぁ? それとも、不思議ですか? どうしてあたしの行為でこんなに気持ちよくなっちゃうのか」
アンナマリアはのろのろとした動きで後者の言葉に首肯した。疲労がたまってぐったりすることはあっても、今みたいに全身に快楽が染みわたるようなことは経 験がない。男たちに技量が足りなかったといえばそれまでかもしれないが、アンナマリアが心的に充足していたジョゼフとの性行ですら起こりえなかったこと だ。
もしかするとあの充足感はわずかに達していたために起こったものかもしれなかったが、どちらにしろ今の感覚よりはずっと易しい。
だから、レリアに原因があるとしかアンナマリアには思えなかった。
「それはですねぇ、あたしが淫魔だからですよ」
「淫魔?」
「そ う、淫魔です。あたしたちの唾液とか、分泌される体液には精力を増幅させる要素があってですね。えっちする人をより性的に興奮させることができるのです。 なので、感度も上がってしまうわけなんですね。そういうわけで、今も自分が得意な状況にしたんですよぉ? まともに戦ったらギヨたんには敵いませんから」
淫魔――そういった種族がいることくらいならアンナマリアも朧気にではあるものの知っていた。魔女に教わった記憶はないので、恐らく制作者たちによって断頭台として生を受ける前に刻まれたものなのだろう。
「で もこれくらいは人が呼吸をするように、淫魔なら全員が持ってる生態なんですけどね。実際は、あたしのえっちが上手だからなんですよ。ギヨたんも女の子だか ら、どこで感じるかなんてもう手に取るように判っちゃうんだから。あ、淫魔には女の人しかいないんですけどね。とにかく、乱暴に男の人に突かれてるだけ じゃ、こうはならなかったでしょー?」
ちゅっ、とレリアが胸にキスをすると、はふっ、とアンナマリアは甘い吐息を洩らす。この薄い胸を滅茶苦茶に揉まれたことは何度かあったが、脳髄が蕩けだしそうになることはなかった。
「ギヨたんったら、ホントにイジメがいがあるんですからっ! もっと食べたくなっちゃった。人間じゃないから先生も文句をいうことはないでしょうし……あっ」
レリアがあるものを見つけて、目を輝かせた。
「そうだ……じゃあ、ギヨたん、次はこうしましょうね」
「え……?」
ようやく頭の回転が戻ってきたアンナマリアを起こすと、レリアはそれの方へと近づいていった。
ふたりはジョゼフの股の間に躯を滑り込ませる。そこには勃起しているペニスがむき出しになっていた。
「ジョゼフくんったら、ギヨたんの喘ぎ声で目を覚ましちゃってたんですよ」
「あ、いや、これはその、盗み聞きをしていたつもりじゃ!」
意識があったといっても夢に微睡んでいるような状態だったジョゼフは、レリアとアンナマリアが動いたことでようやく完全に覚醒した。どうしてこうなっているのか理解はできていないようだったが、現状の認識はできている。
ジョゼフの弁明をレリアは聞く耳すら持たなかった。その目は爛々と輝いて、大きくなっている肉棒に注がれていた。
「ふふっ、おしおきしてないとあげませんよね?」
レリアが竿を握ると、押し殺した呻き声がする。
「さあ、ギヨたん。……一緒に、舐めちゃいましょ?」
アンナマリアの目も、大きくなった性器に釘付けだった。さっき自分が銜えこんでいた陰茎を前にして、あの愉しげな感情が再び胸に戻ってくる。
レリアが舌を伸ばすと、釣られてアンナマリアも舌を伸ばす。ふたりの少女の真っ赤な舌がジョゼフのペニスを舐めあげた。
「うっ!?」
ふたりの口が茎に吸い付いて、肉棒が激しく脈打つ。既に何度もアンナマリアに射精していたにも関わらず亀頭を真っ赤に膨らませたペニスに、レリアが歓声を上げた。
「あはっ、ジョゼフのおちんちんってこうなってたんですねえ。こんなに震えちゃって……」
レリアが眼を細めて、感極まったとでもいうように云った。魔女から止められていたが、ジョゼフのことはこの国にやってきたときからずっと目をつけていたの である。今まで狙った相手はすぐに食べていたレリアとしては、お預けされ続けてきた末に食べることを許されたごちそうであった。
「はむっ」
レリアが亀頭を呑み込む。
ぷちゅっ、と唾液が亀頭に絡んでいやらしい音を立てた。赤く膨れあがった先端に何度も情熱的なキスをする。柔らかく膨れた唇が亀頭を這い回って、舌先が尿道をなぞっていく。その甘美な快感にペニスの射精へのカウントダウンが始まった。
「んー、こっちにキスされる感覚はどうですかぁ? いっぱい愛でてあげちゃいますよー……わっ」
押し寄せる快楽に耐えているジョゼフの顔を眺めながら亀頭にキスしていたレリアの唇に、アンナマリアの唇が触れた。
「ん……」
アンナマリアがレリアの目を一瞥して、彼女の唇を巻き込んで亀頭を愛撫する。ふたつの舌に責められて、切なげな声があがった。
知らずのうちに、アンナマリアは対抗意識に駆られていた。それを見て取ったレリアは面白いと鼻を鳴らす。
「んふっ、そっちがその気ならぁ、こうですよ」
ずぷんっ、とアンナマリアの秘所になにかが突き込まれた。
「ひあっ!」
喉の奥からしゃっくりみたいに声をあげたアンナマリアは、自分の膣に入り込んでいるものを見る。そこにあったのはレリアの手ではなく、彼女の尾骨の辺りからスカートを押し上げつつ現れた黒い尻尾であった。
先端がハート型になった――見ようによっては、男性器に見えなくもない尻尾が、アンナマリアの愛液に濡れながら奥へ奥へと突き進む。男性器と違って膣内で蛇みたいにのたうち回る尻尾に、アンナマリアは快感で足をぴんと伸ばした。
「あっ、ひゃあっ、入って、る!」
「おちんちんとは違いますけどぉ、これなら色んな所も責めてあげられますよ?」
アンナマリアの耳に息を吹きかけて、レリアはさらに尻尾を暴れさせる。男のモノを銜え込み続けていたとはいっても、快感を与えられることに慣れていなかった少女の躯の弱点を探りあてるなどレリアには造作もないことだった。
ずぽっ、ずぽっ、と尻尾のピストン運動にアンナマリアは口淫をしていたことも忘れ、涎を垂らしながら喘ぐ。
「や、やあ……っ、これ以上、されたら……お、おかしくっ」
「はいはーい、お口がお留守ですよぉ」
レリアがアンナマリアの頭を掴んで、ぐっとジョゼフの一物へと近づける。
「あ……」
焦点を失った目でアンナマリアは目の前でそそり立つペニスを銜えた。
尻尾に突かれ、抑えきれぬ喘ぎ声をあげながらも一心不乱に男性器に食らい付くゴシックドレスの少女にレリアは満足そうに頷いて、だらしない顔になっているジョゼフを見上げた。
「それじゃあ、ジョゼフくぅん……たっぷり気持ちよくなってくださいね」
アンナマリアと唇を重ねるように、レリアもまた逞しく勃起した陰茎に口づけをした。
天性の肉体に任せて男を絶頂させていたアンナマリアと違い、レリアの口は染みついた技巧が伴っている。男性の一番敏感なところを熱っぽく幾度とキスする手際に、男は全身を一斉に愛撫されているような錯覚を起こすのだ。
小さな口で涎を垂らしながら一生懸命にペニスを出し入れするアンナマリアに、恵まれた肉体だけでなく経験によって培われた性技を披露するレリア。
奥歯を噛んで脳内で神経が切れてしまっているのではないかと思うくらい我慢していたジョゼフにも限界は目前に迫っていた。
アンナマリアも、また天に向かって上り詰める。躯を突く、乱暴に見えても実は繊細に弱いところを突き上げてくる尻尾に抗うことはできない。きっとジョゼフがイクと同時に彼女も達してしまうだろう。
自身の幼い躯を弄ばれて快楽に苛まれながらも美味しそうにペニスを舐めるアンナマリアは、正気を手放しそうになりながらもわずかに残った脳の片隅で考える。
このまま、イっていいものか――。
でも、我慢することはできない。下半身をがくがくと痙攣させて、アンナマリアの躯はレリアが与えてくれる刺激に陶酔していた。
ただ。このままイかされるのは、嫌だ。
きっと、このままイってしまえば、あまりの気持ちよさに意識を失ってしまうことをアンナマリアは自覚していた。それは、くやしい。
復讐のためにこんなことをしてきて、街を徘徊してきたのに、こんなところで出会ってしまった淫魔を証する少女にあっさりと折られてしまう。そんなの、くやしいに決まっている。
なら、せめて一矢報いてやる――。
アンナマリアはレリアのスカートの中に手を伸ばした。
下着に触れると、そこは興奮のためか愛液でぐっしょりと濡れていた。その合間から、アンナマリアはレリアの秘所に指を差し込んだ。
レリアの膣肉は指を強く締め付け、幾重にも波打つ襞に擦られる。くちゅくちゅと音を鳴らしながら掴まれた指先は、それだけで背筋を走る快感を覚えさせられた。
くふっ、と唇とペニスの合間から息を洩らして、レリアが微笑む。
「ギヨたんったらぁ、その気になっちゃって……うふふ、気持ちいいですよ?」
男のモノなら何度も握ったことはあったが、アンナマリアも他人の女性器を弄るのは初めてだった。そのせいで手つきはたどたどしく、手探りにレリアの下半身をまさぐっている。
「ほら、頑張ってくださいよぉ」
「んぐっ!?」
嗜虐的に云って、レリアは尻尾でアンナマリアの子宮口をぐっと押した。内臓を押し上げられてえづくが、それ以上の快感が躯を浸食する。
「あ、ひゃう」
肺が引きつって、変な声をあげてしまった。涙で視界が歪むのは、悲しいからではなく心地よすぎたからに他ならない。
鼻先のペニスから漂う精と唾液の香りに、激しい挿入でひくひくと痙攣する陰部。
止まりそうになる指先に意識を集中させて、アンナマリアは指の根本までレリアの秘部に挿入した。アンナマリアと同じか、それ以上に小さいレリアの性器は淫らにうごめき、二本も三本も指を銜え込む。
「そうですよぉ、その調子です。ふふっ、少し気持ちよくなってきまし……はうっ!?」
アンナマリアの指の動きに、余裕綽々だったレリアは艶っぽい声をあげた。自分で自分の反応に驚いて、レリアは股をむずむずと動かす。そうすると膣内にある指の感触がより鮮明に感じられた。間違いなく、そこにあるのはアンナマリアの手業に慣れていない細い指先。
「な、なんで? ……ひゃっ! えっ、うそ、なんであたしが感じてるんですかっ」
その反応は奇しくもレリアに責められたときのアンナマリアのそれと似ていた。
アンナマリアは汗ばんだ顔で、眠たそうにした目をレリアに向ける。それは快楽に酔いしれている目であったが、胡乱ではなく――どこまでも続いていきそうな深遠なる闇が垣間見えた。
レリアの中に焦燥感がわき上がる。続いて、対抗心。人になって数日か数週間した経たぬ者に性技で負けるわけにはいかない。ムキになって、尻尾のピストンを跳ね上げた。
「うぐっ」
アンナマリアの腰が跳ね上がる。愛液が比喩ではなしに滝のようにこぼれ落ちた。口からは喘ぎを洩らす。それでも指だけは止めなかった。
ぎこちなかった指の動きは今やよどみないものとなり、女性の――レリアが弱いところを探し当てようと膣内をこねくりまわし、責める。そのたびに少女の躯が反応を返した。
性技に長けたレリアは、もちろん人から受ける快感への耐性も強かった。性技自慢の男たちとまぐわろうとも、相手を搾り殺すことこそすれ、感じることはそう そうない。二度、三度、人間がレリアの躯に経験を積めば話は違うかもしれなかったが、それでも気持ちいいと感じさせるだけに留まるのみだろう。そもそも、 一度目で死んでしまうのだから二度目が来ることすらないのである。
よって、レリアは性行を楽しみこそしても、躯をビクビクと震わせるほどに快感を感じたのは魔女と寝ているときを除いて数百年ぶりだった。
「そ、そんな、どうしてこんなに早くっ」
「だって、教えてくれたでしょう? さっき、わたしの躯で……」
「まっ、まさか! あたしに責められただけで、覚えちゃったんですかぁ!?」
驚くべき事実でも、そうとしか説明のしようがなかった。アンナマリアはレリアの技に身をもって溺れたことで、一気にやり方を吸収してしまったのである。
「で、でも……先にあたしがイかせちゃえばっ! このままならもうジョゼフくんとギヨたんだって限界のはずっ」
その通りだった。アンナマリアの覚えた技は、所詮はレリアの付け焼き刃。いくら驚異的学習能力だとしても、この逆境を跳ね返すだけの力はない。
――そう、この力、だけなら。
はあ、はあっ、と肩で息をして快感に意識を手放しそうになりながら、アンナマリアはレリアの耳元で呟く。
「ねえ……この、ジョゼフって人のこと、好きなの!?」
「はいぃ!? なっ、なにを云ってるんですか! あたしは淫魔ですよ、サキュバスですよ? 人なんて食料に決まってるじゃないですか! ステーキに欲情する人間がいますか? いないでしょう!」
「慌ててる……かわいい」
自分を苦しめたレリアが顔を真っ赤にして否定したものだから、アンナマリアは素直にそう思ってしまった。その言葉が益々レリアに羞恥心を抱かせ、心の隙にアンナマリアの指が入り込み――こじ開ける。
「ひゃっ、あっ、しまっ……だ、駄目です、もう……っ」
うっとりとした表情で、レリアは興奮のままに尻尾を上下させながら、涎まみれの口で陰茎にむしゃぶりつく。
「ひっ、いやぁっ!」
アンナマリアもレリアも限界だった。
ふたりは目の前の肉棒に激しく唇を這わせながら、指と尻尾の勢いを増して――。
「ふぁ、ああああああ――!」
同時に絶頂を迎えた。
びくんっ、と躯を仰け反らせて、口は亀頭に吸い付く。それで肉棒も頂点に達した。
激しく脈打つペニスから飛び出す精の塊。アンナマリアとレリアの顔を熱いスペルマが真っ白に彩った。
むせかえるような精の香り。再度の射精にまたもや意識を手放したジョゼフの下半身に顔を寄せて、口の中に入り込む精子の味に酔いながらふたりも意識を手放した。
路地裏には半裸の三人が倒れていた。それをすぐ近くでひとりの女が見下ろしている。
魔女イザベラは呆れて嘆息した。そこにいたのは、全員彼女の顔見知りであったからだ。云うまでもなく、ジョゼフ、アンナマリア、レリアの三人である。
「まったく、運ぶ身にもなってくれたまえよ。まあ、こうなることは予想できてたんだけど」
ローブをまとい、扇情的に胸元をはだけているイザベラは、呆れはしたものの驚くことはない。今回の出来事はイザベラにとっては想定内のことであったからだ。
「ジョゼフが生き残っていることくらいかな、意外なことは。てっきりギヨたんかレリアに搾り殺されると思ってたけど、その前にダブルノックダウンとはね」
運の良い子だな、と肩を竦める。そこに罪悪感は欠片もない。それを追求すれば、結局生き残っているのだから感じる意味もないとイザベラは断じることだろう。かといって、死んでいても悪びれるかと云えば、そうは思えない様子が彼女にはあった。
例え自分が助けた命でも、死ぬときがくれば死ぬ。それをわざわざ能動的に払ってやろうと行動しない程度に、魔女イザベラはやはり魔女と云える思考の持ち主だった。
けれど、生き残ったのなら、せめて助手共々面倒を見てやらなくては――とイザベラは億劫ながらも腕を突き出し、動作をやめる。
「おや……」
遠くから足音がしていた。それはひとりによるものではない。人が群れをなし、夜闇の中で闊歩していた。
「おい、こっちから声が聞こえてきたよな」
「ああ、もしかすると最近噂の殺人犯かもしれないぞ」
魔女はトレードマークの帽子を手で抑えながら、彼らが何者であるか検討をつけていた。
夜の街を巡回している男たちだ。アンナマリアの所業によって行われた殺人の数々で、ついに重い腰をあげて警邏を強化したのであろう。
どうやら、三人の情事を嗅ぎつけてきたらしい。
「声が大きすぎるよ、君たち……」
三人には届かないと判っていても、イザベラは面倒が増えたことに対する不満を口にするのを抑えられなかった。
そうしているうちに、路地裏を覗く幾つもの影がイザベラの背後に現れた。
「おい、誰かいるぞ」
男のひとりがランプを路地裏に向けた。背中に光の熱を感じて、イザベラはローブを揺らして振り返る。
そこにいたのは四人の男たちだ。腰には鋳型にはめられて作られた安物の剣を下げ、頭部を守るメットとなめし革の鎧を身に着けている。
もし、彼らの想定していた殺人犯が単独犯なら、なるほど、その程度の装備でもなんとかなったかもしれない。相手が人間であるなら、四方を囲めばそれで事が済む。
ただ、それも相手が常人であった場合を想定していたらの話である。イザベラからしてみれば、酷くお粗末な身なりだった。イザベラでなくとも、相応の使い手 ――今まで悟られずに街中で人殺しをおこない続けることができるほどの者となれば、問題なく皆殺しにできてしまえそうである。
「なんだ、娼婦か?」
イザベラとその背後に半裸で倒れる三人を見て、男たちのひとりが疑問の声をあげる。
下半身をむき出しにしたジョゼフと、男性器に纏わり付く少女がふたり。誰が見ても、路上で激しい一夜を過ごしている者たちにしか見えなかった。
さらに、イザベラの格好はおよそ街中を歩く淑女に相応しい身なりではない。ふわふわとした布で躯の線こそ隠れているものの、たわわに実る豊満な胸元は外気 に晒されていた。くわえて、美貌である。月光を受けて輝く銀髪も、その氷像然としていながら飄々と揺れる柳のような相貌も、総ての要素が黄金比率を保って いた。
高級娼婦。否、それ以上。男たちの全財産を叩いても抱けないほどの上玉――。
警邏隊の関心はイザベラと、倒れる少女の裸体にだけ注がれていた。彼女たちこそが警戒しなければいけない集団であるとはまったく考えていなかった。。
「へえ、良い女じゃないか……。そっちのガキ共も、相当手慣れてるみたいだな。男共々気絶してやがる。しかしなあ、俺たちの手を煩わせたんだ……勿論、責任は躯でとってくれるんだろうな?」
警邏隊のひとりがイザベラの腰に腕を回す。色事を前にしただらしない男の顔が息もかかるほどイザベラの顔に近づく。
どうやらこの男がリーダーのようで、他の三人は遠巻きにイザベラたちを見ているだけだった。それでも顔はだらしなく緩んでいる。情事の現場を目撃して興奮したのか、彼らも浮き足だっていた。
イザベラは口元に笑みを浮かべて、自分の腰を抱く男を流し目で見た。それだけで漂う色香が男の胸をくすぐる。
「どうやら、随分たまっているようだね……。ふふ、激務で女を抱く暇もないのかい?」
「ああ、そうさ。それに、誰のために俺たちが働いてやってると思ってる? 国民のためさ……なら、お前たちも俺たちに奉仕する義務がある。そうだろう?」
男は布越しに膨らんだペニスをイザベラのふとももに押しつけながら、彼女の乳房を乱暴に掴んだ。
小さく嬌声をあげてると、イザベラは指先で男の顎をなぞる。
「強引だね。でも、そういう男は嫌いじゃない。私も久方ぶりでね……男が欲しかったところなんだ」
「へえ、話がわかるじゃねえか……。後ろの連中の相手はそっちのガキどもがやってくれるんだろうな? 俺ひとりでってのも気が引けるんでねえ」
「ああ、それは駄目だね。彼女たちは疲れているし……そもそも、キミひとりじゃ私が満足できない」
「なに?」
片眉をあげて問い返す男に、イザベラは妖艶に微笑んで右手を掲げた。
「私がキミたち全員の相手をしてあげよう」
パチン――、と指を弾く音。
それを合図に、世界は変貌した。
*
警邏をしていた四人の中で一番肩身の狭い思いをしていたのが誰かと云えば、もっとも年若い少年だった。
年齢は一六歳で、人と喧嘩をしたことこそあれども殺し合い染みたやりとりはしたことはないという、そこそこに恵まれた少年である。
革命が起きたことで、そんな少年にも剣を持たなければいけないときがきた。王を処刑したのだし、戦時なのだから今まで戦いをしたことのない者でも武器を手にしなければいけないのは考えてみれば当然のことである。
もっとも、少年が警邏に従事しているのは、なにも革命やそれに伴う使命感などではなかった。もし、徴兵を断ったりしたら逆賊として殺されるに決まっている。それが革命によって生まれ変わった国家の選択だった。
これじゃあ、僕たちの戦いに意味などないじゃないか――。
少年は革命を望まなかったが、それを時代は許さなかった。群衆の総意は、いつだって少年みたいな人間を小石のように流れへ巻き込んだ。
少数派を呑み込んで、一丸となって戦いに挑む。それ自体に間違いはないのだろう。統一性がなければ、争いに足を取られてしまう。
呑み込まれた少数派はいつだって不平を洩らすが、所詮、それは大多数から見れば弱者の戯言にすぎない。少数派である彼らの主張が正しくとも、それを他人と 共有できなければ、そこまでの主張であったに過ぎない。少数派が大多数の人間を罵るのは、結局のところそれしかできないから責任と無力感を押しつけている だけなのだ。
そう、革命が、民衆の総意が嫌なら、不平を云うのではなく、立ち上がって声も高らかに宣言しなければならない。リスクを恐れずに総意へ立ち向かわなければいけない。それができないのなら、そもそも見苦しく自身の思想なぞまき散らすべきではないのだ。
だから少年は口を閉じた。
自分にそんな力がないことも、見苦しく不平を垂れることすらもできない小心者であることをよくわかっていたからだ。
「――そう、キミは疲れているんだね」
「え?」
優しい声が少年に語りかけてきて、声をあげる。
いつの間にか、少年はベッドの上にいた。淡いピンク色のシーツが敷かれた、甘い香りが漂うふかふかのベッドだ。
少年の頬に柔らかい手が触れる。ベッドにはもうひとり座っていた。
身を乗り出して手を伸ばしていたのは、少年と同い年くらいの少女である。長い銀髪に、見つめられると背筋が撫でられたみたいな心地になる鋭利な眼が印象的だった。
魅力的な瞳が、少年をいたわるように細められている。頬に触れている手の感触に心奪われて、少年は革命によって荒んでいた精神の海が凪いでいくのを感じた。
「君は誰――そういえば、僕はさっきまで警邏を――」
少年の唇を少女の人差し指が塞いだ。
「何も考えなくて良いよ。私に身も心も任せるといい。大丈夫、優しくエスコートしてあげるよ……天国まで」
少女が少年の肩を押して、唇を奪いながらベッドに寝かせた。
抵抗しようという気持ちはついぞ浮かんでこなくて、少年はこの麗しい少女になにもかも任せることにした。もう、考えるのは疲れていた。この甘い芳香で、悩みがどうでもよくなった。
そういえば、ここはどこなのだろう。ベッドしか見あたらない、よくわからない場所。
――まあ、どうでもいいか。
そう切り捨てて、少年は口の中に入ってくる少女の舌に意識を集中させた。
長い長い全身を包み込むようなキスが終わる。真上で微笑む少女に、少年はひとつだけ訊ねてみた。
「君の、名前は?」
少女は囁く。
「――イザベラ」
リーダー格の男は困惑していた。
自分は先程まで、汚物まみれで臭気漂う路地裏で女の腰を抱いていたはずである。
「なのに、どうして」
悪夢の中に迷い込んだ心地でつぶやいた。
そこはピンク色のシーツが引かれたベッドの上だった。こんなところにやってきた記憶が、男にはまったくない。飲酒もしていなかったし、前後不覚になる理由はなかった。
なによりも、ここにはベッドしかないのが問題だった。周囲を見渡しても、果てが見えない。大海原に放り出されても、こんな不安は抱かないだろう。なにせ、海には海水と空があるのに、ここは文字通りベッド以外の存在が皆無なのである。
「へえ、変化なしか。この私の躯が理想的だったとは、いやはや、女としては誇りに思うね。キミに恋愛感情が抱けていたのなら、きっと心底愛してあげられたはずだよ」
いつの間にか、魔女イザベラがベッドに腰掛けていた。大きな帽子も、ローブも、そのままである。この空間にあって、その姿は異様だった。
「お、おい、いったいここはなんだ。お前がなにかしたのか!」
「その通り。総てが私の思いのままになる、ここが一番好都合なのさ。なにより、ベッドの上の方がムードがあるだろう? それとも、陵辱願望をお持ちだったかな」
イザベラがベッドに引きずり倒された。破れたローブから、片手では覆いきれない乳房が漏れ出る。
「お前、俺をおちょくってんのか!」
「あれ、そのつもりだったんだけど……判らなかったかな?」
男の頭の中が怒りで沸騰した。もう、ここがどこだかなんて考えるのはやめた。今は、この女の躯に後悔の味を刻みつけることに執心した。
ズボンを降ろし、男は勃起した一物をむき出しにする。例えいかに腹の立つ女であったとしても、目の前にいるイザベラは男にとって理想的な肉体をもっていた。
彼女の銀髪を乱暴に掴むと、男はペニスを口の中にねじ込む。魅惑的な赤い唇と白い歯を押しのけ、一気に喉の奥を亀頭で突き上げた。
そのまま髪を引いて、口の中で剛直をピストンさせる。人肌の生ぬるい温度でしめった口腔を犯せば、背徳感と快感が合わさってぞくぞくっと全身を駆け巡った。
夢中になってイザベラの顔を腰に叩きつけ、口蓋と舌を汚れたペニスで蹂躙する。
男性器を慰める気持ちよさに涎を垂らしながら息を乱していることに、当の本人である男は気付いていなかった。
イザベラが髪の毛を掴んでいる男の手首に触れると、軽い衝撃がそこに走る。痛みはなくとも、腱を刺激されたせいで男の手は勝手に開き、銀髪を手放してしまった。
ぬるりと涎まみれの男性器を口から抜いて、イザベラは男相手に上目遣いとなる。
「口よりも、もっと気持ち良いところがあるよ」
そう云って、自身の胸に剛直を挟み込んだ。
異論を唱えるより先に自分自身が胸に包まれたことで、男は情けなく声を洩らしてしまった。
仰向けの体勢で豊満な、それでいてマシュマロみたいに柔らかい乳房で男のペニスを捉えれば、イザベラは胸を上下させた。
ぬちゅっ、ぬちゅっ、と音がして、胸の中で肉棒が暴れる。胸があがれば亀頭まですっぽりと胸に押し包まれる。胸が下がれば、亀頭が胸肉を掻き分けながら顔を出した。
「本物の亀みたいに頭を出したり隠したり……随分とかわいらしいペニスじゃないか」
「はが、あがががが……」
男は腰砕けになりそうなのを必死に堪えていて、イザベラの言葉は耳に入ってこなかった。
彼女の唾液が潤滑液となり、スムーズに胸の谷間を往復する。
鉄のように硬くなったペニスを押しつつむ豊かで柔らかな感触は、まさに天にも昇る心地よさ。
ふつう、女性の乳房は子供にミルクを与える供給器官であるはずなのに、イザベラのそれは男の肉棒からミルクを搾りだすための搾精器官だった。
「熱い、焼けるように熱いな……そんなによがって、よほど私の胸が気持ちいいらしいね」
淫蕩に微笑み、イザベラは自分の乳房を揉みしだきながらペニスを圧迫する。自分で自分の胸を慰めながら男の肉棒を擦り挙げる仕草は目眩がするほどに妖しい。
「我慢する必要はない。たっぷりと玉袋にたまった精子を吐きだしたまえ。この胸の中でね……」
云われるまでもなく、男の脳裏に我慢の二文字はなくなっていた。それ以前に、優しくも無慈悲にペニスを搾る乳房に抗えるとは思えなかった。
亀頭に鮮烈な快感が走る。魔女が目一杯舌を伸ばして、その先端で亀頭を舐めていた。胸の谷間から顔を出したペニスをちろちろと舐めながら、ぎゅっと左右から胸で茎を圧迫する。
尿道にイザベラの舌が入り込んだ瞬間、男のペニスが震えた。
「あ、あ、出る……うわおおおおおおお!」
ぶしゅっ、と白濁の噴水が飛び出した。
イザベラの美麗な顔へ大量に男の子種がまき散らされる。
目を閉じて精子を受け止める。まだ射精は留まることを知らず、乳房の中でのたうち回り黄ばんだ精液を吐きだしていた。
イザベラの顎から細い喉までを真っ白く濡らし、あまりの快感に男が腰を引くと胸の中でも爆発を続けた。ぶわっと乳房から溢れだした精液が谷間に白濁の池を作る。
陰嚢の中にあったものを一度に総て吐きだしたのではないかと思うほどの量がイザベラを汚し、むせかえるほどの青臭さが溢れた。
腰が砕けたのか、男はイザベラに覆い被さる形でベッドに倒れ込む。何十分も全力疾走をしたのかと思うほどに息を荒くする男は、ペニスに再度くわえられる刺激に情けなく呻いた。
イザベラが精液に濡れた乳房で、射精したばかりのペニスをしごいていたのだ。
「ほらほら、どうしたんだい? 男なんだから、まさか一回出しただけで満足なんてことあるわけないよね? 遠慮しなくていいっていったじゃないか……出したまえよ」
男にはそれが悪魔の囁きにしか思えなかった。性欲は旺盛だと自負していた男も、たった一度胸に搾られただけで総ての精子を吐きだしていた。
嗜虐的に笑いながら、イザベラは精液を利用してぬるぬると胸でペニスを責め立てる。いやらしく精子で気泡をたてながら、柔らかい胸が絡みついた。
「はぐっ、ごっぐげっ……ああああああ……っ」
ベッドのシーツに顔を押しつけながら内臓を吐き出しかねない形相で男が悶える。射精した直後のペニスを責める温かくも柔らかい胸は冷酷なまでの快楽を流し込んでいた。
男の苦しみようとは裏腹に限界まで勃起したペニスは白い飛沫を飛ばしながら乳房を堪能している。イザベラが首を傾けて、胸から飛び出た亀頭に吸い付いた。 ずずっ、と精液をすすりながら亀頭にキスをする。精液に口元を濡らしながら亀頭を這い回る唇。イザベラの唇に刻まれている皺のひとつひとつが感じ取れるほ ど、亀頭の感覚ははりつめていた。
「やめ、やめてくれ、出る、また出るっもう出ないのにっやめろ! やめてくれ!」
「嘘はよくないな……キミはまだまだ出せるよ。だって、ほぅら。今だってこんなに膨らんでいる」
聞く耳もたずにイザベラは乳房を操る速度を速め――
「だあああああああああああああああああ――――!?」
男の絶叫と共に、乳房から頭を突き出したペニスが爆発した。
一回目と変わらぬ、むしろそれ以上の勢いで真っ白な液体が溢れる。イザベラの美しい銀髪にもべっとりとかかり、さらに顔と胸に子種を振りかけた。
「おやおや、これでは胸が妊娠してしまうじゃないか」
くっくっ、と喉を鳴らして、胸を白くデコレーションしたペニスに向かって云った。
威勢のよかった男は既に無く、あとには虚ろな目でベッドに横たわる哀れな犠牲者がいるだけだ。
躯を起こしたイザベラは、今にも息絶えそうな男に――そのペニスに手を伸ばした。精液まみれの萎えかけたペニスを掴むと、男の躯が跳ね上がって嬌声をあげた。
「あがぁ……っ」
「まさか、本当にこれで終わりってわけじゃないだろうね。私はまだ胸に挟んだだけで、膣に挿入すらしていないのだよ? それはあまりにも自分本位な性行じゃないか。さあ、本番と行こう」
イザベラが萎えかけたペニスをしごくと、掌の中でむくむくと首をもたげ始める。精液でぬるぬると指を滑らせる手つきに、男は意志と反して挿入可能の状態になるしかなかった。
「な、なんで……なんで、まだ立つんだ……」
けれど、数週間、数ヶ月分の精液を一度に吐きだしたにも関わらず勃起するというのはさすがに異常だった。自分の躯が自分のものではないようで、男は快感ではなく恐怖で震え出す。
「ああ、それはね。ちょっとキミに細工をしただけだよ。私は淫魔と違って人間だからね、精力を刺激する体液を分泌なんてできなくてね。自前のテクニックと魔法でどうにかするしかないのさ」
「ま、魔法? まさか、魔女……!」
男は悲鳴をあげるようにその名を口にした。
魔女について、今更説明するまでもない。悪魔と契約したことにより力を手にした背信者、その総称が魔女である。
魔法使いを恐れる人間は少ない。むしろその力に憧憬すら抱く。だが、魔女は別なのだ。悪魔が無償で契約することは、人が呼吸をしないで生活するのと同じく らいにあり得ない。彼らは必ず、人に交換条件を持って契約を結ぶのだ。より正しく云うなら、人は悪魔に従属することで魔女となる。そもそもの力が違うのだ から対等な契約が結べるわけもない。
そして、悪魔の契約とは常に人間を追い詰めるものである。力を与える代わりに生け贄を寄越せ、なんてものがポピュラーなものだろう。
だからこその魔女狩り。異端なるモノ共の放逐。
人はみな、魔女を恐れていた。彼らは自分たちと同じ人の姿をしているから、隣にいる人が魔女かもしれない。そんな恐怖が常につきまとっていたのだ。
「そ、そんな……魔女狩りがあったはずなのに……」
「魔女狩りか。あれは不味かったね。キミたちが魔女として狩っていたのは、大抵がただの人か淫魔だったんだから。あんなことをおこなわなければ、淫魔が国を支配しようだなんて考えなかったのに」
「い、淫魔……? さ、さっきからそれはなんだ……」
「うーん」
唸って、イザベラが男のペニスを握る手に力を込める。元気さを取り戻したそれにイザベラは舌を寄せた。亀頭を舐めあげ、舌にこびり付いた精液を呑み込む。
「今の私みたいな生き物、かな?」
淫蕩に微笑むイザベラに、男は自分の末路を悟った。
なんて、悪夢だ――。
「悪夢じゃない。淫夢さ」
男の思考に声で応え、イザベラは相手に騎乗すると肉棒を膣に埋めた。
魔女イザベラの扱う魔法の体系は多岐にわたる。それもこれも、無数の悪魔と契約を結ぶという荒技をおこなったがために会得できたものだ。
魔法と一言にいってしまうのは、世界中の食物を総て料理として括ってしまう程度には乱暴な区分であったが、魔女イザベラに対してだけは話が別である。魔法というおおざっぱな区別をしなければいけないほどに彼女の能力は膨大だった。
今、おこなわれているこれも、イザベラの特異な能力故であった。
「なんだ、キミは私みたいな幼子が好きなのかい? それは変態性癖と云わざるを得ないな」
魔女イザベラの声――しかし、幼い。
舌っ足らずな、イザベラに似た声を発したのは一二、一三歳くらいの幼子である。その女の子はピンク色のシーツがひかれたベッドの上に仁王立ちして、ベッドに寝転がる男を見下していた。
警邏隊の四人組、そのうちのひとりである。
男の股間は布越しでも膨れあがっているのが目に見えて判るほどで、幼子は不愉快そうに鼻を鳴らした。
「変態と云われて喜ぶ人種がいるのは知っているが、いつ見ても理解に苦しむな、ペドフィリアめ。さすがにそんなもの、触ってやりたくもないよ」
太腿まで届く靴下を穿いた足で、幼子が男の股間を勢いよく踏みつけた。例え幼子といえども蹴られれば痛みがあったはずだが、男が洩らした声は苦悶ではなく嬌声である。
「あ、ああ……!」
「喘ぐな、耳の毒だ。このまま踏み潰してあげようか?」
男性器を踏む足に力がこもる。ぐりぐり、と足を捻った。
土踏まずの下で余計に膨れあがっていくペニスに、銀髪の幼子は未成熟ながらも美しくなることを予想させる顔をしかめた。
「小さくなるどころか、大きくなるとはね……。こうも欲望に忠実だと逆に関心するよ。よくもそこまで興奮できるものだよ」
変声期も迎えていない幼い喉から発せられる言葉は知的にして老獪で、その差違が彼女を異質たらしめていた。
その追求に、男は上擦った声をあげながら首を振った。
「こっ、興奮なんてしてないぞっ」
慌てて取り繕われると、幼子は足の力を強めて強制的に黙らせる。
「嘘をつくならもっとマシな嘘をつきたまえよ。幼女に踏まれてペニスを勃起させながら云っても説得力なんて皆無だ。ああ、幼女趣味ならおちんちんと云った方が興奮するかな。……するようだね」
足の裏に伝わる感触がさらに硬くなり、幼子は吐き捨てる。男は羞恥で顔を真っ赤にしていた。
「こうしていても仕方のないことだし……まずは一度楽にしてあげよう。……このままね」
幼子が足の指先を器用に使って男のズボンから性器を露出させた。
ぼろんっ、と半分ほどまで皮を被ったペニスがこぼれ出てくる。足先で裏筋を撫でながら皮を引っ張ると、汚臭漂う亀頭が姿を現した。
「うぐ……っ」
「まだ皮を剥かれただけだろうに、どうしてそんなに息を荒くしているのだか。ふふ……童女の足がそんなに好きかね」
すりすりと靴下越しに足がペニスを撫でる。幼子の汗で湿った靴下が亀頭の根本から裏筋を何度も往復して、男は情けなく身を快感でよじった。
尿道から湧き出す我慢汁が幼子の靴下に染みこむ。そして精子混じりの分泌液で濡れた足はペニス全体に我慢汁を塗布した。
濡れて動きやすくなったことで、足の動きが激しくなる。技術もなにもない、精を搾るためではなく汚物を踏みにじる乱雑な足責め。だからこそ男は被虐的な心を刺激された。
額に汗しながらペニスを踏みつける幼子は、真っ白い頬を紅潮させて亀頭を踵でグリグリと捩る。
「はあっ、……ははっ! 踏まれてるだけでおちんちんビクビクさせて、今にもイってしまいそうじゃないか。ほら、出してしまいなよ。無様に悶えて精液を足にかけてしまえばいい」
ぐぎゅっ、と足がはち切れそうになっていた肉棒全体を踏みつけた。
押し潰されそうな強い刺激が我慢という名の理性を蹴破った。
「う、うわあああああ――っ!」
どくっ! どくっ! どくんっ!
ペニスが弾けた。幼い少女の足によって射精に導かれた肉棒は、脈打って濁流のような白濁を噴出する。
真っ白い精液が幼子の足にべったりと降りかかった。純白の樹液が肉感に乏しい太腿からふくらはぎまで垂れて、黒い靴下も精子でてらてらと光る。生殖活動のために精製される子種は幼子の未熟な足を精の色で汚したのだ。
足の裏から伝わってくる大きく熱い肉棒の脈動に幼子は酷薄に笑む。
「あっははっ、本当に足で出すなんて……それも、こんな小さな私に踏まれて精を漏らしてしまうだなんて。ねえ、恥ずかしくないの?」
幼子の言葉が男の胸に突き刺さり、顔は羞恥で真っ赤になる。何も云い返せないほどの恥ずかしさと屈辱に頭が沸騰していた。けれど、その感情さえもゾクゾク とした快感となって背筋を走り抜ける。今も幼子の足で踏みつけられている自分のモノを見下ろして、男は押しとどめ難い疼きを覚えていた。
「あれ、また硬くなってきたね。まさか、踏まれているペニスを見て興奮したのかい? 度し難い性癖だねっ」
一際強く幼子の足が肉棒を踏む。イったばかりなところへ叩きつけられる刺激。
「はうっ」
「小さい女の子に虐められるのが好きなんて……なら、これがお望みなんだろう?」
幼子が自分の下半身を覆っていた布をはぎ取ると、そこには毛すら生えていない秘所があった。
男の視線を釘付けにして、ゆっくりと腰をペニスへと降ろす。亀頭が小さな亀裂を押し広げ――。
ずんっ、と女性器が裂けんばかりにねじ込まれるペニス。だが、悲鳴をあげたのは男の方だった。無数の襞で陰茎をなで回す狭い狭い女陰に、男は一瞬で限界を迎えた。
幼子の躯を突き抜ける勢いで放出される精液。
男に跨った幼子は、自分の下腹部を撫でる。掌には、止まることのない射精に狂ったペニスの感触が伝わってきた。
「はは、出すといい……死ぬまで、私の性器に抱かれて……」
艶然と笑う姿は、幼い姿からは想像できぬほどに淫らだった。
無数の女体が躯に絡みつく。柔らかく、細い腕が男の上半身を抱きしめる。豹のようにしなやかな足が、男の足に纏わり付く。絶世の美女たちが、ひとりの男を全身で愛撫していた。
ピンク色のシーツ、ふかふかのベッド、そしてどこまで続くかもわからない空間――。
ここには世界中のあらゆる快楽が混在していた。
大きな肉の果実が男の背中に押しつけられ、のの字を書くように動き回る。背筋をなぞる乳房の感触に男は脳髄が溶け出して耳から溢れてしまいそうになっていた。
男の股の間には三人の女性が躯を滑り込ませて、熱心にペニスを銜えている。その三人に、それと背後にいる女性も、総て同じ顔をしていた。
それは路地裏であった女性だと男は曖昧になっていく脳で思い出したが、間断なく与え続けられる快楽にそれ以上の思考を働かせることはできない。陰茎をなぞる舌と唇の感触は、女体に溺れる以外の選択肢を奪い去っていた。
だから、どうして警邏で路地裏に立ち寄っていたはずなのに、こんな場所にいるのか――なんて疑問に答えを見つけることもできなかった。
「キミの場合はハーレム願望か――実に判りやすくて健全だね」
背中から男を抱きしめている女性、イザベラが耳元で囁いた。言葉に揺らぎはなく、一定のリズムを保っているのに、耳にかかる息だけは溶岩のように熱い。
「なにが……なにが起こってるんだ……」
熱い吐息に意識がわずかに引き戻され、男はようやく意味のある言葉を発することができた。
イザベラはからかうような声音でそれに答える。
「私はね、相手の嗜好にもっとも適した姿を知ることができるんだよ……欲望っていうのは、あまりに輝きが強すぎるから、手に取るように判るのさ」
「で、でも……なんで、こんなに、人が……」
「そうだね……」
優しく、些細な質問の問いを伝えた。
「私が魔女だから、かな?」
男のペニスに群がっていた三人のイザベラが口淫の速度を速めた。ぴちゃぴちゃと涎を垂らしながら、男の欲望を限界まで導く。
そうして、何度目かも判らなくなるくらいの射精。
イザベラたちは顔を汚す精子を気にせずに、精液を出し続ける肉棒を貪る。射精中に与えられる快感に、男は絶叫する。あまりの快感で脳内の神経がいくつも千切れ飛んだ感覚。
粘度の高い白濁液で顔を汚しながらも奉仕を続ける三人の自分自身を見下ろして、イザベラはもう言葉を理解することもできないであろう男に語りかけた。
「さあ……もっと、楽しもうか――?」
*
夜の路地裏には四つの死体が転がっていた。
全身の水分を吸い取られたミイラのような有様は、吸血鬼に血でも抜き取られたのかと思ってしまうほどに凄惨だった。
「しまったな、少し調子に乗りすぎてしまったか」
その横には、衣服ひとつ乱れていない魔女イザベラの姿がある。悩ましく胸を押し上げる形で腕を組んだ彼女はばつが悪そうな顔になったものの、すぐに頷いて気を取り直すことにした。
「一応、殺すつもりはなかったんだけど……まあ、いいよね。顔を見られていたし、四人分ギヨたんの代わりをしてあげたと思えば逆に感謝されて然るべきだろう」
自分なりの理屈で納得するとイザベラは彼らから視線を外して、未だに意識を失っているジョゼフたちの方へと向かって行く。
実際は、ジョゼフたちが気絶してからまだ五分と経っていなかった。だから、未だにという表現は相応しくない。けれど、男たちの死体は無限とも云える時間の中で朽ちたようにも見える。大事なものがイザベラの周りで噛み合っていなかった。
魔女――。
悪魔と契約し、超常の力を得た人を超えし者。
このとき、イザベラが何をおこなったのか。知る術を持つものは誰ひとりとしていなかった。
第二章/了
目覚めは暗闇の中だった。
アンナマリアが意識を取り戻したとき、外にはまだ闇の帳が降りていた。そう長くないうちに陽が空に昇るのであろうことはなんとなく躯の調子でわかるものの、それでも人が目覚めるにはまだ早い。
天井の木目を見つめて、どうしてこんなところにいるのだろうか、とアンナマリアはぼんやりと思考する。
「……あっ」
意識をなくす直前のことを思い出して、アンナマリアは躯を起こした。何故か彼女はベッドの上で寝ていたが、もちろん見覚えはない。そもそも、ベッドで寝た経験など断頭台であるアンナマリアにはないことだった。
「あの後、どうなったんだろう……?」
レリア・キッスとの戦いで疲弊のあまり、今まで眠ってしまっていたのだ。
「お目覚めかい、ギヨたん」
声をかけられて、アンナマリアは弾かれたようにその方へと振り向く。もし誰かの家に運び込まれていたとしたら面倒だと思ったのだが、そこにいたのは魔女イザベラだった。
「……ギヨたんいうな」
見覚えのある人物でアンナマリアはほっと胸をなで下ろして毒づいた。好意を抱くような人物ではなかったが、今は安心できる。
「ここが貴方の家?」
アンナマリアは部屋の中を見渡す。断頭台として過ごしてきたために人の家がどうなっているかの知識はなかったが、殺風景だと感じることはできた。
寝室だからなのか、目立つ家具は置かれていない。それにしてもベッド以外には本の山しかないのは少々異常だった。イザベラのことだから、そのようなものには頓着していないのだろう。
「そうだよ。まあ、家というよりは、寝床といった方が正しいかもしれないけど。別に愛着はないからね」
「そういうものなんだ」
「少なくとも、私の方はね」
イザベラの言葉には、自分以外の者も住んでいることをほのめかしていた。
「もしかして、あのレリア・キッスっていう子もここにいるの?」
「ああ、私の助手だからね。今はジョゼフと一緒に別の部屋で寝ているよ。ギヨたんは流石に起床が早かったね。断頭台の朝は早いということかな」
「茶化さないで。……酷い目にあったんだから」
後半の文句は羞恥心で小さくなっていた。同性に感じさせられて、最後には気絶してしまったのだ。初めての経験に頬が恥ずかしさで熱くなるのをアンナマリアは抑えることができなかった。
初心な反応にイザベラは笑みを浮かべてアンナマリアに答える。
「仕方ないじゃないか。キミがジョゼフに手を出さなければレリアも襲いかかることはなかったんだ」
「……せっかく、楽しんでたのに」
アンナマリアはベッドで足を抱えて、膝に顔を埋める。レリアによって与えられた感覚は確かに得難いものであったものの、ジョゼフとの性行を邪魔されたことはまだアンナマリアの心の中で尾を引いていた。
「本当、貴方の知り合いに関わると碌なことにならない」
「私はなにもしてないじゃないか。そんなに詰られる謂われはないよ? そもそも、私がこうやって助けていなかったら、ギヨたんたちは今頃詰め所にお持ち帰りされて乱交パーティーでも開かれていただろうさ。それに、キミはレリアに感謝した方がいいかもしれない」
「……なんで?」
むすっ、とした不機嫌さを隠そうともせずに、アンナマリアはイザベラを睨み付けた。レリアに感謝することなどまったく見あたらない。むしろ、愚痴を申したい気分だった。
「彼はジョゼフと云ってね。キミとしては因縁を感じずにはいられない名前だろう、ギヨたん」
「ジョゼフ・ギヨたんとでも云いたいの? それよりも質問に答えて」
その視線を何処吹く風で受け流し、イザベラは逆に問い返した。
「キミ、ジョゼフを見て不思議な気分にはならなかったかね」
「不思議な気分……」
そういえば、どうして自分はあんなにも熱中して行為に耽っていたのだろうか?
イザベラの云うことに心当たりはあったが、理由は思い浮かんでこない。
「ううむ。わからないか。ならストレートに答えを云うとだね。ジョゼフはキミの世話をしていた処刑人の弟だ」
「……え?」
あまりにもあっさりと告げられて、アンナマリアは目を丸くした。なにを云われたのか理解できなかったのである。
「処刑になんて興味のない私がキミを見つけたことを、そもそも不思議には思わなかったのかい? ジョゼフの兄が処刑されるからと聞いて、その日だけ足を運んだんだよ。そうでなければ、キミは今でも断頭台のままさ」
「そ、それ、どういうこと!? だって、あの人は自分に血縁はいないって……」
「そ うだね、彼は弟が死んだと思っていただろう。なにせ、ジョゼフは一度森の中で死にかけたんだ。右腕をばっさりと持って行かれてね。そこを私が通りがかって 助けてあげたのさ。ジョゼフはその後、兄には会わなかったようだから、残された血痕だけを見て死んだと判断したのだろうね」
「そんな……」
アンナマリアの体温が一気に下がり、考えたくもないことが胸の裡で膨れあがった。
もしかして、わたしは彼の家族を、殺すところだった?
処刑人を殺した総意に反逆すると決めた。ならば、国家に所属する総ての人間を自らの手で殺すとアンナマリアは決心を固めていた。
あのときの行為とて例外ではない。如何に愉しんでいたとしても、逃がす気など毛頭なかった。事実、レリアが妨害していなければ間違いなくジョゼフを殺していた。
命とは常に平等だ。生き方、人生に違いがあれど、命の重さ自体に違いはない。聖人も、奴隷も、殺せば死ぬ。よって等価値である。断頭台として産まれて、幾多の首をはねてきたアンナマリアの中に血と共に染みこんだ思想だ。
にも関わらず、処刑人の弟を後一歩で殺すところだったこと、殺してしまっていたときのことを考えると、足が竦んでしまった。
躯を硬直するアンナマリアにイザベラが声をかける。魔女はいつでも冷静にして冷徹だった。
「別に、考えなかったわけじゃないんだろう? 国をひとりで総て滅ぼすということは、自分に関わった関係者だろうが、彼らの家族だろうが、区別なく殺すことだって。それとも、殺す人間を選ぶのかい、断頭台であるキミが。命を分別なく刈り取る断頭台のキミが」
「……やめて」
「もし自分の気に入る人間だけを残して殺戮をおこなうというなら、それはなんて傲慢な行為だろう。そもそも、人殺しの処刑道具に命を測って分ける自由など元よりありはしないのに」
「やめてって云ってるの!」
ぶんっとアンナマリアは枕を投げつける。
真っ直ぐに飛んできた枕をイザベラは身を逸らして簡単に避けてしまった。
すっかり機嫌を悪くして蹲ったアンナマリアを見て、イザベラは大仰に肩を竦めた。
「別 に虐めるつもりで云ったわけではないんだけどね。ただ、キミが当初語っていた国家惨殺の理念と相容れないから、こうして忠告してみたというわけさ。中途半 端な気持ちで国民を皆殺しにするなんて、そう出来るわけがないだろう? 彼らだって生きているんだから死にものぐるいで抵抗する。それこそ、あらゆる手段 でね」
今度は黙ってイザベラの話を聞いていた。
アンナマリアの中には、今も弱まることのない国民への怒りがある。自分に処刑人を殺させた者たちの意志を許すことはできない。
見せ物として、娯楽として、殺されてしまった実直な彼。この世は弱肉強食と誰もが嘯く。そうして、国民の精神の安寧を維持するために弱者である彼は殺され た。殺される方が悪いのだ、と云ってしまえばそれまでのことだ。アンナマリアもその生まれからして、死に対して感傷を抱くわけではない。生死の哲学をおこ なうこともしない。
けれど、大切だった人が奪われたことに対する怒りはどうすればいいのだ。
仕方がないと割り切らなければいけないのか。殺された方が悪いのだと死を許容しなければいけないのだろうか。
国民がそういうならば、その総意ごと斬って捨てる。
そうして歩み出した道であったはずなのに。その過程で、彼が大切にしていたであろう人を殺さなければいけないとしたら――。
「どうすればいいの……」
アンナマリアは声の震えを隠すほどの余裕すらなかった。明確な自意識を持って活動してからの日が浅い彼女に、この問いは重すぎた。
割り切って殺してしまえばいいのか。――けれどそれはただの思考放棄だ。
割り切るということは、なにかを捨てることだ。悩みを解消するために、悩みを捨てることだ。思考を削り落とすことだ。苦悩するのは美徳ではないが、悩まないで愚直に猛進するということは、考える葦であるところの人を止めたということに他ならない。
人を殺すように、こんなものすら斬れたらいいのに。そう思っても、彼女の鎌は思慮を両断することはできなかった。
「どうすればいいか悩むというなら、なにもしないという選択肢もあるよ。ここで止めてしまえばいい。復讐劇はここでお終いだ」
「それは……」
それが、一番いいのではないか、とアンナマリアは思った。
彼のために、彼が好きだったものを壊すのは、本末転倒も良いところだ。処刑人のために復讐する、聞こえはいいが、それは自らのやり場がない怒りを放出するための手段である。自己の充足のために、大切な人の大切なものを殺す。どこまで云っても満たされるのは自分だけだ。
死んだ人に操を立てても、仕方のないことである。
でも……けれど……、そんな風に思考がぐるぐると少女の小さな頭の中で回っていた。
「もうすぐ朝だよ。ギヨたん、広間に戻っておかなければならないんじゃないかな」
イザベラに声をかけられて、窓の外が白み始めていることに気がついた。いつもならばどうでもいい人殺しの仕事が始まる夜明けなのに、今は太陽を無くしてしまいたくなるほどに恨めしい夜明けだった。
でも、いかないと、処刑は凄惨なものに取って代わるだろうことは判っていた。一枚一枚爪を剥がし、肉を抉り、生きながらに内臓を引きずりだし、あらゆる苦痛を罪人――あるいは罪人のレッテルを貼られた人が受けるのだ。使命感などなかったが、それでも許したくはなかった。
アンナマリアは無言でベッドから抜け出すと、イザベラの横を通り抜けて扉のノブに手をかける。
「広間の方へ行きたいなら、ここから北に真っ直ぐと進むと良い」
答えるのも億劫で、アンナマリアは小さく頷くと扉を開けた。
「……あっ」
少年が驚いて声をあげて、アンナマリアもびっくりして立ち止まった。
扉を開けた先には、あの金髪の少年――ジョゼフがいたのである。
改めて、アンナマリアは目の前の少年の顔をまじまじと見つめた。金髪碧眼、それは処刑人と同じで、云われて見れば彼の面影がジョゼフにはある。高い鼻に、彫りの深い精悍は顔立ち。どれもが処刑人を彷彿とさせた。
ただ、処刑人はお世辞にも明るいとは云えない寡黙な男だったのに対し、ジョゼフは溢れんばかりの快活さを持った少年だった。そのせいで、このふたりに血の繋がりがあると想像できなかったのである。見た目は似ているが、中身は正反対だ。
アンナマリアにじっと見つめられて、ジョゼフは顔を赤くする。少ししか見ていないつもりでも、それなりに長い間眺めていたらしい。
「えーと、さっきはどうも」
恥ずかしそうにもじもじとしているジョゼフがアンナマリアには不思議だったが、自分が彼と何度も性行していたことを思い出して納得した。そういえば、自分 と寝た男と話すのはこれが初めての経験だった。そう考えるとアンナマリアも急に居心地が悪くなる。しかも相手が処刑人と同じ顔をしているものだから、その 恥ずかしさも大きい。
表情には出すまいと気を払っていたからだろうか。アンナマリアはおかしなことを口にしてしまう。
「気持ちよかった?」
「え!?」
「なんでもない。忘れて……お願いだから」
本当に、なにを訊ねてしまったのだか。意味を自覚してアンナマリアは顔から火を噴きそうになってしまった。無表情を必死に守っていても、顔だけ真っ赤になっていればやせ我慢だとは誰の目にも明かである。
「あはは、ジョゼフは童貞だからそういうこと云ってもまともなことは返ってこないと思うよ」
「ちょっと! どうしてそんなこと知ってるんですか、魔女先生!」
「それは私が魔女だからさ」
「説得力凄いですよね、それ」
イザベラに云われて恥ずかしさに顔を手で覆ったジョゼフだったが、咳払いをして膝を曲げるとアンナマリアに目線を合わせた。
「えっと、アンナマリアちゃん、だよね。魔女先生に聞いたんだけど兄さんの大事な子なんだよね」
「それは……」
「ジョゼフはギヨたんよりほんの少し早く目が覚めたんでね。ちょっとだけなら話してあげたんだよ。大丈夫、肝心なことは云ってないから」
つまり、アンナマリアが断頭台であるということは話していないのだろう。もっとも、話したところで信じるかどうかは別のことだったが。
「肝心のこと?」
「女の子には男の子に秘密があるのさ。それで、なにか用があったんじゃないの?」
「あ、そうでした」ジョゼフは改めてアンナマリアに向き直る。「えっとね、兄さんはあんなことになっちゃったけど……きみまで自棄にはならないでね」
「自棄?」
「いや……ほら、さっきみたいなこと」
「別に、自棄でやってるわけじゃない」
自分が悩んでいた事柄にずけずけと入り込まれて、アンナマリアは眉間に眉を寄せる。気分を害したのがジョゼフにも伝わったのか、青年は困った顔になった。それでも、ぶれるような気配はない。
「わたしは、わたしの好きでやってるの。他人にとやかく云われる筋合いはないんだから」
「なんであんなことやってるかなんて、そりゃ聞かないけど……。兄さんなら絶対に止めるはずだよ」
ジョゼフの口から処刑人のことがでてくると、どうしてかアンナマリアは平静でいられなかった。自分は産まれてからずっと彼のことを見てきたのに、いきなり出てきたジョゼフが知った風な口を聞くのが、許せない。
脳裏に浮かんでくるのは、いつも寂しげな顔でアンナマリアの刃を拭う処刑人の姿。ついぞ最後までアンナマリアはそれ以外の表情を見ることは叶わなかった。
いつだって、自分はひとりだと呟いていた。本当は、弟が生きているのに。彼がずっとそう思い込んでいたのは、どうしてだか知らないが、ジョゼフが自身の生存を隠していたからだ。明かしていたら、少なくとも死の間際まで嘆きすらしないなんてことはなかった。
「うるさいっ、その兄に自分のことを隠してたくせに!」
「それは……」
予想外の追求にジョゼフは瞠目する。口を何度か開くが、それは水面に浮かんだ魚のように動くだけだ。
肩を怒らせてアンナマリアが玄関の方へ向き、ジョゼフに背を向ける。
「あ、待って! 危ないから送っていくよ!」
「あんなによがってたくせに指図なんてしないでよ!」
「ちょっとぉ!?」
顔を赤くして慌てふためくジョゼフには目もくれずアンナマリアは廊下を早足に歩き出す。
咄嗟にジョゼフは彼女の肩に手を伸ばすが――空を掴むだけだった。
避けられたのではない。途中で、伸ばす手がとまってしまった。ジョゼフの耳の奥には、アンナマリアの台詞がずっとこびり付いていて、彼女を捕まえることをためらわせた。
玄関が乱暴に開かれる音でジョゼフは放心状態から復帰する。もう彼女は家にはいなかった。
未だに腕を伸ばしたままだったことに気付いて、ジョゼフは苦笑しながら腕を降ろす。それは一度森の奥で切り落とされた右腕だった。
「嫌われちゃったな」
自嘲気味にジョゼフは洩らす。普段のまぶしいくらいに浮かべている笑顔はそこにはない。もしアンナマリアがまだここにいたのなら、その顔は処刑人にそっくりだと思っただろう。
一部始終を見ていた魔女が部屋から出てきて、廊下の壁に寄りかかる。
「あれは嫉妬だよ、嫉妬。そんなに気に病む必要はないと思うよ」
「嫉妬、ですか?」
嫉妬される心当たりがなく、ジョゼフは首を捻る。リスみたいな動作にイザベラは微笑した。
「あ あ、嫉妬だよ。彼女がこの世で一番長い時間一緒にいたのは、キミのお兄さんだ。それはね、つまり彼が世界の中心だったというわけだよ。どんなものでも、自 分の一番大切なものを中心としてグルグルと世界を回すのさ。だから、自分よりも処刑人と絆の深い者がいることを許せなかった」
「そんな、嫉妬されるようなことなんてぼくにはないんだけどな。兄さんとの繋がりは、血縁であるってことくらいですよ」
「それが彼女にとっては誰よりも重いのさ。彼女は誰とも血が繋がっていない」
「孤児ってことですか?」
「そんなところだよ」
断頭台だから、とはイザベラも云わなかった。
それでも、どれだけアンナマリアが血の繋がりを重く見ているかはジョゼフにも伝わっただろう。自分と血を分けた存在がいない、その重圧に。
血縁が誰ひとりといないとしても、所詮は他人と呼ぶ者もいる。確かに、人がこの世に生まれ落ちた時点で主観は自分ひとりのものであるし、母との縁もへその 緒を切れば目に見えなくなる。親と子、兄妹の繋がりなんて、結局は自己防衛のために必要とされる最小のコミュニティでしかない。
人間にとってはそうでも、アンナマリアにとっては違った。便宜上、自分を作った者を親とするなら、いる。だが、血は繋がっていない。
人は遺伝子を連綿と受け継ぎ、継続性を持っているものの、アンナマリアは違う。突如としてこの国に生まれた、誰との繋がりも持たない正真正銘の新しい子供。
彼女は産まれたときから庇護してくれる者すらおらず、復讐に身を焦がすだけの、孤独な人だった。
そんな彼女にとっては、血縁という繋がりは誰とも得ることができない。空に手を伸ばしても太陽を掴めないように願ってやまない渇望だったのだ。
ひとりだと悲しそうに云っていた彼にも、弟がいた。それが、彼女には複雑だったのである。処刑人が世界の総てだったのに、血の繋がりという自分では絶対に得られない絆で彼と結ばれている者がいることは。
「あの子にとって、血縁っていうのは本当に特別なんだ。なのに、自分が生きていることを黙っていた。それも許せないんじゃないかな」
「まさか。ぼくはいない方が兄さんも楽だったと思いますよ」
ジョゼフは笑みを浮かべながら首を振って否定した。
「そういえば、あの子はどこに住んでるんですか? 兄さんの代わり……なんておこがましくて云えませんけど、そんな話を聞いたら尚更心配ですよ」
「広間の辺りにいると思うけど、見つからないと思うよ。夜になればまた会えるんじゃないかな」
「そんなに街角に立ってるんですか。珍しい話じゃないですけどね」
そういうわけではなかったが、イザベラもわざわざ訂正して余計ややこしくする気はなかった。夜になればアンナマリアが必ず街を徘徊しているのだから、嘘は云っていない。
「じゃあ、ぼくはそろそろお暇させてもらいます。店長たちも心配してると思いますし、営業準備を手伝わないといけないんで。あっ、レリアちゃんにもよろしく云っておいてください!」
「ああ、気をつけたまえよ。なんだか嫌な気配がするんでね」
「あはは、魔女先生らしい忠告ですね。肝に銘じておきますよ!」
そういって、ジョゼフは騒がしく廊下を駆けていく。その背中を見送って、イザベラは溜息を吐いた。
「さて、今日は助手の機嫌が悪そうだ」
ずっと部屋の扉に寄りかかって廊下の話を聞いていたレリアは特徴的な頭髪を弄りながら、呟いた。
「最後の最後で思い出したように云うんだから」
こつん、と踵で壁を蹴った。
「ジョゼフくんの、ばか」
*
時刻は数刻ほど遡る。まだ深い夜がこの国を覆っていたときの王城、その一角で密やかに狂乱の幕が開かれようとしていた。
入浴行為は、躯に水を浸透させ脆弱にする行為とされた。
少なくとも、この国では風呂に入ることで躯を清潔にするという発想はなかった。それは自らを貶めてしまう悪しきおこないであるとされてきたのである。
それでも、湯で躯を洗うことは何よりも清潔さを保てるものだ。よって、一部のものだけは密かなる楽しみとして入浴していた。
王族、貴族たちである。
湯を沸かし、湯船に溜めるなど、入浴には手間がかかった。それを問題とせずに躯を流せる者は、そのような権力者たちだけの特権であった。
つまり、入浴とは庶民にとって禁忌であり――権力の象徴だったのだ。
ここに、革命後現在の指導権を握った派閥の幹部がいる。彼は今や誰もが認めるこの国の権力者である。市民からここまで成り上がった者が入浴行為に嫌悪と同時に羨望を持っていたのは、まったくおかしなことではなかった。
男は脱衣所で服を脱ぐと、城にあった浴場へと入る。湯船は優に数十人もの人が同時に浸かれそうなほど大きく、当然市民であった頃には親しみはまったくないものだ。
男の分厚い胸板はこの上ない優越感で膨らむ。何故なら、今この瞬間、大浴場はふたりだけのものなのである。
大浴場には、既にひとりの女がいた。
髪の長い女である。椅子に座っていると、世にも珍しい蒼い髪は浴場の床に毛布のように広がっている。男はこの王宮に来てからも、彼女の髪よりも美しい毛皮は見たことがなかった。
一糸まとわぬ姿の女性は振り返り、艶めかしく瑞々しい肌を惜しげもなく男の前に晒す。ピンと上を向く、果実のような胸はいつ見ても男の情欲を掻き立てた。 母性もあり、それに勝る淫靡さがあった。アダムとイブが手にした果実は、きっと彼女の乳房のように手にしなくてはたまらないものであったのだろう。
「お待ちしておりましたわ。さあ、お背中を清めさせていただきます」
「アワリティア」
男は女の名を呼ぶ。その目は夢見るように虚ろだった。
「いつもと同じように頼むよ」
「いつもと同じ、ですね。受けたまわりましたわ」
蒼い髪のアワリティアは物静かな顔立ちに、蕩けてしまいそうになるくらいに蠱惑的な笑みを浮かべた。
湯で濡らした躯に石鹸を塗り込み、アワリティアは自らの乳房を擦り合わせて泡を立てる。悩ましげな声を洩らしながら躯を泡立てると、乳房を男の大きな背中に押しつけた。
躯を上下させ、泡で真っ白になっている胸で背中を擦る。
「おお……」
泡で滑る胸が背中をなぞっていく感覚に男は満足気な溜息を吐いた。筋肉で角張った背中に柔らかな胸肉が入り込んで洗い流していく。時折皮膚を引っ掻いていく乳首の硬さが心地よかった。
「はあっ、どうですか、旦那様。痒い所はございませんか?」
相手の耳を吐息で撫でながら、アワリティアが訊ねる。その間も胸での背中への奉仕は止むことがなく、彼女の乳房は背中を往復していた。
「ああ……前の方が痒いな」
「前……あらあら」
おっとりとした笑み。それでいて含みのあるいやらしい微笑み方。
アワリティアは男の背中に抱きついたまま、その両手を相手の股ぐらへと伸ばした。石鹸の泡で滑って入り込んだ手はそそり立つ陰茎に指を絡ませる。
「こんなにしてらして、掻痒をお感じになられるわけですわ。今、綺麗にして差し上げますね……」
云うと、アワリティアは自分の蒼い長髪を引き寄せて男の一物に絡みつかせる。泡だらけになっている蒼い髪に包み込まれて、それは女の手の中で強く跳ねた。
「こちらも今、綺麗にして差し上げますね」
胸の動きを緩くして、アワリティアは髪越しに男性器を擦り始めた。
これほどの長髪でありながら傷みの見えない毛並みが亀頭を刺激する。アワリティアの手の動きで髪はさらさらと流れ、高級な絹にペニスをなすりつけているような快感と倒錯感を与えられる。
雁首に幾房の髪が絡みつき、彼女の繊細な手ですりすりと亀頭へと滑っていく。その視覚的にも触覚的にも経験のないものに、男は暑い浴場の中でありながら身を震わせた。
「どうかいたしました? 私はただ洗っているだけですのに」
からかう声に男は胸の裡をぞくぞくと這い回る蛇の存在を感じた。耳朶を舐める言葉は脳がマヒしてしまいそうになるほどに甘い。
ある時代、民衆用の風呂屋には入浴以外の用途がもうひとつだけあった。それは、売春である。風呂場とは躯を洗い流すためと、そして女性が春を売る場所なのだ。
男のペニスに髪の毛を巻き付けて、その上から握り締めてくるふたつの手。左手は竿を髪と一緒にしごき――洗い上げ、右手は髪と一緒に亀頭へと添えられてグ リグリと動いている。さらに、背中に押しつけられる泡まみれの乳房も動きを止めてはいなかった。三つの刺激が別々に男を苛んで、意味のない言葉が口から漏 れ出す。たるんだ顔には権力者としての面影は微塵もなかった。
髪の毛がアワリティアの手によってペニスを擦るたびに泡が立ち、もう男の下半身は泡まみれになっている。石鹸が手と髪の動きを円滑にして、粘膜を刺激する無数の髪は膣のようだった。
ぎゅっと左手が陰茎を握り締めて、上下に洗う。適度な締め付けと亀頭を覆う長髪は、男を心地よく高めていた。
躯の神経が鋭敏になっていき、乳房が動き回るだけで背中も性感帯であるかのような快感を訴え出す。無意識に男は股を開いて腰を突き出した。アワリティアの両手と長髪が絡みつくペニスを雄々しく天に掲げて、夢の世界に落ちていこうとしていた。
「ああ――」
女性の膣に挿入したものとは異質な快楽。我慢の限界に達して苦悶の表情で精を吐き出すのと、この心地よさはまったく違っていた。
まるで、全身をマッサージされて疲れをこそぎ落とされていくときの心地だ。
石鹸とアワリティアの混ざり合った香りが肺一杯になって、麻薬みたいに頭蓋骨の中身を溶かしていく。
躯が軽くなって浮いてしまいそうになる浮遊感。
静かに、やさしく。子守歌を聴かされて眠りに落ちそうになる、そんな安らかさが男を押し上げている。
「さあ、気持ちよくなってくださいな、旦那様。だって、お風呂は気持ちの良いものなんですから――」
アワリティアが手の動きを徐々に早めていく。髪の感触と、掌の緩やかな力加減。
髪の房を縫ってモグラのように何度も亀頭を出し入れさせながら与えられる快感に、男は絶頂を迎えた。
「あああ――――」
髪の中でペニスが射精した。
文字通り、天にも昇る安らかな心地。どこまでも飛んでいってしまいそうになる感覚のままに精を放った。
どくどくどくと髪の中でペニスは精液を吐き出して、蒼い髪の中で行き場のなくなった精子が陰茎に纏わりつく。
そして髪の間から何度も白濁とした液体が溢れだした。アワリティアの幻想的な蒼い髪は情欲の液体で白く穢され、指先は泥のような精液でべとべとである。
アワリティアは手足を投げ出している男の肩口から顔を出して、その陶然としている顔を覗き見た。
「旦那様、今はお風呂の時間なのですから……汚してしまっては駄目ではありませんか。私の髪の毛と手も、石鹸より真っ白くされてしまいましたわ」
精液が付着して固まった房を指で梳いて、掌に精液をこそぎ落とすと、アワリティアはそれを自分の口へと運んだ。手に唇が吸い付いて、物静かな顔立ちからは想像できない舌遣いで精子を舐めとると、嚥下する。
「さすが旦那様……こんなに濃くて喉に引っかかる精子は飲んだことがありませんわ。でも、前の方は念入りにお掃除してあげないといけませんね」
アワリティアが男の前へと回り込むと、その胸板に乳房を押しつけながら抱きつく。
その体勢で躯を上下に動かすと、乳房が胸板の上でパン生地のように形を変えた。
うっ、と男が呻く。アワリティアが動く度に彼女のお腹がペニスに擦れていた。引き締まった腹筋の上についた柔らかい脂肪が、勃起したままだったペニスの裏筋を圧迫する。
「どうかしましたか、旦那様」
訊ねながらも笑みを浮かべた彼女の動きは止まらない。
その間にも、アワリティアのおへそに亀頭が引っかかって男は声を洩らす。お腹のくぼみに性器でキスをするのは、男の性欲を掻き立てるには充分すぎた。
硬さを増したペニスの感触にアワリティアは目を丸くすると、男に悪戯小僧を見るような視線を向けた。
「もう、躯を洗っているだけですのに……このままではもっと汚されてしまいそうですわ。そうですね、こちらもたっぷり泡一杯のおっぱいで洗って差し上げますね」
アワリティアは男の股の間にぺたんっと座ると、泡だらけのペニスを乳房に押しつけた。
器用に乳房の間で肉棒を挟み込むと、アワリティアは両手で胸を動かす。
石鹸の泡を羽毛みたいに纏わり付かせた胸がペニスを撫で上げた。陰茎にこびり付いていた精液がふたつの胸に洗い流されていく。
精液と泡は混じりあっていき、ペニスは確かに綺麗にされていた。
けれど、胸での奉仕はまたもや男を絶頂に導く。
ただでさえむしゃぶりついて滅茶苦茶にしてしまいたいほどに魅力的な乳房であるのに、それで男自身を挟み込まれてしまっては肉体的にも精神的にも我慢できるわけがなかった。
アワリティアは搾精の動きではない。本当に胸でペニスを洗うつもりで泡を刷り込んでいた。それが包容力となって男の心を急速に満たしていく。アワリティアに胸でペニスを包まれている感覚は、疲労してベッドに潜り込んだときの充足感と同じだった。
乳房に挟まれて窮屈そうなペニスは、しかしタイトな快感に脈打つ。
「私の胸の中で震えていらっしゃるのがわかりますわ……さあ、ご遠慮なさらず吐き出してしまってくださいな。今度は汚れてしまわぬよう、私の口で受け止めさせていただきます」
乳房でペニスを扱く淫らな姿とはかけ離れた聖母のような笑みをアワリティアは男に向けた。慈愛に満ちた瞳を向けられた男は全身を愛撫されている多幸感に支配される。この女性からの穏やかな手管に逆らえる男などいようはずがなかった。
「ああっ、わかった……飲め、飲み干してくれっ」
男が腰を振って乳房から肉棒を突き出すと、アワリティアの口が亀頭を一口で呑み込む。その生暖かい口腔の感触で男は絶頂を迎えた。
ただの射精ではない。全身が弛緩して魂が口から抜け出てしまいそうになる、リラックスの果てにある空を飛ぶような快感――。
陰嚢が収縮し、一気に男は精液をアワリティアの口内へと放った。
「んふっ」
喉の奥に精液がぶつかってアワリティアが恍惚とした表情のままに唸る。口の中から溢れそうになるほどの精液が砂漠で乾涸らびていた所に見つけたオアシスの水とでもいうように、喉を鳴らして呑み込む。
ごくっ、ごくっ、ごくん……。
長い射精が終わって、男は脱力して椅子から転げ落ちそうになる。
そしてアワリティアがペニスから口を離すと、そこに精液は見あたらず、糸を引く彼女の唾液しか付着していなかった。
唇の端に白い糸を垂らしながら、アワリティアは男にまぶしい笑顔を向けた。
「綺麗になりましたよ、旦那様。さあ……あとは私にお情けをくださいませ」
男はふらふらと頭を左右に揺らしながら、辛うじて彼女の言葉に頷いた。
大浴場の広大な浴場に浸かると、その中でアワリティアは股を開く。彼女の性器は揺れるお湯で波打って見えた。
ゆらゆらと波を作るお湯越しであったとしても、その陰部の美しさに男は生唾を呑み込んでしまう。
何度見ても、目の前の秘所は昔を思い出させた。初めて女を抱いたとき、女性器を直視できなかった記憶である。じっと見つめ続けることで恥ずかしさを覚えて しまうほど、男はアワリティアの女性の部分に釘づけだった。彼だけではない。世にいる男性ならば、等しくこの蒼い陰毛が薄く生えた丘を目の前して平静では いられないのだ。
彼女の男を喜ばせるためだけに削り出された女体の、彫刻に似た優美さが合わさって、その陰部は完成していた。
「さあ、焦らさず……早く、お願いします」
男は答えることも忘れて湯船に入ると彼女の腰を掴み、ペニスを秘部へとあてがう。お湯の中で入り口に亀頭ねじ込まれ、アワリティアが背筋を伸ばして艶のある声を洩らした。
「はあっ、そうです……そのまま、来てください」
云われるまでもなく。男は腰に力を込める。お湯の中だからか、それともアワリティアが濡れていたのか。ペニスは一息に膣を貫いた。
アワリティアの中に挿入して、男は堪らず声を上げる。肉棒に絡みついてくる膣は名器と呼ぶのすら躊躇ってしまうほど、貪欲に精を求めて蠢く搾精機関だった。
自分は膣ではなく、別の生き物に挿入してしまったのではないかと不安になるくらい、アワリティアの中は自在に蠕動していた。ペニスを擦り上げ、捻り、圧迫し、玉袋に溜まった精液を捻りだそうとする肉食動物のごとき活動。
自分と膣の境がわからなくなるほどにぴっちりと張り付いてくる膣に二度も射精して性感を高められていた男が耐えられるわけもなかった。
「男の人なんですから、かっこいいところ見せてくださいね?」
奥歯を噛んで耐えていなければすぐにでも射精してしまいそうな中、アワリティアは悪魔のように男へ囁いた。そうされてしまえば、男は反射的に腰を動かしてしまった。
「うぐ……っ」
歯を食いしばって腰を引き――叩きつける。
肉と肉がぶつかり合う音の代わりに、湯船がばしゃりと盛大に弾けた。
そのまま何度も男はピストン運動を繰り返す。その度にお湯は弾け跳び、獣のような激しさで肉欲に耽る男はアワリティアの肢体を貪った。
「そう、そうよ……そのまま私に精を吐き出してしまうのです……」
だが、貪っているのは男ではなくアワリティアの方だった。彼女の酷薄な笑みに男は気付く余裕すらなく、腰を動かすこととペニスにじゅくじゅくと吸い付く膣の感触に心囚われていた。
「あ、ああああ゛あ゛あ゛――ッ!」
男が絶叫する。アワリティアに一際強く腰を叩きつけ――
ドクン、ドクン、ドクン――。
ありったけの精子をアワリティアの奥に流し込んだ。
「ああ、出ていますよ、旦那様……あなたの子種が私の中を満たしています。本当……素敵……」
人の躯では受け止めきれるとは思えない量の射精。それでもアワリティアはお湯の中でがっちりとペニスを銜え込んで一滴たりとも逃さなかった。
「旦那様、さあ、もっと私に――あら」
アワリティアが目を丸くする。男が自分に倒れかかってきたのだ。
あやうくお湯の中に沈みそうになりながらも男を引き剥がすと、アワリティアは柳眉を寄せた。
「死んで……ますね。困りました、この人にはもっと働いて貰わなくてはいけなかったのですけど――構いませんか。代わりはいくらでもいるのですからね……ふふっ」
絶頂のうちに死亡した男の亡骸を抱いたまま、アワリティアは穏和な顔に底知れぬ笑みを浮かべたのだった。
男たちに死体を処理させたあと、アワリティアは街を歩いていた。
露出の少ない清楚な衣装である。服に過剰な装飾は一切施されておらず、質素な印象を抱かせた。
黒色に近い紺色と純白のみで構成された服装は、アワリティアをシスターのように見せていた。シスター服と違うことがあるといえば、太腿が見えるほどに深く 刻まれたスカートのスリットだろうか。それでも、顔と手以外は露出していないために下品ではない。そのスリットから垣間見える太腿は雨雲から顔を出した太 陽のようだった。
アワリティアが歩いていた場所は街の外れだ。最近、夜に人が死ぬという噂話が氾濫しているせいか誰ともすれ違うことはない。しかし彼女はその噂にはまったく意を介してはいなかった。
平然と街を歩くアワリティアはひとつの施設の前で足を止めた。
シスターのように控えめな服装の彼女とは対照的に、目の前の建物は過剰な装飾が施されていた。優雅さはなく、目が痛くなる派手さは資金がかかっていない見た目だけのものであることを如実に示している。
そこは娼館だった。
とてもではないが、女の訪れるような場所ではない。かといってアワリティアが娼婦かと云えば、彼女の淫蕩な行為を目の当たりにした者でなければそんな発想はでてこないだろう。
その立ち姿には静かな気品が漂っていた。自分を誇り、胸を張ることができて、なおかつそれに伴う生活を過ごしてきた者だけが放つ気品である。前者だけでも、後者だけでも、この手の香るほどに漂う上品さは演出できない。
娼館の扉を両手で押し開くと、アワリティアは誰もいない玄関を進んだ。階段を使って二階に昇ると廊下の奥にある扉の前で足を止めた。
大きな扉である。アワリティアふたり分、いや三人分ほどの大きさがある。この娼館では一番の大部屋だ。
それをノックもせずに開いた。
途端、熱気が肌に纏わり付く。香ってくるのは芳醇で濃厚な蜜の芳香だ。
最後に、狂ったみたいに発せられる女の嬌声。
「あはっ! 良いよ、ボクの奥におちんちん一杯感じてるのっ! もっと突いて、もっと出して……ほら! がんばって……」
七人はいただろうか。その男達はベッドの上で腰を振るひとりの女に群がっていた。
ベッドに寝転がった男に騎乗位で腰を振る女のアナルには別の男のペニスが突き入れられ、両手には別々の勃起した肉棒がある。さらに彼女の目の前には三つの剛直が並んでいた。
髪の短い、ボーイッシュな少女である。
乳房はアワリティアよりも控えめだが、そこには大量の渇いた精液がこびり付いていて、男性を虜にする機能では劣っていないことを示していた。
鍛えられて引き締まったお尻は男の大きなペニスを根本まで銜え込み、括約筋でぎゅうぎゅうと締め付けている。
ボーイッシュといっても、少女としての魅力はまったく損なわれていなかった。
「ルクスリア」
狂乱中の少女にアワリティアは冷たい声をかけた。
「〝もう死んでます〟」
「ふぇ?」
夢中になって腰を振っていたルクスリアと呼ばれたボーイッシュな少女は我に返り、自分がのしかかっている男を見下ろした。
その男は白目を剥き、口を半開きにしてだらしなく舌を垂らし、絶命していた。
息をしていない男はひとりだけではない。この場にいる全員が既にこの世の者ではなかった。
自分の下にいる男の肩を何度か揺すって、ルクスリアは意気消沈する。
「そんなぁー! せっかくこれから楽しくなりそうだったのにぃ……。おちんちんはこんなにカチカチなのにっ」
「それは貴女の躯のせいですよ。死んでいる人間のものですら立たせたままにしてしまうなんて、いったいどれだけ淫乱なんですか」
「アワリティアには云われたくないよー」
七つの死体に囲まれたまま、ルクスリアはくすくすと微笑んだ。少女の様子にアワリティアは渋い顔をしていたが、すぐに苦笑にかわった。
「まったく……もう慣れましたけどね。ちゃんと仕事をしてくれれば私は構いませんよ。ところで貴女が殺した彼らは、権力者ではないでしょうね」
「あ、それは大丈夫だよ。ただの下っ端騎士さんたちだから」
「……ならいいですが、それはそれで今度はスペルビアが怒りそうですね」
そうやってぼやいたものの、アワリティアはすぐにそれはいいか、と思考を切り替えた。やはり、物言わぬ男たちには興味を示さない。
「それよりも、最近、私たち以外でこの街の夜を惑わしている者がいるようです」
「ああ、知ってる知ってる。結局、どうするつもりなの?」
「決まっているでしょう。始末します」
まるで世間話でもするようにアワリティアはよどみなく断言した。
「私たち以外、夜の王は不要ですから。もっとも、こちらの軍門にくだるというなら考えなくもありませんが……それでも事の重大さを理解させるためにも、見せしめは必要です」
「もー、まどろっこしいなあ。早く云ってよ、ボクは他の男と遊んできたいんだから」
「さすが、色欲のルクスリア。性欲は他の淫魔の比ではありませんね」
「強欲のアワリティアがそれを云うかな?」
「いいではないですか。まあ、貴女が飽きてしまわないよう簡潔に云ってしまえば。今日の明朝、対象との関与が疑わしい男を逮捕し、処刑します。ちょうど広場に断頭台がありますからね」
「見せしめってこと? アワリティアって、やってることはホントえげつないよねー」
ルクスリアの言葉に応えるのは酷薄な、寒気すらする笑み。
「ええ、私は――強欲ですから」
この国の人間は知らない。
淫魔と呼ばれる種族に、自分たちが影ながら支配されているという現実を――。
*
ジョゼフが自分の働いているパン屋へとたどりついたときには、既に空からまばゆい日差しが降りかかっている時間だった。
「仕込みの時間に間に合わなかったなあ……どうせ手伝えないんだけど」
怒られないといいな、と淡い期待を抱きながら、ジョゼフはパン屋の入り口に到着する。店名の書かれた木彫りの看板が目印の、この辺りでは珍しい小綺麗な店だ。
表のドアから入ろうとして、ジョゼフはまだ開店時間ではないのでこちらは開いているわけがないことを思い出す。だが、ノブを回してみると鍵は開いていた。
不思議に思って中を覗くと、既に何人かの男性客がパン屋には入っていた。けれど、まだパンは店頭に並べられていない。
ジョゼフに背中を向けていた男たちが、物音で振り返る。
屈強な男たちだった。全員、ただの肉体労働者ではない。人を害するために戦闘訓練を受けた者特有のしっかりとした立ち方だ、とジョゼフは一目で見抜いた。
わけもわからず、キモが冷える。
男たちの肩口から、真っ青になった店主の男の顔が現れた。
「ジョ、ジョゼフ! 逃げろ!」
「え?」
男のひとりが店主の顔を殴った。カウンターの小物を引き倒しながら店主が床に倒れる。
それでジョゼフは逃げるのを躊躇した。このまま逃げたら店主はどうなるのか、それよりも店主は大丈夫なのか案じてしまったのである。
逡巡の時間は数秒。事態を確定させるには充分すぎた。
男がジョゼフの腕を掴み、背中に回して拘束する。その手際は乱暴であったがあっという間で、最早抵抗の余地はなかった。
別の男が眼前にやってくる。ジョゼフの体格は中々のものであったが、その男は更に大きかった。
「貴様を反逆罪、及び犯罪幇助の疑いで逮捕――処刑する」
感情を写さない人形のような双眸が、呆然とするジョゼフを射貫いた。
「そんな、いったいなんで――」
とっさに意義を申し立てようと口を開き、鳩尾に拳を叩き込まれてねじ伏せられた。
息が止まり、床に涎が吐き出される。急速に視野が狭窄していく。
呼吸すらできない激痛の中、ジョゼフは男を見上げた。
その顔を見て、
――まるで、誰かに操られてるみたいだ。
そんな不気味な感想を抱いて、意識を失った。
もう今日だけで三回目だ、などというとりとめのないことも思い浮かべながら。
革命が起こったとはいえ、既存の軍事力がなくなるわけではない。
王に仕えていた軍隊は、そのまま革命者たちの配下となる。そうしなければ国も兵士たちも、破綻してしまう。
もっとも、王を欠いた軍の士気が高いのかといえば、無論その限りではない。
士気のない軍隊の敗北は必至である。
逆に云えば、その戦う動機に火をつけてやれば良いだけのこと。
兵士、男たちに火をつける有用な手段は、古来からたったひとつに決まっていた。
「だ、団長……っ」
まだ垢抜けない少年が切なげな声をあげた。
そばかすが頬に残る少年は軍服をはだけさせられていた。棒立ちになってしまっている少年の下半身を覆う布は剥かれていて、少年の屹立した男性器を隠す物はなにひとつとしてない。
あるとすれば、それは女性の手だった。
床に両膝をついて、少年の股間に顔を寄せている女性がいる。きらきらと黄金のように輝く金髪を紐で馬の尻尾のように纏めた女性だ。ポニーテールの女性の顔 つきは凜としていて、目は意志の強さを感じさせる鋭さがあった。冷徹そうであり、並の人の比ではない力強さが滲みでている。
女性の肢体はしなやかな豹のようであった。躯は引き締まっていて、武術の心得がある者なら相当鍛えていると一目でわかる。しかし、筋肉によってなめらかな躯のラインが損なわれてしまっているかと問われれば、否である。むしろ、その逆だった。
女性は自身がまとっている革製の防具に手をかけると、留め具を外す。音を立てて防具を降ろすと、胸が姿を現した。まだ服で全貌を明らかにしていないもの の、ずっと解かれることのなかった防具がなくなったことで禁断の聖域を目の当たりにしてしまったかのような錯覚を人に抱かせる。
胸にいやらしさなど皆無。なのに、目が自然と谷間に吸い寄せられてしまう。薄手の服の胸元から見える汗ばんだ胸元に、少年は息を飲んだ。
さらに女性は衣服を脱いで、上半身を無造作にさらけ出す。裸になって、躯の線はよりはっきりと見えた。女豹――その印象に狂いはなかった。
鍛えられた筋肉がしっかりと躯を引き締めていて、そこにスタミナを維持するための脂肪がうっすらとついている。腹筋、へそのラインのなめらかさは健康的すぎて逆に妖しさを漂わせていた。
女性の手が少年の男性自身に触れると、か細い声があがった。切れ長な女性の目が少年を見上げる。
「どうした、そう力むな。力を抜け」
「で、ですが……」
「云う通りにしろ。これも訓練と同じだ。それとも、嫌でも力が入らないようにしてやろうか」
云うなり、女性は少年のペニスを一口で呑み込んでしまった。
「ああっ!」
女性の口技は、彼女の顔立ちに反して淫らだった。
ぐちゅっ、ぐちゅっと音を鳴らしながら首を上下に動かし、肉棒を舐めしごく。根本から亀頭まで下がり、亀頭から一気に根本まで呑み込んだ。唾液で濡れた頬肉と舌がねっとりと陰茎にからみつく。
「んっ、ちゅっ……どうした、まだ一〇秒も経っていないぞ?」
ペニスを口から抜き、笛でも吹くように竿に唇を這わせて、女性が笑う。それに答えるだけの余力のない少年は、ただこみ上げてくる快感を堪えるのに必死だった。
早くに限界を迎えるのは恥ずかしいという感情が少年にはあったが、墓穴を掘るとわかっていても、少年は自分の性器に舌を這わせる女性から目を離すことができない。
「スペルビア団長……っ」
少年は荒く息をはきながら、女性の名を口にする。
スペルビアという女性は国の騎士を統括する団長だった。軍隊にいる少年とは所属が違ったが、その卓越した技量から軍の人間はよく稽古をつけてもらっていた。女だてらに騎士の頂点に立った技術と力に敵う男はこの国にはひとりとしていなかった。
くわえて、その美貌である。清廉な厳格さをまとった容姿は見ているだけで気が引き締まるくらいで、誰もが憧れたものだ。幾人もの男を虜にしたが、ずっと高 嶺の花で有り続けたのは彼女の力故である。男に自信を喪失させるほど、スペルビアは強かった。そんな彼女へ無神経にも手を出そうとする愚か者は、この時代 にはいなかったという話だ。
なのに、そんな誰の手にも汚されていないような女性がペニスをしゃぶっている――その光景から目を離すことなんて少年には考えられなかった。
スペルビアは自分の涎と少年の我慢汁で口元をぐちゃぐちゃに汚しながら、首を振りって熱心に少年の亀頭に食らい付く。赤々とした粘膜を這う舌と唇の感触――
「あ、ああ、もうだめ……あああああっ!」
未熟な少年はついに我慢の限界に達した。
あの騎士団長の口の中に射精してしまう、その事実に云いようのない背徳感を感じながら少年は精液をぶちまけた。
スペルビアは顔色ひとつ変えずに、少年の精液を呑み込む。けれど、その口はスペルビアとは独立した存在であるかのように精液を絞り取る機関と化していた。無表情に精液をペニスから吸い出されて、少年は腰が抜けるほどの快感に震える。
がくり、と少年は足から力を抜いて床に倒れる。兵舎の一室の床は冷たかったが、熱を感じることができないほど頭の中に甘い快楽が充満していた。
「これで力は抜けたな」
精子の糸を引きながら少年のペニスから口を離したスペルビアは、膝立ちになって少年の腰に跨った。
既にスペルビアの下半身にはショーツ一枚しかなかった。黒い布地にレースをあしらったもので、スペルビアの印象とあわないような、それとも酷く合致しているような、不思議な感慨を少年に与える。
スペルビアはショーツをずらすと、秘所を相手に見せつけた。
「お前が前線に行く褒美だ……忘れられぬよう脳髄にまで焼き付けるがいい」
愛液で濡れていた女性器に少年のペニスが宛がわれ、一息にスペルビアは腰を落とした。
ずぷんっ、と少年の経験不足なペニスが女性騎士たるスペルビアの躯を貫いた。
子供の陰茎は、未成熟といっても男性としての機能という点においては欲望に忠実な獣。
だが――欲望に忠実という点においては、スペルビアの方が一枚も二枚も上手だった。
「ははっ、この我の中でお前のペニスがどんどん膨らんでいるぞ。物足りぬかもしれぬと懸念していたが、やればできるではないか!」
歓声をあげて、スペルビアは淫らに腰を振る。騎乗位で少年を馬のように扱いながら、結んだ髪を尻尾のように振り乱す。尻尾を振って悦ぶ姿はまるで交尾に夢中の犬かなにかのようだった。
頬を上気させて腰を振り乱せば、スペルビアの膣が少年のペニスをきつく締め付ける。鍛えられた括約筋でしまる膣圧は強く、少年のペニスは押しつぶされてしまいそうだった。けれどスペルビアの膣肉は極上の霜降り肉よりも柔らかい。
「あ、駄目、もうっ」
スペルビアが腰を三回も振らぬうちに、少年の我慢は限界に達した。射精したばかりだったというのに少年は精を騎士団長の秘部にぶちまける。
「手加減してやったというのに……早漏め。ならばしっかりと訓練をつけてやらんとな!」
少年が射精していても、スペルビアは腰の動きを止めることはなかった。むしろ、余計に腰の激しさは増す。肌に珠のような汗を浮かべながら、冷静沈着な騎士団長は愉悦に顔を歪めて少年のペニスを弄んだ。
「あ、ああああ……!!」
彼はもう、悲鳴をあげてスペルビアの中に射精することしかできなかった。
*
事を済ませたスペルビアが向かったのは、この国の牢獄のひとつだった。
「まったく、いきなり人を呼び出すとはどういう了見だ……我は忙しいのだぞ」
愚痴をこぼして腰にはいた剣の石突きを叩く。
現在この国は、革命者たちが指揮する軍で他国と戦争の真っ最中だった。もっとも、戦争の原因は革命軍の方にある。彼らが国の主権を握り、その勢いで他国に まで攻め立てたのだ。問題は、軍は既存のものであるということだ。王に仕えていた者たちがそれを殺した者にすんなり従うわけがない。よって、戦線は酷い有 様である。兵士の士気など最悪である。
そんな状況なので、スペルビアは前線に赴く羽目になった少年の筆卸をしていたのだ。もう二度と祖国の土を踏めない哀れな少年への手向けに。
もっとも、革命の要因を作ったのは他でもないスペルビアを含む三人の高位淫魔であるが。そんなことまで気にしない辺り、騎士とは云えやはりスペルビアも淫魔のひとりだ。
牢獄に到着すると衛兵に声をかけて中に入れて貰う。スペルビアは女官に扮しているアワリティアと高級娼婦を名乗っているルクスリアとは知名度が違うので、ほとんど顔だけで入れて貰えた。
案内を断ってスペルビアはアワリティアとルクスリアに呼ばれた牢獄の一室にやってきた。
そこは牢獄の最奥にある檻だ。
鍵のかかっていない檻の中にアワリティアとルクスリアの姿を確認した。
「おい、こんなところに呼び出して、いったいなんの用だ。お前たちと違って、我には表の仕事があるのだから、わざわざ呼び出すな」
不機嫌さを隠しもしない言葉だったが、檻の中で振り返ったふたりは気を悪くした様子もない。スペルビアは誰に対してもこんな性格なのだと知っているのである。
スペルビアの顔はぞっとするくらい端正であるものだから、必要以上に苛立っている風に見えるのだ。そのため、並の肝っ玉の持ち主なら竦みあがってしまう。その性格が熟知できるくらいに付き合いが長ければ、彼女の表情の変化に戸惑うこともない。
もっとも、実力ある淫魔は己の力に絶対の自信を持っている。例え怒らせても自分が負けるとは考えていないのが恐れない最大の要因だった。
「つれないなあ、スペルビアは。せっかくボクに男を貸してくれたお礼をしてあげようと思ったのに」
ニコニコとしているボーイッシュな褐色の少女にスペルビアは溜息を吐く。
「あれは貸したのではなく、奪われたの間違いだ。貴重な労働力を浪費するな、淫売め」
「もうっ! スペルビアは人間に甘いんだから」
「何を云っている。蟻程度の力しか出せぬ猿も人海戦術には必要だからな。ものは使い用だ。それと、何度も云わせるな。何故我を呼んだ?」
「彼に見覚えがあるでしょう?」
いい加減本当に苛立ってきたスペルビアに答えたのは、長髪を揺らす穏和な顔つきのアワリティアである。
アワリティアが牢の中を手で示すが、丁度灯りの影になっていて何がいるか窺えない。
スペルビアも牢の中に入ってそこにいる人物を見た。
「――ほう」
自分の姿を見て萎縮した青年を見て、苛立ちもどこへやら、スペルビアは口の端をつり上げる。
「まさかまたお前に会うことになるとは思わなかったな、ジョゼフ」
「スペルビア団長……」
両手を背中で拘束されているジョゼフは、呆然とスペルビアを見上げた。
「えっと、この子はスペルビアの知り合いなんだよね? ボクはアワリティアからの又聞きだから良く知らないけど」
「ああ、昔騎士団に居た奴でな。てっきり死んだと思っていた。いや――」
こつん、と人差し指が腰にはいた剣の石突きを叩く。
「我が殺したはずだと思っていたのだがな。壮健そうでなによりだ。切り落としたはずの右腕もどうやら繋がっているらしい」
「……っ」
ぐっ、とジョゼフが奥歯を噛みしめる。怒りはなく、睨むわけでもなかった。それは自分の無力さに打ちひしがれているようだった。
「へえ、殺したってどういうこと?」
「こいつは我が剣を教えていた騎士のひとりでな。その中でも剣の才は飛び抜けていた。まあ、あくまで見習い共の中での話だが……。これの最も優れた才は状況の判断能力でな、革命の機運をいち早く察知して騎士団を脱退したのだよ」
「……そして、ぼくは貴女に斬られた」
「ああ、我がお前の右腕を切り落とした」
悪びれもせず、スペルビアは云った。
「少しでも我の興味を惹いた男は試さずにはいられない。だから斬った。騎士を突然止めたのだから、殺しても適当な理由をでっち上げればそこそこの正当性も得られたからな」
「変なの。気に入ったなら食べちゃえばいいのに」
「お前と一緒にするな。そんなに腰ばかり振っていては脳髄が溶ける。それに今から食べさせてもらう。崖に突き落として這い上がってきた相手ほど虐め甲斐があるからな。どうせ、そうさせるために我を呼んだのだろう、アワリティア」
「ええ。人質ですが、別に殺してしまって構わないでしょう。どうせ相手をおびき寄せるための餌にすぎないのですから、死んでいても悟られなければ仔細問題ありません」
アワリティアは一切言葉を詰まらせることなく云いきった。
ジョゼフを逮捕して処刑を敢行すると宣言したのは、彼が夜を騒がせている者と関連性があると踏んだためである。
危険人物としてアワリティアは魔女イザベラを斥候にマークさせていた。あれほどの力の持ち主、七つの大罪の名を冠するほどの上位淫魔なら気付かぬわけがな い。その家に三人の人物が担ぎ込まれ、うちひとりがジョゼフだった。ふたりいた小柄な少女のうち、片方はイザベラと同居している者であったから、自然と夜 の犯人は見慣れない黒いドレスの少女に絞られてくる。
どうやらジョゼフは夜に吸われた者で唯一の生還者、相手が特別な思い入れをしている可能性は高い。こうすれば、なんらかのアクションがあると踏んだわけだ。
当てが外れたところで特に問題もない。そのときは、国民を満足させるために処刑される哀れな少年がひとり増えるだけの話だ。
「ふふっ、なら遠慮なく頂くとするか」
「な、なにを……」
「なにを? わかり切ったことを聞くのだな」
ジョゼフを鼻で笑って、スペルビアは服を脱いだ。身を守るための鎧を無造作に放り捨てて、仁王立ちになる。
「淫魔がすることなど、ひとつしかあるまい」
「淫魔って、まさか団長が!?」
「ボクたちもそうだよ-」
驚愕しているジョゼフをせせら笑うようにルクスリアが補足した。
ジョゼフは気絶している間にここへ連れてこられて、意識を取り戻したときに見ず知らずのふたりがいたのだ。彼女たちがどんな素性の者達か判っていなかった のも無理からぬ話である。しかも、一度殺されかけたとはいえ、かつて自分の上司であったスペルビアまでもが人ではなかったと云われれば、思考も停止してし まう。
「さて、いつまでそうしているつもりだ。頭が高いぞ、ささっとかしずかんか」
スペルビアはジョゼフの頭を踵で思い切り蹴り飛ばした。
靴底が額を殴打し視界が真っ白に弾ける。ジョゼフは声をあげる暇すらなく床に頭をたたきつけられ、鶏の首を絞めたときのような苦しい声を洩らした。
「ガ……っ」
「苦痛で歪む、いい顔だ……これだから殴り甲斐があるのだよ。あのときも本当に愉しかった、この腕を切り落とした時も!」
ジョゼフの右肩をスペルビアが容赦なく踏みつける。骨が軋む音が聞こえてきそうなほどの力強さのまま、足が捩られてジョゼフは悲鳴をあげた。
「ア、ギ、ッアアア……ッ」
「はっはは! 古傷が痛むか? そうだろうなあ、あのとき我が切り落としたところは丁度ここのはずだ。痛かろうさ。けれど、まだあのときよりはマシであろう? もう一度ここを外してやったら、さぞや懐かしい気分に浸れるだろうな」
傷みを快楽に変えるような手管の女性というのもいるが、スペルビアの場合、そこに加えられた力には一切の加減がなかった。本当にこのままジョゼフの右肩を外して、ちぎり取ってやろうという意気込みを感じるくらいの力が足にこめられている。
「ふふ……意地悪もこれくらいにしてやろうか。お前を苦痛で鳴かせた回数などもう数えることもできんのだ。次はこっちで鳴いてもらおうか」
そういうとスペルビアは下半身を覆っていたショーツを脱ぎ捨てて、ジョゼフの顔の上に腰を落とした。鼻と口に押しつけられた熱く濡れる柔肉に、ジョゼフは目を見開く。視界に広がるのは鼻をこりこりと刺激する陰核とスペルビアの金の平原だけだ。
「ほら、ここがお前の肉棒を銜え込む搾精器だ……たっぷり味わうがいい。なにもしないと、窒息してしまうぞ?」
鼻を塞がれて呼吸ができないジョゼフはスペルビアの云う通りにするしかなかった。
例えそんなリスクがなかったとしても、この甘い液体で濡れた秘部に舌を這わせていたことだろう。人間にとって、スペルビアの愛液に濡れた秘所は昆虫にとっての樹液で濡れた木々同然だった。
アンナマリアの薄い線のようなものではなく、ぱっくりと口を開いた性器に舌を伸ばす。女性の陰部を舐めるなんてジョゼフは初経験だったが、そのことを忘れてしまうほど鼻と口を押さえつけるそれは魅力的。
舌が亀裂をゆるく舐めると、スペルビアの背筋がびくんっと跳ねる。
「あはっ、いいぞ……そのまま中に……んんっ」
舌先が膣の入り口をノックし、肉の道を掻き分けていく。すると舌先から、ジョゼフは全身が震えそうになる快感を流し込まれた。膣肉が侵入してきた舌をペニ スと同じように締め付ける。波打った襞が左右共に別々のうねった動きでもって舌を責め立てる。性器を舐めて感じさせているのはジョゼフのはずなのに、舌を 入れただけでジョゼフの攻守は完全に逆転してしまっていた。
「はっ、ああ……」
ジョゼフの口内から唾液が大量に溢れて口元を赤ん坊のように濡らす。それでも舌を引き抜けないのほどの快感がジョゼフを襲っていた。
口の中に流れ込む愛液を喉が動いて呑み込めば、さらに痺れるような快楽が全身に染みこんでいく。頭がクラクラするのは、なにも酸素が欠乏しているだけではなかった。
「いいぞ、慣れてないにしては上出来だ。我の中でお前の舌が性器みたいにのたうちまわっておるぞ」
舌を膣にいれただけでペニスを触られたように感じてしまったジョゼフを笑う。
「では、お待ちかねだ。そんなに触って欲しいのなら我が喰らってやろう」
スペルビアが躯を捻って体勢を変える。ジョゼフの顔に女性器を押しつけながら、ズボンの中で膨らむペニスに顔を寄せた。
手際良くズボンを脱がせると、がちがちに勃起したペニスがこぼれる。
「ふん、我の性器を舐めさせられただけでこうも硬くするとはな」
スペルビアの舌が陰茎を根本から尿道までぬるりとなぞった。
そのまま亀頭を包み込み、口をすぼめて頬肉と舌を密着させる。鍛えられた騎士団長といえどその口内は柔らかく、亀頭に吸い付く肉の感触は男の躯を悦ばせてあまりあった。
「は……ああ……」
「だらしない声をあげおって……淫魔の愛液をそんなに呑んだのだから当然か」
「そこにスペルビアの唾液をペニスにすり込まれれば、どのような男も正気でいられるわけもありませんね」
淫魔の分泌する体液には精力増強の他にも、媚薬のように性欲を刺激する効果がある。それはもう麻薬と同じで、口に含んでしまえば最後、正常な思考能力を 失ってしまう。たとえどんなに屈強な強者であっても、力を生かすための思考を奪われてしまえば赤子も同然であった。しかも、高位の淫魔たるアワリティア、 ルクスリア、そしてスペルビアの体液は他の淫魔の比ではない。彼女たちと寝てしまった時点で、人は性欲という三大欲求のひとつに執着する精液袋と成り下が るしかないのだ。
「ねえねえ、スペルビアを見てたらボクも欲しくなっちゃったよ。仲間にはいってもいいよね?」
にこりと笑って、スペルビアはジョゼフの股の間に寝転がってペニスに顔を近づけた。ペニスに浮き上がる裏筋へ挨拶代わりに舌を這わせる。
ペニスは熱された鉄のようで、力を込めて無理矢理射精を堪えていた。そんな男の儚い抵抗は淫魔たちには筒抜けで、逆に嗜虐心を煽るだけだ。
「これは今、我の所有物だ。ならぬ。あとにせよ」
「スペルビアの後なんて絶対回ってこないよ。だってずっとやめないんだもん。それにー、もしボクがこの子イかせたら、この躯の方が気に入ってるってことだよね。道具はより上手く使える人に渡るべきだと思いまーす」
「ほう、この我に勝負を挑むか……面白い。なら我より先にジョゼフをイかせることができたならば譲ってやろう」
「やった! じゃあ、いただきまーす」
スペルビアの反対側からルクスリアがペニスに吸い付いた。
ふたりの淫魔の舌と唇にペニスを責め立てられて、ジョゼフにはもう正常な思考能力は残されていなかった。下半身へ反射的に力が集まって辛うじて射精を堪えているだけで、もう天上の快楽から逃れようとする抵抗の意志は根こそぎ取られていた。
「んふっ、ちゅ……あはっ、まだまだ大きくなってるね。ふたりの淫魔に責められたら、どんな短小包茎なおちんちんでもおっきくなっちゃうからね……。こうやってボクたちみたいなすっごく強い淫魔に舐められてるんだから……こんな幸せなこと、滅多にないんだよ?」
牢屋の中はむせかえりそうになるほどの甘い香気が漂っている。ルクスリアとスペルビアの汗ばんだ躯から漂った色香だ。その匂いは嗅がなくとも、肌に触れた だけで男は勃起を抑えることはできないほどの淫蕩な気である。さらにその原液とも云える愛液を呑み、唾液を粘膜にすりつけられれば、男の精神を崩壊させて しまうには充分だった。
「ねえ、スペルビア。お口だけじゃなくて、おっぱいも使おうよ。きっと夢心地であっという間にイっちゃうから」
「胸? ……我の胸はあまり大きくはないが」
「淫魔なのにそんなこといわないの! その胸が逆に男を悩殺しちゃうんだからさ」
「ふむ、そんなものか」
ルクスリアとスペルビアが胸元をはだけると、褐色の美乳と純白の微乳が揺れた。後者はささやかな揺れでも、それが男の背徳感を刺激する。
勃起して天上を指していたペニスを、ルクスリアとスペルビアの胸がサンドイッチにした。ふたりの乳房に亀頭以外を包まれて、ジョゼフはスペルビアの秘所に口を押しつけたまま嬌声をあげる。
「ボクの胸の中でビクビクしてる……亀頭が触られてないからイけないんだね。すっごい苦しそうに膨らんでるよ」
褐色の胸で脈打つペニスを見下ろすと、くふっ、と喉を鳴らしてルクスリアが微笑み、亀頭に舌を伸ばした。
八の字を描くようにして亀頭を舐めると、舌先を尿道に滑り込ませる。
「は、あああっ!?」
「む……このままお前にイかさせてなるものか。我の胸で……」
一生懸命に胸を中央に寄せたスペルビアが躯を揺する。控えめな胸がペニスにこすりつけられて、硬い乳首が雁首を弾いた。
「このおちんちん、もうイっちゃいそうだよ? これはボクの勝ちかな」
「抜かせ、我の胸が良いのだ! ……はむ」
むっちりと肉のついたふとももでジョゼフの顔を挟んで自らの女陰をなめさせながら、スペルビアは胸から顔を出す亀頭を銜える。ルクスリアの唇とスペルビアの唇がひとつのペニスを取り合っていた。
竿にくわえられるふたりの胸の極上な感触と亀頭を這う熱い塊の刺激は、淫魔の気に当てられ昂ぶっていたジョゼフを限界へ引きずり上げた。
「ぁ……ッ、ああああ゛あ゛あ゛あ゛あ゛――――!」
ドクンッ! ドクンッ、ドクドクンッ……!
噴火した火山のごとく白濁とした精液がペニスから噴き出した。
ルクスリアとスペルビアの口で受け止めきれなかったほどの精がふたりの顔にぶち当たり、ペニスを挟んだ乳房の上にだらだらと降りかかる。口に入り込んだ濃い、ぷるぷるとした大量の精液をふたりは舌の上で転がし、呑み込む。
チーズみたいに唇を汚した精液を舌で舐めて、ルクスリアは喉の奥から青臭い吐息を吐いた。
「はあっ、すっごい濃い精液! これだけ出させたんだから、ボクの勝ちだね」
褐色の胸を白くデコレーションした精液を見せつけながら、ルクスリアが得意げにいった。
「戯け、我の躯にこやつが感じたのだ。その証拠に我の女性器に夢中でむしゃぶりついている」
スペルビアが躯を起こして、ジョゼフの顔の上に騎乗する。太腿で頭を固定させたまま腰で円を描いて、男の顔に何度も陰部もなすりつけた。
「くくっ、そのペニスはたっぷり濡れた我が抱きしめてやる予定なのだ」
ようやくスペルビアが立ち上がると、腰の下から現れたジョゼフは虚ろな目で浅い呼吸を繰り返していた。口を解放されたにも関わらず、もう意味のある言葉を出せなかった。
スペルビアが牢の壁に背中を預けて、股を開く。秘部が花弁のように開いて男自身を誘っていた。
「さあ、来い。ここにお前のペニスを突き刺すがいい。抱きしめてやろう……天の果てまでな」
騎士団長の誘惑に乗るほどの理性すらジョゼフには残されていない。それでも、ジョゼフはルクスリアを押しのけて、スペルビアと向かい合う。街灯に群がる蛾のように、抗いがたい誘いに引き寄せられて。
あれだけ盛大に爆発したペニスは淫魔の気、そしてふたりによる暴力的なまでのテクニックで未だに萎えていなかった。
ジョゼフはスペルビアに覆い被さり、ペニスを女性器に近づけていく。
スペルビアの、武器を握ってきたせいで肌がささくれ立った手が肉棒に添えられた。細く綺麗という女性の指の印象からかけ離れていながらも、その指で触れられれば声を洩らしてしまうほどの快楽が染みこんでくる。
男根を期待して、スペルビアの女性器が涎を垂らした。ジョゼフの意志とは裏腹に、肉棒はそこへ吸い寄せられる。
くちゅ、と音を立てて亀頭が秘部に埋まる。瞬間、無数の襞が蠕動した。
亀頭を幾重もの襞はまるで何十、何百という舌を同時に押しつけられたような圧力と快感。
「あ、ああああああッ!」
亀頭の隅々に愛液をすり込もうと蠢く膣の感触に男が耐えられるわけもなかった。
ペニスが膣の入り口で暴発する。どこにそれだけの精があるのか。どう見ても陰嚢に入りきらない量の精液が接合部から溢れだした。
「なんだ……先端をいれただけで達してしまったのか?」
陰茎に添えていたせいで精液まみれになった手を眺めながら、スペルビアが鼻で笑った。
「少し本気になりすぎてしまったか。……さて、お前は奥まで入るうちに幾度射精するのだ?」
精液で汚れた指を口で銜えて綺麗にすると、艶然と微笑むスペルビアはジョゼフの腰に足を絡みつかせた。足に力を入れて、まだ射精の余韻さめやらぬ肉棒を自分の中に押し込んでいく。
ず……ずる……っ。
竿に絡みつく濡れた膣肉は容赦がなかった。きゅっとしまった膣は手で握られているようだが、与えられる無数の襞による感触は明かに手のそれではない。
この圧力はアンナマリアのような小さい膣にいれた時の狭いからきつい、というものではなかった。鍛えられた括約筋による締め付けは緩めるのも強めるのも自由自在で、精を絞りだそうと常に新しい刺激を与えてくるのだ――。
「駄目……これ以上は、無理……!」
ペニスに与えられる感覚はジョゼフの正気すら取り戻させるほどだった。
けれど、膣からペニスを抜くことは叶わない。腰はスペルビアががっちりと足で捕まえていたし、なによりジョゼフは逃げようと思うことができなかった。
これ以上の快楽を拒絶しているのに、不思議とジョゼフの腰はペニスを押し込もうとしている。陰嚢の中はもう空になっているはずなのにだ。
「ど、どうして……っ、止まらない……!?」
「くくっ、わからないようだな、ジョゼフ」
汗で前髪を額に吸い付かせているスペルビアがその動揺を見抜いた。
「我 の気は少々特殊でな……。なに、たいしたことはない。ただ、我の発する気を受けた者は危機に対して愚鈍になってしまってな……逃げようだとか、後退だと か、そういったことが一切できなくなるのだ。逃走本能の鎮圧だな。普段は戦場で自軍の兵士を従えるために使っているが……この状況でも、ありだろう?」
「そんな――」
「以前、お前が我に腕を切り落とされたのも同じ理由だ……お前は逃げようとする意志を知らず破壊されていたのだよ。そうでなければ、力及ばぬと判っている相手を迎撃なぞしないだろう?」
スペルビアの前に立った時点で。あらゆる者は逃げ出すことができなくなる。出会ってしまったときに人は死を覚悟しなければならないのだ。
まさに、恐怖の権化と呼ぶにふさわしい理不尽の象徴。
「さあ、……来い」
「う、うわあああああああっ!」
ぐっ、と引き寄せられ、ジョセフは再び膣の中で射精した。
量は衰えることを知らない。多量の精液がスペルビアの膣に注ぎ込まれていく。なのに、ジョゼフの腰は前進を続けていた。
「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛ァァァ――――!!!」
精を噴き出しても止まらない刺激に絶叫した。脈打っているペニスに纏わり付く襞、その中を突き進むことによって倍増する快感に脳内で神経がいくつもはじけ飛んだ。眼窩の奥で火花が散る。
「ほぅら、ようやく半分! まだまだ行くぞ、そぉれ!」
吐き出した精液のせいで滑りのよくなった膣をペニスが一気に突き進む。
射精が終わらぬうちに、ジョゼフはまた絶頂する。最早止まることなく噴き出し続ける精液。
「あっはっはっはっは! 命諸共総て吐き出してしまえ!」
哄笑を上げて、ついにスペルビアがペニスを根本まで呑み込む。子宮と亀頭がキスをして――生きているように子宮が亀頭に食らい付いた。
「あ、ああ゛あ゛あ゛あ゛あ゛ ――――――!!!」
ドプンッ! ドクッドクッドクン! ドッ、ドッ、ドプッ――!
声にならない声を上げて、ジョゼフは何度目とも思い出せない限界に達した。
「ああ、出てる、すごい精の量だ――」
スペルビアの顔が至福で緩んだ。膣内は注がれる精液を吸収しようと何度も収縮を繰り返す。そうやって精を啜る動作すら、中のペニスを弄ぶ暴力的な動きだった。
「あ、あ……」
ジョゼフの躯から力が抜けた。
がくり、とスペルビアの上にジョゼフが倒れる。自分の上にいる白目を剥いた青年の顔を覗き込んだ。
「ん……ああ、死んでしまったか……」
少年は呼吸を止め、事切れていた。動かなくなったジョゼフを見て、スペルビアは残念だと顔をしかめる。
「もうっ! スペルビアはいっつも早いんだからー!」
「貴女が云うことですか、ルクスリア」
頬を膨らませて怒るルクスリアに、ずっと情事を眺めていたアワリティアが呆れて溜息を吐いた。
そんなふたりには目もくれず、スペルビアはジョゼフの首に手を回す。
「死んでしまったか……」
半開きになった唇を自分の方へと引き寄せた。
「〝なら、天国から引きずり降ろさないとな〟」
スペルビアがジョゼフの唇に唇を重ねた。
熱い、濃厚なキス。
吐息を洩らしながら、長い長いキスの末――
「――!?」
ジョゼフが目を覚ました。
それに気付いて、スペルビアが顔を離す。
「え、いったい、なにが……」
意識を取り戻し、眼前にあるスペルビアの顔にジョゼフが動揺した。何が起こったのか理解していない表情を見て、スペルビアは端正な顔に悪戯を成功させた子供の茶目っ気ある笑みを浮かべる。
「くくっ、自分が死んでいたことも気付かなかったか」
「死ん……!?」
「ああ、お前はさっき我に精を総て吐き出して死んだのだ。当たり前であろう。人にあれほど精液を出すことなどできぬ……。お前の命ごと喰らってやったのよ。そして、それをお前に返してやったのだ……」
事態が飲み込めていないジョゼフだったが、ともかく自分の躯が軽くなっていることに気付く。体力が戻っていることは事実だった。
「わざわざ、助けて……?」
しかし、どうしてそのようなことをしたのかは判らずに、ジョゼフは無垢に首をかしげる。人の好意を信じているようなジョゼフの言葉。確かにスペルビアはそれに好意でもって応じた。ただし、スペルビアの最大の愛情表現での好意。
「ああ、そうとも。――さあ、続きをしようではないか。また、〝最初から〟な」
そして、スペルビアの膣がまた搾精を開始した。
「え、あ、――あぐっ!?」
あれだけ出したというのに、スペルビアに生命力を返還されたジョゼフのペニスは最初の硬度を完全に取り戻していた。体調は、万全だった。精神は度重なる快楽の電流で疲弊したままなのに。
「先程は、奥まで入れることしかできなかったからな……きちんと腰を振ってもらおう」
「そ、んな……団長、これ以上は無理です……っ」
「我ら淫魔にとって精液はごちそうでな……淫魔の躯を構成する必須の栄養がたんまりと含まれているのだ。最高の餌を前にお預けを許容できるほど、我が謙虚に見えるか? 我は傲慢のスペルビアぞ」
押し倒されているのはスペルビアの方であるのに、生殺与奪は体勢とまったくの逆だった。
「そ れにの、よく聞くがいい。我ら淫魔は搾精という一点において進化を続けてきた。中には、我の生命返還のように特異な能力を持った個体も生まれている。つま り、今お前は淫魔の生物として何千、何万、いや、何億年という進化の歴史の頂点と交わっているのだ。光栄に思い、快感に翻弄されるがいい」
「や、やめ……うあああっ」
拒絶の言葉に逆らって、ジョゼフは自分から腰を振っていた。精神はもう疲れ切って快感が苦痛でしかないというのに、復活した躯の方からしてみればスペルビ アの中はまさに極楽浄土だったのだ。それに、スペルビアの躯が無意識にジョゼフの腰を振らせるほどに魔性じみているのである。
ずんっずんっ、と ジョゼフのペニスがスペルビアを突き上げる。手加減されているのか、ジョゼフは少なくとも三回までの挿入運動には辛うじて耐えきった。それでも、一瞬気が 緩んだだけで総てを放出してしまいそうになるほど、淫蕩に濡れた蜜壺の熱い膣肉はペニスを貪っている。
三回は耐えても、四回目は下半身に集う射精感を抑えることはできない。このまま腰を打ち込んで復活一回目の射精をしようとしたとき、ジョゼフの背中に柔らかいものが押しつけられる。
「ふたりだけの正真正銘の二回戦だなんてボクが許さないぞー。見てるだけで濡れちゃったんだから、ボクも混ぜてもらわないとね」
褐色の美乳に渇いた精液をこびりつかせたルクスリアが、ジョゼフの背中に抱きついていた。
「なにをいうかと思えば、二回戦? 最低でも一〇回戦はするつもりなのだが」
スペルビアの言いぐさにジョゼフは顔を強ばらせた。最初の一度ですら脳をミンチにされたように疲弊してしまったのに、それを最低でも一〇回は繰り返す?
きっとその頃には、腰を動かすことしかできない肉の人形が転がっているだろう。その未来にジョゼフは背中を粟だたせた。
「そういうわけだ。邪魔をするな」
「邪魔はしないよ。安心して、ボクはこっちの穴を借りるだけだから」
突然、ルクスリアの人差し指がジョゼフのお尻の穴に侵入した。
「あぐぁっ!?」
「わっ、かわいい声をあげるんだね……こっちは初めてかな」
排泄以外のことに使われていなかったアナルをルクスリアの指がこねくり回した。繊細な指という異物がアナルの中でのたうち回る未知の感覚にジョゼフはあられもない声を上げる。
「んふふ、いい具合。これならボクを受け止められそうだね」
ルクスリアがアナルから指を引っこ抜く。穴から指が出て行く時に排泄と似た甘い感覚が背筋を走り抜け、ジョゼフは男とは思えない無防備な喘ぎ越えを洩らした。
ルクスリアの背中でなにかが揺れる。
黒い、ボロボロなマフラー状の物体。それは鎖骨の辺りからでているようにも見えたし、肩胛骨から翼のように生えているとも見えた。マフラーが一気に広がると、蝙蝠の翼のような姿になる。
「淫魔の翼……こうした方がやりやすいから、ね!」
ルクスリアの尾骨から出た尻尾が、彼女の女性器に入り込む。中で捩れ、膣から漆黒の剛直が飛び出した。
黒一色であることを除けば、ルクスリアの秘部から映えたのは立派なペニスだ。小柄な躯には不釣り合いなほどに大きい。
「やっぱり男女の快楽を両方堪能しなきゃだよね、色欲なんて名前を襲名したんだから。それじゃ……ボクも混ぜて貰うよ?」
ルクスリア自身の愛液で濡れて凶悪な光を反射した黒いペニスがジョゼフのアナルに添えられ――貫いた。
「がはっ」
肛門を無理矢理に押し広げるペニスにジョゼフは咳き込む。内臓が中から押し上げられたような不快さと、アナルの中にあるペニスの存在感に頭の中が真っ白なり――
あと少しでスペルビアの中で達してしまいそうなときにアナルに挿入されたせいで、ジョゼフの堤防は一気に崩壊した。
「あ、あああ、駄目、た、耐えられないっ!」
ジョゼフのアナルがぎゅっと締まってルクスリアのペニスを圧迫しつつ、自分のペニスから精をスペルビアの中に流し込んだ。
「うふ、ボクのおちんちんがアナルに挿入されてイっちゃったね。そんなにお尻好きなんだ……じゃあ、もっとやってあげるっ」
射精の余韻さめやらぬままに、ルクスリアがジョゼフのお尻に腰を叩きつけた。何度も何度もアナルを貫かれる。肛門を前後するペニスの異様な感覚とお尻に触 れるルクスリアのお腹の感触ににジョゼフは身もだえた。その間にも、ジョゼフの躯はスペルビアに夢中で腰を振っている。
前と後ろで別々に与えられる快楽。永遠と続きそうな時間に、ジョゼフは世界が自分から遠退いて行くような錯覚を覚えながら、また射精を繰り返す――。
「さて……そろそろのようですね」
唯一狂乱に参加せず、鑑賞していただけのアワリティアが牢屋の外を振り返る。なにやら牢獄の中はにわかに騒がしくなっていた。
「どうやら、来たようですね」
牢屋がこれほどに騒がしくなることは滅多にない。この監獄にいる犯罪者は既に処刑が決まった者ばかりだ。今更抵抗しようとする者はいないのだから、異分子が紛れ込んだと見て間違いはない。
「お相手さしあげますわ……私たちの愛すべき愚か者よ」
牢屋を襲撃した侵入者たちに向けて、アワリティアはひとりつぶやいた。
「――はあ!? じょ、ジョゼフくんが……拉致されたぁ!?」
閉店中のパン屋の中で、少女の絶叫がこだました。
それは牢獄での拷問から数時間遡る。
アンナマリアが広間で断頭台としての使命を果たし、夕暮れが街を血のような朱色で染め上げているとき。
ジョゼフの勤務するパン屋で聞いた事実は、レリアを驚かせるには充分なものだった。
体当たりで勢いよく扉を開けて魔女の家に転がり込んだレリアは、バンッとテーブルを叩いた。
「ど、どどどどういうことなんですかっ」
帰ってくるなり声を張り上げるレリアに、イザベラはうるさそうに片耳を塞いだ。
「どういうことと云われても、なんの話だい?」
「ジョゼフくんのことですよぉ! 軍人に逮捕されたって……どうしてジョゼフくんが?」
「……ああ、しまった。それはきっと淫魔たちの差し金だね。この家、彼女たちに監視されてるんだよ」
「そんなことは知ってますよ! まさか、なんの対策もしてなかったんですか?」
「だって、する必要もないだろう? 別に見られて困ることもしてないし」
「ああっ、もう! 先生はなんでそんなに肝心なところでずぼらなんですか!」
「そんな視線をいつまでも気にしていられるほどの繊細な神経は当の昔にかすれて消えたのだよ。むしろ、そんなに私の躯は美しいかと照れてしまうね」
「だ、駄目だこの変態……」
云って、皺のよった眉間をレリアは抑えた。
ジョゼフ拉致の一報を知ったのは、ついさっきのことである。
最初におかしいと思ったのは、いつもこの家にパンを配達に来ているジョゼフが一向に姿を現さなかったときだった。昼を過ぎてもやってくることはなく、夕刻にさしかかろうしていてもそれは変わらなかった。
夜が明けてから帰宅したものだからパン屋の主人に怒られて配達に行かせてもらえないのではないか、とレリアは考えてみたものの、あの几帳面なジョゼフがそんな簡単に折れるとは思えない。
イザベラは特に気にしておらず調べる気配がまったくなかったので、レリアは不安になって直接パン屋に出向いたのだ。
そうすれば、案の定その不安は的中した。暴行をくわえられて怪我をした店主から、ジョゼフが捕まったと聞かされたのである。
反逆罪、犯罪幇助。どれもジョゼフには似合わぬ罪状だった。あの人なつっこい子犬みたいな顔をした青年が決起するなんて本気で考えているのだろうか。い や、例え反乱の意志などなくとも捕まえてるのが今のこの国である。不安定な国家情勢、少しでも方針に異を唱える者がいればそれが不和となって国内が分裂し てしまう。戦時下においては疑問を口にしただけで、悪なのだ。
そんな体制に、レリアはあきれかえってなにも云えなかった。人間はレリアにとって 愛すべき食料であるが、それでも彼らの不合理さと個人の意識レベルの低さにはほとほと幻滅する。この国を動かしている人間が悉く高位淫魔によって傀儡とさ れていることはレリアも知っていたが、それにしても、ここまで悪辣だとは。
「なまじ自我があるから衝突や主張なんてするんですね……。あたしたちみたいに、個人主義にもなれなくて、しかも数が多いんだから……これだから人間は……!」
「キミの心配しているジョゼフも人間だってことを忘れちゃ駄目だよ? まあ、今回も淫魔が絡んでいるんじゃないかな。多分、ギヨたんに関してだ」
「あ……もしかして」
「そ う、ジョゼフはギヨたんに襲われて唯一生き残った人間だ。だから、そこに何かあると踏んだのだろう。彼女たちにとって、ギヨたんは目の上のたんこぶだ。な にせ、自分たちの狩場に土足で入り込んだ異分子だからね。ギヨたんをどうにかできるなら、そこにつけ込みたいわけだよ」
「だったら、あたしみたいに直接ギヨたんと戦えばいいのに……」
「こ れまでは、ギヨたんの正体すらわからなかったんだよ。だけど、昨日ここに連れ込んだとき、監視の目がギヨたんを捉えて……そうしてようやく誰か判明したん じゃないかな。ほら、ギヨたんって淫魔じゃなくて無機物だろう? 探そうと思っても見つけられないんだよ。人海戦術をとっても人間じゃギヨたんに殺される だけだからね」
「それで、ギヨたんと接点があるかもしれない子を捕まえて、餌にした……ですか。さすが、一国を簡単に手中に収めただけはある……姑息な手段ですね」
この国はわずか三人の淫魔によって支配されている。支配されているという自覚を誰にも与えず、水が土に染みこむようにしてこの国を支配下においた。水の味を知った土は、もうそれなしでは生きていけない。
個人や、極限られた数人に国家という単位が支配されるのは、別段そこまで珍しいことでもない。人間の中にも独裁者なんていくらでもいた。そして、恋に狂っ て破滅した支配者も。淫魔たちも、それと変わらない。いや、そうやって人を狂わせてきた存在こそが淫魔たちなのだ。彼女たちに気づけないのは、そう、影だ からであり、肉欲によって人を虜にするからである。性欲に支配された者は、もう人ではなく動物なのだから。動物を優しく手なずけることは、淫魔にとって苦 でもなんでもなかった。
「さて、そうやってジョゼフは捕まってしまったわけだが……キミはどうするつもりなんだい、レリア」
「決まってるじゃないですかぁ、助けに行くんですよ!」
「キミも随分と甘くなったものだねえ」
「自分の獲物を同族に奪い取られると、淫魔は誰だってこうなりますよ。吸い殺しちゃったらそれまでですけど、自分以外にされるのは癪なんです」
「なんとも重くて軽い愛だことで。で、ひとりで行くつもり? 云っておくが、私は手伝わないよ。面倒だから」
「最初から期待していません。あたしひとりで充分です。監獄の男なんて、全員食べちゃうんですから!」
「そうかい。では無事帰ってこれるよう期待しておこう――」
バンッ、とそのとき扉が勢いよく開けられた。
ふたりの目がそちらを向く。そこには漆黒のドレスを着た少女が息を切らして立っていた。
「……わたしも行く」
夕焼けが沈んで訪れた闇を背にして、アンナマリアはふたりに宣言した。
*
月明かりを受けて、牢獄が黄金色に染まった輪郭を闇夜に浮き上がらせていた。
煉瓦材の不揃いなおうとつによって複雑なパズルの形をした影を作る牢獄。その門には、ふたりの見張りが槍を携え立っている。彼らはこの牢獄の門番だった。
と、いっても。昨今、この牢獄はほとんど利用されていない国立刑務所である。要塞として使用することを視野に入れて建造されただけに堅牢なものの、囚人も大半が出所していた。
そう、大半が、である。
まだこの牢獄には何人かの囚人が投獄されていた。そのために、このふたりのような門番がいるのだ。
しかし、門番のふたりはどんな人物がここに投獄されているのか知らなかった。おそらく、この牢獄を担当している兵士たちで囚人がいる理由を知っている者の方が少ないだろう。囚人たちの世話は専属の人間たちが行っているのである。
専属の人間は、何故か豪勢な料理を囚人たちに振る舞う。その理由を兵士たちは知らない。多分、追求しない方がいいのだろうと兵士たちは弁えていた。もし、 そんなことを知ろうとしてしまったら、きっと次の日には国に搬送されて広場で生首を晒すことになる。断頭台の一刀でもって。
「交代の時間は、まだなのか?」
兵士である若い男のひとりが、隣にいる同僚に尋ねた。
「まだまだ先だぞ。どうせ敵なんて来ることはない、そう肩肘張るなよ。立ってるだけで飯が食える楽な仕事だと思え」
同僚も兵士で、屈強な男だ。年の頃は四〇を過ぎており、無精髭を生やしている角張った顔は、眠そうにしかめられている。落ち着かない様子で訊ねた男とは正反対で、この男にとっては廃棄されたはずの牢獄の警護などという胡散臭い仕事は雑務と変わらないようだった。
「んなこと云っても……」
「むしろ、どうしてそんなにそわそわしているんだ? おれにはそっちの方が不思議なわけだが」
「いや、今日は珍しく人の出入りが多かっただろ」
「多いといっても、近々処刑される予定の囚人がひとりに……女中と高級娼婦に、騎士団長様じゃないか」
「おかしいだろ。組み合わせがバラバラだ。娼婦は囚人が呼んだとして、女中さんはこの牢獄の専属人たちのご同輩だって考えても……囚人を連れてくる組み合わせじゃない。それに、どうして後から騎士団長がやってくる?」
「おれに訊かれてもな」
「なんだか、嫌な予感がする。嫌な予感が……」
年老いた同僚とは対照的に、若い兵士は冷や汗を流し出す。
そのとき、枯れ草が擦れる音がした。
ふたりは弾かれて音の方を向く。不穏な話をしていたためか、門番の槍を構える動きは俊敏。
賊の集団がでたとしてもふたりだけで拮抗できそうなほどに完璧に訓練された所作。
だが、そこにいる者を見て躯から力を抜く。
枯れ草を踏んだのは、幼い少女のふたりだった。
薄着で肌を大胆に晒した焔色の髪をした少女と、腰まで届く漆黒の長髪と黒いドレスを着た少女。ふたりは太陽と月のように対照的で、そしてこの場にはまったくもって似つかわしくない組み合わせだった。
こんな時間でなくとも、この牢獄は街の人間が近づくような場所ではない。そんな場所にふたりの少女がやってきて、門番は戸惑った。
そこへ、にこり、と短髪の少女の方が兵士に微笑んで明るく声をかける。
「あのー、あたしたち、ここの人に呼ばれてお仕事に来たんですけどぉ」
「し、仕事?」
若い門番が反応すると、彼女は頷いた。
「そうですよぉ。あたしはレリアっていうんですけど、夜の相手をしろって云われて来ました」
「ああ、そういえば、今日はひとり娼婦がやってきてたな……」
「あ、それは先輩ですねー。あたしたちも同じ所から呼ばれてきたんですよぉ」
もうひとりの門番が頷いた。
「なるほど……」
確かに、夜中にこんな格好で出歩く女の子など、そういう仕事をしている者くらいだろう。しかも、こんな所までくるのは。
大方、囚人か他の兵士が呼びつけたに違いない。この刑務所には、娼婦とおぼしき者が何人も出入りしていた。兵士たちが控え、囚人たちを捕らえる牢獄としては実に規則の緩い場所だったのである。
レリアを見てそう判断した年老いた門番が黒いドレスの少女の方へと向く。
「そっちの子もか?」
「はい、そうですよー。ほら、ギヨたん、挨拶して」
「……ギヨたんじゃない、アンナマリア」
ぼそっ、と少女が呟いた。小さいが、よく通る声だ。隣の少女と比べて見た目は暗いが、声はどもることもなく自然と耳朶に吸い込まれる。
「ちょっと無愛想な子ですけど、仕事はちゃーんとこなせますからね」
「へえ、なるほど。それじゃあとっとと中に……」
「ま、待てよ。それは無防備すぎないか? さすがに、証明書でも見せて貰わなきゃ信用できないだろ」
臆病な気質から出た言葉だったが、至極当然の意見だった。表向きは閉鎖され、正式な刑務所としての機能を果たしていない場所だとしても、簡単に訪問者を受 け入れることはできない。今日やってきた者たちは全員が身分を証明できるものを持っていたから立ち入りを許可されたのである。
それにレリアは目を大げさに見開いた。
「ええっ、あたしたちそんなの貰ってませんよ!」
「あー、そりゃ仕方ないな。で、誰が君たちを呼んだんだ? そいつを連れてきてやるよ」
「うーん、それよりもぉ……」
レリアは顎に指を当て、年に似合わぬ妖艶な目つきを兵士に送る。
「躯で証明した方がはやいですよね?」
老いた方の兵士に、そういってレリアは抱きついた。
「へえ、それはまた奉仕の精神が旺盛なことで……」
上目遣いのレリアと目があって、ささくれた頬が薄く笑みを形作る。相変わらず余裕のある仕草だったが、目の奥には淫魔の香りによって火をつけられた情欲の炎が燃え上がっていた。
「おいおい、こんなところで……」
突然のことに、残された門番のひとりが慌てて上擦った声を発する。ふたりの兵士に槍を構えたときの名残は最早なかった。
その兵士の服の裾を、アンナマリアが掴む。思わずふりほどこうとして、兵士は少女と目があう。
それだけで、アンナマリアの深淵な瞳に、兵士の意識は吸い込まれるように魅了されていた。
レリアは膝をつくと、男のズボンを脱がしにかかった。細い指先は慣れた手つきで動くと、あっという間にペニスを月夜の下に導き出す。両手の指が絡みついて、芋虫のような柔らかさだった陰茎は膨張した。
両手からはみ出るほどに大きくなった男のペニスにレリアが興奮で頬を赤らめる。
「あはっ、おじさんのおっきい……。娘さんと同じくらいの女の子でもこんなにガチガチにしちゃうんですね」
両手でペニスをゆっくりと擦り、エラばったグロテスクな亀頭を見つめながら訊いた。
男の一物は体格に見劣りしないもので、レリアの小さな手では握っている手の親指と中指が触れられないほどである。しばらく洗っていないのか鼻につく刺激臭 を発するペニスは年相応に使い込まれているようだった。今まで何人の女性の膣をかき回してきたのかわからぬペニスが、レリアの丁寧な手淫によって掌の中で 脈打つ。
「いや、おれに家族はいないんでな。娘なんてこさえる前にかみさんも死んじまった。確かに、子供がいたらお前くらいの年頃か……」
「へえ、じゃあ遠慮も罪悪感もいらないですね」
にこりとして、レリアが亀頭を一度舐めてからそれを口で銜え込んだ。口内に広がる臭いに喉を鳴らして、舌を思い切り亀頭にこすりつける。
ずるり、と力強く尿道ごとなぞる舌。
唾液をまぶしながら亀頭に累積した垢を舐めとるレリアの舌の動きに、溜まらず男も唸った。余裕のあった表情が快感でこわばる。
「う……っ、娼婦も遠慮なんてするんだな……」
「そりゃ、しますよ? だってぇ、もうおじさんはあたし以外ではイけない躯にされちゃうんですから」
「なに……」
何事か言い返そうとするが、直後に下腹部へと与えられた刺激で二の句を紡げなくなった。
唾液をたっぷりと含んだレリアの口が、男の凶器じみたペニスを呑み込んでいた。顎は外れそうなほど開かれ、亀頭が喉の奥を突いている。それでも入りきらないほど、男のペニスは大きかった。
しかし、レリアは苦悶の表情は浮かべない。大好物を頬張っているように、一心不乱に舌を動かした。
「んっ、んふっ! ちゅ……はぅ、あん……んっ」
亀頭を締め付ける喉奥の感触は膣と同じで、舌と頬肉、口蓋は女性器にはない感触でペニスを責め立てた。くるくると陰茎をなめ回す舌と、唾液で濡れたすべすべの頬肉が雁首を愛撫する。上顎の細かいくぼみはまるで襞となってペニスを擦った。
「お、おおおお……っ」
「ほら、気持ちいいれしょう? もっとあたしで感じてね、――お父さん」
男のペニスを口から離さずに、レリアは茶目っ気たっぷりに云った。
少女は何度も何度も頭を上下させてペニスを刺激する。上目遣いに男を見る目は献身的で、介護されているような気分を相手に与えた。
「ここ、こんなに膨らんで苦しそう……早くレリアで気持ちよくなってね」
髪を揺らしながら、少女は陰茎に唇を這わせ、肉の間に隠れた汚れひとつとして見逃さんとする執拗な丁寧さでペニスに吸い付く。
「娘……娘……」
「そうだよ、レリア、お父さんのためにがんばるよ?」
くすっ、と微笑んでレリアは我慢汁でだらしなく濡れたペニスをしゃぶる。
男は徐々に快感で意識が朦朧としてきた。靄がかった視界はレリア以外なにも見えなくなる。
「お父さん……お父さん……」
何度も呼びかけられる、淫靡に巨大な魔羅をなめ回す娼婦。――いや、愛娘。
急激に男の中で背徳感という名の快楽がわき上がった。
何度も女性を鳴かせたペニスを一生懸命に気持ちよくしようとする娘であるレリアの姿と与えられる快楽の凄まじさに、男はこみ上げるものをとめることができない。
「ああ、駄目だ、駄目だ、レリア……それ以上はもう……っ」
「我慢しちゃう方が躯に毒だよ。だから、ねえ。早く苦しいの全部出しちゃって……この中にあるの全部レリアに」
小さな手が男の陰嚢を包み込む。人肌のぬくもりが冷え切ったそこを暖める。娘に抱きしめられたと錯覚するぬくもりが躯を包み込み、男は親身な奉仕によって絶頂を迎えようとしていた。
「ここにある精液、全部あたしに頂戴……他の人にあげてた精子、全部」
ペニスを銜えながら淫蕩に誘惑してくる娘に、男は理性を忘れた。
「イって……お父さん?」
「う、うおおおおおおおおおおおおおっ」
びんっ、と跳ねてレリアの口から飛び出したペニスはその勢いのままに射精した。
溜まっていた白濁が鉄砲水のようにレリアの顔にぶちあたった。
「あふっ」
眉間に当たって鼻をなぞり落ちていく白い粘液。青臭い精液を男は何度も娘の顔に吐き出した。
熱い白濁液に顔を汚されながら、レリアは陶然とする。
「すごい……一杯でてる」
顎からしたたり落ちる精液を手で受け止めながら、レリアは口元にたれてきた精液を舌で掬いとると喉を鳴らして呑み込んだ。
「臭いも味も、とっても濃いよ……娘のあたしに興奮してくれたんだね? うれしい……」
肩で息をしながら呆然と見下ろしてくる男に、レリアはほほえみかける。
「でも、こっちはまだこんなに元気だね」
唾液をすり込まれてマスケット銃のように光るペニスにレリアが触れた。指の刺激に男は息を呑む。
「じゃあ、まだまだしてあげる……」
そういって、レリアは男の腰に体重をかける。射精直後で気が抜けていた男はあっさりと地面に尻餅をついた。
レリアは立ち上がると、スカートをつまんで下着姿を男に見せつける。ショーツはじんわりと湿っていた。
指をショーツの間にいれて、ずり降ろす。すると、片足を上げて脱いだショーツを男のペニスに落とした。
レリアがショーツの上からペニスを握り締める。想定外の光景に、男は釘付けになった。
「うふ……女の子の下着って布がすべすべして気持ちいいんだよ?」
その手がショーツごとペニスを掴んだまま、ぬるく動き出す。
しゅっ、しゅっ、と先程までレリアの着ていたショーツがペニスを包み込んでなで上げる。上等なきめの細かい布の縫い目ひとつひとつが、敏感となったペニスにはわかった。
娘の愛液でしめったショーツが男の精液を吸い取りながら、ペニスを拭っていく。その倒錯的な状況は、ますます男のペニスを大きくさせた。
「ああ、そんなこと……娘の下着でなんか……」
「いいんだよ、遠慮しなくても。お父さんがあたしの下着に興奮したって……嫌だなんて思わないよ? だって、こすりつけられただけで、こんなに気持ちよさそうなんだから」
わざわざ口に出すレリアに、男は嫌が応にもその異常な状況を脳裏に刻みつけてしまう。
気持ちよくなってはいけない、と理性が歯止めをかける。その焦りが、男の性感をよりいっそう高めた。
「お父さんのおちんちん、あたしのパンツの中でどんどん硬くなってるよ。やっぱり、気持ちいいんだよね、娘のパンツでこすられちゃうのが」
「あ、あああ……!」
絶望的な表情になる男に、レリアは一押しとなる悪魔の誘惑をした。
「あたしのパンツの中で、|射精|(だし)しちゃえ」
「う、うおおおおおっ!?」
ショーツの中でペニスが爆発した。
どぷんっ、どぷんっ、とペニスが射精する。
娘の下着の中での射精の快感が、男の脳天からつま先までに背徳の稲妻となって駆け抜けた。下半身が震えて、精嚢が作り出したありったけの精液を吐き出す。その激しい精液の勢いに、愛液に濡れていたショーツが風船のように何度も膨らんだ。
心ここにあらずといった雰囲気で射精の快感に酔っている男から、レリアはショーツを取り上げる。
人差し指と親指でつまんだショーツは精液をたっぷりと吸い込んでいて、最初とは比べものにならないくらいに重い。精液をしたたり落ちさせるショーツをレリアは顔を赤らめた。
「もうっ、こんなに出しちゃって……。これじゃあ、あたしのパンツが妊娠しちゃうよ」
はむっ、とショーツを銜えて精液を吸うと、すぐに放り出す。
「どうせ妊娠させるなら、こっち……だよ?」
膝立ちになったレリアは両手でスカートをまくると、うっすらと産毛のような毛しか生えていない未成熟な女性器を男の前に見せつけた。そうやって成長しきっていないものであるのに、赤々とした秘所は男欲しさに濡れた口を開いている。
レリアは男の首に腕を絡みつかせながら抱きつく。お互いの息がかかる距離で見つめ合いながら、ゆっくりと腰を下ろした。
二度の射精を経ても頂点を向いたペニスに女陰が触れる。
「ん……っ」
吐息を洩らしながら、レリアはそのまま腰を沈めていく。
幼い少女の躯が受け止めるにはあまりに大きなペニスは、少女の躯を引き裂いてしまいそうだった。男は止めようとしても、亀頭を圧迫する膣口の刺激によって声が詰まった。
「ん……んっ!」
ぐっ、とレリアが腰に力を込める。そうすれば、愛液に濡れた膣が亀頭を呑み込んだ。
「あ、ひゃあっ!」
「うぐっ、ああ……っ」
「お父さん、苦しい? でも、入ったよ……おちんちん。もっと、奥まで、きて……」
痩躯を揺らして、レリアはさらに腰を埋めていく。一度入り口に入れば、後は奥へ奥へとペニスを導いた。
全身に珠の汗を浮かび上がらせて、レリアの躯がペニスを奥まで呑み込む。
「ああっ! 入った……奥まで、お父さんが来てるよ……すっごくおっきいのがっ」
男の首に抱きついたまま、レリアは苦しげな顔で嬌声をあげた。
己の一物によって目と鼻の先で悶える娘の姿に男の中で完全に箍が外れた。
レリアと唇を重ねる。舌と舌を絡める蕩けるほどの深いキス。
ふたりは興奮に昂ぶって、向かい合いながら獣みたいに相手の口を求める。その対面して座り込んだ状態のまま、ふたりは腰を振った。
「ふっ、んっ、ああっ!」
レリアの白い肌が何度も何度も男の腰を叩きつけられ、赤く腫れ上がる。その痛みすら感じないのか、レリアも夢中になって腰を振っていた。
ぎゅうぎゅうにペニスを締め付ける膣は、その襞を余すところなく肉棒に絡みつかせる。愛娘の熟れた蜜壺の心地に、男の頭の中は完全に真っ白になっていた。 もう、娘のこと以外なにも考えられなかった。自分のペニスから子種を絞り取ろうとする女としてのいやらしさに意識は埋もれていった。
「お父さん……頂戴! お父さんの精子頂戴! いっぱい、いっぱい精液注いで!」
狂ったような懇願は興奮を衰えることのない速度で空へと誘っていく。
男はレリアの、娘の腰を掴んで突き上げる。ペニスに絡みついてくる膣の感触は今まで抱いたどの女よりも、妻よりも遙かに馴染んでいた。このまま肉棒と一緒に躯が溶け出してしまいそうな暴力的な快感。
「ああ……っ、あああああああがああああああ――――ッ?!」
耐えられようわけもなかった。
娘の膣内で男のペニスが精液を吐き出した。精子をたっぷりと含んだ精の塊を子宮に撃ち出しながら、男は腰を止められない。この娘の躯が何よりも愛おしい。
射精しながら与えられる快楽に狂った男のペニスは止まることのなく射精を続かせる。
男はとっくに人間らしい思考を放棄していた。今はもう娘の躯が与えてくる極上の快楽を享受するだけだった。
「あは……ごちそうさま……お父さん?」
全身に広がっていく精を満喫して、レリアは動かなくなった男に妖しく語りかけた。
「ふう、まずひとりっと」
ん、と息を吐きながら腰をあげたレリアは満足気に深呼吸をして男から離れた。門番の男は地面に倒れ、もう身動きひとつとらなかった。
「ギヨたーん、そっちは……」
レリアはアンナマリアたちの方へと振り返り、一度言葉を詰まらせる。
「……大丈夫、だったみたいですね」
漆黒のゴシックドレスをまったく乱していないアンナマリアがそこに立っていた。彼女の足下にはもうひとりの門番が倒れている。レリアに弄ばれた門番と同じ末路をたどったことは想像に難くなかった。
衣服をまったく乱さずに相手を倒す、その手際の良さは以前のアンナマリアにはなかったものである。これまでは躯の並外れたスペックで相手を圧倒していただ けなのに、そこへ技量が追従している。行為に慣れた、という言葉だけでは済まされない。前日と今日では、まさに別人だ。
成長というよりは、並外れた環境適応能力による技能の吸収と云った方が正しい。その生態にレリアは期待と不安がない交ぜになった感情を抱く。続いて、嫉妬。
「……って、なに考えてるんですか、あたし」
頭を振って感情を追い払う。別に、アンナマリアに嫉妬する要素はない。そのはずだ。
レリアは淫魔で、だからひとりの男に執着しすぎるといったこともないのである。だから、断じて嫉妬する原因は彼が原因ではない。自分に言い聞かせながら、アンナマリアに声をかけた。
「この門番の人から鍵見つけましたよ。ホント、管理がずさんですねぇ……だから、はやく行きますよぉ」
「……わかった」
口を尖らせたレリアに声をかけられてうなずき、足を踏み出す。
それが、急激に力を失う。足から力が抜けて、アンナマリアは地面に膝をついていた。
「――っ」
アンナマリアは頭を抑えて苦悶に声を洩らす。
「ちょ、ちょっとギヨたん? どうかしたんです?」
さっきまでの不機嫌さはどこへやら。いきなり倒れたアンナマリアに、レリアは慌てて駆け寄った。
しかし、アンナマリアは首を振って差し出される手を断ると、おぼつかない足取りで立ち上がった。
「別に、なんでもない。ちょっとつまずいただけ」
「つまずいたって、そんな感じじゃ……」
それに、とレリアは指摘できないことを心の中で呟く。
――顔、真っ青じゃないですか。
「なんでもない……本当になんでもないの」
顔を背けて、アンナマリアは門へと歩き出す。その言葉が嘘であることは誰の目にも明かだったが、頑なに否定する彼女にレリアはこれ以上追求することができなかった。黙ってアンナマリアの背中に続く。
レリアが門の錠前に鍵を差し込むと、カチリと音を立てて解錠を知らせる金属音が落ちる。ふたりが分厚い木の門を押せば、蝶番を軋ませながら門は開いた。
壁にかけられたランプの明かりで橙色に照らされた、闇の沈殿する牢獄の中。
門の開く音に反応したのか。通路に人の気配が集まってくるのをレリアは感じた。
牢の見た目に反して、思ったよりも常駐している人の数はずっと少ないようだ。それでも、牢獄ひとつを相手どるのは並大抵のことではない。
男たちの気配に、レリアは興奮で唇をなめる。
「なにもないっていうなら……行きますよ、ギヨたん。全員、吸い取っちゃいましょう」
「やってみせる」
こうして牢獄ひとつを陥落させるべく、レリアとアンナマリアは通路の奥から現れる男たちに向かっていった。
牢獄といっても、ここは既に廃棄目前の場所であるようだった。
「ふう……これで、えっと、何十人目でしたっけ」
まあいいか。と自分のつぶやきに結論づけて、レリアは自分の掌で果てて倒れた男から離れる。彼女の背後にある通路には死屍累々と精液を吐き出した男たちが床に伏せていた。
乱れた服装を直そうともせず、控えめに膨らんだ胸を露出したまま、レリアは手についた白濁液を舐めとる。精液に含まれた多量の栄養素は、淫魔の躯に馴染み易い。そのため、摂取するだけで全身に活力が漲った。
「こんなに精液を搾ったのは何年ぶりですかねぇ……質より量も悪くないです」
レリアは秘所から床に流れおちる精液を手で受け止めて、舌で舐める。幼い躯を精液まみれにしてのそんな仕草は、男を妖艶で幼い魅力の虜とするにはあまりあった。
「ん……んっ」
声の方にレリアが振り返ると、そこでは四つん這いになったアンナマリアが後ろから男に突かれていた。
フリルをあしらった黒いドレスのスカートをはしたなく捲り上げられたアンナマリアは、白い臀部が赤くなるまで男に腰を叩きつけられている。何かに取り憑かれたように男が少女の膣にペニスを出し入れすると、漆黒の長髪が揺れて甘い芳香が漂った。
「おおあ……ぅあああああっ!」
絶叫して男がアンナマリアの中に精液を吐き出した。
そうして、糸が切れたマリオネットのように男は仰け反って倒れる。白目を剥いた男の下半身は痙攣しながらアンナマリアの膣に精液を一滴残らず吐き出した。
「は、あぁ……んんっ」
アンナマリアは立ち上がりながら男の一物を引き抜く。成長しきっていない未成熟な性器には渇く間すら許されない愛液と精液の混じりあう混合液がべったりと付着していた。
さすがに体力のある兵士たち、それも砦兼牢獄にいる全員を相手にしてしまえば、急激に成長しているアンナマリアですら消耗を余儀なくされた。これが国にい るただの市民であるならいくらでも相手にできるのだが、そこは戦闘訓練を受けた人間であるだけのことはある。なにをするにも力強い限りだ。
さらにアンナマリアが不利な点をあげるとするなら、淫魔であるレリアと違って精液での体力回復が望めない点だ。栄養源にはある程度なるものの、淫魔のような急激な回復ではない。人間のそれの範疇である。
「そろそろ限界ですかぁ、ギヨたん」
「……まだまだ、問題ない」
からかう声音のレリアの言葉を突っぱねて、アンナマリアは廊下の先を行く。レリアもその一歩後を続いた。
ふたりがこの牢獄にやってきてどれほどの時間が経ったのか。疲労はしているものの、ふたりの手腕は男なら舌を巻いて手も足も出せないほどで、既にほとんどの兵士らしき者たちを撃退していた。
レリアとアンナマリアの靴音が廊下に反響する。人数を狂わせそうな跳ね回る音は不気味だ。
そこでふと、レリアがアンナマリアの背中を見る。
ここまでは休むことなく男を手玉にとっていたためになにも聞くことができなかったものの、こうして小休止を置いてみるとレリアの中で疑問が首をもたげ始めた。
どうして、アンナマリアはここにやってきたのだろう?
レリアがこの牢獄に来たのは、云うまでもなくジョゼフが捕まってしまったからである。彼に対してどんな感情があるかは一先ず置いておくとしても、知り合いが同族に不当な拉致を受けたとあっては納得いくわけがない。
ただ、アンナマリアにはどんな理由があってここにいるのか。国家殲滅の復讐をかかげるほどの断頭台である彼女が、人を助ける道理がいったいどこにあるのだろう。
「どうして」
「ん……?」
「どうして貴女はここに来たんです?」
返答はなかった。云いあぐねてでもいるのか、アンナマリアは沈黙している。
「貴女がジョゼフくんに執着する理由が、あたしにはわかりませんよ」
答えが返ってくるのを待たずに、レリアは踏み込む。
「今朝だって、別れるときに喧嘩してたじゃないですか。しかも、原因はジョゼフくんにも結構ありますし。わざわざ自分を危険に晒してまで来るようなことじゃないでしょう」
「レリアもここに来てる。どうして?」
「あたしの話はしてません」
聞き返されてもレリアは動揺しなかった。心が巌のように硬くなっていた。
だから、遠慮無くアンナマリアに踏み込める。
「もしかして、自分の好きな人の弟だったから、なんて。そんなことのためだけなんです?」
「……っ」
何事か言い返そうとして、結局アンナマリアは意味のある言葉を紡ぐことができなかった。図星だったのか、どう返せばいいのかわからなかったのか。レリアの追求にアンナマリアは無力だった。
「まあ、淫魔のあたしが云うのもなんですけど。もし別の男のためにジョゼフくんを助けて満足しようっていうんなら、今すぐ帰って欲しいですね。正直云って、目障りです」
「それは、その」
初対面からしてふたりは良好な関係とは言い難かったが、こうしてはっきりと拒絶の意志を見せられたのは初めてだった。アンナマリアは人と仲良くしようだなんて一切考えていなかったが、こうして面と向かって宣言されると予想以上に衝撃を受けてしまう。
それとも、衝撃を受けてしまうほどに今の自分は心に隙があったのか。
「……教えて。レリアがジョゼフを助けにきたのは、なんで」
今度は話を逸らすためのものではなく、純粋に知りたかったからアンナマリアは訊ねた。それがレリアにも伝わって、彼女も誤魔化すことはしなかった。
「そうですね……えっと、うん、……もうっ、どうしてあたしまでこんなに恥ずかしいこと思わなきゃいけないんですか」
「なに?」
「彼を、あー……放っておけないからです! これ以上云わせないでください!」
さっきまで平気で男たちを弄んでいた様子からは想像もつかない初心な反応をレリアは見せた。そんな様子だけで、アンナマリアにも充分意図することは伝わった。
「そっか……」
頷いて、またしばらくアンナマリアは黙った。といっても、いつ誰がやってくるかわからない状況である。黙っていたと云ってもものの数秒程度だ。
「わたしが来たのは、レリアの云ったような理由もあるの。もういないあの人の面影を見たから、それで、ここまで来ちゃった」
「なら……」
「でもね、それだけじゃないよ」
アンナマリアはレリアの言葉を遮る。
「あんなことを云ってくれたのは、初めてだったから。迷惑だと反発しちゃっても、あんなに優しい言葉をかけてくれたのは……本当に初めてだったから。しかも、わたしのせいかもしれないなんて知ったら、もういてもたってもいられなかったの」
アンナマリアはジョゼフとの口論を思い出す。なにも知らないで、という怒りは今もある。一言どころかもっと文句をいってやりたいと思う心情はずっと残って いる。けど、それを伝えられないでずっと胸にわだかまらせておくのは嫌だったし、それに、嬉しくなかったと云えばそれも嘘になるのだ。
断頭台か ら人になれるようになったとき、アンナマリアに味方と呼べる人はいなかった。気を一時でも許せる相手もおらず、愚痴や不安をこぼせる場所もない。自身の裡 に溜まるフラストレーションを発散させる手段を一切持っていなかったのだ。箱の鼠と一緒で、暗い世界でひとり蹲っているしかない。
自身を実体化 させた魔女イザベラとて、面識があるだけで味方と呼ぶには分不相応である。彼女はトリックスターで、観察者だ。舞台の仕込みをする機械仕掛けの神であり、 自分の用意した世界で役者がなにを演じるか楽しむ観客なのだ。人の形をしていながら、雲の上にいるような存在。頼ろうなどと安易に思えるわけがない。
国家殲滅なんていう思想がそれに拍車をかけて、アンナマリアはいつだって孤独で、自分だけが唯一信用できる存在だった。
なのに、あんな言葉を。あんな顔でかけられてしまったら。どうしたらいいのか判らなくなってしまったのだ。
「わたしのやっていることとか、相容れない相手だっていうのは判ってるの。でも、このまま何も出来ないで終わってしまう方が……ずっと嫌だった」
「まったく、断頭台っていうのはそんなに不器用でつとまる仕事なんですか? 呆れちゃいますよ、ホントにもう……」
レリアは苦笑いを浮かべた。ただ、今までのように含みはない、清々しさすらある苦笑だ。
「それともうひとつだけある」
「へえ、それはなんです?」
「直接わたしを狙ってこない腰抜けたちの腰を本当に抜かしてやろうかなって」
アンナマリアがレリアを振り返って、愉快気に微笑んだ。そんな彼女が面白くて、レリアもつられて噴き出した。
「あっはは! 意外と大胆なこと考えてるんですね、ギヨたん。いいですよ……ならそれにあたしも乗らせてもらいます。人の獲物に手を出す奴は、馬に蹴られて地獄に落ちろ、です」
「勝手にすればいい。あと、最後にひとつだけ」
「はい?」
「ギヨたんいうな」
ふたりはさらに奥へ奥へと進んでいく。兵士たちは粗方蹴散らしてしまったのか、あとは静かなものだった。
「それにしても、これはいったいなんなんです?」
歩みを止めないで、レリアは左右にある牢屋を見回した。
鉄格子の中はほとんどが空だったが、たまに囚人が投獄されているものがある。
真新しいシーツのベッドと、敷居で隔離されたトイレ。しかも牢の中はそこそこの清潔さを保っている。この国の人間はあまり清潔にしようという意識の薄い人種である、とレリアは認識していたので、きちんと掃除されている囚人の居住環境には違和感があった。
牢の中にいる囚人たちは、どれも大人しい。場に似つかわしくないふたりを見かけても眉ひとつ動かさなかった。ただただぼんやりとしている。
「……まるで、ペットの小屋みたい」
アンナマリアが、その不気味な光景の感想をつぶやく。
「あながち、それ、正解かもしれませんね」
周囲を見渡しながら、レリアは賛同した。
「おおかた、淫魔たちが廃棄予定の牢獄を使って食料庫としているんでしょう。生かさず殺さずの愛玩具。まさしくペットですね」
「悪趣味」
「その通りで……って、なんでそんな目であたしを見るんですかぁ!? 同じ淫魔でもしませんよ、こんなこと!」
疑いの眼差しで見られて、レリアは慌てて反論する。
ガチャッ、とそのとき金属が擦れる音が弛緩した空気を震わせた。
ふたりが身構える。
周囲にあった牢屋の鉄格子が開いていた。
中から、おぼつかない足取りの男たちが現れる。
虚ろな目をした男たちだったが、どれも躯つきは囚人とは思えないほどしっかりとしている。
現れた囚人の数は、八人。ここまで兵士たちを打ち破ってきたふたりにしてみればたいした数字ではない。
「伏兵、ってところでしょうか。この程度で止められると思われるなんて、あたしたちも舐められたものですね」
「関係ない……結局、吸い殺しちゃうんだから」
「あはっ、それもそうですね!」
自分へと手を伸ばしてきた男の腕を掴んで引き寄せると、レリアはそのまま唇を奪った。柔らかい唇を触れさせ、舌を入り込ませる。口の中で動き回る小さな舌に、男の背筋がビクンと震えた。
「キスは得意なんですよ。みんな、すぐにイってがっかりさせないでくださいね?」
くすりと笑って男を誘うと、四人の男がふらふらと蜜へ近づく蝶のようにレリアに群がっていく。
残りの四人は、なにもせずともアンナマリアの方へと吸い寄せられていた。
「……瞬殺してあげる」
挑発的な笑みを浮かべて、アンナマリアも男たちを受け入れるように両腕をゆるゆると開く。例え妖しげな者たちであっても、相手が男ならもう負ける気がしていなかった。
男のひとりがアンナマリアを背中から抱きしめる。手がドレスの上から薄い胸を撫でて、お腹の方へと降りていく。意識があるのかどうかも端から見れば定かではない男の手の動きは、それでも女性に慣れたものだった。
アンナマリアの口から吐息が洩れる。
「えっ?」
躯が反応したことに、彼女は自分でも驚いた。男からの愛撫で感じたことは今までなかったのである。
動揺している間に、三人の男の手もアンナマリアを捕まえていた。
男たちの手のひとつが下半身にのびた。スカートの中にいれられた手が秘部をなぞる。ショーツ越しに這っていく指の手つきに、肩が跳ね上がった。
「ひゃっ!? な、なにこれ……」
その疑問に、同じく快感で躯をよじらせるレリアが答えた。
「う……ちょっと油断してました。この人たちは淫魔たちのペットなんです……彼女たちを悦ばせるための方法を骨の髄まで叩き込まれているんでした! それこそ、性技以外のことは忘れてしまうくらいの勢いで!」
アンナマリアのショーツを下げて、男の指が小さな割れ目に入り込む。与えられた刺激に、躯が前に傾いだ。
「ふぁっ! そ、そんな……それだけでこんなに簡単に……?」
「い、 淫魔と何度も交わったら嫌でも巧くなりますよ、しかも覚えさせることを前提にしていたら。快感に耐性までできちゃって、生半可な刺激じゃ感じなくも……ふ つうは淫魔と一回もすれば死んでしまうから考慮外ですけ、ど……ひゃっ、ちょ、ちょっと人が話してるときに手が早……っ」
淫魔であるレリアも頬を紅くして、男の愛撫に声をあげた。
予想外の伏兵だった。ふたりにとっての敵は、あくまでも他の淫魔たち。牢獄攻略の際に躯を重ねる男たちのことは単なる障害であり、いかに時間と体力を温存して突破するか、の計算にいれているものであったのだ。
アンナマリアを囲う男たちが、虚ろな目のままに下半身を露出する。現れた一物はどれも既に勃起していた。使い込まれた凶悪な代物を向けられて、思わずアンナマリアは躯を震わせる。
長い髪の毛を掴まれて、顔をペニスに近づけられた。汚臭を漂わせる肉棒にアンナマリアの視線が集中すると、男は小さな少女の口の中に亀頭を押し込んだ。
「んぐ……っ」
いきなり口内にいれられたモノの大きさで、苦しさに目を細める。その間に、背中側からアンナマリアに抱きついていた男がそのドレスに手をかけていた。ずるり、と果物の皮でも剥ぐようにドレスが降ろされる。ぴんと淡い色の突起をもった、新鮮な裸身がさらけ出された。
わずかな膨らみの胸を男の手が撫でる。正気を保っていないように見えながら、一番敏感なところには触れない動き。今まで無理矢理するか、されるかしてきたアンナマリアにとって、男から焦らされるのもまた初めての経験だった。
「んんっ、ふ……じゅう……っ」
口の中で暴れるペニスと胸を這う手つきに脳が痺れる。アンナマリアが反撃しようする前に、今度は残りのふたりが動いた。
ひとりがアンナマリアの下で寝転がると、その細い腰のくびれを掴む。腕によって引き寄せられる先には、物欲しげに脈打つペニス。
亀頭と女性器が触れて、濡れたアンナマリアのそこは容易く男自身を呑み込んだ。
「んぐっ、んっ、んーっ!」
熱く、硬くなったペニスに跨らされて、アンナマリアの目が大きく開く。口と、腰の下から突き上げられてくるペニス。ここに至るまで相手にしてきた屈強な兵士たちの肉棒とは違った動き。そして、二本だけでは終わらない。
ずっと後ろから抱きついていた男がアンナマリアの小さなお尻の谷間に陰茎をこすりつけた。臀部に触れた熱い肉の感触にきゅっと穴がしまる。そこへ男は亀頭を押しつけ――力尽くで押し込んだ。
「んあふ……っ」
アンナマリアの秘所から流れ出した愛液と、ここに来るまでに受け止めた兵士の精液で濡れていたアナルは男の肉棒を受け入れた。すぐに腰が動き出して、お尻に男の腰がぶつかる。
穴という穴を塞がれたアンナマリアの躯を男の肉棒が暴力的に突き上げた。
自分より一回りも二回りも大きな男に挟まれて腰を振らされ、口内をペニスに蹂躙される。いやらしい粘液の混ざる音と肉と肉がぶつかる音が牢獄の中で反響した。
男の腰の上で跳ねまわる少女の躯に、最後の一本が押しつけられる。いれる穴がなくなったペニスは、亀頭をアンナマリアの小さな胸にこすりつけた。
我慢汁を胸にすり込むペニスを見て、アンナマリアはゆっくりと手を伸ばす。そのペニスを掴むと、首を振って口内の肉棒を吐き出した。
「どうせなら、二本とも……」
ふたつのペニスを掴んで、アンナマリアは一度に両方の亀頭を口にくわえた。
熱に浮かされて口の周りを唾液まみれにしながら、アンナマリアは長髪を振り乱して熱心に亀頭に吸い付く。陰茎の部分は手でしごきあげると少女から与えられる快感にペニスがさらに膨れあがった。
レリアの方も、状況は似たようなものだった。こちらは仰向けの体勢にされて膣とアナルにペニスをねじ込まれ、口で肉棒を慰めている。男の腰が動いて亀頭が膣を掻き分ける度に幼い躯が激しく揺れた。
「う、動きが速すぎますよぉ……そ、そんなんじゃ……」
かすれ気味の声は男たちに届いていないのか、理不尽にも益々腰のペースは増していく。膣肉を太いペニスが掻き分けていき。
「そんなのじゃ……あっという間にイっちゃいますよ?」
レリアがくすりと笑って、口をすぼめながら腰を捻った。頬肉が中のペニスを圧迫し、膣とアナルは捩れて中のペニスを思い切り締め付けた。
瞬間、
どぷっ、どくっ、どくん、と四本のペニスがそれだけの動きで一気に限界へ達した。
二本のペニスが弾丸のように吐き出した精液がレリアの口から飛び出して口周りを生クリームみたいに汚し、顎から首もとへと流れ落ちる。秘部とアナルはきゅっと締まって、ペニスから吐き出され続ける精液を一滴たりとも逃さなかった。
「あはっ、ほらほら、一杯出してくださいね……ペットちゃん?」
淫魔たちに鍛えられた男たち。
忘れてはいけないのは、淫魔によって性に耐性ができているといっても所詮ペットとしてしか使われていないという点だ。
性技が多少巧くとも、飼い主からしてみればかわいいかわいい愛玩動物でしかなく、よって男たちは少女たちにペニスを挿入した時点で既に勝負は決していた。
「ん……イく? ならイかせてあげる……死ぬまで」
アンナマリアはペニスをくわえたまま上目遣いで男たちに微笑むと、陰茎を扱く手の動きを早める。少女の小ぶりな手はマッサージでもされているような適切な力加減でペニスを握り締めて、亀頭を舐める舌と唇は膣と同じ吸い付きで、それに男が耐えられるわけもなかった。
「はい……終わり」
悪戯な口調で、思い切りペニスを握り締め、
二本のペニスが跳ね上がり、アンナマリアの顔に向けて思い切り精子を噴き出した。
目を細めたアンナマリアのからかうような、それでいて冷ややかな面立ちを白濁とした子種が汚す。熱い粘液を顔に吐き出されながら、陰部とアナルを掻き分けているペニスに意識を移す。
今まで適度に緩めていた力を、一息に腰へと込める。急激に高まった締め付けの力は、気付かぬうちに限界付近で留まっていた男たちを簡単に天へと引き上げた。
「イっちゃえ」
騎乗位で腰を振っていたアンナマリアの中に、男たちは精液を注ぎ込まされる。精液を呑ませる側だと思っていた男たちは、いつの間にか精液を捧げる側へと堕ちていた。
「それで……ペットって何回くらいイけるのかな」
「さあ、試してみるしかないんじゃないですかね? ……時間もないので、手早く、ね」
アンナマリアとレリアが目を合わせて、口元を持ち上げる。
いくら女を悦ばせる知恵を身に着けていたとしても、ペニスを相手に許した時点で、男たちはただ搾取されるだけの存在となっていた。いつも、淫魔たちにされているように。
あとには吸い尽くされて乾涸らびた死体が残るのみだった。
服を整えたふたりは牢獄の中を駆け抜けていた。
ランプで照らされた廊下に長い影を作りながら、アンナマリアとレリアは奥へと向かって足を動かす。
「倒すのは難しくありませんでしたけど、絶倫すぎて時間とられちゃいましたよぉ……ほら、ギヨたんももっと急いで!」
淫魔たちの愛玩動物は徹底された体調管理でもされていたのか、吸っても吸っても精が尽きなかったのだ。ただ搾精されて、しかも長い間淫魔たちを悦ばせるた めの状態。まさしくペットと呼んで相違ない。質の良い精を放つものだから、レリアは時間があればもっと楽しみたいくらいだった。
「わたし、運動、苦手なの……!」
息を切らせながらアンナマリアは走っていた。額には汗が浮かび、男たちと交わっているときよりもよっぽど大変そうに見える。
「男の人とはあんなに運動してる子がどの口で云ってるんですか。あたしみたいに早く走れないんですかぁ?」
「それはっ、走ってるっ、じゃなくてっ、飛んでるって云うの!」
レリアが背中から生やしたボロ布のような羽根を指さして声を荒げた。アンナマリアの云う通りで、レリアは宙に浮いて滑空していた。
「あたしたちの業界では、これを走っていると云うのです」
「なんだか釈然としない……」
ない胸を張ってふんぞり返るレリアに、アンナマリアは非難を込めた視線を送った。けど、どんなに不満だろうともレリアの云う通りで、時間がないのだから走 るしかない。断頭台から人の身に変化したアンナマリアは、ひとつの事柄を除き身体能力は人間並なのだ。レリアのような便利能力はない。
急にレリアの顔付きが変わる。むっ、と眉を寄せて、この先の闇を睨んだ。
「この甘い匂いは……ご同輩の気配! ここを抜ければ、きっとジョゼフくんもそこにいるはずですっ!」
闇の奥には大きな扉があった。
ふたりは勢いに任せて同時に扉を蹴り飛ばした。
音を立てて開いた両開きの扉から中へとなだれ込む。
そこは開けた空間だった。廊下が狭いわけではなかったが、ここは壁際に並べられたランプだけでは全貌を照らすことができないくらいに、広い。
アンナマリアとレリアの目に飛び込んで来たのは、広間の中央に立っているひとりの女性だ。
髪の長い、物静かな女性である。露出を恥じるように肌を隠した衣装は聖職者のようで、牢獄には不釣り合いな姿だった。その姿にアンナマリアは意表を突かれたが、レリアはその女性の正体を一目で見抜いていた。
「絶対に気を抜いちゃ駄目ですよ、ギヨたん。あれは淫魔……かなり高位の淫魔、強欲のアワリティア……七大淫魔の、アワリティアです!」」
今までにないほど真剣な表情で警戒心を露わにするレリアに、女性は柔らかい表情で頭をさげる。
「あら、名乗るまでもありませんでしたか。さすがに、同じ淫魔ともなれば名も知られてしまっているのですね。ええ、その通り。私がアワリティアです」
ジョゼフはどうなっているのか気になってアンナマリアは早く動きたくて仕方なかったが、目の前の女性がそれをさせなかった。アワリティアと名乗った彼女の 一挙手一投足、それはゆったりとした遅さであるはずなのに、迂闊に動けないほどの威圧感があったのだ。レリアの云う通り油断をすれば、そのときにはなんら かの勝敗が決している。先程の男たちのような虚仮威しではない恐ろしさがアンナマリアにもわかるほどにアワリティアから発せられていた。
「そして、奥にいるのが色欲のルクスリアと傲慢のスペルビアです。貴方たちが中々やってこないものですから、ふたりとも奥で盛ってますわ」
アワリティアの浮かべた笑みは寒気がするほどに凄惨で、アンナマリアは胸の内側が急激に凍り付いて行くのを感じた。
広間の奥に目を懲らす。暗闇に慣れていた目が、奥の牢で動く人影を捉えた。
「ジョゼフ……っ」
その光景に目を瞠った。
男ひとりと、女性ふたりが絡み合って乱れていた。男はジョゼフで、その顔に生気はない。白目を剥いた男の躯に女性ふたりが群がっている形である。
ジョゼフの上で凜とした整った顔立ちの女性が腰を振っていた。もうひとりの女性はジョゼフの腕にしがみつきながら、胸板に舌を這わせている。
組み敷かれた逞しい躯が震える。女性の中で果てていた。離れていても香ってくるほどの精子の臭い。よく見れば、その牢にいる女性ふたりは精液まみれだった。いったい、何百回と射精すればあそこまで精子で汚れることができるのか、検討もつかない。
「いったい彼も何度目でしょうか、絶頂してしまうのは。もう痛覚どころか、全身の感覚さえあるかどうか。脳の神経も全部引きちぎれてしまっているかもしれませんね」
「離して……はやく離して!」
「そうです、ジョゼフくんを離しなさい! ただの人間を捕まえる理由もないでしょう?」
ふたりの要求に、アワリティアは笑顔のまま応えた。
「それは聞けない要求ですね。彼にはこの場にて、見せしめのためにも果てていただきます。ええ、正しい意味で果ててもらうのです」
「見せ、しめ……?」
アンナマリアの問いに首肯する。
「え え。貴女が、最近この辺りで男を吸い殺している方ですね? 困るのですよ……そういうことを勝手になされるのは。この国はどの施設も組織も掌握しました が、外国の教会に悟られると面倒なことになってしまうのです。負ける気はしませんが、対異端者用の騎士団というのもありますからね」
「だからって、なんでジョゼフを?」
「貴女にとっては、なにがしかの意味がある相手かと思いまして。どうやら、正解だったようですね?」
アンナマリアは答えられなかった。こうして危険をおかしてまで助けに来たのは事実であるし、否定するような理由はない。それに違うと云っても、ジョゼフが解放されることは万に一つも考えられなかった。
「なに、そう睨まないでください。なにも私たちは争おうという訳ではありません。貴女と……そうですね、そちらの同族さんにも提案があるだけなのです」
「あたしたちに提案、ですか?」
アンナマリアとレリアの顔を見て、アワリティアは背後の狂乱には一切目を向けずに会話を進める。
「はい。どうです、私共と手を組みませんか? そうすれば、精を啜るなとはもうしませんよ。ちょうど、この国をまわすのには三人だけでは面倒になっていたところだったので」
予想外の提案に、ふたりは押し黙った。口を開かないアンナマリアとレリアに、アワリティアは言葉を続ける。
「悪い条件ではないと思いますよ。そちらの淫魔も、どうやらあの魔女に下僕として使役されている様子。これを機に下克上でもどうです?」
「それはそれは……魅力的なお誘いですね」
レリアが薄く笑った。その表情を見て、まさか、とアンナマリアは躯を強ばらせる。しかし、そんなアンナマリアにレリアは片目をつむった。
「でも生憎と、あたしは自分の力だけで先生を屈服させてあげるのが夢なんですよ。他人の力を借りて勝っても消化不良で死ぬまで胃が痛くなっちゃいますからねー。だから、お断りさせてもらいます」
そうやって、レリアは笑顔で高位淫魔の誘いを一蹴した。
返ってきた答えに、アワリティアはわずかに表情を曇らせた。
「そうですか、それは残念です。では、ご自身がここでどうなるか……わかっていますね?」
「わかりませーん、なにされちゃうんです?」
明かに格上の同族を相手に、レリアは臆せず挑発する。
「いいでしょう。では、そちらの貴女は?」
アワリティアの目がアンナマリアの方へと向いた。
「その前に、ひとつだけ」
「なんでしょう?」
「さっき〝見せしめ〟と云った。……どうせわたしたちが承諾しても、ジョゼフは殺すつもりだったのね?」
断頭台として生まれてから数年の間、破格の人数を処刑してきたアンナマリアは悪意には特に鋭敏な触覚を持っていた。だから、ずっとアワリティアの言葉が引っかかっていたのである。
その追求に、アワリティアは一切動じずに頷いた。
「ええ、おっしゃる通りです。どちらにしろ、彼はここで死んで貰うつもりでした。たかが人ひとり、わざわざ特別視して生かしておく必要もないでしょう? 彼の代わりもまた、沢山この世にはいますから」
「じゃあ、わたしの返事も決まってる。……お断りよ、貴女のくだらない口車に乗ってやるつもりは微塵もないわ」
「そうですか、それは残念です。……スペルビア! ルクスリア!」
アワリティアが大きな声をあげて淫蕩に耽るふたりの名を呼んだ。
「もう遊びはいいでしょう? 実行させなさい」
「まったく、我はまだ楽しみ足りないというのに……」
「えー! 結局ボクは入れさせてもらってないんだよ!? こんなのあんまりだー!」
文句を云いながらも、ふたりはジョゼフから離れた。スペルビアとルクスリアが離れると、ジョゼフの躯は床に投げ出されて動かない。もうあの状態で生きていると呼ぶことすら正しいのか、言葉の定義が混乱しそうになる。
スペルビアが文句をいいつつも、指を鳴らした。すると、広間の奥から兵士がひとりやってくる。その手には抜き身の剣が握られていた。
スペルビアが、兵士に命令した。
「首をはね、殺せ。苦しませぬよう一刀でな」
さっ、とアンナマリアとレリアの顔から血の気が引いた。
「やっぱりそう来ますよね……! でも、素直にそんなこと許すと思ってるんですかっ!?」
「貴女の方こそ、私たちが素直に邪魔させると思っているのですか?」
アワリティアが酷薄な笑みを刻む。
アワリティア、スペルビア、ルクスリア。どれもこれも一目見ただけで只者でないことはわかった。全員がアンナマリアとレリアよりも強く、そしてそれが三人 も立ちふさがっている。どれもこれも、飛び抜けた淫魔有数の実力者。その三人を突破して人ひとりを助けられるかといえば――そんなの、無理に決まってい た。
抜き身の剣を掲げて虚ろ目でジョゼフへと近づいていく兵士。ひとりだけ残っていたらしい淫魔たちのペットはジョゼフの横に立つと、剣を振り上げた。
このまま振り下ろせば、無防備はジョゼフは躱すこともできずあっさりと首をはねられる。
首を――。
心臓がうるさい、とアンナマリアは思った。
さっきからなにも云えていなかった。まるで言葉を忘れてしまったようだ。人の姿になってまだ日も浅い、人間らしい機能を忘れてしまうのも、らしいといえばらしいな、とくだらないことを考える。
どうしよう――。
汗が全身から噴き出す。興奮からでも、運動したからでもない。ただただどうしようもなく不安で、怖くて、恐ろしくて、躯が涙を流すように汗を噴出している。
嫌な汗だ。こんな機能が人の躯にあるなんて体験するまで忘れていた。こんなに気持ちの悪いものとは思わなかった。
今から駆けだして、間に合うだろうか。
……間に合うかもしれない。
けれど、それも邪魔が入らなければの話。淫魔三人が見逃してくれるわけもないし、そもそも真っ向から戦って勝てる相手ではないと対面して身に染みるほど自覚した。
人間である限り、もうジョゼフを救うことはできない。
首がはねられる。処刑人のように、彼のように。弟もその末路をたどるのだ。他でもない自分の目の前で、そして弟は自分のせいで。
剣が振り下ろされる。
刃は首に向かって一直線に落ちていく。
鋭い振り下ろし。
ああ、でも――自分ならもっと美しく刃を打ち下ろせるのに、とアンナマリアはうそぶく。
人であっても、断頭台であっても、結局人を目の前で失ってしまうのなら、自分の刃で綺麗に殺してあげたいのに。
――断頭台?
ふと気がついて、アンナマリアは笑いそうになった。
そうだ、断頭台だ。
自分がなんであったかを思い出した。
わたしは――断頭台なのだ。
グキッ、と関節の軋む音。アンナマリアは右手の指をかぎ爪のように曲げる。それをレリアが見て、あっ、と声を出した。
そうである。今も人の姿をしていても、アンナマリアは断頭台であり、処刑機具であり、絶対的な死を宣告する理不尽の象徴なのだ。
レリアはアンナマリアと邂逅したときのことをすぐに思い出した。
あのとき、突然建物に亀裂が走った。
まるで、斬撃のような。
まるで、大きな刃物で切ったような。
では、それが刃であったと過程して――その刃はどこにあって、どこにいったのか?
答えは簡単だ。凶刃は常に目の前にあった。誰も気がつかなかっただけで。
レリアは一瞬、アンナマリアの腕が巨大な刃になるのを幻視した。陽炎のように揺れる刃が腕に纏わり付く姿を幻想した。
だが、それは幻覚などではなかった。それこそが、最初から、彼女の真の姿。
アワリティアが息を呑んだ。
その瞬間、アンナマリアは虚空に向かって腕を振るっていた。
一迅の疾風が空を裂いた。
あらゆるものを引き裂いて、一切の命を区別なく処罰して、その名において安楽の死を与える刃が疾った。
剣を振り下ろしていた兵士が異変に気付いて振り向こうとして、躯が動かないことに気付く。
それもそのはずである。
兵士には、既に躯と呼べるものはなく。上半身だけの姿になって、自分の下半身を見上げ――それが最後に見たものだった。
「あ……」
急にアンナマリアの躯から力が抜けて、床に倒れた。
「ぎ、ギヨたん!?」
呆然としていたレリアははっと我に返り、慌ててアンナマリアを助け起こした。
アンナマリアの顔色は悪い。浅く呼吸を繰り返し、目を見開いて自分の躯を抱きしめていた。
「なんだ……今のは?」
スペルビアが怪訝な表情で死体となった兵士とアンナマリアを交互に見る。武闘派として名高いスペルビアは空気の歪みひとつとして見逃さずに一部始終を見届 けていた。故に、アンナマリアが腕を振るった瞬間に斬撃としか呼べないものが空を疾駆して兵士を切り裂いたと正しく認識していた。だが、それがどうして起 こったのかは理解できない。彼女はアンナマリアの正体を知らなかった。
「これは――いけません。ああ、まさか、まだこんなところにまで王の栄光がちらついているだなんて……! 確かに、この私が殺したはずなのに! 息の根を止めたはずなのに! 死者の分際でまだこの私を虚仮にするだなんて……!」
一度も余裕を崩さなかったアワリティアが、頭を抱えて取り乱していた。もうレリアやアンナマリア、ジョゼフのことなど頭の中にはないようだった。
滅多にないアワリティアの豹変に、ルクスリアが目を丸くする。
「ど、どうしたのアワリティア? そんなに血相変えて……おかしいよ?」
「これが驚かずに居られますか! とにかく、一時退却です!」
「えっ、でもあの娘たちは?」
「今はいいのです、ともかく一刻も速く離れなければ……」
「ジョゼフはどうするのだ?」
「置いておきなさい、今追ってこられたらこちらが困ります」
スペルビアとルクスリアは怪訝な顔をしたが、それでもアワリティアの珍しい様子のために頷いた。
三人は他の者に目もくれず舞い上がると、はめ殺しの窓を叩きわって夜空へと消えていく。レリアはそれをなにもせずに見送って、小刻みに躯を震わせるアンナマリアの背中を撫でた。
「ホント、ギヨたんと一緒だと退屈しませんね……」
レリアの軽口に返ってくる言葉はない。いつの間にか、アンナマリアは目を閉じて眠っていた。
「……ギヨたん云うなって、返してくださいよ」
急に不安になって、レリアはアンナマリアの手を握りしめた。
気絶したジョゼフとアンナマリア。逃げ出した高位淫魔たち。
どうやら、自分の知らぬことがあるらしい――。
ただひとつ判ることは、なにやら嫌な予感がするということ。なにかが始まり、終わろうとしていること。
レリアが頭を上げると、窓の向こうに月が見えた。窓という額縁に切り取られたような三日月。
「月は無慈悲な夜の女王……なんて、ね」
三日月は、地上の人々を笑っているように見えた。
第三章/了
「――拙いな」
窓越しに夜空を見上げて、銀髪の女性は物憂げに呟く。
雨が降っていた。
いきなりの豪雨である。
地面を間断なく叩く雨音は家の壁を貫いて、激しく人の鼓膜を叩いた。目に見えぬ不吉なものの存在を信じてしまいそうになるほどの不気味さで、暴力的な雨脚は掃射された矢が地面で跳ねているような音だった。
そんな中でも夜空で輝く三日月は空が笑っているようで、魔女イザベラは眉を顰めた。
「嵐の中を、青ざめた馬が闊歩する。騎手は死の御使いで、人は震えて頭(こうべ)を隠す」魔女は帽子掛けからハットを取って深くかぶった。「そろそろこの隠遁生活も終わりかな。お節介なちびすけもいなくて案外気に入っていたのだけど……」
珍しく感慨深そうにイザベラは溜息を吐く。
突然、家の扉が弾かれた。
蝶番が壊れそうなくらい勢いよく開かれた扉。それにイザベラは驚かなかった。
イザベラは、玄関の向こう側に向かって微笑む。
「おかえり、三人とも」
玄関の前には、全身で雨を受けながら人を背負ったレリアの小さな姿があった。
終章/夢の終わり La fin du reve...
夢を見ていた。
なんでこれが夢だとすぐに気づけたのか、それは簡単な話で。
もうこの世にはいない人がいたから、だからこれは幸せな夢なのだと思ったのだ。
アンナマリアはぼんやりと目の前にいる男を見ていた。
口の周りにだらしなく無精髭を生やしている、くたびれた金髪の男だ。服を油で汚した男は、アンナマリアに背中を向けて熱心に仕事をこなしている。
油を染みこませた布で、刃にこびり付いた血糊を拭っていた。
娘を愛でるように。恋人を撫でるように。大事な機械を手入れするように。何度も何度も布で断頭台の刃を布で拭く。
その男がアンナマリアを見ることはない。だってこれは夢で、アンナマリアは劇を見る観客に過ぎないから。
いや、男はアンナマリアを見ていなかったが、確かにアンナマリアを見ていた。
――あれは、わたしだ。
あの刃は、断頭台はわたしだ、と理解する。そして、自分の手入れをしている男の背中をアンナマリアはよく知っていた。
男の名前を呼ぼうとして、困惑する。
例えこれが夢の中だとしても。過去の再現だったとしても。断頭台の自分ではなく、人間になった自分の方に振り向いて欲しかった。自分から自分へと視線を奪い去りたい、矛盾した嫉妬心に身を焦がされた。
おかしいのはアンナマリアも自覚していたが、それでも気持ちを押しとどめることはできない。できるわけがない。
自分が殺した男だ。もう二度と会えないことは知っている。その理不尽さにせめて反抗しようと、人の身となって人間に報復しようと決めたのだ。
想い焦がれていた、二度と会えないその姿。
だから、自分に目を向けさせなかった。ずっと大事にしてくれたから、こんな姿で生まれることができたと伝えたかった。
なのに。
「 !」
声は意味をなさない。
ああ、そうだ。――私は彼の名前すら知らなかった。
アンナマリアは背中に駆け寄ろうとした。なのに、どんどんと男の姿は遠くなる。
真っ白な光の彼方に消えていく男の背中へ、必死になって手を伸ばす。かすれていく男に手は届かない。
夢から覚めたくない。せめて、せめて、また声だけは、聞かせて欲しいのに。
男の姿はアンナマリアの視界から薄れていく。
その間際。男がアンナマリアを振り返った。
消えゆく姿で、顔すら霞みに隠されている。
「 」
唇が動いた。
なんといったのだろう。
わからない――。
アンナマリアは夢から覚める。
イザベラがレリアにタオルを渡し、三人の水気を取って風邪をひかないように暖め、落ち着いたときには既に夜明けが間近となっていた。
簡単にイザベラが作った暖かいスープをレリアがすする。調理した人間のせいでスープに具はない。味も水よりはマシという程度だったが、冷え切った躯にはそれでも暖かく染みいった。
毛布を被って両手でカップに入ったスープをレリアが飲んでいると、横のソファに寝かされていたアンナマリアが目を覚ました。
濡れたドレスを脱がされて裸に毛布をかぶせられた状態のアンナマリアは、頭を抑えながらゆっくりと上半身を起こす。
「ここは……帰ってきたの……?」
「レリアがひとりで運んできたんだよ」
まだ状況をうまく飲み込めていないアンナマリアに、イザベラが答えた。
カップの縁から口を離して、レリアは頷く。
「ええ、いきなり、ギヨたんは倒れたんですよ。兵士の首を切り落とした途端に。……びっくりしたんですからね」
「ごめん」
「謝られても困ります」
「……ありがとう」
「それでいいんです」
レリアが表情を緩めたのを見て、アンナマリアは恥ずかしくなって毛布に顔を埋めた。よくよく考えてみると誰かに対して素直に礼をいったのは初めてだった気がして、所在なくなり胸がむずむずとした。
落ち着かなくてきょろきょろと辺りを見ていたアンナマリアは、恥ずかしさを誤魔化すためにふたりへ訊ねた。
「ジョゼフは、どうしたの?」
アンナマリアは夢の中に出てきた男のことを脳裏に浮かべて、云ってから唐突に不安で胸がいっぱいになった。
もしかして、結局助けることはできなかったのではないだろうか?
毛布に爪を立てて握り締めるアンナマリアに、イザベラは奥の扉を示した。
「別の部屋で寝ているよ。一番衰弱していたから、ベッドの上さ」
それを聞いて、アンナマリアは自分自身でも驚くほどに安堵してしまった。胸につっかえていた重りがすとんと落ちて、ほっと息を吐く。
「そう、よかった」
ジョゼフは助けることができた。そのことにアンナマリアは表情が緩むことを抑えられなかった。
「……だけど」
と、そこで口を開いたのはレリアだ。
「淫魔の毒気に当てられています」
「毒?」
「前 にも云いましたよね、あたしたち淫魔は精力を増進する体液を分泌できるって。でも、それには副作用がありまして……連続して長時間その体液を吸収すると、 正常な身体機能を損なってしまうんです。麻薬みたいなものですからね。しかも、ジョゼフくんはそれをたっぷりと躯に取り込んでしまったようで……」
「つまり、どうなってるの?」
「ジョゼフくんは、脳機能に障害を負いました。思考能力がなくなってます。生きてはいても、なにも考えられなくなったんです」
弛緩していたところを力の限り殴られたような心地だった。
それでは、まるで――
「生きた、屍……」
レリアは無言で、スープに口をつける。アンナマリアの言葉を否定する者は誰もいなかった。
「そんな……治らない、の?」
「いや、治るよ」
愕然としているアンナマリアの言葉をイザベラが平然と否定した。
「な、治るの?」
「うん。ふつうなら治らないんだけどね。そこはほら、この偉大な魔法使いの力にかかればなんとでもなるよ」
いつもなら悪態のひとつでも突くところだが、今はアンナマリアの目には本当にイザベラが偉大な人物のように映った。
「ただ、それにはひとつ条件があるんですよ」
レリアが云いにくそうに言葉を濁したので、またもやアンナマリアは不安になる。それもまた、なにか副作用でもあるのだろうか。
「なに、簡単なことじゃないか。ジョゼフと性行して淫魔の毒がたっぷりの精液を搾るだけだ」
「そ、そんな方法で?」
「そんな方法とは心外な。いいかい、精液というモノは欲望の原液であり塊なのだから、そこに邪なものを関連づけて一緒に引きづり出すのは実に正当な方法なのだよ。私の術のお陰でそうやって毒気の摘出ができるのだから、むしろ称讃してほしいくらいだね」
方法が意外だったので驚いたものの、悪い方向の話ではなかったのでアンナマリアは胸をなで下ろした。それでも、レリアの表情は依然としてまだ暗い。
アンナマリアがその理由を訊ねようとすると、イザベラが先に口を開いた。
「で、問題は誰がジョゼフの精を搾るかだ」
「……あ」
ようやく、気まずい雰囲気が流れているのかがわかった。
アンナマリアは口をつぐんでしまう。
誰がジョゼフを搾りとればいいのか。別に、アンナマリア以外でもできることだ。イザベラはなんでも出来そうなものだから性技も余裕であろうし、レリアに至っては淫魔だ。どちらも完璧に仕事をこなしてみせるに違いない。
けれど、とアンナマリアば憮然としてしまう。ジョゼフが自分以外の女に搾精されているのを想像するのは、なんというか、気分が悪かった。
自分以外がするのは嫌なのに、だからといって志願するのは躊躇われる。それもこれも牢獄でレリアに告白されたことを思い出してしまうからだ。
レリアはジョゼフに好意を持っている。一方アンナマリアといえば、兄の面影をジョゼフに見ていないといえば嘘になる。訊ねられれば、それ以外の感情もあると断言するが、代換のように見てしまっている節がないわけではなかった。
その後ろめたさのせいで声をあげることができない。
アンナマリアが黙っていると、案の定レリアが沈黙を破った。
「あたしは辞退します」
「え!?」
びっくりして、アンナマリアは思わず声をあげていた。
「ちょっとギヨたん、声が大きいですよ!」
「ど、どうして!? だって、レリアは……」
「忘れたんですか、あたしは淫魔ですよ」
レリアは寂しげに笑った。
「淫魔の毒気を抜かなきゃいけないのに、また淫魔の体液をすり込んじゃったら何があるかわからないじゃないですか……。だから、あたしは駄目なんですよ」
だから、と云ってレリアはアンナマリアの方を見た。
「ギヨたんにお願いします。大変不本意ですけど」
「あれ、私でもいいんだよ?」
「先生はもっと駄目です。色々と駄目です。駄目駄目です」
「やれやれ、手厳しい助手だ」
腕を組んで肩を竦めるイザベラには目もくれず、アンナマリアはレリアのことを注視していた。
「わたしで、いいの?」
「もうっ、いいって云ってるじゃないですか。あたしの気が変わらないうちにとっとと行ってきちゃってくださいよ!」
「……わかった」
アンナマリアは頷いて、毛布を引きずりながら立ち上がった。
そうして、廊下の方へと出て行き扉が閉まると、レリアは糸が切れたように躯から力を抜いてソファに寝転んだ。
「うー、もう、ホントに……」
毛布を抱きかかえて、もどかしそうに足をばたばたとさせた。そんなレリアをイザベラは笑った。
「いやあ、難儀だねえ。珍しくいじらしくて微笑ましいよ、レリア」
「茶化さないでくださいよぉ……。これでも結構本気で悔しがってるんですから」
「ふむ、そうか。ではこういう趣向はどうだい?」
「はい?」
と、イザベラが何事かを耳打ちすると、レリアの表情がみるみると驚きに変わっていく。
そうして、イザベラは悪戯っぽく笑った。
アンナマリアは人の気配のする部屋の前に立つと、一度息を大きく吸い込んでから扉を開いた。
ベッドの上で起き上がっているジョゼフの姿が目に入り、少しだけ動きを止めた。
ジョゼフがアンナマリアを見る。その目には意志の光はない。ただ、音に反応しただけだ。自分がなにをしているのか、自分がなにを見ているのか、そういったことは一切考えられていない。
雨が地面を叩く音だけが暗い部屋の中で響く。アンナマリアはしばらくジョゼフと目を合わせた後、ベッドの方へと歩き出した。
雨雲の切れ目から覗く月の灯りがアンナマリアとジョゼフをほのかに照らし出す。
ベッドの前まで来ると、アンナマリアは自身の躯を包む毛布をするりと床に落とした。
少女の細い裸体が白銀色の灯りを受けて、暗闇の中で浮かび上がる。控えめな胸の膨らみからすべすべとして柔らかそうなお腹、そこからへこんだへそに、まだ毛も生えていない秘部。それらすべては隠されることもなく、月明かりを受けて浮かび上がっていた。
幻想的な姿だった。
アンナマリアは四つん這いでベッドにあがり、ジョゼフへ抱きつくように身を寄せた。
何が起こっているのかも理解していない、赤ん坊のような瞳を覗き込む。息がかかるほど近くから目を合わせて、アンナマリアはささやいた。
「今、楽に……気持ちよく、してあげるね」
急にわき上がってきた嗜虐心のままに唇を奪う。
アンナマリアは相手をベッドの上に押し倒した。いつの間にか、路地裏で押し倒してたときと同じ嗜虐的な思考がアンナマリアの裡にわき上がっていた。
いつもなら惨めに喘がせて果てさせてやろう、と思うのに、今はみっともなく虐めてやろうと思っている。似ているようで、それは相反するものだった。
男を相手にしている淫魔が抱いている感情と同じものだとはまったく自覚しないまま、アンナマリアは衝動に突き動かされるままに相手の舌に自分のものを絡みつかせる。
「んっ……っ……」
獲物に食らい付く獣のように荒くなった熱い吐息が洩れる。アンナマリアの小さな唇は情熱的に吸い付いて、相手の全身を抱擁するように深く繋がる。
いったいキスだけでどれくらいの時間繋がっていたのか。長く長く繋がっていたふたりは、アンナマリアが躯を起こしたことでようやく離れた。
小さな躯で精一杯献身するように、しかしその実相手を虜にする舌技をこなしたアンナマリアの唇はふたりの混じり合った唾液で濡れていて、細い糸が残滓となってお互いの唇を繋いでいた。
ジョゼフに馬乗りになったアンナマリアは、ついに切れてしまった唾液の糸が名残惜しく、自分の唇を人差し指でなぞる。
自然とアンナマリアの小さな口元が持ち上がった。
心臓がドキドキとしていた。胸の中心に火の塊でも現れたのかのように、そこからジンジンと熱が広がっていた。苦しくも、ましてや不快でもない。なにかが物足りない切なさと、全身をほてらせる満足感があった。
頬が紅潮していることが、アンナマリア自身にもわかる。熱くなっているのが自覚できるくらい、その華奢な肉体は興奮していた。
頭の中には、相手を自分のものにしたいという欲求で満ちている。アンナマリアは本来なら断頭台であり、道具が担い手を決めるなど本来ならあり得ざることだ。
いや、道具だからこそ、自分にふさわしい担い手を決めたくもなる。ただ、今まではそれができるような状況でないがために誰もわからなかっただけのこと。
熱く、強く、深く、抱きしめて――自分だけのものにしたい――。
アンナマリアは今まで自分が感じたことのない想いで頭がパンクしそうだった。クラクラと揺れる頭では、自分でもおかしいと思えるほどに正常な判断がつかな い。なんでこんなことを、と動揺する。けれど、そんな冷静な思考もやがて水に溶けるようにして消えていく。人で例えるなら、アンナマリアはアルコールに 酔っているも同然だった。
ふと、自分のお尻の下で存在を主張するものに気付く。
ジョゼフの下半身に座り込んでいたアンナマリアは躯をずらすと、相手の股間部分が大きく膨らんでいるのを布越しに見た。
それでアンナマリアは、自分は直接ここから毒気に染まった精子を搾り取らなければいけないことを思い出した。
大きく膨らんだペニスを服の上から指でなぞる。亀頭の辺りから根本まで細い指が流れ落ち、ペニスが小刻みに震えた。その素直な反応に、くすりと笑う。
「相変わらず、こっちは素直なままなんだね……男の人って」
服の上から肉棒を握って、上下に扱く。アンナマリアの手の動きで雁首を行ったり来たりする皮と亀頭全体を撫でる布の感触にペニスはますます硬さを増した。
「ふふ……じゃあ、一度このまま出しちゃえ」
自分の手で為す術なく感じてしまうペニスが面白くて、アンナマリアは嗜虐心に従って手の動きを早める。直接陰茎に触れられたわけでもなく、服を脱がされる こともなく続けられる手淫。布も合わせて与えられる快楽はその躯にとって未知のもので、意志を失ったジョゼフが我慢できるわけもない。
白い肩を何度も揺らしながらパン生地でもこねるように両手でペニスを扱き上げるアンナマリアの動きに、性感は瞬く間に高められていき。
ぐぎゅっ、と強く掴まれたままに雁首をなで上げられたとき、ジョゼフは限界を迎えた。
どぷんっ、どぷんっ、と内側から何度もノックされてズボンが膨れあがる。熱く滾った精液が布に染みこんでいき、ペニスを握ったままだったアンナマリアの掌にも熱い精の感触が伝わってきた。
「まず一回目……」
まるでゲームの回数を数えるような気軽な口調ながら、その顔は夜空に浮かぶ月のように妖しく笑っていた。
「それじゃあ、二回目……行こうか?」
アンナマリアがジョゼフのズボンを下げる。すると、自分の出した白濁とした液体でたっぷりと濡れたペニスが姿を現した。大きさも硬さも衰えずに、今にもま た爆発しそうなくらいパンパンに膨らんだ陰茎をアンナマリアは優しく握り込む。熱く、粘っこい精液の感触。指に絡みつく感触を不快とは思わず逆に楽しみな がら、ペニスに精液を塗り込むように指を動かす。
精液を潤滑液代わりにして別々の生き物のようにペニスを這い回る繊細な指先の動きに、達したばかりにも関わらずペニスは射精感を高め出した。
人差し指の腹が尿道口を広げながら撫でる。敏感になっている亀頭の上を指が滑っていく度にペニスは激しく脈打った。
その反応と砂糖のデコレーションでもされたようにたっぷりの精液で濡れた亀頭を見て、アンナマリアは唇を舌で舐める。そして、自身の黒い長髪を手で背中に流しながら亀頭を口で呑み込んだ。
口内に広がる苦々しい精液の味と独特の鼻をつく臭いに、アンナマリアは目を陶然と細める。見た目の錯覚通り、それが砂糖菓子の飾りであるとでも云うように頬をすぼめながらペニスに付着した精液を舐めた。
「んっ、ちゅっ、……ん、ふぅうう、じゅ……んふっ」
根本まで呑み込みながら、一回目にたっぷりと吐き出された精液を呑み込む。口を亀頭の辺りまで引くと今度は陰茎を手で責めながら、亀頭を執拗になめ回す。
いつの間にか、ペニスを濡らすのは精液ではなくアンナマリアの唾液になっていた。ジョゼフの体温も熱くなり、息はアンナマリアよりもずっと激しくなる。
アンナマリアの口淫は搾り取るためだけの動きではなかった。もちろん、それもあるが、なによりも相手に気持ちよくなってもらおうという感情が行為を通して現れていた。
アンナマリアは自分の持っている技量の限りを込めて口の中を蠢かせる。幾多の男たちを絶頂させてきた少女が心から行為に没頭しているのだから、それに男が搾り取られないわけもなく。
幼い少女の口から強制的に与えられる快楽の前に、ジョゼフの躯はまたもや屈服した。
バネで弾かれたように腰を浮かせてアンナマリアの喉を突き、ペニスは精嚢に溜まった欲望を噴出した。
「んっ!?」
最初、アンナマリアは驚いて目を見開いたものの、すぐに眼を細める。妖艶な目つきのままに喉を鳴らした。
どくっ、どくっ、どくっ……。
「んくっ、んくっ……はあ……っ」
一分は続いただろうか。長い射精が終わると、アンナマリアはペニスを口から抜いて満足気な吐息を吐いた。
この二回でジョゼフが射精した精子は、既に精嚢に溜まる量を易々と超過していた。それもこれも、淫魔の体液による精力増進効果の賜である。射精を続けれ ば、やがて精子過剰生産と体力の喪失による死が待っている。もっとも、それ以前にショック死してしまう場合もあるが――その毒気に当てられたジョゼフは、 体液に触れていなくとも同等の効果が躯に現れているのだ。
精力を絶やさぬ力により、ペニスは未だに衰えを知らない。高位淫魔による体液の力と躯ひとつで男たちを搾り殺してきたアンナマリアの肉体があわされば、ペニスが萎えることすら許されないのは当然の結果だった。
それに、今やアンナマリアは躯に頼るだけではなくなっていた。
「淫魔の力ってすごいんだ……ここ、こんなにしちゃって。それとも、そんなに気持ちよかったの?」
クスクスと笑いながら囁く。思考能力を失ってしまっているはずのジョゼフの躯が羞恥に悶えるように身じろいだ。言葉に反応したのか、それとも単なる偶然なのか。定かではないが、アンナマリアは面白くなってペニスを指で弾いた。
「次はどんな風にしてあげようかな……、男の人なんだから。きっと、変態的なこと、考えてるんだよね?」
ペニスを刺激されて背筋を震わせているジョゼフを尻目に、アンナマリアはどうやって気持ちよくしてあげようかと考えを巡らせていた。
「そうだ……。自分からしたことはないけど、こういうのは、どう?」
云うなり、アンナマリアは自分の胸を両手で撫でた。ふっくらと控えめに膨れた胸にたっぷりと精液と唾液の混合液を塗りつけて、ジョゼフの腰に腕を回して抱きつく。そうして、てらてらと光る胸をペニスに押しつけた。
胸は成長途上の未成熟なものということもあり、手で包み隠せるほどの慎ましやかな山でしかなかった。そんな乳房でも、弾力がないわけではない。小さいながらもペニスに押しつけられた胸は柔らかい弾力を敏感な神経に伝えていた。
「ん……おっきくないから挟めない、けど……こういうの、好きな人もいるんでしょう?」
少し自分の胸の大きさを気にしながらも、アンナマリアは躯をゆっくりと動かしてペニスを乳房で撫でる。
豊満な胸で挟んだときのような柔らかい胸の圧力はない。
代わりに、未熟な胸を擦りつけるというのはそれとはまた別の快感をジョゼフに与えていた。
アンナマリアの胸は小さいながらも非常に柔らかく、ペニスが沈み込む。さらに、雁首を何度も刺激する乳首。アンナマリアが息を乱しながら躯を揺する度に擦 りつけられる肌は高級な布で撫でられているようで、ぬるぬると少女の胸元を往復するペニスに伝わる感覚に、ジョゼフの躯は何度も腰を小刻みに震えさせた。
「やっぱり、こういうの好きなんだ。ん、でも、そんなに動くと巧く捕まえてられない……」
辛うじてある谷間から滑って外れそうになるペニスを押しとどめようと、アンナマリアはジョゼフの腰に回した腕に力を込める。きつく抱きついてなんとか固定 できたものの、アンナマリアの胸では精液を塗りつけすぎたせいもあり、いつ滑って溢れ出るかわかったものではなかった。
「う……どうして、ちゃんと止められないの……」
別にアンナマリアは人間体の胸にコンプレックスを抱いていたわけではないのだが、こうして乳房による責めで苦戦してしまうといたく自尊心を傷つけられた。さっきまでの余裕がわずかに崩れ、声は焦りで上擦ってしまう。
「もう、駄目ですよー、ギヨたん。力を入れすぎたら逆にこぼれちゃいますよ」
「え?」
唐突なレリアの忠告に、アンナマリアは目を丸くした。声のした隣を見ると、先程までまったく気配も感じなかったレリアの姿があった。月明かりに照らされたレリアはどうしてかわずかに透けてみえるものの、ゆらゆらと燃える焔色のショートヘアは見間違えようがなかった。
「え、え、なんで?」
いくら行為に夢中だったとはいえ、背後で扉が開く音くらい聞き逃すわけはない。そんな音がした覚えはなかったのにレリアが隣にいて、アンナマリアは驚いた。
「ほらほら、それよりもギヨたんは向かい側にいってください。やっぱり独り占めしようだなんて許しませんよ、あたしにだってご褒美はあってしかるべきなんです。はい」
ひとりで納得しているレリアに急かされながら肩を押され、アンナマリアは股の間から無理矢理退けられた。服をはだけ出すレリアを見て、アンナマリアは慌てた。
「ちょっと待って。どうしてここにいるの!? だって……」
自分じゃなにがあるかわからないからって、と続ける前に別の声がアンナマリアの問いに答えた。
「それはなにを隠そう、この私のお陰というわけさ」
いつの間にか、魔女イザベラがベッドに腰掛けていた。ジョゼフの足先に座ったイザベラ、今度も扉の開く音は聞こえていない。しかも、イザベラの姿も透明な 膜が間にあるかのように輪郭がぼやけて見える。さらにいえば、アンナマリアはレリアに押し出されたときにそちらを見たが間違いなく誰もいなかったはずだ。
しかし、イザベラの姿が見えて余計混乱するということもなく、むしろアンナマリアはいくらか平静を取り戻した。
「……貴方がなにかしたんだ。驚くのも飽きたくらいなんだけど」
断頭台であった自分を人間に変えた魔女のことである。イザベラに関しては、なにができても不思議ではない。おそらく、彼女にできないことなどほとんどないのだろう。もし彼女がなにかをおこなわなかったら、それはできないのではなくやろうとしていないだけのことだ。
なので、イザベラには常識的な思考で相手をしていては混乱するだけなのである。元が人ではないアンナマリアは常識など最初から持ち合わせてはおらず、よって短い付き合いながらイザベラの相手の仕方は心得ていた。
「うむ、その通りだよ。いやあ、このままだとかわいいかわいい助手が不憫でならなくてね。けれどレリアがジョゼフくんの相手をするとうっかり悪化で元に戻れなくなるかもしれない。淫魔の毒に犯された躯に淫魔の躯はきつすぎる」
「それで、どうしてレリアがこれるようになったの?」
「はっはっは、なに、問題なのはレリアの躯なわけだ。つまり、躯がなければなんの問題もないわけでね。今ここにいるレリアは精神思念体……判りやすく云えば生き霊かな?」
「ちょっと先生! なんですかその言いぐさは! 大体今は先生だってそうじゃないですか」
よりにもよって生き霊呼ばわりされたことにレリアが怒る横で、アンナマリアはやっていることの理屈はわからないもののどういう結果になったかは漠然と呑み込んだ。
「それはわかったけど、そもそも躯が無くて触れるの? あ、でも今……?」
云いながら、アンナマリアはさっきレリアに押しのけられたことを思い出す。実体がない霊体のはずなのに、レリアと確かに触れあえていた。
「大丈夫大丈夫、ふつうは触れないものだけど、今回は触りたいと思った相手の五感に作用し、錯覚させて正確な感覚を再現しつつ、大気を操り人体の動きをエミュレートして圧縮させることで押しつけるなどといった行動も可能にしたからね」
「なんでもありなんだから……」
イザベラに順応した、とアンナマリアも思っていたが、いざ事も無げにこういった内容を語られるとつくづく非常識な存在であると再確認してしまう。
驚きを通り越してあきれ果てたアンナマリアは、目を細めてイザベラに抗議した。
「それで、なんで貴方までそっちの姿で……」
「ほらほらギヨたん、そんなことはもういいじゃないですか。そんなに待たせたらこっちがかわいそうですよ?」
レリアがそういって、ふたりが来るまではアンナマリアの胸で押さえつけられていたペニスを撫でた。実体のないレリアの手がジョゼフのモノに触れると、本物の手が触ったかのようにペニスは反応した。
「じゃあ、胸の続きをしましょうか。ギヨたんはそっちから、こっちからあたしで……こんな感じに……」
「ん、こう……?」
レリアに云われるがままにアンナマリアが動くと、ちょうどふたりの胸でひとつのペニスがサンドイッチされる形になった。
胸が控えめなふたりは自然と抱き合うような形で、互いに興奮した吐息の熱を感じた。
レリアはアンナマリアの手をとって握り合うと、自分たちの胸から顔をだす亀頭を見下ろして笑った。
「わー、ホントにこの躯でも挟めてますよ……。たまには先生も良い仕事するんですから」
「たまには余計だ、たまには」
そんなイザベラの軽口も耳には届いていないようで、レリアは目と目が触れそうなほど近くでアンナマリアを見た。
「ほら、ギヨたんはおっぱい小さいからあたしもいた方がいいですよね。こうしたら、もう絶対こぼれませんよ」
「それは大きなお世話で! ……んんっ」
怒ろうとしたアンナマリアの口をレリアが口で塞ぐ。唇に伝わってくる暖かさは確かにレリアのもので、感触もまるで本物の肉体としているようにリアルだった。
びっくりしているアンナマリアからレリアは顔を離した。
「そんなに怒っちゃダメですよ……ね、一緒に楽しませてください。やっぱり仲間外れはくやしいし、さみしいんですよ」
じっとレリアが瞳を見つめる。そこにはいつもの活発な力強さと、茶化していない真摯な感情が込められていた。
さっきまで、アンナマリアはジョゼフを独占してしまいたいと思っていたし、今でもそれは変わらない。独占欲が、じりじりと胸の奥で燻っている。
「……わかった。じゃあ、一緒に」
けれどレリアの気持ちも知っていて、だからアンナマリアは断らなかった。
それとこのままふたりでするということに、アンナマリアは少なからず興奮していた。
――こっちの方が、もっと沢山虐められる。
一度ぞくぞくとした嗜虐心に火がつけば、もう止める術はなかった。
もう一度アンナマリアとレリアは口づけをして、躯を揺らし始める。
ふたりの乳房は押しつけ合って潰れ、その谷間に挟まれたペニスは胸で擦り上げられる。
大きな胸とは違い、陰茎総てを包み込むようなものではなかった。左右は少女たちの胸で柔らかく擦られているが、同時にふたりの躯で締め付けられてもいた。
抱き合うふたりの躯はほどよい圧力で肉棒を締め付け、緩め、精液と愛液の潤滑液で愛撫する。
にゅち、にゅち、と粘っこい音を立てて頭を出したり下げたりする亀頭は快楽で紅く膨れあがり、先端から透明の液体を涙のように流していた。
「ふふっ、我慢汁がいっぱいですよ。舐めとってあげないと」
レリアは尿道口へと舌を伸ばす。途絶えることなくどくどくと流れる透明の液体を綺麗に拭ってしまうと、そのまま亀頭にキスをする。胸で抑えながら、唇を亀頭に吸い付かせた。
「わたしも、混ぜて」
アンナマリアも亀頭に口づけをすると、舌先で雁首を舐めた。レリアと唇が触れあい、ふたりは互いにキスしあうように亀頭をついばむ。
はあ、はあ、と白い靄混じりの吐息を吐きながら、ふたりは精の臭いを漂わせる肉棒で夢中になった。
「ちゅ……ふっ、んはっ! ギヨたんも上手になりましたね……このおちんちん、またイっちゃうみたいですよ」
「こらえ性がないペニスだから……もう、イっちゃえ」
ふたりは悪戯に笑って、亀頭を銜え込む。そのまま、思い切り胸で締め付け――
「ん……あ、あああああ!」
反射的に、ジョゼフの口から絶叫が洩れた。
もう何度も撃ったとは思えない勢いで、ペニスはふたりの口内に射精した。
精液はふたりの口を押し返して胸に溢れ出た。まるで小さな胸から母乳でも出たかのように白濁液が胸をべっとりと濡らす。それでもまだペニスは脈打ち、精液で少女たちの細い輪郭を蹂躙した。
レリアとアンナマリアは互いに相手の頬を伝い落ちる精液を舐める。まるで、猫同士が顔についた食べ残しを拭うように。
そう、蹂躙されているのはこのふたりではなく、目をつけられた男の方がまさしく獲物なのだ。
「えへへ、ギヨたん、精液でびちゃびちゃですよー。って、あたしもですね」
「これなら……満足できるまで、がんばれ」
精液に濡れたふたりの少女は淫蕩に笑って、まだ萎えることも許されないペニスを指で突いた。
いつの間にかふたりの頭の中から淫魔の毒のことは綺麗さっぱり消え失せてしまっていた。
ジョゼフが目を覚ましたとき、目の前は不自然なくらい真っ暗だった。
「んん……あう?」
あれ、と声を出そうとして、なにかに口が塞がれていることに気付く。そうして口を動かすと、塞いでいるものがビクンと痙攣してもっと強く押しつけられる。柔らかい何かで鼻も塞がれて、ジョゼフはびっくりして声をあげた。
「んー!? ぶはっ」
じたばたと暴れると、顔に押しつけられていたものが離れた。何故か顔中が水浸しになっているジョゼフは咳き込みながら大きく息を吸い込んだ。
「な、なに?」
「あっ、ようやくお目覚めですかぁ、ジョゼフくん」
「え……うわっ」
聞き慣れた声が話しかけてきて、ジョゼフはようやく今の状況を認識できるだけの余裕ができた。そして、自分に与えられている刺激にも。
ジョゼフの顔を塞いでいたのは女陰だった。それを顔に押しつけていた女性がベッドの上に膝で立ち上がったために、股の間からジョゼフは自分の下半身を見ることができた。
「え、れ、レリアちゃん、なにを!?」
そこには、ジョゼフのペニスを性器で根本まで銜え込んだレリアの姿があった。
窓から差し込む茜色の朝日が、わずかに透けているレリアの躯を照らしている。全身が燃えるように揺らめく幼い裸体は神聖なものであるようで、同時に酷くいやらしく見えた。自分のペニスに跨っているレリアの姿に、ジョゼフの心臓は大きく脈打った。
「なにってぇ、見て判らないんですかぁ?」
レリアの間延びした口調が、いつにも増して艶っぽいものになっている。騎乗位で繋がっているのに、まるで耳元にささやきかけられたかのような熱さがジョゼフの汗ばんだ首もとを撫でた。
「それは判るけど……ああっ」
ジョゼフの言葉を、レリアが腰を捻って黙らせた。ガチガチに勃起した肉棒を銜え込む狭い秘所が捩られて、刺すような抗いがたい快感がペニスに走る。
「判るんなら、男の人がやらなきゃいけないことはひとつだけですよぉ。――子種、いっぱい注いでくださいね」
「あ、あああああ――!?」
悪戯っぽい笑みのままに愛液で濡れた極上の肉壁が締め付けてきて、いきり立った肉棒は限界に達した。
ぶびゅ! びゅくっ、どくっ! そんな音が鼓膜を震わせる勢いで、ペニスが精液をレリアの子宮に注ぎ込む。もう何度目かもわからない射精でペニスが鈍痛を訴えるものの、それを遙かに上回る快感がジョゼフの脳内を占領した。
「あはっ、でてる、でてる……ホントにあたしの子宮に射精されてるみたいですよ」
「もう淫魔の毒はないはずなのに、こんなに出しちゃうんだから。根っからの変態みたいね」
「う……っ、あ、アンナマリアちゃん?」
息を荒げながら、ジョゼフは自分の目の前にある細い躯を見上げた。白く、ぷにぷにと柔らかそうなお腹をなぞり、渇いた大量の精液を付着させた控えめな胸を通り、黒髪を揺らす少女の顔に行き着く。それは、あのアンナマリアだった。
目が覚めたばかりにこの状況で、ジョゼフは夢でも見ているような心地になる。
「い、いったいなにが……あうっ」
ここに至るまで自分はなにをしていたのかと思い出そうとするが、絶え間なく蠢くレリアの膣に思考を桃色に染め上げられた。
何日も水分をとっていないかのように渇いた喉を震わせて嬌声をあげるしかできないジョゼフに、ひとりの女性が近づいた。
「説明すると話は長くなるのだけどね。それもこれも最初はキミを助けるためだったのだよ、ジョゼフ。まあ、今となっては彼女たち自身が満足するためと目的は変わってしまったがね」
「い、イザベラ先生……って、どうして裸なんですか!」
ベッドの脇に、一糸まとわぬ姿で豊満な胸をさらけだすイザベラが立っていた。手で掴んでもこぼれてしまうくらいの胸はぴんっと張っていて美しく、腰のくび れは腕を回して抱きしめたくなるくらいに引き締まっている。肉感的で、しかしだらしなくない肉体。アンナマリアとレリアとはまったく違う成熟した女性の 瑞々しい肢体に、ジョゼフは生唾を飲んだ。
「いやあ、それはだね。見ていたら私もむらむらとしてきてしまってね。どうせだから仲間に入れて貰おうと思ったのさ。なに、こんなときのために私もレリアと同じ方法でこちらに来たのだ、搾り殺さないように加減はできているはずだよ」
「そ、そういう問題じゃむぐっ!?」
「ほら、喉渇いてるんでしょう? ……いっぱい、呑んじゃえばいいよ」
ジョゼフの顔にまたアンナマリアの性器が押しつけられる。鼻には陰核と肌が強く押しつけられて、また呼吸が苦しくなった。手足を振って暴れても、弱った ジョゼフの躯には少女たちに抵抗するだけの力すら残されてはいなかった。アンナマリアが離してくれる様子もなく、ジョゼフは小さな少女の言葉に従って性器 を舐めて、愛液を掻き出す。
必死になってアンナマリアの亀裂に舌を入り込ませると、無数の肉襞に出迎えられた。奥へ奥へと導くように動く膣内の動きに、ぴりぴりと痺れるのに似た快感が舌をなぶる。
その舌を伝って、愛液が流れ落ちてきた。透明な液体が口の中に入り込むと、強烈な水への欲求がわき上がった。衝動のままに喉を鳴らして、アンナマリアの性器から流れ出した愛液を嚥下していく。
愛液を呑み、そこに酸素不足も相まって、ジョゼフは頭がクラクラとした。倒錯的な行為にふわふわと躯が浮き上がっていくように感じる。
「ふふっ、そう、その調子……息もかかって気持ち良いよ。もっと、はげしく……んっ」
アンナマリアがジョセフの頭の上に両手を置いて、自分で腰を動かし始める。ぴちゃぴちゃと愛液を淫らに鳴らし、アンナマリアはうっとりとした表情で舌の感触を楽しんだ。
「ジョゼフくーん、そっちの方だけに気を取られちゃ、ダメですよ?」
「うぐっ!?」
舌での愛撫だけに持って行かれていたジョゼフの意識を、レリアがペニスを思い切り締め付けて引き寄せた。
「おっと、それだけじゃないのだよ。実体じゃないから、こんなこともできるのさ」
レリアが繋がっているにも関わらず、イザベラがジョゼフの下半身に躯を近づける。すると、その躯はレリアをすり抜けてジョゼフのペニスまで達した。
「同時に与えられる胸と膣内の世にも奇妙な快楽……存分に楽しみたまえ」
そうして、豊満な乳房を手で押さえつけ、肉棒を挟み込んだ。
「ふ、んぐぅっ!」
イザベラの胸に挟まれた快楽は、ジョゼフの想像を絶するものだった。痛いくらいに勃起した肉棒は全体をすっぽりと乳房に呑み込まれ、あらゆる角度から柔らかい締め付けに襲われた。
さらに、ぎゅっとペニスを情熱的に呑み込んだレリアの膣の感触も襲いかかってくる。胸の柔らかすぎない弾力的な感触と、肉襞に締め上げられる快感。本来なら同時に起こりえるはずのない快楽の波に、ジョゼフの目の前は真っ白になった。
「あ、ぐ、ひあっ! あ、あ゛あ゛、あ゛……」
「さらに、これはどうかな?」
イザベラが笑って、乳房から顔を出させた亀頭を口に銜えた。雁首に吸い付く紅い唇のぷるりとした感触と、尿道口を滑る舌。もし口をアンナマリアに塞がれていなかったら、ジョゼフは甲高い嬌声をあげていた。
「ちょっと、先生ばっかり! あたしももっといただくんですっ!」
むっと眉を寄せたレリアが、強く力を込めて腰を落とす。子宮口が亀頭に押しつけられ――ずぶっ、と亀頭が子宮の中へと半分ほど埋まった。
子宮の入り口が、亀頭を思い切り締める。淫魔のそこはまるでもうひとつの唇のように繊細に動いた。
「――――!?!?!?」
精液をほしがって口をぱくぱくと開き亀頭を刺激する子宮口とイザベラの口内に、ジョゼフの脳内回路がいくつもの快楽で混線した。
「次は、もっと躯を動かしてぇ……」
レリアが腰を上げ――落とす。
ずんっ、とまた一気に奥までペニスが導かれる。肉棒をなで上げる膣に、ジョゼフは意識を失っていたときとはまた別の意味で思考できなくなっていく。
「ああっ、おっきいっ、おちんちんがっ、中で暴れてますよ!」
「ん……これで、終わり……っ」
目を蕩けさせたアンナマリアが女性器をより強くジョゼフに押しつける。その背後で、レリアの上下運動は激しさを増していた。
「ふふ……ではイってしまうといい……」
肉棒を乳房で扱きながら亀頭にむしゃぶりつき、イザベラは微笑んだ。
顔を圧迫する愛液にまみれたアンナマリアの女性器に、ペニスへ絶え間なく食らい付くレリアの膣。そして、イザベラの乳房による愛撫――
「あ、あ、――――!!!」
それに男が耐えられるわけもなかった。
「はあっ、あああ!」
そして、アンナマリアとレリアも下半身から上り詰める刺激に嬌声をあげて。
躯の中身ごと総て吐き出しなほどの快感に貫かれながら、肉棒は勢いよく精液を噴出した。
嵐の中で荒れ狂う川のように白濁とした本流がレリアの膣とイザベラの口内にぶちまけられた。膣内と口内を生臭い精子で染め上げても射精の勢いは止まらず、ふたりの霊体を貫通してアンナマリアの背中を熱く滾った精液で白く汚した。
朝日で真っ赤に染まった部屋の中には、男女の荒い吐息の音だけが静かに響いていた。
――数年前。王宮にて。
王宮の玉座にてひとりの男性が組んだ手に額を押し当て、唸っていた。
豪奢な服装の男性であった。肌触りの良さそうな生地で仕立てられた貴族服には絵画に描かれているような模様が編み込まれていて、それは庶民の薄給では一生かかっても手に入りそうにないものだ。
身なりだけではない。それを身に着けた男性にも、余人にはない気品があった。一朝一夕ではけして身に着けることのできない、生まれたときより染みこんだ風格である。喉を鳴らして悩んでいる仕草ひとつとっても、上等な生まれのものでなければ身につかない貫禄があった。
男性が浮世離れした風格を持っているのも当然で、彼こそがこの国の王なのだ。
国家を統べる場所であり、大勢の兵士がつめ、貴族が集まる国の最高機関である王宮の頂点に君臨する最高の権力者。
しかし、普段ならば王の周りにいるはずの兵士も、貴族も、玉座の周りにはひとりとしていなかった。
王は顔をあげて、がらんとした玉座の間に目をやる。キラキラと星のように輝くシャンデリアが灯火を幻想的に揺らしていたが、常ならば絢爛な灯りも今となっ ては薄ら寒いものにしか見えない。消えてしまいしまいそうになりながら頼りなくゆらゆらと揺れる灯に不安を覚えて、王は天井の絵画へと目を向けた。
かつての王が巨額の費用を投じて芸術家に描かせた太陽神の天井画である。そこに描き込まれた太陽神と人々の絵にはこの瞬間にでも動き出しそうな脈動感があった。見ているだけで活力を漲らせてくれるようなその絵画だけが王に残された最後の心のよりどころであった。
王は目を閉じて、耳を澄ます。それでも、本当に遠くの方から人の声がかすかに聞こえる程度だった。王が大声をあげても誰の耳にも届かないくらいに、兵士たちは玉座の間より引き離されていた。
王宮の警護を手薄にしろなどと、王は命じた覚えもない。なのに、どうしてか王宮は腹を見せて寝転んだ獅子のように無防備を晒している。
争いをおこなわずに、対象を無力化する。
そういう手段を得意とした連中を、王は知っていた。そしてなにより懸念し、警戒していたはずなのだ。
連中に対抗する手段を模索し、国家より駆逐する――そのお膳立てを、王はつい最近終えたばかりであった。
その認識が敵につけ込まれる隙を生んでしまったのだろう。王宮の中での出来事で王が認識できないものが増えていったことに気付いたときには、もはや手遅れだった。
これより自身へと降りかかるであろうことを考え、顔が悲壮に歪んだ。
「逃げずに残っているだなんて、その勇気には敬意を表したいですね、王」
王にかけるものとは思えない不遜な女性の物言いが玉座の間に響いた。
扉を開けて入ってきたのは侍女の格好をした女性だ。それでも、王には見覚えのない顔である。王宮に仕えている者たちの顔を全員把握しているというわけではないものの、王は王宮で起こっている異常の元凶が彼女であると判断した。
「例え逃げても、無駄なことなのはわかっている。そうだろう、淫魔よ」
「察しがよくて助かります。ああ、そういえば、名乗りが遅れてしまいましたね。高位淫魔、七柱が一柱、強欲のアワリティア――あなたを果てさせる者です」
「昔、聞いたことがある。淫魔の中でも特に優れた七人の者たちがいると……そうか、そのひとりが入り込んだとあってはこうもなろうな」
「正確には、私だけではありません。騎士団を掌握している騎士団長のスペルビアも七柱のひとりですし、あとひとり、貴族御用達の娼館で働いていますよ。いずれも」
「高位淫魔が三人……この手際のよさも頷ける。これは命運が尽きるのも道理だ」
冷や汗を流しながら、王は毒でも飲まされたように苦しげに頷いた。それでも口調から威厳を手放していないのは、さすがは王といったところか。
「あなたがいけないのですよ。おとなしく人の王として君臨していればよかったのです。そうすれば、私たちも市民に紛れて人間を搾取するだけで干渉は致しませんでしたのに」
王はアワリティアの口ぶりに生唾を呑み込んだ。
自分がやろうとしていたことを淫魔に知られているとは思わなかったのである。
「お前たちも他の淫魔と同じく、魔女狩りのときの報復で人に害をなそうとしているかと思っていたが……よもや、知られていようとはな」
かつて、淫魔は人に紛れて何食わぬ顔で生活をしていた。気ままに人と戯れ、思い付きのままに人を虜にする。迷惑な限りであったが、淫魔たち個人個人の気分 で完結されていたために大きな問題もおきていなかった。それなのに、一部の人間が自分たちとは違う淫魔たちを見抜いてしまった。しかも厄介なことに、彼ら は彼女たちを淫魔ではなく魔女と勘違いしたのだ。
世界中に広まった魔女狩り、それによって処刑された魔女の中には多くの淫魔たちも含まれてい た。これを契機に淫魔たちは人間への態度を家畜に対するそれに変更し、襲うようになった。そのため王は、アワリティアたちが国を支配しようと暗躍していた のは魔女狩りの報復だと思っていたのだ。
そう訊ねられて、アワリティアは笑い話でも聞かされたようにくすくすと笑う。
「何故、私たちが 人に捕まって処刑されてしまうような淫魔たちの復讐をしてあげなくてはいけないのですか? 所詮、彼女たちは自分が弱かったから処刑された……弱肉強食と いうものですよ。私は常に相手を喰らう強者ですので、彼女たちのことも、そしてこれから喰べられてしまうあなたのことも顧みる気などありません」
「……死は覚悟していた。今なら人も来るまい。しかし、ただで殺されるつもりはない」
王は玉座の陰に隠していたマスケット銃の銃把を掴んで構える。こういう日が来ることを予期して手入れを怠ることはなかったものであり、撃てば淫魔といえども無傷ではすむまい。
マスケット銃はアワリティアへと向けられた。銃口が自分をじっと見つめていても、アワリティアの笑みは消えなかった。
「あら、殿方が女性に銃を向けるのですか? ノブレス・オブリージュはどうなっているのでしょう」
「お前たちを排除することこそが、王としての高貴なる義務のひとつだ」
「私たちは人に仇など成してはいないのですけどね。むしろ、悦ばせてあげているのですから、感謝されることはあっても謗られる覚えはありませんよ」
「浅はかな……己の口でそうも語るか。お前たちの毒牙にかかるくらいならば、自害の道を選ぼう」
「強情ですのね。あなたの奥様はあんなにも悦んでくださいましたのに」
「な、なに……?」
王が動揺すると、アワリティアの背後にある扉から褐色の少女が現れた。
王宮にはおよそ似つかわしくない露出の多い服を着ており、腹部や瑞々しいふとももをおしげもなく晒した姿はジプシーかなにかのようで、躯を売り物にしているような相手なのは一目でわかった。
「きましたか、ルクスリア」
「きましたか、じゃないよー。せっかく貴族の男の人たちと遊ぼうと思ってたのに。まあ、新しい玩具も楽しかったからいいけどね」
にこにこと笑っているルクスリアという褐色の少女の言動で、彼女も淫魔なのだと王は理解した。おそらく、先程の話にできてた娼館に勤めている淫魔とやらだ。そして、言いようのない悪寒に襲われる。
「お前たち、まさか……」
「そのまさかですよ。さあ、妃様に入ってきて貰いなさい」
ルクスリアが、扉の外からひとりの女性を引っ張ってきた。思わず、王は声をあげていた。
「そんな、お前たち……妻になんてことを!」
淫魔たちに連れてこられた女性は、王の妃その人であった。
いつもは気丈に、傲岸不遜、傍若無人と振る舞っていた妃――が、その瞳は色欲で濡れていた。焦点を結ばない目は与えられた快楽で意識が朦朧としているためだ。
ひとりで立っていられなくてルクスリアに寄りかかった妃のドレスはスカートの部分が大きく引き裂かれており、むき出しになった股からは放尿でもしたのかと思うほどの愛液が流れ出していた。
「あはっ、妃様とえっちするなんて初めてだったから、つい張り切っちゃって。すっごい抵抗してくれたから、調教のし甲斐があってボクは楽しかったよ?」
「妻から、離れろ!」
無邪気な物言いが癪に障って王はマスケット銃をルクスリアへと向け、すぐにアワリティアが視界から消えていることに気がついた。
どこへ消えた――?
さっと血の気が引き、怒りで熱く燃えていた頭が一気に冷める。マスケット銃を右へ左へと振るもアワリティアは見あたらない。
直後、頭上で鳥が羽ばたくような羽音がした。
はっ、と王はマスケット銃を天井へ向けた――が、急降下してきたアワリティアの足に勢いよく蹴り飛ばされて銃は床を跳ねていった。
衝撃に痛む手に呻く間もなく、王は降ってきたアワリティアによって床へと押し倒された。
「ぐ……っ!?」
「油断大敵ですよ、王。これで、あなたは私たちを殺すことも自害することも選べません」
王へ馬乗りになったアワリティアの背中からは、蝙蝠のものに似た羽根が一対生えていた。男である王の躯すら包み込めそうなほどに大きな羽根は、淫魔が普段は体内に隠しているトレードマークのひとつである。
「ここで死なれては困るのです。あなたは、革命派によって殺されて貰わねばならないのですからね。それらが完了したとき、この国は私たちのものとなるのですよ」
「ならば、舌を噛み切ってでも……」
「させませんよ……そんなこと、考えられなくさせてしまうんですから」
そういって、アワリティアは王へと顔を近づけると相手のそれへと自分の唇を押しつけた。
「んふ……っ、ちゅ……」
しっとりと濡れた赤い唇を重ねて、アワリティアは己の舌を相手の中へとねじ込む。
王はその舌を噛み切ってやろうかと思ったが、アワリティアに歯茎を舐められると快楽で意識が胡乱になった。じんじんと痺れるように浸透する快感で顎に力が入らない。
「う……」
「先程までの威勢はどうなさいましたか? そんなに目を蕩けさせてしまって……奥様も見ていますのよ?」
「こ、殺せ……ひと思いに……」
「そんな無粋なことはしませんよ。私たちの手を煩わせたことに敬意を表して……与えるのは苦痛ではなく、快楽です」
アワリティアは上品な顔で妖しく淫蕩に微笑んで、王の服を留め具をひとつひとつ器用に外していく。服の下から現れた胸板をアワリティアの人差し指がなぞるとそれだけで性器に触れられたような快感があった。
「や、やめろ……。淫魔なぞに犯されるなどと、人としての恥……!」
「その強情が、いつまで続くのでしょうね?」
くすくすと笑み、アワリティアは腰を揺らす。柔らかい尻の肉を押しつけられて、敷かれていた王の股間はあっという間に最高硬度へと到達した。
「それに、こちらをこうも膨らませていては説得力もありませんね」
王の顔が羞恥と怒りに歪む。その表情をアワリティアは愉しんでいた。
「本当は、このまま私の中で果てていただくつもりでしたが……そうですね。機会をあげましょう。もしあなたが私をイかせることができたら、この国から手を引いてあげます。どうします、自分に自信がありませんか?」
見え透いた挑発だった。しかし、このままアワリティアのされるがままになっていても事態が好転しないのは間違いなく、屈辱的な提案だとしても受けざるを得なかった。
「いいだろう……その生意気な口を二度と聞けぬようにしてやろうではないか……!」
「ふふ、楽しみにさせてもらいますわ」
アワリティアは王の上から退くと、床に座り込んで股を広げ、自分の服をはだける。侍女用の服がほどかれ、露わになった胸元は見る者の目を釘付けにするほどに扇情的だった。王も、その姿には思わず生唾を呑む。
「さあ、いらしてくださいな」
アワリティアが手を差し出して指で誘う。無言のままに王はアワリティアの躯に覆い被さった。
妻が、すぐ側にいる。そのことで罪悪感が沸き、それでも抑えきれないほどに淫魔の美しい躯から目が離せない。無意識のうちに露出した一物はガチガチに堅くなったままだった。
そして、王は男のもっとも無防備なところをアワリティアの秘部に押しつける。亀頭に愛液で濡れた膣肉が触れた。亀頭に吸い付く感触に、まだ挿入すらしていないにも関わらず刺激で腰を引いてしまいそうになる。
女を知らぬ少年のように胸を高鳴らせた王はアワリティアの細い腰に腕を回すと、ペニスを彼女の中へと挿入した。
ぬぷっ、と準備万端だった膣の中にペニスが突き入れられる。
「は、っああ……!」
喉の奥から声を洩らしたのはアワリティアではなく王の方であった。
熱く濡れた膣はまるで精液を搾りとろうとする意志でもあるかのようにずるずると肉棒に絡みつく。その感触に王の頭の中からはこの場を切り抜けようと巡らせていた思考が吹き飛んでしまった。
「声などあげてしまわれて、そんなにも私の中は心地よかったのですか? そんな姿を奥様の目の前で晒されるなんて……男性として恥ずかしくはないのですか?」
「お前が、しろとっ」
「ふふっ、私はこの躯をイかせられたら、といったのですよ。それだけなら入れる必要なんてないのです。そうやって腰を動かしているのは……ご自分がなさりたかったことだからでしょう?」
云われてみれば、確かにその通りだった。本当にやりたくないことならば、それを出来るだけ避けて目的を遂行しようとする。それをせずに、この方法を即決し たのは、ひとえに王がアワリティアを抱いてしまいたかったために過ぎない。自分の妻を目の前にしているという状況においてでも。
戸惑う王に、アワリティアは膣に力を込めてペニスを締め付けた。ぎゅるっ、と力強く膣肉が陰茎全体を滑りながら愛撫する。
「ぬ、おおおっ」
「さあ、もっと突いてくださいな。もっと突いて、私を気持ちよくしてくださいね、王様?」
アワリティアは足を王の腰に絡みつかせ、動けなくすると、淫蕩に微笑んだ。
今まで抱いてきたどのような女性よりも心地良い暴力的な膣の感触に、王は既に果ててしまいそうになっていた。アワリティアの躯は自分から一切動いていない のに、膣はうごめいて精液を搾り取ろうとむしゃぶりついてくる。愛液という涎でびしょ濡れになった秘所の食い付きになにもかも吐き出してしまいそうだっ た。
それでも、イってはならない。相手を先にイかせなければ……。わずかに残ったその目的だけを頼りに、王は歯を食いしばって腰をアワリティアに叩きつけた。
ぱんっ、ぱんっ、とアワリティアの躯に男の躯がぶつかる。
「あんっ」
柔らかい肉を叩きながら膣を貫く剛直に、アワリティアはわかりやすい嬌声をあげた。
「ああっ、良いですよ、王様……いつもこうやって奥様を喘がせていたのですね? さあ、もっと、もっと……」
さらに強く懇願するアワリティアに、王は腰の動きを早めた。すぐにでも限界を迎えてしまいそうな快楽の中、王は先に相手をイかせようと何度も子宮を亀頭で突き上げる。
「そんなに激しく突かれては、私はもう……我慢できなくなってしまいますっ」
あと一息……、と頭の片隅で確信して、王はアワリティアの豊満な胸を両手で乱暴に掴んで、一気にペニスで膣を掻き分け。
「精液を、味わいたくて――ですが」
いきなりアワリティアの膣の動きが変わった。たっぷりと愛液に濡れた膣は締め付けを強め、ぐちゅぐちゅと音を立てながらペニスを呑み込んだ。
「お、おお!?」
「では、これでお終いにしてあげますね。さあ、私の中で果ててください」
くいっ、とアワリティアが腰を一度捻り、
「あ、ああああああ!」
一瞬で王の我慢を超えた快楽に、ペニスは為す術なくアワリティアの中に白濁を噴出した。
肉棒から噴き出した白濁とした男臭い精液が子宮に流れ込み、アワリティアは自分の下腹部を撫でながら唇を舌で舐めた。
「王様の精子、いっぱいいただきました。でも、このくらいでは足りませんから……もっと、搾り取らせていただきますね? さあ、王様、精液を全部私の子宮に出し切るか、それより前に私をイかせることができるか……勝負しようではありませんか」
達した衝撃で倒れ込み、アワリティアの胸に顔を埋めている王の頭を撫でて、微笑む。
「もっとも、その様子では……もう私の躯の虜でしょうけれど」
「えー、もう勝負着いちゃったのの? つまんないよー、まだこっちは始まったばかりなのに」
アワリティアがルクスリアの声がした方へと向くと、彼女は股間から生やしたペニスで壁に手を着かせた妃を突いていた。こうして喋っている間にも、ルクスリアはお尻を無防備に突きだしている妃を突くことを忘れなかった。
「あ、あひぅ! ひっ、いやっ、も、もうこんなに……」
「はいはーい、また一緒にイこうねー? ボクの精液たくさん味わってねっ」
ルクスリアは妃に囁いて、ずっ、とペニスで奥まで入れると白濁を妃の中に流し込む。それが子宮を叩くと、妃は一際高い声を発した。
「ひ、い、いやああああああっ」
妃の膝ががくがくと震え、股から溢れた愛液と精液がぴちゃぴちゃと床に大きな水たまりを作った。
もう何度イかされたかも判らぬ妃が腰砕けになって倒れそうになったところを、ルクスリアが腰を支えて押しとどめた。
「まだダーメ、もう一回最初からいこーねー?」
「あ、あああ……ああ……」
口から涎を垂らしながら虚ろな目になっていく妃に、ルクスリアは精液だらけになったペニスで掻き分けはじめだしたのだった。
そんなふたりの様子を見て、アワリティアは膣を一度きゅっと捻り、満足気に王の顔を胸に押しつける。
「これで、あなたがたも、この国も――私たちの、虜です」
それは、国がひとつ淫魔に掌握された瞬間だった。
*
「それで、進行状況はどのようになっていますか?」
不遜にも玉座に腰を降ろしているアワリティアが、正面に立っている騎士スペルビアに訊ねる。その顔色に余裕はなく、追い詰められた鼠のように暗かった。
革製の防具を身に着け、凜として立つスペルビアは、アワリティアが哀れに見えるほどの平静さで返答する。
「なんの問題もない。云われた通り、兵を手配し、魔女狩りと称しての襲撃をおこなう手筈も整った」
淫魔――その名前から連想させる淫蕩な気配は、スペルビアからは一切伺えない。清廉な、騎士たる高貴さを感じさせる立ち姿だった。しかし、鎧の下には淫ら に男を惑わす柔肉が隠されていることは実際に躯を重ねて魅了された男たちしか知らぬことである。もっとも、その大半は帰らぬ人となっているが。
「国の兵を挙げて討伐しようなどと、お前らしからぬ優雅さの欠片もない行為だ」
男を狂わせる肉体を持ちながらそれをおくびにも出さないスペルビアは、それと同じくらいに平静で、動揺もなにも見せていなかった。
アワリティアは疲れを吐き出すように溜息をついて、首を振る。
「貴女に優雅さをとかれるとは思いませんでしたよ。剣などという無粋極まりないものを振り回す貴女に」
「剣が無粋ならば、この世の総ては品性の欠片もない下劣な創造物であろうよ。剣と力ほど洗練された美しいものはない」
「武力に拘るとは、淫魔らしくもない……いえ、知力に拘るのも、淫魔らしくはないのでしょうけれど。それでもやはり自ら力を振るうより、蟲みたいに争う人間相手に高みの見物をする方が性にはあっています」
「ようやく調子がでてきたな。で、いい加減話して貰おうか。何故、兵を挙げて彼奴らを潰そうとする? お前が以前からあの魔女らの存在を危険視していたのは知ってはいたが、一国を手に入れた今、ここまで大事にする意味はあるまい」
アワリティアたちは、この国に革命を起こした。国王に反感を抱く勢力と貴族たちを抱え込んで籠絡し、争いの火種を造り、発火させた。ひとりだったなら苦労 もしたであろうが、高位淫魔が三人も揃えば国家を転覆させることなど造作もなく。王を革命派に処刑させ、誰にも知られることなくアワリティアたちは国を 盗った。
国を盗ることにさえ一度として表舞台に立たず、人を操ることはあっても指示をすることはなかったアワリティアが、今、たった三人を暴力によって潰そうとしていた。それがスペルビアには疑問だった。
「いいえ、違うのですよ……問題は魔女ではない。あの黒いドレスの少女です」
「どういうことだ?」
「私がこの国を落とそうと企てた理由を、知っていますか?」
「そんなものがあったことすら初耳だ。魔女狩りで我等淫魔が虐げられた腹いせで、どこでも良いと思っていたが」
その昔、魔女狩りがおこなわれた。多数の人々が魔女とされ、処刑された儀式である。しかし、魔女とされた中には人に紛れていた淫魔も含まれていたのだ。そ れまでは人とある程度もちつもたれつのような関係で過ごしていた淫魔たちは、それに激怒した。あの出来事以来、淫魔たちの大半は人間を純粋な家畜として見 ており、スペルビアはアワリティアの行動も魔女狩りの報復としてのおこないであると思っていた。
「どうして、私が殺された者たちの報復などしてや らなくてはいけないのですか。腰を振ってあげるだけで悦んで死んでいくような相手に殺されたなんて、淫魔の恥さらしですよ。……私は、単にこの国が驚異 だったからこそ潰そうとしたのです。あの国王は、私たちにとって最悪の天敵でした」
「その国王も、お前の腰の下で果てて処刑台に送られたはずだが……」
「そう、それです。処刑台! あの王が残した遺物。まさか、もう人の形をとれるようになっていたとは思いもしませんでした。一心不乱に私の中へと精を注ぎ込むしかできなかったあの男が、ここにきてこんな隠し球を残していたなんて……」
不安に駆られて強く玉座の肘掛けを握り締めたアワリティアは、いてもたってもいられなくなって立ち上がった。
「スペルビア、戦いの用意を。ルクスリアにもいつなにがあっても良いように伝達しておいてください。今回で、今度こそ総ての憂いを断ちます」
「よかろう。どちらにせよ、横取りされた獲物も取り返してやらねばならぬしな……」
ちろっ、とスペルビアの舌が唇を舐める。その一瞬だけ、女性騎士の本性が垣間見えた。
こうして、自分たちが淫魔たちに操られているとは露とも思わぬ兵士たちはアンナマリアたちを狙って行動を開始した。
*
夜が明け、アンナマリア、イザベラ、レリア、そしてジョゼフはリビングに集まっていた。
「さて、無事ジョゼフを救出することができたわけだ」
ソファに座ったイザベラは周囲にいる全員を見渡しながら、皆の労をねぎらうように口を開く。それに、対面で座っていたジョゼフの顔が引きつった。
「いや、まあ、助けてもらったことはありがたいんですけど……せめて方法というものはなかったんですかね……」
アンナマリア、レリア、イザベラによるジョゼフの体内に溜まった淫魔の毒気を駆除する作業は無事成功していた。一時期は自我を喪失していたジョゼフも、あれから数時間が経過した現在はすっかり以前の状態を取り戻している。
これまでの間に、ジョゼフは淫魔の毒気に当てられていたことの説明を受けていたが、それでも三人におそわれていたときのことを思い出すと恥ずかしさで顔が熱くなるのは止められなかった。
「やだなー、ジョゼフくんったら。みんなで楽しんだんだから良いじゃないですか」
「楽しんでなかったとは、たしかに云えないんだけど……」
にこやかに笑顔を浮かべて躯を寄せてくるレリアにジョゼフは立ち上がってしまいそうな勢いで肩を跳ね上げると、すぐに情けなさで萎縮してしまった。
「元はと言えば、巻き込んだのはわたしの責任だから……責めるなら、いくらでも甘んじて受ける」
三人とは少し離れ、彼らに背を向けて木製の椅子に座っているアンナマリアが呟くと、ジョゼフは慌てて弁明した。
「い、いや! あそこにいた、その、スペルビアって騎士の女の人はぼくの知り合いだったわけでね。だからぼくも無関係ってわけでもなかったから、アンナマリアちゃんだけのせいってわけでもないよ」
「そうだぞ、ギヨたん。物事を気にしすぎて沈んでいたらつまらないじゃないか。そこはもう開き直って捕まる方が悪いと云いきってしまえばいいのだよ」
「……それはそれでどうかと思うんですよ、魔女先生」
あきれ果てるジョゼフにイザベラは笑い、しかしすぐにその表情から珍しく笑みを消した。
「今回ばかりは、いつまでも落ち込んでいられる暇はないということさ」
「え、それってどういうことなんですかぁ、先生」
「そうやっていつまでも余韻に浸ってジョゼフに抱きついているのは結構だけど、それで注意力が散漫になってしまうのは、まるで恋する乙女のようだよ、レリア」
「余計なお世話です!? もうっ、もったいぶらずに早く云ってくださいよ」
「ではまずひとつ。何故、朝なのにギヨたんはいつまでもここに留まっていると思う?」
「……あ」
そういえば、アンナマリアはいつも朝には広場に戻って、断頭台へと姿を変えていた。本来なら広間にあるはずの断頭台がいつまでもなければ、大騒ぎになって しまうからだ。それに、アンナマリアは処刑という行為を自分がおこなうことに一種の義務感までも覚えていた。一番楽に人を殺せ、さらに民衆を満足させる視 覚効果を演出する処刑道具としてはアンナマリアが一番優れていた。
だというのに、この話を聞いていてもアンナマリアには動こうという気配すらなかった。
「えっと、ギヨたん、なんで……?」
「わたしも、行けることなら行きたいけど。今日はその必要もないみたいだから」
「そう、今日は処刑がおこなわれない。何故だかわかるかい? 街中に兵を配置するために人員を割いているから、そんなことをする時間もないのさ。そう、この国を支配しているあの淫魔たちは、とうとう私たちを武力行使で排除しようとしているわけだよ」
「な、なんだか、すごい大事になってますね、魔女先生」
「その一翼を担っているのは、キミのお師匠様だけどね。いや、ジョゼフもえらい淫魔に目をつけられていたものだ」
「淫魔ってだけでも驚きですけどね……そんなのがいるなんて思いもしませんでしたよ」
目が覚めてから、淫魔という種族が人間に混じって生活をしていることをジョゼフは初めて聞かされた。牢屋でスペルビアらに云われたときは驚きで頭がいっぱいであり疑念を抱く余裕もなかったが、改めて聞かされるとそれもまた驚くことばかりである。
「もー、そんなのって酷いですよ、ジョゼフくん」
「え、ああ、ごめん、悪気はなかったんだ……」
「えへへー、わかってますけどねー」
イザベラに敵の動向も聞かされても、レリアはすっかりジョゼフにのぼせ上がった笑顔のままに相手の腕に抱きつく力を強めた。直接の躯でなくとも、狙っていた意中の相手と繋がったことはそれだけレリアにとっては悦びであったのである。
「っていうか、レリア、くっつきすぎ。ジョゼフも、鼻の下伸ばしすぎ」
「伸ばしてないよ! こ、これはただドキドキして……」
「やだー、ギヨたんったら嫉妬ですかっ? こわーい」
「……死なす」
「ちょっとアンナマリアちゃん、落ち着いて! 椅子に座って! 魔女先生もなんとか云ってくださいよ!」
背後に黒い影を背負って立ち上がるアンナマリアに慌てながらジョゼフはイザベラに訴えるが、彼女は面白そうににやにやとしているだけだった。
「いいじゃないか、こんな状況でも普段通りでいられるのは良いことだよ。そもそも私たちにしんみりとした空気は似合わない。そうは思わないか、ジョゼフ」
「そりゃ明るい方がいいですけど」
「ははは、まあ仕方がない。ふたりとも、その辺りにしておきなさい。さすがに時間的な猶予も少なくてね。もう数刻もせずに兵士たちはここに踏み込んでくるだろう。さすがに一国の軍隊ひとつを真正面から相手にするのはきついだろう?」
「そもそも、あたしたちの戦う場所はそこじゃないですからねえ。ジョゼフくんならわかるよねー?」
意味深に笑ってレリアがジョゼフの胸に頭を乗っけると、ジョゼフはビクンと躯を震わせ、アンナマリアの視線がきつくなったことに頬を引きつらせた。
助手の期待通りの返答に、イザベラは満足げに頷く。
「その通り。だから、君たちの戦場で決着をつけようじゃないか」
「……まさか、国の人間全員を一斉にあっちの方で相手をする、なんてこと云い出すつもりなの?」
「ギヨたんの目的はそれだったろう? ちょうどいいじゃないか」
「あ、あはは、先生……そういう力押しも一度はやってみたいことではありますけど……」
数十万、数百万の男女を相手に性技でねじ伏せるようなことは淫魔であるレリアもさすがに考えておらず、ずっと明るかった笑みが引きつった。
「なんて、それは冗談だよ。面白くはあるけど、あとに控えた淫魔たちを続けて相手になんてしたら保たないだろう? だから、取り巻きは無視してしまおうじゃないか。直接、その淫魔たちを叩こう」
「な るほど、あのアワリティアとかいう淫魔たちがいなくなれば、あたしたちは大丈夫ですね。表だって権力を持っているのは騎士団長だけで、他のふたりのことな んて兵士たちは知らないでしょうし。淫魔の虜にされてた人たちも彼女たちが消えてしまえば、総力を挙げてあたしたちを潰せー、なんて命令取り下げますもん ね」
そこで、元騎士団所属だったジョゼフが口を挟む。
「でも、魔女先生。その、あの牢屋から出してくれるくらいだからこのふたりがすご いのは判りますけど、もしその淫魔さんたちが城に立て籠もっていたら接触するのは難しいですよ。ぼくがいたときでさえ、スペルビア団長と軍の人間たちが決 めた警備に穴はなかったんですから、籠城を決めるつもりなら、さらに頑強になっているに決まってます」
「もうっ、ジョゼフくんはあたしたちのこと信用してないんですかぁ? 大丈夫、男の兵隊さんなんて物の数じゃないですよ。ジョゼフくんだって今朝までじっくり体験したじゃないですかぁ」
「そ、そうだけど……」
「まあ、たしかに利口なやり方とは云えないですけどねー。人がどんどん来ちゃいますし、槍とか銃でぐさっぱーんっ、もあり得ますから」
「あ、城攻めの方は大丈夫だよ。私が魔法で直接敵のところへ転送してあげるから」
「……ジョゼフを助けに行く時、それを使ってくれればよかったのに」
「ごめんごめん。これは行ったことのある場所にしか転送できないんだよ。生憎と私は牢獄に入れられるようなことはしてないんでね」
「司法の目をかいくぐってきたって意味でしかないですよねぇ、先生の場合」
レリアの追求もイザベラは微笑で受け流して話を続ける。
「で、 高位淫魔三人……アワリティア、ルクスリア、スペルビアだったかな。この全員を負かしてしまえばいいわけだけど、淫魔の根城にこちらから飛び込もうってい うんだから、力尽くの戦いはできないわけだ。どっちにしろ、レリアもギヨたんも一番得意な戦いは相手と同じだろうから関係ないけど――」
そこでイザベラはジョゼフの方へと向いた。
いつも見ているはずの笑顔なのに、ジョゼフは嫌な予感に胃の入り口がきゅっと絞まるのを感じた。
「問題はジョゼフだね。いやあ、人間の男が淫魔と戦って勝つなんてよっぽどのことがないと無理だけど、まあ、がんばってね」
「え、え、えええええ、ぼくですか!?」
素っ頓狂な声をあげてジョゼフが驚く。イザベラの言葉はアンナマリアとレリアも聞かされていなかったため寝耳に水で、ずっとジョゼフに躯を預けていたレリアも飛び上がってしまうほどの驚きだった。
「ちょっ、先生!? てっきり、あたし、ギヨたん、先生の頭数で淫魔を相手にするつもりだったんですけど!」
「え、私はなにも手伝わないって云わなかったっけ」
「あれってジョゼフくん助けに行くときだけの話じゃなかったんですか!?」
「残念ながら私は世俗に関与しない主義なんだ。さして結果の変わらぬ小事にならともかくとして、介入次第で歴史が変わってしまうようなことに関わるつもりはない。城への手助けをするのだって最大限の協力なんだから。本当は自分たちで方法を探してほしいくらいだよ」
「ぼ、ぼくがまたあの人たちと……」
ジョゼフは牢屋での出来事を思い出して、雨に触れた犬のように身震いした。淫魔たちに与えられた快楽が全身に甦り、脳髄が溶け出しそうな蜜月の記憶に躯が 熱くなる。ただ、同じくらいに、生と死を強制的に繰り返させられて終わることない渦の中に引きずり込まれた畏怖も強かった。
「先生、あたしとギヨたんのふたりで三人を相手にしちゃえばいいじゃないですか。厳しいですけど、できないことは……」
「いや、それが間違いなく無理なんだ。キミとギヨたんはアワリティアとルクスリア相手ならともかく、スペルビア相手では万に一つの勝目もない」
「……それは、どうして?」
絶対に勝てないと断言されて、アンナマリアは無表情の中に不愉快さを覗かせた。牢獄で淫魔たちと出会ったとき、圧倒的な力の差を見せつけられて愕然としたことは記憶に新しいが、それでも一瞬の迷いもなく云われては腹も立ってしまう。
「簡単なことだ。彼女だけは淫魔でもあり、そして騎士であるからだ。スペルビアを押し倒して性技の方で相対するには、まず、暴力的な戦いの方で勝たなければいけないのさ。淫魔の異端であり、そして淫魔が一番敵に回したくないのが傲慢のスペルビアというわけだね」
「うぐっ、あたしたち淫魔はそういう戦いはあんまり必要としませんもんね……。人間相手なら早々負ける気はしませんけど……」
「そういうこと。あとギヨたんもダメな理由は一緒だからね」
「……なんで? わたしは淫魔じゃないし、それに、戦う力なら……」
ある、と続けようとしたアンナマリアの言葉をイザベラは手で制した。
「ああ、キミは優れた殺戮能力を持っている。けど、キミは効率的に首を刎ねることはできても、それを実行するだけの能力がない。起源が道具なんだ、あくまで身体能力が人間と同じなキミじゃ荷が重い」
そこまで云われて、アンナマリアも重く口を噤む。それに、アンナマリアの――断頭台としての本来の――力は、牢獄で一度淫魔たちに目撃されている。もしアンナマリアがスペルビアと相対したとしても、初撃を見切られたら勝つ見込みはない。
「えーと、魔女先生、今のはアンナマリアちゃんが、その、元はギロチンってあることに関係してるんですか? よくわかりませんでしたけど」
「そうだね。まあ、関係のない話だよ。ともかく、スペルビアにはジョゼフが当たって貰う。なに、勝算がないわけじゃない。なんといっても今のジョゼフなら淫魔の快楽にもある程度耐えられるだろうからね」
「あ、そうですね、ジョゼフくんは淫魔といっぱいえっちしましたからね」
ぶっ、とジョゼフはレリアの取り繕い一切なしの言葉に噴き出した。
「そ うそう。レリアだけじゃない、あれだけの高位淫魔と生死の境を何度もさまよいながら交わい続けたんだよ? 躯だって耐えやすくなっているさ。ふつうなら、 慣れる前に死ぬか精神が崩壊するんだけど、ジョゼフの場合は両方乗り越えられているし。そこにギヨたんもいるんだ、多分もうふつうの女の子相手じゃジョゼ フも感じられないんじゃないかな」
「喜んで良いのやら、悪いのやら……。でも、そのお陰でぼくも頭数に加われるんだから、そこには感謝ですけど」
「え、ジョゼフくんそんなにまたスペルビアとしたいんですか?」
「違うよ!?」
「さて、これでジョゼフがスペルビアを相手にすることは納得してもらえたと思うけど、残りはアワリティアとルクスリアだね」
「あ、先生、ルクスリアはあたしが相手をしまーす。スペルビアと一緒にずっとジョゼフくんと絡み合っていたのが許せません」
「はい決定。じゃあアワリティアはギヨたんに任せるよ」
「う、うわあ……適当だなあ……」
「いいじゃないか。とっても妥当で宿命的な組み合わせだと思うよ。特にこの国を転覆させた首謀者を断頭台のギヨたんが相手にするのが特に」
「関係ない。わたしは降りかかる火の粉を払うだけだもの。……それと、別に今すぐしかけるわけじゃないんでしょ? 少し、ひとりで休んでる」
返答を待たずにアンナマリアは立ち上がると廊下の方へと歩き出してしまう。
イザベラは手を叩いて、それを合図にして場に張り詰めていた空気を払った。
「じゃあ、そういうわけで私たちも休もう。じゃ、こっちも準備があるから」
レリアとジョゼフに言い残して、イザベラはアンナマリアの後を追うように部屋を出て行った。
適当な部屋のひとつに入って扉を閉めた瞬間、全身の筋肉が弛緩した。傾く躯に驚いて棚の天板に手をかけても力が入らず、小物を薙ぎ倒しながら床に尻を付いた。
緊張の糸が途切れると、一気に汗が噴き出す。来ている服は汗でぐっしょりと濡れて、額には髪が鬱陶しく張り付いた。
もう我慢する必要はないのに、強く手を握りしめる。掌に突き刺さる爪の感触が辛うじて判り、そのことだけがこの状況においての救いだった。
大丈夫……まだ大丈夫……まだ、わたしは……。
「随分と辛そうだね、ギヨたん」
「……っ!」
熱病に苛まれたように胡乱としていた思考が、一声で覚醒する。
アンナマリアは弾かれたように、声のした方へと顔を上げた。ベッドに腰を下ろしているイザベラの姿に驚愕で目を見開く。
「どうして……ドアは閉めたのに……それに、わたしの方が早く……」
「だからね、私は魔女なんだよ。既存の法則で括ってもらっては困る。そんなことより、よくもまあそんなになるまで隠し通せていたものだね」
「別に、足がもつれて転んだだけ。まだ人間の躯になれきってないから……」
「見え見えの嘘はやめなさい。キミが今どんな状況にあるのか、私は全部わかっているんだよ」
イザベラはベッドから離れて、アンナマリアの前で膝をついた。
「キミがあと少しで死んでしまうこともね」
アンナマリアは息を呑んだ。誰にも悟られまいとしていたことが簡単に見抜かれていて、その事実に声を出すことすら忘れてしまった。
「どう、して」
「レリアに担がれて帰ってきてきたときにね、一発で悟ったよ。そもそもキミに命を与えたのは私だよ、それが消えかかっているくらいわかるさ。それに、死にかかっているかの原因と解決方法すらも判ってる」
「……死なない? 生きられる、方法……。それは、なんなの? 教えて!」
イザベラの肩を掴んで、アンナマリアは掠れた声で懇願した。
「簡単だ。人を殺せばいい」
「……え」
「キミは、処刑道具が人と成ったものだ。だから、己の意志で人を殺せばキミは世界に生存を許される」
「云っている意味が、わからない」
「そ うか、じゃあまず前提条件から話そう。器物が意志を持つには九十九年はかかるものなんだよ。それが人の形を成そうとするなら、倍以上の時間が必要になって しまうわけだ。人を殺す物には呪詛的な力が宿って期間が短縮されるものであるけど、それにしたってたかだか数年で人間になるなんて不可能なんだ」
「でもわたしは貴方の力で……」
「そ う、私はキミを人間にした。ただし、それはキミの存在価値と目的が合一を果たしていたから、その呪詛の力を増幅して所用期間を誤魔化すだけの力を生み出し てあげたに過ぎないんだ。……わかるかな? キミの存在価値と目的がずれた時点で、増幅できる力の源がなくなる。あとは先細りで衰えていくだけだ」
――人を殺せばいい。その言葉がアンナマリアの頭蓋骨の中で反響していた。
「わたしの存在価値……人殺し。それで、人になりたいと願ったのは……」
「そう、復讐。殺害欲求。ほら、ぴったりだろう。けれど、今のキミは復讐をしてやろうだなんて気概が薄れてしまっている」
「そ、そんなこと……」
「存在価値は生まれたときから移り変わることなんて滅多にない。特に、断頭台なんてものの存在価値が殺害以外に変わるとは思えないね」
自分の目的を果たせば、人の形を保っていられる。どちらもアンナマリアの望みで、叶える分にはなんのデメリットもない。
そのはずだ。そのはずだった。
やりたいようにすれば生きられる。最初、男を殺したときと同じで残虐に、冷酷に、嘲笑を持って搾り殺してやればいい。あの彼を殺した国の総意に報復するためにも。
むざむざ彼の処刑を執行させられたときの屈辱は忘れていない。何度も何度も、広場のゴミみたいな民衆に呪詛を投げかけた。
殺してやる、殺してやる、殺してやる……。
お前たちもわたしで殺してやる……。
殺して、殺して、殺し尽くして。
最後には――。
――彼の弟すらも手にかけるか。
「なんで……」
イザベラの肩を掴んでいた手が、落ちる。
「なんで、ないの……どこに行っちゃったの……ずっと、あったはずなのに……殺したいって、思ってたのに……」
狂おしく燃えたぎっていた憎悪の炎が、いつの間にか遠くにあった。他人の記憶でも覗き込んでいるように、まるで余所事でもを眺めるように、その感情は自分のものではなくなってしまっていた。
冷静になって考えてしまえば。
こんな復讐など、ただの八つ当たりでしかなかった。
現実が許せなかった。こんなのは嘘だと思いたかった。けれど、それは叶わない。いくら目を背けようと、残酷な速度で大切な人を欠落させた世界は回り続ける。
彼を殺したのは世界だ。なのに、どうしてそうも無関心でいられるの?
たかだか処刑人ひとりの人生、鑑みる方がどうかしているのだろう。でも、彼を殺した奴が、それに歓喜している奴らがのうのうと生を謳歌しているのは――どうしても気に喰わなかった。
そんなことをして、死者が喜ぶとは思わない。
悲しむことさえ、死者にはできないのだ。
それにアンナマリアは納得できなかった。だからこその復讐である。復讐とは、理不尽に対する裡なる衝動の発露に他ならないのだ。怒りや哀しみといった感情に整理をつけるためにおこなう精神活動なのだ。
アンナマリアの場合、そこに矛盾が生まれてしまった。
国の人間を総て殺してやりたい、願望。それは彼の弟さえも手にかけると云うことだ。
彼のために、彼の弟を殺す――。
否。自分が彼を失った悲しみの穴を忘れるための復讐で、彼の弟を殺すのだ。
断じて復讐は誰の為でもない。総て自分の為にするものなのである。
だからそれは、アンナマリアにとって最大の自己矛盾だった。
――なによりも。
ジョゼフにかけられた優しい言葉が、胸の奥で引っかかっている。
好きとか、嫌いとか、そんな感情ではない。ただ、うれしかった。人を殺してされる感謝は、いつも悲しみか下卑た笑みで満ちていたから。
彼の弟だからではない。ジョゼフだから殺したくなかった。
あんなに殺したじゃないか、とアンナマリアの中でまた別のアンナマリアが囁いた。今更、善人を気取るつもりなのかと。えり好みするのかと。
そんなつもりはなかった。でも、殺そうだなんて思えなかった。
もう、胸の奥の炎は戻ってきてはくれないようだから。
「……判ったようだね、アンナマリア」
一瞬、誰に呼びかけられたのか判らなかった。虚ろだった目でイザベラに焦点を合わせると、どうやら彼女がいったらしいと判る。それくらい、聞いた事のない真剣な声だった。
「も うキミは、人は殺せても復讐心はほとんどない。キミが人間でいられる時間は、保ってあと数日だろう。こればっかりは、残念ながら私でも変えてやることはで きない。しかも残りの時間を自由に使おうにも、兵士たちのせいでそれも難しいだろう。なら最後に、できるだけやり残したことは潰さないかい」
「……ひとつ、きかせて。わたしは死んだらどうなるの?」
「本当は、死ぬという表現は正しくないんだ。キミは人の形を失って、また断頭台に戻ってしまうだけで、正確には眠りにつくといった方が正しい。そしてまた力を蓄えれば、再び人の姿も取り戻せる。しかし……」
「ならいい。そんな、なんでもかんでも身の回りの整理してたら、ホントに死んじゃうみたい。だから、あの淫魔たちを蹴散らしちゃった後に考える。それでいい」
「……よし。キミがそういうなら、私もこれ以上云うまい。それじゃあ、時間になったら声をかけるから、それまではゆっくりとしているんだよ」
「うん、わかってる」
イザベラが立ち上がり、今度はふつうにアンナマリアの背後にある扉を開けた。
すると、廊下側に立っていた者が声をあげた。
「あ……」
そこには、ジョゼフが立っていた。
イザベラと入れ違いで部屋に入ったジョゼフは、アンナマリアをベッドへと移動させて一息ついた。
ふたりはお互い相手に背中を向けてベッドに座っている。これといった理由があるわけではなく、なんとなくの行動だった。
口が重くなる気まずい沈黙が流れ、それを最初に壊したのは落ち着きのない様子のジョゼフではなく、憮然としていたアンナマリアだった。
「全部、聞いてたんだ」
「えっと、死なないでいる方法、って君が訊いてた辺りから」
「やっぱり全部だ」
「……ごめん、盗み聞きするつもりはなかったんだけど」
申し訳なさで肩を落としているジョゼフの姿がアンナマリアには容易く想像できて、つい微笑を洩らしてしまった。
「別に怒ってないよ。誰に知られたって何かが変わるわけでもないから。ただ、恥ずかしいこと、知られちゃったなあ、って」
「ぼくの方ばかり、聞いちゃってるね」
「じゃあ、そっちも何か話して。恥ずかしい話」
「恥ずかしい話? は、恥ずかしい話……」
顎に手を当て、短く唸る。しばし躊躇しながらも、ジョゼフは意を決して話を切り出した。
「それじゃあ、ぼくと兄さんの話を聞いてくれるかな」
そういわれて、アンナマリアの胸が一度だけ大きく跳ねる。
「……うん」
アンナマリアが緊張しながら頷くと、ジョゼフは一呼吸置いてから滔々と語り出した。
「兄は……ぼくが知る中でもっとも働き者で、もっとも立派な人で、そしてもっとも不器用な人だった」
振り向いたわけではなかったが、アンナマリアの脳裏にジョゼフの寂しそうな顔が浮かんでくるくらいに、その声には陰りがあった。
「ぼ くたちの両親は早くに死んでしまって、だからふたりで自立しなきゃいけなかった。でも困ったことにぼくは今よりもずっと小さくて、無力で……だから兄さん はぼくの分まで頑張ってしまったんだ。あの仕事に就いてたのもそういうわけで、他人がやりたがらない仕事を率先してやらなければ子供に人を養うことはでき なかった。でも、兄さんは余計にお金を稼ごうとした……ぼくに教育を受けさせるために」
「教育……」
「学があれば自分ほど苦労しなくてすむ、って。お陰でぼくは勉強ができたし、武芸の稽古まですることができた。けど、兄さんはそのひとつだって受けちゃいない。絶対に、ぼくよりも兄さんの方が優れていたのに……ぼくがいたせいでね」
ジョゼフの声には後悔の感情が色濃くにじんでいた。普段の温厚な性格からは考えられないくらいの重く沈んだ声に、アンナマリアも慎重に言葉を選ぶ。
「でも、それはそのときのジョゼフにはどうしようもなかった。だから、ジョゼフがいなくたって大変なことに代わりは……あ」
口にしていて、思考が整理されたことにより論理のパズルが急速に組み上がっていくのを感じた。頭の中でぐるぐるとしていたものがひとつの答えを導き出し、現れたのは単純で明瞭なパズルの絵面だ。
「ジョゼフは、もしかして、自分が重荷になっていると思ったから」
「そう、兄さんにぼくが生きていることは伝えなかったんだ」
処刑人である彼が孤独に死んでいったことをアンナマリアは覚えている。それで彼に血縁者なんていないと思っていたし、だからこそジョゼフが大怪我を負って生死の境をさまよったとき、処刑人の彼に対して生存を隠していたことをアンナマリアは憤った。
「腕 を切り落とされて、死にかけたとき……良い機会だな、ってね。ぼんやりとしながら思ったんだ。このまま死んでしまえば、兄さんは自由になる、って。結果的 には魔女先生に助けられて、けどぼくは死んだということにしてもらったんだ。でも……きみがあんなに怒ってたんだ、きっと逆効果だったんだろうね」
「うん」アンナマリアは即答した。「逆効果だった。余計なお世話だった。全力で裏目になってた」
「きついなあ」
遠慮のない言葉にジョゼフは苦笑した。けれど、それには不快そうな様子はなくむしろ清々しさすらあった。
「でも、その通り。ぼくもただ、人にいつまでも保護されているのが嫌で、それから逃れたかったんだ。……ね、恥ずかしい話だろう?」
「予想以上に恥ずかしい話で困惑するくらい恥ずかしい話だった」
「う、うん。まったくもって面目次第もなく……」
「本当に、許すとか許さないとかそういうのもわからないくらい、嫌な話だけど……。でも、わたしは断頭台だから、弾劾する方法は首を刎ねることしかできないし。どうにもしてやれないのがくやしい」
ふう、とアンナマリアは疲労を熱い溜息として吐き出した。
「だから、彼が死んでしまうほどに尽くした価値が貴方にあるのか、わたしに見せて」
「それは、どうやって?」
「……パンでも、焼いてくれればいい。もし不味かったら、そのときは首を切り落とすから」
「な、なにそれ、そんなことで!?」
パンを焼くだけで価値を示せるのか、そしてパンの不出来で生死が決まるのか。アンナマリアの不条理な要求にはそんなふたつの驚きがあって、ジョゼフは思わず背後を向く。
すると、同じく振り返っていたアンナマリアとジョゼフの目が合った。小さな少女は、刃のように真っ直ぐな瞳で相手を見つめていた。
「でも、彼にはパンは焼けなかった。彼にできなかったことをできるっていうなら、充分じゃない」
ジョゼフは口を噤む。兄ならばパンくらいすぐに焼けるようになるはずだ、と思う。きっと、自分のよりも美味しいに違いない、とそこまで考えてもジョゼフは 兄が作ったパンの味を想像できなかった。それは兄がパンを焼いたことなど一度もなかったのだから、当然である。作っていたということもなく、もちろんそれ を食べた経験もないジョゼフには、兄の作ったパンというものは空想上の産物にすぎない。
元より。ジョゼフが劣等感を抱いていた兄の姿は、ほとん どが勝手に作り出された虚像だったのだ。自分のために苦心してくれて、身を削ってくれた兄の強さは、ジョゼフの中で誇張されていったのである。それ故に ジョゼフの方が兄より学力や知能もあるのは間違いないのに、それは兄の環境が酷いものだったからそうなっただけだ、といつも思い込んでいた。事実、そう だったかもしれない。けれど、そうでなかったかもしれない。
どちらにしろ、今ある結果が変わるわけでもないのに。いつだって、勝手に作り上げたイメージに負け続けていただけだ。
「そっか、そうだね。……わかった、明日にでも、つくって持ってくるよ」
兄への負い目はジョゼフの中に沈澱して、なくなることはなかった。今でも、もし兄も自分のようにしていたらどうだったのか、との疑問は消えない。けれど、アンナマリアがパンを焼け、といった相手はジョゼフだった。それは、例え兄が生きていたとしてもできなかったことだ。
アンナマリアにパンを焼いてあげるのは、実にやりがいのある仕事に思えた。
「うん、また明日。その前に……少し、眠い」
しょぼしょぼとした目を擦るアンナマリアに、ジョゼフは相好を崩した。
「ぼくも……。時間になるまで、寝てようか」
「うん」
そうして、ふたりはくすくす笑いながらベッドに倒れて、微睡みへと落ちていく。
目覚めたときには、淫魔たちと争うことになる。
それなのに、ふたりの中には不安はない。意識を手放す寸前まで、総ての事が終わったときへと思いを馳せていた。
だから、廊下で聞き耳を立てているレリアには最後まで気付くことはなかった。
数刻が流れ、時刻は昼にさしかかろうとしていた頃、アンナマリアたちはリビングに集まっていた。
イザベラは腕を組んで悩ましい胸を押し上げながら、首を回してアンナマリア、レリア、ジョゼフの三人の顔を見渡す。ひとりは無表情、かたや笑顔に、緊張した様子の者もいると反応は三者三様であった。
「さて、いよいよ時間的猶予もなくなってきた。今はこの家全体に人払いの魔法をかけて隠匿しているが、それもそろそろ限界……。いい加減、こちらから仕掛けようじゃないか」
声を弾ませて陽気に魔女が謳うと、勢いよくレリアが手を挙げた。
「待ってましたぁ! はーいっ、先生、それじゃあ一番手はあたしが行きまーすっ! やっぱり、何事も一番っていうのが大事ですからね。あたしがサクッと勝利を掴んで、ギヨたんとジョゼフくんにお手本を見せてあげますよ」
ふふんっ、とレリアは得意げに鼻を鳴らすとイザベラは苦笑した。
「やれやれ、レリアも威勢がいいなあ。最初からキミに一番手を頼むつもりではあったけどね。この中で唯一の純粋な淫魔であるキミが一番手には適任だ」
「先生もよくわかってますねえ。初見では遅れをとりましたが、今度はあの小生意気な淫魔たちをあひあひ云わせてあげますよ! もうギヨたんたちの出番なんていらないくらいなんですから」
不敵にレリアが笑えば、アンナマリアは怪訝な顔になった。
「……レリア、どうかしたの?」
「へ?」
「なんだか、様子が変」
「べ、別にそんなことないですよ! あたしは普通ですっ」
「そうは見えないけど……」
「ともかく!」とレリアはアンナマリアの言葉を遮った。「最初はあたしがもらいますから! ギヨたんとジョゼフくんはそこで大人しくしててください!」
レリアの強気な言葉に押し切られて、アンナマリアは釈然としていないまま口を噤む。ただ、引っかかっていたのはアンナマリアだけでなくジョゼフも同じだった。
「れ、レリアちゃん、なにをムキになってるの?」
「ムキになんかなってないですっ」
首を傾げるジョゼフに声を荒げたレリアの頬は、心なしか紅くなっているように見えた。
レリアはこれ以上の追求を拒絶するように大股でイザベラの方へと歩み寄る。
「さあ、先生。そういうことですから、あたしを転送してください。ばっちり敵を仕留めてみせますからね!」
「……難儀な性格してるよね、レリアは」
イザベラが眼を細めて頬を緩めると、レリアはますます取り乱した。
「な、なんの話ですか? もうこれ以上待たせないでください!」
「はいはい。……ああ、そうだ、レリア。その前に」
何事かを思い出したイザベラはレリアに躯を寄せる。
「まだなにかあるんですか?」
むすっ、とレリアは頬を膨らませて怒ると、イザベラは身をかがめてその額にキスをした。
「……へ?」
「いってらっしゃいのキス。たまにはこういうのもいいだろう?」
「ば、ばかなことしてないで早くしてくださいっ!」
イザベラの突然の行動に驚いて、レリアは顔を真っ赤にしてイザベラを何度も叩く。ただ、少女の小さな手で叩かれてもイザベラは痛くも痒いもないようだった。
「ははは、――それでは、武運を祈るよ、レリア」
そういって、イザベラはレリアの目の前で指を弾いた。
*
大々的な儀式は必要ない。
余計な呪文も必要なく、
起こった動作は一挙動。
それだけで、レリアの躯は一秒前までいた空間とは別の場所に跳ばされている。
距離を無視するという通常あり得ざる行為が容易であるわけもない。あらかじめ周到に準備を完了させていたのか、それとも魔女にしてみれば造作もないことだったのか。
どちらにしろ、レリアはわかり切っている事実を胸の中で吐き出した。
――そういえば、先生は化け物なのでした。
一瞬、レリアは暗闇に包まれた。その闇が払われたとき、既に周囲は見知らぬものになっていた。
鼻の奥に纏わり付く匂いがして、レリアは深呼吸してみる。甘い、香の匂いだ。そして、それに混じって、肺をねっとりと熱く満たして蹂躙しようとする匂いがあった。それはとても馴染みのあるものだ。
そこは石造りの部屋で、兵士が十人、二十人いても窮屈さを感じさせないだろうと思うほどに広い。壁にかけられている獅子の描かれた立派な絵画といい、王宮の一室であるのは間違いないだろう。
レリアの前で、ひとりの女が踊っていた。服としての役割も真っ当できそうにない薄い生地の服をはだけて、褐色の肌を震わせて腰を激しく振っている。
突然やってきたレリアに気付いているのか、それとも目に入らぬほど夢中になっているのか。女は甘い声をあげて、床の敷物に寝転んだ男の上で踊っていた。
「あっはあっ! いいよっ、おっきなのがボクの中で暴れてる! ほら、またイちゃって? そっちのキミたちもっ」
女の両脇にはペニスを突き出した男がおり、ふたりのペニスは女の手で扱かれていた。我慢汁と唾液にまみれた肉棒を男たちは女のすべすべとした頬に押しつけると、女はふたつの亀頭を一緒に呑み込んだ。
首を振って、ぷるぷるとした赤黒い肉を激しく唇と舌でなめ回しながら、竿を手で握りしめる。
まるで女が犯されているような構図だった。それでも、レリアにはどちらが事の主導権を握っているのか、悩むまでもなく判っていた。
「ん……っ、ほらっ、ほらっ、ほらっ、……イっちゃえ!」
しなやかなの腰を振りながら、女郎蜘蛛の笑みを浮かべて女は二本のペニスに吸い付く。膣と手で思い切り握りしめられたペニスは、それで決壊した。
男たちは唸り声を開けて腰を女に突きだし、その褐色の肌を白濁とした精液で真っ白に染め上げる。勢いよく飛び出した精液は女の口から溢れて胸に流れ落ちると、ナメクジの這ったような跡を残しながら谷間を滑り落ちて腹筋をなぞり、おへその小さなくぼみに流れていった。
「んくっ、んく……っ」
それ以上こぼさないように手で受け皿を作りながら、女はうっとりとした表情で喉を鳴らして男たちの子種を飲み干していく。その間にも女の女陰はぴくぴくと痙攣し、組み敷いた男のペニスから精液を吸い上げていた。
どさっ、と音を立てて男ふたりが倒れた。女の口へ精を放出していたふたりである。
より正しく云うなら、放出していたのではない。女の手管によって搾り取られたのだ。
ふたりには目も向けず、女は唇をてらてらと濡らす精液の残滓を舌で舐めとる。
「あーっ、 満足っ! やっぱり盛りのついた戦場の男は精液の濃さが違うよね。いつ死ぬかわからないと、女の人をいっぱい孕ませようとして沢山精子作っちゃうのか なぁ? そんなに張り切ってもボクたちがおいしく食べちゃうだけで、なーんにもならないのに。人間ってなんでこう、哀れなんだろう。ね、キミもそう思うで しょ?」
中性的な、それでも女らしいかしましさを感じさせる少女はレリアに笑いかけた。
当の昔に事切れていた男の肉棒を膣から引き抜いて立ち上がる少女に、レリアは頷く。
「そうですねぇ。あたしたちにしてみたら、卵を産んでくれる鶏みたいなものです。結局、人間なんてがんばったって自分ごと全部あたしたちに食べられる程度の存在ですよ」
「だよね、だよね! 必死な顔でボクに腰を振って、感じさせてくれて、妊娠させようと精液を流し込んできて……。そんな子たちを堕落させて、引きずり落としちゃうなんて、とっても刺激的な遊びだよね。キミも淫魔だから、やっぱりそういうこと大好きなんだ、うれしいな」
「そうですねぇ、大好きです。特に気に入った男の子の上で腰を振ってあげたときのもどかしそうな顔なんて、思い出しただけでむずむずするくらいですよ。でも、あなたはちょっと勘違いしてますね」
「え、なに?」
「人間が家畜だけじゃなくて人間すら食い物にしてしまうようにですね。あたしはあなたみたいな身の程知らずな淫魔に躯で現実を教え込んであげるのが大好きなんですよ」
挑発的にレリアが微笑むと、少女は目を丸くした。
喘ぎ声がずっと反響していた部屋に流れるわずかは沈黙は、やはり少女によって破られた。
「面白いねぇ、キミ! 牢獄で会ったときは話せなかったから判らなかったや。いいよ、いいね、そういうの! うんっ、ボクも気持ちいいことは大好きだよ。だから、教えてくれるとうれしいかな、……ええと、キミの名前はなんていうの?」
相手の名を呼ぼうとして、少女はレリアの名前すら知らないことに気がついたのか、そう訊ねた。
「レリア。レリア・キッスです。あと、自分が名乗らないのに人に訊ねるのは失礼じゃないですか」
「あ、そうだったね。ごめんごめん、怒らないで。申し遅れましたっ、ボクは淫蕩のルクスリア。いっぱい楽しもうね、レリアちゃんっ!」
「……淫蕩というより、淫乱の間違いですよね。それに、色欲の間違いじゃないですか?」
溜息をついて、レリアは呆れた。
兵士のような荒々しさのない、踊りを生業とする者特有のしなやかな筋肉の付き方をした肢体にはランジェリーのような透けて見える服しか身に着けられていな い。さらに、褐色の肌には精液が塗りたくられて、どこもかしこも壁際で揺れる灯を受けていやらしい光沢を放っている。ここで事切れている男三人以外にも、 ルクスリアが躯を洗う手間すら惜しんで男と行為に没頭していたのは明かだった。
レリアの云いように、ルクスリアは訝しげに眉を寄せた。
「色欲より、淫蕩の方がえっちっぽいよね! ……ええと、淫蕩と淫乱って、なにか違うの?」
「淫乱は、ただ淫蕩に乱されて、振り回されてるんですよ。淫蕩は、人を惑わす現象そのものなのです。持論ですけどね」
「うーん、やっぱりわかんないや。だから、レリアちゃんの躯で教えてね。……そうだ、それならもっと人がいた方がいいよね! おーい、みんなこっちに入って来てー!」
ルクスリアが声を上げると、レリアの背後にある荘厳な装飾の施された扉が開かれる。
レリアが扉を振り返ると、五人ほどの男たちが入ってきたところだった。屈強な肉体を持った、レリアと比べたらクマみたいな大きさの男たちである。腰に剣を はいていることから兵士なのだろうが、それにしては口周りにみっともなく生えた髭といい、煤けた髪といい、あまりに粗野である。まるで手入れをしていな い。
そこまで見て、レリアは男たちの目が虚ろなことで昨日のことを思い出していた。牢獄で襲いかかってきた淫魔のペットに似ているのだ。
「なるほど、あの牢獄の兵士たちはあなたが食べた残り滓だったというわけですね。それと、この人たちも」
道理で見た目が汚いわけである。何故なら、男たちはもう快楽を受けることしか頭には残っていないのだ。放っておいたら食事すらするかどうか。
「残り滓だなんて人聞きが悪いよぉ。あれはね、ただ、多めに手をつけておかないと数がすぐに減っちゃうからだもん」
「加減ができないなんて、さすが淫乱ですね。その性欲には淫魔でも脱帽しますよ。きっと、その淫らさだけで七つの大罪の位を名乗ることを許されたんでしょうねー」
「むむっ、ちゃんと他の淫魔たちをメロメロにして、淫蕩って呼ばれて良い? って聞いたもんっ! まあ、あんまり興味なかったんだけど……みんな涎を垂らしながら頷いてくれたよ。それでね、今からキミもそうなるんだよ」
にこっ、とルクスリアは場にそぐわぬほどの天真爛漫な笑顔を浮かべた。
「それじゃ、みんなー、えっちの時間だよっ」
緩慢だった男たちの動きが速くなる。レリアという見たこともない新しい少女に男は一斉に群がった。リンゴなんて軽々と潰せてしまえるであろう大きな手でレリアの腕を掴むと、男のひとりが床に放り出した。
レリアは尻餅をついて痛みに声をあげると、ルクスリアを睨み付けた。
「ちょっと、女の子はもっと乱暴に扱ってくれなきゃ困りますよ! それとも、激しくされるのがあなたの好みだったんですか?」
「うんっ、やっぱり男は活きがないとダメだよね。そういう人たちから搾ってあげるのが楽しいんだから」
「それは動感ですけどね」
賛同を示したレリアの前で、男のひとりが下半身を露出した。既に臨戦態勢となった垢まみれの剛直が目の前に突き出されて、レリアは目を丸くする。
「うわあ……お馬さんみたいな太さですね」
「ボクが選りすぐった兵隊さんだもん。たっぷり味わってね!」
ルクスリアの言葉を待っていたわけではないだろうが、ちょうどそれを合図にして男はレリアの髪を掴むと口へと乱暴にペニスをねじ込んだ。
「もがっ」
明かに口よりも大きな肉棒を押し込まれて、顎を外れそうになるくらいに開けたレリアは目を丸くした。
男は両手で頭を掴むと、腰ではなくレリアの頭を激しく動かした。蟲でも沸いていそうなくらいに茂った陰毛でレリアの顔を撫でながら、馬並みのペニスは舌と口内の肉を蹂躙する。
その間に別の男が背後に回っていた。尻餅をついたレリアの細い腰を掴むと易々と持ち上げて床の上で四つん這いにさせる。無防備に突き出された白いお尻に、意識のないはずである男は生唾を呑み込んでいた。
こちらもまた馬のように逞しい肉棒を取り出すと、幼い菊座に宛がい、一息で貫く。
「んー!?」
前戯もなにもなしでアナルにペニスを突き込まれて、別のペニスで口を塞がれたレリアは喉で悲鳴をあげた。
男がレリアのお尻に腰をぶつけると、ぱちんっぱちんっ、と柔肉が甲高い音を立てる。男はレリアの腰を掴む手の力を強めるとますますペースをあげてペニスでアナルを貫く。
ドリルのような亀頭に肛門を掻き分けられて、レリアの目が情欲に濡れる。地面につかされていた腕を目の前にいる男の腰に回すと、自分からペニスにむしゃぶりついた。
「じゅ……んんんっ! ん! ふっ、んぐ……あっ、はぁあああ……っ!」
呼吸をするのも忘れて獣のように男の肉棒を舐め上げれば、おおきな男の躯は面白いくらいに震えていた。クマと幼女といったほどに体格差があるというのに、少女の華奢な躯に、男はまるで戦場で命の危機に瀕しているときのように震えているのである。
それはレリアの菊の穴を犯す男とて同じことだった。
性欲を満たすためだけに腰を振る男は、いつしか腰を止めることすらままならなくなっている。例え腰が痛くなろうとも、休むことさえできないのだ。脳内の神 経を巡る快楽に、男は逆に犯されていた。それが少しでも衰えてしまうと気が狂ってしまいそうになっている。もっとも、この快楽が既に男の気を狂わせている からこうもなってしまうわけだが――。
「ふっ……ふふっ」
レリアは妖しい笑みを浮かべて、男を上目遣いで見上げた。目と目が合い、男は心臓を鷲づかみにされたような錯覚に陥る。視界から脳内を犯されているような、甘く蕩ける視線。
そして、レリアは括約筋に力を込める。手で握りしめられたような強い締め付けに、アナルにペニスを突き入れていた男が呻いた。
「ひゃあ……おふぁりです」
終わりです、と宣言して、レリアは頬をすぼめてペニスに吸い付くと同時にかわいらしいお尻を捻った。
舌が蛇みたいに雁首へ絡みつくぬめりとした感覚と、ペニスを襞だらけな肉で締め付ける快楽に選りすぐりの兵士たちといえども耐えることはできなかった。
「んふ……っ、んっ!」
どぷっ! どぷんっ! どぷどぷっ!
男たちの精液が、レリアの口とお尻の穴に注ぎ込まれる。それでもレリアは休むことなく肉棒に吸い付き、お尻をふりふりと振った。
止まらぬ刺激に、男たちの射精もまたとどまる事はなかった。地盤を破って噴き出した間欠泉のように、男たちは尽きることない射精の快楽に声をあげた。
それが一分以上は続いたか。ついに男たちの射精は収まる。
同時に、男たちが力をなくして床に倒れた。そんな中でも、レリアは何事もなかったかのように立ち上がる。指についた精液を淫靡に舐めとるレリアの背中には、一対の羽根がマフラーみたいに揺れていた。
「今日はのんびり男の人と遊ぶつもりなんてないんですよ。――ただの性欲自慢な精液袋に用はありません」
高位淫魔であるルクスリアの躯に慣れさせられた男たちを瞬殺して、レリアは傲岸不遜に言い放った。
「さあ、あなたも遊んでないで付き合って貰いますよ」
そう、男三人の肉棒と戯れているルクスリアに言い放った。
レリアが男二人の相手をしていたときから、ずっとルクスリアは残りの男たちと性行をしていたのである。
最初からルクスリアに男でレリアを犯し尽くして屈服させようなどという肚はなく、楽しむための玩具として呼び出していたのだ。
後座位で男に性器を突かせて、残りふたりのペニスから口で精を啜っていたルクスリアは、にこにこと笑みを浮かべている。
「えへへ、そうだね。そんな、ふたりだけじゃ満足なんてできないよね。うん、わかった。じゃあ……ボクが気持ちよくしてあげるよ」
振っていた腰を止めて、ルクスリアは立ち上がった。ぬぷっ、と秘所から勃起したペニスが抜け落ちる。
「おっと。はい、ご褒美」
名残惜しげにビクビクと震えるペニスに眼を細めて、ルクスリアは足の指でその裏筋をなで上げる。
それだけで、どぷっ! と男の肉棒から精液が溢れだした。
足の裏を汚す暖かい子種の感触に満足して、ルクスリアはレリアの方へと向かう。白目を剥いて射精を続ける男にはもう目を向けなかった。
「それじゃあ、楽しくえっちしようね? うんと、やっぱり沢山気持ちよくなるなら、これがいるよね」
そういって、ルクスリアは愛液と精液に塗れた陰部に手をかけると、陰核をきゅっとつまんだ。すると、陰核は膨張をはじめる。指先ほどの大きさだったもの は、あっという間に勃起した男のペニスへと変貌していた。愛液でべとべとになったペニスは、先程レリアが銜え込んだ男と同等の迫力がある。
「これくらいで、いいかな?」
「立派なものですねぇ。ええ、構いませんよ。あたしの中でたっぷり気持ちよくしてあげますから……」
レリアは自信満々に云いきって、昂揚で乾いた唇を舐めると床に座ってM字に股を開いた。
ルクスリアはレリアに覆い被さり、ペニスの先端をまだ精液で汚れていない性器に押し当てる。野良猫みたいに目を細めて、ルクスリアは相手の目を覗き込んだ。
「それじゃ、行くよ」
つぷっ、と亀頭が女陰に沈み込む。レリアの躯には大きすぎるペニスは、濡れていた愛液で驚くほど簡単に入り込んだ。けれど、簡単に挿入できたのはなにも濡 れていたからではない。初々しい見た目に反して使い込まれたレリアの躯が、むしろその男性自身を淫らに求めていたからだ。
陰核が膨れあがってできた肉棒がレリアの膣肉を掻き分けて、ずんっと奥へと入り込んでいく。竿に加わる甘美な締め付けに、ルクスリアの頬が緩んだ。
「ああっ、すごい……こんな締め付け、久しぶり……っ」
「あたしの中にいれたのが運の尽きでしたね。あはっ、逃がしませんから覚悟してくださいね?」
捉えた獲物に微笑みながら、レリアは足を相手の腰に回してがっちりと捕まえる。そのまま力を込めて、一気にルクスリアを自分の方に引き寄せた。自分の意志とは関係なしに深く挿入されて、褐色の肉体は快楽に打ち震えた。
胸を反らせ、ぴんっと張った淡い色の乳首を突き出したルクスリアは熱く吐息を洩らす。肌を流れ落ちる汗は部屋に焚かれた香よりもなお甘い香りで、精の青臭さと香に汗が交わって、胸を焦がす淫蕩な芳香となって部屋に充満した。
レリアが腰を捻る度に、ルクスリアは面白いほどに喘いだ。膣をねじって襞で雁首を抉り舐めると、口の端から涎を垂らして快感に震えていた。
今にも流れ出すのではないかというほど瞳を蕩けさせたルクスリアの胸に唇を寄せて、レリアは乳首をついばんだ。
「ひゃっ、やっ、そんなとこ吸っちゃダメだよぉ」
それを無視して腰を揺すると、すぐにルクスリアの抗議は嬌声へと変わった。
胸越しに相手の鼓動を感じながら、レリアはルクスリアが本気でよがっていることを確信してほくそ笑む。
ルクスリアの敗因は慢心だった。
淫魔が持つ陰核の役割は、人間の女性と変わらない。性感を高め、快楽を得るために発達したものである。当然、他の部位に比べ殊更に敏感だ。
レリアに挿入されたペニスは、元はと言えばその陰核が強制的に発達させられたものである。膨張した陰核は、通常の男性が持っている肉棒よりもずっと鋭敏な神経を持っていた。例えるなら、ルクスリアの疑似ペニスは総て亀頭と同じ性感なのである。
それでも挿入した相手が人間の女であったなら、ルクスリアはなんの苦もなく犯しぬいていただろう。淫魔で一番敏感な部位といっても、精を搾るために生まれ たような肉体である。生殖の付随機能として快感を覚えるようになった人間の躯程度に快楽で溺れさせられるようなことはない。
けれど、ルクスリアが挿入した相手は人間の女ではなかった。自分と同じ、男を籠絡して精液を搾り取り、天国へと導く搾精器官を持った淫魔なのである。
なのにそんな一物を淫魔の蜜壺に突き入れて、無事で済むわけがなかった。
「あたし、えっちを楽しむのは良いことだって思うんですけど。でも、相手を間違えちゃいましたねぇ?」
ぐちゅっ、ぐちゅっ、とレリアの腰を掴みながらルクスリアは必死になって肉棒で膣を突く。与えられる電流のような快感で、今にもその腰は砕けてしまいそうだった。
「ふぁ、ああ……すごい……こ、腰が止まらないよぉ」
「こんなに気持ちよくなったのは初めてですか? 男の人たちにいっぱい突かれても、こんなに気持ちよくなんてならなかったんですよね? いいですよ、あたしの中に全部出しちゃって。お布団に包まれて眠っちゃうような、そんな心地良さの中で果ててください……」
レリアは足に力を込めて相手と深く深く密着すると、トドメとばかりに膣の力を強める。
ねっとりとした蜜に塗れた膣肉が肉棒を包み込み、ルクスリアは一際高い嬌声をあげた。
「はあっ、だ、ダメ、イク……イっちゃ……ひゃ、あ、ひゃああああああああっ!」
レリアは自分の勝利に勝ち誇った笑みを浮かべて、ルクスリアの精を子宮で受け止めた。
どぷぅうう――っ! どくんっ、どくどくぅ――っ! びゅっ、びゅ――びゅ――っ!
「これで、あなたもあたしのとり、こ……にひゃう!? な、なんですか? や、やだ、来ちゃ……来ちゃうぅううううにゃああああああ!」
ルクスリアの元気が良い射精を受け止めた、そう思ったときにはレリアの頭からつま先にかけて稲妻のような快楽の衝撃が走っている。
それは、レリアが絶頂したことを意味していた。
肉棒から流し込まれる熱い、それこそマグマのようにぐつぐつと煮えたぎった濃厚な精。それはレリアがこれまで搾り取ってきた男たちとは比べものにならない射精の勢いと量、質があった。
その濃厚と云う言葉では足りないほどに濃い精子は拒むこともできずに子宮に流し込まれ、レリアの小さな躯では受け止めきれない精液がふたりの結合部から噴き出した。
「や、やだ、なんなんですか、これ……射精させて、射精されてるだけなのに、なんで……なんでこんなに躯が……ひゃああああっ!」
それでもルクスリアの射精は止まらない。快楽で緩んだ表情のまま腰を突き出して、何度も何度も精液をレリアに流し込む。ねっとりとした白いゲル状の液体に犯されて、レリアの小さな躯は幾度も跳ねて絶頂した。
びゅくっ! とペニスが震えて精を吐くと、ビクンッ! とレリアの躯は震えて達することを繰り返す。
「あ、あ、あ……っ」
目を大きく見開いて、半開きになった口から唾液を垂らすのはルクスリアではなくレリアだ。連続でいったい何回、何十回とイかされたのか。既にその口は肺が痙攣して出す喘ぎ声しか洩らすことはできなくなっていた。
そんなレリアの頬を褐色の手が撫でる。ルクスリアの表情には、まるで我が子を慈しむ母親のような包容力があったが、その仕草はどこまでも淫ら。
「えへへ……どう、気持ちよかったよね、ボクの精子。ホントはこんなに出すつもりはなかったんだけど……レリアちゃんの中が気持ち良いのがいけないんだよ? そうじゃなかったら、こんなにイかなかったんだから……って、聞こえてる?」
ルクスリアが腰を引いて、一気に奥まで突く。
「ひゃう!?」
「あはっ、聞こえてるね?」
「あ、ああ……」
反射的に涙を流しながら呆然としているレリアに、ルクスリアはくすくすと笑った。
「そ んなに味わってくれると、ボクも出した甲斐があるなあ。実はね、ボクの精液にはすっごく強い催淫効果があるんだよ。なんでもね、ボクが呑んできた精気が凝 縮されてるんだってさ。それがこんなに効果覿面なんておかしいよねえ、だってボク、このお城に入る人たちよりちょっと多いかなってくらいの人たちからしか 搾り取ってないのに」
王宮ひとつに入りきらないほどの男の精液を飲み干してきた――。そんな途方もない言葉を、快感に朦朧となったレリアの頭で理解するには長い時間を必要とした。
「どうしたの、レリアちゃん。淫乱と淫蕩の違いを教えてくれるんだよね? ほら、続き、しよっ」
無邪気に笑って、ルクスリアがレリアと唇を重ねた。
「や、やめ……ひゃあっ!?」
キスしたまま、ルクスリアはずんっ、とレリアの子宮口を亀頭でノックした。絶頂の余韻さめやらぬレリアの躯にはあまりにも刺激的すぎて、また軽く達してしまった。
「やめてって、またなんで? ……あ、そっか。ずっと同じ体勢じゃつまらないもんね!」
「そういう意味じゃ……っ」
レリアの文句はルクスリアには届かず、あっという間にふたりの体位は変わっていた。
ルクスリアは背中を床に預けて仰向けになり、その上にレリアが跨る、所謂騎乗位となる。淫魔が男を犯すときによく使う格好だったが、今の主導権は跨っているレリアではなくペニスを銜え込まれたルクスリアにあった。
「あ、これだけじゃ物足りないかな? じゃあ、ふたりとも、レリアちゃんを楽しませてあげてっ」
ルクスリアが呼びかけると、ずっと棒立ちになっていた男ふたりが蜜に群がる蟲のようにふらふらと寄ってきた。屈強な男のペニスはルクスリアにおあずけを喰らっていたためか、既に臨戦態勢をとっていた。
「え、だ、ダメですよ、今は……はうっ」
レリアの言葉は男たちに届かず、無理矢理ペニスを口の中に入れられて頬肉に亀頭を押しつけられた。同時にふたつの馬並みペニスをねじ込まれて、レリアの顎は外れそうなくらいに開かれる。
「ほらほら、下からもっ、行くよ!」
リズミカルに突き上げてくる肉棒にレリアの華奢な躯はバネで押し出されるように跳ねる。
今まで感じたことのないほどの膣をペニスでかき混ぜられる快感。それ故にレリアは咄嗟に快感を受け流すことができない。
「んーっ! んーっ、んーっ、んーっ! んんんん――――っ!」
膣の締め付けが強くなる。それはレリアがまた絶頂を迎えた証拠だった。
男たちはレリアの髪の毛を掴むと、強引に腰を動かして口内を蹂躙する。頬肉に垢を擦りつけ、歯茎をなぞり、舌に竿を扱かせる。
強制される口淫と、突き上げてくる快感。それに文字通りレリアの頭の中は真っ白になっていた。
「ああっ、レリアちゃんの中って最高だよぉ! ボク、またイっちゃうねっ」
何度イっても疲れた様子のないルクスリアの叫びに、レリアは子宮が疼くのを感じた。
もっと、もっと精液が呑みたい――。
気持ちよくなりたい――。
漠然とそう思っていたとき、またしても濃厚な精子が子宮に飛び込んできた。
びゅっ、びゅっ、と勢いは衰えを知らずに膣内を白濁とした淫液で満たしていく。それに遅れて、口内で男たちのペニスが爆発した。
口の中に広がるむせかえりそうになる精の青臭さと、窒息しそうになる精液の量にレリアは目眩を覚えた。
「はう……は、ああ……」
イきすぎて躯に力の入らなくなったレリアは、男の汚い太腿に寄りかかって掠れ声を発するのが精一杯になっていた。
なのに、ルクスリアはまた思い切り下からレリアを突いて無理矢理たたき起こす。
ひゃうっ、と悲鳴をあげる少女に、ルクスリアは笑いかけた。
「……ね? まだ、お終いじゃ、ないよね?」
「あ……ああ……」
底なしの性欲に、レリアはしばし呆然とした。
「こんな程度じゃ、レリアちゃんも満足できないよね? だって、そうでしょ。ボクたち七罪を冠した淫魔は世襲でもなんでもなくて、実力で前任の人をたおしてなるものなんだから……。それに挑もうって淫魔が、こんな簡単に倒れちゃうわけ、ないよね?」
淫魔の社会は、人に比べると穏やかなものだ。彼女たちの社会には明確な競争はないのである。勿論、上昇思考は持っているが、それを最優先事項にすることはまずない。淫魔は淫らでふしだらにして怠惰な生き物なのである。
それは男に頼れば、彼女たちは何不自由なく生活をできるからだ。もし寄生している男が息絶えれば、また別の男のところへ。淫魔の美貌と床の技術は、どんな名家の子息にでも取り入れるだけの力があったのである。
その中での例外が七罪の名を冠する淫魔たちである。
それは高位淫魔として一級の実力があると認められる名誉の称号なのだ。そんな称号をとるためには、前任者を退ける必要がある。淫魔と淫魔で床の勝負である。
故に七罪だけは競争意識があった。さらに、七罪は挑戦者を拒めない、実力主義の頂点。
それだけの競争を勝ち抜いた淫魔の中の淫魔が、そう簡単に倒れるわけもなかったのだ。
「そんな……こ、このままじゃ……っ、あたし、頭がおかしくなっちゃ……」
にこにことルクスリアはボーイッシュな顔で笑った。
「なら、一緒におかしくなっちゃお?」
下から突き上げられて、レリアの口内で溜まっていた男たちの精液が溢れだし躯を真っ白く汚していく。
「ひゃっ!? あ、ああ……っ、あうぅうう……」
もう四肢に力は入らず、レリアの下半身はルクスリア、口は男たちの好きなようにされるだけだった。
レリアの躯に注ぎ込まれる精気は、既に数千、いや、万にも届こうかという男から搾った精と同じ量があった。ルクスリアの肉棒から溢れる精液の密度はそれだ け法外だったのである。いくらアルコールに強い者でも度数が百もあるものを摂取すれば倒れるように、いくら淫魔といえどもこれだけの濃さの精液を一度に叩 きつければ無事では済まない。
そんな精気を溜め込んで平然としていたルクスリアはレリアとは比べものにならない精気の許容量があるということで、基本スペックからして差は歴然だったのだ。
レリアの躯ではルクスリアには遠く及ばない。
そのことを拒みようがないほどに躯へ刻み込まれた。
「レリアちゃんはかわいい声で鳴いてくれるねっ! そんなにボクのおちんちんが気に入ったのかな。それじゃ、もっとイってもらおうかな」
このままでは、犯されてルクスリアの餌となってしまう。
レリアの躯では勝てない。
しかし、ここにきても、まだ揺るがないひとつの事実があった。
ルクスリアの敗因は慢心である。
小さく揺れるレリアの胸に伸ばされたルクスリアの腕が掴まれる。押しとどめたのは他ならないレリアだ。
「あれれ、まだがんばってくれるの?」
「はい……あと三分間だけ、付き合って貰おうかと」
汗と精液に濡れた顔で笑うレリアに、ルクスリアは不思議さで目を丸くした。
「ええ、あと三分だけ……」
レリアの背中から生えていた一対の翼が窓もない部屋の中でゆらゆらと揺れはじめた。
風が吹いていた。
最初は微風。どんどんと風は強くなっていき、前髪が持ち上がって額が見えるほどになっていく。
その風の中心にはレリアの躯があった。
口の中からぬるりと男たちのペニスを離すと、レリアは唇を蛇のように舐めた。
「……付き合って貰います。あたしの本気よりも、もっとすごいものを感じさせてあげますよ」
そうして、少女の躯に変化が生じた。
胸が膨らんでいく。見た目相応の控え目な胸が、ふっくらと姿を変える。
現れるのは、片手で掴んでもこぼれおちてしまうほどに大きな乳房。
変化はそれだけではなかった。
胸の変化に同調して、レリアの躯が大きく変化していた。
手足は長く、舞台の女優のように細く、逞しく、優雅な肉つきのそれに。お尻は思わずむしゃぶりつきたくなるほどの曲線を描く。
数年かけての成長を数秒の間に圧縮すればこうなるのか。短く切られていたオーロラ色の頭髪は腰の位置よりも低く、座っていれば床に落ちるほどに長い。オーロラを夜空から切り取って編んだ帯のようだ――そう幻想を抱かせる、超常的な美しさだった。
いつの間にか、ルクスリアの肉棒を膣で銜え込んでいるのはレリアではなく、彼女の変化した情熱的な美女になっていた。
唖然としているルクスリアに、美女はくすりとほほえみかけた。
「――さて。この躯を使うのは久しぶりなのだけど。改めて挨拶をした方がいいかしら、ルクスリア?」
「え、え、レリアちゃん、だよね……?」
「そうよ。もっとも、この躯のときは襲名した名前を名乗っていたのだけど……そうね。ややこしいから、あたしのことはレリアと呼んで貰って構わないわ。ルクスリアがふたりいては面倒だものね」
「る、ルクスリア? それって、ボクと同じ……もしかして!?」
思いの外察しの良いルクスリアに、レリア――と自称した女性はほほえんだ。
「ええ、お察しの通り。先代の色欲――淫蕩のルクスリアよ。あなたとは初見だけどね」
先程、ルクスリアは自分が淫蕩と呼ばれるために淫魔たちと戦ったと口にしていた。だが、それはおかしい。七つの大罪の襲名は、襲名者を倒すことで得られるものである。他の淫魔たちにわざわざ認めさせる必要はない。
「まあ、それも当然よね。あたしは何年も前に行方をくらましてしまったんだもの。人間にでも倒されたんじゃないかって、騒動にでもなっていたかしら?」
「そ、そりゃすごい大騒ぎになって……って、なんでそんな人がレリアちゃんになってたの!? しかも、敵になってるし!」
「別に称号があったとしても、あたしたちは味方というわけではないでしょう? 利害が違えば敵にだってなるわ。それに、あんなちっちゃい姿になっていたのは……ふふ、あなたたちの思っていた通り。あたしが人間に負けたからよ」
「嘘……」
「あ ら、ホントよ。もっとも、あれは人というより魔女だけど。しかも、その上で力を封印されて、あんなに小さな躯にされて助手としてこき使われたんだか ら……。でも、ちゃんとあのときはあの人をイかせてみせたけどね。あんなに気持ちよさそうにしてる顔を見たのはあれが最初で最後だったわ……」
頬に手をあててうっとりとするレリアを呆けながら見ていたが、はっと我に返るとルクスリアは豊満になったレリアの胸を掴んだ。
うなじを撫でてくるように色っぽい声をあげるレリアを前に、ルクスリアは完全に調子を取り戻していた。
「よく考えたら、レリアちゃんが誰だったかなんて関係ないよね。だって、もっと楽しめることには変わりないんだもんっ」
舌なめずりをして、ルクスリアはまた下からレリアの躯を突き上げる。幼い見た目のためにふわふわと軽かった前までのレリアと違って、今のレリアは十代後半 の完全に成熟した躯。そのため、ペニスに加わる感触もまた違ったものになっている。レリアが重くなって、より奥までペニスがねじ込めるのだ。
両手でレリアの乳房を揉みしだいて、膣の中で肉棒を暴れさせる。ぐちゅぐちゅと蜜壺をかき回す音とレリアの喘ぎ声が卑猥な合唱となって石壁に反響していた。
「んあっ! ああ……っ、まったく、人の話くらい最後まで聞いてから動きなさいな。これだから堪え性のない淫乱はっ」
「レリアちゃんだって、ボクの精液と愛液で中がぐちゅぐちゅだよ? イきたくてイきたくて、我慢できないんだよね! ほら、君たちもぼーっとしてないで……お尻とかおっぱいとか、使ってあげて!」
ルクスリアがレリアの乳房から手を離すと、男のひとりが前に回り込んだ。ルクスリアをまたいで、男は肉棒を正面からレリアの胸へと押し当てる。
ぷにっ、と亀頭に伝わる感触にペニスが射精する間際のように脈打つ。乳房を乱暴に掴むと、そのままペニスを挟み込ませた。
レリアの口から溢れ出た精液で濡れた胸の谷間に極太の肉棒が潜り込む。すっかり大きくなった乳房は、しっかりと男性自身を銜え込んで離さない。
ペニスを包み込む極上のクッションのような乳房の圧力に、男は腰をがくがくと震わせながらレリアの胸を突き上げる。
「んっ、久しぶりのおっぱいなんだから、もっと丁寧に扱ってほしいわ……んあっ」
白濁塗れになって泡を立てながらじゅぽじゅぽと胸の間から顔を出す亀頭を眺めていると、レリアの菊座にもう一人の男のペニスが宛がわれた。
躯が小さかったときに別の男に射精させた精子が、まだ後ろの穴にも残っていた。レリアのアナルは簡単に男のペニスを受け入れる。
ずんっ、と一気に奥までペニスを突き入れられた。その衝撃にレリアは躯を仰け反らせて喉の奥から嬌声を洩らす。
「あっはぁ! 淫魔と男のおちんちんで一緒にされると……すごいわね……っ」
「それがボクにも伝わってくるよ……レリアちゃんの中もきゅんきゅんって締め付けてくる! ボクも気持ちよくて……またイっちゃうね!」
乳房と膣とアナル。同時に三つをかき回さす肉棒の速度はフィニッシュとばかりに動きを早める。
「イくよ、イくよ、レリアちゃん! 全部受け止めてね!」
「んんっ、ああ……あたしも……っ! あああんっ」
レリアの腰を両手で掴んで何度も突き上げていたルクスリアは、形の良いお尻に力をいれて思い切り肉棒を押し込んだ。
大量に出された白濁と愛液の混じり合った混合液で濡れた膣に締め付けられる感覚に酔いしれながら、また精液をレリアの中にぶちまける――。
「あは……出てる、沢山レリアちゃんの中にでてるよっ」
どく……どく、どく……っ! 放出される精液は今日一番の量で、子供を育てる子宮の中をあっという間に白濁とした子種だけで満たしてしまう。
「あ……ああん……っ」
同時に達したレリアの膣が甘くペニスを締め付ける。きゅっ、きゅっ、とまだイっている最中の肉棒を刺激して、それがさらにルクスリアの射精を助長した。
たっぷりと放出される媚薬のような精液に、レリアの美しい顔が艶美に蕩ける。その顔を目掛けて、レリアの胸でペニスを刺激した男も射精した。
胸が変形するほど力を込めて肉棒を圧迫すると、男のペニスから飛び出した精子がレリアの顔を真っ白に染め上げる。ドロドロの砂糖細工でデコレーションされ ていくレリアは、射精を続けるペニスに唇を押しつける。ぷにぷにと弾力のある唇で亀頭に吸い付き、夢中になって精液を呑み込む。
「んん……っ、んー! んふ……っ!」
獣のような激しさで首を振り、ペニスから一滴残らず精子を搾りだそうと自らの手で胸を圧迫する。
そして、レリアの臀部に腰を寄せながら、最後の男もまた限界を迎えていた。
アナルの中に流れ込んでくる、汚らしい男の精子。直腸に直接叩き込まれるどろりとした粘液の感触に、アナルはきゅっと勢いよく絞まった。
性器と、排泄器と、口。レリアはその三つへ同時に子種という白濁を注ぎ込まれていた。
「あはは……これで、ちゃんと先代の淫蕩も堕としちゃったんだ……。これで、誰もボクに文句なんて云わないんだね……」
射精をしながら、ルクスリアは頬を緩ませたまま自分の成した行為の結果に酔いしれる。
「あら、それはどうかしらね……」
「え?」
そういったのは、胸に挟んだペニスから顔を上げたレリアだった。
胸に精液を注いでいた男が直立不動になったまま動かなくなっていた。それをレリアが横に押すと、抵抗なく地面に倒れる。自我をなくした肉人形は精を搾り尽くされて息絶えていた。
もうひとつの何かが倒れるどさり、とした音。レリアの菊座に挿入したまま、最後の男も力尽きていた。
「射精、まだ止まらないみたいだけど?」
「あ、あれ……そんな、おかしいな……なんで、ずっと止まらな……あぁあうっ」
戸惑っているルクスリアのペニスを膣が締め付ける。
「止まらないわよねえ。だって、そうしているんだもの」
「ふぇ……?」
「だってあなた、淫魔としての力はあたしよりも凄いのだけれど。技巧もなにもないじゃない。大方、周りの淫魔たちもこのおちんちんだけで喘がせてただけなんでしょう?」
「そうだけどっ」
「格下ならそれで瞬殺できたでしょうけどね。自分と同等の相手にこんな敏感でかわいらしいもの挿入しちゃったら……それこそ淫魔と人間くらい差が出るに決まってるじゃないの」
レリアが唇についた精液を舌で舐めとる。高位淫魔であるルクスリアですらぞくりとするほどに艶然な仕草だった。
「光栄に思ってね……これが、人間と同じ立場で感じられる、淫魔の妙技よ」
ぐにぐにとレリアの膣が動き出す。襞が上下に、左右に、あるいは捩るように、包み込むように、ぐにぐに、ぐりぐり、ぐにぐに、ぐりぐり……。
「や、や、やめ……っ! だめぇ……しゃ、射精がとまらないよぉ……!」
「止めて欲しいの?」
レリアが首を傾げて、腰を持ち上げる。膣から開放されていくペニスに、ルクスリアは胸を上下させて荒く呼吸を繰り返した。
「ひあ、あ……や、やめ……」
「うふふ、だーめっ」
体重を乗せてレリアは一気に腰を落とした。
ずぷんっ! とルクスリアの肉棒が襞に擦られながら呑み込まれる。とまらない射精で神経がむき出しになったも同然なペニスに与えられる刺激は淫魔をも狂わせた。
「や、あ、あああああああああっ! 頭っ、ボクの頭っ、飛んじゃうよぉおおおお!!」
どくんっ! どくんっ! どくんっ!
びゅくっ! びゅるるっ、びゅるっ!
どぷっ、どぷどぷ……っ、どぷんっ!
「あ、あう、ああ……」
大きくなったレリアの膣内にも入りきらなくなった精液が結合部から流れ出す。床の敷物も吸収しきれないほどの白濁液が水をぶちまけたように床に広がっていった。
「あ、ああ……」
「ふふ……」
終わらない快楽で気絶したルクスリアの頬をレリアの指先が撫でる。それは自分の跡継ぎに向ける賞賛のような行為だった。
「あなたが油断してくれなければ、この姿でも負けていたでしょうね。力を封じた状態で仕掛けて、正解だったわ……」
んっ、と声を出して足に力を込めるとレリアは立ち上がって膣からペニスをぬく。そこで躯に力が入らなくなった。
床に尻餅をつく――そのときには、もう少女の姿に戻っていた。
本来の姿に戻ってちょうど三分が経過していた。
「先生ったら……キスするついでに封印を緩めてくれるんなら、もっと長い間動けるようにしてくださいよね」
不満を零して、レリアは床に大の字になって寝転がる。もう起き上がることすら億劫だった。
レリアは自分に失望していた。
ひとりで他の全員も相手をする。そう啖呵を切ったくせにルクスリアひとりを倒したくらいでこうも疲れて果てている自分自身が、どうしようもなく情けなくなかった。
――あたしが無理をすれば、ギヨたんは何もしなくて済んで、寿命は少しでも延びるかもしれない。
魔が差したと表現のできる思考だった。
レリアも自分らしくない考え方だと自覚していた。
しかも、アンナマリアはいうなれば自分の獲物を奪おうとする敵である。それこそ、この高位淫魔たちよりもレリアにとっては脅威度の高い敵である。
なのに、どうしてだろう。
友情? 同情? 愛情?
考える。
……どれも、違う気がした。
友情と云えるほど綺麗なものはふたりの間にはなかったし、同情に至ってはそんな感情を抱く理由がない。アンナマリアは自分の意志で決断した。その道を哀れ むのは、なによりも彼女を冒涜することだとレリアは思っていた。愛情は論外で、それに類した感情は一切持っていない。躯を重ねたことはあっても、あれは淫 魔にしてみればじゃれているようなもので、スキンシップの一環なのだ。
では、他になにがあるか。
レリアは目を閉じる。
自分を駆り立てた感情がなんであるのか、やはり名前をつけることはできなかった。もやもやと、ぐるぐると、胸の裡で巡る霞みのような気持ちの揺らぎは掴もうとしても指の間をすり抜けていってしまった。
掴もうとしても、逃がしてしまう。それが大切なものであるはずなのに、自分では理解できない。
胸に喪失感が浮かぶ。判るはずの感情、掴めなければおかしいはずの感情を取り逃してしまったが故の悲しみ。
ふと、抱いた感情がアンナマリアに向けている感情と同じであることに気付いた。
ああ、そうだ、とレリアは笑う。ようやくちぐはぐだったパズルのピースが揃った。
――あたしは、寂しかったんだ。
たとえ、出会ってから数日としか経っていなくても。アンナマリアがいなくなってしまうことが寂しいのだ。
安心したら、レリアにどっと疲れによる眠気が押し寄せた。
少し、眠ろう――睡魔に身を委ねる。
意識が闇に落ちる寸前になって、レリアは自分とアンナマリアの関係を表す言葉を思いついた。
そう、ふたりは――くだらないことでも争うような。
そんな、悪友だ。
first battle.
レリア・キッス VS. ルクスリア
Winner レリア・キッス
To be continued Second battle...
「……おや、どうやら、我が不肖の愛弟子は無事役目を果たせたようだね」
ソファに身を沈めていたイザベラは顔をあげると、なんでもないことのように口を開いた。その目は壁の方に向いていただけだったが、どうやら遠い彼方の出来事でも覗き見ているらしかった。
「え、それは本当ですか、魔女先生!」
「本当だとも。あれでも私の助手なのだから、淫魔のひとりくらい倒せるのは当然さ。心配する必要もなかったね」
「……それくらいしてもらわないと、困る」
安堵を隠さぬジョゼフとは正反対に、アンナマリアは鼻を鳴らすだけだった。けれど、よく見るとその口元がわずかにほころんでいる。経過を見ることができず、ただ結果を待つだけという状況では、口でどう云おうとアンナマリアも心配だったのである。
しかし、そこでイザベラは軽く手を叩いてふたりの視線を集めた。
「けれど、さすがにひとりが限界だったみたいだね。というわけで、ジョゼフにも出張ってもらう必要がでたわけだ」
「……覚悟はしていましたよ。巧くいくかはわかりませんけど」
「じゃあ、さっそく次はジョゼフにいってもらおうか。スペルビアは最後に残しておくと兵を指揮されて面倒そうだからね」
改めて要求されて、ジョゼフの顔が緊張で強ばった。今まで淫魔やアンナマリアたちの好きなように扱われていただけの自分が高位淫魔たちと戦わなければならないということにたじろいでいるのだ。
「う……わかりました。でも、確か団長とはまず剣で力比べしなきゃいけないんですよね。ぼく、剣とかもってないんですよ」
「それなら……そうだな、ちょっと待ってなさい。確か倉庫に……」
イザベラはぼそぼそとつぶやきながらリビングから廊下へと出て行き、奥の方へと引っ込んでしまう。奥の部屋の方からゴソゴソと何かを探る大きな音がしたかと思うと、すぐに扉が開いた。
「ふむ、これなら良いだろう。昔、知人に貰ったものだ。さっきまで倉庫で埃を被ってたんだけどね」
戻ってきたイザベラの手には一振りの剣が握られている。華美な装飾はなく、鍔もとにはめ込まれた赤く光る宝石だけがその直剣に施された唯一の飾りだった。 刃渡りは九〇センチ――ジョゼフの上半身ほどもあり、刃にも曇りはなく倉庫に放置されていたとは思えない程の輝きがあった。
「そんな、適当な……」
「でも、充分なだろう?」
無造作に剣を投げられて、ジョゼフはあやうく取りこぼしそうになりながら剣を受け取めた。久しぶりに腕で感じる頼り甲斐のある鉄の重みに、柄を握る手に力がこもった。
「ええ、良い剣です。というか、こんなものをくれる知人ってなんなんですか」
「ええと、パラ……ううむ、長くて名前は思い出せないね。ま、道楽者なのだよ。では、早いところ相手のところにキミを送りこみたいのだけど、準備はいいかい?」
「ああ、はい、どうせこれ以上準備することも……」
服の裾を掴まれて、ジョゼフは言葉を止める。視線を落とすと、アンナマリアの手があった。
「アンナマリアちゃん?」
「……ひとつだけ、」
「なに?」
「夢中になって搾り取られたら殺す」
「取られません!?」
ぱっと手を離すと、アンナマリアは頷いた。
「なら、よし」
「う、うん、それじゃあいってきます……」
ジョゼフが苦笑すると、イザベラが手を差し出す。
「さて、それじゃあ行くよ。ジョゼフ」
「はい!」
笑顔のままにイザベラはジョゼフの目の前に手を持ち上げ――ぱちんっ、と指を弾いた。
それが合図となり、ジョゼフはレリアのようにまだ見ぬ場所へと飛ばされた。
転移術式によって、まるで白昼夢のようにジョゼフがかき消えたのを見届けると、イザベラは押し黙っているアンナマリアを振り返った。
「それで、あれでよかったの?」
「よかったって、なにが」
無愛想な表情のまま、アンナマリアはイザベラを見上げる。不機嫌なわけではなさそうだったが、下から睨み付けているように見えてしまう程度に、アンナマリアの目つきは悪かった。
「もっと、なにか云いたいことがあったんじゃないの?」
「……別に」
一言で突き放すと、アンナマリアは毛布を抱きかかえて顔を埋めた。なにも語ろうとしない様子にイザベラは苦笑して肩を竦めた。
「そうかい。じゃあ、言葉の続きは帰ってからにするといいさ」
アンナマリアは黙ってソファに座ったまま、毛布を被って何も答えなかった。。
*
目を開くと、視界一面に広がるのは深緑だった。
そよ風が頬を撫でていくと、くすぐったさにジョゼフは目を細める。息をすると、青臭い草の香りで胸の中が一杯になる。イザベラの家の中は埃っぽい空気で満たされていただけに、ジョゼフは躯が浄化されていくような印象を受けた。
「ここは――」
顔を上げると木漏れ日が目に入り、まぶしさで顔を手で庇う。
「覚えてないか、我がお前を斬ったところだ」
自分の背中にかけられた声でジョゼフは振り返った。
目に入るのは、革製の防具を着込み、腰に剣をはいた女性の騎士である。
ふたりの距離は一〇メートル。
間合いを詰めるに必要な時間は、瞬きひとつもあれば充分な距離。
女性は革の鎧と裾の長い、露出をとことん抑えた衣服を着ており、厳格さを感じさせる。けれど、その厳しさとは対極にあるだろう妖艶さがその女性からは漂っていた。
例えば邪魔にならぬようにと後頭部で髪を纏めるための紐から外れてしまった後れ毛の妙な色香。シスターのように肌の露出を控えているのに唯一無防備にさらけ出されて、人の視線を集める首もと。
高潔さと淫靡さを危ういバランスで両立させた女騎士。その存在の名をジョゼフは重々しく口にした。
「覚えていますよ、スペルビア団長。腕を切り落とされたなんて経験をした所を、早々忘れられはしません」
ジョゼフは、兄が存命中だったかつて、騎士団に籍を置いていた。そこで革命の雰囲気を敏感に察知し、まだ事を起こす前に退団したのである。けれど、スペルビアはジョゼフを見逃さなかった。ある日、月の下でジョゼフをここまで追跡し、腕を切り落としたのだ。
本来なら出血多量でジョゼフは息絶えていたが、そこを通りがかった魔女イザベラに命を救われたのである。
そんな印象的な出来事を忘れることができようはずもない。意識すると、斬られた右肩の辺りが痛みを思い出してざわめいた。
「今日は自衛をかねて、あのときの返礼をさせてもらいにきましたよ。剣の扱いだけで解決できれば越したことはないんですけど……」
「弱気だなあ、ジョゼフ。それに云っておくが、高位の淫魔たる我を人間が剣技だけで制圧しようなどなどと思いやがりであるぞ。男なら、床の方でも勝負をしてくれなければ、股のものも無用の長物というものよ」
そこまで云って、スペルビアは鼻を鳴らした。
瞬間、木々が絶叫した。まるで突風が吹き抜けたように、激しく激しく枝を擦り合わせ。
「もっとも、剣の方でも負ける気など更々ないがな」
スペルビアから吹き荒れた闘気が木々を打った。そうとしか思えない程の獰猛な気迫を真正面から叩きつけられて、ジョゼフは口内に溜まった生唾を飲み下す。
レリアの戦いが終わるまでの間にイザベラから伝え聞いたスペルビアの情報について、ジョゼフは思い出していた。
〝傲慢の〟スペルビア。それは淫魔の中でも異端の中の異端である。それは一目瞭然で、剣があるからだ。
淫魔は躯を資本とし、生物の精気を栄養素として消費する生態をもっている。よって、人間女性のソレとは違い、躯は人を堕落させるために最適化された肉体として成立しているのだ。
周囲の生物を魅了して自身の虜とすることで対象を自衛手段として使役できる淫魔にとって、自分自身の戦闘能力など些細なものである。よって、淫魔たちは基 本的に腕力に代表される物理的な力を求めない。むしろ、自衛するための手段に困るようでは淫魔として恥ずかしいという風潮すらあるのだ。
強い個人戦闘能力を持つ淫魔は、淫魔の中では即ち人を魅了できないおちこぼれとされ、迫害されるものなのである。地位すら得られず、仮に得たとしても淫魔本来の技量に劣るものがいつまでもその座にいられるわけがない。
だが。このスペルビアはそれらの論を覆す存在だ。
なにせ、剣の腕は中途半端なものではなく、一流。そのくせ、七つの大罪を関する地位に立って、しかも他の淫魔と協力関係を結んで国をひとつ落としたのである。軽蔑されていたとしても対等の関係で取引ができる、そんな規格外の淫魔なのだ。
よってそれは淫魔本来の淫技も、そして剣術も一級品である証左。なによりジョゼフは身をもってスペルビアの手管を体験している。冗談ではなく何度も殺され、蘇生され、を何度も繰り返させられるほどの快楽地獄であった。
ジョゼフは呼吸を整えて、精神を落ち着ける。呼吸は戦いにおいての基本であり、これが乱れれば剣筋も動きも相手に筒抜けになってしまう。当たり前に行っている活動が即生死を別つ要因となる、今立っている世界とはつまりそういうものだ。
「ぼくは負けるつもりなんてありません。だからまずは……この剣であなたを無力化する!」
「いいだろう。ではその気概に免じて、一太刀くれさせる権利をやろう。さあ、どこからでも好きに打ち込んでくるがいい」
スペルビアが腕を組んで傲岸不遜に言い放つと、ジョゼフは厳しい表情で剣を構えた。半身の体勢で剣を腰の高さまで降ろし、油断なく切っ先を相手に向ける。
腕組をした相手に反して、ジョゼフの構え方には一切の驕りや怒りはなかった。ふつうならスペルビアの言葉を侮辱と受け取って怒りそうなものだが、それは自身と相手が対等であると思っている者だからこその発想だ。
力の差は、圧倒的なまでに横たわっている。よってこれは勝機。ならば万全に生かさぬ道理はない。
一拍置く。
肩に剣を担ぎ、
ジョゼフは一気に間合いをつめた。
「は――っ」
迷いなく振り下ろされた一刀は孤を描きスペルビアの首もとへと振り下ろされる。
好機を伺う時間的猶予はジョゼフにはなく、さらに待つだけ時間の無駄と判断したが故の即断の踏み込み。
未だに剣を抜いてすらいなかったスペルビアには到底受けることの適わぬ斬撃。
けれども、それはスペルビアが人間であったらの話だった。
剣が振り切られ、ジョゼフの手に伝わる感触は――無。
空を切った剣にジョゼフは目を見開く。
視界からスペルビアが消失していた。
消えた? 否。ただ、視界から外れただけのこと。そして人の視聴角など、至近距離になればなるほどかいくぐるのは容易。
ならばこの短時間で音もなく跳べる場所は、左右どちらかしかあり得ない。
右か左か、どちらにスペルビアがいるか――。
――ジョゼフは迷わず右へと剣を振るった。
鉄と鉄がぶつかりあって衝撃がジョゼフの腕に走る。重い打撃を受け止めた余韻で腕が電気が流れたように痺れた。
ジョゼフの眼前でスペルビアが笑う。それは好敵手を前にした肉食獣を連想させた。
「ほう、受けたか。以前ならばこれで勝負は必定であったはずなのだがな」
「生き物は、無意識に心臓がある方を庇って左へと動いてしまうもの……右から攻めてくると思ってましたよ。いや、確信を持ったのは以前あなたが切り落としたのが右腕だったということですけどね」
「読まれていたか。そうさな、我はその右腕が気に喰わん。当然よな。なにせかつて斬って捨てたものが亡霊のように舞い戻ったのだ。冥土に送り返さねば気がすまない!」
お互いに相手の剣を押し合ってふたりは距離を取る。
既にスペルビアは剣を抜いた。アドバンテージはない。ここからは、一瞬の判断違いが死を意味する戦場だった。
「征くぞ、精々我を楽しませてみせよ。有象無象の者共との違いを見せねば……ここで屍となれ!」
歯をむき出しにして笑い、スペルビアは突風となってジョゼフに斬りかかった。
頭をかち割ろうと振り上げられた剣、胴を薙ごうと腰で溜められた剣、腕を切り落とそうと跳ね上がる剣。それら三つの予想される太刀筋が幻影のようにジョゼフの視界に重なった。
どの太刀がくるか。受け損なえば即ち敗北。
どれが――どれが正しいのか――。
刹那に見たぬ逡巡。だが、答えを見つけて愕然とした。
これら三刀は総て同時に繰り出される。
スペルビアは人間でなく、よってその練度は人の領域外にある文字通りの人外。
ならば、三者択一なわけがなく。それら総てを同時に成せる。
同時に襲いかかる三刀はどれもが必殺。
よって、この瞬間に人の敗北は定められたも同然だった。
*
「……ジョゼフは、勝てるかな」
イザベラとふたりきりになったせいか、静かな部屋の中でアンナマリアがぽつりと弱音を洩らした。
毛布に顔を埋めているアンナマリアを見て、イザベラは大きな胸を悩ましげに揺らしながら腕を組み、首を傾げる。
「心配かい、ギヨたん」
「だって、前に腕を切り落とされたとか聞いたから。腕は繋ぎ直せても、それで勝てるのかな……」
アンナマリアはジョゼフが剣を振るうところを見たことはなかった。パン生地をこねている姿ならいくらだって思い浮かべることはできても、剣を振るうところ は想像すらできない。そのせいで、ジョゼフの勝算がどれほどのものか、アンナマリアは予想することすら不可能だったのだ。
その心配事に、イザベラが笑った。
「なんだ、そんなことか。そうだね、ギヨたんがそう思い違いをしていたら、それは心配になるわけだ」
「なに、それ。わたしが知らないからって、そんな上から目線」
「いや、私もジョゼフが剣を使っているところなんて見たことはないよ。私がいっているのは別のところだ」
「別の、こと?」
「そうとも」
イザベラは悪戯の種を明かす子供みたいな調子で云った。
「――私が、同じ腕をつけ直すと思うかい?」
「……え?」
「だいたいジョゼフの腕は草花に紛れてどこにいったかわからなかったんだよ。きっと今頃は動物たちの餌になって骨しかないだろうね」
「え、ちょ、ちょっと待って。じゃあ、その……」
アンナマリアはから毛布を腋に投げ捨てて、呆然とイザベラの目を見た。
「今、ついてる、右腕って、なに?」
*
(――栄光の手《ハンド・オブ・グローリー》、起動)
ジョゼフの感覚の中で、右腕のそれが変質を開始した。
まるで、右腕の血流だけが加速させられたような不可思議な感触だった。腕の根本を力一杯紐で縛ればこうなるだろうか。ジョゼフの人体から右腕だけが完全に独立し別系統の生物として活動を始める感覚。
その間にも、一刀による三連の斬撃はジョゼフへと迫り――
「定義:内部加速三倍――!」
ジョゼフの右腕がかき消える。
瞬間、三度剣がぶつかりあう甲高い音が木々を突き刺した。
獲物を定めた猛禽がごとく、スペルビアの目つきが鋭くなる。睨まれただけで背筋が撫でられたような寒気を覚え、跪いてしまいたくなる痺れるような眼孔にジョゼフは危うくたじろぎそうになった。
しかし、スペルビアの口元に浮かぶのは歓喜。
「ほう、その腕、人の理……科学のものですらないな。今の太刀を受けた人間はお前が初めてだ!」
好敵手に巡り逢えたことを歓喜する遠吠え。だが、ジョゼフの内面はスペルビアの歓声に悲鳴で答えそうになっていた。
「ぐぎ……っ」
右腕の筋繊維と血管が何本か断裂した。その痛みが稲妻のように脳を突き上げて、眼球の中でいくつもの火花が散った。
栄光の手――ジョゼフの右腕としてつけられた切り札の名である。
それはイザベラが制作した魔術道具のひとつだ。栄光の手という輝かしい名前から考えられない方法で作られた逸品である。なにせ、材料は死蝋化した腕なのだ。
多くの文献に記された栄光の手の効力は家にいる者の活動を停止させるなり、外部の人物の行動を抑制するお守りであった。
けれど、イザベラの発想は飛び抜けていたのである。ジョゼフが身に着けた栄光の手は、外部ではなく内部、つまり腕そのものの活動に干渉した。しかも、外側ではなく内側に向けることで、効果範囲だけでなく効果そのものまで反転したのである。
即ち、時間を未来方向においてのみ加速させる、そんな化け物じみた代物となった。
欠点はある。まず、腕をこれにすげ替えねばならない。ふたつめに、反動による苦痛がどうしようもないということだ。
死蝋化した腕、人体に馴染んで人肌の体温をもったせいで痛覚までもが復活した。そのために、力を強い度合いで出せば出すほど代償として痛みを負うのだ。実際に血管や神経なんてひとつとして引きちぎれていないとしても。
「……っ、まだ、まっだぁっ!」
栄光の手による効果は、あくまで右腕のみ。それ以外は所詮人並み。腕の加速という切り札が相手に知られた以上、戦いが長引けばそれだけ不利。
よって痛みを振り切ってジョゼフは踏み込んだ。
「定義:内部加速二倍――!」
右腕が倍に加速した。下がっていた剣が瞬時に跳ね上がり顔を薙ぐというあり得ない挙動を実現する。
スペルビアは剣で受けなかった。躯をうしろへ逸らし、紙一重で剣をやり過ごす。掠めた剣で髪が吹雪きのように散った。
「手ぬるいぞ!」
一気呵成、スペルビアの剣が真っ向から落雷のように落とされた。
受け止めるには時間がない。
内部加速、と指令を出そうとして痛みに集中力が阻害された。駆動速度を落としても連続使用による幻痛は脳の腫瘍となって邪魔をする。
ジョゼフは踵で思い切り地面を蹴った。半ば体勢を崩しながら横へ跳ぶと、真横を剣が擦過して地面に激突する。
轟ッ! と地響きを立てて土が舞い上がった。本当に雷が落ちたと錯覚しそうになる力強さ。
受け止めていたら自分の剣ごと頭をかち割られていたかもしれない。その未来を想像して背筋が氷のように冷たくなった。
これ以上時間をかけてスペルビアのエンジンがさらに火を噴けば、栄光の手を持ってしても対抗は不可能となるだろう。
ジョゼフは奥歯をぐっと噛みしめる。歯が軋む嫌な音がした。
ならば、スペルビアが万全となる前、わずかに残った現状の光明を――逃さずに掴むしかない!
「定義:内部加速――三倍!」
剣を振り下ろして無防備になったスペルビアの躯を横から薙ぎ払う。剣の軌跡はジョゼフ自身の目にすら止まらぬ電光石火。
だが、それに反応してみせたスペルビアはまさしく悪夢と呼ぶにふさわしい能力の持ち主であった。
弾かれる剣。スローモーションとなって迎撃される剣の動きがジョゼフに見えた。
力押しでの太刀はその肌に触れることすら許されず、搦め手を駆使しても基本スペックの差で対応される。赤子の躯で大人を倒そうとする方が、まだマシなことのように思えるほどに、身体の差は歴然としていた。
――故に、ジョゼフはさらに無茶をした。
「定義:内部加速――四倍!」
腕が肩から引きちぎられたかとジョゼフは錯覚した。
それほどに腕が振るわれる速度は速く、
けれど、スペルビアはそれに反応していた。
絶望的な反射速度。
剣と剣の激突になるのは最早確定事項であり、
それこそがジョゼフの目的だった。
「定義:内部加速――五倍!」
剣が二段で変化した。だが、その変化はホントにわずかな動き。剣の中ほどで受け止められるはずだった剣を、相手の剣の先端部へ移動させただけだ。
しかし、これだけのことが目的であり勝機。
剣と剣の激突。
何かが宙を舞った。くるくると円を描きながら木漏れ日を反射する物体は、放物線の軌跡で地面に突き立つ。
「……なっ」
絶句したのは、スペルビアだった。
ジョゼフの一刀が、彼女の剣をはじき飛ばしたのである。
それこそがジョゼフの狙いだった。力量ではまず間違いなく及ばない。十回やれば十回負ける。百回やっても、やはり百回負ける。万に一つだった勝てる可能性はない。少なくとも、騎士としての競り合いではだ。
なら、相手を戦えない状態にするしかない。その末に思いついたのが相手の武器を手放させることだった。
膨大な加速度をつけられた鉄の塊が剣の先端にぶつかれば、それを予期していなかった場合なら手で保持していられなくなる。その結果を期待したがための最後の一刀だったのだ。
それでも、相手がまだ全力を出し切っていなかったからこそ出来た芸当である。少しでも当たり所が悪ければ、相手の手にはまだ剣が残っていたことだろう。間 隙の攻防を勝ち抜いてジョゼフが安堵すると、手から剣がこぼれ落ちて地面に突き刺さった。無茶をさせた右手にはもう力が入らず、それを掴むだけの握力は残 されていない。
よってここに武力による戦いは終止符が打たれた。
今のジョゼフはスペルビアなら素手でも殺せるだろうし、剣を拾えば尚のこと簡単に仕留めることができるだろうが、騎士としての誇りが許さないに違いない。よほどこの場でジョゼフを暴力で殺したいというなら話は別だろうが――。
スペルビアは楽しげにしているだけだった。
「すばらしい、よくぞ我の手から剣をはじき飛ばした! これ以上食い下がるのも無粋の極みというもの。我の負けを認めよう。それに、合格だ。我が搾りとって果てさせるに相応しい。殺すならそちらの方でなくては楽しみ甲斐も薄れるものだ」
そう、スペルビアとの戦いは二段構え。それが彼女の強敵たる理由であり、淫魔の中でも別格として誰も触れようとしない原因である。
ジョゼフは感覚が喪失した右手を抑え、額から汗を流した。
「ちょ、ちょっと、休憩を……」
「安心せい。お前のしてほしいことは我がやってやる、存分に求めるがいい。それに、苦痛など感じなくなるほどの快楽を与えてやるからな……麻酔のような、快感を」
スペルビアはその場に膝を突くと、有無を云わさずジョゼフの股間に顔を寄せた。
剣を打ち払われたことによる痛みはスペルビアには残っていないのか、あっという間に慣れた手つきでジョゼフの下半身をむき出しにする。
「口ではどういおうと、やはり男はこうなるものだな……もうガチガチではないか」
「うっ……」
純白の手袋をはめたスペルビアの指先が、勃起した一物に絡みつく。粘膜に伝わるさらさらとした布の感触にジョゼフは切ない声を洩らした。
手袋越しでもわかるほど、スペルビアの指は剣を扱うものとは思えないほど美しいものだった。触感こそ普通の女性より硬さがあるものの、たこや傷のようなものは感じられない。楽器でも扱うような繊細な動作で竿をさすっている。
すりすりと軽く撫でられて、肉棒の硬度は簡単に頂点まで達してしまった。それを見て、スペルビアは口元を持ち上げてからかうように眼を細めた。
「どうした、まだ触れただけだぞ。この様子では、また無様に我の中で果て続けることになるのではないか?」
「こ、今回は大丈夫ですっ」
「そうか? ならば、試してやろう……まずは、我の口でな」
妖艶に微笑んだスペルビアは唇を舌で舐めると、唾液の糸を引く口を開いて――一息に肉棒を呑み込んだ。
「うわ……っ」
ペニスが生暖かい口の中に包み込まれて、思わず腰を引いて声を洩らした。
「ふふ……っ、どうした、まだ……んっ、口に含んだだけだぞ? 唾液で濡れただけなのに、そんな気持ち良いか?」
舌がぬるりと雁首に絡みつく。もしこれが以前のジョゼフだったなら、既に射精していたことだろう。アンナマリアやレリアたち、高位淫魔たちに弄ばれた経験がなければ、もうこの時点で勝負は決していた。
けれど、このままで耐えきれるとは……。
手を握りしめて必死に射精感を堪え、尿道に舌を差し込まれてかき乱される脳内で勝機を探っていると、ジョゼフははたと気がついた。
「……あっ」
「くく、どうした? 今頃気付いたか?」
ペニスの根本を握りながら顔を上げたスペルビアの顔はにしてやったりというものだ。
当たり前のことにジョゼフはようやく気がついた。
スペルビアの口淫にいくら耐えたところで彼女にはなんら快楽は与えられない。このままではやがて射精してしまい為す術なくスペルビアに搾精されるだけなのだ。
「し、しま……っ」
「慣れないことはするものではないよなあ。さて、まずは一発出してもらおうか」
じゅっ、じゅっ、と喉の奥まで亀頭を誘いこむと、スペルビアの柔肉でパンパンに膨れあがったペニスが圧迫された。
――ダメだ、我慢、我慢しないと……っ!
「ほらほら、我慢は躯の毒だぞ? 口が物足りないなら、そうだな、胸でしてやろう」
スペルビアは胸を覆っていた革の鎧を外すと服の下から胸を溢れさせて、唾液に濡れたジョゼフのペニスへ押しつけた。
剣術をおこなっているために引き締まった肉体についた乳房は控え目なものだったが、逆にその小ささがアンバランスな卑猥さを醸し出していた。高潔な女性騎 士の柔らかい胸に亀頭を押しつけられた背徳的な光景と伝わってくる快感の暴力に、ジョゼフはがんばりもむなしく屈してしまった。
「……っ、う、うわあああっ」
どくっ、どくどく……。
そうして、ジョゼフはスペルビアになんら快感を与えることもできず無様に射精してしまった。
「う、うわ……っ、で、て……っ」
腰が引けてくずおれそうになるのを、スペルビアの手が背中に回され支えられた。
「なにも出来ずに出してしまったなあ? それで、こんなに敏感になってしまって……もうなにも出来ないのではないか? 我の中にいれたらそれだけで射精してしまいそうだな」
唇を濡らす精液を舐めとるスペルビアの仕草に、ジョゼフは愕然とした。麻薬のような快楽で脳内を犯されて朦朧となった思考でも、取り返しのつかないことになったのは重々承知できていた。。
男が淫魔に性技で勝つというのはほとんど不可能だと云われていた。挿入した時点で男は圧倒的に不利であるのに、挿入前に射精をさせられて敏感になったペニスでは淫魔の中では一秒とて耐えられない。
つまり、こちらは真実、万に一つの勝目もなくなってしまったのだ。
「さて、もう戦いだなんて気にしないで、あとはたっぷりと我の中を味わって貰おうか」
とんと胸を押されてジョゼフは尻餅をついた。抵抗しようと思ったときには既にスペルビアが馬乗りになって抑え付けている。
「逃がすと思うか?」
「ちょ、待……っ」
スペルビアはジョゼフに顔を寄せて、頬に熱い息を吐きかけた。
「却下だ」
人差し指と中指の間で挟み込まれたペニスをヴァギナに宛がい、スペルビアは腰を落とした。
ずぷっ、とペニスが呑み込まれると、そこは以前体験したあの快楽の坩堝そのままだった。
「あっ、また、で……ううう!?」
肉棒に伝わる甘く暴力的な快感に目の前が真っ白になって、ペニスは爆発した。
淫魔の躯に慣れていたはずなのに、一度射精して敏感になったペニスは一瞬たりとも耐えることができずに精を放出することとなった。
「あ、く、ぁ……」
躯から力が抜けて、ジョゼフは地面の上で無防備に脱力した。その間にも膣肉が手を擦りあわせるように蠕動を繰り返し、ペニスは脈打って精をスペルビアの中に放出し続けていた。
「ははっ、腰を動かしてもいないのだがな……いいぞ、そのまま出し続けろ。安心しろ、死んでも蘇生してやるし……いや、そうだな。夢心地のまま逝かせてやった方がいいかな。痛みは感じさせないでやろう」
腰を挑発的にスペルビアが振ると、そのたびに捩れた膣でペニスを何度も丹念にしごきあげられて精液を搾りとられていく。
「う、うぅううう……」
自分から腰を振ることもできず、したとしても自分の射精を助長することにしかならない。快感で真白く染め上げられる頭と未熟な経験の中では、スペルビアという高位淫魔を打倒する手段は見あたらない。
「ふふ……今、どんな気分だ? 云ってみろ……それとも、もう口もきけぬかな?」
スペルビアが腰を振りながら、指先でジョゼフの腕を撫でた。鋭敏になった感覚のせいで、腕がもうひとつの陰茎にでもなったような感覚で嬌声をあげてしまう。
「どうした、ここを撫でられただけでそんなに感じたか?」
腕に触れられただけで震えていることを手に取るように悟られて、イっているだけでなく恥ずかしさで躯が熱くなり――
――腕?
ジョゼフの脳裏で稲妻のように思考が弾けた。
腕、右腕、操作……。
栄光の手の能力は腕の時間を加速させるものだった。しかし、本来なら外部の時間を操作する魔術道具なのである。ならば、その本来の能力が失われているはずはない。
それに、時間を操作できるなら、もっと対象を限定した変化もできるはず――。
薄れる意識の中で辛うじて掴んだ思い付きだったが、ジョゼフはその賭けにでる覚悟を込めた。
右腕の触感が戻っているのはスペルビアに撫でられて快感を受けられたことで判っている。それでも終わらない射精で巧く動かせない腕を持ち上げて、スペルビアの胸に触れた。
「ふふ、そんなに胸が……我のおっぱいが触りたかったのか。甘えん坊だな」
手に伝わる弾力ある感触と耳に吹きかけられる甘い囁きに脳を蕩けさせられながら、ジョゼフはきわどいところで目的を実行する。
(……定義:外部加速三倍――)
そして、スペルビアの乳輪を指でなぞった。
「……ひぃう!?」
霰もない声をあげて、びくりとスペルビアの躯が跳ねた。とっさに何が起こったのか判らずにスペルビアは目を何度も瞬いている。
(もう一度――今度は、五倍――)
下からスペルビアの乳房を持ち上げて、控え目に握った。
「なぁ!? なっ、なんだ……これは!?」
躯に走り抜ける今まで感じたこともない快感に、スペルビアは嬌声とも悲鳴ともつかぬ声を洩らした。顔を赤らめ、熱くなった肌からは汗が流れ出た。
ジョゼフがしたことは、スペルビアの感度を加速――というよりも増幅させたのである。
この栄光の手は正確には時を操っているのではなく、指定した倍数分の速度を実現させられる程度まで力を増幅するものなのだ。人の睡眠欲求を増幅させて眠ら せたり、そしてこの場合なら相手の躯の感度を上げて指定した倍数分まで快感を増幅するという、それがジョゼフの思いついた応用方法であった。。
「これなら……いける!」
右腕の骨が軋む感覚、それでも腕の速度を加速させていたときと比べればまだまだ軽い。内部加速のときは腕そのものが無茶な動きを要求されたため、物理的な負荷も押しかかっていたのだ。現状の外部加速ならば腕にかかる負担もずっと軽減されていた。
普通に胸を撫でられるものよりも五倍もの快楽を唐突に与えられれば、さしものスペルビアも動揺を隠せなかった。
「くっ、お前、いったいなにをしている!?」
だが、身構えられたらそこは高位淫魔、簡単に対処されてしまう。
あとは短期決戦あるのみ――。
一物をがっしりと銜え込んだスペルビアの性器へと右手を滑り落として、陰核に親指を押しつけた。
「そうか、その右手で!」
完全に気付かれた。つまりこれが最後の一回――
(外部加速……)
軽くなったと云っても右腕の消費がなくなるわけではない。けれど、これが最後の好機というのなら、後先帰り見ずに全力を注ぎ込むのみ。
「……一〇〇倍!」
ぐっと陰核を親指で押し込んだ瞬間、ジョゼフに跨っていたスペルビアの躯が仰け反った。
「ひうっ!? な、こ、これは……これは……こ、この我がイ、イクな……ど……っ、ば、馬鹿な……ぁ、あああああっ!」
陰核から伝わる膨大な刺激がスペルビアを貫いて、膣は愛液を迸らせながらペニスを更に強く締め上げる。
「うあ、き、つ……っ、あああっ」
さらに強められたマシュマロのような膣の圧力に、ジョゼフもまた何倍も強い快感の波を受けて精巣に残った精液の滓までも噴き出させた。
思わず左手でスペルビアの腰を掴んでの射精。体内に流し込まれる精液を、放心していたスペルビアは今までの清廉さとも淫蕩さとも違う緩んだ表情で飲み干していた。
「はは……我がイって、こんなに、出されるとは、な……はは……」
精液を吐き出しきって身動き一つとれなくなったジョゼフの上で、スペルビアは満足そうに自身の下腹部を撫でた。
「なんだ、我よりもお前の方が余力がないではないか。これではあと腰を一捻りしてしまえば正真正銘、お前は果ててしまう他ないようだな」
「そ、そんな……これじゃ、足りなかったなんて……」
増幅された快感で達したスペルビアであったが、それでも精液を出し切ったジョゼフと比べれば余裕は残っていた。例え普段では考えられないほどの刺激でイかされたとしても、高位淫魔をそれだけで屈せさせることはできなかったのだ。
「さあ、お命頂戴といかせてもらおうか」
「う……っ」
ジョゼフは目を閉じて死を覚悟した。
しかし、
「なんて、冗談だ。この勝負、我の負けよ」
そういってスペルビアはジョゼフのペニスを引き抜いてふらふらと立ち上がった。
「淫魔が人間にイかされるなど恥以外のなにものでもない。それにくわえて剣でも一本とられたとあっては、ここで引くのが潔いというものだ」
きっぱりと云いきって、スペルビアは地面に置いていた革の鎧を拾い挙げる。胸にべったりとついた白濁液を手袋で拭うと、上から鎧を装着した。
スペルビアの着替え姿を見守って、ジョゼフはなんとも云えない感慨に襲われて口ごもる。
「団長……その、なんといったらいいか」
「なにも云わずともよい。我は我の中で定めた勝敗条件と照らし合わせた上で負けたと判断したのだ。これ以上やっても我が虚しくなるだけで何も満足感は得られん。それともなにか、お前は我にトドメを刺されることが望みか?」
「い、いえ、滅相もない」
スペルビアに見下ろされ、ジョゼフは残された力を振り絞り頭を振った。
その慌てぶりに苦笑し、スペルビアはジョゼフに背を向ける。
「……どこへ?」
「淫魔らしく、自堕落に国を放浪するさ。ではな弟子よ。我たちの躯にのめり込みすぎるなよ」
スペルビアの姿が唐突にかき消えた。気配が完全になくなったのを感じて、ジョゼフは深い溜息をついた。
「今まで……どうもお世話になりました」
誰も聞いていないのはわかっていつつも最後に呟き、自分の役目を果たせた安心感で意識を深緑の中に預けた。
Second battle.
ジョゼフ VS. スペルビア
Winner ジョゼフ
To be continued Last battle...
――これは夢であるが、夢ではない。
アンナマリアは指先すら動かなくなった自分の躯に力をいれようと悪銭苦闘して、その末にそんな結論を出した。
ジョゼフが戦いに赴いたあとで、アンナマリアは気付いたら眠ってしまっていた、のだろう。と本人は思っている。
気付いたときには、既にアンナマリアはイザベラの家とは違う場所に横たわっていた。
しかし、見覚えがないというわけではない。来たことはなかったが、この内装は〝知っているはず〟なのだ。
まず状況を整理しよう、とアンナマリアは辛うじて動く視野を巡らして辺りを見た。ここはどこか、と考え、建物の中にある一室のようであると判断をつける。 それも、とても大きな建物だ。しかし、部屋の中に豪奢な飾りつけはなく、壁は石が剥き出しのままで壁紙すらない。床も申し訳程度の布きれみたいな敷物があ るだけだ。強固な造りをしているこの建物と比べると、どうにもアンバランスな状態である。これだけの建物に住まえる者が生活する空間とは思えない。
アンナマリアは混乱していた。
どうして自分はここを懐かしく感じるのか。こんな場所には人になってからというもの来たことはない。自分の足で歩けない状態で広場から動けるはずもなく、よってこんな場所を懐かしく感じることなどないはずなのだ。
ここがどこなのか、どうしてこうなっているのか。声も出せず、息も吐けないアンナマリアは静かに混乱していると、扉の開く音がした。けれど仰向けになって寝ている状態のアンナマリアは誰が入ってきたのか確認することはできなかった。
「どうだい、ギヨタン。状態は」
渋みのある男性の声に異議を唱えたが、それは言葉にはならない。そして、すぐにアンナマリアは呼びかけが自分に向けられたものではないことに気がついた。
「ほとんど終わり、といったところかな」
どこからか別の男性が答えていた。アンナマリアが気付かなかっただけで、最初からこの部屋にいたのだろう。声の雰囲気から、先程入ってきた男性より年をとっているようだった。
「ただね、どうにも首を切り取る機構が巧くいかないんだ。刃に細工を施せば良いのだろうが……貴方の意見を聞かせてもらえるかね?」
「そうだな、刃を研ぐのも楽じゃないし……刃の角度を工夫するといい。あとは、重量を増そう。そうすれば、骨に引っかかるなんてことはないはずだ」
「なるほど、では〝この娘〟はそういう風に改良しよう」
アンナマリアの目の前にふたりの男の顔が現れた。白髪の、身なりの良い男である。アンナマリアが搾り殺してきた男たちと違い、育ちが良く、そして聡明なのだろうというのが顔にまで現れていた。
ふたりはじっとアンナマリアを覗き込んでいて、それにびっくりして飛び上がろうとするものの、相変わらず躯はぴくりとも動かなかった。
いきなりわけのわからぬ状況で目が覚め、男に囲まれていることに慌てたが、アンナマリアはふたりの目に悪意が見られないことに気付いた。人としての経験が 短いだけに他人の感情については聡くはないが、断頭台という性質状、常に晒され続けた悪意にだけは敏感なのだ。彼らはアンナマリアに危害を加えようなどと は毛ほども考えていないのである。
どういうことなのだろうとアンナマリアは益々混乱していると、目尻や口元に皺がある男性――年老いて見える方が最初から部屋にいた者だろう――がアンナマリアの躯に触れた。
驚きに身を竦める。が、アンナマリアは一向に自分の肌に何かが触れる感触が訪れないことに気づく。
「できれば、この娘が今の惨たらしい処刑の有様を変えてくれることを願うばかりだよ」
男の目には、深い悲しみの色があった。揺れる瞳には、アンナマリアの鋼色をした躯が映し出されていた。
そう、男はアンナマリアの刃の部分に触れているのだ。
――躯が、人じゃなくなってる!?
躯を断頭台に戻した覚えは、アンナマリアにはなかった。なのに、どうしたことか姿は広場にて罪人を狩る時の姿になっている。
しかも、アンナマリアはもうひとつおかしなことに気付いていた。
躯がバラバラに分解されているのだ。
刃も、台も、柱も、繋がっていない。まるで、組み上がっていないパズルのようである。
さらにいえば、パーツもアンナマリアの知っている形とは微妙に異なっている。
それで、アンナマリアもここがどこで、なんなのかが判った。
――ここは、わたしの昔の記憶だ。
以前、処刑人がでてきたような夢ではない。あれとは違い、これは実際にあったことなのである。眠った拍子に表層では覚えてもいない記憶の中に迷い込んでしまったのだ。
だから、このふたりが誰なのかも判った。アンナマリアの制作者である。つまり、父親だ。
アンナマリアは呆然となった。ふたりの父親のことは覚えていたが、ここまで鮮明に顔を思い出したことはなかった。
その様子は勿論誰にも伝わらず、部屋に入ってきた方の男は老人の言葉に答えていた。
「処刑の現場は変わる。無駄に罪人を苦しめることもなくなり、手段は軽快になり、そしてトラブルに民衆を巻き込む不手際も起こらない。より効率的に、機械的に、被害を抑えて処刑をおこなえる。……ただ、その役目をこの娘に与えるのは、酷な話だろうな」
「ええ、これがただの器物であればなんの問題もなかったことでしょう。けれども、もうひとつの目的を果たすためにはどうしても、細工は必要だった。王が気に病むことではありません」
――王!?
そう呼ばれたことにアンナマリアは心底驚き、男の顔はここではないどこかで見た記憶もあった。
アンナマリアは、この男を殺したことがある。国で革命をおこした者たちによってつれてこられて、広場でアンナマリアを使って処刑されたのだ。あのときはどうしてか、精気を搾り取られたかのような頼りない有様だっただけに、今の今まで気付かなかった。
「すまないな、気を使わせて。せっかく協力者の力のお陰でこの娘を作り出せたのだ。……あとは、神に委ねよう」
これは自分が生まれ落ちる前の記憶、そう悟ったときには、既にアンナマリアの意識はなくなりつつあった。誰かが呼ぶ声がしている。そんな中、王は最後になにか口を開こうとしていた。呼び声を無視して、アンナマリアはその一言に耳を傾ける。
「この子が淫魔を、打倒してくれることを……」
*
「――ギヨたん、ギヨたん、起きなさい、ギヨたん」
「ギヨたんいうなっ」
条件反射で叫びながらアンナマリアはがばっ、と跳ね起きた。
声が自らの鼓膜に届いたことに驚いて、アンナマリアは思わず自分の喉に触れた。
「あ、云えた」
「起きて早々になにをわけのわからないことを云ってるんだい?」
「……いや、普段のあなたほどじゃないから」
目の前にいた、かわいそうな子を見る目をしたイザベラに言い返すと、アンナマリアは自分の両手に目を落とす。そこには傷一つない、小さい真っ白な手がある。先程の記憶に見た無骨な刃からは想像もつかない綺麗な手だ。
軽く、手を握りしめる。指の動く感覚があった。無事に五感が戻ってきたことにアンナマリアは肩から力を抜いて安堵した。いや、元は断頭台であったのだから 人の姿に戻ったと形容するのはおかしな話のはずだ。それなのに、人の姿を望んでいる。自由に動き回れるというのは、それほどまでに度し難い。
うつむきがちになって手を見つめるアンナマリアに、イザベラは首を傾げた。
「いったいどうしたんだい? 寝てたかと思えば、いきなり黙り込んでしまうなんて。悪夢にでも魘されたかい?」
「……違う。ただ、ちょっと、昔のことを思い出していただけ」
一瞬だけ話してしまうか迷ったものの、アンナマリアは気になる言葉を思い出してしまい、誤魔化すことにした。
――淫魔を打倒する? 処刑道具の私が?
王の最後の言葉は、実際にこの耳朶を振るわせたかのように生々しくこびり付いていた。おそらく、妄想ではなく、実際に王はそういったのだろう。
しかし、何故そんなことをいったのか。アンナマリアはあくまで咎人を断罪するための処刑台である。できるだけ苦痛を与えず人道的に殺害する手段として造ら れたのだから、異端審問の道具でもなければ、ましてや淫魔を殺すための道具であるわけでもない。あまりにも、アンナマリアの存在からはかけ離れていた。
ずっと脳内で主張し出すものを振り払って、アンナマリアはもっと大事なことをイザベラに訪ねる。
「それで、ジョゼフはどうなったの?」
「勝ったよ。というよりも、見逃してもらえたと云った方が正しいかな。なにはともあれ、ジョゼフは五体満足で気絶中さ」
「そう……じゃあ、わたしが最後に勝てば、なにもかも解決なんだ」
「ああ、そうだね。相手は今回の国家転覆をおこなった首謀者、その彼女を撃破できれば少なくとも私たちの安全は確保できるだろう。因縁の対決をもって、無事解決できるというものだ」
「前から気になってたけど、その因縁の対決ってなんの話?」
「ああ、それはね。アワリティアは、キミを造った男のひとり――この国の王を屈服させ、キミ自身に殺害させた張本人だからさ」
さっきの夢の中で感じたものは間違いではなかった。あの王と呼ばれた男は、アンナマリア自身が殺した相手なのである。
「でも、わたしは父親のことなんて、ほとんど覚えてない。だから、復讐心みたいなものも、あんまりないんだけど」
「それはそうだろうね。でも、中々に運命的だろう?」
「どちらかというと、悪趣味だけど……まあいい」
アンナマリアは寝転がっていたソファから立ち上がって、服の裾を叩いて直した。
「早く跳ばして。仇打ちとか、そういうのはどうでもいいけど……ついでに、私を悪趣味なことに付き合わせてくれた報いも受けて貰ってくる」
「それでこそ、ギヨたんだ。ではでは幼き姫君、ご案内致しましょう。美しく踊って咲き乱れてきてくるといい」
イザベラはわざと大仰に語ると、手をアンナマリアに差し出した。その手をじとっ、と睨み付けて、アンナマリアは乱暴に手を取る。
そして、アンナマリアは視界が書き換わっていくのを感じた――。
*
どこに跳ばされても、アンナマリアは驚かない覚悟をしていた。
跳んだ先が兵士たちに取り囲まれていようと、地獄のような場所であろうとだ。人ならざるものを相手にしようというのだから、その程度に一々驚いているようでは打倒など到底無理な話である。
そう、気を引き締めていたはずなのだが。
アンナマリアは自分の立っている所を見渡して、呆然とした。見るのも来るのもはじめてな場所だったが、知識だけはあった。そう、ここは――
周囲に気を取られて、アンナマリアの足下はおろそかになっていた。躯を捻ろうとして、足が水に取られて滑りそうになる。
珍しくあられもない声をあげてアンナマリアはその場に踏みとどまって、ほっと一息ついた。
「あら、断頭台はかわいらしい声をあげるものなのですね。はじめて知りました」
背後からかかった声に、アンナマリアはあからさまに眉を顰めた。
「……貴女みたいな品のない人に殺されるなんて、この国の王様も不憫ね」
今度は足下に気を払いながらアンナマリアは振り返った。その先には、素肌の上にベールのような薄布だけを纏って、腕を組み艶然と笑う淫魔アワリティアの姿 がある。しっとりと濡れた長髪を肌に張り付かせ、すっと細められた冷気を孕む視線は、男なら見つめられただけで心を奪われることは間違いない色香があっ た。
「品がないとは失礼な物言いですね。貴女よりもずっと恵まれた生活をしていますよ。ほら、貴女、お風呂なんてご存じでないでしょう?」
アワリティアは緩く片腕を動かして周囲にアンナマリアの注意を向けさせた。
そう、ここは王城の一角にある大浴場の中だった。高価そうなマーブル模様を浮かべた石の床には水溜まりができていて、アンナマリアが足を取られたのもそれのせいである。
アワリティアの手がさした先には人が何十人と一緒に入れそうなほどに広大な浴槽があり、花の蜜に似た香料が湯の熱気に混じってねっとりとアンナマリアの肌に絡みついた。全身を舐められているような暖かさに、じんわりと額が汗を浮き上がらせる。
「こ の浴槽は私の希望で人間に作らせたものです。湯浴みの文化すら俗説を恐れているがために抑圧していたなんて、私たちと比べて劣っているとしか言い様があり ませんね。もっとも、貴女のお父様は王城に浴場設備自体は導入していましたから、その点だけは評価してあげなければいけません。ご褒美にたっぷり天国を見 せてさしあげましたよ」
「……長々と語って、云いたいことはそれだけ?」
アンナマリアは自覚していなかったが、相当に不機嫌なのは声からして明かだった。押し殺された声は獲物を狙う猛獣の唸り声で、目は殺害対象を見据えるもので刀身のように寒々しい。
小気味良い音を関節から立てて、アンナマリアは右手をかぎ爪の形に曲げる。
正直なところ、彼女には相手の得意分野で戦ってやろうなどという殊勝な心がけは微塵もなかった。
レリアは同じ淫魔であるから戦いの方法が同じで、ジョゼフに至ってはそうする以外に手段がないからやむなく性技による戦いを選んだにすぎない。
だが、アンナマリアは違う。
彼女は断頭台。元より人間を、人間の形をしたものを殺害するために産み落とされた処刑機具だ。武闘派であるスペルビア相手には見切られる可能性もあったが、ただの淫魔なら易々と斬首できる力は身に秘めている。
相手が身構えたのを見て、しかしアワリティアは薄く笑った。
「もしかして、監獄で見せた不思議な技でも使うおつもりですか?」
アンナマリアは答えなかったが、沈黙が肯定となっていた。
前回、監獄で放った不可視の一閃。それをアンナマリアは以前も自分の意識下で制御し、撃ったことがある。レリアとの初対面時だ。
あの現象自体は、アンナマリアにとっては別段難しいことではなかった。むしろイザベラの扱う魔法の方がよほど特異なものであるとさえ思っていた。自分のはただ、まっすぐに相手を切り裂くだけのことなのだ。断頭台として当たり前の〝機構〟である。・
だが、その切り裂く方法自体が問題だった。
原理はアンナマリア自身も理解が及んでいない。ただし、イザベラは判っていたようだ。息を整えて、ゆっくりと脳内でこの〝機構〟について思い出す。
不可視の刃――それは鎌鼬などという生やさしい代物ではない。
アンナマリアのそれは謂わば存在を断つ即死の刃だ。対象に刃が当たれば、それが建物であろうがなんであろうが、その強度に関係なく対象は断裂する。しかし、無機物を斬るのが断頭台の真の機能ではない。よって、強度を無視して無機物を斬るには相当な集中力が要求される。
真の機能、目的とは即ち斬首。アンナマリアは人間という存在を断ち切る刃なのだ。
アンナマリアは断頭台のときにおいて、一度も人を仕損じたことはない。一刀一殺。必ず殺している。人の血と呪詛に塗れた断頭台の刃は、これによって魔術的効果を付与された。あらゆる人を殺せる。相手は人である。相手は死ぬ。という三段論法の呪いが。
人の形をした存在にとって、アンナマリアは天敵だった。当たれば、即死。そんな攻撃手段を持っているものが、人にとっての天敵でなくてなんになろう。
アワリティアとてこの攻撃の例外ではない。アンナマリアが腕を振り、斬撃を放ち、当たれば――かすっただけで躯は両断される。
音速で迫るであろう刃を避けることは淫魔といえど肉体を鍛えていなければ到底無理な話。アンナマリアの目の前に出てきただけでアワリティアの進退は窮まっていた。はずだ。
なのに、未だにその顔には余裕があった。
「確 かに、それは脅威です。私も当たれば死んでしまうでしょうね。けど、そんなもので決着をつけるのはいささか無粋ではないでしょうか。やはり仇討ちをするな ら、同じ手段でありませんと雰囲気がありませんよ。そう、貴女のお父様と私がしたように、躯を重ね合わせての戦いでなければ」
「うるさい。――死んじゃえ」
有無を云わせなかった。アンナマリアは間髪入れずに右手を振るっていた。
瞬間、刃が疾駆した。
アンナマリアの正体が見えない刃として顕現したのだ。
風切る音速の斬撃が手から伸びる。それはあまりに理不尽な力の象徴。吸い込まれるようにアワリティアの首に滑り込んだ。
アワリティアの背後の壁に鋭い亀裂が走った。アンナマリアの刃が、破城鎚の直撃にも耐えうる城内の壁をバターのように切り裂いたのである。
無論、壁との合間に立っていたアワリティアが無事なわけもなかった。
アワリティアがその場に立っていたとしたら、だが。
「い、ない!?」
アンナマリアは驚きに目を見開いた。確かに腕を振るう一瞬前までは視線の先にいたはずのアワリティアが忽然とかき消えていたのだ。
そこで混乱に思考停止を起こしてしまうのも無理からぬことだった。アンナマリアは処刑をしたことは数え切れないほどにあったが、人と決闘は愚か喧嘩すらしたことがなかったのである。
だから、自分の真横からの呼びかけには呼吸が止まった。
「こっちですよ、断頭台さん」
咄嗟に振り返ろうとしたところに足を払われて、アンナマリアは水に滑って床に背中を打ち付けた。
アンナマリアの眼前には、得意気な様子になったアワリティアがいた。その背中には一対の翼が風もないのにゆらゆらと揺れており、思わず羽根すら生き物と錯覚しそうになった。
「いったい、いつの間に……」
「淫魔の速度を甘く見ましたね? まあ、ふつうの淫魔なら貴女の下手な攻撃も当たっていたでしょうが、相手を見誤ったのが敗因ですね。翼さえ出せれば、貴女が右腕を振り下ろすよりも早く身を動かせるのですよ」
「くっ……!」
もう一度右腕を振ろうと振り上げるが、その手をアワリティアに掴まれて押しとどめられた。
「無駄ですよ。ただの道具が自分の躯を使いこなせるわけがないでしょう?」
「うるさい、離して……!」
「やれやれ、聞き分けのない子ですね。それでは、素直にさせてあげましょう」
アワリティアはぺろりと自分の唇を舐めると、アンナマリアのそれを奪った。
「んんっ」
小さな躯を強ばらせて侵入してくる舌を拒む。
それにアワリティアは唇を唇でついばんだ。ジンジンと口元の熱くなる甘い快楽に、アンナマリアはつい口を開いてしまった。
そこにぬるりとアワリティアの舌が滑り込む。そこからはもう舌技の虜だった。
口内で舌が動く度にアンナマリアの小さな躯が床の上でぴくぴくと震える。必死に抵抗しようとしていた腕にはいつしか力が入らなくなり、されるがままにアワリティアのキスに酔ってしまっていた。
相手の顔が離れる。アンナマリアの目には涙がたまっていて、頬を紅潮させながらまだキスの余韻に呆然としていた。
「普段は男性を銜えて喘がせてあげるための舌技なのですが……どうやら、相当気持ちよかったようですね。口の中をペニスと同じように舐められて感じてしまうなんて、恥ずかしくないんですか?」
「う、うるさ……い」
口では抵抗するものの、アンナマリアは躯に根を張った快感に躯を振るわせ続ける。無防備なところへ受けるには、あんまりにも情熱的な口づけだった。
精一杯の抵抗にアンナマリアは肩を突き飛ばそうとするが、それはひらりと躱されてしまう。指先が髪の毛一本にすらかすることもなかった。
「あらあら、反抗的な子ですね。これは、教育が必要なようです……。ああ、なら、やはりこういうときは年長者さんたちが導いて差し上げなくてはなりませんよね」
突然、アワリティアが誰かに語りかけているように声を張り上げた。ようやく快感の酔いから覚め始めたアンナマリアが不思議に思うと、すぐに相手の真意を目の当たりにすることとなった。
「さあ、お姉さん、お兄さん、入ってきなさい。この子を丹念に洗ってあげるのです」
すると、浴場の扉が開かれた。
「はい、お母様」
ぞろぞろと浴場に入ってきたのは、十代の子供たちだった。比率としては少女の方が多く、たまに少年が混じっている。彼らはひとりとして衣服を身に着けてお らず、人種も様々であった。差こそあれど、だいたいはこの国の人々と同じく肌の白い者たちだったが、何人か浅黒い肌の子供も混ざっている。
その無作為に集められたような統一感のない子供たちは、しかし動きだけは群体のように統一されていた。
子供たちが近づいてくることに驚いてアンナマリアは慌てて躯を起こすが、あっという間に集まってきた子供たちのひとりに背中から抱きしめられてしまう。
「な、なに……この子たち……」
アンナマリアを背中から抱きしめている少女が妹を叱るように耳元で囁いた。
「こら、年上の人にそんな口の利き方をしちゃ駄目でしょう?」
そういって服の上から胸を撫でられると、アンナマリアは熱い吐息を洩らす。キスによって敏感になった肌は、例え服の上から触れられただけでも性器を愛撫されたように感じてしまった。
その反応にアワリティアはくすりと笑い、アンナマリアを取り囲んだ子供たちに命じる。
「彼女はお風呂も入った経験がないようです。貴方たちの手で躯の隅々まで洗ってあげなさい。新しい姉妹になるかもしれない子ですから」
「はい、お母様」
子供たちは一斉に答えると、その細腕を伸ばしてテキパキとアンナマリアのドレスを脱がしていく。
「や、やだ、ちょっとっ」
躯を捻ってなんとか抵抗しようとするが、元は断頭台といえど見た目相応の力しかないアンナマリアでは数の力には抗いがたく、瞬く間にドレスを脱がされ一糸まとわぬ姿にされてしまった。
何人もの男に跨り、精を搾ってきたアンナマリアだったが、子供たちの純真な視線に晒されて生まれはじめて羞恥心を覚えた。太腿を擦り合わせて毛も生えていない秘所を隠そうとするが、褐色の少女の手によって容易くこじ開けられる。
「なにを恥ずかしがっているの? 隠してたら洗えないよ。それに、これから兄弟になるんだから恥ずかしがることなんてないんだから」
「きょ、兄弟? いったい、なんの……」
それには、また別の少女が答えた。
「お母様に見いだされて、行儀の良い子供になるの。そうして将来、男の人や女の人を喜ばせるお仕事をさせてもらえるのよ」
「そ、そんなの……いやっ」
「こらこら、暴れちゃ駄目だよ」
子供たちに両手足を抱きしめられて、アンナマリアは首をいやいやと振ることしかできなかった。背中にいた少女はアンナマリアの長髪に首を埋めて、周りの子たちに合図をする。
「それじゃあ、みんな、この子を綺麗にしてあげようね」
「はーいっ」
子供たちは行儀良く返事をして、躯を濡らして石鹸を泡立てはじめる。手で泡立て、自分たちの躯にも泡を塗り込むと、次々にアンナマリアの躯へと自分を擦りつけはじめる。
精液とは違うぬるぬるとしたものがすり込まれて、アンナマリアはくすぐったさに声を上げた。
「や、やめ……っ、そんな近づかないで!」
「だから、恥ずかしがっちゃ、めーっ、だよ?」
誰かの手がぬるりとアンナマリアの太腿の間に滑り込んで、泡立った手が秘部を撫でた。
「ひゃっ!?」
「躯を洗ってるだけでそんな声出しちゃうなんて、あなたってえっちなんだね」
「そんなところ触られたら、誰だって……ひゃぁうっ」
膣の中に指が入り込む。泡を潤滑液代わりにした指はぬるぬると前後の動きを繰り返す。
「ほらほら、中も綺麗にしないとね」
背中の少女がアンナマリアの耳元に息を吹きかけながら囁いた。
「こっちの方も綺麗にしようね」
アンナマリアの手足を泡まみれの躯で擦っていた少女たちのひとりが、アンナマリアの菊座へと手を伸ばした。泡に濡れた指で菊の穴を撫でて、一息に貫く。
つぷぅっ、と穴に突き入れられた指の感触にアンナマリアの中がきゅっと、甘く絞まった。
「ひぃうっ……あ、ああ……っ!?」
「もうっ、掃除してあげているだけなのに、そんなかわいい声をあげて……」
悠然と腕を組んでほくそ笑みながら、アワリティアはその痴態を眺めていた。
「それだけ貴方たちの手際がいいのですよ。さあ、もっと奥の方まで洗ってあげなさい」
「はーいっ」
すると、ひとりの男の子がアンナマリアの股の間に躯を滑り込ませた。アンナマリアの膣から少女が指を抜くと、代わりに泡まみれになったペニスを秘所に宛がう。
「それじゃあお姉ちゃん、中まで綺麗にしてあげるね」
返事を待たずに男の子は勃起した肉棒を中へ挿入した。
アンナマリアよりも小さい男の子のペニスは、勃起していても相応の大きさしかなかった。男たちからねじ込まれていた膣を裂くような大きさの陰茎に比べると随分かわいらしい代物だ。挿入されても異物感は少なく、アンナマリアの躯は自然と受け入れてしまっていた。
「うわ……お姉ちゃんの中、すっごく気持ちいいや……。でも、がんばってお掃除するね」
「こ、この……っ」
無邪気な顔で腰を揺する少年を精一杯の敵意を集めて睨み付ける。それでも快楽で涙を浮かべていた目ではかわいらしさしかなかった。
石鹸の泡でぬるぬるになった男の子の小さな肉棒はアンナマリアのひだを丹念に擦り、子宮の入り口に何度も亀頭を押し当てる。
子供たちに纏わり付かれて未知の快感に襲われていたアンナマリアの肢体は、幼い男性器のピストン運動にも初心な反応を返す。ぴくぴくと躯は震え、口元から透明の液体が垂れた。
だが、自分よりも小さな男の子に言い様にされるのはアンナマリアの意地が許さない。
足で男の子の腰をがっちりと掴むと、無理矢理一番奥にペニスをねじ込ませ、反撃を開始した。
「お茶目は、お終い!」
アンナマリアは勢いよく相手のペニスを締め付ける。挿入されたときに入り込んだお湯と愛液、石鹸が混じりあった混合液がじゅくじゅくとペニスに絡みつき、その上からは幾人の男たちを屈服させてきた膣肉が精を貪るように吸い付いた。
ただの人間の男の子がアンナマリアの男慣れした肉体に抗えるわけもない。
「わっ、お、お姉ちゃん、すご……い……あああああっ!」
ぴゅっ、ぴゅっ、とかわいらしさを感じさせる射精がアンナマリアの中で起こった。
泡まみれにされたアンナマリアの躯にしがみついて、男の子は気持ちよさでだらしない表情になりながら子宮の中に精を吐き出させられたのだ。
瞬殺されてしまった男の子は蕩けた目のまま白い肩で息をしてアンナマリアの躯の上に倒れる。その不甲斐ない様子に、少女たちがくすくすと笑った。
アワリティアも子供たちにつられて微笑んでいて、アンナマリアに男の子が倒されたことへの不安は一切浮かんでいない。
「あらあら、この子ったら、躯を洗いながらイってしまうなんて。私の子供たちにもおかしな性癖の子がいてしまったものですね。汚れてしまいましたし、お姉さんたちは弟の面倒もしっかり見てあげましょうね」
「はーい!」
元気のいい挨拶をした姉妹たちは男の子をアンナマリアから離すと、脱力している彼をすぐ横に寝かせた。そして、褐色の肌をした少女が精液にぬれた半勃ちのペニスを口に含んだのである。
頬をすぼめて石鹸と精液の混じった液体で濡れたペニスをしごきあげると、イったばかりだった少年が悲鳴のような嬌声をあげた。
「あぁあうっ! お、お姉ちゃぁん……ま、まだダメ……」
「お風呂なんだからちゃんと綺麗にしないとダメでしょう? それに、お風呂で汚くしちゃった罰だよ」
男の子の懇願もむなしく、姉と呼ばれる少女はじゅぽじゅぷと肉棒を口内で虐める。舌と頬肉による吸引の愛撫に、まだ精経験に乏しいであろう男の子が耐えられるわけもない。
「お、お姉ちゃんっ、またでちゃうっ!」
男の子の腰が跳ねると、今度は褐色の少女の口内に精液を噴出した。
どぷどぷっ、と口の中に精を出されて、少女はペニスを抜くと手で受け皿を作りながら口を開いた。舌の上で白濁とした精液がぷるぷると震えていて、舌から垂れた精液は唇をなぞりながら掌の上にしたたり落ちた。
「もうっ、洗うっていってるのになんで汚しちゃうかな? もっとお仕置きが必要みたいね」
「お、お姉ちゃん、もうやめてぇ……」
そうして少女は男の子を虐めることに専念し始めた。その様子にアワリティアは呆れながらも、そうなることが判っていたのか笑みを崩すことはなかった。
「やれやれ、盛りがついているんですから。貴方たちの方はちゃんとその子を綺麗にしてあげてくださいね」
少女と男の子の動向を見守っていた少女たちも再びアンナマリアへの奉仕をはじめる。お尻の穴に抜き出しされる指の感触、肌の上を滑る少女たちの肢体の感 触。そのどれもがアワリティアが目をかけるだけはある気持ちよさで、アンナマリアは我慢しようと思ってもつい口から喘ぎ声を洩らしてしまっていた。
「は、ああ……っ、いい加減に……っ」
きっ、とアンナマリアは子供たちを睨み付ける。しかし、くすくすと笑われるだけで彼女たちは気にした様子もない。
このままでは弄ばれて骨抜きにされてしまう。気持ちよさで一杯になった脳内にそんな危機感が生まれるが、両手足の自由がきかない状態では抵抗のしようがなかった。先程の男の子のように無防備を晒してくれれば話は別だが、少女たちにはそれを望むこともできない。
「自分は高みの見物で、あんなに偉そうなこと云ってたなんて……随分と、臆病者ね」
「あら、それは挑発のつもりですか?」
進退窮まって発したアンナマリアの言葉はアワリティアを鼻で笑わせるだけだった。
「勘違いしないでくださいね。私は、貴方のためにこうしてあげているのですよ」
「わたしのため?」
「ええ。だって、キスしただけであんなにかわいらしい顔になってしまうんですもの……。私が相手をしてあげたら、貴女は壊れてしまうでしょうね」
キスの感触を思い出してアンナマリアの唇がひりひりと熱くなる。もしアワリティアが本気で相手を籠絡しようと思えば、あれの比ではない快感が躯を走り抜けることだろう。
レリアを除けば常に格下の相手と躯を重ねていたアンナマリアからしてみると、アワリティアの力は想像できない領域にあった。
アンナマリアは雪のように白い頬を朱に染めたまま、股を開いた。
「なら、壊せるかどうか……試してみたら?」
例え圧倒的に不利な状況だったとしても、アンナマリアは賭に出るしかなかった。
一瞬、アワリティアの表情が強ばる。
「……?」
理由がわからず、アンナマリアは怪訝に思った。今までは余裕であったのに、アンナマリアの誘いに突然そんな反応を見せたのだ。
おそらく、アワリティアの本気がアンナマリアを大きく上回っているという事実に偽りはない。実際、キスだけであれだけの快感を流し込んでみせたのだ。七つの大罪の名を冠する淫魔の実力は伊達や酔狂ではあり得ない。
だからこそ、アンナマリアには意味がわからなかった。今の反応は、いったい何故?
だが、アワリティアの表情は既に余裕の笑顔に戻っている。違和感を追求する前に、アワリティアが動いた。
「そうまで云うならいいでしょう。私も自ら貴女のその薄汚れた躯を流してさしあげましょう」
一枚だけ纏っていた薄い布をさらりと床の上に落とすと、美しい裸身がアンナマリアの目の前に現れた。
「この胸を押しつけられて昇天しなかった男はいませんでした。貴女はどこまで耐えられるでしょうね?」
くすくすと笑って、アワリティアは石鹸を泡立てた両手で自身の豊満な胸を持ち上げた。そのまま泡を乳房に馴染ませるために揉みしだく。穏和な顔付きの女性が自らの胸を慰めるように見える姿は官能的で、アンナマリアですら生唾を呑み込んでしまった。
「貴方たちは下がっていなさい。さあ、行きますよ……」
子供たちがアンナマリアから離れると、すぐにアワリティアはアンナマリアを抱きしめた。薄い胸に大きな乳房が押しつけられてつぶれる。。胸を押しつけたままアワリティアはのの字に胸を動かして、乳首と乳首を擦り合わせた。
「く、ぅ……!?」
ただ乳首が触れあっただけなのに、絶妙な硬さになっているアワリティアのそれに引っかけられてアンナマリアは背筋を跳ねさせる。
「どうしました? まだほんの少し動いただけですよ? ……それとも、おっぱいが好きなんですか?」
湯船に張られたお湯からあがる湯気のせいで軽くのぼせたアンナマリアは首を振って問い掛けを否定する。しかし、頭が朦朧とするのはなにも湿気だけのせいでないことは明かだった。
「誰が、貴女の胸なんかに……」
「そうですか。……では、そろそろお顔もあらってあげなくてはいけませんね」
アワリティアがアンナマリアの後頭部に手を回すと、相手の顔を自分の谷間に押しつけた。
「う……っ、ふぅ……っ」
息苦しさに呻き、アンナマリアは顔をなんとかあげようとするが、アワリティアの方が腕力でも上だった。為す術なく胸の弾力に顔を挟まれてその触感に身を委ねるしか、アンナマリアには許されていなかったのである。
なんとか首を捻って谷間の隙間に顔をずらして浅く呼吸をした。すると、鼻腔に甘い芳香が充満した。香料の匂いか、石鹸の香りか、それともアワリティア自身 の色香がわき上がりでもしたのか。その香りは蜂を招き寄せる蜜のように甘美で、アンナマリアは躯から力が抜けていくのを感じた。
「ふふ……どうしました。私のおっぱいはそんな気持ちいいですか?」
アワリティアが躯を揺すると顔に押しつけられた胸がぷるぷると震えながら顔を圧迫する。しかし苦しいとは感じず、アンナマリアは顔を包み込む乳房の心地良さに身を委ねていた。
「あ……う、あ……」
それはアンナマリアにとって未知の感触だった。躯を重ねたことのある同性はレリアだけであったし、母もいないアンナマリアには女性らしい女性との交流が皆無だったのだ。
……そう、母。
アンナマリアはぼんやりと思う。今、自分の胸の中を満たしている幸福感は、まるで母に抱きしめられているときのようだ、と。母親がいたこともないのだから想像でしかないが、溶かされそうなほどの暖かい染み渡る快感はそうとしか説明のしようがなかったのだ。
「ふふ、なにもかも忘れて、身を委ねなさい」
すっ、とアワリティアの片手がアンナマリアの秘所に触れた。射精された精液と石鹸の泡で白く汚れたアンナマリアの膣に、ゆっくりと指が入り込む。
「あ、あぅ……」
拒まなければいけないのに、今までのような無理矢理与えられる快楽ではない、愛でるように染みこんでくる気持ちよさをアンナマリアはふりほどくことができなかった。
くちゅ、くちゅ、とゆっくり秘所を細い指が愛撫する。陰核を子供の頭を撫でるような優しさでなぞり、愛でる――。
胸の谷間から香る蜜の芳香と、顔を締め付ける弾力ある乳房、秘部をかき回す細指の感触。その前に、アンナマリアは反抗心を折られて屈服してしまっていた。
「さあ、このぬくもりの中で果てなさい……」
「あ……あ……っ!」
つぷ――、と秘所を貫かれ続け、ついにアンナマリアは見も心もアワリティアの前に折れた。
「あ――あああ――!」
びくんっ! とアンナマリアの躯が陸に打ち上げられた魚のように跳ねる。それでもアワリティアに力強く抱きしめられて胸から離れられず、アンナマリアは乳房の芳香で頭の中をいっぱいにされながら果てた。
躯の芯を走り抜ける甘い閃光で目の奥に火花を散らし、アンナマリアは潮を吹く。びちゃびちゃとアワリティアの手を汚して、それでも止まらず何度も終わるこ とのない絶頂に身を震わせた。強引にイカされたのではなく、自然と導かれた絶頂は胸を熱く満たしていて、快感は留まるところを知らなかった。
「あう……あ、ああ、ひゃ、ああ……」
「赤ん坊みたいな声を出して、そんなに心地良かったですか? 私の胸が貴女の涎でべとべとですよ……もう、しょうがない子ですね」
アワリティアが頭を撫でると、撫でられた場所がじんじんと熱くなる。髪の毛に手が触れているだけだというのに、そこが性感帯にでもなったかのような錯覚を起こさせられた。
もう躯を押さえる手はなにひとつないというのに、アンナマリアは脱力し、もう完全に抵抗することを諦めていた。いや、もう頭の中からは、このゆりかごにいるような心地良さから逃れようようなどという発想自体が抜け落ちてしまっていたのだ。
「お母様にあんなにされちゃ、もうあの子もなにもできないね」
「うんうん、あたしもあんな風に撫でられてイカされちゃったんだよねぇ」
「こちらも昔はお母様と敵対していましたが……あの優しさの前には……」
周りで見ていた少女たちが口々に感想を言い合う。この子供たちもあのようにされ、アワリティアに心酔した者たちだったのだ。
意識を朦朧とさせたアンナマリアの頭を撫でながら、アワリティアは子守歌でも歌うように耳元で口ずさむ。
「私の娘となりなさい……そうすれば、ずっとこのように愛し続けてあげましょう」
「むすめ……むすめに……」
「ええ。そして、私のために働いてください。行儀良くしてくれる限り、私は無償の愛を貴女に捧げてあげますよ……」
このような、心地の良い母性を――。
蕩けるような、ふわふわと、天にも昇る快感が――。
自分の手にはいる?
その言葉は、アンナマリアにとってこれ以上ないほどに魅力的なものだった。今までの記憶や感情を総てなげうってでもしがみつく価値があると心から思えた。
自分のことを遠巻きに見ている子供たちも、きっと、同じなのだとアンナマリアは理解する。敵として恨んでいたのに、アワリティアの抱擁で骨抜きされてしまった、それがあの子供たちだと。
その一員になるというのも、悪くない。だって、いなかった母親もできて、あんなに沢山の兄弟と一緒になれるのだから。
もう、ひとりぼっちじゃなくなるんだから。
アンナマリアは、そっと目を閉じた――。
――ジジジッ、と蝿の羽音のような雑音が脳内に反響した。
眠ろうとしたのに、このまま呑まれてしまおうとしたのに、その音だけがやかましく邪魔をしてきた。
うるさい、とアンナマリアは眉を顰める。けれど、同時にこの音から耳を背けてはならないという声も心の中であがった。
この音はいったいなんなのだろう。考えてみてもわからない。どんどんと大きくなる音は、次第に無視のできない程に大きくなっていた。
うるさい、うるさい、鳴り止んでしまえ。そう強く念じるが、雑音はさらに悪化するばかりだった。まるで、その音はアンナマリアを呼び起こそうとするベルの音のようで。
我慢できずに、アンナマリアは大声をあげた。
――うるさい! わたしは、このまま眠りたいの! ひとりぼっちはもう嫌なの!
人は死んでしまう。あの処刑人のように、無情に、あっさりと。父のように、強引に、あっさりと。みんな自分を置いて先に逝ってしまうのだ。
だから、そう、アンナマリアが復讐したいと思ったのも、単に自分をひとりぼっちにさせた報いを受けさせたかっただけなのかもしれない。大なり小なり理由は あれど、それが一番重要なことだったのか。処刑人のためだなんてことはただの大義名分で、ただ、どうしようもない理不尽に駄々をこねたかっただけなのだ。
でも、アワリティアなら、淫魔を母とすればその心配はなくなる。自分は多くの姉妹たちに囲まれ、人間たちに束縛されることなく、注がれる愛情を隣人として自由を謳歌することができるのだから。
そこまで云いきって、しかし、アンナマリアはまだ言葉が続くことに気がつく。
――ああ、でも。
自分に愛情を向けてくれる人は、まだいたのではないか。
暗闇の中に亀裂が走ってうっすらとした光が差し込んだ。
なんてことはない。ただ、アンナマリアが閉じていた目を開いただけである。目の前にはアワリティアの乳房があり、ランプの明かりが目に降り注がれた。
アンナマリアが顔をあげると、微笑んでいるアワリティアの顔がすぐそこにあった。目と目があって、頭を優しく撫でられた。
「お目覚めですか? さあ、貴女はこれから末の妹として私たちと……」
「気易く、頭を、触らないで」
自分の頭を撫でるアワリティアの手を振り払った。驚く相手に、アンナマリアは屹然とした目を向けた。
気付いてしまった。たとえ優しく頭を撫でられたとて、母親の手つきではない。ペットを撫でる手つきだと。アンナマリアも、子供たちにも、誰一人とて自分と 同等の存在として扱っていない。ただの、かわいい玩具としか思っていない。アワリティアは、どうしようもなく骨の髄まで淫魔なのであった。
「うそ……お母様の誘惑をはねのけるなんて……」
周囲の子供たちがざわめきだしていた。いつの間にか、男の子の上に跨って腰を振っていた褐色の少女も動きを止めて唖然としている。それほどに、今起こった出来事が信じられなかった。
「あんなに愛してもらったのに、どうして」
動揺する子供たちを、アンナマリアは意志のこもった目で睨み付ける。
「これに愛情なんてない。だって、自分と同じだなんて思ってないんだもの。わたしや、あなたたちは。この人からしてみたら……ただの動物よ」
「だ、黙りなさい!」
アワリティアが慌てて一喝したが、時既に遅かった。
アンナマリアの言葉を聞いた子供たちが、皆一様にして様子を変じさせる。頭痛を堪えるように頭を抑え、床に倒れていくのだ。
「うそ……ぜんぶ、うそ……。おかあさまは……アワリティアは、あたしたちのことなんて……」
「そうだ、最初はアワリティアを倒そうとしていたはずなのに、なんで、こんなことに……」
譫言をつぶやき、体力を使い果たして子供たちは気絶していく。アワリティアの余裕な表情は、ここにきて完全に崩壊した。
「そんな馬鹿な……。私の洗脳がたった一言で解けるだなんて、あり得ません! 大司教クラスの聖職者でさえ解呪には三日三晩を要するはず……!?」
「でも、出来ちゃったものは出来ちゃったんだし」
あっさりと言ってのけるアンナマリアを、アワリティアは悪霊でも見るような目で見た。顔は蒼白になり、もう当初の余裕はどこからも伺えない表情になっていた。
「やはり、貴女は危険です。その力、私のために利用させてもらおうと思っていましたが……ここで果ててもらうほかないようです」
「なにをそんなにビクビクとおびえてるの? わたしが怖いのは、貴女が淫魔だから?」
「な……っ」
アンナマリアは前に見た夢の内容を思い出しながら口にしてみた。あの夢が妄想以外のなにものでもない可能性もあり、鎌をかけだけのつもりだったが、ものの見事にそれは図星を突いていた。
「なんだ、当たりなんだ。よくわからないけど、わたしは貴女みたいな淫魔を倒すために作られたとか聞いた覚えがあったから云ってみただけなんだけど」
「く……っ、人をコケにしたのですか」
「それ、貴女が云う?」
はあ、と溜息をつく。これまでの会話の間で、アンナマリアは自身のペースを取り戻していた。
「理屈はわからない……けど、まだわたしには貴女を倒せる力があるみたい。だから、ここからが……本番」
「たかが洗脳を解いただけのこと。思い上がらないでください」
「だと思う?」
アンナマリアはくすりと笑った。何故か、もうアワリティアに負ける気は微塵も感じなかった。最初は虎に見えていたのに、アワリティアのことをもう子猫のようにしか思えないのだ。
「たぶん、わたし以外だったなら勝てたんだろうけど。わたしたちって、相性が最悪で、最高みたいだから。多分、もう無理だよ」
「それは、試してみなければわからないでしょう?」
ばさっ、とアワリティアが一対となった蝙蝠の羽根を広げる。アワリティアは、自身の躯すら覆い隠せるほどに大きな羽根でアンナマリアを覆った。
「これは……」
躯を覆い隠す羽根には人肌の暖かさがあり、思い切り手足ごとの抱擁。
「淫魔は、自分の羽根を自在に動かせるのですよ。ただ、私は他の淫魔よりも神経が発達していまして……羽根の表面から毛先の一本一本まで自由にできるのです。……今から、それで全身を愛撫してさしあげます。ちなみに、これを受けて生き残った者は……ゼロです」
妖艶な笑顔で宣告し、アワリティアが羽根を動かした。
きゅっ、とアンナマリアは躯を締め付けられる。ふりほどこうとしても手足は動かせず、じたばたと藻掻くしかなかった。
「こんな、もの」
「無駄です。大熊ですら絞め殺せる力すらだせるのですよ……貴女の細腕ではどうにもなりません」
言葉通り、アンナマリアがいくら抵抗したところでこの拘束を緩めることすらできない。じわじわと羽根が躯を強く押し包み、砂のようにざらざらとした皮膚を肌にすり込んでくる。
「さあ、羽根の感触に身悶えなさい」
ざらりとした羽根がアンナマリアの柔肌を撫でた。未熟ながらも触れたお尻を羽根でさすり、股の間に羽根の節を滑り込ませる。秘所に節が宛がわれ、じゅっ、じゅっ、と音を立てながら擦り上げる。
「うひゃ……っ」
「ふふ、陰核と膣を同時に責められる気持ちはどうですか? ざらざらした毛で粘膜をこすられると、腰が震えてしまいますよね。みっともないことです」
さらに、羽根の表面にある毛がさらさらと動き出す。敏感になった全身の肌を優しくブラシがけされているような感覚に、自然とアンナマリアの口から声が洩れていた。
「どうしましたか? さっきの威勢はどこにいってしまったのでしょうね。私の胸と、羽根に夢中ではありませんか。さて、このまま天国まで導いてあげましょうか――」
そこまで云って、アワリティアはアンナマリアの唇によって口を塞がれた。
羽根に抱かれたながらなんとか背伸びをしたアンナマリアがアワリティアの唇を奪ったのだ。
手足を封じられたアンナマリアにできる唯一の抵抗が口づけだったのである。そのことが判っているアワリティアは驚くこともなく、楽しげに唇を細めた。勝て もしない勝負を挑まざるを得なくなったアンナマリアの決死の行動に微笑ましくなって、アワリティアは自分から舌を搦めて相手の行為に乗ってやることにし た。
「ん……ん……っ」
ふたりの呼気が漏れる。そして、片方からは案の定、切羽詰まった喘ぎ声があがった。聞く者を欲情させる艶やかな嬌声をあげて、自分の有様に目を瞠る。
「そ、んな……ばかな……!」
声をあげていたのは、なんとアワリティアだった。
目を蕩けさせ、頬を赤く染めたアワリティアは、口の端から涎を垂らしながらも必死に正気を保とうとしていた。
「こんな、さっきはあんなに拙かったはずです……っ」
「なんだ、そんなこと」
くすりと微笑むアンナマリアの横顔は慌てているアワリティアよりもずっと淫魔のようだった。
「簡単だよ。ただ、貴女のやり方を覚えただけ」
「そんな、簡単に!? いや、まさか、それができるからこそ貴女が、私たちの……!」
淫魔を打倒する――夢の中の言葉をアンナマリアは正確に理解しているわけではなかった。けれど、自分いはそれを成せる力があるらしいということだけはぼんやりとだが自覚し始めていた。
はじめてアワリティアにキスをされたとき、アンナマリアはふりでもなんでもなく、本当にその舌技に圧倒された。だが、一度それを体験してしまえば、どうやって相手が舌を動かし、相手を感じさせたかを理解し、覚えてしまえたのである。
「きっと、わたしが道具だったからかな……。だから、方法さえ教えてくれれば簡単に真似できちゃうみたい」
例えば、人の首を刈ることのように。
アンナマリアは、刃を落とせば人は死ぬということをしっていて、そのための手段を用意された断頭台という存在である。それと同じで、実行するための手段で ある肉体があれば、どうしたら相手を感じさせることができるかという情報さえ手に入れば簡単に再現することができるのだ。そのことを、誰に云われることも なく、アンナマリアは感覚で把握した。
「ですが、所詮は猿真似です。そんな接吻だけで、この私が倒せるとでもお思いですか」
「だから、次はこっち」
アンナマリアがほくそ笑んで、秘部をきゅっと締め付けた。すると陰部を撫でていた羽根の節をつまみ、腰を押しつけながら上下に躯を揺らした。
じゅる――っ、と今度はアンナマリアが動いて羽根を舐め上げた。自慰行為のような行動に、何故かアワリティアが快感で躯を震わせる。
「こんなによく動くってことは、貴女の羽根ってとっても敏感なんでしょ? こうやって撫でてあげたらどうなるかな」
「私としたことが、おしゃべりが過ぎましたか……!」
アンナマリアの指摘は図星であり、アワリティアは悔しそうに顔をしかめた。
アワリティアの羽根は諸刃の剣なのである。神経が発達しているお陰で自由自在に動かすことができるが、神経が密集した分、性感帯のような敏感さを併せ持っ ている。それでも、欠点を抱えながらもアワリティアは自分の羽根に絶対の自信を持っていた。その弱点を相手に知られていても負けたことがないからだ。デメ リットを補って余りある利点が自由に動く羽根にはあったのだ。
しかし、それがここに来て裏目にでていた。
「こ、こんなもの……っ」
アワリティアが羽根を動かして、アンナマリアの秘所から羽根を外す。そのとき、羽根による拘束がわずかに緩んだ。
それで、アンナマリアの右手が自由になった。
隙を突いて右腕を抜き取る。腕を振るうだけのスペースはないが、相手の躯に触れるくらいの余裕はあった。
アンナマリアは自由になった右手で、押しつけられると窒息してしまいそうなくらいに大きな胸に触れると感触を楽しみながら持ち上げ、乳輪を口に含んだ。
「ああっ!?」
口にしてしまえば、後はもうアンナマリアの独壇場だ。アワリティアから学習した男殺しの舌技。それを余すところなく発揮して、その乳首にむしゃぶりついた。
「ちゅ……ちゅぷゅ……はう……っ」
まるで母乳を欲する赤子のような吸い付き。ただし、ただ夢中になって吸い付く赤ん坊と違って、アンナマリアの搾乳は性器すら搾り取ろうとするほどに貪欲だった。
「やっ、そんなに勢いよく吸い付いては……っ!」
乳首から浸透し、乳房を犯して全身を貫く刺激に、アワリティアは切なげに鳴いた。ちゅっ、とアンナマリアが強く乳首を吸う度に刺すような快感が乳首を責めるのである。
「吸い付くのは、だめ? なら、こっちも……貴女の指の技で責めてあげる」
いって、指先をアワリティアの膣に挿入した。
それは、アンナマリアの頭を撫でているときにアワリティアが使った指技であった。繊細に相手を責め立てる指の動きを完全に再現して、技を総てお返しする。
くちゅくちゅと蜜壺をかき回されて、止めどなく愛液が溢れだしてアンナマリアの手を濡らす。乳首と秘部を同時に責められ、アワリティアは目をうっとりと涙で濡らしていた。
「そんな、この私が……こんな、声を、あげてしまうなんて……!」
「それだけ、貴女の技が気持ち良いってことなのかな。今まで男たちを搾り取ってきた自分の技で感じるなんて……恥ずかしいね」
「ちょ、調子に乗って……! ああんっ」
睨み付けてくるアワリティアを子宮に指を差し込むことで黙らせて、アンナマリアは嗜虐心のままにほほえみかけた。
「もう終わりにしよう……自分の技で、みっともなく、イってしまって」
アンナマリアは指の前後運動を早め、ラストスパートをかけながら、口も思い切り乳首に吸い付かせた。
ちゅぱっ、ちゅぱっ、ちゅぱっ、と乳首をむしゃぶる音と、ずぷっ、ずぷっ、ずぷっ、と膣を貫く挿入音。その協奏に鼓膜を刺激され、アワリティアの性感は一気に高められていく――。
「こ、こんな……こんな、嘘です……私がイってしまうなんて、そんなことあるわけ、あるわけぇ……!」
アンナマリアが、最後に乳首をこりっと甘噛みし――アワリティアの躯が跳ね上がった。
「あ、イ、イ、イってしまう……この私が、私が、私がぁ――! あ、ああああっ、ああああああああんっ!!」
虚ろだった目を開いて、淫魔アワリティアは絶頂に達した。
乳房を何度も揺らし、足先をぴくぴくと痙攣させながら、何度も何度も全身を巡る快楽の渦に呑まれて、アンナマリアの前に屈服したのである。
ぐったりと脱力したアワリティアから、羽根を押しのけてアンナマリアが立ち上がった。
大浴場の中でひとり立ち上がり、すぐにまた倒れそうになってしまう。啖呵を切り、アワリティアを退けたものの、アンナマリアの躯に堪った刺激と疲労も相当なものだった。膝はがくがくと笑い、気を抜けばすぐにでも倒れてしまいそうである。
だが、戦いは終わった。
「……わたしの勝ち。さよならアワリティア」
足下に倒れている淫魔に向けて、アンナマリアは右手を突き出す。
アンナマリアの体力ももう限界で、性技でトドメをさせるだけの余力はもう残っていなかった。なら、自分がもっとも得意とする手段で敵を排除するしかない。
生かしておいてはなにがしでかすかわからないのだ。だからアンナマリアは、断頭台の力でアワリティアに引導を渡そうとしていた。
「あまり、調子に乗らない方がいいと、云っているでしょう……」
絶頂の余韻が抜けずに息を荒くしたアワリティアが、アンナマリアの目を見返した。しかしいくら凄もうとも、あの様子では淫魔といえどもしばらく動けないことは明白だった。
「負け惜しみ……? もう云わずに、死んで……しまえ、ば……」
急に全身から力が抜けて、アンナマリアが膝から床に崩れ落ちた。
そのまま躯を支えようとしても腕にも力が入らず、倒れてしまう。疲労が限界に達した、というわけではなかった。急に全身の筋肉が弛緩して動かなくなったのである。
「これ……ひったひ、な、に……」
口にして、ろれつが回らなくなっていることに気付く。これは自然に発生するとは考えられないことだった。
その有様に、アワリティアが喉を鳴らして笑う。顔には余裕が戻っていた。
「ど うやら、保険がきいたようですね……。気付いてはいませんでしたか? この浴場にずっと漂っている甘い香りに。これは催淫効果のある淫魔特製の媚薬なので すが、濃度の濃いものを耐性のない者が吸い続けると筋肉弛緩を引き起こすことがあるのですよ。やはり人の姿を取っている以上、その生理からは逃れられない ようですね……安心しましたよ」
「そ、ん、な……」
アンナマリアは狼狽しながらも右腕を動かそうとする。その手を少し左右に振れば、断頭台の刃がアワリティアに向かって跳ぶというのに、指先すらろくに動かせない。それは、意識だけをマネキンに移植されたかのような気分だった。
絶望的な焦燥が、炙るように胸を焼いた。じりじりと、敗北の足音がすぐそこまで迫っていた。
「これで貴女はもうなにもできませんね……。形勢逆転というやつです」
倒れたアンナマリアにかわって、アワリティアが躯を震わせながらゆっくりと立ち上がる。勝利を確信したアワリティアには既に不安の色はない。
「どうです? いきなり絶望の底に突き落とされた気分は」
床に倒れているアンナマリアの頭をアワリティアが踏みつけた。素足とはいえ力を込められて踏まれて、痛みに小さく声を洩らした。
「く……っ」
「いいです、いいですね、その悔しそうに歪んだ顔。本音を云えばもっと眺めていたいのですが、時間をかけて痛め付け、また不測の事態が起こってしまっても困ります。ですから、これで、お別れです」
羽根が大きく広がった。
大きく広がった一対の漆黒の羽根は、アワリティアの躯よりもさらに大きい。その異様な、美しさすら感じさせる姿は、アンナマリアにとっては死神以外の何者でもなかった。
「淫魔として、搾り殺すことこそ名誉ですが――この際、手段は選ばないことにしましょう。甚だ不本意ではありますが……これで逝っていただきます」
すっ、と手を掲げると、掌の上で何かがふわふわと光り出した。突如、小さかった光が太陽のようなまばゆさを持って輝く。目もあけられぬ光に浴場が照らし出された。
その灯りはすぐに収まった。だが、光自体は長細い槍状のものとなりアワリティアの手に握られていた。
「淫魔が暴力に訴えるのは本当に不名誉なことなのですよ……恥をかかせていただいた分、貴女にも不名誉な死に様を晒していただきます。その首を刎ねさせてもらいますね」
槍の歩先がアンナマリアの首もとに突き付けられた。じりじりと槍の放つ熱で肌が焼ける感触。
「……っ!」
元の姿が断頭台といえども、人の姿をとっている限り身体構造も人のものに倣っている。首を刎ねられれば、アンナマリアといえども死を免れない。死が目前に迫っていることに、断頭台は静かに息を呑んだ。
これまで、数多の人を殺めてきたというのに、いざ自分の前になって恐怖する自分にアンナマリアは恥ずかしさを覚える。厳かに敗北を受け止めて死んでしまえればまだ格好もつくのに、肌を焼く痛みに目頭が熱くなって、どうしようもなく死ぬことが怖かった。
槍を振り払ってアワリティアに飛びかかりたい思いに刈られたが、全身は水銀に覆い被さられたように重く、身動き一つとれない。
このまま、為す術なく、自分は死ぬのだ。
「それでは、断罪のお時間です」
そして、アワリティアが槍に込める力を強めた。
抵抗もなく、槍の穂先は押し込まれる。そのまま刃は石造りの床すら易々と焼き切りながら貫いた。
「……何者です」
殺意を隠さぬ声をアワリティアが洩らした。楽しみに水刺されたと、そういう不快さが滲みでている。
アワリティアの槍は床を貫いたが、貫いたのはそれだけだった。そこにはアンナマリアの躯はなく、薄い水溜まりが出来ているだけである。
剣呑な呼び声に答えたのは、張り詰めた空気には似つかわしくない余裕をたっぷりと砂糖壺一つ程は含んだ声。
「何者だ、と問われれば、そうだね。彼女の保護者と答えようかな」
浴場に始めて響く声。声の主は浴場にはおらず――否、現れた。
アワリティアの目の前に紺のマントが翻る。塔みたいに長い帽子を抑え、マントを払って危なげなく着地する女性は、口元をわずかにつり上げて人をからかうような表情をしていた。その表情こそが彼女の常なのだということはアワリティアの知る所ではない。
だが、それでも、アワリティアが彼女に対して知っていることはある。瑞々しく艶やかな銀髪に、人でありながら淫魔に引けを取らない男を惑わす魔性の肉体。 その立ち姿を忘れることなどそうそう起こりえることではない。特に、出会ったことすらない彼女を常々警戒していたアワリティアにはとって、その可能性は皆 無だった。
「魔女イザベラ……邪魔をしたのは貴女ですか」
「お初にお目にかかるよ、七罪の一柱。興を削いでしまって申し訳ない。本当は私も傍観を決め込むつもりだったのだけどね、いやはやなんとも、私にもまだ人の心というのが残っているらしい。我慢できずに干渉してしまったよ」
「……そうですか。貴女はそれほど情が深い人には思えませんでしたが」
「私もそう思っていたのだけどね。いやあ、母性とはすごいね。さすがの私も〝娘の危機には〟重い腰をあげざるを得なかったよ」
にやりとイザベラが笑った。アワリティアは戦いで疲れ切った躯で精一杯にイザベラを警戒しながら、槍の方もいつでも動かせるようにと気を払った。
「やはり貴女が断頭台制作、秘密にされた最後の協力者……でしたか」
「いかにも。常々私に気を向けていたということは、君は最初から知っていたようだね。さすが強欲のアワリティア。情報にすら欲が深いと見える」
互いに静かな牽制を続けながら、それでもイザベラから余裕が消えることもない。
「王 と開発者からの要請さ。彼女に魔術的効果を付与するためには私の協力が必要でね、この王宮に出向かせてもらっていたよ。いやあ、この浴場も懐かしいなあ。 ギヨたんの人格を作るためにサンプルとして子供を受精したんだけど、そのためにここで何度も王や兵士と躯を重ねたものだよ。みんな途中でへばってたなあ、 懐かしいね」
イザベラの論点が判らなくなるような軽口をアワリティアは相手にせず、冷静に返答する。
「対淫魔用、索敵断罪処刑具……というわけですね。あの学習能力、やはり完成していては我々の脅威となっていたでしょう。王を搾り殺した私の判断は間違っていなかったようですね」
「ギ ヨたんが成熟したら最終的にはもっと凄かったろうからね。自立行動して、淫魔と人を判別し、さらには性技を簡単に躯で覚えられるんだ。きっと世界一の床上 手になっていたと思うよ。あ、最後の機能は私が勝手につけたんだけど。せっかく淫魔と戦うんだからそれくらいないと面白くない」
そこでイザベラが指一本立てる。まるで教え子に講義をする教師のような仕草だった。
「でも、間違っていることがひとつ。それはね、ギヨたんが完成していたとしても君たちの害にはならなかったということだよ」
「……なんですって?」
「王の気が変わったんだよ。ギヨたんを自立行動させるためには知能が必要で、だから私の受精した子供をすぐに摘出して魂だけを移植したわけだけど、それに情が移ってしまったというわけさ」
大げさに肩を竦めて、イザベラは言葉を続けた。
「た だでさえ人化できるほどの力を蓄えさせるために断頭台を選んで人を処刑させていたんだ。人を殺すことはもっとも呪詛を溜め込む手段として優れているから ね。ただ、そのせいで人化の前に意識が目覚め、意志とは関係なく人を殺すという呪われた運命を背負わせたギヨたんに、それ以上の苦行を押しつけることがで きなかったのさ。だから私はギヨたんが目覚めたら自由に生きるようにいってくれって言付けられていたよ。その結果はご覧の通りだったけど」
「……なるほど、大方の事情は飲み込めました。それを知っていたとしても私の行動は変わらなかったでしょうが」
「ほう? 君は王の行動を危険視してこの国を落としたものだと思っていたけど」
「それが大きな理由であったことは否定しません。ですが、根本的に私の中に根付いている願望はおわかりでしょう?」
「二つ名は伊達ではない、か」
イザベラのつぶやきに、アワリティアの口が孤を描いた。
「そ う――強欲。私はね、欲しいのですよ。街が、国が、世界が。そこにある家畜が、民が、富が。私の淫魔としての行動は元をたどればそこに行き着くのです。搾 精をおこなうのも心が満たされるからですし、子供たちを作るのもその一環でしかありません。この世の総てが、私は欲しい」
「世界すら喰らおうとするか。なんとも大言壮語が過ぎる淫魔だ」
「そうでもないでしょう。世界をとるなんて実に淫魔らしいとは思いませんか。いや、世界、より地球と言い換えた方がいいでしょうね。だって、地球は生きているんですもの。生きているなら幾らでも籠絡してさしあげますわ」
「まあ、その槍すらその地球の産物だろうからね。私の魔法もそうだけど……やれやれ、私も人のことをいえないくらい業が深い」
「魔女も淫魔も、魔に通じるものは等しく地球の愛人ですものね」
イザベラとアワリティアの口にしている言葉は、常人には理解のし難いものであったが、ふたりの間では常識のような事柄であった。
空間跳躍を筆頭に超常的な力を振るうイザベラ、虚空から光の槍を取り出したアワリティア。ふたりの行使した力は共に魔法と呼ばれるものである。この力、理論的なところを省略してしまえば、その共通項は〝地球を騙す〟ことなのだ。
地球とは自然という新陳代謝をする生物であり、この世界の時間、空間、そんな普遍的な物理法則すら総て地球自身の生態、行動なのである。よって魔法とは、この地球をどう騙して架空の論理を走らせるか。どう新しい法則を地球に作らせる、信じ込ませるか、に集約する。
「私は魔女だからね。最初に力を手に入れたのは悪魔と契約したからさ。対価を支払わされることになるけど、悪魔から一気に強い力を貰える。魔法使いと違うところだね」
「そう、そうやって貴女が欲望のままに悪魔から力を手に入れたように、私は自分の欲望のままに国を獲ったまでのこと。そしてそれはこれからも続いてゆくのです。……ですから、邪魔な貴女にはここで逝っていただくとしましょう」
「へえ、その調子だと体力は回復できたのかい? 結構時間がかかったね」
飄々と云ったイザベラに、アワリティアは顔を強ばらせた。
「まさか、わかっていたのですか」
「そ うでなければあそこまで口数は多くないよ。と、云いたいところだけど、半分以上は私が話したいから話しただけさ。いや、他人に云えない秘密というのを抱え 込むのが苦手なタチでね。誰かに聞いておいて欲しかったんだよ。ほら、ギヨたん本人に伝えてもどうせお母さんなんて呼んでくれそうにないし」
「たいした余裕ですね。よほどご自身の力に自信があるようですが――その油断が命取りです」
瞬間、光が爆ぜた。
光――ッ、とまばゆい光で浴場が満たされる。目を閉じ手で覆ったとしても肉をつらぬき目を焼きかねない光。
その中を一筋の黒影が疾駆した。
光の槍を携えたアワリティアである。閃光に紛れて駆ける姿は足場の悪さをものともせず豹のように俊敏。
両手で腰の辺りで構えた光の槍、アワリティアはその穂先を人影へ一直線に向けていた。
光が晴れる。しかし、人影は未だに閃光の余韻で呆然と立ち尽くしていた。
目くらましの光に立ち尽くすイザベラが――。
無防備な獲物を前にして酷薄な笑みが浮かんだ。
「さようなら――愚かな魔女さん」
槍は鮮やかな手つきで、迷いなくイザベラの左胸を貫いた。
「ぐ……っ」
イザベラの口から真っ赤な血がこぼれ落ちる。
アンナマリアのときのようなことは起こらなかった。転移する暇すら与えずに、光の槍はイザベラの左胸を刺し、その心臓を貫いたのだ。熱を持った光の槍が音を立てて血を蒸発させながらイザベラを内部から焼き焦がし、脂肪の焼ける酸っぱい匂いが浴場の中に充満する。
「確かに貴女は過信するだけの力を持っていらしたようですが……それも使えなければ意味もありませんでしたね。おとなしくひきこもっていればよかったのに、調子に乗るからそうなるのですよ、お馬鹿さん」
「ああ、慣れないことは、するもんじゃ、ないね……」
イザベラの足から力が抜けて躯が傾ぐ。胸に刺さった槍に体重がかかって、背中へと貫通している槍がさらに深く突き刺さった。
「いかな魔女といえども、死んでしまえばただの肉塊。惨めな最期でしたね。あの世で悪魔への対価で慰みものにでもなっていなさい」
心の臓を貫かれて虫の息になったイザベラに、アワリティアは最後となるであろう言葉を投げかけた。
脱力したイザベラの躯をトドメをさすために槍がさらに深く突き進んでいく。
「いや、別に死んでないけどね。私は」
イザベラの手がアワリティアの胸を押した。
「え――っ」
それだけでアワリティアの躯が吹き飛んだ。
衝撃に槍を手から離してしまったアワリティアが向かいの壁に激突する。背後の壁に亀裂が走るほどの力に、口から苦悶の声があがった。
「いたたた。手が届かないから躯ごと奥に押し込んだけど、さすがに痛いね」
「か、ぁ……っ!? な、何故……」
「どうして生きてるか、だって? いやいや、君が散々云ってたじゃないか。魔女だからだよ」
自分の左胸に突き立った光の槍に、イザベラは熱で手が焼けることも気にせずに掴むと、一息で引き抜いた。傷口は焼け焦げ、血は流れ落ちなかった。
「魔女を人間と思っちゃいけないね。だから弱点が心臓だなんて思い込む。私も心臓を壊されれば痛いけど、それは肺や胃を傷つけられたのと意味に違いはないんだよ。私としては肝臓を刺された方が昔を思い出してまだ気が滅入ってしまうね」
自分の手を焼く光の槍を興味深そうに眺めながら、アワリティアはこれまた講義のような口調で云った。痛みと屈辱で、アワリティアの顔が苦虫を噛みつぶしたソレになった。
「へえ、光を一カ所に止めるように偏光させた槍か。熱は放射せず、直接触れたときにのみ伝導するんだね。温度は五〇〇〇度は超えているか。さすが高位淫魔は作り出せる携行武器も一流だね」
「調子に、乗るなと、云っているでしょう――っ」
アワリティアが吼えた。
一喝で彼女の背中にあった壁が吹き飛ぶ。アワリティアの漆黒の羽根に叩かれ、砕け散ったのだ。
「いいでしょう、そうまで虚仮にされてはこちらも全力で行かせて頂きます。この国に来てから蓄えた精気、それを総て魔法に注ぎ込んで――」
「あ、それは無理。これ以上争う気はないよ」
にこりと笑いながらイザベラが微笑んだ。
「だってもう争いじゃなくて、虐めだからね」
そして、アワリティアは自分の置かれた状況に絶句した。
「あ、ああ……」
頭上から、無数の光がアワリティアを照らしていた。それぞれの光源が青空に浮かぶ太陽を見上げたときのようにまぶしく、人が直視しつづけていては目を悪く してしまいそうなまばゆさだった。そんなことをものともせず、いや、そんなことに気を裂く余裕すらなく、アワリティアは見上げ続けていた。
その頭上には無数の光の槍が雨粒を停止させたような格好で並んでいた。
ずらりと並んだ光の槍。一〇は見ただけで上回ることがわかり、一〇〇ですら足りそうになかった。いったい、何百の槍が頭上に並んでいるのか。もし数え切れてしまったらアワリティアは発狂してしまうだろう。
「君が本気を出してしまえば、このお城くらいなら簡単に消し飛ばしてしまえるだろう。それは困るんだよ。ここに倒れてる子たちも兵士も巻き添えだし、なによりこんな歴史ある建物を壊すなんてもったいない。だから、そうさせる前に終わらせたいんだ」
「なんで、私の、魔法を……」
「んー? わからないかな。私もね、ギヨたんみたいに君の技を覚えたんだよ。もっともギヨたんは道具っていう性質を利用して関連づけしたんだけど、私は悪魔と契約して手に入れた模倣能力さ」
「馬鹿な……転移、怪力、身体の不死性、それに技の模倣……これだけの数の力を契約で与えられる悪魔などいるはずがありません! もし仮にいたとしても、埒外な代償が……」
「簡単な話だよ。私は、複数の悪魔と契約してるんだ。それなら話は簡単だろう?」
「そちらの方があり得ない! 悪魔から要求されるのは魂! 複数の悪魔から代価を要求されれば、生きていることなど……」
「うーん、頭が硬いな。だから、私は悪魔に代価を払わなくていいんだ。だから何体とだって契約できる。ああ、でも全員に一度は払ったかな。躯を重ねるっていう代価をね。ちょっと腰を振ってあげたら、みんな代価を免除してくれたよ」
今度こそ本当にアワリティアは言葉を失った。
魔女イザベラ――アワリティアはその存在をこの国に滞在している人物の中で最重要人物として注意を払っていた。未知数の魔女の力は、高位淫魔である自分自身でも脅威と判断していたのだ。
しかし、心底警戒していたというわけではなかった。常に目の端で姿を追ってはいたが、凝視したことは一度としてはなかったのだ。
アワリティアは最大限に警戒していたつもりだったが、相手の力はそれを軽々と上回るほどに規格外だった。
その力、全力のスペルビアでも勝てるのであろうか――? 淫魔の得意分野である性技でなら、自分でも――。そう思い込もうとして、勝てる想像が一切わいてこないことにアワリティアは絶望で泣きそうになっていた。
「それじゃ、覚悟はいいかな?」
「ま、待って……ください。最後に、ひとつだけ……」
「なんだい?」
時間を稼ごうという気はアワリティアにはなかった。多分、いかなる幸運が重なろうとも自分の死が覆らないだろうということは判っていた。ただ、単純に知りたいことがあったのである。
「貴女は、何者、なのですか……?」
その質問にイザベラは目を瞬き、次いでくすくすと笑い出した。
「ああ、そうか。そうだね。正体の判らぬ相手に殺されたくもないだろう。かといって、何者か、と問われて即答できるほど私は哲学を嗜んではいないんだが……うん、ならこの名なら通りもいいか」
すこし逡巡して、イザベラは自分の異名を口にした。
「シュネー・ヴィットヒェン……〝白雪姫〟、さ」
答えて、白雪姫――イザベラはアワリティアに問い掛ける。
「それじゃ、私からも君にひとつ聞かせてもらおうか」
「え……」
「君は今まで死んだことがあるかな。いや、ほら、こんなに槍があるんだ。即死されてもつまらないだろう。どれだけ蘇られるのかと思ってね」
「そんなことできるわけ……」
そこまで答えて、アワリティアの真っ青になった顔からさらに血の気が引く。イザベラの言葉の意味がわかってしまって、既に顔は死人のそれになっていた。
「ま、さか……あなたは……」
「ああ、そうだね。参考まで云わせてもらうと――私は、三度死んだよ」
今度こそ、アワリティアの理性という堤防は絶望によって決壊する。
「い、いやあああああああああああああああああああ」
無数の槍が投下され、悲鳴は光の彼方に消えた。
これが、この国を騒がせた革命の裏側での決着であった。
以後、真の指揮者を亡くした革命は瓦解していくこととなる――。
*
――エピローグ。
裏で指揮を執っていたものたちが無力化され、淫魔たちによって展開されていた兵士たちに下されていた命令は撤回された。
元より指示されていた人間たちにも理解できない不可解な頼み事だったのである。淫魔たち三人が忽然と消えたとあっては、事態が収束するのも当然と云えた。
さらに、スペルビアだけは騎士団長という表の立場もあったため、彼女の失踪についての調査もある。彼女が淫魔であると知らない大多数の者たちは大慌てで、意味の判らない命令にいつまでも構っている余裕はなかったのだ。
あの騒動から数日が経過していた。
アンナマリア、イザベラ、レリア、ジョゼフの四人はイザベラの家でテーブルをかこっていた。全員の目の前には細長いパンをナイフで切り分けたものがおかれており、できたてなのか香ばしいにおいを漂わせている。
「あー……冷めないうちにどうぞ」
そのパンを焼いた張本人であるジョゼフが遠慮がちに云った。
アンナマリアにパンを焼くという約束を果たすために、ジョゼフが居候をしているパン屋で焼いてきたものである。まともに店頭に並んだこともなく、特別に頼んでいたレリアだけが口にしていたものだが、それが今は全員の前にあった。
「じゃああたしが最初にいただきます!」
即答したのはレリアだ。云っているときには既に手はパンを掴んでいて、女の子でも食べやすいように小さく切りそろえられたパンを勢いよく噛んだ。
「うわっ、我が弟子ながら空気が読めないね、レリア」
「うるひゃいですよ、てんてー」
パンに噛みついたままもごもごと離したレリアは、そのままパンを口に押し込むと小さな喉を上下させて呑み込んだ。
「うんうん、空腹が満たされるパンですね」
「レリアちゃん、味はどうだったかな?」
「それはギヨたんの口から聞いてみるといいですよー」
「ギヨたんいうな」
アンナマリアは相変わらずの不機嫌そうな顔だったが、レリアに急かされてパンに手を伸ばした。
両手でおそるおそるパンを掴む。こんがりとして硬さのあるパンの耳と、真っ白でふわふわとした中の生地をじっと見つめた。元が断頭台であったアンナマリアにとって、パンは初めて口にするものであり、物珍しさで観察してしまっていた。
「さ、さあ、どうぞ」
「……うん」
頷いて、アンナマリアは口元にパンを持っていく。
さくっ、という音をさせて、パンをかじった。
しばしの沈黙の後、パンから口を離してつぶやいた。
「……不味い」
無慈悲な言葉にジョゼフの躯が硬直する。その隣でレリアはにこにこと笑っていた。
「はい、というわけで、あたしの感想も以下同文ですねぇ」
「容赦ない!? 笑顔なようでこの子たちまったく容赦ないですよ!」
「まあ仕方ないんじゃないかな。本当のことなんだし」
ジョゼフの正面に座ってパンをかじったイザベラも頷いて賛同を示していた。頬を引きつらせてジョゼフはうなだれる。
「判ってましたよ、自分が力不足だっていうことくらい……。せっかくだと張り切ってみましたけど……」
「期待して損した」
ざくっ、とアンナマリアの言葉がジョゼフに突き刺さり、体格の良い青年の躯がますます頼りなくしぼんだ。
「まるでやすりでも囓ってるみたい」
「もう追い打ちかけないで!?」
がりがりとパンを食べながら言葉を止めないアンナマリアに、ジョゼフは思わず涙目になりながら叫んでいた。
そこでジョゼフはアンナマリアの皿に載せていたパンが半分以上なくなっていることに気がつく。
「……あの、そんな無理して食べなくてもいいんだよ?」
「なんで?」
「いやなんでって……さっきやすりみたいって……」
「別にわたし、やすりがけされるのは嫌いじゃないけど」
不愉快そうに睨まれて困惑するジョゼフに、レリアがくすくすと笑った。
「やだなあ、ジョゼフくん。ギヨたんは一度だってこのパンが嫌いだなんていってませんよ」
「ギヨたんいうな!」
レリアの顔面にパンの切り身が投げつけられた。不意打ちに仰け反ったレリアは椅子から立ち上がるとむっと眉を寄せてアンナマリアを睨み付ける。
「こらっ、食べ物を粗末にするんじゃありません!」
「うるさいっ、ギヨたんいうな!」
顔を真っ赤にしたアンナマリアも立ち上がってレリアの目を真っ向から睨み付けた。ふたりのにらみ合いにジョゼフが慌てたが、イザベラは何食わぬ顔でパンをスープにつけながらかじっていた。
「ま、魔女先生……見てないでとめてくださいよ!」
「そんなこといわれてもねえ、喧嘩するほど仲が良いともいうし」
スープが染みこんで柔らかくなったパンを口に押し込んで、イザベラは食卓に肘をついた。
「それに、この喧嘩が見られるのは今日が最後だ」
イザベラの口調が、少しだけ重くなっていた。
それは、この場の全員が努めて気にしないようにしていたことだった。一気に部屋が耳の痛くなるほどに鎮まり返る。そうすると誰もが意識してしまう。ふたりの喧嘩にも、空元気が混じっていたということに。
「そのことくらい、みんな知っているんだろう。本人であるギヨたんや、直接話したジョゼフに……それと、立ち聞きをしていたレリアも」
「やっぱり、知られてましたか」
レリアの笑顔にも力がなく、まるで彫刻が微笑んでいるように味気ない。
アンナマリアが人でいられるタイムリミットは、もう目と鼻の先にまで迫っていた。そう、今にでも、瞬きをした次の瞬間には人の姿を保っていられなくなっているかもしれない。それほどまでに少女の躯は不安定になっていた。
「別に、死ぬわけじゃないし。ただ元の形に戻るだけ。そんな大げさなことじゃない」
ただ、当の本人はいつもと同じような顔のままにそういった。イザベラでさえ声の調子が変わっているというのに、この中で一番落ち着いているのはアンナマリア自身であった。
それに戸惑いながら、ジョゼフが声をあげる。
「でも、君はもう自分で喋ったりすることだってできなく……」
「大げさにしないで云ってるじゃない!」
アンナマリアが声を荒げて、ジョゼフははっと我に返った。
断頭台に戻るということは、アンナマリアは喋ることも、自分で考えることすらできなくなるのだ。単なるどこにでもある無機物になってしまうのである。イザ ベラの話では正当に年月を経ればまた目を覚ますことができるようになるとのことだったが、それは数年、数十年という単位ではない。数百年以上かかるもの だ。それほどの長い眠りは、死と同義である。それがおそろしくない訳などあるわけがない。
「あ、ごめん……」
「もういい。外の空気吸ってくる」
「あっ」
アンナマリアは椅子を倒しそうな勢いで机を離れると玄関から飛び出していった。止める間すら与えられなかった。
呆けて開けっ放しになった玄関の扉を見つめるジョゼフの背中を駆け寄ったレリアが思い切り叩いた。
「ほらっ、なにしてるんですか! 早く追うんですよ!」
「う、うん……! ちょっと、待ってーっ!」
頷いて、ジョゼフは後を追って玄関を飛び出した。その姿を見送って、レリアは安堵の溜息をつく。その横ではイザベラが丁度スープを飲み終えたところだった。
「いやはや。レリアは相変わらず苦労性だね。その難儀な性格には思わず目元が緩むよ。さ、あとはふたりに任せて私たちはのんびりするとしようか」
「なにいってるんですか、先生」
「んむ?」
「あたしたちも行くんですよ!」
レリアは思い切りイザベラの背中も叩いた。
「待って、待ってったら!」
人混みを掻き分けて路地を進むアンナマリアに向かってジョゼフは声を張り上げる。しかし、彼女の小さな姿は止まるどころか人の間を器用にくぐって進んでいく。
女の子を追いかけているのを周囲の人々に胡散臭げに見られながらも、ジョゼフはそれらに気を裂いている余裕はなかった。少しでも目を離せば、彼女は手の届 かないところへ消えてしまっている気がしたのだ。そして、次に会うときは物言わぬ姿になっている。そんな想像ばかりが浮かび上がってきて、もうジョゼフに はアンナマリアしか目に入らなかった。
走って、走って、アンナマリアが路地を曲がった。ジョゼフもつられてそこを曲がって進み続けると、急に人の姿がなくなっていく。郊外の奥地にひっそりと立てられたイザベラの家からある程度離れてしまえば、そこはもう人気のない森林地帯だった。
ここまでアンナマリアはすばしっこく逃げ回っていたが、人という障害物がなくなった今なら足の速さでジョゼフに適うものではない。みるみる間に距離を詰めて、ジョゼフはアンナマリアを後ろから抱きしめた。
「捕まえた」
「……離して」
「逃げないなら離すよ」
アンナマリアは答えなかった。ジョゼフは抵抗もしなくなった小さな少女のぬくもりを腕の中に感じながら口を開く。
「ごめんね、君が不安なことに気がついてあげられなくて」
「わたしは、別に……なんでもなかった。ただ、ひとりでいたいから……だからここまできたの」
「それなら、逃げなくてもよかったじゃないか。逃げられたら、追っちゃうよ」
「そんな、勝手なこと……」
そうは云いながらも、アンナマリアの言葉に覇気はなかった。顔を近づけていなければ、なにをいっているのかすら聞き取れないほどに弱々しい。
腕の中で小さくなる黒い少女に、ジョゼフはふと思いつく。
「君は、猫みたいだよね」
「なんで、猫?」
「猫は、自分の死期を悟ると姿を消すんだ。誰にも見られないように」
「それ……勉強して、知ったことなの?」
「さあ、なんだったかな。息抜きに読んだ本にでも書かれてたのかもしれない。だけどね、そうでなくてもぼくは君が猫みたいだと思ったよ」
「わたしは、猫みたいに弱くない」
「そうかな。ぼくには……君が雨に濡れて、帰り道がわからなくなった、かわいい黒猫に見えた」
言葉を失ったアンナマリアに、ジョゼフは腕に込める力を強めた。
「だから、もうひとりで無理なんてしなくていいんだ。やせ我慢して、ひとりで最後を迎えようなんて……そんなことはしなくていいんだ。だから、ぼくやみんな嫌いで逃げたんじゃなければ……看取らせてほしい。君の最後を」
「……嫌いなわけ、ないよ」
アンナマリアの顔はジョゼフからは見えなかったが、その声が震えていることはよくわかった。
「嫌いなわけない……ジョゼフも、レリアも、あの魔女だって……嫌いなんかじゃない。でも、わたしはひとりじゃなきゃいけなくて……ずっと酷いことをし続けなきゃいけなくて……だから、わたしが一緒にいたらみんなあの人みたいに不幸になっちゃうから……」
「不幸だなんて、ぼくは思わなかった。驚いたし、凄い目にだってあったけど、それでもぼくは君を蔑むことなんて一度だってなかった」
「でも……」
「あたしもギヨたんのこと大好きですよ!」
女の子が声を張り上げていた。それはジョゼフとアンナマリアを追いかけてきたレリアによるものだった。
「自分のせいで人が不幸になるだとか、迷惑にさせるとか、なにひとりで被害妄想に耽ってるんですか。あたしの知ってるギヨたんはそんなに殊勝な子じゃなかったですよ!」
「レリア……」
「偉そうにふんぞり返っていればいいんです。弾劾してくる人がいたらそれがどうしたって鼻で笑ってやればいいんです。ギヨたんは自分のことを負い目に感じる必要なんてこれっぽっちもないんですよ!」
「そうとも。むしろ、ひとりで溜め込まれている方が良い迷惑だよ」
レリアに続いたのはあのイザベラだった。急いできたのか肩で呼吸しているレリアと違って息一つ乱していなかったが、それでも、その目は真剣そのものだった。
びっくりして硬直しているアンナマリアに、ジョゼフがそっとつぶやく。
「ほら、みんな、こう云ってる。だからね、後ろめたさなんて覚える必要はないんだ。最後くらい……みんなに囲まれていたって、いいんだ」
「あ……っ」
ジョゼフの掌に熱い雫が落ちた。アンナマリアの小さな躯が震えていて、必死に掌で目元を拭っている。けれど、ジョゼフの手を濡らす雫が減ることはなく、むしろ堰を切ったように溢れていく。
「やだ……今度は、今度は……みんなとさよならしたくない。したくなくて、涙がとまらない……」
「ぼくは、君をひとりにはしないよ。だから、不安にならなくていいんだ。ただ、そう、少しだけ……眠るだけなんだから」
「起きたら、側にいてくれる?」
「勿論」
「それは……」
アンナマリアの小さな手が、ジョゼフの手を握った。
「すごく、安心した」
ジョゼフの腕の中にあった暖かさが徐々に薄れていく。ずっと掴んで離さないと思っていた子の躯からは力が抜けて、魂が抜け落ちたように冷たくなっていって、それを止める術はジョゼフにはなかった。
「さあ、ジョゼフ。もう離れるんだ」
「先生……」
「時間なんだ」
振り返った先にいたイザベラは、沈痛な面持ちで首を振った。レリアもぎゅっと手を握りしめて、動かなくなっていくアンナマリアを見ていた。
あの万能であったイザベラがあんな表情をするのを、ジョゼフは見たことがなく、だからもうどうしようもないのだという事実が胸に押し寄せる。奥歯を噛みしめながら、ジョゼフは少女の躯を地に横たえてその場を離れた。
そして、アンナマリアの躯が変わっていく。質量を無視して、その躯は輪郭を失って大きな断罪の鎌へと変わっていく。あとには、見上げるほどのただただ大きな断頭台が残された。
その処刑道具には、アンナマリアの名残を感じることはできない。無機質で、冷たい刃が、薄く漂う霧で濡れていた。
「ギヨたん……もう、動かないんですね」
レリアが断頭台に歩み寄って、その刃を見上げる。
涙は流していなかった。ただ、その顔には寂しさがあった。
「もう、ギヨたん云うなって、云ってくれないんですね」
こういえば、文句の代わりに刃でも落ちてきてくれそうな気がした。そう夢想して、けれど断頭台は動かない。それはもう道具でしかなく、道具は人が使わなければ動かないのだ。当然の理屈だった。
「さあ、どうする、ジョゼフ。君は彼女に無責任な約束をしてしまったぞ」
黙って断頭台を見ていたジョゼフに、イザベラが厳しい声をかける。
「起きたら側にいるだなんて、人の命では到底無理な話だ。彼女は今後数百年目を覚ますことはないのだから」
「そうですね……きっと、ぼくでは魔女先生みたいにもなれないでしょうし。もう、二度と、ぼくはあの子の姿を見ることはできないんでしょう」
イザベラを振り返る。ジョゼフの瞳に溢れていたのは、しかし、決意だった。
「けど、ぼくは駄目だったとしても。ぼくの息子が、孫が、曾孫が、子孫が……きっと、彼女の側にいてくれるはずです」
「君は……」
「子々孫々、言い伝えますよ」
そっと、その手で断頭台に触れる。
「ちっちゃくて、黒くて、かわいい、意地っ張りな……不器用な女の子がいるんだってことを。その子にあったら、絶対に助けてやってくれって」
ジョゼフは目を閉じた。思い返すのは、家族を全員失ったあとの自分だった。
あのとき感じた気持ちが胸にわき上がって、ジョゼフはイザベラに笑ってみせた。
「だって、目が覚めたときにひとりぼっちだったら、寂しいじゃないですか」
その答えに、イザベラはしばらく言葉を失っていた。彼女がなにかを言い出す前に、静けさはレリアによって打ち消された。
「それっ、あたしもお手伝いしますっ!」
がばっ、と抱きついてくるレリアにジョゼフが顔を真っ赤にしてあたふたと慌てた。
「え、ちょっと、レリアちゃん!?」
「いっぱい子供作って幸せな家庭を作りましょーね! それでそれで、ギヨたんが起きたときには騒がしいくらいの一大一族に!」
「ちょ、ちょっとそんないきなり……むぐーっ」
いきなりキスをされてジタバタと手足を振り回すジョゼフの姿を眺めていて、イザベラは苦笑しながら帽子を抑えて顔を隠した。唯一見える口元は、しっかりとした、皮肉ではない笑みが浮かんでいる。
「なるほど、血の繋がりか……。そうだった、それが人っていう生き物の確かな力だったね。寿命をなくして、久しく意識していなかったことだ」
騒がしいジョゼフとレリアの前でも静かにたたずんでいる断頭台を仰ぎ見て、イザベラは柔らかく目を細めた。
「なにも不安に思うことなんてないよ。だから、ゆっくりとおやすみ。――私(マイネ)の娘(トホター)」
*
「おーい、倉庫なんかでなにしてんだよ。婆ちゃん」
「別に。ちょっと写真を見てただけ。あと婆ちゃん云うな」
「いてっ、別に叩くこたぁねぇだろ! こっちはアンタに作らされた飯ができたから呼びにきてやったんだぞ。まったく、パンなんか焼かせやがって……」
「はいはい。じゃあそのパンを堪能させてもらう。不味かったら死なす」
「相変わらず理不尽っすね婆ちゃん!?」
騒がしい男女の二人組が薄暗い倉庫を後にする。
はめ殺しの窓から差し込む灯りが、地面に落ちた写真に降り注ぐ。
写真には、立派な髭を生やした老人が、若々しい妻と共に断頭台の前で微笑んでいる様が映し出されていたのであった――。
Photo By Isabella.
The End...
あけましておめでとうございます。前回あんなこといって年内に終わらせるつもりがこんなことになりました。というか文庫本換算で60ページ以上ある最終話となりました。総ページ数は大体400ページ!
思えば最初の一話をあげて思い付きで始めたものでしたが、こんなに続くとは自分でも驚きです。ここまで見守ってくださった皆様、本当に今までおつきあいありがとうございました。
せっかく作ったのだし、ということで最終話にして初めてでてくる設定、キャラクターの行動背景を描写したせいで蛇足感もでてしまいましたが、やりたいこと、云わせたいことはこれで終わりです。機会があれば、コメントでもらったような補足的な話もやってみたいですね。
今まで見るだけだったBF小説、実際に書いてみていかに苦労するか思い知らされた苦しくも楽しい期間でした。
それでは。重ね重ね、ここまで目を通していただきありがとうございました!
ソファに身を沈めていたイザベラは顔をあげると、なんでもないことのように口を開いた。その目は壁の方に向いていただけだったが、どうやら遠い彼方の出来事でも覗き見ているらしかった。
「え、それは本当ですか、魔女先生!」
「本当だとも。あれでも私の助手なのだから、淫魔のひとりくらい倒せるのは当然さ。心配する必要もなかったね」
「……それくらいしてもらわないと、困る」
安堵を隠さぬジョゼフとは正反対に、アンナマリアは鼻を鳴らすだけだった。けれど、よく見るとその口元がわずかにほころんでいる。経過を見ることができず、ただ結果を待つだけという状況では、口でどう云おうとアンナマリアも心配だったのである。
しかし、そこでイザベラは軽く手を叩いてふたりの視線を集めた。
「けれど、さすがにひとりが限界だったみたいだね。というわけで、ジョゼフにも出張ってもらう必要がでたわけだ」
「……覚悟はしていましたよ。巧くいくかはわかりませんけど」
「じゃあ、さっそく次はジョゼフにいってもらおうか。スペルビアは最後に残しておくと兵を指揮されて面倒そうだからね」
改めて要求されて、ジョゼフの顔が緊張で強ばった。今まで淫魔やアンナマリアたちの好きなように扱われていただけの自分が高位淫魔たちと戦わなければならないということにたじろいでいるのだ。
「う……わかりました。でも、確か団長とはまず剣で力比べしなきゃいけないんですよね。ぼく、剣とかもってないんですよ」
「それなら……そうだな、ちょっと待ってなさい。確か倉庫に……」
イザベラはぼそぼそとつぶやきながらリビングから廊下へと出て行き、奥の方へと引っ込んでしまう。奥の部屋の方からゴソゴソと何かを探る大きな音がしたかと思うと、すぐに扉が開いた。
「ふむ、これなら良いだろう。昔、知人に貰ったものだ。さっきまで倉庫で埃を被ってたんだけどね」
戻ってきたイザベラの手には一振りの剣が握られている。華美な装飾はなく、鍔もとにはめ込まれた赤く光る宝石だけがその直剣に施された唯一の飾りだった。 刃渡りは九〇センチ――ジョゼフの上半身ほどもあり、刃にも曇りはなく倉庫に放置されていたとは思えない程の輝きがあった。
「そんな、適当な……」
「でも、充分なだろう?」
無造作に剣を投げられて、ジョゼフはあやうく取りこぼしそうになりながら剣を受け取めた。久しぶりに腕で感じる頼り甲斐のある鉄の重みに、柄を握る手に力がこもった。
「ええ、良い剣です。というか、こんなものをくれる知人ってなんなんですか」
「ええと、パラ……ううむ、長くて名前は思い出せないね。ま、道楽者なのだよ。では、早いところ相手のところにキミを送りこみたいのだけど、準備はいいかい?」
「ああ、はい、どうせこれ以上準備することも……」
服の裾を掴まれて、ジョゼフは言葉を止める。視線を落とすと、アンナマリアの手があった。
「アンナマリアちゃん?」
「……ひとつだけ、」
「なに?」
「夢中になって搾り取られたら殺す」
「取られません!?」
ぱっと手を離すと、アンナマリアは頷いた。
「なら、よし」
「う、うん、それじゃあいってきます……」
ジョゼフが苦笑すると、イザベラが手を差し出す。
「さて、それじゃあ行くよ。ジョゼフ」
「はい!」
笑顔のままにイザベラはジョゼフの目の前に手を持ち上げ――ぱちんっ、と指を弾いた。
それが合図となり、ジョゼフはレリアのようにまだ見ぬ場所へと飛ばされた。
転移術式によって、まるで白昼夢のようにジョゼフがかき消えたのを見届けると、イザベラは押し黙っているアンナマリアを振り返った。
「それで、あれでよかったの?」
「よかったって、なにが」
無愛想な表情のまま、アンナマリアはイザベラを見上げる。不機嫌なわけではなさそうだったが、下から睨み付けているように見えてしまう程度に、アンナマリアの目つきは悪かった。
「もっと、なにか云いたいことがあったんじゃないの?」
「……別に」
一言で突き放すと、アンナマリアは毛布を抱きかかえて顔を埋めた。なにも語ろうとしない様子にイザベラは苦笑して肩を竦めた。
「そうかい。じゃあ、言葉の続きは帰ってからにするといいさ」
アンナマリアは黙ってソファに座ったまま、毛布を被って何も答えなかった。。
*
目を開くと、視界一面に広がるのは深緑だった。
そよ風が頬を撫でていくと、くすぐったさにジョゼフは目を細める。息をすると、青臭い草の香りで胸の中が一杯になる。イザベラの家の中は埃っぽい空気で満たされていただけに、ジョゼフは躯が浄化されていくような印象を受けた。
「ここは――」
顔を上げると木漏れ日が目に入り、まぶしさで顔を手で庇う。
「覚えてないか、我がお前を斬ったところだ」
自分の背中にかけられた声でジョゼフは振り返った。
目に入るのは、革製の防具を着込み、腰に剣をはいた女性の騎士である。
ふたりの距離は一〇メートル。
間合いを詰めるに必要な時間は、瞬きひとつもあれば充分な距離。
女性は革の鎧と裾の長い、露出をとことん抑えた衣服を着ており、厳格さを感じさせる。けれど、その厳しさとは対極にあるだろう妖艶さがその女性からは漂っていた。
例えば邪魔にならぬようにと後頭部で髪を纏めるための紐から外れてしまった後れ毛の妙な色香。シスターのように肌の露出を控えているのに唯一無防備にさらけ出されて、人の視線を集める首もと。
高潔さと淫靡さを危ういバランスで両立させた女騎士。その存在の名をジョゼフは重々しく口にした。
「覚えていますよ、スペルビア団長。腕を切り落とされたなんて経験をした所を、早々忘れられはしません」
ジョゼフは、兄が存命中だったかつて、騎士団に籍を置いていた。そこで革命の雰囲気を敏感に察知し、まだ事を起こす前に退団したのである。けれど、スペルビアはジョゼフを見逃さなかった。ある日、月の下でジョゼフをここまで追跡し、腕を切り落としたのだ。
本来なら出血多量でジョゼフは息絶えていたが、そこを通りがかった魔女イザベラに命を救われたのである。
そんな印象的な出来事を忘れることができようはずもない。意識すると、斬られた右肩の辺りが痛みを思い出してざわめいた。
「今日は自衛をかねて、あのときの返礼をさせてもらいにきましたよ。剣の扱いだけで解決できれば越したことはないんですけど……」
「弱気だなあ、ジョゼフ。それに云っておくが、高位の淫魔たる我を人間が剣技だけで制圧しようなどなどと思いやがりであるぞ。男なら、床の方でも勝負をしてくれなければ、股のものも無用の長物というものよ」
そこまで云って、スペルビアは鼻を鳴らした。
瞬間、木々が絶叫した。まるで突風が吹き抜けたように、激しく激しく枝を擦り合わせ。
「もっとも、剣の方でも負ける気など更々ないがな」
スペルビアから吹き荒れた闘気が木々を打った。そうとしか思えない程の獰猛な気迫を真正面から叩きつけられて、ジョゼフは口内に溜まった生唾を飲み下す。
レリアの戦いが終わるまでの間にイザベラから伝え聞いたスペルビアの情報について、ジョゼフは思い出していた。
〝傲慢の〟スペルビア。それは淫魔の中でも異端の中の異端である。それは一目瞭然で、剣があるからだ。
淫魔は躯を資本とし、生物の精気を栄養素として消費する生態をもっている。よって、人間女性のソレとは違い、躯は人を堕落させるために最適化された肉体として成立しているのだ。
周囲の生物を魅了して自身の虜とすることで対象を自衛手段として使役できる淫魔にとって、自分自身の戦闘能力など些細なものである。よって、淫魔たちは基 本的に腕力に代表される物理的な力を求めない。むしろ、自衛するための手段に困るようでは淫魔として恥ずかしいという風潮すらあるのだ。
強い個人戦闘能力を持つ淫魔は、淫魔の中では即ち人を魅了できないおちこぼれとされ、迫害されるものなのである。地位すら得られず、仮に得たとしても淫魔本来の技量に劣るものがいつまでもその座にいられるわけがない。
だが。このスペルビアはそれらの論を覆す存在だ。
なにせ、剣の腕は中途半端なものではなく、一流。そのくせ、七つの大罪を関する地位に立って、しかも他の淫魔と協力関係を結んで国をひとつ落としたのである。軽蔑されていたとしても対等の関係で取引ができる、そんな規格外の淫魔なのだ。
よってそれは淫魔本来の淫技も、そして剣術も一級品である証左。なによりジョゼフは身をもってスペルビアの手管を体験している。冗談ではなく何度も殺され、蘇生され、を何度も繰り返させられるほどの快楽地獄であった。
ジョゼフは呼吸を整えて、精神を落ち着ける。呼吸は戦いにおいての基本であり、これが乱れれば剣筋も動きも相手に筒抜けになってしまう。当たり前に行っている活動が即生死を別つ要因となる、今立っている世界とはつまりそういうものだ。
「ぼくは負けるつもりなんてありません。だからまずは……この剣であなたを無力化する!」
「いいだろう。ではその気概に免じて、一太刀くれさせる権利をやろう。さあ、どこからでも好きに打ち込んでくるがいい」
スペルビアが腕を組んで傲岸不遜に言い放つと、ジョゼフは厳しい表情で剣を構えた。半身の体勢で剣を腰の高さまで降ろし、油断なく切っ先を相手に向ける。
腕組をした相手に反して、ジョゼフの構え方には一切の驕りや怒りはなかった。ふつうならスペルビアの言葉を侮辱と受け取って怒りそうなものだが、それは自身と相手が対等であると思っている者だからこその発想だ。
力の差は、圧倒的なまでに横たわっている。よってこれは勝機。ならば万全に生かさぬ道理はない。
一拍置く。
肩に剣を担ぎ、
ジョゼフは一気に間合いをつめた。
「は――っ」
迷いなく振り下ろされた一刀は孤を描きスペルビアの首もとへと振り下ろされる。
好機を伺う時間的猶予はジョゼフにはなく、さらに待つだけ時間の無駄と判断したが故の即断の踏み込み。
未だに剣を抜いてすらいなかったスペルビアには到底受けることの適わぬ斬撃。
けれども、それはスペルビアが人間であったらの話だった。
剣が振り切られ、ジョゼフの手に伝わる感触は――無。
空を切った剣にジョゼフは目を見開く。
視界からスペルビアが消失していた。
消えた? 否。ただ、視界から外れただけのこと。そして人の視聴角など、至近距離になればなるほどかいくぐるのは容易。
ならばこの短時間で音もなく跳べる場所は、左右どちらかしかあり得ない。
右か左か、どちらにスペルビアがいるか――。
――ジョゼフは迷わず右へと剣を振るった。
鉄と鉄がぶつかりあって衝撃がジョゼフの腕に走る。重い打撃を受け止めた余韻で腕が電気が流れたように痺れた。
ジョゼフの眼前でスペルビアが笑う。それは好敵手を前にした肉食獣を連想させた。
「ほう、受けたか。以前ならばこれで勝負は必定であったはずなのだがな」
「生き物は、無意識に心臓がある方を庇って左へと動いてしまうもの……右から攻めてくると思ってましたよ。いや、確信を持ったのは以前あなたが切り落としたのが右腕だったということですけどね」
「読まれていたか。そうさな、我はその右腕が気に喰わん。当然よな。なにせかつて斬って捨てたものが亡霊のように舞い戻ったのだ。冥土に送り返さねば気がすまない!」
お互いに相手の剣を押し合ってふたりは距離を取る。
既にスペルビアは剣を抜いた。アドバンテージはない。ここからは、一瞬の判断違いが死を意味する戦場だった。
「征くぞ、精々我を楽しませてみせよ。有象無象の者共との違いを見せねば……ここで屍となれ!」
歯をむき出しにして笑い、スペルビアは突風となってジョゼフに斬りかかった。
頭をかち割ろうと振り上げられた剣、胴を薙ごうと腰で溜められた剣、腕を切り落とそうと跳ね上がる剣。それら三つの予想される太刀筋が幻影のようにジョゼフの視界に重なった。
どの太刀がくるか。受け損なえば即ち敗北。
どれが――どれが正しいのか――。
刹那に見たぬ逡巡。だが、答えを見つけて愕然とした。
これら三刀は総て同時に繰り出される。
スペルビアは人間でなく、よってその練度は人の領域外にある文字通りの人外。
ならば、三者択一なわけがなく。それら総てを同時に成せる。
同時に襲いかかる三刀はどれもが必殺。
よって、この瞬間に人の敗北は定められたも同然だった。
*
「……ジョゼフは、勝てるかな」
イザベラとふたりきりになったせいか、静かな部屋の中でアンナマリアがぽつりと弱音を洩らした。
毛布に顔を埋めているアンナマリアを見て、イザベラは大きな胸を悩ましげに揺らしながら腕を組み、首を傾げる。
「心配かい、ギヨたん」
「だって、前に腕を切り落とされたとか聞いたから。腕は繋ぎ直せても、それで勝てるのかな……」
アンナマリアはジョゼフが剣を振るうところを見たことはなかった。パン生地をこねている姿ならいくらだって思い浮かべることはできても、剣を振るうところ は想像すらできない。そのせいで、ジョゼフの勝算がどれほどのものか、アンナマリアは予想することすら不可能だったのだ。
その心配事に、イザベラが笑った。
「なんだ、そんなことか。そうだね、ギヨたんがそう思い違いをしていたら、それは心配になるわけだ」
「なに、それ。わたしが知らないからって、そんな上から目線」
「いや、私もジョゼフが剣を使っているところなんて見たことはないよ。私がいっているのは別のところだ」
「別の、こと?」
「そうとも」
イザベラは悪戯の種を明かす子供みたいな調子で云った。
「――私が、同じ腕をつけ直すと思うかい?」
「……え?」
「だいたいジョゼフの腕は草花に紛れてどこにいったかわからなかったんだよ。きっと今頃は動物たちの餌になって骨しかないだろうね」
「え、ちょ、ちょっと待って。じゃあ、その……」
アンナマリアはから毛布を腋に投げ捨てて、呆然とイザベラの目を見た。
「今、ついてる、右腕って、なに?」
*
(――栄光の手《ハンド・オブ・グローリー》、起動)
ジョゼフの感覚の中で、右腕のそれが変質を開始した。
まるで、右腕の血流だけが加速させられたような不可思議な感触だった。腕の根本を力一杯紐で縛ればこうなるだろうか。ジョゼフの人体から右腕だけが完全に独立し別系統の生物として活動を始める感覚。
その間にも、一刀による三連の斬撃はジョゼフへと迫り――
「定義:内部加速三倍――!」
ジョゼフの右腕がかき消える。
瞬間、三度剣がぶつかりあう甲高い音が木々を突き刺した。
獲物を定めた猛禽がごとく、スペルビアの目つきが鋭くなる。睨まれただけで背筋が撫でられたような寒気を覚え、跪いてしまいたくなる痺れるような眼孔にジョゼフは危うくたじろぎそうになった。
しかし、スペルビアの口元に浮かぶのは歓喜。
「ほう、その腕、人の理……科学のものですらないな。今の太刀を受けた人間はお前が初めてだ!」
好敵手に巡り逢えたことを歓喜する遠吠え。だが、ジョゼフの内面はスペルビアの歓声に悲鳴で答えそうになっていた。
「ぐぎ……っ」
右腕の筋繊維と血管が何本か断裂した。その痛みが稲妻のように脳を突き上げて、眼球の中でいくつもの火花が散った。
栄光の手――ジョゼフの右腕としてつけられた切り札の名である。
それはイザベラが制作した魔術道具のひとつだ。栄光の手という輝かしい名前から考えられない方法で作られた逸品である。なにせ、材料は死蝋化した腕なのだ。
多くの文献に記された栄光の手の効力は家にいる者の活動を停止させるなり、外部の人物の行動を抑制するお守りであった。
けれど、イザベラの発想は飛び抜けていたのである。ジョゼフが身に着けた栄光の手は、外部ではなく内部、つまり腕そのものの活動に干渉した。しかも、外側ではなく内側に向けることで、効果範囲だけでなく効果そのものまで反転したのである。
即ち、時間を未来方向においてのみ加速させる、そんな化け物じみた代物となった。
欠点はある。まず、腕をこれにすげ替えねばならない。ふたつめに、反動による苦痛がどうしようもないということだ。
死蝋化した腕、人体に馴染んで人肌の体温をもったせいで痛覚までもが復活した。そのために、力を強い度合いで出せば出すほど代償として痛みを負うのだ。実際に血管や神経なんてひとつとして引きちぎれていないとしても。
「……っ、まだ、まっだぁっ!」
栄光の手による効果は、あくまで右腕のみ。それ以外は所詮人並み。腕の加速という切り札が相手に知られた以上、戦いが長引けばそれだけ不利。
よって痛みを振り切ってジョゼフは踏み込んだ。
「定義:内部加速二倍――!」
右腕が倍に加速した。下がっていた剣が瞬時に跳ね上がり顔を薙ぐというあり得ない挙動を実現する。
スペルビアは剣で受けなかった。躯をうしろへ逸らし、紙一重で剣をやり過ごす。掠めた剣で髪が吹雪きのように散った。
「手ぬるいぞ!」
一気呵成、スペルビアの剣が真っ向から落雷のように落とされた。
受け止めるには時間がない。
内部加速、と指令を出そうとして痛みに集中力が阻害された。駆動速度を落としても連続使用による幻痛は脳の腫瘍となって邪魔をする。
ジョゼフは踵で思い切り地面を蹴った。半ば体勢を崩しながら横へ跳ぶと、真横を剣が擦過して地面に激突する。
轟ッ! と地響きを立てて土が舞い上がった。本当に雷が落ちたと錯覚しそうになる力強さ。
受け止めていたら自分の剣ごと頭をかち割られていたかもしれない。その未来を想像して背筋が氷のように冷たくなった。
これ以上時間をかけてスペルビアのエンジンがさらに火を噴けば、栄光の手を持ってしても対抗は不可能となるだろう。
ジョゼフは奥歯をぐっと噛みしめる。歯が軋む嫌な音がした。
ならば、スペルビアが万全となる前、わずかに残った現状の光明を――逃さずに掴むしかない!
「定義:内部加速――三倍!」
剣を振り下ろして無防備になったスペルビアの躯を横から薙ぎ払う。剣の軌跡はジョゼフ自身の目にすら止まらぬ電光石火。
だが、それに反応してみせたスペルビアはまさしく悪夢と呼ぶにふさわしい能力の持ち主であった。
弾かれる剣。スローモーションとなって迎撃される剣の動きがジョゼフに見えた。
力押しでの太刀はその肌に触れることすら許されず、搦め手を駆使しても基本スペックの差で対応される。赤子の躯で大人を倒そうとする方が、まだマシなことのように思えるほどに、身体の差は歴然としていた。
――故に、ジョゼフはさらに無茶をした。
「定義:内部加速――四倍!」
腕が肩から引きちぎられたかとジョゼフは錯覚した。
それほどに腕が振るわれる速度は速く、
けれど、スペルビアはそれに反応していた。
絶望的な反射速度。
剣と剣の激突になるのは最早確定事項であり、
それこそがジョゼフの目的だった。
「定義:内部加速――五倍!」
剣が二段で変化した。だが、その変化はホントにわずかな動き。剣の中ほどで受け止められるはずだった剣を、相手の剣の先端部へ移動させただけだ。
しかし、これだけのことが目的であり勝機。
剣と剣の激突。
何かが宙を舞った。くるくると円を描きながら木漏れ日を反射する物体は、放物線の軌跡で地面に突き立つ。
「……なっ」
絶句したのは、スペルビアだった。
ジョゼフの一刀が、彼女の剣をはじき飛ばしたのである。
それこそがジョゼフの狙いだった。力量ではまず間違いなく及ばない。十回やれば十回負ける。百回やっても、やはり百回負ける。万に一つだった勝てる可能性はない。少なくとも、騎士としての競り合いではだ。
なら、相手を戦えない状態にするしかない。その末に思いついたのが相手の武器を手放させることだった。
膨大な加速度をつけられた鉄の塊が剣の先端にぶつかれば、それを予期していなかった場合なら手で保持していられなくなる。その結果を期待したがための最後の一刀だったのだ。
それでも、相手がまだ全力を出し切っていなかったからこそ出来た芸当である。少しでも当たり所が悪ければ、相手の手にはまだ剣が残っていたことだろう。間 隙の攻防を勝ち抜いてジョゼフが安堵すると、手から剣がこぼれ落ちて地面に突き刺さった。無茶をさせた右手にはもう力が入らず、それを掴むだけの握力は残 されていない。
よってここに武力による戦いは終止符が打たれた。
今のジョゼフはスペルビアなら素手でも殺せるだろうし、剣を拾えば尚のこと簡単に仕留めることができるだろうが、騎士としての誇りが許さないに違いない。よほどこの場でジョゼフを暴力で殺したいというなら話は別だろうが――。
スペルビアは楽しげにしているだけだった。
「すばらしい、よくぞ我の手から剣をはじき飛ばした! これ以上食い下がるのも無粋の極みというもの。我の負けを認めよう。それに、合格だ。我が搾りとって果てさせるに相応しい。殺すならそちらの方でなくては楽しみ甲斐も薄れるものだ」
そう、スペルビアとの戦いは二段構え。それが彼女の強敵たる理由であり、淫魔の中でも別格として誰も触れようとしない原因である。
ジョゼフは感覚が喪失した右手を抑え、額から汗を流した。
「ちょ、ちょっと、休憩を……」
「安心せい。お前のしてほしいことは我がやってやる、存分に求めるがいい。それに、苦痛など感じなくなるほどの快楽を与えてやるからな……麻酔のような、快感を」
スペルビアはその場に膝を突くと、有無を云わさずジョゼフの股間に顔を寄せた。
剣を打ち払われたことによる痛みはスペルビアには残っていないのか、あっという間に慣れた手つきでジョゼフの下半身をむき出しにする。
「口ではどういおうと、やはり男はこうなるものだな……もうガチガチではないか」
「うっ……」
純白の手袋をはめたスペルビアの指先が、勃起した一物に絡みつく。粘膜に伝わるさらさらとした布の感触にジョゼフは切ない声を洩らした。
手袋越しでもわかるほど、スペルビアの指は剣を扱うものとは思えないほど美しいものだった。触感こそ普通の女性より硬さがあるものの、たこや傷のようなものは感じられない。楽器でも扱うような繊細な動作で竿をさすっている。
すりすりと軽く撫でられて、肉棒の硬度は簡単に頂点まで達してしまった。それを見て、スペルビアは口元を持ち上げてからかうように眼を細めた。
「どうした、まだ触れただけだぞ。この様子では、また無様に我の中で果て続けることになるのではないか?」
「こ、今回は大丈夫ですっ」
「そうか? ならば、試してやろう……まずは、我の口でな」
妖艶に微笑んだスペルビアは唇を舌で舐めると、唾液の糸を引く口を開いて――一息に肉棒を呑み込んだ。
「うわ……っ」
ペニスが生暖かい口の中に包み込まれて、思わず腰を引いて声を洩らした。
「ふふ……っ、どうした、まだ……んっ、口に含んだだけだぞ? 唾液で濡れただけなのに、そんな気持ち良いか?」
舌がぬるりと雁首に絡みつく。もしこれが以前のジョゼフだったなら、既に射精していたことだろう。アンナマリアやレリアたち、高位淫魔たちに弄ばれた経験がなければ、もうこの時点で勝負は決していた。
けれど、このままで耐えきれるとは……。
手を握りしめて必死に射精感を堪え、尿道に舌を差し込まれてかき乱される脳内で勝機を探っていると、ジョゼフははたと気がついた。
「……あっ」
「くく、どうした? 今頃気付いたか?」
ペニスの根本を握りながら顔を上げたスペルビアの顔はにしてやったりというものだ。
当たり前のことにジョゼフはようやく気がついた。
スペルビアの口淫にいくら耐えたところで彼女にはなんら快楽は与えられない。このままではやがて射精してしまい為す術なくスペルビアに搾精されるだけなのだ。
「し、しま……っ」
「慣れないことはするものではないよなあ。さて、まずは一発出してもらおうか」
じゅっ、じゅっ、と喉の奥まで亀頭を誘いこむと、スペルビアの柔肉でパンパンに膨れあがったペニスが圧迫された。
――ダメだ、我慢、我慢しないと……っ!
「ほらほら、我慢は躯の毒だぞ? 口が物足りないなら、そうだな、胸でしてやろう」
スペルビアは胸を覆っていた革の鎧を外すと服の下から胸を溢れさせて、唾液に濡れたジョゼフのペニスへ押しつけた。
剣術をおこなっているために引き締まった肉体についた乳房は控え目なものだったが、逆にその小ささがアンバランスな卑猥さを醸し出していた。高潔な女性騎 士の柔らかい胸に亀頭を押しつけられた背徳的な光景と伝わってくる快感の暴力に、ジョゼフはがんばりもむなしく屈してしまった。
「……っ、う、うわあああっ」
どくっ、どくどく……。
そうして、ジョゼフはスペルビアになんら快感を与えることもできず無様に射精してしまった。
「う、うわ……っ、で、て……っ」
腰が引けてくずおれそうになるのを、スペルビアの手が背中に回され支えられた。
「なにも出来ずに出してしまったなあ? それで、こんなに敏感になってしまって……もうなにも出来ないのではないか? 我の中にいれたらそれだけで射精してしまいそうだな」
唇を濡らす精液を舐めとるスペルビアの仕草に、ジョゼフは愕然とした。麻薬のような快楽で脳内を犯されて朦朧となった思考でも、取り返しのつかないことになったのは重々承知できていた。。
男が淫魔に性技で勝つというのはほとんど不可能だと云われていた。挿入した時点で男は圧倒的に不利であるのに、挿入前に射精をさせられて敏感になったペニスでは淫魔の中では一秒とて耐えられない。
つまり、こちらは真実、万に一つの勝目もなくなってしまったのだ。
「さて、もう戦いだなんて気にしないで、あとはたっぷりと我の中を味わって貰おうか」
とんと胸を押されてジョゼフは尻餅をついた。抵抗しようと思ったときには既にスペルビアが馬乗りになって抑え付けている。
「逃がすと思うか?」
「ちょ、待……っ」
スペルビアはジョゼフに顔を寄せて、頬に熱い息を吐きかけた。
「却下だ」
人差し指と中指の間で挟み込まれたペニスをヴァギナに宛がい、スペルビアは腰を落とした。
ずぷっ、とペニスが呑み込まれると、そこは以前体験したあの快楽の坩堝そのままだった。
「あっ、また、で……ううう!?」
肉棒に伝わる甘く暴力的な快感に目の前が真っ白になって、ペニスは爆発した。
淫魔の躯に慣れていたはずなのに、一度射精して敏感になったペニスは一瞬たりとも耐えることができずに精を放出することとなった。
「あ、く、ぁ……」
躯から力が抜けて、ジョゼフは地面の上で無防備に脱力した。その間にも膣肉が手を擦りあわせるように蠕動を繰り返し、ペニスは脈打って精をスペルビアの中に放出し続けていた。
「ははっ、腰を動かしてもいないのだがな……いいぞ、そのまま出し続けろ。安心しろ、死んでも蘇生してやるし……いや、そうだな。夢心地のまま逝かせてやった方がいいかな。痛みは感じさせないでやろう」
腰を挑発的にスペルビアが振ると、そのたびに捩れた膣でペニスを何度も丹念にしごきあげられて精液を搾りとられていく。
「う、うぅううう……」
自分から腰を振ることもできず、したとしても自分の射精を助長することにしかならない。快感で真白く染め上げられる頭と未熟な経験の中では、スペルビアという高位淫魔を打倒する手段は見あたらない。
「ふふ……今、どんな気分だ? 云ってみろ……それとも、もう口もきけぬかな?」
スペルビアが腰を振りながら、指先でジョゼフの腕を撫でた。鋭敏になった感覚のせいで、腕がもうひとつの陰茎にでもなったような感覚で嬌声をあげてしまう。
「どうした、ここを撫でられただけでそんなに感じたか?」
腕に触れられただけで震えていることを手に取るように悟られて、イっているだけでなく恥ずかしさで躯が熱くなり――
――腕?
ジョゼフの脳裏で稲妻のように思考が弾けた。
腕、右腕、操作……。
栄光の手の能力は腕の時間を加速させるものだった。しかし、本来なら外部の時間を操作する魔術道具なのである。ならば、その本来の能力が失われているはずはない。
それに、時間を操作できるなら、もっと対象を限定した変化もできるはず――。
薄れる意識の中で辛うじて掴んだ思い付きだったが、ジョゼフはその賭けにでる覚悟を込めた。
右腕の触感が戻っているのはスペルビアに撫でられて快感を受けられたことで判っている。それでも終わらない射精で巧く動かせない腕を持ち上げて、スペルビアの胸に触れた。
「ふふ、そんなに胸が……我のおっぱいが触りたかったのか。甘えん坊だな」
手に伝わる弾力ある感触と耳に吹きかけられる甘い囁きに脳を蕩けさせられながら、ジョゼフはきわどいところで目的を実行する。
(……定義:外部加速三倍――)
そして、スペルビアの乳輪を指でなぞった。
「……ひぃう!?」
霰もない声をあげて、びくりとスペルビアの躯が跳ねた。とっさに何が起こったのか判らずにスペルビアは目を何度も瞬いている。
(もう一度――今度は、五倍――)
下からスペルビアの乳房を持ち上げて、控え目に握った。
「なぁ!? なっ、なんだ……これは!?」
躯に走り抜ける今まで感じたこともない快感に、スペルビアは嬌声とも悲鳴ともつかぬ声を洩らした。顔を赤らめ、熱くなった肌からは汗が流れ出た。
ジョゼフがしたことは、スペルビアの感度を加速――というよりも増幅させたのである。
この栄光の手は正確には時を操っているのではなく、指定した倍数分の速度を実現させられる程度まで力を増幅するものなのだ。人の睡眠欲求を増幅させて眠ら せたり、そしてこの場合なら相手の躯の感度を上げて指定した倍数分まで快感を増幅するという、それがジョゼフの思いついた応用方法であった。。
「これなら……いける!」
右腕の骨が軋む感覚、それでも腕の速度を加速させていたときと比べればまだまだ軽い。内部加速のときは腕そのものが無茶な動きを要求されたため、物理的な負荷も押しかかっていたのだ。現状の外部加速ならば腕にかかる負担もずっと軽減されていた。
普通に胸を撫でられるものよりも五倍もの快楽を唐突に与えられれば、さしものスペルビアも動揺を隠せなかった。
「くっ、お前、いったいなにをしている!?」
だが、身構えられたらそこは高位淫魔、簡単に対処されてしまう。
あとは短期決戦あるのみ――。
一物をがっしりと銜え込んだスペルビアの性器へと右手を滑り落として、陰核に親指を押しつけた。
「そうか、その右手で!」
完全に気付かれた。つまりこれが最後の一回――
(外部加速……)
軽くなったと云っても右腕の消費がなくなるわけではない。けれど、これが最後の好機というのなら、後先帰り見ずに全力を注ぎ込むのみ。
「……一〇〇倍!」
ぐっと陰核を親指で押し込んだ瞬間、ジョゼフに跨っていたスペルビアの躯が仰け反った。
「ひうっ!? な、こ、これは……これは……こ、この我がイ、イクな……ど……っ、ば、馬鹿な……ぁ、あああああっ!」
陰核から伝わる膨大な刺激がスペルビアを貫いて、膣は愛液を迸らせながらペニスを更に強く締め上げる。
「うあ、き、つ……っ、あああっ」
さらに強められたマシュマロのような膣の圧力に、ジョゼフもまた何倍も強い快感の波を受けて精巣に残った精液の滓までも噴き出させた。
思わず左手でスペルビアの腰を掴んでの射精。体内に流し込まれる精液を、放心していたスペルビアは今までの清廉さとも淫蕩さとも違う緩んだ表情で飲み干していた。
「はは……我がイって、こんなに、出されるとは、な……はは……」
精液を吐き出しきって身動き一つとれなくなったジョゼフの上で、スペルビアは満足そうに自身の下腹部を撫でた。
「なんだ、我よりもお前の方が余力がないではないか。これではあと腰を一捻りしてしまえば正真正銘、お前は果ててしまう他ないようだな」
「そ、そんな……これじゃ、足りなかったなんて……」
増幅された快感で達したスペルビアであったが、それでも精液を出し切ったジョゼフと比べれば余裕は残っていた。例え普段では考えられないほどの刺激でイかされたとしても、高位淫魔をそれだけで屈せさせることはできなかったのだ。
「さあ、お命頂戴といかせてもらおうか」
「う……っ」
ジョゼフは目を閉じて死を覚悟した。
しかし、
「なんて、冗談だ。この勝負、我の負けよ」
そういってスペルビアはジョゼフのペニスを引き抜いてふらふらと立ち上がった。
「淫魔が人間にイかされるなど恥以外のなにものでもない。それにくわえて剣でも一本とられたとあっては、ここで引くのが潔いというものだ」
きっぱりと云いきって、スペルビアは地面に置いていた革の鎧を拾い挙げる。胸にべったりとついた白濁液を手袋で拭うと、上から鎧を装着した。
スペルビアの着替え姿を見守って、ジョゼフはなんとも云えない感慨に襲われて口ごもる。
「団長……その、なんといったらいいか」
「なにも云わずともよい。我は我の中で定めた勝敗条件と照らし合わせた上で負けたと判断したのだ。これ以上やっても我が虚しくなるだけで何も満足感は得られん。それともなにか、お前は我にトドメを刺されることが望みか?」
「い、いえ、滅相もない」
スペルビアに見下ろされ、ジョゼフは残された力を振り絞り頭を振った。
その慌てぶりに苦笑し、スペルビアはジョゼフに背を向ける。
「……どこへ?」
「淫魔らしく、自堕落に国を放浪するさ。ではな弟子よ。我たちの躯にのめり込みすぎるなよ」
スペルビアの姿が唐突にかき消えた。気配が完全になくなったのを感じて、ジョゼフは深い溜息をついた。
「今まで……どうもお世話になりました」
誰も聞いていないのはわかっていつつも最後に呟き、自分の役目を果たせた安心感で意識を深緑の中に預けた。
Second battle.
ジョゼフ VS. スペルビア
Winner ジョゼフ
To be continued Last battle...
――これは夢であるが、夢ではない。
アンナマリアは指先すら動かなくなった自分の躯に力をいれようと悪銭苦闘して、その末にそんな結論を出した。
ジョゼフが戦いに赴いたあとで、アンナマリアは気付いたら眠ってしまっていた、のだろう。と本人は思っている。
気付いたときには、既にアンナマリアはイザベラの家とは違う場所に横たわっていた。
しかし、見覚えがないというわけではない。来たことはなかったが、この内装は〝知っているはず〟なのだ。
まず状況を整理しよう、とアンナマリアは辛うじて動く視野を巡らして辺りを見た。ここはどこか、と考え、建物の中にある一室のようであると判断をつける。 それも、とても大きな建物だ。しかし、部屋の中に豪奢な飾りつけはなく、壁は石が剥き出しのままで壁紙すらない。床も申し訳程度の布きれみたいな敷物があ るだけだ。強固な造りをしているこの建物と比べると、どうにもアンバランスな状態である。これだけの建物に住まえる者が生活する空間とは思えない。
アンナマリアは混乱していた。
どうして自分はここを懐かしく感じるのか。こんな場所には人になってからというもの来たことはない。自分の足で歩けない状態で広場から動けるはずもなく、よってこんな場所を懐かしく感じることなどないはずなのだ。
ここがどこなのか、どうしてこうなっているのか。声も出せず、息も吐けないアンナマリアは静かに混乱していると、扉の開く音がした。けれど仰向けになって寝ている状態のアンナマリアは誰が入ってきたのか確認することはできなかった。
「どうだい、ギヨタン。状態は」
渋みのある男性の声に異議を唱えたが、それは言葉にはならない。そして、すぐにアンナマリアは呼びかけが自分に向けられたものではないことに気がついた。
「ほとんど終わり、といったところかな」
どこからか別の男性が答えていた。アンナマリアが気付かなかっただけで、最初からこの部屋にいたのだろう。声の雰囲気から、先程入ってきた男性より年をとっているようだった。
「ただね、どうにも首を切り取る機構が巧くいかないんだ。刃に細工を施せば良いのだろうが……貴方の意見を聞かせてもらえるかね?」
「そうだな、刃を研ぐのも楽じゃないし……刃の角度を工夫するといい。あとは、重量を増そう。そうすれば、骨に引っかかるなんてことはないはずだ」
「なるほど、では〝この娘〟はそういう風に改良しよう」
アンナマリアの目の前にふたりの男の顔が現れた。白髪の、身なりの良い男である。アンナマリアが搾り殺してきた男たちと違い、育ちが良く、そして聡明なのだろうというのが顔にまで現れていた。
ふたりはじっとアンナマリアを覗き込んでいて、それにびっくりして飛び上がろうとするものの、相変わらず躯はぴくりとも動かなかった。
いきなりわけのわからぬ状況で目が覚め、男に囲まれていることに慌てたが、アンナマリアはふたりの目に悪意が見られないことに気付いた。人としての経験が 短いだけに他人の感情については聡くはないが、断頭台という性質状、常に晒され続けた悪意にだけは敏感なのだ。彼らはアンナマリアに危害を加えようなどと は毛ほども考えていないのである。
どういうことなのだろうとアンナマリアは益々混乱していると、目尻や口元に皺がある男性――年老いて見える方が最初から部屋にいた者だろう――がアンナマリアの躯に触れた。
驚きに身を竦める。が、アンナマリアは一向に自分の肌に何かが触れる感触が訪れないことに気づく。
「できれば、この娘が今の惨たらしい処刑の有様を変えてくれることを願うばかりだよ」
男の目には、深い悲しみの色があった。揺れる瞳には、アンナマリアの鋼色をした躯が映し出されていた。
そう、男はアンナマリアの刃の部分に触れているのだ。
――躯が、人じゃなくなってる!?
躯を断頭台に戻した覚えは、アンナマリアにはなかった。なのに、どうしたことか姿は広場にて罪人を狩る時の姿になっている。
しかも、アンナマリアはもうひとつおかしなことに気付いていた。
躯がバラバラに分解されているのだ。
刃も、台も、柱も、繋がっていない。まるで、組み上がっていないパズルのようである。
さらにいえば、パーツもアンナマリアの知っている形とは微妙に異なっている。
それで、アンナマリアもここがどこで、なんなのかが判った。
――ここは、わたしの昔の記憶だ。
以前、処刑人がでてきたような夢ではない。あれとは違い、これは実際にあったことなのである。眠った拍子に表層では覚えてもいない記憶の中に迷い込んでしまったのだ。
だから、このふたりが誰なのかも判った。アンナマリアの制作者である。つまり、父親だ。
アンナマリアは呆然となった。ふたりの父親のことは覚えていたが、ここまで鮮明に顔を思い出したことはなかった。
その様子は勿論誰にも伝わらず、部屋に入ってきた方の男は老人の言葉に答えていた。
「処刑の現場は変わる。無駄に罪人を苦しめることもなくなり、手段は軽快になり、そしてトラブルに民衆を巻き込む不手際も起こらない。より効率的に、機械的に、被害を抑えて処刑をおこなえる。……ただ、その役目をこの娘に与えるのは、酷な話だろうな」
「ええ、これがただの器物であればなんの問題もなかったことでしょう。けれども、もうひとつの目的を果たすためにはどうしても、細工は必要だった。王が気に病むことではありません」
――王!?
そう呼ばれたことにアンナマリアは心底驚き、男の顔はここではないどこかで見た記憶もあった。
アンナマリアは、この男を殺したことがある。国で革命をおこした者たちによってつれてこられて、広場でアンナマリアを使って処刑されたのだ。あのときはどうしてか、精気を搾り取られたかのような頼りない有様だっただけに、今の今まで気付かなかった。
「すまないな、気を使わせて。せっかく協力者の力のお陰でこの娘を作り出せたのだ。……あとは、神に委ねよう」
これは自分が生まれ落ちる前の記憶、そう悟ったときには、既にアンナマリアの意識はなくなりつつあった。誰かが呼ぶ声がしている。そんな中、王は最後になにか口を開こうとしていた。呼び声を無視して、アンナマリアはその一言に耳を傾ける。
「この子が淫魔を、打倒してくれることを……」
*
「――ギヨたん、ギヨたん、起きなさい、ギヨたん」
「ギヨたんいうなっ」
条件反射で叫びながらアンナマリアはがばっ、と跳ね起きた。
声が自らの鼓膜に届いたことに驚いて、アンナマリアは思わず自分の喉に触れた。
「あ、云えた」
「起きて早々になにをわけのわからないことを云ってるんだい?」
「……いや、普段のあなたほどじゃないから」
目の前にいた、かわいそうな子を見る目をしたイザベラに言い返すと、アンナマリアは自分の両手に目を落とす。そこには傷一つない、小さい真っ白な手がある。先程の記憶に見た無骨な刃からは想像もつかない綺麗な手だ。
軽く、手を握りしめる。指の動く感覚があった。無事に五感が戻ってきたことにアンナマリアは肩から力を抜いて安堵した。いや、元は断頭台であったのだから 人の姿に戻ったと形容するのはおかしな話のはずだ。それなのに、人の姿を望んでいる。自由に動き回れるというのは、それほどまでに度し難い。
うつむきがちになって手を見つめるアンナマリアに、イザベラは首を傾げた。
「いったいどうしたんだい? 寝てたかと思えば、いきなり黙り込んでしまうなんて。悪夢にでも魘されたかい?」
「……違う。ただ、ちょっと、昔のことを思い出していただけ」
一瞬だけ話してしまうか迷ったものの、アンナマリアは気になる言葉を思い出してしまい、誤魔化すことにした。
――淫魔を打倒する? 処刑道具の私が?
王の最後の言葉は、実際にこの耳朶を振るわせたかのように生々しくこびり付いていた。おそらく、妄想ではなく、実際に王はそういったのだろう。
しかし、何故そんなことをいったのか。アンナマリアはあくまで咎人を断罪するための処刑台である。できるだけ苦痛を与えず人道的に殺害する手段として造ら れたのだから、異端審問の道具でもなければ、ましてや淫魔を殺すための道具であるわけでもない。あまりにも、アンナマリアの存在からはかけ離れていた。
ずっと脳内で主張し出すものを振り払って、アンナマリアはもっと大事なことをイザベラに訪ねる。
「それで、ジョゼフはどうなったの?」
「勝ったよ。というよりも、見逃してもらえたと云った方が正しいかな。なにはともあれ、ジョゼフは五体満足で気絶中さ」
「そう……じゃあ、わたしが最後に勝てば、なにもかも解決なんだ」
「ああ、そうだね。相手は今回の国家転覆をおこなった首謀者、その彼女を撃破できれば少なくとも私たちの安全は確保できるだろう。因縁の対決をもって、無事解決できるというものだ」
「前から気になってたけど、その因縁の対決ってなんの話?」
「ああ、それはね。アワリティアは、キミを造った男のひとり――この国の王を屈服させ、キミ自身に殺害させた張本人だからさ」
さっきの夢の中で感じたものは間違いではなかった。あの王と呼ばれた男は、アンナマリア自身が殺した相手なのである。
「でも、わたしは父親のことなんて、ほとんど覚えてない。だから、復讐心みたいなものも、あんまりないんだけど」
「それはそうだろうね。でも、中々に運命的だろう?」
「どちらかというと、悪趣味だけど……まあいい」
アンナマリアは寝転がっていたソファから立ち上がって、服の裾を叩いて直した。
「早く跳ばして。仇打ちとか、そういうのはどうでもいいけど……ついでに、私を悪趣味なことに付き合わせてくれた報いも受けて貰ってくる」
「それでこそ、ギヨたんだ。ではでは幼き姫君、ご案内致しましょう。美しく踊って咲き乱れてきてくるといい」
イザベラはわざと大仰に語ると、手をアンナマリアに差し出した。その手をじとっ、と睨み付けて、アンナマリアは乱暴に手を取る。
そして、アンナマリアは視界が書き換わっていくのを感じた――。
*
どこに跳ばされても、アンナマリアは驚かない覚悟をしていた。
跳んだ先が兵士たちに取り囲まれていようと、地獄のような場所であろうとだ。人ならざるものを相手にしようというのだから、その程度に一々驚いているようでは打倒など到底無理な話である。
そう、気を引き締めていたはずなのだが。
アンナマリアは自分の立っている所を見渡して、呆然とした。見るのも来るのもはじめてな場所だったが、知識だけはあった。そう、ここは――
周囲に気を取られて、アンナマリアの足下はおろそかになっていた。躯を捻ろうとして、足が水に取られて滑りそうになる。
珍しくあられもない声をあげてアンナマリアはその場に踏みとどまって、ほっと一息ついた。
「あら、断頭台はかわいらしい声をあげるものなのですね。はじめて知りました」
背後からかかった声に、アンナマリアはあからさまに眉を顰めた。
「……貴女みたいな品のない人に殺されるなんて、この国の王様も不憫ね」
今度は足下に気を払いながらアンナマリアは振り返った。その先には、素肌の上にベールのような薄布だけを纏って、腕を組み艶然と笑う淫魔アワリティアの姿 がある。しっとりと濡れた長髪を肌に張り付かせ、すっと細められた冷気を孕む視線は、男なら見つめられただけで心を奪われることは間違いない色香があっ た。
「品がないとは失礼な物言いですね。貴女よりもずっと恵まれた生活をしていますよ。ほら、貴女、お風呂なんてご存じでないでしょう?」
アワリティアは緩く片腕を動かして周囲にアンナマリアの注意を向けさせた。
そう、ここは王城の一角にある大浴場の中だった。高価そうなマーブル模様を浮かべた石の床には水溜まりができていて、アンナマリアが足を取られたのもそれのせいである。
アワリティアの手がさした先には人が何十人と一緒に入れそうなほどに広大な浴槽があり、花の蜜に似た香料が湯の熱気に混じってねっとりとアンナマリアの肌に絡みついた。全身を舐められているような暖かさに、じんわりと額が汗を浮き上がらせる。
「こ の浴槽は私の希望で人間に作らせたものです。湯浴みの文化すら俗説を恐れているがために抑圧していたなんて、私たちと比べて劣っているとしか言い様があり ませんね。もっとも、貴女のお父様は王城に浴場設備自体は導入していましたから、その点だけは評価してあげなければいけません。ご褒美にたっぷり天国を見 せてさしあげましたよ」
「……長々と語って、云いたいことはそれだけ?」
アンナマリアは自覚していなかったが、相当に不機嫌なのは声からして明かだった。押し殺された声は獲物を狙う猛獣の唸り声で、目は殺害対象を見据えるもので刀身のように寒々しい。
小気味良い音を関節から立てて、アンナマリアは右手をかぎ爪の形に曲げる。
正直なところ、彼女には相手の得意分野で戦ってやろうなどという殊勝な心がけは微塵もなかった。
レリアは同じ淫魔であるから戦いの方法が同じで、ジョゼフに至ってはそうする以外に手段がないからやむなく性技による戦いを選んだにすぎない。
だが、アンナマリアは違う。
彼女は断頭台。元より人間を、人間の形をしたものを殺害するために産み落とされた処刑機具だ。武闘派であるスペルビア相手には見切られる可能性もあったが、ただの淫魔なら易々と斬首できる力は身に秘めている。
相手が身構えたのを見て、しかしアワリティアは薄く笑った。
「もしかして、監獄で見せた不思議な技でも使うおつもりですか?」
アンナマリアは答えなかったが、沈黙が肯定となっていた。
前回、監獄で放った不可視の一閃。それをアンナマリアは以前も自分の意識下で制御し、撃ったことがある。レリアとの初対面時だ。
あの現象自体は、アンナマリアにとっては別段難しいことではなかった。むしろイザベラの扱う魔法の方がよほど特異なものであるとさえ思っていた。自分のはただ、まっすぐに相手を切り裂くだけのことなのだ。断頭台として当たり前の〝機構〟である。・
だが、その切り裂く方法自体が問題だった。
原理はアンナマリア自身も理解が及んでいない。ただし、イザベラは判っていたようだ。息を整えて、ゆっくりと脳内でこの〝機構〟について思い出す。
不可視の刃――それは鎌鼬などという生やさしい代物ではない。
アンナマリアのそれは謂わば存在を断つ即死の刃だ。対象に刃が当たれば、それが建物であろうがなんであろうが、その強度に関係なく対象は断裂する。しかし、無機物を斬るのが断頭台の真の機能ではない。よって、強度を無視して無機物を斬るには相当な集中力が要求される。
真の機能、目的とは即ち斬首。アンナマリアは人間という存在を断ち切る刃なのだ。
アンナマリアは断頭台のときにおいて、一度も人を仕損じたことはない。一刀一殺。必ず殺している。人の血と呪詛に塗れた断頭台の刃は、これによって魔術的効果を付与された。あらゆる人を殺せる。相手は人である。相手は死ぬ。という三段論法の呪いが。
人の形をした存在にとって、アンナマリアは天敵だった。当たれば、即死。そんな攻撃手段を持っているものが、人にとっての天敵でなくてなんになろう。
アワリティアとてこの攻撃の例外ではない。アンナマリアが腕を振り、斬撃を放ち、当たれば――かすっただけで躯は両断される。
音速で迫るであろう刃を避けることは淫魔といえど肉体を鍛えていなければ到底無理な話。アンナマリアの目の前に出てきただけでアワリティアの進退は窮まっていた。はずだ。
なのに、未だにその顔には余裕があった。
「確 かに、それは脅威です。私も当たれば死んでしまうでしょうね。けど、そんなもので決着をつけるのはいささか無粋ではないでしょうか。やはり仇討ちをするな ら、同じ手段でありませんと雰囲気がありませんよ。そう、貴女のお父様と私がしたように、躯を重ね合わせての戦いでなければ」
「うるさい。――死んじゃえ」
有無を云わせなかった。アンナマリアは間髪入れずに右手を振るっていた。
瞬間、刃が疾駆した。
アンナマリアの正体が見えない刃として顕現したのだ。
風切る音速の斬撃が手から伸びる。それはあまりに理不尽な力の象徴。吸い込まれるようにアワリティアの首に滑り込んだ。
アワリティアの背後の壁に鋭い亀裂が走った。アンナマリアの刃が、破城鎚の直撃にも耐えうる城内の壁をバターのように切り裂いたのである。
無論、壁との合間に立っていたアワリティアが無事なわけもなかった。
アワリティアがその場に立っていたとしたら、だが。
「い、ない!?」
アンナマリアは驚きに目を見開いた。確かに腕を振るう一瞬前までは視線の先にいたはずのアワリティアが忽然とかき消えていたのだ。
そこで混乱に思考停止を起こしてしまうのも無理からぬことだった。アンナマリアは処刑をしたことは数え切れないほどにあったが、人と決闘は愚か喧嘩すらしたことがなかったのである。
だから、自分の真横からの呼びかけには呼吸が止まった。
「こっちですよ、断頭台さん」
咄嗟に振り返ろうとしたところに足を払われて、アンナマリアは水に滑って床に背中を打ち付けた。
アンナマリアの眼前には、得意気な様子になったアワリティアがいた。その背中には一対の翼が風もないのにゆらゆらと揺れており、思わず羽根すら生き物と錯覚しそうになった。
「いったい、いつの間に……」
「淫魔の速度を甘く見ましたね? まあ、ふつうの淫魔なら貴女の下手な攻撃も当たっていたでしょうが、相手を見誤ったのが敗因ですね。翼さえ出せれば、貴女が右腕を振り下ろすよりも早く身を動かせるのですよ」
「くっ……!」
もう一度右腕を振ろうと振り上げるが、その手をアワリティアに掴まれて押しとどめられた。
「無駄ですよ。ただの道具が自分の躯を使いこなせるわけがないでしょう?」
「うるさい、離して……!」
「やれやれ、聞き分けのない子ですね。それでは、素直にさせてあげましょう」
アワリティアはぺろりと自分の唇を舐めると、アンナマリアのそれを奪った。
「んんっ」
小さな躯を強ばらせて侵入してくる舌を拒む。
それにアワリティアは唇を唇でついばんだ。ジンジンと口元の熱くなる甘い快楽に、アンナマリアはつい口を開いてしまった。
そこにぬるりとアワリティアの舌が滑り込む。そこからはもう舌技の虜だった。
口内で舌が動く度にアンナマリアの小さな躯が床の上でぴくぴくと震える。必死に抵抗しようとしていた腕にはいつしか力が入らなくなり、されるがままにアワリティアのキスに酔ってしまっていた。
相手の顔が離れる。アンナマリアの目には涙がたまっていて、頬を紅潮させながらまだキスの余韻に呆然としていた。
「普段は男性を銜えて喘がせてあげるための舌技なのですが……どうやら、相当気持ちよかったようですね。口の中をペニスと同じように舐められて感じてしまうなんて、恥ずかしくないんですか?」
「う、うるさ……い」
口では抵抗するものの、アンナマリアは躯に根を張った快感に躯を振るわせ続ける。無防備なところへ受けるには、あんまりにも情熱的な口づけだった。
精一杯の抵抗にアンナマリアは肩を突き飛ばそうとするが、それはひらりと躱されてしまう。指先が髪の毛一本にすらかすることもなかった。
「あらあら、反抗的な子ですね。これは、教育が必要なようです……。ああ、なら、やはりこういうときは年長者さんたちが導いて差し上げなくてはなりませんよね」
突然、アワリティアが誰かに語りかけているように声を張り上げた。ようやく快感の酔いから覚め始めたアンナマリアが不思議に思うと、すぐに相手の真意を目の当たりにすることとなった。
「さあ、お姉さん、お兄さん、入ってきなさい。この子を丹念に洗ってあげるのです」
すると、浴場の扉が開かれた。
「はい、お母様」
ぞろぞろと浴場に入ってきたのは、十代の子供たちだった。比率としては少女の方が多く、たまに少年が混じっている。彼らはひとりとして衣服を身に着けてお らず、人種も様々であった。差こそあれど、だいたいはこの国の人々と同じく肌の白い者たちだったが、何人か浅黒い肌の子供も混ざっている。
その無作為に集められたような統一感のない子供たちは、しかし動きだけは群体のように統一されていた。
子供たちが近づいてくることに驚いてアンナマリアは慌てて躯を起こすが、あっという間に集まってきた子供たちのひとりに背中から抱きしめられてしまう。
「な、なに……この子たち……」
アンナマリアを背中から抱きしめている少女が妹を叱るように耳元で囁いた。
「こら、年上の人にそんな口の利き方をしちゃ駄目でしょう?」
そういって服の上から胸を撫でられると、アンナマリアは熱い吐息を洩らす。キスによって敏感になった肌は、例え服の上から触れられただけでも性器を愛撫されたように感じてしまった。
その反応にアワリティアはくすりと笑い、アンナマリアを取り囲んだ子供たちに命じる。
「彼女はお風呂も入った経験がないようです。貴方たちの手で躯の隅々まで洗ってあげなさい。新しい姉妹になるかもしれない子ですから」
「はい、お母様」
子供たちは一斉に答えると、その細腕を伸ばしてテキパキとアンナマリアのドレスを脱がしていく。
「や、やだ、ちょっとっ」
躯を捻ってなんとか抵抗しようとするが、元は断頭台といえど見た目相応の力しかないアンナマリアでは数の力には抗いがたく、瞬く間にドレスを脱がされ一糸まとわぬ姿にされてしまった。
何人もの男に跨り、精を搾ってきたアンナマリアだったが、子供たちの純真な視線に晒されて生まれはじめて羞恥心を覚えた。太腿を擦り合わせて毛も生えていない秘所を隠そうとするが、褐色の少女の手によって容易くこじ開けられる。
「なにを恥ずかしがっているの? 隠してたら洗えないよ。それに、これから兄弟になるんだから恥ずかしがることなんてないんだから」
「きょ、兄弟? いったい、なんの……」
それには、また別の少女が答えた。
「お母様に見いだされて、行儀の良い子供になるの。そうして将来、男の人や女の人を喜ばせるお仕事をさせてもらえるのよ」
「そ、そんなの……いやっ」
「こらこら、暴れちゃ駄目だよ」
子供たちに両手足を抱きしめられて、アンナマリアは首をいやいやと振ることしかできなかった。背中にいた少女はアンナマリアの長髪に首を埋めて、周りの子たちに合図をする。
「それじゃあ、みんな、この子を綺麗にしてあげようね」
「はーいっ」
子供たちは行儀良く返事をして、躯を濡らして石鹸を泡立てはじめる。手で泡立て、自分たちの躯にも泡を塗り込むと、次々にアンナマリアの躯へと自分を擦りつけはじめる。
精液とは違うぬるぬるとしたものがすり込まれて、アンナマリアはくすぐったさに声を上げた。
「や、やめ……っ、そんな近づかないで!」
「だから、恥ずかしがっちゃ、めーっ、だよ?」
誰かの手がぬるりとアンナマリアの太腿の間に滑り込んで、泡立った手が秘部を撫でた。
「ひゃっ!?」
「躯を洗ってるだけでそんな声出しちゃうなんて、あなたってえっちなんだね」
「そんなところ触られたら、誰だって……ひゃぁうっ」
膣の中に指が入り込む。泡を潤滑液代わりにした指はぬるぬると前後の動きを繰り返す。
「ほらほら、中も綺麗にしないとね」
背中の少女がアンナマリアの耳元に息を吹きかけながら囁いた。
「こっちの方も綺麗にしようね」
アンナマリアの手足を泡まみれの躯で擦っていた少女たちのひとりが、アンナマリアの菊座へと手を伸ばした。泡に濡れた指で菊の穴を撫でて、一息に貫く。
つぷぅっ、と穴に突き入れられた指の感触にアンナマリアの中がきゅっと、甘く絞まった。
「ひぃうっ……あ、ああ……っ!?」
「もうっ、掃除してあげているだけなのに、そんなかわいい声をあげて……」
悠然と腕を組んでほくそ笑みながら、アワリティアはその痴態を眺めていた。
「それだけ貴方たちの手際がいいのですよ。さあ、もっと奥の方まで洗ってあげなさい」
「はーいっ」
すると、ひとりの男の子がアンナマリアの股の間に躯を滑り込ませた。アンナマリアの膣から少女が指を抜くと、代わりに泡まみれになったペニスを秘所に宛がう。
「それじゃあお姉ちゃん、中まで綺麗にしてあげるね」
返事を待たずに男の子は勃起した肉棒を中へ挿入した。
アンナマリアよりも小さい男の子のペニスは、勃起していても相応の大きさしかなかった。男たちからねじ込まれていた膣を裂くような大きさの陰茎に比べると随分かわいらしい代物だ。挿入されても異物感は少なく、アンナマリアの躯は自然と受け入れてしまっていた。
「うわ……お姉ちゃんの中、すっごく気持ちいいや……。でも、がんばってお掃除するね」
「こ、この……っ」
無邪気な顔で腰を揺する少年を精一杯の敵意を集めて睨み付ける。それでも快楽で涙を浮かべていた目ではかわいらしさしかなかった。
石鹸の泡でぬるぬるになった男の子の小さな肉棒はアンナマリアのひだを丹念に擦り、子宮の入り口に何度も亀頭を押し当てる。
子供たちに纏わり付かれて未知の快感に襲われていたアンナマリアの肢体は、幼い男性器のピストン運動にも初心な反応を返す。ぴくぴくと躯は震え、口元から透明の液体が垂れた。
だが、自分よりも小さな男の子に言い様にされるのはアンナマリアの意地が許さない。
足で男の子の腰をがっちりと掴むと、無理矢理一番奥にペニスをねじ込ませ、反撃を開始した。
「お茶目は、お終い!」
アンナマリアは勢いよく相手のペニスを締め付ける。挿入されたときに入り込んだお湯と愛液、石鹸が混じりあった混合液がじゅくじゅくとペニスに絡みつき、その上からは幾人の男たちを屈服させてきた膣肉が精を貪るように吸い付いた。
ただの人間の男の子がアンナマリアの男慣れした肉体に抗えるわけもない。
「わっ、お、お姉ちゃん、すご……い……あああああっ!」
ぴゅっ、ぴゅっ、とかわいらしさを感じさせる射精がアンナマリアの中で起こった。
泡まみれにされたアンナマリアの躯にしがみついて、男の子は気持ちよさでだらしない表情になりながら子宮の中に精を吐き出させられたのだ。
瞬殺されてしまった男の子は蕩けた目のまま白い肩で息をしてアンナマリアの躯の上に倒れる。その不甲斐ない様子に、少女たちがくすくすと笑った。
アワリティアも子供たちにつられて微笑んでいて、アンナマリアに男の子が倒されたことへの不安は一切浮かんでいない。
「あらあら、この子ったら、躯を洗いながらイってしまうなんて。私の子供たちにもおかしな性癖の子がいてしまったものですね。汚れてしまいましたし、お姉さんたちは弟の面倒もしっかり見てあげましょうね」
「はーい!」
元気のいい挨拶をした姉妹たちは男の子をアンナマリアから離すと、脱力している彼をすぐ横に寝かせた。そして、褐色の肌をした少女が精液にぬれた半勃ちのペニスを口に含んだのである。
頬をすぼめて石鹸と精液の混じった液体で濡れたペニスをしごきあげると、イったばかりだった少年が悲鳴のような嬌声をあげた。
「あぁあうっ! お、お姉ちゃぁん……ま、まだダメ……」
「お風呂なんだからちゃんと綺麗にしないとダメでしょう? それに、お風呂で汚くしちゃった罰だよ」
男の子の懇願もむなしく、姉と呼ばれる少女はじゅぽじゅぷと肉棒を口内で虐める。舌と頬肉による吸引の愛撫に、まだ精経験に乏しいであろう男の子が耐えられるわけもない。
「お、お姉ちゃんっ、またでちゃうっ!」
男の子の腰が跳ねると、今度は褐色の少女の口内に精液を噴出した。
どぷどぷっ、と口の中に精を出されて、少女はペニスを抜くと手で受け皿を作りながら口を開いた。舌の上で白濁とした精液がぷるぷると震えていて、舌から垂れた精液は唇をなぞりながら掌の上にしたたり落ちた。
「もうっ、洗うっていってるのになんで汚しちゃうかな? もっとお仕置きが必要みたいね」
「お、お姉ちゃん、もうやめてぇ……」
そうして少女は男の子を虐めることに専念し始めた。その様子にアワリティアは呆れながらも、そうなることが判っていたのか笑みを崩すことはなかった。
「やれやれ、盛りがついているんですから。貴方たちの方はちゃんとその子を綺麗にしてあげてくださいね」
少女と男の子の動向を見守っていた少女たちも再びアンナマリアへの奉仕をはじめる。お尻の穴に抜き出しされる指の感触、肌の上を滑る少女たちの肢体の感 触。そのどれもがアワリティアが目をかけるだけはある気持ちよさで、アンナマリアは我慢しようと思ってもつい口から喘ぎ声を洩らしてしまっていた。
「は、ああ……っ、いい加減に……っ」
きっ、とアンナマリアは子供たちを睨み付ける。しかし、くすくすと笑われるだけで彼女たちは気にした様子もない。
このままでは弄ばれて骨抜きにされてしまう。気持ちよさで一杯になった脳内にそんな危機感が生まれるが、両手足の自由がきかない状態では抵抗のしようがなかった。先程の男の子のように無防備を晒してくれれば話は別だが、少女たちにはそれを望むこともできない。
「自分は高みの見物で、あんなに偉そうなこと云ってたなんて……随分と、臆病者ね」
「あら、それは挑発のつもりですか?」
進退窮まって発したアンナマリアの言葉はアワリティアを鼻で笑わせるだけだった。
「勘違いしないでくださいね。私は、貴方のためにこうしてあげているのですよ」
「わたしのため?」
「ええ。だって、キスしただけであんなにかわいらしい顔になってしまうんですもの……。私が相手をしてあげたら、貴女は壊れてしまうでしょうね」
キスの感触を思い出してアンナマリアの唇がひりひりと熱くなる。もしアワリティアが本気で相手を籠絡しようと思えば、あれの比ではない快感が躯を走り抜けることだろう。
レリアを除けば常に格下の相手と躯を重ねていたアンナマリアからしてみると、アワリティアの力は想像できない領域にあった。
アンナマリアは雪のように白い頬を朱に染めたまま、股を開いた。
「なら、壊せるかどうか……試してみたら?」
例え圧倒的に不利な状況だったとしても、アンナマリアは賭に出るしかなかった。
一瞬、アワリティアの表情が強ばる。
「……?」
理由がわからず、アンナマリアは怪訝に思った。今までは余裕であったのに、アンナマリアの誘いに突然そんな反応を見せたのだ。
おそらく、アワリティアの本気がアンナマリアを大きく上回っているという事実に偽りはない。実際、キスだけであれだけの快感を流し込んでみせたのだ。七つの大罪の名を冠する淫魔の実力は伊達や酔狂ではあり得ない。
だからこそ、アンナマリアには意味がわからなかった。今の反応は、いったい何故?
だが、アワリティアの表情は既に余裕の笑顔に戻っている。違和感を追求する前に、アワリティアが動いた。
「そうまで云うならいいでしょう。私も自ら貴女のその薄汚れた躯を流してさしあげましょう」
一枚だけ纏っていた薄い布をさらりと床の上に落とすと、美しい裸身がアンナマリアの目の前に現れた。
「この胸を押しつけられて昇天しなかった男はいませんでした。貴女はどこまで耐えられるでしょうね?」
くすくすと笑って、アワリティアは石鹸を泡立てた両手で自身の豊満な胸を持ち上げた。そのまま泡を乳房に馴染ませるために揉みしだく。穏和な顔付きの女性が自らの胸を慰めるように見える姿は官能的で、アンナマリアですら生唾を呑み込んでしまった。
「貴方たちは下がっていなさい。さあ、行きますよ……」
子供たちがアンナマリアから離れると、すぐにアワリティアはアンナマリアを抱きしめた。薄い胸に大きな乳房が押しつけられてつぶれる。。胸を押しつけたままアワリティアはのの字に胸を動かして、乳首と乳首を擦り合わせた。
「く、ぅ……!?」
ただ乳首が触れあっただけなのに、絶妙な硬さになっているアワリティアのそれに引っかけられてアンナマリアは背筋を跳ねさせる。
「どうしました? まだほんの少し動いただけですよ? ……それとも、おっぱいが好きなんですか?」
湯船に張られたお湯からあがる湯気のせいで軽くのぼせたアンナマリアは首を振って問い掛けを否定する。しかし、頭が朦朧とするのはなにも湿気だけのせいでないことは明かだった。
「誰が、貴女の胸なんかに……」
「そうですか。……では、そろそろお顔もあらってあげなくてはいけませんね」
アワリティアがアンナマリアの後頭部に手を回すと、相手の顔を自分の谷間に押しつけた。
「う……っ、ふぅ……っ」
息苦しさに呻き、アンナマリアは顔をなんとかあげようとするが、アワリティアの方が腕力でも上だった。為す術なく胸の弾力に顔を挟まれてその触感に身を委ねるしか、アンナマリアには許されていなかったのである。
なんとか首を捻って谷間の隙間に顔をずらして浅く呼吸をした。すると、鼻腔に甘い芳香が充満した。香料の匂いか、石鹸の香りか、それともアワリティア自身 の色香がわき上がりでもしたのか。その香りは蜂を招き寄せる蜜のように甘美で、アンナマリアは躯から力が抜けていくのを感じた。
「ふふ……どうしました。私のおっぱいはそんな気持ちいいですか?」
アワリティアが躯を揺すると顔に押しつけられた胸がぷるぷると震えながら顔を圧迫する。しかし苦しいとは感じず、アンナマリアは顔を包み込む乳房の心地良さに身を委ねていた。
「あ……う、あ……」
それはアンナマリアにとって未知の感触だった。躯を重ねたことのある同性はレリアだけであったし、母もいないアンナマリアには女性らしい女性との交流が皆無だったのだ。
……そう、母。
アンナマリアはぼんやりと思う。今、自分の胸の中を満たしている幸福感は、まるで母に抱きしめられているときのようだ、と。母親がいたこともないのだから想像でしかないが、溶かされそうなほどの暖かい染み渡る快感はそうとしか説明のしようがなかったのだ。
「ふふ、なにもかも忘れて、身を委ねなさい」
すっ、とアワリティアの片手がアンナマリアの秘所に触れた。射精された精液と石鹸の泡で白く汚れたアンナマリアの膣に、ゆっくりと指が入り込む。
「あ、あぅ……」
拒まなければいけないのに、今までのような無理矢理与えられる快楽ではない、愛でるように染みこんでくる気持ちよさをアンナマリアはふりほどくことができなかった。
くちゅ、くちゅ、とゆっくり秘所を細い指が愛撫する。陰核を子供の頭を撫でるような優しさでなぞり、愛でる――。
胸の谷間から香る蜜の芳香と、顔を締め付ける弾力ある乳房、秘部をかき回す細指の感触。その前に、アンナマリアは反抗心を折られて屈服してしまっていた。
「さあ、このぬくもりの中で果てなさい……」
「あ……あ……っ!」
つぷ――、と秘所を貫かれ続け、ついにアンナマリアは見も心もアワリティアの前に折れた。
「あ――あああ――!」
びくんっ! とアンナマリアの躯が陸に打ち上げられた魚のように跳ねる。それでもアワリティアに力強く抱きしめられて胸から離れられず、アンナマリアは乳房の芳香で頭の中をいっぱいにされながら果てた。
躯の芯を走り抜ける甘い閃光で目の奥に火花を散らし、アンナマリアは潮を吹く。びちゃびちゃとアワリティアの手を汚して、それでも止まらず何度も終わるこ とのない絶頂に身を震わせた。強引にイカされたのではなく、自然と導かれた絶頂は胸を熱く満たしていて、快感は留まるところを知らなかった。
「あう……あ、ああ、ひゃ、ああ……」
「赤ん坊みたいな声を出して、そんなに心地良かったですか? 私の胸が貴女の涎でべとべとですよ……もう、しょうがない子ですね」
アワリティアが頭を撫でると、撫でられた場所がじんじんと熱くなる。髪の毛に手が触れているだけだというのに、そこが性感帯にでもなったかのような錯覚を起こさせられた。
もう躯を押さえる手はなにひとつないというのに、アンナマリアは脱力し、もう完全に抵抗することを諦めていた。いや、もう頭の中からは、このゆりかごにいるような心地良さから逃れようようなどという発想自体が抜け落ちてしまっていたのだ。
「お母様にあんなにされちゃ、もうあの子もなにもできないね」
「うんうん、あたしもあんな風に撫でられてイカされちゃったんだよねぇ」
「こちらも昔はお母様と敵対していましたが……あの優しさの前には……」
周りで見ていた少女たちが口々に感想を言い合う。この子供たちもあのようにされ、アワリティアに心酔した者たちだったのだ。
意識を朦朧とさせたアンナマリアの頭を撫でながら、アワリティアは子守歌でも歌うように耳元で口ずさむ。
「私の娘となりなさい……そうすれば、ずっとこのように愛し続けてあげましょう」
「むすめ……むすめに……」
「ええ。そして、私のために働いてください。行儀良くしてくれる限り、私は無償の愛を貴女に捧げてあげますよ……」
このような、心地の良い母性を――。
蕩けるような、ふわふわと、天にも昇る快感が――。
自分の手にはいる?
その言葉は、アンナマリアにとってこれ以上ないほどに魅力的なものだった。今までの記憶や感情を総てなげうってでもしがみつく価値があると心から思えた。
自分のことを遠巻きに見ている子供たちも、きっと、同じなのだとアンナマリアは理解する。敵として恨んでいたのに、アワリティアの抱擁で骨抜きされてしまった、それがあの子供たちだと。
その一員になるというのも、悪くない。だって、いなかった母親もできて、あんなに沢山の兄弟と一緒になれるのだから。
もう、ひとりぼっちじゃなくなるんだから。
アンナマリアは、そっと目を閉じた――。
――ジジジッ、と蝿の羽音のような雑音が脳内に反響した。
眠ろうとしたのに、このまま呑まれてしまおうとしたのに、その音だけがやかましく邪魔をしてきた。
うるさい、とアンナマリアは眉を顰める。けれど、同時にこの音から耳を背けてはならないという声も心の中であがった。
この音はいったいなんなのだろう。考えてみてもわからない。どんどんと大きくなる音は、次第に無視のできない程に大きくなっていた。
うるさい、うるさい、鳴り止んでしまえ。そう強く念じるが、雑音はさらに悪化するばかりだった。まるで、その音はアンナマリアを呼び起こそうとするベルの音のようで。
我慢できずに、アンナマリアは大声をあげた。
――うるさい! わたしは、このまま眠りたいの! ひとりぼっちはもう嫌なの!
人は死んでしまう。あの処刑人のように、無情に、あっさりと。父のように、強引に、あっさりと。みんな自分を置いて先に逝ってしまうのだ。
だから、そう、アンナマリアが復讐したいと思ったのも、単に自分をひとりぼっちにさせた報いを受けさせたかっただけなのかもしれない。大なり小なり理由は あれど、それが一番重要なことだったのか。処刑人のためだなんてことはただの大義名分で、ただ、どうしようもない理不尽に駄々をこねたかっただけなのだ。
でも、アワリティアなら、淫魔を母とすればその心配はなくなる。自分は多くの姉妹たちに囲まれ、人間たちに束縛されることなく、注がれる愛情を隣人として自由を謳歌することができるのだから。
そこまで云いきって、しかし、アンナマリアはまだ言葉が続くことに気がつく。
――ああ、でも。
自分に愛情を向けてくれる人は、まだいたのではないか。
暗闇の中に亀裂が走ってうっすらとした光が差し込んだ。
なんてことはない。ただ、アンナマリアが閉じていた目を開いただけである。目の前にはアワリティアの乳房があり、ランプの明かりが目に降り注がれた。
アンナマリアが顔をあげると、微笑んでいるアワリティアの顔がすぐそこにあった。目と目があって、頭を優しく撫でられた。
「お目覚めですか? さあ、貴女はこれから末の妹として私たちと……」
「気易く、頭を、触らないで」
自分の頭を撫でるアワリティアの手を振り払った。驚く相手に、アンナマリアは屹然とした目を向けた。
気付いてしまった。たとえ優しく頭を撫でられたとて、母親の手つきではない。ペットを撫でる手つきだと。アンナマリアも、子供たちにも、誰一人とて自分と 同等の存在として扱っていない。ただの、かわいい玩具としか思っていない。アワリティアは、どうしようもなく骨の髄まで淫魔なのであった。
「うそ……お母様の誘惑をはねのけるなんて……」
周囲の子供たちがざわめきだしていた。いつの間にか、男の子の上に跨って腰を振っていた褐色の少女も動きを止めて唖然としている。それほどに、今起こった出来事が信じられなかった。
「あんなに愛してもらったのに、どうして」
動揺する子供たちを、アンナマリアは意志のこもった目で睨み付ける。
「これに愛情なんてない。だって、自分と同じだなんて思ってないんだもの。わたしや、あなたたちは。この人からしてみたら……ただの動物よ」
「だ、黙りなさい!」
アワリティアが慌てて一喝したが、時既に遅かった。
アンナマリアの言葉を聞いた子供たちが、皆一様にして様子を変じさせる。頭痛を堪えるように頭を抑え、床に倒れていくのだ。
「うそ……ぜんぶ、うそ……。おかあさまは……アワリティアは、あたしたちのことなんて……」
「そうだ、最初はアワリティアを倒そうとしていたはずなのに、なんで、こんなことに……」
譫言をつぶやき、体力を使い果たして子供たちは気絶していく。アワリティアの余裕な表情は、ここにきて完全に崩壊した。
「そんな馬鹿な……。私の洗脳がたった一言で解けるだなんて、あり得ません! 大司教クラスの聖職者でさえ解呪には三日三晩を要するはず……!?」
「でも、出来ちゃったものは出来ちゃったんだし」
あっさりと言ってのけるアンナマリアを、アワリティアは悪霊でも見るような目で見た。顔は蒼白になり、もう当初の余裕はどこからも伺えない表情になっていた。
「やはり、貴女は危険です。その力、私のために利用させてもらおうと思っていましたが……ここで果ててもらうほかないようです」
「なにをそんなにビクビクとおびえてるの? わたしが怖いのは、貴女が淫魔だから?」
「な……っ」
アンナマリアは前に見た夢の内容を思い出しながら口にしてみた。あの夢が妄想以外のなにものでもない可能性もあり、鎌をかけだけのつもりだったが、ものの見事にそれは図星を突いていた。
「なんだ、当たりなんだ。よくわからないけど、わたしは貴女みたいな淫魔を倒すために作られたとか聞いた覚えがあったから云ってみただけなんだけど」
「く……っ、人をコケにしたのですか」
「それ、貴女が云う?」
はあ、と溜息をつく。これまでの会話の間で、アンナマリアは自身のペースを取り戻していた。
「理屈はわからない……けど、まだわたしには貴女を倒せる力があるみたい。だから、ここからが……本番」
「たかが洗脳を解いただけのこと。思い上がらないでください」
「だと思う?」
アンナマリアはくすりと笑った。何故か、もうアワリティアに負ける気は微塵も感じなかった。最初は虎に見えていたのに、アワリティアのことをもう子猫のようにしか思えないのだ。
「たぶん、わたし以外だったなら勝てたんだろうけど。わたしたちって、相性が最悪で、最高みたいだから。多分、もう無理だよ」
「それは、試してみなければわからないでしょう?」
ばさっ、とアワリティアが一対となった蝙蝠の羽根を広げる。アワリティアは、自身の躯すら覆い隠せるほどに大きな羽根でアンナマリアを覆った。
「これは……」
躯を覆い隠す羽根には人肌の暖かさがあり、思い切り手足ごとの抱擁。
「淫魔は、自分の羽根を自在に動かせるのですよ。ただ、私は他の淫魔よりも神経が発達していまして……羽根の表面から毛先の一本一本まで自由にできるのです。……今から、それで全身を愛撫してさしあげます。ちなみに、これを受けて生き残った者は……ゼロです」
妖艶な笑顔で宣告し、アワリティアが羽根を動かした。
きゅっ、とアンナマリアは躯を締め付けられる。ふりほどこうとしても手足は動かせず、じたばたと藻掻くしかなかった。
「こんな、もの」
「無駄です。大熊ですら絞め殺せる力すらだせるのですよ……貴女の細腕ではどうにもなりません」
言葉通り、アンナマリアがいくら抵抗したところでこの拘束を緩めることすらできない。じわじわと羽根が躯を強く押し包み、砂のようにざらざらとした皮膚を肌にすり込んでくる。
「さあ、羽根の感触に身悶えなさい」
ざらりとした羽根がアンナマリアの柔肌を撫でた。未熟ながらも触れたお尻を羽根でさすり、股の間に羽根の節を滑り込ませる。秘所に節が宛がわれ、じゅっ、じゅっ、と音を立てながら擦り上げる。
「うひゃ……っ」
「ふふ、陰核と膣を同時に責められる気持ちはどうですか? ざらざらした毛で粘膜をこすられると、腰が震えてしまいますよね。みっともないことです」
さらに、羽根の表面にある毛がさらさらと動き出す。敏感になった全身の肌を優しくブラシがけされているような感覚に、自然とアンナマリアの口から声が洩れていた。
「どうしましたか? さっきの威勢はどこにいってしまったのでしょうね。私の胸と、羽根に夢中ではありませんか。さて、このまま天国まで導いてあげましょうか――」
そこまで云って、アワリティアはアンナマリアの唇によって口を塞がれた。
羽根に抱かれたながらなんとか背伸びをしたアンナマリアがアワリティアの唇を奪ったのだ。
手足を封じられたアンナマリアにできる唯一の抵抗が口づけだったのである。そのことが判っているアワリティアは驚くこともなく、楽しげに唇を細めた。勝て もしない勝負を挑まざるを得なくなったアンナマリアの決死の行動に微笑ましくなって、アワリティアは自分から舌を搦めて相手の行為に乗ってやることにし た。
「ん……ん……っ」
ふたりの呼気が漏れる。そして、片方からは案の定、切羽詰まった喘ぎ声があがった。聞く者を欲情させる艶やかな嬌声をあげて、自分の有様に目を瞠る。
「そ、んな……ばかな……!」
声をあげていたのは、なんとアワリティアだった。
目を蕩けさせ、頬を赤く染めたアワリティアは、口の端から涎を垂らしながらも必死に正気を保とうとしていた。
「こんな、さっきはあんなに拙かったはずです……っ」
「なんだ、そんなこと」
くすりと微笑むアンナマリアの横顔は慌てているアワリティアよりもずっと淫魔のようだった。
「簡単だよ。ただ、貴女のやり方を覚えただけ」
「そんな、簡単に!? いや、まさか、それができるからこそ貴女が、私たちの……!」
淫魔を打倒する――夢の中の言葉をアンナマリアは正確に理解しているわけではなかった。けれど、自分いはそれを成せる力があるらしいということだけはぼんやりとだが自覚し始めていた。
はじめてアワリティアにキスをされたとき、アンナマリアはふりでもなんでもなく、本当にその舌技に圧倒された。だが、一度それを体験してしまえば、どうやって相手が舌を動かし、相手を感じさせたかを理解し、覚えてしまえたのである。
「きっと、わたしが道具だったからかな……。だから、方法さえ教えてくれれば簡単に真似できちゃうみたい」
例えば、人の首を刈ることのように。
アンナマリアは、刃を落とせば人は死ぬということをしっていて、そのための手段を用意された断頭台という存在である。それと同じで、実行するための手段で ある肉体があれば、どうしたら相手を感じさせることができるかという情報さえ手に入れば簡単に再現することができるのだ。そのことを、誰に云われることも なく、アンナマリアは感覚で把握した。
「ですが、所詮は猿真似です。そんな接吻だけで、この私が倒せるとでもお思いですか」
「だから、次はこっち」
アンナマリアがほくそ笑んで、秘部をきゅっと締め付けた。すると陰部を撫でていた羽根の節をつまみ、腰を押しつけながら上下に躯を揺らした。
じゅる――っ、と今度はアンナマリアが動いて羽根を舐め上げた。自慰行為のような行動に、何故かアワリティアが快感で躯を震わせる。
「こんなによく動くってことは、貴女の羽根ってとっても敏感なんでしょ? こうやって撫でてあげたらどうなるかな」
「私としたことが、おしゃべりが過ぎましたか……!」
アンナマリアの指摘は図星であり、アワリティアは悔しそうに顔をしかめた。
アワリティアの羽根は諸刃の剣なのである。神経が発達しているお陰で自由自在に動かすことができるが、神経が密集した分、性感帯のような敏感さを併せ持っ ている。それでも、欠点を抱えながらもアワリティアは自分の羽根に絶対の自信を持っていた。その弱点を相手に知られていても負けたことがないからだ。デメ リットを補って余りある利点が自由に動く羽根にはあったのだ。
しかし、それがここに来て裏目にでていた。
「こ、こんなもの……っ」
アワリティアが羽根を動かして、アンナマリアの秘所から羽根を外す。そのとき、羽根による拘束がわずかに緩んだ。
それで、アンナマリアの右手が自由になった。
隙を突いて右腕を抜き取る。腕を振るうだけのスペースはないが、相手の躯に触れるくらいの余裕はあった。
アンナマリアは自由になった右手で、押しつけられると窒息してしまいそうなくらいに大きな胸に触れると感触を楽しみながら持ち上げ、乳輪を口に含んだ。
「ああっ!?」
口にしてしまえば、後はもうアンナマリアの独壇場だ。アワリティアから学習した男殺しの舌技。それを余すところなく発揮して、その乳首にむしゃぶりついた。
「ちゅ……ちゅぷゅ……はう……っ」
まるで母乳を欲する赤子のような吸い付き。ただし、ただ夢中になって吸い付く赤ん坊と違って、アンナマリアの搾乳は性器すら搾り取ろうとするほどに貪欲だった。
「やっ、そんなに勢いよく吸い付いては……っ!」
乳首から浸透し、乳房を犯して全身を貫く刺激に、アワリティアは切なげに鳴いた。ちゅっ、とアンナマリアが強く乳首を吸う度に刺すような快感が乳首を責めるのである。
「吸い付くのは、だめ? なら、こっちも……貴女の指の技で責めてあげる」
いって、指先をアワリティアの膣に挿入した。
それは、アンナマリアの頭を撫でているときにアワリティアが使った指技であった。繊細に相手を責め立てる指の動きを完全に再現して、技を総てお返しする。
くちゅくちゅと蜜壺をかき回されて、止めどなく愛液が溢れだしてアンナマリアの手を濡らす。乳首と秘部を同時に責められ、アワリティアは目をうっとりと涙で濡らしていた。
「そんな、この私が……こんな、声を、あげてしまうなんて……!」
「それだけ、貴女の技が気持ち良いってことなのかな。今まで男たちを搾り取ってきた自分の技で感じるなんて……恥ずかしいね」
「ちょ、調子に乗って……! ああんっ」
睨み付けてくるアワリティアを子宮に指を差し込むことで黙らせて、アンナマリアは嗜虐心のままにほほえみかけた。
「もう終わりにしよう……自分の技で、みっともなく、イってしまって」
アンナマリアは指の前後運動を早め、ラストスパートをかけながら、口も思い切り乳首に吸い付かせた。
ちゅぱっ、ちゅぱっ、ちゅぱっ、と乳首をむしゃぶる音と、ずぷっ、ずぷっ、ずぷっ、と膣を貫く挿入音。その協奏に鼓膜を刺激され、アワリティアの性感は一気に高められていく――。
「こ、こんな……こんな、嘘です……私がイってしまうなんて、そんなことあるわけ、あるわけぇ……!」
アンナマリアが、最後に乳首をこりっと甘噛みし――アワリティアの躯が跳ね上がった。
「あ、イ、イ、イってしまう……この私が、私が、私がぁ――! あ、ああああっ、ああああああああんっ!!」
虚ろだった目を開いて、淫魔アワリティアは絶頂に達した。
乳房を何度も揺らし、足先をぴくぴくと痙攣させながら、何度も何度も全身を巡る快楽の渦に呑まれて、アンナマリアの前に屈服したのである。
ぐったりと脱力したアワリティアから、羽根を押しのけてアンナマリアが立ち上がった。
大浴場の中でひとり立ち上がり、すぐにまた倒れそうになってしまう。啖呵を切り、アワリティアを退けたものの、アンナマリアの躯に堪った刺激と疲労も相当なものだった。膝はがくがくと笑い、気を抜けばすぐにでも倒れてしまいそうである。
だが、戦いは終わった。
「……わたしの勝ち。さよならアワリティア」
足下に倒れている淫魔に向けて、アンナマリアは右手を突き出す。
アンナマリアの体力ももう限界で、性技でトドメをさせるだけの余力はもう残っていなかった。なら、自分がもっとも得意とする手段で敵を排除するしかない。
生かしておいてはなにがしでかすかわからないのだ。だからアンナマリアは、断頭台の力でアワリティアに引導を渡そうとしていた。
「あまり、調子に乗らない方がいいと、云っているでしょう……」
絶頂の余韻が抜けずに息を荒くしたアワリティアが、アンナマリアの目を見返した。しかしいくら凄もうとも、あの様子では淫魔といえどもしばらく動けないことは明白だった。
「負け惜しみ……? もう云わずに、死んで……しまえ、ば……」
急に全身から力が抜けて、アンナマリアが膝から床に崩れ落ちた。
そのまま躯を支えようとしても腕にも力が入らず、倒れてしまう。疲労が限界に達した、というわけではなかった。急に全身の筋肉が弛緩して動かなくなったのである。
「これ……ひったひ、な、に……」
口にして、ろれつが回らなくなっていることに気付く。これは自然に発生するとは考えられないことだった。
その有様に、アワリティアが喉を鳴らして笑う。顔には余裕が戻っていた。
「ど うやら、保険がきいたようですね……。気付いてはいませんでしたか? この浴場にずっと漂っている甘い香りに。これは催淫効果のある淫魔特製の媚薬なので すが、濃度の濃いものを耐性のない者が吸い続けると筋肉弛緩を引き起こすことがあるのですよ。やはり人の姿を取っている以上、その生理からは逃れられない ようですね……安心しましたよ」
「そ、ん、な……」
アンナマリアは狼狽しながらも右腕を動かそうとする。その手を少し左右に振れば、断頭台の刃がアワリティアに向かって跳ぶというのに、指先すらろくに動かせない。それは、意識だけをマネキンに移植されたかのような気分だった。
絶望的な焦燥が、炙るように胸を焼いた。じりじりと、敗北の足音がすぐそこまで迫っていた。
「これで貴女はもうなにもできませんね……。形勢逆転というやつです」
倒れたアンナマリアにかわって、アワリティアが躯を震わせながらゆっくりと立ち上がる。勝利を確信したアワリティアには既に不安の色はない。
「どうです? いきなり絶望の底に突き落とされた気分は」
床に倒れているアンナマリアの頭をアワリティアが踏みつけた。素足とはいえ力を込められて踏まれて、痛みに小さく声を洩らした。
「く……っ」
「いいです、いいですね、その悔しそうに歪んだ顔。本音を云えばもっと眺めていたいのですが、時間をかけて痛め付け、また不測の事態が起こってしまっても困ります。ですから、これで、お別れです」
羽根が大きく広がった。
大きく広がった一対の漆黒の羽根は、アワリティアの躯よりもさらに大きい。その異様な、美しさすら感じさせる姿は、アンナマリアにとっては死神以外の何者でもなかった。
「淫魔として、搾り殺すことこそ名誉ですが――この際、手段は選ばないことにしましょう。甚だ不本意ではありますが……これで逝っていただきます」
すっ、と手を掲げると、掌の上で何かがふわふわと光り出した。突如、小さかった光が太陽のようなまばゆさを持って輝く。目もあけられぬ光に浴場が照らし出された。
その灯りはすぐに収まった。だが、光自体は長細い槍状のものとなりアワリティアの手に握られていた。
「淫魔が暴力に訴えるのは本当に不名誉なことなのですよ……恥をかかせていただいた分、貴女にも不名誉な死に様を晒していただきます。その首を刎ねさせてもらいますね」
槍の歩先がアンナマリアの首もとに突き付けられた。じりじりと槍の放つ熱で肌が焼ける感触。
「……っ!」
元の姿が断頭台といえども、人の姿をとっている限り身体構造も人のものに倣っている。首を刎ねられれば、アンナマリアといえども死を免れない。死が目前に迫っていることに、断頭台は静かに息を呑んだ。
これまで、数多の人を殺めてきたというのに、いざ自分の前になって恐怖する自分にアンナマリアは恥ずかしさを覚える。厳かに敗北を受け止めて死んでしまえればまだ格好もつくのに、肌を焼く痛みに目頭が熱くなって、どうしようもなく死ぬことが怖かった。
槍を振り払ってアワリティアに飛びかかりたい思いに刈られたが、全身は水銀に覆い被さられたように重く、身動き一つとれない。
このまま、為す術なく、自分は死ぬのだ。
「それでは、断罪のお時間です」
そして、アワリティアが槍に込める力を強めた。
抵抗もなく、槍の穂先は押し込まれる。そのまま刃は石造りの床すら易々と焼き切りながら貫いた。
「……何者です」
殺意を隠さぬ声をアワリティアが洩らした。楽しみに水刺されたと、そういう不快さが滲みでている。
アワリティアの槍は床を貫いたが、貫いたのはそれだけだった。そこにはアンナマリアの躯はなく、薄い水溜まりが出来ているだけである。
剣呑な呼び声に答えたのは、張り詰めた空気には似つかわしくない余裕をたっぷりと砂糖壺一つ程は含んだ声。
「何者だ、と問われれば、そうだね。彼女の保護者と答えようかな」
浴場に始めて響く声。声の主は浴場にはおらず――否、現れた。
アワリティアの目の前に紺のマントが翻る。塔みたいに長い帽子を抑え、マントを払って危なげなく着地する女性は、口元をわずかにつり上げて人をからかうような表情をしていた。その表情こそが彼女の常なのだということはアワリティアの知る所ではない。
だが、それでも、アワリティアが彼女に対して知っていることはある。瑞々しく艶やかな銀髪に、人でありながら淫魔に引けを取らない男を惑わす魔性の肉体。 その立ち姿を忘れることなどそうそう起こりえることではない。特に、出会ったことすらない彼女を常々警戒していたアワリティアにはとって、その可能性は皆 無だった。
「魔女イザベラ……邪魔をしたのは貴女ですか」
「お初にお目にかかるよ、七罪の一柱。興を削いでしまって申し訳ない。本当は私も傍観を決め込むつもりだったのだけどね、いやはやなんとも、私にもまだ人の心というのが残っているらしい。我慢できずに干渉してしまったよ」
「……そうですか。貴女はそれほど情が深い人には思えませんでしたが」
「私もそう思っていたのだけどね。いやあ、母性とはすごいね。さすがの私も〝娘の危機には〟重い腰をあげざるを得なかったよ」
にやりとイザベラが笑った。アワリティアは戦いで疲れ切った躯で精一杯にイザベラを警戒しながら、槍の方もいつでも動かせるようにと気を払った。
「やはり貴女が断頭台制作、秘密にされた最後の協力者……でしたか」
「いかにも。常々私に気を向けていたということは、君は最初から知っていたようだね。さすが強欲のアワリティア。情報にすら欲が深いと見える」
互いに静かな牽制を続けながら、それでもイザベラから余裕が消えることもない。
「王 と開発者からの要請さ。彼女に魔術的効果を付与するためには私の協力が必要でね、この王宮に出向かせてもらっていたよ。いやあ、この浴場も懐かしいなあ。 ギヨたんの人格を作るためにサンプルとして子供を受精したんだけど、そのためにここで何度も王や兵士と躯を重ねたものだよ。みんな途中でへばってたなあ、 懐かしいね」
イザベラの論点が判らなくなるような軽口をアワリティアは相手にせず、冷静に返答する。
「対淫魔用、索敵断罪処刑具……というわけですね。あの学習能力、やはり完成していては我々の脅威となっていたでしょう。王を搾り殺した私の判断は間違っていなかったようですね」
「ギ ヨたんが成熟したら最終的にはもっと凄かったろうからね。自立行動して、淫魔と人を判別し、さらには性技を簡単に躯で覚えられるんだ。きっと世界一の床上 手になっていたと思うよ。あ、最後の機能は私が勝手につけたんだけど。せっかく淫魔と戦うんだからそれくらいないと面白くない」
そこでイザベラが指一本立てる。まるで教え子に講義をする教師のような仕草だった。
「でも、間違っていることがひとつ。それはね、ギヨたんが完成していたとしても君たちの害にはならなかったということだよ」
「……なんですって?」
「王の気が変わったんだよ。ギヨたんを自立行動させるためには知能が必要で、だから私の受精した子供をすぐに摘出して魂だけを移植したわけだけど、それに情が移ってしまったというわけさ」
大げさに肩を竦めて、イザベラは言葉を続けた。
「た だでさえ人化できるほどの力を蓄えさせるために断頭台を選んで人を処刑させていたんだ。人を殺すことはもっとも呪詛を溜め込む手段として優れているから ね。ただ、そのせいで人化の前に意識が目覚め、意志とは関係なく人を殺すという呪われた運命を背負わせたギヨたんに、それ以上の苦行を押しつけることがで きなかったのさ。だから私はギヨたんが目覚めたら自由に生きるようにいってくれって言付けられていたよ。その結果はご覧の通りだったけど」
「……なるほど、大方の事情は飲み込めました。それを知っていたとしても私の行動は変わらなかったでしょうが」
「ほう? 君は王の行動を危険視してこの国を落としたものだと思っていたけど」
「それが大きな理由であったことは否定しません。ですが、根本的に私の中に根付いている願望はおわかりでしょう?」
「二つ名は伊達ではない、か」
イザベラのつぶやきに、アワリティアの口が孤を描いた。
「そ う――強欲。私はね、欲しいのですよ。街が、国が、世界が。そこにある家畜が、民が、富が。私の淫魔としての行動は元をたどればそこに行き着くのです。搾 精をおこなうのも心が満たされるからですし、子供たちを作るのもその一環でしかありません。この世の総てが、私は欲しい」
「世界すら喰らおうとするか。なんとも大言壮語が過ぎる淫魔だ」
「そうでもないでしょう。世界をとるなんて実に淫魔らしいとは思いませんか。いや、世界、より地球と言い換えた方がいいでしょうね。だって、地球は生きているんですもの。生きているなら幾らでも籠絡してさしあげますわ」
「まあ、その槍すらその地球の産物だろうからね。私の魔法もそうだけど……やれやれ、私も人のことをいえないくらい業が深い」
「魔女も淫魔も、魔に通じるものは等しく地球の愛人ですものね」
イザベラとアワリティアの口にしている言葉は、常人には理解のし難いものであったが、ふたりの間では常識のような事柄であった。
空間跳躍を筆頭に超常的な力を振るうイザベラ、虚空から光の槍を取り出したアワリティア。ふたりの行使した力は共に魔法と呼ばれるものである。この力、理論的なところを省略してしまえば、その共通項は〝地球を騙す〟ことなのだ。
地球とは自然という新陳代謝をする生物であり、この世界の時間、空間、そんな普遍的な物理法則すら総て地球自身の生態、行動なのである。よって魔法とは、この地球をどう騙して架空の論理を走らせるか。どう新しい法則を地球に作らせる、信じ込ませるか、に集約する。
「私は魔女だからね。最初に力を手に入れたのは悪魔と契約したからさ。対価を支払わされることになるけど、悪魔から一気に強い力を貰える。魔法使いと違うところだね」
「そう、そうやって貴女が欲望のままに悪魔から力を手に入れたように、私は自分の欲望のままに国を獲ったまでのこと。そしてそれはこれからも続いてゆくのです。……ですから、邪魔な貴女にはここで逝っていただくとしましょう」
「へえ、その調子だと体力は回復できたのかい? 結構時間がかかったね」
飄々と云ったイザベラに、アワリティアは顔を強ばらせた。
「まさか、わかっていたのですか」
「そ うでなければあそこまで口数は多くないよ。と、云いたいところだけど、半分以上は私が話したいから話しただけさ。いや、他人に云えない秘密というのを抱え 込むのが苦手なタチでね。誰かに聞いておいて欲しかったんだよ。ほら、ギヨたん本人に伝えてもどうせお母さんなんて呼んでくれそうにないし」
「たいした余裕ですね。よほどご自身の力に自信があるようですが――その油断が命取りです」
瞬間、光が爆ぜた。
光――ッ、とまばゆい光で浴場が満たされる。目を閉じ手で覆ったとしても肉をつらぬき目を焼きかねない光。
その中を一筋の黒影が疾駆した。
光の槍を携えたアワリティアである。閃光に紛れて駆ける姿は足場の悪さをものともせず豹のように俊敏。
両手で腰の辺りで構えた光の槍、アワリティアはその穂先を人影へ一直線に向けていた。
光が晴れる。しかし、人影は未だに閃光の余韻で呆然と立ち尽くしていた。
目くらましの光に立ち尽くすイザベラが――。
無防備な獲物を前にして酷薄な笑みが浮かんだ。
「さようなら――愚かな魔女さん」
槍は鮮やかな手つきで、迷いなくイザベラの左胸を貫いた。
「ぐ……っ」
イザベラの口から真っ赤な血がこぼれ落ちる。
アンナマリアのときのようなことは起こらなかった。転移する暇すら与えずに、光の槍はイザベラの左胸を刺し、その心臓を貫いたのだ。熱を持った光の槍が音を立てて血を蒸発させながらイザベラを内部から焼き焦がし、脂肪の焼ける酸っぱい匂いが浴場の中に充満する。
「確かに貴女は過信するだけの力を持っていらしたようですが……それも使えなければ意味もありませんでしたね。おとなしくひきこもっていればよかったのに、調子に乗るからそうなるのですよ、お馬鹿さん」
「ああ、慣れないことは、するもんじゃ、ないね……」
イザベラの足から力が抜けて躯が傾ぐ。胸に刺さった槍に体重がかかって、背中へと貫通している槍がさらに深く突き刺さった。
「いかな魔女といえども、死んでしまえばただの肉塊。惨めな最期でしたね。あの世で悪魔への対価で慰みものにでもなっていなさい」
心の臓を貫かれて虫の息になったイザベラに、アワリティアは最後となるであろう言葉を投げかけた。
脱力したイザベラの躯をトドメをさすために槍がさらに深く突き進んでいく。
「いや、別に死んでないけどね。私は」
イザベラの手がアワリティアの胸を押した。
「え――っ」
それだけでアワリティアの躯が吹き飛んだ。
衝撃に槍を手から離してしまったアワリティアが向かいの壁に激突する。背後の壁に亀裂が走るほどの力に、口から苦悶の声があがった。
「いたたた。手が届かないから躯ごと奥に押し込んだけど、さすがに痛いね」
「か、ぁ……っ!? な、何故……」
「どうして生きてるか、だって? いやいや、君が散々云ってたじゃないか。魔女だからだよ」
自分の左胸に突き立った光の槍に、イザベラは熱で手が焼けることも気にせずに掴むと、一息で引き抜いた。傷口は焼け焦げ、血は流れ落ちなかった。
「魔女を人間と思っちゃいけないね。だから弱点が心臓だなんて思い込む。私も心臓を壊されれば痛いけど、それは肺や胃を傷つけられたのと意味に違いはないんだよ。私としては肝臓を刺された方が昔を思い出してまだ気が滅入ってしまうね」
自分の手を焼く光の槍を興味深そうに眺めながら、アワリティアはこれまた講義のような口調で云った。痛みと屈辱で、アワリティアの顔が苦虫を噛みつぶしたソレになった。
「へえ、光を一カ所に止めるように偏光させた槍か。熱は放射せず、直接触れたときにのみ伝導するんだね。温度は五〇〇〇度は超えているか。さすが高位淫魔は作り出せる携行武器も一流だね」
「調子に、乗るなと、云っているでしょう――っ」
アワリティアが吼えた。
一喝で彼女の背中にあった壁が吹き飛ぶ。アワリティアの漆黒の羽根に叩かれ、砕け散ったのだ。
「いいでしょう、そうまで虚仮にされてはこちらも全力で行かせて頂きます。この国に来てから蓄えた精気、それを総て魔法に注ぎ込んで――」
「あ、それは無理。これ以上争う気はないよ」
にこりと笑いながらイザベラが微笑んだ。
「だってもう争いじゃなくて、虐めだからね」
そして、アワリティアは自分の置かれた状況に絶句した。
「あ、ああ……」
頭上から、無数の光がアワリティアを照らしていた。それぞれの光源が青空に浮かぶ太陽を見上げたときのようにまぶしく、人が直視しつづけていては目を悪く してしまいそうなまばゆさだった。そんなことをものともせず、いや、そんなことに気を裂く余裕すらなく、アワリティアは見上げ続けていた。
その頭上には無数の光の槍が雨粒を停止させたような格好で並んでいた。
ずらりと並んだ光の槍。一〇は見ただけで上回ることがわかり、一〇〇ですら足りそうになかった。いったい、何百の槍が頭上に並んでいるのか。もし数え切れてしまったらアワリティアは発狂してしまうだろう。
「君が本気を出してしまえば、このお城くらいなら簡単に消し飛ばしてしまえるだろう。それは困るんだよ。ここに倒れてる子たちも兵士も巻き添えだし、なによりこんな歴史ある建物を壊すなんてもったいない。だから、そうさせる前に終わらせたいんだ」
「なんで、私の、魔法を……」
「んー? わからないかな。私もね、ギヨたんみたいに君の技を覚えたんだよ。もっともギヨたんは道具っていう性質を利用して関連づけしたんだけど、私は悪魔と契約して手に入れた模倣能力さ」
「馬鹿な……転移、怪力、身体の不死性、それに技の模倣……これだけの数の力を契約で与えられる悪魔などいるはずがありません! もし仮にいたとしても、埒外な代償が……」
「簡単な話だよ。私は、複数の悪魔と契約してるんだ。それなら話は簡単だろう?」
「そちらの方があり得ない! 悪魔から要求されるのは魂! 複数の悪魔から代価を要求されれば、生きていることなど……」
「うーん、頭が硬いな。だから、私は悪魔に代価を払わなくていいんだ。だから何体とだって契約できる。ああ、でも全員に一度は払ったかな。躯を重ねるっていう代価をね。ちょっと腰を振ってあげたら、みんな代価を免除してくれたよ」
今度こそ本当にアワリティアは言葉を失った。
魔女イザベラ――アワリティアはその存在をこの国に滞在している人物の中で最重要人物として注意を払っていた。未知数の魔女の力は、高位淫魔である自分自身でも脅威と判断していたのだ。
しかし、心底警戒していたというわけではなかった。常に目の端で姿を追ってはいたが、凝視したことは一度としてはなかったのだ。
アワリティアは最大限に警戒していたつもりだったが、相手の力はそれを軽々と上回るほどに規格外だった。
その力、全力のスペルビアでも勝てるのであろうか――? 淫魔の得意分野である性技でなら、自分でも――。そう思い込もうとして、勝てる想像が一切わいてこないことにアワリティアは絶望で泣きそうになっていた。
「それじゃ、覚悟はいいかな?」
「ま、待って……ください。最後に、ひとつだけ……」
「なんだい?」
時間を稼ごうという気はアワリティアにはなかった。多分、いかなる幸運が重なろうとも自分の死が覆らないだろうということは判っていた。ただ、単純に知りたいことがあったのである。
「貴女は、何者、なのですか……?」
その質問にイザベラは目を瞬き、次いでくすくすと笑い出した。
「ああ、そうか。そうだね。正体の判らぬ相手に殺されたくもないだろう。かといって、何者か、と問われて即答できるほど私は哲学を嗜んではいないんだが……うん、ならこの名なら通りもいいか」
すこし逡巡して、イザベラは自分の異名を口にした。
「シュネー・ヴィットヒェン……〝白雪姫〟、さ」
答えて、白雪姫――イザベラはアワリティアに問い掛ける。
「それじゃ、私からも君にひとつ聞かせてもらおうか」
「え……」
「君は今まで死んだことがあるかな。いや、ほら、こんなに槍があるんだ。即死されてもつまらないだろう。どれだけ蘇られるのかと思ってね」
「そんなことできるわけ……」
そこまで答えて、アワリティアの真っ青になった顔からさらに血の気が引く。イザベラの言葉の意味がわかってしまって、既に顔は死人のそれになっていた。
「ま、さか……あなたは……」
「ああ、そうだね。参考まで云わせてもらうと――私は、三度死んだよ」
今度こそ、アワリティアの理性という堤防は絶望によって決壊する。
「い、いやあああああああああああああああああああ」
無数の槍が投下され、悲鳴は光の彼方に消えた。
これが、この国を騒がせた革命の裏側での決着であった。
以後、真の指揮者を亡くした革命は瓦解していくこととなる――。
*
――エピローグ。
裏で指揮を執っていたものたちが無力化され、淫魔たちによって展開されていた兵士たちに下されていた命令は撤回された。
元より指示されていた人間たちにも理解できない不可解な頼み事だったのである。淫魔たち三人が忽然と消えたとあっては、事態が収束するのも当然と云えた。
さらに、スペルビアだけは騎士団長という表の立場もあったため、彼女の失踪についての調査もある。彼女が淫魔であると知らない大多数の者たちは大慌てで、意味の判らない命令にいつまでも構っている余裕はなかったのだ。
あの騒動から数日が経過していた。
アンナマリア、イザベラ、レリア、ジョゼフの四人はイザベラの家でテーブルをかこっていた。全員の目の前には細長いパンをナイフで切り分けたものがおかれており、できたてなのか香ばしいにおいを漂わせている。
「あー……冷めないうちにどうぞ」
そのパンを焼いた張本人であるジョゼフが遠慮がちに云った。
アンナマリアにパンを焼くという約束を果たすために、ジョゼフが居候をしているパン屋で焼いてきたものである。まともに店頭に並んだこともなく、特別に頼んでいたレリアだけが口にしていたものだが、それが今は全員の前にあった。
「じゃああたしが最初にいただきます!」
即答したのはレリアだ。云っているときには既に手はパンを掴んでいて、女の子でも食べやすいように小さく切りそろえられたパンを勢いよく噛んだ。
「うわっ、我が弟子ながら空気が読めないね、レリア」
「うるひゃいですよ、てんてー」
パンに噛みついたままもごもごと離したレリアは、そのままパンを口に押し込むと小さな喉を上下させて呑み込んだ。
「うんうん、空腹が満たされるパンですね」
「レリアちゃん、味はどうだったかな?」
「それはギヨたんの口から聞いてみるといいですよー」
「ギヨたんいうな」
アンナマリアは相変わらずの不機嫌そうな顔だったが、レリアに急かされてパンに手を伸ばした。
両手でおそるおそるパンを掴む。こんがりとして硬さのあるパンの耳と、真っ白でふわふわとした中の生地をじっと見つめた。元が断頭台であったアンナマリアにとって、パンは初めて口にするものであり、物珍しさで観察してしまっていた。
「さ、さあ、どうぞ」
「……うん」
頷いて、アンナマリアは口元にパンを持っていく。
さくっ、という音をさせて、パンをかじった。
しばしの沈黙の後、パンから口を離してつぶやいた。
「……不味い」
無慈悲な言葉にジョゼフの躯が硬直する。その隣でレリアはにこにこと笑っていた。
「はい、というわけで、あたしの感想も以下同文ですねぇ」
「容赦ない!? 笑顔なようでこの子たちまったく容赦ないですよ!」
「まあ仕方ないんじゃないかな。本当のことなんだし」
ジョゼフの正面に座ってパンをかじったイザベラも頷いて賛同を示していた。頬を引きつらせてジョゼフはうなだれる。
「判ってましたよ、自分が力不足だっていうことくらい……。せっかくだと張り切ってみましたけど……」
「期待して損した」
ざくっ、とアンナマリアの言葉がジョゼフに突き刺さり、体格の良い青年の躯がますます頼りなくしぼんだ。
「まるでやすりでも囓ってるみたい」
「もう追い打ちかけないで!?」
がりがりとパンを食べながら言葉を止めないアンナマリアに、ジョゼフは思わず涙目になりながら叫んでいた。
そこでジョゼフはアンナマリアの皿に載せていたパンが半分以上なくなっていることに気がつく。
「……あの、そんな無理して食べなくてもいいんだよ?」
「なんで?」
「いやなんでって……さっきやすりみたいって……」
「別にわたし、やすりがけされるのは嫌いじゃないけど」
不愉快そうに睨まれて困惑するジョゼフに、レリアがくすくすと笑った。
「やだなあ、ジョゼフくん。ギヨたんは一度だってこのパンが嫌いだなんていってませんよ」
「ギヨたんいうな!」
レリアの顔面にパンの切り身が投げつけられた。不意打ちに仰け反ったレリアは椅子から立ち上がるとむっと眉を寄せてアンナマリアを睨み付ける。
「こらっ、食べ物を粗末にするんじゃありません!」
「うるさいっ、ギヨたんいうな!」
顔を真っ赤にしたアンナマリアも立ち上がってレリアの目を真っ向から睨み付けた。ふたりのにらみ合いにジョゼフが慌てたが、イザベラは何食わぬ顔でパンをスープにつけながらかじっていた。
「ま、魔女先生……見てないでとめてくださいよ!」
「そんなこといわれてもねえ、喧嘩するほど仲が良いともいうし」
スープが染みこんで柔らかくなったパンを口に押し込んで、イザベラは食卓に肘をついた。
「それに、この喧嘩が見られるのは今日が最後だ」
イザベラの口調が、少しだけ重くなっていた。
それは、この場の全員が努めて気にしないようにしていたことだった。一気に部屋が耳の痛くなるほどに鎮まり返る。そうすると誰もが意識してしまう。ふたりの喧嘩にも、空元気が混じっていたということに。
「そのことくらい、みんな知っているんだろう。本人であるギヨたんや、直接話したジョゼフに……それと、立ち聞きをしていたレリアも」
「やっぱり、知られてましたか」
レリアの笑顔にも力がなく、まるで彫刻が微笑んでいるように味気ない。
アンナマリアが人でいられるタイムリミットは、もう目と鼻の先にまで迫っていた。そう、今にでも、瞬きをした次の瞬間には人の姿を保っていられなくなっているかもしれない。それほどまでに少女の躯は不安定になっていた。
「別に、死ぬわけじゃないし。ただ元の形に戻るだけ。そんな大げさなことじゃない」
ただ、当の本人はいつもと同じような顔のままにそういった。イザベラでさえ声の調子が変わっているというのに、この中で一番落ち着いているのはアンナマリア自身であった。
それに戸惑いながら、ジョゼフが声をあげる。
「でも、君はもう自分で喋ったりすることだってできなく……」
「大げさにしないで云ってるじゃない!」
アンナマリアが声を荒げて、ジョゼフははっと我に返った。
断頭台に戻るということは、アンナマリアは喋ることも、自分で考えることすらできなくなるのだ。単なるどこにでもある無機物になってしまうのである。イザ ベラの話では正当に年月を経ればまた目を覚ますことができるようになるとのことだったが、それは数年、数十年という単位ではない。数百年以上かかるもの だ。それほどの長い眠りは、死と同義である。それがおそろしくない訳などあるわけがない。
「あ、ごめん……」
「もういい。外の空気吸ってくる」
「あっ」
アンナマリアは椅子を倒しそうな勢いで机を離れると玄関から飛び出していった。止める間すら与えられなかった。
呆けて開けっ放しになった玄関の扉を見つめるジョゼフの背中を駆け寄ったレリアが思い切り叩いた。
「ほらっ、なにしてるんですか! 早く追うんですよ!」
「う、うん……! ちょっと、待ってーっ!」
頷いて、ジョゼフは後を追って玄関を飛び出した。その姿を見送って、レリアは安堵の溜息をつく。その横ではイザベラが丁度スープを飲み終えたところだった。
「いやはや。レリアは相変わらず苦労性だね。その難儀な性格には思わず目元が緩むよ。さ、あとはふたりに任せて私たちはのんびりするとしようか」
「なにいってるんですか、先生」
「んむ?」
「あたしたちも行くんですよ!」
レリアは思い切りイザベラの背中も叩いた。
「待って、待ってったら!」
人混みを掻き分けて路地を進むアンナマリアに向かってジョゼフは声を張り上げる。しかし、彼女の小さな姿は止まるどころか人の間を器用にくぐって進んでいく。
女の子を追いかけているのを周囲の人々に胡散臭げに見られながらも、ジョゼフはそれらに気を裂いている余裕はなかった。少しでも目を離せば、彼女は手の届 かないところへ消えてしまっている気がしたのだ。そして、次に会うときは物言わぬ姿になっている。そんな想像ばかりが浮かび上がってきて、もうジョゼフに はアンナマリアしか目に入らなかった。
走って、走って、アンナマリアが路地を曲がった。ジョゼフもつられてそこを曲がって進み続けると、急に人の姿がなくなっていく。郊外の奥地にひっそりと立てられたイザベラの家からある程度離れてしまえば、そこはもう人気のない森林地帯だった。
ここまでアンナマリアはすばしっこく逃げ回っていたが、人という障害物がなくなった今なら足の速さでジョゼフに適うものではない。みるみる間に距離を詰めて、ジョゼフはアンナマリアを後ろから抱きしめた。
「捕まえた」
「……離して」
「逃げないなら離すよ」
アンナマリアは答えなかった。ジョゼフは抵抗もしなくなった小さな少女のぬくもりを腕の中に感じながら口を開く。
「ごめんね、君が不安なことに気がついてあげられなくて」
「わたしは、別に……なんでもなかった。ただ、ひとりでいたいから……だからここまできたの」
「それなら、逃げなくてもよかったじゃないか。逃げられたら、追っちゃうよ」
「そんな、勝手なこと……」
そうは云いながらも、アンナマリアの言葉に覇気はなかった。顔を近づけていなければ、なにをいっているのかすら聞き取れないほどに弱々しい。
腕の中で小さくなる黒い少女に、ジョゼフはふと思いつく。
「君は、猫みたいだよね」
「なんで、猫?」
「猫は、自分の死期を悟ると姿を消すんだ。誰にも見られないように」
「それ……勉強して、知ったことなの?」
「さあ、なんだったかな。息抜きに読んだ本にでも書かれてたのかもしれない。だけどね、そうでなくてもぼくは君が猫みたいだと思ったよ」
「わたしは、猫みたいに弱くない」
「そうかな。ぼくには……君が雨に濡れて、帰り道がわからなくなった、かわいい黒猫に見えた」
言葉を失ったアンナマリアに、ジョゼフは腕に込める力を強めた。
「だから、もうひとりで無理なんてしなくていいんだ。やせ我慢して、ひとりで最後を迎えようなんて……そんなことはしなくていいんだ。だから、ぼくやみんな嫌いで逃げたんじゃなければ……看取らせてほしい。君の最後を」
「……嫌いなわけ、ないよ」
アンナマリアの顔はジョゼフからは見えなかったが、その声が震えていることはよくわかった。
「嫌いなわけない……ジョゼフも、レリアも、あの魔女だって……嫌いなんかじゃない。でも、わたしはひとりじゃなきゃいけなくて……ずっと酷いことをし続けなきゃいけなくて……だから、わたしが一緒にいたらみんなあの人みたいに不幸になっちゃうから……」
「不幸だなんて、ぼくは思わなかった。驚いたし、凄い目にだってあったけど、それでもぼくは君を蔑むことなんて一度だってなかった」
「でも……」
「あたしもギヨたんのこと大好きですよ!」
女の子が声を張り上げていた。それはジョゼフとアンナマリアを追いかけてきたレリアによるものだった。
「自分のせいで人が不幸になるだとか、迷惑にさせるとか、なにひとりで被害妄想に耽ってるんですか。あたしの知ってるギヨたんはそんなに殊勝な子じゃなかったですよ!」
「レリア……」
「偉そうにふんぞり返っていればいいんです。弾劾してくる人がいたらそれがどうしたって鼻で笑ってやればいいんです。ギヨたんは自分のことを負い目に感じる必要なんてこれっぽっちもないんですよ!」
「そうとも。むしろ、ひとりで溜め込まれている方が良い迷惑だよ」
レリアに続いたのはあのイザベラだった。急いできたのか肩で呼吸しているレリアと違って息一つ乱していなかったが、それでも、その目は真剣そのものだった。
びっくりして硬直しているアンナマリアに、ジョゼフがそっとつぶやく。
「ほら、みんな、こう云ってる。だからね、後ろめたさなんて覚える必要はないんだ。最後くらい……みんなに囲まれていたって、いいんだ」
「あ……っ」
ジョゼフの掌に熱い雫が落ちた。アンナマリアの小さな躯が震えていて、必死に掌で目元を拭っている。けれど、ジョゼフの手を濡らす雫が減ることはなく、むしろ堰を切ったように溢れていく。
「やだ……今度は、今度は……みんなとさよならしたくない。したくなくて、涙がとまらない……」
「ぼくは、君をひとりにはしないよ。だから、不安にならなくていいんだ。ただ、そう、少しだけ……眠るだけなんだから」
「起きたら、側にいてくれる?」
「勿論」
「それは……」
アンナマリアの小さな手が、ジョゼフの手を握った。
「すごく、安心した」
ジョゼフの腕の中にあった暖かさが徐々に薄れていく。ずっと掴んで離さないと思っていた子の躯からは力が抜けて、魂が抜け落ちたように冷たくなっていって、それを止める術はジョゼフにはなかった。
「さあ、ジョゼフ。もう離れるんだ」
「先生……」
「時間なんだ」
振り返った先にいたイザベラは、沈痛な面持ちで首を振った。レリアもぎゅっと手を握りしめて、動かなくなっていくアンナマリアを見ていた。
あの万能であったイザベラがあんな表情をするのを、ジョゼフは見たことがなく、だからもうどうしようもないのだという事実が胸に押し寄せる。奥歯を噛みしめながら、ジョゼフは少女の躯を地に横たえてその場を離れた。
そして、アンナマリアの躯が変わっていく。質量を無視して、その躯は輪郭を失って大きな断罪の鎌へと変わっていく。あとには、見上げるほどのただただ大きな断頭台が残された。
その処刑道具には、アンナマリアの名残を感じることはできない。無機質で、冷たい刃が、薄く漂う霧で濡れていた。
「ギヨたん……もう、動かないんですね」
レリアが断頭台に歩み寄って、その刃を見上げる。
涙は流していなかった。ただ、その顔には寂しさがあった。
「もう、ギヨたん云うなって、云ってくれないんですね」
こういえば、文句の代わりに刃でも落ちてきてくれそうな気がした。そう夢想して、けれど断頭台は動かない。それはもう道具でしかなく、道具は人が使わなければ動かないのだ。当然の理屈だった。
「さあ、どうする、ジョゼフ。君は彼女に無責任な約束をしてしまったぞ」
黙って断頭台を見ていたジョゼフに、イザベラが厳しい声をかける。
「起きたら側にいるだなんて、人の命では到底無理な話だ。彼女は今後数百年目を覚ますことはないのだから」
「そうですね……きっと、ぼくでは魔女先生みたいにもなれないでしょうし。もう、二度と、ぼくはあの子の姿を見ることはできないんでしょう」
イザベラを振り返る。ジョゼフの瞳に溢れていたのは、しかし、決意だった。
「けど、ぼくは駄目だったとしても。ぼくの息子が、孫が、曾孫が、子孫が……きっと、彼女の側にいてくれるはずです」
「君は……」
「子々孫々、言い伝えますよ」
そっと、その手で断頭台に触れる。
「ちっちゃくて、黒くて、かわいい、意地っ張りな……不器用な女の子がいるんだってことを。その子にあったら、絶対に助けてやってくれって」
ジョゼフは目を閉じた。思い返すのは、家族を全員失ったあとの自分だった。
あのとき感じた気持ちが胸にわき上がって、ジョゼフはイザベラに笑ってみせた。
「だって、目が覚めたときにひとりぼっちだったら、寂しいじゃないですか」
その答えに、イザベラはしばらく言葉を失っていた。彼女がなにかを言い出す前に、静けさはレリアによって打ち消された。
「それっ、あたしもお手伝いしますっ!」
がばっ、と抱きついてくるレリアにジョゼフが顔を真っ赤にしてあたふたと慌てた。
「え、ちょっと、レリアちゃん!?」
「いっぱい子供作って幸せな家庭を作りましょーね! それでそれで、ギヨたんが起きたときには騒がしいくらいの一大一族に!」
「ちょ、ちょっとそんないきなり……むぐーっ」
いきなりキスをされてジタバタと手足を振り回すジョゼフの姿を眺めていて、イザベラは苦笑しながら帽子を抑えて顔を隠した。唯一見える口元は、しっかりとした、皮肉ではない笑みが浮かんでいる。
「なるほど、血の繋がりか……。そうだった、それが人っていう生き物の確かな力だったね。寿命をなくして、久しく意識していなかったことだ」
騒がしいジョゼフとレリアの前でも静かにたたずんでいる断頭台を仰ぎ見て、イザベラは柔らかく目を細めた。
「なにも不安に思うことなんてないよ。だから、ゆっくりとおやすみ。――私(マイネ)の娘(トホター)」
*
「おーい、倉庫なんかでなにしてんだよ。婆ちゃん」
「別に。ちょっと写真を見てただけ。あと婆ちゃん云うな」
「いてっ、別に叩くこたぁねぇだろ! こっちはアンタに作らされた飯ができたから呼びにきてやったんだぞ。まったく、パンなんか焼かせやがって……」
「はいはい。じゃあそのパンを堪能させてもらう。不味かったら死なす」
「相変わらず理不尽っすね婆ちゃん!?」
騒がしい男女の二人組が薄暗い倉庫を後にする。
はめ殺しの窓から差し込む灯りが、地面に落ちた写真に降り注ぐ。
写真には、立派な髭を生やした老人が、若々しい妻と共に断頭台の前で微笑んでいる様が映し出されていたのであった――。
Photo By Isabella.
The End...
あけましておめでとうございます。前回あんなこといって年内に終わらせるつもりがこんなことになりました。というか文庫本換算で60ページ以上ある最終話となりました。総ページ数は大体400ページ!
思えば最初の一話をあげて思い付きで始めたものでしたが、こんなに続くとは自分でも驚きです。ここまで見守ってくださった皆様、本当に今までおつきあいありがとうございました。
せっかく作ったのだし、ということで最終話にして初めてでてくる設定、キャラクターの行動背景を描写したせいで蛇足感もでてしまいましたが、やりたいこと、云わせたいことはこれで終わりです。機会があれば、コメントでもらったような補足的な話もやってみたいですね。
今まで見るだけだったBF小説、実際に書いてみていかに苦労するか思い知らされた苦しくも楽しい期間でした。
それでは。重ね重ね、ここまで目を通していただきありがとうございました!

We
weixiefashi
Re: ギロチン少女マジカル☆ギヨたん1-12全
本来想说我来翻译试试的……但是刷页面都刷死机了两次……这样的庞然大物我还是敬谢不敏了……

Ti
tiandangao
Re: ギロチン少女マジカル☆ギヨたん1-12全
确实是……庞然大物……
咕啾……咕啾……。
夜晚的後街小巷裡、傳出陣陣咕啾咕啾的淫猥水聲。
平常這個時候根本不會有人經過的小巷、在盡頭處卻站著一個下半身高高聳立、因為過度悅樂而失神到嘴邊不停流出口水的男人。
「嗯嗯、呼嗯……啾」
在男人兩股間吸含著男人肉棒的是一名穿著黑色鑲白邊哥德洋裝的年幼少女。。黑與白的對比讓人印象深刻、從外表看起來大概還不到十五歲吧。
少女坐在地面上、環抱著男人的腰間、將肉棒吸到喉嚨的最底部、舌頭不停的前後舔舐著整支棒身
不是因為熱情――而是任務式的專注於男人的弱點、就如同愛護玩具一般、少女舔弄著龜頭的前端
「啊呣……、呼嗯……嗯啾」
少女的丁香小舌持續吸舔著龜頭、刺激尿道前端。有如某種不知名的妖異生物纏捲在男人的肉棒上。
從少女年幼的外觀根本無法想像如此高超的口交技巧和如此巨大的淫亂反差、男人不禁兩手抓住跨前少女的頭部加速前後擺動。
「啊、啊啊啊……忍不住、要射了――!」
話音剛落、少女口中的肉棒就一抖一抖的有如間歇泉般噴出了大量的精液
「嗚咕……嗚」
不斷地激烈跳動著的陰莖將白濁液滿滿地在嘴裡射了出來、少女臉上嫌惡的神色一閃而過、隨即無表情的一口口吞嚥。
這麼一丁點花了我兩個小時orz....
期待有人幫忙吧 不然日文不好翻不快...
夜晚的後街小巷裡、傳出陣陣咕啾咕啾的淫猥水聲。
平常這個時候根本不會有人經過的小巷、在盡頭處卻站著一個下半身高高聳立、因為過度悅樂而失神到嘴邊不停流出口水的男人。
「嗯嗯、呼嗯……啾」
在男人兩股間吸含著男人肉棒的是一名穿著黑色鑲白邊哥德洋裝的年幼少女。。黑與白的對比讓人印象深刻、從外表看起來大概還不到十五歲吧。
少女坐在地面上、環抱著男人的腰間、將肉棒吸到喉嚨的最底部、舌頭不停的前後舔舐著整支棒身
不是因為熱情――而是任務式的專注於男人的弱點、就如同愛護玩具一般、少女舔弄著龜頭的前端
「啊呣……、呼嗯……嗯啾」
少女的丁香小舌持續吸舔著龜頭、刺激尿道前端。有如某種不知名的妖異生物纏捲在男人的肉棒上。
從少女年幼的外觀根本無法想像如此高超的口交技巧和如此巨大的淫亂反差、男人不禁兩手抓住跨前少女的頭部加速前後擺動。
「啊、啊啊啊……忍不住、要射了――!」
話音剛落、少女口中的肉棒就一抖一抖的有如間歇泉般噴出了大量的精液
「嗚咕……嗚」
不斷地激烈跳動著的陰莖將白濁液滿滿地在嘴裡射了出來、少女臉上嫌惡的神色一閃而過、隨即無表情的一口口吞嚥。
這麼一丁點花了我兩個小時orz....
期待有人幫忙吧 不然日文不好翻不快...

We
weixiefashi
Re: ギロチン少女マジカル☆ギヨたん1-12全
不够血腥,没有翻译的动力啊……

Ma
max2963116
Re: ギロチン少女マジカル☆ギヨたん1-12全
这个好像超棒,但是确实太大量了,让一个人翻译是不可能了,应该有一个奖励机制给作出时间牺牲的人

Lu
lukewang1988
Re: ギロチン少女マジカル☆ギヨたん1-12全
小日本的小說都相當的刺激,希望有翻譯
很吸引人,小弟試著翻譯了一小段:)
咕啾……咕啾……。
夜晚的後街小巷裡、傳出陣陣咕啾咕啾的淫猥水聲。
平常這個時候根本不會有人經過的小巷、在盡頭處卻站著一個下半身高高聳立、因為過度逾愉悅而失神到嘴邊不停流出口水的男人。
「嗯嗯、呼嗯……啾」
在男人兩股間吸含著男人肉棒的是一名穿著黑色鑲白邊哥德洋裝的年幼少女。。黑與白的對比讓人印象深刻、從外表看起來大概還不到十五歲吧。
少女坐在地面上、環抱著男人的腰間、將肉棒吸到喉嚨的最底部、舌頭不停的前後舔舐著整支棒身
不是因為熱情――而是任務式的專注於男人的弱點、就如同愛護玩具一般、少女舔弄著龜頭的前端
「啊呣……、呼嗯……嗯啾」
少女的丁香小舌持續吸舔著龜頭、刺激尿道前端。有如某種不知名的妖異生物纏捲在男人的肉棒上。
從少女年幼的外觀根本無法想像如此高超的口交技巧和如此巨大的淫亂反差、男人不禁兩手抓住跨前少女的頭部加速前後擺動。
「啊、啊啊啊……忍不住、要射了――!」
話音剛落、少女口中的肉棒就一抖一抖的有如間歇泉般噴出了大量的精液
「嗚咕……嗚」
不斷地激烈跳動著的陰莖將白濁液滿滿地在嘴裡射了出來、少女臉上嫌惡的神色一閃而過、隨即無表情的一口口吞嚥。精液多次在喉嚨間上下移動,最終流下胃裡去了
少女溫熱的喘息從離開了男性生殖器,用舌頭纏上肉棒並卷起殘餘的精液,通紅的可愛香舌舔了舔敏感了的龜頭,把男人還在顫動的雙腳壓制推倒在到死胡同角落。
儘管如此赤裸了的男人的陰莖依然屹立著,少女面無表情一言不發的脫去了自己的內衣跨在男人的身體上,挽起禮服的裙子。未長毛也未成熟的女性器暴露在男性眼前也沒有害羞的樣子,反倒是這樣的舉動讓男人的臉紅了起來。比起那些已成熟的女性的性器官,這個可愛又令人憐惜,看起來卻有奇怪的平衡美感的花瓣一樣的少女的下體對男人來說是更淫靡的。
看了一眼無法轉動身體、一句話也不能開口的男人的陰莖,少女慢慢地垂下了腰,幾乎能讓龜頭碰觸到少女的入口。但是,期待的感覺沒有傳到男人的下身上。
對於自己沒有能夠插入完全出乎意料之外,被愛液潤滑的陰莖只是掃過少女的性器官。男人用著懇求的眼神仰視少女,與那象輕蔑一樣冰冷的視線交匯。
比自己年紀小的輕蔑眼神雖然不是沒有見過,但是男人感覺自己已經成為被蛇盯上的青蛙。在男人在下身僵硬無法思考的時候,少女在男人的下腹部上面坐了下去。可是沒有插入,只是未成熟的女性器官擠壓著男人的陰莖。
少女一動不動地看男人,沿著肉棒動了動腰。慢慢的、輕柔的滑動,兩人性器摩擦著剛剛射精的敏感龜頭,男人發出了女性那樣的嬌喘。
女性器內部像章魚的微小吸盤一樣吸附在陰莖上,以類似吹奏橫笛的方式撫摸的陰莖的全部。被愛液濕透的肉棒的在女性的性器內享受著吸盤帶給他的快感。發出著咕秋、咕秋的滑溜的聲音刺激。
女性器不間斷的給予龜頭刺激。少女對著放入自己體內的陰莖也沒有閑著,持續的在高潮之前停止的對男人的陰莖玩弄著。但是男人不能噴發。只能集中意志力享受著少女的下體所給予的無止盡的快樂地獄。只見少女的腰此時上下快速活動。以高速的速度對著陰莖做著一次又一次磨擦,在女性的下半身內,男人的性慾又到了解放的時候。
阿….那樣…那樣阿——!
噗嗤!!被狂瀉而出的精液。
象徵的生命的種子一邊離開了男己的身體,一邊飛散在少女雪白的大腿上。什麼都沒穿的下半身和穿著衣服的上半身由於自己噴灑而出白色的液體而弄髒了。
舔舐,吸住,男人在少女的肩上喘息而女性用舌頭清理著這些白色體液,再將櫻桃小嘴移向了男人的陰莖。將被白濁粘糊液體塗滿的龜頭銜了起來。
「阿!? 」
象雷擊一般的快感使男人的腰浮起。
「不,不要,停止……」男人不知因為快感而想說出停止還是不要停止,但少女不回答,將男人的精液西入口中。
伴隨著咕秋、咕秋發出格外大的聲音吸吮著龜頭,少女從陰莖上離開喉嚨時似乎很大口、用力的吞嚥吸入口中的白濁液體。而被留下來的,是自己的精子弄髒的悲哀的男人的屍體。
少女的耳朵,聽見腳步聲的靠近。
發現了新的獵物。
將臉轉動到那個方向,少女背對著小巷子離開了。
繼續翻譯中
咕啾……咕啾……。
夜晚的後街小巷裡、傳出陣陣咕啾咕啾的淫猥水聲。
平常這個時候根本不會有人經過的小巷、在盡頭處卻站著一個下半身高高聳立、因為過度逾愉悅而失神到嘴邊不停流出口水的男人。
「嗯嗯、呼嗯……啾」
在男人兩股間吸含著男人肉棒的是一名穿著黑色鑲白邊哥德洋裝的年幼少女。。黑與白的對比讓人印象深刻、從外表看起來大概還不到十五歲吧。
少女坐在地面上、環抱著男人的腰間、將肉棒吸到喉嚨的最底部、舌頭不停的前後舔舐著整支棒身
不是因為熱情――而是任務式的專注於男人的弱點、就如同愛護玩具一般、少女舔弄著龜頭的前端
「啊呣……、呼嗯……嗯啾」
少女的丁香小舌持續吸舔著龜頭、刺激尿道前端。有如某種不知名的妖異生物纏捲在男人的肉棒上。
從少女年幼的外觀根本無法想像如此高超的口交技巧和如此巨大的淫亂反差、男人不禁兩手抓住跨前少女的頭部加速前後擺動。
「啊、啊啊啊……忍不住、要射了――!」
話音剛落、少女口中的肉棒就一抖一抖的有如間歇泉般噴出了大量的精液
「嗚咕……嗚」
不斷地激烈跳動著的陰莖將白濁液滿滿地在嘴裡射了出來、少女臉上嫌惡的神色一閃而過、隨即無表情的一口口吞嚥。精液多次在喉嚨間上下移動,最終流下胃裡去了
少女溫熱的喘息從離開了男性生殖器,用舌頭纏上肉棒並卷起殘餘的精液,通紅的可愛香舌舔了舔敏感了的龜頭,把男人還在顫動的雙腳壓制推倒在到死胡同角落。
儘管如此赤裸了的男人的陰莖依然屹立著,少女面無表情一言不發的脫去了自己的內衣跨在男人的身體上,挽起禮服的裙子。未長毛也未成熟的女性器暴露在男性眼前也沒有害羞的樣子,反倒是這樣的舉動讓男人的臉紅了起來。比起那些已成熟的女性的性器官,這個可愛又令人憐惜,看起來卻有奇怪的平衡美感的花瓣一樣的少女的下體對男人來說是更淫靡的。
看了一眼無法轉動身體、一句話也不能開口的男人的陰莖,少女慢慢地垂下了腰,幾乎能讓龜頭碰觸到少女的入口。但是,期待的感覺沒有傳到男人的下身上。
對於自己沒有能夠插入完全出乎意料之外,被愛液潤滑的陰莖只是掃過少女的性器官。男人用著懇求的眼神仰視少女,與那象輕蔑一樣冰冷的視線交匯。
比自己年紀小的輕蔑眼神雖然不是沒有見過,但是男人感覺自己已經成為被蛇盯上的青蛙。在男人在下身僵硬無法思考的時候,少女在男人的下腹部上面坐了下去。可是沒有插入,只是未成熟的女性器官擠壓著男人的陰莖。
少女一動不動地看男人,沿著肉棒動了動腰。慢慢的、輕柔的滑動,兩人性器摩擦著剛剛射精的敏感龜頭,男人發出了女性那樣的嬌喘。
女性器內部像章魚的微小吸盤一樣吸附在陰莖上,以類似吹奏橫笛的方式撫摸的陰莖的全部。被愛液濕透的肉棒的在女性的性器內享受著吸盤帶給他的快感。發出著咕秋、咕秋的滑溜的聲音刺激。
女性器不間斷的給予龜頭刺激。少女對著放入自己體內的陰莖也沒有閑著,持續的在高潮之前停止的對男人的陰莖玩弄著。但是男人不能噴發。只能集中意志力享受著少女的下體所給予的無止盡的快樂地獄。只見少女的腰此時上下快速活動。以高速的速度對著陰莖做著一次又一次磨擦,在女性的下半身內,男人的性慾又到了解放的時候。
阿….那樣…那樣阿——!
噗嗤!!被狂瀉而出的精液。
象徵的生命的種子一邊離開了男己的身體,一邊飛散在少女雪白的大腿上。什麼都沒穿的下半身和穿著衣服的上半身由於自己噴灑而出白色的液體而弄髒了。
舔舐,吸住,男人在少女的肩上喘息而女性用舌頭清理著這些白色體液,再將櫻桃小嘴移向了男人的陰莖。將被白濁粘糊液體塗滿的龜頭銜了起來。
「阿!? 」
象雷擊一般的快感使男人的腰浮起。
「不,不要,停止……」男人不知因為快感而想說出停止還是不要停止,但少女不回答,將男人的精液西入口中。
伴隨著咕秋、咕秋發出格外大的聲音吸吮著龜頭,少女從陰莖上離開喉嚨時似乎很大口、用力的吞嚥吸入口中的白濁液體。而被留下來的,是自己的精子弄髒的悲哀的男人的屍體。
少女的耳朵,聽見腳步聲的靠近。
發現了新的獵物。
將臉轉動到那個方向,少女背對著小巷子離開了。
繼續翻譯中

He
heyuqifashi
Re: ギロチン少女マジカル☆ギヨたん1-12全
机翻太无力,感谢LS的分享